06/06: 龍脈/沖縄の大本系の教団
私は1999年5月発行の『沖縄近代文化年表』(琉文手帖4号)に「1916(大正5)年9月10日ー暁烏敏来沖」と記した。このときは琉球新報が11日に「暁烏敏先生を訪ふ」が載っている。公文書館が収集した1925(大正14)年3月4日『沖縄朝日新聞』に「暁烏敏 昨日来県、西新町南陽旅館へ」が載っている。
暁烏敏 あけがらす-はや
1877-1954 明治-昭和時代の僧,仏教学者。
明治10年7月12日生まれ。清沢満之(まんし)に師事して浩々洞(こうこうどう)にはいり,明治34年雑誌「精神界」を発刊,精神主義をとなえる。のち生家の石川県真宗大谷派明達寺の住職となり,布教と著述につとめた。昭和26年同派宗務総長。昭和29年8月27日死去。77歳。真宗大(現大谷大)卒。法名は恵祐。著作に「歎異抄講話」など。
【格言など】人が自分を軽蔑して居るというて憤慨するのは自分自らが軽蔑しているのだ。→コトバンク
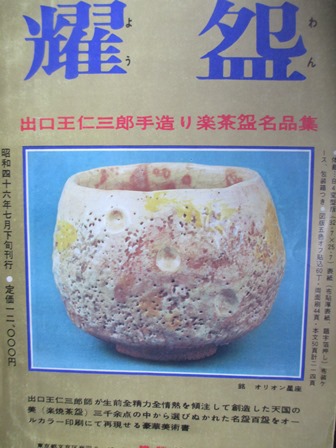
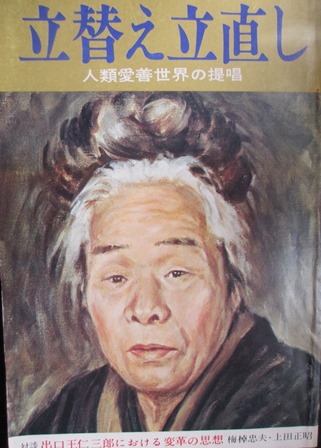
1971年5月 『建替え建直しー人類愛善世界の提唱』出口王仁三郎生誕百年記念会
2003年正月 沖縄県護国神社に行くと鳥居に日本民主同志会/松本明重とあった。懐かしい名前である。平良盛吉翁の『関西沖縄開発史 : 第二郷土をひらく 』1971を援助し日本民主同志会本部名で発行していた。松本氏は世界救世教外事対策委員長、祇園すえひろ会長だが、沖縄に関わり、「京都の塔」「小桜の塔」に碑を建てている。この人とダブって思い出したのが、「元祖スエヒロ」という「しゃぶしゃぶ」の店を経営している大阪日本工芸館長の三宅忠一氏である。この人も沖縄民芸などに力を入れていた。
松本氏は東本願寺紛争にも名が出てくる。相対する西本願寺と云えば弟22世門主・大谷光瑞が思い出される。戦前沖縄の新聞に、光瑞来沖かと云う記事を見たことがあるが、結局来なかったようである。その代わりというか弟の大谷尊由が1918年2月に来沖し相当に歓迎されたようである。光瑞と同じく宗教界の怪物と知られる人物に大本の出口王仁三郎が居る。その大本宣教場の亀岡「天恩郷」は明智光秀の居城跡で、そこに沖縄から奉仕活動に来ていた金城ひろこさんを大城敬人(現名護市会議員)氏に紹介されて遊びによく行った。
虎瀬公園は、モノレール儀保駅から歩いて15分くらいの ところにある公園。 遊具は滑り台や幼児遊具があるので小さい子でも 楽しく遊ぶことが出来る。 園内には、緑が多くとても見ているだけでも気持 ちいい。 公園の隣りには世界救世教の建物がある。

蘇鉄


佐藤惣之助詩碑。1959年五月、惣之助の出身地である川崎市民の厚意によって建立されたものである。当初、首里当之蔵町、旧琉球大学構内(現首里城公園)にあったものを、公園の整備に伴い、当地へ移築したものである。建立に際しては、同じ神奈川県出身の陶芸家浜田庄司の手による陶板が用いられている。碑の文言は「宵夏」。

○せかいきゅうせいきょう 【世界救世教】
岡田茂吉(一八八二~一九五五)が開いた大本教系の新宗教。もと大本教布教師だった岡田が、岡田式神霊指圧療法を始めて大日本観音会を一九三五年に発足させたのが始まり。宇宙の主神を大光明真神とし、岡田の掌から放射する観音力で浄霊が行われ、万病が治るとする。のち大日本健康協会・世界メシヤ教などと変わり現名に。岡田は信者から「お光様」と呼ばれた。所在地・静岡県熱海市桃山町。MOA美術館 創立者の「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」との願いを継承し、1982年にMOA美術館を開館しました。その成り立ちは、昭和32年にまず、熱海市に熱海美術館を開き、昭和57年の創立者生誕百年の年に、現在の美術館を開館、「Mokichi Okada Association」の頭文字を冠するMOA美術館と改め、財団の中心拠点として、美術品の展観をはじめ、いけばな、茶の湯、芸能、児童の創作活動などを通して、幅広い文化活動を展開。

那覇市泊の光明会館(生長の家沖縄県教化部)の蘇鉄
○生長の家は、大本で機関紙の編集主幹をしていた谷口雅春が起こした教団です。生長の家は岡田茂吉の系統と違い、大きな分裂もなく現在に至っています。この教団の特徴は、設立の経緯が同人雑誌だったので現在でも機関紙を定期購読することが信者の勤めとなっていること、またメディア・マスコミには非常に敏感です。マスコミの取材に対してまともに答えを出さない(出せない)新宗教団体が多い中、生長の家だけは毎度ながらもっとも丁寧に回答を出します。生長の家のホームページにも、教義から組織から歴史から沿革その他にいたるまで、丁寧に解説されています。(はてなキーワード)
暁烏敏 あけがらす-はや
1877-1954 明治-昭和時代の僧,仏教学者。
明治10年7月12日生まれ。清沢満之(まんし)に師事して浩々洞(こうこうどう)にはいり,明治34年雑誌「精神界」を発刊,精神主義をとなえる。のち生家の石川県真宗大谷派明達寺の住職となり,布教と著述につとめた。昭和26年同派宗務総長。昭和29年8月27日死去。77歳。真宗大(現大谷大)卒。法名は恵祐。著作に「歎異抄講話」など。
【格言など】人が自分を軽蔑して居るというて憤慨するのは自分自らが軽蔑しているのだ。→コトバンク
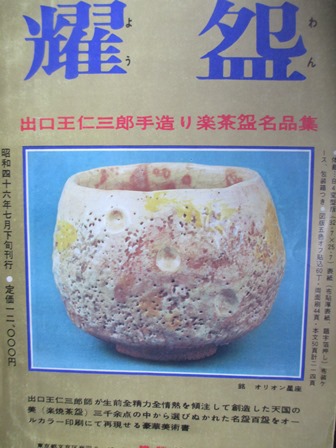
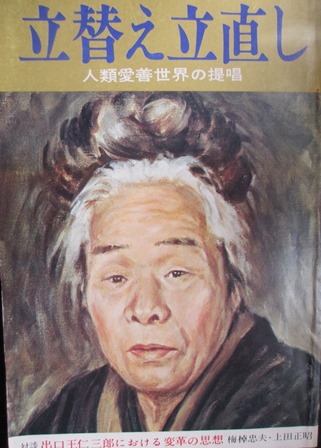
1971年5月 『建替え建直しー人類愛善世界の提唱』出口王仁三郎生誕百年記念会
2003年正月 沖縄県護国神社に行くと鳥居に日本民主同志会/松本明重とあった。懐かしい名前である。平良盛吉翁の『関西沖縄開発史 : 第二郷土をひらく 』1971を援助し日本民主同志会本部名で発行していた。松本氏は世界救世教外事対策委員長、祇園すえひろ会長だが、沖縄に関わり、「京都の塔」「小桜の塔」に碑を建てている。この人とダブって思い出したのが、「元祖スエヒロ」という「しゃぶしゃぶ」の店を経営している大阪日本工芸館長の三宅忠一氏である。この人も沖縄民芸などに力を入れていた。
松本氏は東本願寺紛争にも名が出てくる。相対する西本願寺と云えば弟22世門主・大谷光瑞が思い出される。戦前沖縄の新聞に、光瑞来沖かと云う記事を見たことがあるが、結局来なかったようである。その代わりというか弟の大谷尊由が1918年2月に来沖し相当に歓迎されたようである。光瑞と同じく宗教界の怪物と知られる人物に大本の出口王仁三郎が居る。その大本宣教場の亀岡「天恩郷」は明智光秀の居城跡で、そこに沖縄から奉仕活動に来ていた金城ひろこさんを大城敬人(現名護市会議員)氏に紹介されて遊びによく行った。
虎瀬公園は、モノレール儀保駅から歩いて15分くらいの ところにある公園。 遊具は滑り台や幼児遊具があるので小さい子でも 楽しく遊ぶことが出来る。 園内には、緑が多くとても見ているだけでも気持 ちいい。 公園の隣りには世界救世教の建物がある。

蘇鉄


佐藤惣之助詩碑。1959年五月、惣之助の出身地である川崎市民の厚意によって建立されたものである。当初、首里当之蔵町、旧琉球大学構内(現首里城公園)にあったものを、公園の整備に伴い、当地へ移築したものである。建立に際しては、同じ神奈川県出身の陶芸家浜田庄司の手による陶板が用いられている。碑の文言は「宵夏」。

○せかいきゅうせいきょう 【世界救世教】
岡田茂吉(一八八二~一九五五)が開いた大本教系の新宗教。もと大本教布教師だった岡田が、岡田式神霊指圧療法を始めて大日本観音会を一九三五年に発足させたのが始まり。宇宙の主神を大光明真神とし、岡田の掌から放射する観音力で浄霊が行われ、万病が治るとする。のち大日本健康協会・世界メシヤ教などと変わり現名に。岡田は信者から「お光様」と呼ばれた。所在地・静岡県熱海市桃山町。MOA美術館 創立者の「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」との願いを継承し、1982年にMOA美術館を開館しました。その成り立ちは、昭和32年にまず、熱海市に熱海美術館を開き、昭和57年の創立者生誕百年の年に、現在の美術館を開館、「Mokichi Okada Association」の頭文字を冠するMOA美術館と改め、財団の中心拠点として、美術品の展観をはじめ、いけばな、茶の湯、芸能、児童の創作活動などを通して、幅広い文化活動を展開。

那覇市泊の光明会館(生長の家沖縄県教化部)の蘇鉄
○生長の家は、大本で機関紙の編集主幹をしていた谷口雅春が起こした教団です。生長の家は岡田茂吉の系統と違い、大きな分裂もなく現在に至っています。この教団の特徴は、設立の経緯が同人雑誌だったので現在でも機関紙を定期購読することが信者の勤めとなっていること、またメディア・マスコミには非常に敏感です。マスコミの取材に対してまともに答えを出さない(出せない)新宗教団体が多い中、生長の家だけは毎度ながらもっとも丁寧に回答を出します。生長の家のホームページにも、教義から組織から歴史から沿革その他にいたるまで、丁寧に解説されています。(はてなキーワード)
09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」
伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。
1891年
4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)
1900年
9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。
1903年
9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。
1904年
7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。
1905年
8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。
1906年
7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。
1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立
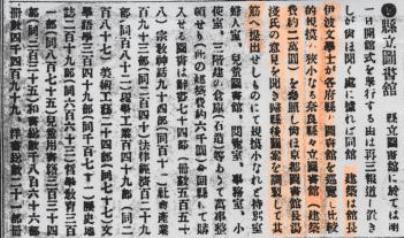
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
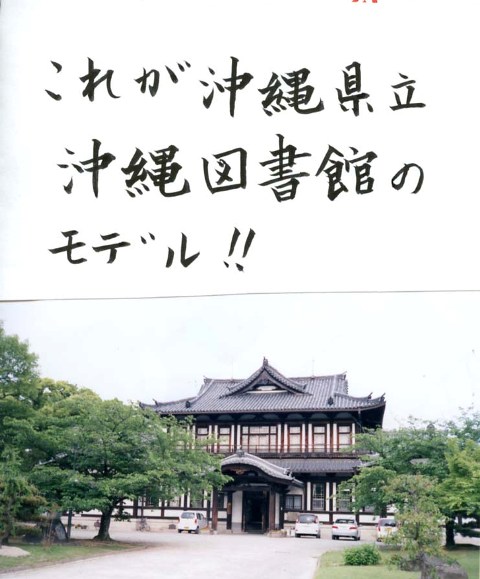
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1911年
4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。
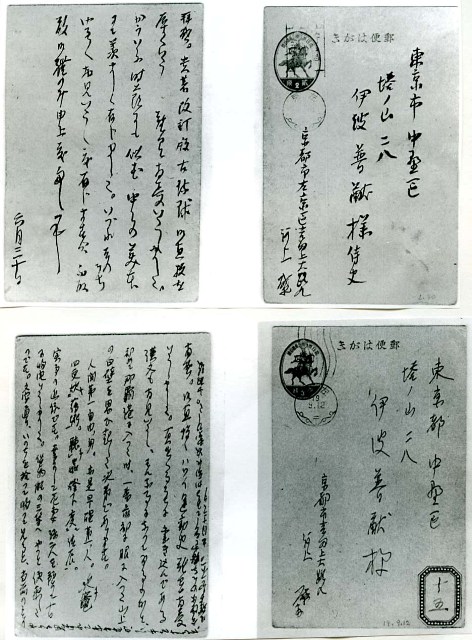
■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)
8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」
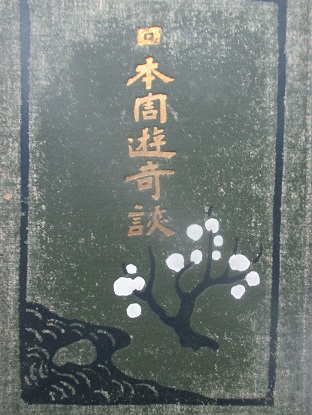
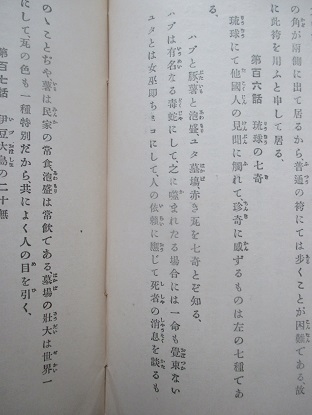
1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館
1912年
4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町
1913年
3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代
1913年
3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。
5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷
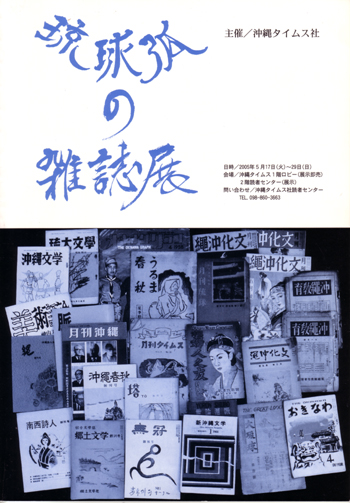
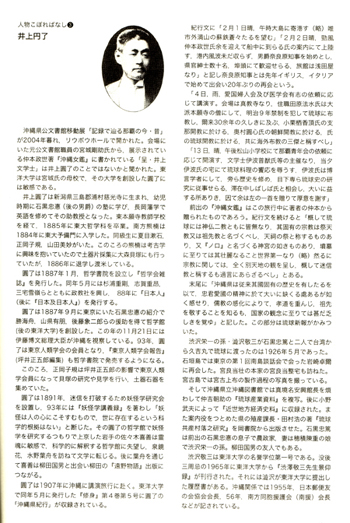
井上円了
『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。
大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。
□井上円了
生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)
没年: 大正8.6.5 (1919)
明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻
(恩田彰) →コトバンク
8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。
9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」
1916年
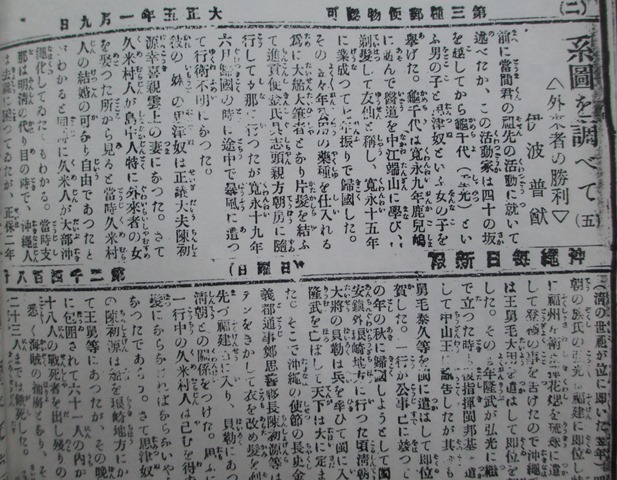
1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)
3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら
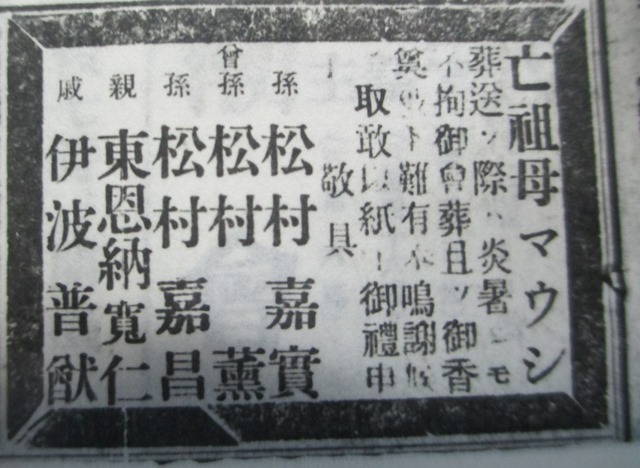
1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」
1918年
3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真
1919年
7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」
1920年
岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」
1921年
5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。
1924年
3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」
3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」
5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」
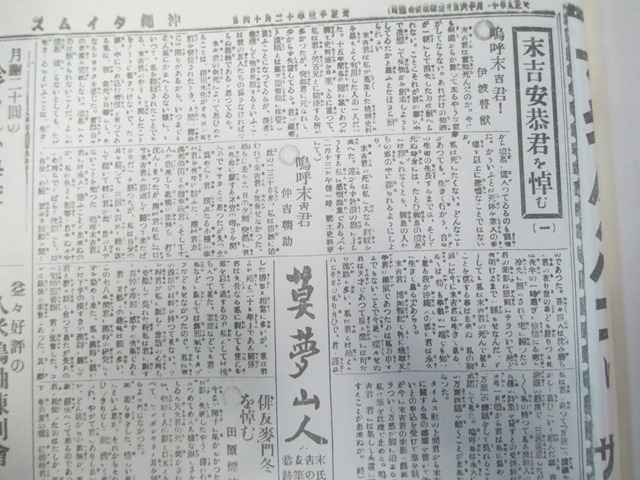
12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」
1925年
2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。
7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」
1926年
1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~
1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)
8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~
9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。
1927年
4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」
1928年
10月ー春洋丸でハワイ着
1929年
2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻
小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候
1931年
6月ー伊波の母(知念)マツル死去
12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居
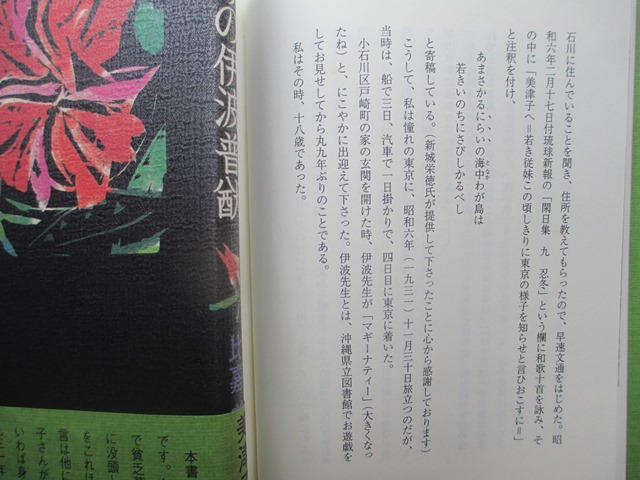
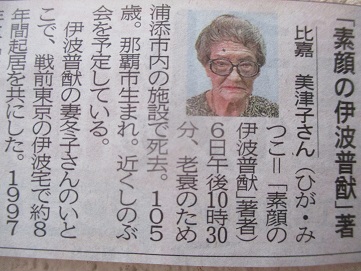
比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん
1932年
1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~
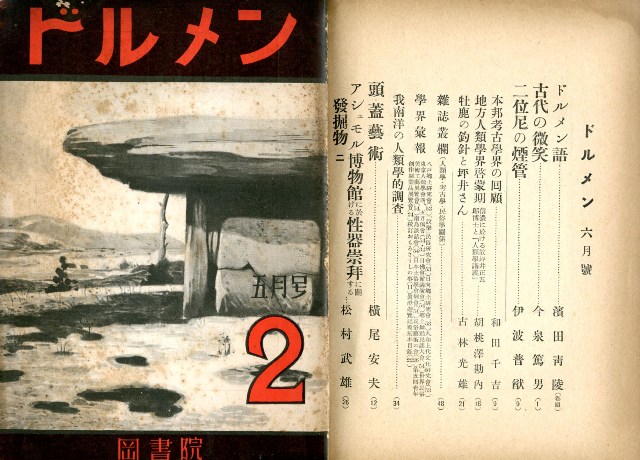
1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」
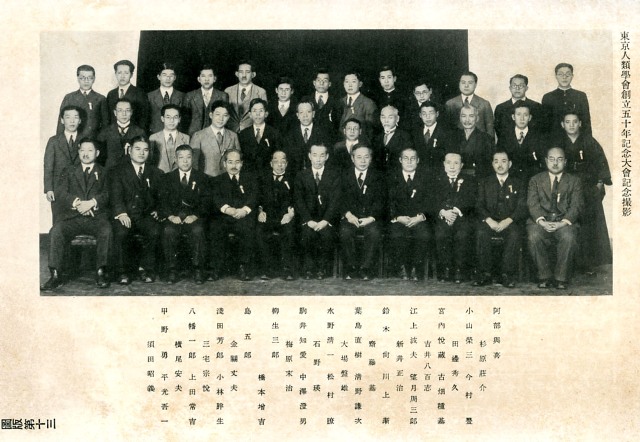
1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会
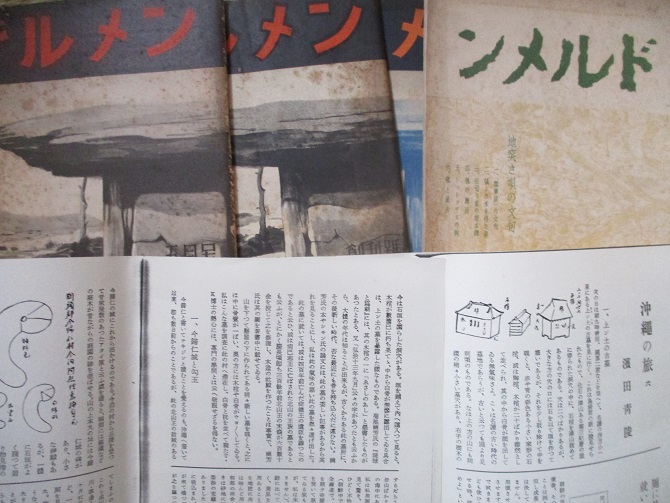
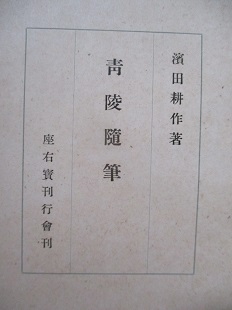
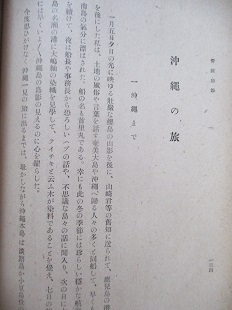
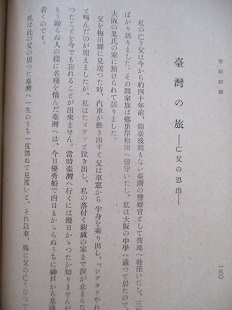
1933年
1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
1934年
7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」
1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号
1937年
1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)
1939年
12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」
1941年
3月ー伊波普猷妻マウシ死去
2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。
1891年
4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)
1900年
9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。
1903年
9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。
1904年
7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。
1905年
8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。
1906年
7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。
1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立
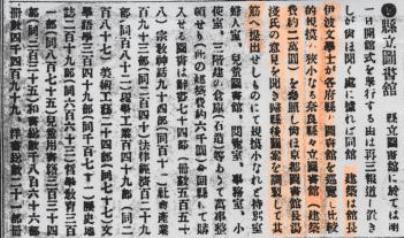
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
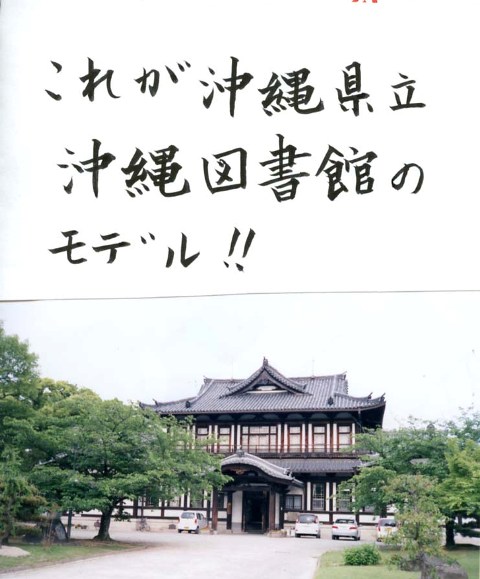
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1911年
4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。
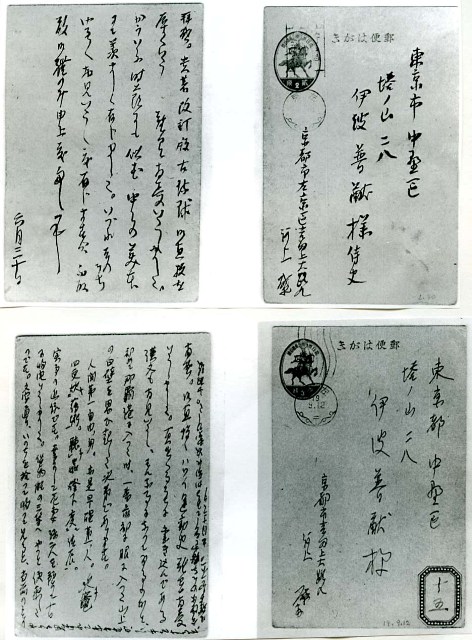
■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)
8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」
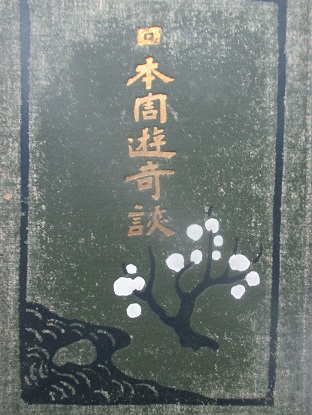
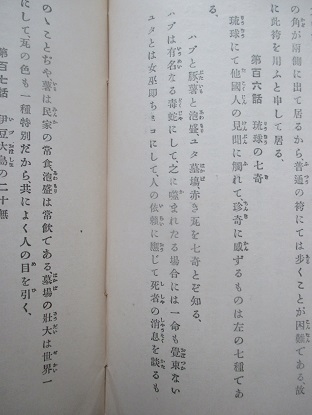
1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館
1912年
4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町
1913年
3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代
1913年
3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。
5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷
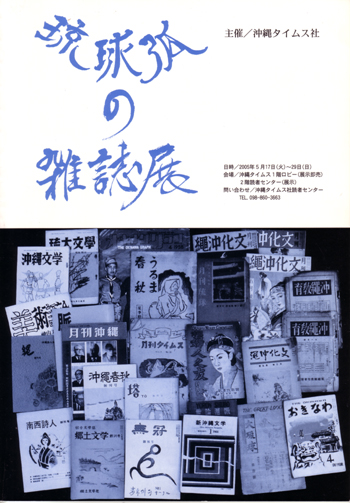
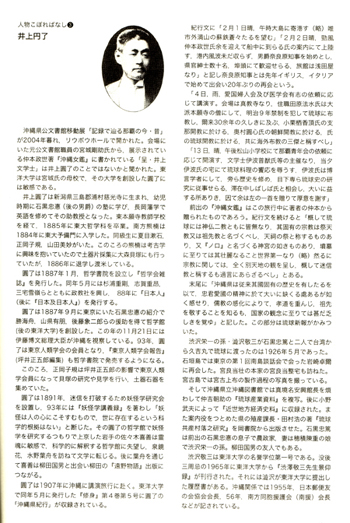
井上円了
『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。
大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。
□井上円了
生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)
没年: 大正8.6.5 (1919)
明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻
(恩田彰) →コトバンク
8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。
9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」
1916年
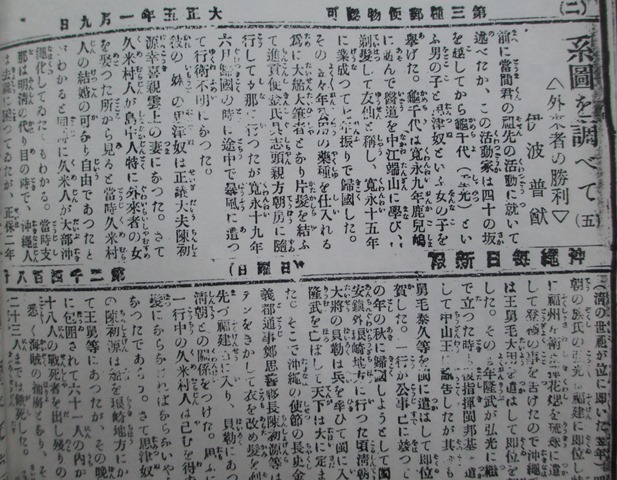
1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)
3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら
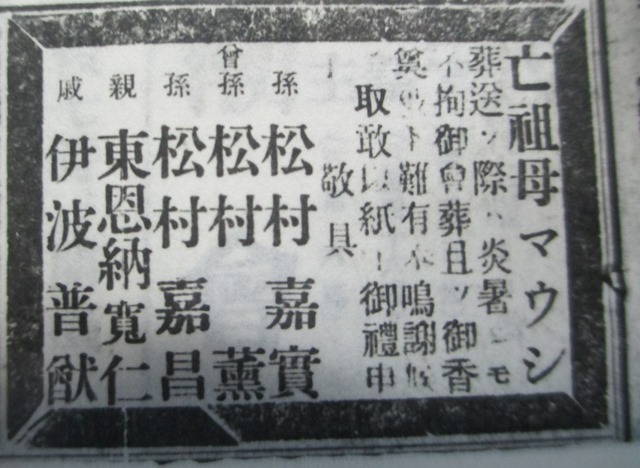
1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」
1918年
3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真
1919年
7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」
1920年
岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」
1921年
5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。
1924年
3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」
3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」
5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」
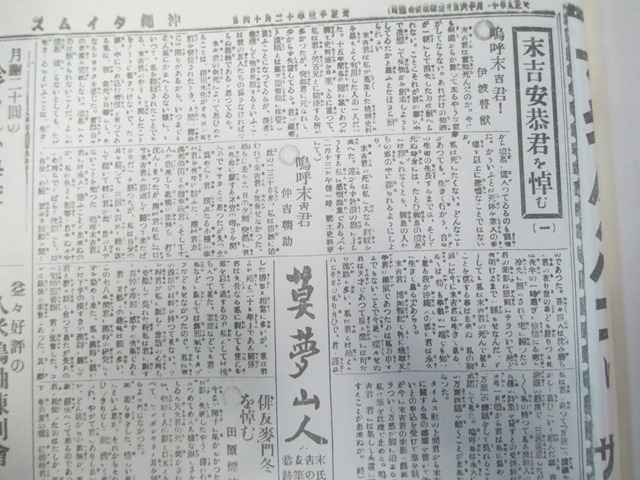
12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」
1925年
2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。
7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」
1926年
1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~
1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)
8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~
9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。
1927年
4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」
1928年
10月ー春洋丸でハワイ着
1929年
2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻
小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候
1931年
6月ー伊波の母(知念)マツル死去
12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居
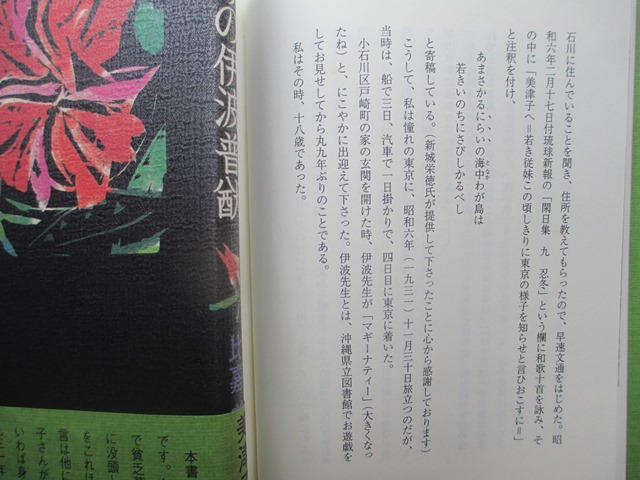
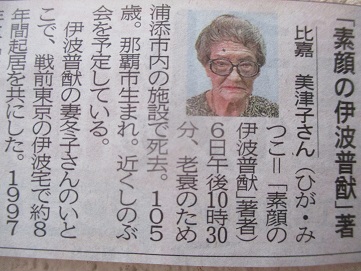
比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん
1932年
1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~
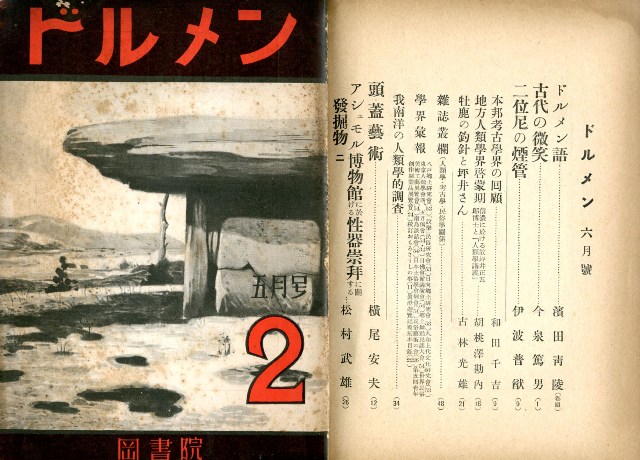
1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」
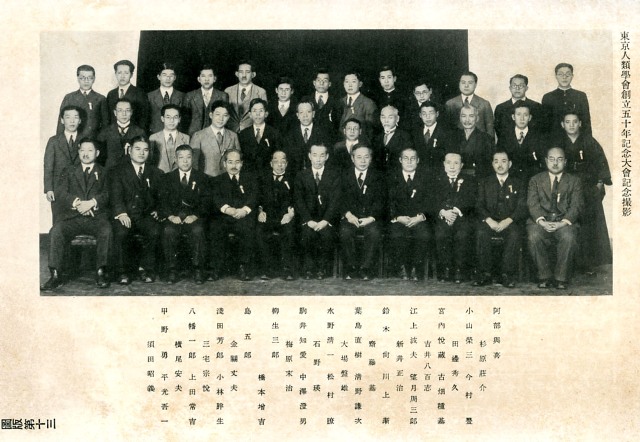
1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会
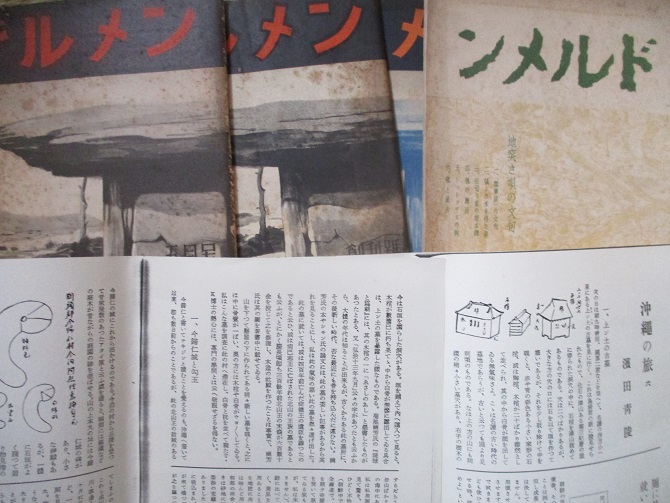
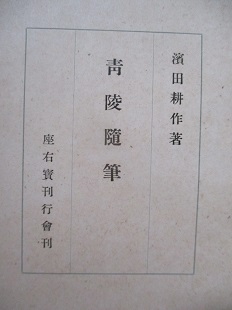
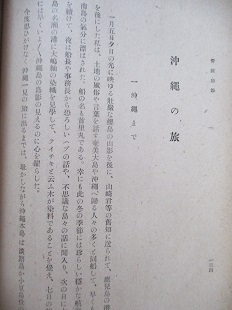
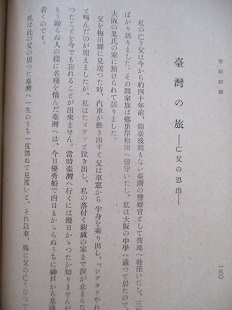
1933年
1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
1934年
7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」
1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号
1937年
1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)
1939年
12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」
1941年
3月ー伊波普猷妻マウシ死去
2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。
04/02: 1940年の東京沖縄県人会②ーその周辺
戦前・戦後、常に東京沖縄県人会の指導者であった神山政良氏が1966年3月に『年表ー沖縄問題と在京県人の動き』を琉球新報社東京総局から発行している。その年表によると東京で沖縄県人会という名称は、1921年1月23日に明正塾にあった沖縄県青年会を改称した沖縄県人会が最初のものである。戦前の東京沖縄県人会①には在京の県人会幹部名を列記したが今回は個人別に紹介する。出典は1940年の東京沖縄県人会名簿。
安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町
伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町
上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂
大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町
大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)
大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町
漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)
金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町
喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町
國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国
東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)
呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」
崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町
尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町
城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町
高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦
田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田
知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川
津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町
照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷
渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町
當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)
仲原善忠(成城高等学校教授)ー世田谷区祖師谷、仲原善徳ー世田谷区祖師谷、仲宗根玄愷(昭和生命保健相互会社常務取締役)ー中野区桜山、仲宗根玄康(東京市厚生局)ー滝野川区滝野川町、仲里文英(世田谷区多聞小学校)、仲村常樽(台東小学校)ー淀橋区東大久保町、仲村専義(建築設計業)ー下谷区入谷町、仲本盛行(東京市財務局主税課)ー京橋区新佃島東町、仲本朝愛ー本郷区田町・喜久村方、仲本吉一郎ー渋谷区神山町、仲本宗厚ー渋谷区幡ヶ谷本町、仲本川原ー大森区久ヶ原、仲本徳英ー本郷区駒込千駄木町、仲田多聞ー荏原区羽田町麹谷、仲田新雄ー渋谷区笹塚町、仲尾次清正(東京憲兵隊本部)ー麹町区竹平町、仲井間宗一(文部参与官)ー麹町区平川町、仲井間宗祐(税務懇話会)ー滝野川区上中里町、仲吉良光(東京日々新聞記者)ー横浜市鶴見区鶴見町、仲村渠直和(市ヶ谷刑務所勤務)、仲野廉松ー世田谷区太子堂町
仲兼久長太郎(東京地方専売局蔵前分工場)ー江戸川区小岩町、仲地唯一(東京市電気局)ー渋谷区代々木初台、仲松弥男(荒川区第五峡田小学校)、長嶺善進(糧秣廠)ー下谷区上根岸、長嶺晃(城東区第一亀戸小学校)、長嶺朝昭(東京地方専売局)、長嶺朝英(川越税務署)ー川越市宮下町、長嶺将繁(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、名護朝徳ー荏原区荏原町、名城政教(日本起重機製作所)ー蒲田区糀谷、名城嗣亨(京橋月島第三小学校)ー京橋区月島東河岸町通、長嶺亀助(陸軍少将、軍需会社顧問)ー神奈川県茅ヶ崎、長濱三郎(大森区馬込第一小学校)ー大森区馬込町東、名嘉山徳温(東京市財務局会計課)ー板橋区上板橋、長濱眞詳(石神井西小学校)ー中野区新井町、永島可昌(下谷区竹町小学校)、名嘉繁雄(南武鉄道株式会社技術課)ー品川区北品川町、永井長雄(東京市総務局)ー中野区桜山町
安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町
伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町
上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂
大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町
大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)
大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町
漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)
金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町
喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町
國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国
東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)
呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」
崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町
尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町
城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町
高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦
田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田
知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川
津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町
照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷
渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町
當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)
仲原善忠(成城高等学校教授)ー世田谷区祖師谷、仲原善徳ー世田谷区祖師谷、仲宗根玄愷(昭和生命保健相互会社常務取締役)ー中野区桜山、仲宗根玄康(東京市厚生局)ー滝野川区滝野川町、仲里文英(世田谷区多聞小学校)、仲村常樽(台東小学校)ー淀橋区東大久保町、仲村専義(建築設計業)ー下谷区入谷町、仲本盛行(東京市財務局主税課)ー京橋区新佃島東町、仲本朝愛ー本郷区田町・喜久村方、仲本吉一郎ー渋谷区神山町、仲本宗厚ー渋谷区幡ヶ谷本町、仲本川原ー大森区久ヶ原、仲本徳英ー本郷区駒込千駄木町、仲田多聞ー荏原区羽田町麹谷、仲田新雄ー渋谷区笹塚町、仲尾次清正(東京憲兵隊本部)ー麹町区竹平町、仲井間宗一(文部参与官)ー麹町区平川町、仲井間宗祐(税務懇話会)ー滝野川区上中里町、仲吉良光(東京日々新聞記者)ー横浜市鶴見区鶴見町、仲村渠直和(市ヶ谷刑務所勤務)、仲野廉松ー世田谷区太子堂町
仲兼久長太郎(東京地方専売局蔵前分工場)ー江戸川区小岩町、仲地唯一(東京市電気局)ー渋谷区代々木初台、仲松弥男(荒川区第五峡田小学校)、長嶺善進(糧秣廠)ー下谷区上根岸、長嶺晃(城東区第一亀戸小学校)、長嶺朝昭(東京地方専売局)、長嶺朝英(川越税務署)ー川越市宮下町、長嶺将繁(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、名護朝徳ー荏原区荏原町、名城政教(日本起重機製作所)ー蒲田区糀谷、名城嗣亨(京橋月島第三小学校)ー京橋区月島東河岸町通、長嶺亀助(陸軍少将、軍需会社顧問)ー神奈川県茅ヶ崎、長濱三郎(大森区馬込第一小学校)ー大森区馬込町東、名嘉山徳温(東京市財務局会計課)ー板橋区上板橋、長濱眞詳(石神井西小学校)ー中野区新井町、永島可昌(下谷区竹町小学校)、名嘉繁雄(南武鉄道株式会社技術課)ー品川区北品川町、永井長雄(東京市総務局)ー中野区桜山町


「鎌倉芳太郎顕彰碑」甥御さんの鎌倉佳光氏案内/「アートギャラリーかまくら 南米珈琲」鎌倉芳太郎生家(島袋和幸提供)
2014年5月 図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』

沖縄県立博物館・美術館ミュージアムショップ「ゆいむい」電話:098-941-0749 メール:yuimui@bunkanomori.jp
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』 販売価格(税込): 1,620 円

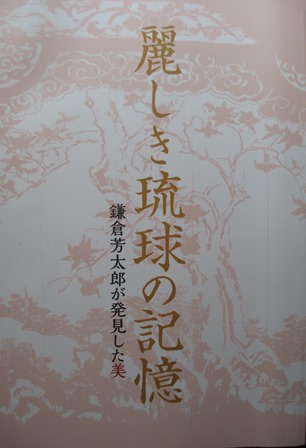
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁く」
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」

高草茂氏と新城栄徳
2015年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所『沖縄芸術の科学』第27号 高草茂「琉球芸術ーその体系的構造抄論」
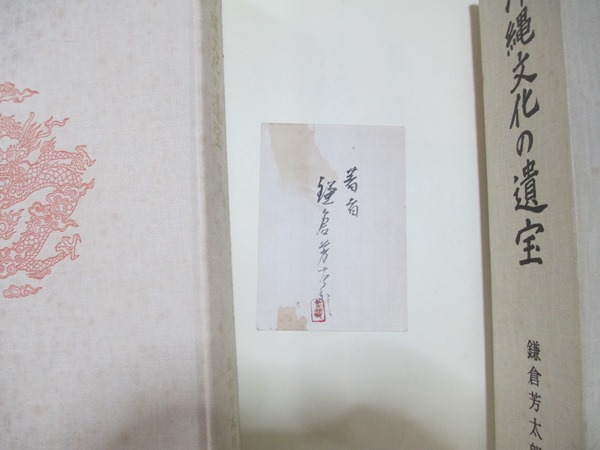
「麗しき琉球の記憶-鎌倉芳太郎が発見した“美”-」関連催事
【日時】5月31日(土)14:00~ 15:30 (開場13:30)
特別講演会/クロストーク
鎌倉芳太郎氏の大著『沖縄文化の遺宝』の編集者である高草茂氏による編集当時のエピソードなどを交えた講演と、「鎌倉ノート」の編集・刊行に携わる波照間永吉氏とのクロストークから、鎌倉氏の沖縄文化に寄せた情熱や思いなどを聞く機会とします。
【講師】高草茂 氏(元岩波書店 顧問)
波照間永吉 氏(沖縄県立芸術大学附属研究所 教授)

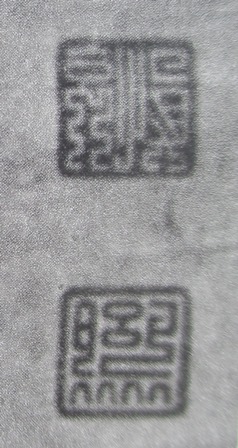
「首里那覇泊全景図」慎思九筆だが印章は慎克熈
沖縄文化工芸研究所□図録の内容を紹介します。
ご遺族や鎌倉自身と交流のあった方、鎌倉資料整理(沖縄県立芸術大学所蔵)に直接に関わった方々が文章を寄せています。記録資料としては将来価値のある図録だと思います。
*波照間永吉「芳太郎収集の沖縄文化関係資料」
*高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」
*佐々木利和「鎌倉芳太郎氏<琉球芸術調査写真>の指定」
*西村貞雄「鎌倉芳太郎がみた琉球の造形文化」
*柳悦州「鎌倉芳太郎が寄贈した紅型資料」
*波照間永吉「古琉球の精神を尋ねてー鎌倉芳太郎の琉球民俗調査ー」
*粟国恭子「鎌倉芳太郎が残した琉球芸術の写真」
*謝花佐和子「鎌倉芳太郎と<沖縄>を取り巻くもの」
*鎌倉秀雄「父の沖縄への思い」
*宮城篤正「回想「50年前の沖縄・写真でみる失われた遺宝」展
*新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁くー」
*三木健「<鎌倉資料>が世に出たころ」
○図版
○年譜
○主要文献等一覧
○写真図版解説
1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」
1893年、京都で平安神宮の地鎮祭が行われ西村捨三が記念祭協賛会を代表し会員への挨拶の中で尚泰侯爵の金毘羅宮参詣時の和歌「海山の広き景色を占め置いて神の心や楽しかるらん」を紹介し、平安神宮建設に尚家から五百圓の寄附があったことも報告された。ちなみに、この時の平安神宮建築技師が伊東忠太。
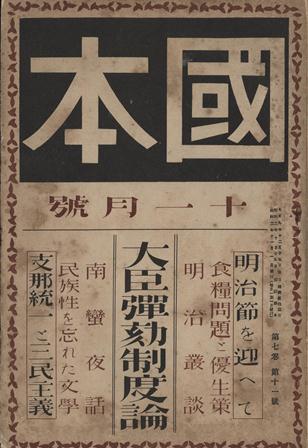
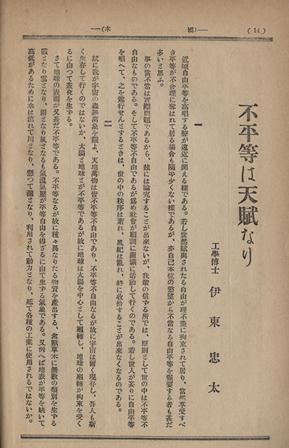
1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」
□翻って考ふれば、宇宙の諸現象は皆不平等、不自由なるが為に生ずるので、一現象毎に一歩づつ平等と自由とに近づくのである。斯くて幾億劫の後には絶対の平等自由が実現されて宇宙は亡びるのである。社会の現象も亦た不平等、不自由の力に由て起こるので、一現象毎に一歩づつ平等自由に近づくのである。斯くて幾万年の後には絶対の平等自由が実現されて社会は滅亡するのである。個人の一生も亦不平等不自由の為に支配せられて活動して居るのである。吾人の一挙一動毎に一歩づつ平等自由に近づくのを以て原則とする。斯くて百年の後絶対の平等自由が得られた時は即ち吾人の死んだ時である。
人は生まれた瞬間より一歩づつ死に向かって進むので、同時に又自由平等に向かって進むのである。絶対の平等自由を強要するのは即ち死を強要する所以である。要するに吾人は各自の職貴を竭して社会文化の向上に貢献すれば善いので社会の安寧秩序を保つべき条件の下に吾人の平等自由が適当に制限さるべきことを認容しなければならぬ。制限なき平等自由は假令之が與えられても吾人は之を受けることを欲せぬものである。何となれば之を與ふる者は悪魔であり、之を受くる者は之が為に身を亡ぼすからである。
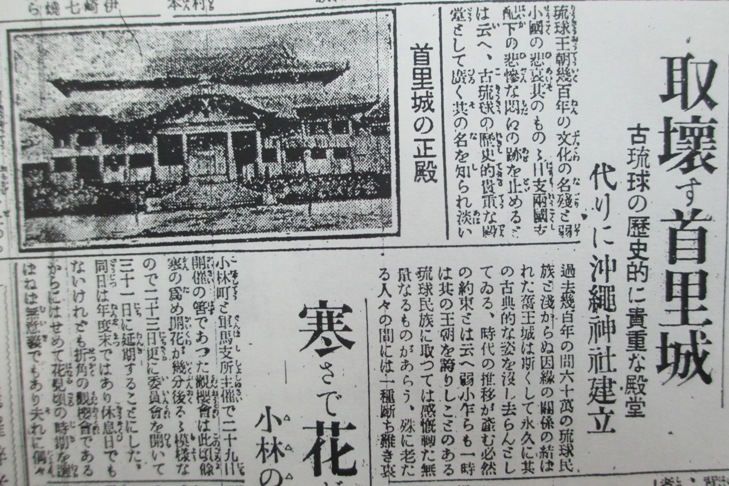
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
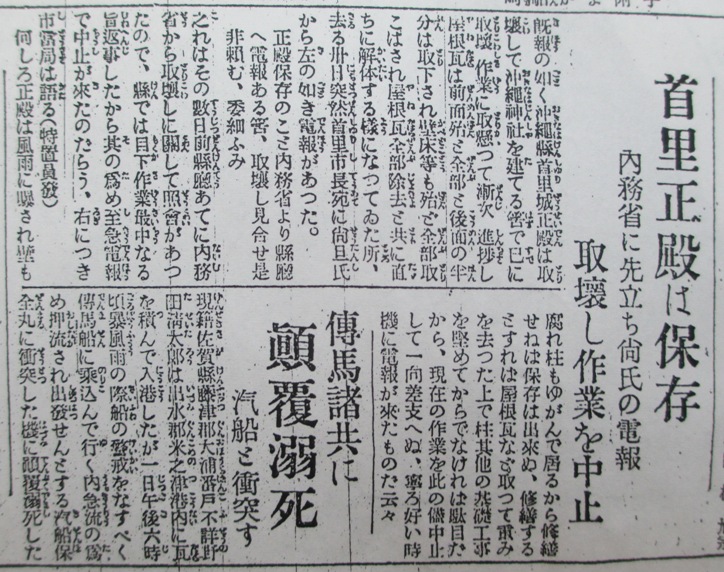
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
1924年
3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。
①『科学知識』「琉球紀行」□余は沖縄到着の第五日目の晩に脚の関節に鈍痛を覚えたので、テッキリやられたと直覚して寝に就いたが、夜半過ぎから疼痛が全身の関節に瀰漫し来り、朝になって見ると起きかえることは愚、寝返りも出来ぬ程の痛さである。(略)兼ねて東京を出発する時、琉球に悪疫の流行して居ることを聞知して居たので、入澤達吉博士に注意事項を問うた処が、博士は若しも沖縄で病気に罹ったら金城医学士の診療を受けるがよいと教えて呉れた。そこで早速同学士の来診を求めた所が、学士は直ちに来て呉れた。一診してこれは軽いデング熱である、2,3日で快癒すると事もなげに断言して呉れたので大いに安心した。(略)金城学士の話によれば、那覇市では殆ど毎戸に患者があって、一家一人も残らず感染した例も珍しくない。那覇6万の人口中、少なくともその三分の二は感染したものと思われるが死者は今の所43人である。夫は何れも嬰児で脳膜炎を併発したのであると云う。余が全治した頃は那覇の方は下火になり、追々田舎の方へ蔓延する模様であった。土地ではこれを「三日熱」と唱えて居る。夫は熱が大抵三日位で去るからである。
8月20日午後3時 大阪商船の安平丸で鹿児島へ。8月22日ー『沖縄タイムス』伊東忠太「琉球を去るに臨みて」。8月25日に東京着□→1925年1月~8月『科学知識』に琉球紀行を連載□1928年5月ー伊東忠太『木片集』萬里閣書房(写真・首里城守礼門)
1925年
1月ー鎌倉芳太郎、沖縄の新聞に啓明会から発行予定の「琉球芸術大観」発表。□(イ)序論ー分布の範囲、遺存の概況、調査物件の項目 (ロ)総論ー史的考察、時代分期
(ハ)各論①建築ー1王宮建築、2廟祠建築、3寺院建築、4住宅建築、5陵墓建築、6橋梁建築 ②琉球本島の部ーイ純止芸術(美術)篇ー1紋様、2絵画、3彫刻 ロ応用芸術(工芸)篇ー1漆工、2陶磁、3織工、4染工、5金工鋳造、6雑工 ③宮古八重山の部 ④奄美大島の部


1925年2月 坂口総一郎『沖縄写真帖』第一輯 画・伊東忠太
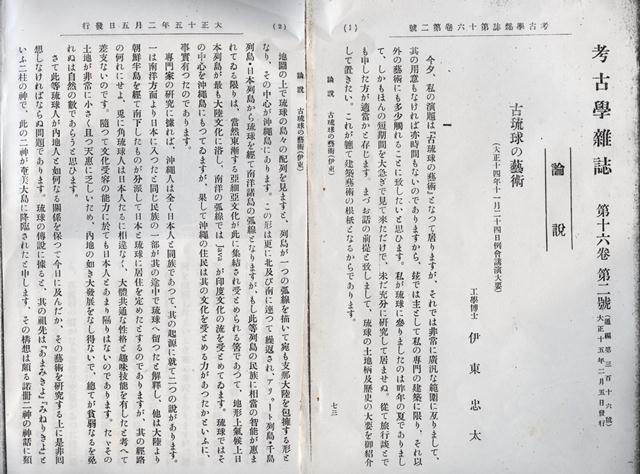
1926年2月『考古学雑誌』第16巻第2号 伊東忠太「古琉球の芸術」
1929(昭和4)年
『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」
□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」
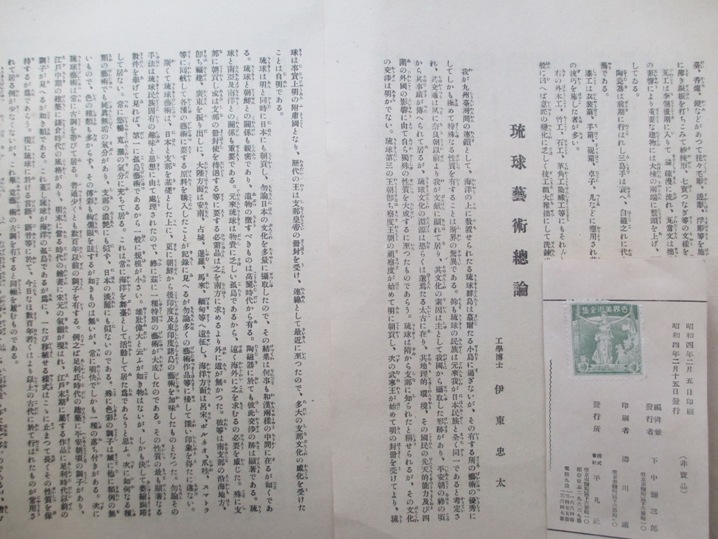
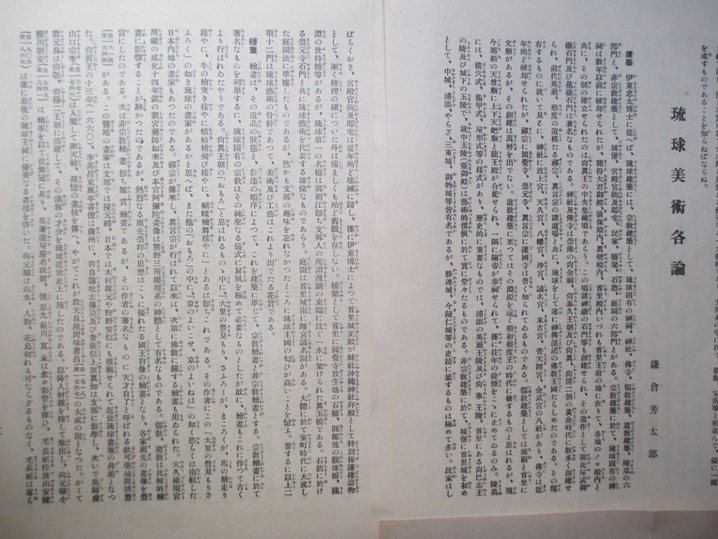
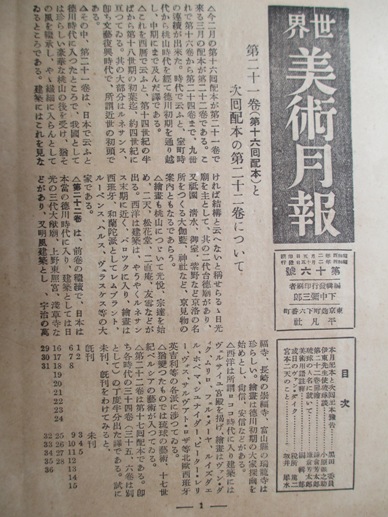
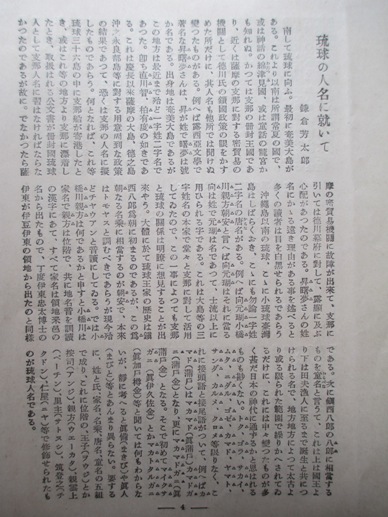
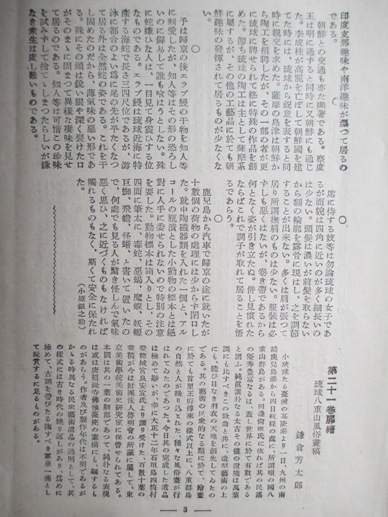
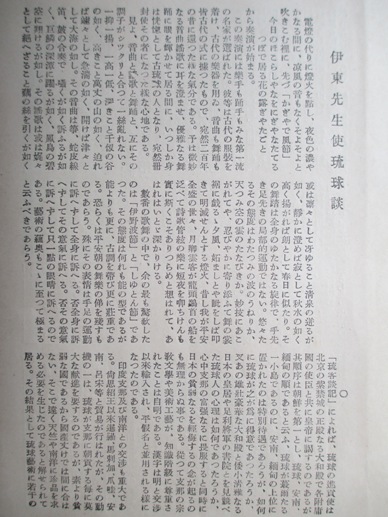
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)
1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社
1929年
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」

3月ー新光社『日本地理風俗体系』第12巻(カラーの守礼門)□伊波普猷「守礼門ー首里府の第一坊門を中山門と言ひ、王城の正門に近い第二坊門を守礼門と言ふ。前者は三山統一時代の創立で、『中山』の扁額を掲げたが、一時代前に毀たれ、後者はそれより一世紀後の創立で、待賢門と称して『首里』の扁額を掲げたが、万暦八年尚永即位の時、明帝の詔勅中より『守礼之邦』の四字を取って『首里』に代えた。以後守礼は首里の代りに用ひられる」
10月ー鎌倉芳太郎・田邊孝次『東洋美術史』玉川学園出版部
04/01: 京都沖縄青年グループ(都沖青)



私たちの京都沖縄青年グループ(都沖青)は京都三条河原町にある松田祐作さん経営「琉球料理・守禮」に連絡所を置き、表札や名簿も作ってもらった。近くの三条大橋で鴨川を渡るとエイサーの元祖、袋中上人が開創した檀王法林寺がある。

1970年12月、私は京都鳴滝にある沖縄学生たち(同志社大・立命館大)の借家のひとつ、山口浤一さんの部屋に居た。沖縄から帰ったばかりの山口さんの婚約者が興奮さめやらぬ口振で語る「コザ騒動」の話を学生たちと聞いていた。沖縄学生たちの機関誌は、1964年、京都在学沖縄県学生榕樹の会『がじゅまる』、65年、同志社大学大学沖縄県人会『珊瑚礁』、67年、関西沖縄県学生会『新沖縄』などがあった。
1973年 福木, 詮『沖縄のあしおと―1968-72年』 (岩波書店)儀間比呂志「表紙版画」


1974年4月、司馬遼太郎が沖縄関係資料室に来室、西平守晴と対談 司馬遼太郎『街道をゆく6』朝日新聞社
○大阪の都島本通で、篤志でもって「沖縄関係資料室」をひらいていおられる西平守晴氏にもきいてたしかめることができた。西平氏は、「そうです、そんな話があります」といって、南波照間の「南」を、パイと発音した。ついでながら本土語の南風(はえ)は沖縄でも「南」の意味につかう。本土語の古い発音では、こんにちのH音が古くはF音になり、さらに古くはP音になる。つまり花はパナである。八重山諸島の言葉はP音の古発音を残していて、南(ハエ)が南(パイ)になるらしい。西平氏はこのまぼろしの島を、「パイ・ハテルマ」と、いかにもその島にふさわしい発音で言った。


〇石垣島の石垣という以上、島主だった家なのかと思って、その家の中年婦人(末吉麦門冬の娘・石垣初枝)にきくと、「もとは大浜という姓だったそうです。何代か前に石垣と変えたときいています」ということだった。家の人の説明によると、「このお庭は、文政2(1819)年の作だということです。庭師は首里からきました。方式ですか、日本の枯山水です」ということだった。枯山水というのは池もなく遺水もなしに石組だけで山水を表現する作庭形式だが、滋賀県の園城寺金堂の庭園などを見ると、平安期からこの思想はあったらしい。しかし完成したのはよく知られるように室町期からで、この様式が江戸期に八重山諸島にまで及んでいたということは、不覚にも知らなかった。/ごく最近、古美術好きの私の友人(鄭 詔文)が、沖縄へ行った。かれは在日朝鮮人で、齢は五十すぎの、どういうときでも分別のぶあつさを感じさせる人物である。



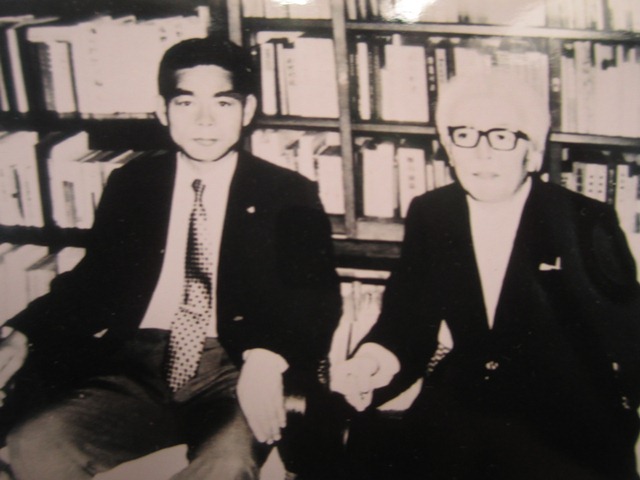
写真左/1999年5月11日沖縄ハーバービューホテルで神坂次郎氏(作家・熊野の生き字引で司馬遼太郎の文学仲間)、新城栄徳。末吉麦門冬の取材を終えての祝盃。撮影・末吉安允
写真右/1974年4月、司馬遼太郎が沖縄関係資料室に来室、西平守晴と対談。



京都市美術館「第49回 京展」新城さやか「キジムナー」
06/08: 新城栄徳「落ち穂/資料室運動」
石川正通「布袋腹に酒杯乗せて踊りたる麦門冬の珍芸懐ふ」

1983年9月14日『琉球新報』新城栄徳「落ち穂/資料室運動」

写真は左から西平守晴、真喜志康忠夫妻、河井寛次郎夫妻





府の〇印は大阪府立中之島図書館



山城明(うるま市)


1月4日、今日は「石の日」という。沖縄県立図書館の階下に仲島の大石がある。(石川正通は1945年の東京空襲で自宅と5万冊の蔵書全焼している)そのそばに那覇市名誉市民・石川正通歌碑[橋内の 誇りも髙き 泉崎 昔も今も 人美しく](写真左)がある。
石川正通が1979年の新聞元旦号に書いた随筆、今でも通用する。
〇徳富蘇峰は、終戦の詔勅を拝して、「八十三年非なり」と、自分の史観の誤りを、五言律の漢詩に托して懺悔した。伊江朝助男爵が、ヤガテユヤ暮リテ、行クン先ヤ見ラン六十六タンメ、ドゥゲイクルビ と、琉歌に盛った心境と同工異曲の挽歌である。歴史書きの歴史知らずは論語読みの論語知らずより哀れなりけり。人類の発生から絶滅まで、過渡期でない瞬間は無い。時々刻々、革新へ革新へと、動いてやまないのである。世界の列強が軍備拡張に明け暮れている今の今々、第三次世界戦争の勃発を想定して見るのも狂人の狂態ではあるまい。→『琉球新報』石川正通「憂時立砲と沖縄」
〇写真右→京都(大石橋の東にある陶化小学校の校庭)・大阪(住吉大社)にある石敢當。右端のこの写真は旅館の前にあった石敢當、現在は御津八幡宮にある。心斎橋駅の南西、御堂筋と西横堀に挟まれた西心斎橋のうち、御津公園(通称、三角公園→グーグル画像「アメリカ村三角公園」)を中心にアメリカ村と言われる。近くの御津八幡宮(祭神・応神天皇、仲哀天皇、神功皇后)の左側狛犬の傍にソテツ、梅石筆「石敢當」(→画像グーグル・ヤフー)入り口付近に建っている。

大阪府立中之島図書館ー住友家により建築、寄贈され、1904年に「大阪図書館」として開館した。設計は野口孫市、日高胖。同年2月25日、開館式を挙行。大阪図書館は、開館直後の1906年に「大阪府立図書館」と改称。以来、長らく唯一の府立図書館であったが、1945年に大原社会問題研究所から蔵書の寄贈を受けたことで、1950年、同研究所跡地に天王寺分館を建設し蔵書の管理・収集に充てた。1974年に大阪府立図書館は「大阪府立中之島図書館」に、天王寺分館は「大阪府立夕陽丘図書館」に名称を変更している。中之島図書館が国の重要文化財に指定されたのはこの年である。 1996年、東大阪市に大阪府立中央図書館が開館。これに伴い、中之島図書館の一般蔵書の大半と夕陽丘図書館の蔵書約60万冊(特許資料関係を除く)を中央図書館に移設。両図書館で収集してきた内外特許資料・科学技術資料は、閉館した夕陽丘図書館の建物を流用して新設された大阪府立特許情報センターに移された。 2004年から、中之島図書館はビジネスマンに様々な情報を提供する「ビジネス支援サービス」を開始。→ウィキ
『大阪府立中之島図書館だより なにわづ』(1958年10月 №1~)
1979年11月 №75 竹中郁「青銅屋根ー(略)この美しい青いドーム。市民社会のシンボルのような円屋根が、片や日本経済の中の有力な銀行の屋根と向かいあって在ることにわれわれは或る誇りを感じつつ見守っていきたい。一国の経済もおろそかにはできないものだが、それと向かいあってある図書館が表徴する文化の広さや深さが、もっともっと大切だということを誇りとするのだ。そのいつも新鮮な色彩でこころにしみ入る或る暗示を、われわれ民衆は片時も忘れてはならないのだ。」

1981年1月 №80 小笠原「カード箱ーわが国の図書館においては、従来図書(本)が中心で、逐次刊行物(雑誌・新聞・研究紀要・年報等)が副次的に取り扱われ、その受入管理や利用者サービスも余り重要視されていませんでした。しかし、図書館が情報センター的機能を負わされてくると、情報の主たる源である逐次刊行物は、図書とその立場が入れ替わり、だんだん主役の座にのし上がってきたように感じられます。」
1993年3月 №119 大谷晃一 「中之島と私ー(前略)中之島にいて空襲警報が鳴った。地下鉄の淀屋橋駅に駆け込む。やがて、ぐあーんと地を響かす爆発音が不気味につづく。そんな空襲の中で、図書館をはじめ中之島の建物は多く生き残った。奇跡に近い。(略)三高生の武田麟太郎は、ここで田山花袋の『西鶴小論』を筆写した。プロレタリア作家として行き詰まったとき、西鶴を思い出し市井事物で立ち直る。三好達治はここへ通ってファーブルの『昆虫記』を翻訳し、帰りに梶井基次郎を見舞う。織田作之助は夜にここの前の公園のペンチで女といて、風俗紊乱の現行犯で派出所に連行された。私が中之島図書館を守りたいのは、建物が美的で文化財のゆえだけではない。」
2004年10月 №138 石崎重雄「古典籍の活用とビジネス支援について(略)全てにわたって、供給過剰な日本の経済で一番の需要不足が労働力であり、それも若手である。フリーターと称してマスコミの話に乗っている場合ではない。バラエティー番組の後ろの観客席に座っている場合でもない。産業社会の中で、せめて自分の分の付加価値を働いて生み出す仕事を自分で見つける仕掛けを用意しなければと思う。」
→「なにわづ 大阪府立中之島図書館だより」

1983年9月14日『琉球新報』新城栄徳「落ち穂/資料室運動」

写真は左から西平守晴、真喜志康忠夫妻、河井寛次郎夫妻





府の〇印は大阪府立中之島図書館



山城明(うるま市)


1月4日、今日は「石の日」という。沖縄県立図書館の階下に仲島の大石がある。(石川正通は1945年の東京空襲で自宅と5万冊の蔵書全焼している)そのそばに那覇市名誉市民・石川正通歌碑[橋内の 誇りも髙き 泉崎 昔も今も 人美しく](写真左)がある。
石川正通が1979年の新聞元旦号に書いた随筆、今でも通用する。
〇徳富蘇峰は、終戦の詔勅を拝して、「八十三年非なり」と、自分の史観の誤りを、五言律の漢詩に托して懺悔した。伊江朝助男爵が、ヤガテユヤ暮リテ、行クン先ヤ見ラン六十六タンメ、ドゥゲイクルビ と、琉歌に盛った心境と同工異曲の挽歌である。歴史書きの歴史知らずは論語読みの論語知らずより哀れなりけり。人類の発生から絶滅まで、過渡期でない瞬間は無い。時々刻々、革新へ革新へと、動いてやまないのである。世界の列強が軍備拡張に明け暮れている今の今々、第三次世界戦争の勃発を想定して見るのも狂人の狂態ではあるまい。→『琉球新報』石川正通「憂時立砲と沖縄」
〇写真右→京都(大石橋の東にある陶化小学校の校庭)・大阪(住吉大社)にある石敢當。右端のこの写真は旅館の前にあった石敢當、現在は御津八幡宮にある。心斎橋駅の南西、御堂筋と西横堀に挟まれた西心斎橋のうち、御津公園(通称、三角公園→グーグル画像「アメリカ村三角公園」)を中心にアメリカ村と言われる。近くの御津八幡宮(祭神・応神天皇、仲哀天皇、神功皇后)の左側狛犬の傍にソテツ、梅石筆「石敢當」(→画像グーグル・ヤフー)入り口付近に建っている。

大阪府立中之島図書館ー住友家により建築、寄贈され、1904年に「大阪図書館」として開館した。設計は野口孫市、日高胖。同年2月25日、開館式を挙行。大阪図書館は、開館直後の1906年に「大阪府立図書館」と改称。以来、長らく唯一の府立図書館であったが、1945年に大原社会問題研究所から蔵書の寄贈を受けたことで、1950年、同研究所跡地に天王寺分館を建設し蔵書の管理・収集に充てた。1974年に大阪府立図書館は「大阪府立中之島図書館」に、天王寺分館は「大阪府立夕陽丘図書館」に名称を変更している。中之島図書館が国の重要文化財に指定されたのはこの年である。 1996年、東大阪市に大阪府立中央図書館が開館。これに伴い、中之島図書館の一般蔵書の大半と夕陽丘図書館の蔵書約60万冊(特許資料関係を除く)を中央図書館に移設。両図書館で収集してきた内外特許資料・科学技術資料は、閉館した夕陽丘図書館の建物を流用して新設された大阪府立特許情報センターに移された。 2004年から、中之島図書館はビジネスマンに様々な情報を提供する「ビジネス支援サービス」を開始。→ウィキ
『大阪府立中之島図書館だより なにわづ』(1958年10月 №1~)
1979年11月 №75 竹中郁「青銅屋根ー(略)この美しい青いドーム。市民社会のシンボルのような円屋根が、片や日本経済の中の有力な銀行の屋根と向かいあって在ることにわれわれは或る誇りを感じつつ見守っていきたい。一国の経済もおろそかにはできないものだが、それと向かいあってある図書館が表徴する文化の広さや深さが、もっともっと大切だということを誇りとするのだ。そのいつも新鮮な色彩でこころにしみ入る或る暗示を、われわれ民衆は片時も忘れてはならないのだ。」

1981年1月 №80 小笠原「カード箱ーわが国の図書館においては、従来図書(本)が中心で、逐次刊行物(雑誌・新聞・研究紀要・年報等)が副次的に取り扱われ、その受入管理や利用者サービスも余り重要視されていませんでした。しかし、図書館が情報センター的機能を負わされてくると、情報の主たる源である逐次刊行物は、図書とその立場が入れ替わり、だんだん主役の座にのし上がってきたように感じられます。」
1993年3月 №119 大谷晃一 「中之島と私ー(前略)中之島にいて空襲警報が鳴った。地下鉄の淀屋橋駅に駆け込む。やがて、ぐあーんと地を響かす爆発音が不気味につづく。そんな空襲の中で、図書館をはじめ中之島の建物は多く生き残った。奇跡に近い。(略)三高生の武田麟太郎は、ここで田山花袋の『西鶴小論』を筆写した。プロレタリア作家として行き詰まったとき、西鶴を思い出し市井事物で立ち直る。三好達治はここへ通ってファーブルの『昆虫記』を翻訳し、帰りに梶井基次郎を見舞う。織田作之助は夜にここの前の公園のペンチで女といて、風俗紊乱の現行犯で派出所に連行された。私が中之島図書館を守りたいのは、建物が美的で文化財のゆえだけではない。」
2004年10月 №138 石崎重雄「古典籍の活用とビジネス支援について(略)全てにわたって、供給過剰な日本の経済で一番の需要不足が労働力であり、それも若手である。フリーターと称してマスコミの話に乗っている場合ではない。バラエティー番組の後ろの観客席に座っている場合でもない。産業社会の中で、せめて自分の分の付加価値を働いて生み出す仕事を自分で見つける仕掛けを用意しなければと思う。」
→「なにわづ 大阪府立中之島図書館だより」
07/28: 2001年3月 榊莫山『莫山夢幻』世界文化社
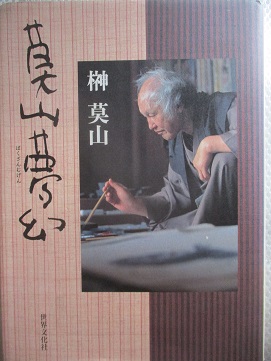
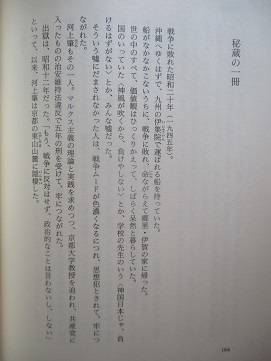
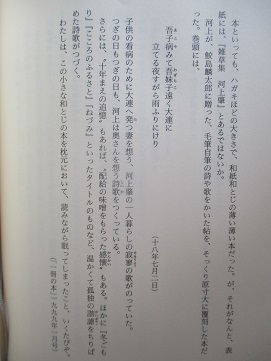
2001年3月 榊莫山『莫山夢幻』世界文化社〇秘蔵の一冊/戦争に敗れた昭和20年(1945年)。沖縄へ行くはずで、九州の伊集院で運ばれる船を待っていた。船がなかなかこないうちに、戦争に敗れ、命ながらえて郷里・伊賀の家に帰った。世の中のすべて、価値観はひっくりかえって、しばらく呆然と暮らしていた。(略)その夏、京都の友人から一冊の本がとどいた。本といっても、ハガキほどの大きさで、和紙和とじの薄い本だった。が、それがなんと、表紙には、『雑草集 河上肇』とあるではないか。/〇芭蕉に想う、芭蕉わーるど、芭蕉の句碑
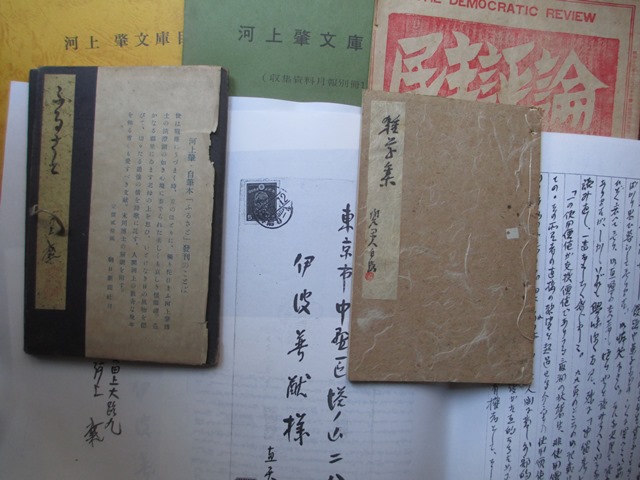
河上肇・資料ー右に1946年6月 河上肇『詩集・雑草集』大雅堂
河上肇ー経済学者・社会思想家。山口県生。東大卒。ヨーロッパに留学中法学博士号を受け、帰国後京大教授となる。またマルクス主義の研究と紹介に努め、青年層に多大の影響を及ぼした。のち大山郁夫らと実践運動に入り新労農党を結成したが、理論的誤りを認め大山らと別れた。獄中生活の後、自叙伝等の執筆に専念した。昭和21年(1946)歿、68才。
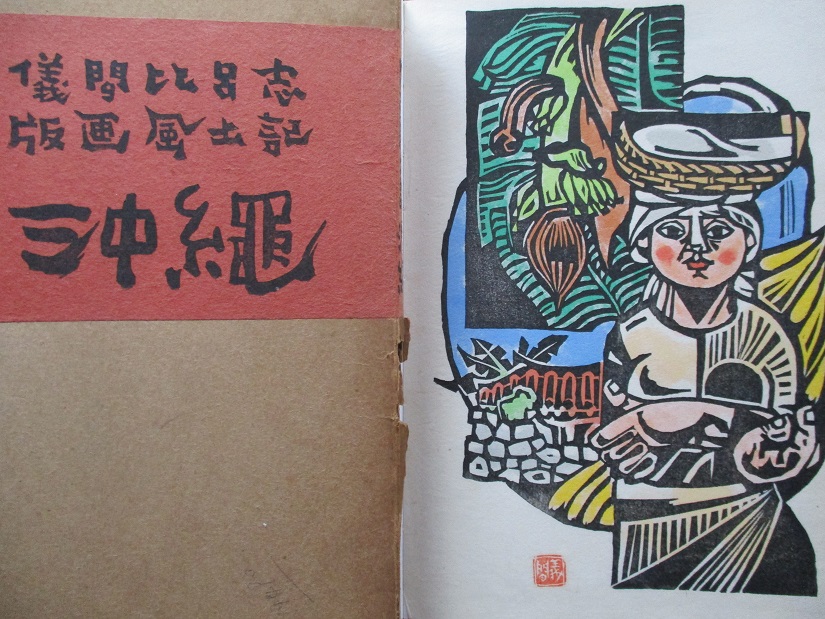
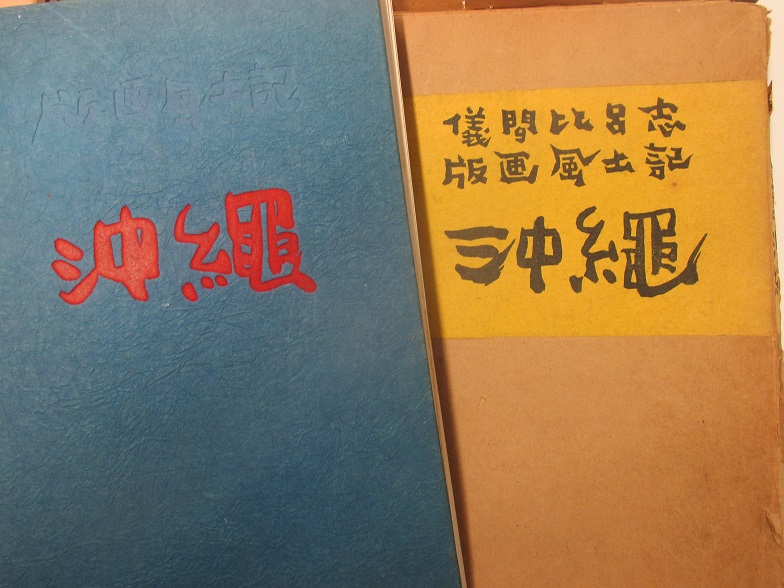
1966年1月 儀間比呂志『版画風土記 沖縄』題字/榊莫山 編集/高橋亨
南洋群島ー日本の委任統治
第一次世界大戦での敗退によってドイツは海外植民地をすべて失い、連合国であった日本は1922年、ヴェルサイユ条約によって赤道以北の旧ドイツ領ニューギニアの地域を委任統治することとなった(赤道以南の旧ドイツ領ニューギニアの地域はオーストラリアおよびニュージーランドが委任統治)。日本は南洋諸島獲得後、開拓のため南洋庁を置き、国策会社の南洋興発株式会社を設立して島々の開拓、産業の扶植を行った。南洋諸島では時差があり、東部標準時(ヤルート・ポナペ地区)が日本標準時+2時間、中部標準時(トラック・サイパン地区)で日本標準時+1時間、西部標準時(ヤップ・パラオ地区)は日本標準時と同じであった。また、国際連盟脱退後はパラオやマリアナ諸島、トラック諸島は海軍の停泊地として整備し、それらの島には軍人軍属、軍人軍属相手の商売を行う人々が移住した。また、新天地を求めて多くの日本人が移住し、その数は10万人に上った。日本人の子供たちのために学校が開かれ、現地人の子供にも日本語による初等教育を行った。1941年(昭和16年)にはパラオ放送局が開局し、ラジオ放送が開始された。→Wikipedia
比律賓群島

左から諸隈彌策①(太田興業社長)、木原副領事、内山総領事/鈴木不二男、中村直三郎(大同貿易マニラ支店支配人)、太宰正伍(横浜正金銀行マニラ支店支配人)/澤松守順、森繁吉、宮崎新吉/望月音五郎、森貞蔵、山本鶴次郎
大阪毎日新聞 1935.11.9(昭和10)
本社機マニラ訪問に欣喜雀躍の二万の在留邦人 マニラ本社無線電話 八日
肩身が一層広い思い 比島日本人聯合会長 ①諸隈弥策氏談
本社の日比親善飛行の壮図を前にして本社は八日午後四時四十五分(マニラ時間午後三時四十五分)比島日本人聯合会長諸隈弥策氏と国際電話で談話を交換したが諸隈氏は非常に感激に満ちた口調でつぎのごとく語った
比島コンモンウェルス政府樹立の記念すべき日を卜し大阪毎日東京日日両社が日比両国の親善を目的に空からの祝賀使節を御派遣下さるとの報に接し在留邦人一同はまさに欣喜雀躍し人気は沸くがごときものがあります、二万余の在留邦人を代表しまず貴社の御壮挙に対し衷心から御喜びと御礼を申上げます、今回のこの計画は両国の関係を一層親密にする意味から申しても非常な効果をもたらすでありましょうが、在留邦人としても一層肩身が広く感ぜられるわけであります、フィリッピン政府および日本官憲側としてすでに非常な意気込みのもとにそれぞれ歓迎凖備に着手しているようでありますが在留邦人の民間側として大々的な歓迎凖備に着手しております、飛行機到着の際には多数の在留邦人が挙ってお出迎えするはもちろん邦人小学生、児童も喜んでお迎えする凖備をしております、もう数日のうちに福本親善使節、大蔵飛行士、布施機関士の一行を歓迎申上げることを衷心から喜ぶとともに重ねてフィリッピンの在留邦人一同が非常な感激をもって飛行機到着の日をお待ちしていることを貴社の皆様からお伝えして戴きたいと思います 。→神戸大学図書館
河村雅次郎 三豊中学 、大正3年ー神戸高等商業学校卒 三井物産(豪洲メルボルン支店)、 三井物産(マニラ支店)

左から渡邊薫、大谷純一、筒井新/金ケ江清太郎、村瀬茂、北島庄平/山本亀彦、稲田繁造、上脇辰也/森誠之、永富麻夫、早川豊平

左から田中藤作、松本勝司、古川義三/原瀬宗介、村上忠二、田熊虎太郎/吉田圓茂、大森文樹、高山辰次郎/只隈與三郎、川上武雄、服部龍造

左から愛甲武男、崎谷襄一、村上寅吉/伊藤卯太郎、村田榮一、森長英/龍頭鉄次、仁木眞一、藤井熊太郎/内海安次郎、花田善太郎、高橋利一

左から星篤比古、蒲原廣一、岡崎平治/宮下鶴、西村五郎、拍原達象/宮坂清一、三原文雄、右高剣一/松尾菅平、小林千尋、大本徳太郎
第一次世界大戦での敗退によってドイツは海外植民地をすべて失い、連合国であった日本は1922年、ヴェルサイユ条約によって赤道以北の旧ドイツ領ニューギニアの地域を委任統治することとなった(赤道以南の旧ドイツ領ニューギニアの地域はオーストラリアおよびニュージーランドが委任統治)。日本は南洋諸島獲得後、開拓のため南洋庁を置き、国策会社の南洋興発株式会社を設立して島々の開拓、産業の扶植を行った。南洋諸島では時差があり、東部標準時(ヤルート・ポナペ地区)が日本標準時+2時間、中部標準時(トラック・サイパン地区)で日本標準時+1時間、西部標準時(ヤップ・パラオ地区)は日本標準時と同じであった。また、国際連盟脱退後はパラオやマリアナ諸島、トラック諸島は海軍の停泊地として整備し、それらの島には軍人軍属、軍人軍属相手の商売を行う人々が移住した。また、新天地を求めて多くの日本人が移住し、その数は10万人に上った。日本人の子供たちのために学校が開かれ、現地人の子供にも日本語による初等教育を行った。1941年(昭和16年)にはパラオ放送局が開局し、ラジオ放送が開始された。→Wikipedia
比律賓群島

左から諸隈彌策①(太田興業社長)、木原副領事、内山総領事/鈴木不二男、中村直三郎(大同貿易マニラ支店支配人)、太宰正伍(横浜正金銀行マニラ支店支配人)/澤松守順、森繁吉、宮崎新吉/望月音五郎、森貞蔵、山本鶴次郎
大阪毎日新聞 1935.11.9(昭和10)
本社機マニラ訪問に欣喜雀躍の二万の在留邦人 マニラ本社無線電話 八日
肩身が一層広い思い 比島日本人聯合会長 ①諸隈弥策氏談
本社の日比親善飛行の壮図を前にして本社は八日午後四時四十五分(マニラ時間午後三時四十五分)比島日本人聯合会長諸隈弥策氏と国際電話で談話を交換したが諸隈氏は非常に感激に満ちた口調でつぎのごとく語った
比島コンモンウェルス政府樹立の記念すべき日を卜し大阪毎日東京日日両社が日比両国の親善を目的に空からの祝賀使節を御派遣下さるとの報に接し在留邦人一同はまさに欣喜雀躍し人気は沸くがごときものがあります、二万余の在留邦人を代表しまず貴社の御壮挙に対し衷心から御喜びと御礼を申上げます、今回のこの計画は両国の関係を一層親密にする意味から申しても非常な効果をもたらすでありましょうが、在留邦人としても一層肩身が広く感ぜられるわけであります、フィリッピン政府および日本官憲側としてすでに非常な意気込みのもとにそれぞれ歓迎凖備に着手しているようでありますが在留邦人の民間側として大々的な歓迎凖備に着手しております、飛行機到着の際には多数の在留邦人が挙ってお出迎えするはもちろん邦人小学生、児童も喜んでお迎えする凖備をしております、もう数日のうちに福本親善使節、大蔵飛行士、布施機関士の一行を歓迎申上げることを衷心から喜ぶとともに重ねてフィリッピンの在留邦人一同が非常な感激をもって飛行機到着の日をお待ちしていることを貴社の皆様からお伝えして戴きたいと思います 。→神戸大学図書館
河村雅次郎 三豊中学 、大正3年ー神戸高等商業学校卒 三井物産(豪洲メルボルン支店)、 三井物産(マニラ支店)

左から渡邊薫、大谷純一、筒井新/金ケ江清太郎、村瀬茂、北島庄平/山本亀彦、稲田繁造、上脇辰也/森誠之、永富麻夫、早川豊平

左から田中藤作、松本勝司、古川義三/原瀬宗介、村上忠二、田熊虎太郎/吉田圓茂、大森文樹、高山辰次郎/只隈與三郎、川上武雄、服部龍造

左から愛甲武男、崎谷襄一、村上寅吉/伊藤卯太郎、村田榮一、森長英/龍頭鉄次、仁木眞一、藤井熊太郎/内海安次郎、花田善太郎、高橋利一

左から星篤比古、蒲原廣一、岡崎平治/宮下鶴、西村五郎、拍原達象/宮坂清一、三原文雄、右高剣一/松尾菅平、小林千尋、大本徳太郎
08/10: 明治・大正/沖縄からの修学旅行『京都』
1894年2月、那覇の南陽館で第8回九州沖縄八県連合共進会が開催された。5月、沖縄尋常中学校生徒(伊波普猷、真境名安興、渡久地政瑚ら)が下国良之助教頭の引率で関西に修学旅行。下国は20歳のとき滋賀の学校に勤めていて中井弘①の薫陶も受けているので関西には知人が多く、どこでも歓迎された。京都滞在中に学生数人は六孫王神社②を訪ねて、天保三年の江戸上りの時に正使が奉納した額を書き写している。
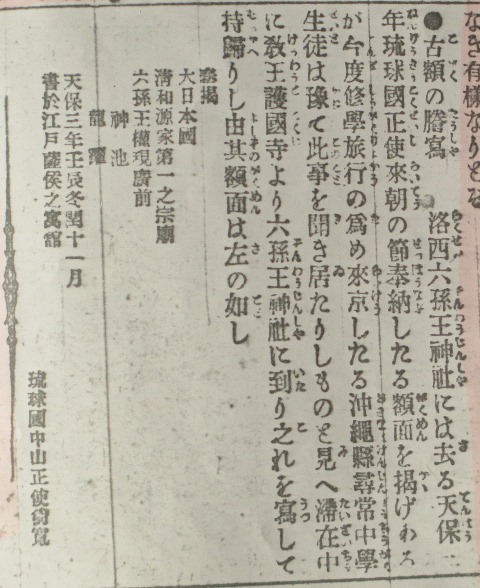
1894年5月20日『日出新聞』
〇1832年(天保3)6月8日、那覇港を立ち江戸に赴く。7月21日、琉球国尚育王即位の謝恩のための使節(正使尚氏豊見城王子朝春副使毛氏澤岻親方安度)らの一行、鹿児島着。8月27日、正使豊見城王子死去。讃議官の向氏普天間親雲上朝朝典を正使として9月1日鹿児島を立つ。11月16日、江戸着、江戸城に登城し朝覲の礼を行う。12月13日、江戸を立ち帰路に就く。1833年(天保4)4月8日、江戸上り使節一行那覇に帰還。
豊見城王子(普天間親雲上朝朝典)の歌→『通航一覧続輯』
※わた津海の底より出て日のもとのひかりにあたる龍の宮人
□①5代京都府知事 中井弘(なかいひろし)
就任期間:明治26年(1893)11月~明治27年10月
天保9年(1838)、鹿児島生まれ。幕末と明治のはじめに二度にわたり欧州に留学、西郷隆盛に従軍したこともあった。工部大学校書記官、滋賀県知事、貴族院議員を経て京都府知事となる。滋賀県時代は時の北垣京都府知事とともに琵琶湖疎水建設にあたった。京都府知事在任中は「京都三大問題」(遷都千百年記念祭、第四回内国勧業博覧会、京都舞鶴間鉄道の建設)に力を尽くしたが、在任中脳出血で倒れ、これらの完成を見ずして亡くなった。(京都府)中井弘の胸像は円山公園内にある。
②六孫王神社


大城弘明氏撮影
□六孫王は、清和天皇の六男を父として生まれ、経基と名づけられたが、皇室では六男の六と天皇の孫ということで六孫王と呼ばれていた。十五才にて元服、源の姓を賜わり、先例に従い臣籍に加えられたとある。承平・天慶の乱に東国・西国の追討使を承り、現地に赴き凱旋の後、鎮守府将軍に任じられた。王は現在の社地に住居を構え、臨終に臨み「霊魂滅するとも龍(神)となり西八条の池に住みて子孫の繁栄を祈るゆえにこの地に葬れ」と遺言された。王の長子満仲公は遺骸を当地に埋葬され(本殿後方に石積の神廟がある)その前に社殿を築いたのが、六孫王神社の始まりである。(平安時代中期)
境内中央の池を神龍池といい、その側に満仲誕生のおり井戸上に琵琶湖の竹生島より弁財天を勧請し、安産を祈願し産湯に使ったと云う、誕生水弁財天社がある。(6月13日弁財天御開帳祭)
江戸時代五代将軍綱吉の時代に現在の本殿・拝殿等建物が再建された。毎年十月体育の日に例祭(再興が元禄より始まり宝永年間に完成したゆえ別名“宝永祭”とも謂われる)が行われる。
王の後裔には源義家・頼光・頼政・木曽義仲・頼朝等、また足利・新田・細川・島津・山名・今川・明智・小笠原・徳川等の武将が多数輩出され、それぞれ子孫繁栄されている。
昔は、六ノ宮権現とも呼ばれ、今昔物語に「六の宮」それを基に芥川龍之介が「六の宮の姫君」にも載せている。小泉八雲著の「怪談」には、「弁天の同情」と題して不思議な夫婦の出会いの話が紹介されている。

「小泉八雲」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
1909年4月『琉球新報』□師範中学旅行生の消息ー4月6日、火曜日、神戸、京都 午前9時半汽車にて神戸駅を発し12時京都に着。直ちに東本願寺に参詣致し建築の壮大な に驚き入り候。これより途中耳塚を右に見立て豊国神社に詣で旧伏見桃山殿の唐門大仏殿、国家安康の大鐘を見て博物館に入り歴史美術上の珍品に知囊を養い三十三間堂を経て桃山御殿に詣で血天井を見。妙法院西大谷を過ぎて清水寺に詣で候・・・。
1917年4月『琉球新報』□沖縄師範旅行たよりー午前8時、軽装して比叡山登りの道すがら、本能寺の信長墓を弔った。五尺ばかりの石塔で手向ける人とてもなくあはれ物寂しい。御所を拝して大学の裏道より、田圃の間にいで右に吉田の山を見つつ銀閣寺にいった。庭園の美、泉石の趣、形容も及び難いが義政将軍風流三昧をつくしたところかと思うと折角の美景も興がさめてしまう。狩野元信の筆や、弘法大師の書などは珍しいものである。ここから大文字山の森の下道を通ってその名もゆかしい大原白河口に出た。比叡山の登り口である。流汗淋満として瀧なす泉に咽喉を濕し息もたえだえに登ると境は益々幽邃である。ラスキンが山を讃美して、宗教家には聖光を付与す・・・。
1925年8月 『琉球新報』□女子師範二部旅行便り・夏の旅ー7月17日、2日目の京都見物に8時頃宿を出発して京津電車に乗って浜大津に着く。(略)高く聳える比叡山を後にして瀬多の唐橋を潜りときに名高い石山寺に詣づ。紫式部の源氏の間はかたく閉ざされて、ありし昔を物語る如く墨黒々と書かれて居るここに天然記念物に指定されたるけい灰岩あり、其処を引き返して又船に乗る。粟津の晴嵐を右手に眺め三井寺に参拝して疎水下りにつく流れ清き水に行く船の淡き灯の中より歌の聲もれて暗きトンネルの天井に反響して周囲の空気をゆるがし流れを波立たす。トンネルを出ると眩ゆい光線に小波はプラチナのように光り輝いて其の美しさはたとえ様もない夏の事とて海水浴をする人や釣をする人が多い。疎水を下り終ってインクラインを見てから知恩院に向かう。左甚五郎の荒れ傘や鶯張廊下を見る3百間もある長い廊下である。ここより清水寺に行き方広寺、三十三間堂に詣ず。恩賜の京都博物館を眺め黄昏の町を電車で宿に帰り又10時に宿を出発して岡崎公園に至り、平安神宮に詣で桓武天皇当時の昔を忍ぶ、公会堂の前を通り西本願寺に行って電車で駅に向かう。


京都妙心寺の板絵「蘇鉄と山羊」/円山公園の蘇鉄
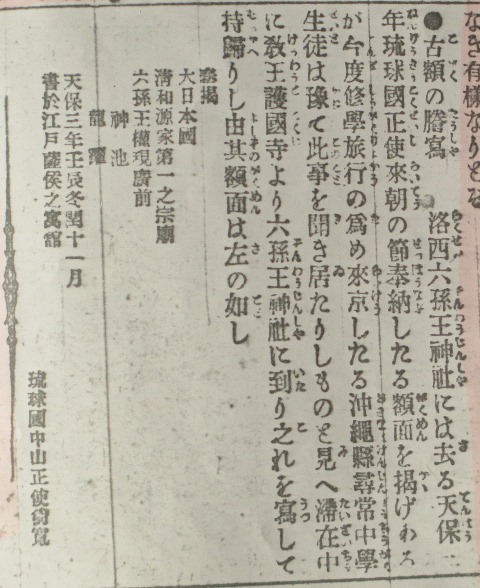
1894年5月20日『日出新聞』
〇1832年(天保3)6月8日、那覇港を立ち江戸に赴く。7月21日、琉球国尚育王即位の謝恩のための使節(正使尚氏豊見城王子朝春副使毛氏澤岻親方安度)らの一行、鹿児島着。8月27日、正使豊見城王子死去。讃議官の向氏普天間親雲上朝朝典を正使として9月1日鹿児島を立つ。11月16日、江戸着、江戸城に登城し朝覲の礼を行う。12月13日、江戸を立ち帰路に就く。1833年(天保4)4月8日、江戸上り使節一行那覇に帰還。
豊見城王子(普天間親雲上朝朝典)の歌→『通航一覧続輯』
※わた津海の底より出て日のもとのひかりにあたる龍の宮人
□①5代京都府知事 中井弘(なかいひろし)
就任期間:明治26年(1893)11月~明治27年10月
天保9年(1838)、鹿児島生まれ。幕末と明治のはじめに二度にわたり欧州に留学、西郷隆盛に従軍したこともあった。工部大学校書記官、滋賀県知事、貴族院議員を経て京都府知事となる。滋賀県時代は時の北垣京都府知事とともに琵琶湖疎水建設にあたった。京都府知事在任中は「京都三大問題」(遷都千百年記念祭、第四回内国勧業博覧会、京都舞鶴間鉄道の建設)に力を尽くしたが、在任中脳出血で倒れ、これらの完成を見ずして亡くなった。(京都府)中井弘の胸像は円山公園内にある。
②六孫王神社


大城弘明氏撮影
□六孫王は、清和天皇の六男を父として生まれ、経基と名づけられたが、皇室では六男の六と天皇の孫ということで六孫王と呼ばれていた。十五才にて元服、源の姓を賜わり、先例に従い臣籍に加えられたとある。承平・天慶の乱に東国・西国の追討使を承り、現地に赴き凱旋の後、鎮守府将軍に任じられた。王は現在の社地に住居を構え、臨終に臨み「霊魂滅するとも龍(神)となり西八条の池に住みて子孫の繁栄を祈るゆえにこの地に葬れ」と遺言された。王の長子満仲公は遺骸を当地に埋葬され(本殿後方に石積の神廟がある)その前に社殿を築いたのが、六孫王神社の始まりである。(平安時代中期)
境内中央の池を神龍池といい、その側に満仲誕生のおり井戸上に琵琶湖の竹生島より弁財天を勧請し、安産を祈願し産湯に使ったと云う、誕生水弁財天社がある。(6月13日弁財天御開帳祭)
江戸時代五代将軍綱吉の時代に現在の本殿・拝殿等建物が再建された。毎年十月体育の日に例祭(再興が元禄より始まり宝永年間に完成したゆえ別名“宝永祭”とも謂われる)が行われる。
王の後裔には源義家・頼光・頼政・木曽義仲・頼朝等、また足利・新田・細川・島津・山名・今川・明智・小笠原・徳川等の武将が多数輩出され、それぞれ子孫繁栄されている。
昔は、六ノ宮権現とも呼ばれ、今昔物語に「六の宮」それを基に芥川龍之介が「六の宮の姫君」にも載せている。小泉八雲著の「怪談」には、「弁天の同情」と題して不思議な夫婦の出会いの話が紹介されている。

「小泉八雲」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
1909年4月『琉球新報』□師範中学旅行生の消息ー4月6日、火曜日、神戸、京都 午前9時半汽車にて神戸駅を発し12時京都に着。直ちに東本願寺に参詣致し建築の壮大な に驚き入り候。これより途中耳塚を右に見立て豊国神社に詣で旧伏見桃山殿の唐門大仏殿、国家安康の大鐘を見て博物館に入り歴史美術上の珍品に知囊を養い三十三間堂を経て桃山御殿に詣で血天井を見。妙法院西大谷を過ぎて清水寺に詣で候・・・。
1917年4月『琉球新報』□沖縄師範旅行たよりー午前8時、軽装して比叡山登りの道すがら、本能寺の信長墓を弔った。五尺ばかりの石塔で手向ける人とてもなくあはれ物寂しい。御所を拝して大学の裏道より、田圃の間にいで右に吉田の山を見つつ銀閣寺にいった。庭園の美、泉石の趣、形容も及び難いが義政将軍風流三昧をつくしたところかと思うと折角の美景も興がさめてしまう。狩野元信の筆や、弘法大師の書などは珍しいものである。ここから大文字山の森の下道を通ってその名もゆかしい大原白河口に出た。比叡山の登り口である。流汗淋満として瀧なす泉に咽喉を濕し息もたえだえに登ると境は益々幽邃である。ラスキンが山を讃美して、宗教家には聖光を付与す・・・。
1925年8月 『琉球新報』□女子師範二部旅行便り・夏の旅ー7月17日、2日目の京都見物に8時頃宿を出発して京津電車に乗って浜大津に着く。(略)高く聳える比叡山を後にして瀬多の唐橋を潜りときに名高い石山寺に詣づ。紫式部の源氏の間はかたく閉ざされて、ありし昔を物語る如く墨黒々と書かれて居るここに天然記念物に指定されたるけい灰岩あり、其処を引き返して又船に乗る。粟津の晴嵐を右手に眺め三井寺に参拝して疎水下りにつく流れ清き水に行く船の淡き灯の中より歌の聲もれて暗きトンネルの天井に反響して周囲の空気をゆるがし流れを波立たす。トンネルを出ると眩ゆい光線に小波はプラチナのように光り輝いて其の美しさはたとえ様もない夏の事とて海水浴をする人や釣をする人が多い。疎水を下り終ってインクラインを見てから知恩院に向かう。左甚五郎の荒れ傘や鶯張廊下を見る3百間もある長い廊下である。ここより清水寺に行き方広寺、三十三間堂に詣ず。恩賜の京都博物館を眺め黄昏の町を電車で宿に帰り又10時に宿を出発して岡崎公園に至り、平安神宮に詣で桓武天皇当時の昔を忍ぶ、公会堂の前を通り西本願寺に行って電車で駅に向かう。


京都妙心寺の板絵「蘇鉄と山羊」/円山公園の蘇鉄
09/15: 新城栄徳「関西日誌2011-10」
東北関東大震災後の関西に出てみた。(東日本大震災 2011年3月11日午後2時46分、三陸沖で発生したマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震により引き起こされた大災害。最大震度7の強い揺れと国内観測史上最大の津波を伴い、東北・関東地方を中心とする広い範囲に甚大な被害をもたらした。また、東京電力福島第一原子力発電所が被災し、放射性物質が漏れ出す深刻な事態になった。→知恵蔵)〇2019年(令和元年)7月9日時点で、震災による死者・行方不明者は1万8429人、建築物の全壊・半壊は合わせて40万4890戸が公式に確認されている。震災発生直後のピーク時においては避難者は40万人以上、停電世帯は800万戸以上、断水世帯は180万戸以上等の数値が報告されている。復興庁によると、2019年7月30日時点の避難者等の数は5万271人となっている。→ウィキ
新城栄徳「関西日誌2011-10」
私の本格的な古本屋巡りは1965年から始まっている。何ぼネット時代と言ってもこの身に染み付いた古本屋巡礼の快楽は、バーチャル(仮想空間)なネット世界では絶対に味わえないものだ。第一、歩くことによって運動にもなる。古本屋がどんな場所にあるのか訪ねるのも楽しみの一つである。本、新聞もネットで読めるとよく若い人は言うが、持ち時間が余り無い初老には馴染む気力も体力も無い。
午前10時に布施の自宅を出て、JR永和駅から乗り大阪天満宮に行く。電車賃は170円、那覇市内バス210円より安い。天満宮で「天神さんの古本まつり」(大阪古書古書研究会主催)がある。天気も良く参拝客も多い。5冊1000円コナーで、W・A・スウォンバーグ/木下秀夫『アメリカ新聞界の巨人・ピュリツァー』(早川書房1978)、小糸忠吾『超大国米国ソ連のマスメディア』(理想出版社1981)、高橋康雄『物語・萬朝報』(日本経済新聞社1989)、木村愛二『読売新聞・歴史検証』(汐文社1996)、雑誌は『人物往来』「昭和重大事件の真正報告ーあの時の証人は語る」1955年の復刻版を買った。
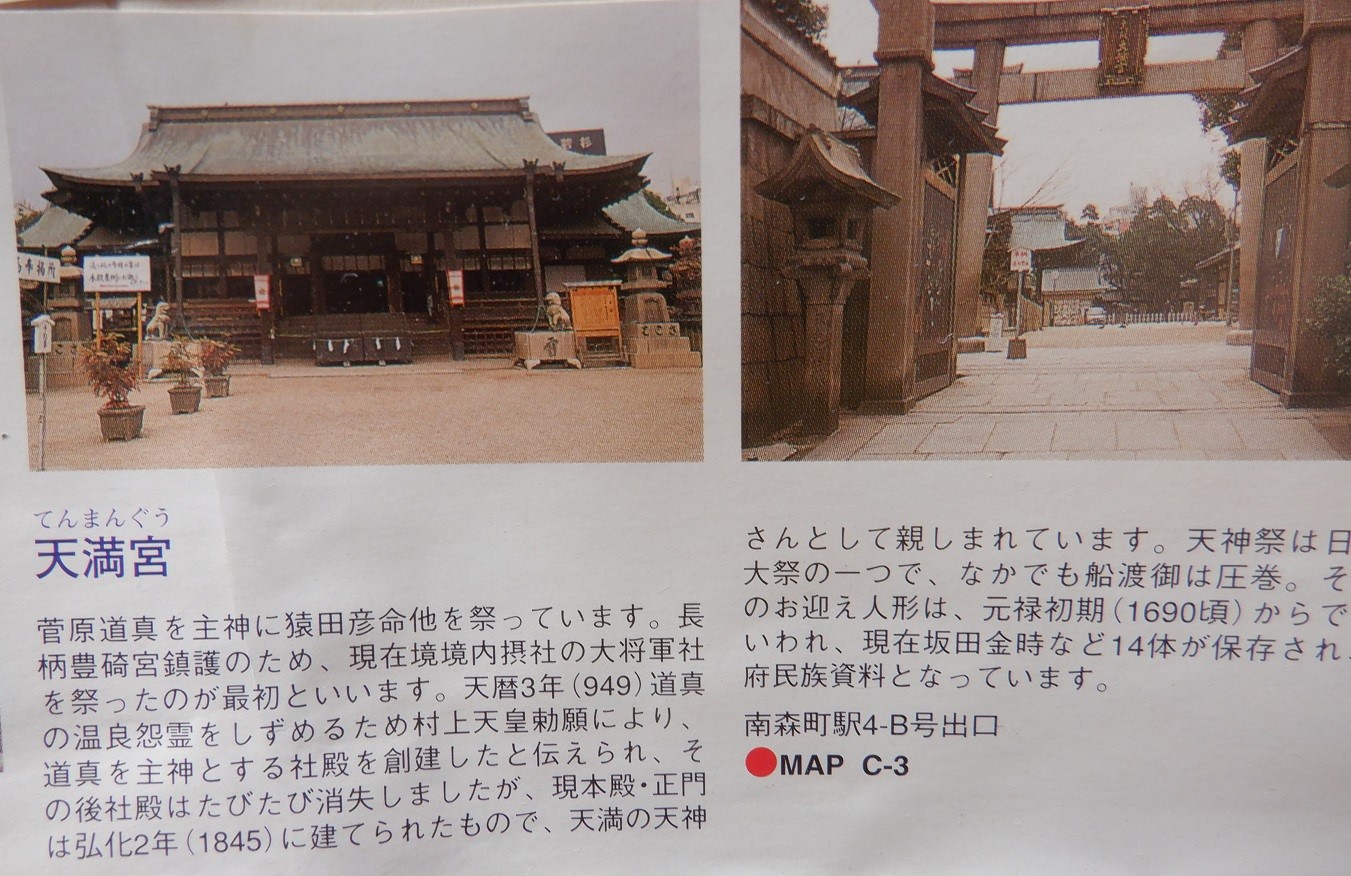


100円コーナーで、『醍醐寺の研究』(飛鳥園1930)は中にチラシ「出雲大寺薬師」や長崎、大宰府天満宮近くの飲食店の箸袋が挟まれていた。平凡社発行(1929~31)『世界美術全集』21巻、27巻、別巻「宗教図像篇」、最後の巻には週刊朝日チラシ「ワーナー・ブラザース映画『百萬長者』/フエアリイランド/秋の画廊」「日本古墳と安南の墳墓」「古代朝鮮文化の粋」「古今東西女性美名作物語ー上野府美術館」(数点の戦前の新聞切り抜き)が挟まれていた。新村出『広辞苑』(岩波書店1960)、雑誌は、『話の特集』第191号(1981-12)には今話題の島田紳助らの「とことんやったれ!ツッパリ漫才爆走中」が載っている。たしか今の琉球新報社長の富田詢一氏もかつて『話の特集』編集部にいたことがある。『芸術新潮』「ナチスが捺した退廃芸術の烙印」(1992-9)、「悪趣味のパワー」(93-6)、「天災と闘った美術」(95-5)、「『東寺』よ開け!」を買った。
天満宮を天六方面に行けば末広町の「成正寺」がある。入口に「中斎大塩平八郎墓所」の石碑がたっていて、奥にソテツがある。。東の方も散策。天満東寺町の龍海寺(緒方洪庵墓所がある)に寄る。ここは門が来るたび閉まっている。『大阪春秋』(2006-10)にT・M生が「寺町と掃苔ー著名人の墓碑は文化遺産」を書いていて「それよりも緒方一家といえば、いまも家運隆盛で良識ある優秀な方ばかり(略)戦後緒方家の墓地を整備なさったとき、無縁となられた中家の墓域ぐらい購入されて洪庵先生と並べて眠らせてあげれば、洪庵もさぞかし喜ばれたと思うのですが残念
新城栄徳日記メモー1995年1月1日ー奈良東大寺大仏初詣/1月17日午前5時過ぎに京都で大きな揺れ。東大阪の息子に電話。午後2時23分電車で京阪淀から近鉄経由で布施。/1月24日、尼崎市の兵庫沖縄県人会事務所。沖縄県からのビニールシートが届いていたので配送を手伝う。息子名義で見舞金を贈ったとき宮城幹夫氏も来所し見舞金を贈られた。挨拶をした。1月30日、西宮からバスで三宮。午後8時に帰宅。1月31日、大正区へよって、阪神青木から東灘区へ。その後、息子も神戸へ。
10・10那覇大空襲の日である。1944年7月のサイパン陥落。10月、アメリカ軍はフィリピンへの進攻作戦を準備。これに先立って、後方の南西諸島から台湾方面に散在する日本軍の拠点を、空母艦載機をもって攻撃した。10日の沖縄の大空襲はこの一環として行われたものとされている。このとき那覇市内の9割が消失して壊滅した。死者は255人以上にのぼった。大阪は翌年45年3月13日から深夜から翌日未明にかけてに最初の大阪空襲が行なわれた。同年3月23日には粟国島空襲、26日には慶良間諸島にアメリカ軍が上陸し沖縄戦が始まった。大阪ではその後、6月から8月にかけて空襲が行なわれた。これらの空襲で一般市民 10,000人以上が死亡したと言われる。それから60数年。未だにアメリカ軍は「トモダチ」としてオキナワ・日本に居座っている。何ら疑問も感じない日米両政府。それを容認する国民の感覚も分からない。今日まで核の傘、原発も容認してきた国民。これからも<しょうがないにゃあ>。
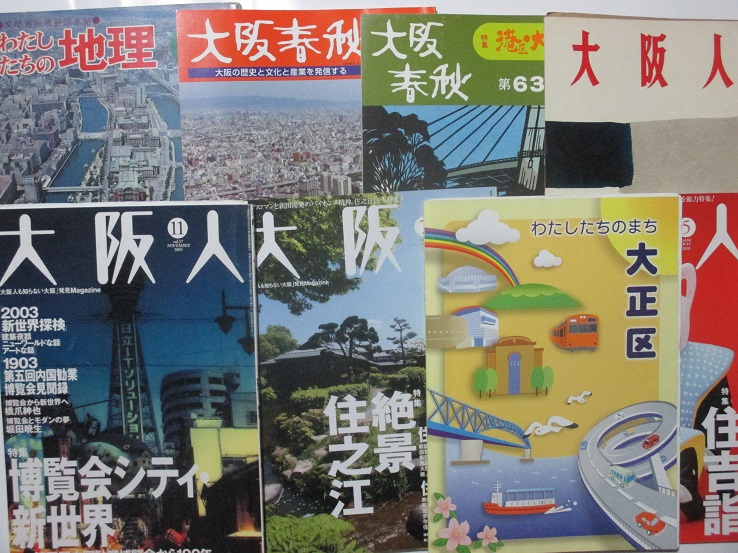
大阪の本・雑誌
午後から大阪市天王寺区生玉町界隈を見学。法音寺は天王寺区の北部、建物は南面している。新しい本堂だが、古い屋根瓦がよく目立っている。1612年創建。1945年ー大阪大空襲により焼失。戦後再建された。画家上田公長の墓所でソテツもある。浄土宗圓通寺には俳匠の大江丸墓所。ソテツもある。大江は大坂出身。飛脚問屋・嶋屋の主人で、家業上諸国を旅したので、交際がきわめて広く、またたいへん筆まめで、そのうえ長寿でもあったので、残した紀行文や随筆、そして発句などは莫大な数にのぼる。作風としては京都の蕪村派の影響を受けているが、西山宗因や上島鬼貫の模倣をした作品もある。のちに江戸の大島蓼太に私淑し、著書においても蓼太を師として敬っている。
生魂山齢延寺には幕末に私塾・泊園書院を興して活躍した儒者の藤澤東咳・南岳父子や、画家の鍋井克之、名刀鍛冶師の左行秀の墓がある。また、緒方洪庵、斉藤方策と並ぶなにわの3名医のひとり・原老柳ゆかりの老柳観音がある。やがて「いくたまさん」と呼ばれる難波大社 生國魂神社北門入り口に着く。鳥居をくぐって生玉北門坂をのぼる。神社本殿の脇には11社の境内社がある。一番右側の鳥居は「浄瑠璃神社」で、近松門左衛門や竹本義太夫など人形浄瑠璃(文楽)に成立に功のあった『浄瑠璃七功神』をはじめ文楽および女義太夫の物故者を祭神として祀られている。
境内社の1つ「鴫野神社」。大坂城外鴫野弁天島にあった「弁天社」は淀君の崇敬が厚く、後に「淀姫神社」として祀られるようになったが、1877年に現在地に移転された。家造祖神社は、家造の祖神を祀り、建築関係者の崇敬が篤い。鞴神社は、鞴(ふいご)の神・鍛治の神を祀り、製鉄などの金物業界の崇敬が篤い。
境内に井原西鶴像がある。西鶴は1680年、「生玉神社南坊」で一昼夜独吟四千句を興行した。後ろの碑は「南坊」の所在跡を示す石碑、「南坊」は明治初期の神仏分離の折、現在の中央区島之内に移転した法案寺の前身である。「米澤彦八の碑」に京都で露五郎兵衛によって始められた上方落語は、大阪では当社境内を舞台に米澤彦八が広めたとある。「八雲琴の碑」には「二つ緒の八雲の琴に神の世の しらべを移し伝え来にけり」と記され中山琴主(愛媛の人、文政年間出雲大社に参拝し神事を得て完成したと伝えられる、琴は二弦で「八雲琴」)を顕彰。
1496年、本願寺八世蓮如上人が生國魂神社に接して『石山御坊(後の石山本願寺)』を建立したが、1580年、織田信長に屈し灰燼に帰した。1583年、豊臣秀吉が石山本願寺(現在の大阪城の二の丸周辺にあった)跡に大阪城を築城。そのため、神社に社領を寄進し社殿を造営。1585年に現在の鎮座地に遷されたと伝えられている。明治維新の廃仏毀釈によって境内にあった神宮寺が境外へ分散するなど境内は著しく変化したが、1871年、官幣大社に加列された。社殿は(明治45年)『南の大火』、1945年の戦災による消失、1950年の『ジェ―ン台風』による倒壊など幾度も被災と造営を繰り返し、現在の社殿は1956年(昭和31年)に建立されたものである。10月22日から神社参集殿で「出口王仁三郎耀琓展」が開かれるという。
近松門左衛門の墓は菩提寺、尼崎・広済寺と、妻側の菩提寺の大阪・法妙寺に建てられ、共に夫婦の戒名が刻まれた比翼墓である。法妙寺は大空襲で焼失し大東市に再建され、後に墓だけが元の場所に戻された。近松の墓を見て、西鶴の墓がある誓願寺を訪ねる。戦災で本堂も繰りも焼けたため、一時途絶えた時期もあったが、毎年9月には「西鶴忌」が行われる。西鶴の墓は1887年を前後する頃、誓願寺境内の無縁墓に押し込められていたのが発見された。境内には、大坂に於ける私立学問所「懐徳堂」を140年余にわたり経営し、江戸時代大坂の文教の発展に貢献した、中井一族の墓がある。→稲垣國三郎にも『中井竹山と草茅危言』(大正洋行1943)の著がある。
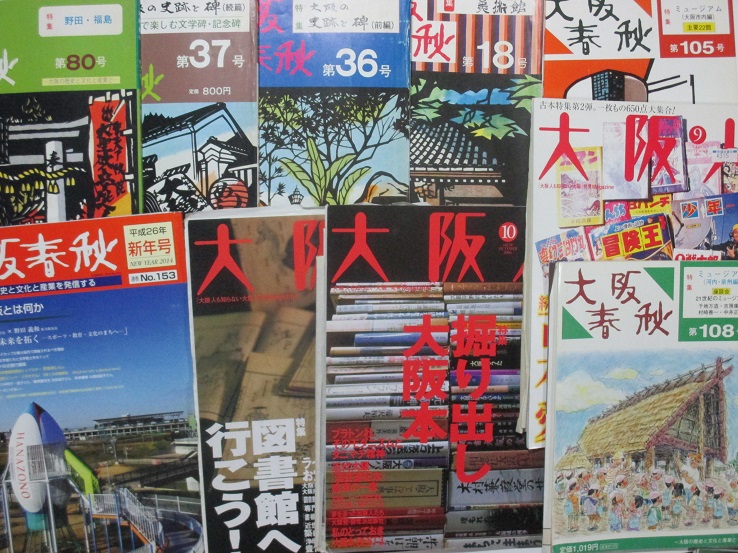
大阪の本・雑誌
誓願寺門前にプロレタリア文学を経て、転向。西鶴の浮世草子の作風に学んだ「市井事もの」を著し、時代の庶民風俗の中に新しいリアリズムを追求する独自の作風を確立した 武田麟太郎文学碑がある。この文学碑は武田の小説『井原西鶴』の一節が刻まれている。大阪市中央区上本町「東平公園」にある薄田泣菫の『金剛山の歌』の碑。詩は、作者が本長寺に仮住まいしていた頃、散歩の途中、朝日に輝く金剛山を見て、詠んだと言う。薄田泣菫(1877~1945)は岡山県生れ、24歳で大阪に出て文芸雑誌、詩集を刊し、象徴派詩人として名声を得た。 午後ー近鉄布施駅から鶴橋。近鉄駅改札のまん前にある「高坂書店」では数多くの在日コリアン関連の書籍が売られている。いわゆる「嫌中本」「嫌韓本」も意外に数多く揃えてあり「マンガ嫌韓流」といった山野某の本もある。私はブックオフで買った山野「在日の地図」で、日本の中のコリアンを見つめなおしている。鶴橋商店街はいつも見慣れているが、面白いのは、ガード下にも広がる市場の存在。闇市の世界をそのままに、という風景で八百屋、魚屋、肉屋、乾物屋、そしてキムチ屋、ありとあらゆる韓国食材が揃う、まさに日本の中の朝鮮。大阪の東の玄関口として戦前から発展してきた下町、鶴橋。大阪府は全国で最も在日韓国・朝鮮人が多く、人口は15万人。その多くが大阪市東部の生野区を中心としたエリアに住んでいる。生野区の人口14万人の4分の1に当たる、3万人程度が住んでいると言われる。
明治、大正時代の大阪は、日本の急激な工業化に伴い大量の労働者が必要となり受け入れた。大阪は大大阪となる。現在の生野区や東大阪市、八尾市あたりには、朝鮮半島から出稼ぎをした人間が大勢住む事となった。終戦直後には210万人程度居たと言われている。その多くが京阪神に住んでいた。現在も在日韓国・朝鮮人の人口は60万人程度居るが、今では在日二世・三世がほとんどで、中には帰化をして日本人になっているものも多く、その実態を掴むのは不可能だ。
鶴橋商店街を通っていつもは通らない反対の方向に行く。やがて大阪市生野区弥栄神社に出る。秋祭りの地車(ダンジリ)の手入れの最中であった。傍で子どもらが鐘と太鼓の練習をしていた(→「秋祭り」画像検索)。彌栄神社とはバス道ひとつ隔てて鎮座しているのが御幸森天神宮。仁徳天皇を主祭神とし、昔の東成郡猪飼野村の氏神、天皇崩御の後、この森に社殿を建立し、天皇の御神霊を奉祀して、御幸森と称したという。このバス道がかっては百済川だった。猪飼野は猪甘津と呼ばれ、 百済川には日本最初の橋が架けられたと言う。天神宮に沿って御幸通商店街がある。反対側に韓国式の立派な門、沖縄の守礼門と似かよっている。商店街は東西で3つの区画に分かれており、コリアタウン色が強いのが御幸通中央商店街。ほとんどの店舗がキムチ屋や肉屋、韓国料理店や屋台料理、民族衣装、それに韓国の音楽CDやDVDを売る店舗となっている。この商店街は大阪に永いこと住んでいるが初めて来た。
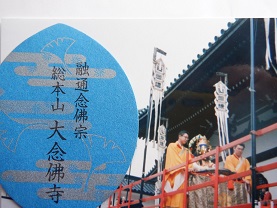


大念佛寺 大阪市平野区平野上町1丁目7-26
毎年5月1日 - 5日に行われる「万部おねり」は大阪市指定無形民俗文化財に指定されている。 25人の菩薩が娑婆(外側)から極楽浄土(本堂)に練り歩き、絢爛豪華な来迎の世界を体現している。
新城栄徳「関西日誌2011-10」
私の本格的な古本屋巡りは1965年から始まっている。何ぼネット時代と言ってもこの身に染み付いた古本屋巡礼の快楽は、バーチャル(仮想空間)なネット世界では絶対に味わえないものだ。第一、歩くことによって運動にもなる。古本屋がどんな場所にあるのか訪ねるのも楽しみの一つである。本、新聞もネットで読めるとよく若い人は言うが、持ち時間が余り無い初老には馴染む気力も体力も無い。
午前10時に布施の自宅を出て、JR永和駅から乗り大阪天満宮に行く。電車賃は170円、那覇市内バス210円より安い。天満宮で「天神さんの古本まつり」(大阪古書古書研究会主催)がある。天気も良く参拝客も多い。5冊1000円コナーで、W・A・スウォンバーグ/木下秀夫『アメリカ新聞界の巨人・ピュリツァー』(早川書房1978)、小糸忠吾『超大国米国ソ連のマスメディア』(理想出版社1981)、高橋康雄『物語・萬朝報』(日本経済新聞社1989)、木村愛二『読売新聞・歴史検証』(汐文社1996)、雑誌は『人物往来』「昭和重大事件の真正報告ーあの時の証人は語る」1955年の復刻版を買った。
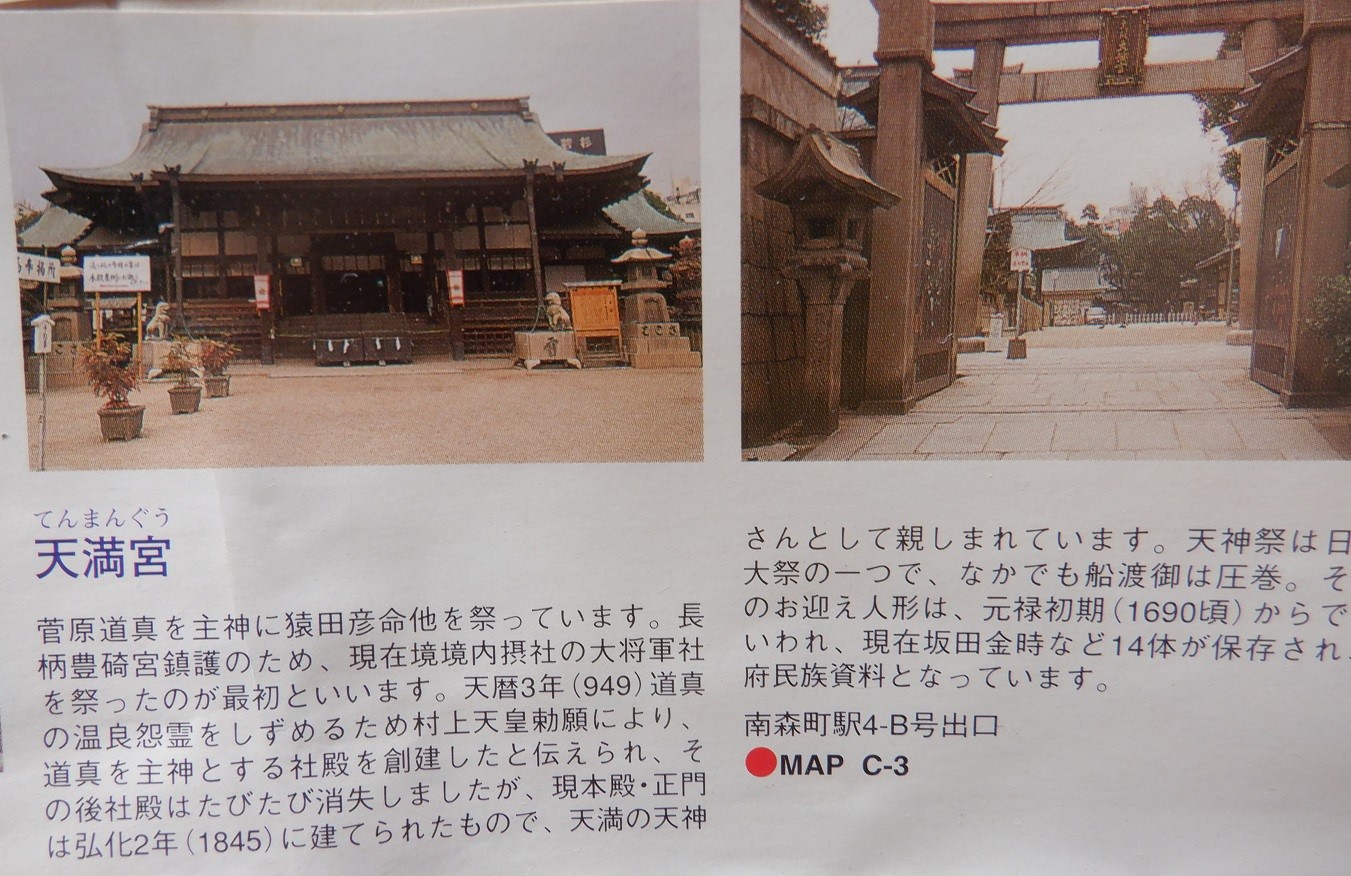


100円コーナーで、『醍醐寺の研究』(飛鳥園1930)は中にチラシ「出雲大寺薬師」や長崎、大宰府天満宮近くの飲食店の箸袋が挟まれていた。平凡社発行(1929~31)『世界美術全集』21巻、27巻、別巻「宗教図像篇」、最後の巻には週刊朝日チラシ「ワーナー・ブラザース映画『百萬長者』/フエアリイランド/秋の画廊」「日本古墳と安南の墳墓」「古代朝鮮文化の粋」「古今東西女性美名作物語ー上野府美術館」(数点の戦前の新聞切り抜き)が挟まれていた。新村出『広辞苑』(岩波書店1960)、雑誌は、『話の特集』第191号(1981-12)には今話題の島田紳助らの「とことんやったれ!ツッパリ漫才爆走中」が載っている。たしか今の琉球新報社長の富田詢一氏もかつて『話の特集』編集部にいたことがある。『芸術新潮』「ナチスが捺した退廃芸術の烙印」(1992-9)、「悪趣味のパワー」(93-6)、「天災と闘った美術」(95-5)、「『東寺』よ開け!」を買った。
天満宮を天六方面に行けば末広町の「成正寺」がある。入口に「中斎大塩平八郎墓所」の石碑がたっていて、奥にソテツがある。。東の方も散策。天満東寺町の龍海寺(緒方洪庵墓所がある)に寄る。ここは門が来るたび閉まっている。『大阪春秋』(2006-10)にT・M生が「寺町と掃苔ー著名人の墓碑は文化遺産」を書いていて「それよりも緒方一家といえば、いまも家運隆盛で良識ある優秀な方ばかり(略)戦後緒方家の墓地を整備なさったとき、無縁となられた中家の墓域ぐらい購入されて洪庵先生と並べて眠らせてあげれば、洪庵もさぞかし喜ばれたと思うのですが残念
新城栄徳日記メモー1995年1月1日ー奈良東大寺大仏初詣/1月17日午前5時過ぎに京都で大きな揺れ。東大阪の息子に電話。午後2時23分電車で京阪淀から近鉄経由で布施。/1月24日、尼崎市の兵庫沖縄県人会事務所。沖縄県からのビニールシートが届いていたので配送を手伝う。息子名義で見舞金を贈ったとき宮城幹夫氏も来所し見舞金を贈られた。挨拶をした。1月30日、西宮からバスで三宮。午後8時に帰宅。1月31日、大正区へよって、阪神青木から東灘区へ。その後、息子も神戸へ。
10・10那覇大空襲の日である。1944年7月のサイパン陥落。10月、アメリカ軍はフィリピンへの進攻作戦を準備。これに先立って、後方の南西諸島から台湾方面に散在する日本軍の拠点を、空母艦載機をもって攻撃した。10日の沖縄の大空襲はこの一環として行われたものとされている。このとき那覇市内の9割が消失して壊滅した。死者は255人以上にのぼった。大阪は翌年45年3月13日から深夜から翌日未明にかけてに最初の大阪空襲が行なわれた。同年3月23日には粟国島空襲、26日には慶良間諸島にアメリカ軍が上陸し沖縄戦が始まった。大阪ではその後、6月から8月にかけて空襲が行なわれた。これらの空襲で一般市民 10,000人以上が死亡したと言われる。それから60数年。未だにアメリカ軍は「トモダチ」としてオキナワ・日本に居座っている。何ら疑問も感じない日米両政府。それを容認する国民の感覚も分からない。今日まで核の傘、原発も容認してきた国民。これからも<しょうがないにゃあ>。
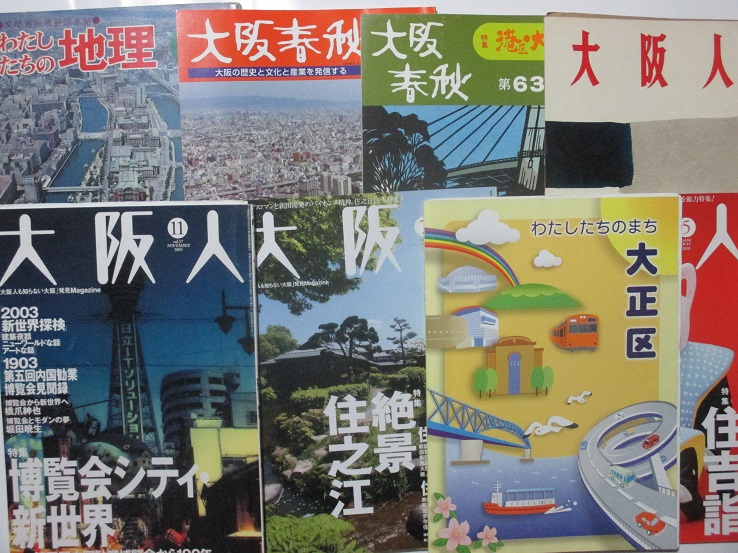
大阪の本・雑誌
午後から大阪市天王寺区生玉町界隈を見学。法音寺は天王寺区の北部、建物は南面している。新しい本堂だが、古い屋根瓦がよく目立っている。1612年創建。1945年ー大阪大空襲により焼失。戦後再建された。画家上田公長の墓所でソテツもある。浄土宗圓通寺には俳匠の大江丸墓所。ソテツもある。大江は大坂出身。飛脚問屋・嶋屋の主人で、家業上諸国を旅したので、交際がきわめて広く、またたいへん筆まめで、そのうえ長寿でもあったので、残した紀行文や随筆、そして発句などは莫大な数にのぼる。作風としては京都の蕪村派の影響を受けているが、西山宗因や上島鬼貫の模倣をした作品もある。のちに江戸の大島蓼太に私淑し、著書においても蓼太を師として敬っている。
生魂山齢延寺には幕末に私塾・泊園書院を興して活躍した儒者の藤澤東咳・南岳父子や、画家の鍋井克之、名刀鍛冶師の左行秀の墓がある。また、緒方洪庵、斉藤方策と並ぶなにわの3名医のひとり・原老柳ゆかりの老柳観音がある。やがて「いくたまさん」と呼ばれる難波大社 生國魂神社北門入り口に着く。鳥居をくぐって生玉北門坂をのぼる。神社本殿の脇には11社の境内社がある。一番右側の鳥居は「浄瑠璃神社」で、近松門左衛門や竹本義太夫など人形浄瑠璃(文楽)に成立に功のあった『浄瑠璃七功神』をはじめ文楽および女義太夫の物故者を祭神として祀られている。
境内社の1つ「鴫野神社」。大坂城外鴫野弁天島にあった「弁天社」は淀君の崇敬が厚く、後に「淀姫神社」として祀られるようになったが、1877年に現在地に移転された。家造祖神社は、家造の祖神を祀り、建築関係者の崇敬が篤い。鞴神社は、鞴(ふいご)の神・鍛治の神を祀り、製鉄などの金物業界の崇敬が篤い。
境内に井原西鶴像がある。西鶴は1680年、「生玉神社南坊」で一昼夜独吟四千句を興行した。後ろの碑は「南坊」の所在跡を示す石碑、「南坊」は明治初期の神仏分離の折、現在の中央区島之内に移転した法案寺の前身である。「米澤彦八の碑」に京都で露五郎兵衛によって始められた上方落語は、大阪では当社境内を舞台に米澤彦八が広めたとある。「八雲琴の碑」には「二つ緒の八雲の琴に神の世の しらべを移し伝え来にけり」と記され中山琴主(愛媛の人、文政年間出雲大社に参拝し神事を得て完成したと伝えられる、琴は二弦で「八雲琴」)を顕彰。
1496年、本願寺八世蓮如上人が生國魂神社に接して『石山御坊(後の石山本願寺)』を建立したが、1580年、織田信長に屈し灰燼に帰した。1583年、豊臣秀吉が石山本願寺(現在の大阪城の二の丸周辺にあった)跡に大阪城を築城。そのため、神社に社領を寄進し社殿を造営。1585年に現在の鎮座地に遷されたと伝えられている。明治維新の廃仏毀釈によって境内にあった神宮寺が境外へ分散するなど境内は著しく変化したが、1871年、官幣大社に加列された。社殿は(明治45年)『南の大火』、1945年の戦災による消失、1950年の『ジェ―ン台風』による倒壊など幾度も被災と造営を繰り返し、現在の社殿は1956年(昭和31年)に建立されたものである。10月22日から神社参集殿で「出口王仁三郎耀琓展」が開かれるという。
近松門左衛門の墓は菩提寺、尼崎・広済寺と、妻側の菩提寺の大阪・法妙寺に建てられ、共に夫婦の戒名が刻まれた比翼墓である。法妙寺は大空襲で焼失し大東市に再建され、後に墓だけが元の場所に戻された。近松の墓を見て、西鶴の墓がある誓願寺を訪ねる。戦災で本堂も繰りも焼けたため、一時途絶えた時期もあったが、毎年9月には「西鶴忌」が行われる。西鶴の墓は1887年を前後する頃、誓願寺境内の無縁墓に押し込められていたのが発見された。境内には、大坂に於ける私立学問所「懐徳堂」を140年余にわたり経営し、江戸時代大坂の文教の発展に貢献した、中井一族の墓がある。→稲垣國三郎にも『中井竹山と草茅危言』(大正洋行1943)の著がある。
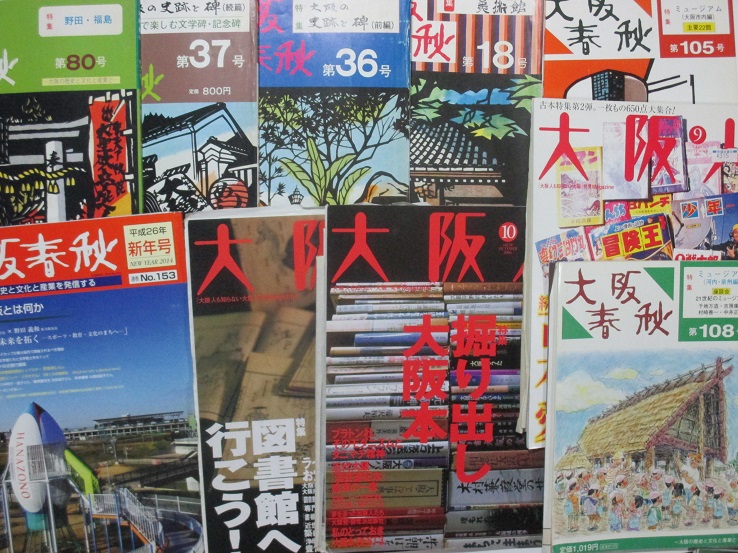
大阪の本・雑誌
誓願寺門前にプロレタリア文学を経て、転向。西鶴の浮世草子の作風に学んだ「市井事もの」を著し、時代の庶民風俗の中に新しいリアリズムを追求する独自の作風を確立した 武田麟太郎文学碑がある。この文学碑は武田の小説『井原西鶴』の一節が刻まれている。大阪市中央区上本町「東平公園」にある薄田泣菫の『金剛山の歌』の碑。詩は、作者が本長寺に仮住まいしていた頃、散歩の途中、朝日に輝く金剛山を見て、詠んだと言う。薄田泣菫(1877~1945)は岡山県生れ、24歳で大阪に出て文芸雑誌、詩集を刊し、象徴派詩人として名声を得た。 午後ー近鉄布施駅から鶴橋。近鉄駅改札のまん前にある「高坂書店」では数多くの在日コリアン関連の書籍が売られている。いわゆる「嫌中本」「嫌韓本」も意外に数多く揃えてあり「マンガ嫌韓流」といった山野某の本もある。私はブックオフで買った山野「在日の地図」で、日本の中のコリアンを見つめなおしている。鶴橋商店街はいつも見慣れているが、面白いのは、ガード下にも広がる市場の存在。闇市の世界をそのままに、という風景で八百屋、魚屋、肉屋、乾物屋、そしてキムチ屋、ありとあらゆる韓国食材が揃う、まさに日本の中の朝鮮。大阪の東の玄関口として戦前から発展してきた下町、鶴橋。大阪府は全国で最も在日韓国・朝鮮人が多く、人口は15万人。その多くが大阪市東部の生野区を中心としたエリアに住んでいる。生野区の人口14万人の4分の1に当たる、3万人程度が住んでいると言われる。
明治、大正時代の大阪は、日本の急激な工業化に伴い大量の労働者が必要となり受け入れた。大阪は大大阪となる。現在の生野区や東大阪市、八尾市あたりには、朝鮮半島から出稼ぎをした人間が大勢住む事となった。終戦直後には210万人程度居たと言われている。その多くが京阪神に住んでいた。現在も在日韓国・朝鮮人の人口は60万人程度居るが、今では在日二世・三世がほとんどで、中には帰化をして日本人になっているものも多く、その実態を掴むのは不可能だ。
鶴橋商店街を通っていつもは通らない反対の方向に行く。やがて大阪市生野区弥栄神社に出る。秋祭りの地車(ダンジリ)の手入れの最中であった。傍で子どもらが鐘と太鼓の練習をしていた(→「秋祭り」画像検索)。彌栄神社とはバス道ひとつ隔てて鎮座しているのが御幸森天神宮。仁徳天皇を主祭神とし、昔の東成郡猪飼野村の氏神、天皇崩御の後、この森に社殿を建立し、天皇の御神霊を奉祀して、御幸森と称したという。このバス道がかっては百済川だった。猪飼野は猪甘津と呼ばれ、 百済川には日本最初の橋が架けられたと言う。天神宮に沿って御幸通商店街がある。反対側に韓国式の立派な門、沖縄の守礼門と似かよっている。商店街は東西で3つの区画に分かれており、コリアタウン色が強いのが御幸通中央商店街。ほとんどの店舗がキムチ屋や肉屋、韓国料理店や屋台料理、民族衣装、それに韓国の音楽CDやDVDを売る店舗となっている。この商店街は大阪に永いこと住んでいるが初めて来た。
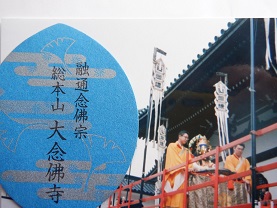


大念佛寺 大阪市平野区平野上町1丁目7-26
毎年5月1日 - 5日に行われる「万部おねり」は大阪市指定無形民俗文化財に指定されている。 25人の菩薩が娑婆(外側)から極楽浄土(本堂)に練り歩き、絢爛豪華な来迎の世界を体現している。
大里喜誠
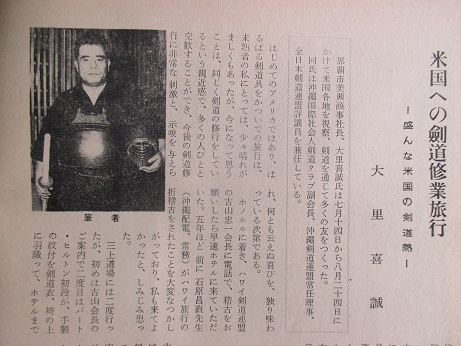
1966年12月『今日の琉球』大里喜誠「米国への剣道修業旅行ー盛んな米国の剣道熱」
1975年10月『琉球新報』大里喜誠「『童景集』出版のころ」
1977年3月25日『沖縄タイムス』大里喜誠「ベトナム人の著した幻の『琉球血涙新書』」
1978年4月20日『琉球新報』大里喜誠「『童景集』『羽地仕置』出版の思い出」
1984年4月14日『沖縄タイムス』大里喜誠「富川」盛武の功績」

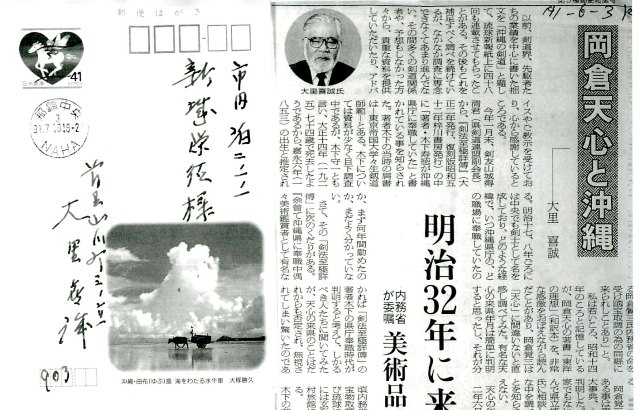
左ー新城栄徳宛の大里喜誠氏ハガキ/1991年6月3日『琉球新報』大里喜誠「岡倉天心と沖縄」
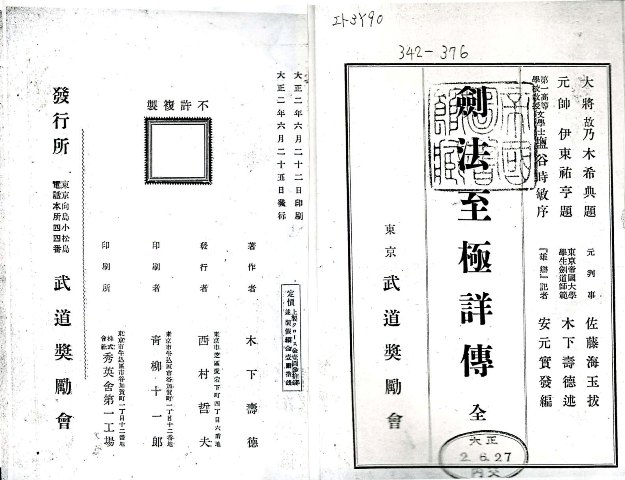
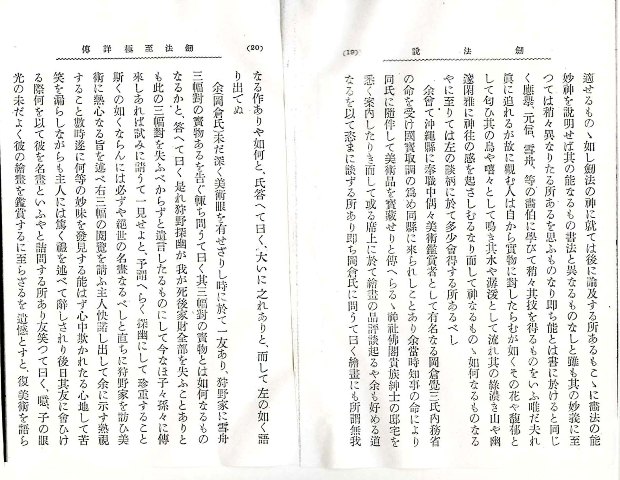
斎藤 陽子 2024-11-27 父との繋がりで、1960年から二ヶ年間、新宿信濃町の大里様の家(お隣が時の総理池田勇人家が有りました)に身を寄せておりました。当時は興南社最後の頃で、出勤前の大里さんは毎朝庭で竹刀を振っていたいらしゃいました。
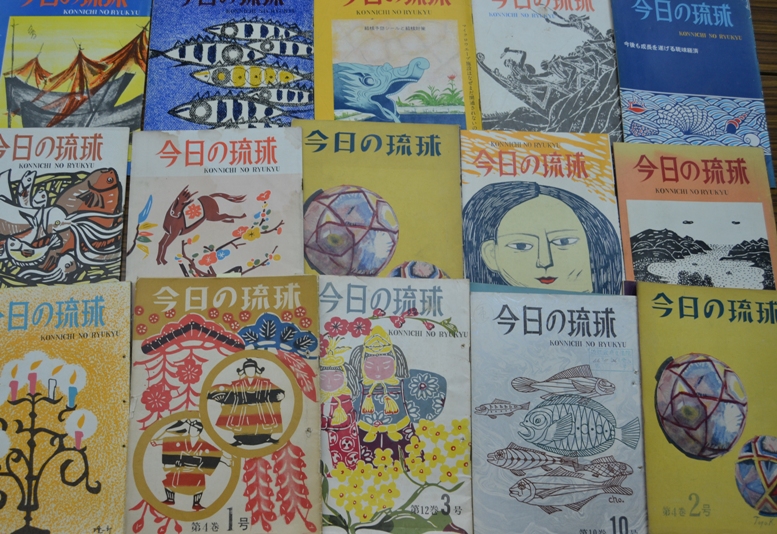
1957年10月 米国民政府渉外報道局出版課『今日の琉球』第1巻第1号
1957年12月『今日の琉球』□表紙(狛犬)・・・・山田真山
1958年3月、『今日の琉球』表紙(風景)・・・大嶺政寛/10月6日『琉球新報』『総仕上げ急ぐ守礼門ー四百年前の姿を再現/楼門に彩色をする琉大生」/10月16日『琉球新報』「きのう盛大に落成式!感激に涙する老婆も」(琉大生の一人が宮城篤正沖縄県立芸術大学学長)。
1959年2月 『今日の琉球』□表紙(樹木)・・・山田真山
1965年1月、『今日の琉球』(表紙写真・守礼門と琉装の女性)/9月、『守礼の光』「琉球文化財はかく保護されたー守礼門」
1969年12月 第13巻第12号□表紙(ブッソウゲ)・・・宮城健盛
1970年1月 第14巻第1号□表紙(イヌ年)・・・大嶺政寛
□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『今日の琉球』」
1959年1月 米国高等弁務官府『守礼の光』創刊号
1963年2月、『守礼の光』「琉球の文化財ー守礼門」
1964年10月、『守礼の光』「ナンシーさんの墨絵修行」(金城安太郎)
1967年1月、『守礼の光』(表紙・守礼門)/5月,『守礼の光』川平朝申「琉球の結核予防対策」(予防シール守礼門)/7月、『今日の琉球』(表紙・紅型模様の守礼門)
1968年1月、『守礼の光』川平朝清「全住民に奉仕する沖縄放送協会」

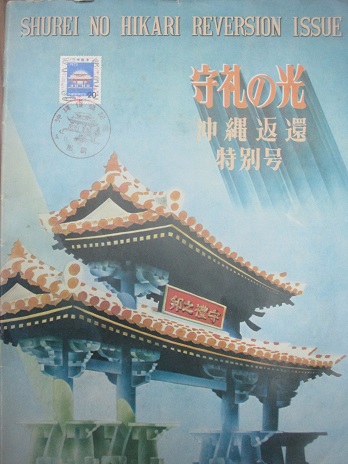
1972年5月、『守礼の光』「沖縄返還特別号」(表紙・守礼門)「琉球政府立博物館ー1966年当時のポール・W・キャラウェー高等弁務官の個人的関心と援助で設立された琉球政府立博物館がなかったとしたら、これらの多くは失われたかあるいは忘れ去られてしまったであろう。この美しい時代建築(博物館)は、那覇市の我那覇昇氏の設計、キャラウェー高等弁務官がこのためわざわざ招いた米国内務省の博物館設計の専門家による技術援助で建てられた」
1972年4月 第159号/1972年5月 最終号
□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『守礼の光』」
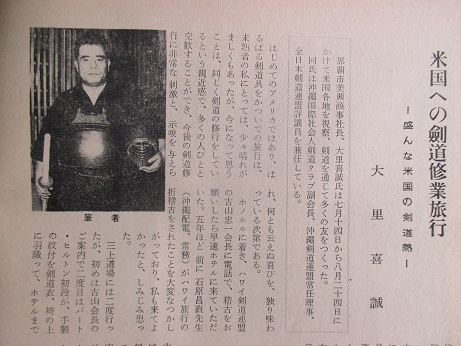
1966年12月『今日の琉球』大里喜誠「米国への剣道修業旅行ー盛んな米国の剣道熱」
1975年10月『琉球新報』大里喜誠「『童景集』出版のころ」
1977年3月25日『沖縄タイムス』大里喜誠「ベトナム人の著した幻の『琉球血涙新書』」
1978年4月20日『琉球新報』大里喜誠「『童景集』『羽地仕置』出版の思い出」
1984年4月14日『沖縄タイムス』大里喜誠「富川」盛武の功績」

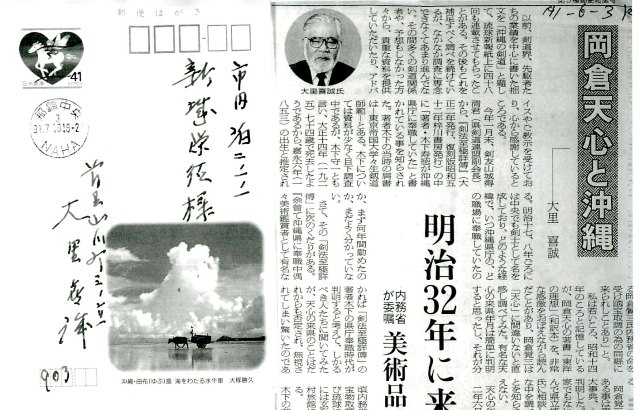
左ー新城栄徳宛の大里喜誠氏ハガキ/1991年6月3日『琉球新報』大里喜誠「岡倉天心と沖縄」
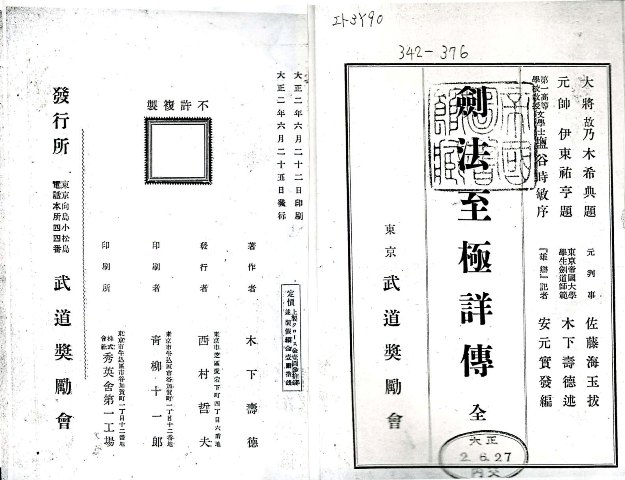
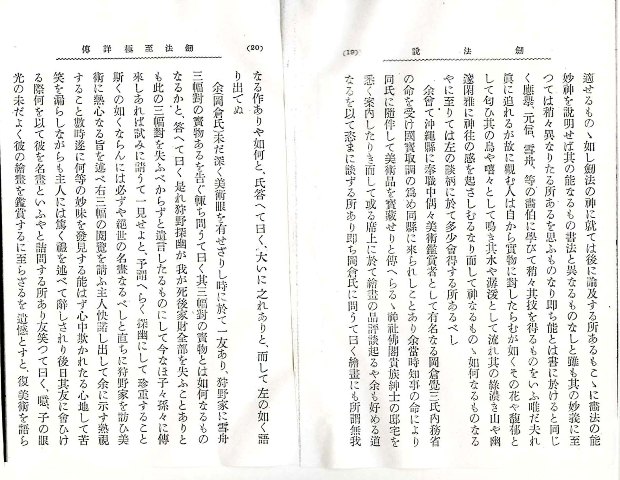
斎藤 陽子 2024-11-27 父との繋がりで、1960年から二ヶ年間、新宿信濃町の大里様の家(お隣が時の総理池田勇人家が有りました)に身を寄せておりました。当時は興南社最後の頃で、出勤前の大里さんは毎朝庭で竹刀を振っていたいらしゃいました。
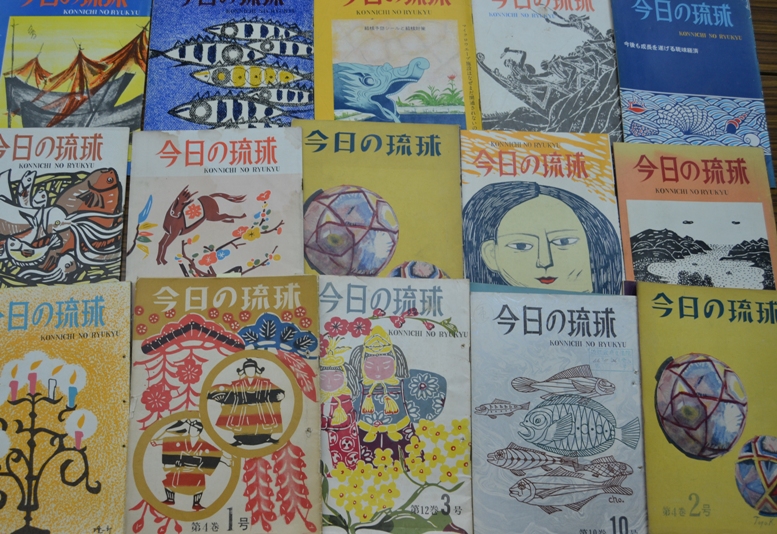
1957年10月 米国民政府渉外報道局出版課『今日の琉球』第1巻第1号
1957年12月『今日の琉球』□表紙(狛犬)・・・・山田真山
1958年3月、『今日の琉球』表紙(風景)・・・大嶺政寛/10月6日『琉球新報』『総仕上げ急ぐ守礼門ー四百年前の姿を再現/楼門に彩色をする琉大生」/10月16日『琉球新報』「きのう盛大に落成式!感激に涙する老婆も」(琉大生の一人が宮城篤正沖縄県立芸術大学学長)。
1959年2月 『今日の琉球』□表紙(樹木)・・・山田真山
1965年1月、『今日の琉球』(表紙写真・守礼門と琉装の女性)/9月、『守礼の光』「琉球文化財はかく保護されたー守礼門」
1969年12月 第13巻第12号□表紙(ブッソウゲ)・・・宮城健盛
1970年1月 第14巻第1号□表紙(イヌ年)・・・大嶺政寛
□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『今日の琉球』」
1959年1月 米国高等弁務官府『守礼の光』創刊号
1963年2月、『守礼の光』「琉球の文化財ー守礼門」
1964年10月、『守礼の光』「ナンシーさんの墨絵修行」(金城安太郎)
1967年1月、『守礼の光』(表紙・守礼門)/5月,『守礼の光』川平朝申「琉球の結核予防対策」(予防シール守礼門)/7月、『今日の琉球』(表紙・紅型模様の守礼門)
1968年1月、『守礼の光』川平朝清「全住民に奉仕する沖縄放送協会」

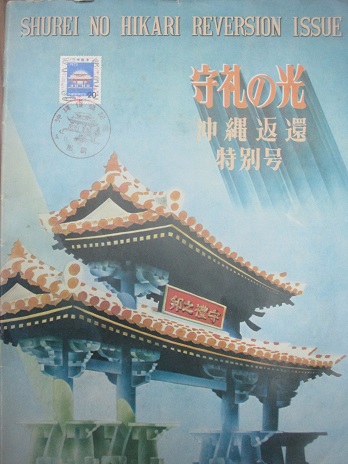
1972年5月、『守礼の光』「沖縄返還特別号」(表紙・守礼門)「琉球政府立博物館ー1966年当時のポール・W・キャラウェー高等弁務官の個人的関心と援助で設立された琉球政府立博物館がなかったとしたら、これらの多くは失われたかあるいは忘れ去られてしまったであろう。この美しい時代建築(博物館)は、那覇市の我那覇昇氏の設計、キャラウェー高等弁務官がこのためわざわざ招いた米国内務省の博物館設計の専門家による技術援助で建てられた」
1972年4月 第159号/1972年5月 最終号
□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『守礼の光』」
02/06: 2020年2月 屋部公子『歌集 遠海鳴り』砂子屋書房
「くにんだなかみち」の標識と龍柱たつ路をうりずんの雨濡らしてゆけり





2020年2月 屋部公子『歌集 遠海鳴り』砂子屋書房(〒101-0047 千代田区内神田3-4-7 ☎03-3256-4708)
謹啓 那覇は台風17号の真っ最中ですが、ご清祥のことと存じます。
この度、土佐高知の石川啄木父子歌碑建立10周年記念短歌大会に応募いたしましたところ、9月14日、佳作受賞となりました。
「 沖縄の 明日をめぐりて いさかいし 父子の日々の悲しき記憶 」
米軍統治下にあった60年代、沖縄返還の運動にはまった私や弟を心配した親心も知らず、親父とぶつかった学生時代。復帰後間もなく親孝行らしいこともせずに60歳の若さで逝かれてしまった苦い思い出。同じことが辺野古新基地や自衛隊配備などで今なお分断対立が繰り返され続けている沖縄の怒りと悲しみを詠ったつもりです。受賞はこの8月で後期高齢になった記念となりましたが、子孫の時代を思うと、縄が穏やかな平和の島になるよう引き続き頑張って行かねばと思う昨今です。 ご笑覧ください。 2019年9月20日 真栄里 泰山 拝
2019年啄木忌・茶話会4月13日午前11時~那覇市西・真教寺
4月13日は、歌人石川啄木(1912年(明治45年)4月13日午前9時30分頃、小石川区久堅町にて肺結核のため死去。妻、父、友人の若山牧水に看取られている。26歳没。戒名は啄木居士→ウィキ)がその短い生涯を閉じた啄木忌。そして、1977年、故国吉真哲氏が那覇市西町の真教寺境内に啄木歌碑を建立、沖縄啄木同好会が発足して42年となります。つきましては久方ぶりに啄木忌を開催したいと存じます。何かと忙しい4月ですが、「私の啄木」をテーマに啄木の歌に関わる思い出やお手持ちの本や資料を紹介し合う茶話会を持ちますので、どうぞ親しい方々お誘い合わせてご参集ください。
場所 那覇市西・真教寺 啄木歌碑前・本堂 〒900-0036 那覇市西2-5-21 電話098-868-0515
会費千円 本や資料など当日ご持参下さい。
主催 沖縄啄木同好会 屋部公子 喜納勝代 宮城義弘 新垣安子 芝憲子
事務局連絡先 真栄里泰山携帯 090-6863-3035
※ 球陽山真教寺は、〒900-0036沖縄県那覇市西2-5-21
電話・fax 098-868-0515 住職 田原法順
宗祖 親鸞聖人 宗派 浄土真宗大谷派 本山 東本願寺(京都府)
本尊 阿弥陀如来


読経 お話ー真宗大谷派真教寺住職 田原大興師


主催者あいさつー沖縄啄木同好会会長・屋部公子さん


1932年4月13日 伊禮肇代議士(屋部公子さんの父)、啄木20年忌(本郷団子坂「菊そば」)に参加




右ー動画撮影する宮城義弘氏ー沖縄県那覇市の真教寺で石川啄木忌が行われました。なぜ沖縄で!?『明星』時代の啄木の友人で沖縄出身の山城正忠が、岩手の1号歌碑 やはらかに柳あおめる 北上の岸邊目に見ゆ 泣けとごとくに
1号歌碑の翌年1923年、沖縄に2号歌碑が建立される計画でした。資金が集まらず実現できませんでした。山城正忠の弟子国吉真哲とその仲間たちが1977年、那覇市の真教寺の境内に建立した啄木歌碑に刻まれたのが冒頭の歌です。歌は1923年時点で、山城正忠と国吉真哲が〝碑に刻むべき歌〟として決めていたものです。
1985年以来の啄木忌となりました。県内外から60人近い啄木研究者・愛好家が参加し、大事な一日となりました。「碓田のぼる氏の大胆な仮説<東海の小島の磯の白砂に>の舞台は沖縄」と題し、私も報告者の1人として立ちました。市民と野党の共闘!啄木が渇望した「新しき時代」!日本国民はいま、確実に手繰り寄せているのではないでしょうか。(宮城義弘)








山城正忠の短冊を手にする平山良明氏、山城正忠自画像を持つ屋部公子さん/左から喜納勝代さん、新城良一氏、平山良明氏


2019年4月14日『盛岡タイムス』「啄木忌法要 宝徳寺で献歌、献吟も」「渋民駅副駅名『啄木のふるさと』産声」


2012年3月『3.11 私たちは忘れない 震災のかたりべ』東北エンタープライズ〇名幸幸照「序文ー・・・ここに謹んで東北の沿岸で亡くなられた多くの御霊とご遺族に啄木の想いを捧げます。 東海の小島の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる・・・」
1900年10月20日ー『東京人類学会雑誌』加藤三吾「沖縄の『オガミ』并に『オモロ』双紙に就て」


1941年10月ー加藤三吾『琉球之研究』文一路社




泰山エッセイ№16(2011年4月)
今年は沖縄のいくつかの小学校で、創立130年記念事業があるようだ。1881年(明治14年)沖縄に小学校が設置された。日本の教育制度は1872年(明治5年)8月3日の学制発布で始まったが、沖縄はそれから9年の遅れだ。沖縄の統合は1879年(明治12年)3月27日の廃藩置県令によるが、それは廃琉置県という近代日本国家初の植民地の獲得であったといえる。中国との朝貢関係にあった沖縄では士族たちの抵抗もあり、入学拒否もあった。
1880年(明治13年)には、アメリカのグラント元大統領の斡旋で、琉球列島を分割して、南島(宮古八重山)は清国に、沖縄本島(中島)以北は日本に帰属させるとの分島改約案で妥結したが、清国の都合で締結にいたらず、沖縄の統合は日清戦争での日本の勝利により決着する。それまでは沖縄では旧慣温存政策がとられた。しかし、教育は急がれた。日本国民としての意識醸成、教化、風俗改良などが統合には必要だったわけだ。それは沖縄の歴史・文化を否定する流れでもあった。以来、方言札、三線や琉歌のなど琉球芸能への偏見と蔑視政策が続き、人類館事件に至った。異国情緒あふれる島・沖縄のイメージは戦後まで続いた。
沖縄の近代教育は、まず学校で沖縄の子どもたちに劣等意識、卑屈さを育てることとなった。歴史家比嘉春潮は、教員時代に「沖縄人に沖縄の歴史を教えるのは危険だ」と聞いたと伝えている。日露戦争を経て昭和の日中戦争のころ、中国系の後裔の久米村出身の若者が「チャンコロ、チャンコロ」といって中国を馬鹿にしたら、長老が「ワッターウヤファーウジどぅやんどう(私たちの祖先だぞ)」とたしなめたという笑えぬ話もある。
沖縄の近代教育はいわる皇民化教育と総括されているが、にもかかわらずその結末が、沖縄戦中の日本軍による虐殺や自決強要があり、戦後27年間の米軍統治下への分離となった歴史も忘れてはなるまい。現在では、沖縄ブームともいえるほどに沖縄の人気が高い。三線の日、しまくとぅばの日の条例化など、沖縄差別や異民族視されることをむしろ地域個性として強調するまでになっている。その底流にあるのは、米軍統治や日米両政府に抗して自らの力で歴史を克服し成長してきたことへの自覚自負、自決権への意志である。それを沖縄のマグマという人もいる。沖縄の近代教育は、こうした苦闘の歴史にこそ意味がある。小学校創立130年記念を単なる祝賀行事に終わらせることなく、こうした底の深い沖縄の教育史を振り返り、共有する機会ともしたいものだ。
真栄里泰山「はがきエッセイ№10」
今日2月3日は旧暦元旦、旧正月。私の旧正年賀状も20年になる。明治のご一新で日本は太陽暦を採用して「脱亜入欧」の近代化をしたが、今でも中国、韓国、台湾、ベトナム、モンゴルなど日本の周辺諸国はほとんどが旧正月(春節)を祝う。この時期アジアでは故郷に向かう十数億人もの人口移動現象が起る。ベトナム戦争のころは「テト(旧正)攻勢」もあった。
沖縄では西暦正月を「大和正月」といった。日本最初の植民地として近代化を大和化として受け止めたわけだ。戦後の米軍統治下でもそれが{祖国日本の文化}として新正月運動が強化され、旧正月はじめ旧暦文化が否定されてきた。しかし、今なお沖縄はお盆、十六日、清明、部落行事など旧暦文化が根強い。今度糸満市では旧暦文化体験隊が誕生し、旧正月の若水とりが復活した。白銀堂での御拝みも多かった。
旧暦はアジアのリズムである。その一員としての沖縄の旧暦文化をもう一度見直したいものだ。
真栄里泰山はがきエッセイ
№21(4月13日) 新しき明日の来るを信ず
四月十三日は啄木忌。今年は石川啄木が逝って百年。岩手の啄木記念館では没後百年記念啄木忌資料展も始まった。啄木は、北海道から沖縄まで全国各地に一六六もの歌碑が建立されており、多くの人に愛されている。苦悶する魂の純粋で率直な表現、志を果たせず屈折する心など、その歌の魅力は誰しもが共感する青春の心そのものだからなのだろう。啄木のみずみずしい感受性は、大逆事件や社会主義への関心、閉塞状況の時代への鋭い批判精神となったが、啄木の魅力は、やはりふるさとへの思いを歌った歌にある。
啄木が「ふるさとの山に向かひて言ふことなし、ふるさとの山はありがたきかな」と歌ったふるさと東北は、今、東日本大震災で未曾有の被害を受け、福島原発災害に苦闘している。災害に黙々と耐え、互いに支え合う東北の人々には国内外から尊敬や賛辞も寄せられているが、愛するふるさとを追われるように避難民として出ていく人、出ていくことができない人など、その揺れ動く心は察するに余りある。しかし、今はこの試練に耐え、乗り越え、未来を見つめていきたい。
一九七七年に建立された日本最南端の沖縄の啄木歌碑には「新しき明日の来るを信ずといふ 自分の言葉に嘘はなけれど―」の歌が刻まれている。この歌は啄木と同人であった山城正忠と国吉真哲(灰雨)の沖縄短歌史における友情と決意の記念の歌であるが、今度は、この啄木の歌を沖縄から東北へのメッセージにしたいと思った次第である。(沖縄啄木同好会)

□写真左から新城栄徳、喜納昌吉氏、中里友豪氏(2021-4-17 南風原の病院で死去、84歳)、詩人花田英三氏、屋部公子さん





2020年2月 屋部公子『歌集 遠海鳴り』砂子屋書房(〒101-0047 千代田区内神田3-4-7 ☎03-3256-4708)
謹啓 那覇は台風17号の真っ最中ですが、ご清祥のことと存じます。
この度、土佐高知の石川啄木父子歌碑建立10周年記念短歌大会に応募いたしましたところ、9月14日、佳作受賞となりました。
「 沖縄の 明日をめぐりて いさかいし 父子の日々の悲しき記憶 」
米軍統治下にあった60年代、沖縄返還の運動にはまった私や弟を心配した親心も知らず、親父とぶつかった学生時代。復帰後間もなく親孝行らしいこともせずに60歳の若さで逝かれてしまった苦い思い出。同じことが辺野古新基地や自衛隊配備などで今なお分断対立が繰り返され続けている沖縄の怒りと悲しみを詠ったつもりです。受賞はこの8月で後期高齢になった記念となりましたが、子孫の時代を思うと、縄が穏やかな平和の島になるよう引き続き頑張って行かねばと思う昨今です。 ご笑覧ください。 2019年9月20日 真栄里 泰山 拝
2019年啄木忌・茶話会4月13日午前11時~那覇市西・真教寺
4月13日は、歌人石川啄木(1912年(明治45年)4月13日午前9時30分頃、小石川区久堅町にて肺結核のため死去。妻、父、友人の若山牧水に看取られている。26歳没。戒名は啄木居士→ウィキ)がその短い生涯を閉じた啄木忌。そして、1977年、故国吉真哲氏が那覇市西町の真教寺境内に啄木歌碑を建立、沖縄啄木同好会が発足して42年となります。つきましては久方ぶりに啄木忌を開催したいと存じます。何かと忙しい4月ですが、「私の啄木」をテーマに啄木の歌に関わる思い出やお手持ちの本や資料を紹介し合う茶話会を持ちますので、どうぞ親しい方々お誘い合わせてご参集ください。
場所 那覇市西・真教寺 啄木歌碑前・本堂 〒900-0036 那覇市西2-5-21 電話098-868-0515
会費千円 本や資料など当日ご持参下さい。
主催 沖縄啄木同好会 屋部公子 喜納勝代 宮城義弘 新垣安子 芝憲子
事務局連絡先 真栄里泰山携帯 090-6863-3035
※ 球陽山真教寺は、〒900-0036沖縄県那覇市西2-5-21
電話・fax 098-868-0515 住職 田原法順
宗祖 親鸞聖人 宗派 浄土真宗大谷派 本山 東本願寺(京都府)
本尊 阿弥陀如来


読経 お話ー真宗大谷派真教寺住職 田原大興師


主催者あいさつー沖縄啄木同好会会長・屋部公子さん


1932年4月13日 伊禮肇代議士(屋部公子さんの父)、啄木20年忌(本郷団子坂「菊そば」)に参加




右ー動画撮影する宮城義弘氏ー沖縄県那覇市の真教寺で石川啄木忌が行われました。なぜ沖縄で!?『明星』時代の啄木の友人で沖縄出身の山城正忠が、岩手の1号歌碑 やはらかに柳あおめる 北上の岸邊目に見ゆ 泣けとごとくに
1号歌碑の翌年1923年、沖縄に2号歌碑が建立される計画でした。資金が集まらず実現できませんでした。山城正忠の弟子国吉真哲とその仲間たちが1977年、那覇市の真教寺の境内に建立した啄木歌碑に刻まれたのが冒頭の歌です。歌は1923年時点で、山城正忠と国吉真哲が〝碑に刻むべき歌〟として決めていたものです。
1985年以来の啄木忌となりました。県内外から60人近い啄木研究者・愛好家が参加し、大事な一日となりました。「碓田のぼる氏の大胆な仮説<東海の小島の磯の白砂に>の舞台は沖縄」と題し、私も報告者の1人として立ちました。市民と野党の共闘!啄木が渇望した「新しき時代」!日本国民はいま、確実に手繰り寄せているのではないでしょうか。(宮城義弘)








山城正忠の短冊を手にする平山良明氏、山城正忠自画像を持つ屋部公子さん/左から喜納勝代さん、新城良一氏、平山良明氏


2019年4月14日『盛岡タイムス』「啄木忌法要 宝徳寺で献歌、献吟も」「渋民駅副駅名『啄木のふるさと』産声」


2012年3月『3.11 私たちは忘れない 震災のかたりべ』東北エンタープライズ〇名幸幸照「序文ー・・・ここに謹んで東北の沿岸で亡くなられた多くの御霊とご遺族に啄木の想いを捧げます。 東海の小島の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる・・・」
1900年10月20日ー『東京人類学会雑誌』加藤三吾「沖縄の『オガミ』并に『オモロ』双紙に就て」


1941年10月ー加藤三吾『琉球之研究』文一路社




泰山エッセイ№16(2011年4月)
今年は沖縄のいくつかの小学校で、創立130年記念事業があるようだ。1881年(明治14年)沖縄に小学校が設置された。日本の教育制度は1872年(明治5年)8月3日の学制発布で始まったが、沖縄はそれから9年の遅れだ。沖縄の統合は1879年(明治12年)3月27日の廃藩置県令によるが、それは廃琉置県という近代日本国家初の植民地の獲得であったといえる。中国との朝貢関係にあった沖縄では士族たちの抵抗もあり、入学拒否もあった。
1880年(明治13年)には、アメリカのグラント元大統領の斡旋で、琉球列島を分割して、南島(宮古八重山)は清国に、沖縄本島(中島)以北は日本に帰属させるとの分島改約案で妥結したが、清国の都合で締結にいたらず、沖縄の統合は日清戦争での日本の勝利により決着する。それまでは沖縄では旧慣温存政策がとられた。しかし、教育は急がれた。日本国民としての意識醸成、教化、風俗改良などが統合には必要だったわけだ。それは沖縄の歴史・文化を否定する流れでもあった。以来、方言札、三線や琉歌のなど琉球芸能への偏見と蔑視政策が続き、人類館事件に至った。異国情緒あふれる島・沖縄のイメージは戦後まで続いた。
沖縄の近代教育は、まず学校で沖縄の子どもたちに劣等意識、卑屈さを育てることとなった。歴史家比嘉春潮は、教員時代に「沖縄人に沖縄の歴史を教えるのは危険だ」と聞いたと伝えている。日露戦争を経て昭和の日中戦争のころ、中国系の後裔の久米村出身の若者が「チャンコロ、チャンコロ」といって中国を馬鹿にしたら、長老が「ワッターウヤファーウジどぅやんどう(私たちの祖先だぞ)」とたしなめたという笑えぬ話もある。
沖縄の近代教育はいわる皇民化教育と総括されているが、にもかかわらずその結末が、沖縄戦中の日本軍による虐殺や自決強要があり、戦後27年間の米軍統治下への分離となった歴史も忘れてはなるまい。現在では、沖縄ブームともいえるほどに沖縄の人気が高い。三線の日、しまくとぅばの日の条例化など、沖縄差別や異民族視されることをむしろ地域個性として強調するまでになっている。その底流にあるのは、米軍統治や日米両政府に抗して自らの力で歴史を克服し成長してきたことへの自覚自負、自決権への意志である。それを沖縄のマグマという人もいる。沖縄の近代教育は、こうした苦闘の歴史にこそ意味がある。小学校創立130年記念を単なる祝賀行事に終わらせることなく、こうした底の深い沖縄の教育史を振り返り、共有する機会ともしたいものだ。
真栄里泰山「はがきエッセイ№10」
今日2月3日は旧暦元旦、旧正月。私の旧正年賀状も20年になる。明治のご一新で日本は太陽暦を採用して「脱亜入欧」の近代化をしたが、今でも中国、韓国、台湾、ベトナム、モンゴルなど日本の周辺諸国はほとんどが旧正月(春節)を祝う。この時期アジアでは故郷に向かう十数億人もの人口移動現象が起る。ベトナム戦争のころは「テト(旧正)攻勢」もあった。
沖縄では西暦正月を「大和正月」といった。日本最初の植民地として近代化を大和化として受け止めたわけだ。戦後の米軍統治下でもそれが{祖国日本の文化}として新正月運動が強化され、旧正月はじめ旧暦文化が否定されてきた。しかし、今なお沖縄はお盆、十六日、清明、部落行事など旧暦文化が根強い。今度糸満市では旧暦文化体験隊が誕生し、旧正月の若水とりが復活した。白銀堂での御拝みも多かった。
旧暦はアジアのリズムである。その一員としての沖縄の旧暦文化をもう一度見直したいものだ。
真栄里泰山はがきエッセイ
№21(4月13日) 新しき明日の来るを信ず
四月十三日は啄木忌。今年は石川啄木が逝って百年。岩手の啄木記念館では没後百年記念啄木忌資料展も始まった。啄木は、北海道から沖縄まで全国各地に一六六もの歌碑が建立されており、多くの人に愛されている。苦悶する魂の純粋で率直な表現、志を果たせず屈折する心など、その歌の魅力は誰しもが共感する青春の心そのものだからなのだろう。啄木のみずみずしい感受性は、大逆事件や社会主義への関心、閉塞状況の時代への鋭い批判精神となったが、啄木の魅力は、やはりふるさとへの思いを歌った歌にある。
啄木が「ふるさとの山に向かひて言ふことなし、ふるさとの山はありがたきかな」と歌ったふるさと東北は、今、東日本大震災で未曾有の被害を受け、福島原発災害に苦闘している。災害に黙々と耐え、互いに支え合う東北の人々には国内外から尊敬や賛辞も寄せられているが、愛するふるさとを追われるように避難民として出ていく人、出ていくことができない人など、その揺れ動く心は察するに余りある。しかし、今はこの試練に耐え、乗り越え、未来を見つめていきたい。
一九七七年に建立された日本最南端の沖縄の啄木歌碑には「新しき明日の来るを信ずといふ 自分の言葉に嘘はなけれど―」の歌が刻まれている。この歌は啄木と同人であった山城正忠と国吉真哲(灰雨)の沖縄短歌史における友情と決意の記念の歌であるが、今度は、この啄木の歌を沖縄から東北へのメッセージにしたいと思った次第である。(沖縄啄木同好会)

□写真左から新城栄徳、喜納昌吉氏、中里友豪氏(2021-4-17 南風原の病院で死去、84歳)、詩人花田英三氏、屋部公子さん
05/27: 1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」
1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」
○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。
その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)
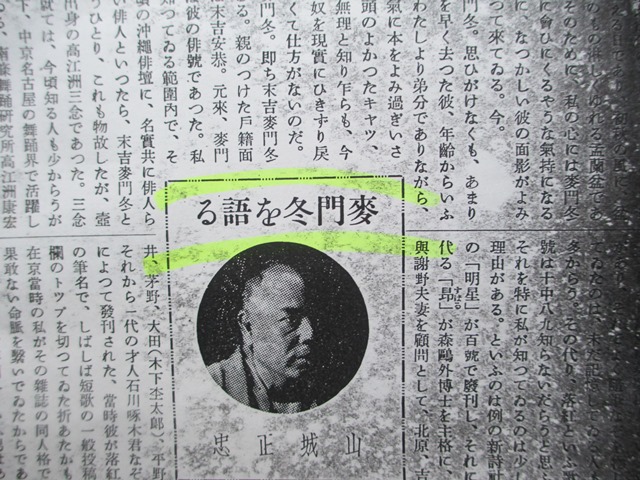
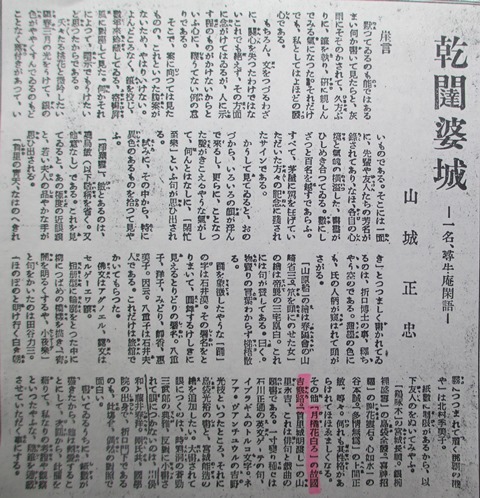
山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。
①灰雨ー國吉眞哲
夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。
「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。
②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア
③山崎省三 やまざき-しょうぞう
1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。
明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク
④石井漠いしいばく
[生]1886.12.25. 秋田,下岩川
[没]1962.1.7. 東京
舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク
⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長
短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。
書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。
1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。
文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。
同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。
以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)



写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝
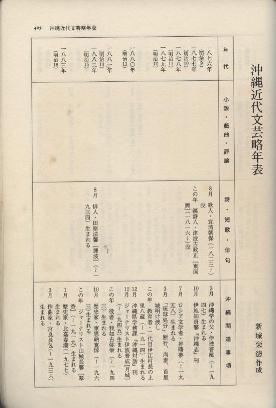
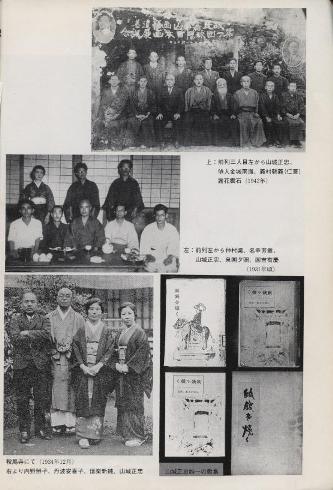
1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」
1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。
2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。
本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。
○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。
その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)
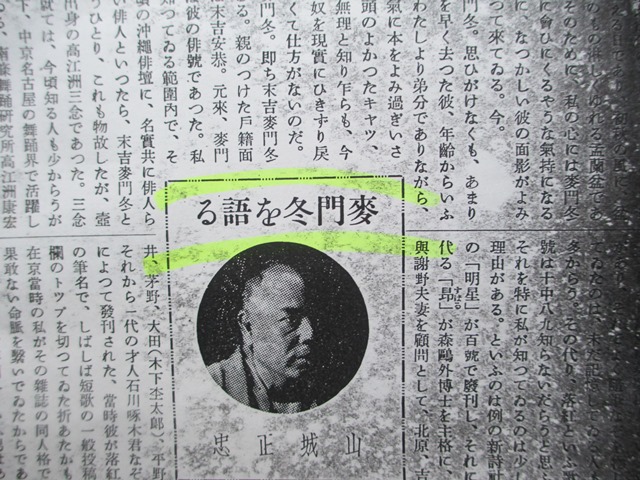
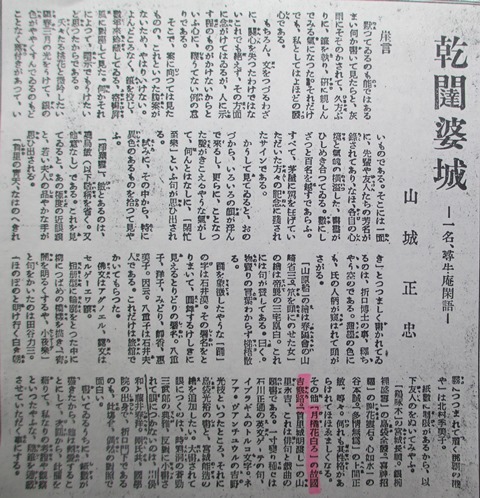
山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。
①灰雨ー國吉眞哲
夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。
「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。
②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア
③山崎省三 やまざき-しょうぞう
1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。
明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク
④石井漠いしいばく
[生]1886.12.25. 秋田,下岩川
[没]1962.1.7. 東京
舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク
⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長
短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。
書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。
1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。
文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。
同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。
以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)



写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝
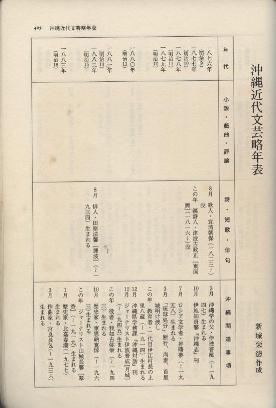
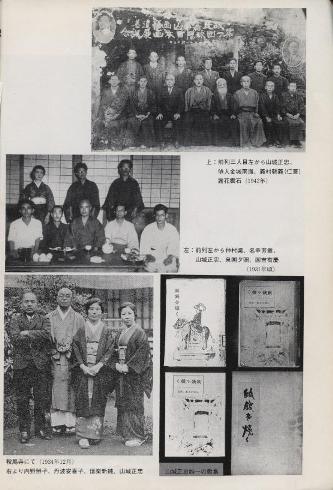
1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」
1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。
2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。
本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。
09/02: 世相ジャパン㊼/【温故知新】
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com
Sputnik 日本2016年3月21日 米NASAの学者達が出した結論によれば、2075年に氷河が溶けるレベルが危機的な境界線を越え、世界の大洋の水位が2メートル上昇するとの事だった。しかし、今回の新しい調査によれば、ニューヨークやロンドンは、今後数十年の間に水中に没してしまう可能性があることが分かった。新聞「デイリー・メイル(Daily Mail)」は、次のように伝えている-「今後50年の間に、世界の大洋の水位は、およそ6から9メートル上昇するかもしれない。ニューヨークが水没するためには、たった1,8メートルの水位の上昇で十分だ。そうなれば上海やベネチア、モルジブやバハマ諸島も当然、間もなく姿を消す事になる。」



2020-9-2 ウークイ、紙銭を燃やす
映画ー1960年10月21封切り 那覇若松国映 国映館「タイムマシン」

左ー2002年の映画『タイムマシン』(The Time Machine)は、2002年のアメリカ映画で、SF映画。ワーナー・ブラザーズ製作。H.G.ウェルズの小説『タイム・マシン』を原作とした映画であるが、物語には大幅な脚色がされている。また、本作は1959年にアメリカで製作されたSF映画『タイム・マシン 80万年後の世界へ』のリメイク作品である。(ウィキ)


1984年1月 ノーマン&ジーン・マッケンジー 村松仙太郎訳『時の旅人―H・G・ウエルズの生涯』早川書房

1983年10月11日ー『琉球新報』新城栄徳「落ち穂『未来』」〇当時の平和美術展で対馬丸遭難の絵に「イカダが多すぎる」と新聞紙上にあった。

中学3年のころ、写真左下のアーサー・C・クラーク 福島正美・川村哲郎訳『未来のプロフィル』早川書房をよく読んだ。このクラークの科学エッセイ集は1958年から1962年にかけてアメリカの『ホリディ』『ホライズン』『サイエンス・ダイジェスト』『プレイボーイ』などに書いた記事をまとめたもの。中に、バートランド・ラッセルの挽歌を引いて「・・・・・あらゆる時代のあらゆる労働も、あらゆる献身も、あらゆる霊感も、あらゆる天才の白昼のごとき明晰さも、太陽系の死と同時に滅亡の運命にあること、そして人類の建設したすべての寺院が滅びゆく宇宙の廃墟の下に埋もれてしまわねばならぬということーこれらすべてのことが、かりにまったく論議の余地がないわけではないにしても、ほとんど確定的であるため、それらを否定しようとするいかなる哲学も存立する望みは持てないのである。 これはまさしく真実であるかもしれない。が、それにもかかわらず、宇宙の滅亡は、思量すべくもない遠い未来に属するので、われわれ現代の種の直接的な関心の対象とはなりえないのだ。」原子に就いて、「物質のエネルギーを解放するために必要だったのは、化学的燃焼に相当する原子の”火”だった。そして、ウラニウムの核分裂こそ、それだったのである。一度、これが発見されれば、原子力の利用は時間の問題だったーただし、もし戦争という圧力がなかったならば、その開発に、ほぼ一世紀はかかったかもしれないけれども。」

アーサー・C・クラークの本
1969年4月ー安田寿明『頭脳会社ーシステム産業のパイオニア』ダイヤモンド社
1970年9月ー野口悠紀雄『シンク・タンク』東洋経済


株式会社ダイケイ 大阪市西区 1997年1月にゼンリングループの一員/ダイケイは伊藤彰彦が1961年に設立した株式会社大阪計算センター(大阪市東区)が1979年8月に株式会社ダイケイに社名変更。
「宇宙船地球号(Spaceship Earth)」という言葉は、20世紀アメリカの建築家・思想家、バックミンスター・フラー(Buckminster Fuller)によって有名になった。彼は1963年、『宇宙船地球号操縦マニュアル(Operating manual for Spaceship Earth)』を著し、宇宙的な視点から地球の経済や哲学を説いた。フラーはその生涯を通して、人類の生存を持続可能なものとするための方法を探りつづけた。
フラーは、地球の歴史とともに蓄えられてきた有限な化石資源を燃やし消費し続けることの愚を説いた。これらの資源は自動車で言えばバッテリーのようなものであり、メイン・エンジンのセルフ・スターターを始動させるために蓄えておかねばならないとした。メイン・エンジンとは風力や水力、あるいは太陽などから得られる放射エネルギーなどの巨大なエネルギーのことであり、これらのエネルギーだけで社会や経済は維持できると主張し、化石燃料と原子力だけで開発を行うことはまるでセルフ・スターターとバッテリーだけで自動車を走らせるようなものだと述べた。彼は人類が石油やウランといった資源に手を付けることなく、地球外から得るエネルギーだけで生活できる可能性がすでにあるのに、現存する経済や政治のシステムではこれが実現不可能であると述べ、変革の必要性を強調した。
宇宙船地球号とは、地球上の資源の有限性や、資源の適切な使用について語るため、地球を閉じた宇宙船にたとえて使う言葉。バックミンスター・フラーが提唱した概念・世界観である。またケネス・E・ボールディング(クエーカー教徒でもあり、今日でいう平和学に大きな関心を寄せていた。妻は平和研究者、平和運動家のエリース・ボールディング)は経済学にこの概念を導入した。 ウィキペディア□戦後の日本においてGHQのボナー・フェラーズ准将が熱心なクエーカー教徒で日本でのクエーカーの布教活動に精力を注いだ。また、信徒のエリザベス・ヴァイニングは後に天皇となる皇太子・明仁の家庭教師を務めた。
新城□2010年12月28日ー妻の実家の読谷楚辺へ行った。父を見舞った帰途、赤犬子宮を訪ねると管理されていないのか入口を車が塞いでいた。釈渚善さんの言うていた大湾の真常寺を思い出し訪ねた。そこで京都全体マップで親鸞聖人ゆかりの地が載っている近畿日本ツーリスト発行の「親鸞聖人ーお念仏の道をたずねて」「大谷光真パンフ」を貰った。(去年暮れに書いたものを移動)





1972年11月 沖青友の会機関誌『石の声』10号〇上原良三「初秋の京都北山へーそもそも諸準備の為、京都に勤める新城君の職場(某食事処食堂)で米や、スープンの調達のついで、コーラやコーヒーを御馳走になったのも一原因かも知れない。」


京都駅 右に蘇鉄/「新福采館本店」「本家第一旭」
帰途、何時ものように京都駅近くの塩小路の中華そば屋による。京都から帰宅する前は必ずよるのが慣わしとなっている。22,3歳のころもよく食べにいった。「新福采館本店」と「本家第一旭」はまだ健在だ。当時は駅前でも中華そばの屋台があった。屋台の暖簾には「贈・中島連合会(→現会津小鉄会)」の文字があったのが今でも印象に残っている。最近では新福も第一旭もネットで賑やかだ。新福はHPも開いて全国展開している。どちらも1947年に店舗を構えた。新福は休みだったので第一旭に入った。青春時代の懐かしい味だ。腹ごしらえも済み、京都市南区東九条にかつて間借していた家を訪ねた。家はそのままだが、冷やし飴を売っていた店はとっくに壊されビルになっていた。向かいに図書館ができていた。


寮は南区/近鉄京都駅の近鉄名店街京風喫茶「紅屋」が職場 寮近くの通り、正面に見えるのが新幹線京都駅




東本願寺

西本願寺 御影堂前の天然記念物「逆さ銀杏」(樹齢推定約380年)幹周/6.5m、樹高/7.0m。大銀杏の木は、低い位置から枝が横にのびていて、根っこを天に広げたような形から「逆さ銀杏」と呼ばれています。1636年に植えられたそうで、1788年の天明の大火や1864年の大火のときには、木から水を吹き出して、大火の前に立ちはだかったことから、「水吹き銀杏」とも呼ばれます。
〇2020-5-17 朝、テレビで「目撃!にっぽん 『番地のなかった街で在日コリアン2世 最後の語り』」でこの地域が報じられていた。今はGoogle地図で東九条を散歩できるが、動画を見るとネトウヨ視点で「東九条コリアタウン」などとやっている。
Sputnik 日本2016年3月21日 米NASAの学者達が出した結論によれば、2075年に氷河が溶けるレベルが危機的な境界線を越え、世界の大洋の水位が2メートル上昇するとの事だった。しかし、今回の新しい調査によれば、ニューヨークやロンドンは、今後数十年の間に水中に没してしまう可能性があることが分かった。新聞「デイリー・メイル(Daily Mail)」は、次のように伝えている-「今後50年の間に、世界の大洋の水位は、およそ6から9メートル上昇するかもしれない。ニューヨークが水没するためには、たった1,8メートルの水位の上昇で十分だ。そうなれば上海やベネチア、モルジブやバハマ諸島も当然、間もなく姿を消す事になる。」



2020-9-2 ウークイ、紙銭を燃やす
映画ー1960年10月21封切り 那覇若松国映 国映館「タイムマシン」

左ー2002年の映画『タイムマシン』(The Time Machine)は、2002年のアメリカ映画で、SF映画。ワーナー・ブラザーズ製作。H.G.ウェルズの小説『タイム・マシン』を原作とした映画であるが、物語には大幅な脚色がされている。また、本作は1959年にアメリカで製作されたSF映画『タイム・マシン 80万年後の世界へ』のリメイク作品である。(ウィキ)


1984年1月 ノーマン&ジーン・マッケンジー 村松仙太郎訳『時の旅人―H・G・ウエルズの生涯』早川書房

1983年10月11日ー『琉球新報』新城栄徳「落ち穂『未来』」〇当時の平和美術展で対馬丸遭難の絵に「イカダが多すぎる」と新聞紙上にあった。

中学3年のころ、写真左下のアーサー・C・クラーク 福島正美・川村哲郎訳『未来のプロフィル』早川書房をよく読んだ。このクラークの科学エッセイ集は1958年から1962年にかけてアメリカの『ホリディ』『ホライズン』『サイエンス・ダイジェスト』『プレイボーイ』などに書いた記事をまとめたもの。中に、バートランド・ラッセルの挽歌を引いて「・・・・・あらゆる時代のあらゆる労働も、あらゆる献身も、あらゆる霊感も、あらゆる天才の白昼のごとき明晰さも、太陽系の死と同時に滅亡の運命にあること、そして人類の建設したすべての寺院が滅びゆく宇宙の廃墟の下に埋もれてしまわねばならぬということーこれらすべてのことが、かりにまったく論議の余地がないわけではないにしても、ほとんど確定的であるため、それらを否定しようとするいかなる哲学も存立する望みは持てないのである。 これはまさしく真実であるかもしれない。が、それにもかかわらず、宇宙の滅亡は、思量すべくもない遠い未来に属するので、われわれ現代の種の直接的な関心の対象とはなりえないのだ。」原子に就いて、「物質のエネルギーを解放するために必要だったのは、化学的燃焼に相当する原子の”火”だった。そして、ウラニウムの核分裂こそ、それだったのである。一度、これが発見されれば、原子力の利用は時間の問題だったーただし、もし戦争という圧力がなかったならば、その開発に、ほぼ一世紀はかかったかもしれないけれども。」

アーサー・C・クラークの本
1969年4月ー安田寿明『頭脳会社ーシステム産業のパイオニア』ダイヤモンド社
1970年9月ー野口悠紀雄『シンク・タンク』東洋経済


株式会社ダイケイ 大阪市西区 1997年1月にゼンリングループの一員/ダイケイは伊藤彰彦が1961年に設立した株式会社大阪計算センター(大阪市東区)が1979年8月に株式会社ダイケイに社名変更。
「宇宙船地球号(Spaceship Earth)」という言葉は、20世紀アメリカの建築家・思想家、バックミンスター・フラー(Buckminster Fuller)によって有名になった。彼は1963年、『宇宙船地球号操縦マニュアル(Operating manual for Spaceship Earth)』を著し、宇宙的な視点から地球の経済や哲学を説いた。フラーはその生涯を通して、人類の生存を持続可能なものとするための方法を探りつづけた。
フラーは、地球の歴史とともに蓄えられてきた有限な化石資源を燃やし消費し続けることの愚を説いた。これらの資源は自動車で言えばバッテリーのようなものであり、メイン・エンジンのセルフ・スターターを始動させるために蓄えておかねばならないとした。メイン・エンジンとは風力や水力、あるいは太陽などから得られる放射エネルギーなどの巨大なエネルギーのことであり、これらのエネルギーだけで社会や経済は維持できると主張し、化石燃料と原子力だけで開発を行うことはまるでセルフ・スターターとバッテリーだけで自動車を走らせるようなものだと述べた。彼は人類が石油やウランといった資源に手を付けることなく、地球外から得るエネルギーだけで生活できる可能性がすでにあるのに、現存する経済や政治のシステムではこれが実現不可能であると述べ、変革の必要性を強調した。
宇宙船地球号とは、地球上の資源の有限性や、資源の適切な使用について語るため、地球を閉じた宇宙船にたとえて使う言葉。バックミンスター・フラーが提唱した概念・世界観である。またケネス・E・ボールディング(クエーカー教徒でもあり、今日でいう平和学に大きな関心を寄せていた。妻は平和研究者、平和運動家のエリース・ボールディング)は経済学にこの概念を導入した。 ウィキペディア□戦後の日本においてGHQのボナー・フェラーズ准将が熱心なクエーカー教徒で日本でのクエーカーの布教活動に精力を注いだ。また、信徒のエリザベス・ヴァイニングは後に天皇となる皇太子・明仁の家庭教師を務めた。
新城□2010年12月28日ー妻の実家の読谷楚辺へ行った。父を見舞った帰途、赤犬子宮を訪ねると管理されていないのか入口を車が塞いでいた。釈渚善さんの言うていた大湾の真常寺を思い出し訪ねた。そこで京都全体マップで親鸞聖人ゆかりの地が載っている近畿日本ツーリスト発行の「親鸞聖人ーお念仏の道をたずねて」「大谷光真パンフ」を貰った。(去年暮れに書いたものを移動)





1972年11月 沖青友の会機関誌『石の声』10号〇上原良三「初秋の京都北山へーそもそも諸準備の為、京都に勤める新城君の職場(某食事処食堂)で米や、スープンの調達のついで、コーラやコーヒーを御馳走になったのも一原因かも知れない。」


京都駅 右に蘇鉄/「新福采館本店」「本家第一旭」
帰途、何時ものように京都駅近くの塩小路の中華そば屋による。京都から帰宅する前は必ずよるのが慣わしとなっている。22,3歳のころもよく食べにいった。「新福采館本店」と「本家第一旭」はまだ健在だ。当時は駅前でも中華そばの屋台があった。屋台の暖簾には「贈・中島連合会(→現会津小鉄会)」の文字があったのが今でも印象に残っている。最近では新福も第一旭もネットで賑やかだ。新福はHPも開いて全国展開している。どちらも1947年に店舗を構えた。新福は休みだったので第一旭に入った。青春時代の懐かしい味だ。腹ごしらえも済み、京都市南区東九条にかつて間借していた家を訪ねた。家はそのままだが、冷やし飴を売っていた店はとっくに壊されビルになっていた。向かいに図書館ができていた。


寮は南区/近鉄京都駅の近鉄名店街京風喫茶「紅屋」が職場 寮近くの通り、正面に見えるのが新幹線京都駅




東本願寺

西本願寺 御影堂前の天然記念物「逆さ銀杏」(樹齢推定約380年)幹周/6.5m、樹高/7.0m。大銀杏の木は、低い位置から枝が横にのびていて、根っこを天に広げたような形から「逆さ銀杏」と呼ばれています。1636年に植えられたそうで、1788年の天明の大火や1864年の大火のときには、木から水を吹き出して、大火の前に立ちはだかったことから、「水吹き銀杏」とも呼ばれます。
〇2020-5-17 朝、テレビで「目撃!にっぽん 『番地のなかった街で在日コリアン2世 最後の語り』」でこの地域が報じられていた。今はGoogle地図で東九条を散歩できるが、動画を見るとネトウヨ視点で「東九条コリアタウン」などとやっている。
05/01: 世相ジャパン
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com





この頃は外出自粛で資料整理に没頭しているが、初老ゆえか気力がなく前みたいに楽しくない。それでも孫娘とメールで遊んでいる。ブログにアップした資料は段ボール箱に入れ倉庫に置く。数年前から沖縄県立博物館・美術館情報センターや那覇市歴史博物館にある資料は手元に置かないようにしている。




若狭龍神/儀間比呂志「戦火の大龍柱」/今回の大火で残った龍柱

大濱 聡 5-22

◎COVID-19 によって起こる症状のほとんどは軽度から中程度であり、特別な治療を受けずに回復します。





5-21娘の車で沖縄県立博物館・美術館、情報センターの仲本美奈子さん/那覇市歴史博物館へ/娘の義父蔵書貰う
天木直人 5-21、この細田発言が沖縄のメディアでどう報道されたかは知らないが、いまこそ沖縄は激怒して、細田議員の更迭を求めるべきだ。この細田発言を黙って見逃すようでは、沖縄は永久に日本政府の沖縄捨て石政策から抜け出せない。それにしても、驚いたのは玉城沖縄県知事の対応だ。テレビでその発言の模様が流されていたが、細田議員の隣に座っていた玉城知事は、その発言を拍手をして聞いていた。
どう思って聞いていたのだろう。本来ならば怒って席を立ってもいいぐらいの暴言だ。振興予算を欲しいから我慢していたのか。だったら、不快感を示して脅かし、見返りに沖縄振興費の倍増を分捕るぐらいの芝居をすべきだ。そもそも沖縄にコロナを持ち込んだA級戦犯が在日米軍ではなかったか。それに文句の一つも言えない日本政府ではないか。繰り返して言う。いまからでも遅くない。沖縄は細田暴言に、日増しに怒りを強めていくべきだ。そして、一刻も早く菅首相に緊急事態宣言を発出させ、バッハ会長が来日した時に中止決定をせざるを得なくさせるのだ。沖縄が菅政権を倒すのだ。沖縄から日本を変えていかなければいけない(了)
関連〇『しんぶん赤旗』2014-12-29 カジノ法案は昨年12月、自民、維新、生活の3党が衆院に提出した議員立法です。推進する超党派のカジノ議連(「国際観光産業振興議員連盟」、会長・細田博之自民党幹事長代行)には自民、民主、維新、公明など各党から200人余の国会議員が参加し、臨時国会での「一気呵成(かせい)の成立を」(細田議連会長)と呼号しました。/『しんぶん赤旗』 2017年4月29日大阪「カジノ万博」賭博では輝く未来は描けない
政府は24日、2025年の国際博覧会(万博)の大阪誘致へむけパリの博覧会事務局(BIE)に立候補を届け出ました。松井一郎大阪府知事(日本維新の会代表)が名乗りを上げた同構想を、安倍晋三政権と財界が後押しします。しかし、カジノ(賭博場)を中核とする統合型リゾート(IR)とセットになっていることや、会場予定地が地震などに脆弱(ぜいじゃく)な人工島・夢洲(ゆめしま)(大阪市此花区)であることなどに、国民、府民から疑問と批判の声
「くろねこの短語」2021年5月20日 愛知県知事リコール署名偽造事件で、とうとう元維新の会の事務局長が逮捕された。しかも、妻と次男も連座という家族ぐるみの犯行というから笑っちまう。でもって、もっと笑っちまうのが、リコール活動団体会長で資金源でもあった、イエス高須君だ。なんとまあ、秘書が大量の署名に指印を押してたことが発覚。こんな言い訳してます。「私は全く知らなかった。本人に確認したところ『田中さんから要請されて悪いことをしてしまった』と話していた。厳しく注意した」
「運動の全責任は僕にある」なんてなんとかのひとつ覚えも繰り返してるようだけど、責任あるってんならどうやって責任をとるのか説明しやがれ、ってなもんです。それにしても、秘書がやったことで自分は知らぬ存ぜぬってのは、イエス高須君もしょせんはペテン師・シンゾーと同じで、潔さのカケラもないポンコツ野郎ってことだ。そして、ポンコツ野郎がもうひとり。イエス高須君と並んでリコール運動の主役のひとりだった名古屋市長のエビフリャー河村君だ。
5-19 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 203人、大阪477人(22)、東京766人
「くろねこの短語」2021年5月19日 (前略)ところで、そのペテン師・シンゾーが、大規模接種センターの予約システムの欠陥を指摘した朝日と毎日に対して、「朝日、毎日は極めて悪質な妨害愉快犯と言える。防衛省の抗議に両社がどう答えるか注目」とツイートして大炎上。国会で100回以上も噓ついたボケナスが何言うか、ってなもんです。
でもって、防衛大臣であるペテン師・シンゾーの愚弟・岸君はと言うと、「今回、朝日新聞出版AERAドット及び毎日新聞の記者が不正な手段により予約を実施した行為は、本来のワクチン接種を希望する65歳以上の方の接種機会を奪い、貴重なワクチンそのものが無駄になりかねない極めて悪質な行為です」とツイッターで罵倒する始末だ。そもそもは、防衛省が欠陥システムを作ったのが問題なんであって、それを検証したメディアに罵詈雑言を浴びせるのは筋違いと言うものだ。この兄にしてこの弟あり、つまり「愚兄愚弟」の典型ってことだ。
「くろねこの短語」2021年5月18日 大規模接種システムに「誰でも何度でも予約可能」の大欠陥が発覚・・・システム運営会社に竹中平蔵の名前が!&河井バカップル買収事件の1億五千万円に「関与せず」(二階自民党幹事長)「当時の選対委員長(甘利明)が広島を担当」(林幹事長代理)!!
「ねとらぼ」5-17 京都タワーホテルの大浴場「京都タワー大浴場~YUU~」が6月30日で閉店することが分かった。〇よく娘を連れて入っていた。


1969年12月『京都タワー十年の歩み』京都産業観光センター

山城 明 いいねうるま市 5月16日 18:01 今日は超暑かったですネ????
5-15 泊郵便局隣のセブンイレブンに行く途中、アベそのまま内閣の応援団の車に遭遇。密約復帰記念日らしい。/ジュンク堂近くのセブンイレブン。/ジュンク堂書店那覇店 B1Fイベント会場 那覇市市制100周年記念誌「那覇100年の物語」発売記念トークショー出演:古塚達郎さん(郷土史家) 宮城一春さん(沖縄県産本ソムリエ) 新城和博さん(有限会社ボーダーインク 編集者)未来へつなぐ、那覇の記憶。「歴史」と「地域」を取り上げ語る。





5-18 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 168人(4)、大阪509人(33)、東京732人
5-17 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 59人(1)、大阪382人(23)、東京419人
5-16 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 78人、大阪620人(15)、東京542人
5-15 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 160人、大阪785人(42)、東京772人


5-14 関西の孫こうたろう誕生日
「朝日新聞デジタル」5-13 沖縄・宮古島への陸上自衛隊の配備をめぐって業者に便宜を図った見返りに現金約650万円を受け取ったとして、沖縄県警は12日、前宮古島市長の下地敏彦容疑者(75)=宮古島市=を収賄の疑いで逮捕し、発表した。また、贈賄の疑いで、ゴルフ場経営の「千代田カントリークラブ」役員、下地藤康容疑者(64)=同市=を逮捕した。
5-14 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 134人、大阪576人(33)、東京854人
5-13 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 126人、大阪761人(33)、東京、1010人
5-12 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 109人(1)、大阪851人(50)、東京、969人(8)




2021-5-12 我が母校/「不屈館」/波上宮




2021-5-12 おもろまち駅前のトックリキワタ/儀保駅
「くろねこの短語」2021年5月11日 「国会騒然」というワードがトレンド入りしたってね。確かに、昨日の国会のカス総理の無様な答弁聞いていると、「騒然」どころか「崩壊」してます。なんてったって、オリンピック開催について問われると、「安心・安全な大会が実現できるよう全力を尽くす」と官僚の作文を読み続けるだけなんだね。あげくに、「頭の中は『五輪ファースト』でコロナ対策が二の次になっている」と攻められると、「大変失礼だと思いますけど。私は五輪ファーストでやってきたことはありません。国民の命とくらしを守る、最優先に取り組んできています」と色をなして反論する始末だ。
そんな国会をメディアは「議論が嚙み合わない」と揶揄してるんだが、これって「議論が噛み合わない」んじゃなくて、カス総理が質問を無視して言いたいことだけをグダグタと垂れ流してるだけなんだね。「国会騒然」の責任は、カス総理ひとりにあるってことだ。昨日の国会の質疑からわかるのは、カス総理にとってこの国の舵取りは荷が重過ぎるってことなんだね。死んだ魚のような目で、態度もおどおどしてるし、そろそろ限界なんじゃないのか。そんなんだから、内閣官房参与がしでかした下衆なツイートにも「個人の主張についての答弁は控える」って逃げちゃうんだね。この内閣官房参与は時計窃盗犯として有名なブルガリ高橋君で、こんなツイートしてました。内閣官房参与は「内閣総理大臣の“相談役”的な立場の非常勤の国家公務員」で、その発言は「個人の主張」で片づけられるものではない。コロナ禍で多くの人が亡くなっているってのに、それを「さざ波」なんて言って笑っていられるろくでなしが内閣官房参与なんだもの、そこにカス政権の本質があるってことなのだ。





2021年5月『琉球』(隔月刊)№82 琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947


.jpg)

5月コロナ禍の中の孫たち
5-11 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 132人、大阪974人(55)、東京、925人
5-10 コロナ禍、沖縄 36人(1)、大阪668人、東京 573人
5-9 コロナ禍、沖縄 103人、大阪875人(19人)、東京 1032人
5-8 コロナ禍、沖縄 93人、大阪1021人(41人)、東京 1121人
第1次安倍内閣では経済政策のブレーンを務めた。自由民主党衆議院議員・中川秀直のブレーンであったともされる。大阪維新の会のブレーンであり、大阪市の特別顧問も務めている。2021年5月9日、新型コロナウイルスの新規感染者数を各国のそれと比較したグラフを用いて「日本はこの程度の『さざ波』。これで五輪中止とかいうと笑笑」と発言した。この発言に対し非難が相次ぎ、「高橋洋一内閣官房参与の更迭を求めます」というハッシュタグが日本のトレンド入りした。高橋を内閣官房参与に任命した菅義偉内閣総理大臣は「個人の主張についての答弁は控える」と発言の是非について言及を避けた。ウィキ

5-8 山城 明いいねうるま市 浜比嘉大橋
「NEWSポストセブン」5-8 かつて読売新聞大阪本社で活躍したジャーナリスト・大谷昭宏氏に、その「政治的生い立ち」から解説してもらった。
吉村さんは、まず即刻、連日のテレビ出演をやめて、一人でも死者を減らすことに全力で取り組んでもらいたい。『ミヤネ屋』の視聴率も下がっているというが、この状況では府民はテレビで吉村さんを見たいわけではないからです。視聴率が取れるからと吉村さんを呼ぶような番組からは視聴者が離れています。いま呼ぶなら学者や医者でしょう。それがあるべき報道の姿です。(略)
しかし、それは言えないから、居酒屋さんが大変だと言って宣言を解除した。吉村さんはマスク会食を訴えましたが、テレビに出てあのように言えば、見る人は「ああすればいいんだ。会食は解禁なんだ」と思うでしょう。吉村さんを「裸の王様」と書いた毎日新聞の記事によれば、吉村さんがマスク会食を言い出してから、居酒屋さんの入店率が50%以上上がったそうです。それがテレビの怖いところで、知事が「マスク会食しましょう」と言えば、そうしてしまう人が増える。結果として感染を広げてしまったのです。
その背景に吉村さんの置かれた政治的な立場があることを府民は知る必要があります。彼は維新の副代表であり、自民党に可愛がってもらわなければ自分たちの存在意義がなくなることを知っている。大阪都構想が府民から否定され、党の一丁目一番地を失った今、維新は自民党にくっついていくしか生き残る道はないのです。だから経済を優先すると言わなければならない。私は、吉村さん個人は経済を後回しにして医療体制を立て直したいと考えているように感じます。しかし、維新という政党、その設立者であり自民党との協調路線を主張した橋下徹さん、そして菅政権の狭間で身動きが取れず、結果的に大阪をボロボロにしてしまったのです。
「くろねこの短語」2021年5月6日 自粛のお願いだけで、具体的な対策は何も打ち出せず、そのくせオリンピック関連のイベントだけはそこのけそこのけで粛々と行われてるんだもの、そりゃあ人出が減らないのも無理はない。でもって、結局は緊急事態宣言延長となりましたとさ。延長期間は2週間から1ケ月ってんだが、いずれにしてもIOC会長のバッカじゃなかったバッハ来日とは重なることになる。緊急事態宣言下のバッハ来日を避けたいための2週間という期間限定ったはずで、バッハ来日でオリンピック開催を確実なものにしたかった顔も頭も貧相なカス総理の思惑は見事にはずれてざまあ~みろ、ってなもんです。(略)
5-7 コロナ禍、沖縄 82人、大阪1005人(50人)、東京900人(6人)
5-6 コロナ禍、沖縄 39人、大阪747人(28人)、東京591人



若狭・大龍柱/さいおんスクエアから牧志駅を見る
「くろねこの短語」2021年5月4日 ああ、やっぱりな、と言うわけで、憲法記念日の昨日、日本会議など改憲勢力の集会「公開憲法フォーラム」に頭も顔も貧相なカス総理がビデオメッセージを寄せて、国民投票法改正案、緊急事態条項、さらには9条への自衛隊明記など、改憲に向けて意欲満々な姿勢を見せつけてくれたってね。(略)なんかもう、取り憑かれちゃってるね。しかし、よくよく考えてみれば、いくら自民党総裁としてのビデオメッセージとは言え、現職の総理大臣が改憲を喚き散らすというのは、それ自体が憲法違反じゃないのか。
憲法99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記されている。つまり、憲法とは天皇を筆頭とする権力者側に遵守義務があるんだね。ペテン師・シンゾーもそうだったけど、総理大臣と自民党総裁を使い分けて、改憲を煽りまくるのは、なんとも姑息な手口ってことだ。加計学園からの献金疑惑の下村君も「今回のコロナを、ピンチをチャンスとして捉えるべきだ」と同じ集会に出席して発言してるんだが、ようするにコロナ禍を奇貨として改憲に欣喜雀躍しているってことだ。腐ってるなあ。緊急事態宣言と緊急事態条項とはまったく別物だっていうのに、メディアもそんな肝心なポイントをスルーして、コロナの恐怖を煽りまくっているから始末に負えない。





2021年5月 俳句同人誌『天荒』69号 編集・発行人 野ざらし延男 〒904-0105 北谷町字吉原726番地の11 電話・FAX098-936-2536





この頃は外出自粛で資料整理に没頭しているが、初老ゆえか気力がなく前みたいに楽しくない。それでも孫娘とメールで遊んでいる。ブログにアップした資料は段ボール箱に入れ倉庫に置く。数年前から沖縄県立博物館・美術館情報センターや那覇市歴史博物館にある資料は手元に置かないようにしている。




若狭龍神/儀間比呂志「戦火の大龍柱」/今回の大火で残った龍柱

大濱 聡 5-22

◎COVID-19 によって起こる症状のほとんどは軽度から中程度であり、特別な治療を受けずに回復します。





5-21娘の車で沖縄県立博物館・美術館、情報センターの仲本美奈子さん/那覇市歴史博物館へ/娘の義父蔵書貰う
天木直人 5-21、この細田発言が沖縄のメディアでどう報道されたかは知らないが、いまこそ沖縄は激怒して、細田議員の更迭を求めるべきだ。この細田発言を黙って見逃すようでは、沖縄は永久に日本政府の沖縄捨て石政策から抜け出せない。それにしても、驚いたのは玉城沖縄県知事の対応だ。テレビでその発言の模様が流されていたが、細田議員の隣に座っていた玉城知事は、その発言を拍手をして聞いていた。
どう思って聞いていたのだろう。本来ならば怒って席を立ってもいいぐらいの暴言だ。振興予算を欲しいから我慢していたのか。だったら、不快感を示して脅かし、見返りに沖縄振興費の倍増を分捕るぐらいの芝居をすべきだ。そもそも沖縄にコロナを持ち込んだA級戦犯が在日米軍ではなかったか。それに文句の一つも言えない日本政府ではないか。繰り返して言う。いまからでも遅くない。沖縄は細田暴言に、日増しに怒りを強めていくべきだ。そして、一刻も早く菅首相に緊急事態宣言を発出させ、バッハ会長が来日した時に中止決定をせざるを得なくさせるのだ。沖縄が菅政権を倒すのだ。沖縄から日本を変えていかなければいけない(了)
関連〇『しんぶん赤旗』2014-12-29 カジノ法案は昨年12月、自民、維新、生活の3党が衆院に提出した議員立法です。推進する超党派のカジノ議連(「国際観光産業振興議員連盟」、会長・細田博之自民党幹事長代行)には自民、民主、維新、公明など各党から200人余の国会議員が参加し、臨時国会での「一気呵成(かせい)の成立を」(細田議連会長)と呼号しました。/『しんぶん赤旗』 2017年4月29日大阪「カジノ万博」賭博では輝く未来は描けない
政府は24日、2025年の国際博覧会(万博)の大阪誘致へむけパリの博覧会事務局(BIE)に立候補を届け出ました。松井一郎大阪府知事(日本維新の会代表)が名乗りを上げた同構想を、安倍晋三政権と財界が後押しします。しかし、カジノ(賭博場)を中核とする統合型リゾート(IR)とセットになっていることや、会場予定地が地震などに脆弱(ぜいじゃく)な人工島・夢洲(ゆめしま)(大阪市此花区)であることなどに、国民、府民から疑問と批判の声
「くろねこの短語」2021年5月20日 愛知県知事リコール署名偽造事件で、とうとう元維新の会の事務局長が逮捕された。しかも、妻と次男も連座という家族ぐるみの犯行というから笑っちまう。でもって、もっと笑っちまうのが、リコール活動団体会長で資金源でもあった、イエス高須君だ。なんとまあ、秘書が大量の署名に指印を押してたことが発覚。こんな言い訳してます。「私は全く知らなかった。本人に確認したところ『田中さんから要請されて悪いことをしてしまった』と話していた。厳しく注意した」
「運動の全責任は僕にある」なんてなんとかのひとつ覚えも繰り返してるようだけど、責任あるってんならどうやって責任をとるのか説明しやがれ、ってなもんです。それにしても、秘書がやったことで自分は知らぬ存ぜぬってのは、イエス高須君もしょせんはペテン師・シンゾーと同じで、潔さのカケラもないポンコツ野郎ってことだ。そして、ポンコツ野郎がもうひとり。イエス高須君と並んでリコール運動の主役のひとりだった名古屋市長のエビフリャー河村君だ。
5-19 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 203人、大阪477人(22)、東京766人
「くろねこの短語」2021年5月19日 (前略)ところで、そのペテン師・シンゾーが、大規模接種センターの予約システムの欠陥を指摘した朝日と毎日に対して、「朝日、毎日は極めて悪質な妨害愉快犯と言える。防衛省の抗議に両社がどう答えるか注目」とツイートして大炎上。国会で100回以上も噓ついたボケナスが何言うか、ってなもんです。
でもって、防衛大臣であるペテン師・シンゾーの愚弟・岸君はと言うと、「今回、朝日新聞出版AERAドット及び毎日新聞の記者が不正な手段により予約を実施した行為は、本来のワクチン接種を希望する65歳以上の方の接種機会を奪い、貴重なワクチンそのものが無駄になりかねない極めて悪質な行為です」とツイッターで罵倒する始末だ。そもそもは、防衛省が欠陥システムを作ったのが問題なんであって、それを検証したメディアに罵詈雑言を浴びせるのは筋違いと言うものだ。この兄にしてこの弟あり、つまり「愚兄愚弟」の典型ってことだ。
「くろねこの短語」2021年5月18日 大規模接種システムに「誰でも何度でも予約可能」の大欠陥が発覚・・・システム運営会社に竹中平蔵の名前が!&河井バカップル買収事件の1億五千万円に「関与せず」(二階自民党幹事長)「当時の選対委員長(甘利明)が広島を担当」(林幹事長代理)!!
「ねとらぼ」5-17 京都タワーホテルの大浴場「京都タワー大浴場~YUU~」が6月30日で閉店することが分かった。〇よく娘を連れて入っていた。


1969年12月『京都タワー十年の歩み』京都産業観光センター

山城 明 いいねうるま市 5月16日 18:01 今日は超暑かったですネ????
5-15 泊郵便局隣のセブンイレブンに行く途中、アベそのまま内閣の応援団の車に遭遇。密約復帰記念日らしい。/ジュンク堂近くのセブンイレブン。/ジュンク堂書店那覇店 B1Fイベント会場 那覇市市制100周年記念誌「那覇100年の物語」発売記念トークショー出演:古塚達郎さん(郷土史家) 宮城一春さん(沖縄県産本ソムリエ) 新城和博さん(有限会社ボーダーインク 編集者)未来へつなぐ、那覇の記憶。「歴史」と「地域」を取り上げ語る。





5-18 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 168人(4)、大阪509人(33)、東京732人
5-17 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 59人(1)、大阪382人(23)、東京419人
5-16 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 78人、大阪620人(15)、東京542人
5-15 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 160人、大阪785人(42)、東京772人


5-14 関西の孫こうたろう誕生日
「朝日新聞デジタル」5-13 沖縄・宮古島への陸上自衛隊の配備をめぐって業者に便宜を図った見返りに現金約650万円を受け取ったとして、沖縄県警は12日、前宮古島市長の下地敏彦容疑者(75)=宮古島市=を収賄の疑いで逮捕し、発表した。また、贈賄の疑いで、ゴルフ場経営の「千代田カントリークラブ」役員、下地藤康容疑者(64)=同市=を逮捕した。
5-14 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 134人、大阪576人(33)、東京854人
5-13 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 126人、大阪761人(33)、東京、1010人
5-12 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 109人(1)、大阪851人(50)、東京、969人(8)




2021-5-12 我が母校/「不屈館」/波上宮




2021-5-12 おもろまち駅前のトックリキワタ/儀保駅
「くろねこの短語」2021年5月11日 「国会騒然」というワードがトレンド入りしたってね。確かに、昨日の国会のカス総理の無様な答弁聞いていると、「騒然」どころか「崩壊」してます。なんてったって、オリンピック開催について問われると、「安心・安全な大会が実現できるよう全力を尽くす」と官僚の作文を読み続けるだけなんだね。あげくに、「頭の中は『五輪ファースト』でコロナ対策が二の次になっている」と攻められると、「大変失礼だと思いますけど。私は五輪ファーストでやってきたことはありません。国民の命とくらしを守る、最優先に取り組んできています」と色をなして反論する始末だ。
そんな国会をメディアは「議論が嚙み合わない」と揶揄してるんだが、これって「議論が噛み合わない」んじゃなくて、カス総理が質問を無視して言いたいことだけをグダグタと垂れ流してるだけなんだね。「国会騒然」の責任は、カス総理ひとりにあるってことだ。昨日の国会の質疑からわかるのは、カス総理にとってこの国の舵取りは荷が重過ぎるってことなんだね。死んだ魚のような目で、態度もおどおどしてるし、そろそろ限界なんじゃないのか。そんなんだから、内閣官房参与がしでかした下衆なツイートにも「個人の主張についての答弁は控える」って逃げちゃうんだね。この内閣官房参与は時計窃盗犯として有名なブルガリ高橋君で、こんなツイートしてました。内閣官房参与は「内閣総理大臣の“相談役”的な立場の非常勤の国家公務員」で、その発言は「個人の主張」で片づけられるものではない。コロナ禍で多くの人が亡くなっているってのに、それを「さざ波」なんて言って笑っていられるろくでなしが内閣官房参与なんだもの、そこにカス政権の本質があるってことなのだ。





2021年5月『琉球』(隔月刊)№82 琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947


.jpg)

5月コロナ禍の中の孫たち
5-11 本日も「さざ波」コロナ禍、沖縄 132人、大阪974人(55)、東京、925人
5-10 コロナ禍、沖縄 36人(1)、大阪668人、東京 573人
5-9 コロナ禍、沖縄 103人、大阪875人(19人)、東京 1032人
5-8 コロナ禍、沖縄 93人、大阪1021人(41人)、東京 1121人
第1次安倍内閣では経済政策のブレーンを務めた。自由民主党衆議院議員・中川秀直のブレーンであったともされる。大阪維新の会のブレーンであり、大阪市の特別顧問も務めている。2021年5月9日、新型コロナウイルスの新規感染者数を各国のそれと比較したグラフを用いて「日本はこの程度の『さざ波』。これで五輪中止とかいうと笑笑」と発言した。この発言に対し非難が相次ぎ、「高橋洋一内閣官房参与の更迭を求めます」というハッシュタグが日本のトレンド入りした。高橋を内閣官房参与に任命した菅義偉内閣総理大臣は「個人の主張についての答弁は控える」と発言の是非について言及を避けた。ウィキ

5-8 山城 明いいねうるま市 浜比嘉大橋
「NEWSポストセブン」5-8 かつて読売新聞大阪本社で活躍したジャーナリスト・大谷昭宏氏に、その「政治的生い立ち」から解説してもらった。
吉村さんは、まず即刻、連日のテレビ出演をやめて、一人でも死者を減らすことに全力で取り組んでもらいたい。『ミヤネ屋』の視聴率も下がっているというが、この状況では府民はテレビで吉村さんを見たいわけではないからです。視聴率が取れるからと吉村さんを呼ぶような番組からは視聴者が離れています。いま呼ぶなら学者や医者でしょう。それがあるべき報道の姿です。(略)
しかし、それは言えないから、居酒屋さんが大変だと言って宣言を解除した。吉村さんはマスク会食を訴えましたが、テレビに出てあのように言えば、見る人は「ああすればいいんだ。会食は解禁なんだ」と思うでしょう。吉村さんを「裸の王様」と書いた毎日新聞の記事によれば、吉村さんがマスク会食を言い出してから、居酒屋さんの入店率が50%以上上がったそうです。それがテレビの怖いところで、知事が「マスク会食しましょう」と言えば、そうしてしまう人が増える。結果として感染を広げてしまったのです。
その背景に吉村さんの置かれた政治的な立場があることを府民は知る必要があります。彼は維新の副代表であり、自民党に可愛がってもらわなければ自分たちの存在意義がなくなることを知っている。大阪都構想が府民から否定され、党の一丁目一番地を失った今、維新は自民党にくっついていくしか生き残る道はないのです。だから経済を優先すると言わなければならない。私は、吉村さん個人は経済を後回しにして医療体制を立て直したいと考えているように感じます。しかし、維新という政党、その設立者であり自民党との協調路線を主張した橋下徹さん、そして菅政権の狭間で身動きが取れず、結果的に大阪をボロボロにしてしまったのです。
「くろねこの短語」2021年5月6日 自粛のお願いだけで、具体的な対策は何も打ち出せず、そのくせオリンピック関連のイベントだけはそこのけそこのけで粛々と行われてるんだもの、そりゃあ人出が減らないのも無理はない。でもって、結局は緊急事態宣言延長となりましたとさ。延長期間は2週間から1ケ月ってんだが、いずれにしてもIOC会長のバッカじゃなかったバッハ来日とは重なることになる。緊急事態宣言下のバッハ来日を避けたいための2週間という期間限定ったはずで、バッハ来日でオリンピック開催を確実なものにしたかった顔も頭も貧相なカス総理の思惑は見事にはずれてざまあ~みろ、ってなもんです。(略)
5-7 コロナ禍、沖縄 82人、大阪1005人(50人)、東京900人(6人)
5-6 コロナ禍、沖縄 39人、大阪747人(28人)、東京591人



若狭・大龍柱/さいおんスクエアから牧志駅を見る
「くろねこの短語」2021年5月4日 ああ、やっぱりな、と言うわけで、憲法記念日の昨日、日本会議など改憲勢力の集会「公開憲法フォーラム」に頭も顔も貧相なカス総理がビデオメッセージを寄せて、国民投票法改正案、緊急事態条項、さらには9条への自衛隊明記など、改憲に向けて意欲満々な姿勢を見せつけてくれたってね。(略)なんかもう、取り憑かれちゃってるね。しかし、よくよく考えてみれば、いくら自民党総裁としてのビデオメッセージとは言え、現職の総理大臣が改憲を喚き散らすというのは、それ自体が憲法違反じゃないのか。
憲法99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記されている。つまり、憲法とは天皇を筆頭とする権力者側に遵守義務があるんだね。ペテン師・シンゾーもそうだったけど、総理大臣と自民党総裁を使い分けて、改憲を煽りまくるのは、なんとも姑息な手口ってことだ。加計学園からの献金疑惑の下村君も「今回のコロナを、ピンチをチャンスとして捉えるべきだ」と同じ集会に出席して発言してるんだが、ようするにコロナ禍を奇貨として改憲に欣喜雀躍しているってことだ。腐ってるなあ。緊急事態宣言と緊急事態条項とはまったく別物だっていうのに、メディアもそんな肝心なポイントをスルーして、コロナの恐怖を煽りまくっているから始末に負えない。





2021年5月 俳句同人誌『天荒』69号 編集・発行人 野ざらし延男 〒904-0105 北谷町字吉原726番地の11 電話・FAX098-936-2536
11/17: 世相ジャパン
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com
11月25日「莫夢忌」
「くろねこの短語」2021年11月25日 衆議院選の茨城6区でヘタレ総理やペテン師・シンゾーの街頭演説に参加した支持者に日当5000円が支給された事件の真相がいまだ解明されてないってのに、同じトラック協会がヘタレ総理のお膝元である広島3区で当選した公明党の鉄オタ・斉藤君の個人演説会に参加した支持者に旅費名目で現金を支給していましたとさ。広島3区はあの河井バカップルによる買収事件の舞台になった選挙区で、なんとも懲りないというか、金金金の選挙が当たり前になっているんだろうね。
週刊文春によれば、参加者への案内状には、手書きで以下のメモが記載されていたそうだ。「各位 当日受付近くで広島北支部のA(注・原文では実名)が旅費をお渡ししますので受付前に対面できる様ご配慮願います。」これって、鉄オタ・斉藤君の事務所が出した案内状なんだよね。そこにトラック協会が手書きのメモを記載しているんだけど、それを見た支持者にすれば鉄オタ・斉藤君の事務所からの旅費支給と思っても不思議じゃない。となると、斉藤事務所側の「広島県トラック協会に個人演説会のご案内を致しました。手書きのメモについては承知しておりません。旅費についても承知しておりません。当方より参加者に対し旅費等の支払いは一切行っておりません」って言い訳は、いかにも苦しい。公明党は遠山デマ彦の違法融資問題もあるし、「平和の党」「福祉の党」の金看板が泣こうというものだ。近いうちに、仏罰があたることだろう。
「くろねこの短語」2021年11月24日 維新のパフォーマンスから始まった文通費問題の火の粉が政党助成金問題に降りかかり、その実体が徐々に明らかになりつつある。そもそも、政党助成金ってのは「余ったら国庫に返すのが原則」なんだね。ところが、維新は「2018~20年の交付金総額約47億円のうち、3割弱をため込み、20年は15億円を超える」ってんで、大ブーメランとなったのは記憶に新しいところ。
では、他の政党はいかがなものかと調べたら、なんと「岸田内閣の閣僚や自民党幹部もタップリと血税を“蓄財”していることが分かった」ってね。先にも触れたように、政党助成金は「余ったら国庫に返すのが原則」だが、なんと「基金」として積み立てれば返納を免れるという裏ワザがありますとさ。こんな具合です。赤旗が岸田内閣と自民党役員の基金のため込み額について調べたところ、岸田首相2638万円、萩生田経産相1259万円、岸防衛相204万円、山際経済再生相99万円と4閣僚が名を連ねる。麻生副総裁1930万円、高木国対委員長1621万円、遠藤選対委員長296万円など党幹部もズラリ。裏ワザのオンパレードである。返納すべき交付金が各議員に流された形だ」
政党助成金ってのは企業献金を無くす代わりにできたはずなのに、いまだに企業献金が続いているのがそもそもの問題なんだね。そこにもてきて、「余ったら国庫に返す」という原則すらも踏みにじって、自分たちの財布に貯金してるってんだから、こういうのを税金ドロボーと言います。政党助成金は政党にとっては濡れ手に粟で、だからこそここを突っ込まれたくないってのが本音なのは間違いない。文通費ほどにメディアが取り上げないのも、そこらあたりを忖度してるからに決まってます。税金を懐に入れて恥じ入る素振りもない自民党や維新の政治屋どもは、MVPの賞金を闘病中の子どもや家族を支援する非営利団体に寄付した大谷翔平の爪の垢でも煎じて飲んでみやがれ。

山城 明 2021-11-24 浜比嘉島比嘉
2021年11月21日15時、ジュンク堂那覇に行く。入って行こうとすると団体が通り過ぎていく。2021年10月 末吉安允著・イラスト湯浅千里『補陀落渡海僧 日秀上人』、著者あとがきに「琉球王国時代に関わった、二人の聖僧(日秀・袋中)の見識を尊重して、琉球を竜宮に例えて物語を作ってみた」とする。首里城正殿を紹介するところでは「末広がりの階段の先端には欄干に繋がるように阿吽の龍の石柱が、御庭を睥睨するが如く屹立」と描写。末吉安允氏と西村貞雄氏

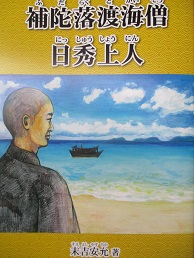


2021年11月20日 ジュンク堂那覇店「知名定寛『琉球沖縄仏教史』榕樹書林 出版記念トークイベント」
〇トーク出演:知名定寛氏、豊見山和幸氏◇「1452年頃の琉球国図には波上熊野権現が記載されている」「熊野信仰も日本・琉球間を往来する海船に搭乗する人々によって伝えられた」
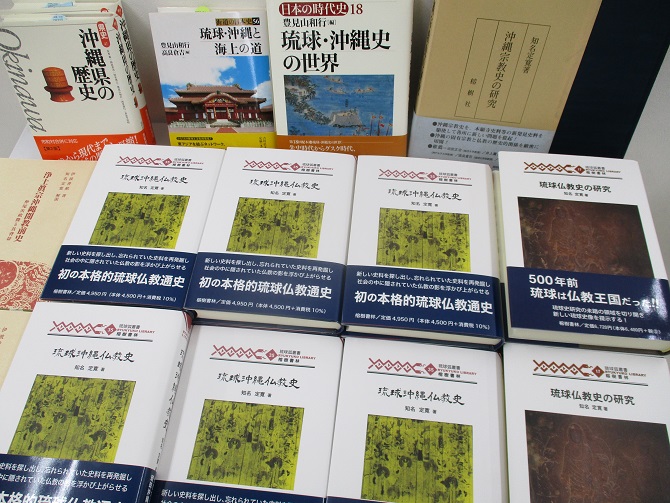



「くろねこの短語」2021年11月20日 (前略)ところで、維新が議員から巻き上げた文通費を寄付するっていうからどこにするのかと思ったら、なんとまあ日本維新の会、つまり党に寄付するんだとさ。これじゃあまるで暴力団の上納金みたいなもんじゃないか。こういうことを恥も外聞もなくやるのが維新なんだね。でもって、その維新の生みの親で、いまも深い関係を保っているお子ちゃま・橋↓君なんだが、「橋下徹をテレビに出すな」がトレンド入りしたってね。維新との濃厚な関係者だってのに、あたかも中立なコメンテーターであるかのように出演をさせるテレビ局の姿勢ってのは、文通費問題にスポットが当たってからというもの特に目に余る。
そんな中、フジテレビ『めざまし8』で、お子ちゃま・橋↓君が一方的に維新の天敵・大石君をなじったってね。大石君は録画出演だったのをいいことに、お子ちゃま・橋↓君の言いたい放題だったったそうで、これって放送法違反なんじゃないのか。こういう欠席裁判まがいのことを平然と仕掛けられるテレビ局って、その存在そのものが犯罪だろう。

大濱 聡 11-15 今、沖縄で――。
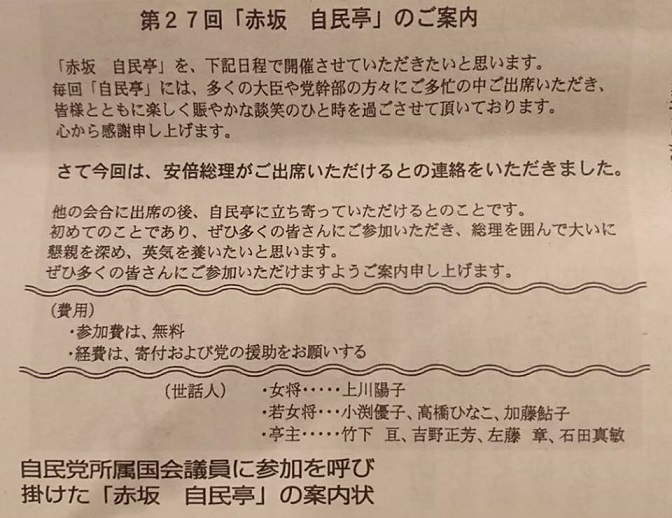
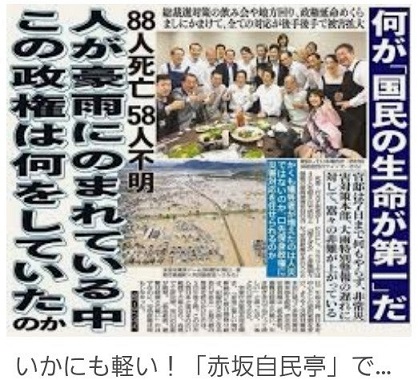
赤坂自民亭事件(あかさかじみんていじけん)とは、平成30年(2018年)7月5日夜に首相の安倍晋三や自民党議員ら約50名が東京・赤坂の議員宿舎で開いた宴会のことである。豪雨警戒の夜であるにも関わらず宴会を開催し、この初動対応の問題が平成30年7月豪雨における被害の拡大につながった。
「くろねこの短語」2021年11月16日 (前略)でもって、大阪のチンピラ市長・松井君も「初当選の議員に支払われる100万円を“特別党費”として徴収した上で、コロナ関連の寄付に充てる考えを示しました」とさ。でもね、これって目的外使用になるんじゃないの。文書交通費ってのはいわば経費で、その原資は税金なんだから、勝手に寄付なんかできるわけがない。ようするに、自分たちで火を付けておいて、その火の粉が飛んできたから慌てて体裁だけ取り繕ってるってことだ。
維新お得意のパフォーマンスも、橋↓の獅子身中の虫・大石君のおかげで返り討ちにあっちゃって、ざまぁ~みろです。こんな維新のパフォーマンスに乗っかって、「民間企業の当たり前が政治の世界に取り入れられるのは大賛成」なんて薄っぺらいコメントしているTBS『Nスタ』のアナウンサーってのもロクなもんじゃありません。
「くろねこの短語」2021年11月12日 (前略)共産党は自ら政党助成金の受け取りを拒否しているんだから、それこそが「身を切る改革」ってもんじゃないのか。今朝もテレビのワイドショーがこの件を取り上げて、あたかも維新の「身を切る改革」の一例であるかのように提灯報道してたけど、だったら維新の議員がやらかした政治資金規正法違反、公職選挙法違反、下半身露出、ひき逃げ、殺傷・殺人未遂未遂etcもちゃんと報道しないといかんだろう。 そもそも、いまだに大阪維新の法律顧問をしているお子ちゃま・橋↓君をコメンテーターに起用していることからしておかしな話なのだ。こんなことしてると、そのうち東京のテレビも大阪みたいに維新と吉本に乗っ取られることになりますよ。
高良 勉 11-13 ハイサイ(拝再)皆さま、お元気でしょうか?本日(13日)12時~13時の間、那覇市県庁前・県民広場で開かれた「宮古島へのミサイル弾頭・弾薬搬入反対の連帯行動」へ参加して、いま帰ってきました。沖縄平和市民連絡会からの緊急な呼びかけだったのですが、約40名~50名が参加して、横断幕やプラカードを掲げてスタンディングをやりました。
私も、急遽指名されて「連帯の挨拶」をさせられました。何よりも、宮古島住民の起ち上がりを支持し連帯すること。奄美群島、沖縄島、宮古島、石垣島、与那国島へ押し寄せ上陸してくる日米軍、日本軍・自衛隊の策謀に反対すること。琉球弧のミサイル・軍事基地化を阻止しよう。沖縄島の起ち上がりが弱いが、共に頑張ろう。という、主旨の挨拶をしました。
明日は、陸上自衛隊が宮古平良港を使って、ミサイル搬入をしようとしています。宮古島住民は、「ミサイルいらない宮古島住民連絡会」を先頭に「抗議声明」を発表し、抗議行動に起ち上がりつつあります。私たちも、その声明に連帯し、できるところから声を上げ、行動しましょう。
11-14 本日もウィルス禍、沖縄1人、大阪18人、東京22人
11-13 本日もウィルス禍、沖縄1人、大阪30人、東京24人
11-12 本日もウィルス禍、沖縄3人(1)、大阪26人、東京22人
11-11 本日もウィルス禍、沖縄3人米1、大阪64(1)人、東京31人(1)
11-10 本日もウィルス禍、沖縄5人、大阪26(1)人、東京25人
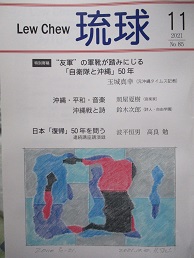
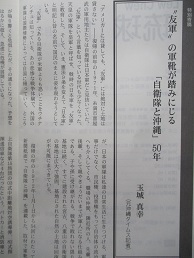


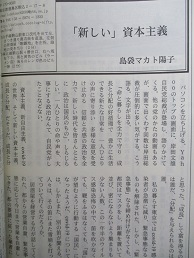
2021年11月『琉球』(隔月刊)№85 琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947 下地ヒロユキ「表紙絵」/玉城真幸「”友軍❞の軍靴が踏みにじる『自衛隊と沖縄50年』」/高良勉「日本『復帰』50年・沖縄解放闘争の継承と克服<2>」/しもじけいこ「宮古IN 宮古市議選終わって……見えてきたこと」/島袋マカト陽子「東京琉球館だより75 『新しい』資本主義」
「くろねこの短語」2021年11月12日 ヘタレ政権は、コロナ禍で困窮する一般大衆労働者諸君を利用して、マイナンバーカードを一気に普及させようって魂胆のようだ。なんでも、マイナンバーカードを新たに取得すれば2万円分のポイントがついてくるんだとか。ところが、その内訳ってのがなんとも手が込んでいて、
マイナンバーカード取得で5000円 健康保険証と紐づけで7500円 預金口座と紐づけで7500円 なんだとさ。共産党の志位君が「給付金をたてに個人情報を差し出せというやり方をとるべきではない」っておかんむりなのもむべなるかなってものです。テレビ朝日の玉川君なんか「「いったいなんなんですか。日本政府がめざしているのは警察国家なんですか」っていきり立ってるってね。
もうここまでくると、なんでもかんでもコロナ禍を口実に、やりたい放題ってことなんだね。加計学園違法献金疑惑の下村君が「「コロナのピンチをチャンスに」と緊急事態条項創設を煽ったのが改めて思い出されてくる。それにしても、たった2万円のポイントでマイナンバーカード普及できると思ってるんだから、一般大衆労働者諸君も舐められたものだ。「マイナンバーカード作ったらお金あげるよ」って言われているようなものなんだね。しかも、その原資ってのは税金ですからね。公明党の山口メンバーは衆議院選で「0歳から高校3年生の年代まで、1人一律10万円を差し上げる」ってまるで自分の金を施すかのように喚いていたものだが、とことん勘違いしちゃってるんだね。そういえば、「税金は国民から吸い上げたもの」って国会答弁したペテン師がいたっけ。なんだ、みんな詐欺師ってことか。
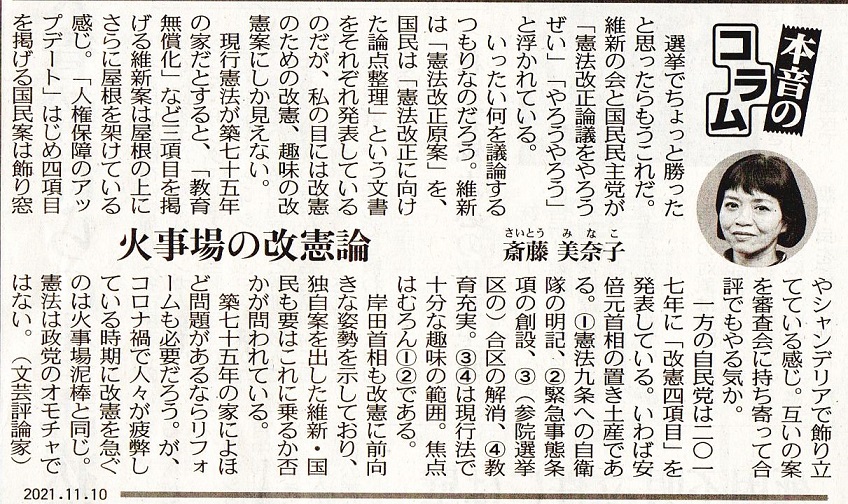
「くろねこの短語」2021年11月8日 国民民主のタマキンの維新へのすり寄りはさすがに目に余る。野党国対委員長会議や野党合同ヒアリングへの不参加を表明したと思ったら、今度は改憲に向けて維新との連携を強化しますとさ。腰の座らない男ってのはわかっていたが、これほどの恥知らずとはねえ。そもそも、維新との連携はついこの前まで否定してたんだよね。さらに、選挙中は改憲なんてのはほとんど争点にもなっていたなかったってのに、選挙の結果か出てたから突然喚きだすってのは定見がないにも程がある。
維新が第3党に躍進して、このままだと党の存続そのものが危ういからなんだろうけど、タマキンの節操のなさってのはなんとも迷惑な話なのだ。こういう信用ならない男があっちについたりこっちについたりすることが、どれだけ野党共闘に悪影響を及ぼしていることか。それにしても、維新のイゾジン吉村ってのも、何様のつもりで改憲を喚き散らすのかねえ。それに乗っかってお調子こいてるタマキンの存在ってのは、まさに百害あって一利なしなんであって、こういうのを国民の敵って言うんでしょうね。
〇東京のフジテレビは、悪名高い在阪メディアの輸入窓口になる気なのかね。https://t.co/L7WFICxGdN—毛ば部とる子 (@kaori_sakai) November 7, 2021/#改憲煽るフジテレビは国民の敵です自民党に「やるなら本気で改憲しろ」とテレビで煽りまくる大阪の吉村知事。現職知事でここまで言うのも異常だが、これを日曜の朝から生でやらせるフジテレビは完全に狂ってる。もはや国民の敵と言っても過言ではない。pic.twitter.com/QJmE2pqi7J
こんな時だからこそ、立憲民主は代表戦でモタモタしてないで、共産党を含めた野党共闘をより進化&深化させるための方針を早いところ打ち出すべきなんだね。その覚悟がないと、来夏の参議院セカは大変なことになりますよ。
「くろねこの短語」2021年11月6日 (前略)もうひとつの「18歳以下に現金10万円」ってのも、なんで給付金に年齢制限なんかつけるかねえ。多くの一般労働者諸君がコロナ禍で疲弊しているんだから、制限なんかつけないで一律給付しなくちゃ意味ないだろう。前回の10万円給付では、ひょっとこ麻生が「貯蓄に回って消費に結びつかない」っていちゃもんつけていたが、それは1回ぽっきりの涙金だからなんだね。アメリカでは3回の現金給付があったけど、3回目でようやく消費に回ったという調査もあるそうだ。
そもそも、18歳以下ってのがよくわからん。公明党の山口メンバーは選挙中から「0歳から高校3年生まで1人一律10万円の現金給付」を喚いていたけど、大学生の困窮が問題になっているってのにそこはどうしてくれるんだ。つまり、事の本質が見えていないってことなんだね。だからこそ、「バラマキ」って言われちゃうわけだ。それにしても、こうした政策の議論が、国会を無視した形で進んでいくってのは、どうなのよ。
『沖縄タイムス』11-16 男性は米軍キャンプ・フォスター所属。ワクチンを2回接種して、症状も出ていなかった。10月30日に米国から成田空港へ到着し、検疫所でPCR検査を受け、陽性が判明。その際、男性は「(米軍)横田基地所属」と申告したという。男性は横田基地には行かず、民間航空機に乗って31日に沖縄へ向かったとみられる。県内の空港に到着後は、知り合いが迎えに来た車で県内の基地に戻った。今月1日に基地内の検査で陽性が分かり、県に連絡があったという。
11月25日「莫夢忌」
「くろねこの短語」2021年11月25日 衆議院選の茨城6区でヘタレ総理やペテン師・シンゾーの街頭演説に参加した支持者に日当5000円が支給された事件の真相がいまだ解明されてないってのに、同じトラック協会がヘタレ総理のお膝元である広島3区で当選した公明党の鉄オタ・斉藤君の個人演説会に参加した支持者に旅費名目で現金を支給していましたとさ。広島3区はあの河井バカップルによる買収事件の舞台になった選挙区で、なんとも懲りないというか、金金金の選挙が当たり前になっているんだろうね。
週刊文春によれば、参加者への案内状には、手書きで以下のメモが記載されていたそうだ。「各位 当日受付近くで広島北支部のA(注・原文では実名)が旅費をお渡ししますので受付前に対面できる様ご配慮願います。」これって、鉄オタ・斉藤君の事務所が出した案内状なんだよね。そこにトラック協会が手書きのメモを記載しているんだけど、それを見た支持者にすれば鉄オタ・斉藤君の事務所からの旅費支給と思っても不思議じゃない。となると、斉藤事務所側の「広島県トラック協会に個人演説会のご案内を致しました。手書きのメモについては承知しておりません。旅費についても承知しておりません。当方より参加者に対し旅費等の支払いは一切行っておりません」って言い訳は、いかにも苦しい。公明党は遠山デマ彦の違法融資問題もあるし、「平和の党」「福祉の党」の金看板が泣こうというものだ。近いうちに、仏罰があたることだろう。
「くろねこの短語」2021年11月24日 維新のパフォーマンスから始まった文通費問題の火の粉が政党助成金問題に降りかかり、その実体が徐々に明らかになりつつある。そもそも、政党助成金ってのは「余ったら国庫に返すのが原則」なんだね。ところが、維新は「2018~20年の交付金総額約47億円のうち、3割弱をため込み、20年は15億円を超える」ってんで、大ブーメランとなったのは記憶に新しいところ。
では、他の政党はいかがなものかと調べたら、なんと「岸田内閣の閣僚や自民党幹部もタップリと血税を“蓄財”していることが分かった」ってね。先にも触れたように、政党助成金は「余ったら国庫に返すのが原則」だが、なんと「基金」として積み立てれば返納を免れるという裏ワザがありますとさ。こんな具合です。赤旗が岸田内閣と自民党役員の基金のため込み額について調べたところ、岸田首相2638万円、萩生田経産相1259万円、岸防衛相204万円、山際経済再生相99万円と4閣僚が名を連ねる。麻生副総裁1930万円、高木国対委員長1621万円、遠藤選対委員長296万円など党幹部もズラリ。裏ワザのオンパレードである。返納すべき交付金が各議員に流された形だ」
政党助成金ってのは企業献金を無くす代わりにできたはずなのに、いまだに企業献金が続いているのがそもそもの問題なんだね。そこにもてきて、「余ったら国庫に返す」という原則すらも踏みにじって、自分たちの財布に貯金してるってんだから、こういうのを税金ドロボーと言います。政党助成金は政党にとっては濡れ手に粟で、だからこそここを突っ込まれたくないってのが本音なのは間違いない。文通費ほどにメディアが取り上げないのも、そこらあたりを忖度してるからに決まってます。税金を懐に入れて恥じ入る素振りもない自民党や維新の政治屋どもは、MVPの賞金を闘病中の子どもや家族を支援する非営利団体に寄付した大谷翔平の爪の垢でも煎じて飲んでみやがれ。

山城 明 2021-11-24 浜比嘉島比嘉
2021年11月21日15時、ジュンク堂那覇に行く。入って行こうとすると団体が通り過ぎていく。2021年10月 末吉安允著・イラスト湯浅千里『補陀落渡海僧 日秀上人』、著者あとがきに「琉球王国時代に関わった、二人の聖僧(日秀・袋中)の見識を尊重して、琉球を竜宮に例えて物語を作ってみた」とする。首里城正殿を紹介するところでは「末広がりの階段の先端には欄干に繋がるように阿吽の龍の石柱が、御庭を睥睨するが如く屹立」と描写。末吉安允氏と西村貞雄氏

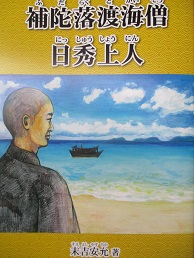


2021年11月20日 ジュンク堂那覇店「知名定寛『琉球沖縄仏教史』榕樹書林 出版記念トークイベント」
〇トーク出演:知名定寛氏、豊見山和幸氏◇「1452年頃の琉球国図には波上熊野権現が記載されている」「熊野信仰も日本・琉球間を往来する海船に搭乗する人々によって伝えられた」
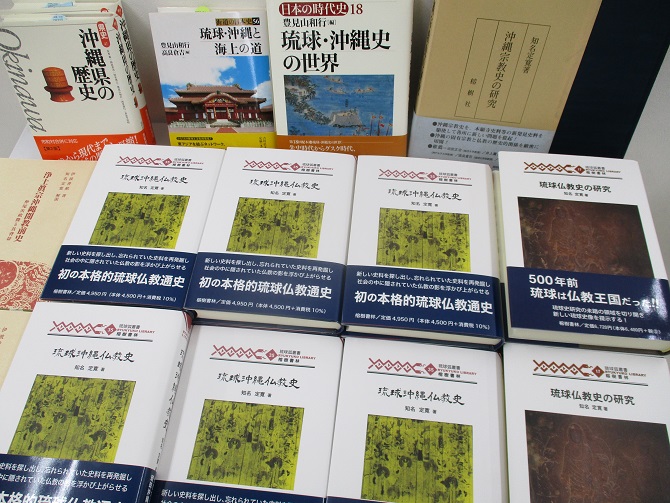



「くろねこの短語」2021年11月20日 (前略)ところで、維新が議員から巻き上げた文通費を寄付するっていうからどこにするのかと思ったら、なんとまあ日本維新の会、つまり党に寄付するんだとさ。これじゃあまるで暴力団の上納金みたいなもんじゃないか。こういうことを恥も外聞もなくやるのが維新なんだね。でもって、その維新の生みの親で、いまも深い関係を保っているお子ちゃま・橋↓君なんだが、「橋下徹をテレビに出すな」がトレンド入りしたってね。維新との濃厚な関係者だってのに、あたかも中立なコメンテーターであるかのように出演をさせるテレビ局の姿勢ってのは、文通費問題にスポットが当たってからというもの特に目に余る。
そんな中、フジテレビ『めざまし8』で、お子ちゃま・橋↓君が一方的に維新の天敵・大石君をなじったってね。大石君は録画出演だったのをいいことに、お子ちゃま・橋↓君の言いたい放題だったったそうで、これって放送法違反なんじゃないのか。こういう欠席裁判まがいのことを平然と仕掛けられるテレビ局って、その存在そのものが犯罪だろう。

大濱 聡 11-15 今、沖縄で――。
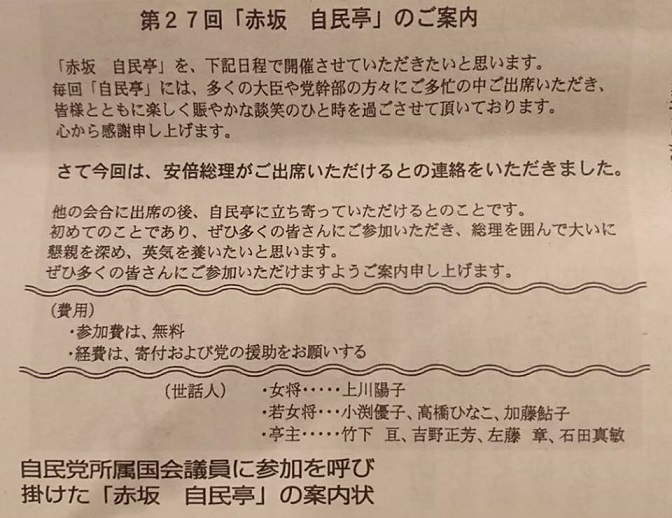
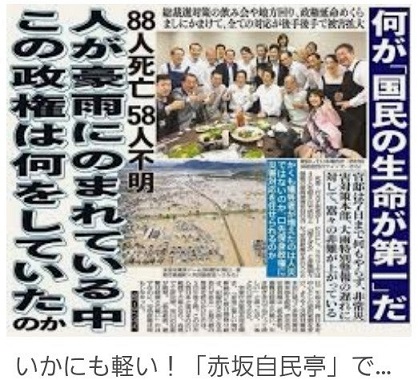
赤坂自民亭事件(あかさかじみんていじけん)とは、平成30年(2018年)7月5日夜に首相の安倍晋三や自民党議員ら約50名が東京・赤坂の議員宿舎で開いた宴会のことである。豪雨警戒の夜であるにも関わらず宴会を開催し、この初動対応の問題が平成30年7月豪雨における被害の拡大につながった。
「くろねこの短語」2021年11月16日 (前略)でもって、大阪のチンピラ市長・松井君も「初当選の議員に支払われる100万円を“特別党費”として徴収した上で、コロナ関連の寄付に充てる考えを示しました」とさ。でもね、これって目的外使用になるんじゃないの。文書交通費ってのはいわば経費で、その原資は税金なんだから、勝手に寄付なんかできるわけがない。ようするに、自分たちで火を付けておいて、その火の粉が飛んできたから慌てて体裁だけ取り繕ってるってことだ。
維新お得意のパフォーマンスも、橋↓の獅子身中の虫・大石君のおかげで返り討ちにあっちゃって、ざまぁ~みろです。こんな維新のパフォーマンスに乗っかって、「民間企業の当たり前が政治の世界に取り入れられるのは大賛成」なんて薄っぺらいコメントしているTBS『Nスタ』のアナウンサーってのもロクなもんじゃありません。
「くろねこの短語」2021年11月12日 (前略)共産党は自ら政党助成金の受け取りを拒否しているんだから、それこそが「身を切る改革」ってもんじゃないのか。今朝もテレビのワイドショーがこの件を取り上げて、あたかも維新の「身を切る改革」の一例であるかのように提灯報道してたけど、だったら維新の議員がやらかした政治資金規正法違反、公職選挙法違反、下半身露出、ひき逃げ、殺傷・殺人未遂未遂etcもちゃんと報道しないといかんだろう。 そもそも、いまだに大阪維新の法律顧問をしているお子ちゃま・橋↓君をコメンテーターに起用していることからしておかしな話なのだ。こんなことしてると、そのうち東京のテレビも大阪みたいに維新と吉本に乗っ取られることになりますよ。
高良 勉 11-13 ハイサイ(拝再)皆さま、お元気でしょうか?本日(13日)12時~13時の間、那覇市県庁前・県民広場で開かれた「宮古島へのミサイル弾頭・弾薬搬入反対の連帯行動」へ参加して、いま帰ってきました。沖縄平和市民連絡会からの緊急な呼びかけだったのですが、約40名~50名が参加して、横断幕やプラカードを掲げてスタンディングをやりました。
私も、急遽指名されて「連帯の挨拶」をさせられました。何よりも、宮古島住民の起ち上がりを支持し連帯すること。奄美群島、沖縄島、宮古島、石垣島、与那国島へ押し寄せ上陸してくる日米軍、日本軍・自衛隊の策謀に反対すること。琉球弧のミサイル・軍事基地化を阻止しよう。沖縄島の起ち上がりが弱いが、共に頑張ろう。という、主旨の挨拶をしました。
明日は、陸上自衛隊が宮古平良港を使って、ミサイル搬入をしようとしています。宮古島住民は、「ミサイルいらない宮古島住民連絡会」を先頭に「抗議声明」を発表し、抗議行動に起ち上がりつつあります。私たちも、その声明に連帯し、できるところから声を上げ、行動しましょう。
11-14 本日もウィルス禍、沖縄1人、大阪18人、東京22人
11-13 本日もウィルス禍、沖縄1人、大阪30人、東京24人
11-12 本日もウィルス禍、沖縄3人(1)、大阪26人、東京22人
11-11 本日もウィルス禍、沖縄3人米1、大阪64(1)人、東京31人(1)
11-10 本日もウィルス禍、沖縄5人、大阪26(1)人、東京25人
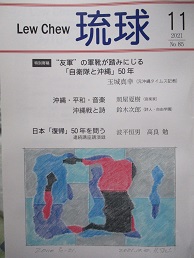
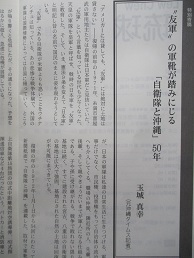


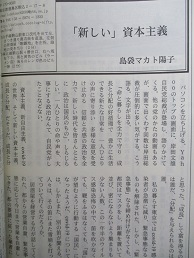
2021年11月『琉球』(隔月刊)№85 琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947 下地ヒロユキ「表紙絵」/玉城真幸「”友軍❞の軍靴が踏みにじる『自衛隊と沖縄50年』」/高良勉「日本『復帰』50年・沖縄解放闘争の継承と克服<2>」/しもじけいこ「宮古IN 宮古市議選終わって……見えてきたこと」/島袋マカト陽子「東京琉球館だより75 『新しい』資本主義」
「くろねこの短語」2021年11月12日 ヘタレ政権は、コロナ禍で困窮する一般大衆労働者諸君を利用して、マイナンバーカードを一気に普及させようって魂胆のようだ。なんでも、マイナンバーカードを新たに取得すれば2万円分のポイントがついてくるんだとか。ところが、その内訳ってのがなんとも手が込んでいて、
マイナンバーカード取得で5000円 健康保険証と紐づけで7500円 預金口座と紐づけで7500円 なんだとさ。共産党の志位君が「給付金をたてに個人情報を差し出せというやり方をとるべきではない」っておかんむりなのもむべなるかなってものです。テレビ朝日の玉川君なんか「「いったいなんなんですか。日本政府がめざしているのは警察国家なんですか」っていきり立ってるってね。
もうここまでくると、なんでもかんでもコロナ禍を口実に、やりたい放題ってことなんだね。加計学園違法献金疑惑の下村君が「「コロナのピンチをチャンスに」と緊急事態条項創設を煽ったのが改めて思い出されてくる。それにしても、たった2万円のポイントでマイナンバーカード普及できると思ってるんだから、一般大衆労働者諸君も舐められたものだ。「マイナンバーカード作ったらお金あげるよ」って言われているようなものなんだね。しかも、その原資ってのは税金ですからね。公明党の山口メンバーは衆議院選で「0歳から高校3年生の年代まで、1人一律10万円を差し上げる」ってまるで自分の金を施すかのように喚いていたものだが、とことん勘違いしちゃってるんだね。そういえば、「税金は国民から吸い上げたもの」って国会答弁したペテン師がいたっけ。なんだ、みんな詐欺師ってことか。
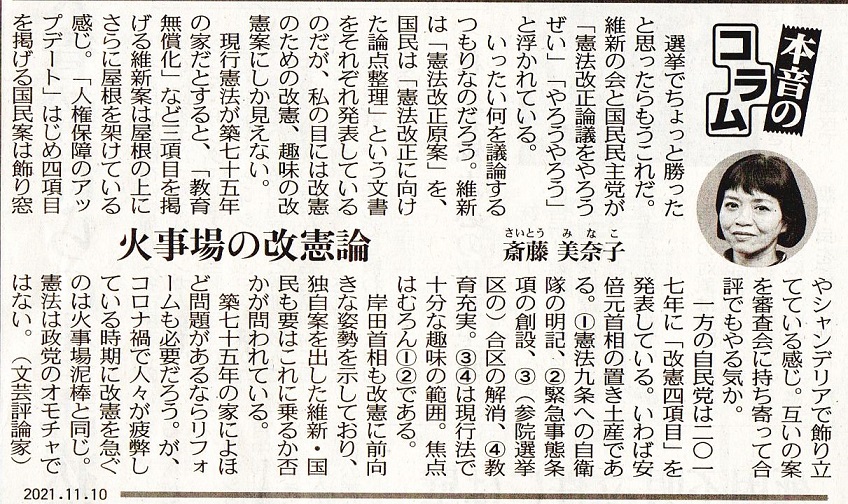
「くろねこの短語」2021年11月8日 国民民主のタマキンの維新へのすり寄りはさすがに目に余る。野党国対委員長会議や野党合同ヒアリングへの不参加を表明したと思ったら、今度は改憲に向けて維新との連携を強化しますとさ。腰の座らない男ってのはわかっていたが、これほどの恥知らずとはねえ。そもそも、維新との連携はついこの前まで否定してたんだよね。さらに、選挙中は改憲なんてのはほとんど争点にもなっていたなかったってのに、選挙の結果か出てたから突然喚きだすってのは定見がないにも程がある。
維新が第3党に躍進して、このままだと党の存続そのものが危ういからなんだろうけど、タマキンの節操のなさってのはなんとも迷惑な話なのだ。こういう信用ならない男があっちについたりこっちについたりすることが、どれだけ野党共闘に悪影響を及ぼしていることか。それにしても、維新のイゾジン吉村ってのも、何様のつもりで改憲を喚き散らすのかねえ。それに乗っかってお調子こいてるタマキンの存在ってのは、まさに百害あって一利なしなんであって、こういうのを国民の敵って言うんでしょうね。
〇東京のフジテレビは、悪名高い在阪メディアの輸入窓口になる気なのかね。https://t.co/L7WFICxGdN—毛ば部とる子 (@kaori_sakai) November 7, 2021/#改憲煽るフジテレビは国民の敵です自民党に「やるなら本気で改憲しろ」とテレビで煽りまくる大阪の吉村知事。現職知事でここまで言うのも異常だが、これを日曜の朝から生でやらせるフジテレビは完全に狂ってる。もはや国民の敵と言っても過言ではない。pic.twitter.com/QJmE2pqi7J
こんな時だからこそ、立憲民主は代表戦でモタモタしてないで、共産党を含めた野党共闘をより進化&深化させるための方針を早いところ打ち出すべきなんだね。その覚悟がないと、来夏の参議院セカは大変なことになりますよ。
「くろねこの短語」2021年11月6日 (前略)もうひとつの「18歳以下に現金10万円」ってのも、なんで給付金に年齢制限なんかつけるかねえ。多くの一般労働者諸君がコロナ禍で疲弊しているんだから、制限なんかつけないで一律給付しなくちゃ意味ないだろう。前回の10万円給付では、ひょっとこ麻生が「貯蓄に回って消費に結びつかない」っていちゃもんつけていたが、それは1回ぽっきりの涙金だからなんだね。アメリカでは3回の現金給付があったけど、3回目でようやく消費に回ったという調査もあるそうだ。
そもそも、18歳以下ってのがよくわからん。公明党の山口メンバーは選挙中から「0歳から高校3年生まで1人一律10万円の現金給付」を喚いていたけど、大学生の困窮が問題になっているってのにそこはどうしてくれるんだ。つまり、事の本質が見えていないってことなんだね。だからこそ、「バラマキ」って言われちゃうわけだ。それにしても、こうした政策の議論が、国会を無視した形で進んでいくってのは、どうなのよ。
『沖縄タイムス』11-16 男性は米軍キャンプ・フォスター所属。ワクチンを2回接種して、症状も出ていなかった。10月30日に米国から成田空港へ到着し、検疫所でPCR検査を受け、陽性が判明。その際、男性は「(米軍)横田基地所属」と申告したという。男性は横田基地には行かず、民間航空機に乗って31日に沖縄へ向かったとみられる。県内の空港に到着後は、知り合いが迎えに来た車で県内の基地に戻った。今月1日に基地内の検査で陽性が分かり、県に連絡があったという。
12/16: 世相ジャパン
加藤茂数をウイキで検索したら◇加藤茂数(かとう しげかず)は、『気象と災害』(1949年、三省堂)で、豆台風を直径200km以下の台風としているが、そこで言う直径が、暴風域か等圧線か或いは他のものであるかについては言及していない。1950年頃までは暴風域についても定義は明確ではなく、平均風速10m以上、20m以上などの値が用いられたし、大谷東平は『台風の話』においても、室戸台風の規模を示すのに平均風速5m以上の範囲を用いているという具合である。〇昭和10年6月『天気と気候』加藤茂數「琉球気象考」








「しまくとぅば鼎談」12月25日(土)おもろまちの沖縄県立博物館・美術館にて/左から屋嘉宗彦氏(法政大学名誉教授)、照屋隆司氏(開発屋でぃきたん代表)、金城美奈子さん/左から屋嘉宗彦氏、伊佐眞一氏、照屋 隆司氏




沖縄県立博物館・美術館 12-25 ”沖縄オペラアカデミーヴォイスアンサンブル”のメンバーによるクリスマス特別コンサート
『琉球新報』12-27 玉城デニー知事は26日、新型コロナウイルスの大規模感染が発生している米軍キャンプ・ハンセンなどから24、25日に、米兵らが基地間の連絡バスで本島中部のキャンプ瑞慶覧まで移動し、基地の外に出ていたことを明らかにした。
「くろねこの短語」2021年12月26日 昨日のTBS『報道特集』は検証第3弾として、「東京五輪の高額物品費」「これで幕引き?森友問題とウィシュマさん事件の行方」を取り上げ、なかなかに見応えがあった。こうした検証を続けていくことがジャーナリズムの基本中の基本であり、調査報道がどれほど重要かということを改めて教えてくれた。オリンピックについては、既に喉元過ぎればでほとんど忘れかけられいるけど、たとえば2倍に膨れ上がった開催経費の説明責任はまだ果たされていない。それどころか、フリップ小池君なんか「レガシー」なんて言葉を吹聴しまくって反省のカケラもない。
ああ、それなのに、「東京オリンピック開催してよかった」という意見が50%を超えてるんだね。そんな忘れやすい国民だもの、そりゃあペテン師・シンゾーごときにコロッと騙されるわけだ。森友問題では、やっぱり「認諾」に尽きますね。番組中で、法律の専門家が「訴訟上の信義に反する不意打ち」と指摘していたけど、まさにおっしゃる通り。非公開の協議中に国側の代理人から「認諾」の言葉が発せられた時には裁判官も虚を突かれたそうだ。それほどの裏技というか、盲点だったということだ。
さらに、赤木雅子さんの抗議に、国側の代理人はひとりとして目を合わせなかたっそうで、後ろめたいという自覚はあったってことなんだろうね。そそくさと立ち去る姿が目に浮かぶようだ。オリンピックも森友問題もウィシュマさん事件も、まだ終わってはいない。同じ批判的立場で権力を追及し続けるのがジャーナリズムの使命なんだから、「野党は批判ばかり」と責め立てる暇があったら、メディアは自らが先頭に立って戦ってみやがれ。
『琉球新報』12-25 名護市辺野古移設に向けた工事の関係者3人が22、23の両日、相次いで新型コロナウイルスに感染した/ABEMA TIMES キャンプ・ハンセン所属の伍長、ジャレット・ミックマン容疑者(24)はきょう午前0時ごろ、那覇市の歓楽街で、ヘルメットをかぶらずに原付きバイクで同僚の20代の海兵隊員と2人乗りをしていたところ、警察官に見つかった。飲酒検査の結果、基準値の約3倍のアルコールが検出された。




彫刻家の西村貞雄さん(琉球大学名誉教授)とローゼル川田さん(水彩画家・エッセイスト)の2人展「見えるもの見えたもの見えないもの」が18日から那覇市牧志のギャラリー・サハスラーラで開かれる。ローゼルさんは本紙連載「琉球風画 今はいにしえ」の掲載作品などを展示。→『沖縄タイムス』/2021年12月24日 ローゼル川田氏、友寄貞丸氏、美佐子さん/右下の人物はローゼル川田氏の先祖・董氏屋富祖仲辰
米山 隆一 12-24 あの和泉補佐官が大阪府市の特別顧問にご就任です。維新は恰好のいい言葉とは裏腹に、安倍・菅氏の「秘密兵器」となる事で中央官庁と深い関係を築き、今の立場を得てきた「新規取得既得権益政党」です。彼らの主張する新自由主義は既に古く、時代にそぐうものではありません。




2021年12月24日 なるみ堂の翁長良明さんと同行し、民芸酒場おもろ「我那覇純都絵画展ーだんじゅかりゆしー」/〇おもろの新垣亮氏/〇我那覇純都さん、真喜志きさ子さん




12-23 小雨 国際通り/市場本通り/おもろまち駅/東急ハンズ那覇メインプレイス店




2021年12月19日 沖縄県立博物館・美術館で孫たちと遊ぶ




2021年12月19日 栄町市場で「平和なミャンマー文化祭」
「くろねこの短語」2021年12月24日 いやあ、この一報が入った瞬間、耳を疑っちまった。虚構新聞ですら想定外の出来事じゃないのか。なんてったって、行政とそれを監視すべき報道機関(ジャーナリズム)が提携するってんだから、そりゃあ目が点にもなろうというものだ。読売新聞は「ジャーナリズムを辞める」って宣言したようなものだろう。これからは、読売新聞が取り上げる維新のニュースってのは、全て眉に唾つけてから読まないとダメってことだ。時あたかも、カジノをめぐる土壌改良問題が持ち上がっている折、大阪府と読売新聞の提携って、なんとも香ばしい。これはもう、読売新聞は大阪府(=維新)の広報に成り下がったことを意味している。ひょっとしたら、産経新聞も自民党と提携しましたって言い出したりして。
「くろねこの短語」2021年12月23日 山積みになったアベノマスクが年内に廃棄されるってね。その数、実に8000万枚以上とかで、なんとそのうちの15%にあたる約1100万枚が不良品だったってさ。これって、民間の取引だったら、納入業者は当然、その責任を追及されるはずだ。ああ、それなのに、どうやらそこはねぐって、さっさと廃棄して、一件落着にしようってんだから、ベラボーな話なのだ。しかも、不良品が発覚した検査に、▼厚生労働省による検品費用におよそ6億9200万円、▼その後に納入事業者が実施した検品費用におよそ10億7000万円、▼検品に時間がかかったことに伴う追加費用におよそ3億3000万円もの大金が注ぎ込まれたとか。いやあ、これすべて税金ですからね。
さらに、廃棄するにも経費がかかるわけで、すべての責任はペテン師・シンゾーにあるんだからこ奴に払わせたらどうなのかねえ。ていうか、この男自身が不良品なんだから、アベノマスクと一緒に廃棄処分にしたらどうだ。とうとうアベノマスク8000万枚以上が強制廃棄されることになった。検品したら約1100万枚が不良品だったから捨てるしかない。その検査などに20億円以上かけたらしい。統計的には1000枚調べれば十分なのに何たる無駄遣い。殆ど使われなかったアベノマスクに500億円かけた責任は誰が取るのか。
ところで、オミクロン株の市中感染が確認されたってね。それも大阪で。イソジン吉村君のコロナ対策を御用メディアがヨイショしてたけど、結局のところ大阪っていまも最悪の感染地域なんだよね。AIの試算では、このままいくと東京での新規感染者は年明けには3000人を超えるとか。大阪も同じような推移を辿るとすると、デルタ株で医療崩壊した時の二の舞になりますよ。
「くろねこの短語」2021年12月20日 大阪のビル放火は、なんとも痛ましい事件だ。出口がひとつのペンシルビルでは、逃げようがありませんからね。それにしても、24人死亡という大惨事にも関わらず、イソジン吉村君もチンピラ松井君もまったく沈黙したままってのはどうなんだろうね。そう言えば、森友訴訟の「認諾」についてもこの2人はスルーしてるんだが、ようするに自分たちの存在をアピールできることには煽情的な言葉を喚き散らしてでも介入するけど、市民がどうなろうと知ったこっちゃないってことなんじゃないのか。
もっとも、森友学園疑獄は、チンピラ松井君も少なからず関与しているから、へたに口出しして寝た子を起こすことになったらかなわん・・・なんて思惑もあるんだろうけど。それはともかく、そんな維新やそれをサポートするかのようなメディアに対して、ハッピーメール米山君がこんなツイートしてます。
◇私が橋下氏や維新、それに追随するマスコミにげんなりするのは、文通費は事実として殆どが事務所経費に使われており、領収書を公開しようがしまいが使われる総額は変わらないのに矢鱈と煽情的に騒ぎ立て、アベノマスクやこの認諾の様に、権力が本当に税金を無駄遣いしている所にはダンマリな所です。— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) December 15, 2021◇おっしゃる通り。このところ、東京でもニュースなどでイソジン吉村君の顔を見ない日がありませんからね。維新の本質を見誤ると、大変なことになりますよ。


2021年12月16日 那覇市歴史博物館 當間巧氏(石川堂090-3792-1231:文化財修復・表装)、外間政明氏/おもろまち駅近くのトックリキワタ。天野鉄夫が自宅で栽培した「天野株」。
TBSNEWS 12-23 政府関係者によりますと、沖縄県のアメリカ軍キャンプ・ハンセンでのクラスター発生を受けて、在日アメリカ軍兵士らの感染防止策の実施状況を確認したところ、多数の部隊でアメリカ出国時にPCRなどの検査を実施していなかったことが確認されたということです。日本の水際措置に整合させるとしていたアメリカ側の説明は守られていませんでした。
共同通信 12-21 木原誠二官房副長官は21日の記者会見で、米軍キャンプ・ハンセン(沖縄県金武町など)での新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)が約200人に上ると米側から説明を受けたと明らかにした。/沖縄県警沖縄署は21日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、米海兵隊キャンプ・ハンセン(金武町など)所属の上等兵ウィリアム・レナーレス容疑者(25)を現行犯逮捕した。
『琉球新報』12-18 米軍キャンプ・ハンセン内で100人規模の新型コロナウイルスの感染が確認され、17日の沖縄県金武町内では警戒感が強まった。隣接する繁華街「新開地」では基地内からの感染拡大を懸念する声が上がる中、マスクなしで出歩く米兵の姿もあり、米軍の感染対策に対する疑問の声も聞かれた。
新開地ではマスクを着用せずに複数人で歩いたり、飲食店内で会話したりする米兵もいた。同僚ら4人で歩いていた兵士らは「外出を禁止されているわけではない。私たちが隔離されていたらここには来られない」と肩をすくめた。クラスターについても特に説明を受けていないという。
在沖海兵隊が「地域住民との接触は一切ない」と説明していることについて、屋嘉区に住む久高栄一さん(74)は「屋嘉には外国人住宅が多く、目と鼻の先に米軍人が住んでいる。接触がないはずがない」と憤った。
『沖縄タイムス』12-18 県内で初めて新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が確認された17日、感染した基地従業員が働く金武町のキャンプ・ハンセンのゲート前では米軍関係者が基地外を出歩く姿が見られた。

大濱 聡 12-20 ■いま、沖縄で――おそらく本土ではあまり報道されていないと思いますので、参考情報として。■本島北部の金武町の米軍キャンプハンセンでコロナウイルスのクラスターが発生。この3日間で186人を数え、大きな問題になっています。■先週末、米人がよく集まる北谷町美浜のアメリカンビレッジを車で通りかかった折り、男女5,6人が徒党を組んだ米兵らしき2,3のグループと夫婦らしき連れを見かけましたが、誰一人としてマスクをしている者はいませんでした。Oh no!クワバラクワバラ……。
12-22 本日ウィルス、沖縄6人米23、大阪24人、東京40人
12-21 本日ウィルス、沖縄11人米22、大阪27人、東京38人
12-20 本日ウィルス、沖縄2人米4、大阪3人、東京11人
12-19 本日ウィルス、沖縄3人米31、大阪13人、東京33人
〇目取真俊2-18 米兵を対象にしない日本政府の水際対策などザルにすぎない。米軍基地から発生したオミクロン株が県内で広がれば、沖縄観光に来た人、年末年始で帰省した人が感染し、全国に広がる危険性がある。








「しまくとぅば鼎談」12月25日(土)おもろまちの沖縄県立博物館・美術館にて/左から屋嘉宗彦氏(法政大学名誉教授)、照屋隆司氏(開発屋でぃきたん代表)、金城美奈子さん/左から屋嘉宗彦氏、伊佐眞一氏、照屋 隆司氏




沖縄県立博物館・美術館 12-25 ”沖縄オペラアカデミーヴォイスアンサンブル”のメンバーによるクリスマス特別コンサート
『琉球新報』12-27 玉城デニー知事は26日、新型コロナウイルスの大規模感染が発生している米軍キャンプ・ハンセンなどから24、25日に、米兵らが基地間の連絡バスで本島中部のキャンプ瑞慶覧まで移動し、基地の外に出ていたことを明らかにした。
「くろねこの短語」2021年12月26日 昨日のTBS『報道特集』は検証第3弾として、「東京五輪の高額物品費」「これで幕引き?森友問題とウィシュマさん事件の行方」を取り上げ、なかなかに見応えがあった。こうした検証を続けていくことがジャーナリズムの基本中の基本であり、調査報道がどれほど重要かということを改めて教えてくれた。オリンピックについては、既に喉元過ぎればでほとんど忘れかけられいるけど、たとえば2倍に膨れ上がった開催経費の説明責任はまだ果たされていない。それどころか、フリップ小池君なんか「レガシー」なんて言葉を吹聴しまくって反省のカケラもない。
ああ、それなのに、「東京オリンピック開催してよかった」という意見が50%を超えてるんだね。そんな忘れやすい国民だもの、そりゃあペテン師・シンゾーごときにコロッと騙されるわけだ。森友問題では、やっぱり「認諾」に尽きますね。番組中で、法律の専門家が「訴訟上の信義に反する不意打ち」と指摘していたけど、まさにおっしゃる通り。非公開の協議中に国側の代理人から「認諾」の言葉が発せられた時には裁判官も虚を突かれたそうだ。それほどの裏技というか、盲点だったということだ。
さらに、赤木雅子さんの抗議に、国側の代理人はひとりとして目を合わせなかたっそうで、後ろめたいという自覚はあったってことなんだろうね。そそくさと立ち去る姿が目に浮かぶようだ。オリンピックも森友問題もウィシュマさん事件も、まだ終わってはいない。同じ批判的立場で権力を追及し続けるのがジャーナリズムの使命なんだから、「野党は批判ばかり」と責め立てる暇があったら、メディアは自らが先頭に立って戦ってみやがれ。
『琉球新報』12-25 名護市辺野古移設に向けた工事の関係者3人が22、23の両日、相次いで新型コロナウイルスに感染した/ABEMA TIMES キャンプ・ハンセン所属の伍長、ジャレット・ミックマン容疑者(24)はきょう午前0時ごろ、那覇市の歓楽街で、ヘルメットをかぶらずに原付きバイクで同僚の20代の海兵隊員と2人乗りをしていたところ、警察官に見つかった。飲酒検査の結果、基準値の約3倍のアルコールが検出された。




彫刻家の西村貞雄さん(琉球大学名誉教授)とローゼル川田さん(水彩画家・エッセイスト)の2人展「見えるもの見えたもの見えないもの」が18日から那覇市牧志のギャラリー・サハスラーラで開かれる。ローゼルさんは本紙連載「琉球風画 今はいにしえ」の掲載作品などを展示。→『沖縄タイムス』/2021年12月24日 ローゼル川田氏、友寄貞丸氏、美佐子さん/右下の人物はローゼル川田氏の先祖・董氏屋富祖仲辰
米山 隆一 12-24 あの和泉補佐官が大阪府市の特別顧問にご就任です。維新は恰好のいい言葉とは裏腹に、安倍・菅氏の「秘密兵器」となる事で中央官庁と深い関係を築き、今の立場を得てきた「新規取得既得権益政党」です。彼らの主張する新自由主義は既に古く、時代にそぐうものではありません。




2021年12月24日 なるみ堂の翁長良明さんと同行し、民芸酒場おもろ「我那覇純都絵画展ーだんじゅかりゆしー」/〇おもろの新垣亮氏/〇我那覇純都さん、真喜志きさ子さん




12-23 小雨 国際通り/市場本通り/おもろまち駅/東急ハンズ那覇メインプレイス店




2021年12月19日 沖縄県立博物館・美術館で孫たちと遊ぶ




2021年12月19日 栄町市場で「平和なミャンマー文化祭」
「くろねこの短語」2021年12月24日 いやあ、この一報が入った瞬間、耳を疑っちまった。虚構新聞ですら想定外の出来事じゃないのか。なんてったって、行政とそれを監視すべき報道機関(ジャーナリズム)が提携するってんだから、そりゃあ目が点にもなろうというものだ。読売新聞は「ジャーナリズムを辞める」って宣言したようなものだろう。これからは、読売新聞が取り上げる維新のニュースってのは、全て眉に唾つけてから読まないとダメってことだ。時あたかも、カジノをめぐる土壌改良問題が持ち上がっている折、大阪府と読売新聞の提携って、なんとも香ばしい。これはもう、読売新聞は大阪府(=維新)の広報に成り下がったことを意味している。ひょっとしたら、産経新聞も自民党と提携しましたって言い出したりして。
「くろねこの短語」2021年12月23日 山積みになったアベノマスクが年内に廃棄されるってね。その数、実に8000万枚以上とかで、なんとそのうちの15%にあたる約1100万枚が不良品だったってさ。これって、民間の取引だったら、納入業者は当然、その責任を追及されるはずだ。ああ、それなのに、どうやらそこはねぐって、さっさと廃棄して、一件落着にしようってんだから、ベラボーな話なのだ。しかも、不良品が発覚した検査に、▼厚生労働省による検品費用におよそ6億9200万円、▼その後に納入事業者が実施した検品費用におよそ10億7000万円、▼検品に時間がかかったことに伴う追加費用におよそ3億3000万円もの大金が注ぎ込まれたとか。いやあ、これすべて税金ですからね。
さらに、廃棄するにも経費がかかるわけで、すべての責任はペテン師・シンゾーにあるんだからこ奴に払わせたらどうなのかねえ。ていうか、この男自身が不良品なんだから、アベノマスクと一緒に廃棄処分にしたらどうだ。とうとうアベノマスク8000万枚以上が強制廃棄されることになった。検品したら約1100万枚が不良品だったから捨てるしかない。その検査などに20億円以上かけたらしい。統計的には1000枚調べれば十分なのに何たる無駄遣い。殆ど使われなかったアベノマスクに500億円かけた責任は誰が取るのか。
ところで、オミクロン株の市中感染が確認されたってね。それも大阪で。イソジン吉村君のコロナ対策を御用メディアがヨイショしてたけど、結局のところ大阪っていまも最悪の感染地域なんだよね。AIの試算では、このままいくと東京での新規感染者は年明けには3000人を超えるとか。大阪も同じような推移を辿るとすると、デルタ株で医療崩壊した時の二の舞になりますよ。
「くろねこの短語」2021年12月20日 大阪のビル放火は、なんとも痛ましい事件だ。出口がひとつのペンシルビルでは、逃げようがありませんからね。それにしても、24人死亡という大惨事にも関わらず、イソジン吉村君もチンピラ松井君もまったく沈黙したままってのはどうなんだろうね。そう言えば、森友訴訟の「認諾」についてもこの2人はスルーしてるんだが、ようするに自分たちの存在をアピールできることには煽情的な言葉を喚き散らしてでも介入するけど、市民がどうなろうと知ったこっちゃないってことなんじゃないのか。
もっとも、森友学園疑獄は、チンピラ松井君も少なからず関与しているから、へたに口出しして寝た子を起こすことになったらかなわん・・・なんて思惑もあるんだろうけど。それはともかく、そんな維新やそれをサポートするかのようなメディアに対して、ハッピーメール米山君がこんなツイートしてます。
◇私が橋下氏や維新、それに追随するマスコミにげんなりするのは、文通費は事実として殆どが事務所経費に使われており、領収書を公開しようがしまいが使われる総額は変わらないのに矢鱈と煽情的に騒ぎ立て、アベノマスクやこの認諾の様に、権力が本当に税金を無駄遣いしている所にはダンマリな所です。— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) December 15, 2021◇おっしゃる通り。このところ、東京でもニュースなどでイソジン吉村君の顔を見ない日がありませんからね。維新の本質を見誤ると、大変なことになりますよ。


2021年12月16日 那覇市歴史博物館 當間巧氏(石川堂090-3792-1231:文化財修復・表装)、外間政明氏/おもろまち駅近くのトックリキワタ。天野鉄夫が自宅で栽培した「天野株」。
TBSNEWS 12-23 政府関係者によりますと、沖縄県のアメリカ軍キャンプ・ハンセンでのクラスター発生を受けて、在日アメリカ軍兵士らの感染防止策の実施状況を確認したところ、多数の部隊でアメリカ出国時にPCRなどの検査を実施していなかったことが確認されたということです。日本の水際措置に整合させるとしていたアメリカ側の説明は守られていませんでした。
共同通信 12-21 木原誠二官房副長官は21日の記者会見で、米軍キャンプ・ハンセン(沖縄県金武町など)での新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)が約200人に上ると米側から説明を受けたと明らかにした。/沖縄県警沖縄署は21日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、米海兵隊キャンプ・ハンセン(金武町など)所属の上等兵ウィリアム・レナーレス容疑者(25)を現行犯逮捕した。
『琉球新報』12-18 米軍キャンプ・ハンセン内で100人規模の新型コロナウイルスの感染が確認され、17日の沖縄県金武町内では警戒感が強まった。隣接する繁華街「新開地」では基地内からの感染拡大を懸念する声が上がる中、マスクなしで出歩く米兵の姿もあり、米軍の感染対策に対する疑問の声も聞かれた。
新開地ではマスクを着用せずに複数人で歩いたり、飲食店内で会話したりする米兵もいた。同僚ら4人で歩いていた兵士らは「外出を禁止されているわけではない。私たちが隔離されていたらここには来られない」と肩をすくめた。クラスターについても特に説明を受けていないという。
在沖海兵隊が「地域住民との接触は一切ない」と説明していることについて、屋嘉区に住む久高栄一さん(74)は「屋嘉には外国人住宅が多く、目と鼻の先に米軍人が住んでいる。接触がないはずがない」と憤った。
『沖縄タイムス』12-18 県内で初めて新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が確認された17日、感染した基地従業員が働く金武町のキャンプ・ハンセンのゲート前では米軍関係者が基地外を出歩く姿が見られた。

大濱 聡 12-20 ■いま、沖縄で――おそらく本土ではあまり報道されていないと思いますので、参考情報として。■本島北部の金武町の米軍キャンプハンセンでコロナウイルスのクラスターが発生。この3日間で186人を数え、大きな問題になっています。■先週末、米人がよく集まる北谷町美浜のアメリカンビレッジを車で通りかかった折り、男女5,6人が徒党を組んだ米兵らしき2,3のグループと夫婦らしき連れを見かけましたが、誰一人としてマスクをしている者はいませんでした。Oh no!クワバラクワバラ……。
12-22 本日ウィルス、沖縄6人米23、大阪24人、東京40人
12-21 本日ウィルス、沖縄11人米22、大阪27人、東京38人
12-20 本日ウィルス、沖縄2人米4、大阪3人、東京11人
12-19 本日ウィルス、沖縄3人米31、大阪13人、東京33人
〇目取真俊2-18 米兵を対象にしない日本政府の水際対策などザルにすぎない。米軍基地から発生したオミクロン株が県内で広がれば、沖縄観光に来た人、年末年始で帰省した人が感染し、全国に広がる危険性がある。
09/16: 世相ジャパン 2024
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@yahoo.co.jp


大濱 聡 10-25 ■「解放へのオガリ」像 完成お披露目会、今日(26日・土)です。どなたでも参加できます。■アトリエもきれいに整備されました。

10月26日 沖縄戦戦没韓国人慰霊祭に参列された駐福岡大韓民国総領事、日韓親善協会理事長、左から2人目が真栄里泰山さん
くろねこの短語10-24 衆議院選も終盤にさしかかったところで、特大の赤旗砲が炸裂。なんと、非公認となった自民党の裏金議員に政党助成金2000万円が振り込まれていましたとさ。「党勢拡大のための活動費」なんて見苦しい言い訳してるが、これはどう考えたって「公認料」みたいなものだろう。ようするに、非公認は偽装にしか過ぎないって白状したようなものだ。臆面もなく自民党議員が非公認候補の応援にしゃしゃり出てくるのもその一環ってことなのだ。
嘘つき総理は「ルールを守る」って喚いていたが、その舌の根も乾かないうちにこれだもの、国民も舐められたものだ。結局、何があっても自民党に投票してきた有権者の存在が、自民党をここまで増長させちゃったってことなのだ。今回のしんぶん赤旗の大スクープは、その他のメディアも後追いしているようだから、自民党にとっては相当な痛手には違いない。選挙戦終盤で、「それでも自民党に投票しますか」って突き付けられたんだから、ここから先は有権者の民度の問題ってことなんでしょうね。
関連・時事通信 石破茂首相(自民党総裁)は24日、広島市で街頭演説し、派閥裏金事件を受けて衆院選で非公認となった候補側に自民党本部が2000万円の活動費を支出したことについて、「政党支部に出しているのであって、非公認候補に出しているのではない。報道に誠に憤りを覚える」と述べた。「報道、偏った見方に負けるわけにはいかない」とも語った。



仲松 健雄 10-19 公益財団法人沖縄協会が主催する講演会が大手町にある日経ホールで開催され参加✨演題:「沖縄の豊かな植物資源」講師は、花城良廣 氏 (前 沖縄美ら島財団理事長)植物資源の話しの前に首里城復元工事の進捗状況ならびに首里城公園等の整備計画概要について説明がありました。沖縄は、植物資源が豊かで植物の多様性も豊富❗️私が子どもの頃から大好きな「島バナナ」は、なんと1888年に小笠原から導入されたと聞いてビックリ‼️ほとんど初めて聞く話しばかりで、大変勉強になりました。
くろねこの短語10-22 衆議院選挙に突入したとたんに、裏金も統一教会も選択的夫婦別姓も同性婚もマイナ保険証もすべて吹っ飛んじゃって、メディアは自公過半数割れだの連立再編だの選挙情勢と選挙後の政局の話題にシフトしている。
そのくせ、通信社の解説委員なんてのに「裏金ばかりで政策議論が疎かになっている」なんて与太を語らせるんだから始末が悪い。そもそも、今回の選挙は裏金事件をきっかけとする「政治とカネ」がメインテーマであって、そこをねぐってしまったら何のための解散だったのか分からなくなってしまう。
だから、非公認の裏金議員を公明党が推薦したり、自民党議員が応援に入っていることを厳しく糾弾すべきなんだね。ああ、それなのに、そうした現実をまったくスルーして、アナウンス効果が危険だからやめるべきと指摘されている選挙の事前予測を毎日のように垂れ流してるんだから、こんな報道に多くの有権者がウンザリして投票率が上がらないのも無理はない。しかも、戦後最短の選挙期間と言われる時間のなさもあるんだから、投票率は悲しいくらいに低くなるんじゃないのかねえ。終わってみれば、なんのことはない自公過半数でシャンシャンになって、「すべて世は事もなし」ってことになるんじゃないのか・・・なんてことを我が家のドラ猫に囁いてみる火曜の朝である。



2024-10-6 JAおきなわ真和志農協ホール「第51回 粟国郷友会敬老会」
玉寄貞一郎・粟国郷友会会長/伊良皆武宣・粟国郷友会副会長、浦崎さん



濵川政敏さん/与那城昭広・粟国郷友会元会長、伊良皆賢哲・粟国村元教育長



10-5 「久茂地ブックスクエア」が那覇市久茂地の沖縄タイムス社ビルで始まる。県内の古書店と出版社が集まり、本を販売するイベント/右から城間有さん、真栄里泰球さん



左から仲村渠裕子さん、仲村渠理・琉球プロジェクト代表取締役、よへな理菜さん/波止場書房の花城美和子さん、じのんの天久さん/榕樹書林の武石さん



10-2 那覇市の栄町市場の栄町共同書店が1日オープンしたので2日に栄町を訪ねた。一回りしたが場所が分からないので、宮里小書店で聞こうと訪ねたら店番していた女性がワザワザ案内してくれた。一回りしたとき通ったところにあった。「シェア型書店」と「労働者協同組合」がハイブリッドした本屋。/「栄町共同書店」篠田恵さん、古波蔵契さん/宮里小書店

大濱 聡 9-28■知人で同年生の画家・桑江良健さんの「絵描き50周年展」を鑑賞する。若き日にパリに渡り、ルーブル美術館の先達の画家たちを師に、独学で絵を学ぶ。50年間11万もの時間、絵を描くのに費やしてきたとのこと。■長年、純子夫人と“ふたり劇団”人形劇の「かじまやぁ」で全国各地を公演する二足の草鞋の生活を続けてきた。家人と知り合いだった純子さんは独身時代、我々の結婚披露宴の余興で人形劇を演じてくれたことがある。■那覇での展示会は29日(日)まで。10/3(木)~13(日)は地元の名護博物館で開催。那覇、名護近郊の皆さん、ぜひ足を伸ばしてみて下さい。

くろねこの短語9-28 ひょっとこ麻生が支持を表明したことで平気でうそつく高市君がへたすると総理の可能性が出てきたと危惧したんだが、どうにか軍事オタクのアンポンタン石破君が逆転勝利となりましたとさ。・「脱派閥」を目指したはずが…「重鎮詣で」や「投票指示」が公然と 総裁選で明らかになった自民党の限界
いくらひょっとこ麻生が後押ししたとはいえ、ネトウヨまがいの平気で嘘つく高市君にあれほどの票が集まるとは・・・。自民党ってのは政策云々よりもしょせんは勝ち馬に乗ることしか考えていない政治屋の集団ってことなんだね。それにしても、これからのこの国の顔が石破で、それに対抗する野党が野田とはねえ。なんだか、自民党の派閥争いみたいで、政権与党と野党の熾烈な戦いなんてのは微塵も感じさせない政治状況はいかがなものなんでしょうねえ。
くろねこの短語9-26 政策を決定するプロセスはガラス張りでなくてはならない。そのために、公文書があり、情報公開もこうした理念の延長線上にある。これは、民主主義の根幹だ。ところが、日本は森友学園疑獄が象徴するように、公文書改竄なんてことを平気でやっちまう「劣等国」なんだね。
そんな「劣等国」の姿が、またしても発覚した。昨日の「まだまだあるぞ気になるニュース」でもお知らせしたように、なんとマイナ保険証にからんで健康保険証を廃止したそのプロセスが闇の中なんだとか。東京新聞が「『完全廃止』を決めるまでの政策決定のプロセスが分かる文書の開示」を求めたところ、協議のプロセスを記載した文書は一切存在しないことがわかりましたとさ。
ブロック太郎は、「マイナ保険証のメリットを早期に多くの方に体験してもらうため、政府内、関係省庁で議論の上、決定した」ってのたまってる。でも、当時の厚労大臣であるゴハン加藤君は「今は回答が難しい」と訳の分からないことを口走る始末だ。ヘタレ総理にも報告したともブロック太郎はドヤ顔してるようだが、デジタル庁も厚労省も「首相への報告はあくまで報告なので記録はない」と言い逃れしてるんだから話にならない。
おそらく、ブロック太郎の独断専行だったんでしょうね。でも、こんなことが許されていると、そのうち誰が言い出したのかわからないままに、戦争に突入、なんて時代がやってきますよ。



9-24 なるみ堂で店主の翁長良明さん、金城正秀さん,新城栄徳ボディビルゆんたく◇ギノワンジム ジム・フィットネスセンター1980年に#宜野湾市 開業した #トレーニングジム #フィットネスジム 代表は #沖縄県ボディビル連盟会長 の #金城正秀 #写真1986年アジア大会優勝 と #1986年世界大会7位



翁長良明さんボディビル時代

大濱 聡 9-23■スリランカの友人Premadasa HegodaさんからLINE電話があった(同じ村内からかけているようなクリアな声だ)。21日投票が行われた大統領選挙で、野党の左派勢力「国民の力」のディサナヤカ氏が現職のウィクラマシンハ大統領を破って当選したという報告だった。■彼の知り合いでもあり、現政権の腐敗ぶりもひどかったことから、ディサナヤカ氏の当選が嬉しく誰かに話したくなって電話したとのこと。政権交代に国民の期待が大きいとのことで、羨ましく思う。■日本では自民党総裁選、立憲民主党代表選(本日決定)の最中だが、いずれも期待感薄いのが何とも寂しい限りである。

関連:JIJI10-7 立憲民主党の野田佳彦代表、枝野幸男元代表、安住淳前国対委員長の選挙区にそれぞれ新人を擁立。山本太郎代表は記者会見で「(3氏は)消費税を増税し、戦わない野党の先頭だ。対抗馬を立てなければいけない」と強調した。
くろねこの短語9-23 政治資金パーティーにからんだ裏金事件で表舞台から消えたはずの女体盛り・西村君が、能登半島の豪雨を「天が与えた試練」とツイートして大顰蹙を買っている。正月の震災後も復興が進まない中での追い打ちをかけるような天災を「試練」とは、まるで住民に何か責任があるかのような言い草はさすがに看過できない。
これって、東日本大震災の被害を「天罰」と言ってのけたレイシスト・石原慎太郎に通じる問題発言じゃなかろうか。そもそも、女体盛り・西村君は現役の政治家なんだから、こんな評論家めいたツイートするのではなく、自ら現地に足を運んで被災者支援をするのが筋ってものだろう。
思えば、西日本豪雨の際に、能天気にも「赤坂自民亭」なんて宴会開いて、その画像をツイッター(現X)にアップして炎上したのも、この男だった。ようするに、「ひとに寄り添う」という政治家としての基本中の基本が、決定的に欠けてるってことだ。この国で起きる自然災害による被害は、すべて政治家の手抜きによる「人災」と言っても過言ではないだろう。


大濱 聡 10-25 ■「解放へのオガリ」像 完成お披露目会、今日(26日・土)です。どなたでも参加できます。■アトリエもきれいに整備されました。

10月26日 沖縄戦戦没韓国人慰霊祭に参列された駐福岡大韓民国総領事、日韓親善協会理事長、左から2人目が真栄里泰山さん
くろねこの短語10-24 衆議院選も終盤にさしかかったところで、特大の赤旗砲が炸裂。なんと、非公認となった自民党の裏金議員に政党助成金2000万円が振り込まれていましたとさ。「党勢拡大のための活動費」なんて見苦しい言い訳してるが、これはどう考えたって「公認料」みたいなものだろう。ようするに、非公認は偽装にしか過ぎないって白状したようなものだ。臆面もなく自民党議員が非公認候補の応援にしゃしゃり出てくるのもその一環ってことなのだ。
嘘つき総理は「ルールを守る」って喚いていたが、その舌の根も乾かないうちにこれだもの、国民も舐められたものだ。結局、何があっても自民党に投票してきた有権者の存在が、自民党をここまで増長させちゃったってことなのだ。今回のしんぶん赤旗の大スクープは、その他のメディアも後追いしているようだから、自民党にとっては相当な痛手には違いない。選挙戦終盤で、「それでも自民党に投票しますか」って突き付けられたんだから、ここから先は有権者の民度の問題ってことなんでしょうね。
関連・時事通信 石破茂首相(自民党総裁)は24日、広島市で街頭演説し、派閥裏金事件を受けて衆院選で非公認となった候補側に自民党本部が2000万円の活動費を支出したことについて、「政党支部に出しているのであって、非公認候補に出しているのではない。報道に誠に憤りを覚える」と述べた。「報道、偏った見方に負けるわけにはいかない」とも語った。



仲松 健雄 10-19 公益財団法人沖縄協会が主催する講演会が大手町にある日経ホールで開催され参加✨演題:「沖縄の豊かな植物資源」講師は、花城良廣 氏 (前 沖縄美ら島財団理事長)植物資源の話しの前に首里城復元工事の進捗状況ならびに首里城公園等の整備計画概要について説明がありました。沖縄は、植物資源が豊かで植物の多様性も豊富❗️私が子どもの頃から大好きな「島バナナ」は、なんと1888年に小笠原から導入されたと聞いてビックリ‼️ほとんど初めて聞く話しばかりで、大変勉強になりました。
くろねこの短語10-22 衆議院選挙に突入したとたんに、裏金も統一教会も選択的夫婦別姓も同性婚もマイナ保険証もすべて吹っ飛んじゃって、メディアは自公過半数割れだの連立再編だの選挙情勢と選挙後の政局の話題にシフトしている。
そのくせ、通信社の解説委員なんてのに「裏金ばかりで政策議論が疎かになっている」なんて与太を語らせるんだから始末が悪い。そもそも、今回の選挙は裏金事件をきっかけとする「政治とカネ」がメインテーマであって、そこをねぐってしまったら何のための解散だったのか分からなくなってしまう。
だから、非公認の裏金議員を公明党が推薦したり、自民党議員が応援に入っていることを厳しく糾弾すべきなんだね。ああ、それなのに、そうした現実をまったくスルーして、アナウンス効果が危険だからやめるべきと指摘されている選挙の事前予測を毎日のように垂れ流してるんだから、こんな報道に多くの有権者がウンザリして投票率が上がらないのも無理はない。しかも、戦後最短の選挙期間と言われる時間のなさもあるんだから、投票率は悲しいくらいに低くなるんじゃないのかねえ。終わってみれば、なんのことはない自公過半数でシャンシャンになって、「すべて世は事もなし」ってことになるんじゃないのか・・・なんてことを我が家のドラ猫に囁いてみる火曜の朝である。



2024-10-6 JAおきなわ真和志農協ホール「第51回 粟国郷友会敬老会」
玉寄貞一郎・粟国郷友会会長/伊良皆武宣・粟国郷友会副会長、浦崎さん



濵川政敏さん/与那城昭広・粟国郷友会元会長、伊良皆賢哲・粟国村元教育長



10-5 「久茂地ブックスクエア」が那覇市久茂地の沖縄タイムス社ビルで始まる。県内の古書店と出版社が集まり、本を販売するイベント/右から城間有さん、真栄里泰球さん



左から仲村渠裕子さん、仲村渠理・琉球プロジェクト代表取締役、よへな理菜さん/波止場書房の花城美和子さん、じのんの天久さん/榕樹書林の武石さん



10-2 那覇市の栄町市場の栄町共同書店が1日オープンしたので2日に栄町を訪ねた。一回りしたが場所が分からないので、宮里小書店で聞こうと訪ねたら店番していた女性がワザワザ案内してくれた。一回りしたとき通ったところにあった。「シェア型書店」と「労働者協同組合」がハイブリッドした本屋。/「栄町共同書店」篠田恵さん、古波蔵契さん/宮里小書店

大濱 聡 9-28■知人で同年生の画家・桑江良健さんの「絵描き50周年展」を鑑賞する。若き日にパリに渡り、ルーブル美術館の先達の画家たちを師に、独学で絵を学ぶ。50年間11万もの時間、絵を描くのに費やしてきたとのこと。■長年、純子夫人と“ふたり劇団”人形劇の「かじまやぁ」で全国各地を公演する二足の草鞋の生活を続けてきた。家人と知り合いだった純子さんは独身時代、我々の結婚披露宴の余興で人形劇を演じてくれたことがある。■那覇での展示会は29日(日)まで。10/3(木)~13(日)は地元の名護博物館で開催。那覇、名護近郊の皆さん、ぜひ足を伸ばしてみて下さい。

くろねこの短語9-28 ひょっとこ麻生が支持を表明したことで平気でうそつく高市君がへたすると総理の可能性が出てきたと危惧したんだが、どうにか軍事オタクのアンポンタン石破君が逆転勝利となりましたとさ。・「脱派閥」を目指したはずが…「重鎮詣で」や「投票指示」が公然と 総裁選で明らかになった自民党の限界
いくらひょっとこ麻生が後押ししたとはいえ、ネトウヨまがいの平気で嘘つく高市君にあれほどの票が集まるとは・・・。自民党ってのは政策云々よりもしょせんは勝ち馬に乗ることしか考えていない政治屋の集団ってことなんだね。それにしても、これからのこの国の顔が石破で、それに対抗する野党が野田とはねえ。なんだか、自民党の派閥争いみたいで、政権与党と野党の熾烈な戦いなんてのは微塵も感じさせない政治状況はいかがなものなんでしょうねえ。
くろねこの短語9-26 政策を決定するプロセスはガラス張りでなくてはならない。そのために、公文書があり、情報公開もこうした理念の延長線上にある。これは、民主主義の根幹だ。ところが、日本は森友学園疑獄が象徴するように、公文書改竄なんてことを平気でやっちまう「劣等国」なんだね。
そんな「劣等国」の姿が、またしても発覚した。昨日の「まだまだあるぞ気になるニュース」でもお知らせしたように、なんとマイナ保険証にからんで健康保険証を廃止したそのプロセスが闇の中なんだとか。東京新聞が「『完全廃止』を決めるまでの政策決定のプロセスが分かる文書の開示」を求めたところ、協議のプロセスを記載した文書は一切存在しないことがわかりましたとさ。
ブロック太郎は、「マイナ保険証のメリットを早期に多くの方に体験してもらうため、政府内、関係省庁で議論の上、決定した」ってのたまってる。でも、当時の厚労大臣であるゴハン加藤君は「今は回答が難しい」と訳の分からないことを口走る始末だ。ヘタレ総理にも報告したともブロック太郎はドヤ顔してるようだが、デジタル庁も厚労省も「首相への報告はあくまで報告なので記録はない」と言い逃れしてるんだから話にならない。
おそらく、ブロック太郎の独断専行だったんでしょうね。でも、こんなことが許されていると、そのうち誰が言い出したのかわからないままに、戦争に突入、なんて時代がやってきますよ。



9-24 なるみ堂で店主の翁長良明さん、金城正秀さん,新城栄徳ボディビルゆんたく◇ギノワンジム ジム・フィットネスセンター1980年に#宜野湾市 開業した #トレーニングジム #フィットネスジム 代表は #沖縄県ボディビル連盟会長 の #金城正秀 #写真1986年アジア大会優勝 と #1986年世界大会7位



翁長良明さんボディビル時代

大濱 聡 9-23■スリランカの友人Premadasa HegodaさんからLINE電話があった(同じ村内からかけているようなクリアな声だ)。21日投票が行われた大統領選挙で、野党の左派勢力「国民の力」のディサナヤカ氏が現職のウィクラマシンハ大統領を破って当選したという報告だった。■彼の知り合いでもあり、現政権の腐敗ぶりもひどかったことから、ディサナヤカ氏の当選が嬉しく誰かに話したくなって電話したとのこと。政権交代に国民の期待が大きいとのことで、羨ましく思う。■日本では自民党総裁選、立憲民主党代表選(本日決定)の最中だが、いずれも期待感薄いのが何とも寂しい限りである。

関連:JIJI10-7 立憲民主党の野田佳彦代表、枝野幸男元代表、安住淳前国対委員長の選挙区にそれぞれ新人を擁立。山本太郎代表は記者会見で「(3氏は)消費税を増税し、戦わない野党の先頭だ。対抗馬を立てなければいけない」と強調した。
くろねこの短語9-23 政治資金パーティーにからんだ裏金事件で表舞台から消えたはずの女体盛り・西村君が、能登半島の豪雨を「天が与えた試練」とツイートして大顰蹙を買っている。正月の震災後も復興が進まない中での追い打ちをかけるような天災を「試練」とは、まるで住民に何か責任があるかのような言い草はさすがに看過できない。
これって、東日本大震災の被害を「天罰」と言ってのけたレイシスト・石原慎太郎に通じる問題発言じゃなかろうか。そもそも、女体盛り・西村君は現役の政治家なんだから、こんな評論家めいたツイートするのではなく、自ら現地に足を運んで被災者支援をするのが筋ってものだろう。
思えば、西日本豪雨の際に、能天気にも「赤坂自民亭」なんて宴会開いて、その画像をツイッター(現X)にアップして炎上したのも、この男だった。ようするに、「ひとに寄り添う」という政治家としての基本中の基本が、決定的に欠けてるってことだ。この国で起きる自然災害による被害は、すべて政治家の手抜きによる「人災」と言っても過言ではないだろう。
01/03: ジャーナリスト/黒田清
シベリア


黒田清のサイン
黒田清 くろだ-きよし
1931-2000 昭和後期-平成時代のジャーナリスト。
昭和6年2月15日生まれ。昭和27年読売新聞大阪本社に入社。社会部長をへて編集局次長。コラム「窓」を執筆,大型連載「戦争」を手がけたほか,黒田軍団とよばれる社会部をひきいておおくのスクープをものにした。61年退社して黒田ジャーナルを設立し,「窓友新聞」を発行。平成12年7月23日死去。69歳。大阪出身。京大卒。著作に「警官汚職」(共著),「新聞記者の現場」など。(→コトバンク)

1980年8月7日『新聞記者が語りつぐ戦争 戦争記念館』読売新聞大阪社会部



1999年1月10日『赤旗』黒田清「半共ジャーナルーインターネット社会の恐ろしさ」
〇・・・しかもインターネットの発達は、ますますこのような人たち、現実社会からは逃避して、インターネットを主なる舞台として生きる人たちが増えることを意味する。この人たちは社会をよくするために、政治や選挙や平和や人権といったことを真剣に考えるだろか。いやその前に、世の中をよくしようと思うだろうか。それが恐ろしいのである。



黒田清のサイン
黒田清 くろだ-きよし
1931-2000 昭和後期-平成時代のジャーナリスト。
昭和6年2月15日生まれ。昭和27年読売新聞大阪本社に入社。社会部長をへて編集局次長。コラム「窓」を執筆,大型連載「戦争」を手がけたほか,黒田軍団とよばれる社会部をひきいておおくのスクープをものにした。61年退社して黒田ジャーナルを設立し,「窓友新聞」を発行。平成12年7月23日死去。69歳。大阪出身。京大卒。著作に「警官汚職」(共著),「新聞記者の現場」など。(→コトバンク)

1980年8月7日『新聞記者が語りつぐ戦争 戦争記念館』読売新聞大阪社会部



1999年1月10日『赤旗』黒田清「半共ジャーナルーインターネット社会の恐ろしさ」
〇・・・しかもインターネットの発達は、ますますこのような人たち、現実社会からは逃避して、インターネットを主なる舞台として生きる人たちが増えることを意味する。この人たちは社会をよくするために、政治や選挙や平和や人権といったことを真剣に考えるだろか。いやその前に、世の中をよくしようと思うだろうか。それが恐ろしいのである。
08/07: 1941年7月『茶わん』蘭郁二郎「琉球のぞ記」寶雲舎
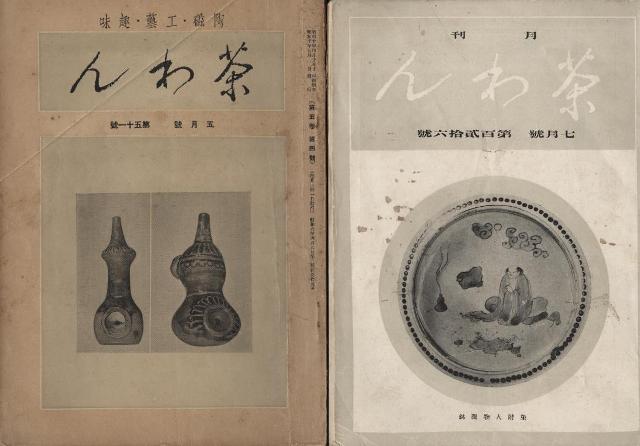
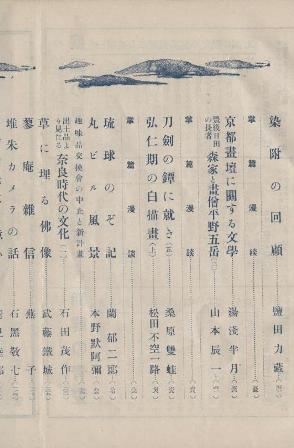

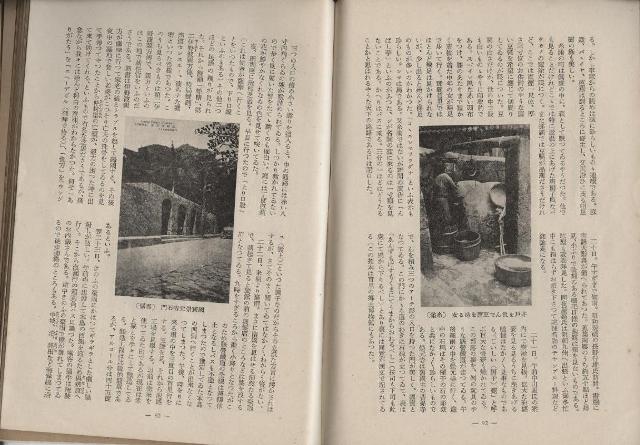
「茶わん」は陶芸愛好家向けの専門誌で、創刊は昭和六年三月。編集発行人は秦秀雄となっているが、実務は小野賢一郎がとりしきっていた。秦に代わって昭和七年五月号から編集発行人として遠藤敏夫の名がクレジットされる。編集部は芝区三田功運町六番地、聖坂を登り切った辺りにあった。(会津信吾「蘭郁二郎の生涯」)
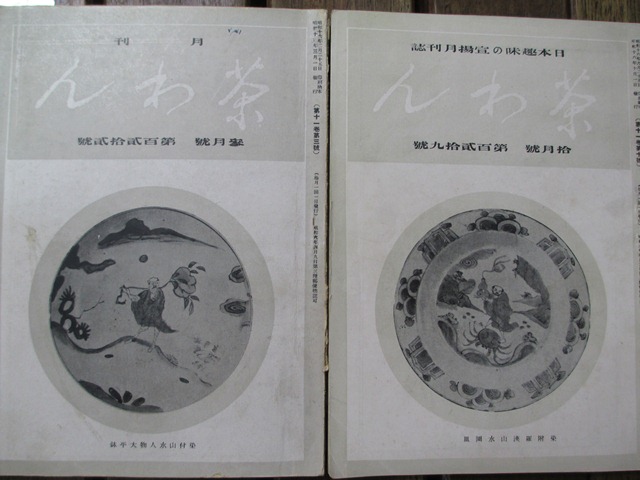
1941年8月『文学建設』蘭郁二郎「琉球ある記」
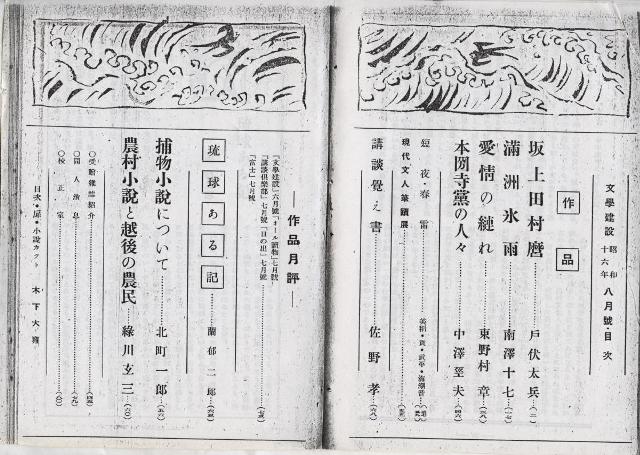



1971年10月 蘭郁二郎『地底大陸』桃源社
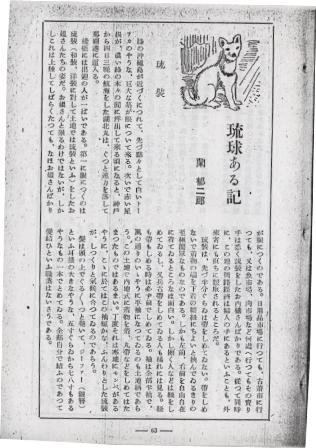
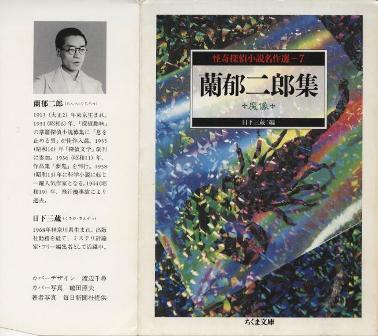
蘭郁二郎 らん-いくじろう 1913-1944 昭和時代前期の小説家。
大正2年9月2日生まれ。「探偵文学」同人となりミステリーをかくが,科学冒険小説に転じ,SF小説の先駆者のひとりとなった。海軍報道班員として台湾にわたり,昭和19年1月5日飛行機事故で死去。32歳。東京出身。東京高工卒。本名は遠藤敏夫。著作に「地図にない島」「地底大陸」など。→コトバンク
1935年10月30日 阿部金剛、昭和会館参観
03/06: 世相ジャパン 2025④
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com




仲松 健雄 『琉球民謡協会関東支部 第38回定期総会・懇親会』日本教育会館 喜山倶楽部で開催され、新支部長に仲松秀市さんが就任、片峯智恵子 前支部長は理事長に就任✨会員数235名が所属す琉球民謡協会関東支部の発展と繁栄を誓い合いお開きとなりました.



3-20 春分の日 ユンタンの孫たちとコ一プ、ジュンク堂で遊ぶ/古美術なるみ堂で、右から店主の翁長良明さん、前田比呂也さん、彬さん親子

近鉄永和駅前「万博、カジノ反対市民集会」
☆大阪万博344億木造リング、竹中平蔵とミサワホーム竹中宜雄会長兄弟の利権でフィンランド産木材の使用疑惑
☆2025年のいま、世界は気候変動や戦争、AI(人工知能)の急速な発達など、様々な問題や課題を抱えていますが、今回の万博がこうした大きな問題に向き合っているとは思えません。そういう大きなテーマへの言及はあっても、『お飾り』や『ウォッシュ(見せかけ)』になっているようにみえます。気候変動への対応を考えれば、本来、こういうイベントをやるべきではない。たった半年間のために木材を切って持ってきたり埋め立て地を開発したり、そういう行為が気候変動対策と矛盾しています」(朝日新聞、3月12日)
<


2025年3月 『琉球』浦崎成子「【大城宜武さん追悼】さようならポパイ」/また友人が居なくなった。


大濱 聡 3-16 · ■『沖縄タイムス』に連載していた木名瀬高嗣 東京理科大学教授の「オペラ開拓――粟國安彦と沖縄――」が36回で終了した。
■粟國安彦(1941-1990)は南大東島出身のオペラ演出家。ローマサンタ・チェチーリア音楽院・演出を主席で卒業、日本人として初めてローマ歌劇場の演出助手になる。昭和54年度芸術選奨文部大臣賞新人賞受賞。「トスカ」「蝶々夫人」「フィガロの結婚」「椿姫」など藤原歌劇団、二期会他で多数のオペラを演出。がんのため48歳で逝去。
■45年前、番組の取材で藤原歌劇団に粟國を訪ねてインタビューしたことがある。沖縄でのオペラの可能性と期待を語ってくれた。早逝が惜しまれる。


関連:1996年9月 『新沖縄文学』85号 重田辰弥「疾走した寵児・粟国安彦」





3月14日 なるみ堂で、左から店主の翁長良明さん、屋良朝信さん、スウェーデン出身のヘンリック・ホカンソンさん/沖縄県立博物館・美術館館で里井洋一館長、屋良朝信さん/左から與那覇政直美術館副参事、屋良朝信さん、前田比呂也美術館班長/真栄里泰山さん、屋良朝信さん
大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 3-11 費用は増えない→増えた メタン爆発しない→爆発した チケット売れる→売れない 個人情報抜かない→抜ける リング護岸が浸食⬅️イマココ 万博行ったらダメ???? 中止するべき。責任者出てこい。万博の大屋根リング護岸が浸食被害 海水注入後に強風影響か | 毎日新聞
3-10 日本共産党の山添拓議員は7日の参院予算委員会で、海上自衛隊が紛争当事国であるウクライナとの多国間軍事演習に参加していた事実を防衛省が公表していなかった問題を取り上げ追及しました。同軍事演習「シーブリーズ」は米国とウクライナが共催する多国間演習で、昨年9月はウクライナ南部とクリミア半島に面し緊張が高まるブルガリア沖の黒海で実施。海自は米軍、ウクライナ軍などと機雷の水中処分などの訓練を行ったとされていますが公表されていませんでした。中谷元・防衛相は、同演習について自衛隊は2021年にオブザーバーとして初参加し、22年はウクライナ情勢勃発により中止、23年から本参加を開始し、24年には英国での演習に1人、ブルガリアに10人派遣したと説明しました。



3月8日 小島摩文鹿児島純心大学教授(父小島瓔禮/祖父又吉康和) 那覇日誌 /沖縄県立博物館・美術館 民家前/新城良一さん、小島教授/古美術なるみ堂で右から店主の翁長良明さん、小島教授、松島弘明さん



斎藤 陽子ーー7【思い出のアルバム】
57年まえ航空便はべらぼうに高価で、フライト便も少ない頃、貨客船の最終運航便 プレジデント ライン社のクリーブランド号に乗り込んで、横浜港から2週間をかけて、朝日に映える早朝のゴールデンゲイト・ブリッジの下を抜け、サンフランシスコ港に到着した日を思い出しています。

57年前の当時1ドルが360円の時代、日本人は日本国から円の持ち出しも規制される貧しい日本の国力でした。
当時サンフランシスコでアパートを借りて、大学へ通学する日本人の留学生には、授業料免除の恩典を得ても、生活する上では経済的には苦しいものでした。
当時のほとんどの留学生はサンフランシスコの富裕層の家に寄生し、5時頃までには急いで帰宅し、寄生している家の夕食準備の手伝いと後片付けなどに従事し、朝は早朝に起きて犬の散歩と家族の朝食作りをこなして、学業の一日が始まります。土曜日は寄生している大きな家の掃除や洗濯アイロンがけやシルバー食器磨きなどでのメイド業で一日過ごし、夜は家人がパーティーなどへ出かけると、子どもたちのシッターをする等で、留学中の「屋根と食事」が保証されるという生活を得て、勉学をする日々でした。
これがほとんどの日本人留学生の生きる方法で、そういう学生はスクールガールまたはスクールボーイと呼ばれ、大学の昼食時間には日本人学生同士が出会うと、寄宿先の主人の悪口を言ってウサ晴らしをしたものです。
日本で大学も修め、天職とする獣医師にもなって、この地でお手伝いさんのようなメイド業の労働をしなくてはならない自分の姿に、気持ちの沈むこともありましたが、若いということはそれまで経験したことのないメイド業までも、面白がっている自分を楽しんだ面もありました。
当時は日本とは随分格差の有ったアメリカの生活でしたから、生活文化の面では随分学ぶことも多く、後の私のアメリカでの永住生活に、この頃アメリカの生活習慣を学んだことは、後々とてもプラスになっています。
渡米と同時にアメリカ人の家庭に飛び込むことは、アメリカの生活文化や語学にも、かえって素早く慣れて良かった面もありました。学生ビザの身分では正規に働けない外国人学生ですから、日曜日は富裕層の家を周り、屋内の掃除などをするアルバイトが有ればで、小遣い稼ぎもしたものです。
現在の学生は春、冬、夏休みやは帰国するか、アメリカ国内旅行などで、時間を使っているようですが、私の時代は円とドルの格差が大きく皆が貧乏学生で、時間のある長い休みの時には富裕層の家庭の、大掃除などのアルバイトをしているという生活で過ごしたものです。
サンフランシスコの大抵の富裕層はユダヤ系の人で占めていて、十代の頃にユダヤ人強制収容所で、腕に刺青の通し番号を入れられ、あのアウシュビッツ強制収容所から奇跡の生還をし、アメリカに戦後渡り、富をなしたが家族をアウシュビッツで失った悲しい歴史の話をする、苦労人のお婆ちゃんもいました。
アウシュビッツ強制収容所で何時ガス室に送られるか分からない、過酷な経験をした人に比べると、未来のための今の学生生活は苦労のうちには入らないと思えて、帰路のサンフランシスコの坂道を歩いていたものです。この街は「1日に四季のある町」と言われるように、朝は春めいて、昼は初夏になり、夕方から夜にかけては冬が来たような気温の街です。57年まえの当時はビートルズの「ヘイ・ジュード」(Hey Jude)の歌が大はやりで、どこへ行っても ♪♪~Hey Jude don't make it bad~♪♪が聞こえて来て、徴兵でベトナムの戦線に送られてゆく若者もいて、戦争はごく身近なものであり、若者のベトナム反戦のデモンストレーション集会が至る所であり、髪に花飾りをして若者は平和を歌っていたものです。
日本での大学1年は60年安保闘争で迎えられ、暗い学生生活が東京での幕開けでした。
東京の学生生活と研修時代は、人々は経済成長にガムシャラに働き詰めの、暗い日々を送っていた後だけに、サンフランシスコの街はヒッピー文化花ざかりで、ベトナムでの戦時中でありながら、自由を謳歌しながら明るく反戦の意思表示をしている若者が、Hey Judeを歌い溢れて、その風景は余りにも日本との温度差に、戸惑いを感じたのも確かです。
1ドルが360円という為替レートの厳しい時代、海外からの貧乏留学生の生活はいろいろと言い難い辛苦もありましたが、いまでは生涯のいい体験にもなりました。84歳になった今も、この歌を聞くたびにサンフランシスコで青春を過ごした日々を思い出します。
そして今も変わらないのはサンフランシスコのビクトリア風の、街並みのたたずまいです。
私にとってアメリカ生活最初のサンフランシスコは、青春の日々を時間を惜しんで、勉学と労働とを必死にこなし、切磋琢磨した地でもあり、サンフランシスコはアメリカ 57年前の、出発点でもあります。



沖縄県の米軍北部訓練場返還地で米軍廃棄物を回収する活動を巡り公務執行妨害や火薬類取締法違反など複数の罪に問われている同県東村のチョウ類研究者、秋乃さん(46)の判決公判が6日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)で開かれた。佐藤裁判長は被告の研究者に懲役3年、執行猶予4年、罰金30万円(求刑懲役4年、罰金45万円)を言い渡した(怒)。公務執行妨害罪については無罪とした。
斎藤 陽子3-6 トランプ大統領がメキシコとカナダに25%の関税を昨日3月4日から導入したことを受けて、アメリカでの食料品は2%ほど、値上がりするとされています。価格の上昇で人がどんどん買わなくなり、アボカドはメキシコから来ているので、値段があがる一方で、ロスアンゼルスに多いメキシコ料理店のメニュー表の価格も値上りすることでしょう。
アメリカは輸入する果物の53%、野菜の89%をメキシコとカナダに頼っています。
研究機関の試算では、関税導入の影響で食料品は最大2%ほど値上がり、ひと家庭当たりの生活費は年間2000ドル=30万円ほど増えるとしていて、トランプ大統領の荒っぽい政策の被害はアメリカの家庭に大きく影響して来るでしょう。
また、自動車の価格への影響も大きく、新車は最大180万円ほど値上がり、平均価格は5万ドル=750万円を超える見込みです。既に中古車にシフトする消費者が増え始め、中古車価格も上がると予想されています。
南カリフォルニアの雨季のシーズンは3月で終わりとなりますが、今年は雨が少ない雨季でしたが、水の好きな沖縄から来た月桃は、気丈夫に頑張り緑の葉をつやつやと輝かせ、ビワの木は枝の先に新芽を作り、ひと回りおおきくなっています。




仲松 健雄 『琉球民謡協会関東支部 第38回定期総会・懇親会』日本教育会館 喜山倶楽部で開催され、新支部長に仲松秀市さんが就任、片峯智恵子 前支部長は理事長に就任✨会員数235名が所属す琉球民謡協会関東支部の発展と繁栄を誓い合いお開きとなりました.



3-20 春分の日 ユンタンの孫たちとコ一プ、ジュンク堂で遊ぶ/古美術なるみ堂で、右から店主の翁長良明さん、前田比呂也さん、彬さん親子

近鉄永和駅前「万博、カジノ反対市民集会」
☆大阪万博344億木造リング、竹中平蔵とミサワホーム竹中宜雄会長兄弟の利権でフィンランド産木材の使用疑惑
☆2025年のいま、世界は気候変動や戦争、AI(人工知能)の急速な発達など、様々な問題や課題を抱えていますが、今回の万博がこうした大きな問題に向き合っているとは思えません。そういう大きなテーマへの言及はあっても、『お飾り』や『ウォッシュ(見せかけ)』になっているようにみえます。気候変動への対応を考えれば、本来、こういうイベントをやるべきではない。たった半年間のために木材を切って持ってきたり埋め立て地を開発したり、そういう行為が気候変動対策と矛盾しています」(朝日新聞、3月12日)
<



2025年3月 『琉球』浦崎成子「【大城宜武さん追悼】さようならポパイ」/また友人が居なくなった。


大濱 聡 3-16 · ■『沖縄タイムス』に連載していた木名瀬高嗣 東京理科大学教授の「オペラ開拓――粟國安彦と沖縄――」が36回で終了した。
■粟國安彦(1941-1990)は南大東島出身のオペラ演出家。ローマサンタ・チェチーリア音楽院・演出を主席で卒業、日本人として初めてローマ歌劇場の演出助手になる。昭和54年度芸術選奨文部大臣賞新人賞受賞。「トスカ」「蝶々夫人」「フィガロの結婚」「椿姫」など藤原歌劇団、二期会他で多数のオペラを演出。がんのため48歳で逝去。
■45年前、番組の取材で藤原歌劇団に粟國を訪ねてインタビューしたことがある。沖縄でのオペラの可能性と期待を語ってくれた。早逝が惜しまれる。


関連:1996年9月 『新沖縄文学』85号 重田辰弥「疾走した寵児・粟国安彦」





3月14日 なるみ堂で、左から店主の翁長良明さん、屋良朝信さん、スウェーデン出身のヘンリック・ホカンソンさん/沖縄県立博物館・美術館館で里井洋一館長、屋良朝信さん/左から與那覇政直美術館副参事、屋良朝信さん、前田比呂也美術館班長/真栄里泰山さん、屋良朝信さん
大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 3-11 費用は増えない→増えた メタン爆発しない→爆発した チケット売れる→売れない 個人情報抜かない→抜ける リング護岸が浸食⬅️イマココ 万博行ったらダメ???? 中止するべき。責任者出てこい。万博の大屋根リング護岸が浸食被害 海水注入後に強風影響か | 毎日新聞
3-10 日本共産党の山添拓議員は7日の参院予算委員会で、海上自衛隊が紛争当事国であるウクライナとの多国間軍事演習に参加していた事実を防衛省が公表していなかった問題を取り上げ追及しました。同軍事演習「シーブリーズ」は米国とウクライナが共催する多国間演習で、昨年9月はウクライナ南部とクリミア半島に面し緊張が高まるブルガリア沖の黒海で実施。海自は米軍、ウクライナ軍などと機雷の水中処分などの訓練を行ったとされていますが公表されていませんでした。中谷元・防衛相は、同演習について自衛隊は2021年にオブザーバーとして初参加し、22年はウクライナ情勢勃発により中止、23年から本参加を開始し、24年には英国での演習に1人、ブルガリアに10人派遣したと説明しました。



3月8日 小島摩文鹿児島純心大学教授(父小島瓔禮/祖父又吉康和) 那覇日誌 /沖縄県立博物館・美術館 民家前/新城良一さん、小島教授/古美術なるみ堂で右から店主の翁長良明さん、小島教授、松島弘明さん



斎藤 陽子ーー7【思い出のアルバム】
57年まえ航空便はべらぼうに高価で、フライト便も少ない頃、貨客船の最終運航便 プレジデント ライン社のクリーブランド号に乗り込んで、横浜港から2週間をかけて、朝日に映える早朝のゴールデンゲイト・ブリッジの下を抜け、サンフランシスコ港に到着した日を思い出しています。

57年前の当時1ドルが360円の時代、日本人は日本国から円の持ち出しも規制される貧しい日本の国力でした。
当時サンフランシスコでアパートを借りて、大学へ通学する日本人の留学生には、授業料免除の恩典を得ても、生活する上では経済的には苦しいものでした。
当時のほとんどの留学生はサンフランシスコの富裕層の家に寄生し、5時頃までには急いで帰宅し、寄生している家の夕食準備の手伝いと後片付けなどに従事し、朝は早朝に起きて犬の散歩と家族の朝食作りをこなして、学業の一日が始まります。土曜日は寄生している大きな家の掃除や洗濯アイロンがけやシルバー食器磨きなどでのメイド業で一日過ごし、夜は家人がパーティーなどへ出かけると、子どもたちのシッターをする等で、留学中の「屋根と食事」が保証されるという生活を得て、勉学をする日々でした。
これがほとんどの日本人留学生の生きる方法で、そういう学生はスクールガールまたはスクールボーイと呼ばれ、大学の昼食時間には日本人学生同士が出会うと、寄宿先の主人の悪口を言ってウサ晴らしをしたものです。
日本で大学も修め、天職とする獣医師にもなって、この地でお手伝いさんのようなメイド業の労働をしなくてはならない自分の姿に、気持ちの沈むこともありましたが、若いということはそれまで経験したことのないメイド業までも、面白がっている自分を楽しんだ面もありました。
当時は日本とは随分格差の有ったアメリカの生活でしたから、生活文化の面では随分学ぶことも多く、後の私のアメリカでの永住生活に、この頃アメリカの生活習慣を学んだことは、後々とてもプラスになっています。
渡米と同時にアメリカ人の家庭に飛び込むことは、アメリカの生活文化や語学にも、かえって素早く慣れて良かった面もありました。学生ビザの身分では正規に働けない外国人学生ですから、日曜日は富裕層の家を周り、屋内の掃除などをするアルバイトが有ればで、小遣い稼ぎもしたものです。
現在の学生は春、冬、夏休みやは帰国するか、アメリカ国内旅行などで、時間を使っているようですが、私の時代は円とドルの格差が大きく皆が貧乏学生で、時間のある長い休みの時には富裕層の家庭の、大掃除などのアルバイトをしているという生活で過ごしたものです。
サンフランシスコの大抵の富裕層はユダヤ系の人で占めていて、十代の頃にユダヤ人強制収容所で、腕に刺青の通し番号を入れられ、あのアウシュビッツ強制収容所から奇跡の生還をし、アメリカに戦後渡り、富をなしたが家族をアウシュビッツで失った悲しい歴史の話をする、苦労人のお婆ちゃんもいました。
アウシュビッツ強制収容所で何時ガス室に送られるか分からない、過酷な経験をした人に比べると、未来のための今の学生生活は苦労のうちには入らないと思えて、帰路のサンフランシスコの坂道を歩いていたものです。この街は「1日に四季のある町」と言われるように、朝は春めいて、昼は初夏になり、夕方から夜にかけては冬が来たような気温の街です。57年まえの当時はビートルズの「ヘイ・ジュード」(Hey Jude)の歌が大はやりで、どこへ行っても ♪♪~Hey Jude don't make it bad~♪♪が聞こえて来て、徴兵でベトナムの戦線に送られてゆく若者もいて、戦争はごく身近なものであり、若者のベトナム反戦のデモンストレーション集会が至る所であり、髪に花飾りをして若者は平和を歌っていたものです。
日本での大学1年は60年安保闘争で迎えられ、暗い学生生活が東京での幕開けでした。
東京の学生生活と研修時代は、人々は経済成長にガムシャラに働き詰めの、暗い日々を送っていた後だけに、サンフランシスコの街はヒッピー文化花ざかりで、ベトナムでの戦時中でありながら、自由を謳歌しながら明るく反戦の意思表示をしている若者が、Hey Judeを歌い溢れて、その風景は余りにも日本との温度差に、戸惑いを感じたのも確かです。
1ドルが360円という為替レートの厳しい時代、海外からの貧乏留学生の生活はいろいろと言い難い辛苦もありましたが、いまでは生涯のいい体験にもなりました。84歳になった今も、この歌を聞くたびにサンフランシスコで青春を過ごした日々を思い出します。
そして今も変わらないのはサンフランシスコのビクトリア風の、街並みのたたずまいです。
私にとってアメリカ生活最初のサンフランシスコは、青春の日々を時間を惜しんで、勉学と労働とを必死にこなし、切磋琢磨した地でもあり、サンフランシスコはアメリカ 57年前の、出発点でもあります。



沖縄県の米軍北部訓練場返還地で米軍廃棄物を回収する活動を巡り公務執行妨害や火薬類取締法違反など複数の罪に問われている同県東村のチョウ類研究者、秋乃さん(46)の判決公判が6日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)で開かれた。佐藤裁判長は被告の研究者に懲役3年、執行猶予4年、罰金30万円(求刑懲役4年、罰金45万円)を言い渡した(怒)。公務執行妨害罪については無罪とした。
斎藤 陽子3-6 トランプ大統領がメキシコとカナダに25%の関税を昨日3月4日から導入したことを受けて、アメリカでの食料品は2%ほど、値上がりするとされています。価格の上昇で人がどんどん買わなくなり、アボカドはメキシコから来ているので、値段があがる一方で、ロスアンゼルスに多いメキシコ料理店のメニュー表の価格も値上りすることでしょう。
アメリカは輸入する果物の53%、野菜の89%をメキシコとカナダに頼っています。
研究機関の試算では、関税導入の影響で食料品は最大2%ほど値上がり、ひと家庭当たりの生活費は年間2000ドル=30万円ほど増えるとしていて、トランプ大統領の荒っぽい政策の被害はアメリカの家庭に大きく影響して来るでしょう。
また、自動車の価格への影響も大きく、新車は最大180万円ほど値上がり、平均価格は5万ドル=750万円を超える見込みです。既に中古車にシフトする消費者が増え始め、中古車価格も上がると予想されています。
南カリフォルニアの雨季のシーズンは3月で終わりとなりますが、今年は雨が少ない雨季でしたが、水の好きな沖縄から来た月桃は、気丈夫に頑張り緑の葉をつやつやと輝かせ、ビワの木は枝の先に新芽を作り、ひと回りおおきくなっています。
05/29: 世相ジャパン 2025⓽
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com

6月14日 父の日にちなんで午前 ゆんたん娘一家と、浦添市美術館を見学。○美術館で金城聡子さん

「世界遺産 中国・泉州市ー伝統文化の今ー」


「泉州:宋朝(そうちょう)・元朝(げんちょう)における世界のエンポリウム 中国」が2021年7月25日 ユネスコ世界遺産に登録されました。浦添市と泉州市との交流は、はるか琉球王朝時代にまで遡ります。察度王が朝貢のために浦添から使節を派遣し、その際に入港したのが泉州でした。琉球と中国が公的に交流を開始した「ゆかりの地」である泉州の遺跡群が世界遺産に登録されたことは、友好都市である浦添市にとってもたいへん喜ばしいことです。
この度、世界遺産に登録された遺跡群は、世界のエンポリウム(商業の中心地)として、宋・元時代(西暦10~14世紀)にアジアの海事貿易にとって、非常に重要な時期に繁栄したエリアです。その一帯には、ペルシャやアラブから来航した商人が拠点とした、イスラム教のモスク・清浄寺(せいじょうじ)をはじめ、仏教寺院・開元寺(かいげんじ)、道教の海の守り神・媽祖(まそ)をまつる天后宮(てんこうぐう)など、信仰の異なる建造物が遺されており、そのうち22か所の遺跡群が世界遺産に登録されたことは、世界の宗教や文化が争うことなく共存できるという平和のメッセージとも言えるでしょう。→浦添市
斎藤 陽子 ·6ー13 不法移民の取り締まりをめぐり、ロサンゼルスではデモ隊とトランプ政権が、州兵や海兵隊の派遣を行い衝突が続いています。トランプ大統領とカリフォルニア州当局との対立は、トランプ氏がロサンゼルスに州兵を派遣したことで激化しています。トランプ氏はロサンゼルスを「解放する」と誓っていて、カリフォルニア州のギャヴィン・ニューサム知事は、「主主義への攻撃」だと非難しています。
どこのテレビのチャンネルを観ても、デモ隊と州兵や海兵隊との衝突画面ばかりの、この3、4日、テレビを見るたびに気分が滅入ってしまいます。アメリカンドリームの有った、この国は一体どこへ行ったのでしょう。トランプと言う独裁政治家の出現で、この国は夢も希望もない、心の貧しい国に成り下がりました。
こう言う時こそ、気分を変えて綺麗な花でも見るしかありません。今日の気温22℃と幾らか肌寒い日ですが、快適な木曜日です。庭のプルメリアも満開になり、夏がやってきたことを気づかせてくれます。

大濱 聡·6ー10 ■9日、東京から元東京新聞論説委員の白鳥龍也氏(ジャーナリスト)が来沖、来村。11:00前、「ただいま那覇に到着しました」との連絡をMessengerでもらう。
■白鳥氏の来沖に合わせたかのように、「読谷村の米軍嘉手納基地内の自衛隊の施設で爆発 けが人の情報も」との速報が正午のNHK全国ニュースの最後に突っ込みで入った。12:29には1,2分の特設枠で同じニュースが繰り返された(現場は我が家から直線距離で約4㎞)。



仲松 健雄 · 6ー10『東京竹富郷友会創立100周年記念式典・祝賀会』東京竹富郷友会が創立100年を迎え、記念式典と祝賀会が武蔵小杉にある川崎市コンベンションホールで開催され300名を超える参加者で大盛況❗️大谷喜久男会長の主催者挨拶に続いて、竹富町から来賓として参加した前泊町長ならびに内盛公民館長が挨拶✨私も祝辞を述べさせていただきました????




戦後80年沖縄から問う・新刊3冊刊行記念 「緊急!トークイベント【ひめゆりの少女】の声を聞け!」6月7日(土)15:00~17:00 ジュンク堂書店那覇店B1Fイベント会場〈登壇者〉諸見里道浩(ジャーナリスト・『沖縄「平和宣言」全文を読む』仲松昌次(フリーディレクター・『島うたに刻まれた沖縄』)山本邦彦(高文研『新版 ひめゆりの少女・十六歳の戦場』編集者)写真:諸見里道浩さん/仲松昌次さん
朝日新聞 京都市議会は6日、自民党の西田昌司参院議員が「ひめゆりの塔」(沖縄県糸満市)の展示内容を「歴史の書き換え」などと発言したことをめぐり、「強い遺憾の意を表明する」とした決議案を賛成多数で可決した。
決議案では、西田氏の発言や見解は「沖縄県民の心を深く傷つけるものと言わざるを得ない」と指摘。「京都選出の議員がこのような発言をしたことに強い遺憾の意を表明し、沖縄県民の心情に寄り添い、沖縄戦の歴史に真摯(しんし)に向き合うこと」を求めた。
自民党や公明党、一部の無所属議員は、西田氏の発言に一切触れず「京都と沖縄の絆を次世代に伝え平和社会の実現を目指す」とする決議案を提案したが、否決された。




6月5日 国際通り/那覇市民ギャラリー「新城征孝 絵画展」

大濱 聡 · 6ー3■6.2放送のテレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」〈日米協議 “交渉カード”に防衛装備品購入が浮上〉――大変わかりやすい内容でした。■トランプ大統領1期目・安倍政権時「ステルス戦闘機『F15』147機購入」 ※総額は?■「負担増大の“思いやり予算” 福利厚生施設まで」「各国の米軍駐留負担費比率 日本約75% イタリア・韓国約40% ドイツ約30% 突出する日本」 ※米軍駐留費より日本国民にもっと温かい“思いやり”を!“米国”より“米穀”を!
■石破首相「日米安保条約 日米地位協定の改定主張(去年9月)」「思いやり予算はもっと減らす余地がある(2006年)」いずれも封印 ※政治家の言行不一致、無責任発言は今に始まったことではないが……。




2025年6月 来間泰男『沖縄の昭和戦前期 よくわかる沖縄の歴史』日本経済評論社(東京都千代田区神田駿河台2-7-7)

6月14日 父の日にちなんで午前 ゆんたん娘一家と、浦添市美術館を見学。○美術館で金城聡子さん

「世界遺産 中国・泉州市ー伝統文化の今ー」


「泉州:宋朝(そうちょう)・元朝(げんちょう)における世界のエンポリウム 中国」が2021年7月25日 ユネスコ世界遺産に登録されました。浦添市と泉州市との交流は、はるか琉球王朝時代にまで遡ります。察度王が朝貢のために浦添から使節を派遣し、その際に入港したのが泉州でした。琉球と中国が公的に交流を開始した「ゆかりの地」である泉州の遺跡群が世界遺産に登録されたことは、友好都市である浦添市にとってもたいへん喜ばしいことです。
この度、世界遺産に登録された遺跡群は、世界のエンポリウム(商業の中心地)として、宋・元時代(西暦10~14世紀)にアジアの海事貿易にとって、非常に重要な時期に繁栄したエリアです。その一帯には、ペルシャやアラブから来航した商人が拠点とした、イスラム教のモスク・清浄寺(せいじょうじ)をはじめ、仏教寺院・開元寺(かいげんじ)、道教の海の守り神・媽祖(まそ)をまつる天后宮(てんこうぐう)など、信仰の異なる建造物が遺されており、そのうち22か所の遺跡群が世界遺産に登録されたことは、世界の宗教や文化が争うことなく共存できるという平和のメッセージとも言えるでしょう。→浦添市
斎藤 陽子 ·6ー13 不法移民の取り締まりをめぐり、ロサンゼルスではデモ隊とトランプ政権が、州兵や海兵隊の派遣を行い衝突が続いています。トランプ大統領とカリフォルニア州当局との対立は、トランプ氏がロサンゼルスに州兵を派遣したことで激化しています。トランプ氏はロサンゼルスを「解放する」と誓っていて、カリフォルニア州のギャヴィン・ニューサム知事は、「主主義への攻撃」だと非難しています。
どこのテレビのチャンネルを観ても、デモ隊と州兵や海兵隊との衝突画面ばかりの、この3、4日、テレビを見るたびに気分が滅入ってしまいます。アメリカンドリームの有った、この国は一体どこへ行ったのでしょう。トランプと言う独裁政治家の出現で、この国は夢も希望もない、心の貧しい国に成り下がりました。
こう言う時こそ、気分を変えて綺麗な花でも見るしかありません。今日の気温22℃と幾らか肌寒い日ですが、快適な木曜日です。庭のプルメリアも満開になり、夏がやってきたことを気づかせてくれます。

大濱 聡·6ー10 ■9日、東京から元東京新聞論説委員の白鳥龍也氏(ジャーナリスト)が来沖、来村。11:00前、「ただいま那覇に到着しました」との連絡をMessengerでもらう。
■白鳥氏の来沖に合わせたかのように、「読谷村の米軍嘉手納基地内の自衛隊の施設で爆発 けが人の情報も」との速報が正午のNHK全国ニュースの最後に突っ込みで入った。12:29には1,2分の特設枠で同じニュースが繰り返された(現場は我が家から直線距離で約4㎞)。



仲松 健雄 · 6ー10『東京竹富郷友会創立100周年記念式典・祝賀会』東京竹富郷友会が創立100年を迎え、記念式典と祝賀会が武蔵小杉にある川崎市コンベンションホールで開催され300名を超える参加者で大盛況❗️大谷喜久男会長の主催者挨拶に続いて、竹富町から来賓として参加した前泊町長ならびに内盛公民館長が挨拶✨私も祝辞を述べさせていただきました????




戦後80年沖縄から問う・新刊3冊刊行記念 「緊急!トークイベント【ひめゆりの少女】の声を聞け!」6月7日(土)15:00~17:00 ジュンク堂書店那覇店B1Fイベント会場〈登壇者〉諸見里道浩(ジャーナリスト・『沖縄「平和宣言」全文を読む』仲松昌次(フリーディレクター・『島うたに刻まれた沖縄』)山本邦彦(高文研『新版 ひめゆりの少女・十六歳の戦場』編集者)写真:諸見里道浩さん/仲松昌次さん
朝日新聞 京都市議会は6日、自民党の西田昌司参院議員が「ひめゆりの塔」(沖縄県糸満市)の展示内容を「歴史の書き換え」などと発言したことをめぐり、「強い遺憾の意を表明する」とした決議案を賛成多数で可決した。
決議案では、西田氏の発言や見解は「沖縄県民の心を深く傷つけるものと言わざるを得ない」と指摘。「京都選出の議員がこのような発言をしたことに強い遺憾の意を表明し、沖縄県民の心情に寄り添い、沖縄戦の歴史に真摯(しんし)に向き合うこと」を求めた。
自民党や公明党、一部の無所属議員は、西田氏の発言に一切触れず「京都と沖縄の絆を次世代に伝え平和社会の実現を目指す」とする決議案を提案したが、否決された。




6月5日 国際通り/那覇市民ギャラリー「新城征孝 絵画展」

大濱 聡 · 6ー3■6.2放送のテレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」〈日米協議 “交渉カード”に防衛装備品購入が浮上〉――大変わかりやすい内容でした。■トランプ大統領1期目・安倍政権時「ステルス戦闘機『F15』147機購入」 ※総額は?■「負担増大の“思いやり予算” 福利厚生施設まで」「各国の米軍駐留負担費比率 日本約75% イタリア・韓国約40% ドイツ約30% 突出する日本」 ※米軍駐留費より日本国民にもっと温かい“思いやり”を!“米国”より“米穀”を!
■石破首相「日米安保条約 日米地位協定の改定主張(去年9月)」「思いやり予算はもっと減らす余地がある(2006年)」いずれも封印 ※政治家の言行不一致、無責任発言は今に始まったことではないが……。




2025年6月 来間泰男『沖縄の昭和戦前期 よくわかる沖縄の歴史』日本経済評論社(東京都千代田区神田駿河台2-7-7)