07/27: 萩原正徳と『旅と伝説』
今は亡き岡本恵徳先生は私の顔を見るたび「もっと奄美資料に注目してくれ」が口癖であった。私は伯父や伯母の連れ合いが奄美出身であったから特に奄美を意識したことがないが、琉球文化には当然に奄美も入っていると思っている。奄美の図書館には島尾敏雄氏に会ってみたいと2回ほど行ったが何時も休館日だった。島尾敏雄氏には会えなかったが、その代わりといっていいか分からないが山下欣一氏に出会った。
喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下欣一氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの萩原資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。山下氏も萩原正徳を当然と言えば当然だが色々と紹介して居られた。それに用いた資料だが次に紹介する。
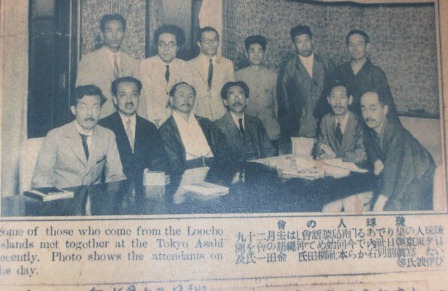

前列右端が柳田国男、左端が比嘉春潮/後列右から萩原正徳、大藤時彦、瀬川清子
1944年3月『民間伝承』柳田国男「『旅と伝説』について」□(略)改めてもう一度、初めから読み返して見たい気がする。公平に批判してどの部分、一ばん後世に役立つ仕事だったかを、考へ且つ説いて見たくもなる。
私の処にはもう主要記事の索引も出来て居るのだが、この判定は実はさう容易な業では無い。しかし先ず大まかに考へて、婚礼誕生葬祭その他の特集号を出し、又昔話を二度まで出した頃などが、全盛期だったと言へるかもしれない。こんなにまで多数の同志があったのかと、驚くほどの人々が全国の各地から、何れも好意づくだけでよい原稿を寄せ、所謂陣容を輝かしてくれたのみならず、此時を境にそれぞれの問題に対する理解常識が、目に見えて躍進したので、之を読んで居ない人の云ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料といふものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを、実地に証明してくれたのである。
その以外に今一つ承認しなければならぬことは、萩原君は故郷の奄美大島の為に、この雑誌を通して中々よく働いて居る。それには同郷知友の共鳴支援といふことも条件ではあったが、とにかくに全十六巻を通じて、奄美大島に関する報告は多く、又清新な第一次の資料が多かったことは争へない。その一つの例として手近に私の心づいたことをあげると、第一巻のたしか二号か三号に、島の先輩の露西亜学者昇曙夢さんが、アモレヲナグ即ち天降女人の事を書いて、我々に大きな印象を与へ、又より多くを知りたがらせて居たのだが、それが約十六年を隔てて最終号の中に、今度は金久正君といふ若い同志が、それを詳しく書いて我々の渇望を医して居る。もう「旅と伝説」さへ大切に保存して置けばこの世界的興味のある一問題は、永久に学問の領分からは消えないのである。或ひはそれほどまで大きな問題だと思はぬであらう人たちの為に、出来るだけ簡単に前後二ヶ所に出て居る天降女人の事を書き伝へ、出来るならば此上にももっと豊富な資料の、集まって来る機縁を促したい。(略)
奄美大島といふところは、私の知る限りでも、内部歴史の珍しく豊かな島であった。書いた記録がといふものは僅かしか残らぬが、近い百年二百年の間にも避ければ避けたかった実に色々な経験をしてゐる。さうして全体に今は古い拘束から解き放たれて、新時代のあらゆる機会を利用し、すぐれた人物が輩出して居るのである。住民自身としては忘れた方がよいやうな、外の者からは是非参考の為に聴いて置きたいやうな、無数の思ひ出をかかへて、まだ其処理を付けずに居るといふ感じがある。此数からいふと、萩原君の如き人がもっと辛抱強く、古い埋もれたことを尋ね出さうとする知友を糾合して居てくれたらと思はずには居られぬのだが、それをもう謂って見ても仕方が無い。それよりも雑誌をその時々の慰みなどとは考へずに、いつまでも之を精読する者の、是から日本にも多くなるやうに、我々もどうかして残るやうな雑誌を作って行きたい。
1981年7月『道之島通信』83号「民俗学開拓に貢献 萩原正徳(1896~1950)」□はじめに 1928年(昭和3年)から1944年(昭和19年)まで、東京で『旅と伝説』という月刊雑誌を発行、日本民族学の発展に著しく貢献したのが萩原正徳である。正徳は、1896年(明治29年)名瀬市金久に生まれ、若くして上京、東京高等工芸学校を卒業、27歳の時夫人ウメさん(千葉県出身)を娶った。弟に利用と厚生がおり、厚生は鹿児島一中から一高、東大へ進んだ奄美の秀才として名を馳せた人である。酒と島うたが好きで、子供が喧嘩して泣いて帰ると「泣かされて帰る奴がいるか、相手を泣かして来い」と、一人息子の正道を叱るくらいの気骨の持ち主でもあった。三元社という写真製版の会社を経営する一方、柳田国男らの民俗研究グループに参加、奄美をはじめ、各地の研究報告を『旅と伝説』に掲載、記録を歴史に残した。「若い頃から頭は、はげていましたので、年の割に老けて見えましたよ」と八十歳になったウメさんは話す。耳が悪かったため、兵役を免れ、柳田国男にどなられても笑っていたという。
1998年10月『柳田國男全集 第6巻 月報13』山下欣一「『海南小記』ー奄美の旅前後」□(略)最初の伊波普猷の奄美来訪は1918年(大正7)1月であった。これは私立大島郡教育会・二部研究会(瀬戸内・宇検)による招聘である。この時の中心になったのは二部研究会長で古仁屋小学校長永井龍一と当時篠川農学校教諭竹島純(沖縄師範卒)であった。この2名は伊波普猷・比嘉春潮を出迎えのために名瀬へ出張するが、船待ちのため十数日滞在を余儀なくされ、その間、奄美の文献資料を調査したりしている。この時『奄美大島史』の著者である坂口徳太郎も鹿児島県立大島中学校に勤務していたので、その指導も受けたと考えられる。
伊波普猷は、この第1回の旅で『南島雑話』、『奄美史談』などを沖縄へ借用し、筆写させ、沖縄県立図書館へ収蔵し閲覧に供したのである。(略)伊波普猷の奄美招聘の中心にいた竹島純は伊波普猷の講演記録を伊波の「序に代へて」を付して1931年(昭和6)に大島郡教育会から『南島史考』としてまとめている。また後で永井龍一は鹿児島に居を移し、『南島雑話』、『補遺篇』、『奄美史談』などの文献資料の自費刊行を試みている。この『南島雑話』刊行に刺激された永井龍一の兄亀彦(博物学者)は『南島雑話』の編著者を薩摩藩上士名越左源太時敏と確認し、また名越家で『遠島日記』をも発見し、これらを自費刊行している。これらは、昭和初年から、終戦直後に及んだ作業であった。永井兄亀・龍一兄弟は名瀬の与人役政家の一族である。父永井長昌喜は漢学者で教育者であった。
亀彦・龍一の姉よしは萩原家に嫁し、その子息が正徳・利用・厚生の兄弟である。叔父に『奄美史談』の著者都成植義(南峰)がいる。亀彦・龍一の甥に当る萩原正徳は上京し、東京高等工業学校で学び、海軍省水路部をへて写真製版業を営み、三元社を興した。柳田国男の指導を受けて『旅と伝説』を刊行した。これには昇曙夢・岩倉市郎・金久正などの奄美の研究者が登場しているのは故なしとしないのである。
喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下欣一氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの萩原資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。山下氏も萩原正徳を当然と言えば当然だが色々と紹介して居られた。それに用いた資料だが次に紹介する。
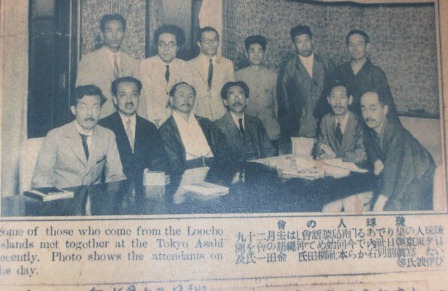

前列右端が柳田国男、左端が比嘉春潮/後列右から萩原正徳、大藤時彦、瀬川清子
1944年3月『民間伝承』柳田国男「『旅と伝説』について」□(略)改めてもう一度、初めから読み返して見たい気がする。公平に批判してどの部分、一ばん後世に役立つ仕事だったかを、考へ且つ説いて見たくもなる。
私の処にはもう主要記事の索引も出来て居るのだが、この判定は実はさう容易な業では無い。しかし先ず大まかに考へて、婚礼誕生葬祭その他の特集号を出し、又昔話を二度まで出した頃などが、全盛期だったと言へるかもしれない。こんなにまで多数の同志があったのかと、驚くほどの人々が全国の各地から、何れも好意づくだけでよい原稿を寄せ、所謂陣容を輝かしてくれたのみならず、此時を境にそれぞれの問題に対する理解常識が、目に見えて躍進したので、之を読んで居ない人の云ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料といふものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを、実地に証明してくれたのである。
その以外に今一つ承認しなければならぬことは、萩原君は故郷の奄美大島の為に、この雑誌を通して中々よく働いて居る。それには同郷知友の共鳴支援といふことも条件ではあったが、とにかくに全十六巻を通じて、奄美大島に関する報告は多く、又清新な第一次の資料が多かったことは争へない。その一つの例として手近に私の心づいたことをあげると、第一巻のたしか二号か三号に、島の先輩の露西亜学者昇曙夢さんが、アモレヲナグ即ち天降女人の事を書いて、我々に大きな印象を与へ、又より多くを知りたがらせて居たのだが、それが約十六年を隔てて最終号の中に、今度は金久正君といふ若い同志が、それを詳しく書いて我々の渇望を医して居る。もう「旅と伝説」さへ大切に保存して置けばこの世界的興味のある一問題は、永久に学問の領分からは消えないのである。或ひはそれほどまで大きな問題だと思はぬであらう人たちの為に、出来るだけ簡単に前後二ヶ所に出て居る天降女人の事を書き伝へ、出来るならば此上にももっと豊富な資料の、集まって来る機縁を促したい。(略)
奄美大島といふところは、私の知る限りでも、内部歴史の珍しく豊かな島であった。書いた記録がといふものは僅かしか残らぬが、近い百年二百年の間にも避ければ避けたかった実に色々な経験をしてゐる。さうして全体に今は古い拘束から解き放たれて、新時代のあらゆる機会を利用し、すぐれた人物が輩出して居るのである。住民自身としては忘れた方がよいやうな、外の者からは是非参考の為に聴いて置きたいやうな、無数の思ひ出をかかへて、まだ其処理を付けずに居るといふ感じがある。此数からいふと、萩原君の如き人がもっと辛抱強く、古い埋もれたことを尋ね出さうとする知友を糾合して居てくれたらと思はずには居られぬのだが、それをもう謂って見ても仕方が無い。それよりも雑誌をその時々の慰みなどとは考へずに、いつまでも之を精読する者の、是から日本にも多くなるやうに、我々もどうかして残るやうな雑誌を作って行きたい。
1981年7月『道之島通信』83号「民俗学開拓に貢献 萩原正徳(1896~1950)」□はじめに 1928年(昭和3年)から1944年(昭和19年)まで、東京で『旅と伝説』という月刊雑誌を発行、日本民族学の発展に著しく貢献したのが萩原正徳である。正徳は、1896年(明治29年)名瀬市金久に生まれ、若くして上京、東京高等工芸学校を卒業、27歳の時夫人ウメさん(千葉県出身)を娶った。弟に利用と厚生がおり、厚生は鹿児島一中から一高、東大へ進んだ奄美の秀才として名を馳せた人である。酒と島うたが好きで、子供が喧嘩して泣いて帰ると「泣かされて帰る奴がいるか、相手を泣かして来い」と、一人息子の正道を叱るくらいの気骨の持ち主でもあった。三元社という写真製版の会社を経営する一方、柳田国男らの民俗研究グループに参加、奄美をはじめ、各地の研究報告を『旅と伝説』に掲載、記録を歴史に残した。「若い頃から頭は、はげていましたので、年の割に老けて見えましたよ」と八十歳になったウメさんは話す。耳が悪かったため、兵役を免れ、柳田国男にどなられても笑っていたという。
1998年10月『柳田國男全集 第6巻 月報13』山下欣一「『海南小記』ー奄美の旅前後」□(略)最初の伊波普猷の奄美来訪は1918年(大正7)1月であった。これは私立大島郡教育会・二部研究会(瀬戸内・宇検)による招聘である。この時の中心になったのは二部研究会長で古仁屋小学校長永井龍一と当時篠川農学校教諭竹島純(沖縄師範卒)であった。この2名は伊波普猷・比嘉春潮を出迎えのために名瀬へ出張するが、船待ちのため十数日滞在を余儀なくされ、その間、奄美の文献資料を調査したりしている。この時『奄美大島史』の著者である坂口徳太郎も鹿児島県立大島中学校に勤務していたので、その指導も受けたと考えられる。
伊波普猷は、この第1回の旅で『南島雑話』、『奄美史談』などを沖縄へ借用し、筆写させ、沖縄県立図書館へ収蔵し閲覧に供したのである。(略)伊波普猷の奄美招聘の中心にいた竹島純は伊波普猷の講演記録を伊波の「序に代へて」を付して1931年(昭和6)に大島郡教育会から『南島史考』としてまとめている。また後で永井龍一は鹿児島に居を移し、『南島雑話』、『補遺篇』、『奄美史談』などの文献資料の自費刊行を試みている。この『南島雑話』刊行に刺激された永井龍一の兄亀彦(博物学者)は『南島雑話』の編著者を薩摩藩上士名越左源太時敏と確認し、また名越家で『遠島日記』をも発見し、これらを自費刊行している。これらは、昭和初年から、終戦直後に及んだ作業であった。永井兄亀・龍一兄弟は名瀬の与人役政家の一族である。父永井長昌喜は漢学者で教育者であった。
亀彦・龍一の姉よしは萩原家に嫁し、その子息が正徳・利用・厚生の兄弟である。叔父に『奄美史談』の著者都成植義(南峰)がいる。亀彦・龍一の甥に当る萩原正徳は上京し、東京高等工業学校で学び、海軍省水路部をへて写真製版業を営み、三元社を興した。柳田国男の指導を受けて『旅と伝説』を刊行した。これには昇曙夢・岩倉市郎・金久正などの奄美の研究者が登場しているのは故なしとしないのである。
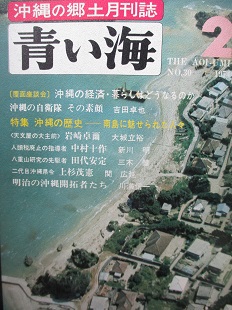

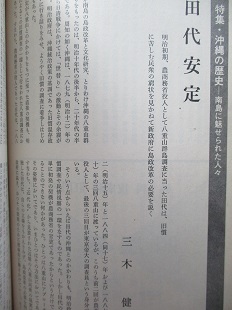
1974年2月号 雑誌『青い海』30号 大城立裕「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」
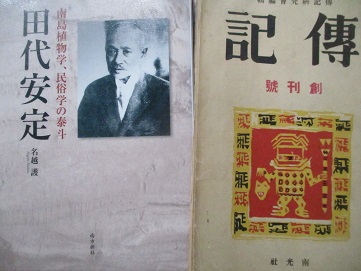
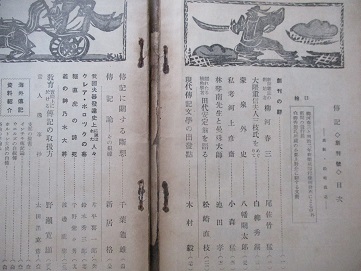


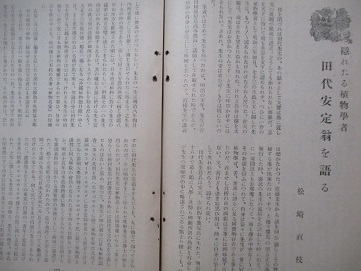
2017年3月 名越護『南島植物学、民俗学の泰斗 田代安定』南方新社/1934年年10月 南光社『傳記』創刊

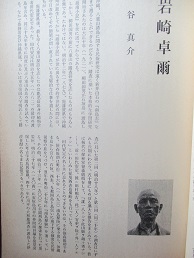

1974年1月『伝統と現代』谷真介「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」
1974年1月『伝統と現代』「日本フォークロアの先駆者」
田代安定(三木健)/笹森儀助(植松明石)/岩崎卓爾(谷真介)/鳥居龍蔵(小野隆祥)/佐々木喜善(菊池照雄)/柳田国男(牧田茂)/折口信夫(村井紀)/早川孝太郎(野口武徳)/筑土鈴寛(藤井貞和)/中山太郎(阿部正路)/南方熊楠(飯倉照平)/渋沢敬三(宮本馨太郎)/金田一京助(浅井亨)/知里真志保(藤本英夫)/伊波普猷(新里金福)/喜捨場永珣(牧野清)/石田英一郎(松谷敏雄)/菅江真澄(石上玄一郎)/近藤富蔵(浅沼良次)
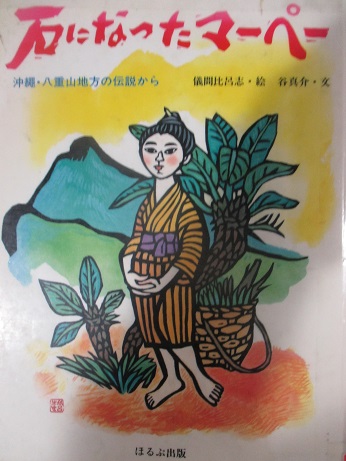
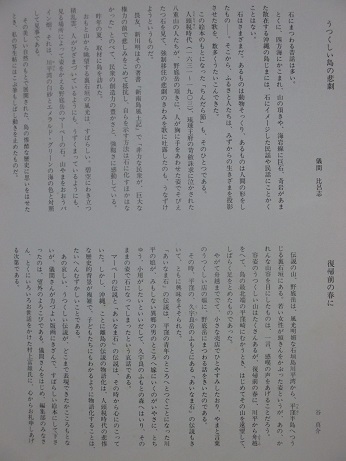
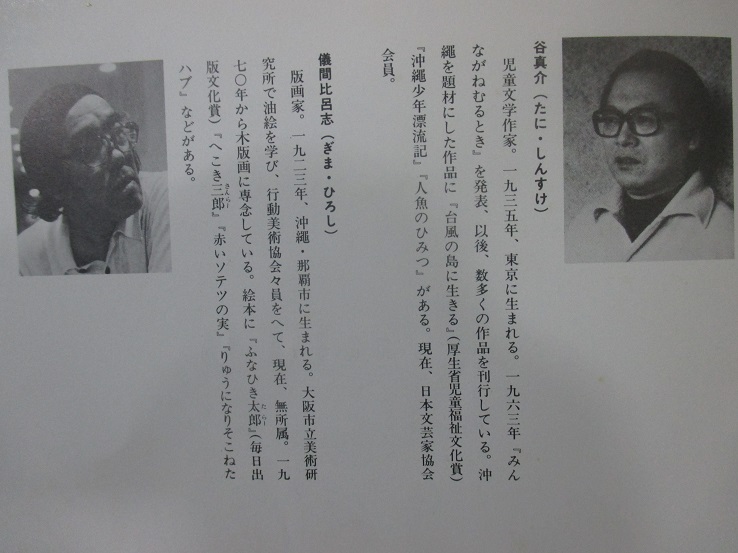
1985年5月 儀間比呂志・絵 谷真介・文『石になったマーペー 沖縄・八重山地方の伝説から』ほるぷ出版
1974年6月 『岩崎卓爾一巻全集』伝統と現代社
ひるぎの一葉/八重山研究/やえまカブヤー/石垣島気候篇/新撰八重山月令/気候雑纂/作品(俳句・短歌・詩)・その他。
註(語彙註)・・・西平守晴・沖縄関係資料室/岩崎卓爾と気候・・・畠山久尚・元気象庁長官/岩崎卓爾と八重山・・・谷川健一・民俗学者/岩崎卓爾翁のことども・・・瀬名波長宣・元石垣島測候所長/父・岩崎卓爾・・・菊池南海子・岩崎卓爾次女/年譜・書誌・・・谷真介①/後記
①谷真介 たに-しんすけ
1935- 昭和後期-平成時代の児童文学作家。
昭和10年9月7日生まれ。子どもの遊びから生まれた冒険世界を多彩な手法でえがき,作品に「みんながねむるとき」「ひみつの動物園」など。「沖縄少年漂流記」,「台風の島に生きる」(昭和51年児童福祉文化奨励賞)など,ノンフィクションも手がける。東京出身。中央大中退。本名は赤坂早苗。→コトバンク
岩崎卓爾年譜(抄録)ー谷真介
1882年ー8月、上杉茂憲、沖縄県令として八重山(石垣島)を巡回。この年、鹿児島の植物学者・田代安定が農商務省官吏として最初の八重山踏査を行う。
1891年ー10月、岩崎卓爾、第二高等中学校を退学し、北海道庁札幌一等測候所に気象研究生として入所。
1893年ー11月、岩崎卓爾、根室一等測候所に配属。この年、青森の笹森儀助が沖縄本島・先島諸島の民情踏査に赴く。
1894年ー5月、笹森儀助『南島探険』刊。8月、日清戦争始まる。
1897年ー6月、岩崎卓爾、富士山頂の測候を命じられる。10月、岩崎卓爾、中央気象台附属石垣島測候所勤務を拝命。12月、石垣島測候所長心得となる。
1899年ー4月、大島測候所長心得として奄美大島名瀬へ赴く。6月、妻・貴志子が仙台より来る。9月、石垣島測候所長として石垣島に帰任。
1900年ー5月、古賀辰四郎は、黒岩恒、宮島幹之助に協力を仰いで尖閣列島を調査。(尖閣列島の命名は黒岩恒)
1902年ーこの年の末、266年にわたって八重山島民を搾取しつづけていた人頭税廃止となる。
1904年ー2月、日露開戦。7月、鳥居龍造、川平仲間嶽貝塚を発掘調査。
1906年ー2月、菊池幽芳、川平大和墓発掘調査。春、岩崎卓爾、蝶の標本として「アカタテハ」「ヤマトシジミ」を岐阜の名和昆虫研究所へ送る。この年、岩崎卓爾、台北より来島した田代安定と会う。
1910年ーこの年。石垣島に白蟻の被害拡がる。イギリスのノルス来島。
1911年ー1月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻に関する通信」、6月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻群飛」。6月、強度の地震あり。岩崎卓爾、名蔵川良峡で「イワサキコノハチョウ」発見。
1912年ー4月、岩崎卓爾『八重山童謡集』刊。5月、岩崎卓爾、粟、稲、麦など害する夜盗虫(アハノヨトウムシ)の駆除法を名和昆虫研究所に問い合わせる。
1913年ー2月、貴志子夫人 7人の子を連れて仙台へ帰る。岩崎卓爾、「イワサキゼミ」「イワサキヒメハルゼミ」の新種発見。
1914年ー3月、岩崎卓爾、八重山通俗図書館を創設。5月、御木本幸吉が石垣島富崎で真珠養殖事業を始める、卓爾に協力を仰ぐ。
1916年ー8月、武藤長平七高教授が来島。
1920年ー9月ごろ岩崎卓爾、台風観測中に右眼を失明す。この年、岩崎卓爾『ひるぎの一葉』刊。
1921年ー岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに柳田国男を石垣港桟橋に迎える。
1922年ー4月17日、岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに上京、柳田国男を訪ねる。4月21日、一ツ橋如水館で開かれた「南島談話会」、出席者、岩崎卓爾、喜舎場永珣、上田万年、白鳥庫吉、三浦新七、新村出、幣原坦、本山桂川、移川子之蔵、中山太郎、折口信夫、金田一京助、東恩納寛惇、松本信広、松本芳夫その他。8月1日、暴風警報が出ているなかを田辺尚雄が民謡研究のため来島。
1923年ー2月、鎌倉芳太郎、桃林寺権現堂の芸術調査で来島。7月、岩崎卓爾、『やえまカブヤー』を八重山通俗図書館から刊行。8月、折口信夫が民俗採集のため来島。
1924年ー9月、岩崎卓爾、文芸同人結社セブン社を主宰、同人誌『せぶん』を創刊。本山桂川、民俗採集で来島、卓爾のすすめに応じて与那国島踏査に赴く→1925年『南島情趣』『与那国島図誌』『与那国島誌』刊行。
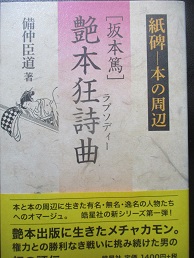
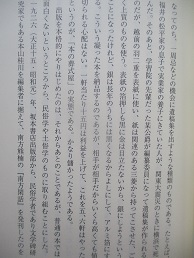
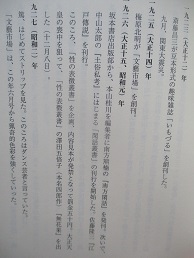
2016年6月 備仲臣道『紙碑ー本の周辺 坂本篤 艶本狂詩曲』皓星社〇1926(大正15・昭和元)年、坂本書店出版部から、民俗学者であり文学碑研究家でもある本山桂川を編集者に据えて、南方熊楠の『南方閑話』を発刊したのを手はじめに、中山太郎の『土俗私考』にはじまる「閑話叢書」を刊行
〇2017年3月 『平成27年度 市立市川歴史博物館館報』三村宜敬(市川歴史博物館学芸員)「本山桂川の足跡を探る」
1926年ー1月、八重山に始めてラジオ受信器設置。
1928年ー4月13日、東京代々木の日本青年館、18日が朝日新聞講堂で初めて八重山芸能(第三回郷土舞踊大会)が公演。
□1974年3月 大城立裕『風の御主前 小説・岩崎卓爾伝』日本放送出版協会
□岩崎卓爾 いわさき-たくじ
1869-1937 明治-昭和時代前期の気象技術者,民俗学者。
明治2年10月17日生まれ。32年沖縄石垣島初代測候所長となる。気象観測のかたわら,八重山の民俗,歴史,生物などを研究。退職後も石垣島にとどまり,「天文屋の御主前(うしゆまい)」としたしまれた。昭和12年5月18日死去。69歳。陸前仙台出身。第二高等学校中退。著作に「ひるぎの一葉」「八重山研究」など。→コトバンク
06/24: 人物カタログ/伊原宇三郎

1954年3月『別冊週刊朝日』伊原宇三郎「琉球の踊子(名護愛子)」
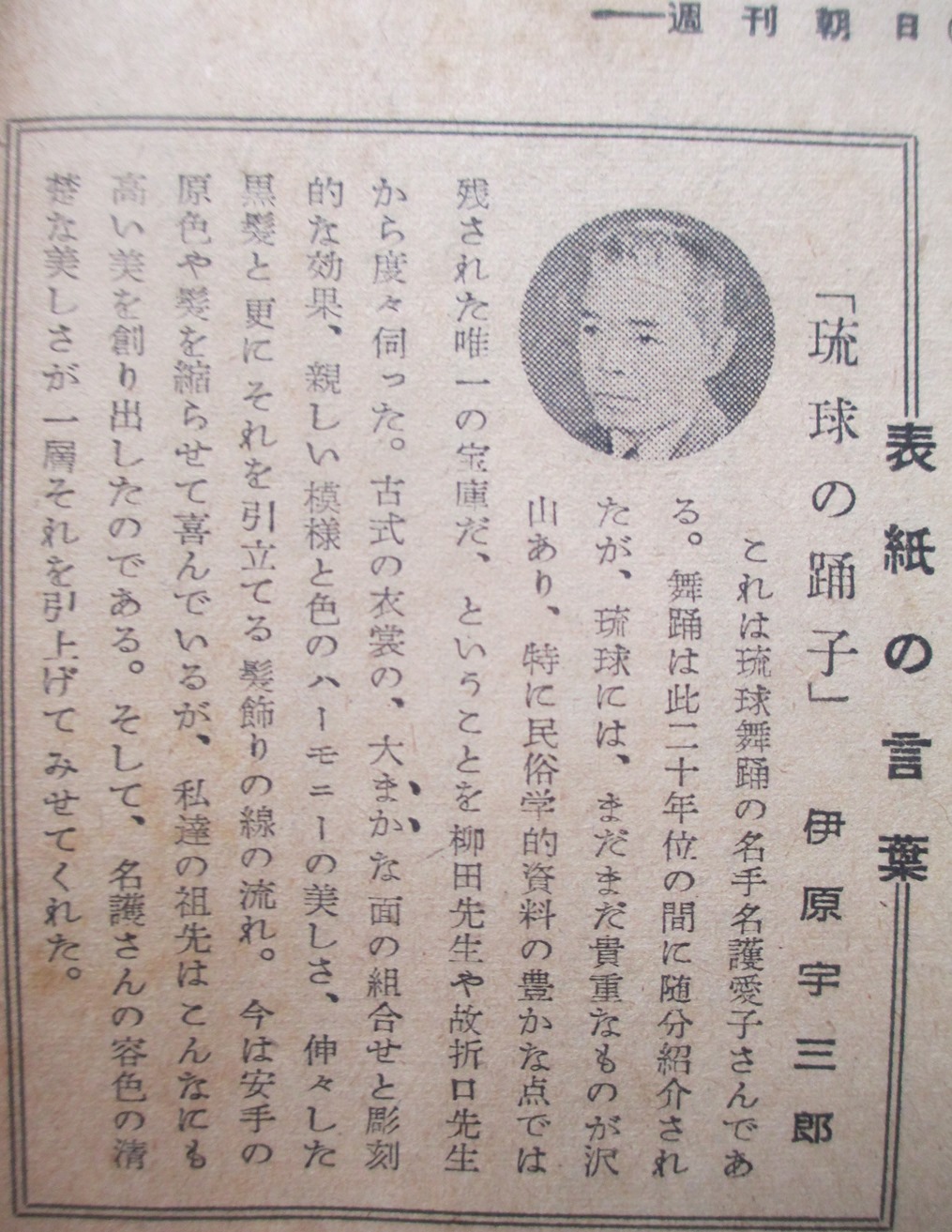
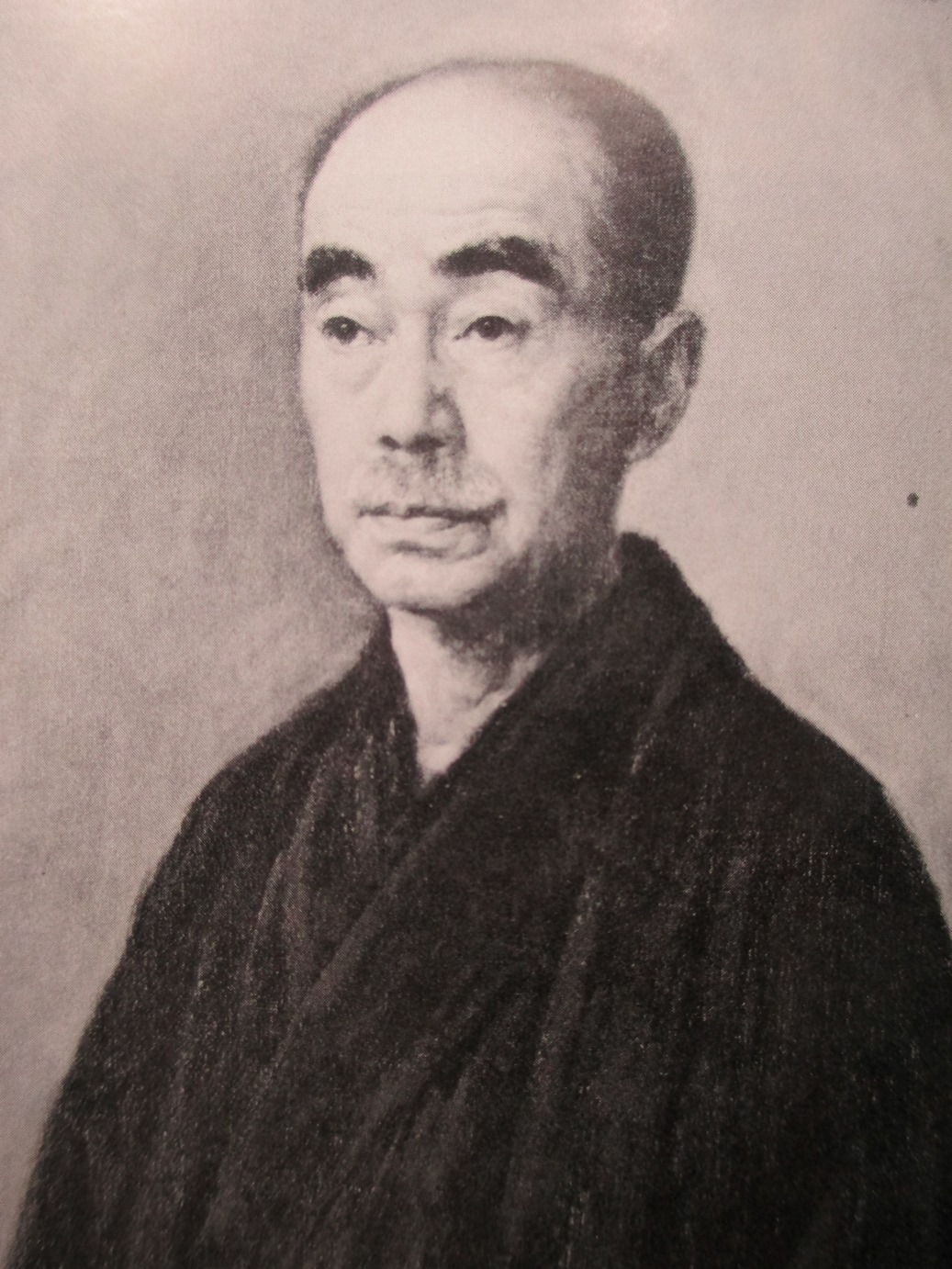
伊原宇三郎「柳田国男」(現在は飯田美術博物館蔵)
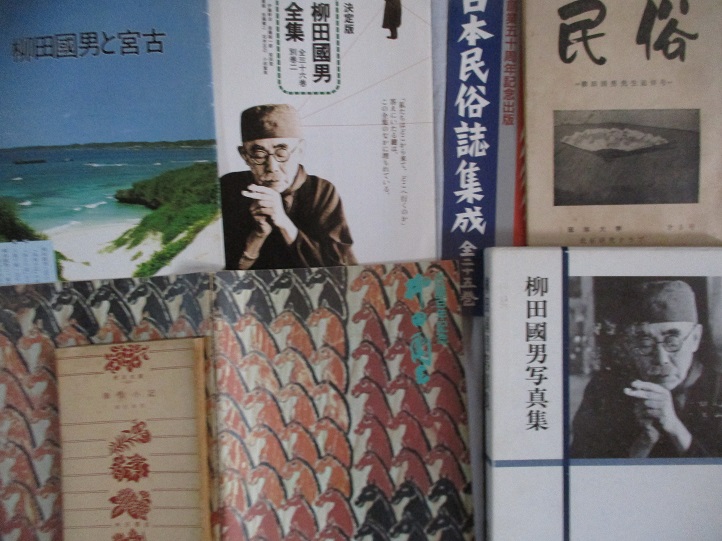
柳田国男 資料

伊原宇三郎「折口信夫」

伊原宇三郎ー洋画家。徳島市生。東美校卒。藤島武二に師事。卒業後渡仏し、帰国して帝展で特選を受賞する等活躍。帝国美術学校(現武蔵野美大)教授、母校助教授をつとめるかたわら戦時中は従軍画家として中国、東南アジアへ赴く。戦後日本美術家連盟創立と同時に委員長となり、美術家の社会的環境の整備に尽力した。フランス政府芸術文化勲章受章。日展参与・審査員。昭和51年(1976)歿、81才。 →コトバンク
11/23: 麦門冬と折口信夫
□1921年7月ー折口信夫、第1回沖縄採訪。折口はカメラを持参し写真を多く撮った。
折口信夫「組踊り以前」(青空文庫)
親友としての感情が、どうかすれば、先輩といふ敬意を凌ぎがちになつてゐる程睦しい、私の友伊波さんの「組み踊り」の研究に、口状役を勤めろ、勤めようと約束してから、やがて、足かけ三年になる。其間に、大分書き貯めた原稿すら、行き方知れずなる位、長い時の空費と、事の繁さが続いた。今日になつて、書きはじめる為のぷらんを立てゝ見ると、何もかも、他人の説でも受けつぐ様な気分がするばかり、興味の鈍つて了うてゐるのに気がついた。こんな無感興・認識未熟の文章が、友の本の情熱に水をさしはすまいか、と案じながら、ほんのぷらんを詞に綴つたと言ふだけの、組踊り成立案を書いて見る。さうせねば時間のない位、もう板行の時が迫つてゐるのを知り乍ら、うか/\してゐた事は、申し訣もない。
かうした解説文も、今六年以前なら、別に其仁があつたのである。亡くなつた麦門冬 末吉安恭さんである。大正十三年の末、那覇港大桟橋の下に吸ひつけられてゐた、なき骸を発見したとの知らせを聞いて、琉球芸能史を身を以て、実証研究する学者は、これで空に帰したのだ、と長大息した事であつた。此文章が、伊波さんの本の役に立つ傍、亡き南島第一の軟流文学・風俗史の組織者――たるべき――末吉さんの為の回向にもなれば、この上なく嬉しいと思ふ。
沖縄演劇史の探究の効果は、決して、東の海の波が西に越え、西の浪が東の磯にうち越える、と言つた孤島を出ないものではない。必、日本の歌舞妓芝居や、小唄類の発達過程を示すことになると言ふ自信だけは持つて居る。それでかうした文章も、この友の誂へをしほとして書いたのである。
南島における演劇関係の書物は、大抵、伊波館長時代の県立図書館の沖縄部屋とも称すべき室に、一週間籠つてゐる間に、そこに蒐められてゐたゞけの物は読んだ。だがもう、其記憶も薄れて来てゐる。それが、首里・那覇の学問の権威の、この本の為に、提供せられた資料の前には、星の光りにも値せぬ事を恥ぢるし、又沖縄人の嫌ふ、他府県人のいらざる世話やきにもなつて、島の彼方で苦笑する人々の、俤の浮ぶのも堪へられぬから、さうした引用や、伊波さんから貰うた、沢山の抜き書きなどは、勝手ながら下積みにさせて頂いて、今の場合、忙しい概念だけを綴る事にした。(以下略)
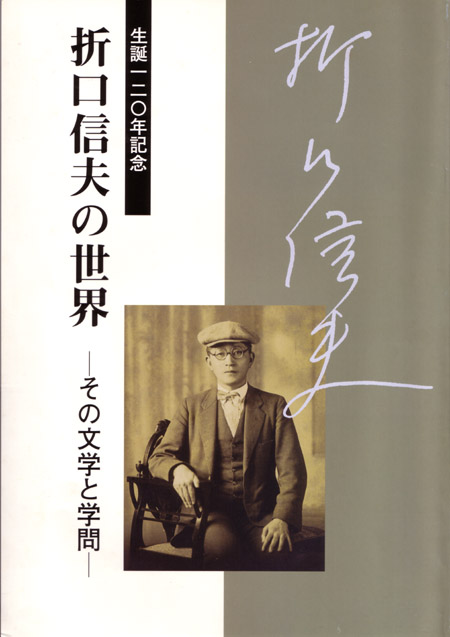
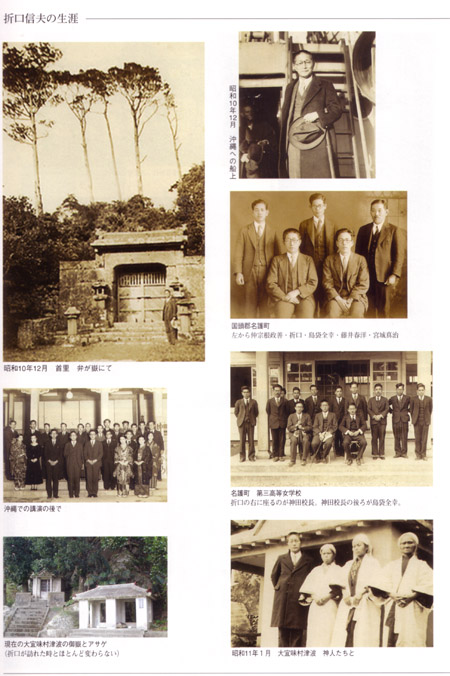
『折口信夫の世界ーその文学と学問』白根記念渋谷区郷土館・文学館、国学院大学学術フロンティア事業委員会・折口博士記念古代研究所

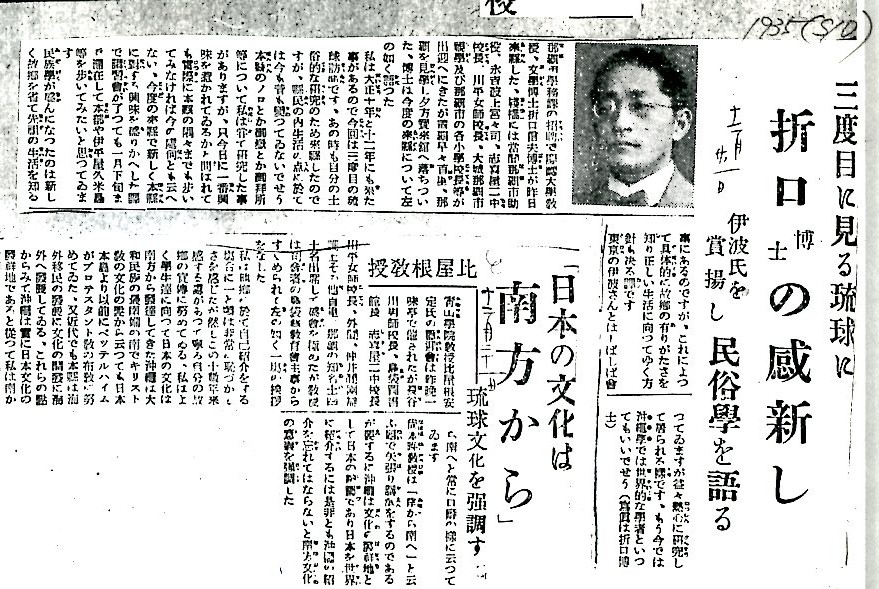
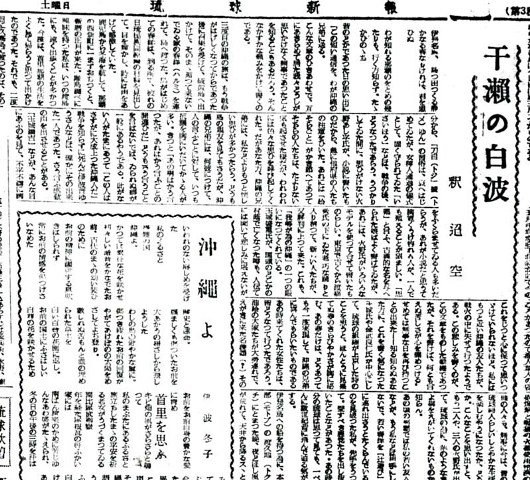
1952年1月5日『琉球新報』釈迢空「千瀬の白波」
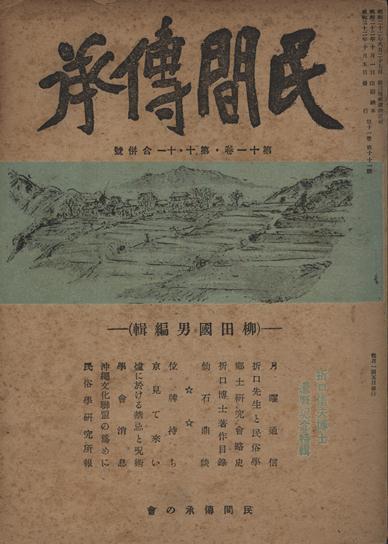
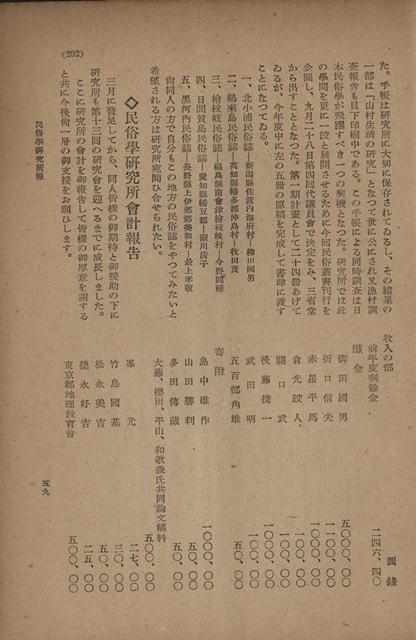
1957年10月 柳田國男編輯『民間傳承』<折口信夫博士還暦記念特輯>
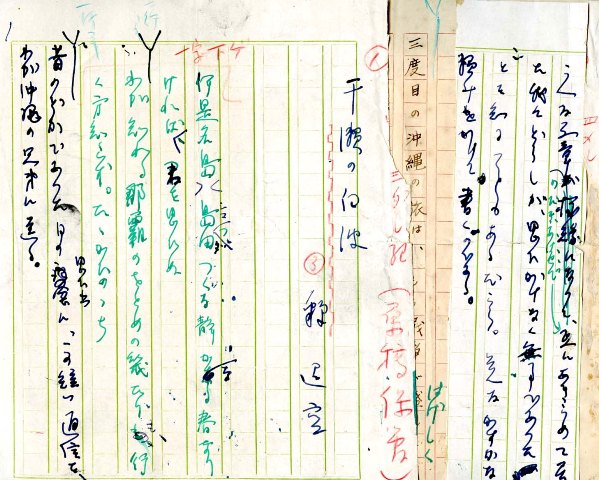
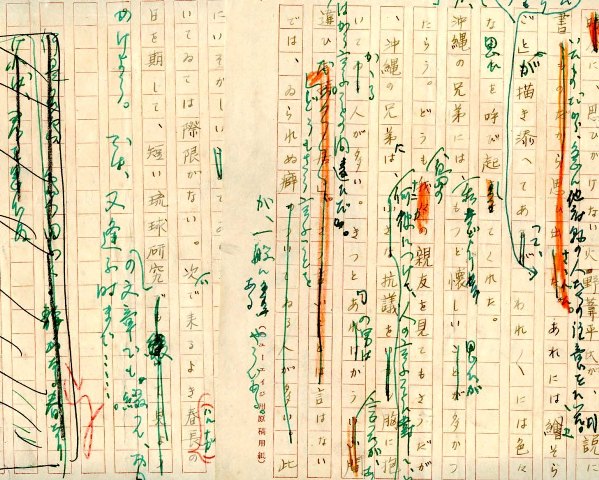
「千瀬の白波」原稿
折口信夫「組踊り以前」(青空文庫)
親友としての感情が、どうかすれば、先輩といふ敬意を凌ぎがちになつてゐる程睦しい、私の友伊波さんの「組み踊り」の研究に、口状役を勤めろ、勤めようと約束してから、やがて、足かけ三年になる。其間に、大分書き貯めた原稿すら、行き方知れずなる位、長い時の空費と、事の繁さが続いた。今日になつて、書きはじめる為のぷらんを立てゝ見ると、何もかも、他人の説でも受けつぐ様な気分がするばかり、興味の鈍つて了うてゐるのに気がついた。こんな無感興・認識未熟の文章が、友の本の情熱に水をさしはすまいか、と案じながら、ほんのぷらんを詞に綴つたと言ふだけの、組踊り成立案を書いて見る。さうせねば時間のない位、もう板行の時が迫つてゐるのを知り乍ら、うか/\してゐた事は、申し訣もない。
かうした解説文も、今六年以前なら、別に其仁があつたのである。亡くなつた麦門冬 末吉安恭さんである。大正十三年の末、那覇港大桟橋の下に吸ひつけられてゐた、なき骸を発見したとの知らせを聞いて、琉球芸能史を身を以て、実証研究する学者は、これで空に帰したのだ、と長大息した事であつた。此文章が、伊波さんの本の役に立つ傍、亡き南島第一の軟流文学・風俗史の組織者――たるべき――末吉さんの為の回向にもなれば、この上なく嬉しいと思ふ。
沖縄演劇史の探究の効果は、決して、東の海の波が西に越え、西の浪が東の磯にうち越える、と言つた孤島を出ないものではない。必、日本の歌舞妓芝居や、小唄類の発達過程を示すことになると言ふ自信だけは持つて居る。それでかうした文章も、この友の誂へをしほとして書いたのである。
南島における演劇関係の書物は、大抵、伊波館長時代の県立図書館の沖縄部屋とも称すべき室に、一週間籠つてゐる間に、そこに蒐められてゐたゞけの物は読んだ。だがもう、其記憶も薄れて来てゐる。それが、首里・那覇の学問の権威の、この本の為に、提供せられた資料の前には、星の光りにも値せぬ事を恥ぢるし、又沖縄人の嫌ふ、他府県人のいらざる世話やきにもなつて、島の彼方で苦笑する人々の、俤の浮ぶのも堪へられぬから、さうした引用や、伊波さんから貰うた、沢山の抜き書きなどは、勝手ながら下積みにさせて頂いて、今の場合、忙しい概念だけを綴る事にした。(以下略)
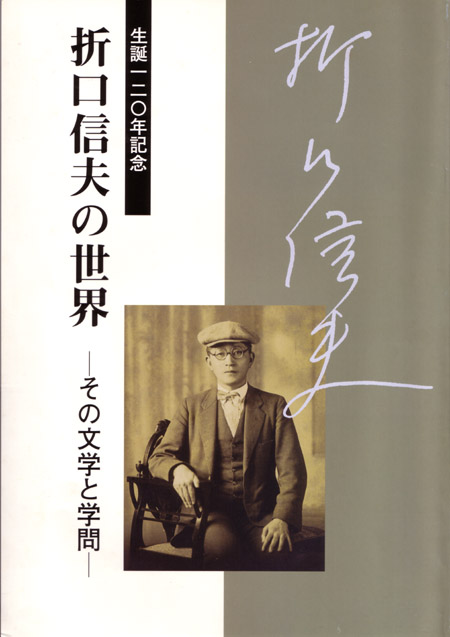
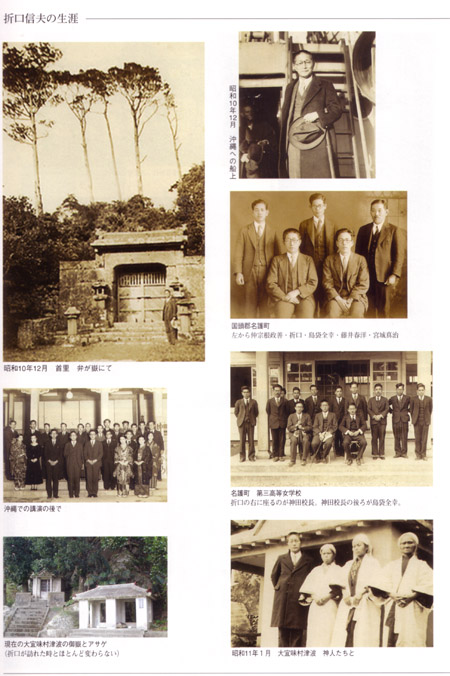
『折口信夫の世界ーその文学と学問』白根記念渋谷区郷土館・文学館、国学院大学学術フロンティア事業委員会・折口博士記念古代研究所

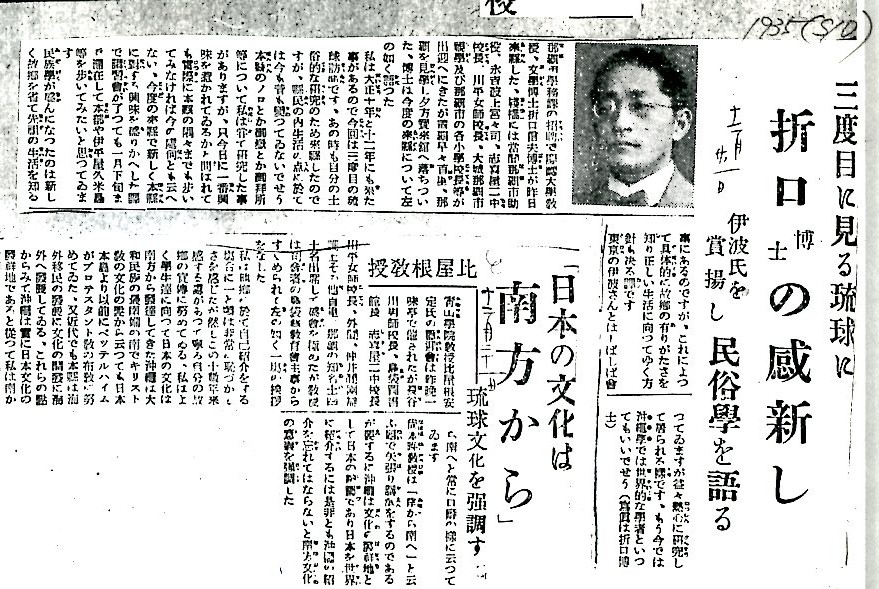
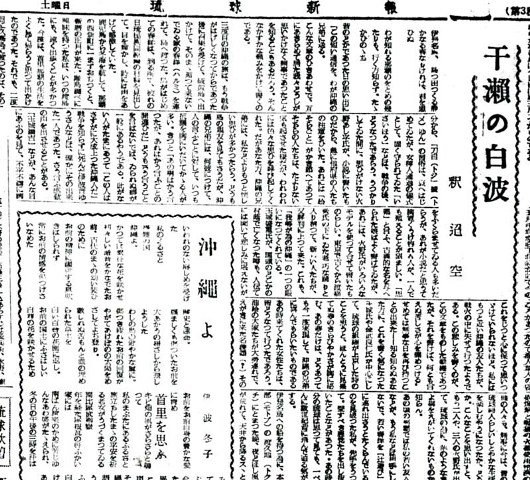
1952年1月5日『琉球新報』釈迢空「千瀬の白波」
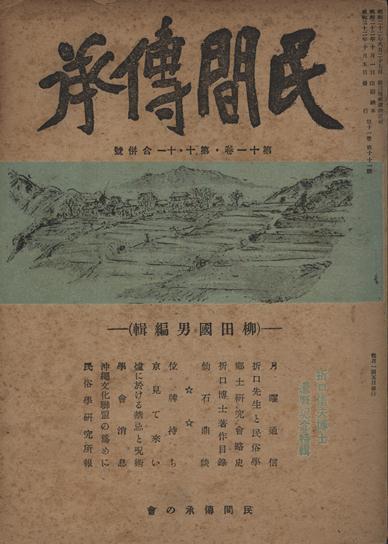
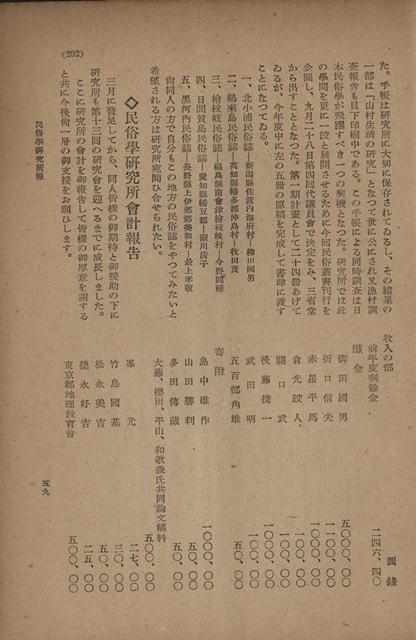
1957年10月 柳田國男編輯『民間傳承』<折口信夫博士還暦記念特輯>
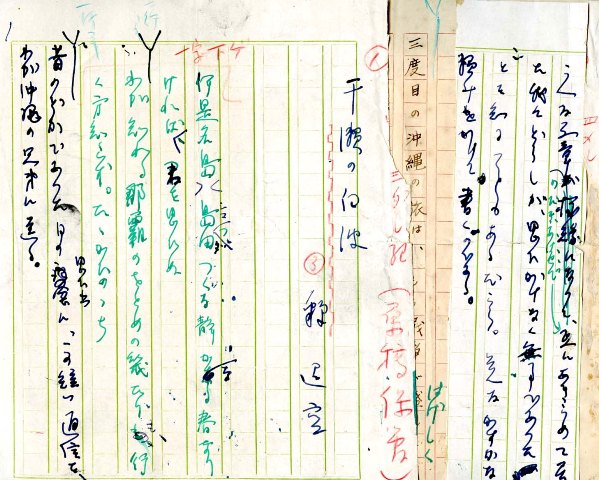
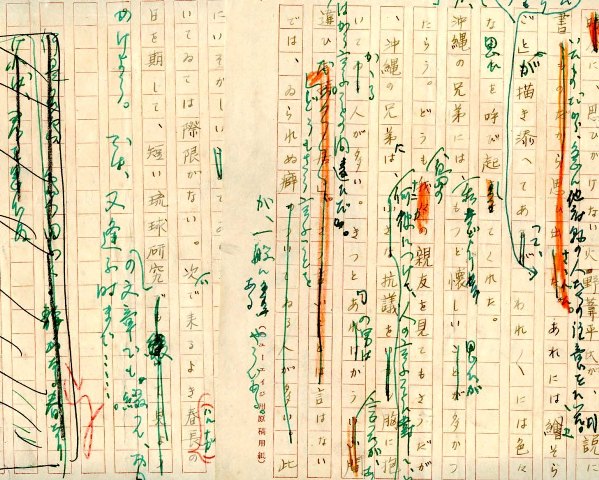
「千瀬の白波」原稿
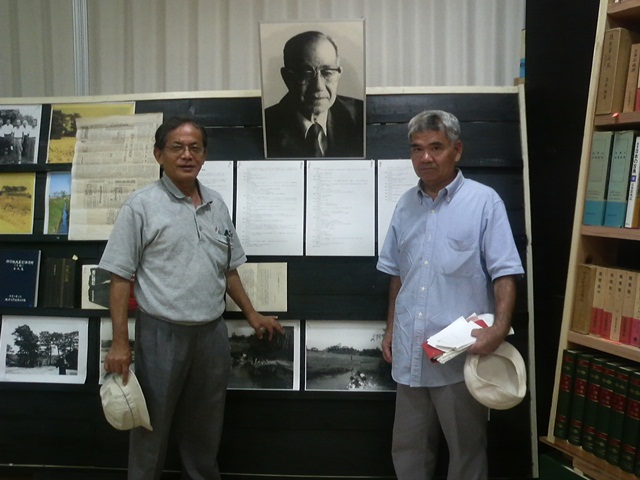
今帰仁村歴史文化センターでー左が館長・仲原弘哲氏と新城栄徳(渚さん撮影)
本日、文化の杜の渚さん運転のクルマで今帰仁と本部を廻った。渚さんは本部生まれで北山高校出身。今帰仁村教育委員会で、今帰仁城発掘や『百按司墓木棺修理報告書』編集にも関わっていて今帰仁に詳しい。今帰仁村歴史文化センターで館長の仲原弘哲氏が出迎えた。仲原氏は渚さんとも旧知の間柄。2012年8月22日寄贈された仲宗根政善の資料・本(100箱余.り)が地下書架に並んでいた。ガラスケースにある『琉球国由来記』(「1946年、山城善光氏帰沖,伊波先生からの手紙と『琉球国由来記』の写本,服部四郎氏から米語辞典が届けられる」と略年譜にある)には仲宗根宛の伊波普猷の署名がある。東江長太郎『通俗琉球北山由来記』(1935年11月)もある。□→1989年3月、東江哲雄、金城善編により那覇出版社から『古琉球 三山由来記集』が刊行された。
全集類は『比嘉春潮全集』(新聞スクラップが貼りこまれている。)『宮良當壮全集』『仲原善忠全集』『琉球史料叢書』などが目についたが、とくに日本図書センターの『GHQ日本占領史』はかなりの巻数である。安良城盛昭『天皇制と地主制』上下もある。
今帰仁関係を始めとして国文学雑誌や、琉球大学関係資料、同僚であった大田昌秀の著書も多数。また伊波普猷との関連で那覇女トリオの新垣美登子、金城芳子、千原繁子の署名入りの贈呈本もある。平山良明の論文原稿①、仲程昌徳『お前のためのバラード』、我部政男、渡邊欣雄、池宮正治、比屋根照夫、野口武徳、川満信一などの本も署名入りが並んでいた。娘婿が編集した『島田寛平画文集 1898-1967」 寛平先生を語る会1994年11月も目についた。
①
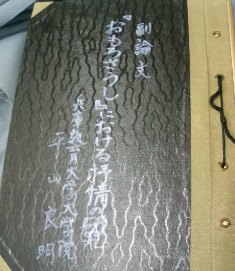 □
□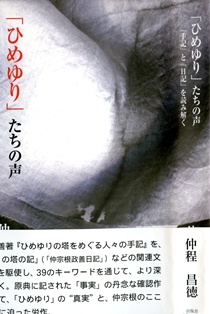 □2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)
□2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)天皇関係、大学紛争を特集した雑誌もある。マクルーハン②の本もあった。マクルーハンは、もともとは文学研究者として出発したが、その後メディア論を論じる(挑発的にして示唆に富んだ)社会科学者として名を成した。60年代後半~80年代前半にかけて爆発的な影響力を誇った。「内容ではなく、むしろそのメディア自身の形式にこそ、人びとに多くをつたえているのだ」と訴えることをつうじて、それまでの活字文化と、ラジオ文化、テレビ文化 相互のあいだにかれが差異線をひいたことは、いまだに重要である。 (ウィキペディア)
②
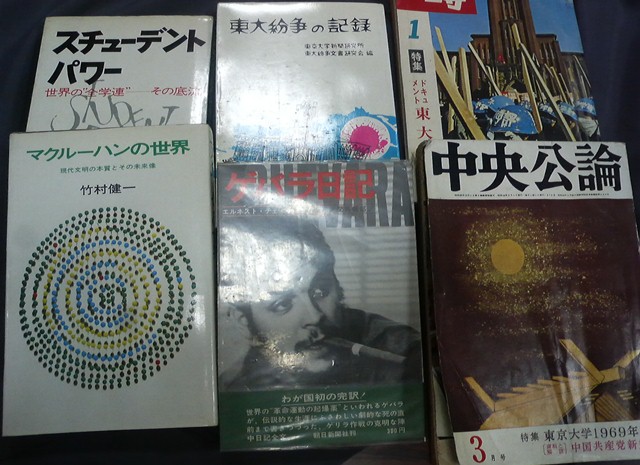
沖縄言語研究センターの「仲宗根政善 略年譜」を見ながら今帰仁村歴史文化センター書架に並んでいる本を思いつくまま記していくことにする。()内・写真・□は新城追加。
1907年(明治40年4月26日)
沖縄県国頭郡今帰仁村字与那嶺にて,父仲宗根蒲二,母カナの長男として生まれる 。生家は農業を営む。母カナは,名護の町を一度見たいというのが夢であったが,終生ついにかなえられなかった。祖父政太郎は,謝花昇(1908年死亡)に私淑していた。謝花は近在まで出張してくる都度,仲宗根家に宿をとった。
□1913年
9月5日 今帰仁村字与那嶺715番地に、父島袋松次郎(教師)、母静子(教師)の長男として霜多正次生まれる。→書架には霜多作品もある。
1914年~1919年(大正3年~8年)
兼次尋常小学校(大正8年4月1日,高等科併置,校名を兼次尋常高等小学校と改名する)に入学。桃原良明校長(4代),安里萬蔵校長(5代),安冨祖松蔵校長(6代),上里堅蒲校長(7代),当山美津(正堅夫人)等から直接教えを受ける。32歳の若さで赴任してきた上里校長に出会ったことによって,生涯を決定される。伊波普猷「血液及び文化の負債」の民族衛生講演で兼次小を訪れる。
1920年(大正9年)
沖縄県立第一中学校に入学。大宜見朝計(書架に1979年発行『大宜見朝計氏を偲ぶ』これに政善は「二人でたどった道」を書いている。川平朝申の文章もある。),島袋喜厚,上地清嗣等, 国頭郡から7名。中城御殿(現博物館)裏にあった駕籠屋新垣小に最初下宿。
母カナ死亡(享年40歳)。14歳になるまで,一晩中目がさえて一睡もできなかったということは一度もなかったが,虫のしらせか母の亡くなった夜だけは,蚊帳の上をぐるぐる飛んでいるホタルが妙に気になって,とうとう一睡もできなかったという経験をする。
泉崎橋の近くで,初めて伊波普猷の姿に接する。4年から5年にかけて,英語を担当していた胡屋朝賞先生の感化を受ける。
1926年(大正15,昭和元年)
福岡高等学校文科乙類に入学。沖縄から最初の入学者であった。級友から珍しがられ,親切にされる。翌27年には,大宜見朝計が入学。
伊波普猷著『孤島苦の琉球史』と『琉球古今記』を買い求め貧り読む。
安田喜代門教授から『万葉集』の講義を聞き,万葉の中に,日常用いている琉球方言がたくさん出て来るのに興味を覚える。また,考古学の玉泉大梁教授から,日本史の中ではじめて琉球史の概要を聞く。ドイツ語担当白川精一教授の感化を受け,ドイツ語に興味を持つ。
1929年(昭和4年)
東京帝国大学文学部国文学科入学。同年入学者に林和比古,永積安明, 吉田精一,犬養孝,岩佐正,西尾光雄等がいた。
本郷妻恋町に最初下宿。2年の時から国語学演習で,橋本進吉教授に厳しく鍛えられる。同ゼミに先輩の服部四郎,有坂秀世氏等がいた。服部氏が,今帰仁村字与那嶺方言のアクセントを調査し整理して,法則を示してくれたことによって, 郷里の方言に一層興味を持つようになる。金田一京助助教授のアイヌ語の講義,佐々木信綱講師の万葉集の講義を受ける。
伊波普猷先生宅に出入りするようになる。
1931(昭和6年)
第二回南島談話会で,はじめて柳田国男,比嘉春潮,仲原善忠, 金城朝永,宮良当壮に会う。
1932(昭和7年)
東京帝国大学文学部国文学科卒業。世は不況のどん底にあって,町にはルンペンがあふれていた。就職口もなく,朝日新聞に広告を出しても家庭教師の口すら年の暮れまで見つけることができないというような状況であった。
たまたま,県視学の幸地新蔵氏から,郷里の第三中学校に来ないかとの手紙があって,伊波普猷先生に相談。「東京でいくら待っても職はないし,2,3年資料でも集めて来てはどうか」と言われ,帰郷する気になる。
★「語頭母音の無声化」(『南島談話』第5号)。
★「今帰仁方言における語頭母音の無声化」(『旅と伝説』)。
1933年(昭和8年)
名護の沖縄県立第三中学校に教授嘱託として赴任。伊波普猷先生から,蚕蛹の方言を調査してほしい旨の手紙を受け,さっそく生徒126名を対象に,国頭郡の各部落の方言を調査し報告する。方言使用禁止の風潮の中で,方言を調べ研究するのを,生徒たちから不思議に思われる。伊礼正次,サイ夫妻の長女敏代と結婚。
1934年(昭和9年)
★「国頭方言の音韻」(『方言』第4巻第10号)。
1936年(昭和11年)
折口信夫先生を嶋袋全幸氏と共に案内。正月を名護で迎える。北山城趾見学の帰り,与那嶺の実家に立ち寄る。
三中から沖縄女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校に転勤を命ぜられる。『姫百合のかおり』(沖縄県女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校,30周年記念号)の編集委員を勤める。
★「加行変格『来る』の国頭方言の活用に就いて」(『南島論叢』)。
1937年(昭和12年)
川平朝令校長から「国民精神文化研究所」に研修に行くことをすすめられ,あまり気のりがしなかったが, 東京へ転ずるきっかけをつかむことができるかも知れないとの希望があって,目黒長者丸にあった同研究所へ入所する。
伊波先生を塔の山の御宅に訪ね,入所報告をすると「紀平正美などが,『神ながらの』道を講じているようだが,あんなのを学問だと思っては大間違いだ。研究所に通うより,うちに来て勉強するがよい」と注意を受けて近くに宿を貸りる。先生に励まされ,研究意欲に燃えて,夏の終わりに帰省。
目次
編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。
沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦
ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷
沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎
地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇
岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣
女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫
性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎
セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠
耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏
万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建
八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮
琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一
琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎
南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫
阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七
尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)
□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。
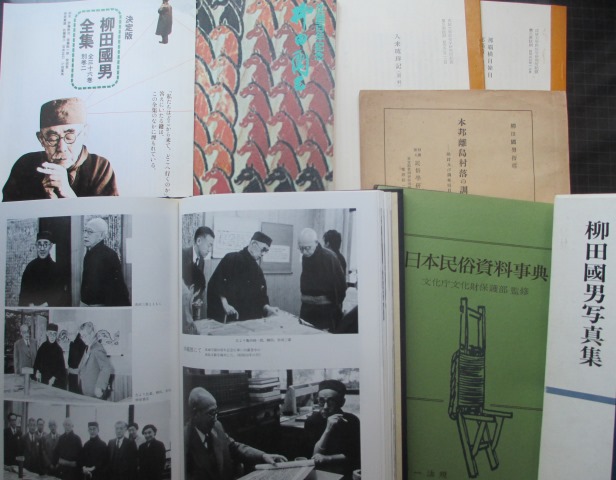
柳田国男 やなぎた-くにお
1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。
明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。
【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク
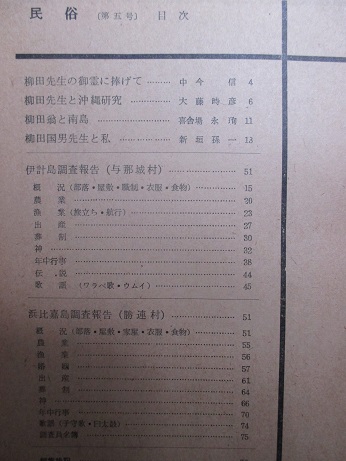
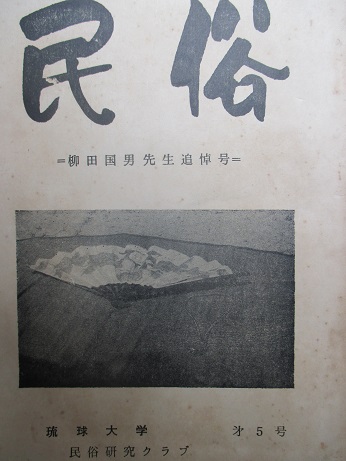
1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号
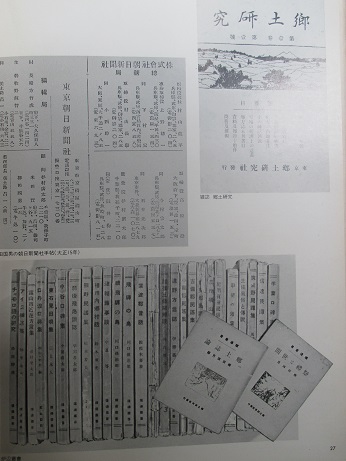
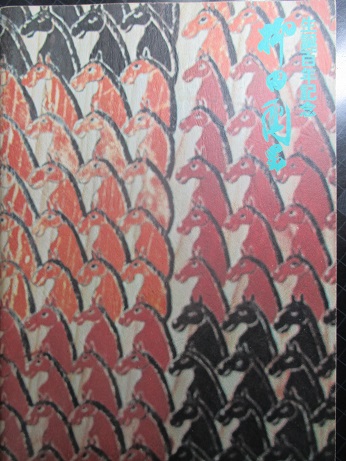
1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展
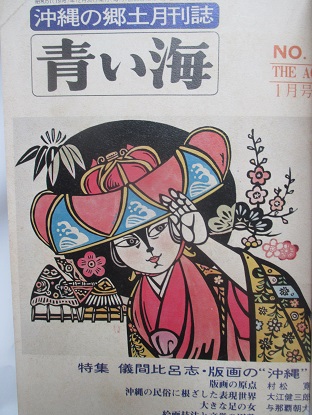
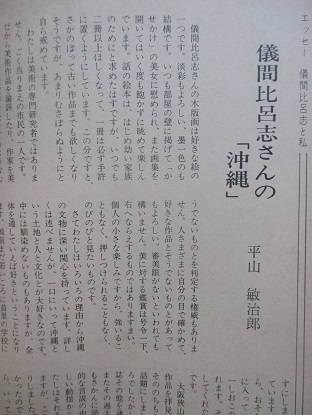
1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」
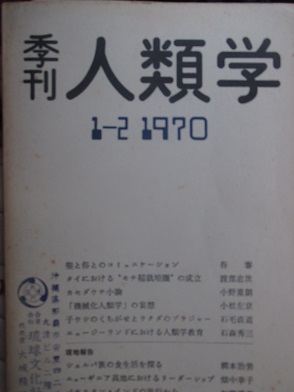
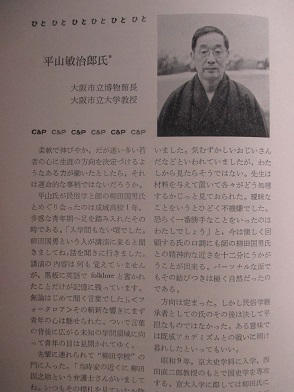
1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」
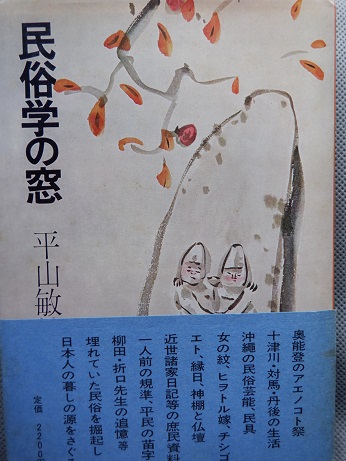
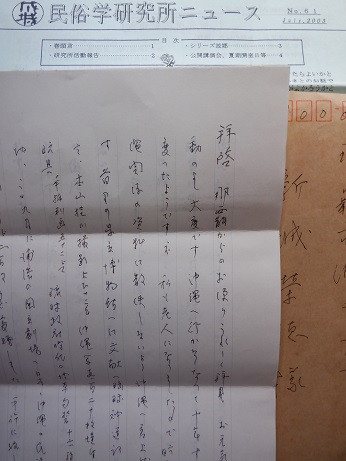
1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡
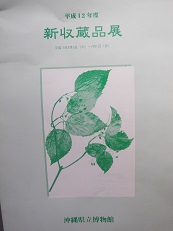

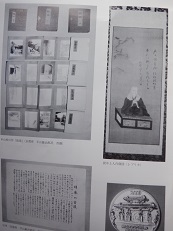
2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈
平山敏治郎
歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)
**略歴
大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。
昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。
**おもな著書
『日本中世家族の研究』(1980)
『民俗学の窓』(1981)
『歳時習俗考』(1984)
『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)
押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)
岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。
浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。
編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。
沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦
ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷
沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎
地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇
岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣
女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫
性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎
セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠
耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏
万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建
八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮
琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一
琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎
南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫
阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七
尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)
□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。
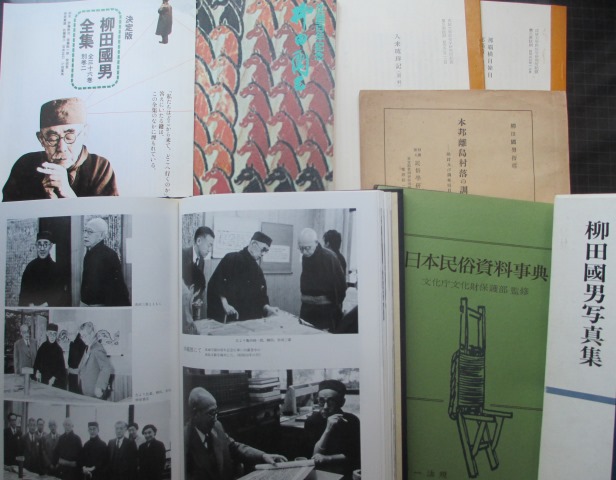
柳田国男 やなぎた-くにお
1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。
明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。
【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク
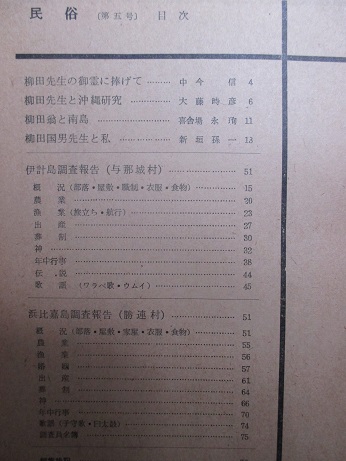
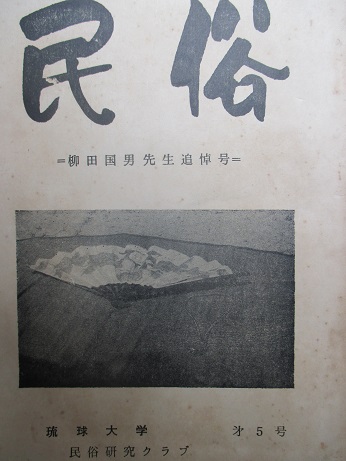
1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号
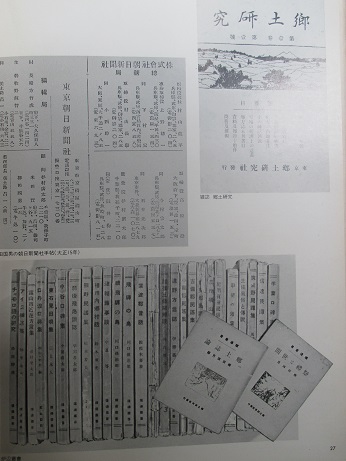
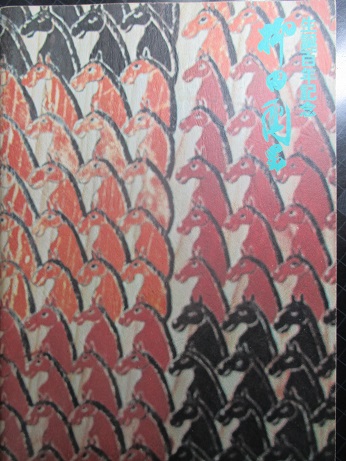
1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展
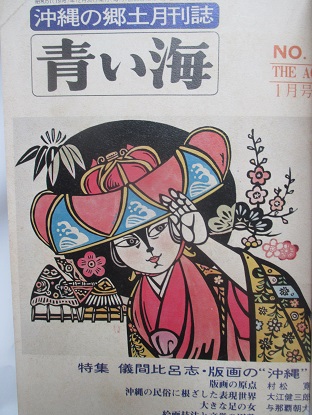
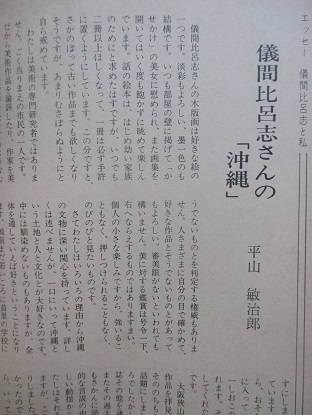
1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」
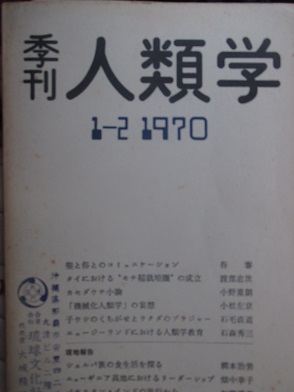
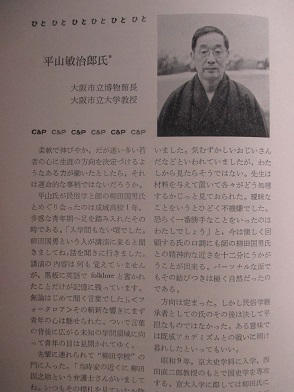
1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」
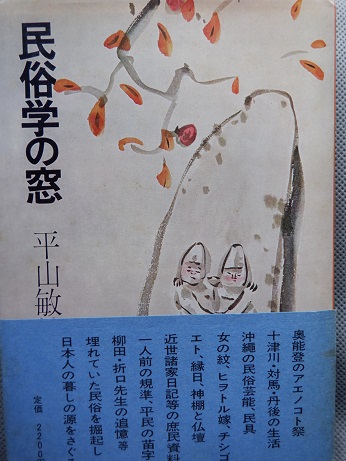
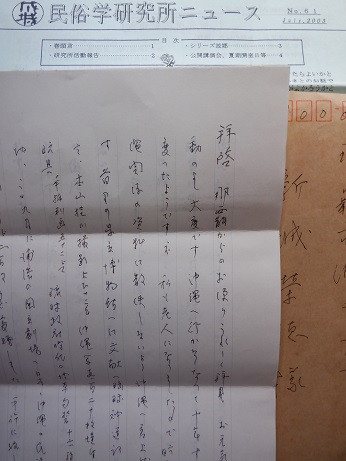
1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡
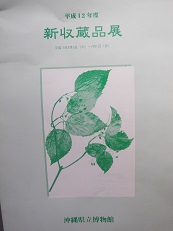

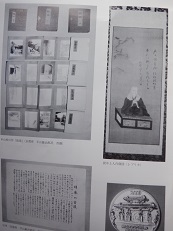
2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈
平山敏治郎
歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)
**略歴
大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。
昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。
**おもな著書
『日本中世家族の研究』(1980)
『民俗学の窓』(1981)
『歳時習俗考』(1984)
『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)
押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)
岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。
浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。
12/04: 宮城眞治

写真左から仲宗根政善、折口信夫、島袋全幸、藤井春洋、宮城眞治
→2006年10月 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館『生誕120年記念 折口信夫の世界ーその文学と学問ー』
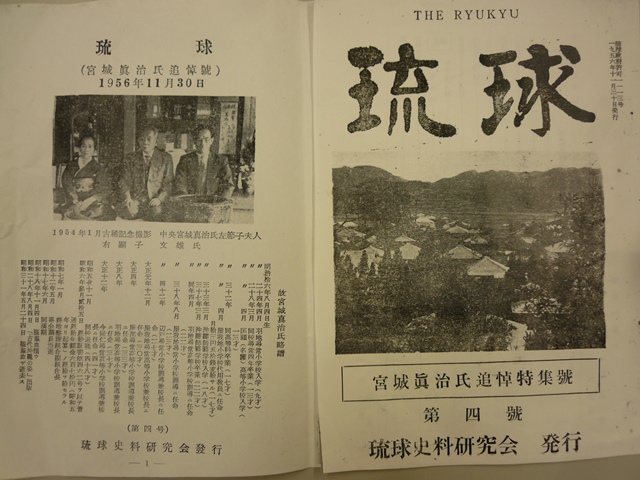
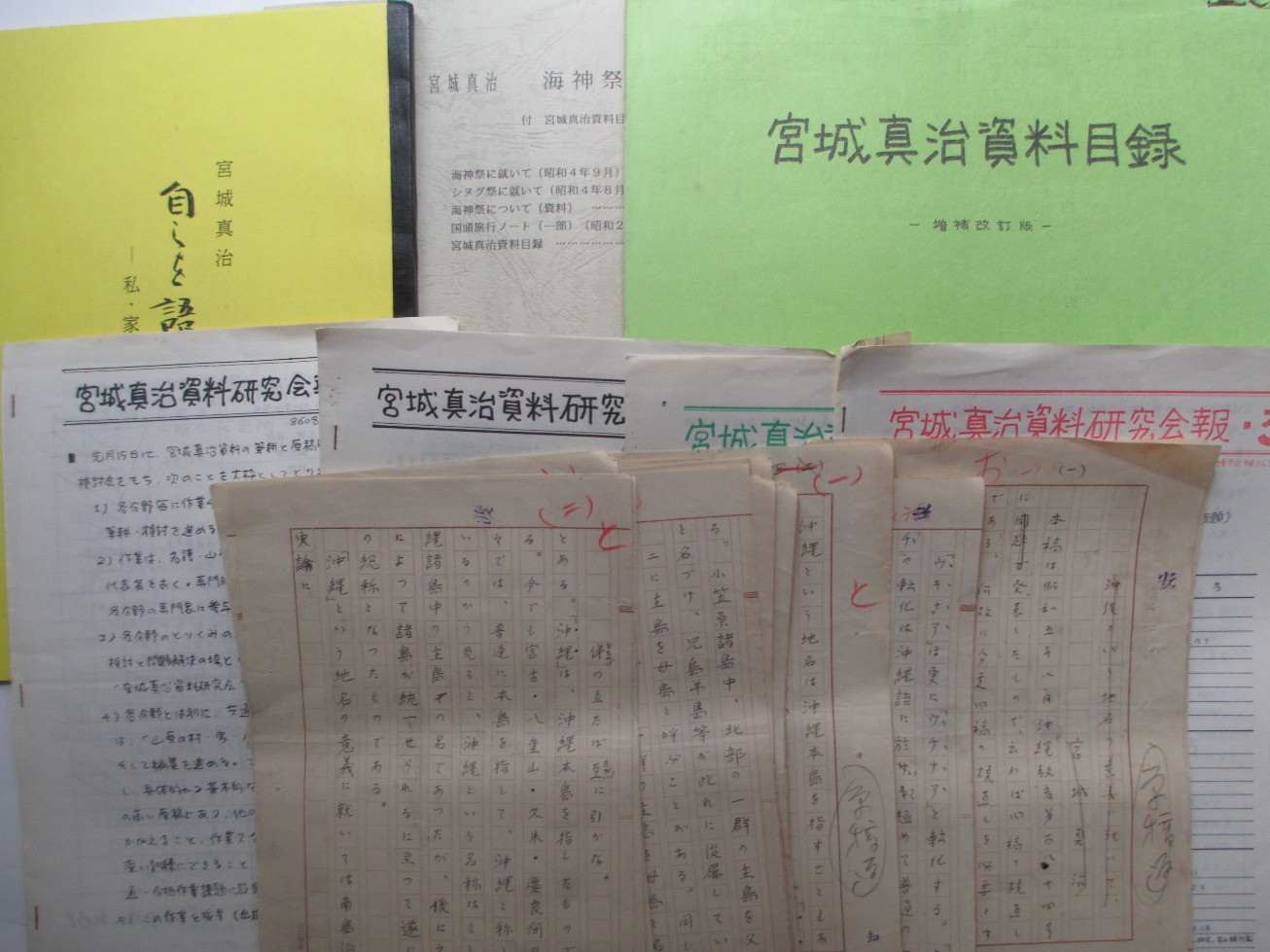
宮城眞治資料(新城栄徳所蔵)
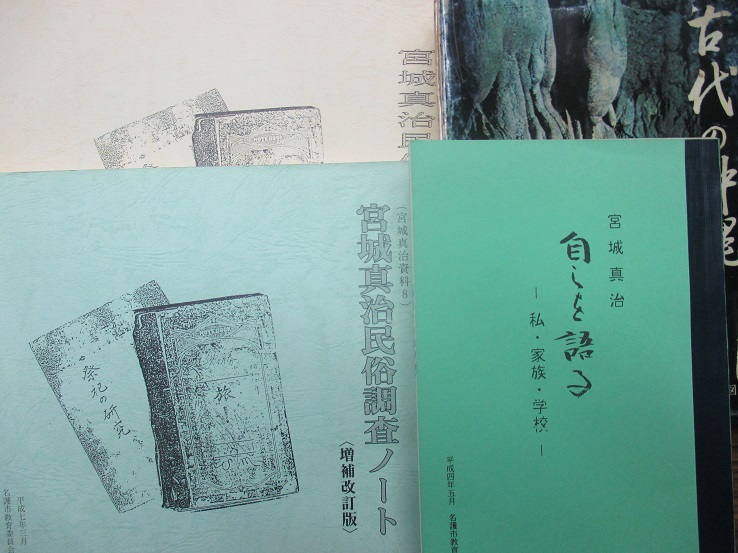
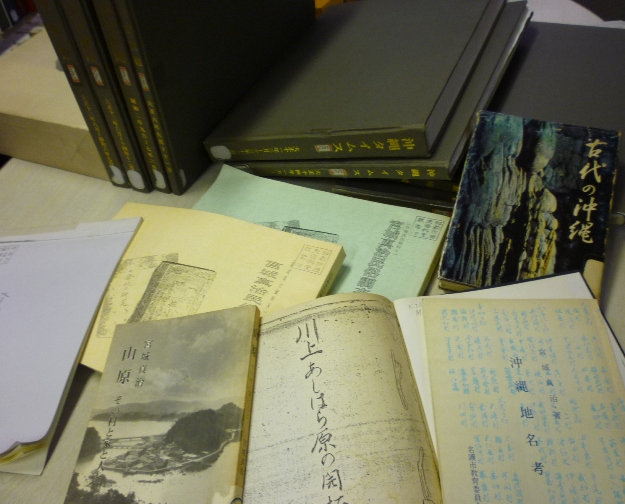
那覇市歴史博物館所蔵の宮城眞治資料
01/11: 新城栄徳「琉球文化史散歩」(豊川善曄)⑥
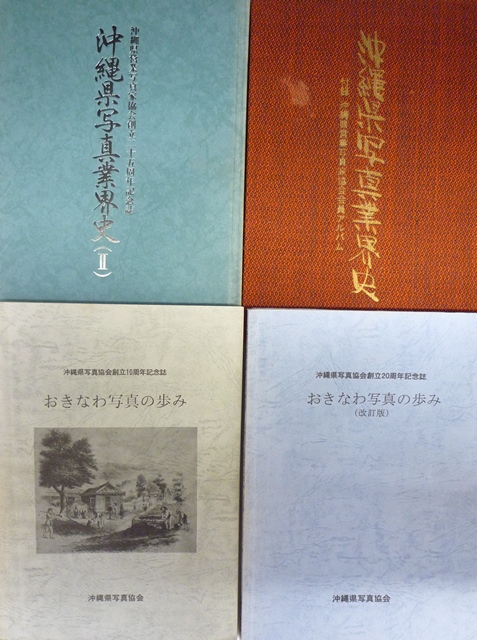
2000年8月21日『沖縄タイムス』「知られざる歴史上の写真ー軍医・渡辺重鋼、教育者・豊川善曄」(島袋和幸)/5月27日『沖縄タイムス』「明治の貴重な写真発掘ー山田実さん保管、新城栄徳さん調査」/10月2日『琉球新報』新城栄徳「近代沖縄観光文化史ノートー沖縄に来た画家たち」/12月3日『琉球新報』新城栄徳「書評ー野々村孝男『写真集・懐かしき沖縄』/2001年10月9日『おきなわ写真の歩み』新城栄徳「沖縄写真史散歩」
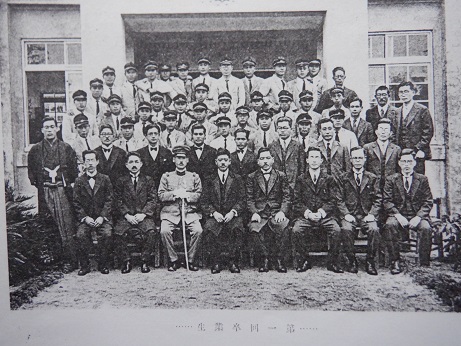
沖縄県立第三中学校 第一回卒業式/前列右から4人目が豊川善曄
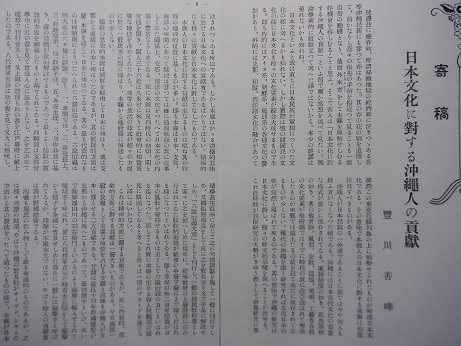
1933年6月 『南燈』豊川善曄「日本文化に對する沖縄人の貢献」
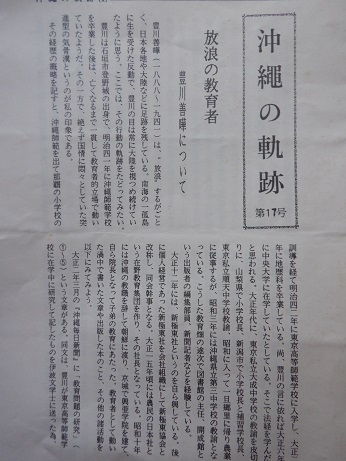
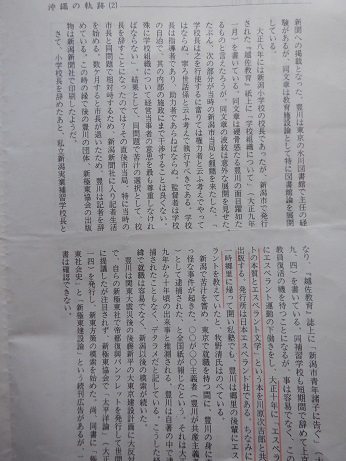
1998年1月 島袋和幸『沖縄の軌跡』17号 「放浪の教育者 豊川善曄について」
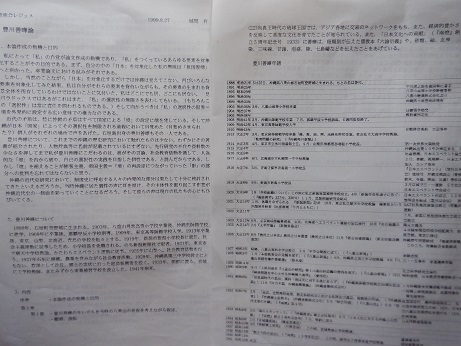
1998年8月 城間有「勉強会レジュメー豊川善曄論」

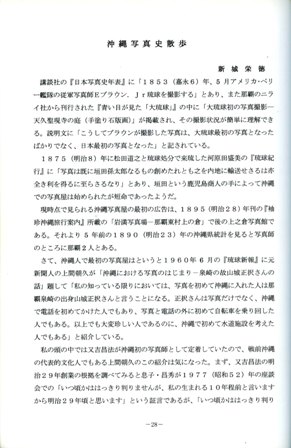
2001年10月ー沖縄県写真協会『おきなわ写真の歩み』新城栄徳「沖縄写真史散歩」
1609年、フィリピン臨時総督ドン・ロドリゴを乗せたサン・フランシスコ号が千葉の御宿沖で座礁、上総国岩和田の村人によって317名が救助されたという。その千葉県御宿には鹿野政直氏が住んでおられる。氏の著『近代日本の民間学』(岩波新書1983年)、『近代日本思想案内』(岩波文庫1999年)がある。何れの本にも私が関心をもっている柳田国男、折口信夫、南方熊楠、柳宗悦、伊波普猷が登場する。2008年2月に岩波書店から『鹿野政直思想史論集』第4巻が刊行された。沖縄特集ということで私も著者から贈られた。中の追記に「末吉麦門冬については、のちに新城栄徳氏から、同氏編・刊『文人・末吉麦門冬』(『琉文手帖』2号、1984年12月)の出ていることを教えられた。小冊ながら、彼の写真・筆蹟・随筆選に、伊佐眞一編の「末吉麦門冬と新聞」「著作目録(抄)」などを収めており、麦門冬研究の基礎文献をなす」と書かれている。また沖縄学について私が提供した新聞にもふれている。
2001年10月ー沖縄県公文書館『写真にみる近代の沖縄』
2006年6月 『山田實クロニカルー沖縄と写真と私』□仲里効「はじめに」、東松照明「戦後写真史の幕開けに立ち会う」、洲鎌朝夫「写真機を操る人。操られる人」
2008年9月 朝日新聞社『アジアとヨーロッパの肖像』(9月11日~国立民族学博物館/国立国際美術館)
2009年1月 沖縄県立博物館・美術館『移動と表現ー変容する身体・言語・文化』
2010年3月 壷屋町民自治会『なつかしの壷屋』(山田實/森幸次郎)
今、『琉球新報』に「山田實が見た戦後沖縄」が連載されている。それを見て思うのは、10・10空襲を得て沖縄戦で灰燼と帰した那覇での写真を始め幼馴染の伊波國男(伊波普猷の次男)の写真と卒業証書や辞令書などが残っていることに驚く。これなどは肉親が県外に住んでいた結果であろう。山田さん本人もシベリア抑留から生還し健在だからこそ、これらの写真、資料が活きている。(2010-3-30)
同年に岩宮武二が『日本の工芸』別巻・琉球の取材で来沖。琉球新報の依頼で山田さんが案内をつとめた。別巻・琉球は外間正幸文で淡交社から刊行された。同著には岩宮のサインがある。69年2月に那覇栄町の栄亭でニッコールクラブの沖縄有志による東松照明歓迎の集合写真もある。74年11月の八汐荘での「沖縄写真学校」は山田さんの写真館が窓口であった。そのときのポースタが山田さんのところにあるが講師の荒木経惟、東松照明、森山大道、深瀬昌久、細江英公の全員のサインがある。
2010年11月 沖縄県立博物館・美術館『母たちの神ー比嘉康雄展』(1968年11月19日未明のB52爆撃機が嘉手納空軍基地で墜落炎上。この事件を転機に嘉手納警察署を退職し、東京写真専門学院報道写真科入学。)
2011年1月 沖縄県立博物館・美術館『安谷屋正義展ーモダニズムのゆくえ』山田實「エッセイ・沖縄美術界の逸材、早い別れ」
2001年3月ー那覇市歴史博物館『????宮城昇の写した世界ー埋もれていた昭和モダン』
2010年3月6日午後1時にパレットくもじ前で「豊前海一粒かき」の試食があった。リウボウ6階では「第12回青森県物産と観光展」が開かれていた。アップルジュースを飲み会場を見る。梅干しもある。梅干は和歌山県というイメージが覆された。和歌山県には秦の徐福の墓があるが、青森県の小泊には徐福の里公園があり徐福像もある。いま巷では坂本龍馬がブームである。その出生地の土佐は南国とも云われている。青森などは北国である。
午後2時、那覇市歴史博物館で「本土人が見た1950年代の沖縄」の撮影者・小野田正欣氏ご本人による当時の状況解説の講演を聞く。展示写真の中に、1953年完成したばかりのペルリ記念館(戦前の首里城北殿に似ている)や、沖縄民政府立首里博物館、東恩納博物館の写真もある。私は沖縄滞在のときの小野田氏の写真と、話をされている小野田氏を比べていた。その当時、私は5,6歳であった。

写真左から仲宗根政善、折口信夫、島袋全幸、藤井春洋、宮城眞治
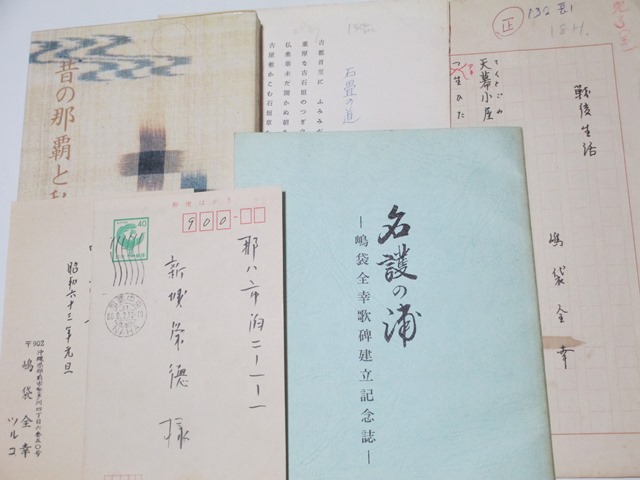
島袋全幸『昔の那覇と私』「折口信夫先生と沖縄と・折口先生と伊波先生・東恩納寛惇先生・比嘉春潮先生・宮城栄昌さん・獏さんと泉さん・那覇および那覇人・市史こぼればなし・電車の開通・ありしひの那覇・那覇の女・むかし那覇の正月風景」昭和61年2月ー若夏社発行
06/02: うちなー芝居・映画史②
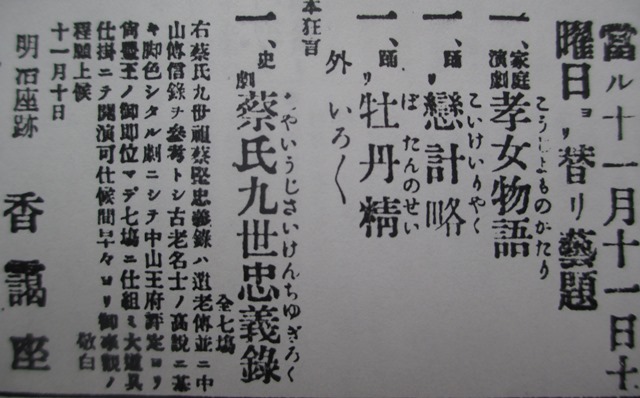
1911年11月『琉球新報』□「蔡氏九世忠義録ー尚豊王御即位マデ七場ニ仕組ミ大道具仕掛ニテ開演可仕候ー」
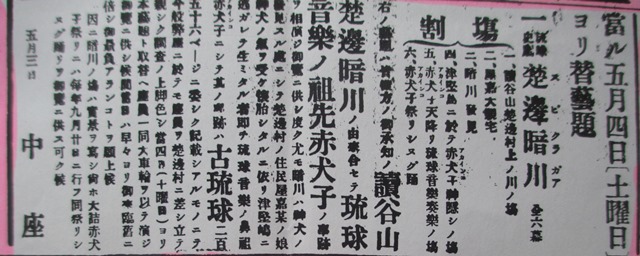
1912年5月『沖縄毎日新聞』「中座 琉球史劇 楚辺暗川ー琉球音楽ノ祖先 赤犬子」
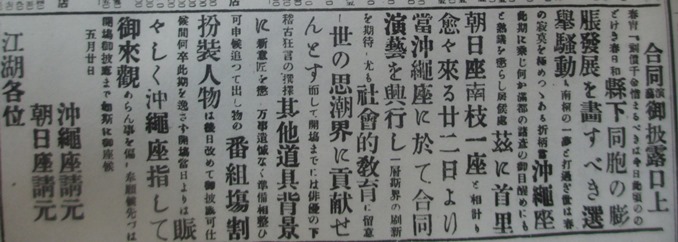
1912年5月20日『琉球新報』
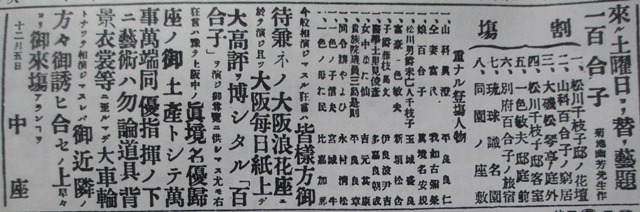
1913年10月15日ー那覇の香靄座、大阪杉本商会特約で活動写真常設館「パリー館」開設
1917年4月『琉球新報』□沖縄師範旅行たよりー午前8時、軽装して比叡山登りの道すがら、本能寺の信長墓を弔った。五尺ばかりの石塔で手向ける人とてもなくあはれ物寂しい。御所を拝して大学の裏道より、田圃の間にいで右に吉田の山を見つつ銀閣寺にいった。庭園の美、泉石の趣、形容も及び難いが義政将軍風流三昧をつくしたところかと思うと折角の美景も興がさめてしまう。狩野元信の筆や、弘法大師の書などは珍しいものである。ここから大文字山の森の下道を通ってその名もゆかしい大原白河口に出た。比叡山の登り口である。流汗淋満として瀧なす泉に咽喉を濕し息もたえだえに登ると境は益々幽邃である。ラスキンが山を讃美して、宗教家には聖光を付与す・・・。
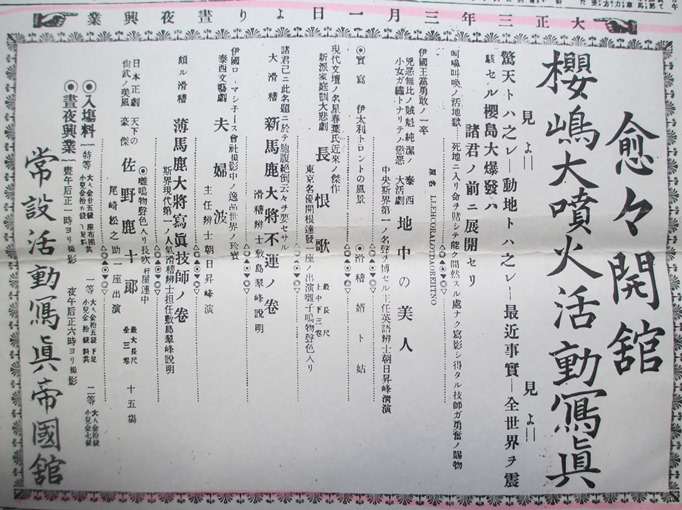
1914年3月1日ー那覇区字東仲毛で「常設活動写真帝国館」開館
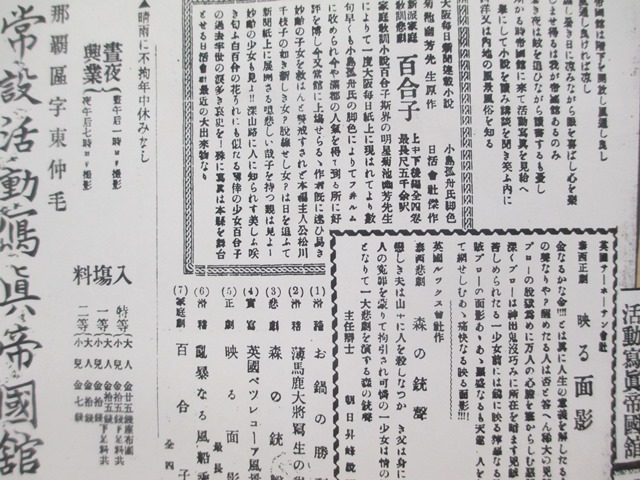
1914年3月 那覇の常設活動写真帝国館で「百合子」上映
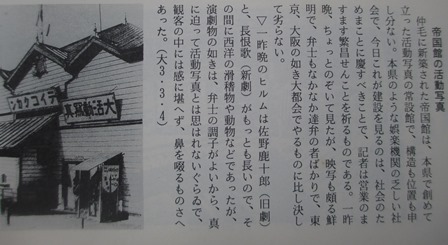
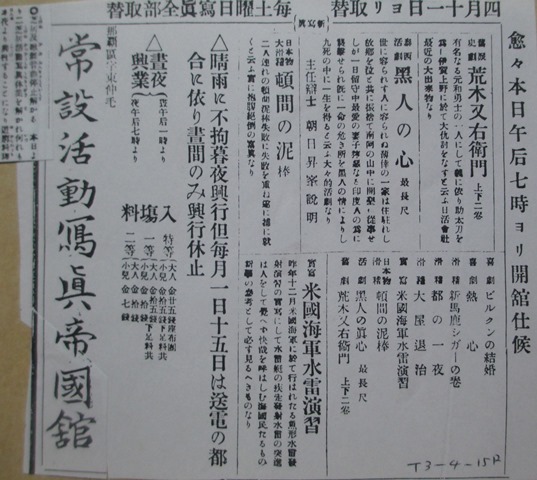
1914年4月 「米国海軍水雷演習」
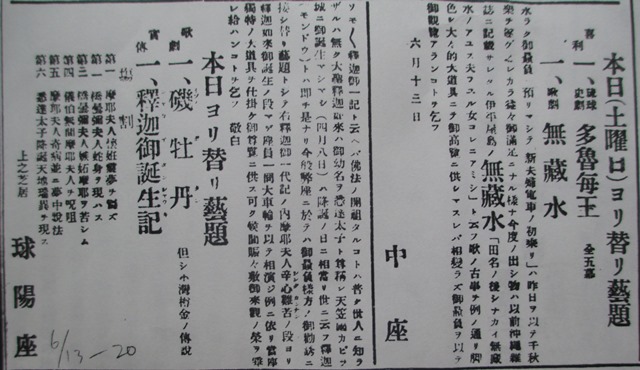
1914年6月『琉球新報』
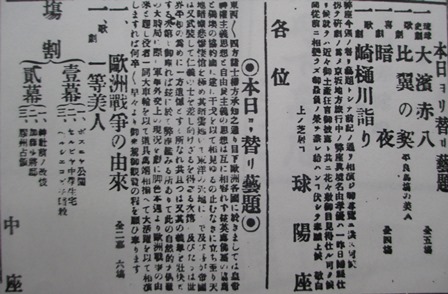
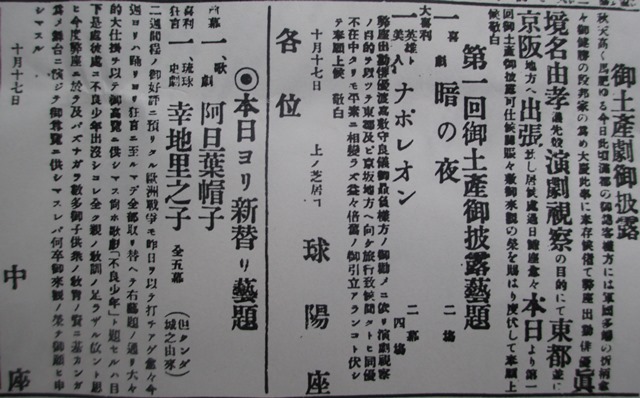
1914年10月『琉球新報』
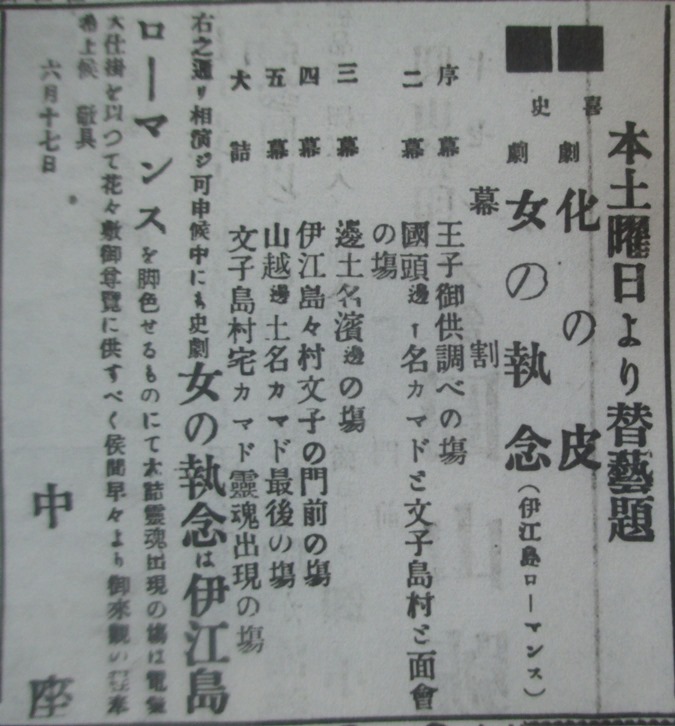
1916年6月16日『琉球新報』

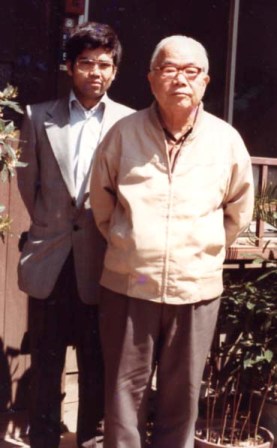 写真ー左・松本(真栄田)三益さん、右・新城栄徳と真栄田三益さん
写真ー左・松本(真栄田)三益さん、右・新城栄徳と真栄田三益さん浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)
『同胞』を詳細に紹介した最初の本は、浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)である。浦崎翁は関西沖縄県人会の創立メンバーで当時を知る有力な人物である。私は1982年5月に浦崎翁を那覇市泊に訪ねて、関西沖縄青年の運動のことを聞いた。浦崎翁は社会運動だけでなく文化全般に通じている。前出の著は国吉真哲翁の序文がある。偶然なことに私は浦崎翁から国吉翁も紹介されることになる。
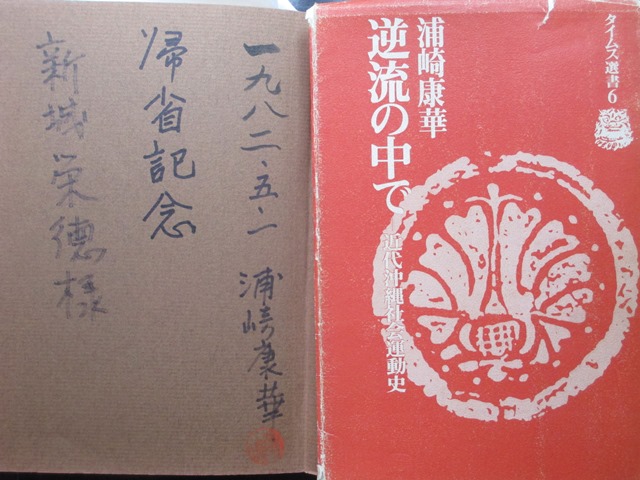
浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)
〇国吉真哲□序ー沖縄は慶長年間のの薩摩の武力侵入にはじまり、明治政府の琉球処分、それに第二次世界大戦によるアメリカの軍事占領と大きな惨禍と犠牲を強いられてきた。明治政府の沖縄に対する植民地政策により明治、大正をつうじて沖縄のこうむった打撃は大きく、明治末年には首里、那覇の中産階級はほとんど凋落し、地方農村も荒廃し沖縄人の生活は窮乏のどん底になげこまれた。ことに明治政府は日清、日露と二度にもわたって戦争を強行し大正に入ってからは第一次世界大戦が1914年(大正3年)8には米騒動が起こって全国的に波及し社会不安が高まって行った。浦崎氏の思想運動・社会運動への出発もこのあたりから始まっている。(略)
沖縄の第一回メーデーは1921年(大正10年)5月1日に行われている。中央メーデーに、わずか1年おくれて行われていることは沖縄の置かれている地位が中央の政治的、社会的諸条件に類似するためであろう。メーデーは無政府主義者の城田徳隆らと社会主義者の山田有幹らの共催によるものであるが、このころはまだアナーキズムとボルシェヴィーズムの対立は生じてなかったようだ。
〇浦崎康華□うるわしい同志愛ー沖縄の初期社会運動家はみんな童名をもっていた。特に首里、那覇出身は本名(名乗)はあまり用いないで、泉正重はカマデー、伊是名朝義はヤマー、座安盛徳はカミジュー、辺野喜英長はマツー、城間康昌はジルー、渡久地政憑はサンルー、東恩納寛敷はタルー、宜保為貞はサンルー、阿波連之智はカミー、松本三益はタルー、比嘉良児はサンルーといった。相手が年長であればヤッチー(兄)をつけてマツー・ヤッチー(マツー兄)と呼んでいたので、非常になごやかで同志愛で結ばれていた。ときにはアナ・ボル論争もあることはあったが目くじらを立てて口論することはなかったし、みんな生存中の友好関係は変わらなかった。われわれからいえばソ連や中国などで、ときどき起こる指導権争いや権力闘争に類したようなことは全くなかった。これは社会運動の分野ばかりでなく新聞人同志もそうであった。
1923年9月1日 関東大震災
この年 普久原朝喜、来阪
1926年10月 沖縄県大阪物産斡旋所設置
1927年3月 宮城清市、来阪
1929年4月4日 照屋林助、大阪で生まれる
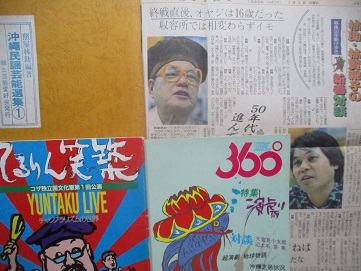

照屋林助・林賢資料/2005-5-12『沖縄タイムス』「照屋林助さん追悼特集(2005-3-10没・75歳)」
1935年5月 大正区沖縄県人会結成(宮城清市会長)
この頃、嘉手苅林昌来阪
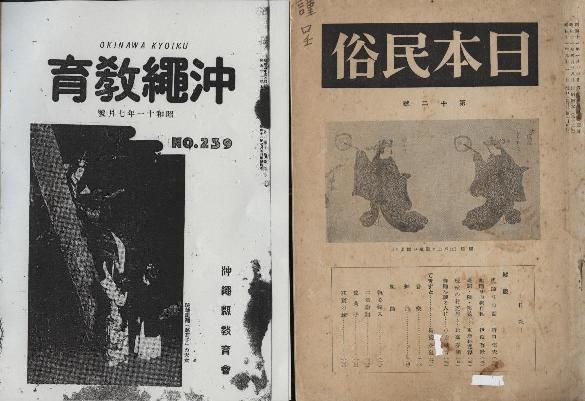
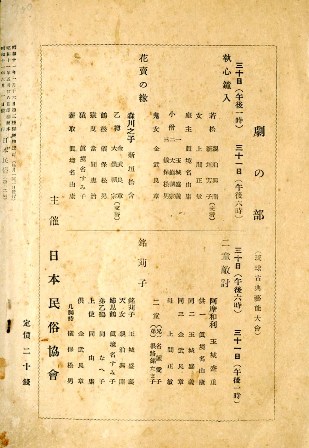
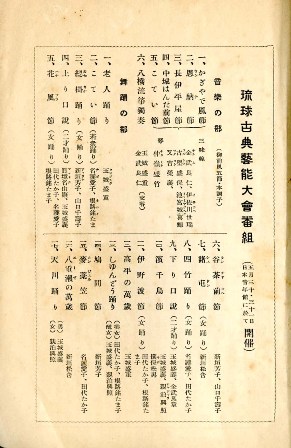
1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔
1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平
1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」
1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆
1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶
1937年 大里喜誠、彦根高等商業学校(現滋賀大学)卒業
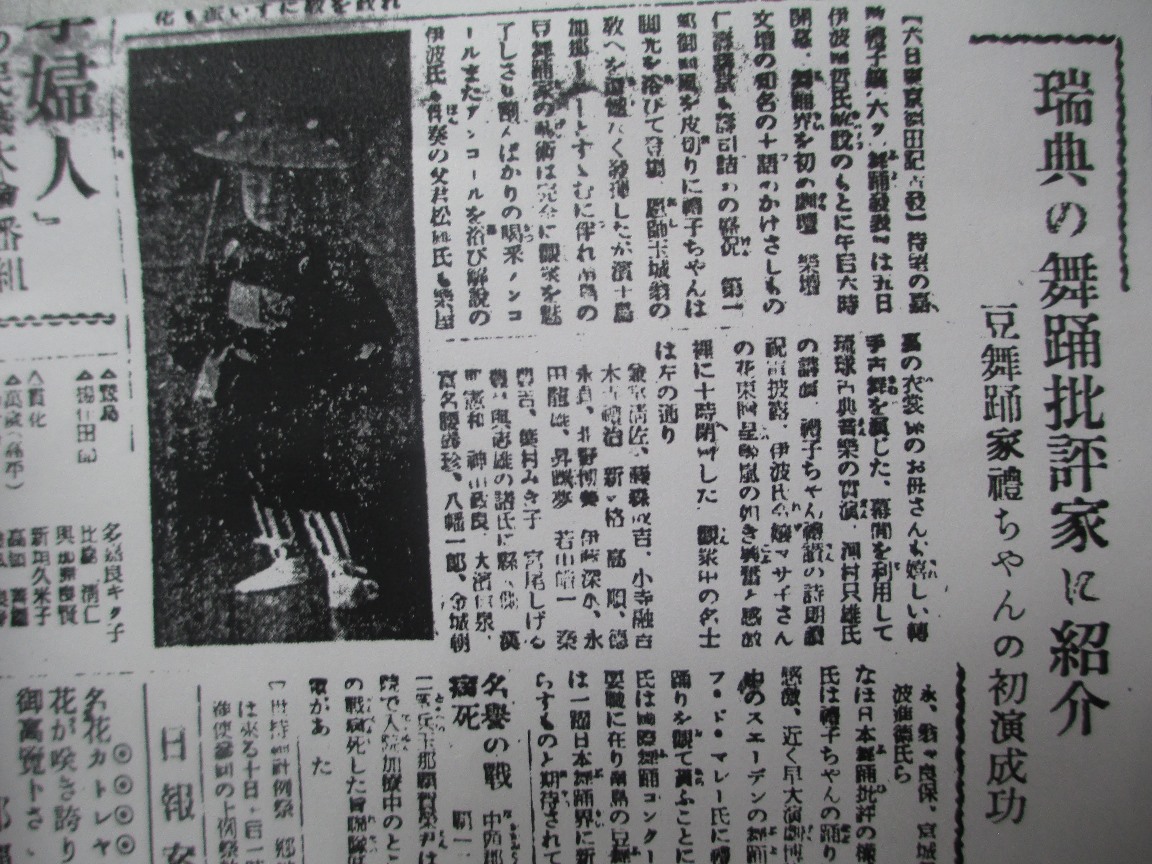
1940年11月8日『沖縄日報』
1941年5月7日ー舞踊家・玉城節子、那覇辻町で生まれる。3ヶ月目に父・友盛の仕事で大阪へ。(1946年、帰沖し石川市に住む)
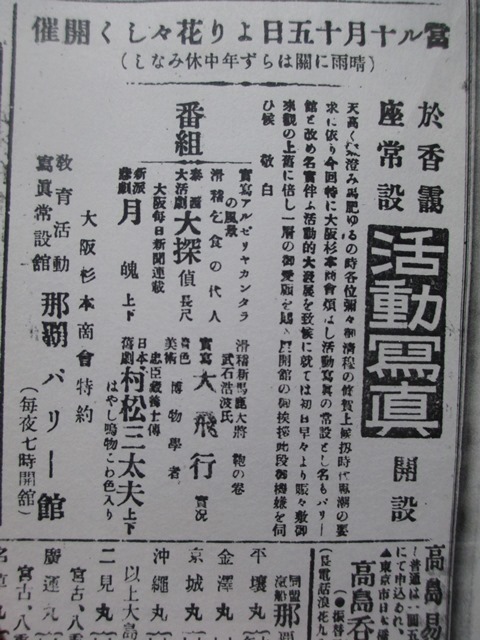
パリー館「アルジェリア カンタラの風景」
11/06: 年譜・末吉麦門冬/1923(大正12)年
1923年1月1日ー『日本及日本人』852号□末吉麦門冬「月徘徊」
3月 島倉龍治ら内務省より沖縄神社創立許可を得る
3月 嘉数南星『赤光』地響詩社(ホノルル市)
春 本部朝基、関西大学、警察などで空手を指導
5月 高嶺朝光、沖縄朝日新聞社に記者として入社
6月 眞境名安興、島倉龍治『沖縄一千年史』日本大学
1923年6月15日ー『日本及日本人』864号□末吉麦門冬「黒坊ー近松門左衛門作、天鼓にー」「助兵衛(1)」(南方熊楠と関連)
1923年7月1日ー『日本及日本人』865号□末吉麦門冬「色情狂の所為」「遠目鏡(1)」(南方熊楠と関連)
1923年7月15日ー『日本及日本人』866号□末吉麦門冬「遠目鏡」「支那人と豚」(南方熊楠と関連)
7月 折口信夫、第二回沖縄採訪(~8月28日)
□沖縄採訪記ー末吉安恭「ふうる」「豚の化けた話」「赤身と白身との話」「かわかまぢぃ?」「火玉」「幽霊」「城人」「馬交を見せた話ー馬をつるませて、女たちに見せた話は、尚灝王にもある。」(●安恭の話は1918年5月の熊楠宛書簡でもふれている。)「うすぢ」「ならびち・くくんざけ」「蚤の船」「三比等のとんち」「<人の犯す事ある動物
1923年8月1日ー『日本及日本人』867号□末吉麦門冬「助兵衛(2)」(南方熊楠と関連)

8月11日『沖縄タイムス』莫夢生「老榕の鬚ー俳諧に現はれたあらぬ戀」
9月1日 関東大震災
下地玄信、高安重正、普久原朝喜ら来阪
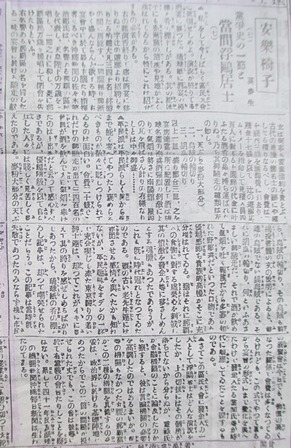

10月1日『沖縄タイムス』莫夢生「安楽椅子ー」
10月 又吉康和、『沖縄教育』編集専任幹事
10月 山城善三、大阪市堀江小学校教員
10月 岩元禧、沖縄県知事(1933年、鹿児島市長)
10月27日 柳田国男、ジュネーブのエスペラントの会で沖縄の話をする

11月15日『沖縄タイムス』莫夢生「おもろに現はれた中頭の四人衆(10)」
12月27日 摂政裕仁、難波大助に狙撃される
12月31日 下國良之助、来沖
3月 島倉龍治ら内務省より沖縄神社創立許可を得る
3月 嘉数南星『赤光』地響詩社(ホノルル市)
春 本部朝基、関西大学、警察などで空手を指導
5月 高嶺朝光、沖縄朝日新聞社に記者として入社
6月 眞境名安興、島倉龍治『沖縄一千年史』日本大学
1923年6月15日ー『日本及日本人』864号□末吉麦門冬「黒坊ー近松門左衛門作、天鼓にー」「助兵衛(1)」(南方熊楠と関連)
1923年7月1日ー『日本及日本人』865号□末吉麦門冬「色情狂の所為」「遠目鏡(1)」(南方熊楠と関連)
1923年7月15日ー『日本及日本人』866号□末吉麦門冬「遠目鏡」「支那人と豚」(南方熊楠と関連)
7月 折口信夫、第二回沖縄採訪(~8月28日)
□沖縄採訪記ー末吉安恭「ふうる」「豚の化けた話」「赤身と白身との話」「かわかまぢぃ?」「火玉」「幽霊」「城人」「馬交を見せた話ー馬をつるませて、女たちに見せた話は、尚灝王にもある。」(●安恭の話は1918年5月の熊楠宛書簡でもふれている。)「うすぢ」「ならびち・くくんざけ」「蚤の船」「三比等のとんち」「<人の犯す事ある動物
1923年8月1日ー『日本及日本人』867号□末吉麦門冬「助兵衛(2)」(南方熊楠と関連)

8月11日『沖縄タイムス』莫夢生「老榕の鬚ー俳諧に現はれたあらぬ戀」
9月1日 関東大震災
下地玄信、高安重正、普久原朝喜ら来阪
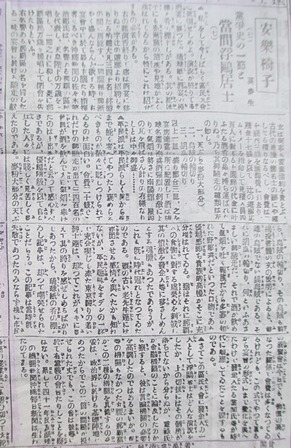

10月1日『沖縄タイムス』莫夢生「安楽椅子ー」
10月 又吉康和、『沖縄教育』編集専任幹事
10月 山城善三、大阪市堀江小学校教員
10月 岩元禧、沖縄県知事(1933年、鹿児島市長)
10月27日 柳田国男、ジュネーブのエスペラントの会で沖縄の話をする

11月15日『沖縄タイムス』莫夢生「おもろに現はれた中頭の四人衆(10)」
12月27日 摂政裕仁、難波大助に狙撃される
12月31日 下國良之助、来沖
12/20: 1972年11月『別冊経済評論』「日本のアウトサイダー」
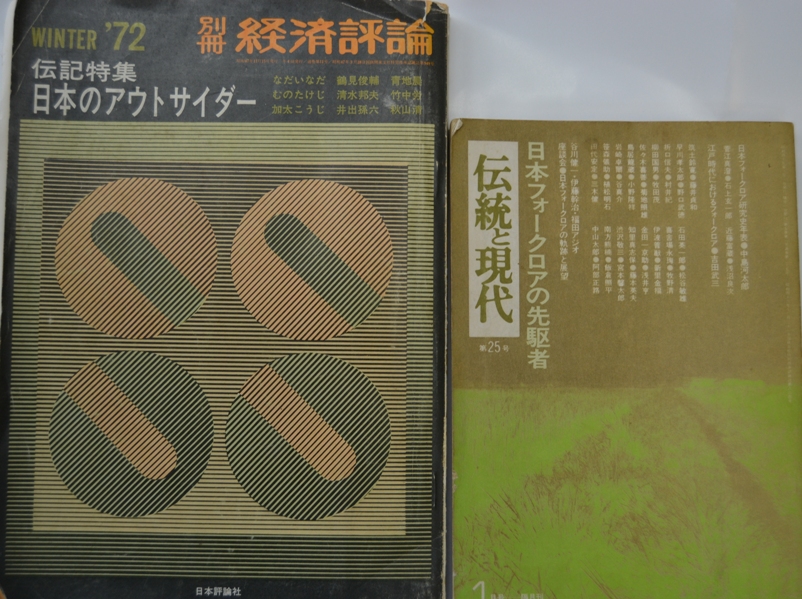
1972年11月『別冊経済評論』「日本のアウトサイダー」
桐生悠々(むのたけじ)/宮武外骨(青地晨)/伊藤晴雨(石子順造)/高橋鐵(竹中労)/沢田例外(森長英三郎)/安田徳太郎(安田一郎)/田中正造(田村紀雄)/菊池貫平(井出孫六)/山口武秀(いいだもも)/北浦千太郎(しまねきよし)/古田大次郎(小松隆二)/平塚らいてぅ(柴田道子)/高群逸枝(河野信子)/長谷川テル(澤地久枝)/宮崎滔天(上村希美雄)/橘撲(髙橋徹)/西田税(松本健一)/謝花昇(大田昌秀)/南方熊楠(飯倉照平)/出口王仁三郎(小沢信男)/山岸巳代蔵(水津彦雄)/尾崎放哉(清水邦夫)/添田唖蝉坊(荒瀬豊)/辻潤(朝比奈誼)/稲垣足穂(折目博子)/天龍(秋山清)/淡谷のり子(加太こうじ)/谷川康太郎(猪野健治)
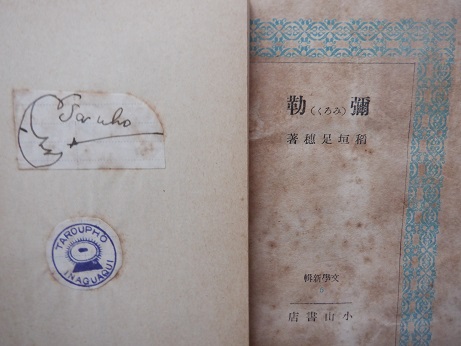
タルホ
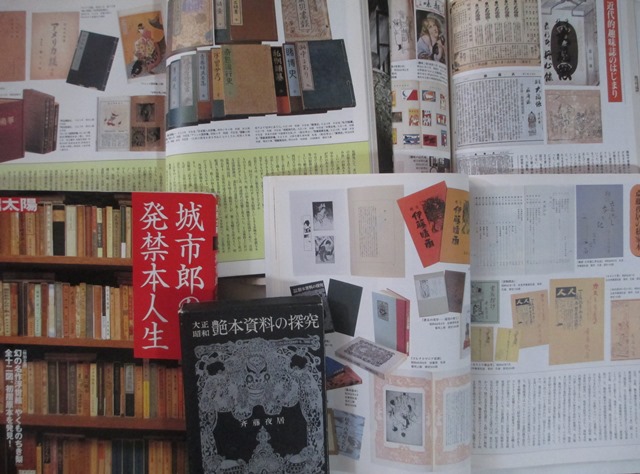
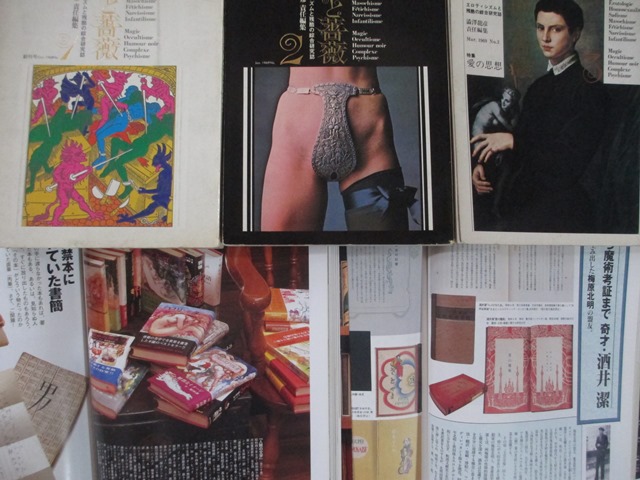
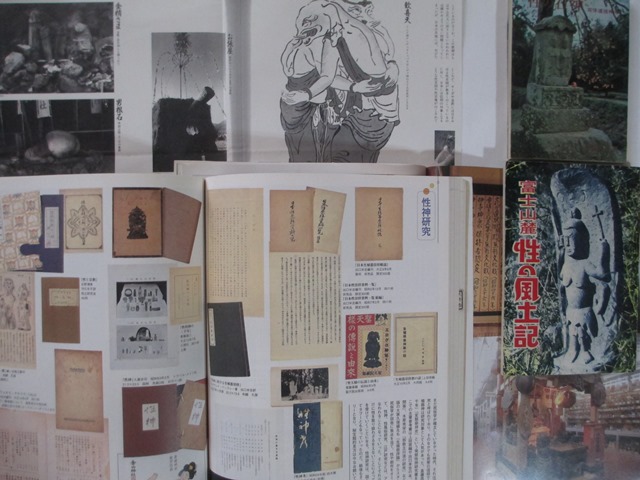
「発禁本」資料
現代筆禍文献大年表
明治28年3月 沖縄県私立教育会雑誌(沖縄県 安井宗明)
明治33年10月 沖縄青年会会報(渡久地政瑚)
大正5年 沖縄民報6月15日第677号
大正10年2月 不穏印刷物2枚「沖縄庶民会創立委員発行」
大正13年11月 沖縄タイムス「11月13日14日亘る難波大助に係る不敬事件判決言渡に関する記事」
大正14年5月 地方行政5月号 神山宗勲「燃え立つ心」
1978年、桃源社発行の酒井潔『愛の魔術』に澁澤龍彦が解説で「酒井潔は堅苦しい学者ではなく、何よりもまず、面白く語って読者を楽しませようとする、根っからのエンターティナーがあった。それは本書をお読みになれば、誰にでも十分に納得のいくことであろう。明治の南方熊楠ほどのスケールの大きさは望むべくもないが、彼自身も南方に傾倒していたように、その方向の雑学精神の系統をひく人物であったことは間違いあるまい」と書いている。
麦門冬ー熊楠ー岩田準一ー乱歩
1931年6月には竹久夢二が元北米の邦人新聞記者・翁久充の企画で、サンフランシスコに入り、1年余にわたり米国に滞在し、ロスを中心に展示会や在米見聞記「I CAME I SAW」の題で新聞連載、スケッチ旅行などをしている。アワビ漁で成功した小谷源之助はポイント・ロボスの海岸に来客用の別荘を建て芸術家や文人、政治家らを宿泊させていた。夢二研究家の鶴谷壽(神戸女子大教授)が夢二と宮城与徳(画家・ゾルゲ事件に連座)が小谷家の方と一緒に写っている写真を発表している。夢二は翁と新聞社のストのことで喧嘩別れをし、気の合う若い与徳としばらく一緒に生活しながら絵を描いていたようである。夢二は翌年の10月にはヨーロッパへと足をのばし、欧州各地を渡り歩き、ドイツの邦人グループと一緒になってユダヤ人救済運動に関わっている。彼は平民社の幸徳秋水とも交流し、医師の安田徳太郎とのつながりもある。彼の反戦のコマ絵をみると、夢二の美人画はもの悲しい憂いにみち、放浪とロマンを追い続けた夢二の後ろ姿に重なる。(大城良治)
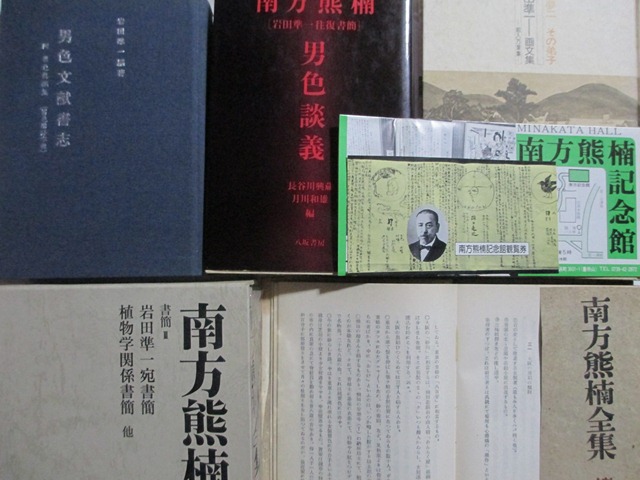
夢二の弟子に岩田準一が居る。□岩田準一 いわた-じゅんいち 1900-1945 昭和時代前期の挿絵画家,民俗研究家。明治33年3月19日生まれ。中学時代から竹久夢二と親交をもつ。江戸川乱歩の「パノラマ島奇譚」「鏡地獄」などに挿絵をかく。郷里三重県志摩地方の民俗伝承の研究や,男色の研究でも知られ,南方熊楠(みなかた-くまぐす)との往復書簡がある。昭和20年2月14日死去。46歳。文化学院卒。旧姓は宮瀬。著作に「志摩のはしりかね」など。(コトバンク)□→「岩田準一と乱歩・夢二館(鳥羽みなとまち文学館」(.所在地〒517-0011三重県鳥羽市鳥羽2丁目 交通アクセス鳥羽駅から徒歩で10分 ..お問合わせ0599-25-2751) .
今年3月15日にJR西日本「おおさか東線」が開業した。5月26日、息子の家(布施)から近い真新しい長瀬駅から乗る。久宝寺駅で乗り換え王子経由で9時前に法隆寺に着く。法隆寺は日本仏教の始祖といわれている聖徳太子を祀っている。日本最初の世界文化遺産でもある。法隆寺には和歌山有田の修学旅行生がバス3台で見学に来ていた。このときは夢殿とその周辺を見て帰った。那覇に帰る前日の6月6日、あけみと一緒に改めて法隆寺見学、金堂は改修工事中で上御堂で御本尊の金銅釈迦三尊像を拝観。1998年に完成した大宝蔵院には百済観音像玉虫厨子などが安置されている。出てすぐの所の大きな蘇鉄の前で、あけみを立たせて記念写真。法輪寺、法起寺の三重塔も見学した。
辛口批評家の谷沢永一氏著『聖徳太子はいなかった』新潮新書によると、柳田国男は聖徳太子が虚構であることを知っていた。古事記や日本書紀について書くのは柳田は慎重であったという。柳田が自分の見るところ信じられるところにしたがって記紀をいじれば、なにしろあの時代においてのことであるから、かならずヤケドするとわかっていた。とくに民俗学は理論をおしすすめてゆくと、当時やかましかった国体の問題につきあたる。折口信夫」も微妙に避けた。現代の学者がおのれの創見であるといなないているテーマのいくつかは、知られていたけど書けなかった、という。俳人・末吉麦門冬も南方熊楠宛の書簡で「小生も嘗て『古事記を読む』の題にて古代人の恋愛問題を論じヨタを飛ばし過ぎた為か、これを載せた新聞の編集人が、検事局に呼出されて叱られた」と書いている。

契沖の出家した妙法寺(今里)
息子の家からほど近いところに司馬遼太郎記念館と、契沖の出家した妙法寺(今里)がある。契中は水戸光圀と出会い『万葉代匠記』をまとめた。本居宣長は契中を「古學の祖」と位置付けた。今里駅から大阪市内に入ると天王寺公園がある。琉球処分のとき警官で来琉したのが池上四郎、大阪の礎を築いた関一市長は著名だが、その関を呼び寄せたのが池上6代目大阪市長である。池上の銅像が天王寺公園にあるが池上の曾孫が沖縄に何かと縁がある秋篠宮紀子さん。北上し中之島に出る。その昔、豊臣秀吉が大阪城築城のときに全国から巨石が集められた。川に落ちたのも多数にのぼる。中之島公会堂近くに豊国神社があった。神社は大阪城内に移された。その跡に木村長門守重成表忠碑がある。碑は元沖縄県令で大阪府知事を退いていた西村捨三と、大阪北の侠客小林佐兵衛が発起し安治川口に沈んでいた築城用の巨石を引きあげ建立したもの。毛馬公園には那覇港築港にも関わった工学士・沖野忠雄の胸像がある。

木邨長門守重成表忠碑(彦根西邨捨三譔 日下部東作書)
【日下部鳴鶴】書家。近江彦根の人。名は東作,字は子暘。彦根藩士日下部三郎右衛門の養子となったが,桜田門の変で父は殉死した。1869年(明治2)東京に出て太政官大書記となったが,後年は書をもって身をたてた。はじめ巻菱湖(まきりようこ)の書風を学ぶが,80年に来朝した楊守敬の影響を受けて六朝書道を研究,のち清国にも遊学して見聞を広め,深い学識と高古な人柄とによって彼の書名は一世を風靡した。現代書道発展の先駆者として,その功績は高く評価されている。→コトバンク
池上四郎
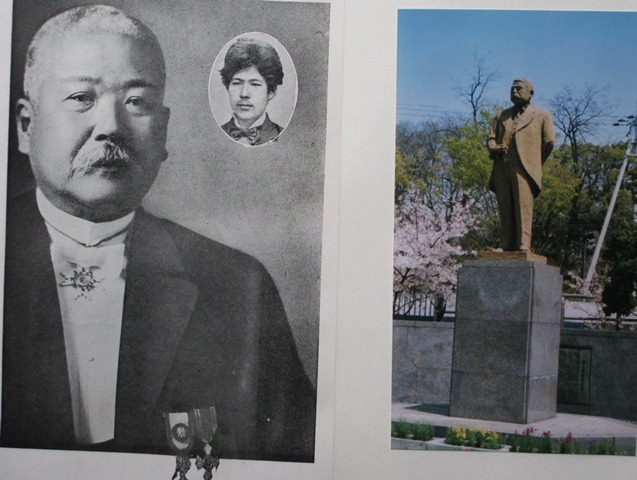
□池上四郎ー1877年、池上は警視局一等巡査として採用され、間もなく警部として石川県に赴任した。その後、富山県などの警察署長、京都府警部などを歴任し、1898年からは千葉県警察部長、兵庫県警察部長を務めた。1900年には大阪府警察部長となり、その後13年間に渡って大阪治安の元締めとして活躍した。その清廉で、自ら現場に立ち責任を果たす働きぶりと冷静な判断力は、多くの市民からの信頼を集めた。1913年、市政浄化のため、池上は嘱望されて大阪市長に就任した。財政再建を進める一方、都市計画事業や電気・水道事業、さらには大阪港の建設などの都市基盤を整備し、近代都市への脱皮を図った。御堂筋を拡張し大阪のメインストリートとする計画は池上の市長時代に立案され、続く関一市長時代に実現を見た。また、市庁舎の新築、博物館や図書館などの教育施設や病院の整備など、社会福祉の充実にも注力した。池上は1915年に天王寺動物園を開園させ、1919年に全国初の児童相談所・公共託児所を開設した。1923年には大阪電燈株式会社を買収し、電力事業を市営化した。また1923年9月に発生した関東大震災では、いち早く大阪港から支援物資を東京に送り、被災者の救済を行った。(ウィキメディア)
1879年3月、松田道之琉球処分官が、後藤敬臣ら内務官僚42人、警部巡査160人余(中に天王寺公園に銅像がある後の大阪市長・池上四郎も居た)、熊本鎮台分遣隊400人をともない来琉し琉球藩を解体、沖縄県を設置した。この時、内務省で琉球処分事務を担当したのが西村捨三であった
1918年、富山県魚津で火蓋を切った米騒動は、瞬く間に全国を席巻し、軍隊の動員を待たねば沈静化せず、ために時の寺内内閣は総辞職した。大阪では、その米騒動の収拾のために米廉売資金が集められていた。その残金を府・市で折半したのであるが、府(林市蔵知事)では発足したばかりの方面委員制度のために利用した。市(池上四郎市長ー秋篠宮妃紀子曽祖父)では「中産階級以下の娯楽機関として市民館創設資金」27万7千円弱が市に指定寄附されたのを受けて、1921年6月20日、天神橋筋六丁目(天六)に日本初の公立セツルメント「市立市民館」を開設したのである。これが、1982年12月に閉館を迎えるまで62年間にわたって、大阪ばかりでなく全国の社会福祉界に歴史的シンボルとして存在した「大阪市立北市民館」(1926年の天王寺市民館開設とともに改称)の始まりであった。
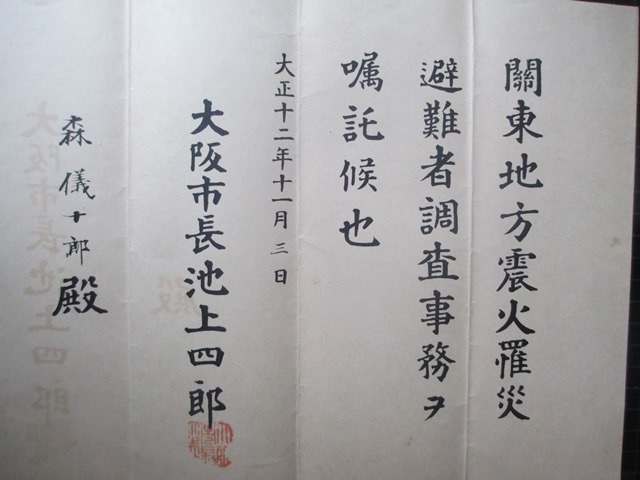
□小林佐兵衛 生年: 文政12 (1829) 没年: 大正6.8.20 (1917)
明治期の侠客。大坂生まれ。通称は北の赤万(明石屋万吉)。年少から侠気を発揮し,幕末には大坂の警備に当たった一柳 対馬守に請われて捕吏頭を務めながら,禁門の変(1864)で敗れた長州藩士の逃亡を助けたりする。維新後に大阪の消防が請負制度になると,渡辺昇知事に頼まれ北の大組頭取として活躍した。米相場で成した資産を投じ,小林授産所を営み,多数の貧民に内職を教え,子どもは小学校へ通わせた。明治44(1911)年9月,米相場の高騰で苦しむ貧民のため,取引所へ乗り込んで相場を崩す。貧民700人の無縁墓を高野山に建立。浪速侠客の典型として,司馬遼太郎の小説『俄』のモデルになる。 (コトバンク)
1932年 東恩納寛惇、年末までに首里侯爵邸に通い2000冊の文献を読破
1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。
1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」
1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。
1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>
1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学
1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く
1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足
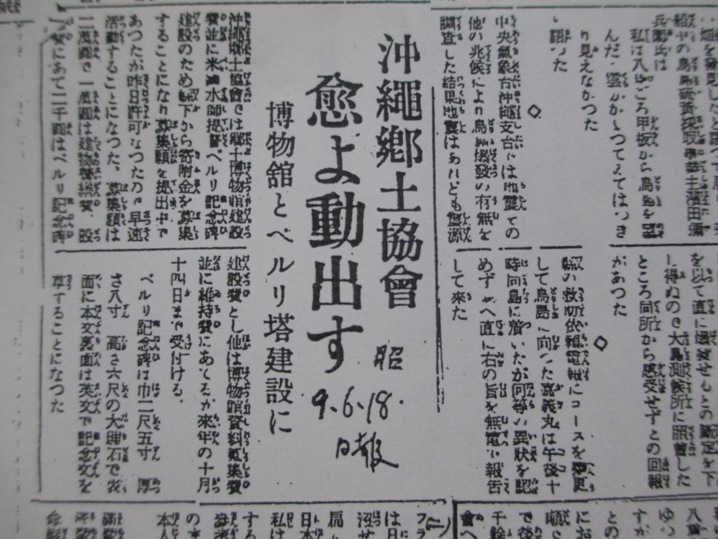
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社
1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式
1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。
□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社
1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)
1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観
1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観
1935年10月 『沖縄教育』第230号
□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部
安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、
1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観
1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」
1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会
1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ
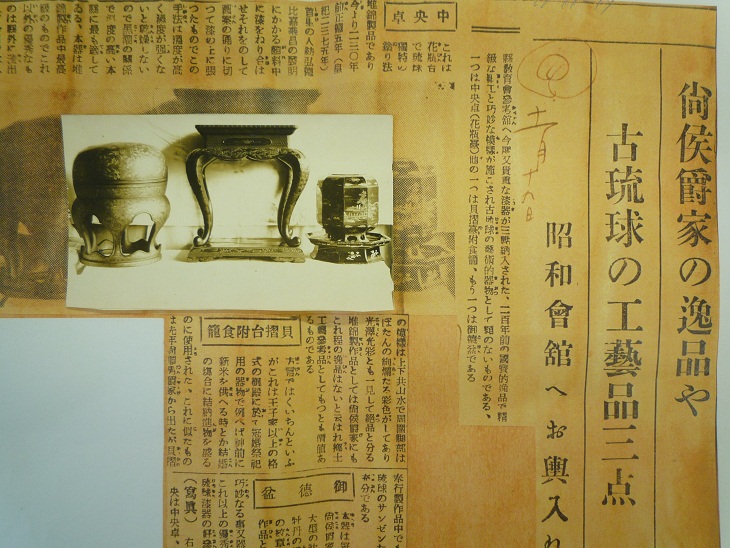
11月19日
1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」
1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観
1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。
1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」
1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。
1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)
1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事
4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)
1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館
1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁
1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。
公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。
又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。
1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」
1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転
1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」
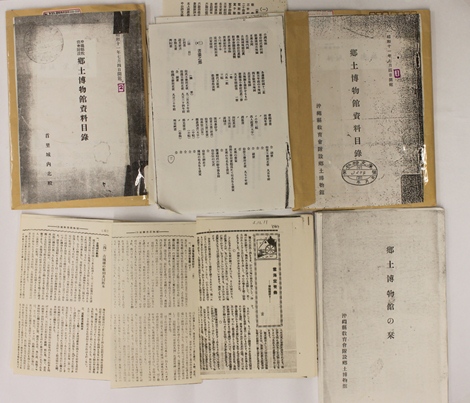
1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」
沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台
□図表之部
喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図
1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房
1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。
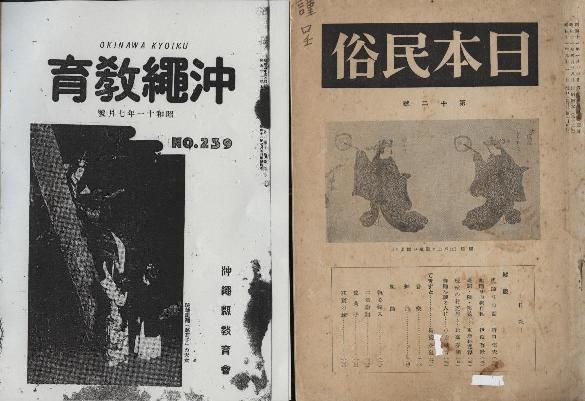
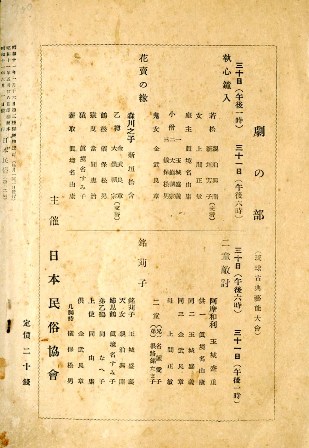
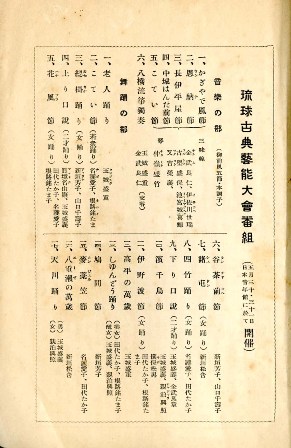
1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔
1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平
1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」
1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆
1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶
1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」
1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通
1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館
1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」
1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。
1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」
□
1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師
1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式
1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」
1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席
1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列
1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」
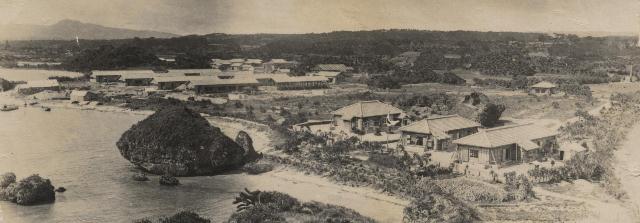
1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」
1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」
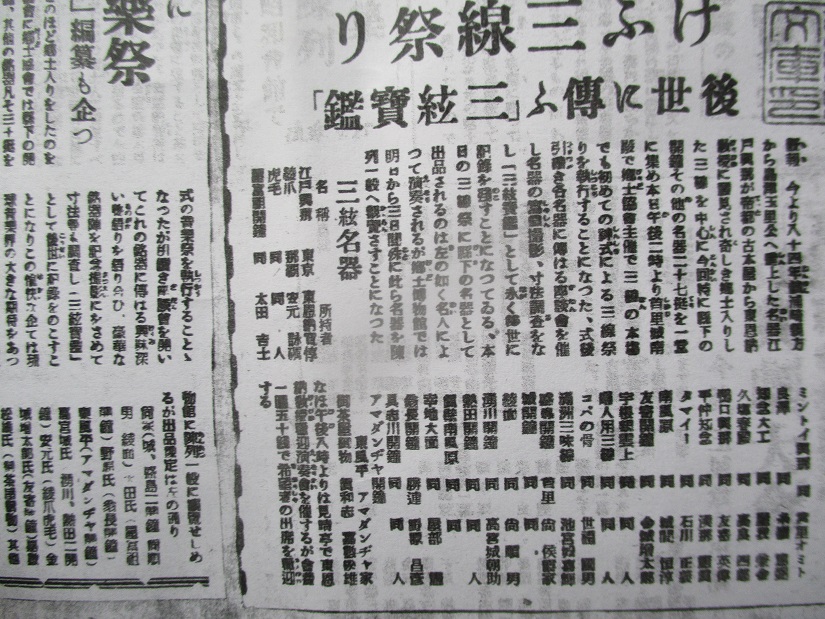
1939年8月5日
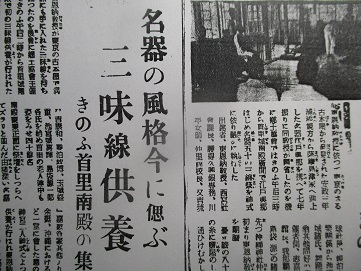
1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」
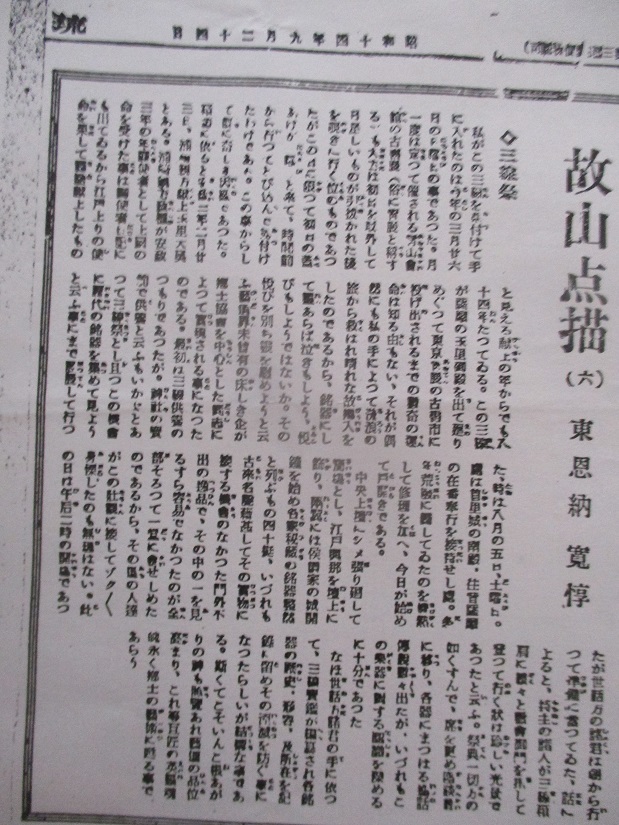
1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」
〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。
1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。
1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」
1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。
1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>
1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学
1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く
1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足
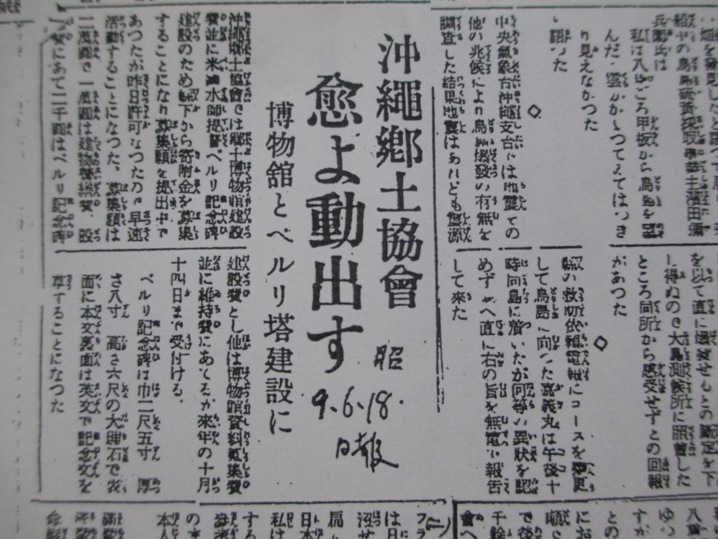
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社
1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式
1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。
□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社
1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)
1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観
1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観
1935年10月 『沖縄教育』第230号
□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部
安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、
1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観
1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」
1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会
1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ
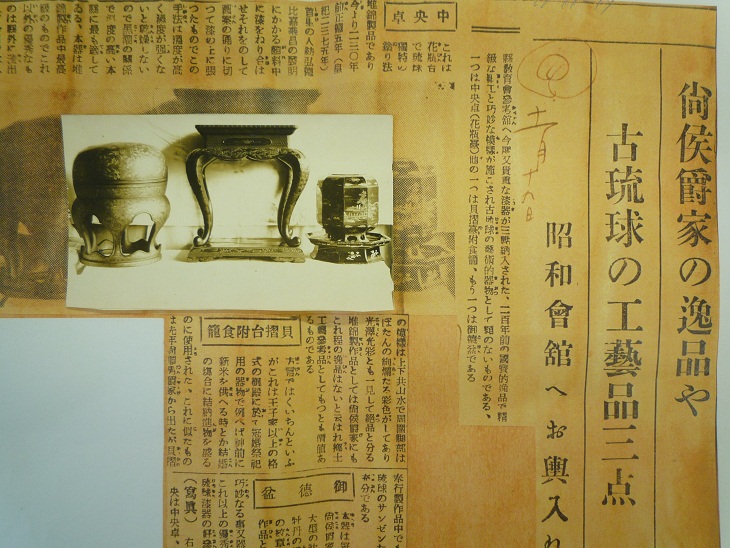
11月19日
1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」
1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観
1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。
1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」
1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。
1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)
1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事
4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)
1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館
1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁
1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。
公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。
又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。
1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」
1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転
1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」
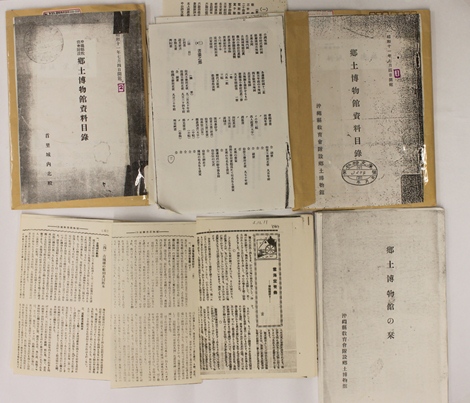
1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」
沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台
□図表之部
喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図
1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房
1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。
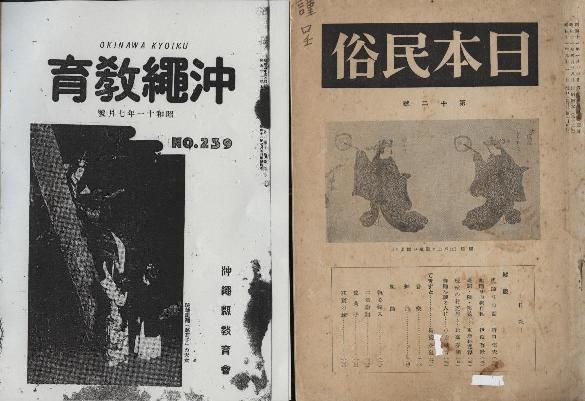
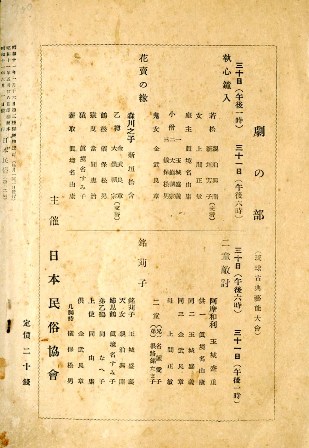
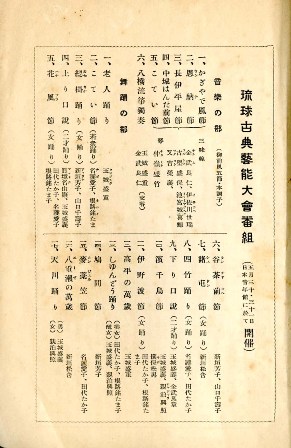
1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔
1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平
1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」
1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆
1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶
1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」
1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通
1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館
1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」
1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。
1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」
□

1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師
1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式
1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」
1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席
1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列
1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」
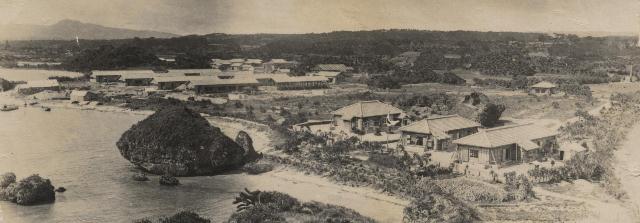
1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」
1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」
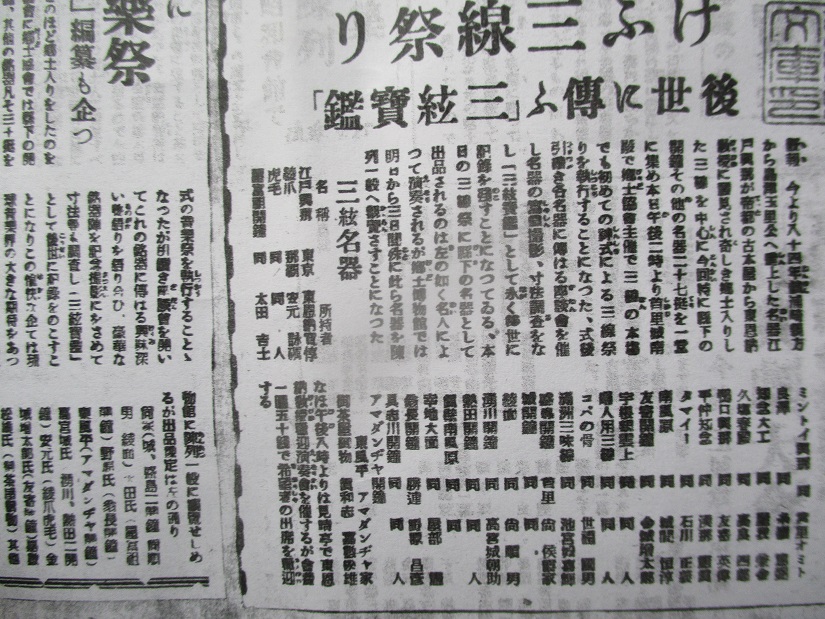
1939年8月5日
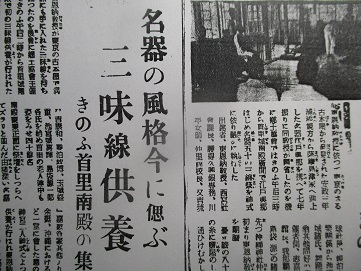
1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」
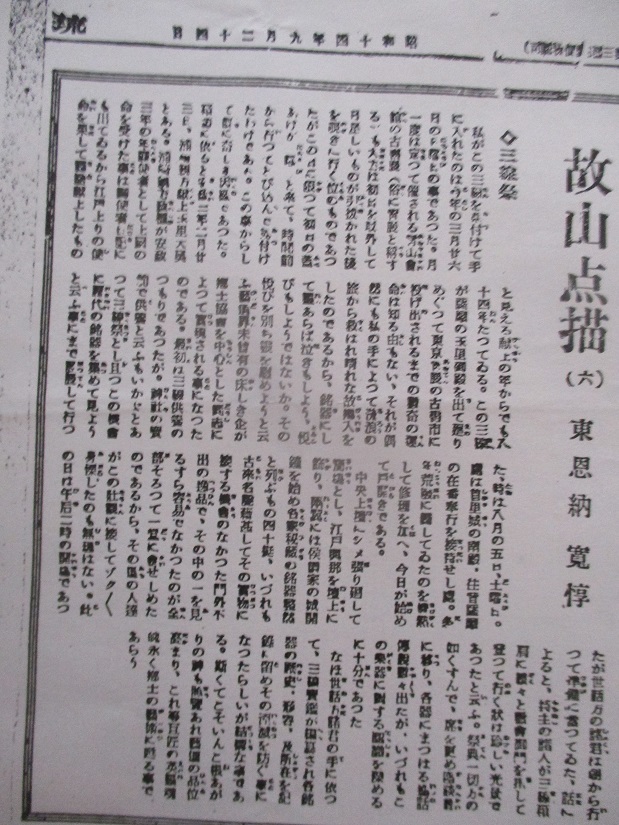
1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」
〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com

2016年8月15日 美栄橋駅 右上にジュンク堂書店の看板が見える

2016年8月15日(今日オキナワは旧盆ウンケー。ヤマトは敗戦忌。ヤマトの重大なエポックの日のはずだが休日ではない それにしても戦勝国アメリカ軍基地の今なお増殖活発のオキナワ アメリカ軍基地維持費は何故かヤマトの負担 辺野古新基地には大手ゼネコン) 美栄橋駅

2016-10-28 前島から中の橋方面を望む。手前で工事中

2016年8月15日 美栄橋駅 右上にジュンク堂書店の看板が見える

2016年8月15日(今日オキナワは旧盆ウンケー。ヤマトは敗戦忌。ヤマトの重大なエポックの日のはずだが休日ではない それにしても戦勝国アメリカ軍基地の今なお増殖活発のオキナワ アメリカ軍基地維持費は何故かヤマトの負担 辺野古新基地には大手ゼネコン) 美栄橋駅

2016-10-28 前島から中の橋方面を望む。手前で工事中
03/29: 作家・川端康成 ①
□笹川良一の父・鶴吉はかねてよりの碁敵川端三八郎(天保12<1841>年4月10日生まれ)を招き、碁盤を挟んで睨み合っていた。三八郎の孫が康成である。(略)ときに川端康成は、第四代日本ペンクラブ会長として国際ペンクラブ大会の招聘などに奔走し、資金調達に大いに腐心していた。そんな折、竹馬の友は進んで資金援助を申し出ている。(2010年10月 工藤美代子『悪名の棺 笹川良一伝』幻冬舎)
1938年2月」19日『沖縄日報』「懐しの歌手 藤山一郎君きのふ思出の那覇へ/川端康成氏来月来訪」
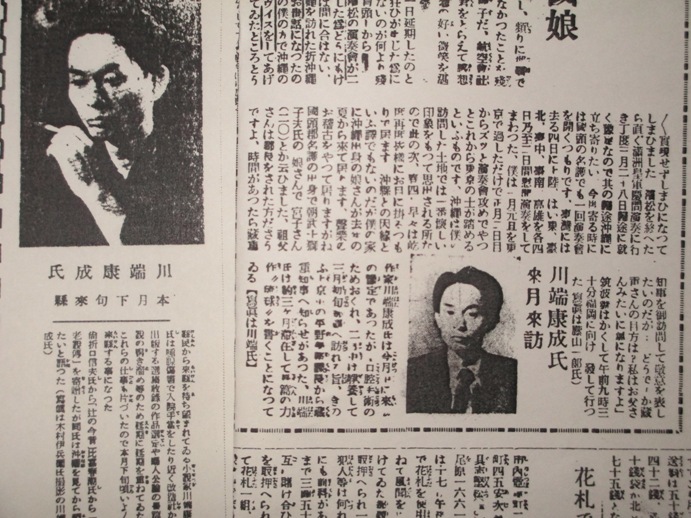
1938年3月『琉球新報』□東京の比嘉春潮から國吉眞哲に「川端康成が沖縄に行く予定で、折口信夫からは『辻の今昔』、比嘉春潮から『遺老説傳』を寄贈された。川端氏は沖縄を見てから読みたい、との話を知らせてきた。が、何らかの事情で来沖は実現しなかった。
1938年4月2日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(2)
1938年4月5日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(4)
1938年4月13日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(3)
1938年4月14日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(4)
1938年4月26日『琉球新報』「簪献納運動に悲鳴の金細工達」
石川正通□「ふりむん随筆」
「雪国」の作者川端康成は、その姉妹篇として沖縄に取材した南国物を書こうと意図して、在京の沖縄知名人に集まってもらって一夕の会談で沖縄に関する予備知識を得ようと会合を催した。何に怖気づいたのか、新感覚派で売り出した「伊豆の踊り子」のこの作家は沖縄行を思い止まって、現地における「沖縄の踊り子」を見る機会を自ら捨てた。
1958年6月3日『琉球新報』「川端康成氏きのう来島」
1958年6月3日『沖縄タイムス』「川端康成氏きのう来島ー誕生日は沖縄で」
1958年6月4日『沖縄タイムス』「二人の作家は沖縄を見るー川端康成氏、内村直也氏」
1958年6月5日『琉球新報』「川端康成氏ー民芸はすばらしい 身をもって沖縄を吸収」
1958年6月8日『沖縄タイムス』「座談会・川端康成氏を囲んでー川端康成、豊平良顕、宮城」聡、南風原朝光、牧港篤三、大城立裕、池田和、太田良博」(上)
1958年6月9日『沖縄タイムス』「々々」(下)
1958年6月9日 「川端康成氏を囲んで(座談会)川端康成、仲宗根政善、中今信、亀川正東、池宮城秀意、上原記者」→6月20日『琉球新報』
1958年6月10日『沖縄タイムス』「琉舞の粋に感慨 川端、鳥海氏ら迎え鑑賞会」
1958年6月11日『沖縄タイムス』「川端、鳥海、沢田、横山4氏の講演会」
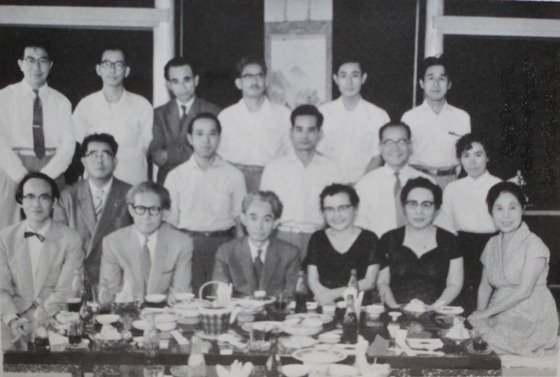

昭和53年9月 千原繁子『随想集 カルテの余白』□1958年6月11日ー前列左から豊平良顕、山里永吉、川端康成、千原繁子、新垣美登子。中列左から具志頭得助、仲本政基、太田良博、牧港篤三。後列左から亀川正東、当真荘平、宮城聡、池宮城秀意、嘉陽安男、船越義彰/写真ー山里永吉案内で糸満の門中墓を見学する川端康成(右)
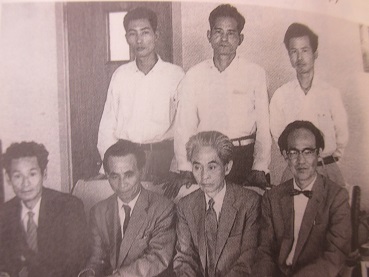
2004年9月 『新生美術』13号「写真前列左よりー南風原朝光、宮城聰、川端康成、豊平良顕/後列左よりー池田和、太田良博、大城立裕」
1958年6月12日『琉球新報』「鳩笛ー川端康成氏は今日のノース・ウェスト機で帰京ーきのうはたまたま川端氏の59回目の誕生日で波上”新鶴”(我那覇文・佐久本嗣子)で、沖縄ペンクラブ主催の別パーティを兼ねた誕生祝」
1958年6月13日『沖縄タイムス』「すばらしい沖縄の踊り 川端氏帰る」/『琉球新報』「川端氏"沖縄独自の美しさ"」

1958年8月『オキナワグラフ』「ペンをかついだお客様ー川端康成氏 来島」
○篤之介のペンネームと感覚的な詩で知られる文学頭取、沖相銀具志頭得助氏の数次にわたる交渉の熱意が実を結び、国際ペンクラブ副会長、日本ペンクラブ会長の川端康成氏が6月2日ひる3時40分、那覇空港着のノースウエスト機で来島した。今回の来島は沖縄ペンクラブの招きによるものであったが、「伊豆の踊子」「雪国」などの作者として文壇でも特異な存在にある同氏の来島は今まで期待されながら不可能視されていただけに、沖縄文化人の喜びは大きく、ペンクラブ会員多数が出迎えた。滞在中はペンクラブの山里、亀川氏や具志頭氏に案内されて、沖縄視察を続けられたが、6月11日、はからずも沖縄で誕生日を迎えたペンの賓客は、ペンクラブ会員、具志頭氏、沖相銀、紅房、那覇薬品、沖縄火災の関係者多数に囲まれ、「私はこんなに誕生日を祝ってもらったのは初めてでしてねエ」と島人達の温かい心づくしにその喜びを語っていた。・・・・
1938年2月」19日『沖縄日報』「懐しの歌手 藤山一郎君きのふ思出の那覇へ/川端康成氏来月来訪」
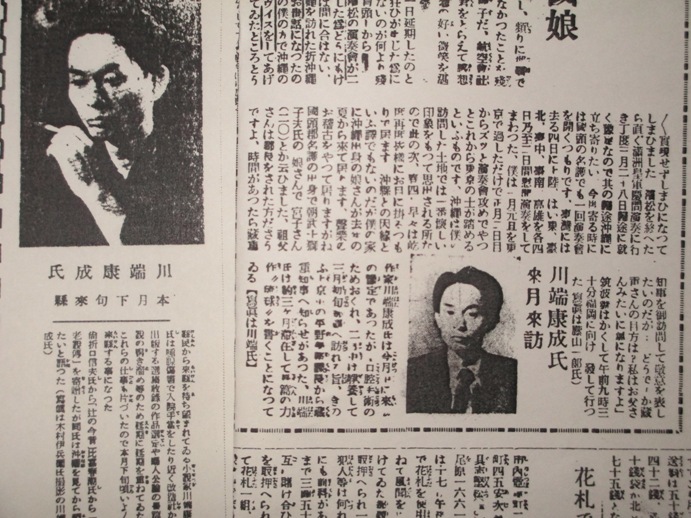
1938年3月『琉球新報』□東京の比嘉春潮から國吉眞哲に「川端康成が沖縄に行く予定で、折口信夫からは『辻の今昔』、比嘉春潮から『遺老説傳』を寄贈された。川端氏は沖縄を見てから読みたい、との話を知らせてきた。が、何らかの事情で来沖は実現しなかった。
1938年4月2日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(2)
1938年4月5日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(4)
1938年4月13日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(3)
1938年4月14日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(4)
1938年4月26日『琉球新報』「簪献納運動に悲鳴の金細工達」
石川正通□「ふりむん随筆」
「雪国」の作者川端康成は、その姉妹篇として沖縄に取材した南国物を書こうと意図して、在京の沖縄知名人に集まってもらって一夕の会談で沖縄に関する予備知識を得ようと会合を催した。何に怖気づいたのか、新感覚派で売り出した「伊豆の踊り子」のこの作家は沖縄行を思い止まって、現地における「沖縄の踊り子」を見る機会を自ら捨てた。
1958年6月3日『琉球新報』「川端康成氏きのう来島」
1958年6月3日『沖縄タイムス』「川端康成氏きのう来島ー誕生日は沖縄で」
1958年6月4日『沖縄タイムス』「二人の作家は沖縄を見るー川端康成氏、内村直也氏」
1958年6月5日『琉球新報』「川端康成氏ー民芸はすばらしい 身をもって沖縄を吸収」
1958年6月8日『沖縄タイムス』「座談会・川端康成氏を囲んでー川端康成、豊平良顕、宮城」聡、南風原朝光、牧港篤三、大城立裕、池田和、太田良博」(上)
1958年6月9日『沖縄タイムス』「々々」(下)
1958年6月9日 「川端康成氏を囲んで(座談会)川端康成、仲宗根政善、中今信、亀川正東、池宮城秀意、上原記者」→6月20日『琉球新報』
1958年6月10日『沖縄タイムス』「琉舞の粋に感慨 川端、鳥海氏ら迎え鑑賞会」
1958年6月11日『沖縄タイムス』「川端、鳥海、沢田、横山4氏の講演会」
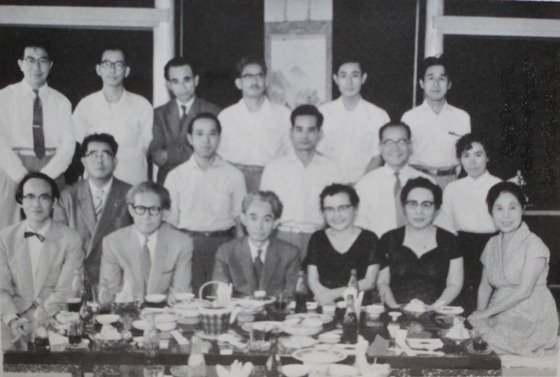

昭和53年9月 千原繁子『随想集 カルテの余白』□1958年6月11日ー前列左から豊平良顕、山里永吉、川端康成、千原繁子、新垣美登子。中列左から具志頭得助、仲本政基、太田良博、牧港篤三。後列左から亀川正東、当真荘平、宮城聡、池宮城秀意、嘉陽安男、船越義彰/写真ー山里永吉案内で糸満の門中墓を見学する川端康成(右)
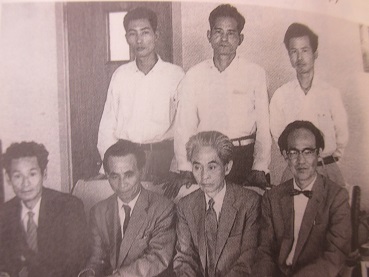
2004年9月 『新生美術』13号「写真前列左よりー南風原朝光、宮城聰、川端康成、豊平良顕/後列左よりー池田和、太田良博、大城立裕」
1958年6月12日『琉球新報』「鳩笛ー川端康成氏は今日のノース・ウェスト機で帰京ーきのうはたまたま川端氏の59回目の誕生日で波上”新鶴”(我那覇文・佐久本嗣子)で、沖縄ペンクラブ主催の別パーティを兼ねた誕生祝」
1958年6月13日『沖縄タイムス』「すばらしい沖縄の踊り 川端氏帰る」/『琉球新報』「川端氏"沖縄独自の美しさ"」

1958年8月『オキナワグラフ』「ペンをかついだお客様ー川端康成氏 来島」
○篤之介のペンネームと感覚的な詩で知られる文学頭取、沖相銀具志頭得助氏の数次にわたる交渉の熱意が実を結び、国際ペンクラブ副会長、日本ペンクラブ会長の川端康成氏が6月2日ひる3時40分、那覇空港着のノースウエスト機で来島した。今回の来島は沖縄ペンクラブの招きによるものであったが、「伊豆の踊子」「雪国」などの作者として文壇でも特異な存在にある同氏の来島は今まで期待されながら不可能視されていただけに、沖縄文化人の喜びは大きく、ペンクラブ会員多数が出迎えた。滞在中はペンクラブの山里、亀川氏や具志頭氏に案内されて、沖縄視察を続けられたが、6月11日、はからずも沖縄で誕生日を迎えたペンの賓客は、ペンクラブ会員、具志頭氏、沖相銀、紅房、那覇薬品、沖縄火災の関係者多数に囲まれ、「私はこんなに誕生日を祝ってもらったのは初めてでしてねエ」と島人達の温かい心づくしにその喜びを語っていた。・・・・
04/15: 沖縄コレクター友の会②
2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。
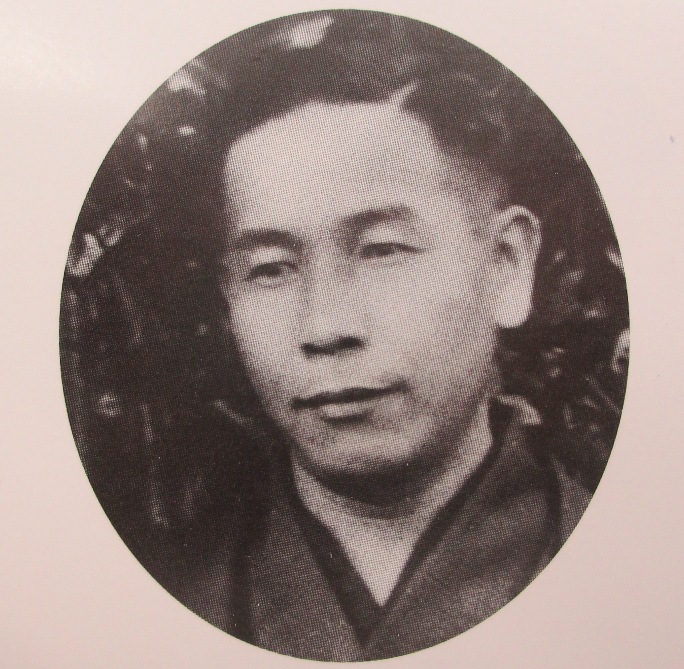
魚住惇吉
○大正13年(1924年)魚住惇吉校長の後を受けて建学当初から教鞭をとられた志喜屋孝信先生が第四代校長に就任した。
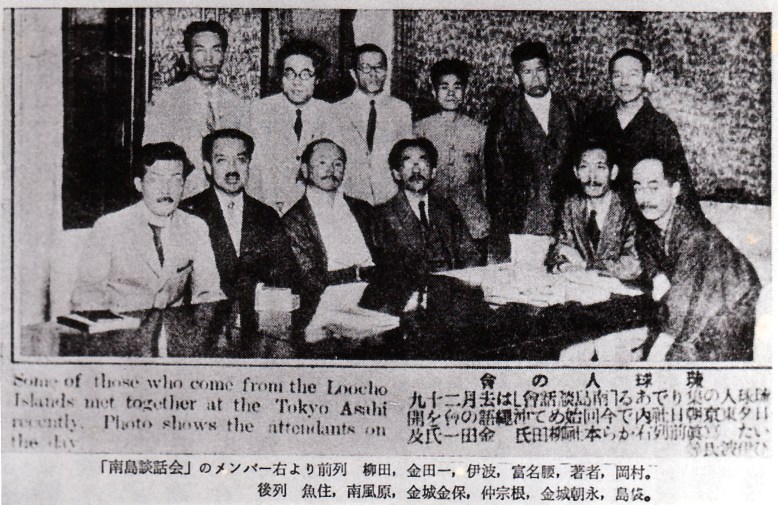
『アサヒグラフ』1927年7月13日号□南島談話会のメンバー/前列右より柳田国男・金田一京助・伊波普猷・富名腰義珍・岡村千秋 後列右より魚住惇吉・南風原驍・金城金保・仲宗根源和・金城朝永・島袋源七

1924年夏 小石川植物園で、向かって右から魚住惇吉、永田千代、
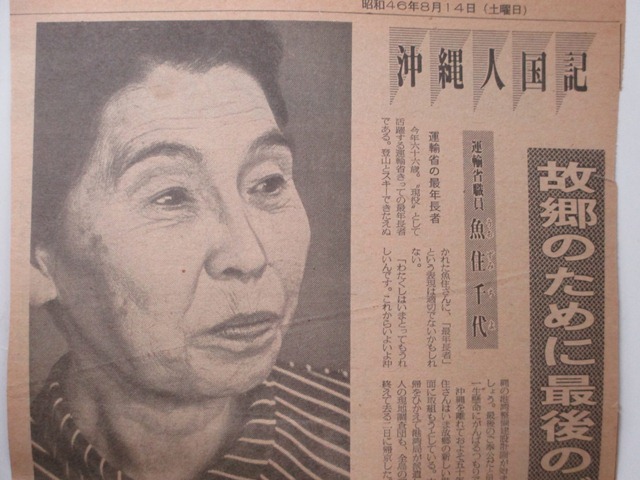
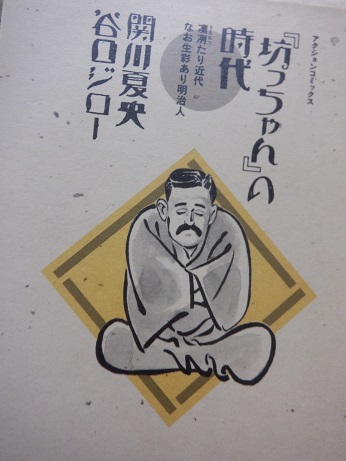
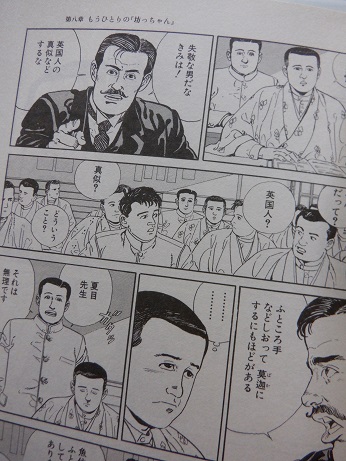
1987年8月 関川夏央・谷口ジロー『「坊っちゃん」の時代』双葉社
1988年8月 日本エッセイスト・クラブ『思いがけない涙』文藝春秋□魚住速人(三菱鉱業セメント副社長)「漱石と隻腕の父ー(略)実をいうと、私の父が、その左手のない学生である。名前は惇吉という。(略)私の父は東大を卒業したあと、中学の英語教師になり、沖縄県立第二中学校の校長を最期に、台湾旅行のとき罹ったマラリアの持病もあって、42歳で早々と引退、自適の生活に入った。ふたたび東大に通い、英文学やラテン語の研究をしていたことを覚えている。(略)私の息子が東大野球部に入り、法政の江川投手を4打数3安打で打ち破ったことがあるのを父が知ったら、さぞかし喜んだことであろう。」
09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」
伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。
1891年
4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)
1900年
9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。
1903年
9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。
1904年
7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。
1905年
8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。
1906年
7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。
1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立
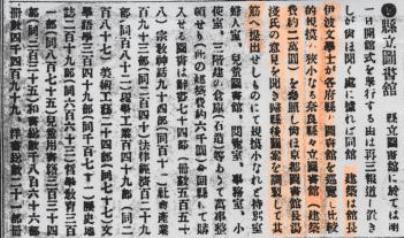
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
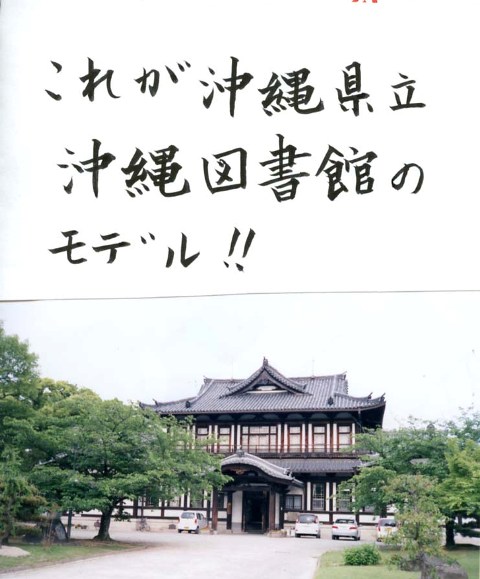
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1911年
4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。
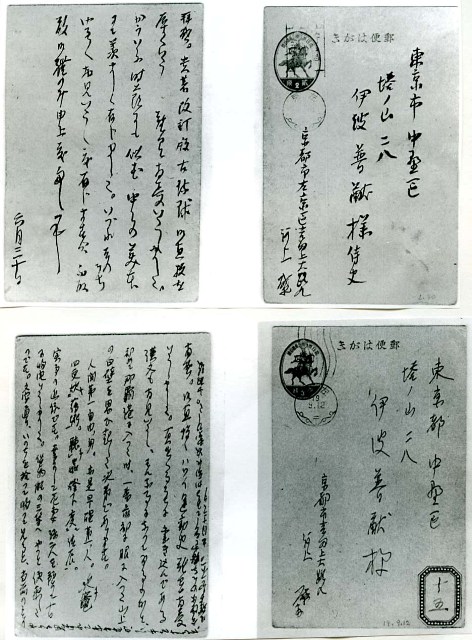
■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)
8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」
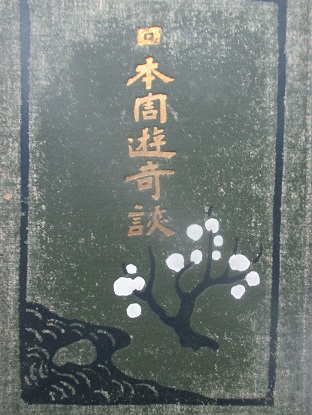
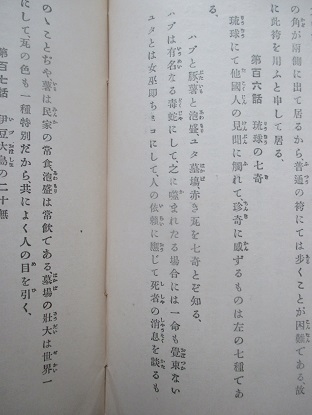
1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館
1912年
4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町
1913年
3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代
1913年
3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。
5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷
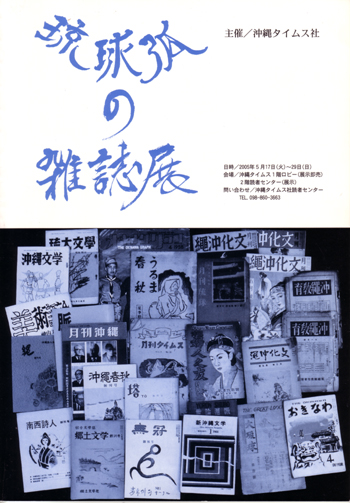
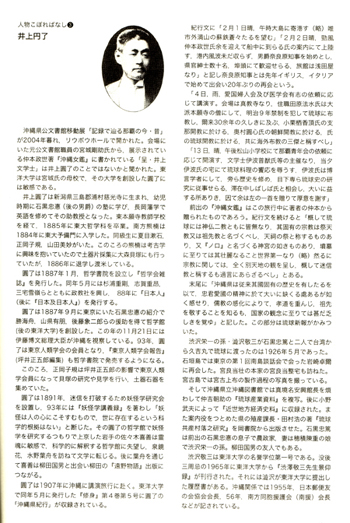
井上円了
『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。
大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。
□井上円了
生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)
没年: 大正8.6.5 (1919)
明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻
(恩田彰) →コトバンク
8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。
9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」
1916年
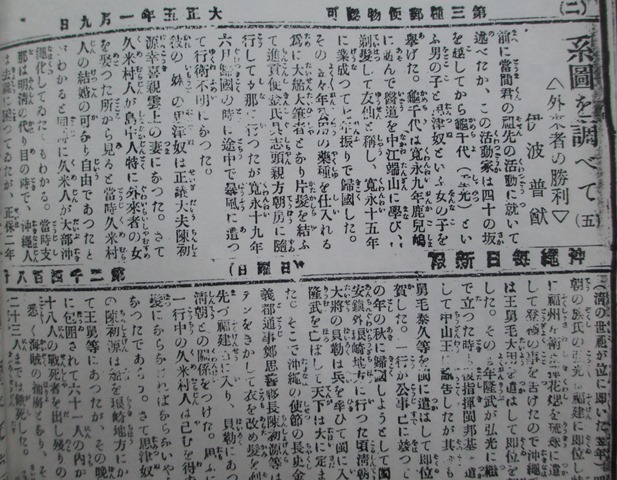
1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)
3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら
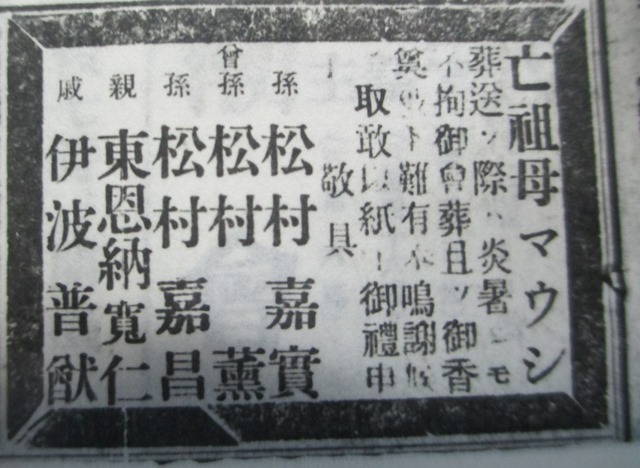
1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」
1918年
3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真
1919年
7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」
1920年
岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」
1921年
5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。
1924年
3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」
3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」
5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」
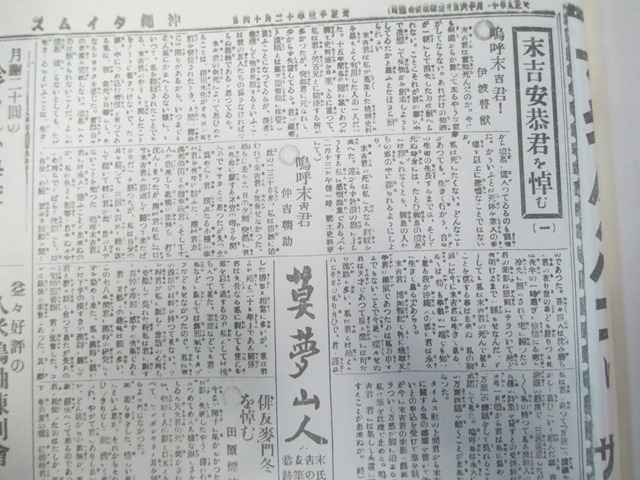
12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」
1925年
2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。
7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」
1926年
1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~
1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)
8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~
9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。
1927年
4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」
1928年
10月ー春洋丸でハワイ着
1929年
2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻
小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候
1931年
6月ー伊波の母(知念)マツル死去
12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居
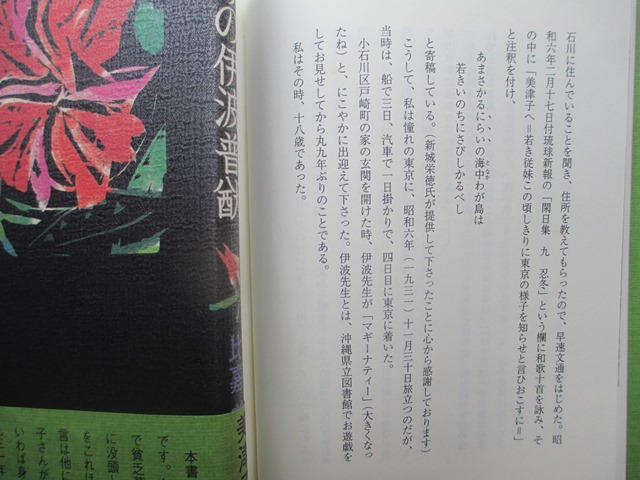
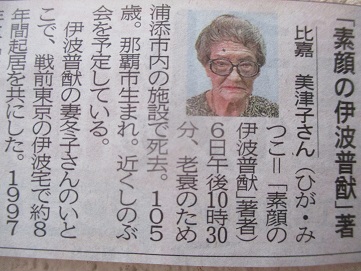
比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん
1932年
1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~
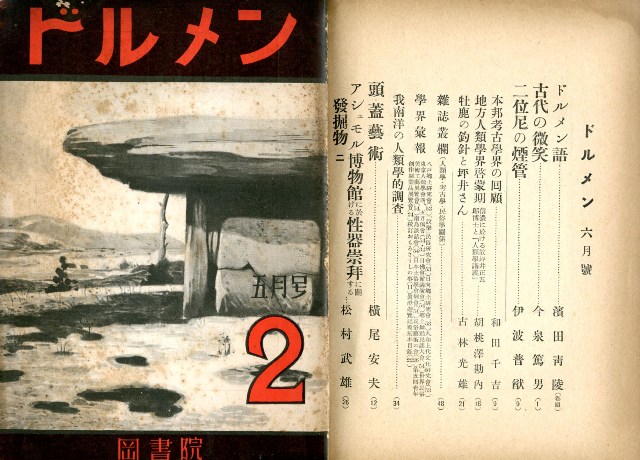
1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」
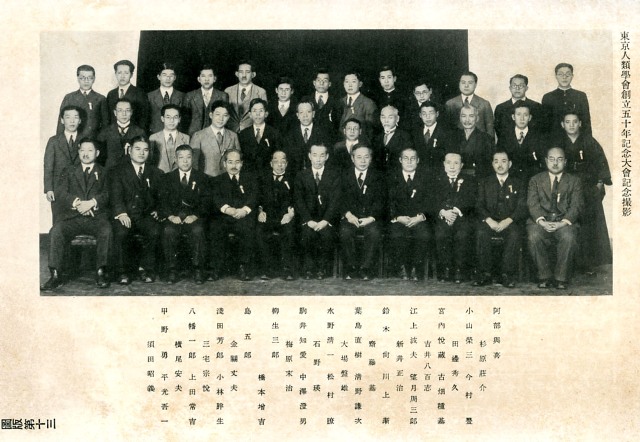
1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会
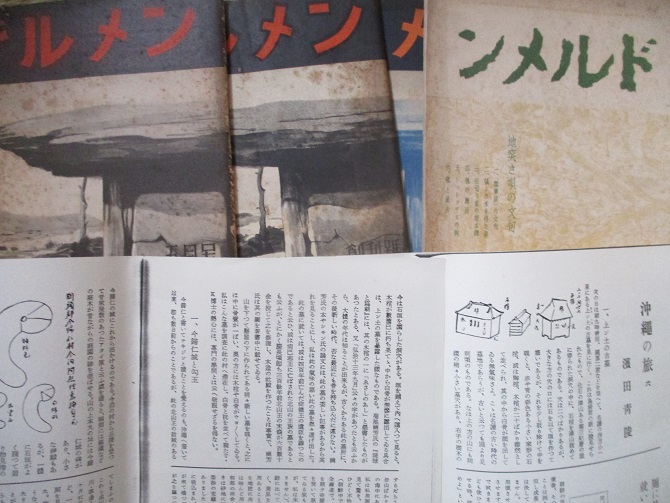
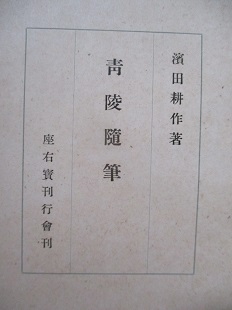
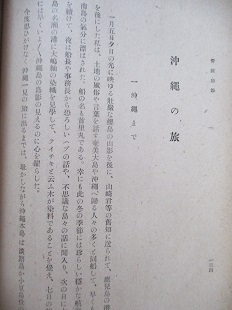
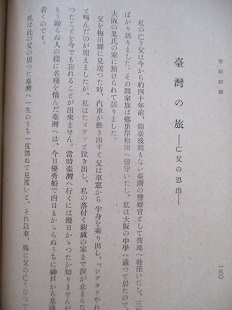
1933年
1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
1934年
7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」
1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号
1937年
1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)
1939年
12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」
1941年
3月ー伊波普猷妻マウシ死去
2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。
1891年
4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)
1900年
9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。
1903年
9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。
1904年
7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。
1905年
8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。
1906年
7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。
1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立
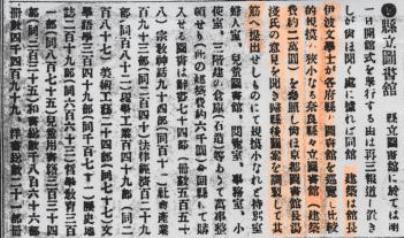
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
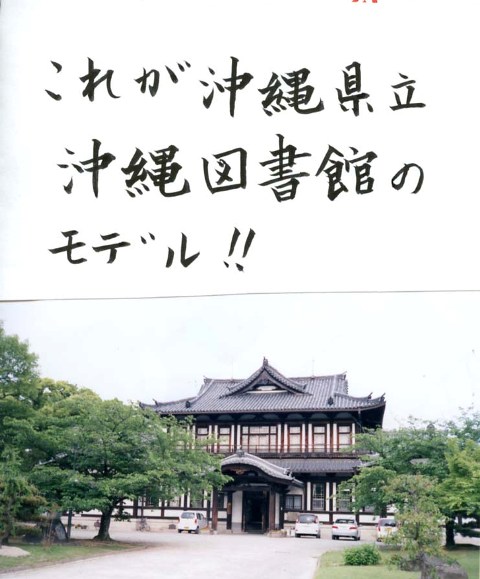
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1911年
4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。
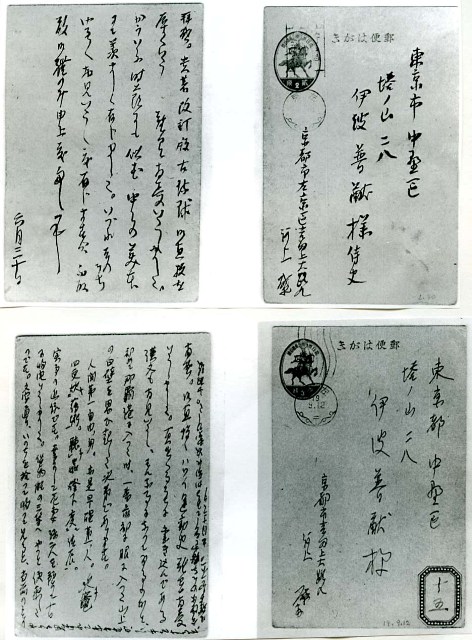
■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)
8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」
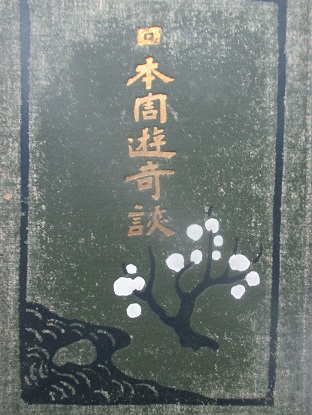
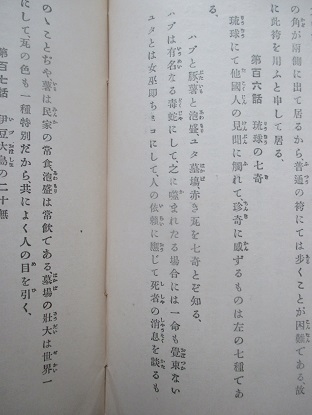
1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館
1912年
4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町
1913年
3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代
1913年
3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。
5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷
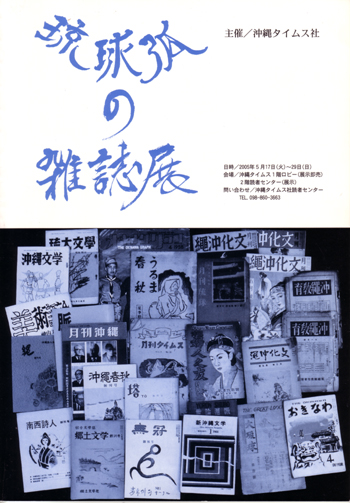
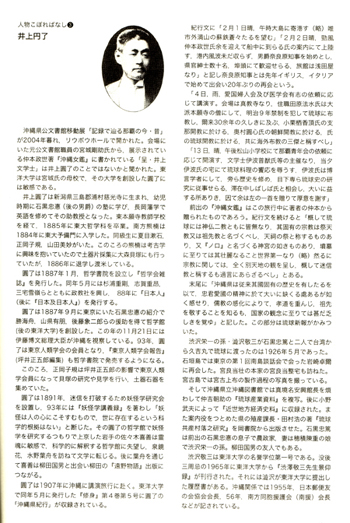
井上円了
『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。
大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。
□井上円了
生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)
没年: 大正8.6.5 (1919)
明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻
(恩田彰) →コトバンク
8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。
9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」
1916年
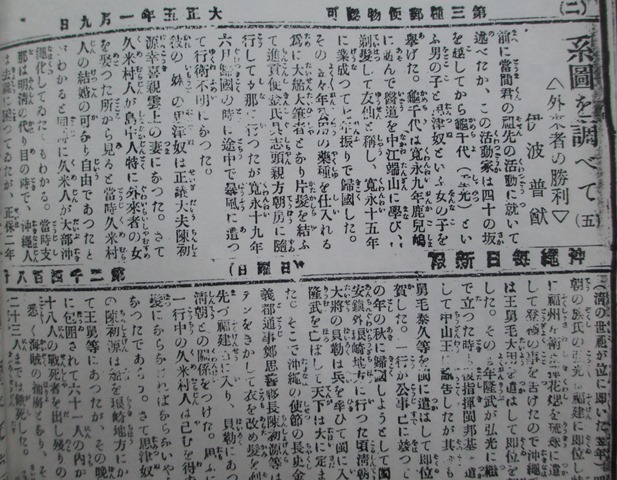
1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)
3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら
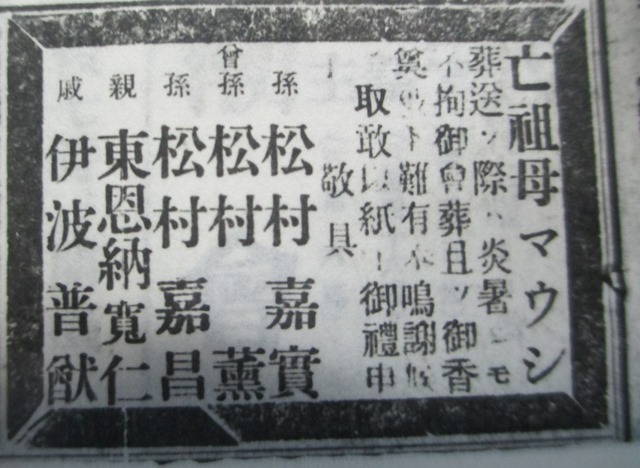
1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」
1918年
3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真
1919年
7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」
1920年
岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」
1921年
5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。
1924年
3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」
3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」
5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」
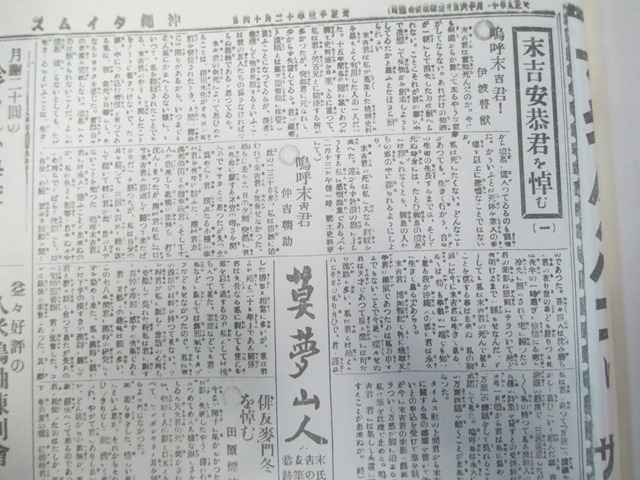
12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」
1925年
2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。
7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」
1926年
1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~
1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)
8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~
9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。
1927年
4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」
1928年
10月ー春洋丸でハワイ着
1929年
2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻
小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候
1931年
6月ー伊波の母(知念)マツル死去
12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居
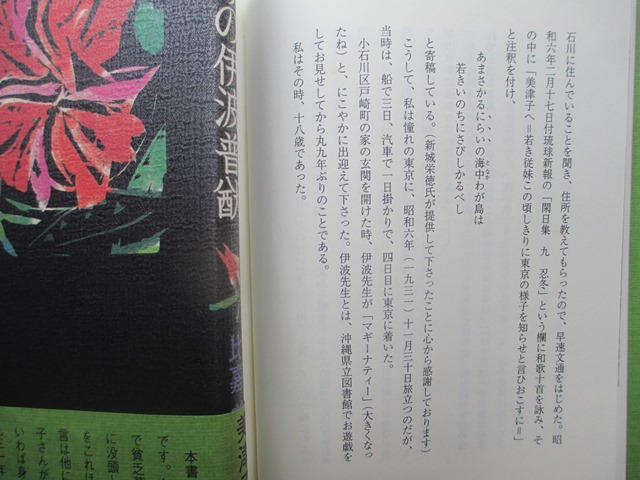
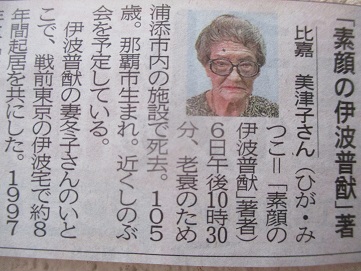
比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん
1932年
1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~
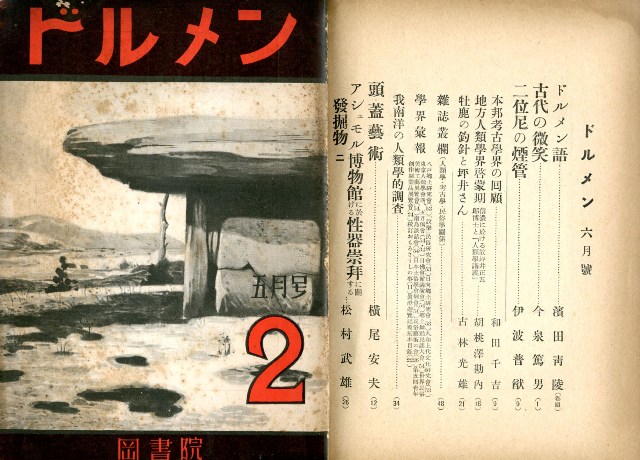
1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」
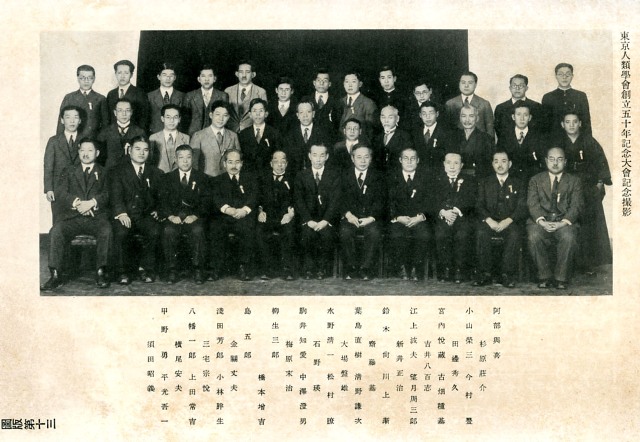
1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会
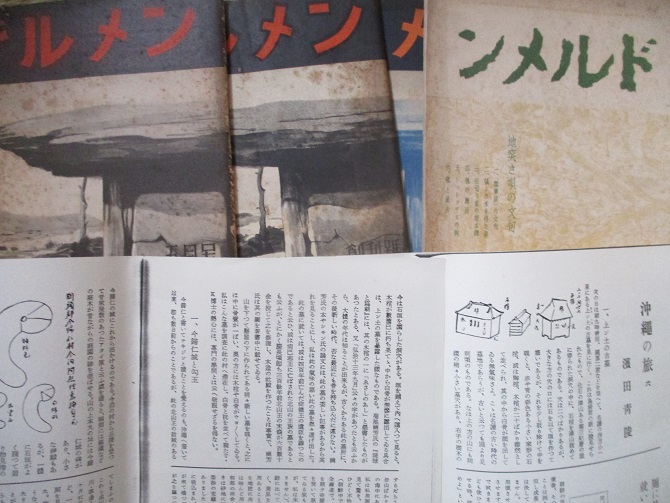
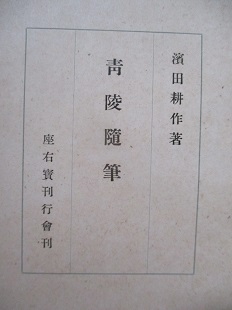
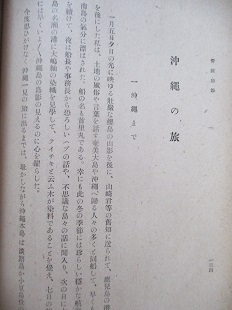
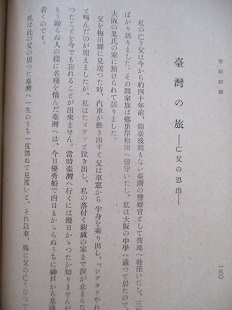
1933年
1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
1934年
7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」
1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号
1937年
1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)
1939年
12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」
1941年
3月ー伊波普猷妻マウシ死去
2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。
10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年
1917年(大正6)
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
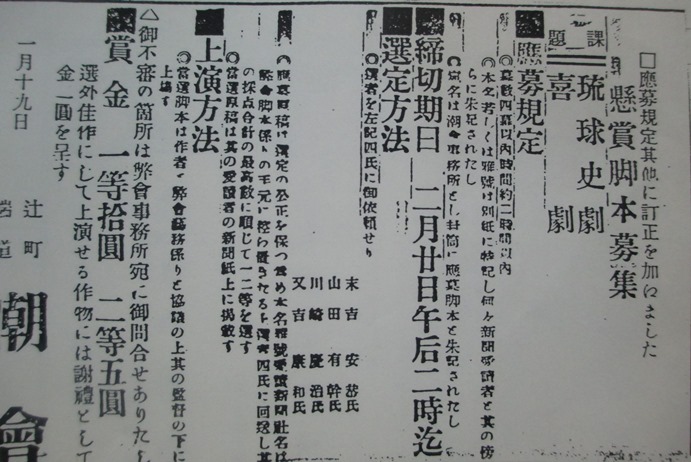
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
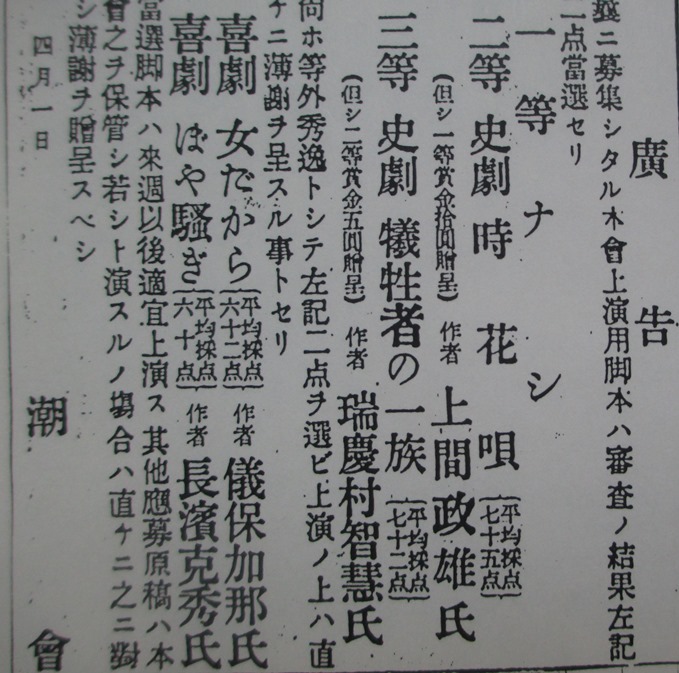
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
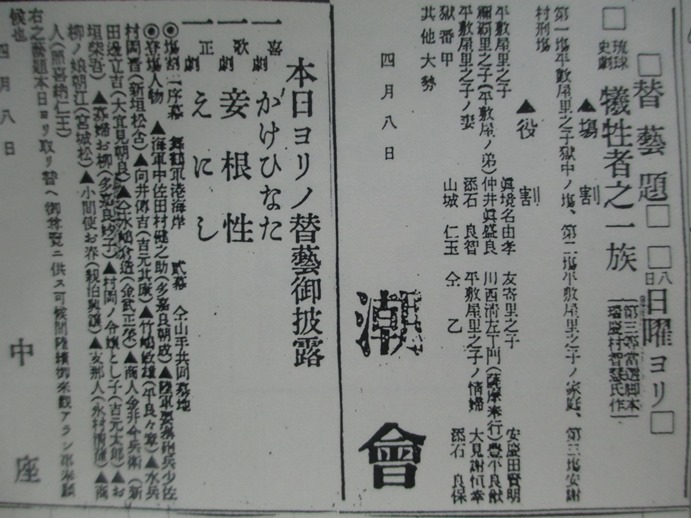
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
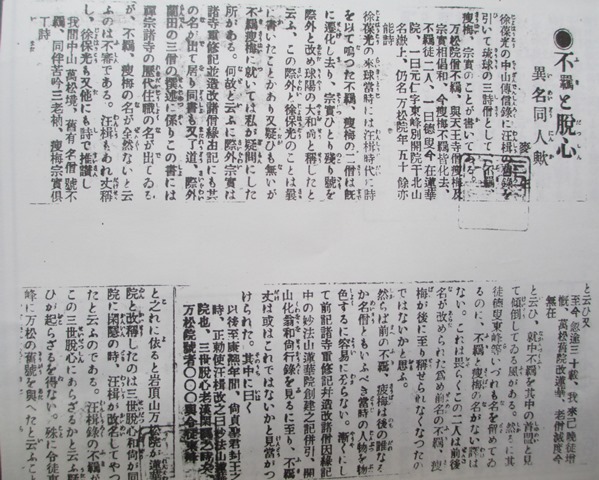
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
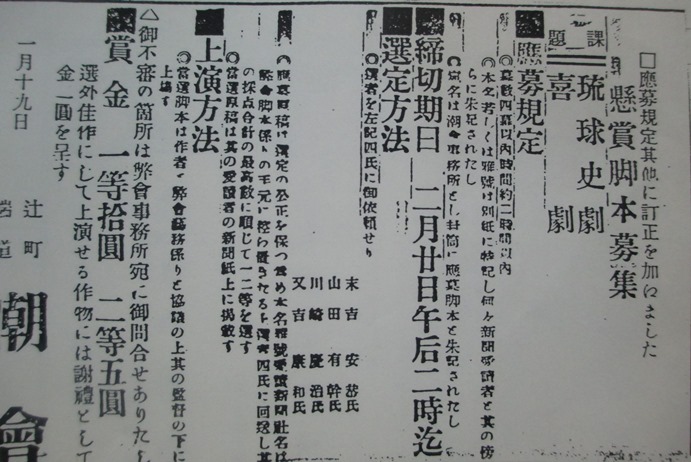
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
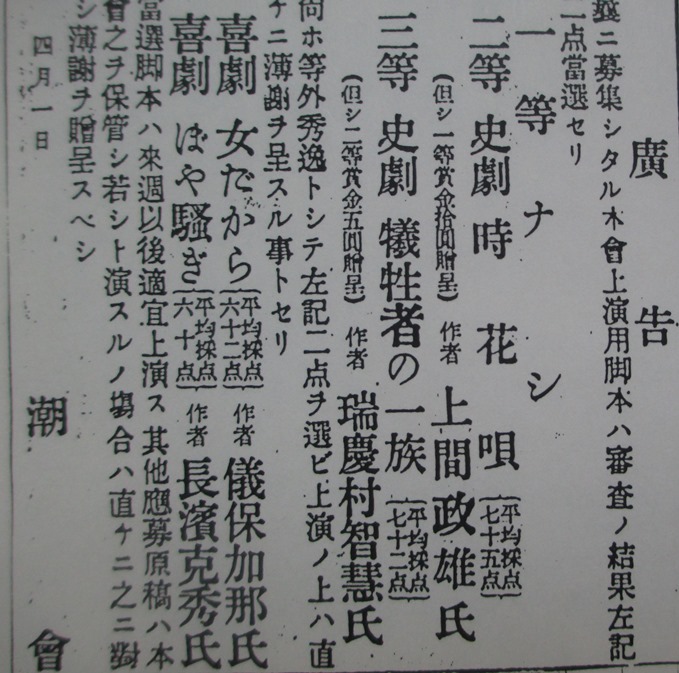
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
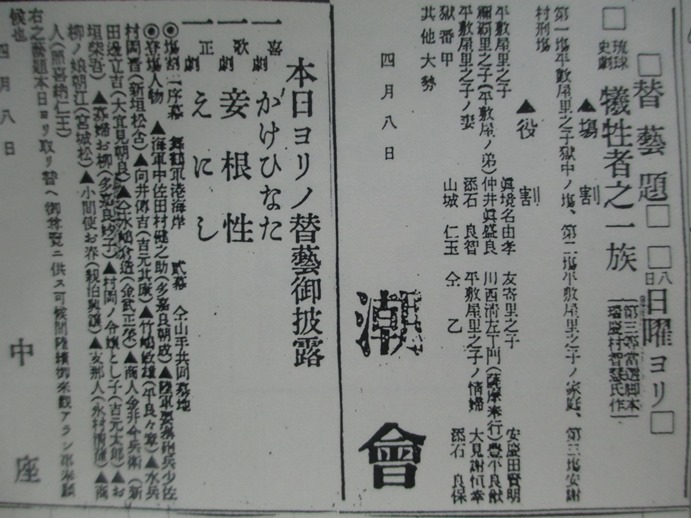
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
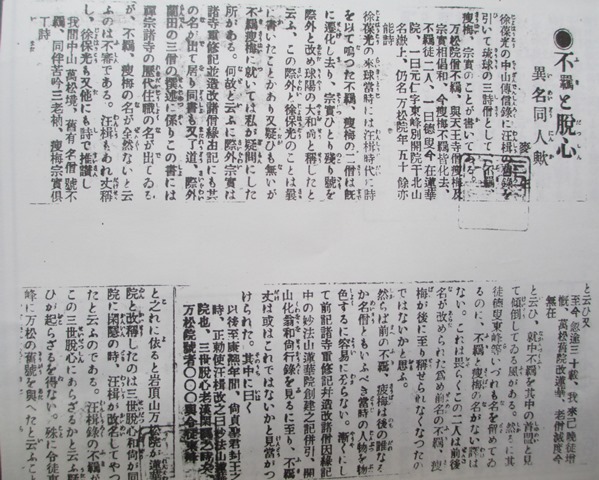
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
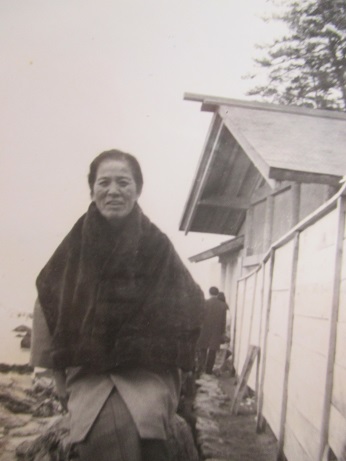
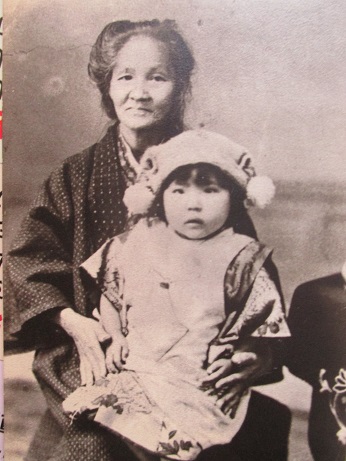
麦門冬妹ウト/貞とパーパー


佐渡山安治御夫妻、二宮忠男・貞御夫妻、末吉麦門冬長女・石垣初枝さん/二宮貞さん
2016年8月18日3時 伊佐眞一氏と首里の万松院通夜室に同行/伊佐氏と共同で作った『琉文手帖』麦門冬特集と、『日本古書通信』「バジル・ホール来琉200周年」をお土産にするという。
2016年8月19日12時 いなんせ斎苑で荼毘

「貞心妙寿信女」 遺族、参列者
2016年8月19日15時 万松院で納骨式

“一握の土”(握り地蔵プロジェクト)二宮貞さん(92)参加

二宮貞の姪であり、麦門冬の孫にあたる石垣市在の、石垣米子詠む
今は亡き 面影しのびつ 捧げなむ
伯母安らかにと 祈る朝夕
今年は二宮貞の姉であり、且つ末吉麦門冬の長女、石垣初枝の25回忌に当たり、その夫である石垣長夫の27回忌を併せて、法要を執り行うとして、麦門冬弟の末吉安久長男で、陶芸家の末吉安允に、法要のお返しとして、お地蔵さんを注文した。そのお地蔵さんを見て米子詠む
おつむなで お顔なでては ほっこりと
合掌地蔵に 心なごめり

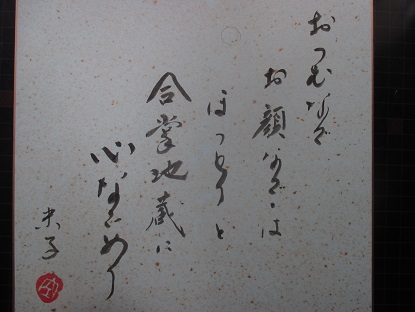
末吉安允作「合掌じぞう」/石垣米子・詠 城谷初治・書


2017年8月16日11時 万松院で「二宮貞1周忌」
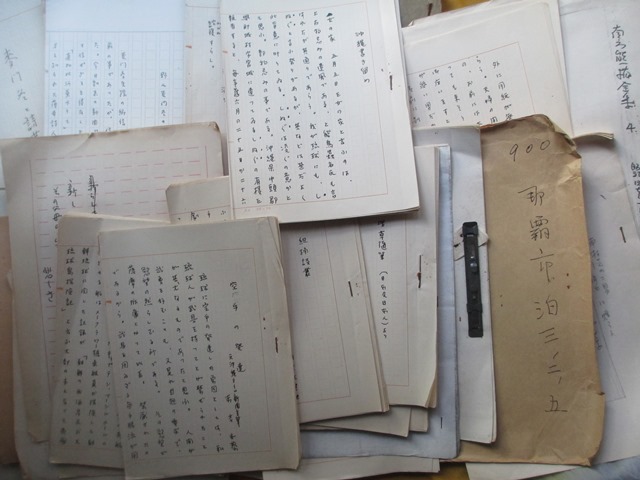
2014年12月5日 首里の末吉安允宅で、安久作成「麦門冬著作・資料」を見る
『琉文手帖』麦門冬特集に富島壮英氏が、麦門冬特集を祝すで「東恩納寛惇の著作・論文などのカード目録を作成していた頃、東恩納文庫の戦前の新聞切抜き帳や各種の目録類に麦門冬の著作・創作などを散見して、彼への関心をもちだしてから10年余になろうか。その頃、元気な宮里栄輝先生から戦前の図書館のこと、研究者のことなどを拝聴している時も麦門冬の話がしばしば出た。このように形成された、おぼろげな麦門冬像は、東恩納寛惇の『野人麦門冬の印象』と相俟って、ますます増長される一方、未知の不思議な人物像の魅力へとつかれていった。7,8年前、麦門冬の末弟の故末吉安久氏が著作集を出すというので、数度東恩納文庫に足を運ばれ、若干の著作のコピーもさし上げたが、ついに日の目を見ずに今日に至っている。おそらく、麦門冬が著作の発表の場とした明治・大正期の雑誌や晩年の30代の新聞が殆どないために、収集に困難をきたしたものと思われる。(後略)」
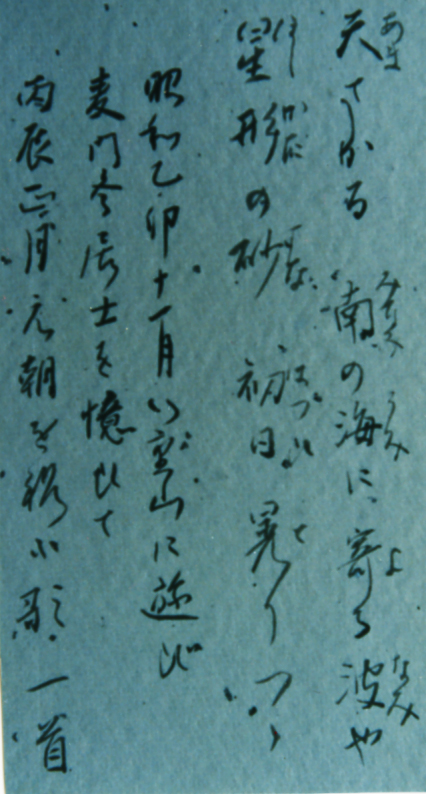
鎌倉芳太郎が1975年11月、八重山に遊び麦門冬の娘・初枝さんと感激の再会。翌年の元旦に詠んだものを書いて石垣市の初枝さんに贈ったもの。
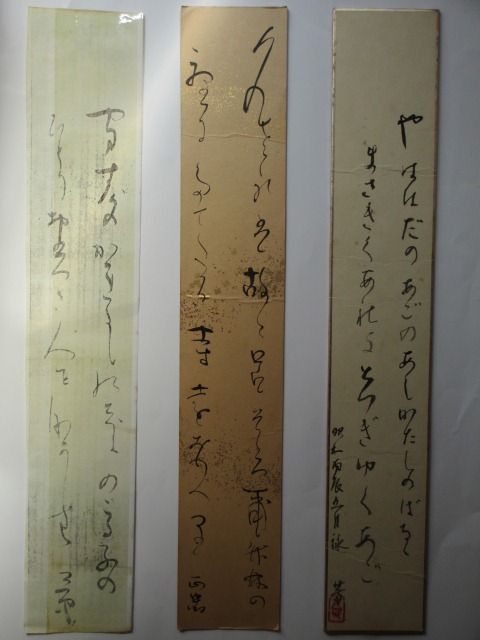
左から折口信夫(複製)短冊ー麦門冬の娘・初枝さんに贈ったもの。/山城正忠/鎌倉芳太郎短冊ー麦門冬のことを聞いた新城栄徳に鎌倉氏が贈ったもの。娘の嫁ぐ日に詠んだ歌だが、その娘の名が恭子さんであるのは偶然なのか。
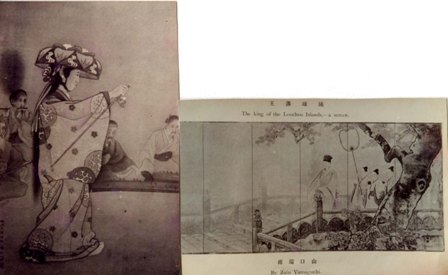
沖縄風俗踊図(1903年)/琉球藩王図(1912年)


1908年5月 菊池幽芳『琉球と為朝』
1911年 那覇尋常高等小学校卒。卒業後香港に渡りイギリス人の会社に就職。5年ほど滞在。
1918年 趣味は琉球古典音楽、古典舞踊、組踊。幼少のころから父・盛輝と祖父・盛矩から影響を受ける。この頃から玉城盛重に琴を師事。さらに三味線を伊佐川世瑞に師事。
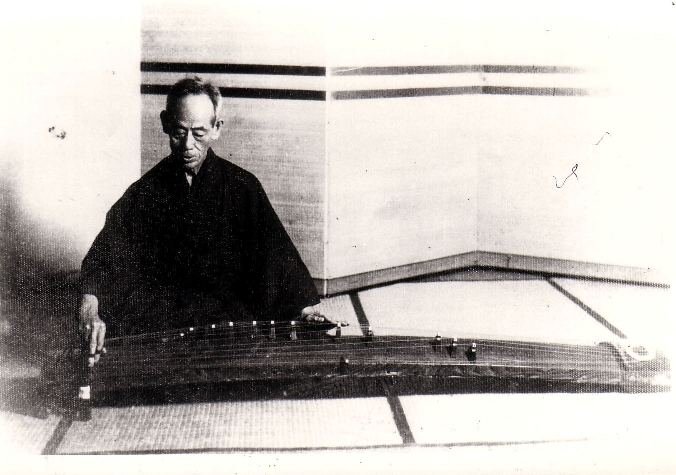
写真ー玉城盛重
□1923年2月24日『沖縄タイムス』田邉尚雄「音楽史上の参考資料ー琉球の琴八橋流 徳川初期のもので今は内地では消滅」
○玉城盛重氏は舞踊の外に八橋流の琴曲も奏せられたが私はここに此の八橋流の琴について一言したいと思ふ、八橋流と云ふのは勿論徳川の初めに京都で八橋検校が開いた箏であって、我が俗箏の開祖である。内地では八橋流は元禄時代に生田流が起こり文化文政時代に江戸で山田流が出たために今では生田や山田に圧倒されて八橋流は全く消えてしまった。然るに琉球には此の八橋流のみが伝わって生田流や山田流はあめり入って居ないのは頗る面白いことであると共に、又内地で滅びたものが琉球に残っていると云ふ点に於いて非常に音楽史上貴重なる材料であると云はなければならぬ。・・・
1922年~1946年 沖縄県鉄道局管理所経理課勤務。

玉城盛重師と仲嶺盛竹(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)
1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁
1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
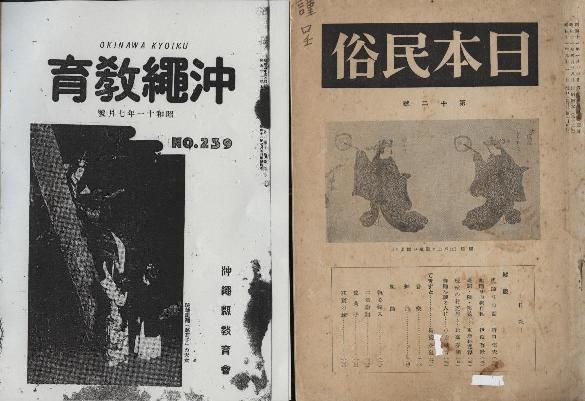
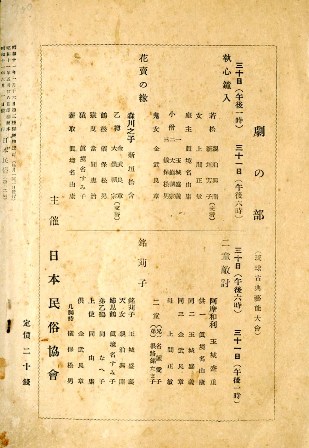
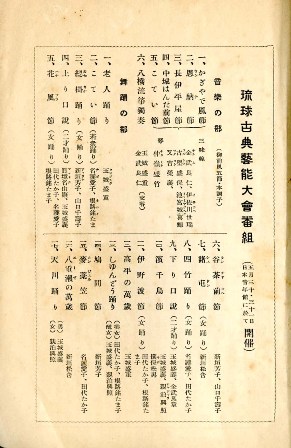
右ー音楽の部に琴・仲嶺盛竹

写真ー前列右から」仲嶺盛竹、玉城盛義、折口春洋、新垣松含、眞境名澄子、玉城盛重、眞境名苗子、伊佐川世瑞、古堅盛保、池宮城喜輝、渡口政興。中央右から眞境名由康、上間正敏、名護愛子、田代タカ、根路銘千鶴子、新垣芳子、二人おいて二代目宜保松男。後列右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照一人おいて山口ちづ子。(雅叙園で)

映画「オヤケアカハチ」制作・東京発声映画製作所/配給・東宝映画/監督・重宗務、豊田四郎/脚本・八田尚之/原作・伊波南哲/撮影・小倉金弥/音楽・大村能章/美術・河野鷹思/録音・奥津武/出演・大日方伝、藤井貢、三井秀男、市川春代、山口勇
写真ー上右から八木明徳、3人目・山城正樹、13人目・山田有登、田代タカ子、玉城盛重、17人目・護得久朝章、19人目・上間朝久、渡口政興、22人目・國場世保、23人目・仲嶺盛竹。中列左端・山田有昴、3人目・奥津。前列左から4人目・藤井貢、監督、8人目・大日方伝、高江洲康享、上間郁子1937年

那覇市歴史資料室収集写真/閑院宮春仁王殿下御前演芸記念写真 /同写真1枚あり/氏名記載あり/前列右より古堅盛保、金城幸吉、玉城盛重、仲嶺盛竹、与世田朝保。後列右より浦崎康華、金城隹子(現在真境名隹子)、渡口政興、国場世保、国場徳八、高嶺てる子。(1941/03/07)
1949年8月『芝居と映画』屋部憲「戦争と藝能」
○終戦当時国頭羽地大川のほとり、川上の山宿で始めて仲嶺盛竹氏の琴を聴いた時、何とはなしに熱ひものが頬を伝はるのを覚えた。別に悲しいのではない。さりとて歓びの感激でもない。勿論生延びた喜びはあるが、それのみの為めじやない。又戦禍に斃れし人々のことを考へた時悲痛の思いはするが、それのみののためでもない。亦死に勝る戦争中の飢餓と労苦を考えた時、血がにじみ出るやうな思ひ出はあるが、然し、その追憶のためでもなひ。今私はこの名状すべからざる感激の詮索に隙を假すことを憚り乍ら、筆を持ちなほしていく。

1954年2月14日 「火野葦平先生招待記念」
前列右から南風原朝光、真境名由康、火野葦平、平良リヱ子、仲嶺盛竹、真境名由祥。中列右から山里永吉、真境名澄子、真境名由苗、宮里春行。後列右から国吉真哲、一人おいて豊平良顕、真境名由乃、真境名佳子、勝連盛重。

1955年 第10回文部省芸術祭公演参加のメンバー(那覇・世界館)前列右から大嶺政寛、玉那覇正吉、國吉眞哲、山本義樹、豊平良顕、南風原朝光、末吉安久、田島清郷。後列右から宮里春行、識名盛人、眞境名由乃、眞境名由苗、牧志尚子、平良雄一、眞境名由康、勝連盛重、宮平敏子、屋嘉宗勝、眞境名佳子、喜納幸子、南風原逸子、仲嶺盛竹、嘉手苅静子、屋嘉澄子、仲嶺盛徳。

仲嶺盛竹(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)□箏は竜になぞらえて作られたと言われ、各部の名称に竜の字が多く使われている。

稽古風景ー仲嶺盛竹師と仲嶺貞夫氏(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)

元氏 仲嶺本家の墓
1993年3月『沖縄芸能史研究会会報』第190号 「第190回研究報告/仲嶺盛竹師を語るー仲嶺貞夫」

写真左が仲嶺貞夫氏(仲嶺盛竹の嗣子)、新城栄徳

写真左が仲嶺貞夫氏(仲嶺盛竹の嗣子)、姪の仲嶺絵里奈さん
本日12月8日未明 (アメリカ時間で7日)の1941年に日本海軍が行なったハワイ真珠湾軍港への奇襲攻撃で太平洋戦争が始った日である。
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑭<この世は遊びに来たところ あの世は休みに行くとこ>
この世は遊びに来たところ あの世は休みに行くところ
これをモットーに生きたので、私にとっては仕事とは遊びでした。嫌なことは一切しない私ですが、戦争のときには、陸軍特別幹部候補生第一期生としての経験もあります。18歳で入隊し、航空兵としての訓練も受けましたが着陸に失敗、大怪我で九死に一生を得ての特攻失格でした。
敗戦の翌日、広島、長崎の出身者は早々に復員を命じられ8月20日、地獄と化した長崎に帰りました。翌日から知友人を尋ねまわりました。熱いので川に飛び込むと、神経を失ったか大きな魚がドスンドスンとぶつかって来ます。はじめは魚とは知らず驚きました。
人に「2,3日前までは川に遺体がたくさん浮いていたよ」と教えられました。今は原爆公園になっている刑務所では全員が死亡と聞きましたので、あの平和記念像には強い思いがあります。
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑮<一茶と去来>
知た名の らく書見へて 秋の暮 一茶 文政句帖 文政五年
文政5年8月29日、60歳の一茶が善光寺を訪れ、ふと本堂の柱を見ると、そこには2日前の日付で長崎の旧友の名前がある。この句を初めて知りました。長崎の旧友とあれば、長崎出身の私が気になるのは当然です。一茶が長崎滞在中に詠んだ句に 君が世や唐人(からびと)も来て冬ごもり(寛政5年)。当時の長崎の俳人といえば去来しか居りません。
私は2度、善光寺の参詣に行きましたが、このらく書を知らず、柱を探すこともありませんでしたので残念です。でも嵯峨野の可愛い去来の墓標に手を合わせたことがあります。両手で抱けるほどの小さな墓石でした。→落柿舎(京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町20)の北側に墓はひっそりと佇む。
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑯<團伊玖磨さんのこと>
福岡時代、私のギャラリーは西鉄ホテルの近くだったので、團伊玖磨さんが来福時には必ず一度はギャラリーにお見えになった。團さんは代々福岡県の人ですが、当時、團さんは八丈島に住んで居られたので野草について色々と詳しい方でした。(1962年、恩師の山田耕筰さんとともに来島、翌年八丈島の樫立に仕事場を作り、以来そこが團さんの「創造の場」となった/八丈島観光 ポータルサイト)。ある時、色紙をあげようと、色紙に線を沢山引かれました。何と「象さん」の楽譜でした。團さんは、自宅に来る手紙で団宛てでくるものは、封を切らず棄てていたそうです。
團さんは朝から必ず机上の硯の墨をすっておく習慣があるだけに、今の陶工たちは水滴を作る人が居ないと嘆いておられたので、そこで私の水滴作りが始まったのですが、私の水滴が出来た時、團さんは黄泉に旅立たれました。
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑰<信州巡り>
飛騨高山は大好きで幾回と出かけました。高速を中津川で降りて高山までの道が春秋を楽しませてくれました。中津川から高山市の中間に熊谷守一美術館⓵があって、そこでの一休みが楽しかったのです。高山市内には、飛騨の匠達が遺したものが沢山ありますし、川沿の朝市には切花には勿体ない花木が並びました。
朝早く起きると、円空佛63体の千光寺に行けるし、乗鞍の中腹まで車で登れます。私の仕事は有名陶芸家の展示会なので、高山の次は松本市で催しますので、上高地では一泊します。槍ヶ岳のの影を浮かべる大正池、そして河童橋、芥川龍之介の「河童」は愛読書ですので河童橋を渡ると河童の聖地のように思われて、この橋を向こうに渡ったことはありません。信州は蕎麦が美味しいところでした。
①熊谷守一つけち記念館は、岐阜県中津川市付知町にある美術館である。 2015年9月、熊谷守一の生まれ故郷の恵那郡付知村に、熊谷守一作品の収集家である小南佐年が私財を投じて設立した。 →ウィキ
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑱<唐津焼の起源>
文禄の役は別名「やきもの戦争」と言われますが、それは朝鮮の陶工を沢山連れ帰りました。その陶工たちが唐津焼、萩焼、薩摩焼、そして有田焼を焼き上げて日本の陶芸史上に輝しい頁を開いたのです。日本の陶芸が世界に高く評価されたことについて、彼ら、李朝の陶工に対する感謝を忘れてはならないと思います。
萩、薩摩の陶工たちは藩に保護されたのですが、鍋島藩の陶工たちは悲惨でした。始め唐津で焼いたのですが、この唐津の土は可塑性が無く、良土を求めて次々と窯を移動しました。その窯跡は延々と有田まで続いたのです。その結果、有田泉山で祖国李朝の白磁に出逢ったのです。
それまであった陶器は美しい有田焼(白磁)に市場を追われたのです。可塑性の悪い唐津焼が生き残れたのは当時勃興した利休の茶道に必要な茶碗や水指が、この土が適合したことと、唐津の名護屋城にいた古田織部の指導があって、茶陶として一楽、二萩、三唐津と評価されるまでになったのです。
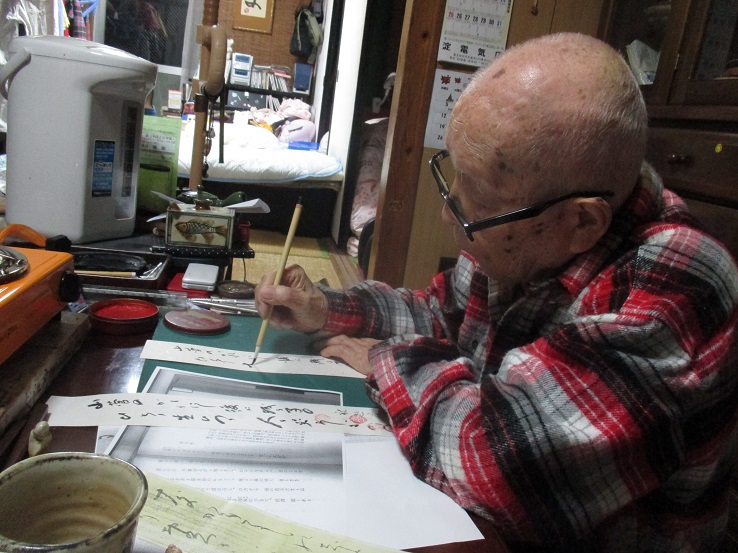
2016年12月7日 折口信夫の歌を短冊に書く城谷翁
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑲<釈超空と沖縄>
友人の末吉氏が新城氏と共に我が家に遊びに来た。新城氏の手には文庫本の『折口信夫全集・第21巻 作品1短歌』。新城氏は末吉氏に紹介されて半年しかならないが、釈超空のファンだと知り驚いたが嬉しくもあった。そして末吉氏から「これを書いてほしい」と示されたのが釈超空の歌。
山菅の かれにし後に残る子の ひとり生ひつつ、人を哭かしむ
末吉安恭は、才能と、善良とを持って、不慮の事に逝いた。思へば、この人にあうたこと、前後二度を越えないであらう。その後、十四を経て、其よい印象は、島の誰の上よりも深く残った。那覇退去の日に近く、遺児某女の訪れを受けた。陳べ難い悲しみを感じて作った萬葉の舊調。故人の筆名の麦門冬は即、舊来、山菅だと解せられているものである。(歌集の添書です)
友人の末吉氏は安恭の甥にあたる人だが、お坊さんがよく似合う人です。
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑭<この世は遊びに来たところ あの世は休みに行くとこ>
この世は遊びに来たところ あの世は休みに行くところ
これをモットーに生きたので、私にとっては仕事とは遊びでした。嫌なことは一切しない私ですが、戦争のときには、陸軍特別幹部候補生第一期生としての経験もあります。18歳で入隊し、航空兵としての訓練も受けましたが着陸に失敗、大怪我で九死に一生を得ての特攻失格でした。
敗戦の翌日、広島、長崎の出身者は早々に復員を命じられ8月20日、地獄と化した長崎に帰りました。翌日から知友人を尋ねまわりました。熱いので川に飛び込むと、神経を失ったか大きな魚がドスンドスンとぶつかって来ます。はじめは魚とは知らず驚きました。
人に「2,3日前までは川に遺体がたくさん浮いていたよ」と教えられました。今は原爆公園になっている刑務所では全員が死亡と聞きましたので、あの平和記念像には強い思いがあります。
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑮<一茶と去来>
知た名の らく書見へて 秋の暮 一茶 文政句帖 文政五年
文政5年8月29日、60歳の一茶が善光寺を訪れ、ふと本堂の柱を見ると、そこには2日前の日付で長崎の旧友の名前がある。この句を初めて知りました。長崎の旧友とあれば、長崎出身の私が気になるのは当然です。一茶が長崎滞在中に詠んだ句に 君が世や唐人(からびと)も来て冬ごもり(寛政5年)。当時の長崎の俳人といえば去来しか居りません。
私は2度、善光寺の参詣に行きましたが、このらく書を知らず、柱を探すこともありませんでしたので残念です。でも嵯峨野の可愛い去来の墓標に手を合わせたことがあります。両手で抱けるほどの小さな墓石でした。→落柿舎(京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町20)の北側に墓はひっそりと佇む。
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑯<團伊玖磨さんのこと>
福岡時代、私のギャラリーは西鉄ホテルの近くだったので、團伊玖磨さんが来福時には必ず一度はギャラリーにお見えになった。團さんは代々福岡県の人ですが、当時、團さんは八丈島に住んで居られたので野草について色々と詳しい方でした。(1962年、恩師の山田耕筰さんとともに来島、翌年八丈島の樫立に仕事場を作り、以来そこが團さんの「創造の場」となった/八丈島観光 ポータルサイト)。ある時、色紙をあげようと、色紙に線を沢山引かれました。何と「象さん」の楽譜でした。團さんは、自宅に来る手紙で団宛てでくるものは、封を切らず棄てていたそうです。
團さんは朝から必ず机上の硯の墨をすっておく習慣があるだけに、今の陶工たちは水滴を作る人が居ないと嘆いておられたので、そこで私の水滴作りが始まったのですが、私の水滴が出来た時、團さんは黄泉に旅立たれました。
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑰<信州巡り>
飛騨高山は大好きで幾回と出かけました。高速を中津川で降りて高山までの道が春秋を楽しませてくれました。中津川から高山市の中間に熊谷守一美術館⓵があって、そこでの一休みが楽しかったのです。高山市内には、飛騨の匠達が遺したものが沢山ありますし、川沿の朝市には切花には勿体ない花木が並びました。
朝早く起きると、円空佛63体の千光寺に行けるし、乗鞍の中腹まで車で登れます。私の仕事は有名陶芸家の展示会なので、高山の次は松本市で催しますので、上高地では一泊します。槍ヶ岳のの影を浮かべる大正池、そして河童橋、芥川龍之介の「河童」は愛読書ですので河童橋を渡ると河童の聖地のように思われて、この橋を向こうに渡ったことはありません。信州は蕎麦が美味しいところでした。
①熊谷守一つけち記念館は、岐阜県中津川市付知町にある美術館である。 2015年9月、熊谷守一の生まれ故郷の恵那郡付知村に、熊谷守一作品の収集家である小南佐年が私財を投じて設立した。 →ウィキ
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑱<唐津焼の起源>
文禄の役は別名「やきもの戦争」と言われますが、それは朝鮮の陶工を沢山連れ帰りました。その陶工たちが唐津焼、萩焼、薩摩焼、そして有田焼を焼き上げて日本の陶芸史上に輝しい頁を開いたのです。日本の陶芸が世界に高く評価されたことについて、彼ら、李朝の陶工に対する感謝を忘れてはならないと思います。
萩、薩摩の陶工たちは藩に保護されたのですが、鍋島藩の陶工たちは悲惨でした。始め唐津で焼いたのですが、この唐津の土は可塑性が無く、良土を求めて次々と窯を移動しました。その窯跡は延々と有田まで続いたのです。その結果、有田泉山で祖国李朝の白磁に出逢ったのです。
それまであった陶器は美しい有田焼(白磁)に市場を追われたのです。可塑性の悪い唐津焼が生き残れたのは当時勃興した利休の茶道に必要な茶碗や水指が、この土が適合したことと、唐津の名護屋城にいた古田織部の指導があって、茶陶として一楽、二萩、三唐津と評価されるまでになったのです。
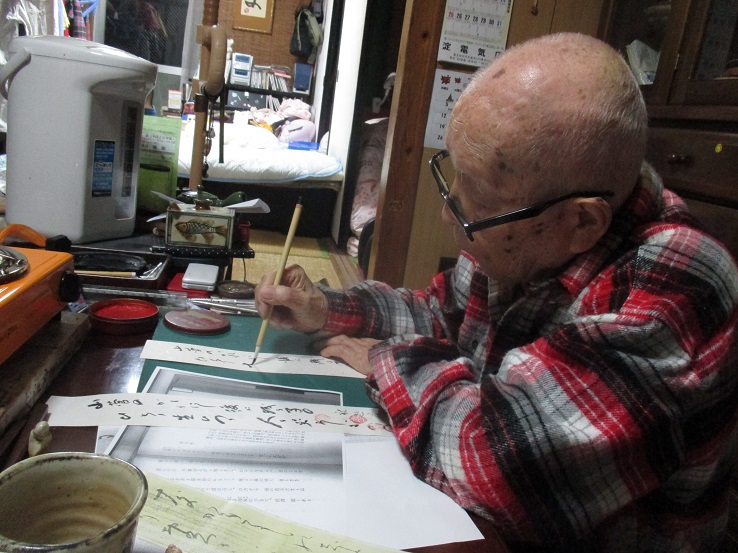
2016年12月7日 折口信夫の歌を短冊に書く城谷翁
2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑲<釈超空と沖縄>
友人の末吉氏が新城氏と共に我が家に遊びに来た。新城氏の手には文庫本の『折口信夫全集・第21巻 作品1短歌』。新城氏は末吉氏に紹介されて半年しかならないが、釈超空のファンだと知り驚いたが嬉しくもあった。そして末吉氏から「これを書いてほしい」と示されたのが釈超空の歌。
山菅の かれにし後に残る子の ひとり生ひつつ、人を哭かしむ
末吉安恭は、才能と、善良とを持って、不慮の事に逝いた。思へば、この人にあうたこと、前後二度を越えないであらう。その後、十四を経て、其よい印象は、島の誰の上よりも深く残った。那覇退去の日に近く、遺児某女の訪れを受けた。陳べ難い悲しみを感じて作った萬葉の舊調。故人の筆名の麦門冬は即、舊来、山菅だと解せられているものである。(歌集の添書です)
友人の末吉氏は安恭の甥にあたる人だが、お坊さんがよく似合う人です。
02/26: 雑誌『おきなわ』/島袋源七
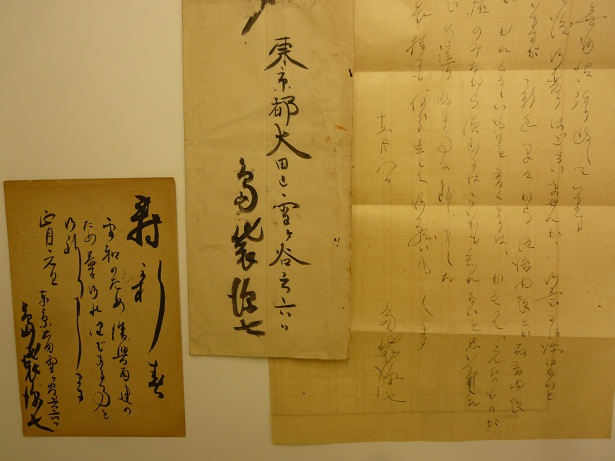
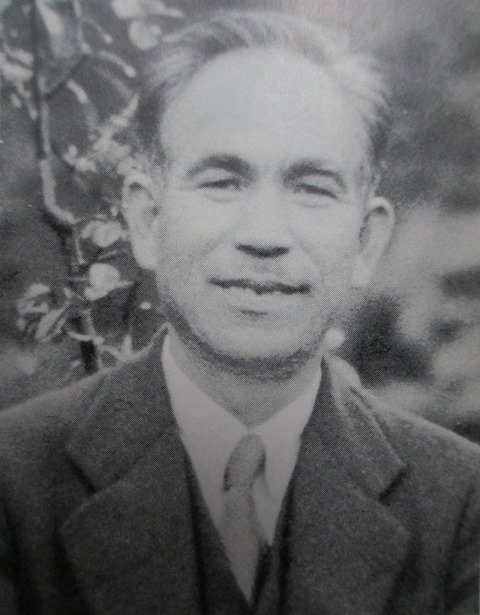
島袋源七
島袋源七 略年譜
1897年(明治30年)
6月11日、沖縄県国頭郡今帰仁間切(村)勢理客に生まれる。
1917年(大正6年)20才
3月、沖縄県立師範学校卒業
4月、北玉尋常小学校を皮切りに、辺野喜、喜如嘉、稲嶺各校を歴任する。
1921年(大正10年)24才
折口信夫が来県したさいに国頭地方を案内。このとき折口に啓発され、以後、精力的に山原(国頭地方)の民俗調査を行う。ウンジャミ・シヌグなどの祭祀習俗を詳細に記録。
1922年(大正11年)25才
柳田国男が組織し多くの民俗・民族・言語学者が参加した南島談話会が創立。創立当初からの会員となる。他に折口信夫、伊波普猷、比嘉春潮、仲原善忠、金城朝永、宮良当壮、仲宗根政善らが会員として名をつらねており、多くの会員との親交・知遇を受ける。
1925年(大正14年)28才
『山原の土俗』と題して民俗誌をまとめる。
1927年(昭和2年)30才
上京、杜松小学校に勤務するかたわら立正大学高等師範部地歴科に学ぶ。
1929年(昭和4年)32才
『山原の土俗』が炉辺叢書の1冊として郷土研究社から出版される。
1931年(昭和6年)34才
3月、立正大学高等師範部地歴科卒業
1934年(昭和9年)37才
立正中学校(旧制)に勤務。
1937年(昭和12年)40才
『今帰仁を中心とした地名の1考察』(「南島論叢)」
1947年(昭和22年)50才
立正高等学校(新制)兼任。その後、教頭として勤務する。
8月、沖縄人連盟内に沖縄文化協会成立。仲原善忠、宮良当壮、比嘉春潮、金城朝永、島袋盛敏、崎濱秀明氏らとおもろ研究会を持つ(戦前からの研究会の復活)。
12月、「阿児奈波の人々」(「沖縄文化叢説」)
1948年(昭和23年)51才
9月、沖縄文化協会が組織再編成し、新たに発足。 11月、会報「沖縄文化」創刊。
1950年(昭和25年)53才
『沖縄の民俗と信仰』(「民族学研究」15巻2号)
1952年(昭和27)55才
ウイーンの世界民俗研究学会より発表の招待を受く。
8月、『沖縄の古神道』を集大成するため、50日余沖縄本島を始め離島各地を踏査する。その折りの疲労が重なり病床に伏す。
1953年(昭和28年)55才
1月15日、昭和医大病院にて気管支喘息心臓麻痺のため逝去。
1月28日、立正大学にて学校葬 (→琉大図書館)
06/02: うちなー芝居・映画史③
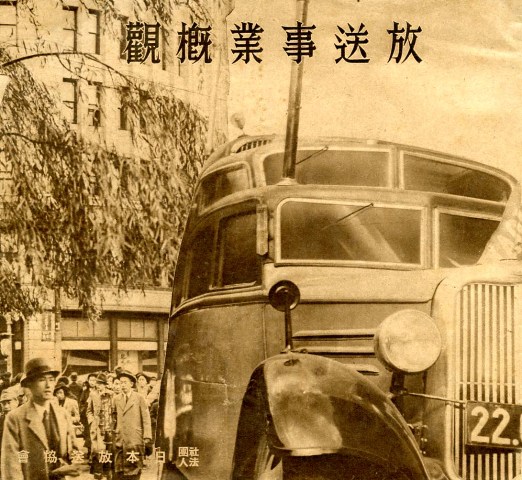
1940年・日本の放送事業
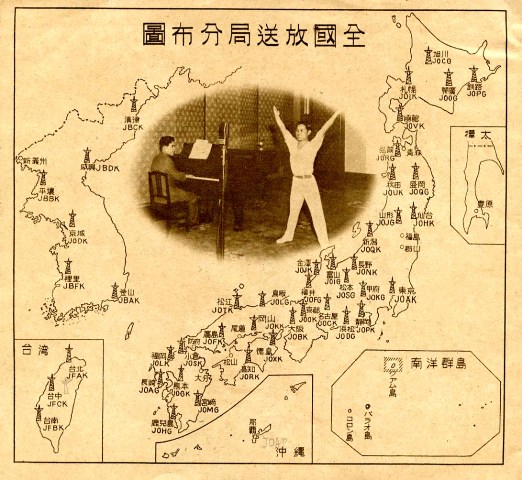
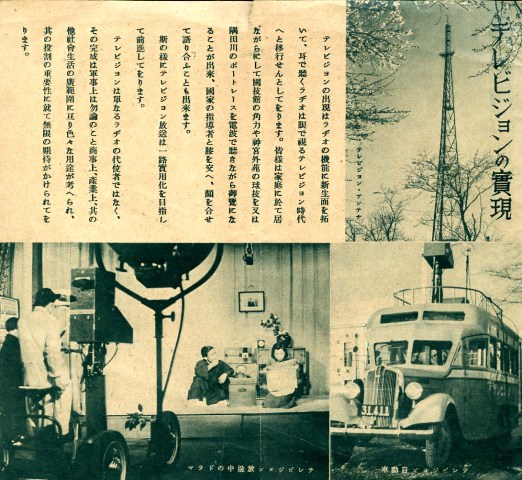
大衆雑誌『芝居と映画』
1949年5月 沖縄劇場協会『芝居と映画』創刊号□編集兼発行人・高良一
山里永吉「雑談」/比嘉正義(松劇団)「劒戟役者放談」/親泊興照、儀保松男「儀保松男追憶談」/平良良勝(沖縄俳優協会長・竹劇団長)「芸道苦心談」/大見謝恒幸(梅劇団)「新俳優研究生時代の思い出」/「映画スター前身調べ 癖しらべ」/仲井眞元楷「演劇漫筆」/編集後記「沖縄で最初の娯楽雑誌としてデヴィウすることになりました。誌名に示すとうり”芝居と映画に関する一切の記 を集録して読者諸賢にまみえるつもりです」
1949年6月 沖縄劇場協会『芝居と映画』6月号□編集兼発行人・志良堂清英
旗岸平「新演劇への第一歩」/伊良波尹吉(梅劇団長)「芸談」/玉城盛義「玉城盛重翁追憶ー叔父を語る」/松村竹三郎「”武士松茂良”余談」/仲今盛良(梅劇団)「芸道苦心談」/山里永吉「雑談(2)」/「演芸ー芝居狂言作者年表(1)」/「演劇映画用語集」
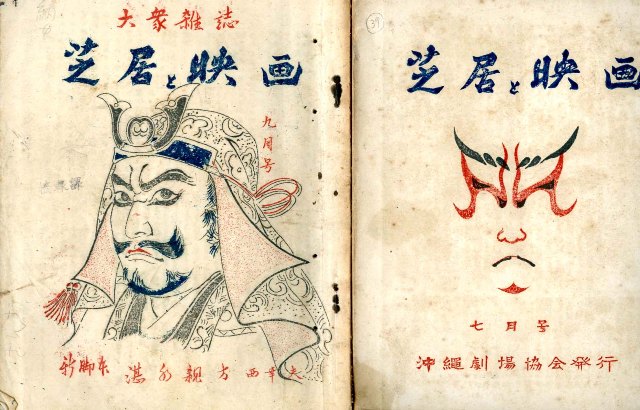


1950年5月ー『演劇と映画』第2巻第1号□上間朝久「名優の思出ー儀保松男」
1950年8月 『演劇映画』7,8月合併号□演劇映画社ー編集兼発行人・志良堂清英 印刷・沖縄ヘラルド印刷局)
山里永吉「演劇放談」/「王将ー大映作品」/川平朝申「沖縄映画製作への雑感」/沖縄ペンクラブ同人「沖縄文化を語る放談会」/上地一史「沖縄ペンクラブ」/小林寂鳥「なが雨の素描」/具志幸孝「幕波に就いて」/伊集田實「演劇雑感」/本部茂「シナリオ 朝から晩まで(2)」/田幸正英「『袈さの良人』の演出について」/サンゴ・タロウ「詩 啓示」/美田太郎「一流館」/又吉つる子「袈さの良人出演後感」/沖縄の芸能ー折口信夫「同胞沖縄芸能の為に」、比嘉良篤「沖縄芸能の味」、式場隆三郎「琉球文化の愛護のために」、今井欣三郎「邦舞への挑戦」、西崎緑「琉球舞踊一年生」、水田龍雄「遥かなる郷愁」
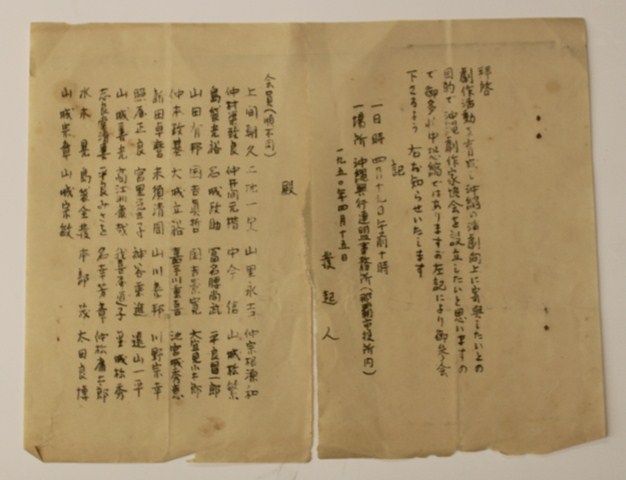
沖縄劇作家協会1950
映画ー1950年代の那覇の映画館・新聞社

劇場
1ー国際劇場、2-中央劇場、3-那覇劇場(芝居)、4-沖縄劇場、5-沖映、6-大宝館、7-大洋劇場、8-珊瑚座、9-オリオン座、10-平和館
新聞社
11-琉球新報社、12-沖縄タイムス社、13-琉球新聞社、14-沖縄朝日新聞社
1950年10月 『演劇映画』10月号□演劇映画社ー編集兼発行人・志良堂清英 印刷・南西印刷所)
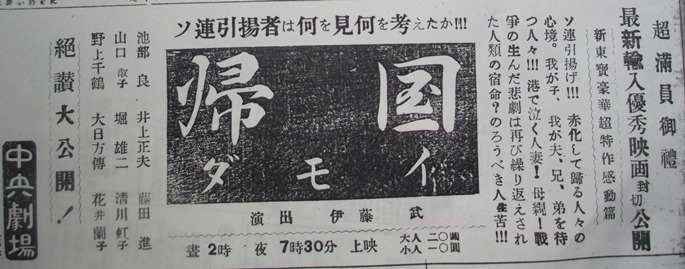
1950年10月『うるま新報』「中央劇場ー帰国ダモイ」

1951年2月 乙姫劇団ハワイ公演
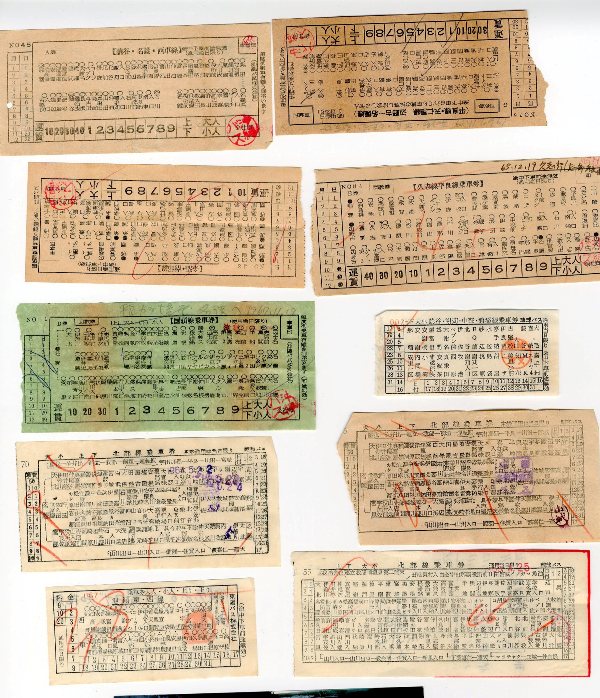
沖縄のバス切符
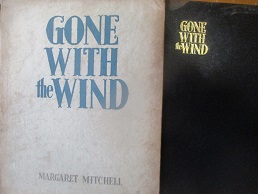
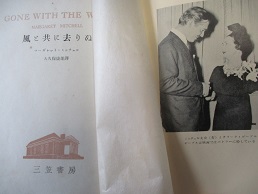
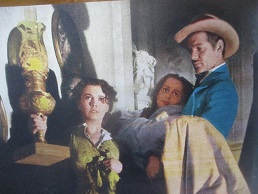
1952年8月 マーガレット・ミッチェル大久保康雄訳『風と共に去りぬ』三笠書房(上映記念 總革装豪華一千部限定版) 大久保康雄訳・初刊は1938年)は、1949年、1950年の年間ベストセラー第3位にランクされるなど、300万部を超える大ベストセラーとなった。なお、映画の日本公開は1952年で、同年もベストセラー第7位に入っている。『風と共に去りぬ』で得た莫大な利益によって、三笠文庫(1951年創刊)、『三笠版現代世界文学全集』(全27巻、別巻4。1953年-1957年)などを刊行している。和書では創業の1933年に内田百閒の随筆『百鬼園随筆』を出版しており、その後も『阿房列車』など、たびたび百閒作品を刊行している。→ウィキ
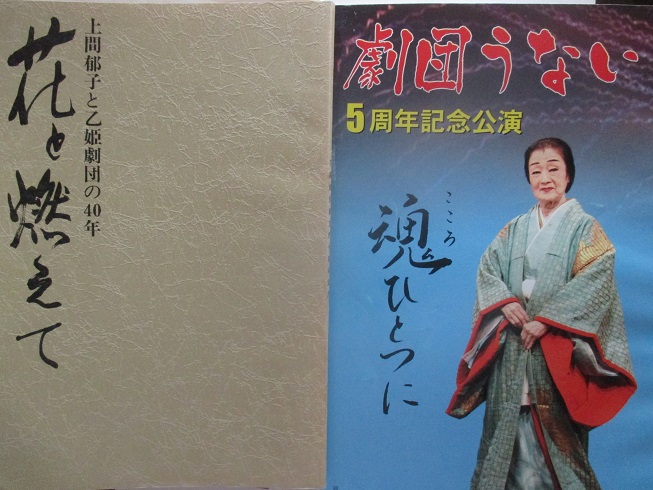
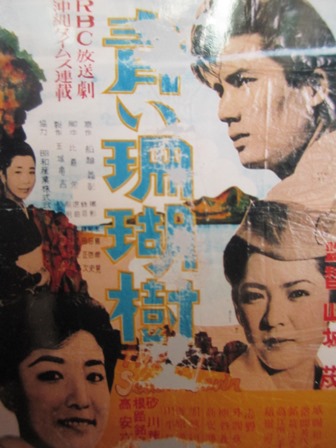
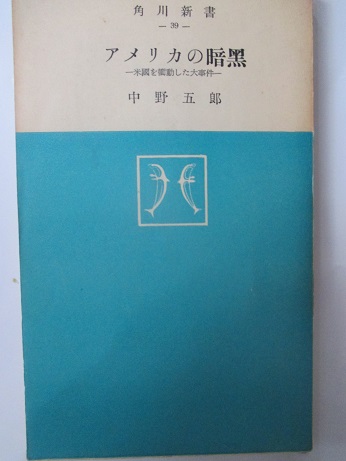
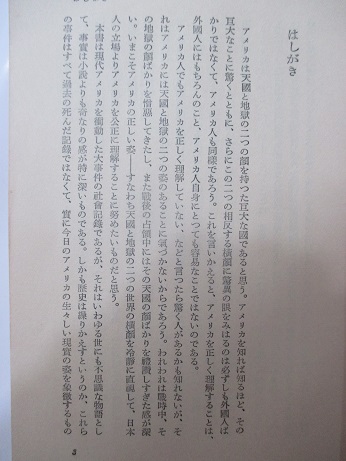
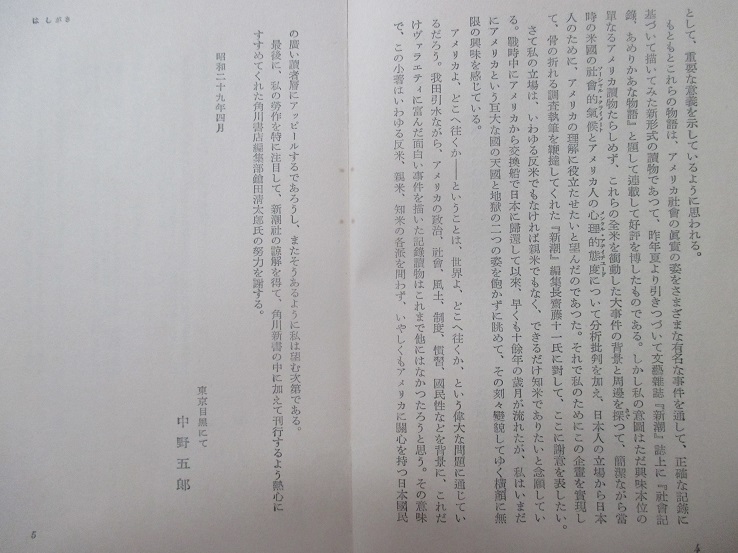
1954年7月 中野五郎『アメリカの暗黒ー米国を衝動した大事件ー』角川書店
1957年4月8日『琉球新報』川平朝申「M・G・M・ダニエル・マン監督の『八月十五夜の茶屋』を観て」
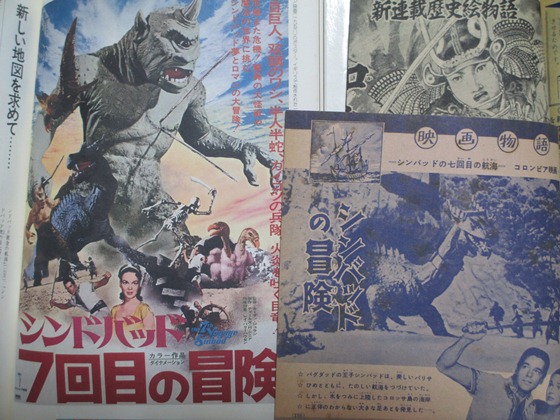
『シンドバッド七回目の冒険』(1958年、公開当時の題名は「シンバッド7回目の航海」)は、ハリーハウゼン①の初のカラー作品となった。1つ目巨人のサイクロプスや、双頭の巨大鷲のロック鳥、ドラゴンなど様々な怪物が登場する。中でも骸骨戦士との剣戟シーンは有名である。
①レイ・ハリーハウゼンは、アメリカ合衆国の特撮映画の監督・特殊効果スタッフで、ストップモーション・アニメーター。映画史上、20世紀の映画における特撮技術の歴史を作ってきたといわれる人物である。1950年代から1970年代に活躍し、多くの特撮SF・ファンタジー映画を手がけた。 本格的なデビュー作となったのは、『原子怪獣現わる』(1953年)である。SF作家・レイ・ブラッドベリ(ハリーハウゼンとは高校時代からの親友であった)の短編『霧笛』を原作としている。水爆実験でよみがえった怪獣がニューヨークを破壊するというこの作品は、日本の特撮映画『ゴジラ』(1954年)にも大きな影響を与えた。→ウィキペディア
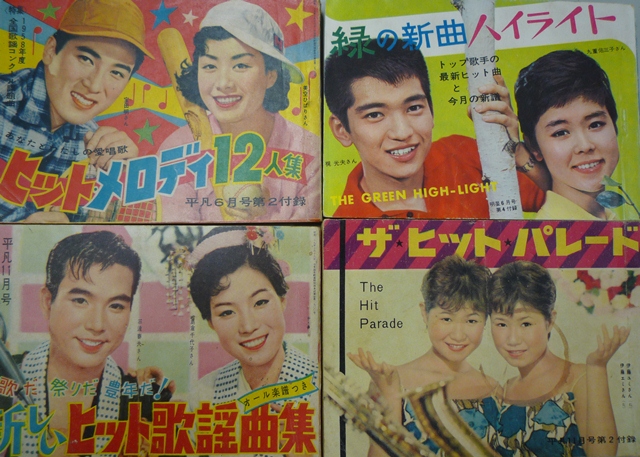
『ヒット曲歌謡集』1958~1961
1959年1月、『守礼の光』が創刊され守礼門が写真で紹介された。6月に宮森小学校にジェット機墜落、大惨事となった。東京の新聞雑誌は大きく報じた。このとき比嘉春潮は第三回沖縄タイムス賞受賞のため帰省中であった。8月には東京で沖縄記者会が設けられ、伊波普猷未亡人・冬子が帰沖した。11月1日、沖縄テレビがNEC日本電気の技術で誕生した。開局祝賀パーティは中継された。出席したのは當間主席、具志頭社長、安里立法院議長、国場組社長、崎山沖縄グラフ社長らであった。同年末の新聞は「街に映るテレビブーム」などと報じた。
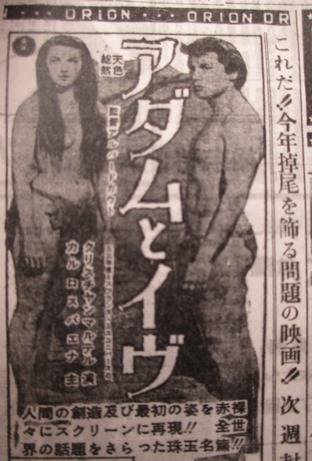
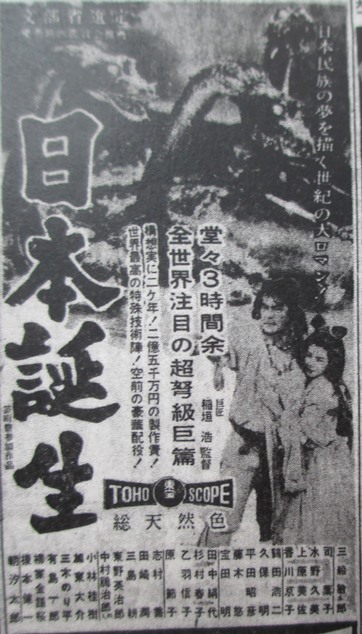
1959年12月 「アダムとイヴ」「日本誕生」
1960年1月の『守礼の光』に外間清が「茶の間で見る世界ー沖縄テレビの話」を書いている。安里慶之助『放送余聞~草創期のラジオ・テレビ』に拠ると、ウチナー芝居が初めてテレビで放送されたのが1959年12月21日の劇団与座の時代劇「片割れ心中」で、あけぼの劇場からのナマ中継であったという。だがウチナー芝居はすぐスタジオ製作に切り替わった。7月、ラジオ沖縄が開局。開局記念に大伸座による「首里城明け渡し」が放送された。その舞台は『オキナワグラフ』8月号で紹介された。60年現在、私設のラジオ有線放送社は那覇に16社、地方に32社、ほかに公営の有線放送は10ヶ所にあった。
1961年1月『オキナワグラフ』「在阪沖縄映画人会」
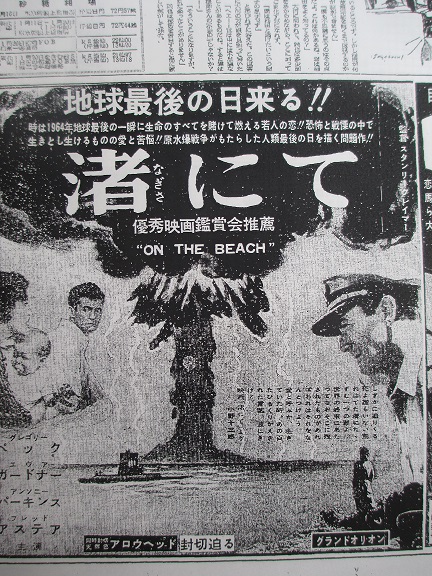
1961年1月 那覇のグランドオリオンで「渚にて」上映
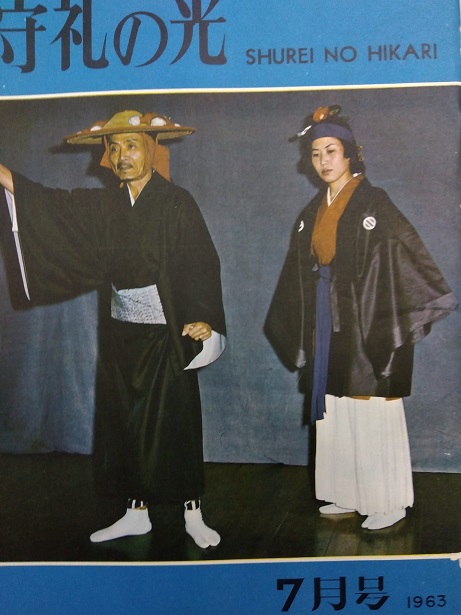
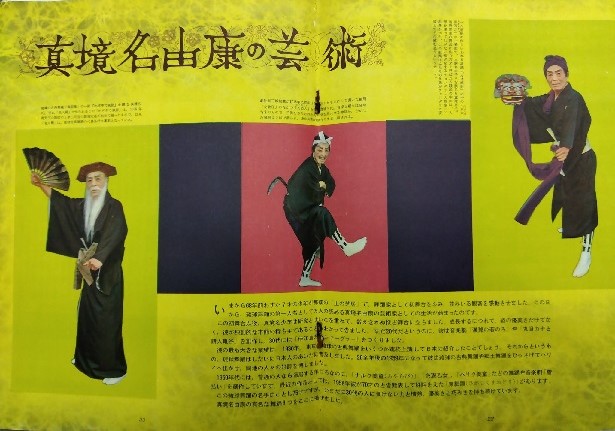
1963年7月 『守礼の光』表紙「自作『雪払い』を踊る真境名由康氏と愛嬢由苗」
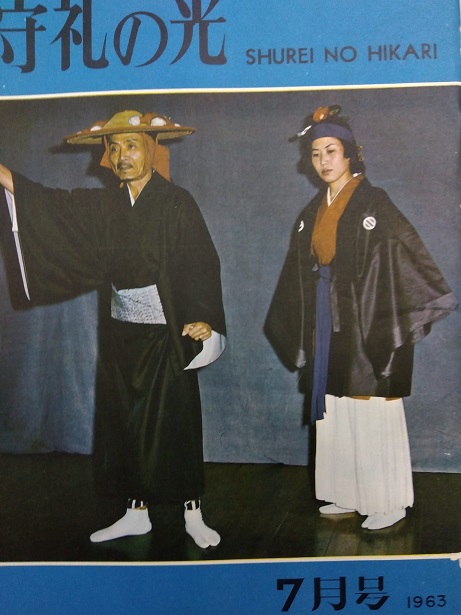
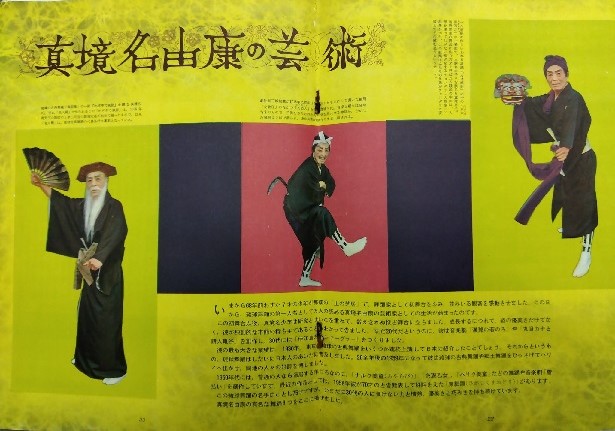
1963年7月 『守礼の光』表紙「自作『雪払い』を踊る真境名由康氏と愛嬢由苗」
1965年5月29日 30日の国映館の東宝まつりに出演の草笛光子、藤本真澄①が日航機で来沖
①藤本真澄 ふじもと-さねずみ
1910-1979 昭和時代の映画プロデューサー。
明治43年7月15日生まれ。昭和12年PCL(現東宝)にはいる。戦後辞職して藤本プロダクションをつくり,「青い山脈」を大ヒットさせ,のち東宝に復帰し取締役,副社長となった。作品はほかに「若大将」シリーズなど。昭和54年5月2日死去。68歳。山口県出身。慶応義塾高等部卒。 →コトバンク
1965年6月6日『琉球新報』「おきなわ出演の千草かほるに聞くーきっかけに困った方言のセリフ」、仲井真元楷「明治 大正 昭和名優伝 嘉手納良芳」
沖映本館「伝説史劇・おきなわ」/グランドオリオン「明治大帝御一代記」(嵐寛寿郎)/東宝劇場「赤ひげ」(三船敏郎)
台湾で琉球芸能紹介、高安六郎一行(フリユンターズ)きょう出発
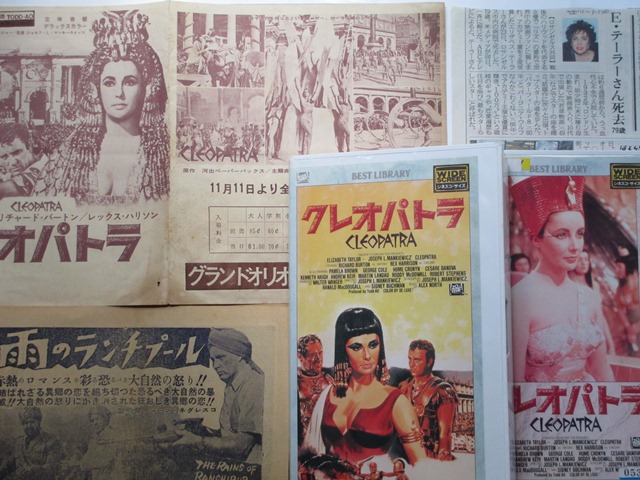
1965年11月ー那覇 グランドオリオン「クレオパトラ」(エリザベス・テイラー)
エリザベス・テイラー 本名:エリザベス・ロズモンド・テイラー。アメリカの映画俳優、女優。愛称リズ。
1932年2月27日、イギリス・ロンドン生まれ。現在に至るまで結婚暦は8回。2011年3月23日死去。(はてなキーワード)
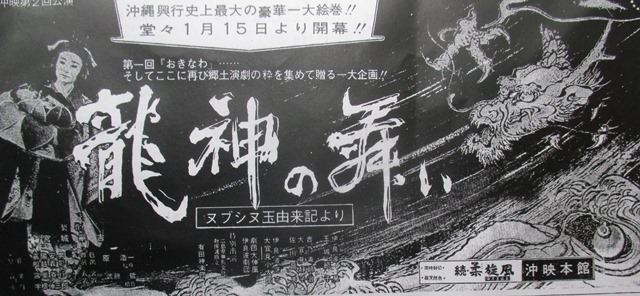
1966年1月15日 沖映本館で沖縄興行史上最大の豪華一大絵巻!!「龍神の舞い」開幕
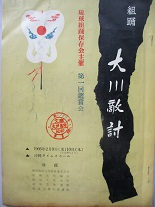
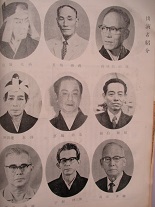

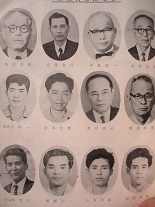
1966年2月9日~10日 沖縄タイムスホール 琉球組踊保存会主催第1回鑑賞会「大川敵討」
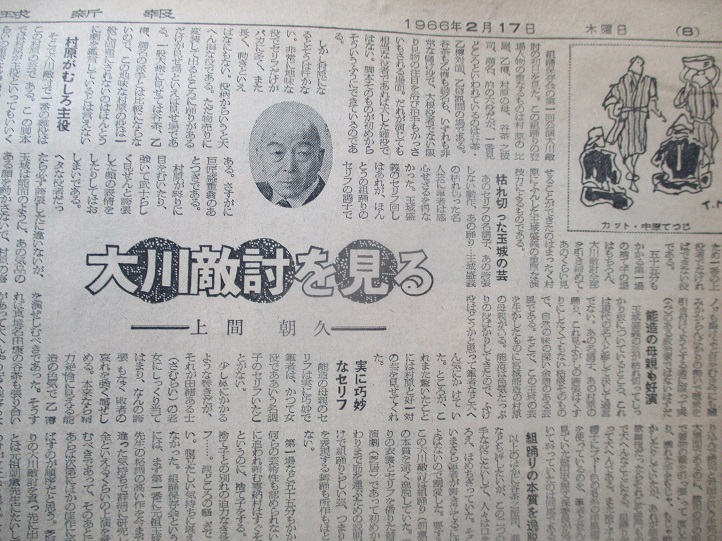
1966年2月17日『琉球新報』上間朝久「大川敵討を見る」
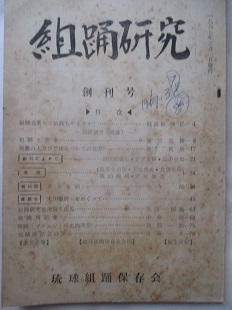
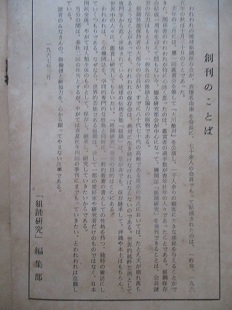
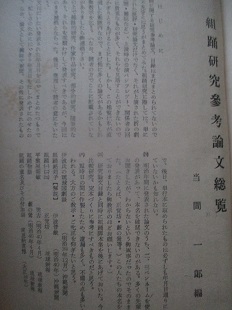
1967年3月 琉球組踊保存会(代表・真境名由康)『組踊研究』創刊号
1967年12月 沖映本館「愛の雨傘」/桜坂オリオン「007ゴールドフィンガー」(ショーンコネリー)
1969年1月『沖縄の芸能』邦楽と舞踊社□3、流派と現状
仲井真元楷「現地における」
石野朝季「本土におけるー『沖縄の伝統芸能は、日本本土で命脈を保っている芸能家の手で保存しないかぎり消えてゆくしかない。さいわい鹿児島には舞踊界の渡嘉敷守良、熊本には野村流音楽の池宮喜輝両師匠(共に故人)が疎開で健在であり、二人を東京に招いて弟子を養成、沖縄に再び平和が甦えるときまで、郷土にかわって伝統保存の担い手になろう』と、1947年春、東京沖縄芸能保存会が伊江朝助、比嘉良篤、戦前沖縄で新聞経営、安富祖流音楽の有数な弾き手でもあった武元朝朗(1953年10月6日没)らの手で結成された。結成翌年の1948年11月には、有楽町の読売ホールで第一回公演。」

1971年7月 『守礼の光』「琉球文化を携えてアメリカを訪問した芸能団」
1972年2月 雑誌『青い海』』№10<復帰不安の沖縄>□「優れた沖縄を語りたいのですー若者が集う『沖縄関係資料室』の西平守晴氏宅」、嘉手川重喜「沖縄の歌劇(4)辺土名ハンドーグヮー」
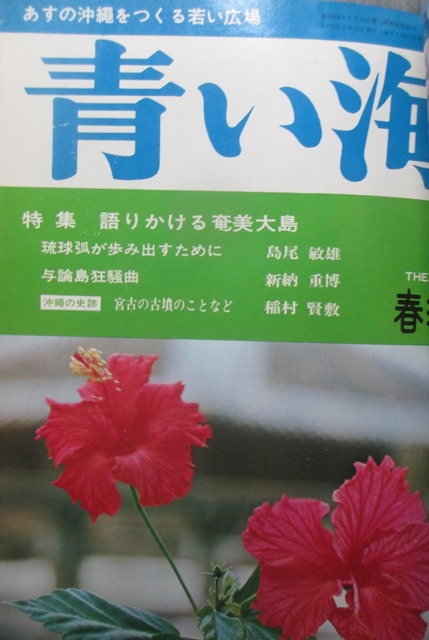
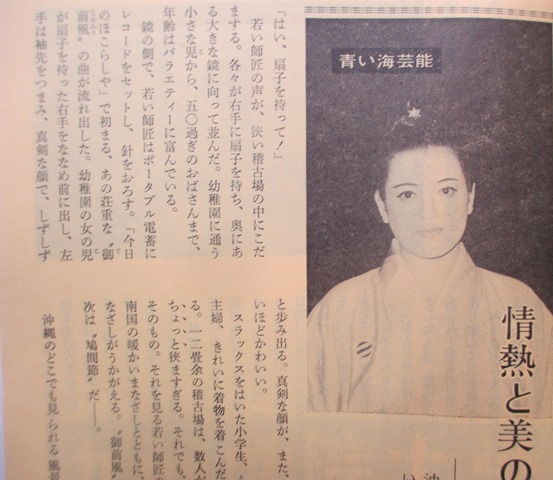
1972年3月 『青い海』春季号 「青い海芸能ー情熱と美の琉舞を大阪の地に 金城康子」
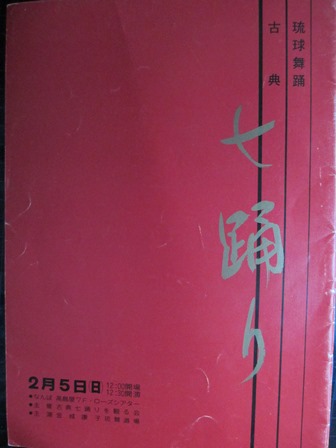
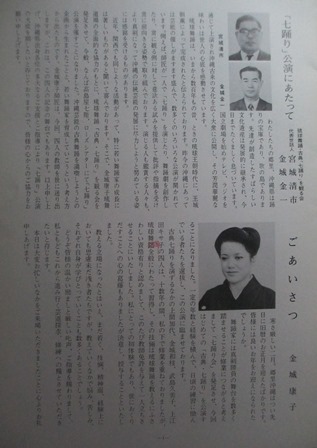
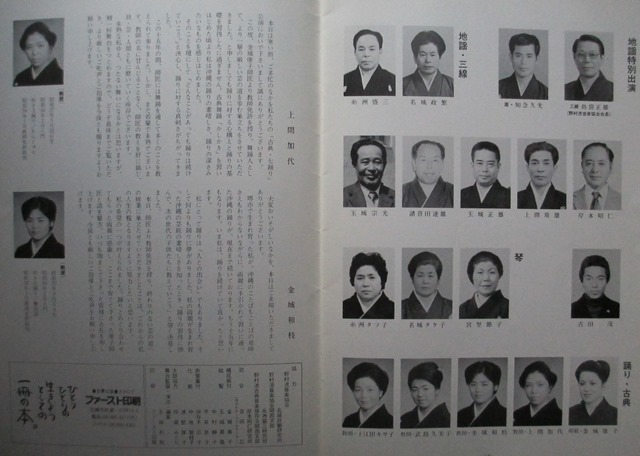

那覇大綱引きで子息の衣装を整える金城康子さん
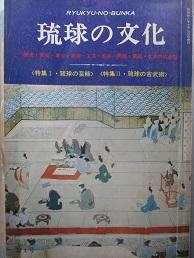
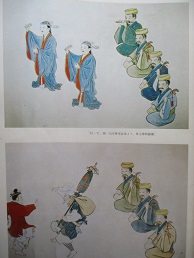

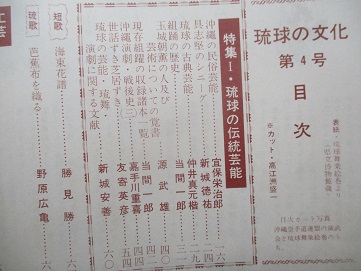
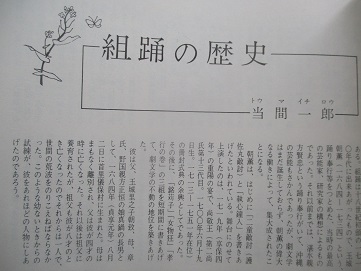
1972年3月『琉球の文化』第4号 琉球文化社
05/27: 1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」
1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」
○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。
その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)
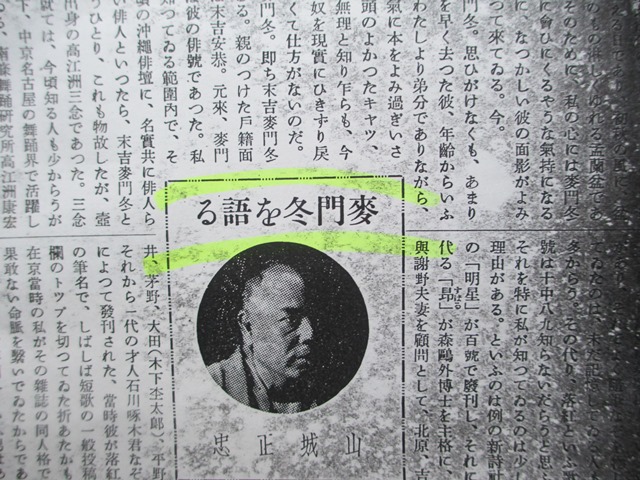
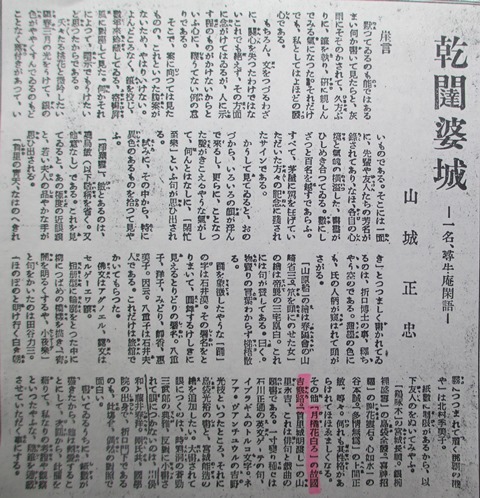
山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。
①灰雨ー國吉眞哲
夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。
「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。
②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア
③山崎省三 やまざき-しょうぞう
1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。
明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク
④石井漠いしいばく
[生]1886.12.25. 秋田,下岩川
[没]1962.1.7. 東京
舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク
⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長
短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。
書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。
1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。
文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。
同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。
以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)



写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝
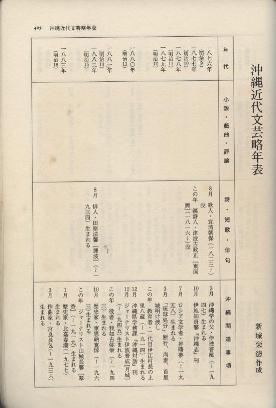
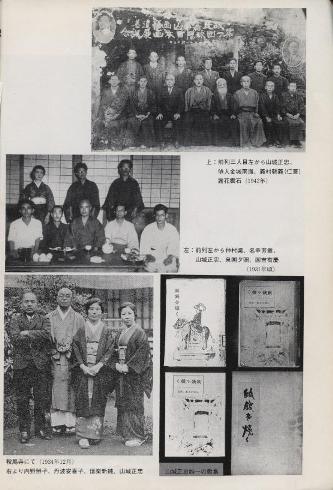
1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」
1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。
2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。
本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。
○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。
その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)
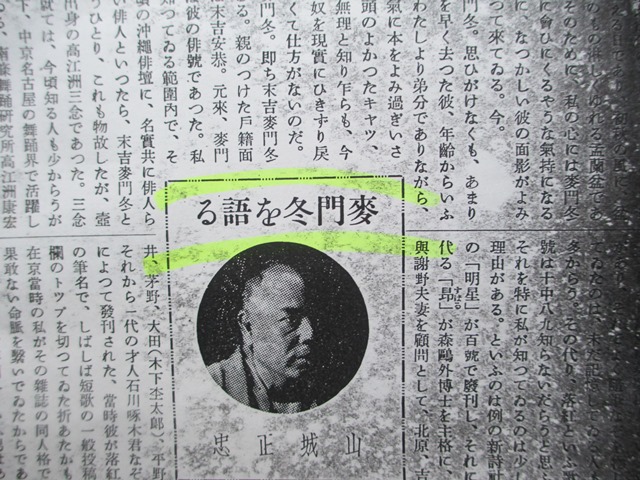
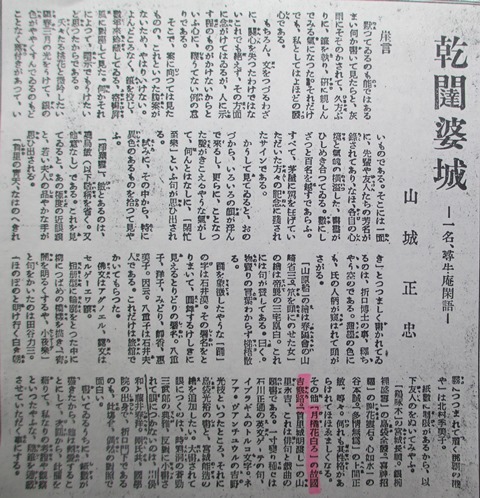
山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。
①灰雨ー國吉眞哲
夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。
「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。
②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア
③山崎省三 やまざき-しょうぞう
1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。
明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク
④石井漠いしいばく
[生]1886.12.25. 秋田,下岩川
[没]1962.1.7. 東京
舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク
⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長
短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。
書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。
1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。
文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。
同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。
以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)



写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝
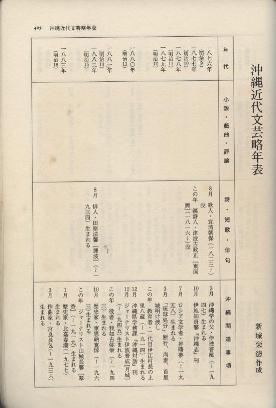
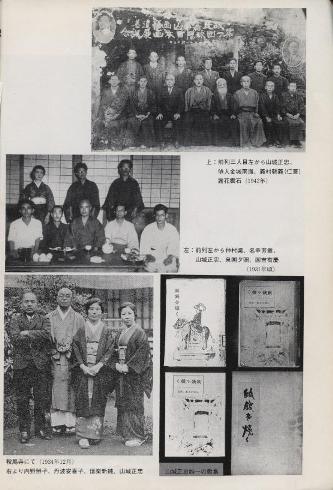
1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」
1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。
2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。
本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。
『琉球新報』2020-6 沖縄芸能研究者の當間一郎(とうま・いちろう)さんが18日午後11時21分、腎臓がんのため糸満市内の病院で死去した。81歳。サイパン生まれ、那覇市出身。
旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。
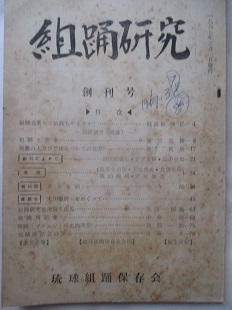
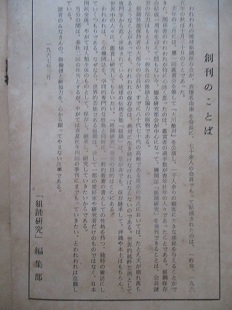
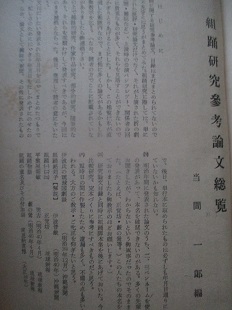
1967年3月 琉球組踊保存会(代表・真境名由康)『組踊研究』創刊号
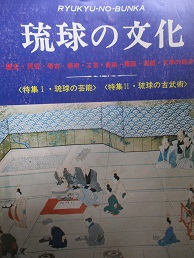
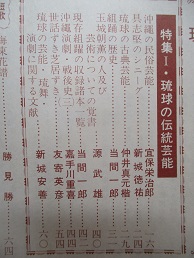
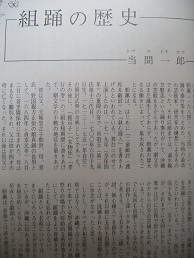
1973年10月『琉球の文化』第4号 当間一郎「組踊の歴史」
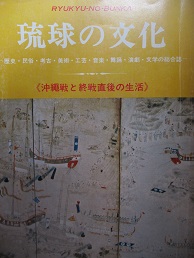
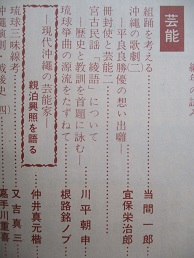
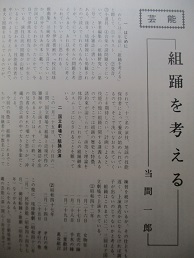
1974年5月『琉球の文化』第5号 当間一郎「組踊を考える」
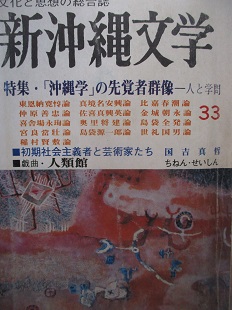
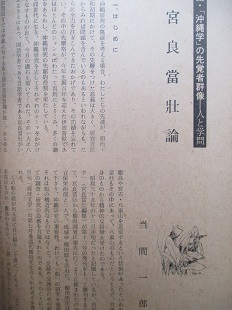
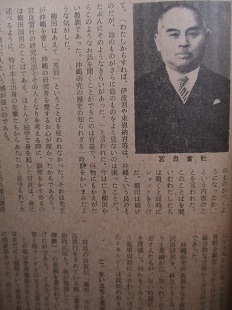
1976年10月 『新沖縄文学』33号 当間一郎「宮良當壯論・・・昭和35年の12月中旬だったと記憶しているが、月刊『琉球文学』(宮良當壯編集)が第12号の発刊をもって廃刊するにあたって、宮良當壯から柳田国男に報告に行くように頼まれたので、友人の宜保栄治郎と二人で、成城の柳田邸を訪ねた。柳田先生は快く迎えて下さり、沖縄研究の重要性、わけても『船』の研究を強調された・・・」
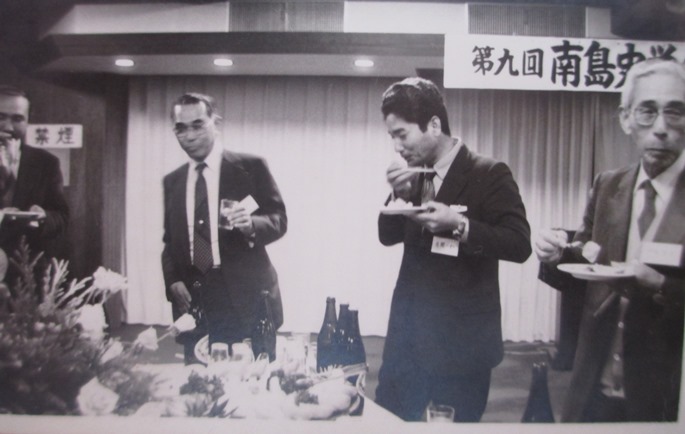

1980年11月24日ー豊中市立婦人会館で開かれた南島史学会第9回研究大会。中央ー窪徳忠氏、當間一郎氏/左から新城栄徳、崎間麗進氏、島袋光晴氏、當間一郎氏
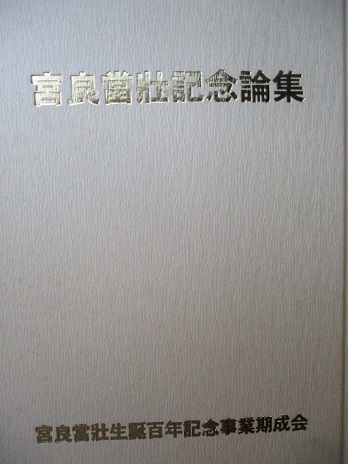
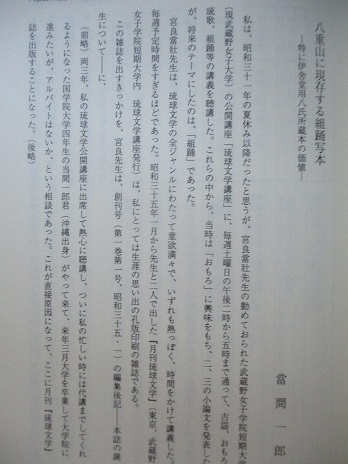
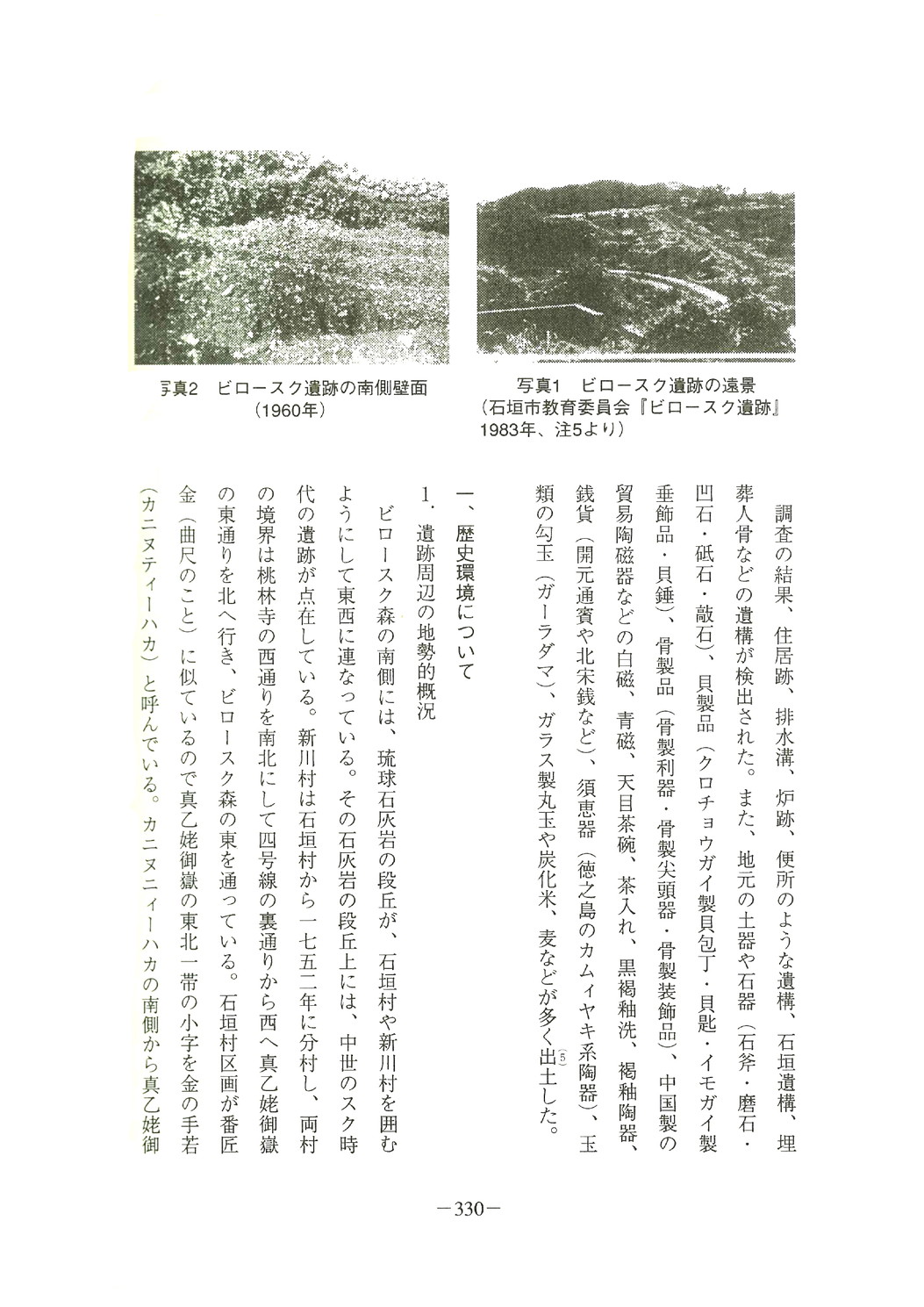
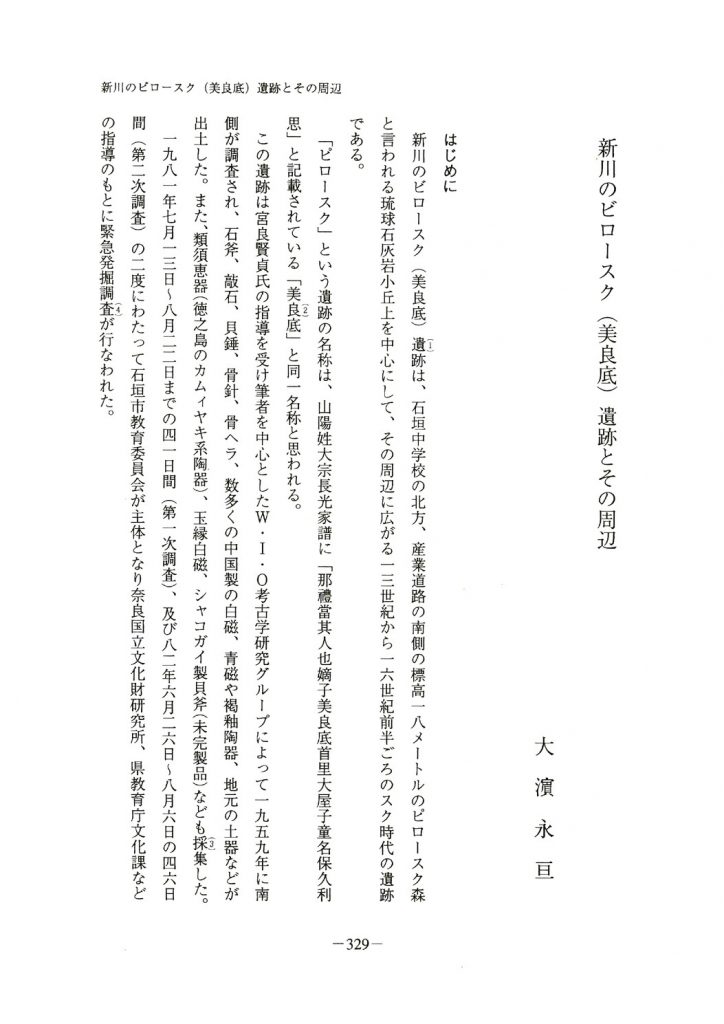
2000年11月『宮良當壯記念論集』宮良當壯生誕百年記念事業期成会(石垣繁)當間一郎「八重山に現存する組踊写本」/大濵 永亘「新川とその周辺のビロースク(美良底)遺跡とその周辺」
末吉麦門冬資料を提供したということで當間一郎氏から2010年6月発行『沖縄芸能史研究会会報』第380号(〒901-0152那覇市小禄808-3 電話098-857-2431)が贈られてきた。末吉安恭の沖縄芸能研究が会報全部を占めている。私が興味を持ったのが、はじめの當間一郎氏と宮良當壮との出会いである。宮良は折口信夫の弟子であった。2の末吉安恭の家系で當間氏は安恭の没した日で悩んでおられるが、安恭「莫夢忌」は11月25日である。5として折口信夫の「沖縄採訪記」(大正12年)の話者としての末吉安恭もある。
6が琉球芸能史の実証研究者で、「組踊談叢ーは、組踊に関するエピソードが紹介されていて、興味深い論考である。『踊が物言ふと法もあるものか』といった話。『出様来る者や』の出端のせりふのきまった話。田里朝直の組踊三番にまつわる話。『花売の縁』の出端の道行歌に関する話。『二山和睦』を創作し、母の49歳のお祝いに演じた話。『大川敵討』『本部敵討』の沖縄本島北部までの道のりを、出かけて実地踏査をしたエピソード等、興味深い話をまとめあげたものである。組踊研究で熟読してきた『組踊小言』は、末吉安恭の博学多才を前面に打ち出した論文である。能や謡曲、狂言、歌舞伎、雅楽、浄瑠璃等、わが国の中世、近世、古代の芸能に造詣が深く、それらを駆使しての一大論文になっている。最後に、独学で築きあげたパワーの偉大さを、読むたびに感じている。詩歌や戯曲等においてもハングリー精神旺盛であった末吉安恭の実力を再確認することができた、としめている。
2000年8月30日ー『琉球新報』新城栄徳「命ど宝!/山里永吉の芝居の世界」
アメリカの歴代の大統領のスキャンダルを紹介している本を読み終わった直後、色男・クリントンの平和の礎での演説をテレビで聞いた。なぜか危険な親しみを感じてしまった。そして、作家の大城立裕氏が本紙に、その演説を批評し話題となったのが「命ど宝」という言葉である。
大城氏の批評を呼んで初めて気づくのだが、尚泰王の「いくさ世もしまちみろく世もやがて嘆くなよ臣下命ど宝」が、実は、芝居「首里城明け渡し」に本来は無かったということである。大城氏は『うらそえ文芸』5号でも「あれは山里永吉の『那覇四町昔気質』という芝居があって、尚泰王がヤマトに連れていかれるときの幕切れで、歌う歌」と厳密に紹介されている。
山里永吉の戯曲「那覇四町昔気質」が琉球新報に掲載されたのは昭和7年3月で、山里はその後記で「この戯曲は多分13日から大正劇場で上演されると思うが、考えて見ると大正劇場に拙作『首里城明け渡し』が上演されたのが一昨年の今頃、ちょうど衆議院の選挙が終わった当座だったと覚えている。それから昨年の正月が『宜湾朝保の死』、今度の『那覇四町昔気質』と共に尚泰王三戯曲がここに完成した」と述べている。
大城氏も指摘されているが、この歌を尚泰王の歌として定着させた功労者、喜納緑村について少し紹介しておこう。第一豊見城小学校の代用教員、『沖縄新聞』記者を経て、大正2年、雑誌『おきなは』を創刊。昭和3年、『沖縄昭和新聞』主筆、昭和5年に沖縄童話発行所を設立し『沖縄童話』を発行、昭和7年に琉球研究社と改称し、『琉球歌物語』『琉歌註釈』を刊行。一般には『琉球昔噺集』の著者として著名である。
大方のウチナーンチュは尚泰王の、この歌はフィクションだと知っている。事実であれば那覇港に大きな「歌碑」が既に立っている。「命ど宝」の言葉自体は當間一郎編『沖縄県史料ー芸能Ⅰ(組踊)』の「屋慶名大主敵討」にある。昨今、「沖縄のこころ」や「命ど宝」という言葉に難癖をつける傾向が「琉大トリオ」をはじめ、学生にも目だっている。これは形ばかりの気の抜けたジャーナリストが横行していることの証明であろう。(最近も居る)
1940年6月 那覇の大正劇場で「首里城明渡し」上演/7月「那覇四町昔気質」上演
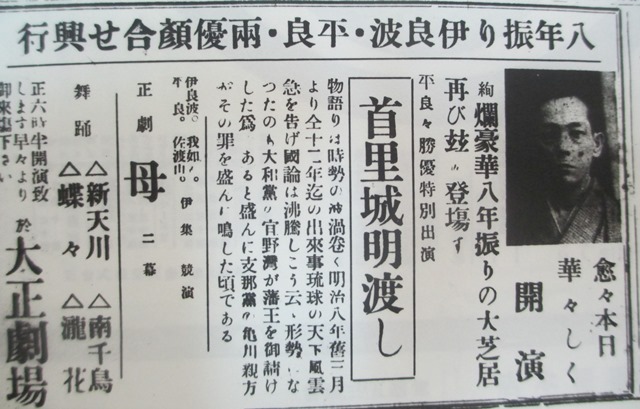
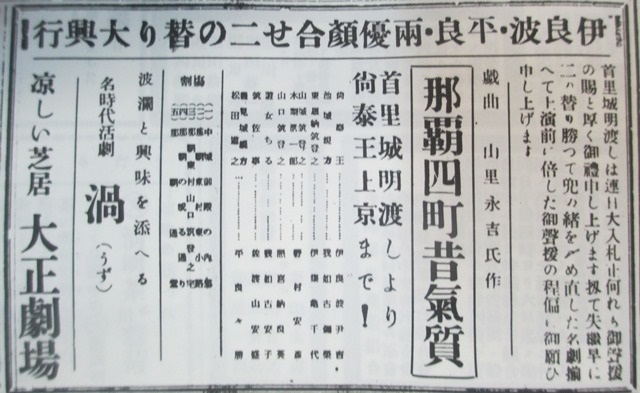
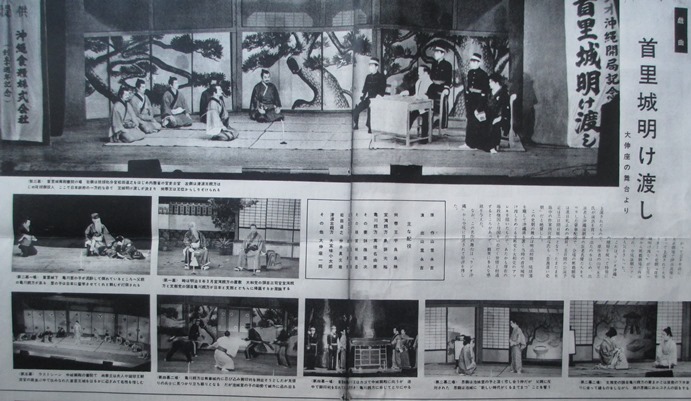
1960年8月『オキナワグラフ』
旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。
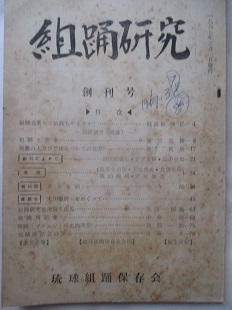
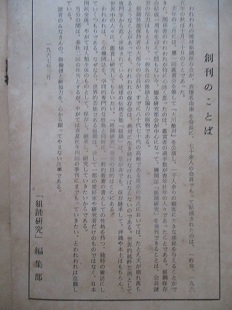
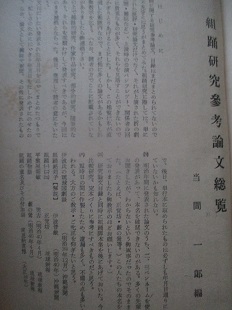
1967年3月 琉球組踊保存会(代表・真境名由康)『組踊研究』創刊号
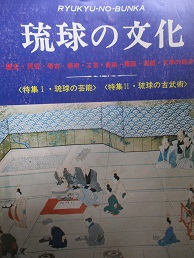
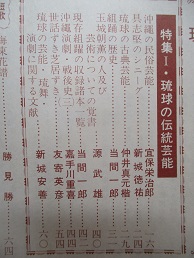
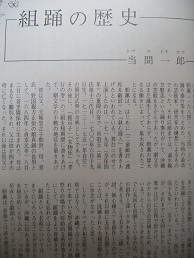
1973年10月『琉球の文化』第4号 当間一郎「組踊の歴史」
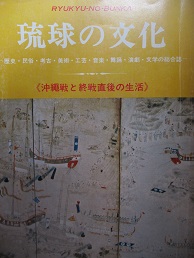
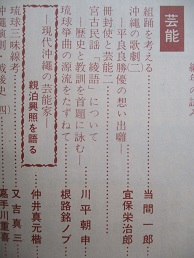
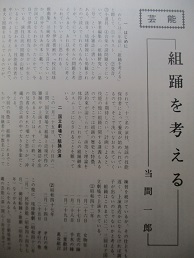
1974年5月『琉球の文化』第5号 当間一郎「組踊を考える」
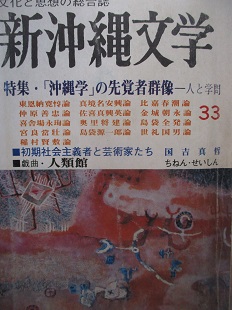
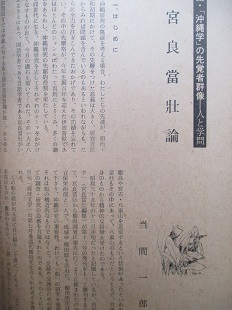
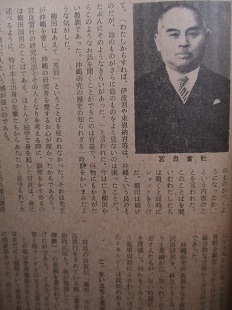
1976年10月 『新沖縄文学』33号 当間一郎「宮良當壯論・・・昭和35年の12月中旬だったと記憶しているが、月刊『琉球文学』(宮良當壯編集)が第12号の発刊をもって廃刊するにあたって、宮良當壯から柳田国男に報告に行くように頼まれたので、友人の宜保栄治郎と二人で、成城の柳田邸を訪ねた。柳田先生は快く迎えて下さり、沖縄研究の重要性、わけても『船』の研究を強調された・・・」
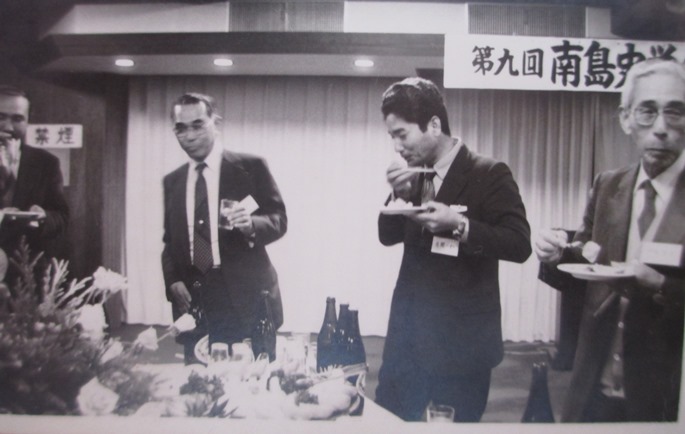

1980年11月24日ー豊中市立婦人会館で開かれた南島史学会第9回研究大会。中央ー窪徳忠氏、當間一郎氏/左から新城栄徳、崎間麗進氏、島袋光晴氏、當間一郎氏
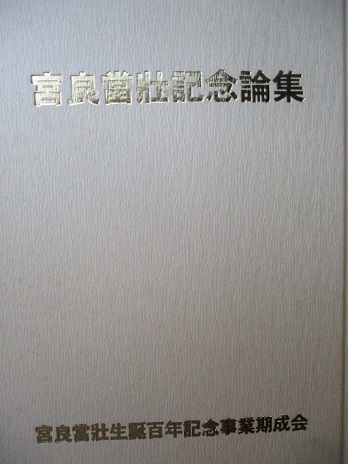
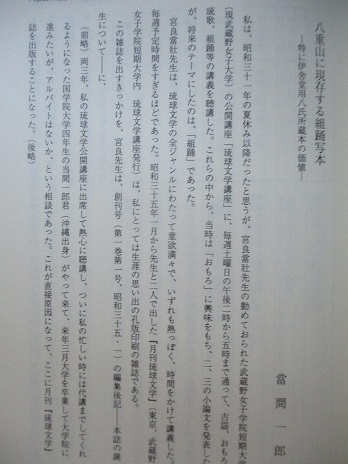
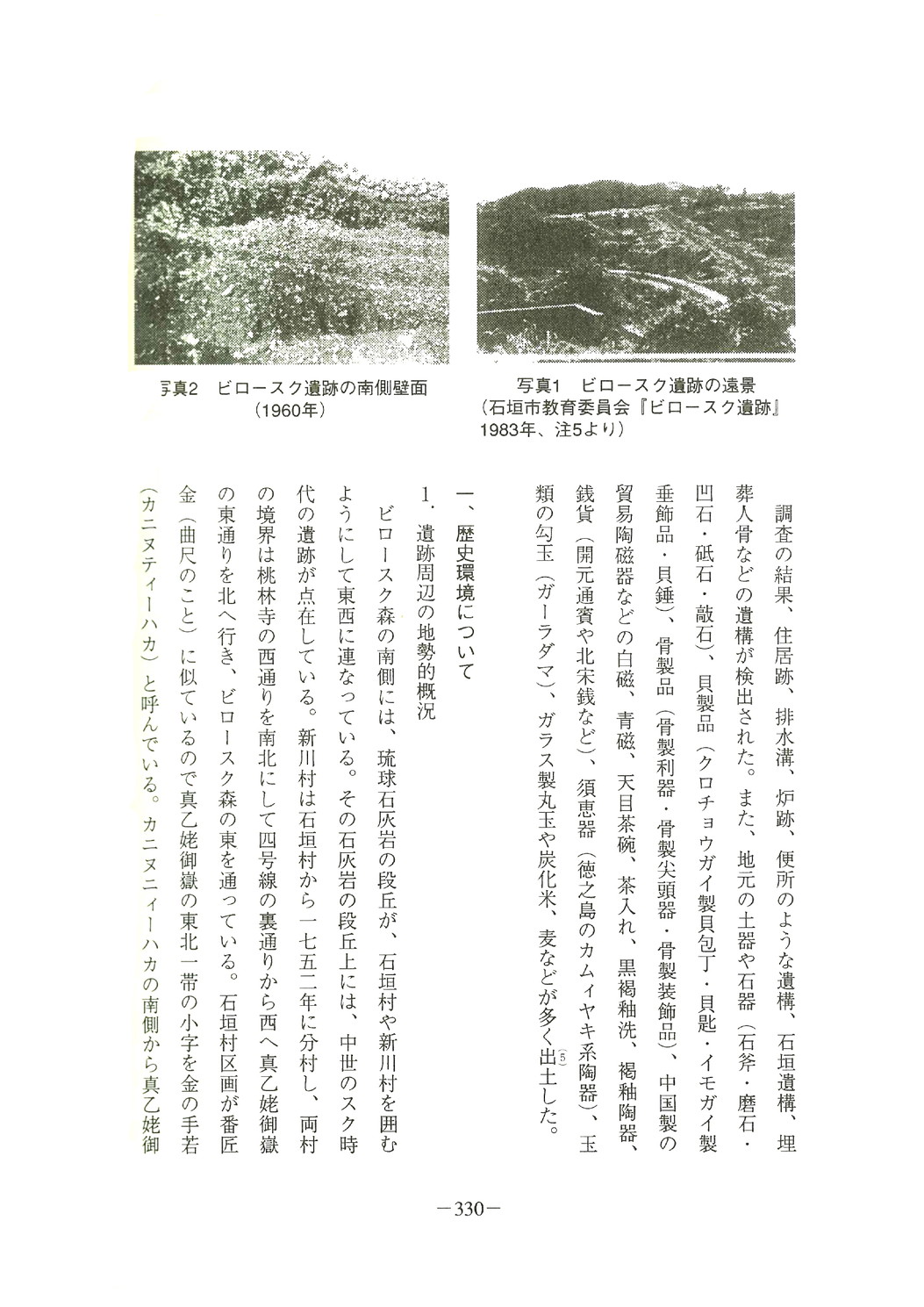
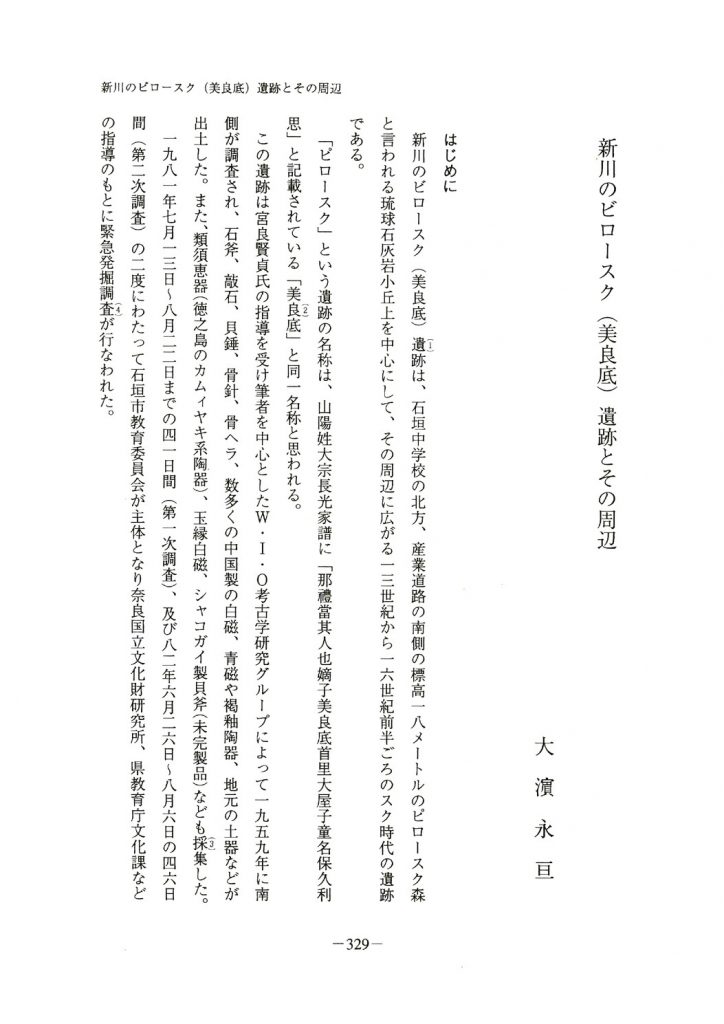
2000年11月『宮良當壯記念論集』宮良當壯生誕百年記念事業期成会(石垣繁)當間一郎「八重山に現存する組踊写本」/大濵 永亘「新川とその周辺のビロースク(美良底)遺跡とその周辺」
末吉麦門冬資料を提供したということで當間一郎氏から2010年6月発行『沖縄芸能史研究会会報』第380号(〒901-0152那覇市小禄808-3 電話098-857-2431)が贈られてきた。末吉安恭の沖縄芸能研究が会報全部を占めている。私が興味を持ったのが、はじめの當間一郎氏と宮良當壮との出会いである。宮良は折口信夫の弟子であった。2の末吉安恭の家系で當間氏は安恭の没した日で悩んでおられるが、安恭「莫夢忌」は11月25日である。5として折口信夫の「沖縄採訪記」(大正12年)の話者としての末吉安恭もある。
6が琉球芸能史の実証研究者で、「組踊談叢ーは、組踊に関するエピソードが紹介されていて、興味深い論考である。『踊が物言ふと法もあるものか』といった話。『出様来る者や』の出端のせりふのきまった話。田里朝直の組踊三番にまつわる話。『花売の縁』の出端の道行歌に関する話。『二山和睦』を創作し、母の49歳のお祝いに演じた話。『大川敵討』『本部敵討』の沖縄本島北部までの道のりを、出かけて実地踏査をしたエピソード等、興味深い話をまとめあげたものである。組踊研究で熟読してきた『組踊小言』は、末吉安恭の博学多才を前面に打ち出した論文である。能や謡曲、狂言、歌舞伎、雅楽、浄瑠璃等、わが国の中世、近世、古代の芸能に造詣が深く、それらを駆使しての一大論文になっている。最後に、独学で築きあげたパワーの偉大さを、読むたびに感じている。詩歌や戯曲等においてもハングリー精神旺盛であった末吉安恭の実力を再確認することができた、としめている。
2000年8月30日ー『琉球新報』新城栄徳「命ど宝!/山里永吉の芝居の世界」
アメリカの歴代の大統領のスキャンダルを紹介している本を読み終わった直後、色男・クリントンの平和の礎での演説をテレビで聞いた。なぜか危険な親しみを感じてしまった。そして、作家の大城立裕氏が本紙に、その演説を批評し話題となったのが「命ど宝」という言葉である。
大城氏の批評を呼んで初めて気づくのだが、尚泰王の「いくさ世もしまちみろく世もやがて嘆くなよ臣下命ど宝」が、実は、芝居「首里城明け渡し」に本来は無かったということである。大城氏は『うらそえ文芸』5号でも「あれは山里永吉の『那覇四町昔気質』という芝居があって、尚泰王がヤマトに連れていかれるときの幕切れで、歌う歌」と厳密に紹介されている。
山里永吉の戯曲「那覇四町昔気質」が琉球新報に掲載されたのは昭和7年3月で、山里はその後記で「この戯曲は多分13日から大正劇場で上演されると思うが、考えて見ると大正劇場に拙作『首里城明け渡し』が上演されたのが一昨年の今頃、ちょうど衆議院の選挙が終わった当座だったと覚えている。それから昨年の正月が『宜湾朝保の死』、今度の『那覇四町昔気質』と共に尚泰王三戯曲がここに完成した」と述べている。
大城氏も指摘されているが、この歌を尚泰王の歌として定着させた功労者、喜納緑村について少し紹介しておこう。第一豊見城小学校の代用教員、『沖縄新聞』記者を経て、大正2年、雑誌『おきなは』を創刊。昭和3年、『沖縄昭和新聞』主筆、昭和5年に沖縄童話発行所を設立し『沖縄童話』を発行、昭和7年に琉球研究社と改称し、『琉球歌物語』『琉歌註釈』を刊行。一般には『琉球昔噺集』の著者として著名である。
大方のウチナーンチュは尚泰王の、この歌はフィクションだと知っている。事実であれば那覇港に大きな「歌碑」が既に立っている。「命ど宝」の言葉自体は當間一郎編『沖縄県史料ー芸能Ⅰ(組踊)』の「屋慶名大主敵討」にある。昨今、「沖縄のこころ」や「命ど宝」という言葉に難癖をつける傾向が「琉大トリオ」をはじめ、学生にも目だっている。これは形ばかりの気の抜けたジャーナリストが横行していることの証明であろう。(最近も居る)
1940年6月 那覇の大正劇場で「首里城明渡し」上演/7月「那覇四町昔気質」上演
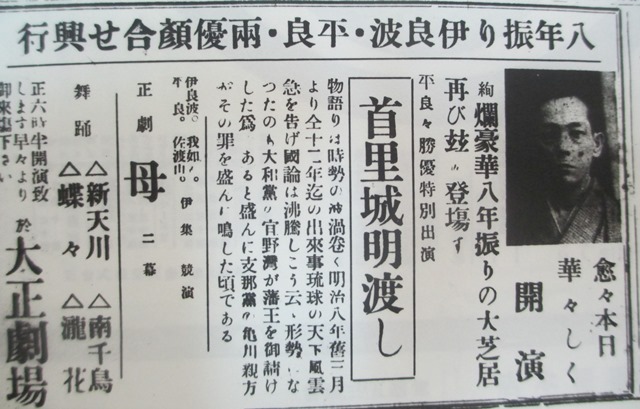
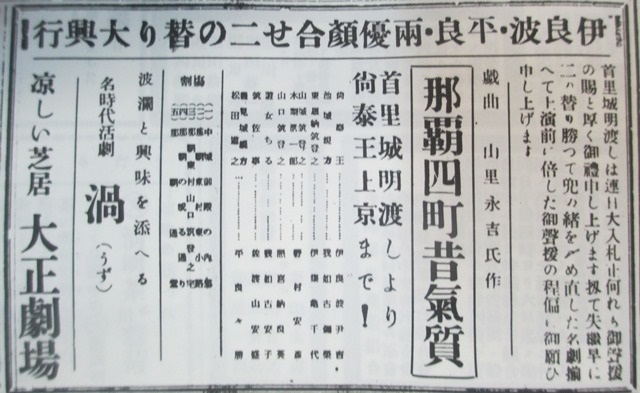
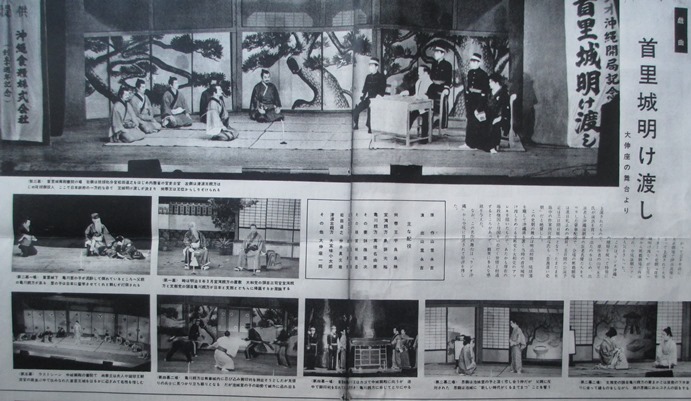
1960年8月『オキナワグラフ』
08/21: 奈良ーシルクロードの終点
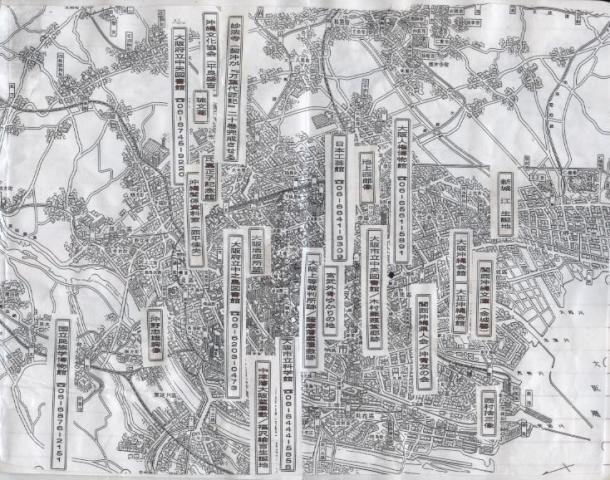
大阪沖縄絵図
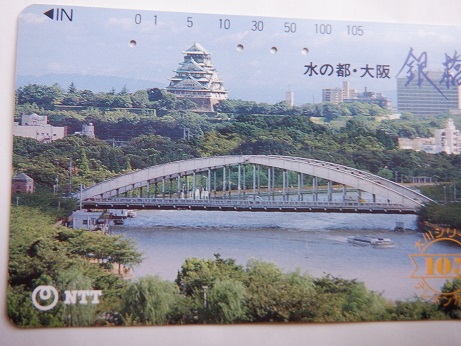
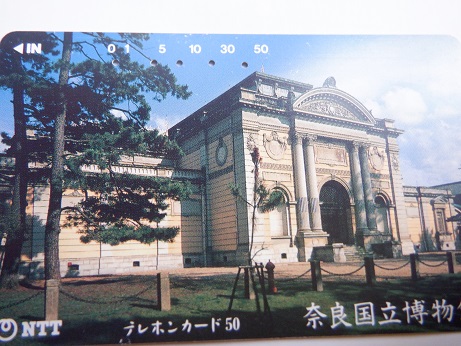
テレホンカード
私の17歳は東京一の繁華街、新宿歌舞伎町の大衆居酒屋「勇駒」で働いた事もある。その頃は若くてパワーもあった。20年ほど前、浅草寺初詣に行ったとき参拝者の列に入ったら全く身動きが取れなく離脱したこともある。とにかく過密都市でのオリンピック開催は気が知れない。いずれにせよ静かな場所に憧れて京都に住み着いたのが1969年であったが、盆地だから夏は暑く、冬は底冷えに寒い。復帰前、沖縄関係資料室主宰の西平守晴さん一家と同行、生駒聖天に初詣したのが生駒との出会いである。その後、私の家族は生駒に直通する近鉄奈良線の布施駅近くに住むことになる。


2022年7月 あけみ、こうた/ユンタンの孫
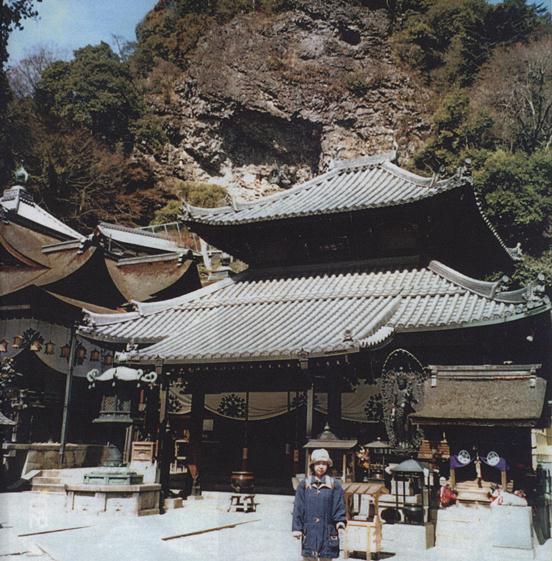
宝山寺と新城あけみ
宝山寺(ほうざんじ)は、奈良県生駒市門前町にある真言律宗大本山の寺院。生駒聖天(いこましょうてん)とも呼ばれる。山号は生駒山(いこまさん)。1678年に湛海律師によって開かれた。本尊は不動明王。鎮守神として歓喜天(聖天)を天堂(聖天堂)に祀っている。仏塔古寺十八尊第十五番。(→ウィキ)
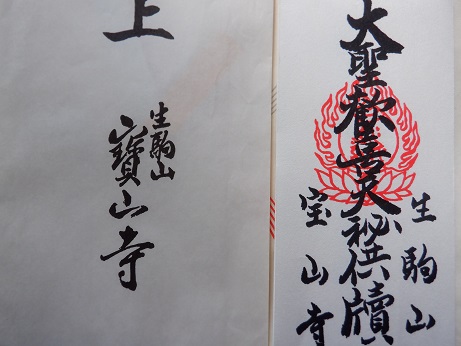
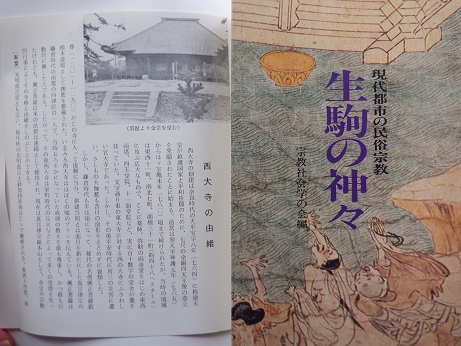
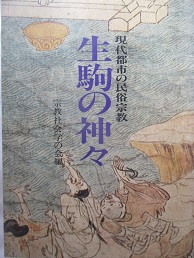
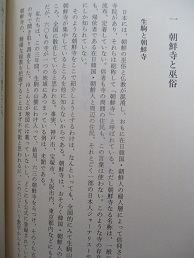

1985年10月 宗教社会学の会編『生駒の神々ー現代都市の民俗宗教』創元社〇朝鮮寺ー在日韓国・朝鮮人の巫俗と信仰ー
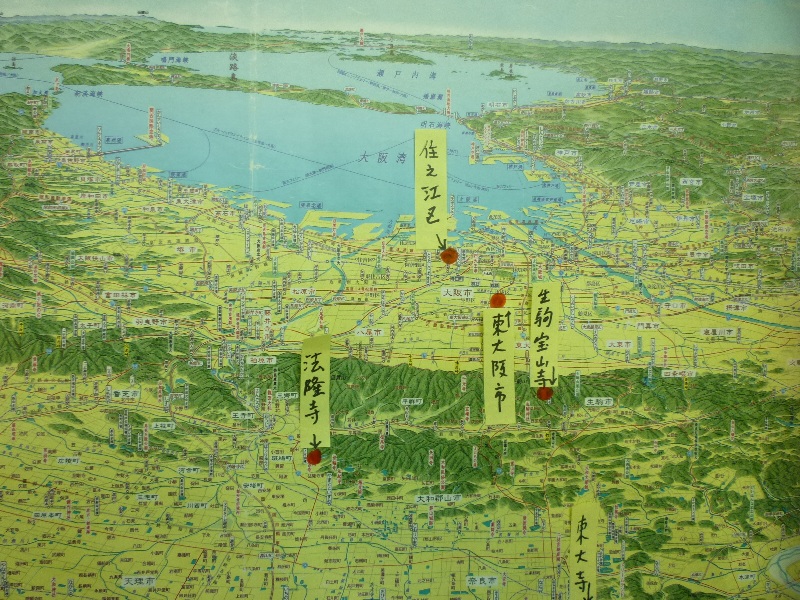
2006「トンビの目のパノラマ地図」
写真ー『沖縄美術全集』4絵画・書 山口宗季「花鳥図」大和文華館所蔵

○我が家は近鉄奈良線の布施駅近く(上の赤丸・東大阪市)にある。奈良公園や、唐招提寺・薬師寺、大和文華館(山口宗季の花鳥図、座間味庸昌の人物画が所蔵されている)、近鉄資料室や大阪ミナミ(道頓堀)に出るのに便利である。奈良はシルクロードの終点と言われているが、1977年発行の辛島昇①編『インド入門』に「日本人のシルクロード好きは、毎秋奈良でひらかれる正倉院展にどっと人があつまる事情と軌を一にしたものである」とし「むかし大東亜共栄圏という日本を扇の要においたひろい意味での文化圏を捏造した国粋主義に通じる」とする。奈良は東大寺の大仏や興福寺の五重塔、阿修羅像でも知られ世界遺産でもある。
①辛島昇 からしま-のぼる
1933- 昭和後期-平成時代の南アジア史学者,インド史学者。
昭和8年4月24日生まれ。専門は南アジア史。昭和50年東大教授。のち大正大教授。平成15年「History and Society in South India:The Cholas to Vijiayanagar(南インドの歴史と社会─チョーラ朝からビジャヤナガル王国へ)」で学士院賞。19年文化功労者。東京出身。東大卒。著作に「インド入門」など。→コトバンク

東大寺大仏殿ー2017年1月/ 『毎日新聞』2019-11-1 那覇市の首里城で起きた火災を受け、奈良県内の文化財でも31日、防火設備の緊急点検などが行われた。 奈良市の東大寺大仏殿では同市中央消防署員ら7人が緊急査察を行い、建物や周辺に設置された消火器や放水銃、自動火災報知機などの防火設備約30カ所を点検した。特に問題はなかったという。

奈良近鉄駅ビル3・4階に歴史・観光の展示館「なら奈良館」(旧・奈良歴史教室)
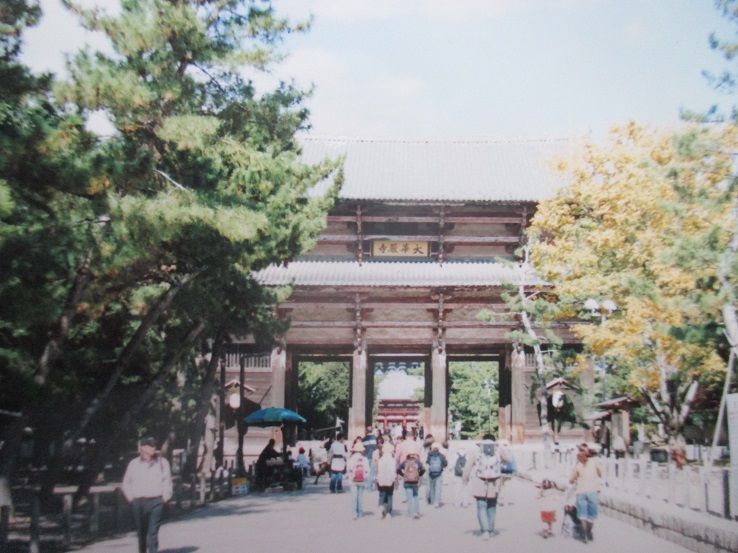
源平争乱によって焼失した東大寺を、重源はその資金を広く寄付にあおいで各地をまわる勧進上人となって、宋人陳和卿の協力を得て再建にあたりました。そのとき採用されたのが、大仏様の建築様式で、大陸的な雄大さ、豪放な力強さを特色するもので、この東大寺南大門が代表的遺構です。

国宝・銅造盧舎那仏坐像/重文・如意輪観音坐像

大仏殿にある広目天像 多聞天像
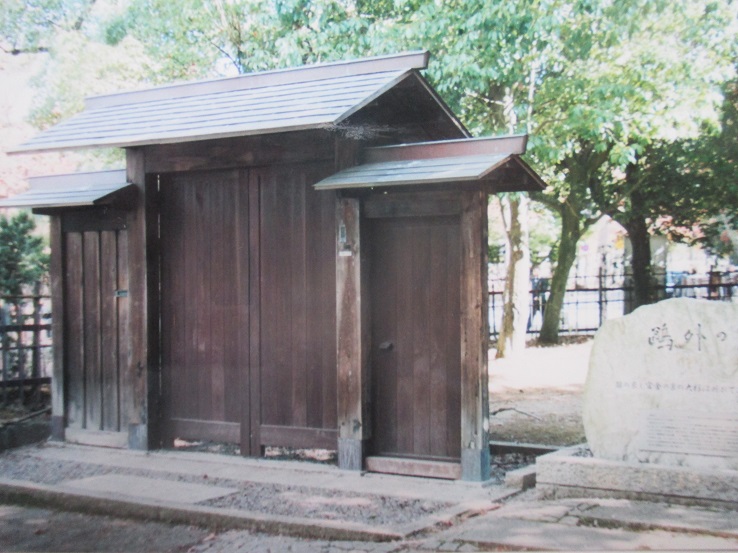
小説家して有名な森鴎外は、大正6年に帝室博物館の総長に任命され、東京・京都・奈良の帝室博物館を統括する要職でした。大正7年から10年まで、秋になると鴎外は正倉院宝庫の開封に立ち合うため奈良を訪れており、滞在中の宿舎はこの場所にありました。
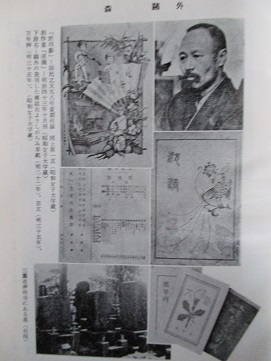
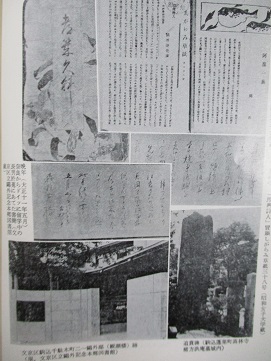
1972月3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書』「森鴎外」第二十巻
2006年5月13日ー午後は、近鉄丹波橋で降りて、御香宮神社に行く。名水「御香水」が境内にある。この神社には京都市天然記念物のソテツがあり、その実は「延命厄除そてつ守」になっている。鳥せい本店側では名水「白菊水」、月桂冠大倉記念館では名水「さかみづ」を飲んだ。同時に昼間からきき酒で顔が赤くなった。
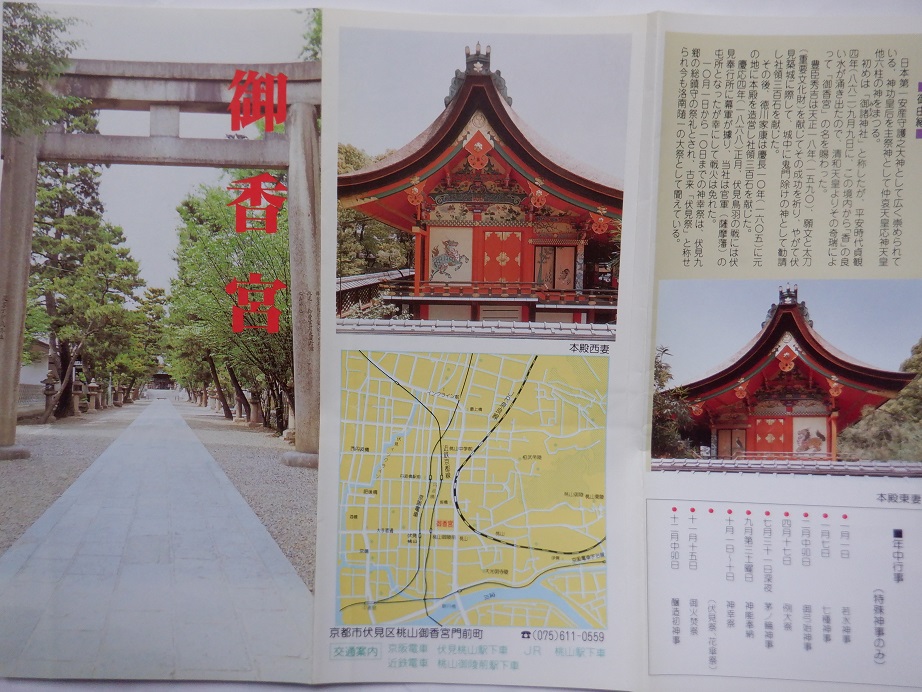

御香宮神社
近鉄奈良駅西口を出て地下道を通って近鉄高天ビルに出て歩道を西の方に歩くと直ぐ通称「山の寺」という看板が見える。奧まったところに「葵」の紋を打った山門が建っているところが浄土宗降魔山「念仏寺」である。門をくぐると降魔山と記された燈篭がある。その傍らに蘇鉄。1614年(慶長19年)11月15日徳川家康が大阪冬の陣の折、木津の戦いで真田幸村の軍勢に敗れ、奈良へ逃げ延び、この地の小字山の寺に至って、桶屋の棺桶の中に隠れ、九死に一生を得た。その後に、家康が豊臣方を破って、天下が治まった、1622年(元和8年)徳川家康の末弟で当時伏見城代を務めていた松平隠岐守定勝が、ここ油坂・漢国町を買い受け、袋中上人を開山として諸堂を建立したのが、山の寺「念仏寺」の始めである。

浄土宗降魔山「念仏寺」
〇御香宮神社は徳川家と深い関わりがある。徳川家康が豊臣秀吉のあとをうけ伏見城で天下の政事をとったおり、尾張、紀伊、水戸の御三家の藩祖と、秀忠の娘千姫はこの伏見で誕生している。御香宮を産土神として特別な崇敬を払っている。御香宮の神門は1622年に水戸中納言頼房(水戸光圀の父)が伏見城大手門を寄進したものと言われている。
□御香宮神社は江戸末期の慶応4年(1868)正月に勃発した「伏見・鳥羽の戦」では、吉井孝助率ら官軍(薩摩藩など)の屯所となった。片や幕府軍は大手筋通りを隔てた南側200mほど離れた伏見奉行所に陣(伝習隊、会津藩、桑名藩、新撰組などが)を構えた。大砲・鉄砲などの弾が激しく飛び交ったが、御香宮は幸いにして戦火には免れている。官軍の屯所となった境内には「明治維新伏見の戦跡」の石碑がある。
寺田屋事件(てらだやじけん)は、江戸時代末期の文久2年4月23日(1862年5月21日)に、伏見の旅館・寺田屋に滞在していた尊皇攘夷の過激派志士が弾圧された事件。薩摩藩の事実上の指導者で藩主茂久の父島津久光はこのとき公武合体を推進する立場で、自らの入京を機に勝手に挙兵討幕を企てる薩摩藩士有馬新七らを快く思わず、志士らの暴発を防止しようと、藩士に命じて従わぬものを上意討ちさせた。同郷の藩士同士が斬り合う凄惨な乱闘となり、7名が死亡して2名が致命傷を負い、後に切腹したものを含めて9人の殉難者を出した。事件後、久光は多くの志士を京都から追放し、勅使大原重徳を擁して江戸に向い、一橋慶喜を将軍後見職、松平慶永を政事総裁職とする幕政改革を行った。→ウィキ
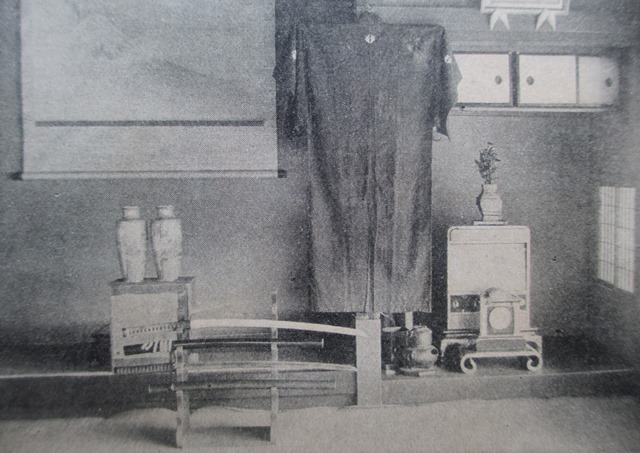
上図単衣は木綿にして奈良原男爵が寺田屋騒動の時着用せられしもの、右肩の白みたる処は血のにじみ付きしものにて五六寸の刀痕あるものなり。/刀ー上段は寺田屋事件の時に用いたもの、下は兄喜左衛門が生麦事件に用いたもの
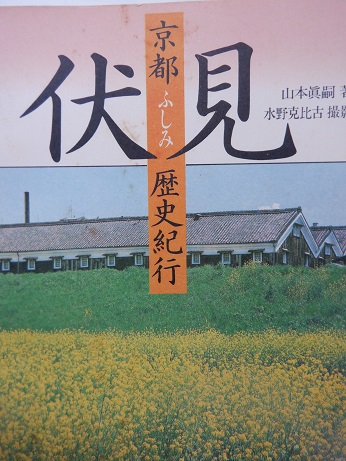
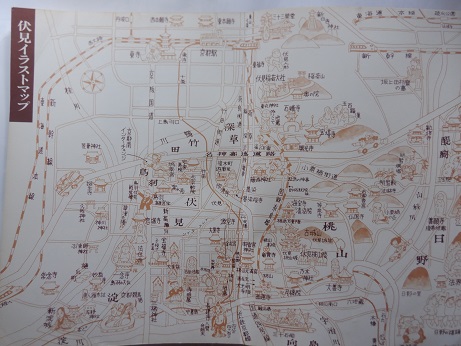
1983年9月 山本眞嗣著・水野克比古撮影『京都伏見歴史紀行』山川出版社
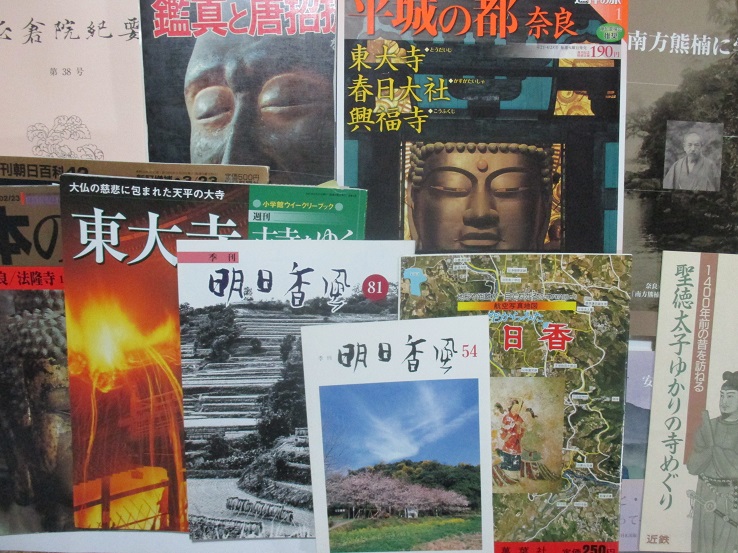
奈良・飛鳥の本
平良盛吉□→1991年1月『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)平良盛吉「村の先生」/平良盛吉(1890年8月28日~1977年6月28日)1912年、沖縄ではじめての総合文化誌『新沖縄』を創刊。琉球音楽研究家。『関西沖縄開発史』の著がある。□→2009年5月『うるまネシア』第10号/新城栄徳「失われた時を求めてー近鉄奈良線永和駅近くに平良盛吉氏が住んでおられた。息子が1歳のとき遊びに行ったら誕生祝をいただいた。袋は今もある」
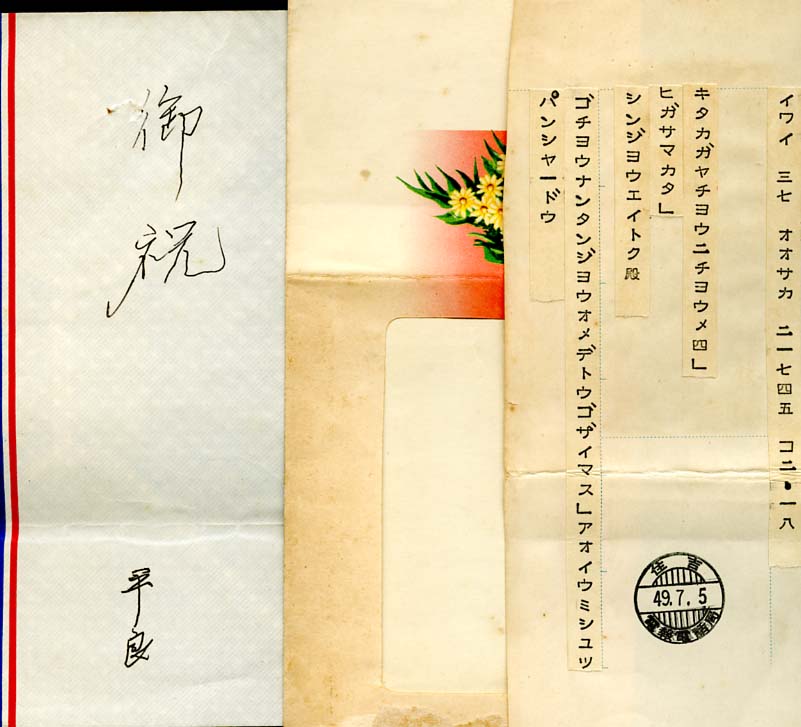
右の電報は青い海出版社から「息子誕生」の祝電である。

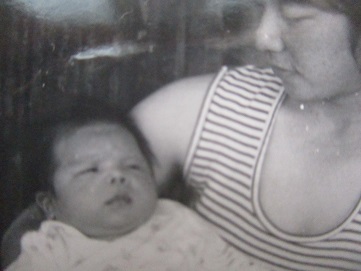
2020-8 こうたろう/1974-7 こうたろうのパパ

伏見桃山城、息子と娘
大阪、奈良の双方から望める金剛生駒国定公園内の大阪生駒霊園に阿氏西平家の墓、近くには大阪沖縄県人会の共同墓地「かりゆしの郷」もある。

元祖阿姓南風原按磁司守忠七世西平親雲上守安四男守秀ー守朋ー守保ー守孝ー守紀ー守諄ー


09/07: 世相ジャパン㊷/「わが青春ー新宿歌舞伎町」
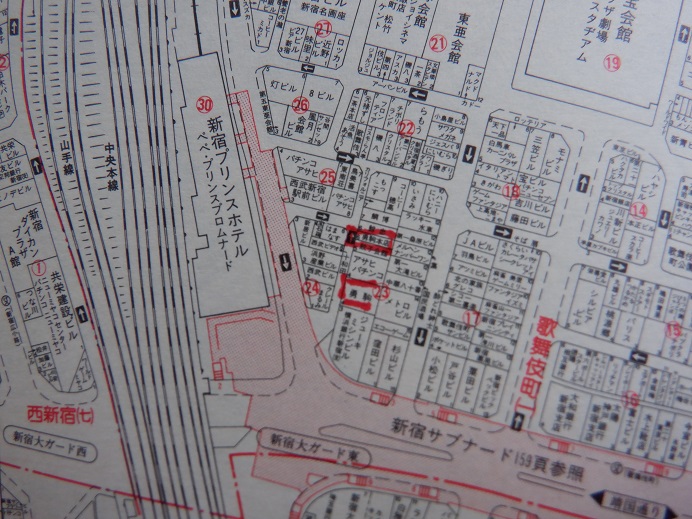
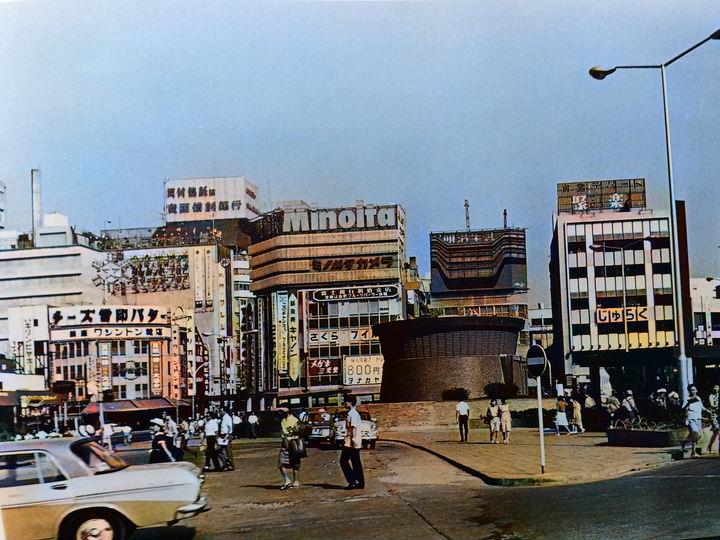


勇駒本店/西口新宿会

勇駒新館で、右が柴田マネジャー、新城栄徳
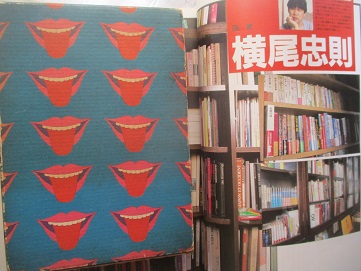
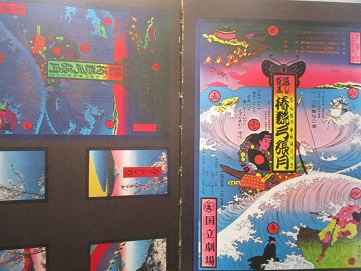
横尾忠則
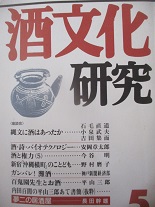
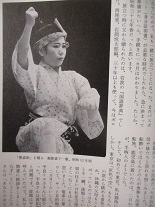


1996年3月『酒文化研究所』第5号 野村磨子「新宿『沖縄横町』のことども」
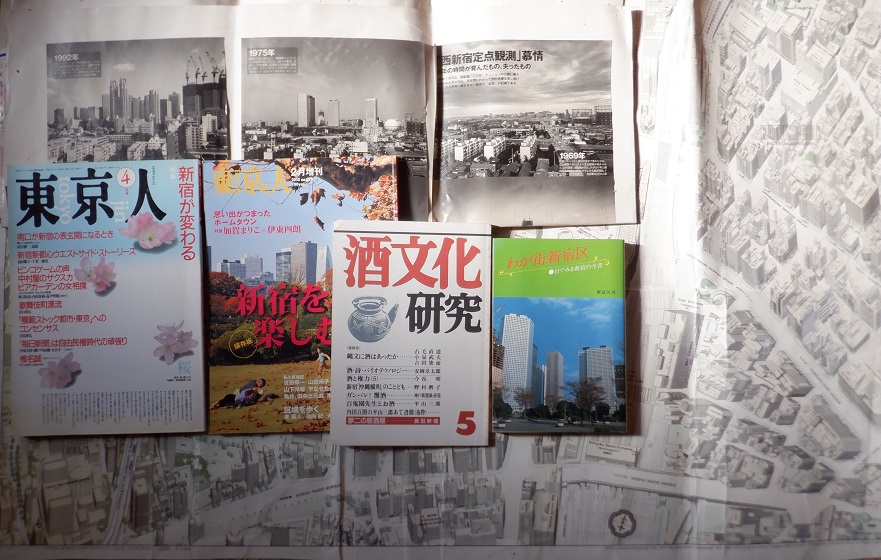
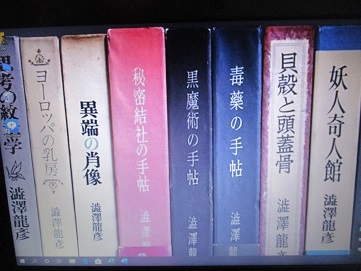
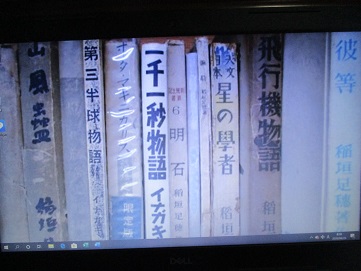
2013年5月16日ー『沖縄タイムス』は一面トップで女性25団体が半グレ大阪市長に抗議、社説にも「橋下氏とともに日本維新の会を率いる石原慎太郎共同代表は『軍と売春は基本的は基本的に付きもので、橋下氏は間違ったことは言っていない』と擁護している。いったい、この党はどういう党」なのだろうか。慰安婦は米国では『性奴隷』と訳される。2人の主張は国際社会では通用しない。」と触れている。時評漫評「迷惑な客引き」も良い。『琉球新報』は一面でなくとも良い「原発廃炉」を一面トップにし、社説には「速やかな撤回、謝罪を」とする。謝(誤)って済む問題ではなかろう。大体地元紙はオスプレイ問題も近頃は少ない。解決するまでキャンペーンを張れ!。
滝川政次郎『遊女の歴史』(至文堂1965年7月)に□柳学)的見地から見れば、云々」とあって、民俗学が振り回されている。氏の土俗学は、正直なところ猿真似に過ぎないが、材料は極めて豊富である。ただしその材料には田國男先生が「巫女考」および「イタカ及びサンカ」なる論文を発表し、民俗学の立場から、我が国遊女の起源が巫女にあることを論ぜられたのは、一大見識であったと言わねばならない。先生のこの論文は考証該博、従来の学者が顧みなかった資料を縦横に駆使して、前人未到の境地を開拓されたものであって、一世を魅了した。この柳田先生の民俗学に魅せられ、その遊女巫女起源説を敷 したものが、中山太郎①氏の『売笑三千年史』と『日本巫女史』であって、この両者にはしばしば「土俗学(民俗、新聞記事の切抜きや、氏が報知新聞の記者として伝聞せられたものが交じっているから、氏の著書を純然たる学術研究書として受け取ることは、いささか危険である。好事家の者として受け取らねばならないような部分も多分に存する。
遊女史も売笑史も、大体同じようなものであるが、売笑史は芸能史と殆ど関係がない。(略)本書にあえて「日本遊女史」の名をもってしたのは、芸能史との関係を強調せんがためである。(略)戦争に敗れた者が戦勝者に女を贈ることによって平和が購われたことは、媾和の「媾」、妥協の「妥」が、いずれも女によって構成されていることによって知られる。(略)万葉集、巻八には 遊行女婦の橘の歌一首「君が家の花橘は成りにけり花なる時にあはましものを」。平安・鎌倉の白拍子は、招かれれば最初に「我が君は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔の生すまで」をうたい、江戸時代の遊女は、「めでためでたの若松さまよ、枝も茂れば葉も茂る」とうたったという。(略)百太夫信仰は、平安中期以来、道祖神信仰と姿を変えた・・・、ゆえに後には陽物そのものが道祖神と考えられるようになり、木石もしくは紙もて製したる男根の形が、道祖神として祭られるようになった。木石もしくは紙もて製したる男根の形をコンセサマ(金勢明神)、ドンキョウサマ(道鏡様)という。本書は最後に「遊女史と男色の関係」にふれている。「明治以後においては、九州の辺境に稚児さん愛好の蛮風が少々残存していた程度で男色の風習全く跡を断ち、稚児物語は昔物語となってしまった。現代の日本人が、中世にあれほど盛んであった男色の風習を全く忘れてしまったということは、性生活史上の大きな変化と言わねばならない」、ここは著者の知ってか知らずか、現代では形を変え堂々とテレビなどの世界で息づいている。
○私は物事を整理してムダを省いた学者のものは理屈っぽく押し付けがましいので読まないが、中山太郎の著書は愛読している。中山にふれておこう。1928年11月『南島研究』に中山太郎「西平氏へー前略・・・・・・老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思い立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見致し候処結婚風俗の特輯號殊に巻頭言に於いて老生の為に種々御厚配被成下候由拝見致し御芳志の段誠に感謝致し候南島の婚姻に関しては在京中の伊波、東恩納、金城、島袋、比嘉の各先輩より承り。之れに故学友佐喜眞氏の著書等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき點も発見致し候、校正の折に出来るだけ御厚意に添べく期し居候 以下略 本郷弓町1ノ116」が載っている。中山と親しい折口信夫は大正10年8月に大阪朝日新聞編集所に絵葉書を送っている、表の琉球美人の説明には「尾類ズリ(遊女)といふもの」と書かれている。
12/22: 世相ジャパン(53)/伊波伊波普猷「おもろ・飛行機」
伊波普猷「おもろ・飛行機ー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
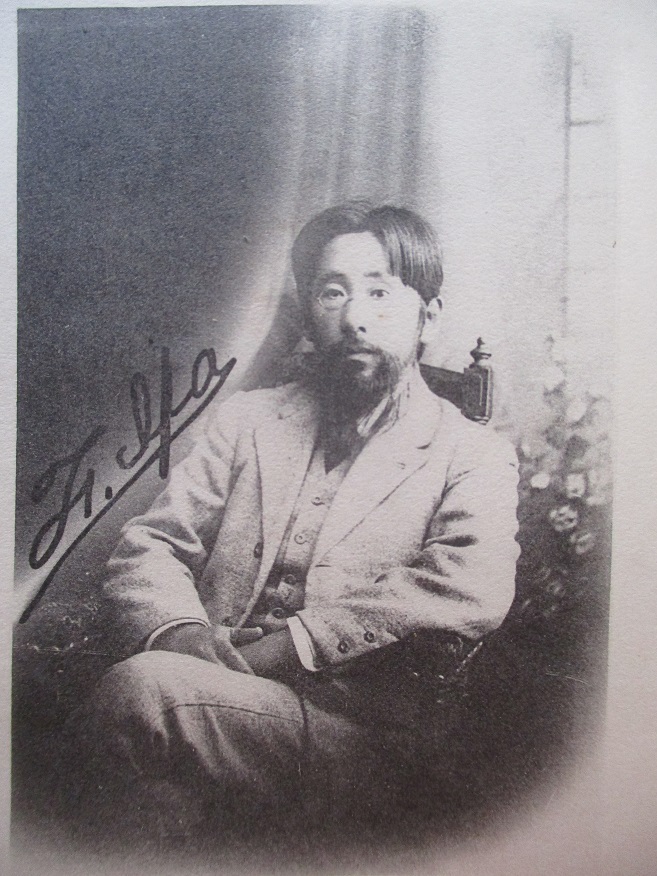
伊波普猷
1929年2月ー伊波普猷、山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ。カリフォルニア各地を巡遊、宮城与徳、屋部憲伝らと交流。
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
伊波普猷のよく知られた言説に「・・・さて、沖縄の帰属問題は、近く開かれる講和会議で決定されるが、沖縄人はそ
れまでに、それに関する希望を述べる自由を有するとしても、現在の世界情勢から推すと、自分の運命を自分で決定することの出来ない境遇におかれてゐることを知らなければならない。彼等はその子孫に対して斯くありたいと希望することは出来ても、斯くあるべしと命令すること出来ないはずだ。といふのは、廃藩置県後僅々七十年間における人心の変化を見ても、うなづかれよう。否、伝統さへも他の伝統にすげかへられることを覚悟しておく必要がある。すべては後に来たる者の意志にに委ねるほか道がない。それはともあれ、どんな政治の下に生活した時、沖縄人は幸福になれるかといふ問題は、沖縄史の範囲外にあるがゆゑに、それには一切触れないことにして、ここにはただ地球上で帝国主義が終わりを告げる時、沖縄人は『にが世』から開放されて、『あま世』を楽しみ十分にその個性を生かして、世界の文化に貢献することが出来る、との一言を附記して筆を擱く。」(1947年11月『沖縄歴史物語』沖縄青年同盟)がある。
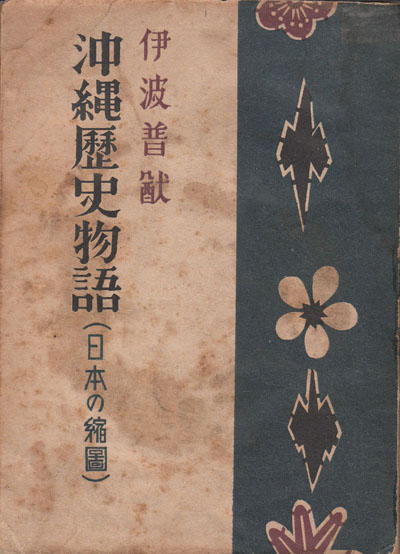
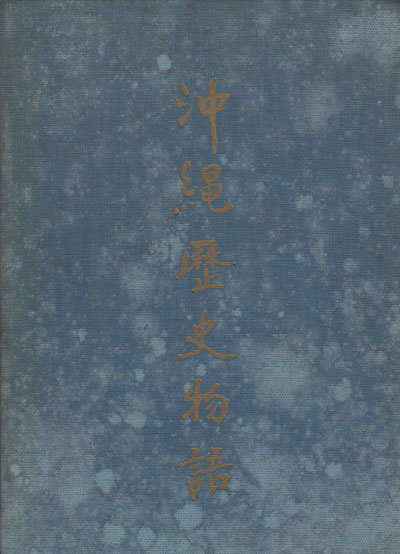
沖縄歴史物語(右がハワイ版)


<あま世>の言葉は、1933年1月15日、琉球新報主催「航空大ページェント」で瀬長島上空を関口飛行士操縦の複葉機から色白の美人・宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りる。それを万余の沖縄県民が見物という新報記事を東京で見た伊波が自身のロサンゼルス上空を飛んだ感動と重ね合わし「おもろ・飛行機」と題し「・・・紫の綾雲、おし分けて出ぢへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにゃ、・・・大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」とよんだことが初出である。
異国船研究も、やはり沖縄学(伊波の学問を沖縄学と称したのは折口信夫)の礎を築いた伊波普猷に立ち戻らないといけない。『東恩納寛惇全集』「伊波君の想出」に寛惇は「日清役の頃か、伊波君が在京沖縄青年会雑誌に『爛額雑記』とか云った表題の随筆で、ヴィクトリヤの僧正の琉球訪問記を紹介した。(略)伊波君が『ヴィクトリヤの僧正』を取上げたのは、琉球語聖書の著者ベッテルハイムや、通事板良敷等に興味を有ったからであったらしい」と記している。1904年6月、伊波は鳥居龍蔵の沖縄調査に同行し横浜から尚家の汽船で帰省。鳥居は伊波宅に投宿。伊波は鳥居を沖縄各地に案内、記念にチェンバレンの『琉球文典』を鳥居より贈られる。
飛び安里研究会
1913年11月 素人飛行家、渡辺又一、勢理客鍋(佐敷村出身)両氏は渡辺氏の作成に係わるカーチス式複葉飛行機の滑走を試みるべく、両氏は数日前よりこれが組立に従事し、いよいよ飛行の当日は、先ず渡辺氏が滑走を試みたる後、勢理客氏又滑走を試みる筈にて行く行くは渡辺氏の飛行機に、勢理客氏の所有にかかるインジン(機関)を据えつけ、佐村氏の監督の下に天晴れ飛行家とならんとの決心を抱き居りたり。然るにピンカム知事は、これら飛行家の苦心を無視し、ハワイ軍区長官カーター少将の命によれりとて、遂に飛行を差し止むるに至りたり。『新聞にみるハワイの沖縄人90年』比嘉武信/編著 1990/10/01 若夏社
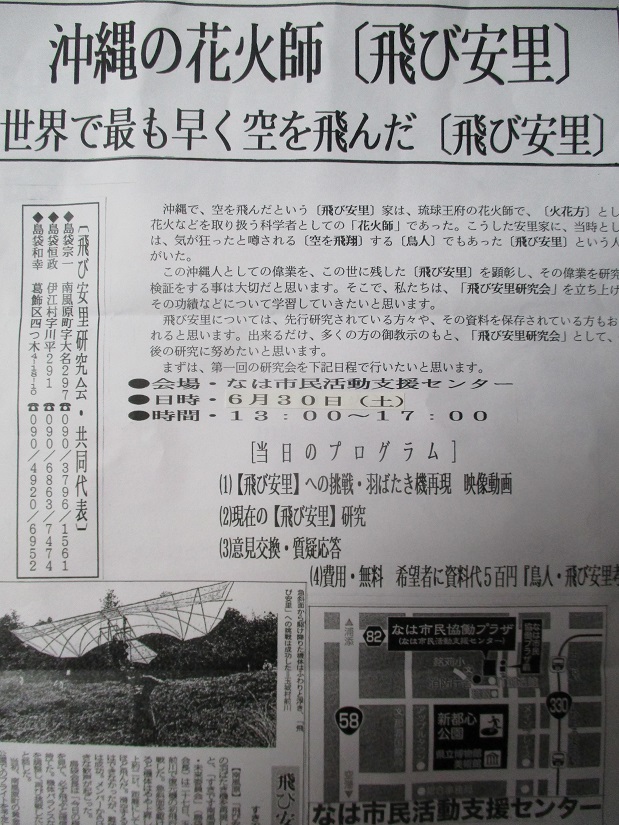
台風7号が接近中の6月30日 なは市民活動支援センター 飛び安里研究会「沖縄の花火師〔飛び安里〕世界で最も早く空を飛んだ」


島袋和幸氏、島袋宗一氏

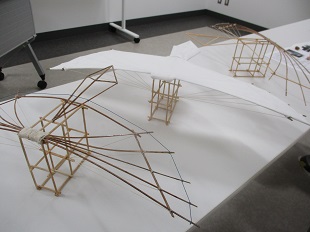
島袋宗一氏
1943年9月 月刊『文化沖縄』新垣源蔵「琉球の火術雑考」
○「頂姓系図」支流(越来村字越来の安里家の系図)によると、この内の一人安里筑登之は、安里家六世の祖安里周英と云ふ者で、この人の父が周當で、有名な火花師である。沖縄で始めて焰硝製出に成功した人である。宮里良保氏の発表された飛行機の発明者も、安里周祥でなくこの周當だと自分は考へている。何故なら周祥はこの人の四男であり、系図には事跡は明らかでない。・・・
1943年10月 月刊『文化沖縄』与那国善三「飛び安里の話」

琉球の「飛び安里」を世界に紹介した宮里良保

自動車の知識(誠文堂十銭文庫 33) 宮里良保 著
宮里の本や資料については島袋和幸に問い合わせてください。〒124-0011東京都葛飾区四つ木4-18-10 ☎03-3695-9276 島袋携帯090-4920-6952
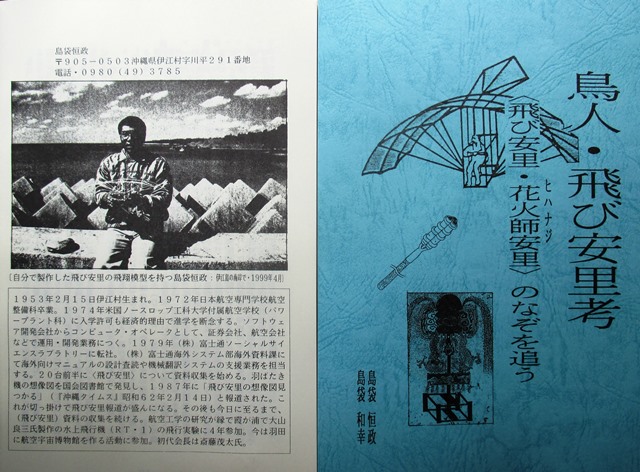
2015年6月 島袋恒政・島袋和幸『鳥人・飛び安里考』大和印刷(電話 03-3862-3236)定価・送料共1000円
発行ー『沖縄の軌跡』発行人・島袋和幸(〒124-0011 葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)
島袋和幸「沖縄の鳥人<飛び安里・花火師>」
沖縄の鳥人<飛び安里・花火師ヒハナジ>は、ことに沖縄では偉人と言われている。それは、約二百年前に<飛行>、つまり空を飛ぶ事について試行錯誤していた可能性があるからだ。その<飛び安里>について、彼が研究したであろう<飛ぶ>という事と、<沖縄の偉人>としてのロマンから、飛び安里について多くの方々が新聞や雑誌。書物などで言及されている。一方マスコミで取り上げられたことも数多いのである。しかし、こうした取り組みの中にあって、決定的な文献が無いとか、実際に飛んだ<飛び安里>とは一体誰なのかとか、又、飛んだ場所等についても諸説があったりで、実際には多くの方々を巻き込んで議論が尽きないのである。
こうした中で島袋恒政氏は、「二百年前の初飛翔/コンピューターで性能解明へ」(『沖縄タイムス』昭和62年2月14日)、「<跳び安里>のロマン再び/資料から模型製作/二百年前に精巧な設計」」(『沖縄タイムス』昭和62年5月10日)という新聞記事になる、<想像図>を国立国会図書館で発見している。それは約30年も前のことで、これ以降、地元新聞紙上や雑誌などで盛んに取り上げられた。その後も、同氏は各種資料や書物に真実を求めて追求してきた。安里家の遺族関係者や、貴重な証言、珍しい資料などが埋もれてしまう前に記録しておきたいという強い思いがある。
私は、約20年前に<飛び安里>研究に緒をつけた『科学画報』の記者、宮里良保について人となりを記録していた。さらに、15年前ほど前から民間航空の始祖である奈良原三次(奈良原繁沖縄県知事の嗣子)についても記録を行っていた。そして、いがいにも沖縄人の飛行機研究者が明治・大正期の早い時期から多かった事を知る。こうした事情等を島袋恒政氏の<飛び安里>についての博識な知識と、資料の記録をお手伝いしたいと思った次第である。
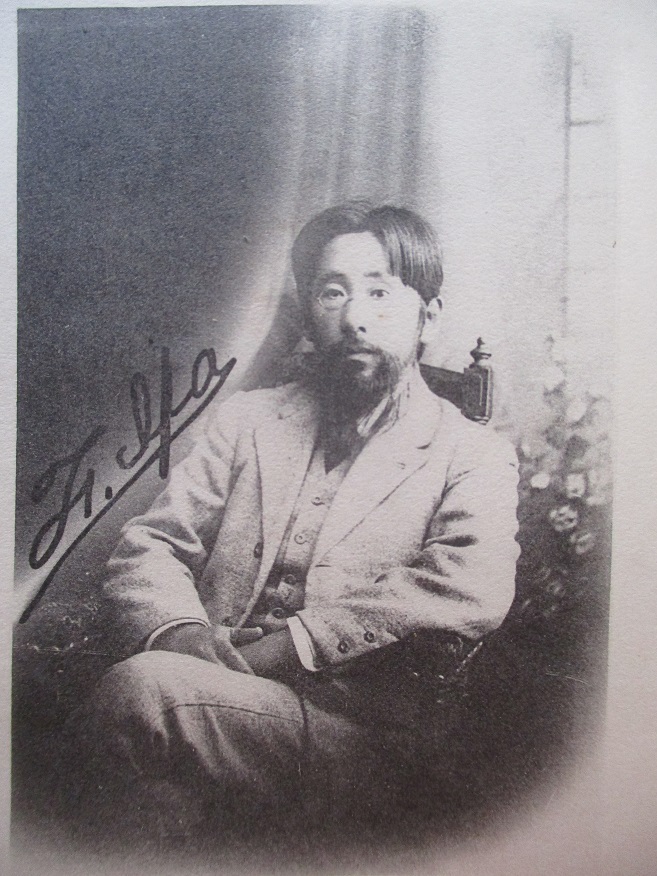
伊波普猷
1929年2月ー伊波普猷、山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ。カリフォルニア各地を巡遊、宮城与徳、屋部憲伝らと交流。
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
伊波普猷のよく知られた言説に「・・・さて、沖縄の帰属問題は、近く開かれる講和会議で決定されるが、沖縄人はそ
れまでに、それに関する希望を述べる自由を有するとしても、現在の世界情勢から推すと、自分の運命を自分で決定することの出来ない境遇におかれてゐることを知らなければならない。彼等はその子孫に対して斯くありたいと希望することは出来ても、斯くあるべしと命令すること出来ないはずだ。といふのは、廃藩置県後僅々七十年間における人心の変化を見ても、うなづかれよう。否、伝統さへも他の伝統にすげかへられることを覚悟しておく必要がある。すべては後に来たる者の意志にに委ねるほか道がない。それはともあれ、どんな政治の下に生活した時、沖縄人は幸福になれるかといふ問題は、沖縄史の範囲外にあるがゆゑに、それには一切触れないことにして、ここにはただ地球上で帝国主義が終わりを告げる時、沖縄人は『にが世』から開放されて、『あま世』を楽しみ十分にその個性を生かして、世界の文化に貢献することが出来る、との一言を附記して筆を擱く。」(1947年11月『沖縄歴史物語』沖縄青年同盟)がある。
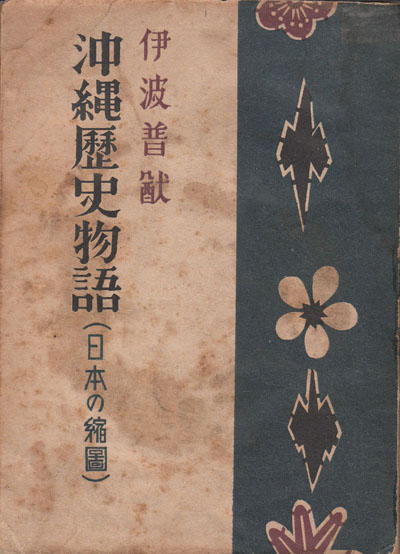
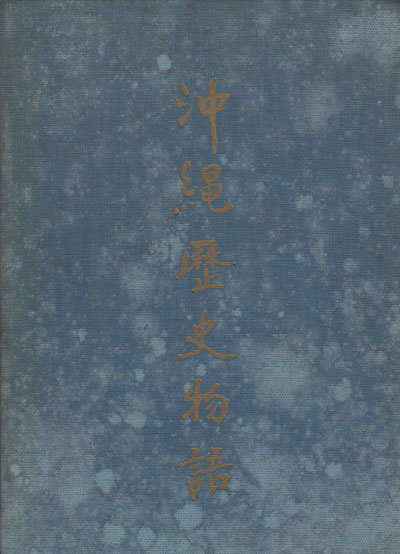
沖縄歴史物語(右がハワイ版)


<あま世>の言葉は、1933年1月15日、琉球新報主催「航空大ページェント」で瀬長島上空を関口飛行士操縦の複葉機から色白の美人・宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りる。それを万余の沖縄県民が見物という新報記事を東京で見た伊波が自身のロサンゼルス上空を飛んだ感動と重ね合わし「おもろ・飛行機」と題し「・・・紫の綾雲、おし分けて出ぢへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにゃ、・・・大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」とよんだことが初出である。
異国船研究も、やはり沖縄学(伊波の学問を沖縄学と称したのは折口信夫)の礎を築いた伊波普猷に立ち戻らないといけない。『東恩納寛惇全集』「伊波君の想出」に寛惇は「日清役の頃か、伊波君が在京沖縄青年会雑誌に『爛額雑記』とか云った表題の随筆で、ヴィクトリヤの僧正の琉球訪問記を紹介した。(略)伊波君が『ヴィクトリヤの僧正』を取上げたのは、琉球語聖書の著者ベッテルハイムや、通事板良敷等に興味を有ったからであったらしい」と記している。1904年6月、伊波は鳥居龍蔵の沖縄調査に同行し横浜から尚家の汽船で帰省。鳥居は伊波宅に投宿。伊波は鳥居を沖縄各地に案内、記念にチェンバレンの『琉球文典』を鳥居より贈られる。
飛び安里研究会
1913年11月 素人飛行家、渡辺又一、勢理客鍋(佐敷村出身)両氏は渡辺氏の作成に係わるカーチス式複葉飛行機の滑走を試みるべく、両氏は数日前よりこれが組立に従事し、いよいよ飛行の当日は、先ず渡辺氏が滑走を試みたる後、勢理客氏又滑走を試みる筈にて行く行くは渡辺氏の飛行機に、勢理客氏の所有にかかるインジン(機関)を据えつけ、佐村氏の監督の下に天晴れ飛行家とならんとの決心を抱き居りたり。然るにピンカム知事は、これら飛行家の苦心を無視し、ハワイ軍区長官カーター少将の命によれりとて、遂に飛行を差し止むるに至りたり。『新聞にみるハワイの沖縄人90年』比嘉武信/編著 1990/10/01 若夏社
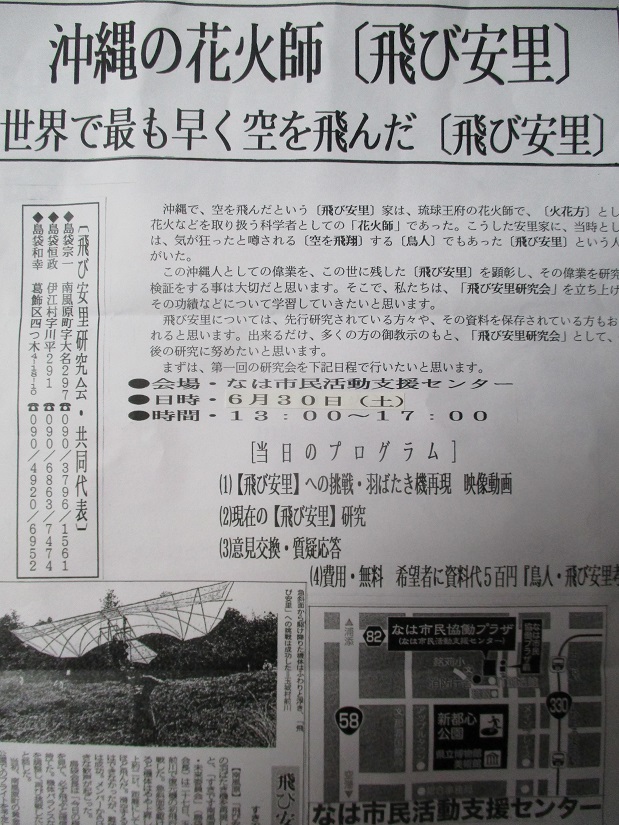
台風7号が接近中の6月30日 なは市民活動支援センター 飛び安里研究会「沖縄の花火師〔飛び安里〕世界で最も早く空を飛んだ」


島袋和幸氏、島袋宗一氏

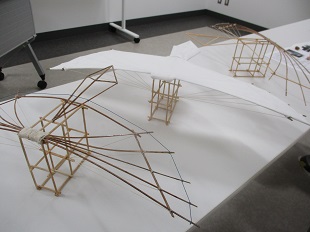
島袋宗一氏
1943年9月 月刊『文化沖縄』新垣源蔵「琉球の火術雑考」
○「頂姓系図」支流(越来村字越来の安里家の系図)によると、この内の一人安里筑登之は、安里家六世の祖安里周英と云ふ者で、この人の父が周當で、有名な火花師である。沖縄で始めて焰硝製出に成功した人である。宮里良保氏の発表された飛行機の発明者も、安里周祥でなくこの周當だと自分は考へている。何故なら周祥はこの人の四男であり、系図には事跡は明らかでない。・・・
1943年10月 月刊『文化沖縄』与那国善三「飛び安里の話」

琉球の「飛び安里」を世界に紹介した宮里良保

自動車の知識(誠文堂十銭文庫 33) 宮里良保 著
宮里の本や資料については島袋和幸に問い合わせてください。〒124-0011東京都葛飾区四つ木4-18-10 ☎03-3695-9276 島袋携帯090-4920-6952
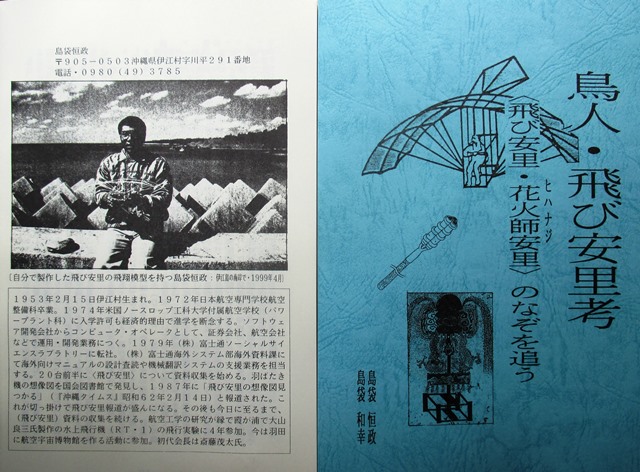
2015年6月 島袋恒政・島袋和幸『鳥人・飛び安里考』大和印刷(電話 03-3862-3236)定価・送料共1000円
発行ー『沖縄の軌跡』発行人・島袋和幸(〒124-0011 葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)
島袋和幸「沖縄の鳥人<飛び安里・花火師>」
沖縄の鳥人<飛び安里・花火師ヒハナジ>は、ことに沖縄では偉人と言われている。それは、約二百年前に<飛行>、つまり空を飛ぶ事について試行錯誤していた可能性があるからだ。その<飛び安里>について、彼が研究したであろう<飛ぶ>という事と、<沖縄の偉人>としてのロマンから、飛び安里について多くの方々が新聞や雑誌。書物などで言及されている。一方マスコミで取り上げられたことも数多いのである。しかし、こうした取り組みの中にあって、決定的な文献が無いとか、実際に飛んだ<飛び安里>とは一体誰なのかとか、又、飛んだ場所等についても諸説があったりで、実際には多くの方々を巻き込んで議論が尽きないのである。
こうした中で島袋恒政氏は、「二百年前の初飛翔/コンピューターで性能解明へ」(『沖縄タイムス』昭和62年2月14日)、「<跳び安里>のロマン再び/資料から模型製作/二百年前に精巧な設計」」(『沖縄タイムス』昭和62年5月10日)という新聞記事になる、<想像図>を国立国会図書館で発見している。それは約30年も前のことで、これ以降、地元新聞紙上や雑誌などで盛んに取り上げられた。その後も、同氏は各種資料や書物に真実を求めて追求してきた。安里家の遺族関係者や、貴重な証言、珍しい資料などが埋もれてしまう前に記録しておきたいという強い思いがある。
私は、約20年前に<飛び安里>研究に緒をつけた『科学画報』の記者、宮里良保について人となりを記録していた。さらに、15年前ほど前から民間航空の始祖である奈良原三次(奈良原繁沖縄県知事の嗣子)についても記録を行っていた。そして、いがいにも沖縄人の飛行機研究者が明治・大正期の早い時期から多かった事を知る。こうした事情等を島袋恒政氏の<飛び安里>についての博識な知識と、資料の記録をお手伝いしたいと思った次第である。
02/04: 新城栄徳「末吉安恭(麦門冬)没90年」研究発表に寄せて」
新城栄徳「末吉安恭(麦門冬)没90年」研究発表に寄せて」
18日の沖縄タイムス文化欄に、沖縄近代史家の伊佐眞一氏が県知事選の結果を読む、として、もはや翁長雄志氏に疑心暗鬼に精力を裂くときではない。基地問題は第2ステージに入っており、自恃(じじ)のウチナーンチュがひとりでも多くなればなるほど、私たちの郷土は真に自立した道を確実に歩めるはずだ、と書いている。
伊佐・比屋根照夫共編『太田朝敷選集』に、東恩納寛惇宛の書簡で太田は「私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云ふより寧(むし)ろ民族的団体と云ふ見地です。国民の頭から民族差別観念を消して仕舞ふことは吾々に取っては頗(すこぶ)る重要な問題だと考へて居ります」と書いているが、この太田の予言は現在の沖縄にも通底する。
このほか、太田選集には俳句や小説、歴史、民俗など近代沖縄文化の幅広い分野で活躍したジャーナリスト、末吉安恭(麦門冬)を追悼して「私が沖縄時事新報社を新設するに当たり君は私の微力なるを思ひ私の請に応じて快く助筆たるを承諾して呉れた(略)琉球社以来の同志も亦、又吉君を始め君を先輩として敬意を表するに吝(やぶさか)ならなかったのである」と載っている。社会運動家の東恩納寛敷も「沖縄タイムス」の追悼文で「波上軒で麦門冬が酔って興に乗じ幸徳秋水の漢詩を戸板一杯に書いた見事な筆蹟であった」と書いている。
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
鎌倉芳太郎は麦門冬から沖縄美術史の手解きを受けたが、後年「大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、(略)またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育った。」(1977年・『国語科通信№36』)と当時を回想している。
末吉安恭を通して近代沖縄の歩みを振り返ることは、現在の私たちの沖縄社会を考え直す契機になる。 (「琉文21」主宰)
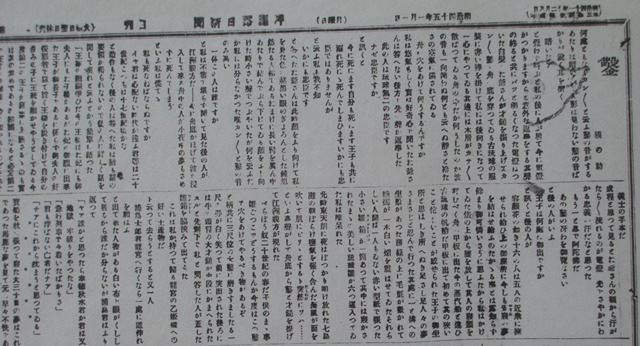
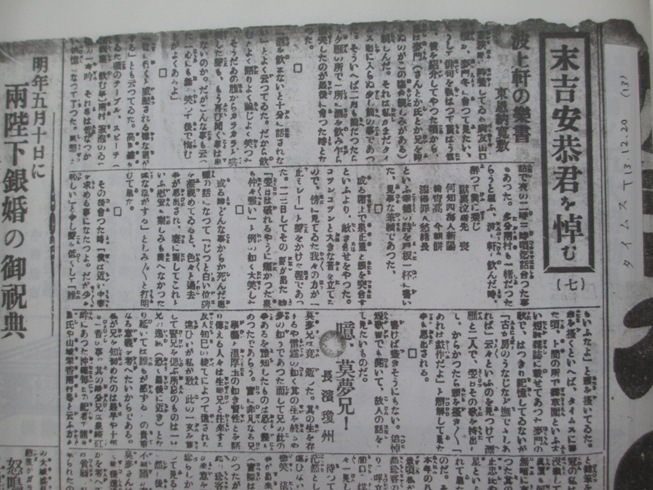
1924年12月20日『沖縄タイムス』東恩納寛敷「末吉安恭君を悼む」
2011年1月ジュンク堂那覇店に行くと大逆事件100年ということで関係書籍が積まれていた。1972年、大阪梅田の古書店で入手したのが『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』であった。幸徳秋水はどういう人物かは知らなかったが写真集といこうことで買った。
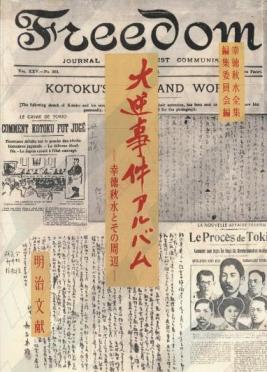
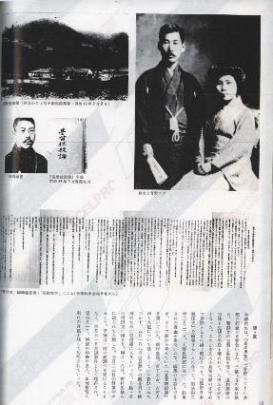
1972年4月ー幸徳秋水全集編集委員会『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』明治文献
1910年6月28日『沖縄毎日新聞』「無政府黨の陰謀」
6月29日『沖縄毎日新聞』「本社発行人(伊舎良平吉)検事の取調べを受ける」
幸徳秋水
生年: 明治4.9.23 (1871.11.5) 没年: 明治44.1.24 (1911)
明治期の社会思想・運動家。高知県中村町の薬種業,酒造業篤明と多治の次男として生まれる。本名は伝次郎で,秋水は師・中江兆民から授かった号である。生後1年たらずで父を失い,維新の社会変動のなか家業も没落し,しかも生来病気がちで満足な教育を受けられなかったことが,秋水をして不平家たらしめ,他面では理想主義に向かわせた。高知県という土地柄もあり,幼くして自由民権思想の影響を受けた。明治21(1888)年より中江兆民のもとに寄寓し,新聞記者となることを目ざし,『自由新聞』『中央新聞』に勤めた。『万朝報』記者時代(1898~1903),社会主義研究会,社会主義協会の会員となり,社会主義者としての宣言を行う。34年5月,日本で最初の社会主義政党である社会民主党の創立者のひとりとして名を連ねた。秋水の著作『社会主義神髄』(1903)は当時の社会主義関係の著書としては最も大きな影響を与えた。36年,日露戦争を前にして戦争反対を唱え,堺利彦と平民社を結成。平和主義,社会主義,民主主義を旗印として週刊『平民新聞』を刊行したが,38年筆禍で5カ月間入獄。出獄後渡米し,権威的社会主義を否定し,クロポトキンなどの影響を受けて無政府共産主義に傾く。39年帰国。43年,説くところの政治的権力と伝統的権威を否定する思想,並びに労働者による直接行動の提唱が,宮下太吉らの明治天皇暗殺計画に結びつけられ,いわゆる大逆事件の首謀者とみなされ,絞首刑に処せられた。<著作>『廿世紀之怪物帝国主義』『基督抹殺論』『幸徳秋水全集』<参考文献>飛鳥井雅道『幸徳秋水』,神崎清『実録幸徳秋水』,大原慧『幸徳秋水の思想と大逆事件』,塩田庄兵衛『幸徳秋水』 (山泉進)□→コトバンク

幸徳秋水の墓ー島袋和幸氏撮影
18日の沖縄タイムス文化欄に、沖縄近代史家の伊佐眞一氏が県知事選の結果を読む、として、もはや翁長雄志氏に疑心暗鬼に精力を裂くときではない。基地問題は第2ステージに入っており、自恃(じじ)のウチナーンチュがひとりでも多くなればなるほど、私たちの郷土は真に自立した道を確実に歩めるはずだ、と書いている。
伊佐・比屋根照夫共編『太田朝敷選集』に、東恩納寛惇宛の書簡で太田は「私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云ふより寧(むし)ろ民族的団体と云ふ見地です。国民の頭から民族差別観念を消して仕舞ふことは吾々に取っては頗(すこぶ)る重要な問題だと考へて居ります」と書いているが、この太田の予言は現在の沖縄にも通底する。
このほか、太田選集には俳句や小説、歴史、民俗など近代沖縄文化の幅広い分野で活躍したジャーナリスト、末吉安恭(麦門冬)を追悼して「私が沖縄時事新報社を新設するに当たり君は私の微力なるを思ひ私の請に応じて快く助筆たるを承諾して呉れた(略)琉球社以来の同志も亦、又吉君を始め君を先輩として敬意を表するに吝(やぶさか)ならなかったのである」と載っている。社会運動家の東恩納寛敷も「沖縄タイムス」の追悼文で「波上軒で麦門冬が酔って興に乗じ幸徳秋水の漢詩を戸板一杯に書いた見事な筆蹟であった」と書いている。
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
鎌倉芳太郎は麦門冬から沖縄美術史の手解きを受けたが、後年「大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、(略)またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育った。」(1977年・『国語科通信№36』)と当時を回想している。
末吉安恭を通して近代沖縄の歩みを振り返ることは、現在の私たちの沖縄社会を考え直す契機になる。 (「琉文21」主宰)
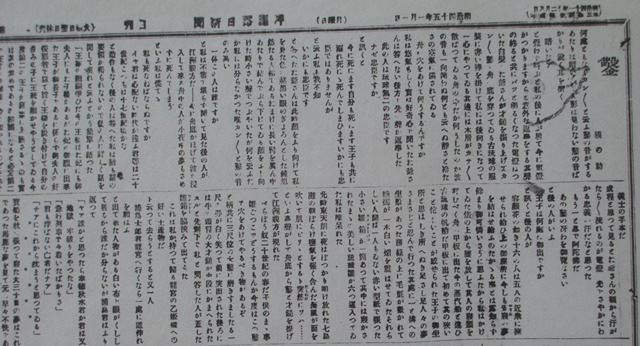
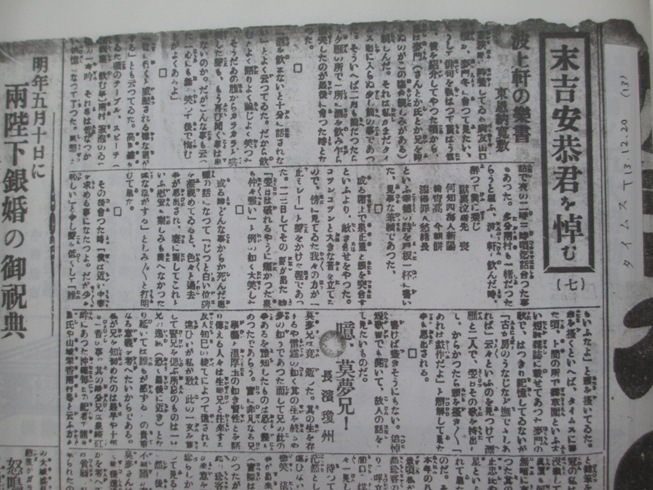
1924年12月20日『沖縄タイムス』東恩納寛敷「末吉安恭君を悼む」
2011年1月ジュンク堂那覇店に行くと大逆事件100年ということで関係書籍が積まれていた。1972年、大阪梅田の古書店で入手したのが『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』であった。幸徳秋水はどういう人物かは知らなかったが写真集といこうことで買った。
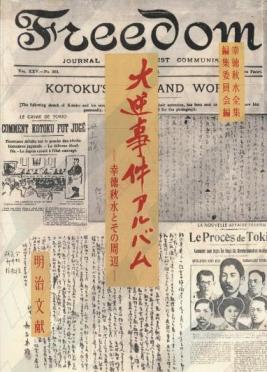
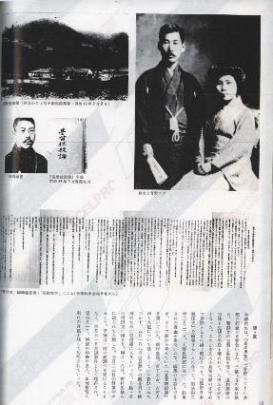
1972年4月ー幸徳秋水全集編集委員会『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』明治文献
1910年6月28日『沖縄毎日新聞』「無政府黨の陰謀」
6月29日『沖縄毎日新聞』「本社発行人(伊舎良平吉)検事の取調べを受ける」
幸徳秋水
生年: 明治4.9.23 (1871.11.5) 没年: 明治44.1.24 (1911)
明治期の社会思想・運動家。高知県中村町の薬種業,酒造業篤明と多治の次男として生まれる。本名は伝次郎で,秋水は師・中江兆民から授かった号である。生後1年たらずで父を失い,維新の社会変動のなか家業も没落し,しかも生来病気がちで満足な教育を受けられなかったことが,秋水をして不平家たらしめ,他面では理想主義に向かわせた。高知県という土地柄もあり,幼くして自由民権思想の影響を受けた。明治21(1888)年より中江兆民のもとに寄寓し,新聞記者となることを目ざし,『自由新聞』『中央新聞』に勤めた。『万朝報』記者時代(1898~1903),社会主義研究会,社会主義協会の会員となり,社会主義者としての宣言を行う。34年5月,日本で最初の社会主義政党である社会民主党の創立者のひとりとして名を連ねた。秋水の著作『社会主義神髄』(1903)は当時の社会主義関係の著書としては最も大きな影響を与えた。36年,日露戦争を前にして戦争反対を唱え,堺利彦と平民社を結成。平和主義,社会主義,民主主義を旗印として週刊『平民新聞』を刊行したが,38年筆禍で5カ月間入獄。出獄後渡米し,権威的社会主義を否定し,クロポトキンなどの影響を受けて無政府共産主義に傾く。39年帰国。43年,説くところの政治的権力と伝統的権威を否定する思想,並びに労働者による直接行動の提唱が,宮下太吉らの明治天皇暗殺計画に結びつけられ,いわゆる大逆事件の首謀者とみなされ,絞首刑に処せられた。<著作>『廿世紀之怪物帝国主義』『基督抹殺論』『幸徳秋水全集』<参考文献>飛鳥井雅道『幸徳秋水』,神崎清『実録幸徳秋水』,大原慧『幸徳秋水の思想と大逆事件』,塩田庄兵衛『幸徳秋水』 (山泉進)□→コトバンク

幸徳秋水の墓ー島袋和幸氏撮影
04/09: 島袋慶福翁

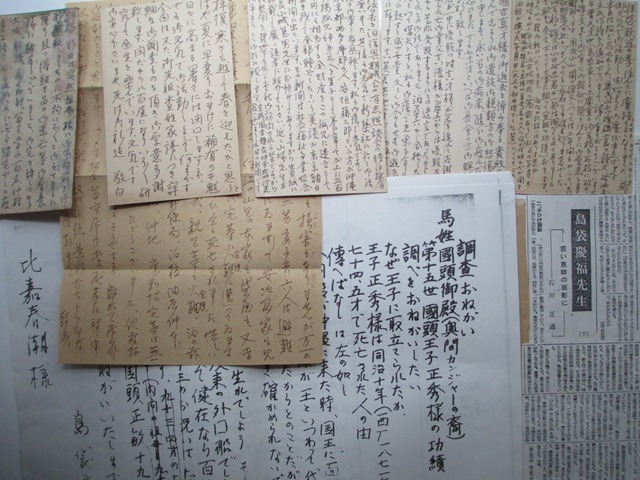
島袋慶福翁の筆跡
□1964年3月23日『琉球新報』石川正通「島袋慶福先生・恩師の若い日の面影ー31歳の陸軍少尉 島袋慶福先生に、明治43年(1910)の一年間、12歳の神村孝太郎、平良宗訓らの同級生といっしょに、愛の教育で、みっちり仕込まれた私たちのいまの、礼儀正しさと姿勢を崩さない端正さは、全く生徒愛の権化 島袋慶福先生のご薫陶の賜物だと種明かしの告白を聞いたら意外に思う人があるかも知れない・・・・」

私と芝居との付き合いは粟国島で生まれた時からで、私の実家の近隣は首里士族の末裔だと称し集まり実家の隣に「首里福原」という集会所を造った。そこでは毎年旧正月に村芝居が上演され、私の父(新城三郎)も一度だけ「金細工」のモーサー役と二才踊りで出演、母方の伯父(玉寄貞夫)は「伊江島ハンドーグヮー」のカナーヒー役で二度も出演したと当時の記録にある。私の9歳のときには伯父が照屋林助、嘉手苅林昌を粟国に連れてきて民謡ショーを開いたという。
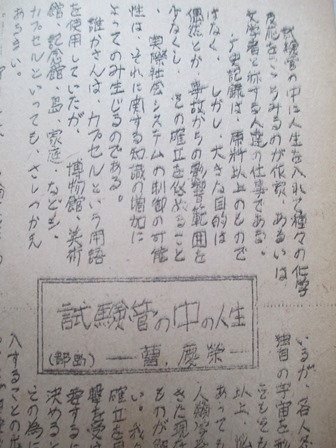
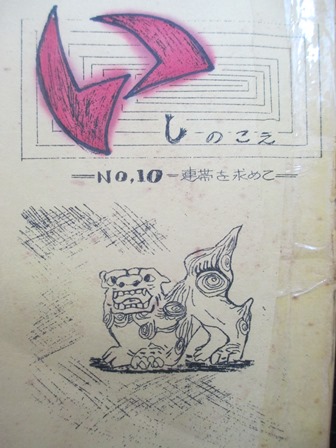
1972年11月 『石の声』№10 曹慶榮(新城栄徳)「試験管の中の人生」
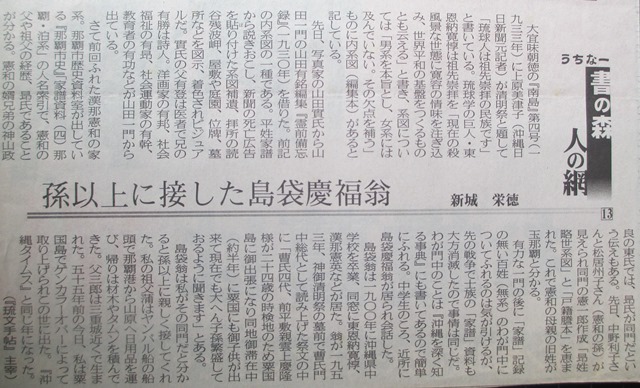
2003年12月27日ー『沖縄タイムス』新城栄徳「うちなー書の森 人の網⑬」孫以上に接した島袋慶福翁
有力な一門の後に「家譜」記録の無い百姓(無系)のわが門中についてふれるのは気が引けるが、先の戦争で士族の「家譜」資料も大方消滅したので事情は同じだ。わが門中のことは『沖縄を深く知る事典』にも書いてあるので簡単にふれる。中学生のころ、近所に島袋慶福翁が居られ会話した。
島袋翁は1900年に沖縄県中学校を卒業、同窓に東恩納寛惇、漢那憲英などが居た。翁が1953年、神御清明祭の墓前で曹氏門中総代として読み上げた祭文の中に「曹氏4代、前平敷親雲上慶隆様が24歳の時検地のため粟国島に御出張になり同地御滞在中(約半年)に粟国にも御子供が出来て現在でも大へん子孫繁盛しておるように聞きます」とある。
島袋翁は私がその同門だと分かると孫以上に親しく接してくれた。私の祖父蒲はヤンバル船の船頭で那覇港から山原へ日用品を運び、帰りは材木やタムンを積んできた。父三郎は三重城近くで生まれた。55年前の今日、私は粟国島でゲンカラーオバーによって取り上げられこの世に出た。『沖縄タイムス』と同じ年になった。
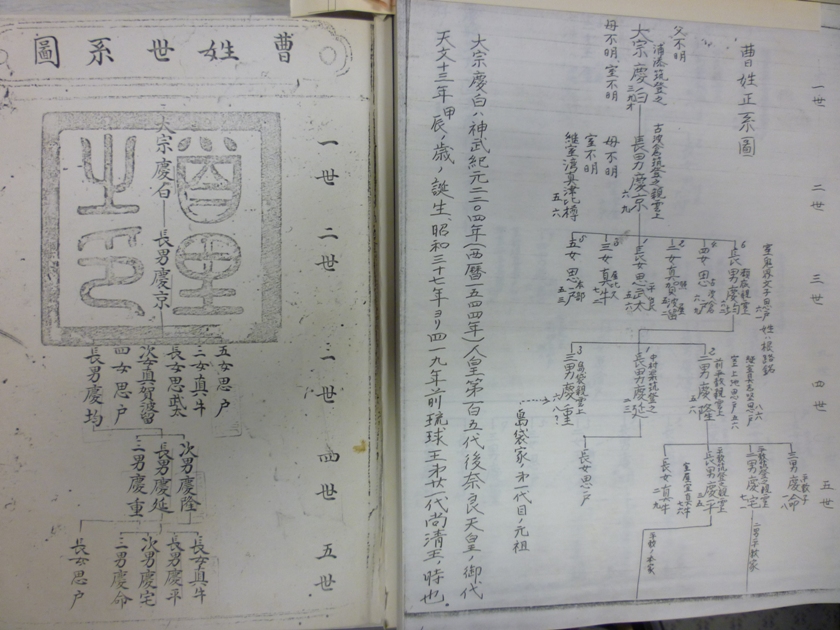
大宗 慶白ー慶京ー慶均ー慶隆
三世 慶均 瀬底親雲上ー1645年 本国中絵図ト為リ薩州ヨリ鬼塚源太左衛門殿 遠武軍介殿 大脇民部左ヱ門殿 簗瀬清右ヱ門殿 渡来ノ時案内者ト為リ東氏当山親雲上政左、李氏長嶺親雲上由恒筆者ト為リテ勤ム
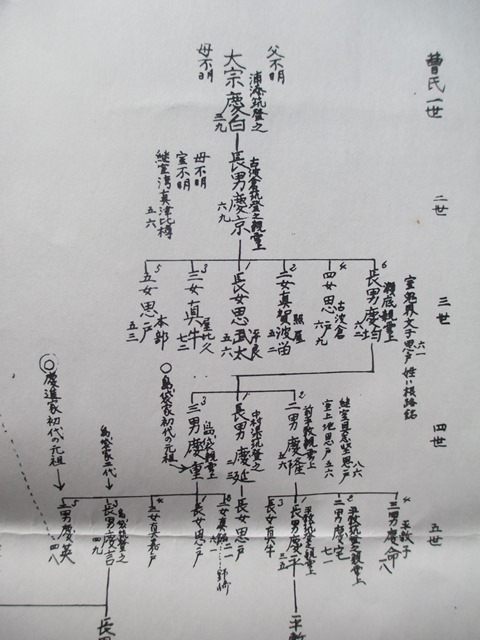
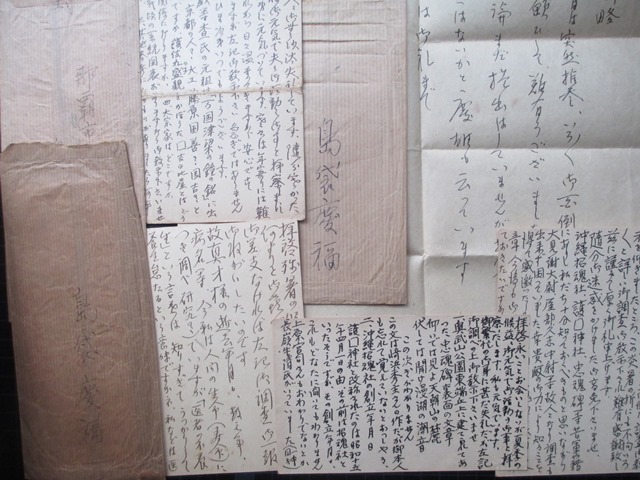
1925年 秋ー????宮城昇、仲泊良夫(白金三光町の明治学院文科の寄宿舎)と伊波文雄(小石川の伊波普猷宅に寄宿)に連れられて中野の山里永吉下宿を訪ねる。仲泊の同級生に仲村渠、渡辺修三、平川泰三、矢島などがいた。またダダイストの辻潤、詩人サトウハチロー、後藤寿夫(林房雄)らと交遊していた。
沖縄/ 1933年7月 『詩誌 闘魚』第貮輯 カット・装・ジュン
仲泊良夫「抽象の魔術ー(略)言語は残酷な死刑執行人である。私は自分の書きたいと思う事を書いていない。脳髄を全部露出することは醜悪なる猿である。創造を現実的に考えることは私には不可能である。凡ての現実は凡ての箴言に過ぎない。私は箴言を信じないように精神を信じない。抽象を精神的に考える人間は浪漫的な猫に過ぎない。抽象は異常なる砂漠の花に等しい。抽象は夢想ではない。私は私の創造に就ては極端に孤独なタングステン電球である。人間の馬鹿げた文學活動それはインク瓶をさげた犬の活動にすぎない。どうして諸兄は対象に向かって本能的批判をするのか。詩人のスタイルは本能の鎖をたちきった時に開くバラである。・・・」
闘魚消息ー 山之口貘氏・通信は東京市本所区東両国4ノ56吉川政雄気付/與儀二郎氏・6月10日出覇/仲泊良夫氏・島尻郡与那原2080/比嘉時君洞氏・6月初め久米島より出覇/泉國夕照氏・5月下旬退院/山里永吉氏・『戯曲集』新星堂書房より近く刊行さる、目下印刷中/國吉眞善氏・第参輯より闘魚同人加盟/イケイ雅氏・病気療養中。
沖縄/1933年9月 『詩誌 闘魚』第参輯 カット・装・ジュン
仲泊良夫「世界の創造ー或ひは観念への革命ー乾燥した時間に於て生誕する救世主/循環する世界それは革命する世界である/透明な詩人の純粋の夢/海底の少女と海底の美少年の戦争」
馬天居士『おらが唄』石敢當社(豊見城高良)ー著者馬天居士氏は、ゴミゴミした都会に住んでいる人ではない。そして世に謂う文藝人ではない。氏はあくまでも土に生きる人であり、野に遊ぶ人である。この”おらが唄〝の一巻を愛誦してみたまえ。俳句あり、川柳あり、短歌あり、そして軍歌あり、更に琵琶歌がある。だがそれらの作品はわれわれに何を考えさせるか。われわれは文藝意識に縛られている自分らのいぢけた存在をふりかえってにるにちがいない。それだけにおらが唄の一巻は、野性的な香りを放ち、自由な奔放さに流れ、また一面には辛辣すぎる皮肉さがある。社会のあらゆる階級的の上に端座したる馬天居士氏の八方睨みの静けさを愛する。
闘魚消息ー 與儀二郎氏・7月御祖母死去謹んで哀悼を表す/ 外山陽彦氏・島尻郡久米島仲里村役場気付/新屋敷幸繁・8月10日帰省。8月28日上鹿/南青海氏・与那原216/宮里靜湖氏・島尻郡久米島仲里校/川野逸歩氏・島尻郡具志川村役場/伊波南哲氏・東京市淀橋区淀橋643/志良堂埋木氏・朝日新聞社主催の文芸懇談会を風月樓にて7月22日開催す/イケイ雅氏・休暇中は中頭郡与那城村字饒邊3へ滞在/山里永吉氏・『山里永吉集』出づ大衆小説「心中した琉球王」文芸春秋社オール読物号8月号へ所載。
沖縄/ 1933年11月 『詩誌 闘魚』第四輯 カット・装・ジュン
闘魚消息ー與儀二郎氏・名護町字名護801山入端方へ転居/宮良高夫氏・現在沖縄日報社内/花城具志氏・闘魚社内気付/外山陽彦氏・土木工事多忙の為休稿/有馬潤氏・菓子店「ひなた屋」開業/原神青醉・歌誌「みちしほ」編輯せる氏は同誌一周年紀念号発刊に際し原神青醉歌集を近刊/山里永吉氏・「永吉集」好評。9月上旬 幸楽亭に於いて刊行祝賀会。出席者50名盛況
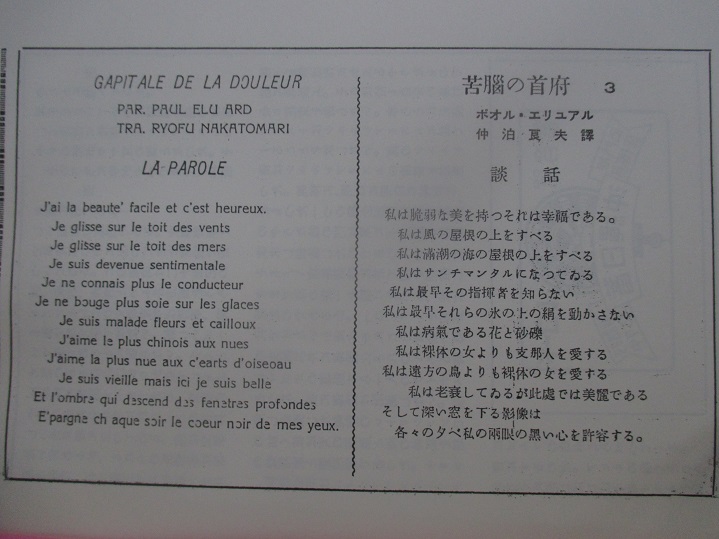
1936年5月『沖縄教育』第237号 仲泊良夫 訳「苦悩の首府」

写真1935年頃辻ー後列右からー山里永吉、仲泊良夫 前列中央が松田枕流(賀哲の弟)
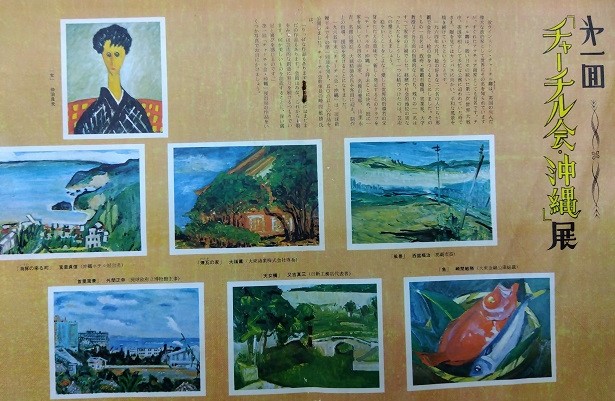
沖縄/ 1933年7月 『詩誌 闘魚』第貮輯 カット・装・ジュン
仲泊良夫「抽象の魔術ー(略)言語は残酷な死刑執行人である。私は自分の書きたいと思う事を書いていない。脳髄を全部露出することは醜悪なる猿である。創造を現実的に考えることは私には不可能である。凡ての現実は凡ての箴言に過ぎない。私は箴言を信じないように精神を信じない。抽象を精神的に考える人間は浪漫的な猫に過ぎない。抽象は異常なる砂漠の花に等しい。抽象は夢想ではない。私は私の創造に就ては極端に孤独なタングステン電球である。人間の馬鹿げた文學活動それはインク瓶をさげた犬の活動にすぎない。どうして諸兄は対象に向かって本能的批判をするのか。詩人のスタイルは本能の鎖をたちきった時に開くバラである。・・・」
闘魚消息ー 山之口貘氏・通信は東京市本所区東両国4ノ56吉川政雄気付/與儀二郎氏・6月10日出覇/仲泊良夫氏・島尻郡与那原2080/比嘉時君洞氏・6月初め久米島より出覇/泉國夕照氏・5月下旬退院/山里永吉氏・『戯曲集』新星堂書房より近く刊行さる、目下印刷中/國吉眞善氏・第参輯より闘魚同人加盟/イケイ雅氏・病気療養中。
沖縄/1933年9月 『詩誌 闘魚』第参輯 カット・装・ジュン
仲泊良夫「世界の創造ー或ひは観念への革命ー乾燥した時間に於て生誕する救世主/循環する世界それは革命する世界である/透明な詩人の純粋の夢/海底の少女と海底の美少年の戦争」
馬天居士『おらが唄』石敢當社(豊見城高良)ー著者馬天居士氏は、ゴミゴミした都会に住んでいる人ではない。そして世に謂う文藝人ではない。氏はあくまでも土に生きる人であり、野に遊ぶ人である。この”おらが唄〝の一巻を愛誦してみたまえ。俳句あり、川柳あり、短歌あり、そして軍歌あり、更に琵琶歌がある。だがそれらの作品はわれわれに何を考えさせるか。われわれは文藝意識に縛られている自分らのいぢけた存在をふりかえってにるにちがいない。それだけにおらが唄の一巻は、野性的な香りを放ち、自由な奔放さに流れ、また一面には辛辣すぎる皮肉さがある。社会のあらゆる階級的の上に端座したる馬天居士氏の八方睨みの静けさを愛する。
闘魚消息ー 與儀二郎氏・7月御祖母死去謹んで哀悼を表す/ 外山陽彦氏・島尻郡久米島仲里村役場気付/新屋敷幸繁・8月10日帰省。8月28日上鹿/南青海氏・与那原216/宮里靜湖氏・島尻郡久米島仲里校/川野逸歩氏・島尻郡具志川村役場/伊波南哲氏・東京市淀橋区淀橋643/志良堂埋木氏・朝日新聞社主催の文芸懇談会を風月樓にて7月22日開催す/イケイ雅氏・休暇中は中頭郡与那城村字饒邊3へ滞在/山里永吉氏・『山里永吉集』出づ大衆小説「心中した琉球王」文芸春秋社オール読物号8月号へ所載。
沖縄/ 1933年11月 『詩誌 闘魚』第四輯 カット・装・ジュン
闘魚消息ー與儀二郎氏・名護町字名護801山入端方へ転居/宮良高夫氏・現在沖縄日報社内/花城具志氏・闘魚社内気付/外山陽彦氏・土木工事多忙の為休稿/有馬潤氏・菓子店「ひなた屋」開業/原神青醉・歌誌「みちしほ」編輯せる氏は同誌一周年紀念号発刊に際し原神青醉歌集を近刊/山里永吉氏・「永吉集」好評。9月上旬 幸楽亭に於いて刊行祝賀会。出席者50名盛況
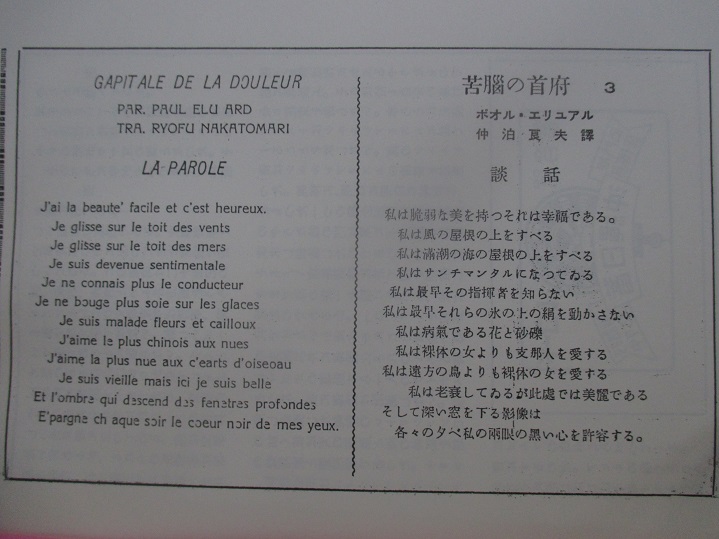
1936年5月『沖縄教育』第237号 仲泊良夫 訳「苦悩の首府」

写真1935年頃辻ー後列右からー山里永吉、仲泊良夫 前列中央が松田枕流(賀哲の弟)
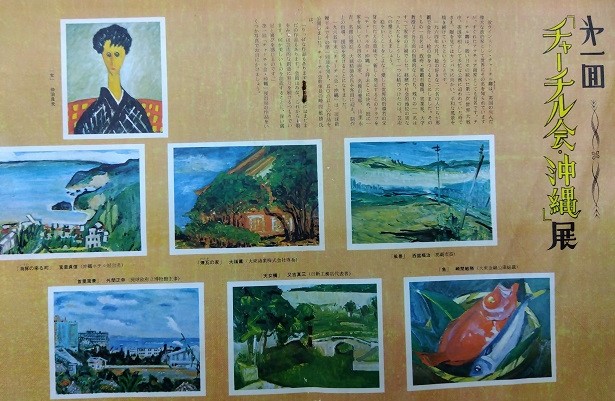
04/22: 2002年8月 谷沢永一『書物耽溺 』講談社
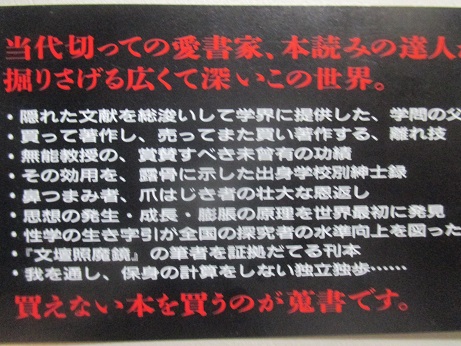
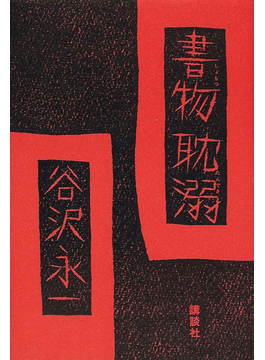
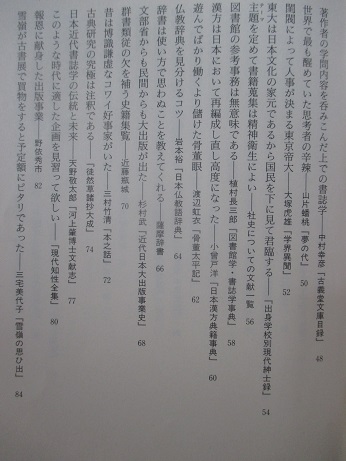
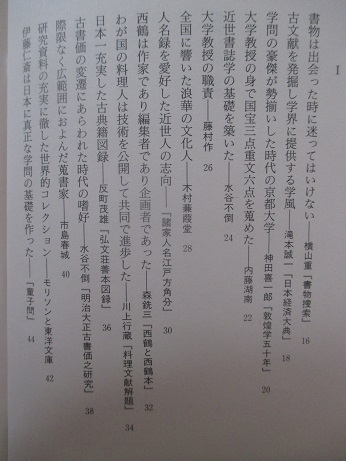
〇書物は出会った時に迷ってはいけないー横山重『書物捜索』「六 富士の人穴」「本地物あれこれ」
☆富士の人穴:麦門冬も「富士の人穴草紙」を見ている。
☆本地物:御伽草子(おとぎぞうし)における、社寺の神仏の由来縁起を人間の物語として語る作品群の総称。その形式は経典類に載る本生譚(ほんしょうたん)・前生譚(ジャータカ)に似ている。本地垂迹(すいじゃく)説や和光同塵(どうじん)の宗教理念に支えられたもので、説経節(説経浄瑠璃(じょうるり))や古浄瑠璃にもよくみられる物語構造である。その先蹤(せんしょう)的なものは南北朝期の『神道集(しんとうしゅう)』所収の縁起物語にみられ、室町時代には多数の作品が生まれた。前代までの物語にはなかった形式のもので、御伽草子の代表的世界といってよく、また神仏の始源を宗教的、信仰的に物語るという意味で、古代神話の形態の中世的復活ともみなしうる物語類である。通常はその作品名に「本地」の語を付しているが、これに従わぬものもある。在地的な説話や民間伝承の諸モチーフを巧みに結合させたロマンあふれるものが多い。作品には『熊野の本地』『厳島(いつくしま)の本地』『阿弥陀(あみだ)の本地』『月日の本地』『七夕(たなばた)の本地』『竹生島(ちくぶじま)の本地』『天神の本地』『伊豆箱根の本地』『毘沙門(びしゃもん)の本地』『梵天国(ぼんてんごく)』『貴船(きぶね)の本地』『諏訪(すわ)の本地』などがあり、『浦島太郎』『物くさ太郎』なども末尾は本地物の形になっている。[徳田和夫]
古文献を発掘し学界に提供する学風ー滝本誠一『日本経済大典』/学問の豪傑が勢揃いした時代の京都大学ー神田喜一郎『敦煌学五十年』/大学教授の身で国宝三点重文六点を蒐めたー内藤湖南/近世書誌学の基礎を築いたー水谷不倒/大学教授の職責ー藤村作/全国に響いた浪華の文化人ー木村蒹葭堂/人名録を愛好した近世人の志向ー諸家人名江戸方角分/西鶴は作家であり編集者であり企画者であったー森銑三『西鶴と西鶴本』/わが国の料理人は技術を公開して共同で進歩したー川上行蔵『料理文献解題』
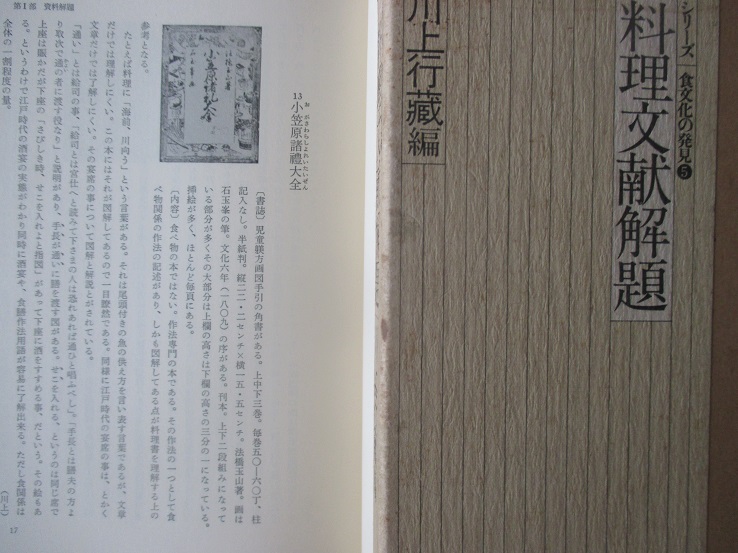
1978年1月 河上行蔵『料理文献解題』柴田書店
日本一充実した古典籍図録ー反町茂雄『弘文荘善本図録』/古書価の変遷にあらわれた時代の嗜好ー水谷不倒『明治大正古書価之研究』/際限なく広範囲におよんだ蒐書家ー市島春城/研究資料の充実に徹した世界的コレクションーモリソンと東洋文庫/伊藤仁斎は日本に真正な学問の基礎を作ったー『童子間』/著作者の学問内容を呑みこんだ上での書誌学ー中村幸彦『古義堂文庫目録』/世界で最も醒めていた思考者の辛辣ー山片蟠桃『夢の代』/閨閥によって人事が決まる東京帝大ー大塚虎雄『学界異聞』/東大は日本文化の家元であるから国民を下に見て君臨するー『出身学校別現代紳士録』/主題を定めて書籍蒐集は精神衛生によいー社史についての文献一覧/図書館の参考事務は無意味であるー植村長三郎『図書館学・書誌学事典』/漢方は日本において再編成し直し高度になったー小曾戸洋『日本漢方典籍辞典』/遊んでばかり働くより儲けた骨董眼ー渡辺虹衣『骨董太平記』/仏教辞典を見分けるコツー岩本裕『日本仏教語辞典』/辞書は使い方で思わぬことを教えてくれるー薩摩辞書/文部省からも民間からも大出版が出たー杉村武『近代日本大出版事業史』/群書類従の欠を補う史籍集覧ー近藤瓶城/昔は博識謙虚なコワイ好事家がいたー三村竹清『本之話』/古典研究の究極は注釈であるー『徒然草諸抄大成』/日本近代書誌学の伝統と未来ー天野敬太郎『河上肇博士文献志』/このような時代に適した企画を見習って欲しいー『現代知性全集』/報恩に献身した出版事業ー野依秀市/雪嶺が古書展で買物をすると予定額にピタリであったー三宅美代子『雪嶺の思ひ出』
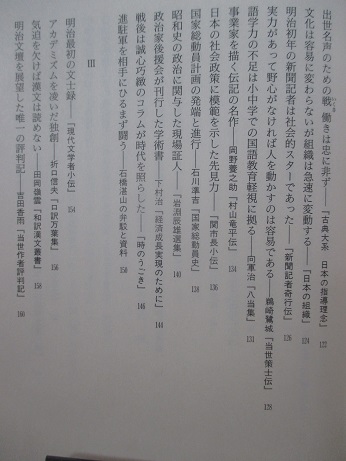
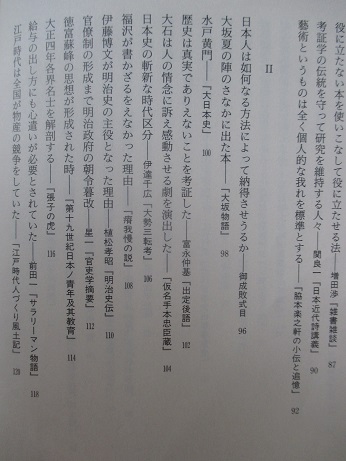
〇役に立たない本を使いこなして役に立たせる法ー増田渉『雑書雑談』/考証学の伝統を守って研究を維持する人々ー関良一『日本近代詩講義』/藝術というものは全く個人的な我れを標準とするー『脇本楽之軒の小伝と追憶』/日本人は如何なる方法によって納得させうるかー御成敗式目/大坂夏の陣のさなかに出た本ー『大坂物語』/水戸黄門ー『大日本史』/歴史は真実でありえないことを考証したー富永仲基『出定後語』/大石は人の情念に訴え感動させる劇を演出したー『仮名手本忠臣蔵』/日本史の斬新な時代区分ー伊達千広『大勢三転考』/福沢が書かざるをえなかった理由ー『瘦我慢の説』/伊藤博文が明治史の主役となった理由ー植松孝昭『明治史伝』/官僚制の形成まで明治政府の朝令暮改-星一『官吏学摘要』/徳富蘇峰の思想が形成された時ー『第十九世紀日本ノ青年及其教育』/大正四年各界名士を解剖するー『張子の虎』/給与の出し方にも心遣いが必要とされていたー前田一『サラリーマン物語』/江戸時代は全国が物産の競争をしていたー『江戸時代人づくり風土記』/出世名声のための戦働きは忠に非ずー『古典大系 日本の指導理念』

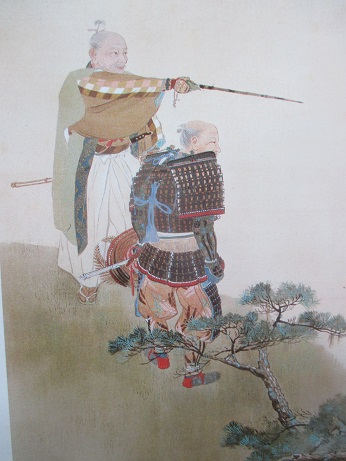
右ー安田靫彦「豊臣秀吉と徳川家康」
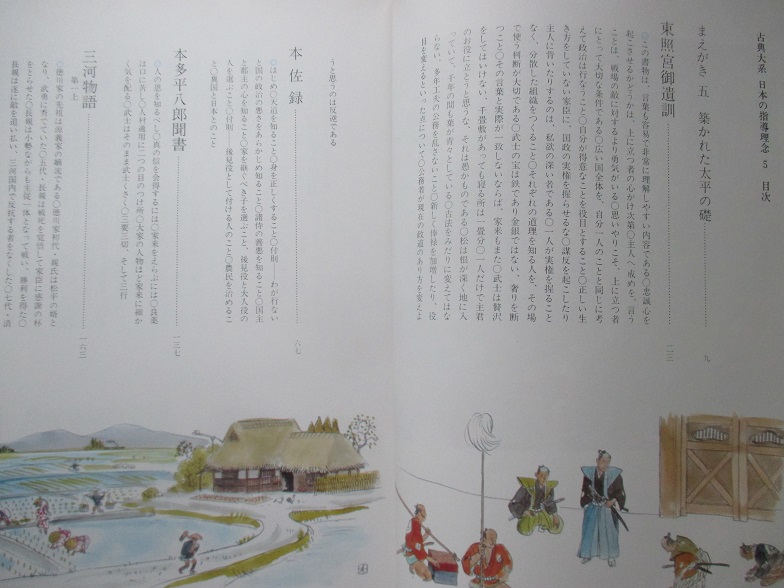
穂積和夫「挿絵」
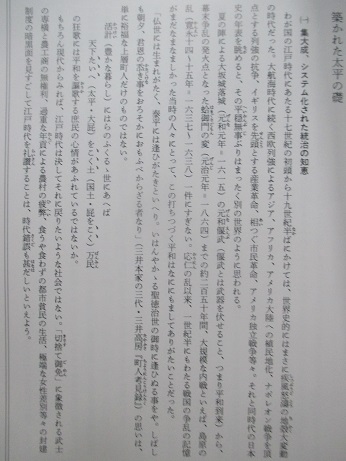

右ー大坂夏の陣に向かう徳川家康
1983年10月『古典体系 日本の指導理念5 創業の初心②築かれた太平の礎』第一法規出版
文化は容易に変わらないが組織は急速に変動するー『日本の組織』金融も生産も激流に乗って構造変化しているのに、官僚帝国だけは、いまだに世襲が行われている現状を、労政協の『天下り白書』があきらかにしている/明治初年の新聞記者は社会的スターであったー『新聞記者奇行伝』/実力があって野心がなければ人を動かすのは容易であるー鵜崎鷺城『当世策士伝』/語学力の不足は小中学での国語教育軽視に拠るー向軍治『八当集』/事業家を描く伝記の名作ー岡野養之助『村山竜平伝』/日本の社会政策に模範を示した先見力ー『関市長小伝』/国家総動員計画の発端と進行ー石川準吉『国家総動員史』/昭和史の政治に関与した現場証人ー『岩淵辰雄選集』/政治家後援会が刊行した学術書ー下村治『経済成長実現のために』/戦後は誠心巧緻のコラムが時代を照らしたー『時のうごき』/進駐軍を相手にひるまず闘うー石橋湛山の弁駁と資料/明治最初の文士録ー『現代文学者小伝』/アカデミズムを凌いだ独創ー折口信夫『口訳万葉集』/気迫を欠けば漢文は読めないー田岡嶺雲『和訳漢文叢書』/明治文壇を展望した唯一の評判記ー吉田香雨『当世作者評判記』
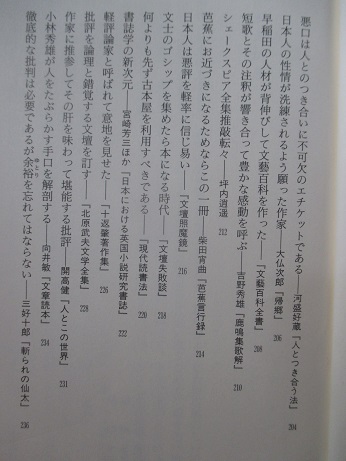
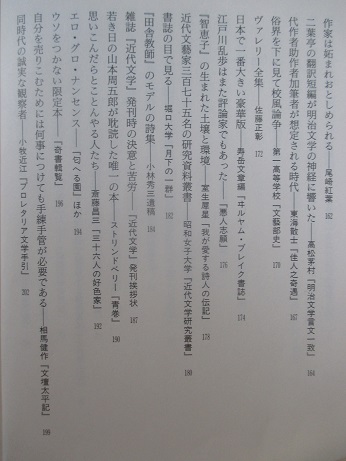
〇作家は妬まれおとしめられるー尾崎紅葉/二葉亭の翻訳短篇が明治文学の神経に響いたー高松茅村『明治文学言文一致』/代作者助作者加筆者が想定される時代ー東海散士『佳人之奇遇』/俗界を下に見て校風論争ー第一高等学校『文藝部』/ヴァレリー全集ー佐藤正昭/日本で一番大きい豪華版ー寿岳文章編『ヰルヤム・ブレイク書誌』天野敬太郎は昭和22年という早い時期に、「目録の時代を経て今や索引の時代に進んでいる」と喝破した。その索引も人名や書名に非ず、事項索引でなければならぬのである/江戸川乱歩はまた評論家でもあったー『悪人志願』/『智恵子』の生まれた土壌と環境ー室生犀星『我が愛する詩人の伝記』/近代文藝家三百七十五名の研究資料叢書ー昭和女子大学『近代文学研究叢書』/書誌の目で見るー堀口大学『月下の一群』/『田舎教師』のモデルの詩集ー小林秀三遺稿/雑誌『近代文学』発刊時の決意と苦労ー『近代文学』発刊挨拶状/若き日の山本周五郎が耽読した唯一の本ーストリンドベリー『青巻』/思いこんだらとことんやる人たちー斎藤昌三『三十六人の好色家』/エロ・グロ・ナンセンスー『匂へる園』ほか/ウソをつかない限定本ー集古洞人編『奇書輯覧』/自分を売りこむためには何事につけても手練手管が必要であるー相馬健作『文壇太平記』/同時代の誠実な観察者ー小牧近江『プロレタリア文学手引』/悪口は人とのつき合いに不可欠のエチケットであるー河盛好蔵『人とつき合う法』/日本人の性情が洗練されるよう願った作家ー大仏次郎『帰郷』/早稲田の人材が背伸びして文藝百科を作ったー『文藝百科全書』/短歌とその注釈が響き合って豊かな感動を呼ぶー吉野秀雄『鹿鳴集歌解』/シェークスピア全集推敲転々ー坪内逍遥/芭蕉にお近づきになるためならこの一冊ー柴田宵曲『芭蕉言行録』/日本人は悪評を軽率に信じ易いー田口掬汀『文壇照魔境』/文士のゴジップを集めたら本になる時代ー『文壇失敗談』/何よりも先ず古本屋を利用すべきであるー田中菊雄『現代読書法』カズオ書店、津田喜代獅、天牛書店の尾上政太郎、広島の黒木書店が元町へ/書誌学の新次元ー宮崎芳三ほか『日本における英国小説研究書誌』/軽評論家と呼ばれて意地を見せたー『十返肇著作集』/批評を論理と錯覚する文壇を訂すー『北原武夫文学全集』/作家に推参してその肝を味わって堪能する批評ー開高健『人とこの世界』/小林秀雄が人をたぶらかす手口を解剖するー向井敏『文章読本』/徹底的な批判は必要であるが余裕を忘れてはならないー三好十郎『斬られの仙太』
谷沢永一『書物耽溺 』(講談社) 2002/08
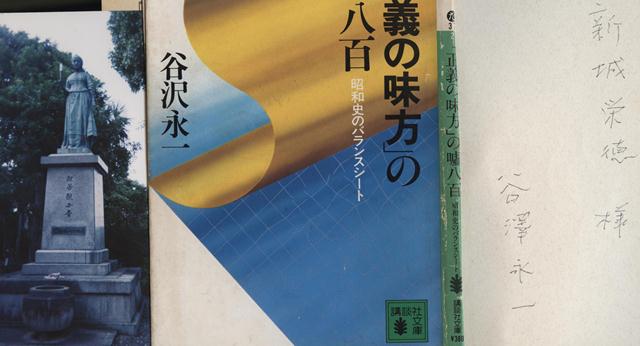

2004年6月30日ー川西能勢口駅から蔵書家・谷沢永一氏の自宅に行く。沖縄から来たということで何か警戒されていたようで話をすると快くサインしてくれた。近くにフローレンス ナイチンゲール(救苦観世音)像がある。
1994年3月 谷沢永一『大国・日本の「正体」』講談社〇芥川龍之介が『レーニン』という題で、「最も民衆を愛した君は、最も民衆を軽蔑した君だ」という詩のようなものを遺している。これは芥川ならではの名文句で、「知的傲慢さ」というものは、日本の風土に合わないようだ。(略)抽象的な理念だけに閉じこもっている日本においてだけ、社会党と共産党はごく小人数残るだろう。もっと言わせてもらえば日本の社会党・共産党は恐らく最後に「世界の珍品」として日本に残るのではないか。
谷沢永一 たにざわ-えいいち
1929-2011 昭和後期-平成時代の書誌学者,文芸評論家。
昭和4年6月27日生まれ。関西大在学中から同人雑誌「えんぴつ」を主宰し,開高健(たけし),向井敏(さとし)らと知りあう。昭和44年から平成3年まで母校の教授。近代文学の分析と論評,書誌研究で知られ,昭和55年「完本―紙つぶて」でサントリー学芸賞。平成16年「文豪たちの大喧嘩」で読売文学賞。平成23年3月8日死去。81歳。大阪出身。著作はほかに「谷沢永一書誌学研叢」「書物耽溺」など。(→コトバンク)
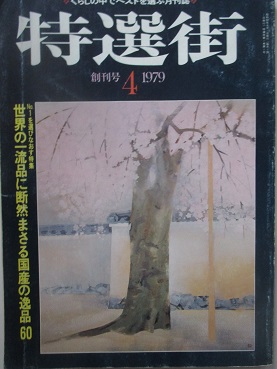
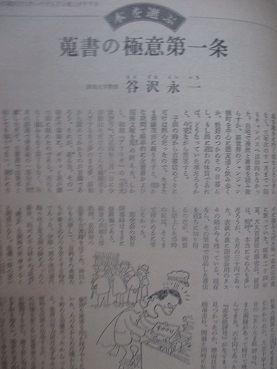
1979年4月『特選街』4月創刊号 谷沢永一「蒐書の極意第一条」

御茶ノ水駅



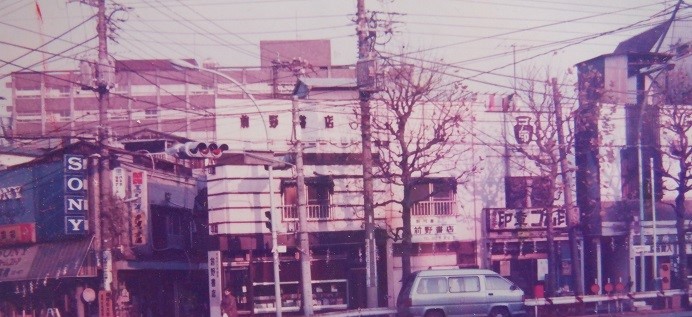
早稲田の古書街
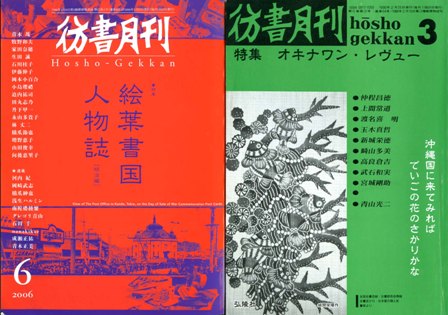
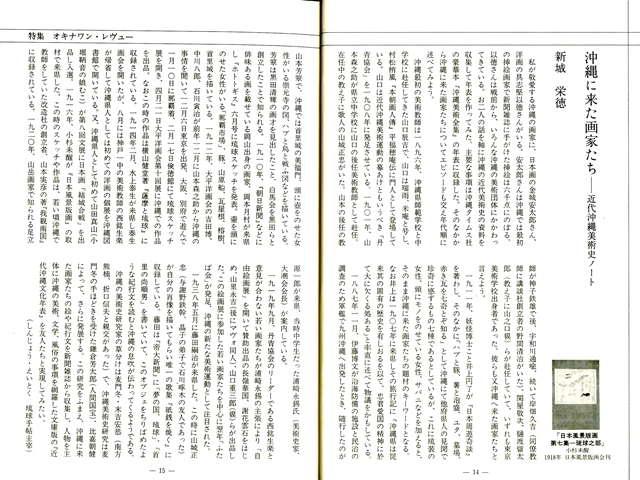
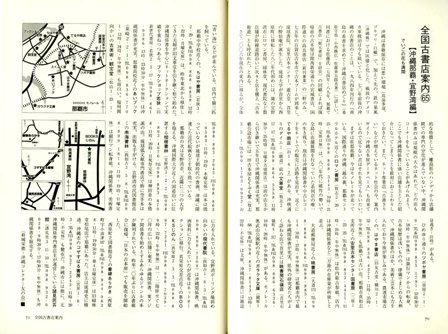
1990年2月『彷書月刊』54号□新城栄徳「沖縄に来た画家たちー(略)沖縄の美術史研究家の草分けは麦門冬・末吉安恭(南方熊楠、折口信夫と親交があった)で、沖縄美術史研究は麦門冬の手ほどきを受けた鎌倉芳太郎(人間国宝)、比嘉朝健によって、さらに発展する。この研究をふまえ、沖縄に来た画家たちの絵や紀行文を新聞雑誌から収集し、人物を主体に沖縄の美術、文学、風俗の事項を網羅した文庫版の『近代沖縄文化年表』を友人たちと実現してみたい。」/この文化年表は下記のように『琉文手帖』4号として1999年5月に発行した。「文人・末吉麦門冬」を補足するものである。/2006年5月『彷書月刊』248号□新城栄徳「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾編」
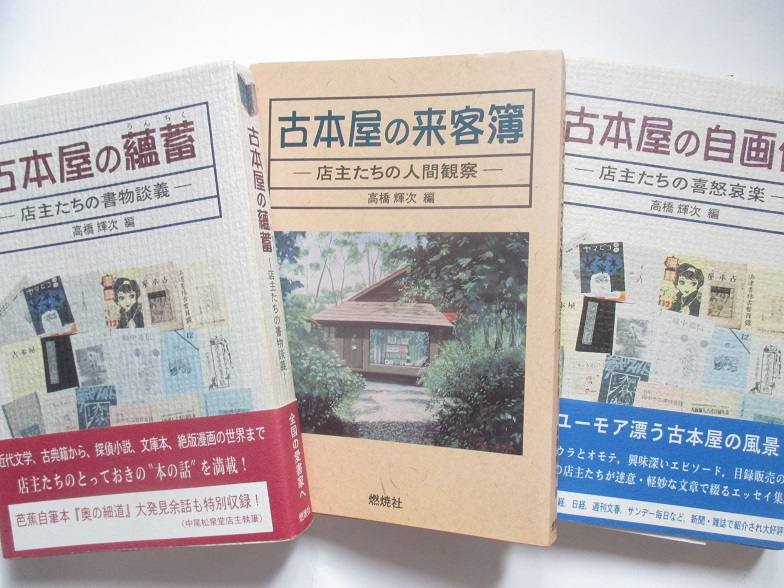
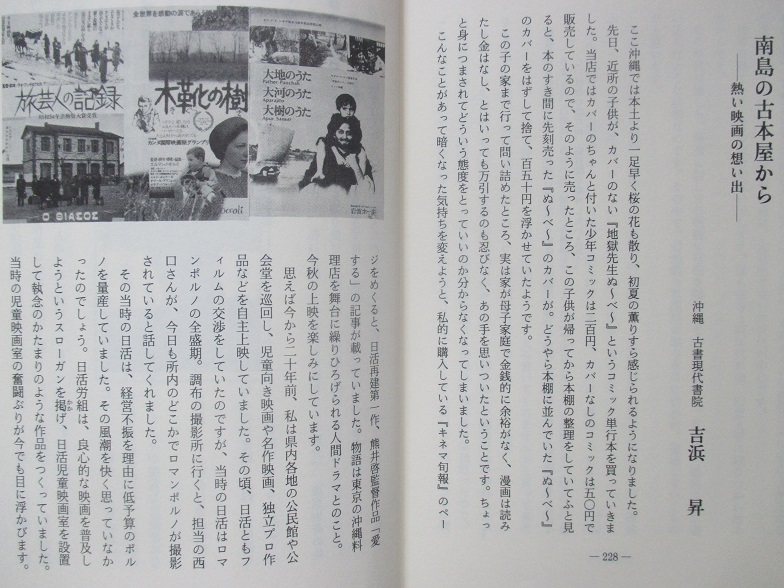
1997年10月 高橋輝次『古本屋の来客簿』燃焼社/吉浜昇「南島の古本屋からー熱い映画の想い出ー」
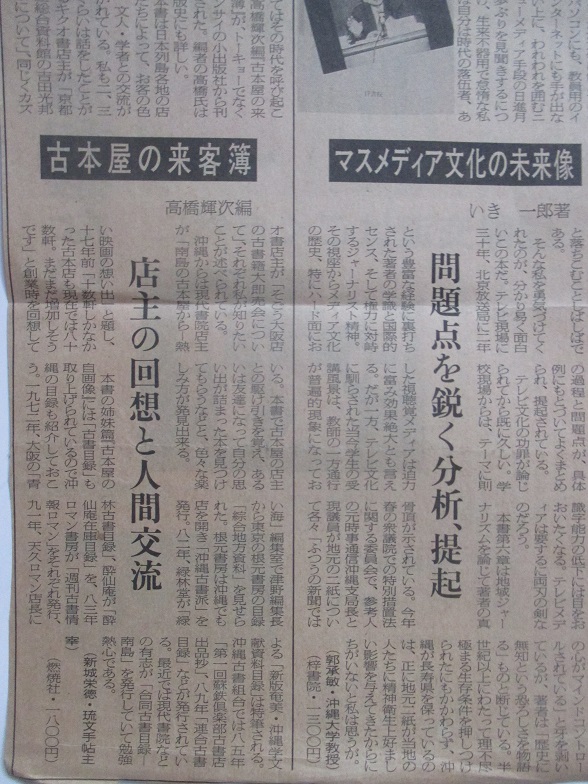
1997年10月26日 『琉球新報』新城栄徳「書評/古本屋の来客簿」/郭承敏「書評/マスメディア文化の未来像」
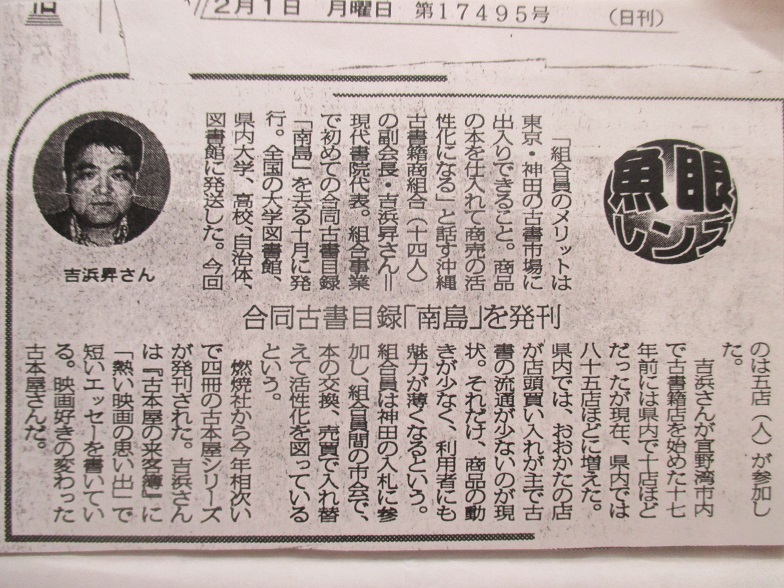
『彷書月刊』(ほうしょげっかん)は、1985年9月に創刊された日本の月刊誌。株式会社彷徨舎から刊行。のち弘隆社より刊行。古書と古書店をテーマにした情報誌で、毎号異なる特集記事、本に関する連載、古書即売会の情報のほか、巻末には数十ページの古書店目録(古書店が売り物を公表するカタログ)が掲載されている。編集長は田村治芳(田村七痴庵)。2010年10月号(300号)をもって休刊した。→ウィキ
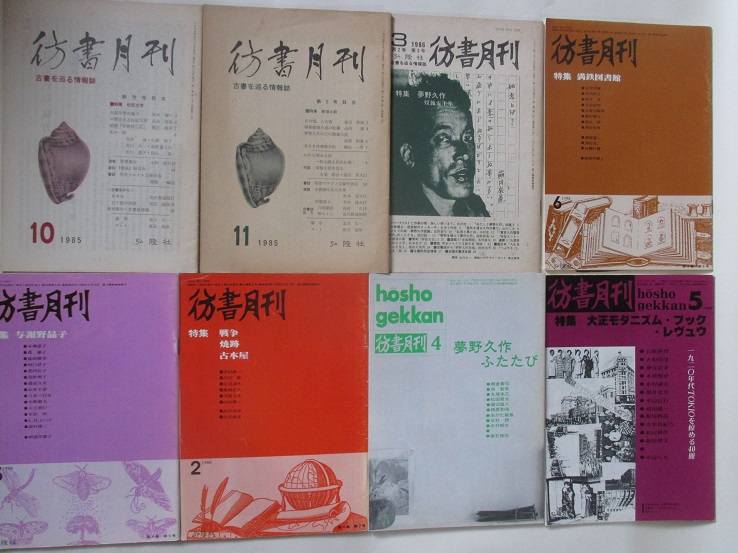
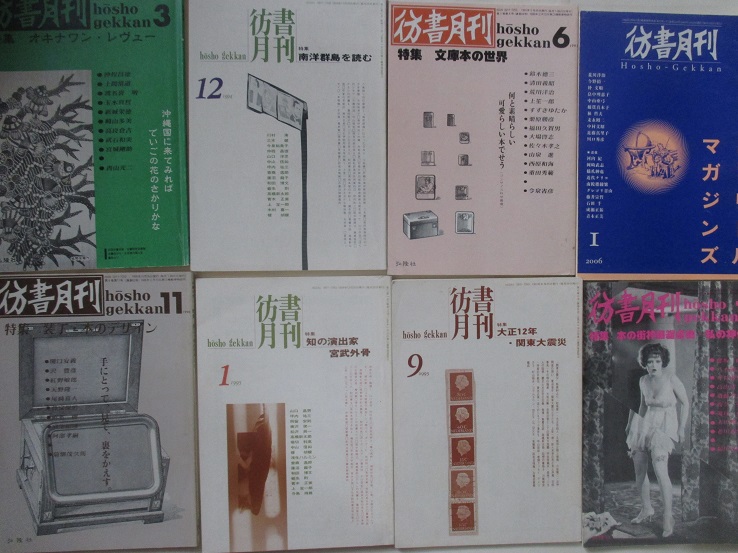
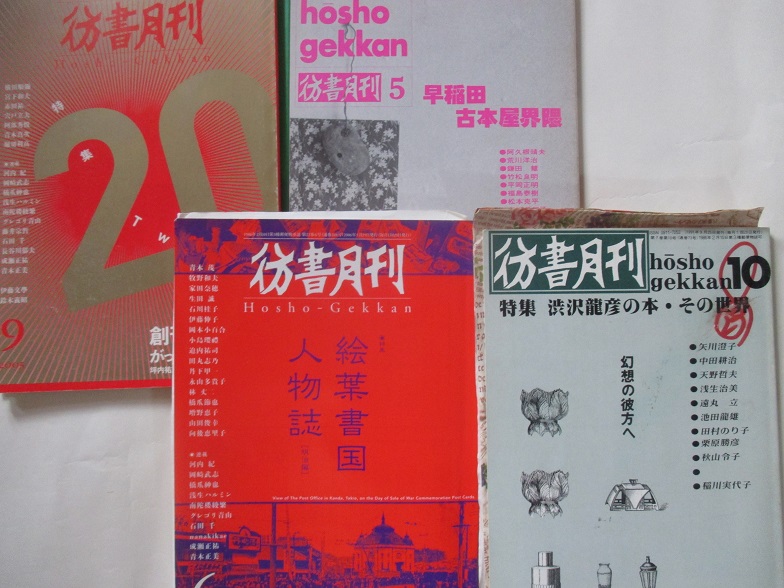
田村治芳、元日に逝く
2011年の元日に、田村治芳が死んだ。享年60。食道がんだった。2日の朝、星谷章くんが電話で知らせてくれた。→源泉館備忘録2011年01月06日
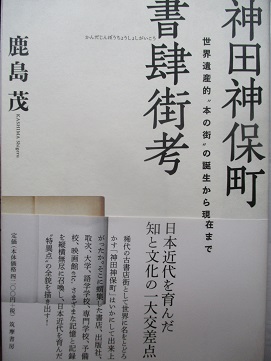
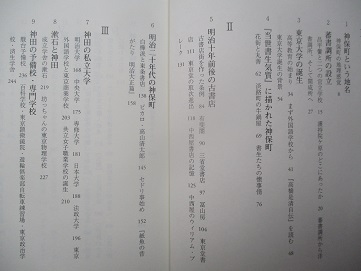
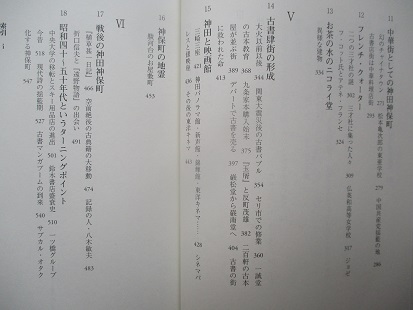
2017年2月 鹿島茂『神田神保町書肆街考-世界遺産的”本の街〟の誕生から現在まで』筑摩書房〇目次ーⅠ・神保町という地名/蕃所調所の設立/東京大学の誕生/『当世書生気質』に描かれた神保町/Ⅱ・明治十年前後の古書店/明治二十年代の神保町/Ⅲ・神田の私立大学/漱石と神田/神田の予備校・専門学校/Ⅳ・神田神保町というトポス/中華街としての神田神保町/フレンチ・クォーター/お茶の水のニコライ堂/Ⅴ・古書肆街の形成/神田と映画館/神保町の地霊/Ⅵ・戦後の神田神保町/昭和四十~五十年代というターニングポイント
◇「学者が去って、オタクがやってきた」私が田村書店洋書部の奥平禎男氏と2001年に月刊誌「東京人」で対談したときの見出しにはたしかにこう書かれていたはずだ。これは果たして、神田神保町の未来を開くことになるのかそれとも閉じることになるのか(略)政府がクール・ジャパンの輸出などと浮かれたことを言っているあいだに、オタクの牙城である神田神保町が崩壊しないとは限らない。杞憂に終わることを祈るのみである。
◇クールジャパンとは、日本の内閣府「クールジャパン戦略のねらい」によると「外国人がクールととらえる日本の魅力」であり、クールジャパンの情報発信・海外展開・インバウンド振興によって世界の成長を取り込み日本の経済成長を実現するブランド戦略「クールジャパン戦略」政策で使われている用語である。 →ウィキペディア
◇青木 正美(あおき まさみ、男性、1933年4月22日 - )は、古書店主、日本近代文学研究者。 東京生まれ。1950年(昭和25年)東京都立上野高等学校定時制課程中退。半年ほど玩具工場に勤務したのち、1953年(昭和28年)東京都葛飾区堀切に古本屋・青木書店 (開業当時の名称は一間堂)を開業する(2008年現在の店主は、青木正一)。 古書店業のかたわら、文筆活動にも精力的に取り組む。神保町の業者中心の「明治古典会」の会員となり、のち会長をつとめた。→ ウィキペディア


「鎌倉芳太郎顕彰碑」甥御さんの鎌倉佳光氏案内/「アートギャラリーかまくら 南米珈琲」鎌倉芳太郎生家(島袋和幸提供)
2014年5月 図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』

沖縄県立博物館・美術館ミュージアムショップ「ゆいむい」電話:098-941-0749 メール:yuimui@bunkanomori.jp
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』 販売価格(税込): 1,620 円

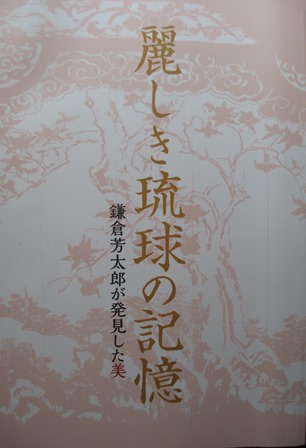
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁く」
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」

高草茂氏と新城栄徳
2015年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所『沖縄芸術の科学』第27号 高草茂「琉球芸術ーその体系的構造抄論」
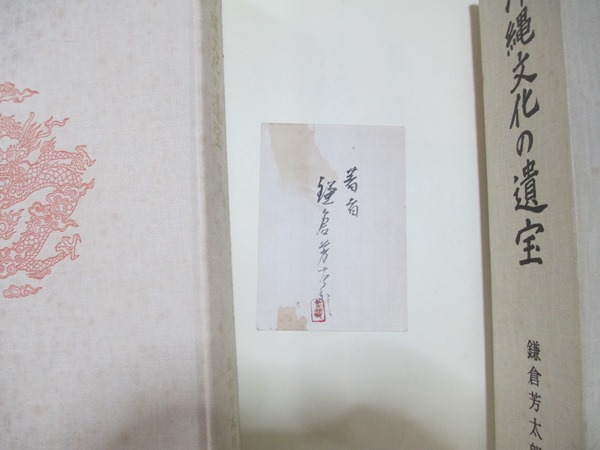
「麗しき琉球の記憶-鎌倉芳太郎が発見した“美”-」関連催事
【日時】5月31日(土)14:00~ 15:30 (開場13:30)
特別講演会/クロストーク
鎌倉芳太郎氏の大著『沖縄文化の遺宝』の編集者である高草茂氏による編集当時のエピソードなどを交えた講演と、「鎌倉ノート」の編集・刊行に携わる波照間永吉氏とのクロストークから、鎌倉氏の沖縄文化に寄せた情熱や思いなどを聞く機会とします。
【講師】高草茂 氏(元岩波書店 顧問)
波照間永吉 氏(沖縄県立芸術大学附属研究所 教授)

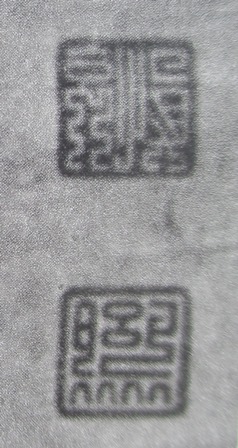
「首里那覇泊全景図」慎思九筆だが印章は慎克熈
沖縄文化工芸研究所□図録の内容を紹介します。
ご遺族や鎌倉自身と交流のあった方、鎌倉資料整理(沖縄県立芸術大学所蔵)に直接に関わった方々が文章を寄せています。記録資料としては将来価値のある図録だと思います。
*波照間永吉「芳太郎収集の沖縄文化関係資料」
*高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」
*佐々木利和「鎌倉芳太郎氏<琉球芸術調査写真>の指定」
*西村貞雄「鎌倉芳太郎がみた琉球の造形文化」
*柳悦州「鎌倉芳太郎が寄贈した紅型資料」
*波照間永吉「古琉球の精神を尋ねてー鎌倉芳太郎の琉球民俗調査ー」
*粟国恭子「鎌倉芳太郎が残した琉球芸術の写真」
*謝花佐和子「鎌倉芳太郎と<沖縄>を取り巻くもの」
*鎌倉秀雄「父の沖縄への思い」
*宮城篤正「回想「50年前の沖縄・写真でみる失われた遺宝」展
*新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁くー」
*三木健「<鎌倉資料>が世に出たころ」
○図版
○年譜
○主要文献等一覧
○写真図版解説
1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」
1893年、京都で平安神宮の地鎮祭が行われ西村捨三が記念祭協賛会を代表し会員への挨拶の中で尚泰侯爵の金毘羅宮参詣時の和歌「海山の広き景色を占め置いて神の心や楽しかるらん」を紹介し、平安神宮建設に尚家から五百圓の寄附があったことも報告された。ちなみに、この時の平安神宮建築技師が伊東忠太。
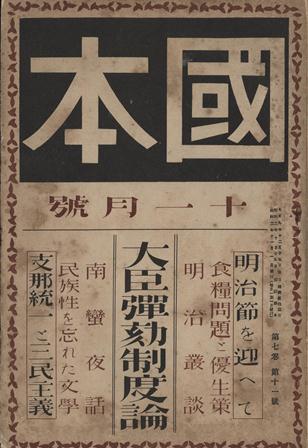
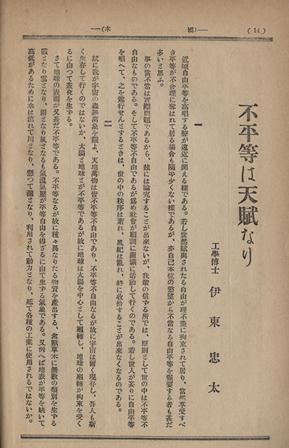
1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」
□翻って考ふれば、宇宙の諸現象は皆不平等、不自由なるが為に生ずるので、一現象毎に一歩づつ平等と自由とに近づくのである。斯くて幾億劫の後には絶対の平等自由が実現されて宇宙は亡びるのである。社会の現象も亦た不平等、不自由の力に由て起こるので、一現象毎に一歩づつ平等自由に近づくのである。斯くて幾万年の後には絶対の平等自由が実現されて社会は滅亡するのである。個人の一生も亦不平等不自由の為に支配せられて活動して居るのである。吾人の一挙一動毎に一歩づつ平等自由に近づくのを以て原則とする。斯くて百年の後絶対の平等自由が得られた時は即ち吾人の死んだ時である。
人は生まれた瞬間より一歩づつ死に向かって進むので、同時に又自由平等に向かって進むのである。絶対の平等自由を強要するのは即ち死を強要する所以である。要するに吾人は各自の職貴を竭して社会文化の向上に貢献すれば善いので社会の安寧秩序を保つべき条件の下に吾人の平等自由が適当に制限さるべきことを認容しなければならぬ。制限なき平等自由は假令之が與えられても吾人は之を受けることを欲せぬものである。何となれば之を與ふる者は悪魔であり、之を受くる者は之が為に身を亡ぼすからである。
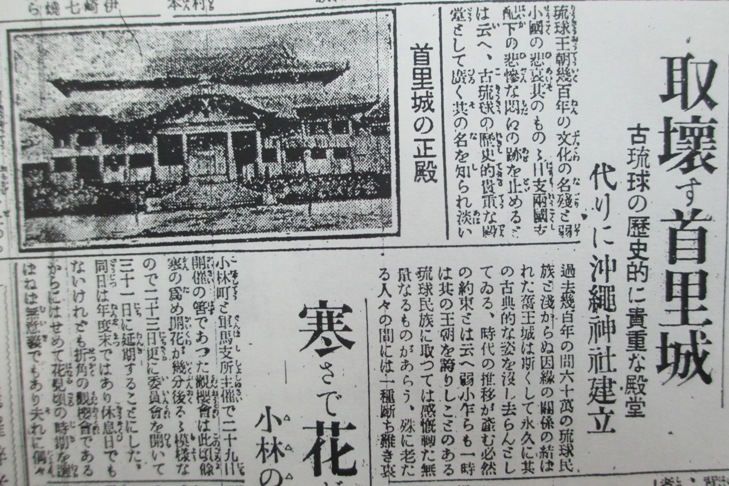
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
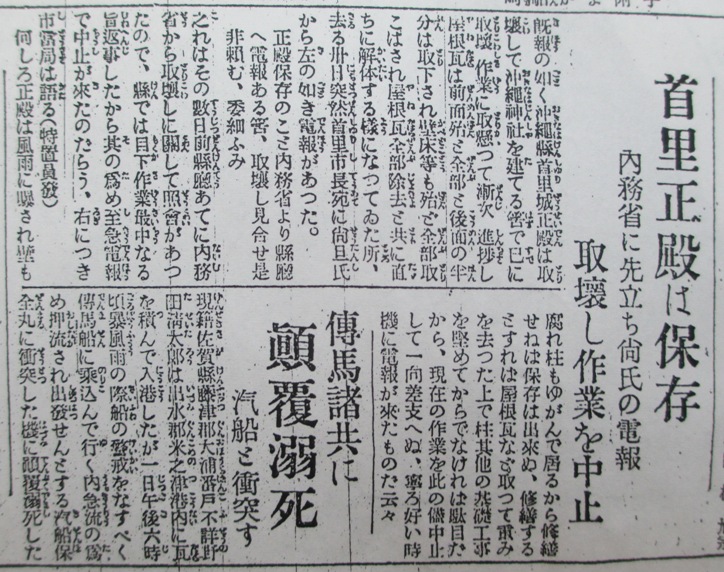
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
1924年
3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。
①『科学知識』「琉球紀行」□余は沖縄到着の第五日目の晩に脚の関節に鈍痛を覚えたので、テッキリやられたと直覚して寝に就いたが、夜半過ぎから疼痛が全身の関節に瀰漫し来り、朝になって見ると起きかえることは愚、寝返りも出来ぬ程の痛さである。(略)兼ねて東京を出発する時、琉球に悪疫の流行して居ることを聞知して居たので、入澤達吉博士に注意事項を問うた処が、博士は若しも沖縄で病気に罹ったら金城医学士の診療を受けるがよいと教えて呉れた。そこで早速同学士の来診を求めた所が、学士は直ちに来て呉れた。一診してこれは軽いデング熱である、2,3日で快癒すると事もなげに断言して呉れたので大いに安心した。(略)金城学士の話によれば、那覇市では殆ど毎戸に患者があって、一家一人も残らず感染した例も珍しくない。那覇6万の人口中、少なくともその三分の二は感染したものと思われるが死者は今の所43人である。夫は何れも嬰児で脳膜炎を併発したのであると云う。余が全治した頃は那覇の方は下火になり、追々田舎の方へ蔓延する模様であった。土地ではこれを「三日熱」と唱えて居る。夫は熱が大抵三日位で去るからである。
8月20日午後3時 大阪商船の安平丸で鹿児島へ。8月22日ー『沖縄タイムス』伊東忠太「琉球を去るに臨みて」。8月25日に東京着□→1925年1月~8月『科学知識』に琉球紀行を連載□1928年5月ー伊東忠太『木片集』萬里閣書房(写真・首里城守礼門)
1925年
1月ー鎌倉芳太郎、沖縄の新聞に啓明会から発行予定の「琉球芸術大観」発表。□(イ)序論ー分布の範囲、遺存の概況、調査物件の項目 (ロ)総論ー史的考察、時代分期
(ハ)各論①建築ー1王宮建築、2廟祠建築、3寺院建築、4住宅建築、5陵墓建築、6橋梁建築 ②琉球本島の部ーイ純止芸術(美術)篇ー1紋様、2絵画、3彫刻 ロ応用芸術(工芸)篇ー1漆工、2陶磁、3織工、4染工、5金工鋳造、6雑工 ③宮古八重山の部 ④奄美大島の部


1925年2月 坂口総一郎『沖縄写真帖』第一輯 画・伊東忠太
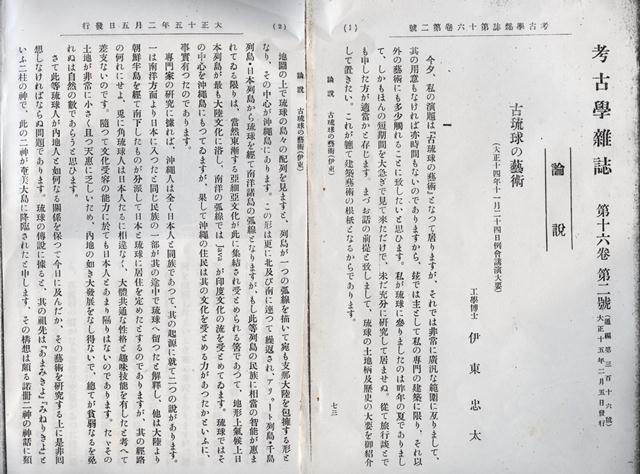
1926年2月『考古学雑誌』第16巻第2号 伊東忠太「古琉球の芸術」
1929(昭和4)年
『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」
□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」
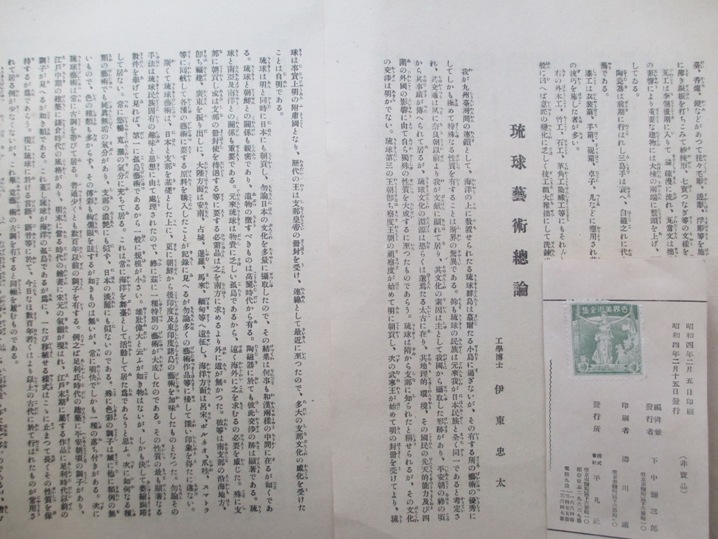
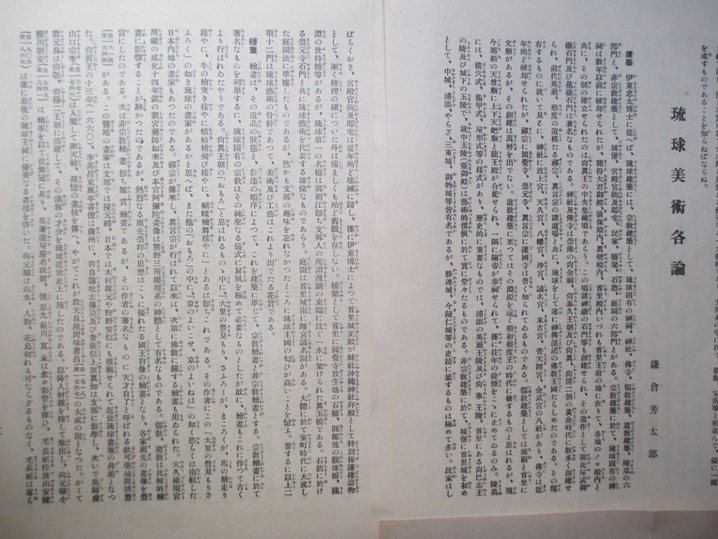
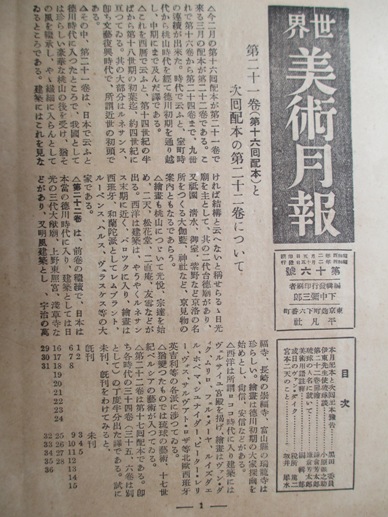
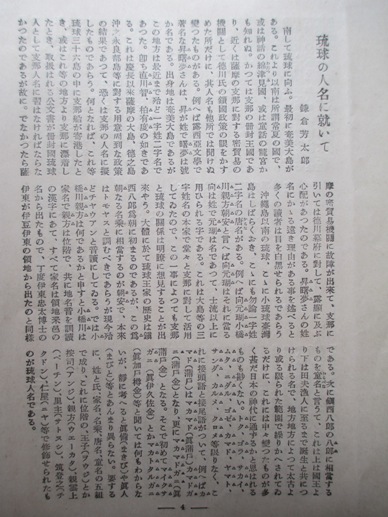
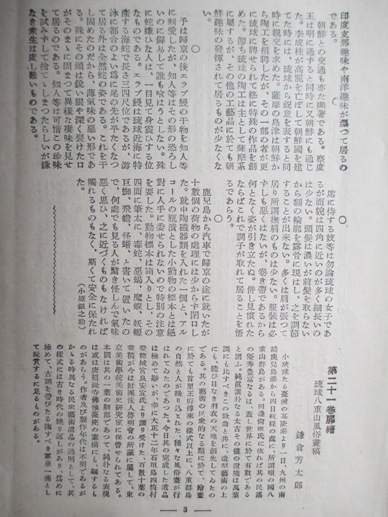
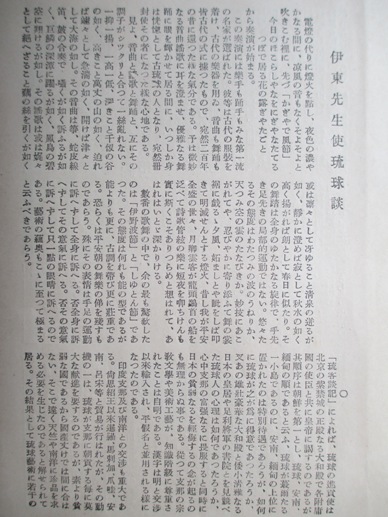
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)
1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社
1929年
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」

3月ー新光社『日本地理風俗体系』第12巻(カラーの守礼門)□伊波普猷「守礼門ー首里府の第一坊門を中山門と言ひ、王城の正門に近い第二坊門を守礼門と言ふ。前者は三山統一時代の創立で、『中山』の扁額を掲げたが、一時代前に毀たれ、後者はそれより一世紀後の創立で、待賢門と称して『首里』の扁額を掲げたが、万暦八年尚永即位の時、明帝の詔勅中より『守礼之邦』の四字を取って『首里』に代えた。以後守礼は首里の代りに用ひられる」
10月ー鎌倉芳太郎・田邊孝次『東洋美術史』玉川学園出版部
2015年1月『月刊琉球』12・1月合併号 <500円+消費税> Ryukyu企画〒901-2226 宜野湾市嘉数4-17-16 ☎098-943-6945 FAX098-943-6947
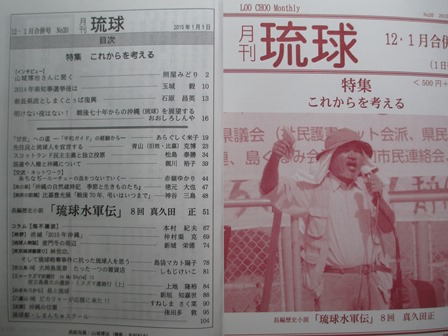
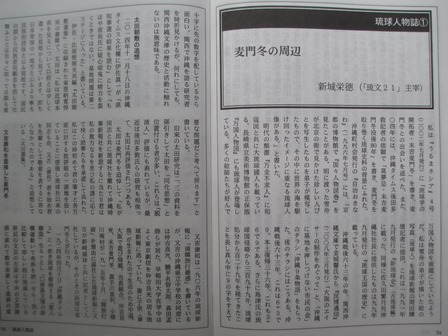
新城栄徳「麦門冬の周辺」
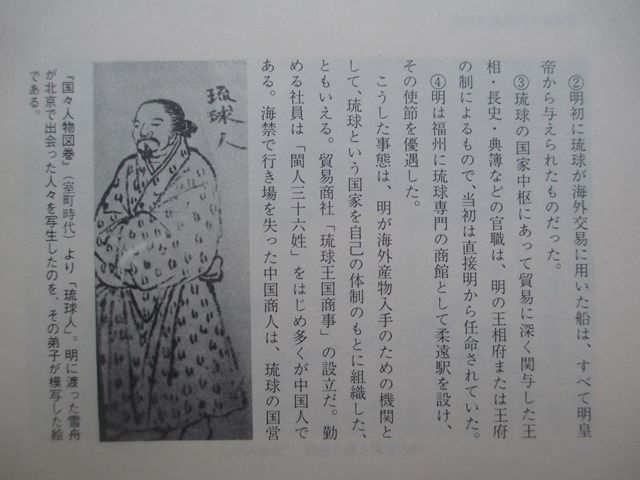
國吉眞哲翁から、そのころ貘と一緒に末吉麦門冬の家に遊びに行った話を伺った。玄関から書斎まで本が積んであって、麦門冬が本を広げている上を鶏が糞を垂れ流しながら走りまわっていたのが印象に残っているとの話であった。思うに貘はそのとき麦門冬の旧号・獏を夢を喰う意味での「獏夢道人」をいくぶん意識に植えつけたのではなかろうか。
又吉康和は一九二三年に『沖縄教育』編集主任になると、麦門冬に「俳句ひかへ帳ー言葉の穿鑿」を書かせている。二五年九月発行『沖縄教育』には、表紙題字を山城正忠に依頼、カット「獅子」を山口重三郎(貘)に依頼し、貘の詩「まひる」「人生と食後」も載せている。編集後記に「山之口貘氏は今般中央の『抒情詩』に日向スケッチ他三篇入選しました之より琉球詩人がどしどし中央の詩壇に出現せんことを念じます。救世者は政治家ではなく、それは詩人と哲人であります」と記して、甥にあたる國吉眞哲と共に上京の旅費を集め貘を東京に送りだしている。
写真上は1925年8月16日、貘2度目の上京前に上左から又吉康和、国吉真哲、国吉真才、一人置いて貘。写真下は貘が戦後帰郷の時。

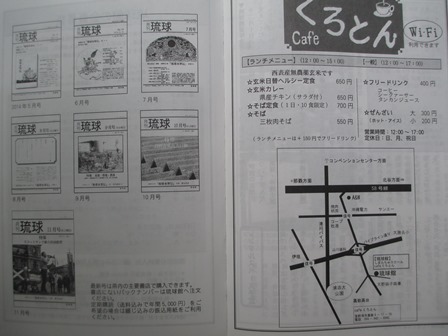
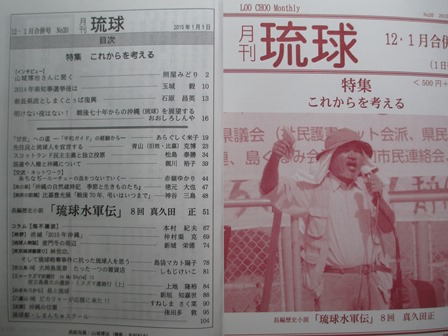
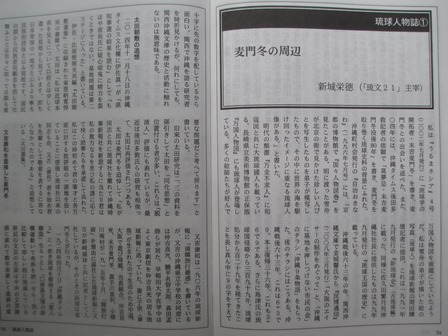
新城栄徳「麦門冬の周辺」
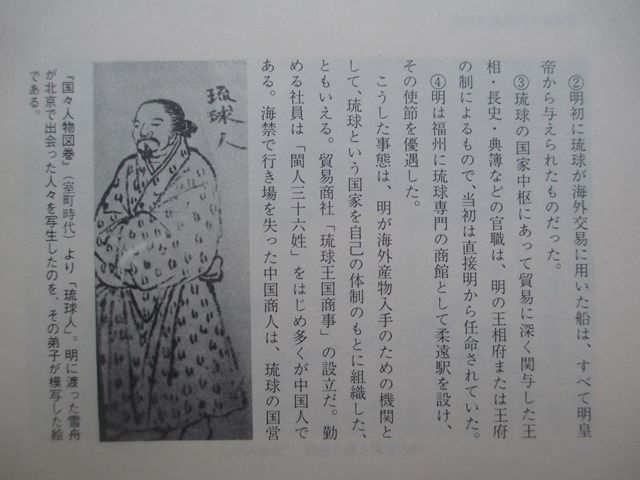
國吉眞哲翁から、そのころ貘と一緒に末吉麦門冬の家に遊びに行った話を伺った。玄関から書斎まで本が積んであって、麦門冬が本を広げている上を鶏が糞を垂れ流しながら走りまわっていたのが印象に残っているとの話であった。思うに貘はそのとき麦門冬の旧号・獏を夢を喰う意味での「獏夢道人」をいくぶん意識に植えつけたのではなかろうか。
又吉康和は一九二三年に『沖縄教育』編集主任になると、麦門冬に「俳句ひかへ帳ー言葉の穿鑿」を書かせている。二五年九月発行『沖縄教育』には、表紙題字を山城正忠に依頼、カット「獅子」を山口重三郎(貘)に依頼し、貘の詩「まひる」「人生と食後」も載せている。編集後記に「山之口貘氏は今般中央の『抒情詩』に日向スケッチ他三篇入選しました之より琉球詩人がどしどし中央の詩壇に出現せんことを念じます。救世者は政治家ではなく、それは詩人と哲人であります」と記して、甥にあたる國吉眞哲と共に上京の旅費を集め貘を東京に送りだしている。
写真上は1925年8月16日、貘2度目の上京前に上左から又吉康和、国吉真哲、国吉真才、一人置いて貘。写真下は貘が戦後帰郷の時。

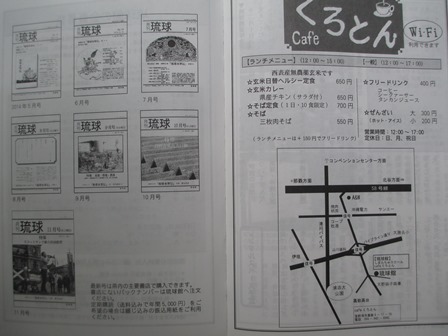
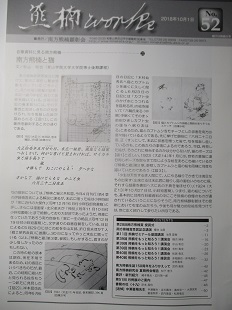


2018年10月4日-『熊楠ワークス』№52に「[追悼]中瀬喜陽先生」が載っている。飯倉照平氏の「先駆的な仕事」の追悼文も載っている。このお二人と神坂次郎氏は、1964年以降、南方熊楠と末吉麦門冬との交流を追及(研究ではない)する過程で出会った。私の熊楠イメージ形成には飯倉氏が1972年『別冊経済評論ー伝記特集・日本のアウトサイダー』に書いた熊楠伝が大半を占める。特に中瀬氏には氏の主宰する俳句雑誌『貝寄風』にエッセイを書かせてもらった。
俳句雑誌『貝寄風』
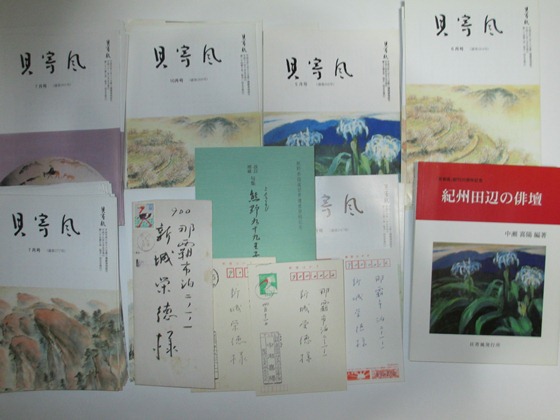
□27年間発行されてきた俳誌「貝寄風(かいよせ)」が、8月号(通巻326号)で終刊となる。主宰の中瀬喜陽さん(78)=和歌山県田辺市神子浜1丁目=は「残念に思うがやむを得なかった。後に残る活動ができた」と振り返っている。貝寄風は、中瀬さんが編集を担当していた俳誌「花蜜柑」の主宰者が亡くなり、中瀬さんが知人の田辺市の串上青蓑さんに声を掛け、1984年7月、串上さんを主宰者として創刊。以来月1回発行し、串上さんが亡くなった後に中瀬さんが主宰を引き継いだ。終刊を惜しむ声もあるが、中瀬さんの体調による理由でやむを得ず決めた。
俳誌には会員の俳句や、中瀬さんによる俳句や短歌の紹介などを掲載している。会員が俳句を作った経緯や思いを掲載しているコーナー「一句の周辺」は、作った俳句を見つめ直すきっかけにしようと設けた。俳句の作り方が分かるという声もあり、人気があるという。会員は創刊当初と同程度の約200人。田辺市や周辺町の住民を中心に、ふるさとについて知ることができるということで県外に住む県出身者らもいる。俳誌のほか、会員で句集「熊野九十九王子」や、創刊20周年を記念した「紀州田辺の俳壇」も発行してきた。また、中瀬さんが研究する南方熊楠を追悼する意味の「熊楠忌」は約10年前、俳人協会に季語として登録された。登録できた背景について中瀬さんは「貝寄風というグループの力があったからこそ」と話している。(→紀伊民報2012年5月19日土曜日)
『貝寄風』 - 新城栄徳「琉球の風」
Category: 99-未分類 Posted by: ryubun
「琉球の風」第1回は2005年4月発行で、作家・神坂次郎氏との出会いを記し「その昔、外様大名の島津家久が徳川家康の許可を得て琉球に出兵し支配下に置いた。そして中国との交易のため『琉球王国』はのこした。島津氏は琉球士族に対して琉球人らしく振舞うよう奨励した。琉球士族は歴史書編纂などで主体性の確立につとめた。清朝から琉球久米村の程順則が持ち帰った『六諭衍義』は島津を介して徳川吉宗に献上された。幕府によって『六諭衍義』は庶民教育の教科書として出版された。それが江戸文学への遠因ともなり滝沢馬琴のベストセラー小説『椿説弓張月』(北斎挿絵)にもつながる。また、清朝の使者歓待のため玉城朝薫がヤマト芸能を参考に『組踊』が生まれるなど新たな琉球文化が展開された」と記した。
平成17年12月 俳句誌『貝寄風』』(編集発行・中瀬喜陽)新城栄徳「琉球の風③末吉安恭と南方熊楠」
7月、立教大学の小峯和明氏と奈良女子大学の千本英史氏から南方熊楠特集『國文学』8月号を恵まれた。小峯氏は「熊楠と沖縄」を執筆され「それにしても、末吉安恭との文通が半年(1918年2月~9月)あまりでとだえてしまったのはなぜであろうか」と疑問を呈しておられる。千本氏は「等身大の熊楠へ」で「熊楠はいたずらに祀り上げるのでなく、その、すぐれた可能性を引き継いでいくことが求められている」としている。
そこで熊楠と末吉安恭の文通の周辺をみてみたい。柳田国男が『郷土研究』を創刊した1913年3月に柳田は伊波普猷に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡を送っている。程なく沖縄県庁では筆耕に『中山世譜』など写本を命じている。6月、黒頭巾・横山健堂が来沖し伊波普猷や安恭らと親しく交わり『大阪毎日新聞』に「薩摩と琉球」を連載。無論、沖縄の新聞にも転載された。
1914年に安恭らは同人雑誌『五人』を創刊、安恭は古手帖(抜書き)をもとに男色をテーマに「芭蕉の恋」を書いた。7月、伊波普猷、真境名安興らは県知事から沖縄史料編纂委員を拝命。1915年の1月に沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁から沖縄県立図書館に移された。主任は安恭の友人で同じ池城毛氏一門の真境名安興である。当然、先の『中山世譜』などは県立沖縄図書館のものとダブルことになる。安恭は安興から『中山世譜』『球陽』などの写本を譲り受けた。安恭は『球陽』などを引用して『琉球新報』に「定西法師と琉球」「琉球飢饉史」、朝鮮史料で「朝鮮史に見えたる古琉球」を書き琉球学の開拓にこれつとめた。
熊楠宛の書簡で安恭は前出の「芭蕉の恋」に関連して「芭蕉翁も男色を好みし由自ら云へりと鳴雪翁の説なりしが、芭蕉がそれを文章に書き著せるもの見当たらず候が、御承知に候はば、御示し下され度候」とある。いかにも見た目には学究的だがその気質は芸術家である。安恭は俳人として麦門冬、歌人として落紅、漢詩人として莫夢山人と号したが俳諧が気質に合っていたようだ。前出の古手帖には「芭蕉」「子規」「俳句に詠まれた琉球」「俳句の肉欲描写」「沖縄の組踊の男色」などが記されている。
安恭は熊楠と文通を通じてお互いに聞きたいことは殆ど聞いたと思う。文通が直接には途絶えても沖縄の事は安恭贈呈の『球陽』で当面間に合う。『日本及日本人』誌上では安恭は亡くなるまで熊楠と投稿仲間であった。1919年1月、折口信夫編集『土俗と伝説』には熊楠の「南方随筆」と並んで安恭の「沖縄書き留め」がある。しかも同年6月、安恭は安興らと「沖縄歴史地理談話会」を設置し活動に入り安恭も自ら企画・講演をなしその内容を新聞記者として、創刊メンバーとして『沖縄時事新報』にも書く忙しさである。
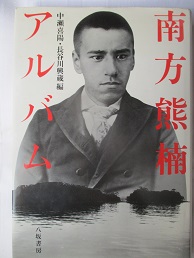
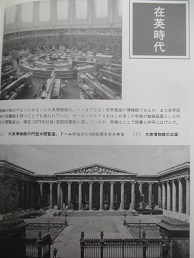
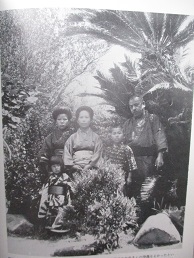
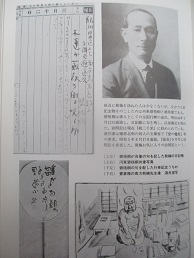
1990年6月 中瀬喜陽・長谷川興蔵編『南方熊楠アルバム』八坂書房
私の手元に中瀬喜陽さん編著『紀州田辺の俳壇』がある。序に「田辺に俳人が訪れたであろう最初を大淀三千風の『行脚文集』に依るのが従来の定説だった」とある。安恭も1917年9月の『日本及日本人』に「大淀三千風の日本行脚文集に『雨雲をなとかは横に寝さすらむ名は正直(ろく)な神風』といふ歌あり、ろくに正直といふ意味ありしか」と『行脚文集』を引用している。同じく中瀬さん共著『南方熊楠アルバム』の1911年3月・熊楠日記には河東碧梧桐俳句「木蓮が蘇鉄の側に咲く所」」と河東写真が並んでいる。碧梧桐は1910年5月に来沖し安恭の俳句は「将来有望」と述べた。
05/07: 藤田嗣治と岡本太郎
1905年ー北大路魯山人、版下書きを志し、岡本可亭(伊勢の人。籐堂藩に仕えた儒者岡本安五郎の二男)に師事。福田可逸を名乗る。息子の岡本一平を知る。可亭のもとからの出向で帝国生命保険会社の文書掛となる。
1910年-岡本一平、かの子(21歳)、和田英作の媒酌にて結婚。8月31日入籍
1912年-岡本一平、朝日新聞社員となる。
1917年-岡本一平、かの子と植村正久を訪ねる。かの子、のちに親鸞『歎異鈔』に傾倒する。
1927年-岡本かの子、仏教研究家として世に知られる。
1938年
4月28日『琉球新報』「世界の藤田画伯来県」/『沖縄日報』「きのう雨の港大賑わい、ようこそ!藤田さんー久米町で借家住まい」
5月1日『琉球新報』「藤田画伯に物を訊く座談会」連載
5月10日『琉球新報』「二高女で藤田画伯講演『為にならぬ面白い話』」
5月15日『琉球新報』「南陽薬品で藤田嗣治画伯作品観賞会」
5月19日『琉球新報』「藤田画伯きょう帰京」
5月20日『琉球新報』藤田嗣治「沖縄へ送る讃美」
5月25日『琉球新報』我部政達「藤田先生と其の絵」連載
6月20日『帝国大学新聞』藤田嗣治「首里の尚順男」
1941年-11月6日ー銀座三越で「岡本太郎滞欧作品展」ーパンフレットに藤田嗣治の「岡本太郎君」
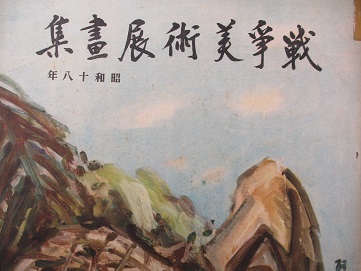
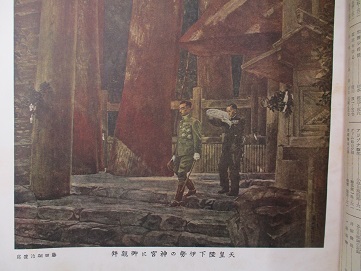
1944年1月 「戦争美術展畫集」朝日新聞社
岡本太郎『沖縄文化論ー忘れられた日本』□私が沖縄に強くひかれた、そもそものはじまりは、そういうクラシックを見てからだった。終戦後間もない頃、偶然の機会に、」その時分はまだひどく珍しかった沖縄料亭に案内された。そこで見た踊りに、すっかりイカレてしまったのだ。空間的で、自由で、優美、それは異様なリズムだった。しかしはじめてふれる私の心にも無条件に喰い入ってくる。(略)「沖縄」は私にとって踊りの代名詞のようなものであった。
1956年10月ー岡本太郎『日本の伝説』光文社
1958年2月22日『琉球新報』「パリの藤田嗣治画伯」
1959年11月17日『沖縄タイムス』「岡本太郎画伯、二科会沖縄支部の招きで来島ー沖縄はあこがれの島」(写真・大城皓也氏の出迎えをうけた岡本太郎氏)
1960年1月1日『琉球新報』「沖縄を料理するー毒舌ことはじめ大宅壮一・岡本太郎」/1月12日『琉球新報』岡本太郎「沖縄の再発見」@
1961年1月1日『沖縄タイムス』岡本太郎「絵と文・忘れられた日本」
1966年12月25日『琉球新報』「岡本太郎画伯が来沖ーイザイホーの研究で」/12月29日『琉球新報』「関係者の見たイザイホー 岡本太郎」
1967年ー福田清人/平野睦子『岡本かの子ー人と作品』清水書院/3月ー岡本太郎『今日をひらく 太陽との対話』講談社□日本発見ー神々の島 久高島
1968年2月ー岡本太郎『原色の呪文』文藝春秋□「何もないこと」の眩暈-沖縄文化論
1971年3月29日『琉球新報』「沖縄文化への提言ー岡本太郎氏を囲み座談会」(池宮城秀意、山里永吉)/3月30日『沖縄文化を語るー岡本太郎・豊平良顕』/10月28日『琉球新報』「沖縄で初めての潮講演会ー開高健、岡本太郎」(潮出版社・琉球新報社共催)
1980年7月24日ー那覇市山形屋で「岡本太郎の世界展」(沖縄タイムス社主催・琉球放送後援)/7月24日『沖縄タイムス』「目みはる作品ズラリー『岡本太郎の世界展』開幕」/7月25日『沖縄タイムス』「岡本太郎氏が来沖ー展示会通し沖縄を触発」/7月27日『沖縄タイムス』「沖縄タイムスホールで岡本太郎氏が講演ー藝術は全身で感じるもの」
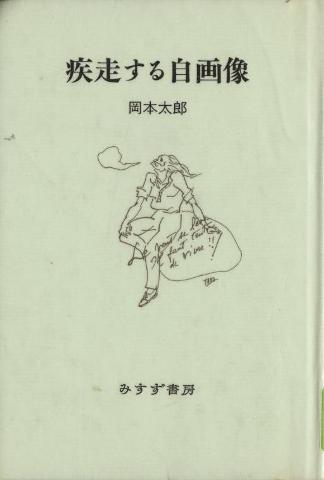

2001年4月ー岡本太郎『疾走する自画像』みすず書房
2006年
2月10日『沖縄タイムス』「藤田画伯の『孫』、沖縄県が約4千万で購入」
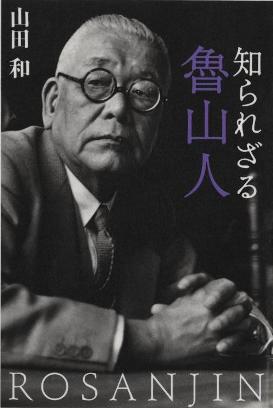
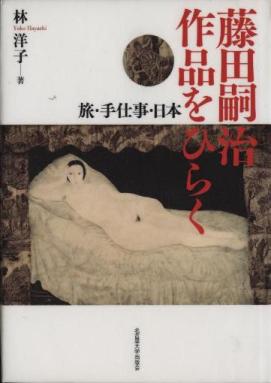
2007年10月ー山田和『知られざる魯山人』文藝春秋/2008年5月ー林洋子『藤田嗣治 作品をひらく』名古屋大学出版会
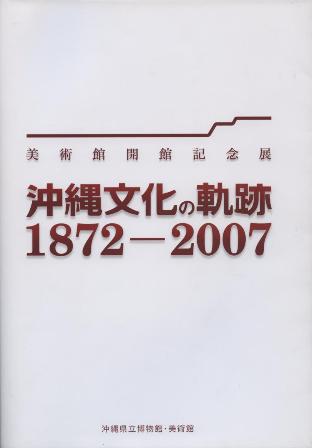
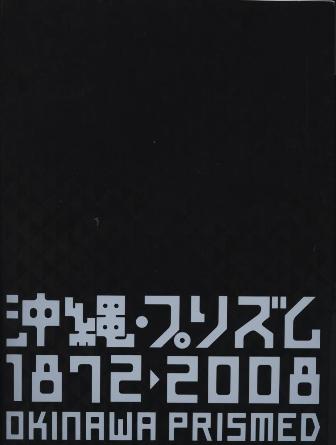
2007年ー『沖縄文化の軌跡1872-2007』沖縄県立博物館・美術館□新城栄徳「麦門冬の果たした役割」/『沖縄・プリズム1872-2008』東京国立近代美術館
2011年1月1日『沖縄タイムス』「藝術は爆発だー岡本太郎生誕100年」/1月1日『日本経済新聞』「岡本太郎生誕100年」
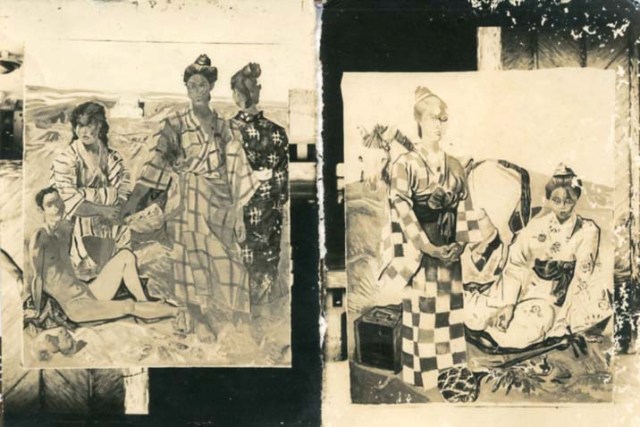 写真ー戦前の大城皓也作品
写真ー戦前の大城皓也作品
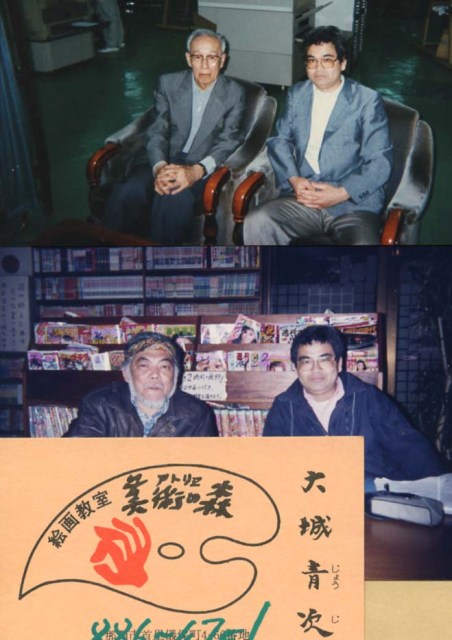 写真上ー平野政吉美術館館長と新城栄徳/大城皓也の子息・青次氏と新城栄徳
写真上ー平野政吉美術館館長と新城栄徳/大城皓也の子息・青次氏と新城栄徳
1910年-岡本一平、かの子(21歳)、和田英作の媒酌にて結婚。8月31日入籍
1912年-岡本一平、朝日新聞社員となる。
1917年-岡本一平、かの子と植村正久を訪ねる。かの子、のちに親鸞『歎異鈔』に傾倒する。
1927年-岡本かの子、仏教研究家として世に知られる。
1938年
4月28日『琉球新報』「世界の藤田画伯来県」/『沖縄日報』「きのう雨の港大賑わい、ようこそ!藤田さんー久米町で借家住まい」
5月1日『琉球新報』「藤田画伯に物を訊く座談会」連載
5月10日『琉球新報』「二高女で藤田画伯講演『為にならぬ面白い話』」
5月15日『琉球新報』「南陽薬品で藤田嗣治画伯作品観賞会」
5月19日『琉球新報』「藤田画伯きょう帰京」
5月20日『琉球新報』藤田嗣治「沖縄へ送る讃美」
5月25日『琉球新報』我部政達「藤田先生と其の絵」連載
6月20日『帝国大学新聞』藤田嗣治「首里の尚順男」
1941年-11月6日ー銀座三越で「岡本太郎滞欧作品展」ーパンフレットに藤田嗣治の「岡本太郎君」
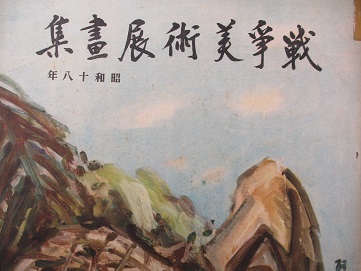
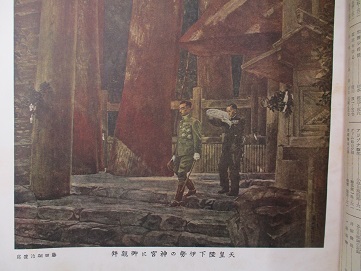
1944年1月 「戦争美術展畫集」朝日新聞社
岡本太郎『沖縄文化論ー忘れられた日本』□私が沖縄に強くひかれた、そもそものはじまりは、そういうクラシックを見てからだった。終戦後間もない頃、偶然の機会に、」その時分はまだひどく珍しかった沖縄料亭に案内された。そこで見た踊りに、すっかりイカレてしまったのだ。空間的で、自由で、優美、それは異様なリズムだった。しかしはじめてふれる私の心にも無条件に喰い入ってくる。(略)「沖縄」は私にとって踊りの代名詞のようなものであった。
1956年10月ー岡本太郎『日本の伝説』光文社
1958年2月22日『琉球新報』「パリの藤田嗣治画伯」
1959年11月17日『沖縄タイムス』「岡本太郎画伯、二科会沖縄支部の招きで来島ー沖縄はあこがれの島」(写真・大城皓也氏の出迎えをうけた岡本太郎氏)
1960年1月1日『琉球新報』「沖縄を料理するー毒舌ことはじめ大宅壮一・岡本太郎」/1月12日『琉球新報』岡本太郎「沖縄の再発見」@
1961年1月1日『沖縄タイムス』岡本太郎「絵と文・忘れられた日本」
1966年12月25日『琉球新報』「岡本太郎画伯が来沖ーイザイホーの研究で」/12月29日『琉球新報』「関係者の見たイザイホー 岡本太郎」
1967年ー福田清人/平野睦子『岡本かの子ー人と作品』清水書院/3月ー岡本太郎『今日をひらく 太陽との対話』講談社□日本発見ー神々の島 久高島
1968年2月ー岡本太郎『原色の呪文』文藝春秋□「何もないこと」の眩暈-沖縄文化論
1971年3月29日『琉球新報』「沖縄文化への提言ー岡本太郎氏を囲み座談会」(池宮城秀意、山里永吉)/3月30日『沖縄文化を語るー岡本太郎・豊平良顕』/10月28日『琉球新報』「沖縄で初めての潮講演会ー開高健、岡本太郎」(潮出版社・琉球新報社共催)
1980年7月24日ー那覇市山形屋で「岡本太郎の世界展」(沖縄タイムス社主催・琉球放送後援)/7月24日『沖縄タイムス』「目みはる作品ズラリー『岡本太郎の世界展』開幕」/7月25日『沖縄タイムス』「岡本太郎氏が来沖ー展示会通し沖縄を触発」/7月27日『沖縄タイムス』「沖縄タイムスホールで岡本太郎氏が講演ー藝術は全身で感じるもの」
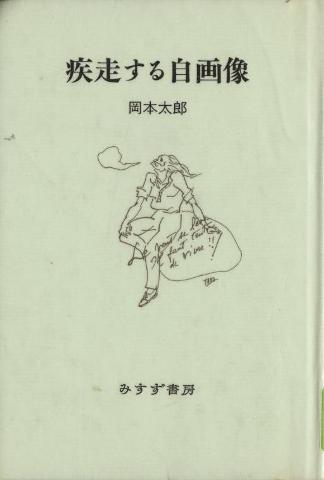

2001年4月ー岡本太郎『疾走する自画像』みすず書房
2006年
2月10日『沖縄タイムス』「藤田画伯の『孫』、沖縄県が約4千万で購入」
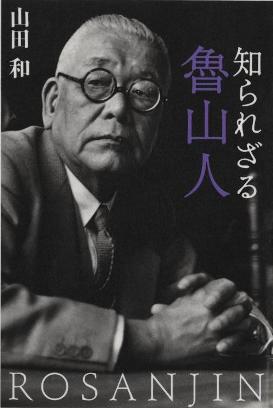
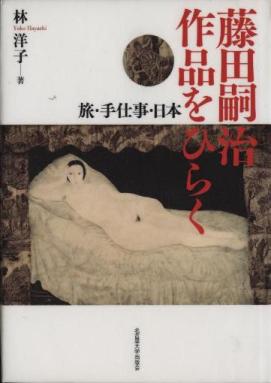
2007年10月ー山田和『知られざる魯山人』文藝春秋/2008年5月ー林洋子『藤田嗣治 作品をひらく』名古屋大学出版会
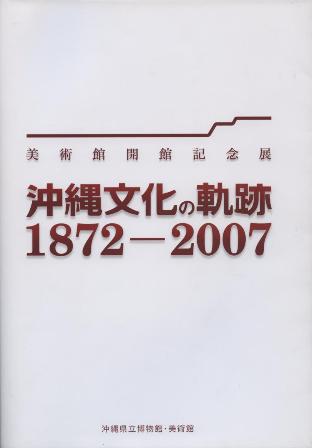
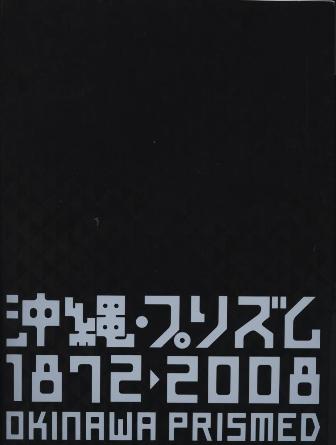
2007年ー『沖縄文化の軌跡1872-2007』沖縄県立博物館・美術館□新城栄徳「麦門冬の果たした役割」/『沖縄・プリズム1872-2008』東京国立近代美術館
2011年1月1日『沖縄タイムス』「藝術は爆発だー岡本太郎生誕100年」/1月1日『日本経済新聞』「岡本太郎生誕100年」
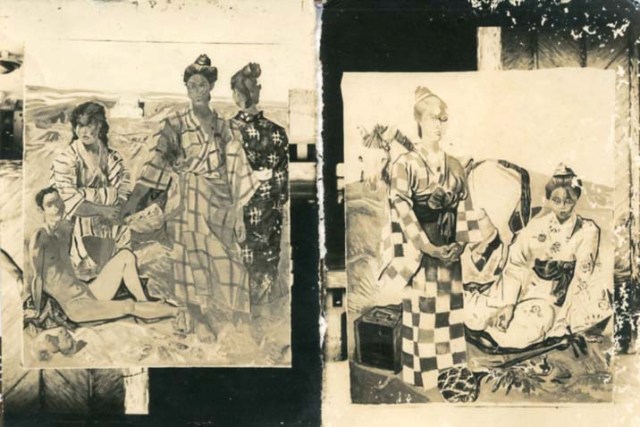 写真ー戦前の大城皓也作品
写真ー戦前の大城皓也作品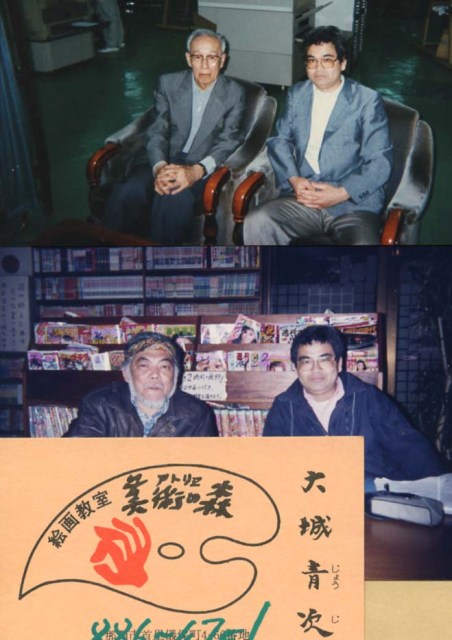 写真上ー平野政吉美術館館長と新城栄徳/大城皓也の子息・青次氏と新城栄徳
写真上ー平野政吉美術館館長と新城栄徳/大城皓也の子息・青次氏と新城栄徳