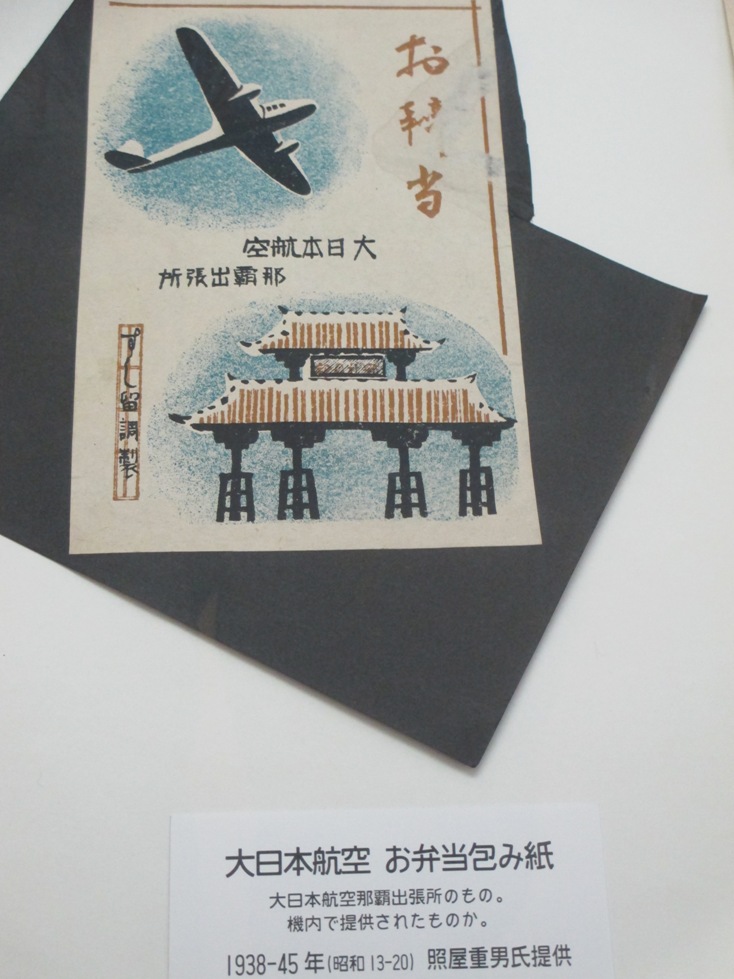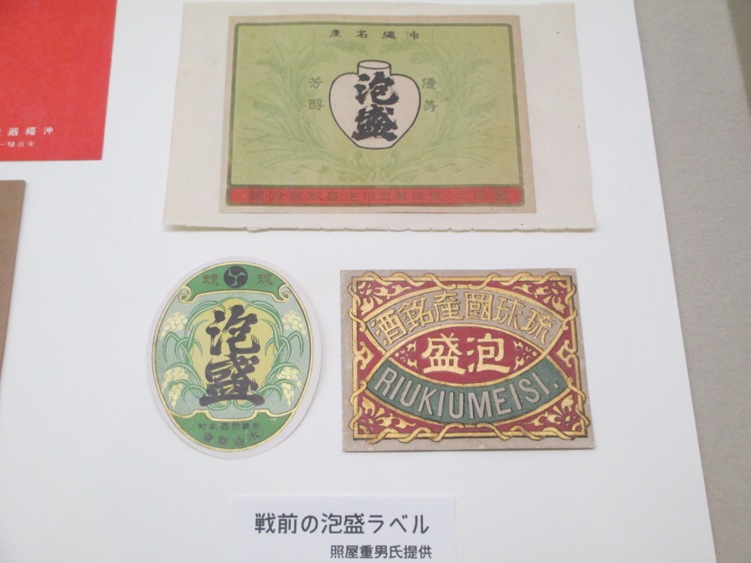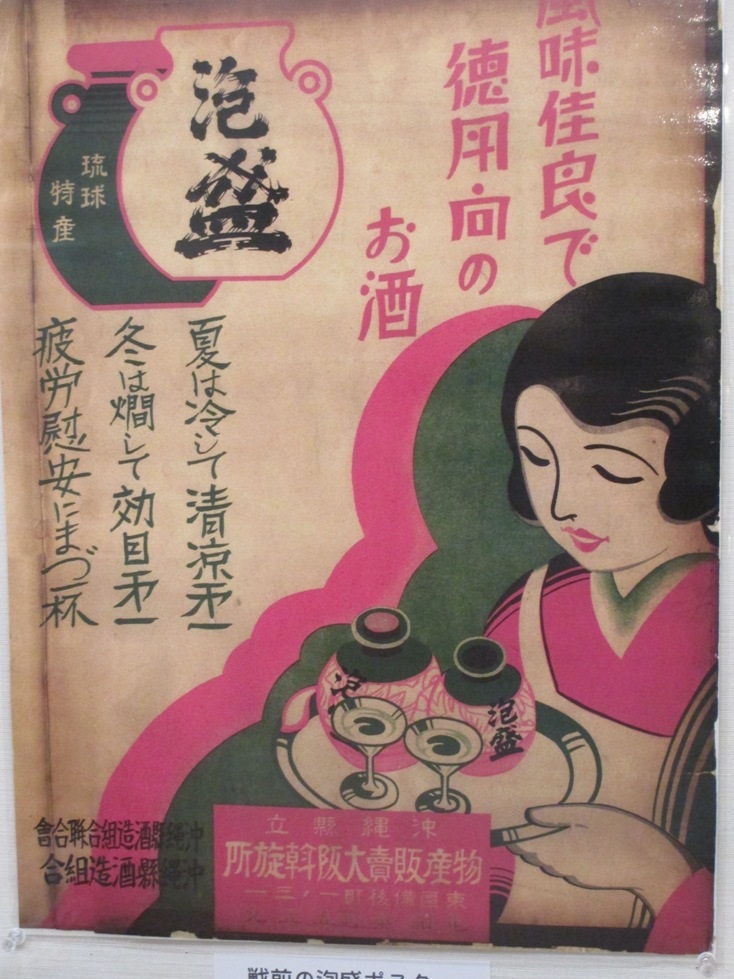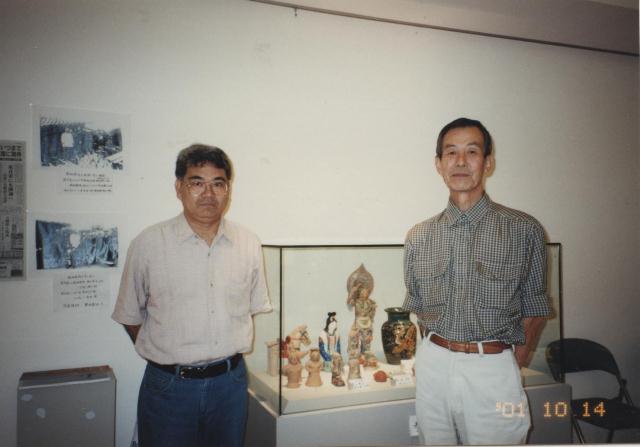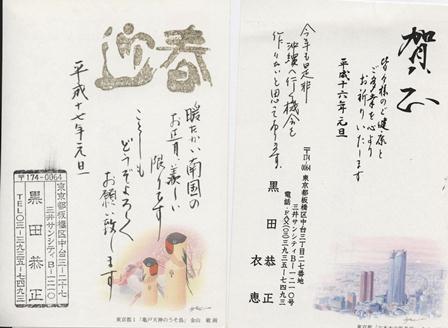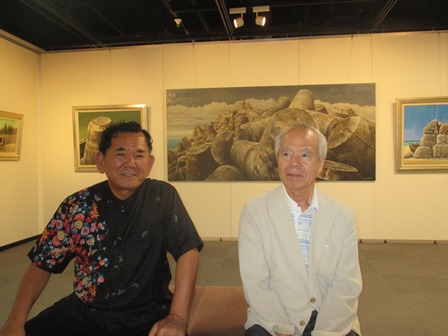01/20: 沖縄コレクター友の会顧問・宮里朝光さん

沖縄コレクター友の会メンバーと宮里さん(新城栄徳撮影)
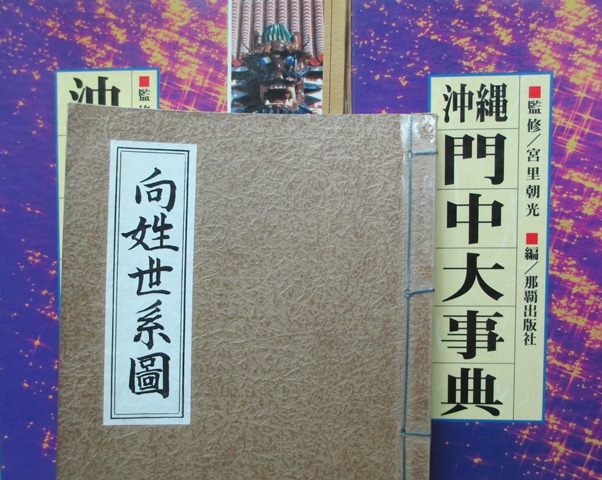
宮里朝光の本

2013年5月18日、南風原レストランで沖縄コレクター友の会例会
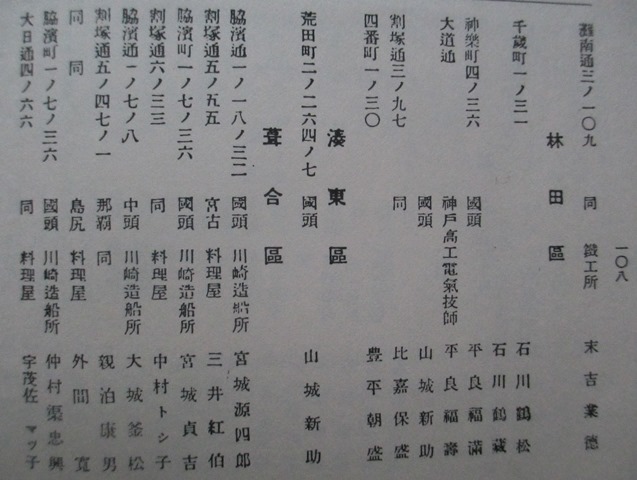
左から9番目に宮城源四郎(大宜味村字塩屋)の名がある。宮城保氏の父である。

沖縄コレクター友の会ー前列右から二人目ー宮城保氏
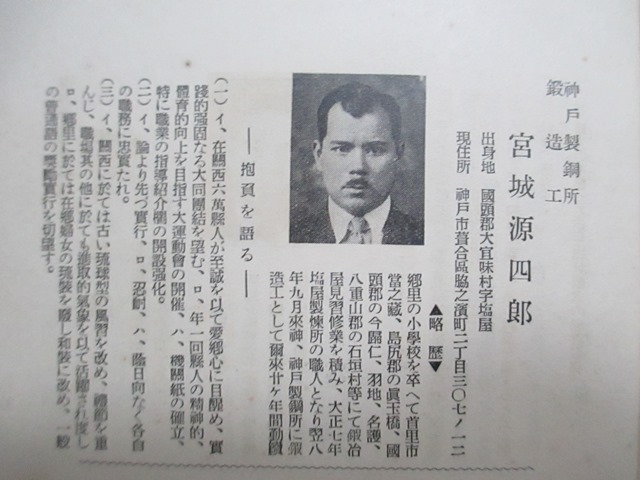
大阪は1923年に関東大震災を機に沖縄青年たちの赤琉会が結成された。それを母体にして24年に関西沖縄県人会(渡口精鴻会長)が結成された。28年には『(関西)沖縄県人住所案内』が発行された。1935年8月には大阪市西成区鶴見橋通り6ノ4の関西沖縄興信社から『関西沖縄興信名鑑」』が発刊された。同社の顧問、編集同人に豊川忠進、眞栄田勝朗、下地玄信、山城興善、翁長良孝、古波蔵太郎、比嘉繁雄、古波蔵加壽が居る。
本名鑑の序文「関西地方は大阪市を中心として我国産業都市の中心地であると共に又最大の経済都市である。就中大阪市は人口三百有余人を擁し近代的文化施設は施され世界第三位の大都市である。殊に関西地方を理想郷に求めて来阪する県民は其数実に5万人と註されて居る。学者、弁護士、医師、実業家、学生、労働者、紡績女工等ありて各方面に亘りて各々其の職業生線(ママ)に健闘しつつあるは刮目に値する。近時我が県民が各方面に著々として地位を確保し成功しつつあるは吾人の意を強うして祝福せざるを得ない。然るにいまだ県民の消息近況を知るに完全なる機関なきは甚だ遺憾とする所である。茲に於いて吾人は『関西沖縄興信名鑑』を上梓し県民の頒布状態並びに活動状態及び職業、居所を詳細に記述して県民諸氏の座右に供せんとす。幸いに本名鑑が県民多数の連絡機関と徒然の好伴侶として聊かなりとも裨益する所あらば幸甚である。」とする。

2014年1月30日 おもろまち
04/19: 琉球芸能史散歩③
2003年10月11日『沖縄タイムス』新城栄徳「うちなー書の森 人の網⑧當間清弘」
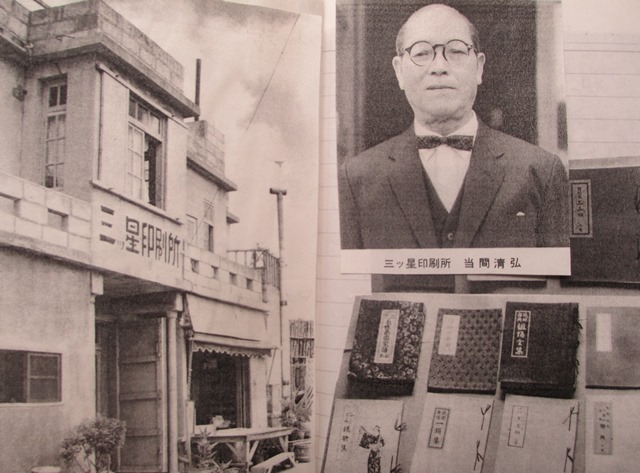
郷土史へ導いてくれた當間清弘氏
母方の伯父や伯母の連れ合いが奄美大島の出身だから、小学生のころから奄美大島は琉球の一部だと理解していた。父・三郎の出会いはちょっと違っていた。1947年、父が那覇の栄町「栄亭」のコック長のとき、用心棒代を店に要求にきた大島ヤクザに立腹し包丁で一人の鼻先を削いでしまった。父はグループの報復を恐れ糸満の親戚の所に身を隠した。翌年に生まれた私の名前の「栄」は、栄町からも来ている。
名瀬市は1972年前後3回、訪ねたが図書館はいつも休館日。だから島尾敏雄とついに出会うこともなかった。しかし、私にとってそれに匹敵する出会いが山下欣一氏だった。氏の『奄美のシャーマニズム』はもう古典的存在である。私も義母がユタをしていたので、それにまつわる話には関心がある。氏が私に資料を贈る義理は無いが気を使ってくださる。
喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。印刷者の神山邦彦は久米蔡氏で元警察官、戦後『辻情史』をまとめ発行し1977年83歳で亡くなった。
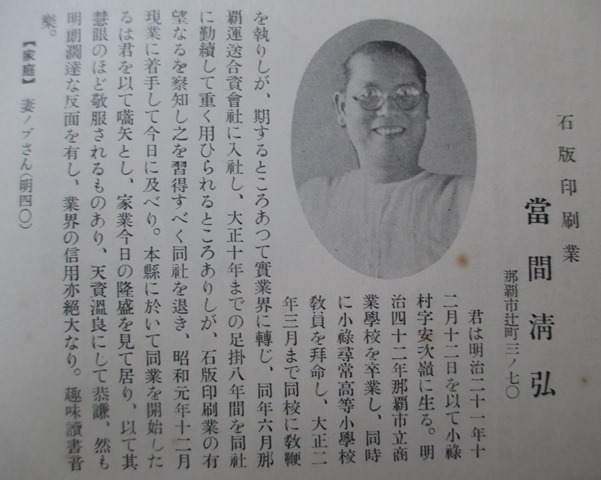
當間清弘
小学4年のころ、首里の琉潭池側の琉球政府立博物館へ「首里那覇港図」をよく見にいった。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

「昭和初期の那覇絵地図」(昭和石版印刷所 辻町3ノ70)
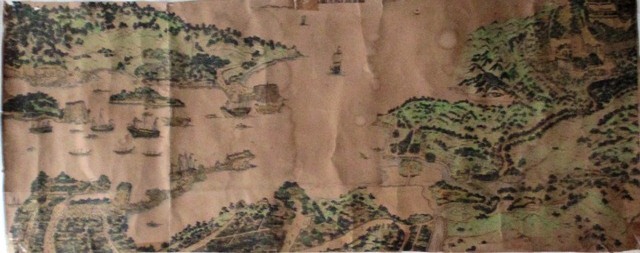
「首里那覇鳥瞰図」氏作成

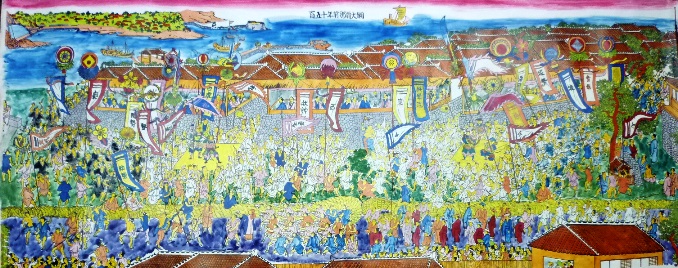
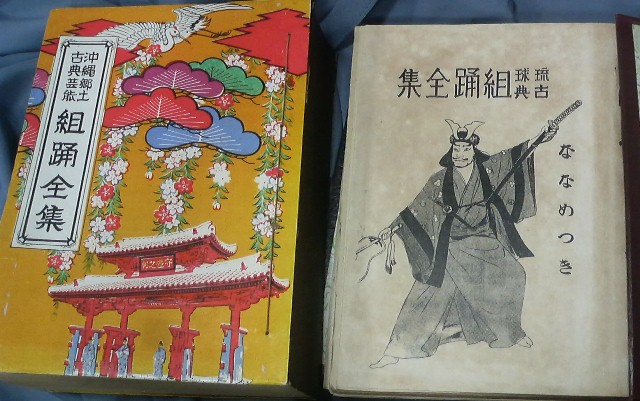
□8月 『琉球古典組踊全集』當間清弘(三ツ星印刷所)→左の本・1965年9月『沖縄郷土古典芸能 組踊全集』
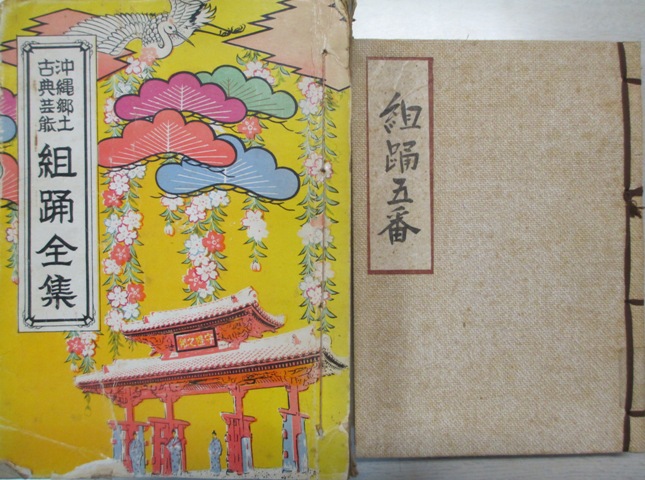
沖縄県立博物館の裏手に「みどり印刷」がある。開業したのは石川逢正氏で、氏はミルクイシチャーと呼ばれる一門の家に生まれた。1955年に開業した当初は首里バスの切符、伝票、名刺などを印刷していた。石川氏は戦前、嘉味田朝春の向春印刷所から始まって戦後は新聞などを印刷していた中丸印刷所を経て独立。今は、息子の石川和男氏が業務をこなす。「みどり印刷」←iここをクリック
2014-9-5 沖縄県立博物館・美術館にて「くしの日 美ら姿 結い遊び(主催:玉木流 琉装からじ結い研究所)」がありました。




モデル・仲里なぎささん
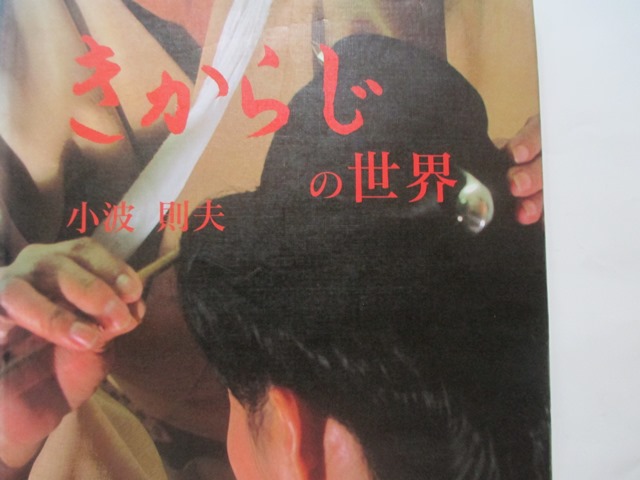
1995年10月 小波則夫/宜保榮治郎『きからじの世界』小波則夫
○グラビア/第一章ー実技編1、小波式琉髪の結い方 2、歌劇にみる髪型 /第二章ー髪型・資料編1、琉球風俗絵図 2、諸外国にみる髪型 3、琉髪と簪の歴史概説 /第三章ー対談1、小波則夫の足跡2、小波則夫の芸談 小波則夫・年譜
○写真ー金武良章、志田房子、佐藤太圭子、親泊興照、真境名由康、宮城能造、島袋光裕、宜保榮治郎、ウミングヮ役の小波則夫、久高将吉、比嘉清子、与座つる、浜元澄子・朝保、比嘉正義、玉城盛重、前田幸三郎、翁長小次郎、小山明子

2013年12月21日 沖縄県立博物館文化講座「『きからじ』と『ジーファー』」

写真左から写真家の山田實さん、牧野浩隆氏、沖縄髪結いの小波則夫氏
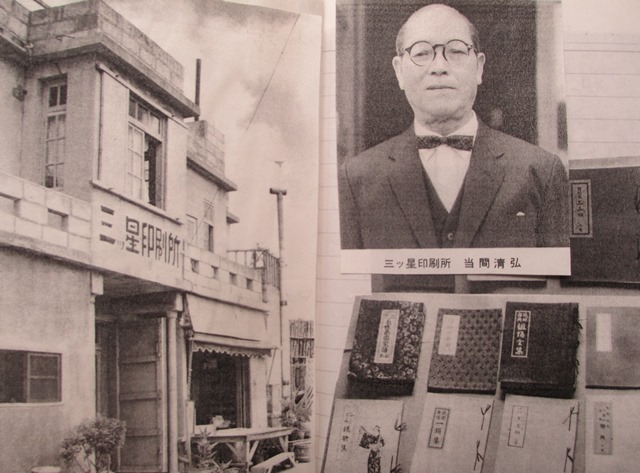
郷土史へ導いてくれた當間清弘氏
母方の伯父や伯母の連れ合いが奄美大島の出身だから、小学生のころから奄美大島は琉球の一部だと理解していた。父・三郎の出会いはちょっと違っていた。1947年、父が那覇の栄町「栄亭」のコック長のとき、用心棒代を店に要求にきた大島ヤクザに立腹し包丁で一人の鼻先を削いでしまった。父はグループの報復を恐れ糸満の親戚の所に身を隠した。翌年に生まれた私の名前の「栄」は、栄町からも来ている。
名瀬市は1972年前後3回、訪ねたが図書館はいつも休館日。だから島尾敏雄とついに出会うこともなかった。しかし、私にとってそれに匹敵する出会いが山下欣一氏だった。氏の『奄美のシャーマニズム』はもう古典的存在である。私も義母がユタをしていたので、それにまつわる話には関心がある。氏が私に資料を贈る義理は無いが気を使ってくださる。
喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。印刷者の神山邦彦は久米蔡氏で元警察官、戦後『辻情史』をまとめ発行し1977年83歳で亡くなった。
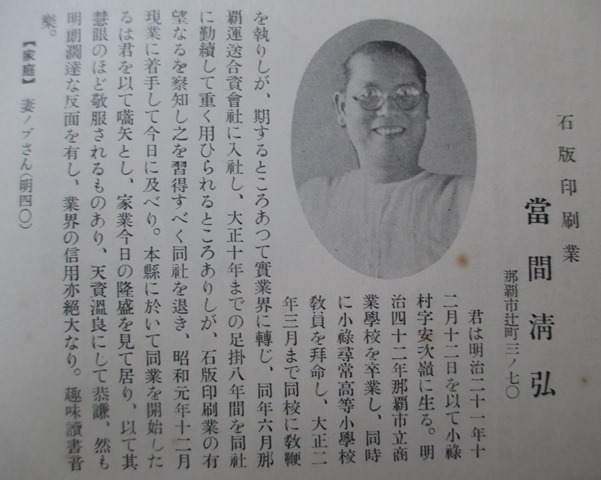
當間清弘
小学4年のころ、首里の琉潭池側の琉球政府立博物館へ「首里那覇港図」をよく見にいった。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

「昭和初期の那覇絵地図」(昭和石版印刷所 辻町3ノ70)
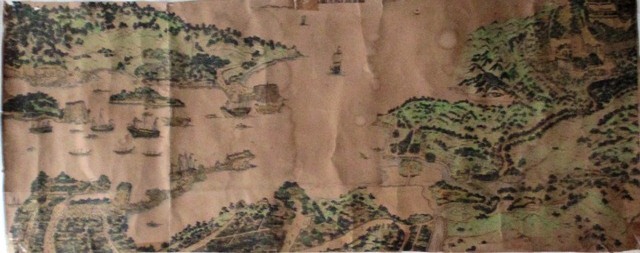
「首里那覇鳥瞰図」氏作成

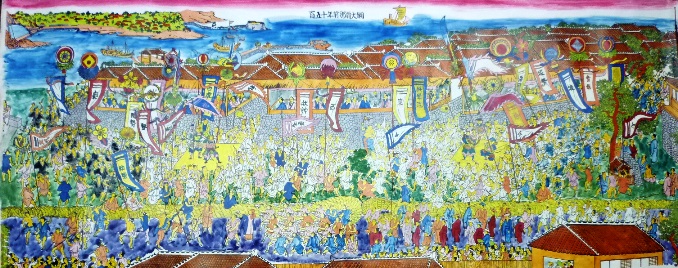
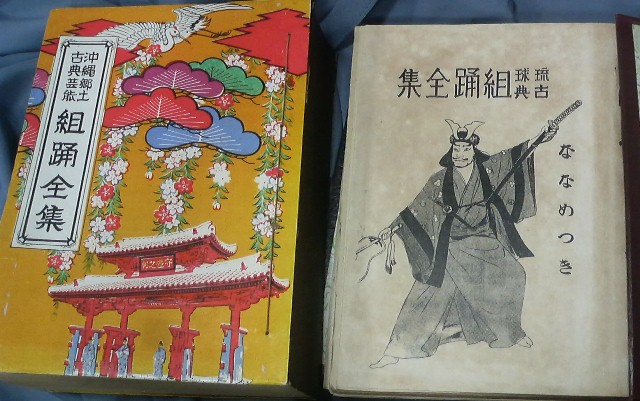
□8月 『琉球古典組踊全集』當間清弘(三ツ星印刷所)→左の本・1965年9月『沖縄郷土古典芸能 組踊全集』
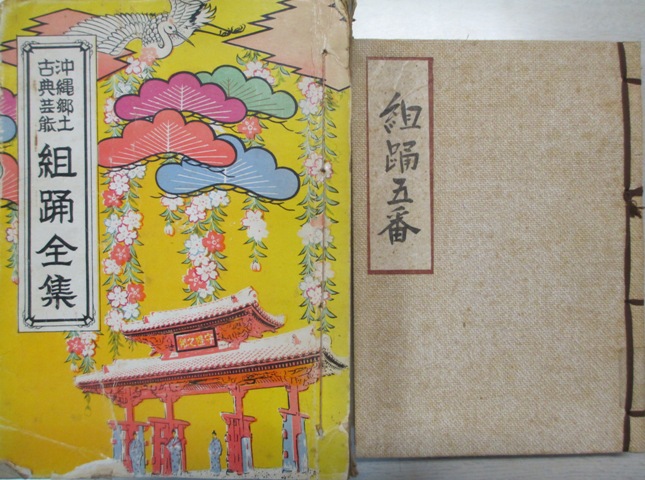
沖縄県立博物館の裏手に「みどり印刷」がある。開業したのは石川逢正氏で、氏はミルクイシチャーと呼ばれる一門の家に生まれた。1955年に開業した当初は首里バスの切符、伝票、名刺などを印刷していた。石川氏は戦前、嘉味田朝春の向春印刷所から始まって戦後は新聞などを印刷していた中丸印刷所を経て独立。今は、息子の石川和男氏が業務をこなす。「みどり印刷」←iここをクリック
2014-9-5 沖縄県立博物館・美術館にて「くしの日 美ら姿 結い遊び(主催:玉木流 琉装からじ結い研究所)」がありました。




モデル・仲里なぎささん
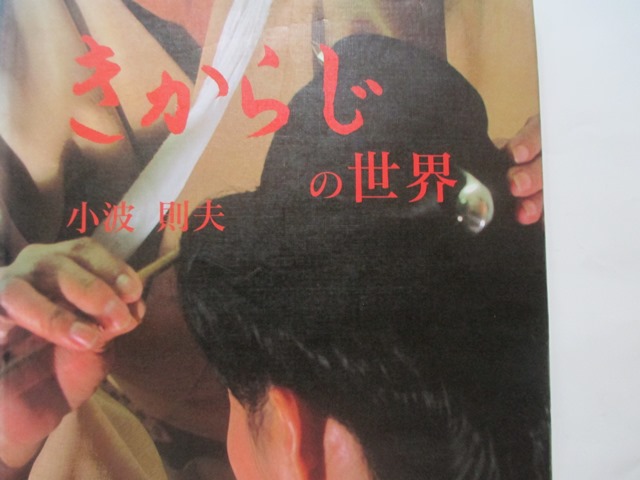
1995年10月 小波則夫/宜保榮治郎『きからじの世界』小波則夫
○グラビア/第一章ー実技編1、小波式琉髪の結い方 2、歌劇にみる髪型 /第二章ー髪型・資料編1、琉球風俗絵図 2、諸外国にみる髪型 3、琉髪と簪の歴史概説 /第三章ー対談1、小波則夫の足跡2、小波則夫の芸談 小波則夫・年譜
○写真ー金武良章、志田房子、佐藤太圭子、親泊興照、真境名由康、宮城能造、島袋光裕、宜保榮治郎、ウミングヮ役の小波則夫、久高将吉、比嘉清子、与座つる、浜元澄子・朝保、比嘉正義、玉城盛重、前田幸三郎、翁長小次郎、小山明子

2013年12月21日 沖縄県立博物館文化講座「『きからじ』と『ジーファー』」

写真左から写真家の山田實さん、牧野浩隆氏、沖縄髪結いの小波則夫氏
1994年3月 沖縄県立博物館友の会『博友』第8号 翁長良明「幻の中山通寳を追いかけてー私の古銭夢譚ー」<
〇(略)私が古銭を集め始めたのは、小学校の1年生の時でした。古銭との出会いは、自宅の机の引き出しからみつけた4,5枚の古銭であったと思います。それは、寛永通寳と明治の2銭銅貨、それに昭和のアルミ貨だったと記憶しています。その時手にした古銭を通して、私はある種の感慨を催しました。それ以後、古銭を単なる金以上の別のものとして、興味を持ち、少しずつ集めるようになりました。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。
期間中は、台風による悪天候ではあったものの多くの親子や普段のワンダーミュージアムでは見られない層の人達が多く来場しており、大盛況で終わることができました。
☆「沖縄のお金、世界のお金展」の主なトピックス
9月13日 宜野湾市教育文化課(同市博物館長兼務)和田敬悟氏来場
9月16日 沖縄タイムス朝刊掲載
9月18日 琉球新報朝刊掲載
9月20日 外国人が多く、翁長氏が片言の英語で古銭について説明
9月21日 こども童謡教室の宮城葉子先生が、昔の沖縄のお金について、こどもたちに伝えるため来館
9月21日 同日、NHKニュース放送
☆「沖縄のお金、世界のお金展」について
ワンダーミュージアムにおいては、那覇市に在住の”古銭・古美術なるみ堂”(TEL:098-987-5530)の翁長良明氏のご協力をいただき、古き時代に思いを馳せる古銭の企画展を開催。
琉球時代からアメリカ、本土復帰に至る沖縄の歴史の変遷に伴うお金の変化と、それに対比させる形で世界の国々のお金、また世界最古のお金、世界で一番大きいお札、一番重いお金など、翁長氏の貴重なコレクションの中から厳選して企画展を組み立てた。
お金は時代・歴史を映す鏡であることをこどもたちに伝えると同時に、世界の1年間の軍事費と飢えに苦しむ人々を1年間救う費用を対比させ、お金の大切さ→金銭教育にも視野に入れたものとした。

2013年1月30日ー左から翁長良明氏、不二出版の船橋治氏と細田哲史氏
〇(略)私が古銭を集め始めたのは、小学校の1年生の時でした。古銭との出会いは、自宅の机の引き出しからみつけた4,5枚の古銭であったと思います。それは、寛永通寳と明治の2銭銅貨、それに昭和のアルミ貨だったと記憶しています。その時手にした古銭を通して、私はある種の感慨を催しました。それ以後、古銭を単なる金以上の別のものとして、興味を持ち、少しずつ集めるようになりました。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。
期間中は、台風による悪天候ではあったものの多くの親子や普段のワンダーミュージアムでは見られない層の人達が多く来場しており、大盛況で終わることができました。
☆「沖縄のお金、世界のお金展」の主なトピックス
9月13日 宜野湾市教育文化課(同市博物館長兼務)和田敬悟氏来場
9月16日 沖縄タイムス朝刊掲載
9月18日 琉球新報朝刊掲載
9月20日 外国人が多く、翁長氏が片言の英語で古銭について説明
9月21日 こども童謡教室の宮城葉子先生が、昔の沖縄のお金について、こどもたちに伝えるため来館
9月21日 同日、NHKニュース放送
☆「沖縄のお金、世界のお金展」について
ワンダーミュージアムにおいては、那覇市に在住の”古銭・古美術なるみ堂”(TEL:098-987-5530)の翁長良明氏のご協力をいただき、古き時代に思いを馳せる古銭の企画展を開催。
琉球時代からアメリカ、本土復帰に至る沖縄の歴史の変遷に伴うお金の変化と、それに対比させる形で世界の国々のお金、また世界最古のお金、世界で一番大きいお札、一番重いお金など、翁長氏の貴重なコレクションの中から厳選して企画展を組み立てた。
お金は時代・歴史を映す鏡であることをこどもたちに伝えると同時に、世界の1年間の軍事費と飢えに苦しむ人々を1年間救う費用を対比させ、お金の大切さ→金銭教育にも視野に入れたものとした。

2013年1月30日ー左から翁長良明氏、不二出版の船橋治氏と細田哲史氏
03/09: "1894年来沖ー伊藤篤太郎"
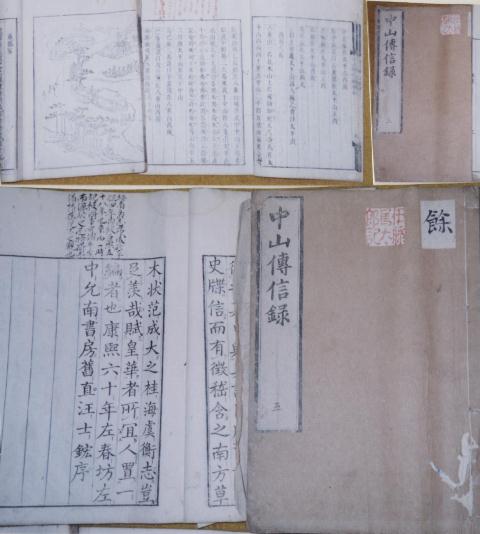
伊藤篤太郎蔵書印がある『中山傅信録』(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)
1997年3月 沖縄県教育委員会『沖縄県史研究紀要』第3号 当山昌直・小野まさ子「伊藤篤太郎琉球八重山列島動植物採集雑記の翻刻と解題」
伊藤篤太郎 いとう-とくたろう
1866*-1941 明治-昭和時代前期の植物学者。
慶応元年11月29日生まれ。伊藤圭介(けいすけ)の孫。明治17年イギリスに留学。28年鹿児島高等中学造士館教授,大正10年東北帝大講師となる。博物会の雑誌「多識会誌」を編集した。昭和16年3月21日死去。77歳。尾張(おわり)(愛知県)出身。著作に「大日本植物図彙(ずい)」など。(→コトバンク)
2017年4月『熊楠WORKS』№49 郷間秀夫「南方熊楠と同時代人 伊藤篤太郎について」
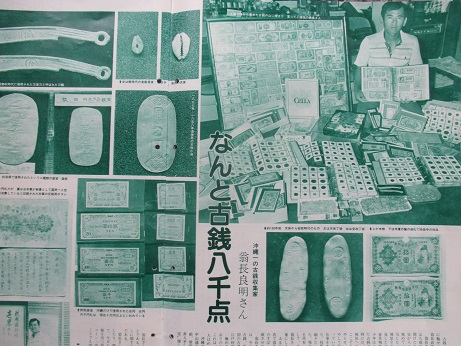
1984年11月『オキナワグラフ』「なんと古銭8千点ー沖縄一の古銭収集家・翁長良明さん」
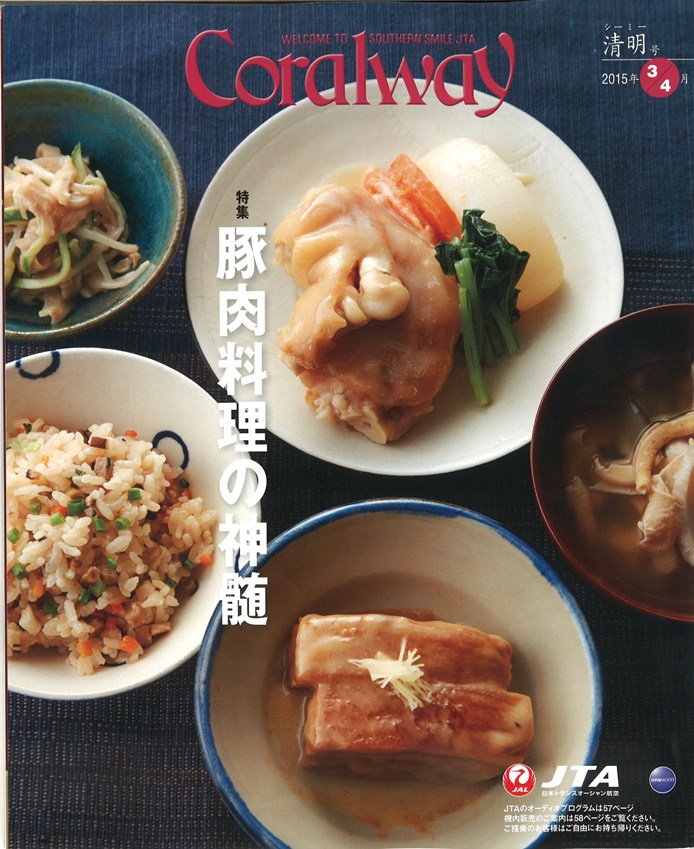

JTA機内誌『Coralway』「情熱あふれる沖縄屈指のコレクター 翁長良明」
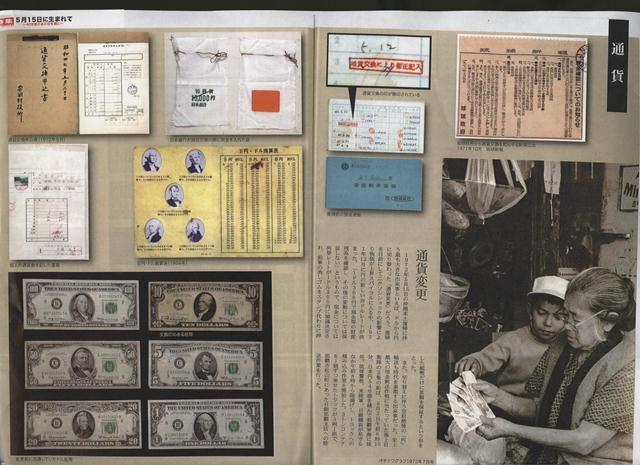
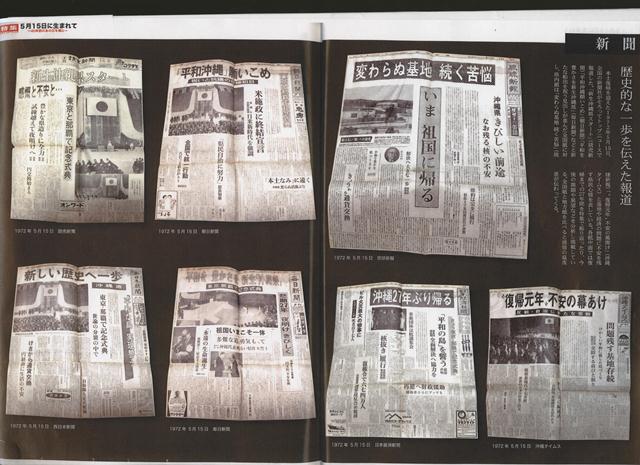

2012年5月ー『オキナワグラフ』「翁長良明コレクション」

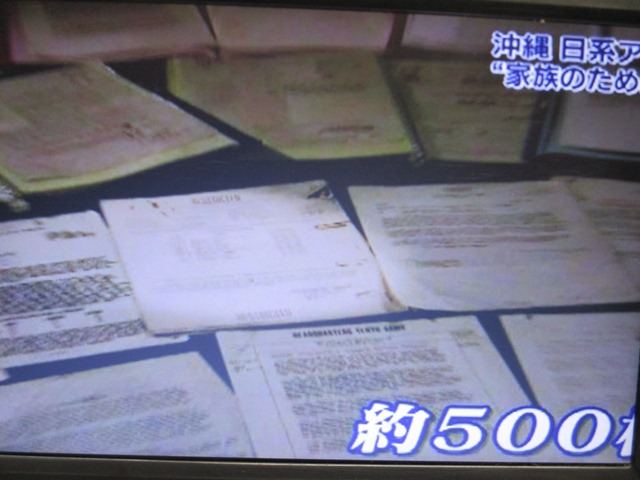
2015年4月15日9時 NHK総合「ニュースウオッチ9」に翁長コレクション登場





自宅(泊)屋上のソテツ
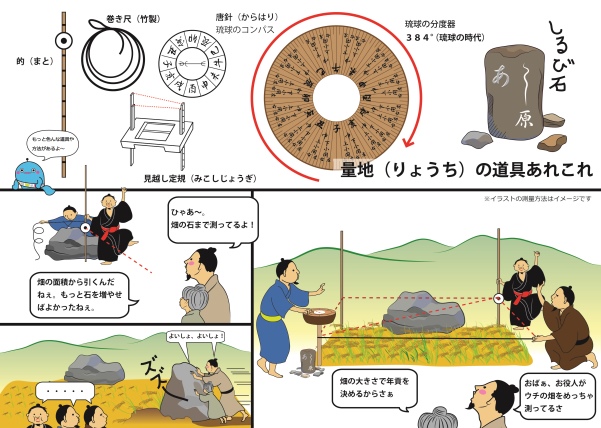
2014年月11月30日『新報小中学生新聞ーりゅうPON!』島袋百恵 絵「琉球の測量技術」

2014年月10月5日『新報小中学生新聞ーりゅうPON!』島袋百恵 絵「壺屋焼」
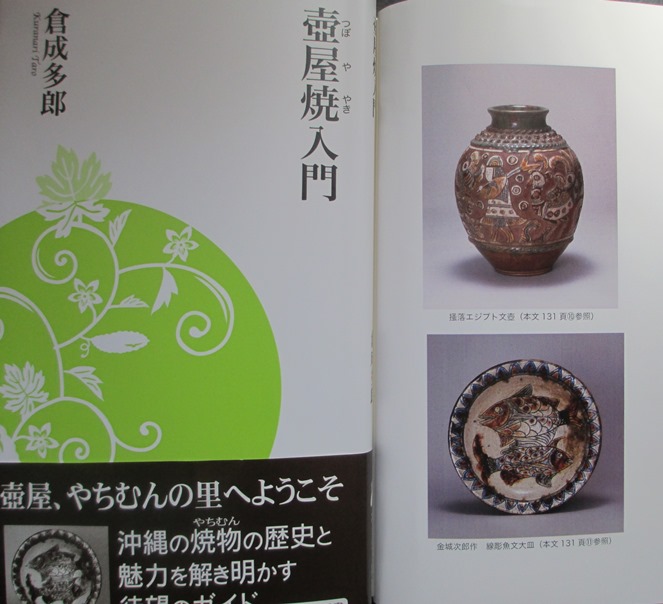
2014年7月 倉成多郎『壺屋焼入門』ボーダーインク

2014年6月14日ー写真左から岡本亜紀さん(浦添美術館)、粟国恭子さん(沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員)、倉成多郎氏(壺屋焼物博物館)、新城栄徳

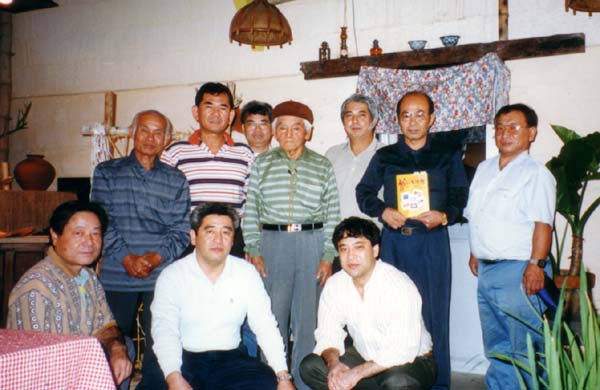
2001年11月ー「沖縄コレクター友の会発足」佐敷町ちゃんくすば中央が真栄城勇会長
私は1984年4月発行の『琉文手帖』1号の金城安太郎特集で東恩納を紹介した。うるま市にある石川歴史民俗資料館は戦後沖縄行政の出発点、沖縄諮詢会、沖縄県立博物館の前身の東恩納博物館、戦後初の小学校、終戦直後の松竹梅劇団、米軍服、HBTの更生衣料、2×4の材木でつくった規格住宅、カンカラ三線などを資料、写真で展示している。
1972年11月発行の雑誌『青い海』に園山精助(日本郵趣協会理事)が「琉球切手は語りつづける」と題し「沖縄切手のアルバムをひろげてみると、動物、魚、植物、風景、民俗、古文化財とよくもこれだけそろえられたものだと思う。こうしてみると、沖縄の歴史、文化の、ミニ百科事典ではないか」と記している。切手、古銭はコレクターの定番である。
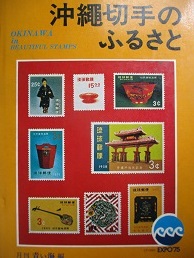
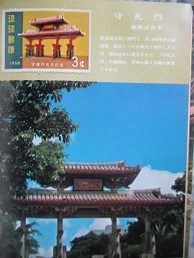
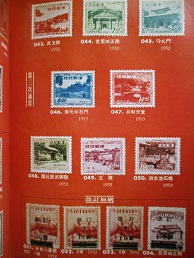
1973年3月 月刊青い海編『沖縄切手のふるさと』高倉出版会
2000年の10月、切手のコレクターとしても著名な真栄城勇氏の「勇のがらくた展」が佐敷町のちゃんくすばガーデンで開かれた。
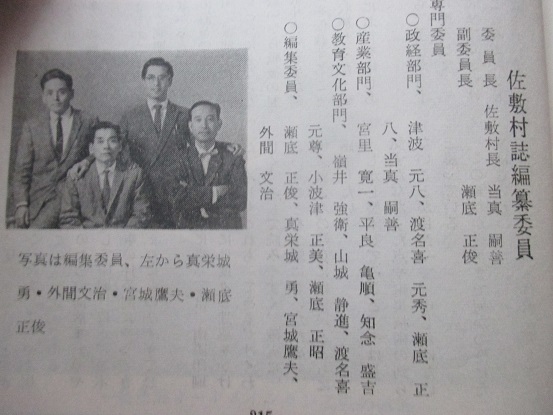
1964年3月 『佐敷村誌』佐敷村
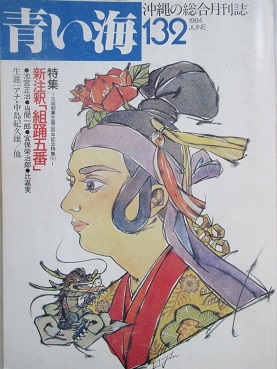

1984年5月 雑誌『青い海』132号 中島紀久雄「”生涯一アナ〟」
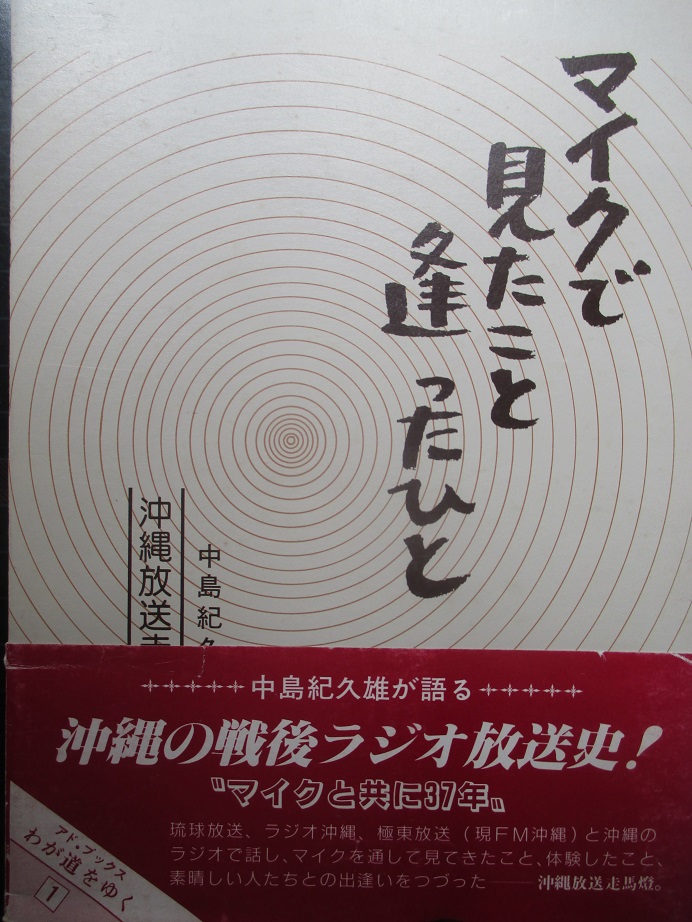
1989年10月 中島紀久雄『マイクで見たこと逢った人ー沖縄放送走馬燈』アドバイザー(西江弘孝)
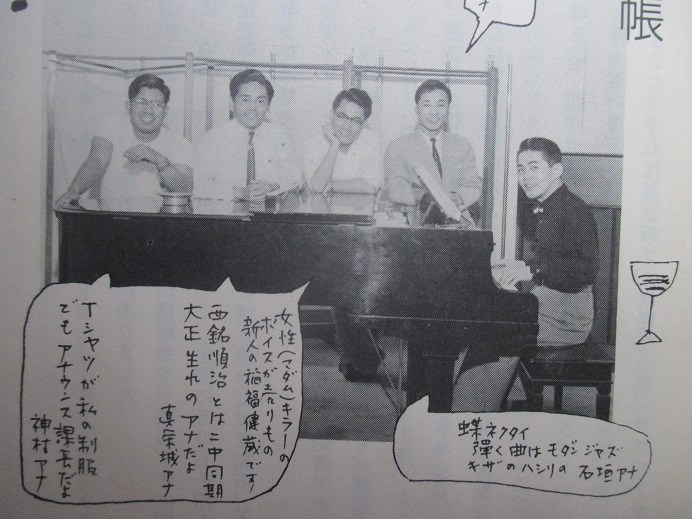
左から神村孝栄、真栄城勇、稲福健蔵、中島紀久雄、石垣正夫
眞栄城勇(琉球郵趣理事)ー南城市佐敷字伊原162-2 ℡946-6101
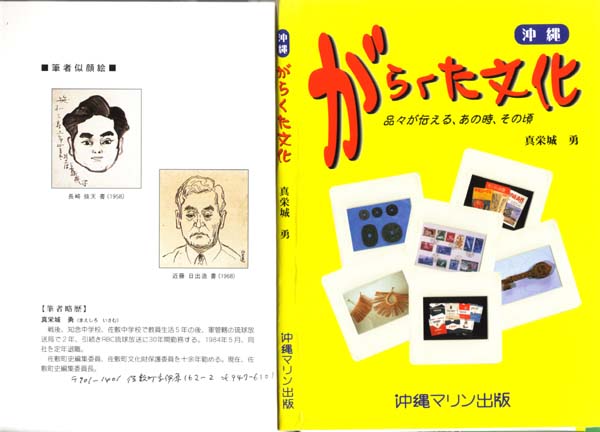
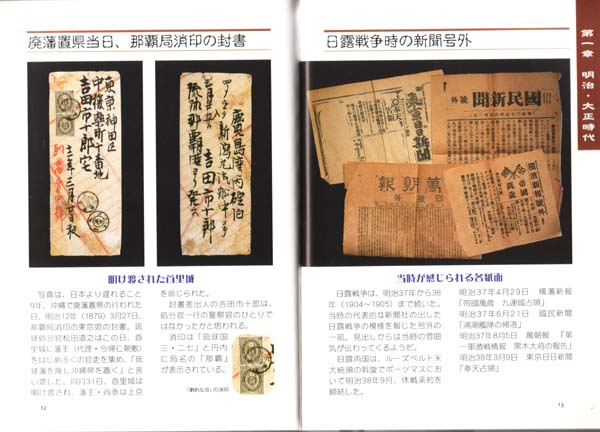
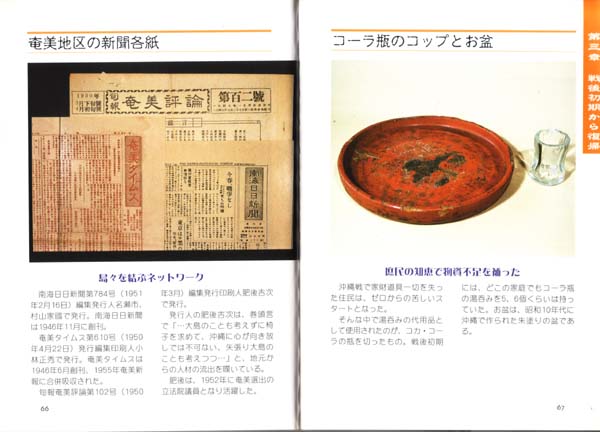
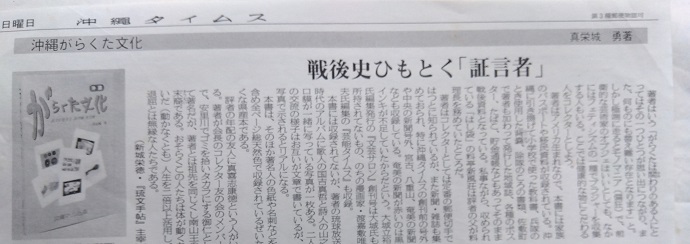
2001年8月ー眞栄城勇『がらくた文化ー品々が伝える、あの時、その頃』沖縄マリン出版/この本が切っ掛けで沖縄コレクター友の会が発足した。
2001年4月、前回と同じ場所で真栄城氏は「真栄城勇コレクション新聞号外展」を開いた。8月には沖縄マリン出版から真栄城勇著『沖縄がらくた文化ー品々が伝える、あの時、その頃』が出版された。私は、『沖縄タイムス』にその書評を書いたのが切っ掛けで2001年11月の佐敷町ちゃんくすばでのコレクター友の会発足に何となく参加した。

新城栄徳(左)、真栄城勇氏

新城栄徳、真栄城勇氏、鳥山やよいさん
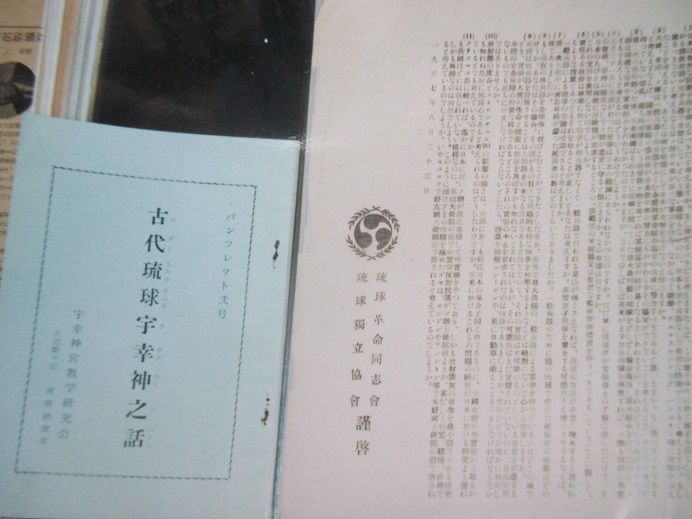
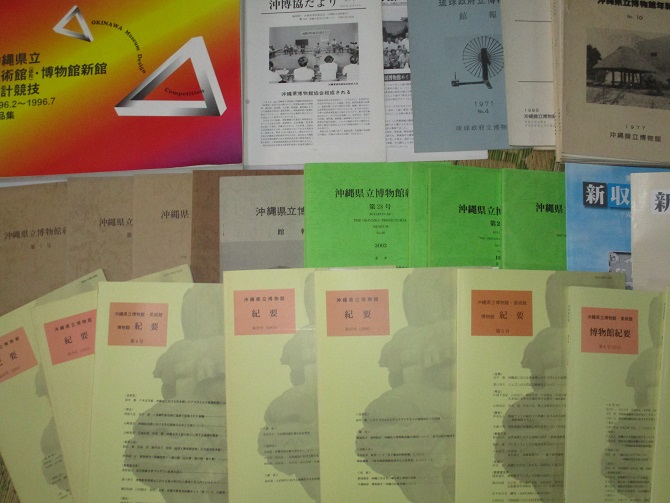
沖縄県立博物館・美術館

2023-3 ライブハウスの一角に「あいち沖縄文庫」誕生 800冊、渡久地政司さん、阪井芳貴さんらが寄贈
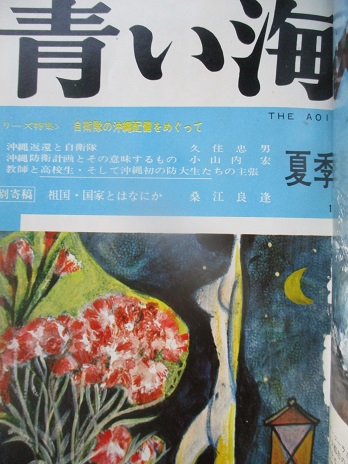
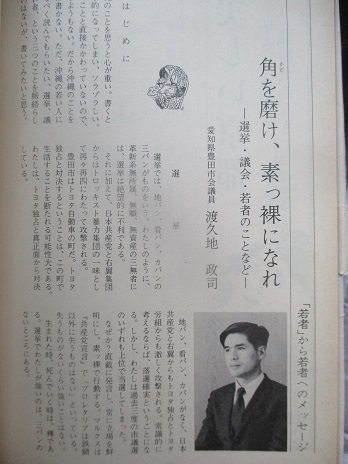
1971年8月 雑誌『青い海』4号 渡久地政司「角を磨け、素っ裸になれー選挙・議会・若者のことなどー」
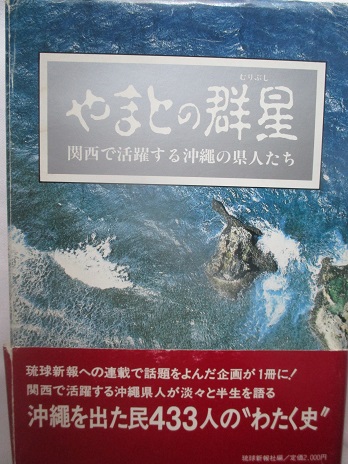
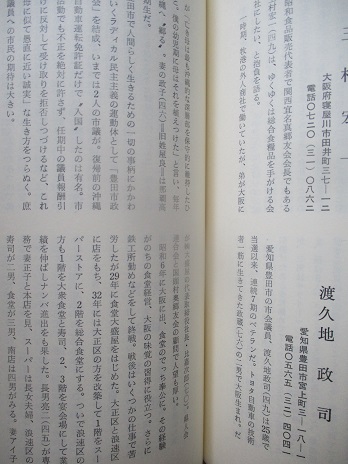
1987年8月 『やまとの群星/関西で活躍する沖縄の県人たち』琉球新報社 「渡久地政司」→本書は元『青い海』編集発行人で作家の津野創一が編集協力した。
愛知の中の沖縄 事柄覚 渡久地政司作成


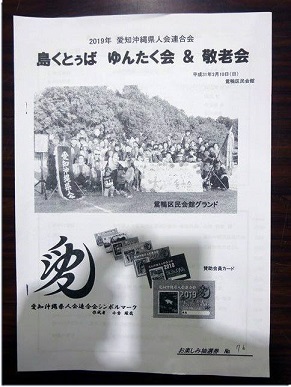

愛知沖縄県人会連合会総会・ゆんたく会・敬老会■ 2019年3月10日 豊田市鴛鴨町・鴛鴨公民館
最長老の屋嘉比信子さん(95)と比嘉俊太郎さん(80)屋嘉比さんは名古屋市今池で沖縄料理「糸満」を30~50年前に経営されていた方です。比嘉さんは、那覇高→名古屋工業大学→愛知工業大学名誉教授→愛知沖縄県人会連合会会長をなさった方です。お二人ともお元気でした。
1986年3月、琉球新報の松島弘明記者から、名古屋、三重のウチナーンチュの取材で大阪に来るという葉書(中城城跡)をもらった。後に琉球新報大阪支社に行き、私も旧知の人たちに会いたく名古屋に同行した。名古屋の県事務所の職員は大阪の県事務所でなじみのある人たちばかりであったので名古屋、三重のウチナーンチュ情報はすぐに得られた。
松島記者は取材過程で、「愛知県沖縄県人会会員名簿」「でいごの会会員名簿」(1974年10月)、「三重県沖縄県人会名簿」(1974年)、「沖縄県名古屋経営者会名簿」(1985年)などを入手した。麦門冬・末吉安恭の甥の佐渡山安正、佐渡山安治さん兄弟、粟国の末吉和一郎さんの取材には同行した。大濱皓氏は病気で会えなかった。
2010年1月31日、沖縄文化の杜で仲村顕さんから愛知の沖縄の話を聞いた。豊橋市に田島利三郎、犬山市には久志富佐子の墓があるという(後日、墓の写真も見た)。
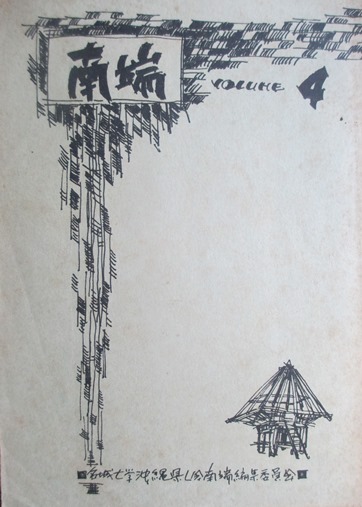
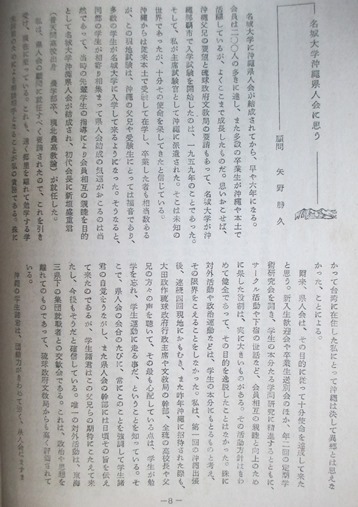
1965年7月 名城大学沖縄県人会『南端』(責任者・糸数哲夫)
糸数哲夫
昭和36年ー那覇高校卒。昭和44年ー名城大学大学院法学研究科修、商学修士、法学修士。昭和44年ー名古屋在加茂会事務所入所。昭和50年ー那覇市にて税理士事務所開業→現在は沖縄県宜野湾市字我如古。
大阪・沖縄関係資料室で『阿姓家譜』(阿姓南風原按司守忠 7世西平親雲上守安4男)の原本を見たことがある。資料室主宰の西平守晴氏が実兄から譲られたものである。複製本が那覇市歴史博物館にある。『氏集』を見ると、阿氏には前川、渡名喜、西平、小濱、渡嘉敷、宮平、瀬良垣、伊舎堂、與儀、喜瀬、山元、安和、佐久田、眞謝、江田、金城、照屋の諸家がある。
名古屋の渡久地政司(とぐち まさしー1937(昭和12)年6月2日、大阪市で生れる。豊田市で育つ。73歳、第3の人生のスタート。体と思考を「解す」だけでなく鍛える。)氏のブログに氏の調査で「○ 太田守松 父渡名喜守重、母なべの長男として沖縄県那覇市東町1丁目20番地で明治35年(1902)生まれる。泉崎小学校、沖縄1中卒、神戸高等商業学校卒。滋賀県立彦根商業学校教諭(大正14年4月)。昭和3年短歌会『国民文学』に入社・植松寿樹に師事。以後、短歌運動。昭和22年3月、日本キリスト教団彦根教会で洗礼。1947年(昭和22年10月)、渡名喜姓を先祖が使用していた太田姓に改名。昭和23年、彦根市立西中学校校長。昭和27年、彦根YWCA創立理事長。昭和34年、井伊大老開国百年祭奉賛会事務局次長。昭和38年、原水爆禁止彦根市協議会会長。昭和45年1月、脳溢血で逝去(67)。
○ 太田菊子 父豊見山安健、母オト(1882年生まれ)の長女として 1905年(明治38)沖縄県那覇市で生まれる。沖縄県立第1高等女学校卒業1921年(大正10)、東京山脇高等女学校卒業1924年(大正13)。大正14年12月、渡名喜守松と結婚。平成5年(1993)逝去(88)・1962年(昭和37年2月)。長年同居の母オト逝去(80歳)。」と太田守松と夫人が紹介されている。守松氏も阿氏である。


2019年3月5日 寒緋桜 満開■沖縄・名護市の農事試験場をルーツにする寒緋桜が満開となりました。場所は宮上公園東側とその後方。3月5日、青空をもピンクにしかねないくらいの勢い、通行中の人々は「まぁ奇麗」の歓声をあげていました。
「渡久地政司ブログ」(略記)2005年7月28日
■ 愛知の中の沖縄 事柄覚 ■
● 名古屋市東区徳川町にある徳川美術館には、琉球王国の文化財が多く収蔵されている。…徳川美術館に20点の琉球楽器、むかし御座楽(うざがく)に使われた楽器が保存
…、寛政8(1796)年に江戸上がりの使者から贈られたという記録が残って…出自がはっきりしているのは、日本中で徳川美術館の楽器だけ…。
大野道雄「徳川美術館の琉球楽器」から抜粋。
● 琉球王国賀慶使・恩謝使(琉球国使江戸上がり)が1610年から1872年までの間、18回おこなわれている。上がり、下がりを入れると約34回、愛知の土地を通過している。
1610(慶長15)年の場合、上がり…8月2日美濃大垣泊、3日尾張清州・成興寺泊、5日岡崎泊、6日吉田(豊橋)泊。下り…9月22日木曽福島泊、24日美濃路落合泊、27日岐阜本誓寺泊…であった。
佐渡山安治(詳細は後記)の調査によれば、寛延(1749)年の江戸上がりの時に殉死した「麻氏渡嘉敷親雲上真厳玄性居士之墓」(古塚達朗「江戸上りの足跡」96-4-2沖縄タイムスでは墓は行方不明とある。しかし、佐渡山安治資料「寛延2年の墓碑」76-3-28沖縄タイムスでは、所在地を発見、と写真入りの記事がある。)と天保3(1832)年に殉死した富山親雲上の墳墓が名古屋市緑区鳴海の瑞泉寺にある。佐渡山安治資料昭和54-12-14沖縄タイムスには、…11月4日、26年ぶりで待望の琉球行列を名古屋に迎える段になって「琉球人通行朝7ツ(午前4時)より本町通京町其外通りに提灯をだし賑合、此日薩摩五ツ過(午前8時)頃御通行、琉球人の行列に先立って、稲葉宿から棺桶が一つ、ひっそりと運ばれて…」。
● 明治26(1893)年9月1日から10日ま で名古屋市で沖縄芝居の興行が行われている。御園座の近くにあった千歳座(広小路南桑名町)。出し物は女花笠踊、上りの口説、下りの口説、女団扇踊、国頭(クンジャン)さばくいなど…、全部ウチナーグチで演じ、客の入りはよくなかったようで、入場料の値引きをしている。明治30(1897)年6月13日、再び名古屋を訪れ、南伏見町の音羽座で公演している。 大野道雄資料から抜粋。
01/09: 沖縄県立博物館・美術館「大城精徳の仕事」
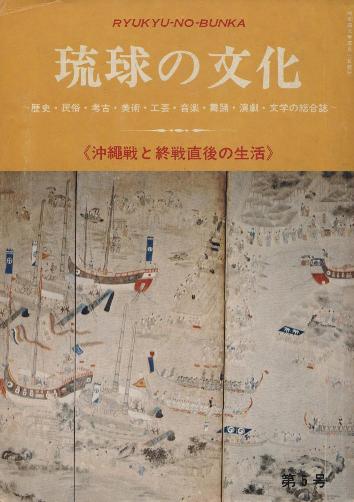
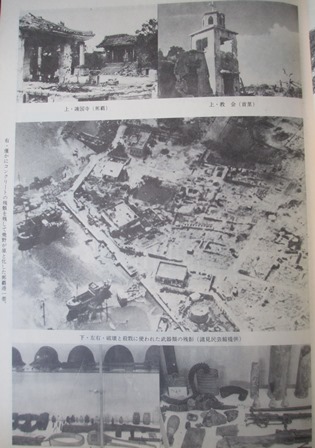
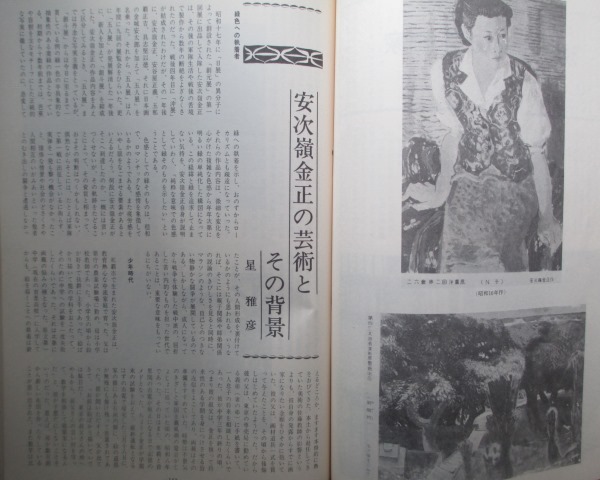
1974年5月ー『琉球の文化』第五号 星雅彦「安次嶺金正の芸術とその背景」
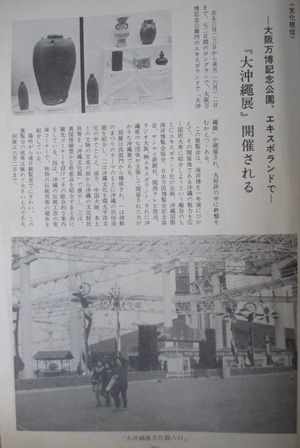
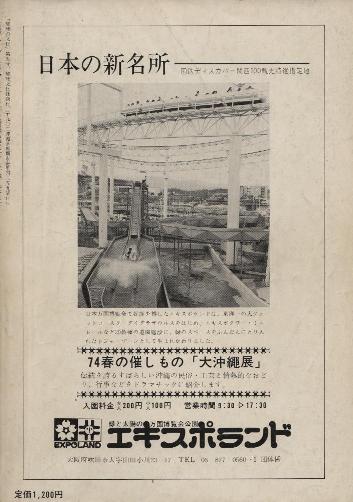
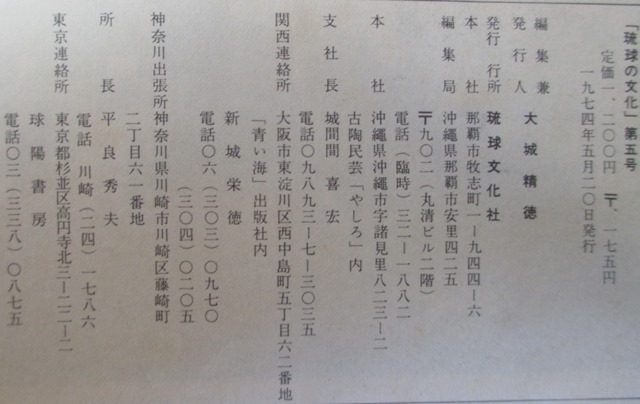
1974年5月ー『琉球の文化』第五号<沖縄戦と終戦直後の生活>
琉球文化社(編集発行人・大城精徳)本社〒那覇市牧志町1-944-6 編集局〒902那覇市安里425丸清ビル2階
関西連絡所ー大阪市東淀川区西中島町5-62青い海出版社内(新城栄徳)
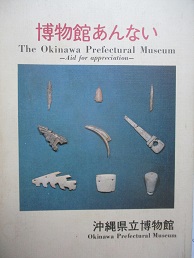
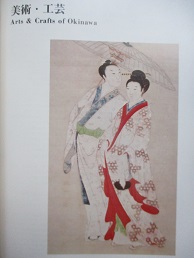
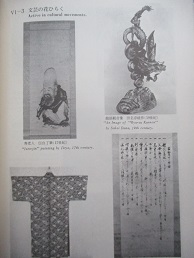
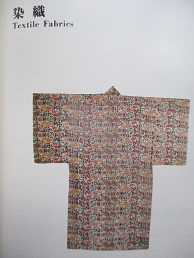
1975年6月 沖縄県立博物館『博物館あんない』琉球文化社
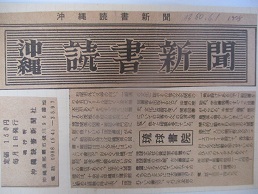
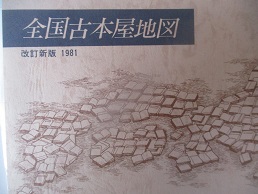
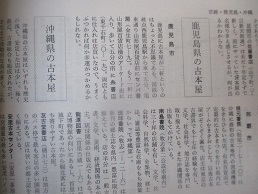
1975年6月1日『沖縄読書新聞』「琉球書院」/1981年6月『全国古本屋地図』「沖縄県の古本屋」
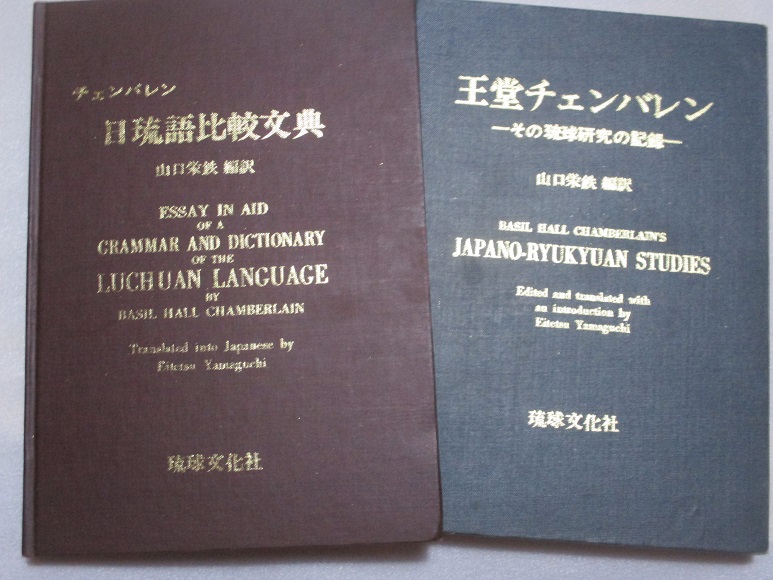

1976年3月 山口栄鉄『チェンバレン 日琉語比較文典』琉球文化社 1976年5月 山口栄鉄『王堂チェンバレンーその琉球研究の記録ー』琉球文化社/写真・1978年8月ー那覇市一銀通りの琉球書院(琉球文化社)と青い海出版社の看板が見える。
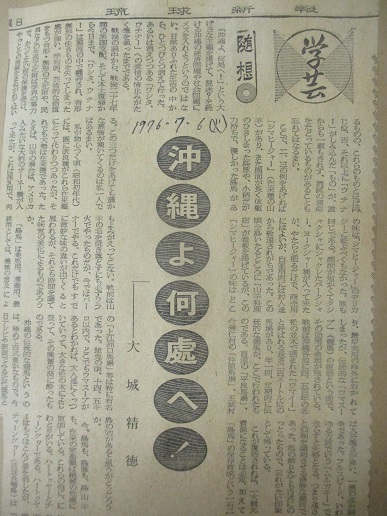
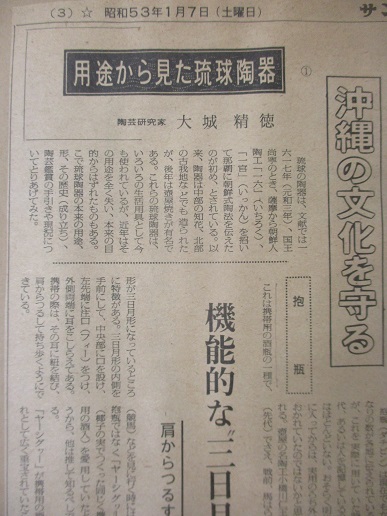
1976年7月9日『琉球新報』大城精徳「沖縄よ何處へ!」/1978年1月7日『サンデーおきなわ』大城精徳「沖縄の文化を守るー用途から見た琉球陶器①」
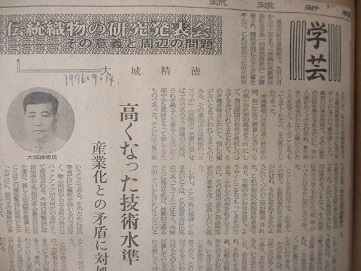
佐久田繁ー沖縄戦の写真、あなたでも買えます/琉球文化社の大城精徳君によると、『金さえ出せば、ペンタゴンでは誰でも買えるんだ』というのである。そして大城君が注文した写真が二か月後に、ペンタゴンから郵送されてきた。その写真をもとに私は、1977年8月『日本最後の戦い・沖縄戦記録写真集』を出版、沖縄三越で写真展もやった。/佐久田繁さんにはアメリカ行きの資金がありません。そのとき、たまたま琉球文化社(出版社)の大城精徳氏が渡米するという話を小耳に挟み、佐久田さんが同氏の描いた絵を買い取ることを条件に旅費の一部を負担して、資料収集を依頼しました。大城氏なら沖縄戦の資料価値を適切に判断できると踏んだのです。→藤田修司(新日本教育図書社長)「異能の人、逝くー出版人佐久田繁氏との思い出」『沖縄県産本ニュース』2005年9月
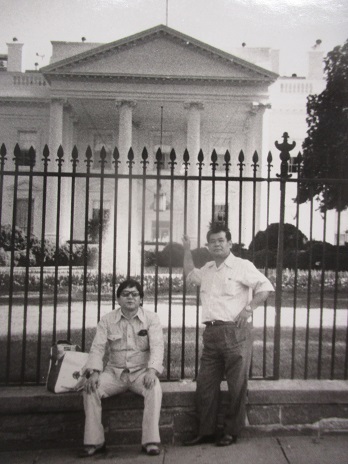

ワシントンⅮ,Ⅽホワイトハウス/18世紀当時の歴史深い建物に囲まれた、ミシシッピ川沿いのジャクソンスクエアは、特に音楽、アート好きなら絶対立ち寄りたい、現代文化と歴史がうまく調合した、活気あふれた公園です。公園内に入ると、ここをアートスタジオとする、公園中に見られるアーティストたちの才能にも絶句ものです。ご自分へのお土産に、ポートレイトやカリカチュアを描いてもらうのもいいです。


1977年5月
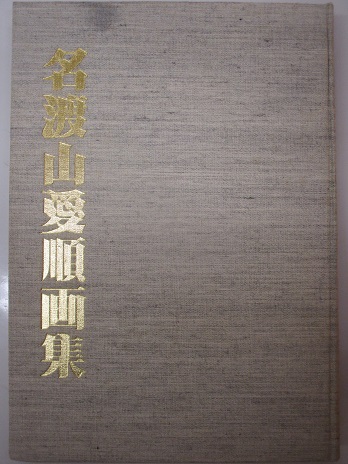

1979年7月 『名渡山愛順画集』琉球新報社〇刊行委員会ー池宮城秀意、石野朝季、大城精徳、久場トヨ、高江洲盛一、田積友吉郎、名渡山愛擴、比嘉良勝、又吉真三、宮城篤正、山元文子」
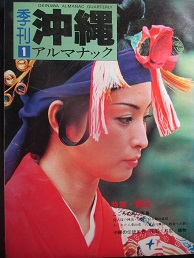
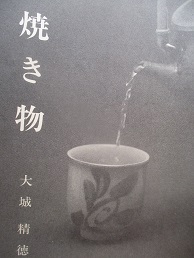
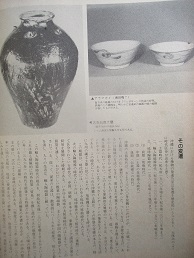
1979年10月『沖縄アルマナック』大城精徳「沖縄の伝統工芸ー焼き物」社会経済研究所
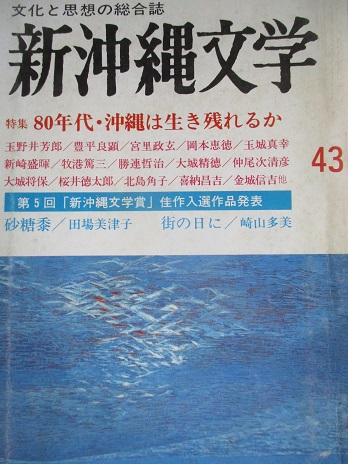
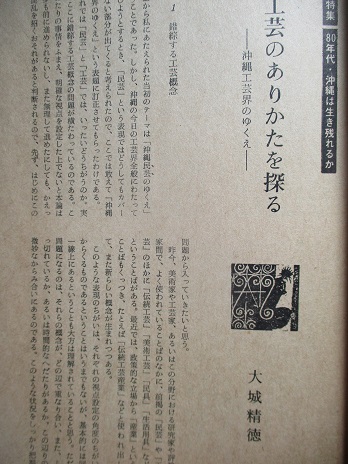
1979年11月『新沖縄文学』43号 大城精徳「工芸のありかたを探るー沖縄工芸界のゆくえ」
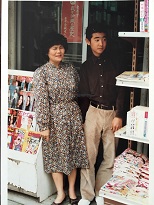


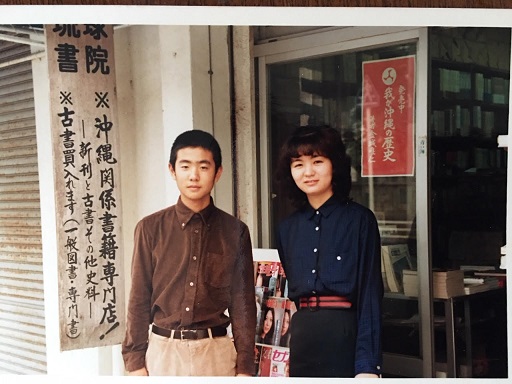
1980年 琉球文化社の前でー大城修くん、澄子さん、藤子さん
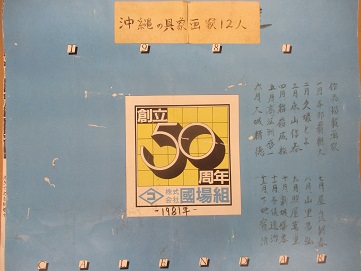
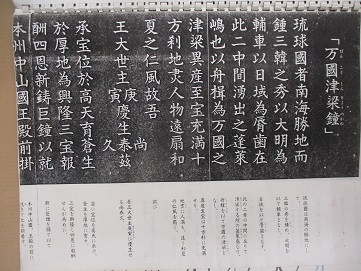


1981年 「沖縄の12人の画家たち」(國場組創立50周年カレンダー)大城精徳「島の浜辺」F60号(金城竹治氏所蔵)


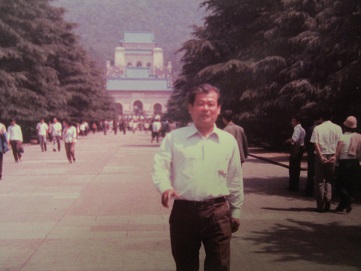
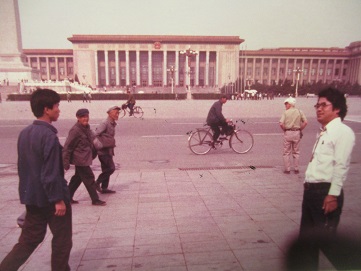

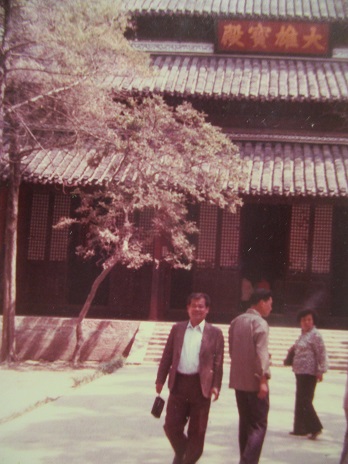
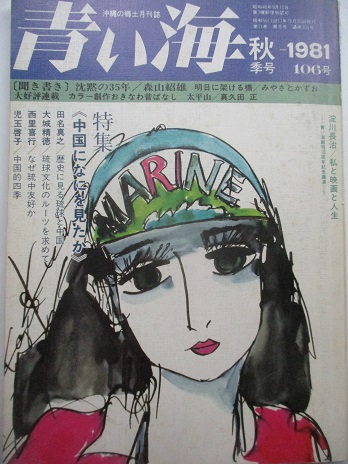
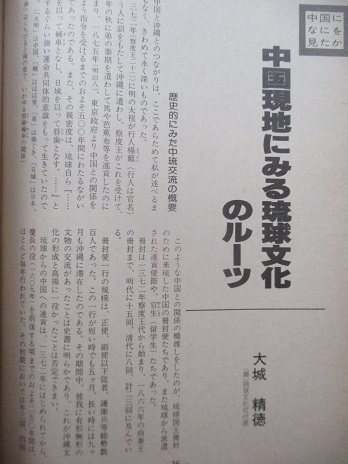
1981年9月 沖縄の雑誌『青い海』106号 大城精徳「中国現地にみる 琉球文化のルーツ」







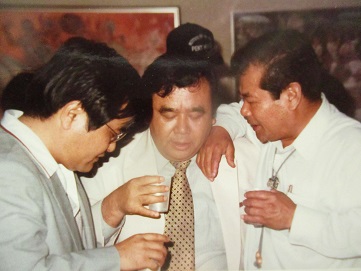
1982年1月10日 「新生美術協会」発足(大嶺政寛会長)
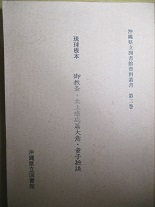
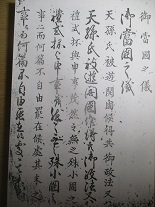
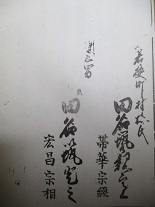
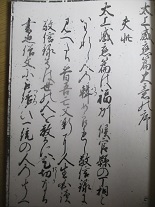
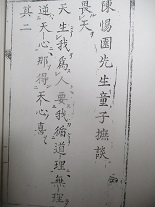
1982年3月 『琉球刊本 御教条・太上感応大意・童子摭談』(沖縄県立図書館資料叢書 第三巻)発売元・琉球文化社
1982年3月 『大里村史』(通史編 資料編)編集委員・大城精徳
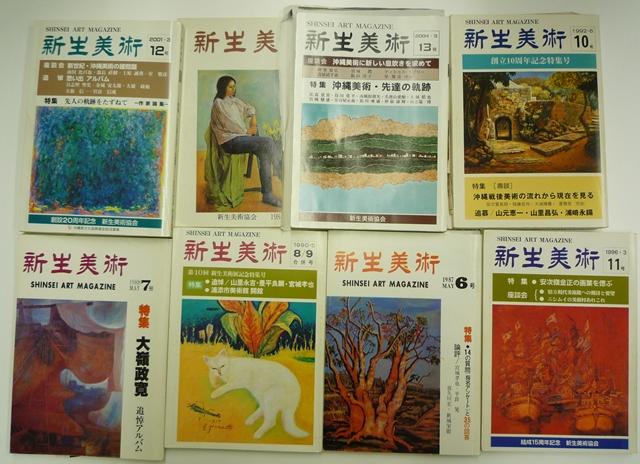
1982年9月『新生美術』創刊号 事務局・沖縄県那覇市牧志1-12-6 琉球文化社
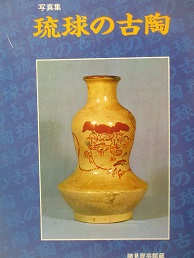
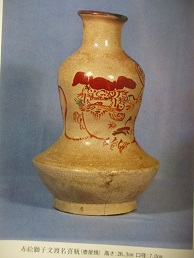
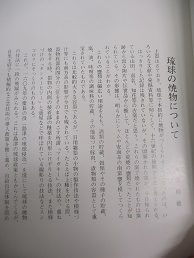
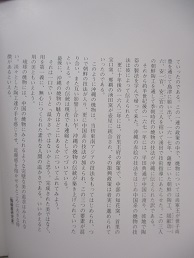
1982年5月 『琉球の古陶』大城精徳「琉球の焼物について」諸見民芸館
1982年5月 新城栄徳、天久宮近くの関西沖縄県人会運動の先駆者・浦崎康華翁を訪ねる。同年9月の八汐荘の大里康永氏の出版祝賀会に同行。帰りも同行し、国吉真哲翁の家の前で「ここは親友の家」と紹介された。のちに国吉家にも出入りする。
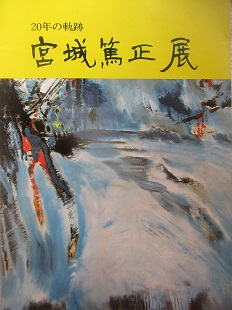
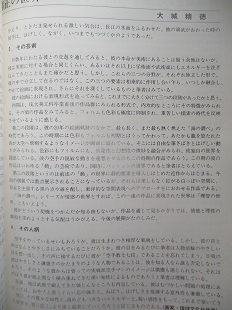
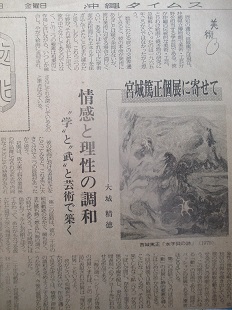
1982年9月18日~21日 浦添市民会館中ホール『宮城篤正展』大城精徳「学術と武術と芸術の調和の上に築かれた宮城篤正の世界」/9月17日『沖縄タイムス』大城精徳「宮城篤正展に寄せて」
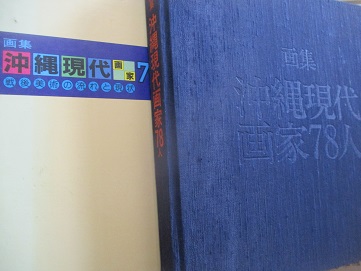
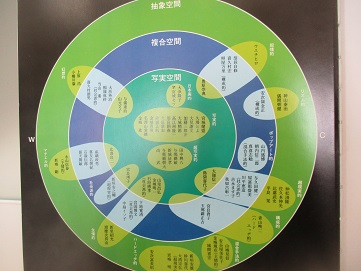
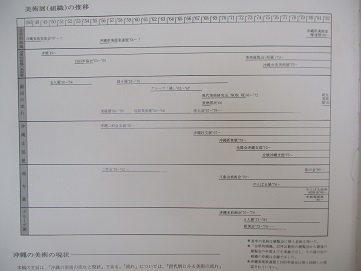
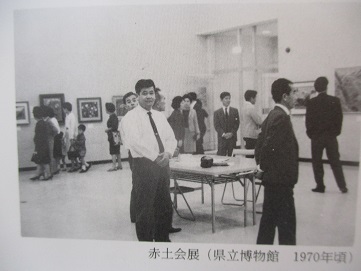
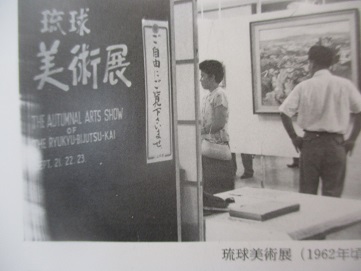
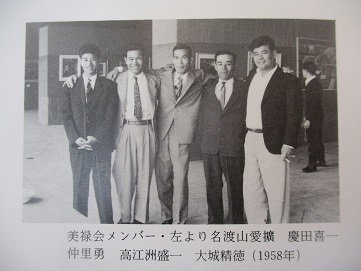
1982年11月 島袋捷子『沖縄現代画家78人』月刊沖縄社


1988年6月28日「われら同期会」沖縄県立農林学校旧校舎の一角/出版祝賀会
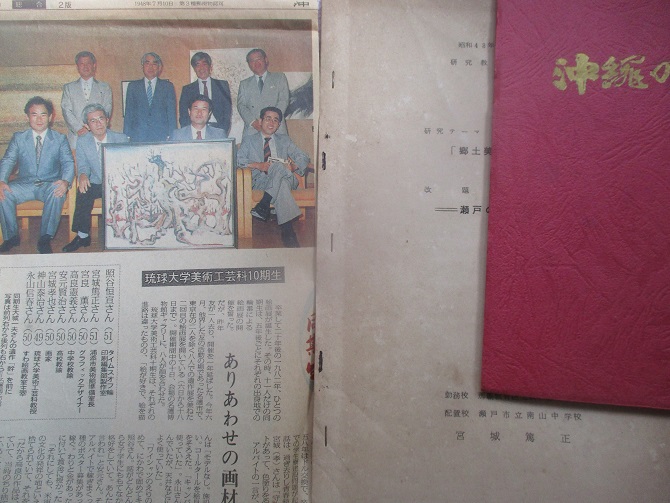
1989年6月15日『沖縄タイムス』「われら同期生ー琉球大学美術工芸科10期生/照屋恒宣、宮城篤正、宮良薫、高良憲義、安元賢治、宮城孝也、神山泰治、永山信春ー同期生大城一夫さんの遺作『幹』を前に」/1968年12月宮城篤正『沖縄の美術』
1982年12月『新沖縄文学』54号 「座談会・食文化の交流ー大城精徳・高良倉吉、比嘉政夫、又吉盛清、宮城篤正」
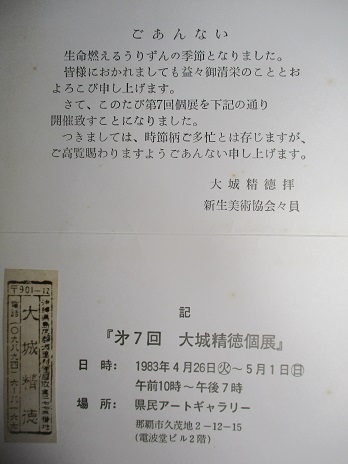

1983年4月26日~5月1日 県民アートギャラリー(電波堂ビル2階)「第7回 大城精徳個展」/2019年12月25日「古美術なるみ堂」にてー「房指輪」「ジーファー」を見る店主の翁長良明氏、哲楽家・紀々さん→紀々の公式サイト「首里城が出来た時の龍のモチーフを見て生まれた『龍神伝説』という曲」。→ 電波堂☆沖縄ソニー坊や博物館

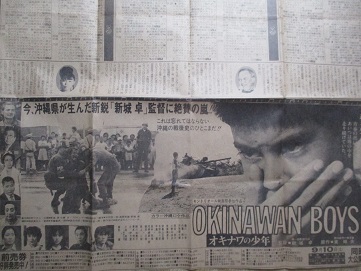
1983年8月21日『琉球新報』
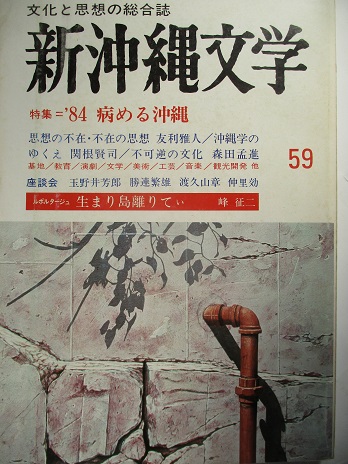
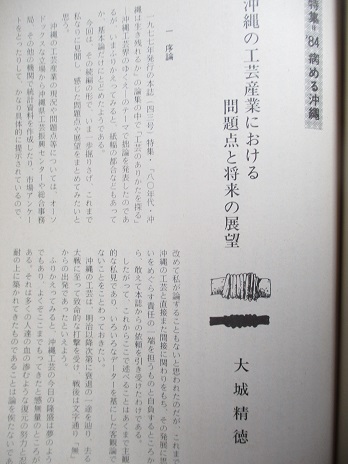
1984年3月『新沖縄文学』59号 大城精徳「沖縄工芸産業における問題点と将来の展望」
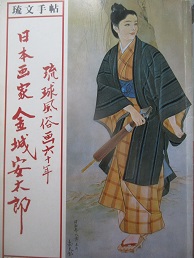
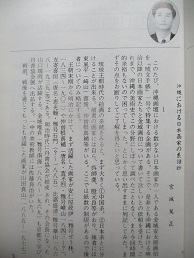
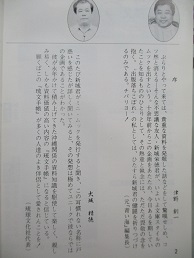
1984年4月 新城栄徳『琉文手帖』1号「琉球風俗画六十年 日本画家 金城安太郎」津野創一/大城精徳「序」、宮城篤正「沖縄における日本画家の系譜抄」
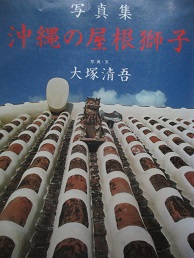
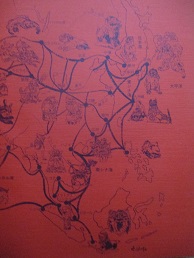

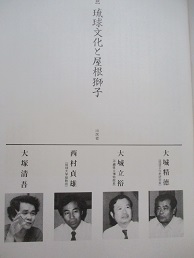
1984年4月 大塚清吾『写真集 沖縄の屋根獅子』「座談ー琉球文化と屋根獅子/大城精徳・大城立裕・西村貞雄・大塚清吾」葦書房(福岡市)
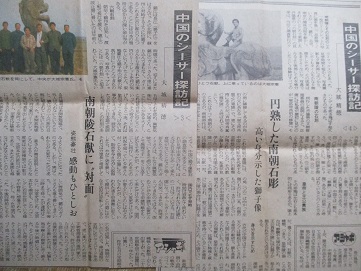
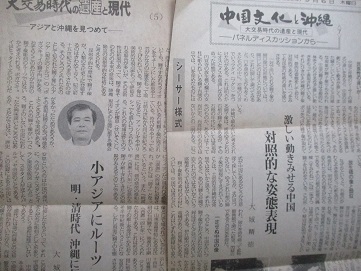
1984年6月『琉球新報』大城精徳「中国のシーサー探訪記」/大城精徳「大交易時代の遺産と現代ー獅子像」「中国文化と沖縄―シーサー様式」
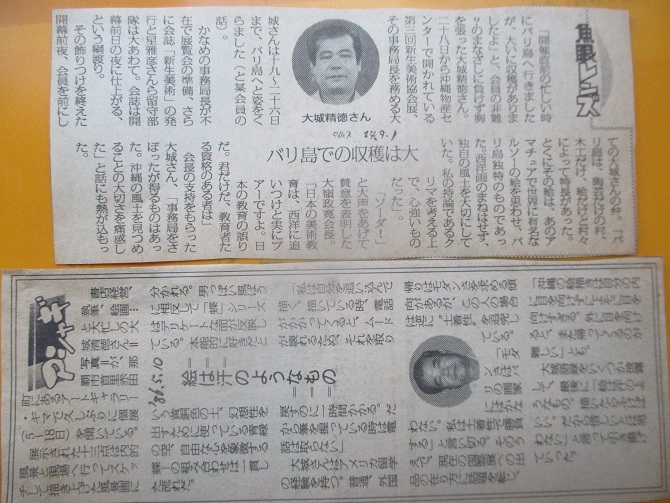
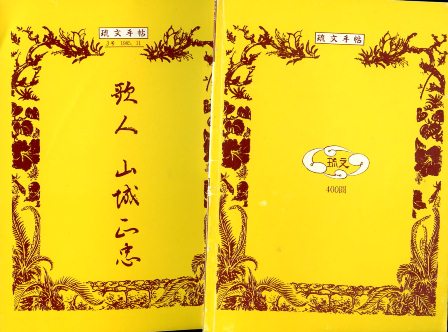
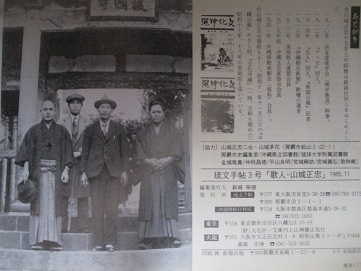
1985年11月『琉文手帖』3号「歌人 山城正忠」「歌人・山城正忠」の題字は彦根の井伊文子さん。

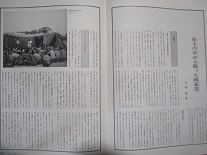
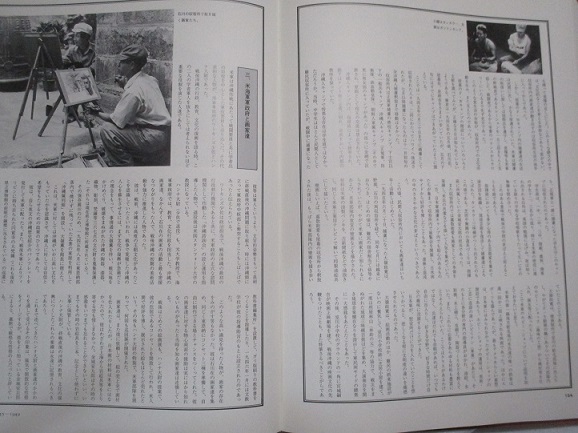
1986年5月『写真集 沖縄戦後史』那覇出版社 大城精徳「焦土の中から甦った画家たち」
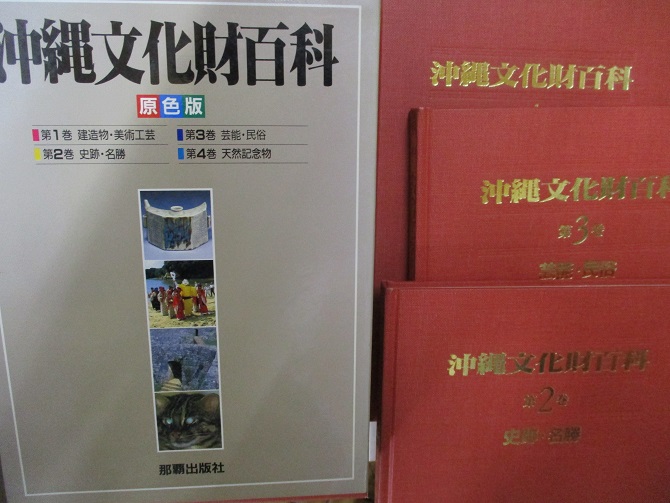
1988年4月 『沖縄文化財百科』「監修者・又吉真三、富島壮英、宮城篤正、大城精徳、名嘉真宜勝、大城志津子、糸数兼治、嵩元政秀、当間一郎、宜保栄治郎、池原貞雄、多和田真淳」那覇出版社
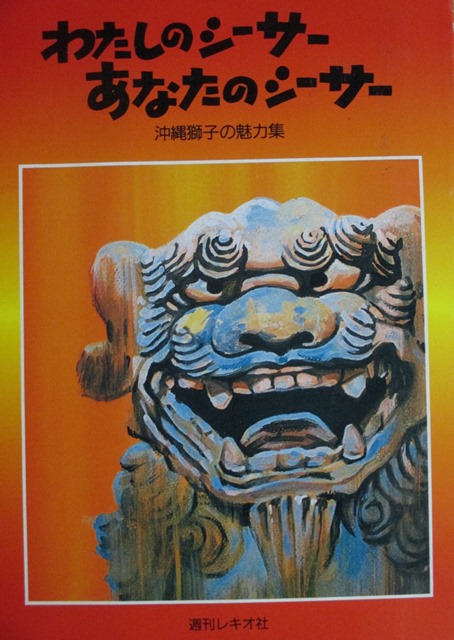
1989年2月 『わたしのシーサー あなたのシーサー 沖縄獅子の魅力集』週刊レキオ社
大城精徳□獅子が中国伝来のことばであることはいうまでもないが、先に述べた日本語のシシとは違い、中国語ではライオンを意味することばなのである、しかし中国には元来ライオンは棲息していないので、この中国語も外来語だった。中国人がライオンに接したのは西域との交易を通してであった。時代は漢代であよそ2千年前である。西暦76年には今のアフガニスタンとイラン東部に興った「安息」(パルティア帝国)という国から獅子が献上品としてもちこまれたこともあった。この地方の当時のことばではライオンのことを「シ」(SHI)といった。この「シ」という音に中国では、はじめ「師」という漢字を当て、のちに犭偏をつけて「獅」になったとのことである。獅子の「子」については中国語によくみうけられる接尾語で特別な意味はない。
1989年11月 『沖縄美術全集』沖縄タイムス社 宮城篤正「琉球の陶器」/大城精徳「近・現代沖縄の焼物」

左から新城栄徳、宮城篤正氏、大城精徳氏
写真ー1983年4月 『師父 志喜屋孝信』志喜屋孝信先生遺徳顕彰事業期成会 志喜屋孝信(1884年4月19日~1955年1月26日)〇1904年3月、沖縄県立中学校卒業、志喜屋孝信、川平朝令、山川文信、久高将旺、山田有登。4月ー志喜屋孝信、広島高等師範学校(数物化学科)入学。このころ内村鑑三を愛読。玉川学園の創始者小原国芳と親交。1908年3月卒業。4月、岡山県金光中学校に奉職。岡山出身の山室軍平の思想に親近感を抱く。12月、熊本県立鹿本中学校に転任。1911年12月、沖縄県立第二中学校に赴任。1924年3月、校長に就任。1936年3月、二中校長辞し、私立開南中学校を創設、理事長兼校長となる。
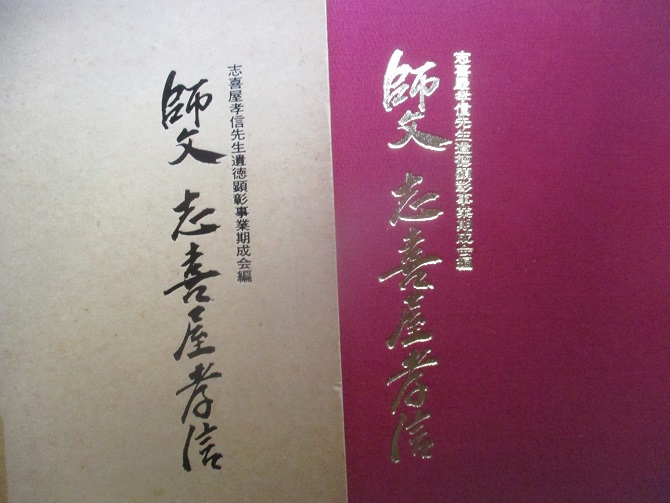
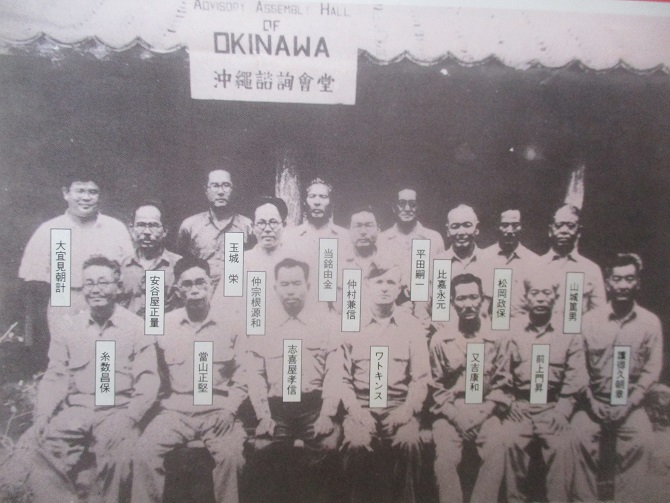
写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。
写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳
写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

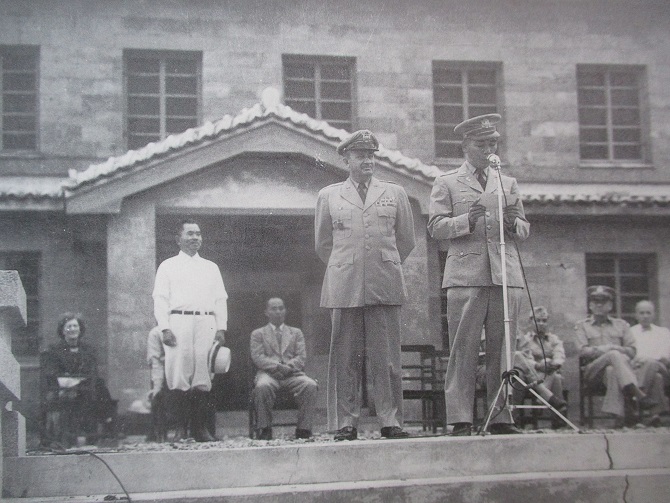
本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。
昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。
1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。
1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。
1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」
1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。
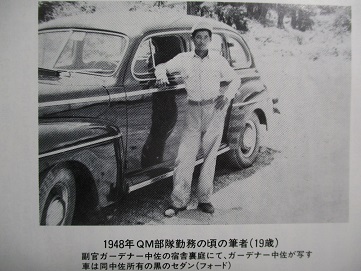
1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号
〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。
1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

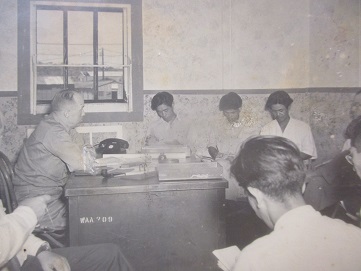
写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

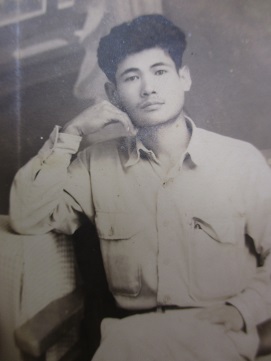
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて


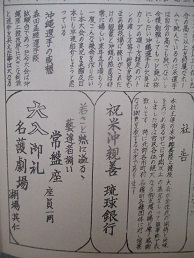
1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号
1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。
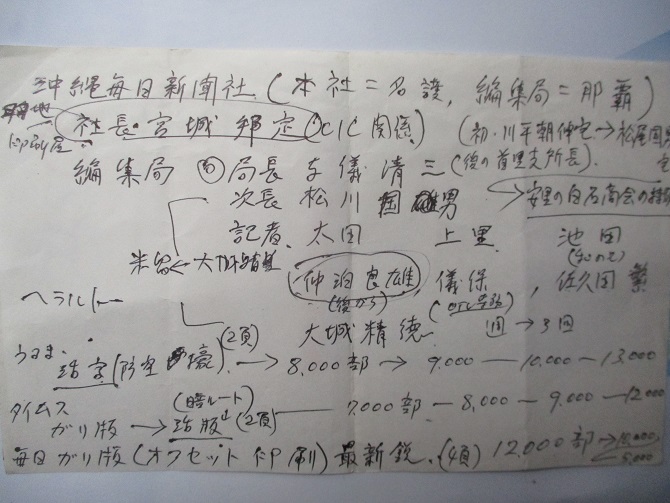
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展
1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。


写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳
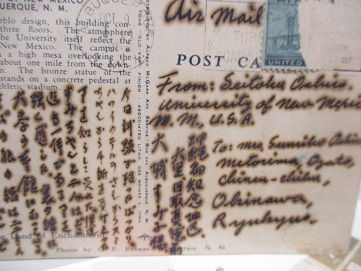
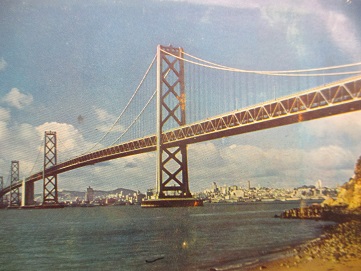
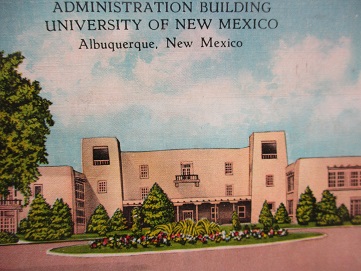

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳


1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山
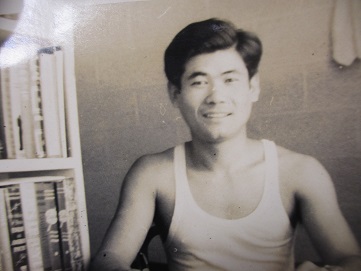

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順
ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」
1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
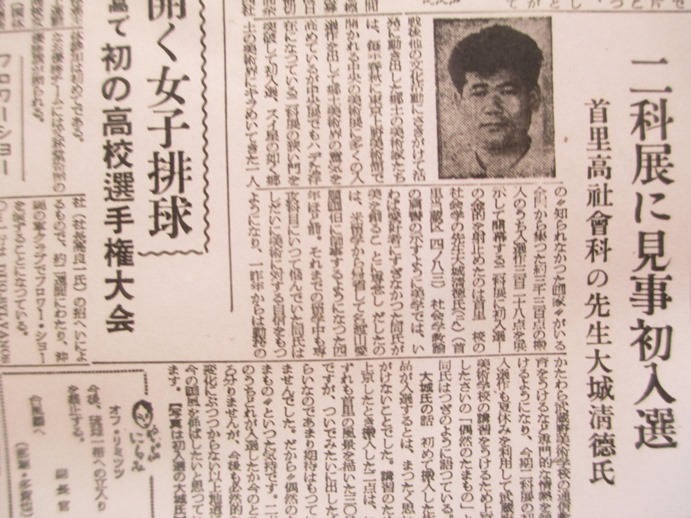
1956年9月1日『琉球新報』

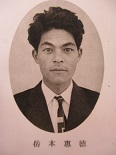
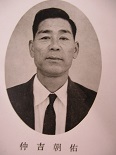
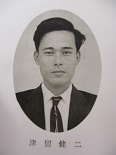
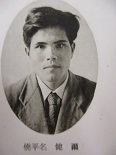
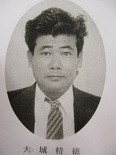
首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク
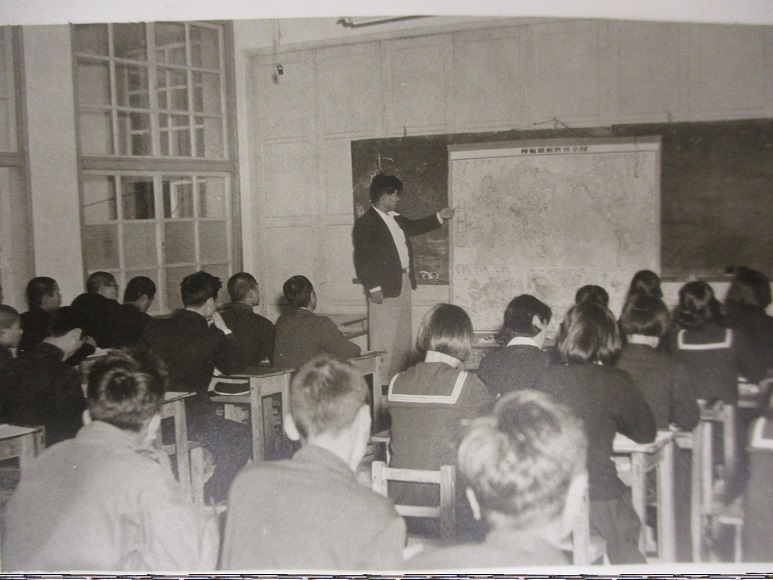
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

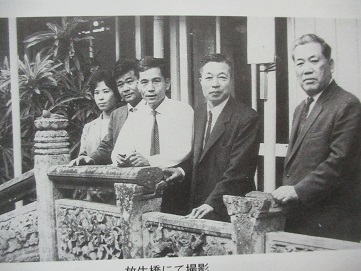
左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』
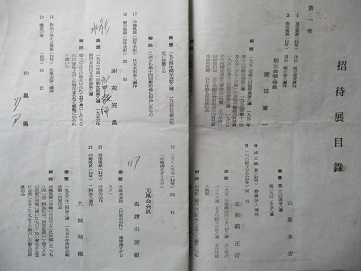
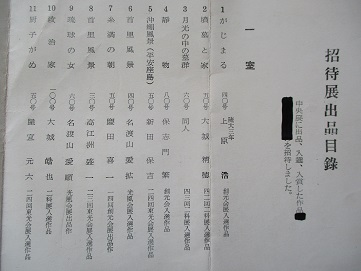
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
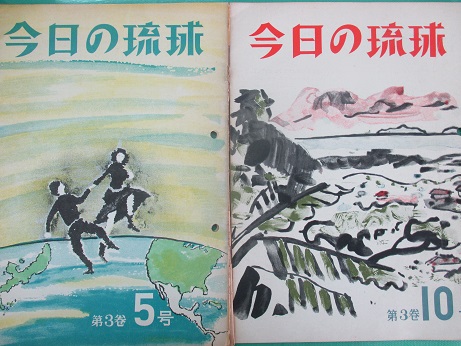
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

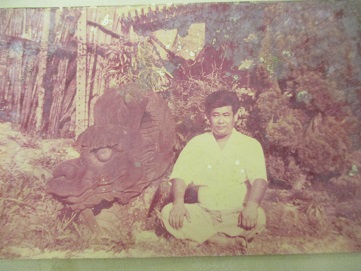


1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて
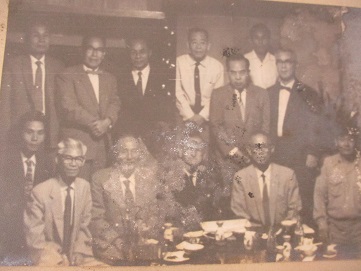

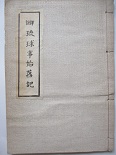




1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。
1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)
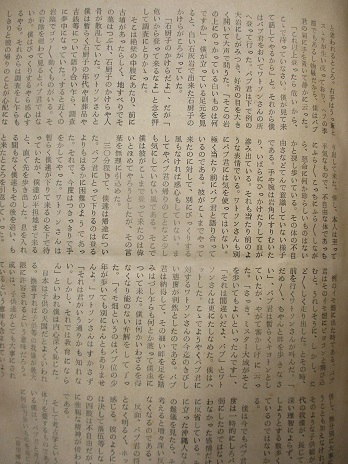
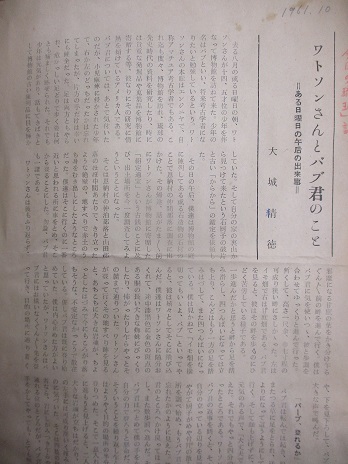
1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」
1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。
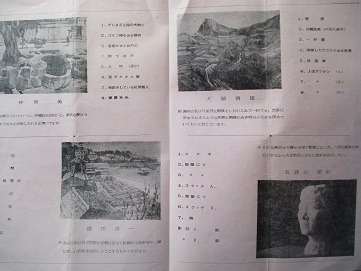
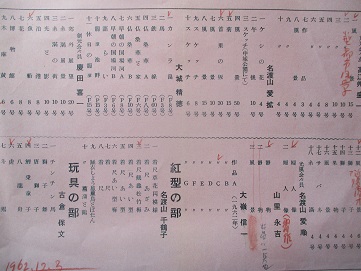
1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館
1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。
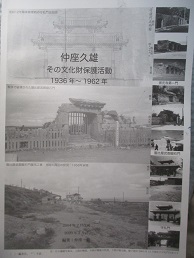
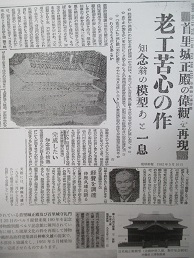
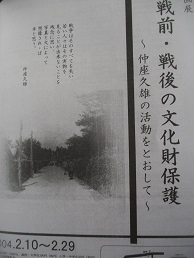
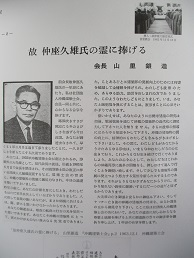
【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』
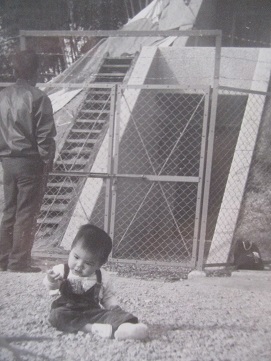
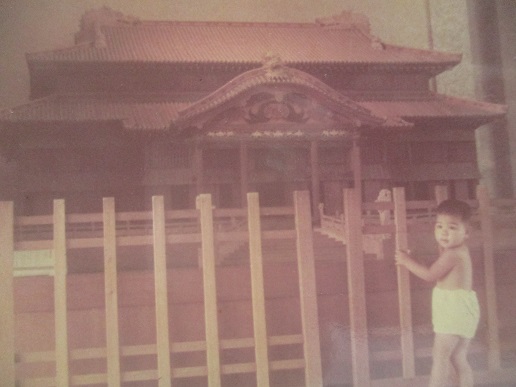
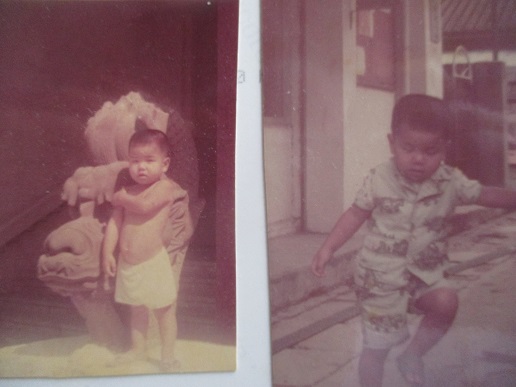
【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

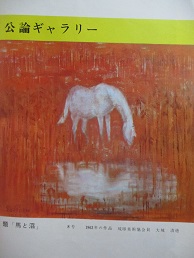
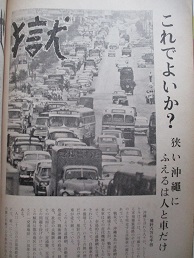
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
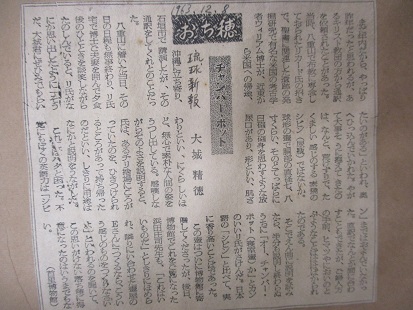
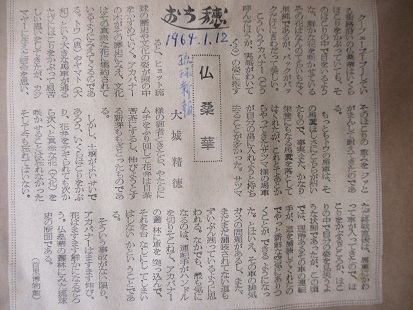
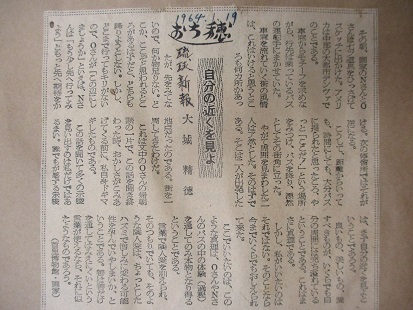
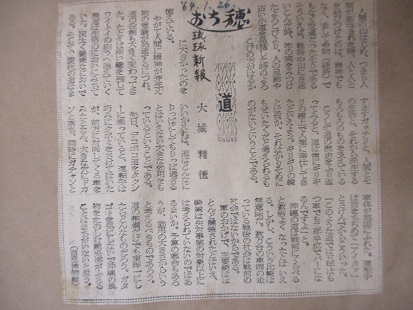
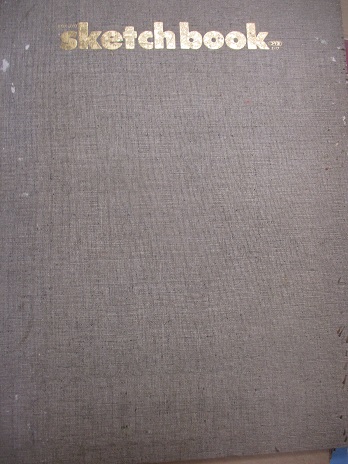

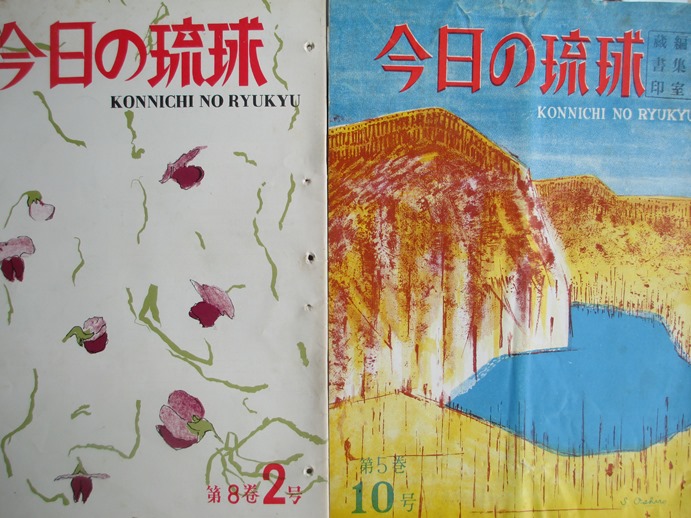
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」
1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。
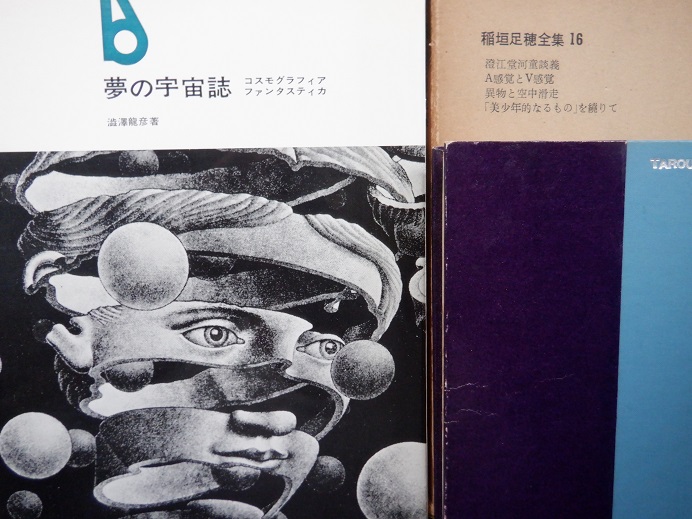
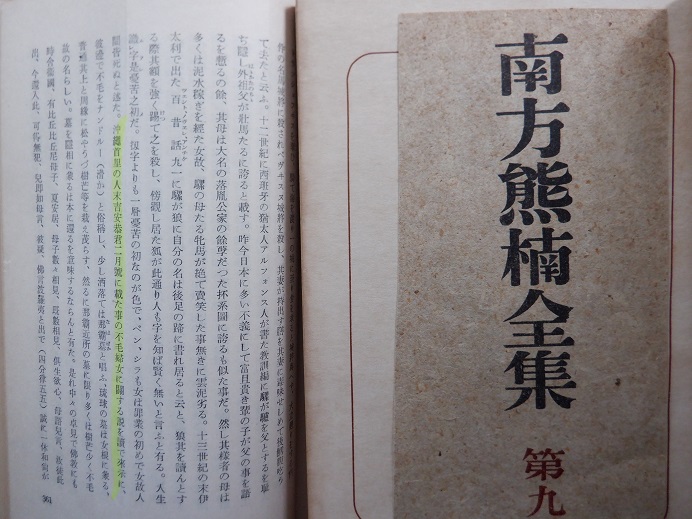
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
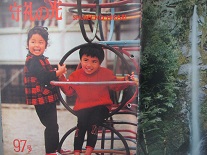
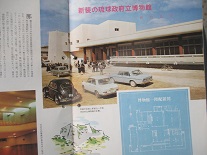
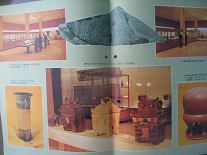

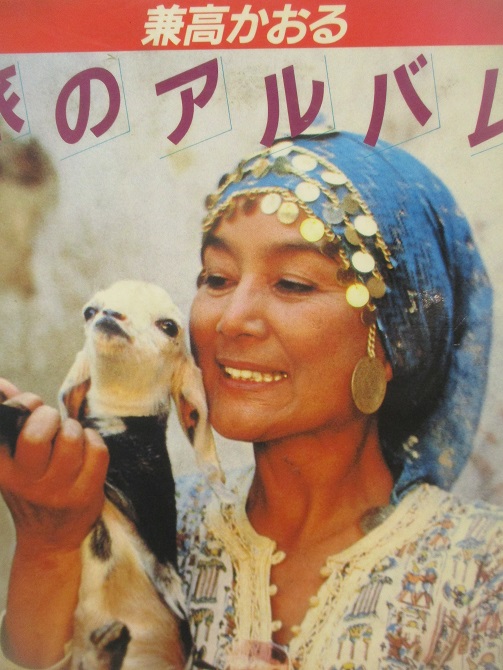
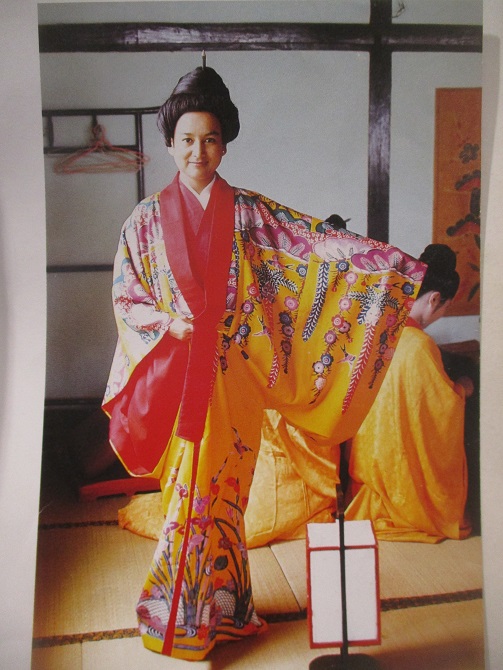
1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社
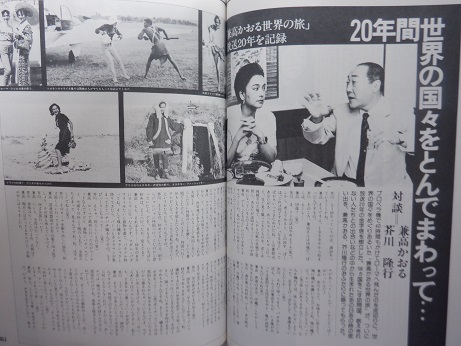
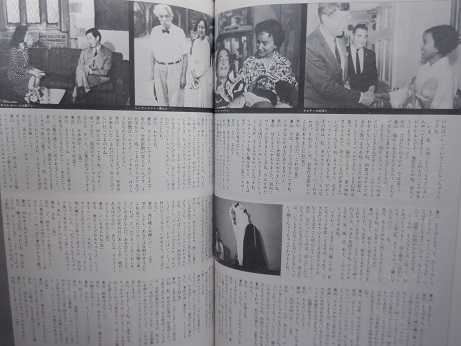
1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号
1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」
1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。


1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会
1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足
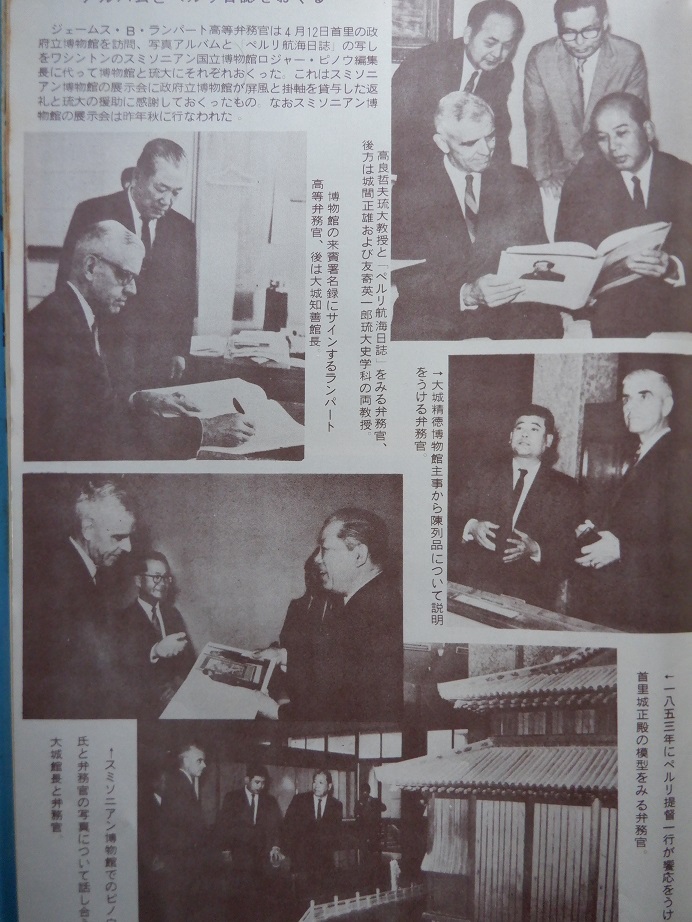
1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社
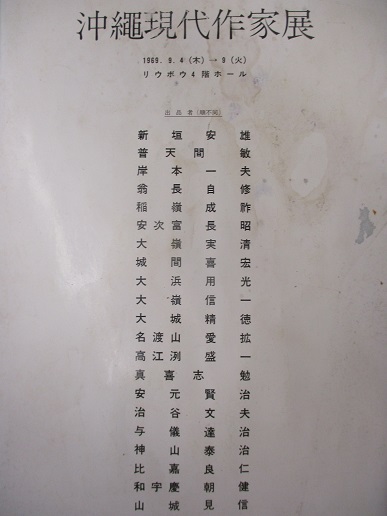
1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」
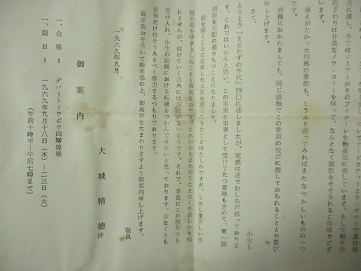
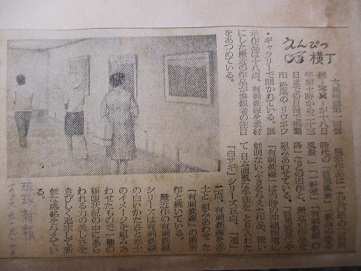
1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」
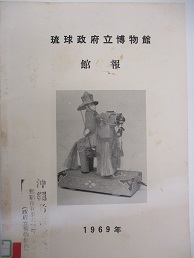
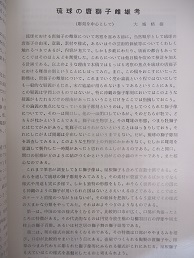
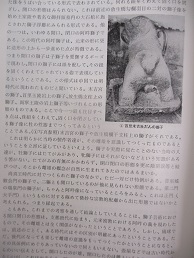
1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」
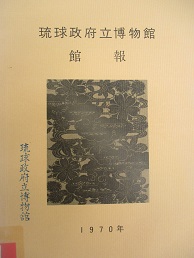
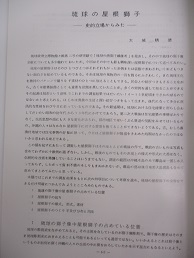
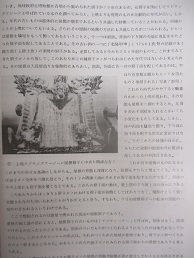
1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社
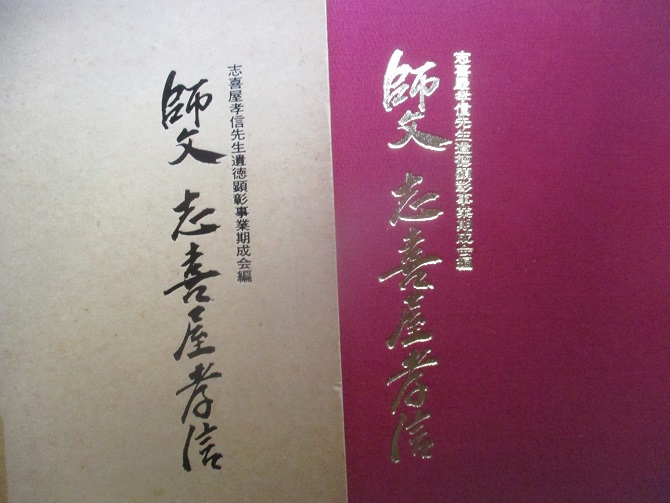
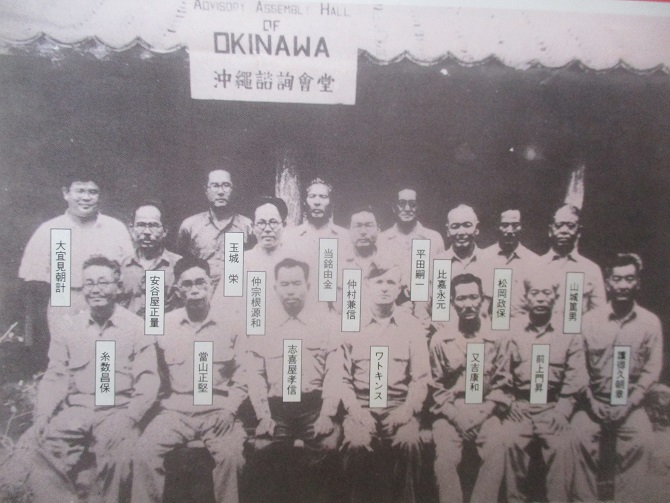
写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。
写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳
写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

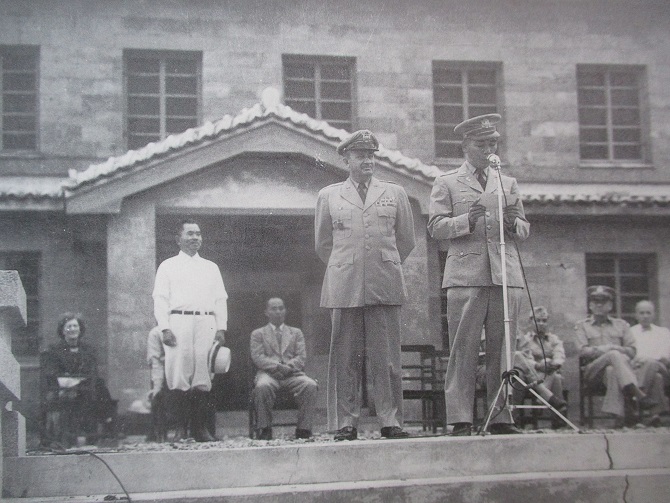
本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。
昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。
1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。
1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。
1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」
1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。
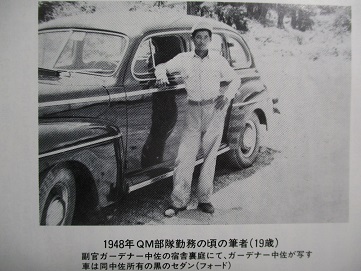
1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号
〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。
1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

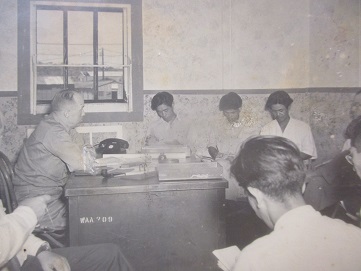
写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

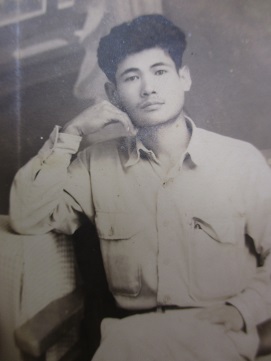
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて


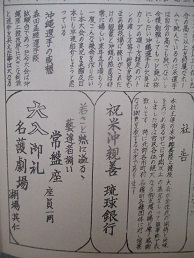
1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号
1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。
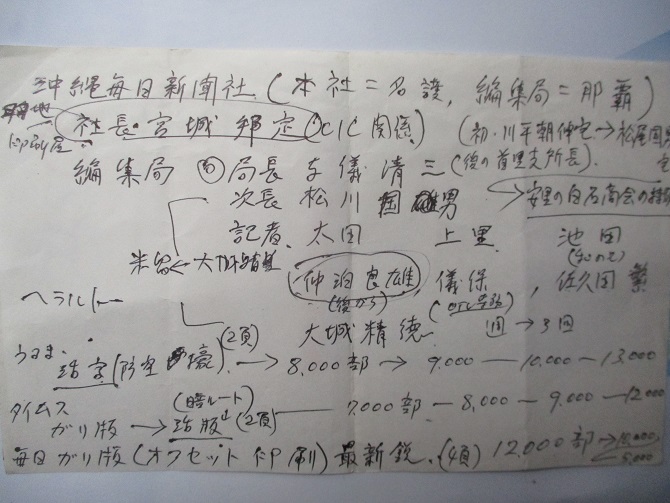
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展
1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。


写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳
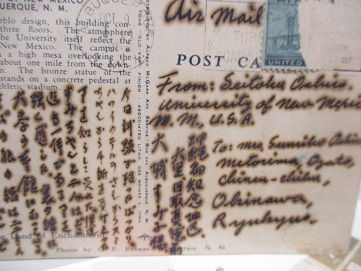
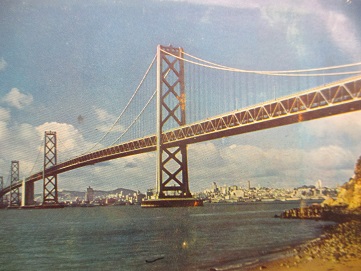
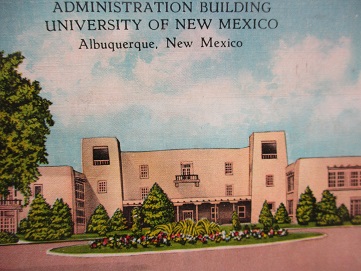

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳


1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山
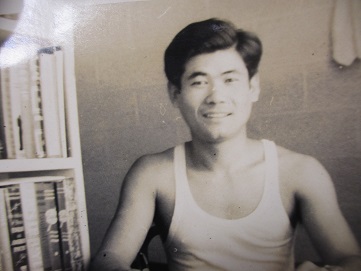

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順
ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」
1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
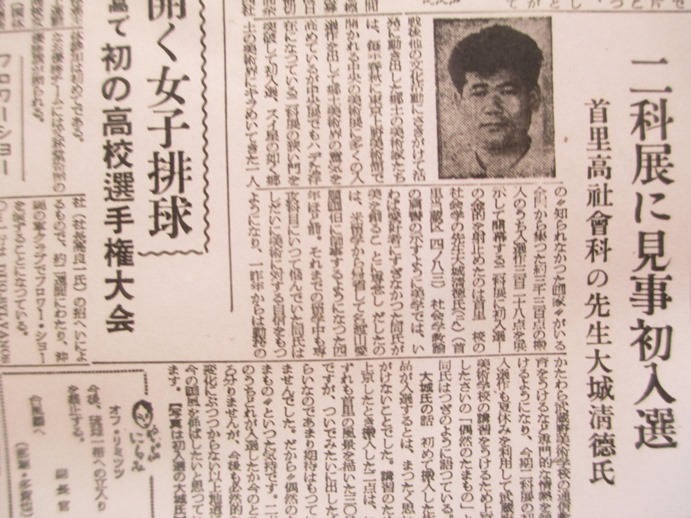
1956年9月1日『琉球新報』

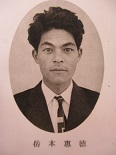
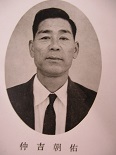
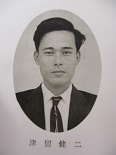
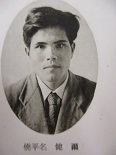
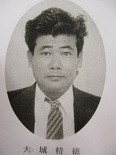
首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク
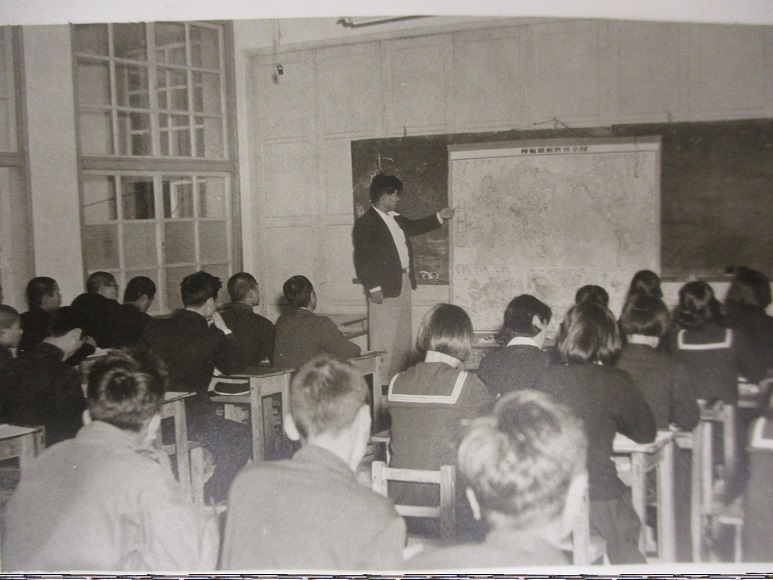
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

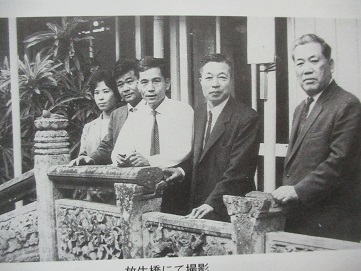
左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』
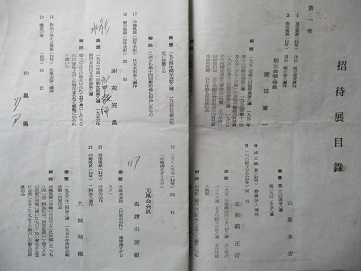
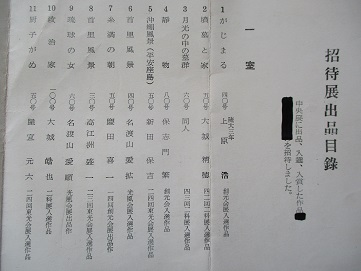
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
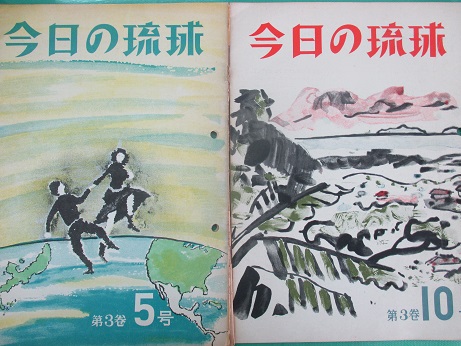
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

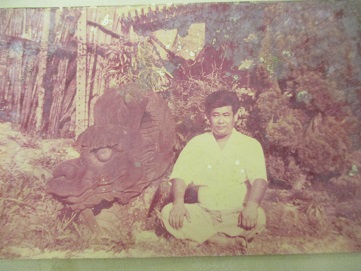


1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて
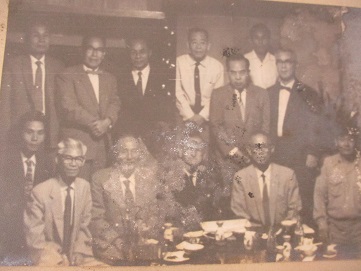

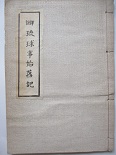




1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。
1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)
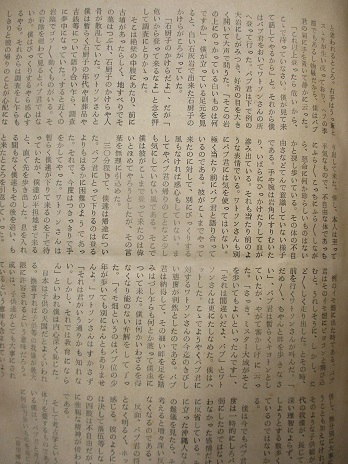
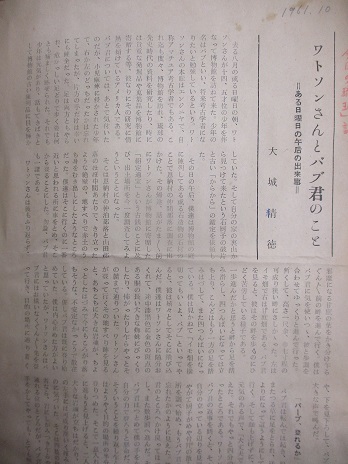
1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」
1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。
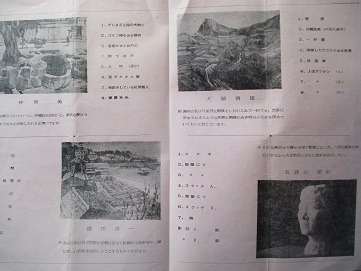
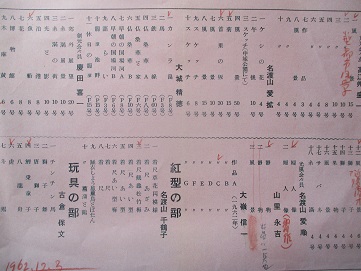
1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館
1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。
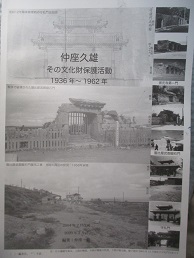
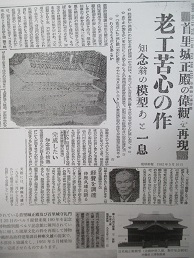
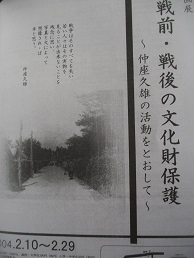
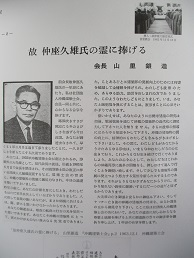
【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』
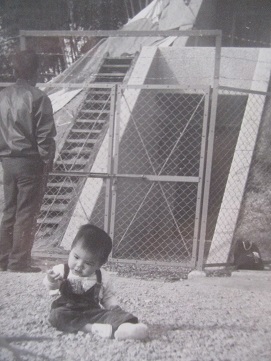
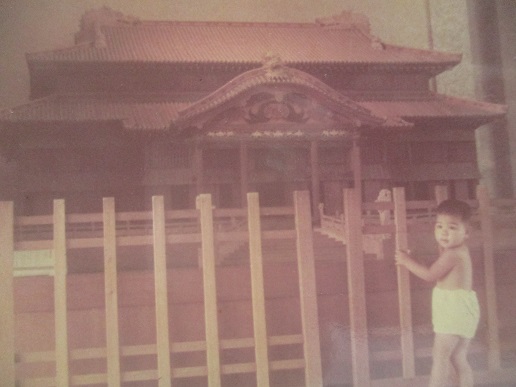
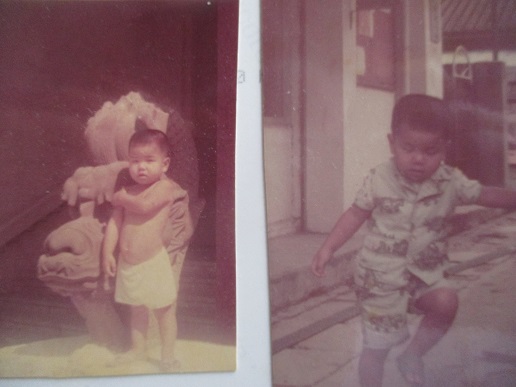
【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

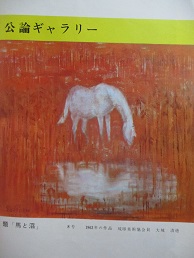
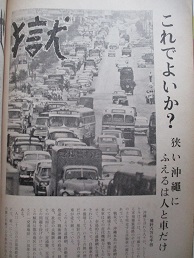
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
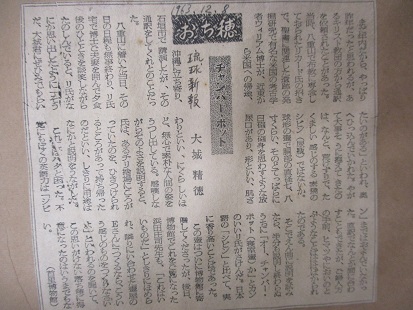
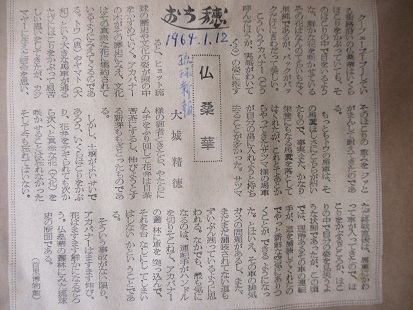
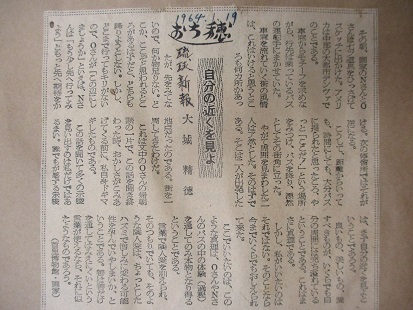
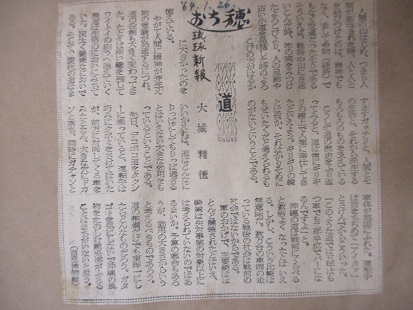
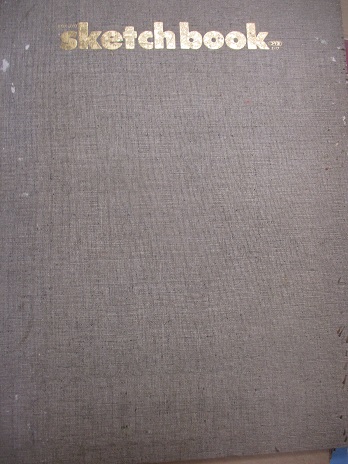

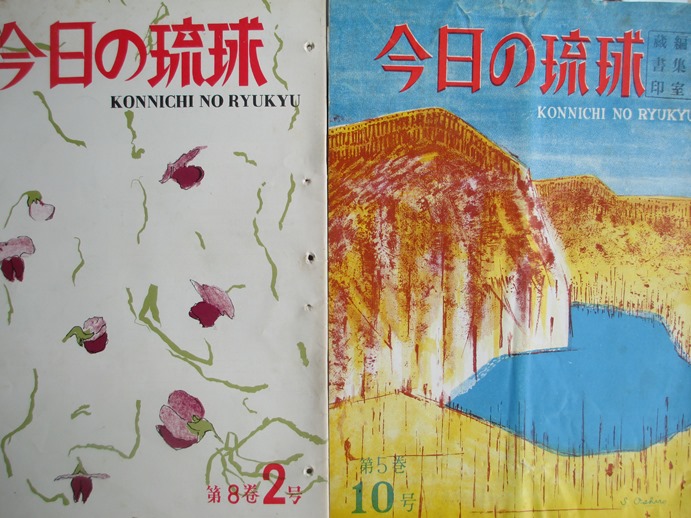
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」
1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。
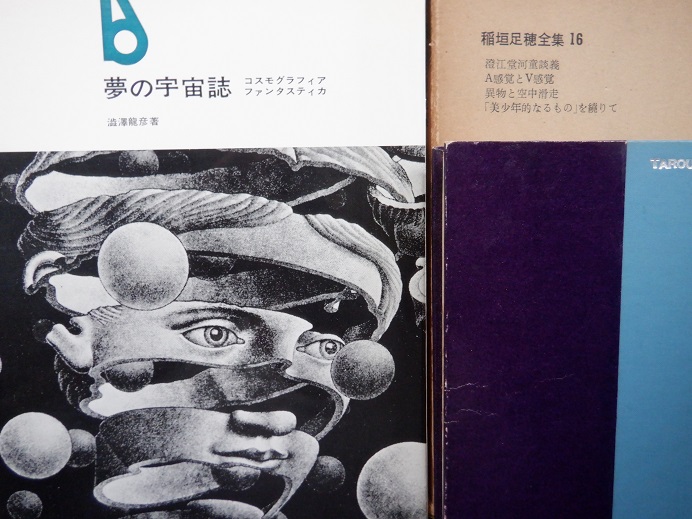
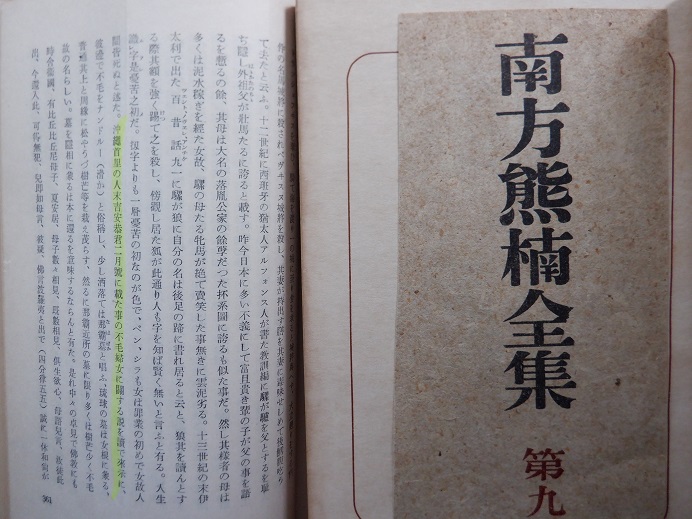
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
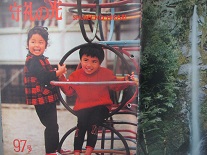
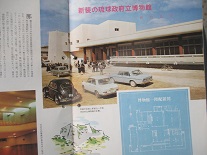
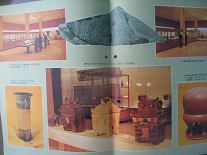

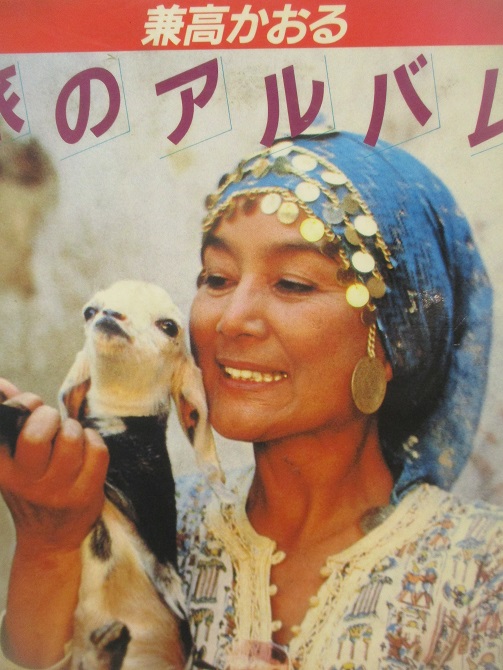
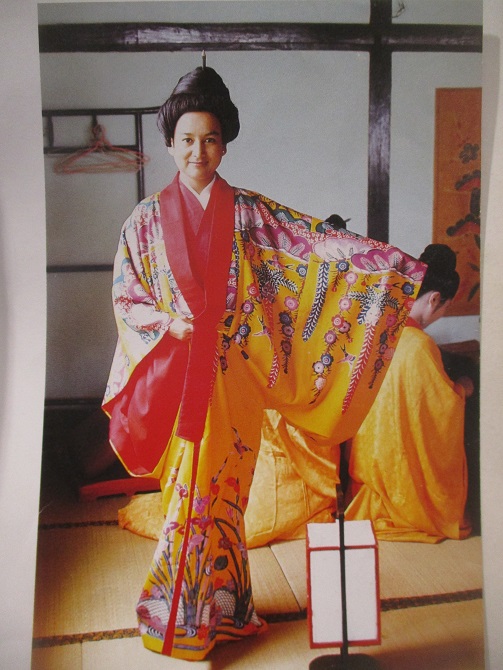
1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社
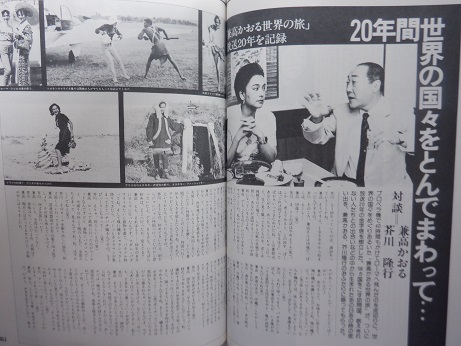
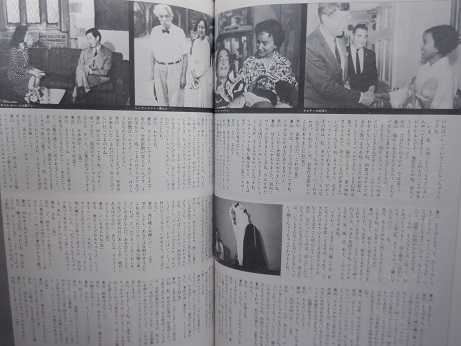
1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号
1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」
1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。


1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会
1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足
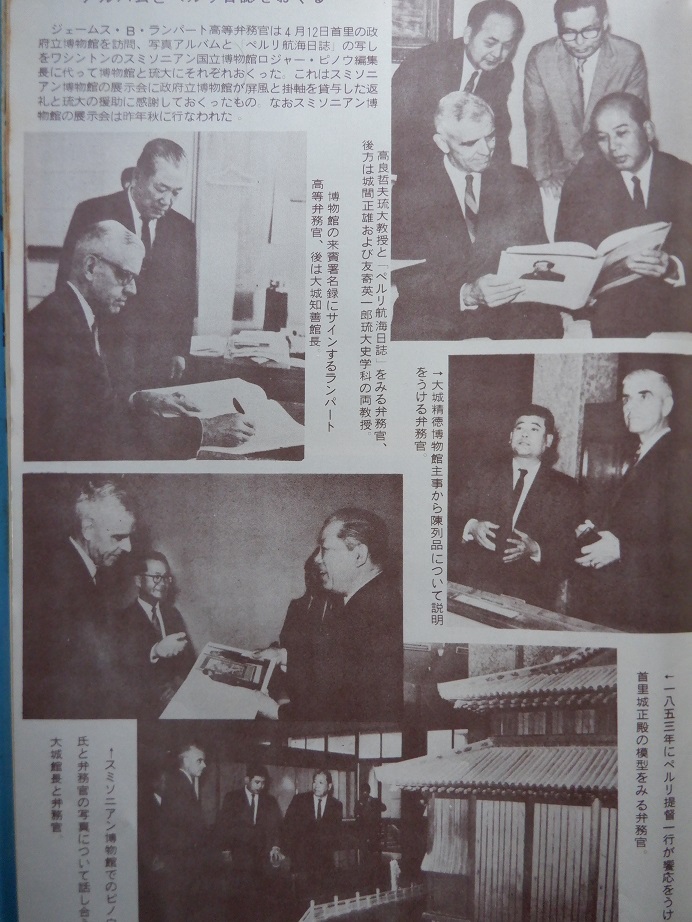
1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社
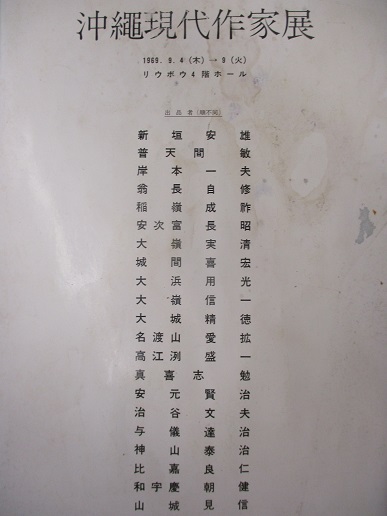
1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」
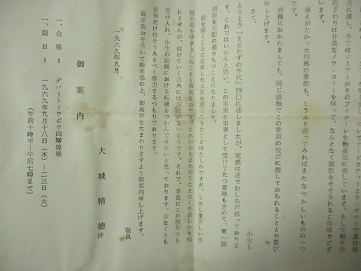
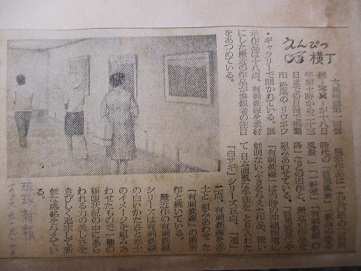
1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」
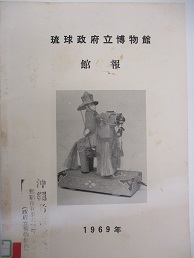
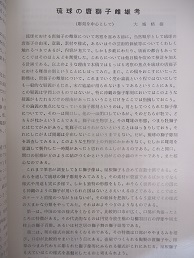
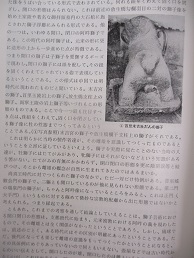
1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」
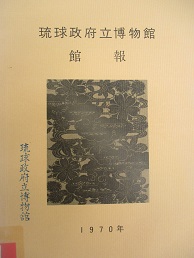
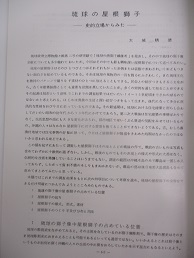
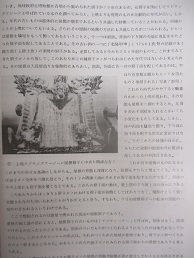
1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社
04/01: 世相ジャパン
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com


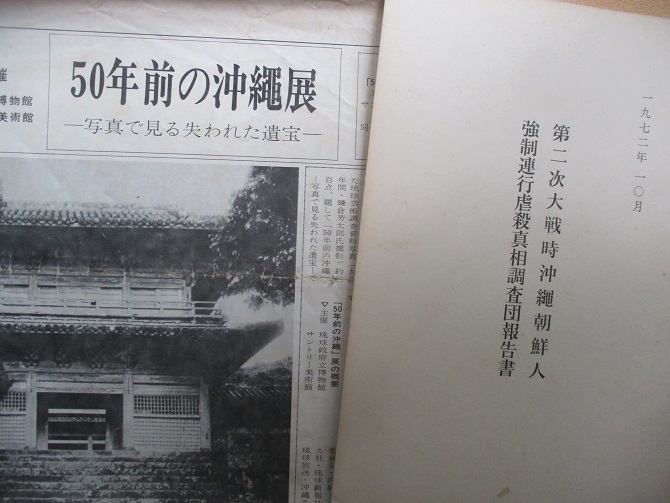
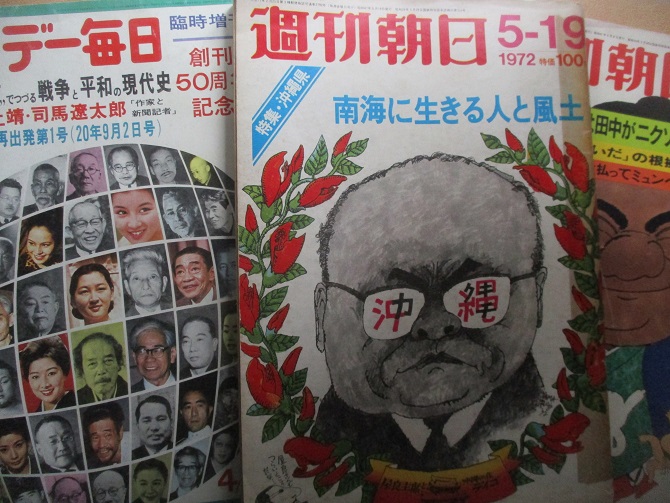
密約復帰の年1972年の資料袋から新聞、週刊誌を出してみた。ほとんど忘れていたが見ると思い出すものだ。1972-4-3『琉球新報』新崎盛敏「王衣の竜」、佐木隆三「『オキナワの少年』の漂着地は?」/1972-5-15『赤旗』「大阪・千日デパート火災」「沖縄の燃える青年 高江洲義寛氏(29)」/1972-2 琉球政府立博物館「50年前の沖縄展」「1972-10『第二次大戦沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団報告』 」/1972 『週刊朝日』 1972-4『サンデー毎日』臨時増刊」〇1972年5月13日ー大阪『日本経済新聞』「民芸品・図書を守ろうー都島の『沖縄資料室』」□密約によりアメリカ軍の占領意識が露骨に見えても、体制順応主義の国民(沖縄も含む)が多いので異を唱えない。しかもコロナ禍にも関わらずアメリカ詣ではするは、国民監視のデジタル庁は熱心なアベそのまま内閣。


1972年10月13日『週刊朝日』/1976年9年24日『週刊朝日』
「AERA」4-20 大阪府の吉村洋文知事は4月20日にも新型コロナウイルス感染急増を受け、政府に緊急事態宣言の再発令を要請する。菅義偉首相が週内に見極めて最終判断するという。だが、政府関係者は大阪の蔓延を「人災」と憤る。「とにかく大阪の病床はもう持ちません。今週中と言わず、大阪には一刻も早く宣言を発出すべきです。実際、大阪ではコロナ病床が埋まってしまったことで入院できず、亡くなられた方も出ています。これはこんな状況なのに呑気に訪米をしていた菅首相と日米首脳会談が終わるまで我慢し、“忖度”していた吉村知事による人災です。吉村知事は菅首相の帰国を待って19日にようやく要請を表明しました」一方、東京都の小池百合子知事は吉村知事より1日早い18日夜、緊急事態宣言を要請する方針を表明していた。
「くろねこの短語」2021年4月19日 やってる感を強調するためのコピーが思いつかなくなったのか、フリップ小池君が緊急事態宣言再要請の検討をしてるってね。「先手先手の対応が不可欠だ。緊急事態宣言の要請も視野に入れて、スピード感を持って検討するよう、職員に指示した」とさ。何が先手先手だ。そもそも、オリンピック開催にこだわって、コロナ対策をほったらかしにして、あげくに開催延期が決定したとたん「ロックダウン」だのと喚き散らしたのはどこのどいつだ。
そもそも、オリンピック開催延期が決定した時の国内のコロナ感染者数って、1000人いくかいかないか程度だったんだよね。それがいまでは1日当たり4000人超なんだから、なんでオリンピック中止の声が出てこないのか。まさに、不思議の国ニッポンとしか言いようがない。カス総理がスルーした「公衆保健の専門家らが準備できていないと話す状況でオリンピックを推進するのは無責任ではないのか」というロイターの記者の質問は、まさに世界の常識なんだね。そこにもってきての緊急事態宣言となれば、これはもうオリンピック中止に向けて雪崩を打って政局は動いて行くんじゃないのかねえ。
最後に、カス総理とバイデンのハンバーガー付き会談が面白おかしくネットを駆け巡っている。京都では帰ってほしい客に「ぶぶ漬けどうどすか」という言い回しがあるそうだが、それと同じですね。20分くらいの首脳会談にハンバーガーなんか普通は出さないだろう。鳩山ポッポ君が、「夕食会を断られハンバーガー付きの20分の首脳会談では哀れ」とツイートしていたが、今は亡き小松の親分さんならさしずめ「みじめみじめ」と退場するところか。
「くろねこの短語」2021年4月18日 不要不急の訪米は、予想通りに何の成果もなく終わったようだ。それどころか、「東シナ海や南シナ海などの問題で中国の挑戦を受けて立つ」というバイデンの喧嘩買ってやろうじゃないの発言にまんまと乗せられて、「強制や脅迫で現状を変えようとするいかなる試みにも反対する」ってカス総理は提灯持ちする始末だ。
案の定、中国はざけんじゃねえって強く反発しているようで、へたして台湾有事なんてことになったら自衛隊派遣なんてこともあるかもしれない。ていうか、訪米の見返りに自衛隊派遣を約束させられたりしてないだろうねえ。・日本「厚遇」の裏で軍事リスク共有? 対中強硬一致で高まる緊張<日米首脳会談>でもって、おそらく今回の訪米の重要なテーマのひとつであったろうオリンピックについて、バイデンからは色よい返事が得られなかったようですね。苦し紛れに共同宣言にこんなコメントを加えてもらっただけなんだね。
「バイデン大統領は、安心・安全なオリンピック及びパラリンピック競技大会を今夏開催するために菅首相が行っている努力を支持する。両首脳はこれら大会のためにトレーニングに励み、両競技に参加して最良の形で五輪精神の伝統を体現せんとする日米双方の選手たちへの誇りを表明した」ようするに、「開催への努力を支持する」って言ってるだけで、「開催を支持する」とは一言も言ってない。こういうのを、適当にあしらわれたと世間では言います。でもって、会談後の共同記者会見で、海外メディアの記者の質問をガン無視するという非礼を働いてくれちゃいました。ロイターの記者とのやり取りがそれなんだが、ハフポストによればこんな具合です。
1965年5月 鈴木幸夫『閨閥ー結婚で固められる日本の支配者集団』光文社〇白洲次郎は、神戸の綿布問屋の息子で、夫人正子は、随筆家、能研究家として知られている。元枢府顧問官樺山愛輔伯は、正子の父である。樺山は薩摩出身である。だから、かねがね岳父の関係から薩摩に因縁浅からぬものを感じ、かつ樺山を崇拝していた吉田茂とは、あい通じ合うものがあった。また、吉田も、近衛元首相とは接触があったが、白洲も近衛グループの一人だった。この点、二人は、おたがいに似たような政治コースをたどっていた。白洲は幣原内閣当時、外相だった吉田と親交を深め、終戦連絡部長、貿易庁長官を歴任し、ますます吉田と堅く結びついた。ちなみに白洲は、父の財力でケンブリッジに遊学したことがあるが、このときの後輩が麻生太賀吉である。その関係からも、白洲が吉田の次女和子と麻生太賀吉の仲人になった。(略)吉田が麻生との閨閥によって、政治活動の台所をまかなったように、白洲は、麻生との関係を軸に、思う存分、政・財界街道を泳ぎ回ったのである。
「くろねこの短語」2021年4月17日 愛知県知事へのリコール偽造事件で、とうとうリコール活動団体の事務局幹部が関与を認め、事務局長の指示だったと証言したってね。事務局長は田中孝博と言って、日本維新の会愛知5区支部長だった男で、リコール偽造事件が発覚して支部長を辞任している。おそらく、維新の会に火の粉がかからないように言い含められてのことなのだろう。リコール偽造事件には、イソジン吉村君もかなり熱心に関わっていたようで、維新の会はけっこう大きな影響力を持ってたんじゃないのかねえ。でも、リコール偽造ってのは民主主義を否定する前代未聞の事件で、維新の会の関与を疑われる前に事務局長の首を切ったってことなのだろう。
それにしても、メディアは、この事件にあまり関心がないのはどうしたわけだろう。維新の会が深く関わっていることを知った上で、何らかの忖度してるってことか。そう考えれば、メディアの報道で事務局長のキャリアから元日本維新の会って事実がスッポリ抜け落ちているのも頷けるというものだ。リコール運動のリーダーのひとりでもあった。名古屋市長のエビフリャー河村君は「勇気を出して真相をしゃべった。(活動団体事務局長の)田中氏も話をしないといけない」なんて他人事のようにコメントしてるけど、関与を認めた事務局幹部だけに罪をおっかぶせてトカゲの尻尾切りで逃げおおせると思ってるのかもね。
事務局長への逮捕状が出るかどうかで愛知県警のやる気度がわかるだろうから、そうなればエビフリャー河村君だけでなくイエス高須君もお縄になる可能性が高いんじゃないのかねえ。是非ともそのシーンを見てみたい今日この頃なのだ。
古美術なるみ堂 〒900-0013那覇市牧志3-2-40 翁長良明・携帯090-3793-8179














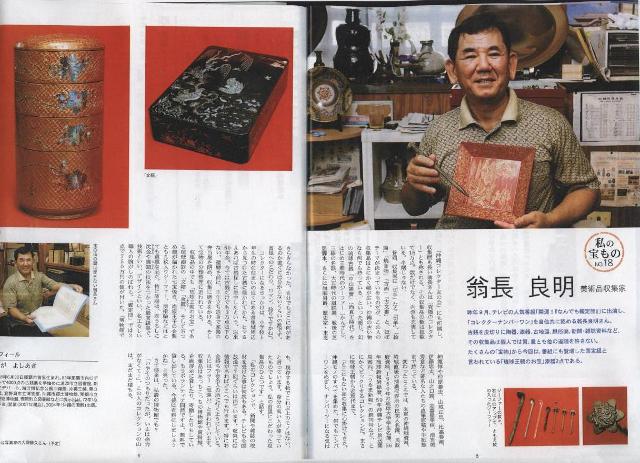

山城 明いいねうるま市 4月1日(木)おはようございます!コロナ感染者の急増で今日から21日迄飲食店などへ営業時間短縮の要請が出ましたよ。感染しない、させないで感染対策を万全にして自分の命は自分で守りましょうネ
『女性自身』4-16 3月の緊張事態宣言解除時、会見で感染抑止のために「できることはすべてやり抜く」と語っていた菅首相。しかし、目立った陣頭指揮も見られないままの“バイデン詣で”に、SNS上では批判の声が多くあがった。《第4波の非常事態に 渡米してる場合じゃないだろう》《菅首相が今日の国会で第4波聞かれ、否定。専門家も認めている。明日から渡米。何しに行くの。》《コロナ禍を放置して訪米の菅首相。バイデンとの親密さを誇示し、オリンピックにこだわる。国民の生命は二の次といわざるを得ない》《菅総理の無責任さには腹がたっています。こんな状況下で明日からは訪米》
E・K 4-14 佐倉の歴博で、海の帝国とか、スターウオーズみたいなタイトルの沖縄の展覧会「海の帝国琉球-八重山・宮古・奄美からみた中世-開催期間2021年3月16日(火)~5月9日(日)」/天才夢来山 「東京に来ないで下さい」と言ってる国が世界各国から五輪選手とその関係者の6万人を招くという笑い話(笑)。
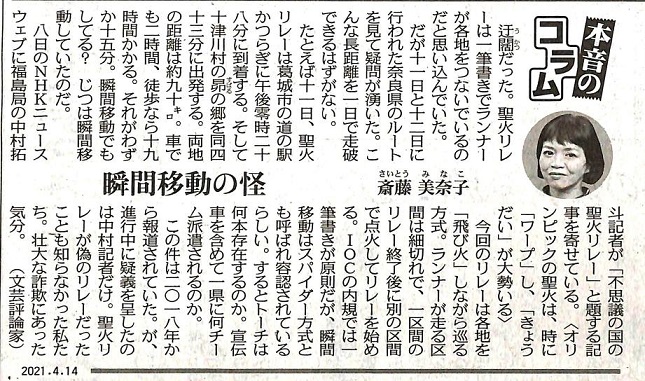
斎藤美奈子
「くろねこの短語」2021年4月15日 コロナ感染者が4000人/日を超え、大阪は過去最多の1130人、兵庫も遂に500人を上回り、東京も591人と順調に(?)感染者が増えている中、褌締め直すの尾身シェンシェイが「いわゆる『4波』と言っても差し支えない」と国会で答弁。・コロナ変異株、急速に置き換わり 感染者、1月28日以来4千人超
感染爆発と言っても過言ではない状況だと言うのに、聖火リレーは相変わらずで、それに加えて東京オリンピック100日前のセレモニーでフリップ小池君は満面の笑みを浮かべ、それがテレビのニュースで流れるんだから、この国のメディアは何考えてるんだか。「オリンピック観戦はオリンピック感染」の危険が囁かれる中、そんな日本のメディアに呆れたわけではなかろうが、とうとう世界のメディアが警告を発し始めた。
米ニューヨーク・タイムズは「ワクチン接種が遅れている日本では聖火リレーが大阪などで中止になったが、東京五輪はパンデミックと医療危機という最悪のタイミングで強行される。3週間の大会は日本全土に死と病気をもたらす一大感染イベントになる可能性がある」と指摘。英ガーディアンも「日本とIOCは五輪開催を本当に正しいと言えるのか自問する必要がある」「中止による経済的損失なども、五輪がパンデミックを悪化させるリスクと合わせて検討されなければならない」と社説で警告している。
共同通信はこうした海外メディアの報道を配信しているけど、本当ならこういう声は日本のメディアから上がってこなければけないんだよね。でも、メディアはオリンピックのスポンサーでもあるから、どうしても腰が引けちゃって、コロナとオリンピッをリンクした報道ができない。・海外から五輪中止の声も…政府と組織委は“五輪選手だけ守る”コロナ対策で乗り切り画策! 数億円の療養施設、パラ選手を口実にワクチン優先
そんなんだから、IOCのコーツごときに「大会は開催され、可能な限り最も安全なものとなるだろうと躊躇なく言える」と恫喝まがいの発言されちゃうんだね。国民の80%が反対か延期と言ってるってのに、IOCの委員がこんな発言するんだから、舐められたものです。もし東京ではなく、たとえばパリでの開催だったら、コーツがこんな発言しただろうか。強気な姿勢の背景には、人種的な差別意識が匂ってくるのは穿ち過ぎと言うものだろうか。・IOCコーツ調整委員長 五輪開催を断言それはともかく、第4波がジワジワと広がる中で、オリンピックなんてできるのか。ひょっとしたら、今日からのカス総理の訪米って、オリンピック開催に向けて選手団派遣をお願いしに行ったんじゃないのか。でもって、基地経費の肩代わりの見返りを約束されたんじゃ、たまったもんじゃありません・・・妄想だけど。
〇4-14 新型コロナウイルスの感染が再拡大する中、日本全国を回っている聖火リレー。その運営経費は全国の自治体が負担しているが、その総額が少なくとも約116億円に及ぶことが、「週刊文春」の取材でわかった。




2021年4月9日 中の橋/沖縄県立博物館・美術館民家/金城美奈子さん
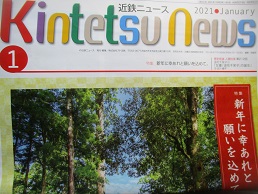

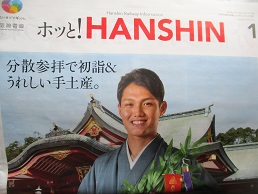

あけみさんからの『近鉄ニュース』新年号、『ホッと!HANSHIN』新年号。近鉄ニュースを検索すると「新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2021年3月号より発行を休止させていただきます」と、ある。
「くろねこの短語」2021年4月9日 (前略)では、まんえん防止措置で具体的にどんな対策をするかっていうと、これが飲食店への時短要請がメインってんだから、バッカじゃなかろかなのだ。これまでさんざん時短要請してきてもコロナの猛威を抑えきることはできなかったのに、ちったあ考え方を切り替えるくらいの知恵はないのかねえ。
たとえば、PCR検査を「いつでも、どこでも、誰でも」受けられるようにして、陽性者を隔離保護した上で、陰性者で経済を回す・・・そのくらいのことはシロートだって考えつくけどねえ。そう言えば、オリンピック警備の警察官宿舎を軽症の感染者用に改修したのに、結局は使うことなくまた元の状態に戻すそうで、その費用は40億円だとさ。そんな無駄遣いしておいて、緊急事態宣言だ、まんえん防止措置だで国民に自粛をお願いすることしかできないんだから、何をかいわんやなのだ。それにしても、感染爆発してるってのに、いまさらまんえん防止等重点措置なんて、間が抜けてますよ、ったく。ま、これでオリンピック中止が、ようやく現実味を帯びてきたというものだ。


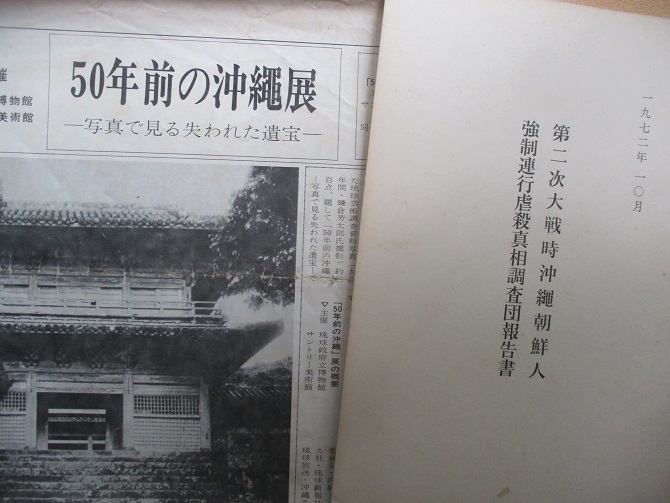
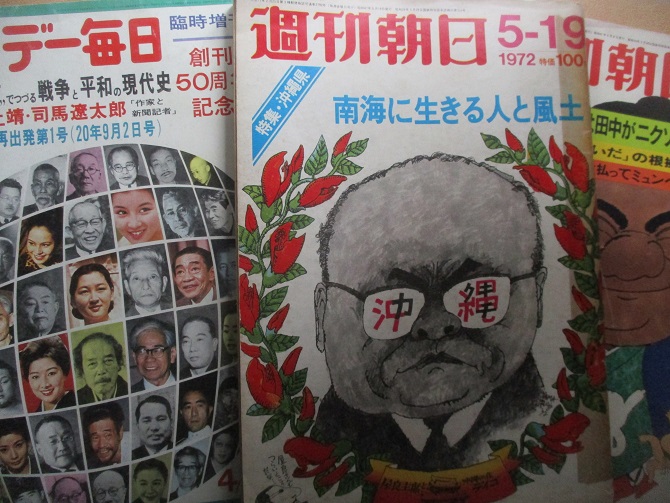
密約復帰の年1972年の資料袋から新聞、週刊誌を出してみた。ほとんど忘れていたが見ると思い出すものだ。1972-4-3『琉球新報』新崎盛敏「王衣の竜」、佐木隆三「『オキナワの少年』の漂着地は?」/1972-5-15『赤旗』「大阪・千日デパート火災」「沖縄の燃える青年 高江洲義寛氏(29)」/1972-2 琉球政府立博物館「50年前の沖縄展」「1972-10『第二次大戦沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団報告』 」/1972 『週刊朝日』 1972-4『サンデー毎日』臨時増刊」〇1972年5月13日ー大阪『日本経済新聞』「民芸品・図書を守ろうー都島の『沖縄資料室』」□密約によりアメリカ軍の占領意識が露骨に見えても、体制順応主義の国民(沖縄も含む)が多いので異を唱えない。しかもコロナ禍にも関わらずアメリカ詣ではするは、国民監視のデジタル庁は熱心なアベそのまま内閣。


1972年10月13日『週刊朝日』/1976年9年24日『週刊朝日』
「AERA」4-20 大阪府の吉村洋文知事は4月20日にも新型コロナウイルス感染急増を受け、政府に緊急事態宣言の再発令を要請する。菅義偉首相が週内に見極めて最終判断するという。だが、政府関係者は大阪の蔓延を「人災」と憤る。「とにかく大阪の病床はもう持ちません。今週中と言わず、大阪には一刻も早く宣言を発出すべきです。実際、大阪ではコロナ病床が埋まってしまったことで入院できず、亡くなられた方も出ています。これはこんな状況なのに呑気に訪米をしていた菅首相と日米首脳会談が終わるまで我慢し、“忖度”していた吉村知事による人災です。吉村知事は菅首相の帰国を待って19日にようやく要請を表明しました」一方、東京都の小池百合子知事は吉村知事より1日早い18日夜、緊急事態宣言を要請する方針を表明していた。
「くろねこの短語」2021年4月19日 やってる感を強調するためのコピーが思いつかなくなったのか、フリップ小池君が緊急事態宣言再要請の検討をしてるってね。「先手先手の対応が不可欠だ。緊急事態宣言の要請も視野に入れて、スピード感を持って検討するよう、職員に指示した」とさ。何が先手先手だ。そもそも、オリンピック開催にこだわって、コロナ対策をほったらかしにして、あげくに開催延期が決定したとたん「ロックダウン」だのと喚き散らしたのはどこのどいつだ。
そもそも、オリンピック開催延期が決定した時の国内のコロナ感染者数って、1000人いくかいかないか程度だったんだよね。それがいまでは1日当たり4000人超なんだから、なんでオリンピック中止の声が出てこないのか。まさに、不思議の国ニッポンとしか言いようがない。カス総理がスルーした「公衆保健の専門家らが準備できていないと話す状況でオリンピックを推進するのは無責任ではないのか」というロイターの記者の質問は、まさに世界の常識なんだね。そこにもってきての緊急事態宣言となれば、これはもうオリンピック中止に向けて雪崩を打って政局は動いて行くんじゃないのかねえ。
最後に、カス総理とバイデンのハンバーガー付き会談が面白おかしくネットを駆け巡っている。京都では帰ってほしい客に「ぶぶ漬けどうどすか」という言い回しがあるそうだが、それと同じですね。20分くらいの首脳会談にハンバーガーなんか普通は出さないだろう。鳩山ポッポ君が、「夕食会を断られハンバーガー付きの20分の首脳会談では哀れ」とツイートしていたが、今は亡き小松の親分さんならさしずめ「みじめみじめ」と退場するところか。
「くろねこの短語」2021年4月18日 不要不急の訪米は、予想通りに何の成果もなく終わったようだ。それどころか、「東シナ海や南シナ海などの問題で中国の挑戦を受けて立つ」というバイデンの喧嘩買ってやろうじゃないの発言にまんまと乗せられて、「強制や脅迫で現状を変えようとするいかなる試みにも反対する」ってカス総理は提灯持ちする始末だ。
案の定、中国はざけんじゃねえって強く反発しているようで、へたして台湾有事なんてことになったら自衛隊派遣なんてこともあるかもしれない。ていうか、訪米の見返りに自衛隊派遣を約束させられたりしてないだろうねえ。・日本「厚遇」の裏で軍事リスク共有? 対中強硬一致で高まる緊張<日米首脳会談>でもって、おそらく今回の訪米の重要なテーマのひとつであったろうオリンピックについて、バイデンからは色よい返事が得られなかったようですね。苦し紛れに共同宣言にこんなコメントを加えてもらっただけなんだね。
「バイデン大統領は、安心・安全なオリンピック及びパラリンピック競技大会を今夏開催するために菅首相が行っている努力を支持する。両首脳はこれら大会のためにトレーニングに励み、両競技に参加して最良の形で五輪精神の伝統を体現せんとする日米双方の選手たちへの誇りを表明した」ようするに、「開催への努力を支持する」って言ってるだけで、「開催を支持する」とは一言も言ってない。こういうのを、適当にあしらわれたと世間では言います。でもって、会談後の共同記者会見で、海外メディアの記者の質問をガン無視するという非礼を働いてくれちゃいました。ロイターの記者とのやり取りがそれなんだが、ハフポストによればこんな具合です。
1965年5月 鈴木幸夫『閨閥ー結婚で固められる日本の支配者集団』光文社〇白洲次郎は、神戸の綿布問屋の息子で、夫人正子は、随筆家、能研究家として知られている。元枢府顧問官樺山愛輔伯は、正子の父である。樺山は薩摩出身である。だから、かねがね岳父の関係から薩摩に因縁浅からぬものを感じ、かつ樺山を崇拝していた吉田茂とは、あい通じ合うものがあった。また、吉田も、近衛元首相とは接触があったが、白洲も近衛グループの一人だった。この点、二人は、おたがいに似たような政治コースをたどっていた。白洲は幣原内閣当時、外相だった吉田と親交を深め、終戦連絡部長、貿易庁長官を歴任し、ますます吉田と堅く結びついた。ちなみに白洲は、父の財力でケンブリッジに遊学したことがあるが、このときの後輩が麻生太賀吉である。その関係からも、白洲が吉田の次女和子と麻生太賀吉の仲人になった。(略)吉田が麻生との閨閥によって、政治活動の台所をまかなったように、白洲は、麻生との関係を軸に、思う存分、政・財界街道を泳ぎ回ったのである。
「くろねこの短語」2021年4月17日 愛知県知事へのリコール偽造事件で、とうとうリコール活動団体の事務局幹部が関与を認め、事務局長の指示だったと証言したってね。事務局長は田中孝博と言って、日本維新の会愛知5区支部長だった男で、リコール偽造事件が発覚して支部長を辞任している。おそらく、維新の会に火の粉がかからないように言い含められてのことなのだろう。リコール偽造事件には、イソジン吉村君もかなり熱心に関わっていたようで、維新の会はけっこう大きな影響力を持ってたんじゃないのかねえ。でも、リコール偽造ってのは民主主義を否定する前代未聞の事件で、維新の会の関与を疑われる前に事務局長の首を切ったってことなのだろう。
それにしても、メディアは、この事件にあまり関心がないのはどうしたわけだろう。維新の会が深く関わっていることを知った上で、何らかの忖度してるってことか。そう考えれば、メディアの報道で事務局長のキャリアから元日本維新の会って事実がスッポリ抜け落ちているのも頷けるというものだ。リコール運動のリーダーのひとりでもあった。名古屋市長のエビフリャー河村君は「勇気を出して真相をしゃべった。(活動団体事務局長の)田中氏も話をしないといけない」なんて他人事のようにコメントしてるけど、関与を認めた事務局幹部だけに罪をおっかぶせてトカゲの尻尾切りで逃げおおせると思ってるのかもね。
事務局長への逮捕状が出るかどうかで愛知県警のやる気度がわかるだろうから、そうなればエビフリャー河村君だけでなくイエス高須君もお縄になる可能性が高いんじゃないのかねえ。是非ともそのシーンを見てみたい今日この頃なのだ。
古美術なるみ堂 〒900-0013那覇市牧志3-2-40 翁長良明・携帯090-3793-8179














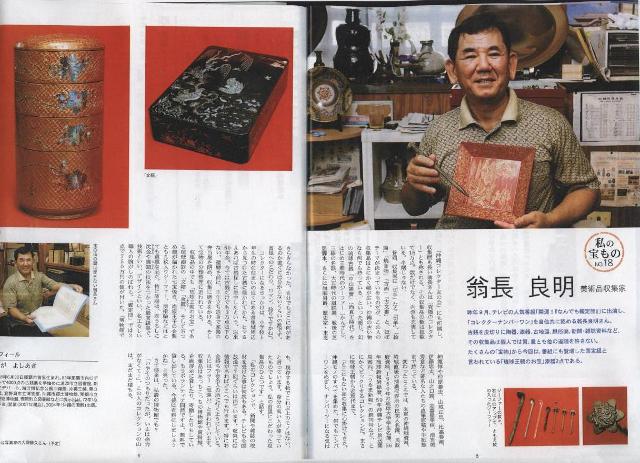

山城 明いいねうるま市 4月1日(木)おはようございます!コロナ感染者の急増で今日から21日迄飲食店などへ営業時間短縮の要請が出ましたよ。感染しない、させないで感染対策を万全にして自分の命は自分で守りましょうネ
『女性自身』4-16 3月の緊張事態宣言解除時、会見で感染抑止のために「できることはすべてやり抜く」と語っていた菅首相。しかし、目立った陣頭指揮も見られないままの“バイデン詣で”に、SNS上では批判の声が多くあがった。《第4波の非常事態に 渡米してる場合じゃないだろう》《菅首相が今日の国会で第4波聞かれ、否定。専門家も認めている。明日から渡米。何しに行くの。》《コロナ禍を放置して訪米の菅首相。バイデンとの親密さを誇示し、オリンピックにこだわる。国民の生命は二の次といわざるを得ない》《菅総理の無責任さには腹がたっています。こんな状況下で明日からは訪米》
E・K 4-14 佐倉の歴博で、海の帝国とか、スターウオーズみたいなタイトルの沖縄の展覧会「海の帝国琉球-八重山・宮古・奄美からみた中世-開催期間2021年3月16日(火)~5月9日(日)」/天才夢来山 「東京に来ないで下さい」と言ってる国が世界各国から五輪選手とその関係者の6万人を招くという笑い話(笑)。
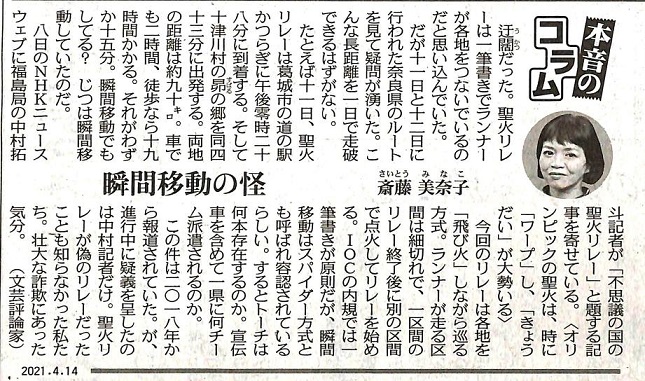
斎藤美奈子
「くろねこの短語」2021年4月15日 コロナ感染者が4000人/日を超え、大阪は過去最多の1130人、兵庫も遂に500人を上回り、東京も591人と順調に(?)感染者が増えている中、褌締め直すの尾身シェンシェイが「いわゆる『4波』と言っても差し支えない」と国会で答弁。・コロナ変異株、急速に置き換わり 感染者、1月28日以来4千人超
感染爆発と言っても過言ではない状況だと言うのに、聖火リレーは相変わらずで、それに加えて東京オリンピック100日前のセレモニーでフリップ小池君は満面の笑みを浮かべ、それがテレビのニュースで流れるんだから、この国のメディアは何考えてるんだか。「オリンピック観戦はオリンピック感染」の危険が囁かれる中、そんな日本のメディアに呆れたわけではなかろうが、とうとう世界のメディアが警告を発し始めた。
米ニューヨーク・タイムズは「ワクチン接種が遅れている日本では聖火リレーが大阪などで中止になったが、東京五輪はパンデミックと医療危機という最悪のタイミングで強行される。3週間の大会は日本全土に死と病気をもたらす一大感染イベントになる可能性がある」と指摘。英ガーディアンも「日本とIOCは五輪開催を本当に正しいと言えるのか自問する必要がある」「中止による経済的損失なども、五輪がパンデミックを悪化させるリスクと合わせて検討されなければならない」と社説で警告している。
共同通信はこうした海外メディアの報道を配信しているけど、本当ならこういう声は日本のメディアから上がってこなければけないんだよね。でも、メディアはオリンピックのスポンサーでもあるから、どうしても腰が引けちゃって、コロナとオリンピッをリンクした報道ができない。・海外から五輪中止の声も…政府と組織委は“五輪選手だけ守る”コロナ対策で乗り切り画策! 数億円の療養施設、パラ選手を口実にワクチン優先
そんなんだから、IOCのコーツごときに「大会は開催され、可能な限り最も安全なものとなるだろうと躊躇なく言える」と恫喝まがいの発言されちゃうんだね。国民の80%が反対か延期と言ってるってのに、IOCの委員がこんな発言するんだから、舐められたものです。もし東京ではなく、たとえばパリでの開催だったら、コーツがこんな発言しただろうか。強気な姿勢の背景には、人種的な差別意識が匂ってくるのは穿ち過ぎと言うものだろうか。・IOCコーツ調整委員長 五輪開催を断言それはともかく、第4波がジワジワと広がる中で、オリンピックなんてできるのか。ひょっとしたら、今日からのカス総理の訪米って、オリンピック開催に向けて選手団派遣をお願いしに行ったんじゃないのか。でもって、基地経費の肩代わりの見返りを約束されたんじゃ、たまったもんじゃありません・・・妄想だけど。
〇4-14 新型コロナウイルスの感染が再拡大する中、日本全国を回っている聖火リレー。その運営経費は全国の自治体が負担しているが、その総額が少なくとも約116億円に及ぶことが、「週刊文春」の取材でわかった。




2021年4月9日 中の橋/沖縄県立博物館・美術館民家/金城美奈子さん
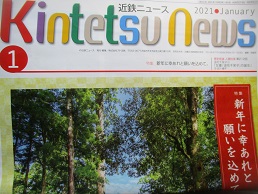

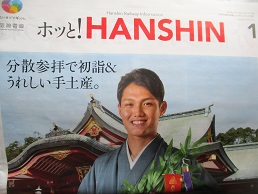

あけみさんからの『近鉄ニュース』新年号、『ホッと!HANSHIN』新年号。近鉄ニュースを検索すると「新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2021年3月号より発行を休止させていただきます」と、ある。
「くろねこの短語」2021年4月9日 (前略)では、まんえん防止措置で具体的にどんな対策をするかっていうと、これが飲食店への時短要請がメインってんだから、バッカじゃなかろかなのだ。これまでさんざん時短要請してきてもコロナの猛威を抑えきることはできなかったのに、ちったあ考え方を切り替えるくらいの知恵はないのかねえ。
たとえば、PCR検査を「いつでも、どこでも、誰でも」受けられるようにして、陽性者を隔離保護した上で、陰性者で経済を回す・・・そのくらいのことはシロートだって考えつくけどねえ。そう言えば、オリンピック警備の警察官宿舎を軽症の感染者用に改修したのに、結局は使うことなくまた元の状態に戻すそうで、その費用は40億円だとさ。そんな無駄遣いしておいて、緊急事態宣言だ、まんえん防止措置だで国民に自粛をお願いすることしかできないんだから、何をかいわんやなのだ。それにしても、感染爆発してるってのに、いまさらまんえん防止等重点措置なんて、間が抜けてますよ、ったく。ま、これでオリンピック中止が、ようやく現実味を帯びてきたというものだ。
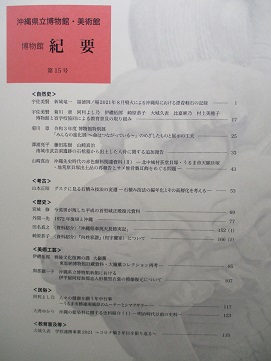
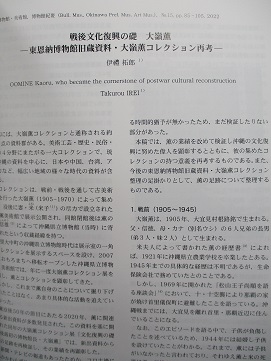
2022年3月 沖縄県立博物館・美術館『博物館紀要』第15号 伊禮拓郎「戦後文化復興の礎 大嶺薫ー東恩納博物館旧蔵資料・大嶺薫コレクション再考ー」
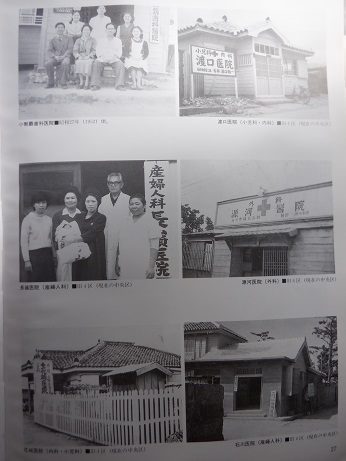
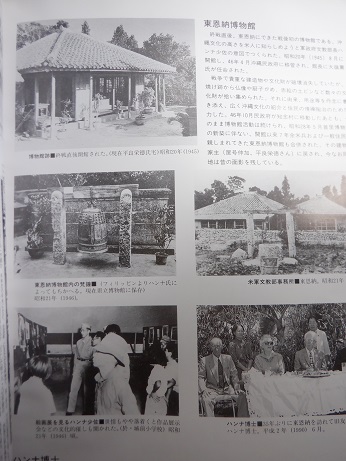
1990年9月 市制45周年記念『『いしかわ』沖縄県石川市
1921年 沖縄県立農林学校卒
 )
)
1969年11月 デパートリウボウ・琉球新報社「南蛮古陶展」で、左から外間正幸(1969年~1981年ー琉球政府立博物館館長)、大嶺薫(1946年~53年ー東恩納博物館長)、山里永吉(1955年~58年ー琉球政府立博物館館長/写真中央が朝潮、左が大嶺薫
朝潮 太郎(あさしお たろう、1929年(昭和4年)11月13日 - 1988年(昭和63年)10月23日)は、本名・米川 文敏、鹿児島県徳之島出身(出生地は兵庫県武庫郡、現在の神戸市)で、高砂部屋に所属していた大相撲第46代横綱。→ウィキペディア
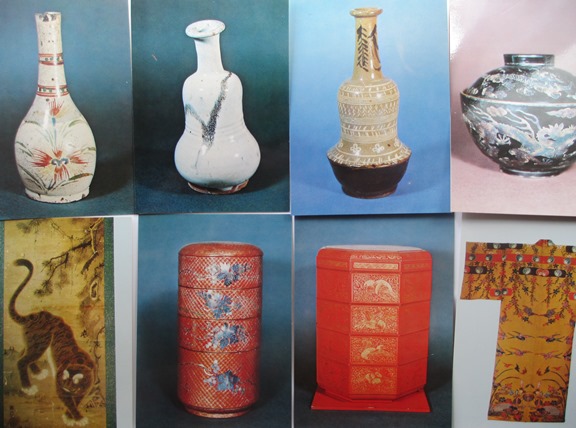
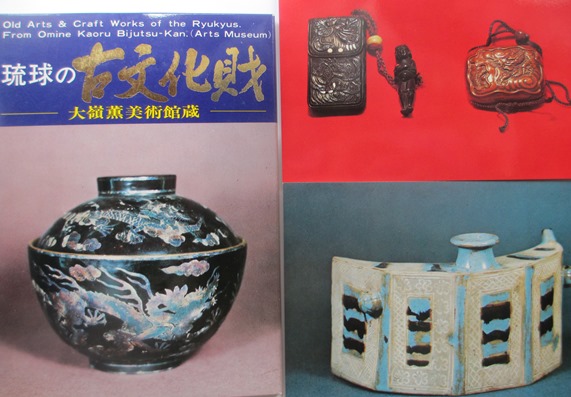
1945年8月 石川市東恩納にアメリカ軍政府「沖縄陳列館」設立
□今秋、那覇新都心に沖縄県立博物館・美術館がオープンする。外見からも最高の文化施設になると確信するのは私一人ではないと思う。「沖縄の戦後は石川から始まった」とよく聞くが、戦後初の博物館が石川市にあったことを知る人は少なくなってきている。東恩納の民家を使っての博物館で民家は今も健在で2005年3月に石川市の文化財として指定を受けている。民家は沖縄市から石川に向け国道329号の栄野比の坂を上がり切ったところの交差点を右に入った住宅地にある。
1945年8月に米国海軍政府のハンナ少佐らが中心となり、石川市東恩納の軍政府コンセット群の一隅残っていた民家(平良栄徳宅)を転用し沖縄陳列館が設立された。大宜味村に避難していた大嶺薫が招かれハンナ少佐の下で陳列館の資料収集に駆け回る。大嶺は琉球の古美術、歴史、考古学に幅広い知識を持った研究者でもあり戦前から古美術品を収集していた。私のコレクションに東恩納博物館当時の事務資料がまとまってある。紙面の都合上主なものを紹介する。

(2007年10月7日『琉球新報』翁長良明(携帯090-3793-8179)「戦後の象徴『石川』旧東恩納博物館」)
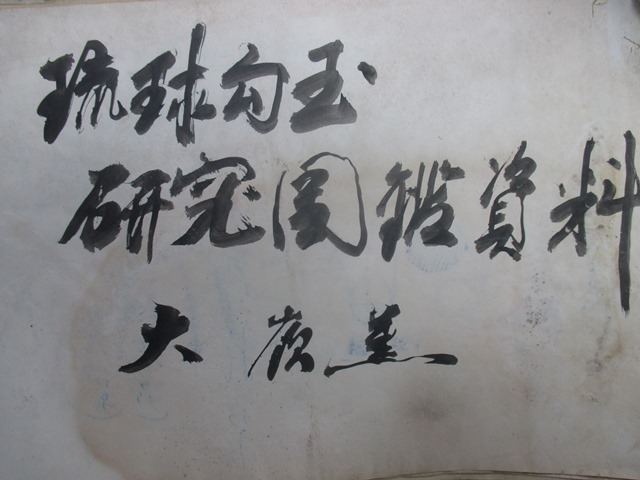
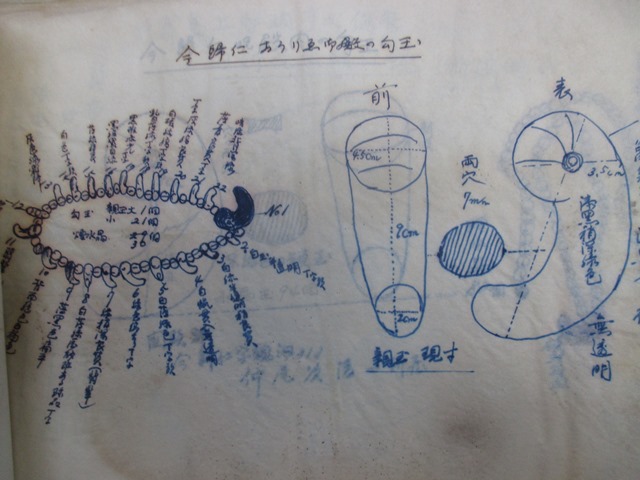
1970年10月12日『琉球新報』山里永吉「シュープ大将と大嶺薫」








テレビの取材を受ける翁長良明氏/田名真之氏、人間国宝の照喜名朝一氏、大城學氏


2019年2月17日 琉球三線楽器保存・育成会「三線ゆんたく会」ー左から上江洲義昭氏、銘苅春政氏、岸本尚登氏/銘苅春政氏(1934年 玉城村生まれる。沖縄県指定工芸士(三線部門)。現代の名工。胡弓奏者としても県から沖縄伝統芸術の技能保持者)

1988年10月30日『琉球新報』宮里春行「私と三線ー名器100挺に寄せて①」、31日 玉栄昌治②、11月2日 比嘉常俊③、11月3日 比嘉常俊④、11月4日 宜保栄治郎⑤)
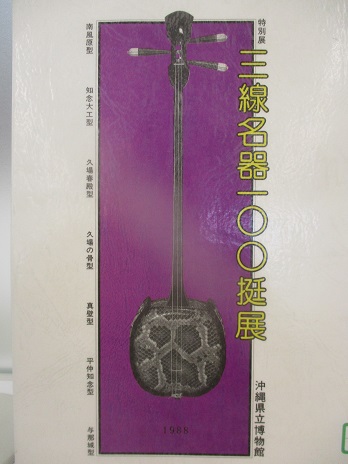
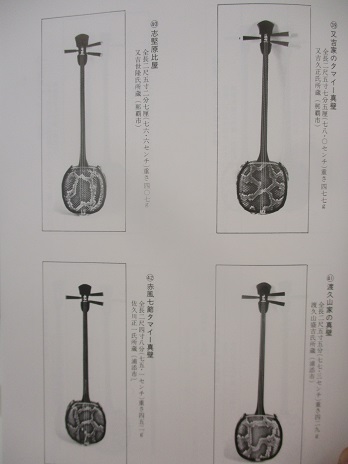
1988年11月 沖縄県立博物館「特別展『三線名器100挺展』」


2019年1月 沖縄タイムス販売店『ウチナー昔たび』第128号「沖縄を愛するコレクター 古美術なるみ堂 翁長良明さん(前編)」/2019年2月『ウチナー昔たび』第129号「沖縄を愛するコレクター 古美術なるみ堂 翁長良明さん(後編)」
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com




2020-4-18昼 沖映通り/国際通り




2020-4-18昼 市場本通り/むつみ橋通り/平和通り/古美術なるみ堂
メジロかごの名工/友寄英春・、宮城宏友

2012年1月7日『沖縄タイムス』堀川幸太郎「復帰40年 うちなぁ時の旅③メジロかご」
宮城宏友/連絡先・翁長良明 ☏090-3793-8179
2011年4月12日ー普天間返還合意から15年
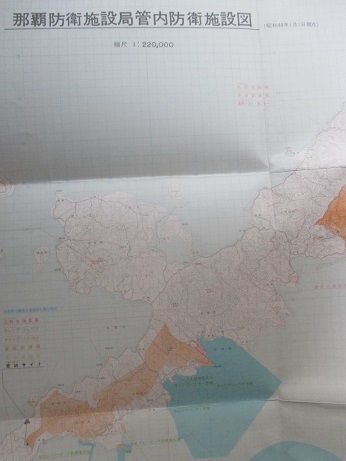
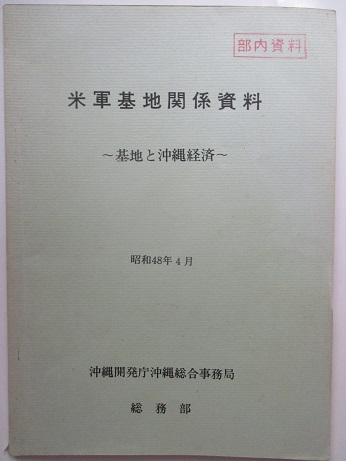
1973年4月 『米軍基地関係資料~基地と沖縄経済~』沖縄開発庁沖縄総合事務局 総務部
地元紙は東北・関東大震災の対応で追いまくられているのか肝心要の自分の頭の蝿(アメリカ基地)の問題を普天間合意という些細な問題にすり替えた論調を展開している。要は沖縄・日本から異民族の基地を撤廃させるのが本来の目標でなかったか。今回の「原発事故」でも解るように来るべき「核戦争」に対し如何に米軍が無能であることがハッキリした。核攻撃や自爆はテロリストでもできるが、逆に攻撃されたらなす術が無いのが今のアメリカ軍の実態である。
今、アメリカ海軍の佐世保基地に横須賀基地配備の空母などが相次ぎ寄港している。原発事故に伴う横須賀入港の回避措置だが、原発事故は収束のめどが立たず、あろうことか、横須賀の在日アメリカ海軍司令部が放射能をさけるため佐世保に移転という笑えない情報もある。早くアメリカへ避難した方が良い。放射能が怖い軍隊は無用の長物だ。
4月13日の地元紙は辺野古テント村での、世界の国が軍事費を直面する危機のために使うように求めたグローバル行動の一環として「思いやり予算を被災地支援に」の訴えを小さく扱っていた。また真に国防が必要なら「思いやり予算」でアメリカ青年の失業対策に使うでなしに、自国の青年や中年の失業対策の一環としても、国防に担ってもらいながら純粋に国防のための機器(兵器ではない)を開発しながら、防災に強い国土造成も重要な任務として膨大な予算をつぎ込まなければならない。その際、戦後の日米軍事利権に関わった自衛隊幹部の粛清はいうまでもない。

2010年12月17日ー沖縄県庁前でのカン総理への抗議集会プラカード




2020-4-18昼 沖映通り/国際通り




2020-4-18昼 市場本通り/むつみ橋通り/平和通り/古美術なるみ堂
メジロかごの名工/友寄英春・、宮城宏友

2012年1月7日『沖縄タイムス』堀川幸太郎「復帰40年 うちなぁ時の旅③メジロかご」
宮城宏友/連絡先・翁長良明 ☏090-3793-8179
2011年4月12日ー普天間返還合意から15年
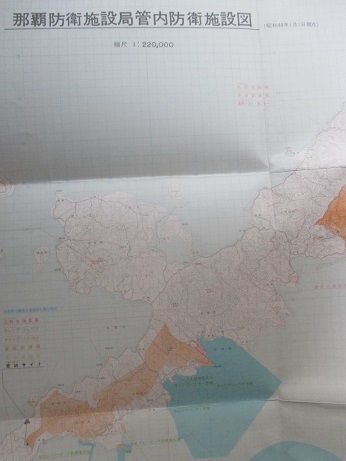
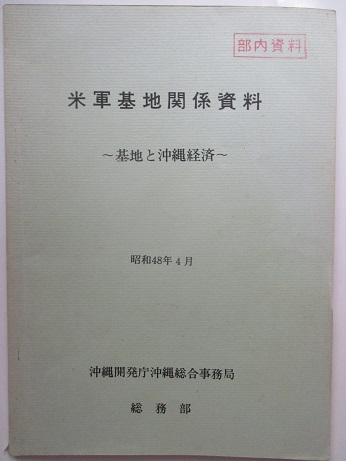
1973年4月 『米軍基地関係資料~基地と沖縄経済~』沖縄開発庁沖縄総合事務局 総務部
地元紙は東北・関東大震災の対応で追いまくられているのか肝心要の自分の頭の蝿(アメリカ基地)の問題を普天間合意という些細な問題にすり替えた論調を展開している。要は沖縄・日本から異民族の基地を撤廃させるのが本来の目標でなかったか。今回の「原発事故」でも解るように来るべき「核戦争」に対し如何に米軍が無能であることがハッキリした。核攻撃や自爆はテロリストでもできるが、逆に攻撃されたらなす術が無いのが今のアメリカ軍の実態である。
今、アメリカ海軍の佐世保基地に横須賀基地配備の空母などが相次ぎ寄港している。原発事故に伴う横須賀入港の回避措置だが、原発事故は収束のめどが立たず、あろうことか、横須賀の在日アメリカ海軍司令部が放射能をさけるため佐世保に移転という笑えない情報もある。早くアメリカへ避難した方が良い。放射能が怖い軍隊は無用の長物だ。
4月13日の地元紙は辺野古テント村での、世界の国が軍事費を直面する危機のために使うように求めたグローバル行動の一環として「思いやり予算を被災地支援に」の訴えを小さく扱っていた。また真に国防が必要なら「思いやり予算」でアメリカ青年の失業対策に使うでなしに、自国の青年や中年の失業対策の一環としても、国防に担ってもらいながら純粋に国防のための機器(兵器ではない)を開発しながら、防災に強い国土造成も重要な任務として膨大な予算をつぎ込まなければならない。その際、戦後の日米軍事利権に関わった自衛隊幹部の粛清はいうまでもない。

2010年12月17日ー沖縄県庁前でのカン総理への抗議集会プラカード




山田真萬


2020年7月20日 京一郎氏(右)、店主の翁長良明氏
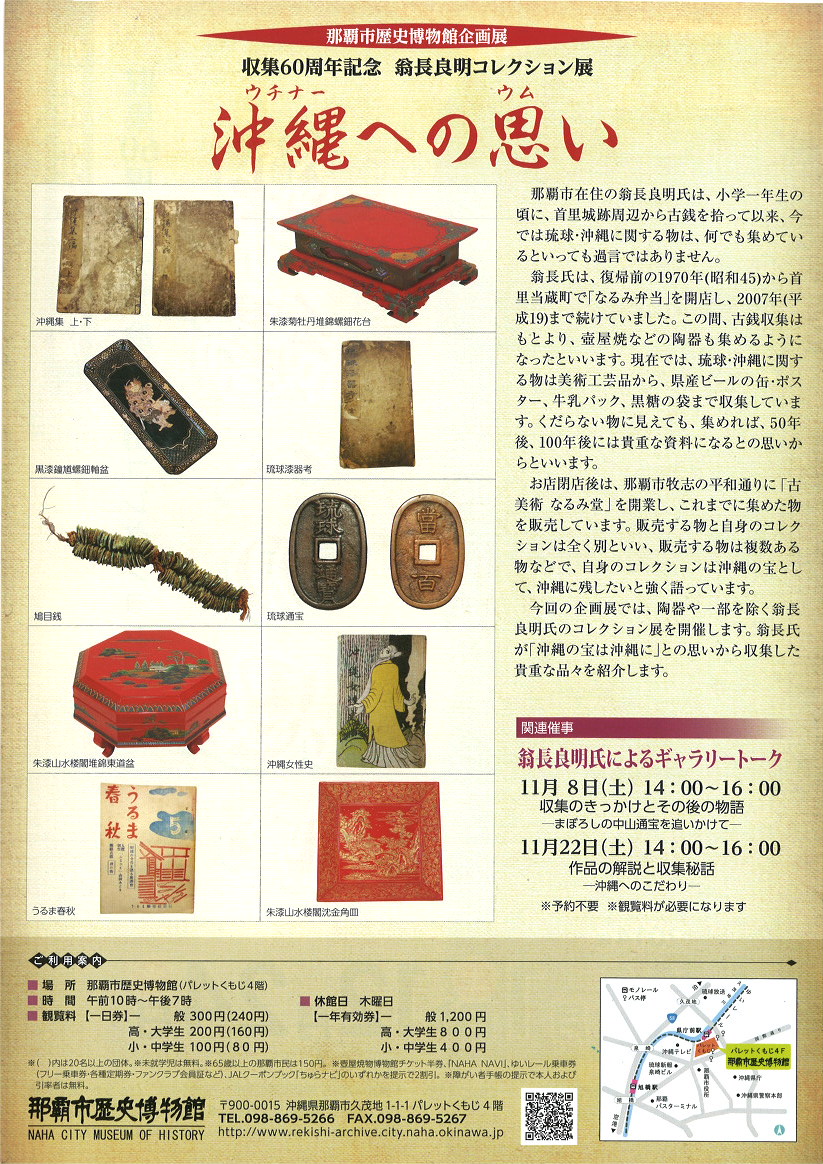
古美術なるみ堂 ☏098-987-5530
1階

首里西森焼のシーサー



「古美術 なるみ堂」ここをクリック











2008年12月 なるみ堂「沖縄のメディア展 新聞・ラジオ・テレビ」
沖縄の新聞
<2008年11月9日「新聞資料研究会」琉球新報新聞博物館
琉球新報本社には新聞博物館(http://ryukyushimpo.jp/info/page-129.html ) (2005年4月開館)がある。その機関紙『あめく通信』9号(2008年)に新聞収集家として著名な羽島知之氏の琉球新報での講演「新聞と私ー新聞収集研究60年」と、羽島氏が新聞博物館に寄贈した新聞原紙の目録が載っている。2008年11月9日に新聞博物館で「新聞資料研究会第19回大会」があった。会長の羽島氏以下15人が県外から参加した。沖縄側から岡田館長、新聞研究家の下地智子さん、沖縄コレクター友の会から会長の上原実、副会長の翁長良明、新城栄徳が参加した。新城は羽島会長から『スタンプマガジン』(2008年10月)を恵まれた。同誌には羽島会長の「号外コレクションが語る近現代史」が連載されている。なお横浜にある日本新聞博物館には羽島コレクションが10万点収蔵されている。

左から、上原実(沖縄コレクター友の会会長)、羽島知之(新聞資料研究会会長)、新城栄徳(沖縄コレクター友の会)、翁長良明(沖縄コレクター友の会副会長)。□→琉文手帖通信①
12/17: 年譜・末吉麦門冬/1919(大正8)年①
1919年1月1日ー『日本及日本人』747号□末吉麦門冬「再び琉球三味線に就いて」「小ぢよく」「かんから太鼓」(吉田芳輝氏提供)
1919年6月ー末吉麦門冬『沖縄時事新報』創刊に参画
1919年6月『日本及日本人』759号 末吉麦門冬□「経済ーエコノミーを経済と譯するの適否は如らず、會澤正志の新論に「或毛擧細故、唯貨利是談、自称経済之學」云々とあり、政治が今日謂ふ所の経済に重きを置くことが、近世的傾向たるにより、訳者をして此の語を選ばしめ、敢て不適当を感ぜしめざるに至りしやも知るべからず。又支那にも後世に至り経済を倹約の意に用ひしことありや。清朝の詩人舒位の詩に「一屋荘厳妻子佛、六時経済米鹽花」とあり、猶ほ考ふべし。」□南方熊楠□「夜啼松ー佐夜の中山より十町斗りを過て夜啼の松あり、此松をともして見すれば子供の夜啼を止るとて往来の人削り取きり取ける程に、其松遂に枯て今根斗りに成けりと、絲亂記より六十二年前に成た東海道名所記三に見ゆ。其頃早く枯れ居たのだ。」
1919年7月15日ー『日本及日本人』761号□末吉麦門冬「琉球風と王子の歌」
1919年8月15ー『日本及日本人』763号□南方熊楠「ストライキー麦生君は自笑の常世誰が身の上に依って、徳川幕府の中葉既にストライキが多少本邦で行われたと立証されたー」
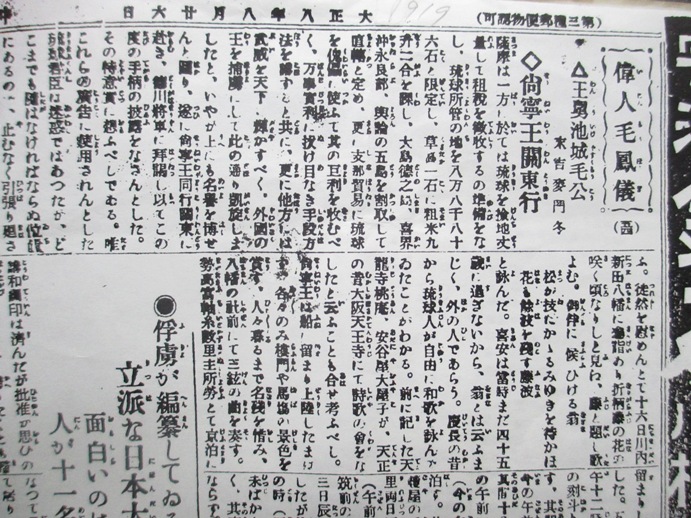
1919年8月26日 『沖縄朝日新聞』末吉麦門冬「偉人 毛鳳儀ー王舅池城毛公」」(喜安日記)
1919年9月 『沖縄時事新報』麦門冬「南山俗語考を見て(下)」
▲古賀精里の序文にも南山主人の跋文にもなくして、今一つの重要なる事があって、薩摩をして支那語研究をなさしむる動機となり目的となった。それが又南山俗語考を作らしむる動機ともなり目的ともなった。それは琉球を仲介としての支那貿易をなしている特殊の関係が薩摩にあったことだ。この特殊の関係がある故に彼等は色々の詭計を設けて、例えば藩士に琉装せしめ、琉球人と共に支那に派したりしたこともある従って支那語に堪能ならなければならぬ必要は琉球に劣らざるものがあった。23歳の一青年たる南山主人をして俗語考を著はす考を起さしめたのもこれが重大であらうと思ふ武藤長平氏の説に依ると、流石に大名が金をかけ長い年月を費やして作ったものだけありて、長崎辺から出た支那語の辞書などとは比較にならぬ程、この辞書は正確なものであるとの事だ。薩摩よりも官話ならこっちが本場だと思はれた、琉球人までがこの書を官話研究の唯一の手引としたのも又偶然にあらずと思ふ。
▲これより彼と琉球との関係の片影を一寸紹介して見たい、彼は延享2年の生まれであるから琉球の読谷山王子朝憲とは同庚である。それも一つの原因であったのだらう読谷山王子とは甚だ懇意であったらしい。明和元年11月21日「琉球國読谷山王子を携えて営に上る」と寛政重修諸家譜に出ている。其時に貰ったのか其後かは知らないが、読谷山家に彼の書が遺蔵されている「萬世之寶」と書いて南山主人の落款がついているとのことだが私はまだ拝見せぬ。南聘紀考に依ると安永2年当時太子であった中城王子尚温も、15歳に及びたるにより恒例の如く薩摩に往訪した。その時にも読谷山王子は随行した。文化3年に尚灝王は又読谷山王子を使して江戸に入貢すとあるから、同王子と重豪とは会する機会が多かったことが知られる。
▲武藤長平氏は其の目下琉球紙上に連載されている薩藩の琉球統治の中に「歴代の薩藩主中最も学問的に琉球を利用したのが、島津重豪で之を学問的にも、将た又経済的にも、利用したのが島津斉彬である」と云はれた。それは当っているだらうが、重豪は単に学問的ばかりでなく彼は又経済的にも琉球及び琉球人を利用している事実がある。利用し得たと云ふ程のものでなければ利用せんとしていた事実は明らかである。それは稿を改めて書こう。
1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」


1919年9月14日ー『沖縄時事新報』末吉麦門冬「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人」(~9月22日)


○1990年3月 『新琉球史ー近世編(下)』琉球新報社
池宮正治「和文学の流れ」□さきに、『小門の汐干』に入集している、渡久山政順と渡久山政規の関係について、「親子か兄弟といった近い関係かと思われるが、琉歌集にも心あたりの人はいない。あるいは『沖縄集』の玻名城親方政順かとも考えられるが詳細は不明」と述べておいた。すると早速特異な資料ハンター新城栄徳氏から連絡があり、名護市立博物館に収蔵されている宮城真治氏の新聞切抜きにある、末吉麦門冬(1886~1924)が「沖縄時事新報」(1919~1925)に発表した「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人ー」のコピーを恵まれた。宮城真治切抜き資料については、沖縄県の組踊調査のさい見ているが、組踊関係の資料を収集しただけで、見過ごしてしまったようだ。この麦門冬論文は、私の積年の宿題を一挙に解消してくれるものであった。
1918年11月16日 大里村で「沖縄歴史地理講話会」
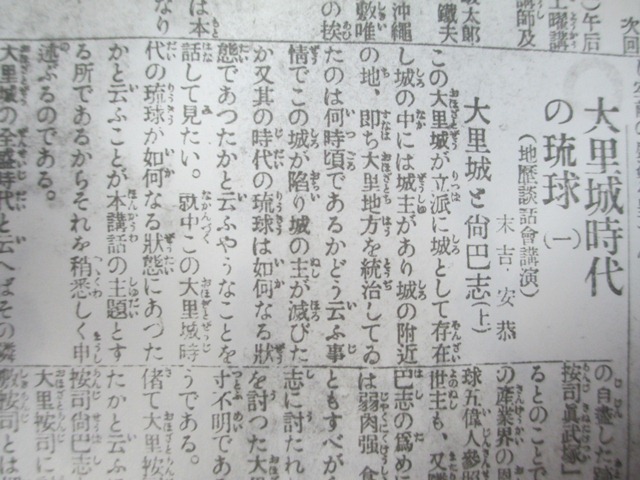
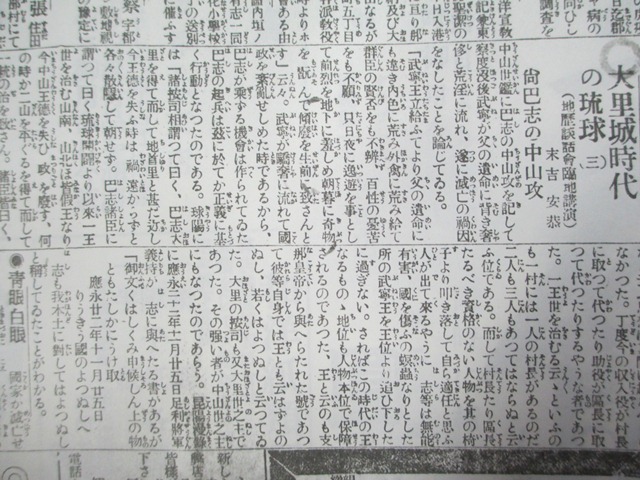
○この三山分裂に就いては説をなす者あり、もと方々に部落をなした住民が地勢によりて、山北は山北で一団、中山は中山で一団、南山は南山で一団になりて次第に発達して、その勢力が対敵行為をなすようになったので、嘗て中山に統一されたものが分離したものでないと。地勢によりて住民が割拠の勢いをなしたと云ふことは私も承認する、(略)英祖王の時代、遠く大島までが服従した位だから既にこのときは国内を漸く統一していたことが知れる。それが玉城王の時に中央の勢力が衰微に乗じて瓜分割拠の勢いを呈したのではあるまいか。
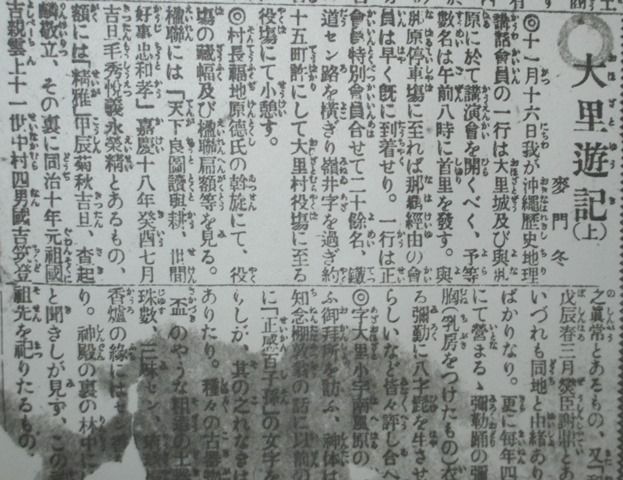
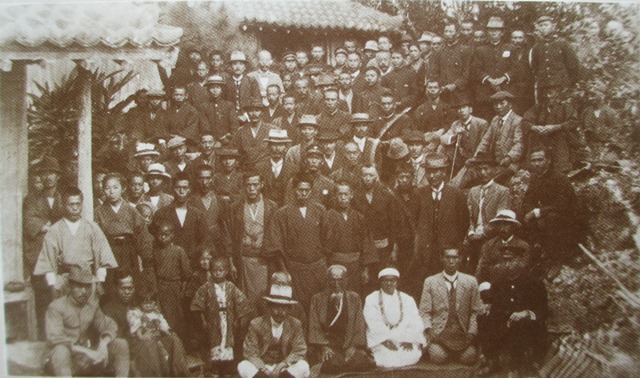
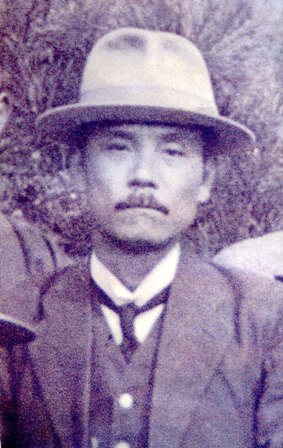
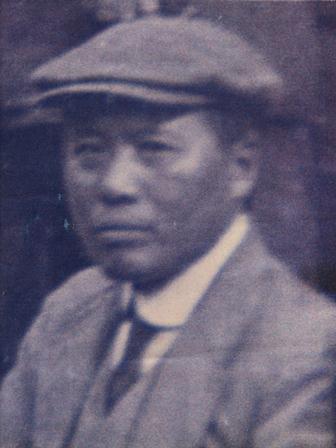
当日の真境名安興/末吉安恭
11月22日『沖縄時事新報』安良城盛雄(上海)「田島先生」(1)
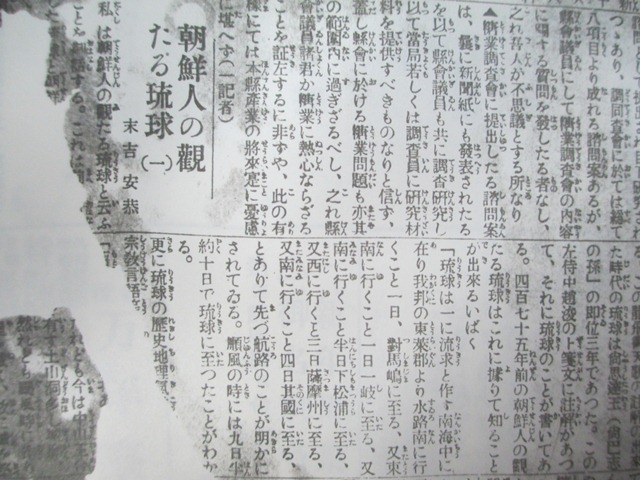
1919年12月8日 『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」
12月12日『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」(4)
12月 『沖縄時事新報』広告「神村朝忠薬店(首里儀保町酒ヤ知念小ノ向)ー1、諸売薬特ニ眼病ト梅毒ノ1、名薬/一枚コヨミト畧本暦/1、北斗中正暦ト柱コヨミ/1、東京神誠館発行御寿寶/1、易者一般ノ必要各種」
1919年6月ー末吉麦門冬『沖縄時事新報』創刊に参画
1919年6月『日本及日本人』759号 末吉麦門冬□「経済ーエコノミーを経済と譯するの適否は如らず、會澤正志の新論に「或毛擧細故、唯貨利是談、自称経済之學」云々とあり、政治が今日謂ふ所の経済に重きを置くことが、近世的傾向たるにより、訳者をして此の語を選ばしめ、敢て不適当を感ぜしめざるに至りしやも知るべからず。又支那にも後世に至り経済を倹約の意に用ひしことありや。清朝の詩人舒位の詩に「一屋荘厳妻子佛、六時経済米鹽花」とあり、猶ほ考ふべし。」□南方熊楠□「夜啼松ー佐夜の中山より十町斗りを過て夜啼の松あり、此松をともして見すれば子供の夜啼を止るとて往来の人削り取きり取ける程に、其松遂に枯て今根斗りに成けりと、絲亂記より六十二年前に成た東海道名所記三に見ゆ。其頃早く枯れ居たのだ。」
1919年7月15日ー『日本及日本人』761号□末吉麦門冬「琉球風と王子の歌」
1919年8月15ー『日本及日本人』763号□南方熊楠「ストライキー麦生君は自笑の常世誰が身の上に依って、徳川幕府の中葉既にストライキが多少本邦で行われたと立証されたー」
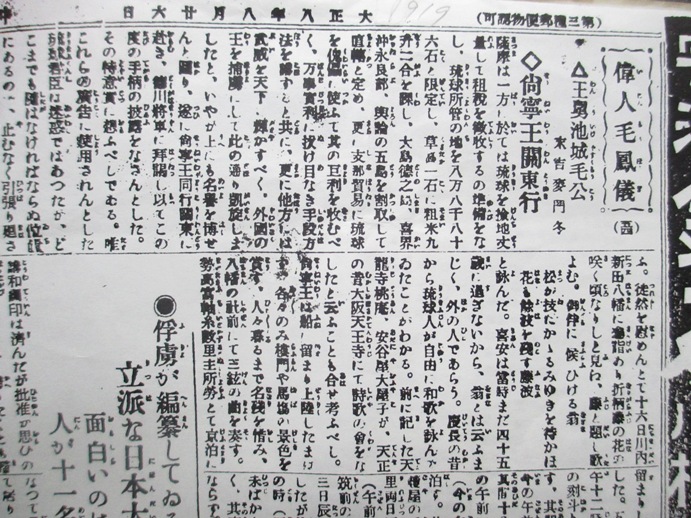
1919年8月26日 『沖縄朝日新聞』末吉麦門冬「偉人 毛鳳儀ー王舅池城毛公」」(喜安日記)
1919年9月 『沖縄時事新報』麦門冬「南山俗語考を見て(下)」
▲古賀精里の序文にも南山主人の跋文にもなくして、今一つの重要なる事があって、薩摩をして支那語研究をなさしむる動機となり目的となった。それが又南山俗語考を作らしむる動機ともなり目的ともなった。それは琉球を仲介としての支那貿易をなしている特殊の関係が薩摩にあったことだ。この特殊の関係がある故に彼等は色々の詭計を設けて、例えば藩士に琉装せしめ、琉球人と共に支那に派したりしたこともある従って支那語に堪能ならなければならぬ必要は琉球に劣らざるものがあった。23歳の一青年たる南山主人をして俗語考を著はす考を起さしめたのもこれが重大であらうと思ふ武藤長平氏の説に依ると、流石に大名が金をかけ長い年月を費やして作ったものだけありて、長崎辺から出た支那語の辞書などとは比較にならぬ程、この辞書は正確なものであるとの事だ。薩摩よりも官話ならこっちが本場だと思はれた、琉球人までがこの書を官話研究の唯一の手引としたのも又偶然にあらずと思ふ。
▲これより彼と琉球との関係の片影を一寸紹介して見たい、彼は延享2年の生まれであるから琉球の読谷山王子朝憲とは同庚である。それも一つの原因であったのだらう読谷山王子とは甚だ懇意であったらしい。明和元年11月21日「琉球國読谷山王子を携えて営に上る」と寛政重修諸家譜に出ている。其時に貰ったのか其後かは知らないが、読谷山家に彼の書が遺蔵されている「萬世之寶」と書いて南山主人の落款がついているとのことだが私はまだ拝見せぬ。南聘紀考に依ると安永2年当時太子であった中城王子尚温も、15歳に及びたるにより恒例の如く薩摩に往訪した。その時にも読谷山王子は随行した。文化3年に尚灝王は又読谷山王子を使して江戸に入貢すとあるから、同王子と重豪とは会する機会が多かったことが知られる。
▲武藤長平氏は其の目下琉球紙上に連載されている薩藩の琉球統治の中に「歴代の薩藩主中最も学問的に琉球を利用したのが、島津重豪で之を学問的にも、将た又経済的にも、利用したのが島津斉彬である」と云はれた。それは当っているだらうが、重豪は単に学問的ばかりでなく彼は又経済的にも琉球及び琉球人を利用している事実がある。利用し得たと云ふ程のものでなければ利用せんとしていた事実は明らかである。それは稿を改めて書こう。
1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」


1919年9月14日ー『沖縄時事新報』末吉麦門冬「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人」(~9月22日)


○1990年3月 『新琉球史ー近世編(下)』琉球新報社
池宮正治「和文学の流れ」□さきに、『小門の汐干』に入集している、渡久山政順と渡久山政規の関係について、「親子か兄弟といった近い関係かと思われるが、琉歌集にも心あたりの人はいない。あるいは『沖縄集』の玻名城親方政順かとも考えられるが詳細は不明」と述べておいた。すると早速特異な資料ハンター新城栄徳氏から連絡があり、名護市立博物館に収蔵されている宮城真治氏の新聞切抜きにある、末吉麦門冬(1886~1924)が「沖縄時事新報」(1919~1925)に発表した「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人ー」のコピーを恵まれた。宮城真治切抜き資料については、沖縄県の組踊調査のさい見ているが、組踊関係の資料を収集しただけで、見過ごしてしまったようだ。この麦門冬論文は、私の積年の宿題を一挙に解消してくれるものであった。
1918年11月16日 大里村で「沖縄歴史地理講話会」
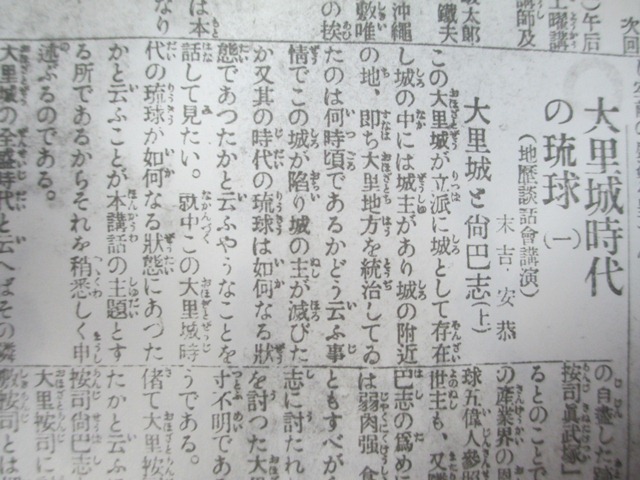
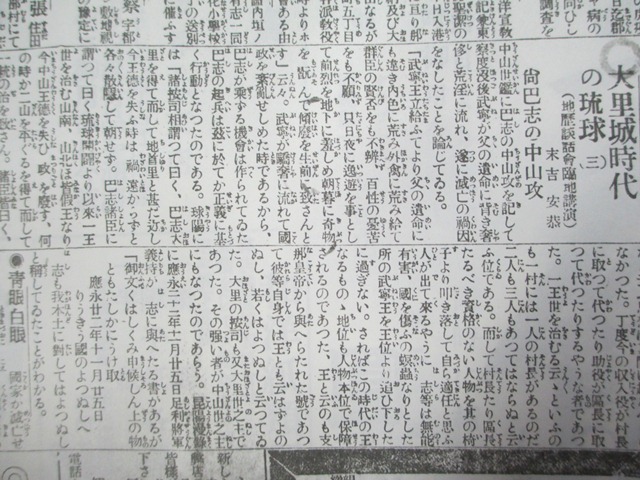
○この三山分裂に就いては説をなす者あり、もと方々に部落をなした住民が地勢によりて、山北は山北で一団、中山は中山で一団、南山は南山で一団になりて次第に発達して、その勢力が対敵行為をなすようになったので、嘗て中山に統一されたものが分離したものでないと。地勢によりて住民が割拠の勢いをなしたと云ふことは私も承認する、(略)英祖王の時代、遠く大島までが服従した位だから既にこのときは国内を漸く統一していたことが知れる。それが玉城王の時に中央の勢力が衰微に乗じて瓜分割拠の勢いを呈したのではあるまいか。
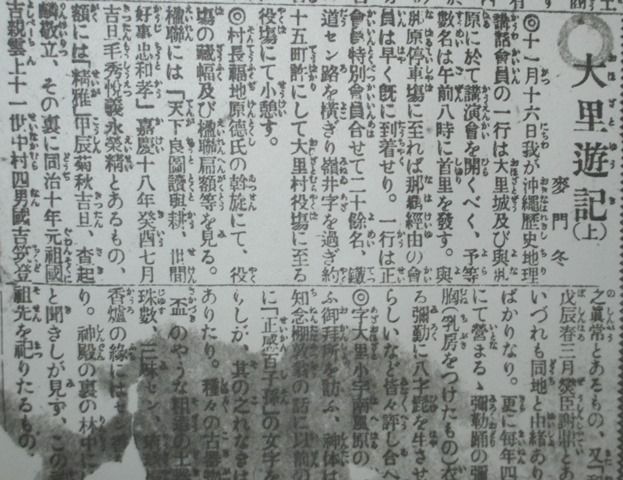
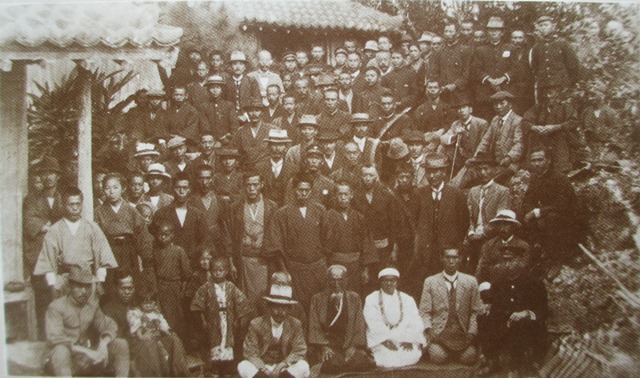
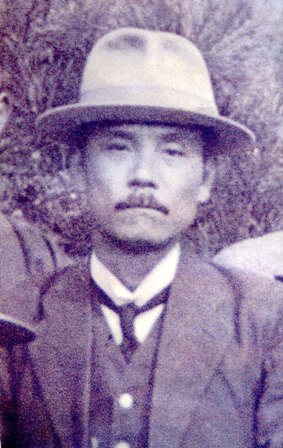
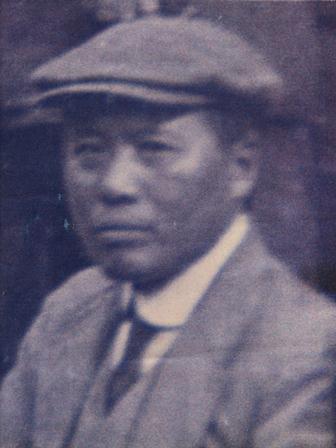
当日の真境名安興/末吉安恭
11月22日『沖縄時事新報』安良城盛雄(上海)「田島先生」(1)
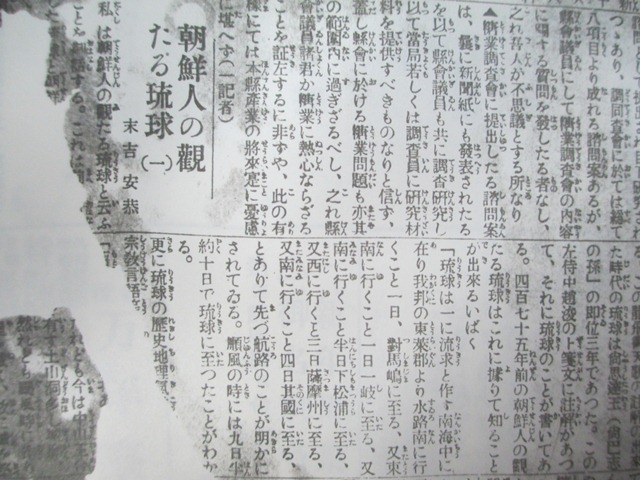
1919年12月8日 『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」
12月12日『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」(4)
12月 『沖縄時事新報』広告「神村朝忠薬店(首里儀保町酒ヤ知念小ノ向)ー1、諸売薬特ニ眼病ト梅毒ノ1、名薬/一枚コヨミト畧本暦/1、北斗中正暦ト柱コヨミ/1、東京神誠館発行御寿寶/1、易者一般ノ必要各種」
03/03: 日米誌②
1940年1月、在米沖縄県人会『琉球』7号□幸地新政「太平洋の危機と在米同胞ー第一次世界大戦の終わりと共に、来るべき世界制覇の舞台は、周知の如く太平洋に移動したのである。(略)若し、日米間に万一のことがあれば、その直接の発火点は疑いもなく蘭印問題であろう。(略)米国政府は1939年7月26日に日本政府に向かって日米通商航海条約の廃止を通告した。これは日支事変に対する米国の日本への抗議の一形態であり、さらに軍需品禁輸断行の事前工作である。米国にも日米開戦論があると同時に又、日米非戦論即ち日米親善論も決して侮るべからざるものを内包している」


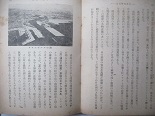
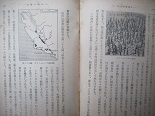
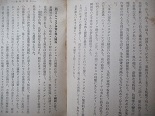
1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。
アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)
1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官
1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。
□731部隊 - Wikipediaja
初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。
原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)
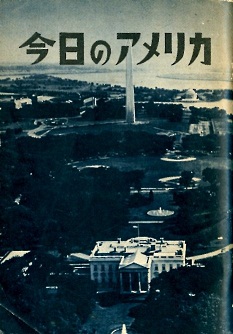

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年
1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ
1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸
1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ
1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。
1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」
1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)
1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」
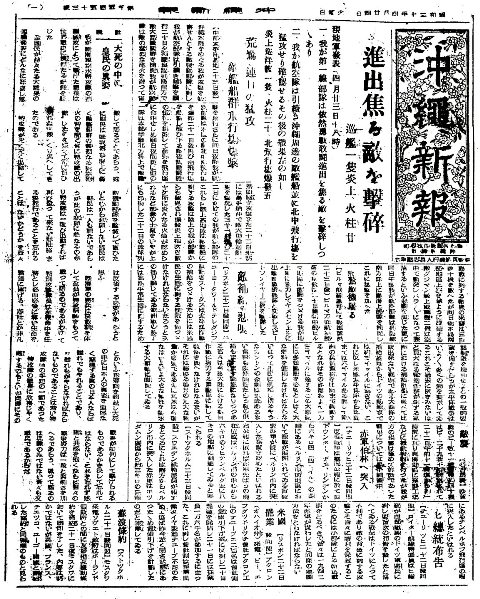
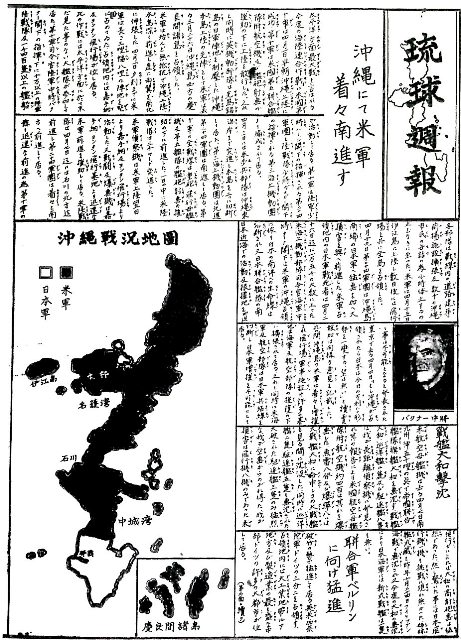
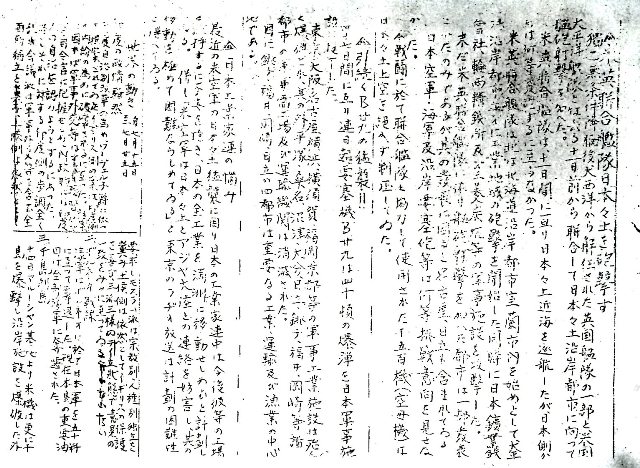
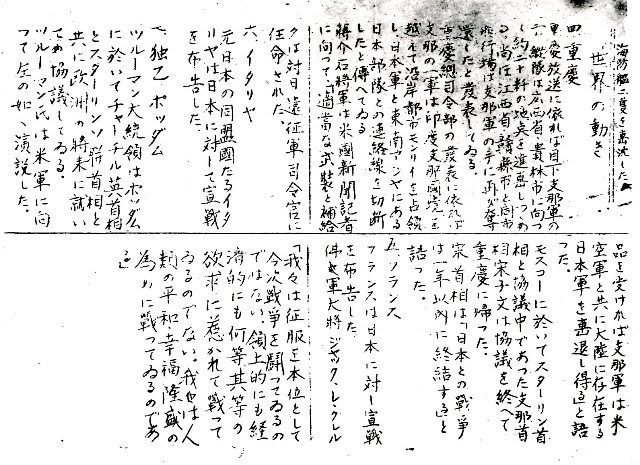
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア
1945年5月7日 石川に城前初等学校開校
1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」
1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動
1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」
1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人
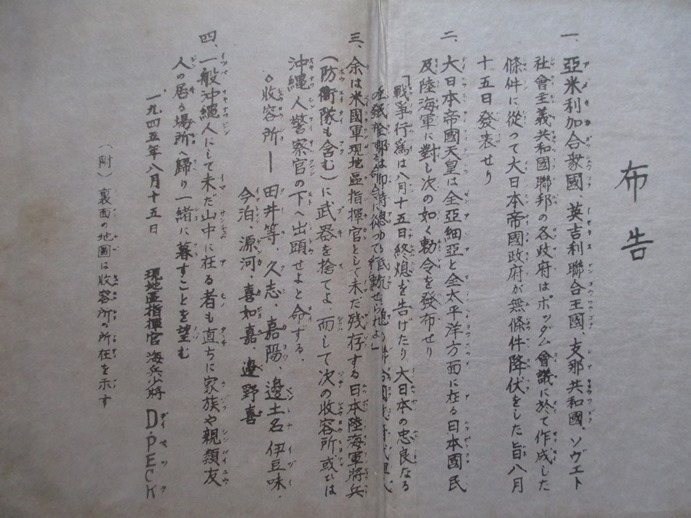
1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」
1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」
1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足
1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」
1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)
1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」
1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」
NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。
ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ
参考資料ー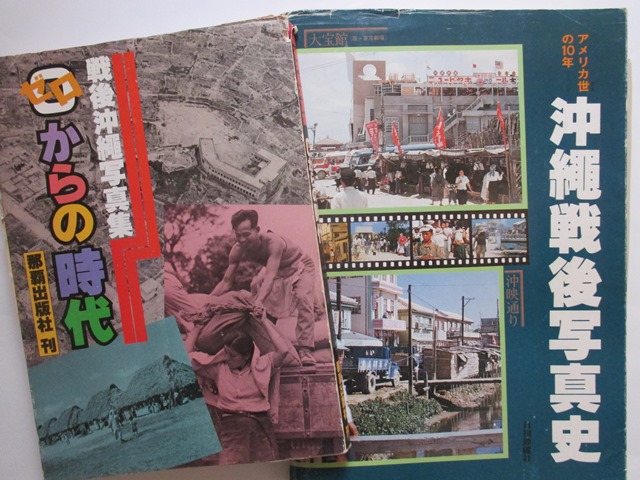
1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社
2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」
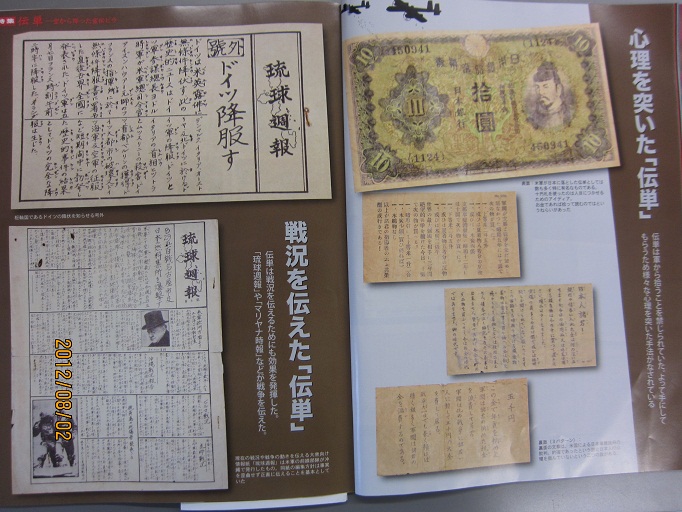
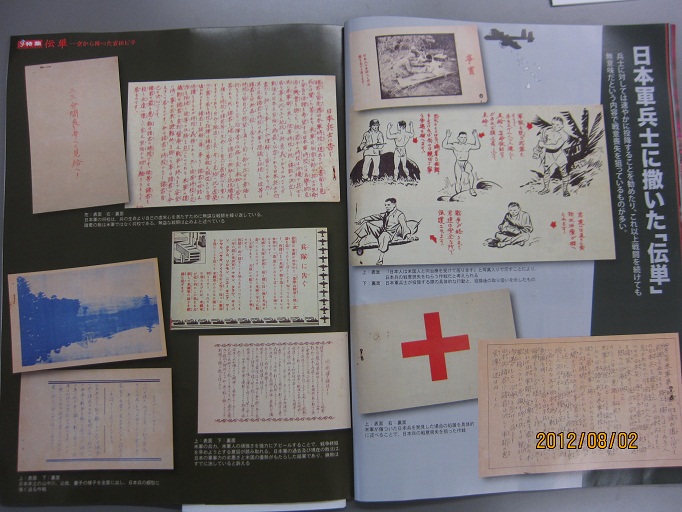
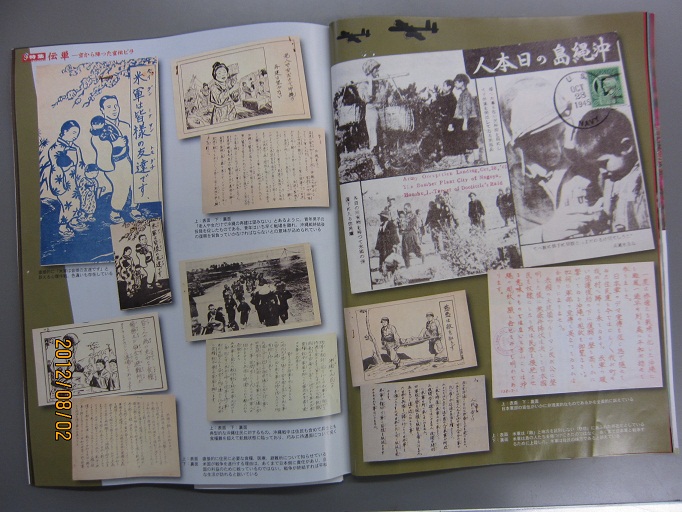
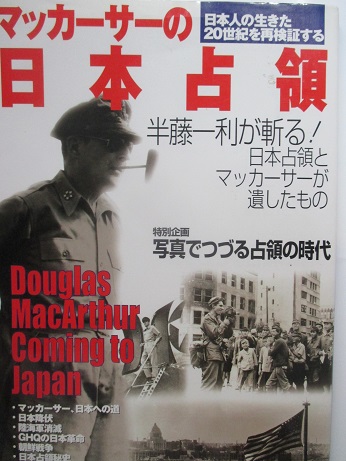
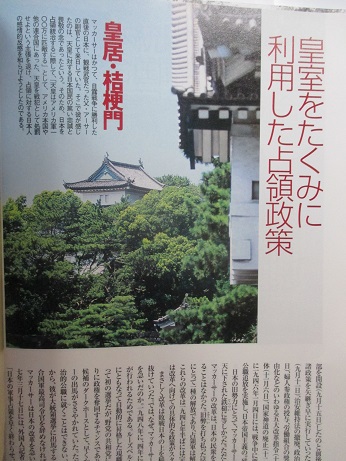
2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社
マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月
。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)
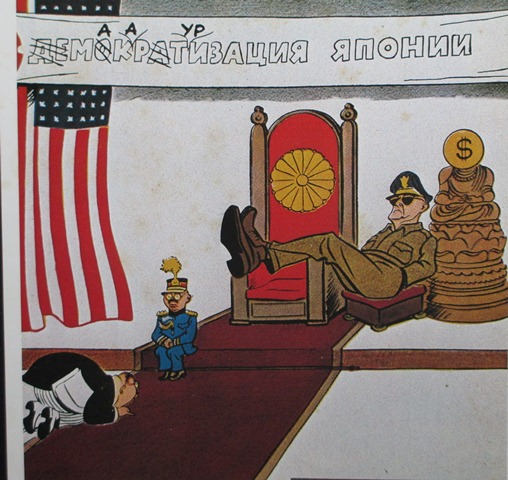
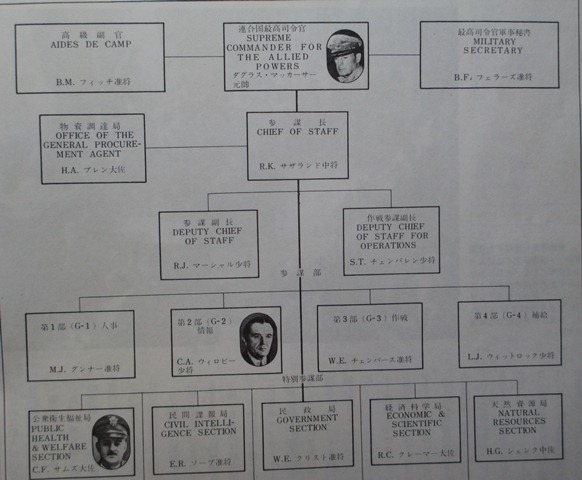
○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。
1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。
1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。
石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。
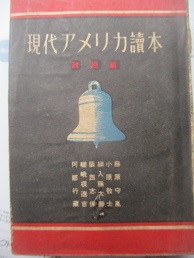
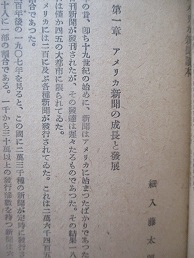

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」
1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ
1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺
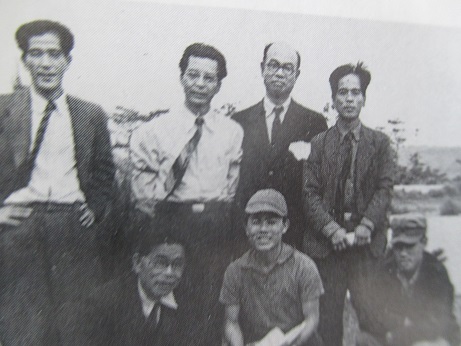
1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝


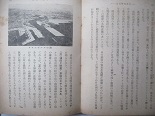
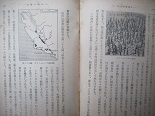
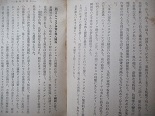
1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。
アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)
1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官
1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。
□731部隊 - Wikipediaja
初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。
原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)
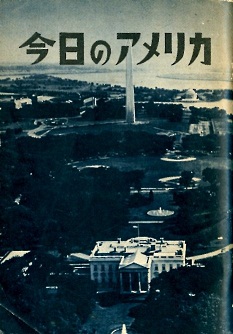

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年
1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ
1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸
1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ
1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。
1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」
1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)
1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」
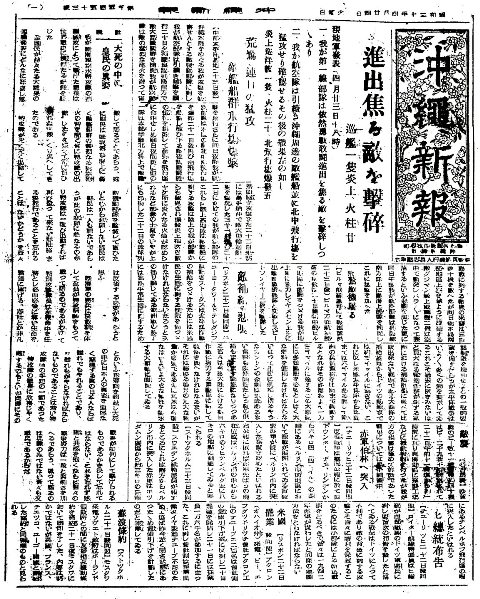
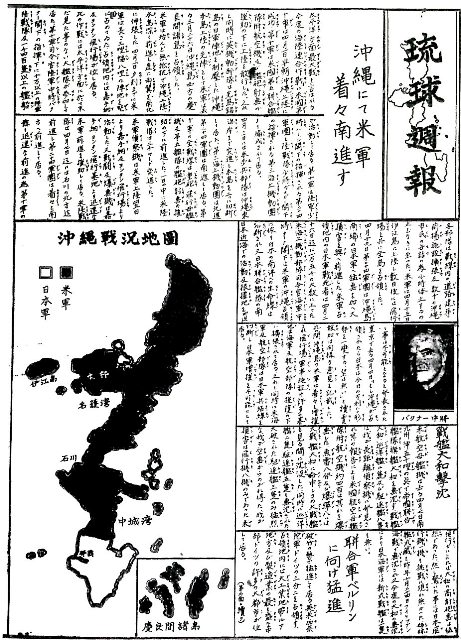
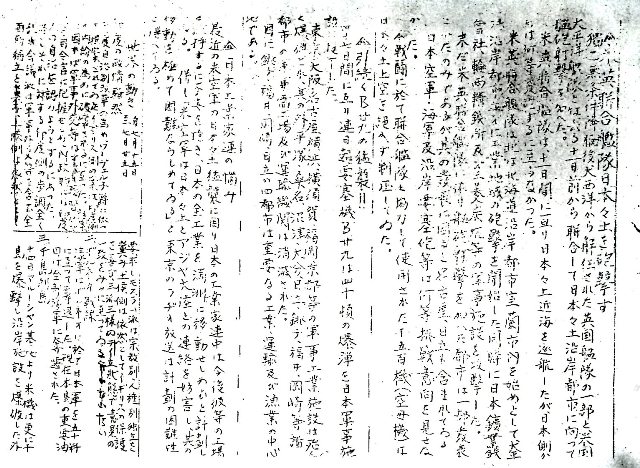
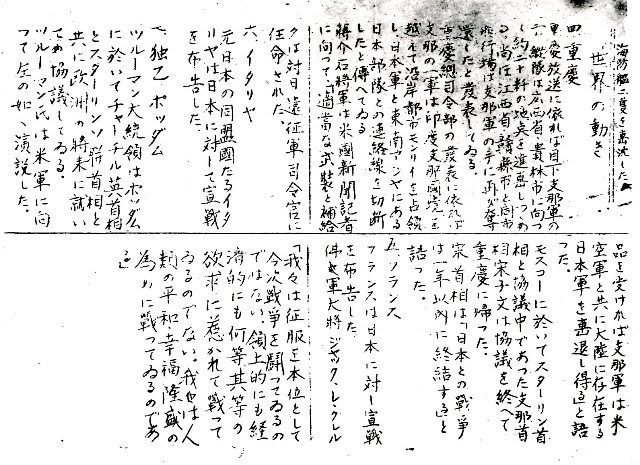
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア
1945年5月7日 石川に城前初等学校開校
1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」
1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動
1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」
1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人
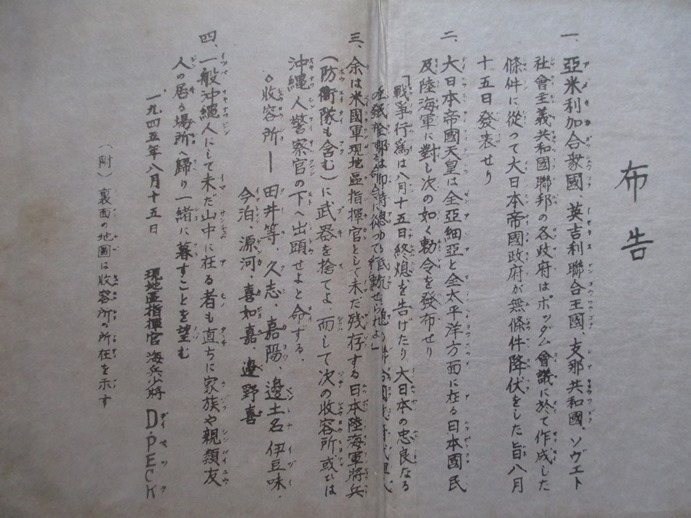
1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」
1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」
1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足
1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」
1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)
1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」
1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」
NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。
ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ
参考資料ー
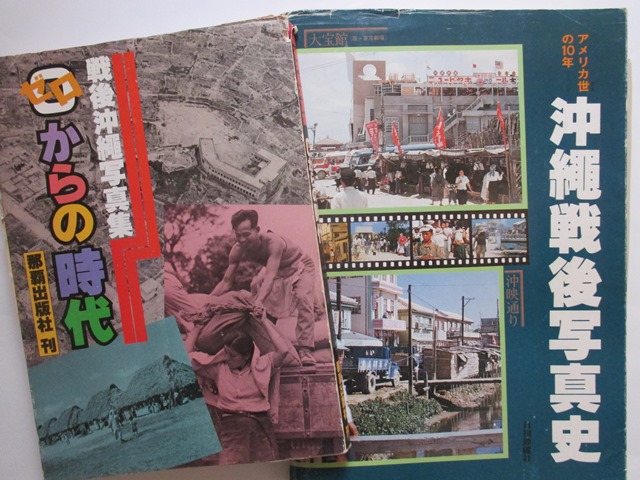
1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社
2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」
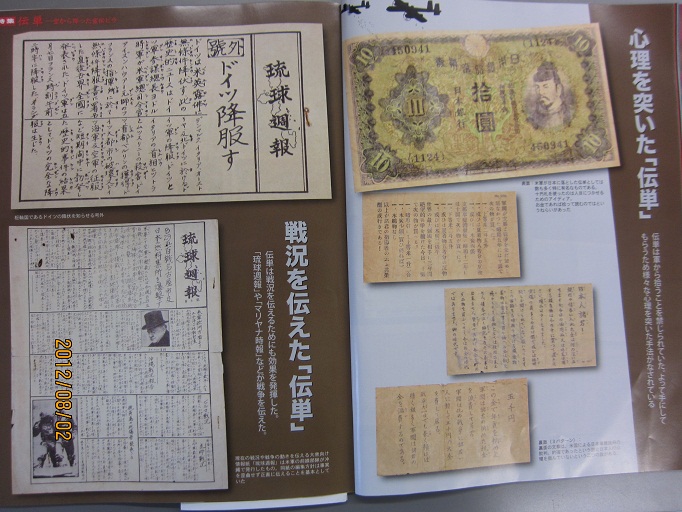
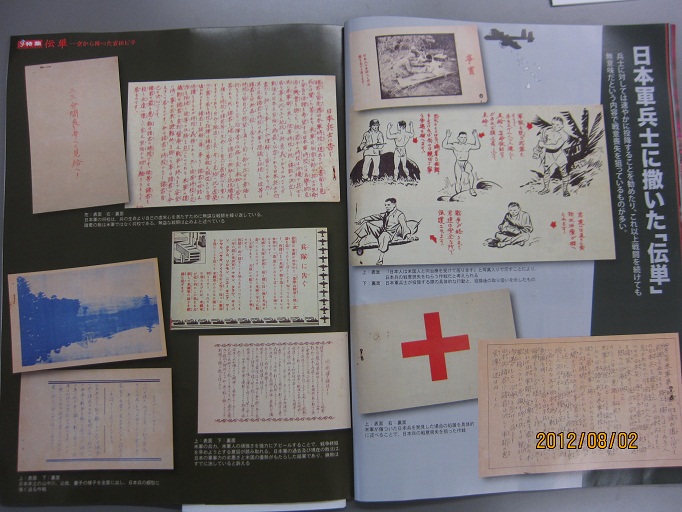
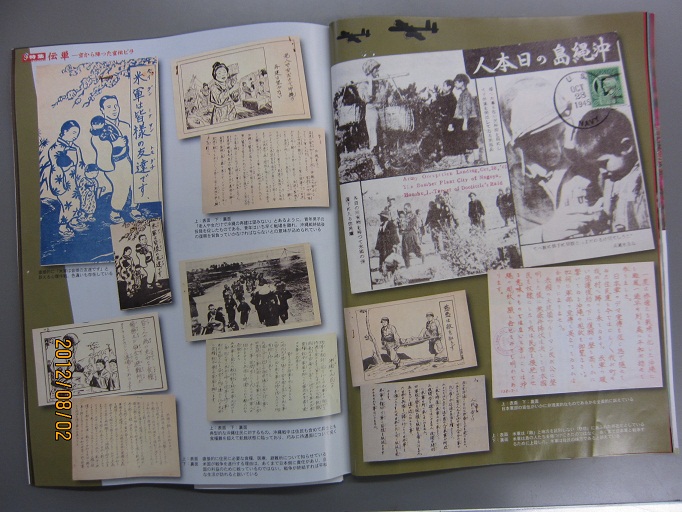
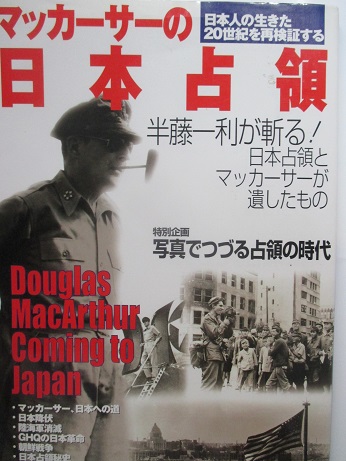
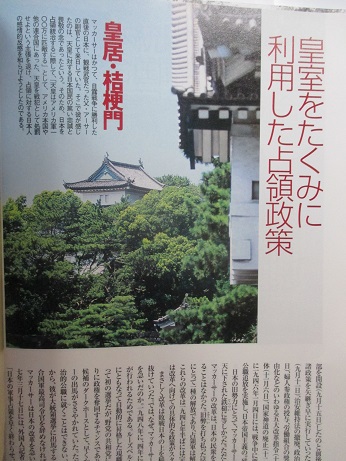
2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社
マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月
。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)
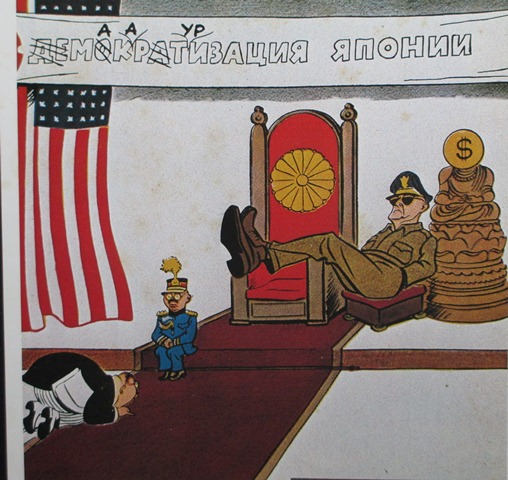
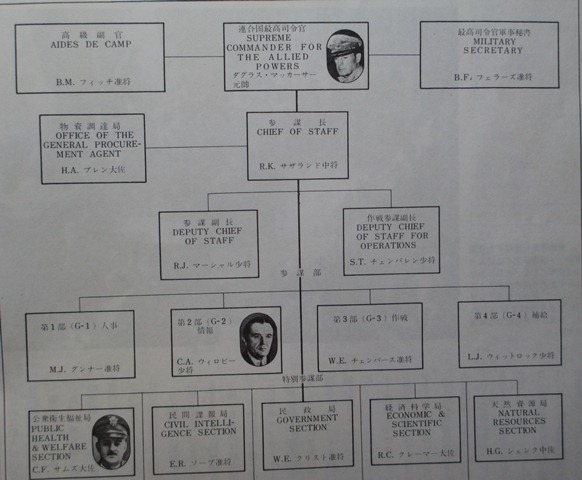
○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。
1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。
1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。
石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。
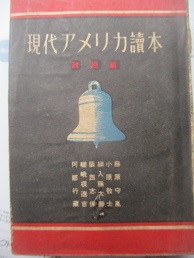
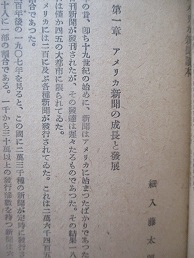

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」
1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ
1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺
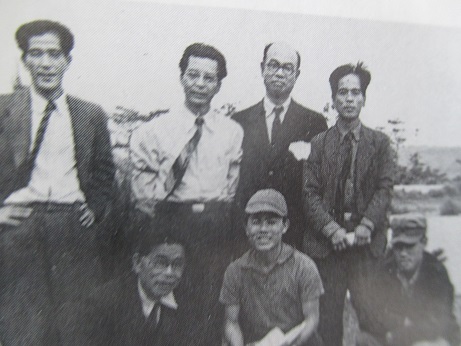
1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝
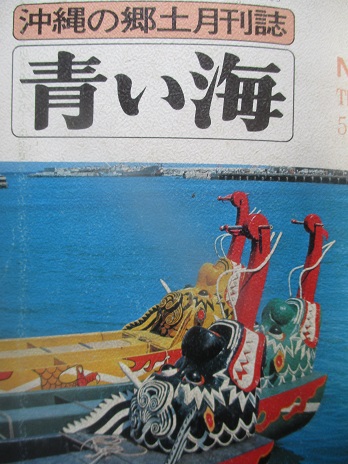
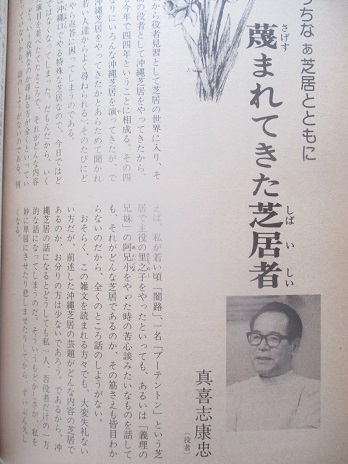
1978年 雑誌『青い海』5月号 真喜志康忠「うちなぁ芝居とともにー蔑まれてきた芝居者」
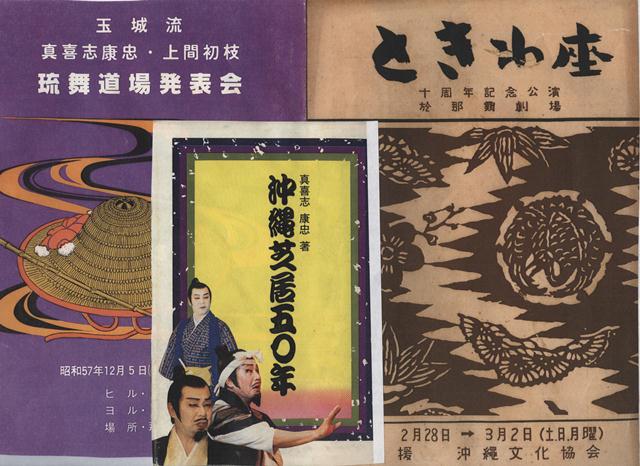
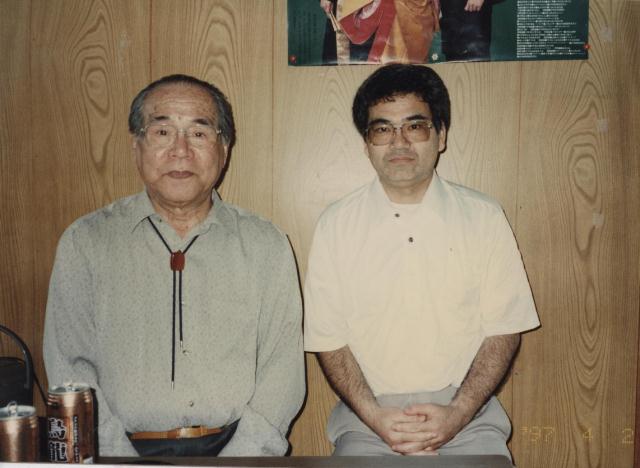
真喜志康忠・上間初枝琉舞道場で真喜志康忠優(左)に山之口貘の思い出を聞く新城栄徳

1996年11月19日ー國吉眞哲翁告別式で芝憲子さんと話す真喜志康忠優


2003年5月 眞喜志康忠宅で、右から平良リエ子さん、平良次子さん、康忠優、眞喜志康徳さん(撮影・新城栄徳)。
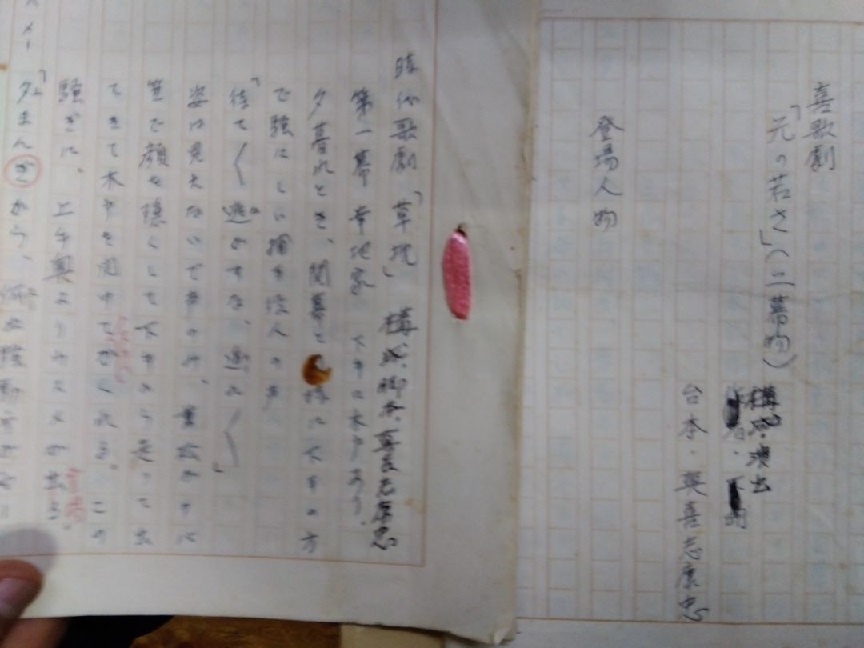
眞喜志康忠「原稿」翁長良明氏所蔵
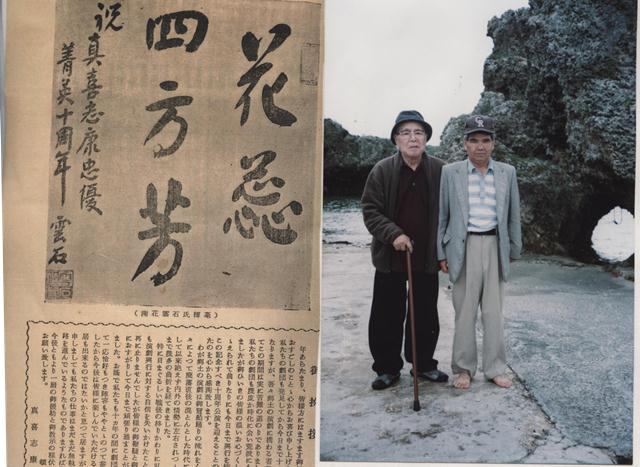
写真右ー真喜志康忠優(左)、新城栄徳/浜比嘉島・あまみこ神の足跡を訪ねて(真喜志康徳・撮影)


山城 明 2021-6-23 浜比嘉島浜 左手の小さな岩の島がアマミチューの墓ですよ!
1910年4月『スバル』落紅・末吉安恭「親の親の遠つ親より伝へたるこの血冷すな阿摩彌久の裔」
06/12: 山里永吉と古陶
翁長良明コレクション
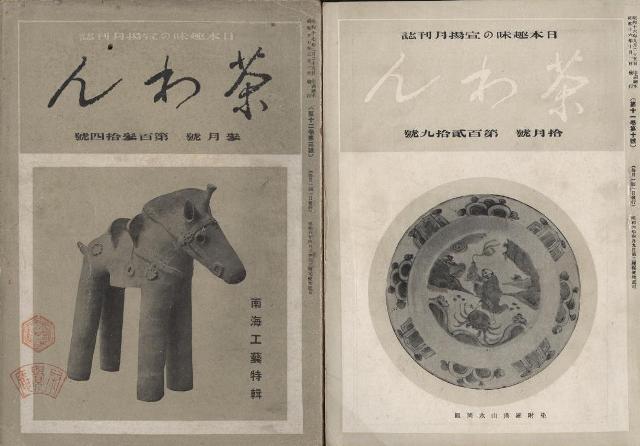
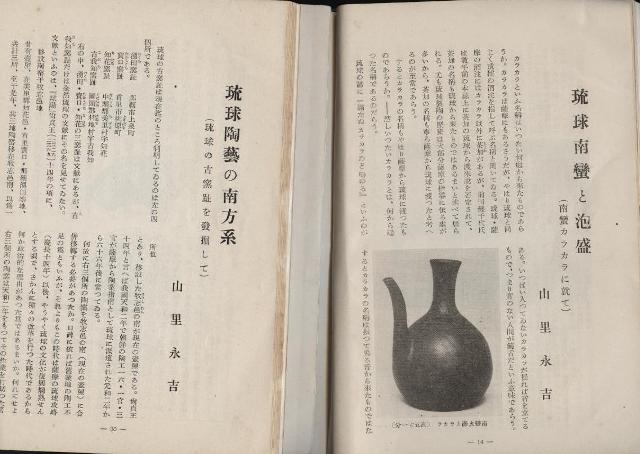

〇山里永吉編『松山王子尚順遺稿』(1969年8月)に「古酒の話」が載っているが、上記の山里永吉「琉球南蛮と泡盛」には尚順の泡盛古酒壺の写真がある。

古美術なるみ堂 ☏098-987-5530


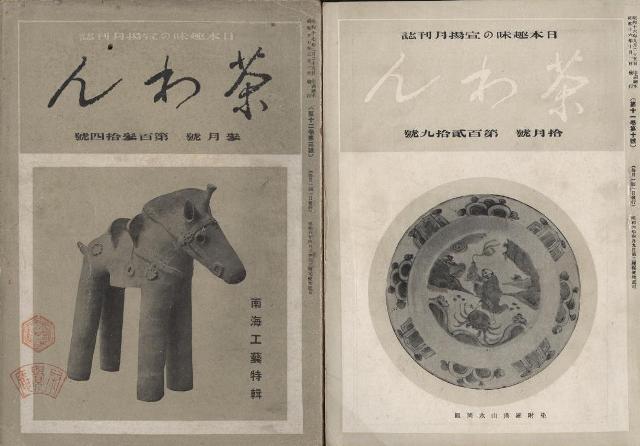
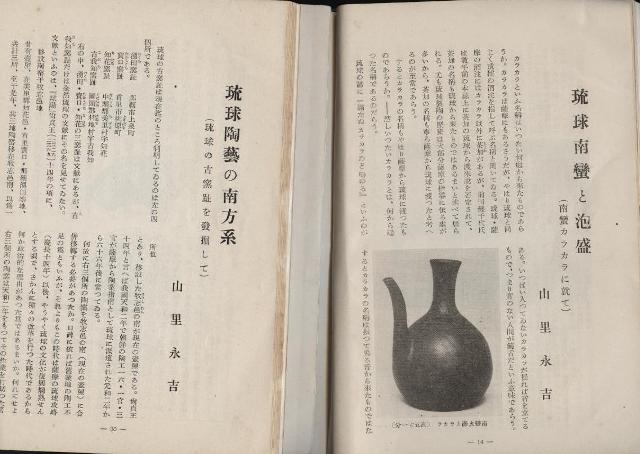

〇山里永吉編『松山王子尚順遺稿』(1969年8月)に「古酒の話」が載っているが、上記の山里永吉「琉球南蛮と泡盛」には尚順の泡盛古酒壺の写真がある。

古美術なるみ堂 ☏098-987-5530


08/15: 芸能/松村宏
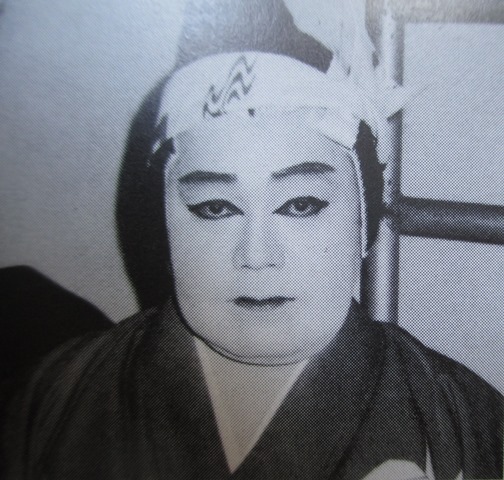
松村宏優
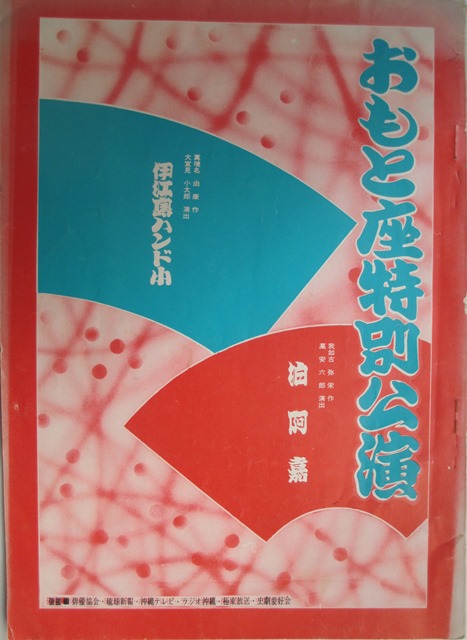
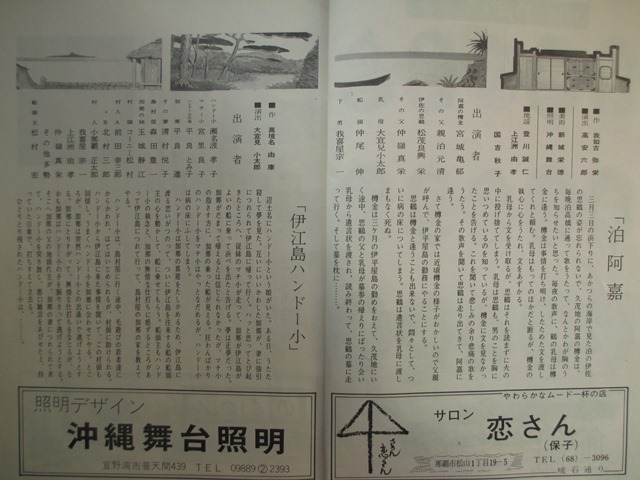
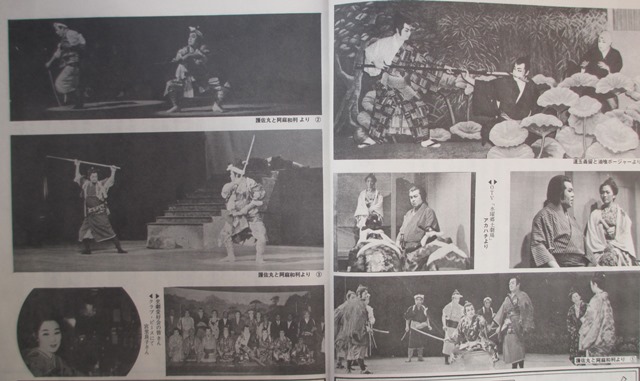
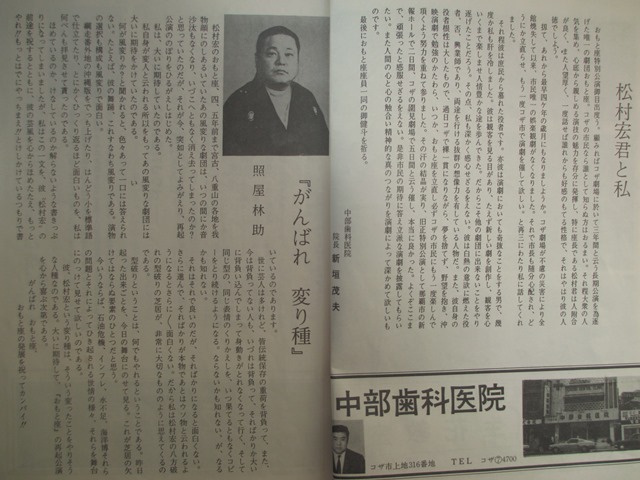
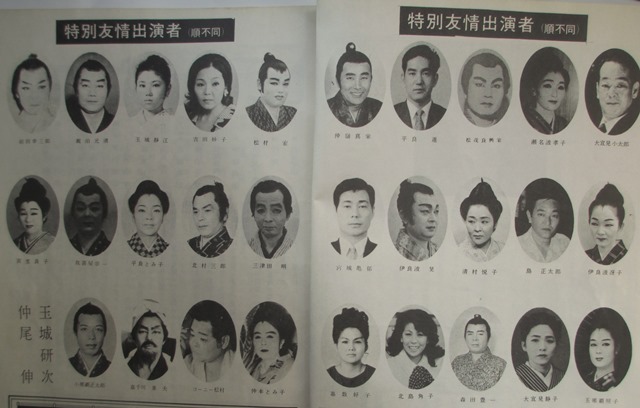
(翁長良明コレクション)


資料の大半を提供している翁長良明氏(携帯090-3793-8179)なるみ堂主人、左・新城栄徳


2013年7月29日 玉那覇展江さん(沖縄タイムス社ミニコミ紙担当記者)と翁長良明氏


2013年7月28日~8月31日 平和通り三越側入口「平和通りアーカイブス展」

山田實 写真コーナー
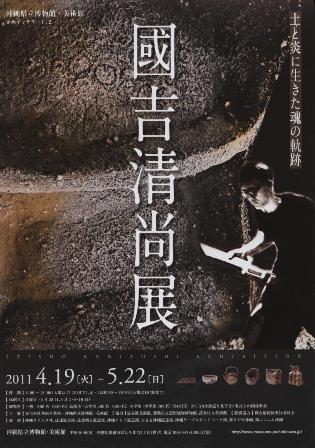
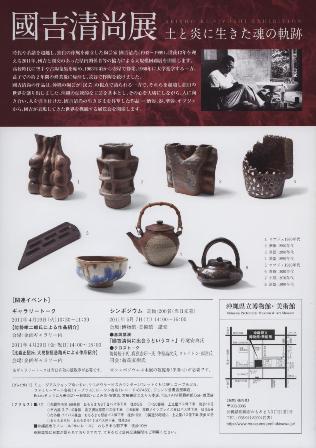
2011年4月19日-5月22日「國吉清尚展」沖縄県立博物館・美術館
3月23日ー放射能騒ぎの東京から奥間政作氏が大震災前からの予定していた帰省で帰沖。3時すぎ那覇市歴史博物館で志村学芸員と共に会った。そして写真家の山田實氏のところに寄った。平和通りの古美術なるみ堂に寄ると店主の翁長良明氏、画家の新城喜一氏が居られた。六時前に沖縄文化の杜で金城さん、謝花さん、仲里さん、國吉さんと会う。元琉大教授の西村貞雄氏も居られた。奥間氏は2006年7月に早稲田大学で開催された「沖縄の壺体 國吉清尚」展にも関わったこともある。後、私の家を案内した。
03/08: ウチナー美の森「描かれたジュリ」③
1966年12月ー神山邦彦『辻情史』神山青巧舎
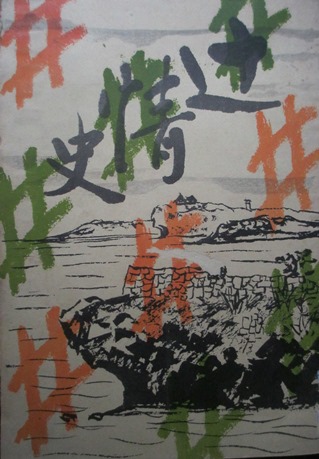

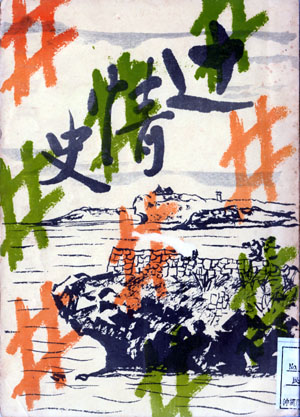
神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書
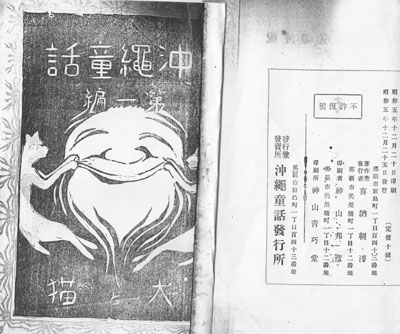
1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂
1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」
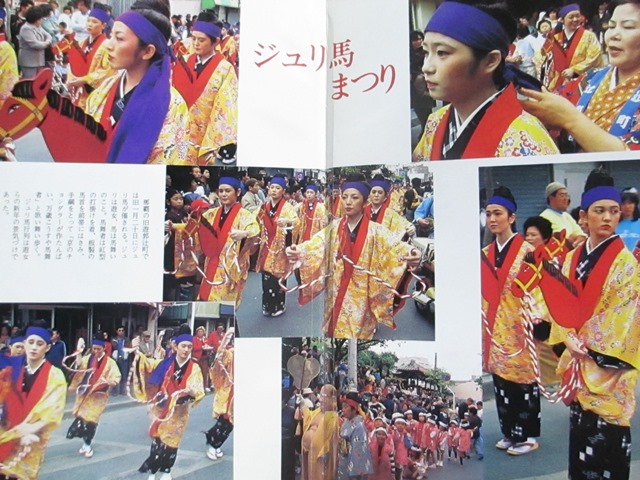
□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会
□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」


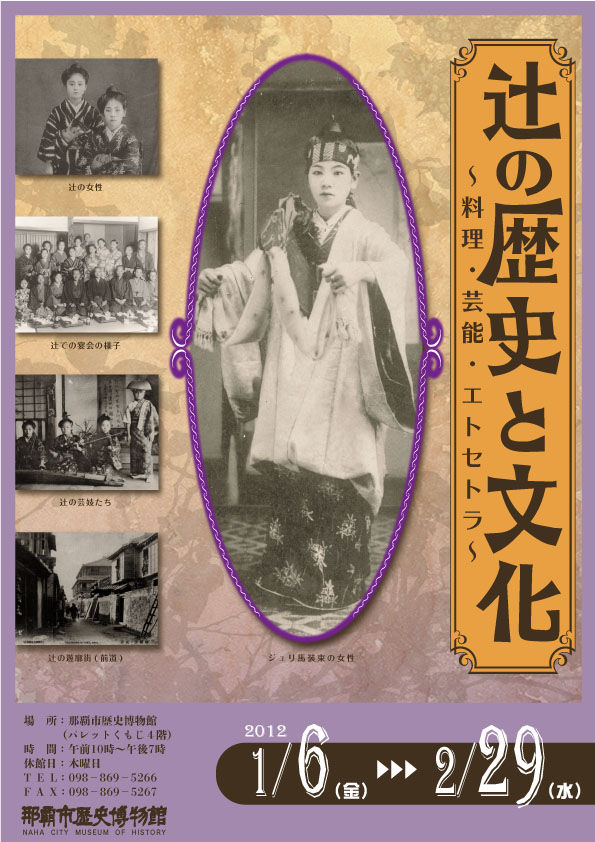
2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」
2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』
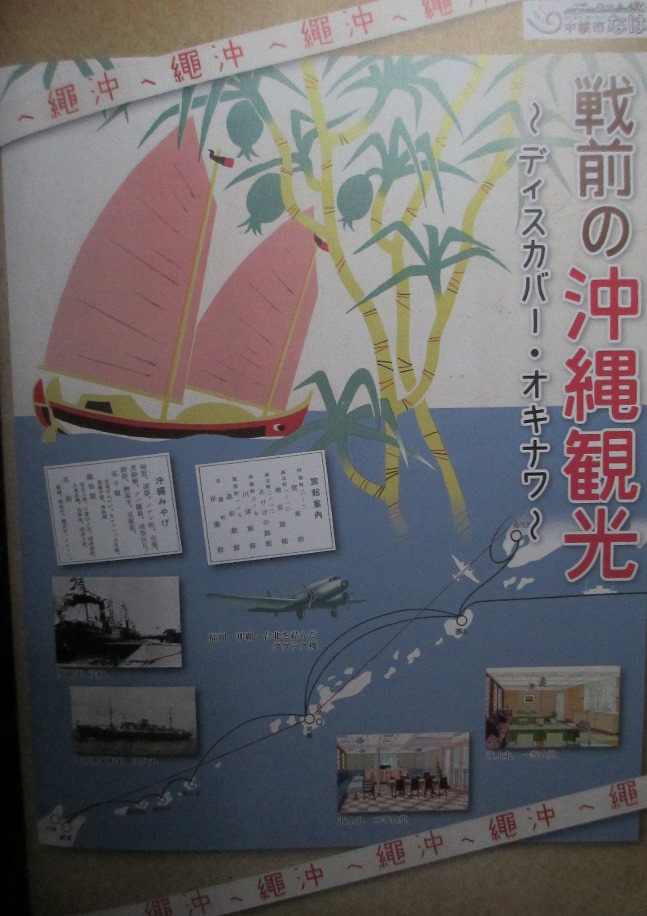
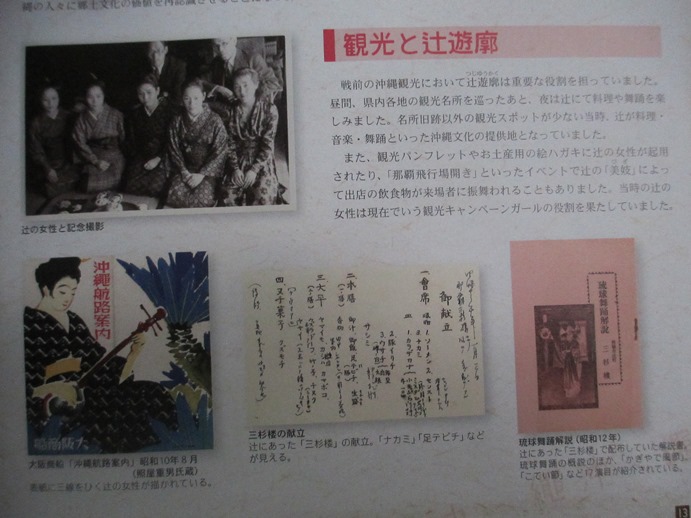
辻遊廓
戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。
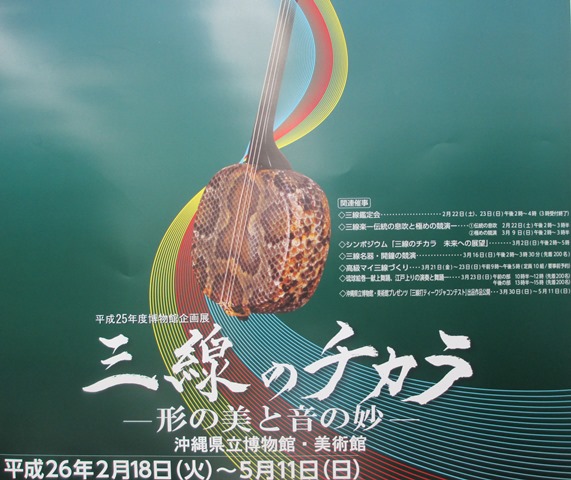
2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」
□三線をひくジュリの絵も展示されている。
沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相
場所:沖縄県立博物館・美術館
日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30




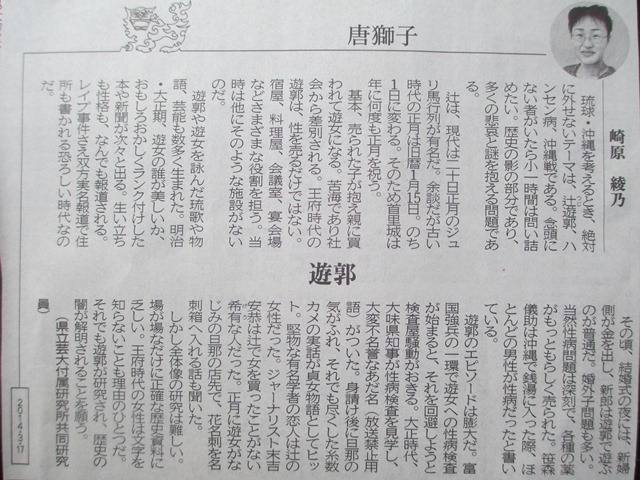
2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」
1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。
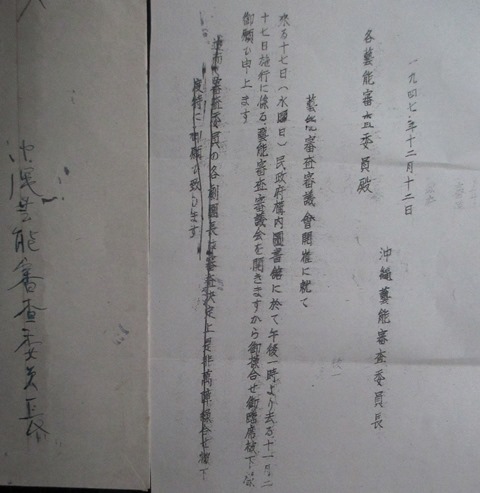
1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣
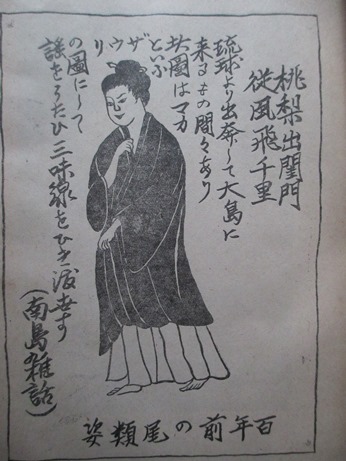
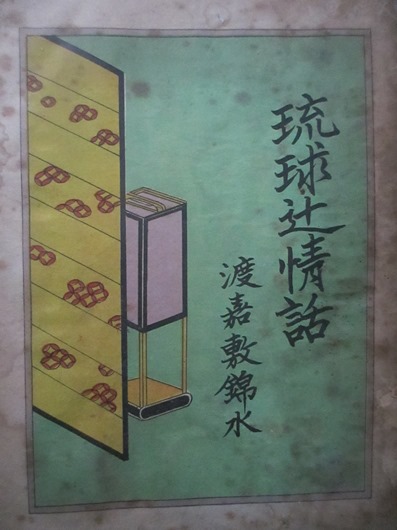
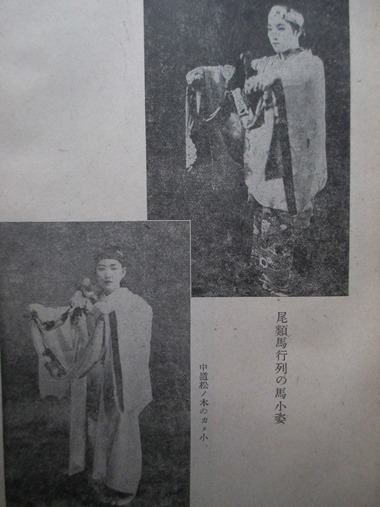
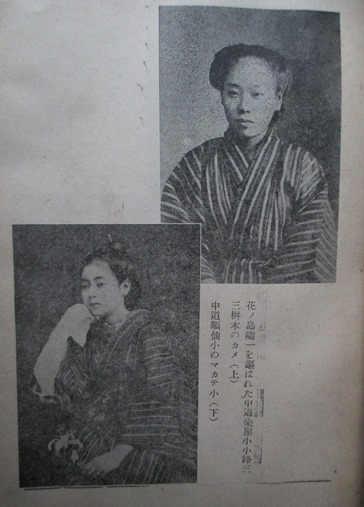
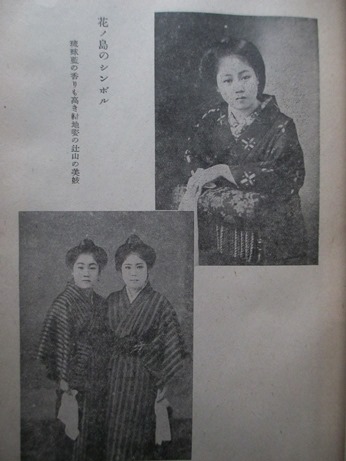
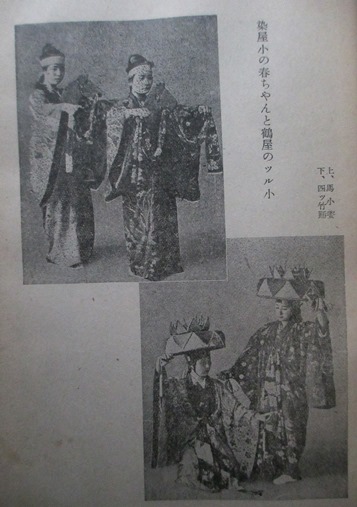




1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)
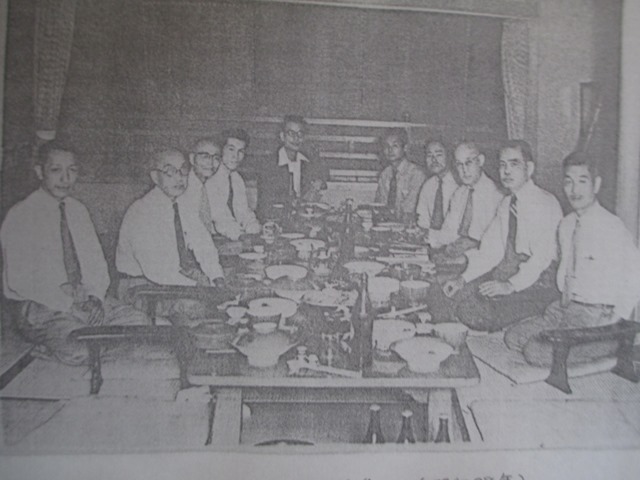
第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠
1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店
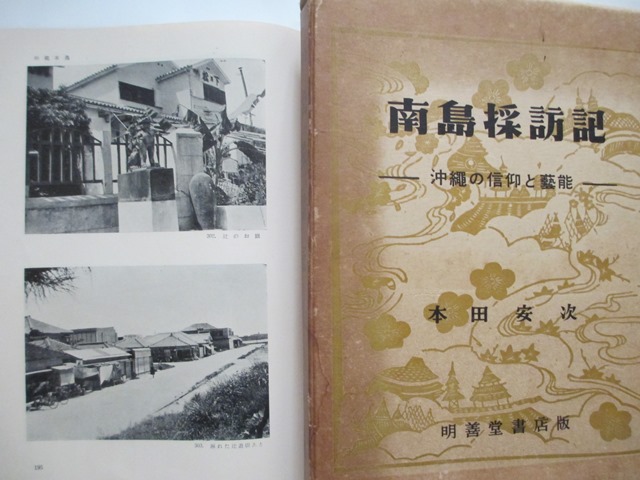
上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと
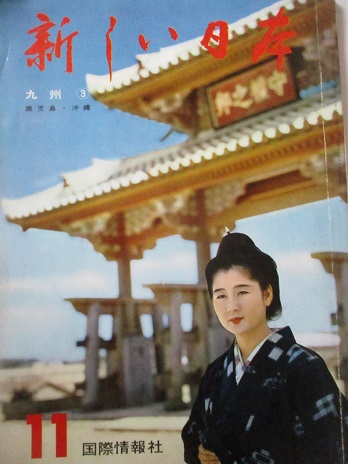
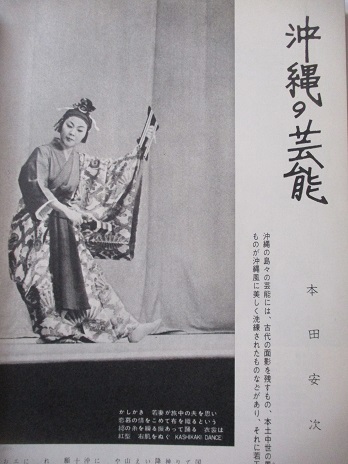
1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」
本田安次 ほんだ-やすじ
1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。
明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク
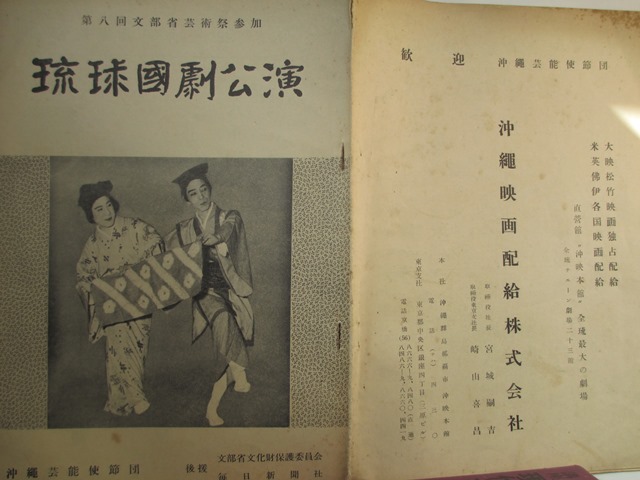
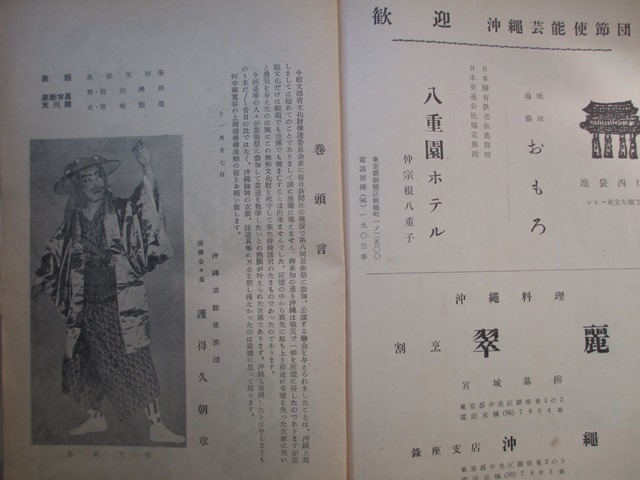
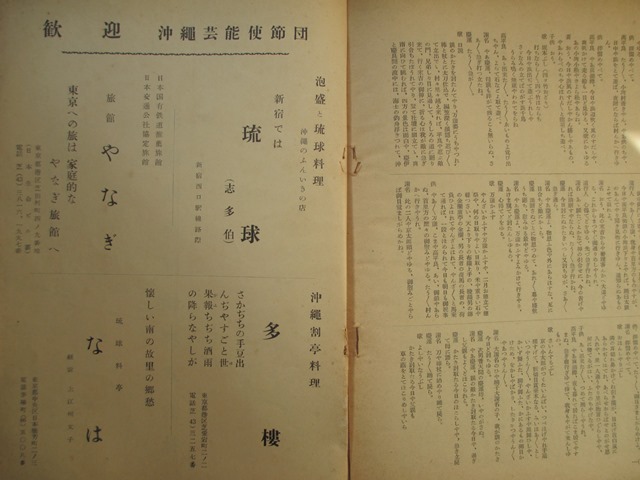
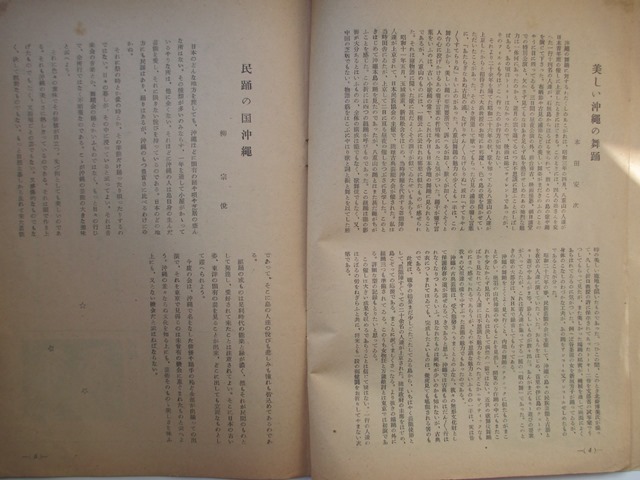
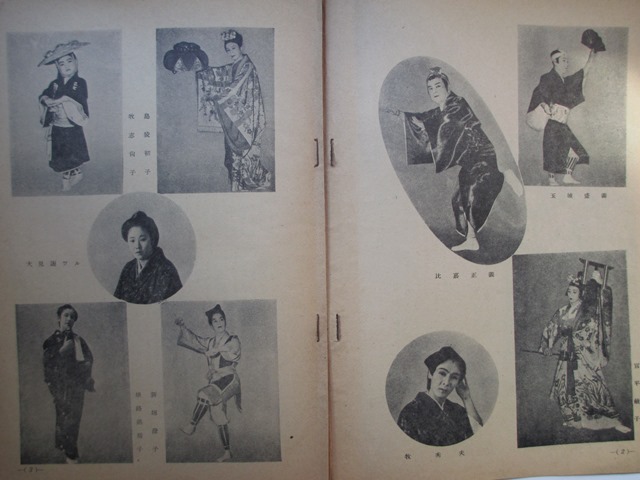
(翁長良明コレクション)
1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」
11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」
11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載
12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載
12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)
12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」
1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」
1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」
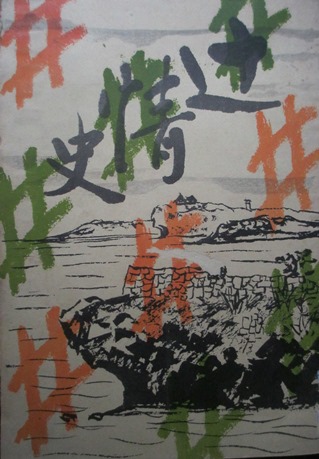

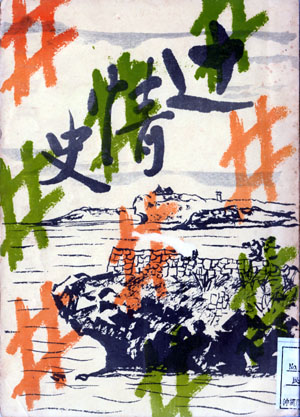
神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書
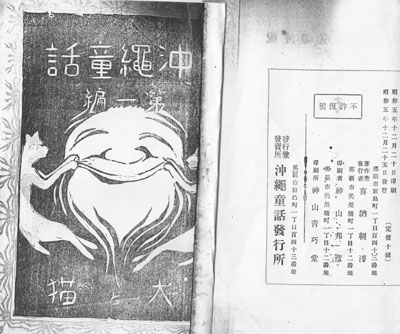
1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂
1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」
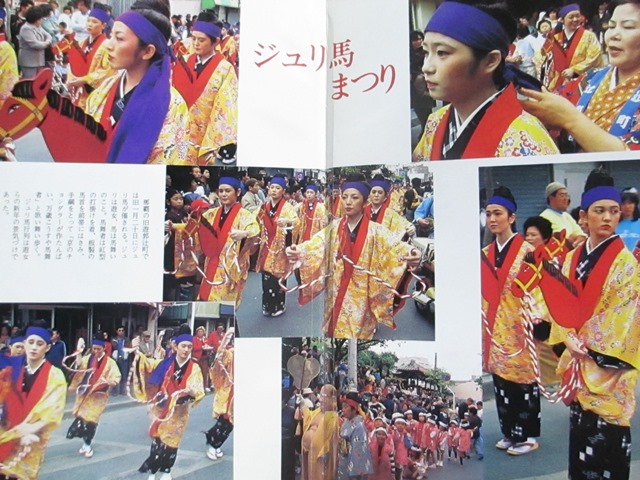
□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会
□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」


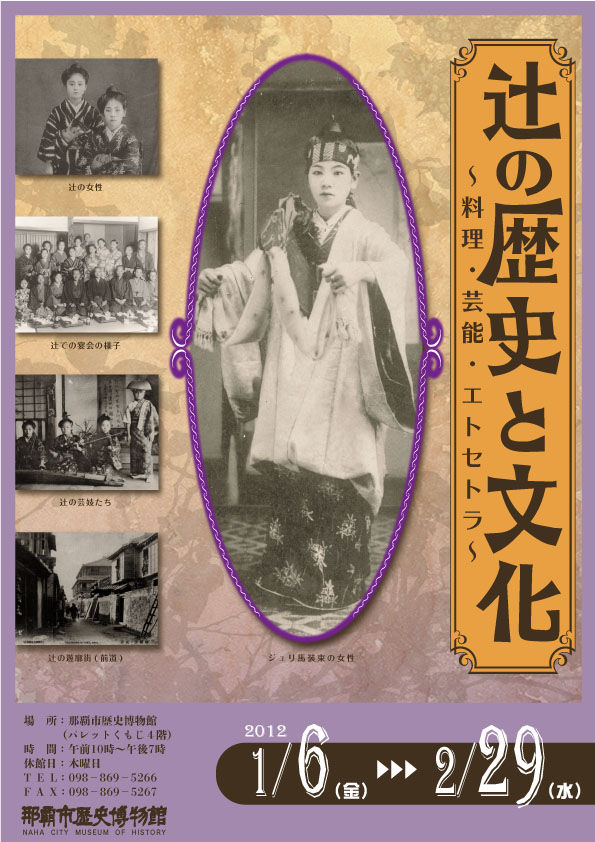
2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」
2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』
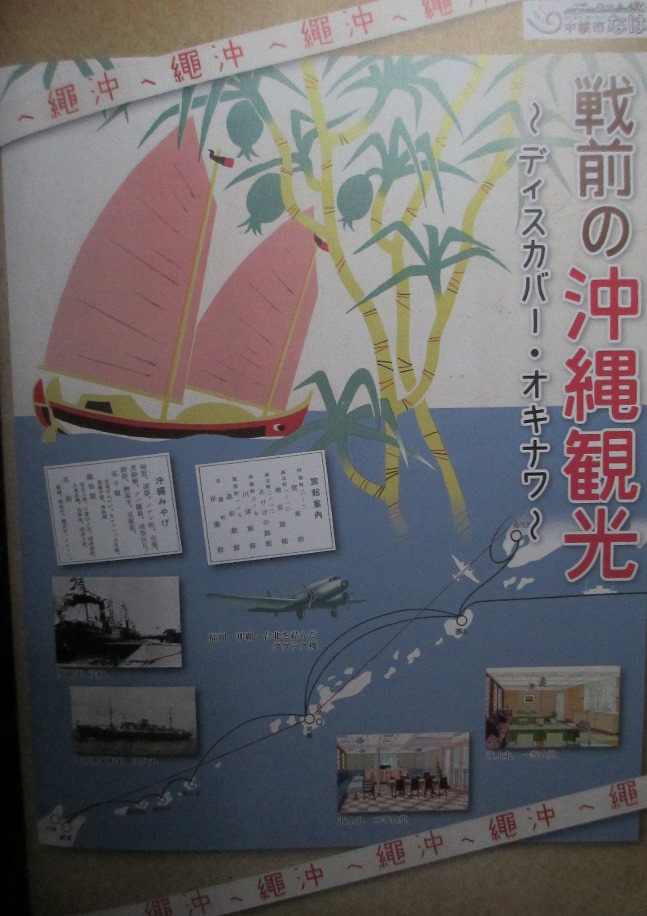
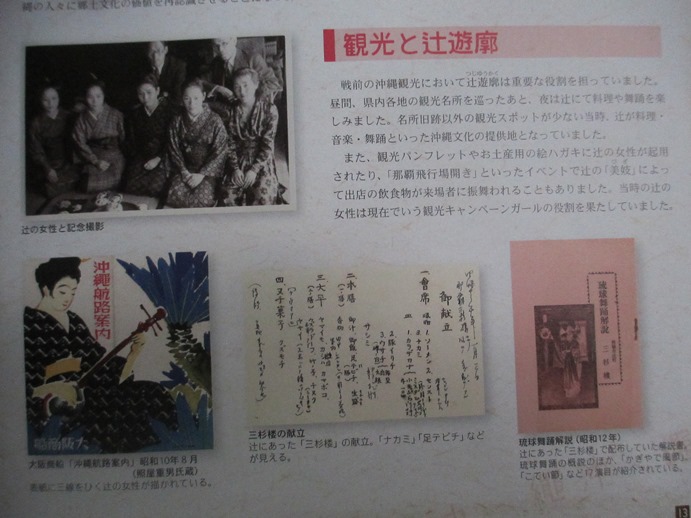
辻遊廓
戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。
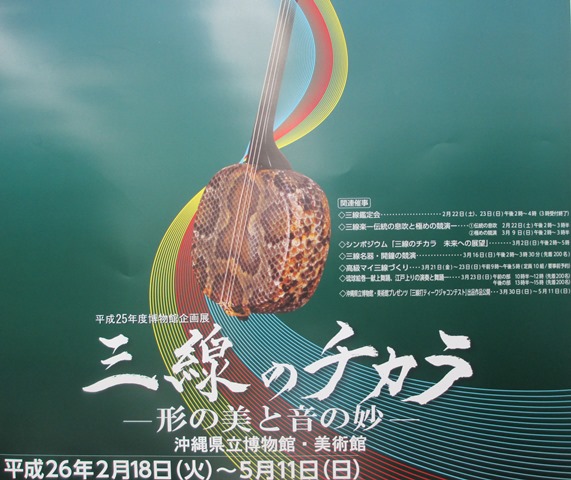
2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」
□三線をひくジュリの絵も展示されている。
沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相
場所:沖縄県立博物館・美術館
日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30




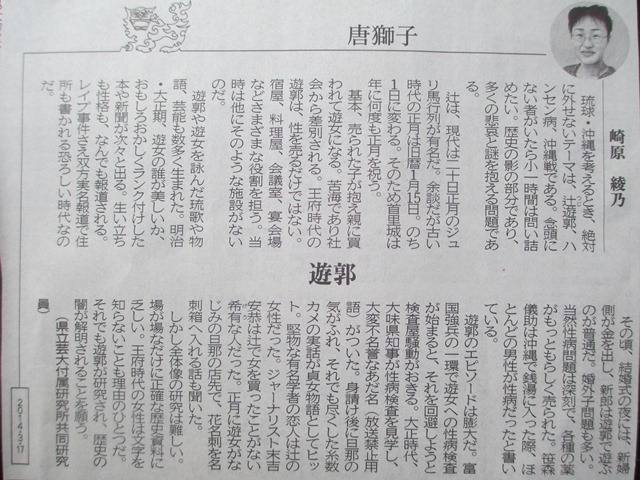
2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」
1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。
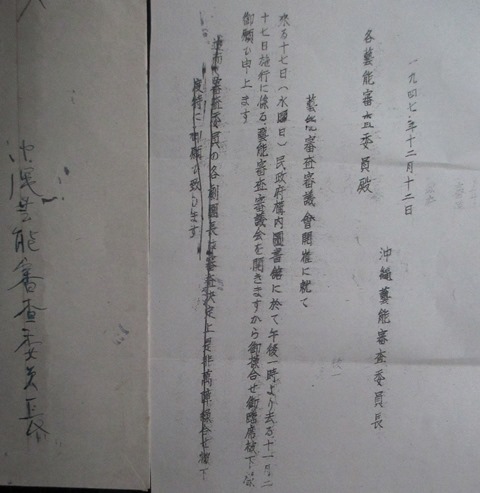
1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣
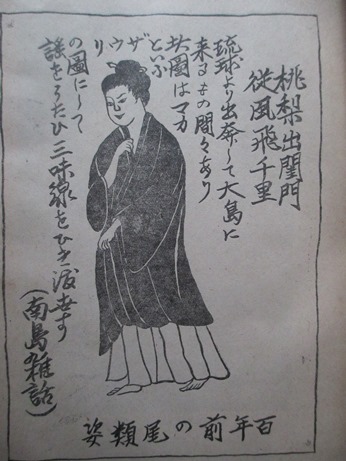
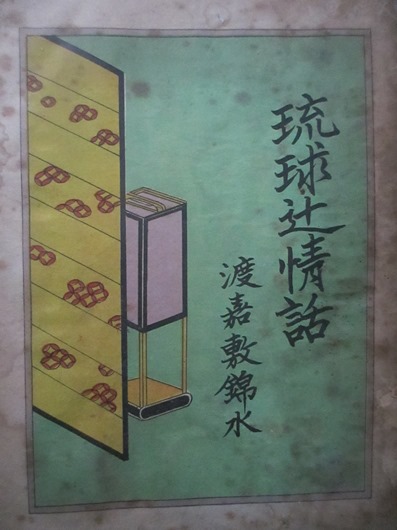
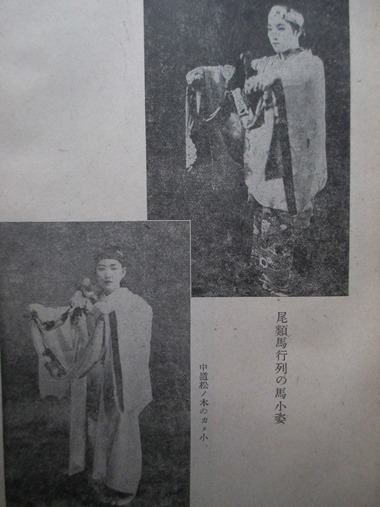
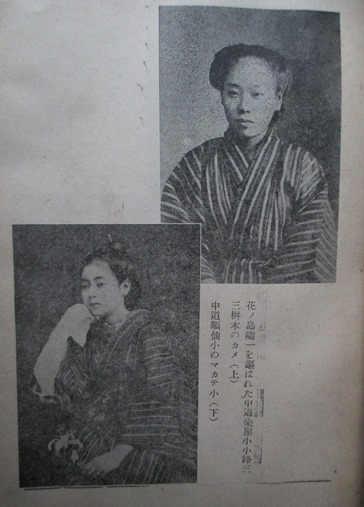
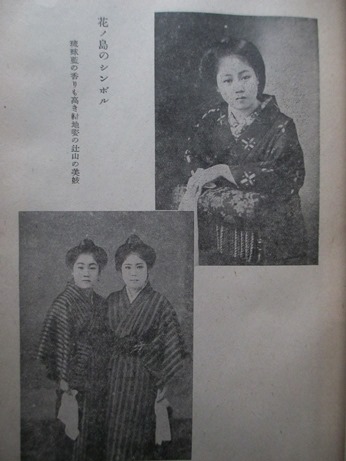
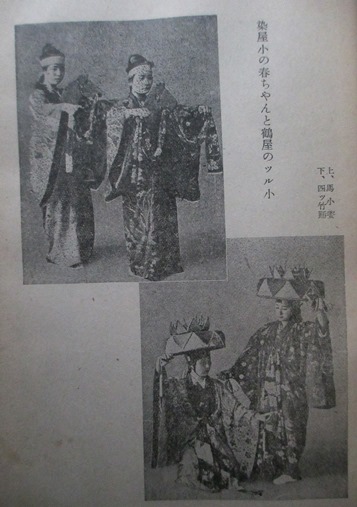




1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)
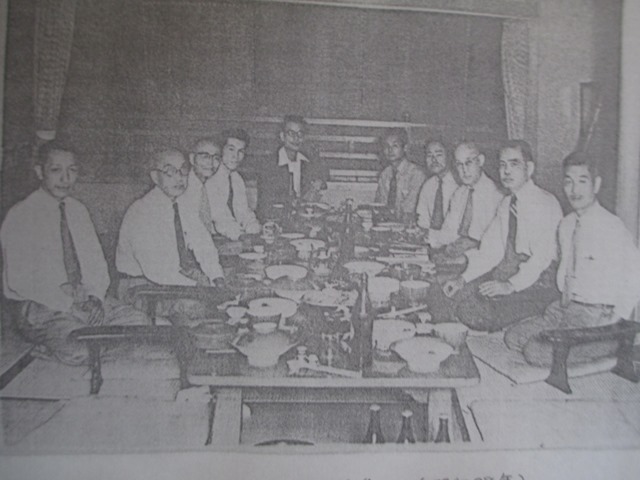
第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠
1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店
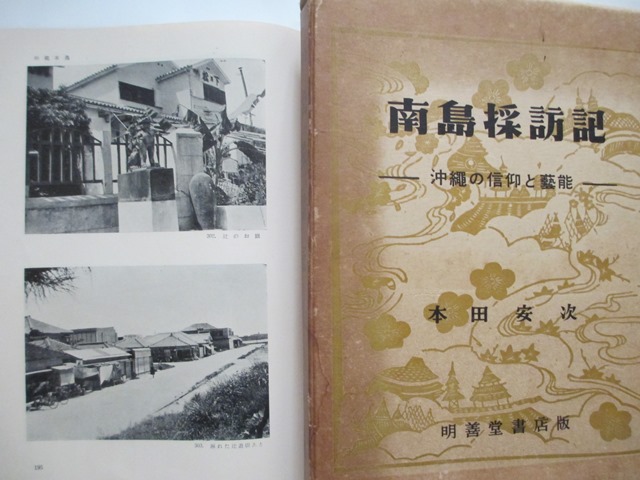
上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと
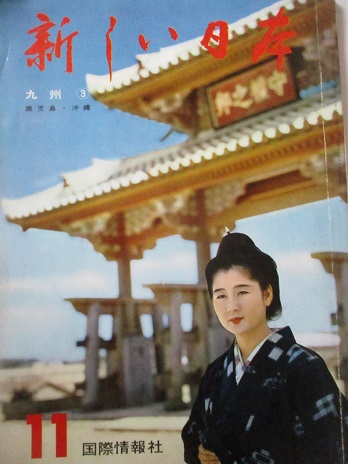
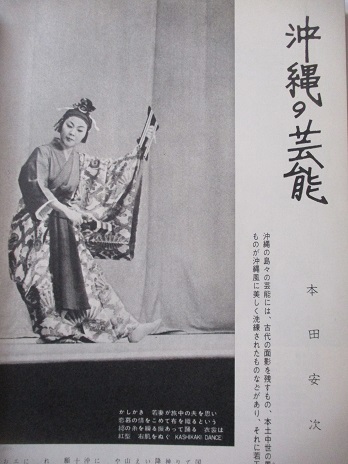
1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」
本田安次 ほんだ-やすじ
1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。
明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク
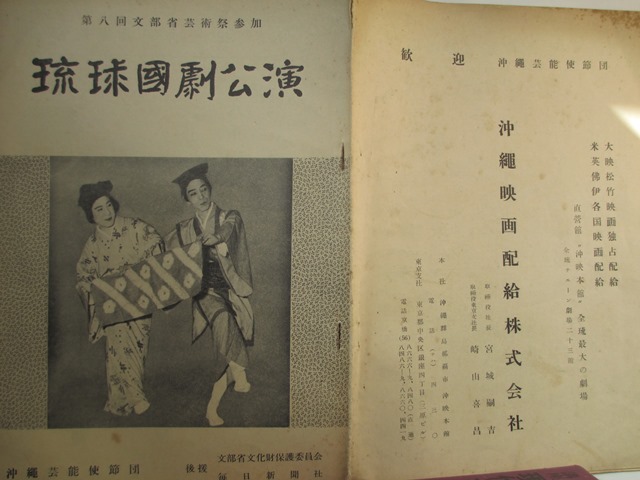
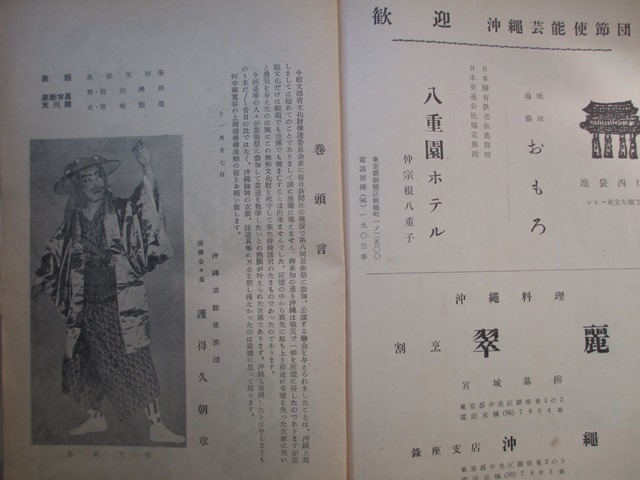
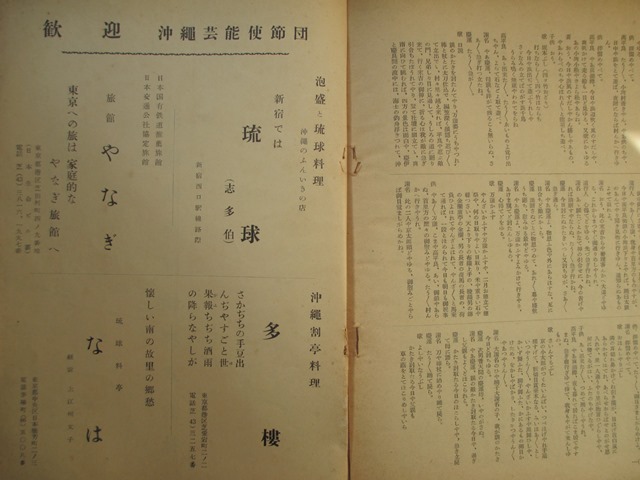
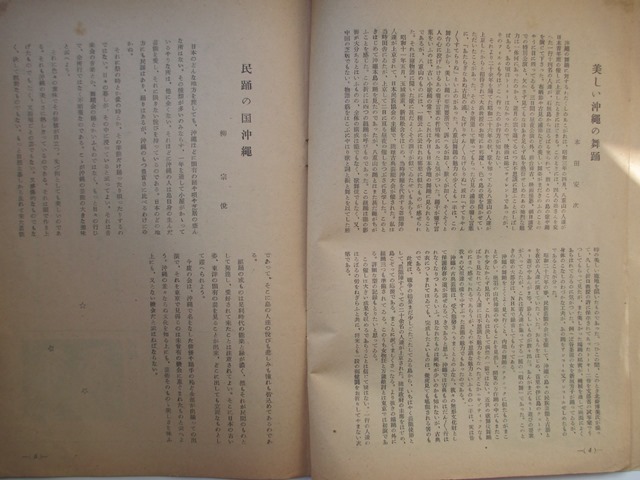
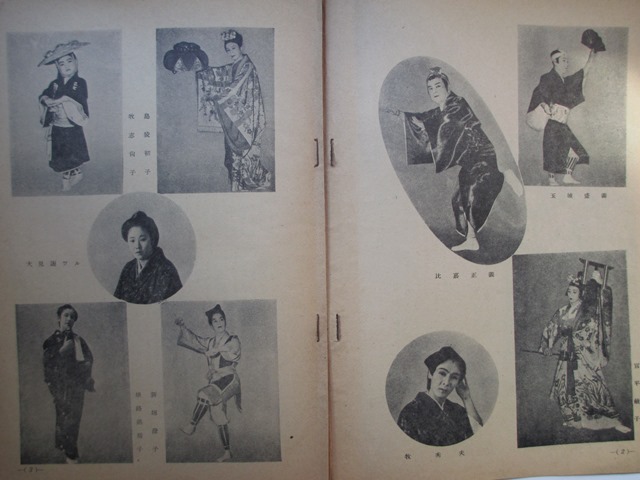
(翁長良明コレクション)
1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」
11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」
11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載
12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載
12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)
12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」
1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」
1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」
04/15: 沖縄コレクター友の会②
2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。
08/04: 芸能/与世山澄子

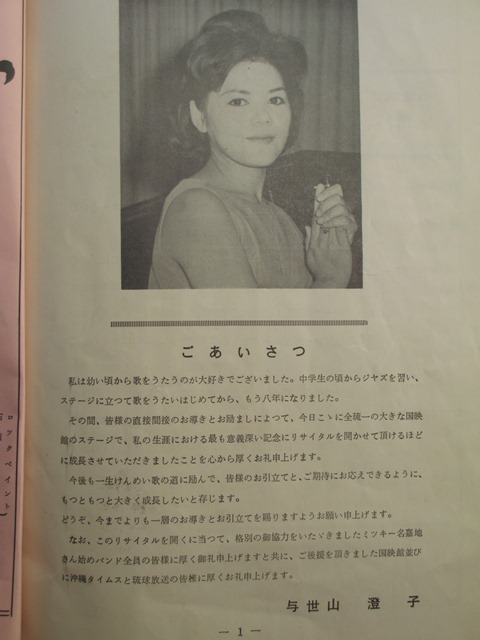
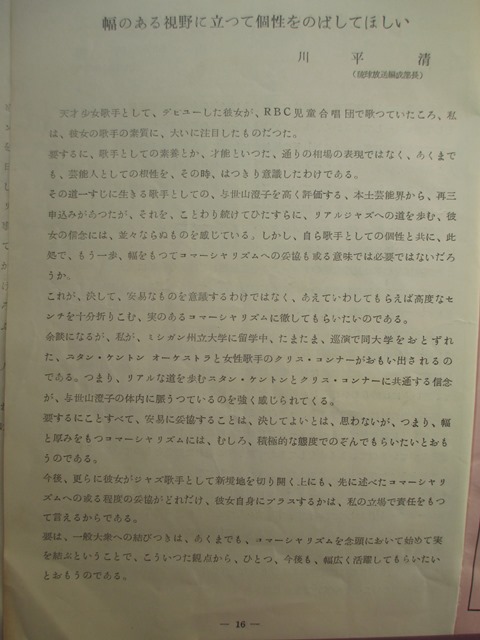
与世山澄子
ジャズシンガー、1940年生まれ、沖縄県八重山郡の小浜島出身
ビリー・ホリデイをほうふつとさせる歌声で知られるジャズ・シンガー、マル・ウォルドロンとの共演作もあり、20年ぶりの新作「インタリュード」では菊池成孔、南博、安カ川大樹がバックをつとめ、パードン木村がプロデューサーとしてZAKがエンジニアとして参加した。→はてなキーワード
(翁長良明コレクション)
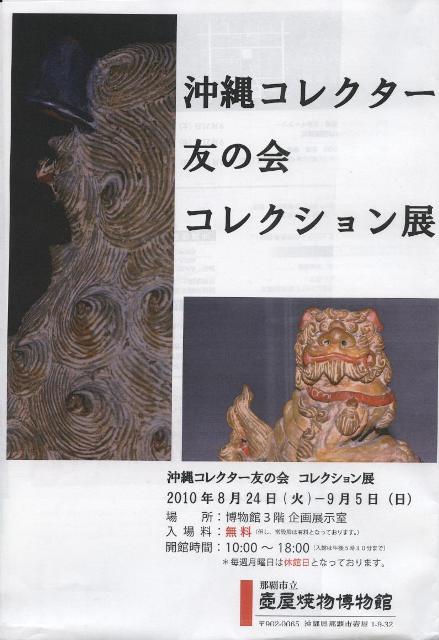
沖縄コレクター友の会

南風原レストラン「沖縄コレクター友の会例会」
眞喜志康徳(郷土歴史研究会眞玉会)ー南風原町字与那覇79 ℡889-4261

『オキナワグラフ』2009年8月号
会長兼事務局
上原実ー糸満市西崎1-33-6 ℡090-1941-5268

『オキナワグラフ』2008年9月号
会員
伊禮吉信(諸見民芸館館長)ー沖縄市諸見里3-11-10 ℡090-9789-9289
与儀達憲(壺屋焼物博物館友の会会長)ー那覇市古島1-5-6 ℡090-4470-3738
和田正義(古文書収集家)ー那覇市上間344-1-804 ℡831-6257
□2009年12月8日『琉球新報』高良由加利「松田道之の書簡発見/那覇市の和田正義さん、1872年『滋賀新聞』も」

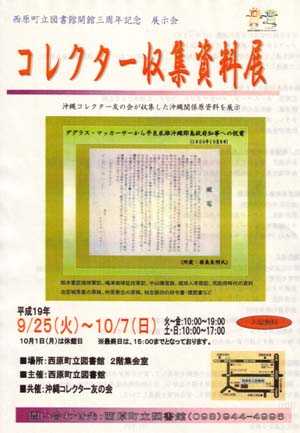
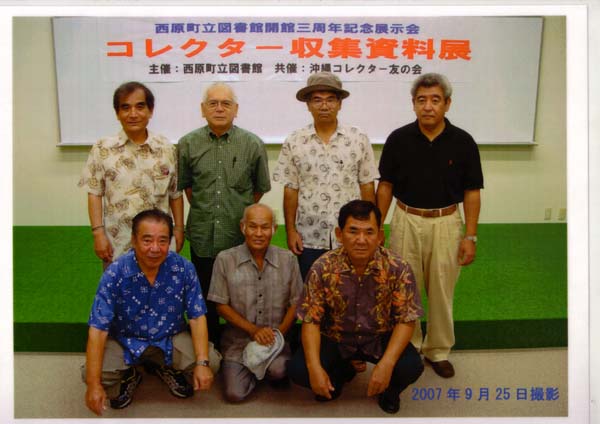
2010年8月25日『琉球新報』高良由加利「はと笛ー『人とモノの物語 沖縄コレクター友の会会員コレクション展』が24日、那覇市立壺屋焼物博物館で始まった。-」
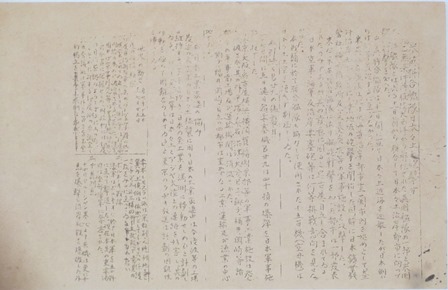
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
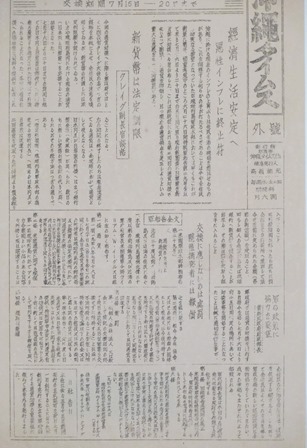
1948年6月29日『沖縄タイムス』創刊前に号外「通貨切り換え」
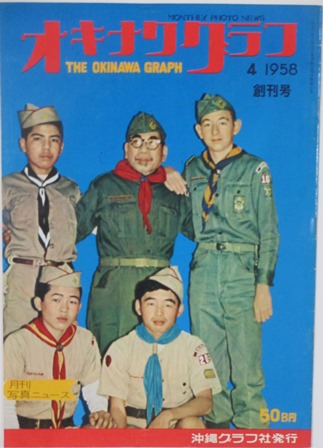
1958年4月『オキナワグラフ』創刊号
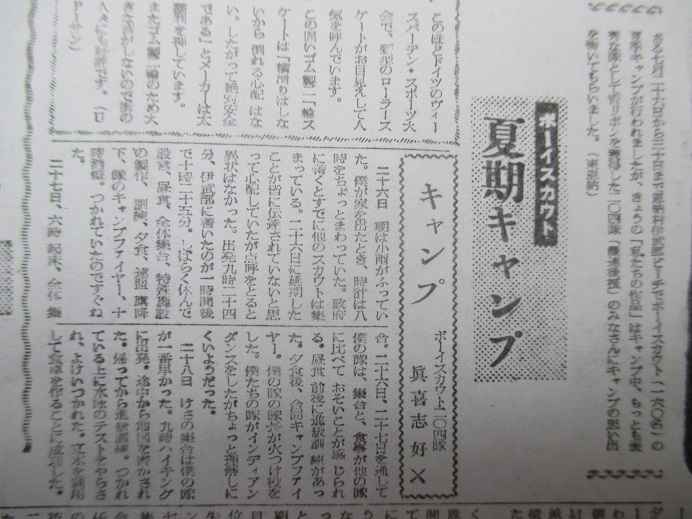
1958年8月21日『琉球新報』真喜志好一「キャンプ」
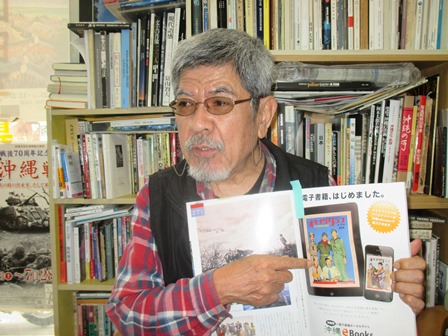

グラフ表紙左上が真喜志好一氏/2016年3月15日 山田写真機店で左から、新城栄徳、山田勉氏、真喜志好一氏

11/02: 『琉球新報』略史②
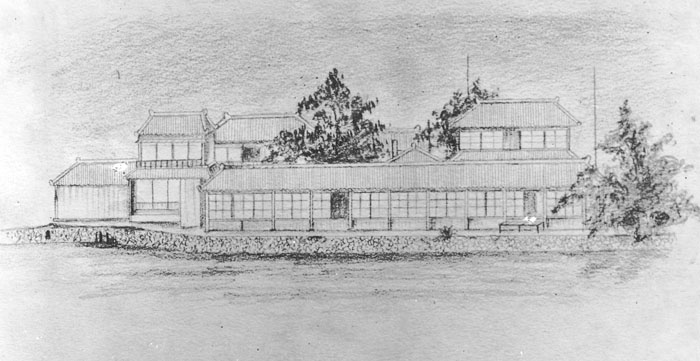

1940年12月6日『琉球新報』□共同声明ー光輝ある紀元二千六百年を迎へ大政翼賛運動の力強き発足に當り県下朝刊三新聞社は新体制に即応して来る12月15日より新たに沖縄新報を創刊し三新聞社は欣然その傘下に合同することになりました。新しい沖縄新報は組織ある統制と清新なる計画性を以って県民に対し豊富」なる報道と適切なる指導を以って、高度国防国家の建設へ微力を尽くし、併せて県勢の振興と文化の発展に貢献しやうとするものであります。県民各位もまた本県文化史上この画期的、新新聞の誕生を歓迎しこの快挙を絶対に支持して下さるものと信じて疑ひません 右声明致します 12月6日
琉球新報社 沖縄朝日新聞社 沖縄日報社
1940年12月14日『琉球新報』本山裕児「美しき争ひー映画の魅力 上」15日 下
1940年12月16日『琉球新報』「母カメ 83歳で昨日死去 男 金城松 金城山吉(在南米) 孫 金城安太郎」
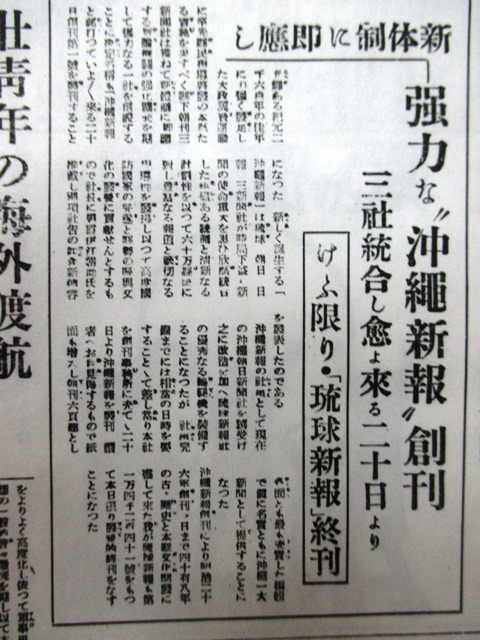
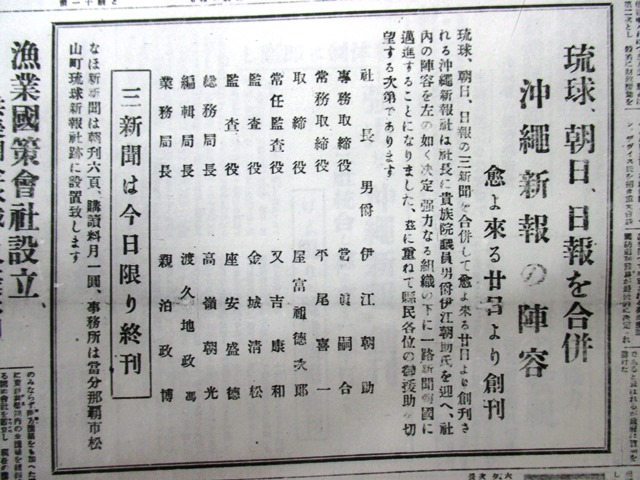
1945年4月
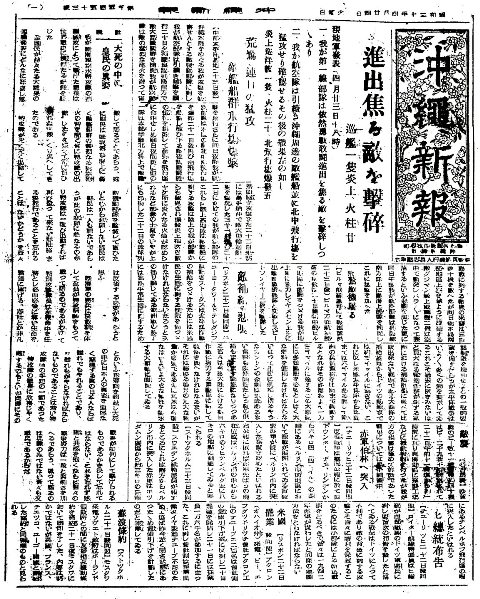
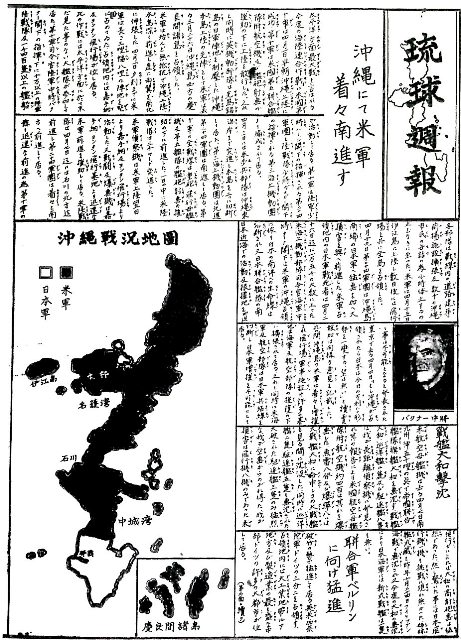
1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。 参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
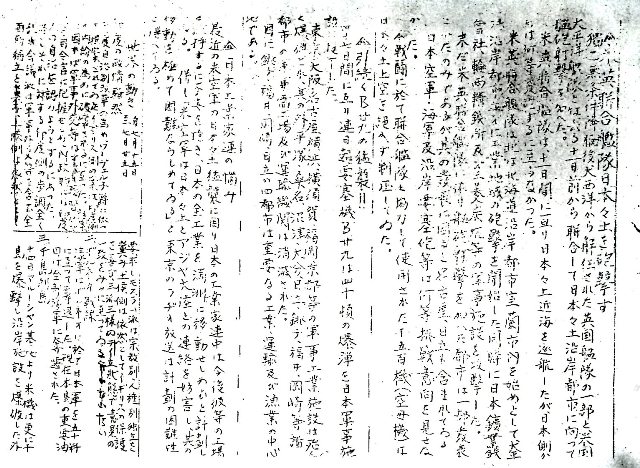
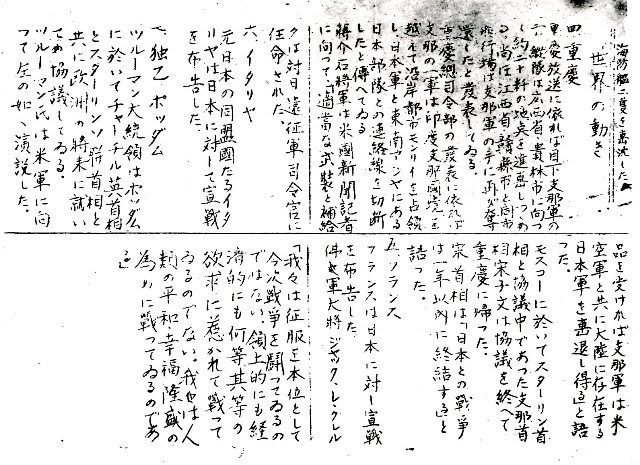
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
1945年9月ー外間政彰、ウルマ新報記者

石川時代の琉球新報本社社屋、2階が編集、階下が業務。右の平屋が工務。


1946年ー前列中央・瀬長亀次郎社長、右が池宮城秀意編集長、2列中央・外間政彰
1948年7月ーうるま新報社、那覇市三区に新築移転
1950年 仲地米子、うるま新報記者
1951年3月 外間政彰、琉球契約学生として上智大学入学→4月 外間政彰、早稲田大学新聞学科転入
この年、『琉球学生新聞』、日月社『祖国なき沖縄』に関わる
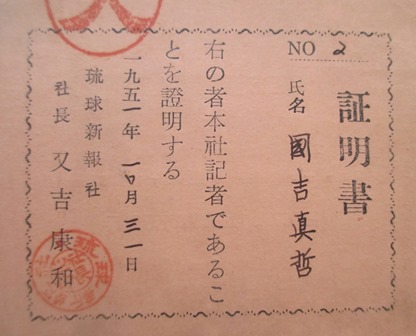
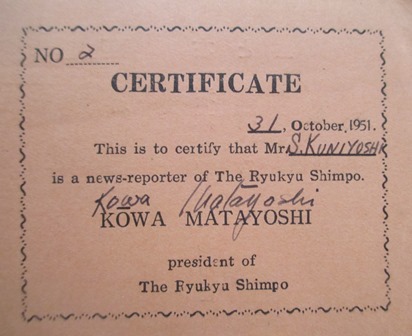

中央ー又吉康和
1951年9月8日 対日平和条約・日米安全保障条約調印→1952.4.28発効
『うるま新報』は講和会議の締結を機に9月10日『琉球新報』と改題した。
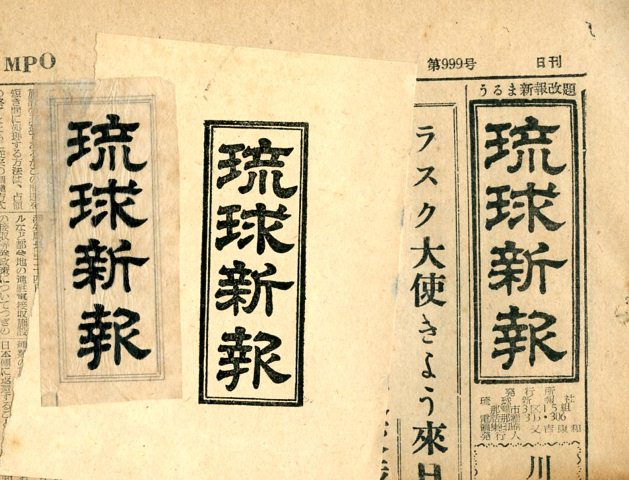
□1951年6月26日『うるま新報』國吉眞哲「声・新聞名改題について」□琉球日報社は6月23日付の同紙紙上に社移転の社告を掲載しその中に「琉球日報」を「琉球新報」に改めて新発足すると述べ6月25日付のうるま新報、沖縄タイムス、沖縄新聞に掲載し同様「琉球新報」として新しく発足する旨述べている。琉球日報が何故「琉球新報」に改題するかの理由については何も述べていないのでその企図は不明である。
(略)
又吉康和、平尾喜一の両氏を始め当時の社員が20数名健在で新聞または他の職場に活動しているが何れも元「琉球新報社員」ということが経歴の重要部をなしまた社会信用の中心にもなっている。又吉康和先生その他旧社員に関係のない琉球日報が「琉球新報」を称することは快いものではない。新聞人の信頼に訴えて琉球日報社長及び同人に再考をお願いしたいと思う。(那覇市三原三区)
来る5月15日は「密約復帰の日」である。那覇市歴史博物館は4月21日から「あれから40年~Okinawaから沖縄へ~」、沖縄県立博物館は9月28日から「本土復帰40周年記念『Okinawaから沖縄へ(仮称)』」が開催される。何れも沖縄の現実を見れば祝賀とは縁遠い。それで、「あれから40年」とか、「Okinawaから沖縄へ」という表記になるのだろう。5月15日には野田首相も来沖するというが冗談としか思えない。
1951年6月28日 元琉球新報社員の沖縄群島知事平良辰雄への陳情書(解決したので使われなかった)
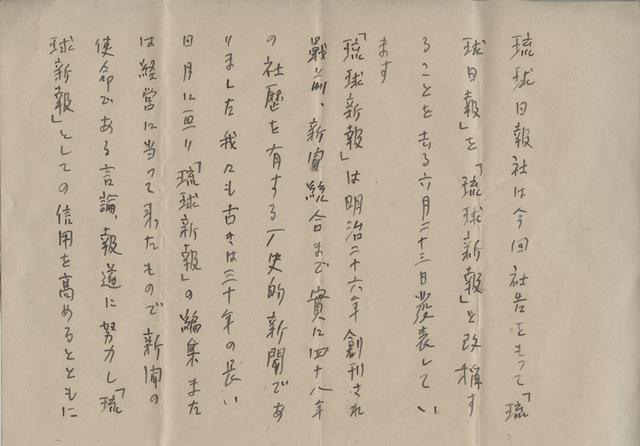
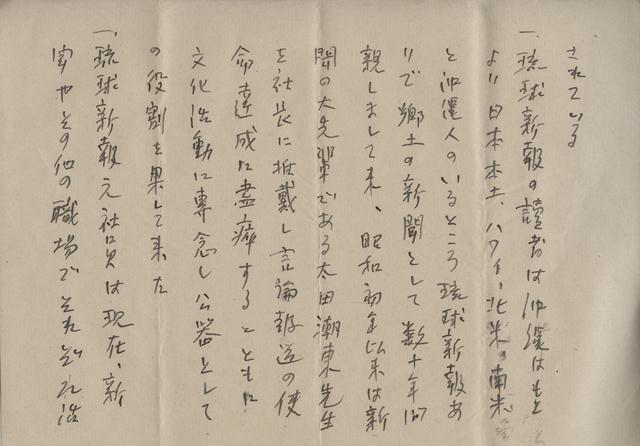
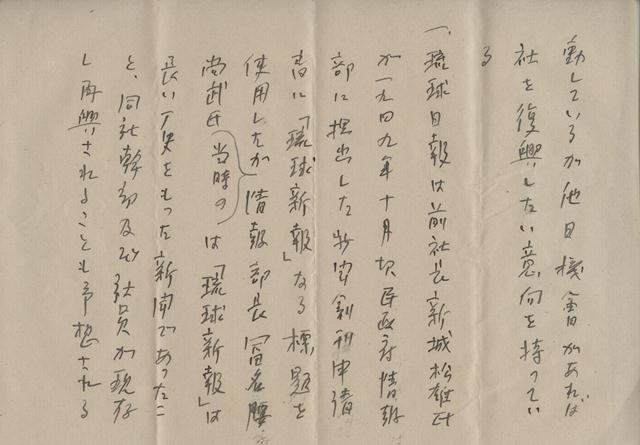
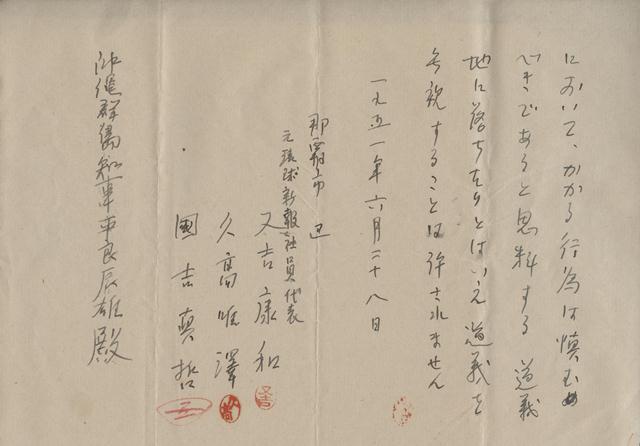

『琉球新報』1953年1月ー中央・又吉康和社長、左・島袋全発主筆、又吉社長から右一人おいて國吉眞哲。
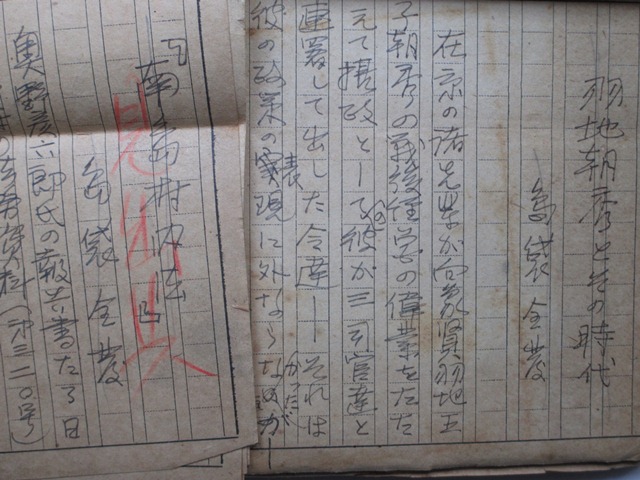
島袋全発筆跡
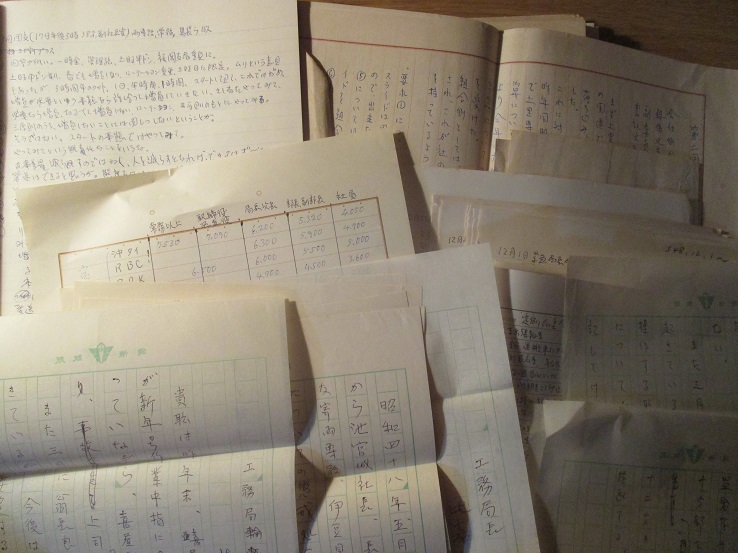
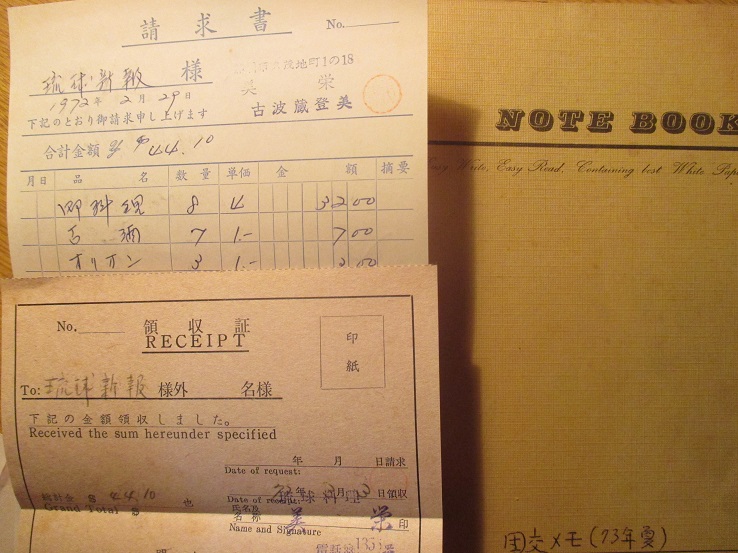
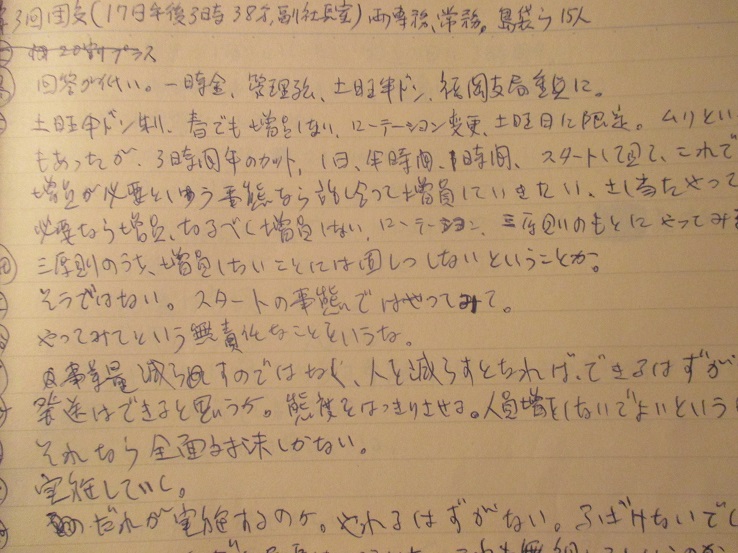
1972、73年局長団交メモ
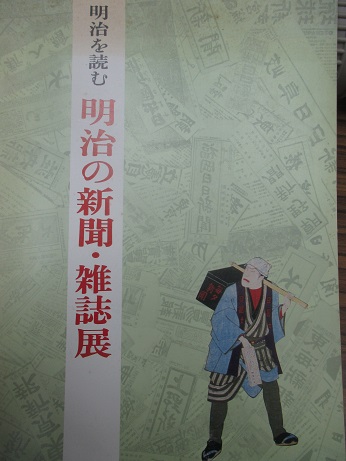
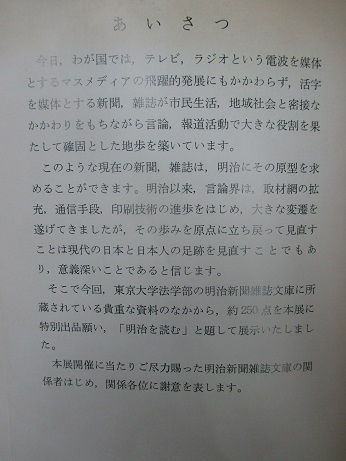
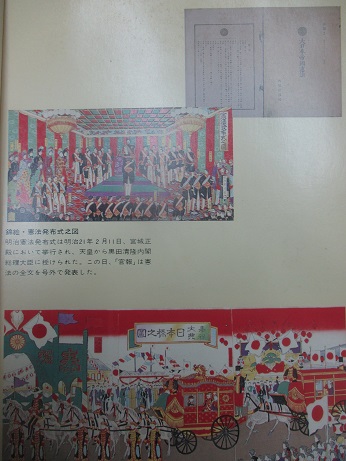
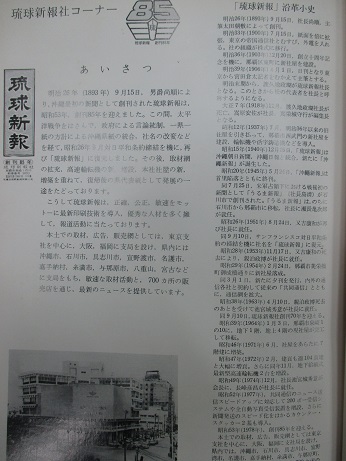
1978年9月13日~18日 琉球新報社 東京大学・明治新聞雑誌文庫 主催「明治の新聞・雑誌展ー近代日本ジャーナリズムの源流ー」デバート・リウボウ
1986年8月13日ー『琉球新報』「『ウルマ新報』創刊号見つかるー故大嶺薫さんが保存。大嶺コレクションを整理していた富島壮英資料課長が発見」
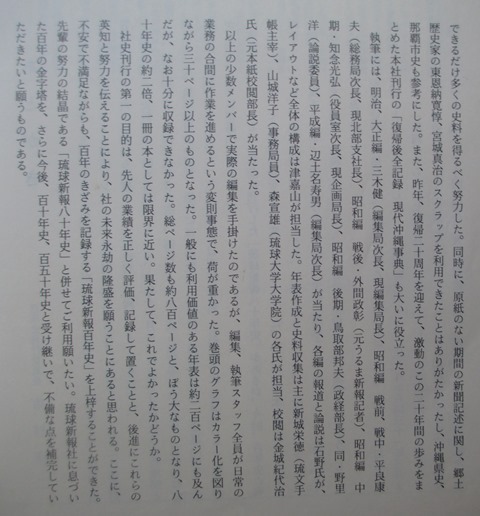
1993年9月『琉球新報百年史』
新城栄徳作成「1893年9月『琉球新報』創刊から現在までの新聞・機関紙相関図」
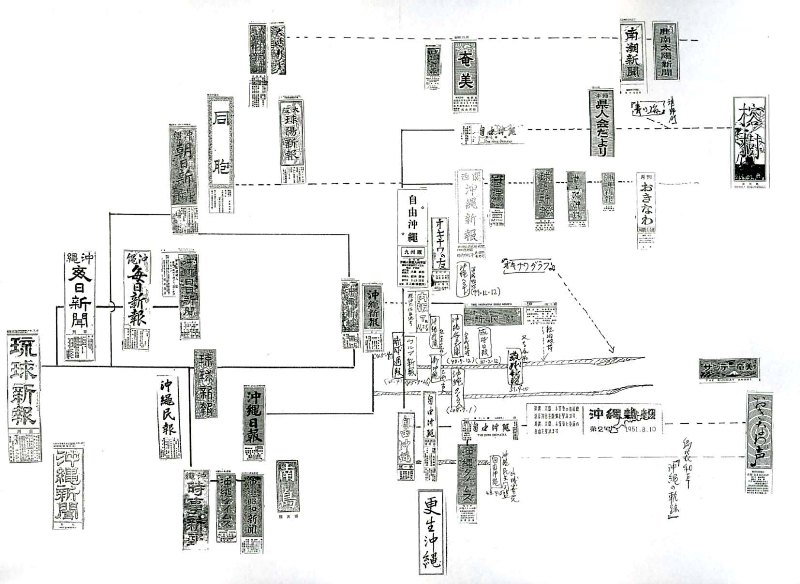
2012年1月3日ー『琉球新報』友寄貞丸「辰年に寄せてー『竜頭蛇尾』の民主党」
2012年1月4日ー『琉球新報』「対談 大城立裕さん×知念ウシさん」
2012年1月12日ー『琉球新報』矢部宏治「落ち穂ー米軍基地観光ガイド」
2012年3月4日ー『琉球新報』「新琉球考今沖縄を語るー古謝美佐子(民謡歌手)『母から沖縄戦のことをしょっちゅう聞かされていた。日本軍に対して、いいことは言ってなかった。目の前で見たみたいですよ、沖縄の人を銃剣で殺しているのを。・・・』(共同通信那覇支局)」
2012年3月6日ー『琉球新報』矢部宏治「落ち穂ー基地と原発④前回、米軍機は日本の航空法の適用除外になっているので、どんな『無法な』飛行もできる。(略)それと全く同じ。日本には汚染を阻止するための立派な法律があるのに、放射性物質はその適用除外となっているのだ!」
2012年3月13日『琉球新報』「社説ー公金返還知事謝罪ー不正の付け県民が払うのか」
2012年3月14日『琉球新報』「社説ー思いやり予算ー被災地の復興に充てよ」
2012年3月14日『琉球新報』「社説ー高江着陸帯訴訟ー沖縄に基地を押し付け続ける国の不正義と住民負担の深層に背を向けた、木を見て森を見ない判断と言えよう。(略)これ以上住民の声を封じる愚を重ねてはならない。」
2012年3月17日『琉球新報』「社説ー『捨て石』削除ー沖縄戦の本質から目を覆う暴挙だ」
2012年3月18日『琉球新報』「社説ー改正沖振法ー(略)1972年の日本復帰後、10兆1千億円を超える沖縄関係予算が投入され、道路や公共施設などの社会基盤が整備された。半面、投下された資金の多くは本土に還流した。沖縄関係予算が県内にとどまり地域の発展に直接結び付く仕組みをつくらねばならない。」/27面ー32軍壕・緊急学習会ー消される沖縄戦(上)山内栄さん「軍隊の本質考える場、捨て石は沖縄戦の肝」
2012年3月25日『琉球新報』1面「32軍司令部 説明板、沖縄県が設置」
所感→□誰に対してお調子者のカジノチジは受けを狙っているのだろうか知らないがこれでチジと「沖縄のこころ」は相いれないことが証明された。とにかくも沖縄電力時代の弱みを国に握られているのは間違いない。
1928年7月 『南島研究』第三輯
口絵「琉球の結婚風俗」
編輯者より・・・西平賀譲
▽研究・雑録△
禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)
▽資料△
1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿
①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没
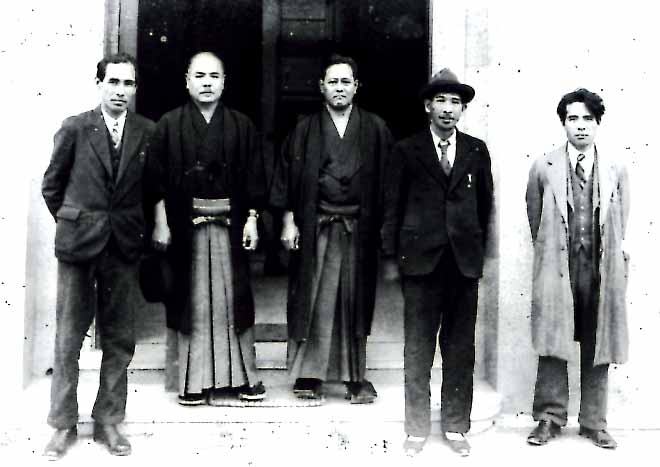
写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)
1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」
1928年11月 『南島研究』第四輯
口絵「進貢船の那覇港解纜」
▽史論・雑録△
北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ
○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。
1929年3月 『南島研究』第5輯
口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」
▽史論・研究△
名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信と寄贈雑誌
○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)
1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社
1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」
1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告
1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」
1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東
口絵「琉球の結婚風俗」
編輯者より・・・西平賀譲
▽研究・雑録△
禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)
▽資料△
1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿
①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没
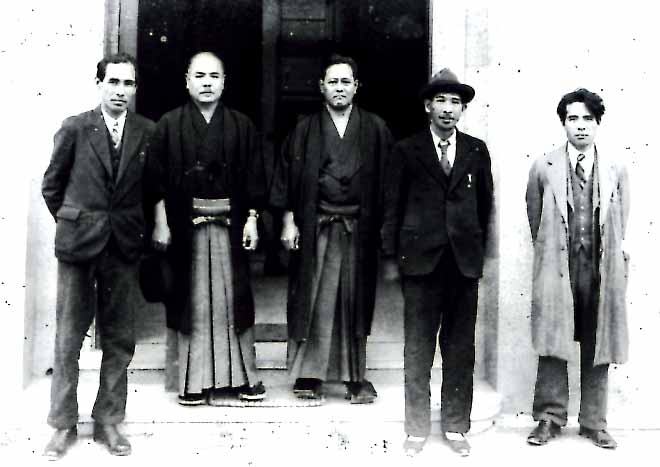
写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)
1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」
1928年11月 『南島研究』第四輯
口絵「進貢船の那覇港解纜」
▽史論・雑録△
北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ
○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。
1929年3月 『南島研究』第5輯
口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」
▽史論・研究△
名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信と寄贈雑誌
○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)
1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社
1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」
1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告
1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」
1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東
07/04: 麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安持(1887年~1907年)
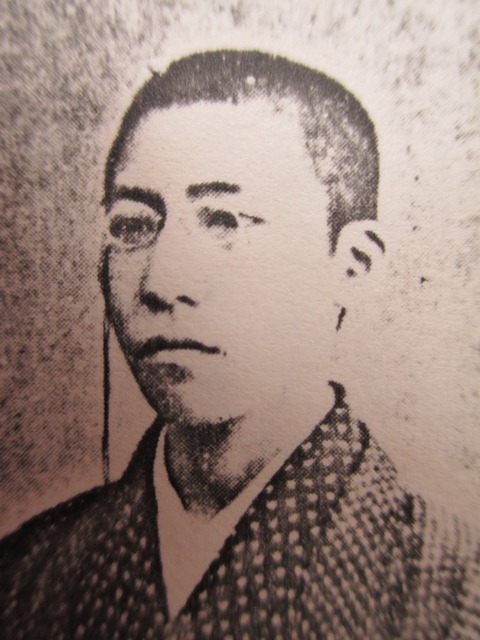
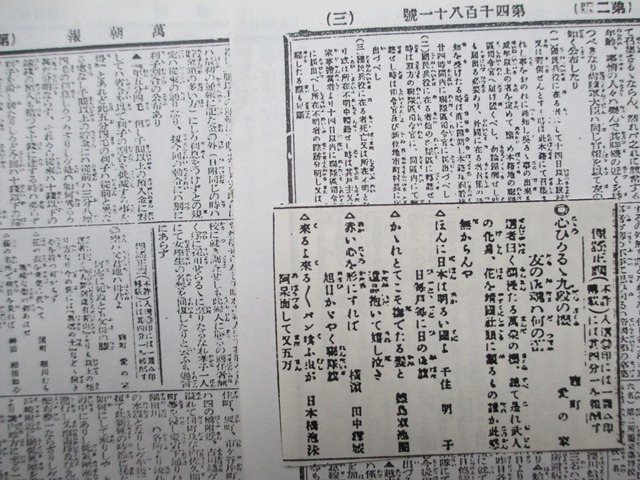
1905年3月25日『萬朝報』愛の家・末吉安持「心ひかるる九段の櫻 友の御魂は何の蕾」
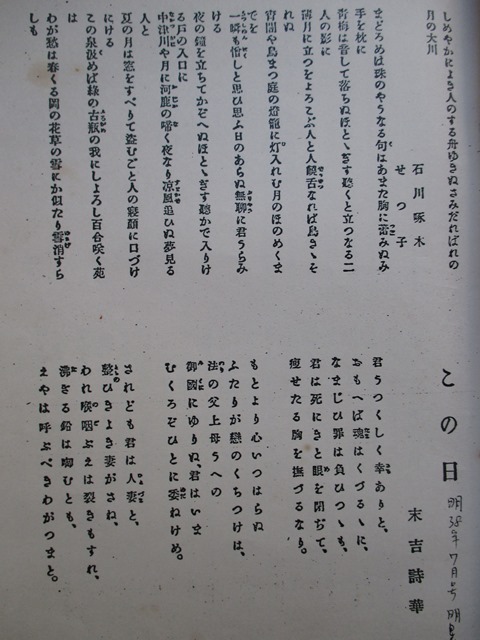
1905年『明星』7月号○下ー末吉詩華「この日」/上に石川啄木せつ子夫妻の歌
1907年『明星』3月号「故末吉安持」
与謝野寛○余は佐々木秀道を亡くして一箇月の後に、また新詩社同人末吉安持をうしなった。秀道の死も意外であったが、安持の死は突然であると共に、まことに語るに忍びざる程悲惨であった。氏は二月の九日に藝苑社の講演を聴いて飯田町の下宿に帰ったが、翌十日の午前三時頃、どうしたはづみか、机上の洋燈が落ち掛かり、全身三分の二を火傷して人事不省となり、同家の友人に送られて神保院と云ふ病院に入院した。医師は種々の治術を施したが、立会った友人等は皆な目を掩うて之を見るに忍びなかった。三日の後、氏は仰臥の儘身じろぎの成らぬに拘わらず非常に元気を回復したが、併し医師は其れを却て危険なる兆候だと云った。果たして十六日の夜から昏睡にに陥り、十七日の午前五時終に不帰の人と成った。享年二十一.このうら若い、将来のある詩人を、突然と過失のために、斯かる悲惨な最期に終わらしめたのは、痛嘆至極、何と慰むる言葉も無い。
氏は沖縄県首里区字儀保の素封家末吉安由氏の二男であった。中学にあった頃は常に優等の成績を示したと云ふ。父兄が文学の嗜好を以って居る所から、その感化を受けて文学を好むだが、父兄も氏が文学者となることを望み、氏も其積もりで三十七年の二月に出京し、爾来英語を国民英学会に学んで居た。初め長詩を前田林外氏等の雑誌『白百合』や『天鼓』に投じて居たが、三十八年の三月に新詩社に加わり、其後は専ら『明星』にのみ作物を載せた。氏は短歌を作らず、長詩のみの作者で、毎月必ず二三篇を余の手許に送った。十六歳から詩を作り始めたといふが、確かに詩人たる情熱と、独創の力と、物事に対して一種他人と異なった睨みかたとが有って、漫に先人の模倣を事とする無定見者流とは選を異にして居った。三十七年頃は児玉、平木二氏の詩風を慕ひ、三十八以後は薄田、蒲原二家の詩集を愛読し、殊に上田氏の『海潮音』に由って詩眼を開くことを得た一人であった。また能く余が厳格なる批判に聴いて『明星』に採録する氏の詩が、その所作の十が一にも過ぎざるに拘わらず、毫も不満に思ふ色なく、之に激励せられて益々慎重の心掛を加へ、精苦の作を試みた。その詩は昨年に入って頓に進境が見え出したが、本年三月の『明星』に載せた「ねたみ」一篇が、図らずも絶筆と成った。(以下略)
山城正忠○ああ、僕が詩歌の交際に於いて親しい友の一人なる詩華末吉安持君は、本年二月十七日二十一歳を一期に、燃ゆるやうな青春の希望を抱いて、空しく白玉楼中の人となってしまった。回顧すれば、僕が君を知ったのは、三十六年の夏の頃で、或友の紹介を得て、初めて君をその邸宅に訪ふたが、白百合を紫色した薬瓶に活けた氏の書斎に通され、親しくその風丰に接することを得た。『僕は山城といふものですが、以後どうぞ宜しく』と挨拶をすると、君は優しい眉根を、こころもち上げて『あ、さうですか・・・・・・』と云ったきり、何とも言って呉れぬ。そこで、僕は何だか気にくはなかった。少し横柄な人だなと、心中密かに氏の人格を疑った。併し、だんだん話して見ると、思ったよりはさばけた人で、僕の考は全く邪推に過ぎなかった。其日は面白く君の気焔にまかれて、帰ったが、それが縁となって、逢ふことが度かさなるにつれ、互いに胸襟を開いて話すやうになった。
時には徹夜して酒を飲みながら詩を語り、或る時は深夜奥の山公園の松林で月を賞して、清興を共にした。又或時は、たわいもない事から口論をやることもあったが、それもほんの一時で、直ぐあとは光風雲月といふ塩梅に、一笑に附して了った。君は情の人で意志」の人ではなかった。その情の厚かったことは、友達が一度困厄して居るのを見ると、実に萬腔の同情を以って之を慰籍し、且つ救護したのである。それから酒を飲むとなかなか面白い男で、いつでも団十郎や菊五郎の假色をつかふのが十八番であったらしい。その頃から君は新詩社の詩風に私淑して居って、詩の話になると、すぐ『紫』や『みだれ髪』を持出し、言葉を極めて賞讃した。それに僕も与謝野氏の歌は『東西南北』『天地玄黄』時代から、ひそかに景仰して居ったのであるから、互いに負けぬ気になって、讃辞を交換すると云ふ風であった。それからもう一人君の敬慕して居た詩人は薄田泣菫氏で、その『行く春』『暮笛集』は、いつ行っても氏の机の上に飾られてあった。その為め僕も君に感化せられては又泣菫氏の詩を愛読するやうになり愈愈両人は趣味が一致した。
これが僕等の交際をして益々親密ならしめた楔子である。泰国の詩人では、君はバイロンとダンテを称揚し、僕はアナクレオンを賛美した。今一人我国では、故人樗牛氏を崇拝して居たらしい。併し近頃は何う変わって居たか、琉球と東京と隔って居たから僕には分からない。なんでも夏目氏と上田敏氏とに大層私淑して居たといふことを外から聞いた。さうかうする内、君は突然上京して了ったので、僕は何だか離れ小島に独りとり残された思がした。爾来音信を絶つこと殆ど二年、時々友人からその消息の一端を聞くばかりで、氏からは端書一枚をも寄越してくれない。随って互いに疎遠に成って居た。然るに三十八年の四月、僕は補充兵で上京し、青山の第四聯隊に入営することになった。毎日練兵が忙しくって、つい君を尋ねることも出来ず、直ぐ近所の与謝野氏の御宅にさへ伺ふことが出来ぬと云ふ始末、それが殆ど七箇月に亘って、十月の中頃、病気に罹って召集解除となり、再び故山の人となった。
兵営を出て明日帰郷すると云ふ晩、神田の或る本屋の店頭で『天鼓』といふ雑誌を見た。何心なく披いて見ると、末吉詩花として『平和の歌』(たしかさうであったとおもふ)といふ新體詩が出ているので急になつかしい思がした。併し尋ねるにも君の下宿が分からないから終に其儘逢はずに帰国して了ったのは、今から思ふと実に遺憾である。それから僕が琉球に帰って、初めて末吉君は近来『明星』に筆を執って居るといふことを聞いて、愈愈素志の如くやり出したなと、密かに氏の努力を羨んだ。昨年の夏君は帰省したので、久し振りに某酒亭に会して、親しく新詩社の現状を聞き且つ与謝野氏の御話なども受売して貰った。その時氏の語る所によると『与謝野氏は一見何だかコハイやうな方だが、詩に就いては至極親切に指導して下さるから有難い。君も新詩社の一人に加わって真面目に詩を作りたまへ』とのことであった。併し、僕はまだ早からうと述べた。その日は月の佳い夜であった。その月の光が、君と僕と此世で一緒に浴びる最終のものだとは、両人ともつゆ想ひ及ばなかった。ああその夜の光景と君が音容とは、今猶ありありと想ひ泛べ得るのに、君は既に世に居ないのであらうか。僕はまだ何うも君が死を信じ得られない
○1987年8月『沖縄県図書館協会誌』弟12号 仲程昌徳「新詩社同人・詩崋の作品ー末吉安持ノートー」
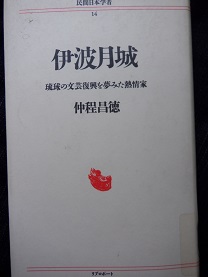
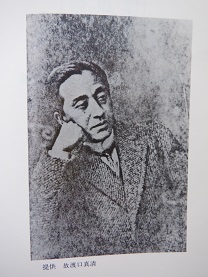
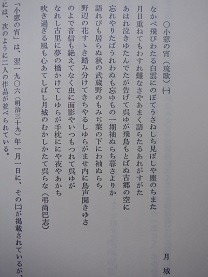
1988年5月 仲程昌徳『伊波月城ー琉球の文芸復興を夢見た熱情家』リプロポート
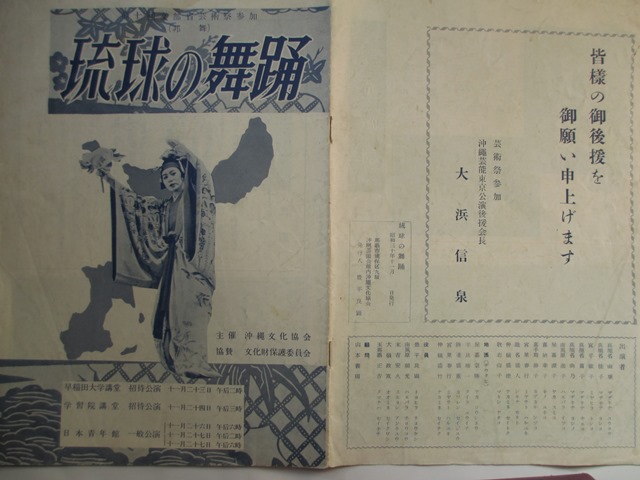
宮平敏子
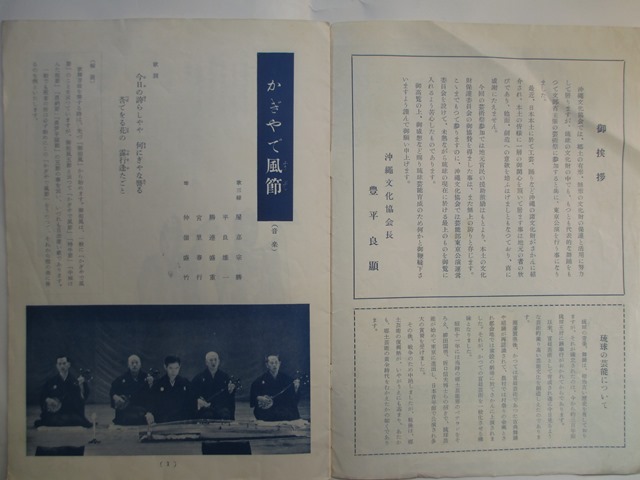
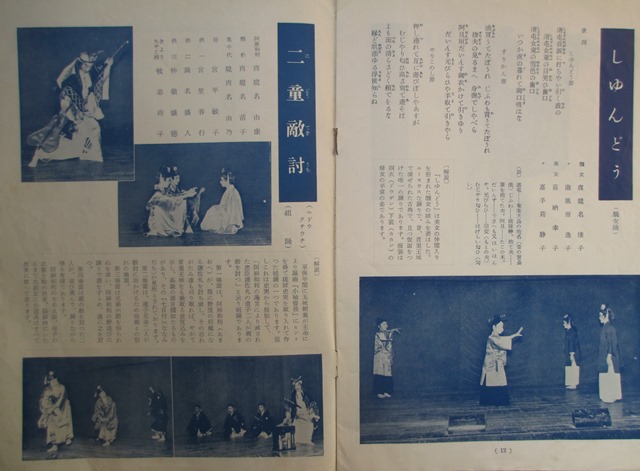
(翁長良明コレクション)
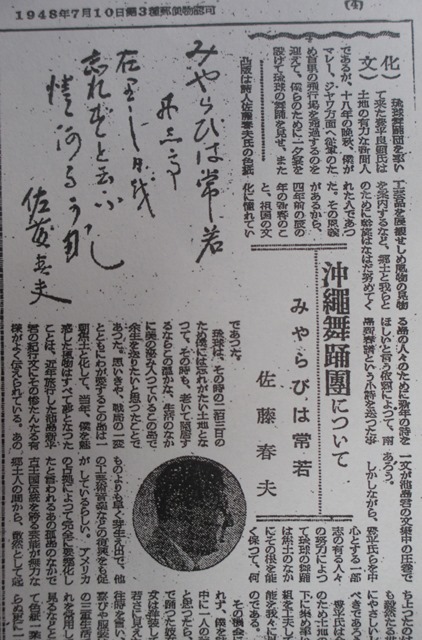
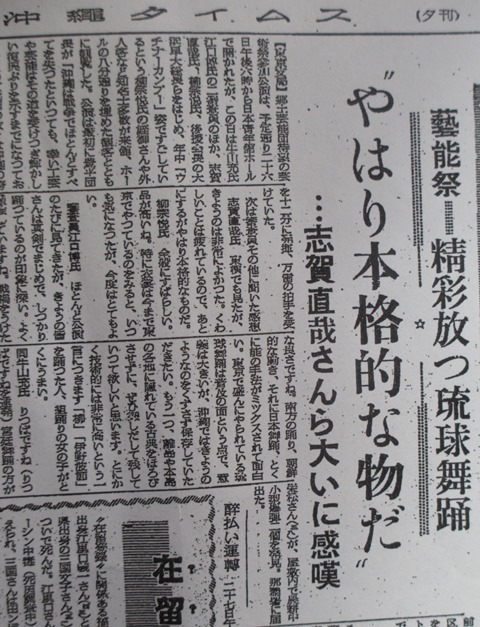
1955年12月11日『沖縄タイムス』佐藤春夫「沖縄舞踊団についてーみやらびは常若」/11月27日『沖縄タイムス』「芸能祭」
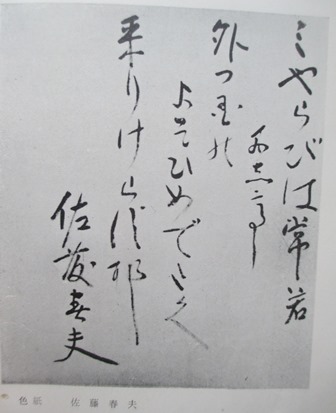
12月15日『沖縄タイムス』「文部省主催の芸術祭ー沖縄舞踊が団体入賞」
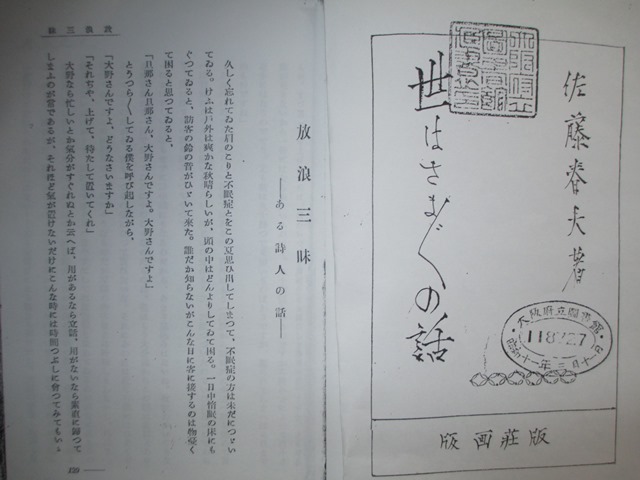
1933年1月 佐藤春夫作「世はさまざまの話」
青山恵昭 2021-8-31 佐藤春夫は山之口貘がお世話になった等々、沖縄通としても知られていますね。1929年28歳の時、台湾基隆社寮島(現和平島)の琉球人集落を訪ねたことを記した短編随筆「社寮島旅情記」があります。友人2人して舢舨(サンパン)で島へ渡り、琉球料亭で一席をもうけて泡盛を嗜み、三線、琉舞に興じた様子が軽妙に描かれています。湾生として興味深々読みました。
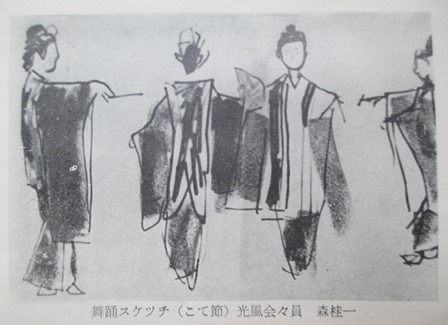
森 桂一モリ ケイイチ
昭和期の洋画家 千葉大学名誉教授;明徳短期大学名誉学長。
生年明治37(1904)年8月10日没年昭和63(1988)年3月16日
出身地岐阜県恵那市 別名号=林人子
学歴〔年〕東京美術学校〔昭和3年〕卒
主な受賞名〔年〕勲三等旭日中綬章〔昭和49年〕
経歴昭和3年帝展初入選。27年から45年まで千葉大教授。50年から56年まで明徳短大学長。美術教育を研究するかたわら、日展委嘱洋画家としても活躍。著書に「美術教育概説」など。→コトバンク
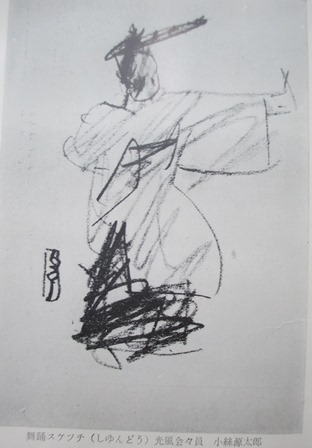
小糸源太郎 こいと-げんたろう
1887-1978 大正-昭和時代の洋画家。
明治20年7月13日生まれ。東京美術学校(現東京芸大)在学中に文展入選,昭和5年,6年に帝展で連続特選となる。官展の審査員,光風会会員として活躍し,29年「春雪」などで芸術院賞。40年文化勲章。昭和53年2月6日死去。90歳。東京出身。作品はほかに「山粧ふ」「繚乱(りょうらん)」など。 →コトバンク
05/05: 嘉陽安男
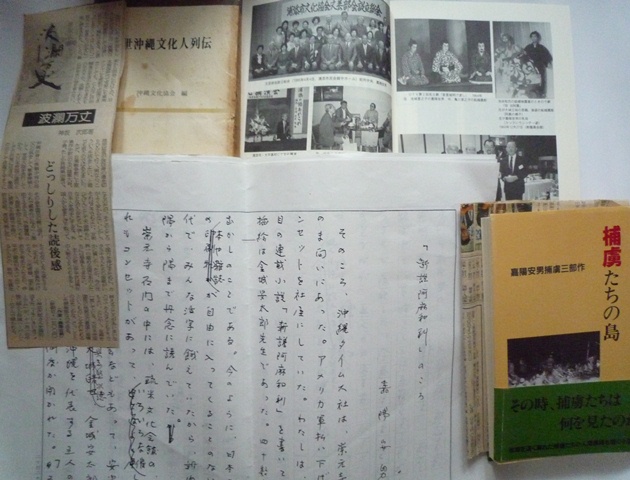

写真左から星雅彦氏、嘉陽安男氏、新城栄徳

写真左から嘉陽安男氏、新城栄徳、亀島靖氏
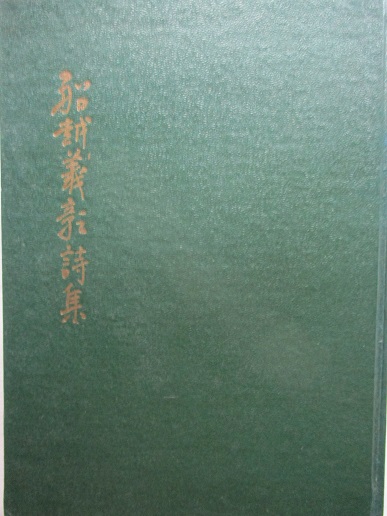
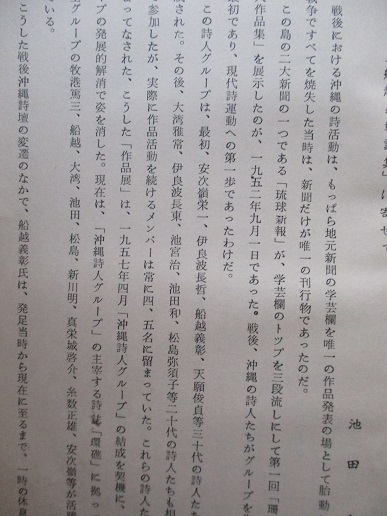
1959年3月『船越義彰詩集』南陽印刷所
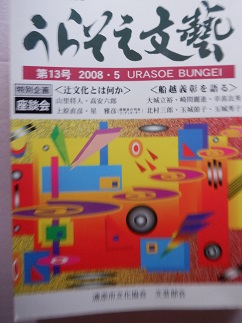
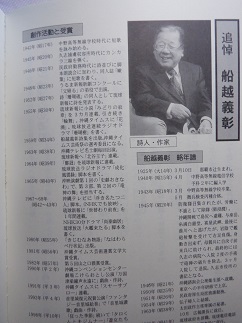
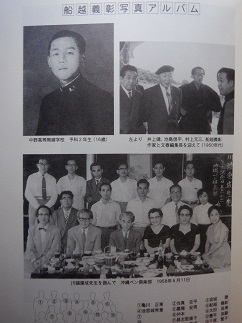
2008-5 『うらそえ文藝』<船越義彰を語る>第13号
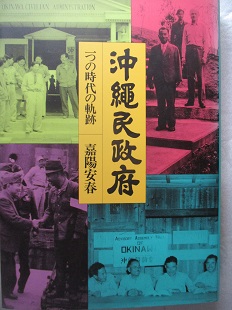
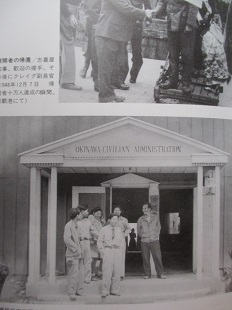
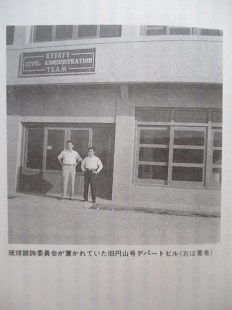
1986年12月 嘉陽安春『沖縄民政府―一つの時代の軌跡』久米書房


写真ー1989年6月1日、泊の自宅で民政府の表示板をバックにして國吉眞哲翁/1991年1月30日『琉球新報』
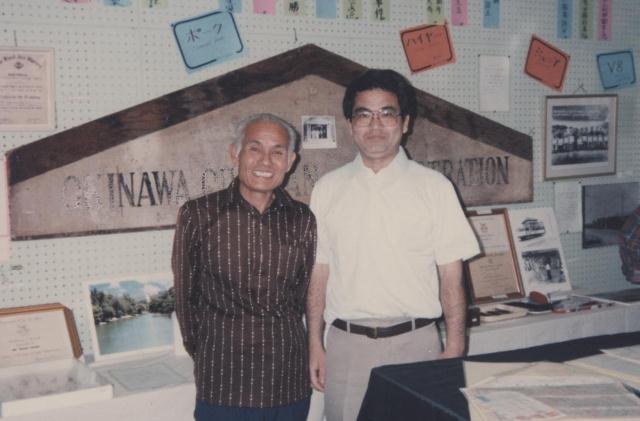
11/01: 琉球建築史家・又吉眞三
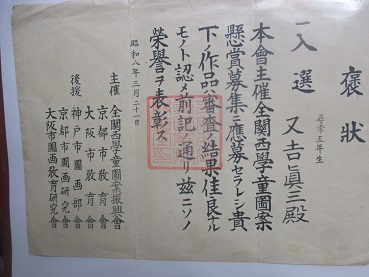
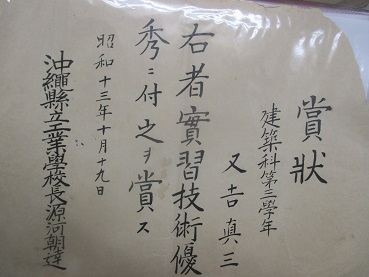
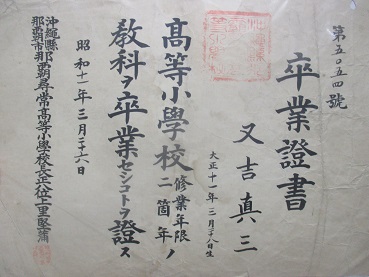
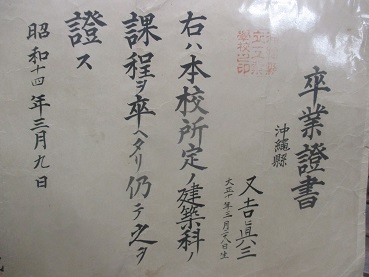
(翁長良明コレクション)
1973年12月ー又吉眞三『琉球歴史・文化史総合年表』琉球文化社
この年表は一級建築士の著者より署名入りで贈られた。首里城復元に関わった人で、崎間麗進氏や大阪の沖縄関係資料室主宰の西平守晴、琉球文化社の大城精徳社長とは親交があった。私も色々とお世話になった。 →□ 郷土史年表


写真左から、又吉眞三氏、新城栄徳、伊敷勝美さん、武石和実氏
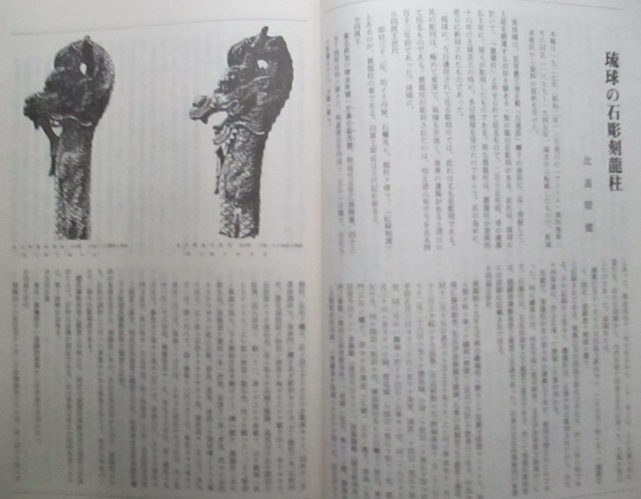

又吉眞三氏を囲んでー右から3人目が又吉眞三氏、左奥から西村貞雄氏、新城栄徳
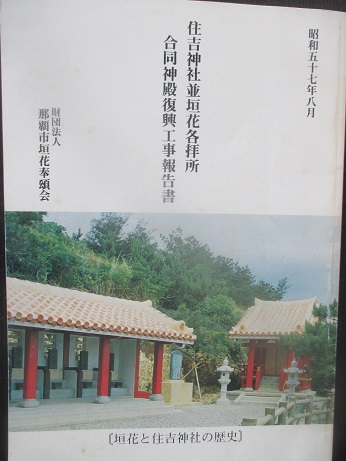
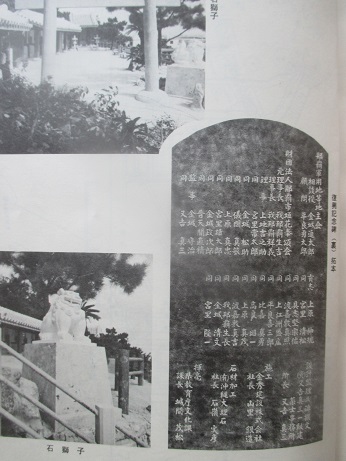
1982年8月 又吉真三『住吉神社並垣花各拝所合同神殿復興工事報告書』那覇市垣花奉頌会


「鎌倉芳太郎顕彰碑」甥御さんの鎌倉佳光氏案内/「アートギャラリーかまくら 南米珈琲」鎌倉芳太郎生家(島袋和幸提供)
2014年5月 図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』

沖縄県立博物館・美術館ミュージアムショップ「ゆいむい」電話:098-941-0749 メール:yuimui@bunkanomori.jp
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』 販売価格(税込): 1,620 円

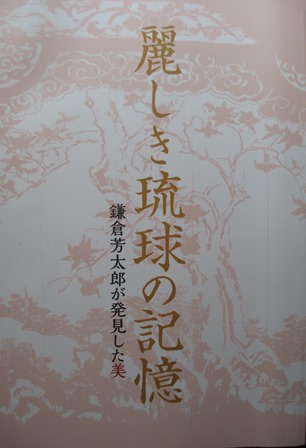
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁く」
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」

高草茂氏と新城栄徳
2015年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所『沖縄芸術の科学』第27号 高草茂「琉球芸術ーその体系的構造抄論」
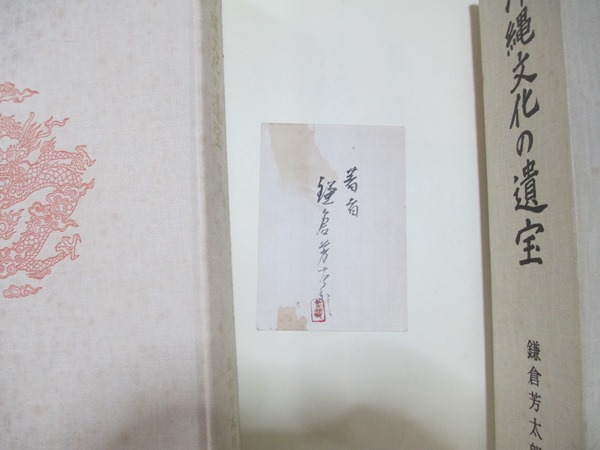
「麗しき琉球の記憶-鎌倉芳太郎が発見した“美”-」関連催事
【日時】5月31日(土)14:00~ 15:30 (開場13:30)
特別講演会/クロストーク
鎌倉芳太郎氏の大著『沖縄文化の遺宝』の編集者である高草茂氏による編集当時のエピソードなどを交えた講演と、「鎌倉ノート」の編集・刊行に携わる波照間永吉氏とのクロストークから、鎌倉氏の沖縄文化に寄せた情熱や思いなどを聞く機会とします。
【講師】高草茂 氏(元岩波書店 顧問)
波照間永吉 氏(沖縄県立芸術大学附属研究所 教授)

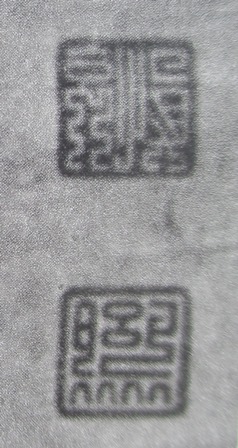
「首里那覇泊全景図」慎思九筆だが印章は慎克熈
沖縄文化工芸研究所□図録の内容を紹介します。
ご遺族や鎌倉自身と交流のあった方、鎌倉資料整理(沖縄県立芸術大学所蔵)に直接に関わった方々が文章を寄せています。記録資料としては将来価値のある図録だと思います。
*波照間永吉「芳太郎収集の沖縄文化関係資料」
*高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」
*佐々木利和「鎌倉芳太郎氏<琉球芸術調査写真>の指定」
*西村貞雄「鎌倉芳太郎がみた琉球の造形文化」
*柳悦州「鎌倉芳太郎が寄贈した紅型資料」
*波照間永吉「古琉球の精神を尋ねてー鎌倉芳太郎の琉球民俗調査ー」
*粟国恭子「鎌倉芳太郎が残した琉球芸術の写真」
*謝花佐和子「鎌倉芳太郎と<沖縄>を取り巻くもの」
*鎌倉秀雄「父の沖縄への思い」
*宮城篤正「回想「50年前の沖縄・写真でみる失われた遺宝」展
*新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁くー」
*三木健「<鎌倉資料>が世に出たころ」
○図版
○年譜
○主要文献等一覧
○写真図版解説
1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」
1893年、京都で平安神宮の地鎮祭が行われ西村捨三が記念祭協賛会を代表し会員への挨拶の中で尚泰侯爵の金毘羅宮参詣時の和歌「海山の広き景色を占め置いて神の心や楽しかるらん」を紹介し、平安神宮建設に尚家から五百圓の寄附があったことも報告された。ちなみに、この時の平安神宮建築技師が伊東忠太。
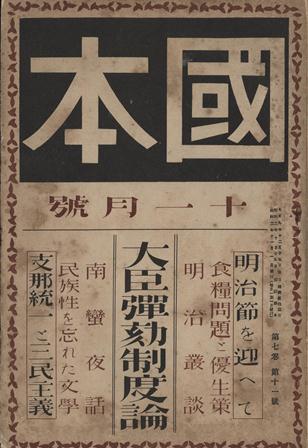
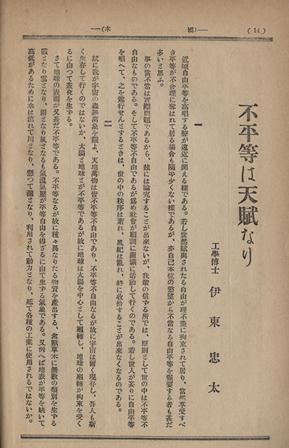
1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」
□翻って考ふれば、宇宙の諸現象は皆不平等、不自由なるが為に生ずるので、一現象毎に一歩づつ平等と自由とに近づくのである。斯くて幾億劫の後には絶対の平等自由が実現されて宇宙は亡びるのである。社会の現象も亦た不平等、不自由の力に由て起こるので、一現象毎に一歩づつ平等自由に近づくのである。斯くて幾万年の後には絶対の平等自由が実現されて社会は滅亡するのである。個人の一生も亦不平等不自由の為に支配せられて活動して居るのである。吾人の一挙一動毎に一歩づつ平等自由に近づくのを以て原則とする。斯くて百年の後絶対の平等自由が得られた時は即ち吾人の死んだ時である。
人は生まれた瞬間より一歩づつ死に向かって進むので、同時に又自由平等に向かって進むのである。絶対の平等自由を強要するのは即ち死を強要する所以である。要するに吾人は各自の職貴を竭して社会文化の向上に貢献すれば善いので社会の安寧秩序を保つべき条件の下に吾人の平等自由が適当に制限さるべきことを認容しなければならぬ。制限なき平等自由は假令之が與えられても吾人は之を受けることを欲せぬものである。何となれば之を與ふる者は悪魔であり、之を受くる者は之が為に身を亡ぼすからである。
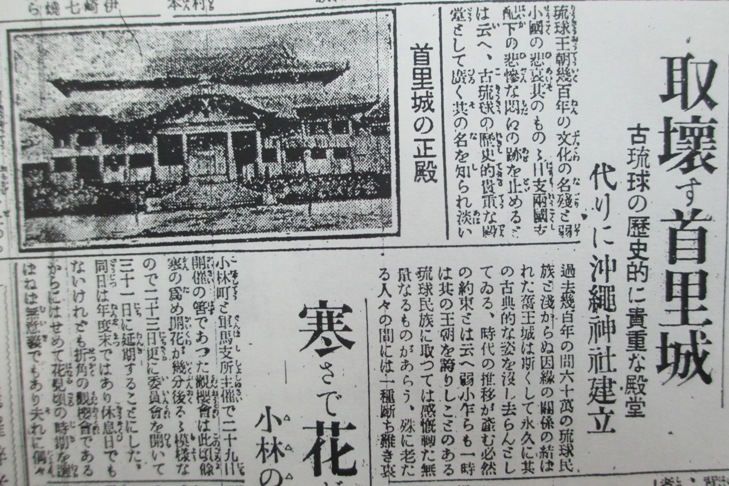
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
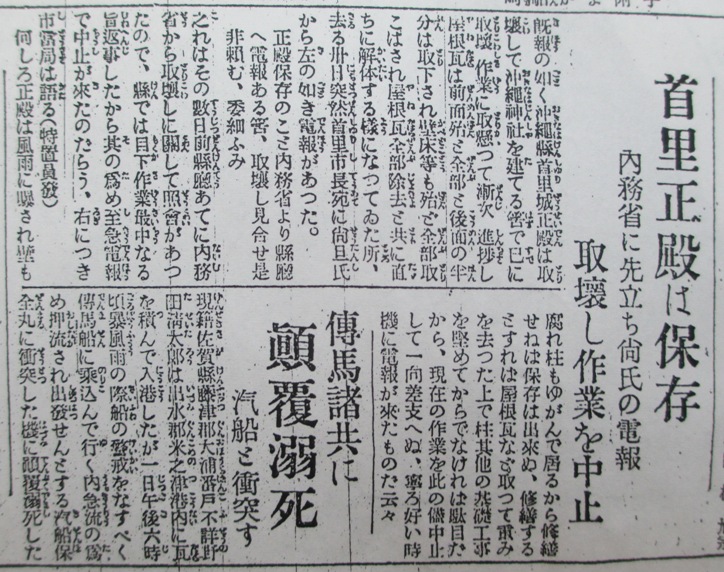
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
1924年
3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。
①『科学知識』「琉球紀行」□余は沖縄到着の第五日目の晩に脚の関節に鈍痛を覚えたので、テッキリやられたと直覚して寝に就いたが、夜半過ぎから疼痛が全身の関節に瀰漫し来り、朝になって見ると起きかえることは愚、寝返りも出来ぬ程の痛さである。(略)兼ねて東京を出発する時、琉球に悪疫の流行して居ることを聞知して居たので、入澤達吉博士に注意事項を問うた処が、博士は若しも沖縄で病気に罹ったら金城医学士の診療を受けるがよいと教えて呉れた。そこで早速同学士の来診を求めた所が、学士は直ちに来て呉れた。一診してこれは軽いデング熱である、2,3日で快癒すると事もなげに断言して呉れたので大いに安心した。(略)金城学士の話によれば、那覇市では殆ど毎戸に患者があって、一家一人も残らず感染した例も珍しくない。那覇6万の人口中、少なくともその三分の二は感染したものと思われるが死者は今の所43人である。夫は何れも嬰児で脳膜炎を併発したのであると云う。余が全治した頃は那覇の方は下火になり、追々田舎の方へ蔓延する模様であった。土地ではこれを「三日熱」と唱えて居る。夫は熱が大抵三日位で去るからである。
8月20日午後3時 大阪商船の安平丸で鹿児島へ。8月22日ー『沖縄タイムス』伊東忠太「琉球を去るに臨みて」。8月25日に東京着□→1925年1月~8月『科学知識』に琉球紀行を連載□1928年5月ー伊東忠太『木片集』萬里閣書房(写真・首里城守礼門)
1925年
1月ー鎌倉芳太郎、沖縄の新聞に啓明会から発行予定の「琉球芸術大観」発表。□(イ)序論ー分布の範囲、遺存の概況、調査物件の項目 (ロ)総論ー史的考察、時代分期
(ハ)各論①建築ー1王宮建築、2廟祠建築、3寺院建築、4住宅建築、5陵墓建築、6橋梁建築 ②琉球本島の部ーイ純止芸術(美術)篇ー1紋様、2絵画、3彫刻 ロ応用芸術(工芸)篇ー1漆工、2陶磁、3織工、4染工、5金工鋳造、6雑工 ③宮古八重山の部 ④奄美大島の部


1925年2月 坂口総一郎『沖縄写真帖』第一輯 画・伊東忠太
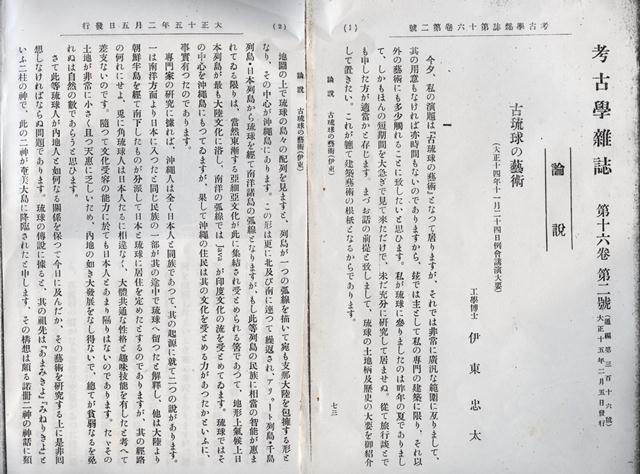
1926年2月『考古学雑誌』第16巻第2号 伊東忠太「古琉球の芸術」
1929(昭和4)年
『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」
□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」
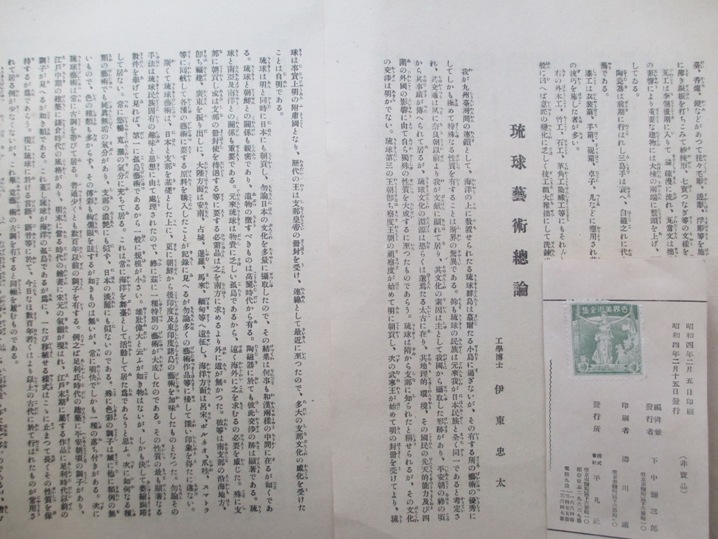
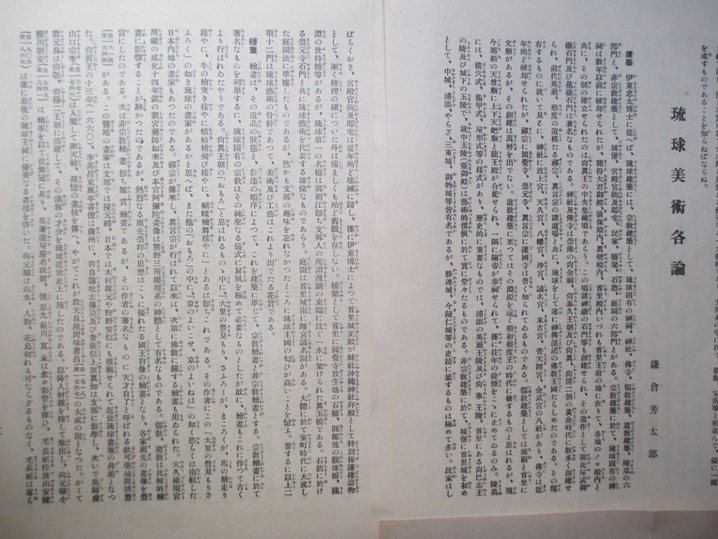
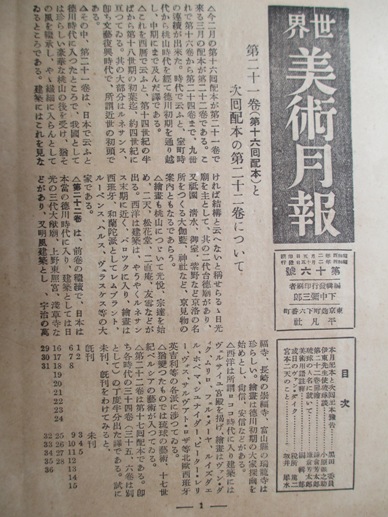
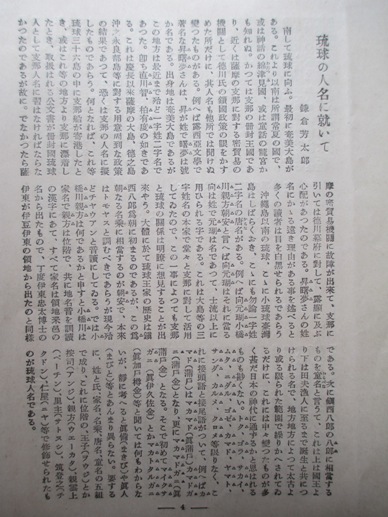
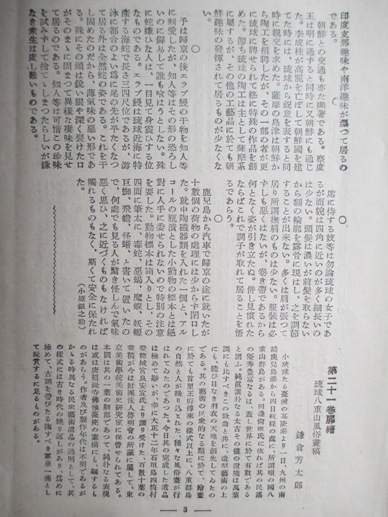
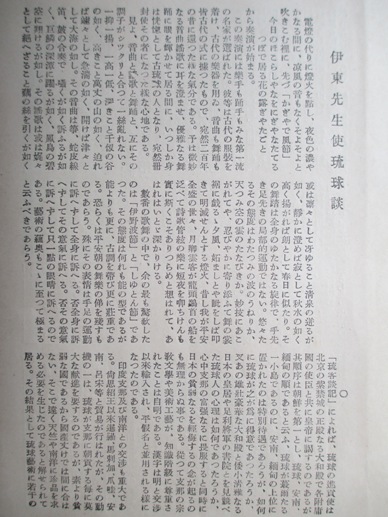
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)
1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社
1929年
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」

3月ー新光社『日本地理風俗体系』第12巻(カラーの守礼門)□伊波普猷「守礼門ー首里府の第一坊門を中山門と言ひ、王城の正門に近い第二坊門を守礼門と言ふ。前者は三山統一時代の創立で、『中山』の扁額を掲げたが、一時代前に毀たれ、後者はそれより一世紀後の創立で、待賢門と称して『首里』の扁額を掲げたが、万暦八年尚永即位の時、明帝の詔勅中より『守礼之邦』の四字を取って『首里』に代えた。以後守礼は首里の代りに用ひられる」
10月ー鎌倉芳太郎・田邊孝次『東洋美術史』玉川学園出版部
2006年3月ー『史料編集室紀要』第31号 新里彩「琉球文学における『千鳥』の諸相」
□はじめにー琉球文学において、千鳥はどのように表れているのだろうか。千鳥の歌を集めてみると、琉歌うたわれる千鳥、おもろや古謡にうたわれる千鳥、組踊や舞踊の詞章にうたわれる千鳥などがあることがわかった。そして、そのうたわれ方は、和歌の伝統的な文学イメージでうたわれる他に、琉球文学特有のうたわれ方があることが浮かび上がる。
2007年3月ー『史料編集室紀要』第32号 新里彩「浅地・紺地の琉歌について」
□正直で真面目な泊染屋の職人と辻で名高い遊女マカテとの恋物語『染屋の恋唄』は、古典落語及び浪曲の『紺屋高尾』を題材にしたものであり、物語の展開、登場人物の性格などほぼ同じである。作者は髙江洲紅矢という人物であるが、制作年代は不詳である。
□関東大震災で焼け出された浪曲家・篠田実(日畜専属)の「紺屋高尾」が大当たりした。♬遊女は客に惚れたといい 客は来もせでまたくるという 嘘と嘘との色廓でー♬があちこちのレコードから聞こえた。→内山惣十郎『浪曲家の生活』雄山閣1974年


新城喜一氏と新里彩さん

2015年9月9日ー左から翁長良明氏、新里彩さん

2015年9月9日沖縄県立博物館・美術館屋外展示場「民家」で、新里彩さん
□はじめにー琉球文学において、千鳥はどのように表れているのだろうか。千鳥の歌を集めてみると、琉歌うたわれる千鳥、おもろや古謡にうたわれる千鳥、組踊や舞踊の詞章にうたわれる千鳥などがあることがわかった。そして、そのうたわれ方は、和歌の伝統的な文学イメージでうたわれる他に、琉球文学特有のうたわれ方があることが浮かび上がる。
2007年3月ー『史料編集室紀要』第32号 新里彩「浅地・紺地の琉歌について」
□正直で真面目な泊染屋の職人と辻で名高い遊女マカテとの恋物語『染屋の恋唄』は、古典落語及び浪曲の『紺屋高尾』を題材にしたものであり、物語の展開、登場人物の性格などほぼ同じである。作者は髙江洲紅矢という人物であるが、制作年代は不詳である。
□関東大震災で焼け出された浪曲家・篠田実(日畜専属)の「紺屋高尾」が大当たりした。♬遊女は客に惚れたといい 客は来もせでまたくるという 嘘と嘘との色廓でー♬があちこちのレコードから聞こえた。→内山惣十郎『浪曲家の生活』雄山閣1974年


新城喜一氏と新里彩さん

2015年9月9日ー左から翁長良明氏、新里彩さん

2015年9月9日沖縄県立博物館・美術館屋外展示場「民家」で、新里彩さん
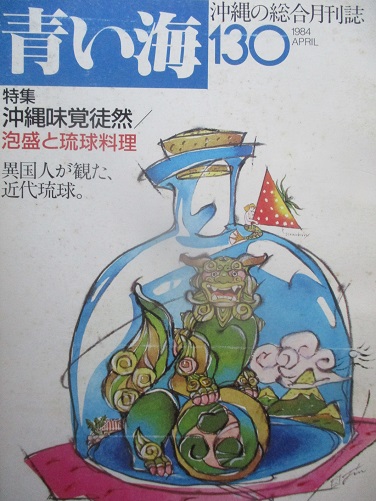
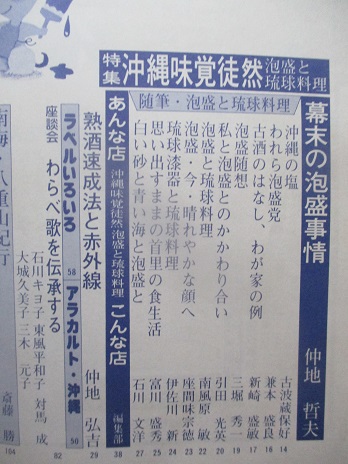
1984年3月 雑誌『青い海』130号「特集・沖縄味覚徒然/」泡盛と琉球料理
1980年9月ー藤井つゆ『シマ ヌ ジュウリ』道の島社1981年
1月ー日本調理師協会『協調』「沖縄に招かれて」(写真)
12月ー日本調理師協会『協調』「沖縄県支部第4回・秋の料理大講習会」(写真)
1982年
1月ー日本調理師協会『協調』「沖縄県支部料理講習会」(写真)
2月ー日本調理師協会『協調』「琉球料理献立」(写真)
沖縄県調理師協会(安里幸一郎会長)『沖調会報』創刊号
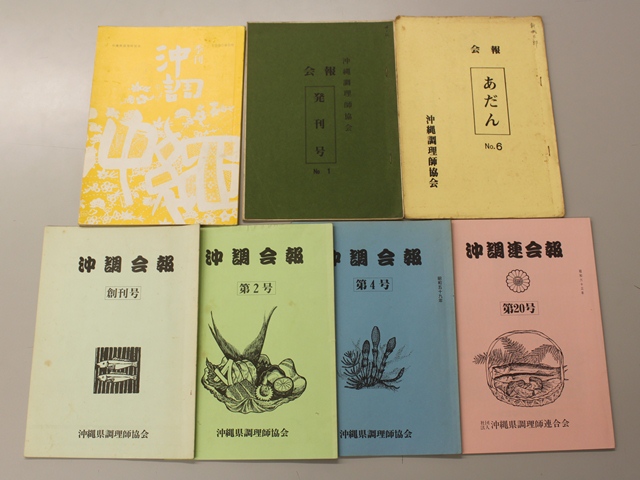
1983年9月 『沖縄ハーバービューホテル 10年のあゆみ』琉球総合開発
1983年 日本調理師協会誌『協調』「写真ー沖縄秋の料理大講習会」
1984年
1月ー沖縄の雑誌『青い海』120号<沖縄そばと生活文化史>
9月ー沖縄ハーバービューホテル調理部『沖縄の素材を生かす西洋料理』新星図書出版
1985年
1月ー沖縄調理師協会『沖調会報』第7号□略歴・中村喜代治、玉寄博昭、山川敏光、福永平四郎
1月ー日中調沖縄県支部『交友誌』
4月ー安里幸一郎『沖縄の海産物料理』新星図書出版
6月ー石川調理師会『石調だより』第2号
7月ー『月刊専門料理』<創刊20周年記念号>柴田書店
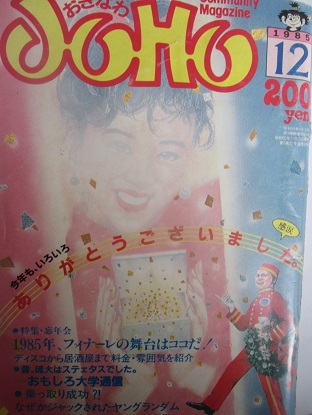

1985年11月『おきなわJOHO』「中ノ橋食堂」

昭和60年度「現代の名工・調理師部門」左から村上信夫氏、土井廣次氏、安里幸一郎氏
1987年3月 日本調理師協会誌『協調』「写真ー昭和62年度 沖縄県調理師連合会新年の集い」/辻元亮裕「沖縄調理師会新春総会」
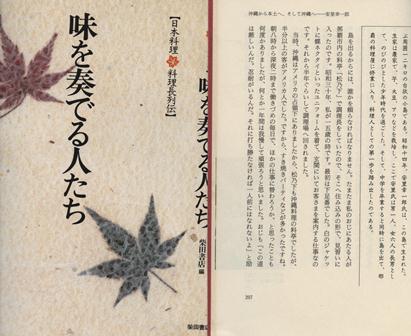
1988年4月ー柴田書店書籍部『味を奏でる人たち』「安里幸一郎(魚安)ー沖縄から本土へ、そして沖縄へ」
1988年4月 喜屋武マサ『沖縄豆腐料理80選』那覇出版社
1988年4月 『聞き書 沖縄の食事』農文協
1988年9月 『塩浜康盛追想集』(ホテル球陽館館主、沖縄ペルー協会初代会長)
1989年6月27日『琉球新報』「コンベンションセンターで第27回全飲連全国沖縄県大会ー21世紀の食文化は沖縄から」
1990年5月 『東急ホテルの歩み』東急ホテルチェーン
1991年8月ー(社)日本全職業調理士協会『料理四季報』<沖縄特集・沖縄 夏の料理>表紙□安里幸一郎「調理一言ー郷土料理は、『土産土法』という料理の原点である。郷土の素材を開発し、料理人として満足のいく献立を作っていくことが、調理師の使命であろう。さらに召し上がる人のことを念頭におき思いやりという心の薬味を添えたいと思って、常に庖丁を握っている。」
1993年1月ー『FUKUOKA STYE ⅤoⅠ.6』「特集・屋台ー食文化と都市の装置」
1993年11月27日『沖縄タイムス』「土曜グラフィックス こんにちは外国のおコメ」
1994年5月18日『琉球新報』「ビジュアル版 コメ戦争ー崩壊寸前の食管制度」
1997年 『サライ』大8号「中華街ーチャイナタウン三都物語」
2000年11月 リゾート時代の波受け「那覇東急ホテル」閉館
2002年3月3日『沖縄タイムス』新城栄徳 書評/中田謹介『笹森儀助「南島探検」百年後を歩く』編集工房風
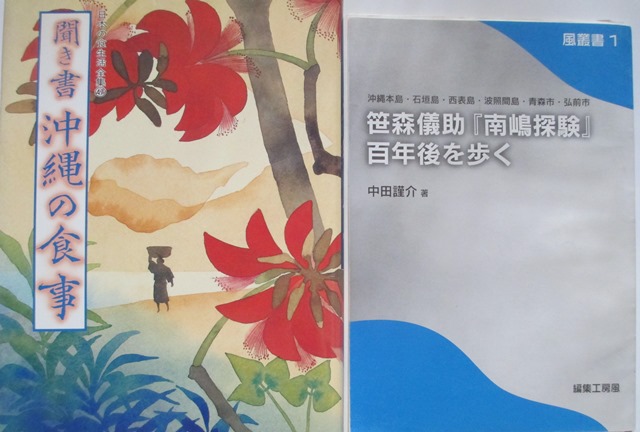
沖縄にかかわりのある東京の編集者といえば、岩波書店を辞めて『酒文化研究』を創刊した田村義也氏などが浮かぶが、本書の著者・中田謹介氏も農文協(社団法人農山漁村文化協会)に36年間勤め『日本農書全集』(第34巻は沖縄編)や、『日本の食生活全集』(第48巻は沖縄の食事は沖縄タイムス出版文化賞を受賞)などの企画・編集に携わった。そして沖縄近世文書探索の先に明治の3大探検家の一人といわれた笹森儀助に出会い、その著『南島探検』が描いた沖縄と中田氏が見た沖縄によって本書が生まれた。
本書はまず笹森のいう女の元服「入墨」(針突)にふれ「いま沖縄で入墨をした女性を見るのは困難である」とし、知人たちのそれぞれのおばあさんの思い出を記し、友人を介して手に入墨をした老人ホームのおばあさんに面談する。次に風土病(マラリア)について「八重山の歴史は、マラリアとの闘いの歴史といっても過言ではない」と戦争マラリアにもふれ、昨今の「癒しのシマ」とか言われ観光ボケした”沖縄土人”が忘れがちなことを思い出させる。
「首里城の語る百年」の項では、前出の編集にかかわった尚弘子、新島正子、仲地哲夫の諸氏に首里城復元についての感想を聞いている。そしてドイツ人の著した『大正時代の沖縄』を引用し「たまたま偶然に居合わせた一人の建築家(伊東忠太)の干渉によってー」、首里城はからくも消滅を免れたとある。が、たまたまではなく、鎌倉芳太郎が沖縄からの新聞を見て伊東に首里城正殿の取り壊しを報告。そして伊東が内務省から取り壊し中止の電報を出し、尚侯爵家で神山政良、東恩納寛惇らと協議を成し沖縄調査に赴いたものである。
本書は編集者が、どのように本を作っていたのか、どう沖縄に向かい合っていたのか分かり資料的にも価値がある。終わりに中田氏の川柳「ヘリポート生むは騒音サンゴの死/普天間の移設皇居が最適地」を紹介する。中田氏を、こころ優しき無頼派と見た。
2004年10月19日『琉球新報』「ビジュアル版 キノコの世界」
2008年10月29日『琉球新報』「ビジュアル版 世界の肥満事情」
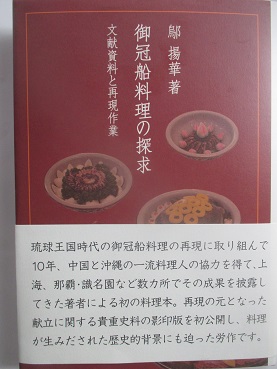
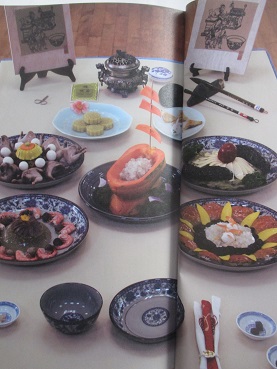
2017年11月 鄔揚華(ウ・ヤンファ)『御冠船料理の探究 文献資料と再現作業』 出版舎Muɡen

左から、新城栄徳、鄔揚華さん、天願恭子さん
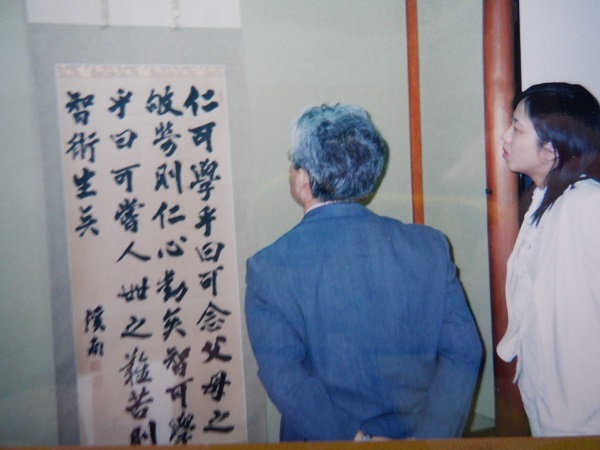
湖城渓南の書を観る鄔揚華さん、屋部夢覚氏
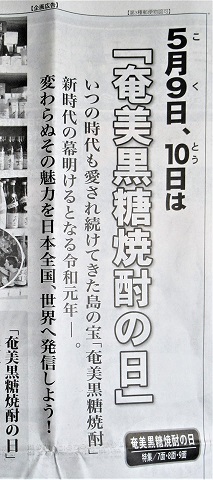

青山恵昭 2019-5-10 〇今日の〝黒糖酒記念日〟は笠利出身の友人からいただいた「里の曙」を、スクトーフをつまみにして嗜むことにしよう!そして、父の生マリジマ・ゆんぬの「島有泉」で仕上げよう。人口11万余の島々に蔵元が18もあるってスゴイ!
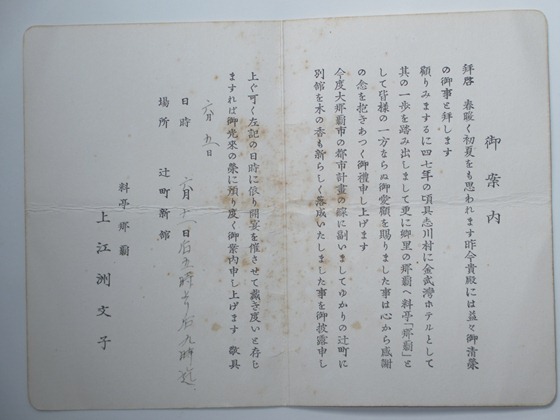
料亭那覇
01/18: 大城精徳と『琉球の文化』① 宮城篤正
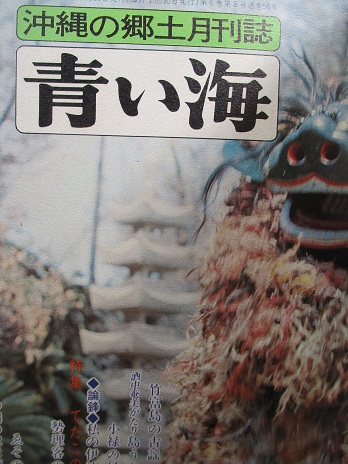
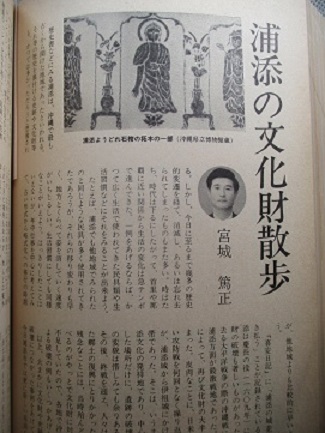
1976年9月『青い海』56号 宮城篤正「浦添の文化財散歩」
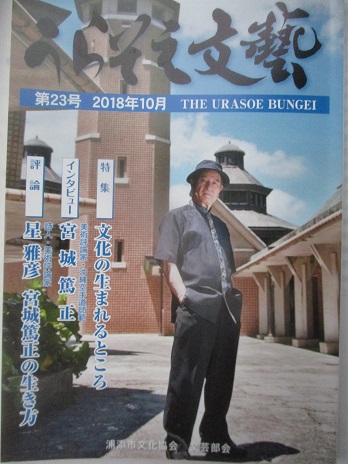
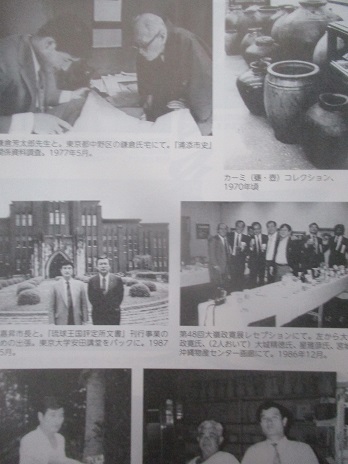
2018年10月 『うらそえ文藝』第23号「特集・宮城篤正」

2019年1月6日『沖縄タイムス』「週刊沖縄空手第93号-宮城篤正さん(79)」

写真左から宮城篤正氏、平川信幸氏、倉成多郎氏、前田孝允氏、新城栄徳、佐藤文彦氏、翁長良明氏
1913年
6月ー『琉球新報』大崎範一「琉球の陶器問題」連載

昭和期ー沖縄県物産大連斡旋所主催「琉球古典焼漆器即売会」
1970年7月ー『ヤチムン研究会誌』創刊号□事務局・那覇市首里大中町1の1琉球政府立博物館内
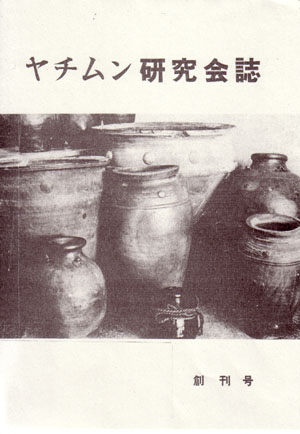
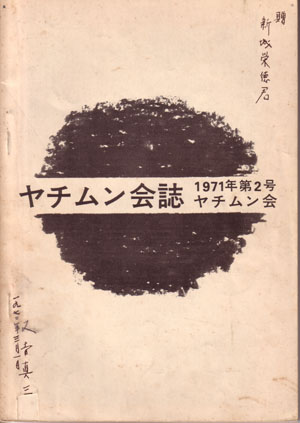
1971年
8月ー『ヤチムン会誌』第2号□事務局・琉球政府立博物館内
1972年
3月ー『琉球の文化』<特集・琉球の焼物>創刊
8月ー『ヤチムン会誌』第3号□編集責任・宮城篤正(沖縄県立博物館)
10月ー大城精徳、宮城篤正『琉球の古陶ー古我知焼』琉球文化社
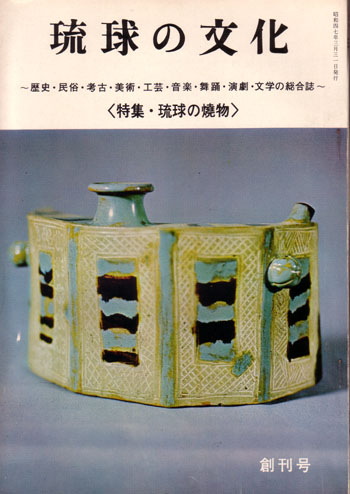
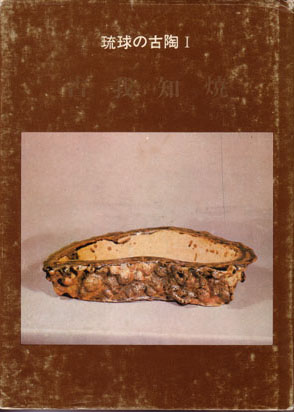
1973年
12月ー『やちむん』<特集・壺屋>□編集ヤチムン会(宮城篤正)発行・琉球文化社
1975年
4月ー『やちむん』第5号□編集責任・宮城篤正(沖縄県立博物館)
1977年
5月ー『やちむん』第6,7号<特集・沖永良部島>□沖縄県立博物館(宮城篤正)
1979年
10月ー『沖縄の名匠・金城次郎陶器作品集』沖縄タイムス社
10月ー『図録・沖縄の古窯』やちむん会□沖縄県立博物館内(宮城篤正)
1984年
10月ー『やちむん』<特集・浜比嘉島>第8号□事務局・琉球文化社内
1986年
7月ー『やちむん』第9号□事務局・琉球書院内
1987年
12月ー『企画展・現代沖縄の陶芸ー天野鉄夫コレクション』沖縄県立博物館
1989年
8月ー小渡清孝「沖縄の古窯」(第179回沖縄県立博物館文化講座)
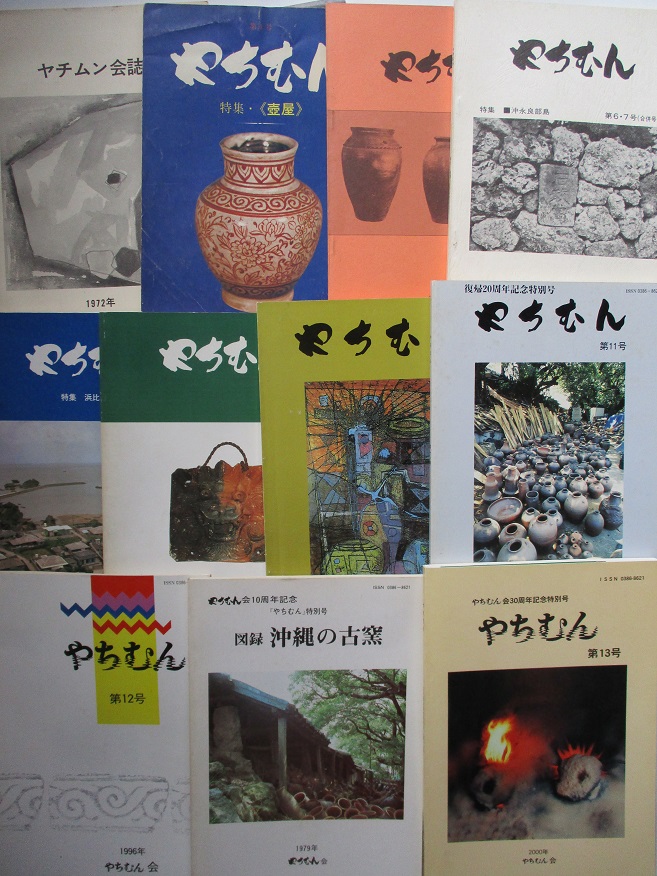
1991年9月ー『企画展・壺屋陶工遺作展』沖縄県立博物館
1996年
11月ー『沖縄の古窯・古我知焼』名護博物館
1998年
2月ー『壺屋焼物博物館常設展ガイドブック』
2001年
1月ー『企画展・くらしの焼物』宜野湾市立博物館
2004年
9月ー宮城篤正監修『翁長良明コレクション・琉球の酒器』
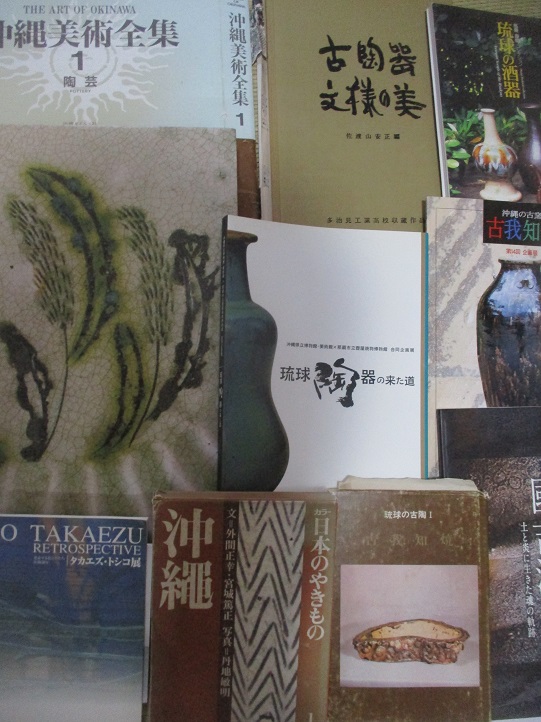
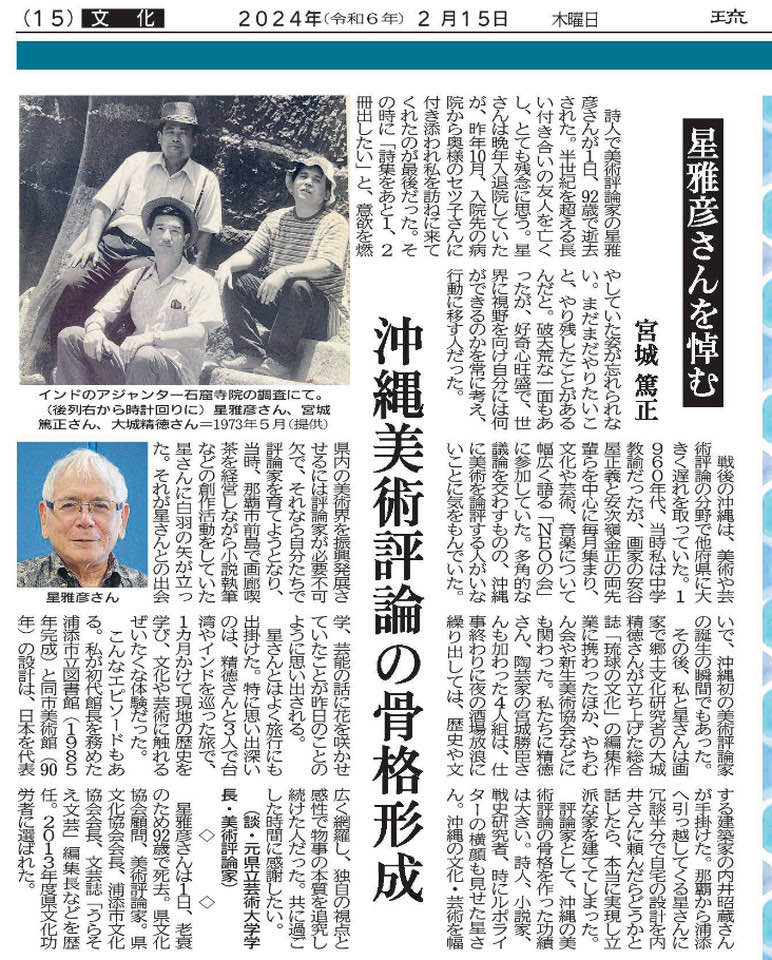
宮城篤正「星雅彦さんを悼む」
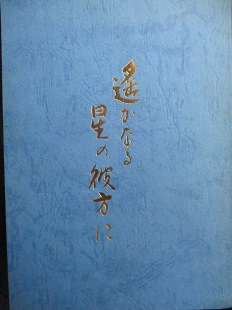
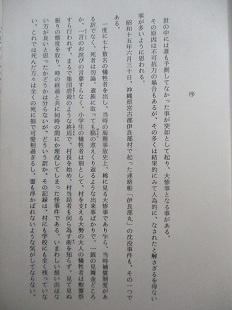
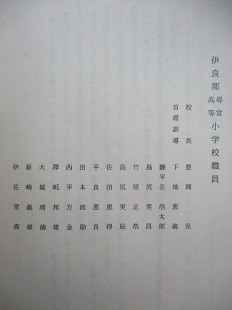
1983年3月 伊佐常喜(尼崎市)『遥かなる星のかなたに』「1940年6月30日ー伊良部村の連絡船『伊良部丸』沈没事件で70数名の犠牲者」
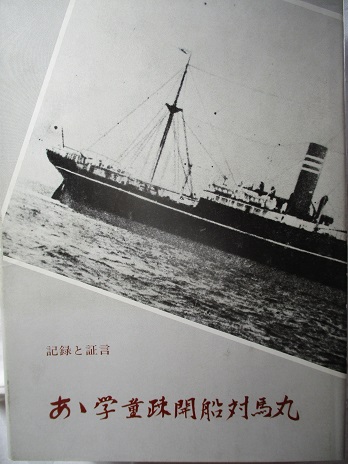
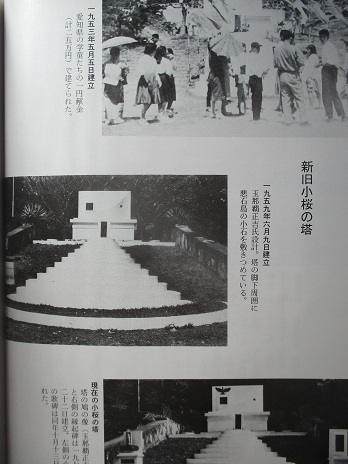
1978年8月 新里清篤編『記録と証言 あゝ学童疎開船対馬丸』対馬丸遭難者遺族会
ヒーサン(寒い)、ヤーサン(ひもじい)、シカラーサン(寂しい)
〇沖縄から本土への学童疎開は1944(昭和19)年7月7日、政府の緊急閣議で決定した。この日サイパン島が玉砕、民間人を巻き込んだ戦闘は衝撃を与えた。次は沖縄である。閣議決定は「本土へ8万人、台湾へ2万人、計10万人を7月中に引き揚げさせよ」であった。鹿児島県知事へも奄美群島からの引き揚げを命じている。疎開業務は警察部が所管となり、進められた。学童疎開は文部省の指示を受け県教育課が計画を推進した。疎開業務は容易には進まなかった。米軍の潜水艦が沖縄・鹿児島間の海上で日本の艦船を沈め、多くの犠牲者が出ていることは公然の秘密になっていた。県外へ、しかも危険な航海。親たちは反対した。校長らは説得に懸命になった。一人でも多くの疎開学童を集められる教師が優秀な先生といわれた。→『沖縄学童たちの疎開』琉球新報社
〇他府県での学童疎開も1944年8月から国民学校初等科3年から6年生を対象に始まった。大都市への本格的空襲が予想されるようになり、被害を防ぐ観点から戦火にさらされそうな地域に居住する学童をより安全な地域に一時移住させた。防空体勢の強化、次代の戦力を培養する目的の国策として実施された。具体的には東京、川崎、横浜、横須賀、名古屋、大阪、神戸などから約45万人の学童が34都道府県の旅館や寺院など約7千カ所に疎開した。→『沖縄学童たちの疎開』琉球新報社
〇1943年4月、新里清篤は妻の千代子と共に本部国民学校にへ赴任した。翌年7月にはサイパン島が玉砕、間もなく沖縄県内政部長名で「学童集団疎開実地要綱」の通報が学校に届いた。立場上、新里は「父兄、学童に疎開を呼び掛けるには、まずわが家族を率先させねば・・・・・・」と考えた。鹿児島への海路は既に何隻もの船が撃沈され、”魔の海„と化しており、船旅は一大決心を必要としていた。対馬丸には千代子、長男、二男、長女の3人の子供、そして「孫が疎開するなら、自分も」と言ってきた母親のナベの5人が乗船、全員が帰らぬ人となってしまう。→『沖縄学童たちの疎開』琉球新報社
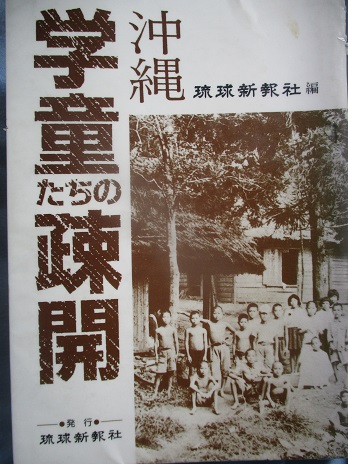
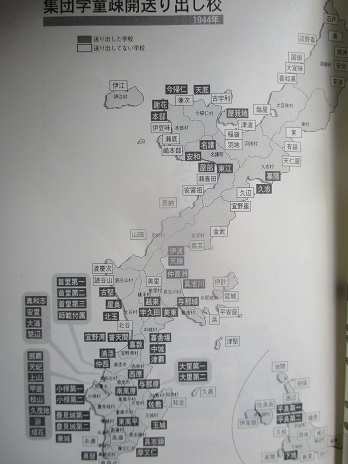
1995年5月 琉球新報編集局学童疎開取材班(池間一武、照屋直、崎原孫雄)『沖縄学童たちの疎開』琉球新報社
1913年 第一大里尋常小学校の分教場として御殿山に開設され,1941年 与那原国民学校として独立校として開校された。→与那原町立 与那原小学校
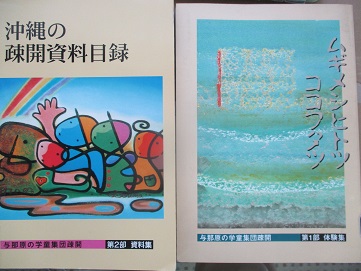
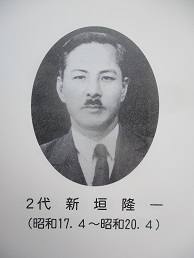
1995年8月 与那原町学童疎開史編集委員会『与那原の学童集団疎開』与那原町教育委員会/新垣隆一2代与那原国民学校長(1943年の教職員名簿に「與那原國民学校 校長 正七 六待一五六〇加 新垣隆一」)
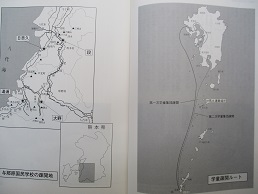
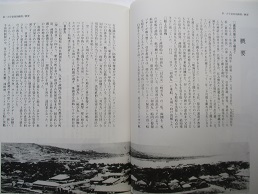
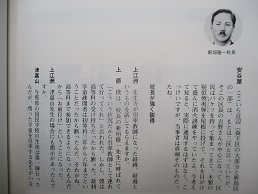
1995年8月 与那原町学童疎開史編集委員会『与那原の学童集団疎開』与那原町教育委員会
上原敏雄・引率教諭「与那原国民学校第一次学童疎開」1944年8月15日ー疎開申込児童188名、引率教員、養護婦、世話人、合計218名が親川に集合し、トラック3台に分乗して那覇に向かった。那覇では宿舎浦崎旅館に男子、那覇旅館に女子、津波旅館に女子と家族が分宿して乗船待機をした。8月17日ー「いかだ用の棒と縄の準備をせよ」との達示で海上輸送の不安を感じた父兄が、18日早朝、疎開取り消しのため宿舎に殺到して混乱状態になった。新垣隆一校長の出覇、父兄会、大多数取消し、荷物整理に津嘉山朝吉先生を主任に全力を注いで下さった。
残り児童95名、引率関係者合わせて119名、8月21日午後7時ー和浦丸(那覇の子どもたちの荷物も乗せる)に乗船。左右に2隻の護衛艦の5船団で、時折飛んでくる飛行機に守られ、航海を続ける。22日夜半ー僚船対馬丸の悲報、最悪状態。魚雷が左右に白波を立てて、舷めがけてやって来る。ジグザグの航路・・・(略)1946年10月26日帰還。那覇港に降り立つとDDTの洗礼を受け、トラックに乗せられ、懐かしい荒れ果てた与那原を右手に見ながら久場埼の収容所に下り立った。玉那覇栄三先生に迎えられ感激の涙がしみ込み、実にうれしかった。一夜明かし、あこがれの与那原へ向かった。変わり果てた親川で、子どもたちを父兄に引き渡すことが出来たことを、疎開関係各位に心からお礼を申し上げる。帰還を迎えて下さるはずの新垣隆一校長は戦死、佐久本嗣矩校長先生ほか、疎開児童の父兄方に迎えられ、帰還報告を済ませた。児童たちと引率教員は、佐久本先生を校長とする与那原初等学校所属となった。
安谷屋勇・引率教諭「与那原国民学校第一次学童疎開」昭和19年。それはよい年ではなかった。日本軍は南方戦線で次々と敗れ、7月7日にはついにサイパン島が陥落して、米軍の沖縄上陸は必至の状況になっていた。すでに沖縄には守備軍として、球部隊、山部隊、石部隊、武部隊の約10万に及ぶ精鋭が配備されていた。国民学校はいずれもその兵舎に併用され、兵隊と児童の雑居で、正常の授業はできなくなっていた。与那原国民学校にも部隊の一隊が駐屯していたが、その行事板には米軍上陸予想月日が掲示され、上陸近しを感じさせるほど、戦局は緊迫していた。
8月21日ー焼けつくような酷暑の中、那覇港近くの西新町広場に集結した。何しろ一般疎開を含めて約5千人に及ぶ大集団に、それを取り巻く見送り人で混雑を極めていた。(略)港外には護衛艦二隻と輸送船三隻の、計五隻編成の船団が待っていた。輸送船はいずれも、陸軍所属の老巧化した数千トン以上の貨物船だと言われていた。それは和浦丸、対馬丸、暁空丸であった。島尻地区は最初、対馬丸に割り当てられていたが、いつの間にか和浦丸に変更され、対馬丸には那覇地区が割り当てられていた。対馬丸は僚船三隻中、最も外観が良かった。真偽のほどは不明だが、那覇地区のクレームによって変更されたとのうわさが流れていた。船団は午後7時ごろ錨を上げ、ゆっくり動き出して港を後にした。行く先は長崎港、疎開先は熊本県日奈久町である。・・・
津嘉山朝吉・引率教諭「与那原国民学校第二次学童疎開」わが子を戦火にさらすより疎開させようと、学童疎開を希望する残余の生徒が集められた。時の新垣隆一校長の強い要請により、最終的に私が引率教師となった。昭和19年9月15日には、学童疎開第二陣(学童数40人、安里国民学校の5人を含む)として、輸送艦「室戸丸」で那覇港を出航した。室戸丸が最後の学童疎開船だったようだ。9月24日ー室戸丸、鹿児島に入港(錦生旅館に投宿)。9月30日ー疎開先の熊本県湯浦町(現芦北町湯浦)に到着。宿舎は寿旅館。湯浦国民学校に転入。
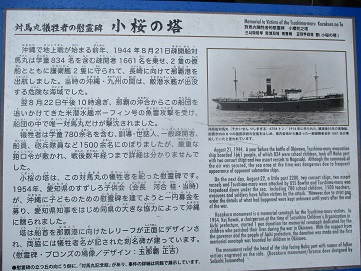
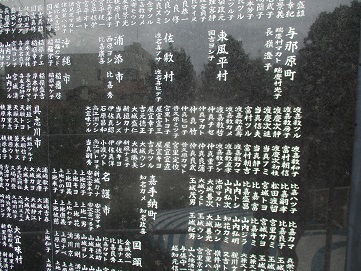
対馬丸犠牲者(1、484人)の慰霊碑・小桜の塔/対馬丸犠牲者「刻銘板」与那原出身は瑞慶村マカト、瑞慶村光子、長嶺澄子
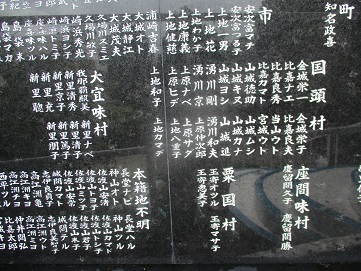

対馬丸犠牲者「刻銘板」粟国出身は玉寄オツル、玉寄マサ子、玉寄恵美子/海鳴りの像-赤城丸犠牲者(406人)・嘉義丸犠牲者(368人)・開城丸犠牲者(10人)・湖南丸犠牲者(577人)・台中丸犠牲者(186人)
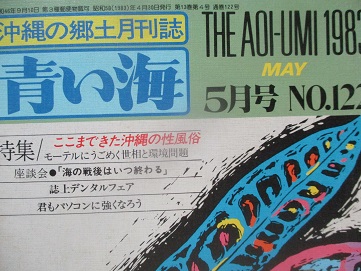
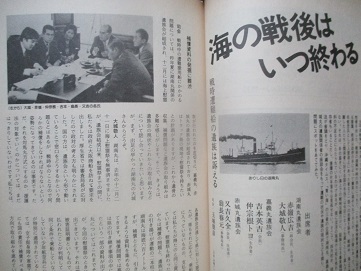
1983年4月雑誌『青い海』№122 「座談会ー海の戦後はいつ終わるー戦時遭難船の遺族は訴える」出席者・湖南丸遺族会・赤嶺広吉、大城敬人/嘉義丸遺族会・吉本英吉、仲宗根トヨ/赤城丸遺族会・又吉久全、翁長春元 司会・玉城朋彦
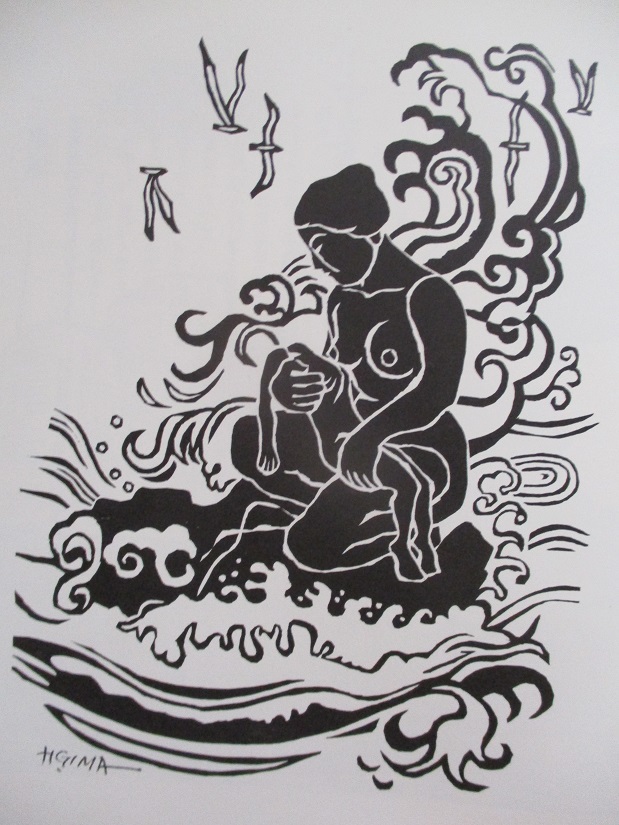
儀間比呂志「モニュメント『海鳴りの像』戦後の沖縄の心は『戦はならんどー』である」
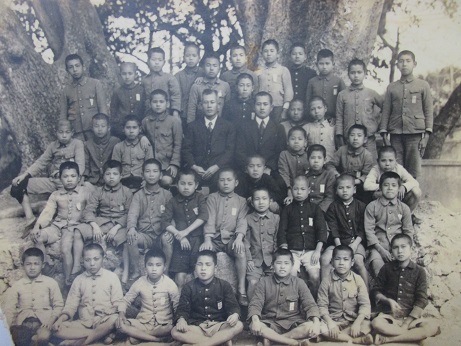
写真ー全員対馬丸に乗り込んだ学童たち。後列左から4人目 山里昌男14歳(翁長良明所蔵)
「日の本」2014年8月16日12時33分秋篠宮ご夫妻は16日、長男・悠仁さまらお子さま方と東京・新宿の京王プラザホテルを訪れ、戦時中に約1500人が犠牲になった「対馬丸事件」の慰霊の集い「学童疎開船を語り継ぐつどい2014」に出席した。会場で、秋篠宮ご一家は「対馬丸事件」の生存者らとともに黙禱(もくとう)し、犠牲者をしのんだ。続いて、沖縄県から参加した小学生が、生存者の仲田清一郎さん(78)に質問するコーナーがあり、悠仁さまは長女・眞子さま、次女・佳子さまと熱心に聴き入っていた。また、ご一家は対馬丸事件関連の展示も鑑賞。悠仁さまは紀子さまの説明を受けながら、生存者が当時の様子を描いた絵などに見入っていた。
仲田清一郎2020-5-12 秋篠宮ご一家の前で20分間対馬丸についてお話致しましたが、主催者から与えらた時間内ではとてもお話しできるものではなく、今でも心残りがしています。その後も秋篠宮様にはお会いする機会がありましたが、TV画面と違って、男前といった感じでした。また紀子様は琉球舞踊を習われた方で、外間守善先生のセミナーに参加され私も近くで拝見しました。また小学2年生の悠仁親王が気を付けの姿勢で私にお辞儀をされたのと、20分間姿勢をお崩しにならなかったのも驚きでありました。
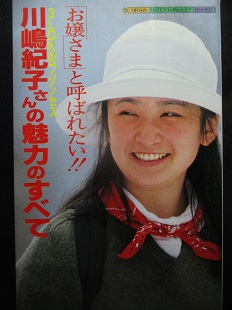
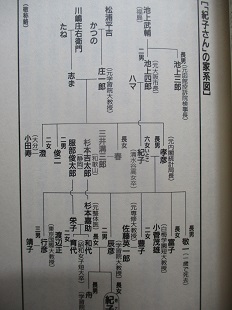
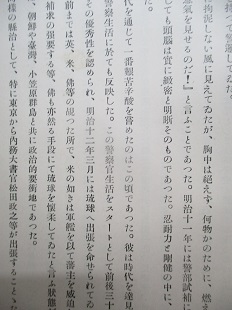
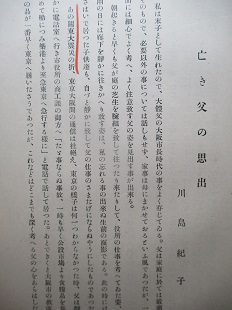
1990年6月 『川嶋紀子さんの魅力のすべて』ブレーン出版/1941年2月 『元大阪市長池上四郎君照影』元大阪市長池上四郎君彰徳會
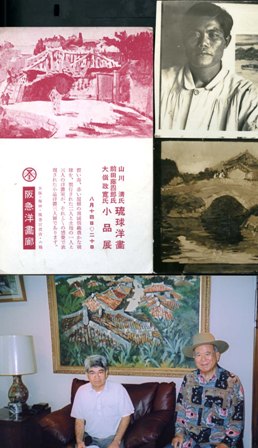
ジミー創業者の稲嶺盛保氏宅の大嶺政寛の作品、新城栄徳、稲嶺盛保氏
□2007年7月『オキナワグラフ』「私の宝ものー稲嶺盛保」
稲嶺盛保さんと翁長良明(沖縄コレクター友の会副会長)とは、長年にわたる大家と店子の関係で親しい。
□2008年2月『オキナワグラフ』「私の宝ものー翁長良明」
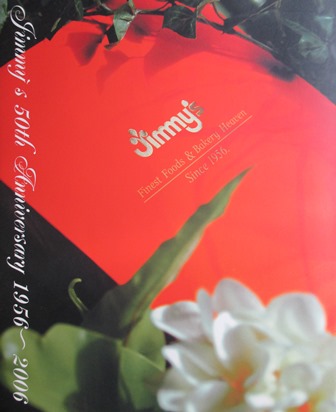
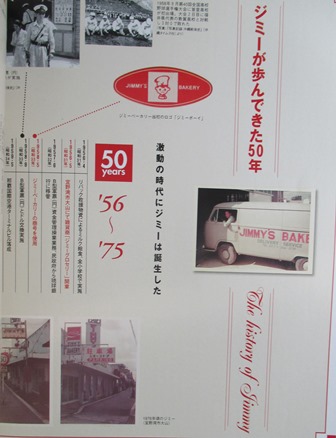
□戦後まもない1947年、沖縄の人びとも、ようやく雨露をしのげる家を持ち、ほっと一息ついていたそんな頃、創業者の稲嶺盛保は米軍基地内で働いていました。基地の外の食糧配給売店では、米・小麦粉・トウモロコシ・缶詰などが政府の統制下で売られていた時代です。それとは対照的に、基地の中では豊かな物資であふれた別世界が広がっていました。
基地内で働くうち、アメリカ人の友人も出来、稲嶺はジミーというニックネームで呼ばれるようになりました。そんなある日、基地内のベーカリーで働く友人に声をかけられ、香ばしいパンが出来上がるのを見て、基地の外でのパンづくりを思い立ったのです。それから、鍋などの道具は何でも手作りし、パン焼きに必要な機械を揃え、1956年ついに宜野湾市大山にて店舗をオープンさせました。店の名前は、ニックネーム「ジミー」より、「ジミーグロセリー」に決めました。基地からベーカリー専門の技術者を招き、おいしいパン作りを探究しながら、製品の流通・販売なども手がけていくうちに、地道なパンづくりと商いが実を結び、事業は順調に伸びていきました。
そんな矢先、沖縄復帰が決まり、基地雇用者の大量解雇や物価の高騰、ドルショックやオイルショックなどの経済変動に直面し、一時経営不振に陥ります。稲嶺は、その打開策として、スーパー、レストラン、ベーカリーの3本柱にしぼるという経営転換策を打ち出しました。そして、1976年有限会社ジミーベーカリーに組織を変更、同年12月ジミー大山店新店舗完成。日本国内だけでなく、ヨーロッパ、ハワイ等世界各国のベーカリーや流通産業を巡り、その優れた技術やシステムを導入。さらに、那覇店、室川店、ダイナハ店と確実な拠点づくりを行い、技術の習得や品質の向上など食に対する様々な研究を重ね、1984年7月には「株式会社ジミー」を設立しました。 1989年、宜野湾市大山に最新設備と規模を誇る本社・工場が完成し、常に安全で美味しい食品づくりを目指す食の総合企業として今日に至っています。→JIMMY's INFORMATION
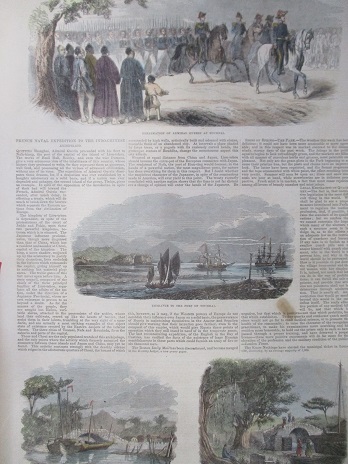
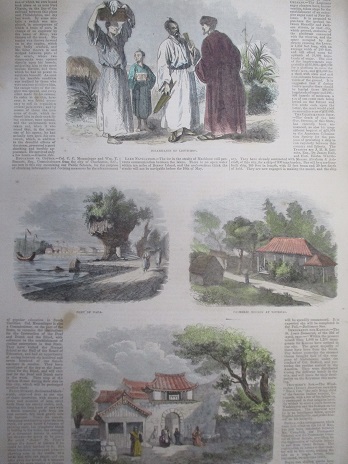
1856年 琉球を紹介した(翁長良明コレクション)『フランク・レスリー ILLUSTRATED NEWSPAPER』
1884年2月6日、大阪中之島の自由亭で尚典新婚帰郷の饗応に岩村通俊、西村捨三、建野郷三らが参加した。3月12日に大阪西区立売堀に鹿児島沖縄産糖売捌所が設立された。5月12日には大阪北区富島町で大阪商船会社が開業。8月、尚泰侯爵、西村捨三と同行し大有丸で那覇港に着く。→1996年6月『大阪春秋』堀田暁生「自由亭ホテルの創業ー大阪最初のホテルー」
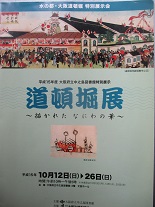
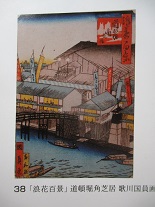
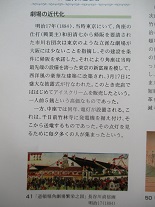
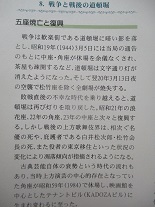
2003年10月 大阪府立中之島図書館「道頓堀展」
1889年11月ー松山傳十郎(1866年10月~1935年2月7日)『琉球浄瑠璃』いろは家→「松山傳十郎」
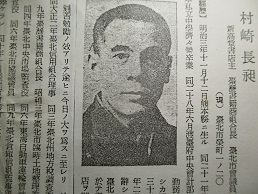

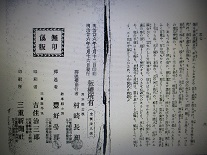
1893年7月 村崎長昶(私立済々中学卒業後沖縄に渡り、沖縄芝居に係る。1894年6月台湾総督府官吏、数年後書店を起こし台湾に永住)・豊好戞郎 『琉球踊狂言』三重新聞社→国会図書館デジタルアーカイブ
□1893年、角座の仕打澤野新七他一名の代理寺内某が来沖し、料理屋「東家」の協力を得て沖縄芝居の俳優らを雇い関西興行をなす(7月・大阪角座、8月・京都祇園座、9月・名古屋千歳座)。俳優のひとり真栄平房春は病没し大阪上町の了性寺に葬られた。1893年7月『歌舞伎新報』「琉球芝居ー沖縄県琉球には昔より音楽師と称えて一種の歌舞を演奏するもの士族の間に伝えられ居たるところ去る明治22年中いづれも俳優の鑑札を受けて我が役者の如きものとなり其の組5組もあるよしにてこのたび其の一組が大阪角の芝居へ乗り込むことに決定し既に去る2日を以って那覇港を解覧し本日ごろは遅くも到着したる手筈なるがー」
「琉球国演劇」の横断幕があるのが角座。下が角座で配られたもの
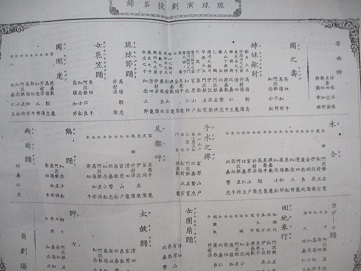
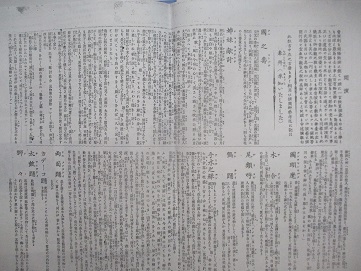
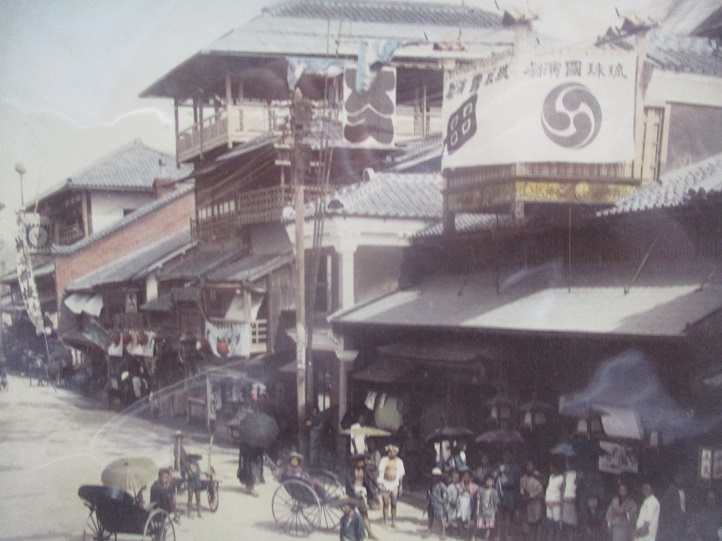
「角座」(翁長良明コレクション)
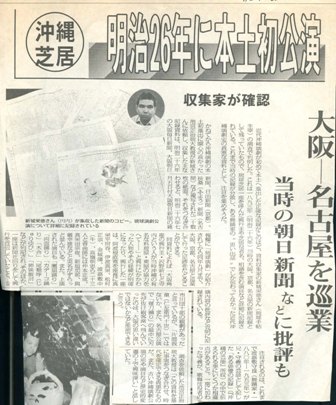

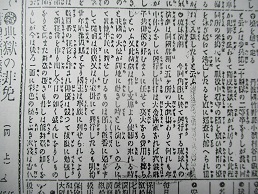
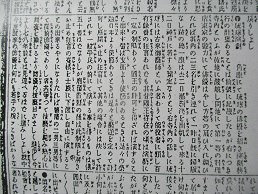
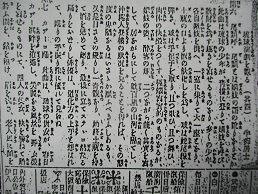
□沖縄芝居ー1893年に大阪・京都・名古屋で公演
◇1991年1月、池宮正治琉大教授と電話で大阪の新聞で沖縄関係を調べているとの話をすると、それなら芸能、特に渡嘉敷守良の芝居も心がけて見てくれと示唆された。それで見当をつけて中之島図書館で大阪朝日新聞、大阪毎日新聞を、京都府総合資料館で日出新聞、名古屋では扶桑新聞をめくると次々と沖縄芝居の記事が出てきた。国会図書館にも行き雑誌も見た。
1897年2月26日 大田朝敷、小川鋠太郎や西常央らとともに沖縄人類学会の発起人となる。
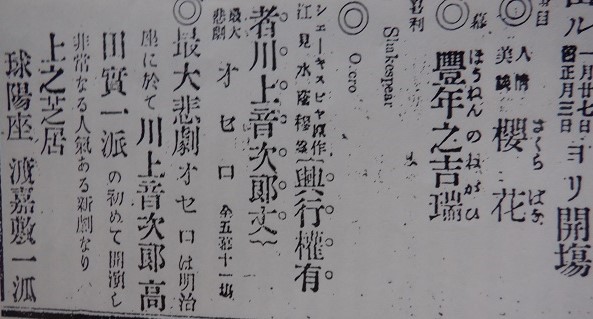
1906年1月 渡嘉敷一派「オセロ」
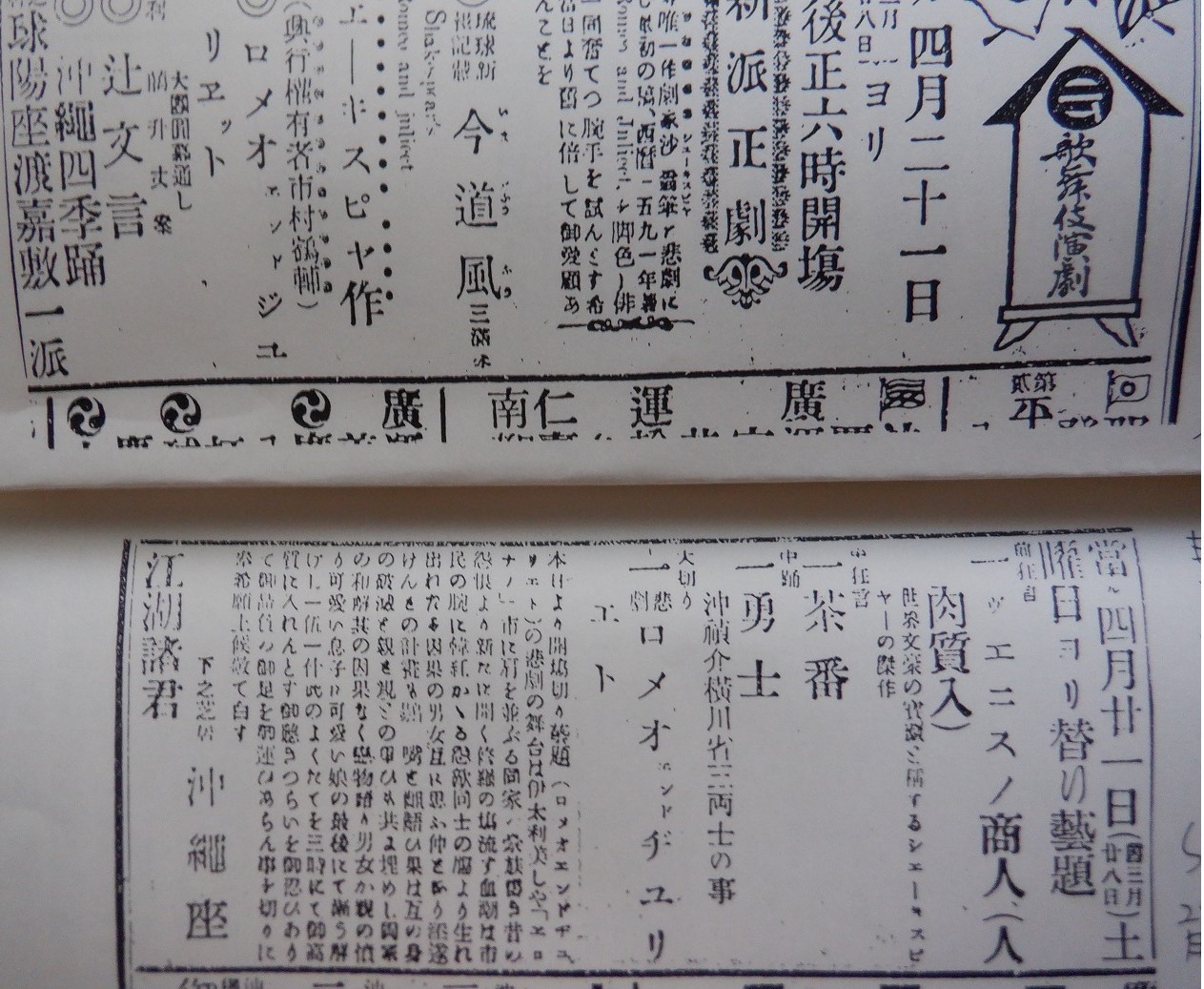
1906年4月渡嘉敷一派「ロメオエンドジュリエット」/沖縄座「ヴエニスノ商人(人肉質入)」「ロメオエンドヂユリエット
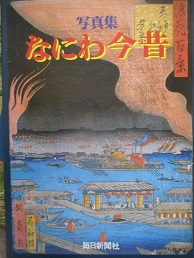

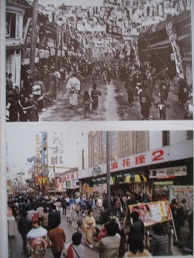
1983年7月『写真集・なにわ今昔』毎日新聞社「道頓堀」(左の写真が角座)
1894年5月 『早稲田文学』第63号 佐々木笑受郎「琉球演劇 手水の縁」
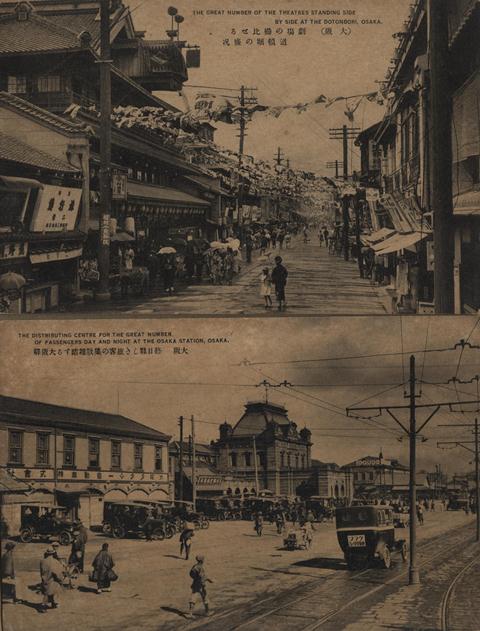
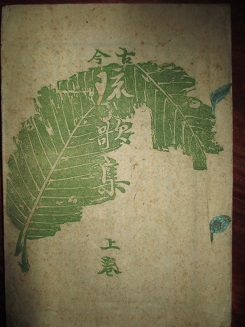
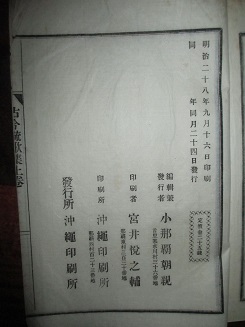
1895年9月 小那覇朝親『古今琉歌集』上卷 沖縄印刷所(宮井悦之輔)
※1907年4月 首里区字山川252小那覇朝親 腸チブスで死去
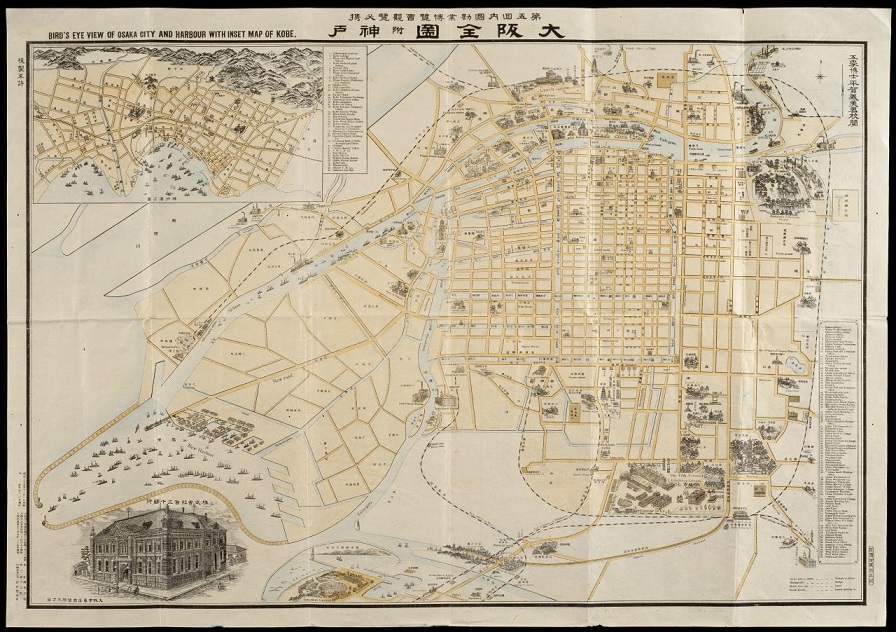
1902年12月『第五回内国勧業博覧会観覧必携 大阪全図 附神戸 博覧会場見取図附』作成者 印刷兼発行所 大阪市東区北久宝寺町 田村豊成堂
1913年4月25日~11月22日『大阪毎日新聞』菊池幽芳「百合子」
1913年10月6日ー大阪道頓堀浪花座で「百合子」劇が開演、百合子役に川上貞奴。来阪中の眞境名安規(桂月)が琉球踊りアヤグを指導。
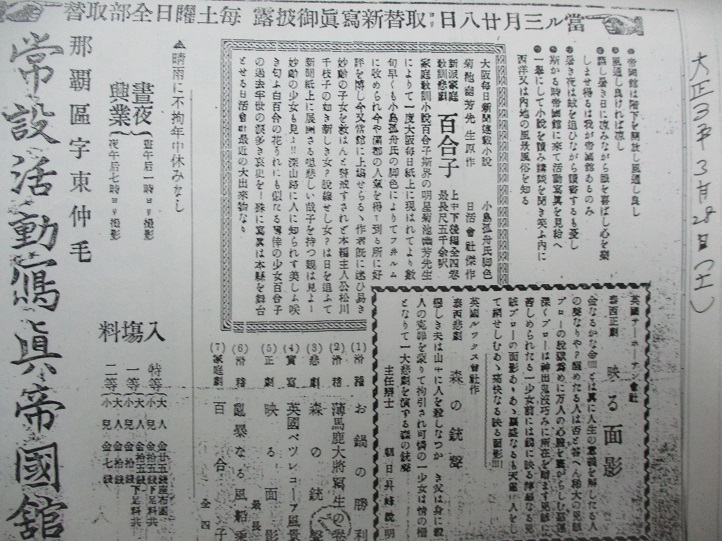
1914年3月

1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊りー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」

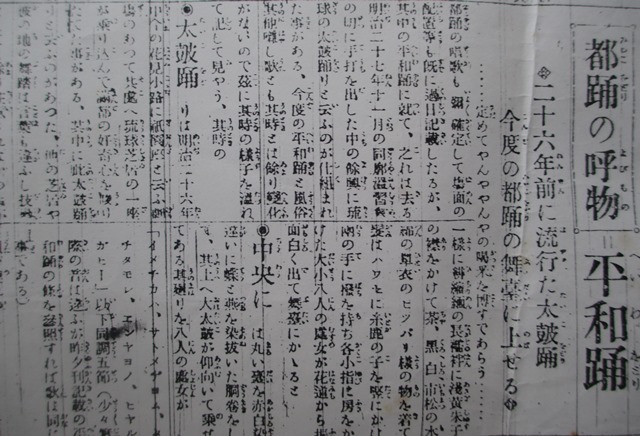

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」
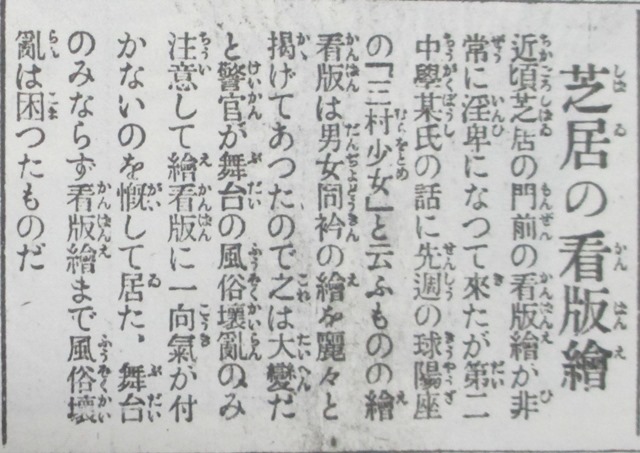
1919年9月14日ー『沖縄時事新報』
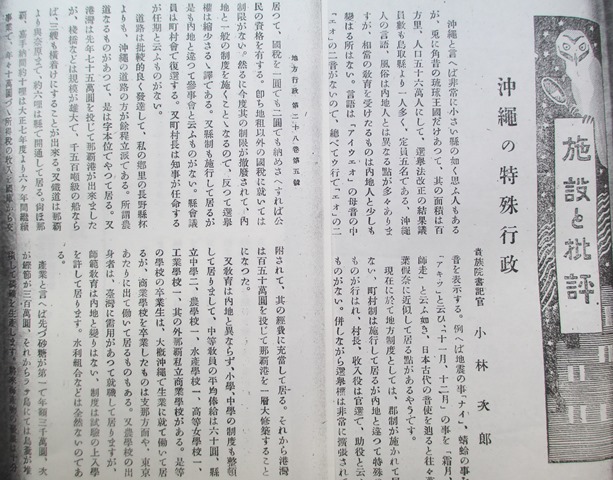
1920年5月 『地方行政』小林次郎「沖縄の特殊行政」
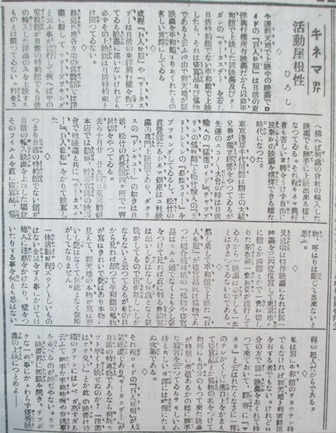
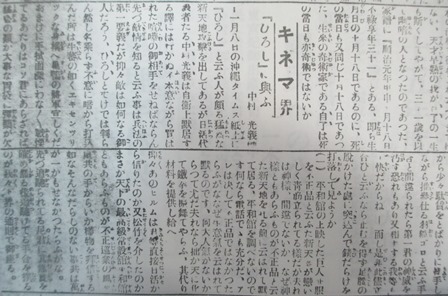
1925年11月『沖縄タイムス』
1932年
●山里永吉の戯曲「那覇四町昔気質」が琉球新報に掲載されたのは昭和7年3月で、山里はその後記で「この戯曲は多分13日から大正劇場で上演されると思うが、考えて見ると大正劇場に拙作『首里城明け渡し』が上演されたのが一昨年の今頃、ちょうど衆議院の選挙が終わった当座だったと覚えている。それから昨年の正月が『宜湾朝保の死』、今度の『那覇四町昔気質』と共に尚泰王三戯曲がここに完成した」と述べている。
1930年11月 那覇の平和館で①「百年後の世界(原名メトロポリス)」/「江戸城総攻メ」上映
①『メトロポリス』(Metropolis)は、フリッツ・ラング監督によって1926年(大正15年)製作、1927年に公開されたモノクロサイレント映画で、ヴァイマル共和政時代に製作されたドイツ映画である。
製作時から100年後のディストピア未来都市を描いたこの映画は、以降多数のSF作品に多大な影響を与え、世界初のSF映画とされる『月世界旅行』が示した「映画におけるサイエンス・フィクション」の可能性を飛躍的に向上させたSF映画黎明期の傑作とされている。SF映画に必要な要素が全てちりばめられており「SF映画の原点にして頂点」と称される。→ウィキペディア
□1985年2月 那覇の国映館で「メトロポリス」上映
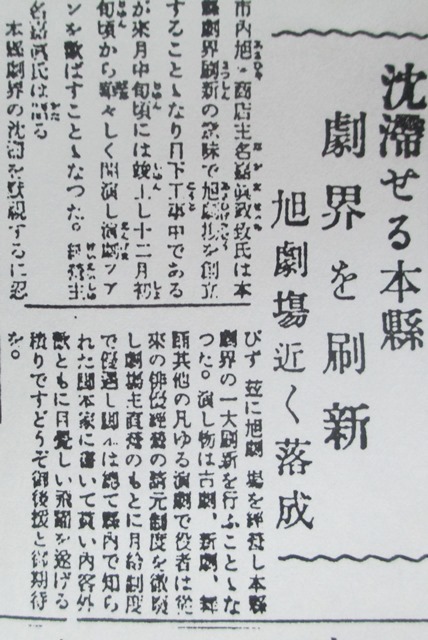
1930年11月『沖縄朝日新聞』




青年劇1935
1935年
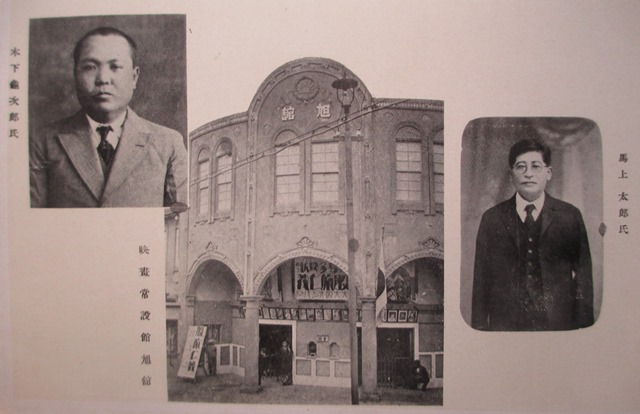
旭館
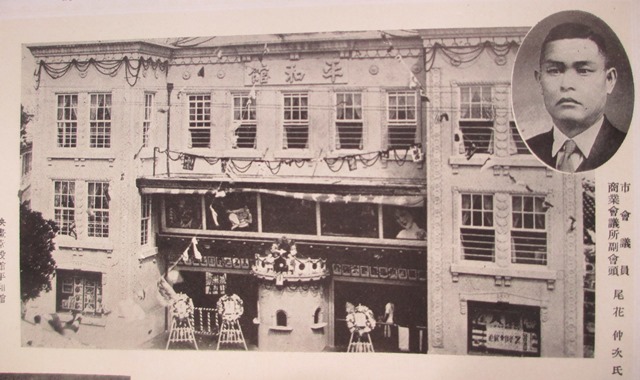
平和館
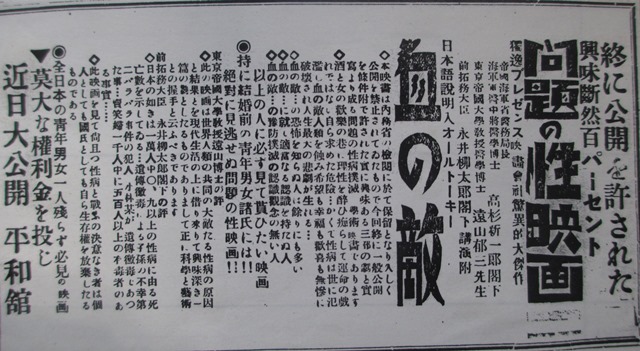
1936年11月
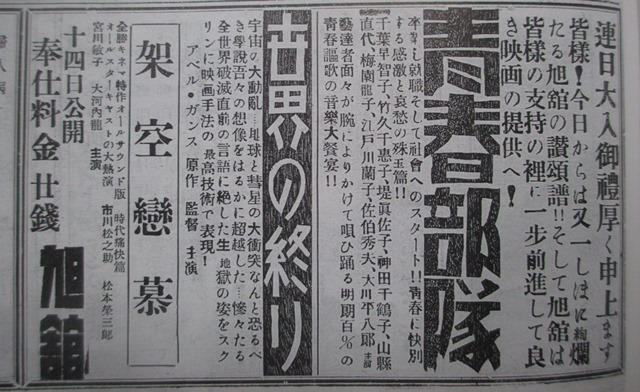
1937年6月 那覇の旭館で「世界の終り」上映
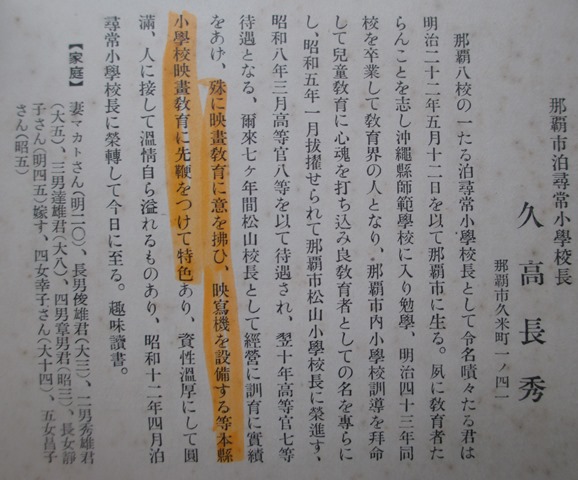
1937年9月 『沖縄県人事録』沖縄朝日新聞社「久高長秀」
1938年2月 那覇の旭館で「巨人コーレム」上映□『巨人ゴーレム』(きょじんゴーレム、Le Golem)は、1936年にチェコで制作されたモンスター・ホラー映画。→ウィキペディア
1938年3月、那覇の旭館で漫画祭、パラマウント映画「ポパイの快投手」「ポパイの動物園荒らし」上映
1938年3月 那覇の平和館で「禁男の家」上映□『禁男の家』( きんだんのいえ、原題: Club de femmes )は、1936年に製作されたフランス映画。1956年に『乙女の館』という作品で再映画化されている。→ウィキペディア

1957年 大阪道頓堀
06/08: 琉球誌③
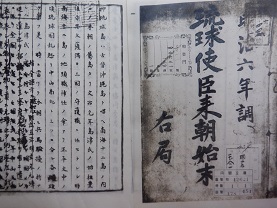
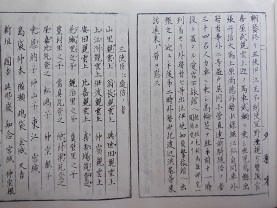
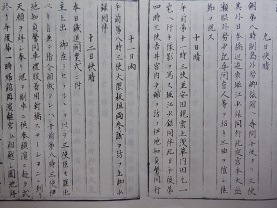


明治6年調『琉球使臣来朝始末』/1872年 三使に隋行し上京したのは山里親雲上(長賢)、翁長親雲上、與世田親雲上、上江洲親雲上、伊波親雲上、仲嶺親雲上、安田親雲上、比嘉親雲上、喜舎場筑登之、花城里之子、親泊里之子、真壁里之子、豊村里之子、當真筑登之、仲村渠筑登之、屋嘉比筑登之、松嶋子、仲宗根子、東恩納子、仲山子、東江、宮城、島袋、仲本、備瀬、嶋袋、金城、又吉、新垣、國吉、與那嶺、知念、宮城、仲宗根。
/9月10日晴 右から喜屋武朝扶親雲上(讃議官)、伊江王子朝直(正使)、宜野湾親方朝保(副使)、後列左は安田親雲上、外務省通弁の堀江弘貞少録
/9月12日快晴 本日鉄道開通式,琉装の伊江王子 ※1872年、明治5年9月、東京の新橋と神奈川県の横浜(よこはま)、およそ29キロメートルのあいだに、日本最初の鉄道が開通しました。 平均時速は32キロ。 当時、最も早い乗り物だった馬とほぼ同じスピードで、新橋と横浜をおよそ50分で結びました。
1874年7月12日 琉球藩事務、内務省管轄になる
1876年2月 内務小丞木梨精一郎内務省出張所勤務
1879年3月 木梨精一郎を県令心得に任命し、内務省出張所を仮県庁を置く
1884年 志賀重昴、札幌農学校を卒業し、県立長野中学では植物科を担当し、長野県中学校教諭も務め、また長野県師範学校講師として地理科を教えた。だが、酒席での県令・木梨精一郎(1879年3月 沖縄県令心得)とのトラブルで翌年辞職し、上京して丸善に勤めた
1887年2月、森有礼文部大臣が来沖した。6月、尚家資本の広運社が設立され球陽丸を那覇-神戸間に運航させる。11月に伊藤博文総理大臣、大山巌①陸軍大臣が軍艦で画家の山本芳翠、漢詩人の森槐南を同行して来沖した。1888年4月に大阪西区立売堀南通5丁目に琉球物産会社「丸一大阪支店」を設置する。9月18日に丸岡莞爾が沖縄県知事として赴任。10月には塙忠雄(塙保己一曾孫)が沖縄県属として赴任した。
大山柏ー父・大山巌①公爵は維新の元勲の一人で、日清・日露の両戦役では参謀総長や満州軍総司令官として国運を賭けた大勝負で日本を勝利に導き、晩年に至るまで元老の一人として国政の枢機に接した元帥陸軍大将。母・捨松は、明治初年に初の官費女子留学生の一人として11歳で渡米し、11年後に日本人女性として初めて米国大学の普通科を卒業して学士号を得た。柏はその次男。→ウイキ
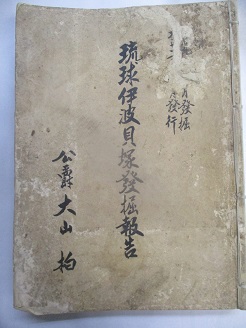
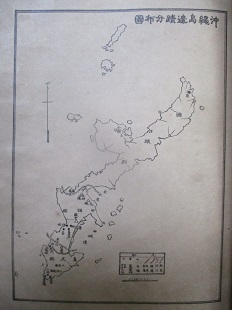
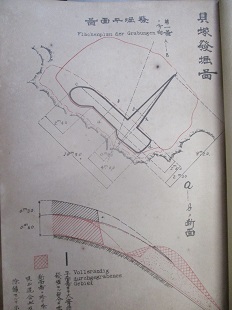
1922年9月 大山柏『琉球伊波貝塚発掘報告』→翁長良明コレクション
伊波貝塚 いはかいづかー沖縄県うるま市石川伊波にある貝塚。荻堂(おぎどう)貝塚と並ぶ沖縄先史時代(貝塚時代という)前期を代表する貝塚で、国指定史跡。1904年(明治37)鳥居龍蔵(とりいりゅうぞう)によって発見、調査され、20年(大正9)に大山柏(かしわ)の手で本格的な発掘調査が行われ、その結果は『琉球伊波貝塚発掘報告』(岸文庫所蔵)としてまとめられている。
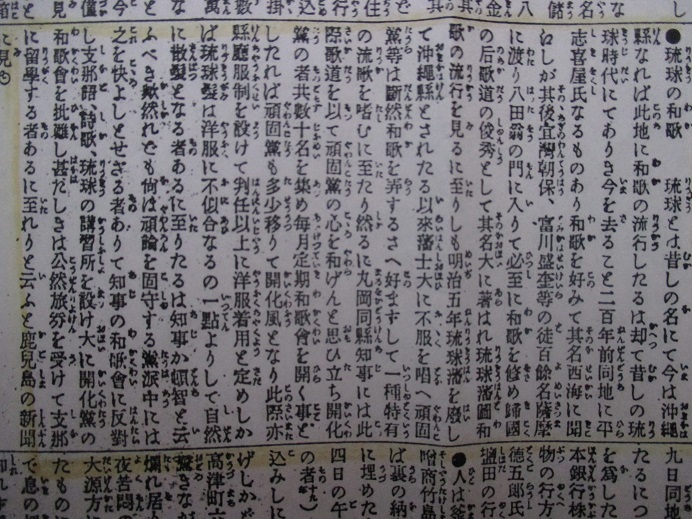
1889年12月11日『大阪朝日新聞』「琉球の和歌」
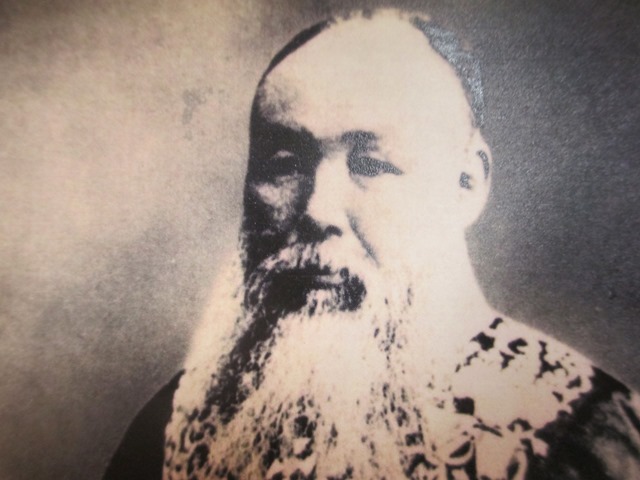
写真ー丸岡莞爾 まるおか-かんじ
1836-1898 幕末-明治時代の官僚,歌人。
天保(てんぽう)7年5月28日生まれ。鹿持雅澄(かもち-まさずみ)に国学をまなび,坂本竜馬(りょうま)らとまじわり脱藩して長崎にすむ。維新後,内務省社寺局長などをへて沖縄県知事,高知県知事となる。明治31年3月6日死去。63歳。土佐(高知県)出身。本姓は吉村。字(あざな)は山公。通称は三太,長俊。号は建山,掬月,蒼雨など。歌集に「蒼雨余滴」。(コトバンク)

斎藤 陽子(Walnut, California)2017年3月11日 · 【思い出のアルバム】高知・桂浜の海岸にたたずみ、龍馬が太平洋を眺め、海の彼方の未知なる国に行きたかった気持ちを思い、何故か50年近く前に、無我夢中でアメリカに渡った自分とがダブり、龍馬の夢見たアメリカで頑張っている私の気持ちと、海を渡りたかった龍馬を思い、アメリア生活50年間が走馬灯のように駆け巡り、海を眺めていました。なぜかこみ上げる感慨深い気持ちが一層増し、桂浜の海の碧さが心に染みました。

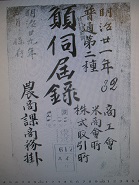

芝原佐一資料
□琉球新報創刊を報じたヤマトの新聞を見ることにする。9月15日の『東京朝日新聞』に「琉球新報の発刊-琉球新報は日刊として沖縄県那覇より本日十五日初号を発刊することとなり主任は同地名族護得久朝惟、高嶺朝教両氏(共に久しく慶応義塾に留学せし人)又東京にても岸本賀昌、今西恒太郎の両氏は同社の成立に尽力せりと」。同日に『時事新報』『郵便報知新聞』『毎日新聞』も同じように報じた。
1893年、京都で平安神宮の地鎮祭が行われ西村捨三が記念祭協賛会を代表し会員への挨拶の中で尚泰侯爵の金毘羅宮参詣時の和歌「海山の広き景色を占め置いて神の心や楽しかるらん」を紹介し、平安神宮建設に尚家から五百圓の寄附があったことも報告された。ちなみにこの時の平安神宮建築技師が伊東忠太であった。同年12月に平尾喜一が父喜三郎と母ハルエの間に生まれた。喜一は後に琉球新報社長となる。
1894年2月、那覇の南陽館で第8回九州沖縄八県連合共進会が開催された。5月、沖縄尋常中学校生徒(伊波普猷、真境名安興、渡久地政瑚ら)が下国良之助教頭の引率で関西に修学旅行。下国は20歳のとき滋賀の学校に勤めていて中井弘①の薫陶も受けているので関西には知人が多く、どこでも歓迎された。京都滞在中に学生数人は六孫王神社②を訪ねて、天保三年の江戸上りの時に正使が奉納した額を書き写している。
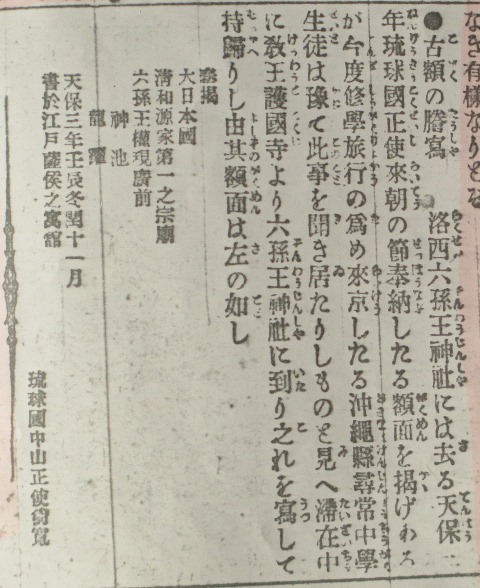
1894年5月20日『日出新聞』

②六孫王神社


大城弘明氏撮影
1870年□名妓小三-鳥取藩士松田道之と祇園下河原の大和屋お里との間に、ぎん(鈴木小三)が生まれる。

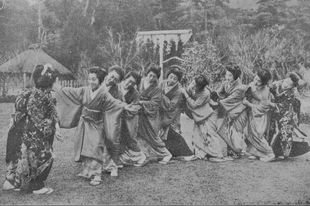
写真ー名妓小三
1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。
1875年9月、日本国郵便蒸気汽船会社解散にともない明治政府は大有丸を琉球藩に下付。11月、郵便汽船三菱会社が琉球航路を開始した。
1876年8月27日の『朝野新聞』に「沖縄は他県からの商人50人、陸軍省派遣の職工138人、女性1人」と報じられた。同年、琉球正史『球陽』の書き継ぎが終わっている。
1879年3月、松田道之琉球処分官が、後藤敬臣ら内務官僚42人、警部巡査160人余(中に天王寺公園に銅像がある後の大阪市長・池上四郎も居た)、熊本鎮台分遣隊400人をともない来琉し琉球藩を解体、沖縄県を設置した。この時、内務省で琉球処分事務を担当したのが西村捨三であった。西村は 近藤勇について「背高く色黒く中肉にて痘痕あり。中々落ち着き払いたる天晴の武士なりき」と述べている。
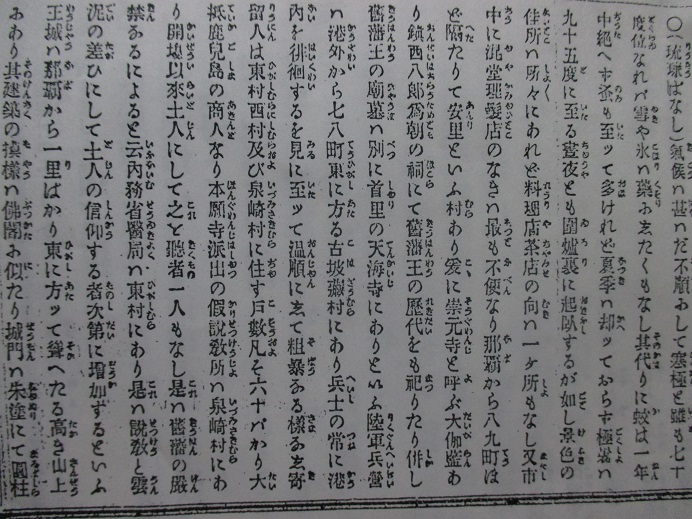
1879年5月4日 京都『西京新聞』「琉球ばなし」
1879-5-27 藩王尚泰、東海丸で東京向け那覇港出帆(6-4神戸で2泊)
1880年6月に、郵便汽船三菱会社の貫効丸が琉球、鹿児島・大島、神戸間を運航をはじめた。翌1881年3月に東京上野で開催の第二回内国勧業博覧会に沖縄からも織物、陶器、漆器が出品された。
1881年5月18日に上杉茂憲が沖縄県令として赴任してきた。7月の大阪『朝日新聞』に「沖縄県泡盛酒」の広告が載った。翌1882年の『朝日新聞』の3月「首里城が陸軍省所轄永世保存城と定まる」の記事、6月には「琉球カスリ-西平筑登之」の広告も載った。
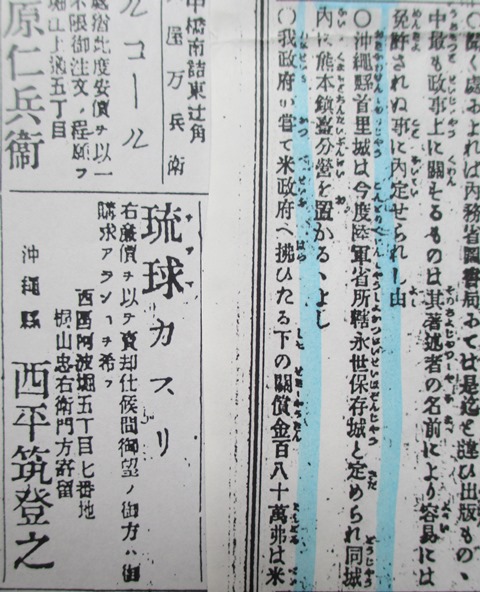
1882年11月16日、第1回沖縄県費留学生の大田朝敷、謝花昇、岸本賀昌、高嶺朝教、今帰仁朝蕃が那覇港から平安丸で上京、29日には神戸に寄っている。
1883年4月に岩村通俊が沖縄県令として赴任した。12月には西村捨三が沖縄県令となる。
1884年2月6日、大阪中之島の自由亭で尚典新婚帰郷の饗応に岩村通俊、西村捨三、建野郷三らが参加した。3月12日に大阪西区立売堀に鹿児島沖縄産糖売捌所が設立された。5月12日には大阪北区富島町で大阪商船会社が開業。8月、尚泰侯爵、西村捨三と同行し大有丸で那覇港に着く。→1996年6月『大阪春秋』堀田暁生「自由亭ホテルの創業ー大阪最初のホテルー」
1884年6月 岡倉覚三,古社寺調査で法隆寺を開扉、秘仏救世観音を拝す
1884年 志賀重昴、札幌農学校を卒業し、県立長野中学では植物科を担当し、長野県中学校教諭も務め、また長野県師範学校講師として地理科を教えた。だが、酒席での県令・木梨精一郎(1879年3月 沖縄県令心得)とのトラブルで翌年辞職し、上京して丸善に勤めた
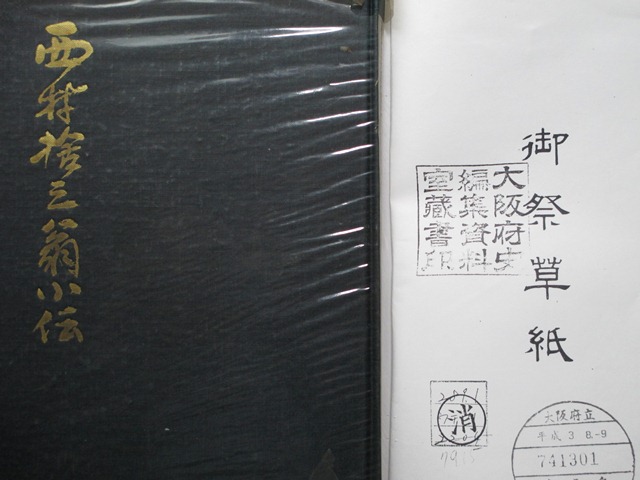
①ことひら‐ぐう 【金刀比羅宮】
香川県仲多度(なかたど)郡琴平(ことひら)町にある神社。祭神は大物主神を主神とし、崇徳天皇を配祀(はいし)。海上安全の守護神として信仰される。明治初頭までは神仏習合で、象頭山(ぞうずさん)金毘羅(こんぴら)大権現と称した。琴平神社。こんぴらさん。→コトバンク
〇2020-6-12 「ダイヤモンドSCOOP」「こんぴらさん」の呼び名と参道の785段(奥社まで1368段)もの石段で有名な、香川県の金刀比羅宮が、全国8万社の神社を包括する宗教法人、神社本庁の傘下からの離脱を決めたことが12日、ダイヤモンド編集部の取材で分かった。背景には、不祥事や疑惑が続出する神社本庁への反発がある。

写真ー尚泰
06/14: 大城精徳と『琉球の文化』②

1979年3月 『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳

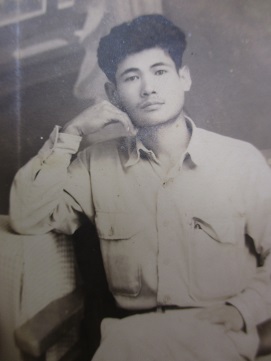
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて
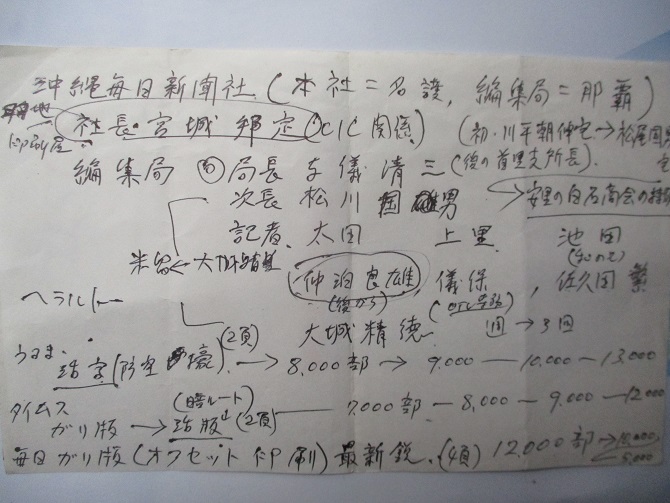
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
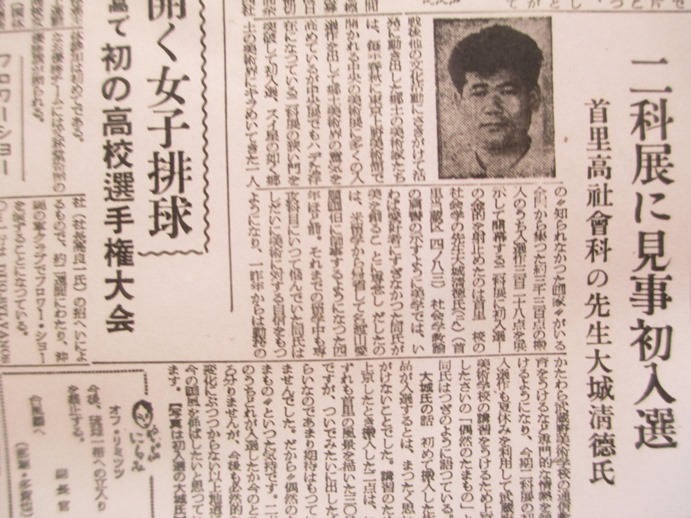
1956年9月1日『琉球新報』

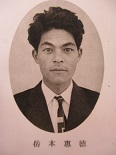
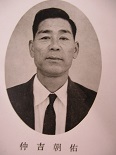
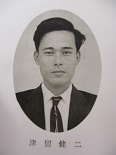
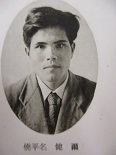
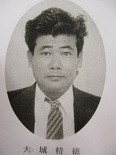
首里高等学校同僚
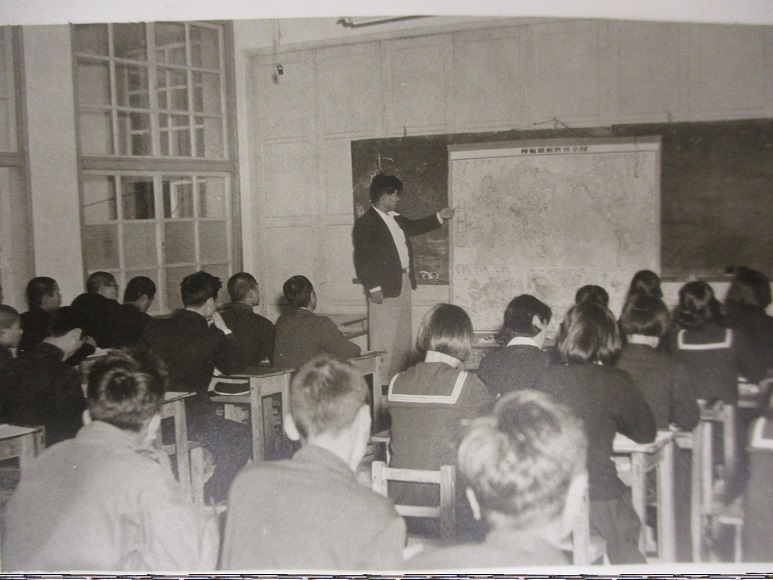
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
2019年10月 『浦添健 作品集』↓

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
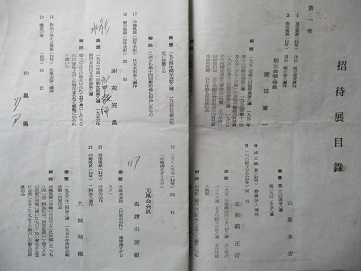
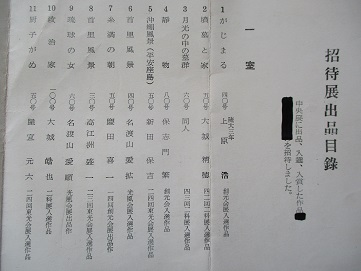
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
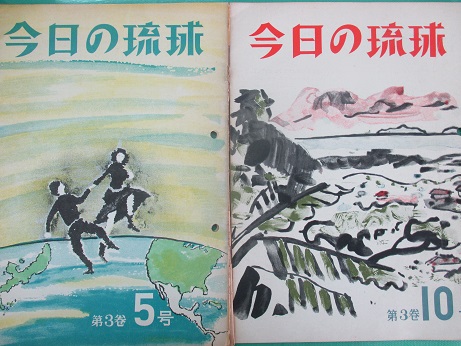
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

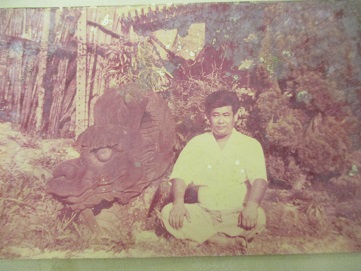
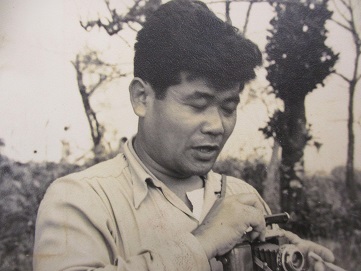

1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室
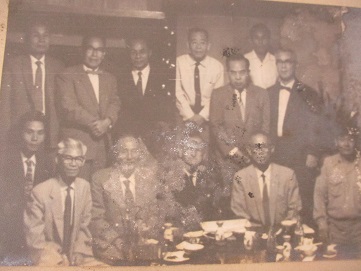

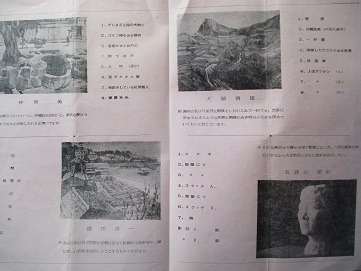
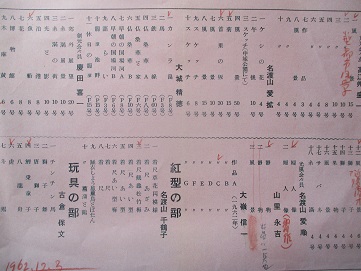
第1回 美緑会展 /1962年12月 「琉球美術展」琉米文化会館

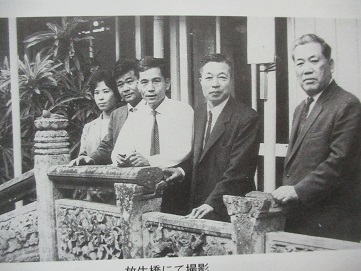
前列左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳
1996年 『沖縄県立博物館50年史』〇大城精徳・主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年

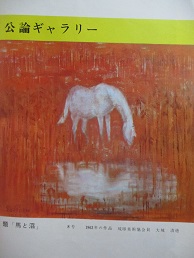
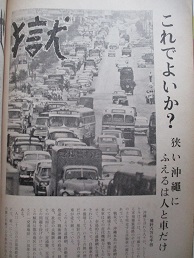
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
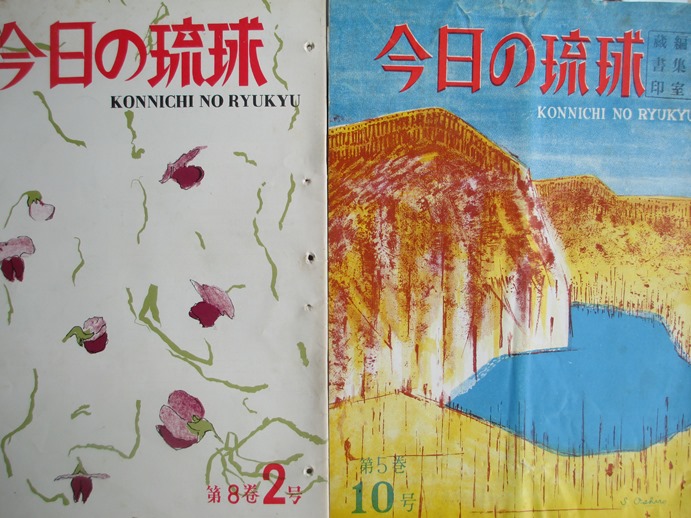
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
○ワシントン市のスミソニアン博物館(The Smithsonian lnstitution)-ここの巡回展示部の主催で、先年、琉球の古文化財がおよそ全米に紹介されたり、また最近では文化人類学室のアジア・ホールに沖縄関係資料陳列ケース(紅型、織物および玩具数点)を新たに加えるなど、沖縄とも関係の深い機関である。筆者はここで4週間の視察研修を受けたが、毎日が驚きの連続であった。(略)スミソニアンは国立になっているが、連邦政府のどの省にも属さず、大統領、副大統領、大審院首席判事、それに大統領の閣僚を会員とする特別な機関である。その運営の最高機関はスミソニアン理事会で、これには副大統領、大審院首席判事、上下両院の議員各々3名、そして国会から任命された一般市民6名の計14名からなっている。一般市民6名のうち、2人は首都ワシントン居住者で、他の4名は各々違った州から任命され同州から2名任命することはできない。アメリカの博物館は公共私立を問わず、ほとんどがこの理事会制度をもって運営されている。
○公立の博物館ー代表的なものとして、筆者が訪ねた中ではミルウォーキー公立博物館とオークランド公立博物館がある。ミルウォーキー公立博物館は自然史博物館の性格に、その地方の歴史資料を加えたもので、ここも総工費6百万ドルを投じて1963年4月に新館が落成したばかりである。陳列場以外は殆ど旧館からの移動も終わり、活気に溢れていたが、陳列場の移動は3割程度で、年次計画で1971年までかかるとのことであった。(略)博物館に対する寄付は多くの場合「博物館の友」を通じてなされ、また、この種の寄付に対しては、学校や教会に対するそれと同じように、年間所得の30パーセントまでは免税されるという特典があたえられていた。このような免税制度は、もてる国アメリカよりも、むしろ沖縄のようなところで、絶対に施されるべき性質のものではないかと考えられた。
カリフォルニア州のオークランド市では、現在歴史博物館と自然科学博物館、それに2カ所に分設された美術館があるが、これらを1カ所にまとめようとやはり6百万ドルの建築費を投じて新館を建設中であった。館長の説明によると、完成のあかつきには博物館活動のみでなく、オークランド市のあらゆる文化活動の中心になる一大文化センターになるということだった。オークランド市はオークランド湾をはさんで、サンフランシスコと向かい合っている人口約40万の都市である。建設の過渡期にある那覇市としては、これまで文化事業面に力を入れる余裕がなかったと思われるが、そろそろ文化面に市政を反映させてもいいころではなかろうか。
私立のボストン美術館は、中国、日本、インド、メソポタミア、エジプト、ギリシャ、ローマ、ヨーロッパ諸国およびアメリカの美術工芸品をアメリカで最も多く所蔵している世界屈指の美術館の一つである。今少し具体的にいうと、同美術館の東洋部(岡倉天心と最もゆかりが深い)の収蔵品数が約40万点でアメリカで最大、西洋画部は、12世紀のフレスコ画、14,15,16世紀のパネル画、そして17世紀から今日に至るキャンバス画、総計約2千点、そのうちの印象派の作品数がアメリカで最大、たとえば印象派の巨匠モネーの作品が陳列されているだけでも60余点に及んでいた。(略)同美術館についてどうしても言及しなければならないものに、教育普及活動がある。特に同博物館は、教育活動の先駆者といわれるだけあって、大変な力の入れようであった。
■関連・1997年7月 電通総研『情報ビッグバン・日本の挑戦ー「日本と日本人の未来を描く」フォーラムからの提言』○文化だけが社会づくりの求心力であるとすれば、社会は過去に引きずられてしまいます。社会を新しい変化の側に引き寄せていく求心力は、来るべき社会へのイメージの共有と、次なる変化への合意形成の中から生まれます。/情報ネットワーク社会が、インターネットや携帯電話、多チャンネル放送などによって、その姿を現すにつれ、日本でも海外でも、負の側面が観察され指摘されるようになりました。そのひとつが、社会から孤立した「孤人化」「オタク化」の現象。個人情報がハッカーなどの手によって漏れ、匿名で悪意に満ちたウワサを流し、マネーカード暗証番号の流用などのリスクの問題も出てきた。
スミソニアン博物館ー1848年、イギリス人の科学者ジェームズ・スミソンが「知識の向上と普及に」と委託した遺産を基金としてにつくられた。スミソニアン協会が運営する19の博物館並びに研究センターの施設群であり、多くはワシントンD.C.の中心部にあるナショナル・モールに設けられているが、ニューヨーク市、バージニア州、アリゾナ州、メリーランド州や海外(パナマのスミソニアン熱帯研究所(英語版))に置かれたものも含まれる。収集物は1億4200万点にも及ぶ。
運営資金はアメリカ合衆国連邦政府の財源及び寄付、寄贈、ミュージアムショップ、出版物からの利益で賄われているため、入場料は無料である。
世界各国の本物の航空機を展示している国立航空宇宙博物館は特に有名で、月の石の展示や、広島の原爆展を企画したことでも知られている(後者は実際には展示できなかった)。他に、国立アメリカ歴史博物館、産業・技術史の博物館や国立アメリカ・インディアン博物館などもある。それら9つの博物館とナショナル・ギャラリー(国立美術館。スミソニアン協会とは別)は、国会議事堂前に展開する広い道路「ナショナル・モール」の両脇に配置され、一帯は広大な博物館地域となっている。国立動物園等はワシントンD.C.の他地域に、クーパー・ヒューイット国立デザイン博物館、国立アメリカ・インディアン博物館が管轄するジョージ・グスタフ・ヘイ・センターはニューヨーク市にある。これに類する博物館群は他の国ではほとんど例をみず、ドイツのベルリン美術館も複数の美術館、博物館群だが規模が比較の対象にならない。→ウィキ
カリフォルニア・オークランド博物館(OMCA)ーカリフォルニアの過去・現在・未来を称え、そのハイライトを紹介する心躍るようなギャラリーを備え、参加型のアクティビティ、教育プログラム、コミュニティイベントを行っているこの博物館は、オークランドのレイクメリットに近い中心的な文化施設です。1969年に設立された「人々のための博物館」であるOMCAは、芸術、歴史、自然科学のコレクションが、美しいテラス付きの庭園に囲まれた建物に集結しています。
ミルウォーキーへようこそ!
シカゴから北へ90マイル(145キロ)、五大湖で2番目に大きな美しいミシガン湖のほとりにたたずむミルウォーキー。街並みを楽しく散策できるフレンドリーでクリーンなミルウォーキーには、アメリカ中西部の魅力がぎっしりと詰まっています。印象的な建築物、さまざまなタイプのホテル、全米屈指のレストラン、美しいリバーウォークへと繋がる活気あふれる街角、そして夏中繰り広げられるフェスティバルなど、ミルウォーキーは、気軽にアクセスできるユニークなアトラクションの宝庫です。
ミルウォーキー公立博物館では、コスタリカの熱帯雨林の展示と、一年中蝶々が舞うバタフライガーデンを探訪してください。世界最大の恐竜の頭蓋骨や、神秘的なエジプトのミイラも注目です。「古きミルウォーキーのストリート(Streets of Old Milwaukee)」をそぞろ歩けば、ガスランプに照らされた石畳の舗道にタイムスリップ。伝統を感じさせるお店や住宅などを目にすることができます。
ボストン美術館は、1870年に地元の有志によって設立され、アメリカ独立百周年にあたる1876年に開館した。王室コレクションや大富豪のコレクションが元になった美術館と異なり、ゼロからスタートし、民間の組織として運営されてきた点は、ニューヨークのメトロポリタン美術館と類似している。所蔵品は50万点を数え、「古代」、「ヨーロッパ」、「アジア、オセアニア、アフリカ」、「アメリカ」、「現代」、「版画、素描、写真」、「染織、衣装」および「楽器」の8部門に分かれる。エジプト美術、フランス印象派絵画などが特に充実している。2010年には北中南米の芸術を展示するアメリカウィングが増築され、28%の増床となった。ボストン美術館は、仏画、絵巻物、浮世絵、刀剣など日本美術の優品を多数所蔵し、日本との関係が深いことでも知られる。20世紀の初めには、岡倉天心が在職しており、敷地内には彼の名を冠した小さな日本庭園「天心園」が設けられている。→ウィキ
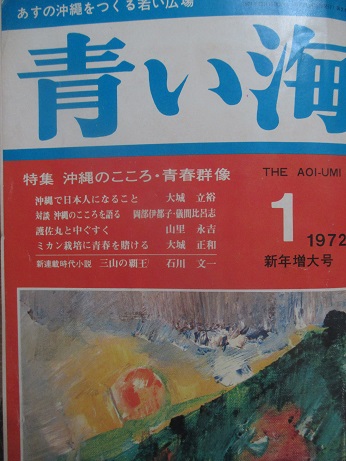
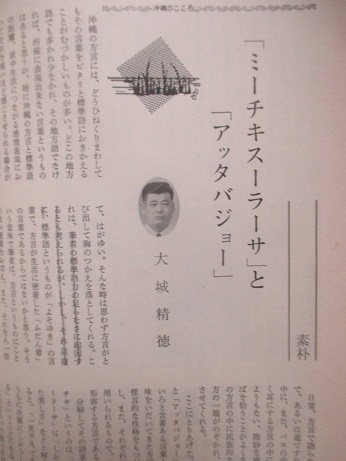
1972年1月 沖縄の雑誌『青い海』9号 大城精徳「ミーチキスーラーサー」と「アッタバジョー」
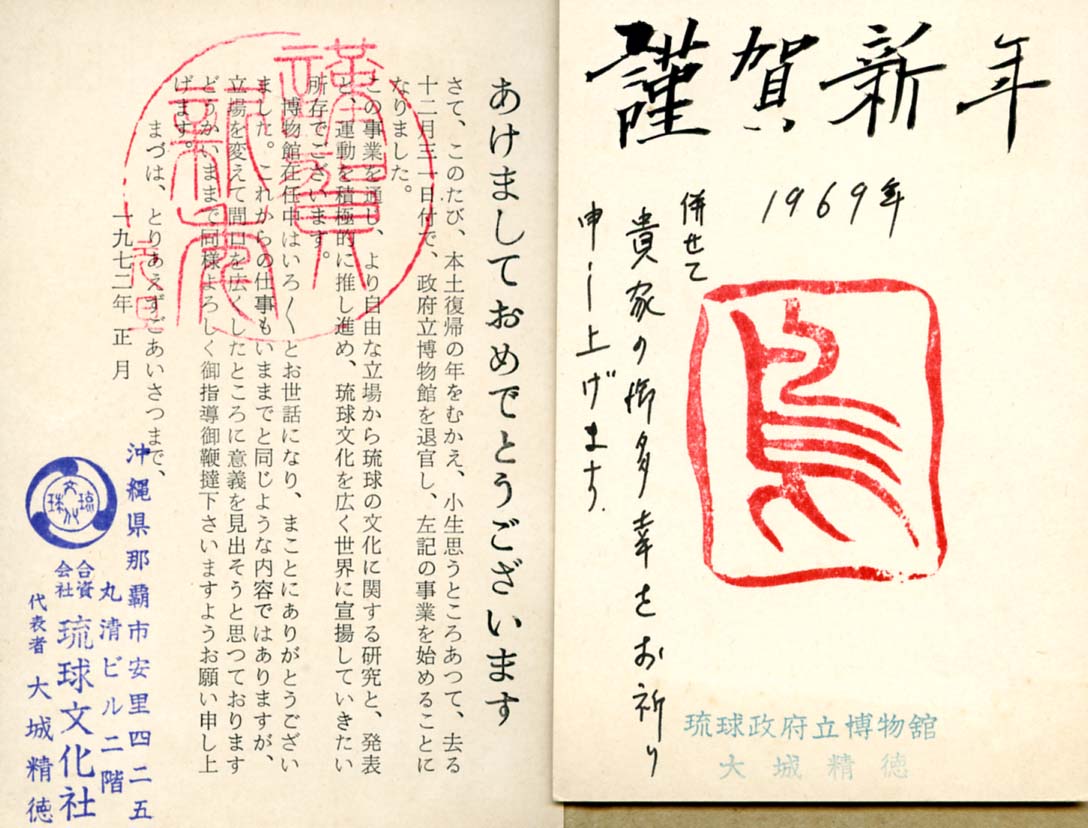
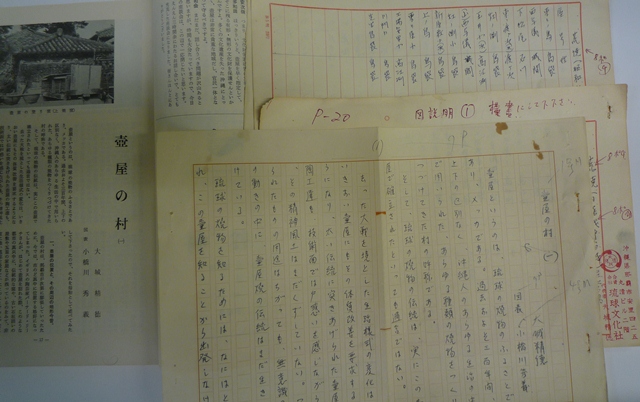
1972年3月 『琉球の文化』創刊号<特集・琉球の焼物>琉球文化社
□大城精徳/小橋川秀義・図表「壷屋の村(1)」(原稿・翁長良明コレクション)
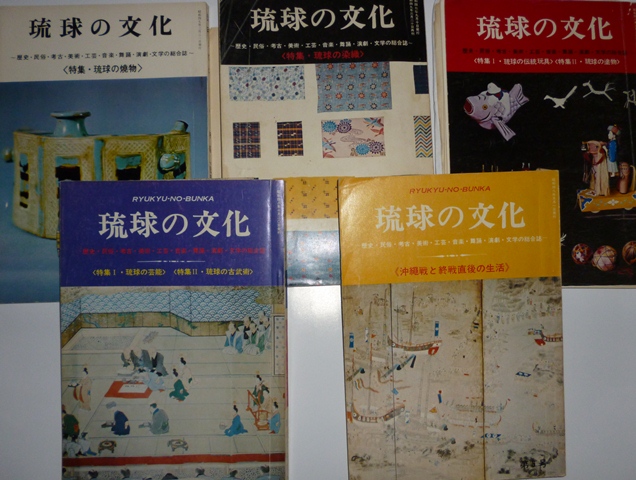
『琉球の文化』1号~5号
ネットで『琉球の文化』を検索すると読谷村立図書館蔵書で出てきた。『琉球の文化』は大城精徳元沖縄県立博物館副館長が1972年3月に創刊した。創刊号の特集は<琉球の焼物>、72年9月・第二号は<琉球の染織>、73年3月・第三号は<琉球の伝統玩具・琉球の塗物>、73年10月・第四号は<琉球の芸能・琉球の古武術>、74年5月・第五号は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。私と発行人の大城精徳琉球文化社社長とは、72年に又吉眞三氏の建築設計事務所に大阪の西平守晴沖縄関係資料室主宰と同行し訪ねた折、そこに大城精徳氏が出来たばかりの『琉球の文化』創刊号を持参したときに出会った。
翌日、安里の琉球文化社事務所を訪ねると意気投合し琉球文化社関西支局を引き受けることになった。このときは私はまだ筆不精で文章を書いたことがない。結局、『琉球の文化』には書く機会がないまま休刊を迎えた。その後、大城精徳も関わっていた『新生美術』には美術史らしきものを書くようになった。今、東京発の「沖縄文化論」がテレビ・雑誌などを通じて沖縄に侵蝕。それらが今、沖縄の新聞紙上を占めている。そういうことを予見し危機感を持っていた大城精徳は「日本人としての誇りを得るために、沖縄人としての誇りを捨ててはいけない」とし日本復帰前に『琉球の文化』を創刊した。その初心に立ちかえりネット上で『琉球の文化』活動を復活し新たに補足・改訂を加え立体的に「琉球の文化」を捉えなおしてみたい。(2010-7-8-15時記)
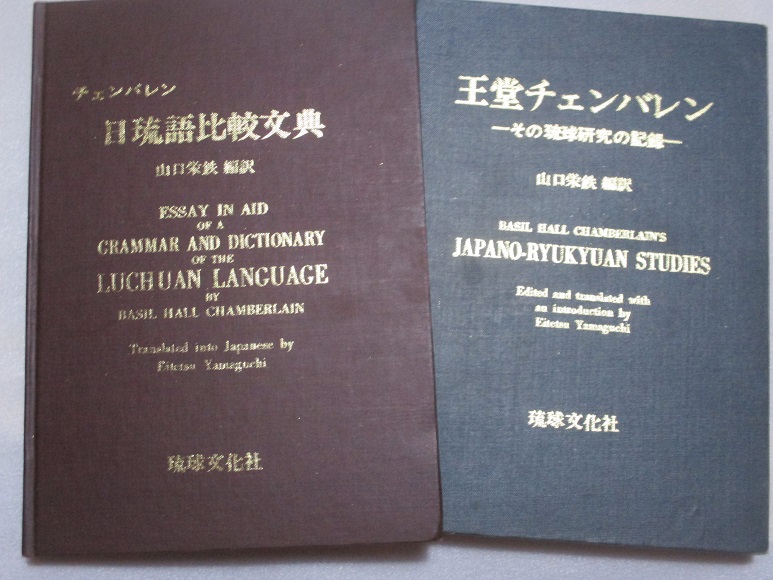
1976年3月 山口栄鉄『チェンバレン 日琉語比較文典』琉球文化社/1976年5月 山口栄鉄『王堂チェンバレンーその琉球研究の記録ー』琉球文化社
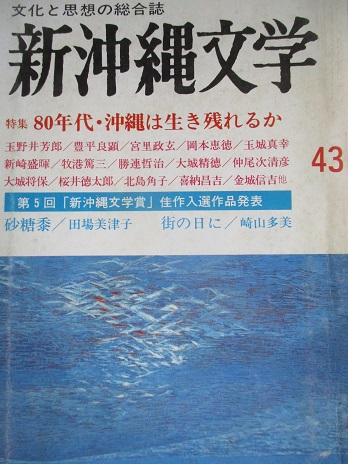
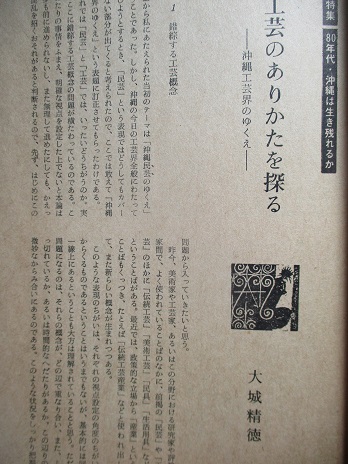
1979年11月『新沖縄文学』43号 大城精徳「工芸のありかたを探るー沖縄工芸界のゆくえ」
12/20: 世相ジャパン⑭/2019-12

2019年12月16日『しんぶん赤旗』「」沖縄県中部・読谷村にある『恨之碑』の前に立つ製作者の金城実さん

2019年12月25日「古美術なるみ堂」にてー「房指輪」「ジーファー」を見る店主の翁長良明氏、哲楽家・紀々さん→紀々の公式サイト「首里城が出来た時の龍のモチーフを見て生まれた『龍神伝説』という曲」。→ 電波堂☆沖縄ソニー坊や博物館




2019-12-23 沖縄県立博物館・美術館「作家と現在」内覧会 本展では、沖縄県の内外で広く活動し、さらなる活躍が期待されている沖縄の4名のアーティスト石川竜一、伊波リンダ、根間智子、ミヤギフトシを紹介。作家はそれぞれの現場で制作に取り組み、いまなお探求を続けています。その探求の足跡を、展覧会を通してたどります。/町田恵美さん、仲嶺絵里奈さん、金城美奈子さん/新城栄徳、写真家タイラジュン
12-22 生協にある花屋で生まれてはじめてポインセチアを買う。700円消費税70円


『沖縄タイムス』2019年11月29日ー首里城再建に役立ててもらおうと、舞台美術家の新城喜一さん(86)=那覇市=が記憶や写真を頼りに戦前戦後の沖縄を描いた画集「失われた沖縄の風景」シリーズをジュンク堂書店那覇店など県内の書店で再販売し、全収益を寄付する。戦前の首里城の姿も知る新城さんは「沖縄の宝を早く取り戻してほしい」と願う。

パレットくもじー沖縄県那覇市久茂地にある複合商業施設。管理運営会社は久茂地都市開発株式会社。 核店舗はリウボウグループの百貨店事業を行う株式会社リウボウインダストリーである。→ウィキ/哲楽家・紀々ー「ラララ♪りうぼう」は、特に子どもたちに大人気!私が作者だということを聞くと、その場で元気よくうたってくれる姿も多く、感激です。一緒にコラボの機会も出てきて…今後の広がりにワクワク。みなさんも、どうぞ楽しくご一緒下さい♪


戸澤 裕司12-10 今日は山田淳巳さんの参加するグループ展にお邪魔しました。大変美味しい八重山料理を堪能し、素晴らしい写真と共によい夜を過ごせました。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。
「祈りの海 願いの祭 写真展」【 豊里友行・山田淳巳・Juncot∞ 】【場所】てるりん館 東京(八重山そば みやら製麺 2F)東京都台東区上野1-2-8【日時】2019年12月7日(土)〜8日(日)・14日(土)〜15日(日)、12:00〜19:00・入場無料 開催期間中、1F みやら製麺は、土曜日11:30〜15:00・18:00〜22:00、日曜日11:30〜19:00 営業。美味しい自家製麺の八重山そばを食べに行きがてら、お気軽にお越しください。展示作品の販売も行います。


2019年12月8日 那覇市民ギャラリー「第8回あけもどろ総合文化祭 美術工芸展」/岸本作品「蒼然」をはさんで岸本徹也氏、宮里旭氏


宮里旭氏と作品「盛夏の識名園」
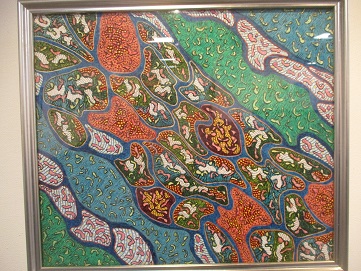
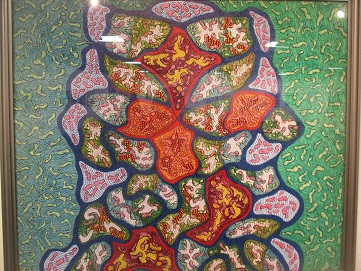
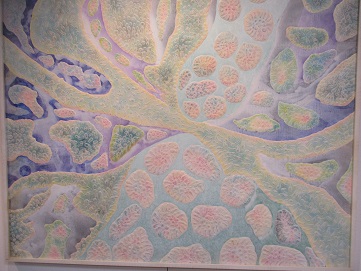

小橋川肇 作品、下は関連
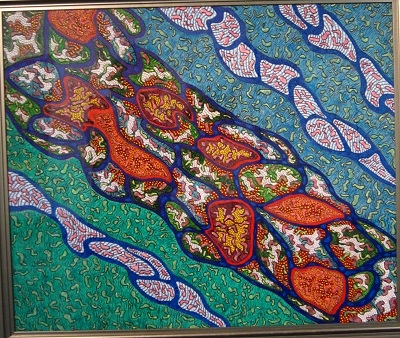
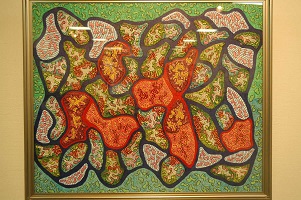


フリーペーパー「夕焼けアパート」の写真展が12月3~8日、那覇市の県立博物館・美術館県民ギャラリー3で開催される。同誌で文章と写真を担当する、たまきまさみさん(国立劇場おきなわ企画制作課)が撮影した地域の祭祀(さいし)やなくなってしまった風景の写真など誌面未掲載のものを中心に56点展示する予定だ。→『沖縄タイムス』
海鳴りの島から2019-11-28 ランプウェイ台船は3隻が土砂を満載していた。1隻にガット船2隻分、10トンダンプカーで300台分ほどの土砂が積み込まれている。2隻なら600台分だ。これが毎日キャンプ・シュワブのゲートから入るのを想像してほしい。海から運ばれているから目立たないだけで、毎日大量の土砂が運ばれ、海に投入されているのだ。
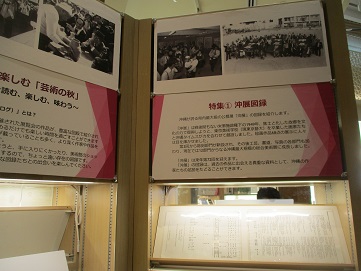
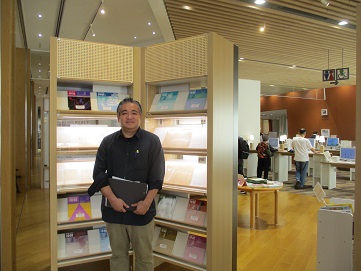
2019年11月27日 沖縄県立図書館「特集①沖展図録」沖縄タイムス社の吉田伸氏

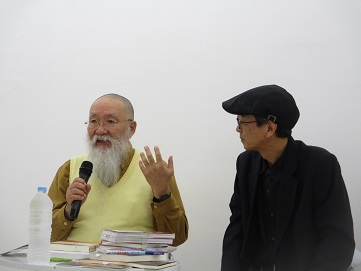
2019年11月22日19時~ジュンク堂書店 那覇店【イベント情報】首里城復興支援チャリティートークイベント「首里城から琉球の歴史を学ぶ」 会場:ジュンク堂書店那覇店B1Fイベント会場 トーク出演:古塚達朗さん(郷土史家・元那覇市歴史博物館館長)聞き手:宮城一春さん(編集者・沖縄出版協会)
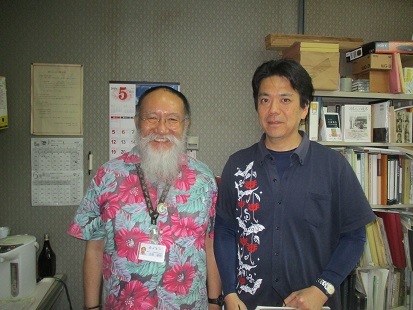
古塚達朗氏と外間政明氏
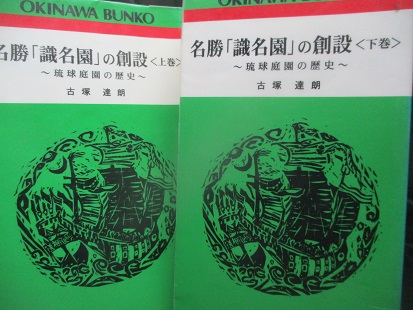


2000年5月 古塚達朗『名勝「識名園」創設~琉球庭園の歴史~』ひるぎ社
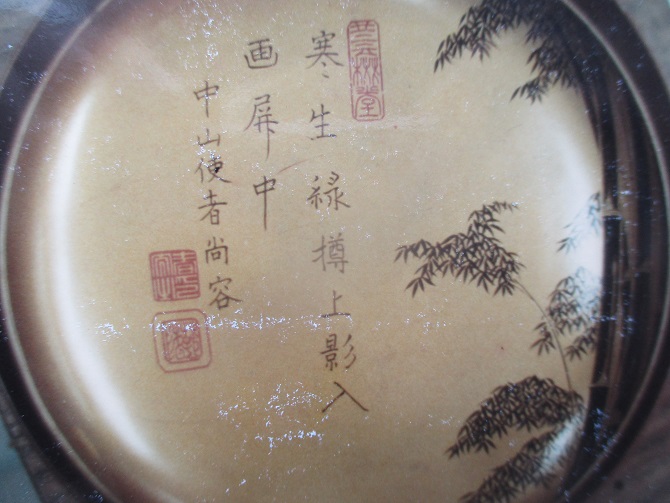
尚容(1765~1827)尚穆4男 宜野湾王子朝陽(小禄家の祖)



2016-3-5「ブラタモリ 那覇は二つある!?」那覇を案内する那覇市歴史博物館 館長の古塚達朗さん。

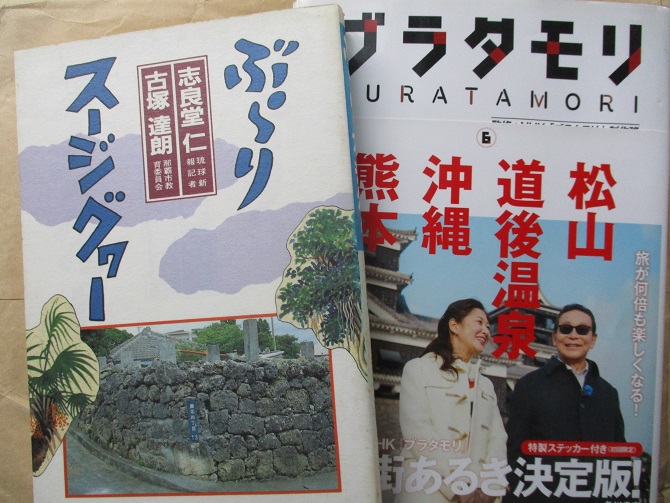
01/13: 「沖縄のシンボル 守礼門」


二千円札 「二千円札大使認定証」二千円札流通促進委員長・湖城英知/サンクス平尾(平尾本通商店街)。リトル沖縄として有名な大正区平尾の商店街
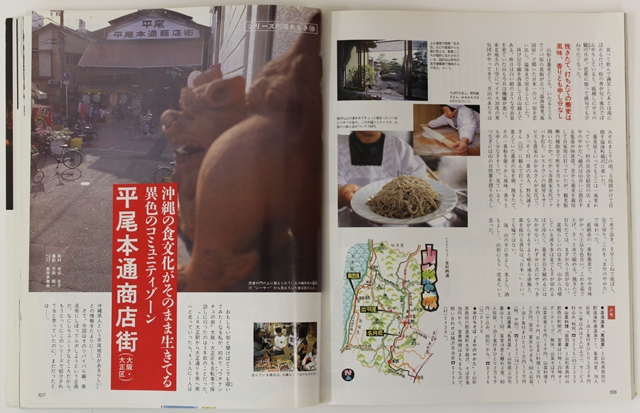
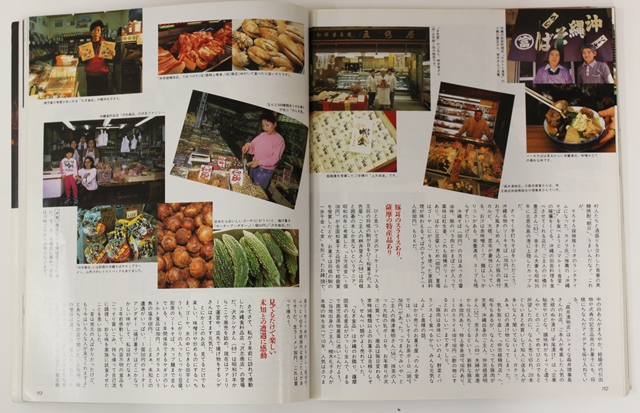
『あまから手帖』1993年6月号
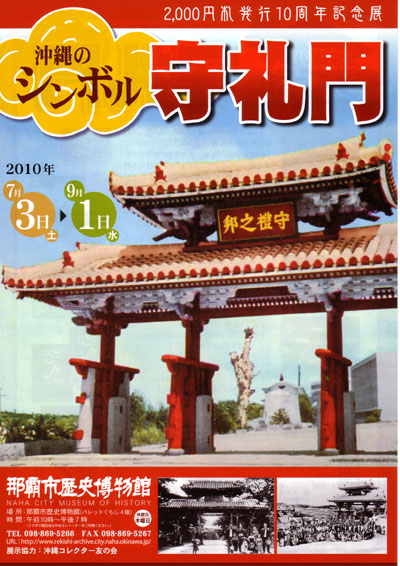
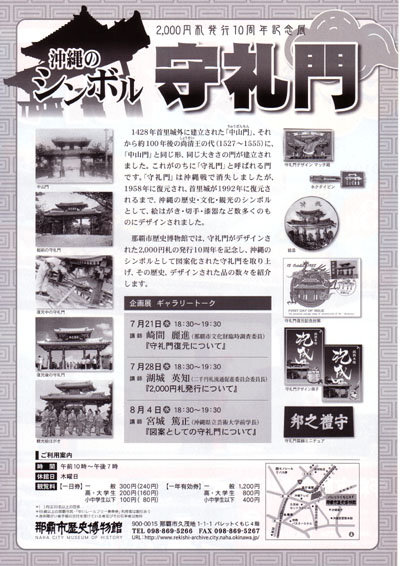
大阪の沖縄関係資料室に守礼門の扁額「守禮之邦」の拓本がある。沖縄学の祖、伊波普猷は1932年10月『琉球新報』「『首里』の語源は結局わからないー東恩納学士の浦添旧都説を裏書きすべき一史料」の中で、尚眞王以前は瑞泉門が正門、守礼之邦の最初の意味は「首里親国」「しよりくに」とする。
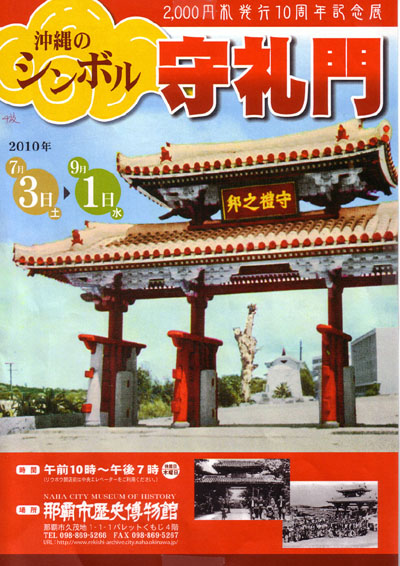
改訂前のチラシ


2010年7月28日ーギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。/2010年8月4日ーギャラリートーク 宮城篤正氏を囲んで。
1428(尚巴志7)年ー国門を創建す。傍に曰く、中山と(旧記に曰く、中山の2字は内官柴山進めて以って額と為すと)
1477年ー歓会門創建
1534年ー陳侃『使琉球録』「是の日黎明、世子、衆官をして館門の外に候たしめ、詔勅を導引して国に之く。国門は、館を距たる路三十里、山海の間に介在す。険側高卑斉しからず。砥の如く矢の如く能はず。将に国に至らんとす。五里の外に牌坊一座有り。扁して中山と曰ふ。此れより以往、路皆平坦にして九軌を容るべし。旁に石墻を壘ね、亦百雉の制の若し。世子、此に候つ。龍亭至りて、五拝三叩頭の礼を行い、之を国門に導く。門は歓会曰ふ」
1561年ー郭汝霖、李際春渡琉□『重編使琉球録』「国につくとき、その五里外に、一座あり、『中山』の額がかけられている。これから先は、道はすべて平坦で、九軌をいれることができる。道のかたわらは、石垣をつみあげて、百雉の制ににている。世子はそこ(中山坊の所)で待っていた」
1606年ー夏子陽『使琉球録』「吉日を卜して万暦三十四年七月二十一日に封王礼を挙行した。この日の明け方、世子は衆官をしてすべて吉服せしめ、天使館の外へ出迎えさせた。私は詔勅をささげて龍亭の中に安置したてまつり、国王と妃へ頒賜される服と物とを取って彩亭の中に置いた。儀注通りに国へ前導した。路の両側はすべて兵を並べて儀衛とし、隊伍を整えて立っていた。国は一里ばかりで、坊があり、その額に『中山』とある。ここから進むと首里坊である。現在は『守礼之邦』の額である。わが中国の声数の及んだことを記したのである。天使館から東へ行き、ここにつくと、地勢はやっと平坦となる。世子は守礼坊の下で出迎え、龍亭の到着を見るや五拝三拝叩頭の礼をおこない、国門へ案内した。門は『歓会』という」(原田
1719年ー徐葆光、海宝が冊封で渡琉→□『中山伝信録』「中山王府ー坊牓があって『中山』という。道の南に安国寺がある。その向い側の町並の、切石を積んで削いだような石垣があるのが世子邸である。道の両側は、すべて切石の低い石垣で、高さは三,四である。道の真ん中に、蘇鉄の一叢があり、まわりを石で囲っている。更に進むと半里ばかりで坊牓があり、『守礼之邦』とある。中山王は、平伏して、詔をこの坊の下の道のかたわらで迎えた」(原田訳)
1731年11月ー『琉球国旧記』「坊楼ー1392年、閩人三十六姓を賜り、文教は大いに明らかとなり、礼楽は日々に新たとなり、中国同様の世となり、礼楽制度は中華とちがわなくなった。太祖皇帝は、これをおほめになり、『守礼之邦』と申された。後に、改めてこの額をかけた《昔は、いつもは『首里』の額をかけており、勅使がお出でになった時だけ、改めて『守礼之邦』の額をかけていた。近頃から、常時『守礼之邦』の額をかけている》。」(原田訳)
1756年ー周煌『琉球国志略』「世子は、衆官を従えて、守礼坊の外で平伏して(勅使を)迎える。龍亭はしばらくとどまる。世子と衆官は立ち上がる。天使は、前へゆき、龍亭の左右に分かれて立つ。引礼官が『排班』と唱える。世子は衆官を従えて、三跪九叩頭の接詔礼を行う。世子は前導して国門(歓会)を入り、正殿の下に立つ」
1853年6月ーペルリ、首里城訪問□→1926年10月ー神田精輝『ペルリ提督琉球訪問記』/1935年3月ー土屋喬雄『ペルリ提督日本遠征記』弘文荘/1947年2月ー大羽綾子『ペルリ提督遠征記』酣燈社/1962年6月ー外間政章『対訳ペリー提督沖縄訪問記』研究社/1985年10月ー金井圓『ペリー日本遠征日記』雄松堂
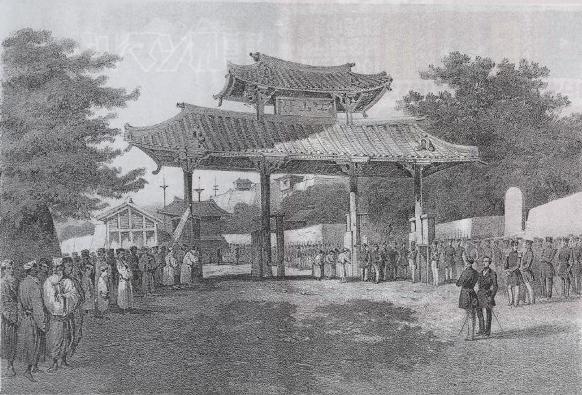
1879年2月ー渡邊重綱『琉球漫録』「首里ハ主府ニシテ中頭省南隅ニアリ其地高燥十丁方余十七ヶ村ニ分ツ王城中央ニアリ西ニ面ス墻壁橋梁石ヲ畳ンデ造ル第一門ヲ中山ト曰フ(毎門名号ノ扁額アリ)第二守禮(守禮之邦明帝ヨリ贈ル)第三歓会第四瑞泉ー」
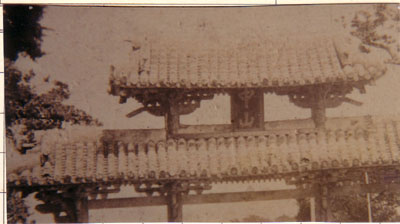
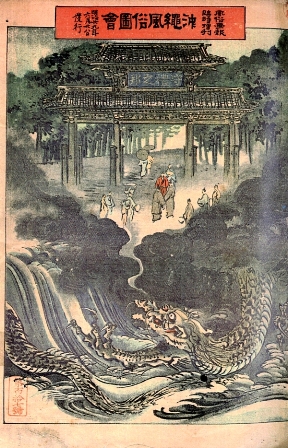
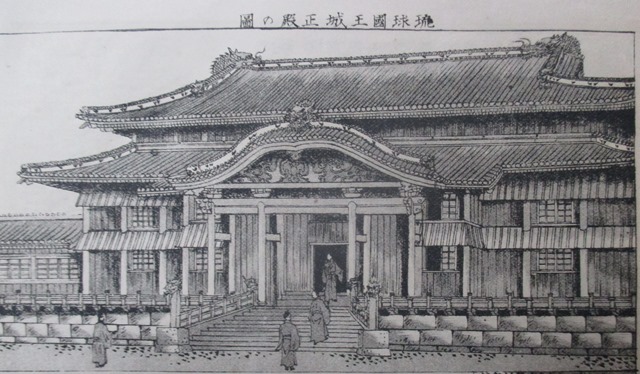
1896年6月ー『風俗画報臨時増刊/沖縄風俗図会』東陽堂
1905年4月22日ー『琉球新報』籠城夫「嗚呼中山門ー嗚呼首里の生命」
4月27日ー『琉球新報』放浪生「嗚呼中山門」
1907年
12月18日ー『琉球新報』東恩納寛惇「守礼門考ー坦々たる首里街道の正面に千古の翠色を堪えて立っている守礼門は、今尚暗黙の裏に中山の古い歴史を語って居るが、其のささやきに耳傾けたものはいない。曾つて其下をくぐった長袖寛帯の支那人も、碧眼黄髪の西洋人も、乃至は肩で風切った薩人も、甚だしきは沖縄の物識先生も、皆此の活きた歴史に就いて表面の解釈を下しているに過ぎない。それが物数奇な旅行者の日記に書きこまれて諸方に撒き散らされ、沖縄を誤り伝ふる一の材料となっているー」
1908年6月4日ー『琉球新報』「中山門の入札の結果ー仝門は一昨日正午十二時頃額面及び敷石を除くの外全部入札を挙行したるが入札者七名にて(略)首里区字寒川水旧三十七番地宮里加那が五十二圓二十七銭にて落札したる由」
1909年7月11日~12日『琉球新報』東恩納寛惇「歴史的遺物の保存に就いて識者に協るー(略)吾々は昔中山王国の正門で有った処の中山門を、僅かに三十弐円の薪として売り払った者の罪を、天下後世に鳴らす積もりである。諸君、吾々は上下幾千年に亙る郷土の歴史を調べて、吾々が誠に優秀な国民で有ると曰ふ自覚の上に立って、自ら琉球人たる事を天下に名乗るを矜りとする者であるー」
12月ー東恩納寛惇『大日本地名辞書』(第二 琉球)「中山門跡」「守礼門ー中山門は、当初板葺なりしを、康煕二十二年瓦を以て覆ひたり、守礼門も同様なるべきか。○山里親雲上系譜云、康煕二十二年辛酉三月八日、修補中山門、任惣奉行職、此時改版木蓋以工瓦。-」
1917年8月ー親泊朝擢『沖縄県写真帖』(守礼門)
1919年8月ー『琉球案内』沖縄實業時報社(守礼門)
1920年9月ー親泊朝擢『沖縄県案内』(写真・首里守礼門)
1923年6月ー眞境名安興・島倉龍治『沖縄1千年史』日本大学□「中山門ー球陽に云ふ宣宗使を遣はし、皮弁冠を賜ひ、並に生漆及び各色磨石を買はしむ。宣徳三年(尚巴志即位七年)創めて國門を建て、榜して中山と云ふと」「守禮之邦ー球陽天正七年の條に首里坊門の榜字を易へて守禮の邦といふとあり。蓋し本國支那に通じてより職を修め、貢を入れ、書を読み、禮を学ばしむ。仍って明の太祖称して禮義の邦と為す。嘉靖年間禮部奏して曰く、琉球は海中の諸國に在りて頗る守禮と称す。又尚永王封を受くるとき、制詔に云ふあり、世々職貢を修め、守禮の邦と称するに足ると。是に由り、王法司に命じ、始めて守禮之邦の四字を以て額と為す。然れども平常はただ首里の二字を用ひ、冊使賁臨に会する毎に守禮之邦の四字を以てするを例とすと。康煕二年(寛文三年皇紀二三二三)癸卯始めて榜字を定め守禮之邦と曰ふとあり」
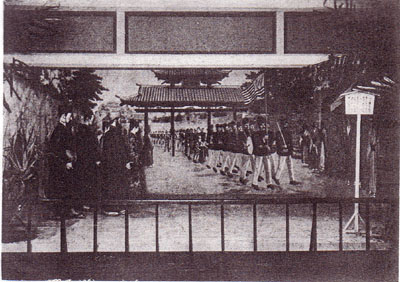
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」、写真・ペルリ提督の首里城訪問のジオラマ

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社
1932年6月 『婦人公論』久志冨佐子「滅びゆく琉球女の手記」(カット・守礼門)1940年
2月ー大阪戎座で「中山門建築史/ターバーゼーク」
10月ー日本民芸協会『工芸』百三号 柳宗悦□守禮門ー首里城の第2の坊門である。姉妹であった中山門が哀れにも破壊せられて了った今日、此の門が守護を受けて保存せらるるに至ったことは感謝の至りである。構造は支那に発するであろうが、よく咀嚼して独自の風格を示した。結構、均等甚だよく、特に4個の脚柱に用いられた石材の形は見事である。此の門、最初は「賢待門」と呼ばれ、後に「首里門」とも称へられ、又俗間「上の鳥居」とも「上綾門」とも云われた。前の大通りを此の門に因んで綾門大路と名づけた。美しく彩られた門のある大通りとの意であろう。尚清王時代の建立と云うから、今から四百年を越える。中山王国の幾多の歴史的場面は、此の門の前で行われた。一国の威厳を示した國門であって、幾度か冊封使は此の大門をくぐった。かのペルリー一行を接し迎えたのも茲である。「守禮之邦」と題した扁額は、琉球の心を語るように見える。此の門を通して遠く首里城の正門を臨む。繁栄な昔は去った。併し此の門が佇む限り日々新たなる遠来の客を集めるであろう。歴史は変わるとも文化の跡を慕る心は人間あら消えない。首里城が保護せられ、修理せられ、整備せられるなら、此の古都に新な繁栄が来ないと誰が云い得よう。

1935年9月 東洋文化協會『幕末・明治・大正回顧八十年史 』「五姓田芳柳 藩使東上の図」

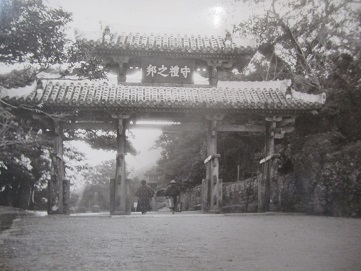
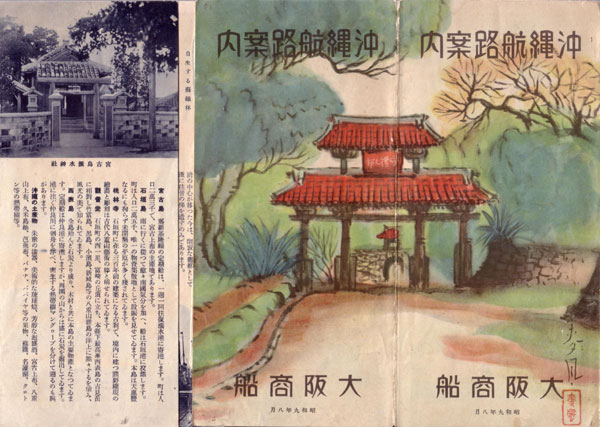
1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)
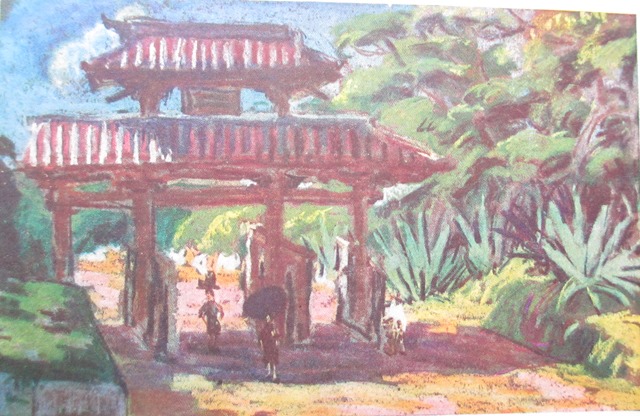
詳細不明だがネット上に次の書籍が見える。富安路葭, 岡茂政著『筑後本吉清水観世音東山名所図会』昭和堂書店, 1931.5
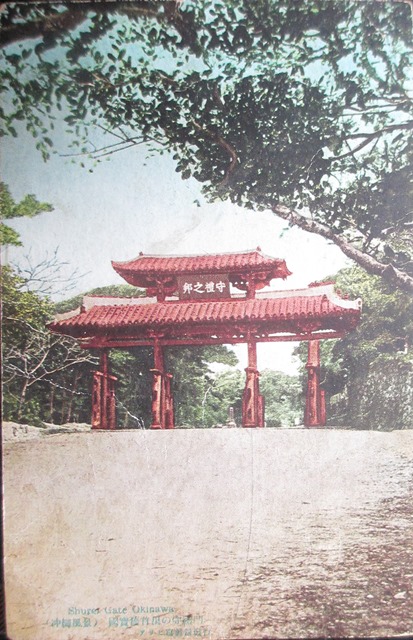

1941年10月ー加藤三吾著・早川孝太郎校訂『琉球の研究』文一路社□「中山門といふのは首里城の第一坊で、下のアエヂョウと呼び、明の宣徳三年に欽差正使柴山が尚巴志を冊封した時に、中山といふ扁額を携へて来て此門に掲げたのであったが、今は門と共に撤去された。守禮門は第二坊で、上のアエヂョウと呼び、明の嘉靖七年に尚清王が封を請うた時の創建で、初は扁額に『待賢』の二字を掲げてあったが、中頃に『首里』の二字に改め、冊封使の来る時のみは『守禮之邦』といふ金字の額を懸けて、左右の門柱には
嘉慶丑年歳次庚申桂秋 廿有王承冊命 三十六島環中山 錦州李鼎元題
といふ聯床を垂れたのであった。しかし後には『守禮之邦』の大額を其儘に掲げて置くことになったので、今も観光者の最も嘱目するものの一になっている」
1947年11月ー日本民芸協会・沖縄人連盟主催「沖縄工芸展」日本民藝館
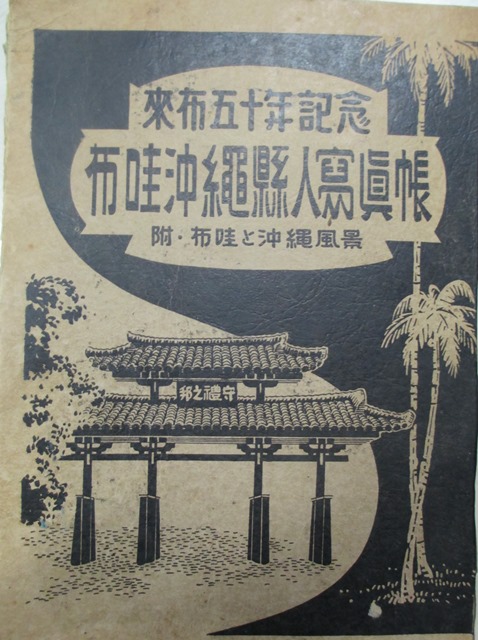
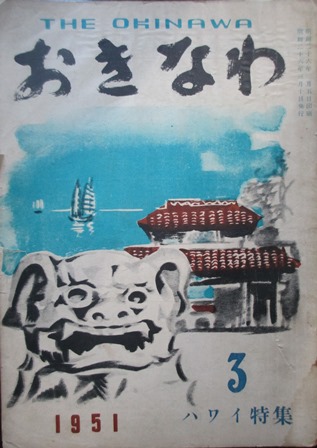
1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』/1951年3月 雑誌『おきなわ』<ハワイ特集>
1951年11月12日ー『沖縄タイムス』石野径一郎「守禮の國」(金城安太郎の守礼門の挿絵)
1954年1月ー社団法人「沖縄観光協会」設立(事務所・那覇市勧業課内)。□→57年4月ー琉球政府工交局内。
1956年2月ー金城唯恭編『新沖縄文化史』仲座久雄「郷土の国宝建築・首里城守礼門ー1953年5月、ペルリ記念祭に際し仲座久
雄、知念朝英により5分の1の模型が造られ首里城正殿と共に首里博物館ペルリ記念館に陳列」
1958年10月6日ー『琉球新報』「総仕上げ急ぐ守礼門ー4百年前の姿を再現」 12月15日ー『琉球新報』伊波南哲「十字架の下に」(カット・守礼門)
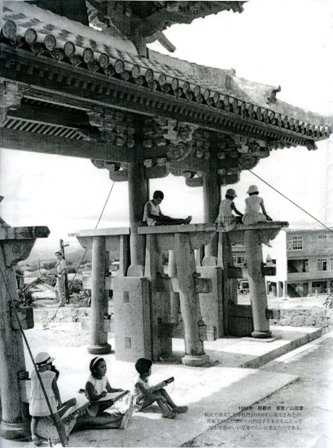
写真・守礼門と少女たち/山田實・撮影
02/02: 世相ジャパン⑲/2020
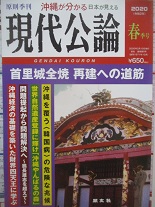
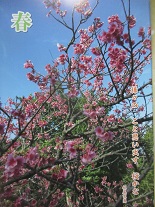

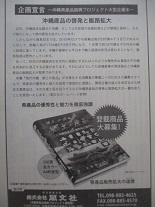
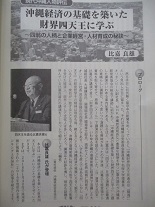
2020年2月『現代公論』<首里城全焼 再建への道筋>閣文社〇友寄貞丸「進退両難の玉城県政」/「企画『現代沖縄 郷土の産品』」比嘉良雄「沖縄経済を築いた財界四天王に学ぶ」→株式会社 閣文社(かくぶんしゃ)公式サイト
一月(いちげつ)往(い)ぬる二月(にげつ)逃(に)げる三月(さんげつ)去(さ)る
「くろねこの短語」2020年2月9日ー行政が政策を進めるために都合の悪い情報を隠蔽し、あまつさえ虚偽の情報を垂れ流すってのは犯罪のはずなのに、初老の小学生・ペテン総理の圧政下の元ではそれが官僚の習い性となっちまったようだ。なんと、防衛省が辺野古のマヨネーズ上の軟弱地盤について、「七十メートルまで地盤改良すれば施工可能」と説明してきたのは、実はまったく根拠のないことが発覚したってね。それどころか、最深部の地盤調査はやっていないと言い切ってたのに、それもまた嘘だったんだとさ。工事請負業者の調査で70mよりも深い地盤も「軟弱」というデータが出ていたのを、「業者が独断で行った調査で信頼性が低い」という理由をつけて隠蔽していたというからたちが悪い。
軟弱地盤改良のために今後30年はかかるとされる新基地建設工事は、これでまた大幅な設計変更が必要になってくる可能性が出てきたってことだ。今日明日にも解決しなくちゃならない普天間の危険性ってのは、どうなっちゃうんだろうね。ていうか、30年もかかる移転に何の意味があるんだ。つまり、辺野古の新基地建設ってのは、普天間はあくまでも建前で、その実は自衛隊のための基地建設ってのが、どうやら正解のようなんだね。だから1兆円を大幅に超える建設費をものともせずに、工事を強行しているってわけだ。これまでの国会答弁との整合性を問われて、防衛省整備計画局は「正確な説明ではなかったかもしれないが、嘘をついたつもりはない」と言い放ってくれてるけど、これもまた「ごはん論法」のひとつなんだね。防衛省が国民に嘘をつくのは、「撤退」を「転進」、「全滅」を「玉砕」と言い替えた戦前の軍部から続く「DNA」の成せる業ってことだ。
「くろねこの短語」2020年2月8日ーTVのワイドショーは新型コロナウイルスの不安を煽りに煽りまくるってるようだが、アメリカではインフルエンザで2万人の死者が出ている。致死率は極めて低いとされる新型コロナウイルスより、こちらの方がよっぽど深刻な問題だろう。この凄まじいインフルエンザの猛威を、なんで新聞・TVは無視し続けるのかねえ。中国人の入店お断りなんて張り紙する店もある中、そんな報道したらインフルエンザの危険性があるアメリカ人はどうよ、って声が上がるのを怖れているんじゃあるまいね。そんなことより、国会だ。いやあ、凄いのが出てきちゃったね。答弁に窮したあげくに、「え…、ん…」と唸ったまま立往生しちゃうんだから、これぞ世界一のポンコツと命名させていただこう。
「くろねこの短語」2020年2月6日ー新聞・TVは、新型コロナウイルスとアメリカ大統領選の話題で持ちきり。新型コロナウイルスなんか、「煽るな、煽るな」とエクスキューズしながら、その実は感染の恐怖を煽りまくるんだから、去年の台風の時に「命を守るため、早めの備え、避難を」ってアナウンサーが血相変えて呼びかけていたのを思い出しちまった。
高野孟2-6 (略)同記者によると、立憲の枝野幸男代表が安易な組織合併に慎重なのは、ある意味で当然で、2017年の総選挙目前に民進党を解党して希望の党に合流し小池百合子を担いで政権取りに突き進もうという、バカげたとしか言いようのない前原誠司の仕掛けに、コロリと騙されて乗っていったのが国民民主の人たちである。


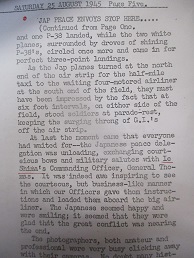
2月5日、平和通りの「なるみ堂」に遊びに行くと、店主の翁長良明氏から前日、新報、タイムスに出た記事「緑十字機 歴史伝える」を見せて、これに関する伊江島のアメリカ海軍の機関紙と思われるものを見せてくれた。機関紙(1945年8月25日)には「日本の平和使節団は、伊江島のアメリカ軍司令官と丁重なお辞儀と敬礼を交わしながら、荷物を降ろしていた」などが記されていた。早速、家で「緑十字飛行 - Wikipedia」検索「1945年8月14日のポツダム宣言受諾により、後の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)最高司令官となるダグラス・マッカーサーは、日本の大本営に対し、日本政府、大本営の代表使節団のアメリカ領マニラへの派遣を要請した。混乱を避けるため、マッカーサーは、代表使節団の使用機材、外装、通信波長に至るまで細かく指定し、機体の塗装に関しては『全面を白色に塗り、胴体の中央部に大きな緑十字を描け』とした。「緑十字飛行」「緑十字機」という名称はこれに由来する。 この飛行は本土と伊江島の伊江島飛行場間であり、伊江島からマニラまでは米軍機で移動した」とある。
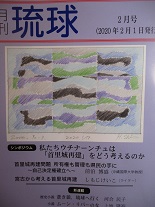




2020年2月『月刊琉球』№73 琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947
前泊博盛「首里城再建問題 所有権も管理も県民の手に~自己決定権確立へ~」/しもじけいこ「宮古から考える首里城再建」/与那嶺功「沖縄振興ー『明治維新150年』を問う 大東亜・植民政策・ナショナリズム⑮『富山編』」/河合民子「蒼き狼、琉球へ行く 第1回」
斎藤 陽子(Walnut, California)2-6 気温が20℃を越し、庭のサクラや白梅などの花ばなも満開で、冬物のの厚手の上着を脱いで、春がやって来たと喜んでいた先週ですが、昨日からロスアンゼルスは急に寒気到来、冬に逆戻りで日中は12℃、夜間は何と1℃になる寒さです。コロナウィルス騒ぎの日本ですが、こちらではインフルエンザが猛威を振るっています。想定外の破天荒なトランプという指導者を得て、我慢した4年間ですが、今日はトランプ弾劾裁判(Impeachment trial)も無罪を得て、昨日は民主党(Democratic Party)の次期大統領候補者選考がアイオア州で始まりましたが、どの候補者もパッとせず、トランプに勝てる人材はいない様な雲行きで、どうやら次期大統領は再びトランプで我慢しなければいけないような雲行きです。この国は一体どのように歩むのでしょう。



さて、我が家の裏庭に鉄の鎖で吊り下げてある、40年物の観葉植物、鹿角羊歯(ビカクシダ)またの名をコウモリランPlatyceriumが、生き生きと大きくなっています。樹木などに着生し大きくなるシダで、鹿のツノのような肉厚な葉が大きく、葉の付け根は外套葉という茶色の葉でおおわれ、水をやると、この外套葉が水を溜める仕組みです。40年以上生きているのこの植物、大きさは1メートル.50センチは有り、重量は100キロほど、植物に詳しい人が見ると、その大きさに驚く事もあります。コウモリランは全世界に17種あると言われており、、主に東オーストラリアなどの亜熱帯地域の海岸近くの森の中で、木々の幹や岩場に住まいを借りて生きる大型の着生シダ植物です。
先日次男が六本木の園芸店で見た50㌢ほどのこの植物が、45万円の正札が付いていたと驚き、写真を送付してきました。わが家に来る植物好きの人は、100㌔の重さは有るこのシダの大きさに驚きます。高温多湿を好みますので、年中乾燥している南カリフォルニアですから、暖かい季節にはシャワーをかけて水浴びをマメにしてあげるのは私の役目です。

O・S 2-5 〇新聞の折り込みにこんなチラシが――「嘉手納・普天間基地騒音訴訟の原告を募集します」東京の二つの法律事務所の共同広告のようだ。ついにこういうものにまで食指が動いたか。嘉手納・普天間の爆音訴訟は、沖縄の弁護士たちが長年にわたって原告住民に寄り添って取り組んできたものだ。そこにうまく乗じようというのだろうか。因みに、沖縄では切実に「爆音」だが、東京の感覚では「騒音」でしかないようだ。
〇2000年10月に弁護士広告が解禁されてから民放のTV、ラジオでのCMがやたら目(耳)につくようになった。18年に弁護士が4万人を突破、「10年で1.5倍 訴訟数は横ばい」(1.26『毎日新聞』)「弁護士の仕事は増えていない。法律事務所に就職できない新人も多い」(7.18『日本経済新聞』)という状況の中で、貪欲に新たな草刈場にしようという魂胆だろうか。/M・H 先日、あるTV番組でやっていましたが弁護士は、ITにとって代わられる仕事との筆頭らしいですよ?
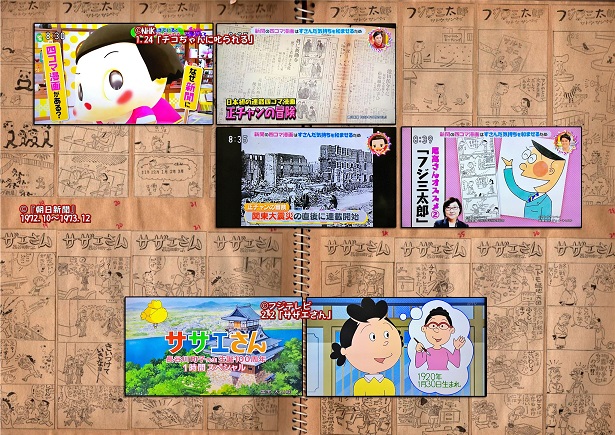
大濱聡 2-4 ■2日(日)のフジTV「サザエさん」は、原作者の長谷川町子生誕100周年1時間スペシャル版。100年前(1920年・大正9年)の1月30日に誕生。■その前週1/24(金)のNHK「チコちゃんに叱られる」で「なぜ新聞に四コマ漫画がある?」の出題――正解は「すさんだ気持ちを和ませるため」。
日本初の四コマ漫画は、1923(大正12)年の関東大震災直後から『朝日新聞』で連載が始まった「正ちゃんの冒険」とのこと。■番組の中で、日本新聞博物館の尾高 泉館長は「気持ちが和む 四コマ漫画傑作選」4本のひとつに、「フジ三太郎」(『朝日新聞』1965.4/1-1991.9/30)を選んでいた。■20歳の時、「フジ三太郎」と「サザエさん」(いずれも『朝日』)が好きで、1年間(1972.10-1973.11)スクラップを続けた(今も保管)。東京でのひとり暮らし、気持ちを和ませるためにやっていたのだろうか。
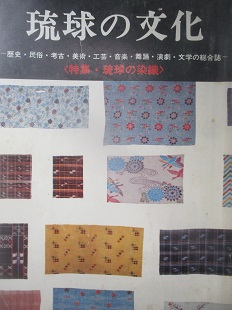
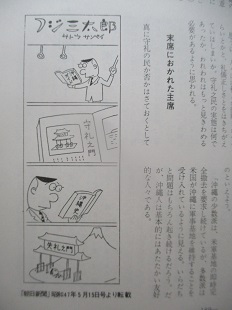
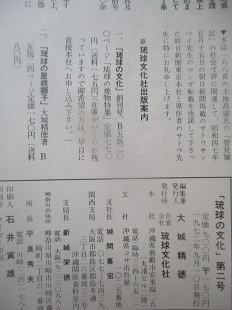
1972年9月『琉球の文化』2号 上地昌盛「社会寸評ー管見雑記」「編集後記・昭和47年5月15日の朝日新聞掲載のサトウサンペイ先生のマンガ転載を快諾して下さった朝日新聞東京本社と原作者のサトウ先生に特にお礼申し上げます。」
2020-2-4新型肺炎のドサクサ紛れ【官邸支配、汚染検察 無法国家がすでに完成】ゴーン弁護士の弘中事務所への捜索にもたまげたが露骨な官邸支配を裏付けた高検検事長の定年延長、それをちっとも書かない大メディアの腐敗堕落にマトモな識者は戦慄している 検事の定年延長は検察庁法違反の疑い(日刊ゲンダイ)
「くろねこの短語」2020年2月4日ーカジノ汚職・秋元君が追起訴されたその日に、同じく100万円を受け取っていたギョロ目の元防衛大臣・岩屋君、沖縄基地利権王・下地君など5人のシェンシェイ方の立件が見送りだとさ。このタイミングを狙ってたんだろうね。ギョロ目の岩屋君は、早速に100万円返還のパフォーマンスだ。どうやら、ペテン政権は小物の秋元君をスケープゴートにして、一件落着に持っていこうとしてるようだ。このまま追及が続くと、政権中枢まで捜査の手が伸びる可能性がありますからね。このところ話題の黒川弘務東京高検検事長の定年延長ってのも、そうした動きにけっして無関係ではないのだろう。
検事長の定年延長ってのは、どう見たって政権による検察人事への介入で、これにより黒川君は次期検事総長が約束されたも同然と言われている。エダノンが「脱法行為」と指摘するす暴挙をこのタイミングで仕掛けてきたのには深いワケがあるんだね。つまり、カジノ汚職をはじめ、香典疑惑の菅原君や河井バカップルの公選法違反、そして総理大臣の犯罪の疑いのある「桜を見る会」問題を、どうにか穏便に済ますための布石ってことだ。でなけりゃ、官邸の代理人と揶揄される黒川君の検事総長への道を約束する閣議決定はしません。ここまで露骨な人事介入を強行するってのは、いかにこの国のメディアが舐められてるかってことでもある。ていうか、手下に成り下がっちゃってるんたね。
『読売新聞』2-4 厚生労働省は3日、横浜港(横浜市)からクルーズ船に乗った香港住民の男性が新型コロナウイルスに感染していたとして、この日同港に戻ってきた船を沖に停泊させた状態で、すべての乗客・乗組員(約3500人)の健康状態を船内で調べる検疫を始めた。同船では海外から那覇市に入った際に検疫を行っているが、香港の男性の感染判明を受け、同省は異例の「再検疫」を実施することにした。関連「朝日新聞」2-3ー大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号。運航会社のホームページなどによると、船は約11万6千トン、全長290メートル、18階建ての大型客船。ラウンジや、プール、カジノなどの娯楽施設も備えている。乗務員は約1100人で、乗客定員は約2700人。
ママの会 2-4国会でじわじわ追い詰める野党に鋭い援護射撃する郷原信郎弁護士!学校へ納めたPTA会費を学校長が自分のために使うのと同じ、それ怒らない人いますか?同じ形でもっと巨額を使っちゃってるんですよ、日本の総理大臣は。メガトン級の指摘 ホテルが寄付したか安倍事務所が公選法違反、もはや逃げられない❗️ もう、衝撃すぎ第1回目 コロナ対策本部 (1/30) 専門家が誰一人いない????しかもたったの、、、10分 、、、10分⁉️これ、本当ですか⁉️ 真実ですか⁉️どうか、世界中のメディアのみなさん、日本政府へ取材をお願いします‼️ 号泣 日本のメディアは一部を除いて、ポンコツばかりなので、よろしくお願いいたします‼️????もう涙しか、、、ない
ママの会 2-3 総理独裁政権の完成です。どんな悪事をしようと、もみ消しでっち上げ堂々とします。それでも手錠なんて嵌められない。批判する人が逮捕されます。
FBH・T2-3安倍首相を批判した公の記事をシェアしたら、FB規約違反なんだそうです。納得できないと返答したら、現在審議中とのこと。忖度するんだ・・・ポチは。FBG・Sそんなことより、新型肺炎等で出てくるフェイクニュースを取り締まって欲しいですね。
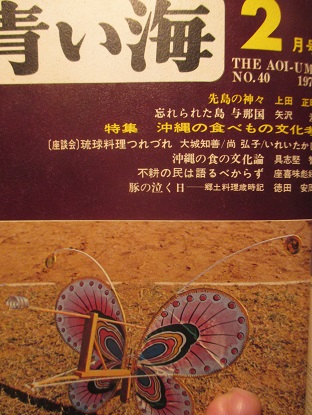
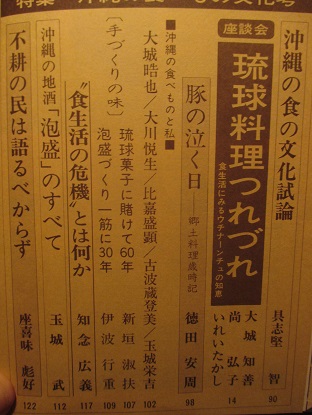
1975年2月 雑誌『青い海』40号 「沖縄の食べもの文化考/豚の泣く日」
1898年、那覇区泉崎の豊盛書林と、西の三笑書店には沖縄県尋常小学校読本も販売しているが、一般書も扱っている。世界年鑑、中等東洋史、中等日本歴史、算術新教科書、新撰算術、新式速記術、新撰日本外史、通俗世界歴史、世界文明史、詠歌自在、詠歌辞典などがある。
同時期の『琉球新報』には一般書や印刷物の広告が載っている。今でいう通信販売である。大阪の芳文館写真部「奇形嬌態裸体美人写真」、大阪の明文社の「画入男女たのしみ草紙」などである。学生向けの通信教育に東京学館の「自宅独習生徒募集」や帝国中学協会「諸学講義録」があるが、どちらも英学、国語学、心理学、論理学、教育学、算術、詩文学、幾何学、三角法、簿記学、代数学、化学、速記学などで内容は共通している。相前後して「ライオンはみがき」、「鳥井合名会社」の広告も目立つ。
1900年、村田弥三郎が、那覇警察署前で東京各新聞の取次ぎを始めている。博愛堂(小沢朝蔵)も新聞広告に近事画報社の「戦時画報臨時増刊号・日本海大海戦紀念帖」を載せ売り出しを図っている。近事画報社は1901年の『琉球新報』に広告「通俗小説文庫ー毎月1冊刊行」を載せている。並んで、東京日本橋の三越呉服店や「中将湯」の広告もある。
1902年の『琉球新報』の広告に京都の島津製作所の「博物地理歴史標本」がある。04年の広告には太田胃散、浅田飴、今治水なども出てくる。07年には十合呉服店(大阪・神戸・京都)、アサヒ、サッポロ、エビスビールの広告も目立つようになる。08年の広告に「実業之日本」、1911年の広告には博文館の常用日記や、「女学世界」、冨山房の「新日本」がある。那覇の円山勉強店の「キリンビール」売り出し広告もある。
1905年11月23日ー志賀重昴、粟国島来着→著1909年『大役小志』
1906年3月5日ー菊池幽芳、粟国島に来着/10月ー『地学雑誌』第18年第214号□脇水鉄五郎「沖縄視察談・粟国」
粟国に来島した志賀重昂
1905年11月23日ー午前3時、運輸丸、久米島発▼6時、珊瑚礁の激浪を琉球形小船にて乗り切り、渡名喜島上陸(略)10時半、粟国島著、上陸、粟国は渡名喜島を距る15浬、面積半方里、磽确たる一珊瑚島、而かも戸数8百余、人口5千余、食糧に欠乏するを以て蘇鉄を食ひ、婦女は那覇、首里に下女奉公をなし、男子は琉球本島及び布哇等に移住する者多く、鱶ノ鰭、烏賊、鰹を輸出す▼夕、那覇港着、上陸。→近代デジタルライブラリー - 大役小志
1922年2月11日ー新城三郎、那覇市三重城近くの借家で生まれる。父・蒲は山原船の船頭。従兄弟の安里蒲の商売(薪)も手伝っていた。出生時は奄美近海に流されていた。母カマと姉(ウト)が世話をした。
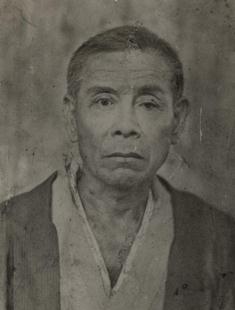

写真ー新城三郎の父・蒲と母カマ(抱いているのは新城栄徳、二人にとって初孫である。)
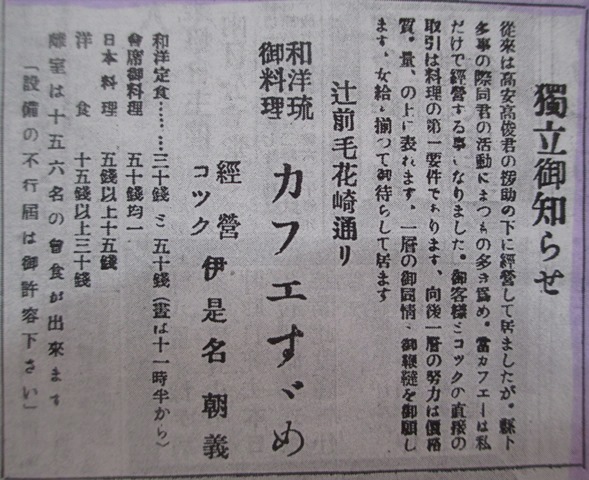
〇向宣恭・伊是名朝信(朝宜三男、生没年不詳)は明治大正時代に郵便局に勤務し、糸満郵便局で定年退職し、那覇上之屋に居を構え、その夫人が作る首里仕込みの豆腐餻が近くの辻町で評判となり、この豆腐餻作りで晩年の生計が助けられた。朝信の一人息子の向得遠・伊是名朝義がロシア革命の影響を受けて沖縄の左翼活動の嚆矢となった為、勘当されて壷屋地区に移り住み政治活動を行った。 →ウイキ
1924年3月-伊佐三郎、粟国尋常高等小学校訓導
1927年4月-新城三郎、粟国尋常高等小学校入学/5月ー伊佐三郎、白金小学校(牧口常三郎校長)に新里朝彦の斡旋で同校訓導
1929年4月ー仲里誠順「万人屋」開業
1934年1月ー新城三郎、那覇市辻町(御願の坂)國吉料理店で板場修行。同年の粟国出身の調理士は、四つ竹の新里。みはらしの玉寄松。玉川の仲間、一味亭の新城、仲里、山城、新城。京ヤの又吉。國吉料理店は与那 風月ロの糸洲、仲里、新里。三杉ロの福本。幸楽の安里、新川幸栄。美崎の玉寄米吉、赤嶺、玉寄三郎。花咲の上原保一、新里次郎、上原健夫。木村屋の安里善徳。ならはら館の上原。宝来館の新城。山本は浦崎。川津館の新城。モリタ館の与那城。
業者ー万人ヤの仲里。朝日ヤの神里。三角ヤの吉元。みかさヤの与儀。井筒ヤの新里。一味ヤの新城。福力ヤの神里。公園入口の金城。朝日橋前の新城。松田橋前の新城。安里松竹の糸洲。
1935年8月『関西沖縄興信名鑑』ー東淀川区之部 安里善盛(大戦前に那覇に引き揚げ食堂経営、戦争で一家全滅)、仁祥、善太郎(のち安村書店主)、勇祥(のちレストランアサヒ経営)
1936年10月2日ー沖縄県知事正五位勲四等・蔵重久「粟国村字東9490番地の新城蒲(50)、8月1日午後9時に那覇市北明治橋右海岸に於いて那覇市垣花町1の88平良カメ(31)が溺死せんとするを救助したるは殊勝なりよって金1封を贈りこれを賞す」
1939年4月5日ー安里幸一郎、粟国村字東で生まれる。父・宗幸、母チヨ(イザニサ大ヤー)
1946年から47年まで戦地や他府県からシマンチュが引き揚げてきて粟国島の我が家の周囲は賑やかになった。しかし生活は貧しく心を癒すものを求めた。その一つが村芝居であった。やがて我が家の隣に茅葺のクラブが建てられ伊江島ハンドーグァーや大新城親方などの芝居が旧正月に演じられた。伯父・玉寄貞夫は初期のころからの中心的に芝居活動をやってきた。1956年、玉寄貞夫の従兄弟・安村善太郎、勇祥兄弟の多額の寄付でクラブを鉄筋コンクリート建てにする(写真・左)。
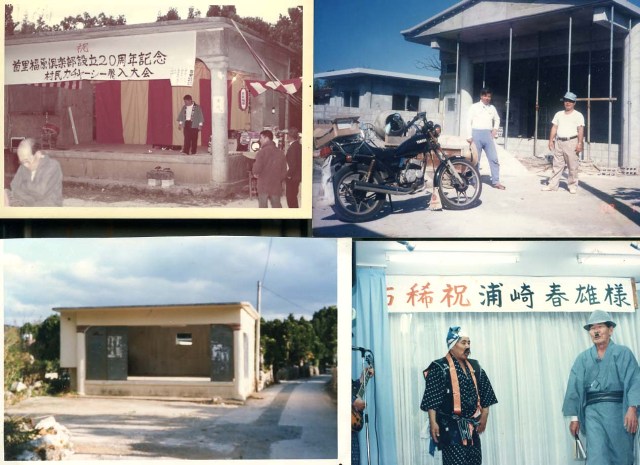
1948年ーガーブ橋前に「大洋食堂」(勢理客(町田)定正)
1949年
安里大通りに「丸屋食堂」そば・すし・めし(久場景善)。7月ーホテル新風荘(崎原マサ)民政府構内に開業。8月ー料亭「喜仙」(仲本盛智)。9月ー料亭「幸楽」、安里に「丸久食堂」(久高将金)。11月ー真和志に食堂「ゆたかや」(西銘政弘)、那覇市場前に「木村屋食堂」
1950年
国際劇場前に「みなと屋」(豊見山義康)、2月ー元国際食堂跡に「井筒屋」、7月ー那覇料理屋組合が毎月第二日曜を公休とする、「一富士」みつ豆・冷し西瓜(当真嗣正)、9月ー那覇区に井筒屋新装開店、神里原に大衆食堂「三角屋」そば・すし(渡口トミ)

写真・沖縄調理師会ー前列右から安里信祐(現・伊勢海老料理「味の店三郎」店主)、新城三郎、左端に玉寄米吉
1950年ー沖縄と奄美出身者で調理師会「沖美会」結成。中村喜代治、新城三郎、玉寄博昭、福永平四郎、赤崎一成、又吉太郎らが参加□奄美が日本復帰する1953年に「沖縄調理師会」と改称。

【関連】1975年 伊勢海老料理「味の店三郎」で食事会ー新城栄徳、息子、あけみ、新城敏子
1951年
1月ー那覇料理組合・花咲、喜仙、花園、南海、清風荘、清風、松屋、美園、那覇、香那恵、皆美亭、若梅、幸楽、田鶴、三原、新栄亭、新風荘、オール倶楽部、ほがらか亭、やよい、よつ竹、若杉、玉家、八千代、有楽、松竹、だるま亭、よかろう、左馬、若藤、春芳、一心亭、一廣、ときわ、松の家、美杉、一楽、やすらか、栄亭、よし乃、新月亭、大楽。糸満町にみなとや飲食店(新城野枝)。安村勇祥(新城三郎従兄弟)、平和通りで「かき氷屋」開店。□→「レストランアサヒ」/1986年2月ー安村勇祥『想いでの記』。
7月ー那覇市10区に琉球料理「玉川屋」うなぎ蒲焼。10月ー料亭那覇がうなぎ料理、12月ー神里原に食堂「美松」手打そば。
1951年 『球陽新報』「沖縄そばの味自慢ー宮里政栄(大阪西成区鶴見橋)」
1952年
5月ー神里原に「龍凰閣」「台北楼」、「レストランアサヒ」
1955年5月ー安里幸一郎、オジ玉寄松のいる料亭松乃下に見習いとして住み込む。
1956年2月ー粟国島で「親子ラジオ」譲渡式/4月ー末吉保朝(粟国中学校教諭)、文部省派遣で大阪市文の里中学校へ/1959年2月ー『オキナワグラフ』「発足した沖縄唯一の事務機のデーパト合資会社・沖縄事務機社(新里有四郎社長)」/5月ー宜野湾市大山で雑貨商「ジミーグロセリー」開業□→2006年8月『Jimmy’s 50th Anniversary 1956~2006』株式会社ジミー/6月8日ー『琉球新報』「粟国村のソテツは村の守り神」。
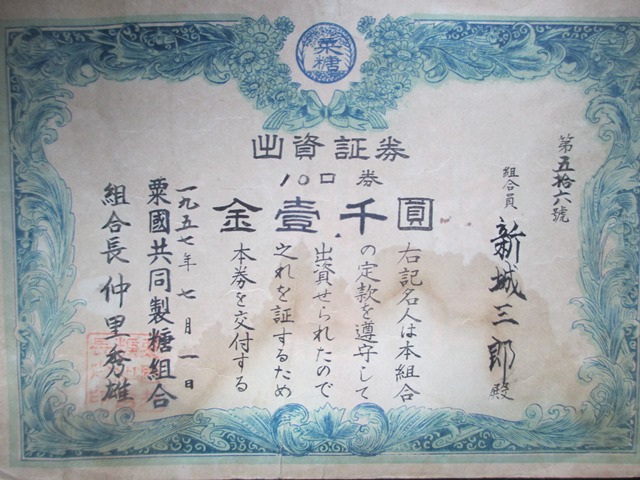
1957年3月 与那国善三『新沖縄案内』沖縄観光協会/印刷・おきなわ社
○広告「沖縄唯一の百貨店 観光お土産にもっとも喜ばれる品々」「サービスのオアシス 料亭小川荘(小橋川和子)」「沖縄観光協会指定旅館 鶴よし」「ホテル琉球」「沖縄観光協会指定 沖縄ホテル」「コザホテル(国吉鶴子)」「大津旅館(津波幸盛)」「ホテル森乃(名嘉真キヨ)」「沖縄観光協会指定旅館 初音館」「沖縄観光協会指定 観光ホテル厚養館(岸本金光)」「料亭・山手(長峯春良)」「料亭・登美の家(金城利江)」「料亭・新鶴(我那覇文子/佐久本嗣子)」「料亭・那覇/東京支店・琉球亭なは(上江洲文子)」「レストラン松屋(前田義善)」
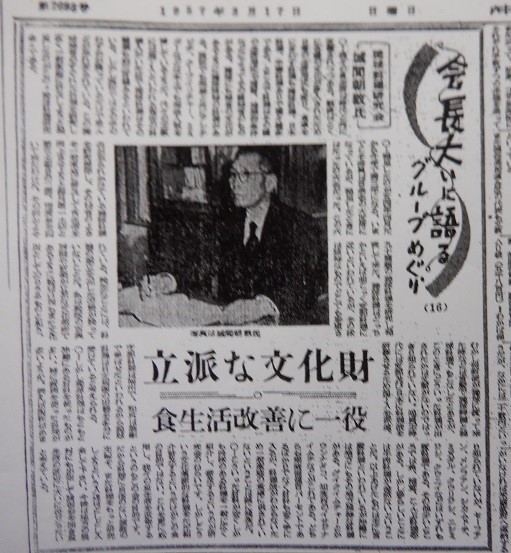
〇1957年3月17日『沖縄タイムス』「会長大いに語る グループめぐり(16)琉球料理研究会 城間朝教会長」
1959年2月ー新城三郎、[食堂]経営。
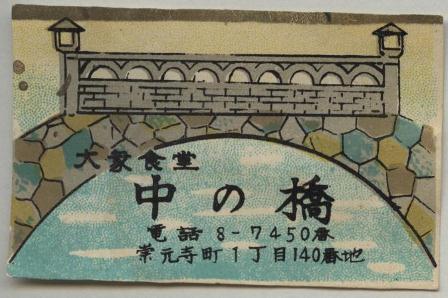

1959年5月27日『琉球新報』「オリンピック東京に決まる」
1960年 川崎お大師様の近所で伊礼松子が「沖縄ソバ」「三月菓子」を自家製造販売
1960年1月8日『琉球新報』島袋盛敏「仲宗根章山翁の思い出ー首里城懐古」(写真/)仲宗根真吉、摩文仁憲和、新垣良光、島袋盛敏。明治42,3年)
1960年1月10日『琉球新報』「新春インタビュー石野記者/朝倉文夫×浜田庄司」
1960年1月17日『琉球新報』坂口総一郎「順応する生活態度ー40年前クリ舟で体験した人生観」
1960年10月8日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと①島本豊氏(日航沖縄支店長)独自の風土活かせ」
1960年10月9日『琉球新報』「座談会/本土経済人の見た沖縄ー観光地として有望」今里広記/湯浅佑一/五島昇/鹿内信隆
「観光沖縄にひとこと②松川久仁男氏ー海の特色売り物に
1960年10月10日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと③太田守徳氏(国際中央通りほしい立派な歩道」
1960年10月11日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと④儀間光裕氏ーきたないガーブ川」
1960年10月12日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと⑤東盛良恒氏ー”南国沖縄„打ち出せ」
1960年10月13日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと⓺島袋清氏(ハワイ球陽観光団長)全住民も関心持て」
1960年10月14日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと⑦宮里辰彦(リウボウ専務)政府、住民も協力を」/糸満盛信「沖縄の古武術」①
1960年10月15日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと⑧荻堂盛進氏ー島ぐるみで協力を」/「あれから15年ー本土の沖縄開拓村を行く 千葉県三里塚の沖縄農場」
1960年10月16日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと⑨宮里定三氏ーホテル施設の充実」→2016年6月ー那覇空港見学者デッキに「沖縄観光の父・宮里定三」(ブロンズ像)設置
1960年10月17日『琉球新報』「観光沖縄にひとこと⑩宮城仁四郎氏ー花いっぱい運動を」
1960年10月18日『琉球新報』「あれから15年ー本土の沖縄開拓村を行く 東京新生会」
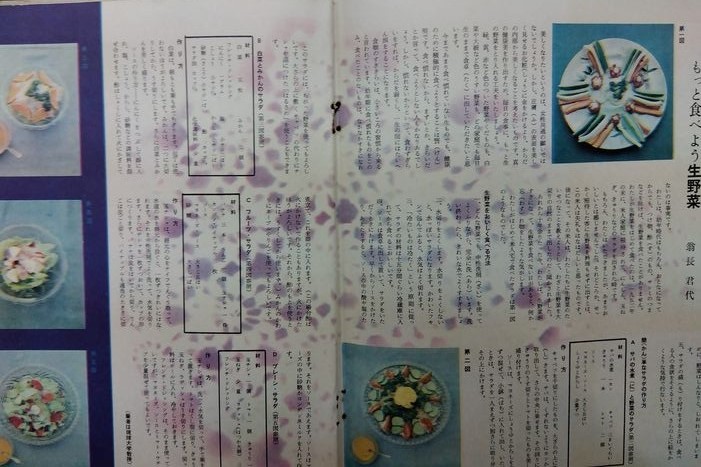
〇1963年3月 『守礼の光』第50号 翁長君代「もっと食べよう生野菜」
1963年4月 『守礼の光』第51号 翁長君代「たまごを使った料理」
1963年5月 『守礼の光』第52号 翁長君代「衣類はこうして保存しましょう」
1963年6月 『守礼の光』第53号 翁長君代「エチケット」
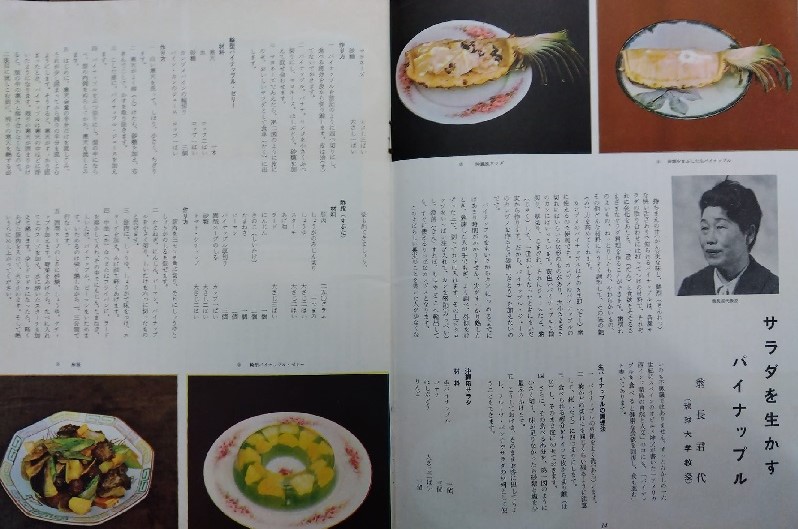
〇1963年7月 『守礼の光』第54号 翁長君代「サラダを生かすパイナップル」
1963年8月 『守礼の光』第55号 翁長君代「生活にもっと花を」
1963年9月 『守礼の光』第56号 翁長君代「お茶のいれ方」
1963年10月 『守礼の光』第57号 翁長君代「さかなの料理法」
1963年11月 『守礼の光』第58号 翁長君代「ふきんとお菜ばし」
1963年12月 『守礼の光』第59号 翁長君代「お正月のおせち料理」
1964年4月 『守礼の光』第63号 翁長君代「主婦に便利なケーキミックス」
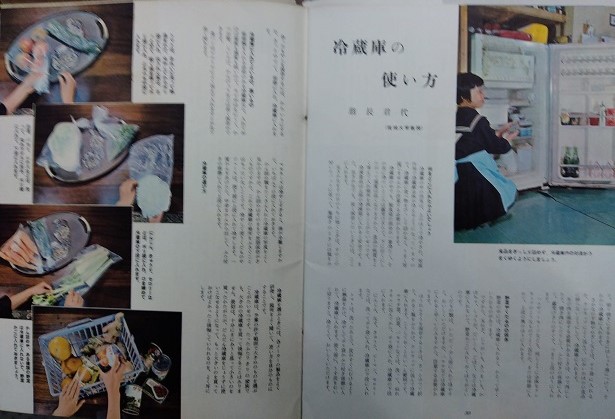
〇1964年7月 『守礼の光』第66号 翁長君代「冷蔵庫の使い方」
1964年8月 『守礼の光』第67号 翁長君代「台所の熱器具はいつもきれいに」
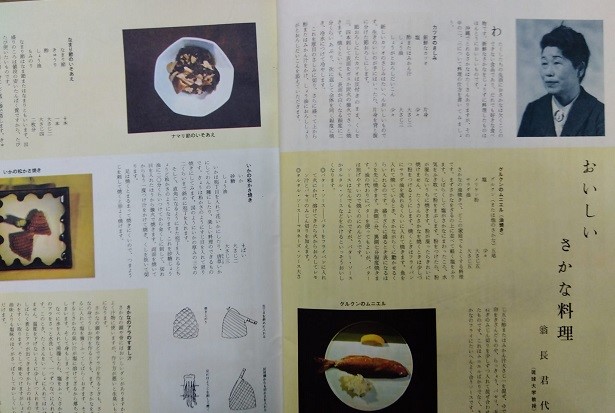
〇1964年9月 『守礼の光』第68号 翁長君代「おいしいさかな料理」
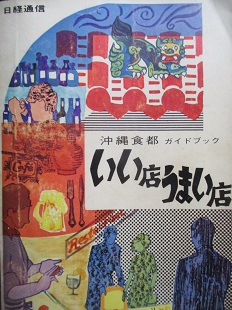
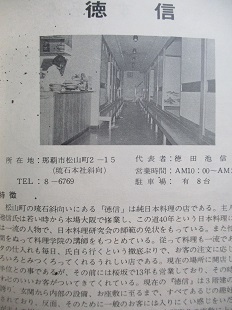
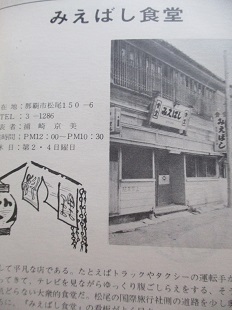
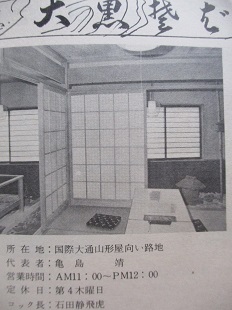
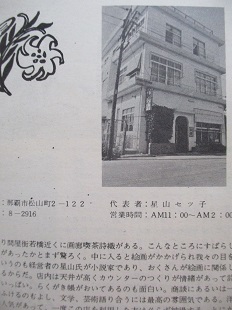
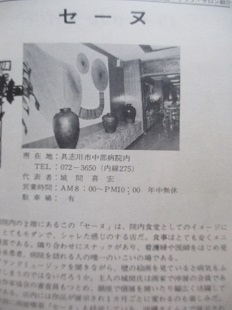
1970年10月 『沖縄食都ガイドブック いい店うまい店』日経通信
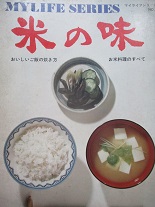
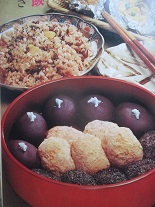
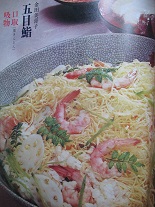
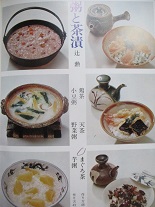
1972年10月 『米の味』グラフ社




1975年5月 江原恵『まな板文化論』河出書房新社
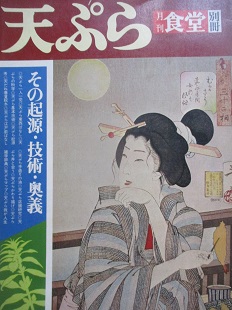
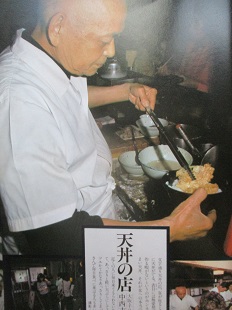
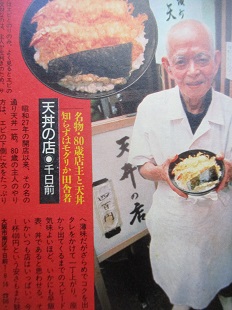
1976年7月 『月刊食堂別冊「天ぷら」柴田書店〇天丼の店(中西吉太郎)は大阪ミナミにある小さな店で、、私もかれこれ10回は食べている。熱々で美味しい。

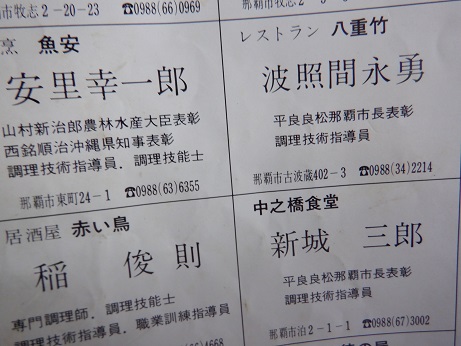
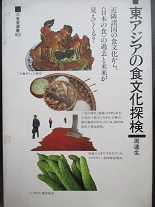


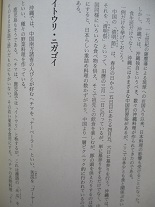
1991年7月 周達生『東アジアの食文化探検』三省堂〇沖縄の「肉」/沖縄の特徴/イトウリ・ニガゴイー沖縄では、中国南方諸省の人びとが好むヘチマを「ナーベーラー」といい、苦瓜を「ゴーヤー」といい、種々の野菜料理を作っている。
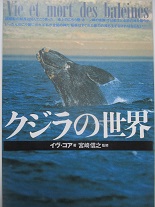
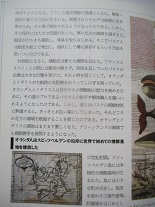


1991年12月 イヴ・コア/宮崎信之『クジラの世界』創元社
04/24: アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年
1945年4月
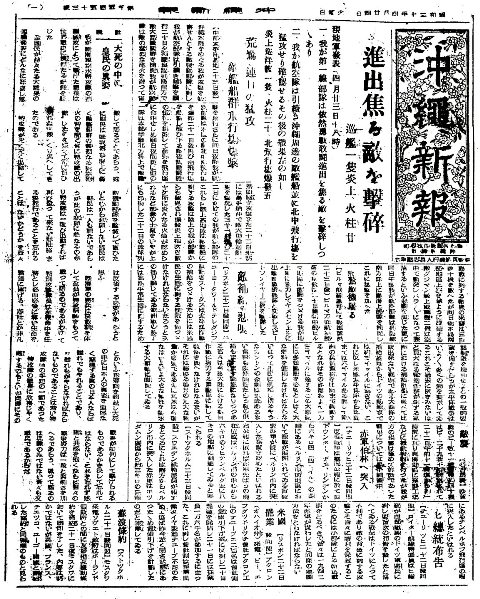
『沖縄新報』
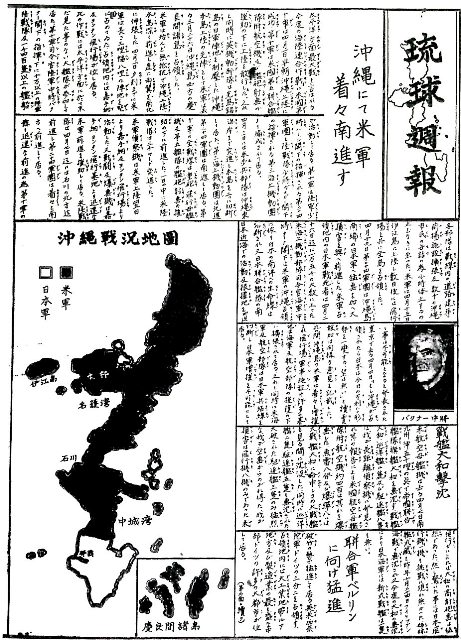
『琉球週報』
1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
1945年5月7日 石川に城前初等学校開校
1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」
1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動
1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」
1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人
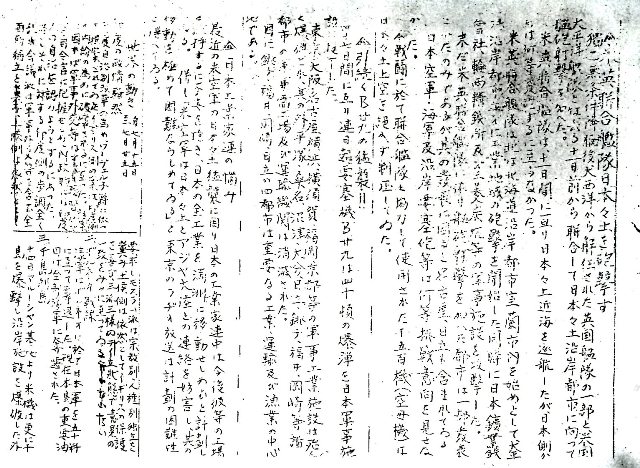
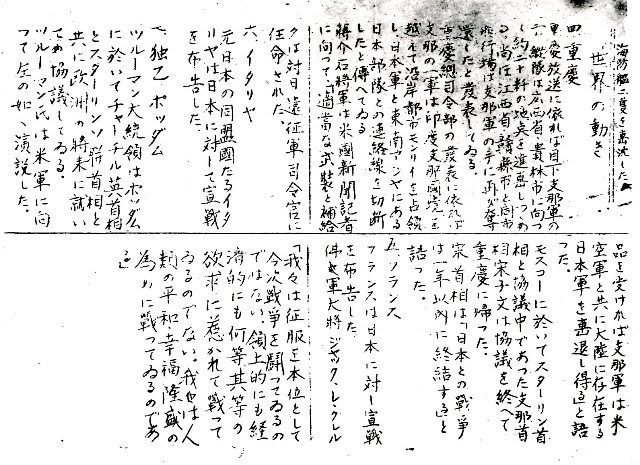
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
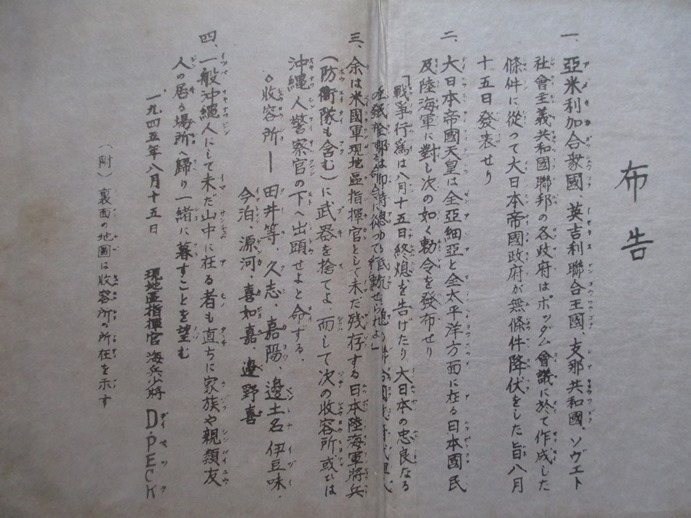
1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」
1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」
1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足
1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」
1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)
1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」
1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」
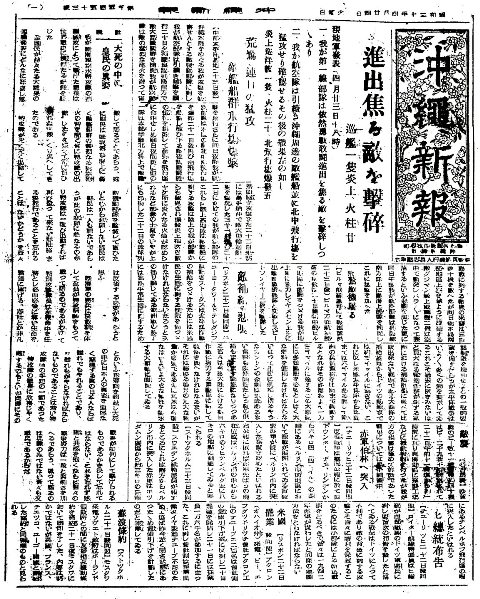
『沖縄新報』
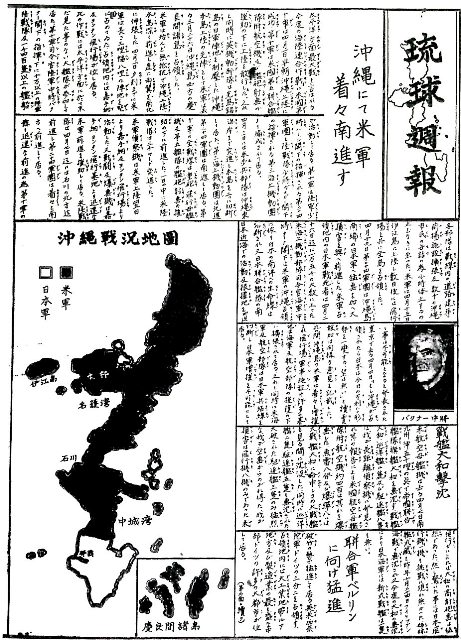
『琉球週報』
1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
1945年5月7日 石川に城前初等学校開校
1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」
1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動
1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」
1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人
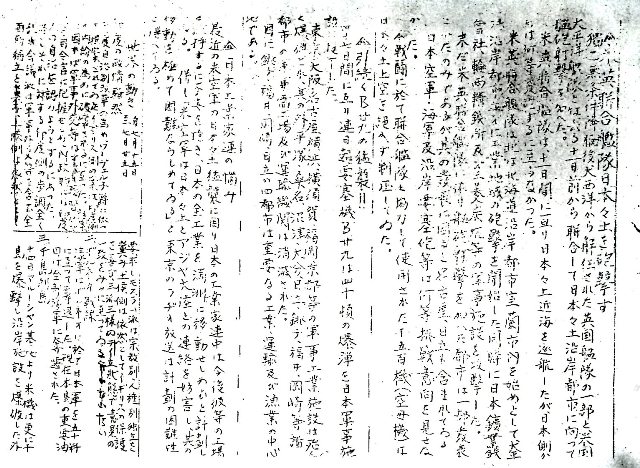
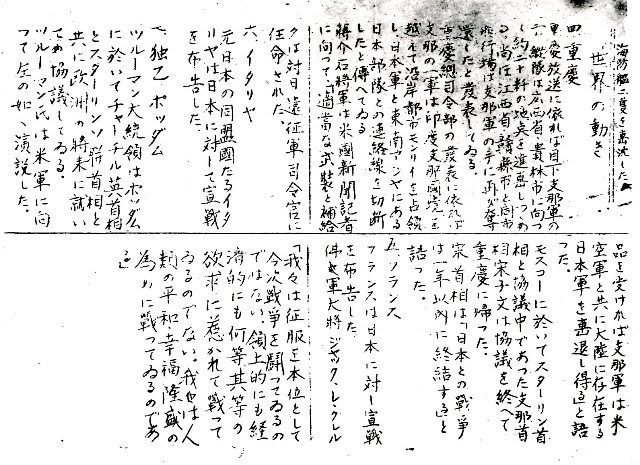
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
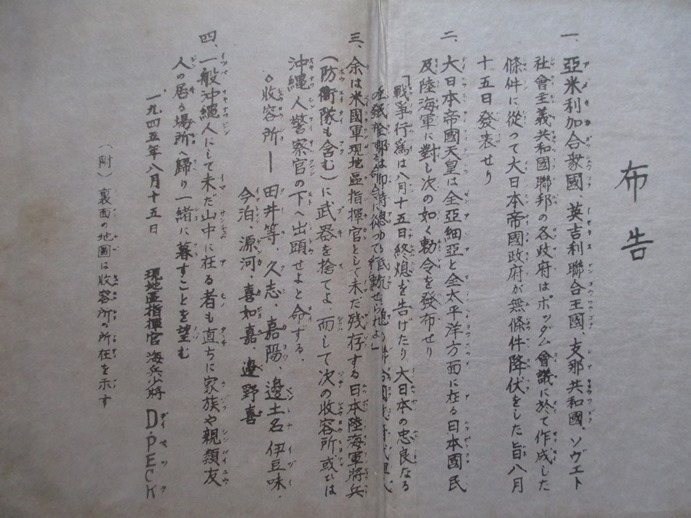
1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」
1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」
1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足
1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」
1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)
1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」
1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」
2015年6月6日14:00~16*00 沖縄県立博物館・美術館3F講堂 講演会「ファンタジー・魔法・ドリーマー」講師 大城冝武
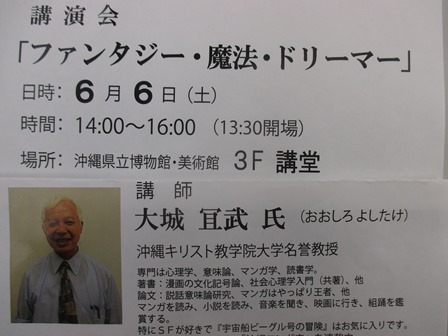
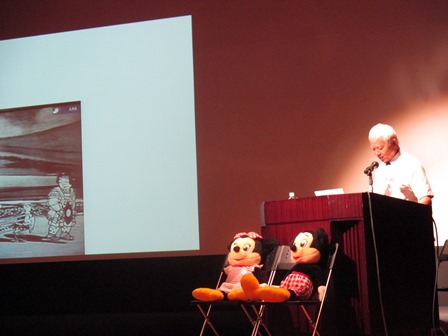
大城冝武氏

大城冝武氏、國吉貴奈さん
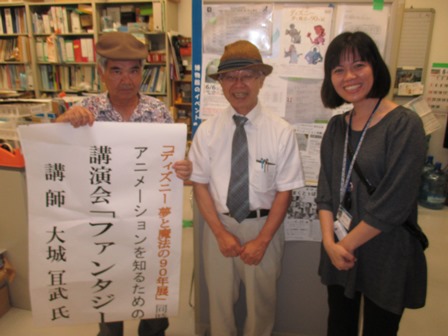
左から新城栄徳、大城冝武さん、海勢頭利江さん
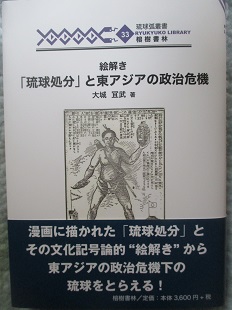
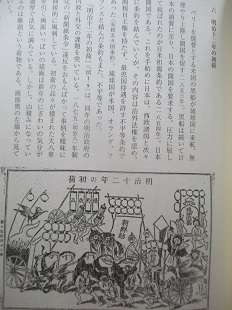
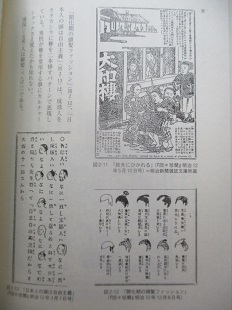
2019年12月 大城冝武『絵解き 「琉球処分」と東アジアの政治危機』榕樹書林
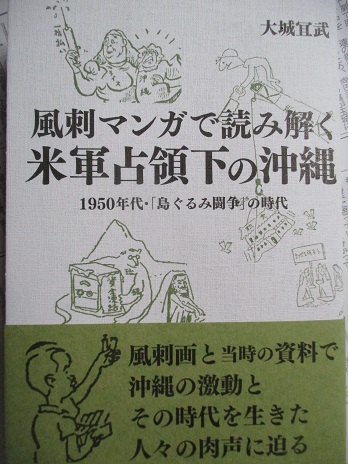
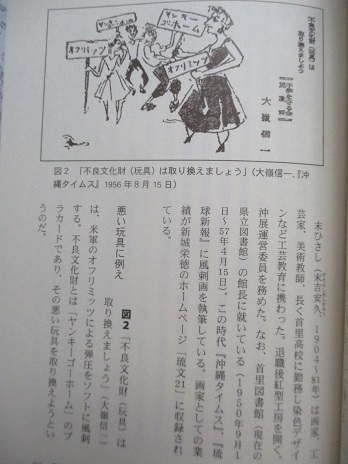
2020年3月 大城冝武『風刺マンガで読み解く 米軍占領下の沖縄』沖縄タイムス社
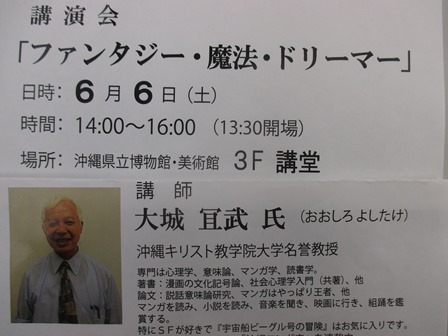
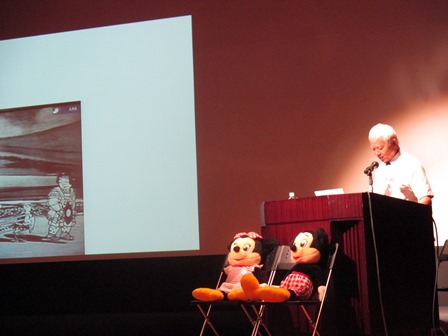
大城冝武氏

大城冝武氏、國吉貴奈さん
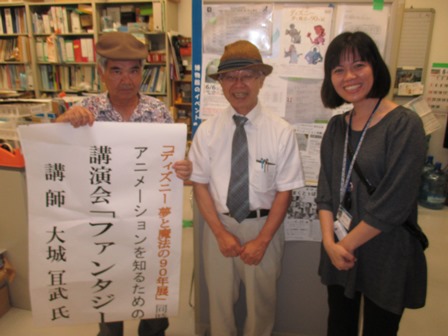
左から新城栄徳、大城冝武さん、海勢頭利江さん
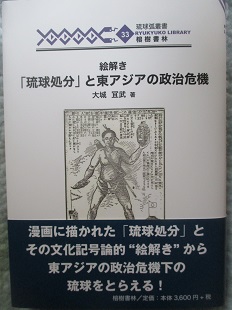
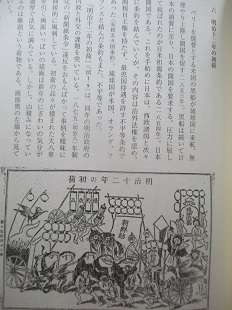
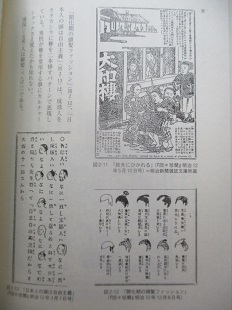
2019年12月 大城冝武『絵解き 「琉球処分」と東アジアの政治危機』榕樹書林
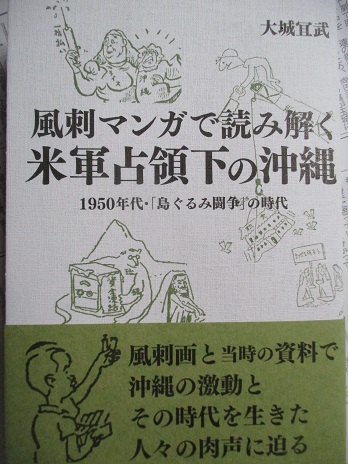
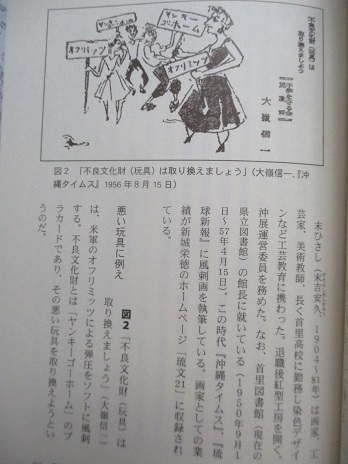
2020年3月 大城冝武『風刺マンガで読み解く 米軍占領下の沖縄』沖縄タイムス社
02/18: 世相ジャパン(57)
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com
「くろねこの短語」2021年2月28日 (前略)で、笑っちゃうのが、夫婦別姓反対しておきながら、自分は旧姓の「丸川」を使ってるんだから、何考えてんだか。もっとも、このネーチャンに政治的信念なんかないのはわかってることだけど・・・。丸川珠代の他にも、野田聖子、三原じゅん子が旧姓を使用しているんだね。そう言えば、飲み会を断らない女・山田広報官も旧姓使用組だ。てことは、「選択的夫婦別姓」を実現してるようなもんじゃないのか。
それはともかく、“ジェンダー平等の旗振り役”である男女共同参画担当大臣が、「選択的夫婦別姓」に反対するってのは大いなる矛盾であって、そんな無節操な政治屋が「あらゆる差別と闘う」というオリンピズムを遵守すべき五輪担当大臣でもあるなんて、へそが茶を沸かしますよ、ったく。/昭恵の女子会で、昭恵の隣をキープする山田真貴子の写真、貼っておこう。端っこに谷査恵子、昭恵の隣に小野さんも居るよ〜有能な人かもしれないが、自民党政権の中で腐れていくのは気の毒だ。


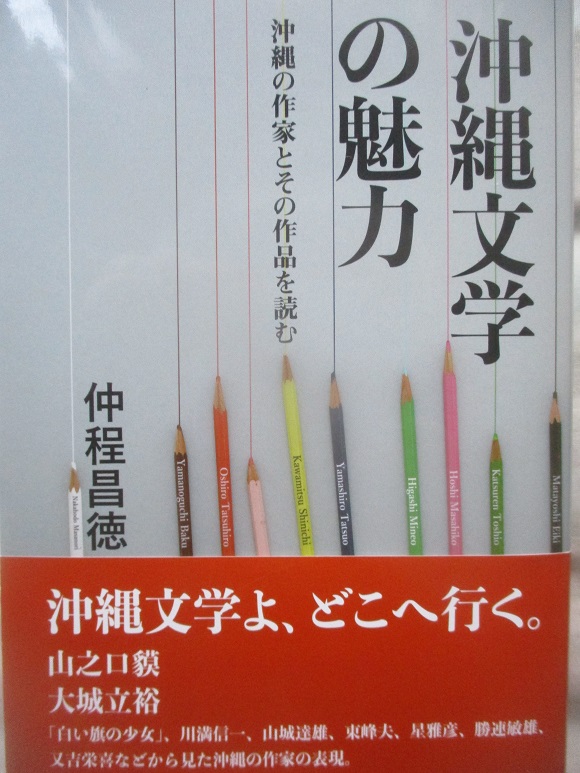
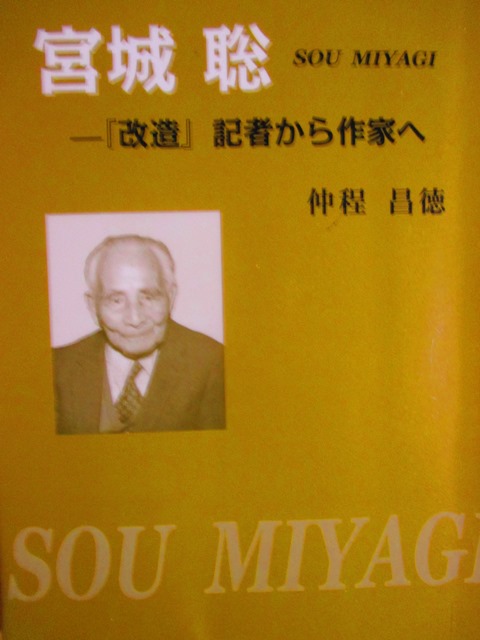
2021年2月 仲程昌徳『沖縄文学の魅力』ボーダーインク/2014年5月 仲程昌徳『宮城聡』ボーダーインク
2-27 今日はジュールクニチは、グソーの正月。昨年は家の母が95歳で亡くなったので初十六日。東大阪の息子夫婦も参加するはずがコロナ禍で無理。昼、弟の車で高速道路を通って、読谷の父母の墓の掃除、花を活けて供養。その後、泊の家でお供え物でウチカビ。読谷の娘親子もきた。








2-26 曇り空なので出る気はないが、家の前を左に直進すると、なかのはし薬局がみえる。近隣は病院が多い。さらに進むと泊小学校が左に見える、息子、娘の母校。進むと「黄金森公園(くがにむいこうえん)」。側の階段を上ると、右にNHK、YAMADA。その向こうが沖縄県立博物館・美術館。
海鳴りの島から 2-26 長年にわたり遺骨を収集してきた人たちは尊敬するし、戦死者の遺骨の上に軍事基地を作るのは、私も我慢がならない。ただ、これから使用される予定の南部の土砂が話題になる一方で、北部の土砂を使って現に進められている辺野古の埋め立てには、どれだけの関心が向けられているか、と日々疑問が湧き起こる。止めることができないまま、埋め立てが進行している現場(現実)から目をそらしているのではないか。
「くろねこの短語」2021年2月26日 「木で鼻を括る」「糠に釘」「暖簾に腕押し」「馬耳東風」・・・いやいやそれより「蛙の面に小便」って言うのが最もふさわしい。何がって、昨日の衆議院予算委員会における飲み会を断らない女・山田真貴子君の答弁だ。言葉の端々から覗くのは、「全体の奉仕者」なんてことは考えたこともないだろう権力志向に陥った官僚のおぞましさなんだね。「反省」を口にはするけど、腹の中では「知ったことか」って居直っているのに違いない。
たとえば、NHKに抗議の電話をかけたかって質問に「携帯の履歴を調べないとわからない」ときたもんだ。カス総理のロン毛の息子についても「(カス総理が総務大臣時代に)秘書官だったことはこの騒動で初めて知った」とさ。会食の際に「名刺交換はしていない」なんてことものたまってくれたようだが、ここまでくるとその面の皮の厚さに拍手したくなるほどだ。
2-25 14時、泊・家の前の通りを左に直進して久米の山田写真機店までの風景。ローソン前島店改装準備中。魚料理屋が座席は密状態で、表に並んでいる。セブンイレブン前島店入ったら密状態なのですぐに出た。美栄橋駅、県庁前駅
右、




「くろねこの短語」2021年2月24日 (前略)新悪いことはできないもので、エビフリャー河村君に対するリコール運動の動きもあるってんだから愉快な展開になったきたものだ。イエス高須君もこのままだと責任者として逮捕される可能性もあるから、しばらくは眠れない夜が続くことだろう。眠れないのは大阪のチンピラ市長も同じで、署名偽造の実行者と疑われている事務局長は維新の仲間ですからね。リコールを支援していたイソジン吉村君共々、とにかく火の粉が飛んでこないことを必死に祈っていることだろう。
[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米国で22日、新型コロナウイルス感染症による累計の死者が50万人を突破した。新型コロナのパンデミック(世界的大流行)が始まってから、米国民の673人に1人が犠牲になったことを意味する。バイデン米大統領はこの日、ホワイトハウスで開催した新型コロナ犠牲者の追悼式で演説し、米国民に対し、党派的な対立を脇に置いて新型コロナとの闘いで団結するよう呼び掛けた。
バイデン氏は「われわれはきょう、非常に残酷で悲痛な節目を迎えた。このパンデミックで1年間に50万0071人の方々が亡くなった。これは第1次世界大戦、第2次世界大戦、ベトナム戦争を合わせた死者よりも多い」と指摘。とあるが、南北戦争は両軍合わせて50万人近くの戦死者を出している。→ウィキ
いんしゃあ かなす 2-20 今日の宮古島地元紙より◼️クラスターが発生し、自衛隊が「応援」に入った老健施設で、昨日発表で6名(合計9名)の死亡者が出たというニュース。私は知人の看護師からこの施設で死亡者が複数出ていることを聞いていたが、なぜ発表されないのか?と疑問に思っていた。40名もの自衛隊(看護官5名)が入り、医療体制はどのようになっていたのか?自衛隊が引き上げるまで発表を引き延ばしていたかのようなタイミングだ。◼️地震の多い宮古島。毎月140回もの地震。活断層も多い。しかも地下水の島。こういうことろに、基地など作るべきではない!/M・T それをいいことに、嘘とごまかしで 権力の維持継続をもくろむ 敵基地攻撃能力で南西諸島での軍備増強 やりたい放題の米軍の演習も我関せず 沖縄県民の命、コロナで苦しむ国民など、政治の眼中にない 世界の物笑いの種ばかりの政治をこのまま続けるのか。
「くろねこの短語」2021年2月20日 (前略)新聞テレビが総務省接待疑惑を叩けない理由 検察もまったく動く気配を見せないし、ロンゲの息子を守るために、高級官僚の左遷で一件落着とは、国民を舐めるのも大概にしやがれ・・・・ってなもんです。ところで、橋本セクハラ聖子君が自民党を離党した。ちょいと様子見してたんだろうが、「自民党の自民党による自民党のためのオリンピック」なんて声が漏れ聞こえてきたのだろう。早々に自民党離党を決めましたとさ。
組織委員会会長騒動がとりあえずおさまって、メディアからはオリンピックに前向きな報道もチラついているけど、そうは問屋が卸しませんよ。なんと、福島第一原発の1、3号機格納容器の水位が先日の地震で低下しているそうだ。サメの脳みその女性蔑視発言よりも、こちらの問題の方がオリンピック中止の理由に十分なり得るんだね。日本は、原子力緊急事態宣言の最中にある、ってことを忘れちゃいけない。オリンピサクなんかにかまけている場合じゃないだろうと改めて思い知らされる今日この頃なのだ。
「くろねこの短語」2021年2月17日 (前略)ところで、経済同友会の桜田謙悟代表幹事が、企業で女性の役員登用が進んでいない理由を問われ「女性側にも原因がないことはない」とし、「チャンスを積極的に取りにいこうとする女性がまだそれほど多くないのではないか」との認識を示した。ってね。積極的な女性を排除するシステムこそが問題なのに、「女性側にも原因がないことはない」とはねえ。
土建政治の二階君が、「自民党の幹部会議に女性議員を発言権のないオブザーバーとして出席させてやる」って偉そうにのたまったそうだが、これも経済同友会代表幹事の発言とその根は同じなんだね。こんなひとたちの存在が日本のジェンダーギャップ指数を世界144か国中114位という情けないレベルに引き下げてるのは間違いない。最後に、愛知県知事リコール不正は、維新と日本会議の影がチラつくようで、イエス高須とエビフリャー河村の両君は、どうあがいてもお咎めなしではすみそうにありません。逮捕も十分にある展開で、どえりゃーことになってきましたとさ。
『週刊ポスト』2021年2月26日・3月5日号 政治の失敗、人災であることを示している。“コロナ戦犯政治家”の筆頭に挙げられるのは安倍晋三・前首相だろう。コロナ対策の初動を誤って感染を広げながら、途中で政権を投げ出し、“敵前逃亡”を決め込んだ。安倍政権は中国が武漢を封鎖後も、予定されていた習近平・国家主席の来日に影響が出ることを恐れて中国からの入国禁止措置の発動が遅れ、中国人観光客を受け入れた。(略)
そうした最悪の事態を予期しながら、感染第2波さなかの8月28日に突然、持病の悪化を理由に退陣を表明し、菅義偉・首相が政権を継いだ。当時は、「病気なら仕方ない」と同情された。ところが、退陣後の安倍氏は入院や静養するのではなく、コロナ対応を投げ出したことを棚に上げて「ポストコロナの経済政策を考える議員連盟」会長に就任して政治活動を再開。「“再々登板”に意欲がある」(細田派幹部)といわれるほどだ。
安倍政権の初動の失敗には、「これは風邪だから、はやり病だから」と楽観視していた麻生太郎・副総理兼財務相をはじめ、梶山弘志・経産相、赤羽一嘉・国交相、萩生田光一・文科相ら菅政権で再任された大臣たちも連帯責任を負っている。

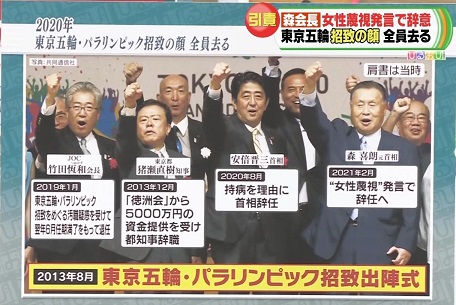
HIRO 2-16 森喜朗氏の五輪関連で年間六千万の話。復興五輪とは名ばかりで、人件費や資材の高騰で復興の妨げになっていた。国民の8割が中止や延期を望んでいるのに、何としても開催したい政府と東京都。大きく膨れ上がった五輪予算は利権漁りの温床になっている。森氏だけの問題ではない。徹底的な調査が必要だ。//『毎日新聞』12日 12日に開かれた東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の評議員と理事による緊急会合で、森喜朗会長(83)は辞任すると表明した。森氏の辞任で東京オリンピックの招致の「顔」だった4人が、いずれも不本意な形で表舞台から去った。2013年9月の招致決定当時、東京都知事だった猪瀬直樹氏(74)、日本オリンピック委員会(JOC)会長だった竹田恒和氏(73)、首相だった安倍晋三氏(66)、そして招致委員会評議会議長だった森氏だ。JOC関係者は「やはり、東京五輪は呪われているのだろうか」と表情を曇らせた。
斎藤 陽子 (Walnut, California) 2021-2ー6 7年前Facebook本社を訪ねた後、Google社の本社へも行ってきました。【思い出のアルバム】Facebook本社に寄った後、シリコン・バレーの北カリフォルニア・マウンティンビュー、アンフィシアター・パークウェーにあります、Google本社にも行ってきました。こちらもFacebook同様、セキュリティーが厳しく、会社訪問はいろいろ手続きが要ります。5年ほど前に、初めて空中からの鮮明な自宅写真をGoogleの空中写真で見た時の驚きは忘れられません。みなさまもご存知のように、この会社のニュースやオンライン翻訳サービス、画像検索やマップなどと、私たちの身辺の「お助け」役として、便利さを求めて何かと身近な存在の会社です。
1998年に、この近くにありますスタンフォード大学の学生が作った会社として有名です。この会社もFacebook社同様、各国の料理を無料で社員に提供し始めたことでも話題を呼んでいますが、ユニークなことは猫以外のペットを職場に持ち込むことも可能だということです。おもちゃの遊び道具なども仕事場にあり、フィトネスのジムやサウナもあり、仕事のストレスを如何に緩和してもらうかとユニークなことを導入している会社で、世界の人々に利用されている検索エンジンの会社です。Google本社の中に点在する棟にゆくための、社員が使うグーグル・カラーのカラフルな自転車が、社内敷地の各地の自転車置き場にありました。従業員はグーグル・カラーの椅子に座り、芝生の中庭でくつろぎながら仕事をしている風景は大学のキャンパス風景にも似ています。




斎藤 陽子 (Walnut, California) 2021-2ー5 遠くふる里 日本とアメリカを瞬時に結んでくれるFscebookは私にとって神々しい存在ですが、7年前にそのFscebook本社を訪問することができました。【思い出のアルバム】
シリコン・バレーと言われている、北カリフォルニア州パロアルト・メンロパークにある、Facebookの本社を訪問しました。私は2009年からお世話になっていますこのFacebook会社、みなさんの中には、毎日お世話になったている方も多いと思います。本社前には「いいね」の看板と1 Hacker Wayの住所の表記がありますが、通常はここから先の駐車場含め本社には関係者以外入る事が出来ず、セキュリティーが厳しい会社で、唯一この会社で働いている友人の招待で、見学がかないました。シリコンバレーにはこの他 Apple や Google 等の、世界的な大企がありますが、これらの利益が多い会社はそこの地域に納める税金の額も莫大という事から、地域の住所の名前を名付ける権利を与えられている場合が多いです。 Facebookの住所は『1 Hacker Way』と付けれていますが、これは世界で一番のハッカー(エンジニア)が集まるという意味を込めているようにも思え、ユーモアを感じます。
Facebook社は2004年創業で、従業員はこの本社だけで400人ほどとのことですが全世界支社のFB社員数を含めるとは相当数になります。FB社の立ち上げ当初の会員はハーバード大学のドメインのメールアドレスを持つ学生に限定されている学生仲間だけのものでした。やがてボストン地域の大学、アイビーリーグの大学、スタンフォード大学へと対象が拡大されてゆき、徐々にさまざまな大学の学生も対象に加わり、やがて高校生にも開放され、最終的には13歳以上のすべての人に開放され、現在のFacebookに至ったとのことで、ユーザー登録時に13歳以上であることを宣言すれば誰でも会員になれることになりました。会社に入って見学終了するまで、セキュリティーが厳しく、ここで働いている友人のエスコートが、見学終了するまで必要です。
この会社の建物は公園内のような敷地に幾つも有り、大学キャンパスのような雰囲気からか、彼らはここをキャンパスと呼んでいました。本社はメインの大通りに沿って、街並みがあるような通りで、無料のレストラン、これも無料のアイスクリームショップなどや、お土産物屋、自転車ショップなどが用意され、各所に有るも飲料水の自販機もすべて無料です。社員食堂ではアメリカンから、寿司有りイタリアン多国籍まで様々な料理が用意され、キャフテリア方式で常時無料で食べられ、社員と並んで社食も食べてきました。Facebookと言えば有名な Facebook Wall もFacebook本社内の至るところに用意されており、訪問者が記念に落書きをする壁もありました。中庭には、社員用のバーベキューなども有りました、もちろん無料です。本社の中庭は広いので、社員は他の棟に行く時には二人乗り三輪車が交通手段でした。創業者マーク・ザッカーバーグがハーバードの大学寮から、Facebook を起こし、スタートアップの急成長で、これほど世界的大企業に成長させた、若者の偉業を驚嘆する思いで見てきました。




「くろねこの短語」2021年2月28日 (前略)で、笑っちゃうのが、夫婦別姓反対しておきながら、自分は旧姓の「丸川」を使ってるんだから、何考えてんだか。もっとも、このネーチャンに政治的信念なんかないのはわかってることだけど・・・。丸川珠代の他にも、野田聖子、三原じゅん子が旧姓を使用しているんだね。そう言えば、飲み会を断らない女・山田広報官も旧姓使用組だ。てことは、「選択的夫婦別姓」を実現してるようなもんじゃないのか。
それはともかく、“ジェンダー平等の旗振り役”である男女共同参画担当大臣が、「選択的夫婦別姓」に反対するってのは大いなる矛盾であって、そんな無節操な政治屋が「あらゆる差別と闘う」というオリンピズムを遵守すべき五輪担当大臣でもあるなんて、へそが茶を沸かしますよ、ったく。/昭恵の女子会で、昭恵の隣をキープする山田真貴子の写真、貼っておこう。端っこに谷査恵子、昭恵の隣に小野さんも居るよ〜有能な人かもしれないが、自民党政権の中で腐れていくのは気の毒だ。


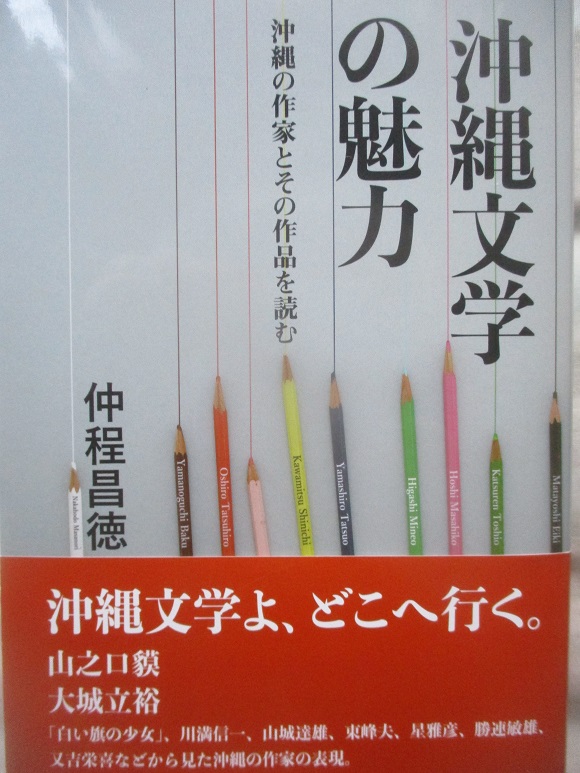
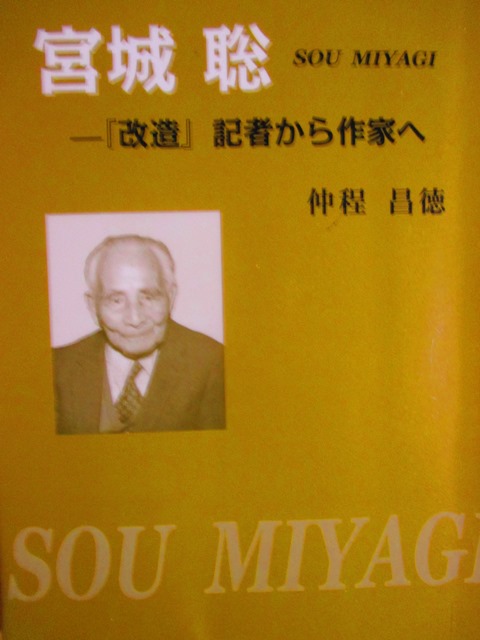
2021年2月 仲程昌徳『沖縄文学の魅力』ボーダーインク/2014年5月 仲程昌徳『宮城聡』ボーダーインク
2-27 今日はジュールクニチは、グソーの正月。昨年は家の母が95歳で亡くなったので初十六日。東大阪の息子夫婦も参加するはずがコロナ禍で無理。昼、弟の車で高速道路を通って、読谷の父母の墓の掃除、花を活けて供養。その後、泊の家でお供え物でウチカビ。読谷の娘親子もきた。








2-26 曇り空なので出る気はないが、家の前を左に直進すると、なかのはし薬局がみえる。近隣は病院が多い。さらに進むと泊小学校が左に見える、息子、娘の母校。進むと「黄金森公園(くがにむいこうえん)」。側の階段を上ると、右にNHK、YAMADA。その向こうが沖縄県立博物館・美術館。
海鳴りの島から 2-26 長年にわたり遺骨を収集してきた人たちは尊敬するし、戦死者の遺骨の上に軍事基地を作るのは、私も我慢がならない。ただ、これから使用される予定の南部の土砂が話題になる一方で、北部の土砂を使って現に進められている辺野古の埋め立てには、どれだけの関心が向けられているか、と日々疑問が湧き起こる。止めることができないまま、埋め立てが進行している現場(現実)から目をそらしているのではないか。
「くろねこの短語」2021年2月26日 「木で鼻を括る」「糠に釘」「暖簾に腕押し」「馬耳東風」・・・いやいやそれより「蛙の面に小便」って言うのが最もふさわしい。何がって、昨日の衆議院予算委員会における飲み会を断らない女・山田真貴子君の答弁だ。言葉の端々から覗くのは、「全体の奉仕者」なんてことは考えたこともないだろう権力志向に陥った官僚のおぞましさなんだね。「反省」を口にはするけど、腹の中では「知ったことか」って居直っているのに違いない。
たとえば、NHKに抗議の電話をかけたかって質問に「携帯の履歴を調べないとわからない」ときたもんだ。カス総理のロン毛の息子についても「(カス総理が総務大臣時代に)秘書官だったことはこの騒動で初めて知った」とさ。会食の際に「名刺交換はしていない」なんてことものたまってくれたようだが、ここまでくるとその面の皮の厚さに拍手したくなるほどだ。
2-25 14時、泊・家の前の通りを左に直進して久米の山田写真機店までの風景。ローソン前島店改装準備中。魚料理屋が座席は密状態で、表に並んでいる。セブンイレブン前島店入ったら密状態なのですぐに出た。美栄橋駅、県庁前駅
右、




「くろねこの短語」2021年2月24日 (前略)新悪いことはできないもので、エビフリャー河村君に対するリコール運動の動きもあるってんだから愉快な展開になったきたものだ。イエス高須君もこのままだと責任者として逮捕される可能性もあるから、しばらくは眠れない夜が続くことだろう。眠れないのは大阪のチンピラ市長も同じで、署名偽造の実行者と疑われている事務局長は維新の仲間ですからね。リコールを支援していたイソジン吉村君共々、とにかく火の粉が飛んでこないことを必死に祈っていることだろう。
[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米国で22日、新型コロナウイルス感染症による累計の死者が50万人を突破した。新型コロナのパンデミック(世界的大流行)が始まってから、米国民の673人に1人が犠牲になったことを意味する。バイデン米大統領はこの日、ホワイトハウスで開催した新型コロナ犠牲者の追悼式で演説し、米国民に対し、党派的な対立を脇に置いて新型コロナとの闘いで団結するよう呼び掛けた。
バイデン氏は「われわれはきょう、非常に残酷で悲痛な節目を迎えた。このパンデミックで1年間に50万0071人の方々が亡くなった。これは第1次世界大戦、第2次世界大戦、ベトナム戦争を合わせた死者よりも多い」と指摘。とあるが、南北戦争は両軍合わせて50万人近くの戦死者を出している。→ウィキ
いんしゃあ かなす 2-20 今日の宮古島地元紙より◼️クラスターが発生し、自衛隊が「応援」に入った老健施設で、昨日発表で6名(合計9名)の死亡者が出たというニュース。私は知人の看護師からこの施設で死亡者が複数出ていることを聞いていたが、なぜ発表されないのか?と疑問に思っていた。40名もの自衛隊(看護官5名)が入り、医療体制はどのようになっていたのか?自衛隊が引き上げるまで発表を引き延ばしていたかのようなタイミングだ。◼️地震の多い宮古島。毎月140回もの地震。活断層も多い。しかも地下水の島。こういうことろに、基地など作るべきではない!/M・T それをいいことに、嘘とごまかしで 権力の維持継続をもくろむ 敵基地攻撃能力で南西諸島での軍備増強 やりたい放題の米軍の演習も我関せず 沖縄県民の命、コロナで苦しむ国民など、政治の眼中にない 世界の物笑いの種ばかりの政治をこのまま続けるのか。
「くろねこの短語」2021年2月20日 (前略)新聞テレビが総務省接待疑惑を叩けない理由 検察もまったく動く気配を見せないし、ロンゲの息子を守るために、高級官僚の左遷で一件落着とは、国民を舐めるのも大概にしやがれ・・・・ってなもんです。ところで、橋本セクハラ聖子君が自民党を離党した。ちょいと様子見してたんだろうが、「自民党の自民党による自民党のためのオリンピック」なんて声が漏れ聞こえてきたのだろう。早々に自民党離党を決めましたとさ。
組織委員会会長騒動がとりあえずおさまって、メディアからはオリンピックに前向きな報道もチラついているけど、そうは問屋が卸しませんよ。なんと、福島第一原発の1、3号機格納容器の水位が先日の地震で低下しているそうだ。サメの脳みその女性蔑視発言よりも、こちらの問題の方がオリンピック中止の理由に十分なり得るんだね。日本は、原子力緊急事態宣言の最中にある、ってことを忘れちゃいけない。オリンピサクなんかにかまけている場合じゃないだろうと改めて思い知らされる今日この頃なのだ。
「くろねこの短語」2021年2月17日 (前略)ところで、経済同友会の桜田謙悟代表幹事が、企業で女性の役員登用が進んでいない理由を問われ「女性側にも原因がないことはない」とし、「チャンスを積極的に取りにいこうとする女性がまだそれほど多くないのではないか」との認識を示した。ってね。積極的な女性を排除するシステムこそが問題なのに、「女性側にも原因がないことはない」とはねえ。
土建政治の二階君が、「自民党の幹部会議に女性議員を発言権のないオブザーバーとして出席させてやる」って偉そうにのたまったそうだが、これも経済同友会代表幹事の発言とその根は同じなんだね。こんなひとたちの存在が日本のジェンダーギャップ指数を世界144か国中114位という情けないレベルに引き下げてるのは間違いない。最後に、愛知県知事リコール不正は、維新と日本会議の影がチラつくようで、イエス高須とエビフリャー河村の両君は、どうあがいてもお咎めなしではすみそうにありません。逮捕も十分にある展開で、どえりゃーことになってきましたとさ。
『週刊ポスト』2021年2月26日・3月5日号 政治の失敗、人災であることを示している。“コロナ戦犯政治家”の筆頭に挙げられるのは安倍晋三・前首相だろう。コロナ対策の初動を誤って感染を広げながら、途中で政権を投げ出し、“敵前逃亡”を決め込んだ。安倍政権は中国が武漢を封鎖後も、予定されていた習近平・国家主席の来日に影響が出ることを恐れて中国からの入国禁止措置の発動が遅れ、中国人観光客を受け入れた。(略)
そうした最悪の事態を予期しながら、感染第2波さなかの8月28日に突然、持病の悪化を理由に退陣を表明し、菅義偉・首相が政権を継いだ。当時は、「病気なら仕方ない」と同情された。ところが、退陣後の安倍氏は入院や静養するのではなく、コロナ対応を投げ出したことを棚に上げて「ポストコロナの経済政策を考える議員連盟」会長に就任して政治活動を再開。「“再々登板”に意欲がある」(細田派幹部)といわれるほどだ。
安倍政権の初動の失敗には、「これは風邪だから、はやり病だから」と楽観視していた麻生太郎・副総理兼財務相をはじめ、梶山弘志・経産相、赤羽一嘉・国交相、萩生田光一・文科相ら菅政権で再任された大臣たちも連帯責任を負っている。

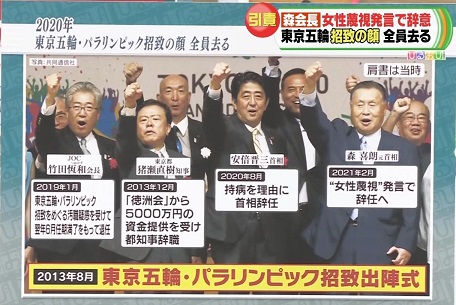
HIRO 2-16 森喜朗氏の五輪関連で年間六千万の話。復興五輪とは名ばかりで、人件費や資材の高騰で復興の妨げになっていた。国民の8割が中止や延期を望んでいるのに、何としても開催したい政府と東京都。大きく膨れ上がった五輪予算は利権漁りの温床になっている。森氏だけの問題ではない。徹底的な調査が必要だ。//『毎日新聞』12日 12日に開かれた東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の評議員と理事による緊急会合で、森喜朗会長(83)は辞任すると表明した。森氏の辞任で東京オリンピックの招致の「顔」だった4人が、いずれも不本意な形で表舞台から去った。2013年9月の招致決定当時、東京都知事だった猪瀬直樹氏(74)、日本オリンピック委員会(JOC)会長だった竹田恒和氏(73)、首相だった安倍晋三氏(66)、そして招致委員会評議会議長だった森氏だ。JOC関係者は「やはり、東京五輪は呪われているのだろうか」と表情を曇らせた。
斎藤 陽子 (Walnut, California) 2021-2ー6 7年前Facebook本社を訪ねた後、Google社の本社へも行ってきました。【思い出のアルバム】Facebook本社に寄った後、シリコン・バレーの北カリフォルニア・マウンティンビュー、アンフィシアター・パークウェーにあります、Google本社にも行ってきました。こちらもFacebook同様、セキュリティーが厳しく、会社訪問はいろいろ手続きが要ります。5年ほど前に、初めて空中からの鮮明な自宅写真をGoogleの空中写真で見た時の驚きは忘れられません。みなさまもご存知のように、この会社のニュースやオンライン翻訳サービス、画像検索やマップなどと、私たちの身辺の「お助け」役として、便利さを求めて何かと身近な存在の会社です。
1998年に、この近くにありますスタンフォード大学の学生が作った会社として有名です。この会社もFacebook社同様、各国の料理を無料で社員に提供し始めたことでも話題を呼んでいますが、ユニークなことは猫以外のペットを職場に持ち込むことも可能だということです。おもちゃの遊び道具なども仕事場にあり、フィトネスのジムやサウナもあり、仕事のストレスを如何に緩和してもらうかとユニークなことを導入している会社で、世界の人々に利用されている検索エンジンの会社です。Google本社の中に点在する棟にゆくための、社員が使うグーグル・カラーのカラフルな自転車が、社内敷地の各地の自転車置き場にありました。従業員はグーグル・カラーの椅子に座り、芝生の中庭でくつろぎながら仕事をしている風景は大学のキャンパス風景にも似ています。




斎藤 陽子 (Walnut, California) 2021-2ー5 遠くふる里 日本とアメリカを瞬時に結んでくれるFscebookは私にとって神々しい存在ですが、7年前にそのFscebook本社を訪問することができました。【思い出のアルバム】
シリコン・バレーと言われている、北カリフォルニア州パロアルト・メンロパークにある、Facebookの本社を訪問しました。私は2009年からお世話になっていますこのFacebook会社、みなさんの中には、毎日お世話になったている方も多いと思います。本社前には「いいね」の看板と1 Hacker Wayの住所の表記がありますが、通常はここから先の駐車場含め本社には関係者以外入る事が出来ず、セキュリティーが厳しい会社で、唯一この会社で働いている友人の招待で、見学がかないました。シリコンバレーにはこの他 Apple や Google 等の、世界的な大企がありますが、これらの利益が多い会社はそこの地域に納める税金の額も莫大という事から、地域の住所の名前を名付ける権利を与えられている場合が多いです。 Facebookの住所は『1 Hacker Way』と付けれていますが、これは世界で一番のハッカー(エンジニア)が集まるという意味を込めているようにも思え、ユーモアを感じます。
Facebook社は2004年創業で、従業員はこの本社だけで400人ほどとのことですが全世界支社のFB社員数を含めるとは相当数になります。FB社の立ち上げ当初の会員はハーバード大学のドメインのメールアドレスを持つ学生に限定されている学生仲間だけのものでした。やがてボストン地域の大学、アイビーリーグの大学、スタンフォード大学へと対象が拡大されてゆき、徐々にさまざまな大学の学生も対象に加わり、やがて高校生にも開放され、最終的には13歳以上のすべての人に開放され、現在のFacebookに至ったとのことで、ユーザー登録時に13歳以上であることを宣言すれば誰でも会員になれることになりました。会社に入って見学終了するまで、セキュリティーが厳しく、ここで働いている友人のエスコートが、見学終了するまで必要です。
この会社の建物は公園内のような敷地に幾つも有り、大学キャンパスのような雰囲気からか、彼らはここをキャンパスと呼んでいました。本社はメインの大通りに沿って、街並みがあるような通りで、無料のレストラン、これも無料のアイスクリームショップなどや、お土産物屋、自転車ショップなどが用意され、各所に有るも飲料水の自販機もすべて無料です。社員食堂ではアメリカンから、寿司有りイタリアン多国籍まで様々な料理が用意され、キャフテリア方式で常時無料で食べられ、社員と並んで社食も食べてきました。Facebookと言えば有名な Facebook Wall もFacebook本社内の至るところに用意されており、訪問者が記念に落書きをする壁もありました。中庭には、社員用のバーベキューなども有りました、もちろん無料です。本社の中庭は広いので、社員は他の棟に行く時には二人乗り三輪車が交通手段でした。創業者マーク・ザッカーバーグがハーバードの大学寮から、Facebook を起こし、スタートアップの急成長で、これほど世界的大企業に成長させた、若者の偉業を驚嘆する思いで見てきました。




03/01: 世相ジャパン(58)
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com

3月20日 彼岸(祖先供養の行事)仏壇に御馳走を供えて祖先供養を行う。紙銭を焼く
「くろねこの短語」2021年3月19日 (前略)ようするに、シンキロー森とオリンピッグ佐々木君がクリエイティフチームを乗っ取って、いわば五輪開閉会式の私物化を図ったってことなのだろう。これって、エンブレムの盗作騒動を思い起こさせてくれる。あの時も、盗作疑惑のデサイナーの人間関係が問題になりましたからね。渡辺直美を豚に見立てたことばかりに焦点が当てられているけど、実はもっとどす黒いスキャンダルがその裏にはあるってことだ。そもそも、1年も前のLINEの内容が漏れるなんてことはありませんよ。つまり、こうした動きを快く思わないひとたちがいて、いわば告発したようなものなんじゃないのかねえ。
でなけりゃ、オリンピッグ佐々木君もこうも簡単に辞任しないんじゃないのか。なんてったって職場放棄したようなものだから、契約不履行で損害賠償請求される可能性だってありますからね。オリンピック中止を見込んで、さらに窮地に追い込まれる前にドロ船から逃げ出したってことかもね。妄想だけど。
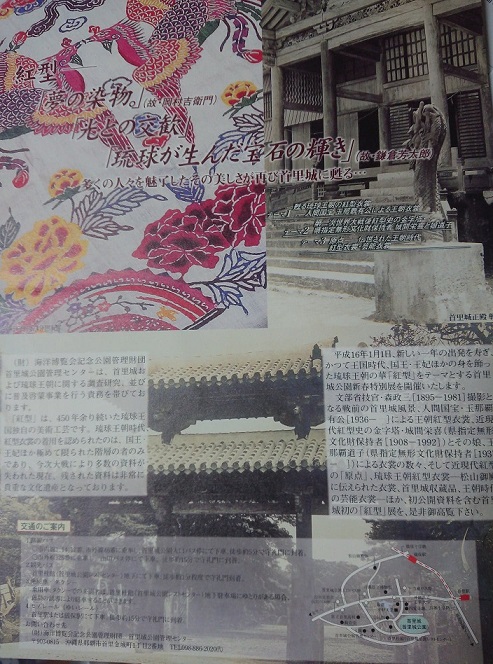
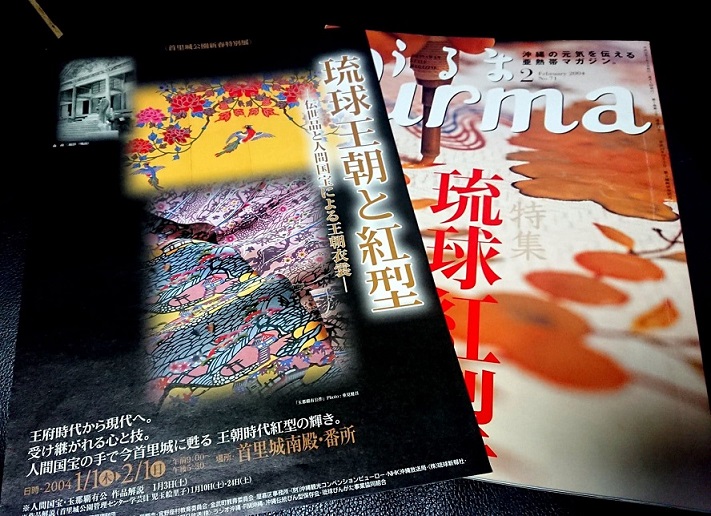
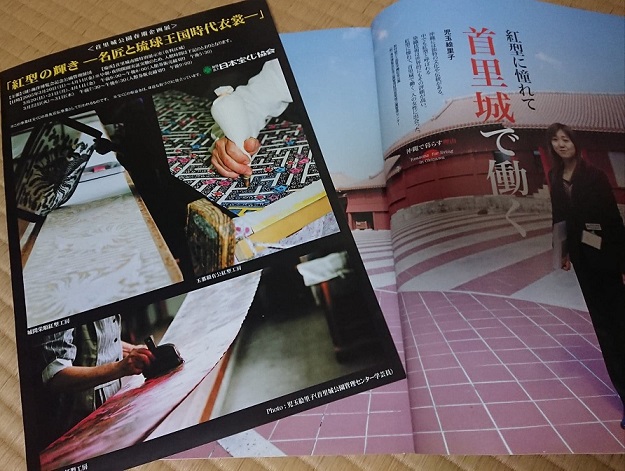
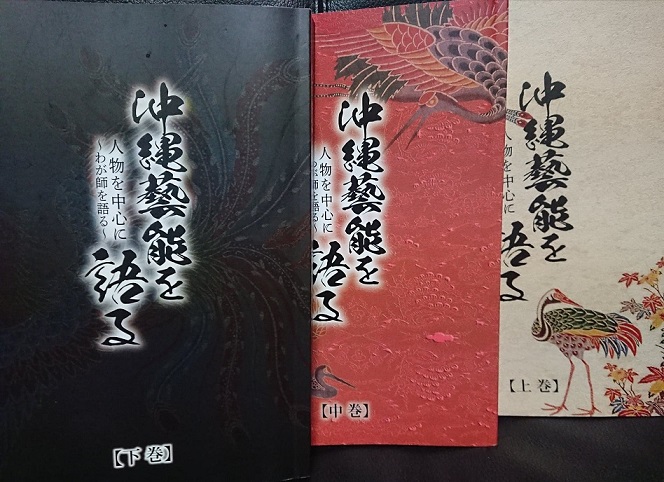
児玉絵里子・博士(文学、早大) /第10回木村重信民族藝術学会賞 ????著書『琉球紅型』ADP『図説 琉球の染めと織り』河出書房 ????第47回三菱財団人文科学研究助成 ????筋トレ・ジム好き????舞踊するひと????????
写真ー首里城で初めて企画担当した展覧会/2004年2月号『「うるま Uruma』 №71<特集 琉球紅型>児玉絵里子が企画した首里城の紅型展とタイアップで雑誌を出したい、と、三浦クリエイティブのスタッフさんが連絡をくれて、実現した。この号の全体の編集にアドバイス・協力し紅型職人を紹介したり、琉舞の写真に助言したりした。巻頭解説「琉球王朝と紅型」は児玉絵里子の文章。/2020年7月 編集責任者・當間一郎『沖縄芸能を語る 人物を中心に~わが師を語る~』株式会社国際印刷 恩師の當間一郎先生の遺作。この「沖縄芸能を語る」の下巻の目次を見たら、當間先生の御執筆された本田安次論の次に、わたしの拙論を続けて下さっていました。→児玉絵里子談


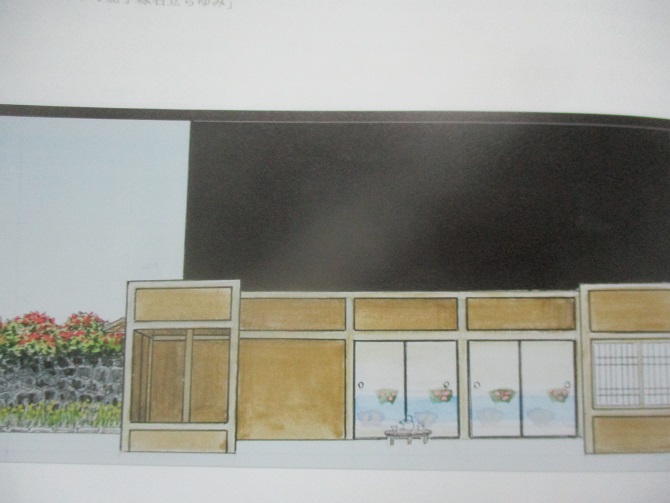

画中画・絵の中に、描写対象としてさらにイラストや絵画、または写真が描かれている状態のこと。同じ意味のタグとしては「絵中絵」の方が多い。入れ子式にいくつもの絵を描き入れることも可能ではある。(ピクシブ百科事典)/京都の妙心寺退蔵院には蘇鉄と山羊が描かれた板戸がある。この寺は襖絵でも知られていて、寺のホームページに方丈の襖絵は狩野光信の高弟であった狩野了慶は、探幽と共に活躍した狩野派の絵師で、この襖絵は高台寺の屏風絵や西本願寺の襖絵などとともに、桃山後期の優れた遺品とされています。/挿絵画家の金城安太郎さん、舞台美術家の新城喜一さんの襖が描かれたものを見る。
昨年の清須市はるひ絵画の岡本秀展にふれ井上昇治記者が展評「明治以降の日本画に通じる水脈である屏風、扇面図、掛け軸、絵巻物、ふすま絵や、調度品などとともにあった日本の古美術の形式や、西洋絵画のフレーム、デジタル画像、架空の妖怪など、多様な要素をいくつもの階層の入れ子構造にして組み立ててあるのだ」と書き、続けて「『日本画』」自体が明治時代に作りあげられた仮構であったことを考えると、さまざまな変質に合わせて、『日本画』の隘路を乗り越え、「『日本画』」のように二重かっこに入れた日本画を新たに仮構しているようである」「日本の伝統絵画を軸に、西洋絵画の構造、現代のイメージなど、さまざまな次元を行き来し、眼差しを巡らせる、情報量の多い作品である」とする。
襖からくりは人形芝居の舞台などの奥に設けられた高座に組み込んだ襖を巧みに操作して、舞台背景を一瞬に転換するものである。
画家・金城安太郎とも親しい宮城能造が描いた手書きの幕もあった。遠近法をもちいた襖絵には菖蒲と鶴が描かれる。能造が、約1ヶ月間、伊是名村仲田に滞在した折、制作された。1956年(昭和31)頃のことである。座敷幕の現物は失われている。現在の公民館造成に伴い、新しい幕制作の見本として日本本土の「緞帳屋」に送った後に所在不明となったという。同幕は、1978年頃まで使用されていたが、現在は、能造の幕を元に本土の緞帳屋が制作したものを使用。生地はメリケン袋をつなぎ合わせて「道で縫った」もので、伊禮一昇によれば、住民達が見守る中、能造は「即興で」この幕を描いたという。
.jpg)



岡本秀作品/企画展「大ふすま展」2019年9月6日、越前市にある紙の文化博物館/宮城能造が描いた手書きの幕/我が家の襖
「くろねこの短語」2021年3月18日 (前略)でもって、文春砲はオリンピックもターゲットに、さらに号砲を放ってくれました。なんと、開閉会式の責任者であるクリエイティブディレクターが、タレントの渡辺直美を豚に見立てた演出プランを提案して炎上したあげくに、辞表提出しましたとさ。
いやいや、ここまでアヤがついたオリンピックって、さすがに前代未聞だろう。それにしても、今回の東京オリンピックって、なんでこれほどに下衆な野郎どもばかりなんだろうね。そもそも、「アンダーコントロール」というペテン師・シンゾーの大嘘から始まったオリンピックだから、さもありなんてことか。「平和の祭典」が聞いて呆れますよ、ったく。
「くろねこの短語」2021年3月17日 (前略)そもそも、いつから民間人は国会に呼ばないってことになったんだ。古くは、ロッキード事件の際に、国際興業の小佐野賢治はじめ丸紅や全日空の幹部が国会に証人喚問されている。ダグラス・グラマン事件では日商岩井の海部副社長が国会に呼ばれ、証人喚問の宣誓の際に手が震えてなかなか署名が出来ないシーンがいまでも忘れられない。国会の国政調査権ってのは、それほどに権威があるものなんだね。ところがどっこい。いまの自民党にかかると、国政調査権なんてのはないも同然。数で勝るのをいいことに、都合の悪い人物は「民間人」ということで国会招致を拒否しちまう。
今回の谷脇君の辞職ってのも、悪いようにはしないからって言い含められてのことに違いない。でなけりゃ、退職金も保留なんてことに本人が納得するわけはありません。なぜなら、総務省の接待疑惑ってのはカス総理の存在があてこそなんだから。ま、いつもの妄想だけど。だからこそ、鈴木某なんていうチンピラ役人が、シレっと「記憶にありません」って国会で言い募ることができるんだね。東北新社が「外資規制違反を報告した」という証言は日付も具体的で、どう考えても疑念の余地がない。そもそも、東北新社が嘘つく必要もない。
ロッキード事件では国際興業の小佐野賢治が「記憶にございません」を連発したものだが、民間人が訴追の恐れからそれを口にするのは戦術としてはあり得ることだ。でも、国家公務員がそれを言っちゃおしめえ~よ。新聞・TVも、「谷脇氏辞職 国会招致困難」だの「総務省の本人は『記憶にない』」だの、他人事みたいな報道していないで、週刊文春を見習って独自の調査報道してみやがれ。それでこそ、ジャーナリズムとしての矜持が保てるというものだ。
「くろねこの短語」2021年3月16日 (前略)そもそも、カス総理が携帯料金値下げを口にしたのが2018年8月の沖縄知事選の時だったんだね。そこから総務省とNTTとの会食が頻繁になってくる。まさに「疑念を招く会食」なんだよね。なんだかんだ理屈をつけようと、利害関係者との会食は国家公務員倫理規程違反なのは明らかで、疑念を招こうと招くまいとそんなのは関係ないってことだ。新聞・TVがそうした正論に目を閉ざして、総務省を舞台にした接待疑惑を文春まかせで傍観していることに怒り心頭の火曜の朝である。




3月11日、天気がいいので平和通りまで。京都FB友の末次さんの仙台四郎の話を写真ー「古美術なるみ堂」主人の翁長さん(☎090-3793-8179)に聞いた。FB友の名古屋の阪井さんは翁長さんと懇意だ。写真ー店の一階に張っている「仙台四郎」。写真ー1957年9月の知念高校『知高新聞』を見せてもらった。後の人間国宝・照喜名朝一さんが生徒会長だ。

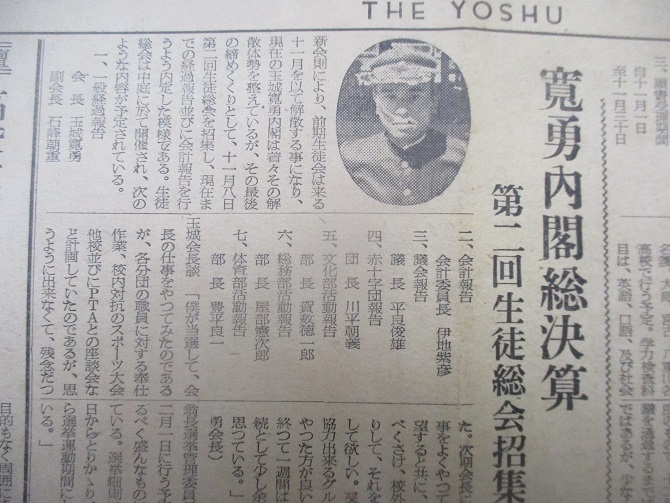


照喜名朝一さん、翁長良明さん/1952年11月、首里高校『養秀』「総務部部長・屋部憲次郎、体育部部長・豊平良一」/「舞」/琉球芭蕉紙で作った「張子人形」/1956年10月『沖縄ヤクルトの栞』
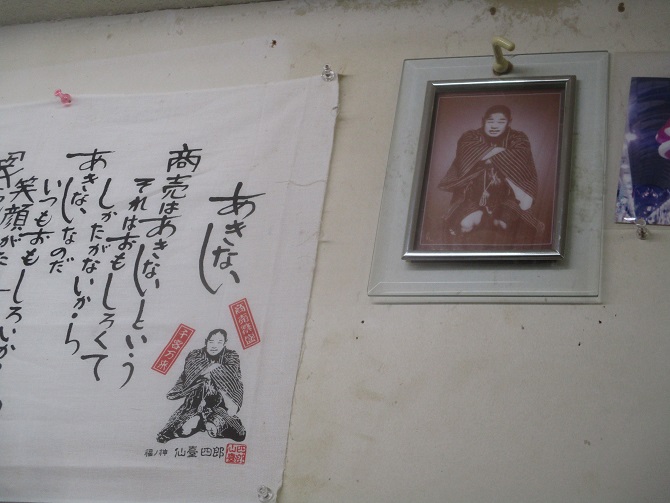
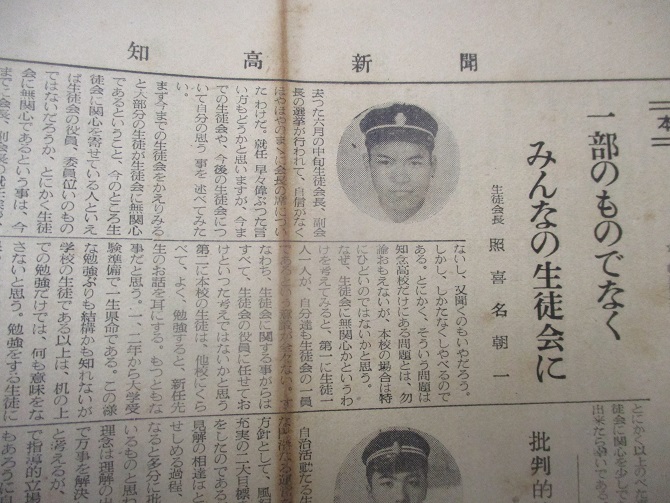

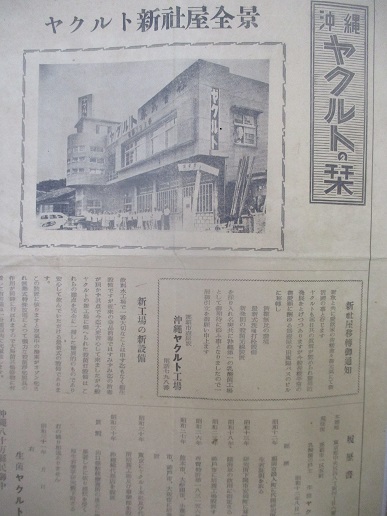
「くろねこの短語」2021年3月11日 東日本大震災+福島第一原発事故から10年。行方不明者はいまなお2525人、避難生活を送る被災者は4万1000人。さらに、原子力緊急事態宣言はいまだ解除されず。こんな状況で、何が「復興五輪」だ。
ところで、昨日の参院予算委員会が、公職選挙法違反で書類送検されたことのある総務大臣・武田君の発言をめぐて紛糾。そのまま散会になりましたとさ。立憲民主党の白眞勲参議院議員とのやりとりの中でのことなんだが、こんな具合です。
「国民に疑念を抱くような会食・会合に応じたことは一切ございません」って強弁しながら、「NTTとの会食の有無」には答えようとしないのは、「ご飯論法」ここに極まれり、ってなもんです。ようするに、「会食はした」って言ってるんだよね。総務大臣が国会で立往生しているのと時を同じくして、文春砲が炸裂。なんと、総務大臣だった時の出戻り・聖子君と化粧崩れの高市君がNTTと会食してましたとさ。記事によれば、「NTTは総務省の政務三役(大臣、副大臣、政務官)を退任した政治家にも接待を繰り返しており、計15人、延べ41回にのぼる」ってさ。
つまり、総務省とNTTはズフズブの関係で、その大元締めは特高顔のカス総理なんじゃないのかねえ。なんてったって、総務省はカス総理の天領と言われるほど、その権勢は隅々にまで行きわたっていますからね。出戻りと化粧崩れも、その手の内で動いてたんじゃないのかねえ。妄想だけど。 いずれにしても、これで官僚だけでなく、政治家にも接待疑惑、ひいては贈収賄の可能性が出てきたわけで、これはひょっとするとひょっとしますよ。
海鳴りの島から3-11 座間味島や辺戸岬付近で低空飛行訓練を行っている映像や写真が広がり、県内では批判と中止を求める声が上がっている。米軍機による低空飛行訓練は全国的に問題になっているにもかかわらず、米軍は一顧だにしないし、日本政府もまともに物が言えない。日本の「属国」ぶりを示す光景であり、全国的な問題として国会でも追及すべきだ。
「くろねこの短語」2021年3月10日 特高顔のカス総理にかしずいたのが運の尽き。高額接待に溺れて大臣官房付きに更迭された谷脇君が退職金をガッポリ手に入れて今月末に定年を迎えますとさ。飲み会を断らない女・山田君と一緒で、これで退職を理由に国会に呼び出されることもなくなるってわけか。でも、マルチ商法の広告塔・下等官房長官が言い募る「退職者からの事実確認はしない」ってのに、どれだけの法的根拠があるのだろう。国家公務員倫理法に「退職者には適用しない」なんて条文はどこにもないんだよね。どうして、こうした疑問を新聞・TVは下等官房長官に投げつけてやらないのだろう。でないと、やった者勝ちで、辞職したらすべてチャラという高級官僚天国になっちまいますよ。
ところで、オリンピックなんだが、どうやら海外からの一般観客の受け入れは見送るってね。でもって、IOCは「スポンサー関連の招待客の観戦を要望」しているんだとか。いやあ、もしそうなったら、まるで皇帝や貴族が熱狂した古代ローマのコロッセオだ。オリンピック、辞めちまえ!!最後に、私立幼稚園連合会の使途不明金問題は、ひょっとしたらひょっとするかも。なんてったって、疑惑の会長はオリンピックの組織委員会の顧問で、山口県の公安委員もやってたんだよね。山口県と言えば、あの虚けの地元ですからね。香ばしいことになってきましたよ。
3月9日 東北・関東大地震発生後、現実の大問題で歴史的文化的な「琉球学」は暫し休止しないといけなくなった。かわり中古古書店で科学雑誌を買い「地球学」を復習する。そう考えていた矢先、近くのマンションにお住いの国吉多美子さんから『ナショナルジオグラフィック』をあげるという。この雑誌重いので母が生前使って手押し車で本日から運び始めた。
最近、ブックオフで今まで手にしたことのない『月刊ナショナルジオグラフィック日本版』 (ナショナル ジオグラフィック協会)のジャンルは地理学、科学、歴史、自然で、そのバックナンバーを買い求めている。付録が好い。写真家の山田實さんのところに英語版があった。
月刊誌として年間12冊発行されており、それに加えて付録の地図を発行している。また、時に特別号も発行している。地理学、人類学、自然・環境学、ポピュラーサイエンス、歴史、文化、最新事象、写真などの記事を掲載している。現在の編集長は Chris Johns で、2008年10月 Advertising Age 誌で American Magazine Conference から Editor of the Year を授与された。世界中で33カ国語で発行されており、5000万人以上が定期購読している[要出典]。日本語版の発行部数は約8万4千部(ABC2009年公査部数)[2]であり、読者は首都圏のみで42%を超える。また、読者の平均世帯年収(SA)が高く、日本における高級誌の一角を占めている。
National Geographic Magazine の創刊号は、協会が創設されたわずか9カ月後の1888年に発行された。ナショナル ジオグラフィックの特徴は学術誌でありながら絵や写真を多用した雑誌だという点で、1905年1月号に掲載されたロシア帝国の2人の探検家 Gombojab Tsybikov と Ovshe Norzunov によるチベット探検時の写真をページ全面の大きさで掲載したことにその特徴がよく現れている。1985年7月号の表紙にはアフガニスタンの13歳の少女 Sharbat Gula の写真が使われ、同誌の歴史上最も有名なイメージの1つとなっている。→出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/05/25 21:46 UTC 版)
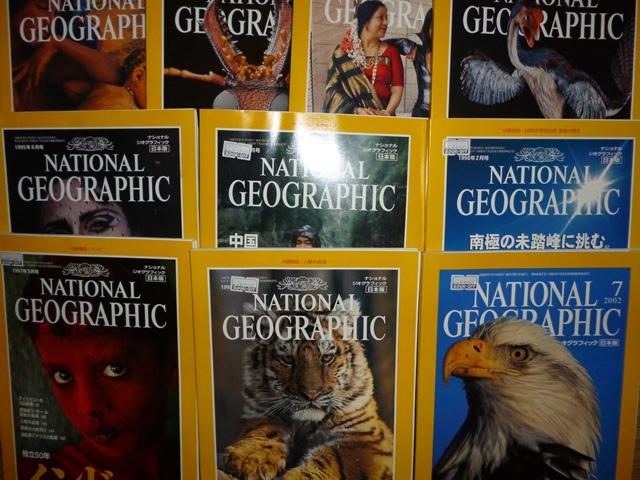

2002-7□パドゥーカ(ケンタッキー州)核燃料処理施設のパドゥーカガス拡散ウラン濃縮工場。劣化ウランを詰めた約3万8000本の容器が屋外に置かれている。

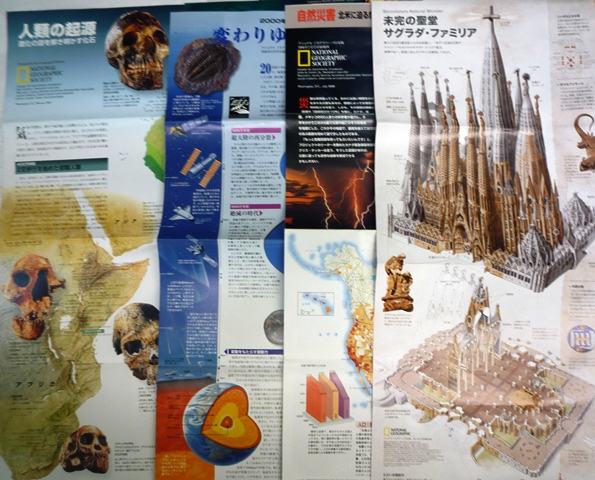
「くろねこの短語」2021年3月8日 (前略)「政治責任の定義というのはないんじゃないでしょうか」 だとさ。これは、5日の参議院予算委員会にける立憲民主の若武者・小西君との質疑応答の中で出てきたものだ。総務省接待疑惑で官僚が処分されたことについて「政治責任は一切ないとお考えですか?」との問いかけに、カス総理は何をとち狂ったのか無責任極まりない放言をしてくれちゃったということだ。
おそらく、「政治責任」について自分なりの理念ていうか、哲学というか、信念というか、つまり何も考えたことなんかないのに違いない。だからこその驚天動地の「政治責任の定義というのはない」なんて言葉が平然と口をついて出てきちゃったんだね。・【詳報】首相「心からおわび」も「政治責任の定義ない」立川談四楼師匠が「もう屁もでない」と呆れていたけど、ああ、それなのに、今朝の読売新聞によれば内閣支持率が9ポイントもアップしたんだとさ。どこまでおまかせ民主主義が染み込んでるんだ、日本人!!








M・T 3-6「中国が攻めて来たらどうするって、ほんと、うっせーわ、です。攻めてくるものですか。それより、アメリカに現に支配されて苦しめられている方がよっぽど酷いのに。そして利権のために完成する」はずもない辺野古新基地のためにこんなひどいことを防衛局、政府がしようとしているのに。
戦没者遺骨を辺野古に使わせないハンスト会場には知り合いも来ていた。マスコミの取材に応える具志堅隆さん。
写真ー国会議員も激励に来ていた。左から赤嶺政賢氏、伊波洋一氏、高良鉄美氏/マスクをしているのに分かるものだ。海勢頭豊氏、新垣邦雄氏、比嘉豊光氏(写真)
海鳴りの島から 3-6 消失した首里城正殿や北殿では、鉄筋コンクリートも使用されていたはずだ。完全な復元ではなかったのであり、そういう実態も県民に広く知らせたうえで、木材の調達について検討すべきだ。

3月20日 彼岸(祖先供養の行事)仏壇に御馳走を供えて祖先供養を行う。紙銭を焼く
「くろねこの短語」2021年3月19日 (前略)ようするに、シンキロー森とオリンピッグ佐々木君がクリエイティフチームを乗っ取って、いわば五輪開閉会式の私物化を図ったってことなのだろう。これって、エンブレムの盗作騒動を思い起こさせてくれる。あの時も、盗作疑惑のデサイナーの人間関係が問題になりましたからね。渡辺直美を豚に見立てたことばかりに焦点が当てられているけど、実はもっとどす黒いスキャンダルがその裏にはあるってことだ。そもそも、1年も前のLINEの内容が漏れるなんてことはありませんよ。つまり、こうした動きを快く思わないひとたちがいて、いわば告発したようなものなんじゃないのかねえ。
でなけりゃ、オリンピッグ佐々木君もこうも簡単に辞任しないんじゃないのか。なんてったって職場放棄したようなものだから、契約不履行で損害賠償請求される可能性だってありますからね。オリンピック中止を見込んで、さらに窮地に追い込まれる前にドロ船から逃げ出したってことかもね。妄想だけど。
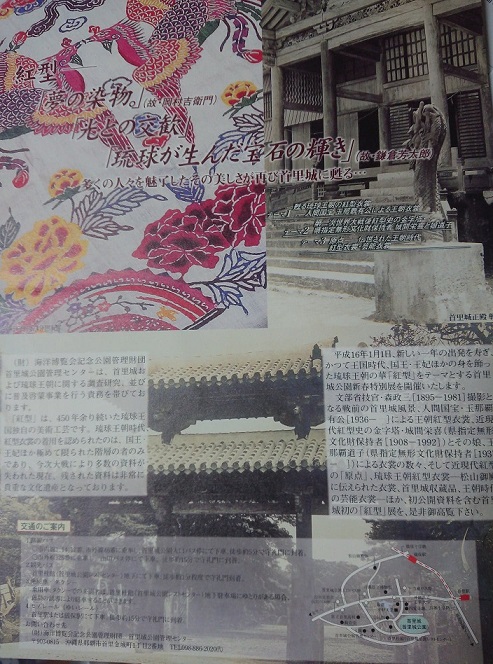
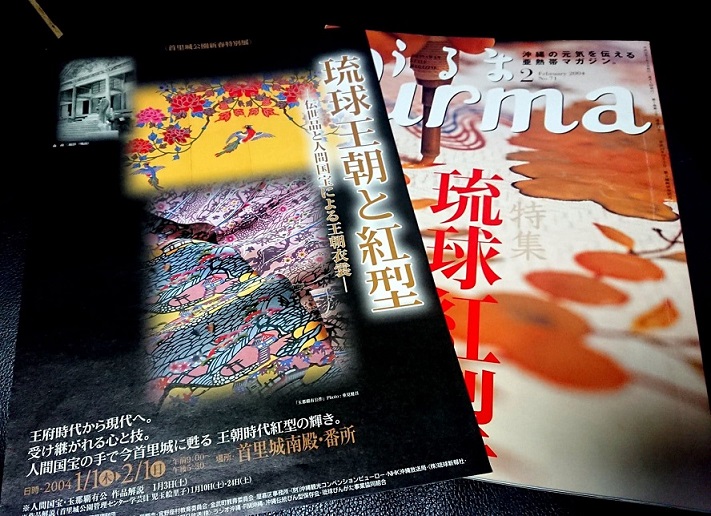
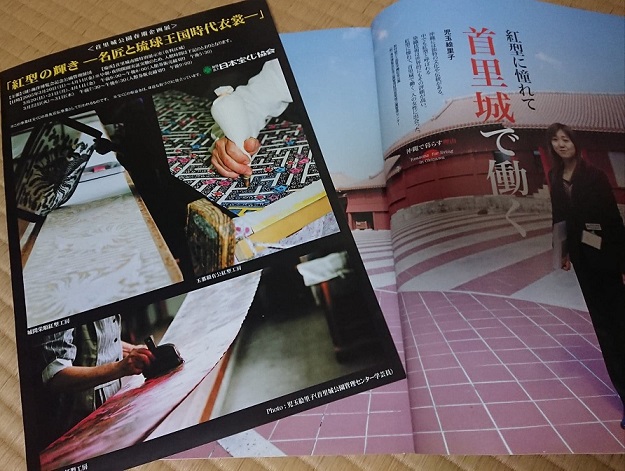
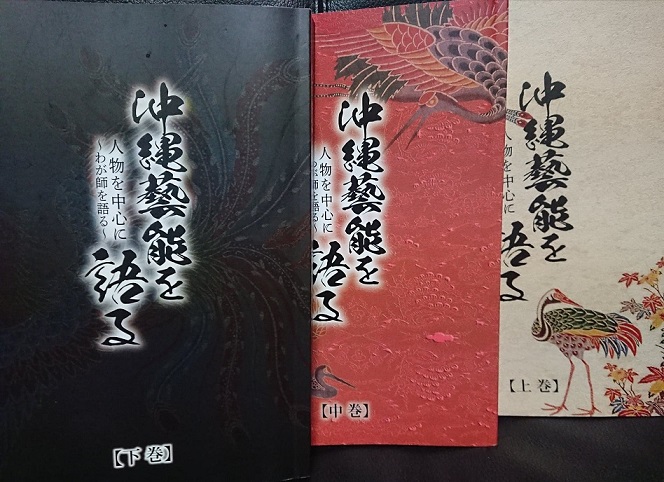
児玉絵里子・博士(文学、早大) /第10回木村重信民族藝術学会賞 ????著書『琉球紅型』ADP『図説 琉球の染めと織り』河出書房 ????第47回三菱財団人文科学研究助成 ????筋トレ・ジム好き????舞踊するひと????????
写真ー首里城で初めて企画担当した展覧会/2004年2月号『「うるま Uruma』 №71<特集 琉球紅型>児玉絵里子が企画した首里城の紅型展とタイアップで雑誌を出したい、と、三浦クリエイティブのスタッフさんが連絡をくれて、実現した。この号の全体の編集にアドバイス・協力し紅型職人を紹介したり、琉舞の写真に助言したりした。巻頭解説「琉球王朝と紅型」は児玉絵里子の文章。/2020年7月 編集責任者・當間一郎『沖縄芸能を語る 人物を中心に~わが師を語る~』株式会社国際印刷 恩師の當間一郎先生の遺作。この「沖縄芸能を語る」の下巻の目次を見たら、當間先生の御執筆された本田安次論の次に、わたしの拙論を続けて下さっていました。→児玉絵里子談


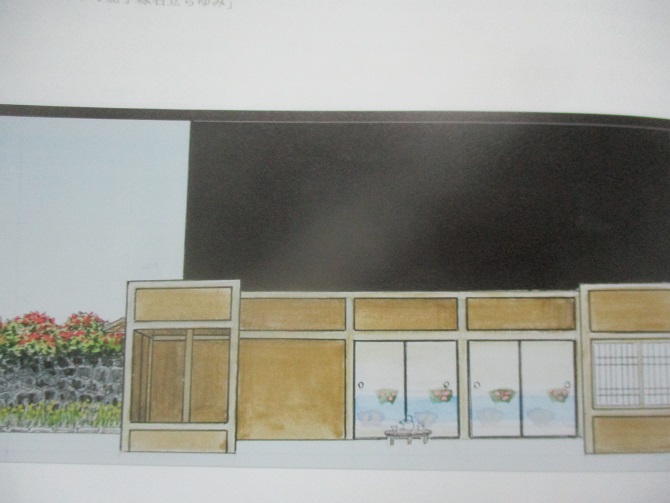

画中画・絵の中に、描写対象としてさらにイラストや絵画、または写真が描かれている状態のこと。同じ意味のタグとしては「絵中絵」の方が多い。入れ子式にいくつもの絵を描き入れることも可能ではある。(ピクシブ百科事典)/京都の妙心寺退蔵院には蘇鉄と山羊が描かれた板戸がある。この寺は襖絵でも知られていて、寺のホームページに方丈の襖絵は狩野光信の高弟であった狩野了慶は、探幽と共に活躍した狩野派の絵師で、この襖絵は高台寺の屏風絵や西本願寺の襖絵などとともに、桃山後期の優れた遺品とされています。/挿絵画家の金城安太郎さん、舞台美術家の新城喜一さんの襖が描かれたものを見る。
昨年の清須市はるひ絵画の岡本秀展にふれ井上昇治記者が展評「明治以降の日本画に通じる水脈である屏風、扇面図、掛け軸、絵巻物、ふすま絵や、調度品などとともにあった日本の古美術の形式や、西洋絵画のフレーム、デジタル画像、架空の妖怪など、多様な要素をいくつもの階層の入れ子構造にして組み立ててあるのだ」と書き、続けて「『日本画』」自体が明治時代に作りあげられた仮構であったことを考えると、さまざまな変質に合わせて、『日本画』の隘路を乗り越え、「『日本画』」のように二重かっこに入れた日本画を新たに仮構しているようである」「日本の伝統絵画を軸に、西洋絵画の構造、現代のイメージなど、さまざまな次元を行き来し、眼差しを巡らせる、情報量の多い作品である」とする。
襖からくりは人形芝居の舞台などの奥に設けられた高座に組み込んだ襖を巧みに操作して、舞台背景を一瞬に転換するものである。
画家・金城安太郎とも親しい宮城能造が描いた手書きの幕もあった。遠近法をもちいた襖絵には菖蒲と鶴が描かれる。能造が、約1ヶ月間、伊是名村仲田に滞在した折、制作された。1956年(昭和31)頃のことである。座敷幕の現物は失われている。現在の公民館造成に伴い、新しい幕制作の見本として日本本土の「緞帳屋」に送った後に所在不明となったという。同幕は、1978年頃まで使用されていたが、現在は、能造の幕を元に本土の緞帳屋が制作したものを使用。生地はメリケン袋をつなぎ合わせて「道で縫った」もので、伊禮一昇によれば、住民達が見守る中、能造は「即興で」この幕を描いたという。
.jpg)



岡本秀作品/企画展「大ふすま展」2019年9月6日、越前市にある紙の文化博物館/宮城能造が描いた手書きの幕/我が家の襖
「くろねこの短語」2021年3月18日 (前略)でもって、文春砲はオリンピックもターゲットに、さらに号砲を放ってくれました。なんと、開閉会式の責任者であるクリエイティブディレクターが、タレントの渡辺直美を豚に見立てた演出プランを提案して炎上したあげくに、辞表提出しましたとさ。
いやいや、ここまでアヤがついたオリンピックって、さすがに前代未聞だろう。それにしても、今回の東京オリンピックって、なんでこれほどに下衆な野郎どもばかりなんだろうね。そもそも、「アンダーコントロール」というペテン師・シンゾーの大嘘から始まったオリンピックだから、さもありなんてことか。「平和の祭典」が聞いて呆れますよ、ったく。
「くろねこの短語」2021年3月17日 (前略)そもそも、いつから民間人は国会に呼ばないってことになったんだ。古くは、ロッキード事件の際に、国際興業の小佐野賢治はじめ丸紅や全日空の幹部が国会に証人喚問されている。ダグラス・グラマン事件では日商岩井の海部副社長が国会に呼ばれ、証人喚問の宣誓の際に手が震えてなかなか署名が出来ないシーンがいまでも忘れられない。国会の国政調査権ってのは、それほどに権威があるものなんだね。ところがどっこい。いまの自民党にかかると、国政調査権なんてのはないも同然。数で勝るのをいいことに、都合の悪い人物は「民間人」ということで国会招致を拒否しちまう。
今回の谷脇君の辞職ってのも、悪いようにはしないからって言い含められてのことに違いない。でなけりゃ、退職金も保留なんてことに本人が納得するわけはありません。なぜなら、総務省の接待疑惑ってのはカス総理の存在があてこそなんだから。ま、いつもの妄想だけど。だからこそ、鈴木某なんていうチンピラ役人が、シレっと「記憶にありません」って国会で言い募ることができるんだね。東北新社が「外資規制違反を報告した」という証言は日付も具体的で、どう考えても疑念の余地がない。そもそも、東北新社が嘘つく必要もない。
ロッキード事件では国際興業の小佐野賢治が「記憶にございません」を連発したものだが、民間人が訴追の恐れからそれを口にするのは戦術としてはあり得ることだ。でも、国家公務員がそれを言っちゃおしめえ~よ。新聞・TVも、「谷脇氏辞職 国会招致困難」だの「総務省の本人は『記憶にない』」だの、他人事みたいな報道していないで、週刊文春を見習って独自の調査報道してみやがれ。それでこそ、ジャーナリズムとしての矜持が保てるというものだ。
「くろねこの短語」2021年3月16日 (前略)そもそも、カス総理が携帯料金値下げを口にしたのが2018年8月の沖縄知事選の時だったんだね。そこから総務省とNTTとの会食が頻繁になってくる。まさに「疑念を招く会食」なんだよね。なんだかんだ理屈をつけようと、利害関係者との会食は国家公務員倫理規程違反なのは明らかで、疑念を招こうと招くまいとそんなのは関係ないってことだ。新聞・TVがそうした正論に目を閉ざして、総務省を舞台にした接待疑惑を文春まかせで傍観していることに怒り心頭の火曜の朝である。




3月11日、天気がいいので平和通りまで。京都FB友の末次さんの仙台四郎の話を写真ー「古美術なるみ堂」主人の翁長さん(☎090-3793-8179)に聞いた。FB友の名古屋の阪井さんは翁長さんと懇意だ。写真ー店の一階に張っている「仙台四郎」。写真ー1957年9月の知念高校『知高新聞』を見せてもらった。後の人間国宝・照喜名朝一さんが生徒会長だ。

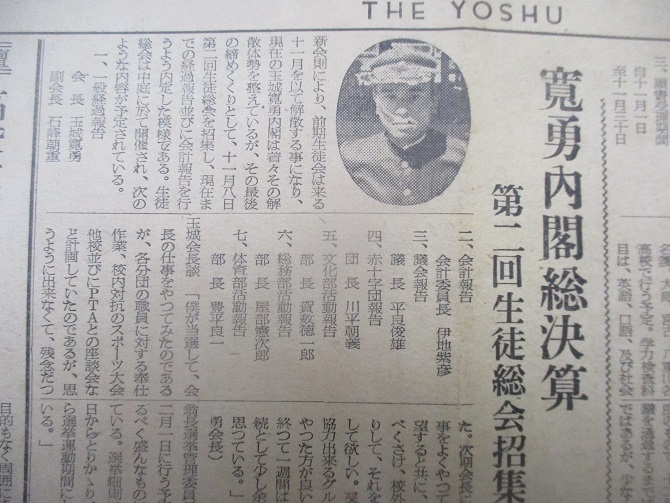


照喜名朝一さん、翁長良明さん/1952年11月、首里高校『養秀』「総務部部長・屋部憲次郎、体育部部長・豊平良一」/「舞」/琉球芭蕉紙で作った「張子人形」/1956年10月『沖縄ヤクルトの栞』
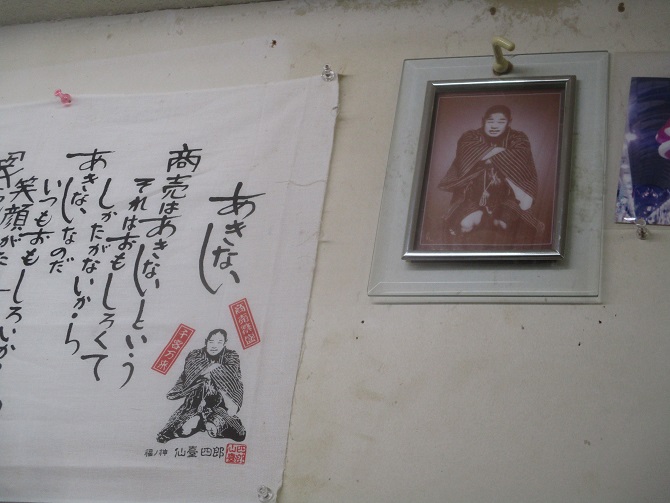
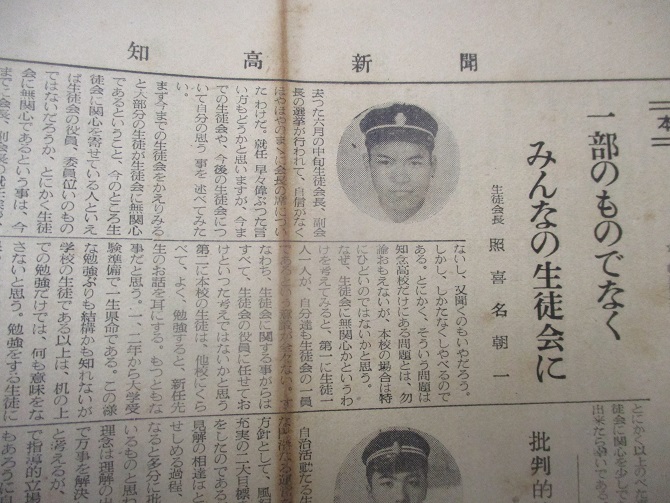

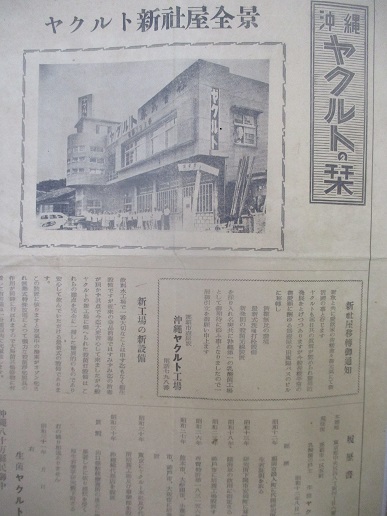
「くろねこの短語」2021年3月11日 東日本大震災+福島第一原発事故から10年。行方不明者はいまなお2525人、避難生活を送る被災者は4万1000人。さらに、原子力緊急事態宣言はいまだ解除されず。こんな状況で、何が「復興五輪」だ。
ところで、昨日の参院予算委員会が、公職選挙法違反で書類送検されたことのある総務大臣・武田君の発言をめぐて紛糾。そのまま散会になりましたとさ。立憲民主党の白眞勲参議院議員とのやりとりの中でのことなんだが、こんな具合です。
「国民に疑念を抱くような会食・会合に応じたことは一切ございません」って強弁しながら、「NTTとの会食の有無」には答えようとしないのは、「ご飯論法」ここに極まれり、ってなもんです。ようするに、「会食はした」って言ってるんだよね。総務大臣が国会で立往生しているのと時を同じくして、文春砲が炸裂。なんと、総務大臣だった時の出戻り・聖子君と化粧崩れの高市君がNTTと会食してましたとさ。記事によれば、「NTTは総務省の政務三役(大臣、副大臣、政務官)を退任した政治家にも接待を繰り返しており、計15人、延べ41回にのぼる」ってさ。
つまり、総務省とNTTはズフズブの関係で、その大元締めは特高顔のカス総理なんじゃないのかねえ。なんてったって、総務省はカス総理の天領と言われるほど、その権勢は隅々にまで行きわたっていますからね。出戻りと化粧崩れも、その手の内で動いてたんじゃないのかねえ。妄想だけど。 いずれにしても、これで官僚だけでなく、政治家にも接待疑惑、ひいては贈収賄の可能性が出てきたわけで、これはひょっとするとひょっとしますよ。
海鳴りの島から3-11 座間味島や辺戸岬付近で低空飛行訓練を行っている映像や写真が広がり、県内では批判と中止を求める声が上がっている。米軍機による低空飛行訓練は全国的に問題になっているにもかかわらず、米軍は一顧だにしないし、日本政府もまともに物が言えない。日本の「属国」ぶりを示す光景であり、全国的な問題として国会でも追及すべきだ。
「くろねこの短語」2021年3月10日 特高顔のカス総理にかしずいたのが運の尽き。高額接待に溺れて大臣官房付きに更迭された谷脇君が退職金をガッポリ手に入れて今月末に定年を迎えますとさ。飲み会を断らない女・山田君と一緒で、これで退職を理由に国会に呼び出されることもなくなるってわけか。でも、マルチ商法の広告塔・下等官房長官が言い募る「退職者からの事実確認はしない」ってのに、どれだけの法的根拠があるのだろう。国家公務員倫理法に「退職者には適用しない」なんて条文はどこにもないんだよね。どうして、こうした疑問を新聞・TVは下等官房長官に投げつけてやらないのだろう。でないと、やった者勝ちで、辞職したらすべてチャラという高級官僚天国になっちまいますよ。
ところで、オリンピックなんだが、どうやら海外からの一般観客の受け入れは見送るってね。でもって、IOCは「スポンサー関連の招待客の観戦を要望」しているんだとか。いやあ、もしそうなったら、まるで皇帝や貴族が熱狂した古代ローマのコロッセオだ。オリンピック、辞めちまえ!!最後に、私立幼稚園連合会の使途不明金問題は、ひょっとしたらひょっとするかも。なんてったって、疑惑の会長はオリンピックの組織委員会の顧問で、山口県の公安委員もやってたんだよね。山口県と言えば、あの虚けの地元ですからね。香ばしいことになってきましたよ。
3月9日 東北・関東大地震発生後、現実の大問題で歴史的文化的な「琉球学」は暫し休止しないといけなくなった。かわり中古古書店で科学雑誌を買い「地球学」を復習する。そう考えていた矢先、近くのマンションにお住いの国吉多美子さんから『ナショナルジオグラフィック』をあげるという。この雑誌重いので母が生前使って手押し車で本日から運び始めた。
最近、ブックオフで今まで手にしたことのない『月刊ナショナルジオグラフィック日本版』 (ナショナル ジオグラフィック協会)のジャンルは地理学、科学、歴史、自然で、そのバックナンバーを買い求めている。付録が好い。写真家の山田實さんのところに英語版があった。
月刊誌として年間12冊発行されており、それに加えて付録の地図を発行している。また、時に特別号も発行している。地理学、人類学、自然・環境学、ポピュラーサイエンス、歴史、文化、最新事象、写真などの記事を掲載している。現在の編集長は Chris Johns で、2008年10月 Advertising Age 誌で American Magazine Conference から Editor of the Year を授与された。世界中で33カ国語で発行されており、5000万人以上が定期購読している[要出典]。日本語版の発行部数は約8万4千部(ABC2009年公査部数)[2]であり、読者は首都圏のみで42%を超える。また、読者の平均世帯年収(SA)が高く、日本における高級誌の一角を占めている。
National Geographic Magazine の創刊号は、協会が創設されたわずか9カ月後の1888年に発行された。ナショナル ジオグラフィックの特徴は学術誌でありながら絵や写真を多用した雑誌だという点で、1905年1月号に掲載されたロシア帝国の2人の探検家 Gombojab Tsybikov と Ovshe Norzunov によるチベット探検時の写真をページ全面の大きさで掲載したことにその特徴がよく現れている。1985年7月号の表紙にはアフガニスタンの13歳の少女 Sharbat Gula の写真が使われ、同誌の歴史上最も有名なイメージの1つとなっている。→出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/05/25 21:46 UTC 版)
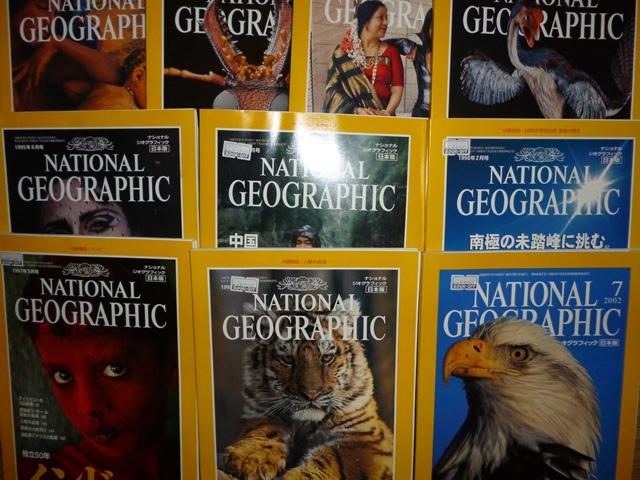

2002-7□パドゥーカ(ケンタッキー州)核燃料処理施設のパドゥーカガス拡散ウラン濃縮工場。劣化ウランを詰めた約3万8000本の容器が屋外に置かれている。

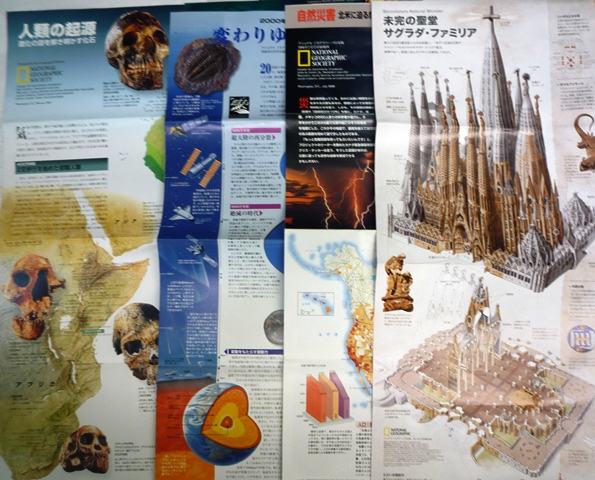
「くろねこの短語」2021年3月8日 (前略)「政治責任の定義というのはないんじゃないでしょうか」 だとさ。これは、5日の参議院予算委員会にける立憲民主の若武者・小西君との質疑応答の中で出てきたものだ。総務省接待疑惑で官僚が処分されたことについて「政治責任は一切ないとお考えですか?」との問いかけに、カス総理は何をとち狂ったのか無責任極まりない放言をしてくれちゃったということだ。
おそらく、「政治責任」について自分なりの理念ていうか、哲学というか、信念というか、つまり何も考えたことなんかないのに違いない。だからこその驚天動地の「政治責任の定義というのはない」なんて言葉が平然と口をついて出てきちゃったんだね。・【詳報】首相「心からおわび」も「政治責任の定義ない」立川談四楼師匠が「もう屁もでない」と呆れていたけど、ああ、それなのに、今朝の読売新聞によれば内閣支持率が9ポイントもアップしたんだとさ。どこまでおまかせ民主主義が染み込んでるんだ、日本人!!








M・T 3-6「中国が攻めて来たらどうするって、ほんと、うっせーわ、です。攻めてくるものですか。それより、アメリカに現に支配されて苦しめられている方がよっぽど酷いのに。そして利権のために完成する」はずもない辺野古新基地のためにこんなひどいことを防衛局、政府がしようとしているのに。
戦没者遺骨を辺野古に使わせないハンスト会場には知り合いも来ていた。マスコミの取材に応える具志堅隆さん。
写真ー国会議員も激励に来ていた。左から赤嶺政賢氏、伊波洋一氏、高良鉄美氏/マスクをしているのに分かるものだ。海勢頭豊氏、新垣邦雄氏、比嘉豊光氏(写真)
海鳴りの島から 3-6 消失した首里城正殿や北殿では、鉄筋コンクリートも使用されていたはずだ。完全な復元ではなかったのであり、そういう実態も県民に広く知らせたうえで、木材の調達について検討すべきだ。