07/27: 萩原正徳と『旅と伝説』
今は亡き岡本恵徳先生は私の顔を見るたび「もっと奄美資料に注目してくれ」が口癖であった。私は伯父や伯母の連れ合いが奄美出身であったから特に奄美を意識したことがないが、琉球文化には当然に奄美も入っていると思っている。奄美の図書館には島尾敏雄氏に会ってみたいと2回ほど行ったが何時も休館日だった。島尾敏雄氏には会えなかったが、その代わりといっていいか分からないが山下欣一氏に出会った。
喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下欣一氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの萩原資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。山下氏も萩原正徳を当然と言えば当然だが色々と紹介して居られた。それに用いた資料だが次に紹介する。
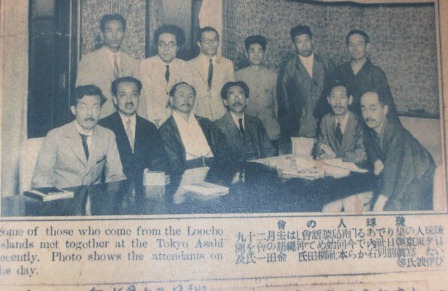

前列右端が柳田国男、左端が比嘉春潮/後列右から萩原正徳、大藤時彦、瀬川清子
1944年3月『民間伝承』柳田国男「『旅と伝説』について」□(略)改めてもう一度、初めから読み返して見たい気がする。公平に批判してどの部分、一ばん後世に役立つ仕事だったかを、考へ且つ説いて見たくもなる。
私の処にはもう主要記事の索引も出来て居るのだが、この判定は実はさう容易な業では無い。しかし先ず大まかに考へて、婚礼誕生葬祭その他の特集号を出し、又昔話を二度まで出した頃などが、全盛期だったと言へるかもしれない。こんなにまで多数の同志があったのかと、驚くほどの人々が全国の各地から、何れも好意づくだけでよい原稿を寄せ、所謂陣容を輝かしてくれたのみならず、此時を境にそれぞれの問題に対する理解常識が、目に見えて躍進したので、之を読んで居ない人の云ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料といふものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを、実地に証明してくれたのである。
その以外に今一つ承認しなければならぬことは、萩原君は故郷の奄美大島の為に、この雑誌を通して中々よく働いて居る。それには同郷知友の共鳴支援といふことも条件ではあったが、とにかくに全十六巻を通じて、奄美大島に関する報告は多く、又清新な第一次の資料が多かったことは争へない。その一つの例として手近に私の心づいたことをあげると、第一巻のたしか二号か三号に、島の先輩の露西亜学者昇曙夢さんが、アモレヲナグ即ち天降女人の事を書いて、我々に大きな印象を与へ、又より多くを知りたがらせて居たのだが、それが約十六年を隔てて最終号の中に、今度は金久正君といふ若い同志が、それを詳しく書いて我々の渇望を医して居る。もう「旅と伝説」さへ大切に保存して置けばこの世界的興味のある一問題は、永久に学問の領分からは消えないのである。或ひはそれほどまで大きな問題だと思はぬであらう人たちの為に、出来るだけ簡単に前後二ヶ所に出て居る天降女人の事を書き伝へ、出来るならば此上にももっと豊富な資料の、集まって来る機縁を促したい。(略)
奄美大島といふところは、私の知る限りでも、内部歴史の珍しく豊かな島であった。書いた記録がといふものは僅かしか残らぬが、近い百年二百年の間にも避ければ避けたかった実に色々な経験をしてゐる。さうして全体に今は古い拘束から解き放たれて、新時代のあらゆる機会を利用し、すぐれた人物が輩出して居るのである。住民自身としては忘れた方がよいやうな、外の者からは是非参考の為に聴いて置きたいやうな、無数の思ひ出をかかへて、まだ其処理を付けずに居るといふ感じがある。此数からいふと、萩原君の如き人がもっと辛抱強く、古い埋もれたことを尋ね出さうとする知友を糾合して居てくれたらと思はずには居られぬのだが、それをもう謂って見ても仕方が無い。それよりも雑誌をその時々の慰みなどとは考へずに、いつまでも之を精読する者の、是から日本にも多くなるやうに、我々もどうかして残るやうな雑誌を作って行きたい。
1981年7月『道之島通信』83号「民俗学開拓に貢献 萩原正徳(1896~1950)」□はじめに 1928年(昭和3年)から1944年(昭和19年)まで、東京で『旅と伝説』という月刊雑誌を発行、日本民族学の発展に著しく貢献したのが萩原正徳である。正徳は、1896年(明治29年)名瀬市金久に生まれ、若くして上京、東京高等工芸学校を卒業、27歳の時夫人ウメさん(千葉県出身)を娶った。弟に利用と厚生がおり、厚生は鹿児島一中から一高、東大へ進んだ奄美の秀才として名を馳せた人である。酒と島うたが好きで、子供が喧嘩して泣いて帰ると「泣かされて帰る奴がいるか、相手を泣かして来い」と、一人息子の正道を叱るくらいの気骨の持ち主でもあった。三元社という写真製版の会社を経営する一方、柳田国男らの民俗研究グループに参加、奄美をはじめ、各地の研究報告を『旅と伝説』に掲載、記録を歴史に残した。「若い頃から頭は、はげていましたので、年の割に老けて見えましたよ」と八十歳になったウメさんは話す。耳が悪かったため、兵役を免れ、柳田国男にどなられても笑っていたという。
1998年10月『柳田國男全集 第6巻 月報13』山下欣一「『海南小記』ー奄美の旅前後」□(略)最初の伊波普猷の奄美来訪は1918年(大正7)1月であった。これは私立大島郡教育会・二部研究会(瀬戸内・宇検)による招聘である。この時の中心になったのは二部研究会長で古仁屋小学校長永井龍一と当時篠川農学校教諭竹島純(沖縄師範卒)であった。この2名は伊波普猷・比嘉春潮を出迎えのために名瀬へ出張するが、船待ちのため十数日滞在を余儀なくされ、その間、奄美の文献資料を調査したりしている。この時『奄美大島史』の著者である坂口徳太郎も鹿児島県立大島中学校に勤務していたので、その指導も受けたと考えられる。
伊波普猷は、この第1回の旅で『南島雑話』、『奄美史談』などを沖縄へ借用し、筆写させ、沖縄県立図書館へ収蔵し閲覧に供したのである。(略)伊波普猷の奄美招聘の中心にいた竹島純は伊波普猷の講演記録を伊波の「序に代へて」を付して1931年(昭和6)に大島郡教育会から『南島史考』としてまとめている。また後で永井龍一は鹿児島に居を移し、『南島雑話』、『補遺篇』、『奄美史談』などの文献資料の自費刊行を試みている。この『南島雑話』刊行に刺激された永井龍一の兄亀彦(博物学者)は『南島雑話』の編著者を薩摩藩上士名越左源太時敏と確認し、また名越家で『遠島日記』をも発見し、これらを自費刊行している。これらは、昭和初年から、終戦直後に及んだ作業であった。永井兄亀・龍一兄弟は名瀬の与人役政家の一族である。父永井長昌喜は漢学者で教育者であった。
亀彦・龍一の姉よしは萩原家に嫁し、その子息が正徳・利用・厚生の兄弟である。叔父に『奄美史談』の著者都成植義(南峰)がいる。亀彦・龍一の甥に当る萩原正徳は上京し、東京高等工業学校で学び、海軍省水路部をへて写真製版業を営み、三元社を興した。柳田国男の指導を受けて『旅と伝説』を刊行した。これには昇曙夢・岩倉市郎・金久正などの奄美の研究者が登場しているのは故なしとしないのである。
喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下欣一氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの萩原資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。山下氏も萩原正徳を当然と言えば当然だが色々と紹介して居られた。それに用いた資料だが次に紹介する。
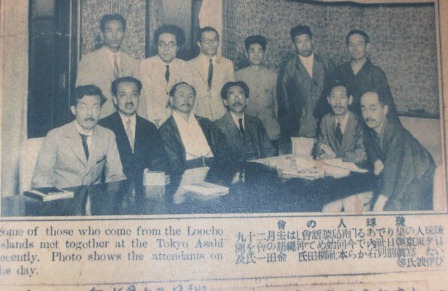

前列右端が柳田国男、左端が比嘉春潮/後列右から萩原正徳、大藤時彦、瀬川清子
1944年3月『民間伝承』柳田国男「『旅と伝説』について」□(略)改めてもう一度、初めから読み返して見たい気がする。公平に批判してどの部分、一ばん後世に役立つ仕事だったかを、考へ且つ説いて見たくもなる。
私の処にはもう主要記事の索引も出来て居るのだが、この判定は実はさう容易な業では無い。しかし先ず大まかに考へて、婚礼誕生葬祭その他の特集号を出し、又昔話を二度まで出した頃などが、全盛期だったと言へるかもしれない。こんなにまで多数の同志があったのかと、驚くほどの人々が全国の各地から、何れも好意づくだけでよい原稿を寄せ、所謂陣容を輝かしてくれたのみならず、此時を境にそれぞれの問題に対する理解常識が、目に見えて躍進したので、之を読んで居ない人の云ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料といふものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを、実地に証明してくれたのである。
その以外に今一つ承認しなければならぬことは、萩原君は故郷の奄美大島の為に、この雑誌を通して中々よく働いて居る。それには同郷知友の共鳴支援といふことも条件ではあったが、とにかくに全十六巻を通じて、奄美大島に関する報告は多く、又清新な第一次の資料が多かったことは争へない。その一つの例として手近に私の心づいたことをあげると、第一巻のたしか二号か三号に、島の先輩の露西亜学者昇曙夢さんが、アモレヲナグ即ち天降女人の事を書いて、我々に大きな印象を与へ、又より多くを知りたがらせて居たのだが、それが約十六年を隔てて最終号の中に、今度は金久正君といふ若い同志が、それを詳しく書いて我々の渇望を医して居る。もう「旅と伝説」さへ大切に保存して置けばこの世界的興味のある一問題は、永久に学問の領分からは消えないのである。或ひはそれほどまで大きな問題だと思はぬであらう人たちの為に、出来るだけ簡単に前後二ヶ所に出て居る天降女人の事を書き伝へ、出来るならば此上にももっと豊富な資料の、集まって来る機縁を促したい。(略)
奄美大島といふところは、私の知る限りでも、内部歴史の珍しく豊かな島であった。書いた記録がといふものは僅かしか残らぬが、近い百年二百年の間にも避ければ避けたかった実に色々な経験をしてゐる。さうして全体に今は古い拘束から解き放たれて、新時代のあらゆる機会を利用し、すぐれた人物が輩出して居るのである。住民自身としては忘れた方がよいやうな、外の者からは是非参考の為に聴いて置きたいやうな、無数の思ひ出をかかへて、まだ其処理を付けずに居るといふ感じがある。此数からいふと、萩原君の如き人がもっと辛抱強く、古い埋もれたことを尋ね出さうとする知友を糾合して居てくれたらと思はずには居られぬのだが、それをもう謂って見ても仕方が無い。それよりも雑誌をその時々の慰みなどとは考へずに、いつまでも之を精読する者の、是から日本にも多くなるやうに、我々もどうかして残るやうな雑誌を作って行きたい。
1981年7月『道之島通信』83号「民俗学開拓に貢献 萩原正徳(1896~1950)」□はじめに 1928年(昭和3年)から1944年(昭和19年)まで、東京で『旅と伝説』という月刊雑誌を発行、日本民族学の発展に著しく貢献したのが萩原正徳である。正徳は、1896年(明治29年)名瀬市金久に生まれ、若くして上京、東京高等工芸学校を卒業、27歳の時夫人ウメさん(千葉県出身)を娶った。弟に利用と厚生がおり、厚生は鹿児島一中から一高、東大へ進んだ奄美の秀才として名を馳せた人である。酒と島うたが好きで、子供が喧嘩して泣いて帰ると「泣かされて帰る奴がいるか、相手を泣かして来い」と、一人息子の正道を叱るくらいの気骨の持ち主でもあった。三元社という写真製版の会社を経営する一方、柳田国男らの民俗研究グループに参加、奄美をはじめ、各地の研究報告を『旅と伝説』に掲載、記録を歴史に残した。「若い頃から頭は、はげていましたので、年の割に老けて見えましたよ」と八十歳になったウメさんは話す。耳が悪かったため、兵役を免れ、柳田国男にどなられても笑っていたという。
1998年10月『柳田國男全集 第6巻 月報13』山下欣一「『海南小記』ー奄美の旅前後」□(略)最初の伊波普猷の奄美来訪は1918年(大正7)1月であった。これは私立大島郡教育会・二部研究会(瀬戸内・宇検)による招聘である。この時の中心になったのは二部研究会長で古仁屋小学校長永井龍一と当時篠川農学校教諭竹島純(沖縄師範卒)であった。この2名は伊波普猷・比嘉春潮を出迎えのために名瀬へ出張するが、船待ちのため十数日滞在を余儀なくされ、その間、奄美の文献資料を調査したりしている。この時『奄美大島史』の著者である坂口徳太郎も鹿児島県立大島中学校に勤務していたので、その指導も受けたと考えられる。
伊波普猷は、この第1回の旅で『南島雑話』、『奄美史談』などを沖縄へ借用し、筆写させ、沖縄県立図書館へ収蔵し閲覧に供したのである。(略)伊波普猷の奄美招聘の中心にいた竹島純は伊波普猷の講演記録を伊波の「序に代へて」を付して1931年(昭和6)に大島郡教育会から『南島史考』としてまとめている。また後で永井龍一は鹿児島に居を移し、『南島雑話』、『補遺篇』、『奄美史談』などの文献資料の自費刊行を試みている。この『南島雑話』刊行に刺激された永井龍一の兄亀彦(博物学者)は『南島雑話』の編著者を薩摩藩上士名越左源太時敏と確認し、また名越家で『遠島日記』をも発見し、これらを自費刊行している。これらは、昭和初年から、終戦直後に及んだ作業であった。永井兄亀・龍一兄弟は名瀬の与人役政家の一族である。父永井長昌喜は漢学者で教育者であった。
亀彦・龍一の姉よしは萩原家に嫁し、その子息が正徳・利用・厚生の兄弟である。叔父に『奄美史談』の著者都成植義(南峰)がいる。亀彦・龍一の甥に当る萩原正徳は上京し、東京高等工業学校で学び、海軍省水路部をへて写真製版業を営み、三元社を興した。柳田国男の指導を受けて『旅と伝説』を刊行した。これには昇曙夢・岩倉市郎・金久正などの奄美の研究者が登場しているのは故なしとしないのである。
11/13: 1933年1月 金城朝永『異態習俗考』六文館

1934年7月 金城朝永『異態習俗考』成光館書店
□琉球の遊女ー(略)琉球の遊女に関連しては尚多くの書くべき事柄が本稿には取り残されてている。その琉球史上に於ける詳細な文献學的考証と論究は前記の『沖縄女性史』の御一読を御勧めするとして、その外でも、琉球の農村と遊女との関係、今一つ廓内の「尾類馬行列」に就いては書いて見る積りであった。殊に後者は、遊廓の行事と云ふよりも那覇の町にとってもその年中行事の大きなものの一つに数えてもよい位で是は旧正月廿日に挙行されるので、土地では「廿日正月」と云へば「尾類馬行列」を意味している程有名なものであるが、その詳細に就いて述べるには、本文と等しい紙数を要さねばならないから止むなく割愛することにした。それから本稿に於いては平易なものの外は引用文献の再録を避けて単に摘意に止めたり、又はその書名をも二三除いては省略して置いたが、之は故意に先人の功を閑却した訳ではなく、可なり型ぐるしい記述を採用しなかった為めであるから、切に読者諸賢の寛怒を請ふ次第である。

1932年1月 『犯罪科学』金城朝永「頭蓋骨崇拝」
1931年2月 『デカメロン』創刊号 金城朝永「琉球の遊女」
□裏表紙に原浩三『ポムペイの美術』風俗資料刊行会の広告。「ポムペイ!この名に籠っている響の強さはどうだ。其処は2千年の長い間 地下に葬られていた都市であり、特別な女郎屋とか淫祠でなく普通の家庭の寝間に春画が飾られ、妙な彫刻が置かれてあった処である」と刊行の辞がある。
□戦後の1969年10月発行『愛苑』は髙橋鐵監修だが巻頭にカラーで「古代人の愛 ポンベイ壁画集」が載っている。
1933年1月 『人情地理』創刊号 金城朝永「迷信のろーかる・からー」


金城朝永の手紙

金城朝永の本

金城芳子の本
1996年10月 阿部達彦『沖縄の遊女についてー宗教社会学ー』近代文芸社
○沖縄の遊女についてー沖縄の遊女/旅行者(渡辺重剛、バジル・ホール・チェンバレン、笹森儀助、加藤三吾、リヒャルト・ゴールドシュミット)の見た遊女たち/信心と生きるための智慧
○浩々洞と精神主義運動ー清沢満之を中心にー
2014・8/不二出版「『犯罪科學』解説・総目次・索引」





「『犯罪科學』解説・総目次・索引」の執筆者索引を見て、沖縄に関わりのある人物を紹介する。

安藤盛は戦前、来沖した人物で、ジュンク堂那覇店で青木澄夫『放浪の作家ー安藤盛と「からゆきさん」』(風媒社)を入手した。私の知らない安藤の沖縄関連の著作もその目録にあった。本誌に収録されてない琉球新報の1938年6月の記事を紹介する「南洋及び支那通として知られていた著述家安藤盛氏は21日東京の自宅において逝去した。氏は昭和11年、同12年の2回に亘り本県に来遊し週刊朝日其他の雑誌で紀行文を発表、本県紹介に努め県人から親しまれていた。なほ生前本社へ長編小説(琉球新報に連載「紅雀」絵・西銘生一)を寄せたが未発表のうちに急逝し遂に遺稿となった享年41」とある。

関連資料ー2001年9月『けーし風』第32号「特集 旧南洋群島のウチナーンチュ」
伊東忠太、伊波普猷、岩田準一(琉球の男色を調査)、巌谷小波、大宅壮一、喜田貞吉(1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」)金城朝永、東郷青児、西村眞次、宮尾しげを、①饒平名紀芳らが居る。
①

1938年4月19日『琉球新報』「饒平名紀芳氏 7年振に帰る」


コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com
石川正通 1934年1月1日 今人生の峠に立って 夜明けを待つ身に鬼気は迫る 過去の夢は貘に食わそう 未来は神に預けておこう さあ現在だ永劫の現在だ 全き憩いに若水を汲もう
1929年9月1日『沖縄朝日新聞』「昭和5年1月、三越において本県物産の展覧会を開催することについては斡旋者たる我部政達氏・・・」(この頃、三越に1919年入店の瀬長良直が居る。1934年、銀座支店長。1937年、大阪支店長)
1930年 世界恐慌が波及
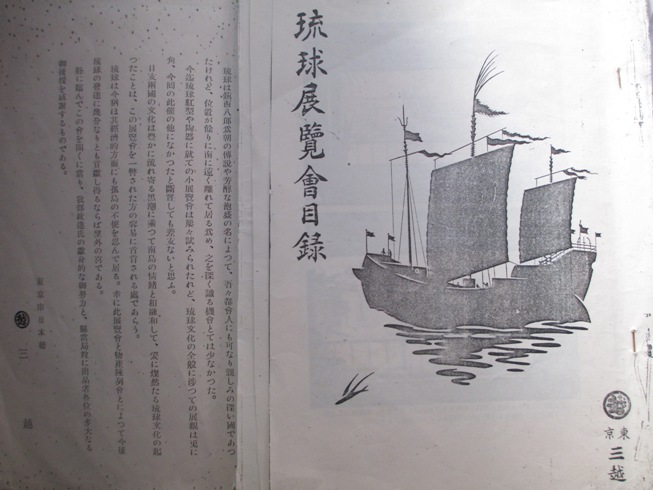

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」
1930年6月 『犯罪科学』1巻6号 伊波普猷「古琉球貴族の性生活」
1931年2月 『デカメロン』創刊号 金城朝永「琉球の遊女」
1931年7月 『犯罪科学』別巻2巻8号 伊波普猷「布哇物語」
1931年9月 『犯罪公論』2巻1号 伊波普猷「布哇産業史の裏面」
1931年9月 満州事変おこる
1932年1月 『犯罪科学』金城朝永「頭蓋骨崇拝」
1932年3月 『犯罪科学』3巻3号 伊波普猷「性に関する南島の民謡」
1932年3月 満州国建国
1932年5月15日 海軍将校ら首相官邸など襲撃、犬養毅首相を射殺


1933年1月1日 大宜味朝徳『南島』創刊
1933年1月 『人情地理』創刊号 金城朝永「迷信のろーかる・からー」
1933年1月 金城朝永『異態習俗考』六文館 伊波普猷「序に代へてー八重山のまくた遊び」
1933年3月 日本、国際連盟脱退
1933年6月ー仲原善徳『大南洋評論』第1巻第2巻(仲原善徳編集)□金城朝永「南洋関係図書目録」


1933年7月 仲宗根源和『沖縄縣人物風景寫眞帖』沖縄縣人物風景寫眞帖刊行會


唐手ー冨名腰義珍


昭和8年 東京琉球泡盛商組合(金城時男会長)発会式/東京八重山郷友会


1933年3月5日 大宜味朝徳『南島』第3号/4月5日 大宜味朝徳『南島』第4号


東京江戸川 伊江島郷友会/鶴見沖縄会館


東京沖縄県人会/在京首里人会


横浜市鶴見沖縄県人同志会/富士瓦斯紡績株式会社川崎工場 沖縄県人女工


1933年8月5日『南島』第7号 久志芙沙子「若葉から拾った哲学」/1934年1月1日『南島』第9号 久志芙沙子「無題」


1934年1月1日 大宜味朝徳『南島』第九号 久米仙「わが郷里の人々・東京県人会ーかつて筆者は自分の事を『俺は琉球人だ』と謂ったことに対して叱られ、『俺は芋を喰って育った』と書いたので絶交を宣告された経験がある・・・恩河朝健、は副会長で計理士を職業とする。元来計数的智能に乏しい郷土の人々に、近来計理士の多く出る微候の見えるのは喜ばしい事である。」


1934年2月10日 大宜味朝徳『南島』第十号 久米仙「わが故郷の人々・学者ー教育者ー文士」

1934年7月 金城朝永『異態習俗考』成光館書店 伊波普猷「序に代へてー八重山のまくた遊び」


1935年10月 上原永盛『沖縄縣人物風景寫眞大観』沖縄通信社




県外篇ー長嶺亀助、神山政良、仲宗根玄愷、渡口精鴻、東恩納寛惇、伊波普猷、翁長良保、銘苅正太郎、大濱信泉、伊豆味元永、比嘉良篤、伊元富爾、八幡一郎、大城盛隆、高嶺明達、宮城新昌、富名腰義珍、翁長良奎、宮城仁勇、奥島憲仁、當山寛、上原健男、島袋全達、田崎昌亮、久高將吉、田崎朝盛、多嘉良憲秀、大城兼眞、仲吉朝敏、仲地昌元、我謝秀裕、安次富長英、


眞玉橋朝起、國吉眞俊、比嘉春潮、仲本興正(サイパン沖縄縣人會々長)、饒平名智太郎、宮城清、安村師福、仲原善忠、嘉手刈信世、恩河朝健、大宜味朝徳、多田喜導、宮里良保、當間惠榮、親泊康永、島袋源七、山盛哲、宮城出隆、石川元康、多嘉良憲福、漢那朝常、與座弘晴、宮里興保、東風平玄宋,、與世山彦士、我喜屋宗信(大阪湯浅商店代表社員)、平尾喜代松(大阪平尾商店主)、豊川忠進(大阪沖縄県人会会長)、山城興善(益榮商会主)、玉城克巳、下地玄信、翁長良孝




1936年2月26日 皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官・兵を率いて起こした日本のクーデター未遂事件。 この事件の結果、岡田内閣が総辞職し、後継の廣田内閣が思想犯保護観察法を成立させた。
1936年11月 『訓練』仲原善徳「フィリッピン観光記(上)」
1937年1月 帝室博物館「琉球風俗品陳列」
1937年3月ー仲原善徳『南洋千一夜一夜物語』日本書房
1937年3月ー『国際パンフレット通信』第998号 仲原善徳「蘭領ニューギニアの実相」
1937年4月ー『改造』仲原善徳「蘭領ニューギニア」
1937年7月 新宿伊勢丹で「琉球と薩摩の文化展覧会」
1938年4月 国家総動員法公布(5月5日施行)日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和13年(1938)制定、同20年廃止。
1938年12月ー『比律賓年鑑』仲原善徳「比律賓群島の諸民族」
石川正通 1934年1月1日 今人生の峠に立って 夜明けを待つ身に鬼気は迫る 過去の夢は貘に食わそう 未来は神に預けておこう さあ現在だ永劫の現在だ 全き憩いに若水を汲もう
1929年9月1日『沖縄朝日新聞』「昭和5年1月、三越において本県物産の展覧会を開催することについては斡旋者たる我部政達氏・・・」(この頃、三越に1919年入店の瀬長良直が居る。1934年、銀座支店長。1937年、大阪支店長)
1930年 世界恐慌が波及
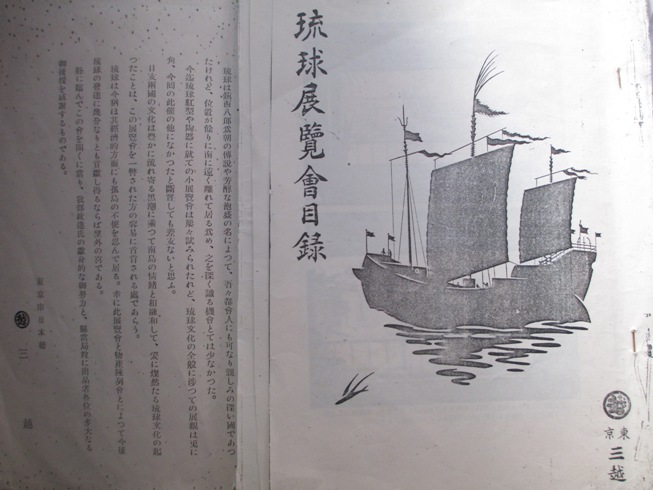

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」
1930年6月 『犯罪科学』1巻6号 伊波普猷「古琉球貴族の性生活」
1931年2月 『デカメロン』創刊号 金城朝永「琉球の遊女」
1931年7月 『犯罪科学』別巻2巻8号 伊波普猷「布哇物語」
1931年9月 『犯罪公論』2巻1号 伊波普猷「布哇産業史の裏面」
1931年9月 満州事変おこる
1932年1月 『犯罪科学』金城朝永「頭蓋骨崇拝」
1932年3月 『犯罪科学』3巻3号 伊波普猷「性に関する南島の民謡」
1932年3月 満州国建国
1932年5月15日 海軍将校ら首相官邸など襲撃、犬養毅首相を射殺


1933年1月1日 大宜味朝徳『南島』創刊
1933年1月 『人情地理』創刊号 金城朝永「迷信のろーかる・からー」
1933年1月 金城朝永『異態習俗考』六文館 伊波普猷「序に代へてー八重山のまくた遊び」
1933年3月 日本、国際連盟脱退
1933年6月ー仲原善徳『大南洋評論』第1巻第2巻(仲原善徳編集)□金城朝永「南洋関係図書目録」


1933年7月 仲宗根源和『沖縄縣人物風景寫眞帖』沖縄縣人物風景寫眞帖刊行會


唐手ー冨名腰義珍


昭和8年 東京琉球泡盛商組合(金城時男会長)発会式/東京八重山郷友会


1933年3月5日 大宜味朝徳『南島』第3号/4月5日 大宜味朝徳『南島』第4号


東京江戸川 伊江島郷友会/鶴見沖縄会館


東京沖縄県人会/在京首里人会


横浜市鶴見沖縄県人同志会/富士瓦斯紡績株式会社川崎工場 沖縄県人女工


1933年8月5日『南島』第7号 久志芙沙子「若葉から拾った哲学」/1934年1月1日『南島』第9号 久志芙沙子「無題」


1934年1月1日 大宜味朝徳『南島』第九号 久米仙「わが郷里の人々・東京県人会ーかつて筆者は自分の事を『俺は琉球人だ』と謂ったことに対して叱られ、『俺は芋を喰って育った』と書いたので絶交を宣告された経験がある・・・恩河朝健、は副会長で計理士を職業とする。元来計数的智能に乏しい郷土の人々に、近来計理士の多く出る微候の見えるのは喜ばしい事である。」


1934年2月10日 大宜味朝徳『南島』第十号 久米仙「わが故郷の人々・学者ー教育者ー文士」

1934年7月 金城朝永『異態習俗考』成光館書店 伊波普猷「序に代へてー八重山のまくた遊び」


1935年10月 上原永盛『沖縄縣人物風景寫眞大観』沖縄通信社




県外篇ー長嶺亀助、神山政良、仲宗根玄愷、渡口精鴻、東恩納寛惇、伊波普猷、翁長良保、銘苅正太郎、大濱信泉、伊豆味元永、比嘉良篤、伊元富爾、八幡一郎、大城盛隆、高嶺明達、宮城新昌、富名腰義珍、翁長良奎、宮城仁勇、奥島憲仁、當山寛、上原健男、島袋全達、田崎昌亮、久高將吉、田崎朝盛、多嘉良憲秀、大城兼眞、仲吉朝敏、仲地昌元、我謝秀裕、安次富長英、


眞玉橋朝起、國吉眞俊、比嘉春潮、仲本興正(サイパン沖縄縣人會々長)、饒平名智太郎、宮城清、安村師福、仲原善忠、嘉手刈信世、恩河朝健、大宜味朝徳、多田喜導、宮里良保、當間惠榮、親泊康永、島袋源七、山盛哲、宮城出隆、石川元康、多嘉良憲福、漢那朝常、與座弘晴、宮里興保、東風平玄宋,、與世山彦士、我喜屋宗信(大阪湯浅商店代表社員)、平尾喜代松(大阪平尾商店主)、豊川忠進(大阪沖縄県人会会長)、山城興善(益榮商会主)、玉城克巳、下地玄信、翁長良孝




1936年2月26日 皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官・兵を率いて起こした日本のクーデター未遂事件。 この事件の結果、岡田内閣が総辞職し、後継の廣田内閣が思想犯保護観察法を成立させた。
1936年11月 『訓練』仲原善徳「フィリッピン観光記(上)」
1937年1月 帝室博物館「琉球風俗品陳列」
1937年3月ー仲原善徳『南洋千一夜一夜物語』日本書房
1937年3月ー『国際パンフレット通信』第998号 仲原善徳「蘭領ニューギニアの実相」
1937年4月ー『改造』仲原善徳「蘭領ニューギニア」
1937年7月 新宿伊勢丹で「琉球と薩摩の文化展覧会」
1938年4月 国家総動員法公布(5月5日施行)日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和13年(1938)制定、同20年廃止。
1938年12月ー『比律賓年鑑』仲原善徳「比律賓群島の諸民族」
1928年7月 『南島研究』第三輯
口絵「琉球の結婚風俗」
編輯者より・・・西平賀譲
▽研究・雑録△
禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)
▽資料△
1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿
①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没
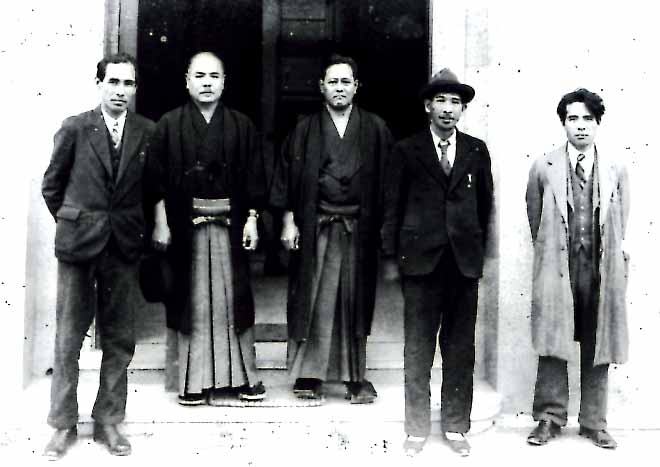
写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)
1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」
1928年11月 『南島研究』第四輯
口絵「進貢船の那覇港解纜」
▽史論・雑録△
北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ
○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。
1929年3月 『南島研究』第5輯
口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」
▽史論・研究△
名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信と寄贈雑誌
○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)
1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社
1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」
1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告
1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」
1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東
口絵「琉球の結婚風俗」
編輯者より・・・西平賀譲
▽研究・雑録△
禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)
▽資料△
1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿
①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没
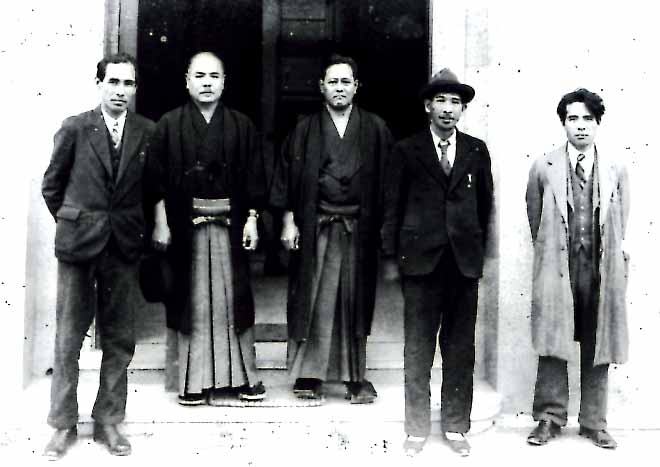
写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)
1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」
1928年11月 『南島研究』第四輯
口絵「進貢船の那覇港解纜」
▽史論・雑録△
北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ
○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。
1929年3月 『南島研究』第5輯
口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」
▽史論・研究△
名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信と寄贈雑誌
○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)
1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社
1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」
1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告
1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」
1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東
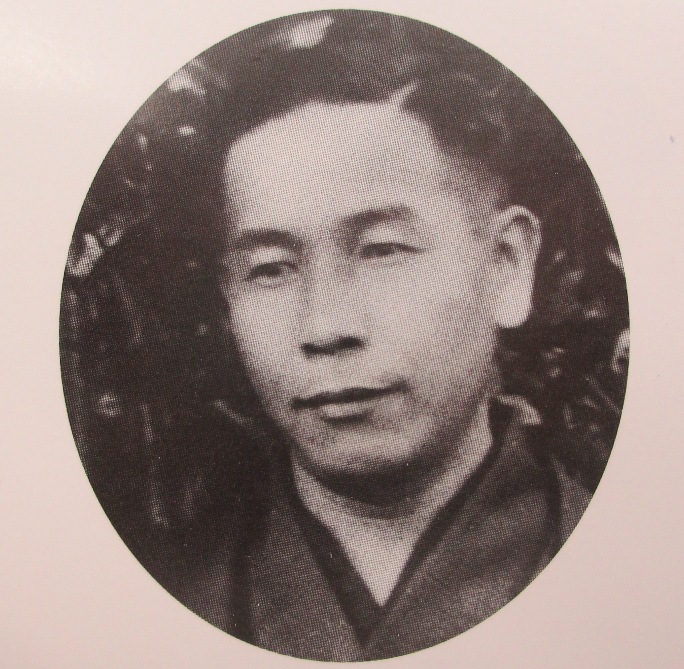
魚住惇吉
○大正13年(1924年)魚住惇吉校長の後を受けて建学当初から教鞭をとられた志喜屋孝信先生が第四代校長に就任した。
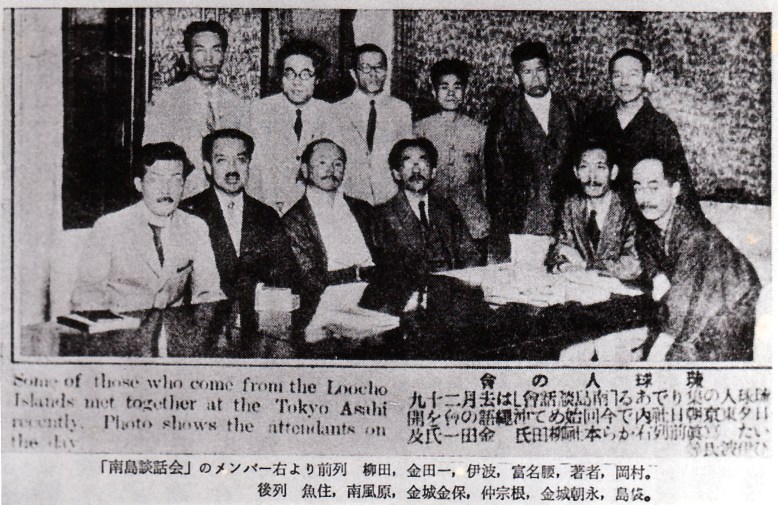
『アサヒグラフ』1927年7月13日号□南島談話会のメンバー/前列右より柳田国男・金田一京助・伊波普猷・富名腰義珍・岡村千秋 後列右より魚住惇吉・南風原驍・金城金保・仲宗根源和・金城朝永・島袋源七

1924年夏 小石川植物園で、向かって右から魚住惇吉、永田千代、
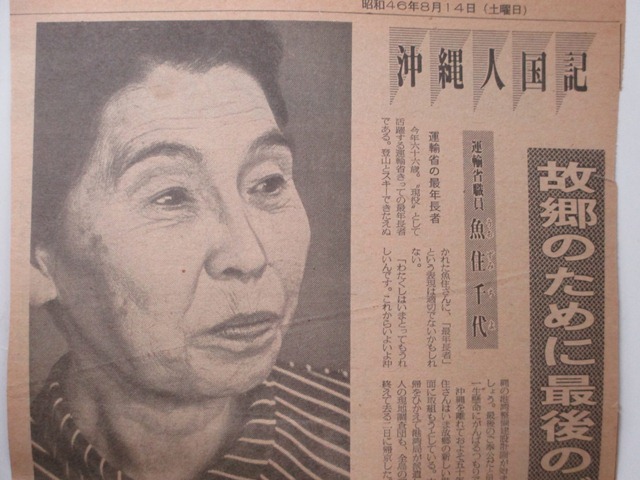
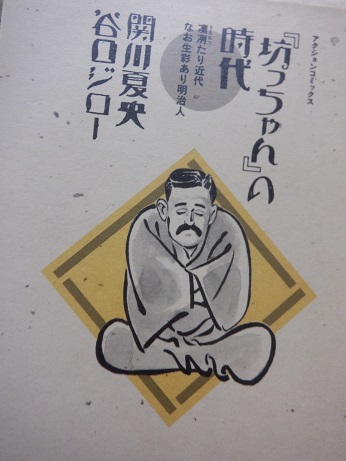
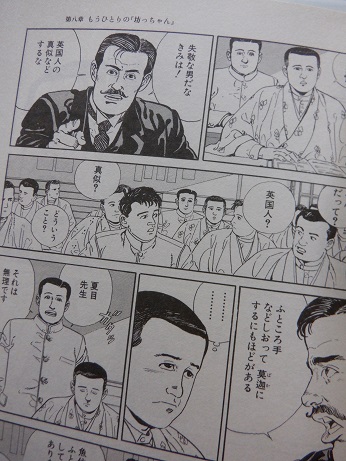
1987年8月 関川夏央・谷口ジロー『「坊っちゃん」の時代』双葉社
1988年8月 日本エッセイスト・クラブ『思いがけない涙』文藝春秋□魚住速人(三菱鉱業セメント副社長)「漱石と隻腕の父ー(略)実をいうと、私の父が、その左手のない学生である。名前は惇吉という。(略)私の父は東大を卒業したあと、中学の英語教師になり、沖縄県立第二中学校の校長を最期に、台湾旅行のとき罹ったマラリアの持病もあって、42歳で早々と引退、自適の生活に入った。ふたたび東大に通い、英文学やラテン語の研究をしていたことを覚えている。(略)私の息子が東大野球部に入り、法政の江川投手を4打数3安打で打ち破ったことがあるのを父が知ったら、さぞかし喜んだことであろう。」
02/19: 神村朝堅 雑誌『おきなわ』創刊への道
1945年8月、国吉真哲・宮里栄輝・源武雄が早く帰還できるよう「県人会」結成を相談。宮里栄輝、熊本沖縄県人会長になる。/女子挺身隊救済で尼崎沖縄県人会結成。
9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。
11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎
11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会
11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行
12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)
1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦
1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。
2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」
3月、『関西沖縄新報』創刊
4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳
4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇
8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久
1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正
1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称
1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮
1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。
1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」
1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。
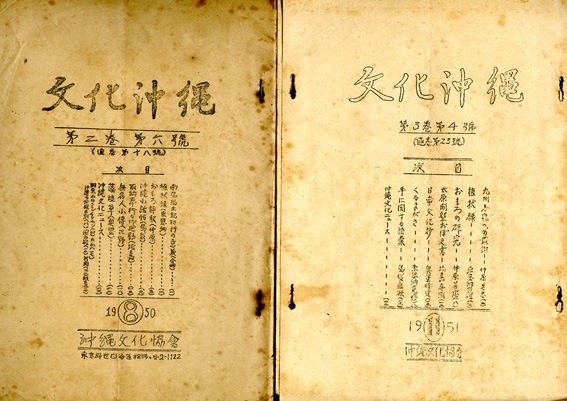
この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝
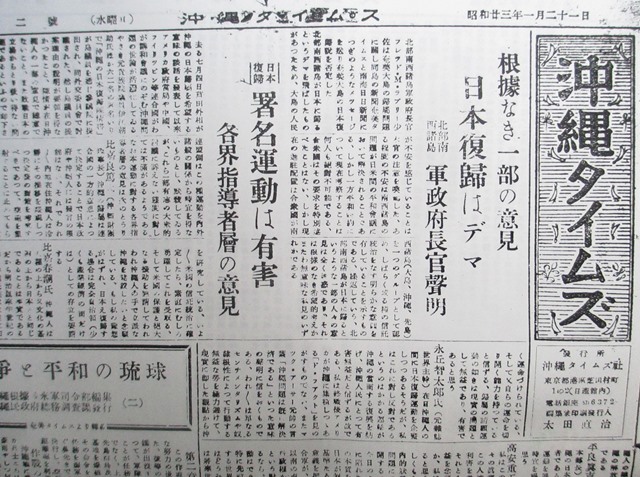
1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号
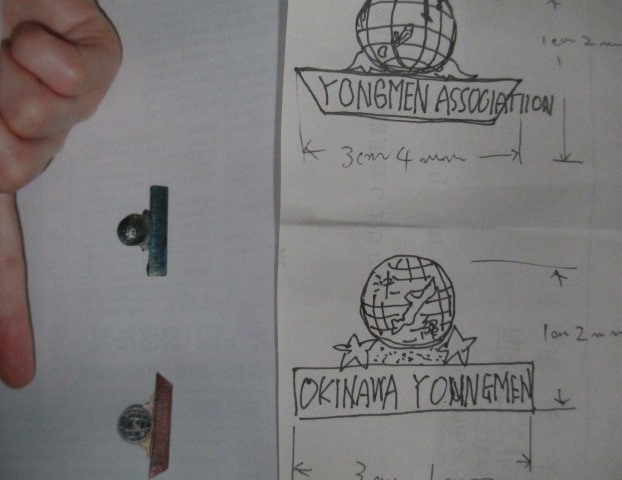
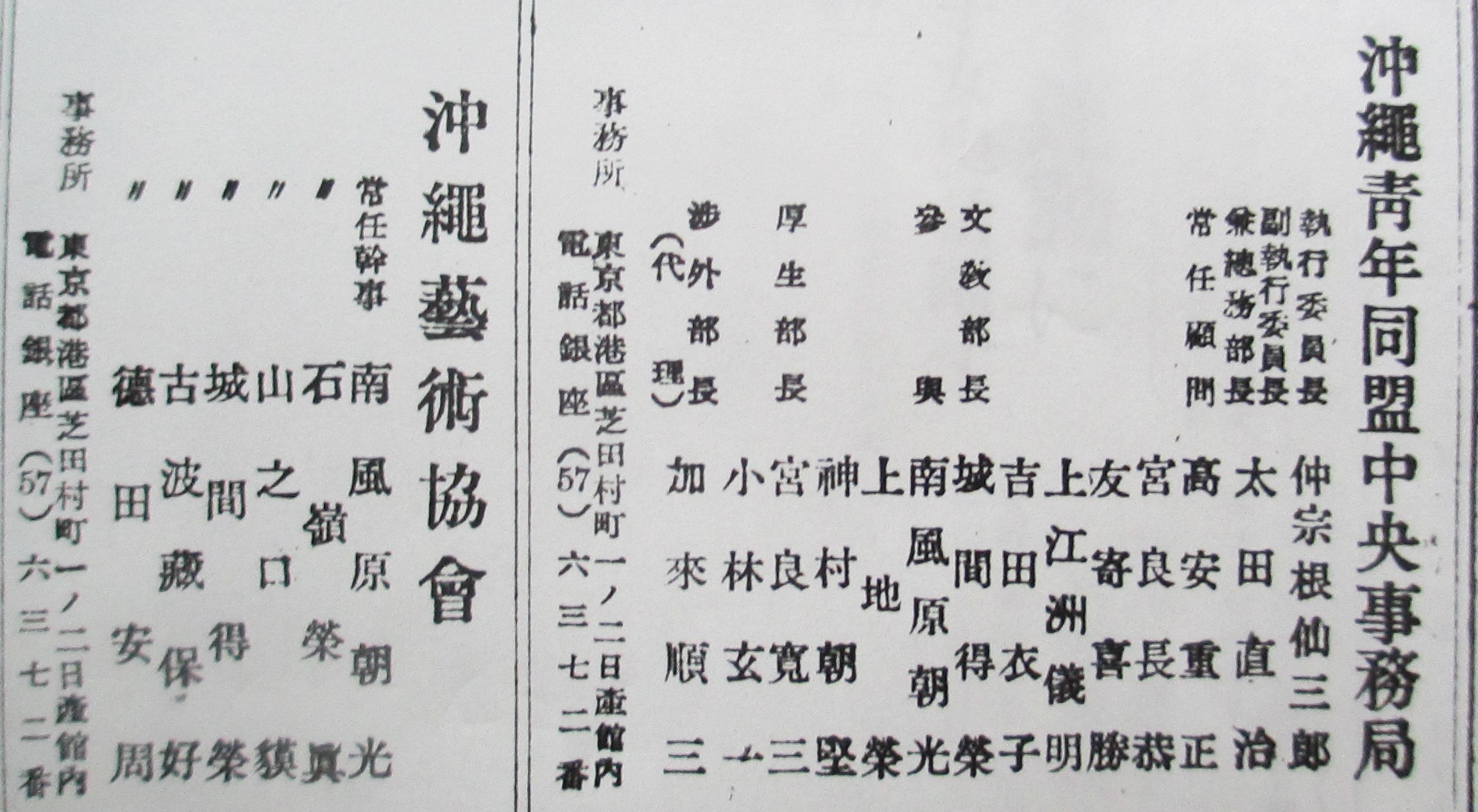
1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号
1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。
②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。
1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。
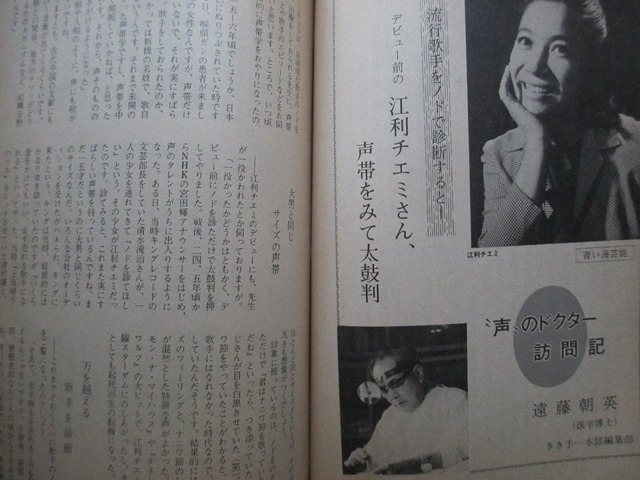
『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士
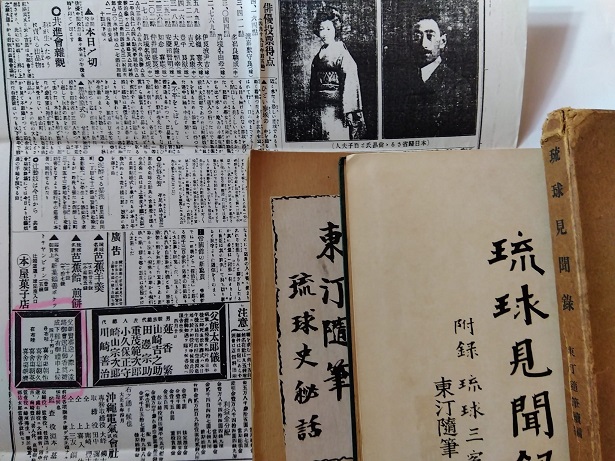
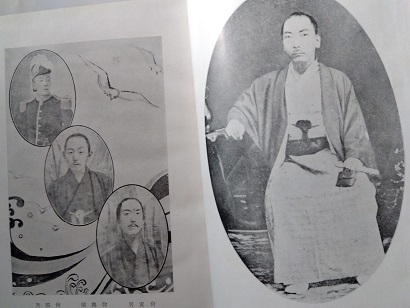
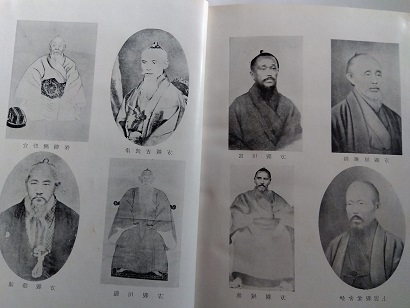
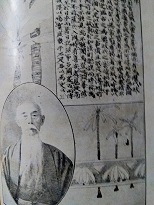
『琉球見聞録』東汀遺著刊行会、1952年11月。
喜舎場 朝賢(きしゃば ちょうけん、1840年〈天保11年〉 - 1916年〈大正5年〉4月14日)は、琉球王国末期の官僚。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、『琉球見聞録』を著した。童名は次郎。唐名は向(しょう)延翼。号は東汀。
晩年の1914年(大正3年)、琉球処分時の記録を『琉球見聞録』として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波普猷が「序に代えて 琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文を、巻末には発行者の親泊朝擢が「喜舎場朝賢翁小伝」をそれぞれ寄せている。波平恒男は、『琉球見聞録』の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で、差し障りがあったのではないかと推測している。→ウイキ
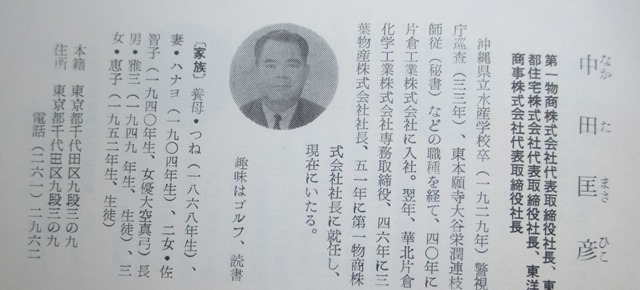
1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』
大空真弓 おおぞら-まゆみ
1940- 昭和後期-平成時代の女優。
昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。
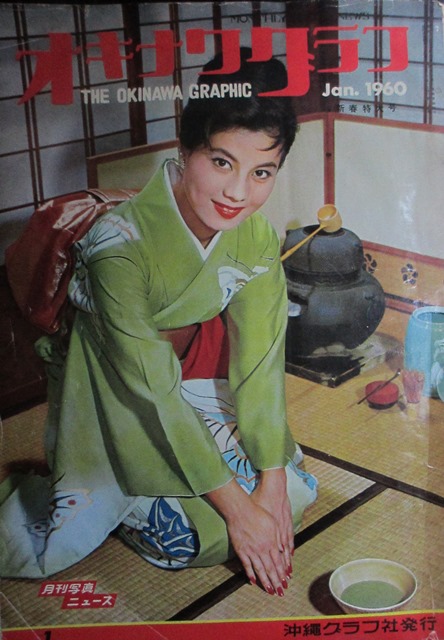
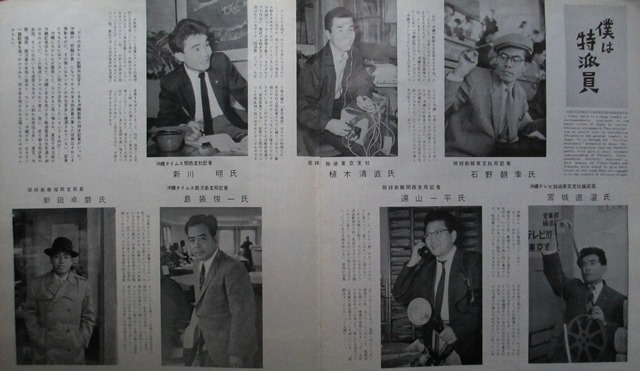
『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。
1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社
1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅
1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社
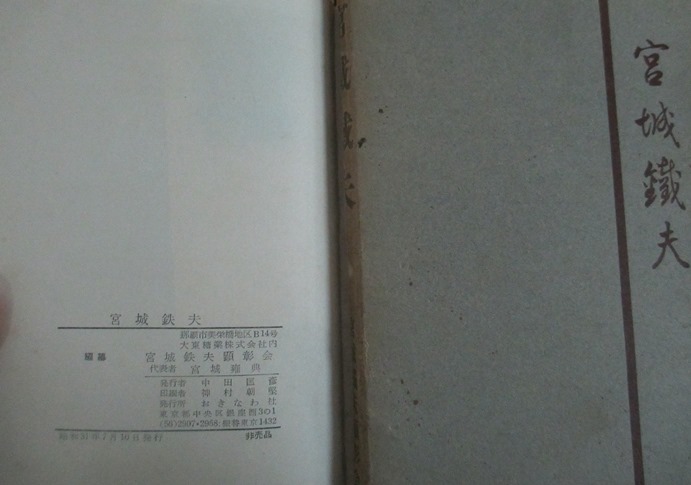 (BOOKSじのん在庫)
(BOOKSじのん在庫)
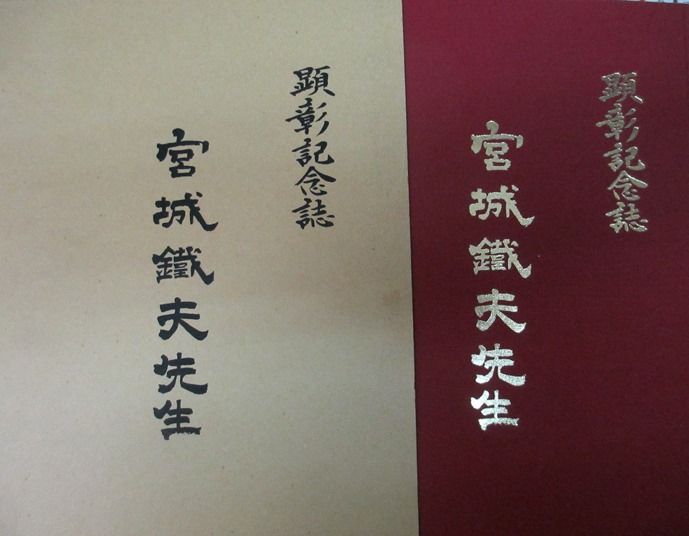
平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)
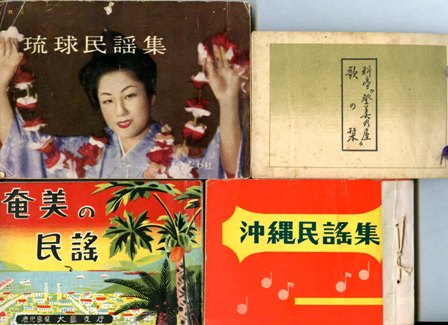
1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)
1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅
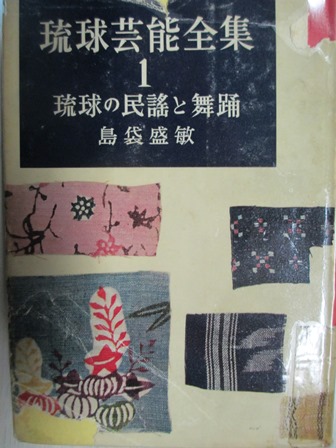
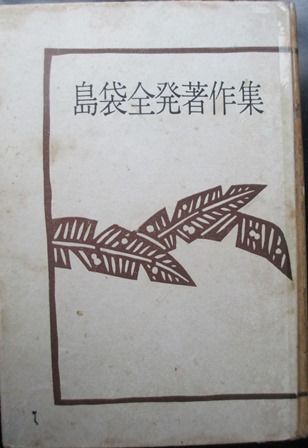
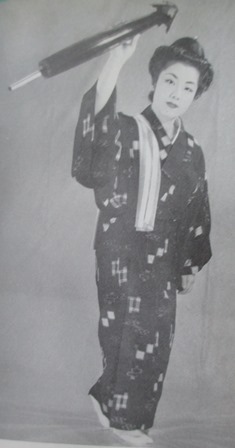
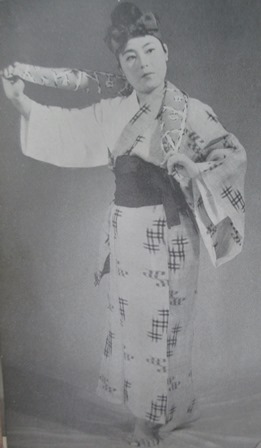
1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社
1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社
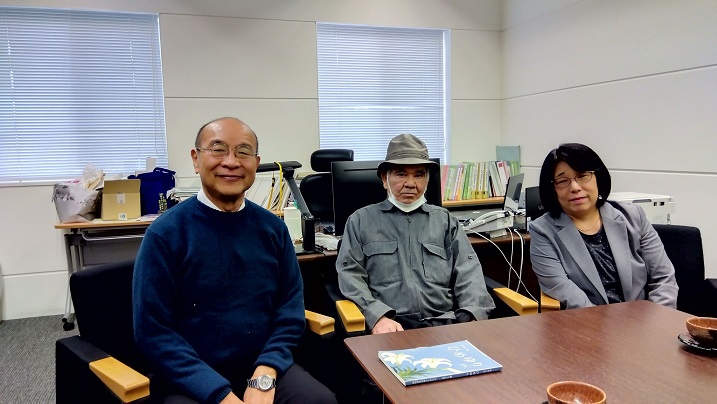
2025-2-5 沖縄県立博物館・美術館館長室:里井洋一館長、新城栄徳、大里知子法政大学沖縄文化研究所 准教授・専任所員
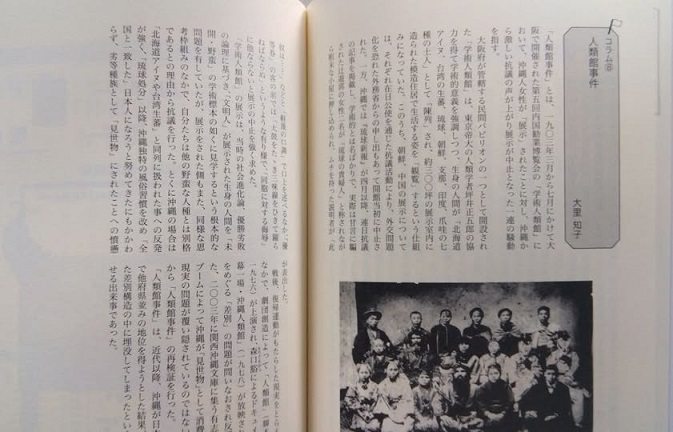
2021-11 『沖縄近現代史』ボーダーインク 大里知子「人類館事件」
1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社
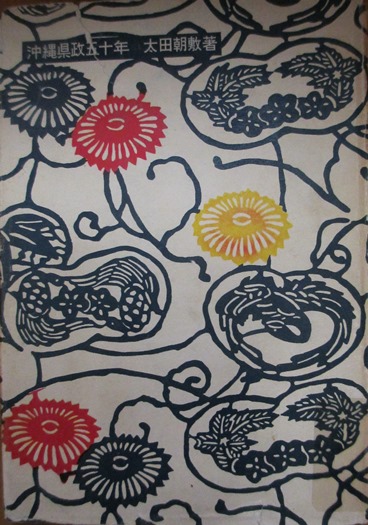
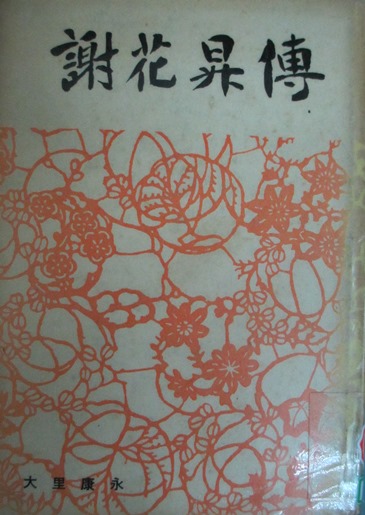
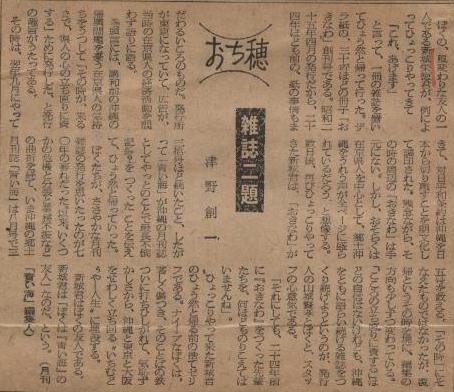
1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」
○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。
巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。
数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。
「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。
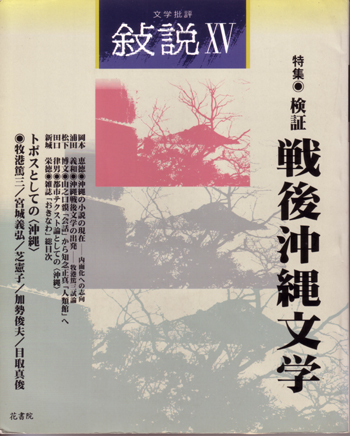

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」
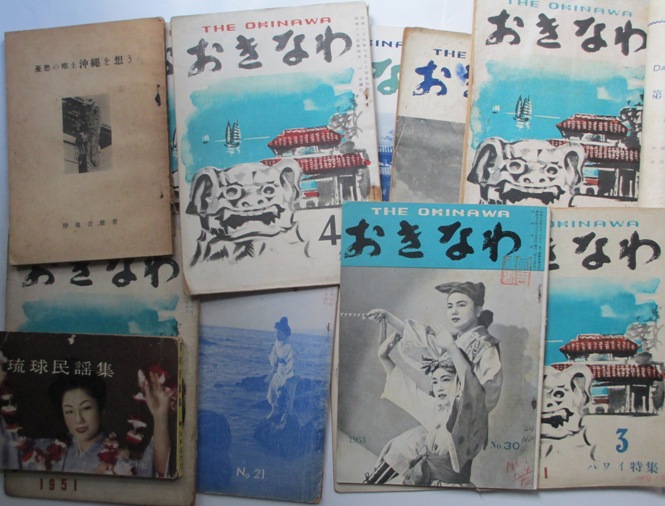
雑誌『おきなわ』
9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。
11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎
11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会
11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行
12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)
1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦
1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。
2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」
3月、『関西沖縄新報』創刊
4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳
4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇
8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久
1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正
1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称
1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮
1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。
1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」
1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。
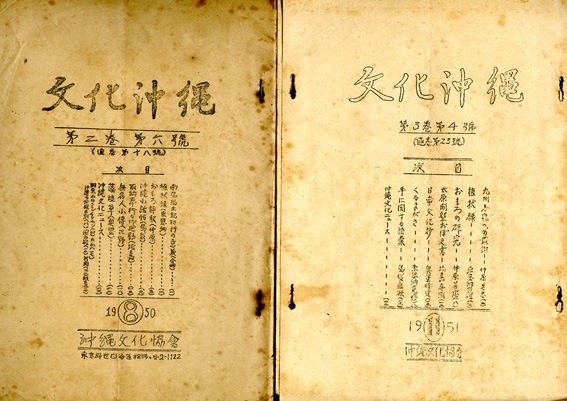
この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝
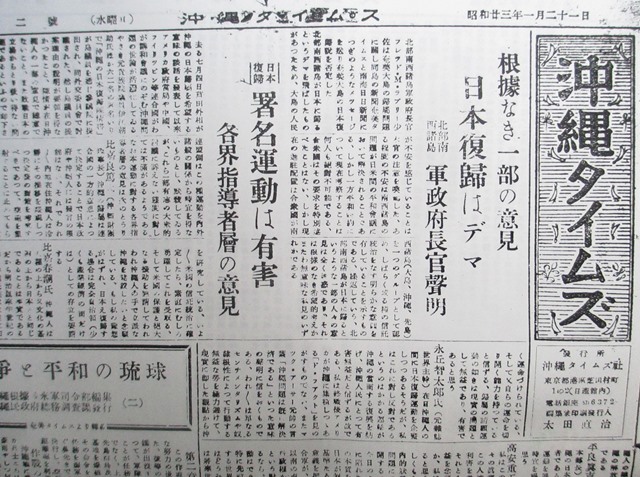
1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号
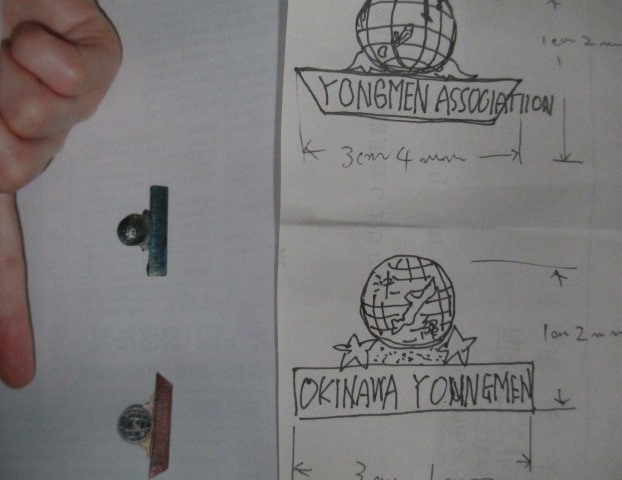
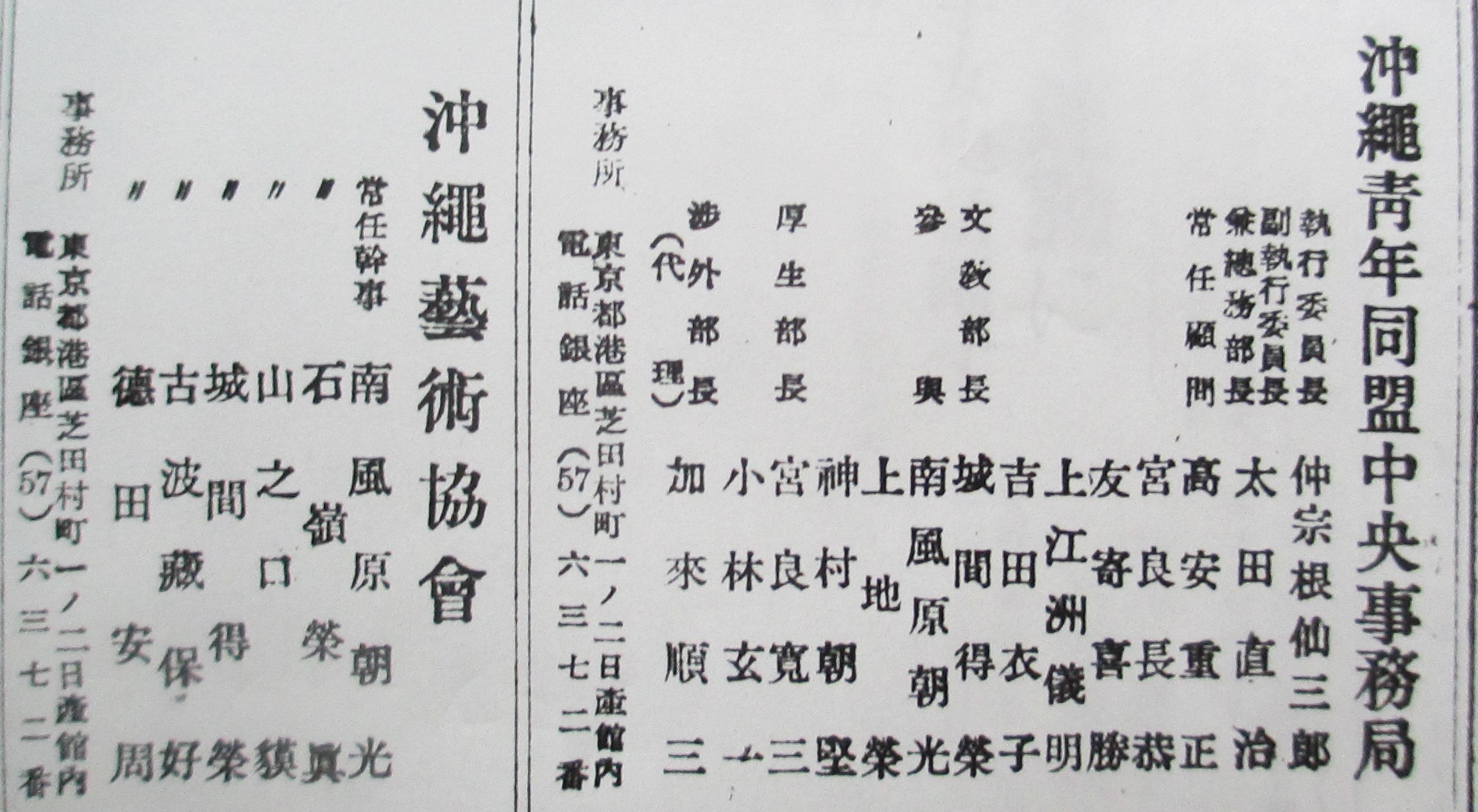
1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号
1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。
②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。
1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。
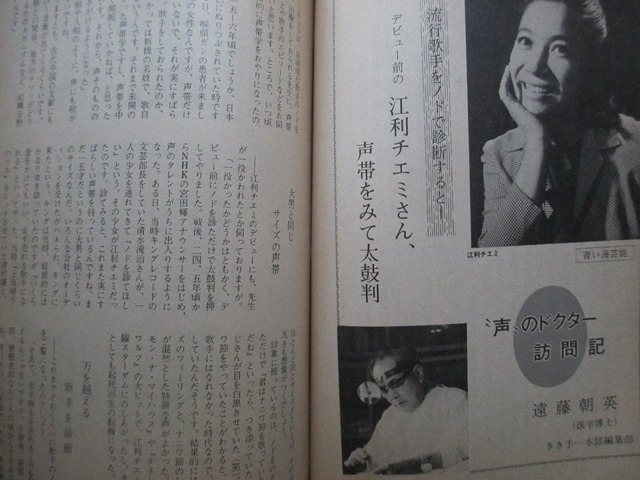
『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士
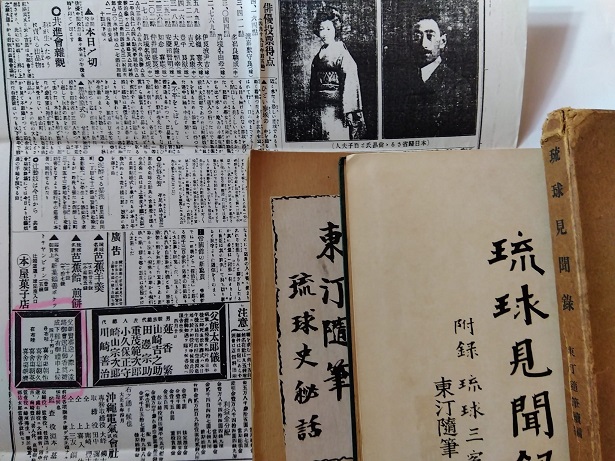
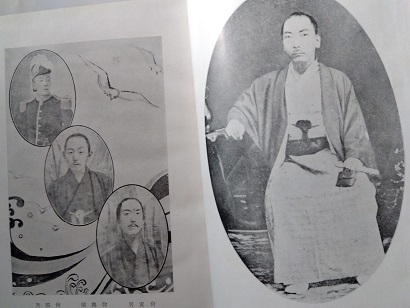
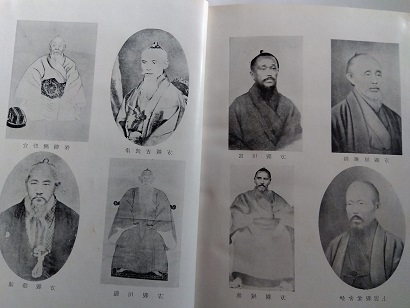
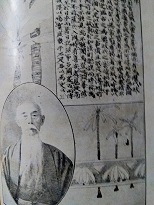
『琉球見聞録』東汀遺著刊行会、1952年11月。
喜舎場 朝賢(きしゃば ちょうけん、1840年〈天保11年〉 - 1916年〈大正5年〉4月14日)は、琉球王国末期の官僚。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、『琉球見聞録』を著した。童名は次郎。唐名は向(しょう)延翼。号は東汀。
晩年の1914年(大正3年)、琉球処分時の記録を『琉球見聞録』として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波普猷が「序に代えて 琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文を、巻末には発行者の親泊朝擢が「喜舎場朝賢翁小伝」をそれぞれ寄せている。波平恒男は、『琉球見聞録』の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で、差し障りがあったのではないかと推測している。→ウイキ
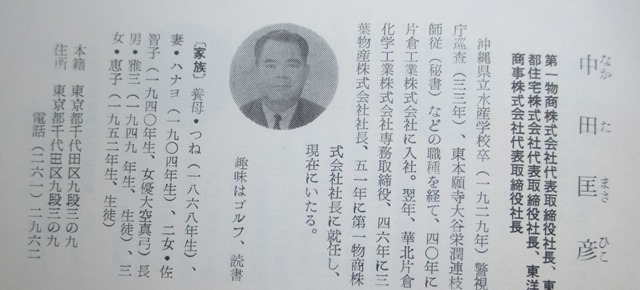
1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』
大空真弓 おおぞら-まゆみ
1940- 昭和後期-平成時代の女優。
昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。
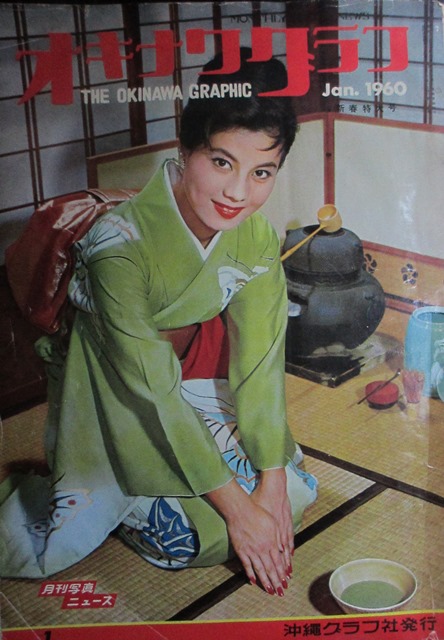
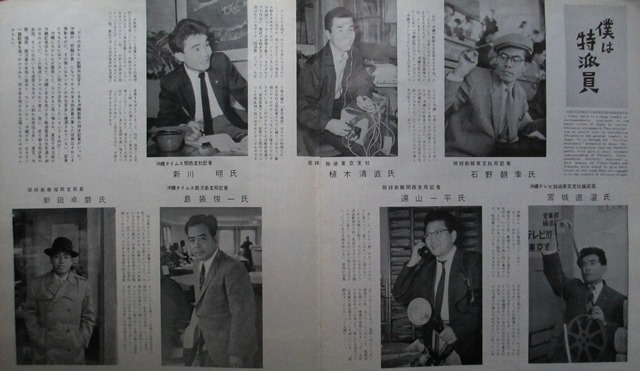
『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。
1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社
1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅
1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社
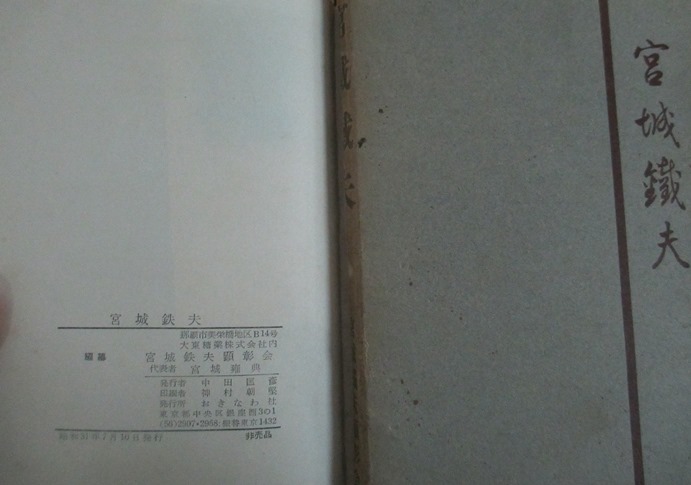 (BOOKSじのん在庫)
(BOOKSじのん在庫)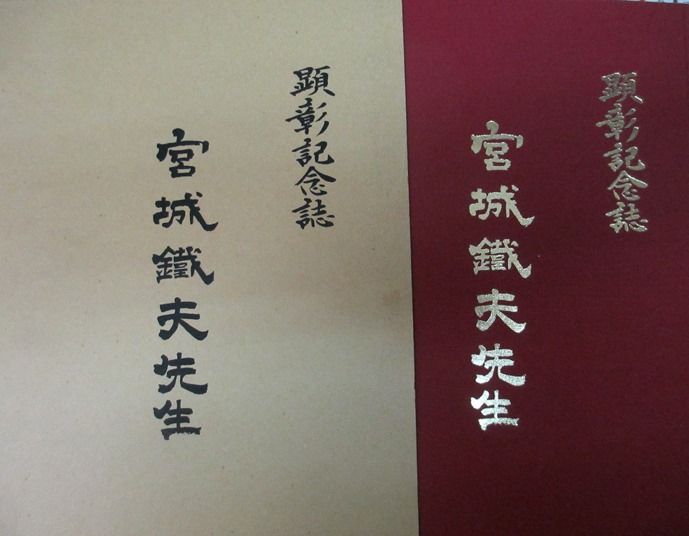
平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)
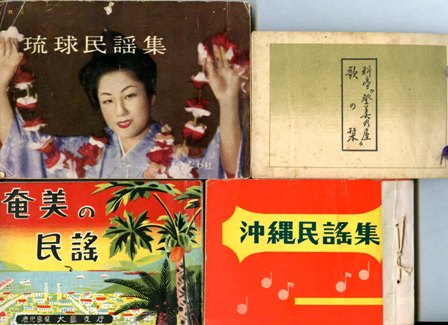
1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)
1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅
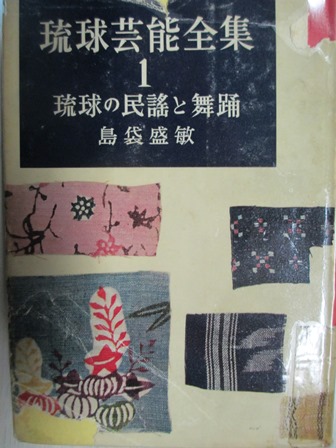
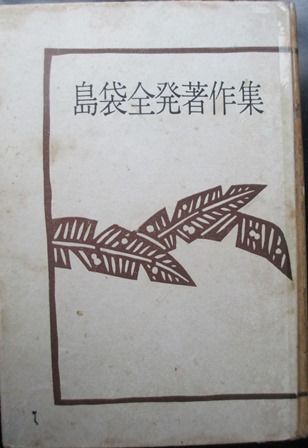
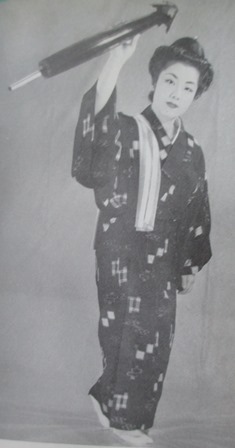
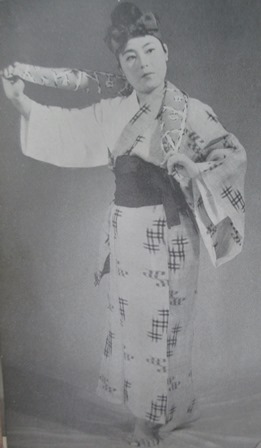
1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社
1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社
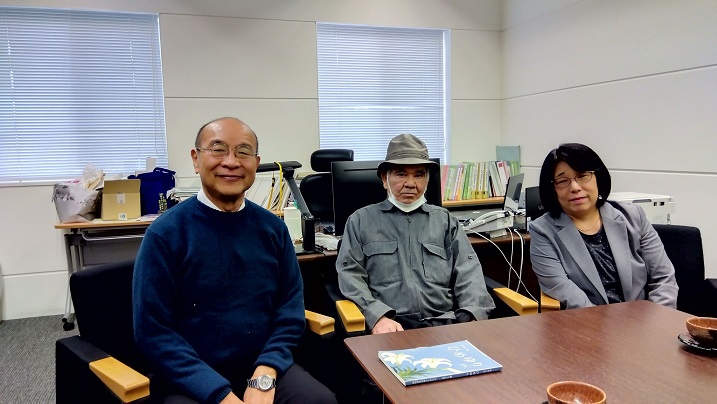
2025-2-5 沖縄県立博物館・美術館館長室:里井洋一館長、新城栄徳、大里知子法政大学沖縄文化研究所 准教授・専任所員
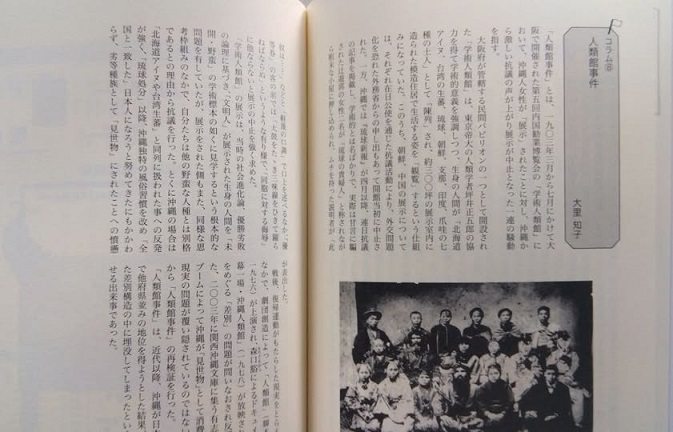
2021-11 『沖縄近現代史』ボーダーインク 大里知子「人類館事件」
1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社
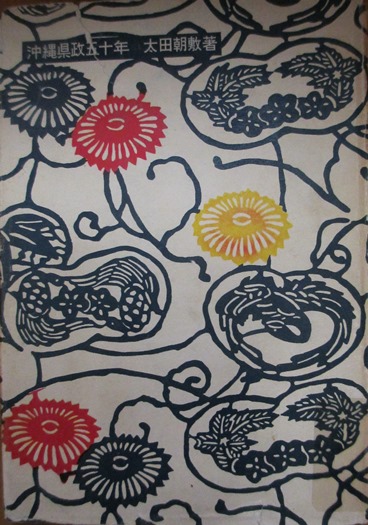
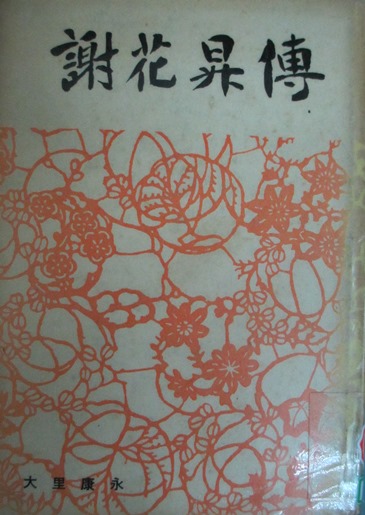
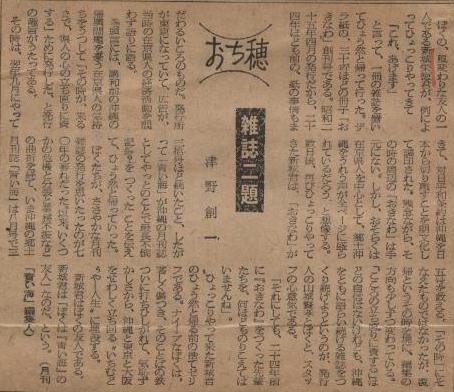
1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」
○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。
巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。
数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。
「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。
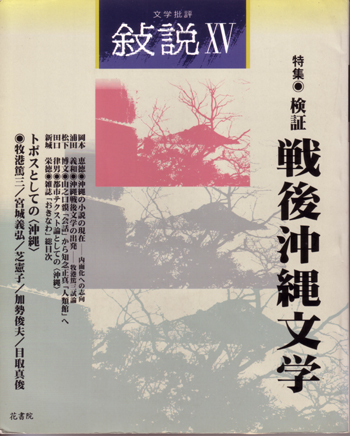

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」
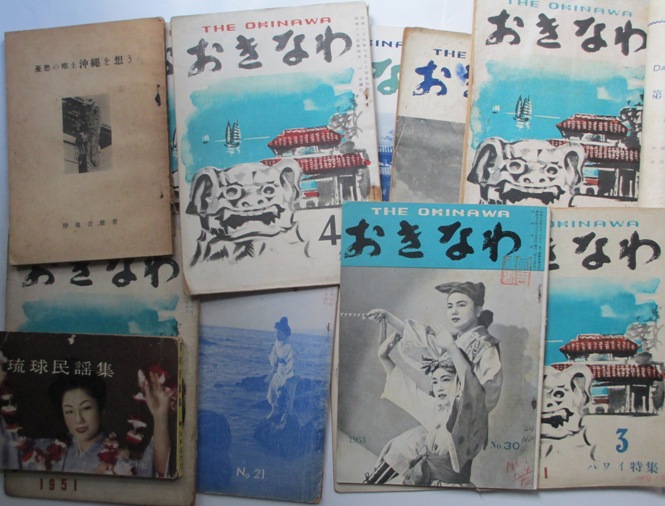
雑誌『おきなわ』
09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」
伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。
1891年
4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)
1900年
9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。
1903年
9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。
1904年
7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。
1905年
8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。
1906年
7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。
1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立
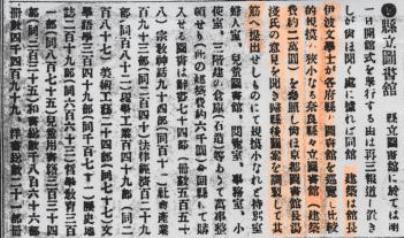
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
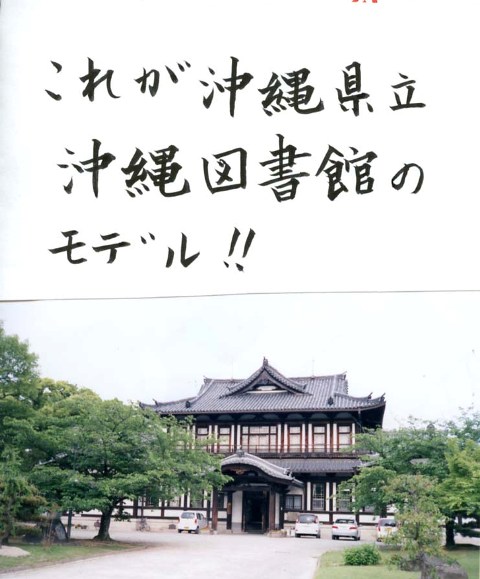
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1911年
4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。
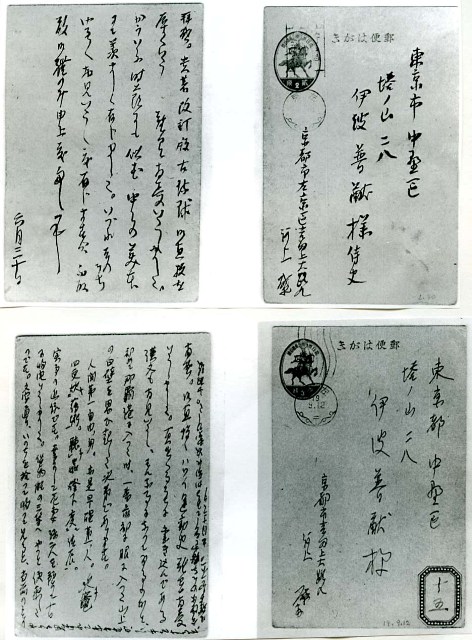
■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)
8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」
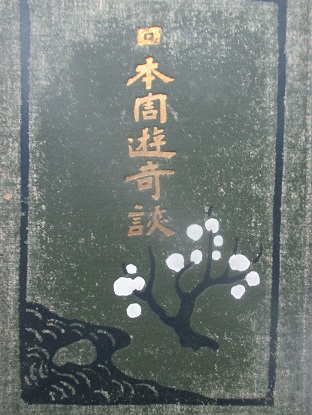
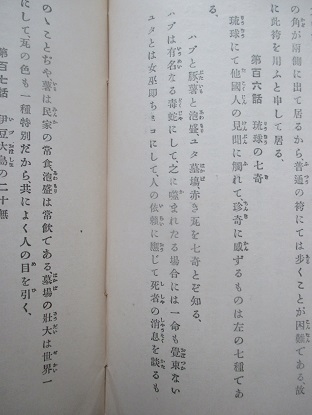
1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館
1912年
4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町
1913年
3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代
1913年
3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。
5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷
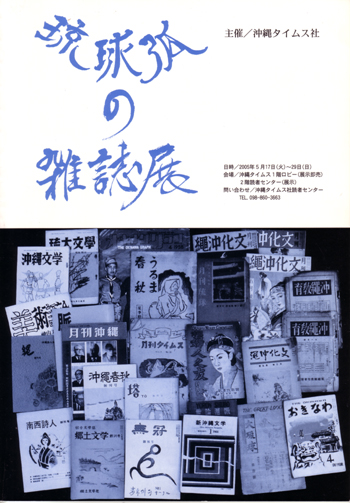
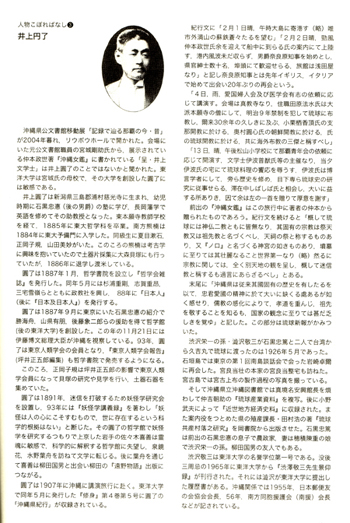
井上円了
『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。
大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。
□井上円了
生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)
没年: 大正8.6.5 (1919)
明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻
(恩田彰) →コトバンク
8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。
9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」
1916年
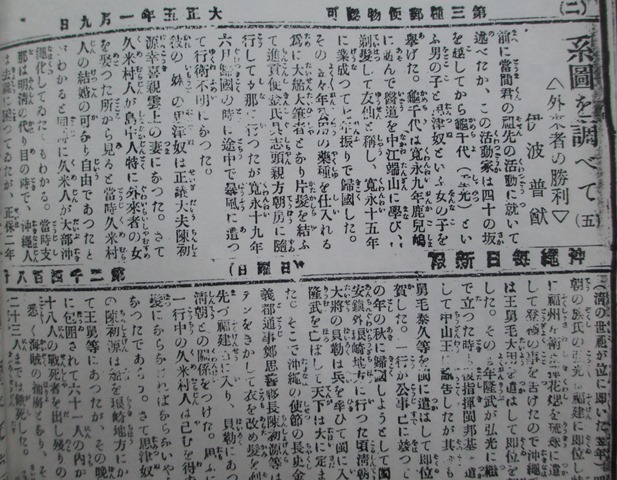
1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)
3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら
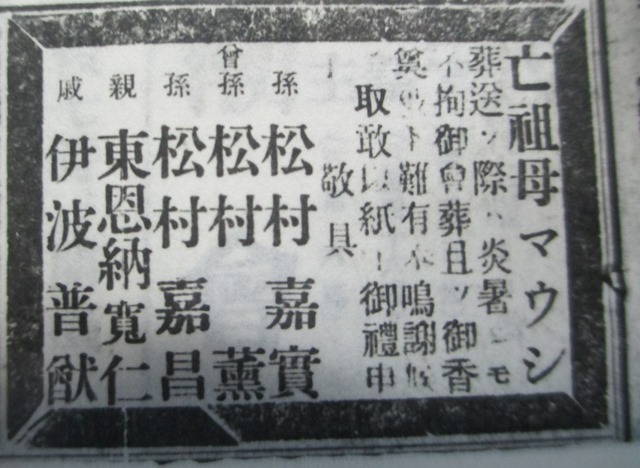
1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」
1918年
3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真
1919年
7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」
1920年
岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」
1921年
5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。
1924年
3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」
3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」
5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」
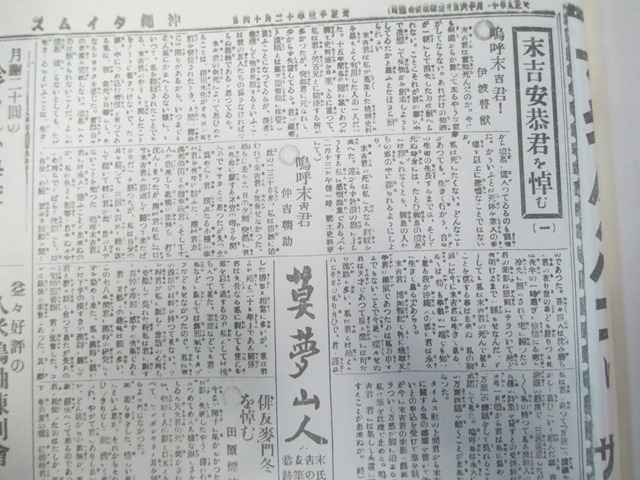
12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」
1925年
2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。
7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」
1926年
1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~
1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)
8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~
9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。
1927年
4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」
1928年
10月ー春洋丸でハワイ着
1929年
2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻
小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候
1931年
6月ー伊波の母(知念)マツル死去
12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居
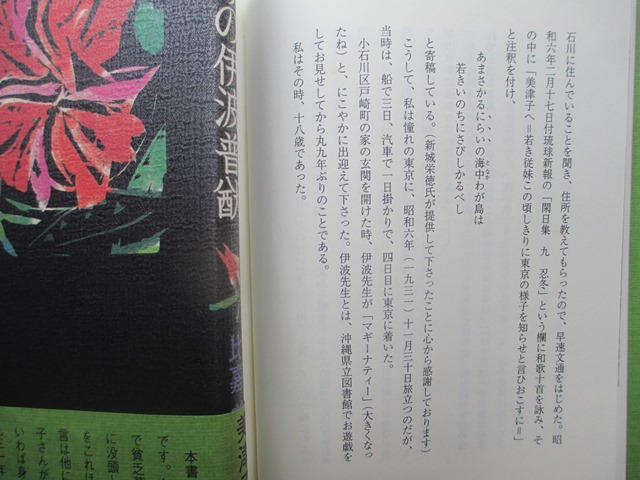
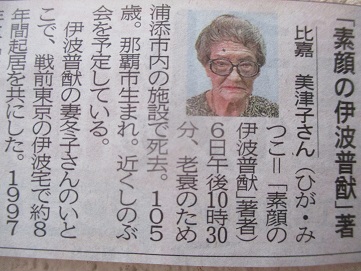
比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん
1932年
1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~
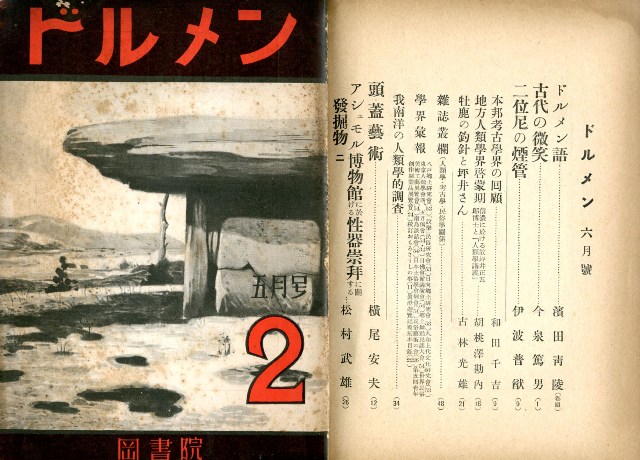
1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」
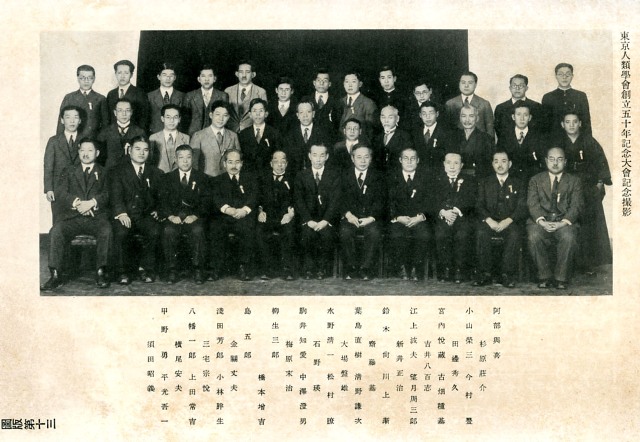
1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会
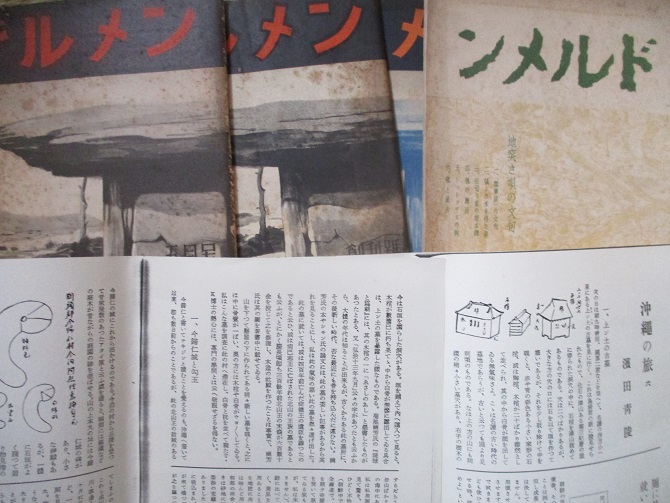
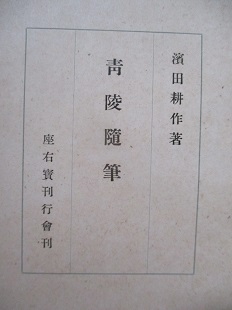
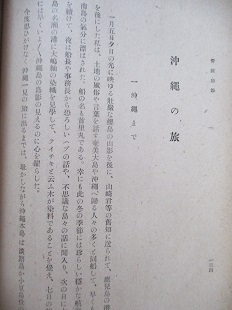
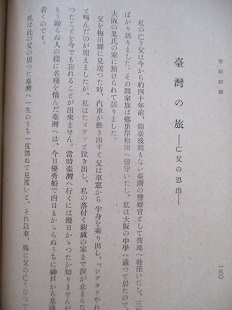
1933年
1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
1934年
7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」
1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号
1937年
1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)
1939年
12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」
1941年
3月ー伊波普猷妻マウシ死去
2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。
1891年
4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)
1900年
9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。
1903年
9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。
1904年
7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。
1905年
8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。
1906年
7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。
1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立
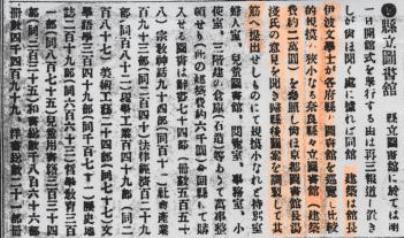
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
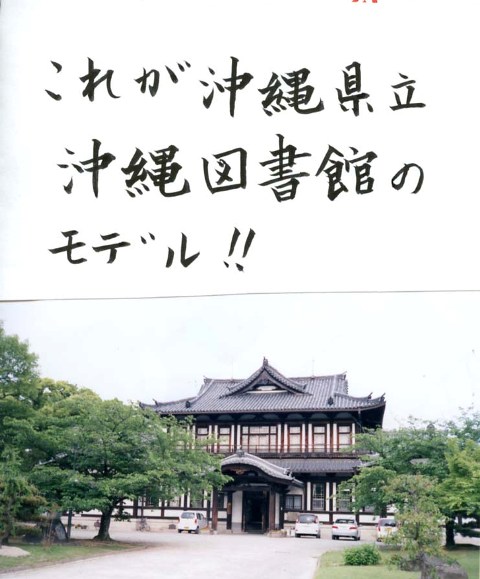
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1911年
4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。
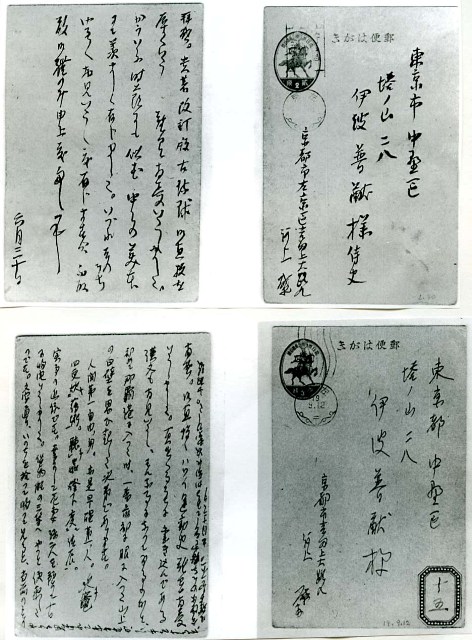
■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)
8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」
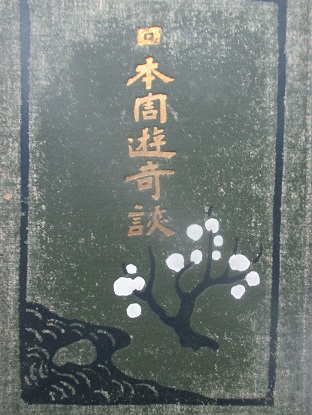
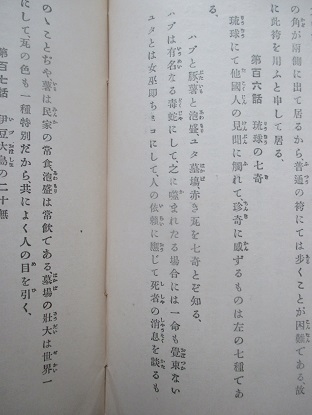
1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館
1912年
4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町
1913年
3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代
1913年
3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。
5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷
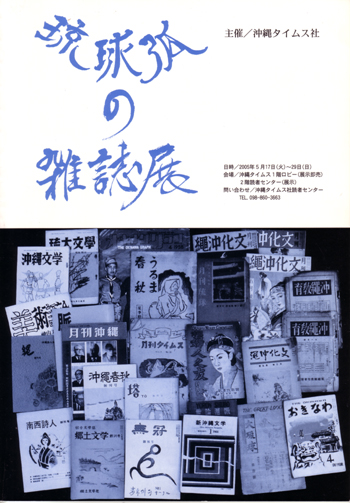
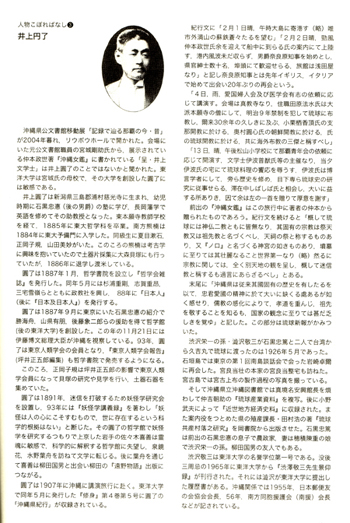
井上円了
『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。
大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。
□井上円了
生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)
没年: 大正8.6.5 (1919)
明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻
(恩田彰) →コトバンク
8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。
9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」
1916年
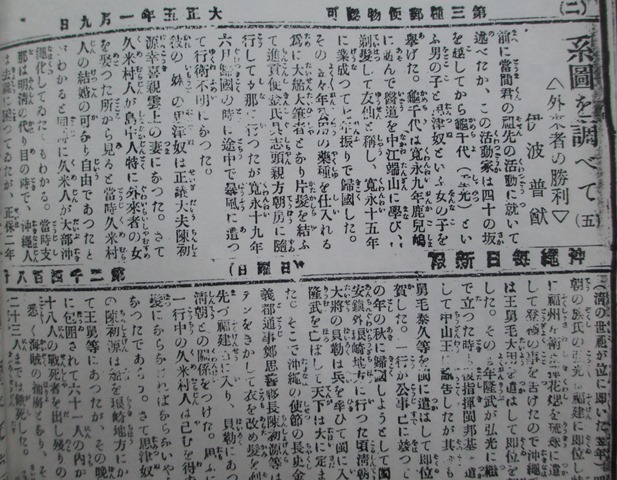
1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)
3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら
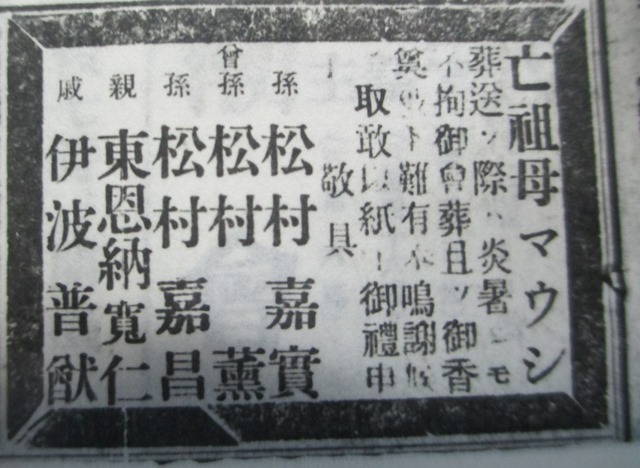
1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」
1918年
3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真
1919年
7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」
1920年
岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」
1921年
5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。
1924年
3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」
3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」
5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」
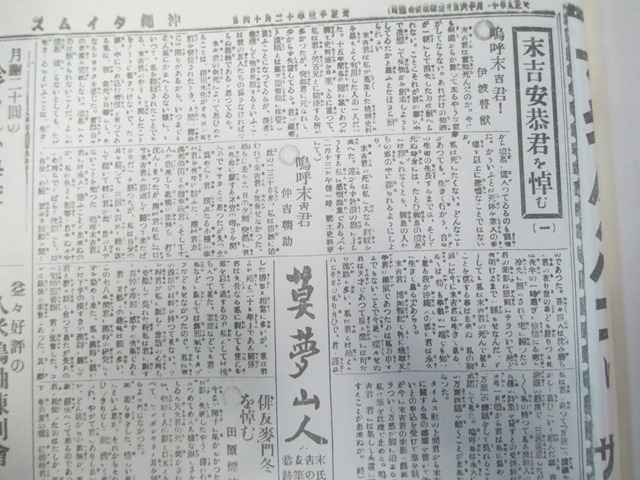
12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」
1925年
2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。
7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」
1926年
1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~
1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)
8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~
9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。
1927年
4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」
1928年
10月ー春洋丸でハワイ着
1929年
2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻
小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候
1931年
6月ー伊波の母(知念)マツル死去
12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居
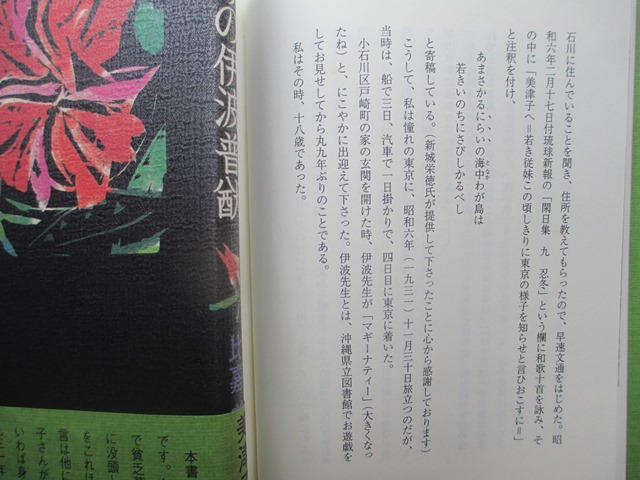
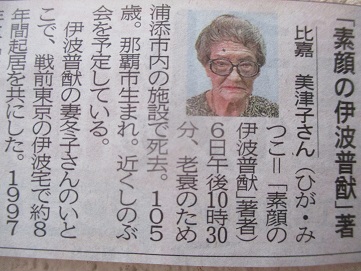
比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん
1932年
1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~
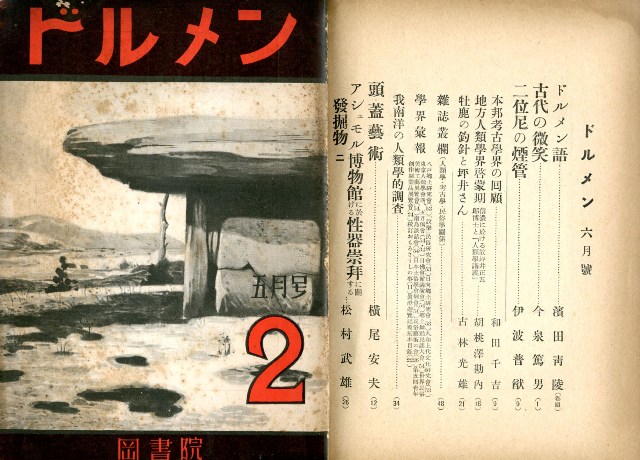
1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」
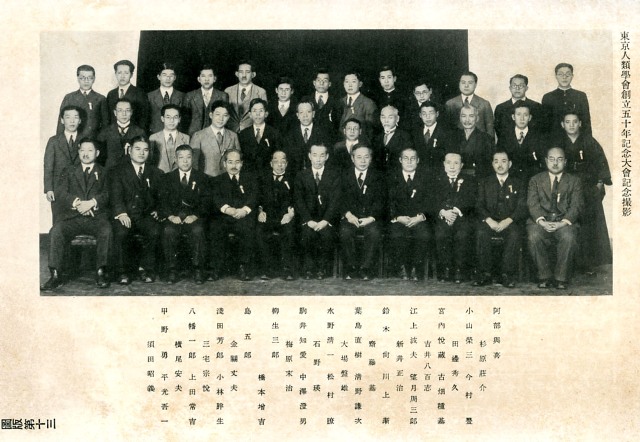
1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会
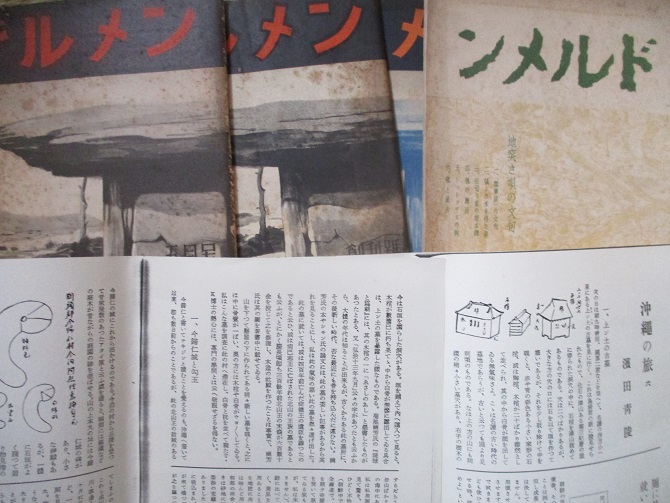
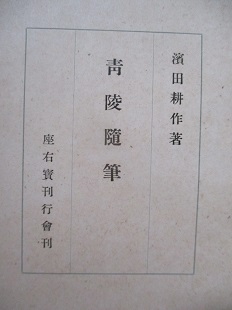
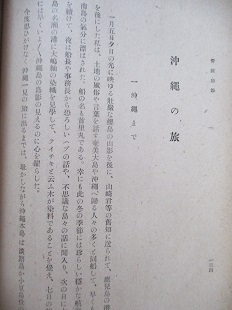
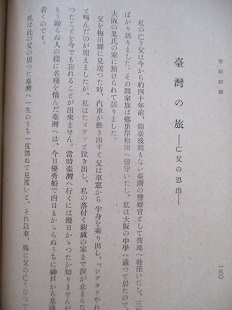
1933年
1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
1934年
7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」
1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号
1937年
1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)
1939年
12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」
1941年
3月ー伊波普猷妻マウシ死去
2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。
02/26: 雑誌『おきなわ』/島袋源七
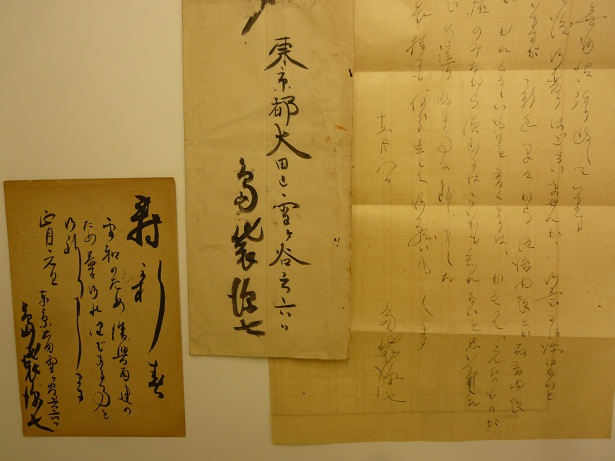
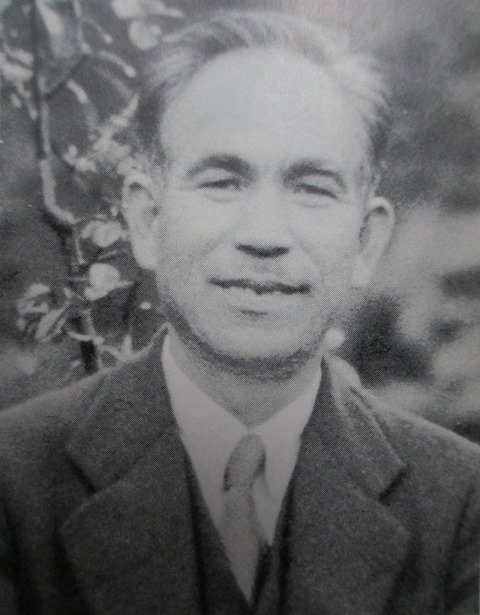
島袋源七
島袋源七 略年譜
1897年(明治30年)
6月11日、沖縄県国頭郡今帰仁間切(村)勢理客に生まれる。
1917年(大正6年)20才
3月、沖縄県立師範学校卒業
4月、北玉尋常小学校を皮切りに、辺野喜、喜如嘉、稲嶺各校を歴任する。
1921年(大正10年)24才
折口信夫が来県したさいに国頭地方を案内。このとき折口に啓発され、以後、精力的に山原(国頭地方)の民俗調査を行う。ウンジャミ・シヌグなどの祭祀習俗を詳細に記録。
1922年(大正11年)25才
柳田国男が組織し多くの民俗・民族・言語学者が参加した南島談話会が創立。創立当初からの会員となる。他に折口信夫、伊波普猷、比嘉春潮、仲原善忠、金城朝永、宮良当壮、仲宗根政善らが会員として名をつらねており、多くの会員との親交・知遇を受ける。
1925年(大正14年)28才
『山原の土俗』と題して民俗誌をまとめる。
1927年(昭和2年)30才
上京、杜松小学校に勤務するかたわら立正大学高等師範部地歴科に学ぶ。
1929年(昭和4年)32才
『山原の土俗』が炉辺叢書の1冊として郷土研究社から出版される。
1931年(昭和6年)34才
3月、立正大学高等師範部地歴科卒業
1934年(昭和9年)37才
立正中学校(旧制)に勤務。
1937年(昭和12年)40才
『今帰仁を中心とした地名の1考察』(「南島論叢)」
1947年(昭和22年)50才
立正高等学校(新制)兼任。その後、教頭として勤務する。
8月、沖縄人連盟内に沖縄文化協会成立。仲原善忠、宮良当壮、比嘉春潮、金城朝永、島袋盛敏、崎濱秀明氏らとおもろ研究会を持つ(戦前からの研究会の復活)。
12月、「阿児奈波の人々」(「沖縄文化叢説」)
1948年(昭和23年)51才
9月、沖縄文化協会が組織再編成し、新たに発足。 11月、会報「沖縄文化」創刊。
1950年(昭和25年)53才
『沖縄の民俗と信仰』(「民族学研究」15巻2号)
1952年(昭和27)55才
ウイーンの世界民俗研究学会より発表の招待を受く。
8月、『沖縄の古神道』を集大成するため、50日余沖縄本島を始め離島各地を踏査する。その折りの疲労が重なり病床に伏す。
1953年(昭和28年)55才
1月15日、昭和医大病院にて気管支喘息心臓麻痺のため逝去。
1月28日、立正大学にて学校葬 (→琉大図書館)



1974年1月 雑誌『青い海』29号 比嘉春潮「この頃のことなど」

2006年9月『比嘉春潮顕彰』/2006年2月『篤学の沖縄研究者 比嘉春潮』
1945年8月、国吉真哲・宮里栄輝・源武雄が早く帰還できるよう「県人会」結成を相談。宮里栄輝、熊本沖縄県人会長になる。/女子挺身隊救済で尼崎沖縄県人会結成。
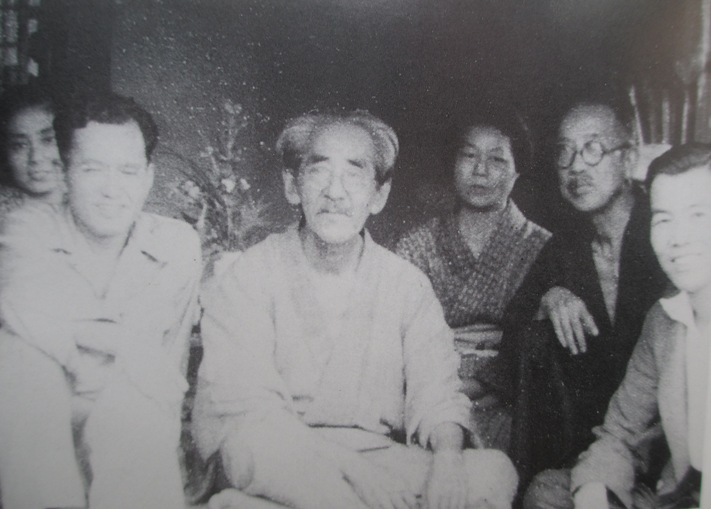
1945年 9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。比嘉春潮宅で、左端松本ツル、中央・伊波普猷、右隣りへ冬子夫人、比嘉春潮、松本三益
11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎
11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山 の県人会


1945年12月6日『自由沖縄』第1号(編集・比嘉春潮)/1947年2月20日『自由沖縄』(城間得栄・編)、1947年12月25日『自由沖縄』(上原永盛・編)
1945年12月9日ー東京神田教育会館で「引揚民救済沖縄県人大会」、伊波普猷が沖縄人聯盟代表として「無謀な戦争の為に国民はあるいはたおれ、あるいは傷つきー」と演説した。


1946年8月5日沖縄人聯盟九州本部『自由沖縄 九州版』(大嶺政和・編)、1948年2月15日『自由沖縄 大阪版』(城間盛雄・編)

1947年
8月19日ー『朝日新聞』「伊波普猷氏(沖縄人連盟会長)13日午後2時杉並区西田町1ノ566比嘉氏方でノウイッ血で死去、73歳、沖縄出身者の言語、民俗学者、おもろ研究の権威であった」、8月22日『自由沖縄』「先覚!今は亡し」(伊波普猷追悼特集)、9月26日『うるま新報』「われ等の先覚伊波氏逝く」
比嘉春潮と沖縄文化協会
1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。
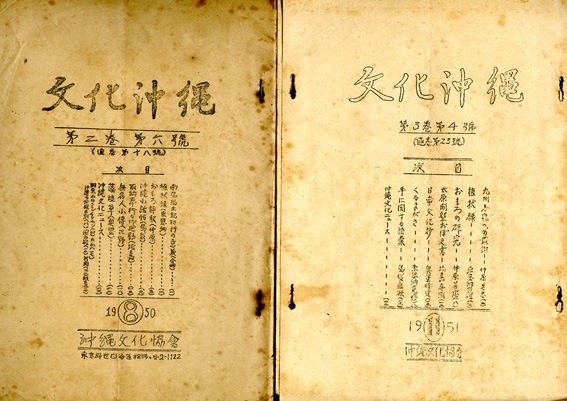
この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)
沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝

我部政男教授から頂いた『沖縄文化』資料

2007年3月 沖縄県『史料編集室紀要』納富香織「比嘉春潮論への覚書」/我部政男「比嘉春潮先生著作ノート」

06/26: 神奈川大学(後田多 敦)



2022年3月 『非文字資料研究センター News Letter』№47 後田多 敦「新作組踊『塩売』ー『新作』から『組踊』を考える」
2022年3月 『神奈川大学史紀要』第7号 後田多 敦「コロナ禍2020年度の神奈川大学の教員と学生ー教員の対応と『日本文化史B』のレポートから」
2022年4月 『神奈川大学評論』後田多 敦「『神奈川大学評論』創刊100号に寄せて」




2021-9 『非文字資料研究センター News Letter』№46 神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター ◇後多田 敦(神奈川大学国際日本学部歴史民俗学科教授)「ギルマール写真と伊藤勝一収集首里城正殿写真」



2021年9月 神奈川大学人文学会『人文研究』第203号 後田多 敦「資料紹介・土屋寛信『琉球紀行 全』ー沖縄県設置直後のコレラ感染と政治の記録」□新設沖縄県の初代トップは木梨精一郎(1879年3月11日、内務省出張所長に沖縄県令心得の辞令)である。1879年8月29日、土屋寛信・遠藤達那覇着。鍋島沖縄県令が7月下旬にコレラ感染、尚泰夫人(平良按司)は8月26日コレラで死去。/1879年の置県後、人口およそ33万人余の沖縄で、この年のコレラで6千人を超える人々が亡くなった。〇1910年5月6日『沖縄毎日新聞』「木梨精一郎男薨去」

2014年10月26日 沖縄県立博物館・美術館「神奈川大学常民文化研究所非文字資料研究センター『日本近世生活絵引』奄美・沖縄編」
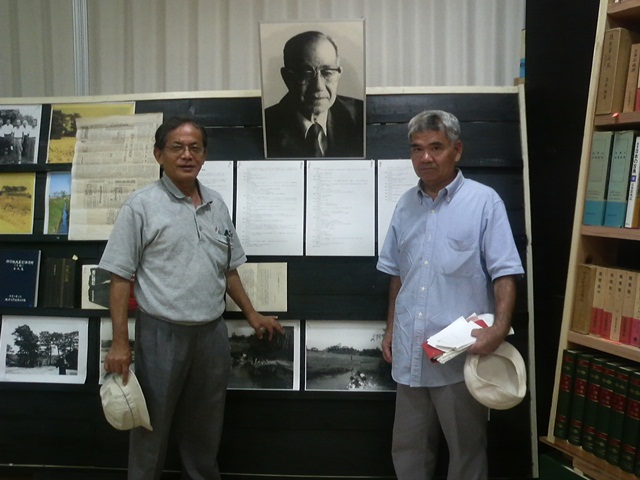
今帰仁村歴史文化センターでー左が館長・仲原弘哲氏と新城栄徳(渚さん撮影)
本日、文化の杜の渚さん運転のクルマで今帰仁と本部を廻った。渚さんは本部生まれで北山高校出身。今帰仁村教育委員会で、今帰仁城発掘や『百按司墓木棺修理報告書』編集にも関わっていて今帰仁に詳しい。今帰仁村歴史文化センターで館長の仲原弘哲氏が出迎えた。仲原氏は渚さんとも旧知の間柄。2012年8月22日寄贈された仲宗根政善の資料・本(100箱余.り)が地下書架に並んでいた。ガラスケースにある『琉球国由来記』(「1946年、山城善光氏帰沖,伊波先生からの手紙と『琉球国由来記』の写本,服部四郎氏から米語辞典が届けられる」と略年譜にある)には仲宗根宛の伊波普猷の署名がある。東江長太郎『通俗琉球北山由来記』(1935年11月)もある。□→1989年3月、東江哲雄、金城善編により那覇出版社から『古琉球 三山由来記集』が刊行された。
全集類は『比嘉春潮全集』(新聞スクラップが貼りこまれている。)『宮良當壮全集』『仲原善忠全集』『琉球史料叢書』などが目についたが、とくに日本図書センターの『GHQ日本占領史』はかなりの巻数である。安良城盛昭『天皇制と地主制』上下もある。
今帰仁関係を始めとして国文学雑誌や、琉球大学関係資料、同僚であった大田昌秀の著書も多数。また伊波普猷との関連で那覇女トリオの新垣美登子、金城芳子、千原繁子の署名入りの贈呈本もある。平山良明の論文原稿①、仲程昌徳『お前のためのバラード』、我部政男、渡邊欣雄、池宮正治、比屋根照夫、野口武徳、川満信一などの本も署名入りが並んでいた。娘婿が編集した『島田寛平画文集 1898-1967」 寛平先生を語る会1994年11月も目についた。
①
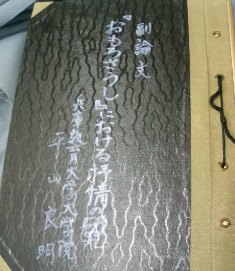 □
□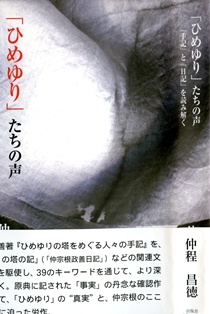 □2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)
□2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)天皇関係、大学紛争を特集した雑誌もある。マクルーハン②の本もあった。マクルーハンは、もともとは文学研究者として出発したが、その後メディア論を論じる(挑発的にして示唆に富んだ)社会科学者として名を成した。60年代後半~80年代前半にかけて爆発的な影響力を誇った。「内容ではなく、むしろそのメディア自身の形式にこそ、人びとに多くをつたえているのだ」と訴えることをつうじて、それまでの活字文化と、ラジオ文化、テレビ文化 相互のあいだにかれが差異線をひいたことは、いまだに重要である。 (ウィキペディア)
②
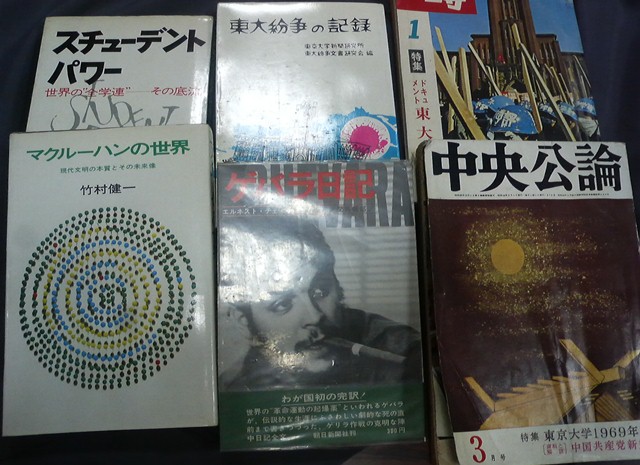
沖縄言語研究センターの「仲宗根政善 略年譜」を見ながら今帰仁村歴史文化センター書架に並んでいる本を思いつくまま記していくことにする。()内・写真・□は新城追加。
1907年(明治40年4月26日)
沖縄県国頭郡今帰仁村字与那嶺にて,父仲宗根蒲二,母カナの長男として生まれる 。生家は農業を営む。母カナは,名護の町を一度見たいというのが夢であったが,終生ついにかなえられなかった。祖父政太郎は,謝花昇(1908年死亡)に私淑していた。謝花は近在まで出張してくる都度,仲宗根家に宿をとった。
□1913年
9月5日 今帰仁村字与那嶺715番地に、父島袋松次郎(教師)、母静子(教師)の長男として霜多正次生まれる。→書架には霜多作品もある。
1914年~1919年(大正3年~8年)
兼次尋常小学校(大正8年4月1日,高等科併置,校名を兼次尋常高等小学校と改名する)に入学。桃原良明校長(4代),安里萬蔵校長(5代),安冨祖松蔵校長(6代),上里堅蒲校長(7代),当山美津(正堅夫人)等から直接教えを受ける。32歳の若さで赴任してきた上里校長に出会ったことによって,生涯を決定される。伊波普猷「血液及び文化の負債」の民族衛生講演で兼次小を訪れる。
1920年(大正9年)
沖縄県立第一中学校に入学。大宜見朝計(書架に1979年発行『大宜見朝計氏を偲ぶ』これに政善は「二人でたどった道」を書いている。川平朝申の文章もある。),島袋喜厚,上地清嗣等, 国頭郡から7名。中城御殿(現博物館)裏にあった駕籠屋新垣小に最初下宿。
母カナ死亡(享年40歳)。14歳になるまで,一晩中目がさえて一睡もできなかったということは一度もなかったが,虫のしらせか母の亡くなった夜だけは,蚊帳の上をぐるぐる飛んでいるホタルが妙に気になって,とうとう一睡もできなかったという経験をする。
泉崎橋の近くで,初めて伊波普猷の姿に接する。4年から5年にかけて,英語を担当していた胡屋朝賞先生の感化を受ける。
1926年(大正15,昭和元年)
福岡高等学校文科乙類に入学。沖縄から最初の入学者であった。級友から珍しがられ,親切にされる。翌27年には,大宜見朝計が入学。
伊波普猷著『孤島苦の琉球史』と『琉球古今記』を買い求め貧り読む。
安田喜代門教授から『万葉集』の講義を聞き,万葉の中に,日常用いている琉球方言がたくさん出て来るのに興味を覚える。また,考古学の玉泉大梁教授から,日本史の中ではじめて琉球史の概要を聞く。ドイツ語担当白川精一教授の感化を受け,ドイツ語に興味を持つ。
1929年(昭和4年)
東京帝国大学文学部国文学科入学。同年入学者に林和比古,永積安明, 吉田精一,犬養孝,岩佐正,西尾光雄等がいた。
本郷妻恋町に最初下宿。2年の時から国語学演習で,橋本進吉教授に厳しく鍛えられる。同ゼミに先輩の服部四郎,有坂秀世氏等がいた。服部氏が,今帰仁村字与那嶺方言のアクセントを調査し整理して,法則を示してくれたことによって, 郷里の方言に一層興味を持つようになる。金田一京助助教授のアイヌ語の講義,佐々木信綱講師の万葉集の講義を受ける。
伊波普猷先生宅に出入りするようになる。
1931(昭和6年)
第二回南島談話会で,はじめて柳田国男,比嘉春潮,仲原善忠, 金城朝永,宮良当壮に会う。
1932(昭和7年)
東京帝国大学文学部国文学科卒業。世は不況のどん底にあって,町にはルンペンがあふれていた。就職口もなく,朝日新聞に広告を出しても家庭教師の口すら年の暮れまで見つけることができないというような状況であった。
たまたま,県視学の幸地新蔵氏から,郷里の第三中学校に来ないかとの手紙があって,伊波普猷先生に相談。「東京でいくら待っても職はないし,2,3年資料でも集めて来てはどうか」と言われ,帰郷する気になる。
★「語頭母音の無声化」(『南島談話』第5号)。
★「今帰仁方言における語頭母音の無声化」(『旅と伝説』)。
1933年(昭和8年)
名護の沖縄県立第三中学校に教授嘱託として赴任。伊波普猷先生から,蚕蛹の方言を調査してほしい旨の手紙を受け,さっそく生徒126名を対象に,国頭郡の各部落の方言を調査し報告する。方言使用禁止の風潮の中で,方言を調べ研究するのを,生徒たちから不思議に思われる。伊礼正次,サイ夫妻の長女敏代と結婚。
1934年(昭和9年)
★「国頭方言の音韻」(『方言』第4巻第10号)。
1936年(昭和11年)
折口信夫先生を嶋袋全幸氏と共に案内。正月を名護で迎える。北山城趾見学の帰り,与那嶺の実家に立ち寄る。
三中から沖縄女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校に転勤を命ぜられる。『姫百合のかおり』(沖縄県女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校,30周年記念号)の編集委員を勤める。
★「加行変格『来る』の国頭方言の活用に就いて」(『南島論叢』)。
1937年(昭和12年)
川平朝令校長から「国民精神文化研究所」に研修に行くことをすすめられ,あまり気のりがしなかったが, 東京へ転ずるきっかけをつかむことができるかも知れないとの希望があって,目黒長者丸にあった同研究所へ入所する。
伊波先生を塔の山の御宅に訪ね,入所報告をすると「紀平正美などが,『神ながらの』道を講じているようだが,あんなのを学問だと思っては大間違いだ。研究所に通うより,うちに来て勉強するがよい」と注意を受けて近くに宿を貸りる。先生に励まされ,研究意欲に燃えて,夏の終わりに帰省。
12/02: 莫夢忌/島袋全発
1920年代、琉球史随筆で大衆を喜ばせた新聞人、末吉麦門冬が24年11月に水死した。その追悼文で島袋全発は「友人麦門冬」と題し「私共の中学時代 客気に駆られ一種の啓蒙運動をなしつつあった頃 麦門冬は蛍の門を出でず静かに読書に耽って居た。あの頃の沖縄は随分新旧思想の衝突が激しかったが物外さんを初め私共の応援家も頗る多かった。氏も恐らく隠れたる同情者の1人であったに違いない。其後私が高等学校に入ってから氏と交わる様になったが一見旧知の如くやはり啓蒙運動家の群の1人たるを失わなかった。私共は苦闘して勝った。啓蒙運動とは何ぞと問われたら少し困る。文化運動と云ってもいい。それを近いうちに麦門冬氏が書くと云っていたそうだが遂に今や亡し。該博なる智識そのものよりも旺盛」なる智識欲が尊い。そして旺盛なる智識欲よりも二十年諭らざる氏の友情は更に尊い。私は稀にしか氏とは会わなかった。喧嘩もした。然し淡々たること水の如くして心底に流動する脉々たる友情はいつでも触知」されていたのである。去年の今頃は私の宅で忘年会をした。そして萬葉集今年の山上憶良の貧窮問答「鼻ひしひしに」や「しかとあらぬひげかきあげし」やに笑い した後 矢張り啓蒙運動の話に夢中になった。今年の春は大根の花咲くアカチラを逍遥し唐詩選の句などを口吟、波之上の茶亭に一夜の清遊を試み歓興湧くが如くであった。せめて晩年の往来をしたので良かったと思う。麦門冬氏の如き詩人は多い。氏の如き郷土史家は少ない。氏の如き友情に至っては今の世極めて稀。今や忽焉として亡し。噫」。
全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。
1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。
1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。
濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。
島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。
また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。
1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。
1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。
全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。
1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。
1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。
濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。
島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。
また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。
1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。
1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。
07/25: 1923年8月 『思想』「ケーベル先生追悼号」岩波書店
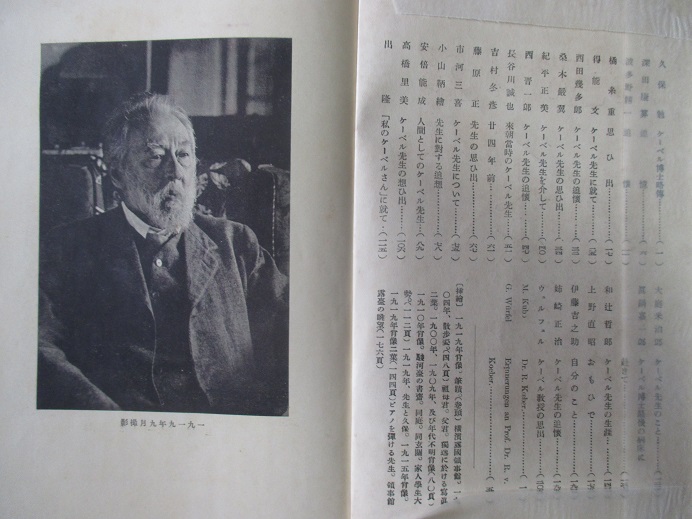
1923年8月 『思想』「ケーベル先生追悼号」岩波書店
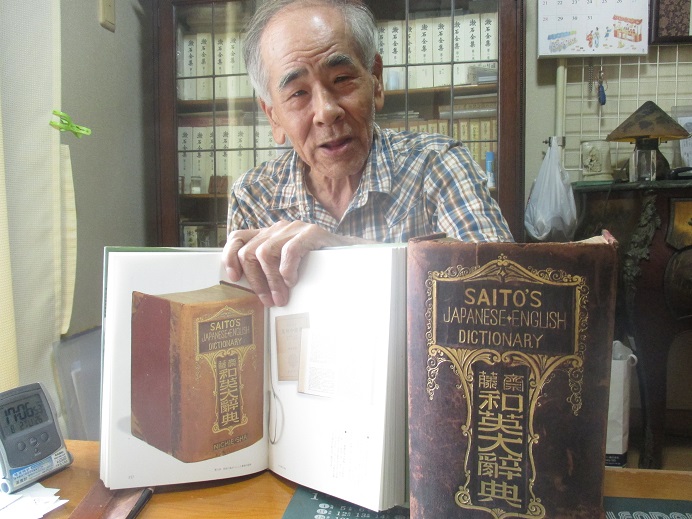
新城良一氏の手にしているのは紀田順一郎『日本博覧人物史』(左)に載っている1928年6月再版発行の齋藤秀三郎『齋藤和英大辞典』東勇治
斎藤秀三郎○1880年(14歳) 工部大学校(現在の東京大学工学部)入学。純粋化学、造船を専攻。後に夏目漱石の師となるスコットランド人教師ディクソン (James Main Dixon) に英語を学ぶ。後々までイディオムの研究を続けたのは彼の影響だったと後年述べている。また、図書館の英書は全て読み、大英百科事典は2度読んだ、という逸話が残っている。/1883年(17歳) 工部大学校退学。/1884年(18歳) 『スウヰントン式英語学新式直訳』(十字屋・日進堂)を翻訳出版。その後、仙台に戻り、英語塾を開設(一番弟子は、伝法久太郎である。また、学生の中に土井晩翠がいる)。1885年に来日したアメリカ人宣教師W・E・ホーイの通訳を務める。その後、1887年9月第二高等学校助教授(1888年9月教授)、1889年11月岐阜中学校(この時代、、濃尾地震に遭遇。この体験は、その後、地震嫌いとして斎藤の生活に影響を及ぼすことになる)、1892年4月長崎鎮西学院、9月名古屋第一中学校を経て、1893年7月第一高等学校教授。1888年5月とら子と結婚。/1896年10月神田錦町に正則英語学校(現在の正則学園高等学校)を創立して校長。以後、死亡するまで、(一時期、第一高等学校に出講したが)、ここを本拠として教育・研究に生涯を尽くした。→ウィキ
1916年 石川正通、一中退学、私立麻布中学校へ転校。3月29日、真玉橋朝起、武元朝朗、竹内弘道たちに見送られて沖縄丸で上京、甲板上で明大受験の城間恒昌、杉浦重剛校長の日本中学に転校する我部政達と3人で雑談に耽る。4月3日東京駅に着く。翌日、比屋根安定が大八車で荷物を一緒に運んでくれる。斎藤秀三郎校長の抜擢で正則英語学校講師となる。後に比嘉春潮(荻窪)、島袋盛敏(成城)、比屋根安定(青山学院構内)、仲吉良光(鶴見)、八幡一郎(東中野)、金城朝永(大塚)、石川正通(本郷)の7人で七星会結成する。

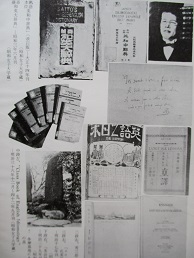

1970年3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書 31』「齋藤秀三郎」
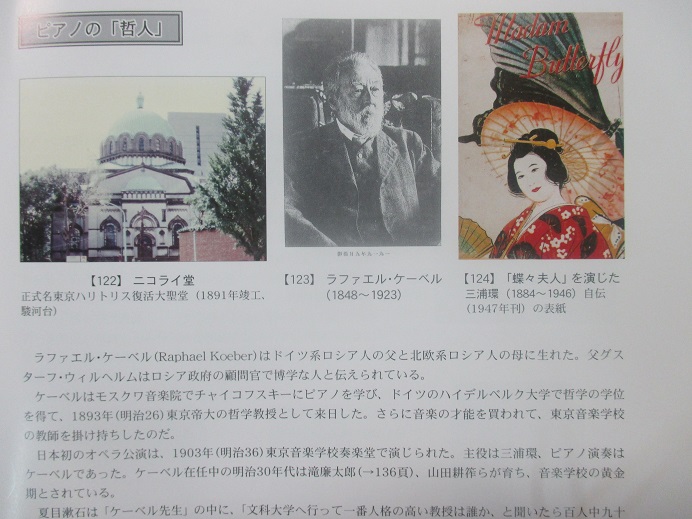
2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
2014年1月21日『琉球新報』ピアニスト長堂奈津子のリサイタル「ピアノ協奏曲とケーベル歌曲の夕べ」が17日、南城市文化センター・シュガーホールであった。明治期、日本のピアノ界に大きな影響を与えたロシア出身の哲学者ラファエル・フォン・ケーベルの歌曲「9つの歌」を沖縄初演したほか、バッハ、シューマンのピアノ協奏曲をカンマーゾリステン21(指揮・庭野隆之、コンサートマスター・屋比久潤子)と共に演奏した。長堂はケーベル研究に没頭し、2011年に他界した父・島尻政長(ケーベル会初代会長)への追悼の思いを、厳かな演奏に重ね描いた。
ラファエル・フォン・ケーベル(ドイツ語: Raphael von Koeber, 1848年1月15日 - 1923年6月14日)は、ロシア出身(ドイツ系ロシア人)の哲学者、音楽家。明治政府のお雇い外国人として東京帝国大学で哲学、西洋古典学を講じた。友人のエドゥアルト・フォン・ハルトマンの勧めに従って1893年(明治26年)6月に日本へ渡り、同年から1914年(大正3年)まで21年間東京帝国大学に在職し、イマヌエル・カントなどのドイツ哲学を中心に、哲学史、ギリシア哲学など西洋古典学も教えた。美学・美術史も、ケーベルが初めて講義を行った。学生たちからは「ケーベル先生」と呼ばれ敬愛された。夏目漱石も講義を受けており、後年に随筆『ケーベル先生』を著している。他の教え子には安倍能成、岩波茂雄、阿部次郎、小山鞆絵、九鬼周造、和辻哲郎、 深田康算、大西克礼、波多野精一、田中秀央など多数がいる。和辻の著書に回想記『ケーベル先生』がある。また漱石も寺田寅彦も、ケーベル邸に行くと深田がいたと記されている。→ウィキ
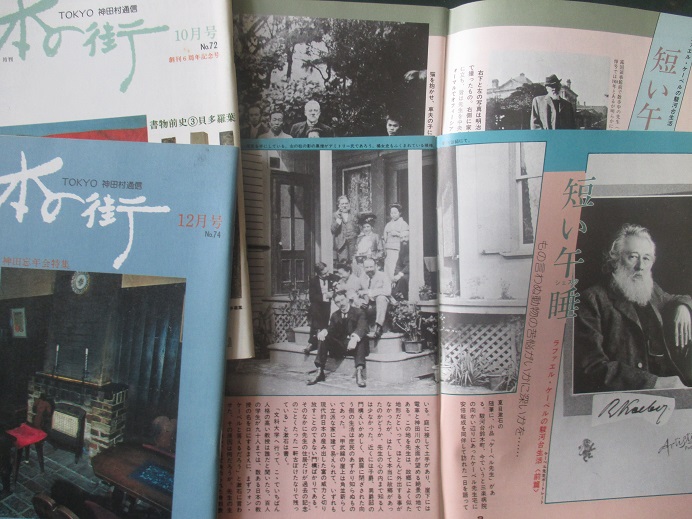
『本の街』1986年~87年の「ケーベル」を改めて見る。泊の島尻政長のケーベル会の「ケーベル会誌」はネットでも紹介されている。

本の街編集室『月刊文化情報誌 神田 御茶の水 九段 本の街』
2011年12月『本の街』第34巻1号〇村上泰賢(東善寺住職)「小栗上野介の日本改造」65/秋山岩夫「フォト・ージャーナリスト 林忠彦」⓺/山川正光「総和の旅人44 みどりの窓口/自動券売機」/世田谷文学館・世田谷美術館共同企画展「都市から郊外へ 1930年代の東京」/酒部一太郎「勝海舟追慕・首都圏散策17」/銭谷功「神田ディスカバリー 神田淡路っ子の小宇宙38 ボクは見た10秒間のマッカーサー/ボクら中学生は、世界の新知識を吸収しようと夢中になった。一番素晴らしかったにはリーダース・ダイジェスト日本版発行と、輸入映画の解禁だった。」/「古くて、一寸心に残るもの・・・・・176 辰年ですから龍の話です」/永井英夫「南米の旅 ペルー編・下」/井東冨二子「レコード屋のおかみさん65年」/朝山邦夫「♪神田の東工か♪東工の神田かー実学の達人 中尾哲二郎」/「アート情報」/戸田慎一「ジャズの周辺④ジャズ出版の全体像(前期)」
2012年1月『本の街』第34巻2号〇酒部一太郎「勝海舟追慕・首都圏散策18」/秋山岩夫「フォト・ージャーナリスト 林忠彦ー銀座・酒場『ルパン』を概説する」⑦/戸田慎一「ジャズの周辺⑤ジャズ出版の全体像(中期)」
2015年10月『本の街』第37巻11号〇酒部一太郎「樋口一葉②」
2016年1月『本の街』第38巻2号〇藤田瑞穂「ぼくの庭86 絵は究極のミニマリズム-人間の外付けハードディスクがすべてをまかなうといったところか。なにを今更という思いがする。古来日本には、最小限主義が伝統的にある。茶の湯、能や禅、短歌や俳句、方寸の庵での黙考、等等。」/酒部一太郎「樋口一葉④」
青空文庫ー夏目漱石「ケーベル先生」
木この葉はの間から高い窓が見えて、その窓の隅すみからケーベル先生の頭が見えた。傍わきから濃い藍色あいいろの煙が立った。先生は煙草たばこを呑のんでいるなと余は安倍あべ君に云った。
この前ここを通ったのはいつだか忘れてしまったが、今日見るとわずかの間まにもうだいぶ様子が違っている。甲武線の崖上がけうえは角並かどなみ新らしい立派な家に建て易かえられていずれも現代的日本の産み出した富の威力と切り放す事のできない門構もんがまえばかりである。その中に先生の住居すまいだけが過去の記念かたみのごとくたった一軒古ぼけたなりで残っている。先生はこの燻くすぶり返った家の書斎に這入はいったなり滅多めったに外へ出た事がない。その書斎はとりもなおさず先生の頭が見えた木の葉の間の高い所であった。
余と安倍君とは先生に導びかれて、敷物も何も足に触れない素裸すはだかのままの高い階子段はしごだんを薄暗がりにがたがた云わせながら上のぼって、階上の右手にある書斎に入った。そうして先生の今まで腰をおろして窓から頭だけを出していた一番光に近い椅子に余は坐すわった。そこで外面そとから射さす夕暮に近い明りを受けて始めて先生の顔を熟視した。先生の顔は昔とさまで違っていなかった。先生は自分で六十三だと云われた。余が先生の美学の講義を聴きに出たのは、余が大学院に這入った年で、たしか先生が日本へ来て始めての講義だと思っているが、先生はその時からすでにこう云う顔であった。先生に日本へ来てもう二十年になりますかと聞いたら、そうはならない、たしか十八年目だと答えられた。先生の髪も髯ひげも英語で云うとオーバーンとか形容すべき、ごく薄い麻あさのような色をしている上に、普通の西洋人の通り非常に細くって柔かいから、少しの白髪しらがが生えてもまるで目立たないのだろう。それにしても血色が元の通りである。十八年を日本で住み古した人とは思えない。(以下略)
01/04: 大阪・沖縄関係資料運動(3)
1965年5月 沖縄興信所(代表・大宜味朝徳)『琉球紳士録』「本土在住琉球紳士録」

写真左から外間盛安、仲嶺真助、安里貞雄/知念精吉、具志保男、天願保永/津嘉山朝吉、儀間真福、新里与旌
1965年12月 『守礼の光』「実現間近い家庭用原子力発電」
1966年5月ー『オキナワグラフ』「ハワイだよりー髙江洲敏子さん」
1966年10月 『守礼の光』坂本万七「写真・伊藤若冲」
1967年3月 『守礼の光』せそこ・ちずえ「琉球昔話 空を飛ぼうとした男(安里周当)」、比屋根忠彦「久高島のイザイホー」
1967年12月 『守礼の光』「5年後に110階建て 世界貿易センター出現」
1968年2月 『守礼の光』「現代にも呼びかけるエイブラハム・リンカーンのことば」「アジア地区米陸軍特殊活動隊 粟国・渡名喜両島で奉仕活動」「原子力科学者が語る未来の原子力『食品工場』」
1968年4月 『守礼の光』ジョン・A・バーンズ(ハワイ知事)「琉球の文化的姉妹島ハワイ」
1969年5月 『守礼の光』宮国信栄」「放射能はどこまで人体に安全か」

1969年10月3日『毎日新聞』「本土のなかの沖縄ー私設沖縄文庫」
1969年7月 『今日の琉球』亀川正東「アメリカ文学の話(107)死んだアプトン・シンクレアのこと」
1969年9月 チェンバレン著/高梨健吉訳『日本事物誌』(東洋文庫)平凡社
○日本語(Language)琉球列島で話されている姉妹語を除けば、日本語には同族語はない。/琉球(Luchu)土地の人はドゥーチューと発音し、日本人はリューキューと呼ぶ。琉球人は、民族と言語の点で日本人と密接に結びついている。しかし多くの世紀のあいだ両民族はお互いに交渉がなかったように思われる。
1972年2月号『青い海』10号 「若者が集う『沖縄関係資料室』の西平守晴氏宅」

□ここで資料の内容の一部を紹介しよう。開設当時200冊足らずだった書籍・雑誌は、現在約3200冊。新聞や週刊誌などのスクラップが300冊。沖縄に関する資料については、関西隋一と言われる。▽人物関係ー「謝花昇伝」「平良辰雄回顧録」「伊波普猷選集」などの伝記、回顧録、全集もの。▽市町村関係ー「北谷村誌」「南大東村誌」 比嘉景常「久米島紀行」など。▽歴史関係ー「沖縄県史」(直接主席から贈呈される。関西では天理図書館と資料室ぐらいだろうとの話) 「琉球建築」 田代安定「沖縄結縄考」 金城朝永「異態習俗考」や戦史・戦記もの。▽文芸関係ー「山之口貘詩集」「新沖縄文学」や大城立裕、石野径一郎、霜田正次、石川文一などの諸作品。▽芸能関係ー「組踊大観」「工工四」など。▽政府刊行物ー「立法院議事録」 白書類。▽ミニコミー「沖縄差別」「石の声」「沖縄月報」「寮友」「琉大文学」や本土各大学の県学生会の機関誌・パンフなど。▽地図ー「首里古地図」その他。これらの資料を整理したり、購入したり目録をつくるなど、一人でするにはたいへんな仕事である。西平守晴さんは保育園の仕事もあり忙しいので、現在もっぱら新城栄徳君(23)が動きまわっている。


1972年6月の『豊川忠進先生の長寿を祝う会』では、沖縄の又吉真三氏から文化財の碑文の拓本を借りて展示して参加者を感動させ、平良盛吉翁らを豊川氏の隣りに座らせて感激させた。」
平良盛吉□→1991年1月『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)平良盛吉「村の先生」/平良盛吉(1890年8月28日~1977年6月28日)1912年、沖縄ではじめての総合文化誌『新沖縄』を創刊。琉球音楽研究家。『関西沖縄開発史』の著がある。□→2009年5月『うるまネシア』第10号/新城栄徳「失われた時を求めてー近鉄奈良線永和駅近くに平良盛吉氏が住んでおられた。息子が1歳のとき遊びに行ったら誕生祝をいただいた。袋は今もある」
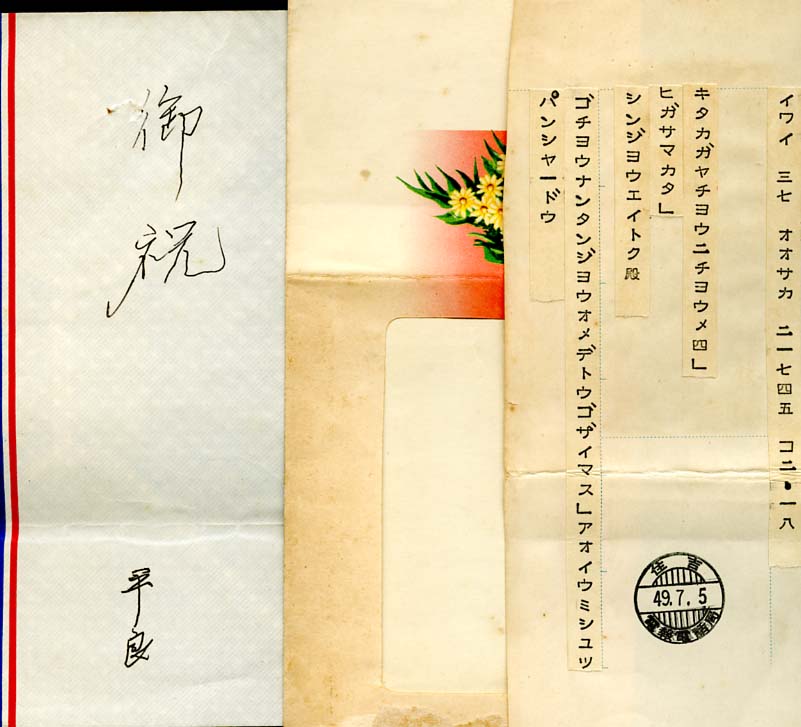

1975年2月16日『沖縄タイムス』石原英夫「話題の広場/西平守晴ー離島の子供たちに文化の灯を」/6月23日石原英夫「がじゅまるの会」

1976年1月10日『サンデー沖縄』「沖縄資料室を開放ー西平守晴」

写真ー左・息子と西平守晴さん
1978年4月 友寄英一郎『西洋史稿』琉球大学史学会○異国船琉球来航史ノート
1980年5月15日『朝日新聞』(大阪版)「西平守晴ー琉歌でつづる沖縄戦後史」

1982年6月、沖縄県人会兵庫県本部『ここに榕樹ありー沖縄県人会兵庫県本部35年史』(新城栄徳資料提供)
1980年11月『南島史学』第一六号
○室町幕府と琉球との関係の一考察・・・・・・・・・・・・・・・・田中健夫

1980年11月24日ー豊中市立婦人会館で開かれた南島史学会第9回研究大会。右手前2人目が安良城盛昭氏と牧野清氏、左端が喜舎場一隆氏同日、受付の永峰眞名さんに安良城盛昭氏を確認してもらう。大会終了後、安良城氏を都島の沖縄関係資料室まで案内。色々と歓談する。資料室で自著を見つけた安良城氏が本代を払いそれに署名献本した。このとき以来、理論嫌いな私でも沖縄出身の理論家については、これ傾聴に努めることにした。

1981年ー第17回 沖縄県印刷人大会で、左端が西平守晴の従兄弟、西平守栄会長。隣が後の仲井眞知事
1982年2月『南島史学』第一九号
○原琉球語をたどるー鍬・蜻蛉・蚊などー・・・・・・・・・・・・・・・・・・中本正智
○奄美の民族に関する既刊文献の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下欣一
1982年9月『南島史学』第20号
○江戸時代の「琉球」認識ー新井白石・白尾国柱・伴信友ー・・・・・横山學
○ハワイ沖縄県人の団結力・・・・・・・・・・・・・・・・・・崎原貢

1984年9月『南島史学』第24号
○琉球の稀書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸秋正

1986年7月 ベイジル・ホール著/春名徹 訳『朝鮮・琉球航海記』岩波文庫

沖縄都ホテルで新城栄徳と元沖縄都ホテル社長・桑原守也氏
1987年4月『南島史学』第29号
○続・琉球の稀書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸秋正

写真左から外間盛安、仲嶺真助、安里貞雄/知念精吉、具志保男、天願保永/津嘉山朝吉、儀間真福、新里与旌
1965年12月 『守礼の光』「実現間近い家庭用原子力発電」
1966年5月ー『オキナワグラフ』「ハワイだよりー髙江洲敏子さん」
1966年10月 『守礼の光』坂本万七「写真・伊藤若冲」
1967年3月 『守礼の光』せそこ・ちずえ「琉球昔話 空を飛ぼうとした男(安里周当)」、比屋根忠彦「久高島のイザイホー」
1967年12月 『守礼の光』「5年後に110階建て 世界貿易センター出現」
1968年2月 『守礼の光』「現代にも呼びかけるエイブラハム・リンカーンのことば」「アジア地区米陸軍特殊活動隊 粟国・渡名喜両島で奉仕活動」「原子力科学者が語る未来の原子力『食品工場』」
1968年4月 『守礼の光』ジョン・A・バーンズ(ハワイ知事)「琉球の文化的姉妹島ハワイ」
1969年5月 『守礼の光』宮国信栄」「放射能はどこまで人体に安全か」

1969年10月3日『毎日新聞』「本土のなかの沖縄ー私設沖縄文庫」
1969年7月 『今日の琉球』亀川正東「アメリカ文学の話(107)死んだアプトン・シンクレアのこと」
1969年9月 チェンバレン著/高梨健吉訳『日本事物誌』(東洋文庫)平凡社
○日本語(Language)琉球列島で話されている姉妹語を除けば、日本語には同族語はない。/琉球(Luchu)土地の人はドゥーチューと発音し、日本人はリューキューと呼ぶ。琉球人は、民族と言語の点で日本人と密接に結びついている。しかし多くの世紀のあいだ両民族はお互いに交渉がなかったように思われる。
1972年2月号『青い海』10号 「若者が集う『沖縄関係資料室』の西平守晴氏宅」


□ここで資料の内容の一部を紹介しよう。開設当時200冊足らずだった書籍・雑誌は、現在約3200冊。新聞や週刊誌などのスクラップが300冊。沖縄に関する資料については、関西隋一と言われる。▽人物関係ー「謝花昇伝」「平良辰雄回顧録」「伊波普猷選集」などの伝記、回顧録、全集もの。▽市町村関係ー「北谷村誌」「南大東村誌」 比嘉景常「久米島紀行」など。▽歴史関係ー「沖縄県史」(直接主席から贈呈される。関西では天理図書館と資料室ぐらいだろうとの話) 「琉球建築」 田代安定「沖縄結縄考」 金城朝永「異態習俗考」や戦史・戦記もの。▽文芸関係ー「山之口貘詩集」「新沖縄文学」や大城立裕、石野径一郎、霜田正次、石川文一などの諸作品。▽芸能関係ー「組踊大観」「工工四」など。▽政府刊行物ー「立法院議事録」 白書類。▽ミニコミー「沖縄差別」「石の声」「沖縄月報」「寮友」「琉大文学」や本土各大学の県学生会の機関誌・パンフなど。▽地図ー「首里古地図」その他。これらの資料を整理したり、購入したり目録をつくるなど、一人でするにはたいへんな仕事である。西平守晴さんは保育園の仕事もあり忙しいので、現在もっぱら新城栄徳君(23)が動きまわっている。


1972年6月の『豊川忠進先生の長寿を祝う会』では、沖縄の又吉真三氏から文化財の碑文の拓本を借りて展示して参加者を感動させ、平良盛吉翁らを豊川氏の隣りに座らせて感激させた。」
平良盛吉□→1991年1月『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)平良盛吉「村の先生」/平良盛吉(1890年8月28日~1977年6月28日)1912年、沖縄ではじめての総合文化誌『新沖縄』を創刊。琉球音楽研究家。『関西沖縄開発史』の著がある。□→2009年5月『うるまネシア』第10号/新城栄徳「失われた時を求めてー近鉄奈良線永和駅近くに平良盛吉氏が住んでおられた。息子が1歳のとき遊びに行ったら誕生祝をいただいた。袋は今もある」
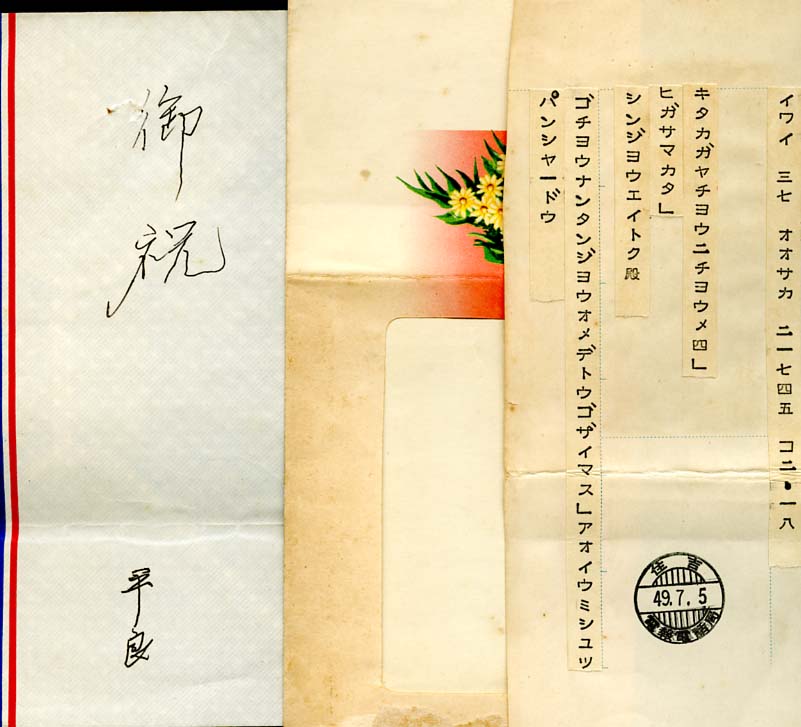

1975年2月16日『沖縄タイムス』石原英夫「話題の広場/西平守晴ー離島の子供たちに文化の灯を」/6月23日石原英夫「がじゅまるの会」

1976年1月10日『サンデー沖縄』「沖縄資料室を開放ー西平守晴」

写真ー左・息子と西平守晴さん
1978年4月 友寄英一郎『西洋史稿』琉球大学史学会○異国船琉球来航史ノート
1980年5月15日『朝日新聞』(大阪版)「西平守晴ー琉歌でつづる沖縄戦後史」

1982年6月、沖縄県人会兵庫県本部『ここに榕樹ありー沖縄県人会兵庫県本部35年史』(新城栄徳資料提供)
1980年11月『南島史学』第一六号
○室町幕府と琉球との関係の一考察・・・・・・・・・・・・・・・・田中健夫

1980年11月24日ー豊中市立婦人会館で開かれた南島史学会第9回研究大会。右手前2人目が安良城盛昭氏と牧野清氏、左端が喜舎場一隆氏同日、受付の永峰眞名さんに安良城盛昭氏を確認してもらう。大会終了後、安良城氏を都島の沖縄関係資料室まで案内。色々と歓談する。資料室で自著を見つけた安良城氏が本代を払いそれに署名献本した。このとき以来、理論嫌いな私でも沖縄出身の理論家については、これ傾聴に努めることにした。

1981年ー第17回 沖縄県印刷人大会で、左端が西平守晴の従兄弟、西平守栄会長。隣が後の仲井眞知事
1982年2月『南島史学』第一九号
○原琉球語をたどるー鍬・蜻蛉・蚊などー・・・・・・・・・・・・・・・・・・中本正智
○奄美の民族に関する既刊文献の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下欣一
1982年9月『南島史学』第20号
○江戸時代の「琉球」認識ー新井白石・白尾国柱・伴信友ー・・・・・横山學
○ハワイ沖縄県人の団結力・・・・・・・・・・・・・・・・・・崎原貢

1984年9月『南島史学』第24号
○琉球の稀書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸秋正

1986年7月 ベイジル・ホール著/春名徹 訳『朝鮮・琉球航海記』岩波文庫

沖縄都ホテルで新城栄徳と元沖縄都ホテル社長・桑原守也氏
1987年4月『南島史学』第29号
○続・琉球の稀書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸秋正
01/10: 沖縄人民党中央機関紙『人民』
1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社
ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ
写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。
悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫
○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。
郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長
善意の記録として・・・・沖縄県学生会
○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。
第一部
拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人
第二部
土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道
島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光
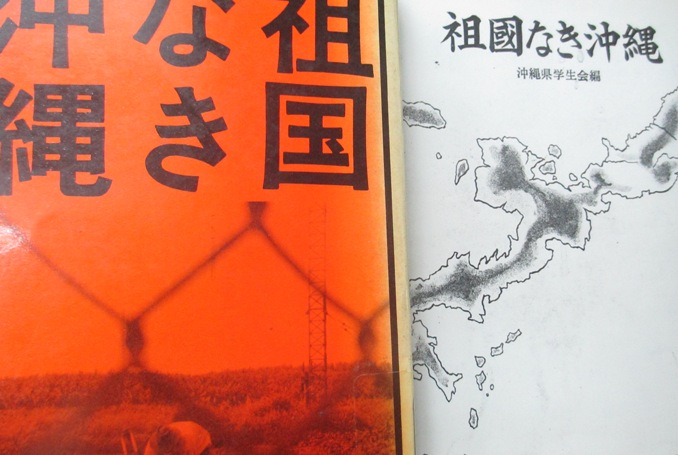
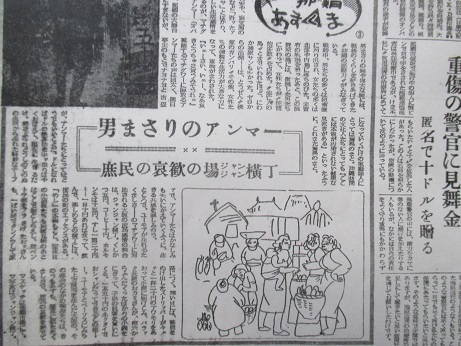
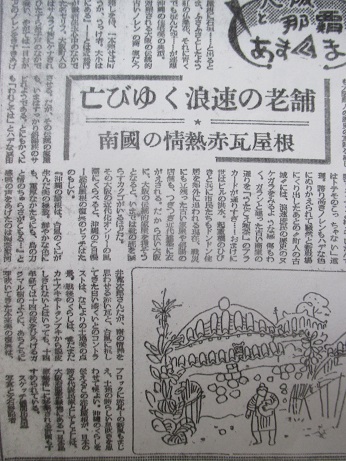
1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」
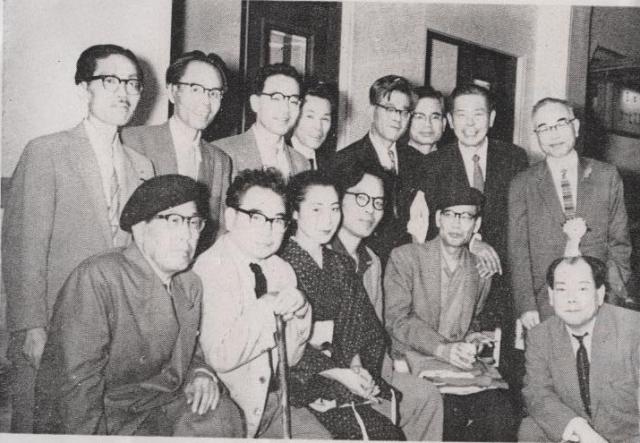
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子
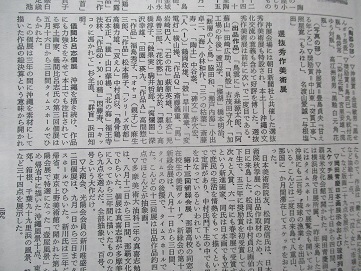

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』
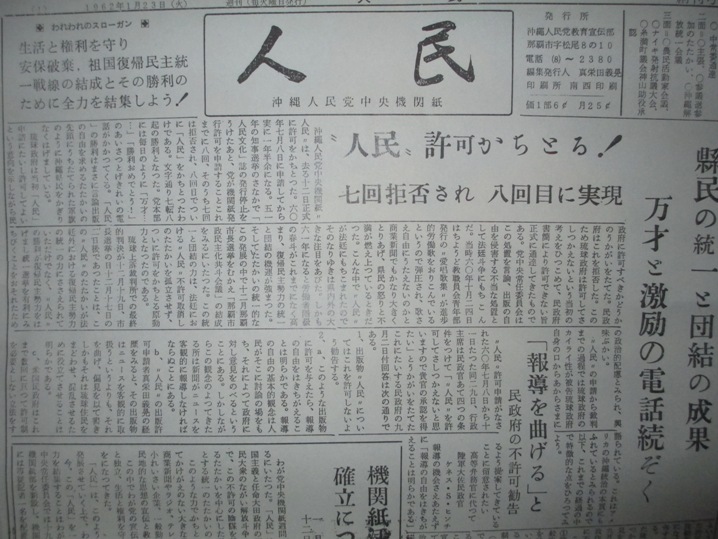

1963年
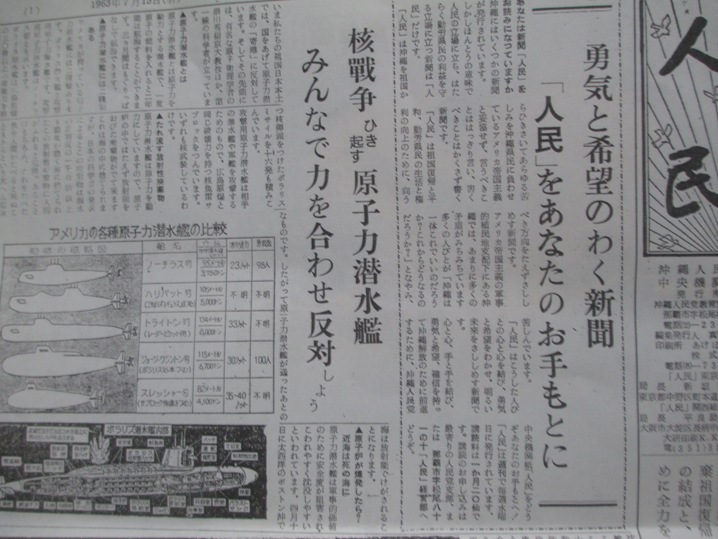
7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」
1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」
1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社
○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫
○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫
○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの
○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二
○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光
○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会
1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」
1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」
2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」
7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)
7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」
9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」
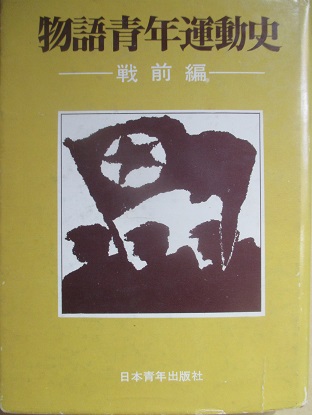

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社
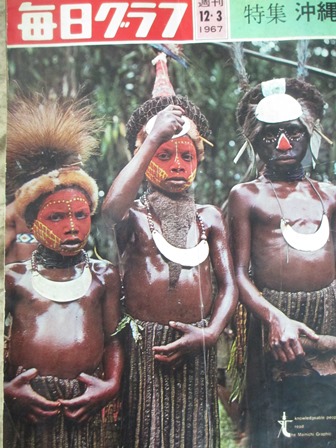
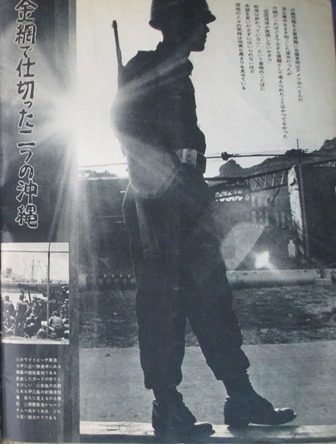
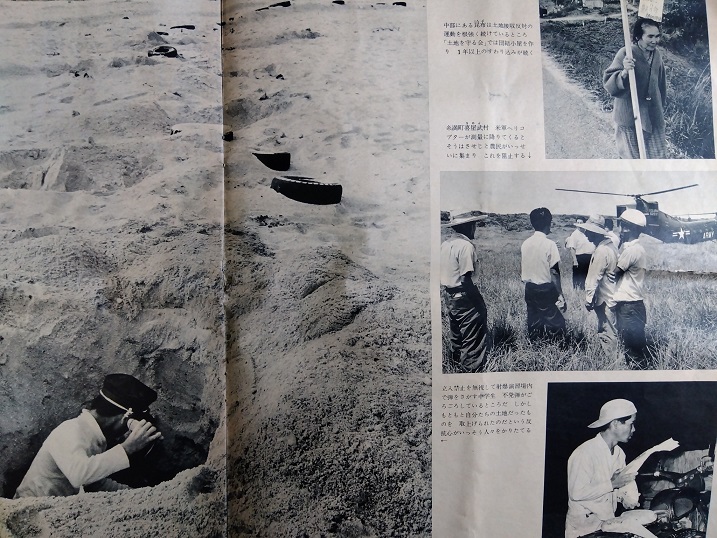
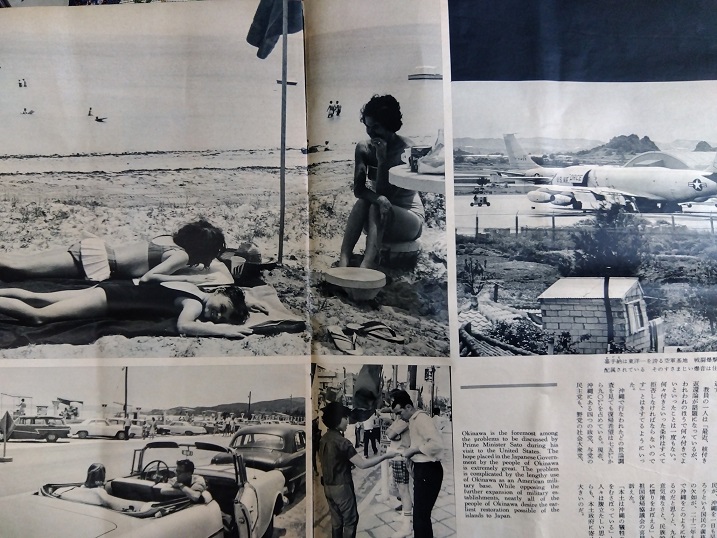
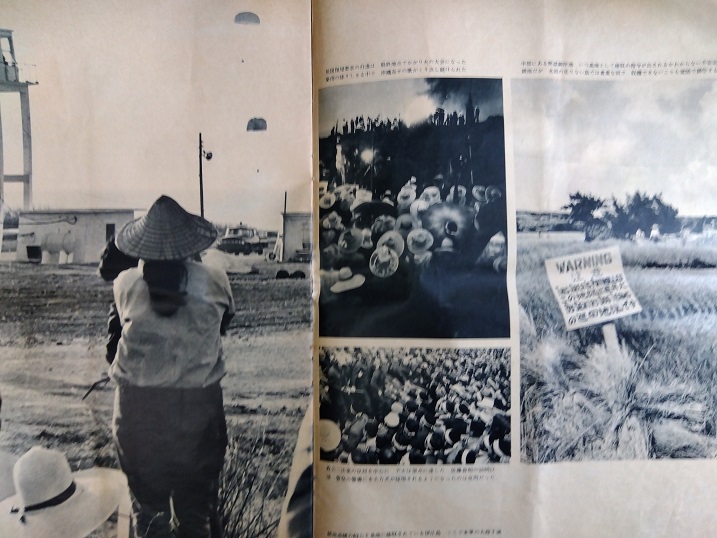
12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」
1968年
6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」
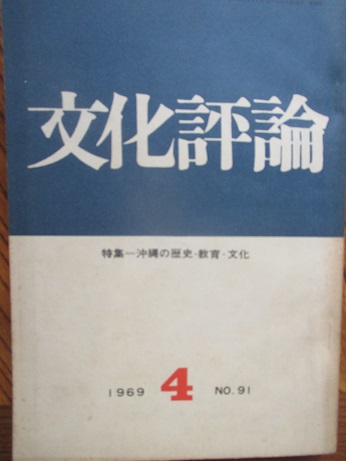
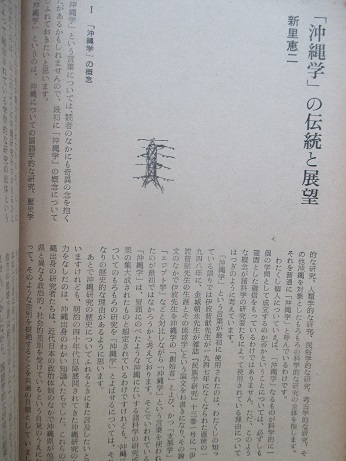
1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」
1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)
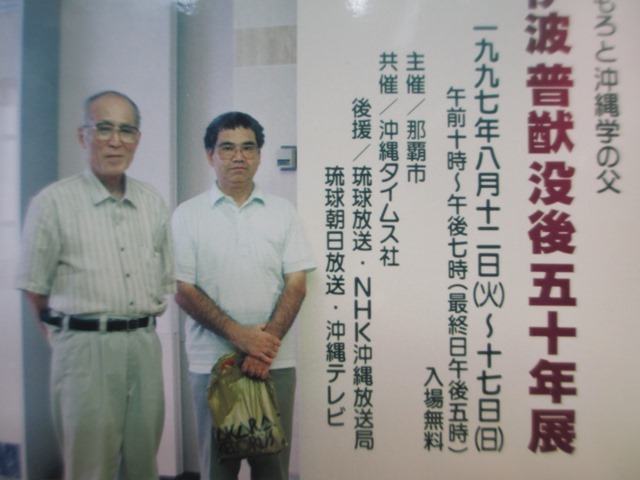
伊波廣定氏と新城栄徳
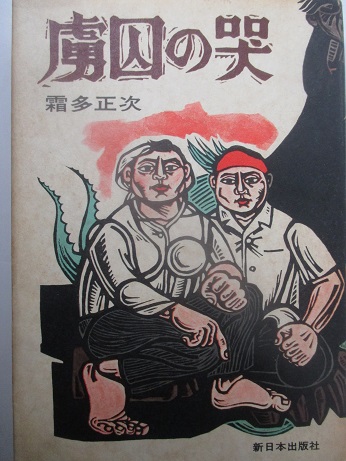
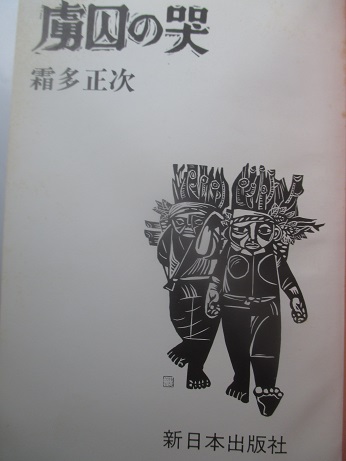
1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」
5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)
8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」
①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)
9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』
□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために
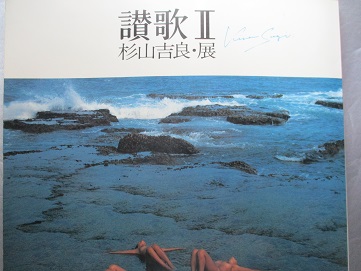
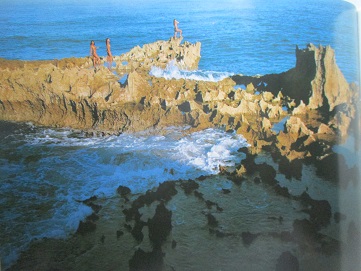
1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』
1971年
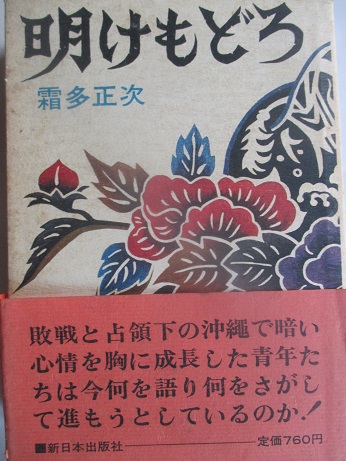
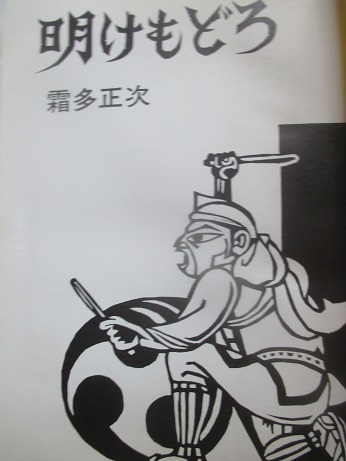
1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」
1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」
1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」
1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」
1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」
2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」
2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」
4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」
5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」
5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④
5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」
6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」
6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」
7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」
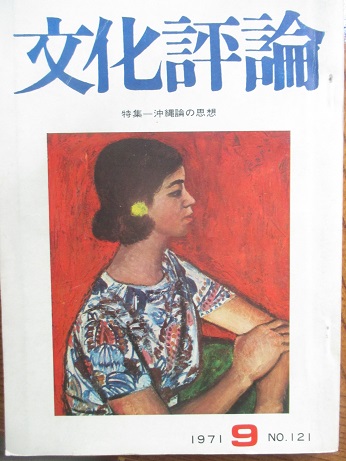
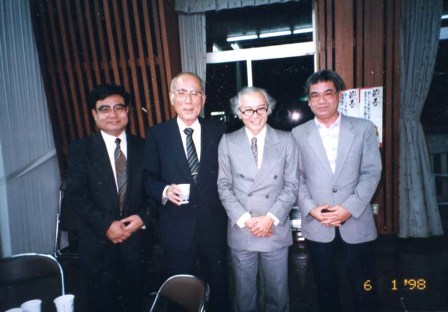
1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
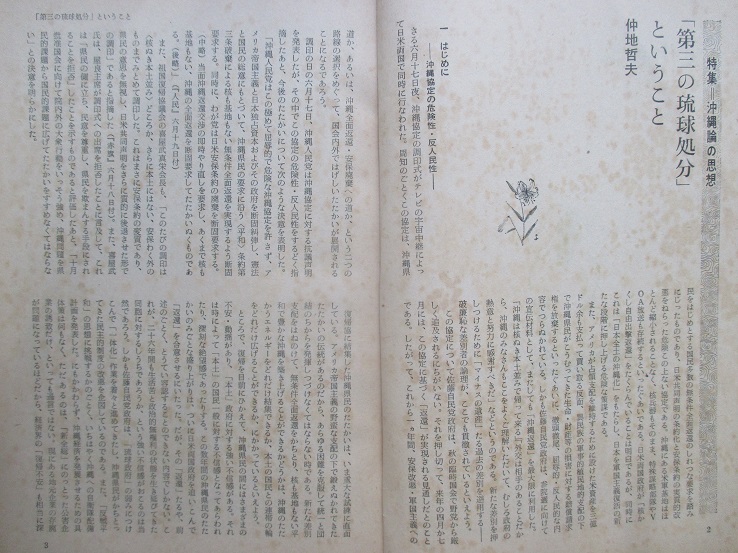
10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」
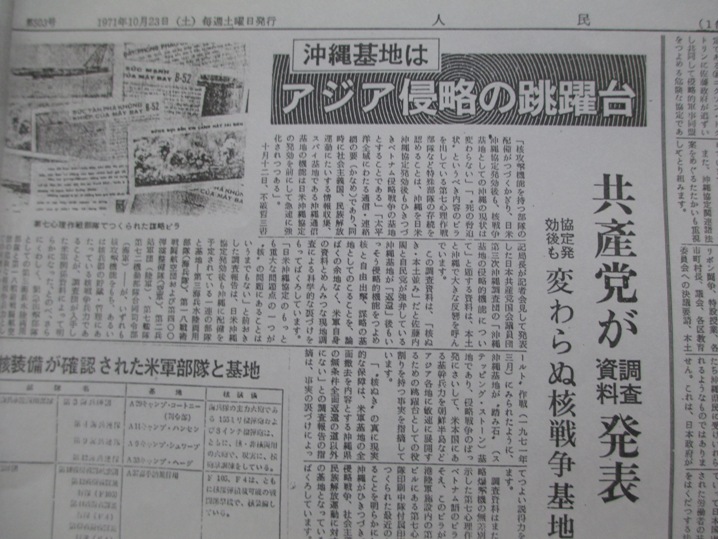
10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」


写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益
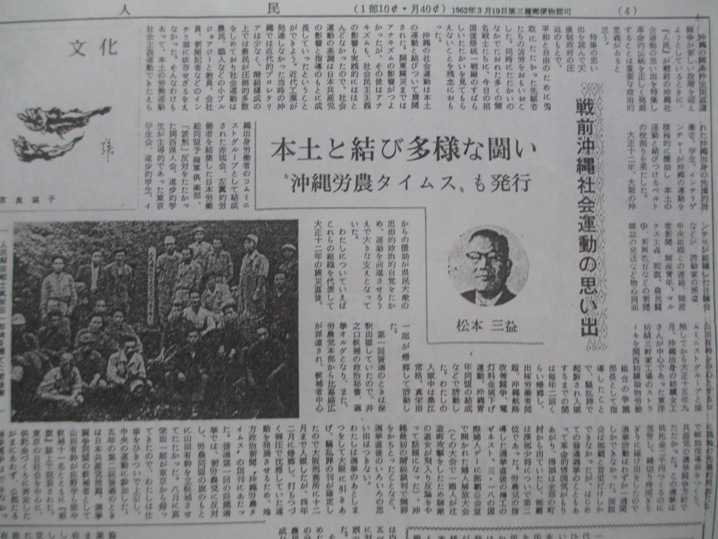
12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」
12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」
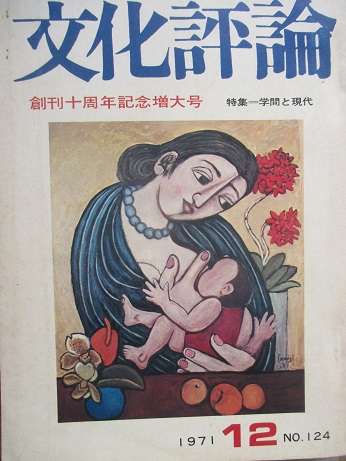
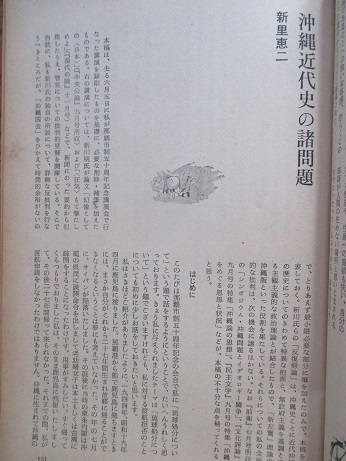
1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」
1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>
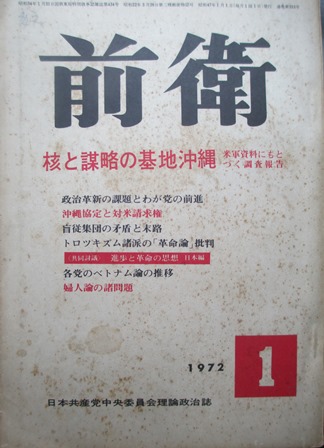

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫
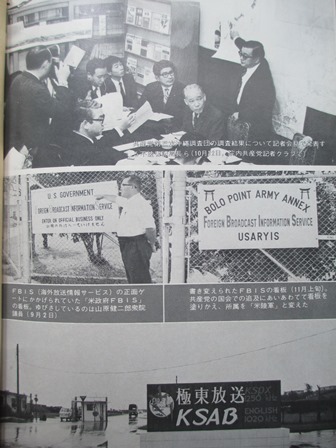
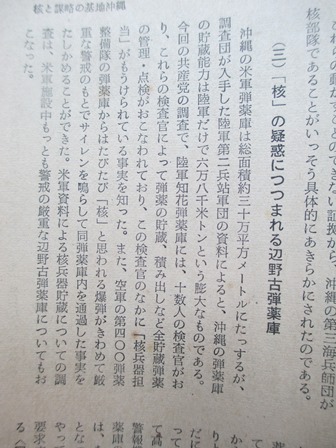
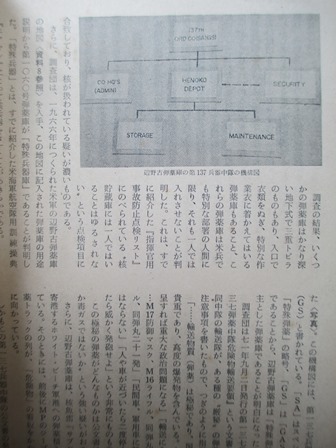
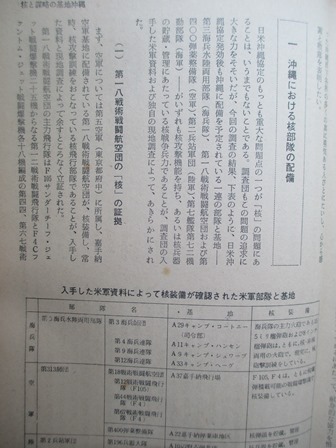


1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」
1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」
2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」
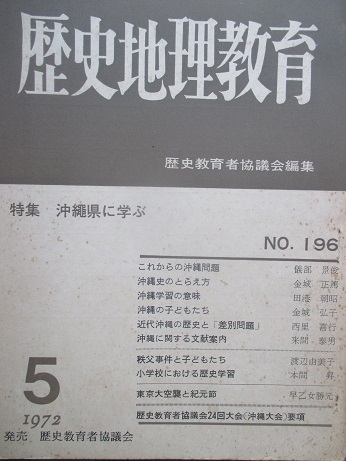
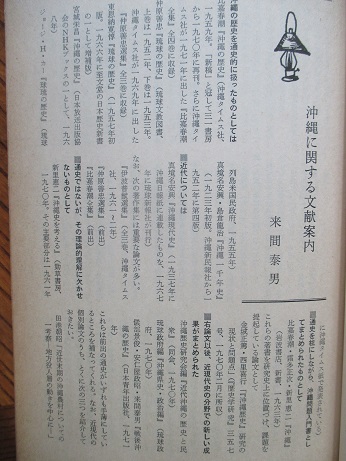
1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」
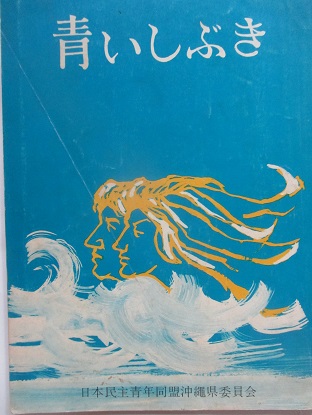
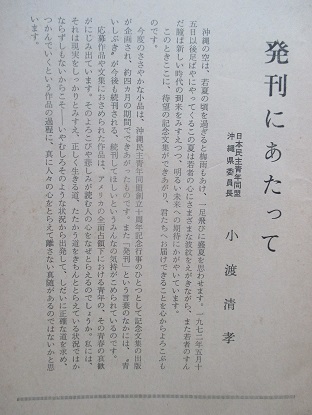
1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

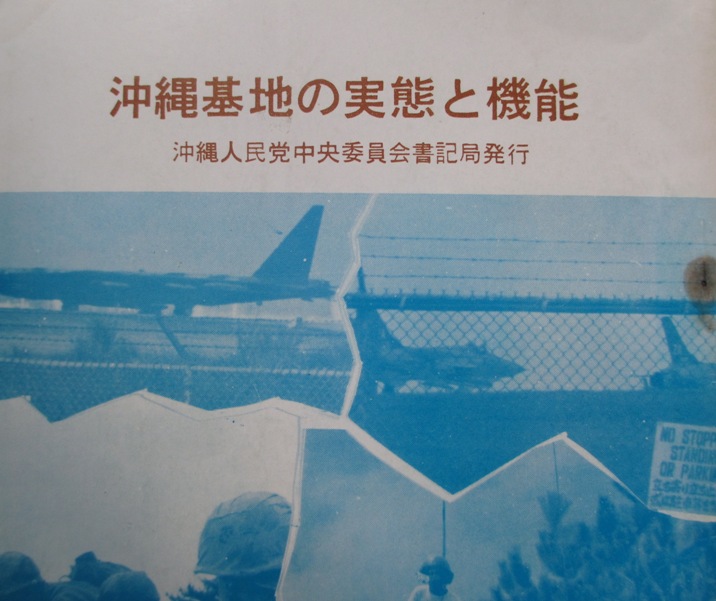
写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』
1973年
1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」
4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」
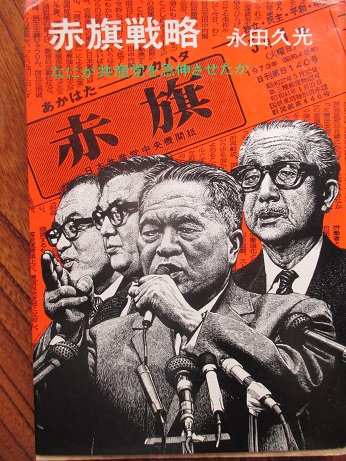
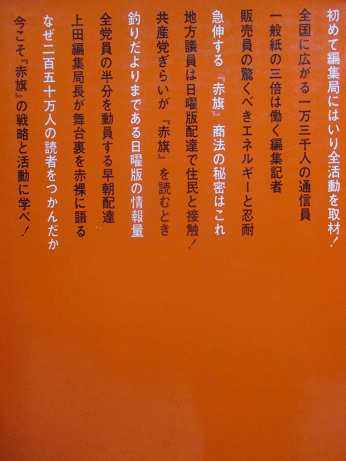
1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社
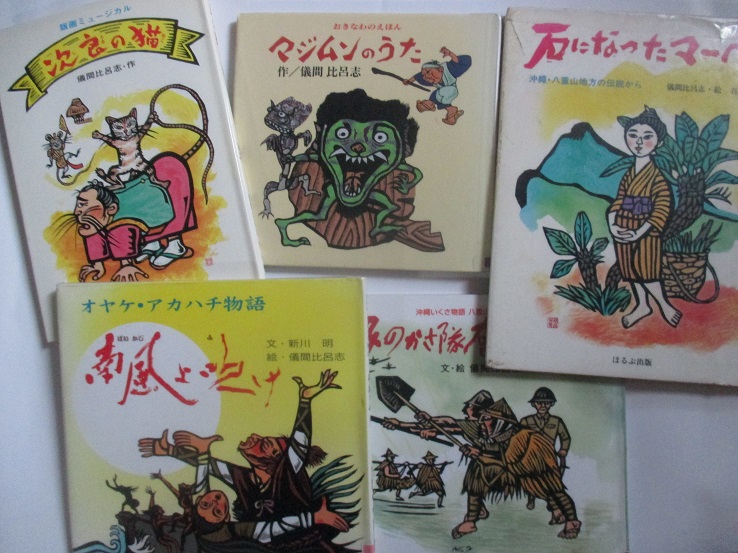
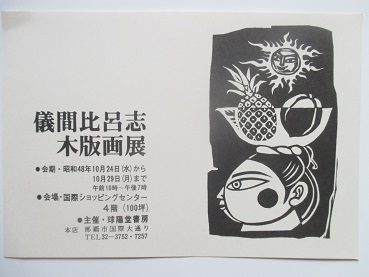
右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房
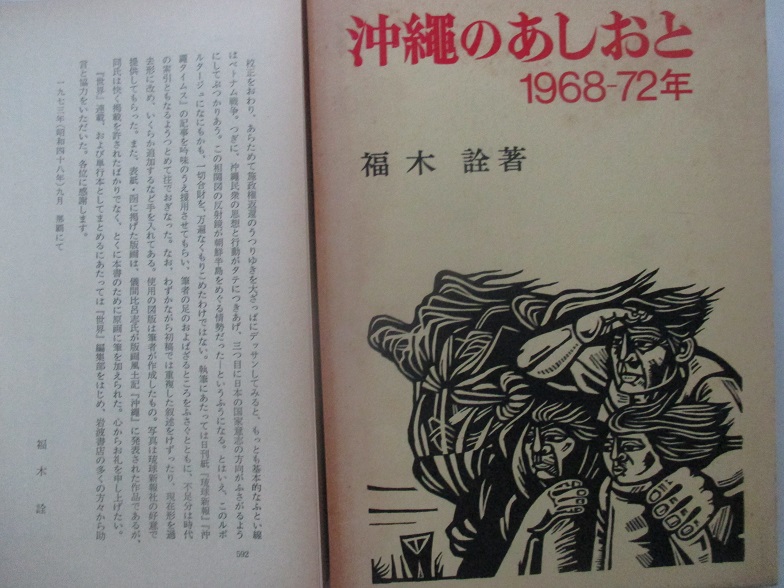
1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。
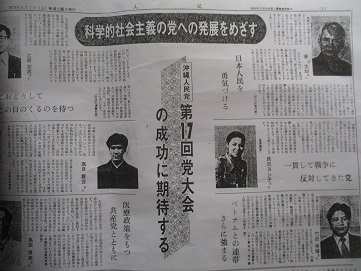
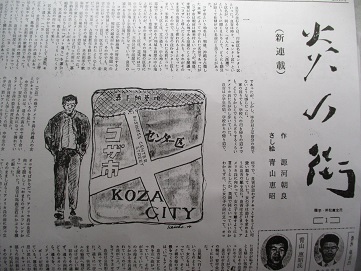
『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭
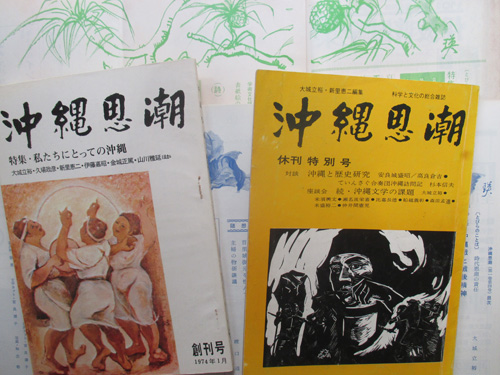
1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」
☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。
1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」
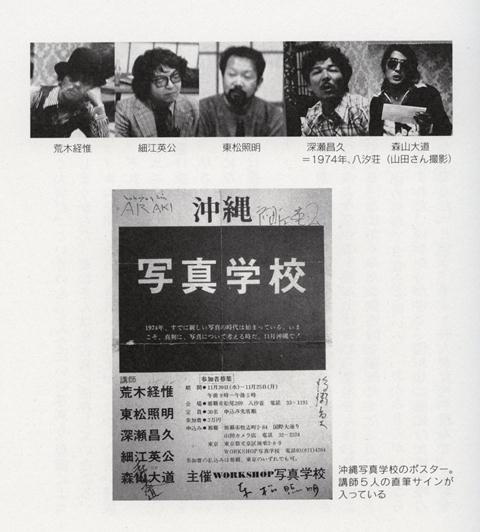
1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」
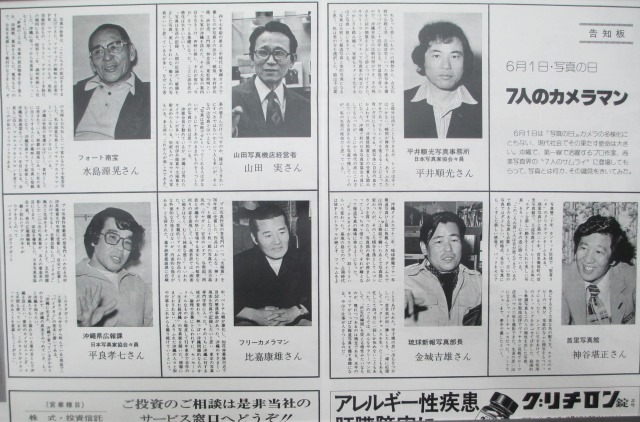
1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」
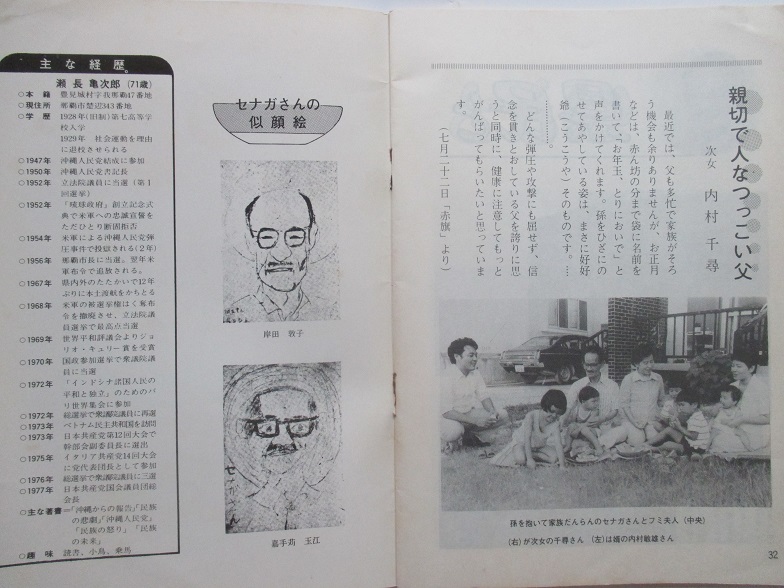
1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会


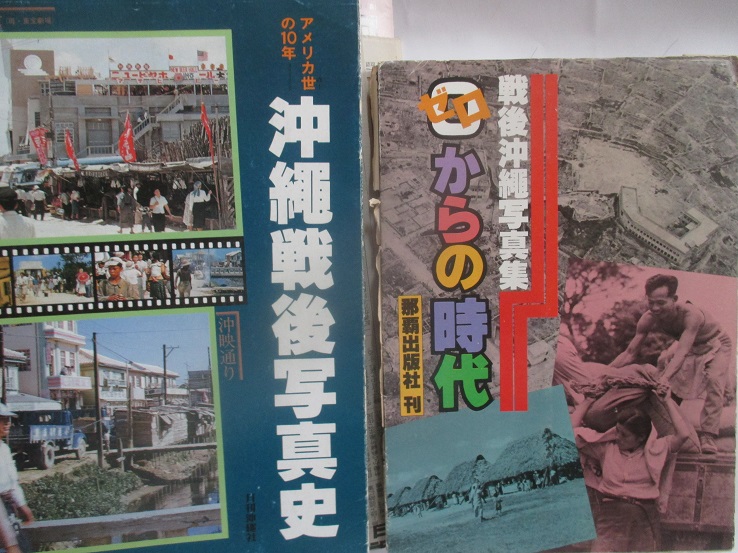
1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社
☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)
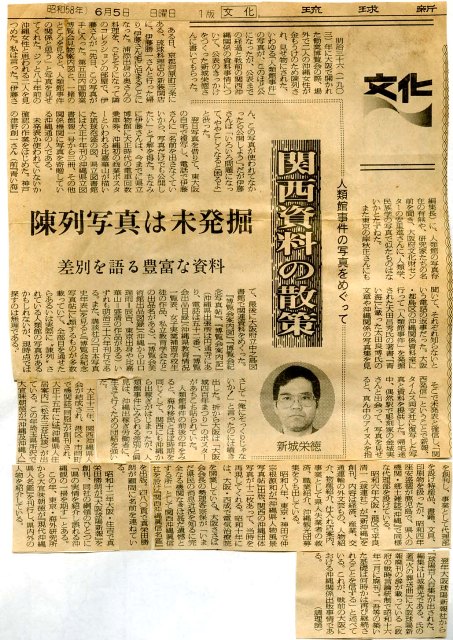
□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」
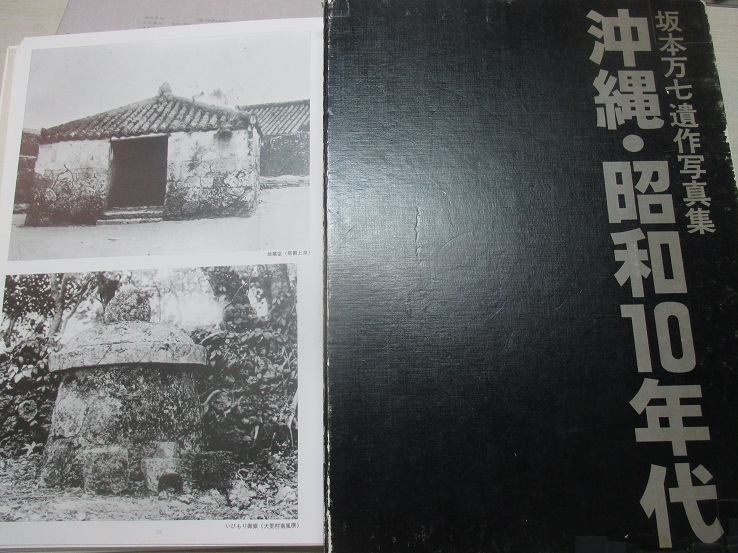
1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書
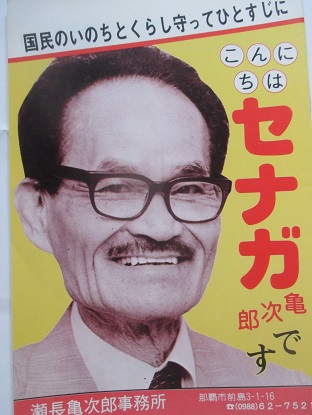
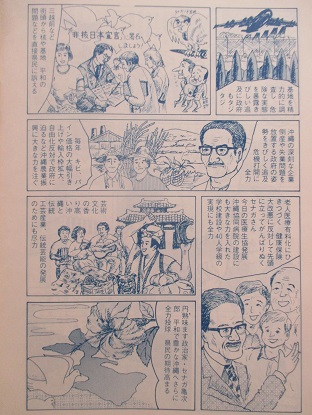
1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所
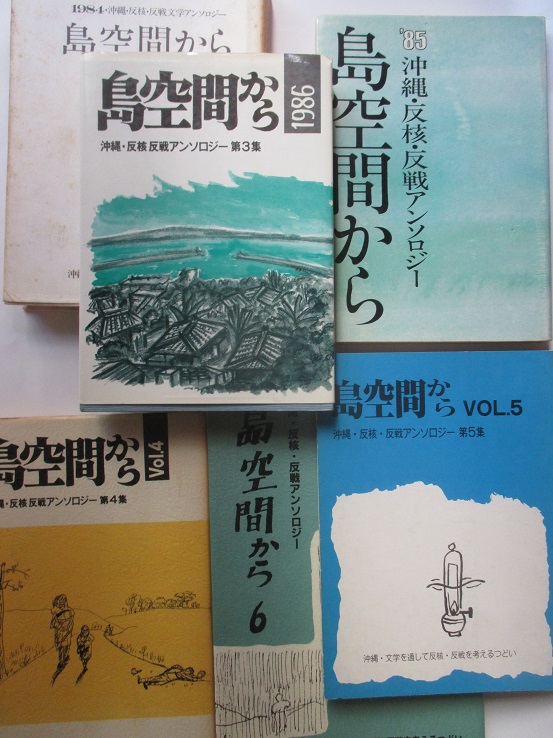
1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)
〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。
いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。
文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。
米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。
1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』
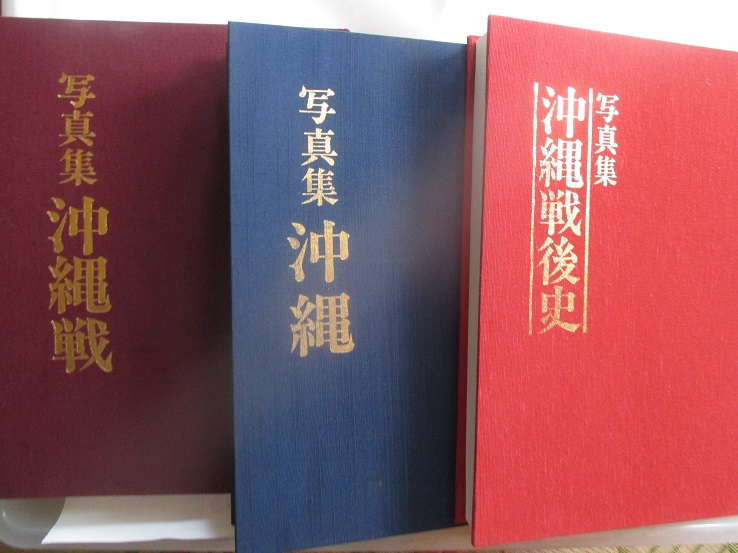
那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實
1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」
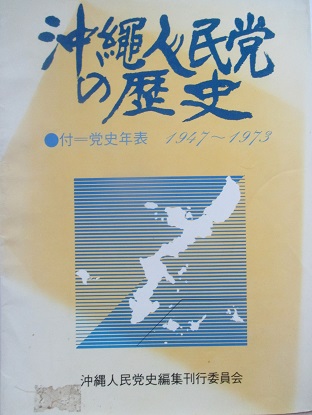
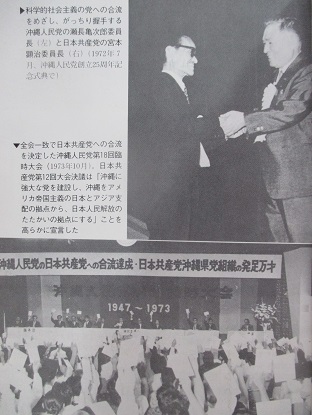
1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会
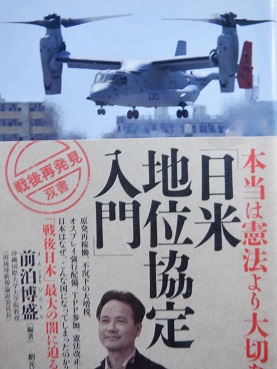
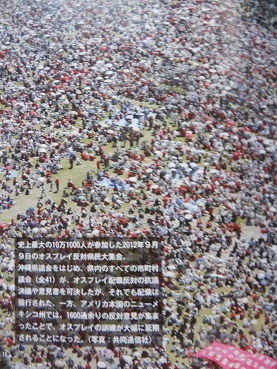
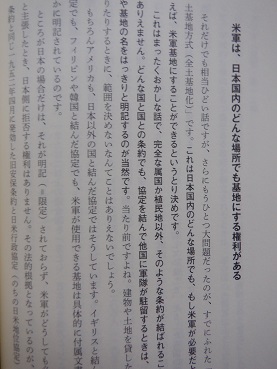
2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社
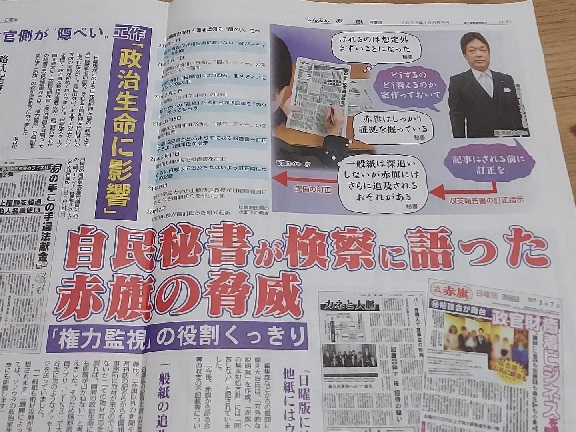
ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ
写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。
悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫
○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。
郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長
善意の記録として・・・・沖縄県学生会
○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。
第一部
拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人
第二部
土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道
島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光
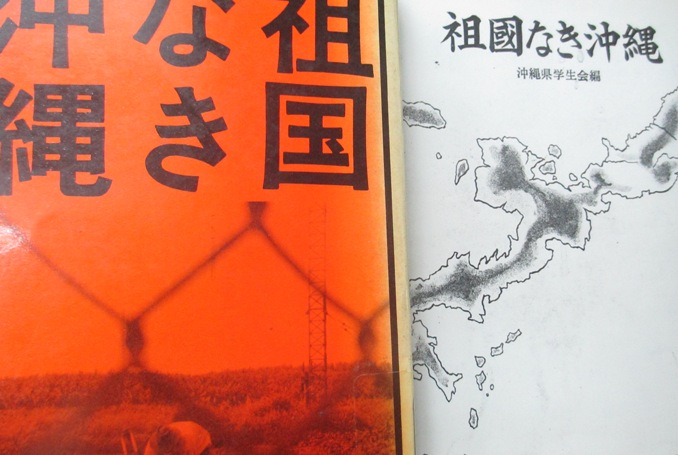
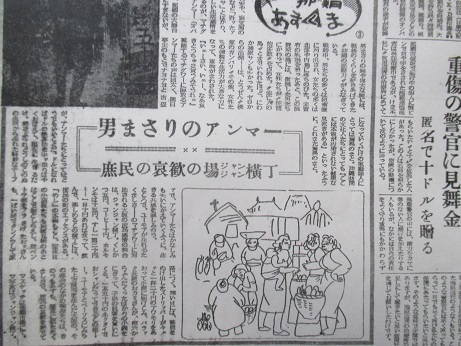
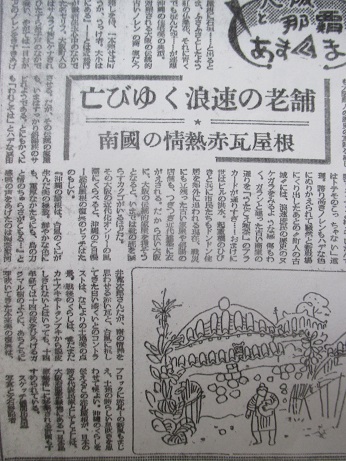
1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」
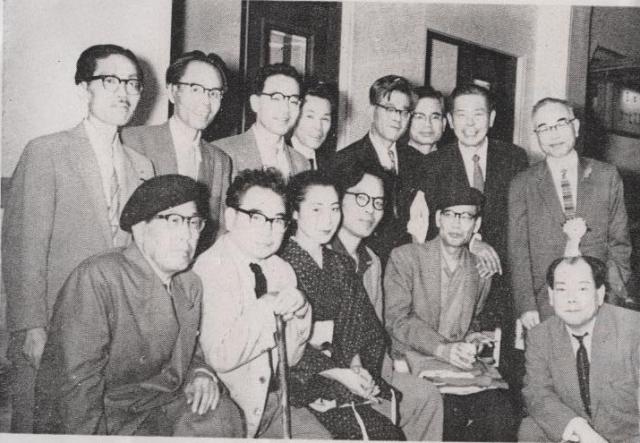
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子
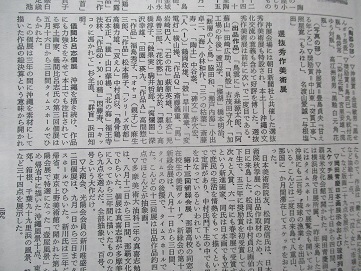

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』
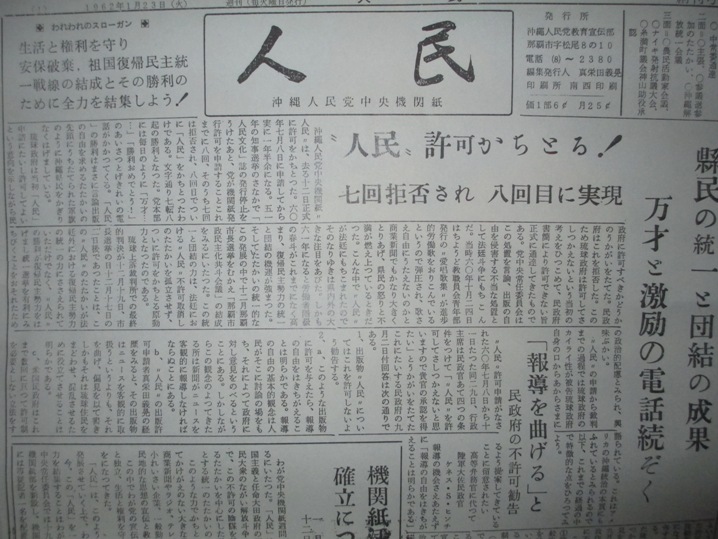

1963年
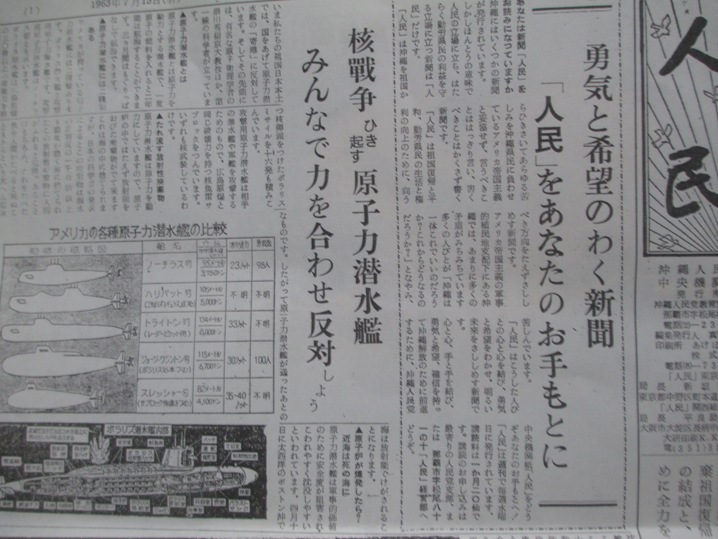
7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」
1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」
1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社
○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫
○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫
○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの
○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二
○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光
○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会
1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」
1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」
2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」
7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)
7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」
9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」
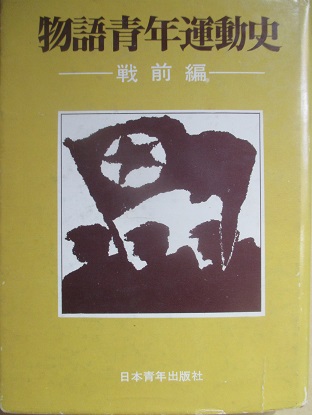

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社
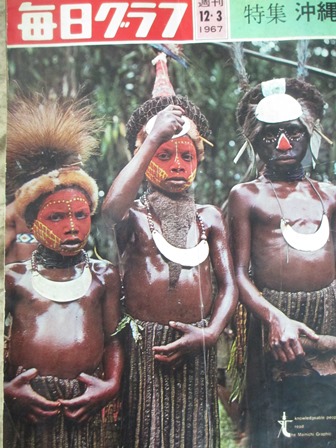
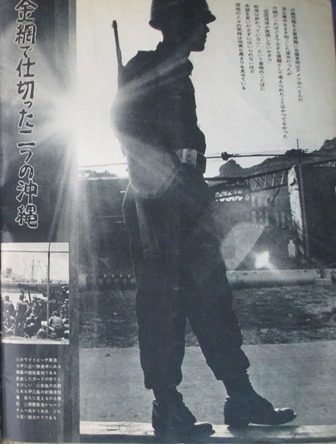
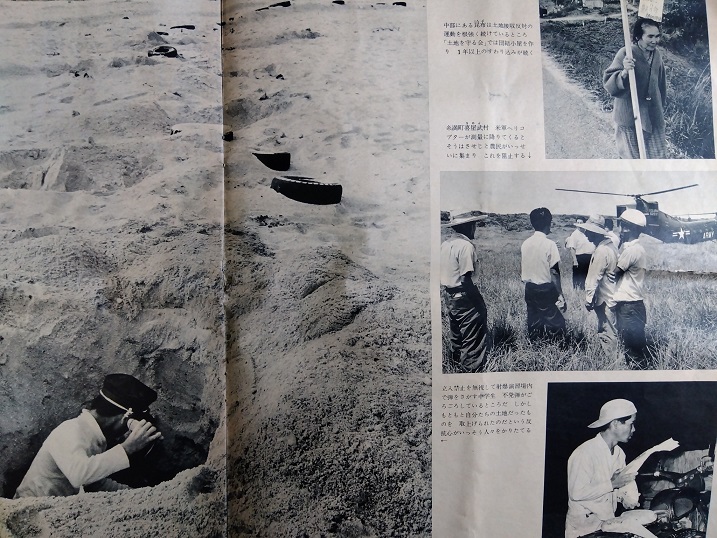
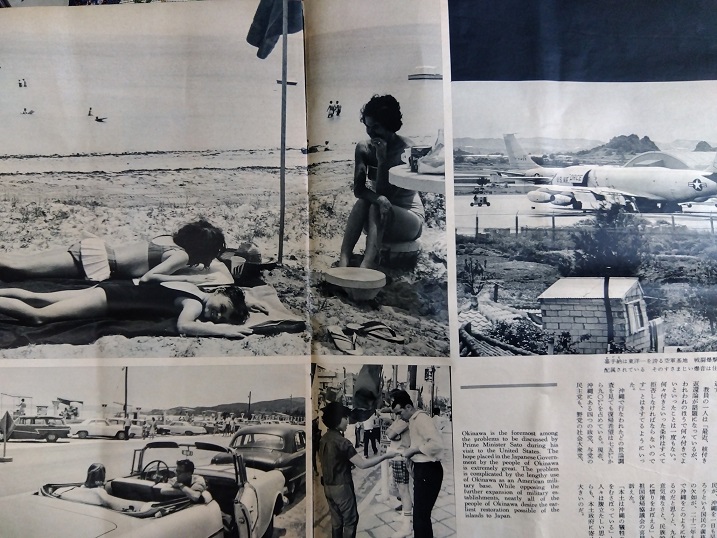
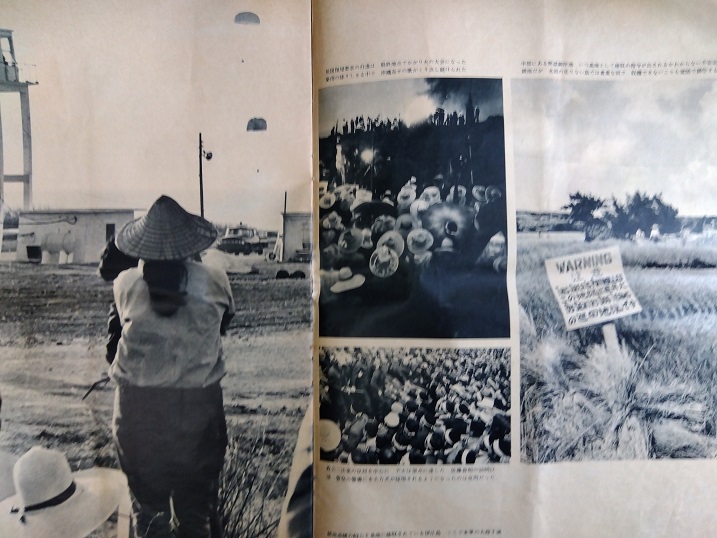
12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」
1968年
6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」
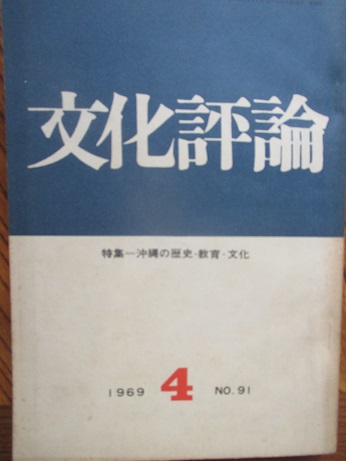
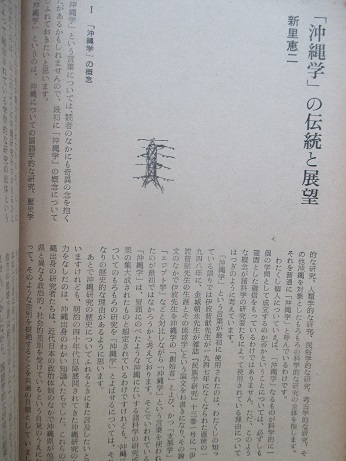
1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」
1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)
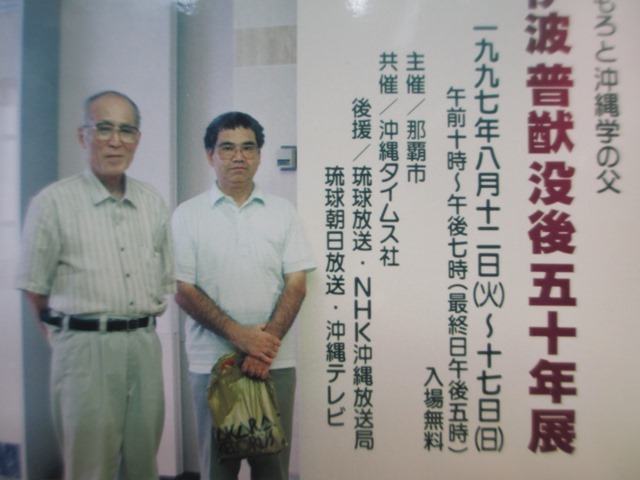
伊波廣定氏と新城栄徳
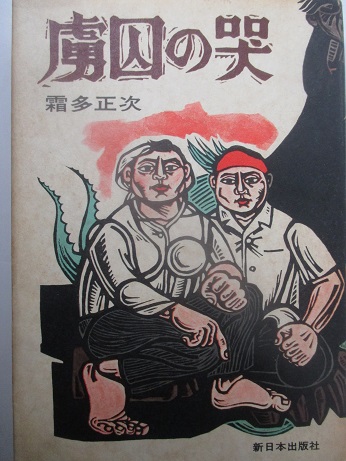
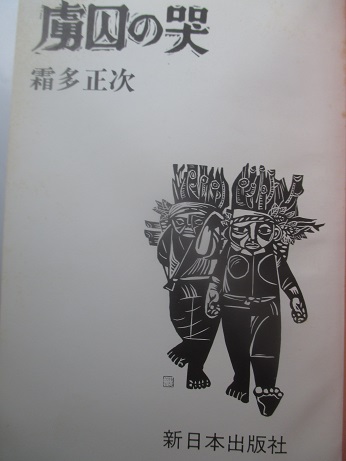
1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」
5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)
8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」
①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)
9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』
□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために
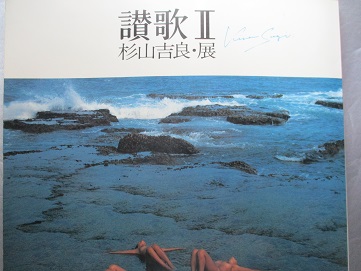
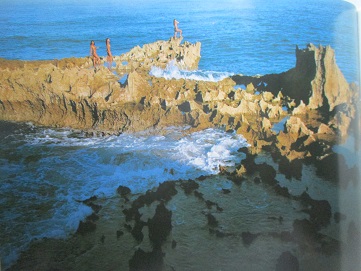
1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』
1971年
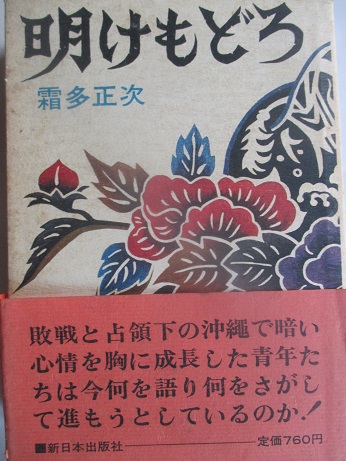
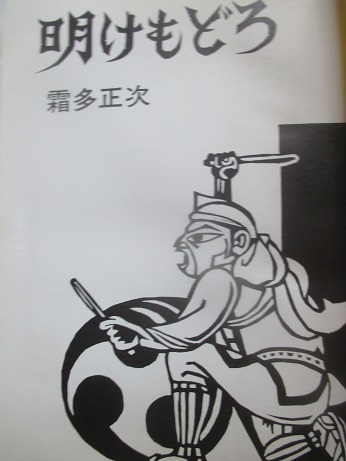
1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」
1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」
1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」
1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」
1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」
2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」
2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」
4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」
5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」
5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④
5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」
6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」
6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」
7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」
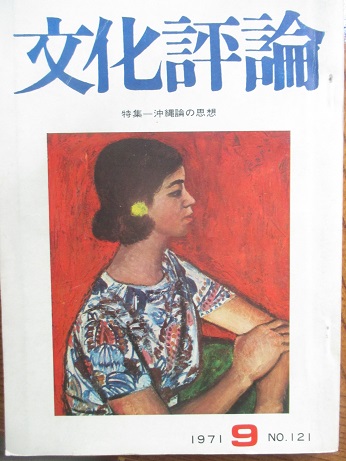
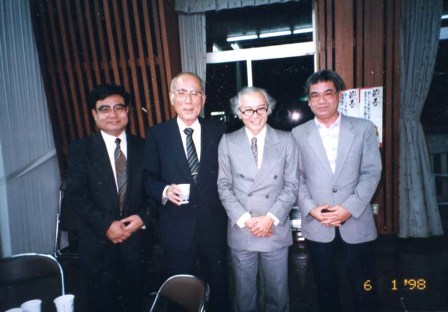
1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
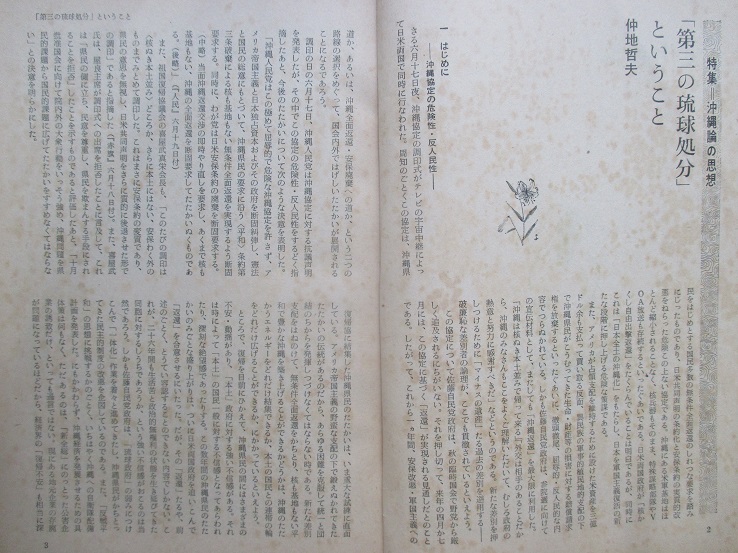
10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」
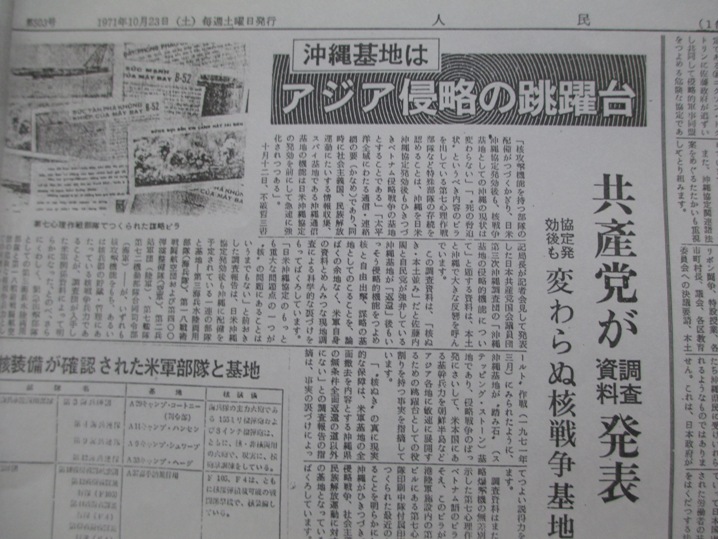
10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」


写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益
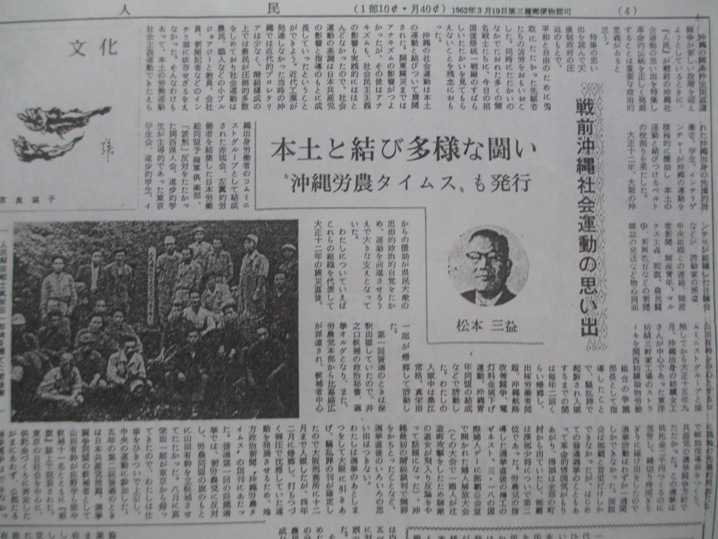
12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」
12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」
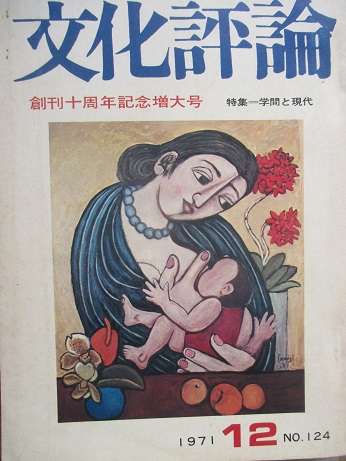
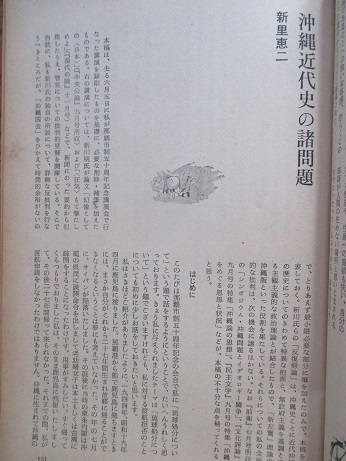
1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」
1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>
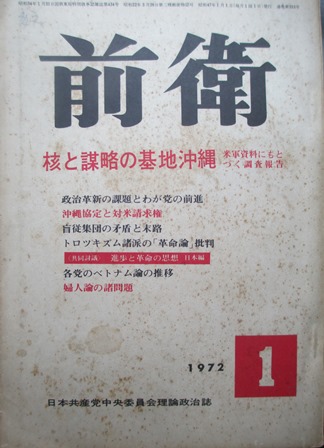

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫
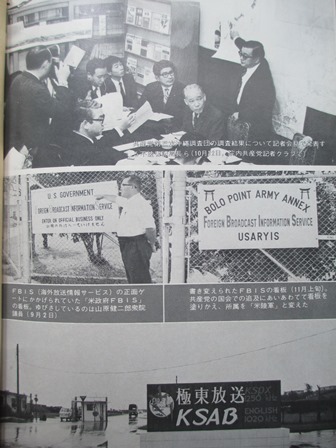
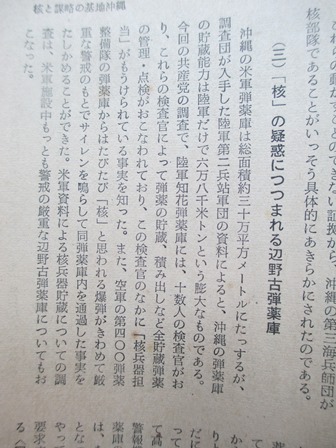
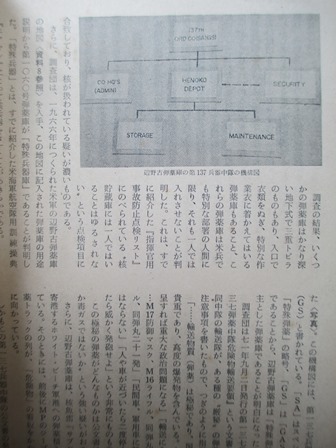
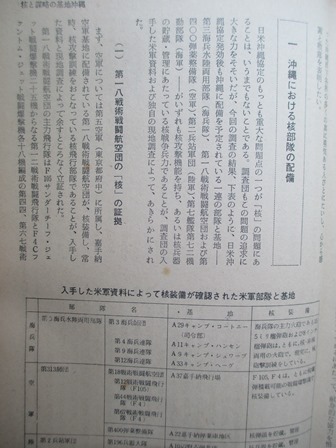


1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」
1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」
2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」
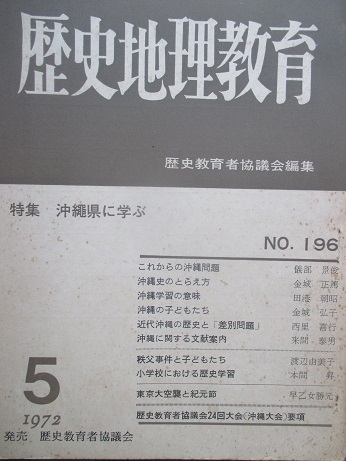
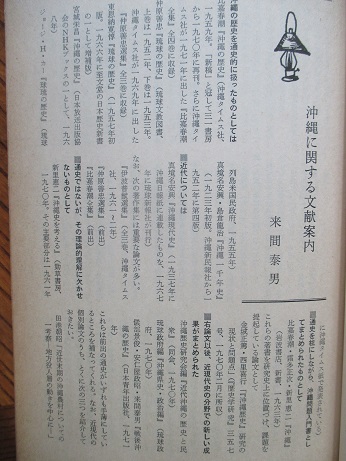
1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」
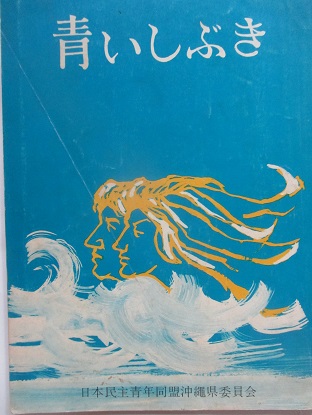
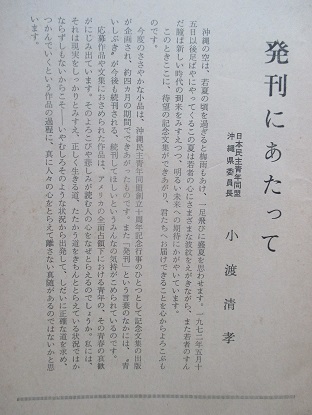
1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

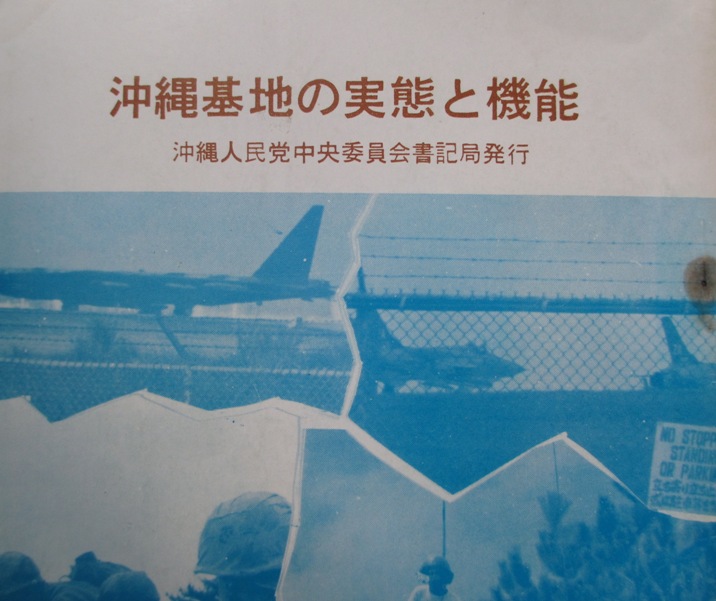
写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』
1973年
1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」
4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」
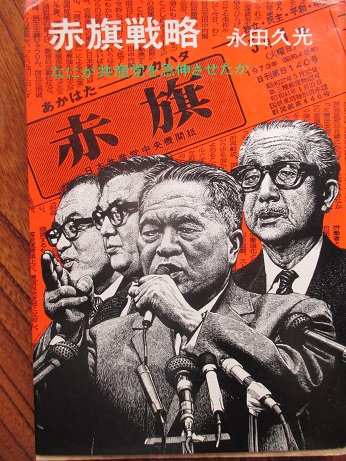
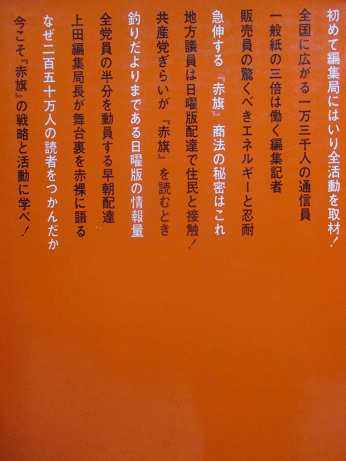
1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社
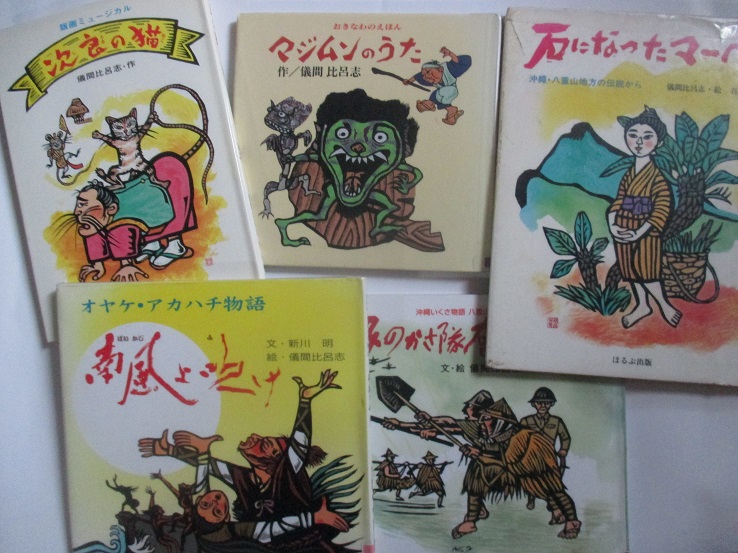
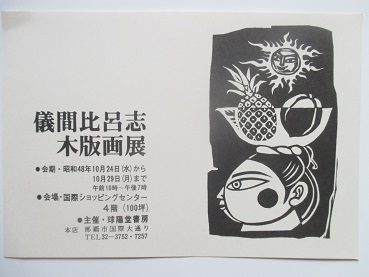
右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房
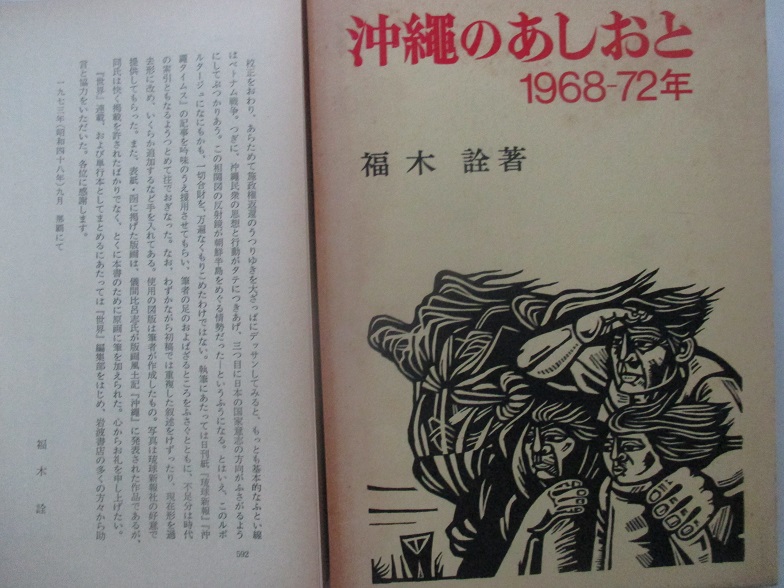
1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。
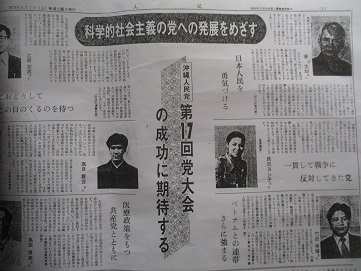
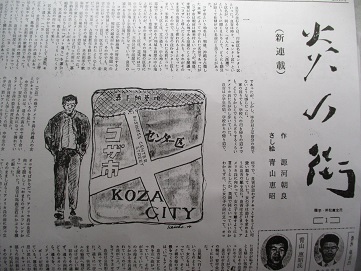
『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭
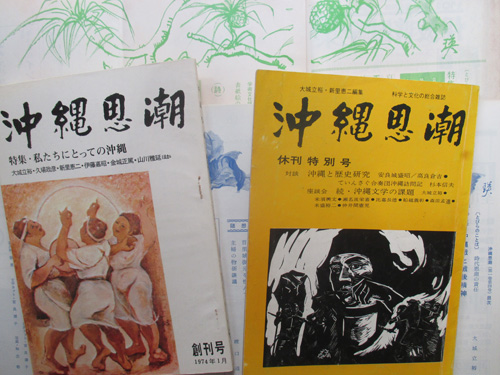
1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」
☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。
1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」
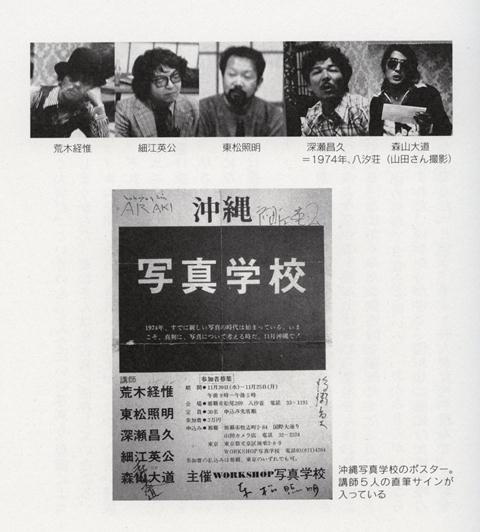
1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」
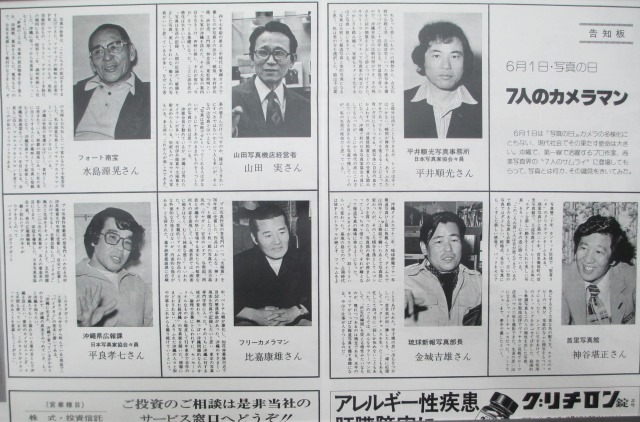
1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」
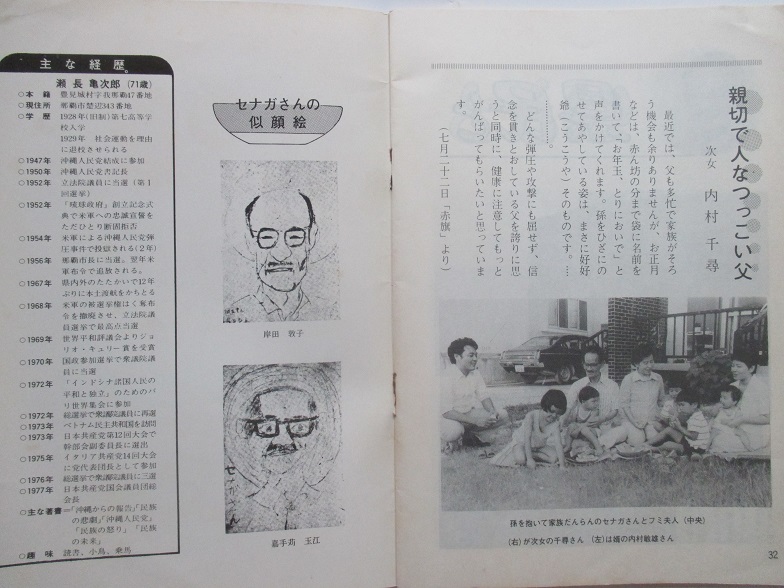
1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会


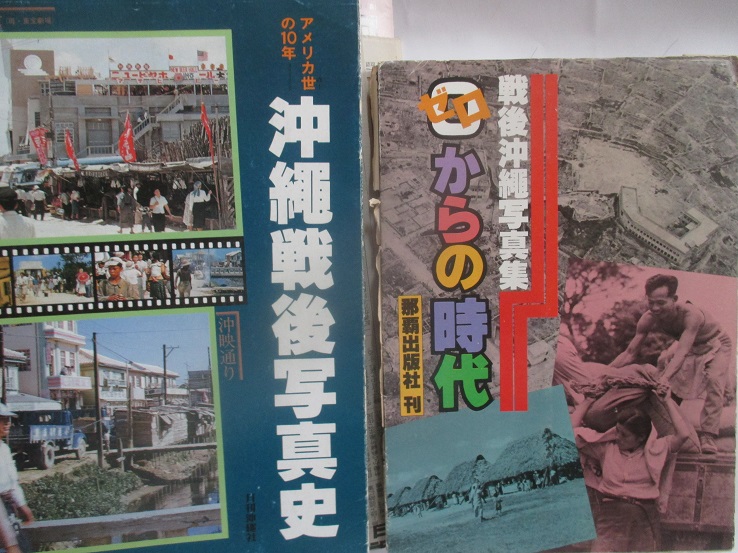
1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社
☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)
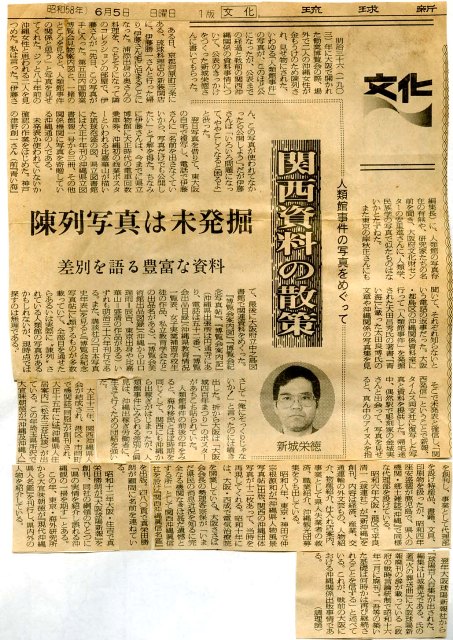
□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」
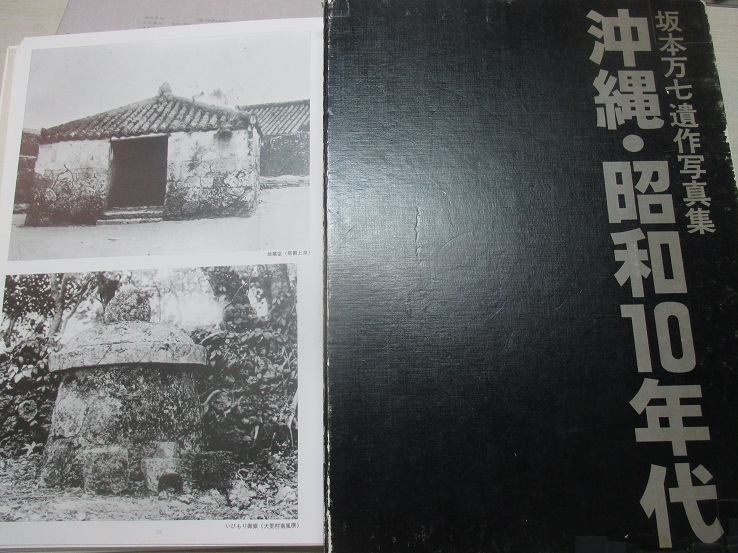
1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書
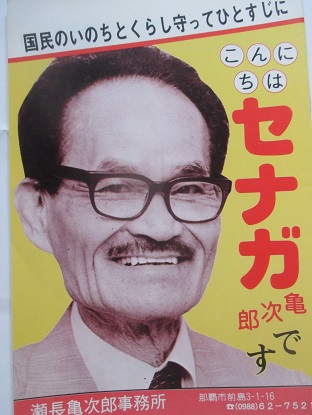
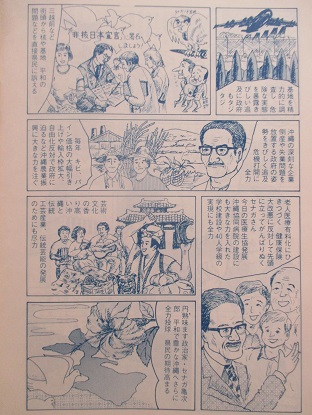
1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所
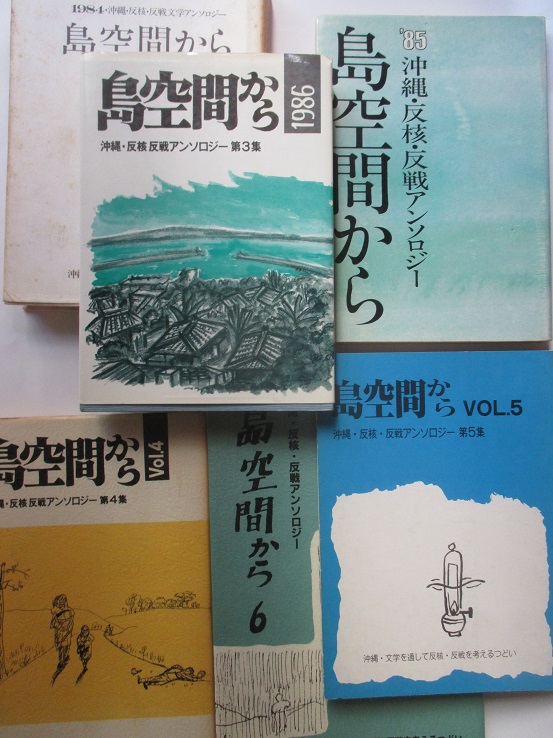
1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)
〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。
いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。
文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。
米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。
1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』
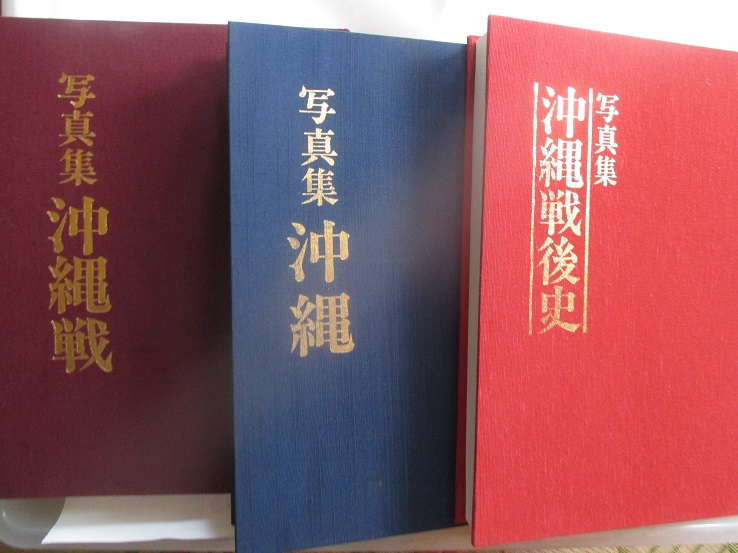
那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實
1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」
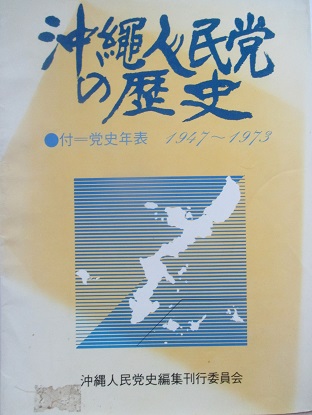
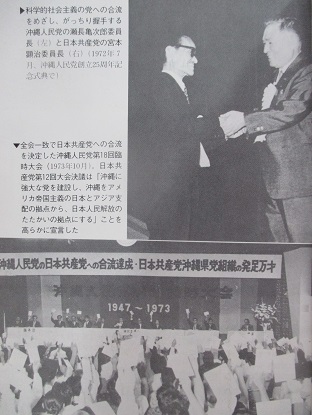
1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会
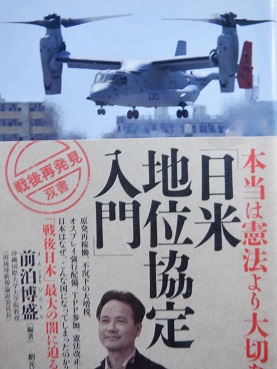
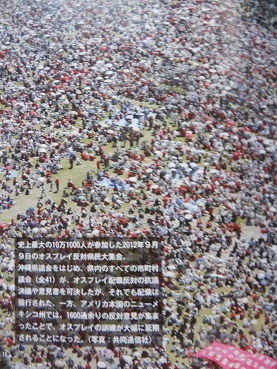
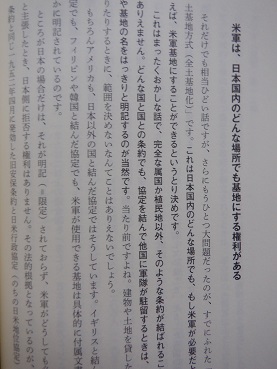
2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社
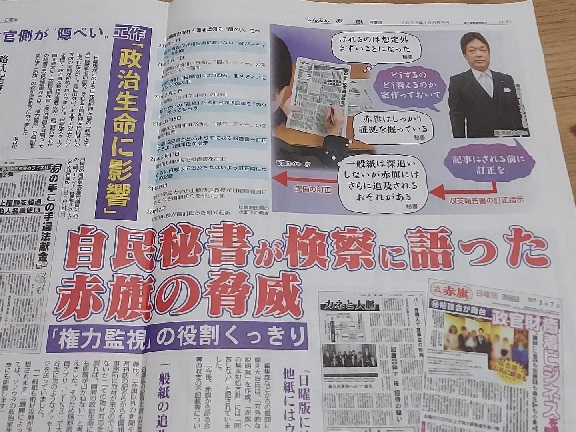
04/14: 仲原善徳(1888年~1946)と仲原善忠

写真ー仲原善徳とバゴボ族の酋長
1933年6月ー仲原善徳『大南洋評論』第1巻第2巻(仲原善徳編集)□金城朝永「南洋関係図書目録」
1936年11月 『訓練』仲原善徳「フィリッピン観光記(上)」
1937年3月ー仲原善徳『南洋千一夜一夜物語』日本書房
1937年3月ー『国際パンフレット通信』第998号 仲原善徳「蘭領ニューギニアの実相」
1937年4月ー『改造』仲原善徳「蘭領ニューギニア」
1938年12月ー『比律賓年鑑』仲原善徳「比律賓群島の諸民族」

1942年2月ー仲原善徳『比律賓紀行』河出書房

1942年7月ー仲原善徳『比律賓群島の民族と生活』南方出版社

1942年7月ー仲原善徳『ボルネオとセレベス』寶雲社
1942年7月ー『海を越えて』仲原善徳「比律賓雑誌」
1942年10月ー『海を越えて』仲原善徳「新比律賓の面貌」


1942年11月ー仲原善徳『ミンダナオ島物語』興亜書房(寺内萬治郎・画)
寺内萬治郎ー洋画家生年明治23(1890)年11月25日
没年昭和39(1964)年12月14日 出生地大阪府大阪市
学歴〔年〕東京美術学校(現・東京芸術大学)西洋画科本科〔大正5年〕卒
主な受賞名〔年〕帝展特選(第6回)〔大正14年〕「裸婦」,帝展特選(第8回)〔昭和2年〕「インコと女」,日本芸術院賞〔昭和26年〕
経歴明治42年白馬会葵橋洋画研究所に入り黒田清輝に師事。東京美術学校では藤島武二の指導を受ける。大正7年文展に初入選。11年耳野卯三郎らと金塔社を結成。14年第6回帝展で「裸婦」が、昭和2年第8回帝展で「インコと女」が、それぞれ特選となる。昭和初期から埼玉県浦和に住む。4年光風会会員となり、同会をはじめ帝展、新文展の審査員を歴任。戦後は23年ころより裸婦制作一筋に打ち込み、26年第6回日展出品の「横臥裸婦」および一連の裸婦作品によって日本芸術院賞を受賞した。35年日本芸術院会員、日展理事。東京美術学校などの講師として後進の指導にも当たった。「コドモノクニ」「幼年倶楽部」の挿絵画家としても親しまれた。→ コトバンク
1943年1月ー『海を越えて』仲原善徳「比律賓を巡る島々」
1943年2月ー仲原善徳『日本人ミンダナオ島開拓略史』南洋経済研究所
1943年4月ー『海を越えて』仲原善徳「比律賓の諸問題」
1943年10月ー『海を越えて』仲原善徳「フィリッピン史上の二人物」


1943年10月ー仲原善徳『バコボ族覚書』改造社
1943年11月ー『海を越えて』仲原善徳「フィリッピン在留邦人気質」


本間雅晴「序文」、葛生能久「序文」/右ー頭山満「題字」

写真中央ー犬養毅、頭山満
1944年9月ー仲原善徳『フィリピン独立正史』中文館書店
04/02: 1940年の東京沖縄県人会②ーその周辺
戦前・戦後、常に東京沖縄県人会の指導者であった神山政良氏が1966年3月に『年表ー沖縄問題と在京県人の動き』を琉球新報社東京総局から発行している。その年表によると東京で沖縄県人会という名称は、1921年1月23日に明正塾にあった沖縄県青年会を改称した沖縄県人会が最初のものである。戦前の東京沖縄県人会①には在京の県人会幹部名を列記したが今回は個人別に紹介する。出典は1940年の東京沖縄県人会名簿。
安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町
伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町
上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂
大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町
大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)
大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町
漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)
金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町
喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町
國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国
東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)
呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」
崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町
尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町
城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町
高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦
田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田
知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川
津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町
照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷
渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町
當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)
仲原善忠(成城高等学校教授)ー世田谷区祖師谷、仲原善徳ー世田谷区祖師谷、仲宗根玄愷(昭和生命保健相互会社常務取締役)ー中野区桜山、仲宗根玄康(東京市厚生局)ー滝野川区滝野川町、仲里文英(世田谷区多聞小学校)、仲村常樽(台東小学校)ー淀橋区東大久保町、仲村専義(建築設計業)ー下谷区入谷町、仲本盛行(東京市財務局主税課)ー京橋区新佃島東町、仲本朝愛ー本郷区田町・喜久村方、仲本吉一郎ー渋谷区神山町、仲本宗厚ー渋谷区幡ヶ谷本町、仲本川原ー大森区久ヶ原、仲本徳英ー本郷区駒込千駄木町、仲田多聞ー荏原区羽田町麹谷、仲田新雄ー渋谷区笹塚町、仲尾次清正(東京憲兵隊本部)ー麹町区竹平町、仲井間宗一(文部参与官)ー麹町区平川町、仲井間宗祐(税務懇話会)ー滝野川区上中里町、仲吉良光(東京日々新聞記者)ー横浜市鶴見区鶴見町、仲村渠直和(市ヶ谷刑務所勤務)、仲野廉松ー世田谷区太子堂町
仲兼久長太郎(東京地方専売局蔵前分工場)ー江戸川区小岩町、仲地唯一(東京市電気局)ー渋谷区代々木初台、仲松弥男(荒川区第五峡田小学校)、長嶺善進(糧秣廠)ー下谷区上根岸、長嶺晃(城東区第一亀戸小学校)、長嶺朝昭(東京地方専売局)、長嶺朝英(川越税務署)ー川越市宮下町、長嶺将繁(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、名護朝徳ー荏原区荏原町、名城政教(日本起重機製作所)ー蒲田区糀谷、名城嗣亨(京橋月島第三小学校)ー京橋区月島東河岸町通、長嶺亀助(陸軍少将、軍需会社顧問)ー神奈川県茅ヶ崎、長濱三郎(大森区馬込第一小学校)ー大森区馬込町東、名嘉山徳温(東京市財務局会計課)ー板橋区上板橋、長濱眞詳(石神井西小学校)ー中野区新井町、永島可昌(下谷区竹町小学校)、名嘉繁雄(南武鉄道株式会社技術課)ー品川区北品川町、永井長雄(東京市総務局)ー中野区桜山町
安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町
伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町
上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂
大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町
大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)
大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町
漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)
金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町
喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町
國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国
東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)
呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」
崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町
尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町
城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町
高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦
田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田
知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川
津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町
照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷
渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町
當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)
仲原善忠(成城高等学校教授)ー世田谷区祖師谷、仲原善徳ー世田谷区祖師谷、仲宗根玄愷(昭和生命保健相互会社常務取締役)ー中野区桜山、仲宗根玄康(東京市厚生局)ー滝野川区滝野川町、仲里文英(世田谷区多聞小学校)、仲村常樽(台東小学校)ー淀橋区東大久保町、仲村専義(建築設計業)ー下谷区入谷町、仲本盛行(東京市財務局主税課)ー京橋区新佃島東町、仲本朝愛ー本郷区田町・喜久村方、仲本吉一郎ー渋谷区神山町、仲本宗厚ー渋谷区幡ヶ谷本町、仲本川原ー大森区久ヶ原、仲本徳英ー本郷区駒込千駄木町、仲田多聞ー荏原区羽田町麹谷、仲田新雄ー渋谷区笹塚町、仲尾次清正(東京憲兵隊本部)ー麹町区竹平町、仲井間宗一(文部参与官)ー麹町区平川町、仲井間宗祐(税務懇話会)ー滝野川区上中里町、仲吉良光(東京日々新聞記者)ー横浜市鶴見区鶴見町、仲村渠直和(市ヶ谷刑務所勤務)、仲野廉松ー世田谷区太子堂町
仲兼久長太郎(東京地方専売局蔵前分工場)ー江戸川区小岩町、仲地唯一(東京市電気局)ー渋谷区代々木初台、仲松弥男(荒川区第五峡田小学校)、長嶺善進(糧秣廠)ー下谷区上根岸、長嶺晃(城東区第一亀戸小学校)、長嶺朝昭(東京地方専売局)、長嶺朝英(川越税務署)ー川越市宮下町、長嶺将繁(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、名護朝徳ー荏原区荏原町、名城政教(日本起重機製作所)ー蒲田区糀谷、名城嗣亨(京橋月島第三小学校)ー京橋区月島東河岸町通、長嶺亀助(陸軍少将、軍需会社顧問)ー神奈川県茅ヶ崎、長濱三郎(大森区馬込第一小学校)ー大森区馬込町東、名嘉山徳温(東京市財務局会計課)ー板橋区上板橋、長濱眞詳(石神井西小学校)ー中野区新井町、永島可昌(下谷区竹町小学校)、名嘉繁雄(南武鉄道株式会社技術課)ー品川区北品川町、永井長雄(東京市総務局)ー中野区桜山町
04/16: 世界のなかのウチナー⑦

1972年2月号『青い海』10号 「若者が集う『沖縄関係資料室』の西平守晴氏宅」

1972年1月ー『青い海』10号□若者が集う「沖縄関係資料室」の西平守晴氏宅ー西平沖縄関係資料室主宰「柳宗悦という人を皆さんもよく知っていると思う。沖縄の民芸を高く評価した人だが、その人が昭和14年に書いた『琉球の富』の序に次のような言葉がある。<人々は今まで余りにも暗い沖縄を語り過ぎていたのです。私たちは優れた沖縄を語りたいのです。それは私達を明るくし島の人々を明るくさせるでしよう。私達は実に多くの富に就いて語り合いたいのです。沖縄に就いて歎く人々のために、又この島に就いて誤った考えを抱く人々のために、又自国を余りにも卑下して考える土地の人々のために、そうして真理を愛する凡ての人々のために、この一文が役立つことを望んで止まないのです。> この30年も前の文章が、私の今の気持ちを言い当てています。-」
□ここで資料の内容の一部を紹介しよう。開設当時200冊足らずだった書籍・雑誌は、現在約3200冊。新聞や週刊誌などのスクラップが300冊。沖縄に関する資料については、関西隋一と言われる。▽人物関係ー「謝花昇伝」「平良辰雄回顧録」「伊波普猷選集」などの伝記、回顧録、全集もの。▽市町村関係ー「北谷村誌」「南大東村誌」 比嘉景常「久米島紀行」など。▽歴史関係ー「沖縄県史」(直接主席から贈呈される。関西では天理図書館と資料室ぐらいだろうとの話) 「琉球建築」 田代安定「沖縄結縄考」 金城朝永「異態習俗考」や戦史・戦記もの。▽文芸関係ー「山之口貘詩集」「新沖縄文学」や大城立裕、石野径一郎、霜田正次、石川文一などの諸作品。▽芸能関係ー「組踊大観」「工工四」など。▽政府刊行物ー「立法院議事録」 白書類。▽ミニコミー「沖縄差別」「石の声」「沖縄月報」「寮友」「琉大文学」や本土各大学の県学生会の機関誌・パンフなど。▽地図ー「首里古地図」その他。これらの資料を整理したり、購入したり目録をつくるなど、一人でするにはたいへんな仕事である。西平守晴さんは保育園の仕事もあり忙しいので、現在もっぱら新城栄徳君(23)が動きまわっている。


1972年6月の『豊川忠進先生の長寿を祝う会』では、沖縄の又吉真三氏から文化財の碑文の拓本を借りて展示して参加者を感動させ、平良盛吉翁らを豊川氏の隣りに座らせて感激させた。」
1984年2月24日『琉球新報』「アシャギー新城栄徳『琉文手帖』で資料紹介」/3月17日『琉球新報』「さし絵人生40年ー金城安太郎さん」/『琉文手帖』「日本画家・金城安太郎」/5月『青い海』「新刊案内ー『琉文手帖』「日本画家・金城安太郎」

6月23日『朝日新聞』(大阪版)「沖縄のこころを本土にー大阪の西平守晴さん」
8月14日『毎日新聞』(大阪版)「反戦平和へ遍路10年ー沖縄出身の西平守晴さん」

9月10日、沖縄協会機関紙『沖縄』「21世紀へはばたけ沖縄青年ー新城栄徳さん」/12月7日『琉球新報』「俳人・末吉麦門冬が没して60年」/12月、『琉文手帖』2号「文人・末吉麦門冬」

1985年5月23日『沖縄タイムス』「30周年を迎える沖縄資料室ー大阪・西平守晴さんの個人文庫」


1988年11月 史海同人『史海』№6 新城栄徳「関西と沖縄」


10月11日『琉球新報』「駅前広場ー西平守晴さん」/10月31日『沖縄タイムス』「自宅に沖縄関係資料室ー石垣出身の西平守晴さん」/11月6日『朝日新聞』(大阪版)「自宅を改造して沖縄を学ぶ拠点にー大阪の西平守晴さん」/11月、『琉文手帖』3号「歌人・山城正忠」/12月15日、東京沖縄県人会機関紙『おきなわの声』「琉文手帖『歌人・山城正忠』を読む」

1986年1月15日、東京沖縄県人会機関紙『おきなわの声』「此処に人ありー新城栄徳さん」/4月15日『沖縄タイムス』「関西沖縄県人会機関誌『同胞』創刊号はガリ版刷りー新城栄徳さんが確認」/12月、沖縄県歌会『金真弓』新城栄徳「沖縄近代美術の流れと文学」/12月、『北谷町史』第2巻「争議にともなう財産調書」(新城栄徳寄贈)
1987年4月25日『琉球新報』「われらウチナンチュー西平守晴さん」/5月『新生美術』新城栄徳「浦崎永錫画伯美術史を語る」/9月、沖縄県立博物館「特別展・沖縄近代の絵画」(新城栄徳協力)
1987年6月 大阪沖縄県人会連合会40周年記念誌『雄飛ー大阪の沖縄』西平守晴「就学前教育と児童福祉」「沖縄関係資料室」
1987年9月15日、東京沖縄県人会機関紙『おきなわの声』新城栄徳「人物・沖縄近代美術略史」/10月1日『琉球新報』「明治の沖縄の画家一堂にー東京の島袋和幸さんが見つけ、新城栄徳さんが人物確認」

1988年2月19日『週刊レキオ』「先人の足跡を残したいー新城栄徳さん」/4月、緑林堂『琉球弧文献目録』新城栄徳「沖縄出版史ノート(戦前篇)」/6月『新沖縄文学』№76□新城栄徳「近代沖縄の新聞人群像」/7月4日『琉球新報』「首里那覇鳥瞰図の作者は阿嘉宗教ー新城栄徳さんが確認」/9月、南風原英育『南の島の新聞人』ひるぎ社(新城栄徳資料提供)/11月『史海』№6□新城栄徳「関西と沖縄」
大田静男 英育さん八重山の海南時報、沖縄タイムスで活躍されました。特に戦後八重山の混乱期に岳父の浦添為貴を助け、浦添亡き後は経営されました。戦後、八重山のルネサンスをつくられた立役者の一人です。同郷の南西印刷社長西平守栄と親しく、ひるぎ社のおきなわ文庫から沖縄の新聞人を出版されました。私は沖縄タイムの沖縄の言論人で八重山の先島新聞創刊者松下晩翠と八重山新報の比嘉統凞を書き終えていた頃で、手紙のやりとりもありました。い~や~懐かしい。東京にいかれても心の核は八重山でした。妻の叔母の夫は戦時中の悲劇を繰り返してはならないと西表島南風見の岩に忘勿石を刻んだ、識名信升です。
新川明さんは八重山で多感な時期を過ごされました。新川さんの厳し論法のなかにも、なぜか八重山の情緒を感じるのは私ひとりでしょうか。沖縄中を敵に回しているような人を社長にとは考えられないでしょう。南風原さんも凄いですね。タイム出版文化賞を新川さんからいただきました。緊張しましたね。栄徳さん懐かしいのが次々と出て来るので目がはなせないサー。
1989年4月18日『沖縄タイムス』「神山宗勲の小説『闘へる沖縄人』、新城栄徳さんが見つける」
7月、西平守晴、琉球新報の落ち穂を担当





10月、沖縄県立図書館「沖縄の同人誌展」(新城栄徳協力)/11月、『沖縄美術全集』(辞典・年表・文献委員ー新城栄徳)/11月30日『琉球新報』「琉球新報初代主筆『野間像』鮮明にー新城栄徳さんが見つける」/12月2日『琉球新報』「金口木舌ー新城栄徳と野間五造」

(上)1996年12月7日/大阪・大正駅前「居酒屋ゆんた」で、左から金城勇(演劇「人類館」上演を実現させたい会)、息子、諸見里芳美(演劇「人類館」上演を実現させたい会)、仲間恵子(大阪人権博物館学芸員)、崎浜盛喜(奈良沖縄県人会副会長)、右端がゆんた主人の玉城利則(関西沖縄青少年の集い「がじゅまるの会」初代会長。1981年、『ハイサイおきなわ』編集人、発行人は嘉手川重義(現大阪沖縄県人会連合会長)と夫人、真ん中の女性はお客さん。撮影・新城栄徳/(下)1996年12月8日/大阪港区・池島保育園(近鉄の野茂英雄投手も同園出身)階上で、左より西平久子、西平守晴夫妻、娘、後に息子。撮影・新城栄徳


1972年5月13日ー大阪『日本経済新聞』「民芸品・図書を守ろうー都島の『沖縄資料室』」
1973年5月14日ー大阪『朝日新聞』「守れ!沖縄の心と自然ー埋もれた文化掘起す」<
平良盛吉□→1991年1月『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)平良盛吉「村の先生」/平良盛吉(1890年8月28日~1977年6月28日)1912年、沖縄ではじめての総合文化誌『新沖縄』を創刊。琉球音楽研究家。『関西沖縄開発史』の著がある。□→2009年5月『うるまネシア』第10号/新城栄徳「失われた時を求めてー近鉄奈良線永和駅近くに平良盛吉氏が住んでおられた。息子が1歳のとき遊びに行ったら誕生祝をいただいた。袋は今もある」
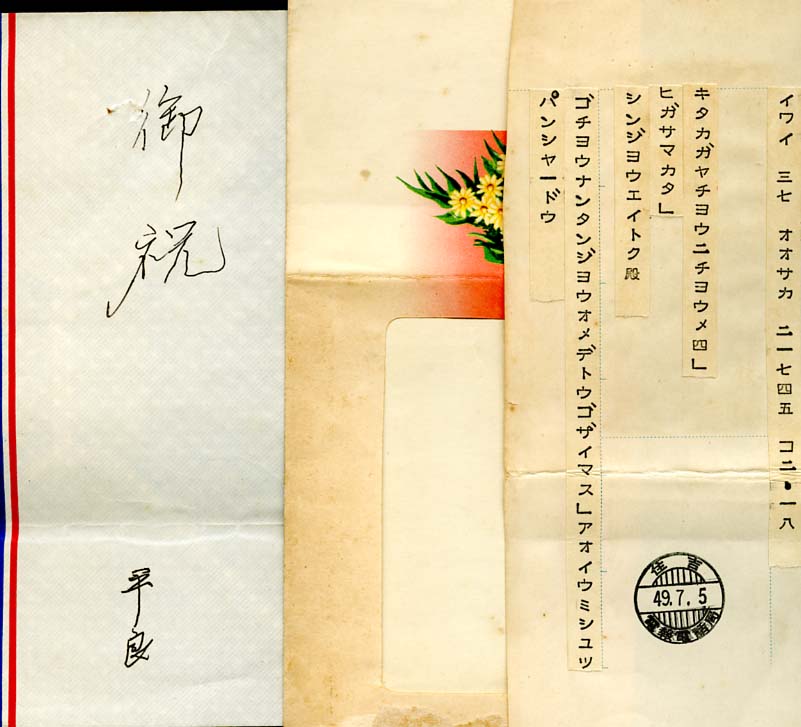




沖縄関係資料室



1962年、真喜志康忠優の関西公演のとき京都五条坂の河井寛次郎からの招待を受け西平守晴(沖縄関係資料室主宰)の案内で訪ねる。帰り河井作品を貰ったのは言うまでもない。
写真は左から西平守晴、真喜志康忠夫妻、河井寛次郎夫妻
1932年 東恩納寛惇、年末までに首里侯爵邸に通い2000冊の文献を読破
1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。
1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」
1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。
1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>
1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学
1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く
1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足
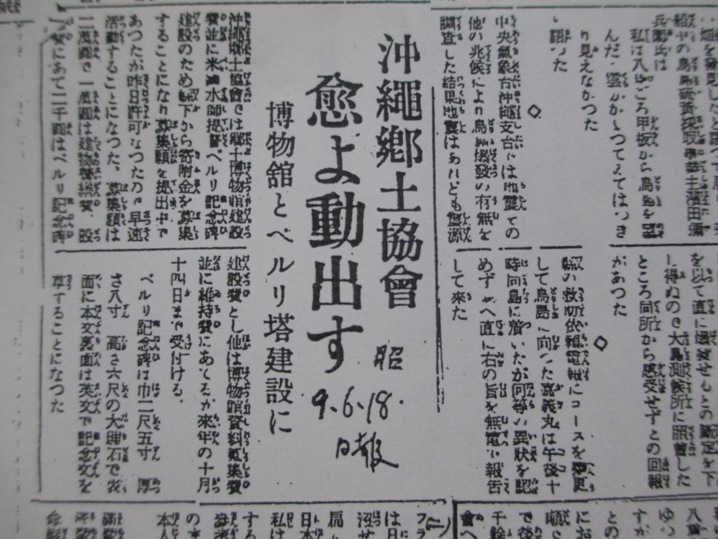
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社
1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式
1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。
□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社
1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)
1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観
1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観
1935年10月 『沖縄教育』第230号
□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部
安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、
1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観
1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」
1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会
1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ
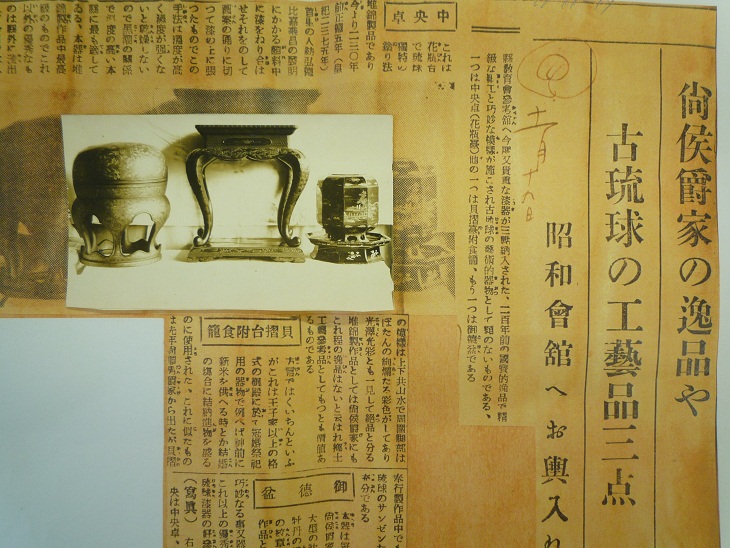
11月19日
1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」
1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観
1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。
1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」
1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。
1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)
1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事
4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)
1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館
1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁
1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。
公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。
又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。
1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」
1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転
1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」
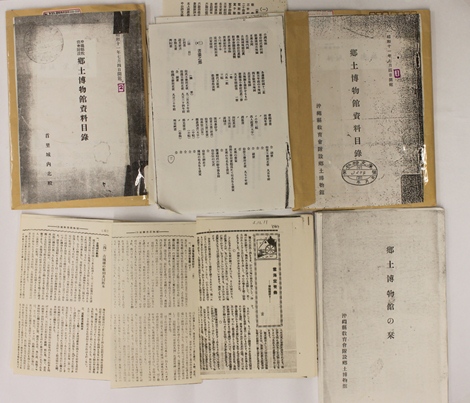
1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」
沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台
□図表之部
喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図
1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房
1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。
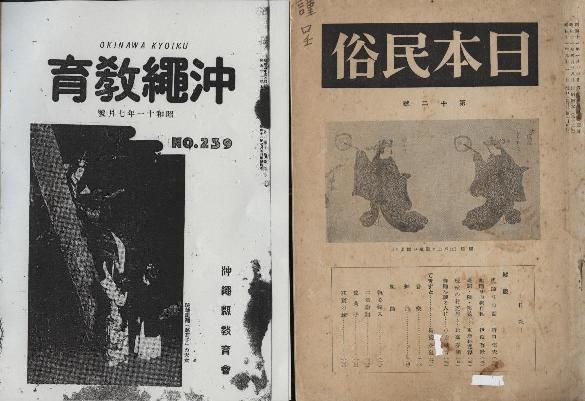
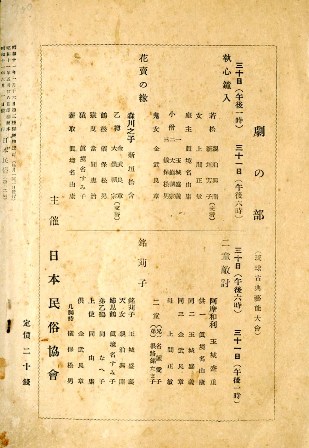
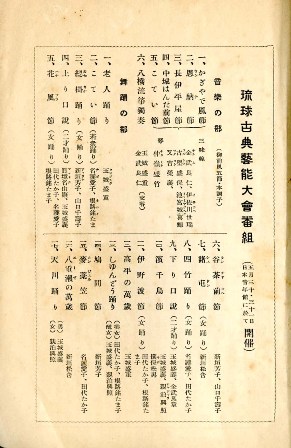
1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔
1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平
1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」
1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆
1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶
1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」
1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通
1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館
1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」
1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。
1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」
□
1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師
☆大田静男/ハンセン病者救済に奔走したキリスト教関係者ですね。花城武男は、八重山出身です。彼の出身地である大浜村にも村を動かして小屋を造り救済に当たりました。愛楽園が開設しないうちに本土へ移動となりました。戦後は郷里に帰り八重山農本党を結成し総裁となりました。その後、琉球食糧庁職員となり那覇へ出ました。世界救
1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式
1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」
1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席
1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列
1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」
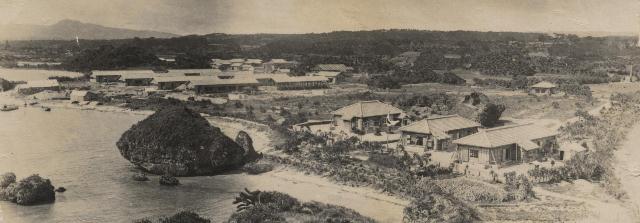
1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」
1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」
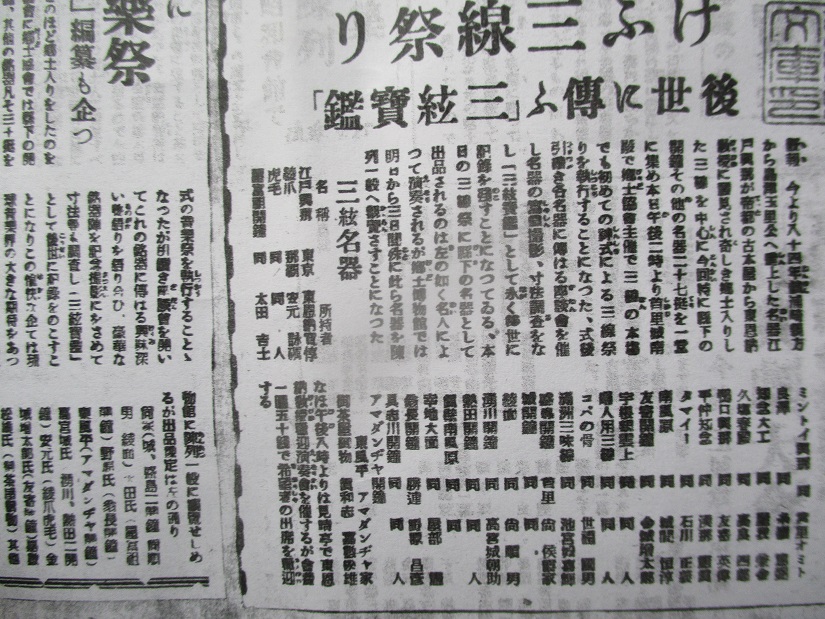
1939年8月5日
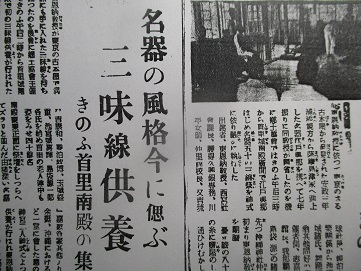
1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」
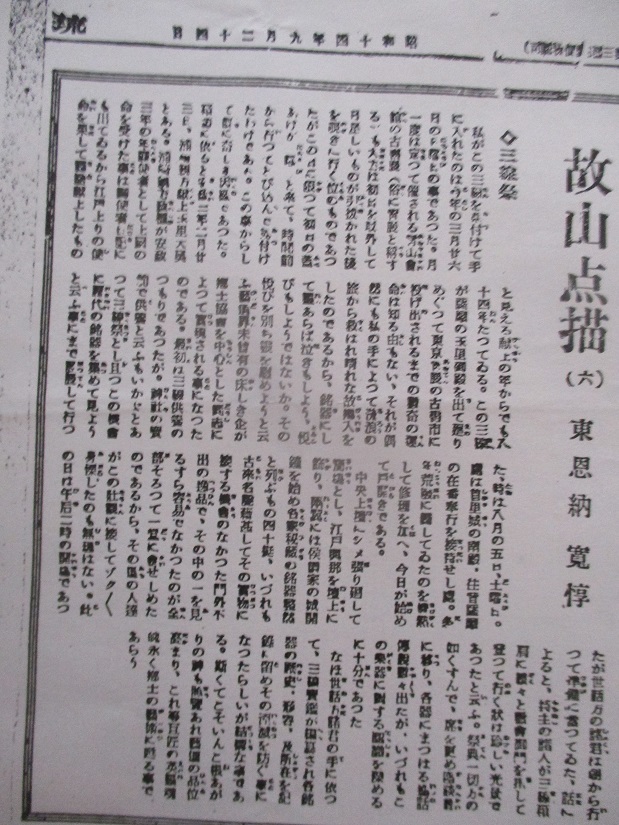
1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」
〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。
1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。
1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」
1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。
1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>
1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学
1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く
1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足
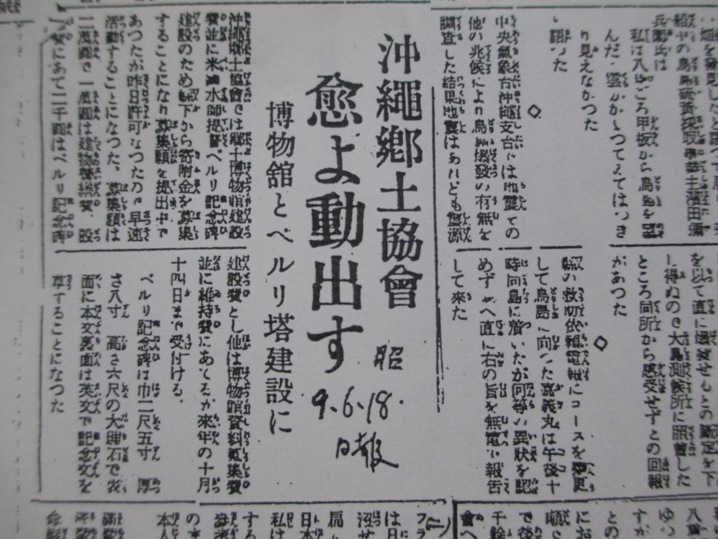
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社
1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式
1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。
□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社
1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)
1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観
1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観
1935年10月 『沖縄教育』第230号
□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部
安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、
1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観
1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」
1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会
1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ
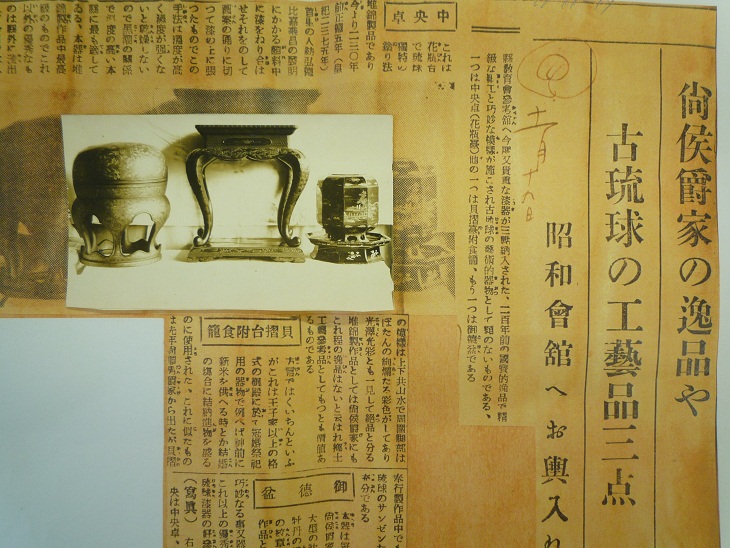
11月19日
1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」
1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観
1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。
1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」
1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。
1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)
1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事
4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)
1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館
1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁
1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。
公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。
又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。
1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」
1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転
1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」
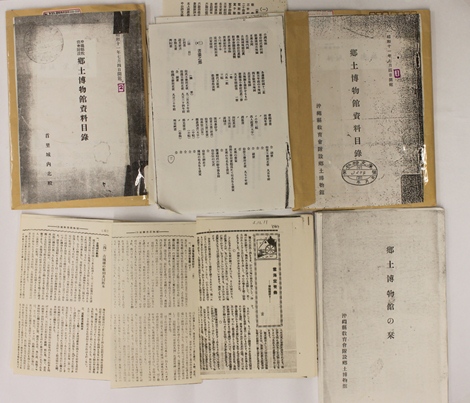
1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」
沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台
□図表之部
喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図
1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房
1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。
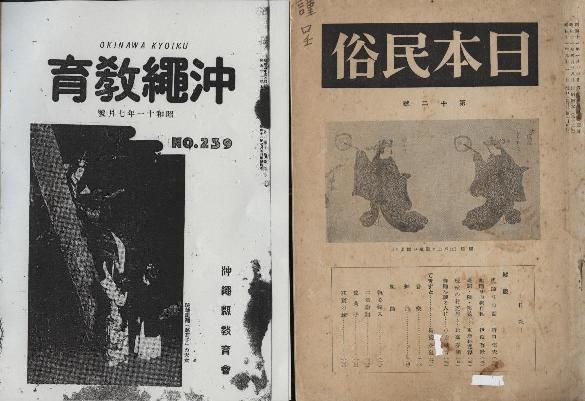
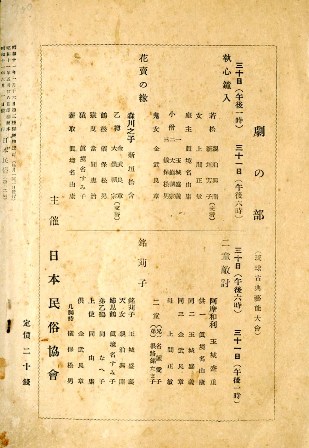
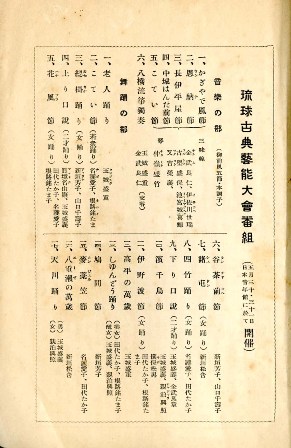
1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔
1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平
1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」
1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆
1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶
1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」
1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通
1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館
1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」
1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。
1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」
□

1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師
☆大田静男/ハンセン病者救済に奔走したキリスト教関係者ですね。花城武男は、八重山出身です。彼の出身地である大浜村にも村を動かして小屋を造り救済に当たりました。愛楽園が開設しないうちに本土へ移動となりました。戦後は郷里に帰り八重山農本党を結成し総裁となりました。その後、琉球食糧庁職員となり那覇へ出ました。世界救
1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式
1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」
1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席
1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列
1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」
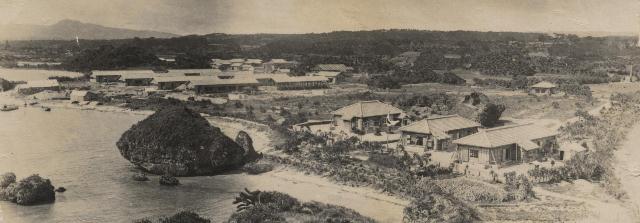
1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」
1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」
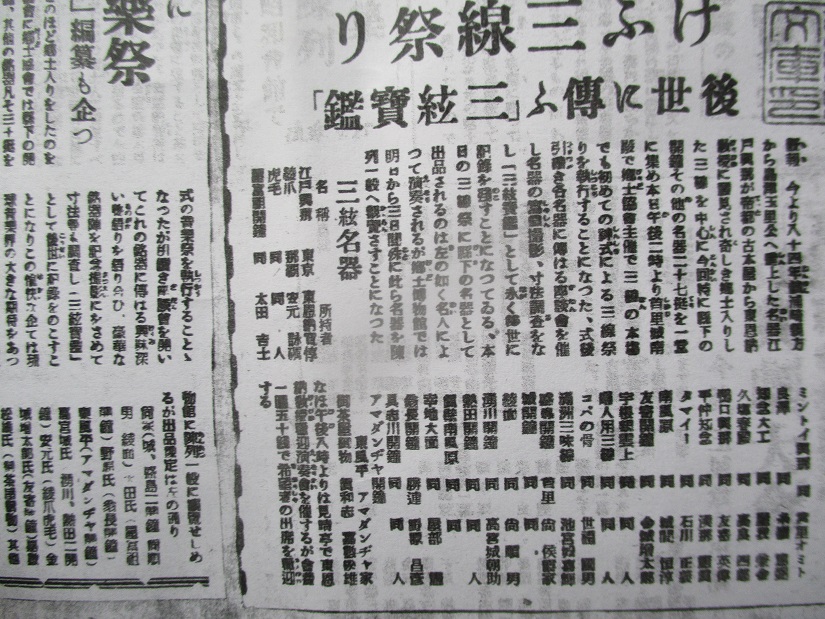
1939年8月5日
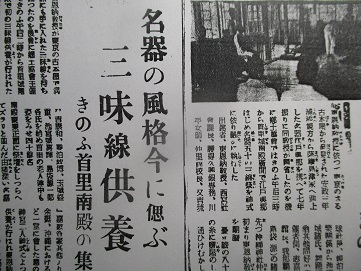
1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」
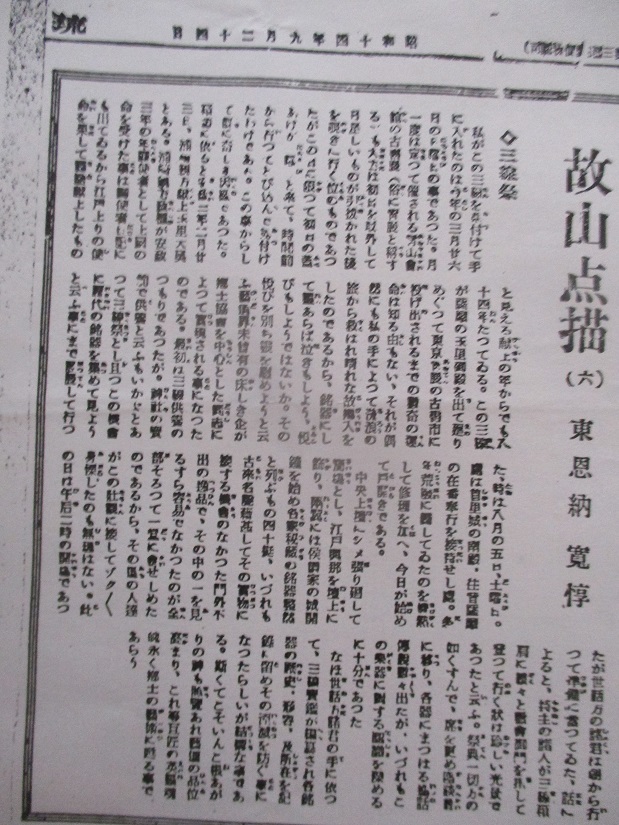
1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」
〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。
06/17: 東京/那覇っ子 石川正通(1897年~1982年)
1897年 9月25日ー沖縄県那覇区下泉町にて父正芳・母ツルの二男一女の長男として出生
1905年 那覇区立甲辰尋常小学校
5年生頃よりメソジスト教会牧師H・B・シュワルツ師に英語を学ぶ。この時の恩師が佐久本嗣宗。正通□佐久本先生は私達が甲辰尋常小学校の生徒であったとき、沖縄の天地創造や三山統一の歴史を熱心に説かれた。日本歴史には、蘇我物部、藤原菅原、南朝北朝、源平、豊臣徳川、勤王佐幕、といつも二つの対立しかないのに、沖縄には北山中山南山と三つの鼎立のあった史実を知って、二より三が多いというむつかしい算術まで知っていた私は、大沖縄帝国は広いなあと子供心に言い知れぬ誇りを感じたものである。→城間正八・佐久本嗣宗『隠れたる偉人ー城間正安翁ー』玻名城印刷所1932年5月
1911年 沖縄県立第一中学校入学
1915年 6月6日、那覇尋常高等小学校で琉球新報主催「学生雄弁大会」一中代表として石川正通英語演説「立てよ沖縄青年」と云う題下に流暢明快の弁を揮った。商業の玻名城政博は「統計上より本県の輸出入関係」を述べ警醒を促した。商業の渡久地政憑「立てよ日本青年」と題し日本の将来を考えよと提唱。徒弟の真栄城玄明は「犠牲的精神の涵養」と題し述べた。他に県農の比嘉盛宮、徒弟の中原政良、二中の安慶田正松、商業の宮城邦英「道徳の効果」、師範の石垣信知、一中の大浜用介「沖縄の宝庫は八重山なり」、徒弟の原秀樹、二中の前田豊、水産の東恩納寛成、一中の平野弘「冒険的日本男児たれ」、二中の嵩原佐久利、師範の佐久川饒、水産の勢頭眞佐、県農の田港朝全、師範の前堂貞烋が演説した。
石川正通〇南方熊楠は、山口沢之助校長と同郷和歌山県の大先輩、奇行に富む世界的大学者。山口校長が折に触れて話された、南方熊楠の逸話は一冊の本にも纏め得るほど、僕はあざやかに覚えている。山口校長の講義は、僕にとっては生理学でなく、熊楠学であったと、今でも有難く思っている。脱線学の妙味ここにあり。(1980年12月『養秀百年』)
1916年 一中退学、私立麻布中学校へ転校。3月29日、真玉橋朝起、武元朝朗、竹内弘道たちに見送られて沖縄丸で上京、甲板上で明大受験の城間恒昌、杉浦重剛校長の日本中学に転校する我部政達と3人で雑談に耽る。4月3日東京駅に着く。翌日、比屋根安定が大八車で荷物を一緒に運んでくれる。斎藤秀三郎校長の抜擢で正則英語学校講師となる。後に比嘉春潮(荻窪)、島袋盛敏(成城)、比屋根安定(青山学院構内)、仲吉良光(鶴見)、八幡一郎(東中野)、金城朝永(大塚)、石川正通(本郷)の7人で七星会結成する。
□斎藤秀三郎 【さいとう・ひでさぶろう】
生年: 慶応2.1.2 (1866.2.16) 没年: 昭和4.11.9 (1929)
明治大正時代の英語教育者。仙台生まれ。仙台藩士で運上方の斎藤永頼の長男。父の手ほどきで英語を学び,宮城英語学校を経て明治14(1881)年工部大学校に入学。在学中に英語教師のJ.M.ディクソンから強い感化を受けた。その後,岐阜,長崎,東京の一高などで英語を教えたが,明治29年正則英語学校設立以後,精力的に英語の文法書,読本の註解書,和英・英和辞書の編纂に従事した。その作文練習問題や和英辞典の用例には自伝的要素が濃厚。多磨墓地に墓がある。妹は明治女学校生だった斎藤ふゆ,次男は音楽家の斎藤秀雄,次女の婿は無教会伝道者の塚本虎二。<著作>『熟語本位英和中辞典』<参考文献>大村喜吉『斎藤秀三郎伝』 (コトバンクー加納孝代)
1918年 国民英学会講師、逗子開成中学校講師(ここでの教え子に、平野威馬雄、岡田時彦・女優茉莉子の父、徳山環ー歌手)、大成中学校講師、東洋商業学校講師

□平野威馬雄の本
1919年 保善商業学校講師(国語担当)、明治学院専門部講師(現明治学院大学)
1922年 第三版『全訳・シャーロックホームズ』越山堂。文部省中等教員英語科検定試験合格
1923年 8月ー沖縄県立第二中学校講堂で石川正通「英語講座」、伊佐三郎、赤嶺康成ら参加
1924年 東北帝国大学法文学部文学科入学。在学中、土井晩翠の寵愛を受けた。
土井晩翠
仙台市生れ。本名、土井(つちい)林吉。姓は1934年から‘どい’という通常音を容認。1894年、東大英文科に入学、
同年末に結成された帝国文学会に加入。その機関誌「帝国文学」に1895年11月から新体詩を載せ始め 翌年3月から編
集にも携わり、1898年、ユゴーの詩集『光と影』の序文を訳載した。この年、東京音楽学校の依頼で『荒城の月』を
書いた。大学卒業後 1901年6月に私費で外遊、ロンドンで夏目漱石と同居し、滝廉太郎とも会っている。1904年10月
までに至る欧州諸国での感興はその詩作の主要なモチーフとなった。「帝国文学」などに寄せられた諸詩篇は『天地
有情』(1899)『暁鐘』(1901)『東海遊子吟』(1906)の3集にまとめられた。 その作は一貫して文語で書かれ、漢語利
用の効果も目立ち、はじめ七五調によったが、さらに他の定形にも手を染め、自由詩の試作にも及んでいる。1945年
7月、戦災によって万巻の蔵書を、また1948年までに妻子のすべてを失い、没年まで孤寂の時を過した。前記3集の他
『曙光』(1919)、『天馬の道に』(1920)、『アジアに叫ぶ』(1932)、『神風』(1936)があり、他に数種の選集も出た。
尚、唱歌や校歌の類も多く、短歌の制作もあって後に『晩翠歌抄』(1949)に収められた。/「日本現代詩辞典」
1925年1月29日『沖縄朝日新聞』石川正通「朝日歌壇ー雪の●日本/冬空に茜さす日は登りたり 小鳥よ啼け雪遠き間に/この寒さいよ つのらば川の音も 氷の下にひそまるらんか/日の照りつ雪の舞ひ舞ふ冬空に こだまを返し鶏はひた鳴く/久方に映えし朝日ををろがむと 窓を開けば雪片の舞ひ入る/変装の雪は悲しも舞ひ舞へど このたまゆらの白雪にして/憎らしく可愛きものよじやれ雪は 我が唇に止りては消ゆ/冬籠る我が部屋ぬちに炭聞きつ 幼き●の友想ふなり」
1928年 東北帝国大学法文学部国文科卒業。卒論「近松門左衛門の世話浄瑠璃について」。国民英学会講師に復職、京華高等学校教諭、日本女子高等学院英文学科教授
1929年 雑誌『イギリス文学』に「ヘルンの『沙翁論』」
1933年 『南島』1月1日□石川正通氏ー伊波普猷先生と共力で近く日英両文の沖縄案内を発刊する由
『南島』4月5日□石川正通「三十七歳の曙光」「玉城朝薫の二百年祭に當りて」
『南島』8月5日□石川正通氏ー7月24日、澄子夫人同伴帰郷 約1カ月滞在予定、二高女で英語講習会開催□石川正通「夏は故郷で=鎖夏漫筆=」
1934年 『南島』8月1日□石川正通「友の首途を祝して故郷を語る=武元朝朗・國吉休微両君を叱咤する=(略)最近出た某書店の百科辞典を引いて見たが、おもろ、蔡温、程順則、尚泰侯爵も出て居ない。沢田正二郎、田健次郎等は写真まで出て居る。土田杏村が第二の万葉集と言った『おもろ』も国語国文学校の士すら全般的に知られて居ない。」
1934年 青山学院専門部講師
1936年1月 『沖縄教育』(有銘興昭)石川正通「東京生活二十年」「年賀集ー下村宏、山城東榮、新屋敷幸繁、石川正通、川出麻須美、北里闌、アブラタニ キクジロー、村尾三郎、辻木、末原貫一郎、青山於菟、堀池英一、石井漠、田場盛義、島袋盛敏、安部金剛・安部ツヤコ」
1938年

1939年


このころ母校一中で講演
1939年 1月『月刊琉球』石川正通「傷心の友に」

1939年1月1日『琉球新報』石川正通「幽明を境して=太田朝敷先生と語る=(略)皮肉屋の斎藤緑雨君と飲んで居た末吉麦門冬君’娑婆からは十 億土一またぎと駄句って’」

1905年 那覇区立甲辰尋常小学校
5年生頃よりメソジスト教会牧師H・B・シュワルツ師に英語を学ぶ。この時の恩師が佐久本嗣宗。正通□佐久本先生は私達が甲辰尋常小学校の生徒であったとき、沖縄の天地創造や三山統一の歴史を熱心に説かれた。日本歴史には、蘇我物部、藤原菅原、南朝北朝、源平、豊臣徳川、勤王佐幕、といつも二つの対立しかないのに、沖縄には北山中山南山と三つの鼎立のあった史実を知って、二より三が多いというむつかしい算術まで知っていた私は、大沖縄帝国は広いなあと子供心に言い知れぬ誇りを感じたものである。→城間正八・佐久本嗣宗『隠れたる偉人ー城間正安翁ー』玻名城印刷所1932年5月
1911年 沖縄県立第一中学校入学
1915年 6月6日、那覇尋常高等小学校で琉球新報主催「学生雄弁大会」一中代表として石川正通英語演説「立てよ沖縄青年」と云う題下に流暢明快の弁を揮った。商業の玻名城政博は「統計上より本県の輸出入関係」を述べ警醒を促した。商業の渡久地政憑「立てよ日本青年」と題し日本の将来を考えよと提唱。徒弟の真栄城玄明は「犠牲的精神の涵養」と題し述べた。他に県農の比嘉盛宮、徒弟の中原政良、二中の安慶田正松、商業の宮城邦英「道徳の効果」、師範の石垣信知、一中の大浜用介「沖縄の宝庫は八重山なり」、徒弟の原秀樹、二中の前田豊、水産の東恩納寛成、一中の平野弘「冒険的日本男児たれ」、二中の嵩原佐久利、師範の佐久川饒、水産の勢頭眞佐、県農の田港朝全、師範の前堂貞烋が演説した。
石川正通〇南方熊楠は、山口沢之助校長と同郷和歌山県の大先輩、奇行に富む世界的大学者。山口校長が折に触れて話された、南方熊楠の逸話は一冊の本にも纏め得るほど、僕はあざやかに覚えている。山口校長の講義は、僕にとっては生理学でなく、熊楠学であったと、今でも有難く思っている。脱線学の妙味ここにあり。(1980年12月『養秀百年』)
1916年 一中退学、私立麻布中学校へ転校。3月29日、真玉橋朝起、武元朝朗、竹内弘道たちに見送られて沖縄丸で上京、甲板上で明大受験の城間恒昌、杉浦重剛校長の日本中学に転校する我部政達と3人で雑談に耽る。4月3日東京駅に着く。翌日、比屋根安定が大八車で荷物を一緒に運んでくれる。斎藤秀三郎校長の抜擢で正則英語学校講師となる。後に比嘉春潮(荻窪)、島袋盛敏(成城)、比屋根安定(青山学院構内)、仲吉良光(鶴見)、八幡一郎(東中野)、金城朝永(大塚)、石川正通(本郷)の7人で七星会結成する。
□斎藤秀三郎 【さいとう・ひでさぶろう】
生年: 慶応2.1.2 (1866.2.16) 没年: 昭和4.11.9 (1929)
明治大正時代の英語教育者。仙台生まれ。仙台藩士で運上方の斎藤永頼の長男。父の手ほどきで英語を学び,宮城英語学校を経て明治14(1881)年工部大学校に入学。在学中に英語教師のJ.M.ディクソンから強い感化を受けた。その後,岐阜,長崎,東京の一高などで英語を教えたが,明治29年正則英語学校設立以後,精力的に英語の文法書,読本の註解書,和英・英和辞書の編纂に従事した。その作文練習問題や和英辞典の用例には自伝的要素が濃厚。多磨墓地に墓がある。妹は明治女学校生だった斎藤ふゆ,次男は音楽家の斎藤秀雄,次女の婿は無教会伝道者の塚本虎二。<著作>『熟語本位英和中辞典』<参考文献>大村喜吉『斎藤秀三郎伝』 (コトバンクー加納孝代)
1918年 国民英学会講師、逗子開成中学校講師(ここでの教え子に、平野威馬雄、岡田時彦・女優茉莉子の父、徳山環ー歌手)、大成中学校講師、東洋商業学校講師

□平野威馬雄の本
1919年 保善商業学校講師(国語担当)、明治学院専門部講師(現明治学院大学)
1922年 第三版『全訳・シャーロックホームズ』越山堂。文部省中等教員英語科検定試験合格
1923年 8月ー沖縄県立第二中学校講堂で石川正通「英語講座」、伊佐三郎、赤嶺康成ら参加
1924年 東北帝国大学法文学部文学科入学。在学中、土井晩翠の寵愛を受けた。
土井晩翠
仙台市生れ。本名、土井(つちい)林吉。姓は1934年から‘どい’という通常音を容認。1894年、東大英文科に入学、
同年末に結成された帝国文学会に加入。その機関誌「帝国文学」に1895年11月から新体詩を載せ始め 翌年3月から編
集にも携わり、1898年、ユゴーの詩集『光と影』の序文を訳載した。この年、東京音楽学校の依頼で『荒城の月』を
書いた。大学卒業後 1901年6月に私費で外遊、ロンドンで夏目漱石と同居し、滝廉太郎とも会っている。1904年10月
までに至る欧州諸国での感興はその詩作の主要なモチーフとなった。「帝国文学」などに寄せられた諸詩篇は『天地
有情』(1899)『暁鐘』(1901)『東海遊子吟』(1906)の3集にまとめられた。 その作は一貫して文語で書かれ、漢語利
用の効果も目立ち、はじめ七五調によったが、さらに他の定形にも手を染め、自由詩の試作にも及んでいる。1945年
7月、戦災によって万巻の蔵書を、また1948年までに妻子のすべてを失い、没年まで孤寂の時を過した。前記3集の他
『曙光』(1919)、『天馬の道に』(1920)、『アジアに叫ぶ』(1932)、『神風』(1936)があり、他に数種の選集も出た。
尚、唱歌や校歌の類も多く、短歌の制作もあって後に『晩翠歌抄』(1949)に収められた。/「日本現代詩辞典」
1925年1月29日『沖縄朝日新聞』石川正通「朝日歌壇ー雪の●日本/冬空に茜さす日は登りたり 小鳥よ啼け雪遠き間に/この寒さいよ つのらば川の音も 氷の下にひそまるらんか/日の照りつ雪の舞ひ舞ふ冬空に こだまを返し鶏はひた鳴く/久方に映えし朝日ををろがむと 窓を開けば雪片の舞ひ入る/変装の雪は悲しも舞ひ舞へど このたまゆらの白雪にして/憎らしく可愛きものよじやれ雪は 我が唇に止りては消ゆ/冬籠る我が部屋ぬちに炭聞きつ 幼き●の友想ふなり」
1928年 東北帝国大学法文学部国文科卒業。卒論「近松門左衛門の世話浄瑠璃について」。国民英学会講師に復職、京華高等学校教諭、日本女子高等学院英文学科教授
1929年 雑誌『イギリス文学』に「ヘルンの『沙翁論』」
1933年 『南島』1月1日□石川正通氏ー伊波普猷先生と共力で近く日英両文の沖縄案内を発刊する由
『南島』4月5日□石川正通「三十七歳の曙光」「玉城朝薫の二百年祭に當りて」
『南島』8月5日□石川正通氏ー7月24日、澄子夫人同伴帰郷 約1カ月滞在予定、二高女で英語講習会開催□石川正通「夏は故郷で=鎖夏漫筆=」
1934年 『南島』8月1日□石川正通「友の首途を祝して故郷を語る=武元朝朗・國吉休微両君を叱咤する=(略)最近出た某書店の百科辞典を引いて見たが、おもろ、蔡温、程順則、尚泰侯爵も出て居ない。沢田正二郎、田健次郎等は写真まで出て居る。土田杏村が第二の万葉集と言った『おもろ』も国語国文学校の士すら全般的に知られて居ない。」
1934年 青山学院専門部講師
1936年1月 『沖縄教育』(有銘興昭)石川正通「東京生活二十年」「年賀集ー下村宏、山城東榮、新屋敷幸繁、石川正通、川出麻須美、北里闌、アブラタニ キクジロー、村尾三郎、辻木、末原貫一郎、青山於菟、堀池英一、石井漠、田場盛義、島袋盛敏、安部金剛・安部ツヤコ」
1938年


1939年



このころ母校一中で講演
1939年 1月『月刊琉球』石川正通「傷心の友に」

1939年1月1日『琉球新報』石川正通「幽明を境して=太田朝敷先生と語る=(略)皮肉屋の斎藤緑雨君と飲んで居た末吉麦門冬君’娑婆からは十 億土一またぎと駄句って’」

02/27: 雑誌『おきなわ』/比屋根安定
比屋根安定 ひやね-あんてい1892-1970 大正-昭和時代の宗教史学者。
明治25年10月3日生まれ。16歳でメソジスト派に入信。キリスト教の布教と宗教研究に生涯をささげる。青山学院神学部,東京神学大,日本ルーテル神学大などの教授をつとめた。昭和45年7月10日死去。77歳。東京出身。東京帝大卒。著作に「日本宗教史」「日本基督教史」など(コトバンク)

1950年11月 仲井間宗裕・伊佐栄二『沖縄と人物』
□著1935年12月ー比屋根安定『五餅二魚』日曜世界社「本書は随筆集である。所謂随筆は、閑文学を以って称せられるが、予は、多少のレイゾン・デエトルを具したつもりである。我国の基督教文壇に、説教あり、神学論あり、聖書講解あり、信仰談あり、時評あり、伝記もあるが、唯々随筆に至っては、殆ど見なかった。然し随筆なき基督教文壇は、前菜なき料理の如くである」/1937年3月ー比屋根安定『世界巡礼記』教文館「人生も亦、逆旅である。本朝の『朝比奈三郎廻島記』、唐土の『西遊記』、西洋の『ピルグリムス・プログレス』の如きは、紀行文的稗史を籍りて、実は人生行程を敍したるに外ならない。この『世界巡礼記』は、所謂紀行文であると共に、これも亦予が半歳に亘れる未曾有の生活記録を兼ねている」

比屋根安定の本
1945年6月沖縄戦が終って、その11月11日東京に沖縄人連盟が結成された時、比嘉春潮もその発企人の一人であった。その翌々1947年の8月15日芝労働会館で沖縄連盟総本部の部長会議が開かれたとき、言語文学部の宮良当壮氏、民族史学部の島袋源七氏、宗教部の比屋根安定氏が沖縄連盟内に沖縄文化協会なる部局を置くことを決定し、宮良氏がその会長格をつとめることになった。同時期、比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、島袋盛敏、金城朝永、宮良当壮(後に崎浜秀明も参加)は毎月一回、仲原君を中心におもろ研究会も開かれた。

アメリカ軍の爆撃で廃墟と化したキリスト教会(1950年11月 仲井間宗裕『沖縄と人物』同刊行会)
○那覇市歴史博物館の2010年図録「本土人が見た1950年代の沖縄」に、米軍爆撃で廃墟と化した那覇久米キリスト教会の写真がある。米軍兵士はキリスト教会を目の敵にしているようで、よっぽど十字架がにくらしかったにちがいない。これは下記の原爆の事例でも分かる。
★浦上教会 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1945年8月9日、原爆投下により、爆心地から至近距離に在った浦上天主堂はほぼ原形を留めぬまでに破壊された(また、原爆投下時間に聖母被昇天を迎えて、ゆるしの秘跡(告解)が行われていた。そのため中にいた神父を始めとする信者の全員が死亡している)。
明治25年10月3日生まれ。16歳でメソジスト派に入信。キリスト教の布教と宗教研究に生涯をささげる。青山学院神学部,東京神学大,日本ルーテル神学大などの教授をつとめた。昭和45年7月10日死去。77歳。東京出身。東京帝大卒。著作に「日本宗教史」「日本基督教史」など(コトバンク)

1950年11月 仲井間宗裕・伊佐栄二『沖縄と人物』
□著1935年12月ー比屋根安定『五餅二魚』日曜世界社「本書は随筆集である。所謂随筆は、閑文学を以って称せられるが、予は、多少のレイゾン・デエトルを具したつもりである。我国の基督教文壇に、説教あり、神学論あり、聖書講解あり、信仰談あり、時評あり、伝記もあるが、唯々随筆に至っては、殆ど見なかった。然し随筆なき基督教文壇は、前菜なき料理の如くである」/1937年3月ー比屋根安定『世界巡礼記』教文館「人生も亦、逆旅である。本朝の『朝比奈三郎廻島記』、唐土の『西遊記』、西洋の『ピルグリムス・プログレス』の如きは、紀行文的稗史を籍りて、実は人生行程を敍したるに外ならない。この『世界巡礼記』は、所謂紀行文であると共に、これも亦予が半歳に亘れる未曾有の生活記録を兼ねている」

比屋根安定の本
1945年6月沖縄戦が終って、その11月11日東京に沖縄人連盟が結成された時、比嘉春潮もその発企人の一人であった。その翌々1947年の8月15日芝労働会館で沖縄連盟総本部の部長会議が開かれたとき、言語文学部の宮良当壮氏、民族史学部の島袋源七氏、宗教部の比屋根安定氏が沖縄連盟内に沖縄文化協会なる部局を置くことを決定し、宮良氏がその会長格をつとめることになった。同時期、比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、島袋盛敏、金城朝永、宮良当壮(後に崎浜秀明も参加)は毎月一回、仲原君を中心におもろ研究会も開かれた。

アメリカ軍の爆撃で廃墟と化したキリスト教会(1950年11月 仲井間宗裕『沖縄と人物』同刊行会)
○那覇市歴史博物館の2010年図録「本土人が見た1950年代の沖縄」に、米軍爆撃で廃墟と化した那覇久米キリスト教会の写真がある。米軍兵士はキリスト教会を目の敵にしているようで、よっぽど十字架がにくらしかったにちがいない。これは下記の原爆の事例でも分かる。
★浦上教会 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1945年8月9日、原爆投下により、爆心地から至近距離に在った浦上天主堂はほぼ原形を留めぬまでに破壊された(また、原爆投下時間に聖母被昇天を迎えて、ゆるしの秘跡(告解)が行われていた。そのため中にいた神父を始めとする信者の全員が死亡している)。
1950年6月 雑誌『おきなわ』高嶺明達「南島風土記に奇すー東恩納先生は又『自分は最後の沖縄人を以て自ら任ずる者である』と云われた。私も亦沖縄人、而も善かれ悪しかれ最も日本化した沖縄人を秘かに任ずる者である。先生に云わせれば、そんなのは沖縄人でないと云われるかも知れないが。自分のことを申し上げ過ぎて恐縮だが、私は那覇の久米村で生まれた・・・」
1952年11月 高嶺明達『太平洋の孤児 米国統治下の琉球』沖縄通商


高嶺明達
高嶺明達 (たかみね・めいたつ)
1898~1966(明治31.8.22~昭和41.11.8) 官吏。旧姓・楚南。那覇市久米生まれ。東京帝大卒後、商工省入り。軍需省総務局長など歴任。戦後、B級戦犯で公職追放。復帰前の沖縄と政府のパイプ役を果たす。→沖縄コンパクト事典
妻・芳子は岸本賀昌の娘

1950年9月 雑誌『おきなわ』第1巻第5号 高里良恭「敗残者わが祖父」

1966年『現代沖縄人物三千人』沖縄タイムス社「高里良恭」
1951年1月 雑誌『おきなわ』第2巻第1号 新垣淑明「学園回顧/一中篇ー起て中山の健男児」

1966年『現代沖縄人物三千人』沖縄タイムス社
1993年5月1日 『おきなわの声』第161号 新垣淑明「散歩道/虎頭山周辺①」
1993年6月15日 『おきなわの声』第162号 新垣淑明「散歩道/虎頭山周辺②」
1952年11月 高嶺明達『太平洋の孤児 米国統治下の琉球』沖縄通商


高嶺明達
高嶺明達 (たかみね・めいたつ)
1898~1966(明治31.8.22~昭和41.11.8) 官吏。旧姓・楚南。那覇市久米生まれ。東京帝大卒後、商工省入り。軍需省総務局長など歴任。戦後、B級戦犯で公職追放。復帰前の沖縄と政府のパイプ役を果たす。→沖縄コンパクト事典
妻・芳子は岸本賀昌の娘

1950年9月 雑誌『おきなわ』第1巻第5号 高里良恭「敗残者わが祖父」

1966年『現代沖縄人物三千人』沖縄タイムス社「高里良恭」
1951年1月 雑誌『おきなわ』第2巻第1号 新垣淑明「学園回顧/一中篇ー起て中山の健男児」

1966年『現代沖縄人物三千人』沖縄タイムス社
1993年5月1日 『おきなわの声』第161号 新垣淑明「散歩道/虎頭山周辺①」
1993年6月15日 『おきなわの声』第162号 新垣淑明「散歩道/虎頭山周辺②」
04/10: 関西と沖縄②
『琉球新報』2016年9月27日「ひやみかち大阪<上>」○「私たちは自分たちの手で自分を、兄弟・姉妹を守る」。沖縄の若者たち(がじゅまるの会①)約250人が立ち上がった。若者たちは「根底に沖縄差別がある」と考えた。(略)第一回沖縄青年の祭りから42年。名勝替えした「エイサー祭り」は大正区内外から延べ約2万人集める一大イベントにまで成長した。県人たちへの差別への苦悩と、差別をはねのけようと打って出た若者らの思いに共感が広がっている。




「がじゅまるの会」資料
1975年9月14日ーパーランクーの音が大阪大正区に鳴り響く
1977年10月『青い海』67号 「大阪の空にエイサーのリズムが響きわたるー第三回沖縄青年祭り。9月15日、尼埼市。18日、大正区千島グラウンドで山端立昌大阪沖縄連合会副会長挨拶、東京ゆうなの会、愛知沖縄青年会のあいさつ、彫刻家・金城実もあいさつ。見物の人も含めて約150人が参加」「儀間比呂志展、沖縄物産センターで開かる」
1978年6月『青い海』74号 永峰真名「苦悩を乗り越える沖縄青年たちーIさん問題とがじゅまるの会ー」/儀間比呂志、安谷屋長也、金城順亮、浦添正光、島袋純子「<座談会>地域に根ざした児童文化を」


エイサー会場で走りまわるフトシ君(今のFutoshiの片鱗? )とコウ君


Rabu Barroco[パフォーマンスアートフェスティバル2019の連帯]一緒にいる人: Juan Pablo Martirez、Chumpon Apisuk、Graciela Ovejero Postigo、Warattaya Chaisin、Prashasti Wilujeng Putri、Futoshi Moromizato/Boyet De Mesa休む時間だけど, まずグルーピー 友達: Futoshi Moromizato、Boyet De Mesa????


2019-9 Randy Valiente一緒にいる人: Boyet De Mesa、Rica Reyes-dela Cruz


2019-9 沖縄は友達と沖縄ミルクティーを味わう.Mv Munoz Prashasti Wilujeng Putri Warattaya Chaisin Mark Stephen Artillero Angelo Chua
1978年10月 雑誌『青い海』77号 「那覇市八汐荘ホール 賑わった出版祝賀会”鳥類館〟儀間比呂志『七がつエイサー』『りゅうとにわとり』、新川明『新南島風土記』、川満信一『沖縄・根からの問い』3氏を展示して大騒ぎ。豊川善一、北島角子、高江洲義寛、幸喜良秀、海勢頭豊、南条喜久子、森田吉子、玉城秀子、嶋袋浩(福木詮)ら参加」「パーランク高らかにー第四回沖縄青少年の祭り」


1986年4月 『小説推理』津野創一「響け!パーランクー」


2004年9月 儀間比呂志『おきなわのえほん エイサーガーエー』ルック


「第30回記念エイサー祭り」会場の儀間さん。金城馨と談笑
2018年9月1日ー嘉陽夫妻、儀間比呂志展を鑑賞


写真ーミュージアムショップ「ゆいむい」 で池宮城啓子さん、嘉陽宗博氏/左から金城美奈子さん、仲原穣氏、嘉陽宗博氏




1978年7月 儀間比呂志『七がつエイサー』福音館書店




1970年9月 大江健三郎『沖縄ノート』岩波書店 儀間比呂志「挿絵カット」


Ko Yoshioka2023年3月14日 · 『日兵逆殺』墓石の裏に刻まれた四つの大文字。日本兵に虐殺された、という衝撃的な文字だ。日付は1945年5月22日。この日は、沖縄戦史によれば、第32軍(沖縄守備軍)が首里の司令部壕を棄て南部撤退を決定した、とある。降伏を拒否した日本軍が、逃げ惑う住民を道連れに、最後の決戦場として南部、糸満の地を選んだ日だ。『日兵逆殺』は、その日のどこかで起きたことなのだろう。
墓石の表には「弓太郎」「タガ子」というふたりの名前が並んでいる。検索してもなかなかヒットせず、どういう人物だったのかをネット上で調べていくのは、いまも厳しい。私がこのふたりの存在と『日兵逆殺』の墓石を知ったのは、1972年、沖縄が復帰する2ヶ月前、雑誌『世界』の取材で大江健三郎さんとご一緒したときだった。弓太郎とは新垣弓太郎のことで、タガ子はその妻。「逆殺」されたのは妻、タガ子だと知った。
大江さんの話から、墓碑の四文字の由来を理解したとき、心臓が高鳴ったことを覚えている。それは、沖縄戦の真実のひとつがこの四文字のひとつひとつに込められているとリアルに想像できたからだった。撮影は1972年3月21日。南風原村にて。墓石の文字を書き写す在りし日の大江健三郎さん。36歳。


1971年11月 『青い海』8号 宜保栄治郎「沖縄のエイサーー勇壮なパーランクーの響き」



1997年11月 宜保榮治郎『エイサー 沖縄の盆踊り』那覇出版社/1998年3月 沖縄市企画部平和文化振興課『エイサー360°ー歴史と現在ー』沖縄全島エイサーまつり実行委員会


2018年11月21日ー儀間比呂志展で、ひろみ/2019年2月 ギャラリー象で、妙子さん、あけみ
2001年3月ー『けーし風』第30号「大阪のなかの沖縄」(屋良朝光、金城馨、諸見里芳美、仲間恵子、玉城利則、崎浜盛喜、伊差川寛、金城良明、金城宗和、金城正樹、我謝実、上地武、當山清朝、大城康代)
1956年7月1日ー大阪市中之島公園で「沖縄土地取上げ反対国民集会」
1956年7月7日ー『琉球新報』「沖縄問題在京郷土人の声ー大浜信泉、神山政良、山之口ばく、比嘉良篤、伊江朝助、尚裕」
1956年7月8日ー『琉球新報』「浅沼社会党書記長ー沖縄の『ハワイ化』阻止」
1956年7月10日ー『琉球新報』「沖縄を守ろうー仙台河北新報発・宮城県庁前広場で沖縄問題解決促進宮城県大会」
1958年8月2日ー『琉球新報』「死の灰 ソ連核実験でふえる」
1958年8月15日ー『琉球新報』「恐るべき放射線の影響ー人類の将来に危険」
1968年1月5日ー『毎日グラフ』「本土の中の沖縄(南風サークル/大城真栄/普久原朝喜/金城良明)」「万国博へ全力投球(岡本太郎「抵抗あるものを」)」


金城良明氏

中央が金城良明氏
1971年4月ー『沖縄差別』№1金城良明「大正区で生まれた、2世の声を聞いてほしい」
1971年8月ー『沖縄差別』№2金城良明「沖縄差別とわたし」

写真左から諸見里宗博氏、新城栄徳、金城良明氏




「がじゅまるの会」資料
1975年9月14日ーパーランクーの音が大阪大正区に鳴り響く
1977年10月『青い海』67号 「大阪の空にエイサーのリズムが響きわたるー第三回沖縄青年祭り。9月15日、尼埼市。18日、大正区千島グラウンドで山端立昌大阪沖縄連合会副会長挨拶、東京ゆうなの会、愛知沖縄青年会のあいさつ、彫刻家・金城実もあいさつ。見物の人も含めて約150人が参加」「儀間比呂志展、沖縄物産センターで開かる」
1978年6月『青い海』74号 永峰真名「苦悩を乗り越える沖縄青年たちーIさん問題とがじゅまるの会ー」/儀間比呂志、安谷屋長也、金城順亮、浦添正光、島袋純子「<座談会>地域に根ざした児童文化を」


エイサー会場で走りまわるフトシ君(今のFutoshiの片鱗? )とコウ君


Rabu Barroco[パフォーマンスアートフェスティバル2019の連帯]一緒にいる人: Juan Pablo Martirez、Chumpon Apisuk、Graciela Ovejero Postigo、Warattaya Chaisin、Prashasti Wilujeng Putri、Futoshi Moromizato/Boyet De Mesa休む時間だけど, まずグルーピー 友達: Futoshi Moromizato、Boyet De Mesa????


2019-9 Randy Valiente一緒にいる人: Boyet De Mesa、Rica Reyes-dela Cruz


2019-9 沖縄は友達と沖縄ミルクティーを味わう.Mv Munoz Prashasti Wilujeng Putri Warattaya Chaisin Mark Stephen Artillero Angelo Chua
1978年10月 雑誌『青い海』77号 「那覇市八汐荘ホール 賑わった出版祝賀会”鳥類館〟儀間比呂志『七がつエイサー』『りゅうとにわとり』、新川明『新南島風土記』、川満信一『沖縄・根からの問い』3氏を展示して大騒ぎ。豊川善一、北島角子、高江洲義寛、幸喜良秀、海勢頭豊、南条喜久子、森田吉子、玉城秀子、嶋袋浩(福木詮)ら参加」「パーランク高らかにー第四回沖縄青少年の祭り」


1986年4月 『小説推理』津野創一「響け!パーランクー」


2004年9月 儀間比呂志『おきなわのえほん エイサーガーエー』ルック


「第30回記念エイサー祭り」会場の儀間さん。金城馨と談笑
2018年9月1日ー嘉陽夫妻、儀間比呂志展を鑑賞


写真ーミュージアムショップ「ゆいむい」 で池宮城啓子さん、嘉陽宗博氏/左から金城美奈子さん、仲原穣氏、嘉陽宗博氏




1978年7月 儀間比呂志『七がつエイサー』福音館書店




1970年9月 大江健三郎『沖縄ノート』岩波書店 儀間比呂志「挿絵カット」


Ko Yoshioka2023年3月14日 · 『日兵逆殺』墓石の裏に刻まれた四つの大文字。日本兵に虐殺された、という衝撃的な文字だ。日付は1945年5月22日。この日は、沖縄戦史によれば、第32軍(沖縄守備軍)が首里の司令部壕を棄て南部撤退を決定した、とある。降伏を拒否した日本軍が、逃げ惑う住民を道連れに、最後の決戦場として南部、糸満の地を選んだ日だ。『日兵逆殺』は、その日のどこかで起きたことなのだろう。
墓石の表には「弓太郎」「タガ子」というふたりの名前が並んでいる。検索してもなかなかヒットせず、どういう人物だったのかをネット上で調べていくのは、いまも厳しい。私がこのふたりの存在と『日兵逆殺』の墓石を知ったのは、1972年、沖縄が復帰する2ヶ月前、雑誌『世界』の取材で大江健三郎さんとご一緒したときだった。弓太郎とは新垣弓太郎のことで、タガ子はその妻。「逆殺」されたのは妻、タガ子だと知った。
大江さんの話から、墓碑の四文字の由来を理解したとき、心臓が高鳴ったことを覚えている。それは、沖縄戦の真実のひとつがこの四文字のひとつひとつに込められているとリアルに想像できたからだった。撮影は1972年3月21日。南風原村にて。墓石の文字を書き写す在りし日の大江健三郎さん。36歳。


1971年11月 『青い海』8号 宜保栄治郎「沖縄のエイサーー勇壮なパーランクーの響き」



1997年11月 宜保榮治郎『エイサー 沖縄の盆踊り』那覇出版社/1998年3月 沖縄市企画部平和文化振興課『エイサー360°ー歴史と現在ー』沖縄全島エイサーまつり実行委員会


2018年11月21日ー儀間比呂志展で、ひろみ/2019年2月 ギャラリー象で、妙子さん、あけみ
2001年3月ー『けーし風』第30号「大阪のなかの沖縄」(屋良朝光、金城馨、諸見里芳美、仲間恵子、玉城利則、崎浜盛喜、伊差川寛、金城良明、金城宗和、金城正樹、我謝実、上地武、當山清朝、大城康代)
1956年7月1日ー大阪市中之島公園で「沖縄土地取上げ反対国民集会」
1956年7月7日ー『琉球新報』「沖縄問題在京郷土人の声ー大浜信泉、神山政良、山之口ばく、比嘉良篤、伊江朝助、尚裕」
1956年7月8日ー『琉球新報』「浅沼社会党書記長ー沖縄の『ハワイ化』阻止」
1956年7月10日ー『琉球新報』「沖縄を守ろうー仙台河北新報発・宮城県庁前広場で沖縄問題解決促進宮城県大会」
1958年8月2日ー『琉球新報』「死の灰 ソ連核実験でふえる」
1958年8月15日ー『琉球新報』「恐るべき放射線の影響ー人類の将来に危険」
1968年1月5日ー『毎日グラフ』「本土の中の沖縄(南風サークル/大城真栄/普久原朝喜/金城良明)」「万国博へ全力投球(岡本太郎「抵抗あるものを」)」


金城良明氏

中央が金城良明氏
1971年4月ー『沖縄差別』№1金城良明「大正区で生まれた、2世の声を聞いてほしい」
1971年8月ー『沖縄差別』№2金城良明「沖縄差別とわたし」

写真左から諸見里宗博氏、新城栄徳、金城良明氏
04/16: 神保町・お茶の水 神保町古書店街:


神保町・お茶の水 神保町古書店街:日本一の古書店街として名高い神保町。靖国通りを駿河台下交差点から西へ向かうと、およそ130店もの古書店が建ち並び、中には美術、武道、洋書、料理、など一つのジャンルの本を専門に扱う店も。そんな神保町を代表する書店や、古書店をきっかけに発展していった喫茶店、カレー屋も併せてご紹介します。
駅から徒歩2分の場所にあるのが、創業大正7年の歴史を誇る「矢口書店」。ここは映画や演劇、戯曲、シナリオにまつわる古本を中心に扱う古書店です。棚に並ぶのは、古くからの名作や最近発表されたものまで、幅広い年代の作品を取り扱っています。中でも、人気の品は1950年代から1960年代の映画パンフレットなんだそう。


1983年10月「神田古書店地図帖」/毎日新聞発行の『アミューズ』1999年、よく古本屋を特集する。

東京文学の散歩道/日本近代文学館/東京都近代文学博物館

1995年12月27日『琉球新報』「戦後50年 日本文学の軌跡」


グラビア・カメラでちょっと・ひとめぐり/オフセット・省線・私鉄・遠距離バス交通図
戦後の東京の風俗について・・・大宅壮一/戦後の東京の服装について・・・伊藤道郎/東京女と関西女について・・・山本嘉次郎/東京弁と関西弁について・・・野元菊雄/五十年前の思出ばなし
見物の東京 A・一般コース B・盛り場と裏通り・どん底の街・さんや デッドエンドの街・たかばし



アメリカの東京基地・・・佐々宇賛丸/東京周辺のアメリカの軍事基地と工場早わかり
娯楽の東京ー映画館/スポーツ場/劇場・寄席/競輪・競馬場/ストリップ/ダンスホール
女の東京ーバーキャバレーと女給のチップ/温泉マークの内幕と活用法/待合と芸者あそび入門/赤線区域の泊り方ー花の吉原から田園調布迄のシマ案内/青線区域のさがし方ーパンパン遊び・処女でも啞でもお好み次第






1956年9月 『別冊知性・現代の裏窓ー日本のブラック・メモ』河出書房(河出孝雄)◇船越義英「沖縄ーこの踏みにじられたものー売られ行く島オキナーワ!極東唯一の原爆基地オキナーワ!」◇三木淳「東京の裏窓ー超望遠カメラで捉えた都会の素顔」◇ギャンブル報国精神万才!競輪、競馬、パチンコ、宝くじーなどとならべてくると、日本ほどバクチで明け暮れている国はちょっと世界に例がないような気になる。ことに競馬、競輪、宝くじなどというのが何れも堂々と官営、公営されているなど、どうしてもモナコとまではゆかなくとも、少なくとも日本全体が、かつての上海、香港なみな植民地都市にでもなったのではないかという気がしてくる。(原四郎)
河出書房新社 1886年(明治19年)に河出靜一郎(1857年 - 1936年)によって岐阜の「成美堂書店」の東京支店として日本橋に設立されたのが始まりである。当時は教科書や学習参考書を中心に出版していたが、農学関係書の刊行が次第に増えていった。 1933年(昭和8年)に2代目(靜一郎の女婿)の河出孝雄(1901年 - 1965年)が河出書房に改称し、文芸書や思想書を中心に刊行するようになった。1944年(昭和19年)には改造社より文芸雑誌『文藝』を買い取った。1945年(昭和20年)の東京大空襲で被災し、千代田区神田小川町に移転する。 1950年(昭和25年)に刊行した笠信太郎『ものの見方について』がベストセラーとなる。
1954年(昭和29年)に創業70周年記念企画として総合雑誌『現代生活』の創刊を公告するも、立ち上げの資金を編集スタッフに持ち逃げされた。『現代生活』は『知性』という名で創刊するが、これが遠因となって1957年(昭和32年)に経営破綻、新たに河出書房新社を創設し再建された。同年3月には女性週刊誌の先駆けである『週刊女性』を創刊していたが、倒産に伴い、4号で休刊。同年8月に同誌の編集・発行権を主婦と生活社へ譲渡した。 1965年(昭和40年)、河出孝雄が死去し、河出朋久(1938年 - )が3代目社長となる。1967年(昭和42年)に会社更生法を申請し再度倒産、再建され中島隆之が社長となる。1968年(昭和43年)12月、吉本隆明の『共同幻想論』を刊行する。 1977年(昭和52年)に品川区東大井から新宿区住吉町に移転し、清水勝が社長となる。2年後に千駄ヶ谷に移転し現在に至る。旧社は登記のみ残し休眠状態だったが、2000年(平成12年)から東大井で営業再開した。2007年(平成19年)、新社と業務提携、販売契約を締結した。 →ウィキ




1953年2月 宮本顕治『宮本百合子集』河出書房/1988年3月 澁澤龍彦『三島由紀夫おぼえがき』中公文庫


河出文庫(澁澤龍彦、稲垣足穂)・河出新書/神保町、本郷、早稲田の古本街はよく行ったが、そこは静のイメージがある。仕事場は新宿歌舞伎町。その周辺ではアンダーグラウンド(1960年代後半に起こった、商業性を無視した前衛的・実験的な芸術運動)や派手な極彩色を用いたデザイン「サイケ調」も流行っていたので、相まってシュールレアリスムとかダダの芸術の本を読んでいた。




2002年3月 澁澤龍彦『旅のモザイク』河出文庫/2012年6月 藤原新也『コスモスの影にはいつも誰かが隠れている』河出文庫
私は1964年に錦糸町駅ビルの本屋で、サド裁判の被告で著名な澁澤龍彦の『夢の宇宙誌』を買った。その本で南方熊楠(末吉麦門冬)、稲垣足穂、日夏耿之介を知る。澁澤龍彦に会おうと思ったのは、テレビで千円雑誌『血と薔薇』発行が報じられたからである。5日後、鎌倉に澁澤を訪ねたのは1968年の10月9日であった。年配の女性がお茶を持ってきてくれたり応対してくれた。(同年、澁澤は夫人・矢川澄子と別れたばかりであったから母堂であろう。)そのうち2楷からトックリシャツ姿でパイプを持った澁澤が応接間の椅子に座り、甲高く透き通る声でいろいろ話をしてくれた。「京都に行く機会があれば稲垣足穂さんに是非会うといい。子どものような純粋な精神の持ち主だ」「沖縄出身の友人に彫刻家が居る」とか、発禁本の話もしてくれた。澁澤は1987年8月5日、59歳で亡くなった。

1929年4月 『郷土雑誌 沖縄』 神山宗勲『悪魔』編集発行・座安盛徳/沖縄社鹿児島市上荒田1770のノ2
新城栄徳 2020-4-15 私の敬愛する編集者に上間常道氏が居た。氏は大阪生まれの今帰仁2世。東京大学文学部卒。『現代の理論』編集部、その発売元の河出書房新社に無試験で入社。『ドストエーフスキー全集』『トルストイ全集』などを編集する。復帰を機に沖縄に移住。出版社などを経て沖縄タイムスに入る。沖縄タイムス発刊35周年記念で『沖縄大百科事典』(上中下の3巻別刊1巻、約17000項目を収録)の編集を担当、同社より83年5月刊行。06年より出版舎Mugenを主宰。私は河出書房の話は聞いたかもしれないが記憶にない。
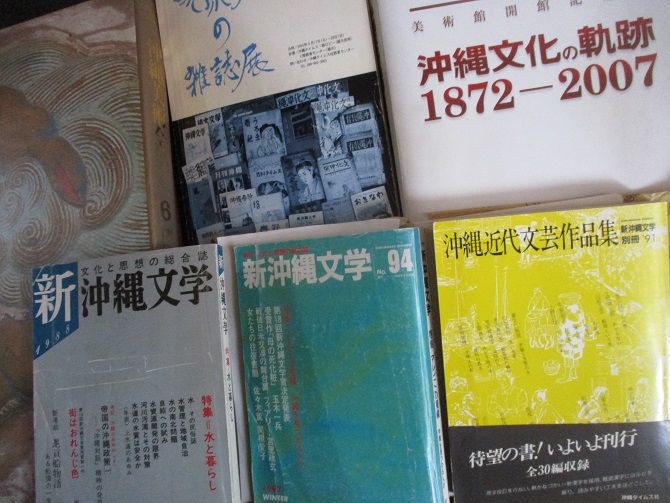
新城栄徳と上間常道氏の共同作業『沖縄美術全集』「年表」/『沖縄近代文芸作品集』/『琉球弧の雑誌展』
社会主義の実験
1920年ーボリショイ劇場前でのレーニン演説の写真、右にトロッキーとカーメネフが居る
写真ー1938年、メキシコにてトロッキー、ブルトン
トロッキー○1917年のロシア十月革命における指導者の1人であり、ウラジーミル・レーニンに次ぐ中央委員会の一員であった。赤軍の創設者および指揮官として、ソビエト連邦の初期の頃には外務人民委員(外相)として外交問題を担当。ソ連共産党政治局員の1人でもあった。→ウィキ
カーメネフ○レーニンの死後、ジノヴィエフと組んで1925年秋から「新しい反対派」の指導者となる。第14回党大会では、スターリンの「一国社会主義」に反対し、共産党に「首領(ウォシチ)」はいらないと主張した。→ウィキ



アラビアのロンドンーいちおうロンドンについても触れておいたほうがいいかもしれない。前に法的権利擁護委員会のムハンマド・マスアリーがロンドンに逃げたという話を紹介した。なぜ彼らはロンドンに逃げるのか。実はロンドンというのはイスラーム原理主義の組織という点ではある意味、中東以上に重要な場所なのである。ロンドンには文字どおり数え切れないほどのイスラーム系組織が存在している。インド系、パキスタン系、バングラデシュ系といった旧インド帝国領のムスリムおよびそこからの移住者が中心だが、アラブ諸国からも多数の移住者、亡命者を受け入れている。とくに湾岸やエジプト、スーダンなどはかつての宗主国ということもあり、観光客を含め、膨大な人数をイギリスに送り込んでいる。そのためロンドンなどには、アラブ人街とでも呼べるような中東度のきわめて高い地域が出現してきている。
そうしたところではアラブ料理屋、アラビア語の本屋が建ちならび、不動産屋でもアラビア語の案内が幅を利かす。イギリスではアラビア語の日刊紙だけで少なくとも5紙存在する。それだけアラブ人口が多いということであろう。問題なのはこうした連中がロンドンを中心に反政府活動を展開することであろう。もちろんここでいう反政府とは反イギリスではない。反サウジアラビアであり、反エジプトであり、反バハレーンの反政府活動なのである。幸か不幸かイギリスにおいてはそれぞれの本国ではけっして享受できない自由がある。彼らは欧米的な人権で守られながら、自由に情報を得、自由に情報を流すことができる。→」2011年 保坂修司『 新版 オサマ・ビンラディンの生涯と聖戦』朝日選書

ガストン・バシュラール(Gaston Bachelard, 1884年6月27日 - 1962年10月16日)は、フランスの哲学者・科学哲学者。科学的知識の獲得の方法について考察した。また、詩的想像力の研究にも多くの業績を残した。
写真ー1983年4月 『師父 志喜屋孝信』志喜屋孝信先生遺徳顕彰事業期成会 志喜屋孝信(1884年4月19日~1955年1月26日)〇1904年3月、沖縄県立中学校卒業、志喜屋孝信、川平朝令、山川文信、久高将旺、山田有登。4月ー志喜屋孝信、広島高等師範学校(数物化学科)入学。このころ内村鑑三を愛読。玉川学園の創始者小原国芳と親交。1908年3月卒業。4月、岡山県金光中学校に奉職。岡山出身の山室軍平の思想に親近感を抱く。12月、熊本県立鹿本中学校に転任。1911年12月、沖縄県立第二中学校に赴任。1924年3月、校長に就任。1936年3月、二中校長辞し、私立開南中学校を創設、理事長兼校長となる。
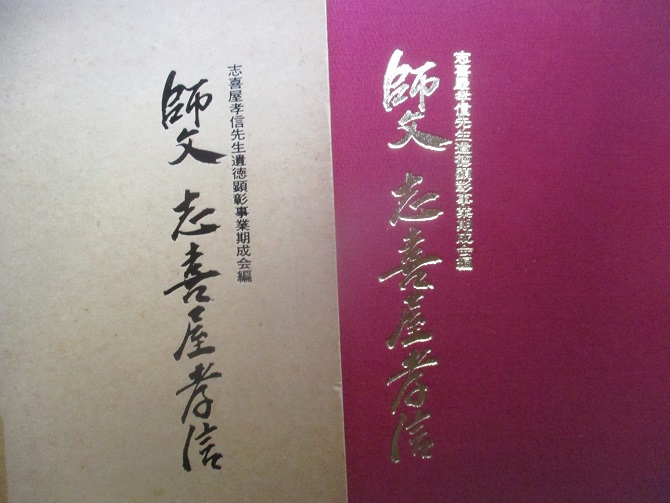
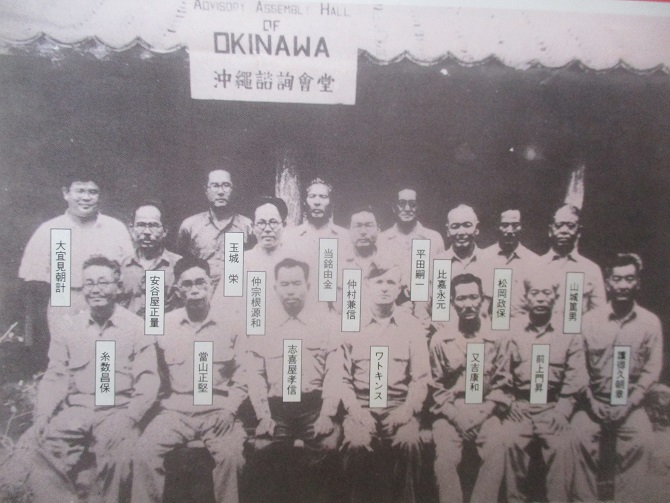
写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。
写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳
写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

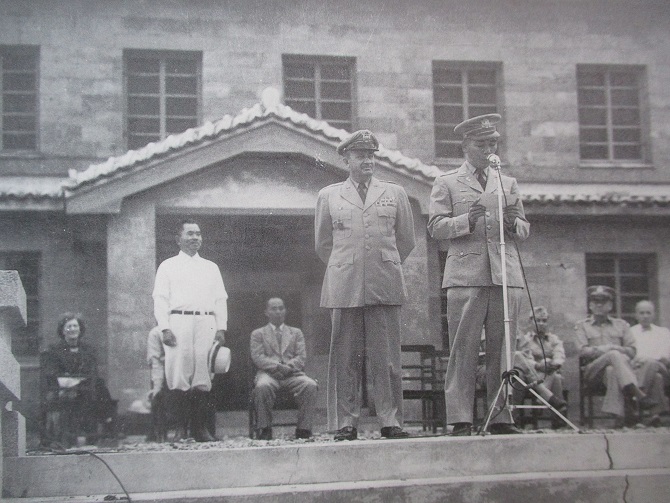
本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。
昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。
1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。
1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。
1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」
1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。
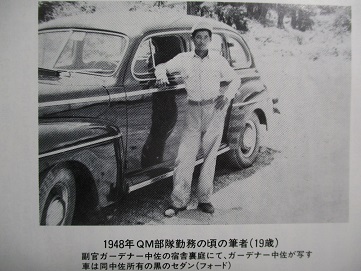
1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号
〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。
1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

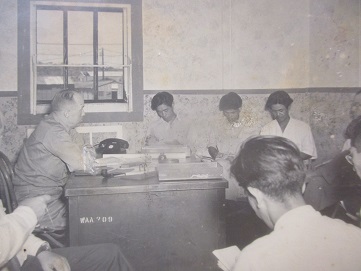
写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

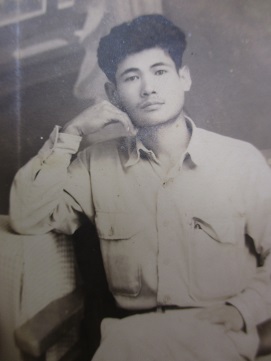
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて


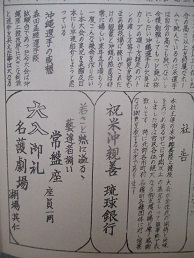
1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号
1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。
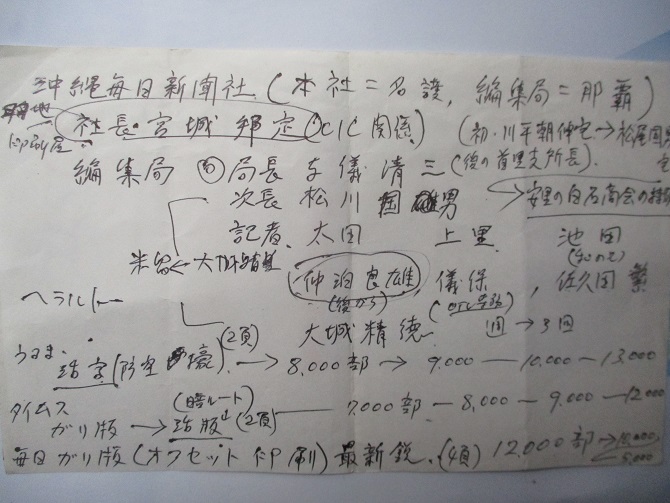
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展
1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。


写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳
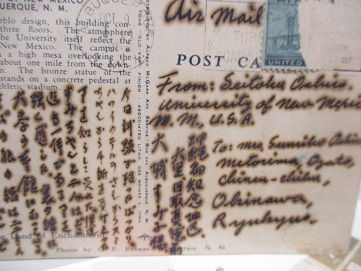
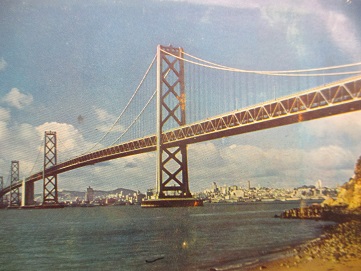
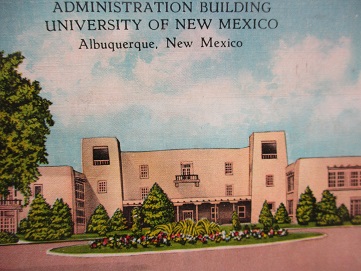

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳


1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山
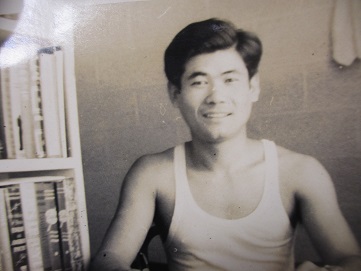

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順
ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」
1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
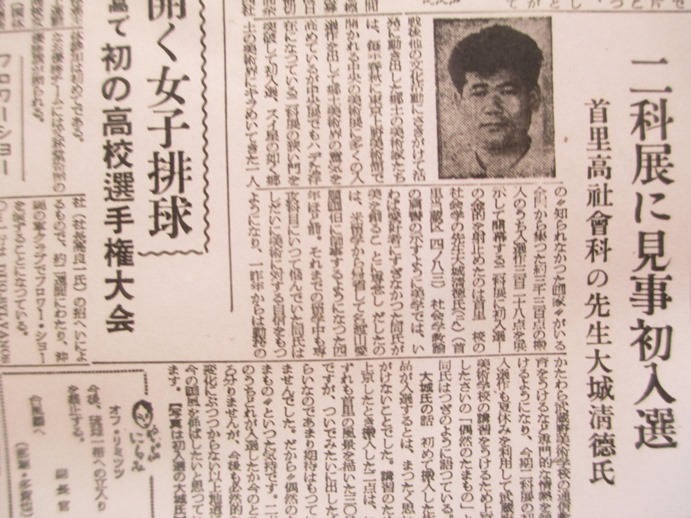
1956年9月1日『琉球新報』

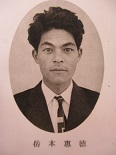
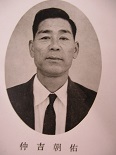
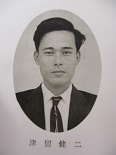
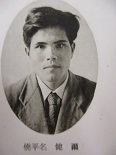
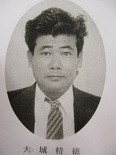
首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク
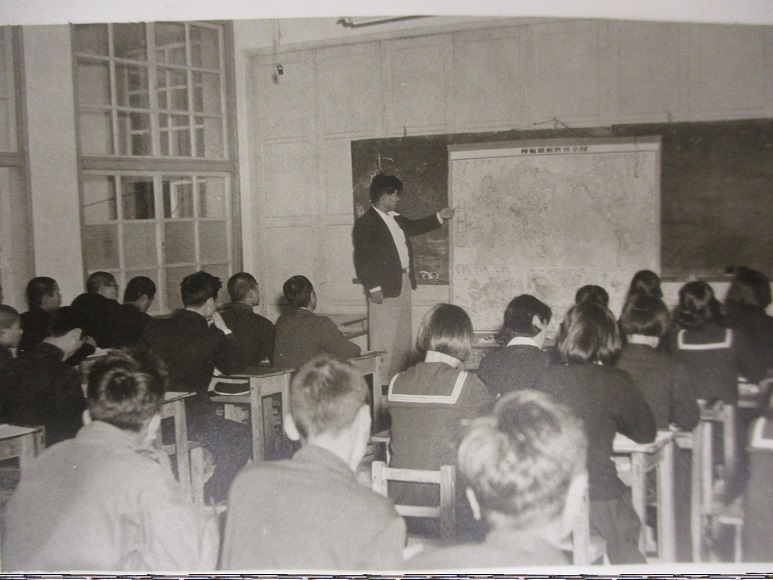
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

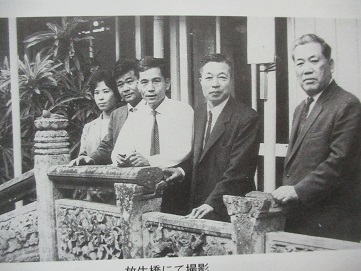
左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』
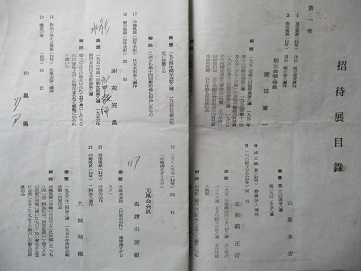
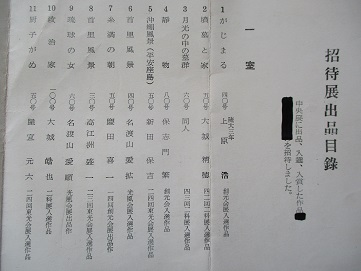
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
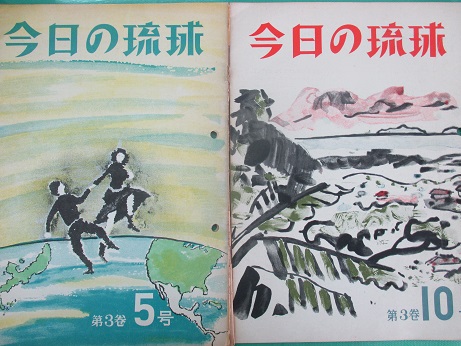
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

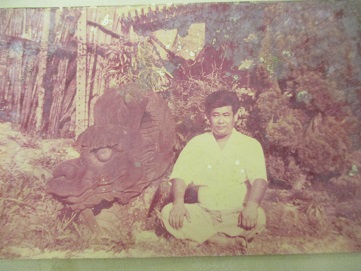


1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて
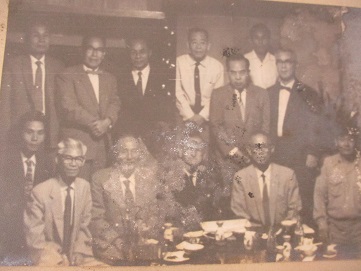

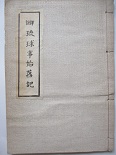




1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。
1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)
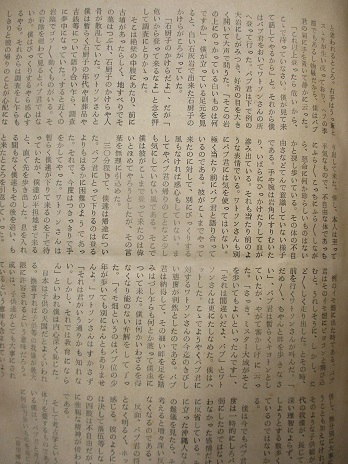
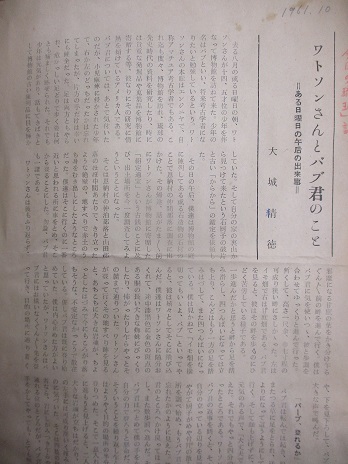
1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」
1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。
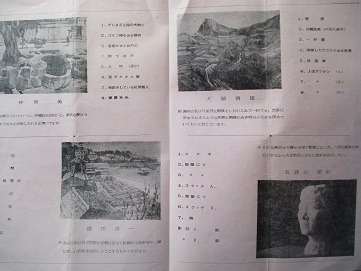
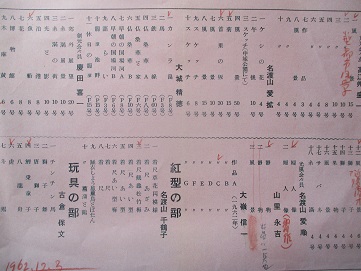
1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館
1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。
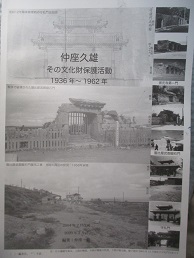
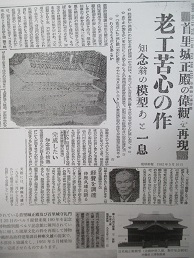
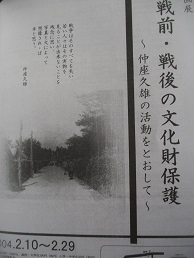
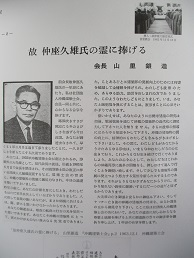
【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』
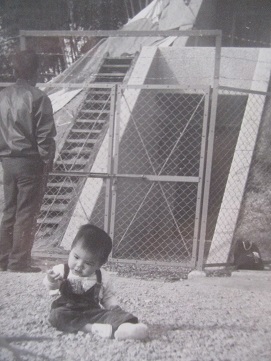
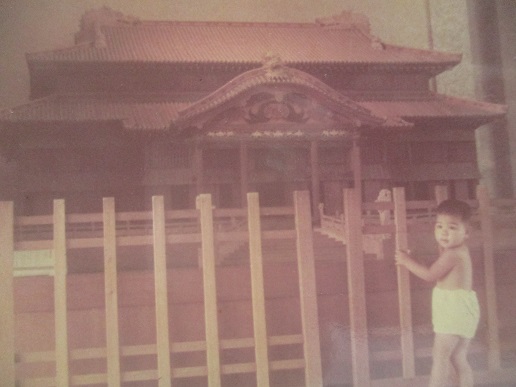
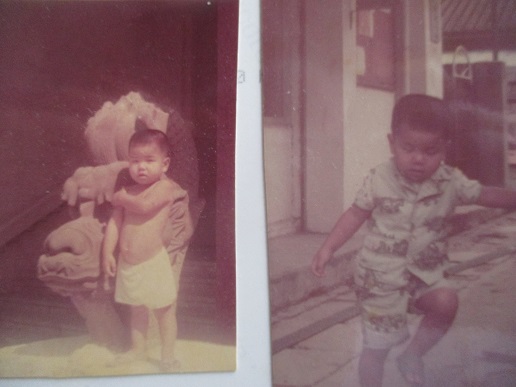
【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

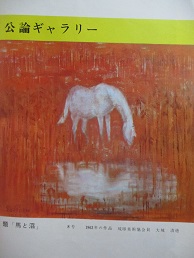
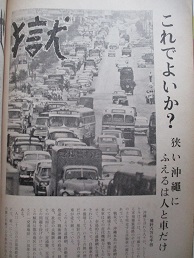
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
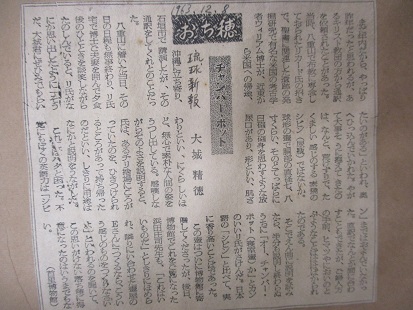
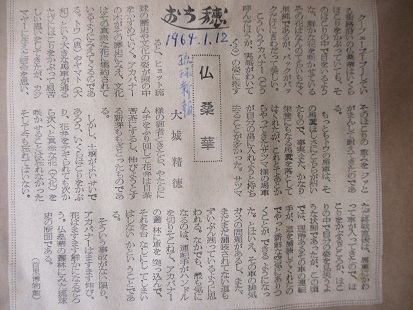
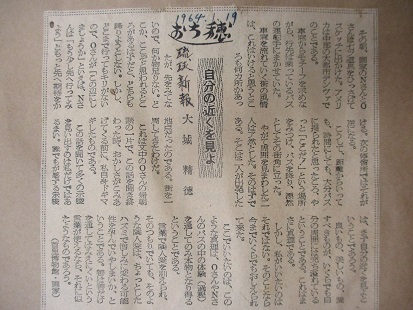
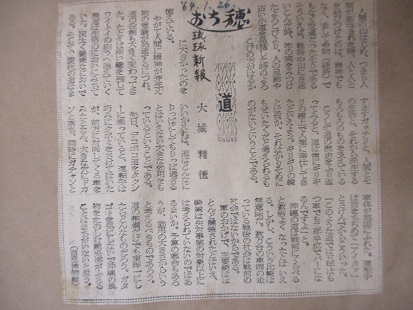
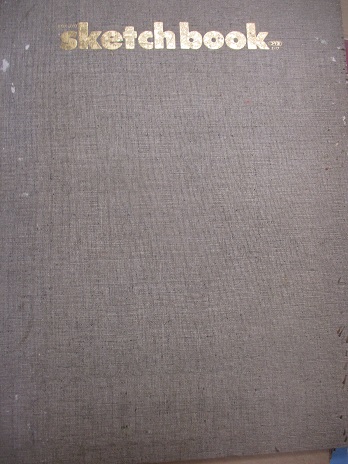

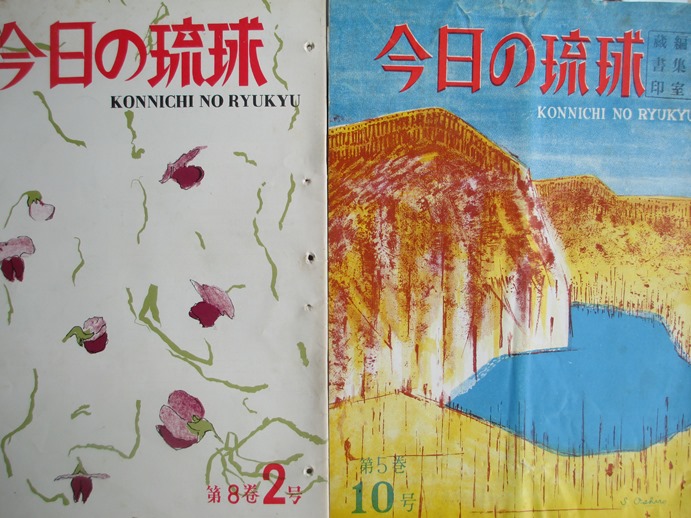
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」
1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。
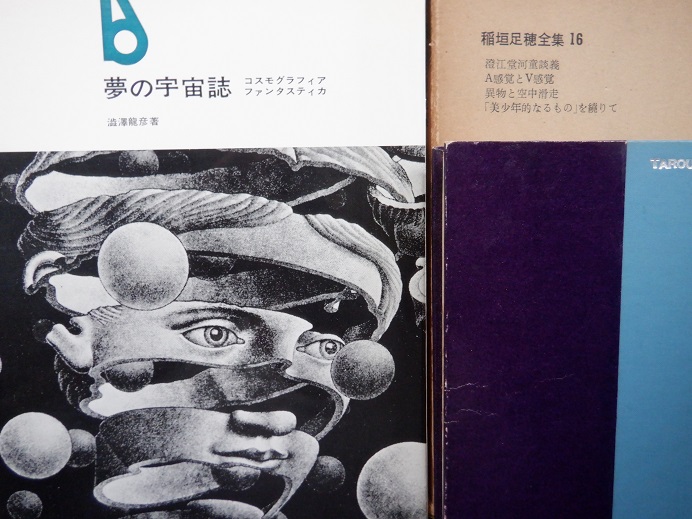
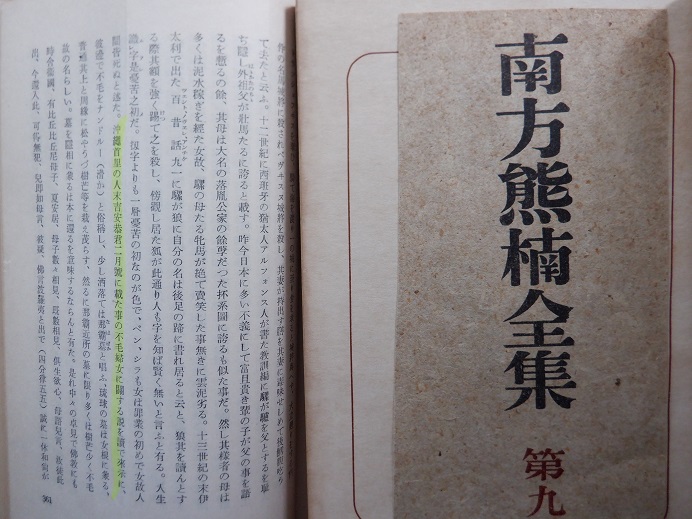
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
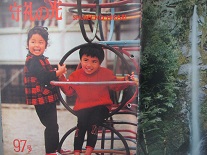
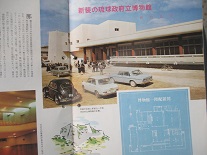
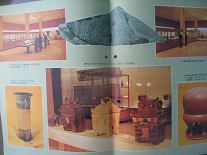

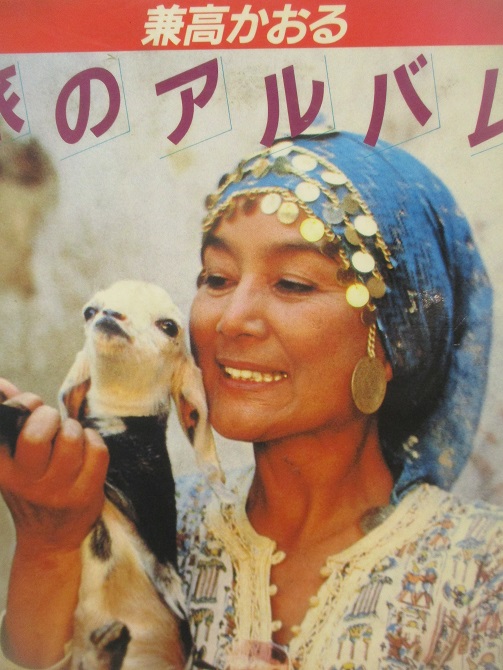
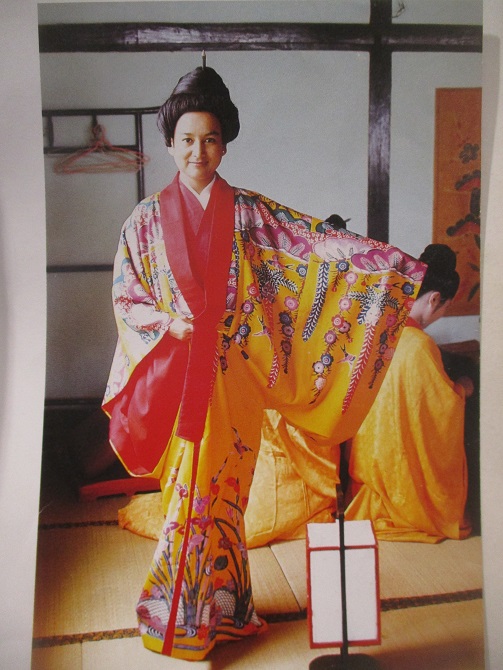
1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社
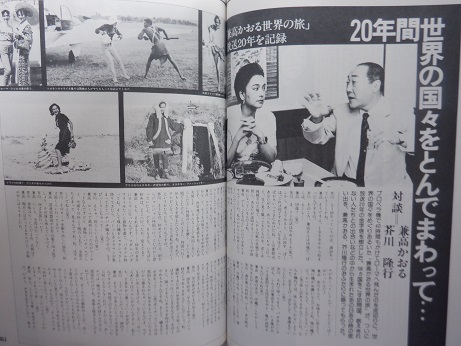
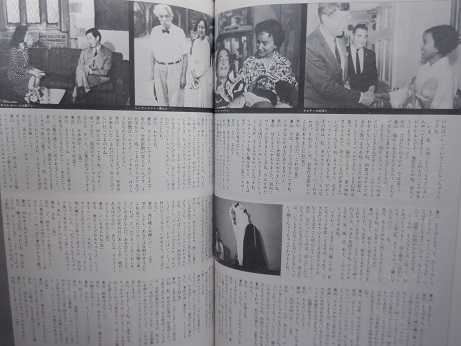
1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号
1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」
1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。


1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会
1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足
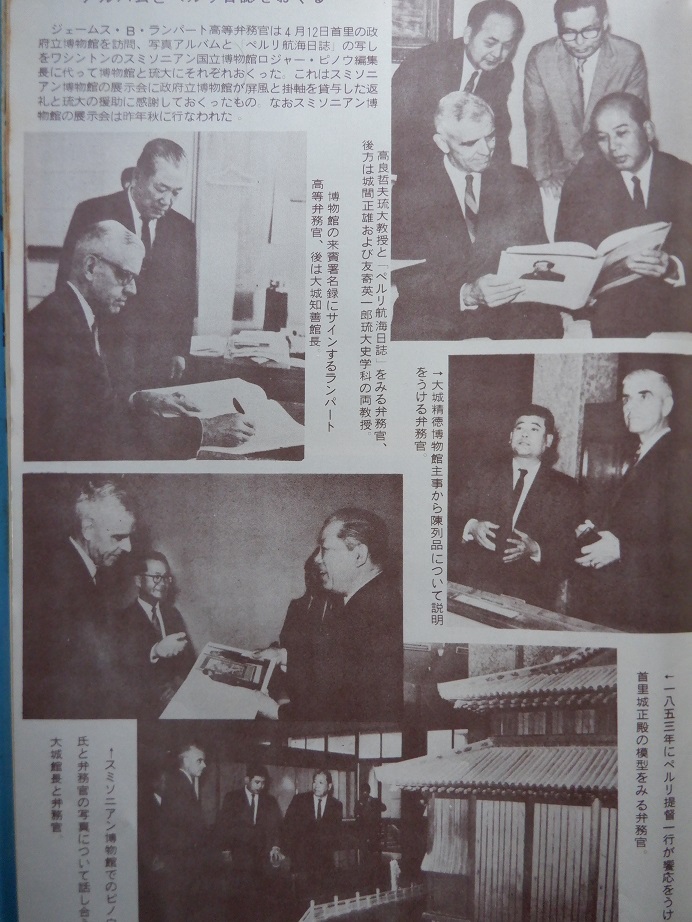
1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社
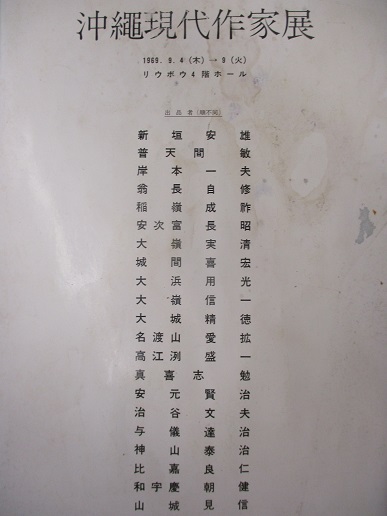
1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」
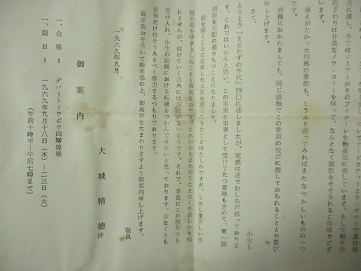
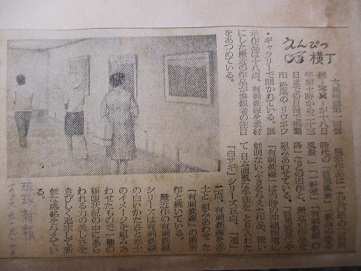
1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」
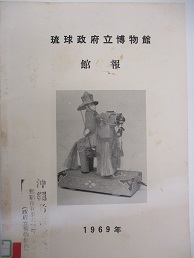
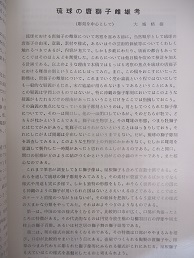
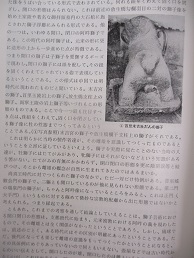
1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」
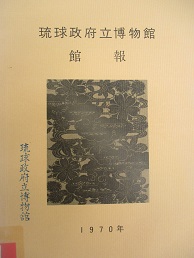
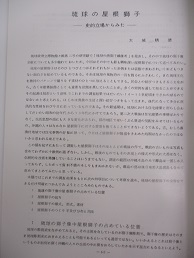
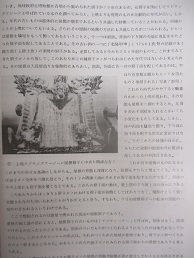
1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社
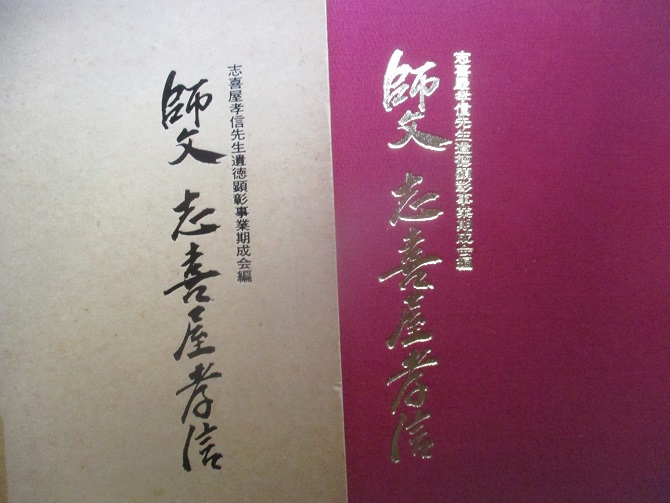
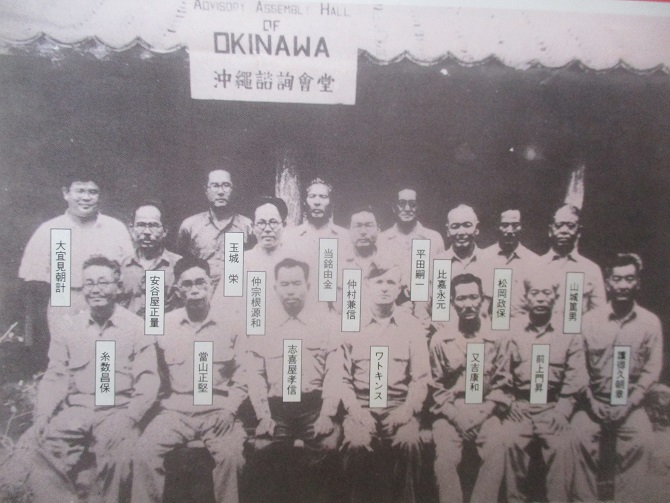
写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。
写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳
写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

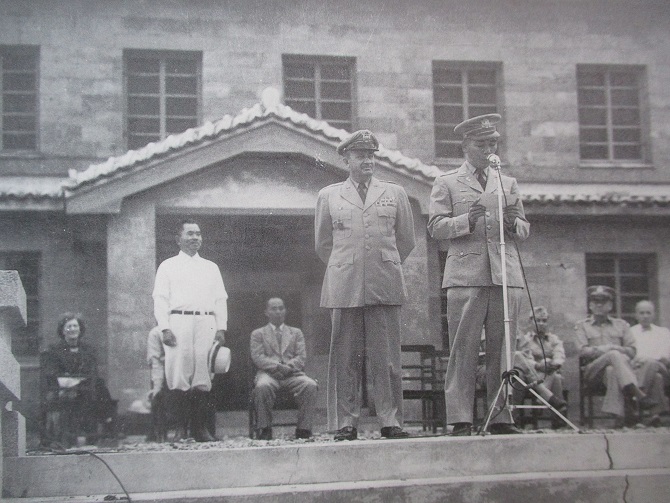
本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。
昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。
1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。
1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。
1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」
1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。
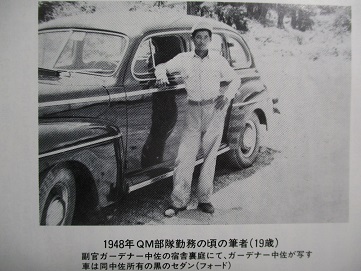
1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号
〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。
1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

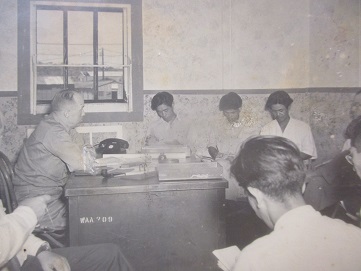
写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

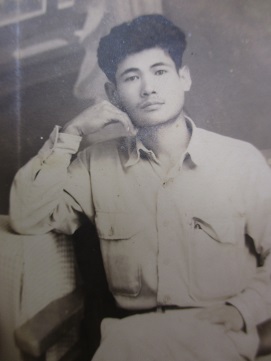
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて


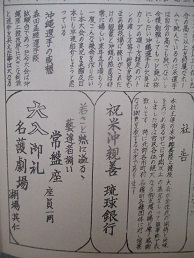
1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号
1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。
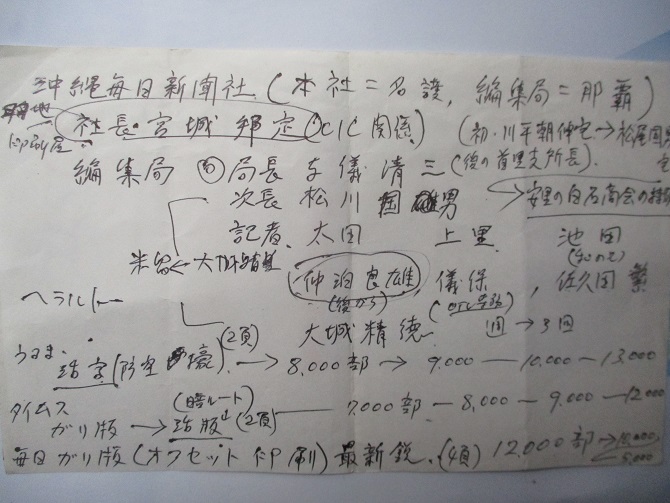
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展
1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。


写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳
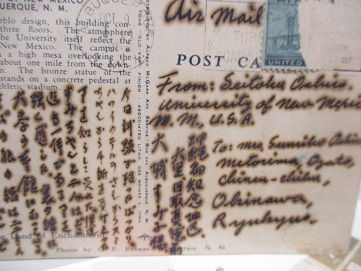
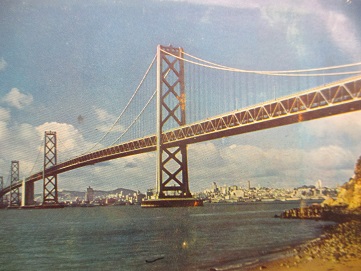
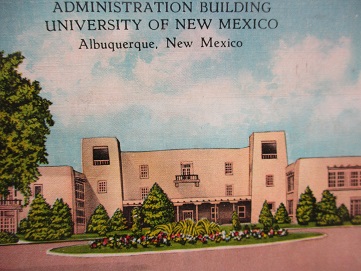

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳


1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山
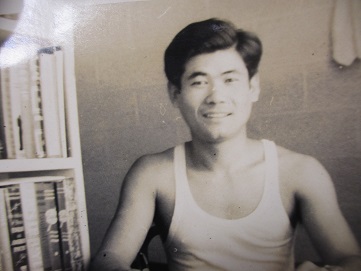

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順
ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」
1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
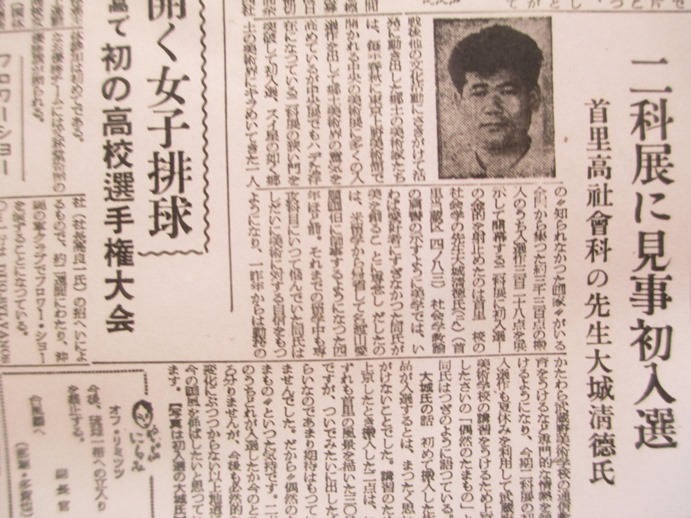
1956年9月1日『琉球新報』

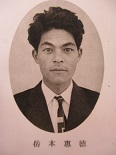
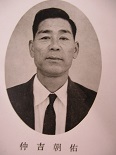
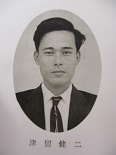
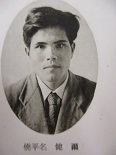
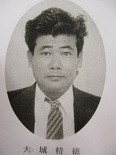
首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク
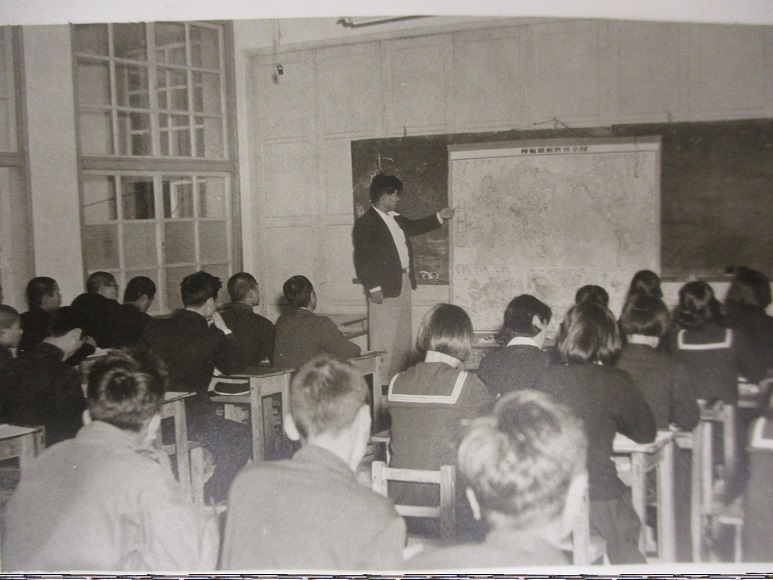
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

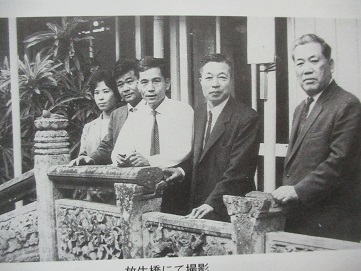
左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』
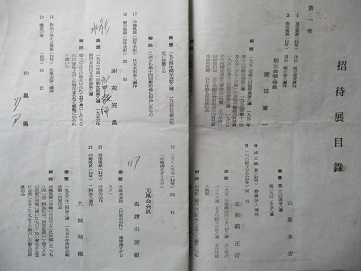
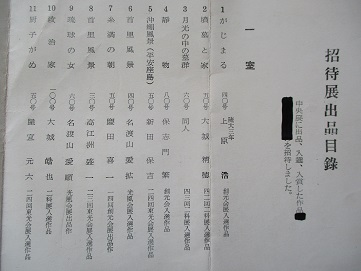
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
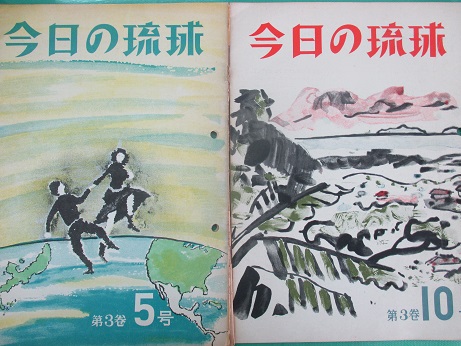
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

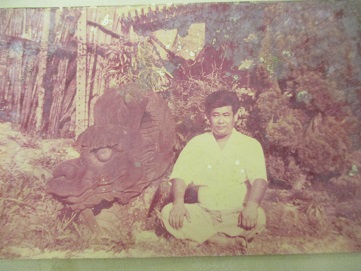


1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて
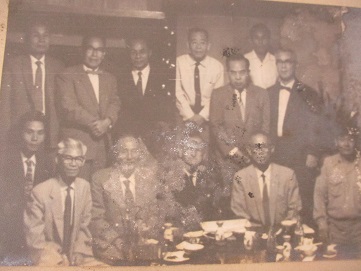

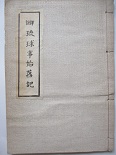




1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。
1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)
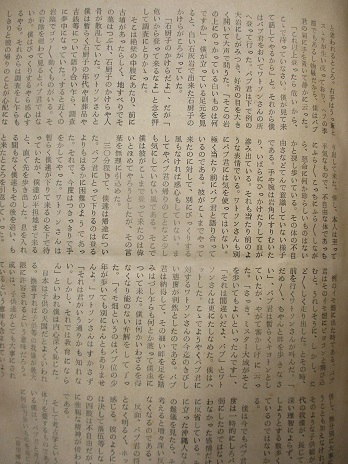
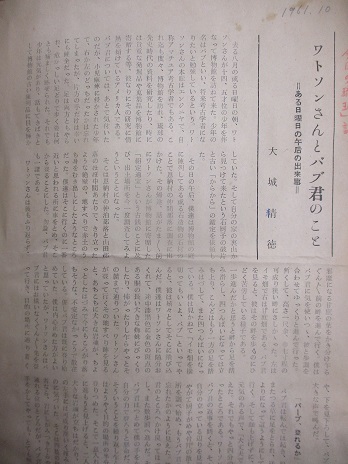
1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」
1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。
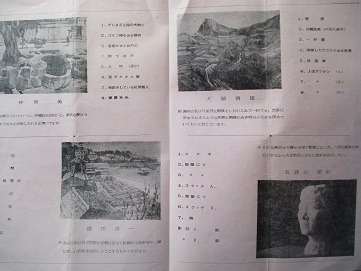
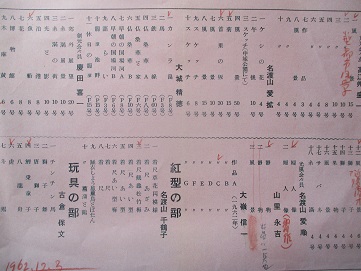
1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館
1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。
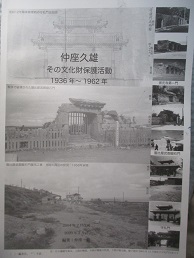
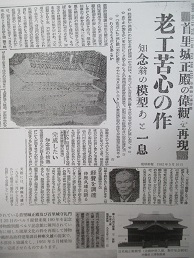
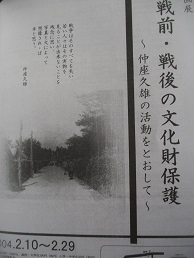
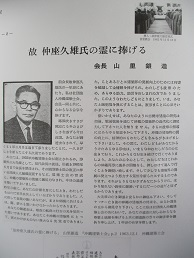
【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』
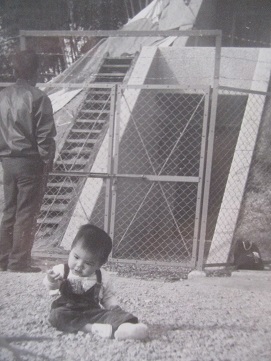
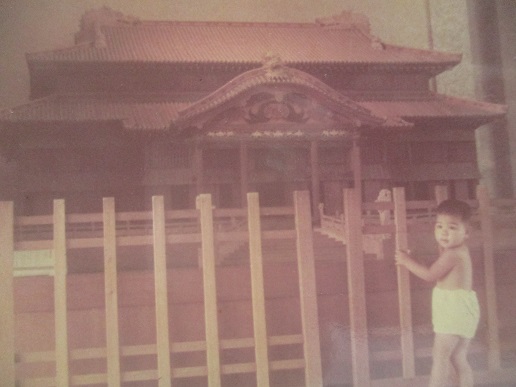
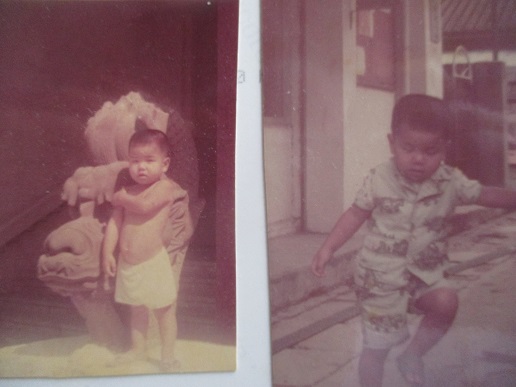
【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

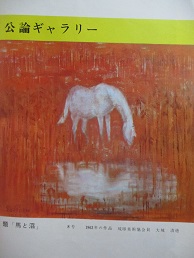
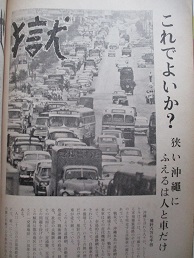
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
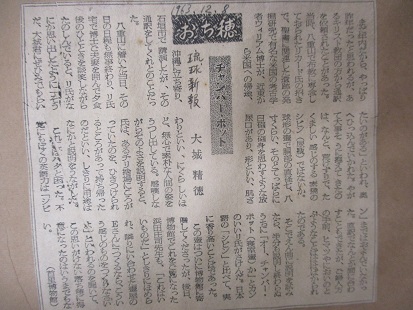
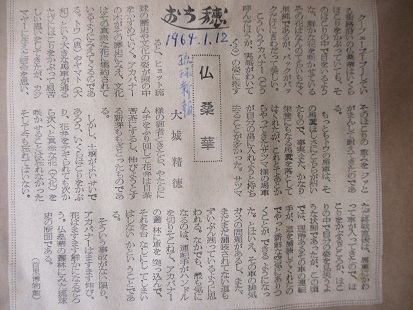
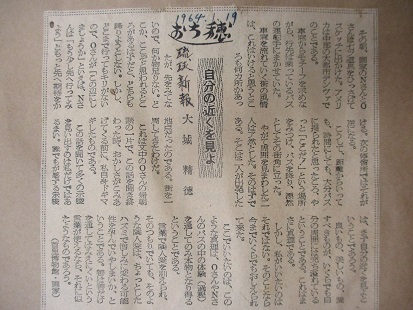
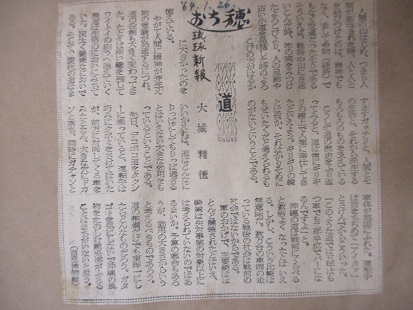
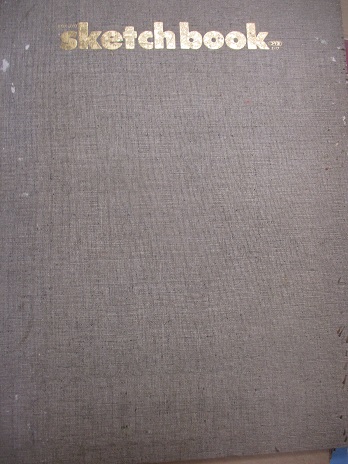

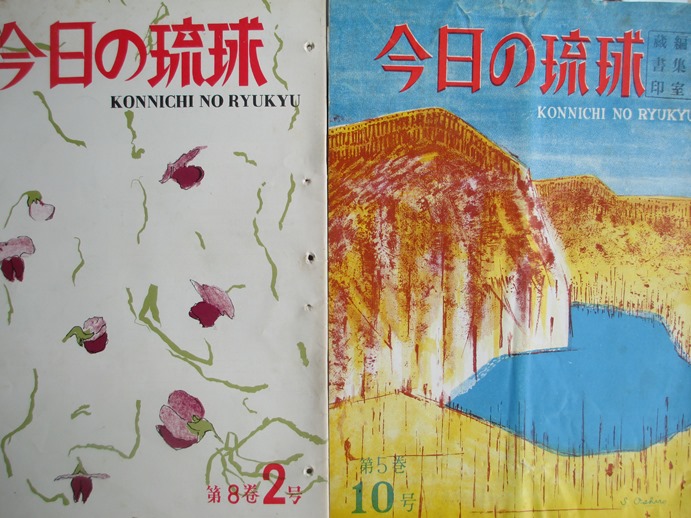
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」
1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。
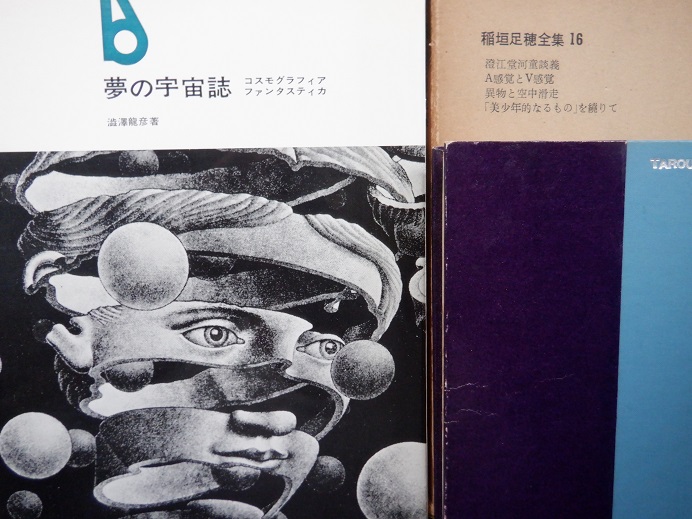
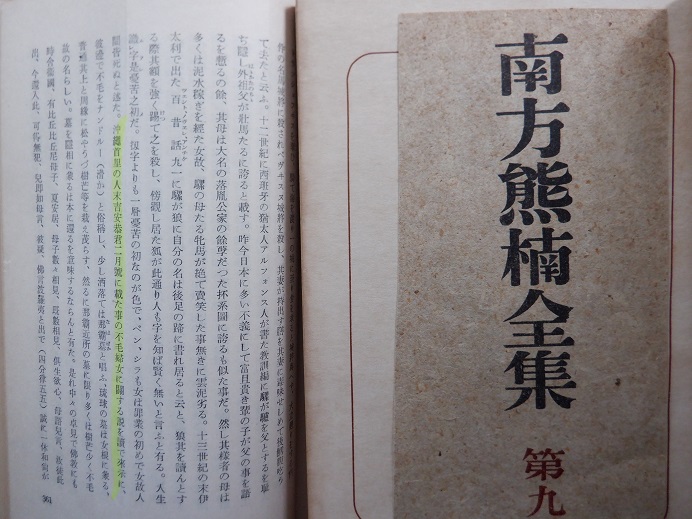
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
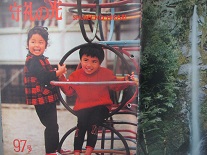
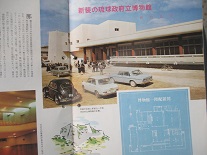
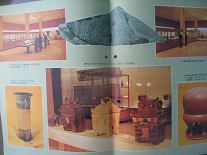

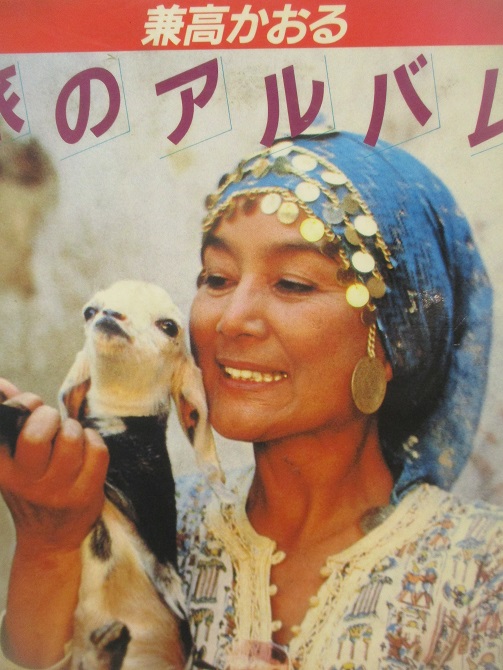
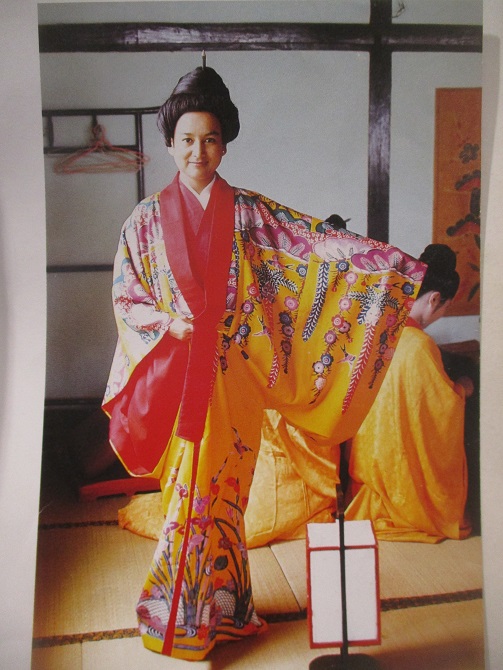
1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社
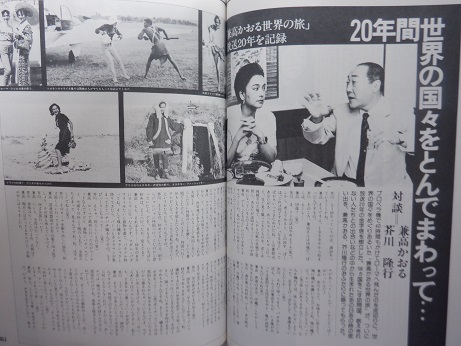
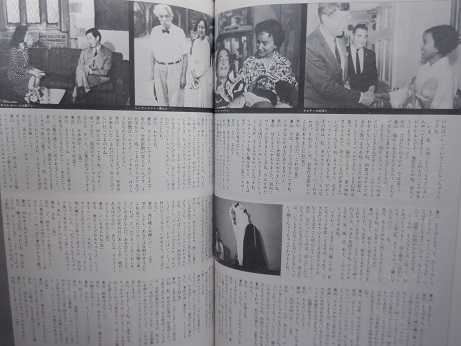
1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号
1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」
1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。


1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会
1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足
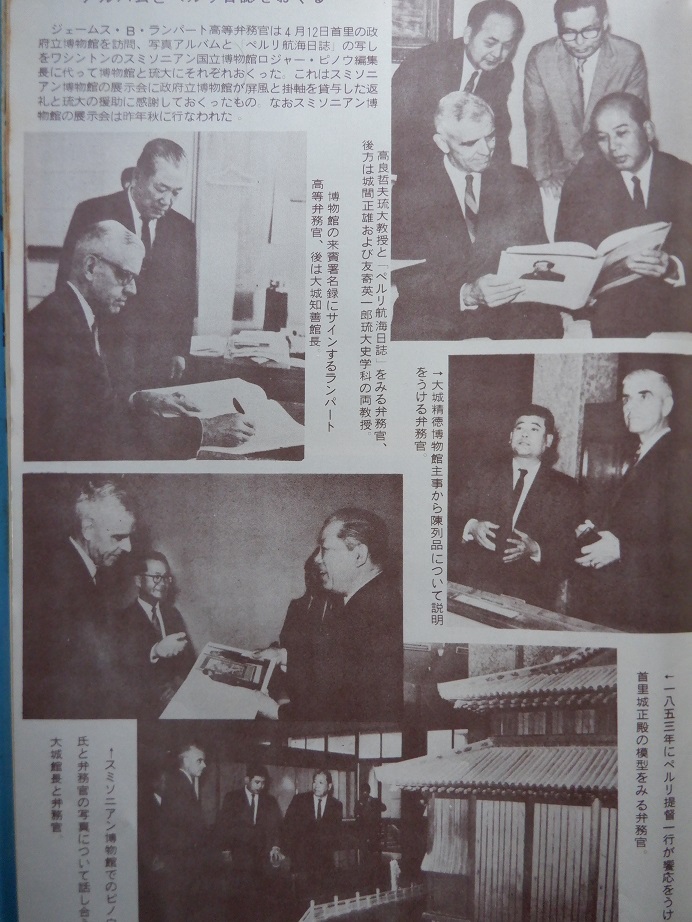
1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社
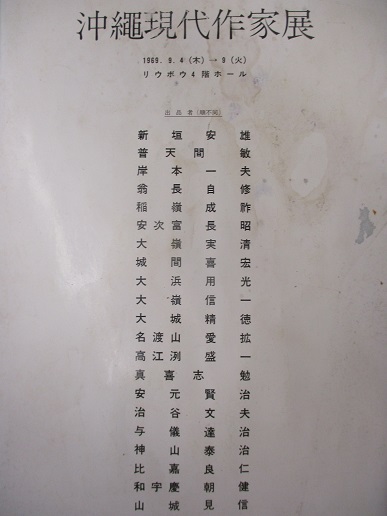
1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」
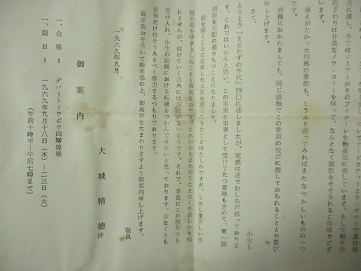
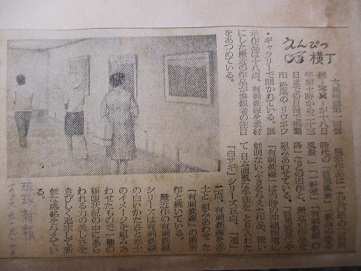
1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」
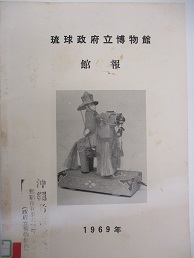
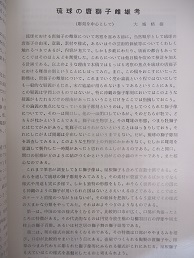
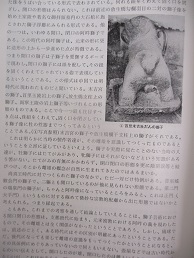
1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」
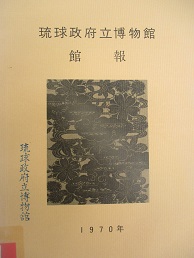
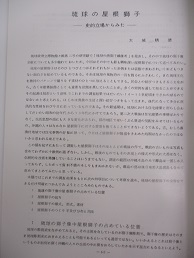
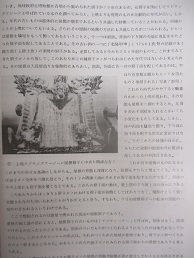
1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社



1973年9月 『青い海』久志冨佐子「滅びゆく琉球女の手記」(昭和7年)






1973年11月 『青い海』27号/1991年1月『新沖縄文学 別冊』「与儀正昌」
NHK 目撃!にっぽん 筆を折った“幻の女性作家”~沈黙の人生をたどる旅~」8月2日 日曜日 午前6:10~6:44(全国放送)直木賞作家・大島真寿美さんの小説「ツタよ、ツタ」。モデルはデビュー作への激しいバッシングで筆を折り、沈黙を貫いた女性作家・久志芙沙子。孫がその人生をたどる旅へ。昭和初期、沖縄初の女性作家として注目を浴びながら、わずか1作品を発表しただけで筆を折った小説家がいた。久志芙沙子。沖縄の現実をありのままにつづり、同郷の人から激しいバッシングを浴び絶筆。いま、彼女をモデルとした小説が話題となり、再び脚光を浴びている。家族にも過去を語らなかった芙沙子。祖母はなぜ筆を折ったのか。孫が祖母の人生をたどる旅に出た。芙沙子のまっすぐな生き方は私たちに何を問いかけているのか。

大濱聡




左から仲村顕さん、宮城晴美さん、宮里(仲村)初枝さん


1971年4月 雑誌『青い海』創刊号 仲村初枝「私の力で生きてみたいー少女にとって本土とは無限の可能性なのだー」/2020年3月27日・沖縄県立博物館・美術館ー左から、朝隈芽生さん、宮里(仲村)初枝さん、豊見山(津野)愛さん


1974年新年号『青い海』伊波南哲「久志芙沙子さんの思い出」〇さて、われわれは、久志芙沙子を慰め激励するために、明治神宮表参道の尚志会館で会合を持った。南島文化協会主催の金城朝永氏らの主催で、その晩集まった人々は、伊波普猷、東恩納寛惇、比嘉春潮、仲原善忠、仲吉良光、石川正通、八幡一郎、(芙沙子記ー比屋根安定、宮里良栄)、その他30人ほどであった。各人はそれぞれ、作者を激励したのであるが、石川正通氏は例のごとくユーモアで「この石川正通は石川啄木の身内であるが、作家は貧乏、苦悩、不遇はつきもので、それを克服するところに勝利がある。これは啄木が口癖のように言っていた。また真理である。久志芙沙子さんもこれにへこたれずに、チバイミソーリヨー」と駄洒落を飛ばして、会の空気を和らげていた。〇石川正通夫人・澄子(弟に渡嘉敷唯信)は久志(坂野)芙沙子の1年先輩。1987年6月発行の『ひめゆり一女師・一高女沿革誌』に澄子は「修学旅行の思い出」を書き、その傍には芙沙子の「追憶」が載っている。


〇大部前の話です。これも再従兄の琉大にいた今は亡き翁長俊郎が、私宅へ寄ってSさんの話をされた。

1974年6月 『青い海』№33 久志芙沙子「あの頃の事 その後のこと」

1915年2月11日『琉球新報』久志ツル(芙沙子)
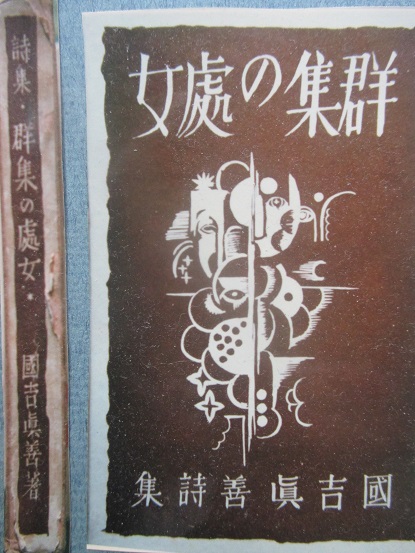
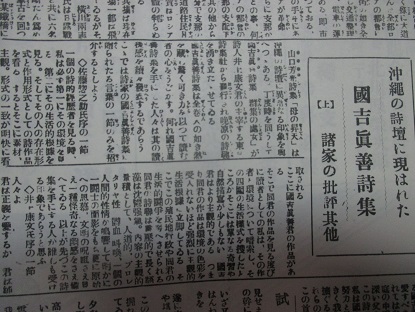
1929年5月 國吉眞善『詩集・群集の處女』「序:佐藤惣之助」
〇伊波南哲ー大東亜戦の最中であった。新三河島に泡盛の店を出している詩友の國吉真善が、ある晩、珍しい所に案内しようといって、私を久志芙沙子さんの家につれていった。まるで夢のようで雑あった。小さな貨店を経営して泡盛も売っていた。国吉真善のはからいらしい。子供が二人ほどいた。/久志芙沙子ー国吉真善氏という方は沖縄人にちょいちょい見受けられる規格品からはみ出したような人物、そのような方ではないかと思う。
1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/3月12日南島倶楽部例会、久志芙沙子、大宜味ツル子参加
/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』

1933年8月5日『南島』第7号 久志芙沙子「若葉から拾った哲学」
1933年12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」

2019年8月22日『新三河タイムス』




『[月刊J-novel』2015年 実業之日本社 辺□大島真寿美①「或る女の生涯 ツタよ、ツタ」(久志芙紗子がモデル)仲村顕氏提供
①大島 真寿美(おおしま ますみ、1962年 - )は、日本の小説家。愛知県名古屋市出身。南山短期大学卒業。
1992年、「春の手品師」で第74回文學界新人賞受賞。2012年、「ピエタ」で第9回本屋大賞第3位。2014年、「あなたの本当の人生は」で第152回直木三十五賞候補。→ウィキペディア


2016年2月 森川満理子『歌集 若夏の風』不識書院(仲村顕氏提供)表紙のおびに○ 亡き父の故郷はけふ「慰霊の日」いまに
戦後のつづく沖縄 著者は、名古屋市生まれ、市立菊里高校音楽科(ヴァイオリン科)卒、旧姓(安良城)。

渡久地 政司 2020-3-31■久志芙沙子再々発見の経緯■直木賞作家大島真寿美著『ツタよツタ』(小学館文庫)発刊までの経緯について、今年2月NHK名古屋が報道。つづいてこの話題について、3月27日・28日・29日に毎日新聞愛知版が3回シリーズで掲載しました(写真)。沖縄と愛知を結ぶ90年に及ぶ幻の女性作家をめぐるドラマが、わかりやすく文字化されて解説されました。不肖・私も2回目の一部に紹介させていただきました。


2007年1月 新城俊昭『琉球・沖縄 歴史人物伝』沖縄時事出版

島袋百恵・画「久志芙沙子」2013年11月3日『新報小中学生新聞 りゅうPОN!』仲村顕「人ものがたり㉛久志芙沙子(1903~1986)幻の女流作家」
斎藤陽子(Walnut, California)2019-11-28 久志芙沙子さんは親戚筋で、名古屋の開業医と結婚していました。父が「琉歌大全集」の編集で、1年間 東京大学に通っている時には、私も東京で学生でしたので1年間は父と同居しておりました時に、良く芙沙子さんが父を訪ねていらしゃいましたので、芙沙子さんは良く存じております。
安良城盛雄、台湾銀行 1920年(大正9) ~1927年(台北、九江、嘉義)
● 久志ツル(芙沙子)と結婚1922年(大正11)、長男・繁誕生1923年(大正12)、繁は2歳になるかならないうちに夭逝。台湾銀行は、安良城盛雄が退職してまもなく深刻化した世界金融恐慌(1929年~)では、日本で最初に倒産した。
安良城盛雄、1928年(昭和3年) 名古屋市立貿易学校、中国語教師 1年
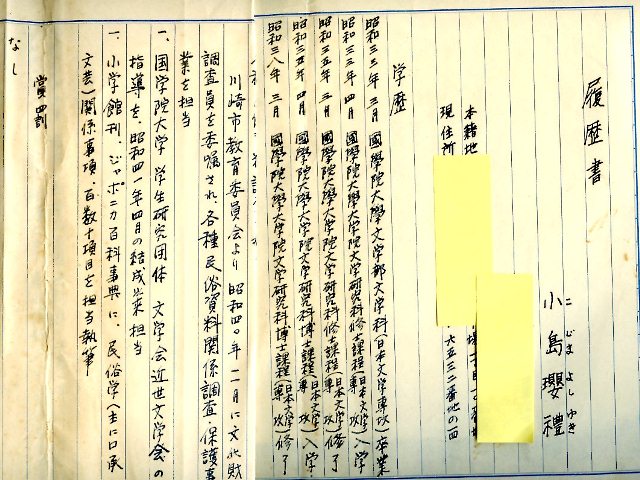

1983年1月 琉球新報文化部『沖縄学の群像』「小島瓔禮」本邦書籍
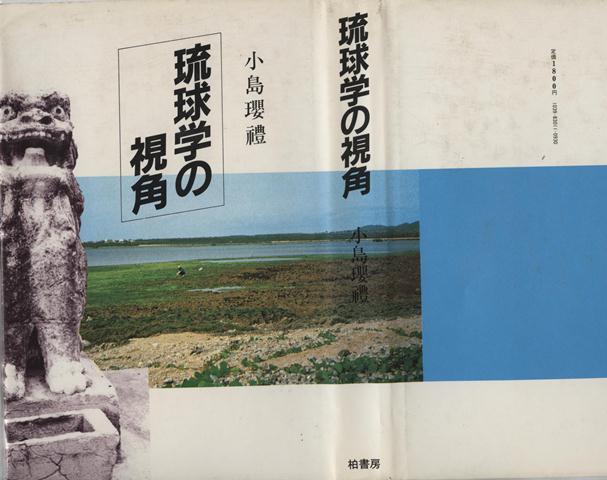
1983年4月ー小島瓔禮『琉球学の視角』柏書房
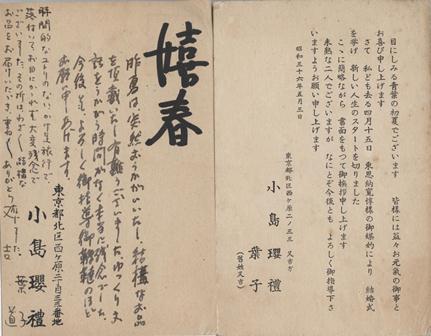

1991-5-31『琉球新報』小島瓔禮「梵鐘(ぼんしょう)の世紀」
小島 瓔礼(小島 瓔禮、こじま よしゆき、1935年4月5日 - 2025年5月13日)は、日本の神話・民俗学者。琉球大学名誉教授。神奈川県出身。神奈川県立厚木高等学校を経て 國學院大學文学部卒、1963年同大学院国文学博士課程満期退学、琉球大学教育学部助教授、教授。2001年定年退官、名誉教授 。1976年武田祐吉博士記念賞受賞 。2000年、第39回柳田賞受賞。
小島瓔禮琉大教授に柳田賞/著作「太陽と稲の神殿」が評価 2000年8月29日『琉球新報』
優れた民俗学研究者に贈られる第39回柳田賞(成城大学・柳田賞委員会主催)が25日決まった。受賞者は、「太陽と稲の神殿」(白水社)を著した小島瓔禮(よしゆき)・琉球大学教授と、「日本人と宗教」(岩波書店)などを著した故宮田登・筑波大学名誉教授の二氏。賞金は各30万円。小島教授は「高校時代に柳田國男の『田社考』を読んで民俗学を志したので、この賞は大変感慨深い」と喜びを語った。
受賞対象となった小島教授の「太陽と稲の神殿」は、朝廷の稲作儀礼の奥に、狩猟時代の面影を伝える儀式があることを指摘し、それが沖縄の民俗行事に残っていることを紹介している。その行事というのは、動物の骨を縄に挟んで村の入り口などに張る「シマクサラシ」と呼ばれているもので、本島南部のある村では現在でも旧暦2月に牛を殺して各戸に配る行事が残っており、与那国島では田を開いた時に鶏か牛の肉を供えたという伝承が残っている、と例を挙げている。

新城栄徳(左)、小島摩文氏(鹿児島純心女子大学 附属博物館館長)
11/27: 沖縄郷土協会初代会長・太田朝敷
1926年7月8日『沖縄朝日新聞』太田潮東「布哇の其の後」
□ヒロの滞在は悠々保養のつもりであったがヒロ市在留の県人もなを 席の宗教談でも聞きたいという希望があり、ホノムの佛教婦人会からも今一回講演して貰いたいと云う頼みが来たので、これも何かの因縁と思うて快く引き受け、この二席の講演は愈々お名残の講演であるから、多少趣きを加え金儲けと宗教を結びつけて話した。
ハワイに来て居る人々の多くは何れも金儲けを目的として来たに相違ないが、さて佛教に於いてもキリスト教に於いても、その他の宗教に於いても、教壇から金儲けの話しをすることは余りしないようだ。ところが金と云う奴は実に重宝なもので、誰でもこれが嫌いなものは居ない。佛教の或る開教師がしこたま金をためて帰ったそうだが或る人がそれを難したら、その坊さん平然として曰く「佛と云う字は人偏に弗と云う字じゃないか」この坊さんの如きは寧ろ正直の方で、金に執着がないような顔をして居る宗教家中にも、その実内ふくのものが可なり居るようだ。
要するに金を得たいというのは万人が万人共通の欲望だ。吾々の前に開けられている広い広い道は、只この欲望を満足する活動の為に開かれたかのように思わるる位いだ。ところがこの広い道には人の目に見えぬ陥穽もあれば深淵もあり所によっては毒蛇も居れば猛獣も居る。世の中には金儲けの上手と言わるる人が随分多いが、これらの人々は畢竟この危険極まる道の案内をよく知って居るのだ。
陥穽や深淵をよけて通り、毒蛇や猛獣を避け、然も相当に欲望を充たし得るのがマア世渡り上手と言ってよかろう。世渡り上手と云へば一種狡猾なわるがしこい人間のように考えるものが多いようだがこの種の人間はうまく世を渡ろうが、儲け口にありつこうが、それは外面だけのことで内面に於いては常に四苦八苦で少しも満足を得て居ない。
佛教に自利々他の覚行 云うことがあるが、ここに利と云うのは坊さん達に言わすと物質から離脱した精神的の利に局限されて居るが私はそうは見て居ない。詰まり二方に渉った自利々他である。自らも利し他も利する自利共利の道を求むる所に宗教もあり道徳もあるのだ。宗教家はややもすれば消極的にこの危険を避けようとする。殊に佛教徒中には禁欲を根本本義と考えて居るものが多いが、それは佛教の根本義を知らないからだ。
これは私独創の見ではない、佛も一切法は観を根本と為すと説かれてある。欲を殺してしまったら活動はないのだ。既に活動がなければこの世界に生命と称すべきもののある筈はない、即ち世界の死滅だ。然もこの欲を充たす道は自らも利し他も利し自他共に利する所に佛教の眞精神は存するのである。危険を避けて安全に通られる世渡りの自道も此の処に開かれているのである。私の信ずる所の佛教はこれであるから私はこの根本義を宣伝したのだ。
ハワイ各島の中でハワイ島は近来非常に宗教熱が盛んで我が県人を中心とする「真宗深信協会」と称する団体もありその例会の時には三四十哩から出席するのもある。私はかかる状態を見て私が佛教を味わって居たことを多幸と思うた。若し私に佛教の思想がなかったならばハワイ各島の巡講中県人に対するのは兎や角お茶を滑し得たとしても所謂一般講演の場合には聊か困ったらうと思った。
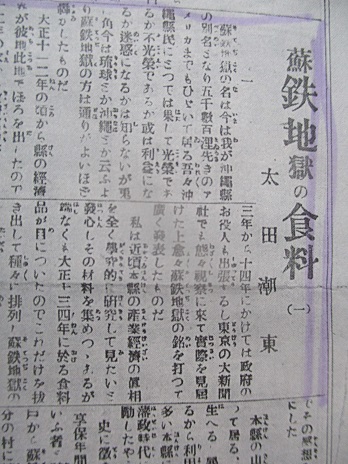
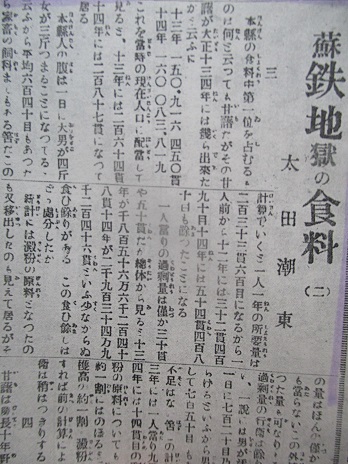
1927年10月13日『沖縄朝日新聞』太田潮東「蘇鉄地獄の食料」
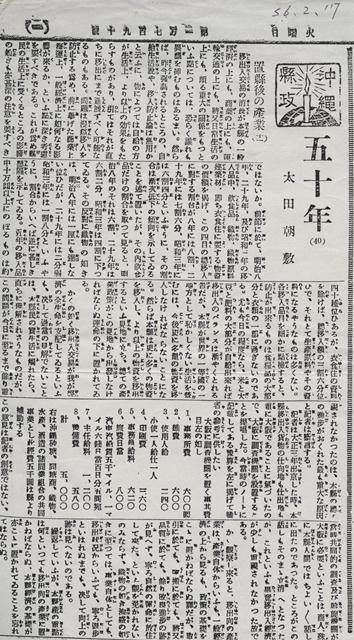
1934年4月27日ー沖縄郷土研究会(1931年1月発足。真境名安興発起)と沖縄県文化協会(1933年8月発足。太田朝敷会長)が合同、沖縄郷土協会が発足し初代会長に太田朝敷が就任。
東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡
□その後はご無沙汰致して居ります。琉球紙の25周年の記念号には広告を通しての社会観を深き興味を以って拝見しましたが今又「離れて観たるその後の沖縄」今朝は只一回しか見ないが物質生活の方面より思想の方面より政治の方面より道徳の方面より種々の形をとって現れた所謂蘇鉄地獄の種々相をえがかれた所一読直ちに「さすがは」と独り叫びました。(略)適者生存の理法は遂にこの士魂を駆逐してしまい物質主義に対しては何らこれを裁制する法則もなく、今日では全く物質的享楽という唯一残された、この思想を最も鮮明に最も適切に見ようとするなら我が沖縄が即ち帝国の縮図です。この縮図の中に一年も生活して居ると夫子自らも矢張り画中の人となり当初の感じは漸次薄らいでくるのです。環境の力の恐ろしさを今更ながら適切に感じます。
□東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡
私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云うより寧ろ民族的団体と云う見地です。(日本)国民の頭から民族的差別観念を消してしまうことは吾々に取っては頗る重要な問題だと考えて居ります。
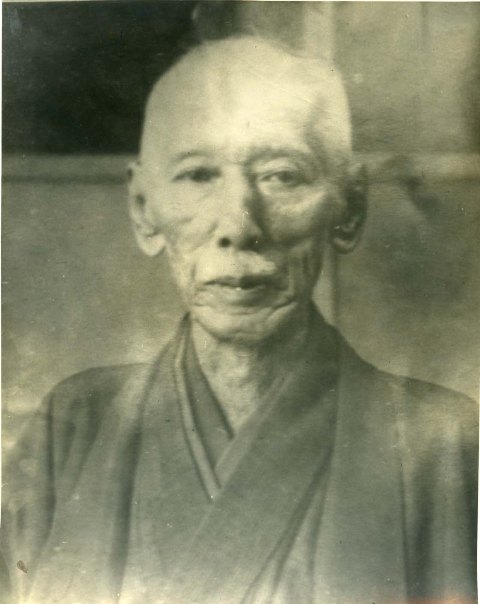
□1991年1月 伊佐真一編『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子
○(略)赤と黒の綱引きは相拮抗しており、それはそれで学問的に大いに議論をすればよいことである。だが、時として世の中にはこうした自由な言論・報道を封じ込めようとする者がいるものである。たとえばその一例、この赤黒論争が新聞紙上や巷間でにぎわっていたころ、沖縄総合事務局開発建設部の村山和義公園調整官から、18名の元委員に宛て、首里城にかかわる発言を統制しようという文書が出されている。その内容は、首里城正殿及び公園に関する出版物の刊行、公演、取材等多岐にわたる「マスコミ等への報道」を「公園調整官を窓口として一本化」するというものであった。これに対して、又吉真三氏と前田氏と前田氏はただちに抗議を行ったが、事の重大さに気づいた当局は6月12日付で、先の文書の廃棄処分するに至った(『琉球新報』1989年7月25日付夕刊)。戦前の大政翼賛会まがいの行為をしたわけであるから当然といえば当然である。(略)
□2009年10月 屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』世織書房
○(略)高良倉吉氏のそのような直接的な政治的役割にかんしてではない。琉球史研究という学問的意匠による非政治的立場を装いながら、きわめて政治的な役割を果たしている、その<政治性>の問題についてである。それは、党派的な主義主張やイデオロギーなどの「政治性」とは位相」を異にした、関係における認識や解釈などの<政治性>の問題である。
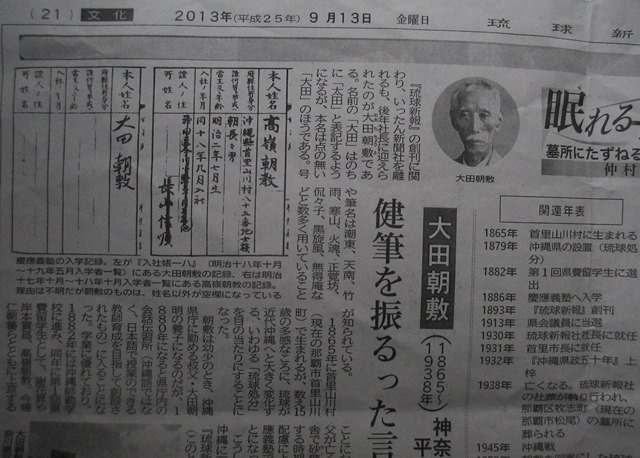
2013年9月13日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー大田朝敷」
□ヒロの滞在は悠々保養のつもりであったがヒロ市在留の県人もなを 席の宗教談でも聞きたいという希望があり、ホノムの佛教婦人会からも今一回講演して貰いたいと云う頼みが来たので、これも何かの因縁と思うて快く引き受け、この二席の講演は愈々お名残の講演であるから、多少趣きを加え金儲けと宗教を結びつけて話した。
ハワイに来て居る人々の多くは何れも金儲けを目的として来たに相違ないが、さて佛教に於いてもキリスト教に於いても、その他の宗教に於いても、教壇から金儲けの話しをすることは余りしないようだ。ところが金と云う奴は実に重宝なもので、誰でもこれが嫌いなものは居ない。佛教の或る開教師がしこたま金をためて帰ったそうだが或る人がそれを難したら、その坊さん平然として曰く「佛と云う字は人偏に弗と云う字じゃないか」この坊さんの如きは寧ろ正直の方で、金に執着がないような顔をして居る宗教家中にも、その実内ふくのものが可なり居るようだ。
要するに金を得たいというのは万人が万人共通の欲望だ。吾々の前に開けられている広い広い道は、只この欲望を満足する活動の為に開かれたかのように思わるる位いだ。ところがこの広い道には人の目に見えぬ陥穽もあれば深淵もあり所によっては毒蛇も居れば猛獣も居る。世の中には金儲けの上手と言わるる人が随分多いが、これらの人々は畢竟この危険極まる道の案内をよく知って居るのだ。
陥穽や深淵をよけて通り、毒蛇や猛獣を避け、然も相当に欲望を充たし得るのがマア世渡り上手と言ってよかろう。世渡り上手と云へば一種狡猾なわるがしこい人間のように考えるものが多いようだがこの種の人間はうまく世を渡ろうが、儲け口にありつこうが、それは外面だけのことで内面に於いては常に四苦八苦で少しも満足を得て居ない。
佛教に自利々他の覚行 云うことがあるが、ここに利と云うのは坊さん達に言わすと物質から離脱した精神的の利に局限されて居るが私はそうは見て居ない。詰まり二方に渉った自利々他である。自らも利し他も利する自利共利の道を求むる所に宗教もあり道徳もあるのだ。宗教家はややもすれば消極的にこの危険を避けようとする。殊に佛教徒中には禁欲を根本本義と考えて居るものが多いが、それは佛教の根本義を知らないからだ。
これは私独創の見ではない、佛も一切法は観を根本と為すと説かれてある。欲を殺してしまったら活動はないのだ。既に活動がなければこの世界に生命と称すべきもののある筈はない、即ち世界の死滅だ。然もこの欲を充たす道は自らも利し他も利し自他共に利する所に佛教の眞精神は存するのである。危険を避けて安全に通られる世渡りの自道も此の処に開かれているのである。私の信ずる所の佛教はこれであるから私はこの根本義を宣伝したのだ。
ハワイ各島の中でハワイ島は近来非常に宗教熱が盛んで我が県人を中心とする「真宗深信協会」と称する団体もありその例会の時には三四十哩から出席するのもある。私はかかる状態を見て私が佛教を味わって居たことを多幸と思うた。若し私に佛教の思想がなかったならばハワイ各島の巡講中県人に対するのは兎や角お茶を滑し得たとしても所謂一般講演の場合には聊か困ったらうと思った。
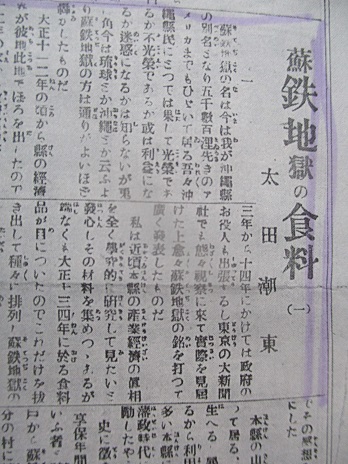
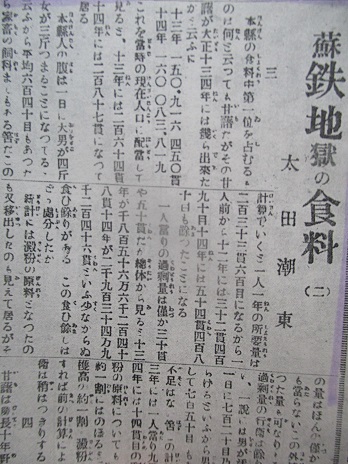
1927年10月13日『沖縄朝日新聞』太田潮東「蘇鉄地獄の食料」
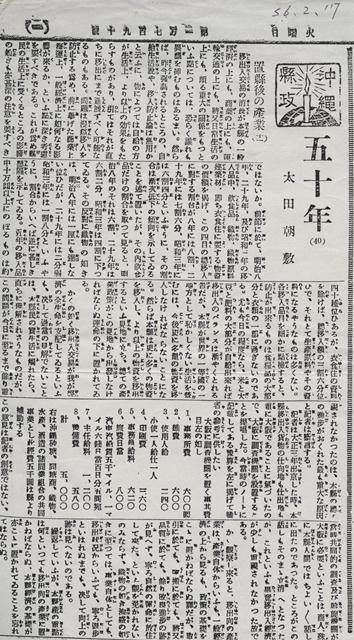
1934年4月27日ー沖縄郷土研究会(1931年1月発足。真境名安興発起)と沖縄県文化協会(1933年8月発足。太田朝敷会長)が合同、沖縄郷土協会が発足し初代会長に太田朝敷が就任。
東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡
□その後はご無沙汰致して居ります。琉球紙の25周年の記念号には広告を通しての社会観を深き興味を以って拝見しましたが今又「離れて観たるその後の沖縄」今朝は只一回しか見ないが物質生活の方面より思想の方面より政治の方面より道徳の方面より種々の形をとって現れた所謂蘇鉄地獄の種々相をえがかれた所一読直ちに「さすがは」と独り叫びました。(略)適者生存の理法は遂にこの士魂を駆逐してしまい物質主義に対しては何らこれを裁制する法則もなく、今日では全く物質的享楽という唯一残された、この思想を最も鮮明に最も適切に見ようとするなら我が沖縄が即ち帝国の縮図です。この縮図の中に一年も生活して居ると夫子自らも矢張り画中の人となり当初の感じは漸次薄らいでくるのです。環境の力の恐ろしさを今更ながら適切に感じます。
□東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡
私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云うより寧ろ民族的団体と云う見地です。(日本)国民の頭から民族的差別観念を消してしまうことは吾々に取っては頗る重要な問題だと考えて居ります。
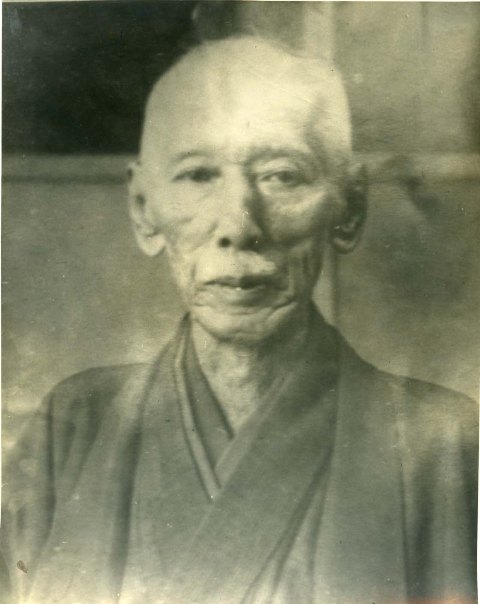
□1991年1月 伊佐真一編『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子
○(略)赤と黒の綱引きは相拮抗しており、それはそれで学問的に大いに議論をすればよいことである。だが、時として世の中にはこうした自由な言論・報道を封じ込めようとする者がいるものである。たとえばその一例、この赤黒論争が新聞紙上や巷間でにぎわっていたころ、沖縄総合事務局開発建設部の村山和義公園調整官から、18名の元委員に宛て、首里城にかかわる発言を統制しようという文書が出されている。その内容は、首里城正殿及び公園に関する出版物の刊行、公演、取材等多岐にわたる「マスコミ等への報道」を「公園調整官を窓口として一本化」するというものであった。これに対して、又吉真三氏と前田氏と前田氏はただちに抗議を行ったが、事の重大さに気づいた当局は6月12日付で、先の文書の廃棄処分するに至った(『琉球新報』1989年7月25日付夕刊)。戦前の大政翼賛会まがいの行為をしたわけであるから当然といえば当然である。(略)
□2009年10月 屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』世織書房
○(略)高良倉吉氏のそのような直接的な政治的役割にかんしてではない。琉球史研究という学問的意匠による非政治的立場を装いながら、きわめて政治的な役割を果たしている、その<政治性>の問題についてである。それは、党派的な主義主張やイデオロギーなどの「政治性」とは位相」を異にした、関係における認識や解釈などの<政治性>の問題である。
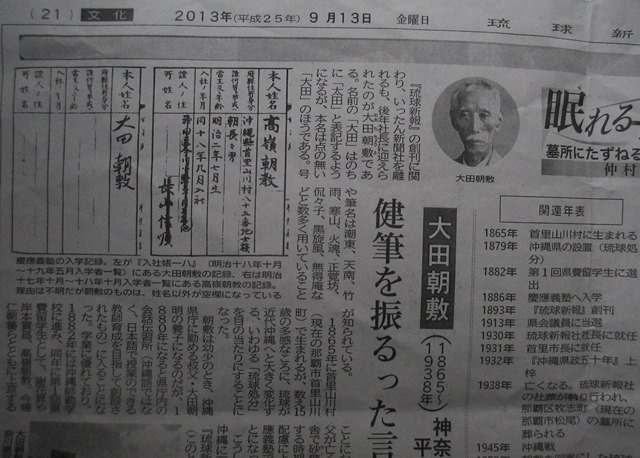
2013年9月13日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー大田朝敷」
04/15: 沖縄コレクター友の会②
2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。
03/25: 1928年2月 南島研究会『南島研究』創刊号
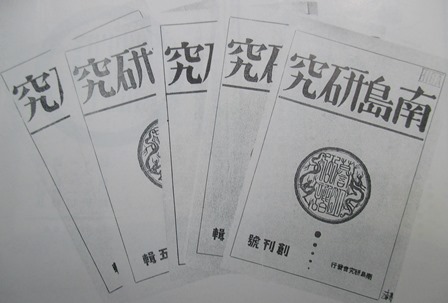
写真ー『南島研究』
南島研究発刊について
世界の文明が、地中海からして大西洋に移り、それから今や漸く太平洋に転ぜんとしつつあるといふ、所謂過渡期に於いて、この太平洋に裾を洗われて居る我が日本の先覚者が、太平洋問題を提げて学界に馳駆せようとせらるることは、近来の痛快事である。これ地中海①に七十倍し、大西洋に二倍するといふ、范々たる大海原のうちには、あらゆる気候とあらゆる人種、あらゆる文化が宝蔵されて居るからである。而して九州の南端から奄美大島を貫いて、東北よりして西南に延び、数十顆の連珠のやうな大島小嶼が、宮古島を経て八重山島の与那国島に至って尽き、この面積が百三十九万里を算しているのが、即ち我が沖縄群島である。この外にも、今から三百余年前に、政治的に切り離されて、鹿児島県に隷属して居る奄美大島諸島も、亦天然の配置としては、往古より琉球王の治下に属し、その人情風俗言語習慣などより考察しても、純然たる琉球人であることは、誰しも首肯せられるだろうと思われる。これらの群島は、東は一帯に太平洋に面して、北は鹿児島県に隣接し、南は一衣帯水の台湾と相呼応し、西は海を隔てて南支那の福建省と相対峙し、而して西南の方は遥かに南洋群島を顧望して居るのであるから、面積の割合にその拡がりは、なかなか大きいように観ぜられるのである。これらの主島が、今日の所謂沖縄島で、我邦本土では、既に一千余年前に於いて、阿児奈波島として知られ、国史とも多くの交渉を保って居るようである。のみならず記録にあらわれた時代からしても、既に五六百年から支那本国や安南、暹羅、馬刺加、朝鮮なども交通し、また爪哇や、比律賓などの南洋諸国とも貿易をやっていたのであるが、之れらは今から三百余年前の所謂薩摩と附庸関係を生じた慶長の役を末期として断絶してしまったのである。
斯やうに沖縄は、往古からして我が本土とは勿論密接な関係があり、また支那本国や南洋諸島などとも関係を有していたために、之れらの影響をうけたのであらうか、一種独特の文化を生んだ一島国であったのである。が交通が不便で顧みられなかったために、今古千年の夢は封ぜられ、恰も武陵桃源のやうな仙境にあったので、外界から能くその真相を知られる機会がなかったのである。それが、幸か、不幸か、その地理的環境のために、能く外国の文化を我が本土に伝へる中継場となると同時に、また我が本土の古文明を忠実に保存する倉庫のやうな、作用をなしていたのである。併しかやうな、神秘的な島国も、廃藩置県後の文明の風潮には、抵抗することが出来なかったやうで、所謂新文明の醗酵すると共に、古琉球の文化は危機に瀕した時代もあったのである。即ち一知半解の徒輩が琉球研究を以て復古思想の再燃と誤解し、古文書の棄却や、名所旧跡の破壊が到る所で企てられ、将に薩州治下に於ける、奄美大島の覆轍を踏まふとしたのであった。
此時に当ってー即ち明治二十五六年頃ー県の中学校に教鞭を執られて居った田島利三郎氏や新田義尊氏や黒岩恒氏などが、琉球の過去現在に趣味を持たれて、その歴史や、歌謡言語及び自然科学などの研究をはじめ出して、漸くこれが価値づけられて、彼等の自覚を促がしこれと前後してわが分科大学講師のチャンバレン氏等も亦渡琉せられて研究をされたのである。是から引きつづいて幣原坦博士や、鳥居龍蔵博士・金沢庄三郎博士なども来県されて、各部門の研究を発表され、暗黒なる琉球が漸く光明へ出されるやうになったのである。而してこれより先土着の沖縄人にも、亦故喜舎場朝賢翁や山内盛憙翁などのやうな郷土研究家もあったけれども、之れが最も高潮されたのは明治の末期からで、即ち畏友伊波普猷氏や、東恩納寛惇氏や、故末吉安恭氏等の研究であったやうに思はれる。これから、古琉球の文化が漸く識者の間に認めらるるやうになったが、未だ一般には徹底しないで疑心を以て迎へられたようであった。然るに最近に至り、柳田国男氏や、伊東忠太博士、黒板勝美博士等の来県があり、これら巨擘を中心として在京諸友は勿論県外の人では、畏友鎌倉芳太郎氏などが、その専門の立場からして、熾に中央で琉球の文化を紹介せられ、又南島談話会なども生まれて東都に於ける琉球研究者の機関も出来るやうになり、殊に啓明会などの財団法人もその研究に同情されて資金を投ぜられ、これで一層鼓吹されたやうに思はれる。
而して琉球研究は、その本場を離れて、中央に持ち出された喜ばしい現象であるが一方郷土に於ても亦之れが閑却せられているといふ訳ではない。逐年この種の研究や紹介は、却って熱烈さを加へて進んでゆくやうであるけれども、之れが機関となるべき定時刊行物がなかったのを最も遺憾とする次第であった。然るに、今回微力を揣らず、吾々同人が主となって、此の「南島研究」といふ小冊子を刊行する機運になlったのは、相互にその研究を援助してこれを発表批判すると同時に、広くこの種研究家の声援を得て、その内容を豊富にし、且つ琉球に関する、滅びゆく古今の研究資料を蒐集して附録とし、広く一般学界の参考に供したい為である。この恵まれたる地理的環境からして、日支文明の交叉点ともいはれまた我邦文化の中継所となり、倉庫ともなった南島、即ち奄美大島から八重山の先端与那国島までの島彙が吾々の研究に資すべき舞台面である。が、この未開拓の曠野からして、何か新生命が見出されて、我が学界に光を投じ得るや否やは、未来の問題で、切に識者各位の熱誠なる御同情と、御後援を待つばかりである。 十一月廿日 県立図書館郷土資料室にて 真境名安興
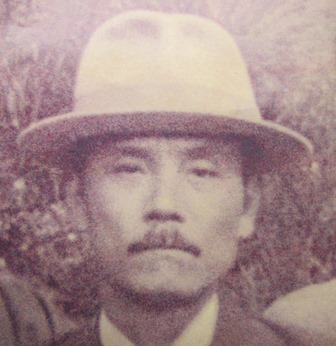
写真ー真境名安興
目次
口絵「泉崎及び金武の火神」
○編集者よりー資料や文献は割拠して居る、系統的に出来た索引のないことはその資料及文献の蒐集に不便な、地方の孤独な研究家をただ空しき努力に終わらせるばかりだ。と云ふことはしばしば吾等が聞く言葉でありました。即ち既に何人かの手によって研究、発表せられた事柄を、これから準備し、これから研究し、かくて仔々倦まざる多年の努力が空しき結果に終ると云ふことになると、本人ばかりの失望でなく、同じ研究者の一員としても見るに忍びないところであります。かくの如き有様でありますから、われらの念頭からは絶えず、何等かの方法で、かかる孤立の研究者たちと連絡をとり、各自の分担的研究を漸次進めて行きたいと云ふ念が去りませんでした。
そこに生まれたのが南島研究でした。なるほど本誌は小冊子ではあり、特に南島研究と銘をうってはありますが、吾等は目を睜つて南島を見たい、そして南島から広い世界を見たいのであります。本誌の主義も、事実の忠実なる採録、文献の尊重と比較研究法の正確を期することに重きを置きたいものだと思って居ます。かくて本誌は読者諸君の本誌であり、又諸君の薀蓄を傾け、互に幇助示導しつつ、吾等の拠るべき、向ふべき道を進んで行きたいのでありまして、吾等は零碎なる報告、交詢の類と雖も克明にこれを雑誌に網羅するに吝ではないのであります。吾等の雑誌は割拠もしなければ、対峙もしない、どこまでも吾等の過去及び現在の記録としたいものであります。
本誌の誇として特筆すべきは、古琉球に関するあらゆる史料の採録で、これのみにても既に一大事業ー吾等としてはーと云ふに恥じないつもりであります。本号から「琉球國中山世鑑」「球陽遺老説傳」「東汀随筆」の三種を採録しました。これは読者諸君の便をはかり、まとまった一冊の本に製本の出来る様に丁附を別にしてあります。
史論・雑録
南島研究の発刊について・・・真境名安興/奈良帝室博物館の雲板について(琉球國王尚泰久の鋳造)・・・真境名安興/火神の象・・・奥野彦六郎/沖縄の士族階級・・・島袋全発/昔の蘇鉄地獄・・・T生/鬼餅伝説(ホーハイに就いて)・宜野湾新城のムーチー/歴史は繰返すー蔡温の林業政策ー/「あこん」に就いて・・・岩崎卓爾/萬葉歌と琉歌・・・エス・エス生
史料
1、琉球國中山世鑑 2、球陽遺老説傳 3、東汀随筆
通信
柳田國男氏より盛敏氏へ/伊波氏より島袋全発氏へ/東恩納氏より真境名笑古氏へ/岩崎氏より真境名氏へ
莫夢忌/1924年12月14日 『沖縄タイムス』仲吉朝助「嗚呼末吉君」
○此の二三十日来、私は俗務に追われて末吉君と面会せなかった。然るに去る9日の夕刻、突然に君の生命に関する不安の噂さを聞いたのでマサカとは思ったが先ず念のためにと君の親友なる小橋川南村君を夜中に訪ふた、南村方で漢那浪笛と小嶺幸欣君とそして主人が鼎座して悲痛の面持ちで打ち沈んでおったが、南村君は私に「只今末吉君を葬送して帰って来たばかりだ」と語ったが、私は自分の耳を疑って、2回も3回も繰り返して聴いて終に君が此の世の人でないことを知った。嗚呼末吉君、君には永久に逢うことが出来ぬのか、私は何とも形容の出来ぬ不安の心持ちでしばらく沈黙して、只だ自分の心臓が波高き鼓動を聞くのであった。吾々4人は沈み勝ちに君の在り世の事ども語りつつ私は夜半の1時過ぎに愴悽たる寒月の冷光に照らされて宅に帰ったが君の面影は眼前にチラついて殆ど夜明まで一睡もせなんだ。ドーしても私は末吉君の死んで居ることを信ずる事は出来ぬ、私の胸裏には今に末吉君は生きて居る、恐らくは苟も学芸の一端でも知って居る我が沖縄人の頭に君は永久に生きて居るであろう。
末吉君、博聞強記で特に琉球文学界の権威であったのは私の申すまでもないことで今更に喋々せぬ、君は天才であって同人間には可なり逸話も多い。私と君とは殆ど十六七年来の知り合いで、君と謹談した機会も相当に多いが、私は君より殆ど二十も年上である関係で君は九骨なる私に対しても常に先輩を以て過ごするので私としては愧ち入って居た、宴席などでも君は私などに対しては無邪気なイタヅラなどもせなかったので、私は君の逸話の材料を持って居ない。ソレ程君が私に対して尊敬の心持ちで交際して呉れた程私は君に対する哀悼を深刻に感ずる次第である。君は文芸上の趣味は頗る多い。この七八年間君は漢詩の研究にも手を染めて来た、私も漢に就いては下手の横好きで漢詩に関して君と数々話し合って居たが先月の中旬頃 図書館で君と面会した、コレは最後の面会であった、其の際 私は君に向かって「万葉」の講議を聞かして貰いたいと頼んだ処、君は謙譲の態度で二三回遠慮したがトウトウ私の持って居る清朝人の四五種の詩集を貸すとの交換条件で来年1月頃から君は私の為に「万葉」の講議をして呉れることを承諾して居た。嗚呼 私は永久に君の万葉講議を聴くことが出来なくなった。
タイムス社の上間君から末吉君に関する私の感想を書いて欲しいとの申込を受けて筆を執ったが、今に末吉君の面影が眼前にチラついて万感が胸に迫るので、私は筆を此辺で止める。嗚呼末吉君、君には果たして永遠に面会することが出来ないのか。
仲吉朝助(1867年4月6日~1926年9月3日)

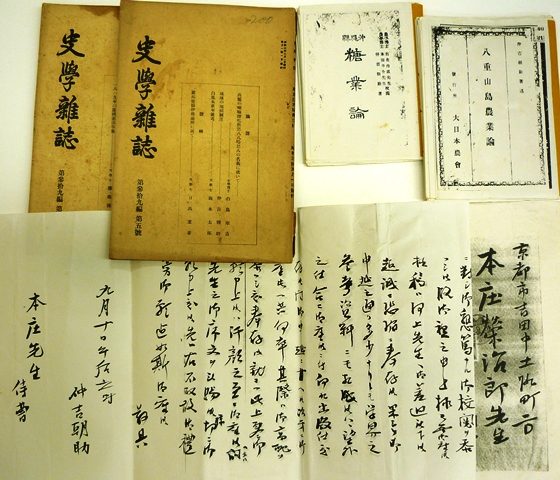
本庄栄治郎 ほんじょう-えいじろう
1888-1973 大正-昭和時代の経済史学者。
明治21年2月28日生まれ。大正12年京都帝大教授。昭和17年大阪商大学長。戦後は上智大,大阪府立大の教授を歴任。近世日本経済史・経済思想史を専攻。日本経済史研究所を設立して後進の育成にもつくした。「本庄栄治郎著作集」がある。40年文化功労者。昭和48年11月18日死去。85歳。京都出身。京都帝大卒。(→コトバンク)
01/04: 西平守晴・雇用主協会事務局長

1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』


1963年1月 『月刊沖縄』「はだかのインタビュー①比嘉良篤」
○・・・月刊沖縄の、西平守晴関西支局長がきた。大阪の県人有志が、集団就職できている若い人たちを、夜学にでも行かせようと、今、基金を作っているから、アドバイスしてくれーという西平氏の話には一も二もなく賛成した・・・。

1964年3月『オキナワグラフ』「座談会ー沖縄娘は働き者」(西平守晴・雇用主協会事務局長)

1964年7月『オキナワグラフ』「大阪沖縄県人連合会主催/第二回関西沖縄芸能祭(企画編成・西平守晴)」

1965年11月『オキナワグラフ』「大浜先生の栄誉を讃えてー勲一等を祝う大阪の会」

1966年 左側手前から喜納政泰、安里嗣副、比屋根有信、西平守晴、山端立昌、名嘉正成、翁長良孝

1966年2月 『オキナワグラフ』(表紙・翁長千鶴子)「翁長千鶴子×西平守晴沖縄グラフ大阪支局長」「希望訪問・知ってもらいたい大阪の愛郷心ー翁長良孝氏」



○1969年11 『オキナワグラフ』「大阪のリーダー翁長良孝さん逝く」


1966年5月『今日の琉球』外間政章「ぺルリ提督の首里城訪問」

1966年6月『オキナワグラフ』「共感を呼んだ松岡構想」(大阪松友会事務局長)

1966年7月『今日の琉球』「ぺルリ提督の首里城訪問を再現」
1967年3月19日『サンケイスポーツ』「座談会ー働く沖縄青少年のために」(司会・西平守晴)
1967年





5月26日『琉球新報』「私費で『沖縄関係資料室』つくる大阪・西平守晴さん」/5月、沖縄八重山芸能公演会(西平守晴企画構成)

1968年6月『今日の琉球』「那覇商工祭を飾るぺルリ仮装行列」

1968年10月9日『沖縄時報』「大阪に沖縄関係資料室を開設」
11/01: 沖縄写真史散歩

1992年9月16日ー『沖縄タイムス』
講談社の『日本写真年表』に「1853年(嘉永6)年、5月アメリカのペリー艦隊の従軍写真師Eブラウン.Jr琉球を撮影する」とあり、また那覇のニライ社から刊行された『青い眼が見た「大琉球」』の中にその撮影状況の石版刷りが掲載されている。
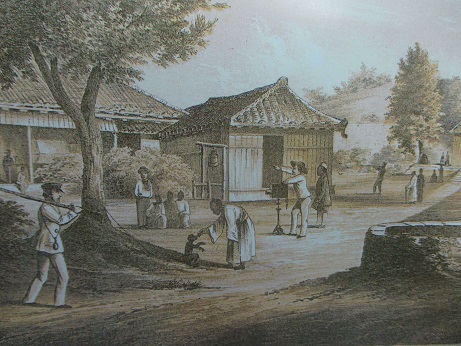
1875年(明治8)年に松田道之と琉球処分で来琉した河原田盛美の『琉球紀行』に「写真は既に垣田孫太郎なるもの創めたれとも之を内地に輸送せさるは亦全き利を得るに至らさるなり」とあり、垣田という鹿児島商人の手によって沖縄での写真屋は始められたが短命であったようだ。
現時点で見られる沖縄写真屋の最初の広告は、1895(明治28)年の『袖珍沖縄旅行案内』所載の「岩満写真場ー那覇東村上の倉」で後の上之倉写真館である「那覇東村上の倉・岩満写真場「写真ー琉球絶景の眞趣を穿つは写真なり弊店写真中優等なる者は首里城、中城殿、師範学校、崇元寺、波の上、墓所、辻遊廓、市場、通堂浜、那覇市街、吾妻館、奥武山、港口、三重城中島海岸、蓬莱山なり琉球の眞景を知り度き人は続々御注文を乞う」とある。この沖縄旅行案内には旅店遊廓及び割烹店も紹介されている「遊廓ー辻を第一とし中島渡地之に次ぐ辻にて」有名なるものは荒神の前大福渡名喜伊保柳香々小新屋染屋小等とし又内地芸妓を養ひ宴会の席に侍せしむる所を通堂とし辻中島渡地を通じて貸座敷631戸娼妓1442人芸妓辻9人中島4人又通堂の貸座席兼割烹店は東屋芸妓21人を有し常盤芸妓9人小徳芸妓10人海月3人合計46人」、演劇場は「本演芸場中毛演芸場壬辰座及び首里演芸場等なり開場は毎日午后2時より6時半より12時迄木戸銭は晝四銭夜三銭場代とてはなし」とある。同書発行5年前の1890年『沖縄県統計』を見ると写真師のところに那覇2人となっている。
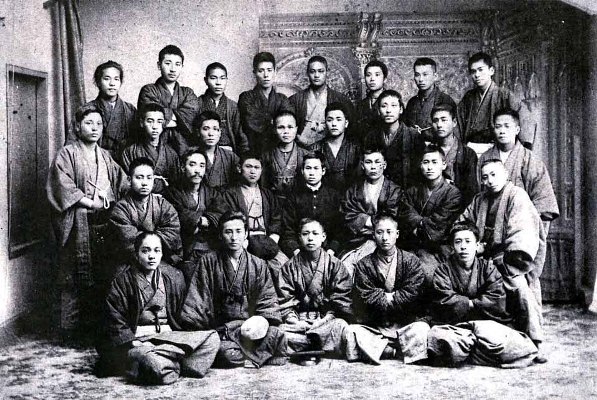
沖縄青年会卒業生送別会記念写真ー1896年4月2日/前列右2人目・宮里良盛、4人目・渡久地政勗、2列右から4人目・高良隣徳、3列右2人目・山城正擇(後に写真師)、5人目・富川盛睦ー沖縄県立図書館所蔵
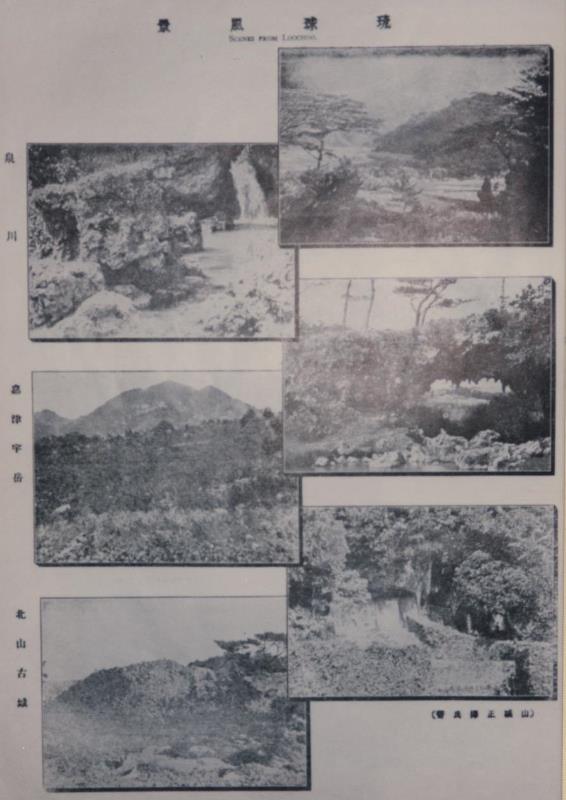
1900年2月 『太陽』第6巻第2号 山城正澤撮影「琉球風景」
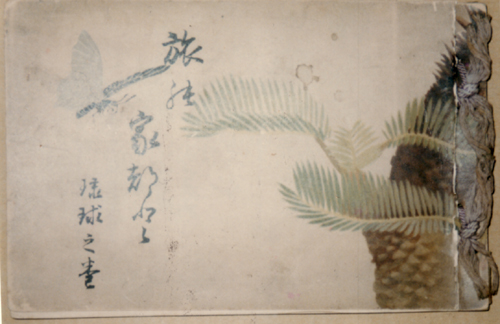
1901年2月ー写真集『旅野家都登』第35号(琉球之巻・中山門、守礼門)□発行所は光村利藻。光村は1893年に慶応義塾入学、そこで渡部乙羽、巌谷小波と親しく交わる。

1901年6月『東京人類学会雑誌』加藤三吾「沖縄通信(をがん、仮面、舞踊、丸木弓、古鏡、曲玉等の)ー1月27日の日曜に小生は那覇写真師・山城正澤並に琉球新報主筆・太田天南(両人とも沖縄人にて太田氏は慶応義塾出身に侯)同道にて参り山城は其外面一部を撮影致候」
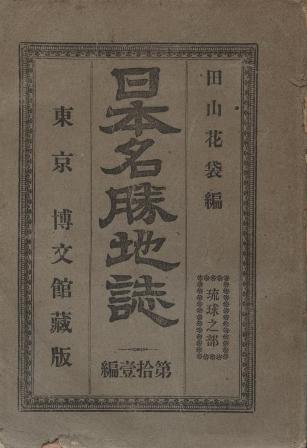
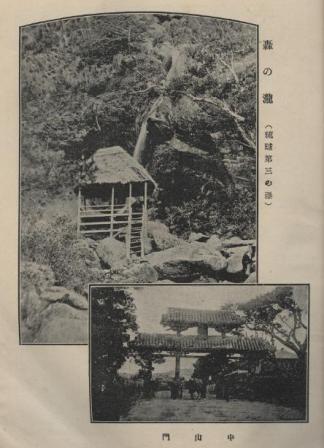
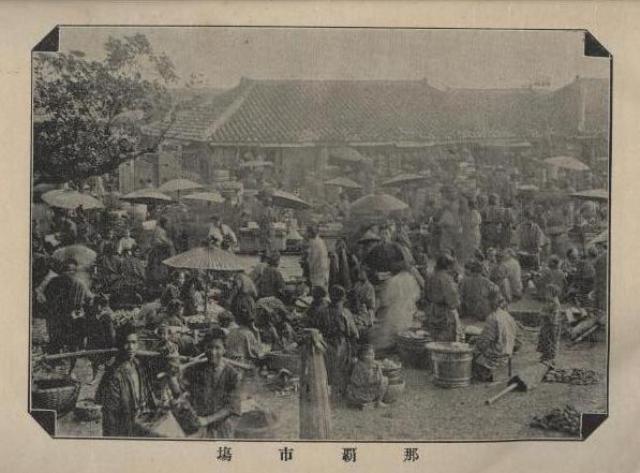
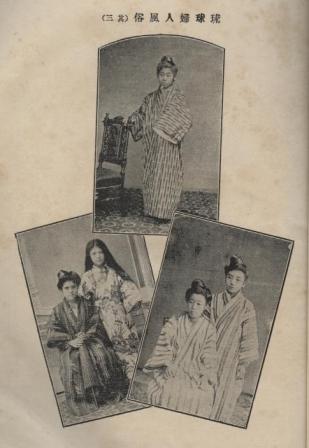
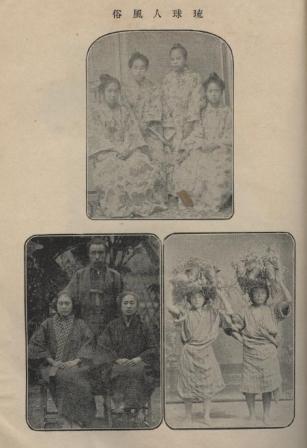
1901年11月ー田山花袋『琉球名勝地誌ー琉球之部』博文館
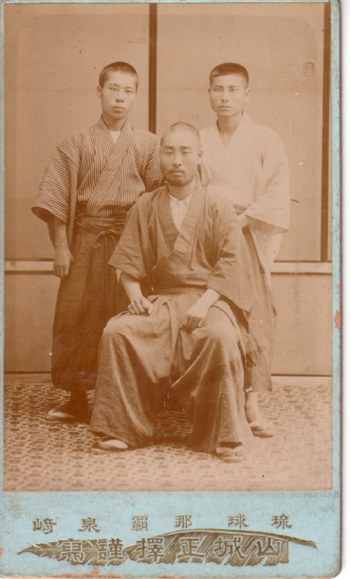
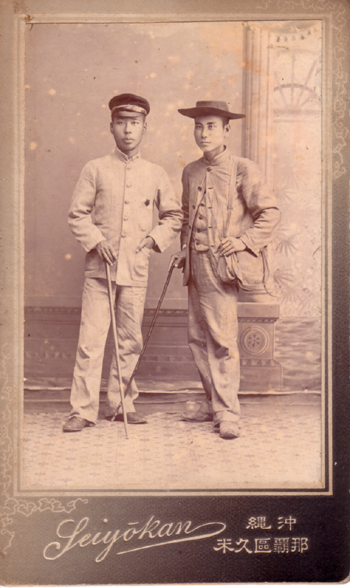
山城正擇写真館/清容館(吉村貞)

1900年4月28日ー写真左から小嶺幸得、渡久地政勗、小嶺幸慶、前列左から渡久地政憑、小嶺幸秀、幸厚(山城正擇謹写)
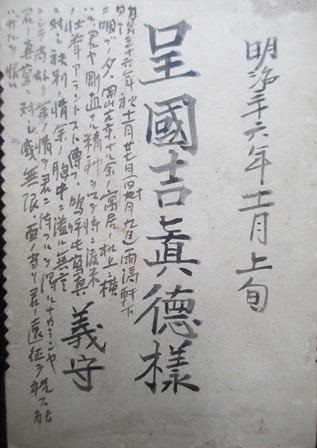
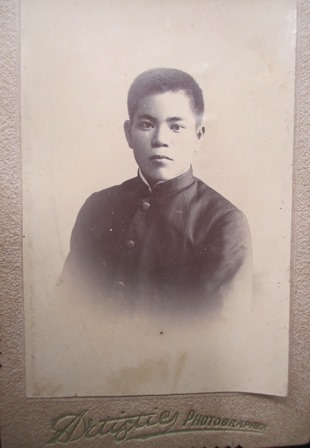
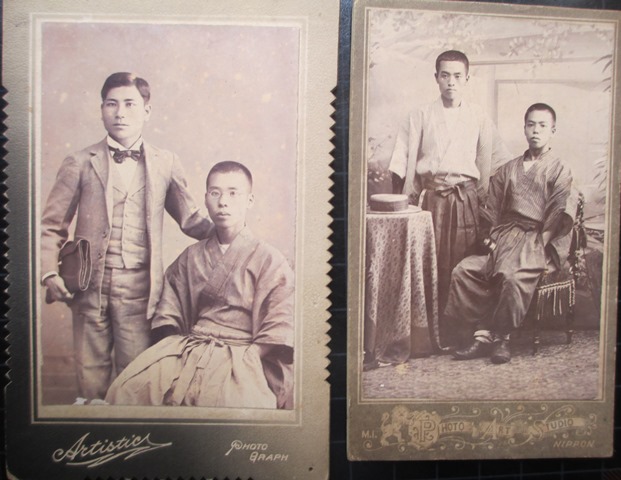
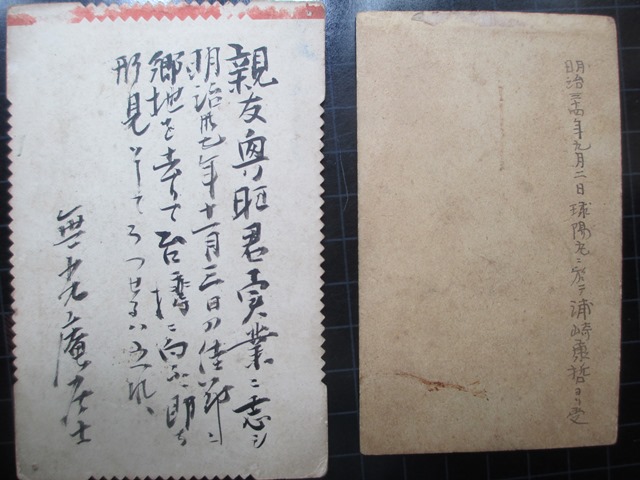

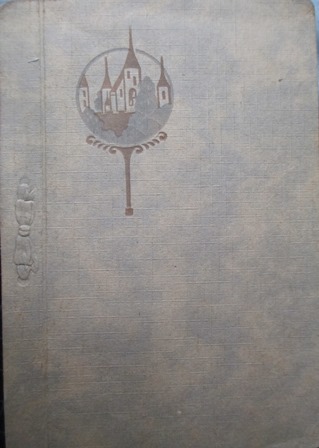
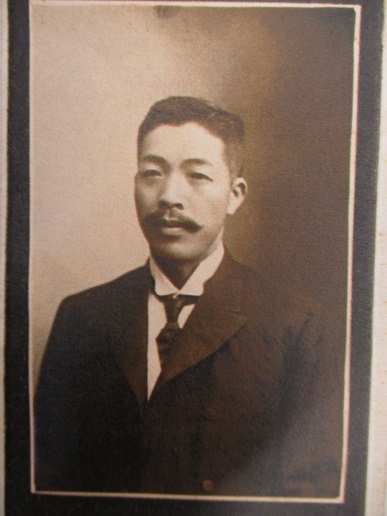
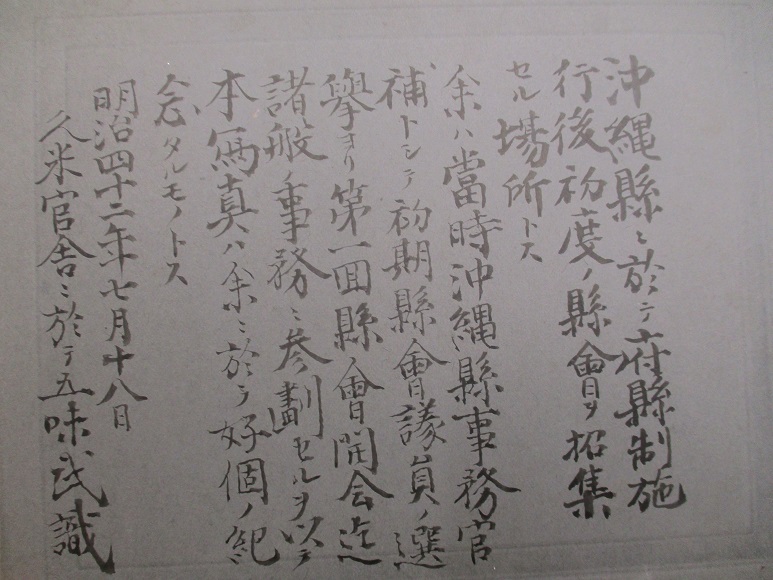



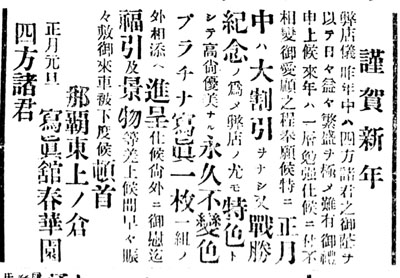

〇那覇上之倉春華園謹製「沖縄縣會議場」(山梨県甲府市の五味武子孫より公文書館の久部良和子さんに贈られたもの)
2011年『琉球新報』伊佐眞一「沖縄と日本の間でー伊波普猷・帝大卒論への道」10月25日(39回)に、伊波普猷夫妻、金城朝永夫妻と山之口貘、伊波普哲らの写っている写真を金城朝永関連で琉文21から引用している。
11月29日(43回)に「伊波の『海の沖縄人』ー『海上王国』を喚起 沖縄人の自覚、矜持示す」とし伊波を高く評価していることに意表を突かれた。この連載は確か伊波批判が主題ではなかったか。本人に聞くと「いや、見るべきものはチャント見ている」と言うことらしい。
写真家・????宮城昇探求
宮城昇は沖縄j県第二中学校を卒業、1924年に東京高等工芸学校に入学した。
在学中の昇は1926年11月、表調社主催の写真展に「白衣を着たる少女」を出品する。27年11月には表調社第3回展覧会に「詠子さんの像」「MaKe up」を出品。同年、東京写真研究会主催の第16回展覧会に「ひろ子さん」出品し入選する。28年3月、東京写真専門学校()卒業。同年、第3回日本写真美術展覧会(大阪毎日新聞社・東京日日新聞社主催)で特選を受賞。このころ写真雑誌『フォトタイムス』に論考を発表していると思われる。
1930年10月、秀英舎(現・大日本印刷)を退社し帰郷。31年、那覇で「昇スタヂオ」開業する。
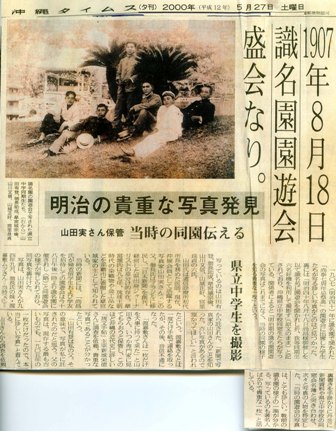
2000年5月27日『沖縄タイムス』写真人物、右から山田有登(写真家・山田實の父)、翁長助成、????宮城宗倫(写真家・????宮城昇の父)、山川文信、山城正好、宮里良貞
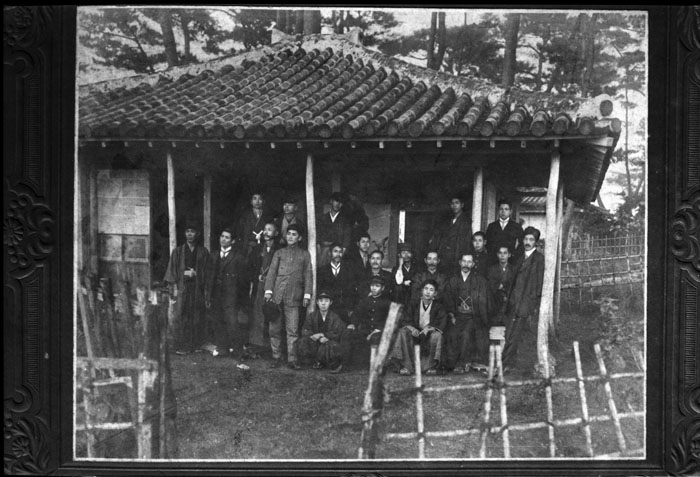
1912年2月ー太平洋画会の吉田博、石川寅治、中川八郎と丹青協会ー前列右端に座っているのが山城正綱。真ん中の柱の中列右が瑞雨。左端が比嘉崋山、右へ一人おいて兼城昌興
1
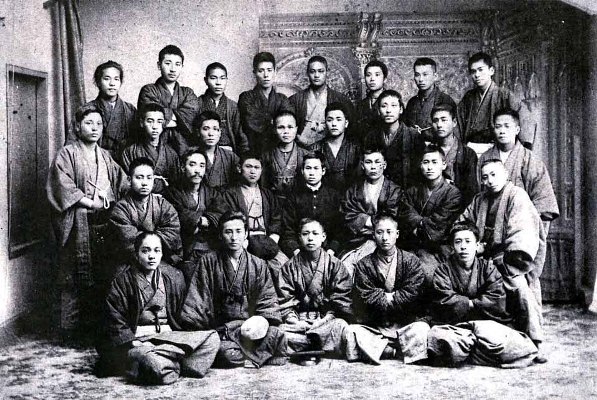
沖縄青年会卒業生送別会記念写真ー1896年4月2日/前列右2人目・宮里良盛、4人目・渡久地政勗、2列右から4人目・高良隣徳、3列右2人目・山城正擇(後に写真師)、5人目・富川盛睦ー沖縄県立図書館所蔵
富名腰義珍『琉球拳法 唐手』の処女出版は武侠社から発行された。装幀は小杉未醒、山城正綱が挿絵。山城正綱の父は山城正澤。
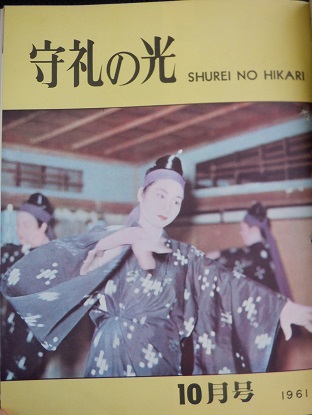
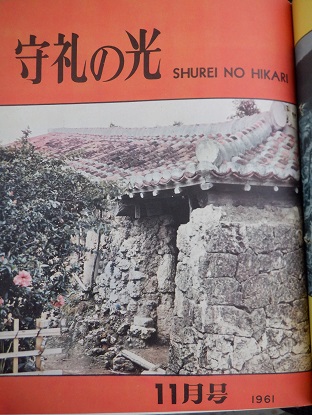
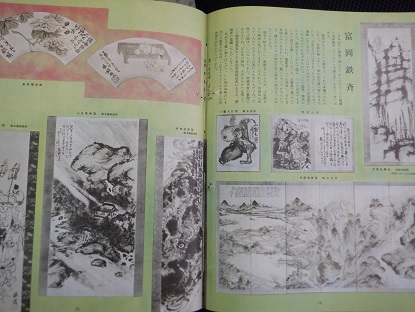
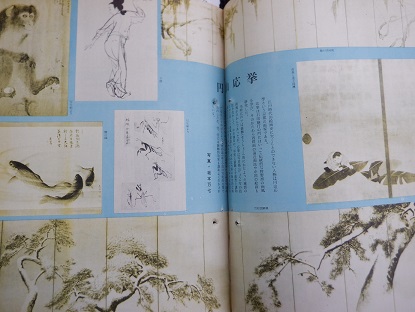
坂本万七(さかもと まんしち、1900年1月13日 - 1974年4月19日)は、日本の写真家。特に民藝品や仏像の撮影に才能を発揮した。その遺作「沖縄・昭和10年代」は戦前の沖縄各地で撮影した貴重な写真が掲載されており、テレビ放送等で資料として使用されている。
1961年 (昭和36年) 61歳 細川コレクションの中国清代文房具の撮影。水戸山上コレクションの撮影と編集。京都、奈良、島根などの美術品の撮影。円空上人彫刻資料撮影のため愛知、岐阜をまわる。戦後初の沖縄訪問をし、その変わり様に驚く。「古備前名品図譜」(河出書房新社)、「船箪笥」(日本民藝協会)。→ウィキ
※坂本万七は1960年3月から『守礼の光』に写真を載せている。〇1961年10月『守礼の光』表紙「おどる琉球美人」
〇1961年11月 『守礼の光』表紙「ぶっそうげのある風景」
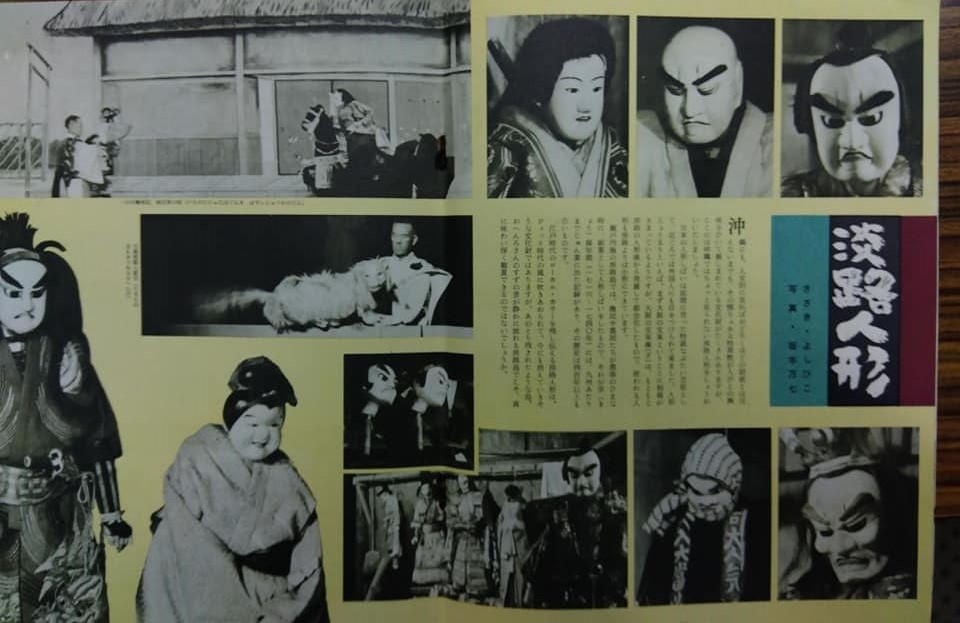
1961年2月 『守礼の光』坂本万七「淡路人形」
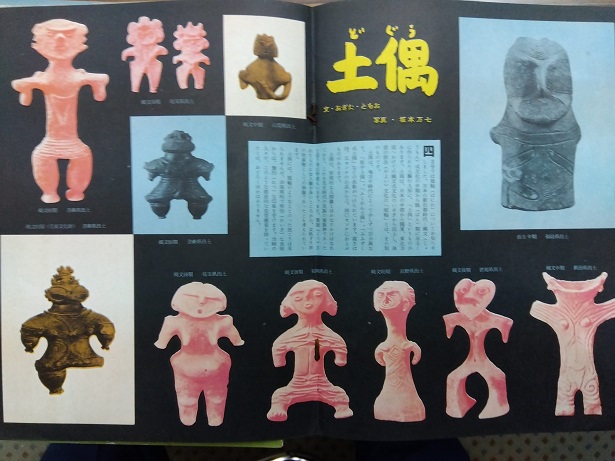
1961年5月 『守礼の光』坂本万七「土偶」

1961年8月 『守礼の光』坂本万七「高麗の水注」

1961年9月 『守礼の光』坂本万七「人形さまざま」
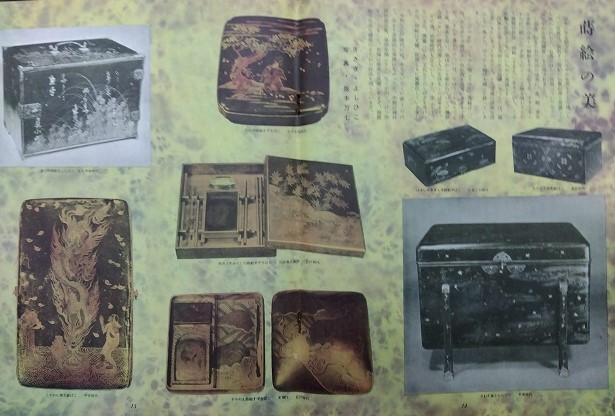
1961年10月 『守礼の光』坂本万七「蒔絵の美」
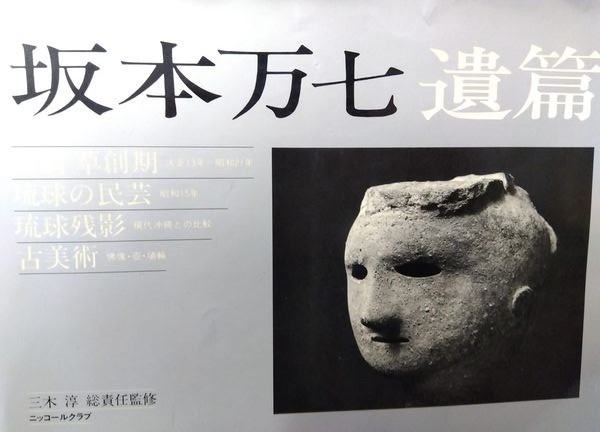

1985年3月 『写真集「坂本万七遺篇」』ニッコールクラブ
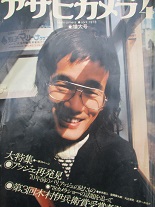
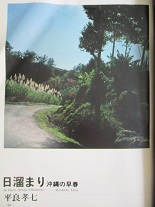



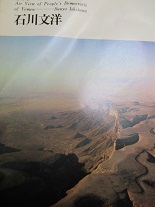

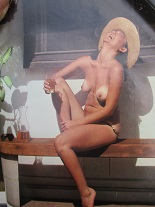
1978年4月『アサヒカメラ』平良孝七「日溜まり 沖縄の早春」
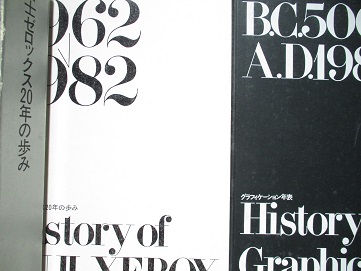
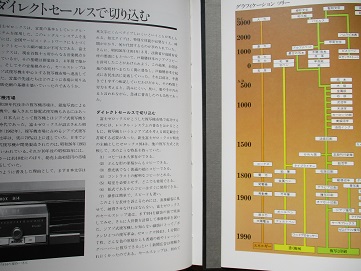
1983年4月『富士ゼロックス20年の歩み』
戦後写真集ー1979年2月『ゼロからの時代 戦後沖縄写真集』那覇出版社/1979年3月『アメリカ世の10年 沖縄戦後写真史』月刊沖縄社/1986年5月『写真集 沖縄戦後史』那覇出版社
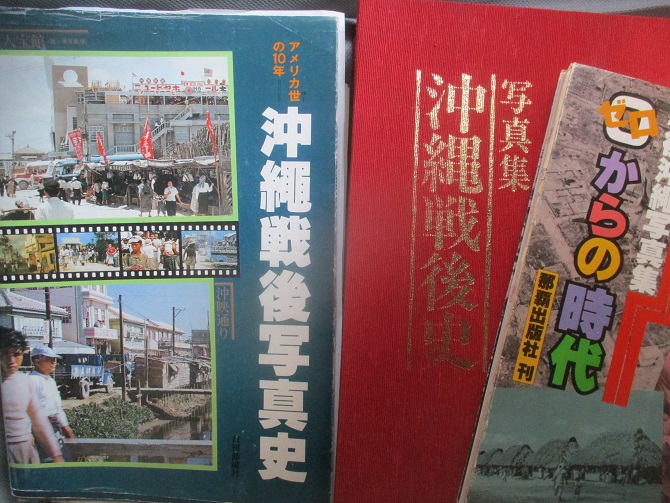
1998年12月 杵島隆『裸像伝説』書苑新社
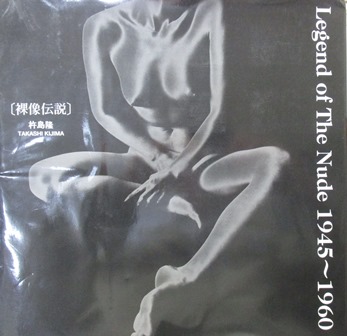
杵島隆 きじま-たかし
1920-2011 昭和後期-平成時代の写真家。
大正9年12月24日アメリカのカリフォルニア州生まれ。植田正治(しょうじ)にまなび,昭和28年ライトパブリシティに入社。コマーシャル写真を手がけ,31年フリー。29年第1回朝日広告賞,31年毎日広告写真賞,51年日本写真協会年度賞。平成23年2月20日死去。90歳。日大卒。旧姓は渡辺。写真集に「蘭」「義経千本桜」など。 →コトバンク
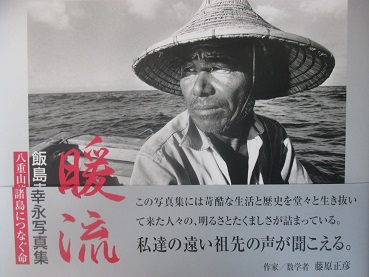
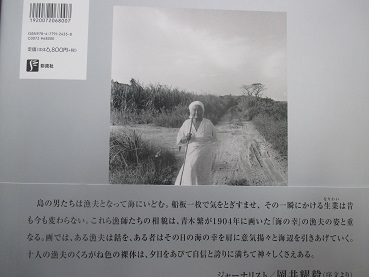
2017年11月 『暖流ー飯島幸永写真集』彩流社

1995年3月 金城棟永『私の歩んだ写真の記録』/1998年3月 『人びと 水島源晃写真集』
1953年1月、源和は東京の雑誌『おきなわ』に「ウチナー・ヌ・ハナシ」を書いた。同年3月に琉球評論社(平山源宝)から『政党を裁く』を発行。55年、源和は評論社を設け1月に『評論集・政界診断書』、4月に『沖縄から琉球へ』を刊行した。6月『話題』を創刊、創刊号の表紙は屋嘉澄子(琉舞の山田貞子門下)、源和は「空手雑話」、友を語るとして「桑江朝幸君」を書いている。同年8月、2号を発行。表紙は琉舞の上津真紀子。平みさを「南方おけ対策」、自己を語るとして比嘉秀平が「辞書をマル暗記」を書いている。話題アルバムには1898年の久孔子廟那覇尋常小学校分教場の写真、池宮城積宝や上原恵里が居るという。
『話題』3号の表紙は根路銘房子、上間朝久の「舞姫・根路銘房子嬢」、幸地亀千代「三味線と伴に五十年間」。4号は1956年4月発行で、表紙は安元啓子。話題アルバムには首里城正殿などの建物が爆撃直前に撮られた写真が載っている。永田芳子「女の幸福」、大城朝亮「辻ものがたり」、島袋光裕芸談、安里永太郎「金城珍善」、荻堂盛進「ヌード喫茶」、船越義彰「男・女・裸体」、赤嶺親助「戦塵訓」が載っている。5号は56年8月発行で、表紙は伊礼公子。玉城盛義芸談などがある。


源和は1956年3月には『手紙』を創刊した。内容は手紙形式で質問、呉我春信、護得久朝章が答えている。教科書が手に渡るまでを当銘由金が答えて「戦前の教科書はご存知のように国定で全国一律。そのために新学期の4月には桜の未だ咲かない北海道の生徒達も、既に桜は散ってしまった沖縄の生徒達も口を揃えて『サイタ、サイタ、サクラガサイタ』を学ぶという変則的な教育を強いられて来ました。こうした教育法によって国民を戦争にかりたてた」とあり今の教科書検定問題の問題はこのときから準備されていた。戦争への反省どころか戦争準備の教育に余念がない文部省ではある。永田芳子「アメリカ便り」も載っている
1956年10月発行の『手紙』は軍用地問題特集で、「干拓事業は大資源の発掘である」、「セメント製造を急げ」の記事が載っている。今では温暖化問題もあり到底受け入れることの出来ない提案である。源和は1957年3月に『事業と人物』を創刊、宮城嗣吉邸宅、沖映本館を設計した宮平久米男の紹介、「1956年主要年誌」が付いている。58年4月、『オキナワグラフ』が創刊。同年、源和は琉球果樹園株式会社を創立し社長となる。
1960年10月、『琉球画報』が創刊。61年9月、琉球画報の編集長だった佐久田繁が玉城盛英を発行人とし『月刊沖縄』を創刊した。この年は他にも金城五郎の『沖縄公論』、金城宏幸『沖縄マガジン』の雑誌が創刊されている。62年11月の『月刊沖縄』に源和は「長老会議崩壊の底辺」、12月には「稲嶺一郎伝」を書いている。63年2月は月刊沖縄のインタビューに応じ「パクリ屋といわばいえ!」、5月の『月刊沖縄』に「瀬長亀次郎伝」を書いている。1968年、源和は本部開発株式会社を創立し会長となる。
1973年5月、源和は月刊沖縄社から『琉球から沖縄へ』を再版する。75年4月の『新沖縄文学』のインタビューに応じ「仲宗根源和氏に聞くー大正期沖縄青年の軌跡」として掲載された。
□仲宗根源和は1895年、本部間切渡久地で父源一郎、母うしの長男として生まれた。手元の「仲宗根門中世系図」に大宗が仲宗根親雲上で源和はその8世、妻のところには錦子、後妻ミサヲ、子はないとある。仲宗根源和は1938年9月に東京図書から『武道極意物語』を、43年11月、萬里閣から『武道物語』を出版した。

左から 仲宗根源和、大宜味朝徳、兼次佐一、瀬長亀次郎



仲宗根源和『沖縄から琉球へ=米軍政混乱期の政治事件史=』

『話題』3号の表紙は根路銘房子、上間朝久の「舞姫・根路銘房子嬢」、幸地亀千代「三味線と伴に五十年間」。4号は1956年4月発行で、表紙は安元啓子。話題アルバムには首里城正殿などの建物が爆撃直前に撮られた写真が載っている。永田芳子「女の幸福」、大城朝亮「辻ものがたり」、島袋光裕芸談、安里永太郎「金城珍善」、荻堂盛進「ヌード喫茶」、船越義彰「男・女・裸体」、赤嶺親助「戦塵訓」が載っている。5号は56年8月発行で、表紙は伊礼公子。玉城盛義芸談などがある。


源和は1956年3月には『手紙』を創刊した。内容は手紙形式で質問、呉我春信、護得久朝章が答えている。教科書が手に渡るまでを当銘由金が答えて「戦前の教科書はご存知のように国定で全国一律。そのために新学期の4月には桜の未だ咲かない北海道の生徒達も、既に桜は散ってしまった沖縄の生徒達も口を揃えて『サイタ、サイタ、サクラガサイタ』を学ぶという変則的な教育を強いられて来ました。こうした教育法によって国民を戦争にかりたてた」とあり今の教科書検定問題の問題はこのときから準備されていた。戦争への反省どころか戦争準備の教育に余念がない文部省ではある。永田芳子「アメリカ便り」も載っている
1956年10月発行の『手紙』は軍用地問題特集で、「干拓事業は大資源の発掘である」、「セメント製造を急げ」の記事が載っている。今では温暖化問題もあり到底受け入れることの出来ない提案である。源和は1957年3月に『事業と人物』を創刊、宮城嗣吉邸宅、沖映本館を設計した宮平久米男の紹介、「1956年主要年誌」が付いている。58年4月、『オキナワグラフ』が創刊。同年、源和は琉球果樹園株式会社を創立し社長となる。
1960年10月、『琉球画報』が創刊。61年9月、琉球画報の編集長だった佐久田繁が玉城盛英を発行人とし『月刊沖縄』を創刊した。この年は他にも金城五郎の『沖縄公論』、金城宏幸『沖縄マガジン』の雑誌が創刊されている。62年11月の『月刊沖縄』に源和は「長老会議崩壊の底辺」、12月には「稲嶺一郎伝」を書いている。63年2月は月刊沖縄のインタビューに応じ「パクリ屋といわばいえ!」、5月の『月刊沖縄』に「瀬長亀次郎伝」を書いている。1968年、源和は本部開発株式会社を創立し会長となる。
1973年5月、源和は月刊沖縄社から『琉球から沖縄へ』を再版する。75年4月の『新沖縄文学』のインタビューに応じ「仲宗根源和氏に聞くー大正期沖縄青年の軌跡」として掲載された。
□仲宗根源和は1895年、本部間切渡久地で父源一郎、母うしの長男として生まれた。手元の「仲宗根門中世系図」に大宗が仲宗根親雲上で源和はその8世、妻のところには錦子、後妻ミサヲ、子はないとある。仲宗根源和は1938年9月に東京図書から『武道極意物語』を、43年11月、萬里閣から『武道物語』を出版した。

左から 仲宗根源和、大宜味朝徳、兼次佐一、瀬長亀次郎



仲宗根源和『沖縄から琉球へ=米軍政混乱期の政治事件史=』

1949年9月5日『沖縄新民報』第106号「姫百合隊の波紋ひろがるー元沖縄師範女子部兼沖縄第一高等女学校長・西岡一義(50)は教え子を特志看護婦に仕立てて軍の鼻息をうかがい(略)自らは安全な地帯に居て生徒職員は最前線に送り全滅させ、捕虜にまじって日本に落ちのびたー」
「卑劣な師範女子部長」 『月刊・潮』1971.11月号「生き残った沖縄県民100人の証言」より □仲里まさえ (当時沖縄師範女子部「ひめゆり部隊」・20 歳、現在主婦)
私たち沖縄師範女子部の生徒は、南風原の陸軍野戦病院へ看護婦として従軍するその晩、師範女子部長兼県立一高女の校長である静岡県出身の西岡一義部長の官舎の庭に集まったのをおぼえている。最後に部長は「私はこれから第三十二軍の命によって、軍司令部の参謀室に行くことになった。君たちは、先生方といっしょになって極力軍に協力してもらいたい。自分もいっしょに行きたいが、軍命では仕方がない。日本の国のために、とにかくがんばってもらいたい」という意味のことをいって、私たちひとりひとりと激励のつもりか握手を交わした。一同は感きわまった表情で、訓辞を聞いていたが、その後、事実関係が明らかになると、西岡部長はもっとも安全な首里の軍司令部に避難するために参謀室付けになるウラエ作を必死になってやっていたのである。しかも彼は、当時彼の住宅当番であった師範付属の訓導で、八重山生まれの独身の某女をともなって避難していたということも、その後明らかにされた。 …女生徒たちは、いっさいを知らずに、戦場へ臨む自らの運命にただ涙するばかりであった。





「卑劣な師範女子部長」 『月刊・潮』1971.11月号「生き残った沖縄県民100人の証言」より □仲里まさえ (当時沖縄師範女子部「ひめゆり部隊」・20 歳、現在主婦)
私たち沖縄師範女子部の生徒は、南風原の陸軍野戦病院へ看護婦として従軍するその晩、師範女子部長兼県立一高女の校長である静岡県出身の西岡一義部長の官舎の庭に集まったのをおぼえている。最後に部長は「私はこれから第三十二軍の命によって、軍司令部の参謀室に行くことになった。君たちは、先生方といっしょになって極力軍に協力してもらいたい。自分もいっしょに行きたいが、軍命では仕方がない。日本の国のために、とにかくがんばってもらいたい」という意味のことをいって、私たちひとりひとりと激励のつもりか握手を交わした。一同は感きわまった表情で、訓辞を聞いていたが、その後、事実関係が明らかになると、西岡部長はもっとも安全な首里の軍司令部に避難するために参謀室付けになるウラエ作を必死になってやっていたのである。しかも彼は、当時彼の住宅当番であった師範付属の訓導で、八重山生まれの独身の某女をともなって避難していたということも、その後明らかにされた。 …女生徒たちは、いっさいを知らずに、戦場へ臨む自らの運命にただ涙するばかりであった。





コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com



2020年3月3日 13時ー人通りが少ない ...!むつみ橋通り/市場本通り/平和通り
『琉球新報』3月4日ー県内旅行業大手の沖縄ツーリスト(OTS、東良和会長)が、観光客減少に伴う経営の悪化に伴い、県外支店を含む社員570人のうち250人について4日から業務を休ませることを決めた。/『沖縄タイムス』3月4日ー沖縄タイムス社は4日、ANAアリーナ浦添(浦添市民体育館)で21日から4月5日に開催を予定していた第72回「沖展」の中止を決めた。関連式典の表彰式や合同祝賀会などすべての行事を取りやめる。毎春開催している沖展は16日間の会期中、幅広い世代が3万人近く来場しているが、現段階で感染拡大の収束の見通しが立たないことや、作品保護のため会場の窓を開けられず十分な換気を行えないことなどから、不特定多数の人が濃厚接触する恐れがあると判断し、感染予防のため中止を決めた。那覇市港町のホテルアレキサンダーロイヤルリゾート沖縄が休業していることが3日までに分かった。ホテル入口には「新型コロナウイルスの影響で2月12日を持って休業する」との案内文が貼り出されている。ホテルを運営するアレキサンダー・アンド・サン(東京)は、取材に「担当者不在で何も答えられない」としており、再開の見通しなど詳細は不明。日本郵政が運営する「かんぽの宿那覇レクセンター」が2015年8月、経営難で閉鎖された後、アレキサンダー・アンド・サンが所有権を取得。改装した上で、16年4月に運営を開始した。
「沖縄タイムス」3-5 沖縄県の新型コロナウイルス検査で、4日夕から5日朝にかけて結果が判明した新規検査対象者6人は全て陰性だった。県内では2月20日を最後に新たな感染は確認されていない。
「日刊ゲンダイ」3-5 中国、韓国、イタリアなど、新型コロナの感染国の多くは今、季節が冬の北半球だ。しかし、真夏の南半球でも感染が広がりつつある。オーストラリアでは30人超の感染者が確認されて、ニュージーランドや、南米初となるブラジルでも先月末、感染者が出た。チリとアルゼンチンでも感染が初確認された。そんな中、気になるのが、赤道直下で高温多湿のシンガポールで感染者が100人を超えていることだ。シンガポールの人口は約560万人。感染密度はかなり高い。今のシンガポールは、気温が26~32度ほどで湿度は80%を超える。日本の初夏のような気候で感染が拡大しているのだ。
ウイルスと気温や湿度の関係について、ハーバード大学院卒で医学博士の左門新氏はこう言う。「風邪やインフルエンザなどウイルスによる感染症は通常、冬に流行します。空気が乾燥しているので、ウイルスが生存しやすいからです。例えば、乾燥により、のどや鼻の粘液が少なくなると、ウイルスを体外に排出しにくくなる。冬場、人間の体はウイルスに対して防御が弱くなるのです。季節性インフルエンザの流行は12~3月、コロナウイルスであるSARS(重症急性呼吸器症候群)も春以降、終息に向かいました。ただ、季節外れの流行も珍しくありません」
昨年の季節性インフルエンザは、晩夏から流行が始まっている。8月下旬から沖縄で流行し、9月末時点で約4500人と前年同期比6倍の患者が報告された。東京では前年より約3カ月早い9月26日に、流行開始の目安となる1医療機関当たりの患者数が1・0人を超えた。残暑の頃に、“冬のウイルス”が拡大したのだ。
「新型コロナウイルスについて、米ハーバード大の研究チームが、中国各地、タイ、シンガポール、韓国、日本の湿度と感染の関係を調査しました。低湿度で感染者が多いデータがある一方、高湿度で感染者が多いデータもあった。研究チームは『湿度と気温と新型コロナウイルスの感染力は関係がない』と結論付けています。2月末に速報で公表したため、現時点で論文としての信頼性は不十分ですが、傾聴に値する報告です。『春に終息する』という“期待”は捨て、夏まで続くことを前提に対策すべきです」(左門新氏)東京五輪の開催可否の判断は5月末がリミットといわれる。「5月終息」のシナリオは狂いそうだ。



2020年3月3日 13時ー人通りが少ない ...!むつみ橋通り/市場本通り/平和通り
『琉球新報』3月4日ー県内旅行業大手の沖縄ツーリスト(OTS、東良和会長)が、観光客減少に伴う経営の悪化に伴い、県外支店を含む社員570人のうち250人について4日から業務を休ませることを決めた。/『沖縄タイムス』3月4日ー沖縄タイムス社は4日、ANAアリーナ浦添(浦添市民体育館)で21日から4月5日に開催を予定していた第72回「沖展」の中止を決めた。関連式典の表彰式や合同祝賀会などすべての行事を取りやめる。毎春開催している沖展は16日間の会期中、幅広い世代が3万人近く来場しているが、現段階で感染拡大の収束の見通しが立たないことや、作品保護のため会場の窓を開けられず十分な換気を行えないことなどから、不特定多数の人が濃厚接触する恐れがあると判断し、感染予防のため中止を決めた。那覇市港町のホテルアレキサンダーロイヤルリゾート沖縄が休業していることが3日までに分かった。ホテル入口には「新型コロナウイルスの影響で2月12日を持って休業する」との案内文が貼り出されている。ホテルを運営するアレキサンダー・アンド・サン(東京)は、取材に「担当者不在で何も答えられない」としており、再開の見通しなど詳細は不明。日本郵政が運営する「かんぽの宿那覇レクセンター」が2015年8月、経営難で閉鎖された後、アレキサンダー・アンド・サンが所有権を取得。改装した上で、16年4月に運営を開始した。
「沖縄タイムス」3-5 沖縄県の新型コロナウイルス検査で、4日夕から5日朝にかけて結果が判明した新規検査対象者6人は全て陰性だった。県内では2月20日を最後に新たな感染は確認されていない。
「日刊ゲンダイ」3-5 中国、韓国、イタリアなど、新型コロナの感染国の多くは今、季節が冬の北半球だ。しかし、真夏の南半球でも感染が広がりつつある。オーストラリアでは30人超の感染者が確認されて、ニュージーランドや、南米初となるブラジルでも先月末、感染者が出た。チリとアルゼンチンでも感染が初確認された。そんな中、気になるのが、赤道直下で高温多湿のシンガポールで感染者が100人を超えていることだ。シンガポールの人口は約560万人。感染密度はかなり高い。今のシンガポールは、気温が26~32度ほどで湿度は80%を超える。日本の初夏のような気候で感染が拡大しているのだ。
ウイルスと気温や湿度の関係について、ハーバード大学院卒で医学博士の左門新氏はこう言う。「風邪やインフルエンザなどウイルスによる感染症は通常、冬に流行します。空気が乾燥しているので、ウイルスが生存しやすいからです。例えば、乾燥により、のどや鼻の粘液が少なくなると、ウイルスを体外に排出しにくくなる。冬場、人間の体はウイルスに対して防御が弱くなるのです。季節性インフルエンザの流行は12~3月、コロナウイルスであるSARS(重症急性呼吸器症候群)も春以降、終息に向かいました。ただ、季節外れの流行も珍しくありません」
昨年の季節性インフルエンザは、晩夏から流行が始まっている。8月下旬から沖縄で流行し、9月末時点で約4500人と前年同期比6倍の患者が報告された。東京では前年より約3カ月早い9月26日に、流行開始の目安となる1医療機関当たりの患者数が1・0人を超えた。残暑の頃に、“冬のウイルス”が拡大したのだ。
「新型コロナウイルスについて、米ハーバード大の研究チームが、中国各地、タイ、シンガポール、韓国、日本の湿度と感染の関係を調査しました。低湿度で感染者が多いデータがある一方、高湿度で感染者が多いデータもあった。研究チームは『湿度と気温と新型コロナウイルスの感染力は関係がない』と結論付けています。2月末に速報で公表したため、現時点で論文としての信頼性は不十分ですが、傾聴に値する報告です。『春に終息する』という“期待”は捨て、夏まで続くことを前提に対策すべきです」(左門新氏)東京五輪の開催可否の判断は5月末がリミットといわれる。「5月終息」のシナリオは狂いそうだ。
04/30: 世相ジャパン㉘/「わが青春ー新宿歌舞伎町」



「くろねこの短語」2019年1月3日-(前略)それはともかく、紀伊国屋書店が売文芸人の百田シェンシェイと有本香のサイン本に欣喜雀躍のツイートして呆れられている。節操のカケラもなくなっちまったんだなあ。田辺茂一が草葉の陰で泣いてるぞ!!◆あけましておめでとうございます。本日、百田尚樹先生、有本 香先生にご来店いただき、『日本国紀』および『「日本国紀」の副読本』にサインを入れていただきました。元旦からありがとうございます!サイン本お取り置きは2階売場☎︎03-3354-5702で承っております。 — 紀伊國屋書店 新宿本店 (@KinoShinjuku) 2019年1月
◆総理(新制成蹊高等学校出身)!今夜もごちそう様!2018.2.02(金)18:58~21:07-ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町内「OASIS GARDEN」にて、後藤高志西武ホールディングス社長(新制成蹊高等学校出身)様、高井昌史紀國屋書店社長(成蹊大学政治経済学部)様らと総理はご会食なされました。


2018年5月5日『沖縄の軌跡』第188号《静子さん・志多伯克進を語る》 編集発行人・島袋和幸(葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)
志多伯克進「酒禮門」新宿・歌舞伎町

上ー志多伯克進(1908年2月~1979年3月14日)写真ウラに「1936年6月、ある同志のカメラに向いてー志賀進」と記されている。


1956年 四原則貫徹・県民代表として本土渡航の瀬長亀次郎沖縄人民党書記長を羽田空港で出迎える松本三益(瀬長の右)、志多伯克進(瀬長の左)/1967年11月 新宿・酒礼門で「瀬長亀次郎歓迎会」中央に瀬長亀次郎、その左が松本三益、右隣りに比嘉春潮
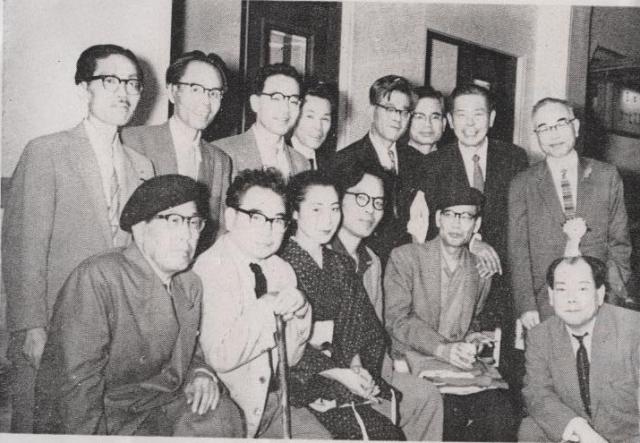
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

□1960年10月『オキナワグラフ』ー新宿の人気男「志多伯のおやじ」新宿コマ劇場の横丁にある”コマ小路”というバー街に、この春から異様な門構えのアワモリ酒亭ができてなかなか繁昌している。
屋号は「酒礼門」。勿論”守礼之門”をモジッてつけたもので、故伊江朝助男爵が名付の親だということだが、ゲン語学者の石川正通先生にいわすと、その語イはー酒の友こそ真の友 礼を守りて盃酌めば 門は大道無門にてーだそうだ。
店構えが異様なら、ここの主人もまた変わり種。志多伯克進という名前からしてコクのよい銘酒を思わせるが、無類の好々爺で、ジュクの酒徒からは”シタハクのオヤジ”と愛称されている。
目マユがこく長く、デップリ太って、みるからにアワモリ天国のエビス様とう感じ、いつあっても、赤ら顔に満面笑みをたたえてさも愉快そうに話し出す。どんな酒癖の悪いインマヤーでもすぐなついてくる。
しかし、このオヤジが庶民の街で名物オヤジとしたわれているのは、ただこの人がお人好しだということばかりではなさそうだ。この人には往年の社会運動の体験から得た”庶民哲学”とジュクのヨタ公共をまかす位の”度胸”が備わっている。愛すべき志士だ。このスジ金の入ったところがまた魅力となって学生や労働者たちに好かれるのだろう。
この人の哲学というのは、先ず人間は平等だということ、第2に貧乏人を蔑まず金持を恐れないこと、第3に真心を以って事に当たること、だそうだが、これはやはり戦前の社会運動時代に豚バコにブチ込まれたり、法廷に立たされた苦闘の中から生まれたものに違いない。非常に正義感が強い人で、終戦直後、新宿のテキヤ安田組を向こうに廻して空手で打ち負かしたという武勇伝は有名だが、いまでもヨタ公同志の決闘に”流血を避けるため”顔をかすこともあるという。
都内の泡盛屋は大小入れて40軒を数えるといわれるが、この総元締格が志多伯のオヤジさんである。泡盛屋の歴史は古く、昭和12年に若い奥さんと大塚駅前で「デーゴ」を開いたのが始り、それからまもなく本所深川の「泡泉」に移った。新宿駅西口に乗り込んだのは終戦直後。ヤミ屋の横行する焼跡で「志多伯」の赤チョウチンを下げ、カッポウ衣に前カケをしめてジュウジュウ鳥焼きとアワモリのサービスに励むかたわら、西口の開拓にも力を注いで今日の繁華街を築きあげた。独得な風貌と誰にも好かれる人柄と親身の世話焼きで忽ち西口の人気オヤジとなり、つい最近まで飲食組合の会長にまつりあげられていた。
『オヤジもトウトウ成り上がったかー』東口に酒礼門を開いたとき西口店のナジミがこう歎いた。お座敷酒亭より西口の番台でバタバタニコニコしていた方がオヤジらしい、ということだろうが、しかしオヤジの庶民性はどこへ行っても消えうせない。むしろ新しい酒礼門こそ庶民の酒亭だ。そこには南の芸術がある。文化がある、ラフティを食べ、アワモリを酌みながら踊りをみる。<しかもフトコロの心配もない、なければオヤジに話せばわかるのだー。あなたふと讃酒之仁義ありという 酒礼門にて酔い泣かんかも(石川正通)
私の17歳は、東京・新宿歌舞伎町の大衆割烹・勇駒新館で働いていた。勇駒本店隣に鮒忠①もあった。当時、新宿は副都心と称していた。現在は伏魔殿と謂われた都庁があるので都心であろうか。新宿は個人の存在など歯牙にもかけない喧噪で無味乾燥なビルが林立する巨大歓楽街であった。夕刻、新宿駅から仕事を終えたサラリーマンが歌舞伎町に大量に弾き出され勇駒新館はたちまち地下、2階も満杯になる。仕事が終わり寮に帰ると朝霧が立ち込めゴミが散乱する早朝の静寂は何とも言えない退廃的な雰囲気であった。職場には学費を稼がなければならない大学生バイト(早稲田が多かった)が5人も居たのでヒマな学生の政治運動やスポーツには興味も関心も無かった。沖縄出身に元出版社に居たという神里氏、いつも朝にヌンチャクの稽古をしていた。王城(喫茶)にも入口に沖縄出身の用心棒が居て、「困っていることがあれば相談に来い」と言ってくれた。

当時の新宿歌舞伎町(真鍋博1968年12月)

当時の新宿駅東口


歌舞伎町の大衆割烹・勇駒本店


1977年8月 桜井華子『東京の味Ⅲ』保育社「いそ料理 勇駒」
①根本忠雄(ねもと ただお、1913年 - 1988年)が1946年9月1日に同年9月1日、浅草千束に川魚料理の店「鮒忠」創業。川魚の捕れない冬場のメニューとして、進駐軍向けの鶏肉(ブロイラー)を串焼きにした「焼き鳥」の販売を開始。焼き鳥を大衆へ大々的に販売することを始めたのは日本初と言われ、「焼き鳥の父」と呼ばれたという。根本忠雄『年商十五億のやきとり商法―鮒忠立志伝』 柴田書店 (1965年)『鮒忠の江戸ッ子商法』 東京経済 (1972年)→Wikipedia。現在、勇駒はネット上出てこないが、鮒忠はもう老舗となって三代目が卸、ケータリング、レストランの3事業をネットも活用し引き継いでいる。
勇駒新館の支配人は漫画家さいとう・たかお似の出っぷりとした人で読書人。週に一回は紀伊國屋本店に雑誌や本を買いに行かされた。もちろん私も本屋は大好きだから喜んで行った。紀伊國屋本店には名物社長の田辺茂一がいたが見たことはない。この年は、「夢の島」の蠅騒動、ベ平連、河野一郎・江戸川乱歩・谷崎潤一郎・高見順らの死去、横井英樹襲撃で東京を震撼させた安藤組の安藤昇が映画俳優として登場したのが週刊誌を賑わしていた。店にはヤクザの長老も常連で来る。その一人(若いころはドス○○)が「近くで安藤昇のロケがあったのだが奴は小柄だからいかに大きく見せるかで周囲が悩んでいた」という。これを聞いて思い出したのが、以前、錦糸町のボウリング場で美川憲一が雑誌の取材でボールを投げるポーズをしていた。誌面では見事にストライクとなっていた。何事でも演出は必要だと思った。集団就職での上京の目的のひとつに、神田の古書街に通うことがあった。新宿は夜の街で前衛的な文化(サブカルチャー)の街で芸術文学の分野も幻想、終末、刹那・頽廃なものであふれていた。安藤昇のレコード「新宿無情」[1965]も出ていたが今ではYouTubeで聴くことができる。『月刊専門料理』の創刊は、1966年11月、この創刊号も勇駒新館の事務所で見た。

右に新宿コマ劇場
〇新宿コマ劇場とは、東京都新宿区歌舞伎町一丁目にあり、1956年12月28日から2008年12月31日まで株式会社コマ・スタジアムによって運営されていた劇場である。「演歌の殿堂」として広く認知され、数々のミュージカル作品も上演された。コマ劇や新コマとも言う。/1956年(昭和31年)2月にコマ・スタジアムが設立。大阪・梅田にあった梅田コマ・スタジアム(梅田コマ劇場の前身)の姉妹劇場として当劇場が建設され、同年12月28日に開場した。開場当初は「新宿コマ・スタジアム」と呼称していた。阪急・東宝グループの創始者である小林一三が抱いた「新しい国民演劇(新歌舞伎)の殿堂を作る」という理念に基づいて創設し歌舞伎町の地名のもととなった。客席数2,088席は首都圏で最大級であった。→ ウィキ
〇2011年7月11日、東宝が新宿コマ劇場及び新宿東宝会館の跡地に複合インテリジェントビル「新宿東宝ビル」を建設することを発表した。地上31階地下1階建て、高さ130メートル、延べ床面積55,390平方メートル、1階と2階に飲食店、3階から6階にTOHOシネマズが運営するIMAXシアターを導入して12スクリーン約2500席の都内最大級シネマコンプレックス「TOHOシネマズ新宿」、9階から31階に藤田観光が運営する約1030室のホテル「ホテルグレイスリー新宿」などが入居し、2015年4月17日に開業した。コマ劇場の中核だった演劇場は収益性が低いとして入居が見送られた。 → ウィキ


新宿・勇駒新館でー左に座っているのが新城栄徳、柴田マネジャー。柴田マネジャーに早稲田の学生がバイトさせてくれという、即採用。/新宿コマ劇場近くには琉球泡盛屋が数軒あった。志多伯克進、「志多伯のおやじ」という新宿名物的人物も居たが見たことはない。当時は未成年だから覗くだけで、新橋の沖縄料理屋には「沖縄そば」を食べにいったことがある。新宿の南風②は1974年にオヤジさんに『青い海』を贈呈しユンタクした。

1950年11月 仲井間宗裕・伊佐栄二『沖縄と人物」
②『琉球新報』2015年3月7日 新宿歌舞伎町で67年 沖縄料理店「南風」閉店ー【東京】創業67年を数え、東京の沖縄料理店で草分け的存在の新宿歌舞伎町の「南風(なんぷう)」が今月末で閉店することになった。店主の前田清美さん(68)は「体力的にきつくなって、継ぐ人もいない。引き際だと思う」と話す。沖縄出身者の心のよりどころだった老舗が消えることになる。南風は戦後の焼け野原だった新宿で前田さんの両親の嘉手納知春さん(本部町出身)、幸子さん(大宜味村出身)夫妻が始めた。苦労して沖縄の食材を得、三線の名手だった知春さんが民謡で客をもてなした。
一度離れると容易には帰れなかった米統治下の沖縄。沖縄出身者は遠い故郷を思い、南風に通った。知春さんは苦学する若者に食事をさせ、終電後はたびたび店に泊め、「始まりも終わりもない店」と呼ばれた。店の2階に住んでいた清美さん姉弟は朝、寝ている酔客をまたいで登校したという。学生時代から60年、南風に通う渡久山長輝東京沖縄県人会長は「おやじから三線を習い、土間で寝たこともある。多くの沖縄人(ウチナーンチュ)の慰めとなっただった」と懐かしむ。清美さんは嘉手納清美として歌手や女優として活躍した後、82年に店主となった。バブルのころは地上げ屋の標的にもなったが店を守り続け、浮き沈みの激しい歌舞伎町の中で、老舗の一つだ。清美さんは「毎晩、お客さんが島唄を大合唱し、カチャーシーを舞った。沖縄人が楽しんでくれたから67年も続けられた」と話した。
柴田マネジャーは秋田の人、生真面目な人で未熟な人生観の持ち主の私を色々と注意してくれた。自宅にも連れて行かれ、マネジャーの痩躯にくらべふっくらとした色白の奥様の手料理を御馳走になった。寮の相棒に熊本出身の23歳の青年が居た。小柄だが休みの日にはコマ劇場の前などでプレイガールをお茶に誘い旅館に行き、その女性との一夜をこと細かく手帳に記していた。今だったら一流のホストになっていたが、私はそれでよく性病を移されなかったものだと感心した。店には茨城出身の威勢のいい2歳年上の子も居た。彼は駐車中の車を弄り人身事故を起こしその賠償金を払うため働いているという。また別の相棒に長崎出身の同じ年頃の子も居た。彼は年に似合わず、木の根っこを入手、磨きあげオブジェにして楽しむ人物であったが、繊細ゆえ「ゴールデン街」の人となった。後に柴田マネジャーは高円寺で焼鳥屋「秋田料理・鳥海」を開いた。
11/14: 古都・鎌倉

古都・鎌倉



かまくら‐の‐だいぶつ 【鎌倉の大仏】神奈川県鎌倉市高徳院にある、高さ3丈5尺(約11.39メートル)の阿弥陀如来の銅の鋳像。建長4年(1252)造立。室町期に仏殿が倒壊し、今日まで露座のままである。長谷の大仏。ほぼ造立当初の像容を保ち、我が国の仏教芸術史上ひときわ重要な価値を有しています。→コトバンク/鎌倉に里見弴を訪ねた宮城聡夫妻


那覇在住の宮城聡宛の手紙、葉書
里見弴

1888-1983 明治-昭和時代の小説家。
明治21年7月14日生まれ。有島武の子。有島武郎(たけお),有島生馬(いくま)の弟。志賀直哉の影響をうけ,明治43年「白樺」の創刊にくわわる。大正5年短編集「善心悪心」でみとめられる。8年久米正雄らと「人間」を創刊。「多情仏心」「安城家の兄弟」と長編の代表作をかきつぎ,戦後は「極楽とんぼ」などを発表した。昭和34年文化勲章。昭和58年1月21日死去。94歳。神奈川県出身。東京帝大中退。本名は山内英夫。(→コトバンク)


1995年11月 新潮日本文学アルバム63『大佛次郎』新潮社◇1962年3月2日 大佛次郎・今日出海・柴田錬三郎、第四回文春講演会で来沖

裏辺研究所(日本の旅・鉄道見聞:瑞鹿山 円覚興聖禅寺と称する臨済宗円覚寺派の総本山
1967年 紀田順一郎『古書店地図帖ー東京・関東・甲信越』図書新聞社
東京古書会館の古書即売展で、金城朝永の『異態習俗考』を入手し、酒井潔『愛の魔術』の贅沢版を捲ったことがある。酒井は、風俗大衆雑誌のオルガナイザーの梅原北明の盟友で、澁澤龍彦の「魔道」にも先鞭をつけている。金城も伊波普猷も風俗雑誌に論考を発表していた。
1967年、東京で紀田順一郎の『古書店地図帖ー東京・関東・甲信越』図書新聞社を入手した。専修大学の方には移転する前の長門屋書房と同じ通りに巌南堂、崇文堂、向かいの通りに篠村書店、原書房、高山本店などがある。反対の御茶ノ水駅に向っては明倫館書店、一誠堂、田村書店、小宮山書店、玉英堂書店、東陽堂書店、弘文堂書店、大屋書房、三茶書房、文庫川村などがある。この本を片手に東京古書会館に出入りした。また高円寺の球陽書房も知った。この本が最初に出合った紀田順一郎氏の著書である。今では紀田氏書斎も大体想像できる。後に紀田氏がこの本の発行年を誤植、それを指摘すると、紀田氏自筆の葉書をもらった。これは私の宝物となっている。
東京・球陽書房↓