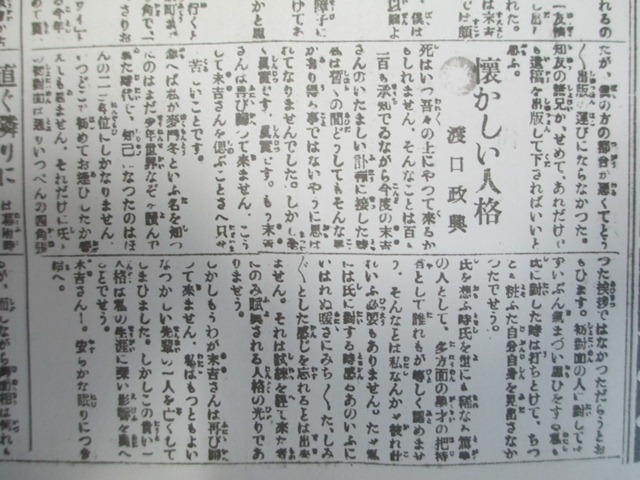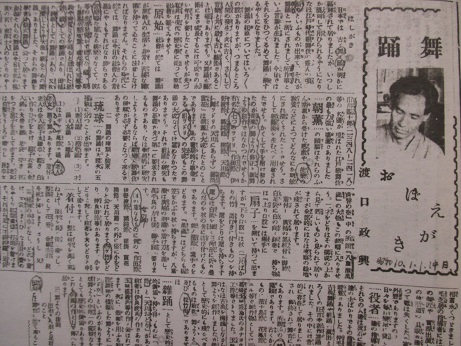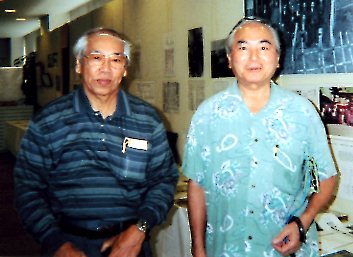11/14: 末吉安恭『麦門冬句集』②
1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」
1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」
1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」
1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」
1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」
1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」
1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」
1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」
1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」
1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」
1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」
1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」
1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」
1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」
1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」
1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」
1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」
1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」
1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」
1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」
1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」
1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」
1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」
1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」
1909年11月『趣味』麦門冬「秋の蚊の溺れて乾く硯かな」
1909年12月『文庫』麦門冬「衝入の人驚きぬ大鏡/猪の子の眠れる穴や草暗し/鹽猪を苞にして山男かな/小夜更けて人のけはひや菊畑/旅にして扇を置けば淋しやな/帰んな里の妻々砧打つ/長き夜は又古き夜や思ひ事」
1909年12月『趣味』麦門冬「素車白馬粛々として露の中」
1910年2月『ホトトギス』麦門冬「魚蝦に富む家刀自艶に鴨の聲」
1910年4月『ホトトギス』麦門冬「薊喰はぬ馬のかぶりや牧の草」
1910年4月『趣味』麦門冬「春の水子別れ馬の顔洗へ/うつろ木の朽葉だまりや蛙なく」
1910年5月『趣味』麦門冬「椿落ちてまた廣がりし水輪かな」
1910年6月『文庫』麦門冬「親梅に子梅つれ咲く日和かな/朝寒の水にひらめく小鰕かな/鳥尽きて我武淋しき案山子かな」
1912年11月25日『沖縄毎日新聞』麦門冬「落葉ー斧研かん今朝砥水落葉上□澄めり/焚火に足がつき落葉林に捕つたり/鶏の掘る種子物に垣す落葉かな/山寒に焔□ると登山落葉□もなき/落葉火佛に茶湯す勘当の子を思ふ/貧の窃み捨て置けと曰や庭落葉/旅の女性湯参らそ落葉山冷えに/駿馬化石の口牌見ればげに落葉も/錠錆び祠落葉積むに人の詣つると」
1912年12月7日『沖縄毎日新聞』麦門冬「時雨雲水仙の魂も伴ふか/句黙録黙水仙に冬籠る」
1912年12月20日『沖縄毎日新聞』麦門冬「隼の啼けり末枯野の空晴れて/友と二た昔を語る岩姫隈柳未枯野を」
麦門冬「兎にも家してやらん冬近し/寒いぞや兎は籠に飢ふるぞや/筆持ちて物書く吾も海鼠ならん/一本の木橋渡らば枯野かな/天井に話の響く夜寒かな/冬構まづ障子より白うせり/冬も吊る蚊帳の煤けて哀れなり/掛取の来べき宵なり鎖ささん/貧厨の只打ち煙る年のくれ/角めだる妻を憎むや年の暮/親になき春省羨む年の暮/貧すれば悪の華咲く年の暮」
1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」
1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」
1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」
1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」
1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」
1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」
1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」
1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」
1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」
1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」
1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」
1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」
1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」
1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」
1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」
1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」
1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」
1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」
1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」
1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」
1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」
1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」
1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」
1909年11月『趣味』麦門冬「秋の蚊の溺れて乾く硯かな」
1909年12月『文庫』麦門冬「衝入の人驚きぬ大鏡/猪の子の眠れる穴や草暗し/鹽猪を苞にして山男かな/小夜更けて人のけはひや菊畑/旅にして扇を置けば淋しやな/帰んな里の妻々砧打つ/長き夜は又古き夜や思ひ事」
1909年12月『趣味』麦門冬「素車白馬粛々として露の中」
1910年2月『ホトトギス』麦門冬「魚蝦に富む家刀自艶に鴨の聲」
1910年4月『ホトトギス』麦門冬「薊喰はぬ馬のかぶりや牧の草」
1910年4月『趣味』麦門冬「春の水子別れ馬の顔洗へ/うつろ木の朽葉だまりや蛙なく」
1910年5月『趣味』麦門冬「椿落ちてまた廣がりし水輪かな」
1910年6月『文庫』麦門冬「親梅に子梅つれ咲く日和かな/朝寒の水にひらめく小鰕かな/鳥尽きて我武淋しき案山子かな」
1912年11月25日『沖縄毎日新聞』麦門冬「落葉ー斧研かん今朝砥水落葉上□澄めり/焚火に足がつき落葉林に捕つたり/鶏の掘る種子物に垣す落葉かな/山寒に焔□ると登山落葉□もなき/落葉火佛に茶湯す勘当の子を思ふ/貧の窃み捨て置けと曰や庭落葉/旅の女性湯参らそ落葉山冷えに/駿馬化石の口牌見ればげに落葉も/錠錆び祠落葉積むに人の詣つると」
1912年12月7日『沖縄毎日新聞』麦門冬「時雨雲水仙の魂も伴ふか/句黙録黙水仙に冬籠る」
1912年12月20日『沖縄毎日新聞』麦門冬「隼の啼けり末枯野の空晴れて/友と二た昔を語る岩姫隈柳未枯野を」
麦門冬「兎にも家してやらん冬近し/寒いぞや兎は籠に飢ふるぞや/筆持ちて物書く吾も海鼠ならん/一本の木橋渡らば枯野かな/天井に話の響く夜寒かな/冬構まづ障子より白うせり/冬も吊る蚊帳の煤けて哀れなり/掛取の来べき宵なり鎖ささん/貧厨の只打ち煙る年のくれ/角めだる妻を憎むや年の暮/親になき春省羨む年の暮/貧すれば悪の華咲く年の暮」
08/07: 末吉安恭「末吉麦門冬句集」
1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。
1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」
1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」
1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」
1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」
1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」
1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」
1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」
1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」
1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」
1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」
1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」
1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」
1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」
1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」
1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」
1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」
1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」
1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」
1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」
1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」
1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」
1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」
1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」
1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」
1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」
1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」
1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」
1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」
1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」
1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」
1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」
1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」
1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」
1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」
1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」
1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」
1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」
1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」
1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」
1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」
1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」
1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」
1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」
1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」
1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」
1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」
1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」
1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」
02/04: 新城栄徳「末吉安恭(麦門冬)没90年」研究発表に寄せて」
新城栄徳「末吉安恭(麦門冬)没90年」研究発表に寄せて」
18日の沖縄タイムス文化欄に、沖縄近代史家の伊佐眞一氏が県知事選の結果を読む、として、もはや翁長雄志氏に疑心暗鬼に精力を裂くときではない。基地問題は第2ステージに入っており、自恃(じじ)のウチナーンチュがひとりでも多くなればなるほど、私たちの郷土は真に自立した道を確実に歩めるはずだ、と書いている。
伊佐・比屋根照夫共編『太田朝敷選集』に、東恩納寛惇宛の書簡で太田は「私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云ふより寧(むし)ろ民族的団体と云ふ見地です。国民の頭から民族差別観念を消して仕舞ふことは吾々に取っては頗(すこぶ)る重要な問題だと考へて居ります」と書いているが、この太田の予言は現在の沖縄にも通底する。
このほか、太田選集には俳句や小説、歴史、民俗など近代沖縄文化の幅広い分野で活躍したジャーナリスト、末吉安恭(麦門冬)を追悼して「私が沖縄時事新報社を新設するに当たり君は私の微力なるを思ひ私の請に応じて快く助筆たるを承諾して呉れた(略)琉球社以来の同志も亦、又吉君を始め君を先輩として敬意を表するに吝(やぶさか)ならなかったのである」と載っている。社会運動家の東恩納寛敷も「沖縄タイムス」の追悼文で「波上軒で麦門冬が酔って興に乗じ幸徳秋水の漢詩を戸板一杯に書いた見事な筆蹟であった」と書いている。
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
鎌倉芳太郎は麦門冬から沖縄美術史の手解きを受けたが、後年「大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、(略)またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育った。」(1977年・『国語科通信№36』)と当時を回想している。
末吉安恭を通して近代沖縄の歩みを振り返ることは、現在の私たちの沖縄社会を考え直す契機になる。 (「琉文21」主宰)
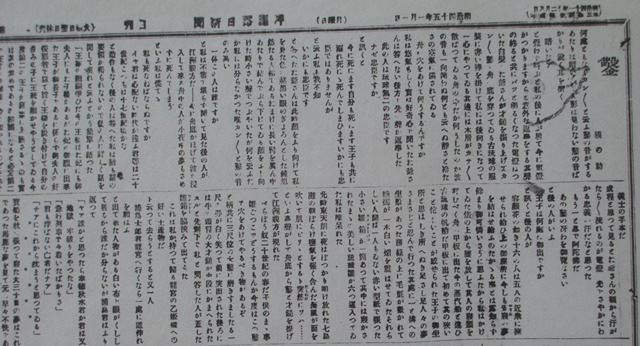
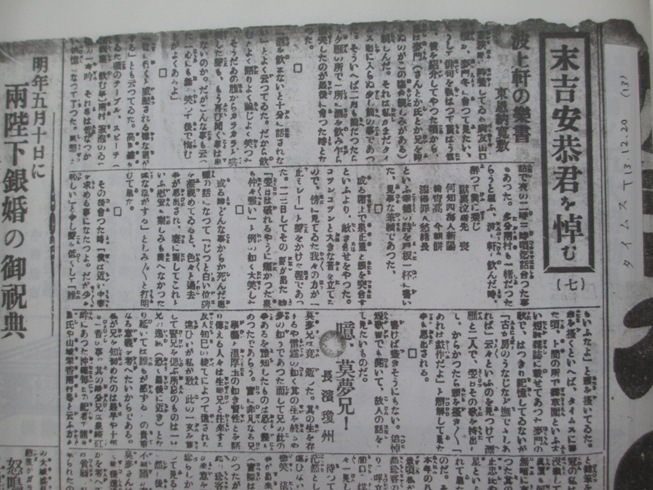
1924年12月20日『沖縄タイムス』東恩納寛敷「末吉安恭君を悼む」
2011年1月ジュンク堂那覇店に行くと大逆事件100年ということで関係書籍が積まれていた。1972年、大阪梅田の古書店で入手したのが『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』であった。幸徳秋水はどういう人物かは知らなかったが写真集といこうことで買った。
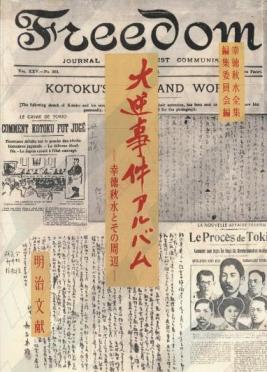
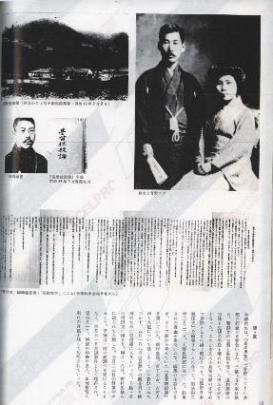
1972年4月ー幸徳秋水全集編集委員会『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』明治文献
1910年6月28日『沖縄毎日新聞』「無政府黨の陰謀」
6月29日『沖縄毎日新聞』「本社発行人(伊舎良平吉)検事の取調べを受ける」
幸徳秋水
生年: 明治4.9.23 (1871.11.5) 没年: 明治44.1.24 (1911)
明治期の社会思想・運動家。高知県中村町の薬種業,酒造業篤明と多治の次男として生まれる。本名は伝次郎で,秋水は師・中江兆民から授かった号である。生後1年たらずで父を失い,維新の社会変動のなか家業も没落し,しかも生来病気がちで満足な教育を受けられなかったことが,秋水をして不平家たらしめ,他面では理想主義に向かわせた。高知県という土地柄もあり,幼くして自由民権思想の影響を受けた。明治21(1888)年より中江兆民のもとに寄寓し,新聞記者となることを目ざし,『自由新聞』『中央新聞』に勤めた。『万朝報』記者時代(1898~1903),社会主義研究会,社会主義協会の会員となり,社会主義者としての宣言を行う。34年5月,日本で最初の社会主義政党である社会民主党の創立者のひとりとして名を連ねた。秋水の著作『社会主義神髄』(1903)は当時の社会主義関係の著書としては最も大きな影響を与えた。36年,日露戦争を前にして戦争反対を唱え,堺利彦と平民社を結成。平和主義,社会主義,民主主義を旗印として週刊『平民新聞』を刊行したが,38年筆禍で5カ月間入獄。出獄後渡米し,権威的社会主義を否定し,クロポトキンなどの影響を受けて無政府共産主義に傾く。39年帰国。43年,説くところの政治的権力と伝統的権威を否定する思想,並びに労働者による直接行動の提唱が,宮下太吉らの明治天皇暗殺計画に結びつけられ,いわゆる大逆事件の首謀者とみなされ,絞首刑に処せられた。<著作>『廿世紀之怪物帝国主義』『基督抹殺論』『幸徳秋水全集』<参考文献>飛鳥井雅道『幸徳秋水』,神崎清『実録幸徳秋水』,大原慧『幸徳秋水の思想と大逆事件』,塩田庄兵衛『幸徳秋水』 (山泉進)□→コトバンク

幸徳秋水の墓ー島袋和幸氏撮影
18日の沖縄タイムス文化欄に、沖縄近代史家の伊佐眞一氏が県知事選の結果を読む、として、もはや翁長雄志氏に疑心暗鬼に精力を裂くときではない。基地問題は第2ステージに入っており、自恃(じじ)のウチナーンチュがひとりでも多くなればなるほど、私たちの郷土は真に自立した道を確実に歩めるはずだ、と書いている。
伊佐・比屋根照夫共編『太田朝敷選集』に、東恩納寛惇宛の書簡で太田は「私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云ふより寧(むし)ろ民族的団体と云ふ見地です。国民の頭から民族差別観念を消して仕舞ふことは吾々に取っては頗(すこぶ)る重要な問題だと考へて居ります」と書いているが、この太田の予言は現在の沖縄にも通底する。
このほか、太田選集には俳句や小説、歴史、民俗など近代沖縄文化の幅広い分野で活躍したジャーナリスト、末吉安恭(麦門冬)を追悼して「私が沖縄時事新報社を新設するに当たり君は私の微力なるを思ひ私の請に応じて快く助筆たるを承諾して呉れた(略)琉球社以来の同志も亦、又吉君を始め君を先輩として敬意を表するに吝(やぶさか)ならなかったのである」と載っている。社会運動家の東恩納寛敷も「沖縄タイムス」の追悼文で「波上軒で麦門冬が酔って興に乗じ幸徳秋水の漢詩を戸板一杯に書いた見事な筆蹟であった」と書いている。
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
鎌倉芳太郎は麦門冬から沖縄美術史の手解きを受けたが、後年「大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、(略)またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育った。」(1977年・『国語科通信№36』)と当時を回想している。
末吉安恭を通して近代沖縄の歩みを振り返ることは、現在の私たちの沖縄社会を考え直す契機になる。 (「琉文21」主宰)
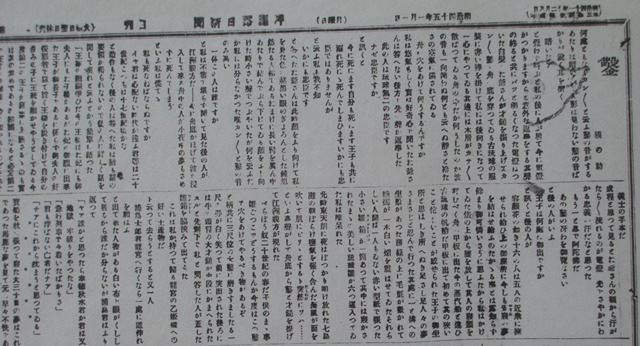
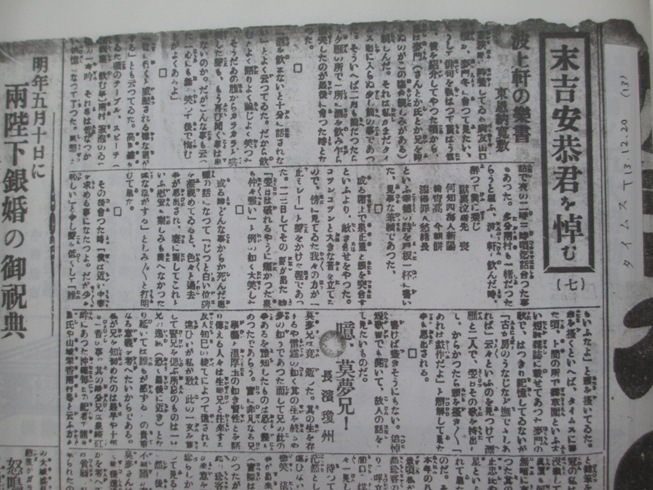
1924年12月20日『沖縄タイムス』東恩納寛敷「末吉安恭君を悼む」
2011年1月ジュンク堂那覇店に行くと大逆事件100年ということで関係書籍が積まれていた。1972年、大阪梅田の古書店で入手したのが『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』であった。幸徳秋水はどういう人物かは知らなかったが写真集といこうことで買った。
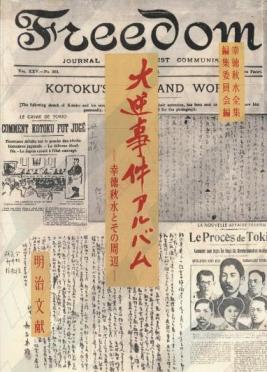
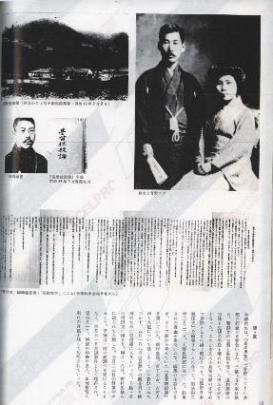
1972年4月ー幸徳秋水全集編集委員会『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』明治文献
1910年6月28日『沖縄毎日新聞』「無政府黨の陰謀」
6月29日『沖縄毎日新聞』「本社発行人(伊舎良平吉)検事の取調べを受ける」
幸徳秋水
生年: 明治4.9.23 (1871.11.5) 没年: 明治44.1.24 (1911)
明治期の社会思想・運動家。高知県中村町の薬種業,酒造業篤明と多治の次男として生まれる。本名は伝次郎で,秋水は師・中江兆民から授かった号である。生後1年たらずで父を失い,維新の社会変動のなか家業も没落し,しかも生来病気がちで満足な教育を受けられなかったことが,秋水をして不平家たらしめ,他面では理想主義に向かわせた。高知県という土地柄もあり,幼くして自由民権思想の影響を受けた。明治21(1888)年より中江兆民のもとに寄寓し,新聞記者となることを目ざし,『自由新聞』『中央新聞』に勤めた。『万朝報』記者時代(1898~1903),社会主義研究会,社会主義協会の会員となり,社会主義者としての宣言を行う。34年5月,日本で最初の社会主義政党である社会民主党の創立者のひとりとして名を連ねた。秋水の著作『社会主義神髄』(1903)は当時の社会主義関係の著書としては最も大きな影響を与えた。36年,日露戦争を前にして戦争反対を唱え,堺利彦と平民社を結成。平和主義,社会主義,民主主義を旗印として週刊『平民新聞』を刊行したが,38年筆禍で5カ月間入獄。出獄後渡米し,権威的社会主義を否定し,クロポトキンなどの影響を受けて無政府共産主義に傾く。39年帰国。43年,説くところの政治的権力と伝統的権威を否定する思想,並びに労働者による直接行動の提唱が,宮下太吉らの明治天皇暗殺計画に結びつけられ,いわゆる大逆事件の首謀者とみなされ,絞首刑に処せられた。<著作>『廿世紀之怪物帝国主義』『基督抹殺論』『幸徳秋水全集』<参考文献>飛鳥井雅道『幸徳秋水』,神崎清『実録幸徳秋水』,大原慧『幸徳秋水の思想と大逆事件』,塩田庄兵衛『幸徳秋水』 (山泉進)□→コトバンク

幸徳秋水の墓ー島袋和幸氏撮影
03/15: 龍脈/麦門冬・末吉安恭

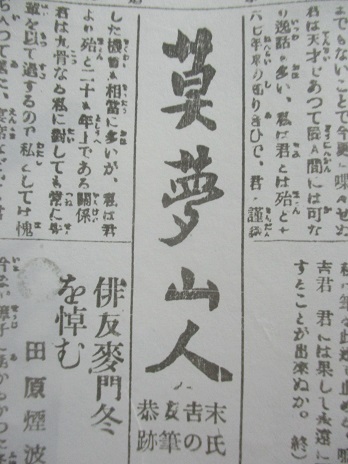
島袋百恵 画「末吉麦門冬」
麦門冬・末吉安恭は1886年5月に首里儀保で生まれた。沖縄師範附属小学校を卒業後の1902年上京した。杉浦重剛の日本中学や、神田の英語学校に通いながら演説会に行ったり、図書館で好きな本を読んで抜書きしたりして新しい知識を貪欲に求めた。1904年に一時帰郷し、名護真松と結婚。1905年再上京、弟の安持と同居。1906年、長男・安慶が生まれると帰郷。
麦門冬(龍の鬚・ヤブラン藪蘭)とは俳号のことで、歌人として落紅、漢詩人として莫夢山人と色々と使い分けていた。麦門冬も身内(先祖)の毛鳳儀を1919年の『沖縄朝日新聞』に「王舅・池城毛公」として長期連載している。
末吉麦門冬家は毛氏池城一門で、その始祖は新城親方安基、俗に<大新城>といい、トーナーは毛龍○<口+全>である。一門は八重山でも繁盛していて1928年9月の『先島朝日新聞』には「八重山毛氏一門の美挙 当地毛姓には本年大祖大新城親方の三百五十年忌に相当するを以って門族相図り記念運動場南の墓地に大祖の記念碑を建設し去る2日盛大に其の三百五十年祭を挙行せり」として毛姓・池城安伸の祭文まで記されている。
07/21: 年譜・末吉麦門冬/1914(大正3)年
1月 親泊朝擢『沖縄県案内』発行/仲吉朝主、印刷/三秀舎「新聞雑誌ー琉球新報、沖縄毎日新聞、沖縄新聞、発展、撫子新聞、福音、沖縄教育、おきなは、演劇週報」
1月 横山健堂『薩摩と琉球』
1月 島津長丸男爵、観光で来沖
1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立
1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社
3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」
卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2
照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6
沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去
6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」
6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」
7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」
7月3日『琉球新報』笑古「初夏遊奥山」
7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」
7月7日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選」
7月11日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」
7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」
7月26日『琉球新報』麦門冬「弔薬師楽山君-
7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」
8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」、琉球歌壇ー草秋選 らくこう『球陽座を見て』」
8月3日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選 らくこう『中座の「さんげ劇』を見て』」
8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」
8月16日『琉球新報』「俳紫電」
8月18日『琉球新報』「俳紫電」
8月19日『琉球新報』「俳紫電」
8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」「俳紫電」
8月21日『琉球新報』「俳紫電」
8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」「俳紫電」
8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」「俳紫電」
8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」「俳紫電」
8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」「俳紫電」
8月29日『琉球新報』「俳紫電」
8月30日『琉球新報』「俳紫電」
1月 横山健堂『薩摩と琉球』
1月 島津長丸男爵、観光で来沖
1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立
1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社
3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」
卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2
照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6
沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去
6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」
6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」
7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」
7月3日『琉球新報』笑古「初夏遊奥山」
7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」
7月7日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選」
7月11日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」
7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」
7月26日『琉球新報』麦門冬「弔薬師楽山君-
7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」
8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」、琉球歌壇ー草秋選 らくこう『球陽座を見て』」
8月3日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選 らくこう『中座の「さんげ劇』を見て』」
8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」
8月16日『琉球新報』「俳紫電」
8月18日『琉球新報』「俳紫電」
8月19日『琉球新報』「俳紫電」
8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」「俳紫電」
8月21日『琉球新報』「俳紫電」
8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」「俳紫電」
8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」「俳紫電」
8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」「俳紫電」
8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」「俳紫電」
8月29日『琉球新報』「俳紫電」
8月30日『琉球新報』「俳紫電」
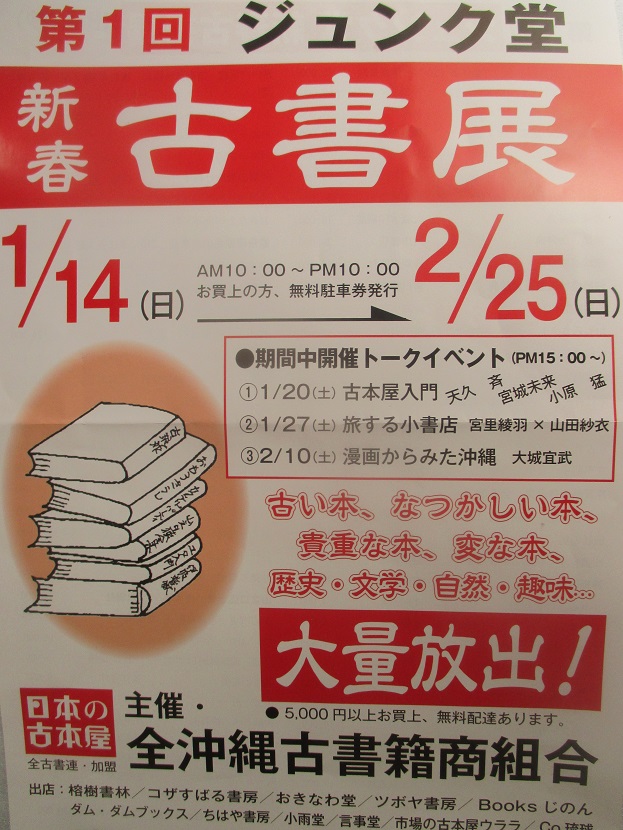



2018年1月29日ー榕樹書林(沖縄宜野湾市)の武石和美社長、ひより

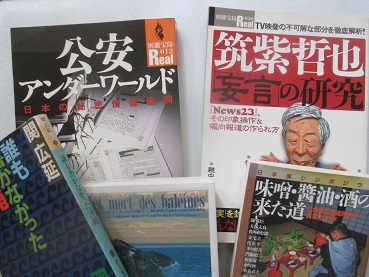
会場で、私は宝島社の出版物に興味があったので2001年4月『公安アンダーワールドー日本の秘密情報機関』と2004年2月 宝島社『筑紫哲也「妄言」の研究』を買った。宝島社『筑紫哲也「妄言」の研究』〇与那原恵「迷惑な沖縄愛 悲劇の島、癒しの島というステレオタイプー筑紫哲也のような、平和、人権を唱えるタイプの人間が興味を抱きつづける場所は『沖縄』である。沖縄には彼らが求めるさまざまなテーマがある。」
◎与那原恵・執筆記事・著書→ウィキペディア
『別冊宝島107号 女がわからない!』(JICC出版、1990年1月23日)に寄稿。AVギャルを取材した初の女性ライターとなる。
「AV撮影現場を体験するーモニターの中でだけ一瞬輝ける女の子たちがいた!」(『別冊宝島124号 セックスというお仕事ー女が見た女を売る女たち 』、JICC出版、1990年12月 )
「妻たちの、昼下がりの売春ー風の中の雌鶏」『別冊宝島224号 売春するニッポンー素人が売春する時代への処方箋』(JICC出版、1995年6月、『物語の海 揺れる島』収録)
「モデルの時間ー荒木経惟と過ごした冬の日の午後」(雑誌「Stwitchvol.10 No1 荒木経惟 写狂人日記」1992年3月号、『物語の海 揺れる島』収録)
「フェニミズムは何も答えてくれなかった<オウムの女性信者たち>」(『宝島30』1995年8月号、『物語の海 揺れる島』収録)
「ひめゆりの物語は、もういらない」( 『宝島30』1995年12月号、『物語の海 揺れる島』収録)
「メディア異人列伝」(岡留安則編集『噂の真相』1997年10月号、㈱噂の真相)
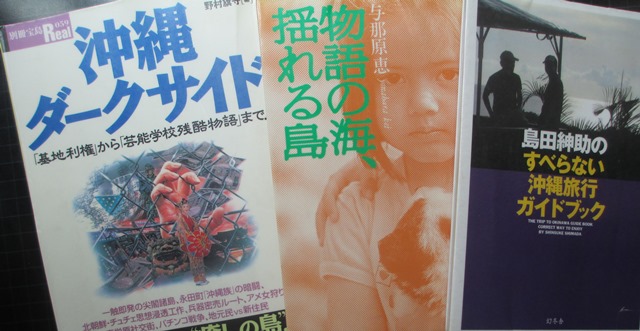
1997年4月ー与那原恵『物語の海、揺れる島』小学館
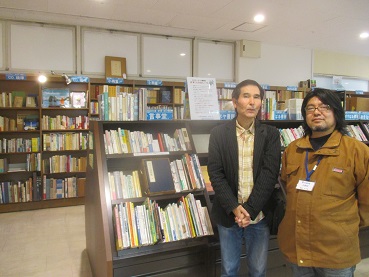
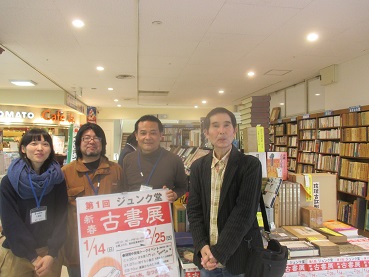
2018年1月16日ー左 銘苅和義(ツボヤ書房 ☎098-879-4545 携帯080-4315ー5437)、新垣英樹 (小雨堂 ☎098-894-5202) 右 宮城未来(言事堂 ☎fax098-864-0315)、新垣英樹、天久斉(Booksじのん ☎098-897-7241)、銘苅和義




トークショー 1月20日(土)15時~「古本屋入門」天久斉(BOOKSじのん)×宮城未来(言事堂)×小原猛(ダムダムブックス)


2月10日 ジュンク堂那覇店 大城宜武「漫画からみた沖縄」/写真左から武石和実氏、大城宜武さん、森本浩平ジュンク堂那覇店長
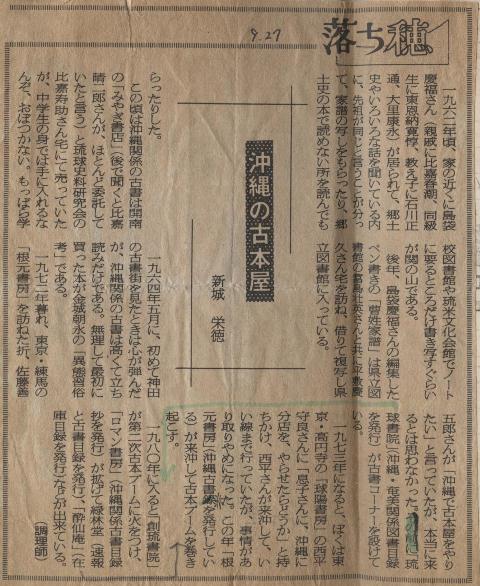
1983年ー『琉球新報』
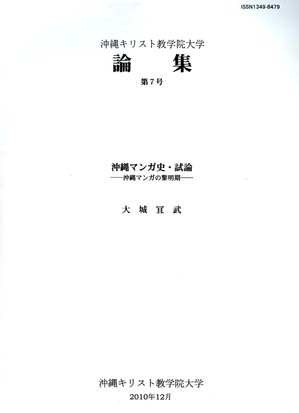
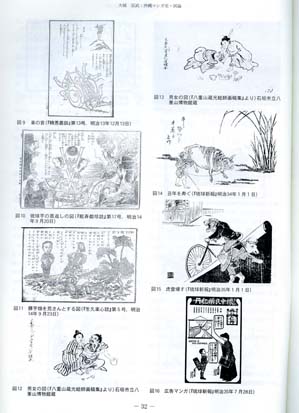
2010年12月ー『沖縄キリスト教学院大学論集』第7号□大城冝武「沖縄マンガ史・試論ー沖縄マンガの黎明期
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
「華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽とか雪舟とか趙子昂とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代」もあったと安恭は記しているが、この美術家の夢は弟の安久によって実現された。
また大正末期、沖縄県立沖縄図書館長の伊波普猷がスキャンダルの最中、麦門冬の友人たちは後継館長に麦門冬と運動していた。山里永吉の叔父・比嘉朝健は最も熱心で、父の友人で沖縄政財界に隠然たる影響を持つ尚順男爵邸宅に麦門冬を連れていった。かつて麦門冬が閥族と新聞で攻撃した当人である。しかし麦門冬の語る郷土研究の情熱を尚順も理解を示し料理で歓待し長男・尚謙に酌をさせるなど好意を示した。それらは麦門冬の不慮の死で無に帰した。これも弟・安久が戦後、沖縄県立図書館の歴代図書館長に名を連ねている。
麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)
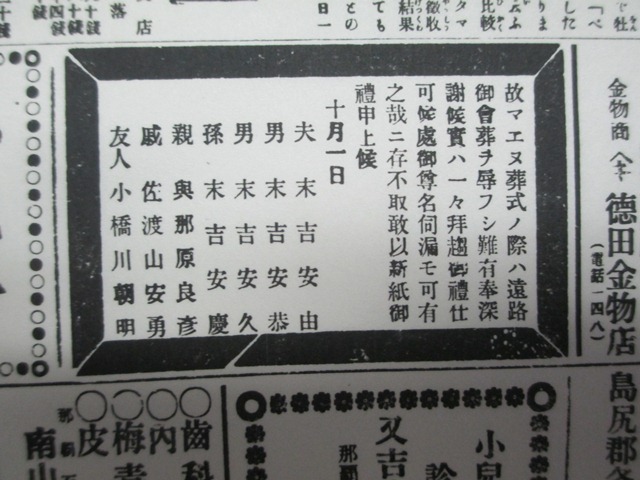
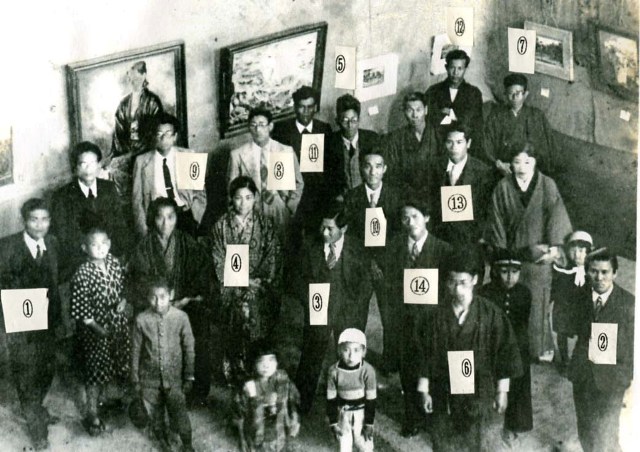
1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

写真左から末吉安久、桃原思石、許田重勲
1944年ー夏 学童疎開の引率で宮崎に
1946年ー秋 首里高校美術科教官に就任するや沖縄民政府文教局にデザイン科の設置を要請し首里に伝わる紅型の復活を図りたい」と嘆願し実現に導いた。

右端が末吉安久
1949年3月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」
1949年4月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」
1949年5月 『月刊タイムス』№4□末吉安久「表紙・カット」
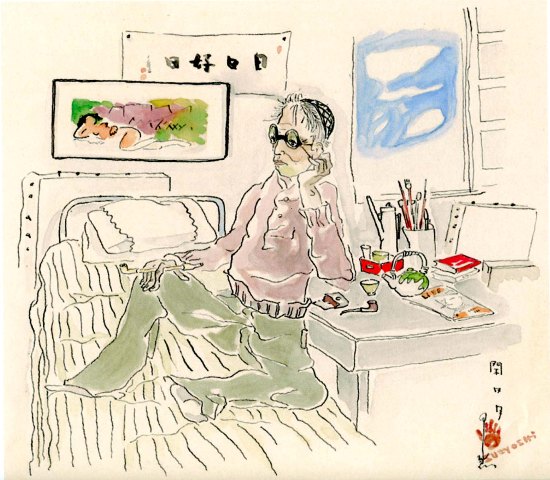
末吉安久「閑日月」

末吉安久「子供達」
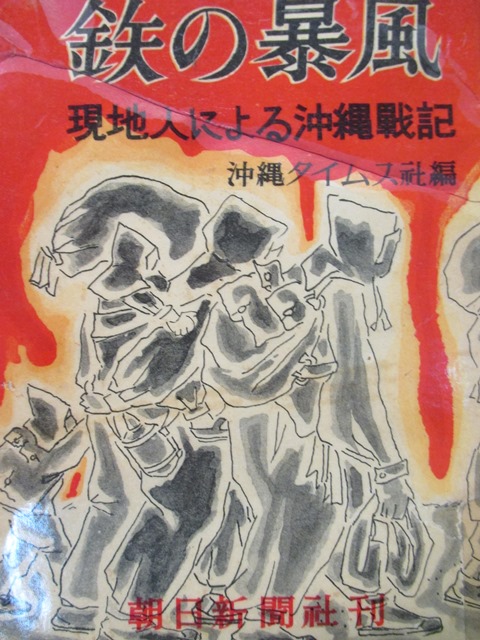
1950年8月 朝日新聞社『鉄の暴風』末吉安久「装幀」/牧港篤三「挿絵」
1950年9月 末吉安久、首里図書館長就任(1957-4)
1951年11月 琉米文化会館「第3回沖縄美術展覧会」末吉安久「子供達」/金城安太郎「楽屋裏」
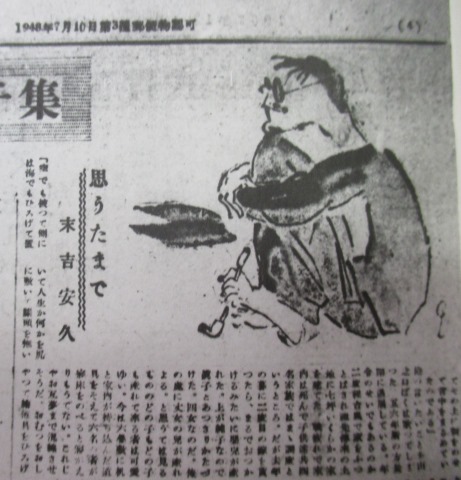
1952年1月1日『沖縄タイムス』末吉安久「思うたまで」

1952年1月1日『琉球新報』末吉安久(Q)「漫画漫詩」

1953年1月1日『沖縄タイムス』「漫画アンデパンダン展」末吉安久「乾かすのか掲げるのか」
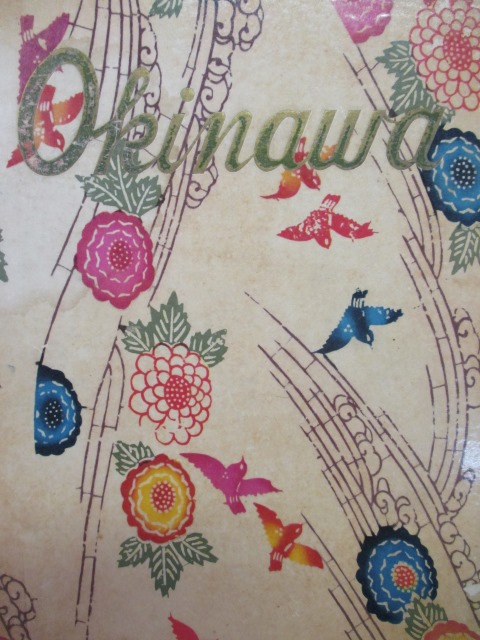
1954年12月に写真集『基地沖縄』が東京新宿市ヶ谷加賀町の大日本印刷で印刷され沖縄タイムス社から発行された。編集は豊平良顕、上間正諭、牧港篤三、金城久重で、装幀が南風原朝光、末吉安久であった。零よりの出発と題して農夫の写真が掲載されていて、説明文に「戦争の破壊は、とにかく地上の人間の営みを根こそぎ奪い去った。戦後の復興はすべて零よりの出発と云ってよい。この老農夫の姿そのままが、零のスタート・ラインに立った終戦直後のオキナワを象徴している」とある。
1955年3月 第7回沖展に末吉安久「花」「サバニ」「静物」「金魚」
1956年3月 第8回沖展に末吉安久「黄色の部屋」「魚」「静物」
1956年8月15日 『沖縄タイムス』末ひさし「居タ居タ鳩ダ」
1956年8月19日 『沖縄タイムス』末ひさし(Q)「静かなデモ」

左から真境名安興、伊波普猷、末吉麦門冬(末吉安久画)
1956年11月 『沖縄タイムス』島袋盛敏「新遺老説傳 沖縄むかしばなし」末吉安久(Q)・絵
1957年3月 第9回沖展に末吉安久「静物」
1958年3月 第10回沖展に末吉安久「黒い月」「漁師たち」
1959年3月 第11回沖展に末吉安久「魚」「月」「大学の丘」「死せる生物」
1960年3月 第12回沖展に末吉安久「石」「根」「花」「珊瑚礁」
1961年3月 第13回沖展に末吉安久「作品」「墓場」
1961年3月 『養秀』養秀同窓会□養秀「表紙装丁カット」「金城紀光氏に聞くー聞き手/末吉安久」
1962年3月 第14回沖展に末吉安久「墓地A」「墓地B」「墓地C」
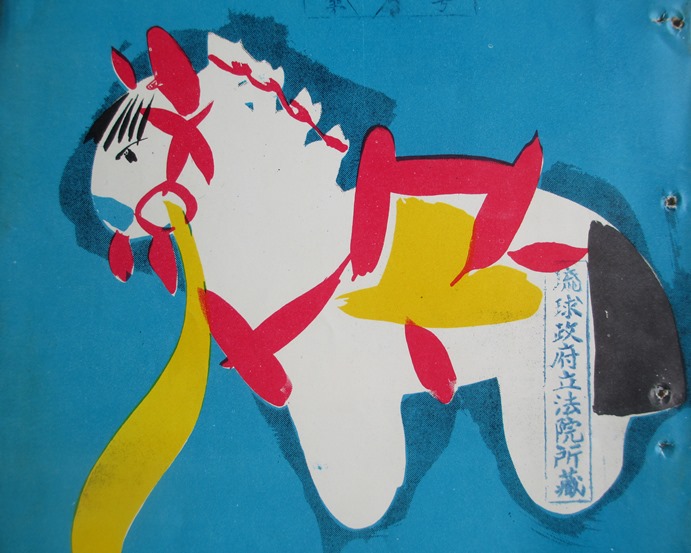
末吉安久/表紙絵 1962年8月『今日の琉球』58号「琉球の玩具」

写真ー末吉安久氏と大城皓也画伯

沖縄県立図書館の左側には「安冨祖流楽祖之碑」がある。安冨祖流絃聲会が1964年1月18日に建立しものだが、設計は末吉安久である。ちなみに、揮毫は島袋光裕、刻字が安里清謙、施行が安里清福である。沖縄県立図書館の館長室には歴代図書館長の一人として末吉安久の写真も飾られている。
1969年2月 『新沖縄文学』第12号 末吉安久「貘さんに る幻想」
1975年1月28日 山之口貘詩碑建立期成会発足(宮里栄輝会長、末吉安久副会長)
1975年7月23日 与儀公園で山之口貘詩碑除幕式
1975年9月7日 那覇文化センターで山之口貘記念会発足
1976年12月 『沖縄風俗絵図』月刊沖縄社□末吉安久「ケンケンパー」「足相撲」「ビー玉」「イットゥガヨー」「ジュークーティ」「クールーミグラセー」「クールーオーラセー」□末吉安久紅型「醜童舞い」「浜千鳥」「馬」「桃売りアングヮー」「カンドーフ売り」
1977年11月29日『沖縄タイムス』「佐渡山安健『名馬・仲田青毛』末吉安久宅に」
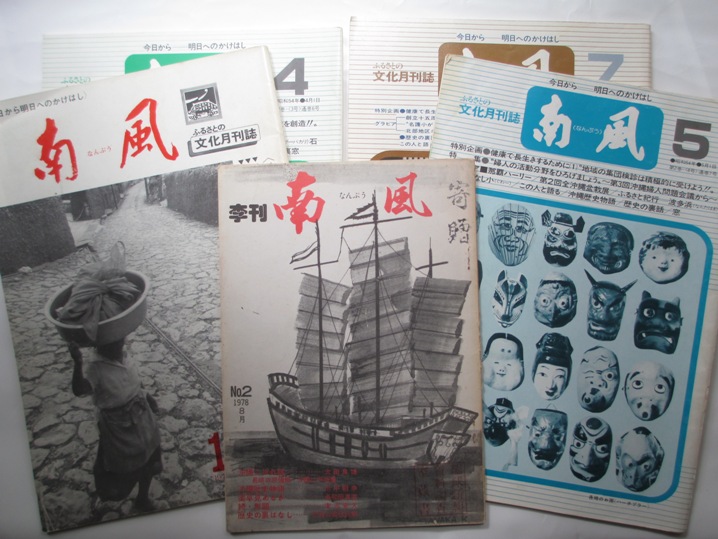
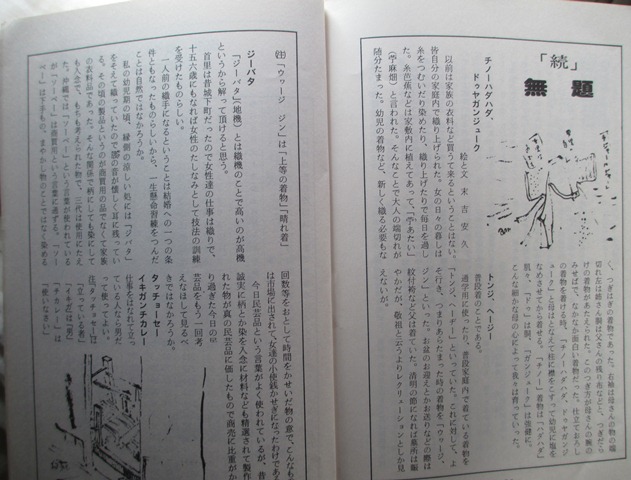
1978年8月 『季刊 南風』№2 末吉安久・絵と文「続・無題」
2015年10月16日『沖縄タイムス』大城冝武「沖縄マンガ史34(末ひさし)末吉安久/大嶺信一」
「華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽とか雪舟とか趙子昂とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代」もあったと安恭は記しているが、この美術家の夢は弟の安久によって実現された。
また大正末期、沖縄県立沖縄図書館長の伊波普猷がスキャンダルの最中、麦門冬の友人たちは後継館長に麦門冬と運動していた。山里永吉の叔父・比嘉朝健は最も熱心で、父の友人で沖縄政財界に隠然たる影響を持つ尚順男爵邸宅に麦門冬を連れていった。かつて麦門冬が閥族と新聞で攻撃した当人である。しかし麦門冬の語る郷土研究の情熱を尚順も理解を示し料理で歓待し長男・尚謙に酌をさせるなど好意を示した。それらは麦門冬の不慮の死で無に帰した。これも弟・安久が戦後、沖縄県立図書館の歴代図書館長に名を連ねている。
麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)
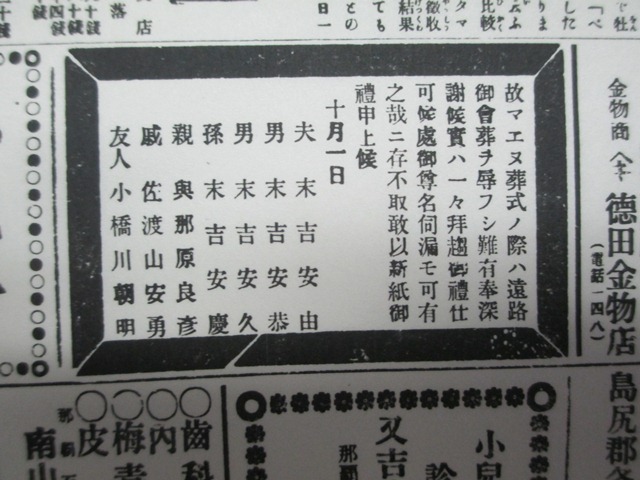
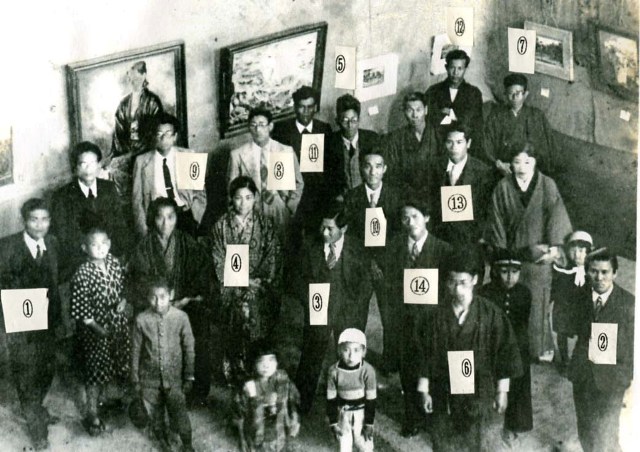
1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

写真左から末吉安久、桃原思石、許田重勲
1944年ー夏 学童疎開の引率で宮崎に
1946年ー秋 首里高校美術科教官に就任するや沖縄民政府文教局にデザイン科の設置を要請し首里に伝わる紅型の復活を図りたい」と嘆願し実現に導いた。

右端が末吉安久
1949年3月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」
1949年4月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」
1949年5月 『月刊タイムス』№4□末吉安久「表紙・カット」
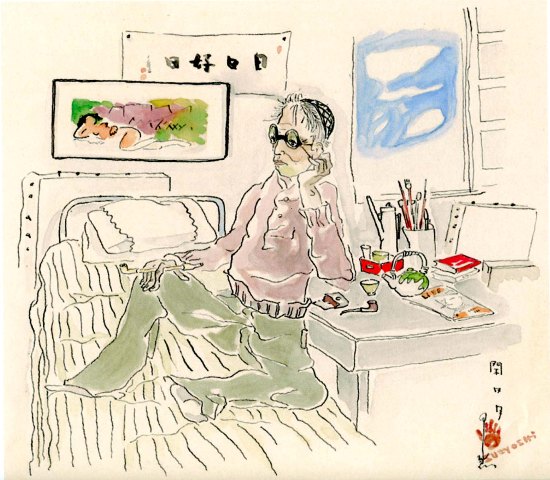
末吉安久「閑日月」

末吉安久「子供達」
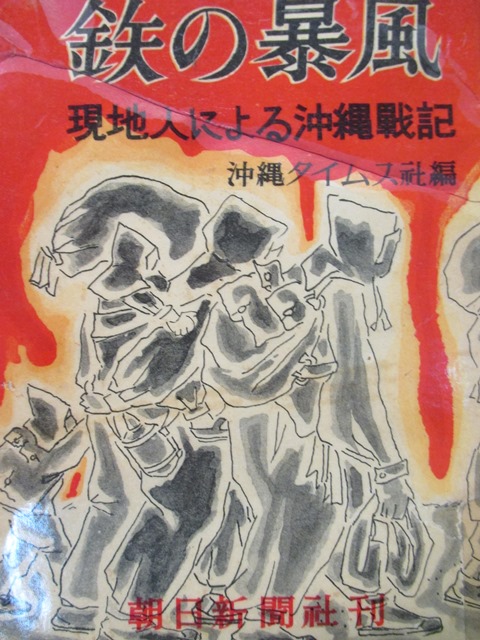
1950年8月 朝日新聞社『鉄の暴風』末吉安久「装幀」/牧港篤三「挿絵」
1950年9月 末吉安久、首里図書館長就任(1957-4)
1951年11月 琉米文化会館「第3回沖縄美術展覧会」末吉安久「子供達」/金城安太郎「楽屋裏」
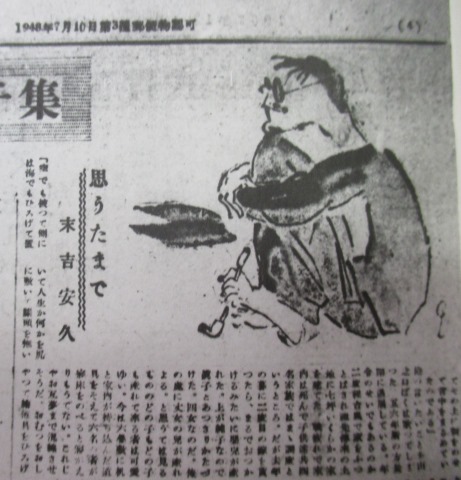
1952年1月1日『沖縄タイムス』末吉安久「思うたまで」

1952年1月1日『琉球新報』末吉安久(Q)「漫画漫詩」

1953年1月1日『沖縄タイムス』「漫画アンデパンダン展」末吉安久「乾かすのか掲げるのか」
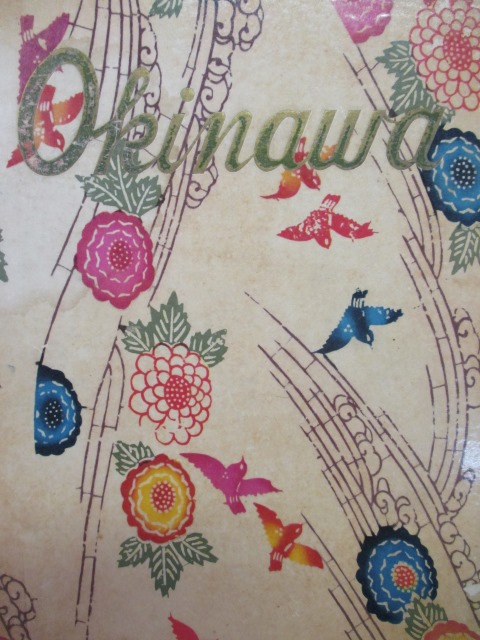
1954年12月に写真集『基地沖縄』が東京新宿市ヶ谷加賀町の大日本印刷で印刷され沖縄タイムス社から発行された。編集は豊平良顕、上間正諭、牧港篤三、金城久重で、装幀が南風原朝光、末吉安久であった。零よりの出発と題して農夫の写真が掲載されていて、説明文に「戦争の破壊は、とにかく地上の人間の営みを根こそぎ奪い去った。戦後の復興はすべて零よりの出発と云ってよい。この老農夫の姿そのままが、零のスタート・ラインに立った終戦直後のオキナワを象徴している」とある。
1955年3月 第7回沖展に末吉安久「花」「サバニ」「静物」「金魚」
1956年3月 第8回沖展に末吉安久「黄色の部屋」「魚」「静物」
1956年8月15日 『沖縄タイムス』末ひさし「居タ居タ鳩ダ」
1956年8月19日 『沖縄タイムス』末ひさし(Q)「静かなデモ」

左から真境名安興、伊波普猷、末吉麦門冬(末吉安久画)
1956年11月 『沖縄タイムス』島袋盛敏「新遺老説傳 沖縄むかしばなし」末吉安久(Q)・絵
1957年3月 第9回沖展に末吉安久「静物」
1958年3月 第10回沖展に末吉安久「黒い月」「漁師たち」
1959年3月 第11回沖展に末吉安久「魚」「月」「大学の丘」「死せる生物」
1960年3月 第12回沖展に末吉安久「石」「根」「花」「珊瑚礁」
1961年3月 第13回沖展に末吉安久「作品」「墓場」
1961年3月 『養秀』養秀同窓会□養秀「表紙装丁カット」「金城紀光氏に聞くー聞き手/末吉安久」
1962年3月 第14回沖展に末吉安久「墓地A」「墓地B」「墓地C」
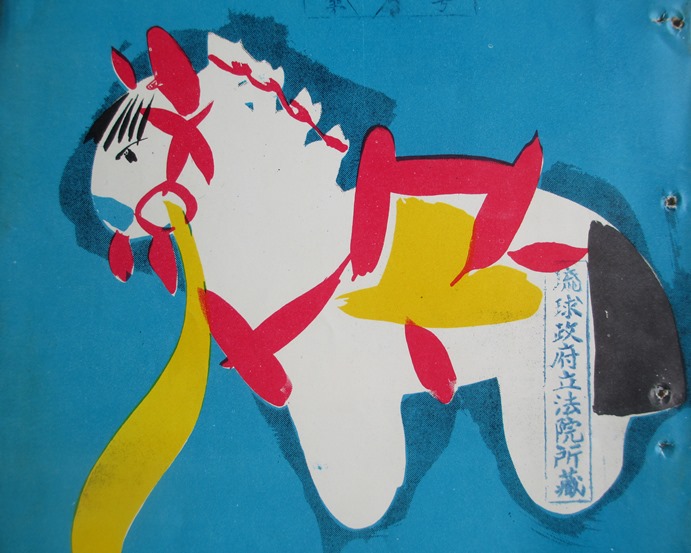
末吉安久/表紙絵 1962年8月『今日の琉球』58号「琉球の玩具」

写真ー末吉安久氏と大城皓也画伯

沖縄県立図書館の左側には「安冨祖流楽祖之碑」がある。安冨祖流絃聲会が1964年1月18日に建立しものだが、設計は末吉安久である。ちなみに、揮毫は島袋光裕、刻字が安里清謙、施行が安里清福である。沖縄県立図書館の館長室には歴代図書館長の一人として末吉安久の写真も飾られている。
1969年2月 『新沖縄文学』第12号 末吉安久「貘さんに る幻想」
1975年1月28日 山之口貘詩碑建立期成会発足(宮里栄輝会長、末吉安久副会長)
1975年7月23日 与儀公園で山之口貘詩碑除幕式
1975年9月7日 那覇文化センターで山之口貘記念会発足
1976年12月 『沖縄風俗絵図』月刊沖縄社□末吉安久「ケンケンパー」「足相撲」「ビー玉」「イットゥガヨー」「ジュークーティ」「クールーミグラセー」「クールーオーラセー」□末吉安久紅型「醜童舞い」「浜千鳥」「馬」「桃売りアングヮー」「カンドーフ売り」
1977年11月29日『沖縄タイムス』「佐渡山安健『名馬・仲田青毛』末吉安久宅に」
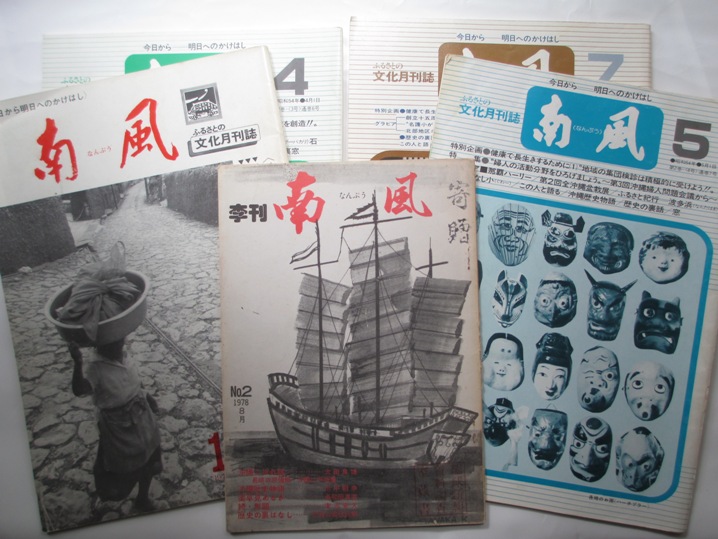
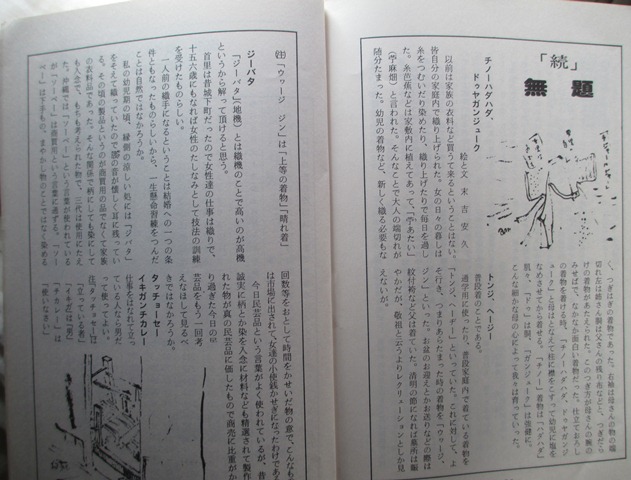
1978年8月 『季刊 南風』№2 末吉安久・絵と文「続・無題」
2015年10月16日『沖縄タイムス』大城冝武「沖縄マンガ史34(末ひさし)末吉安久/大嶺信一」
12/17: 年譜・末吉麦門冬/1919(大正8)年①
1919年1月1日ー『日本及日本人』747号□末吉麦門冬「再び琉球三味線に就いて」「小ぢよく」「かんから太鼓」(吉田芳輝氏提供)
1919年6月ー末吉麦門冬『沖縄時事新報』創刊に参画
1919年6月『日本及日本人』759号 末吉麦門冬□「経済ーエコノミーを経済と譯するの適否は如らず、會澤正志の新論に「或毛擧細故、唯貨利是談、自称経済之學」云々とあり、政治が今日謂ふ所の経済に重きを置くことが、近世的傾向たるにより、訳者をして此の語を選ばしめ、敢て不適当を感ぜしめざるに至りしやも知るべからず。又支那にも後世に至り経済を倹約の意に用ひしことありや。清朝の詩人舒位の詩に「一屋荘厳妻子佛、六時経済米鹽花」とあり、猶ほ考ふべし。」□南方熊楠□「夜啼松ー佐夜の中山より十町斗りを過て夜啼の松あり、此松をともして見すれば子供の夜啼を止るとて往来の人削り取きり取ける程に、其松遂に枯て今根斗りに成けりと、絲亂記より六十二年前に成た東海道名所記三に見ゆ。其頃早く枯れ居たのだ。」
1919年7月15日ー『日本及日本人』761号□末吉麦門冬「琉球風と王子の歌」
1919年8月15ー『日本及日本人』763号□南方熊楠「ストライキー麦生君は自笑の常世誰が身の上に依って、徳川幕府の中葉既にストライキが多少本邦で行われたと立証されたー」
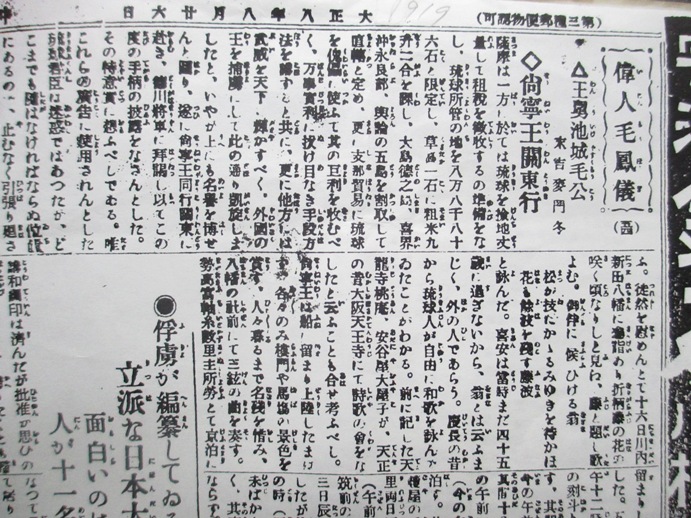
1919年8月26日 『沖縄朝日新聞』末吉麦門冬「偉人 毛鳳儀ー王舅池城毛公」」(喜安日記)
1919年9月 『沖縄時事新報』麦門冬「南山俗語考を見て(下)」
▲古賀精里の序文にも南山主人の跋文にもなくして、今一つの重要なる事があって、薩摩をして支那語研究をなさしむる動機となり目的となった。それが又南山俗語考を作らしむる動機ともなり目的ともなった。それは琉球を仲介としての支那貿易をなしている特殊の関係が薩摩にあったことだ。この特殊の関係がある故に彼等は色々の詭計を設けて、例えば藩士に琉装せしめ、琉球人と共に支那に派したりしたこともある従って支那語に堪能ならなければならぬ必要は琉球に劣らざるものがあった。23歳の一青年たる南山主人をして俗語考を著はす考を起さしめたのもこれが重大であらうと思ふ武藤長平氏の説に依ると、流石に大名が金をかけ長い年月を費やして作ったものだけありて、長崎辺から出た支那語の辞書などとは比較にならぬ程、この辞書は正確なものであるとの事だ。薩摩よりも官話ならこっちが本場だと思はれた、琉球人までがこの書を官話研究の唯一の手引としたのも又偶然にあらずと思ふ。
▲これより彼と琉球との関係の片影を一寸紹介して見たい、彼は延享2年の生まれであるから琉球の読谷山王子朝憲とは同庚である。それも一つの原因であったのだらう読谷山王子とは甚だ懇意であったらしい。明和元年11月21日「琉球國読谷山王子を携えて営に上る」と寛政重修諸家譜に出ている。其時に貰ったのか其後かは知らないが、読谷山家に彼の書が遺蔵されている「萬世之寶」と書いて南山主人の落款がついているとのことだが私はまだ拝見せぬ。南聘紀考に依ると安永2年当時太子であった中城王子尚温も、15歳に及びたるにより恒例の如く薩摩に往訪した。その時にも読谷山王子は随行した。文化3年に尚灝王は又読谷山王子を使して江戸に入貢すとあるから、同王子と重豪とは会する機会が多かったことが知られる。
▲武藤長平氏は其の目下琉球紙上に連載されている薩藩の琉球統治の中に「歴代の薩藩主中最も学問的に琉球を利用したのが、島津重豪で之を学問的にも、将た又経済的にも、利用したのが島津斉彬である」と云はれた。それは当っているだらうが、重豪は単に学問的ばかりでなく彼は又経済的にも琉球及び琉球人を利用している事実がある。利用し得たと云ふ程のものでなければ利用せんとしていた事実は明らかである。それは稿を改めて書こう。
1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」


1919年9月14日ー『沖縄時事新報』末吉麦門冬「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人」(~9月22日)


○1990年3月 『新琉球史ー近世編(下)』琉球新報社
池宮正治「和文学の流れ」□さきに、『小門の汐干』に入集している、渡久山政順と渡久山政規の関係について、「親子か兄弟といった近い関係かと思われるが、琉歌集にも心あたりの人はいない。あるいは『沖縄集』の玻名城親方政順かとも考えられるが詳細は不明」と述べておいた。すると早速特異な資料ハンター新城栄徳氏から連絡があり、名護市立博物館に収蔵されている宮城真治氏の新聞切抜きにある、末吉麦門冬(1886~1924)が「沖縄時事新報」(1919~1925)に発表した「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人ー」のコピーを恵まれた。宮城真治切抜き資料については、沖縄県の組踊調査のさい見ているが、組踊関係の資料を収集しただけで、見過ごしてしまったようだ。この麦門冬論文は、私の積年の宿題を一挙に解消してくれるものであった。
1918年11月16日 大里村で「沖縄歴史地理講話会」
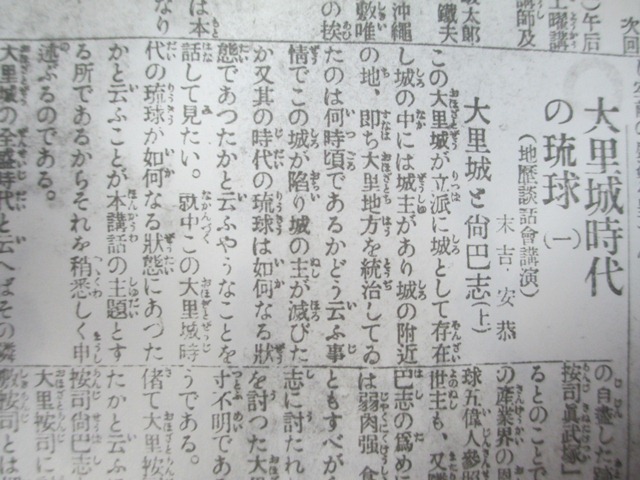
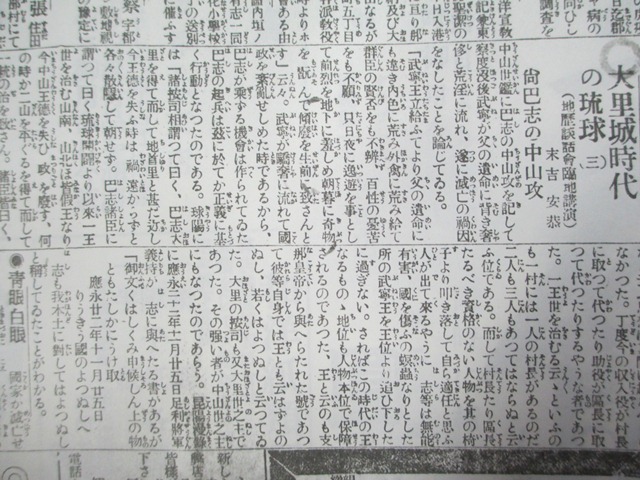
○この三山分裂に就いては説をなす者あり、もと方々に部落をなした住民が地勢によりて、山北は山北で一団、中山は中山で一団、南山は南山で一団になりて次第に発達して、その勢力が対敵行為をなすようになったので、嘗て中山に統一されたものが分離したものでないと。地勢によりて住民が割拠の勢いをなしたと云ふことは私も承認する、(略)英祖王の時代、遠く大島までが服従した位だから既にこのときは国内を漸く統一していたことが知れる。それが玉城王の時に中央の勢力が衰微に乗じて瓜分割拠の勢いを呈したのではあるまいか。
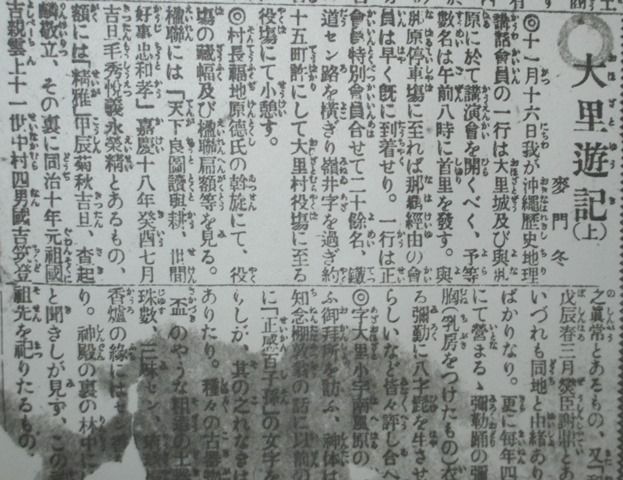
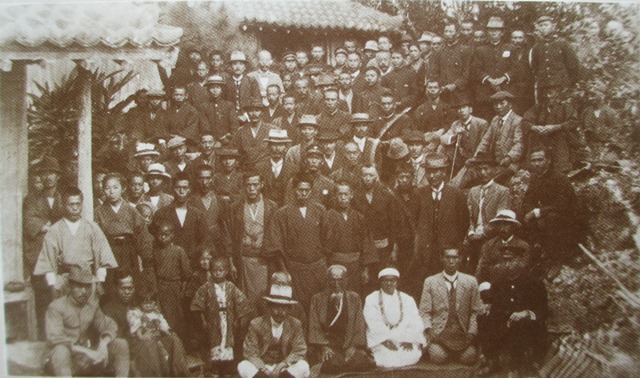
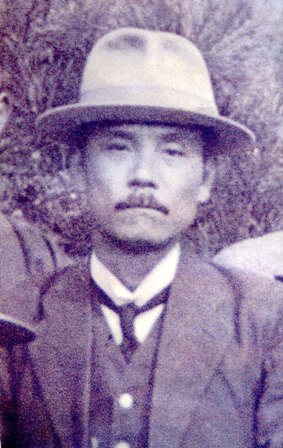
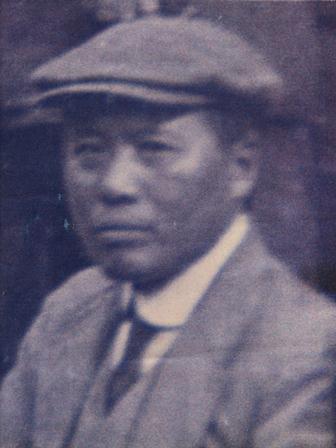
当日の真境名安興/末吉安恭
11月22日『沖縄時事新報』安良城盛雄(上海)「田島先生」(1)
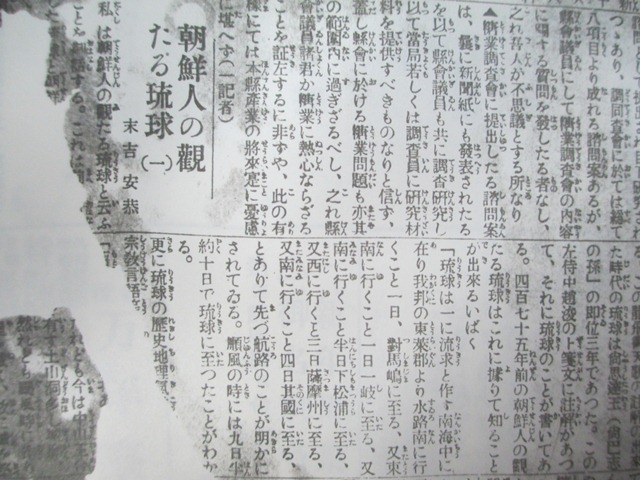
1919年12月8日 『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」
12月12日『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」(4)
12月 『沖縄時事新報』広告「神村朝忠薬店(首里儀保町酒ヤ知念小ノ向)ー1、諸売薬特ニ眼病ト梅毒ノ1、名薬/一枚コヨミト畧本暦/1、北斗中正暦ト柱コヨミ/1、東京神誠館発行御寿寶/1、易者一般ノ必要各種」
1919年6月ー末吉麦門冬『沖縄時事新報』創刊に参画
1919年6月『日本及日本人』759号 末吉麦門冬□「経済ーエコノミーを経済と譯するの適否は如らず、會澤正志の新論に「或毛擧細故、唯貨利是談、自称経済之學」云々とあり、政治が今日謂ふ所の経済に重きを置くことが、近世的傾向たるにより、訳者をして此の語を選ばしめ、敢て不適当を感ぜしめざるに至りしやも知るべからず。又支那にも後世に至り経済を倹約の意に用ひしことありや。清朝の詩人舒位の詩に「一屋荘厳妻子佛、六時経済米鹽花」とあり、猶ほ考ふべし。」□南方熊楠□「夜啼松ー佐夜の中山より十町斗りを過て夜啼の松あり、此松をともして見すれば子供の夜啼を止るとて往来の人削り取きり取ける程に、其松遂に枯て今根斗りに成けりと、絲亂記より六十二年前に成た東海道名所記三に見ゆ。其頃早く枯れ居たのだ。」
1919年7月15日ー『日本及日本人』761号□末吉麦門冬「琉球風と王子の歌」
1919年8月15ー『日本及日本人』763号□南方熊楠「ストライキー麦生君は自笑の常世誰が身の上に依って、徳川幕府の中葉既にストライキが多少本邦で行われたと立証されたー」
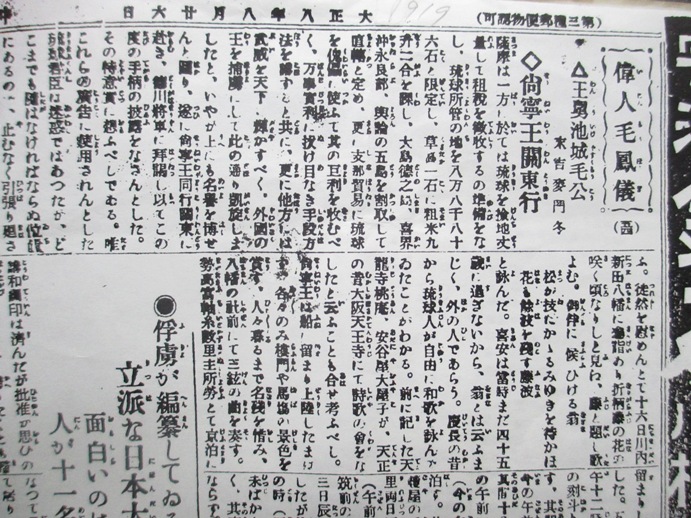
1919年8月26日 『沖縄朝日新聞』末吉麦門冬「偉人 毛鳳儀ー王舅池城毛公」」(喜安日記)
1919年9月 『沖縄時事新報』麦門冬「南山俗語考を見て(下)」
▲古賀精里の序文にも南山主人の跋文にもなくして、今一つの重要なる事があって、薩摩をして支那語研究をなさしむる動機となり目的となった。それが又南山俗語考を作らしむる動機ともなり目的ともなった。それは琉球を仲介としての支那貿易をなしている特殊の関係が薩摩にあったことだ。この特殊の関係がある故に彼等は色々の詭計を設けて、例えば藩士に琉装せしめ、琉球人と共に支那に派したりしたこともある従って支那語に堪能ならなければならぬ必要は琉球に劣らざるものがあった。23歳の一青年たる南山主人をして俗語考を著はす考を起さしめたのもこれが重大であらうと思ふ武藤長平氏の説に依ると、流石に大名が金をかけ長い年月を費やして作ったものだけありて、長崎辺から出た支那語の辞書などとは比較にならぬ程、この辞書は正確なものであるとの事だ。薩摩よりも官話ならこっちが本場だと思はれた、琉球人までがこの書を官話研究の唯一の手引としたのも又偶然にあらずと思ふ。
▲これより彼と琉球との関係の片影を一寸紹介して見たい、彼は延享2年の生まれであるから琉球の読谷山王子朝憲とは同庚である。それも一つの原因であったのだらう読谷山王子とは甚だ懇意であったらしい。明和元年11月21日「琉球國読谷山王子を携えて営に上る」と寛政重修諸家譜に出ている。其時に貰ったのか其後かは知らないが、読谷山家に彼の書が遺蔵されている「萬世之寶」と書いて南山主人の落款がついているとのことだが私はまだ拝見せぬ。南聘紀考に依ると安永2年当時太子であった中城王子尚温も、15歳に及びたるにより恒例の如く薩摩に往訪した。その時にも読谷山王子は随行した。文化3年に尚灝王は又読谷山王子を使して江戸に入貢すとあるから、同王子と重豪とは会する機会が多かったことが知られる。
▲武藤長平氏は其の目下琉球紙上に連載されている薩藩の琉球統治の中に「歴代の薩藩主中最も学問的に琉球を利用したのが、島津重豪で之を学問的にも、将た又経済的にも、利用したのが島津斉彬である」と云はれた。それは当っているだらうが、重豪は単に学問的ばかりでなく彼は又経済的にも琉球及び琉球人を利用している事実がある。利用し得たと云ふ程のものでなければ利用せんとしていた事実は明らかである。それは稿を改めて書こう。
1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」


1919年9月14日ー『沖縄時事新報』末吉麦門冬「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人」(~9月22日)


○1990年3月 『新琉球史ー近世編(下)』琉球新報社
池宮正治「和文学の流れ」□さきに、『小門の汐干』に入集している、渡久山政順と渡久山政規の関係について、「親子か兄弟といった近い関係かと思われるが、琉歌集にも心あたりの人はいない。あるいは『沖縄集』の玻名城親方政順かとも考えられるが詳細は不明」と述べておいた。すると早速特異な資料ハンター新城栄徳氏から連絡があり、名護市立博物館に収蔵されている宮城真治氏の新聞切抜きにある、末吉麦門冬(1886~1924)が「沖縄時事新報」(1919~1925)に発表した「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人ー」のコピーを恵まれた。宮城真治切抜き資料については、沖縄県の組踊調査のさい見ているが、組踊関係の資料を収集しただけで、見過ごしてしまったようだ。この麦門冬論文は、私の積年の宿題を一挙に解消してくれるものであった。
1918年11月16日 大里村で「沖縄歴史地理講話会」
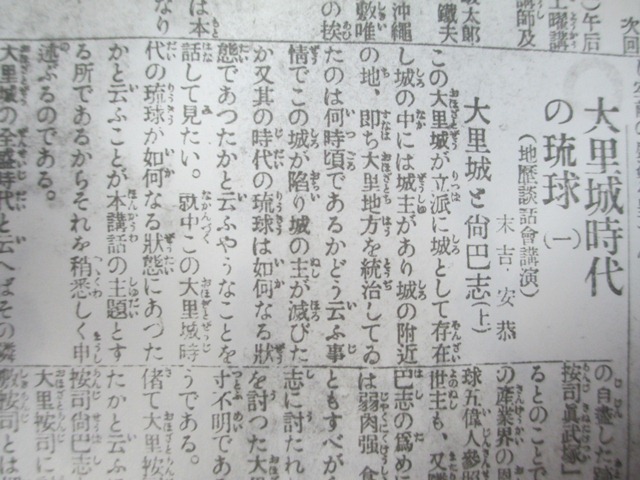
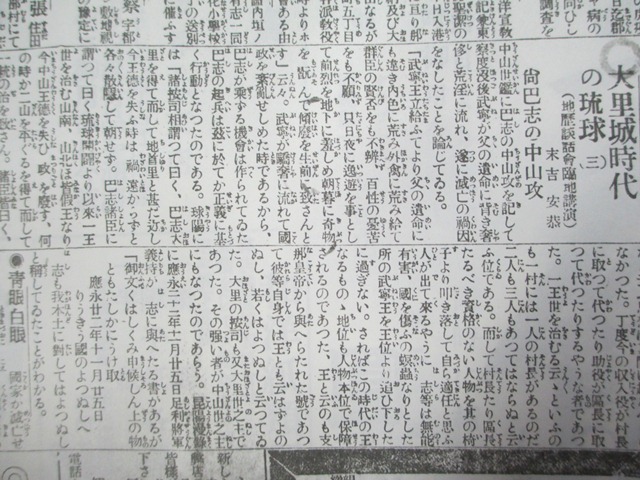
○この三山分裂に就いては説をなす者あり、もと方々に部落をなした住民が地勢によりて、山北は山北で一団、中山は中山で一団、南山は南山で一団になりて次第に発達して、その勢力が対敵行為をなすようになったので、嘗て中山に統一されたものが分離したものでないと。地勢によりて住民が割拠の勢いをなしたと云ふことは私も承認する、(略)英祖王の時代、遠く大島までが服従した位だから既にこのときは国内を漸く統一していたことが知れる。それが玉城王の時に中央の勢力が衰微に乗じて瓜分割拠の勢いを呈したのではあるまいか。
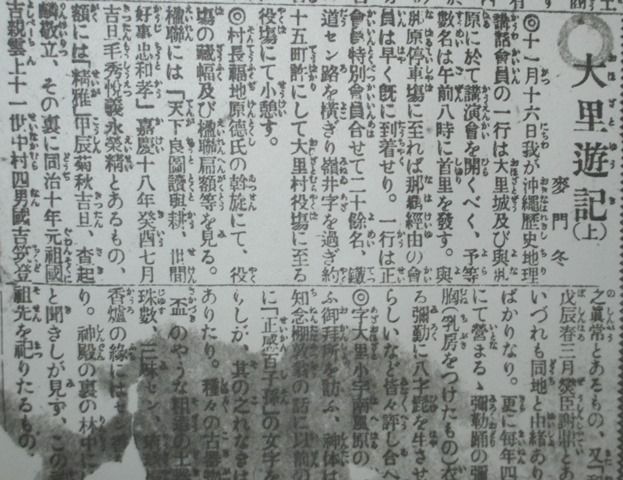
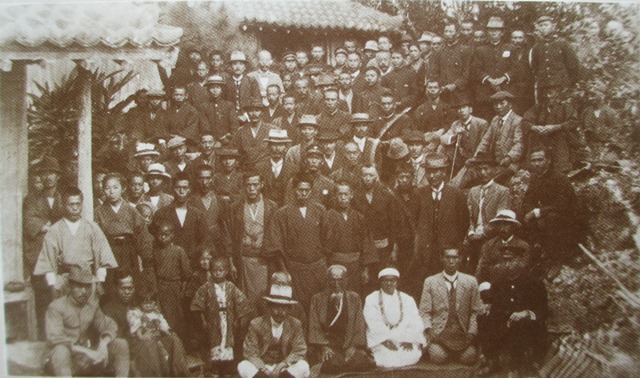
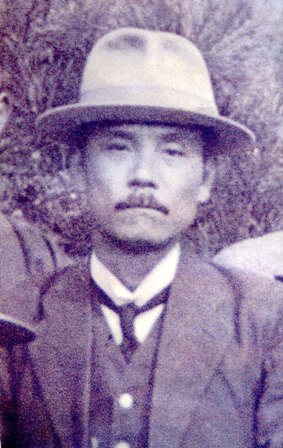
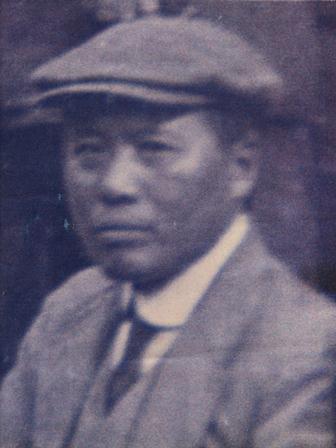
当日の真境名安興/末吉安恭
11月22日『沖縄時事新報』安良城盛雄(上海)「田島先生」(1)
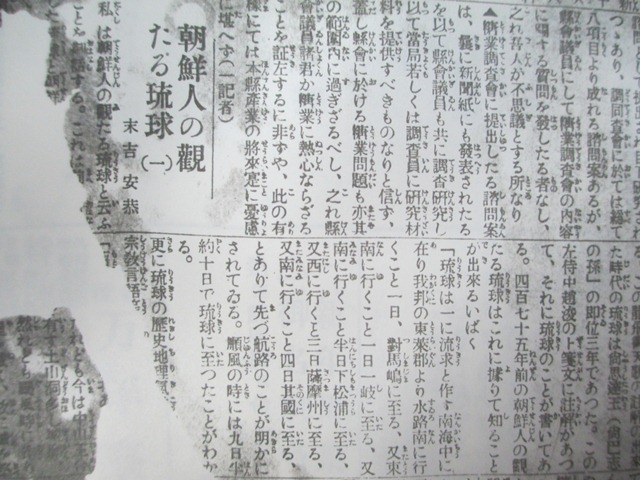
1919年12月8日 『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」
12月12日『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」(4)
12月 『沖縄時事新報』広告「神村朝忠薬店(首里儀保町酒ヤ知念小ノ向)ー1、諸売薬特ニ眼病ト梅毒ノ1、名薬/一枚コヨミト畧本暦/1、北斗中正暦ト柱コヨミ/1、東京神誠館発行御寿寶/1、易者一般ノ必要各種」
昨年暮れ、沖縄県立博物館・美術館指定管理者の「文化の杜共同企業体」から今年5月に開催される企画展「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した“美”」の図録に末吉麦門冬と鎌倉芳太郎についての原稿依頼があった。奇しくも今年11月25日は末吉麦門冬の没後90年で、展覧会場の沖縄県立博物館・美術館に隣接する公園北端はかつて末吉家の墓があった場所である。加えて、文化の杜には麦門冬曾孫の萌子さんも居る。私は2007年の沖縄県立美術館開館記念展図録『沖縄文化の軌跡』「麦門冬の果たした役割」の中で「琉球美術史に先鞭をつけたのは麦門冬・末吉安恭で、その手解きを受けた一人が美術史家・比嘉朝健である。安恭は1913年、『沖縄毎日新聞』に朝鮮小説「龍宮の宴」や支那小説「寒徹骨」などを立て続けに連載した。そして15年、『琉球新報』に『吾々の祖先が文字に暗い上に筆不精(略)流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の国ではある』と朝鮮の古書『龍飛御天歌』『稗官雑記』などを引用し、『朝鮮史に見えたる古琉球』を連載した。
画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬
安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。
麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
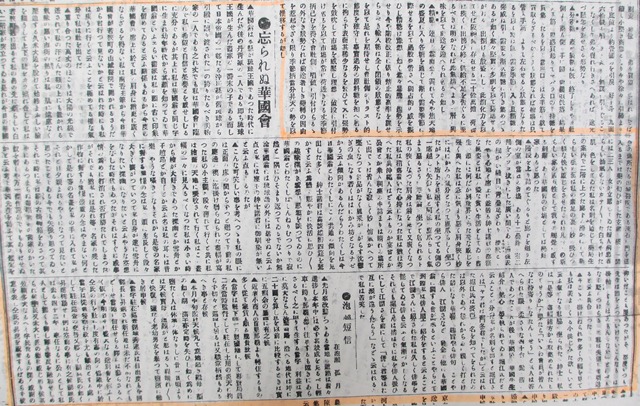
華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・
麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

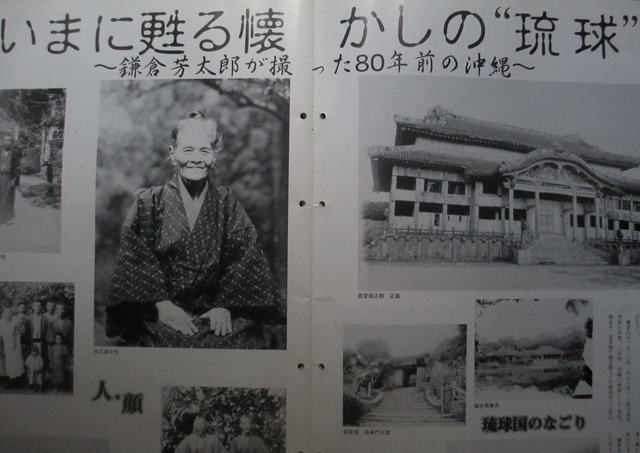
画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬
安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。
麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
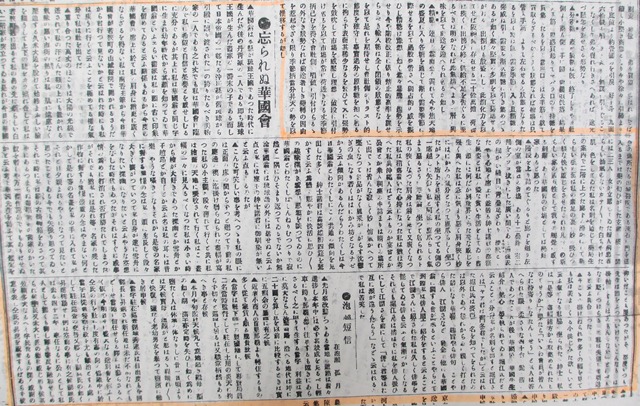
華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・
麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

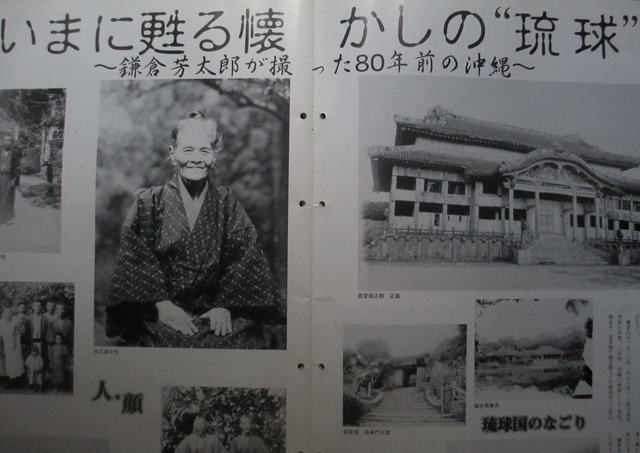
10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年
1917年(大正6)
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
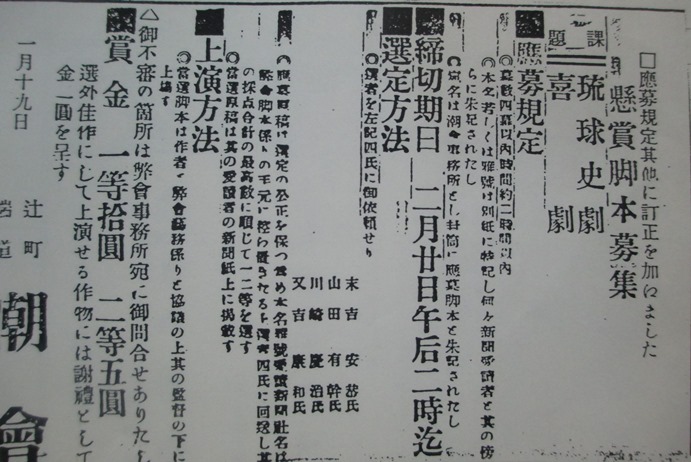
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
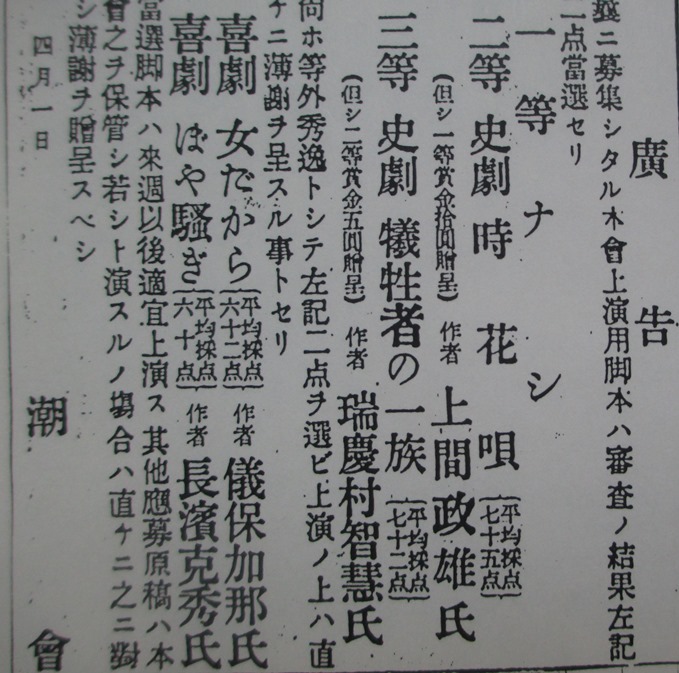
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
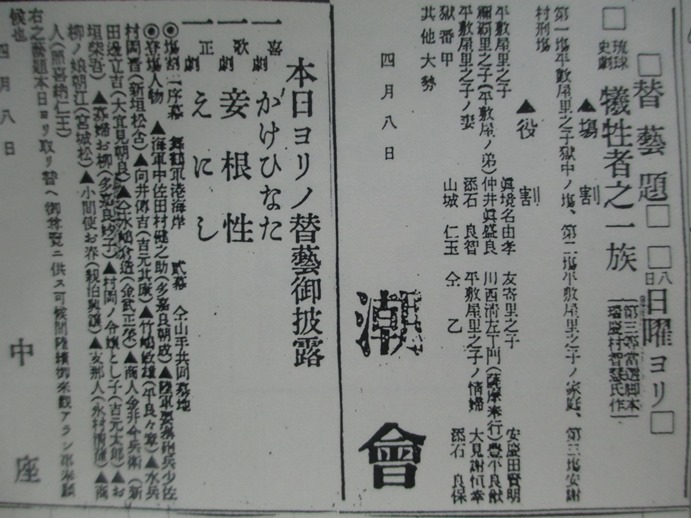
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
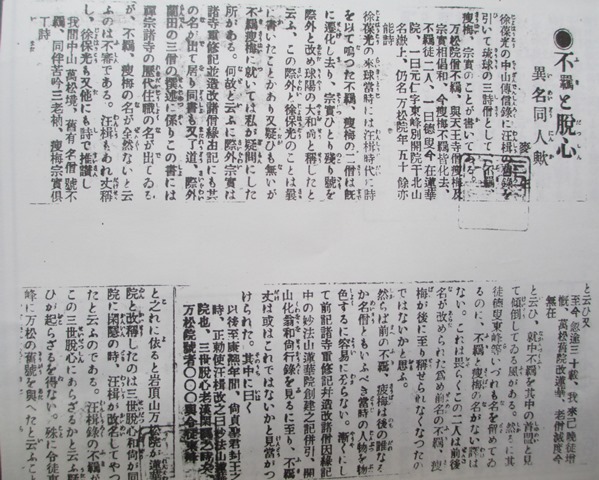
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
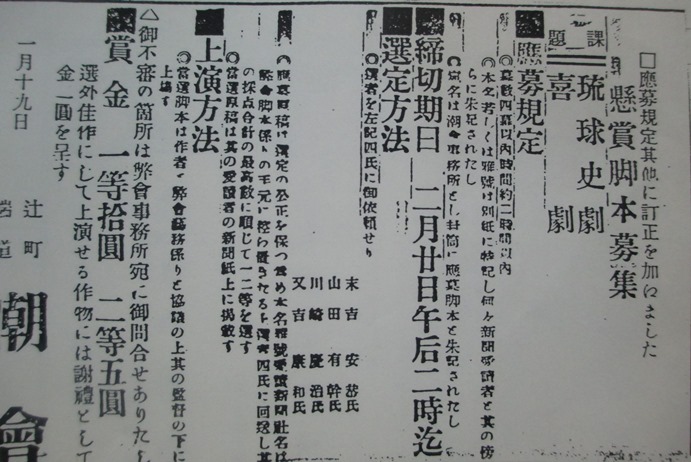
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
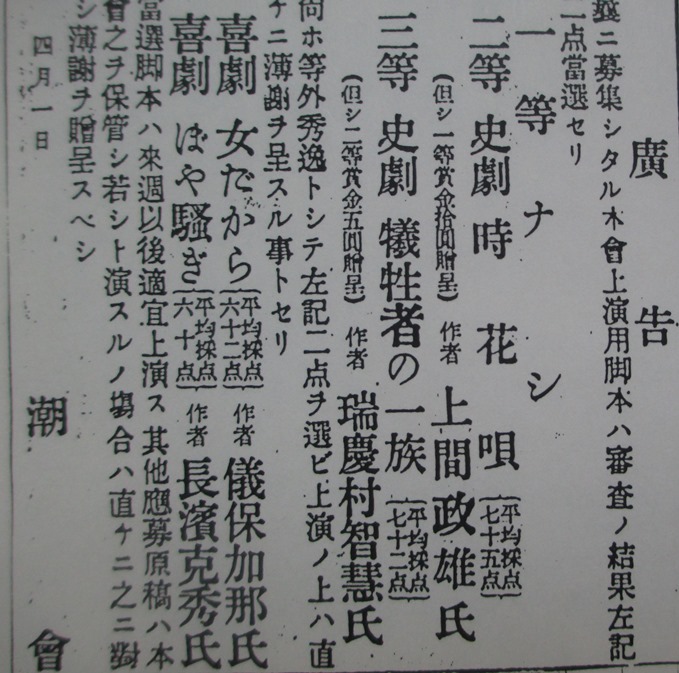
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
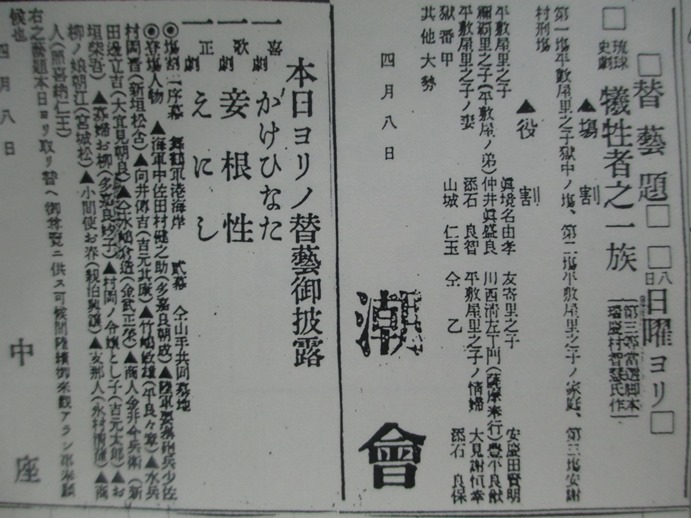
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
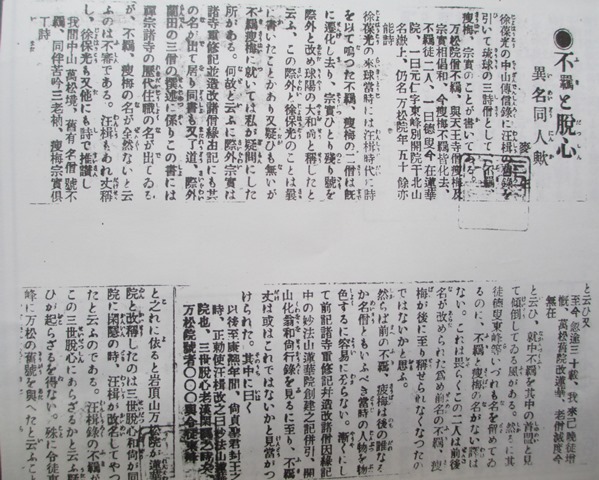
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
07/04: 麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安持(1887年~1907年)
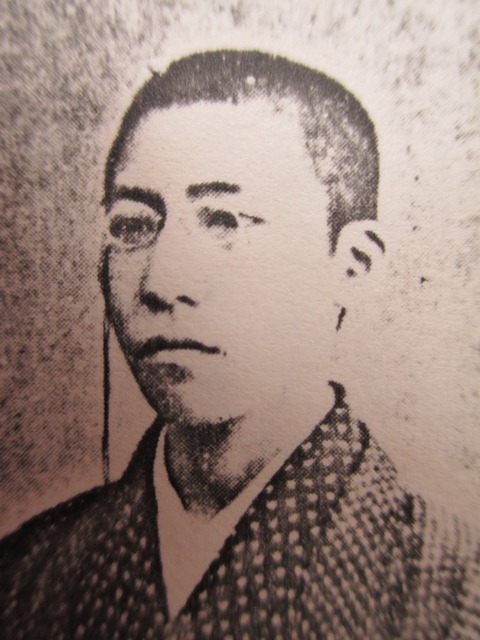
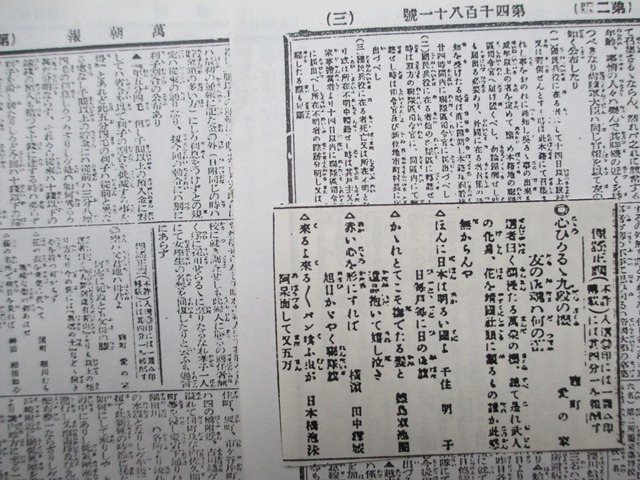
1905年3月25日『萬朝報』愛の家・末吉安持「心ひかるる九段の櫻 友の御魂は何の蕾」
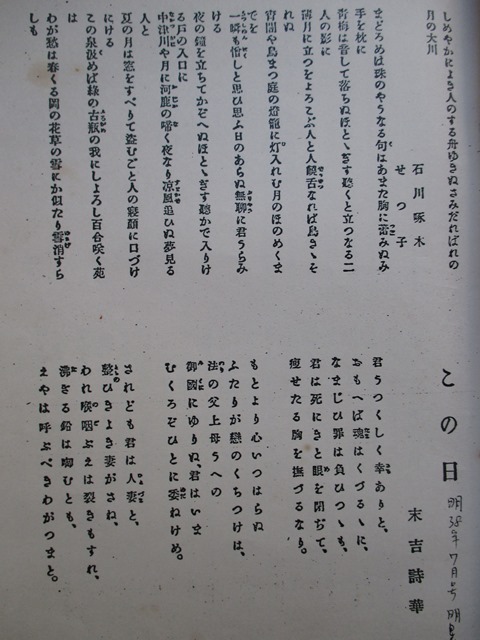
1905年『明星』7月号○下ー末吉詩華「この日」/上に石川啄木せつ子夫妻の歌
1907年『明星』3月号「故末吉安持」
与謝野寛○余は佐々木秀道を亡くして一箇月の後に、また新詩社同人末吉安持をうしなった。秀道の死も意外であったが、安持の死は突然であると共に、まことに語るに忍びざる程悲惨であった。氏は二月の九日に藝苑社の講演を聴いて飯田町の下宿に帰ったが、翌十日の午前三時頃、どうしたはづみか、机上の洋燈が落ち掛かり、全身三分の二を火傷して人事不省となり、同家の友人に送られて神保院と云ふ病院に入院した。医師は種々の治術を施したが、立会った友人等は皆な目を掩うて之を見るに忍びなかった。三日の後、氏は仰臥の儘身じろぎの成らぬに拘わらず非常に元気を回復したが、併し医師は其れを却て危険なる兆候だと云った。果たして十六日の夜から昏睡にに陥り、十七日の午前五時終に不帰の人と成った。享年二十一.このうら若い、将来のある詩人を、突然と過失のために、斯かる悲惨な最期に終わらしめたのは、痛嘆至極、何と慰むる言葉も無い。
氏は沖縄県首里区字儀保の素封家末吉安由氏の二男であった。中学にあった頃は常に優等の成績を示したと云ふ。父兄が文学の嗜好を以って居る所から、その感化を受けて文学を好むだが、父兄も氏が文学者となることを望み、氏も其積もりで三十七年の二月に出京し、爾来英語を国民英学会に学んで居た。初め長詩を前田林外氏等の雑誌『白百合』や『天鼓』に投じて居たが、三十八年の三月に新詩社に加わり、其後は専ら『明星』にのみ作物を載せた。氏は短歌を作らず、長詩のみの作者で、毎月必ず二三篇を余の手許に送った。十六歳から詩を作り始めたといふが、確かに詩人たる情熱と、独創の力と、物事に対して一種他人と異なった睨みかたとが有って、漫に先人の模倣を事とする無定見者流とは選を異にして居った。三十七年頃は児玉、平木二氏の詩風を慕ひ、三十八以後は薄田、蒲原二家の詩集を愛読し、殊に上田氏の『海潮音』に由って詩眼を開くことを得た一人であった。また能く余が厳格なる批判に聴いて『明星』に採録する氏の詩が、その所作の十が一にも過ぎざるに拘わらず、毫も不満に思ふ色なく、之に激励せられて益々慎重の心掛を加へ、精苦の作を試みた。その詩は昨年に入って頓に進境が見え出したが、本年三月の『明星』に載せた「ねたみ」一篇が、図らずも絶筆と成った。(以下略)
山城正忠○ああ、僕が詩歌の交際に於いて親しい友の一人なる詩華末吉安持君は、本年二月十七日二十一歳を一期に、燃ゆるやうな青春の希望を抱いて、空しく白玉楼中の人となってしまった。回顧すれば、僕が君を知ったのは、三十六年の夏の頃で、或友の紹介を得て、初めて君をその邸宅に訪ふたが、白百合を紫色した薬瓶に活けた氏の書斎に通され、親しくその風丰に接することを得た。『僕は山城といふものですが、以後どうぞ宜しく』と挨拶をすると、君は優しい眉根を、こころもち上げて『あ、さうですか・・・・・・』と云ったきり、何とも言って呉れぬ。そこで、僕は何だか気にくはなかった。少し横柄な人だなと、心中密かに氏の人格を疑った。併し、だんだん話して見ると、思ったよりはさばけた人で、僕の考は全く邪推に過ぎなかった。其日は面白く君の気焔にまかれて、帰ったが、それが縁となって、逢ふことが度かさなるにつれ、互いに胸襟を開いて話すやうになった。
時には徹夜して酒を飲みながら詩を語り、或る時は深夜奥の山公園の松林で月を賞して、清興を共にした。又或時は、たわいもない事から口論をやることもあったが、それもほんの一時で、直ぐあとは光風雲月といふ塩梅に、一笑に附して了った。君は情の人で意志」の人ではなかった。その情の厚かったことは、友達が一度困厄して居るのを見ると、実に萬腔の同情を以って之を慰籍し、且つ救護したのである。それから酒を飲むとなかなか面白い男で、いつでも団十郎や菊五郎の假色をつかふのが十八番であったらしい。その頃から君は新詩社の詩風に私淑して居って、詩の話になると、すぐ『紫』や『みだれ髪』を持出し、言葉を極めて賞讃した。それに僕も与謝野氏の歌は『東西南北』『天地玄黄』時代から、ひそかに景仰して居ったのであるから、互いに負けぬ気になって、讃辞を交換すると云ふ風であった。それからもう一人君の敬慕して居た詩人は薄田泣菫氏で、その『行く春』『暮笛集』は、いつ行っても氏の机の上に飾られてあった。その為め僕も君に感化せられては又泣菫氏の詩を愛読するやうになり愈愈両人は趣味が一致した。
これが僕等の交際をして益々親密ならしめた楔子である。泰国の詩人では、君はバイロンとダンテを称揚し、僕はアナクレオンを賛美した。今一人我国では、故人樗牛氏を崇拝して居たらしい。併し近頃は何う変わって居たか、琉球と東京と隔って居たから僕には分からない。なんでも夏目氏と上田敏氏とに大層私淑して居たといふことを外から聞いた。さうかうする内、君は突然上京して了ったので、僕は何だか離れ小島に独りとり残された思がした。爾来音信を絶つこと殆ど二年、時々友人からその消息の一端を聞くばかりで、氏からは端書一枚をも寄越してくれない。随って互いに疎遠に成って居た。然るに三十八年の四月、僕は補充兵で上京し、青山の第四聯隊に入営することになった。毎日練兵が忙しくって、つい君を尋ねることも出来ず、直ぐ近所の与謝野氏の御宅にさへ伺ふことが出来ぬと云ふ始末、それが殆ど七箇月に亘って、十月の中頃、病気に罹って召集解除となり、再び故山の人となった。
兵営を出て明日帰郷すると云ふ晩、神田の或る本屋の店頭で『天鼓』といふ雑誌を見た。何心なく披いて見ると、末吉詩花として『平和の歌』(たしかさうであったとおもふ)といふ新體詩が出ているので急になつかしい思がした。併し尋ねるにも君の下宿が分からないから終に其儘逢はずに帰国して了ったのは、今から思ふと実に遺憾である。それから僕が琉球に帰って、初めて末吉君は近来『明星』に筆を執って居るといふことを聞いて、愈愈素志の如くやり出したなと、密かに氏の努力を羨んだ。昨年の夏君は帰省したので、久し振りに某酒亭に会して、親しく新詩社の現状を聞き且つ与謝野氏の御話なども受売して貰った。その時氏の語る所によると『与謝野氏は一見何だかコハイやうな方だが、詩に就いては至極親切に指導して下さるから有難い。君も新詩社の一人に加わって真面目に詩を作りたまへ』とのことであった。併し、僕はまだ早からうと述べた。その日は月の佳い夜であった。その月の光が、君と僕と此世で一緒に浴びる最終のものだとは、両人ともつゆ想ひ及ばなかった。ああその夜の光景と君が音容とは、今猶ありありと想ひ泛べ得るのに、君は既に世に居ないのであらうか。僕はまだ何うも君が死を信じ得られない
○1987年8月『沖縄県図書館協会誌』弟12号 仲程昌徳「新詩社同人・詩崋の作品ー末吉安持ノートー」
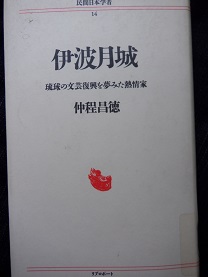
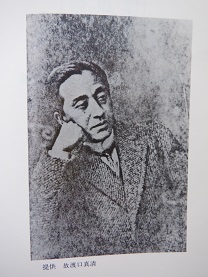
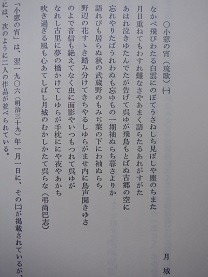
1988年5月 仲程昌徳『伊波月城ー琉球の文芸復興を夢見た熱情家』リプロポート
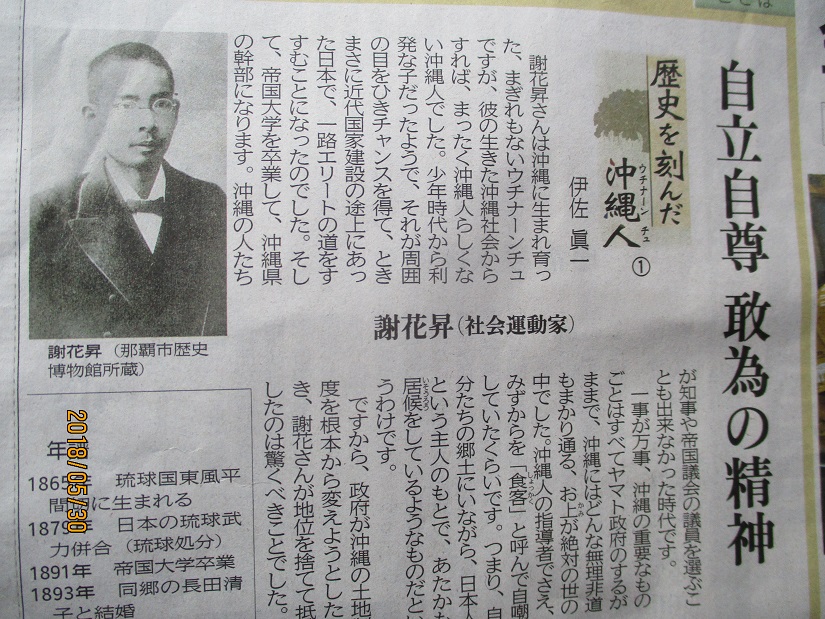
2018年4月8日『沖縄タイムス』伊佐眞一「歴史を刻んだ沖縄人①謝花昇 自立自尊 敢為の精神」
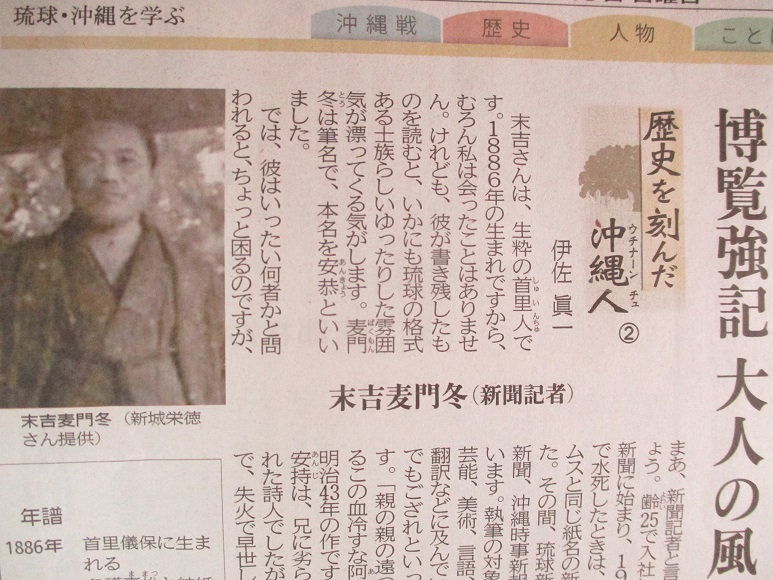
2018年5月13日『沖縄タイムス』伊佐眞一「末吉麦門冬(新聞記者)博覧強記 大人の風格」
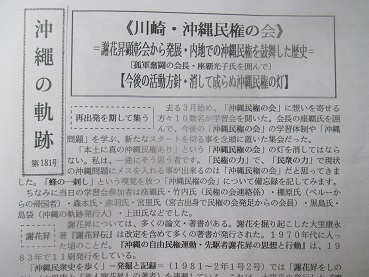
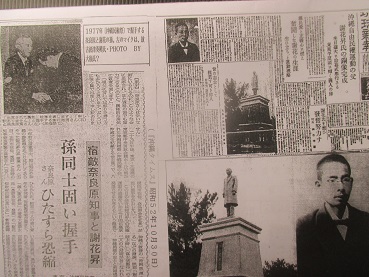
2018年3月3日 『沖縄の軌跡』「《川崎・沖縄民権の会》=謝花昇顕彰会から発展・内地での沖縄民権を鼓舞した歴史=」181号 編集発行人・島袋和幸(葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)
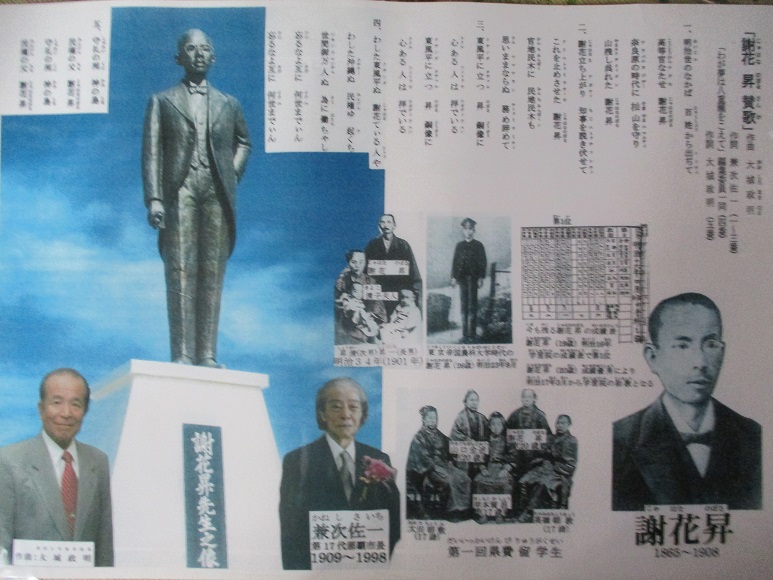

「謝花昇 賛歌」作詞・兼次佐一/作曲・大城政明/大城政明氏、伊佐眞一氏
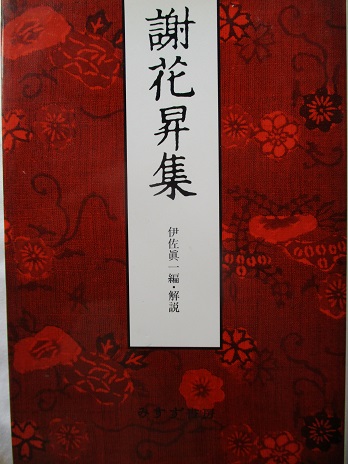
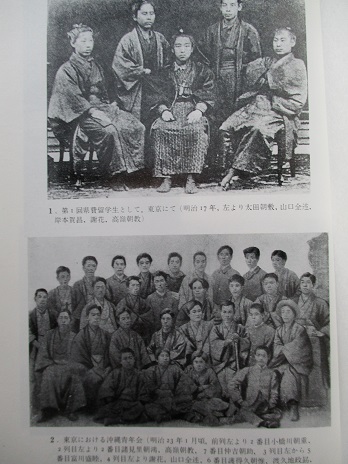
1998年6月 伊佐眞一『謝花昇集』みすず書房
1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号
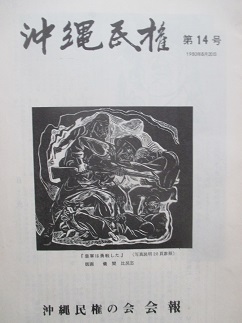
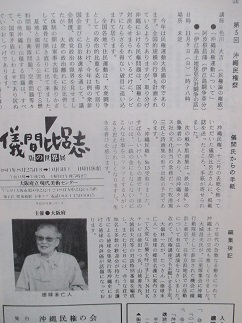
1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)□古波津英興「方言使用スパイ処分文書」
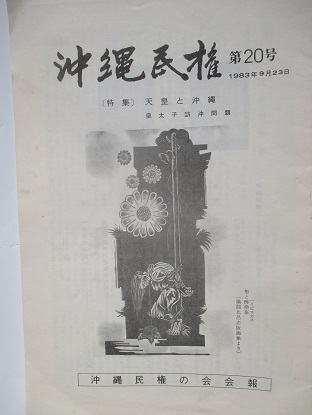
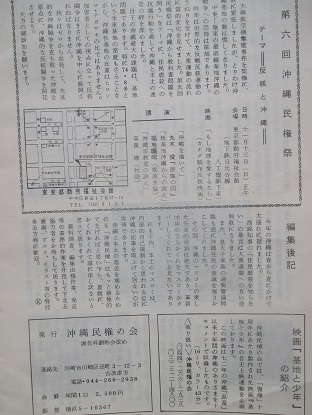
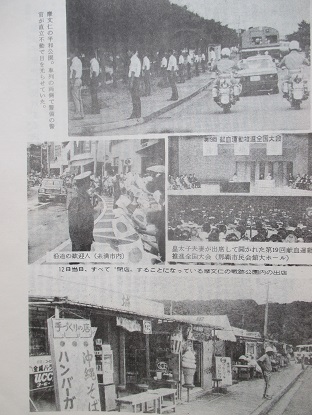

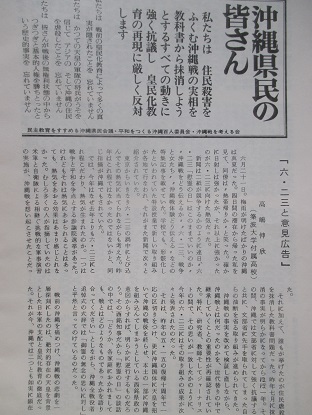
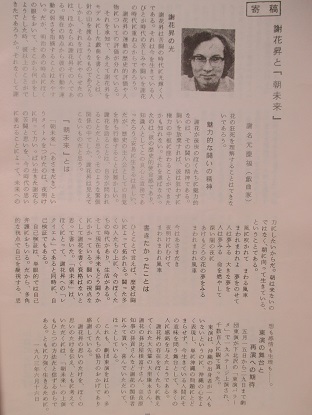
1983年9月23日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「菊と仏桑華」第20号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)


2018年3月14日 みどり印刷前でー石川和男氏(左)、島袋和幸氏/南風原文化センター前で島袋和幸氏
「みどり印刷」←iここをクリック
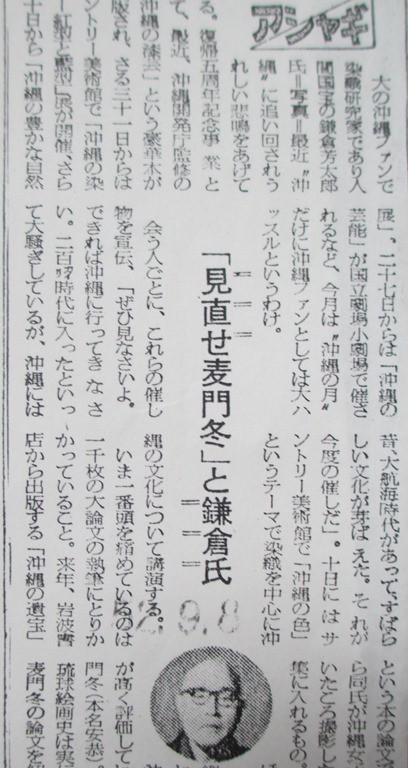
1977年9月8日『琉球新報』「アシャギー『見直せ麦門冬』と鎌倉氏」
1977年 『国語科通信№36』角川書店□鎌倉芳太郎(重要無形文化財<紅型研究>・玉川大学名誉教授)「首里言葉と那覇言葉ー(略)大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、世の中の傾向がデモクラシーの社会運動にゆさぶられている時代であったので、またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育って行った。・・・」
1978-4 『人間国宝シリーズ14 鎌倉芳太郎』講談社
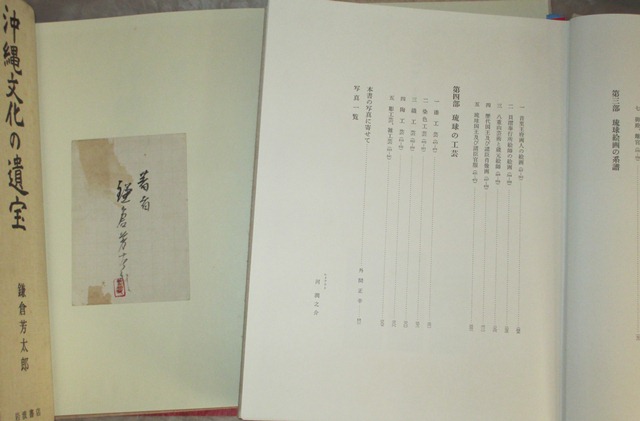
1982-10 鎌倉芳太郎『沖縄文化の遺宝』岩波書店
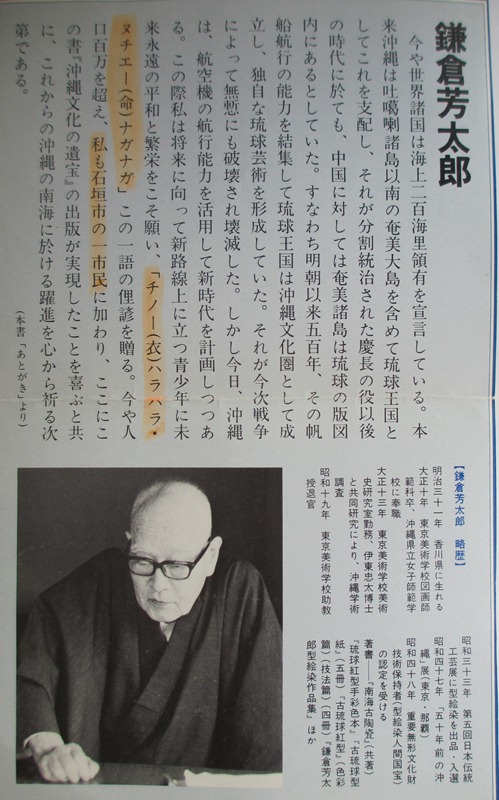
1998年 『沖縄県立博物館紀要』第24号□外間正幸、萩尾俊章「沖縄県立博物館草創期における文化財収集とその背景」
○1、首里博物館の時代 2、日本本土における文化財収集活動ー(1)1958年の文化財収集ー仲原善忠先生と我部政達氏 (2)1959年における文化財収集活動ー森政三氏、神山政良氏、東恩納寛惇先生 (3)1959年~61年の文化財収集ー鎌倉芳太郎先生
2003-9 浦添市美術館「今甦る80年前の沖縄~鎌倉芳太郎の撮った遺宝・風物~」沖縄テレビ・琉球新報社
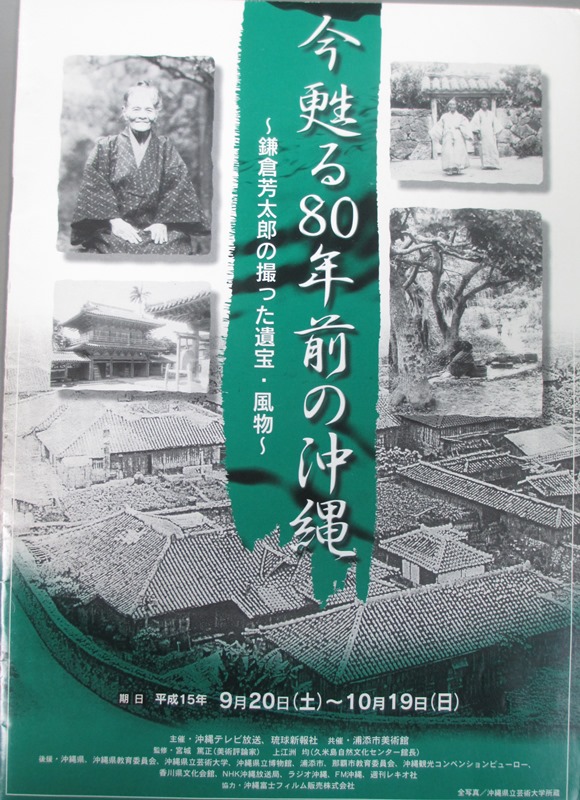
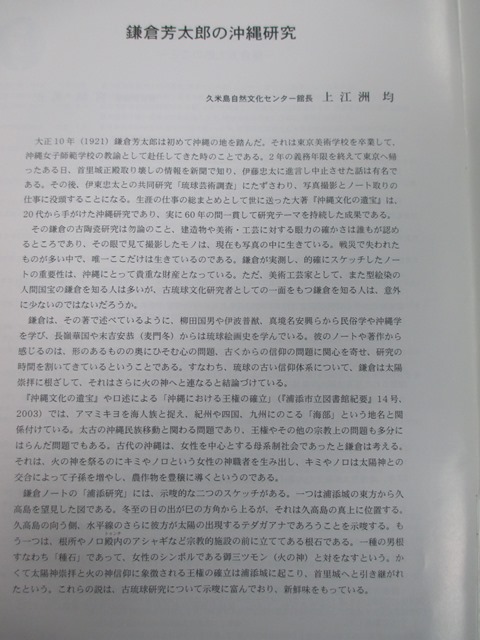
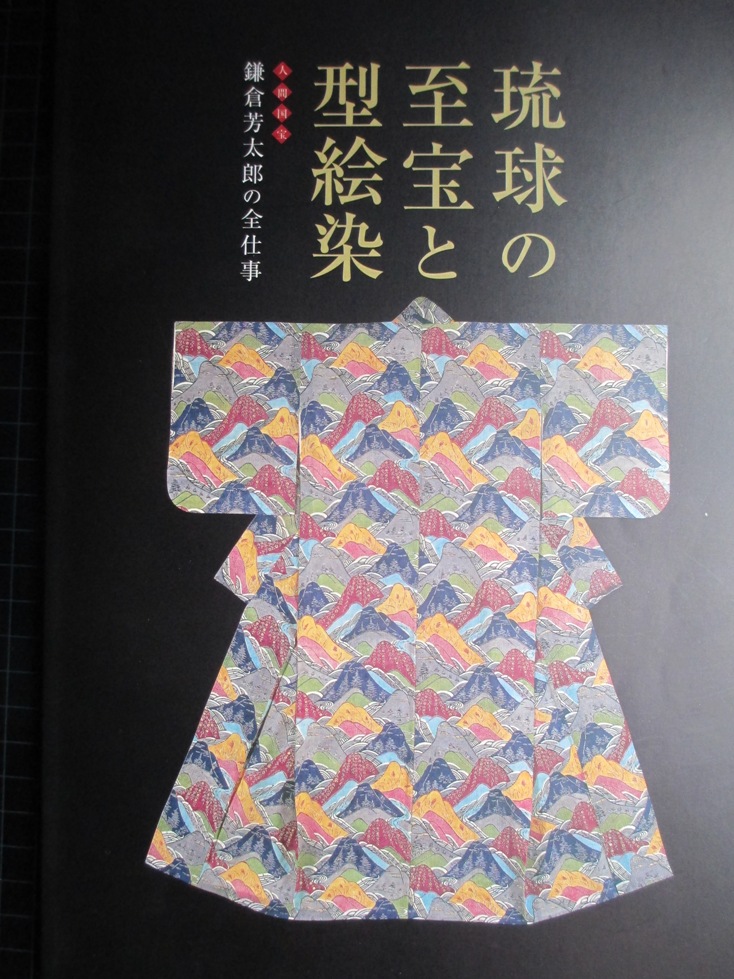
2003-11

2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号/2008年3月『沖縄芸術の科学』第20号
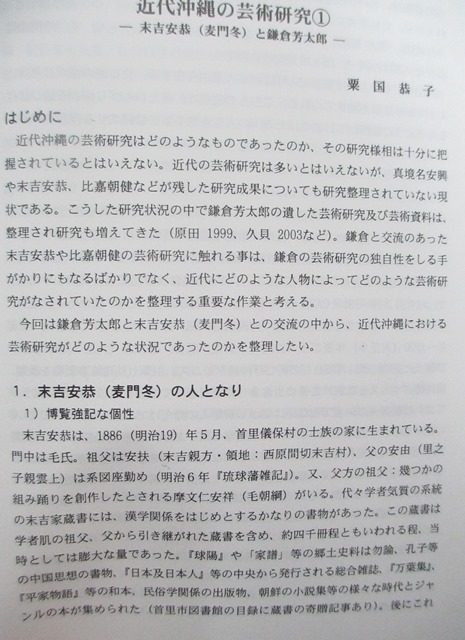
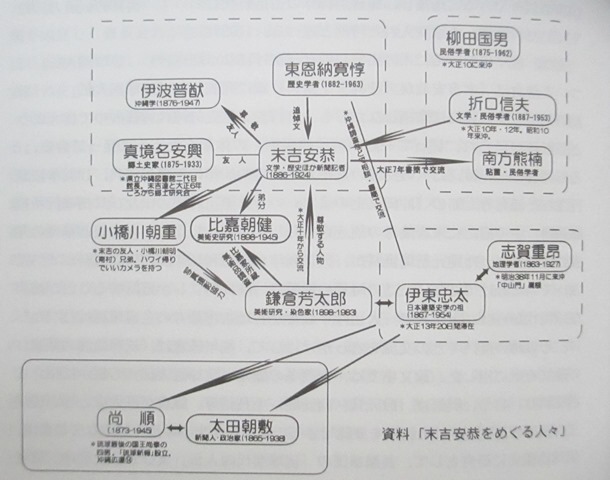
2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号□粟国恭子「近代沖縄の芸術研究①-末吉安恭(麦門冬)と鎌倉芳太郎」
06/08: 関西沖縄誌

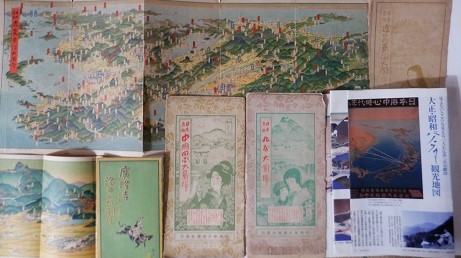
吉田 初三郎(よしだ はつさぶろう、1884年(明治17年)3月4日 - 1955年(昭和30年)8月16日)は、大正から昭和にかけて活躍した鳥瞰図絵師。元の姓は泉。生涯に約1600点とも3000点以上ともいわれる鳥瞰図を制作し、「大正の広重」と呼ばれた。→ウィキ
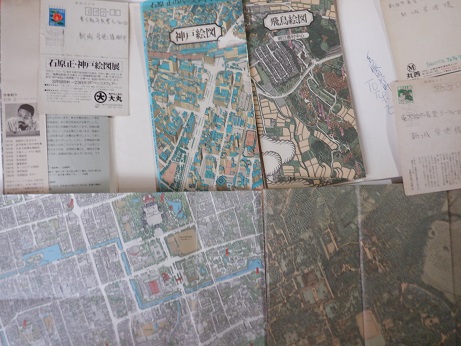
石原 正(いしはら ただし、1937年3月2日 - 2005年3月8日)は、日本の鳥瞰図絵師。北海道函館市出身。北海道函館西高等学校を経て、金沢美術工芸大学を卒業。広告会社に勤務していた時にヘルマン・ボルマンのニューヨーク鳥瞰図に出会い衝撃を受け、1969年に独立。以降、鳥瞰図制作の第一人者として活躍し続けた。→ウィキ

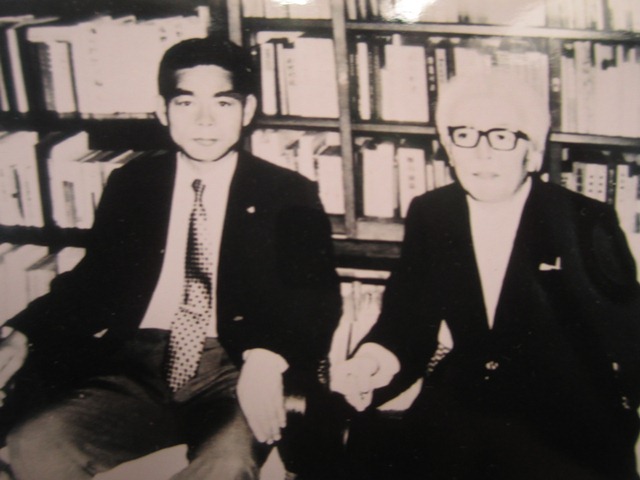
写真左/1999年5月11日沖縄ハーバービューホテルで神坂次郎氏(作家・熊野の生き字引で司馬遼太郎の文学仲間)、新城栄徳。麦門冬・末吉安恭の取材を終えての祝盃。撮影・末吉安允
写真右/1974年4月、司馬遼太郎が沖縄関係資料室に来室、西平守晴と対談司馬遼太郎『街道をゆく6』朝日新聞社
○大阪の都島本通で、篤志でもって「沖縄関係資料室」をひらいていおられる西平守晴氏にもきいてたしかめることができた。西平氏は、「そうです、そんな話があります」といって、南波照間の「南」を、パイと発音した。ついでながら本土語の南風(はえ)は沖縄でも「南」の意味につかう。本土語の古い発音では、こんにちのH音が古くはF音になり、さらに古くはP音になる。つまり花はパナである。八重山諸島の言葉はP音の古発音を残していて、南(ハエ)が南(パイ)になるらしい。西平氏はこのまぼろしの島を、「パイ・ハテルマ」と、いかにもその島にふさわしい発音で言った。
1158年 太宰大弐に任ぜられた平清盛は、太宰府に赴任することはなかったが、宋商船が運んでくる唐物に強い興味を抱き、やがて宋人を太宰府から瀬戸内海へと招いた。
☆神戸の灘の薬師さんの傍らで長年「国語」の研究に専念していた奥里将建翁、最後のまとめとして1964年「沖縄に君臨した平家」を沖縄タイムスに連載(10-8~12-11)した。□10月11日ー『沖縄タイムス』奥里将建「沖縄に君臨した平家」(4)怪傑・平清盛をして天寿を全うさせ、彼が抱いていた南宋貿易の夢を実現させ、中世日本の様相はすっかり一変していたかも知れない。(略)戦後のわが歴史学界において、清盛に対する評価が大分改まって来たのも、彼の経綸と人間的魅力を高く買って来たために外ならない」→「琉文21」雑誌『おきなわ』/1926年4月ー奥里将建『琉球人の見た古事記と萬葉』青山書店
1167年 平清盛、太政大臣となる


写真ー重要文化財本堂 昭和大修営落慶記念 昭和四十四年五月十八日 六波羅蜜寺(新城栄徳所蔵)
六波羅蜜寺は、天暦5年(951)醍醐天皇第二皇子光勝空也上人により開創された西国第17番の札所である。当時京都に流行した悪疫退散のため、上人自ら十一面観音像を刻み、御仏を車に安置して市中を曵き回り、青竹を八葉の蓮片の如く割り茶を立て、中へ小梅干と結昆布を入れ仏前に献じた茶を病者に授け、歓喜踊躍しつつ念仏を唱えてついに病魔を鎮められたという。(現在も皇服茶として伝わり、正月三日間授与している)
現存する空也上人の祈願文によると、応和3年8月(963)諸方の名僧600名を請じ、金字大般若経を浄写、転読し、夜には五大文字を灯じ大萬灯会を行って諸堂の落慶供養を盛大に営んだ。これが当寺の起こりである。上人没後、高弟の中信上人によりその規模増大し、荘厳華麗な天台別院として栄えた。平安後期、平忠盛が当寺内の塔頭に軍勢を止めてより、清盛・重盛に至り、広大な境域内には権勢を誇る平家一門の邸館が栄え、その数5200余りに及んだ。寿永2年(1183)平家没落の時兵火を受け、諸堂は類焼し、独り本堂のみ焼失を免れた。
源平両氏の興亡、北条・足利と続く時代の兵火の中心ともなった当寺はその変遷も甚だしいが、源頼朝、足利義詮による再興修復をはじめ火災に遭うたびに修復され、豊臣秀吉もまた大仏建立の際、本堂を補修し現在の向拝を附設、寺領70石を安堵した。徳川代々将軍も朱印を加えられた。現本堂は貞治2年(1363)の修営であり、明治以降荒廃していたが、昭和44年(1969)開創1,000年を記念して解体修理が行われ、丹の色も鮮やかに絢爛と当時の姿をしのばせている。なお、解体修理の際、創建当時のものと思われる梵字、三鈷、独鈷模様の瓦をはじめ、今昔物語、山槐記等に記載されている泥塔8,000基が出土した。重要文化財の質、量において文字どおり藤原、鎌倉期の宝庫と謂われる所以である。
1260年 英祖王、即位☆麦門冬・末吉安恭は、この時代を「仏教の起源と芸術の揺籃」と称した。
補陀落僧禅鑑、葦軽船で琉球に漂着、英祖王保護のもと極楽寺(のち龍福寺)を創建
1281年 島津長久ら薩摩国の兵を率いて壱岐にて元軍を攻める。
1372年 1月、楊載、来琉
1377年 琉球国王察度、南山王承察度ら明に使者を遣わし馬、方物を貢す。北山王帕尼芝、明に使者、方物を貢す。頼重法印(真言宗)、薩摩坊津から 来琉。
1402年 足利義満、島津伊久に明を侵す鎮西海賊の取締を命ず。
明使が北山第に足利義満を訪ね国書・大統暦、賜物を伝える。
1404年 時中、来琉し武寧に皮弁冠服が頒賜される。
1406年 武寧、寨官の子石達魯ら6人を明に遣わし国子監に学ばせる。
1410年 琉球国官生模都古ら2人、明の国子監に入り学を受ける。
1413年 中山王思紹、太勃奇を明に遣わし馬を貢し、寨官の子ウ同志久・周魯毎らを送り国子監で学ばせる
1415年 琉球国山南王汪応祖の世子他魯らを明朝に遣わす。足利義持、琉球国思紹に「りうきう国よのぬし」で書簡を送る。
1418年 琉球国中山王思紹、長史の懐機らを明に遣わす
1425年 柴山(中官)来琉、勅を齎らし巴志に中山王を嗣がせる。「中山門」扁額を掲げる。
1427年 安国山樹華木之記碑「壮者時有りて舞ひ、老者時有りて歌ふ」
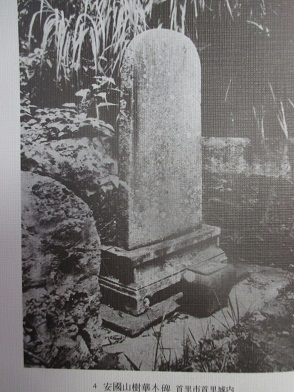
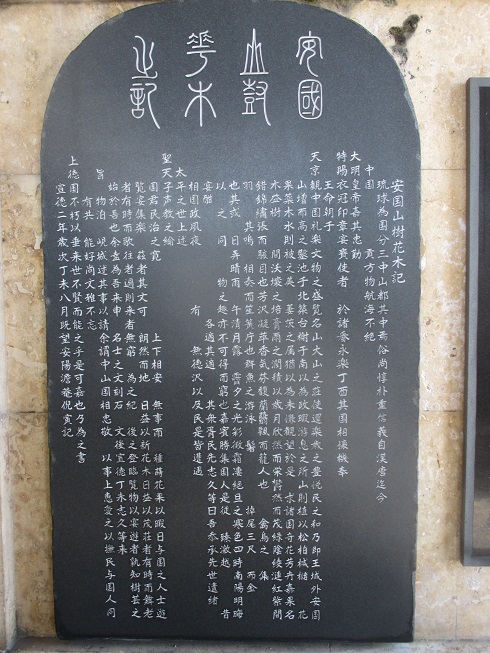
右ー沖縄県公文書館玄関にある安国山樹華木之記□首里王城の威容を増し、合わせて遊息の地とするため、王城の外の安国山に池(龍潭)を掘り、台を築き、松柏・花木を植え、太平の世のシンボルとして永遠の記念とする。
1429年 巴志、三山統一
1430年 巴志、明帝から尚姓を授けられる
1443年 朝鮮通信使の書状官として申叔舟が来日
1453年 朝鮮国、琉球国使者道安の齎らした日本琉球地図表装
1456年 尚泰久王、梵鐘を鋳造し大聖寺、天尊殿、相国寺、普門寺、建善寺、長寿寺、天竜寺、広厳寺、報恩寺、大安寺に寄進
1457年 尚泰久王、梵鐘を鋳造し霊応寺、永福寺、大禅寺、上天妃宮、天妃宮、竜翔寺、潮音寺、万寿寺、魏古(越来)に寄進
1458年 尚泰久王、万国津梁の鐘を正殿にかける。


万国津梁の鐘(沖縄県立博物館・美術館)
尚泰久王、梵鐘を鋳造し永代院に寄進
尚泰久王、梵鐘を鋳造し一品権現御宝殿、東光寺に寄進
1461年 島津立久、尚徳の国王即位を祝い太平書を賜う
1466年 琉球国王尚徳の使者芥隠承琥、足利義政に拝謁、方物を献ず。
□7月28日ー琉球の使者一行が将軍・足利義政に謁見、方物も献上する。
8月1日ー琉球正使・芥隠西堂から蔭涼軒(季瓊)真蘂に大軸(中国から琉球国王に贈られたもの)、南蛮酒を贈る。(義政時代6度目の琉球人 参洛)。
雪舟が描いた琉球人
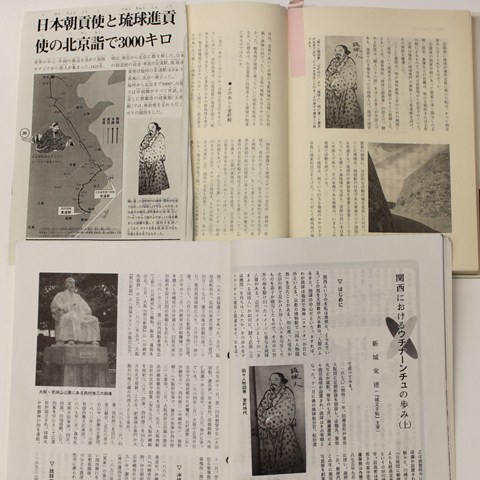
『自治おきなわ』1996年7月号に私(新城栄徳)は「京都の博物館で『国々人物図巻』を見たことがある。明に渡った雪舟が北京の街で見かけた珍しい人びとを写生したものを弟子が模写したもので、その中に世界の海を駆け回ったイメージに重なる琉球人像がある。」と書いた。明代の類書『万金不求人』に和寇図と共に大琉球國人も載っている。長崎県立美術博物館の正保版『万国人物図』にも琉球人が登場している。多くの絵師たちが好んで万国人物図を画題にしていたようだ。私は雪舟の弟子の絵の写真(琉球人)を琉球新報の岡田輝雄記者に提供。これは1991年9月発行の『新琉球史』(古琉球編)に載った。同様に佐久田繁月刊沖縄社長に提供したものは99年9月発行の『琉球王国の歴史』に載った。
1474年 尚円、島津忠昌の家督相続を祝う
1480年 足利幕府、応仁・文明の乱が終わったので琉球に朝貢船を送るよう島津忠昌に催促させる。
1482年 琉球国尚真、奏して陪臣の子蔡賓ら5人を南京国子監において読書させることを乞う。
1492年 ドイツ人地理学者マルティン・ベハイム、地球儀を作成
1492年 尚真王、先王尚円を祀るため円覚寺建設に着手
1497年 万歳嶺記、官松嶺記を建設。円覚寺禅寺記碑
1502年 朝鮮王季揉から贈られた方冊蔵経収集のため円鑑池に小堂を建設(1621年に弁財天像を安置)
1507年 尚真王、書を島津忠昌に送り修好の意志を伝える
1508年 島津忠治、尚真に書を送り、島津氏の印判(琉球渡海朱印状)を持たない商人を点検し船財等を収公を許す
1510年 尚真王、官生蔡進ら5人を南京国子監において読書を乞う。
1527年 尚清王、智仙鶴翁を遣わし明皇帝の日本宛の国書を齎す。足利義晴、書を尚清に送り日明和与の斡旋を謝す。
1530年 月船寿桂、「鶴翁(智仙)字銘并序」で為朝伝、琉球附庸説に言及。
1531年 『おもろさうし』第一巻、成る
1534年 5陳侃(正史)、高澄(副史)那覇着。7尚清冊封の礼。9冊封使、開洋。10陳侃『使琉球録』著わす
1550年 5月4日ー足利義晴、近江穴太(現滋賀県大津市穴太)にて死去。享年40(満39歳没)。
1556年 島津貴久、尚元王が建善寺月泉を遣わしたことに答書し隣交を求める。
1561年 郭汝霖(正史)、李際春(副史)
1568年(永禄11)9月 織田信長、将軍足利義昭を奉じ上洛、当面の仮御所として義昭は本國寺に入り、信長は清水寺を宿所とした。
1569年(永禄12) 仮幕府のおかれた本國寺が襲撃にあったことから、信長は義昭のために二条城(二条御所)を築く。
1569年(永禄12年)、将軍・足利義昭を擁して台頭していた織田信長と二条城の建築現場で初めて対面。既存の仏教界のあり方に信長が辟易していたこともあり、ルイス・フロイスはその信任を獲得して畿内での布教を許可され、グネッキ・ソルディ・オルガンティノなどと共に布教活動を行い多くの信徒を得た。その著作において信長は異教徒ながら終始好意的に描かれている。フロイスの著作には『信長公記』などからうかがえない記述も多く、戦国期研究における重要な資料の一つになっている。その後は九州において活躍していたが、1580年(天正8年)の巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの来日に際しては通訳として視察に同行し、安土城で信長に拝謁している。1583年(天正11年)、時の総長の命令で宣教の第一線を離れ、日本におけるイエズス会の活動の記録を残すことに専念するよう命じられる。以後フロイスはこの事業に精魂を傾け、その傍ら全国をめぐって見聞を広めた。この記録が後に『日本史』とよばれることになる。→ウィキ
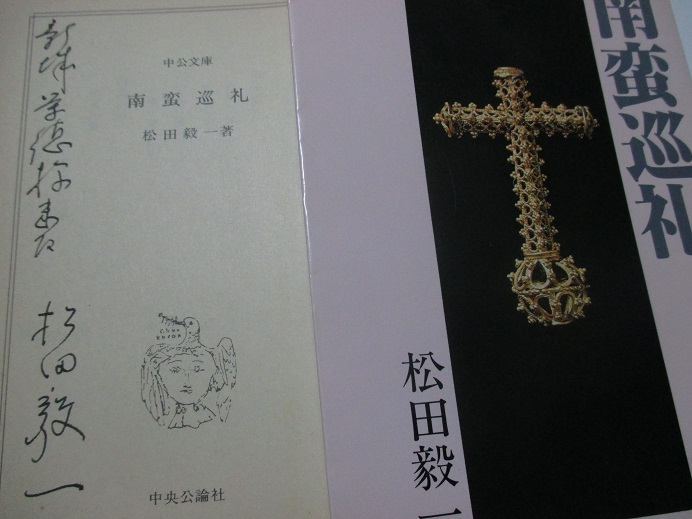
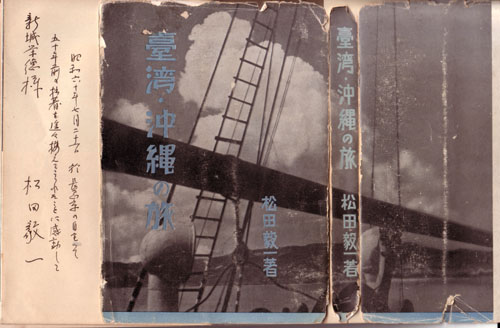
松田 毅一(まつだ きいち、1921年5月1日 - 1997年5月18日)は、日本の歴史学者。香川県高松市出身、大阪市育ち。専門は戦国時代から江戸時代初期の日欧交渉史、特にポルトガル・スペインとの関係史。ヨーロッパ各地(ポルトガル・スペイン・バチカン等)やフィリピン、マカオ等の文書館に保存されている日本関係史料の発見・翻訳・紹介に取り組み、また多数の著書・論文を発表して日本における上記分野の研究の進展に貢献する一方、こうした研究成果の一般市民への啓発・普及、関係諸国との学術・文化交流にも尽力した。→ウィキ
1575年 琉球国の紋船(使僧天界寺南叔、使者金武大屋子)、鹿児島に着く。印判を持たない商船に交易を許したこと、島津使僧広済寺雪芩津興を粗略のことに島津氏に弁明。
1579年 簫崇業(正史)、謝杰(副史)来琉。簫崇業「那覇と首里の二ヶ所で、馬市(mashi)が設けられている。物を売るのはおおむね女-」。
1580年 琉球国尚真、島津義久に九州大半の帰伏を祝い隣交を求める。
1586年(天正14) 豊臣秀吉、聚楽第、方広寺大仏殿造営はじまる。
○国立博物館隣にある豊国神社は、豊臣秀吉死去の翌年の1599年、遺体が遺命により方広寺の近くの阿弥陀ヶ峰山頂に埋葬され、その麓に方広寺の鎮守社として廟所が建立されたのに始まる。後陽成天皇から正一位の神階と豊国大明神(ほうこくだいみょうじん)の神号が贈られ鎮座祭が盛大に行われた。方広寺にあった大仏は、天保年間に現在の愛知県の有志が、旧大仏を縮小した肩より上のみの木造の大仏像と仮殿を造り、寄進した。この大仏は私もよく見にいったが1973年3月28日深夜の火災によって焼失した。

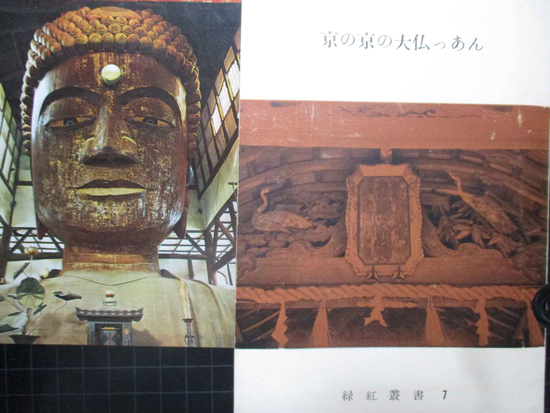
方広寺の大仏
1587年 島津義久、豊臣秀吉に降伏。
1590年 豊臣秀吉、尚寧王に書を送り、全国統一を強調。政化を異域に弘め四海を一家となす志を述べる。
1594年 尚寧王、島津義久に国家衰微のため唐入りの軍役は調達できない旨答える。
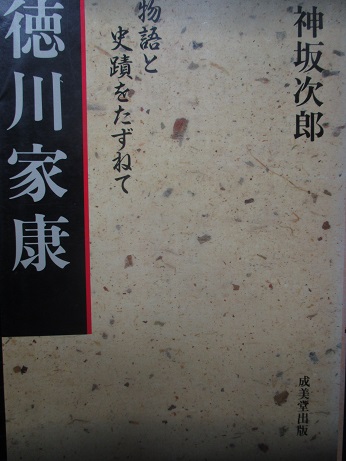
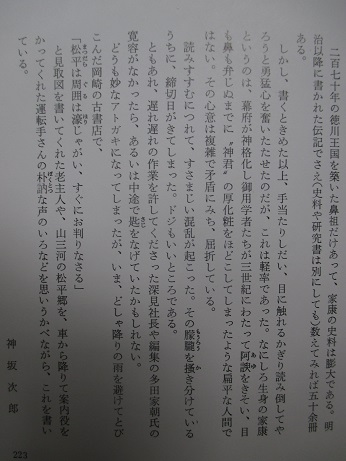
1976年2月 神坂次郎『徳川家康ー物語と史蹟をたずねて』成美堂出版
○二百七十年の徳川王国を築いた鼻祖だけあって、家康の史料は膨大である。明治以降に書かれた伝記でさえ(史料や研究書は別にしても)数えてみれば五十余冊ある。しかし、書くときめた以上、手当たりしだい、目に触れるかぎり読み倒してやろうと勇猛心を奮いたたせたのだが、これは軽率であった。なにしろ生身の家康というのは、幕府が神格化し御用学者たちが三世紀にわたって阿諛(おもねりへつらう意)をきそい、目も鼻も弁じぬまでに”神君〟の厚化粧をほどこしてしまったような扁平な人間ではない。その心意は複雑で矛盾にみち、屈折している。・・・
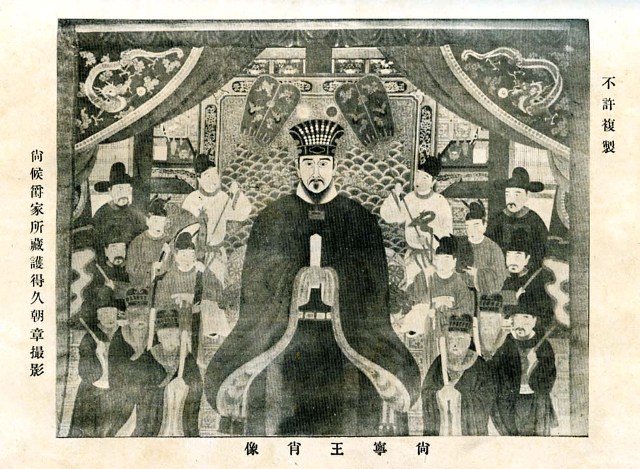
尚寧王
1602年 徳川家康、陸奥国伊達氏領に船で漂着した琉球人を島津忠恒に送還させる。
1604年 野国総官、渡唐、帰国(05年)のとき蕃薯を持ち帰る。
1605年 本多上野介正純、長崎奉行小笠原一庵に平戸漂着の琉球船の荷物没収を命ず。
1606年 山口駿河守直友、薩摩商人の渡海が琉球出兵の妨げにならないよう分別を促す。
1608年 山口駿河守直友、島津家久に、琉球出兵の準備と、再度琉球国王に家康への来聘を促す交渉を命ず。
1609年 3-4島津軍、琉球出兵で山川湊を出帆。
1609年(慶長14)4月 薩摩軍、琉球侵攻/5月 鹿児島に中山王・尚寧を連れ帰る
1610年(慶長15)8月2日 島津家久、中山王・尚寧を連れて駿府に参る/8日 島津家久、中山王・尚寧を連れて登城し徳川家康に拝謁/王弟、具志頭王子尚宏、家康に対面後に病死し興津の清見寺に葬られた。/18日 家久と中山王・尚寧に饗応で猿楽、頼宣、頼房が舞う。その間酒宴
1610年(慶長15)8月25日 島津家久、中山王・尚寧を連れて江戸に参着/28日 尚寧、登城し台徳院(秀忠)に拝謁/9月20日 島津家久、中山王・尚寧を連れて木曽路より帰国
〇大正13年12月 藤田親義『琉球と鹿児島』末吉莫夢「薩摩関係の琉球五異人ー鄭迵謝那利山/薩摩関係の異人として、私は先ず第一に鄭迵謝那親方利山を挙げる。彼は慶長役の時の三司官の一人で、琉球に於いて最も勢力を振い、遂に対薩摩外交を誤り、其身も薩摩に於いて戮された人であるが、琉球の歴史に於いては出色の人物である。」
1611年9月19日 鄭迵・謝名親方利山、斬首
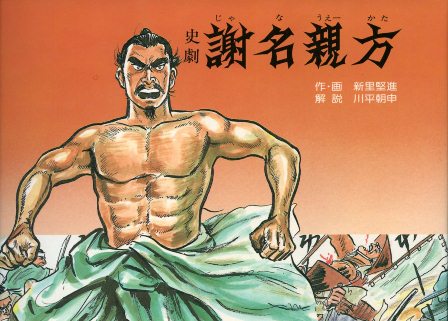
○1983年12月 新里堅進作画(川平朝申解説)『史劇 謝名親方』全教出版
謝名 利山(じゃな りざん、嘉靖28年(1549年/天文18年) - 万暦39年9月19日(1611年10月24日/慶長15年))は、琉球王国の政治家。謝名親方(ウェーカタ)の呼び方で一般に知られる。
唐名は鄭迵(ていどう)。称号は親方。鄭氏湖城家九世。久米村(現・那覇市久米)出身で久米三十六姓の末裔の一人。父・鄭禄の次男として生まれる。1565年、16歳のとき官生に選ばれて明に留学し、翌年、南京の国子監へ入学する。1572年、帰琉。その後は都通事をへて長史となり、進貢使者として数度渡唐する。1580年、総理唐栄司(久米村総役)となる。 1605年、城間親方盛久を讒言して百姓の身分に貶め、自らは三司官となった。薩摩侵略の際には三重城に陣取り那覇港の防衛を行うも尚寧王の降伏によりともに連行される。その後、薩摩藩から起請文に署名するよう求められるが、ただ一人これを拒否し処刑された。(→ウィキペディア)
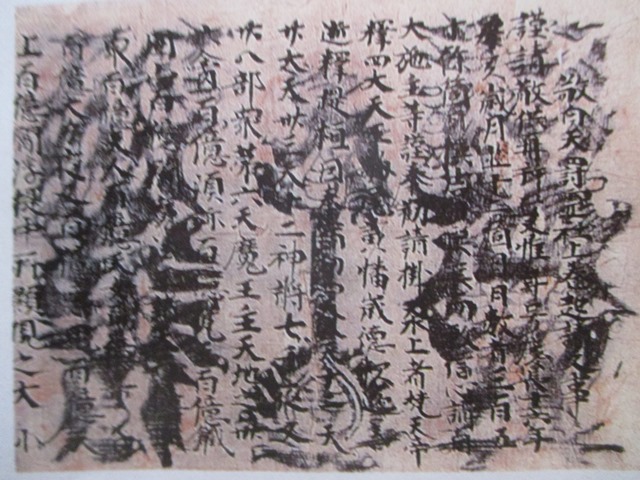
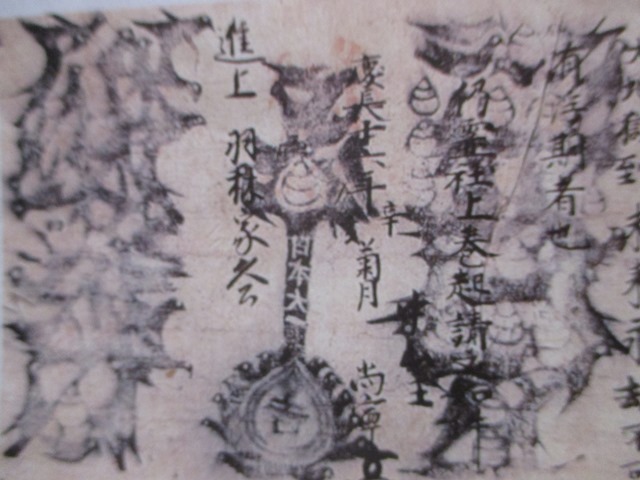
○琉球国中山王尚寧起請文(部分・島津家文書)。起請文は戦国時代、忠誠を誓うもの。豊臣秀吉の拾丸(秀頼)への忠節を尽くさせる血判誓紙も烏点の牛王(うてんのごおう)宝印があるので熊野信仰の流れのひとつであろう。
〇熊野那智大社は、那智山青岸渡寺とともに熊野信仰の中心地として栄華を極め、古来より多くの人々の信仰を集めました。今なお多くの参詣者が訪れ、熊野速玉大社・熊野本宮大社とともに熊野三山の一つ。夫須美神(ふすみのかみ)を御主神としてそれぞれに神様をお祀りしている。伊弉冉尊(いざなみのみこと)とも言われる夫須美神は、万物の生成・育成を司るとされ、農林・水産・漁業の守護神、縁結びの神様また、諸願成就の神としても崇められている。社殿は、仁徳天皇の御世(317年)に現在の位置に創建され、平重盛が造営奉行となってから装いを改め、やがて、織田信長の焼討に遭ったのを豊臣秀吉が再興した。徳川時代に入ってからは、将軍吉宗の尽力で享保の大改修が行われている。→「那智勝浦観光ガイド」参照

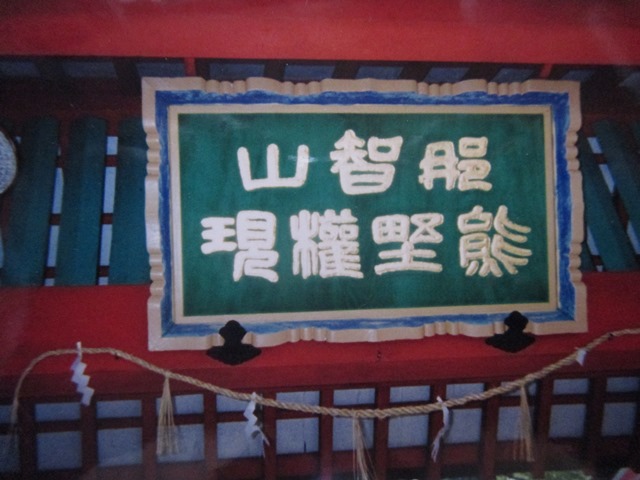


2008年10月15日~12月21日まで 大阪人権博物館で「アジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街」(10月15日~12月21日)と題し展示会があった。見に行って学芸員の仲間恵子さんから『図録』を入手した。中に上田正昭氏が「アジアのなかの大阪ー東アジアと難波津」を執筆されて、完全な「鎖国」の時代はなかった、と説く。仲間さんはアジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街と題して「近現代の大阪についても、生野区のコリアタウンや『リトル沖縄』と称される大正区を訪れることで、人と人との交流が生みだす文化に触れることができる。」と強調している。
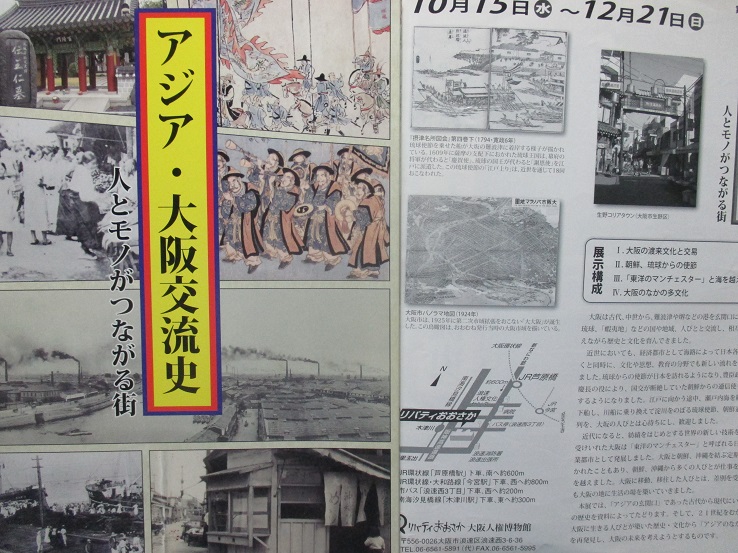
○アジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街・・・・・仲間恵子
○アジアのなかの大阪ー東アジアと難波津・・・・・・・上田正昭
1 大阪の渡来文化
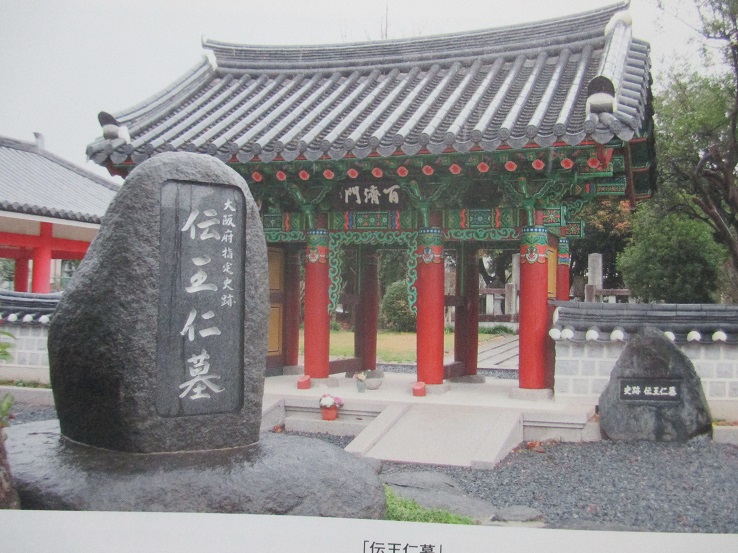
伝王仁墓 - 大阪府枚方市藤阪東町二丁目に王仁の墓が伝えられている。/王仁大明神 - 大阪府大阪市北区大淀中3丁目(旧大淀区大仁町)にある一本松稲荷大明神(八坂神社)は王仁大明神とも呼ばれ、王仁の墓と伝えられていた。また近辺に1960年代まであった旧地名「大仁(だいに)」は、王仁に由来していると伝えられている。→ウィキ
2 朝鮮、琉球からの使節
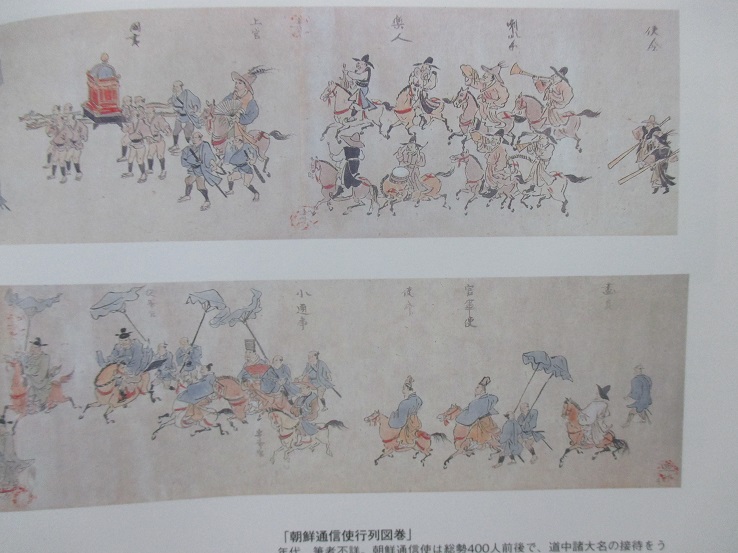
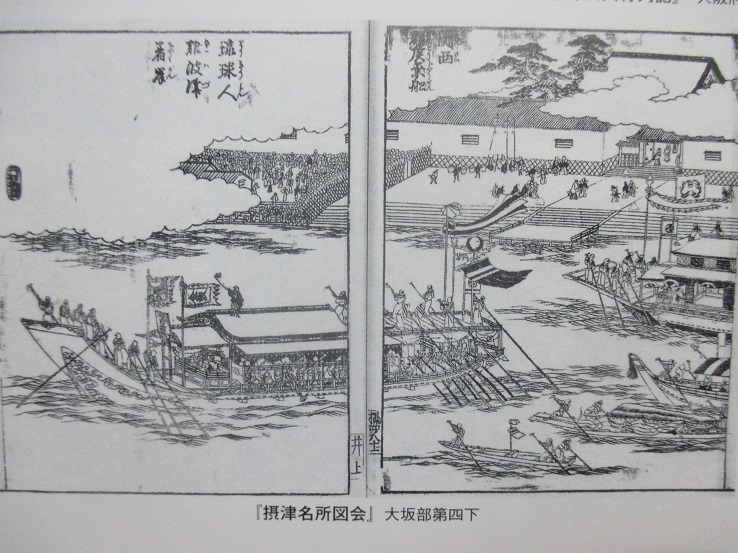
3 「東洋のマンチェスター」と海を越えた人びと
4 大阪のなかの多文化
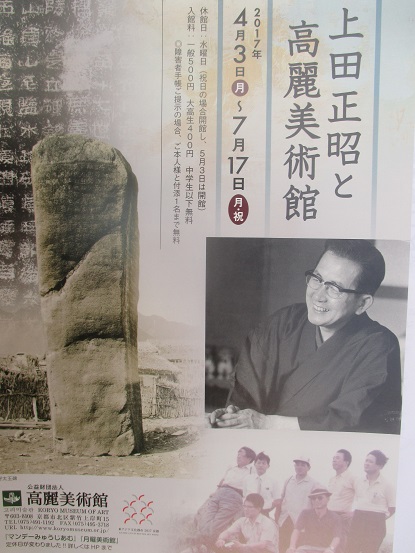
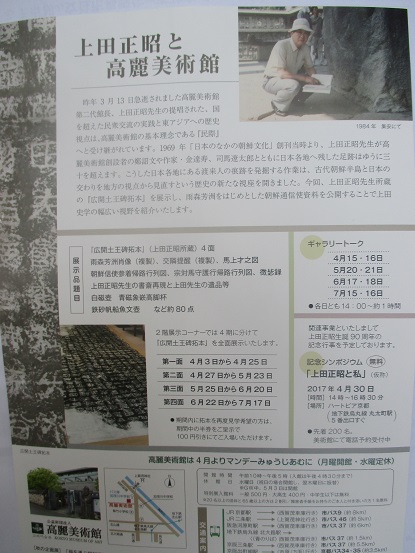
2017年4月3日~7月17日 高麗美術館「上田正昭と高麗美術館」
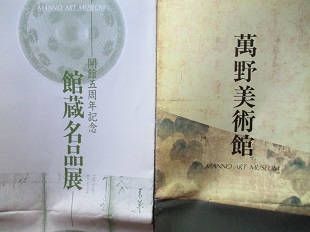
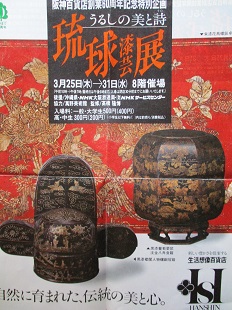


萬野美術館/『2011年度 首里城公園管理センター 萬野裕昭コレクション調査報告書』
07/28: 2001年3月 榊莫山『莫山夢幻』世界文化社
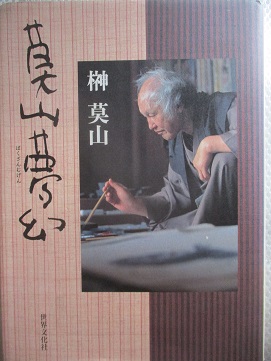
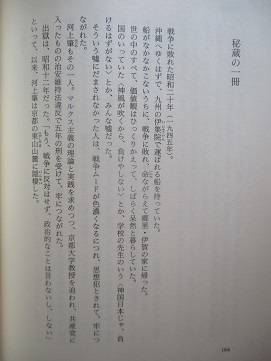
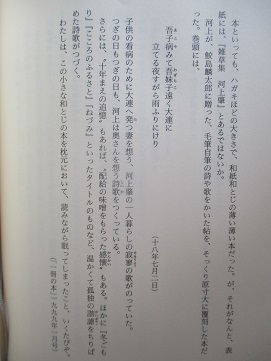
2001年3月 榊莫山『莫山夢幻』世界文化社〇秘蔵の一冊/戦争に敗れた昭和20年(1945年)。沖縄へ行くはずで、九州の伊集院で運ばれる船を待っていた。船がなかなかこないうちに、戦争に敗れ、命ながらえて郷里・伊賀の家に帰った。世の中のすべて、価値観はひっくりかえって、しばらく呆然と暮らしていた。(略)その夏、京都の友人から一冊の本がとどいた。本といっても、ハガキほどの大きさで、和紙和とじの薄い本だった。が、それがなんと、表紙には、『雑草集 河上肇』とあるではないか。/〇芭蕉に想う、芭蕉わーるど、芭蕉の句碑
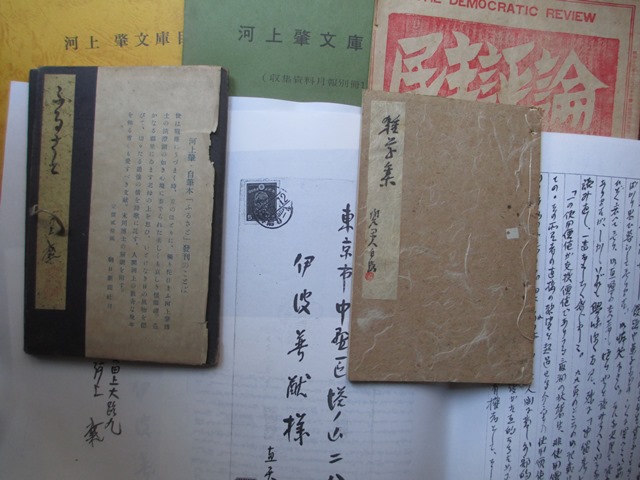
河上肇・資料ー右に1946年6月 河上肇『詩集・雑草集』大雅堂
河上肇ー経済学者・社会思想家。山口県生。東大卒。ヨーロッパに留学中法学博士号を受け、帰国後京大教授となる。またマルクス主義の研究と紹介に努め、青年層に多大の影響を及ぼした。のち大山郁夫らと実践運動に入り新労農党を結成したが、理論的誤りを認め大山らと別れた。獄中生活の後、自叙伝等の執筆に専念した。昭和21年(1946)歿、68才。
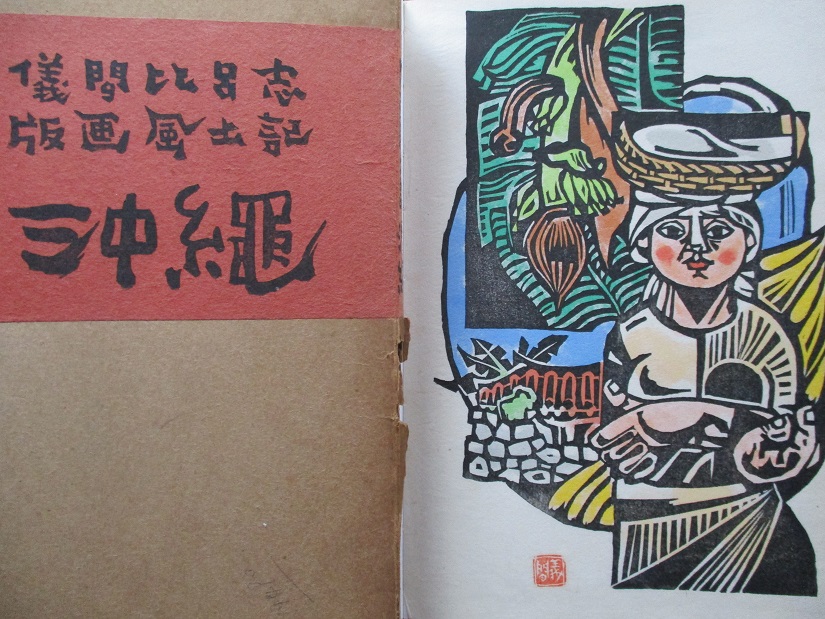
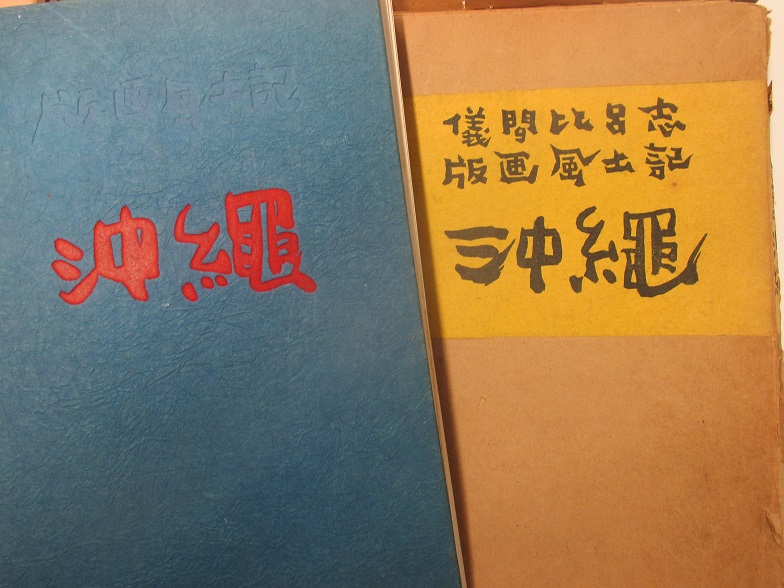
1966年1月 儀間比呂志『版画風土記 沖縄』題字/榊莫山 編集/高橋亨
05/27: 1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」
1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」
○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。
その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)
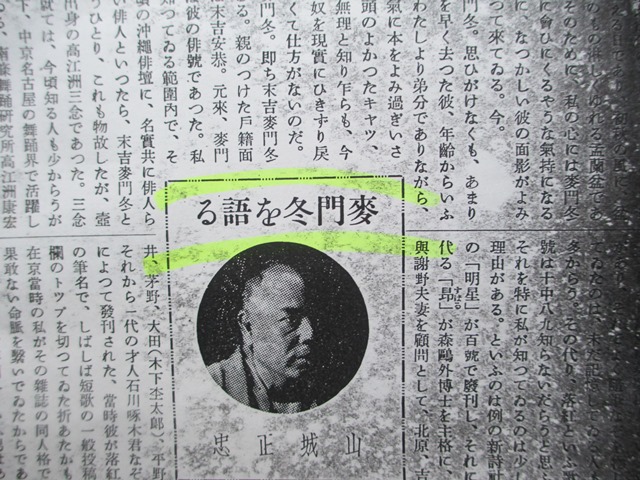
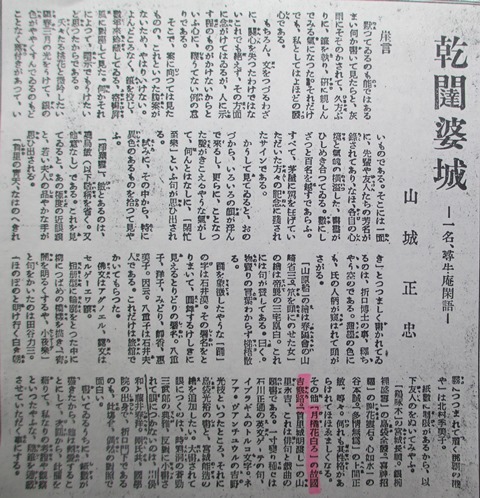
山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。
①灰雨ー國吉眞哲
夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。
「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。
②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア
③山崎省三 やまざき-しょうぞう
1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。
明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク
④石井漠いしいばく
[生]1886.12.25. 秋田,下岩川
[没]1962.1.7. 東京
舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク
⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長
短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。
書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。
1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。
文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。
同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。
以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)



写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝
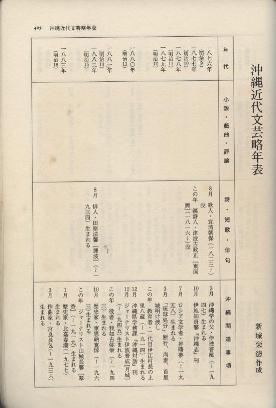
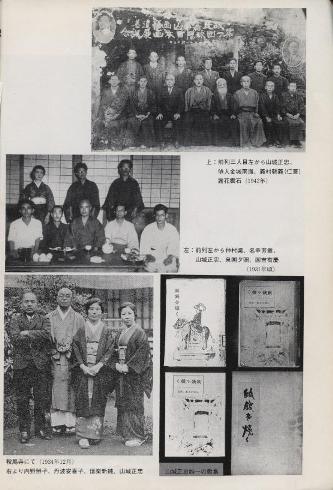
1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」
1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。
2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。
本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。
○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。
その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)
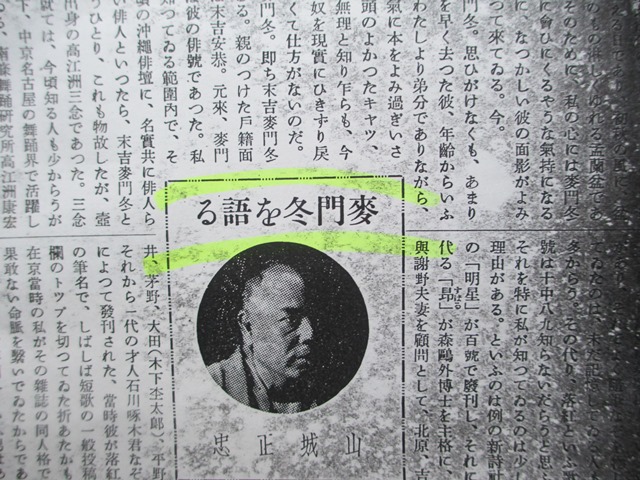
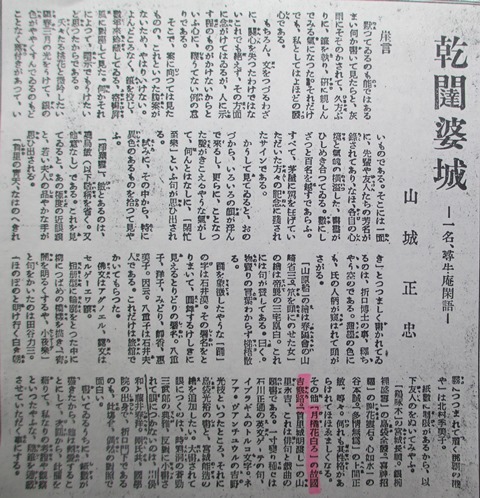
山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。
①灰雨ー國吉眞哲
夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。
「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。
②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア
③山崎省三 やまざき-しょうぞう
1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。
明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク
④石井漠いしいばく
[生]1886.12.25. 秋田,下岩川
[没]1962.1.7. 東京
舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク
⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長
短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。
書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。
1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」
○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。
文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。
同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。
以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)



写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝
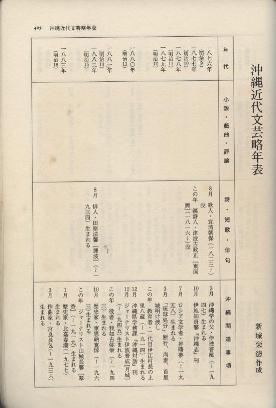
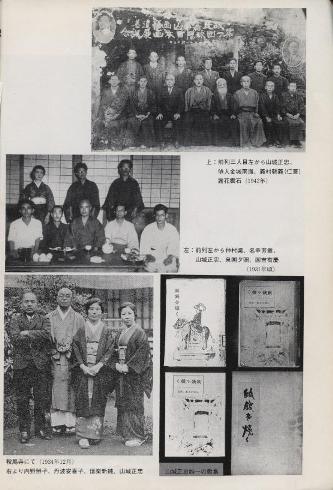
1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」
1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。
2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。
本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。
07/28: 愛知/麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安治
「江戸上り」研究家・佐渡山安治


後左ー佐渡山安治氏
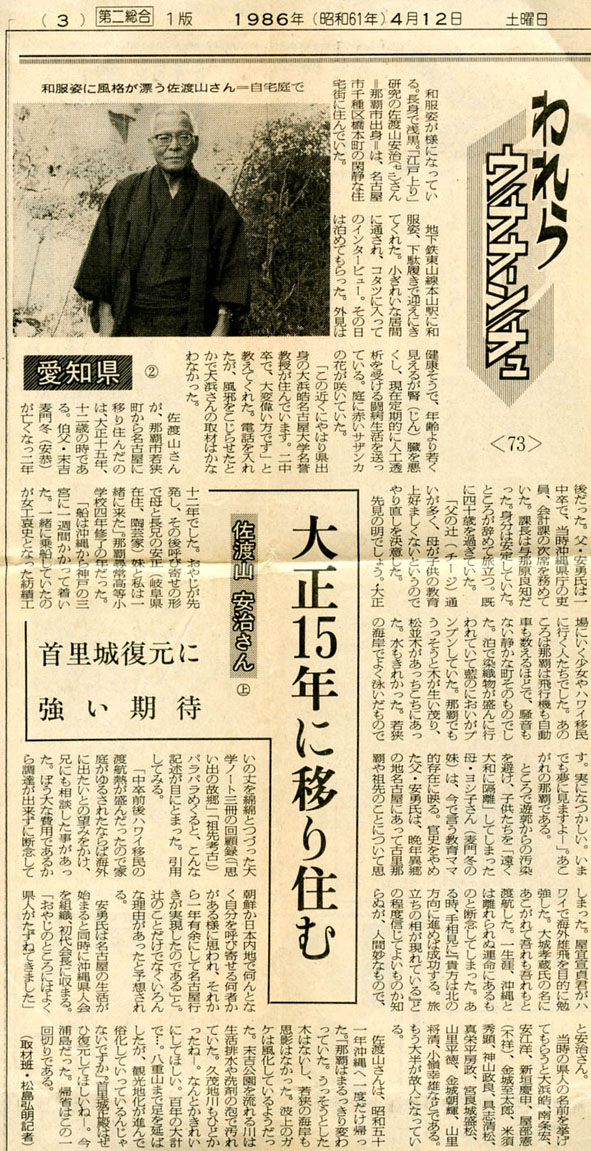
麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安治著作目録(抄)
1935年 『紫煙』 佐渡山安治「俳諧からみた煙草」
1942年『日本及日本人』3月号 佐渡山生「楓橋夜泊の詩」/『日本及日本人』8月号 莫生「アルコールの原料」「鼓山の禅師」/『日本及日本人』9月号 莫生「生味噌の效」
1943年『日本及日本人』5月号 莫生「琉球馬」
1974年 5月ー『琉球の文化』第5号「辻の話(佐渡山安勇遺稿)」
1975年3月16日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー琉球の棋客」/7月13日ー『沖縄タイムス』「墨俣宿の灯籠」
1976年3月13日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー琉球塚」/7月2日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー程順則の片りん」/7月20日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー唐海賊情報」
1977年/3月15日ー『沖縄タイムス』「『富士山の漢詩』について」/ 6月ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー行路難」/8月18日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー雅懐」/12月ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー伊波普猷の憤慨」
1978年1月10日ー『沖縄タイムス』「ブサーばなし」/ 5月25日ー『沖縄タイムス』「『江戸上り』の吟行と萍水奇賞」
1979年5月17日ー『沖縄タイムス』「風禍」
1980年 8月ー『沖縄アルマナック』「江戸上り賛歌」
1982年11月22日ー『沖縄タイムス』「鞆の浦哀歌ー琉球司楽向生碑を訪ねて」/11月27日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー花売りの縁作者考」
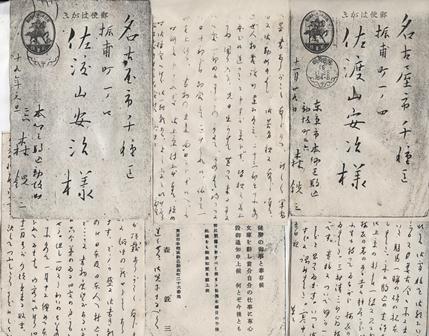
森銑三①→佐渡山安治宛葉書
①森 銑三モリ センゾウ-大正・昭和期の書誌学者,随筆家
生年明治28(1895)年9月11日 没年昭和60(1985)年3月7日
出生地愛知県碧海郡刈谷町(現・刈谷市)
学歴〔年〕文部省図書館講習所〔大正15年〕卒
主な受賞名〔年〕読売文学賞(第23回・研究翻訳部門)〔昭和46年〕「森銑三著作集」
経歴郷里の刈谷図書館開館に伴い寄贈された国学者・村上忠順の蔵書整理・目録編纂に従事。東京大道社、代用教員、市立名古屋図書館などを経て、東京帝大史料編纂所勤務。この間、三古会、伝記学会などを創立。昭和14年尾張徳川家・蓬左文庫主任。近世の埋もれた人物の発掘、研究に力を注ぎ、在野の歴史家として「平賀源内」「渡辺崋山」「池大雅」ら多くの人物研究、伝記を手がけたが、戦災により一切の研究資料を焼失し人物研究を断念。23年古典籍商である弘文荘に入社。傍ら、25〜40年早稲田大学講師として書誌学を講じたが、その間“西鶴の浮世草子は「好色一代男」だけで他は西鶴自身の著作ではない”と論じて学界に波紋をまき起こした。主著に「近世文芸史研究」「おらんだ正月」「井原西鶴」「明治東京逸聞史」などがあり、「森銑三著作集」(全12巻・別巻1 中央公論社)、「森銑三著作集続編」(全16巻・別巻1)がある。→コトバンク


後左ー佐渡山安治氏
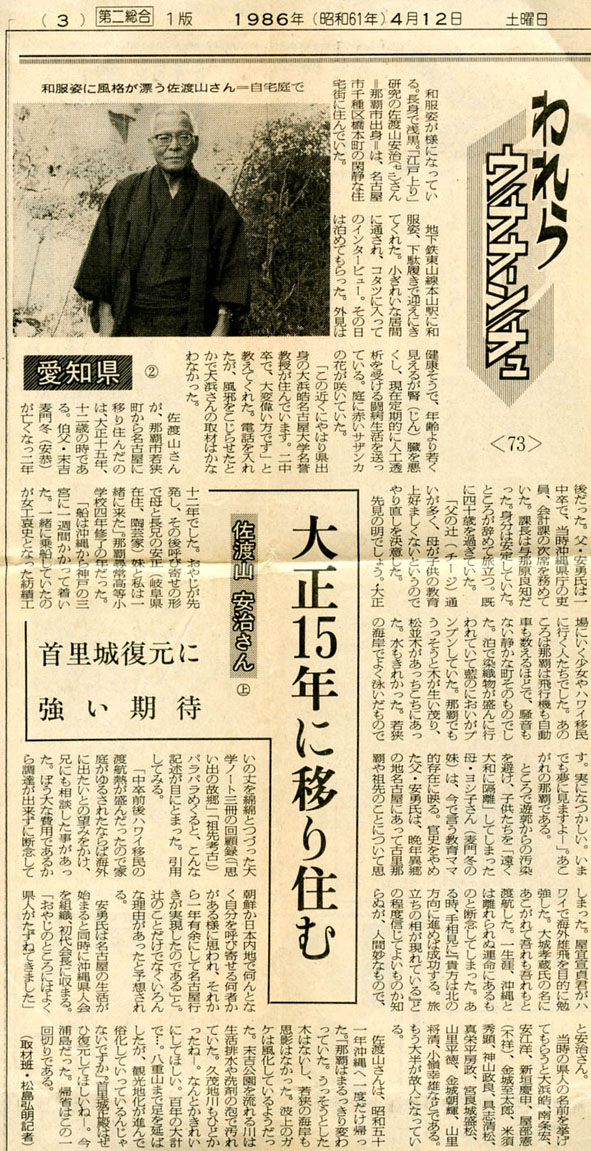
麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安治著作目録(抄)
1935年 『紫煙』 佐渡山安治「俳諧からみた煙草」
1942年『日本及日本人』3月号 佐渡山生「楓橋夜泊の詩」/『日本及日本人』8月号 莫生「アルコールの原料」「鼓山の禅師」/『日本及日本人』9月号 莫生「生味噌の效」
1943年『日本及日本人』5月号 莫生「琉球馬」
1974年 5月ー『琉球の文化』第5号「辻の話(佐渡山安勇遺稿)」
1975年3月16日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー琉球の棋客」/7月13日ー『沖縄タイムス』「墨俣宿の灯籠」
1976年3月13日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー琉球塚」/7月2日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー程順則の片りん」/7月20日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー唐海賊情報」
1977年/3月15日ー『沖縄タイムス』「『富士山の漢詩』について」/ 6月ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー行路難」/8月18日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー雅懐」/12月ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー伊波普猷の憤慨」
1978年1月10日ー『沖縄タイムス』「ブサーばなし」/ 5月25日ー『沖縄タイムス』「『江戸上り』の吟行と萍水奇賞」
1979年5月17日ー『沖縄タイムス』「風禍」
1980年 8月ー『沖縄アルマナック』「江戸上り賛歌」
1982年11月22日ー『沖縄タイムス』「鞆の浦哀歌ー琉球司楽向生碑を訪ねて」/11月27日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー花売りの縁作者考」
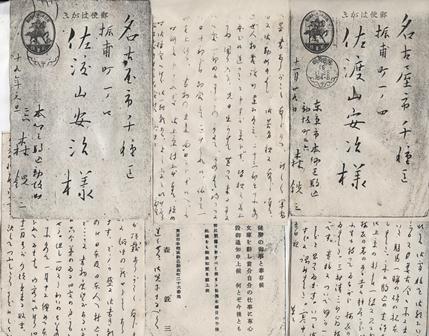
森銑三①→佐渡山安治宛葉書
①森 銑三モリ センゾウ-大正・昭和期の書誌学者,随筆家
生年明治28(1895)年9月11日 没年昭和60(1985)年3月7日
出生地愛知県碧海郡刈谷町(現・刈谷市)
学歴〔年〕文部省図書館講習所〔大正15年〕卒
主な受賞名〔年〕読売文学賞(第23回・研究翻訳部門)〔昭和46年〕「森銑三著作集」
経歴郷里の刈谷図書館開館に伴い寄贈された国学者・村上忠順の蔵書整理・目録編纂に従事。東京大道社、代用教員、市立名古屋図書館などを経て、東京帝大史料編纂所勤務。この間、三古会、伝記学会などを創立。昭和14年尾張徳川家・蓬左文庫主任。近世の埋もれた人物の発掘、研究に力を注ぎ、在野の歴史家として「平賀源内」「渡辺崋山」「池大雅」ら多くの人物研究、伝記を手がけたが、戦災により一切の研究資料を焼失し人物研究を断念。23年古典籍商である弘文荘に入社。傍ら、25〜40年早稲田大学講師として書誌学を講じたが、その間“西鶴の浮世草子は「好色一代男」だけで他は西鶴自身の著作ではない”と論じて学界に波紋をまき起こした。主著に「近世文芸史研究」「おらんだ正月」「井原西鶴」「明治東京逸聞史」などがあり、「森銑三著作集」(全12巻・別巻1 中央公論社)、「森銑三著作集続編」(全16巻・別巻1)がある。→コトバンク

左から東風平汀鳥、麦門冬、國吉朝秀、末吉安慶、名護朝扶、不詳
清盛ー入道は襟かき合しかき合しなるやうにせよと清盛腹で云ひ
正行ー正行は其の時遺言思い出し怨敵の使者に正行禮を述べ
師直(四条畷)ー師直はたった一ど声名乗あげ
舜天王ー尊敦も外へ出づれば琉球語
道鏡ー三度まで目まぜをしたが感通寺○
道鏡どうきょう[生]? [没]宝亀3(772).下野
奈良時代末期の法相宗の僧。義淵の弟子。その本貫は河内国志紀郡弓削 (ゆげ) 。そのためか弓削道鏡と呼ばれる。初め葛木山で修業,のち東大寺に入り,天平宝字5 (761) 年保良宮 (ほらのみや) で孝謙上皇の病気を癒やして以来信任され,少僧都となり,同8年恵美押勝 (藤原仲麻呂 ) 失脚後は仏教政治をしき,翌年太政大臣禅師,天平神護2 (766) 年法王となった。 →コトバンク
養老ー孝行な子が酔ざめの水を汲み一杯は息子も呑んで顔赤め
大公望ー文王が来るとあはてて釣る真似し
竹林七賢ー七賢のどの先生と薮医が来
白楽天ー門前の婆も到頭うるさがり
伯夷叔斉ー周の天下采邑の民二人ありしばらくと伯夷叔斉右左り冥途へば譲り合はぬで伴に行き
○伯夷・叔斉はくい・しゅくせいBo Yi Shu Qi
中国,殷周交代期 (前 1100頃) に現れた賢人の兄弟。孤竹国 (河北省?) の公子。父が弟の叔斉を世継ぎにしたが,叔斉は兄の伯夷に譲ろうとし,ついに2人とも位を捨て去った。彼らは周の文王を慕って,その地に行ったところ,武王の伐殷の役にあい,これを不仁な行いとして武王に諫言した。 →コトバンク
浦島ー浦島は尻まくりしてヒヨイと乗り
李太白ー出来が悪い詩白ふでふと詠じ
○李白りはくLi Bo
[生]長安1(701) [没]宝応1(762).当塗
中国,盛唐の詩人。字,太白。号,青蓮居士。若い頃は任侠を好み,四川を振出しに,江南,山東,山西を遊歴。 42歳のとき長安に出て賀知章らに推挙されて翰林供奉 (ぐぶ) となったが,高力士に憎まれてまもなく追われ,また放浪生活に入り,その間,杜甫とともに旅をしたこともある。 →コトバンク
頼朝ー頼朝は生まれながらに大頭
俊寛ー泣きやん 俊寛砂に文字を書き
熊谷ー熊谷は涙片手に首抱へ
羽衣ー天人のモデル口では話されず
謙信ー謙信のピカピカやんで夕立し
信玄ー信玄は膏薬張って出陣し
牛若ー牛若は母の乳房に歯形入れ
寒山拾得ー拾得が掃けば寒山尻を据え
竹取の翁ー胞桶に翁は火吹竹を入れ人形が這入って居ると初手思ひ
桃太郎ー黍団子鬼も一つと頂戴し犬猿雉の人員検査三ですみ土産物配られるやうなものもなし<
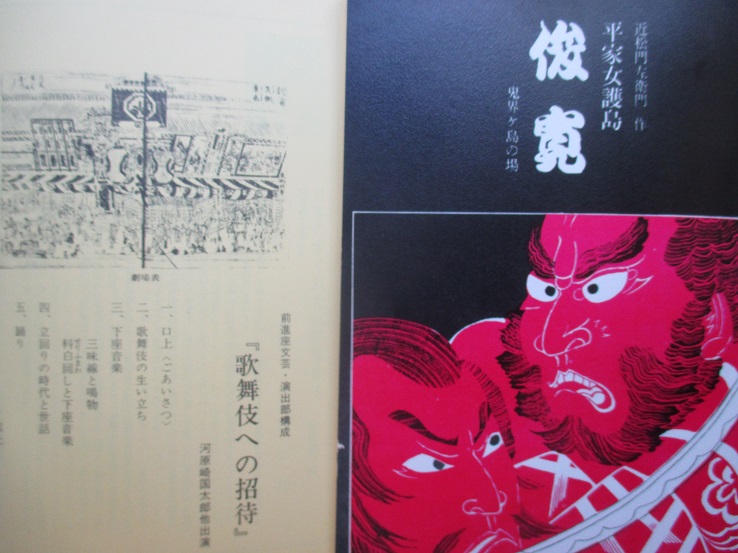
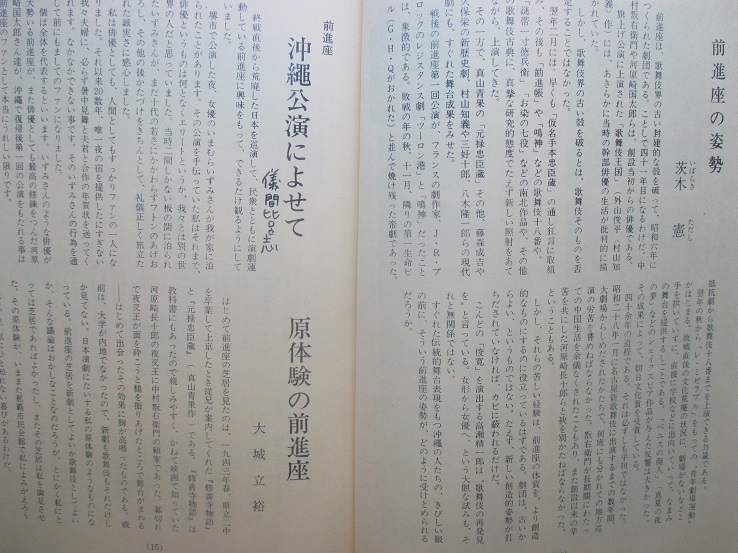
1972年10月 那覇市主催「前進座/平家女護島・俊寛」

僧俊寛の墓;平家転覆の陰謀が暴露し、喜界島に流罪された俊寛僧都は、赦免されることなく、この地に滅びました。坊主前(ボウズンメイ)と呼ぶこの地に墓があり、島の人々や観光客の供える花や線香は絶えません。→喜界町
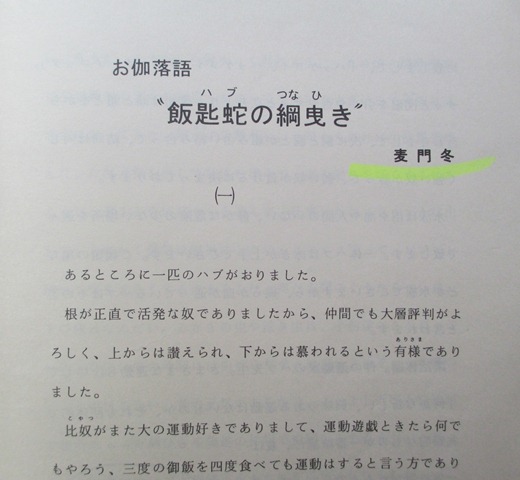
1977年9月 吉田朝啓『ハブと人間』麦門冬「飯匙蛇の綱曳き」琉球新報社
2014年4月29日『琉球新報』の論壇に吉田朝啓氏が「都道府県立・沖縄市町村経営『海の家』ー健康リゾート観光推進」を投稿しておられる。末尾に「カジノや基地関連収入よりもはるかに健全で、自然保護と公衆衛生の理念にもかなう健康リゾート観光を進めてほしいと考える。軍事基地撤去を訴えるだけでは、日本国民は動かせない」と、尤もな正論である。沖縄の革新も反戦平和を唱えるだけでは半グレ国民には通用しない、と考えるべきだ。また沖縄の地元紙も日頃のヤマトでも発言しても通用する文化論を少なくし、こう云う建設的な沖縄ならでの提案を論壇で済まさず特集を組むべきだ。
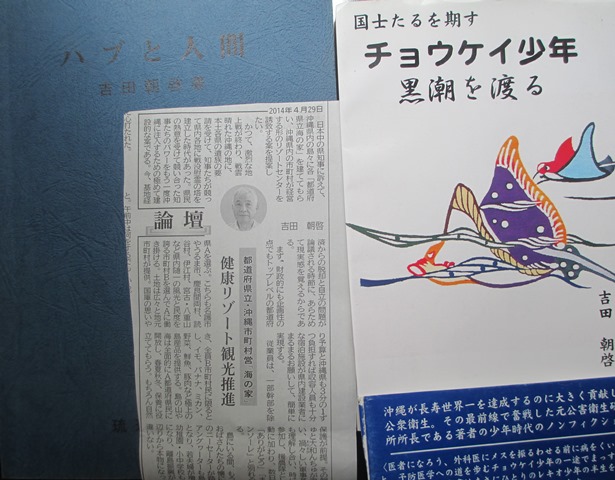
2014年5月4日『沖縄タイムス』吉田朝啓「論壇ー健康長寿センター構想ー沖縄の貴重な経験 観光活用」
2014年12月20日『琉球新報』吉田朝啓「論壇ーたばこ病の弊害ー国・県は強力な禁煙対策を」
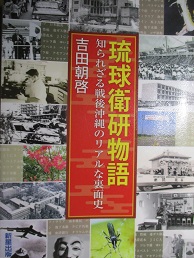
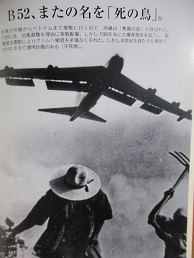
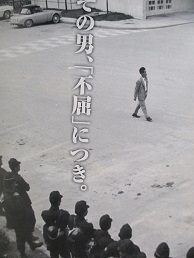
2018年1月 吉田朝啓『琉球衛研物語ー知られざる戦後沖縄のリアルな裏面史』新星出版
「未来の医師は薬を用いないで、人体の骨格構造・栄養・そして病気の原因と予防に注意を払うようになるだろう。」エジソン
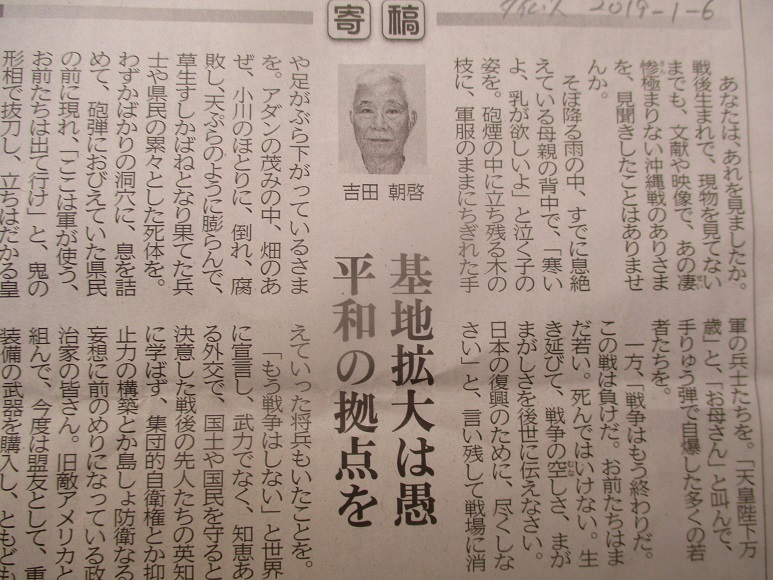
2019年1月6日『沖縄タイムス』吉田朝啓「寄稿ー基地拡大は愚 平和の拠点を」
『沖縄タイムス』2016年10月7日[大弦小弦]上京時、こんなに沖縄料理店があるのかと…
上京時、こんなに沖縄料理店があるのかと驚く人も多いだろう。銀座にもあちこちにあり、周辺都市でももれなく見つけられる。沖縄人気の象徴だろう
▼その料理店に県産の酒や野菜、鮮魚を卸している香那ホールセールの宇根良樹さん(40)と会った際に話題になった。もっと沖縄食材を広げる方策はないかと
▼宇根さんは「沖縄のメーカーは過去に成功体験があるので、営業が受け身になっていないか」と懸念を漏らした。人気に乗って商品はそこそこ売れてきた。でも、移り変わるニーズを把握しているか、東京の舌が欲するものとの乖離(かいり)はないか。要は、現場にもっと足を運んで情報収集してもいいとの提案である
▼ビジネスであれ、スポーツ、芸術の世界であれ、ちやほやされるまま努力を怠ると、いつの間にか消えてしまう。沖縄の作り手に限らず、こちらの沖縄料理店にも、宇根さんの提案は当てはまる
▼創意工夫があり、予約が取れない店もあれば、料理と値段を見て「ちょっとねー」とグチが出そうな店も案外ある。あとは市場が淘汰(とうた)する…、いやいや沖縄のイメージさえも損ないかねないから、座視できないであろう
▼沖縄の生産者が料理店に、新たな食材やメニューを提案しながら、販路を広げる手もある。まずは実情把握に、東京との往来を増やしてはいかがだろう。(宮城栄作)
『琉球新報』2016年10月7日<金口木舌>おにぎり捨てますか
おにぎり1~2個を1年間毎日捨て続けてください。こう言われたら、何をばかなと拒むだろう。しかし残念ながら、計算上は全国民がそれを実行しているのが今の日本だ
▼食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」の国内量は年間約500万~800万トン(2010年農水省統計)。1人当たりに換算すると、おにぎり1~2個に相当する。世界の食料援助量の年間約400万トンを軽く上回る
▼家庭での賞味期限切れや食べ残し、店頭での売れ残りなどによって、食べ物をごみに変えてしまっている。昨年の農水省調査では、宴会で14%、結婚披露宴で12%の食べ残しがあった
▼宴会の食品ロスを減らそうと、長野県松本市は11年から「30・10(さんまる・いちまる)運動」を始めた。宴会開始後30分間と終了前10分間は席に着き、料理を味わおうという呼び掛けだ。食品廃棄が半減した店もあり、効果は上々だ
▼「30・10運動」は全国に広がり今や約20自治体が取り組んでいる。“もったいない”の意識は日本にとどまらない。フランスでは今年2月に大型スーパーの食品廃棄を禁じる法律が成立した
▼国連によると、世界で飢餓に苦しむのは9人に1人。一方で先進国は飽食をむさぼる。食品ロスの半分は家庭から出たものだ。買い過ぎや冷蔵庫の詰め込みなど日常を見直すだけで、地球市民として小さな務めを果たせる。
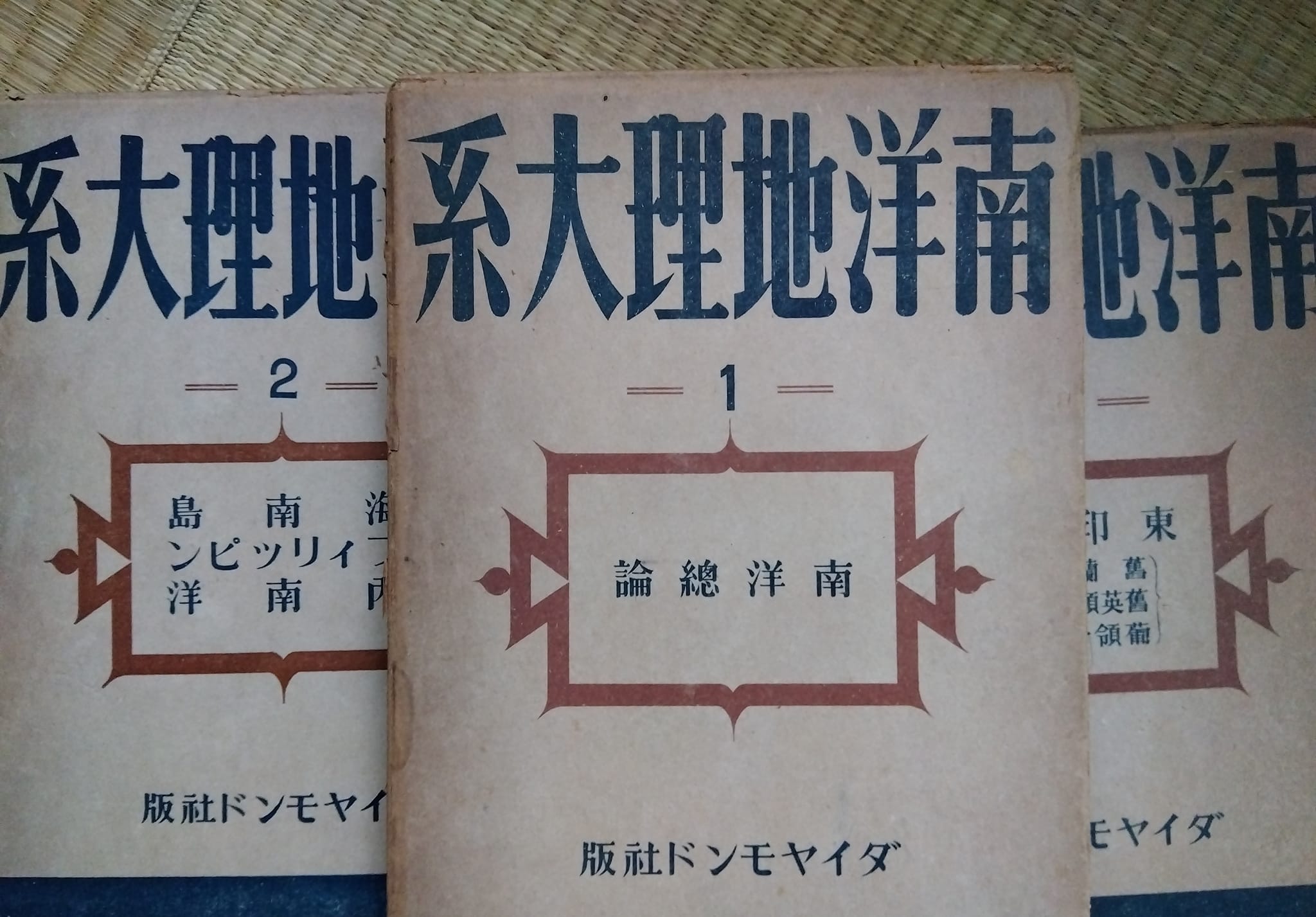
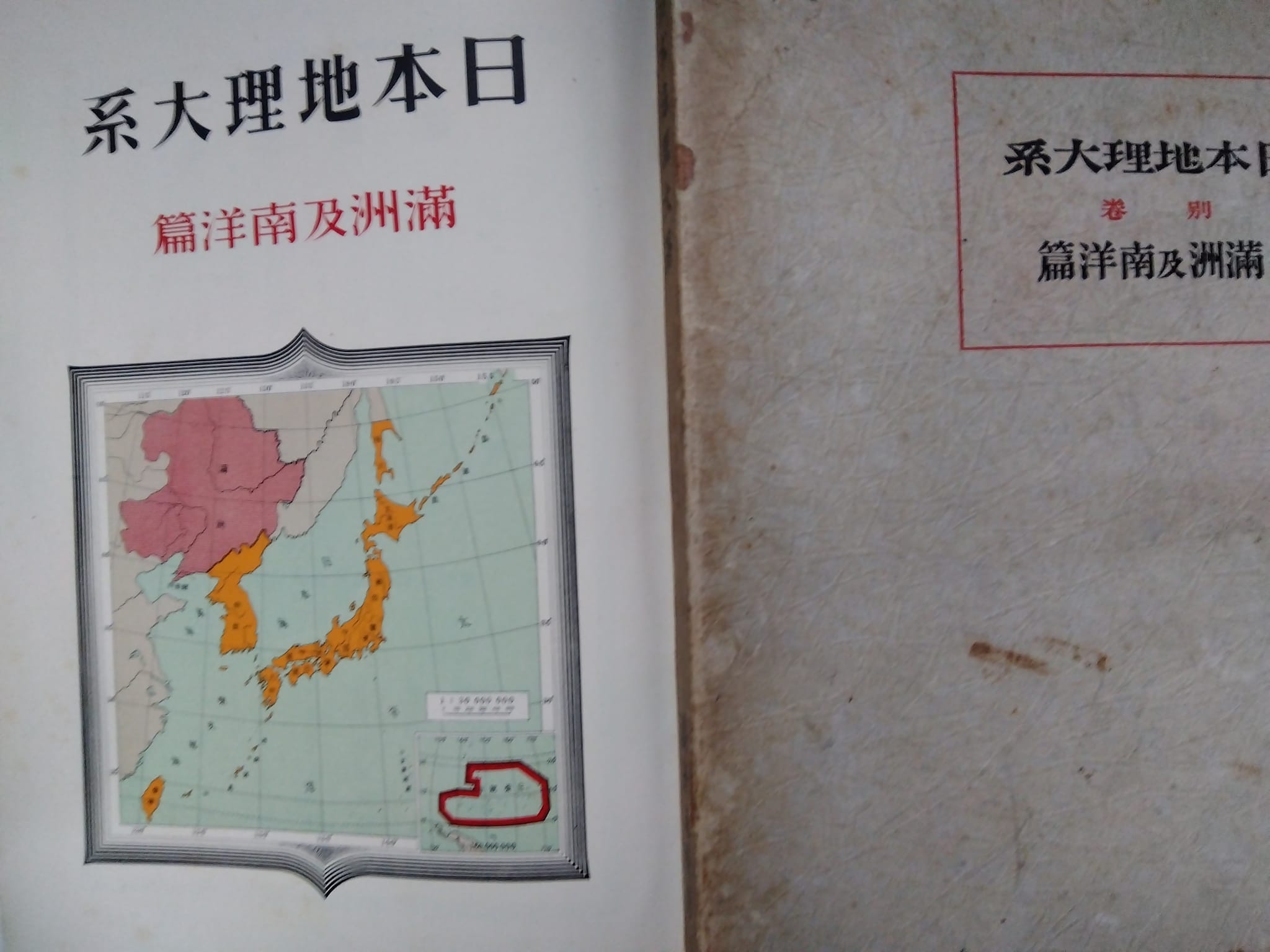
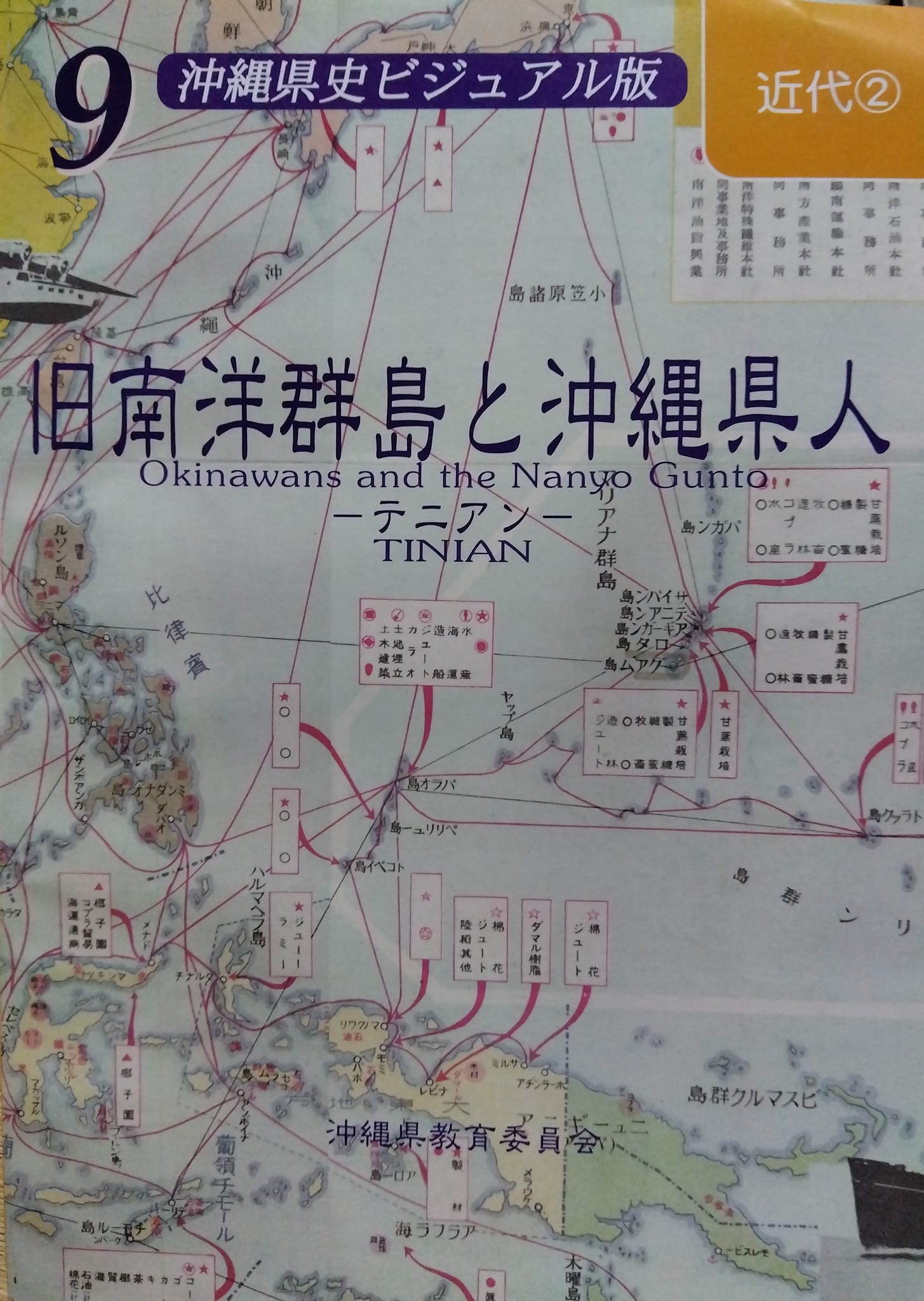
南洋群島○昭和5年12月 『日本地理大系別巻 満州及南洋篇』改造社○昭和17年5月 『南洋地理大系』ダイヤモンド社○2002年 『旧南洋群島と沖縄県人』沖縄県教育委員会
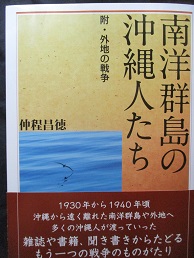
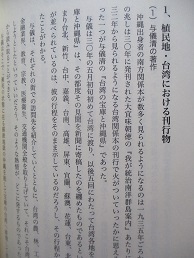

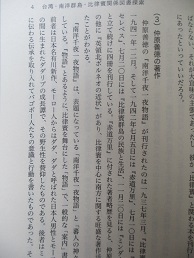
2020年6月 仲程昌徳『南洋群島の沖縄人たち 附・外地の戦争』ボーダーインク
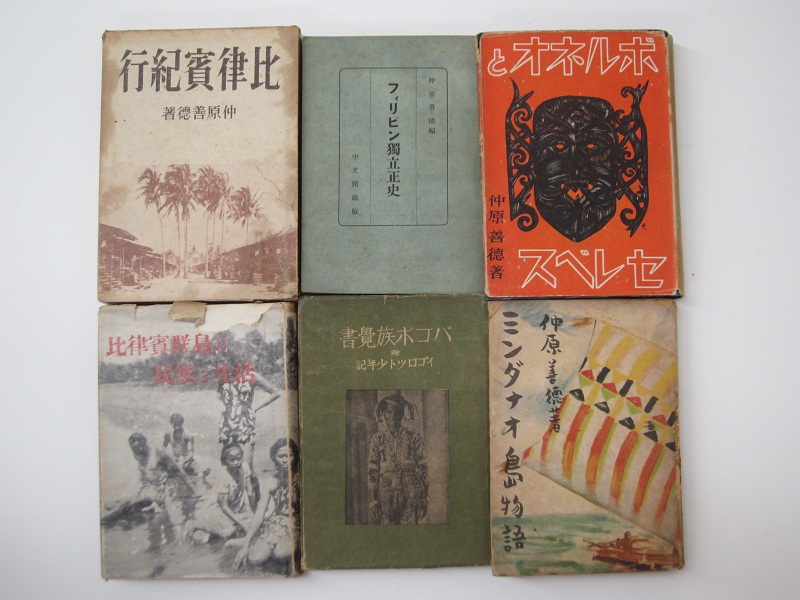
仲原善徳の本
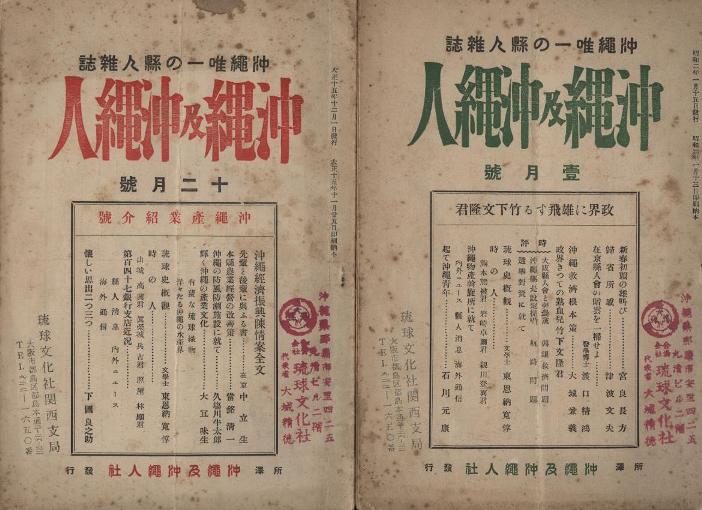
1926年5月ー大宜味朝徳『沖縄及沖縄人』<沖縄救済問題号>創刊号□埼玉公論社・埼玉県所沢町
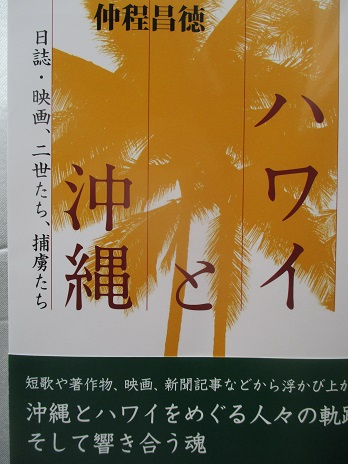
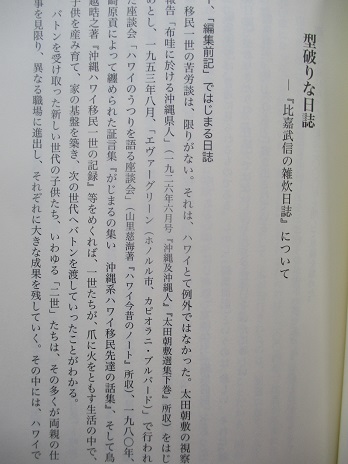
2019年5月 仲程昌徳『ハワイと沖縄 日誌、映画、二世たち、捕虜たち』ボーダーインク
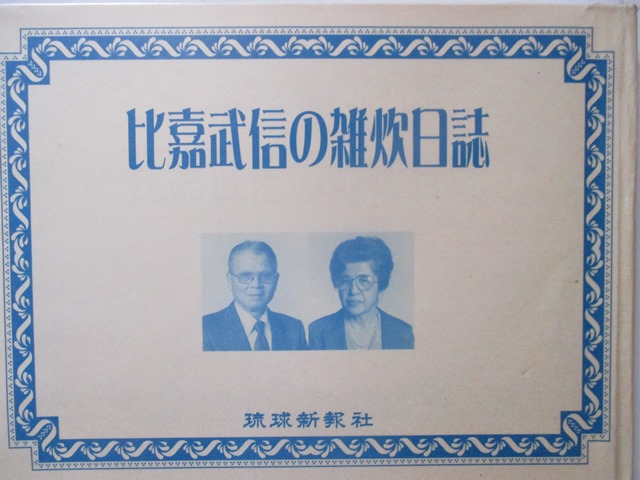
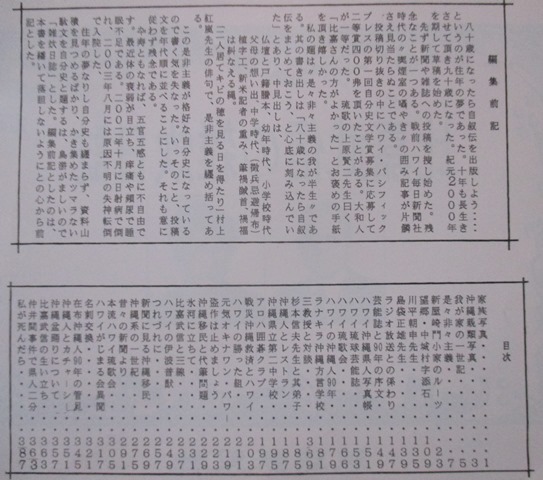
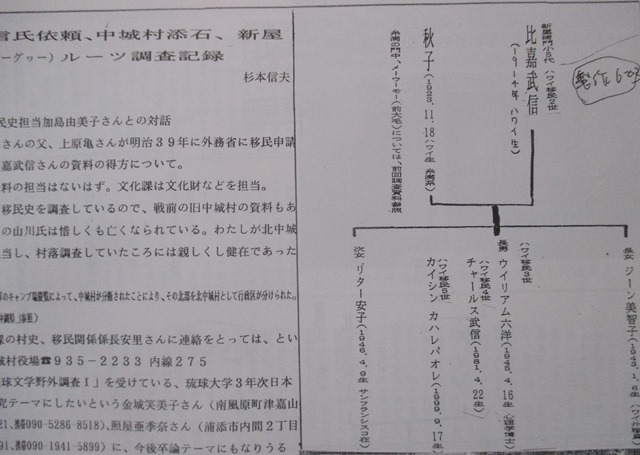

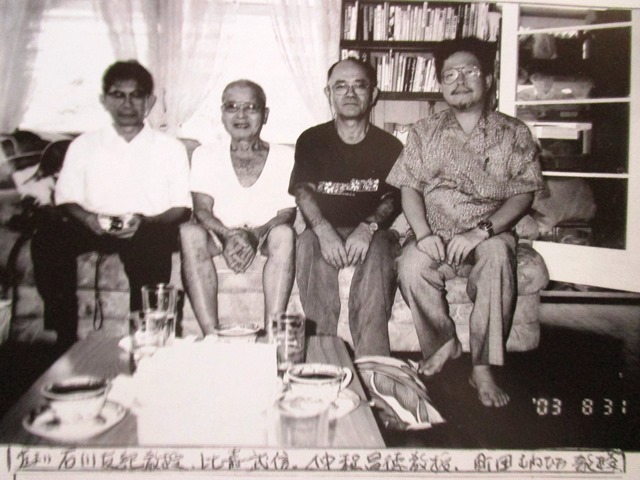
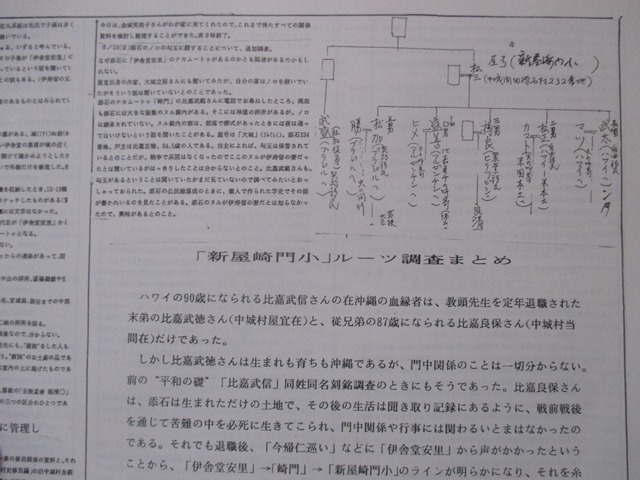
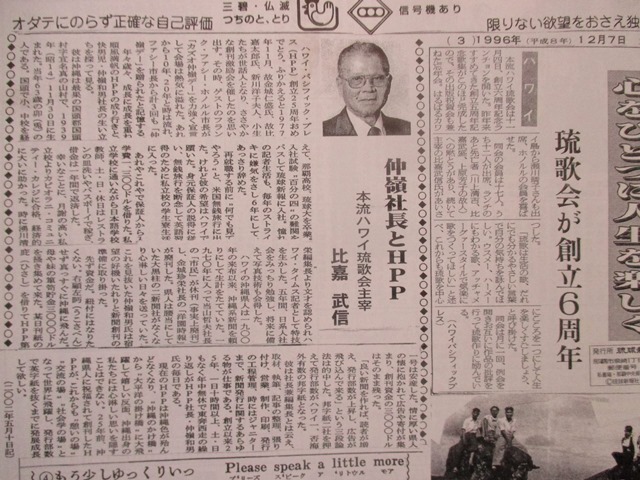
2004年4月 比嘉武信『比嘉武信の雑炊日誌』琉球新報社
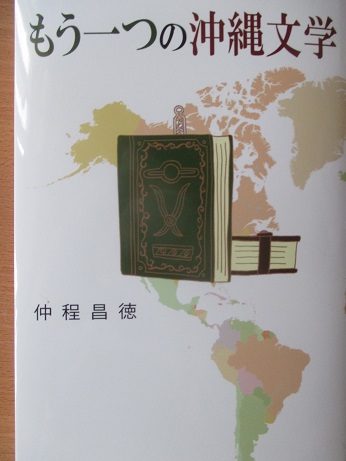
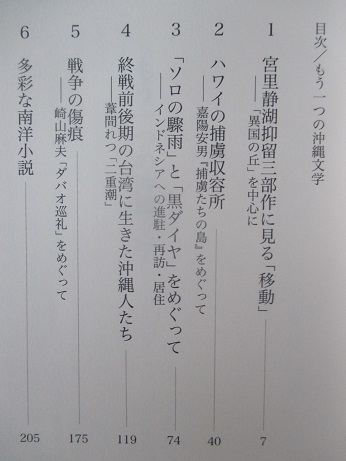
2017年4月 仲程昌徳『もう一つの沖縄文学』ボーダーインク
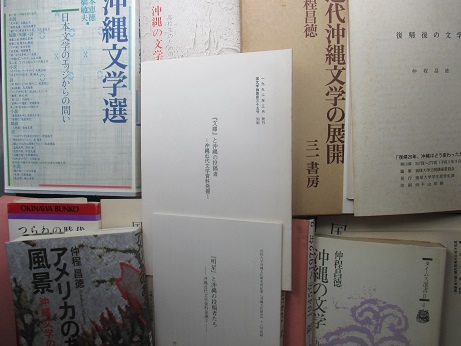
仲程昌徳の本
03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館




1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」
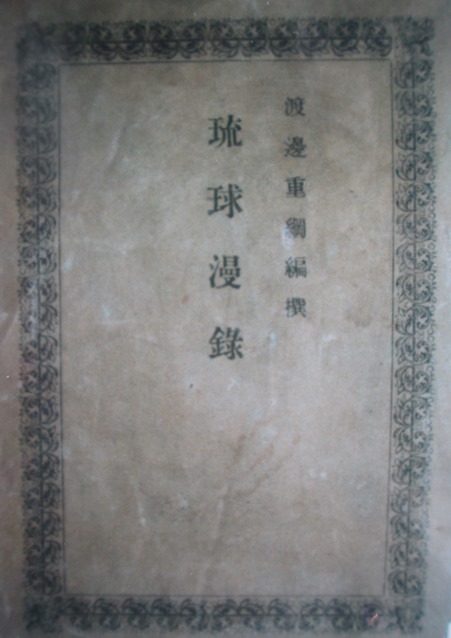

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治
うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。
討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。
1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

兼城昌興


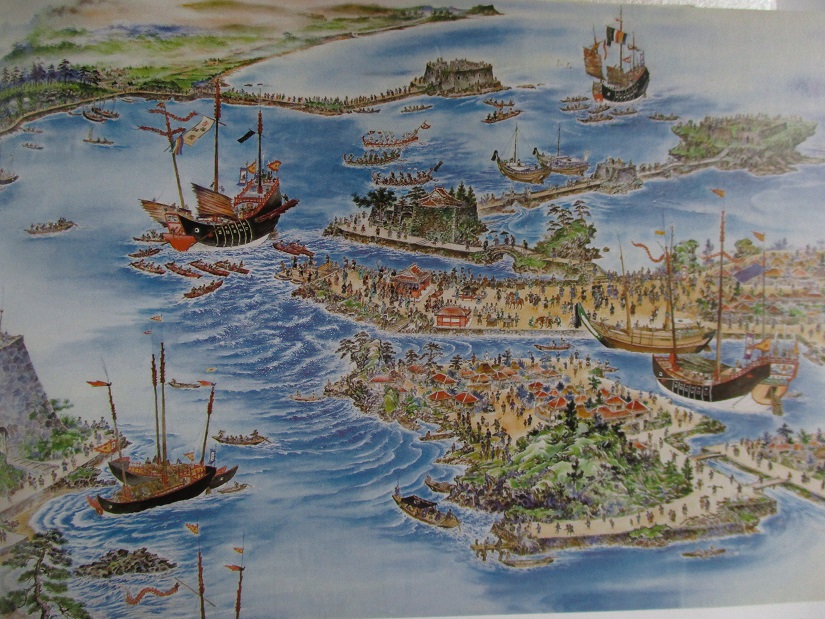
金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」
06/14: 麦門冬/1912年 『沖縄毎日新聞』
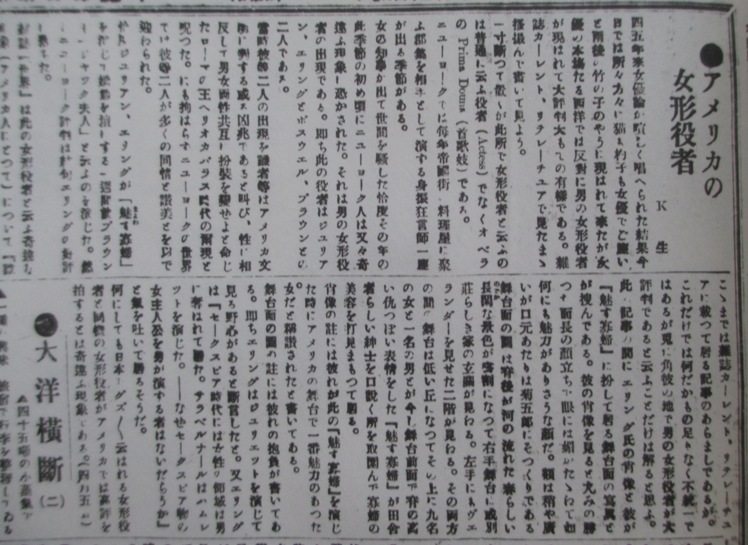
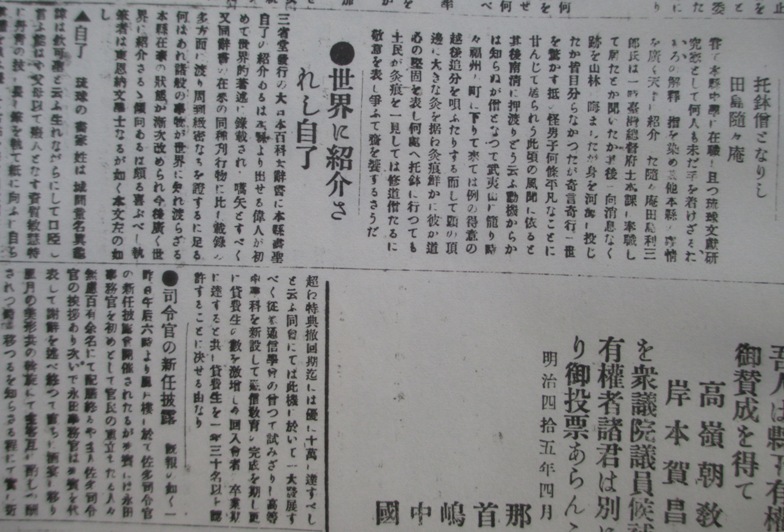
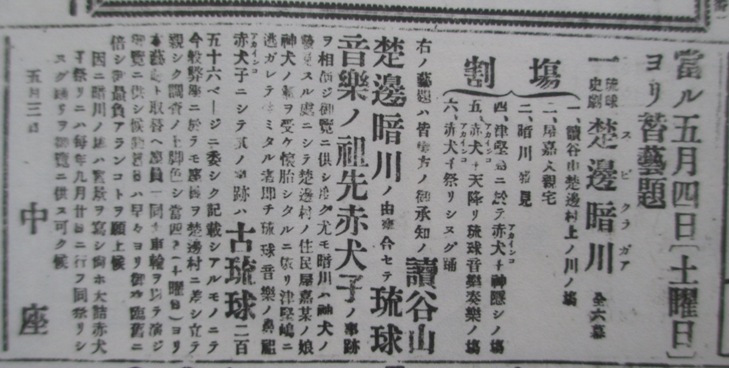
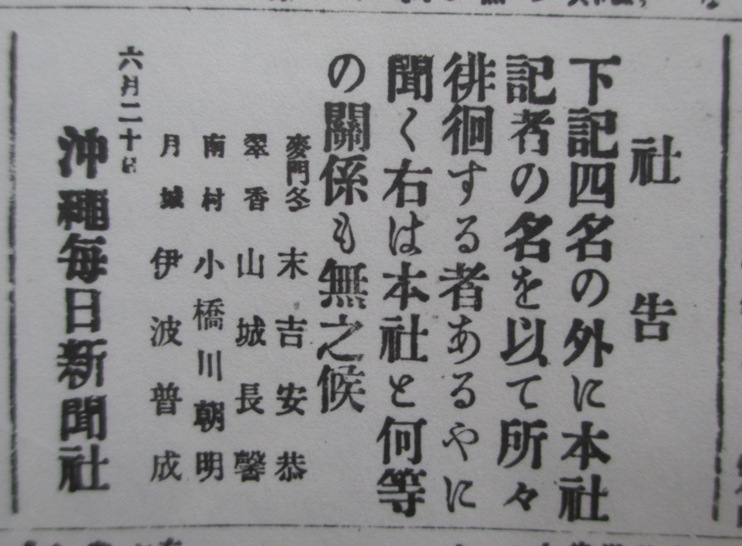
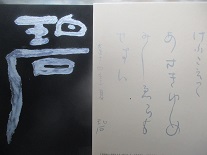
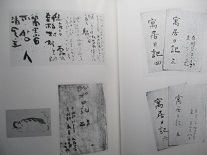
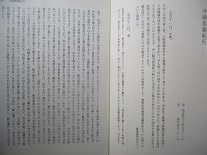
2007年1月 『河東碧梧桐全集』第12巻「沖縄那覇紀行」 文藝書房
〇1910年5月18日に伊波普猷と会話した河東碧梧桐は「沖縄那覇紀行」で伊波の話を紹介している。□5月18日。半晴。臺灣、朝鮮には目下土着人を如何に馴致すべきかの重大な問題が何人の頭をも重圧しつつある。琉球のように多年親日の歴史ある土地に、さような社会問題があろうとは夢想だもせぬところであった。が、人種上に生ずる一種の敵愾心、表面に現れた痕跡は絶無であるにしても、心の奥底に拭うべからざるある印象の存することは争われぬ。伊波文学士ー沖縄人ーの観察はあるいは一方面であるかも知れぬが、這般の消息について多少聞くべきものがある。曰く琉球が親日に勤めたことは、すでに数百年前のことで、時の為政者は大抵そのために種々の施設をしておる。なかんずく向象賢などは時の名宰相であったのであるが、その親日に尽くしたことも一通りではなかった。下って宜湾朝保の如き、八田知紀の門下生となって三十一文字の道にも心を寄せたという位である。が、琉球人の方を主として見ると、島津氏の臨監は、これを支那の恩恵に比すると余り苛酷であった。支那は琉球から租税を徴したことがない。進貢船を派しても、必ずそれ以上の物と交易して呉れる。のみならず、能く諸生の教導をして、留学生なども懇篤な待遇をした。沖縄人が親日の束縛を受けながらも、暗に支那に欸を通じて、衷心その恩を忘れざるものはこれがためである。殊に廃藩置県の際における内地人の処置は、沖縄人の心あるものをして、新たなる敵愾心を起さしめた。蓋し土着の沖縄人を軽蔑することその極に達したからである。
爾来その敵愾心は学問の上に進展して、沖縄人と雖も習字次第内地と拮抗するに足ることを証拠立てた。今日如何に焦燥れても如何に運動しても一種の不文律は沖縄人に政治上及び実業上の権力は与えられぬ。已むなくさる制裁のない学問に向かって力を伸ばす外はないのである。この気風は殊に今日の青年間に隠約の勢力となっておる。今日小中学または師範学校などの教師ー内地人ーは内地で時代後れになった人が多い。新進気鋭の秀才が、かかる南洋の一孤島に来ぬのは自然の数であるけれども、現在の権力掌握者はまた余りに時勢に取り残され方が甚だしい。そこになると、青年の方が遥かに時代の推移を知っておる。如何に圧制的に新刊の書を読むなと禁じても、生徒は暗に、どういうことが書いてあるかも知らずに、と冷笑しておる始末である。殊に我々は沖縄人だという自覚の上に、このまま単に内地人の模倣に終わるべきであろうかという疑問がある。つまらぬ事のようであるけれども、島津氏に対する祖先伝来の一種の嫌悪心も手伝ふて来る。さらばというてもとより沖縄県庁に対して謀反を計るなどという馬鹿なこともないが、それらの暗々裡の不平は、いつか妙な方向に走らせて、青年に社会主義の書物や、露西亜小説の悲痛な物やなど読むものが多くなった。もしこの気風が段々助長して行けば、あるいは人種上の恐るべき争いとならぬとも限らぬ。要するにこの十年前までは単に旧物破壊、日本模倣の単純な社会であったのが、今日は沖縄人としての自覚が芽を萌して、旧物保存、模倣敗斥の端を啓いたのである。
1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」
1910年6月 『ホトトギス』岡本月村「琉球スケッチ」
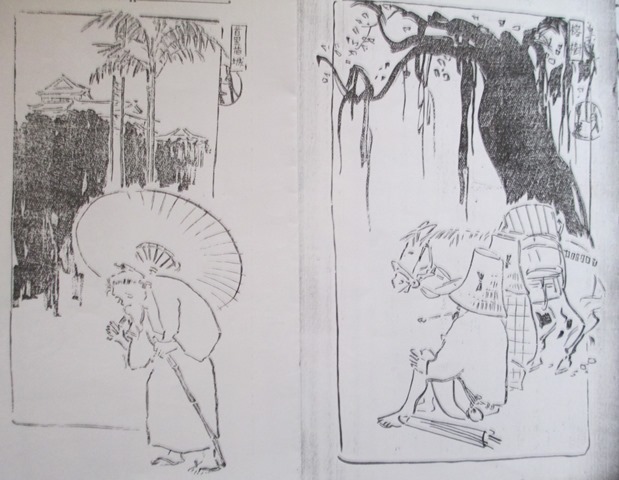

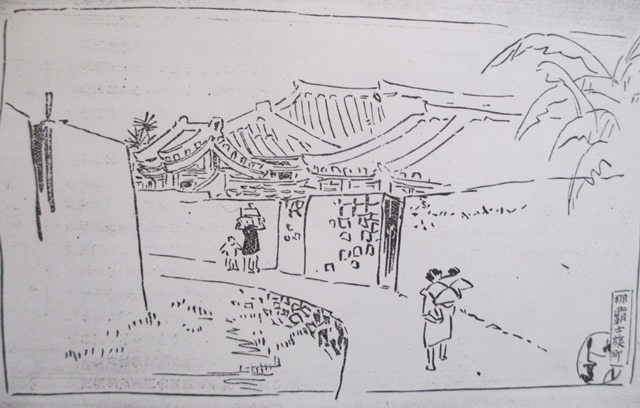
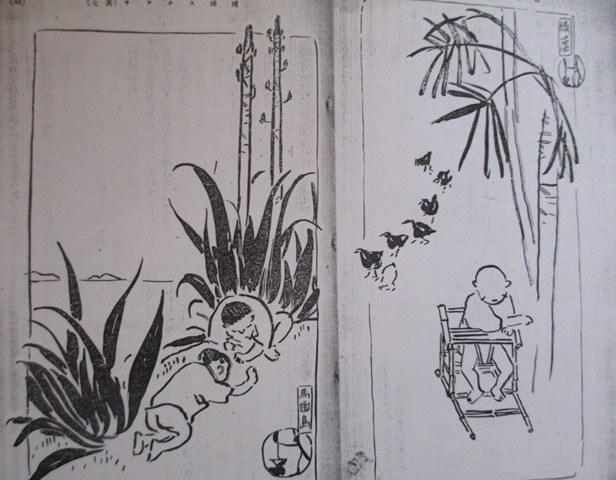
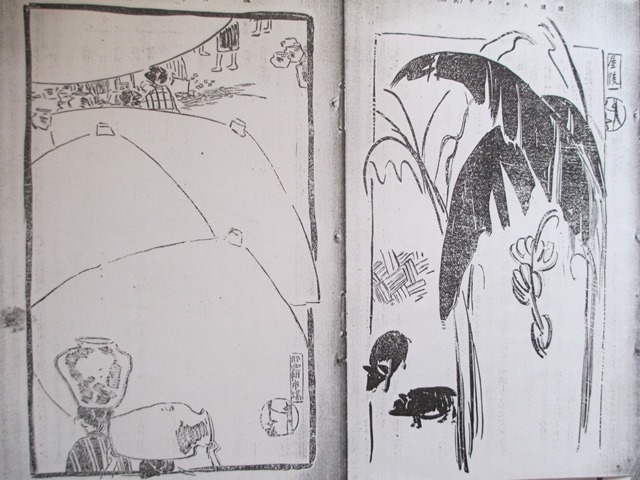
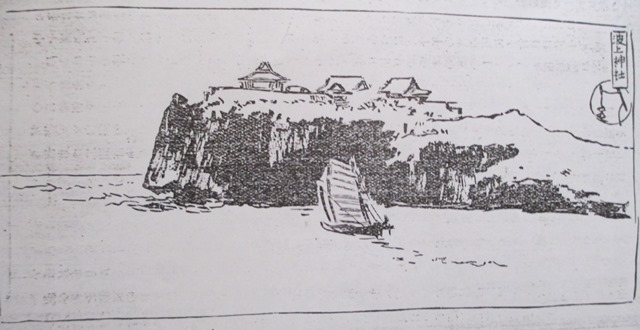
□岡本月村(1876年9月10日~1912年11月11日)
上道郡西大寺(現、岡山市)の人。名は詮。幼くして画技を好み、13歳で徳島県の天蓋芝堂、次いで京都の今尾景年に、また洋画を浅井忠に学んだ。神戸新聞、大阪朝日新聞に俳味ある漫画を載せて異彩を放つ。旅行を好み俳句にも長ず。
麦門冬と河東碧梧桐
1984年12月発行の『琉文手帖』「文人・末吉麦門冬」で1921年以降の『ホトトギス』の俳句も末吉作として収録した。これは別人で熊本の土生麦門冬の作品であるという。土生麦門冬には『麦門冬句集』(1940年9月)があった。1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖したとき、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。
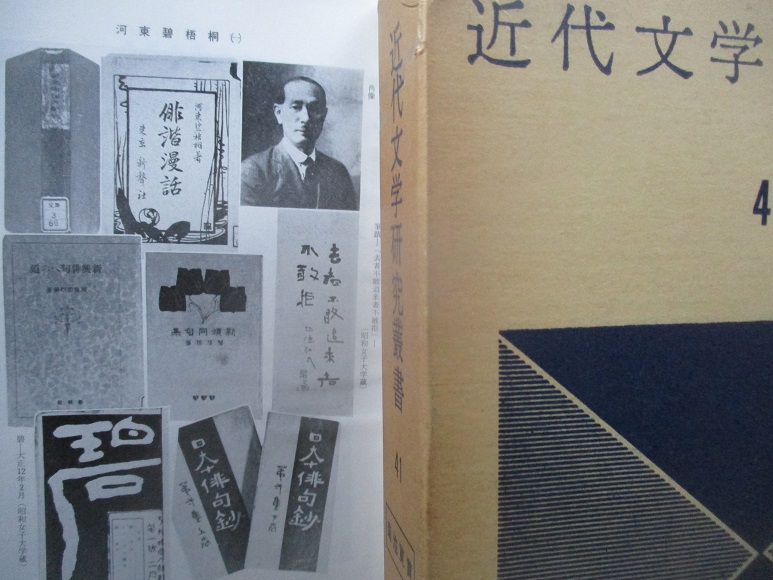
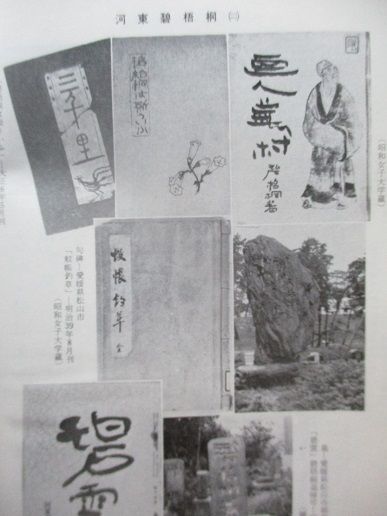
1975年5月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学叢書』41巻「河東碧梧桐」 昭和女子大学近代文化研究所
河東碧梧桐 かわひがし-へきごとう
1873-1937 明治-昭和時代前期の俳人。
明治6年2月26日生まれ。高浜虚子とともに正岡子規にまなび,新聞「日本」の俳句欄の選者をひきつぐ。のち新傾向俳句運動をおこし,中塚一碧楼(いっぺきろう)らと「海紅」を創刊,季題と定型にとらわれない自由律俳句にすすむ。大正12年「碧(へき)」,14年「三昧(さんまい)」を創刊。昭和12年2月1日死去。65歳。愛媛県出身。本名は秉五郎(へいごろう)。作品に「碧梧桐句集」,紀行文に「三千里」など。(コトバンク)
04/12: 麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安正
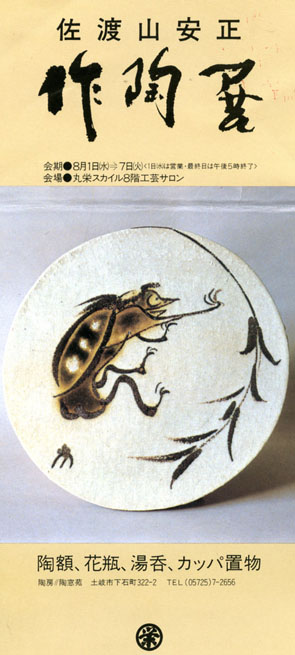
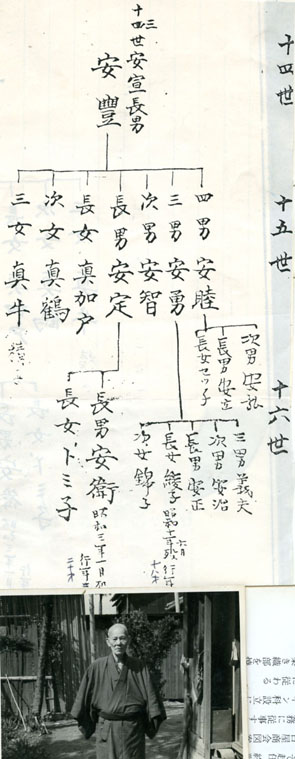
写真右・佐渡山安勇

写真・佐渡山安正
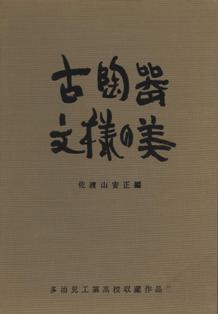
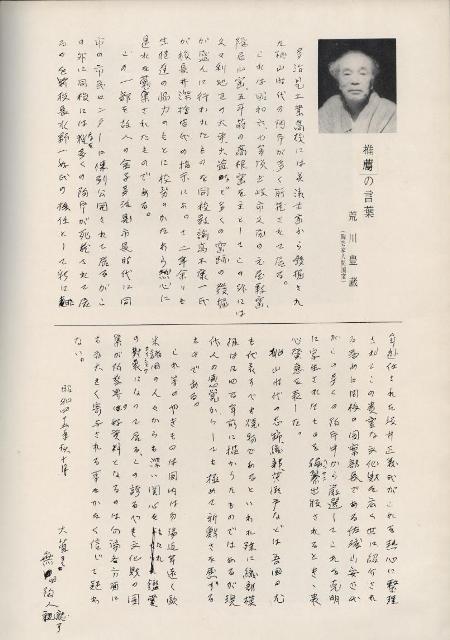
1970年12月ー佐渡山安正『古陶器文様の美』東文堂
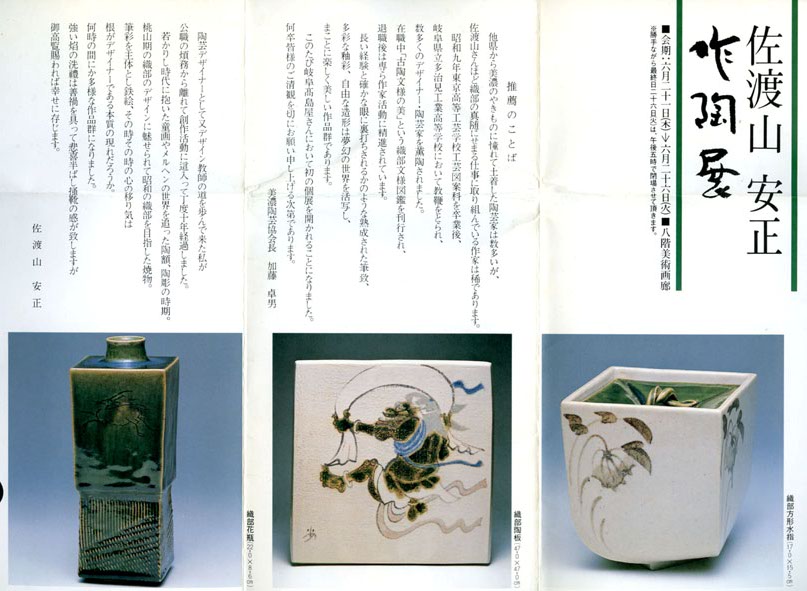
○今日、岐阜県土岐市下石というところに行ってきました。
愛知の沖縄調査の仕事です。で、ついでに、この町を流れる川に架かる橋のたもとに据えられているシーサーを見てきました。しっかり橋と町を守っているようですね。これは、琉球王国時代の絵師佐渡山安健を先祖に持つ、故佐渡山安正の作品です。
町を守りながら、遠く故郷を望んでいるように見えました。写真ではわかりづらいですが、町を囲む山々の紅葉も見頃で、その紅葉をバックに、シーサーもとても見栄えがしました。→2007年12月01日「干瀬のまれびとの座ーまれびとの見る沖縄を語る」
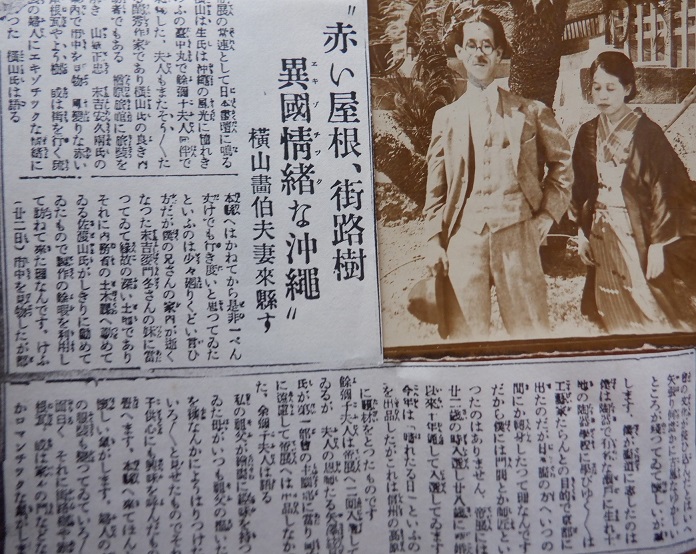
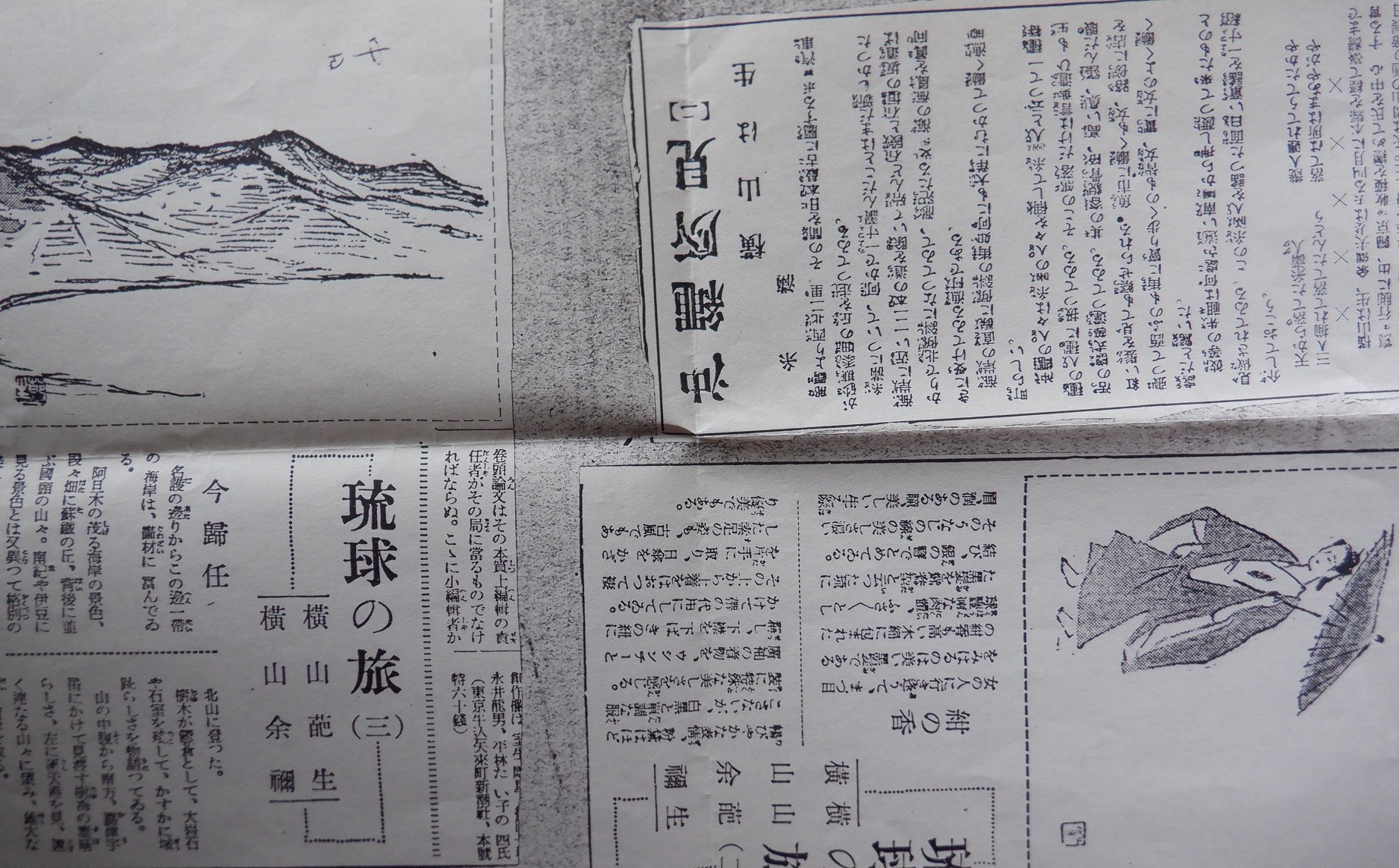
横山葩生、余彌子夫妻来沖
□1936年4月ー台中丸で、帝展画家の横山葩生、余彌子夫妻来沖。「横山画伯夫妻けふ沖縄訪問ー氏の義姉は故末吉麦門冬氏の妹にあたり、古くから憧れていた南島沖縄訪問がやっとこの日実現されたものである。なお氏の来遊に就いて名古屋在住の佐渡山安勇氏より島袋全発図書館長へ世話方を依頼して来ている。」/「」10月ー『塔影』「青樹社第三回展ー名古屋伊藤銀行中支店楼上に開催。同社は横山葩生君を中心とする団体、葩生君の『南国風景』」
横山葩生 (よこやまはせい) 生年 / 没年 : 1899 / 1974
生地 / 没地 : 愛知県瀬戸市 / 愛知県名古屋市 第2回帝展(1920) 中京美術院 青樹社→愛知県美術館

写真ー金城安太郎氏と石垣さん親子(末吉麦門冬娘)
11/09: 末吉麦門冬没後90年/11月25日は「莫夢忌」①

1925年11月15日『沖縄タイムス』
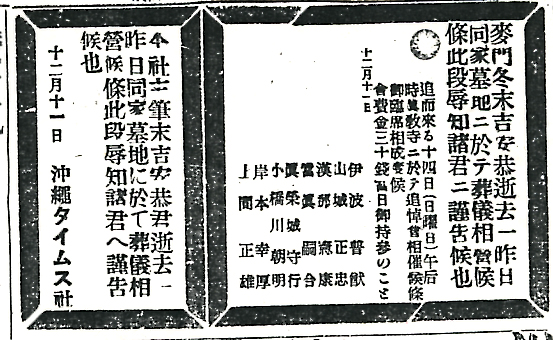
1924年12月11日『沖縄タイムス』「麦門冬末吉安恭逝去一昨日同家墓地ニ於テ葬儀相営候此段辱知諸君ニ謹告候也 追而来る14日(日曜日)午後時眞教寺ニ於テ追悼会相催候條御臨席)相成度候 会費金30銭当日御持参のこと/伊波普猷、山城正忠、漢那憲康、眞栄城守行、小橋川朝明、岸本幸厚、上間正雄」
1924年12月15日『沖縄朝日新聞』「麦門冬・末吉安恭氏の追悼会は既報の如く昨14日午後2時より眞教寺佛堂に於いて執行されたが故人の知己友人等相会する者両市各方面の階級を網羅して百数十名に上り、主催者代表として岸本タイムス社長挨拶を述べ次いで田原法馨師以下役僧の讀経があり故人と近かった仲吉朝助、川平朝令の両氏は交々悲痛なる弔辞を述べ終わって参会者一同順次に焼香を済まし同4時散会した。清く咲き誇れる梅花を■に淋しくも法灯に護られたる『莫夢釈安居』の法名の白木の位牌は故人の在りし日の面影を偲ばせ人々の悲しみを新たならしめた。」
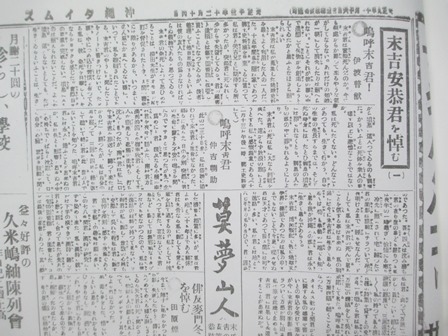
12月14日 『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(1)ー伊波普猷、仲吉朝助、田原煙波」
○伊波普猷ー末吉君は実際死んだのか。今にも何処からか帰って来るやうな気がしてならない。あれだけの知識が一朝にして消失したのは耐へられない。ことにそれが彼の頭の中で温醸して何物かを創造しょうとしていたかと思ふとなほさら耐へられない。末吉君は私が蒐集した琉球史料を最もよく利用した人の一人だった。15年間私の隠れ家であった郷土史料室を見棄てるに当って、私は君と笑古兄に期待する所が多かったが、突然君に死なれて、少からず失望している。君の蔵書と遺稿とは県立図書館に保管して貰ふことになっているが、後者を整理して他日出版するといふことは彼の友人たちの為さなければならぬ義務であると思っている。
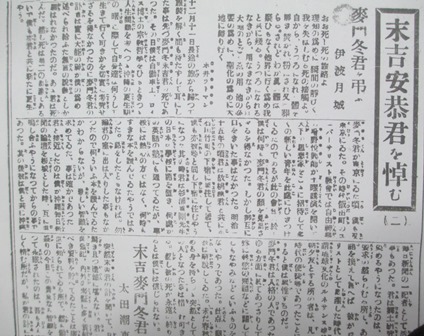
1924年12月15日ー『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む」(2)
□伊波月城「麦門冬君を弔ふ」
おお死ー死の旅路よ
理知の為めに瞬間の静けく
我を愛し失はしむる死の接触よ。
自ら、うつろになれ 體を
解き焚かれ粉にされ又 葬らる。
されどわが眞の體は
疑いもなく他界に行く為我と共に残る。
うつろになれるなきがら。
用なきなきがらは大 のとご いの用 他の必要
の為に、聖化の為に大地に帰り行く
ホイットマン
12月11日長途の旅から帰って旅装を解く間も待たずして耳にした事は先ず麦門冬末吉君の死であった。その日僕は自働車上 ロイス博士の宗教哲学をひもときつつ人生問題を考えつつ沖縄の更生期の曙に際して自分達は如何して生きて行く可きかを切実に考究せざるを得なかったのに麦門冬君の訃音は実に大能の神が僕の為 述べられ給うた無言の説教としか思われなかったのだ。ああ君は死んだ。然し死は第二の出産である。いで僕も亦君と共に新たな更生しよう。
麦門冬君が東京にいた頃、僕も又東京にいた。その時代飯田町のユニバーサリスト教会では自由神学の増野悦興師が土曜講演を開いて天下の思想家をここに招待して多くの新しい青年を此処ににひきつけていたのであるが此の会合に於いて僕は何時も麦門冬君の顔を見出さざるを得なかった。しかしお互いに口をきいた事はなかった。明治35年の頃君は故桃原君と共に小石川竹町の下宿に居住していて、僕も亦彼等と同じ下宿に住むようになった。其の時君は杉浦重剛先生の日本中学校に籍を置き、何処かの英語の塾にも通っていたが、学校には熱心の方ではなく、何時もすきな本を読んでいたようではあった。話をしたこともなければ勿論君の室に出入りした事もなかったので何ういう本を読んでいたかわからないが、新しい智識を求めていた事は確かであった。
君と接近したのは僕が沖縄毎日新聞の論壇を根拠とした時、互いに共鳴し合うようになってからの事であった。其の後彼は僕と共に沖縄毎日新聞の一記者として活動した事もあった。君は郷土研究に指を染めるようになったのは、時代の要求の然らしむ所であって、語を換えて言へば、彼がジアナリストとして出産した時代は、所謂琉球文化のルネサンス時代 其の朝夕友とする所の者は、凡て新時代の使徒等であったことに起因すると僕は思惟するのだ。
麦門冬君は人格の人であった。あらゆる方面に於いてあっさりしている。殊に性欲の問題などに関しては少しも悩みなどというものを知らないようであった。この点に関して彼は解脱していた。未だ春秋に富める身を持ちつつ突然として他界の人となった事は惜しむ可きである。然し彼の死が永遠に終わりであるとは僕には信じられない。
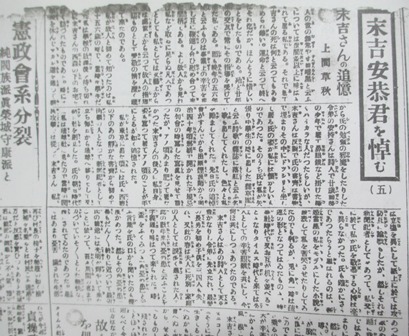
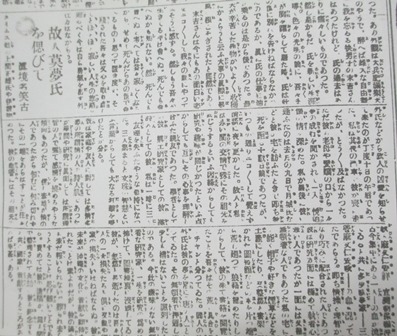
12月18日『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(5)ー上間草秋、眞境名笑古」

12月20日『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(7)ー東恩納寛敷、長浜瓊州」
12月26日『沖縄タイムス』東恩納寛惇「野人麦門冬の印象」
12/02: 莫夢忌/島袋全発
1920年代、琉球史随筆で大衆を喜ばせた新聞人、末吉麦門冬が24年11月に水死した。その追悼文で島袋全発は「友人麦門冬」と題し「私共の中学時代 客気に駆られ一種の啓蒙運動をなしつつあった頃 麦門冬は蛍の門を出でず静かに読書に耽って居た。あの頃の沖縄は随分新旧思想の衝突が激しかったが物外さんを初め私共の応援家も頗る多かった。氏も恐らく隠れたる同情者の1人であったに違いない。其後私が高等学校に入ってから氏と交わる様になったが一見旧知の如くやはり啓蒙運動家の群の1人たるを失わなかった。私共は苦闘して勝った。啓蒙運動とは何ぞと問われたら少し困る。文化運動と云ってもいい。それを近いうちに麦門冬氏が書くと云っていたそうだが遂に今や亡し。該博なる智識そのものよりも旺盛」なる智識欲が尊い。そして旺盛なる智識欲よりも二十年諭らざる氏の友情は更に尊い。私は稀にしか氏とは会わなかった。喧嘩もした。然し淡々たること水の如くして心底に流動する脉々たる友情はいつでも触知」されていたのである。去年の今頃は私の宅で忘年会をした。そして萬葉集今年の山上憶良の貧窮問答「鼻ひしひしに」や「しかとあらぬひげかきあげし」やに笑い した後 矢張り啓蒙運動の話に夢中になった。今年の春は大根の花咲くアカチラを逍遥し唐詩選の句などを口吟、波之上の茶亭に一夜の清遊を試み歓興湧くが如くであった。せめて晩年の往来をしたので良かったと思う。麦門冬氏の如き詩人は多い。氏の如き郷土史家は少ない。氏の如き友情に至っては今の世極めて稀。今や忽焉として亡し。噫」。
全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。
1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。
1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。
濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。
島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。
また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。
1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。
1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。
全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。
1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。
1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。
濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。
島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。
また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。
1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。
1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。
○本土で既に廃れた言葉でも、沖縄にはまだ現存して居るのが幾何もあるされば古語の語原の分からぬのでも沖縄の言葉で考える即ぐに解釈がつく伊波文学士なども頻りに其学を研究して居らるるが是は実に有益の研究で沖縄人が日本人種と同一人種であると云ふ立証が明にさるると共に沖縄語の日本語研究の管鍵として沖縄の価値を高め一概に沖縄を以て蛮音訣舌として軽蔑する者流の誤見を訂正するに足るのである。私はフト幸田露伴①氏の蝸蘆雑談と云ふ文章を見て感づいたことがある。其の文章は神武天皇の東征史実を論じて露伴一流の綿密なる考証と穏健なる論断がされてあった。私の特に其中で発見したのは長髓彦②の名に就いての考証である。氏の説によると長髓と云ふのは邑の名で、彼の別名登美彦といふ。登美が地名なると同一で本名ではない本名は記録には見えない、記には長髓は是邑の本の号と見えている。それから髓といふのはずね土の義にして本居宣長③などは骨中の脂の借字ならんと疑へりとある。この説は実に穏当である。長髓が「すね土」即ち骨中脂で、其土地の地質から命名した地名として其の土地に生まれた豪族の名となった、と云ふことは如何にも能く肯かれる、それを猶、吾々沖縄人が見るとこの説が一層有力なることを証明される。
これを如何と云ふに本土では今や長髓を以て姓名とする者はなけれども、沖縄ではまだ長髓姓がある。怪しむ勿れ、長髓は即ち仲宗根である。本県には仲宗根の知名と人名が未だに現存するのである。人名は地名から来たものである。人名には仲宗根清などの如き紳士もあり、又仲宗根朝信といふ人も居る。これ等は皆長髓彦彦と同名の人である。或は何か縁故があるかも知れぬ。恁麿な訳で本土に廃減した語名称が沖縄には今日流布通用していると云ふことは実に面白いではないか。本居宣長や幸田露伴の長髓彦考は沖縄に来て始めて立派な照明を得たと云ふても過言ではない。若し仲宗根清君朝信君が露伴氏の蝸牛庵へでも訪づねて、私はナカゾネと申す者でと名乗り出たら2千年前の長髓彦の再来かとばかりに氏を叱驚させるに違いない。又屹度歓待するに違いない。
戯談は廃して私は露伴氏の説に依りて沖縄では、仲宗根の「ゾネ」が何の意味だか分からぬのを「ずね」といふ義なることを教えられたことを感謝すると共に、一つ感付いたことがある。それは本居氏も幸田氏もナカズネを地名とし本名にあらずとする迄はよいが、別に本名が記録にないと云って不足らしく且つ本名が有る様に云はれたのは何かと思ふ。私の考えでは長髓彦には別に本名なんと云ふものは無かったらう、彼は長髓邑の長であって丁度謝那の大主が謝那村の地頭であると同格の者ではなかったらうか姓名を称ぶのは後世のことで太古はそんな面倒なものは必要としないツイ近頃まで辺鄙の地方に行くと本名のない人民がいたのでも判る。能登半島の何とか云ふ部落には明治以前には住民は本名がなかったが明治になってから戸籍上不便だと云って皆な名をつけさせたそれも戸籍吏が一日につけてやった為め出鱈目に海産物の名をクッつけて色々可笑しな名が沢山あるとのことだ。長髓彦時代も其麼な有様であって地名を本名とするに止り別に本名なんと云ふ者を必要としなかったであろう。
1912年6月24日『沖縄毎日新聞』笑古(真境名安興)「ス子の解」
○過日紙上に御掲載相成候麦門冬君の「ナガスネヒコ」考は面白く被読候。仲宗根といふ地名に付きては余も宿説有し「スネ」が果たして「土」の義なりと本居翁始め我が古学者の申されしは兎に角この「スネ」は普通の「土」の義なりや或は特殊なる「土」を意味せしやは考究の余地有之候。余は沖縄にて「スネ」といふは魚類の群棲する箇所を指せしものにて(今も然り)即ち海峡の一角が海底の隆起或は陥落して魚族の保護上の好適所か若しくは餌食の豊富なる箇所かと愚考致候。然ればこの「土」は普通の土にあらずして河海の作用にて出来上がりし沖積地の如きものの土地を指称せしものにては無之候哉。余は沖縄の仲宗根なる地名の語源は従来「中ノスネ」或は「長ノスネ」と解せり。昔時にありては海底にありて魚族の群棲せし箇所が時代の推移と天然力の作用に依りて陸地と化し遂に村落を形造りしものが今にその名称に残りしものならんと考証致候。亦一面より観察するも魚族の群棲する箇所は原人の部落を造るに好適の土地柄歟と被存候。先は貴説を読み感想に浮かびし一端を御参考迄に一言致し申候。敬具
①長髄彦
ながすねひこ
『古事記』『日本書紀』に登場する大和地方の族長。『古事記』には登美能那賀須泥毘古 (とみのながすねびこ) と記される。神武天皇の東征に抵抗し,大いに悩ましたが,天皇の弓に止った金色のとびに目を射られて敗退。 →コトバンク
②幸田露伴
小説家・随筆家。東京生。名は成行、号は蝸牛庵。電信修技学校卒業後電信技手として北海道へ赴任するが、文学への思いやまず帰京。『露団々』『風流仏』などの作品によって理想派の作家として文名を確立、写実派の尾崎紅葉と人気を二分した。代表作に『五重塔』『一口剣』等。芸術院会員。文化勲章受章。昭和22年(1947)歿、80才。 →コトバンク
③本居宣長
江戸後期の国学者。伊勢松坂生。号は芝蘭・春庵・鈴屋。初め堀景山に儒学を学び、のち賀茂真淵に入門。国学四大人の一人。『古事記伝』『玉くしげ』等著書は多く、全国に多数の門人を雍した。享和元年(1801)歿、72才。→コトバンク
これを如何と云ふに本土では今や長髓を以て姓名とする者はなけれども、沖縄ではまだ長髓姓がある。怪しむ勿れ、長髓は即ち仲宗根である。本県には仲宗根の知名と人名が未だに現存するのである。人名は地名から来たものである。人名には仲宗根清などの如き紳士もあり、又仲宗根朝信といふ人も居る。これ等は皆長髓彦彦と同名の人である。或は何か縁故があるかも知れぬ。恁麿な訳で本土に廃減した語名称が沖縄には今日流布通用していると云ふことは実に面白いではないか。本居宣長や幸田露伴の長髓彦考は沖縄に来て始めて立派な照明を得たと云ふても過言ではない。若し仲宗根清君朝信君が露伴氏の蝸牛庵へでも訪づねて、私はナカゾネと申す者でと名乗り出たら2千年前の長髓彦の再来かとばかりに氏を叱驚させるに違いない。又屹度歓待するに違いない。
戯談は廃して私は露伴氏の説に依りて沖縄では、仲宗根の「ゾネ」が何の意味だか分からぬのを「ずね」といふ義なることを教えられたことを感謝すると共に、一つ感付いたことがある。それは本居氏も幸田氏もナカズネを地名とし本名にあらずとする迄はよいが、別に本名が記録にないと云って不足らしく且つ本名が有る様に云はれたのは何かと思ふ。私の考えでは長髓彦には別に本名なんと云ふものは無かったらう、彼は長髓邑の長であって丁度謝那の大主が謝那村の地頭であると同格の者ではなかったらうか姓名を称ぶのは後世のことで太古はそんな面倒なものは必要としないツイ近頃まで辺鄙の地方に行くと本名のない人民がいたのでも判る。能登半島の何とか云ふ部落には明治以前には住民は本名がなかったが明治になってから戸籍上不便だと云って皆な名をつけさせたそれも戸籍吏が一日につけてやった為め出鱈目に海産物の名をクッつけて色々可笑しな名が沢山あるとのことだ。長髓彦時代も其麼な有様であって地名を本名とするに止り別に本名なんと云ふ者を必要としなかったであろう。
1912年6月24日『沖縄毎日新聞』笑古(真境名安興)「ス子の解」
○過日紙上に御掲載相成候麦門冬君の「ナガスネヒコ」考は面白く被読候。仲宗根といふ地名に付きては余も宿説有し「スネ」が果たして「土」の義なりと本居翁始め我が古学者の申されしは兎に角この「スネ」は普通の「土」の義なりや或は特殊なる「土」を意味せしやは考究の余地有之候。余は沖縄にて「スネ」といふは魚類の群棲する箇所を指せしものにて(今も然り)即ち海峡の一角が海底の隆起或は陥落して魚族の保護上の好適所か若しくは餌食の豊富なる箇所かと愚考致候。然ればこの「土」は普通の土にあらずして河海の作用にて出来上がりし沖積地の如きものの土地を指称せしものにては無之候哉。余は沖縄の仲宗根なる地名の語源は従来「中ノスネ」或は「長ノスネ」と解せり。昔時にありては海底にありて魚族の群棲せし箇所が時代の推移と天然力の作用に依りて陸地と化し遂に村落を形造りしものが今にその名称に残りしものならんと考証致候。亦一面より観察するも魚族の群棲する箇所は原人の部落を造るに好適の土地柄歟と被存候。先は貴説を読み感想に浮かびし一端を御参考迄に一言致し申候。敬具
①長髄彦
ながすねひこ
『古事記』『日本書紀』に登場する大和地方の族長。『古事記』には登美能那賀須泥毘古 (とみのながすねびこ) と記される。神武天皇の東征に抵抗し,大いに悩ましたが,天皇の弓に止った金色のとびに目を射られて敗退。 →コトバンク
②幸田露伴
小説家・随筆家。東京生。名は成行、号は蝸牛庵。電信修技学校卒業後電信技手として北海道へ赴任するが、文学への思いやまず帰京。『露団々』『風流仏』などの作品によって理想派の作家として文名を確立、写実派の尾崎紅葉と人気を二分した。代表作に『五重塔』『一口剣』等。芸術院会員。文化勲章受章。昭和22年(1947)歿、80才。 →コトバンク
③本居宣長
江戸後期の国学者。伊勢松坂生。号は芝蘭・春庵・鈴屋。初め堀景山に儒学を学び、のち賀茂真淵に入門。国学四大人の一人。『古事記伝』『玉くしげ』等著書は多く、全国に多数の門人を雍した。享和元年(1801)歿、72才。→コトバンク
08/17: 島袋百恵 画「末吉麦門冬」


島袋さん(左)、萌子さん
島袋百恵
1986年 沖縄県沖縄市生まれ。室川小、安慶田中
2002年 沖縄県立コザ高校入学 美術部在籍
2005年 同校卒業
2009年 沖縄県立芸術大学美術工芸学部絵画専攻卒業
専門は日本画と版画
2009年 グループ展「ユメテン」(沖縄市)
2010年グループ「tetra works Ⅴo1」(那覇市)
□蔵書票
.jpg)
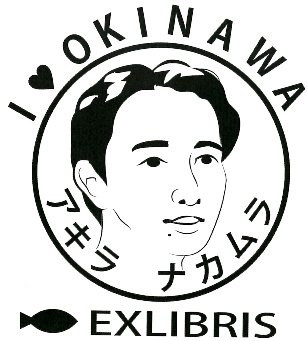
07/19: 年譜・末吉麦門冬/1912(明治45)年
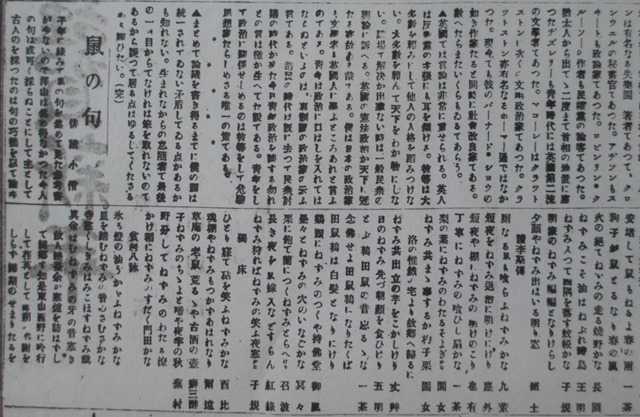
1914年1月1日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「俳諧 鼠の句」
○俳諧 鼠の句ー子年に縁みて鼠の句を集めて見た。参考書が少ないので沢山は集め得なかった今人の句は成可く採らぬことにして主として古人のを採ったのは句の巧拙を以て論せずに古いのが有難いといふ骨董味から出た為めである。それから新年の鼠に嫁が君と云ふ異称があるが、それは俳諧では独立の題になっているので茲にはわざと省いたのである。
1月 親泊朝擢『沖縄県案内』発行/仲吉朝主、印刷/三秀舎「新聞雑誌ー琉球新報、沖縄毎日新聞、沖縄新聞、発展、撫子新聞、福音、沖縄教育、おきなは、演劇週報」
1月 横山健堂『薩摩と琉球』
1月 島津長丸男爵、観光で来沖
1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立
1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社
3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」
卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2
照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6
沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去
6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」
6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」
7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」
7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」
711日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」
7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」
7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」
8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」
8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」
8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」
8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」
8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」
8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」
8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」
9月2日『琉球新報』「我海軍の精華▽悉是れ良智驍勇」「常設活動写真帝国館ー女馬賊」
9月4日『琉球新報』「太平洋に於ける独墺洪海軍力」
9月5日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写着色・ベルサイユ宮殿」
9月6日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・黒金座主(電気応用)、踊り・七月ゑひさあ、歌劇・可憐児(継親念仏)」
9月12日『琉球新報』「球陽座ー琉球史劇・琉球と薩摩」「常設活動写真帝国館ー実写・ピスピユス山噴火」
9月14日『琉球新報』「本社記者 渡口政成退社し沖縄民報社に入社」
9月15日『琉球新報』「『月刊雑誌 五人』ーダヌンチョの死せる街ー嘉手川重利/白き血ー山城正忠/脚本時計ー上間正男/小説題未定ー安次嶺栄裕/芭蕉の恋ー末吉麦門冬/本県婦人観ー美鳩楓渓/希臘思想ー仲吉良光/音楽論ー矢野勇雄/小説帽子ー池宮城寂泡/題未定ー漢那浪笛/サヨリ釣ー潮東庵主人/完成の人孔子ー山田有幹」
9月18日『琉球新報』「粟国事情」「斎藤用之助島尻郡長令弟、中頭郡書記・斎藤熊太郎死去、」
9月26日『琉球新報』素位「泡津海記ーテラの岩屋、日本一の墓、マハナ崎」「球陽座ー琉球史劇・普天間権現之由来記」
10月3日 『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・ノールウェ汽車旅行」「球陽座ー喜利 狂言・伊賀の水月(荒木又右エ門武勇伝)渡嘉敷守禮脚色 」
10月8日 『琉球新報』清村泉水「宮古女性史」①
10月11日 『琉球新報』「三越の新館成る」「常設活動写真帝国館ー実写・伊多利シシリー市街」」「球陽座ー琉球史劇・大濱赤八」
10月15日 『琉球新報』らくこう「琉球歌壇 印度古詩まはばらだ物語を読みて(1)ー我が情我れの衣につつみ行くシャンタヌ王の面白きかな/この河を渡らん人に舟漕かん王者も渡れ乞食人も/絶ち難き情の絆王もなほ黒き瞳の忘れかねつも/天人は樂を奏しぬ花降りぬ若きピスマの願ひの浄きに/仙人の神通力もいかにせむ美人を見て破れけるかも/呪はるることの恐ろしサチヤワチは岸の浮草靡かんとする/十万の矢を空中に射返して流れを下る婿選ひ舟」
10月17日 『琉球新報』「悲惨極まるラサ島移民①」「球陽座ー大喜利・英雄ト美人ーナポレオン(真境名由孝土産)」
10月21日 『琉球新報』らくこう「琉球歌壇 印度古詩まはばらだ物語を読みて(2)ーカミアカの森に入りぬる一千の宮女の群よ夕日春●/五王子は雲を支へて立てるてふサミが木ぬれに刃隠しぬ/あはれなるドラウバテイの艶なるに王妃はめでぬ且つ嫉みつつ/美しき者にともなふ禍を神よ解き去れドラウバテイに/兄嫁の為めにはかりて猛きピーマ敵を取りぬ肉丸にして/アルジユナは怖るる所ろ更にな●一騎手に持つカンデイワの弓/クリシナは高く叫びぬ天神地祇我と共にあり愚かなもの哉/武士の魂さこうカルナ行かず仕ふる家と運を共にせむ」
□『マハーバーラタ』(サンスクリット語: महाभारतम् Mahābhārata)は、古代インドの宗教的、哲学的、神話的叙事詩。ヒンドゥー教の聖典のうちでも重視されるものの1つで、グプタ朝の頃に成立したと見なされている。「マハーバーラタ」は、「バラタ族の物語」という意味であるが、もとは単に「バーラタ」であった。「マハー(偉大な)」がついたのは、神が、4つのヴェーダとバーラタを秤にかけたところ、秤はバーラタの方に傾いたためである。→ウィキペディア
10月31日 『琉球新報』「秦蔵吉、樺山氏主宰の沖縄社に入社」
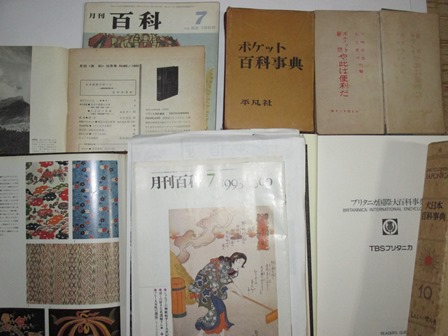
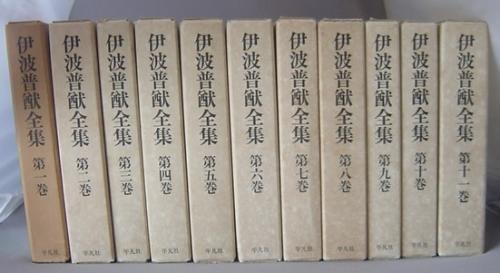
伊波普猷全集』全11巻(1974~76・平凡社)○沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価値は高い。加えて 麦門冬・末吉安恭との交流も示される。
第1巻: 古琉球 古琉球の政治 第2巻: 南島史考 : 琉球を中心としたる 孤島苦の琉球史 沖縄歴史物語 : 日本の縮図
第3巻: 校註琉球戯曲集 第4巻: 南島方言史攷 沖縄考 第5巻: をなり神の島 日本文化の南漸
第6巻: 琉球聖典おもろさうし選釈 : オモロに現はれたる古琉球の文化 校訂おもろさうし おもろ覚書 : 琉球古代社会の片影 おもろ論考
第7巻: 琉球人種論 琉球史の趨勢 琉球の五偉人 沖縄女性史 琉球古今記 琉球風俗史考
第8巻: 琉球戯曲辞典 琉球語便覧 言語論考
第9巻: 文学論考 民俗論考
第10巻: 図版(自作おもろ「飛行機」)嗚呼末吉(安恭)君! 眞境名(安興)君の思出 「ぺルリ提督琉球訪問記」序
第11巻: 琉球語大辞典 : 草稿 大辞典 年譜 著作目録 総索引
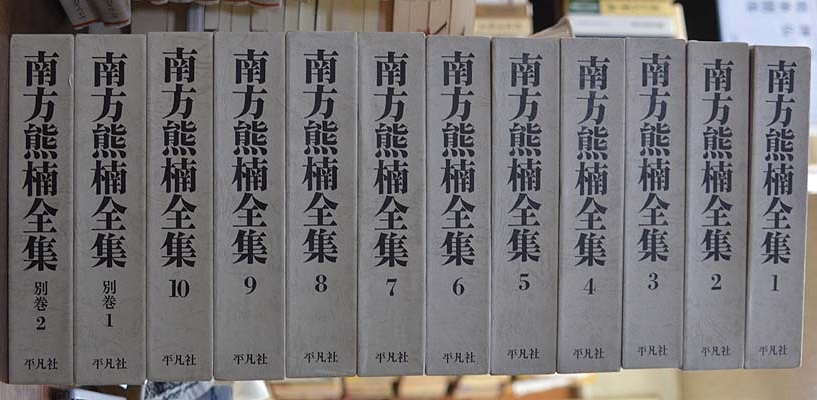
南方熊楠(1867~1941)は明治、大正、昭和の3代にわたり、終生、野にあって人文・自然両分野の学の蘊奥をきわめた知的巨人である。和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。随筆には 琉球在住の麦門冬・末吉安恭との交流も示される。
南方熊楠全集 全 12 巻 平凡社 1971~1975 年 ○ 第1巻 十二支考[雑誌『太陽』(博文館)1914~1923] 第2巻 南方閑話[坂本書店 1926]南方随筆[岡書院 1926]続南方随筆[岡書院 1926]*南方の著書の うち生前に刊行されたのはこの3冊のみである。 第3巻=雑誌論考Ⅰ[『東洋学芸雑誌』ほか雑誌 20 誌に掲載された論考] 第4巻=雑誌論考Ⅱ[『彗星』ほか雑誌 12 誌に掲載された論考] 第5巻=雑誌論考Ⅲ[『ドルメン』ほか雑誌7誌に掲載された論考] 第6巻=新聞随筆[『牟婁新報』ほか8紙の新聞及び『週刊朝日』に掲載された随筆と、未発表の随筆を収録] 第7巻=書簡Ⅰ[主として明治時代のもの。在米時代・神社合祀問題関係他] 第8巻=書簡Ⅱ[柳田国男、高木敏雄、その他民俗学関係の人々に宛てた書簡] 第9巻=書簡Ⅲ[第7・8巻収録以外の多方面に及ぶ書簡] 第 10 巻=英文論考・英訳方丈記・初期文集他 A Japanese Thoreau of twelfth century(英訳『方 丈記』) [ 『英国王立アジア協会雑誌』(1905)掲載 文末に鴨長明に関する2つの註釈あり。ロンドン大学総 長ディキンズとの共訳] The constellations of the far east(極東の星座) [ 『Nature』 (1893)掲 載] Footprints of Gods(神跡考) [『Notes and Queries』 (1900)掲載]他 別巻1=書簡補遺・論考補遺 The origin of the swallow-stone myth(英文『燕石考』) [草稿 1899? ~1903]他、補遺 別巻2=日記・年譜・著述目録・総索引
平凡社の歴史ー1914 下中弥三郎が自著の小百科事典「や、此は便利だ」の販売のため創立。
1927 「現代大衆文学全集」60巻の刊行開始。円本時代を築く。1928 「大百科事典」全28巻刊行を発表(1934年完結)。名実ともに「事典の平凡社」となる。
1945 戦時中の休業状態から再出発。「大百科事典」復刻、「社会科事典」「家庭科事典」「世界美術全集」「世界歴史事典」「児童百科事典」など刊行。
1954 創業40周年記念として「世界大百科事典」全32巻刊行を発表(1959年完結)。1961 「国民百科事典」刊行開始。空前の百科事典ブーム。1963 日本初の本格的グラフィック月刊誌「太陽」創刊。
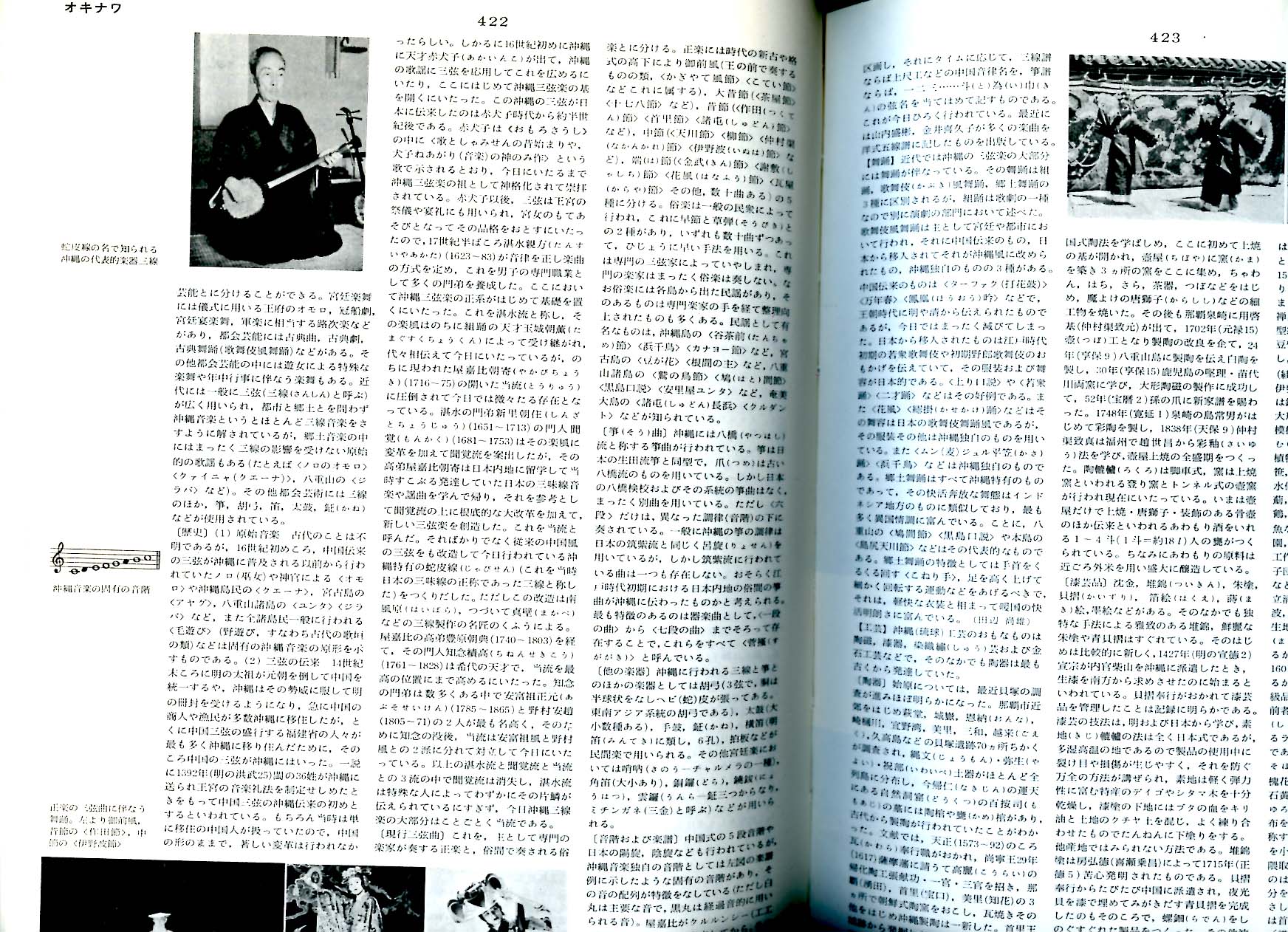
1964年11月ー平凡社『世界大百科事典』明石染人「沖縄ー工芸」
1969 初のオールカラー事典「アポロ百科事典」刊行。1972 「別冊 太陽」創刊。ムックの先駆けとなる。
1973~ 「南方熊楠全集」「中国の歴史」「中国石窟」シリーズ、「日本の野生植物」、新版「大百科事典」「世界大博物図鑑」「動物大百科」、「日本歴史地名大系」(刊行中)、「日本史大事典」など刊行。1993 文庫「平凡社ライブラリー」創刊。1997 デジタル百科「CD-ROM版 マルチメディア・マイペディア」発売。
1998 「CD-ROM版 世界大百科事典プロフェッショナル版」発売。「日本動物大百科」全11巻が完結。1999 「平凡社新書」創刊。
2001 「日本の野生植物」全7巻、「白川静著作集」全12巻が完結。2004 「日本歴史地名大系」本巻48巻が完結。白川静「新訂 字統」刊行。2007 改訂新版 世界大百科事典 刊行。
1928年 世界美術全集 平凡社 全 36冊
10/08: 丹青協会初代会長・山口瑞雨
1908年9月4日~14日ー沖縄美術運動の夜明・丹青協会第一回絵画展覧会
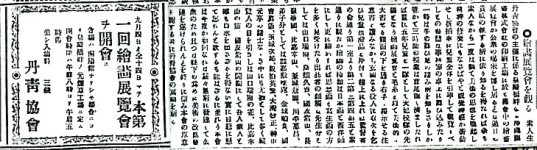
出品者 山口瑞雨(沖縄師範学校教諭心得)、岸畑久吉(沖縄県立中学校教諭心得)、國友朝次郎(首里区立工業徒弟学校助教諭 日本画ー四條派 岡田玉翠に学ぶ)、長嶺華國、比嘉華山、兼城恵園、川平恵昌、渡嘉敷唯選、金城唯貞、大湾政正、神山元享、親泊英繁、玉城次郎、国吉真義(刑務所職員)
瑞雨・山口辰吉はその名が示すごとく1868年(明治元年/戊辰)10月21日に生まれた。辰は、十二支の中で唯一「実在しない生き物」で、これは、或る種のカリスマ性の要因となると云われている。
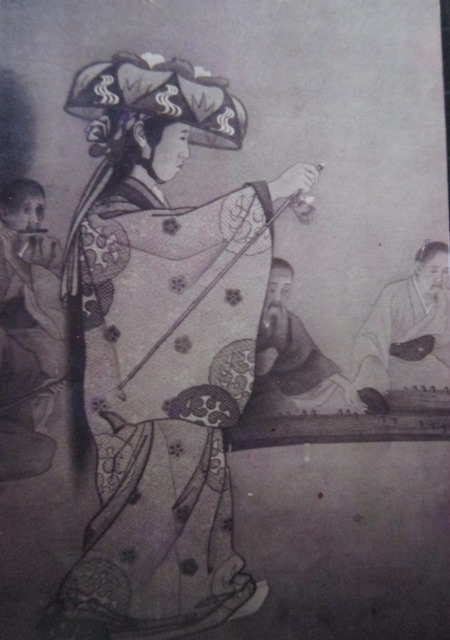

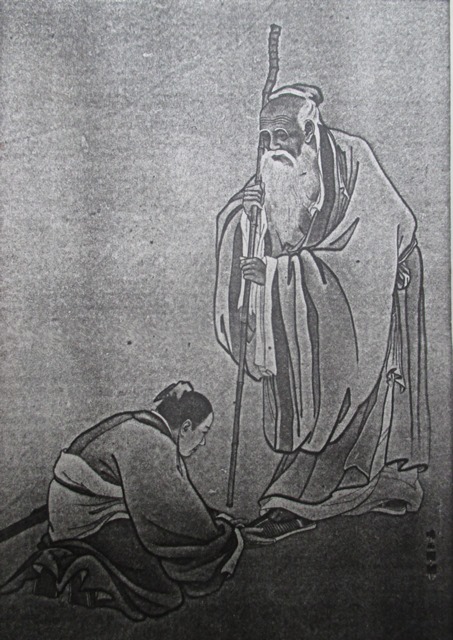
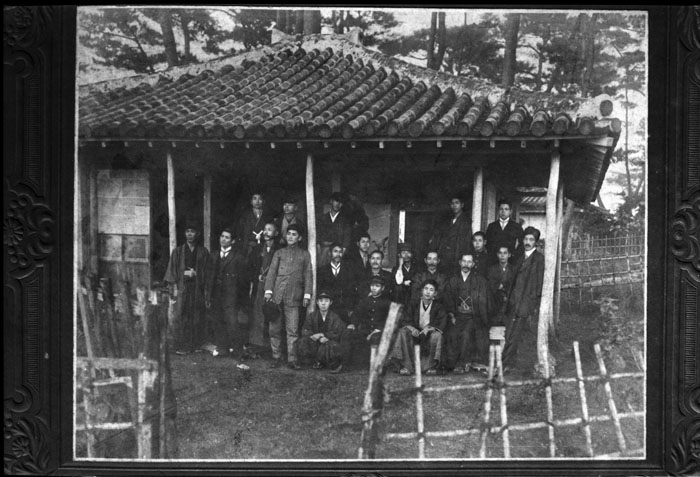
1912年2月ー太平洋画会の吉田博、石川寅治、中川八郎と丹青協会ー真ん中の柱の中列右が瑞雨。瑞雨の上が瑞雨の息子の山口清。左端が比嘉崋山、右へ一人おいて兼城昌興

1908年、沖縄最初の美術団体「丹青協会」が結成されその会長に瑞雨が就いた。11年、2年かがりの「程順則肖像図」の模写が完成。12年の1月、太平洋画会の吉田博、中川八郎、石川寅治が沖縄写生旅行のときの写真には瑞雨や丹青協会メンバーが写っている。
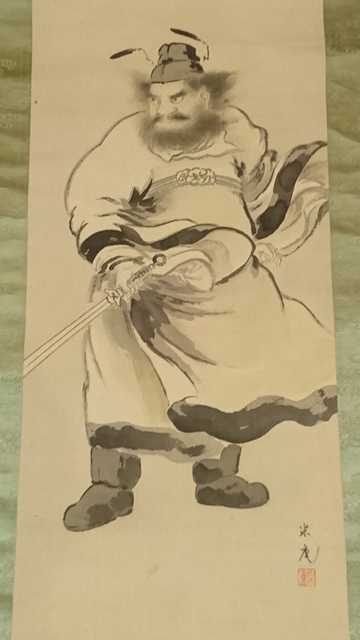
私は山口米庵のひ孫で、善丸と申します。 昨年 12月7日に父 順造が92歳で他界し、山口家のことは今私が記録を残さなければ子孫には皆目わからずじまいになりかねないと、初代、米庵について調べたところ、琉文21に沖縄時代の記録を見ることが出来ました。心より感謝申し上げます。山口家の墓は都営多磨霊園にあります。初代、米庵 瑞雨院米庵智堂居士。 以来代々が埋葬されています。 30年前に母が亡くなった時、墓には地下室が無く、お骨壷を直に埋めていましたが、すべてのお骨壷を掘りあげて一箇所に収納出来るように改修しました。その時、米庵の骨壷はすごく小さいものしか有りませんでした。 なお、家に残っている米庵の掛け軸の写真を添付いたします。

写真左から山口善丸氏、島袋和幸氏
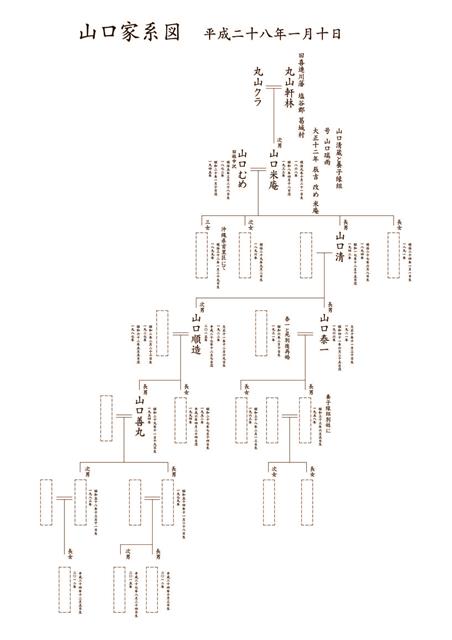

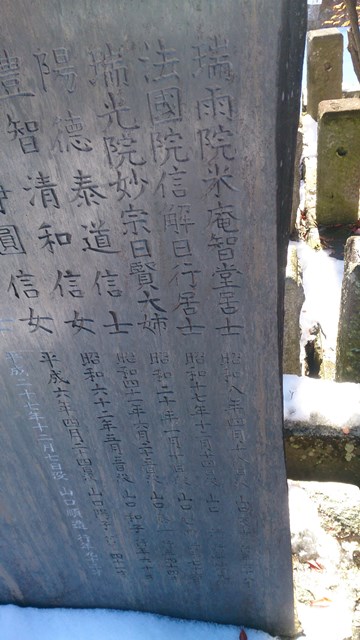
山口瑞雨次女 山口まさ(明治29年9月2日生まれ。大正9年6月21日 浅草にて海上晴①と婚姻)
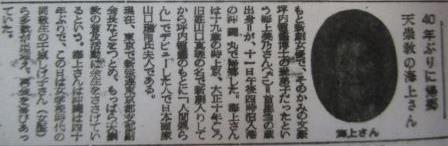
1959年10月12日『琉球新報』□40年ぶりに帰郷 天崇教の海上さんーもと新劇女優で、そのかみの文豪坪内逍遥博士の愛弟子だったという海上美乃さん(62)=首里当蔵出身=が、11日午後4時 泊入港の沖縄丸で帰郷した。海上さんは19歳の時上京、大正10年ごろ旧姓山口真瑳の名で新劇入りしてから坪内逍遥のもとに「人間親鸞」でデビューした人で日本画家山口瑞雨夫人(ママ)である。現在、東京で新宗連東京都支部副会長などをつとめ、もっぱら天崇教の普及活動に余生をささげているという。海上さんは沖縄は40年ぶりで、この日は女学校時代の同級生の千原繁子さん(女医)ら多数が出迎え、再会を喜びあっていた。→1933年5月『沖縄県立第一高等女学校同窓会』に1913年 第10回卒業生に林まさ 旧姓 山口 東京市中野/第12回卒業生に千原繁子 旧姓 渡嘉敷 那覇市上之蔵1ノ18千原医院。
①海上晴
1894年(明治27年)、東京府東京市浅草区(現在の東京都台東区浅草)に生まれる。旧制・早稲田実業学校(現在の早稲田大学系属早稲田実業学校高等部)を中途退学したが、早稲田大学の坪内逍遥に入門し、文学を学ぶ。島村抱月、沢田正二郎ら演劇人と親交を結び、新劇の世界に入る。「創生劇」を主宰、日比谷野外音楽堂で公演を行った。1920年(大正9年)、日活向島撮影所の革新運動に参加し、同撮影所第三部が製作した田中栄三監督の『朝日さす前』に主演する。以降、同部の消滅まで出演をつづけた。関東大震災以降の1925年(大正14年)、兵庫県西宮市の東亜キネマ甲陽撮影所で映画出演する。1928年(昭和3年)6月、加藤精一、佐々木積とともに帝国劇場専属俳優となる。
1936年(昭和11年)、お告げを受け、天崇教を創立する[1]。教祖としての名は「海上晴帆」である。第二次世界大戦後、1948年(昭和23年)に宗教法人登録を行う。1952年(昭和27年)、黒澤明監督の『生きる』で映画界に復帰、以降、東宝作品を中心に出演する。初期の岡本喜八監督作品の常連で、体格がよく貫禄のある役どころが多かった。→林幹 - Wikipedia
1905年4月『琉球教育』第106号「中頭郡女子研究会ー本年1月中頭郡に遊戯唱歌塗板画の講習会開会せし以来女子は遊戯唱歌に男子は塗板画に興味を起こし且つ教授上に大に必要を感じ引続き有志者の集会を企画し男子は首里山口瑞雨氏宅に女子は宜野湾間切普天間に毎月集合して研究怠らず・・・」
1910年4月6日『沖縄毎日新聞』「丹青協会批評会ー去る3日第10回の作品批評会を若狭町クラブに会するも日本画の山口瑞雨を筆頭として董園、比嘉華山、国吉沖山、義村竹斉、洋画の関屋敬治、親泊、渡嘉敷唯選、松島、山城、中村の面々・・・・」
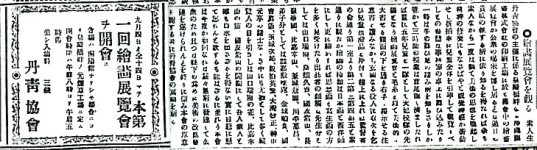
出品者 山口瑞雨(沖縄師範学校教諭心得)、岸畑久吉(沖縄県立中学校教諭心得)、國友朝次郎(首里区立工業徒弟学校助教諭 日本画ー四條派 岡田玉翠に学ぶ)、長嶺華國、比嘉華山、兼城恵園、川平恵昌、渡嘉敷唯選、金城唯貞、大湾政正、神山元享、親泊英繁、玉城次郎、国吉真義(刑務所職員)
瑞雨・山口辰吉はその名が示すごとく1868年(明治元年/戊辰)10月21日に生まれた。辰は、十二支の中で唯一「実在しない生き物」で、これは、或る種のカリスマ性の要因となると云われている。
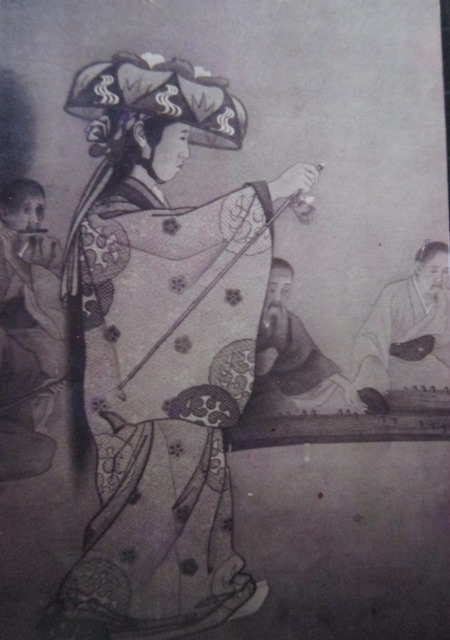

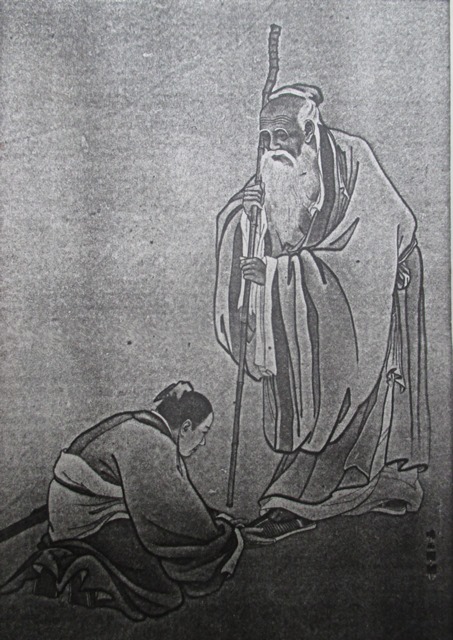
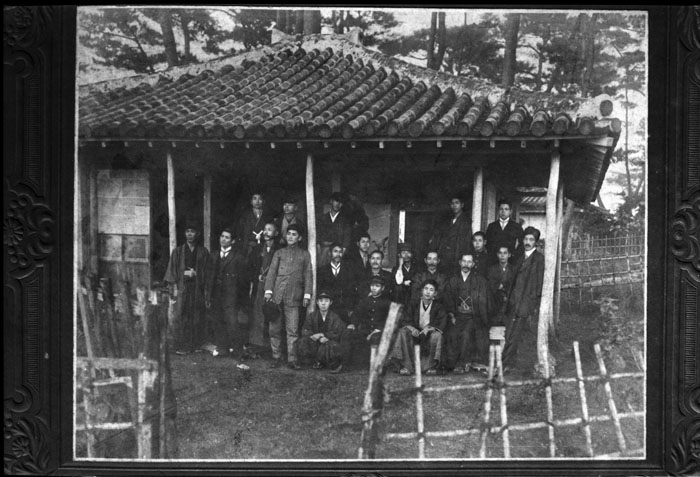
1912年2月ー太平洋画会の吉田博、石川寅治、中川八郎と丹青協会ー真ん中の柱の中列右が瑞雨。瑞雨の上が瑞雨の息子の山口清。左端が比嘉崋山、右へ一人おいて兼城昌興

1908年、沖縄最初の美術団体「丹青協会」が結成されその会長に瑞雨が就いた。11年、2年かがりの「程順則肖像図」の模写が完成。12年の1月、太平洋画会の吉田博、中川八郎、石川寅治が沖縄写生旅行のときの写真には瑞雨や丹青協会メンバーが写っている。
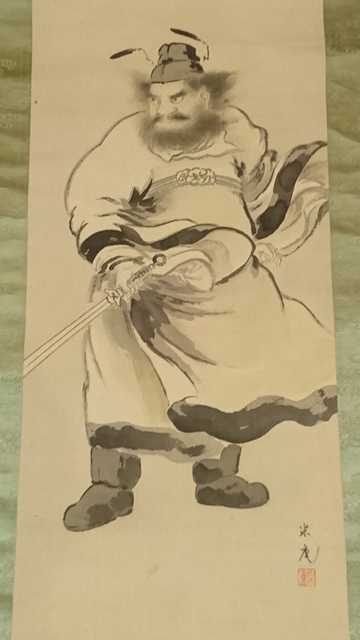
私は山口米庵のひ孫で、善丸と申します。 昨年 12月7日に父 順造が92歳で他界し、山口家のことは今私が記録を残さなければ子孫には皆目わからずじまいになりかねないと、初代、米庵について調べたところ、琉文21に沖縄時代の記録を見ることが出来ました。心より感謝申し上げます。山口家の墓は都営多磨霊園にあります。初代、米庵 瑞雨院米庵智堂居士。 以来代々が埋葬されています。 30年前に母が亡くなった時、墓には地下室が無く、お骨壷を直に埋めていましたが、すべてのお骨壷を掘りあげて一箇所に収納出来るように改修しました。その時、米庵の骨壷はすごく小さいものしか有りませんでした。 なお、家に残っている米庵の掛け軸の写真を添付いたします。

写真左から山口善丸氏、島袋和幸氏
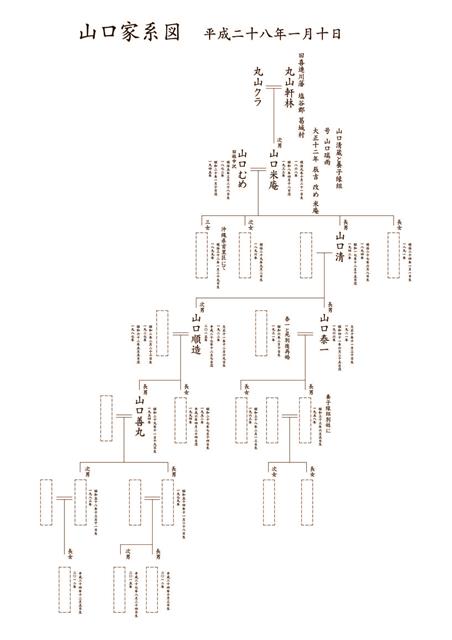

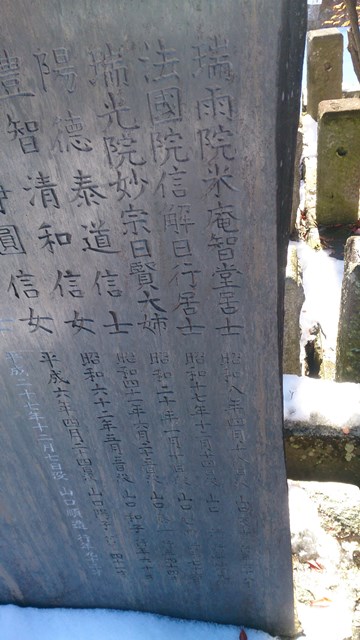
山口瑞雨次女 山口まさ(明治29年9月2日生まれ。大正9年6月21日 浅草にて海上晴①と婚姻)
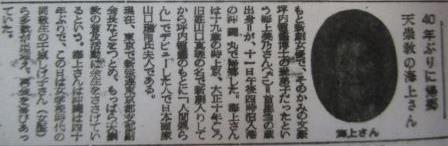
1959年10月12日『琉球新報』□40年ぶりに帰郷 天崇教の海上さんーもと新劇女優で、そのかみの文豪坪内逍遥博士の愛弟子だったという海上美乃さん(62)=首里当蔵出身=が、11日午後4時 泊入港の沖縄丸で帰郷した。海上さんは19歳の時上京、大正10年ごろ旧姓山口真瑳の名で新劇入りしてから坪内逍遥のもとに「人間親鸞」でデビューした人で日本画家山口瑞雨夫人(ママ)である。現在、東京で新宗連東京都支部副会長などをつとめ、もっぱら天崇教の普及活動に余生をささげているという。海上さんは沖縄は40年ぶりで、この日は女学校時代の同級生の千原繁子さん(女医)ら多数が出迎え、再会を喜びあっていた。→1933年5月『沖縄県立第一高等女学校同窓会』に1913年 第10回卒業生に林まさ 旧姓 山口 東京市中野/第12回卒業生に千原繁子 旧姓 渡嘉敷 那覇市上之蔵1ノ18千原医院。
①海上晴
1894年(明治27年)、東京府東京市浅草区(現在の東京都台東区浅草)に生まれる。旧制・早稲田実業学校(現在の早稲田大学系属早稲田実業学校高等部)を中途退学したが、早稲田大学の坪内逍遥に入門し、文学を学ぶ。島村抱月、沢田正二郎ら演劇人と親交を結び、新劇の世界に入る。「創生劇」を主宰、日比谷野外音楽堂で公演を行った。1920年(大正9年)、日活向島撮影所の革新運動に参加し、同撮影所第三部が製作した田中栄三監督の『朝日さす前』に主演する。以降、同部の消滅まで出演をつづけた。関東大震災以降の1925年(大正14年)、兵庫県西宮市の東亜キネマ甲陽撮影所で映画出演する。1928年(昭和3年)6月、加藤精一、佐々木積とともに帝国劇場専属俳優となる。
1936年(昭和11年)、お告げを受け、天崇教を創立する[1]。教祖としての名は「海上晴帆」である。第二次世界大戦後、1948年(昭和23年)に宗教法人登録を行う。1952年(昭和27年)、黒澤明監督の『生きる』で映画界に復帰、以降、東宝作品を中心に出演する。初期の岡本喜八監督作品の常連で、体格がよく貫禄のある役どころが多かった。→林幹 - Wikipedia
1905年4月『琉球教育』第106号「中頭郡女子研究会ー本年1月中頭郡に遊戯唱歌塗板画の講習会開会せし以来女子は遊戯唱歌に男子は塗板画に興味を起こし且つ教授上に大に必要を感じ引続き有志者の集会を企画し男子は首里山口瑞雨氏宅に女子は宜野湾間切普天間に毎月集合して研究怠らず・・・」
1910年4月6日『沖縄毎日新聞』「丹青協会批評会ー去る3日第10回の作品批評会を若狭町クラブに会するも日本画の山口瑞雨を筆頭として董園、比嘉華山、国吉沖山、義村竹斉、洋画の関屋敬治、親泊、渡嘉敷唯選、松島、山城、中村の面々・・・・」
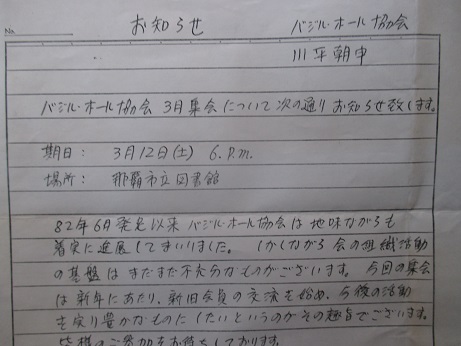
1982年6月、戦前から異国船に関心を持ってきた川平朝申や、国吉真哲、中今信、曽根信一ら数十人が集い、琉球航海記を中心とした沖縄の歴史・文化・人文の研究調査の発展をはかり、地域社会の思想・文化の向上に寄与することを目的に、会長に川平朝申、事務局に外間政彰で異国船琉球航海記研究会(通称バジル・ホール協会)が発足した。発会の記念講演は照屋善彦琉大教授で、会場にはぺルリ艦隊の乗組員の曾孫にあたるヨセフハンディー夫妻も参加した。川平会長の母と、西平守晴南島史学会大阪支部長夫人の母とは姉妹の関係で、大阪在住の新城栄徳も会員として末席をけがした。
私(新城栄徳)と川平朝申さんとの出会いは、1959年の『今日の琉球』誌上に連載されていた川平さんの「若き人々のための琉球歴史」を読んだことにさかのぼる。それから10年後。大阪の沖縄関係資料室に叔母さんを訪ねて川平さんが来室していた。夜、私が資料室に行くと、暑い熱いと下着姿の川平さんが「君が新城(あらぐすく)君か、西平(にしんだ)君から君のことを聞いているよ」と握手をしてきた。そして麦門冬に話がおよぶと「君は麦門冬の名前を知っているのか、それだけでも尊敬に値するよ」といって、太い万年筆で「故郷に生まれ故郷で育ち、今また異郷にありて故郷を想う心尊し」と書いてくれた。
1910(明治43)年9月15日、冨山房発行『學生』第一巻第六号 中村清二「琉球とナポレオン」
中村清二(女優の中村メイコは兄の孫にあたる)「チェンバレン氏は英国の使節を廣東に上陸させて待っている間に朝鮮と琉球を見物し、帰国の途次セントヘレナ島を訪れてナポレオンに会見し琉球の物語をしたとある。」と記している。
□東京大学明治文庫の原本で、1910(明治43)年9月15日、冨山房発行『學生』第一巻第六号:ナポレオン号に「琉球とナポレオン」中村清二(7頁)が掲載されていることが確認出来ました。 その記事の挿絵にはバジル・ホールの著作と同じ挿絵が使用されています。冒頭でバジル・ホール・チェンバレンの祖父としてバジル・ホールが紹介され、はじめの小見出しは「セントヘレナ上陸」。途中の小見出しに「武器なき国」とありました。(2016年7月28日 不二出版 小林淳子)
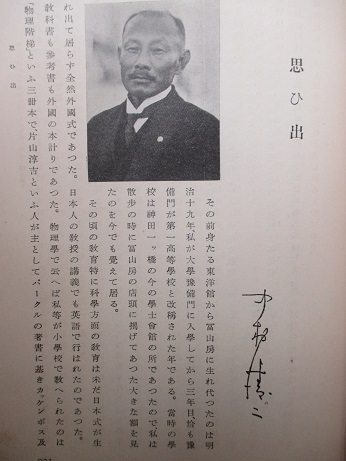
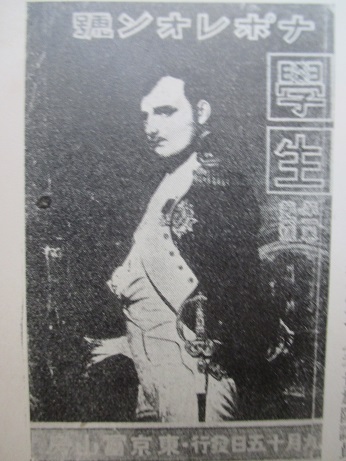
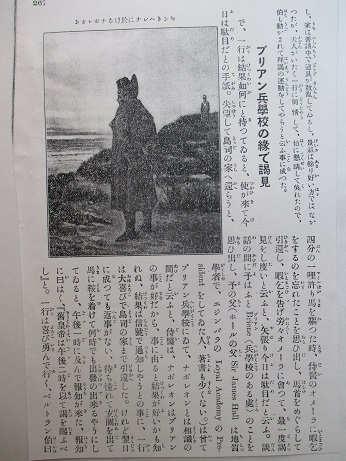
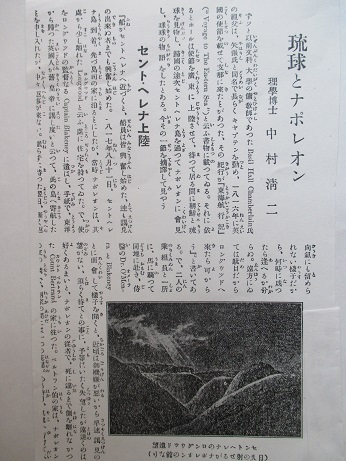
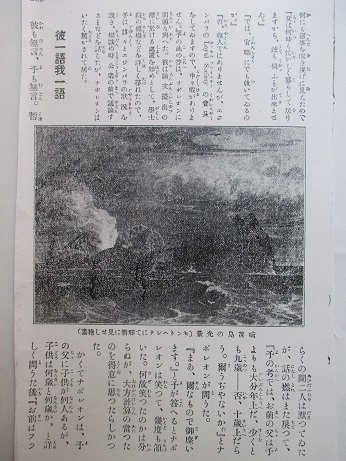
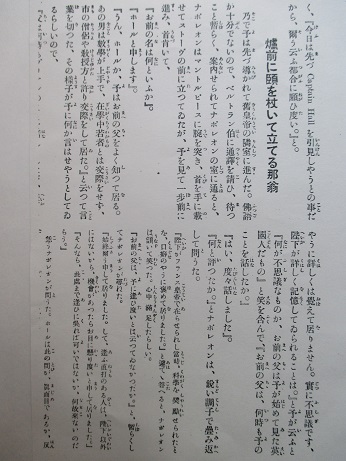
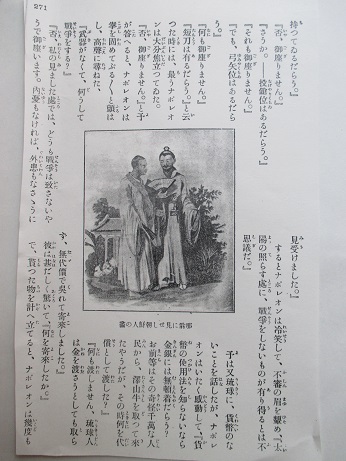
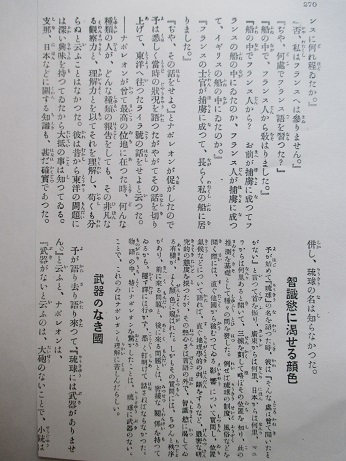
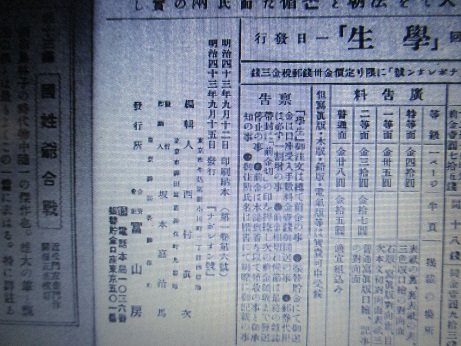
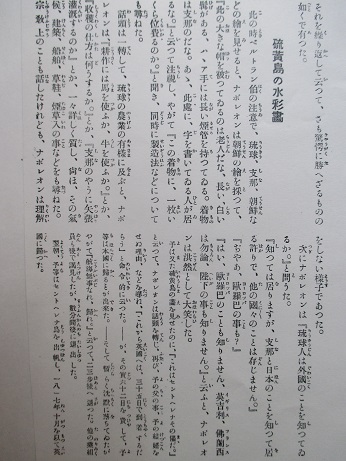
伊波普猷の弟・普成は1912年9月の『沖縄毎日新聞』に「ベージル・ホール 琉球探検記」連載、11月には「ビクトリヤの僧正 琉球訪問記」(クリフォードの名が出てくる)、1913年4月は「ぺルリ日記」、8月「チャールズ・ルブンウォース 琉球島」を連載している。
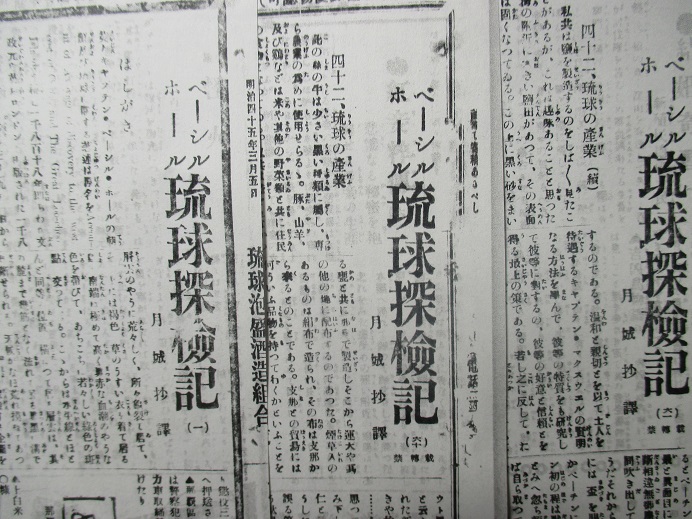
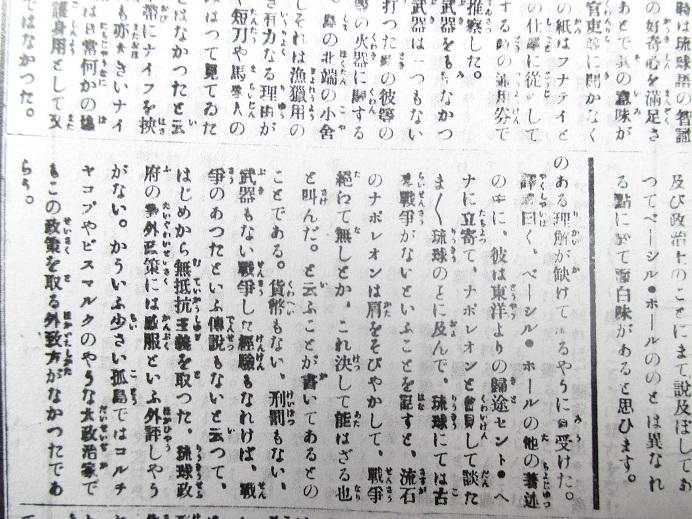
1912年11月8日『沖縄毎日新聞』「ベージル・ホール 琉球探検記」
○譯者曰く、ベージル・ホールの他の著述の中に、彼は東洋よりの帰途セント・ヘナに立ち寄って、ナポレオンと会見して談たまたま琉球のことに及んで、琉球にては古来戦争がないといふことを話すと、流石のナポレオンは肩をそびやかして、戦争絶えて無しとか、これ決して能はざる也と叫んだ。といふことが書いてあるとのことである。貨幣もない、刑罰もない、武器もない戦争した経験もなければ、戦争のあったといふ伝説もないと云って、はじめから無抵抗主義を取った。琉球政府の対外政策には感服といふ他評しやうがない。かういふ小さい孤島ではコルチャコブやビスマルクのやうな大政治家でもこの政策を取る外致し方がなかったであらう。
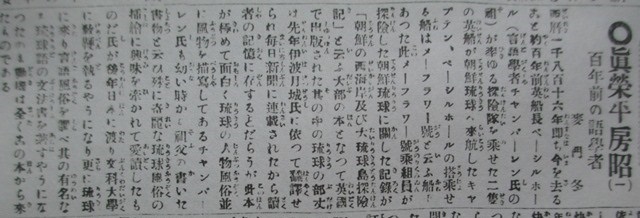
1915年4月9日『琉球新報』麦門冬「眞栄平房昭ー百年前の語学者」
1924年5月『沖縄教育』末吉麦門冬「百年前の英語通ー眞栄平房昭」
□西暦一千八百十六年、即ち今を去ること百八年前、英國の船長ベーシルホール(言語学者チャンバーレン氏の祖父)が率いる探見隊を乗せた二隻の英鑑が朝鮮から琉球へと回航した。キャンプテン、ベージルホールの塔乗した船はメーフラワー號と云ふのであった。此メ―フラワー號乗組員が探見した朝鮮琉球に関した記録が「朝鮮の西海岸及び大琉球探見記」と云ふ浩澣な本となって、英國で出版された。其の原本は沖縄図書館にも一部蔵されている。その琉球の部分だけは先年伊波月城氏に依って飜訳せられ沖縄毎日新聞に連載されたから、記憶された方もあろうかと思ふ。この本は極めて面白く琉球の風土文物が記述描写せられてあるので、言語学者のチャンバーレン氏も、幼い時から、殊に祖父さんがこしらへた本として飜閲愛翫したそうである。チャンバーレン氏が後年日本に渡り文科大学に教鞭を執るようになり、更にわが琉球に来り、言語風俗を調査し、其の有名な琉球語の文法書等を著すようになったのも、動機を溯ればこの本が与えた刺激からであったといふ。
扨て私が茲に紹介せんとする眞榮平房昭とは何人かと云ふに、ベージルホール、チャンバーレン氏の探見記に活躍している一人物メーデーラーのことである。メーフラワー號の乗組員中にヘンリー、ホップナーと云ふ青年学者がいた。この人が調べた琉球語の研究が探見記の巻末に載っているが、ホップナーはメーデーラー即ち眞榮平房昭の助力によりて、あれだけの語彙を蒐集したのである。其の時メーデーラーも又帳面と矢立とを携えて、頻りにホップナーに就いて英語を教わり、双方交換教授をしたといふことである。(以下略)
○1928年ー市河三喜編輯『岡倉先生記念論文集』に豊田實が「沖縄英学史稿」を寄せている。豊田は沖縄県の依頼で1928年3月22日から28日まで英語講習のため那覇に滞在した。そこで沖縄県立沖縄図書館長の真境名安興などの協力を得て沖縄英学史を調べたのが前出の沖縄英学史稿として結実した。中に末吉麦門冬の「百年前の英語通」も引用し真栄平房昭の家譜を書いている。(2011年11月)
豊田実 とよだ-みのる
1885-1972 大正-昭和時代の英語学者。
明治18年9月16日生まれ。青山学院教授などをへて,大正14年九州帝大教授となる。戦後,青山学院院長,同大初代学長。日本英学史学会初代会長。昭和47年11月22日死去。87歳。福岡県出身。東京帝大卒。著作に「日本英学史の研究」など。→コトバンク
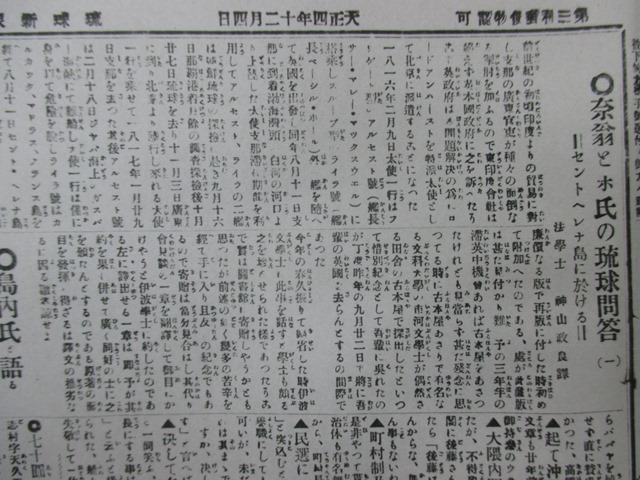
1915年12月4日 『琉球新報』神山政良 訳「奈翁とホ氏の琉球問答=セントヘレナ島に於ける=」(1)
12月13日 『琉球新報』神山政良 訳「奈翁とホ氏の琉球問答」(9)
12月14日 『琉球新報』金口木舌ーナポレオンは英の一船長を引見した時▲「卿は曾て尊父が予の事を話すのを聞かれた事があるか▲卿は曾て尊父が予に逢いたいと云うのを聞いたことがあるか▲と云うようなことを荐(しきり)に聴いて居る▲之が絶世の英雄ナポレオンの言葉である▲罪のない可愛い人間性が現れて居るではないか▲又彼が彼の少年時代を送ったブリアンの事なら如何に詰まらぬ事にも非情な興味を持って居た▲と云う事にも人間性の懐味が滲み出て居るではないか▲偶像化された英雄豪傑でも祭壇から引きずり下して見ると▲意外に無邪気な人間性の欠点や凡庸人と異らない人情味が見出される▲近世の芸術は一切の偶像を祭壇から引き下ろそうとして居る▲それは然うとナポレオンが琉球の地理的位置を聴いて▲琉球人の風習制度等が他国の干渉によって影響されたに相違ない▲と話したと云う事は其の炯眼に驚かざるを得ない▲事実我が琉球は他国の干渉に依って風習や制度に影響される處があった▲其處が又渾身活動慾制服慾に満たされたナポレオンが想像することも出来ない▲全然武器なき國として立って行かれた所以となったのだ

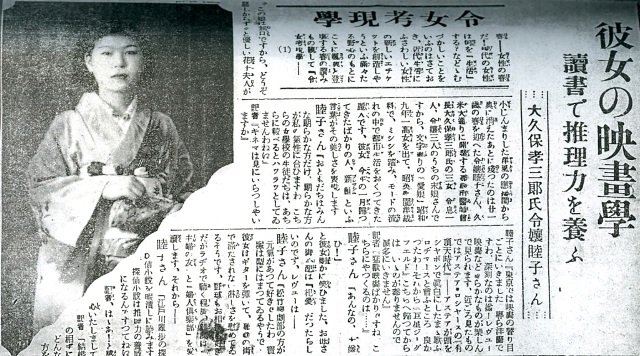
メソジスト教会、後列左が伊波普猷、右2人目が伊波普成、前列和服姿が大久保孝三郎医師、中央がシュワルツ宣教師/1938年『琉球新報』「令女考現学」
1931年12月『琉球新報』伊波普猷「ナポレオンと琉球」/1932年1月 『改造』伊波普猷「ナポレオンと琉球」
12/02: 沖縄県立沖縄図書館
私にとって、絵本は保育園や幼稚園を連想する。敗戦前の那覇市内の幼稚園をみる。1876年に東京に官立の「東京女子師範学校附属幼稚園」が設立されている。那覇では遅れて、1893年に天妃尋常高等小学校附属幼稚園が設立された。1907年4月、真教寺の田原法馨らが真教幼稚園を設立している。同年1月の『琉球新報』に森柳子が「愛花幼稚園生に就いて」を書いている。翌年11月の『琉球新報』には「森柳子主宰になれる那覇区内字久米安仙坂の善隣幼稚園は元愛花幼稚園の改称せしもの」とある。1930年に永田ツルが愛泉幼稚園、32年に那覇市が上山幼稚園を設立した。33年には八重山でヤエマ幼稚園が設立されている。
□→2004年1月 斎木喜美子『近代沖縄における児童文化・児童文学の研究』風間書房
沖縄県立沖縄図書館の初代館長は言うまでもなく伊波普猷であるが、厳密には嘱託館長で正式な館長になったのは12年後である。伊波の図書館には当時としては画期的な児童室があった。ここで、その背景をみてみる。1874年、新島襄がアメリカでの修行と勉学を終えて帰国。故郷の群馬県安中に一時帰郷した。そこでアメリカ文化やキリスト教の話を若者たちにした。その中に16歳の湯浅半月も居た。1875年11月、新島襄は山本覚馬、J・D・ディヴィスと協力して「同志社英学校を」を設立した。1877年、半月は同志社に入学。
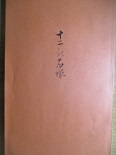




1885年10月 湯浅半月(本名吉郎)『十二の石塚』(一大長編叙事詩)湯浅吉郎
1885年に渡米しオハイオ州オペリン大学神学科やエール大学で学んだ。1891年、帰国し直ちに母校同志社の教授。1899年に平安教会の牧師。1901年に新設の京都帝大法学部講師となり大学附属図書館事務にも従事した。
1900年9月、伊波普猷は京都の第三高等学校に入学。01年夏に京都でコレラ流行、伊波は一時東京に避難したという。このころ極度の神経衰弱で、気を散らすため考古学会に入り宇治辺りまで出かけた。また西本願寺の仏教青年会主催の講義や平安女学園音楽講師だったオルドリッチ女史のバイブルクラスにも出入りした。伊波は03年7月に第三高等学校を卒業し9月、東京帝大文科大学に入学した。
1902年、湯浅半月(44歳)はアメリカへ図書館事業調査のため旅立った。アメリカではシカゴ大学図書館学校、オルバニー市の図書館学校で貸出の必要性と児童室の必要性を学んだ。1904年、半月は京都府立図書館長に就任。京都府は09年に岡崎公園内に工費15万円を投じ、図書館本館を完成(□→武田五一)。そこには日本最初の児童閲覧室が設けられた。また半月はM・デューイの「十進分類法」を取り入れ「和漢図書分類目録」(美術工芸編、歴史地誌編等10分類全16冊)を刊行した。このときの蔵書は現在、京都府立総合資料館にある。因みに京都府立図書館の一部と、奈良県立図書館( http://www.library.pref.nara.jp/index.html )の建物は移築され今も残っている。

京都府立図書館長
1906年、宮古の比嘉財定が第五高等学校を終え東京帝大法科大学に入学した。在学中、柳田國男に出会い、比嘉は柳田に「比嘉村の話」をする。比嘉は10年7月に東京帝大を卒業。農商務省勤務を経て1915年にアメリカ留学。17年にカリフォルニア州立スタリント病院で死去。
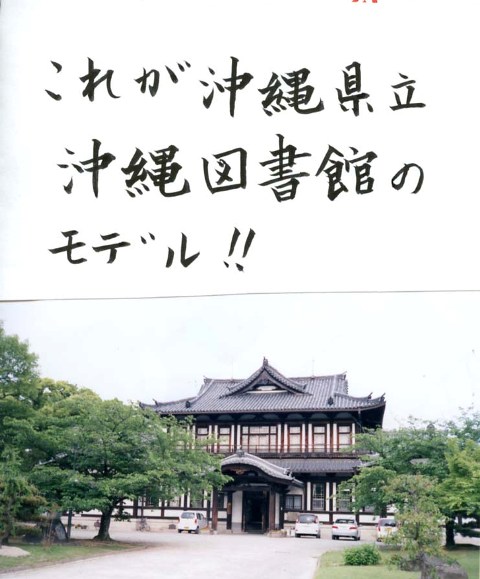
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。 1909年8月、伊波普猷は3週間にわたって鹿児島、山口、大阪、京都、奈良の図書館を視察する。そこで伊波は財政的規模を奈良図書館に求め、運営に関しては湯浅半月京都図書館長のアドバイスを受けた。

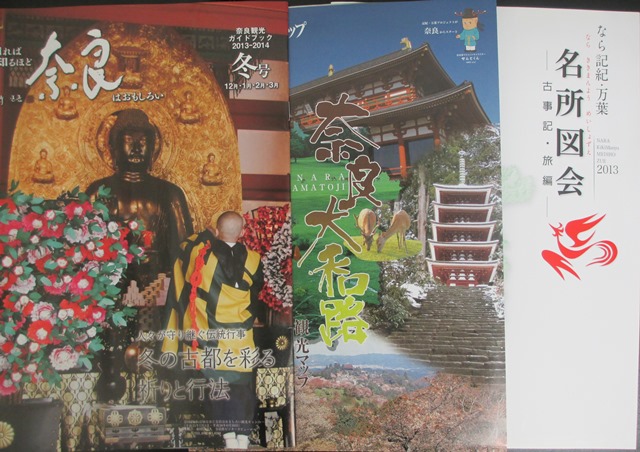
2014年1月8日~20日 沖縄県立図書館「奈良県立図書情報館交流展示」
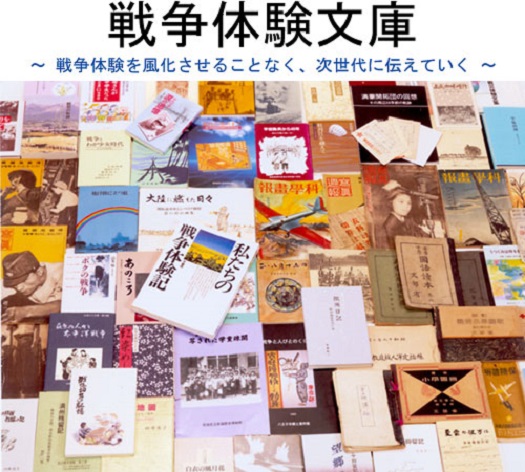
「戦争体験文庫」は、奈良県立図書情報館3Fの戦争体験文庫コーナーで公開。戦中戦後の体験に関する資料群で、全国の方々からの寄贈によって成り立っています。現在約5万点の資料を収集しています。 「戦争体験文庫」が当時の人々の思いや生活を知る手がかりになることを願っています。→奈良県立図書情報館
□1910年7月、伊波普猷は関西において比較的規模の狭小なる奈良県立図書館を視察し、湯浅京都図書館長のアドバイスを受けて沖縄県立沖縄図書館の図案を調製し其の筋へ提出したと、新聞に報じられた。私は、2008年5月8日に奈良県立図書情報館を初めて訪ねた。2Fで「Yahoo!」と「Google」の日本、アメリカでのサービス開始時期をみる。いずれも1990年代である。3Fで司書の人をわずらわして同図書情報館の前身で1909年に開館した奈良県立図書館の建物の写真を調べた。建物は戦後も図書館として使われたが、奈良県文化会館・図書館建設にともない。大和郡山城内に移築された。図書情報館の帰途、郡山城を訪ね、旧図書館の建物が今も健在で教育施設になっている。初期のころの奈良県立図書館長は奈良県内務部長が兼任していて、初代館長が小原新三、2代目が川越壮介であった。川越はのちに沖縄県知事となる。伊波普猷がアドバイスを受けた湯浅京都図書館長は湯浅吉郎(半月)といい明治・大正期の一流の文化人であったことは、1998年10月発行の京都府立『総合資料館だより』に詳しい。1909年4月に京都府立図書館の新館が岡崎に開館した。設計者は武田五一で湯浅館長は早くから児童閲覧室を設けていた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1910年5月、伊波の友人、八重山の岩崎卓爾が図書館に新渡戸稲造『英文武士道』など、漢那憲行が薄田泣菫『二十五弦』ほか、浦添朝忠は『資治通鑑』など700冊を寄贈。6月には末吉麦門冬が『俳句の研究』『蜀山人全集』などを寄贈している。かくして琉球学センターとも云うべき沖縄県立沖縄図書館は8月1日、那覇の南陽館で開館式を迎えた。折りしも8月22日は「日韓併合」があった。沖縄図書館の児童書は「中学世界、少女世界、少女之友、少年之友、日本少年、少年、少女、幼年之友、幼年画報」などがあった。
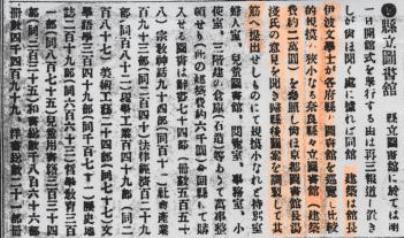
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
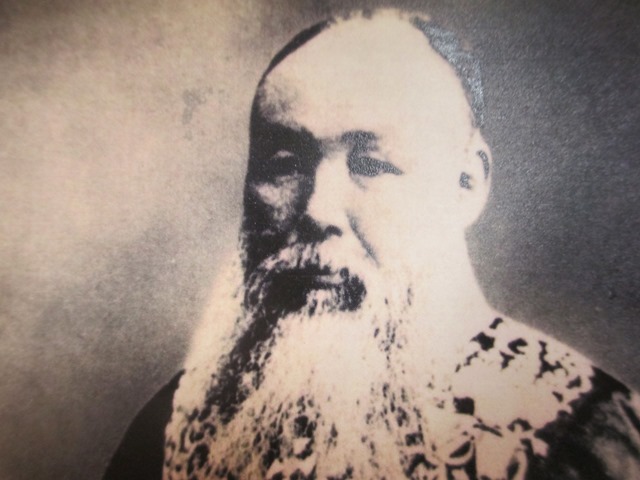
丸岡莞爾と「琉球史料」
丸岡莞爾1836-1898 幕末-明治時代の官僚,歌人。
天保(てんぽう)7年5月28日生まれ。鹿持雅澄(かもち-まさずみ)に国学をまなび,坂本竜馬(りょうま)らとまじわり脱藩して長崎にすむ。維新後,内務省社寺局長などをへて沖縄県知事,高知県知事となる。明治31年3月6日死去。63歳。土佐(高知県)出身。本姓は吉村。字(あざな)は山公。通称は三太,長俊。号は建山,掬月,蒼雨など。歌集に「蒼雨余滴」。(コトバンク)
1887年2月、森有礼文部大臣が来沖した。6月、尚家資本の広運社が設立され球陽丸を那覇-神戸間に運航させる。11月に伊藤博文総理大臣、大山巌陸軍大臣が軍艦で画家の山本芳翠、漢詩人の森槐南を同行して来沖した。1888年4月に大阪西区立売堀南通5丁目に琉球物産会社「丸一大阪支店」を設置する。9月18日に丸岡莞爾が沖縄県知事として赴任。10月には塙忠雄(塙保己一曾孫)を沖縄県属として赴任させる。丸岡知事在任中、琉球塗の監獄署にての改良、夫人による養蚕の奨励、歌人として護得久朝置、朝惟らと歌会での交友。そして「琉球史料」の編纂をさせた。1892年7月 沖縄県知事を解任され、故郷の高知県知事に転出。
<資料>1992年4月 南西印刷出版部『地域と文化』第70号 池宮正治「丸岡莞爾沖縄県知事の演説(速記録)」
1992年8月 南西印刷出版部『地域と文化』第72号 望月雅彦「丸岡莞爾関係資料にについて」
□丸岡桂 まるおか-かつら
1878-1919 明治-大正時代の歌人,謡曲研究家。
明治11年10月17日生まれ。丸岡莞爾(かんじ)の長男。歌誌「あけぼの」「莫告藻(なのりそ)」を創刊する。明治36年板倉屋書房を創立し,義弟松下大三郎と「国歌大観」を刊行。のち謡曲研究に専心,観世流改訂本刊行会を設立し,大正3年「謡曲界」を創刊した。大正8年2月12日死去。42歳。東京出身。号は月の桂のや,小桜など。→コトバンク
□丸岡明 まるおか-あきら
1907-1968 昭和時代の小説家。
明治40年6月29日生まれ。丸岡桂(かつら)の長男。昭和5年「三田文学」に「マダム・マルタンの涙」を発表。戦後「三田文学」復刊につくす。能楽の普及と外国への紹介にもつとめた。昭和43年8月24日死去。61歳。東京出身。慶大卒。著作に「生きものの記録」,「静かな影絵」(41年芸術選奨)など。→コトバンク

薬師寺:奈良市ホームページ
1971年11月ー琉球新報社、沖縄、那覇、名護の青年会議所と共催で文芸評論家・村岡剛と薬師寺管主・高田好胤を招き「文化講演会」開催。
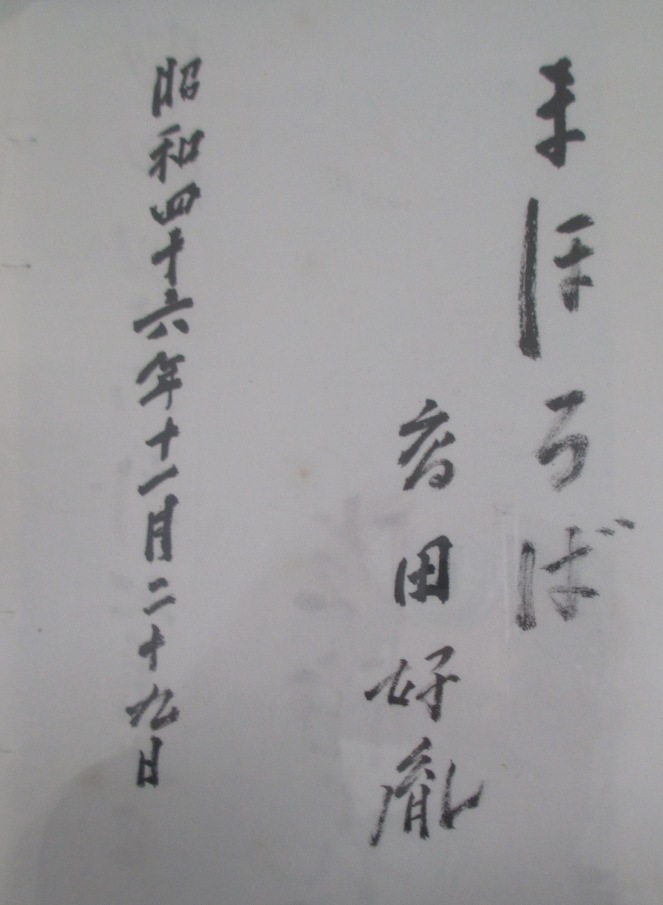

高田好胤と真喜志康徳
高田好胤 たかだ-こういん
1924-1998 昭和-平成時代の僧。
大正13年3月30日生まれ。昭和10年12歳で奈良の薬師寺にはいり,橋本凝胤(ぎょういん)に師事。戦後薬師寺参観者のガイド役をつとめ,修学旅行生らに説教をつづける。42年同寺管主,43年法相宗管長。金堂の再建を計画し,100万巻般若心経写経勧進をおこす。51年落慶,のち西塔も再建。平成10年6月22日死去。74歳。大阪出身。竜谷大卒。著作に「心」「愛に始まる」など。
【格言など】やたらに忙しいのはどんなものでしょう。「忙」という字は「心が亡びる」と書きます。→コトバンク


薬師如来、右が日光菩薩、左が月光菩薩
□→2004年1月 斎木喜美子『近代沖縄における児童文化・児童文学の研究』風間書房
沖縄県立沖縄図書館の初代館長は言うまでもなく伊波普猷であるが、厳密には嘱託館長で正式な館長になったのは12年後である。伊波の図書館には当時としては画期的な児童室があった。ここで、その背景をみてみる。1874年、新島襄がアメリカでの修行と勉学を終えて帰国。故郷の群馬県安中に一時帰郷した。そこでアメリカ文化やキリスト教の話を若者たちにした。その中に16歳の湯浅半月も居た。1875年11月、新島襄は山本覚馬、J・D・ディヴィスと協力して「同志社英学校を」を設立した。1877年、半月は同志社に入学。
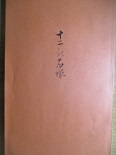




1885年10月 湯浅半月(本名吉郎)『十二の石塚』(一大長編叙事詩)湯浅吉郎
1885年に渡米しオハイオ州オペリン大学神学科やエール大学で学んだ。1891年、帰国し直ちに母校同志社の教授。1899年に平安教会の牧師。1901年に新設の京都帝大法学部講師となり大学附属図書館事務にも従事した。
1900年9月、伊波普猷は京都の第三高等学校に入学。01年夏に京都でコレラ流行、伊波は一時東京に避難したという。このころ極度の神経衰弱で、気を散らすため考古学会に入り宇治辺りまで出かけた。また西本願寺の仏教青年会主催の講義や平安女学園音楽講師だったオルドリッチ女史のバイブルクラスにも出入りした。伊波は03年7月に第三高等学校を卒業し9月、東京帝大文科大学に入学した。
1902年、湯浅半月(44歳)はアメリカへ図書館事業調査のため旅立った。アメリカではシカゴ大学図書館学校、オルバニー市の図書館学校で貸出の必要性と児童室の必要性を学んだ。1904年、半月は京都府立図書館長に就任。京都府は09年に岡崎公園内に工費15万円を投じ、図書館本館を完成(□→武田五一)。そこには日本最初の児童閲覧室が設けられた。また半月はM・デューイの「十進分類法」を取り入れ「和漢図書分類目録」(美術工芸編、歴史地誌編等10分類全16冊)を刊行した。このときの蔵書は現在、京都府立総合資料館にある。因みに京都府立図書館の一部と、奈良県立図書館( http://www.library.pref.nara.jp/index.html )の建物は移築され今も残っている。

京都府立図書館長
1906年、宮古の比嘉財定が第五高等学校を終え東京帝大法科大学に入学した。在学中、柳田國男に出会い、比嘉は柳田に「比嘉村の話」をする。比嘉は10年7月に東京帝大を卒業。農商務省勤務を経て1915年にアメリカ留学。17年にカリフォルニア州立スタリント病院で死去。
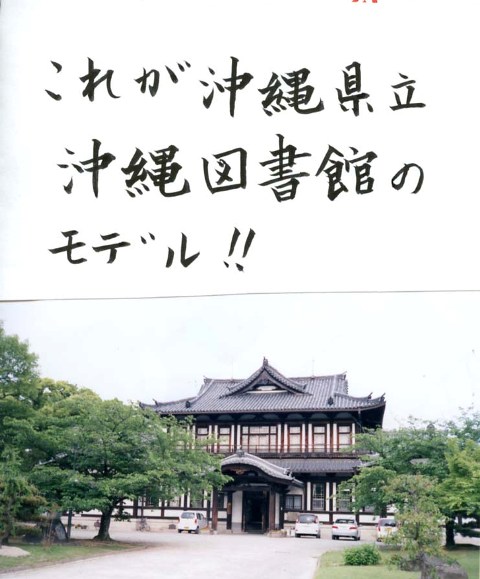
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。 1909年8月、伊波普猷は3週間にわたって鹿児島、山口、大阪、京都、奈良の図書館を視察する。そこで伊波は財政的規模を奈良図書館に求め、運営に関しては湯浅半月京都図書館長のアドバイスを受けた。

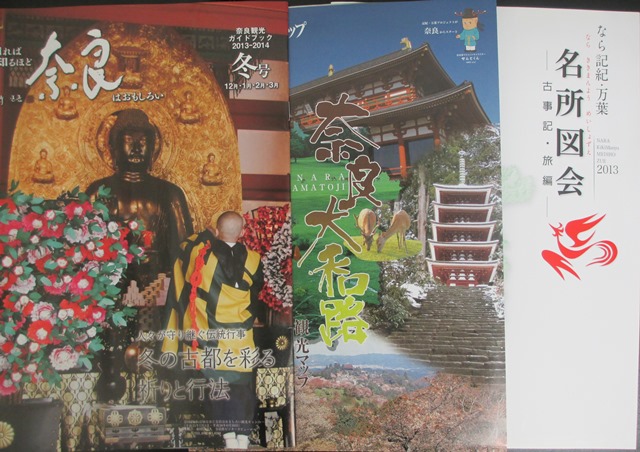
2014年1月8日~20日 沖縄県立図書館「奈良県立図書情報館交流展示」
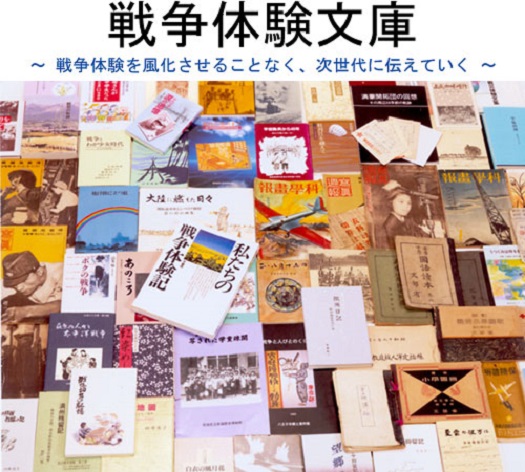
「戦争体験文庫」は、奈良県立図書情報館3Fの戦争体験文庫コーナーで公開。戦中戦後の体験に関する資料群で、全国の方々からの寄贈によって成り立っています。現在約5万点の資料を収集しています。 「戦争体験文庫」が当時の人々の思いや生活を知る手がかりになることを願っています。→奈良県立図書情報館
□1910年7月、伊波普猷は関西において比較的規模の狭小なる奈良県立図書館を視察し、湯浅京都図書館長のアドバイスを受けて沖縄県立沖縄図書館の図案を調製し其の筋へ提出したと、新聞に報じられた。私は、2008年5月8日に奈良県立図書情報館を初めて訪ねた。2Fで「Yahoo!」と「Google」の日本、アメリカでのサービス開始時期をみる。いずれも1990年代である。3Fで司書の人をわずらわして同図書情報館の前身で1909年に開館した奈良県立図書館の建物の写真を調べた。建物は戦後も図書館として使われたが、奈良県文化会館・図書館建設にともない。大和郡山城内に移築された。図書情報館の帰途、郡山城を訪ね、旧図書館の建物が今も健在で教育施設になっている。初期のころの奈良県立図書館長は奈良県内務部長が兼任していて、初代館長が小原新三、2代目が川越壮介であった。川越はのちに沖縄県知事となる。伊波普猷がアドバイスを受けた湯浅京都図書館長は湯浅吉郎(半月)といい明治・大正期の一流の文化人であったことは、1998年10月発行の京都府立『総合資料館だより』に詳しい。1909年4月に京都府立図書館の新館が岡崎に開館した。設計者は武田五一で湯浅館長は早くから児童閲覧室を設けていた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1910年5月、伊波の友人、八重山の岩崎卓爾が図書館に新渡戸稲造『英文武士道』など、漢那憲行が薄田泣菫『二十五弦』ほか、浦添朝忠は『資治通鑑』など700冊を寄贈。6月には末吉麦門冬が『俳句の研究』『蜀山人全集』などを寄贈している。かくして琉球学センターとも云うべき沖縄県立沖縄図書館は8月1日、那覇の南陽館で開館式を迎えた。折りしも8月22日は「日韓併合」があった。沖縄図書館の児童書は「中学世界、少女世界、少女之友、少年之友、日本少年、少年、少女、幼年之友、幼年画報」などがあった。
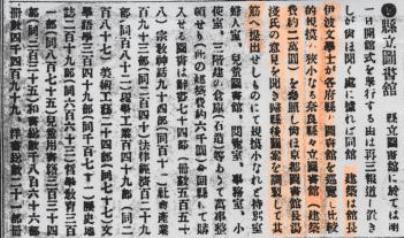
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
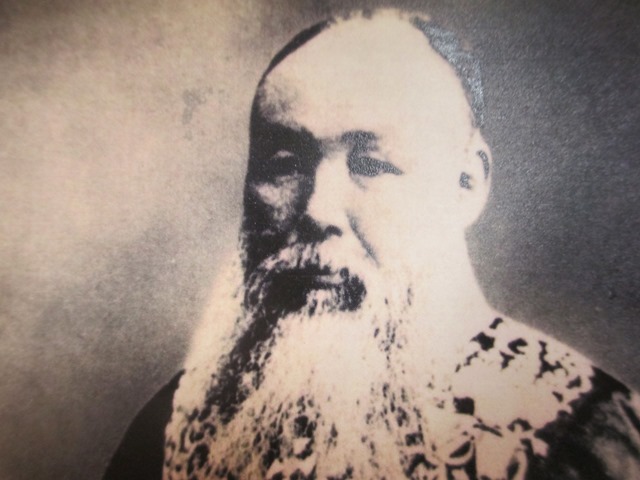
丸岡莞爾と「琉球史料」
丸岡莞爾1836-1898 幕末-明治時代の官僚,歌人。
天保(てんぽう)7年5月28日生まれ。鹿持雅澄(かもち-まさずみ)に国学をまなび,坂本竜馬(りょうま)らとまじわり脱藩して長崎にすむ。維新後,内務省社寺局長などをへて沖縄県知事,高知県知事となる。明治31年3月6日死去。63歳。土佐(高知県)出身。本姓は吉村。字(あざな)は山公。通称は三太,長俊。号は建山,掬月,蒼雨など。歌集に「蒼雨余滴」。(コトバンク)
1887年2月、森有礼文部大臣が来沖した。6月、尚家資本の広運社が設立され球陽丸を那覇-神戸間に運航させる。11月に伊藤博文総理大臣、大山巌陸軍大臣が軍艦で画家の山本芳翠、漢詩人の森槐南を同行して来沖した。1888年4月に大阪西区立売堀南通5丁目に琉球物産会社「丸一大阪支店」を設置する。9月18日に丸岡莞爾が沖縄県知事として赴任。10月には塙忠雄(塙保己一曾孫)を沖縄県属として赴任させる。丸岡知事在任中、琉球塗の監獄署にての改良、夫人による養蚕の奨励、歌人として護得久朝置、朝惟らと歌会での交友。そして「琉球史料」の編纂をさせた。1892年7月 沖縄県知事を解任され、故郷の高知県知事に転出。
<資料>1992年4月 南西印刷出版部『地域と文化』第70号 池宮正治「丸岡莞爾沖縄県知事の演説(速記録)」
1992年8月 南西印刷出版部『地域と文化』第72号 望月雅彦「丸岡莞爾関係資料にについて」
□丸岡桂 まるおか-かつら
1878-1919 明治-大正時代の歌人,謡曲研究家。
明治11年10月17日生まれ。丸岡莞爾(かんじ)の長男。歌誌「あけぼの」「莫告藻(なのりそ)」を創刊する。明治36年板倉屋書房を創立し,義弟松下大三郎と「国歌大観」を刊行。のち謡曲研究に専心,観世流改訂本刊行会を設立し,大正3年「謡曲界」を創刊した。大正8年2月12日死去。42歳。東京出身。号は月の桂のや,小桜など。→コトバンク
□丸岡明 まるおか-あきら
1907-1968 昭和時代の小説家。
明治40年6月29日生まれ。丸岡桂(かつら)の長男。昭和5年「三田文学」に「マダム・マルタンの涙」を発表。戦後「三田文学」復刊につくす。能楽の普及と外国への紹介にもつとめた。昭和43年8月24日死去。61歳。東京出身。慶大卒。著作に「生きものの記録」,「静かな影絵」(41年芸術選奨)など。→コトバンク

薬師寺:奈良市ホームページ
1971年11月ー琉球新報社、沖縄、那覇、名護の青年会議所と共催で文芸評論家・村岡剛と薬師寺管主・高田好胤を招き「文化講演会」開催。
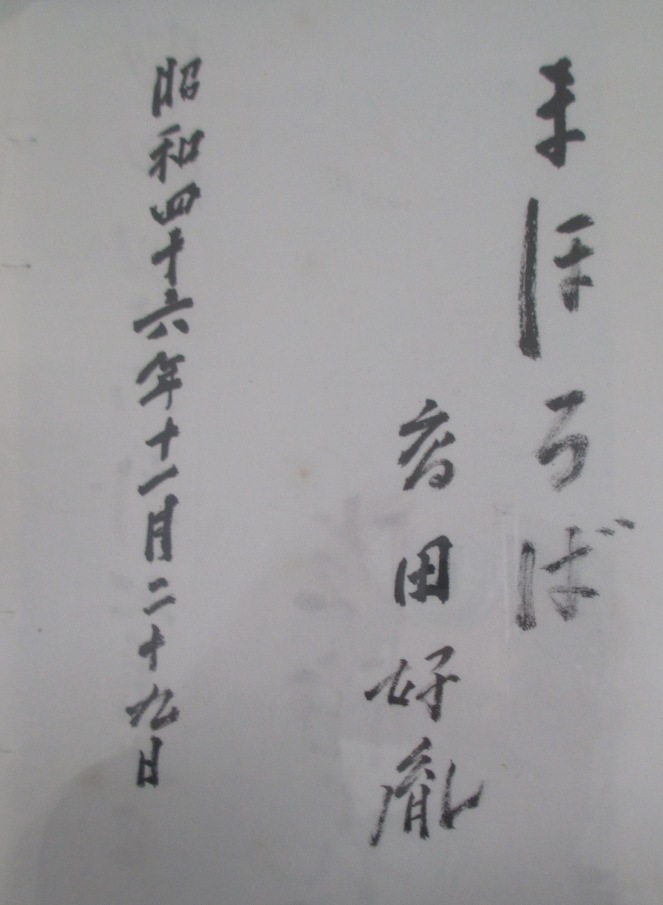

高田好胤と真喜志康徳
高田好胤 たかだ-こういん
1924-1998 昭和-平成時代の僧。
大正13年3月30日生まれ。昭和10年12歳で奈良の薬師寺にはいり,橋本凝胤(ぎょういん)に師事。戦後薬師寺参観者のガイド役をつとめ,修学旅行生らに説教をつづける。42年同寺管主,43年法相宗管長。金堂の再建を計画し,100万巻般若心経写経勧進をおこす。51年落慶,のち西塔も再建。平成10年6月22日死去。74歳。大阪出身。竜谷大卒。著作に「心」「愛に始まる」など。
【格言など】やたらに忙しいのはどんなものでしょう。「忙」という字は「心が亡びる」と書きます。→コトバンク


薬師如来、右が日光菩薩、左が月光菩薩
12/20: 1972年11月『別冊経済評論』「日本のアウトサイダー」
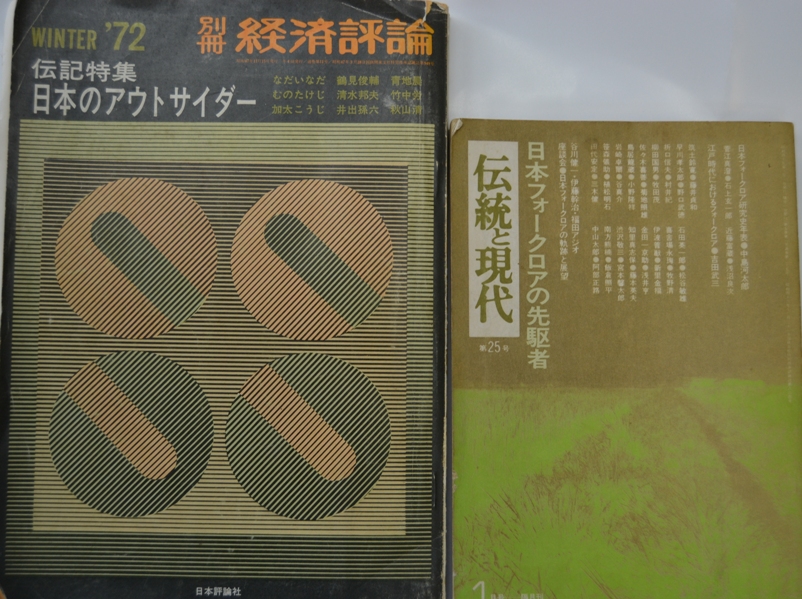
1972年11月『別冊経済評論』「日本のアウトサイダー」
桐生悠々(むのたけじ)/宮武外骨(青地晨)/伊藤晴雨(石子順造)/高橋鐵(竹中労)/沢田例外(森長英三郎)/安田徳太郎(安田一郎)/田中正造(田村紀雄)/菊池貫平(井出孫六)/山口武秀(いいだもも)/北浦千太郎(しまねきよし)/古田大次郎(小松隆二)/平塚らいてぅ(柴田道子)/高群逸枝(河野信子)/長谷川テル(澤地久枝)/宮崎滔天(上村希美雄)/橘撲(髙橋徹)/西田税(松本健一)/謝花昇(大田昌秀)/南方熊楠(飯倉照平)/出口王仁三郎(小沢信男)/山岸巳代蔵(水津彦雄)/尾崎放哉(清水邦夫)/添田唖蝉坊(荒瀬豊)/辻潤(朝比奈誼)/稲垣足穂(折目博子)/天龍(秋山清)/淡谷のり子(加太こうじ)/谷川康太郎(猪野健治)
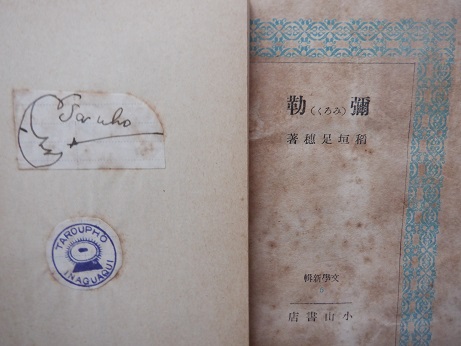
タルホ
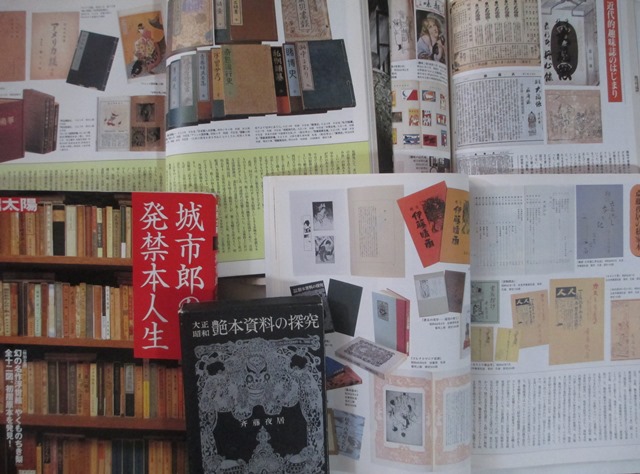
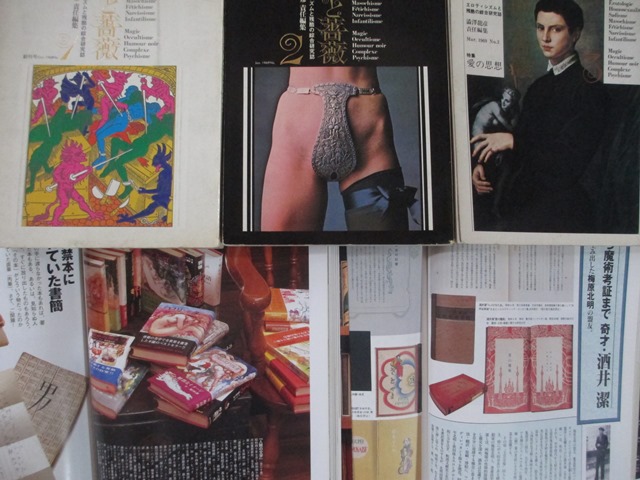
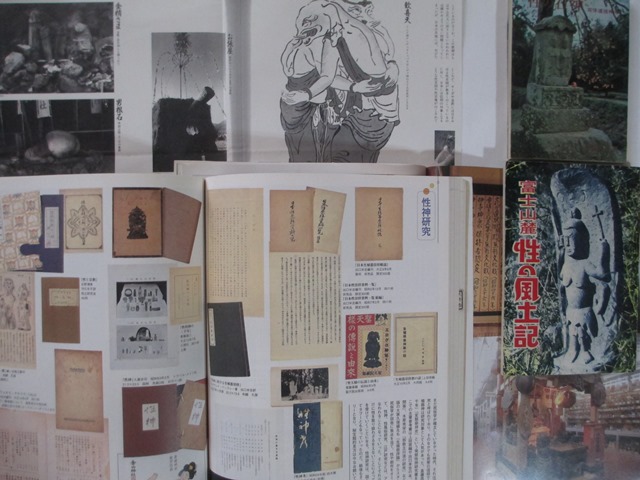
「発禁本」資料
現代筆禍文献大年表
明治28年3月 沖縄県私立教育会雑誌(沖縄県 安井宗明)
明治33年10月 沖縄青年会会報(渡久地政瑚)
大正5年 沖縄民報6月15日第677号
大正10年2月 不穏印刷物2枚「沖縄庶民会創立委員発行」
大正13年11月 沖縄タイムス「11月13日14日亘る難波大助に係る不敬事件判決言渡に関する記事」
大正14年5月 地方行政5月号 神山宗勲「燃え立つ心」
1978年、桃源社発行の酒井潔『愛の魔術』に澁澤龍彦が解説で「酒井潔は堅苦しい学者ではなく、何よりもまず、面白く語って読者を楽しませようとする、根っからのエンターティナーがあった。それは本書をお読みになれば、誰にでも十分に納得のいくことであろう。明治の南方熊楠ほどのスケールの大きさは望むべくもないが、彼自身も南方に傾倒していたように、その方向の雑学精神の系統をひく人物であったことは間違いあるまい」と書いている。
麦門冬ー熊楠ー岩田準一ー乱歩
1931年6月には竹久夢二が元北米の邦人新聞記者・翁久充の企画で、サンフランシスコに入り、1年余にわたり米国に滞在し、ロスを中心に展示会や在米見聞記「I CAME I SAW」の題で新聞連載、スケッチ旅行などをしている。アワビ漁で成功した小谷源之助はポイント・ロボスの海岸に来客用の別荘を建て芸術家や文人、政治家らを宿泊させていた。夢二研究家の鶴谷壽(神戸女子大教授)が夢二と宮城与徳(画家・ゾルゲ事件に連座)が小谷家の方と一緒に写っている写真を発表している。夢二は翁と新聞社のストのことで喧嘩別れをし、気の合う若い与徳としばらく一緒に生活しながら絵を描いていたようである。夢二は翌年の10月にはヨーロッパへと足をのばし、欧州各地を渡り歩き、ドイツの邦人グループと一緒になってユダヤ人救済運動に関わっている。彼は平民社の幸徳秋水とも交流し、医師の安田徳太郎とのつながりもある。彼の反戦のコマ絵をみると、夢二の美人画はもの悲しい憂いにみち、放浪とロマンを追い続けた夢二の後ろ姿に重なる。(大城良治)
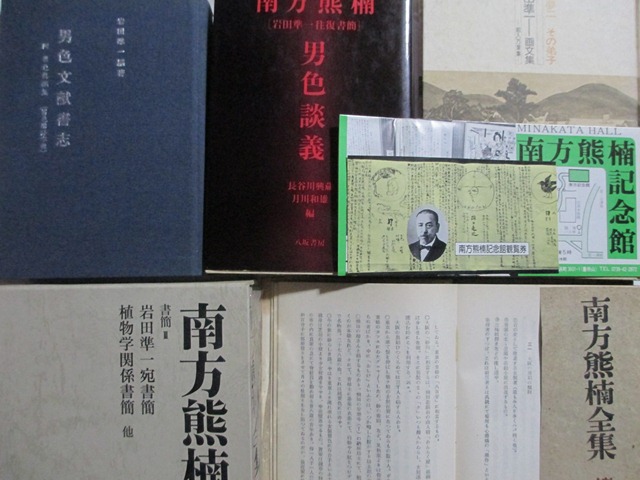
夢二の弟子に岩田準一が居る。□岩田準一 いわた-じゅんいち 1900-1945 昭和時代前期の挿絵画家,民俗研究家。明治33年3月19日生まれ。中学時代から竹久夢二と親交をもつ。江戸川乱歩の「パノラマ島奇譚」「鏡地獄」などに挿絵をかく。郷里三重県志摩地方の民俗伝承の研究や,男色の研究でも知られ,南方熊楠(みなかた-くまぐす)との往復書簡がある。昭和20年2月14日死去。46歳。文化学院卒。旧姓は宮瀬。著作に「志摩のはしりかね」など。(コトバンク)□→「岩田準一と乱歩・夢二館(鳥羽みなとまち文学館」(.所在地〒517-0011三重県鳥羽市鳥羽2丁目 交通アクセス鳥羽駅から徒歩で10分 ..お問合わせ0599-25-2751) .
今年3月15日にJR西日本「おおさか東線」が開業した。5月26日、息子の家(布施)から近い真新しい長瀬駅から乗る。久宝寺駅で乗り換え王子経由で9時前に法隆寺に着く。法隆寺は日本仏教の始祖といわれている聖徳太子を祀っている。日本最初の世界文化遺産でもある。法隆寺には和歌山有田の修学旅行生がバス3台で見学に来ていた。このときは夢殿とその周辺を見て帰った。那覇に帰る前日の6月6日、あけみと一緒に改めて法隆寺見学、金堂は改修工事中で上御堂で御本尊の金銅釈迦三尊像を拝観。1998年に完成した大宝蔵院には百済観音像玉虫厨子などが安置されている。出てすぐの所の大きな蘇鉄の前で、あけみを立たせて記念写真。法輪寺、法起寺の三重塔も見学した。
辛口批評家の谷沢永一氏著『聖徳太子はいなかった』新潮新書によると、柳田国男は聖徳太子が虚構であることを知っていた。古事記や日本書紀について書くのは柳田は慎重であったという。柳田が自分の見るところ信じられるところにしたがって記紀をいじれば、なにしろあの時代においてのことであるから、かならずヤケドするとわかっていた。とくに民俗学は理論をおしすすめてゆくと、当時やかましかった国体の問題につきあたる。折口信夫」も微妙に避けた。現代の学者がおのれの創見であるといなないているテーマのいくつかは、知られていたけど書けなかった、という。俳人・末吉麦門冬も南方熊楠宛の書簡で「小生も嘗て『古事記を読む』の題にて古代人の恋愛問題を論じヨタを飛ばし過ぎた為か、これを載せた新聞の編集人が、検事局に呼出されて叱られた」と書いている。

契沖の出家した妙法寺(今里)
息子の家からほど近いところに司馬遼太郎記念館と、契沖の出家した妙法寺(今里)がある。契中は水戸光圀と出会い『万葉代匠記』をまとめた。本居宣長は契中を「古學の祖」と位置付けた。今里駅から大阪市内に入ると天王寺公園がある。琉球処分のとき警官で来琉したのが池上四郎、大阪の礎を築いた関一市長は著名だが、その関を呼び寄せたのが池上6代目大阪市長である。池上の銅像が天王寺公園にあるが池上の曾孫が沖縄に何かと縁がある秋篠宮紀子さん。北上し中之島に出る。その昔、豊臣秀吉が大阪城築城のときに全国から巨石が集められた。川に落ちたのも多数にのぼる。中之島公会堂近くに豊国神社があった。神社は大阪城内に移された。その跡に木村長門守重成表忠碑がある。碑は元沖縄県令で大阪府知事を退いていた西村捨三と、大阪北の侠客小林佐兵衛が発起し安治川口に沈んでいた築城用の巨石を引きあげ建立したもの。毛馬公園には那覇港築港にも関わった工学士・沖野忠雄の胸像がある。

木邨長門守重成表忠碑(彦根西邨捨三譔 日下部東作書)
【日下部鳴鶴】書家。近江彦根の人。名は東作,字は子暘。彦根藩士日下部三郎右衛門の養子となったが,桜田門の変で父は殉死した。1869年(明治2)東京に出て太政官大書記となったが,後年は書をもって身をたてた。はじめ巻菱湖(まきりようこ)の書風を学ぶが,80年に来朝した楊守敬の影響を受けて六朝書道を研究,のち清国にも遊学して見聞を広め,深い学識と高古な人柄とによって彼の書名は一世を風靡した。現代書道発展の先駆者として,その功績は高く評価されている。→コトバンク
池上四郎
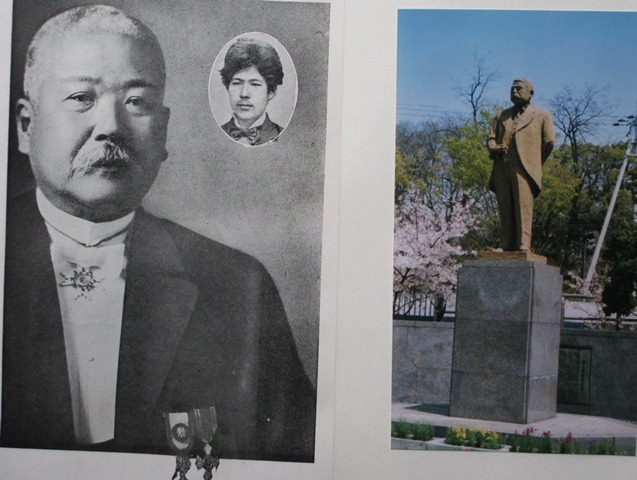
□池上四郎ー1877年、池上は警視局一等巡査として採用され、間もなく警部として石川県に赴任した。その後、富山県などの警察署長、京都府警部などを歴任し、1898年からは千葉県警察部長、兵庫県警察部長を務めた。1900年には大阪府警察部長となり、その後13年間に渡って大阪治安の元締めとして活躍した。その清廉で、自ら現場に立ち責任を果たす働きぶりと冷静な判断力は、多くの市民からの信頼を集めた。1913年、市政浄化のため、池上は嘱望されて大阪市長に就任した。財政再建を進める一方、都市計画事業や電気・水道事業、さらには大阪港の建設などの都市基盤を整備し、近代都市への脱皮を図った。御堂筋を拡張し大阪のメインストリートとする計画は池上の市長時代に立案され、続く関一市長時代に実現を見た。また、市庁舎の新築、博物館や図書館などの教育施設や病院の整備など、社会福祉の充実にも注力した。池上は1915年に天王寺動物園を開園させ、1919年に全国初の児童相談所・公共託児所を開設した。1923年には大阪電燈株式会社を買収し、電力事業を市営化した。また1923年9月に発生した関東大震災では、いち早く大阪港から支援物資を東京に送り、被災者の救済を行った。(ウィキメディア)
1879年3月、松田道之琉球処分官が、後藤敬臣ら内務官僚42人、警部巡査160人余(中に天王寺公園に銅像がある後の大阪市長・池上四郎も居た)、熊本鎮台分遣隊400人をともない来琉し琉球藩を解体、沖縄県を設置した。この時、内務省で琉球処分事務を担当したのが西村捨三であった
1918年、富山県魚津で火蓋を切った米騒動は、瞬く間に全国を席巻し、軍隊の動員を待たねば沈静化せず、ために時の寺内内閣は総辞職した。大阪では、その米騒動の収拾のために米廉売資金が集められていた。その残金を府・市で折半したのであるが、府(林市蔵知事)では発足したばかりの方面委員制度のために利用した。市(池上四郎市長ー秋篠宮妃紀子曽祖父)では「中産階級以下の娯楽機関として市民館創設資金」27万7千円弱が市に指定寄附されたのを受けて、1921年6月20日、天神橋筋六丁目(天六)に日本初の公立セツルメント「市立市民館」を開設したのである。これが、1982年12月に閉館を迎えるまで62年間にわたって、大阪ばかりでなく全国の社会福祉界に歴史的シンボルとして存在した「大阪市立北市民館」(1926年の天王寺市民館開設とともに改称)の始まりであった。
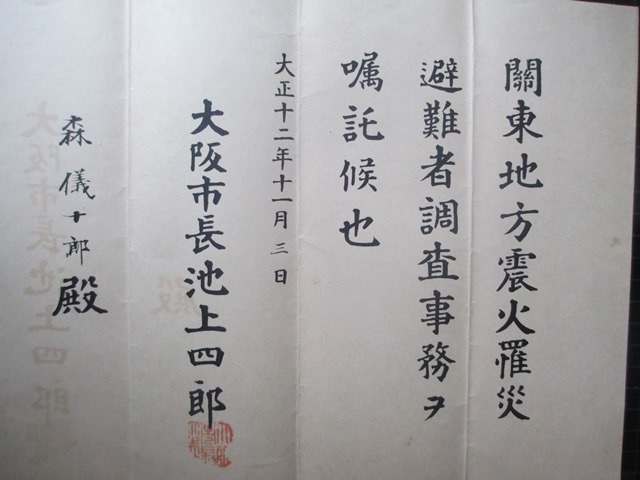
□小林佐兵衛 生年: 文政12 (1829) 没年: 大正6.8.20 (1917)
明治期の侠客。大坂生まれ。通称は北の赤万(明石屋万吉)。年少から侠気を発揮し,幕末には大坂の警備に当たった一柳 対馬守に請われて捕吏頭を務めながら,禁門の変(1864)で敗れた長州藩士の逃亡を助けたりする。維新後に大阪の消防が請負制度になると,渡辺昇知事に頼まれ北の大組頭取として活躍した。米相場で成した資産を投じ,小林授産所を営み,多数の貧民に内職を教え,子どもは小学校へ通わせた。明治44(1911)年9月,米相場の高騰で苦しむ貧民のため,取引所へ乗り込んで相場を崩す。貧民700人の無縁墓を高野山に建立。浪速侠客の典型として,司馬遼太郎の小説『俄』のモデルになる。 (コトバンク)

2023-3 ライブハウスの一角に「あいち沖縄文庫」誕生 800冊、渡久地政司さん、阪井芳貴さんらが寄贈
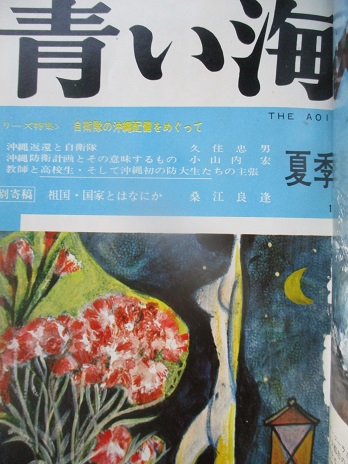
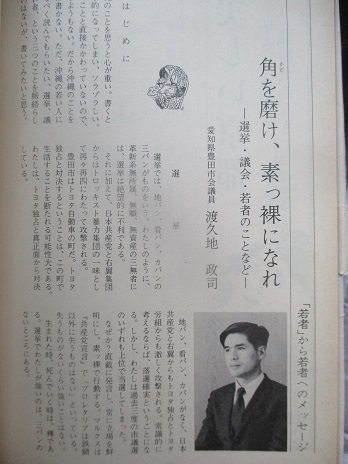
1971年8月 雑誌『青い海』4号 渡久地政司「角を磨け、素っ裸になれー選挙・議会・若者のことなどー」
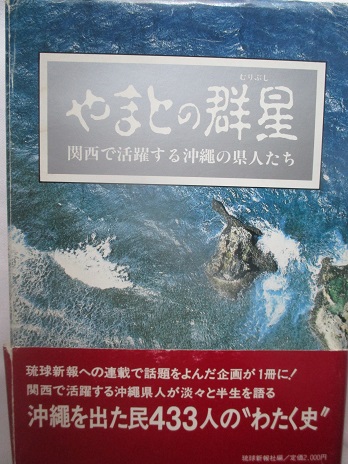
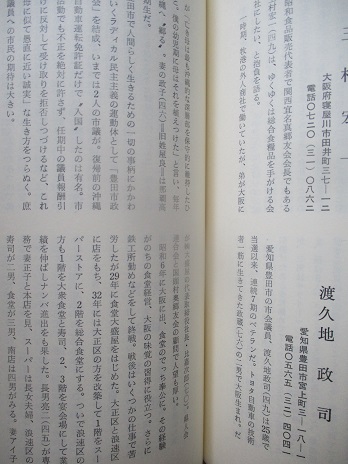
1987年8月 『やまとの群星/関西で活躍する沖縄の県人たち』琉球新報社 「渡久地政司」→本書は元『青い海』編集発行人で作家の津野創一が編集協力した。
愛知の中の沖縄 事柄覚 渡久地政司作成


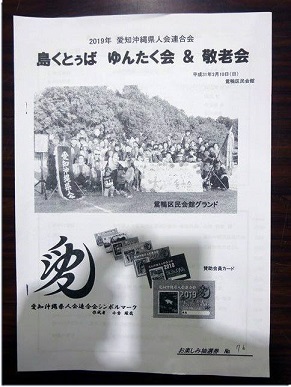

愛知沖縄県人会連合会総会・ゆんたく会・敬老会■ 2019年3月10日 豊田市鴛鴨町・鴛鴨公民館
最長老の屋嘉比信子さん(95)と比嘉俊太郎さん(80)屋嘉比さんは名古屋市今池で沖縄料理「糸満」を30~50年前に経営されていた方です。比嘉さんは、那覇高→名古屋工業大学→愛知工業大学名誉教授→愛知沖縄県人会連合会会長をなさった方です。お二人ともお元気でした。
1986年3月、琉球新報の松島弘明記者から、名古屋、三重のウチナーンチュの取材で大阪に来るという葉書(中城城跡)をもらった。後に琉球新報大阪支社に行き、私も旧知の人たちに会いたく名古屋に同行した。名古屋の県事務所の職員は大阪の県事務所でなじみのある人たちばかりであったので名古屋、三重のウチナーンチュ情報はすぐに得られた。
松島記者は取材過程で、「愛知県沖縄県人会会員名簿」「でいごの会会員名簿」(1974年10月)、「三重県沖縄県人会名簿」(1974年)、「沖縄県名古屋経営者会名簿」(1985年)などを入手した。麦門冬・末吉安恭の甥の佐渡山安正、佐渡山安治さん兄弟、粟国の末吉和一郎さんの取材には同行した。大濱皓氏は病気で会えなかった。
2010年1月31日、沖縄文化の杜で仲村顕さんから愛知の沖縄の話を聞いた。豊橋市に田島利三郎、犬山市には久志富佐子の墓があるという(後日、墓の写真も見た)。
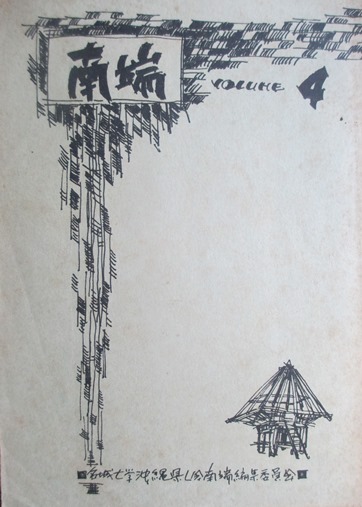
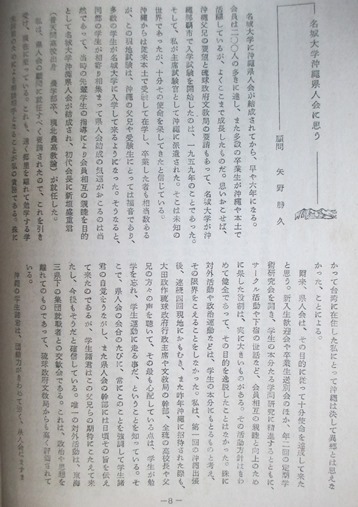
1965年7月 名城大学沖縄県人会『南端』(責任者・糸数哲夫)
糸数哲夫
昭和36年ー那覇高校卒。昭和44年ー名城大学大学院法学研究科修、商学修士、法学修士。昭和44年ー名古屋在加茂会事務所入所。昭和50年ー那覇市にて税理士事務所開業→現在は沖縄県宜野湾市字我如古。
大阪・沖縄関係資料室で『阿姓家譜』(阿姓南風原按司守忠 7世西平親雲上守安4男)の原本を見たことがある。資料室主宰の西平守晴氏が実兄から譲られたものである。複製本が那覇市歴史博物館にある。『氏集』を見ると、阿氏には前川、渡名喜、西平、小濱、渡嘉敷、宮平、瀬良垣、伊舎堂、與儀、喜瀬、山元、安和、佐久田、眞謝、江田、金城、照屋の諸家がある。
名古屋の渡久地政司(とぐち まさしー1937(昭和12)年6月2日、大阪市で生れる。豊田市で育つ。73歳、第3の人生のスタート。体と思考を「解す」だけでなく鍛える。)氏のブログに氏の調査で「○ 太田守松 父渡名喜守重、母なべの長男として沖縄県那覇市東町1丁目20番地で明治35年(1902)生まれる。泉崎小学校、沖縄1中卒、神戸高等商業学校卒。滋賀県立彦根商業学校教諭(大正14年4月)。昭和3年短歌会『国民文学』に入社・植松寿樹に師事。以後、短歌運動。昭和22年3月、日本キリスト教団彦根教会で洗礼。1947年(昭和22年10月)、渡名喜姓を先祖が使用していた太田姓に改名。昭和23年、彦根市立西中学校校長。昭和27年、彦根YWCA創立理事長。昭和34年、井伊大老開国百年祭奉賛会事務局次長。昭和38年、原水爆禁止彦根市協議会会長。昭和45年1月、脳溢血で逝去(67)。
○ 太田菊子 父豊見山安健、母オト(1882年生まれ)の長女として 1905年(明治38)沖縄県那覇市で生まれる。沖縄県立第1高等女学校卒業1921年(大正10)、東京山脇高等女学校卒業1924年(大正13)。大正14年12月、渡名喜守松と結婚。平成5年(1993)逝去(88)・1962年(昭和37年2月)。長年同居の母オト逝去(80歳)。」と太田守松と夫人が紹介されている。守松氏も阿氏である。


2019年3月5日 寒緋桜 満開■沖縄・名護市の農事試験場をルーツにする寒緋桜が満開となりました。場所は宮上公園東側とその後方。3月5日、青空をもピンクにしかねないくらいの勢い、通行中の人々は「まぁ奇麗」の歓声をあげていました。
「渡久地政司ブログ」(略記)2005年7月28日
■ 愛知の中の沖縄 事柄覚 ■
● 名古屋市東区徳川町にある徳川美術館には、琉球王国の文化財が多く収蔵されている。…徳川美術館に20点の琉球楽器、むかし御座楽(うざがく)に使われた楽器が保存
…、寛政8(1796)年に江戸上がりの使者から贈られたという記録が残って…出自がはっきりしているのは、日本中で徳川美術館の楽器だけ…。
大野道雄「徳川美術館の琉球楽器」から抜粋。
● 琉球王国賀慶使・恩謝使(琉球国使江戸上がり)が1610年から1872年までの間、18回おこなわれている。上がり、下がりを入れると約34回、愛知の土地を通過している。
1610(慶長15)年の場合、上がり…8月2日美濃大垣泊、3日尾張清州・成興寺泊、5日岡崎泊、6日吉田(豊橋)泊。下り…9月22日木曽福島泊、24日美濃路落合泊、27日岐阜本誓寺泊…であった。
佐渡山安治(詳細は後記)の調査によれば、寛延(1749)年の江戸上がりの時に殉死した「麻氏渡嘉敷親雲上真厳玄性居士之墓」(古塚達朗「江戸上りの足跡」96-4-2沖縄タイムスでは墓は行方不明とある。しかし、佐渡山安治資料「寛延2年の墓碑」76-3-28沖縄タイムスでは、所在地を発見、と写真入りの記事がある。)と天保3(1832)年に殉死した富山親雲上の墳墓が名古屋市緑区鳴海の瑞泉寺にある。佐渡山安治資料昭和54-12-14沖縄タイムスには、…11月4日、26年ぶりで待望の琉球行列を名古屋に迎える段になって「琉球人通行朝7ツ(午前4時)より本町通京町其外通りに提灯をだし賑合、此日薩摩五ツ過(午前8時)頃御通行、琉球人の行列に先立って、稲葉宿から棺桶が一つ、ひっそりと運ばれて…」。
● 明治26(1893)年9月1日から10日ま で名古屋市で沖縄芝居の興行が行われている。御園座の近くにあった千歳座(広小路南桑名町)。出し物は女花笠踊、上りの口説、下りの口説、女団扇踊、国頭(クンジャン)さばくいなど…、全部ウチナーグチで演じ、客の入りはよくなかったようで、入場料の値引きをしている。明治30(1897)年6月13日、再び名古屋を訪れ、南伏見町の音羽座で公演している。 大野道雄資料から抜粋。
08/11: 朝鮮史と末吉麦門冬
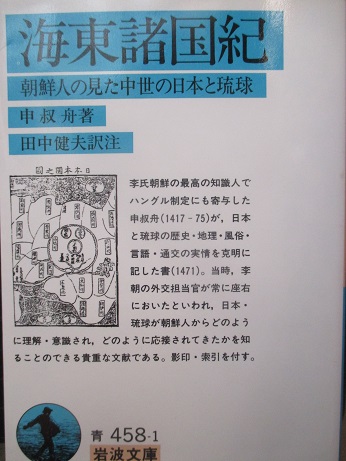
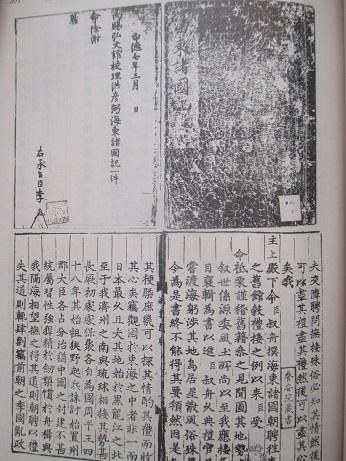
田中健夫訳注 『海東諸国紀 朝鮮人の見た中世の日本と琉球』 岩波文庫、1991年
海東諸国紀』(かいとうしょこくき, 朝鮮語: 해동제국기)は、李氏朝鮮領議政(宰相)申叔舟(しん しゅくしゅう、シン・スクチュ)が日本国と琉球国について記述した漢文書籍の歴史書。1471年(成宗2年)刊行された。 これに1501年(燕山君7年)、琉球語の対訳集である「語音翻訳」が付け加えられ現在の体裁となった。1443年(世宗25年)朝鮮通信使書状官として日本に赴いた後、成宗の命を受けて作成したもので、日本の皇室や国王(武家政権の最高権力者)、地名、国情、交聘往来の沿革、使臣館待遇接待の節目などを記録している。「語音翻訳」は1500年(燕山君6年)に来訪した琉球使節から、宣慰使成希顔が聞き書きし、翌年に兵曹判書李季仝の進言で付け加えられた。→ウィキ
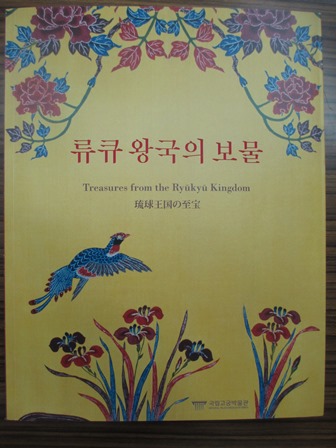
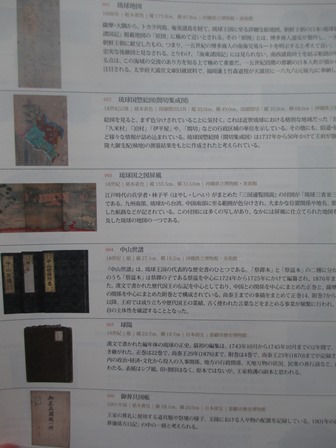
2014年12月9日~韓国・ソウルの国立古宮博物館で「琉球王国の至宝」展
2014年12月9日『沖縄タイムス』琉球王が着用した国宝の「玉冠(たまのおかんむり)」など、琉球国に関する資料約200点を一堂に集めた「琉球王国の至宝」展が9日、韓国・ソウルの国立古宮博物館で開幕する。来年2月8日まで、東アジアの中で独自の歴史と文化を築いた琉球国を、韓国の人々に紹介する。 展示資料は那覇市歴史博物館、県立博物館・美術館、浦添市美術館、美ら島財団(首里城公園)、東京国立博物館などが貸し出している。王族の衣装や当時の風景を描いた絵、高い技術を伝える漆器など第1級の資料が並び、琉球国の文化を伝える。
〇1992年にオープンした国立古宮博物館は、朝鮮時代の宮中で使われていた貴重な物品を文化財として保存、展示しているところです。景福宮、昌徳宮、昌慶宮、宗廟などに分散し埋もれていたこれらの文化財約20,000点あまりを所蔵しています。
1913年5月 『沖縄毎日新聞』襄哉(末吉安恭)譯「朝鮮小説 龍宮の宴」
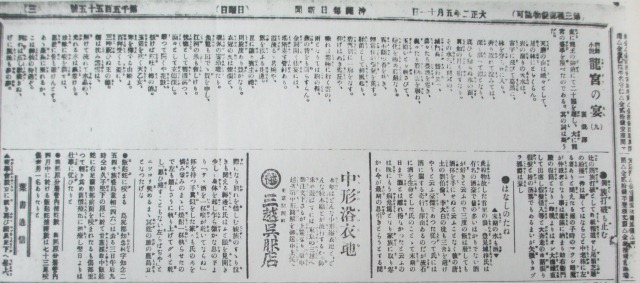
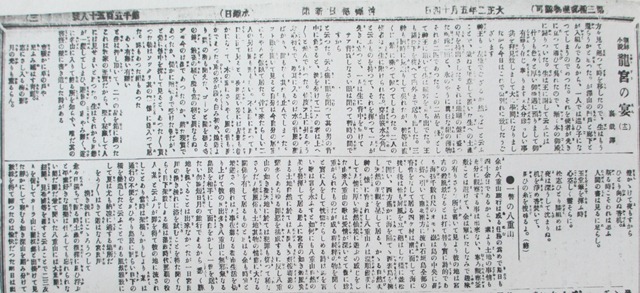
松都に天磨山と云ふ山がある。高く天に沖りてグッと聳へ立った山の姿が厳かなので天磨山の稱も成程と思はせる。この山の中に一つの池がある。周囲は窄いけれど深さが底の知れぬ池で、恰度瓢箪ののやうな形をしてるので瓢淵と云ふ名が利た。
■「金鰲新話」 朝鮮時代初期に政治家であり文学者であった金時習によって書かれた漢文文語体の朝鮮最初の小説です。《萬福寺樗蒲記》《李生窺牆傳》《醉遊浮碧亭記》《龍宮赴宴録》《南炎浮洲志》の5編で構成されています。後世の研究者に依れば元々はそれ以上に書かれていたと推測されていますが、残された資料が少なく定かではありません。また、この作品がその後に書かれた小説に大きな影響を与えたと言われています。ぜひ皆さんもイージー文庫の連載『金鰲新話(クモシナ)』をお楽しみください
王からの招待
松都(高麗時代の都=開城)には天磨山と呼ばれる山がある。その山の高さが天に届く程で、その険しく秀麗である事からその様な名前が付いた。山の中に大きな滝があったが、滝の名を*朴淵(パギョン)と言った。滝つぼの広さはそれ程広くは無かったが、深さは如何程か分からないほどであり、水が落ちてくる滝の高さはとても高かった。この朴淵瀑布(パギョンポクポ)の景色が非常に美しく、地方から松都に来た人々は必ずこの地を訪れて見物して行くの常だった。また、昔からこの滝つぼには神聖な存在が居るとの言い伝えがあり、朝廷では毎年の名節の折に牛を供えて祭祀を執り行っていた。 *朴淵瀑布:高さ37m、幅1.5mの開城にある滝で、金剛山の九龍瀑布、雪岳山の大勝瀑布 と併せて朝鮮三大名瀑に数えられる。
高麗の時代の話である。韓氏の姓を持つ書生が居たが、若い時から書に優れていることで朝廷にも知られ称賛を受けていた。ある日、韓生(ハンセング)は自分の部屋で一日過ごしていると、官吏の正装をした二人の男が天から降りてきて庭にひざまずいた。「朴淵の神龍さまがお呼びで御座います。」韓生は驚きの余り顔色が変わった。「神と人の間は遮られているのに、如何して行き交う事ができるのですか?まして神龍様の居られる水府は水の奥深くにあり、滝の水が激しく落ちるのに如何して行く事ができましょうか?」二人が言った。「門の外に駿馬を準備致しました。どうか遠慮なさらずにお使い下さい。」二人は身体を曲げつつ韓生の袖を引いて門の外に連れ出した。すると外には馬が一頭用意されていたが、金で出来た鞍と玉と絹で作られた手綱で仕立てられており馬には翼が付いてた。その傍には赤い頭巾で額を隠した絹の服を着た10余名の侍従が立っていた。侍従は韓生が馬にまたがるのを助けると、一隊の前に立って先導し、女官と楽隊が後に続いた。また、先の二人も互いに手を取り合って続いた。馬が空中に舞い上がると、その下に見えるのは立ち込めた煙と雲だけであり、他には何も見る事が出来なかった。やがて韓生は龍宮門に到着した。馬から下りると門番たちが蟹、海老、亀の鎧を着て杖を持って立っていたが、その目がとても大きかった。彼らは韓生を見ると皆こぞって頭を下げてお辞儀し用意された席まで案内して休息を勧めた。予め到着を待っていた様であった。彼を案内して来た二人がいち早く中に入って到着を伝えると、すぐに青い服を着た二人の童子が恭しく出迎えて挨拶すると先導を代わった。韓生は先導に従いゆっくりと歩いて宮殿に向った。韓生が門の中に入ると龍王が*切雲冠をかぶり剣を差したまま、手に竹簡を持って階(きざはし)まで降りて迎えた。龍王は韓生を誘い殿閣に上がると座る様に勧めたが、それは水晶宮の中にある白玉の椅子であった。 *切雲冠:雲を衝くほどに高くそびえ立った冠
末吉麥門冬が最初に朝鮮史にふれたのは1915年6月22日『琉球新報』末吉麦門冬「朝鮮史に見えたる古琉球」(1)からである。
1915年6月22日『琉球新報』末吉麦門冬「朝鮮史に見えたる古琉球」(1)
□松下見林の『異称日本伝』の例に倣った訳でもないが、記者は年来琉球史の記実が詳細を欠き、漠として雲を掴むような観あるを、常に憾みとしていた。其の原因は吾々の祖先が文字に暗い上に、筆不精と来てるので、有る事実も材料も使い得ず、官命を帯びて不性無性、筆を執って偶々物したのが、僅かに球陽、中山世譜位のもので其れも憖じいに廻らぬ筆の陳文漢文だから要を得ぬ所が多いのである。其れは先ず正史の方だが沖縄には元来野乗随筆と云った物が無い。正史の缼を補うような材料が得られない。歴史家困らせである。
目下県の事業として真境名笑古氏が満幅の精神を傾けて、材料蒐集に従事して居らるるが、氏も常に語って委しからず、録して汎ねからぬ史籍に憾みを抱き是ではならぬと本邦の史籍は無論支那朝鮮の史料まで眼を通さねばならぬと云って望洋の歎を発している。幸いに氏が不撓の努力と燃犀の史眼は、沙礫の中から珠玉を拾うような苦心で新材料が一つ一つ机の上に転がって来る。其の愉快は又学者ならでは味わえぬことだろう。此の新材料提供の泉の一つが朝鮮の古書である。流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の國ではある。蔚然たる古記録には東洋各國の史料が束になって這いっている。一たび其の堆土の中に熊手を入るれば、敕々雑々として葉山の秋の落葉を掻くが如きものがある。記者も眠気醒ましに熊手代わりの雑筆を揮いて高麗山の落葉を掻いて荒れたる史田の肥料にでもと思い立ちぬ。
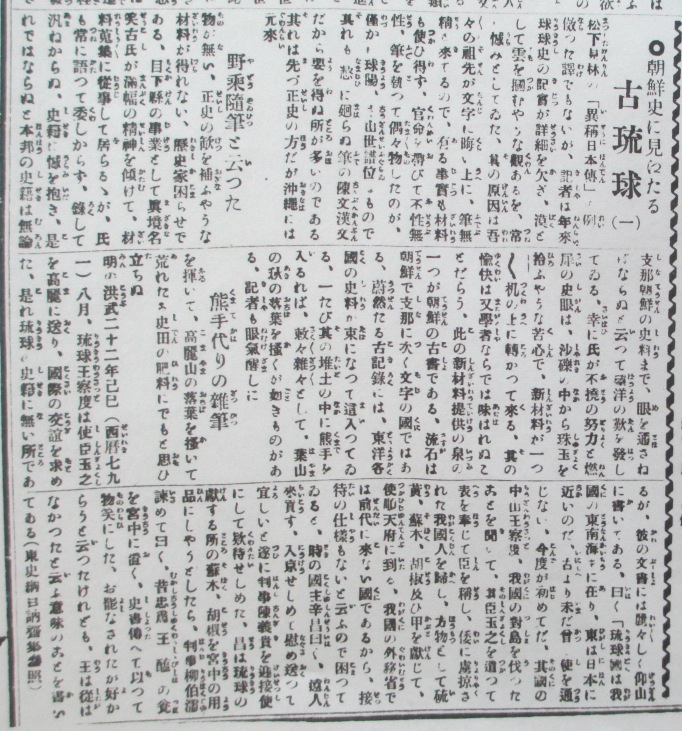
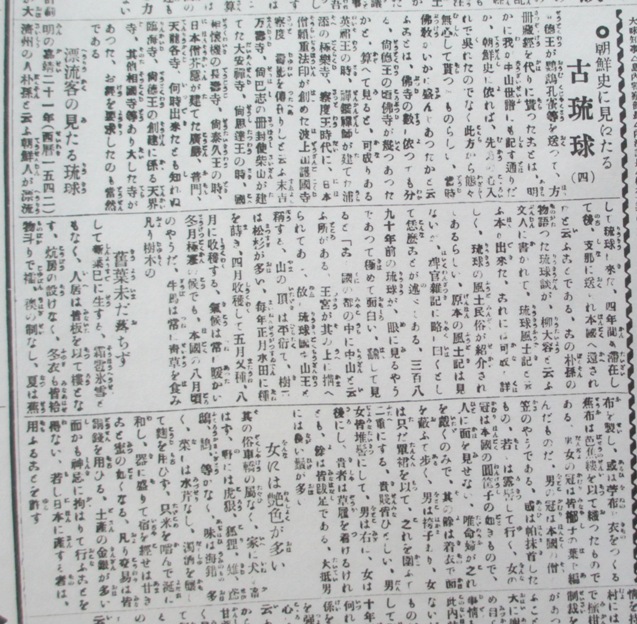
麦門冬が引用した文献資料
○りゅうひぎょてんか【竜飛御天歌】 朝鮮の李朝建国叙事詩。鄭麟趾らの撰。1447年刊,木版本。10巻,125章から成る。初章1聯,終章3聯以外は2聯で,対になったハングル歌,そして漢詩訳が続く。前聯は中国の故事,後聯は朝鮮の事跡で建国の正当性を主張する。世宗(せいそう)前6代祖の事跡を述べるが,太祖(李成桂)に最も詳しい。110章以降は後代の王への訓誡。ハングル(1446年訓民正音として制定)による最初の資料で,注は漢文で書かれて長く,高麗末から李朝初期の中国東北部や日本に関する記事もあり,文学・語学・歴史的にも重要である。
(コトバンク)
○櫟翁稗説・筆苑雑記 李斉賢/徐居正著
高麗・朝鮮王朝の古典の翻訳
韓半島に栄えた高麗・李氏朝鮮の両王朝の2人の高官が書き残したさまざまな人物評や風聞、笑い話、風俗、官僚の姿、制度などの記述に豊富な注と解説を加えた歴史的古典の翻訳。 韓流ブームの中にあって、解説書や入門書の紹介は数多いが、本格的な当時の古文書を翻訳したものは少ないので貴重な書籍である。 とはいえ、全体が短い文でつづられているので、出てくる人物のことやその他の情報を知るにはいささか厳しい。それこそ多数の人物が登場するが、注を読んでもさっぱり分からないことが多い。 しかし、当時の人物が直接書いた感想や評伝なので、歴史的な事実の裏側を知るには貴重な文献とは言えるだろう。 高麗王朝の高官だった李斉賢の「櫟翁稗説」の解説には、当時の高麗王が元の侵略によって、その後の王の名前に「忠」が付いたものが多いことが指摘されている(「忠烈王」「忠宣王」「忠粛王」「忠恵王」など)。
これは解説によれば、「元の圧力によって高麗王は『宗』や『祖』を名乗れなくなったのである」とある。要するに、「『忠』などというのは臣下の徳目であって、王の徳目としてはありえない。最高主権者は『忠』であるべき対象をもたないはずだが、高麗王は元の皇帝に『忠』であることを強制されたのである」。 そのことは世継ぎを「太子」と呼ぶのではなく、「世子」と呼ぶようになったのも元の干渉からきていると訳者は指摘している。 また、李氏朝鮮王朝の高官だった徐居正の「筆苑雑記」では科挙の試験に昔は酒食がふるまわれたことや日本の戦国大名の大内氏の祖先が新羅から来ているのではないかと考察したものや7代王の世祖の時代に「女と見まがう容貌」の男がいて、罪人として法によって処刑することを司法関係の役所では願ったが、王が大目に見て却下したことなど興味深いエピソードが記されている。 (梅山秀幸訳) 中山雅樹


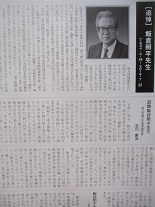
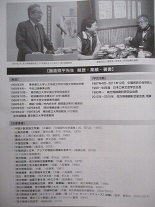
2020年4月1日 南方熊楠顕彰会『熊楠ワークス』№55 「第30回南方熊楠賞決定 北原糸子氏(立命館大学歴史都市防災研究所客員研究員)」/「[追悼]飯倉照平先生」
南方熊楠顕彰館 7月25日 ー南方熊楠顕彰会の前副会長(2011年4月~2015年3月)で、南方熊楠特別賞(第14回時)を受賞された飯倉照平先生が2019年7月24日に逝去されました。飯倉先生は、第1回南方熊楠特別賞受賞者の長谷川興蔵先生とともに、平凡社刊『南方熊楠全集』の刊行に携わられるとともに、『南方熊楠-森羅万象を見つめた少年』などの著書をもって、熊楠翁の業績や人となりを広く世に紹介されました。また、南方熊楠資料研究会の会長として、翁の残した膨大な資料の調査を通して「南方熊楠の基礎的研究」を進められ、『熊楠研究』の編集や『南方熊楠邸蔵書目録』『南方熊楠邸資料目録』の刊行等にもご尽力いただきました。ここに改めて、飯倉照平先生のご功績、並びに南方熊楠顕彰事業へのご尽力に対し敬意と感謝を申し上げますとともに、南方熊楠特別賞ご受賞時の選考報告、コメントとお写真を紹介し、ご冥福をお祈り申し上げます。
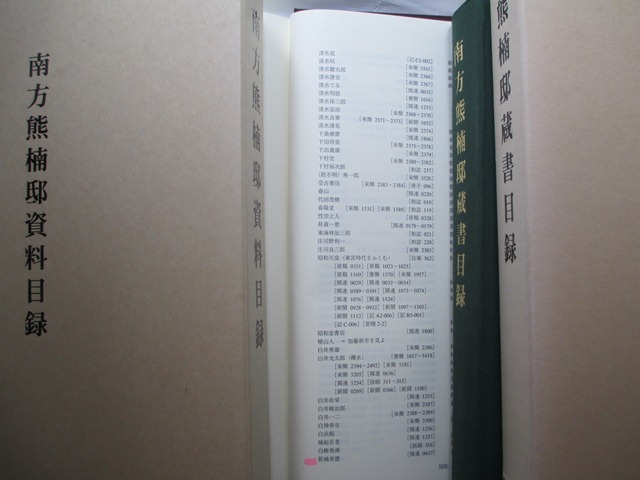
平成17年7月 俳句誌『貝寄風』』(編集発行・中瀬喜陽)新城栄徳「琉球の風②」
4月、南方熊楠顕彰会から『南方熊楠邸資料目録』が贈られてきた。巻末の人名索引に私の名前が有る。驚くと同時に記憶が甦った。1984年の夏、麦門冬・末吉安恭書の軸物「松山うれしく登りつめ海を見たり」を背に担ぎ熊本城を経て、田辺の熊楠邸を訪ねた。折よく文枝さんが居られたので麦門冬の写真を仏壇に供えてくださいと差上げたものであるが、大事に保存され且つ目録にまで記されるとは夢にも考えなかった。飯倉照平先生に電話で伺うと、研究会では熊楠没後の写真なので収録することに悩んだという。と書いた。そして麦門冬の親友・山城正忠を紹介した。正忠は那覇若狭の漆器業の家に生まれた。若狭は漆器業が多い。麦門冬の手ほどきで琉球美術史研究に入った鎌倉芳太郎(人間国宝)は「思うに(福井県)若狭はその地勢、畿内に接して摂津と表裏し(略)、古来日本海における外国貿易の起点となっていたが、十五世紀の初頭以来南蛮船も着船し、この地の代官も書をもって朝鮮国と通交しており、小浜から出て東シナ海に向かい、琉球に新しく出来た那覇港に、貿易物資(漆器)生産のための若狭の居留地が造成された」(『沖縄文化の遺宝』)と推定している。

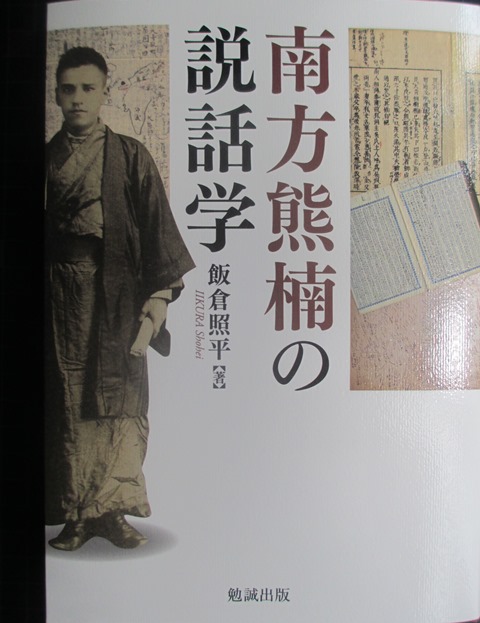
飯倉照平氏(南方熊楠顕彰館)/2013年10月 飯倉照平『南方熊楠の説話学』勉誠出版
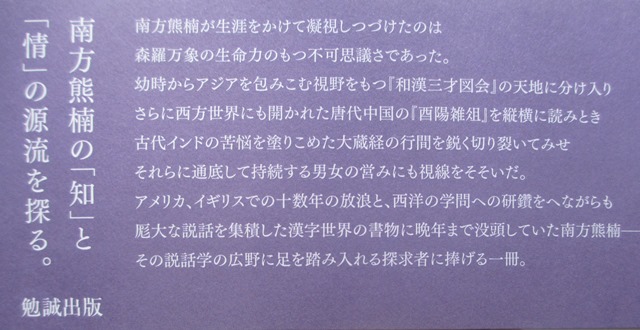
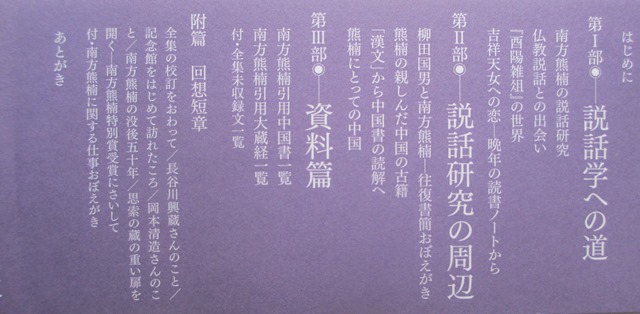
本書『南方熊楠の説話学』にも、「『南方熊楠全集』の校訂をおわって」と題して「平凡社の池田敏雄さんが、そのころまだ代々木駅の近くにあった中国の会の事務所へたずねて来てくれたのは、たしか1969年のはじめごろ{正しくは4月}であったと思う。乾元社版の『南方熊楠全集』に手を加えて出したいが、誤植も少なくないと思われるので目を通してほしいこと、さらに引用されている漢文を読み下し文に直し、全体の表記も読みやすくしたいので手伝ってもらえないか、というのが用件であった。戦争中に『民俗台湾』という雑誌の編集をしていた池田さんから、わたしは中国の昔話や民俗学の本を借りたことがある。また、わたしが以前によその出版社で校正の仕事をしていたことも、依頼されたきっかけの一つになっていたかもしれない。」と「『南方熊楠全集』の校訂に携わるきっかけを書かれておられる。
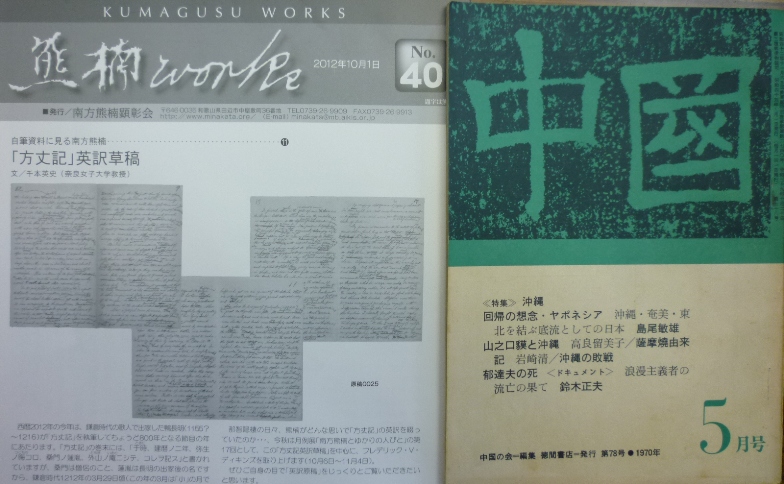
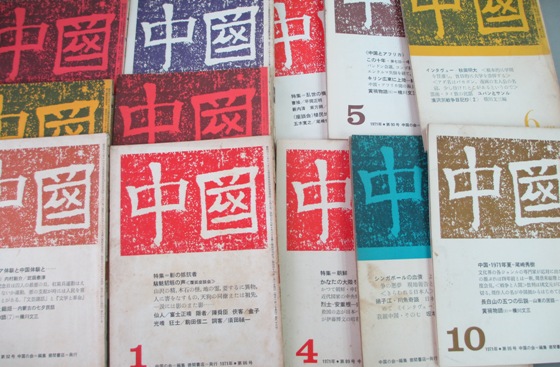
2012年10月『熊楠WORKS』№40に飯倉照平さんが「『漫画』好きの伊東忠太」を記され中に「筆者は、平凡社の『南方熊楠』全集の校訂にたずさわる前に、前後10年近く歴史の復習を旨とする雑誌『中国』の編集を手伝っていた時期がある。」と、かつて私も愛読していた『中国』との関わりについてもふれておられる。同号には考古学者・森浩一氏の第22回南方熊楠賞授賞式も載っていた。
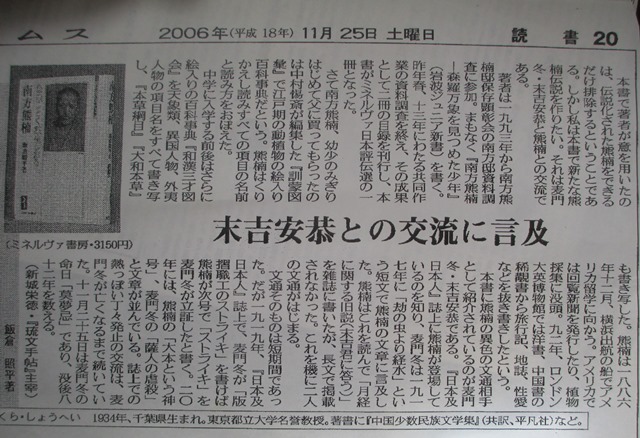
飯倉照平氏は千葉県山武郡大網白里町に住んでおられる。氏の著の書評を2回、沖縄の新聞に書いた。2006年11月25日『沖縄タイムス』新城栄徳(書評)飯倉照平『南方熊楠ー梟のごとく黙座しおる』ミネルヴァ書房ー本書で著者が意を用いたのは、伝説化された熊楠をできるだけ排除するということである。しかし私は本書で新たな熊楠伝説を作りたい。それは麦門冬・末吉安恭と熊楠との交流である。著者は1993年から南方熊楠邸保存顕彰会の南方邸資料調査に参加。まもなく『南方熊楠ー森羅万象を見つめた少年』(岩波ジュニア新書)を書く。昨年春、13年にわたる共同作業を終え、その成果として2冊の目録を刊行し、本書がミネルヴァ日本評伝選の1冊となった。
さて、南方熊楠、幼少のみぎりはじめて父に買ってもらったのは中村惕斎が編集した『訓蒙図彙』で江戸期の動植物の絵入り百科事典だという。熊楠はくりかえし読みすべての項目の名前と読み方をおぼえた。中学に入学する前後はさらに絵入りの百科事典『和漢三才図会』を天象類、異国人物、外夷人物の項目名をすべて書き写し、『本草綱目』『大和本草』も書き写した。熊楠は1886年12月、横浜出航の船でアメリカ留学に向かう。アメリカでは回覧新聞を発行したり、植物採集に没頭。92年、ロンドン大英博物館では洋書、中国書の希覯書から旅行記、地誌、性愛などを抜き書きしたという。
本書に熊楠の異色の文通相手として紹介されているのが麦門冬・末吉安恭である。『日本及日本人』誌上に熊楠が登場しているのを知り、麦門冬は1917年に「劫の虫より経水」という短文で熊楠の文章に言及した。熊楠はこれを読んで「月経に関する旧説(末吉君に答う)」を雑誌に書いたが、長文で掲載されなかった。これを機に2人の文通がはじまる。
文通そのものは短期間であった。だが1919年、『日本及日本人』誌上で、麦門冬が「版摺職工のストライキ」を書けば熊楠が次号で「ストライキ」を麦門冬が立証したと書く。20年には、熊楠の「大本という神号」、麦門冬の「薩人の虐殺」と文章が並んでいる。誌上での熱っぽい丁丁発止の交流は、麦門冬が亡くなるまで続いていた。11月25日は麦門冬の命日「莫夢忌」であり、没後82年を数える。
07/13: 沖縄の新聞『沖縄タイムス』略史
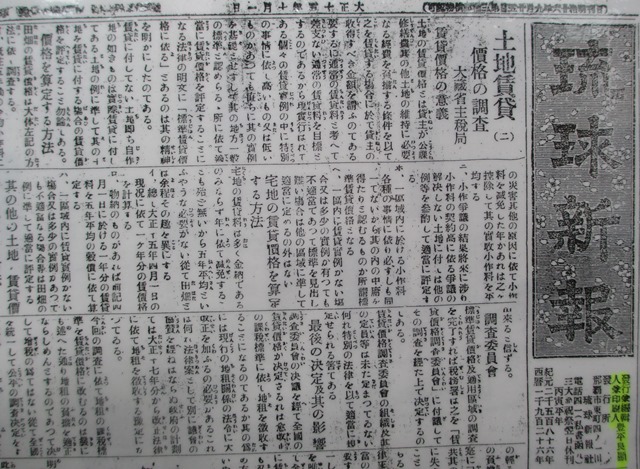
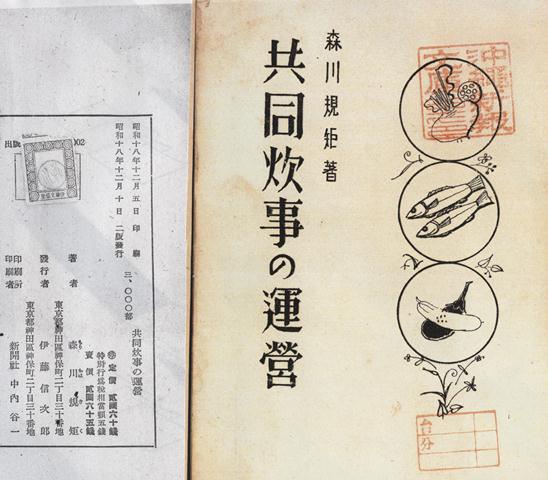
沖縄新報文庫の印が捺されている。
1943年 □仲本政基「私が沖縄新報の記者になったのは、昭和18年の10月であった。当時、沖縄は一県一紙になっており、琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報の3社が合併(昭和15年12月)してできたのが沖縄新報である。当時の社長は伊江朝助男爵で、専務が当真嗣合、常務が平尾喜一、総務局長兼編集局長が高嶺朝光、営業局長は親泊政博の各氏であった。工務局長はおらず、阿加嶺のターリーが工場長だったとおぼえている。編集局の陣容は、高嶺朝光氏の下に、外電関係整理が國吉眞哲氏、政経部に上地一史、仲泊良夫、与儀清三、座喜味盛良、勝連勇の諸氏、社会部は福地友珍、大城徳三(現在の牧港篤三)、友寄喜光、大山一夫の各氏が健筆をふるっていた。(以下略)」→1975年9月『那覇市史 戦時記録 資料篇第2巻中の6』
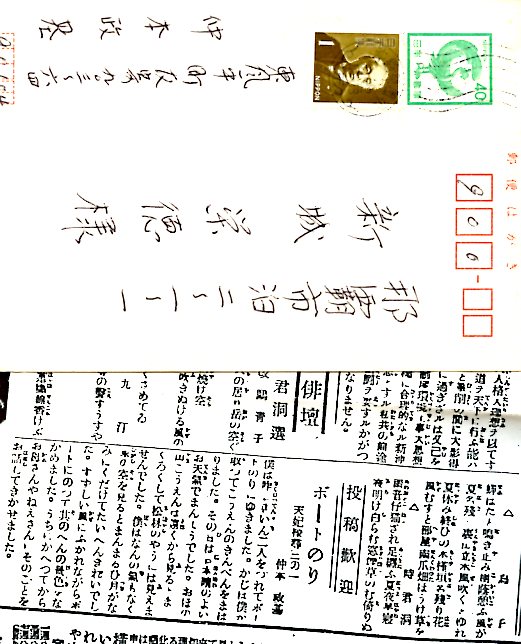
新城栄徳宛、仲本政基ハガキ「先日はさっそくコピーを送っていただき誠に有難うございます。大変なつかしく拝見いたしました。また記事の中に昭和俳壇の選者比嘉時君洞さんの名前が出ており、これもなつかしく拝見いたしました。(略)」
□1928年9月9日『沖縄昭和新聞』

『沖縄タイムス』写真1951年ー一人おいて比嘉秀平琉球臨時中央政府主席、ビートラー軍政副長官、ザルツバーグ・ニューヨーク・タイムズ社長、高嶺朝光、上地一史、座安盛徳、豊平良顕、ディフェンダーファー米民政府情報教育部長

1951年10月22日、米民政府情報教育部で開かれ「琉球の声・AKAR」から放送された第一回新聞週間・各新聞編集長座談会。向かって右から司会・川平朝申(放送部長)、ハードウィック(新聞部長)、國吉眞哲(琉球新報)、金城直吉(琉球新聞)、豊平良顕(沖縄タイムス)、比嘉憲蔵(沖縄朝日新聞)、宮城鷹夫(琉球弘報)、外間征四郎(琉球弘報)
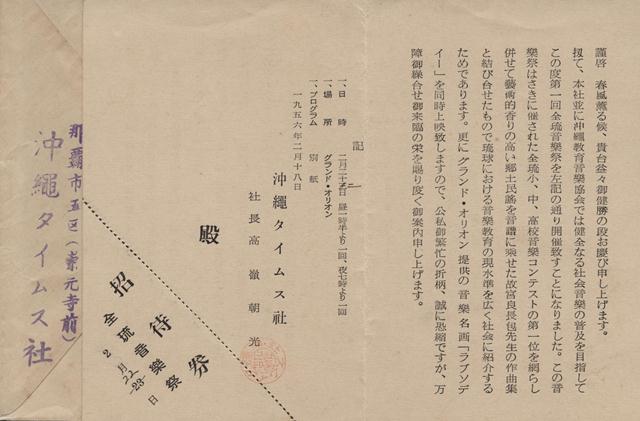
1956年
1966年4月『新沖縄文学』創刊
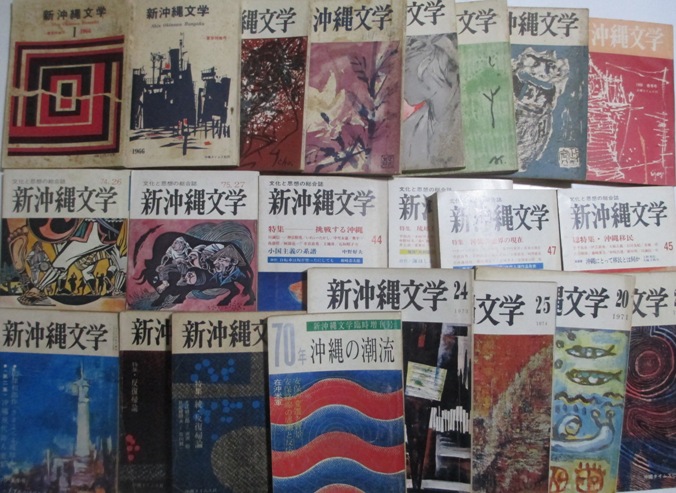
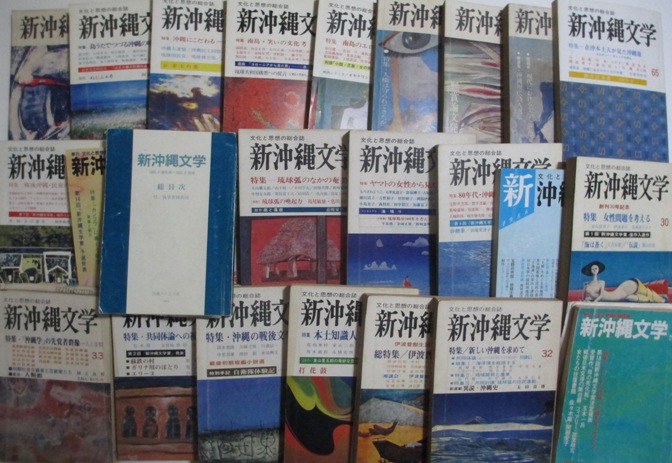
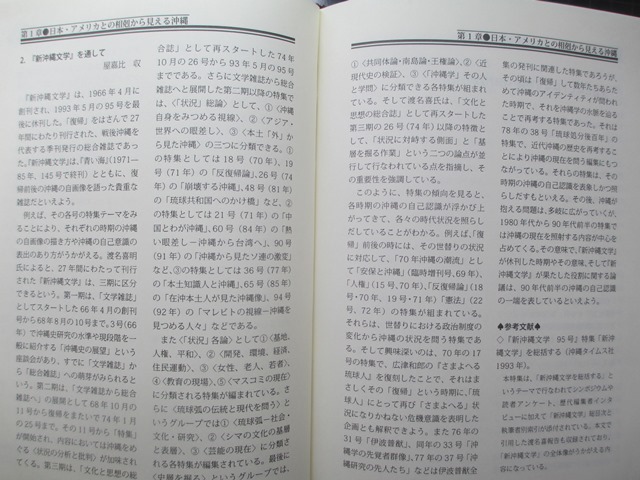

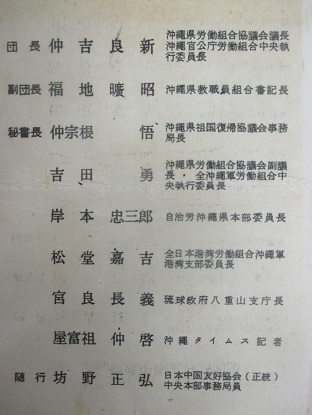
2017年9月2日 那覇市歴史博物館ー左から外間政明氏、屋冨祖仲啓氏、新城栄徳

1993年5月『新沖縄文学』95号 屋冨祖仲啓「本誌歴代編集長インタビュー/」重要な節目ごとに、考える作業をしてきたことは大きい」
2003年2月 『沖縄を深く知る事典』屋嘉比収「沖縄の雑誌に見る『自己意識』ー『新沖縄文学』を通して」

上里佑子さん、銘苅氏、川満信一氏、新川明氏、
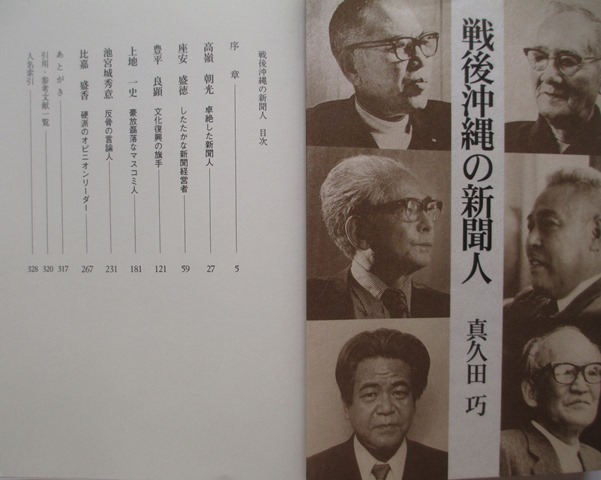
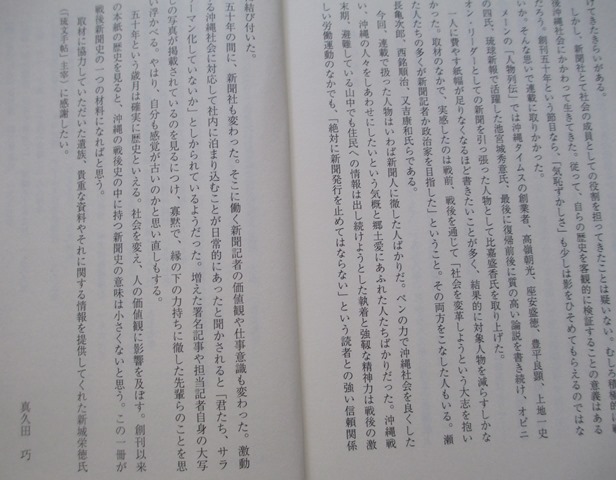
1999年10月 真久田巧『戦後沖縄の新聞人』沖縄タイムス社

左から豊平良一氏、新城栄徳

左からー新城栄徳、諸見里道浩氏、平良知二氏
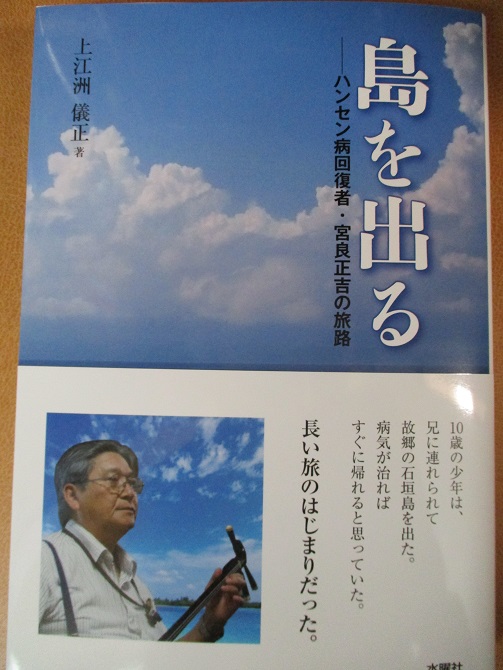
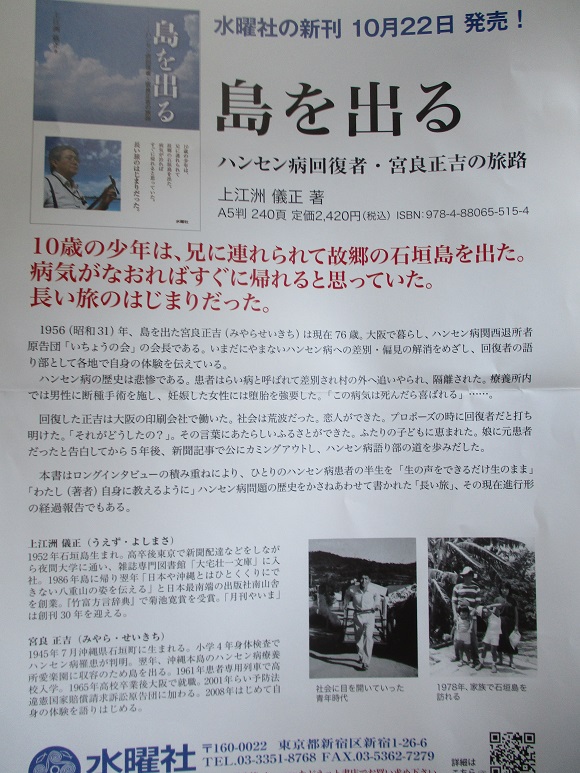
2021年10月 上江洲儀正『島を出るーハンセン病回復者・宮良正吉の旅路』水曜社(新宿区)
10歳の少年は、兄に連れられて故郷の石垣島を出た。病気がなおればすぐに帰れると思っていた。長い旅のはじまりだった。1956(昭和31)年、島を出た宮良正吉(みやらせいきち)は現在76歳。大阪で暮らし、ハンセン病関西退所者原告団「いちょうの会」の会長である。いまだにやまないハンセン病への差別・偏見の解消をめざし、回復者の語り部として各地で自身の体験を伝えている。ハンセン病の歴史は悲惨である。患者はらい病と呼ばれて差別され村の外へ追いやられ、隔離された。療養所内では男性に断種手術を施し、妊娠した女性には堕胎を強要した。「この病気は死んだら喜ばれる」……。
回復した正吉は大阪の印刷会社で働いた。社会は荒波だった。恋人ができた。プロポーズの時に回復者だと打ち明けた。「それがどうしたの?」。その言葉にあたらしいふるさとができた。ふたりの子どもに恵まれた。娘に元患者だったと告白してから5 年後、新聞記事で公にカミングアウトし、ハンセン病語り部の道を歩みだした。本書はロングインタビューの積み重ねにより、ひとりのハンセン病患者の半生を「生の声をできるだけ生のまま」「わたし(著者)自身に教えるように」ハンセン病問題の歴史をかさねあわせて書かれた「長い旅」、その現在進行形の経過報告でもある。
宮良 正吉(みやら・せいきち)1945 年7月沖縄県石垣町に生まれる。小学4年身体検査でハンセン病罹患が判明。翌年、沖縄本島のハンセン病療養所愛楽園に収容のため島を出る。1961年患者専用列車で高校入学。1965 年高校卒業後大阪で就職。2001年らい予防法違憲国家賠償請求訴訟原告団に加わる。2008年はじめて自身の体験を語りはじめる。
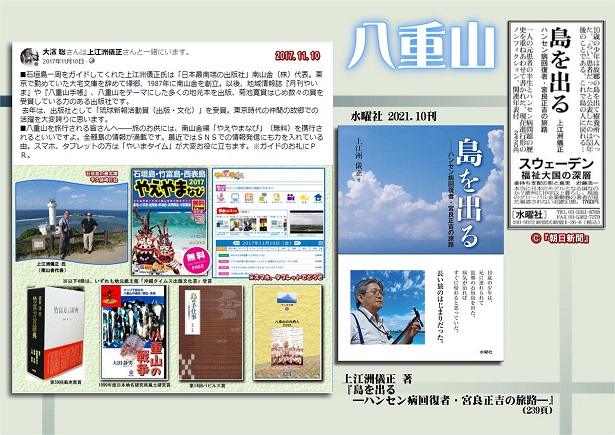
大濱 聡 2021年11月■「過去の思い出を振り返ってみましょう」として2017.11.10の投稿が。「日本最南端の出版社」南山舎と、代表の友人・上江洲儀正さん(現会長)についての紹介でした。■1987年の創業以来、八重山をテーマに数々の良書を世に送り出してきましたが、このたび初めて自身の本『島を出る―ハンセン病回復者・宮良正吉の旅路―』(水曜社刊)を出版。2019-20年の2年にわたって、南山舎発行の『月刊やいま』で自ら10回連載したルポ「島を出た八重山人」に加筆修正してまとめたものです。
■ハンセン病患者として10歳の幼い身で親元を離れ、島外の療養所でひとりで生きていかねばならなかった人生――〈一人の元患者の半生とハンセン病問題の歴史を重ねあわせて書かれた、現在進行形のノンフィクション〉(新聞広告より)■〈島を出る。島人にとってこのことばは特別な響きがある〉〈島を出るのは、若者にとって宿命のようなものである。しかも一度出てしまうと、島に働く場はそう多くはないから、なかなか戻ることはできない。したがって、「島を出る」ということばには、覚悟、希望、別れ……などさまざまな思いが入り混じる〉(あとがきより)読み応えのある本です。お薦めします。
週刊誌は個人で保存するには限界がある。後に雑誌図書館・大宅壮一文庫が開館したときは早速に訪ね整理法を学んだ。そのときは西沢昌司氏が応対してくれた。次に行くと、八重山出身の上江洲榕氏と出会った。『琉文手帖』2号の東京連絡所が大宅文庫(http://www.oya-bunko.or.jp/)となっているのは上江洲氏が引き受けたからである。
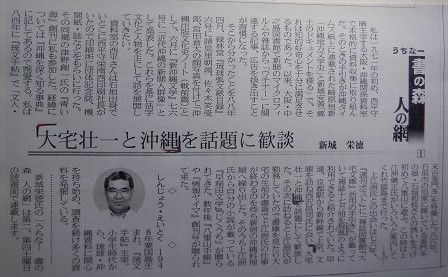
上江洲儀正氏との出会いは1976年。『週刊ポスト』に「雑誌図書館『大宅文庫』活用の手引き」が載っていて雑誌17万冊を辞典のように利用できると紹介されていた。早速、京都駅から新幹線で上京。文庫を訪ね西沢昌司氏に会い「大宅壮一と沖縄」を話題にして歓談した。その次に尋訪ねると上江洲氏が居たので書庫を見たり大宅の生前の書斎で上江洲氏の仕事が終わるのを待ち新宿の沖縄料理屋へ繰り出した。そのうち上江洲氏から自分の小説が載っている『早稲田文学』『じくうち』が贈られてきた。手元にある『大宅壮一文庫索引目録』の扉には彼に押して貰った文庫の印がある。そのときの名刺には「財団法人大宅壮一文庫事務局次長」とあった。彼は『じくうち』の同人で4号に東京とシマをテーマに小説「二ーラン神の島」を書いている。5号に「肝苦さんさあ」、6号に「義足」、7号「人形」であった。私は彼が文庫に居る時、松島記者担当の『琉球新報』落ち穂欄にエッセイを書いてもらったが今では良い記念となっている。数年後『八重山手帳』や『情報ヤイマ』創刊号が贈られてきた。那覇で会ったときの名刺には「企画・出版・情報処理・南山舎」とあった。

2014年12月12日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー新垣筑兵衛/嘉手納憑武」
○1924年12月発行の藤田親義『琉球と鹿児島』に麦門冬・末吉莫夢は「薩摩関係の琉球五異人」と題し、新垣筑兵衛を紹介している。12月16日は「紙の日」と上記に言う。麦門冬も首里の自宅近くの製紙業の変遷で大見武憑武にも触れている。
1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」
▲首里区の製紙業を改良せしめ、元始的製造法より文明的製造法に代らしめやうと云ふのは、極めて必要なことである。今同区にある所の製紙業の幼稚なことたら実にお話にならぬものだが、それでも長い歴史を有するから面白い、而して今の同業は却て往昔のものの退化したものであることを認めざるを得ない。
▲沖縄で初めて紙製造をやったのは尚貞王の18年我貞享3年(西暦1686)で即ち今を去ること二百三十四年前である。那覇の人関忠勇大宜味(●大見武の誤記)筑登之親雲上憑武と云ふ者が薩摩に往って草野五右衛門と云ふ人に就て学び、其製法を伝へ帰った。それが8年後の元禄7年政府より造紙主取と云ふ職を授けられ、官営の製紙業が設けられ、彼はその主任となって経営に任した。而して大見武筑登之は功により宅地を首里金城村大樋川辺に賜りそこにて盛んに紙を製した、製紙の種類はわからないが、國用に供したとあるから、今の紙などよりは遥かに上等な紙であり其製法も進歩したものであったらうと思ふ。
□(略)天保11年(1840)即ち今より80年前、政府は儀保の寶口に家屋を建て紙製造所となし、比嘉親雲上を主任として官営で出来たのは百田紙であった。弘化3年(1846)即ち今より74年前、比嘉親雲上が寶口で始めてより7年後のことである。那覇泉崎の人豊氏金城筑登之親雲上順應が先年薩州に赴き製紙の法を学び来るにより、試みにこの年彼を召し紙座に於いてその所伝の紙を漉かしめ見るに、上紙、下紙、百田紙、美濃紙、宇田紙、杉原等諸紙の紙を漉いて杉原の外はすべて見事に出来上がった。是により製紙界の革命児たる金城は直ちに登用せられ紙座の主任となり盛んに製紙業を開いた。(以下略)


宝口樋川ー「宝樋」碑、近くに「紙漉所跡」がある。
01/22: 伊江朝貞
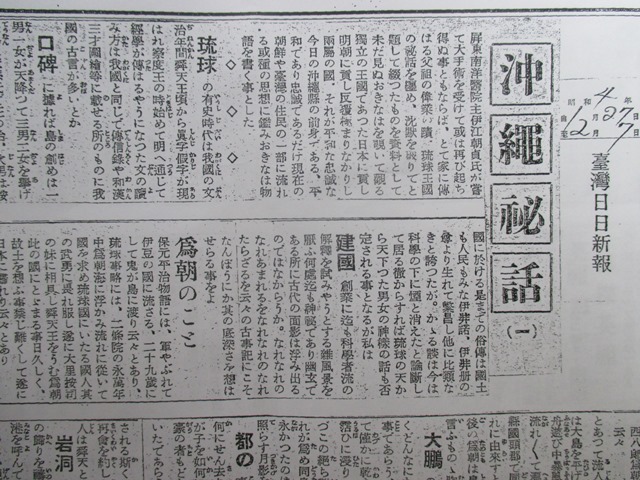
1929年1月27日『臺灣日日新報』(仲村顕氏提供)
○屏東南洋医院主伊江朝貞氏が嘗て大手術を受けて或は再び起ち得ぬ事ともならば、とて家に伝わる父祖の偉業の蹟、琉球王国の秘話を纏め、沈黙を破りてと題して綴ったものを資料として未だ見ぬおきなはを覗いて観る独立の王国であった日本に貢し明朝に貢し反覆極まりなかりし両属の国、それが平和な忠誠な今日の沖縄県の前身である。平和であり忠誠であるだけ現在の朝鮮やた臺灣の住民の一部に流れる或種の思想に鑑みおきなは物語を書く事とした。(麦門冬)
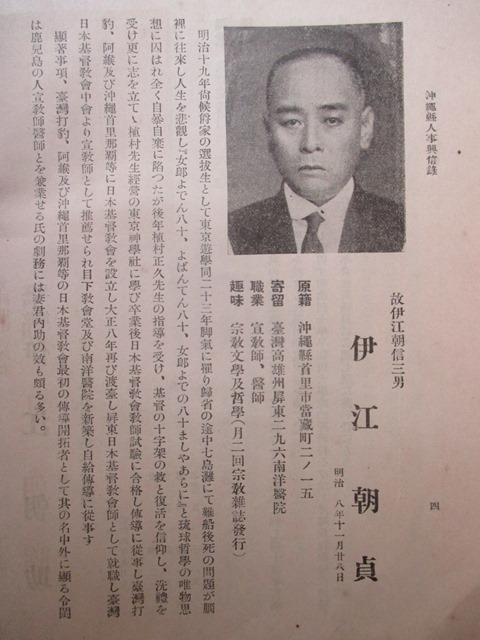
1929年3月『沖縄県人事興信録』「伊江朝貞」
新垣信一(1887年~1945年)
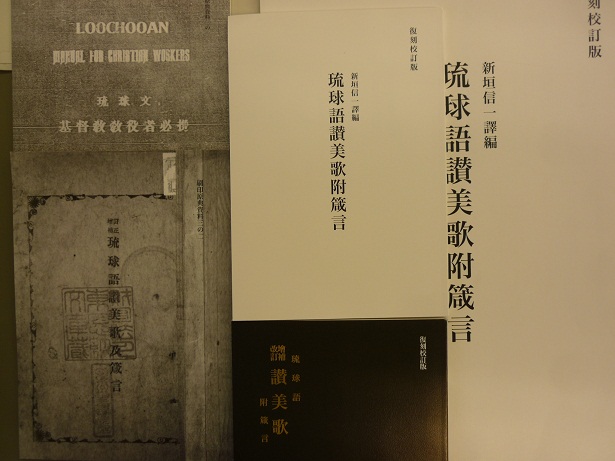
首里の石川和男氏から1915年1月発行の新垣信一訳編『琉球語讃美歌附箴言』資料、CDが贈られてきた。
□石川和男 みどり印刷〒903-0823沖縄県那覇市首里大中町1-36-2 TEL098-884-3702
新垣信一略年譜
1887年11月25日 西原間切末吉村の農家の長男として生まれる
1907年3月 新垣信一、沖縄県師範学校卒業、同期に島袋源一郎、大山岩蔵が居た。→1982年1月 大山一雄、山川岩美『遺稿・回想 大山岩蔵』
宜野湾尋常高等小学校訓導
1908年2月 日本メソヂスト首里教会大保富哉氏より受洗
1915年1月 「標準語励行の喧しい時代に於いてなお、琉球語(方言)は農村地域では心に響く言であり、『太初に言あり、言は神と偕にあり、言は神なりき。』(ヨハネ傳福音書第一章第一節)に説く如く、新垣信一師が津覇傳道所(日本基督教会首里傳道所の伊江朝貞指揮監督のもと)を設立してすぐに、その傳道の書として『訂正増補琉球語賛美歌及箴言』を出版したのも茲にその基があるといえよう。」
1930年2月 新垣信一訳編『増補改訂琉球語讃美歌附箴言』那覇基督教会青年会 印刷者・照屋寛範
1934年7月 新垣信一訳編『改訂増補琉球語讃美歌附箴言』那覇基督教会青年会 印刷者・照屋寛範

CD「首里日本基督教会牧師 新垣信一譯編 増補改訂琉球語讃美歌附箴言」
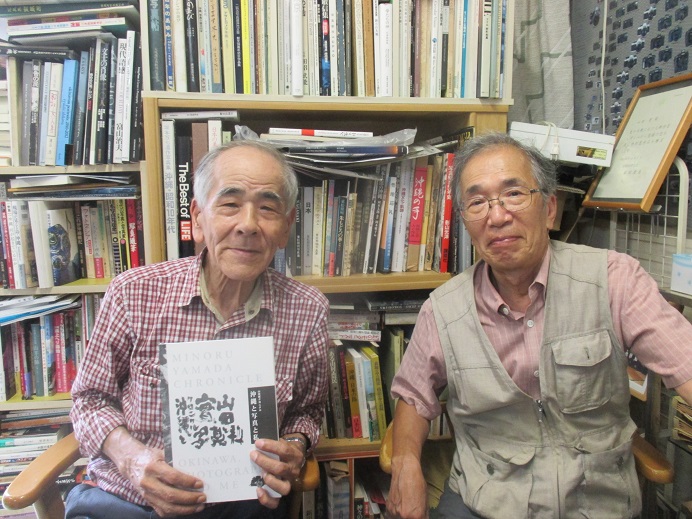
2016年7月30日 写真左が新城良一氏、山田勉氏

2016年7月30日 左から玉城よし子さん、呉屋周子さん、新城良一氏、輝広志氏

2016年7月24日 末吉家にて左が末吉安允氏、新城良一氏
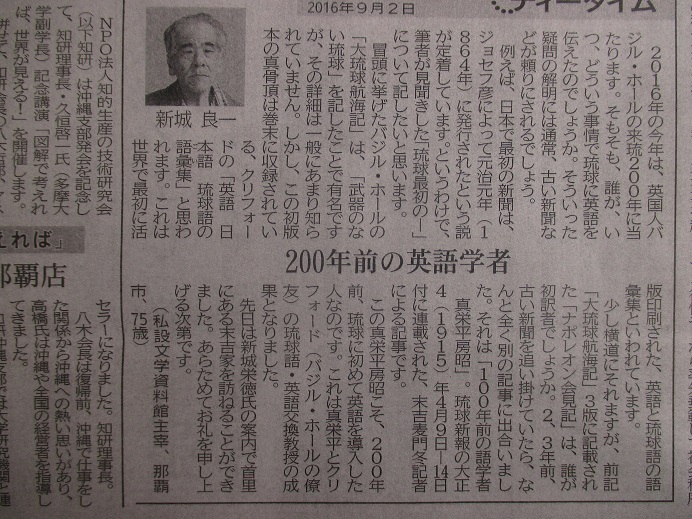
2016年9月2日『琉球新報』新城良一「ティータイム/200年前の英語学者」
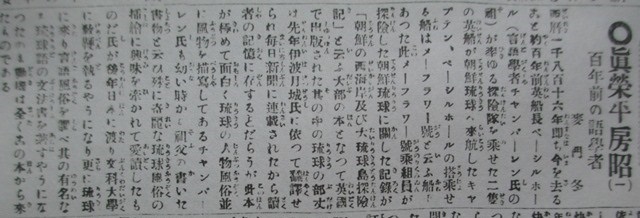
1915年4月9日『琉球新報』麦門冬「眞栄平房昭ー百年前の語学者」

1928年ー市河三喜編輯『岡倉先生記念論文集』に豊田實が「沖縄英学史稿」を寄せている。豊田は沖縄県の依頼で1928年3月22日から28日まで英語講習のため那覇に滞在した。そこで沖縄県立沖縄図書館長の真境名安興などの協力を得て沖縄英学史を調べたのが前出の沖縄英学史稿として結実した。中に末吉麦門冬の「百年前の英語通」も引用し真栄平房昭の家譜を書いている。(2011年11月)
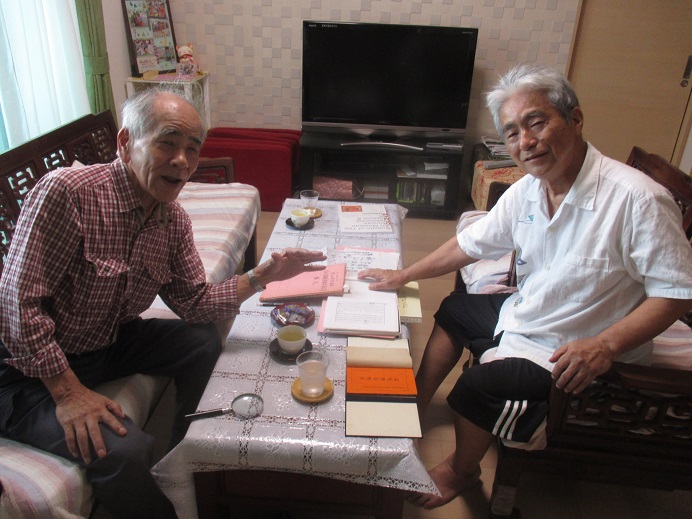
2016年7月24日 屋部家にて右が屋部憲次郎氏(夢華書道・琉訳聖書教室主宰)、新城良一氏
○1996年5月11日 リウボウ「おきなわ聖書展」ミニ講演会/屋部憲次郎
ベッテルハイム「琉訳聖書」と琉球語ー沖縄の伝統文化の一つである組踊の中に、キリスト教あるいは聖書と何らかの意味でひじょうに関係のある作品が一編ありまして、ここでご紹介したいと思います。『大川敵討』(忠孝婦人またはムラバルーとも称する)と題する組踊(戯曲)でありますが、これから興味深い台詞を二つ引用します。まず満納という悪役の台詞「はあ、面付もかはて悪魔やな女、夫喰ゆる悪生切支丹。鬼見ちやる人の此の世界にをゆめ。是ど鬼やゆる。・・・」(読み方「ハー、ツィラツィチンカワティ アクマ ヤナイナグ、ウトゥクヮユル アクショー キリシタ。ウニンーチャルフィトゥヌ クヌシケーニ ウユミ。クリドゥウニヤユル」)でして、キリシタン、悪魔、鬼などの語に注目されます。この組踊は1838年、尚育王冊封の重陽の宴で演じられましたが、当時の異国船がひんぱんに渡来したいわば不安な世相をよく反映しているといえましょう。ベッテルハイムが来沖したのは実にその十年後でした。・・・
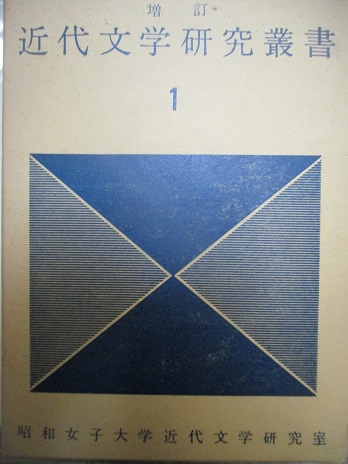
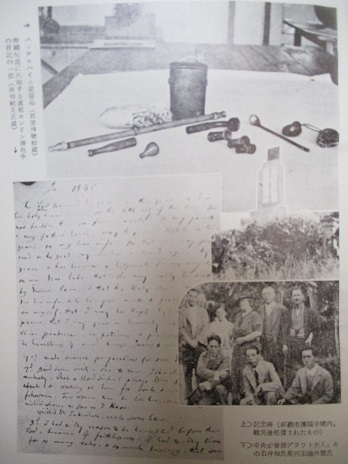
1969年3月 昭和女子大学近代文学研究室『増訂 近代文学叢書』「B・J・ベッテルハイム」第一巻 昭和女子大学
2019年9月『月刊琉球』№69「幻の名著『沖縄の歩み』復刻記念シンポジウム」琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947
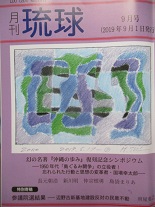



後田多敦「史窓・東恩納寛惇のメッセージ」/しもじけいこ「宮古IN・バブル・オーバーツーリズムって??観光地になるということはどんなこと?水は?」




与那嶺功「沖縄振興ー『明治維新150年』を問う 大東亜・植民政策・ナショナリズム⑬」/土岐直彦「安倍官邸『独裁』の不条理ー官僚支配・国会軽視・辺野古・・・」
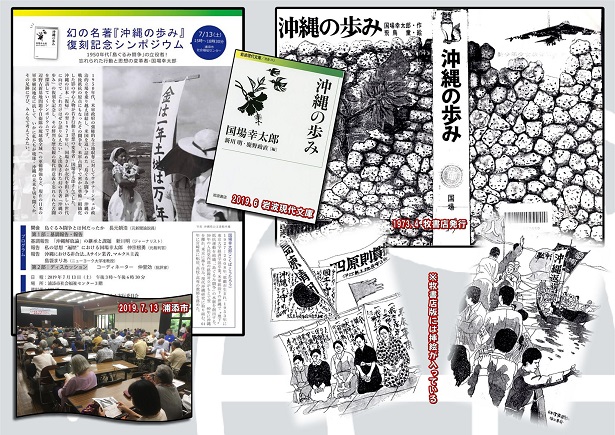
大濱聡2019-7-15
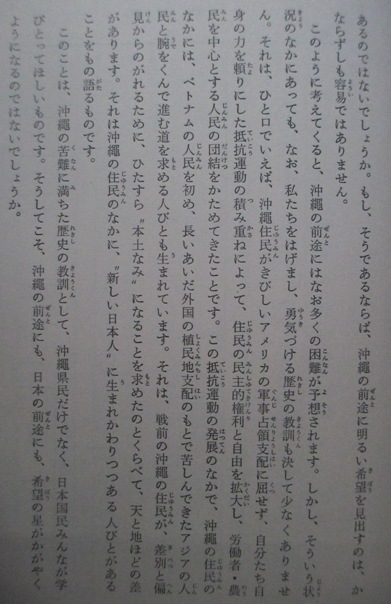

1973年4月ー国場幸太郎『沖縄の歩み』牧書店
目次-まえがき/1、けわしい戦争の雲ゆき/2、沖縄戦の悲劇/3、遠い昔の沖縄/4、江戸時代の沖縄/5、明治時代の沖縄/6、大正・昭和前期の沖縄/7、第二次大戦の沖縄/あとがき□主な参考文献・比嘉春潮『親稿 沖縄の歴史』三一書房、新里・田港・金城『沖縄県の歴史』山川出版社、太田昌秀『近代沖縄の政治構造』勁草書房、上地一史『沖縄戦史』時事通信社、沖縄県教職員組合編「これが日本軍だー沖縄における残虐行為」、平凡社刊『沖縄文化論叢』1~4、谷川健一編『叢書わが沖縄』1~6木耳社、中野・新崎『沖縄問題二十年』岩波書店、中野・新崎『沖縄・70年前後』岩波書店
2019年8月『月刊琉球』№68琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947
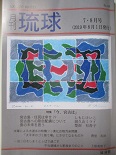



しもじけいこ「宮古島・住民は幸せ??」/渡久山ミライ「宮古島への陸自配備について」/楚南有香子「島の未来を思う」




すねしまさく菜「西表IN・『東京西表島郷友会』総会に出席してー32年ぶりの再会」/与那嶺功「沖縄振興ー『明治維新150年』を問う 大東亜・植民政策・ナショナリズム⑫」/豊里友治「米軍による水道水の有機フッ素化合物汚染問題『太平洋のゴミ捨て場』にさせてなるものか」
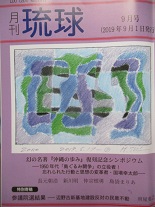



後田多敦「史窓・東恩納寛惇のメッセージ」/しもじけいこ「宮古IN・バブル・オーバーツーリズムって??観光地になるということはどんなこと?水は?」




与那嶺功「沖縄振興ー『明治維新150年』を問う 大東亜・植民政策・ナショナリズム⑬」/土岐直彦「安倍官邸『独裁』の不条理ー官僚支配・国会軽視・辺野古・・・」
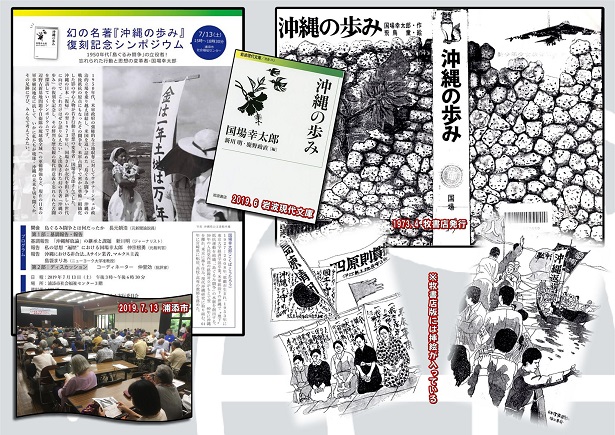
大濱聡2019-7-15
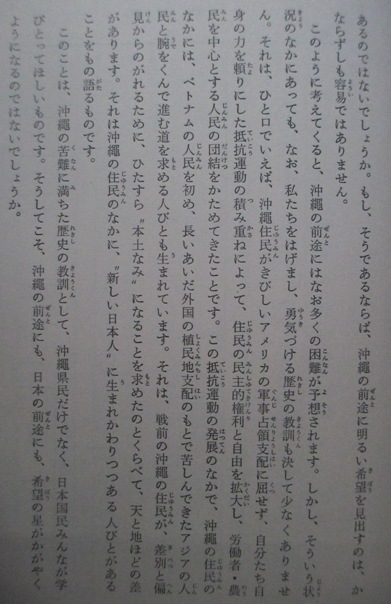

1973年4月ー国場幸太郎『沖縄の歩み』牧書店
目次-まえがき/1、けわしい戦争の雲ゆき/2、沖縄戦の悲劇/3、遠い昔の沖縄/4、江戸時代の沖縄/5、明治時代の沖縄/6、大正・昭和前期の沖縄/7、第二次大戦の沖縄/あとがき□主な参考文献・比嘉春潮『親稿 沖縄の歴史』三一書房、新里・田港・金城『沖縄県の歴史』山川出版社、太田昌秀『近代沖縄の政治構造』勁草書房、上地一史『沖縄戦史』時事通信社、沖縄県教職員組合編「これが日本軍だー沖縄における残虐行為」、平凡社刊『沖縄文化論叢』1~4、谷川健一編『叢書わが沖縄』1~6木耳社、中野・新崎『沖縄問題二十年』岩波書店、中野・新崎『沖縄・70年前後』岩波書店
2019年8月『月刊琉球』№68琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947
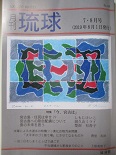



しもじけいこ「宮古島・住民は幸せ??」/渡久山ミライ「宮古島への陸自配備について」/楚南有香子「島の未来を思う」




すねしまさく菜「西表IN・『東京西表島郷友会』総会に出席してー32年ぶりの再会」/与那嶺功「沖縄振興ー『明治維新150年』を問う 大東亜・植民政策・ナショナリズム⑫」/豊里友治「米軍による水道水の有機フッ素化合物汚染問題『太平洋のゴミ捨て場』にさせてなるものか」
04/22: 年譜・末吉麦門冬/1913(大正2)年
1913年1月1日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「俳諧 牛の國」
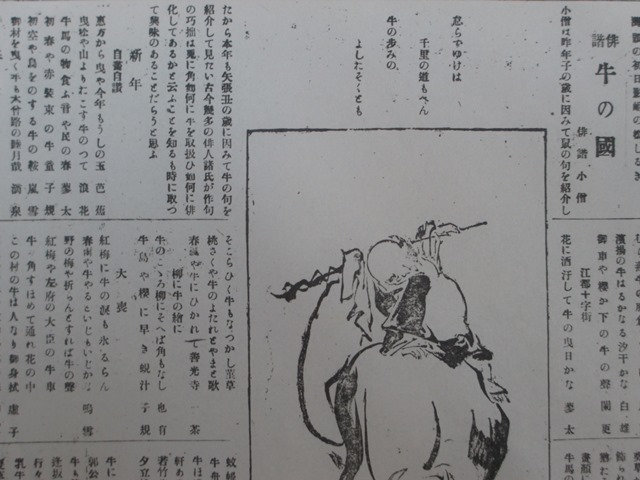
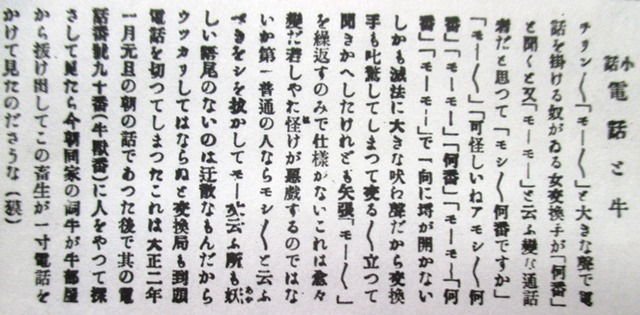
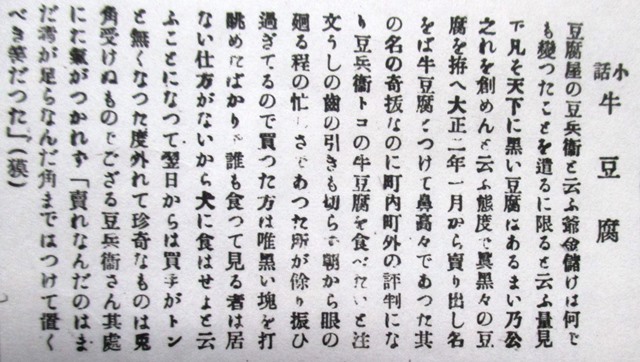
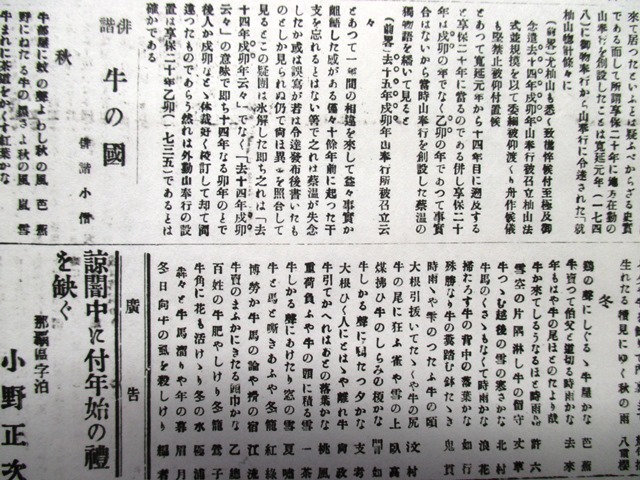
1914年1月3日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「俳諧 牛の國俳諧」「毎日二句」
1914年1月5日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「続俳諧 牛の国」「毎日二句」
1914年1月7日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「続俳諧 牛の国」「毎日二句」
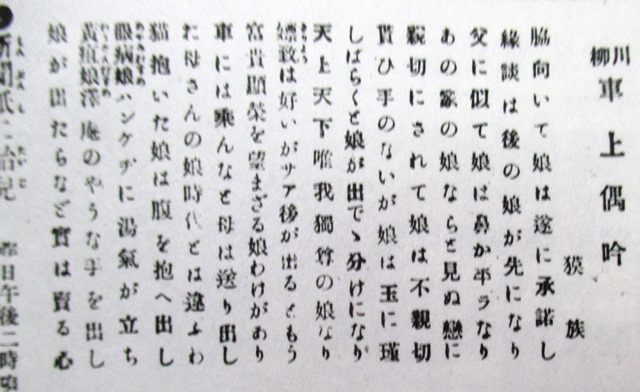
1913年2月8日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟」
1913年2月11日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー章魚ゆでて爺は風呂を上けり」
1913年2月13日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー火事」
1913年2月15日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー火事 山火事」
1913年2月19日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー詠史 猪早太」
1913年2月20日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー居候」
1913年2月26日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー泥濘」
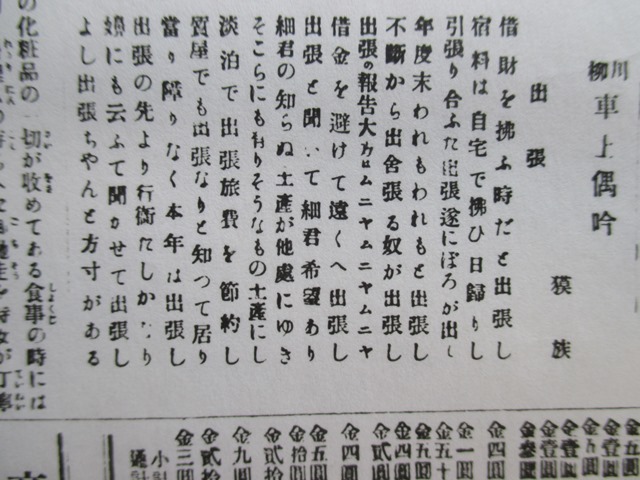
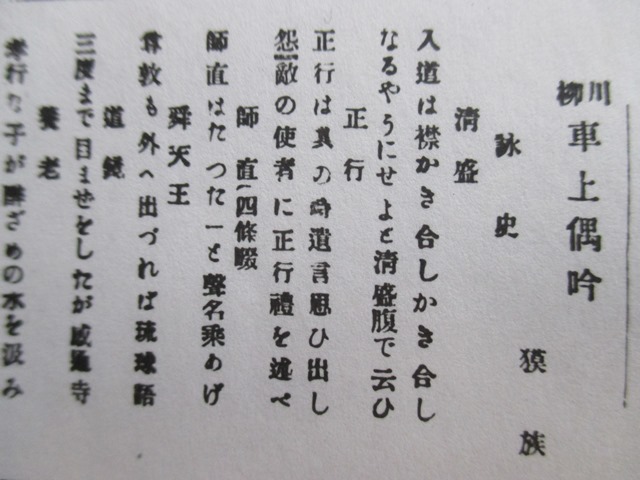
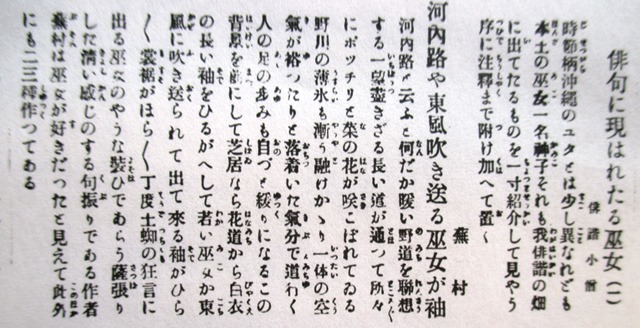
1913年3月2日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー巫女」
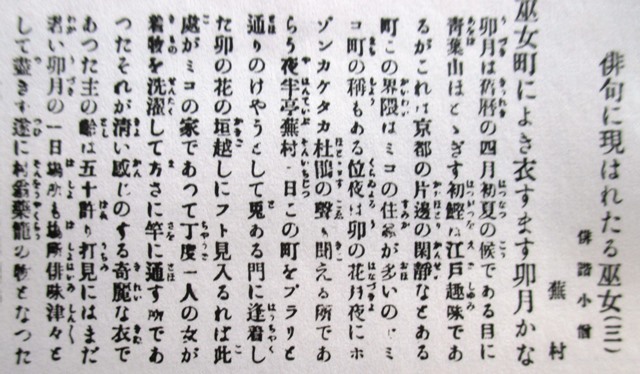
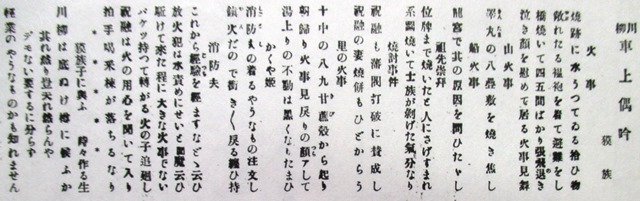
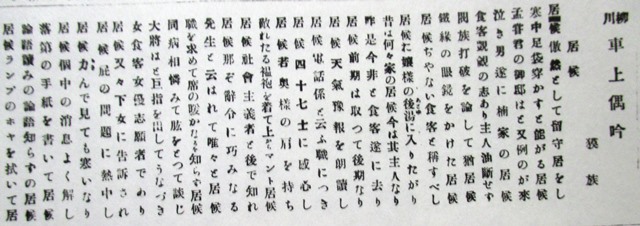
1913年3月5日『沖縄毎日新聞』玉代勢法雲「病室より」①
1913年3月6日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉麦門冬)「俳句に現はれたる巫女(1)」
○時節柄沖縄のユタとは少し異なれども本土の巫女一名神子それも我俳諧の畑に出てたるものを一寸紹介して見よう。序に注釈まで附け加えて置く
河内路や東風吹き送る巫女が袖 蕪村
河内路と云ふと何だか暖かい野道を連想する一望尽きざる長い道が通って所々にポッチリと菜の花が咲きこぼれている。野川の薄氷も漸う融けかかり一体の空気が裕ったりと落着いた気分で道行く人の足の歩みも自づと緩りになるこの背景を前にして芝居なら花道から白衣の長い袖をひるがえして若い巫女が東風に吹き送られて出て来る袖がひらひら裳裾がほらほら丁度土蜘の狂言に出る巫女のやうな装ひであらう薩張りした清い感じのする句振りである作者蕪村は巫女が好きだったと見えて此外にも二三種作ってある。
1913年3月7日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉麦門冬)「俳句に現はれたる巫女(2)」
○春風や廻廊下る巫女か袖 満米
今しも神楽堂で神すずしめの朝神楽が終わり古香人を襲ふて幽然たる社殿を廻りて更に続く廻廊を小忌衣の袖長う垂れシュツシュツと衣すれの音して下り来るみこの姿は端厳なるかなかかる時けにや彼女は人間の物にあらず白鳩のやうな神の使いのやうな思ひに人をして振り仰いて恍惚たらしむ春風吹いて普き洛陽の天地この境にこの景あり。
1913年3月8日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉麦門冬)「俳句に現はれたる巫女(3)」
○巫女町によき衣すます卯月かな 蕪村
卯月は旧暦の四月初夏の候である目に青葉山ほととぎす初鰹は江戸趣味であるがこれは京都の方邊の閑静なとある町この界隈はミコの住家が多いのでミコ町の称もある位夜は卯の花月夜にホゾンカケタカ杜鵑の聲も聞こえる所であろう。夜半亭蕪村●日この町をブラリと通りのけようとして兎ある門に逢着した卯の花の垣越しにフト見入るれば此処がミコの家であって丁度一人の女が着物を洗濯してまさに竿に通す所であったそれが清い感じのする綺麗な衣であった主の齢は五十許り打見にはまだ若い卯月の一日場所俳味津々として尽きず遂に村翁薬籠の物となった。
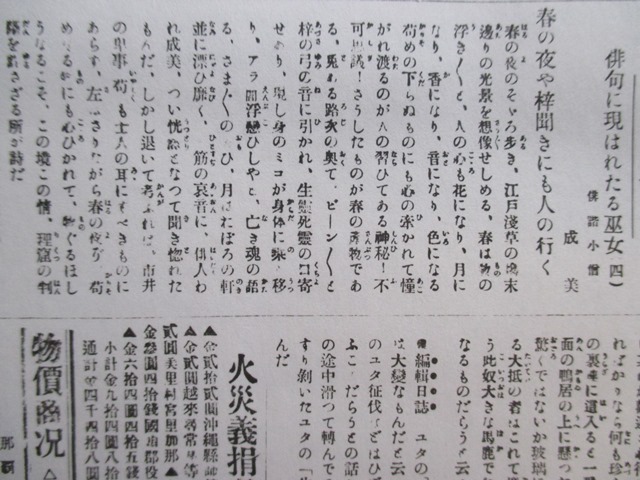
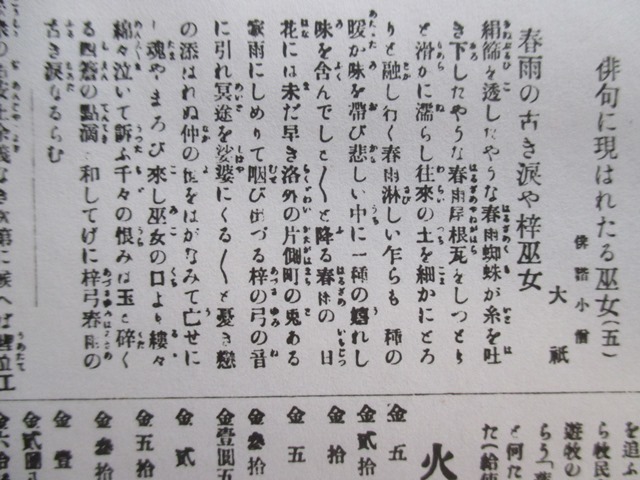
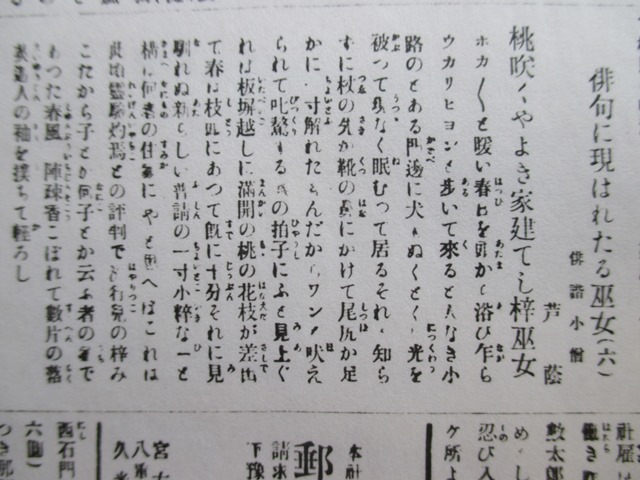
1913年7月5日『沖縄毎日新聞』南村「禁煙日誌ー煙草を吸い始めたのは確か16才の頃であったと記憶する・・・」
1913年7月8日『沖縄毎日新聞』南村「禁煙日誌ー中学での昼食時間は僕等喫煙党の最も楽しい1時間であった・・・」
1913年7月9日『沖縄毎日新聞』南村「禁煙日誌」
1913年7月10日『沖縄毎日新聞』南村「禁煙日誌」
1913年7月23日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(1)
1913年7月24日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(2)
1913年7月25日『琉球新報』松檮濤「菊栽培法に就いて」(3)
1913年7月27日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(4)
1913年7月29日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(5)
1913年8月1日『琉球新報』松檮濤「菊栽培法に就いて」(6)
1913年8月5日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(7)
1913年8月6日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(8)
1913年8月8日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(9)
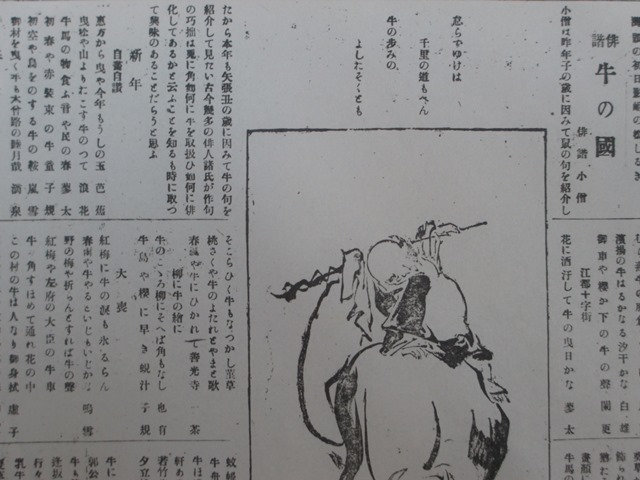
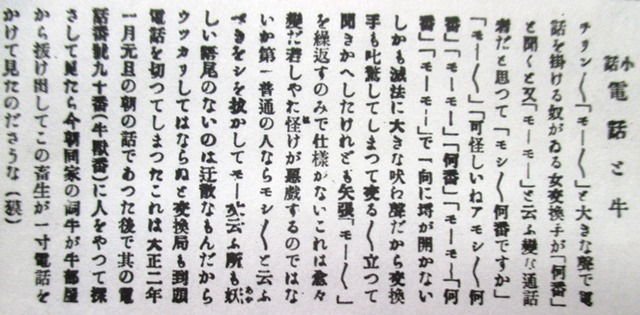
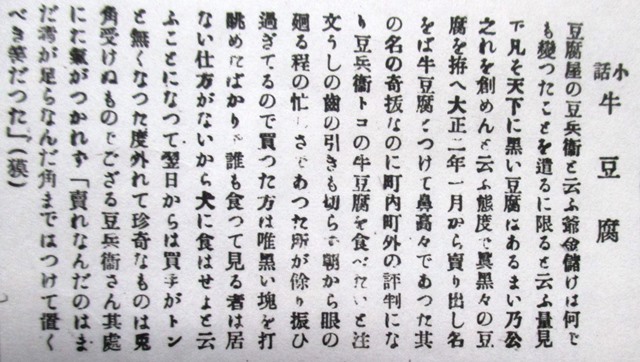
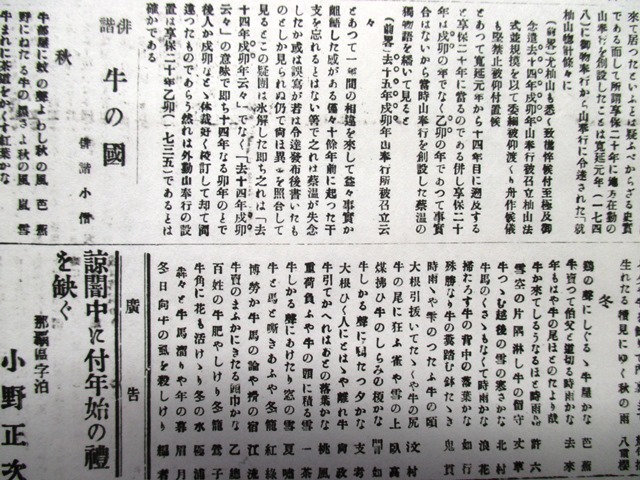
1914年1月3日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「俳諧 牛の國俳諧」「毎日二句」
1914年1月5日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「続俳諧 牛の国」「毎日二句」
1914年1月7日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「続俳諧 牛の国」「毎日二句」
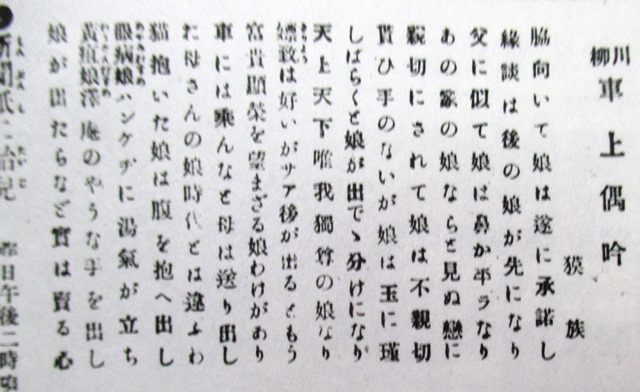
1913年2月8日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟」
1913年2月11日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー章魚ゆでて爺は風呂を上けり」
1913年2月13日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー火事」
1913年2月15日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー火事 山火事」
1913年2月19日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー詠史 猪早太」
1913年2月20日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー居候」
1913年2月26日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー泥濘」
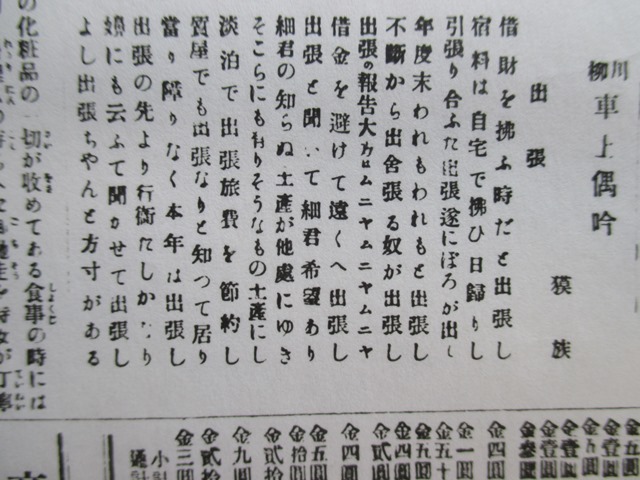
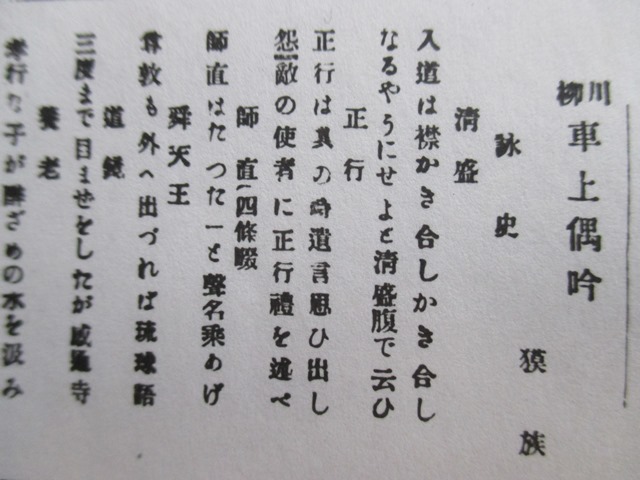
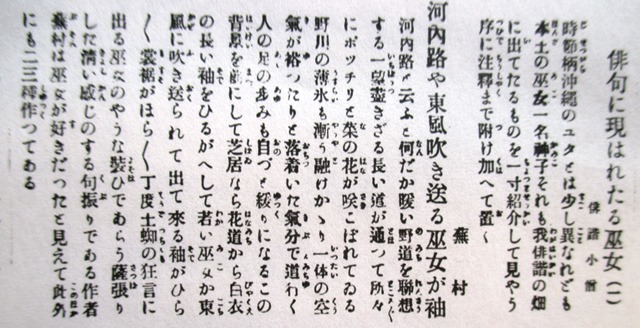
1913年3月2日『沖縄毎日新聞』獏族「川柳 車上偶吟ー巫女」
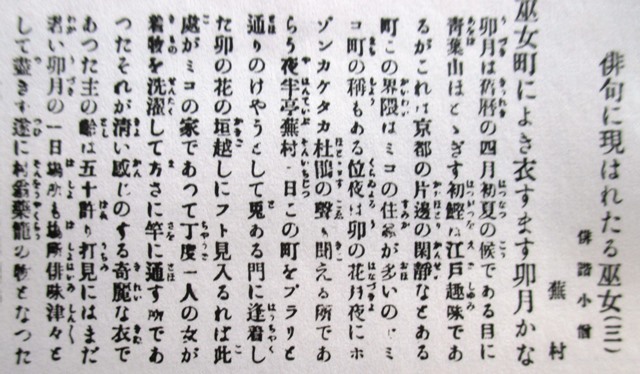
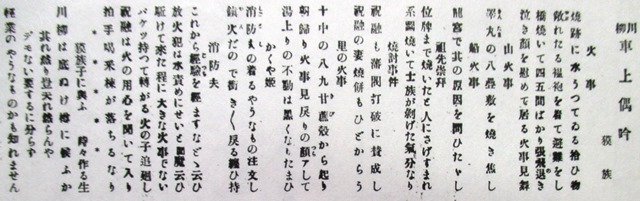
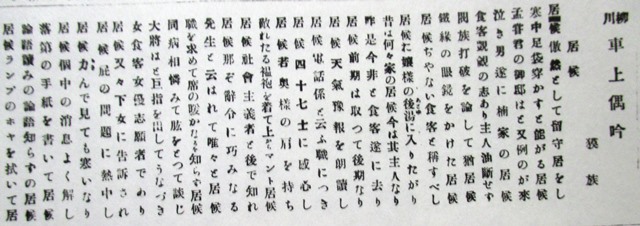
1913年3月5日『沖縄毎日新聞』玉代勢法雲「病室より」①
1913年3月6日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉麦門冬)「俳句に現はれたる巫女(1)」
○時節柄沖縄のユタとは少し異なれども本土の巫女一名神子それも我俳諧の畑に出てたるものを一寸紹介して見よう。序に注釈まで附け加えて置く
河内路や東風吹き送る巫女が袖 蕪村
河内路と云ふと何だか暖かい野道を連想する一望尽きざる長い道が通って所々にポッチリと菜の花が咲きこぼれている。野川の薄氷も漸う融けかかり一体の空気が裕ったりと落着いた気分で道行く人の足の歩みも自づと緩りになるこの背景を前にして芝居なら花道から白衣の長い袖をひるがえして若い巫女が東風に吹き送られて出て来る袖がひらひら裳裾がほらほら丁度土蜘の狂言に出る巫女のやうな装ひであらう薩張りした清い感じのする句振りである作者蕪村は巫女が好きだったと見えて此外にも二三種作ってある。
1913年3月7日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉麦門冬)「俳句に現はれたる巫女(2)」
○春風や廻廊下る巫女か袖 満米
今しも神楽堂で神すずしめの朝神楽が終わり古香人を襲ふて幽然たる社殿を廻りて更に続く廻廊を小忌衣の袖長う垂れシュツシュツと衣すれの音して下り来るみこの姿は端厳なるかなかかる時けにや彼女は人間の物にあらず白鳩のやうな神の使いのやうな思ひに人をして振り仰いて恍惚たらしむ春風吹いて普き洛陽の天地この境にこの景あり。
1913年3月8日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉麦門冬)「俳句に現はれたる巫女(3)」
○巫女町によき衣すます卯月かな 蕪村
卯月は旧暦の四月初夏の候である目に青葉山ほととぎす初鰹は江戸趣味であるがこれは京都の方邊の閑静なとある町この界隈はミコの住家が多いのでミコ町の称もある位夜は卯の花月夜にホゾンカケタカ杜鵑の聲も聞こえる所であろう。夜半亭蕪村●日この町をブラリと通りのけようとして兎ある門に逢着した卯の花の垣越しにフト見入るれば此処がミコの家であって丁度一人の女が着物を洗濯してまさに竿に通す所であったそれが清い感じのする綺麗な衣であった主の齢は五十許り打見にはまだ若い卯月の一日場所俳味津々として尽きず遂に村翁薬籠の物となった。
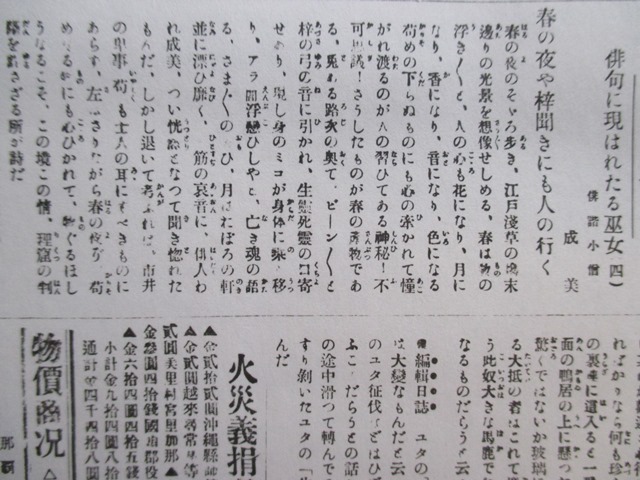
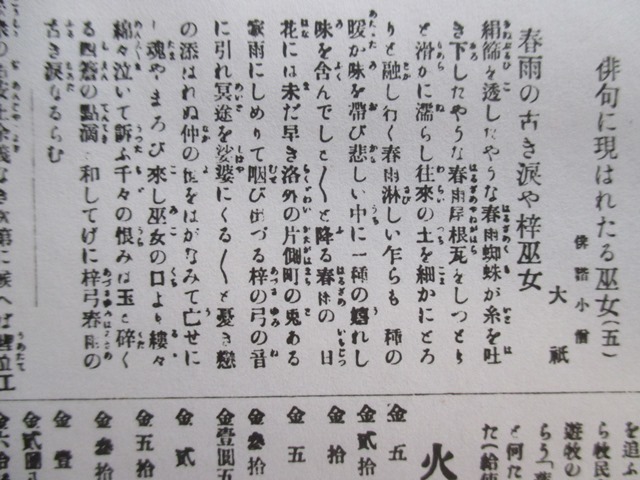
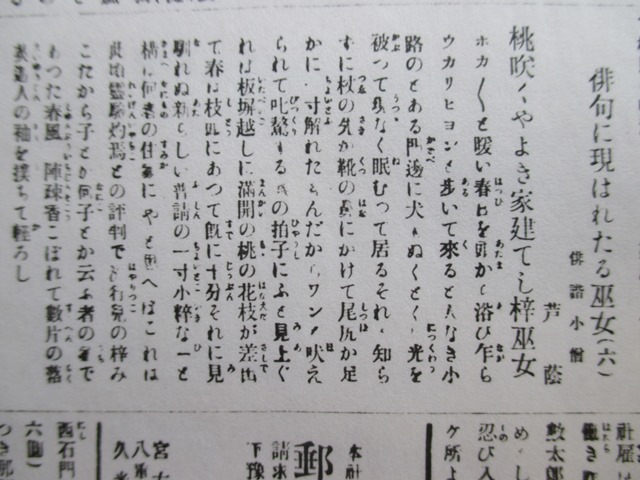
1913年7月5日『沖縄毎日新聞』南村「禁煙日誌ー煙草を吸い始めたのは確か16才の頃であったと記憶する・・・」
1913年7月8日『沖縄毎日新聞』南村「禁煙日誌ー中学での昼食時間は僕等喫煙党の最も楽しい1時間であった・・・」
1913年7月9日『沖縄毎日新聞』南村「禁煙日誌」
1913年7月10日『沖縄毎日新聞』南村「禁煙日誌」
1913年7月23日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(1)
1913年7月24日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(2)
1913年7月25日『琉球新報』松檮濤「菊栽培法に就いて」(3)
1913年7月27日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(4)
1913年7月29日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(5)
1913年8月1日『琉球新報』松檮濤「菊栽培法に就いて」(6)
1913年8月5日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(7)
1913年8月6日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(8)
1913年8月8日『琉球新報』松濤「菊栽培法に就いて」(9)
03/03: 日米誌②
1940年1月、在米沖縄県人会『琉球』7号□幸地新政「太平洋の危機と在米同胞ー第一次世界大戦の終わりと共に、来るべき世界制覇の舞台は、周知の如く太平洋に移動したのである。(略)若し、日米間に万一のことがあれば、その直接の発火点は疑いもなく蘭印問題であろう。(略)米国政府は1939年7月26日に日本政府に向かって日米通商航海条約の廃止を通告した。これは日支事変に対する米国の日本への抗議の一形態であり、さらに軍需品禁輸断行の事前工作である。米国にも日米開戦論があると同時に又、日米非戦論即ち日米親善論も決して侮るべからざるものを内包している」


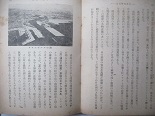
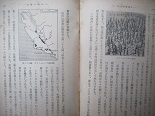
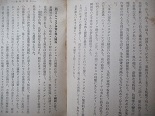
1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。
アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)
1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官
1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。
□731部隊 - Wikipediaja
初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。
原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)
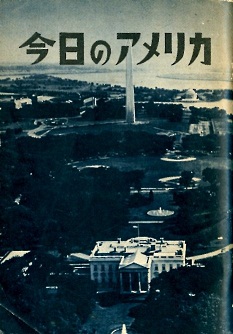

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年
1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ
1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸
1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ
1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。
1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」
1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)
1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」
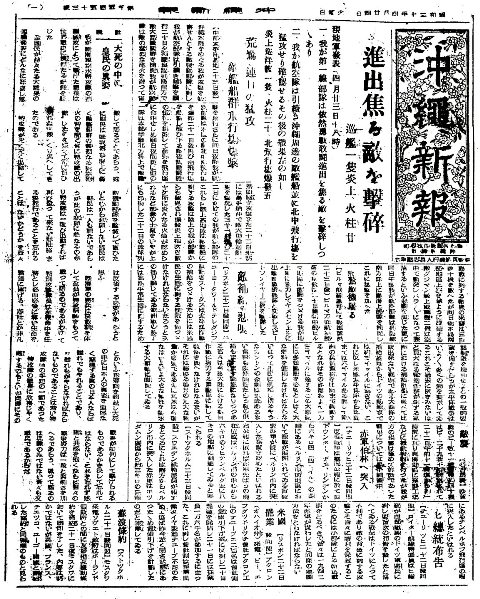
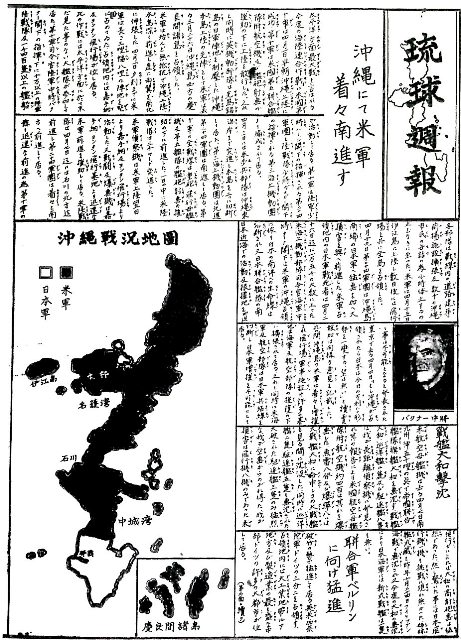
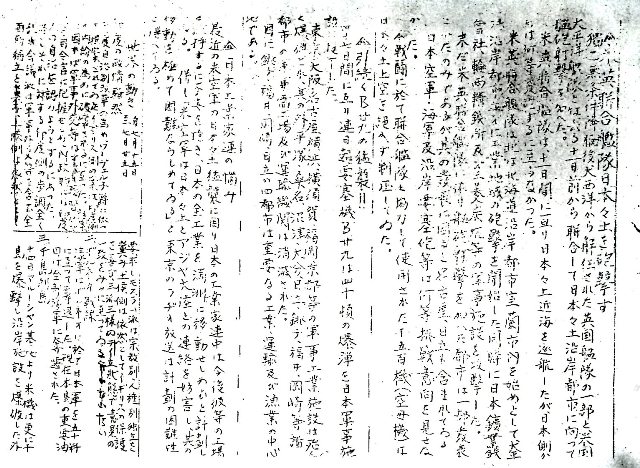
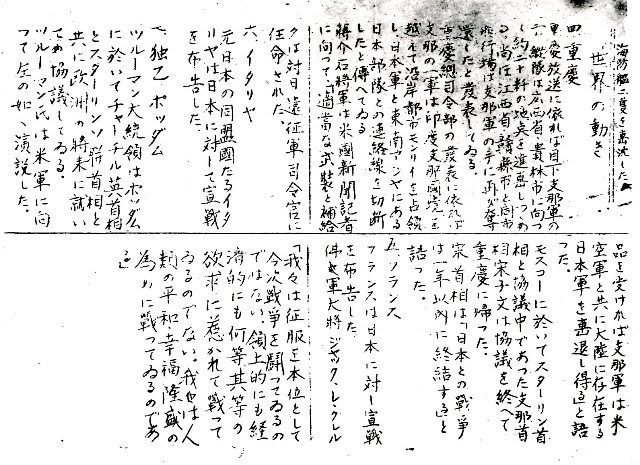
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア
1945年5月7日 石川に城前初等学校開校
1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」
1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動
1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」
1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人
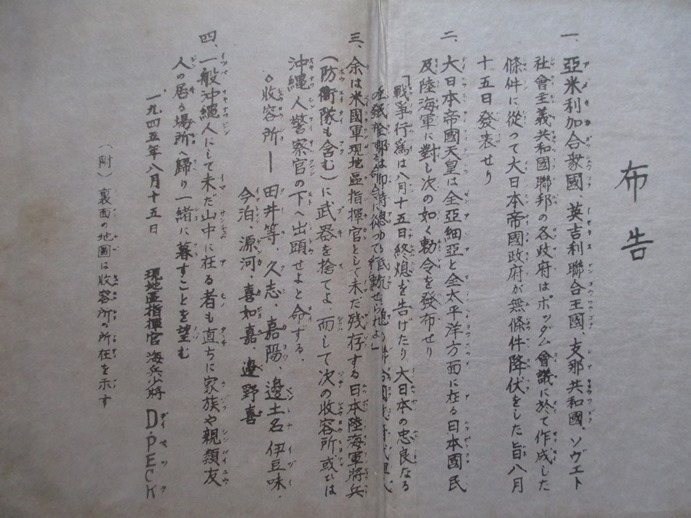
1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」
1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」
1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足
1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」
1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)
1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」
1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」
NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。
ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ
参考資料ー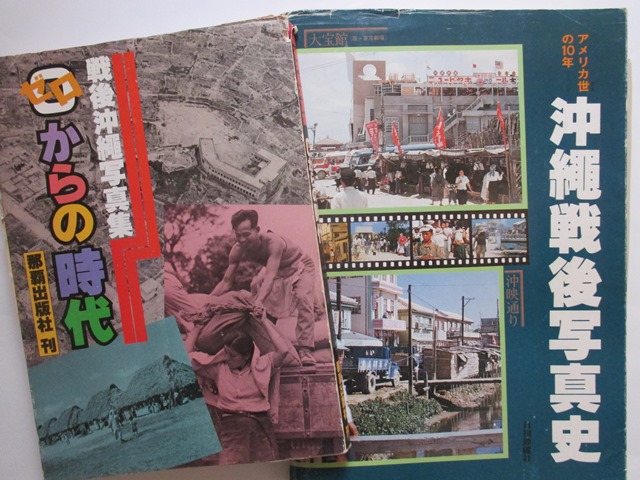
1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社
2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」
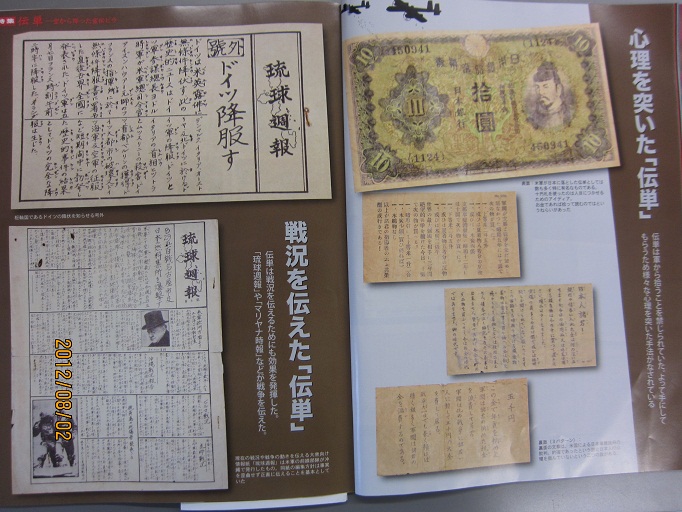
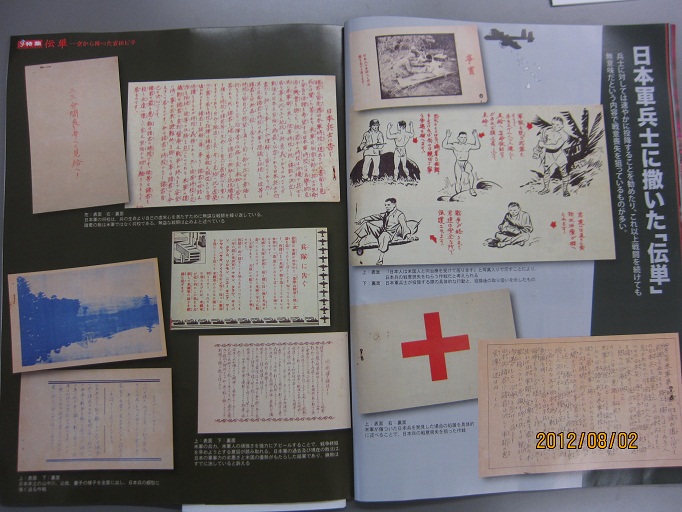
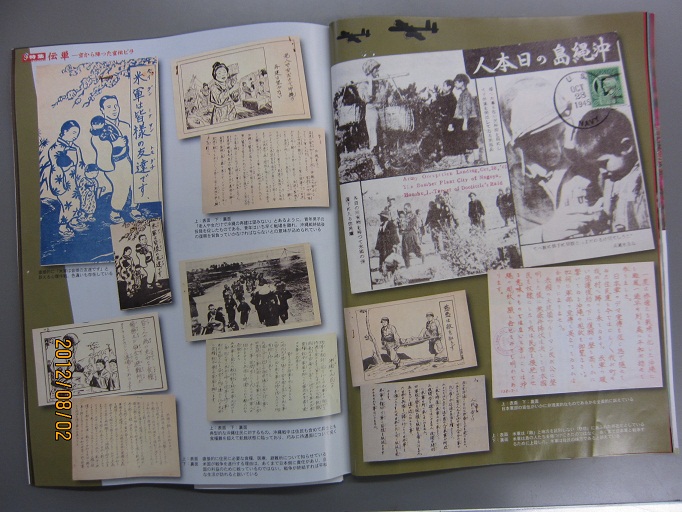
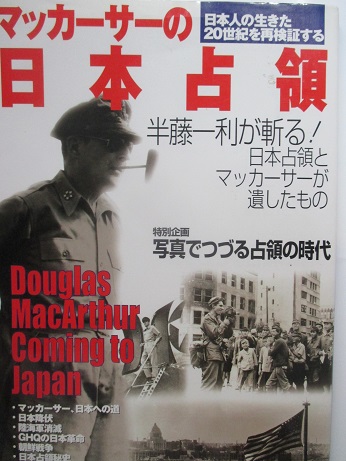
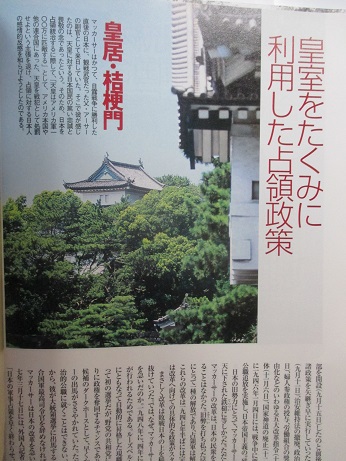
2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社
マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月
。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)
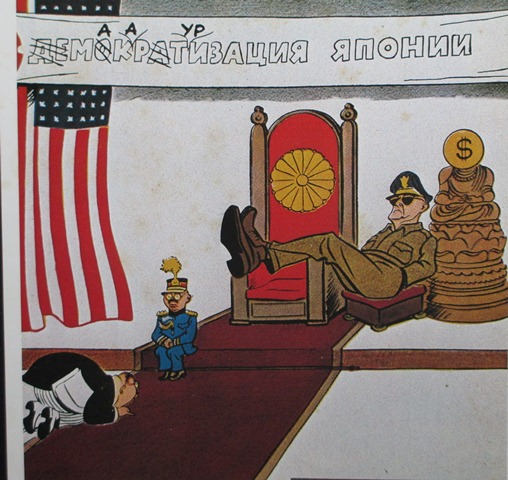
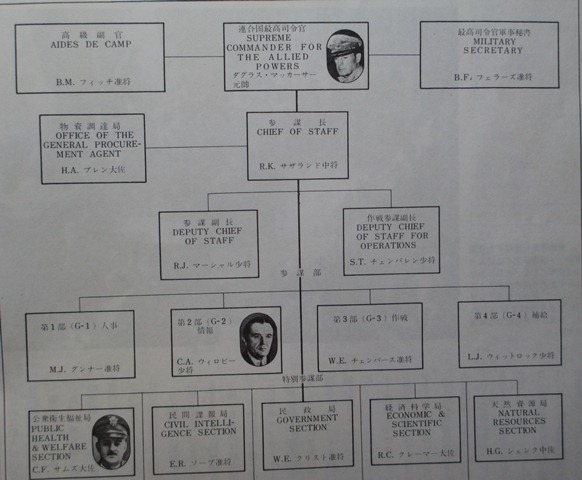
○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。
1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。
1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。
石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。
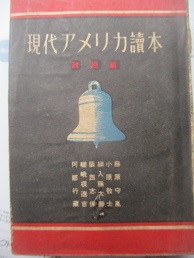
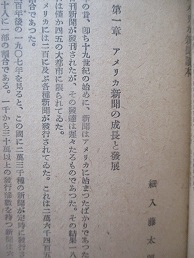

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」
1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ
1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺
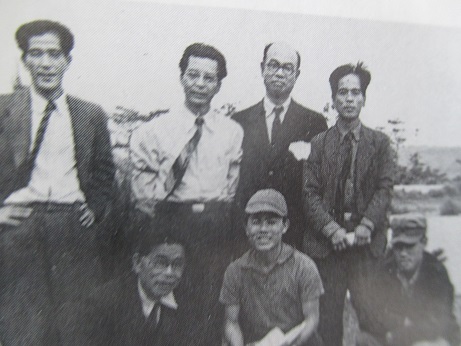
1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝


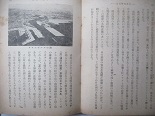
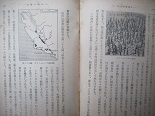
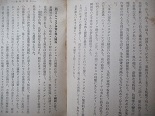
1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。
アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)
1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官
1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。
□731部隊 - Wikipediaja
初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。
原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)
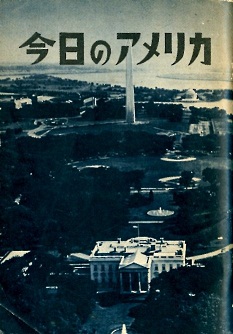

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年
1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ
1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸
1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ
1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。
1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」
1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)
1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」
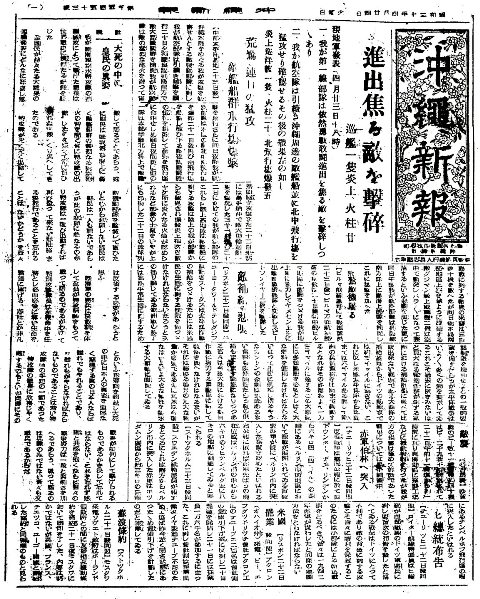
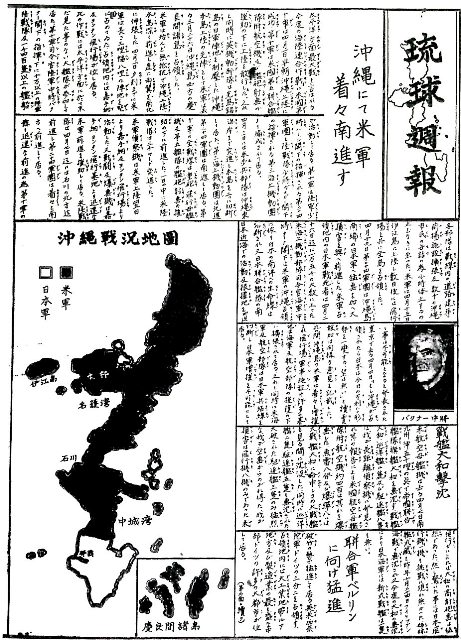
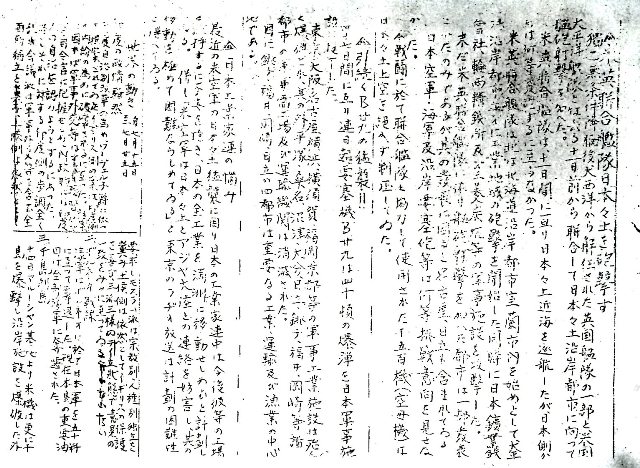
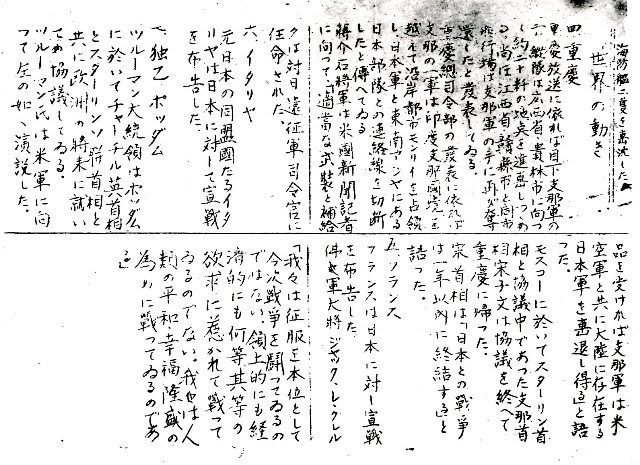
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア
1945年5月7日 石川に城前初等学校開校
1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」
1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動
1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」
1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人
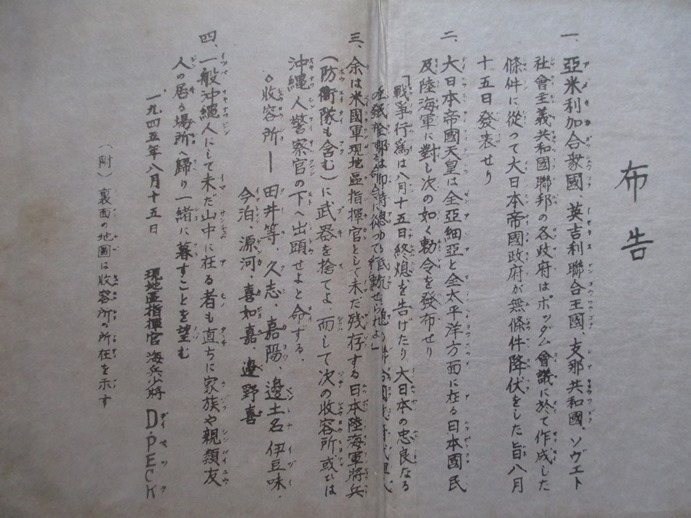
1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」
1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」
1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足
1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」
1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)
1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」
1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」
NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。
ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ
参考資料ー
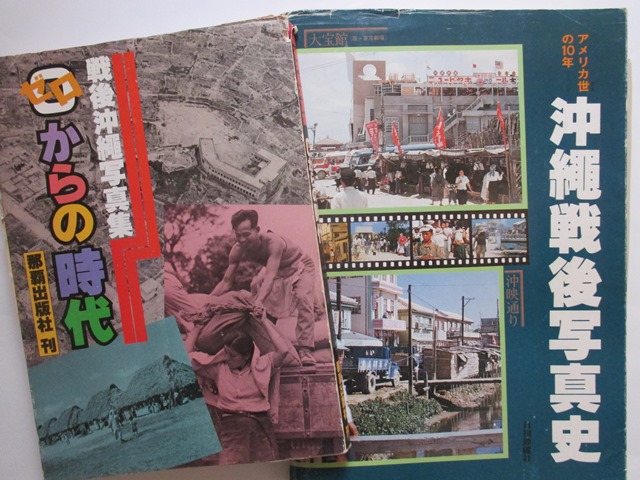
1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社
2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」
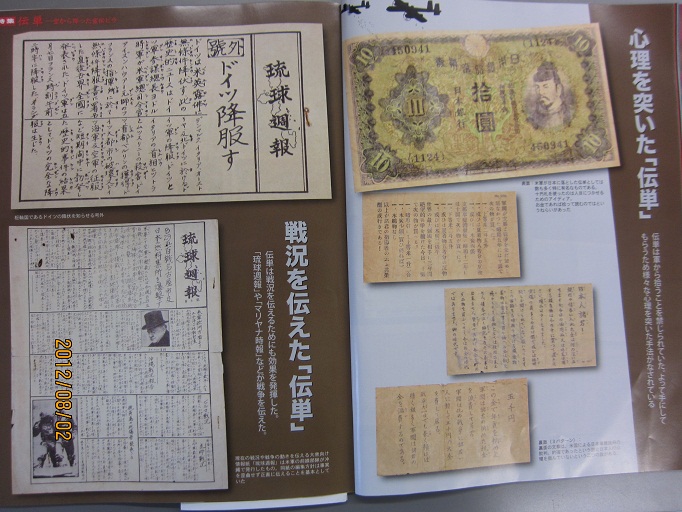
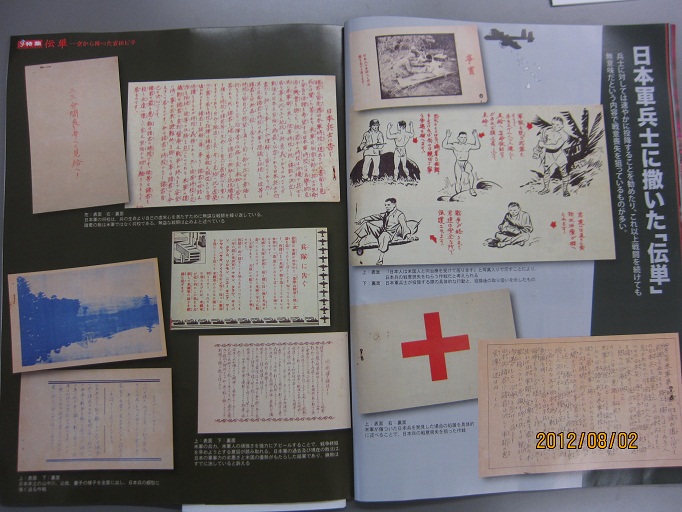
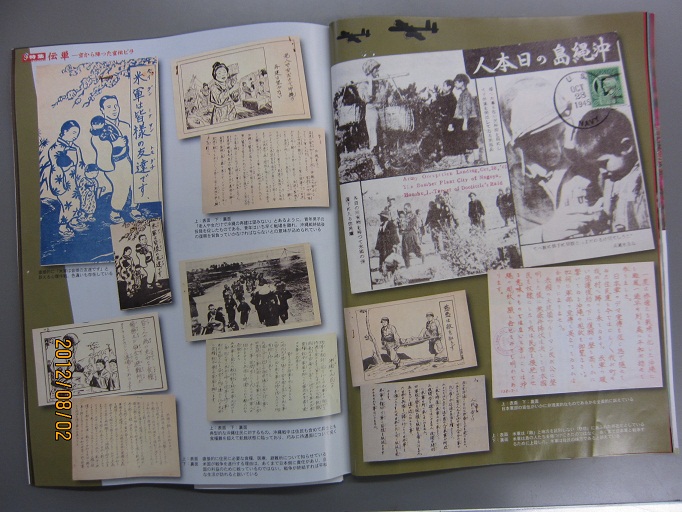
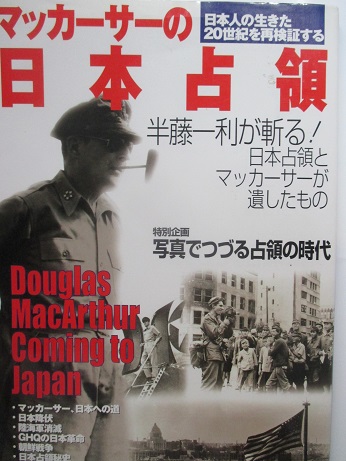
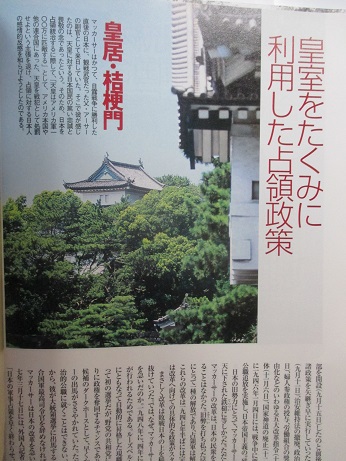
2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社
マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月
。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)
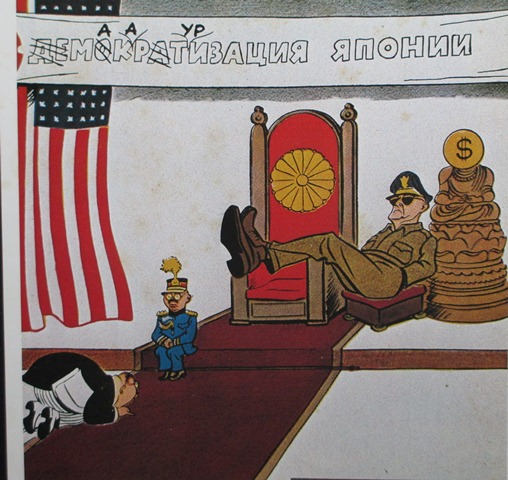
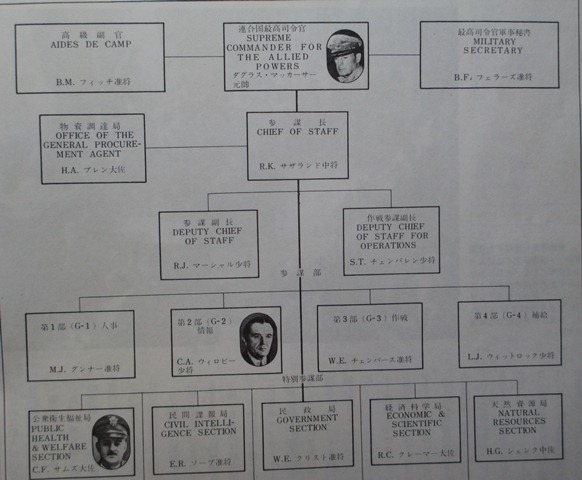
○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。
1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。
1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。
石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。
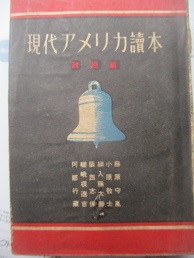
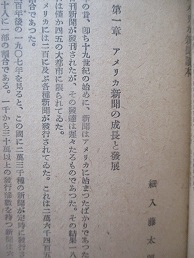

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」
1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ
1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺
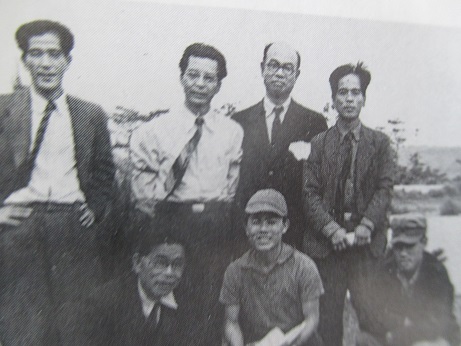
1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝
04/10: 『ペリー提督日本遠征記 』1856年アメリカ政府発刊

『ペリー提督日本遠征記』はペリー提督自身の日記とその部下の日誌や報告書などから編集された記録。同書には、琉球や小笠原諸島、浦賀や横浜、下田や箱館での様々な出来事が記され、多くの石版画や木版画の挿絵が掲載されている。挿絵は、艦隊に従軍した写真家のエリファレット・ブラウン・ジュニアが撮影したダゲレオタイプや、画家のウィリアム・ハイネらが描いた絵をもとに作成されたもの。エリファレットが当時撮影したダゲレオタイプは数枚の現存が確認できるのみで、ほとんどがいまだに発見されていない。石版画や木版画には、ダゲレオタイプをもとに作成された鮮明な画像が描かれている。→JCIIフォトサロン2019年7月
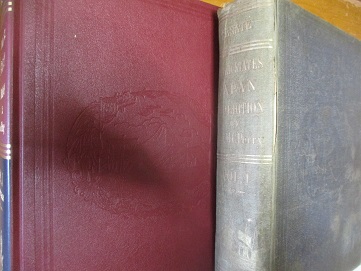
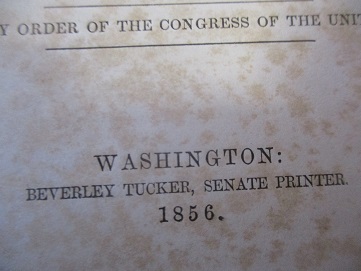
左、復刻版、右、『ペリー提督日本遠征記 』1856年アメリカ政府発刊
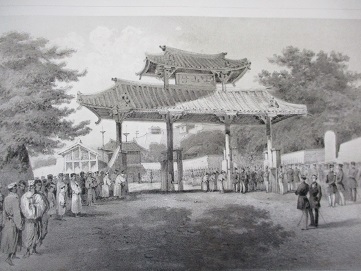
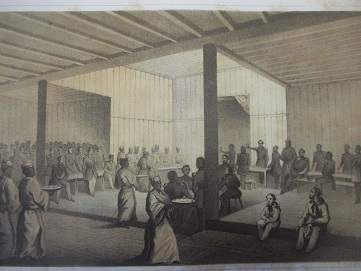


講談社の『日本写真年表』に「1853年(嘉永6)年、5月アメリカのペリー艦隊の従軍写真師Eブラウン.Jr琉球を撮影する」とあり、また那覇のニライ社から刊行された『青い眼が見た「大琉球」』の中にその撮影状況の石版刷りが掲載されている。
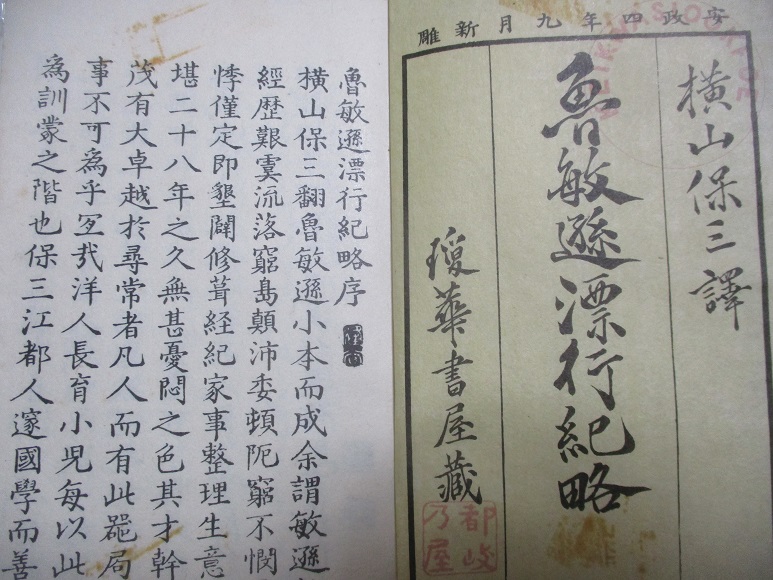
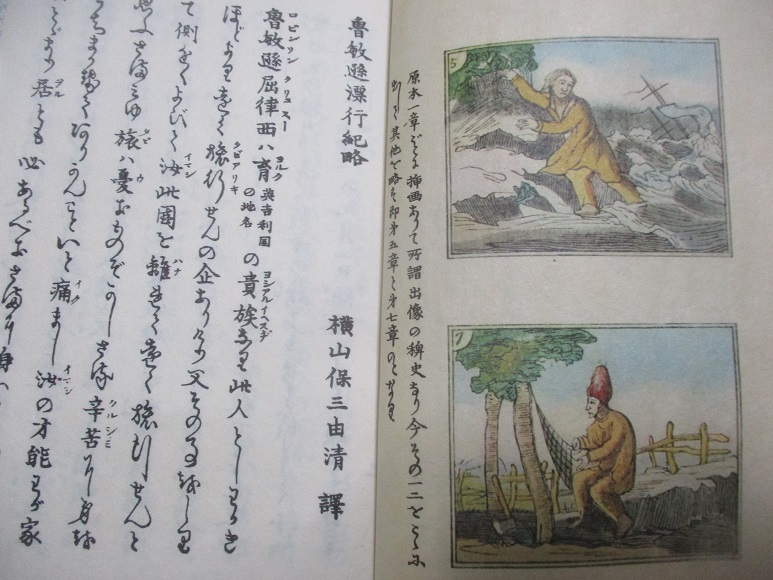
1857年年9月、横山由清訳『魯敏遜漂行紀略』。川上冬崖の色刷木版挿絵

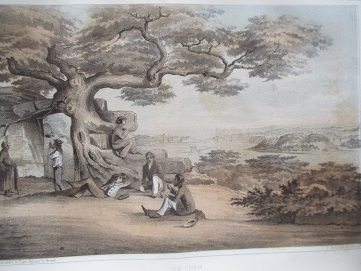
ミシシッピ号(USS Mississippi)は、米国海軍の蒸気外輪フリゲート艦である。名前はミシシッピ川に由来する。マシュー・ペリー代将の個人的な監督の下、フィラデルフィア海軍工廠で起工。1841年12月に就役した。嘉永6年(1853年)のペリーの日本来航の際の四隻の黒船の1隻。 →ウィキ
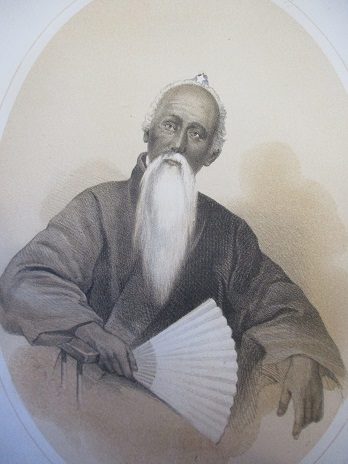
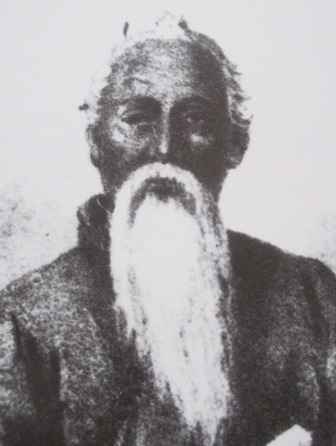
□左の石版画より右の方が末吉安扶に似ていると思われる。
1981年9月 山口栄鉄『異国と琉球』本邦書籍□付録「琉球を語る」ー師弟交信録より(外間政章先生との往復書簡)
外間ー私は先日首里儀保在住の末吉安久氏を訪ねました。氏は元首里高校の美術の先生だった方で、この方の祖父が毛玉麟のようであります。那覇長官を勤めた人は安久氏の祖父安扶だったとのこと。(略)安久氏の長兄安恭は麥門冬と号し新聞記者で有名な作家でしたが、那覇港での事故で溺死された方です。安恭氏は存命中、ブラウン(ペルリ提督一行)の描いたあの威厳のある琉球人の肖像画を見て、これは自分達のタンメーを描いたものといつも話していたそうです。(1901年6月ー末吉安扶没)
末吉麦門冬の甥で「江戸上り」研究家・佐渡山安治氏は本邦書籍発行の『江戸期琉球物資料集覧』第4巻に「琉球使節使者名簿」で1850年(嘉永3)の琉球使節の正使・玉川王子尚愼、副使・野村親方 向元模、儀衛正・魏國香ら99名の一人賛渡使・末吉親雲上を安扶としている。中に後の三司官・与那原良傑も居る。
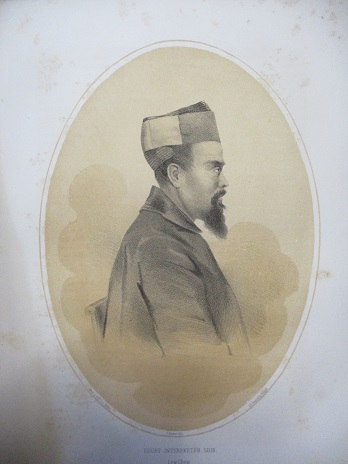
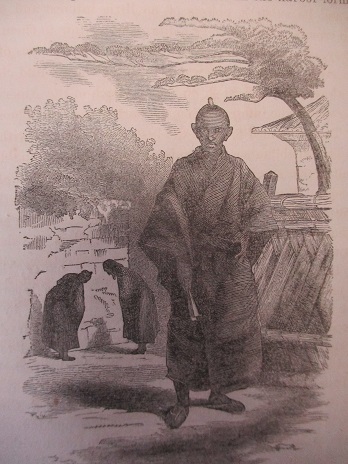
牧志朝忠 生年:尚灝15(1818)没年:尚泰15.7.19(1862.8.14)幕末期の琉球国末期の首里士族。当初は板良敷,次いで大湾,のちに牧志と称した。中国語や英語に堪能で異国通事となる。開化路線を展開した薩摩藩主島津斉彬 から目をかけられ,尚泰10(1857)年には軽輩出ながら表十五人(首里王府の評議機関)の内の日帳主取にまでのぼった。しかし,斉彬の死(1858)を契機に,首里王府内の守旧派は斉彬によって罷免された三司官座喜味盛普の後任人事をめぐる疑獄事件の首謀者として牧志,御物奉行恩河朝恒,三司官小禄良忠を逮捕・投獄した(牧志・恩河事件)。事件は牧志が鹿児島で座喜味を誹謗したことや,その後任選挙において贈賄などによる画策を図ったとの風聞に端を発していた。首里王府の守旧派は,フランス艦船購入の対外政策や斉彬路線に難色を示す座喜味の追放,国王廃立の陰謀を企てたものとの嫌疑をかけたが,明白な証拠をあげることができず,すべて牧志の自白によって審理が展開された。その結果,牧志は久米島へ10年の流刑,小禄は伊江島の照泰寺へ500日の寺入れ,恩河は久米島へ6年の流刑とされた。だが恩河は尚泰13年閏3月13日に獄死。牧志は薩摩藩によって英語教授役とするため保釈されたが,鹿児島への途上,伊平屋島沖合いで投身自殺したとされる。<参考文献>金城正篤「伊江文書牧志・恩河事件の記録について」(『歴代宝案研究』2号) (豊見山和行)

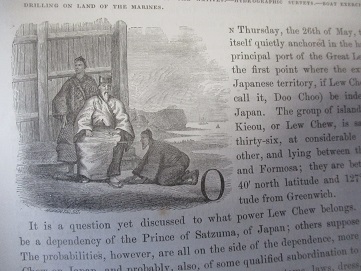


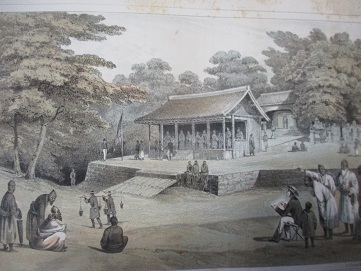
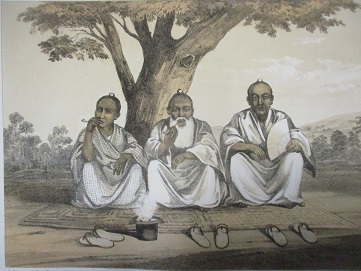
金武番所/
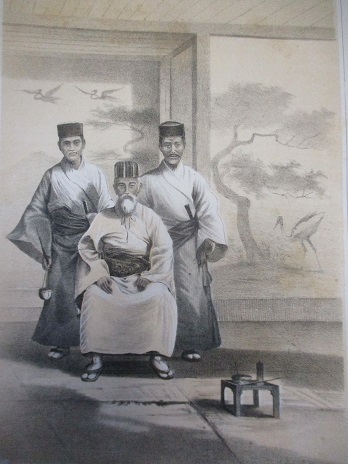

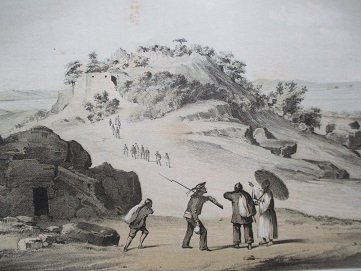

→琉球切手
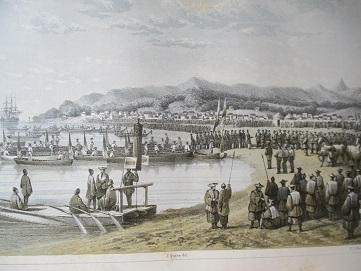
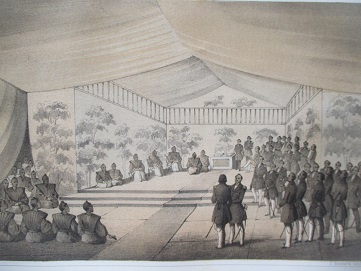

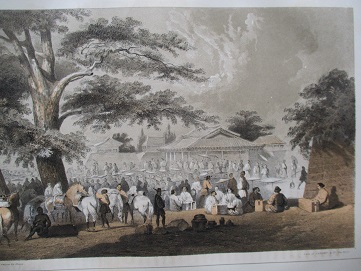
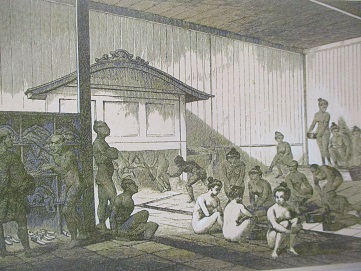

画家ハイネが実景から写生したものを、黄・淡藍・墨の3色刷の砂目石版に複製した「下田の公衆浴場の図」
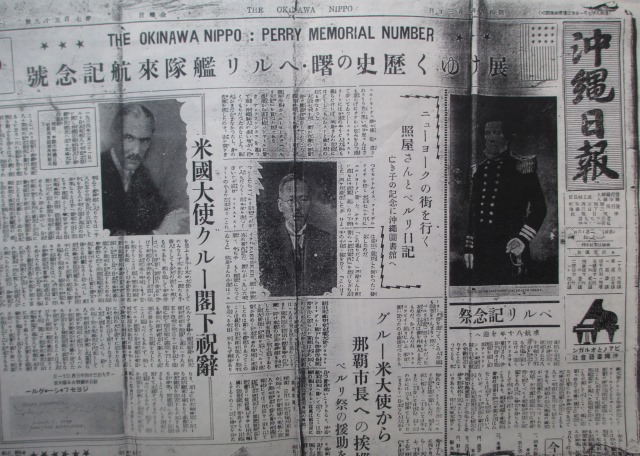

1934年3月30日ー『沖縄日報』「展けゆく歴史の曙・ペルリ艦隊来航記念号」/沖縄日報主催「ペルリ日本来航80年記念祭」講演/神田精輝・島袋源一郎
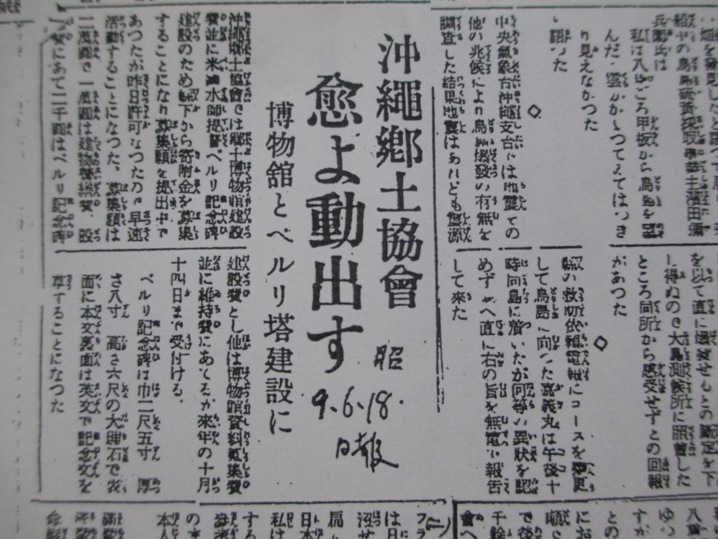
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
関連○2015年3月 『記憶と忘却のアジア』青弓社 泉水英計「黒船来航と集合的忘却ー久里浜・下田・那覇」
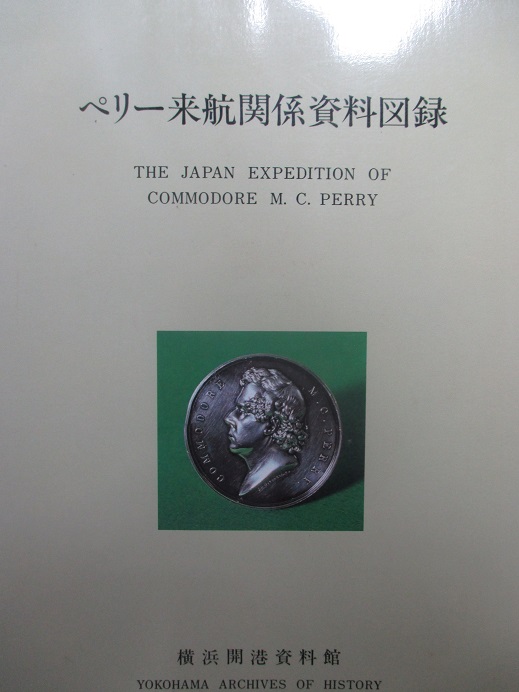
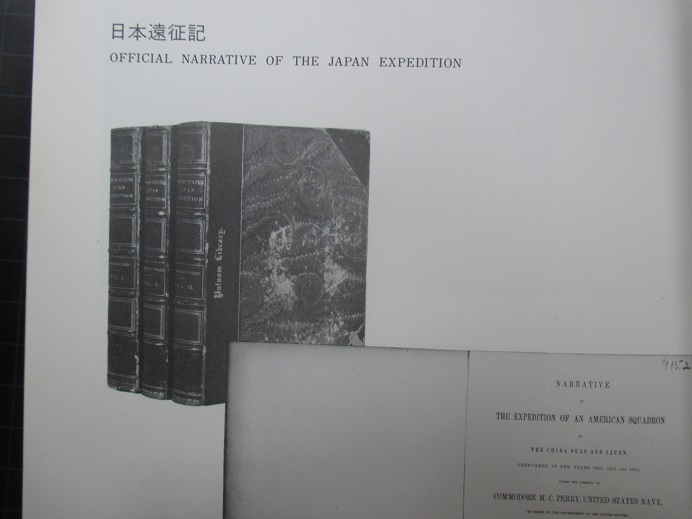
1982年3月 『ペリー来航関係資料図録』横浜開港資料普及協会
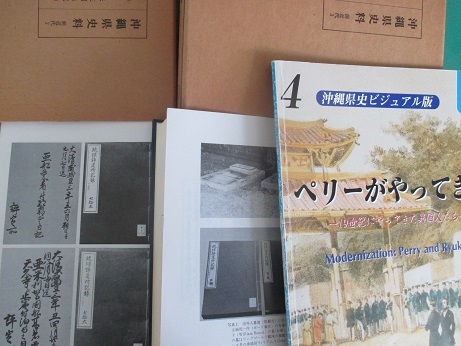
1982年3月『沖縄県史料 前近代2 ペリー来航関係記録1』沖縄県教育委員会

2003年5月30日『琉球新報』「ペリー来琉150周年」
1849年に始まる”ゴールドラッ シュ”に唯一、日本人として足 跡を残したのはジョン万次郎 だといわれる。1841年、14歳の とき漁に出て足摺岬沖で漂流、 鳥島に漂着し、幸運にも米捕鯨 船に救出されその後、捕鯨船長 他の庇護もありアメリカ暮らしと なる。当時は鎖国政策のため、 うかつに本国に戻れなかった時 代だ。望郷の念、止みがたく、帰国 に必要な資金を稼ぎ出すため ゴールドラッシュの噂を耳にし た万次郎はカリフォルニアを目 指した。金鉱で働き二カ月余り で600ドル(当時)の金を得て 1 8 5 2 年 に 首 尾 よく 帰 国 を 果 た す 。
アメ リ カ 移 民 の日 本 女 性 第 1 号ー 同じころの日本、1868年秋、 会津藩が薩摩藩・土佐藩を中心とする明治新政府軍に攻め入られ 鶴ヶ城が陥落した。翌年の春、会津に見切りをつけ、新天地カリフォルニアに渡った藩の一団があっ た。当時、会津藩に使えていたオランダ国籍のヘンリー・シュネル という人物が、農園をつくるため カリフォルニアに土地を購入「Wakamatsu Tea & Silk Farm Colony」と名付け、養蚕やお茶な どの栽培を計画したのだ。藩士と 家族37名が、開拓団に加わった。 長らく知られていなかったが、こ の一団にシュネルとその子どもの 世話係として加わった”おけい”と呼ばれる少女がいた。横浜から米船籍のチャイナ号という船に乗った 一行は、サンフランシスコに到着。 そこからは蒸気船でサクラメント 川を遡り、さらに荷馬車でゴールド ラッシュに沸くコロマ村のゴールド ヒルという原野に落ち着いた。天候 不順(干ばつ)や資金不足から、わずか2年でこの事業は失敗し解体に至る。一説には鉱山作業の影響 で近くの水源が「鉄分と硫黄」に 汚染されていたためともいわれる。
若松コロニーの存在の風化とともに人々の記憶から遠ざかる。コ ロニーも消滅して40年余が過ぎ た1915年(大正4年)の初夏、現地で農園を経営する日本人と邦字新聞「日米新聞」の記者によって, この墓が発見される。最初はなぜこんなところに19歳 の日本人女性の墓があるのか分か らなかったが、近くに住むビーアカ ンプ家を訪ねたところ、そこでおけいの存在と若松コロニーのことを知る。コロニーがなくなった後、おけいはこのビーアカンプ家に引き 取られ働き、同じように引き取られた日本人の桜井松之助らが、おけいのために現地に墓を建てたこ ともわかった。翌年、日系新聞の記 事が掲載され、大きな反響を呼び 世間の知るところとなった。訪れる人もいない墓には、「OKEI」と刻まれていた。「In Memory of OKEI Died 1871, Aged19 years, (A Japanese Girl)おけいの墓 行年一九才」。 2014年 12月、友人とコロマを訪ねた折におけいの墓のある ゴールドヒルに立ち寄った。 コロマから南に8キロほどか。


関連右〇おけいは、会津藩軍事顧問のプロシア人、ヘンリー・スネル家の子守役でした。戊辰戦争後、スネルをリーダーとする会津藩士らとともにカリフォルニアに入植しましたが、開拓に失敗、移民団は離散してしまいました。残されたおけいは、アメリカ人に引き取られましたが、熱病にかかり、19歳の短い生涯を終えました。カリフォルニア州ゴールドヒルと同様の墓が背あぶり山にたてられています。 →会津若松観光ナビ
ゴールドラッシュ時代、数多い絞首刑が行われたので、「ハングタ ウン」とも呼ばれるプラサビルへ の途中の田園地帯だ。移民団入植 から100周年を迎えた1969年には、 当時カリフォルニア州知事だった ロナルド・レーガンが若松コロ ニーの跡地をカリフォルニア州の歴史史跡に指定。同年、ゴールド・ トレイル小学校に隣接する敷地に 「日本移民百周年記念碑」が建立された。カリフォルニア州エルドラ ド郡の小学4年生は読書プログラ ムの一環で、日本からカリフォルニ アに来たおけいの生涯を伝える本 「Okei-san: A Girl’s Journey, Japan to California, 1868-1871」を読むという。 記念碑を訪ねた後、すぐ先のゴー ルドヒルに向かった。入口には倉庫 と思しき大きな木造の家があり、 Okeiに因んだフェスティバル開催 のポスターがあちこちに貼られてい た。30代ぐらいの青年と行きあっ たので”地元の方か?”と聞くと” ここに土地を借りて住んでいるが、 特段おけいとのつながりでここに いるわけではない”とのことだった。 さぁ、だいぶ先に見える丘の上まで30分とみて頂上に向かった。途中、ぬかるみや藪道もあったがのんびり歩き進むうちに丘の上についた。
丘の上にある大木は、元は150年前 に、若松コロニー開拓団が日本から 持参し植えたケヤキの苗木が育っ たものだという。西に向かって遥か 先にサンフランシスコ湾、太平洋を 挟んでその向こうが会津だ。サン フランシスコ湾まで200-300キロか。 晴れていれば海を望めるだろう。 おけいはビーアカンプ家に世話に なっていた時にもこの丘の上まで 足を運んだ。ひとしきり登り道を歩 いて汗をかいた。四方を見渡して 150年前も今もこのあたりの風景は あまり変っていないのかも知れな いと思った。 補遺;2019-6-19日本から最初 にアメリカ本土に入植した移民団 がカリフォルニア州北部ゴールド ヒルにアメリカ本土初の日本人入 植地「若松コロニー」を形成してから8日で150年を迎えた。同日、跡地では記念式典が行われ、日米にいる移民団の末裔や関係者らが 出席。会津松平家の末裔も日本から訪れた。→『鍍金の世界』2019年11月号 屋良朝信「旅の記憶」
麦夢忌/田原煙波
1924年12月14日『沖縄タイムス』/田原煙波①「俳友麦門冬を痛む」
○今まで障子に明るかった冬の日陰に失 したように薄れ行くを見つめて滅入るような淋しさを覚えている矢先君の死を聞かされた私は、物語る人の顔と口元とを見比べて、ただボンヤリと耳を傾けるより外はなかった。気の毒な事をした、惜しい事をしたといふ思が、それからそれへとひっきりなしに胸に湧いて来る。●●れ、やがて君のありし日の面影や、どん底からの表情が私の印象に蘇生へって来るのであった。君と相知ったのはたしか、明治四十●年の夏の頃、紅梯梧君の宅で亡三念③君の紹介によってであったと覚えている。其の年の秋亡柴舟君の宅で沖縄で初めての子規忌句会を催した時に君は「糸瓜忌や叱咤に洩れし人ばかり」といふ句を吐いて、私をして君の俳想凡ならずと感せしめたのであった。これより先、紅梯梧、(山下)紫海、私とが相合して沖縄俳界の革命者として自認し、三念其他の同志を糾合して在来の月並派に反旗を翻したのであったが其後更に亡楽山④と共に蘇鉄吟社を結んで、月並派を駆逐したのであった。然し私等の進みは遅れた。
君はやがて第二の革命者として名乗りをあげたのである。それは私等が子規派の句にたるみを感じて、碧梧桐先生一派の新傾向の句を研究せむとする頃、たまたま碧梧桐先生が来県せられた時、君は「潮ガボと吸ふ磯田 蘭刈●す」といふ句を発表して先生の賛辞を得たので私等は茲に目醒めざるを得なかったのである。私等は覚めた、そして連夜新傾向の句を批評し、感味した、やがて今迄の日本派が去って新傾向派として立つようになったのは慥かに君によって啓発された或物を感じたからであったのである。其後三念去り、楽山逝き、同人相離れて、いつの間にか君も私も俳界を遠ざかる様になったが、最近君の研究は学者として史家として世の造詣を深くするに至り、詩才は更に延びて漢詩に及び 優に一家をなすまでに心境を見たのであったが、惜しい事をした、もうこの世の人ではない。手元に遺っている君の旧作を漁りつつあり●昔の追憶に耽る時、北荒れの強い風と浪の音にまじって千鳥が寂しげに啼いている。君の魂は定めて君自身の道に躍進しつつあるであらふ、嗚呼
悼句 「君逝くと聞く薄るる冬日」「独りはぐれて野冬行く人」「遺句拾ひ偲ぶ千鳥啼く夜なり」「寒さしみじみと浪の音荒れて」
①田原煙波
1882年8月5日~1934年11月7日 本名・法馨。俳人・星佛、白水居。真教寺住職。那覇西村生まれ。1906年(明治39)東京真宗大学卒業。翌年、西新町において真教寺幼稚園創設、初代園長となる。
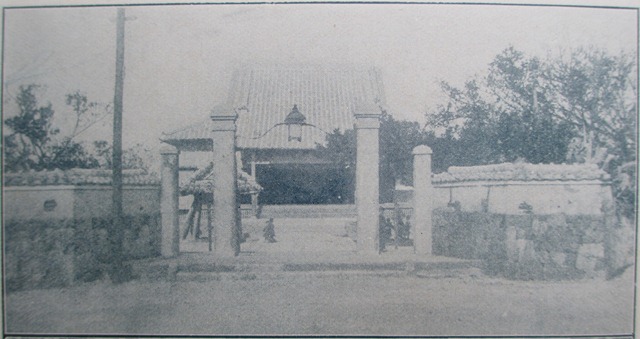
那覇の眞教寺
③三念・髙江洲康健
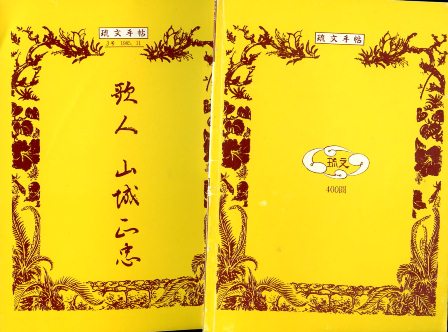
『琉文手帖』「歌人 山城正忠」
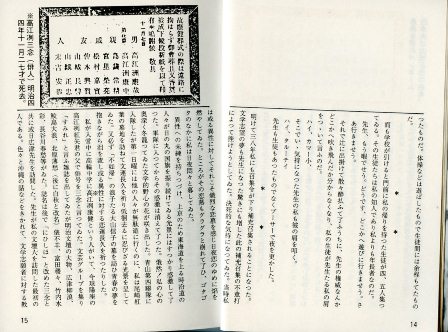
□私が入営中に高輪中学に髙江洲康健という人がいて、今、球陽座の髙江洲紅矢君の父で俳号を三念と言っていた。(『琉球新報』1932年5月)
④楽山・薬師吾吉
1924年12月14日『沖縄タイムス』/田原煙波①「俳友麦門冬を痛む」
○今まで障子に明るかった冬の日陰に失 したように薄れ行くを見つめて滅入るような淋しさを覚えている矢先君の死を聞かされた私は、物語る人の顔と口元とを見比べて、ただボンヤリと耳を傾けるより外はなかった。気の毒な事をした、惜しい事をしたといふ思が、それからそれへとひっきりなしに胸に湧いて来る。●●れ、やがて君のありし日の面影や、どん底からの表情が私の印象に蘇生へって来るのであった。君と相知ったのはたしか、明治四十●年の夏の頃、紅梯梧君の宅で亡三念③君の紹介によってであったと覚えている。其の年の秋亡柴舟君の宅で沖縄で初めての子規忌句会を催した時に君は「糸瓜忌や叱咤に洩れし人ばかり」といふ句を吐いて、私をして君の俳想凡ならずと感せしめたのであった。これより先、紅梯梧、(山下)紫海、私とが相合して沖縄俳界の革命者として自認し、三念其他の同志を糾合して在来の月並派に反旗を翻したのであったが其後更に亡楽山④と共に蘇鉄吟社を結んで、月並派を駆逐したのであった。然し私等の進みは遅れた。
君はやがて第二の革命者として名乗りをあげたのである。それは私等が子規派の句にたるみを感じて、碧梧桐先生一派の新傾向の句を研究せむとする頃、たまたま碧梧桐先生が来県せられた時、君は「潮ガボと吸ふ磯田 蘭刈●す」といふ句を発表して先生の賛辞を得たので私等は茲に目醒めざるを得なかったのである。私等は覚めた、そして連夜新傾向の句を批評し、感味した、やがて今迄の日本派が去って新傾向派として立つようになったのは慥かに君によって啓発された或物を感じたからであったのである。其後三念去り、楽山逝き、同人相離れて、いつの間にか君も私も俳界を遠ざかる様になったが、最近君の研究は学者として史家として世の造詣を深くするに至り、詩才は更に延びて漢詩に及び 優に一家をなすまでに心境を見たのであったが、惜しい事をした、もうこの世の人ではない。手元に遺っている君の旧作を漁りつつあり●昔の追憶に耽る時、北荒れの強い風と浪の音にまじって千鳥が寂しげに啼いている。君の魂は定めて君自身の道に躍進しつつあるであらふ、嗚呼
悼句 「君逝くと聞く薄るる冬日」「独りはぐれて野冬行く人」「遺句拾ひ偲ぶ千鳥啼く夜なり」「寒さしみじみと浪の音荒れて」
①田原煙波
1882年8月5日~1934年11月7日 本名・法馨。俳人・星佛、白水居。真教寺住職。那覇西村生まれ。1906年(明治39)東京真宗大学卒業。翌年、西新町において真教寺幼稚園創設、初代園長となる。
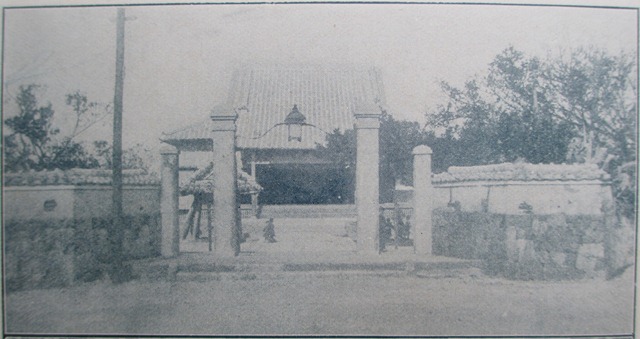
那覇の眞教寺
③三念・髙江洲康健
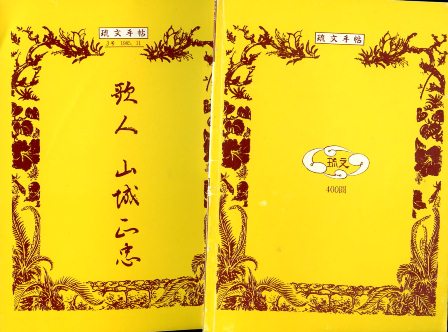
『琉文手帖』「歌人 山城正忠」
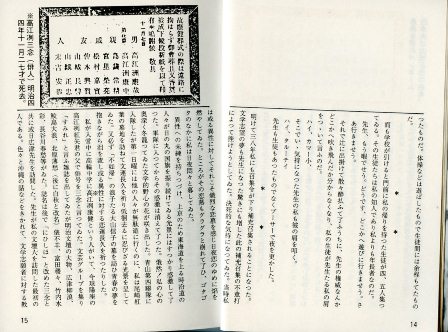
□私が入営中に高輪中学に髙江洲康健という人がいて、今、球陽座の髙江洲紅矢君の父で俳号を三念と言っていた。(『琉球新報』1932年5月)
④楽山・薬師吾吉
01/01: 元旦(旧12月8日)「密約復帰40周年」
本日は元旦。旧暦のムーチーの日、新暦の12月8日は太平洋戦争開戦の日。その結果の「密約復帰」から40周年の幕開けである。昼は屋部公子さん、山田實さんに若水(前日ー末吉宮近くの湧水をペットボトルに汲み、その帰途、宮里朝光翁と出会う)を持参。若水は沖縄県立博物館・美術館のトーゥジなどにかける。
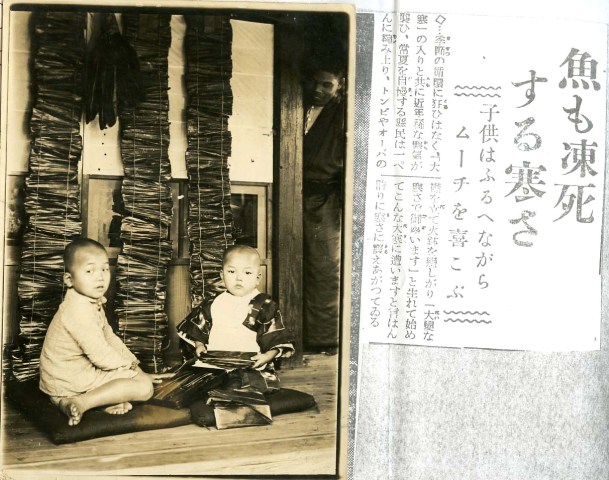
下「ムーチーづくり」(絵/親泊英繁)
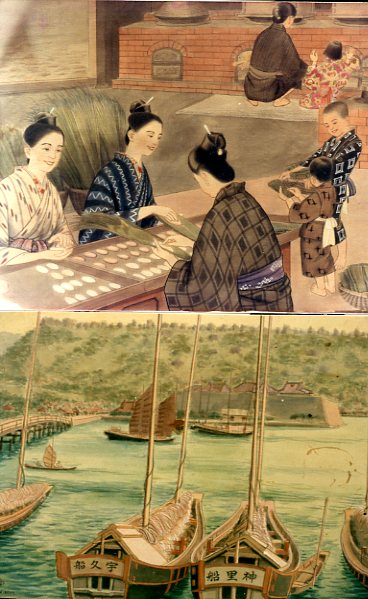
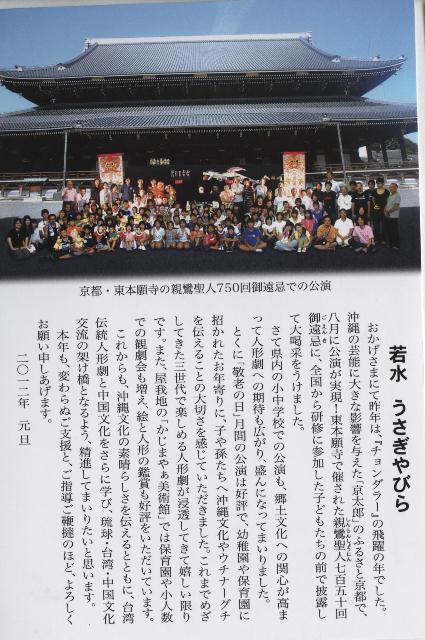
人形劇団かじまやぁ・名護市字済井出226-2 ☏FAX0980ー52-8084 携帯090-2513-6255
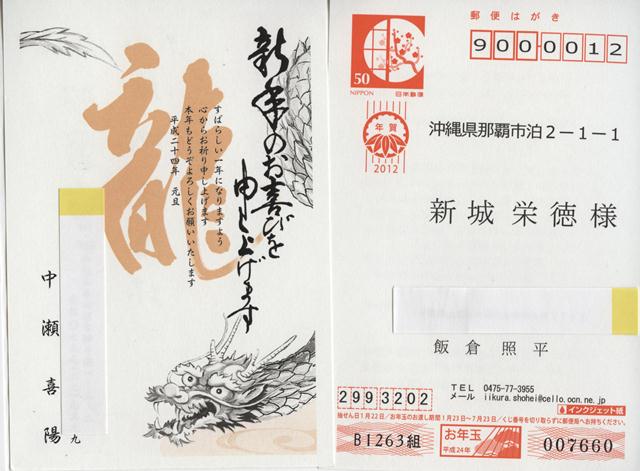
上の年賀状は末吉麦門冬関連での交流の方々である。
中瀬喜陽氏
1933年和歌山県生まれ。東洋大学文学部卒業。高校教諭を経て、現在、南方熊楠顕彰会副会長、田辺市文化財審議会委員長。著書に『覚書南方熊楠』『南方熊楠独白』、共編に『南方熊楠アルバム』等がある。
飯倉 照平氏
1934年生まれ。中国文学者。南方熊楠研究で著名、東京都立大学名誉教授。
千葉県生まれ。東京都立大学中国文学科卒業。出版社勤務、神戸大学文学部講師、東京都立大助教授・教授、1998年定年退官。『南方熊楠全集』、『同選集』(平凡社)の校訂、中国民話の会世話人、南方熊楠邸保存顕彰会で資料整理・刊行に当たっている。2004年に南方熊楠賞特別賞受賞。
うちなー正月(そーがち)でーびる
若(わか)太陽(てぃーだ) 拝(うが)でぃ 若水(わかみじ)ゆ孵(す)でぃてぃ 美(きゆ)ら世(ゆ)・沖縄 うんぬきやびら
2011年は、いろいろと大変な年でしたが、被災地の気仙沼高校3年生今野さんの「止まらずに 私は未来(つぎ)に 進んでく 隣に君が いないとしても」の歌に勇気をもらいました。
昨年は、第4次糸満市総合計画の答申、泊小学校創立130年、第3回沖縄民衆議会、南城市市民大学、沖縄県地域史協議会30年記念事業、福州市・山東省曲阜の孔子廟訪問、那覇市立博物館講座などに関わりましたが、初孫の誕生、手術入院などもあり、本当にいろいろでした。
旧臘、中城城址で冬至明けの若太陽に、新年は摩文仁の平和祈念堂の火祭、地元安里の拝所巡りと、万感の思いで新しい年の平穏と幸せを祈りましたが、今年は沖縄返還40年。沖縄の基地問題、地域自治、原発、災害の復旧・復興や今後の対策、社会保障、雇用や経済格差など、根本から変らなければとの思いを一層深くしています。
本年も、引き続き、ご指導ご厚誼の程お願い申し上げます。
2012年壬辰 旧正月
学校法人沖縄大学理事・同客員教授
真栄里 泰山
俳句同人誌『天荒』41号□編集・発行人 野ざらし延男 〒904-0105北谷町字吉原726番地の11 電話FAX098-936-2536
□俳句も今や国際化の時代である。季語の自縛から解放し、グローバルな視点での俳句文学の自立が問われている。(延男)
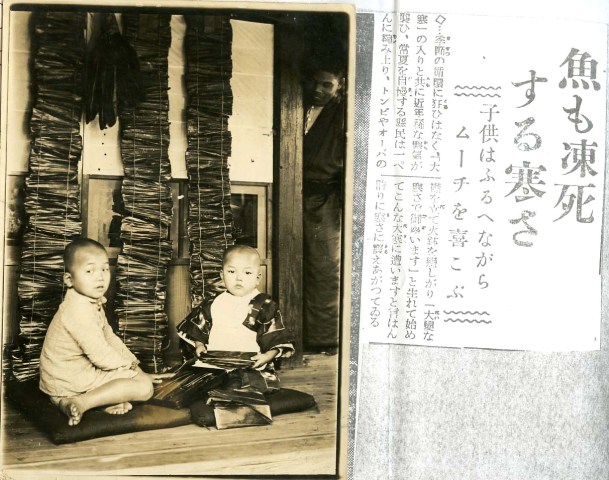
下「ムーチーづくり」(絵/親泊英繁)
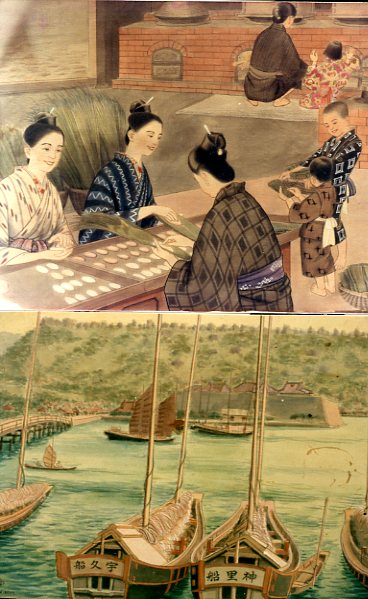
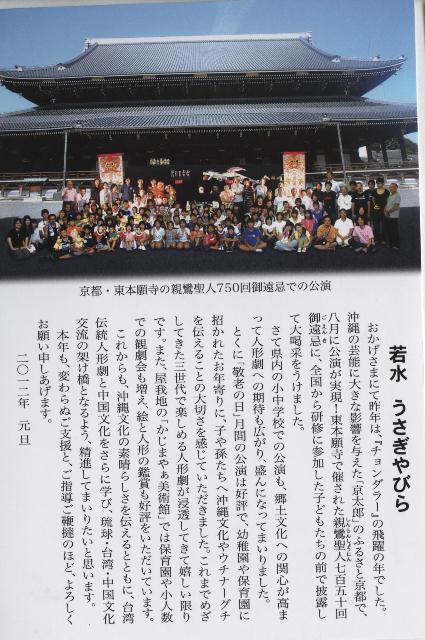
人形劇団かじまやぁ・名護市字済井出226-2 ☏FAX0980ー52-8084 携帯090-2513-6255
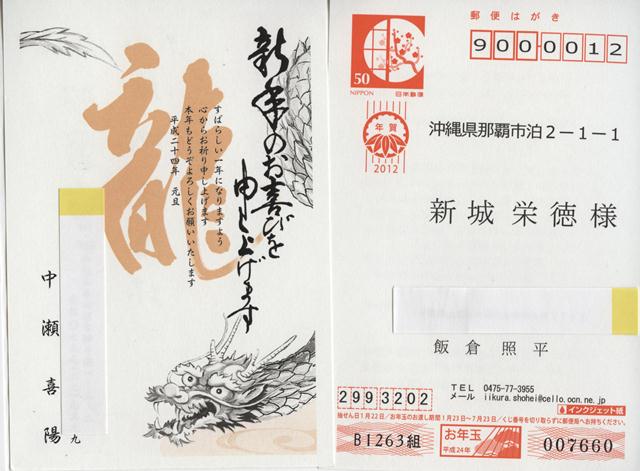
上の年賀状は末吉麦門冬関連での交流の方々である。
中瀬喜陽氏
1933年和歌山県生まれ。東洋大学文学部卒業。高校教諭を経て、現在、南方熊楠顕彰会副会長、田辺市文化財審議会委員長。著書に『覚書南方熊楠』『南方熊楠独白』、共編に『南方熊楠アルバム』等がある。
飯倉 照平氏
1934年生まれ。中国文学者。南方熊楠研究で著名、東京都立大学名誉教授。
千葉県生まれ。東京都立大学中国文学科卒業。出版社勤務、神戸大学文学部講師、東京都立大助教授・教授、1998年定年退官。『南方熊楠全集』、『同選集』(平凡社)の校訂、中国民話の会世話人、南方熊楠邸保存顕彰会で資料整理・刊行に当たっている。2004年に南方熊楠賞特別賞受賞。
うちなー正月(そーがち)でーびる
若(わか)太陽(てぃーだ) 拝(うが)でぃ 若水(わかみじ)ゆ孵(す)でぃてぃ 美(きゆ)ら世(ゆ)・沖縄 うんぬきやびら
2011年は、いろいろと大変な年でしたが、被災地の気仙沼高校3年生今野さんの「止まらずに 私は未来(つぎ)に 進んでく 隣に君が いないとしても」の歌に勇気をもらいました。
昨年は、第4次糸満市総合計画の答申、泊小学校創立130年、第3回沖縄民衆議会、南城市市民大学、沖縄県地域史協議会30年記念事業、福州市・山東省曲阜の孔子廟訪問、那覇市立博物館講座などに関わりましたが、初孫の誕生、手術入院などもあり、本当にいろいろでした。
旧臘、中城城址で冬至明けの若太陽に、新年は摩文仁の平和祈念堂の火祭、地元安里の拝所巡りと、万感の思いで新しい年の平穏と幸せを祈りましたが、今年は沖縄返還40年。沖縄の基地問題、地域自治、原発、災害の復旧・復興や今後の対策、社会保障、雇用や経済格差など、根本から変らなければとの思いを一層深くしています。
本年も、引き続き、ご指導ご厚誼の程お願い申し上げます。
2012年壬辰 旧正月
学校法人沖縄大学理事・同客員教授
真栄里 泰山
俳句同人誌『天荒』41号□編集・発行人 野ざらし延男 〒904-0105北谷町字吉原726番地の11 電話FAX098-936-2536
□俳句も今や国際化の時代である。季語の自縛から解放し、グローバルな視点での俳句文学の自立が問われている。(延男)
1909年3月19日ー『沖縄毎日新聞』伊波月城「誓閑寺時代の回顧」(以って入社の辞に代ふ)9年前のことである。家兄が京都に行った後で、迷子同様になった自分は、当時國光社に居られた恩師田島隋々庵氏の京橋南小田原町の僑居に這入り込むことになった所が、元来閑静な所が好きな自分は、間もなく牛込は喜久井なる誓閑寺に、今の甲辰の校長東恩納氏と同居して自炊することになった。お寺に引越したのは8月の上旬である。日はよくは覚えていないが、恰度同郷の友人を誓閑寺の隣なる大龍寺の墓地に葬ってから2日目の夕暮れであった。お寺は浄土宗で、住職の外に、小学校に通う子供と仙台辺の田舎者だと云う婆さんがいた。その婆さんが住職の梵妻なので、住職より10歳も老けて見えた。自分は三畳の室をあてがわれた。室は南向きで風通しはよかったが、戸端から一間先に、墳墓が並んでいたのには、聊か閉口した。併し後では墳墓と親しむようになった。自分が今日墓畔を逍遥するを一種の快楽とするようになったのは詩人イプセンの感化ばかりでもないのである。10日位たつと当間浮鷗氏が其の親戚の外間氏と共に引越して来て仲間になった。それから間もなく諸見里南香氏が上京された。沖縄時論が解散したので、この10年間は郷里には帰れないといって居られた。南香氏は10日ばかりすると日本新聞の記者となられた。誓閑時は俄かに賑わったのである。
8月中は、学校が休みなので、何れものんきに法螺を吹いて暮らしていた。朝は木魚の音と読経の声に目が覚める。総がかりで朝飯の支度をする。朝飯がすむと銘々で散歩に出かける。散歩から帰って来ると昼飯の用意に取りかかる。昼飯がすむと、下町の方に出かけるものもあれば、華胥の國に遊ぶのもいた。共同生活の快楽は一つ釜から飯を食べるということである。併し社会主義というものが、到底地上で行われるべきでないと思ったのはこの時である。一番戦闘力が強かったのは東恩納氏で、一番戦闘力が弱かったのは外間氏であった。外間氏は列強の略奪に遭って泣き出したこともある。浮鷗氏は此頃からの潔癖家である。東恩納氏は有名な無精者で、自分が座っていた2尺平方の掃除も碌にしなかった位である。南香氏は郷里で奮闘した結果、意気消沈してしまって、何らの特色も発揮しなかった。自分は其時からの酔漢で、5名のうちで酒屋の信用が一番重かった方である。
木魚の音と読経の声は聞きなれると心持のよいものである。浮鷗氏が禅味を帯び始めたのもこの頃からであろう。自分が耶蘇に帰依したのも此頃である。誓閑寺時代は自分に取っては忘れることの出来ない時代である。今から考えて見ると誓閑寺の一隅は沖縄の社会の或る一部の縮図であった。9月になって皆下町の方に引越した。思えば昨今のことのようであるが、足かけた年になる。自分は依然たる呉下の旧阿の蒙である。
毎日紙の発刊当時、自分は社友となって、いかがわしい翻訳物を出して世の物笑となって居る所に、去る15日の朝、當間氏から来て呉れとの手紙を受けて、早速いって見ると記者にするつもりであるが如何かとのことであった。自分は一人で決定が出来ないので、帰ってきて家兄と相談した後で承諾と云う意味の手紙を出した。所が文章一つ書けけない自分がどうして記者などになれる。家兄に聞くと君が平常使用している普通語で、君の思想感情を飾りなく、、偽りなくせんじつめて吐き出せ。形容詞も知らなければ知らないでいい。漢字も知らなければ知らなくてもいい。只だ耳障りにならないように書け、10年も書いたらいくらか物になるとのことである。自分は此教訓に遵って書くつもりである。
新聞を起こして見ようということは誓閑寺時代から先輩諸氏が口ぐせのようにいっていたことであるが、10年後の今日この小理想は漸く実現せられて、自分までが編集室の一椅子を占めるようになった。さアこれから自分は、どういう方面に、どう働いたらよかろう?心配でたまらない。(をはり)
◇新宿区喜久井町61 亀鶴山易行院誓閑寺 深川靈嚴寺末
寛永七年靈岸嶋に起立、明暦大火後宗参寺領の内庚申塚に借地移轉。寛文六年七月喜久井町に移る。開山重蓮社本譽上人誓閑和尚、寛永二年五月十五日卒。舊境内借地二千百八十一坪、古跡年貢地済松寺領百三十三坪。境内に直径二尺六寸の大鐘があり、元和二年二月藤原兼長の作で、鐘銘に『荏原郡』と記入してあるので、史家の間に注意されたものである。書上に『境内小川あり、荏原郡と豊島郡との境なり、本堂のある方を荏原と云』とある。(「牛込區史」より)/夏目漱石は自宅すぐ近くの誓閑寺の鉦の音について、随筆「硝子戸の中」でふれている。今は近くに漱石山房記念館、草間彌生美術館。
1900年4月8日「東京・沖縄青年会ー平良保一君卒業記念」

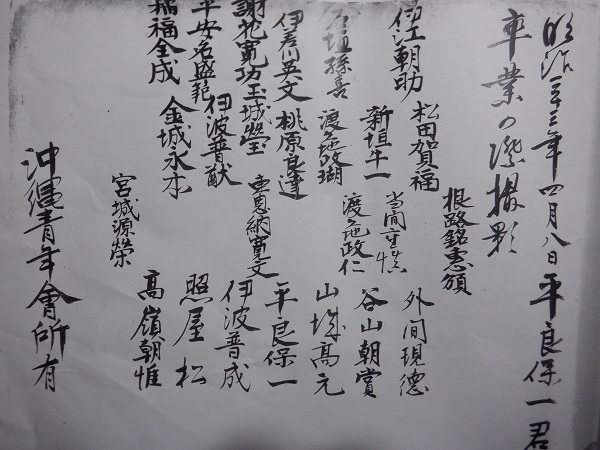
〇伊江朝助、伊波普猷、伊波普成、當間重慎、渡久地政瑚、東恩納寛文ら後に沖縄の新聞界で活躍する面々が居並ぶ。ちなみに外間現徳は前列左端、この写真は沖縄県立図書館の東恩納洋資料にあるもの。この写真の時代背景は伊波普成が1909年3月19日『沖縄毎日新聞』に書いた入社の辞「誓閑寺時代の回顧」でよく分かる。私が最初にこの写真を紹介したのは1994年『沖縄タイムス』粟国恭子「末吉麦門冬」の8月8日。次いで1997年、那覇市文化局資料室の『おもろと沖縄学の父・伊波普猷ー没後50年』に収録した。
8月中は、学校が休みなので、何れものんきに法螺を吹いて暮らしていた。朝は木魚の音と読経の声に目が覚める。総がかりで朝飯の支度をする。朝飯がすむと銘々で散歩に出かける。散歩から帰って来ると昼飯の用意に取りかかる。昼飯がすむと、下町の方に出かけるものもあれば、華胥の國に遊ぶのもいた。共同生活の快楽は一つ釜から飯を食べるということである。併し社会主義というものが、到底地上で行われるべきでないと思ったのはこの時である。一番戦闘力が強かったのは東恩納氏で、一番戦闘力が弱かったのは外間氏であった。外間氏は列強の略奪に遭って泣き出したこともある。浮鷗氏は此頃からの潔癖家である。東恩納氏は有名な無精者で、自分が座っていた2尺平方の掃除も碌にしなかった位である。南香氏は郷里で奮闘した結果、意気消沈してしまって、何らの特色も発揮しなかった。自分は其時からの酔漢で、5名のうちで酒屋の信用が一番重かった方である。
木魚の音と読経の声は聞きなれると心持のよいものである。浮鷗氏が禅味を帯び始めたのもこの頃からであろう。自分が耶蘇に帰依したのも此頃である。誓閑寺時代は自分に取っては忘れることの出来ない時代である。今から考えて見ると誓閑寺の一隅は沖縄の社会の或る一部の縮図であった。9月になって皆下町の方に引越した。思えば昨今のことのようであるが、足かけた年になる。自分は依然たる呉下の旧阿の蒙である。
毎日紙の発刊当時、自分は社友となって、いかがわしい翻訳物を出して世の物笑となって居る所に、去る15日の朝、當間氏から来て呉れとの手紙を受けて、早速いって見ると記者にするつもりであるが如何かとのことであった。自分は一人で決定が出来ないので、帰ってきて家兄と相談した後で承諾と云う意味の手紙を出した。所が文章一つ書けけない自分がどうして記者などになれる。家兄に聞くと君が平常使用している普通語で、君の思想感情を飾りなく、、偽りなくせんじつめて吐き出せ。形容詞も知らなければ知らないでいい。漢字も知らなければ知らなくてもいい。只だ耳障りにならないように書け、10年も書いたらいくらか物になるとのことである。自分は此教訓に遵って書くつもりである。
新聞を起こして見ようということは誓閑寺時代から先輩諸氏が口ぐせのようにいっていたことであるが、10年後の今日この小理想は漸く実現せられて、自分までが編集室の一椅子を占めるようになった。さアこれから自分は、どういう方面に、どう働いたらよかろう?心配でたまらない。(をはり)
◇新宿区喜久井町61 亀鶴山易行院誓閑寺 深川靈嚴寺末
寛永七年靈岸嶋に起立、明暦大火後宗参寺領の内庚申塚に借地移轉。寛文六年七月喜久井町に移る。開山重蓮社本譽上人誓閑和尚、寛永二年五月十五日卒。舊境内借地二千百八十一坪、古跡年貢地済松寺領百三十三坪。境内に直径二尺六寸の大鐘があり、元和二年二月藤原兼長の作で、鐘銘に『荏原郡』と記入してあるので、史家の間に注意されたものである。書上に『境内小川あり、荏原郡と豊島郡との境なり、本堂のある方を荏原と云』とある。(「牛込區史」より)/夏目漱石は自宅すぐ近くの誓閑寺の鉦の音について、随筆「硝子戸の中」でふれている。今は近くに漱石山房記念館、草間彌生美術館。
1900年4月8日「東京・沖縄青年会ー平良保一君卒業記念」

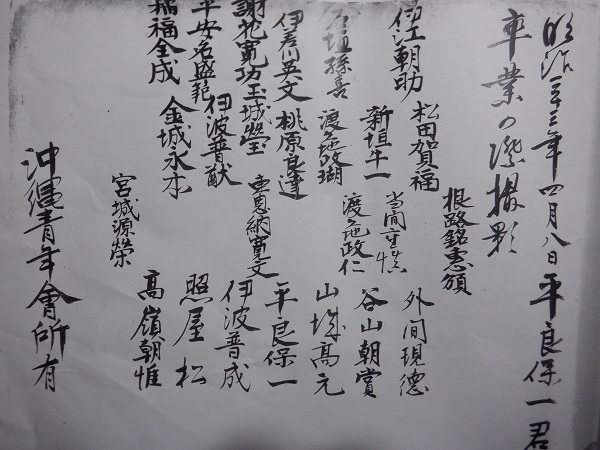
〇伊江朝助、伊波普猷、伊波普成、當間重慎、渡久地政瑚、東恩納寛文ら後に沖縄の新聞界で活躍する面々が居並ぶ。ちなみに外間現徳は前列左端、この写真は沖縄県立図書館の東恩納洋資料にあるもの。この写真の時代背景は伊波普成が1909年3月19日『沖縄毎日新聞』に書いた入社の辞「誓閑寺時代の回顧」でよく分かる。私が最初にこの写真を紹介したのは1994年『沖縄タイムス』粟国恭子「末吉麦門冬」の8月8日。次いで1997年、那覇市文化局資料室の『おもろと沖縄学の父・伊波普猷ー没後50年』に収録した。