05/08: 琉舞ん雑筆①
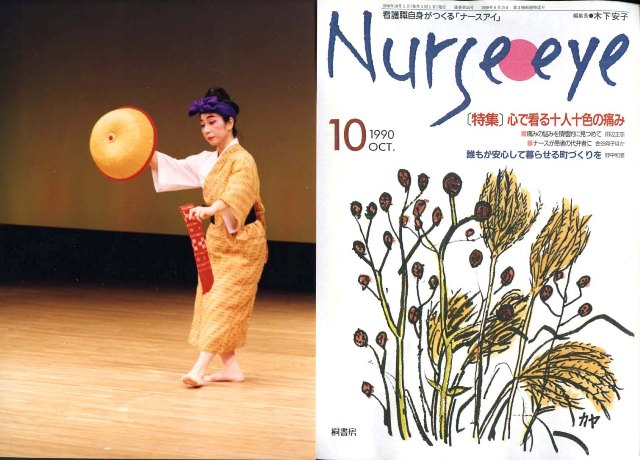
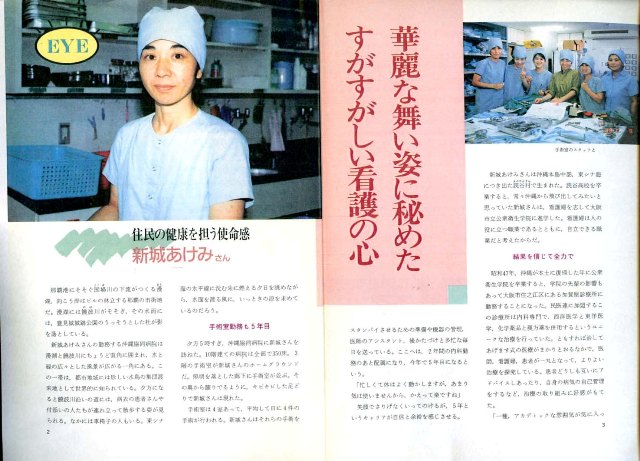
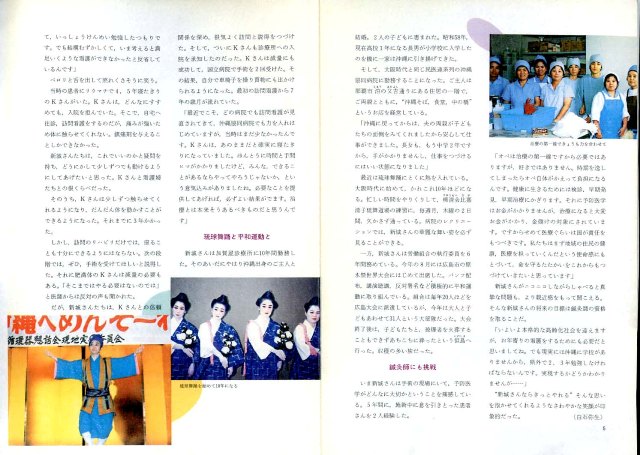
1990年10月ー桐書房『ナースアイ』第24号□白石弥生「住民の健康を担う使命感ー新城あけみさん」
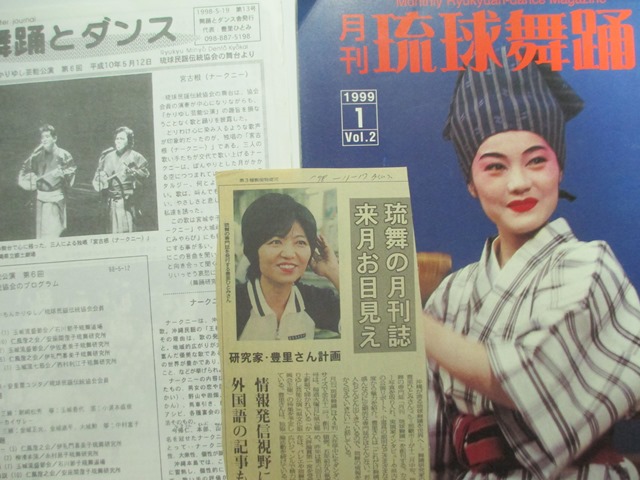
1998年11月17日『沖縄タイムス』「琉舞の月刊誌 来月お目見え 豊里ひとみさん計画」



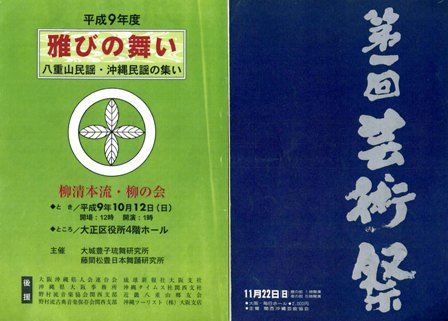
1997年10月12日ー柳清本流・柳の会「雅びの会ー八重山民謡・沖縄民謡の集いー大城豊子、大城奈津子、新城あけみ他」
1981年11月22日ー関西沖縄芸能協会「第一回芸術祭ー舞台監督・宮城正雄、助監督・玉城利則、ナレーター・与那嶺伸枝/小浜節(藤間松豊琉舞研究所)藤間松豊、山本勝子、上間照美、新城あけみ、他9名」
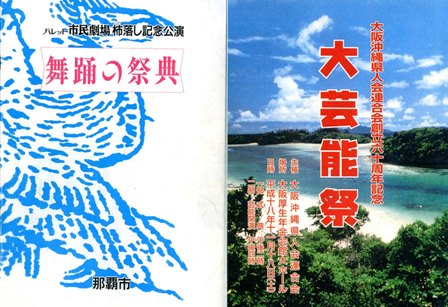
1991年6月12日ーパレット市民劇場杮落とし記念公演「舞踊の祭典ー月夜浜(柳清会比嘉清子琉舞研究所)比嘉倫子、大城鶴子、新城恵子、長嶺江美、与那嶺順子、金城恵美子、金城博恵、新城あけみ」
2006年11月18日ー大阪沖縄県人会連合会創立60周年記念「大芸能祭ー夏姿(柳清本流柳豊会・大城豊子・大城奈津子琉舞研究所)新城あけみ他」

真境名本流/島袋本流
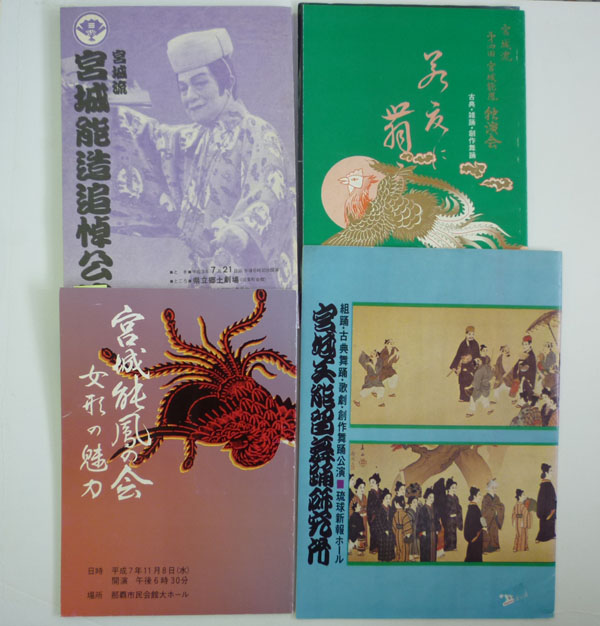
宮城流
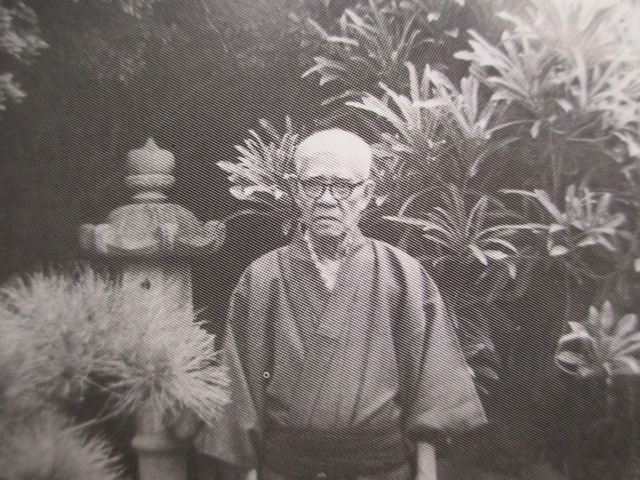
写真ー松田賀哲
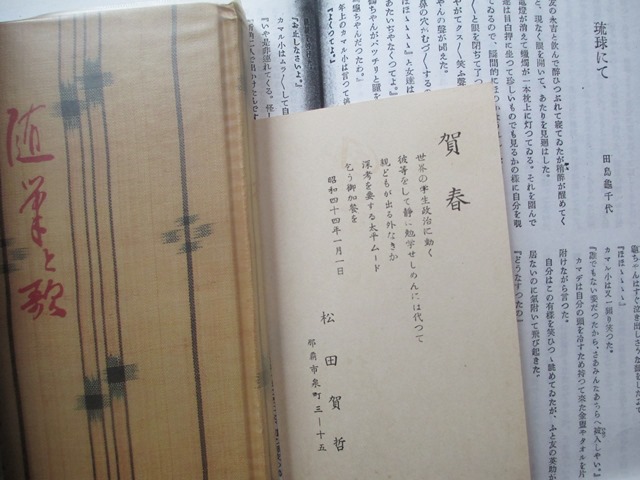
○1986年1月 松田賀哲『随筆と歌』

写真1935年頃辻ー後列右からー山里永吉、仲泊良夫 前列中央が松田枕流(賀哲の弟)

右ー松田賀孝氏(一橋大学経済学博士、琉球大学名誉教授)
目次
編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。
沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦
ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷
沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎
地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇
岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣
女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫
性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎
セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠
耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏
万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建
八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮
琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一
琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎
南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫
阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七
尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)
□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。
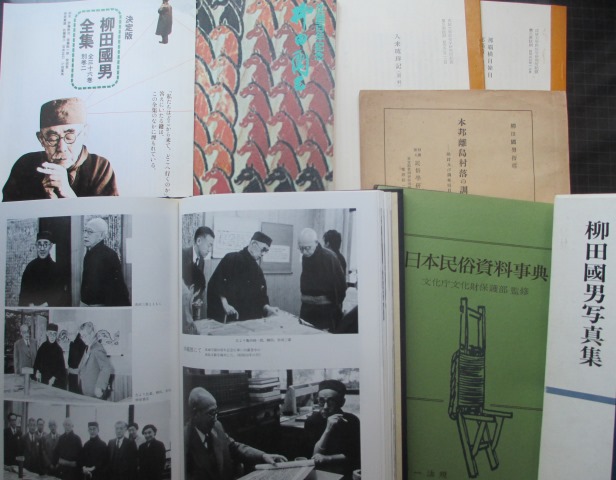
柳田国男 やなぎた-くにお
1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。
明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。
【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク
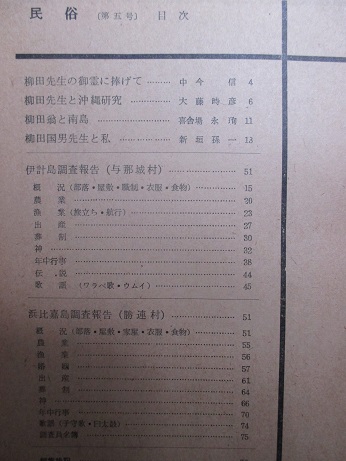
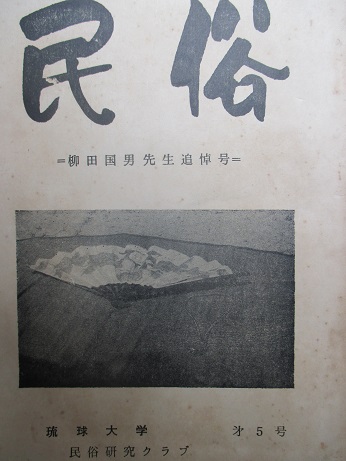
1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号
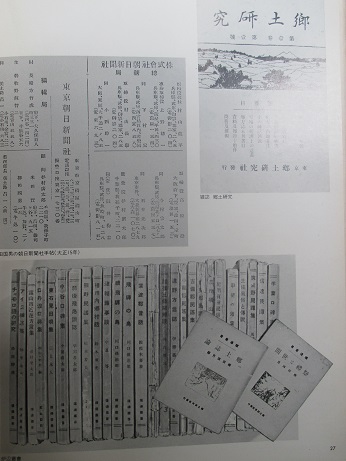
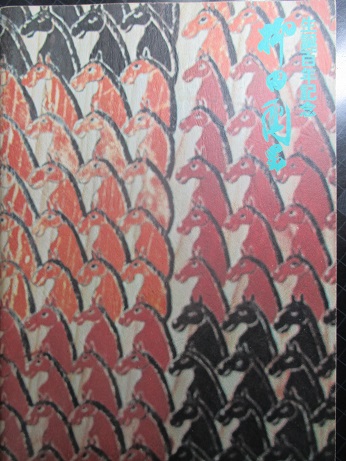
1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展
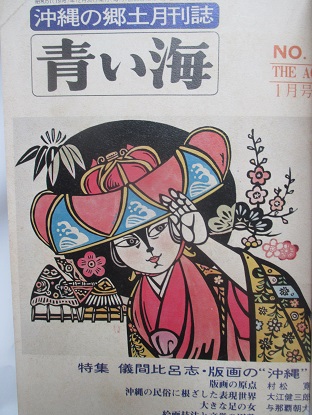
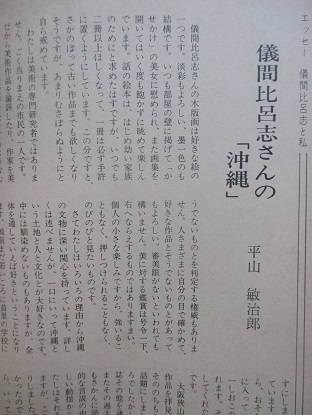
1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」
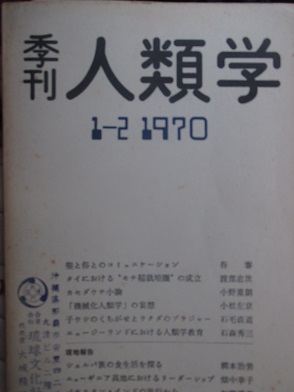
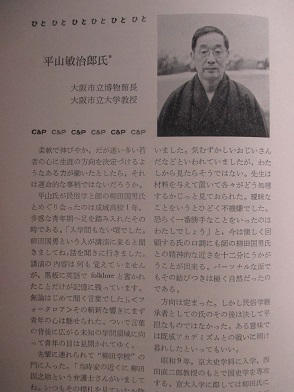
1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」
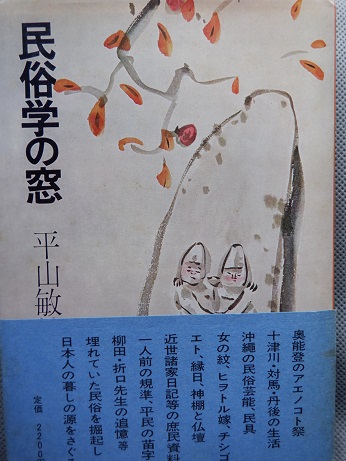
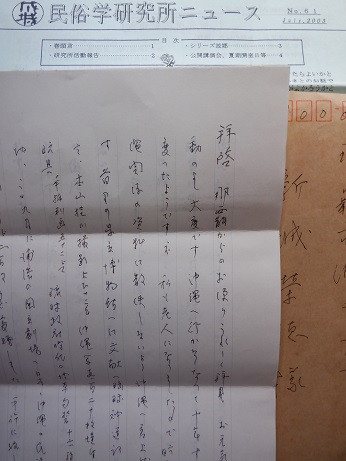
1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡
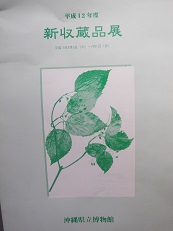

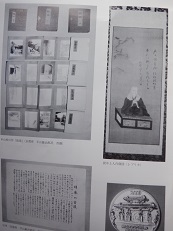
2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈
平山敏治郎
歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)
**略歴
大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。
昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。
**おもな著書
『日本中世家族の研究』(1980)
『民俗学の窓』(1981)
『歳時習俗考』(1984)
『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)
押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)
岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。
浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。
編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。
沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦
ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷
沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎
地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇
岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣
女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫
性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎
セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠
耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏
万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建
八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮
琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一
琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎
南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫
阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七
尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)
□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。
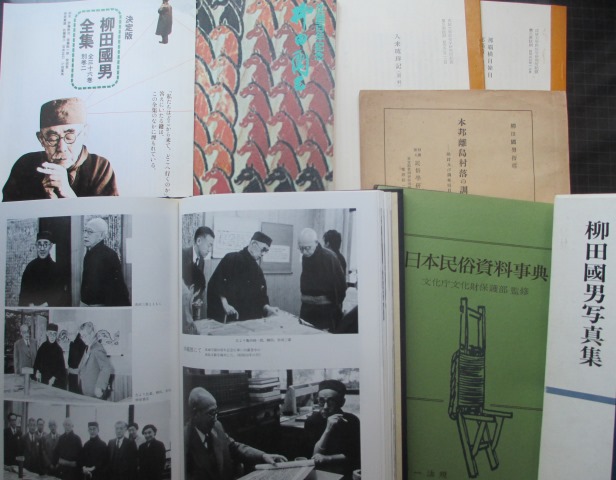
柳田国男 やなぎた-くにお
1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。
明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。
【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク
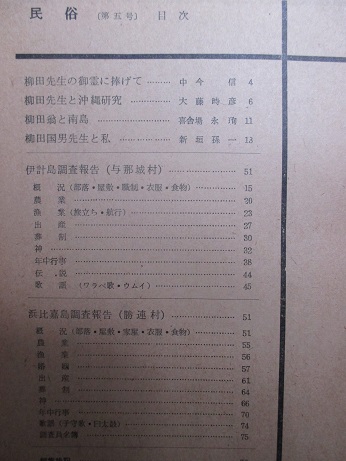
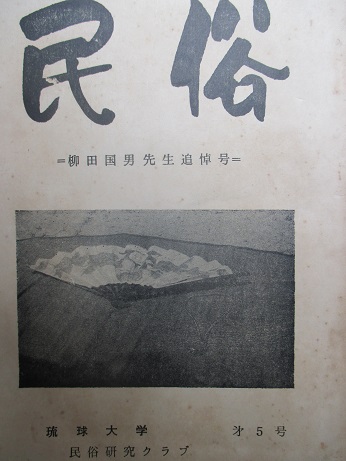
1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号
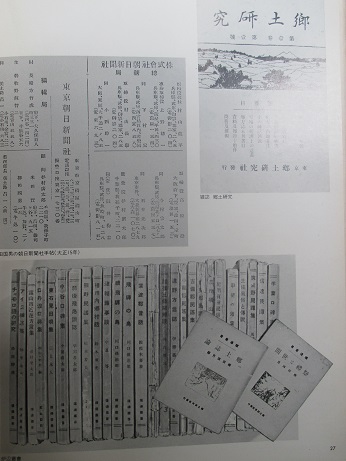
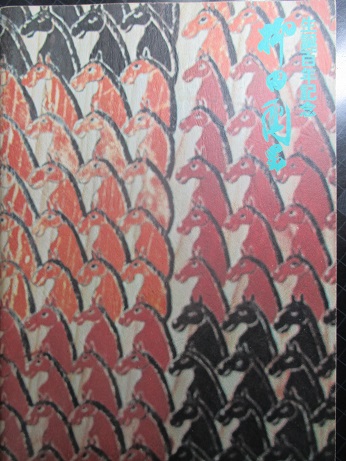
1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展
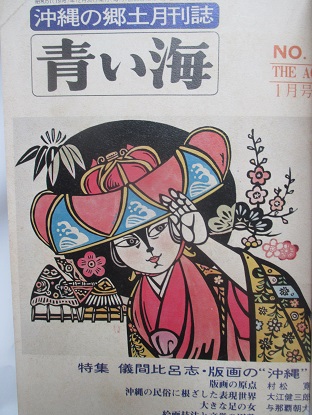
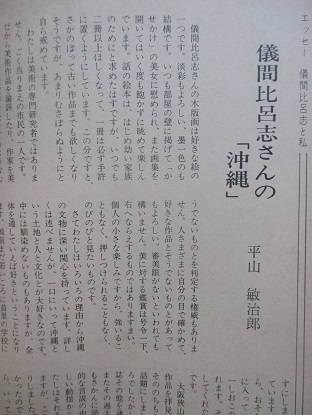
1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」
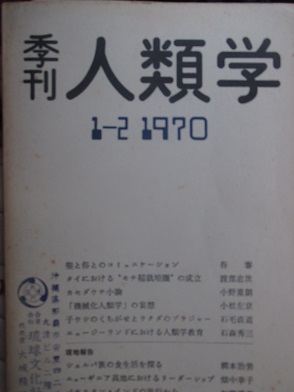
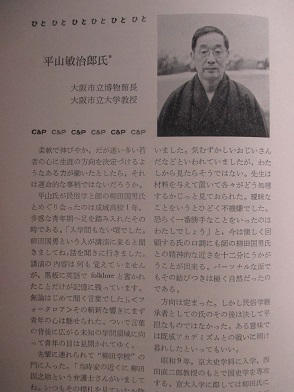
1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」
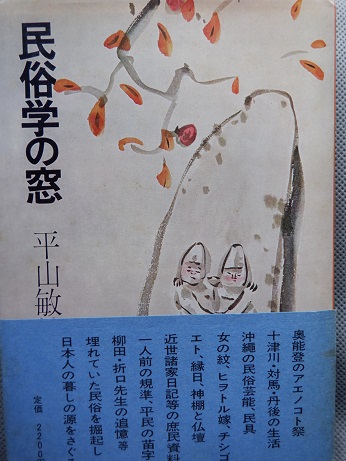
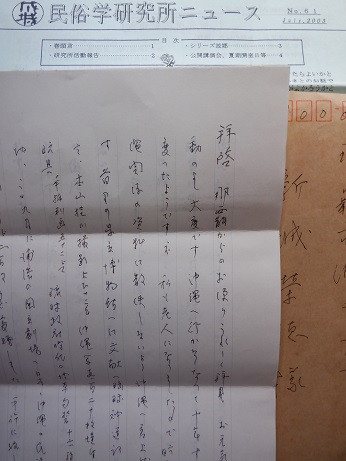
1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡
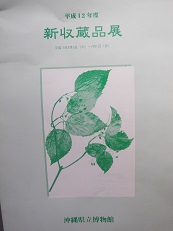

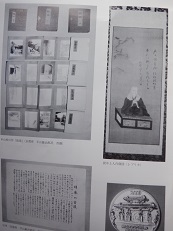
2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈
平山敏治郎
歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)
**略歴
大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。
昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。
**おもな著書
『日本中世家族の研究』(1980)
『民俗学の窓』(1981)
『歳時習俗考』(1984)
『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)
押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)
岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。
浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。
02/26: 観光文化/「描かれたジュリ」②
1913年6月5日、岡田雪窓 那覇港から鹿児島へ


1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」
1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」
1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」
1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」
1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」
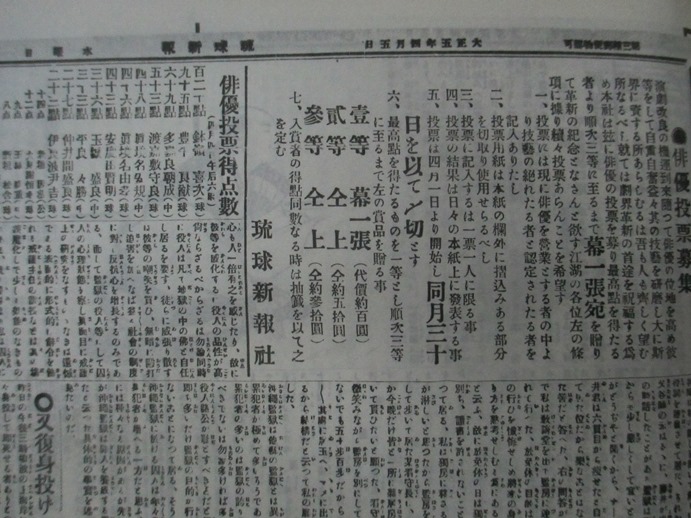
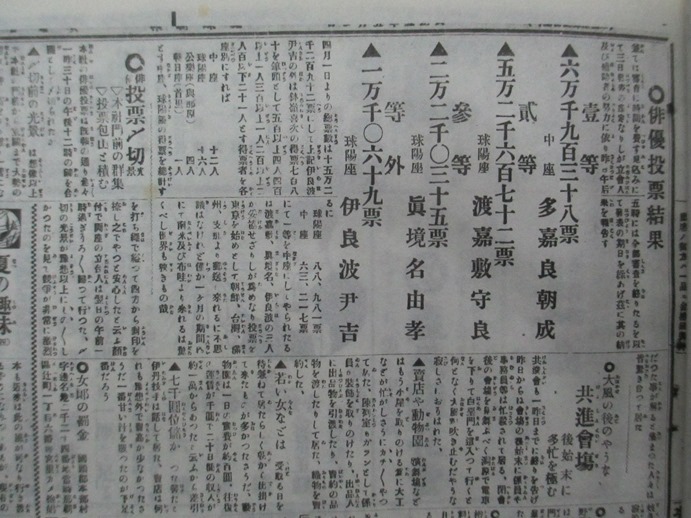
1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」
1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会
1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」
1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店
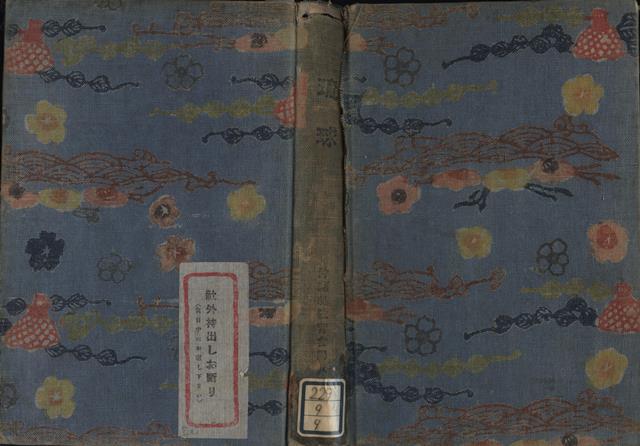
□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。
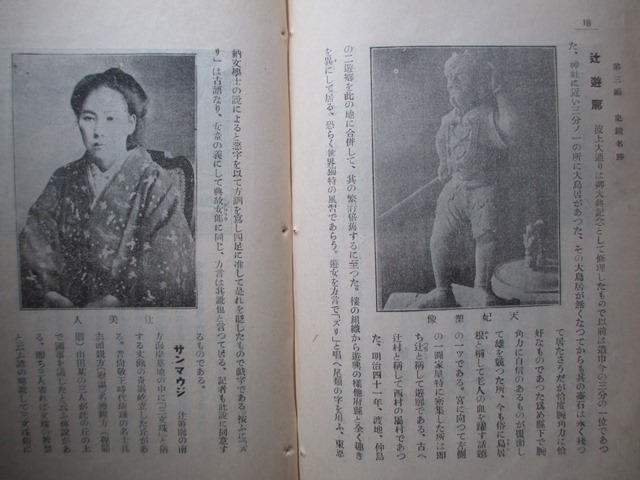
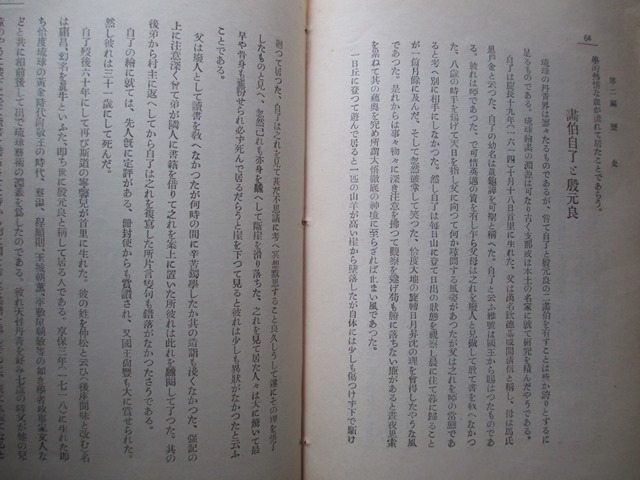
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」


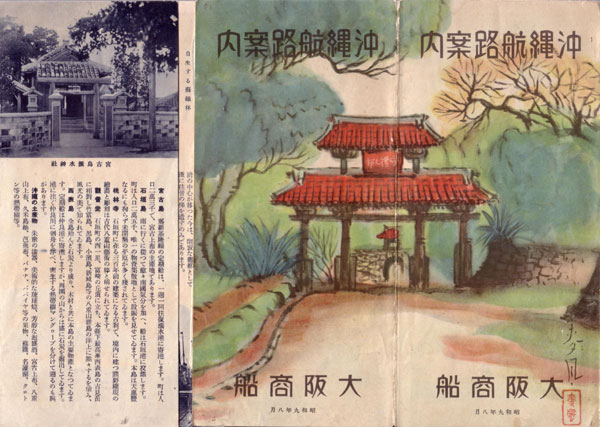
1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)
有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)
1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店
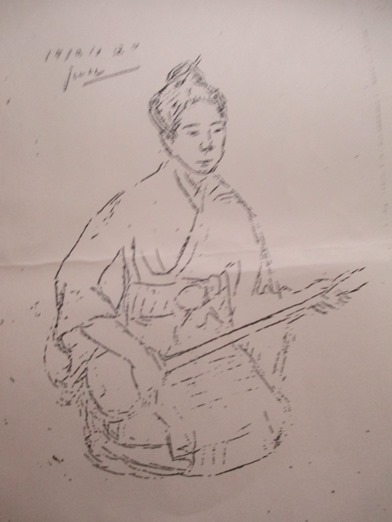
○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」
○ひなた、他九篇
ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。
○佛さま、他十篇
佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。
○母と子、他八篇
○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)




1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

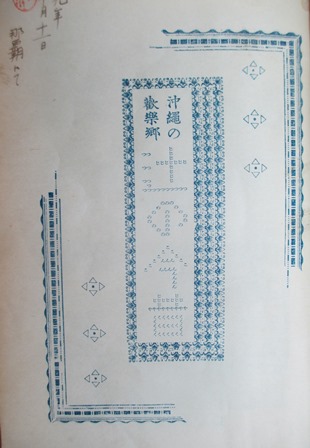


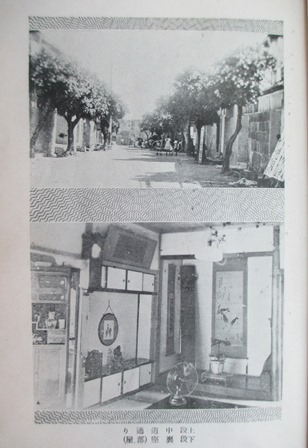
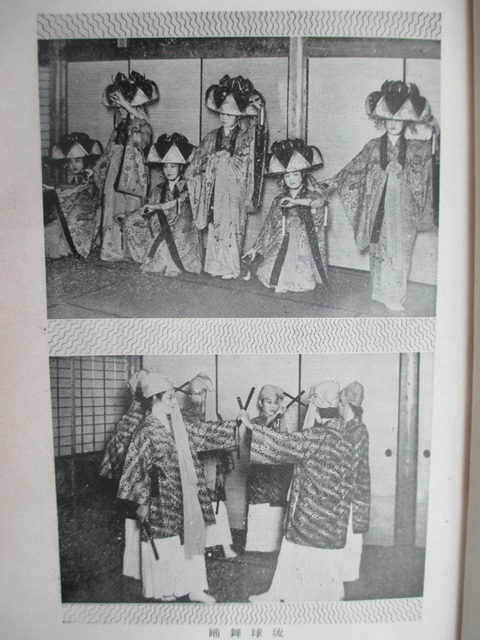
○一向宗の法難と廓
王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。
また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。
明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。
備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。
1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。
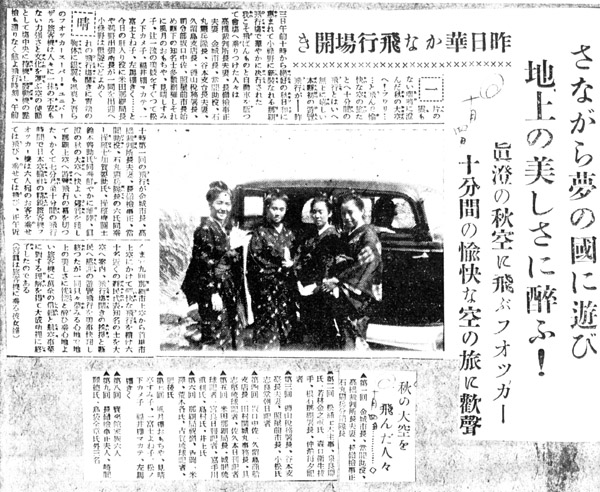
1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行
1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」
1938年9月15日『大阪球陽新報』
□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。
家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。
県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。
辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。


1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」
1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」
1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」
1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」
1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」
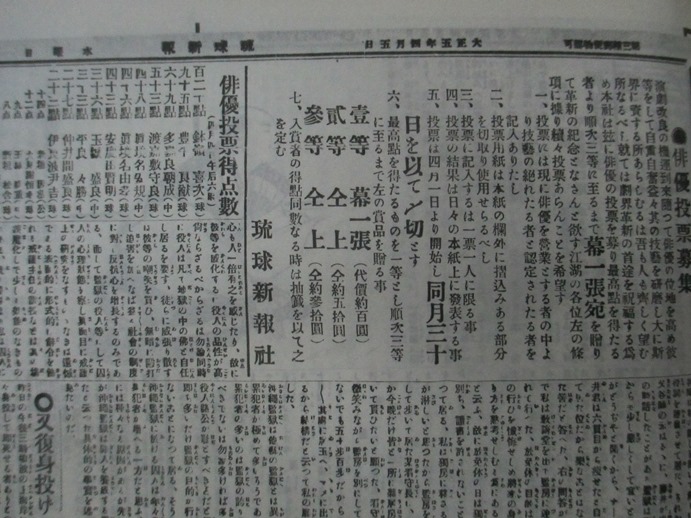
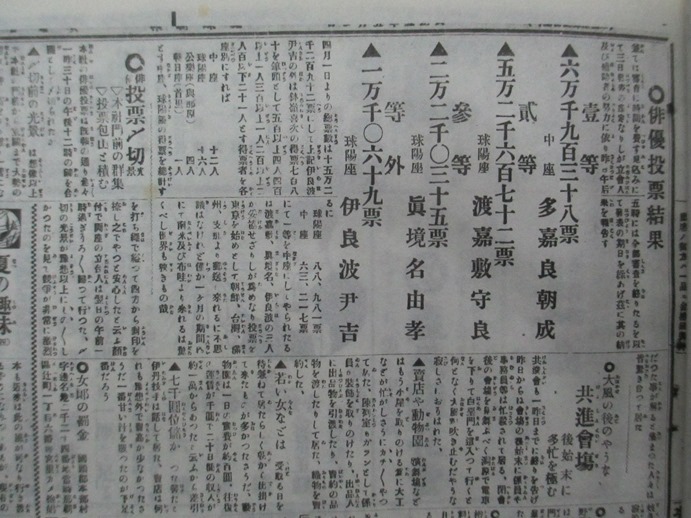
1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」
1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会
1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」
1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店
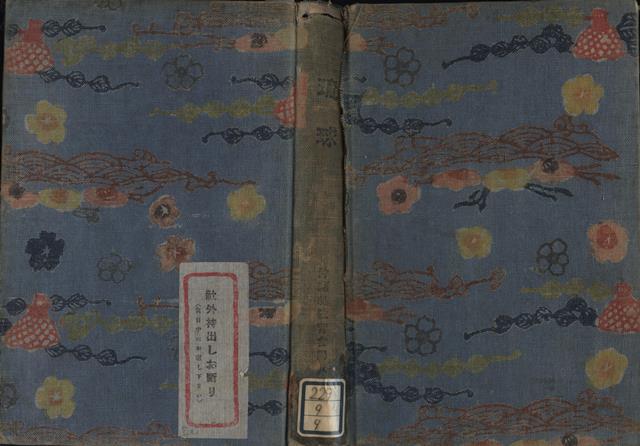
□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。
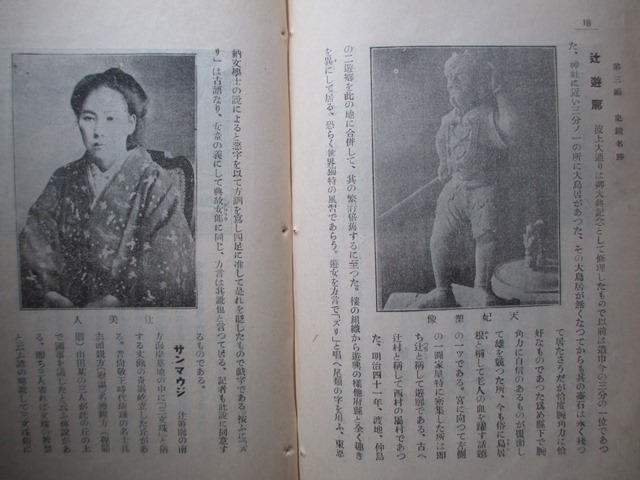
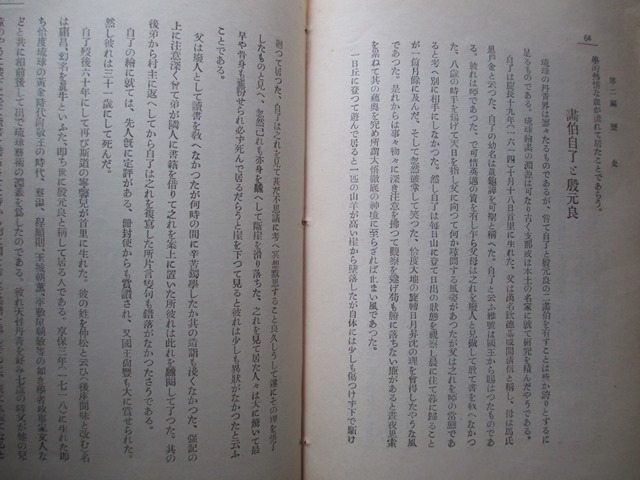
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」


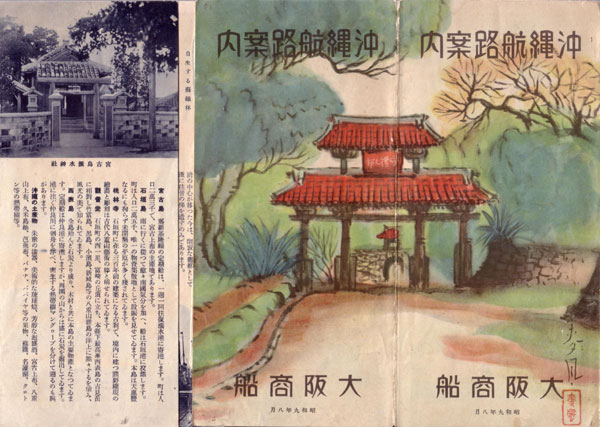
1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)
有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)
1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店
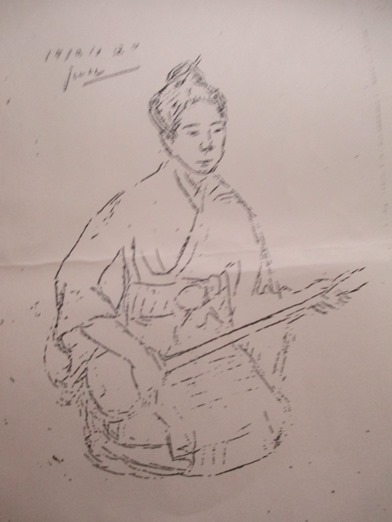
○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」
○ひなた、他九篇
ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。
○佛さま、他十篇
佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。
○母と子、他八篇
○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)




1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

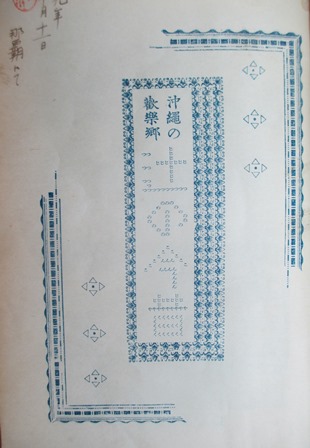


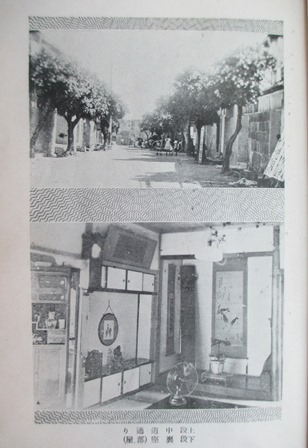
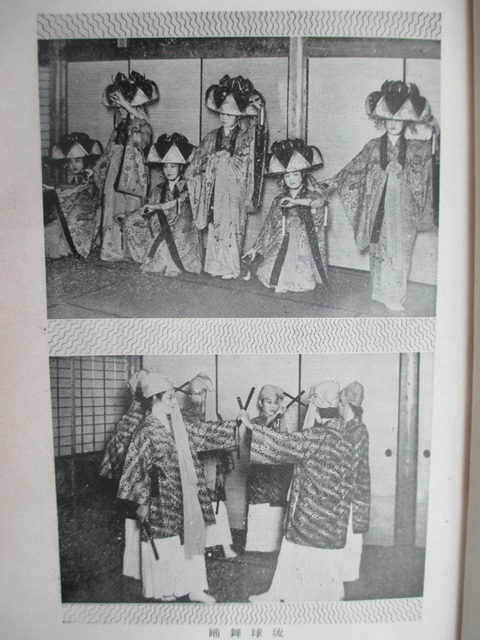
○一向宗の法難と廓
王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。
また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。
明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。
備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。
1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。
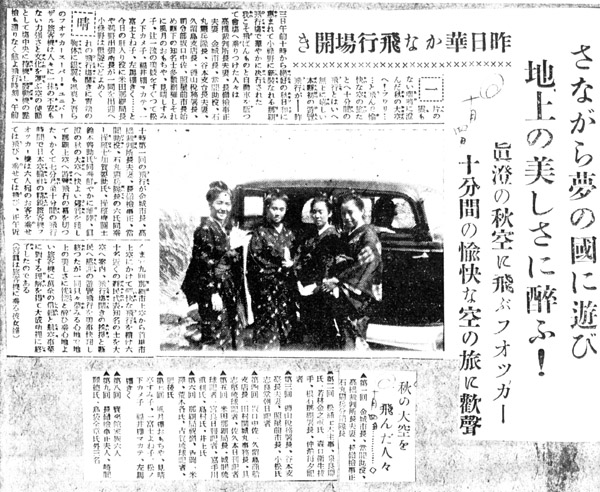
1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行
1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」
1938年9月15日『大阪球陽新報』
□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。
家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。
県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。
辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。
03/08: ウチナー美の森「描かれたジュリ」③
1966年12月ー神山邦彦『辻情史』神山青巧舎
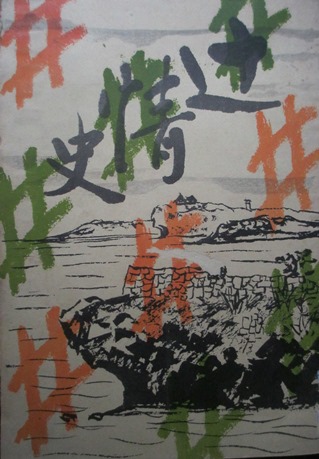

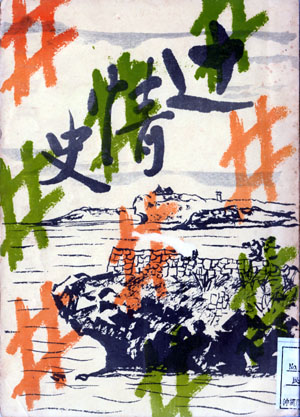
神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書
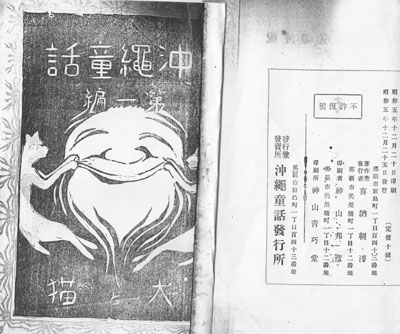
1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂
1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」
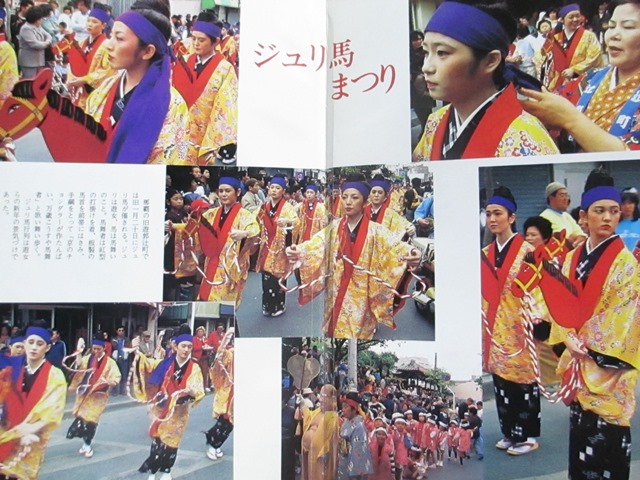
□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会
□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」


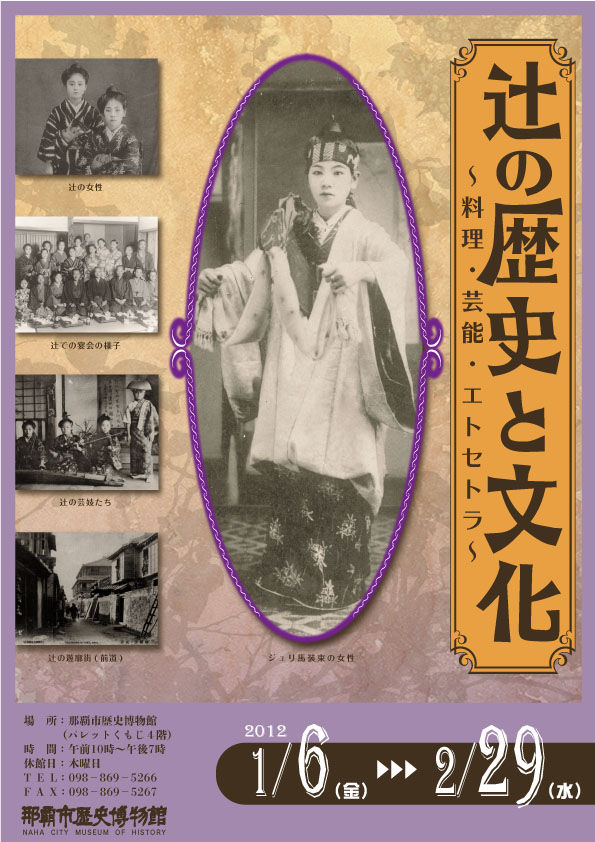
2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」
2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』
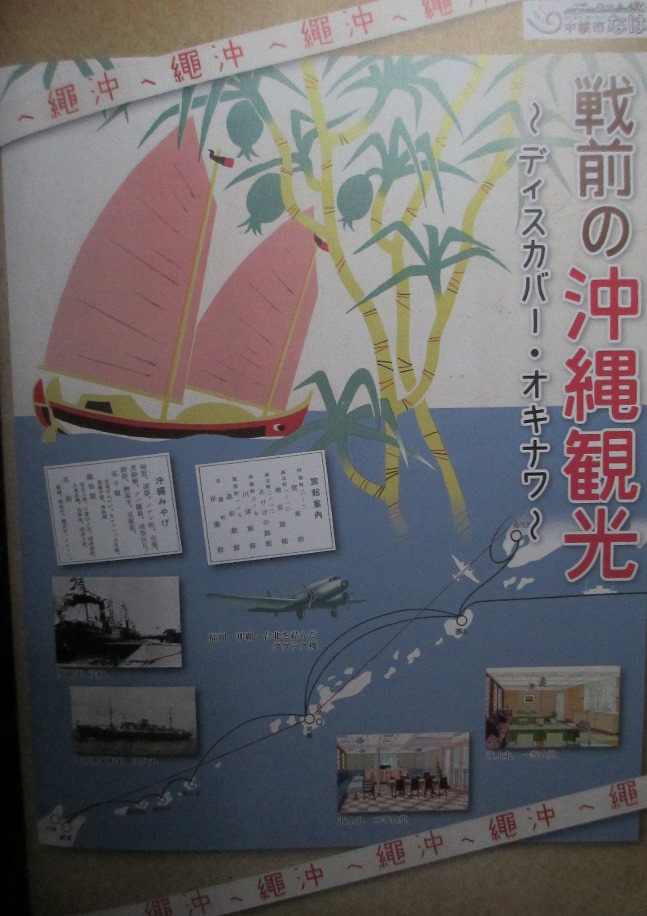
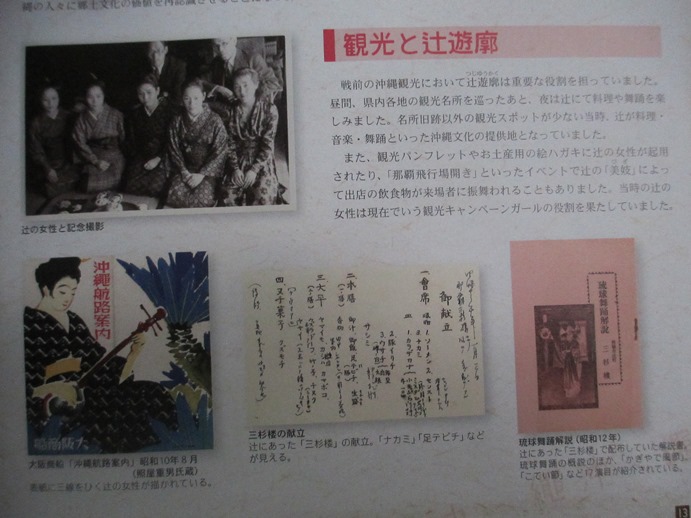
辻遊廓
戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。
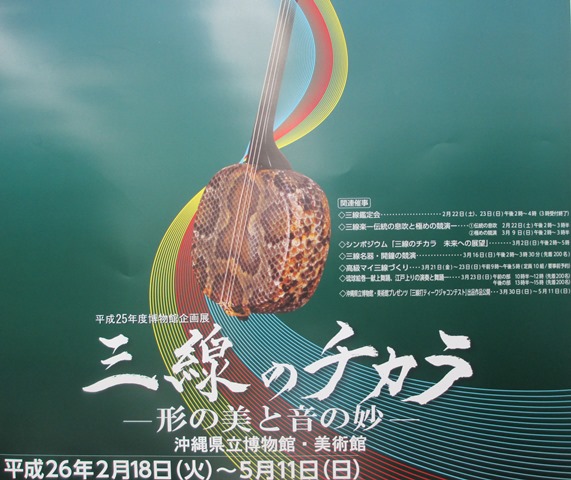
2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」
□三線をひくジュリの絵も展示されている。
沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相
場所:沖縄県立博物館・美術館
日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30




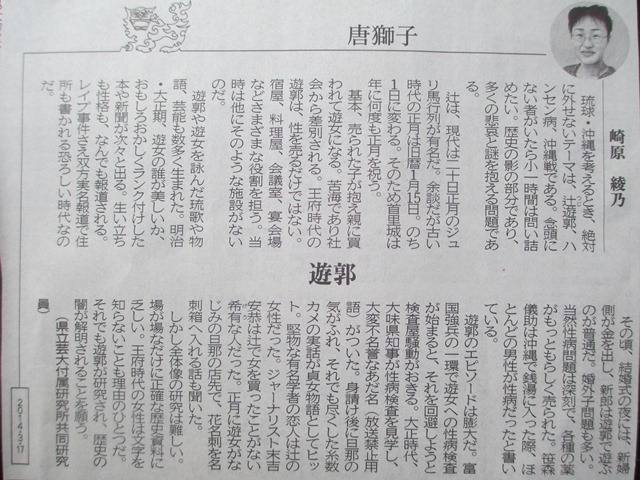
2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」
1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。
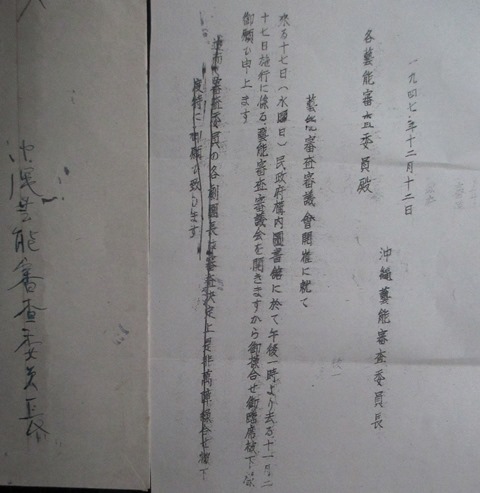
1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣
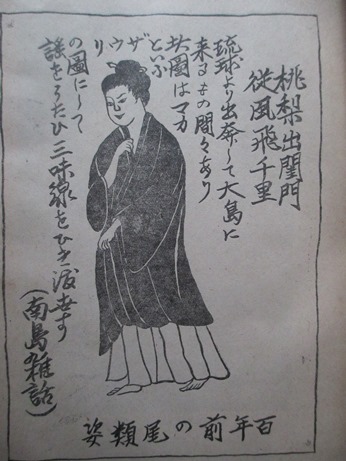
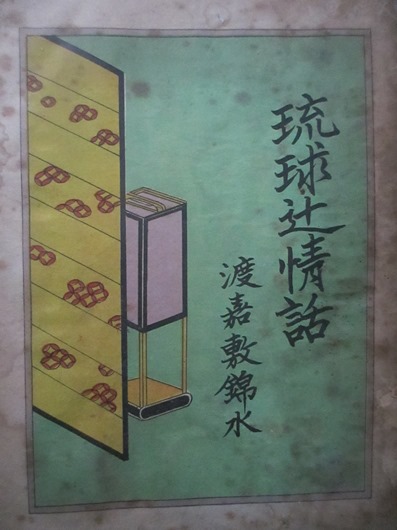
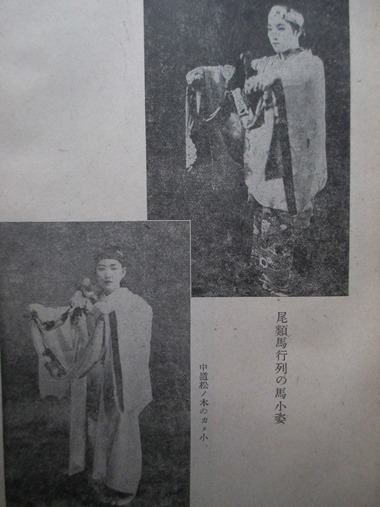
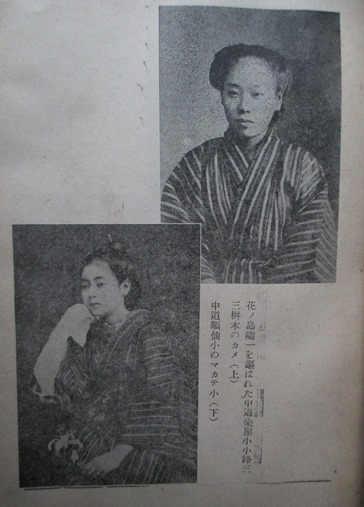
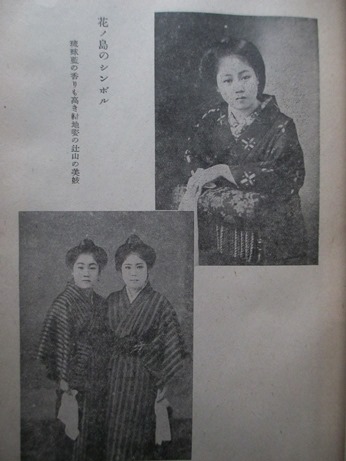
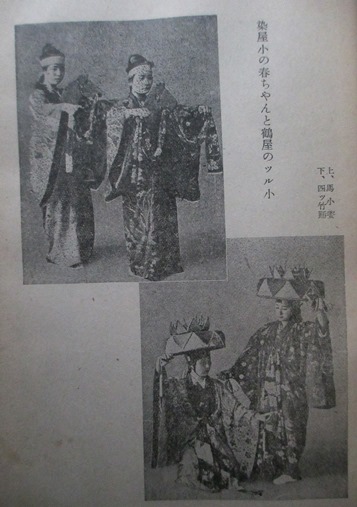




1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)
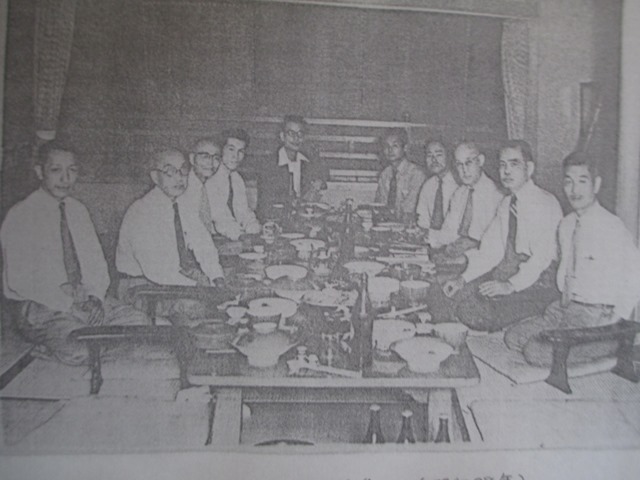
第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠
1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店
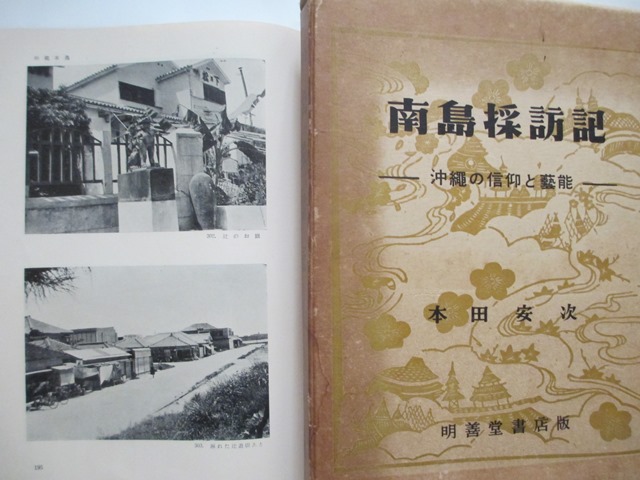
上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと
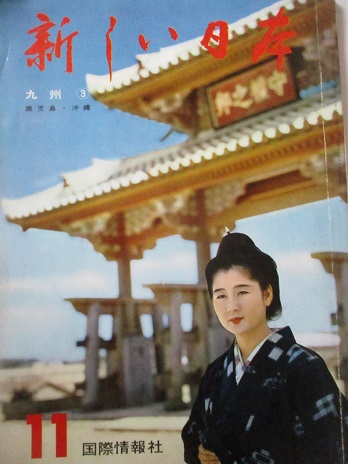
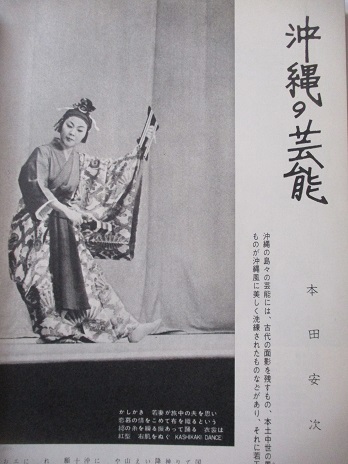
1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」
本田安次 ほんだ-やすじ
1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。
明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク
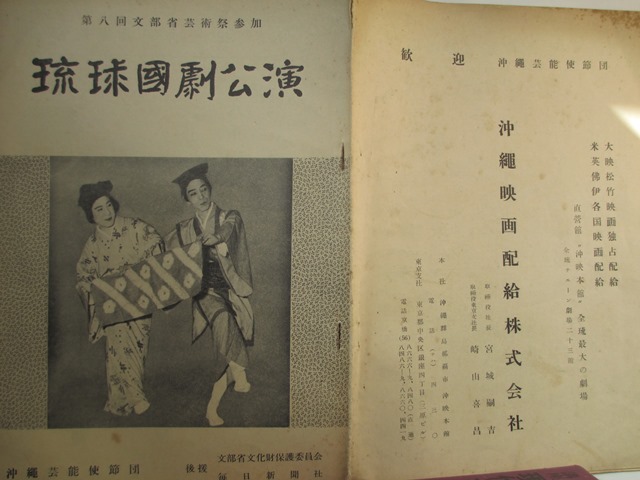
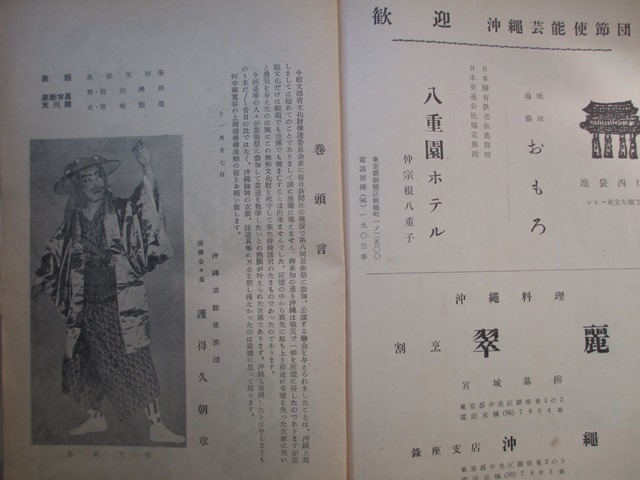
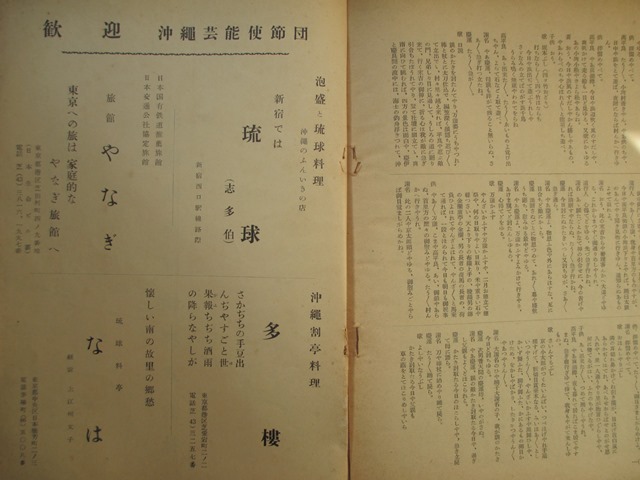
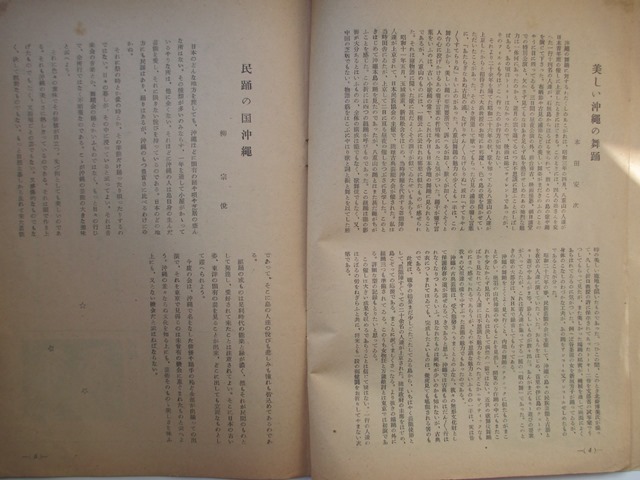
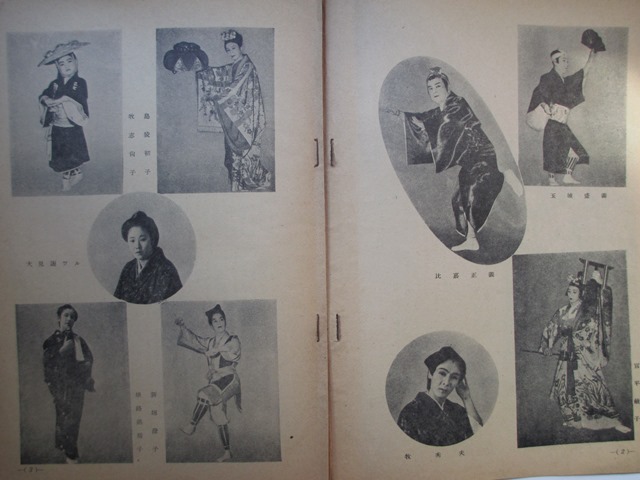
(翁長良明コレクション)
1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」
11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」
11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載
12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載
12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)
12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」
1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」
1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」
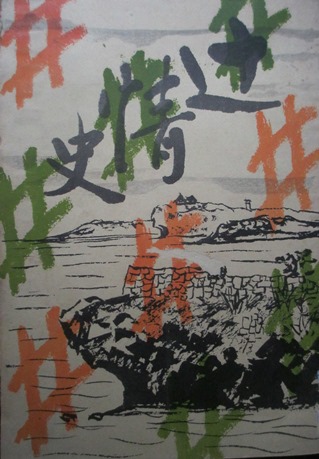

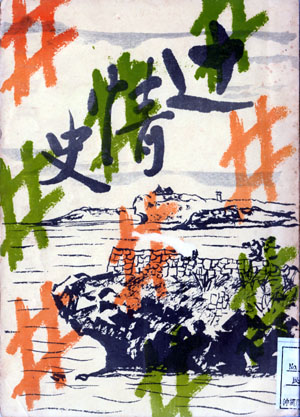
神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書
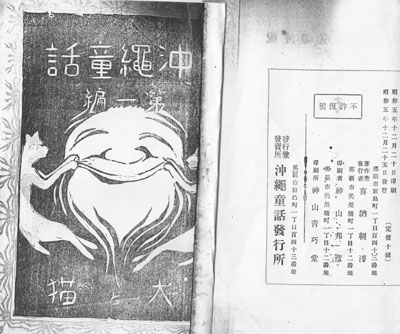
1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂
1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」
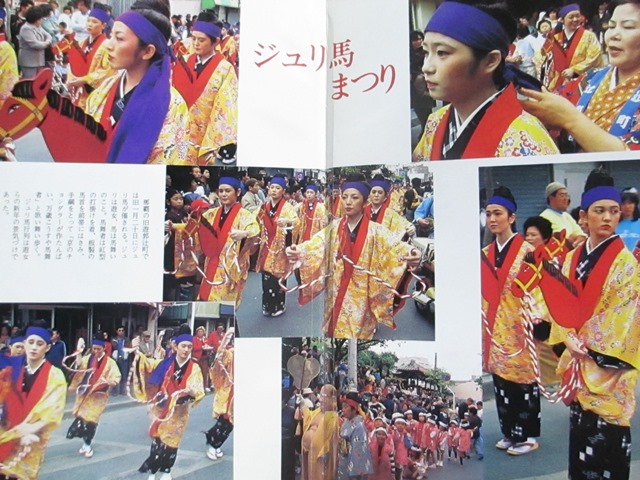
□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会
□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」


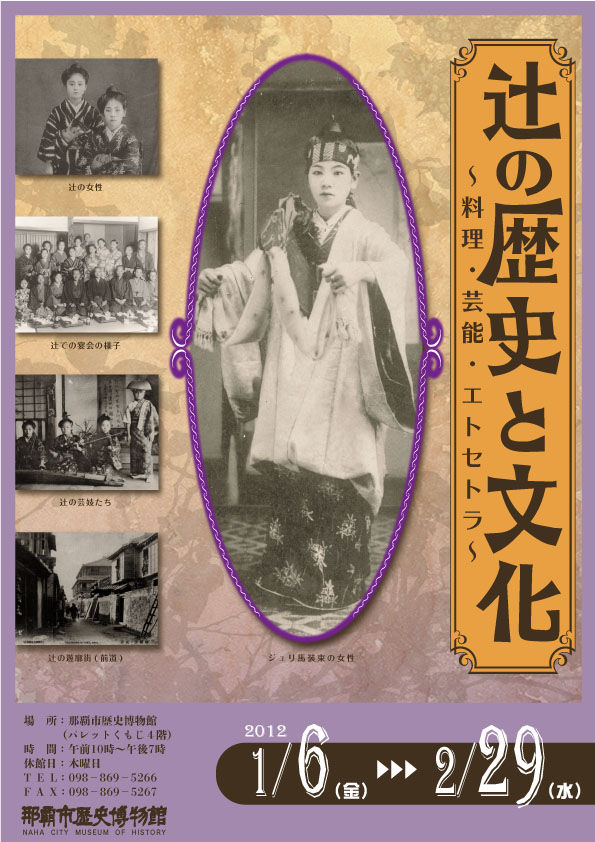
2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」
2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』
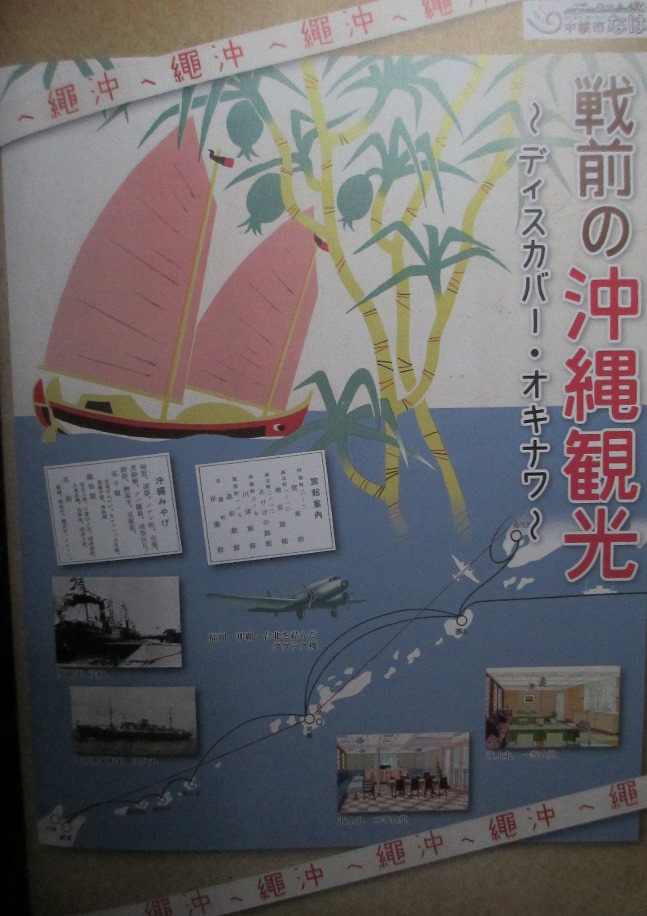
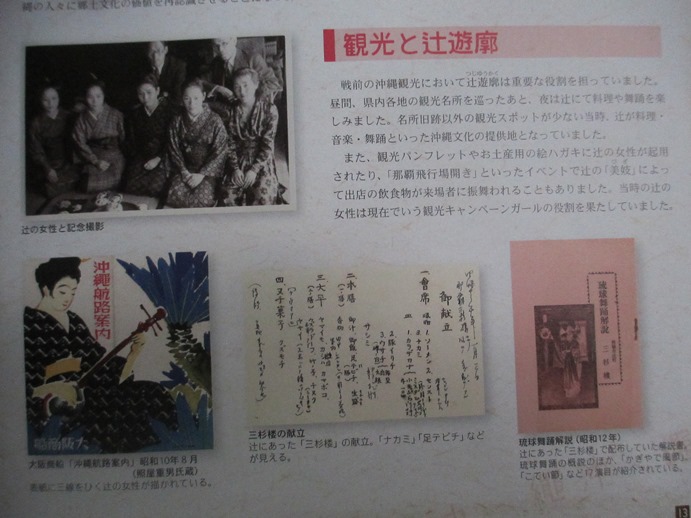
辻遊廓
戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。
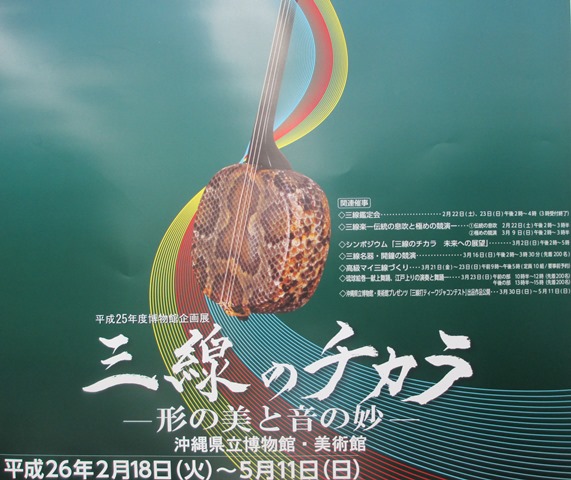
2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」
□三線をひくジュリの絵も展示されている。
沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相
場所:沖縄県立博物館・美術館
日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30




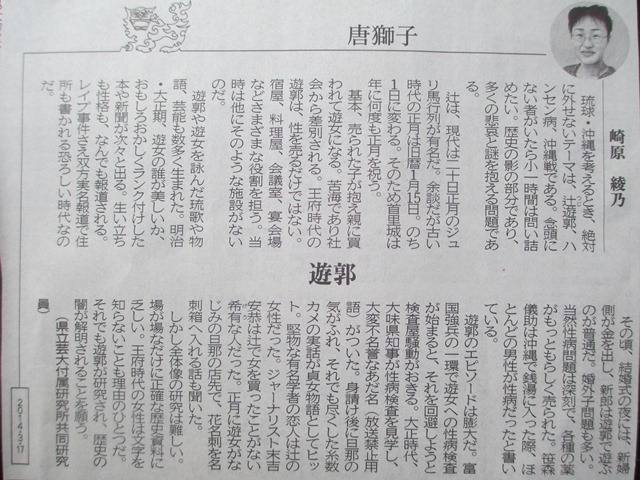
2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」
1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。
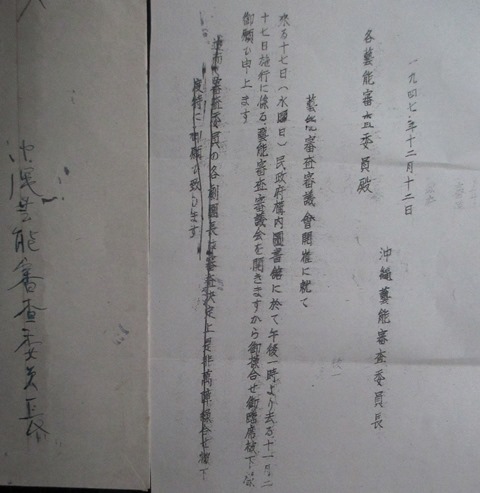
1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣
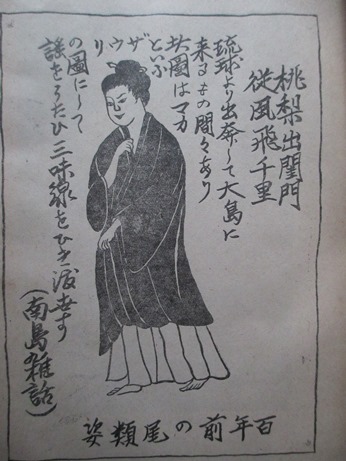
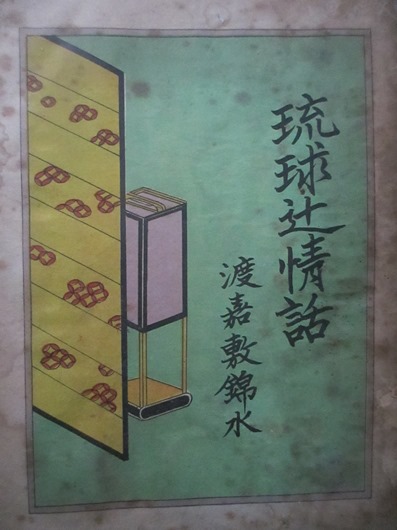
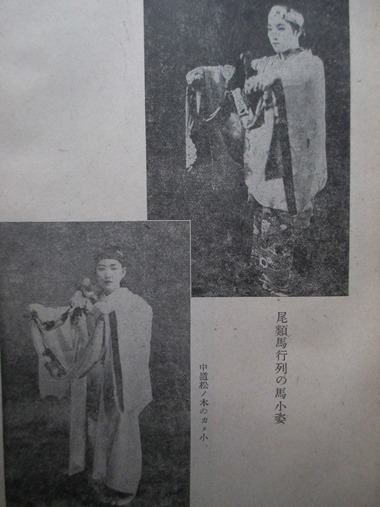
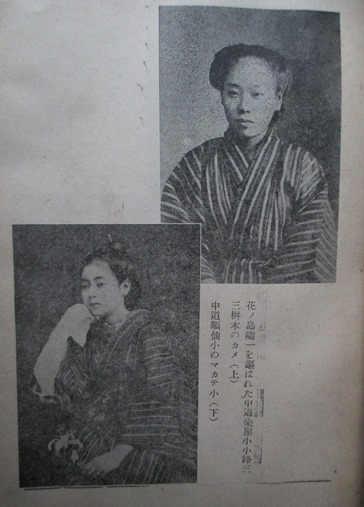
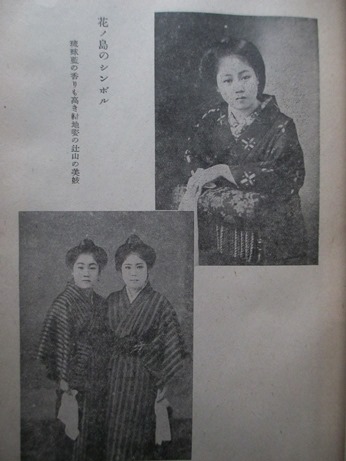
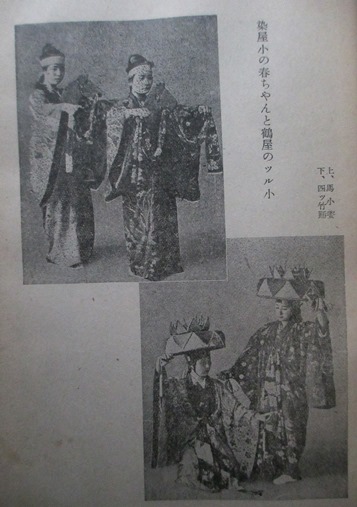




1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)
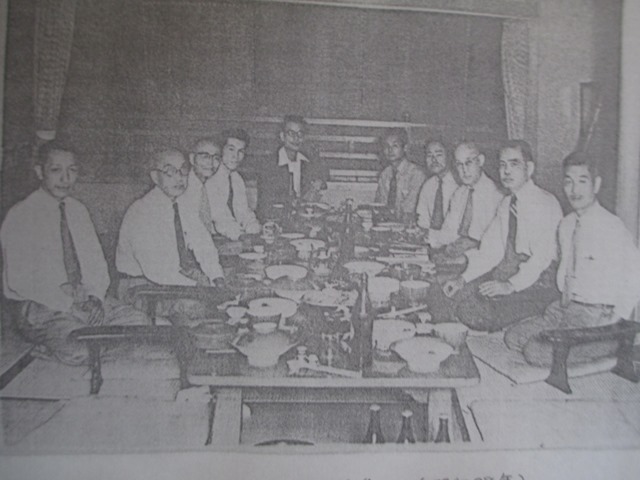
第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠
1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店
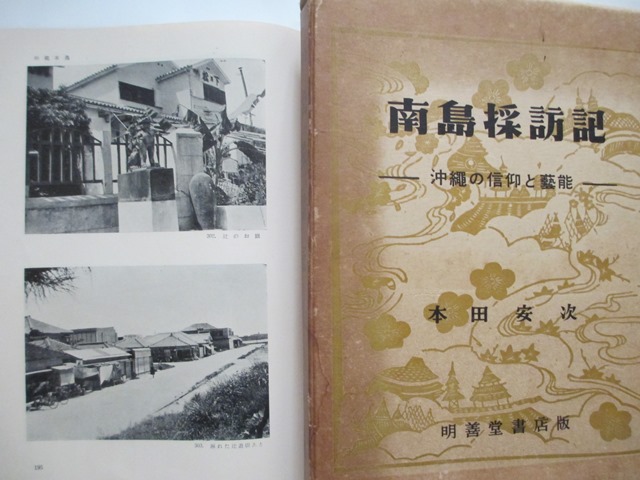
上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと
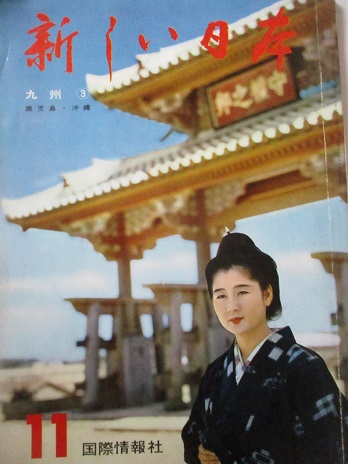
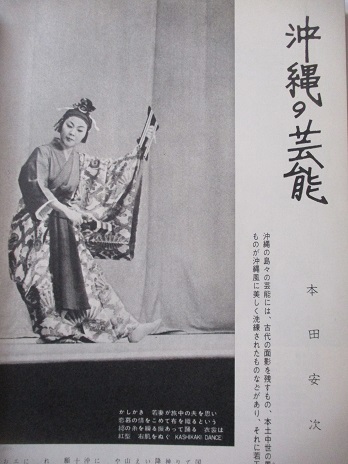
1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」
本田安次 ほんだ-やすじ
1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。
明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク
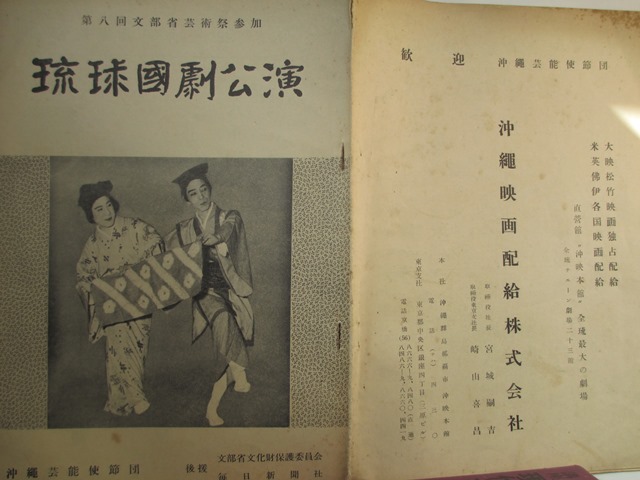
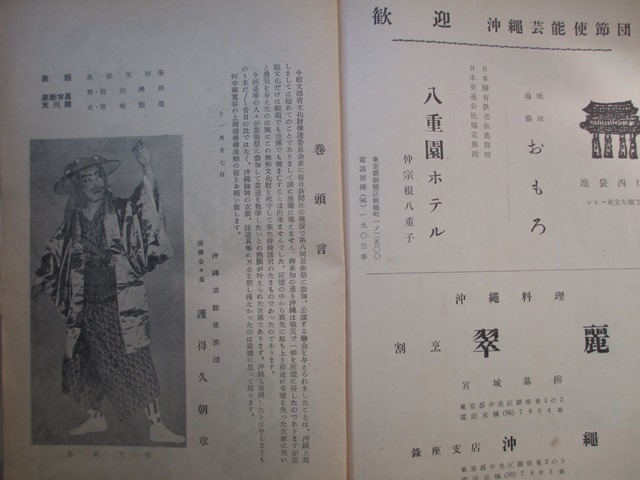
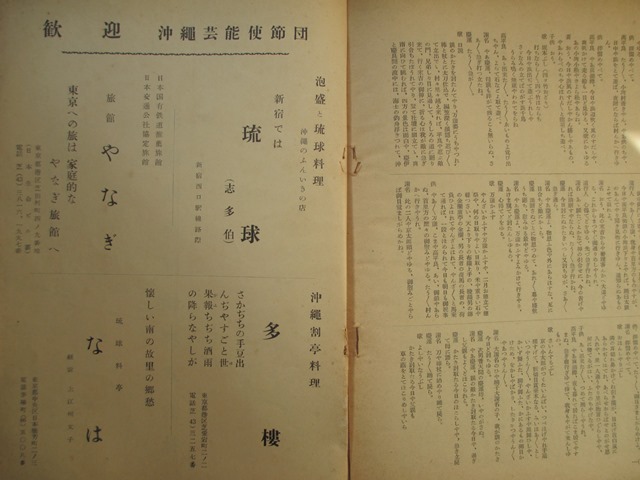
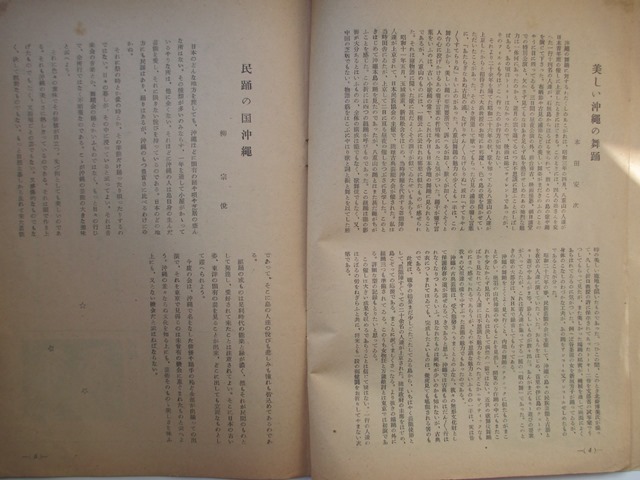
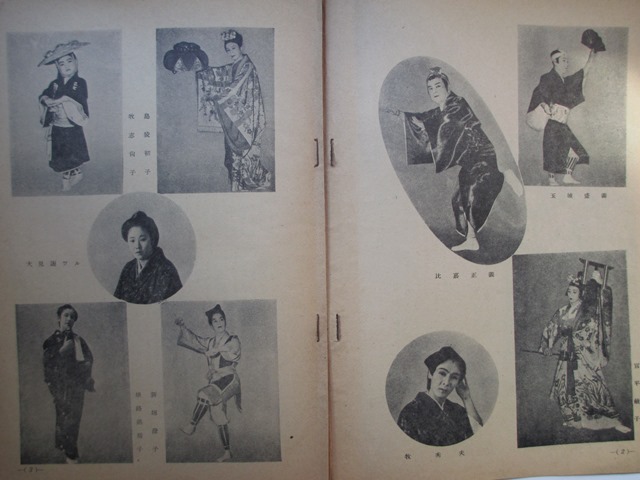
(翁長良明コレクション)
1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」
11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」
11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載
12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載
12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)
12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」
1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」
1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」
04/15: 沖縄コレクター友の会②
2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。
「みどり印刷」ここをクリック
ミルクウンケー(琉球語 うちなーぐち)直訳すれば「弥勒様のお迎え」とすればいいのだろうか?今年は8月17日(日)午後4時30分、赤田首里殿内(アカタスンドゥンチ)跡の赤田クラブから弥勒様御一行がお出ましになる、僕もバイクに飛び乗り駆けつけた。「ミルクウンケー」については『沖縄タイムス大百科』から以下転載する。
弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化生といわれる中国唐代の禅僧、布袋和尚(ほていおしょう)が、七福神の一つとして京都の祭礼の行列〈風流〉に登場したのは室町時代といわれる。
首里では350年程前、石川門中の祖、求道 〈ぐどう〉長老により、赤田首里殿内に弥勒面が祀られ、7月14日に泰安所を開き、16日に門中を中心に道ジュネー(行列)があった。赤田マチグチ(赤田市場口、今のウフカクジャー交差点から南に100メートル足らずの路肩一帯は赤田市の跡で沖縄戦まで、食肉、豆腐、野菜、雑穀など、主として食料品の相対売り市場であった。←久手堅憲夫著『首里の地名』より)突き当たり右に直角に曲がるあたりに舞台を設け、その中央に面や胴、衣装一式を安置し、まわりには弥勒御愛子(ミルクウミングヮ、ミルクングヮ)が並び大香炉に香を焚き、東に向かって(←ここ重要)世界風
ユガフ、豊作、健康を祈願した後、祭主の本家、大石川(ウフイシチャー、首里石川の宗家)の家長が面と作り物の胴をつけ、ドゥジン・袴をつけ胸をはだけて大団扇(うちわ)で豊年を招き寄せながら、舞台をしずしずと一周する。
弥勒面は戦災で焼失したが、平成6年に復元された。 行列は高張提灯一対を持ち、先頭に警護役、弥勒、路次楽隊(ろじがくたい)、ミルクングヮ、赤田の村人の順に、首里殿内跡の赤田クラブを出発して、弥勒節を歌い、且つ奏でながら赤田マチグチに向かう。(赤田市のない今では、赤田クラブの庭に舞台を設え、赤田クラブを出て赤田町の外周を1時間ほどかけて、マチマーイ(街廻り)をした後、クラブの舞台でのウトゥイムチとなる。 転載ここまで。( )の解説は筆者。
通り沿いには大人に混じって小さな子を抱いた人や、ベビーカーの赤ちゃんが詰めかけ弥勒の団扇の洗礼を待ち受けていた。2~3歳くらいの子等は弥勒様の大きな顔にビックリして泣き出したり、逃げだす子もいて、見ていて楽しい。今回見ていて、「時代だよなぁ~」と思ったのは、ペットの犬や猫を抱いて待ち受ける人達がいたことだ。でも心優しい吾ら弥勒加那志(ミルクガナシー〈ガナシーは尊称〉は人畜の分け隔てなく、その福の風を送るのでした。
ミルクのゆったりとした行列が移動するにつれて、笑顔や歓声の波が移って行く、それがやがて赤田町全体を包み込んでいく・・・・・極楽浄土の風が吹いているんだ!この光景を見ながら僕は例によって「俺は今、天の御国にいる!」と呟いたのだった。
ミルクングヮと チャンチャンと ピーラルラー
ミルクングヮはンカジバタ(百足旗)ムカデの足のようなヒラヒラの付いた三角旗を持っている。保育園児から小学校中学年(3~4年生)の児童からなる。僕のオヤジも2回でたと言っていた。(左写真)路次楽隊の端のメガネをかけた女子中学生が持っているのが「チャンチャン」中華シンバルと名付けておく。 (写真右) 主旋律を奏でるピーラルラー(確かにそのような音色がするが、チャンチャンといい、このピーラルラーといい、琉球の先人達の音色をそのままに、その楽器の名称にするセンスには笑っちゃうのだ)ピーラルラーはチャルメラともいうらしい。思わずインスタントラーメンの外装に描かれた屋台のオジサンを思い出した。「夜鳴きソバ屋」のない沖縄でも、あの「ソラシーラソ・ソラシラソラー」の旋律を思い出す。 チャルメラとあの旋律については面白いので調べて『番外編』を後付けする。
ウトゥイムチ
赤田町を一周して赤田クラブに帰ってくると、クラブの庭に設えたバンクと呼ばれるステージでのウトゥイムチ(ミルク様への お・も・て・な・し タイムです)歌や踊り、空手の演武などで、ミルク様と下界の衆生との年に一度の邂逅(かいこう)を供に歓び、その幸せを皆で分かち合うのです。直会(なおらい)、沖縄でいうウサンデーです。喜びも悲しみも、そして食べ物も供に分かち合い戴く、そしてその歓びを確認していく事はとても大切な事です・・・・ここをクリック
弥勒菩薩と布袋さん
今回、友人の一人と「赤田のミルクウンケー」の話しをしている中、「あれは、弥勒菩薩ではなく、布袋さんだぜ!」と意見が一致した。10歳を過ぎた頃から(もの心の付いた頃)から、ミルクの話は父から何度となく聴かされてきたが、布袋だの弥勒だのという話題になった事は無く石川門中でも「肥満体のジーチャンイコール 「ミルク様」と言う考えが固定化されているのだと思う。(ミルク様悪口じゃないのですゴメンナサイ!) とても新鮮な気付きであった。
弥勒菩薩といえば、京都広隆寺の半跏思惟像(はんかしいぞう)が有名である。(写真左、郵便切手にもなった)。修学旅行で半跏思惟像に初めて出会った時は、その美しさ、静けさに、しばし、動くのもためらわれた記憶がある。それにしても大きなお腹で明るく、豪放磊落な熱血漢、たくさんの子供たちを引き連れて旅をしていた布袋さんと、慈愛に満ちて思慮深そうな弥勒菩薩ではイメージのギャップは甚だしい。
そこで、この謎を解明しようと弥勒菩薩と布袋さんとの関係をネットで調べてみた。
インドで生まれ、中国を経て日本に伝来した仏教は、その時代や地域と複雑に絡み合い、変化し、日本の神仏習合まで併せると、とても僕のような凡人には他人に説明などできないと思い知った。そこで、おもいきりハショリ、平ベッタク云えば。弥勒菩薩が一般の衆生を救済する時には垂迹して(本地垂迹説の垂迹)布袋さんの姿を借りて人間世界に現れる化生としての布袋さん・・・というところに辿りついた。布袋和尚は800年代後半に生まれ、916年に没した実在の禅僧である。(神とキリストの関係に少し似ている。)
弥勒菩薩が七福神の一人となった今、そのご利益は、夢を育て、人格を磨き、円満な家庭を築いて、金運を招福するということで、慈恵(いつくしみ)と和合の神様、予知と金運の神様として信仰されているようである。
そういえば、七福神のなかの紅一点、弁財天も龍潭の東に、天女橋とともに弁財天堂として県民に親しまれている。
ミルクウンケー(琉球語 うちなーぐち)直訳すれば「弥勒様のお迎え」とすればいいのだろうか?今年は8月17日(日)午後4時30分、赤田首里殿内(アカタスンドゥンチ)跡の赤田クラブから弥勒様御一行がお出ましになる、僕もバイクに飛び乗り駆けつけた。「ミルクウンケー」については『沖縄タイムス大百科』から以下転載する。
弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化生といわれる中国唐代の禅僧、布袋和尚(ほていおしょう)が、七福神の一つとして京都の祭礼の行列〈風流〉に登場したのは室町時代といわれる。
首里では350年程前、石川門中の祖、求道 〈ぐどう〉長老により、赤田首里殿内に弥勒面が祀られ、7月14日に泰安所を開き、16日に門中を中心に道ジュネー(行列)があった。赤田マチグチ(赤田市場口、今のウフカクジャー交差点から南に100メートル足らずの路肩一帯は赤田市の跡で沖縄戦まで、食肉、豆腐、野菜、雑穀など、主として食料品の相対売り市場であった。←久手堅憲夫著『首里の地名』より)突き当たり右に直角に曲がるあたりに舞台を設け、その中央に面や胴、衣装一式を安置し、まわりには弥勒御愛子(ミルクウミングヮ、ミルクングヮ)が並び大香炉に香を焚き、東に向かって(←ここ重要)世界風
ユガフ、豊作、健康を祈願した後、祭主の本家、大石川(ウフイシチャー、首里石川の宗家)の家長が面と作り物の胴をつけ、ドゥジン・袴をつけ胸をはだけて大団扇(うちわ)で豊年を招き寄せながら、舞台をしずしずと一周する。
弥勒面は戦災で焼失したが、平成6年に復元された。 行列は高張提灯一対を持ち、先頭に警護役、弥勒、路次楽隊(ろじがくたい)、ミルクングヮ、赤田の村人の順に、首里殿内跡の赤田クラブを出発して、弥勒節を歌い、且つ奏でながら赤田マチグチに向かう。(赤田市のない今では、赤田クラブの庭に舞台を設え、赤田クラブを出て赤田町の外周を1時間ほどかけて、マチマーイ(街廻り)をした後、クラブの舞台でのウトゥイムチとなる。 転載ここまで。( )の解説は筆者。
通り沿いには大人に混じって小さな子を抱いた人や、ベビーカーの赤ちゃんが詰めかけ弥勒の団扇の洗礼を待ち受けていた。2~3歳くらいの子等は弥勒様の大きな顔にビックリして泣き出したり、逃げだす子もいて、見ていて楽しい。今回見ていて、「時代だよなぁ~」と思ったのは、ペットの犬や猫を抱いて待ち受ける人達がいたことだ。でも心優しい吾ら弥勒加那志(ミルクガナシー〈ガナシーは尊称〉は人畜の分け隔てなく、その福の風を送るのでした。
ミルクのゆったりとした行列が移動するにつれて、笑顔や歓声の波が移って行く、それがやがて赤田町全体を包み込んでいく・・・・・極楽浄土の風が吹いているんだ!この光景を見ながら僕は例によって「俺は今、天の御国にいる!」と呟いたのだった。
ミルクングヮと チャンチャンと ピーラルラー
ミルクングヮはンカジバタ(百足旗)ムカデの足のようなヒラヒラの付いた三角旗を持っている。保育園児から小学校中学年(3~4年生)の児童からなる。僕のオヤジも2回でたと言っていた。(左写真)路次楽隊の端のメガネをかけた女子中学生が持っているのが「チャンチャン」中華シンバルと名付けておく。 (写真右) 主旋律を奏でるピーラルラー(確かにそのような音色がするが、チャンチャンといい、このピーラルラーといい、琉球の先人達の音色をそのままに、その楽器の名称にするセンスには笑っちゃうのだ)ピーラルラーはチャルメラともいうらしい。思わずインスタントラーメンの外装に描かれた屋台のオジサンを思い出した。「夜鳴きソバ屋」のない沖縄でも、あの「ソラシーラソ・ソラシラソラー」の旋律を思い出す。 チャルメラとあの旋律については面白いので調べて『番外編』を後付けする。
ウトゥイムチ
赤田町を一周して赤田クラブに帰ってくると、クラブの庭に設えたバンクと呼ばれるステージでのウトゥイムチ(ミルク様への お・も・て・な・し タイムです)歌や踊り、空手の演武などで、ミルク様と下界の衆生との年に一度の邂逅(かいこう)を供に歓び、その幸せを皆で分かち合うのです。直会(なおらい)、沖縄でいうウサンデーです。喜びも悲しみも、そして食べ物も供に分かち合い戴く、そしてその歓びを確認していく事はとても大切な事です・・・・ここをクリック
弥勒菩薩と布袋さん
今回、友人の一人と「赤田のミルクウンケー」の話しをしている中、「あれは、弥勒菩薩ではなく、布袋さんだぜ!」と意見が一致した。10歳を過ぎた頃から(もの心の付いた頃)から、ミルクの話は父から何度となく聴かされてきたが、布袋だの弥勒だのという話題になった事は無く石川門中でも「肥満体のジーチャンイコール 「ミルク様」と言う考えが固定化されているのだと思う。(ミルク様悪口じゃないのですゴメンナサイ!) とても新鮮な気付きであった。
弥勒菩薩といえば、京都広隆寺の半跏思惟像(はんかしいぞう)が有名である。(写真左、郵便切手にもなった)。修学旅行で半跏思惟像に初めて出会った時は、その美しさ、静けさに、しばし、動くのもためらわれた記憶がある。それにしても大きなお腹で明るく、豪放磊落な熱血漢、たくさんの子供たちを引き連れて旅をしていた布袋さんと、慈愛に満ちて思慮深そうな弥勒菩薩ではイメージのギャップは甚だしい。
そこで、この謎を解明しようと弥勒菩薩と布袋さんとの関係をネットで調べてみた。
インドで生まれ、中国を経て日本に伝来した仏教は、その時代や地域と複雑に絡み合い、変化し、日本の神仏習合まで併せると、とても僕のような凡人には他人に説明などできないと思い知った。そこで、おもいきりハショリ、平ベッタク云えば。弥勒菩薩が一般の衆生を救済する時には垂迹して(本地垂迹説の垂迹)布袋さんの姿を借りて人間世界に現れる化生としての布袋さん・・・というところに辿りついた。布袋和尚は800年代後半に生まれ、916年に没した実在の禅僧である。(神とキリストの関係に少し似ている。)
弥勒菩薩が七福神の一人となった今、そのご利益は、夢を育て、人格を磨き、円満な家庭を築いて、金運を招福するということで、慈恵(いつくしみ)と和合の神様、予知と金運の神様として信仰されているようである。
そういえば、七福神のなかの紅一点、弁財天も龍潭の東に、天女橋とともに弁財天堂として県民に親しまれている。
11/27: 1933東京の泡盛➁
「東京琉球泡盛商一覧」(1933年3月5日ー大宜味朝徳『南島』第三号)
麹町区
飯田町1の9-嵩原安智/丸の内丸ビル2階264-恩河朝健
神田区
淡路町2の15-宮城清/錦町3の16-鵜木清治/北神保町17-二幸商店/松富町1-前里宗恭/五軒町35-亀島靖治/鍋町201-比嘉林繁/美土代町1の2-加納太三次/今川小路1の1-瀬長カナ/榮町2-儀間偸/西小川町2の5-吉岡宏/北神保町17-高島喜代治
日本橋区
鉄砲町24(眞人園)-山田眞山/蠣殻町(うるま)ー松山清之丞
京橋区
槇町3の5龍宮園ー宜保友厚/八丁堀4の2-渋谷三郎/八丁堀3の6-嘉手苅信世/月島通り1の7-新垣清次郎/湊町1の6南国屋ー伊藤辰巳/湊町1の3の3-入江藤五郎□「私は琉球泡盛を取り扱ってから30余年になるが、(略)何といっても泡盛の黄金時代は明治30年ごろから明治38,9年の日露戦争直後の頃であった。日露戦争の時には泡盛を火薬の原料にすると云うので僕は海江田の代人として三萬圓の保証金を陸軍に供託して泡盛を陸軍に納入したのであるが其のときは容器が不足し阪神から酒樽を買い集めて沖縄に送りそれに泡盛を詰め込んで直航船で輸送したものである。火薬の原料であるから色とか香には頓着なく45度の度さえあればどしどし納入出来たものであるから愉快なものであった。(略)泡盛が今日の如く盛大になったことは鹿児島商人の力もあづかって大きい。初め東京に鹿児島の商人の手を経て売り込んだもので、鹿児島の商人は沖縄の酒造家に米を供給し其の代償に酒を受け取っていたので応でも之を売り捌かねばならぬので、盛んに宣伝したものであった」/新富町2ー田島清
芝区
新橋7の2-北浦未次郎/琴平町31-宮城邦英/金杉町4の10-田里丕顕/浜松町2の2-小堀幾志/浜松町市電停留所前ー未廣屋泡盛店/浜松町13の7-根路銘安昌/札ノ辻市電終点際ー宇崎市蔵
麻布区
龍土町32-森川清次郎
小石川区
江戸川町1春海ー宮城新保/新諏訪町1-有岡豊次郎/柳町11うるまー渡邉亀吉/大塚坂下町187三喜ー坂本トヨ/音羽町1の8-石川甚太郎
本郷区
駒込蓬莱町5-大宜味朝徳/駒込千馱木町218-山口光輝/台町2-漢那朝常/駒込曙町17-本部朝基/元町ー太田洋酒店/根津八重垣町20三金ー關ハル/真砂町37-和田榮次郎
下谷区
金杉下町105-亀島商店/竹町131-崎原嘉子/上車坂2-三島支店/御徒町1の56-松永美三/竹町12-儀間新/谷中初音町4の187-松島泡盛店/上根岸58-王冠泡盛店
浅草区
東仲町7-道政清次郎/北清島町25-小泉元松/七軒町2-外間則榮/山谷4の5-國吉眞善/千束3の146-三島支店/吉原裏門前ー佐原屋洋酒店/向柳原町1の11-小笠原ヒロ子/田中町72沖縄屋-矢賀宗友/新谷町12-スタンド呑樂/松清町4-寺田庄一
本所区
松井町2の1-平敷安用/亀澤町3の1ー川原田歳雄/緑町274-浦崎政永/江東橋町1の4寶屋ー久馬清光/吾妻橋2の1-宇辰重直/石原町4の26-小關信四郎
深川区
安宅町7電本1235-川村禎二/牡丹町3の11-新垣商店/東森下町40-山田利喜造/東森下町109-崎山喜昌/石島町163-平良幸盛/永代町1の10-屋宜盛繁
豊島区
巣鴨町2の34-金城時男/駒込6の535-山川喜蔵/駒込市電車庫下うるまー原口三次/巣鴨町3丁目ー増田屋泡盛店/池袋891-越中屋ー清水安次郎/駒込ー北島藤光
品川区
大井権現町3724-砂川泰教/東大崎居木橋際うるまー玉川庄右衛門
澁谷区
幡ケ谷本町679-仲本宗厚
中野区
打越25-上里参治
板橋区
清水町163-石川静子
淀橋区
東大久保290-河村高矩 /戸塚町3丁目うるまー杉本信夫/百人町うるまー北島三代吉/目黒区上目黒2の1963-照屋林仁
足立区
千住中居町6-小島金康
荒川区
南千住2の78-小林友次郎/北千住本町2の5-山盛泡盛店/南千住町2の76-鈴木長吉/日暮里旭町2の92-折原由太郎
瀧ノ川区
田端町380-八藤勅山/西ヶ原694-島田正義
荏原区
戸越350-大久保志郎
江戸川区
小松川2の60-今井清松/小岩町1の1288-三島支店
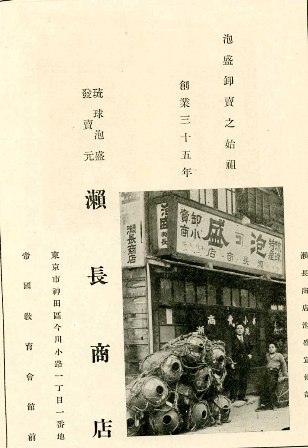
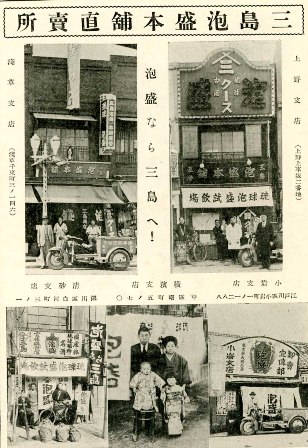
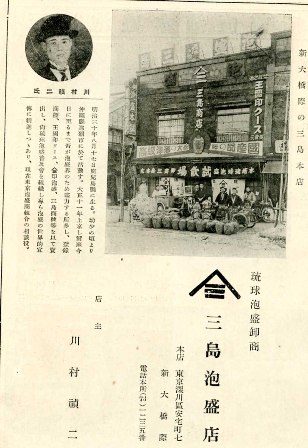
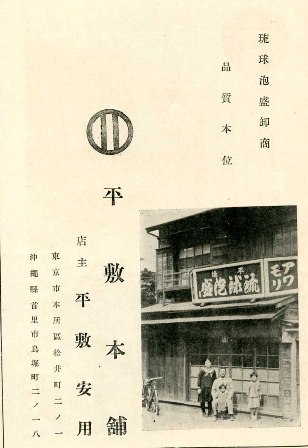
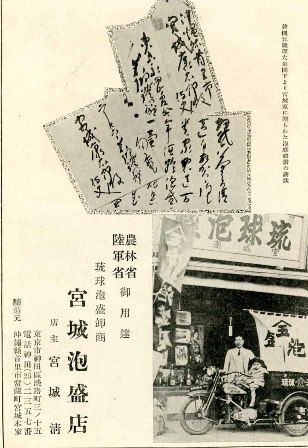
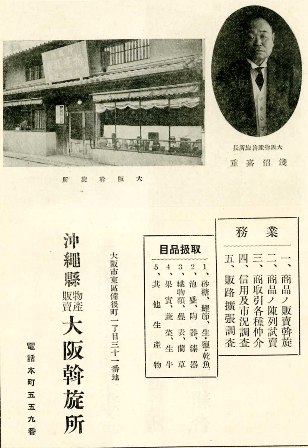
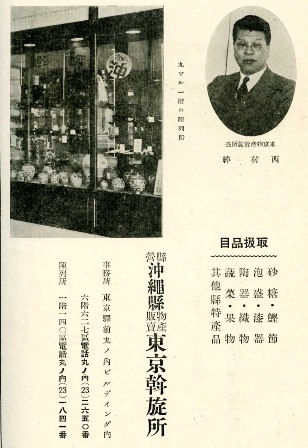
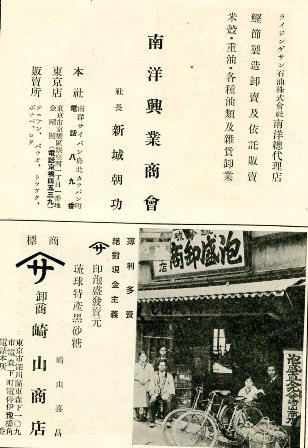
麹町区
飯田町1の9-嵩原安智/丸の内丸ビル2階264-恩河朝健
神田区
淡路町2の15-宮城清/錦町3の16-鵜木清治/北神保町17-二幸商店/松富町1-前里宗恭/五軒町35-亀島靖治/鍋町201-比嘉林繁/美土代町1の2-加納太三次/今川小路1の1-瀬長カナ/榮町2-儀間偸/西小川町2の5-吉岡宏/北神保町17-高島喜代治
日本橋区
鉄砲町24(眞人園)-山田眞山/蠣殻町(うるま)ー松山清之丞
京橋区
槇町3の5龍宮園ー宜保友厚/八丁堀4の2-渋谷三郎/八丁堀3の6-嘉手苅信世/月島通り1の7-新垣清次郎/湊町1の6南国屋ー伊藤辰巳/湊町1の3の3-入江藤五郎□「私は琉球泡盛を取り扱ってから30余年になるが、(略)何といっても泡盛の黄金時代は明治30年ごろから明治38,9年の日露戦争直後の頃であった。日露戦争の時には泡盛を火薬の原料にすると云うので僕は海江田の代人として三萬圓の保証金を陸軍に供託して泡盛を陸軍に納入したのであるが其のときは容器が不足し阪神から酒樽を買い集めて沖縄に送りそれに泡盛を詰め込んで直航船で輸送したものである。火薬の原料であるから色とか香には頓着なく45度の度さえあればどしどし納入出来たものであるから愉快なものであった。(略)泡盛が今日の如く盛大になったことは鹿児島商人の力もあづかって大きい。初め東京に鹿児島の商人の手を経て売り込んだもので、鹿児島の商人は沖縄の酒造家に米を供給し其の代償に酒を受け取っていたので応でも之を売り捌かねばならぬので、盛んに宣伝したものであった」/新富町2ー田島清
芝区
新橋7の2-北浦未次郎/琴平町31-宮城邦英/金杉町4の10-田里丕顕/浜松町2の2-小堀幾志/浜松町市電停留所前ー未廣屋泡盛店/浜松町13の7-根路銘安昌/札ノ辻市電終点際ー宇崎市蔵
麻布区
龍土町32-森川清次郎
小石川区
江戸川町1春海ー宮城新保/新諏訪町1-有岡豊次郎/柳町11うるまー渡邉亀吉/大塚坂下町187三喜ー坂本トヨ/音羽町1の8-石川甚太郎
本郷区
駒込蓬莱町5-大宜味朝徳/駒込千馱木町218-山口光輝/台町2-漢那朝常/駒込曙町17-本部朝基/元町ー太田洋酒店/根津八重垣町20三金ー關ハル/真砂町37-和田榮次郎
下谷区
金杉下町105-亀島商店/竹町131-崎原嘉子/上車坂2-三島支店/御徒町1の56-松永美三/竹町12-儀間新/谷中初音町4の187-松島泡盛店/上根岸58-王冠泡盛店
浅草区
東仲町7-道政清次郎/北清島町25-小泉元松/七軒町2-外間則榮/山谷4の5-國吉眞善/千束3の146-三島支店/吉原裏門前ー佐原屋洋酒店/向柳原町1の11-小笠原ヒロ子/田中町72沖縄屋-矢賀宗友/新谷町12-スタンド呑樂/松清町4-寺田庄一
本所区
松井町2の1-平敷安用/亀澤町3の1ー川原田歳雄/緑町274-浦崎政永/江東橋町1の4寶屋ー久馬清光/吾妻橋2の1-宇辰重直/石原町4の26-小關信四郎
深川区
安宅町7電本1235-川村禎二/牡丹町3の11-新垣商店/東森下町40-山田利喜造/東森下町109-崎山喜昌/石島町163-平良幸盛/永代町1の10-屋宜盛繁
豊島区
巣鴨町2の34-金城時男/駒込6の535-山川喜蔵/駒込市電車庫下うるまー原口三次/巣鴨町3丁目ー増田屋泡盛店/池袋891-越中屋ー清水安次郎/駒込ー北島藤光
品川区
大井権現町3724-砂川泰教/東大崎居木橋際うるまー玉川庄右衛門
澁谷区
幡ケ谷本町679-仲本宗厚
中野区
打越25-上里参治
板橋区
清水町163-石川静子
淀橋区
東大久保290-河村高矩 /戸塚町3丁目うるまー杉本信夫/百人町うるまー北島三代吉/目黒区上目黒2の1963-照屋林仁
足立区
千住中居町6-小島金康
荒川区
南千住2の78-小林友次郎/北千住本町2の5-山盛泡盛店/南千住町2の76-鈴木長吉/日暮里旭町2の92-折原由太郎
瀧ノ川区
田端町380-八藤勅山/西ヶ原694-島田正義
荏原区
戸越350-大久保志郎
江戸川区
小松川2の60-今井清松/小岩町1の1288-三島支店
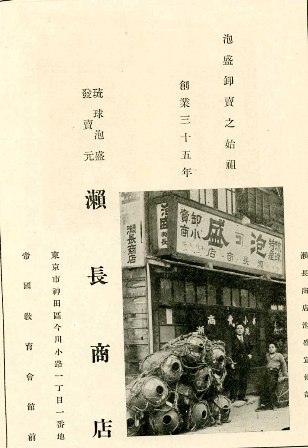
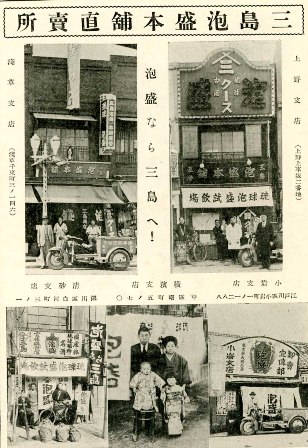
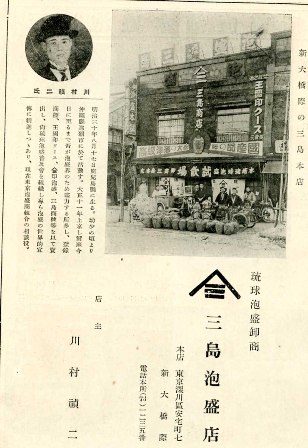
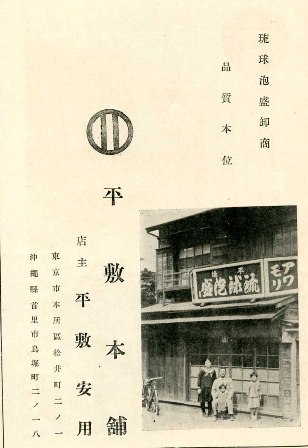
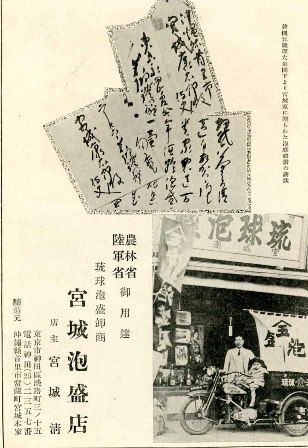
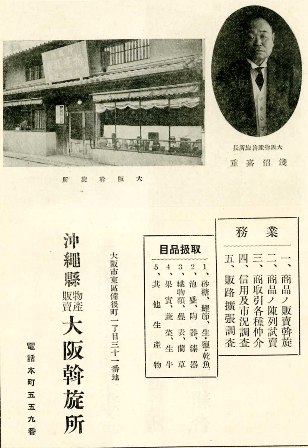
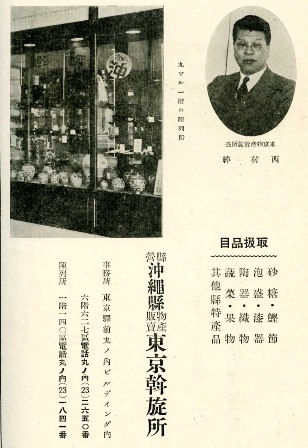
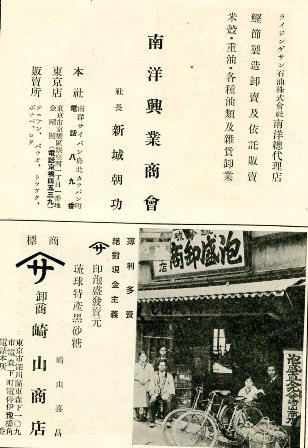
03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館




1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」
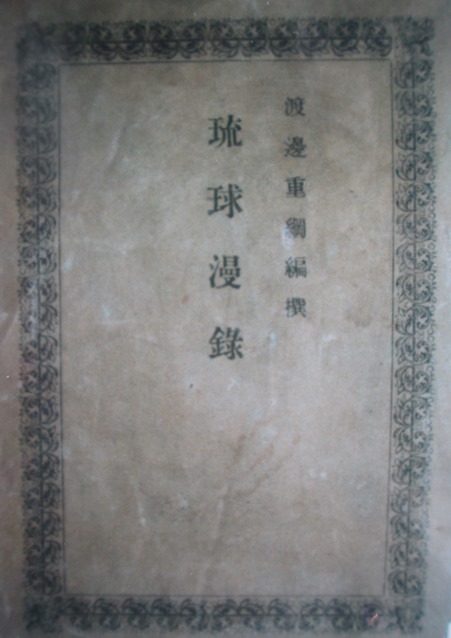

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治
うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。
討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。
1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

兼城昌興


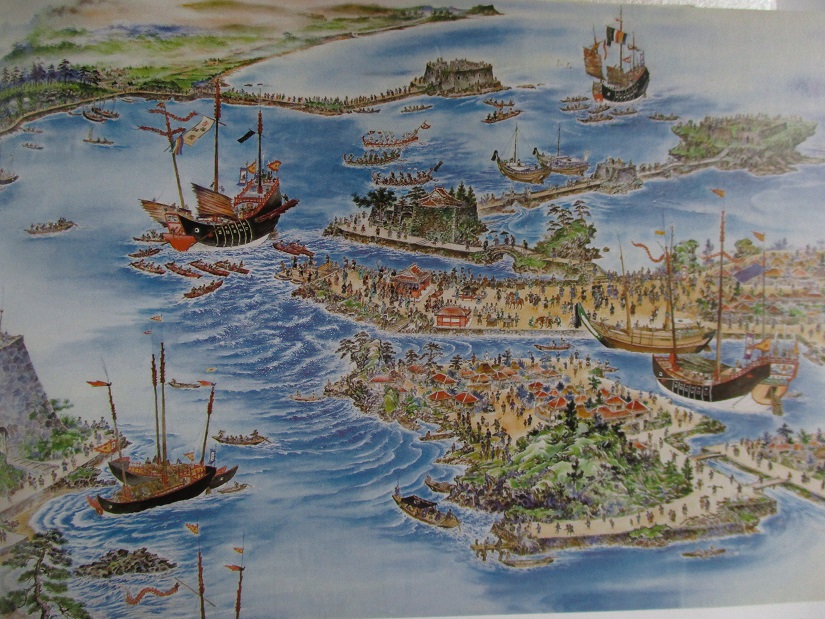
金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」

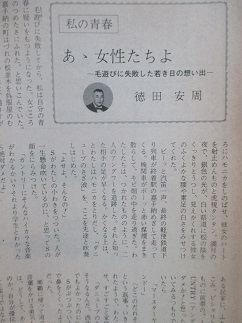

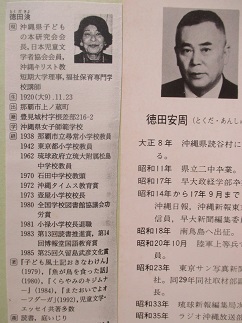
沖縄の雑誌『青い海』1971年5月号 徳田安周「私の青春/あゝ女性たちよー毛遊びに失敗した若き日の想い出ー」
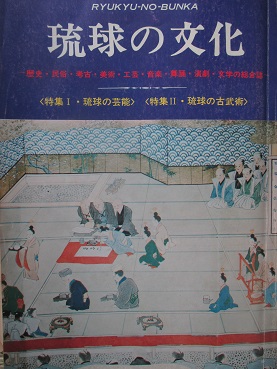
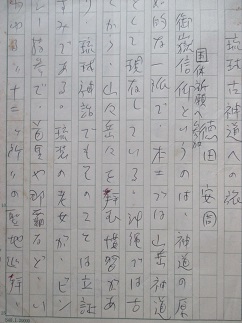
1973年10月 『琉球の文化』第四号 徳田安周「琉球古神道への旅」
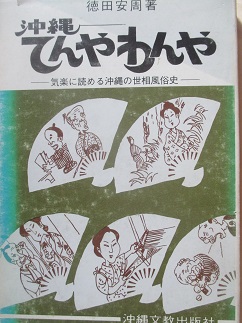
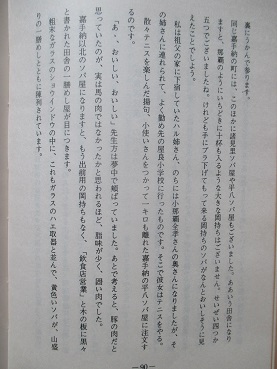
1975年8月 徳田安周『沖縄てんやわんやー気楽に読める沖縄の世相風俗史ー』沖縄文教出版社(神山吉光)
川平朝申

1960年ごろ料亭松の下にて野町良夫牧師(1937年、那覇日基教会牧師)歓迎会。前列右から3人目・当山正堅夫人、野町夫妻、古賀善次。後列右・山田實、4人目・川平朝申、大嶺政寛、一人置いて天願俊貞、一人置いて当山堅一。徳田安周も居る。
1951年11月 第3回沖展(琉米文化会館) 川平朝申「西陽射す頃」「思い出の丘」
1955年3月 第7回沖展(壷屋小学校) 川平朝申「旧知事官舎」
1958年3月 第10回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真「みーにし」「影」
1959年3月 第11回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真「河童」「古都の石畳道」「ビルとドブ川」「晩秋」
1960年3月 第12回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真「或る踊り」「暮色の国際通り」
1963年3月 第15回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真「富士とチャンパ葵」
1963年5月 『沖縄芸能マガジン』川平朝申「沖縄演劇の将来を思う!-現役俳優へ希うこと!」
○私は若い頃から郷土史や郷土の民俗、土俗に就いて深い興味をもっていた。それは私が中学の頃、台湾に移住し、郷土に対する郷愁が、こうして私の心を郷土の総てに愛着をよせるようにしたのかもしれない。とりわけ郷土の演劇に対しては私の心をすっかり、とりこにしてしまった。それと云うのも私の父が非常に芝居好きで、よく父に連れられて辻町のはたみちの芝居に行ったものである。「球陽座」「中座」等、芝居がはねると父はきまったように楽屋まで足を運び、幹部俳優に挨拶をし、「今日の芝居は上出来だった!」等と激励をしていた。
1968年3月 第20回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真カラー「夕陽その1」 前原基男「旧家」
西村貞雄「S子の首」
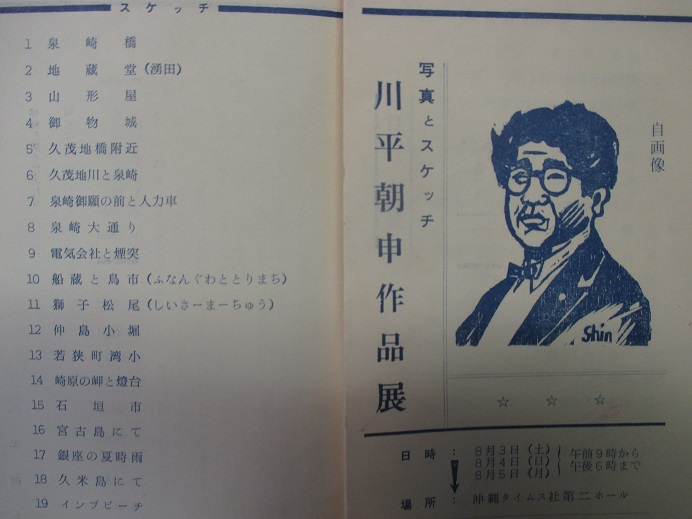
1968年8月 沖縄タイムス社ホール「川平朝申作品展ー写真とスケッチ」
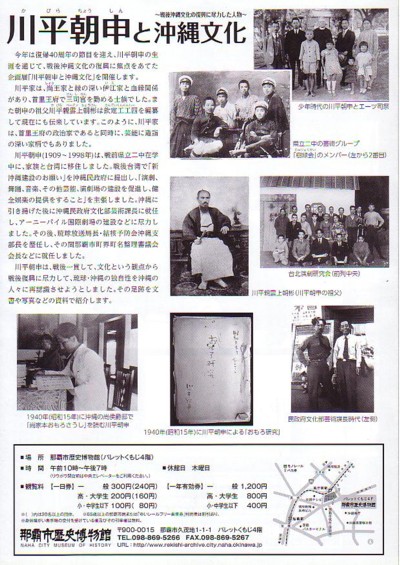
1888年・第1回卒業ー高嶺朝申、仲吉朝助(農大乙科卒)、百名朝計(沖縄銀行頭取)/1889年・第2回卒業ー石原榮輔、村山盛福/1891年・第3回卒業ー伊地柴本(首里市役所)、恩河朝祐、金城紀長、仲吉朝紀、若山忠次郎/1893年3月・第4回卒業ー呉屋健哉」、重久雄吉(宮古郡税務署長)、谷川益太郎、與儀喜英(産業銀行) 同年5月・第5回卒業ー大城盛祐(長崎控訴院書記)、大城朝健、仲濱政数(台湾製糖会社那覇事務所)/1894年・第6回卒業ー新垣壽助(小倉電気商会)、赤嶺新竹、奥川鐘太郎(在東京)、島袋松、瀘名波起益、玉那覇重善、知念堅輝(農大実科卒産業銀行重役 大里村長)、照屋孚能、長嶺紀啓、橋本諭吉(在台湾)、安元實得(在米)/1895年・第7回卒業ー伊藤雅二(那覇池田店 那覇市議)、蒲原秀一、本村啓介、久場景述、崎間永行、玉城瑩(早稲田卒)、富盛寛卓(宮古小学校)、比嘉賀学(那覇市助役)、山城瑞喜
1896年・第8回卒業ー伊波普猷(文学士 県立図書館長)、小橋川朝松(八重山)、下地昌道/1897年・第9回卒業ー新垣隆永、伊波善思(県会議員)、伊差川英文、親泊朝輝(愛媛県宇和郡長)、金城紀光(医学士 元順病院 那覇市議)、小禄恵芝、酒井豊雄、松原寛功、祝嶺春棟、高嶺朝扶(早稲田大卒 首里)、武富良秀、照屋徳太郎、友寄善直、名嘉眞武煌、肥後傳熊、真境名安興、山内盛能、屋比久孟昌/1898年・第10回卒業ー浦崎康信、許田普永、久高友輔(首里郵便局長 首里市会議員)、兒玉銓吉、高山徹(元玉那覇 農学士 山本農相別邸)、天願貞靜、渡久地政瑚、田中豊彦、西弘海、根路眼恵頒(普天間)、野原春太郎、饒平名紀腆(名古屋医専卒 那覇波上病院)、東恩納盛亮(台湾高雄州旗山第二公学校)、平野益照(大島庁々書記)、藤田孝男(海軍機関大尉)、古堅宗祐、外間現篤(法学士 朝鮮大邱 弁護士)
1899年・第11回卒業ー新城源次郎、新川善義、新川善長(臺灣花蓮港林田駅内徳森製材所)、石川親忠、伊波普成(牧師 那覇)、喜屋武盛長(在米)、久場守益(那覇 石炭運送業)、熊谷照英、古波蔵信貞、小嶺幸欣(那覇東)、崎山宗秀(東京高等師範卒 文学士 京都大学院)、佐久原好傳(伝道師 メソジスト教会)、玉那覇平益、照屋孚至(久米島登記所)、宮城鐵夫(農学士 台南製糖社宅)、山代質、與古田良成/1900年・第12回卒業ー有川五郎(長崎医専卒)、赤嶺仁太、池ノ上嘉(在台北)、伊波興旺、岩城長蔵、糸数青盛(那覇市役所)、臺数弘榮(県立師範学校教諭)、漢那憲英(那覇甲辰小学校訓導)、國吉眞徳、小嶺幸慶(法学士 勧銀支店)、小波津清榮、崎浜秀主(早稲田高等師範卒 商銀専務取締役)、島袋慶福(真壁小学校長)、富原守昌、仲里貞助(宮崎小林税務署)、仲村渠寛忠、野村安保、東恩納寛惇(文学士 東京府立第一中学校教諭)、肥後武二郎(台南製糖会社西原工場)、比嘉盛珍(福岡県若松炭坑株式会社)、藤田猛(長崎医専卒 長崎開業)、福永兼吉(歩兵大尉 熊本十三聯隊中隊長)、福永福要、眞榮平房貞、山田朝常、與那覇政敷
1901年・第13回卒業ー安次嶺榮華(専修大学卒 那覇市役所)、糸数東榮(在布)、大山岩雄(早稲田大学文科卒 県立農学校教諭)、大山辰二(長崎医専卒 臺灣臺北市西門街開業)、小野榮(商業学校教諭)、大城元次郎(名護村長)、金城加那(那覇技芸学校)、金城盛行、神田橋榮助、金城普照(農大実科卒 島尻郡役所技手)、金城兼吉、城間恒用、城間宏恵(長崎医専卒 支那漢口医院)、桑江良行(早稲田大卒 県立二中教諭)、久場守友(与那原郵便局長)、酒井豊静(開業医)、座喜味盛彰、島袋盛昌、玉城濶(千葉医専卒 糸満開業)、平良仁五郎、玉城安盛、手登根順義、照屋久八(在台湾)、當山順吉(恩納村 役場員)、仲本興賀、仲村政哲(那覇商業銀行)、名嘉山安忠(長崎医専卒 撫臺街開業)、仲本政春(歩兵中尉 那覇市議)、仲村渠榮行(在米)、仲宗根新一郎、前田忠(高商卒 横浜正金銀行シンガポール支店長)、百名朝敏(青山学院卒 尚家家扶心得)、前堂昌俊、松元完榮(県師範学校書記)、宮城寛良(那覇港務所)、宮城嗣謹(八王子小学校教員)、宮里仁榮(大阪医専卒 秋田県山本郡扇淵村)、宮城助友(八重山炭鉱)、勝屋米雄(臺灣総督府通信局)、山城範益(首里市会議員 砂糖委託組合理事)、山城正鳴(臺灣公学校)、與儀正道(在米)
1902年・第14回卒業ー伊仲浩(農大実科卒 那覇)、稲福蒲戸、大橋敬二(巣鴨監獄看守長)、大濱保篤(農大実科卒 鹿児島専売局)、大城幸蔵(ヒリピン大田興行株式会社副社長)、神山政良(法学士 東京市外淀橋専売支局)、金城嘉保(金沢医専卒 那覇医院主)、賀数仁王(開業医 高嶺村與座)、我部政明、嘉手納並藝(後備歩兵少尉 那覇港務所)、喜瀬知彦(宮崎税務署)、國吉眞文(商船学校卒 神戸市日本郵船会社気付デラゴヤ丸)、久高唯忠(医専卒 東京大塚辻町愛仁堂)、小嶺幸輝(名古屋高工卒)、古波鮫唯仁、米須秀松、多嘉良憲(農学士)、玉城實雄(京都医専卒)、高宮城朝三(内閣印刷局)、高嶺朝安(早稲田専門卒)、平良淳榮、渡口精秀(商船学校卒)、渡嘉敷唯續(金沢医専卒 在臺灣)、渡嘉敷通達(県庁)、長嶺亀助(歩兵少佐 陸大卒 参謀本部)、仲本盛松、仲吉朝宏(中城小学校長)、長嶺但吉、仲尾次喜與(在米國桑港)、仲村渠良保、西村助八(農大実科卒 県産業技師物産検査所長)、毛嘉富良、平田直保(県属会計課)、比嘉盛敬、平敷安興(在米)、外間現長(大阪高医卒 大阪府技師)、外間現多(青山学院卒)、丸山芳樹(京大工学士 朝鮮総督府技師)、眞栄平房寛、牧港朝謙(首里市役所)、宮城幸安(商船学校卒 日本郵船会社機関長)、屋富祖徳次郎(金沢医専卒 泊開業)、山川朝棟(沖縄銀行首里支店長)、與儀正榮(農大実科卒 新高製糖会社農課長)
1896年・第8回卒業ー伊波普猷(文学士 県立図書館長)、小橋川朝松(八重山)、下地昌道/1897年・第9回卒業ー新垣隆永、伊波善思(県会議員)、伊差川英文、親泊朝輝(愛媛県宇和郡長)、金城紀光(医学士 元順病院 那覇市議)、小禄恵芝、酒井豊雄、松原寛功、祝嶺春棟、高嶺朝扶(早稲田大卒 首里)、武富良秀、照屋徳太郎、友寄善直、名嘉眞武煌、肥後傳熊、真境名安興、山内盛能、屋比久孟昌/1898年・第10回卒業ー浦崎康信、許田普永、久高友輔(首里郵便局長 首里市会議員)、兒玉銓吉、高山徹(元玉那覇 農学士 山本農相別邸)、天願貞靜、渡久地政瑚、田中豊彦、西弘海、根路眼恵頒(普天間)、野原春太郎、饒平名紀腆(名古屋医専卒 那覇波上病院)、東恩納盛亮(台湾高雄州旗山第二公学校)、平野益照(大島庁々書記)、藤田孝男(海軍機関大尉)、古堅宗祐、外間現篤(法学士 朝鮮大邱 弁護士)
1899年・第11回卒業ー新城源次郎、新川善義、新川善長(臺灣花蓮港林田駅内徳森製材所)、石川親忠、伊波普成(牧師 那覇)、喜屋武盛長(在米)、久場守益(那覇 石炭運送業)、熊谷照英、古波蔵信貞、小嶺幸欣(那覇東)、崎山宗秀(東京高等師範卒 文学士 京都大学院)、佐久原好傳(伝道師 メソジスト教会)、玉那覇平益、照屋孚至(久米島登記所)、宮城鐵夫(農学士 台南製糖社宅)、山代質、與古田良成/1900年・第12回卒業ー有川五郎(長崎医専卒)、赤嶺仁太、池ノ上嘉(在台北)、伊波興旺、岩城長蔵、糸数青盛(那覇市役所)、臺数弘榮(県立師範学校教諭)、漢那憲英(那覇甲辰小学校訓導)、國吉眞徳、小嶺幸慶(法学士 勧銀支店)、小波津清榮、崎浜秀主(早稲田高等師範卒 商銀専務取締役)、島袋慶福(真壁小学校長)、富原守昌、仲里貞助(宮崎小林税務署)、仲村渠寛忠、野村安保、東恩納寛惇(文学士 東京府立第一中学校教諭)、肥後武二郎(台南製糖会社西原工場)、比嘉盛珍(福岡県若松炭坑株式会社)、藤田猛(長崎医専卒 長崎開業)、福永兼吉(歩兵大尉 熊本十三聯隊中隊長)、福永福要、眞榮平房貞、山田朝常、與那覇政敷
1901年・第13回卒業ー安次嶺榮華(専修大学卒 那覇市役所)、糸数東榮(在布)、大山岩雄(早稲田大学文科卒 県立農学校教諭)、大山辰二(長崎医専卒 臺灣臺北市西門街開業)、小野榮(商業学校教諭)、大城元次郎(名護村長)、金城加那(那覇技芸学校)、金城盛行、神田橋榮助、金城普照(農大実科卒 島尻郡役所技手)、金城兼吉、城間恒用、城間宏恵(長崎医専卒 支那漢口医院)、桑江良行(早稲田大卒 県立二中教諭)、久場守友(与那原郵便局長)、酒井豊静(開業医)、座喜味盛彰、島袋盛昌、玉城濶(千葉医専卒 糸満開業)、平良仁五郎、玉城安盛、手登根順義、照屋久八(在台湾)、當山順吉(恩納村 役場員)、仲本興賀、仲村政哲(那覇商業銀行)、名嘉山安忠(長崎医専卒 撫臺街開業)、仲本政春(歩兵中尉 那覇市議)、仲村渠榮行(在米)、仲宗根新一郎、前田忠(高商卒 横浜正金銀行シンガポール支店長)、百名朝敏(青山学院卒 尚家家扶心得)、前堂昌俊、松元完榮(県師範学校書記)、宮城寛良(那覇港務所)、宮城嗣謹(八王子小学校教員)、宮里仁榮(大阪医専卒 秋田県山本郡扇淵村)、宮城助友(八重山炭鉱)、勝屋米雄(臺灣総督府通信局)、山城範益(首里市会議員 砂糖委託組合理事)、山城正鳴(臺灣公学校)、與儀正道(在米)
1902年・第14回卒業ー伊仲浩(農大実科卒 那覇)、稲福蒲戸、大橋敬二(巣鴨監獄看守長)、大濱保篤(農大実科卒 鹿児島専売局)、大城幸蔵(ヒリピン大田興行株式会社副社長)、神山政良(法学士 東京市外淀橋専売支局)、金城嘉保(金沢医専卒 那覇医院主)、賀数仁王(開業医 高嶺村與座)、我部政明、嘉手納並藝(後備歩兵少尉 那覇港務所)、喜瀬知彦(宮崎税務署)、國吉眞文(商船学校卒 神戸市日本郵船会社気付デラゴヤ丸)、久高唯忠(医専卒 東京大塚辻町愛仁堂)、小嶺幸輝(名古屋高工卒)、古波鮫唯仁、米須秀松、多嘉良憲(農学士)、玉城實雄(京都医専卒)、高宮城朝三(内閣印刷局)、高嶺朝安(早稲田専門卒)、平良淳榮、渡口精秀(商船学校卒)、渡嘉敷唯續(金沢医専卒 在臺灣)、渡嘉敷通達(県庁)、長嶺亀助(歩兵少佐 陸大卒 参謀本部)、仲本盛松、仲吉朝宏(中城小学校長)、長嶺但吉、仲尾次喜與(在米國桑港)、仲村渠良保、西村助八(農大実科卒 県産業技師物産検査所長)、毛嘉富良、平田直保(県属会計課)、比嘉盛敬、平敷安興(在米)、外間現長(大阪高医卒 大阪府技師)、外間現多(青山学院卒)、丸山芳樹(京大工学士 朝鮮総督府技師)、眞栄平房寛、牧港朝謙(首里市役所)、宮城幸安(商船学校卒 日本郵船会社機関長)、屋富祖徳次郎(金沢医専卒 泊開業)、山川朝棟(沖縄銀行首里支店長)、與儀正榮(農大実科卒 新高製糖会社農課長)
03/29: 作家・川端康成 ①
□笹川良一の父・鶴吉はかねてよりの碁敵川端三八郎(天保12<1841>年4月10日生まれ)を招き、碁盤を挟んで睨み合っていた。三八郎の孫が康成である。(略)ときに川端康成は、第四代日本ペンクラブ会長として国際ペンクラブ大会の招聘などに奔走し、資金調達に大いに腐心していた。そんな折、竹馬の友は進んで資金援助を申し出ている。(2010年10月 工藤美代子『悪名の棺 笹川良一伝』幻冬舎)
1938年2月」19日『沖縄日報』「懐しの歌手 藤山一郎君きのふ思出の那覇へ/川端康成氏来月来訪」
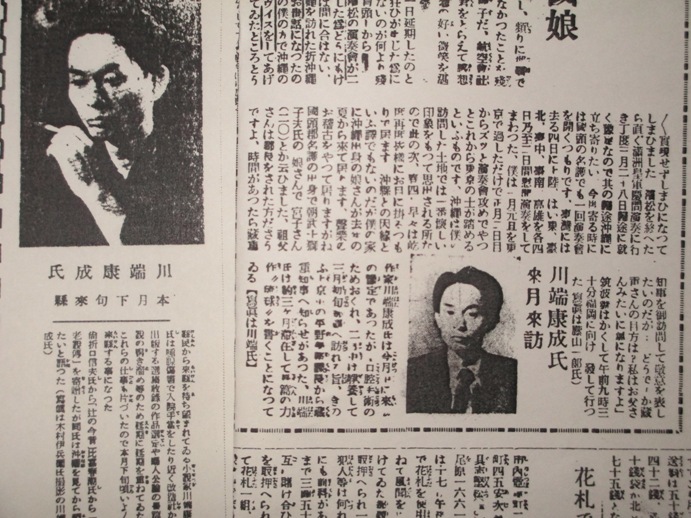
1938年3月『琉球新報』□東京の比嘉春潮から國吉眞哲に「川端康成が沖縄に行く予定で、折口信夫からは『辻の今昔』、比嘉春潮から『遺老説傳』を寄贈された。川端氏は沖縄を見てから読みたい、との話を知らせてきた。が、何らかの事情で来沖は実現しなかった。
1938年4月2日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(2)
1938年4月5日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(4)
1938年4月13日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(3)
1938年4月14日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(4)
1938年4月26日『琉球新報』「簪献納運動に悲鳴の金細工達」
石川正通□「ふりむん随筆」
「雪国」の作者川端康成は、その姉妹篇として沖縄に取材した南国物を書こうと意図して、在京の沖縄知名人に集まってもらって一夕の会談で沖縄に関する予備知識を得ようと会合を催した。何に怖気づいたのか、新感覚派で売り出した「伊豆の踊り子」のこの作家は沖縄行を思い止まって、現地における「沖縄の踊り子」を見る機会を自ら捨てた。
1958年6月3日『琉球新報』「川端康成氏きのう来島」
1958年6月3日『沖縄タイムス』「川端康成氏きのう来島ー誕生日は沖縄で」
1958年6月4日『沖縄タイムス』「二人の作家は沖縄を見るー川端康成氏、内村直也氏」
1958年6月5日『琉球新報』「川端康成氏ー民芸はすばらしい 身をもって沖縄を吸収」
1958年6月8日『沖縄タイムス』「座談会・川端康成氏を囲んでー川端康成、豊平良顕、宮城」聡、南風原朝光、牧港篤三、大城立裕、池田和、太田良博」(上)
1958年6月9日『沖縄タイムス』「々々」(下)
1958年6月9日 「川端康成氏を囲んで(座談会)川端康成、仲宗根政善、中今信、亀川正東、池宮城秀意、上原記者」→6月20日『琉球新報』
1958年6月10日『沖縄タイムス』「琉舞の粋に感慨 川端、鳥海氏ら迎え鑑賞会」
1958年6月11日『沖縄タイムス』「川端、鳥海、沢田、横山4氏の講演会」
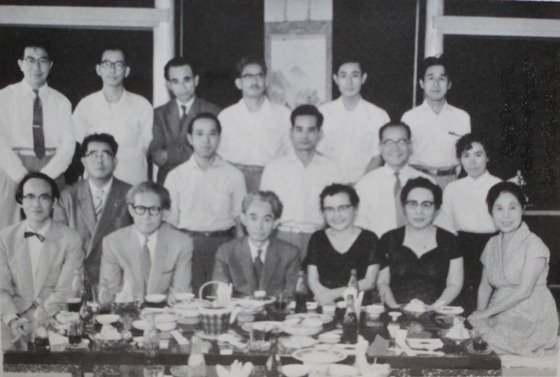

昭和53年9月 千原繁子『随想集 カルテの余白』□1958年6月11日ー前列左から豊平良顕、山里永吉、川端康成、千原繁子、新垣美登子。中列左から具志頭得助、仲本政基、太田良博、牧港篤三。後列左から亀川正東、当真荘平、宮城聡、池宮城秀意、嘉陽安男、船越義彰/写真ー山里永吉案内で糸満の門中墓を見学する川端康成(右)
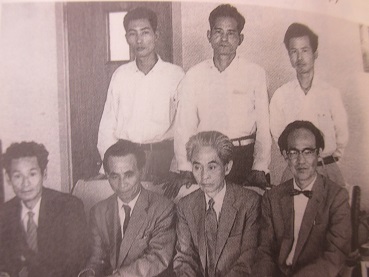
2004年9月 『新生美術』13号「写真前列左よりー南風原朝光、宮城聰、川端康成、豊平良顕/後列左よりー池田和、太田良博、大城立裕」
1958年6月12日『琉球新報』「鳩笛ー川端康成氏は今日のノース・ウェスト機で帰京ーきのうはたまたま川端氏の59回目の誕生日で波上”新鶴”(我那覇文・佐久本嗣子)で、沖縄ペンクラブ主催の別パーティを兼ねた誕生祝」
1958年6月13日『沖縄タイムス』「すばらしい沖縄の踊り 川端氏帰る」/『琉球新報』「川端氏"沖縄独自の美しさ"」

1958年8月『オキナワグラフ』「ペンをかついだお客様ー川端康成氏 来島」
○篤之介のペンネームと感覚的な詩で知られる文学頭取、沖相銀具志頭得助氏の数次にわたる交渉の熱意が実を結び、国際ペンクラブ副会長、日本ペンクラブ会長の川端康成氏が6月2日ひる3時40分、那覇空港着のノースウエスト機で来島した。今回の来島は沖縄ペンクラブの招きによるものであったが、「伊豆の踊子」「雪国」などの作者として文壇でも特異な存在にある同氏の来島は今まで期待されながら不可能視されていただけに、沖縄文化人の喜びは大きく、ペンクラブ会員多数が出迎えた。滞在中はペンクラブの山里、亀川氏や具志頭氏に案内されて、沖縄視察を続けられたが、6月11日、はからずも沖縄で誕生日を迎えたペンの賓客は、ペンクラブ会員、具志頭氏、沖相銀、紅房、那覇薬品、沖縄火災の関係者多数に囲まれ、「私はこんなに誕生日を祝ってもらったのは初めてでしてねエ」と島人達の温かい心づくしにその喜びを語っていた。・・・・
1938年2月」19日『沖縄日報』「懐しの歌手 藤山一郎君きのふ思出の那覇へ/川端康成氏来月来訪」
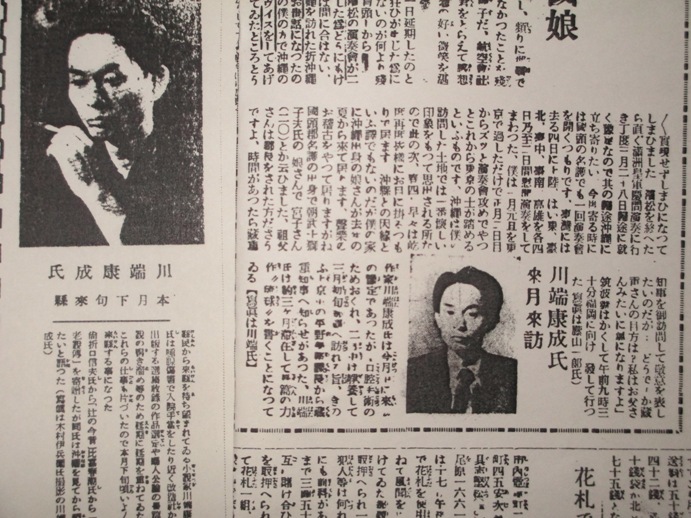
1938年3月『琉球新報』□東京の比嘉春潮から國吉眞哲に「川端康成が沖縄に行く予定で、折口信夫からは『辻の今昔』、比嘉春潮から『遺老説傳』を寄贈された。川端氏は沖縄を見てから読みたい、との話を知らせてきた。が、何らかの事情で来沖は実現しなかった。
1938年4月2日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(2)
1938年4月5日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(4)
1938年4月13日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(3)
1938年4月14日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(4)
1938年4月26日『琉球新報』「簪献納運動に悲鳴の金細工達」
石川正通□「ふりむん随筆」
「雪国」の作者川端康成は、その姉妹篇として沖縄に取材した南国物を書こうと意図して、在京の沖縄知名人に集まってもらって一夕の会談で沖縄に関する予備知識を得ようと会合を催した。何に怖気づいたのか、新感覚派で売り出した「伊豆の踊り子」のこの作家は沖縄行を思い止まって、現地における「沖縄の踊り子」を見る機会を自ら捨てた。
1958年6月3日『琉球新報』「川端康成氏きのう来島」
1958年6月3日『沖縄タイムス』「川端康成氏きのう来島ー誕生日は沖縄で」
1958年6月4日『沖縄タイムス』「二人の作家は沖縄を見るー川端康成氏、内村直也氏」
1958年6月5日『琉球新報』「川端康成氏ー民芸はすばらしい 身をもって沖縄を吸収」
1958年6月8日『沖縄タイムス』「座談会・川端康成氏を囲んでー川端康成、豊平良顕、宮城」聡、南風原朝光、牧港篤三、大城立裕、池田和、太田良博」(上)
1958年6月9日『沖縄タイムス』「々々」(下)
1958年6月9日 「川端康成氏を囲んで(座談会)川端康成、仲宗根政善、中今信、亀川正東、池宮城秀意、上原記者」→6月20日『琉球新報』
1958年6月10日『沖縄タイムス』「琉舞の粋に感慨 川端、鳥海氏ら迎え鑑賞会」
1958年6月11日『沖縄タイムス』「川端、鳥海、沢田、横山4氏の講演会」
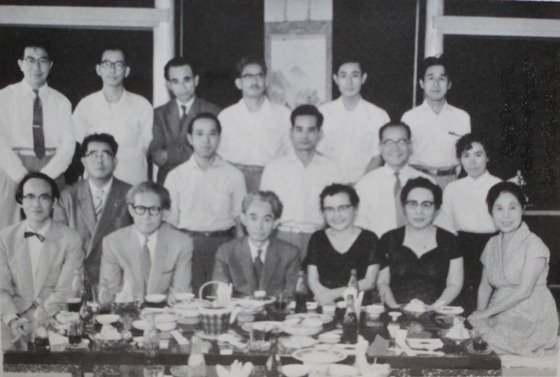

昭和53年9月 千原繁子『随想集 カルテの余白』□1958年6月11日ー前列左から豊平良顕、山里永吉、川端康成、千原繁子、新垣美登子。中列左から具志頭得助、仲本政基、太田良博、牧港篤三。後列左から亀川正東、当真荘平、宮城聡、池宮城秀意、嘉陽安男、船越義彰/写真ー山里永吉案内で糸満の門中墓を見学する川端康成(右)
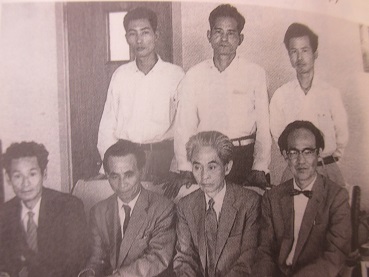
2004年9月 『新生美術』13号「写真前列左よりー南風原朝光、宮城聰、川端康成、豊平良顕/後列左よりー池田和、太田良博、大城立裕」
1958年6月12日『琉球新報』「鳩笛ー川端康成氏は今日のノース・ウェスト機で帰京ーきのうはたまたま川端氏の59回目の誕生日で波上”新鶴”(我那覇文・佐久本嗣子)で、沖縄ペンクラブ主催の別パーティを兼ねた誕生祝」
1958年6月13日『沖縄タイムス』「すばらしい沖縄の踊り 川端氏帰る」/『琉球新報』「川端氏"沖縄独自の美しさ"」

1958年8月『オキナワグラフ』「ペンをかついだお客様ー川端康成氏 来島」
○篤之介のペンネームと感覚的な詩で知られる文学頭取、沖相銀具志頭得助氏の数次にわたる交渉の熱意が実を結び、国際ペンクラブ副会長、日本ペンクラブ会長の川端康成氏が6月2日ひる3時40分、那覇空港着のノースウエスト機で来島した。今回の来島は沖縄ペンクラブの招きによるものであったが、「伊豆の踊子」「雪国」などの作者として文壇でも特異な存在にある同氏の来島は今まで期待されながら不可能視されていただけに、沖縄文化人の喜びは大きく、ペンクラブ会員多数が出迎えた。滞在中はペンクラブの山里、亀川氏や具志頭氏に案内されて、沖縄視察を続けられたが、6月11日、はからずも沖縄で誕生日を迎えたペンの賓客は、ペンクラブ会員、具志頭氏、沖相銀、紅房、那覇薬品、沖縄火災の関係者多数に囲まれ、「私はこんなに誕生日を祝ってもらったのは初めてでしてねエ」と島人達の温かい心づくしにその喜びを語っていた。・・・・
06/12: 古美術・観宝堂

古美術 観宝堂2022-10-28 店主の吉戸直氏と屋良朝信氏

古美術 観宝堂2019-12-13 店主の吉戸直氏と新城栄徳。直氏の父君は吉戸 栄造.、満州から福岡県久留米市
古美術観宝堂は、1972年(昭和47年)沖縄本土復帰の記念すべき年に琉球古美術専門店として創業を開始しました。以来、39年の間より良い品物を求めて常に最善を尽くして参りました。1992年(平成4年)には東京の表参道(旧ハナエ・モリビル)に支店を出店し、現在は根津美術館横の南青山に移転し営業をしております。現在の当店の専門分野は琉球美術及び九州古陶磁であり、特に琉球古美術の分野においては非常に高い評価を受けており、国内外のコレクター様のみならず、県内外の美術館博物館へも多数の琉球古美術の優品を納入させて頂いております。ご興味のある方はお気軽にお立寄りください。
〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-23-11-23-1 MatsuyamaNaha-city, Okinawa Japan.Tel. 098-863-2643, Fax. 098-863-0583



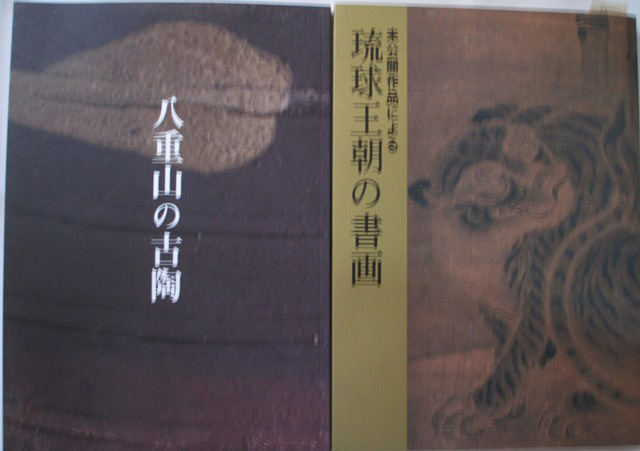
右ー40周年記念として発行された『八重山の古陶』
吉戸直氏の関西大学の先輩
辻合 喜代太郎(つじあい きよたろう、1908年6月25日 - 1993年7月2日)は、服飾史研究者。
大阪府出身。大阪天王寺師範学校卒、関西大学法文学部哲学科卒。1959年「日本上代文様の研究」で関西大学文学博士。大阪市立大学家政学部助教授、教授、京都府立大学教授。72年定年退官、琉球大学教授、帝国女子大学教授。→ウィキ
桑原守也(くわはら もりや)1918年6月17日 三重県熊野市生まれ。1942年9月 関西大学法学部卒業。1946年10月 近畿日本鉄道入社、局長。その後 近畿日本ツーリスト常務。1976年12月 沖縄都ホテル社長 2002年6月5日逝去
2017年12月17日ー昨日、息子夫婦が訪ねたというので、観宝堂に行く。店主の吉戸直氏と娘さんと息子の妻との関わり、吉戸氏の経歴などを聞く。国際通りに用があるというので同行す。明日東京だと話されるのでグーグルマップで南青山店を見ると、根津美術館が横にあって、岡本太郎記念館も近い。





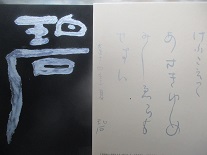
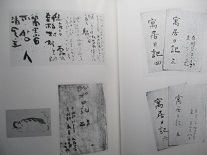
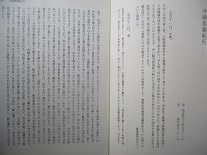
2007年1月 『河東碧梧桐全集』第12巻「沖縄那覇紀行」 文藝書房
〇1910年5月18日に伊波普猷と会話した河東碧梧桐は「沖縄那覇紀行」で伊波の話を紹介している。□5月18日。半晴。臺灣、朝鮮には目下土着人を如何に馴致すべきかの重大な問題が何人の頭をも重圧しつつある。琉球のように多年親日の歴史ある土地に、さような社会問題があろうとは夢想だもせぬところであった。が、人種上に生ずる一種の敵愾心、表面に現れた痕跡は絶無であるにしても、心の奥底に拭うべからざるある印象の存することは争われぬ。伊波文学士ー沖縄人ーの観察はあるいは一方面であるかも知れぬが、這般の消息について多少聞くべきものがある。曰く琉球が親日に勤めたことは、すでに数百年前のことで、時の為政者は大抵そのために種々の施設をしておる。なかんずく向象賢などは時の名宰相であったのであるが、その親日に尽くしたことも一通りではなかった。下って宜湾朝保の如き、八田知紀の門下生となって三十一文字の道にも心を寄せたという位である。が、琉球人の方を主として見ると、島津氏の臨監は、これを支那の恩恵に比すると余り苛酷であった。支那は琉球から租税を徴したことがない。進貢船を派しても、必ずそれ以上の物と交易して呉れる。のみならず、能く諸生の教導をして、留学生なども懇篤な待遇をした。沖縄人が親日の束縛を受けながらも、暗に支那に欸を通じて、衷心その恩を忘れざるものはこれがためである。殊に廃藩置県の際における内地人の処置は、沖縄人の心あるものをして、新たなる敵愾心を起さしめた。蓋し土着の沖縄人を軽蔑することその極に達したからである。
爾来その敵愾心は学問の上に進展して、沖縄人と雖も習字次第内地と拮抗するに足ることを証拠立てた。今日如何に焦燥れても如何に運動しても一種の不文律は沖縄人に政治上及び実業上の権力は与えられぬ。已むなくさる制裁のない学問に向かって力を伸ばす外はないのである。この気風は殊に今日の青年間に隠約の勢力となっておる。今日小中学または師範学校などの教師ー内地人ーは内地で時代後れになった人が多い。新進気鋭の秀才が、かかる南洋の一孤島に来ぬのは自然の数であるけれども、現在の権力掌握者はまた余りに時勢に取り残され方が甚だしい。そこになると、青年の方が遥かに時代の推移を知っておる。如何に圧制的に新刊の書を読むなと禁じても、生徒は暗に、どういうことが書いてあるかも知らずに、と冷笑しておる始末である。殊に我々は沖縄人だという自覚の上に、このまま単に内地人の模倣に終わるべきであろうかという疑問がある。つまらぬ事のようであるけれども、島津氏に対する祖先伝来の一種の嫌悪心も手伝ふて来る。さらばというてもとより沖縄県庁に対して謀反を計るなどという馬鹿なこともないが、それらの暗々裡の不平は、いつか妙な方向に走らせて、青年に社会主義の書物や、露西亜小説の悲痛な物やなど読むものが多くなった。もしこの気風が段々助長して行けば、あるいは人種上の恐るべき争いとならぬとも限らぬ。要するにこの十年前までは単に旧物破壊、日本模倣の単純な社会であったのが、今日は沖縄人としての自覚が芽を萌して、旧物保存、模倣敗斥の端を啓いたのである。
1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」
1910年6月 『ホトトギス』岡本月村「琉球スケッチ」
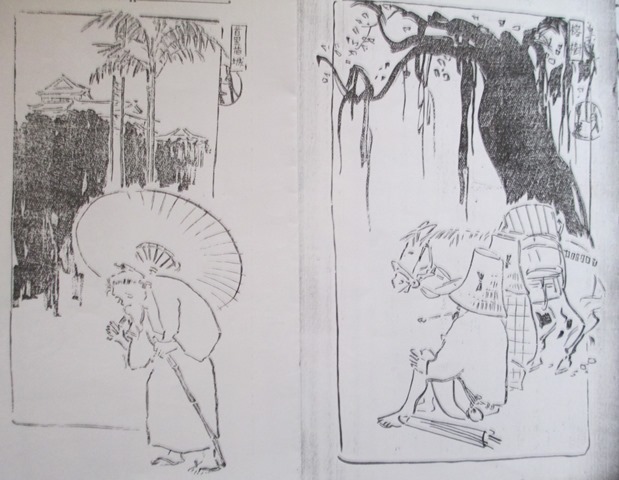

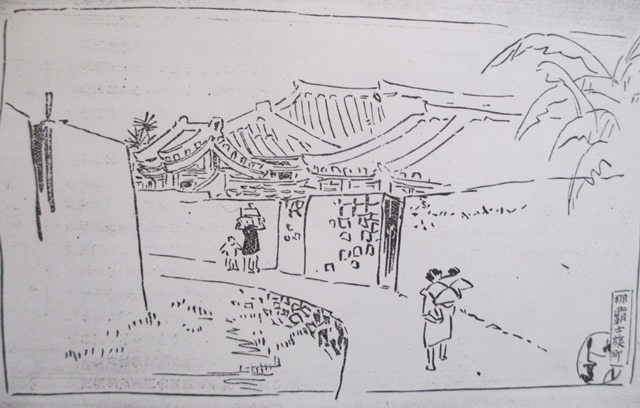
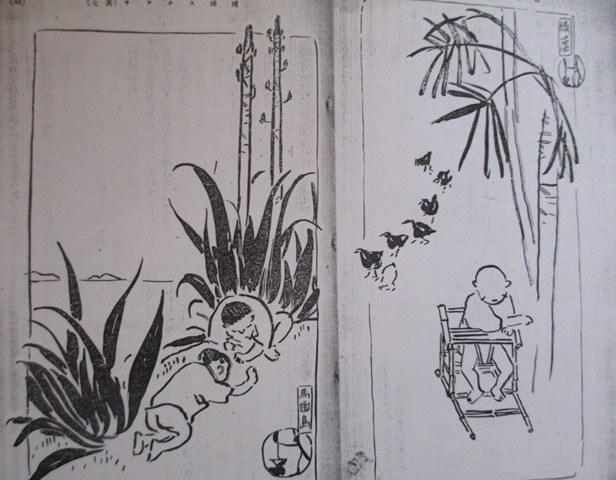
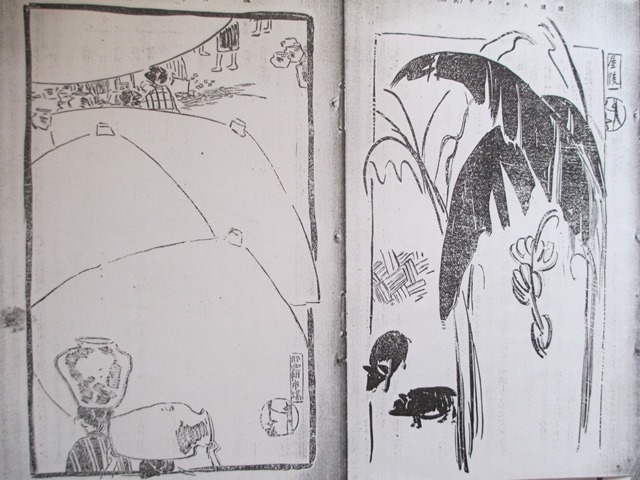
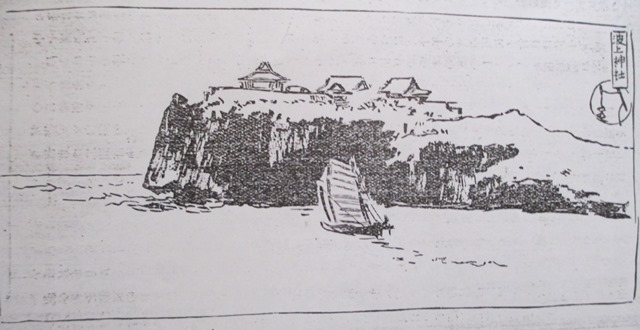
□岡本月村(1876年9月10日~1912年11月11日)
上道郡西大寺(現、岡山市)の人。名は詮。幼くして画技を好み、13歳で徳島県の天蓋芝堂、次いで京都の今尾景年に、また洋画を浅井忠に学んだ。神戸新聞、大阪朝日新聞に俳味ある漫画を載せて異彩を放つ。旅行を好み俳句にも長ず。
麦門冬と河東碧梧桐
1984年12月発行の『琉文手帖』「文人・末吉麦門冬」で1921年以降の『ホトトギス』の俳句も末吉作として収録した。これは別人で熊本の土生麦門冬の作品であるという。土生麦門冬には『麦門冬句集』(1940年9月)があった。1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖したとき、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。
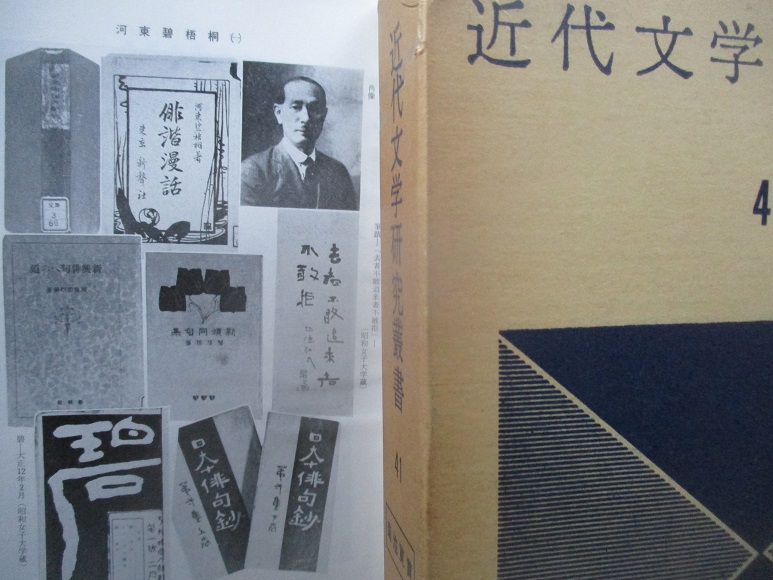
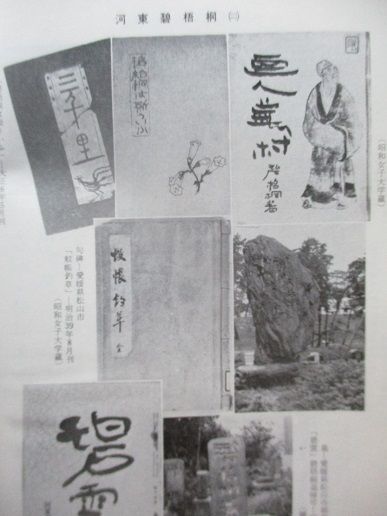
1975年5月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学叢書』41巻「河東碧梧桐」 昭和女子大学近代文化研究所
河東碧梧桐 かわひがし-へきごとう
1873-1937 明治-昭和時代前期の俳人。
明治6年2月26日生まれ。高浜虚子とともに正岡子規にまなび,新聞「日本」の俳句欄の選者をひきつぐ。のち新傾向俳句運動をおこし,中塚一碧楼(いっぺきろう)らと「海紅」を創刊,季題と定型にとらわれない自由律俳句にすすむ。大正12年「碧(へき)」,14年「三昧(さんまい)」を創刊。昭和12年2月1日死去。65歳。愛媛県出身。本名は秉五郎(へいごろう)。作品に「碧梧桐句集」,紀行文に「三千里」など。(コトバンク)
11/04: 土門拳(戦前)
1935年11月 写真館の見習いであった土門拳は『アサヒカメラ』掲載の求人広告に応募して日本工房の門をたたく。□→2006
年2月 毎日新聞社『名取洋之助と日本工房[1931-45]-報道写真とグラフィック・デザインの青春時代』
柳宗悦・第三回訪沖
12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。
1940年
1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。
1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。
1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。
□那覇市歴史資料室収集写真に坂本万七「与那原の瓦窯」がある。それには山里永吉と土門拳が話しこんでいたり、柳宗悦が瓦を見ている、左上の方には????宮城昇が撮影の坂本を見ている光景が確認できる。
1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。
1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。
1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。
1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。
1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。
1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。
1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。
1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。
年2月 毎日新聞社『名取洋之助と日本工房[1931-45]-報道写真とグラフィック・デザインの青春時代』
柳宗悦・第三回訪沖
12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。
1940年
1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。
1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。
1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。
□那覇市歴史資料室収集写真に坂本万七「与那原の瓦窯」がある。それには山里永吉と土門拳が話しこんでいたり、柳宗悦が瓦を見ている、左上の方には????宮城昇が撮影の坂本を見ている光景が確認できる。
1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。
1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。
1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。
1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。
1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。
1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。
1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。
1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。
03/21: 平姓・山田家②
1937年10月の『月刊琉球』の葉書回答に山田有登の返事がある。「子供たちの名をお尋ねですが、夫々生まれた土地とも関係します。長女は石川県金沢市で宿し三州田原町の生まれ、女は貞操が第一と貞子、長男は三河武士家内の里が勝の通り名ゆえ有勝。次女は兵庫県鳴尾生まれ信子、次男も鳴尾で10月生まれ宅の前が一面稲田が實っていたので實。三男は城崎温泉近くの竹野鉱山で9月生まれ、田舎は豊年満作なりしゆえ豊。四男は竹野で宿し博々たる海を越え沖縄での初児。五男は大正14年2月純沖縄産で昭としたら次年が昭和となり偶然でした。六男は保、よく保つように」と記されている。
長女貞は一高女卒業で、那覇泉崎の旧家・仲尾次家の二男に嫁ぎ、その子孫は東京に男4人、女3人が居る。豊は精神科の医者で、戦争中は軍医、ニューギニア戦線で2回も乗っていた軍艦が沈没させられ無事だった。戦後は名古屋医大、国立の病院に勤めた。昭は戦前、那覇の自宅で柳宗悦、棟方志功を見た。またビルマ戦線での生き残りだ。戦後は中学校の教諭をつとめた。昭氏の詩集『老人戯画』に「ふるさとの那覇の人混みを歩きながら/わたしは独りユーラシア大陸のことを考えていた/友らはみんな死んで/わたしばかりが避難したのか/林立するビル群には少年の日のかけらもなく/迷路のような市場の辻を/わずかにつむじ風が動いて消えた」と戦争を引きずっている。
保は歯医者で兄のバトラー歯科医院につとめた。長女に山田美保子が居る。その兄・山田有勝は同人誌『カルト・ブランシュ』を1938年に創刊した。稲垣足穂(注2)はその第14号に「あべこべになった世界に就いて」を書いた。足穂に原稿を依頼したのが編集発行人の山田有勝である。有勝は詩集『残照』で「我が家の明治大正期の古い本は既に色あせ 古い辞書の皮革はボロボロとなる/岩本修蔵さんのロイドメガネ イナガキタルホさんの鼻メガネ」と足穂が出てくる。また過ぎた日と題し「六十三年前の思い出 阪神電車の鳴尾駅を降りて 右へつきあたり 左へ折れて 一町先の左側 白壁の四軒長屋 その端のガチョウが二羽いた家」が山田實さんの出生地である。
いながきたるほ【稲垣足穂】
1900‐77(明治33‐昭和52)
プランクの量子定数の発見とともに大阪に生まれ,少年期の飛行機幻想をそのまま70余年の孤高の日々にもちこんだ異色作家。10代後半に構想をまとめたという代表作《一千一秒物語》(1923)や,日本文学大賞受賞作の《少年愛の美学》(1968)にみられる〈人間をオブジェとして扱う手法〉は,タルホ・コスモロジーと言われる宇宙論的郷愁とあいまって,全作品に共通する特徴である。都市の幾何学,飛行精神,人工模型,英国ダンディズム,男色趣味,謡曲の幻想世界,物理学的審美主義,ヒンドゥーイズム,キネティックな手法,月光感覚などを駆使した作品群は,世界文芸史上にも類がない。(→コトバンク)
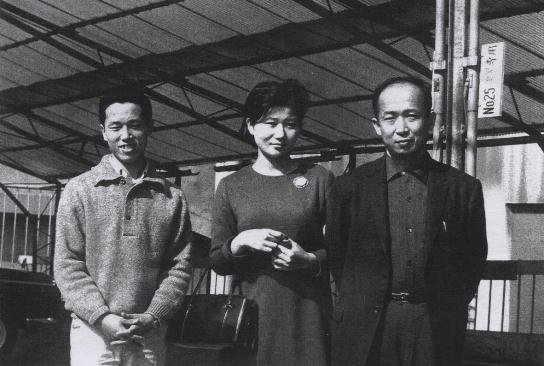
写真左から山田晋氏、太田治子さん(桜庭氏、教員時代の教え子)、山田實氏の弟・桜庭昭氏ー1968年
◎はじめまして。桜庭暁子と申します。桜庭昭の娘です。この度は、琉文21に父のことを紹介して戴きまして
ありがとうございました。父も喜んでおりました。山田勉氏(従兄)から連絡を受け知りました。實伯父がいつまでも元気でいることを願っております。
これからもどうぞよろしくお願い致します。(2012-3-27)
太田治子 おおた-はるこ
1947- 昭和後期-平成時代の小説家。
昭和22年11月12日生まれ。太宰治(だざい-おさむ)と太田静子の娘。結婚して高木姓となる。高校2年のとき手記「十七歳のノート」を発表。昭和61年亡母を追想した小説「心映えの記」で坪田譲治文学賞。神奈川県出身。明治学院大卒。著作はほかに「石の花」「恋する手」「母の万年筆」「私のヨーロッパ美術紀行」など。(→コトバンク)

東松照明写真集発刊の集いー前列左から2人目が山田實氏,]3人目・東松照明氏
長女貞は一高女卒業で、那覇泉崎の旧家・仲尾次家の二男に嫁ぎ、その子孫は東京に男4人、女3人が居る。豊は精神科の医者で、戦争中は軍医、ニューギニア戦線で2回も乗っていた軍艦が沈没させられ無事だった。戦後は名古屋医大、国立の病院に勤めた。昭は戦前、那覇の自宅で柳宗悦、棟方志功を見た。またビルマ戦線での生き残りだ。戦後は中学校の教諭をつとめた。昭氏の詩集『老人戯画』に「ふるさとの那覇の人混みを歩きながら/わたしは独りユーラシア大陸のことを考えていた/友らはみんな死んで/わたしばかりが避難したのか/林立するビル群には少年の日のかけらもなく/迷路のような市場の辻を/わずかにつむじ風が動いて消えた」と戦争を引きずっている。
保は歯医者で兄のバトラー歯科医院につとめた。長女に山田美保子が居る。その兄・山田有勝は同人誌『カルト・ブランシュ』を1938年に創刊した。稲垣足穂(注2)はその第14号に「あべこべになった世界に就いて」を書いた。足穂に原稿を依頼したのが編集発行人の山田有勝である。有勝は詩集『残照』で「我が家の明治大正期の古い本は既に色あせ 古い辞書の皮革はボロボロとなる/岩本修蔵さんのロイドメガネ イナガキタルホさんの鼻メガネ」と足穂が出てくる。また過ぎた日と題し「六十三年前の思い出 阪神電車の鳴尾駅を降りて 右へつきあたり 左へ折れて 一町先の左側 白壁の四軒長屋 その端のガチョウが二羽いた家」が山田實さんの出生地である。
いながきたるほ【稲垣足穂】
1900‐77(明治33‐昭和52)
プランクの量子定数の発見とともに大阪に生まれ,少年期の飛行機幻想をそのまま70余年の孤高の日々にもちこんだ異色作家。10代後半に構想をまとめたという代表作《一千一秒物語》(1923)や,日本文学大賞受賞作の《少年愛の美学》(1968)にみられる〈人間をオブジェとして扱う手法〉は,タルホ・コスモロジーと言われる宇宙論的郷愁とあいまって,全作品に共通する特徴である。都市の幾何学,飛行精神,人工模型,英国ダンディズム,男色趣味,謡曲の幻想世界,物理学的審美主義,ヒンドゥーイズム,キネティックな手法,月光感覚などを駆使した作品群は,世界文芸史上にも類がない。(→コトバンク)
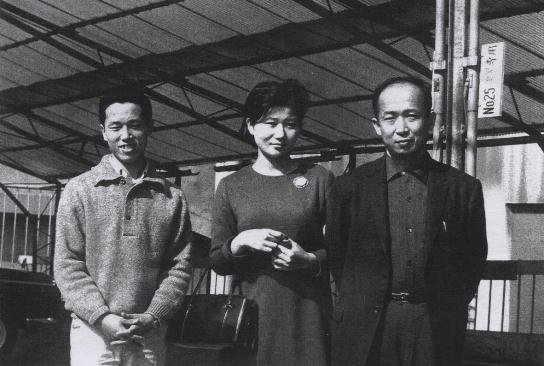
写真左から山田晋氏、太田治子さん(桜庭氏、教員時代の教え子)、山田實氏の弟・桜庭昭氏ー1968年
◎はじめまして。桜庭暁子と申します。桜庭昭の娘です。この度は、琉文21に父のことを紹介して戴きまして
ありがとうございました。父も喜んでおりました。山田勉氏(従兄)から連絡を受け知りました。實伯父がいつまでも元気でいることを願っております。
これからもどうぞよろしくお願い致します。(2012-3-27)
太田治子 おおた-はるこ
1947- 昭和後期-平成時代の小説家。
昭和22年11月12日生まれ。太宰治(だざい-おさむ)と太田静子の娘。結婚して高木姓となる。高校2年のとき手記「十七歳のノート」を発表。昭和61年亡母を追想した小説「心映えの記」で坪田譲治文学賞。神奈川県出身。明治学院大卒。著作はほかに「石の花」「恋する手」「母の万年筆」「私のヨーロッパ美術紀行」など。(→コトバンク)

東松照明写真集発刊の集いー前列左から2人目が山田實氏,]3人目・東松照明氏
04/12: 麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安正
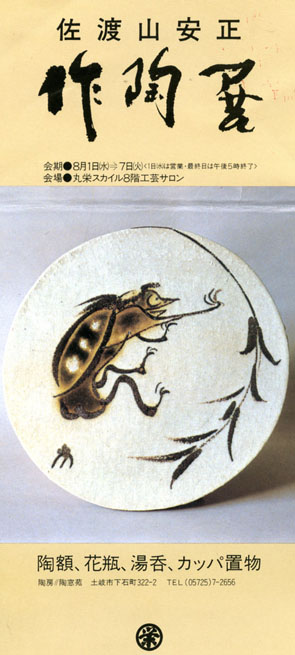
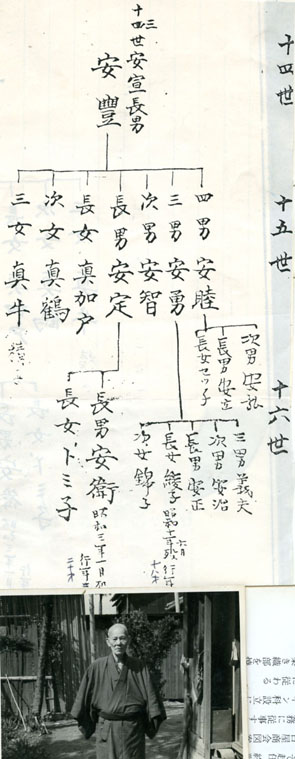
写真右・佐渡山安勇

写真・佐渡山安正
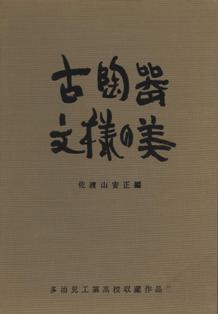
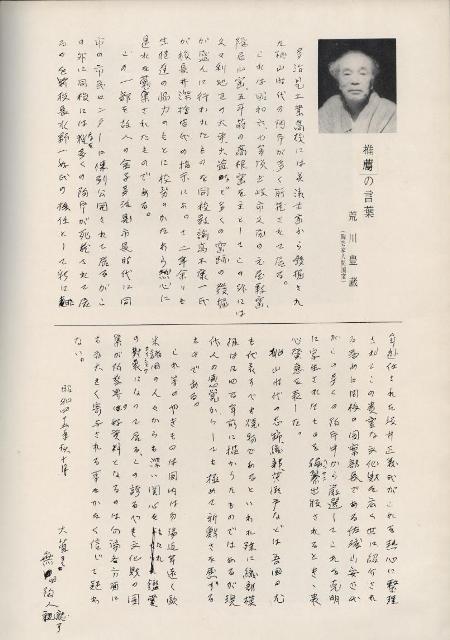
1970年12月ー佐渡山安正『古陶器文様の美』東文堂
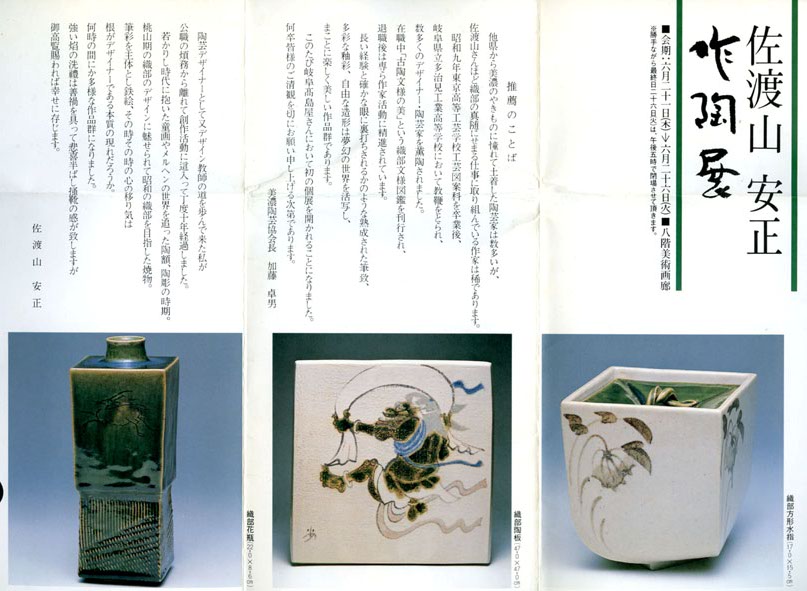
○今日、岐阜県土岐市下石というところに行ってきました。
愛知の沖縄調査の仕事です。で、ついでに、この町を流れる川に架かる橋のたもとに据えられているシーサーを見てきました。しっかり橋と町を守っているようですね。これは、琉球王国時代の絵師佐渡山安健を先祖に持つ、故佐渡山安正の作品です。
町を守りながら、遠く故郷を望んでいるように見えました。写真ではわかりづらいですが、町を囲む山々の紅葉も見頃で、その紅葉をバックに、シーサーもとても見栄えがしました。→2007年12月01日「干瀬のまれびとの座ーまれびとの見る沖縄を語る」
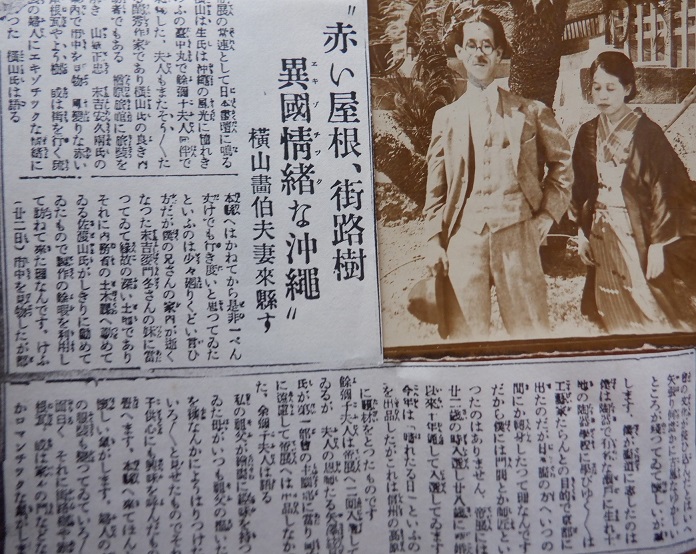
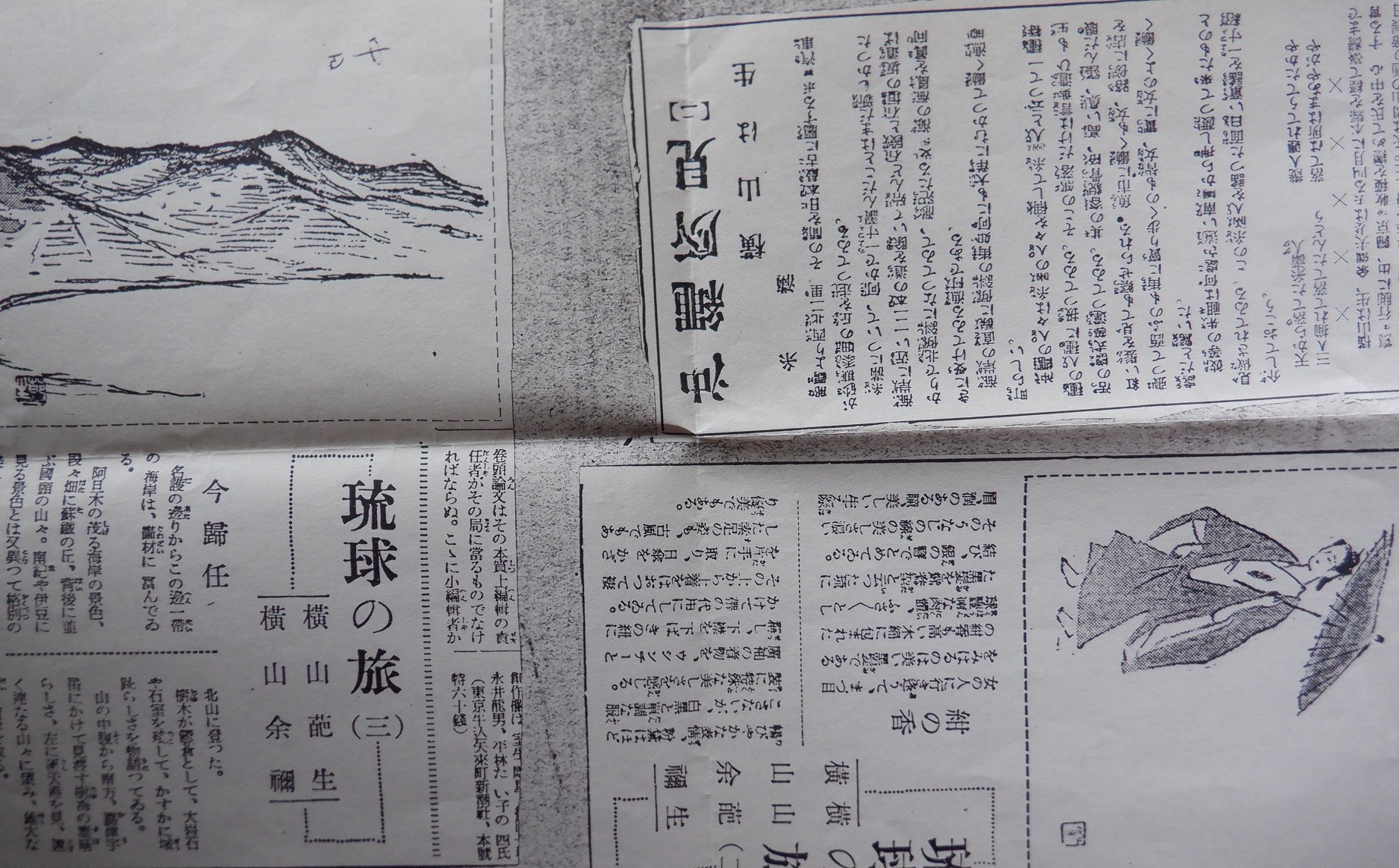
横山葩生、余彌子夫妻来沖
□1936年4月ー台中丸で、帝展画家の横山葩生、余彌子夫妻来沖。「横山画伯夫妻けふ沖縄訪問ー氏の義姉は故末吉麦門冬氏の妹にあたり、古くから憧れていた南島沖縄訪問がやっとこの日実現されたものである。なお氏の来遊に就いて名古屋在住の佐渡山安勇氏より島袋全発図書館長へ世話方を依頼して来ている。」/「」10月ー『塔影』「青樹社第三回展ー名古屋伊藤銀行中支店楼上に開催。同社は横山葩生君を中心とする団体、葩生君の『南国風景』」
横山葩生 (よこやまはせい) 生年 / 没年 : 1899 / 1974
生地 / 没地 : 愛知県瀬戸市 / 愛知県名古屋市 第2回帝展(1920) 中京美術院 青樹社→愛知県美術館

写真ー金城安太郎氏と石垣さん親子(末吉麦門冬娘)
10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年
1917年(大正6)
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
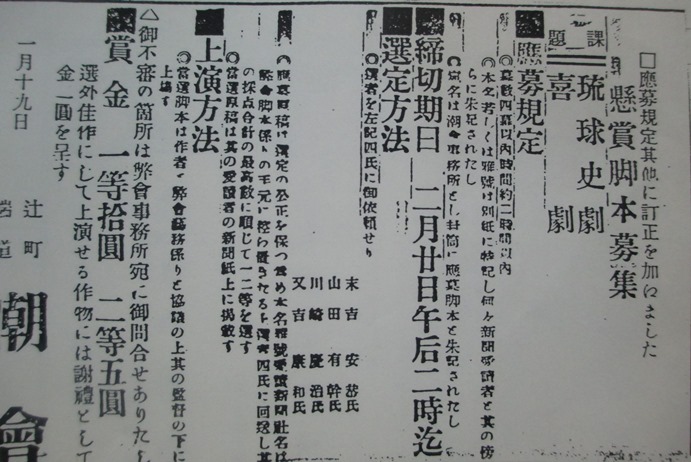
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
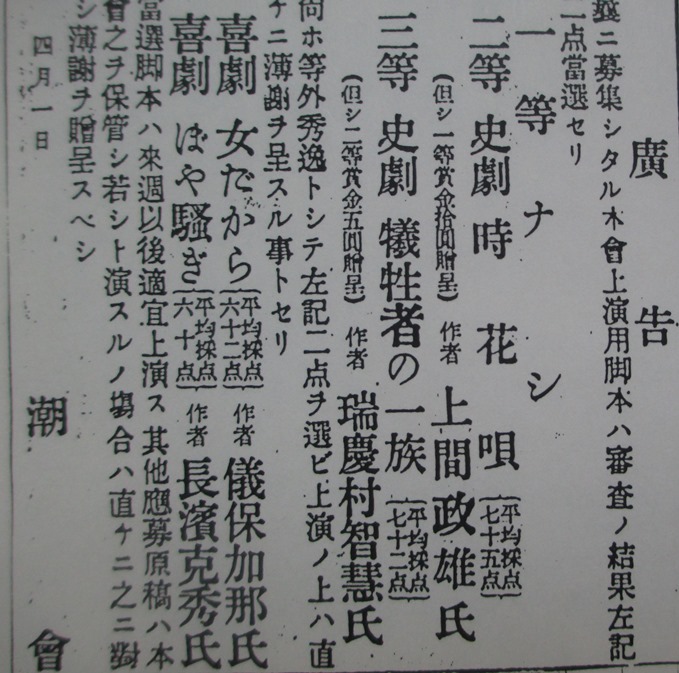
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
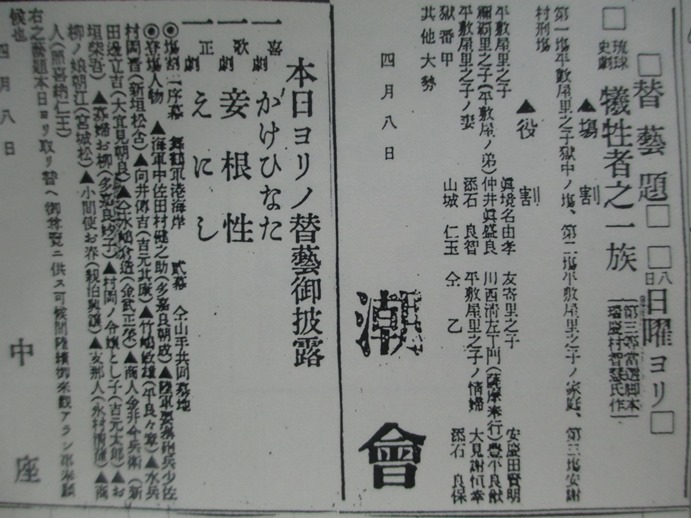
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
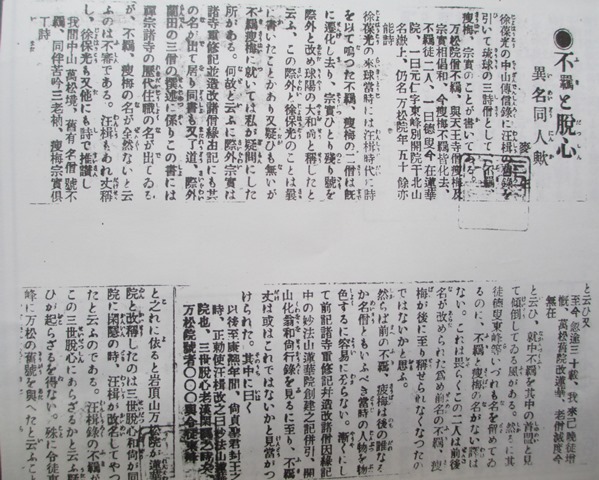
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
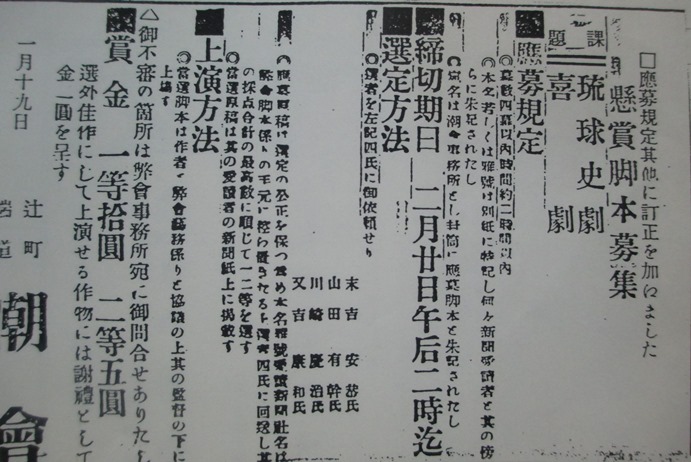
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
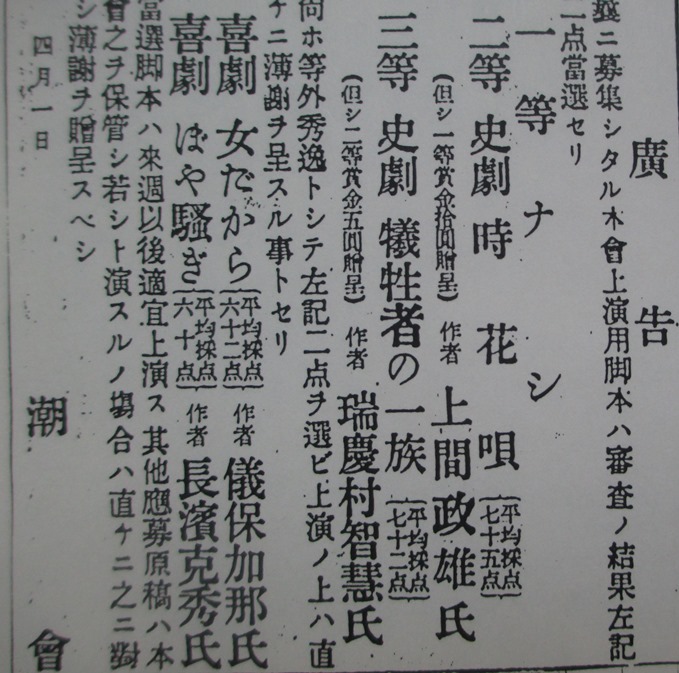
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
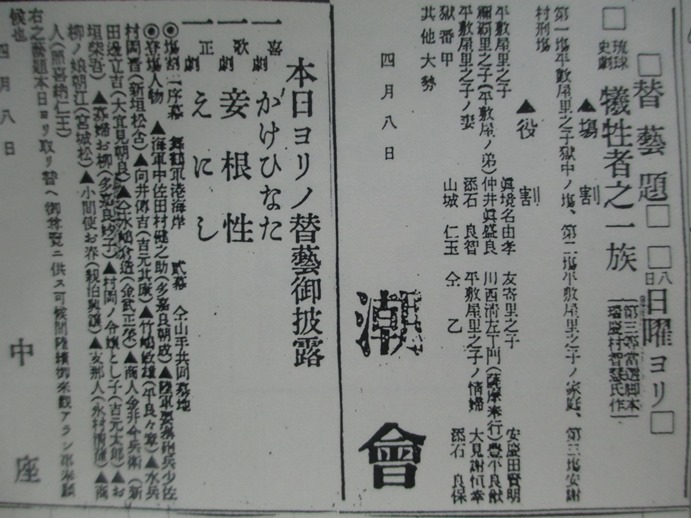
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
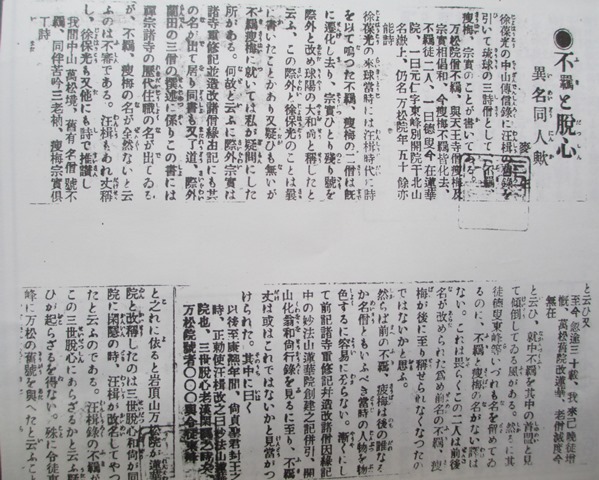
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
11/14: 末吉安恭『麦門冬句集』②
1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」
1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」
1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」
1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」
1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」
1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」
1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」
1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」
1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」
1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」
1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」
1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」
1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」
1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」
1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」
1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」
1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」
1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」
1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」
1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」
1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」
1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」
1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」
1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」
1909年11月『趣味』麦門冬「秋の蚊の溺れて乾く硯かな」
1909年12月『文庫』麦門冬「衝入の人驚きぬ大鏡/猪の子の眠れる穴や草暗し/鹽猪を苞にして山男かな/小夜更けて人のけはひや菊畑/旅にして扇を置けば淋しやな/帰んな里の妻々砧打つ/長き夜は又古き夜や思ひ事」
1909年12月『趣味』麦門冬「素車白馬粛々として露の中」
1910年2月『ホトトギス』麦門冬「魚蝦に富む家刀自艶に鴨の聲」
1910年4月『ホトトギス』麦門冬「薊喰はぬ馬のかぶりや牧の草」
1910年4月『趣味』麦門冬「春の水子別れ馬の顔洗へ/うつろ木の朽葉だまりや蛙なく」
1910年5月『趣味』麦門冬「椿落ちてまた廣がりし水輪かな」
1910年6月『文庫』麦門冬「親梅に子梅つれ咲く日和かな/朝寒の水にひらめく小鰕かな/鳥尽きて我武淋しき案山子かな」
1912年11月25日『沖縄毎日新聞』麦門冬「落葉ー斧研かん今朝砥水落葉上□澄めり/焚火に足がつき落葉林に捕つたり/鶏の掘る種子物に垣す落葉かな/山寒に焔□ると登山落葉□もなき/落葉火佛に茶湯す勘当の子を思ふ/貧の窃み捨て置けと曰や庭落葉/旅の女性湯参らそ落葉山冷えに/駿馬化石の口牌見ればげに落葉も/錠錆び祠落葉積むに人の詣つると」
1912年12月7日『沖縄毎日新聞』麦門冬「時雨雲水仙の魂も伴ふか/句黙録黙水仙に冬籠る」
1912年12月20日『沖縄毎日新聞』麦門冬「隼の啼けり末枯野の空晴れて/友と二た昔を語る岩姫隈柳未枯野を」
麦門冬「兎にも家してやらん冬近し/寒いぞや兎は籠に飢ふるぞや/筆持ちて物書く吾も海鼠ならん/一本の木橋渡らば枯野かな/天井に話の響く夜寒かな/冬構まづ障子より白うせり/冬も吊る蚊帳の煤けて哀れなり/掛取の来べき宵なり鎖ささん/貧厨の只打ち煙る年のくれ/角めだる妻を憎むや年の暮/親になき春省羨む年の暮/貧すれば悪の華咲く年の暮」
1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」
1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」
1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」
1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」
1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」
1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」
1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」
1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」
1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」
1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」
1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」
1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」
1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」
1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」
1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」
1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」
1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」
1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」
1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」
1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」
1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」
1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」
1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」
1909年11月『趣味』麦門冬「秋の蚊の溺れて乾く硯かな」
1909年12月『文庫』麦門冬「衝入の人驚きぬ大鏡/猪の子の眠れる穴や草暗し/鹽猪を苞にして山男かな/小夜更けて人のけはひや菊畑/旅にして扇を置けば淋しやな/帰んな里の妻々砧打つ/長き夜は又古き夜や思ひ事」
1909年12月『趣味』麦門冬「素車白馬粛々として露の中」
1910年2月『ホトトギス』麦門冬「魚蝦に富む家刀自艶に鴨の聲」
1910年4月『ホトトギス』麦門冬「薊喰はぬ馬のかぶりや牧の草」
1910年4月『趣味』麦門冬「春の水子別れ馬の顔洗へ/うつろ木の朽葉だまりや蛙なく」
1910年5月『趣味』麦門冬「椿落ちてまた廣がりし水輪かな」
1910年6月『文庫』麦門冬「親梅に子梅つれ咲く日和かな/朝寒の水にひらめく小鰕かな/鳥尽きて我武淋しき案山子かな」
1912年11月25日『沖縄毎日新聞』麦門冬「落葉ー斧研かん今朝砥水落葉上□澄めり/焚火に足がつき落葉林に捕つたり/鶏の掘る種子物に垣す落葉かな/山寒に焔□ると登山落葉□もなき/落葉火佛に茶湯す勘当の子を思ふ/貧の窃み捨て置けと曰や庭落葉/旅の女性湯参らそ落葉山冷えに/駿馬化石の口牌見ればげに落葉も/錠錆び祠落葉積むに人の詣つると」
1912年12月7日『沖縄毎日新聞』麦門冬「時雨雲水仙の魂も伴ふか/句黙録黙水仙に冬籠る」
1912年12月20日『沖縄毎日新聞』麦門冬「隼の啼けり末枯野の空晴れて/友と二た昔を語る岩姫隈柳未枯野を」
麦門冬「兎にも家してやらん冬近し/寒いぞや兎は籠に飢ふるぞや/筆持ちて物書く吾も海鼠ならん/一本の木橋渡らば枯野かな/天井に話の響く夜寒かな/冬構まづ障子より白うせり/冬も吊る蚊帳の煤けて哀れなり/掛取の来べき宵なり鎖ささん/貧厨の只打ち煙る年のくれ/角めだる妻を憎むや年の暮/親になき春省羨む年の暮/貧すれば悪の華咲く年の暮」
5月11日莫夢生「青すだれー清明上河図と日章旗(4)」
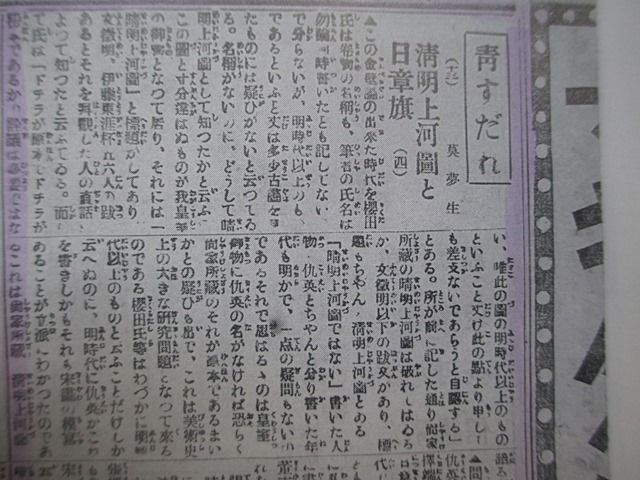
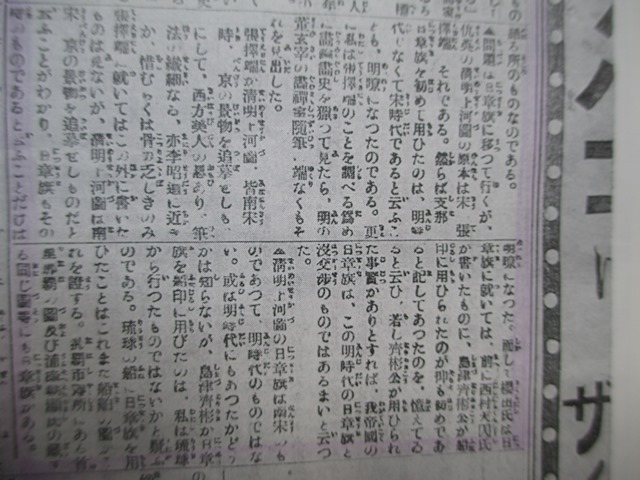
▲問題は日章旗に移って行くが、仇英の清明上河図の原本は宋の張択端のそれである。然らば支那の日章旗を初めて用ひたのは、明時代でなくて宋時代であると云ふことも、明瞭になったのである。更に私は張択端のことを調べる為めに画論画史を猟って見たら、明の董玄宰の画禅室随筆に端なくもそれを見出した。 張択端が清明上河図、皆南宋時、 京の景物を追慕せしも にして、西方美人の思あり、筆法の繊細なる、亦季昭 に近きか、惜むらくは骨力乏しきのみ
張択端に就いてはこの外に書いたものは見ないが、清明上河図は南宋 京の景物を追慕せしものだと云ふことがわかり、日章旗もその時のものであると云ことだけは明瞭になった。而して桜田氏は日章旗に就いては、前に西村天囚氏にが書いたものに、島津斉彬公が船印に用ひられたのが抑も初めであると記してあったのを、憶えていると云ひ、若し斉彬公が用ひられた事実がありとすれば、我帝国の日章旗は、この明時代の日章旗と没交渉のものではあるまいと云った。
▲清明上河図の日章旗は南宋のものであって、明時代のものではない。或は明時代にもあったかは知らないが、島津斉彬が日章旗を船印に用ひたのは、私は琉球から行ったものではないかと疑ふのである。琉球の船に日章旗を用ひたことはこれまた船舶の図がそれを証する。那覇市役所にある首里那覇の図及び浦添朝顕氏の蔵する同じ図等にも日章旗がある。

國立故宮博物院
5月14日『沖縄タイムス』莫夢生「青すだれー東西刺客観」
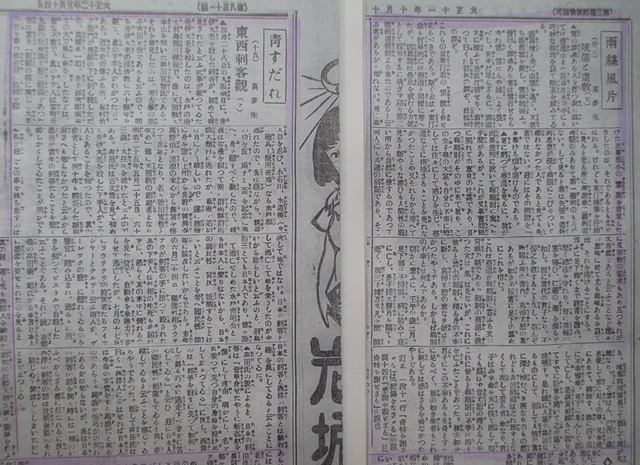
1923年5月 『沖縄タイムス』莫夢生「青すだれー東西刺客観」
○在独逸の高田義一郎氏が日本及日本人に感想を寄せられたのを見ると、「日本の刺客は皆申し合わせたように斬姦状を懐にして理由を明らかにし名を名乗って先ず自分の身体を投げ出してかかっている。」「西洋の刺客は辻斬り強盗のそれと同じ・・・」
1922年10月 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー琉儒と道教」
○李鼎元の使琉球記を読んでー沖縄には道教の寺はない。即ち支那にあるような道観、道士こそなけれ、道家の思想は早くからあったのである。○唐御竈、他に天妃、関帝王、文昌帝君、土地君などは道教の神様。久米の学者先生達は支那伝来の天妃廟を敬すること孔子廟同様である。○道教思想のあらわれとして、現世的因果応報の最も面白い例は、私は組踊の孝行巻に於いてこれを発見する。
○蔡温はまた蓑翁片言の中にも弁妄を試みている。○東汀随筆を仔細に見ると翁は矢張り道教的思想が深く頭脳にこびりついて離れなかった人・・・○これは蔡温が程順則への書簡、これに依ると流石の順則も積もる身の不幸に対し、哀悼尤怒の意なき能わなかったようである。
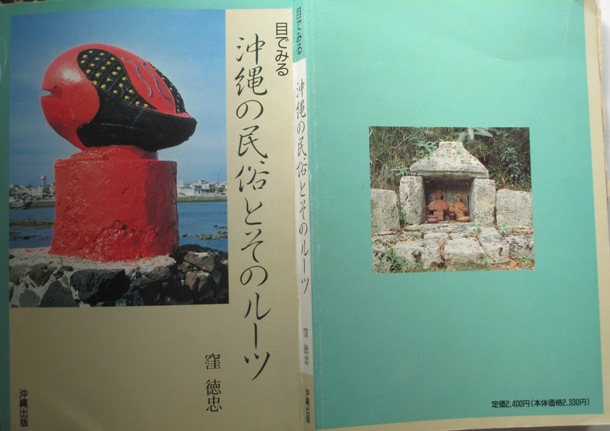
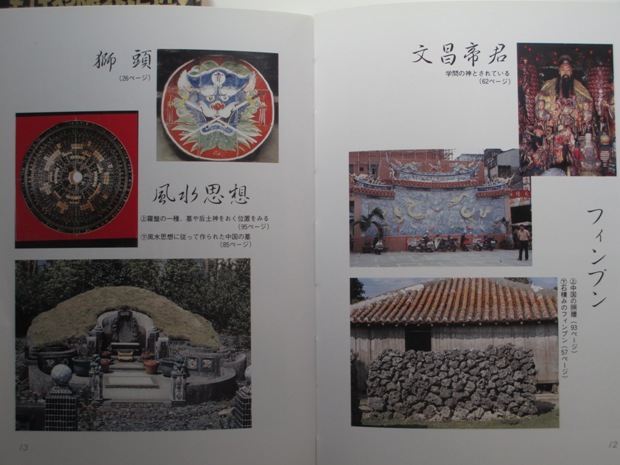
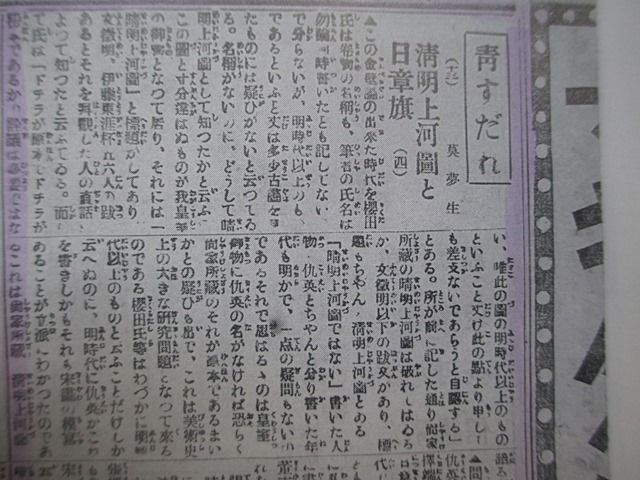
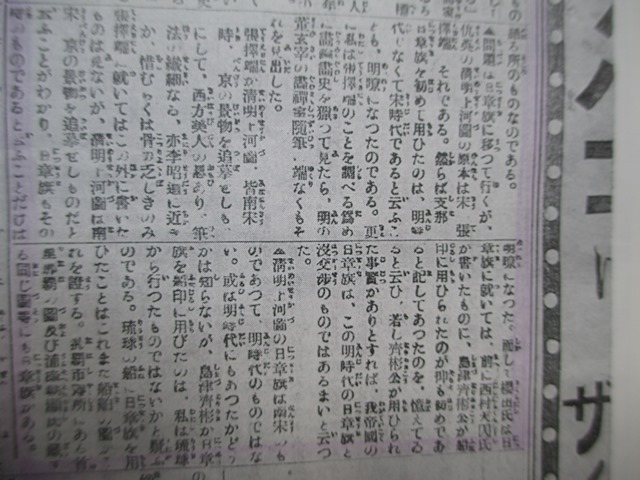
▲問題は日章旗に移って行くが、仇英の清明上河図の原本は宋の張択端のそれである。然らば支那の日章旗を初めて用ひたのは、明時代でなくて宋時代であると云ふことも、明瞭になったのである。更に私は張択端のことを調べる為めに画論画史を猟って見たら、明の董玄宰の画禅室随筆に端なくもそれを見出した。 張択端が清明上河図、皆南宋時、 京の景物を追慕せしも にして、西方美人の思あり、筆法の繊細なる、亦季昭 に近きか、惜むらくは骨力乏しきのみ
張択端に就いてはこの外に書いたものは見ないが、清明上河図は南宋 京の景物を追慕せしものだと云ふことがわかり、日章旗もその時のものであると云ことだけは明瞭になった。而して桜田氏は日章旗に就いては、前に西村天囚氏にが書いたものに、島津斉彬公が船印に用ひられたのが抑も初めであると記してあったのを、憶えていると云ひ、若し斉彬公が用ひられた事実がありとすれば、我帝国の日章旗は、この明時代の日章旗と没交渉のものではあるまいと云った。
▲清明上河図の日章旗は南宋のものであって、明時代のものではない。或は明時代にもあったかは知らないが、島津斉彬が日章旗を船印に用ひたのは、私は琉球から行ったものではないかと疑ふのである。琉球の船に日章旗を用ひたことはこれまた船舶の図がそれを証する。那覇市役所にある首里那覇の図及び浦添朝顕氏の蔵する同じ図等にも日章旗がある。

國立故宮博物院
5月14日『沖縄タイムス』莫夢生「青すだれー東西刺客観」
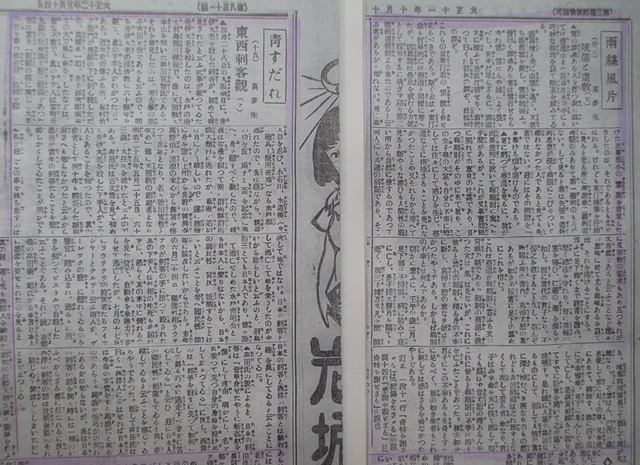
1923年5月 『沖縄タイムス』莫夢生「青すだれー東西刺客観」
○在独逸の高田義一郎氏が日本及日本人に感想を寄せられたのを見ると、「日本の刺客は皆申し合わせたように斬姦状を懐にして理由を明らかにし名を名乗って先ず自分の身体を投げ出してかかっている。」「西洋の刺客は辻斬り強盗のそれと同じ・・・」
1922年10月 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー琉儒と道教」
○李鼎元の使琉球記を読んでー沖縄には道教の寺はない。即ち支那にあるような道観、道士こそなけれ、道家の思想は早くからあったのである。○唐御竈、他に天妃、関帝王、文昌帝君、土地君などは道教の神様。久米の学者先生達は支那伝来の天妃廟を敬すること孔子廟同様である。○道教思想のあらわれとして、現世的因果応報の最も面白い例は、私は組踊の孝行巻に於いてこれを発見する。
○蔡温はまた蓑翁片言の中にも弁妄を試みている。○東汀随筆を仔細に見ると翁は矢張り道教的思想が深く頭脳にこびりついて離れなかった人・・・○これは蔡温が程順則への書簡、これに依ると流石の順則も積もる身の不幸に対し、哀悼尤怒の意なき能わなかったようである。
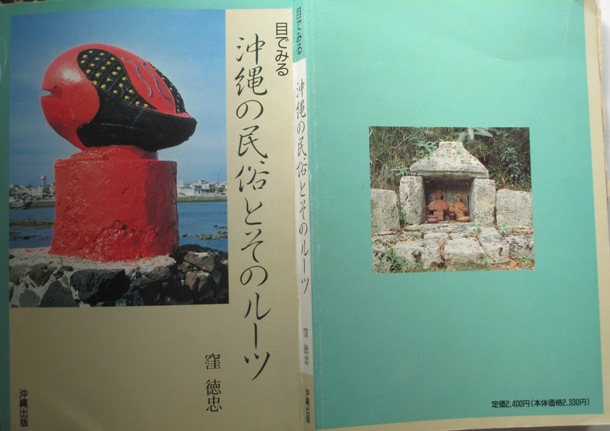
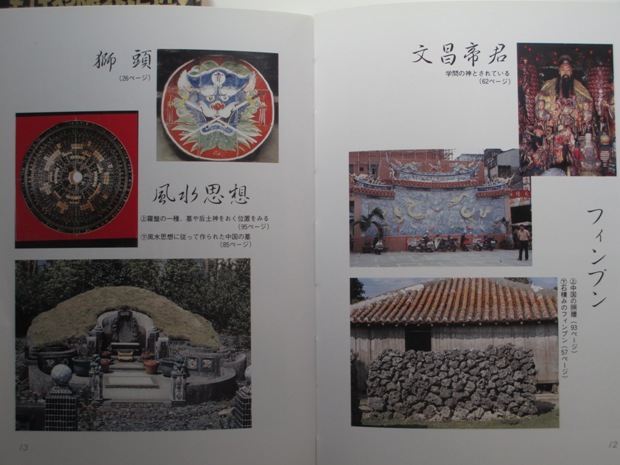
10/09: 辻/松村梅叟 まつむら-ばいそう
1885-1934 明治-昭和時代前期の日本画家。
明治18年8月生まれ。円山派の今尾景年にまなび,京都市立絵画専門学校(現京都市立芸大)を卒業。文展でたびたび褒状をうける。のち日本自由画壇の同人。昭和9年3月2日死去。50歳。京都出身。本名は仁一郎。作品に「画室の花」など。(コトバンク)
□1910年8月9日ー馬山丸で第2観光団(70人余)の一人、松村梅叟(京都市立絵画専門学校生徒)来沖

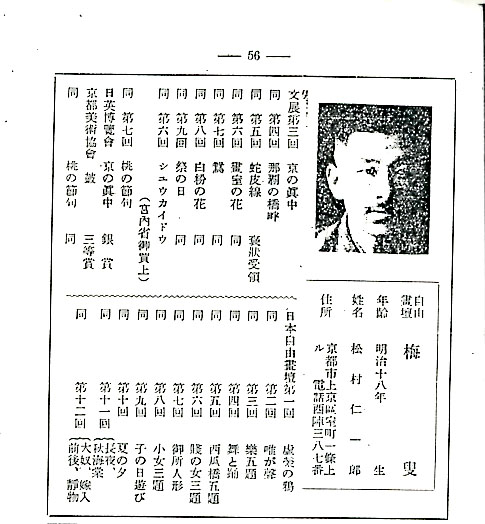

.jpg)

1930年代ー首里城 歓会門
首里城の城郭内へ入る第一の正門で、俗に「あまへ御門(あまえうじょう)」といいます。「あまへ」は古い言葉で「よろこび」を意味しており、「歓会」はその漢訳になります。第二尚氏尚真王代(1477~1526)に創建されたといわれるこの門は、中央部に木造の櫓があります。
沖縄戦で焼失しましたが、1974年(昭和49)に復元されました。□→「首里城公園」
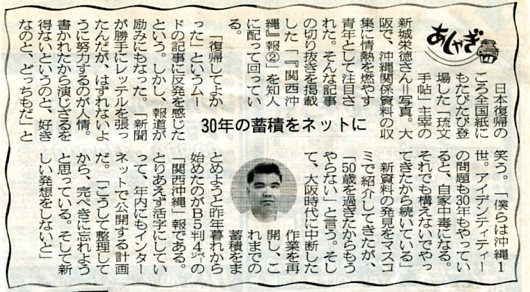
2003年1月15日『琉球新報』「あしゃぎー新城栄徳さん・30年の蓄積をネットに」
明治18年8月生まれ。円山派の今尾景年にまなび,京都市立絵画専門学校(現京都市立芸大)を卒業。文展でたびたび褒状をうける。のち日本自由画壇の同人。昭和9年3月2日死去。50歳。京都出身。本名は仁一郎。作品に「画室の花」など。(コトバンク)
□1910年8月9日ー馬山丸で第2観光団(70人余)の一人、松村梅叟(京都市立絵画専門学校生徒)来沖

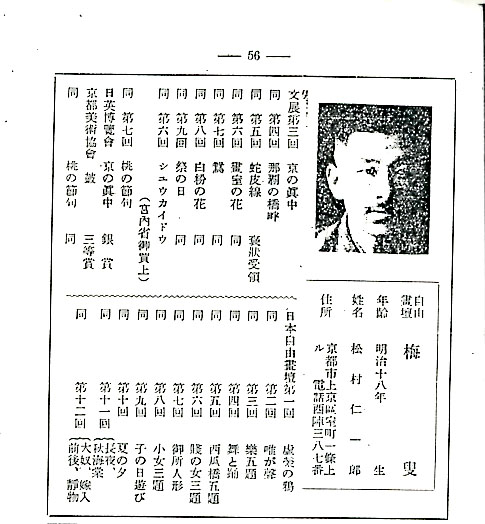

.jpg)

1930年代ー首里城 歓会門
首里城の城郭内へ入る第一の正門で、俗に「あまへ御門(あまえうじょう)」といいます。「あまへ」は古い言葉で「よろこび」を意味しており、「歓会」はその漢訳になります。第二尚氏尚真王代(1477~1526)に創建されたといわれるこの門は、中央部に木造の櫓があります。
沖縄戦で焼失しましたが、1974年(昭和49)に復元されました。□→「首里城公園」
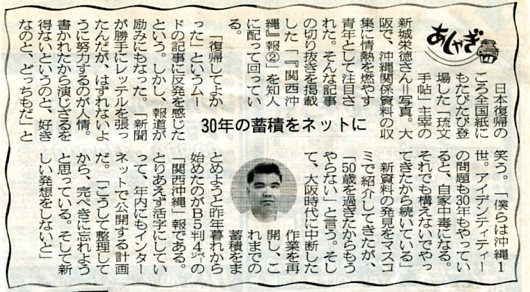
2003年1月15日『琉球新報』「あしゃぎー新城栄徳さん・30年の蓄積をネットに」
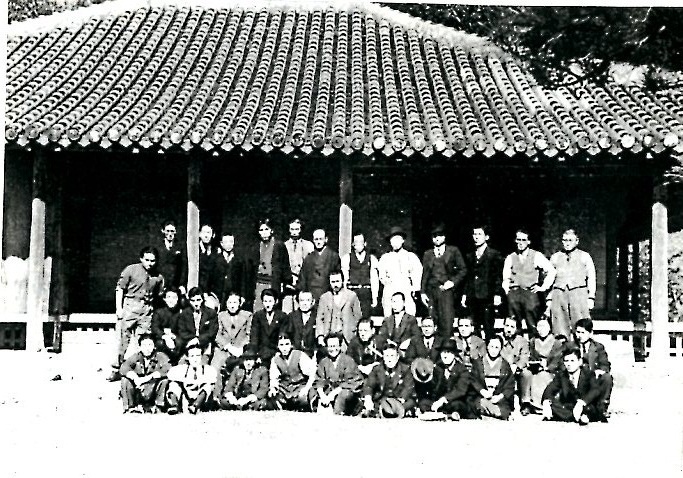
1940年 日本民藝協会同人(識名園で)ー2列目右から5人目が島袋源一郎、前列左から2人目が田中俊雄、左端が土門拳から3人目が式場隆三郎、3列目左が山里永吉、右へ3人目が保田與重郎。3列目右2人目が坂本万七、中央が柳宗悦、前が棟方志功(坂本、土門が写っているので、撮影者は????宮城昇であろう)
第三回訪沖
12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。
井上昇三(日本旅行協会)/1940年3月ー『月刊民藝』□観光地としての沖縄ー今回、日本民藝協会が主体となって沖縄見学団が組織された際、水沢氏と小生とは観光方面の仕事に協力する目的で参加したのであった。そして幾多の収穫を得て帰ることが出来た。見学の一端は雑誌「旅」に発表する義務があったのだが、それを果たすに際して非常なる困難に逢着したのである。沖縄を琉球と云はぬ様、沖縄県を物珍しく取り扱はぬ様、特異の風俗・言語を他府県と比較したりその差を強調したりしない様等の注意を払ふ必要を感じたのである。他府県の者として沖縄を旅しての印象を正直に記したり、まだ沖縄を知らぬ人々に出来るだけ沖縄に興味を抱かせる様に紹介しようとしたら、恐らく其の筆者は沖縄県民の多大の激怒を買ふに至るのであらうといふ不安があつたのである。
かかる不徹底なる態度で書かなければならなかつた事は私としては誠に不愉快であり、執筆を終わりても其の後味の悪さは日が経過しても薄くならなかつた。所が本誌から原稿を求められて、ここに「旅」には発表し得なかつた部分と、鮮明な態度をとつている本誌に発表するの機会を与へられた事は深く感謝する次第である。
沖縄は気象学、動物学、植物学、言語学、民俗学殊に最近は工藝等の領域に於いては相当の研究がなされ且つ学界には発表せられている様ではあるが、観光学の分野に於いては他の諸学に比して数段遅れている事は否めない。何故かくもこの沖縄県のみ観光的に残されていたのかといふと、他に種々の理由もあらうけれども第一に本州の諸島と余りにも離れていたといふ簡単な理由に過ぎないと思ふ。同じ島でも佐渡の如くに近いと観光的に発展し過ぎてしまふ位にまでなつてしまふのである。この地理的条件は不幸でもあつたらうが他面に発展を伴ふ堕落から免れる幸福もあつたわけである。
次に兎角観光地といふ所では他から来た観光客の好んで見たがる箇所は地元では見せたくない場所が多いといふ問題がある。之は何処でも起こる問題で日本全体としても考慮しなければならないのである。何も沖縄県だけが考へなければならない問題ではないし、何処の府県でもお互い様である。之はもつと気楽に考へて宜しい問題だと思ふ。唯、好意的に観察して貰ふ様に充分なる説明をして納得して行く事は望ましい事である。之は案内記の書き方に依つて相当の効果は挙げる事が可能だらうと思はれる。
以上先ず云ひ難い点を敢て云つておいて本題に入る事としよう。
今回の沖縄の旅ほど、旅は有益であると知つた経験は従来無かつた。百閒も一見に如かざるの真理も充分に知る事が出来た。沖縄県の観光資源の豊富に恵まれていたのには驚嘆した。一月といふ時季に行つた為に特に感じたのかと思ふが、冬季の温暖な事は強味だと思ふ。霜雪を知らぬ土地に育つ植物の見事さ、沖縄全体が温室の如きではないか。寒中に露地で赤々と花の咲いている國が他にあらうか。海の水は空を溶かした様に綺麗だし、海岸の風景は到る処絵の様に美しい。島全体を風致地区として保存したい位だ。口腹の満足せしむる沖縄料理の美味に泡盛の清烈は此の土地で味つてこそ意義がある。加之、目と耳を楽しませるものには民謡と踊りと芝居がある。其の各々に有機的な機関があつて地方色が強くしみ込んで居り、且つ、にじみ出して居る。之等は一つ一つ切り離すべきではない。だから、どうしても沖縄に来られよ、と呼びかけなければいけない。呼びかける以上は相当の自信を以て臨むべきであらう。
観光地沖縄として出来るなれば次の3項目を実行し得たら立派な観光地として自慢出来ると思ふ。現在の社会、経済事情として早急の実現は困難であらうとは思ふが、なるべく其の実現に努力して完成の日の近からむ事を希望する次第である。何でもかんでも作れるなど無理な事を云ふのではない。出来る時にやれる様に常に心掛けておく事が必要なのである。
交通機関の完備 現在の県営鉄道は観光客には利用されていない様である。船は那覇名護間も毎日は通っていない様であるから、どうしても一番頼りにするのは乗合自動車といふ事にならう。そのバスが常に満員であつた事は、時節柄減車の已むなき為でもあつたらうが、もつと運転回数を多くする必要を示すものであらう。バスの能率増進は道路次第であるから、島内の道路網の拡充は他の意味から云つても重要な事業と云へよう。坂の比較的少ない路線は木炭車でも配してみては如何であらうか。一方には遊歩道も欲しいものである。首里と那覇の間は自動車で早々に過ぎ去るには残念な位眺望の良い所がある。殊に首里から那覇へ下りて来る道が良い。私はわざわざ一度人力車で下つてみた。尤も之はバスに乗れなかつたからでもあつたのだけれども、想像以上によい景色に感嘆の声を発した程であつた。道路は全部ペーヴメントとはならなくても今日国頭方面でも自由にバスを通じてる程度のものがあるのだから、其の完成には比較的困難を感じないですむのではないかとも思はれる。そして自由にバスが走り廻れれば申し分ない。
宿泊設備 旅館は現在に於いては余り優秀とは云い難い様に思はれる。旅館の発達しない理由の一に辻の存在が考へられるかも知れない。が、然し、それとは別に切離しても設備の整つた旅館がもう少し欲しい。何も外国人向きのホテルを建てよと叫ぶわけでは決してない。短期滞在の客はいいとして長期滞在の客に対する設備が不完全ではないだらうか。下宿をするといふ事は事実上不可能らしい。この方面の要望は従来なかつたものか、将来の客一に後考を煩したい問題の一である。僅か20数名の団体客が2軒の旅館に下宿しなければならないといふ事は遺憾であつた。せめて30名は一軒に泊まれなくては不便である。
序でに旅館の食事に就いて一言しておく。旅館に泊まる人といへば原則としてその土地の人ではないのであるから、其の土地の料理を出して貰ひたいものである。この事は沖縄だけの問題ではなく、全国的に共通の大問題なのである。某先生が「旅とは米の飯と鮪の刺身と灘の酒の全国的統一である」と云はれるのを聞いた事がある。が現在では白米が7分搗きに代つただけで他は同様である。尤も沖縄では灘の酒より泡盛が幅を利かしているのは僅かな地方差である。旅館では土地で採れるものを土地風に料理して出せ、といふ要望はこの10数年来幾度か叫ばれて来ながら少しも実行されていない。沖縄でも此の例に洩れなかった。沖縄料理を出してくれと特別に注文しても「豚の角煮」が一度出た位のものであつた。もう我々はうんざりしてしまつて、なるべく旅館では朝飯以外に食はない様に努力せざるをえなかつた。郷に入っては郷に従へといふ事もあるのだから、他の土地に来た者には一度は黙つて土地の料理を食はせる。それではいかんといふ客には所謂旅館の料理ー之を標準料理と云つた友人がいたが一寸面白いと思つたーを出せばよい。少なくとも郷土料理か標準料理か何れを希望するか位は聞いて貰ひたい。況や特に注文しても出さないのは言語道断である。古くなつた鮪の刺身を出して特にもてなしたつもりで居られたのではこつちは大迷惑である。聊か脱線したが、沖縄の如く郷土色の豊かで而も美味な料理が残つている所では一層注意して頂きたいと敢えて述べる次第である。
観光地の施設 崇元寺の電柱や旧首里城の龍樋の柵の如き悪例は出来るだけ速やかに改善して頂きたい。将来は棒杭一本、案内板一枚を立てるのにも注意して頂けば結構である。同じ表示板を立てるにしても、風致を破壊する事も出来れば風致を増す事も出来るのである。ぶちこはしは容易だが、其の回復は困難である。例へば万座毛の鳥居の如きである。故に最初の施設が肝要である。ペンキ塗りの棒杭を立てるよりは豊富に産する石材を用いて工夫すれば却つて効果をあげる事さへ出来はしないだらうか。然し徒に風致保存を唱へて住民の生活を犠牲にしてまでも実行せよなどなどわけのわからない事は云はない。ただ何れにしても建てるものであつたら良きものを建てる事にするといふ心掛けは常に失つて頂き度くないのである。
最後に念を押して申上げておきたい事は観光施設の行き過ぎにならぬ様に戒しむ可き事である。観光地として流行した場所で堕落しなかつた土地は先ず無いといつてよい位である。大阪商船の案内書ではないが「観光処女地」沖縄を汚したくないのは県民・観光客共に望む所でなくてはなるまい。尚一言したい事は、沖縄を観光的に発展せしめて一体どうするのか、といふ質問が出るかも知れないので、敢へて述べるならば、之は県の発展、県民の幸福にまで導かれる事だと云ひたいのである。県として最も恵まれたる観光資源を活用して観光客を吸収し、他府県人に金を落させて、而して県として裕福になれば之が県民の幸福にならないものであらうか。妄言多謝(15、2、9)
1940年
1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

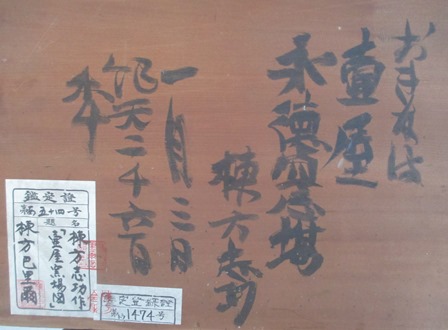
棟方志功「壺屋窯場の図」サエラ(携帯080-1533-3859)所蔵
1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。
1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。
1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。
1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。
1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。
1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。
1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。
1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。
1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。
1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。
第四回訪沖
7月24日ー11月開催予定の皇紀二千六百年奉祝事業の「琉球工藝文化大展覧会」準備のため田中俊雄、坂本万七を伴ない、4回目の訪沖に出発。 沖縄では、言語問題論争がなお続いていた。
8月2日ー沖縄県庁で知事渕上房太郎氏と会見し、標準語絶対反対論者と決めつけられた理由の説明を求める。この日「敢えて学務部の責任を問ふ」を琉球新報に載せる。 展覧会への出品依頼に、尚家をはじめ各方面から古作優品が出さ、陶器百点の外、絵画、染織も加わる。
写真撮影は、主として、「琉球風物写真展」(銀座三越)用の風物撮影を行う。 この間、坂本と撮影した海岸の写真が、海洋警備上の秘密を撮したとされ、警察に連行され、坂本は一夜留置された。
8月22日ー浮島丸にて那覇を発つ。
8月24日ー神戸着
12/23: 莫夢忌/『日本及日本人』誌上での末吉麦門冬と南方熊楠
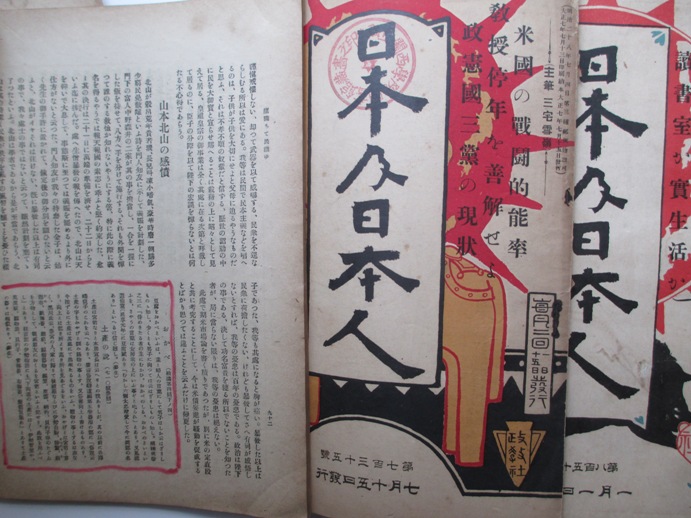
『日本及日本人』赤線内が麦門冬執筆
○この雑誌は、政教社の日本人誌と陸羯南の日本新聞とを継いでいる。これらは元々兄弟のような間柄だったが、1906年、日本新聞社の後任社長伊藤欽亮の運営を不服として、社員12人が政教社に移り、三宅雪嶺が『日本人』誌と『日本新聞』との伝統を継承すると称して、翌年元日から『日本人』誌の名を『日本及日本人』と変え、彼の主宰で発行したのである。創刊号の号数も、『日本人誌』から通巻の第450号だった。雪嶺は1923年(大正12年)秋まで主筆を続けたが、関東大震災後の政友社の再建を巡る対立から、去った。それまでが盛期だった。雪嶺は、西欧を知り、明治政府の盲目的な西欧化を批判する開明的な国粋主義者で、雑誌もその方向に染まっていた。題言と主論説は雪嶺、漢詩の時評の『評林』は日本新聞以来の国分青崖、時事評論の『雲間寸観』は主に古島一雄、俳句欄は内藤鳴雪、和歌欄は三井甲之が担当し、一般募集の俳句欄『日本俳句』は河東碧梧桐が選者で、彼は俳論・随筆も載せた。ほかに、島田三郎、杉浦重剛、福本日南、池辺義象、南方熊楠、三田村鳶魚、徳田秋声、長谷川如是閑、鈴木虎雄、丸山幹治、鈴木券太郎らの在野陣が執筆した。月2回刊、B5より僅か幅広の判だった。たびたび発禁処分を受けた。大正期に入ってからは、三井甲之の論説が増え、中野正剛、五百木良三、植原悦二郎、安岡正篤、土田杏村、布施辰治、寒川鼠骨らが書いて、右翼的色彩も混ざった。1923年(大正12年)の関東大震災に、発行所の政教社は罹災した。雪嶺と女婿の中野正剛とは、社を解散し新拠点から雑誌を継続発行すべきとし、他の同人が反対し、碧梧桐・如是閑が調停したが、雪嶺は去った。以降の『日本及日本人』は、同名の無関係の雑誌とする論もある。1924年年初、政教社が発行し直した『日本及日本人』は、体裁はほぼ以前通りだったが、内容は神秘的国粋論が多くなった。1930年(昭和5年)、五百木良三が政教社社長となって『日本及日本人』を率いた、1935年からは月一回発行になった。(ウィキペディア)
1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」
1912年2月ー柳田国男、伊波普猷より『古琉球』3冊寄贈される。
1913年4月ー沖縄県庁でこの程、筆耕に令し『中山世譜』の筆写をなさしめつつある。
1914年7月ー沖縄県知事より、伊波普猷、真境名安興ら沖縄県史編纂委員拝命
1915年1月ー沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁より沖縄県立沖縄図書館に移される(真境名安興主任)
1917年7月15日ー『日本及日本人』709号□末吉麦門冬「十三七つに就いて」「雲助」「劫の虫より経水」(南方熊楠と関連)
1917年9月1日ー『日本及日本人』712号□末吉麦門冬「楽屋の泥亀汁」
1918年2月12日ー東京日本橋区本町三丁目博文館・南方熊楠殿、末吉安恭書簡「拝啓 先生の御執筆の十二支伝説は古今東西に渡りて御渉猟のこととて毎年面白く拝読いたし候(略)琉球にも馬に関する伝説、少なからず候み付、茲に小生の存知の分を記録に出でたるものは原文の侭、然らざるは、簡単に記述いたし候間、御採択なされ候はば幸甚に候。失礼には候へど、御ねがひいたし度きこと沢山これあり候につき御住所御知らせ下さるまじくや(略)」(『球陽』『琉球国旧記』引用)
1918年8月15日ー『日本及日本人』737号□末吉麦門冬/しなだれ(輪講第二回中)第70号141にしなだれの解出づるも、その語源に就いては更に考ふべきものなきか、松屋筆記に日本霊異記等を引きて詳しく解釈せり、霊異記の■(門+也)は訓註に「シナダリクボ」と見ゆ「シナダリ」はシナダリの通音也。婬汁はしシタダリナガル、物なればシタダリと云ひ、クボ」は玉門のことにいへりとし、又今昔物語の婬もシナダリと訓むべしと云へり、これに依ればしなだれかかると云ふ語も、■れかかる義には相違なけれど、其の出所の元は婬汁のシナダリよりせしとすべきか。/焼餅の値(輪講参照)竹田出雲の小栗判官車街道(元文3年)に、桔梗屋の常陸といふ女郎が千二百両で身請けされたと聞き、二条樋の口の焼餅屋曰く「千二百両の金目を二文賣の焼餅の数に積って見れば、百五十四萬五千六百といふ焼餅が買われるげな」とあり、焼餅の値が二文づつなりしことが知らる。
1918年10月1日ー『日本及日本人』741号□末吉麦門冬/おかべ(輪講第四回下ノ四)豆腐をおかべといふは、素の婦人の言葉にして男子はしか云はざりしものの如し、少なくとも男子に向かっては云はざりしものの如し。醒睡笑巻之三に「侍めきたる者の主にむかひ、おかべのしる、おかべのさいといふを、さやうの言葉は女房衆の上にいふ事ぞと叱られ」とあり。又風流遊仙窟(延び享元年)に豆腐賦あり「むかし六弥田忠澄愛して今に岡部の名あり」といへるは信じ難し。/土産の説(七一〇号参照)土産は宮笥なりと本居宣長は云へりとの説ありしが、其の以前に井澤幡龍子①のこれを云へるあり、廣益俗説辯遺編第五巻期用の部に「俗説云土産の字をみやげと訓み賜物の事とす、又俗書向上と書けるものあり、今按ずるに土産は其処にて出来たるものをいふ、贈物の事とするは非なり、向上とは低き所より高き所を見あぐるをいふ、みやげとは宮笥と書く、黒川氏云、参宮の人、家に帰りて後祓箱ならびに伊勢白粉、陟のり、弱海布、麩海苔、鰹節、鯨髯器物、編笠、笙笛、柄杓、貝柄杓等のたぐいを方物として、親戚朋友におくるを宮笥といふと記せり、此説を用ふべし」とあり、狂言記の伊勢物語にも「下向道の土産には土産には伊勢菅笠や、萬度祓、鯨物差、貝柄杓、青海苔、布海苔、笙笛買集め」とありて土産の品々は相似たり。
①井沢 蟠竜『廣益俗説辨コウエキ ゾクセツベン 』 広益俗説弁, 序目1巻正編20巻後編5巻遺編5巻附編7巻殘編8巻
1919年1月1日ー『日本及日本人』747号□末吉麦門冬「再び琉球三味線に就いて」/「小ぢよくー近松の栬狩劔本地に『親をだしに遺ふは、物どりの奥の手、ヤイ小童今度は是を喰ふかと、杵振上れば』とあり、小童と云はれたのは男の子なり」/「かんから太鼓ー八笑人三編追加上の巻、頭武『イヨイヨヤンヤヤンヤのお声がたよりぢやァ、是はカンカラ太鼓をかりて行かうか』とあり、此編文政7年の作なりと云へば、その以前既にカンカラ太鼓ありと知るべし。安政3年よりも三十三年前なり。」(吉田芳輝氏提供)
1919年4月ー『日本及日本人』□末吉麦門冬「無筆の犬ー無筆の犬といふ話は早く醒睡笑(元和9年)に出づ。曰く『人喰ひ犬のある処へは何とも行かれぬなど語るに、さる事あり、虎といふ字を手の内に書いて見すれば、喰はぬと教ゆる。後犬を見、虎といふ字を書きすまし、手をひろげ見せけるが、何の詮もなく、ほかと喰ふたり。悲く思ひ、或僧に語りければ、推したり、其犬は一圓文盲にあったものよ』云々」
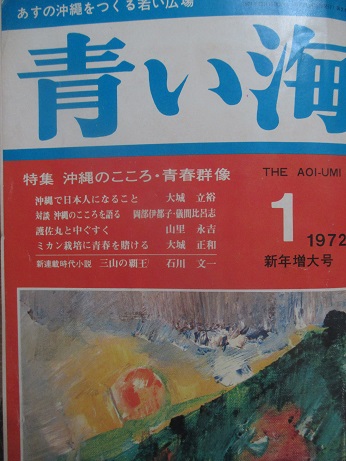

1972年1月 沖縄の雑誌『青い海』9号 山里永吉「沖縄の史跡 護佐丸と中ぐすく」
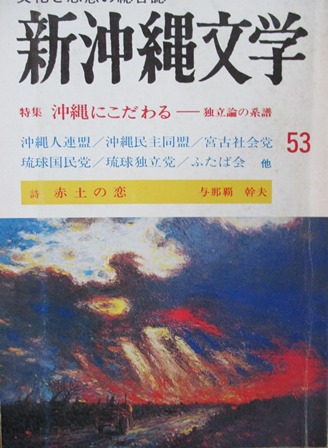

1982年(昭和57) 9月 「山里永吉瞥見」『新沖縄文学』第53号 沖縄タイムス社
【内容】 石鼓 教科書問題の本質 (特集)沖縄にこだわる -独立論の系譜 独立論の位相 川満信一著. 沖縄人連盟 新崎盛暉著.沖縄民主同盟 仲宗根勇著. 宮古社会党 平良好児著. 不発の独立論 大田静男著. 琉球国民党 島袋邦著. 琉球独立党 平良良昭著. ふたば会 太田良博著. 琉球巴邦・永世中立国構想の挫折 仲程昌徳著. 山里永吉暼見 岡本恵徳著.コラム 帰属問題めぐり街の声を聴く/ /反映させよ住民の希望 沖縄自立・独立論関係図書目録 潮流 私学問題と官尊民卑(教育) 「一坪反戦地主会」の発足(住民運動) 多様化する反戦運動(社会) 検定に対する検定を(文化) 沖縄史そぞろある記(10) 嘉手納宗徳著. 動物の鳴き声 儀間進著. 日本人の沖縄人像 親泊寛信著. 琉球の地頭性(3) 宮城栄昌著. 海外ジャーナル 話題ふたつ(アメリカ) 宮城悦二郎著. 新聞とのつきあい(フランス) 大下祥枝著. 香港の漁村にて(東南アジア) 比嘉政夫著. 書評 「地図の風景」 「蝶の島」 「聞書西表炭坑」 「ある二世の轍」 「石扇回想録」 「ふるさとばんざい」 「沖縄の悲哭」 「瞳詩篇」「芝憲子詩集」 「沖縄-戦争と平和」 「沖縄の戦記」 「対馬丸」 「句集琉球切手」 「わが沖縄ノート」 「琉球文学小見」 「琉球の言語と文化」 「沖縄行政機構変遷史料」 「生贄は今」 「沖縄資料センター目録」 第8回「新沖縄文学賞」予選発表 詩 赤土の恋 与那覇幹夫著※与那覇幹男1939年11月26日~2020年1月20日。『赤土の恋』で1983年、第七回山之口貘賞。与那嶺さんは新報でよく出会ったが、2019年に初めての長い電話をくれた。お別れのつもりだっただろう。晶子夫人から僕のことを聞いていたからであろうか。亡くなられたのを知ったのは森口豁さんのFacebook2020-9であった。
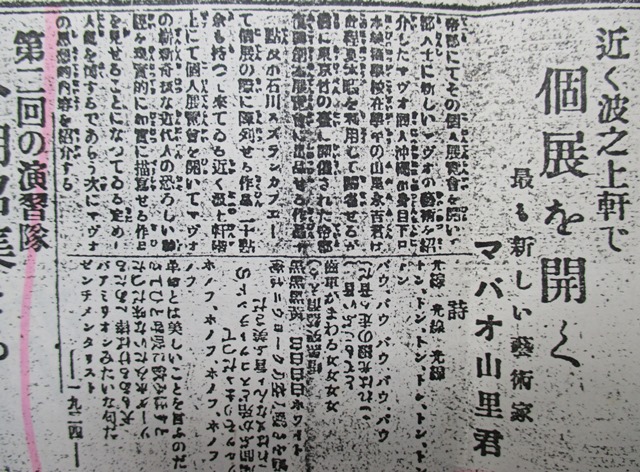
1924年7月18日『沖縄タイムス』
山里永吉が1924年、那覇の波之上軒で開いた個展には「村山知義によって踊られたるワルツ」「インペコーフェンの踊り」もあった。山里永吉自伝□東京では『マヴォ』の雑誌が発売禁止になり、同人は全員、警察の身元調査を受けていて、警視庁からの連絡で私の家にも那覇署員がやってきた。息子の身元調査に親父はびっくりしたらしい。幸い私はその時東京に帰っており行きちがいであった。そんなことがあって親父は東京にいた山田真山先生へ手紙を出し息子を預かってくれと依頼した。真山先生は那覇で展覧会を開いたとき、私の家に泊まっていたので父とは旧知の間柄だった。早速、使いがきて、私は荻窪の先生の家へ引き取られ、お預けの身になった。一年そこら御世話になったが、父が死んで、東京にいてもつまらないので、沖縄へ引き揚げた。昭和2年4月のことである。
1926年9月 『沖縄教育』156号 山里永吉「小説ゆめ」
1933年5月 『沖縄教育』201号 山里永吉「明治神宮壁画『琉球藩設置』」
大火で辻にあった貸家は全部まる焼け、保険金は一文もかけていない。それで父は農工銀行を辞めて生前、漆器店(丸山漆器店ー那覇市上ノ蔵町・電話441番)を始めており、兄貴は勧業銀行の那覇支店に勤めて高給をとっているので辞めようとしない。「お前店番をしろ」というわけで東京から帰った私に申しつけたが、私はそういう仕事は向かない。店のことはいい加減にして、脚本や評論などを新聞に発表したりしていた。

丸山漆器
それからしばらくして伊良波尹吉、真境名由康、島袋光裕の俳優3人が、顔をそろえてやってきて「芝居の脚本を書いてくれ」と懇請された。沖縄芝居はそのころ衰退気味で、新聞を読むほどの人なら芝居を見にいかない。「これじゃ、どうにもならん、ひとつ協力してくれ」と持ちかけてきたものである。最初に書いたのが「一向宗法難記」だった。2作目が「首里城明け渡し」で大当たりに当たった。
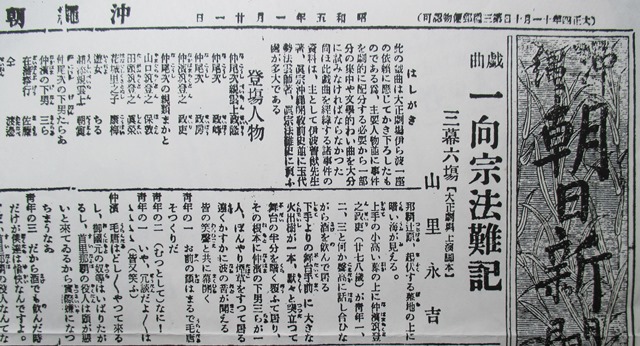
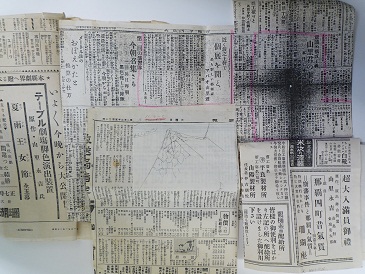
.jpg)
1960年3月30日ー崇元寺調査、黒板、杢、中央の顔が隠れているのが山里永吉
□1960年3月28日ー琉球文化財保護のため文部省文保委会「第一次琉球文化財調査団」の黒板昌夫調査官、杢正夫技官が来沖。
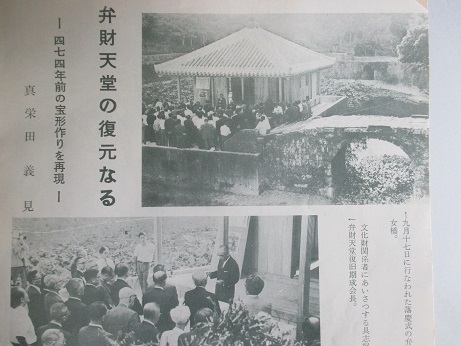
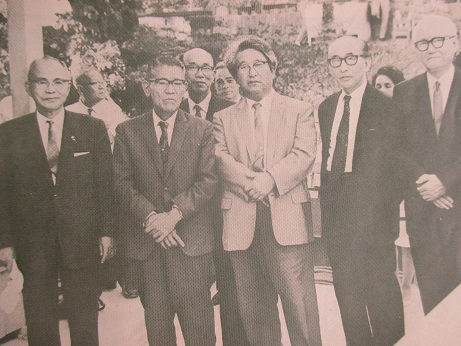
写真左から具志堅宗精復旧期成会長、真栄田義見、川平朝申、不詳、山里永吉
1968年11月『今日の琉球』真栄田義見「弁財天堂の復元なるー474年前の宝形作りを再現」
1971年1月6日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー中央集権とも関連 半世紀の内乱にこりる」<上>
1971年1月7日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー撤廃は歴史家の定説 『反戦平和』の思想思い起こせ」<下>
□1972年9月ー『佛教藝術』88<沖縄の文化と美術特集> 毎日新聞社
沖縄の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新屋敷幸繁
沖縄文化史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉 春潮
沖縄の宗教・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・源 武雄
おもろ十首・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外間 守善
沖縄の梵鐘と金石文・・・・・・・・・・・・・外間 正幸
琉球漆器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡田 譲
沖縄の陶芸史・・・・・・・・・・・・・・・・・・山里 永吉
琉球紅型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鎌倉芳太郎
沖縄の舞踊と楽器・・・・・・・・・・・・・・・仲井真元楷
琉球の建築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田辺 泰
沖縄文化財建造物等の復旧事業・・・杢 正夫
口絵解説・殷元良筆「鶉図」・・・・・・・・真保 亨
沖縄の重要文化財

1960年6月6日 伊野波節石くびれ 左より池宮喜輝、国吉真哲(山里永吉文化財保護委員長・撮影)
.jpg)
石くびりと山里永吉

1989年5月8日『琉球新報』川平朝申「山里永吉氏の逝去を悼む」
1989年5月8日『沖縄タイムス』船越義彰「追悼ー那覇人に徹した山里氏」
「ふりむん随筆 未完成公共学(一)」□私は自由の月である。フリームーンである。現在は順天堂大学医科大学教授で英語と文学(国語漢文を含む)の主任教授であるが、学生はわたしのことを「シュセキキョウジュ」と呼んで親しんだりこわがったりしているが「首席教授」の意味だが「酒席狂需」の意味だか、忙しくて辞書を引く暇がないので自分でもよくわからない。どんな辞書を引いたらよいか沖縄隋一の学聖否全日本でも無類の碩学 東恩納寛惇(有名人敬称略、御免)に質してからゆっくり調べることにする。
昔から「金持ち暇無し」と言う通り、事実私は暇がないのである。アルバイトとして桐葉予備校、文京予備校、国際予備校の3校の英語主任も兼務して居り、日本英学院で英文学も講じて居り、丁度目下那覇の大宝館で上映中のグレイアム・グリーンの「落ちた偶像」の原作を英語で講義中である。ささやかながら自分の石川英語学院も手離せない。二つの出版会社の編集顧問も引き受けている関係で原稿依頼も多い。
「ありが英語小や、ゆくしぬうふさぬ、わー英語小けんそーれー」と日夜歌っている身になってごらんなさい。英語ニコヨンはつらいです。ウランダ口アチョールドウは悲しいです。「大和口使て、ウランダ口ならーち、唐書物読むる沖縄二才我身や」と大日本帝国はなやかなりし頃、那覇の一角、中島小掘のほとりでき門の望に明け暮れる母に琉歌を送ってなぐさめた、我が厚顔の青年の日が、昨日や今日のように思い出されて胸がうずく。「日本語も英語も知らぬアンマーはワッター次郎を故郷に待つ」と涙ながらに和琉ちゃんぼの忍び泣きに異郷滞在の不孝の罪を心にわびたのもその頃である。
「ふりむん随筆 未完成公共学(七)」□「大傷繃帯日」も私の予言である。大東亜戦争が天皇の名で宣せられ「大詔奉載日」が制定されるや、私が愛国の至情から国難を予言した)「大傷繃帯日」は物の見事に的中した敗戦直後(終戦という言葉でごまかすな)伊波普猷の家で会ったとき松本三益に「石川先生は徹底的に敗戦論者でしたね」と妙なことを覚えられていて、比嘉春潮も「そうだったか」と私を見直した。「そてつ(蘇鉄)地獄」と沖縄の窮乏をなげき、「ブーサー極楽」と故郷の退廃を憂えていたとき「人口過剰の無人島」と人物缺乏を痛嘆した40年前の私の寸鉄は今日の日本に対する予言となって実現している。「天ぴ大和口」という奇語も私の発明だったかどうか忘れたが、今沖縄ではどんな標準はずれの標準語を使って金をもうけ、恋を語って居るであろうか。
キヤメルを鹿小と呼び、ラッキー・ストライキを旗小と称し、フィリップモリスを黒ん坊と唱えている由、私はふるさと人の語感を頼もしく思い、既に天下をのんでいるその意気に敬意を表して頭を下げる。パチンコと競輪にうつつをぬかして夢中になっている知性の無い今の大和民族にはそんな意気やゆとりのかけらも無い。一度は政治的に亡んだこの国は、今精神的亡国の寸前にある。だからいつまでもまずい煙草をのまされているのだ。煙草から立ち登る煙にすらレジスタンスをしめす気力がないのである。
「竹島は明らかに韓国領土だ。その証拠にはあの島にはパチンコ屋は一軒も無い」と李承晩大統領にすらなめられているていたらくである。日本の大学生はパチンコをしたついでに学校に通う。李承晩ラインの故智にならったわけでもあるまいが、沖縄の周囲に精神的愛郷の比嘉秀平ラインを張りめぐらして人生冒涜の亡国遊戯パチンコの神聖なる沖縄侵入を断固排していると聞く我が同僚沖縄民政府主席比嘉秀平の明智と良しきと勇気に対して在京沖縄人全体ではなく私一人を代表して厚く謝辞を述べて益々その健闘を祈らずには居られない。
「ふりむん随筆 未完成公共学(九)」□(略)当間重剛を語る門外不出の材料も一中、三高、京大、司法官時代と沢山ある。唯彼に一つの欠点がある。それは私に話しかけるとき、パリー語や那覇語を使わないで最初大和口を使うことである。それはよろしくない。今度彼が東京に出て来たら、大いに叱ってやろうと思っている。飲む前に叱るのだ。「石川正通 当間重剛を叱るの図」これは素敵な画題だ。山田真山の麗筆に触れれば雪舟、応挙の塁を摩し、金城安太郎の絹布に上れば、歌麿、写楽を彷彿させ、嘉数能愛のパレットに踊っては関屋敬次の風格と画風を再現し大城皓也のカンバスに現れては曽太郎、龍三郎の域に迫り、渡嘉敷唯夫の画用紙に捕らわれは、近藤日出造、池部均をしのぐ傑作となr山里永吉の画板に乗ればピカソかマチスかマボーあたりを顔色なからしめる旋風を起こすであろう。更にまた瀬名波良持の紅型に染めぬかれれば鳥羽僧正の遺風を伝えて永久に博物館を飾る国宝に指定されるであろう。
波之上神社の鳥居と那覇市役所の馬鹿塔と当間重禄の医者の看板を那覇の三大不用物と指摘したのは崎山嗣朝の余りにも有名な警句で政争の激しかった大正末期の名残を留めて如何にも泊人らしい気概に満ちている。和辻哲郎の「偶像再建」を読むまでもなくヨーロッパの中世思想に抗して興った近代ヨーロッパのアイコノクラズム(偶像破壊)の思想も今日では思想史の数頁をかろうじて占める哲学の足跡に過ぎない。わがふるさとも偶像再建の機運に近づきつつあることと思う。波之上神社の鳥居はカンプーサバチでどうなったか知らないが、前よりも大きな鳥居を建てたらどうだろう。もし神社が残っていたら。それは神の家の門として建ててもやがては那覇の風物詩の一つとなるであろうから。
昔から「金持ち暇無し」と言う通り、事実私は暇がないのである。アルバイトとして桐葉予備校、文京予備校、国際予備校の3校の英語主任も兼務して居り、日本英学院で英文学も講じて居り、丁度目下那覇の大宝館で上映中のグレイアム・グリーンの「落ちた偶像」の原作を英語で講義中である。ささやかながら自分の石川英語学院も手離せない。二つの出版会社の編集顧問も引き受けている関係で原稿依頼も多い。
「ありが英語小や、ゆくしぬうふさぬ、わー英語小けんそーれー」と日夜歌っている身になってごらんなさい。英語ニコヨンはつらいです。ウランダ口アチョールドウは悲しいです。「大和口使て、ウランダ口ならーち、唐書物読むる沖縄二才我身や」と大日本帝国はなやかなりし頃、那覇の一角、中島小掘のほとりでき門の望に明け暮れる母に琉歌を送ってなぐさめた、我が厚顔の青年の日が、昨日や今日のように思い出されて胸がうずく。「日本語も英語も知らぬアンマーはワッター次郎を故郷に待つ」と涙ながらに和琉ちゃんぼの忍び泣きに異郷滞在の不孝の罪を心にわびたのもその頃である。
「ふりむん随筆 未完成公共学(七)」□「大傷繃帯日」も私の予言である。大東亜戦争が天皇の名で宣せられ「大詔奉載日」が制定されるや、私が愛国の至情から国難を予言した)「大傷繃帯日」は物の見事に的中した敗戦直後(終戦という言葉でごまかすな)伊波普猷の家で会ったとき松本三益に「石川先生は徹底的に敗戦論者でしたね」と妙なことを覚えられていて、比嘉春潮も「そうだったか」と私を見直した。「そてつ(蘇鉄)地獄」と沖縄の窮乏をなげき、「ブーサー極楽」と故郷の退廃を憂えていたとき「人口過剰の無人島」と人物缺乏を痛嘆した40年前の私の寸鉄は今日の日本に対する予言となって実現している。「天ぴ大和口」という奇語も私の発明だったかどうか忘れたが、今沖縄ではどんな標準はずれの標準語を使って金をもうけ、恋を語って居るであろうか。
キヤメルを鹿小と呼び、ラッキー・ストライキを旗小と称し、フィリップモリスを黒ん坊と唱えている由、私はふるさと人の語感を頼もしく思い、既に天下をのんでいるその意気に敬意を表して頭を下げる。パチンコと競輪にうつつをぬかして夢中になっている知性の無い今の大和民族にはそんな意気やゆとりのかけらも無い。一度は政治的に亡んだこの国は、今精神的亡国の寸前にある。だからいつまでもまずい煙草をのまされているのだ。煙草から立ち登る煙にすらレジスタンスをしめす気力がないのである。
「竹島は明らかに韓国領土だ。その証拠にはあの島にはパチンコ屋は一軒も無い」と李承晩大統領にすらなめられているていたらくである。日本の大学生はパチンコをしたついでに学校に通う。李承晩ラインの故智にならったわけでもあるまいが、沖縄の周囲に精神的愛郷の比嘉秀平ラインを張りめぐらして人生冒涜の亡国遊戯パチンコの神聖なる沖縄侵入を断固排していると聞く我が同僚沖縄民政府主席比嘉秀平の明智と良しきと勇気に対して在京沖縄人全体ではなく私一人を代表して厚く謝辞を述べて益々その健闘を祈らずには居られない。
「ふりむん随筆 未完成公共学(九)」□(略)当間重剛を語る門外不出の材料も一中、三高、京大、司法官時代と沢山ある。唯彼に一つの欠点がある。それは私に話しかけるとき、パリー語や那覇語を使わないで最初大和口を使うことである。それはよろしくない。今度彼が東京に出て来たら、大いに叱ってやろうと思っている。飲む前に叱るのだ。「石川正通 当間重剛を叱るの図」これは素敵な画題だ。山田真山の麗筆に触れれば雪舟、応挙の塁を摩し、金城安太郎の絹布に上れば、歌麿、写楽を彷彿させ、嘉数能愛のパレットに踊っては関屋敬次の風格と画風を再現し大城皓也のカンバスに現れては曽太郎、龍三郎の域に迫り、渡嘉敷唯夫の画用紙に捕らわれは、近藤日出造、池部均をしのぐ傑作となr山里永吉の画板に乗ればピカソかマチスかマボーあたりを顔色なからしめる旋風を起こすであろう。更にまた瀬名波良持の紅型に染めぬかれれば鳥羽僧正の遺風を伝えて永久に博物館を飾る国宝に指定されるであろう。
波之上神社の鳥居と那覇市役所の馬鹿塔と当間重禄の医者の看板を那覇の三大不用物と指摘したのは崎山嗣朝の余りにも有名な警句で政争の激しかった大正末期の名残を留めて如何にも泊人らしい気概に満ちている。和辻哲郎の「偶像再建」を読むまでもなくヨーロッパの中世思想に抗して興った近代ヨーロッパのアイコノクラズム(偶像破壊)の思想も今日では思想史の数頁をかろうじて占める哲学の足跡に過ぎない。わがふるさとも偶像再建の機運に近づきつつあることと思う。波之上神社の鳥居はカンプーサバチでどうなったか知らないが、前よりも大きな鳥居を建てたらどうだろう。もし神社が残っていたら。それは神の家の門として建ててもやがては那覇の風物詩の一つとなるであろうから。
06/09: 戦時体制下の沖縄/月刊『文化沖縄』 比嘉榮眞「病歴」
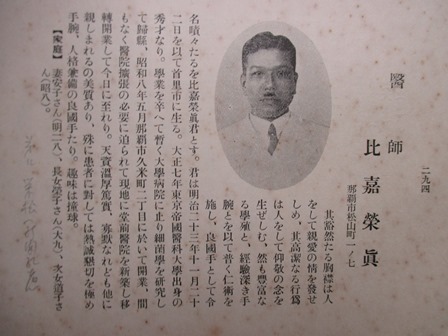
1937年9月 『沖縄県人事録』沖縄朝日新聞社「比嘉榮眞」
1943年1月 月刊『文化沖縄』第4巻第1号
病歴・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・・・・44
○此の稿は勿論未完成の儘である。嘗て医師会事業として提唱した問題である。而して今度は私が3,4年間に集めた分だけを書いたものである。只手付けの一端を披瀝しておけば、会員各位の記憶を呼び起こして以って応援も多からんことを希望して止まない次第である。
1、正月 自粛の年、国民生活を出来るだけ切り下げて行く決戦下に於いて、物の不足は漸く馴れて、お正月といへども昔みたい様に暴飲暴食するといふ事はないと思ふ。が未だ所謂お正月気分といふものがあって多少とも弛みが出る。その隙に色々の病気に犯さるるものである。
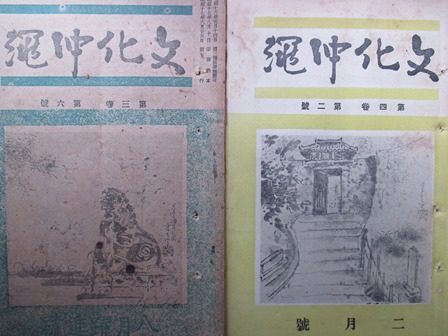
1943年2月 月刊『文化沖縄』第4巻第2号
愛国百人一首評釈・・・・・歌壇諸大家・・・・・・・2
琉球使節を歌へる歌・・・・林 秀雄・・・・・・・・・6
護国の神々に仕ふ・・・・・・仲村渠政権・・・・・・7
身邊小話・・・・・・・・・・・・・・長田紀秀・・・・・・・・9
随筆三題・・・・・・・・・・・・・・喜久川鼎・・・・・・・11
歴史と命魂・・・・・・・・・・・・・高良忠一・・・・・・15
琉球とおもろ双紙(和歌)・・山口由幾子・・・・16
病歴(二月)・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・22
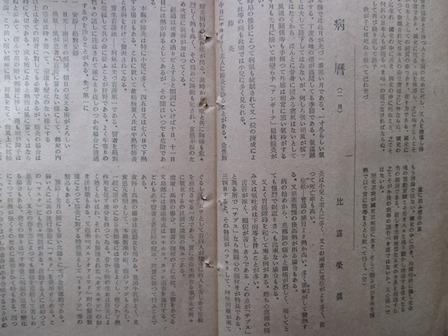
比律賓群島の糸満漁民・・・比嘉 榮・・・・・・・27
名士の演説振・・・・・・・・・・・伊地 啓・・・・・・・30
南洋通信・・・・・・・・・・・・・・・大宜味朝徳・・・・32
労務雑記・・・・・・・・・・・・・・・山城興純・・・・・・33
くすりを求めて(1)・・・・・・・・久場仙眼・・・・・・36
方圓録・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍・・・・・・40
療園四年・・・・・・・・・・・・・・・・松田並子・・・・・・44
1943年3月 月刊『文化沖縄』第4巻第3号
病歴(3月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・37
○2月からの余勢は流れて先月からの流行は引き続き依然として顕はれてくる。陽気がポカポカと暖かくなり出して街路の黄塵が吹きまくって、相変わらずノド、鼻カゼが多く安魏那が多い。
1943年4月 月刊『文化沖縄』第4巻第4号
病歴(4月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・36
○気温と脳ー梯梧の花盛りー 陽春4月ー誰れかれの別なく自然と共に心が浮き浮きしてくるものである。而してこの春になると脳の変調が来て脳神経系統の病気が多くなる。其の理由は気温が上昇する関係である。気温が上がると人体皮膚の下の血管がフクランで来る。それと同時に頭蓋の内の血が降りてそれに因る刺激症状を起こすもので「フルチ」「ハンゲーイモノ」(微毒)等が続発してくるのもこの期節で、又神経痛、ロイマチス等もよく再発してくるものである。
1943年5月 月刊『文化沖縄』第4巻第5号
病歴(5月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・24
○昭和14年、15、16年は麻疹が続々と流行して、今月は正に猖獗を極めている時期であった。而して其当時死亡率も多かった様に感ぜられた。昔から疱瘡は器量定め、麻疹は命定めといわr、これから暑気に向かって行くと特に本県では死亡率が多くなる様である。風疹、暑さに向ふてチョイチョイ流行るものにハシカとまぎわらしい風疹といふものがある。俗に「三日ハシカ」とも称へられ、方言で「台湾イリガサ」ともいわれて親御サン達をして、よくまごつかしめるものである。又大人にも罹ることがあって、よく辻町の女子連中に見うけられる場合が多い。
1943年6月 月刊『文化沖縄』第4巻第6号
病歴(六月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・27
○これから愈々南島は本格的な夏に入るのである。私の友人県の農林技師をしていた方の話によると、本県は気候と土地の関係上6,7,8の三ヶ月間はどうしても青野菜類は発育し難いとの事である。これによって此季節にはややもすると青物不足の所謂「ヴィタミンC」欠乏症とか又は野菜物に含有する「ヒスタミン」が無い為に脚気の様な胃腸障碍を見る事が多い。
1943年7月 月刊『文化沖縄』第4巻第7号
病歴(七月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・30
○盛夏・・・・・これから愈々茹る様な暑気が続いて来る。これから吾々は喝を覚えることが甚だしく、水を、特に冷水を要求する事が多くなる。これに因って自然に口からの病気が急に増えてくる。されば最初に先ず「真夏の衛生と」しての三か条を挙げて見たい。(1)蝿の駆除 (2)水特に飲料水の選択 (3)指尖の清潔
1943年8月 月刊『文化沖縄』第4巻第8号
病歴(八月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・28
○相変わらず感冒が多い炎暑の最中で而かも一番暑い月である。東京其他ではめったにこういふ事はない筈である。本県では如何なる月でも風邪は多い。一つは気候の不順なることも原因となるだろうが、今一ツは県人一般に咽頭が悪い関係もある。先天的に即ち遺伝的(素質)に咽頭が悪く且つ之を保護する含嗽といふことを等閑視している全て風邪といふものは其の名前の如く「ノド」「ハナ」から入るものだといふことを注意すれば含嗽は何よりも真っ先に実行すべき事柄である。
1943年9月 月刊『文化沖縄』第4巻第8号
病歴(九月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・30
○残暑の候より「新西ミーニシ」といふ季節風が吹く。即ち気候変わりに移るのである。気候変わりには必ず風邪は伴ふものであるが、而し只水っぱなをたらすだ丈に止る。此季節に「ユジナ」(疫)即ち鷹渡来にちなむ「タカバナシチ」が流行する。俗に鷹の小便といふてチラチラと小雨が降って来る。子供等がそれに濡れて知らず知らずに罹る「カゼ」である。
1943年10月 月刊『文化沖縄』第4巻第10号
病歴(十月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・15
○九月と殆ど同じ気候で、又同じ様な病気が引き続き多く見られる。朝夕は多少涼しくなるが相変わらず「ミヅツパナ」と「ノドカゼ」が多い、又「シブリ腹」も多い。
1943年11月 月刊『文化沖縄』第4巻第11号
病歴(十一月)・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・18
○此月から12月にかけて、生理的に実に良好なる月である。十月の末頃から十一月一ぱいと尚十二月にひいて俗に「アチハテ十月」といはれて、社会一般に閑散期である。医業も割り方隙になる時である。何しろ気候はよくなるし、人全てが食欲が増進して健康の秋は近づいてくるのである。大根は出る。菠薐草其他青野菜の出盛る月である。大抵の慢性疾患も一様に良好に趣いて自然に病者も少なくなる天高く馬肥ゆるの候である。
05/29: 麦門冬と比嘉朝健
比嘉朝健(1899年11月22日~1945年)
1899年向氏亀山、比嘉カナの間に比嘉次良(次郎)妻はカマド。朝健は父次良、母は辻の女。
1900年7月『琉球新報』「広告ー1、唐茶類 1、銅鑼かね 其他種々ー小生儀此迄諸品買入の為福州へ渡航滞在候處這般帰県右品々廉価に差上げ申候間続々御購求被成下度偏に奉希候也 茶商 比嘉次郎 那覇警察署後通西詰」
1911年1月26日 『琉球新報』「亀山朝恆儀転地療養ノ為メ実父所国頭郡金武村字漢那ニ於テ静養中薬石効ナク去ル二十日死去致シ候此段生前巳知諸君ニ謹告ス 亀山朝奉/朝矩/朝摸/比嘉次郎/朝盛」
沖縄県立第一中学校中退
「女学校の三年生のころ、私はある裕福な家の息子(比嘉朝健)と縁談が進み、卒業までにウブクイ(結納)もとりすましていた。これは松山小学校の教師時代と思うが、解消した。当の婚約者も組合教会に来ていて、私とは話も交わしたりしたが、どうもピンとこない。とっかかりもひっかかりもない感じなのだ。もうこのころ私は、恋愛をへない結婚なんてあるものかとはっきり思っていたので、自分の気持ちが動かないのに困惑した。(略)私は意を決して、二人はどうも合わないと思うので、結婚はやめた方がいいのではと、自分で婚約者に申し出た。ところが相手は母親とは生さぬ仲だったので、自分の方からはどうしても言い出せないから、君の方から直接言い戻してくれという。」金城芳子『なはをんな一代記』(沖縄タイムス社1977年9月)
1920年 沖縄タイムス記者
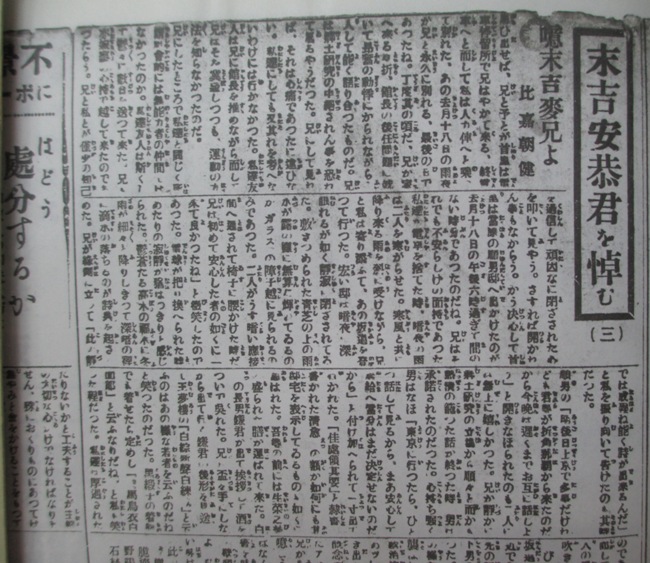
1924年12月16日『沖縄タイムス』比嘉朝健「末吉安恭君を悼む」
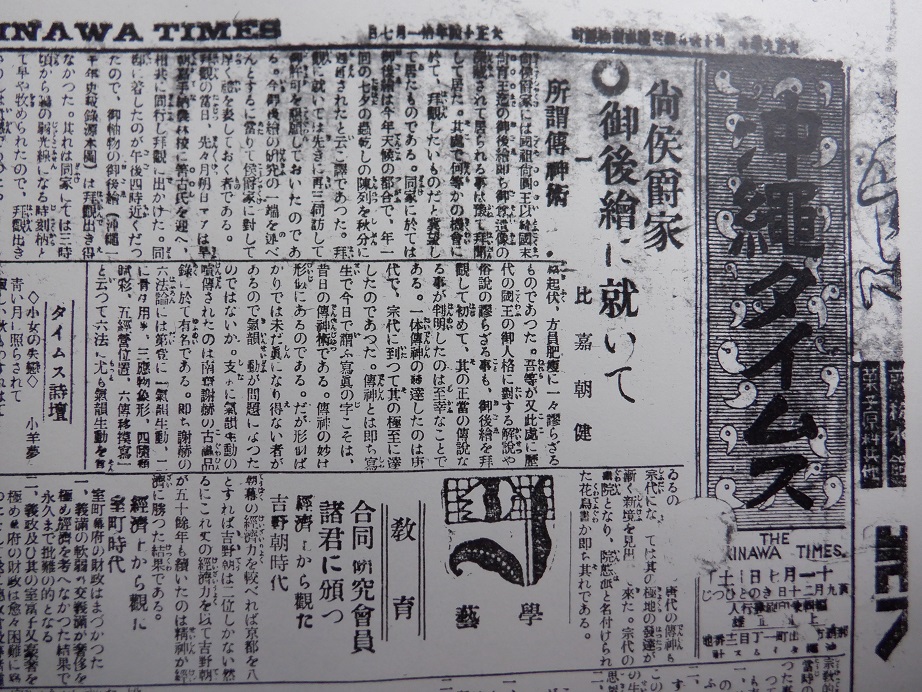
1926年3月、那覇市役所庶務課
1927年6月20日、帝国大学文学部史料編纂掛雇(~1932年1月)
□同僚に森銑三.史料編纂官ー中山久四郎(東洋諸国史料調査)
1937年3月『沖縄教育』第247号/仲吉朝宏「雲海空青録ー博物館たより」
□3月5日帰省中の比嘉朝健氏来訪、之で第2回目である。氏は多年東京に生活せられ、芸術方面の蘊蓄の深い人『陶器講座』第2巻に「琉球の陶器」を紹介せられ、嘗ては自己所有の殷元良の「墨山山水図」を帝室博物館に寄贈せられた特志の人である。今帝室博物館年報の殷元良の記事を録すると
隼者、殷元良は琉球の代表的画人であって、清朝、乾隆帝時代に活躍し、その画風は宗元画風の影響に成り、墨 画彩絵ともに能くした。本図の如きは琉球画の山水図として逸品といふべく、その趣致また日本画と一脈相通ずるも のあるは、日支間に位置する琉球の芸術として感興深きものである。
殷元良の面目躍如たりである。又氏は今迄多数の人が疑問にしていた首里城正殿前の龍柱についても、その作者が謝敷宗相なること、石材が瀬長島海岸から採掘したものなることを、已に大正10年頃に発表せられたとのこと。日支琉の古代芸術の逸品などについて語らるる豊富な話題には只目をみはるのみである。『沖縄などには逸品はありませんよ』と捨台詞のやうな言葉を残して、佐敷方面へ殷元良の先生であった山口呉師虔の子孫を訪問すべく出かけられました。
1899年向氏亀山、比嘉カナの間に比嘉次良(次郎)妻はカマド。朝健は父次良、母は辻の女。
1900年7月『琉球新報』「広告ー1、唐茶類 1、銅鑼かね 其他種々ー小生儀此迄諸品買入の為福州へ渡航滞在候處這般帰県右品々廉価に差上げ申候間続々御購求被成下度偏に奉希候也 茶商 比嘉次郎 那覇警察署後通西詰」
1911年1月26日 『琉球新報』「亀山朝恆儀転地療養ノ為メ実父所国頭郡金武村字漢那ニ於テ静養中薬石効ナク去ル二十日死去致シ候此段生前巳知諸君ニ謹告ス 亀山朝奉/朝矩/朝摸/比嘉次郎/朝盛」
沖縄県立第一中学校中退
「女学校の三年生のころ、私はある裕福な家の息子(比嘉朝健)と縁談が進み、卒業までにウブクイ(結納)もとりすましていた。これは松山小学校の教師時代と思うが、解消した。当の婚約者も組合教会に来ていて、私とは話も交わしたりしたが、どうもピンとこない。とっかかりもひっかかりもない感じなのだ。もうこのころ私は、恋愛をへない結婚なんてあるものかとはっきり思っていたので、自分の気持ちが動かないのに困惑した。(略)私は意を決して、二人はどうも合わないと思うので、結婚はやめた方がいいのではと、自分で婚約者に申し出た。ところが相手は母親とは生さぬ仲だったので、自分の方からはどうしても言い出せないから、君の方から直接言い戻してくれという。」金城芳子『なはをんな一代記』(沖縄タイムス社1977年9月)
1920年 沖縄タイムス記者
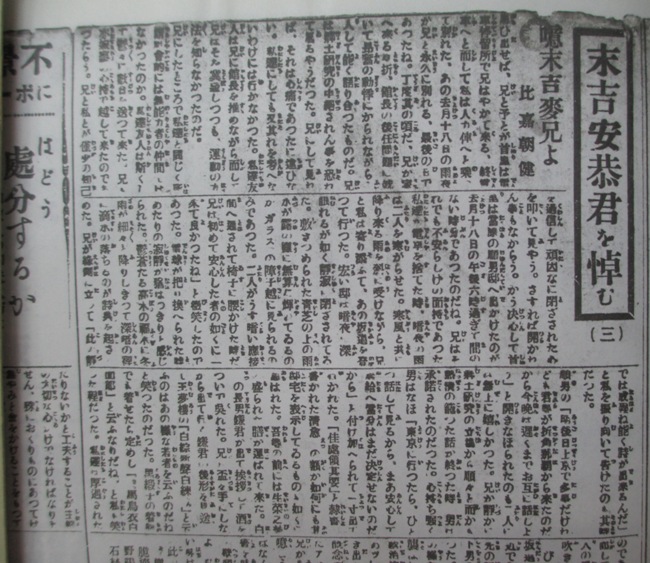
1924年12月16日『沖縄タイムス』比嘉朝健「末吉安恭君を悼む」
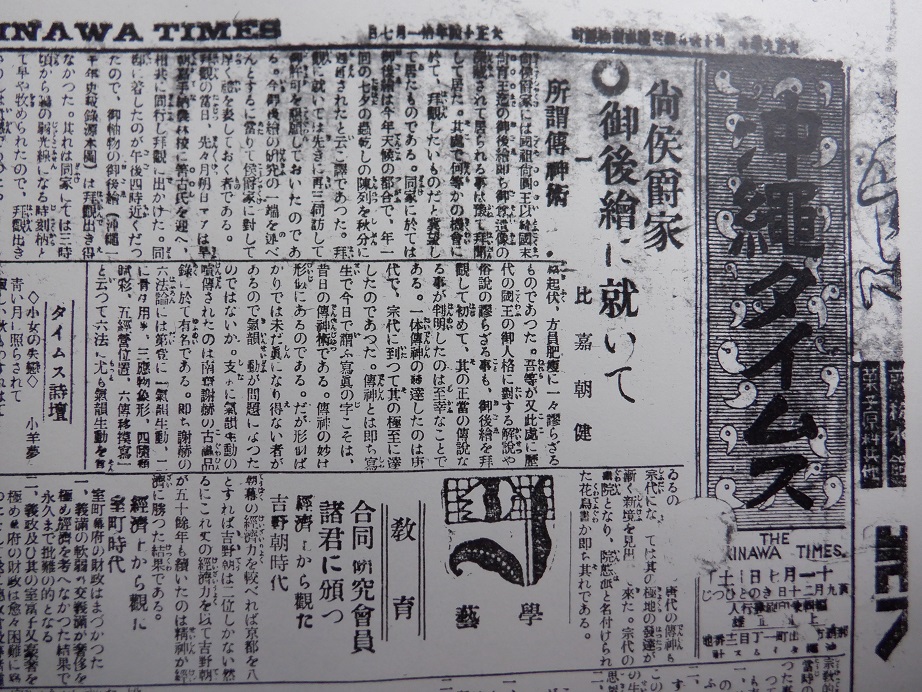
1926年3月、那覇市役所庶務課
1927年6月20日、帝国大学文学部史料編纂掛雇(~1932年1月)
□同僚に森銑三.史料編纂官ー中山久四郎(東洋諸国史料調査)
1937年3月『沖縄教育』第247号/仲吉朝宏「雲海空青録ー博物館たより」
□3月5日帰省中の比嘉朝健氏来訪、之で第2回目である。氏は多年東京に生活せられ、芸術方面の蘊蓄の深い人『陶器講座』第2巻に「琉球の陶器」を紹介せられ、嘗ては自己所有の殷元良の「墨山山水図」を帝室博物館に寄贈せられた特志の人である。今帝室博物館年報の殷元良の記事を録すると
隼者、殷元良は琉球の代表的画人であって、清朝、乾隆帝時代に活躍し、その画風は宗元画風の影響に成り、墨 画彩絵ともに能くした。本図の如きは琉球画の山水図として逸品といふべく、その趣致また日本画と一脈相通ずるも のあるは、日支間に位置する琉球の芸術として感興深きものである。
殷元良の面目躍如たりである。又氏は今迄多数の人が疑問にしていた首里城正殿前の龍柱についても、その作者が謝敷宗相なること、石材が瀬長島海岸から採掘したものなることを、已に大正10年頃に発表せられたとのこと。日支琉の古代芸術の逸品などについて語らるる豊富な話題には只目をみはるのみである。『沖縄などには逸品はありませんよ』と捨台詞のやうな言葉を残して、佐敷方面へ殷元良の先生であった山口呉師虔の子孫を訪問すべく出かけられました。
編輯発行兼印刷人・馬上太郎
月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳
表紙ー崇元寺本堂
巻頭言 ”舟楫を以て萬國の津梁と為し、異産至寶十方に充満せり云々”の雄渾無比なる快文字の銘せられたる梵鐘が、その昔掛着せられたと云ふ首里城内に此の程安置された。古の我が琉球國は、唇歯輔車の仲に在る日本、支那は固より、北は三韓より、南は遠く安南、暹羅、満刺加、爪哇蘇門答刺等の諸域を比隣の如くに往来して、その異産至寶を将来し、その諸種の文化を鍾聚することに力めた。此の雄偉勁抜なる気魄を有したればこそ、洋中の蕞爾(さいじ)たる一小王国たるに拘わらず、清新溌剌たる気分の充満し、闊達にして高雅なる趣致の横溢せる藝術乃至文化を産出することも出来たのであった。
高遠なる大東亜共栄の理想郷建設を豫示するが如き銘文の刻せられたる梵鐘が還元したるを機として、歪曲せられざりし我が民族の本来の面目に立ち帰り、皇国の新進路に向かって活溌溌地の大活動をなさねばならぬ。それに付けても吾人は、郷土史家を糾合して完全なる一大郷土史の編成を期せんことを敢えて提言し度い。従来幾多の郷土史はあれども、或物は忠実なる史料の羅列に過ぎず、或物は簡明なるが如きも粗雑に失するの嫌がある。されば衆智に依って整然たる、学問的な信憑すべき歴史を大成することは今日の急務ではなかろうか。
大舛大尉に就いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤野憲夫・・・・2
大舛大尉を偲ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・糸洲朝松・・・・3
秋夜想出せる詩歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鷺泉・・・・・・・・6
首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11
寒露漫筆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊野波石逕・・・・15
病暦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・18
新発足したる商工経済会に就て・・・・・・・・・・護得久朝章・・・・・20
勤労奉仕(○○造船所にて)・・・・・・・・・・・・・・徳田安俊・・・・・・21
佛領印度支那旅行記(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・與儀喜宣・・・・・23
梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26
無縁墓を訪ねて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐渡山安治①・・28
僕の周囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・徳村静農・・・30
四美具はる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍・・・34
伊豆味・瀬底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉國夕照・・37
編輯後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍
舟楫を萬國の津梁と為す 本来の面目に帰り 大舛大尉に続かん
1942年1月ー月刊『文化沖縄』第3巻第1号 編輯発行兼印刷人・本山豊
月刊文化沖縄社ー那覇市久米町1ノ32 東京支社ー東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局ーパラオ島コロール町 印刷所・向春商会印刷部ー那覇市通堂町2ノ1
巻頭歌「進め一億 火の玉だ!!」
戦捷の感激を生かせ!!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
佐藤惣之助①「決意」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
まこと、戦ふべき時、遂に来る/満を持して、進もう、戦をう/この光輝ある歴史のまへに/この穢れなき皇土のうへに/死すべき命のいかに幸ひなるかな/歓べよ、われら、死し徹して/今ぞ、あらゆる理念を超克し/暴戻なる米英に宣戦しつつ/血と血はたぎり、歯と歯はふるふ/この攻防に於て、究局に進んで/ただ肉を斬らして骨を斬れ/骨を劈いて隋を踏みにじれ/悠然、爆死は桜のちるが如く/笑ってみ國に殉ずることなり/死なんかな、いざ、あくまでも/われらが持場の巨弾にゆらぐまで/必勝の決意に全我の生活を緊め/敢然と進もう、戦をう/つばさは天に、戦艦は海に/見よ、鉄壁の堅陣を有す/われらその奥底の魂に位置し/その凄まじき実相をつかんで/いかなる困苦も来らば来れ/血と血をつなぎ、骨と骨を組み/激しい一億の心臓を堵して/輝く日本の新歴史を作ろう!(宣戦布告の日)
①佐藤惣之助
さとうそうのすけ
[生]1890.12.3. 川崎[没]1942.5.15. 東京
詩人。正規の学業につかず少年の頃から佐藤紅緑の門に入って俳句を学び,18~19歳頃から千家元麿,福士幸次郎らと交友。『白樺』派の影響を受けた詩集『正義の兜』 (1916) ,『狂へる歌』 (17) では人道主義的詩風を示した。→コトバンク
蔵原伸二郎②「大詔を拝し奉りて」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
大詔を拝し奉りて/雀躍勇途にのぼる/一億の草莾/みたみわれら/今ぞ/一天に雲なき/磐空を仰ぎて征かん/ああ 早くも/天涯に敵なく/七つの海に敵なきが如し/見よ わが海鷲潜艦のゆくところ/身命を祖国に捧げ/心を天に奉るもの/歴史の光栄に生きるもの/開戦劈頭たちまち/敵の慴伏を見たり/南海におどれるわれらが血よ/大海原に羽搏くわれらが魂よ/熱河熱山を征くわれらが志よ/神武天皇の向ふところ/烏合百万の敵何するものぞ/敵国よ/更に大軍を擁して来れかし/敵いよいよ多くして/同胞殉国の志いよいよ固く/われらただ/大みことのりを奉じ/最後の一人といへども/闘ひ抜かんのみ
②蔵原伸二郎 くらはら-しんじろう
1899-1965 昭和時代の詩人。
明治32年9月4日生まれ。蔵原惟人の従兄(いとこ)。萩原朔太郎の「青猫」の影響をうけて詩作をはじめ,昭和14年第1詩集「東洋の満月」を出版。16年「四季」同人。昭和40年3月16日死去。65歳。熊本県出身。慶大卒。本名は惟賢(これかた)。詩集に「乾いた道」「岩魚(いわな)」など,詩論集に「東洋の詩魂」。コトバンク
地方文化と生活文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北川鉄夫・・4
戦争手帳「戦争と通信基地」「ボルネオに日本人島」「戦略と天気象」4ー8
「布哇の邦人」「ビール罎」「屠れ!米英 われ等の敵だ!」
本県女教師に望む(上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・米國三郎・・・6
1人1語・戦争と文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田徳太郎・・・9
戦捷 笑唄話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9-10
新体制は遊女より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渡口精鴻・・・10
「この一戦 何がなんでもやり抜くぞ!!」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
島尻郡教育会修養部「教育振興座談会」於 昭和会館・・・・・・・・・・・・・・11
見たか戦果 知ったか底力 進め! 一億火の玉だ!」・・・・・・・・・・・・・・13
連載 琉球記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一・・・14
情報局で壁新聞「空襲に血走るな」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
偉大なる一人の詩人(伊東静雄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新垣淑明・・・16
豆戦艦ABCD陣「比律賓群島」「ミンダナオ島ダヴアオ」「香港」・・・・・・・・・・・16-23
「ウエーキ島」「ペナン島」「グアム島」「ミツドウエイ島」「米の航空機生産高」
ブラジル風景=サン・パウロ=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤清太郎・・・18
敵性撃滅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土岐善麿③・・・19
ルーズヴエルト一チャーチルのことにあらず世界の敵性を一挙に屠れ
ルーズヴエルトよ汝が頼みし戦艦は一瞬にして「顛覆」をせり
チャーチルよ頼みがたなきアメリカを頼みしことを国民に謝せ
世界戦争の煽動者たる「光栄」をアメリカ大統領よ墓に持ちてゆけ
忍び難きを忍びしはただ大東亜の平和のためと思ひ知るべし
③土岐善麿
歌人・国文学者。東京生。哀果と号する。早大卒。中学時代金子薫園の「白菊会」に参加し、大学時代は窪田空穂・若山牧水の影響を受けた。のち石川啄木と知り合い、二人で生活派短歌の基礎を作った功績は大きい。学士院賞受賞。文学博士。芸術院会員。昭和55年(1980)歿、94才。→コトバンク
琉球の古来工芸品(上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・沖縄県工業指導所・・・20
子供の文化を覗く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・亀谷長輝・・・・22
雷火・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・太田水<穏ママ>・・・・・24
天つちの神もおどろけ巌ゆるぐ大き憤りのおほみことのり
しのびきて今ぞ宣らすと仰せ給ふ畏こさに沁みてわれは泣かるる
電撃機雷火を吐くとみる否やとどろきをあげて艦くつがへる
ふきあがる焔のなかに蒼白の照らし出されたる顔おもひ見む
馬来半島クワンタン沖のたたかひに覆へりたるは艦ばかりは
「尽せ総力 護れよ東亜」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
戦時体制下の沖縄/1942年1月ー月刊『文化沖縄』第3巻第1号
和光同塵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本山裕児・・・26
短篇小説「馬」金城安太郎・絵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新垣庸一・・・27
祝 皇軍之大勝 祝 御武運長久 輝やかし大東亜戦勝利の朝謹壽
一億進軍の春 皇紀二千六百二年正月・・・・・月刊 文化沖縄社社員一同
大東亜戦戦果日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳
表紙ー崇元寺本堂
巻頭言 ”舟楫を以て萬國の津梁と為し、異産至寶十方に充満せり云々”の雄渾無比なる快文字の銘せられたる梵鐘が、その昔掛着せられたと云ふ首里城内に此の程安置された。古の我が琉球國は、唇歯輔車の仲に在る日本、支那は固より、北は三韓より、南は遠く安南、暹羅、満刺加、爪哇蘇門答刺等の諸域を比隣の如くに往来して、その異産至寶を将来し、その諸種の文化を鍾聚することに力めた。此の雄偉勁抜なる気魄を有したればこそ、洋中の蕞爾(さいじ)たる一小王国たるに拘わらず、清新溌剌たる気分の充満し、闊達にして高雅なる趣致の横溢せる藝術乃至文化を産出することも出来たのであった。
高遠なる大東亜共栄の理想郷建設を豫示するが如き銘文の刻せられたる梵鐘が還元したるを機として、歪曲せられざりし我が民族の本来の面目に立ち帰り、皇国の新進路に向かって活溌溌地の大活動をなさねばならぬ。それに付けても吾人は、郷土史家を糾合して完全なる一大郷土史の編成を期せんことを敢えて提言し度い。従来幾多の郷土史はあれども、或物は忠実なる史料の羅列に過ぎず、或物は簡明なるが如きも粗雑に失するの嫌がある。されば衆智に依って整然たる、学問的な信憑すべき歴史を大成することは今日の急務ではなかろうか。
大舛大尉に就いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤野憲夫・・・・2
大舛大尉を偲ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・糸洲朝松・・・・3
秋夜想出せる詩歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鷺泉・・・・・・・・6
首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11
寒露漫筆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊野波石逕・・・・15
病暦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・18
新発足したる商工経済会に就て・・・・・・・・・・護得久朝章・・・・・20
勤労奉仕(○○造船所にて)・・・・・・・・・・・・・・徳田安俊・・・・・・21
佛領印度支那旅行記(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・與儀喜宣・・・・・23
梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26
無縁墓を訪ねて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐渡山安治①・・28
僕の周囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・徳村静農・・・30
四美具はる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍・・・34
伊豆味・瀬底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉國夕照・・37
編輯後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍
舟楫を萬國の津梁と為す 本来の面目に帰り 大舛大尉に続かん
1942年1月ー月刊『文化沖縄』第3巻第1号 編輯発行兼印刷人・本山豊
月刊文化沖縄社ー那覇市久米町1ノ32 東京支社ー東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局ーパラオ島コロール町 印刷所・向春商会印刷部ー那覇市通堂町2ノ1
巻頭歌「進め一億 火の玉だ!!」
戦捷の感激を生かせ!!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
佐藤惣之助①「決意」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
まこと、戦ふべき時、遂に来る/満を持して、進もう、戦をう/この光輝ある歴史のまへに/この穢れなき皇土のうへに/死すべき命のいかに幸ひなるかな/歓べよ、われら、死し徹して/今ぞ、あらゆる理念を超克し/暴戻なる米英に宣戦しつつ/血と血はたぎり、歯と歯はふるふ/この攻防に於て、究局に進んで/ただ肉を斬らして骨を斬れ/骨を劈いて隋を踏みにじれ/悠然、爆死は桜のちるが如く/笑ってみ國に殉ずることなり/死なんかな、いざ、あくまでも/われらが持場の巨弾にゆらぐまで/必勝の決意に全我の生活を緊め/敢然と進もう、戦をう/つばさは天に、戦艦は海に/見よ、鉄壁の堅陣を有す/われらその奥底の魂に位置し/その凄まじき実相をつかんで/いかなる困苦も来らば来れ/血と血をつなぎ、骨と骨を組み/激しい一億の心臓を堵して/輝く日本の新歴史を作ろう!(宣戦布告の日)
①佐藤惣之助
さとうそうのすけ
[生]1890.12.3. 川崎[没]1942.5.15. 東京
詩人。正規の学業につかず少年の頃から佐藤紅緑の門に入って俳句を学び,18~19歳頃から千家元麿,福士幸次郎らと交友。『白樺』派の影響を受けた詩集『正義の兜』 (1916) ,『狂へる歌』 (17) では人道主義的詩風を示した。→コトバンク
蔵原伸二郎②「大詔を拝し奉りて」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
大詔を拝し奉りて/雀躍勇途にのぼる/一億の草莾/みたみわれら/今ぞ/一天に雲なき/磐空を仰ぎて征かん/ああ 早くも/天涯に敵なく/七つの海に敵なきが如し/見よ わが海鷲潜艦のゆくところ/身命を祖国に捧げ/心を天に奉るもの/歴史の光栄に生きるもの/開戦劈頭たちまち/敵の慴伏を見たり/南海におどれるわれらが血よ/大海原に羽搏くわれらが魂よ/熱河熱山を征くわれらが志よ/神武天皇の向ふところ/烏合百万の敵何するものぞ/敵国よ/更に大軍を擁して来れかし/敵いよいよ多くして/同胞殉国の志いよいよ固く/われらただ/大みことのりを奉じ/最後の一人といへども/闘ひ抜かんのみ
②蔵原伸二郎 くらはら-しんじろう
1899-1965 昭和時代の詩人。
明治32年9月4日生まれ。蔵原惟人の従兄(いとこ)。萩原朔太郎の「青猫」の影響をうけて詩作をはじめ,昭和14年第1詩集「東洋の満月」を出版。16年「四季」同人。昭和40年3月16日死去。65歳。熊本県出身。慶大卒。本名は惟賢(これかた)。詩集に「乾いた道」「岩魚(いわな)」など,詩論集に「東洋の詩魂」。コトバンク
地方文化と生活文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北川鉄夫・・4
戦争手帳「戦争と通信基地」「ボルネオに日本人島」「戦略と天気象」4ー8
「布哇の邦人」「ビール罎」「屠れ!米英 われ等の敵だ!」
本県女教師に望む(上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・米國三郎・・・6
1人1語・戦争と文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田徳太郎・・・9
戦捷 笑唄話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9-10
新体制は遊女より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渡口精鴻・・・10
「この一戦 何がなんでもやり抜くぞ!!」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
島尻郡教育会修養部「教育振興座談会」於 昭和会館・・・・・・・・・・・・・・11
見たか戦果 知ったか底力 進め! 一億火の玉だ!」・・・・・・・・・・・・・・13
連載 琉球記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一・・・14
情報局で壁新聞「空襲に血走るな」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
偉大なる一人の詩人(伊東静雄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新垣淑明・・・16
豆戦艦ABCD陣「比律賓群島」「ミンダナオ島ダヴアオ」「香港」・・・・・・・・・・・16-23
「ウエーキ島」「ペナン島」「グアム島」「ミツドウエイ島」「米の航空機生産高」
ブラジル風景=サン・パウロ=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤清太郎・・・18
敵性撃滅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土岐善麿③・・・19
ルーズヴエルト一チャーチルのことにあらず世界の敵性を一挙に屠れ
ルーズヴエルトよ汝が頼みし戦艦は一瞬にして「顛覆」をせり
チャーチルよ頼みがたなきアメリカを頼みしことを国民に謝せ
世界戦争の煽動者たる「光栄」をアメリカ大統領よ墓に持ちてゆけ
忍び難きを忍びしはただ大東亜の平和のためと思ひ知るべし
③土岐善麿
歌人・国文学者。東京生。哀果と号する。早大卒。中学時代金子薫園の「白菊会」に参加し、大学時代は窪田空穂・若山牧水の影響を受けた。のち石川啄木と知り合い、二人で生活派短歌の基礎を作った功績は大きい。学士院賞受賞。文学博士。芸術院会員。昭和55年(1980)歿、94才。→コトバンク
琉球の古来工芸品(上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・沖縄県工業指導所・・・20
子供の文化を覗く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・亀谷長輝・・・・22
雷火・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・太田水<穏ママ>・・・・・24
天つちの神もおどろけ巌ゆるぐ大き憤りのおほみことのり
しのびきて今ぞ宣らすと仰せ給ふ畏こさに沁みてわれは泣かるる
電撃機雷火を吐くとみる否やとどろきをあげて艦くつがへる
ふきあがる焔のなかに蒼白の照らし出されたる顔おもひ見む
馬来半島クワンタン沖のたたかひに覆へりたるは艦ばかりは
「尽せ総力 護れよ東亜」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
戦時体制下の沖縄/1942年1月ー月刊『文化沖縄』第3巻第1号
和光同塵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本山裕児・・・26
短篇小説「馬」金城安太郎・絵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新垣庸一・・・27
祝 皇軍之大勝 祝 御武運長久 輝やかし大東亜戦勝利の朝謹壽
一億進軍の春 皇紀二千六百二年正月・・・・・月刊 文化沖縄社社員一同
大東亜戦戦果日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
編輯発行兼印刷人・馬上太郎
月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳
首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11
○国難が愈々具体化し、学徒出陣の強い羽搏ちは洵に歴史的壮観であり、全国民の覚悟を新たにした。此の時、此の島に於いて由緒深い首里城正殿の巨鐘を元の御城に迎へ郷土博物館に安置することが出来たのは戦勝の前兆であり、大東亜共存共栄圏建設の暗示であらねばならない。
荒井警察部長が仲吉市長と鐘銘に三嘆したと云ふ晩、偶々或る会場で一緒になり、部長は余程感激したと見へ重ねて大鐘の由来を諮かれたから、親泊政博君と二人で交々その経緯までもお話し、尚ほ国民精神の昂揚に資すべく眞教寺から首里城内に還元するやう御尽力を願ったところ、数日の後親泊壮年団長の案内で実物実見に及び一入感銘を深くし、早速非公式に交渉したら、田原住職を始め信徒総代も快諾された。(略)東恩納先生が喜ぶであらう。源一郎君が生きて居たらと全発君等と話し合って法悦に浸た。回顧すれば昭和8年東恩納教授は英独佛に調査研究を命じられたが、希望して支那及び南洋諸国に変更されたことは一大見識であらねばならない。その鹿島立に際し「私は之から祖先の偉大なる魄を迎へにまなんばんへ参ります」と郷土の人々にメッセーヂーを送られた、其の偉大なる魂は此の鐘銘にも躍動している。
追記 伊江男と東恩納教授から左記の如き祝辞と感謝の御芳書を戴いた。
鐘を無事に元の御城に美御迎へしたことは近来の大快亊ですから尽力せられし各位に衷心より感謝と敬意を表します。(伊江朝助)
豫々念願の大鐘漸く旧棲に戻り候趣落花流水其根源に帰し候段本懐至極偏に御尽力の責と感謝に不耐第一回の御書面は17日落手その為に祝意間に不合遺憾に存居候何卒諸君へもよろしく御伝声被下度願上候(東恩納寛惇)
梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26
月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳
首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11
○国難が愈々具体化し、学徒出陣の強い羽搏ちは洵に歴史的壮観であり、全国民の覚悟を新たにした。此の時、此の島に於いて由緒深い首里城正殿の巨鐘を元の御城に迎へ郷土博物館に安置することが出来たのは戦勝の前兆であり、大東亜共存共栄圏建設の暗示であらねばならない。
荒井警察部長が仲吉市長と鐘銘に三嘆したと云ふ晩、偶々或る会場で一緒になり、部長は余程感激したと見へ重ねて大鐘の由来を諮かれたから、親泊政博君と二人で交々その経緯までもお話し、尚ほ国民精神の昂揚に資すべく眞教寺から首里城内に還元するやう御尽力を願ったところ、数日の後親泊壮年団長の案内で実物実見に及び一入感銘を深くし、早速非公式に交渉したら、田原住職を始め信徒総代も快諾された。(略)東恩納先生が喜ぶであらう。源一郎君が生きて居たらと全発君等と話し合って法悦に浸た。回顧すれば昭和8年東恩納教授は英独佛に調査研究を命じられたが、希望して支那及び南洋諸国に変更されたことは一大見識であらねばならない。その鹿島立に際し「私は之から祖先の偉大なる魄を迎へにまなんばんへ参ります」と郷土の人々にメッセーヂーを送られた、其の偉大なる魂は此の鐘銘にも躍動している。
追記 伊江男と東恩納教授から左記の如き祝辞と感謝の御芳書を戴いた。
鐘を無事に元の御城に美御迎へしたことは近来の大快亊ですから尽力せられし各位に衷心より感謝と敬意を表します。(伊江朝助)
豫々念願の大鐘漸く旧棲に戻り候趣落花流水其根源に帰し候段本懐至極偏に御尽力の責と感謝に不耐第一回の御書面は17日落手その為に祝意間に不合遺憾に存居候何卒諸君へもよろしく御伝声被下度願上候(東恩納寛惇)
梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26
08/07: 末吉安恭「末吉麦門冬句集」
1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。
1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」
1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」
1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」
1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」
1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」
1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」
1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」
1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」
1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」
1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」
1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」
1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」
1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」
1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」
1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」
1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」
1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」
1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」
1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」
1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」
1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」
1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」
1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」
1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」
1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」
1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」
1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」
1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」
1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」
1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」
1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」
1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」
1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」
1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」
1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」
1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」
1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」
1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」
1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」
1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」
1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」
1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」
1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」
1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」
1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」
1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」
1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」
1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」
06/22: 観光/1895年2月ー奥島 憲順『袖珍沖縄旅行案内 全』
松籟生「序文」□冊子甚だ小にして記する所実に簡なりと雖も以て沖縄旅行の栞とするに余りあり 沖縄は無数の島嶼より成ると雖も其面積より云へば漸く薩摩湾を埋むるに過ぎず其人口より云へば帝国の総人口の百分の一に過ぎず然れども日本帝国が全世界に向かって其勢力を澎漲しつつあるの今日に於いて東洋南部に向かって其先鋒の任に当たる者は我沖縄なり殊に沖縄の問題が目を追うて内地政界の議に上り有志の士足をこの地に入れんとする者多きを加るの今日に於いて奥島子のこの著あるは決して徒労にあらざるなり否其効決して尠なからざるなり
元来沖縄に来る者其地形産物より寧ろ重に歴史に注目するは余が往々事実に於いて見る所なりこの著歴史の概要を記せざるは余が遺憾とする所なり故に余は歴史としては中山世鑑、球陽、世譜、王代記、南島記事、沖縄誌、歴史材料の雑書としては遺老傳、羽地按司仕置、具志頭親方独物語、林政八書、其他教育上の雑書としては「御教条」文学としては平敷屋朝敏の「苔の下」「若草物語」「貧家記」宜湾朝保の歌集等あることを旅行者に紹介し以て聊か本著の遺漏を補うと云爾
目次 地勢/行政区画/県庁より各蕃所に至る里程/警察区画/租税/租税納期/郵便逓送差立到着時間表/学校/病院及医館/船舶改所並船舶/諸会社銀行/公会堂/都邑/汽船賃/物産/輸出入品/明治二十七年中汽船発着表
名区勝地並に県庁よりの里程-波の上 那覇市街の内に在り官幣小社あり眺望絶佳なり(十丁余)、御物見城 那覇江中に在り那覇臺又吾妻館と称し山水兼備那覇の勝を双眸に集む(四丁余)、奥武山 那覇江中御物見城の後に在り所謂蓬莱山の在る処最散歩に宜し、淵佐 那覇市端に在り(十丁余)、大嶺村 海辺廣濶の遊歩場小禄間切に在り(一里余)、崇元寺 泊村に在り舜天王以来の廟所なり(廿一丁余)、首里城 一里一丁余、社壇 西原間切末吉村に在り眺望廣濶なり(一里七丁余)、識名 真和志間切に在り尚家の別荘にして邸内頗る風景に富む(一里十丁)、瓣の嶽 西原間切に在り(一里二丁余)、普天間 宜野湾間切に在り奇岩怪石を以て疊みたる洞窟なり(三里廿三丁余),浦添茶園 浦添間切に在り尚家の別業にして尤幽邃なり(二里二丁余)、中城城址 中城間切に在り古忠臣護佐丸の居城せし跡にて眺望殊に佳絶なり(四里廿二丁余)、護佐丸墓 中城城下に在り(仝)、与那原港 大里間切に在り津堅久高を眼下に見下ろし風色甚美なり(一里卅丁余)、糸満漁場 兼城間切に在り本県第一の漁場にして人戸稠密村落の第一位を占む(二里廿六丁余)、南山古城 高嶺間切に在り古南山王の住せし処(三里卅三丁余)、運天港 今帰仁間切に在り源為朝公の始めて飃着せし処にて海深く大船を泊すべし(廿二里十丁余)、轟の瀧 名護間切数久田村に在り本島第一の瀑布なり(十七里六丁余)、許田の手水 有名なる井水なり(十五里 )、百按司墓 今帰仁間切に在り古へ戦乱を避けて死したる貴人等を合葬せし処なり(廿二里九丁余)、万座毛 恩納間切に在り曠原にして万人を座せしむべし(十一里廿二丁余)
神社仏閣-神社・波上宮官幣小社(那覇若狭町村)、識名宮(真和志間切識名村)、普天間宮(宜野湾間切普天間村)。仏閣・円覚寺(首里當蔵村)、天界寺(同金城村)、天王寺(同當蔵村)、観音堂(同山川村)、崇元寺(那覇泊村)、龍福寺(浦添間切浦添村)、以上禅宗なり。護国寺(那覇若狭町村)、臨海寺(同西村)、遍照寺(西原間切末吉村)、以上真言宗なり。眞教寺(那覇西村)眞宗なり。
旅店遊廓及び割烹店ー遊廓・辻を第一とし中島渡地之れに次ぐ辻にて有名なるものは荒神の前大福渡名喜伊保柳香々小新屋染屋小等とし又内地藝妓を養ひ宴会の席に侍せしむる所を通堂とし辻中島渡地を通じて貸座敷六百卅一戸娼妓一千四百四十二人藝妓辻九人中島四人又通堂の貸席兼割烹店は東屋藝妓廿一人を有し常盤仝九人小徳仝十人海月三人券番三人合計四十六人。貸席・最高尚にして眺望絶佳なるものを吾妻館とし域内に西洋料理蓬莱温泉あり座敷最廣きを常盤新席とす。割烹店・席貸を兼ぬるものは東屋分店とし其の他三國屋京亀玉川屋いろは等あり。
演劇場ー本演芸場中毛演芸場壬辰座及び首里演芸場等なり開場は毎日午后二時より六時迄夜は六時半より十二時迄木戸銭は晝四銭夜三銭場代とてはなし。
旅宿ー那覇の池畑回漕店浅田山川森田を最上として嘉手納前兼久名護等あり。
広告ー吾妻館主塚本平吉「景色無双吾妻館」「那覇通堂・東家本店」「那覇東村警察署前・東家分店」/那覇東村・林支舗「沖縄名産漆器類監獄署製 味噌醤油其他種々 肥後米 薩摩米 唐白米 卸小売商」/小嶺漆工場主「琉球漆器改良広告」/那覇東村上の倉・岩満写真場「写真ー琉球絶景の眞趣を穿つは写真なり弊店写真中優等なる者は首里城、中城殿、師範学校、崇元寺、波の上、墓所、辻遊廓、市場、通堂浜、那覇市街、吾妻館、奥武山、港口、三重城中島海岸、蓬莱山なり琉球の眞景を知り度き人は続々御注文を乞う」/那覇港・池畑回漕店/那覇港西村五十二番地・浅田五三郎「御旅館」/那覇西村百七十番地・三國屋「御料理いろいろ鰻は最も御好評を辱ふす」琉球新報社「沖縄の事情を詳かにせんと欲せば先ず琉球新報を読め 琉球新報は沖縄唯一の新聞紙なり」/那覇通堂・常盤楼/京都三条小橋西入・萬屋甚兵衛「沖縄県庁御用宿」/那覇西村四百六十番地・山川新五郎「御旅館」/那覇大門通・柳屋「諸印章彫刻 和洋小間物販売店」
元来沖縄に来る者其地形産物より寧ろ重に歴史に注目するは余が往々事実に於いて見る所なりこの著歴史の概要を記せざるは余が遺憾とする所なり故に余は歴史としては中山世鑑、球陽、世譜、王代記、南島記事、沖縄誌、歴史材料の雑書としては遺老傳、羽地按司仕置、具志頭親方独物語、林政八書、其他教育上の雑書としては「御教条」文学としては平敷屋朝敏の「苔の下」「若草物語」「貧家記」宜湾朝保の歌集等あることを旅行者に紹介し以て聊か本著の遺漏を補うと云爾
目次 地勢/行政区画/県庁より各蕃所に至る里程/警察区画/租税/租税納期/郵便逓送差立到着時間表/学校/病院及医館/船舶改所並船舶/諸会社銀行/公会堂/都邑/汽船賃/物産/輸出入品/明治二十七年中汽船発着表
名区勝地並に県庁よりの里程-波の上 那覇市街の内に在り官幣小社あり眺望絶佳なり(十丁余)、御物見城 那覇江中に在り那覇臺又吾妻館と称し山水兼備那覇の勝を双眸に集む(四丁余)、奥武山 那覇江中御物見城の後に在り所謂蓬莱山の在る処最散歩に宜し、淵佐 那覇市端に在り(十丁余)、大嶺村 海辺廣濶の遊歩場小禄間切に在り(一里余)、崇元寺 泊村に在り舜天王以来の廟所なり(廿一丁余)、首里城 一里一丁余、社壇 西原間切末吉村に在り眺望廣濶なり(一里七丁余)、識名 真和志間切に在り尚家の別荘にして邸内頗る風景に富む(一里十丁)、瓣の嶽 西原間切に在り(一里二丁余)、普天間 宜野湾間切に在り奇岩怪石を以て疊みたる洞窟なり(三里廿三丁余),浦添茶園 浦添間切に在り尚家の別業にして尤幽邃なり(二里二丁余)、中城城址 中城間切に在り古忠臣護佐丸の居城せし跡にて眺望殊に佳絶なり(四里廿二丁余)、護佐丸墓 中城城下に在り(仝)、与那原港 大里間切に在り津堅久高を眼下に見下ろし風色甚美なり(一里卅丁余)、糸満漁場 兼城間切に在り本県第一の漁場にして人戸稠密村落の第一位を占む(二里廿六丁余)、南山古城 高嶺間切に在り古南山王の住せし処(三里卅三丁余)、運天港 今帰仁間切に在り源為朝公の始めて飃着せし処にて海深く大船を泊すべし(廿二里十丁余)、轟の瀧 名護間切数久田村に在り本島第一の瀑布なり(十七里六丁余)、許田の手水 有名なる井水なり(十五里 )、百按司墓 今帰仁間切に在り古へ戦乱を避けて死したる貴人等を合葬せし処なり(廿二里九丁余)、万座毛 恩納間切に在り曠原にして万人を座せしむべし(十一里廿二丁余)
神社仏閣-神社・波上宮官幣小社(那覇若狭町村)、識名宮(真和志間切識名村)、普天間宮(宜野湾間切普天間村)。仏閣・円覚寺(首里當蔵村)、天界寺(同金城村)、天王寺(同當蔵村)、観音堂(同山川村)、崇元寺(那覇泊村)、龍福寺(浦添間切浦添村)、以上禅宗なり。護国寺(那覇若狭町村)、臨海寺(同西村)、遍照寺(西原間切末吉村)、以上真言宗なり。眞教寺(那覇西村)眞宗なり。
旅店遊廓及び割烹店ー遊廓・辻を第一とし中島渡地之れに次ぐ辻にて有名なるものは荒神の前大福渡名喜伊保柳香々小新屋染屋小等とし又内地藝妓を養ひ宴会の席に侍せしむる所を通堂とし辻中島渡地を通じて貸座敷六百卅一戸娼妓一千四百四十二人藝妓辻九人中島四人又通堂の貸席兼割烹店は東屋藝妓廿一人を有し常盤仝九人小徳仝十人海月三人券番三人合計四十六人。貸席・最高尚にして眺望絶佳なるものを吾妻館とし域内に西洋料理蓬莱温泉あり座敷最廣きを常盤新席とす。割烹店・席貸を兼ぬるものは東屋分店とし其の他三國屋京亀玉川屋いろは等あり。
演劇場ー本演芸場中毛演芸場壬辰座及び首里演芸場等なり開場は毎日午后二時より六時迄夜は六時半より十二時迄木戸銭は晝四銭夜三銭場代とてはなし。
旅宿ー那覇の池畑回漕店浅田山川森田を最上として嘉手納前兼久名護等あり。
広告ー吾妻館主塚本平吉「景色無双吾妻館」「那覇通堂・東家本店」「那覇東村警察署前・東家分店」/那覇東村・林支舗「沖縄名産漆器類監獄署製 味噌醤油其他種々 肥後米 薩摩米 唐白米 卸小売商」/小嶺漆工場主「琉球漆器改良広告」/那覇東村上の倉・岩満写真場「写真ー琉球絶景の眞趣を穿つは写真なり弊店写真中優等なる者は首里城、中城殿、師範学校、崇元寺、波の上、墓所、辻遊廓、市場、通堂浜、那覇市街、吾妻館、奥武山、港口、三重城中島海岸、蓬莱山なり琉球の眞景を知り度き人は続々御注文を乞う」/那覇港・池畑回漕店/那覇港西村五十二番地・浅田五三郎「御旅館」/那覇西村百七十番地・三國屋「御料理いろいろ鰻は最も御好評を辱ふす」琉球新報社「沖縄の事情を詳かにせんと欲せば先ず琉球新報を読め 琉球新報は沖縄唯一の新聞紙なり」/那覇通堂・常盤楼/京都三条小橋西入・萬屋甚兵衛「沖縄県庁御用宿」/那覇西村四百六十番地・山川新五郎「御旅館」/那覇大門通・柳屋「諸印章彫刻 和洋小間物販売店」
10/03: 新城栄徳「琉球人物誌⑩那覇っ子 石川正通」
石川正通は1897年9月25日ー沖縄県那覇区下泉町にて父正芳・母ツルの二男一女の長男として出生。 1905年、那覇区立甲辰尋常小学校入学。5年生頃よりメソジスト教会牧師H・B・シュワルツ師に英語を学ぶ。この時の小学校の恩師で薫陶を受けたのが佐久本嗣宗。甲辰小学校を初の六年制で卒業。嘉手納時代の沖縄県立第二中学校に入学、通学不便で沖縄県立第一中学校へ入学したのが1911年。当時メソジスト教会牧師のH・B・シュワルツに英語を学んでいた正通は、すでに中学の先生の水準を抜いていた。在学中の1914年に一中代表として英語演説。南方熊楠は、山口沢之助校長と同郷和歌山県の大先輩、奇行に富む世界的大学者。山口校長が折に触れて話した、南方熊楠の逸話は一冊の本にも纏め得るほど、あざやかに正通は覚えている。山口校長の講義は、正通にとっては生理学でなく、熊楠学であった。脱線学の妙味ここにあり、という。
1916年、一中退学し、私立麻布中学校へ転校。傍ら、正則英語学校文学科教室で斎藤秀三郎校長に英語を学ぶ。いつも最前列に陣取り、全身を耳にして講義を聴いていた。ある講義のとき、斉藤先生の誤りを指摘「違います」、再三指摘すると校長室に呼ばれた。斉藤先生「君、あしたからこの学校の先生になれ」の鶴の一声で正則英語学校講師となる。1918年、国民英学会講師、逗子開成中学校講師(ここでの教え子に、平野威馬雄、岡田時彦・女優茉莉子の父、徳山環ー歌手)。
1919年、保善商業学校講師(国語担当)、明治学院専門部講師(現明治学院大学)。1922年、第三版『全訳・シャーロックホームズ』越山堂。文部省中等教員英語科検定試験合格。1923年、8月ー沖縄県立第二中学校講堂で石川正通「英語講座」、伊佐三郎、赤嶺康成ら参加。1924年、東北帝国大学法文学部文学科入学。在学中、土井晩翠の寵愛を受けた。
1922年5月に正通は饒平名智太郎の依頼で鹿子木員信・饒平名智太郎『ガンヂと真理の把握』改造社の英訳も手伝った。
後年、土井晩翠の荒城の月を引いて、正通は漫筆「大阪礼讃 工場の月」の中で、月ヤ昔カラ変ル事無サミ 変テ行ク物ヤ人ヌ心 月には故郷があり、故郷には月がある。十海ヤ距ミテン照ル月ヤ一チ アリン眺ミユラ今日ヌ月ヤ 十海でも渡海でもよい。月で心を清め、心で故郷を浄めよう。「太陽と月と、どちらが必要だ」「勿論、月だ。太陽は明るい昼間に照る。月は暗い夜を照らす」斯ういう二人のウスノロの問答にも捨て難い味がある。通堂港頭で交す「儲キテ来ーヨー」という激励の挨拶に全沖縄の運命は宿り、全沖縄人の希望は繋がる。私は世界語の中にこれほど力強さと哀調とのいみじく融け合った言葉を知らない。故郷への送金額第一位の王座を占める関西五万の沖縄ン人御スーヨー、高らかに歌いましょう。 春工場の鼻の煙/廻る機械に油注して/那覇の港を船出し/ウルマの光今此処に(1939年8月)。
1928年、東北帝国大学法文学部国文科卒業。卒論「近松門左衛門の世話浄瑠璃について」。国民英学会講師に復職、京華高等学校教諭、日本女子高等学院英文学科教授。1929年、雑誌『イギリス文学』に「ヘルンの『沙翁論』」。1933年、『南島』1月1日の消息欄に石川正通氏ー伊波普猷先生と共力で近く日英両文の沖縄案内を発刊する由」。1934年の『南島』8月の漫筆に「友の首途を祝して故郷を語る=武元朝朗・國吉休微両君を叱咤する=(略)最近出た某書店の百科辞典を引いて見たが、おもろ、蔡温、程順則、尚泰侯爵も出て居ない。沢田正二郎、田健次郎等は写真まで出て居る。土田杏村が第二の万葉集と言った『おもろ』も国語国文学校の士すら全般的に知られて居ない」と記す。
1934年4月15日『琉球新報』に山城正忠「旅塵抄」の連載がある。その16回に「東京も琉球」と題し、東京の石川正通の自宅を訪ねたときのことが書かれている。
山城です。と名乗りを上げると、矢庭に襖が放いて、見知り越しの奥さんが顔を見せる。 上がれといふので、遠慮無しにあがった。小ざっぱりとした、八畳の間である。(略)額が二面、襖の上にかかっている。ひとつは、英文で斎藤秀三郎先生の毛筆揮毫だとすぐ判った。勿論、私にそれが読める筈もないが、かねて此家の主人から、その事をきいて居たからである。今ひとつは、巻紙に書いた手紙を表装したもので、おしまひの処に、短歌が一首、書かれて有ったやうに覚えて居る。能くこなされた筆づかひで、酒悦な風格を偲ばせる迫力があった。何人の心憎い業であらうかと、態々立上ってみると「晩翠」といふ署名が鮮やかに、私の網膜に映った。それと同時に、これが、その昔、有名な「天地有情」によって、一代の詩名を謳はれた、土井先生の筆蹟だといふ事を知ったので、一しほ、懐かしく仰がれた。(略)こんな閑寂な処にいて、常住心を落ちつけていたら、きっとそのうちには、自然の脈搏が聴かれるだらう。そしたら、思ふ存分に、自分の貧しい想も練られて行くにちがいない。などと、空想してる所へ「ハイサイ。イチメンソウチャガ」と、例の開けっ放しな聲で、斯う云ひ乍らはいって来たのは、紛れもない、あるじの石川正通君であった。正忠は触れていないが庭には空手家の本部サールーが建てた巻藁もあった。
1944年、戦時中の英語教育政策により京華高等学校退職。東洋大学講師、本海上火災保険に入社(外国課勤務)、同年1月の月刊『文化沖縄』第五巻第一号に石川正通は「産後銃後」と題して母の思い出を書いている。
「(略)母は私達の生まれる前から、春風秋雨、夏冬の分ちなく、渡地中島辻と那覇三村の街々を素足で頭の上には重い石油と更に重い一家族の生命を載せてその石油を行商しながら良人と我々3人の兄弟妹を何不自由なく育てて下さったー自分は多くの不自由を忍びつつ。地球上の如何なる名花、如何なる香料の香よりも私は石油の香が好きだ。私は死ぬ時は石油の香を嗅ぎつつ死に度い。母の背中に負われて嗅いだあの石油、幼年時代の全ての思ひ出を秘めているあの石油の香を。那覇の電燈は伝統的に暗い。私の母が石油を売っていた時代の那覇の夜は今の那覇の夜よりも、断然明るかったに違ひない。私は自分の母ながら、母を那覇を明るくした恩人の一人に数へさせて戴き度い。その母の為にも尊い石油を空費する米英の巨頭一味は憎むべき敵だ。親の仇を討つ日本精神の強烈さに於いて私は敢て曾我兄弟に譲らない。米英の戦争挑発さへ無かったらば石油は人類殺戮の為に悪用されず、人類の福祉向上の為に善用されたであらう」。戦後、正通は親しい友人・横内圓次に母を偲んで詠んだ歌「果てし日も 骨さえ分かぬ命かも 母親返えせ 昭和天皇」を披露している。
1916年、一中退学し、私立麻布中学校へ転校。傍ら、正則英語学校文学科教室で斎藤秀三郎校長に英語を学ぶ。いつも最前列に陣取り、全身を耳にして講義を聴いていた。ある講義のとき、斉藤先生の誤りを指摘「違います」、再三指摘すると校長室に呼ばれた。斉藤先生「君、あしたからこの学校の先生になれ」の鶴の一声で正則英語学校講師となる。1918年、国民英学会講師、逗子開成中学校講師(ここでの教え子に、平野威馬雄、岡田時彦・女優茉莉子の父、徳山環ー歌手)。
1919年、保善商業学校講師(国語担当)、明治学院専門部講師(現明治学院大学)。1922年、第三版『全訳・シャーロックホームズ』越山堂。文部省中等教員英語科検定試験合格。1923年、8月ー沖縄県立第二中学校講堂で石川正通「英語講座」、伊佐三郎、赤嶺康成ら参加。1924年、東北帝国大学法文学部文学科入学。在学中、土井晩翠の寵愛を受けた。
1922年5月に正通は饒平名智太郎の依頼で鹿子木員信・饒平名智太郎『ガンヂと真理の把握』改造社の英訳も手伝った。
後年、土井晩翠の荒城の月を引いて、正通は漫筆「大阪礼讃 工場の月」の中で、月ヤ昔カラ変ル事無サミ 変テ行ク物ヤ人ヌ心 月には故郷があり、故郷には月がある。十海ヤ距ミテン照ル月ヤ一チ アリン眺ミユラ今日ヌ月ヤ 十海でも渡海でもよい。月で心を清め、心で故郷を浄めよう。「太陽と月と、どちらが必要だ」「勿論、月だ。太陽は明るい昼間に照る。月は暗い夜を照らす」斯ういう二人のウスノロの問答にも捨て難い味がある。通堂港頭で交す「儲キテ来ーヨー」という激励の挨拶に全沖縄の運命は宿り、全沖縄人の希望は繋がる。私は世界語の中にこれほど力強さと哀調とのいみじく融け合った言葉を知らない。故郷への送金額第一位の王座を占める関西五万の沖縄ン人御スーヨー、高らかに歌いましょう。 春工場の鼻の煙/廻る機械に油注して/那覇の港を船出し/ウルマの光今此処に(1939年8月)。
1928年、東北帝国大学法文学部国文科卒業。卒論「近松門左衛門の世話浄瑠璃について」。国民英学会講師に復職、京華高等学校教諭、日本女子高等学院英文学科教授。1929年、雑誌『イギリス文学』に「ヘルンの『沙翁論』」。1933年、『南島』1月1日の消息欄に石川正通氏ー伊波普猷先生と共力で近く日英両文の沖縄案内を発刊する由」。1934年の『南島』8月の漫筆に「友の首途を祝して故郷を語る=武元朝朗・國吉休微両君を叱咤する=(略)最近出た某書店の百科辞典を引いて見たが、おもろ、蔡温、程順則、尚泰侯爵も出て居ない。沢田正二郎、田健次郎等は写真まで出て居る。土田杏村が第二の万葉集と言った『おもろ』も国語国文学校の士すら全般的に知られて居ない」と記す。
1934年4月15日『琉球新報』に山城正忠「旅塵抄」の連載がある。その16回に「東京も琉球」と題し、東京の石川正通の自宅を訪ねたときのことが書かれている。
山城です。と名乗りを上げると、矢庭に襖が放いて、見知り越しの奥さんが顔を見せる。 上がれといふので、遠慮無しにあがった。小ざっぱりとした、八畳の間である。(略)額が二面、襖の上にかかっている。ひとつは、英文で斎藤秀三郎先生の毛筆揮毫だとすぐ判った。勿論、私にそれが読める筈もないが、かねて此家の主人から、その事をきいて居たからである。今ひとつは、巻紙に書いた手紙を表装したもので、おしまひの処に、短歌が一首、書かれて有ったやうに覚えて居る。能くこなされた筆づかひで、酒悦な風格を偲ばせる迫力があった。何人の心憎い業であらうかと、態々立上ってみると「晩翠」といふ署名が鮮やかに、私の網膜に映った。それと同時に、これが、その昔、有名な「天地有情」によって、一代の詩名を謳はれた、土井先生の筆蹟だといふ事を知ったので、一しほ、懐かしく仰がれた。(略)こんな閑寂な処にいて、常住心を落ちつけていたら、きっとそのうちには、自然の脈搏が聴かれるだらう。そしたら、思ふ存分に、自分の貧しい想も練られて行くにちがいない。などと、空想してる所へ「ハイサイ。イチメンソウチャガ」と、例の開けっ放しな聲で、斯う云ひ乍らはいって来たのは、紛れもない、あるじの石川正通君であった。正忠は触れていないが庭には空手家の本部サールーが建てた巻藁もあった。
1944年、戦時中の英語教育政策により京華高等学校退職。東洋大学講師、本海上火災保険に入社(外国課勤務)、同年1月の月刊『文化沖縄』第五巻第一号に石川正通は「産後銃後」と題して母の思い出を書いている。
「(略)母は私達の生まれる前から、春風秋雨、夏冬の分ちなく、渡地中島辻と那覇三村の街々を素足で頭の上には重い石油と更に重い一家族の生命を載せてその石油を行商しながら良人と我々3人の兄弟妹を何不自由なく育てて下さったー自分は多くの不自由を忍びつつ。地球上の如何なる名花、如何なる香料の香よりも私は石油の香が好きだ。私は死ぬ時は石油の香を嗅ぎつつ死に度い。母の背中に負われて嗅いだあの石油、幼年時代の全ての思ひ出を秘めているあの石油の香を。那覇の電燈は伝統的に暗い。私の母が石油を売っていた時代の那覇の夜は今の那覇の夜よりも、断然明るかったに違ひない。私は自分の母ながら、母を那覇を明るくした恩人の一人に数へさせて戴き度い。その母の為にも尊い石油を空費する米英の巨頭一味は憎むべき敵だ。親の仇を討つ日本精神の強烈さに於いて私は敢て曾我兄弟に譲らない。米英の戦争挑発さへ無かったらば石油は人類殺戮の為に悪用されず、人類の福祉向上の為に善用されたであらう」。戦後、正通は親しい友人・横内圓次に母を偲んで詠んだ歌「果てし日も 骨さえ分かぬ命かも 母親返えせ 昭和天皇」を披露している。
03/03: 写真家・????宮城昇①
2001年10月ー沖縄県写真協会『おきなわ写真の歩み』□新城栄徳ー沖縄写真史散歩ー前に写真家・山田實さんから、父山田有登とその沖縄県立中学校同窓の山川文信、翁長助成、山城正好、宮里良貞、????宮城宗倫が写っている1907(明治40)年の識名園園遊会での写真①を見せてもらった。中のひとり????宮城宗倫の息子が????宮城昇である。他に1904年の同窓生は川平朝令、志喜屋孝信、比嘉徳、久高将旺が居る。昇は東京写真専門学校在学中の1927(昭和2)年に東京写真研究会主催の展覧会に応募、入選するなど意欲的に写真に取り組んだ。沖縄に帰り写真館・昇スタジオを那覇市上之蔵に開業。明視堂写真部と共催で写真展を開いたり、新聞に作品を発表したり、短編小説を<時計の宣告>と題し「今日は昨日の連続である。人生は瞬間の連続である。その瞬間をいかに朗らかに楽しむか」などを発表した。とにかくいろいろな表現を試み写真も芸術写真を志向したー。

①識名園遊会での写真

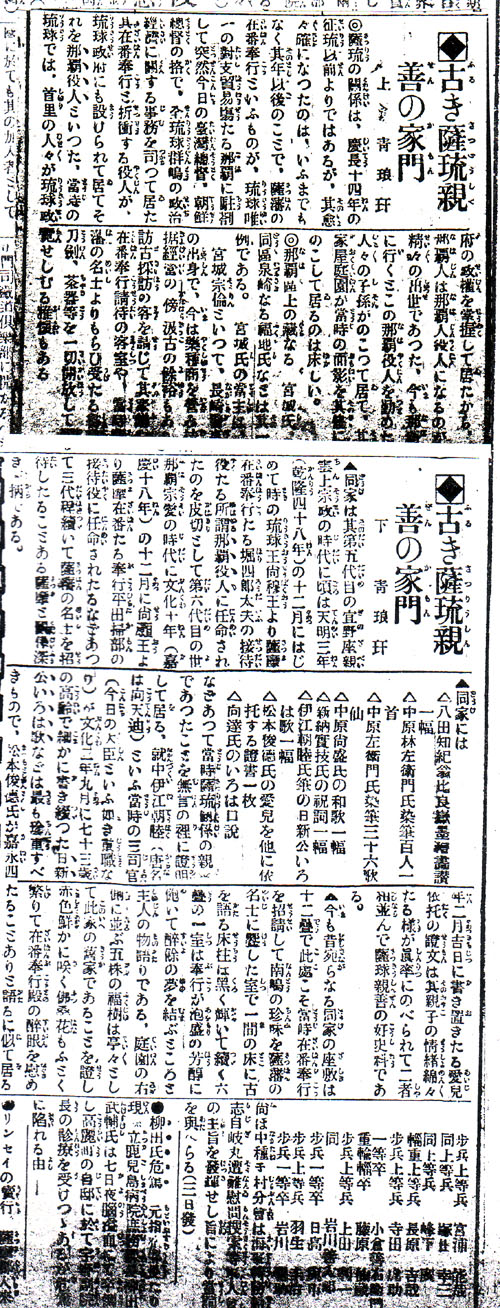

1919年9月ー『鹿児島新聞』で「古き薩琉親善の家門」として????宮城家当主の宗倫が紹介され「宮城宗倫といって、長崎医専の出身で、今は薬種商を営み(略)訪古採訪の客を請じてその家譜や在番奉行請待の客室や、当時薩藩の名士よりもらい受けたる書簡、刀剣、茶器等を一切開放して閲覧せしむるー」と出て一般に家宝を公開していることがわかる。下の写真は????宮城宗倫を中心に左に真境名安興、右に冨名腰義珍も見える。
1926年1月ー坂口総一郎『沖縄写真帖』/池野成一郎□序ー私は大正14年1月沖縄本島を旅行した。しかも此写真帖の著者坂口君の御親切な案内を受けて、その旅は実に愉快であった。その旅の事を考えると今でもその時の愉快さがありありと頭の中に浮み出でて胸のあたりがすつとする。私は旅が大好きだ。明治21年生まれて初めての旅をして以来私は毎年多少の旅行をしない事はない。外国の旅行は別として日本内地は勿論、台湾、朝鮮、樺太その外小笠原島や対馬、隠岐の様な離れ島でも私の足はその土を踏んでいる。その数百回に亘る旅行はいつでも多少面白かつたに相違ないが併し大正14年1月の沖縄旅行は私が尤も面白いと思つた旅行の中の一つである。沖縄にはフルギがある、ヘゴがある、アダンがある、ガジュマルがある、植物の平凡な東京に住む植物学者の私に取つて沖縄が面白いのは当然だが併し沖縄の面白いのはただ植物ばかりでは無い。動物も面白い、風俗、建物、言語、風景皆内地と違つているから面白い隋つて植物学者も行くべし、動物学者も行くべし、人類学者も、建築学者も、博言学者も誰れも彼れも、苟くも珍奇な事物を見て智識を得ようと思ふ人は皆行くべしだ。併し如何に沖縄へ旅行したくとも暇のない人もあり、又旅費が思ふ様にならない人もある。それ等の人は此写真帖を見て沖縄の動植物や、建物、風俗抔の一班を知るがよい。尚ほ沖縄も内地との交通が繁くなるにつれ、風俗等も段々内地のものに近くなり、古い建築物も追々朽ちはて、おまけにヘゴやヒルギの様な珍しい植物がやたらに切り倒される今日だから今の内に此写真帖が出版されるのは誠に時を得たものだと思ふ。此点に於て坂口君の御骨折を感謝すると同時に此写真帖が第三輯以下次々と出版される事を祈る。
1936年
1938年
9月ー『アトリエ』<二科会特集>藤田嗣治「孫」、藤川栄子「琉球のキモノ」、加治屋隆二「糸満の井戸」
11月ー大阪阪急百貨店で「琉球漆器陳列会」
1939年
5月17日ー日本民芸協会一行、尚順邸で歓待を受ける。
5月19日ー又吉康和の招待で辻正鶴楼で歓迎会
11月ー『月刊民芸』<琉球特集>□尚順「古酒」、比嘉景常「石」、山田有邦「芝居」、島袋源一郎「郷土博物館」、仲里誠吉「市場」、世禮國男「三線」、島袋全発「童謡」、石野径一郎「うた」、比嘉春潮「衣・食・住」
1940年3月ー『月刊民藝』水澤澄夫(国際観光局)「沖縄の風物と観光」□1月7日ー午後、那覇市公会堂で、「観光座談会」が催された。両市(首里・那覇)の主だった人達はじめ県警察部長、師範学校長、図書館長、大阪商船支店長等が地元から出られ、こちら側からは柳(宗悦)先生はじめ濱田庄司氏、式場隆三郎博士、日本旅行協会の井上昇三氏、わたしなど十人余り出席した。話は崇元寺前の折角の美しい石門の風致を害する電柱の取りつけのことから端を開き、わたしは、四日間だまって見物して得たところを材料として、1、開発していただきたいもの、2、保存してもらいたいもの、3、禁止してほしいもの、これら3者について具体例をあげて希望を述べた。すなわち、旅館、道路、下水の問題、標準語の問題、勝地に於いて風趣を損ずる立札等の問題(糸満白銀堂の寄進名表、満座毛のコンクリートの鳥居と卓、首里城々門下の井戸柵など)。結局沖縄は観光地として資源の上から十分発展の可能性がある。現下の世界情勢において急に国際観光地として立つわけには行くまいが、国際観光事業は「見えざる輸出」として貿易外収入の道として忽せに出来ぬ事業であるから、御考慮願いたい。このことは国内観光事業の場合、一県を主体にとって考えれば同じ趣旨が成り立つものである、というようなことを言った。
この会ではわたしの持ち出した標準語問題と式場博士の言い出した墓保存の意見とがはしなくも論議の種になり、御数日は賑やかな沖縄ジャーナリズムの問題となった。標準語問題というのは、女学校の壁に張られた県で募集した標準語励行当選標語に、「沖縄を明るく伸ばす標準語」「一家そろって標準語」「いつもはきはき標準語」などというものがあり、県当局の意向も判りはするが、少し行きすぎたところがありはしないか言い出したのに端を発する。標語というものは概していくらか滑稽なところがあり行きすぎがちなものである。そして、その割に効果少ないものである。この問題も県としては重大な問題に相違ないが、実際的な正しい効果をあげる方法は多分他にあるのではなからうか。前にもしるしたように沖縄語は一方言としてとりあつかうにはあまりに古格のある言葉である。人は郷土の言葉にこそ生き生きした息吹を感ずる。標準語は方便である。沖縄の人も冷静に考えればこのことは十分判ることであろう。わたくしの言から緒を発した県当局の意見と柳先生の論旨とは根本的に論拠がちがうのである。そのことを県の人々も一般人士も気づいてほしい。観光的観点から見れば、言葉も亦郷土色を彩る重大な要素の一つである。切に沖縄語の正しい保存を希求して止まない。墓の問題も同然、論点が異なるのである。式場博士の説を十分に咀嚼してもらいたいと思う。
出立の前日人づてに尚順男があいたいと言って来られたので首里桃原の邸に伺った。尚順男は現尚侯爵の叔父に当たる方で69歳、嘗ては貴族院議員として又銀行頭取として県下に威を振った人である。いまは博学多識な老紳士として、しかもなお衰えを見せぬ県内第一の人物である。話は男の経営にかかる那覇市西新町の埋立地に関してであった。現在約六千坪であるが3年後には約3倍の面積に達する。ここに小公園を置き、水族館を設ける予定であるが、更にホテルを築造してはどうかと言われるのである。-相当の室数と宴会場を持ったホテルは実際那覇にとっては必要なのだ。ここには辻という特殊な花街があるが、そこは待合娼家旅館料理屋宴会場を兼ねている。その組織も独特なものである。それが現在旅館の少ない那覇の不備を補っているし、宴会といえば知事の招宴でもここを用いなければならない。しかも一方、県当局はここの廃止を企てたりする。これは現在の状態においては一つの矛盾ではないか。そこで私は宴会場をもったホテルを提唱するのである。そこにはステージをつくって沖縄舞踊の見聞に便ならしめ、琉球料理、洋食、支那料理を設備する。沖縄においても最も簡単に出来るのは材料の関係からいって琉球料理はともかくとして西洋料理である。又、遊覧の為には那覇湾頭珊瑚礁には約二千種の魚介類が棲息するから、、ガラス底の船を出して之を見せる。
一里程離れた小湾は最もよい海水浴場であり、尚侯、尚男の別荘がある。そこへサンドイッチくらい持ってドライブするのもいいだろう。又山の方は桃原農園にもっと、熱帯植物を養殖して一大植物園とし、ホテルの別館を置くのもいい。ゴルフ場も出来るし、例えば恩納岳に螺旋状自動車をつくるのも面白いと思う。沖縄はよき観光地である。殊に冬季は絶好の避寒地である。-男の話は雄大であり、実際的であり、傾聴すべき意見であった。古稀に垂れんとする老紳の熱情をかたむけての話をわたくしはゆるがせには聞けなかった。しかもその老紳士たる、沖縄においては声威並びない人なのである。この人の夢が実現しない筈がない。わたくしは微力ながら出来るだけの努力は惜しまない旨答えて辞去したのであった。

①識名園遊会での写真

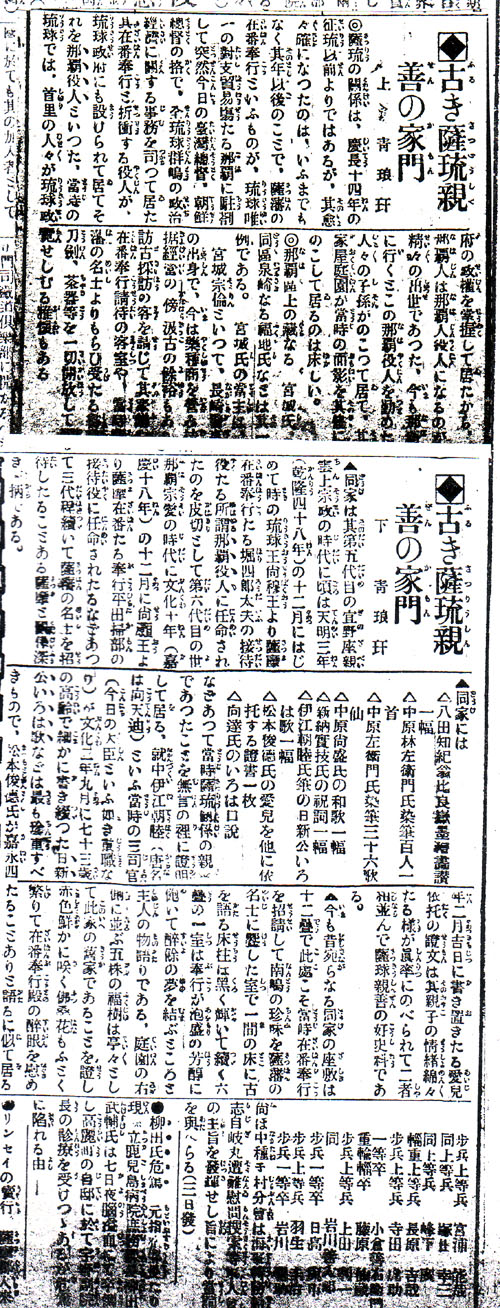

1919年9月ー『鹿児島新聞』で「古き薩琉親善の家門」として????宮城家当主の宗倫が紹介され「宮城宗倫といって、長崎医専の出身で、今は薬種商を営み(略)訪古採訪の客を請じてその家譜や在番奉行請待の客室や、当時薩藩の名士よりもらい受けたる書簡、刀剣、茶器等を一切開放して閲覧せしむるー」と出て一般に家宝を公開していることがわかる。下の写真は????宮城宗倫を中心に左に真境名安興、右に冨名腰義珍も見える。
1926年1月ー坂口総一郎『沖縄写真帖』/池野成一郎□序ー私は大正14年1月沖縄本島を旅行した。しかも此写真帖の著者坂口君の御親切な案内を受けて、その旅は実に愉快であった。その旅の事を考えると今でもその時の愉快さがありありと頭の中に浮み出でて胸のあたりがすつとする。私は旅が大好きだ。明治21年生まれて初めての旅をして以来私は毎年多少の旅行をしない事はない。外国の旅行は別として日本内地は勿論、台湾、朝鮮、樺太その外小笠原島や対馬、隠岐の様な離れ島でも私の足はその土を踏んでいる。その数百回に亘る旅行はいつでも多少面白かつたに相違ないが併し大正14年1月の沖縄旅行は私が尤も面白いと思つた旅行の中の一つである。沖縄にはフルギがある、ヘゴがある、アダンがある、ガジュマルがある、植物の平凡な東京に住む植物学者の私に取つて沖縄が面白いのは当然だが併し沖縄の面白いのはただ植物ばかりでは無い。動物も面白い、風俗、建物、言語、風景皆内地と違つているから面白い隋つて植物学者も行くべし、動物学者も行くべし、人類学者も、建築学者も、博言学者も誰れも彼れも、苟くも珍奇な事物を見て智識を得ようと思ふ人は皆行くべしだ。併し如何に沖縄へ旅行したくとも暇のない人もあり、又旅費が思ふ様にならない人もある。それ等の人は此写真帖を見て沖縄の動植物や、建物、風俗抔の一班を知るがよい。尚ほ沖縄も内地との交通が繁くなるにつれ、風俗等も段々内地のものに近くなり、古い建築物も追々朽ちはて、おまけにヘゴやヒルギの様な珍しい植物がやたらに切り倒される今日だから今の内に此写真帖が出版されるのは誠に時を得たものだと思ふ。此点に於て坂口君の御骨折を感謝すると同時に此写真帖が第三輯以下次々と出版される事を祈る。
1936年
1938年
9月ー『アトリエ』<二科会特集>藤田嗣治「孫」、藤川栄子「琉球のキモノ」、加治屋隆二「糸満の井戸」
11月ー大阪阪急百貨店で「琉球漆器陳列会」
1939年
5月17日ー日本民芸協会一行、尚順邸で歓待を受ける。
5月19日ー又吉康和の招待で辻正鶴楼で歓迎会
11月ー『月刊民芸』<琉球特集>□尚順「古酒」、比嘉景常「石」、山田有邦「芝居」、島袋源一郎「郷土博物館」、仲里誠吉「市場」、世禮國男「三線」、島袋全発「童謡」、石野径一郎「うた」、比嘉春潮「衣・食・住」
1940年3月ー『月刊民藝』水澤澄夫(国際観光局)「沖縄の風物と観光」□1月7日ー午後、那覇市公会堂で、「観光座談会」が催された。両市(首里・那覇)の主だった人達はじめ県警察部長、師範学校長、図書館長、大阪商船支店長等が地元から出られ、こちら側からは柳(宗悦)先生はじめ濱田庄司氏、式場隆三郎博士、日本旅行協会の井上昇三氏、わたしなど十人余り出席した。話は崇元寺前の折角の美しい石門の風致を害する電柱の取りつけのことから端を開き、わたしは、四日間だまって見物して得たところを材料として、1、開発していただきたいもの、2、保存してもらいたいもの、3、禁止してほしいもの、これら3者について具体例をあげて希望を述べた。すなわち、旅館、道路、下水の問題、標準語の問題、勝地に於いて風趣を損ずる立札等の問題(糸満白銀堂の寄進名表、満座毛のコンクリートの鳥居と卓、首里城々門下の井戸柵など)。結局沖縄は観光地として資源の上から十分発展の可能性がある。現下の世界情勢において急に国際観光地として立つわけには行くまいが、国際観光事業は「見えざる輸出」として貿易外収入の道として忽せに出来ぬ事業であるから、御考慮願いたい。このことは国内観光事業の場合、一県を主体にとって考えれば同じ趣旨が成り立つものである、というようなことを言った。
この会ではわたしの持ち出した標準語問題と式場博士の言い出した墓保存の意見とがはしなくも論議の種になり、御数日は賑やかな沖縄ジャーナリズムの問題となった。標準語問題というのは、女学校の壁に張られた県で募集した標準語励行当選標語に、「沖縄を明るく伸ばす標準語」「一家そろって標準語」「いつもはきはき標準語」などというものがあり、県当局の意向も判りはするが、少し行きすぎたところがありはしないか言い出したのに端を発する。標語というものは概していくらか滑稽なところがあり行きすぎがちなものである。そして、その割に効果少ないものである。この問題も県としては重大な問題に相違ないが、実際的な正しい効果をあげる方法は多分他にあるのではなからうか。前にもしるしたように沖縄語は一方言としてとりあつかうにはあまりに古格のある言葉である。人は郷土の言葉にこそ生き生きした息吹を感ずる。標準語は方便である。沖縄の人も冷静に考えればこのことは十分判ることであろう。わたくしの言から緒を発した県当局の意見と柳先生の論旨とは根本的に論拠がちがうのである。そのことを県の人々も一般人士も気づいてほしい。観光的観点から見れば、言葉も亦郷土色を彩る重大な要素の一つである。切に沖縄語の正しい保存を希求して止まない。墓の問題も同然、論点が異なるのである。式場博士の説を十分に咀嚼してもらいたいと思う。
出立の前日人づてに尚順男があいたいと言って来られたので首里桃原の邸に伺った。尚順男は現尚侯爵の叔父に当たる方で69歳、嘗ては貴族院議員として又銀行頭取として県下に威を振った人である。いまは博学多識な老紳士として、しかもなお衰えを見せぬ県内第一の人物である。話は男の経営にかかる那覇市西新町の埋立地に関してであった。現在約六千坪であるが3年後には約3倍の面積に達する。ここに小公園を置き、水族館を設ける予定であるが、更にホテルを築造してはどうかと言われるのである。-相当の室数と宴会場を持ったホテルは実際那覇にとっては必要なのだ。ここには辻という特殊な花街があるが、そこは待合娼家旅館料理屋宴会場を兼ねている。その組織も独特なものである。それが現在旅館の少ない那覇の不備を補っているし、宴会といえば知事の招宴でもここを用いなければならない。しかも一方、県当局はここの廃止を企てたりする。これは現在の状態においては一つの矛盾ではないか。そこで私は宴会場をもったホテルを提唱するのである。そこにはステージをつくって沖縄舞踊の見聞に便ならしめ、琉球料理、洋食、支那料理を設備する。沖縄においても最も簡単に出来るのは材料の関係からいって琉球料理はともかくとして西洋料理である。又、遊覧の為には那覇湾頭珊瑚礁には約二千種の魚介類が棲息するから、、ガラス底の船を出して之を見せる。
一里程離れた小湾は最もよい海水浴場であり、尚侯、尚男の別荘がある。そこへサンドイッチくらい持ってドライブするのもいいだろう。又山の方は桃原農園にもっと、熱帯植物を養殖して一大植物園とし、ホテルの別館を置くのもいい。ゴルフ場も出来るし、例えば恩納岳に螺旋状自動車をつくるのも面白いと思う。沖縄はよき観光地である。殊に冬季は絶好の避寒地である。-男の話は雄大であり、実際的であり、傾聴すべき意見であった。古稀に垂れんとする老紳の熱情をかたむけての話をわたくしはゆるがせには聞けなかった。しかもその老紳士たる、沖縄においては声威並びない人なのである。この人の夢が実現しない筈がない。わたくしは微力ながら出来るだけの努力は惜しまない旨答えて辞去したのであった。
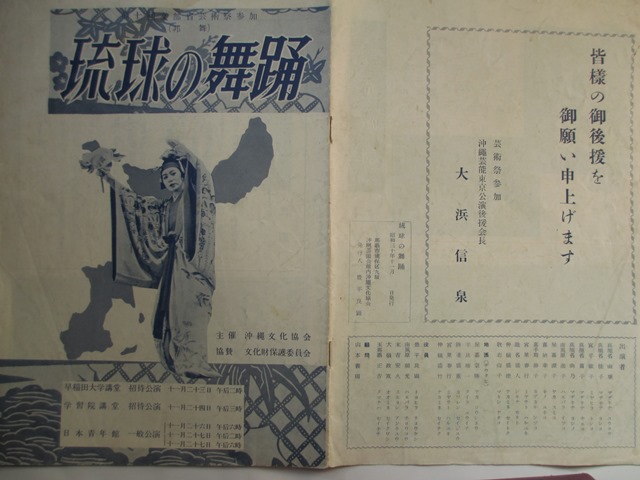
宮平敏子
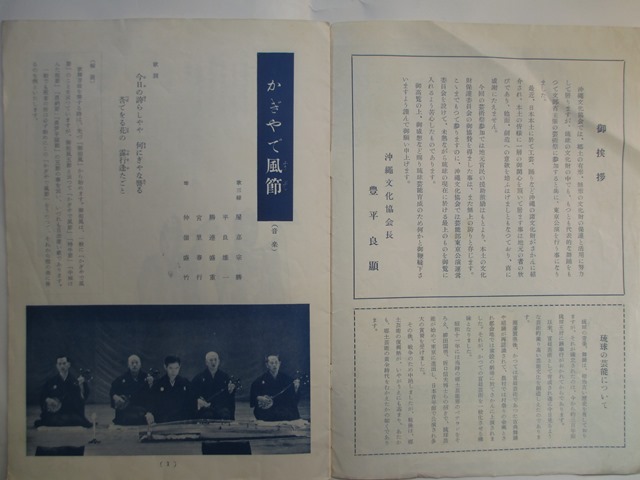
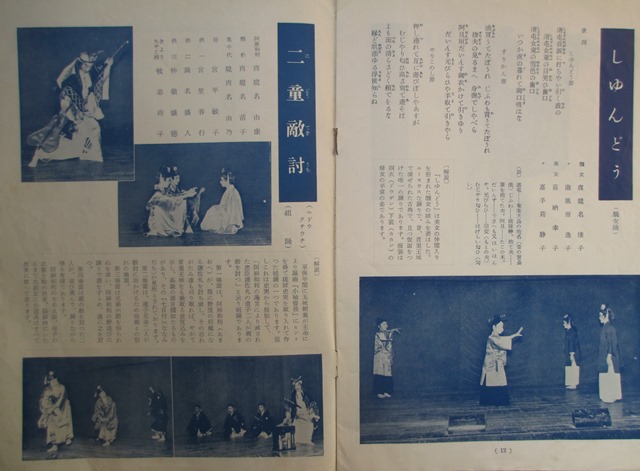
(翁長良明コレクション)
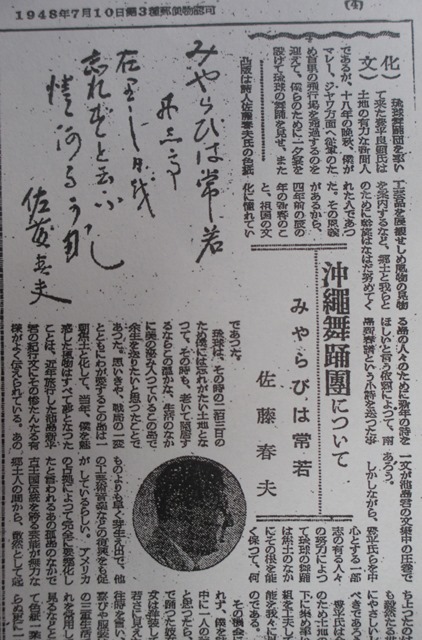
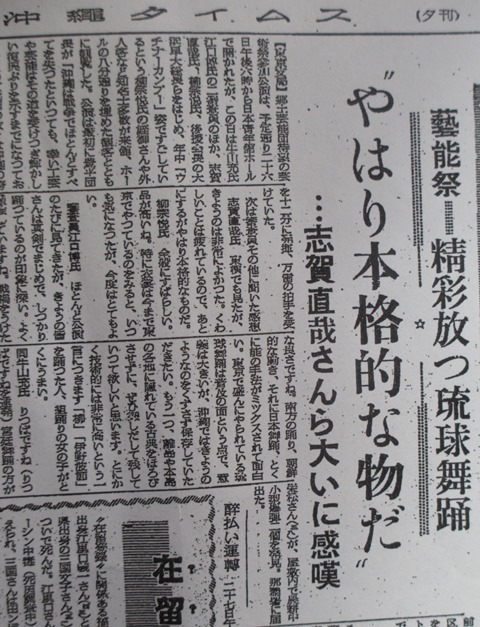
1955年12月11日『沖縄タイムス』佐藤春夫「沖縄舞踊団についてーみやらびは常若」/11月27日『沖縄タイムス』「芸能祭」
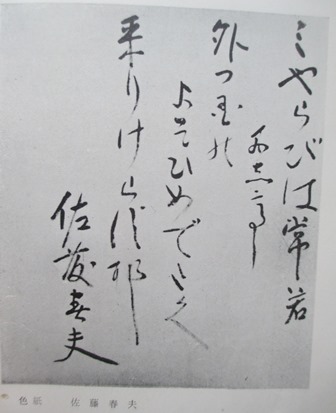
12月15日『沖縄タイムス』「文部省主催の芸術祭ー沖縄舞踊が団体入賞」
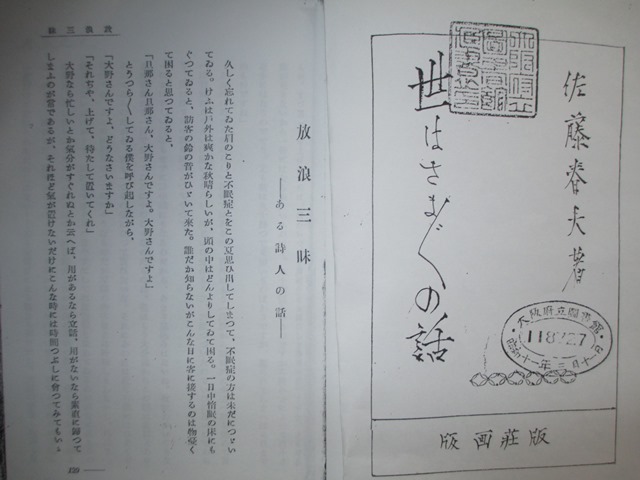
1933年1月 佐藤春夫作「世はさまざまの話」
青山恵昭 2021-8-31 佐藤春夫は山之口貘がお世話になった等々、沖縄通としても知られていますね。1929年28歳の時、台湾基隆社寮島(現和平島)の琉球人集落を訪ねたことを記した短編随筆「社寮島旅情記」があります。友人2人して舢舨(サンパン)で島へ渡り、琉球料亭で一席をもうけて泡盛を嗜み、三線、琉舞に興じた様子が軽妙に描かれています。湾生として興味深々読みました。
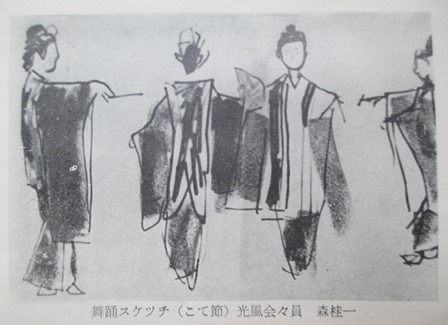
森 桂一モリ ケイイチ
昭和期の洋画家 千葉大学名誉教授;明徳短期大学名誉学長。
生年明治37(1904)年8月10日没年昭和63(1988)年3月16日
出身地岐阜県恵那市 別名号=林人子
学歴〔年〕東京美術学校〔昭和3年〕卒
主な受賞名〔年〕勲三等旭日中綬章〔昭和49年〕
経歴昭和3年帝展初入選。27年から45年まで千葉大教授。50年から56年まで明徳短大学長。美術教育を研究するかたわら、日展委嘱洋画家としても活躍。著書に「美術教育概説」など。→コトバンク
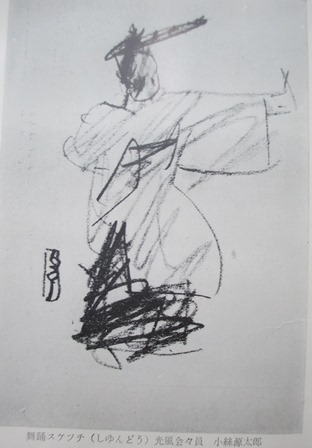
小糸源太郎 こいと-げんたろう
1887-1978 大正-昭和時代の洋画家。
明治20年7月13日生まれ。東京美術学校(現東京芸大)在学中に文展入選,昭和5年,6年に帝展で連続特選となる。官展の審査員,光風会会員として活躍し,29年「春雪」などで芸術院賞。40年文化勲章。昭和53年2月6日死去。90歳。東京出身。作品はほかに「山粧ふ」「繚乱(りょうらん)」など。 →コトバンク
07/25: 1923年8月 『思想』「ケーベル先生追悼号」岩波書店
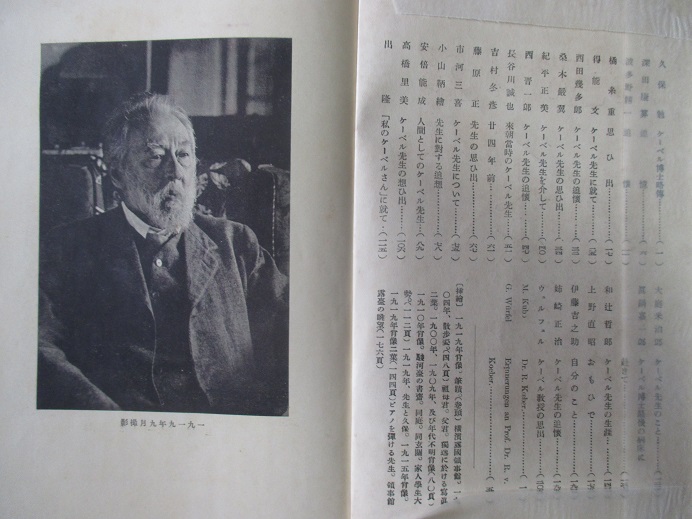
1923年8月 『思想』「ケーベル先生追悼号」岩波書店
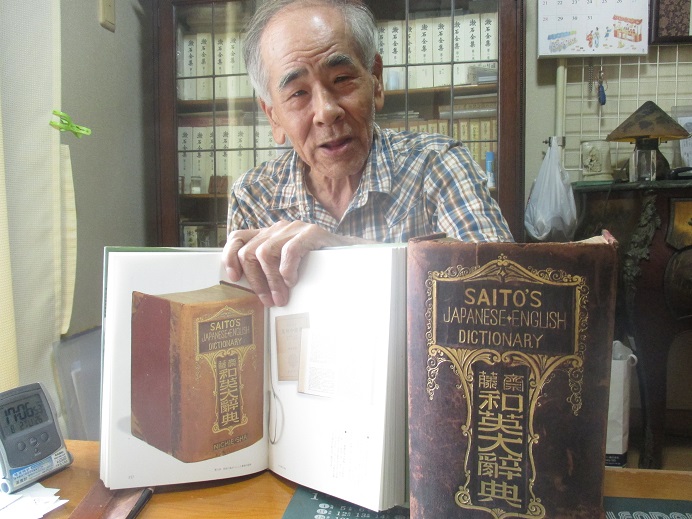
新城良一氏の手にしているのは紀田順一郎『日本博覧人物史』(左)に載っている1928年6月再版発行の齋藤秀三郎『齋藤和英大辞典』東勇治
斎藤秀三郎○1880年(14歳) 工部大学校(現在の東京大学工学部)入学。純粋化学、造船を専攻。後に夏目漱石の師となるスコットランド人教師ディクソン (James Main Dixon) に英語を学ぶ。後々までイディオムの研究を続けたのは彼の影響だったと後年述べている。また、図書館の英書は全て読み、大英百科事典は2度読んだ、という逸話が残っている。/1883年(17歳) 工部大学校退学。/1884年(18歳) 『スウヰントン式英語学新式直訳』(十字屋・日進堂)を翻訳出版。その後、仙台に戻り、英語塾を開設(一番弟子は、伝法久太郎である。また、学生の中に土井晩翠がいる)。1885年に来日したアメリカ人宣教師W・E・ホーイの通訳を務める。その後、1887年9月第二高等学校助教授(1888年9月教授)、1889年11月岐阜中学校(この時代、、濃尾地震に遭遇。この体験は、その後、地震嫌いとして斎藤の生活に影響を及ぼすことになる)、1892年4月長崎鎮西学院、9月名古屋第一中学校を経て、1893年7月第一高等学校教授。1888年5月とら子と結婚。/1896年10月神田錦町に正則英語学校(現在の正則学園高等学校)を創立して校長。以後、死亡するまで、(一時期、第一高等学校に出講したが)、ここを本拠として教育・研究に生涯を尽くした。→ウィキ
1916年 石川正通、一中退学、私立麻布中学校へ転校。3月29日、真玉橋朝起、武元朝朗、竹内弘道たちに見送られて沖縄丸で上京、甲板上で明大受験の城間恒昌、杉浦重剛校長の日本中学に転校する我部政達と3人で雑談に耽る。4月3日東京駅に着く。翌日、比屋根安定が大八車で荷物を一緒に運んでくれる。斎藤秀三郎校長の抜擢で正則英語学校講師となる。後に比嘉春潮(荻窪)、島袋盛敏(成城)、比屋根安定(青山学院構内)、仲吉良光(鶴見)、八幡一郎(東中野)、金城朝永(大塚)、石川正通(本郷)の7人で七星会結成する。

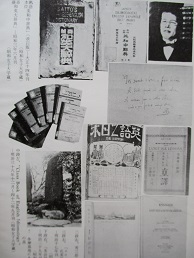

1970年3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書 31』「齋藤秀三郎」
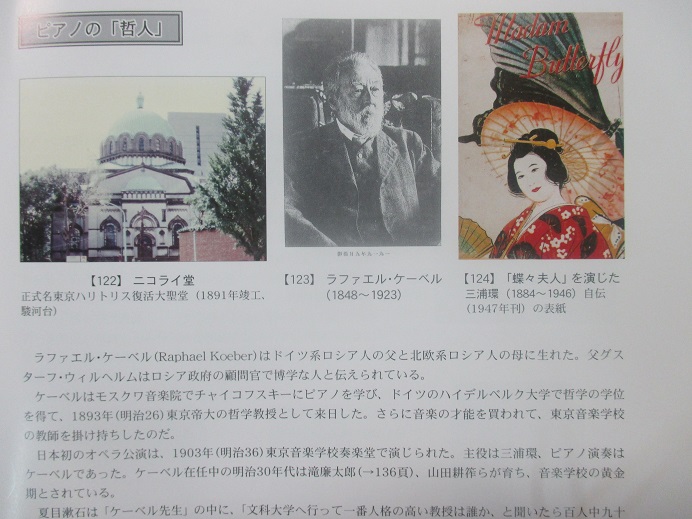
2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
2014年1月21日『琉球新報』ピアニスト長堂奈津子のリサイタル「ピアノ協奏曲とケーベル歌曲の夕べ」が17日、南城市文化センター・シュガーホールであった。明治期、日本のピアノ界に大きな影響を与えたロシア出身の哲学者ラファエル・フォン・ケーベルの歌曲「9つの歌」を沖縄初演したほか、バッハ、シューマンのピアノ協奏曲をカンマーゾリステン21(指揮・庭野隆之、コンサートマスター・屋比久潤子)と共に演奏した。長堂はケーベル研究に没頭し、2011年に他界した父・島尻政長(ケーベル会初代会長)への追悼の思いを、厳かな演奏に重ね描いた。
ラファエル・フォン・ケーベル(ドイツ語: Raphael von Koeber, 1848年1月15日 - 1923年6月14日)は、ロシア出身(ドイツ系ロシア人)の哲学者、音楽家。明治政府のお雇い外国人として東京帝国大学で哲学、西洋古典学を講じた。友人のエドゥアルト・フォン・ハルトマンの勧めに従って1893年(明治26年)6月に日本へ渡り、同年から1914年(大正3年)まで21年間東京帝国大学に在職し、イマヌエル・カントなどのドイツ哲学を中心に、哲学史、ギリシア哲学など西洋古典学も教えた。美学・美術史も、ケーベルが初めて講義を行った。学生たちからは「ケーベル先生」と呼ばれ敬愛された。夏目漱石も講義を受けており、後年に随筆『ケーベル先生』を著している。他の教え子には安倍能成、岩波茂雄、阿部次郎、小山鞆絵、九鬼周造、和辻哲郎、 深田康算、大西克礼、波多野精一、田中秀央など多数がいる。和辻の著書に回想記『ケーベル先生』がある。また漱石も寺田寅彦も、ケーベル邸に行くと深田がいたと記されている。→ウィキ
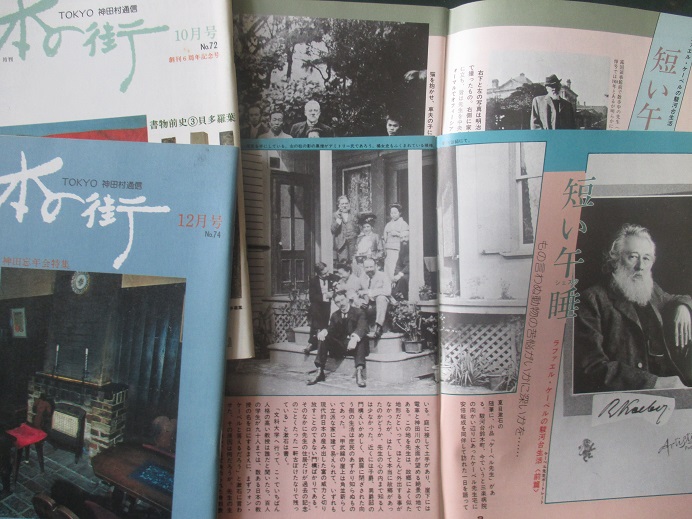
『本の街』1986年~87年の「ケーベル」を改めて見る。泊の島尻政長のケーベル会の「ケーベル会誌」はネットでも紹介されている。

本の街編集室『月刊文化情報誌 神田 御茶の水 九段 本の街』
2011年12月『本の街』第34巻1号〇村上泰賢(東善寺住職)「小栗上野介の日本改造」65/秋山岩夫「フォト・ージャーナリスト 林忠彦」⓺/山川正光「総和の旅人44 みどりの窓口/自動券売機」/世田谷文学館・世田谷美術館共同企画展「都市から郊外へ 1930年代の東京」/酒部一太郎「勝海舟追慕・首都圏散策17」/銭谷功「神田ディスカバリー 神田淡路っ子の小宇宙38 ボクは見た10秒間のマッカーサー/ボクら中学生は、世界の新知識を吸収しようと夢中になった。一番素晴らしかったにはリーダース・ダイジェスト日本版発行と、輸入映画の解禁だった。」/「古くて、一寸心に残るもの・・・・・176 辰年ですから龍の話です」/永井英夫「南米の旅 ペルー編・下」/井東冨二子「レコード屋のおかみさん65年」/朝山邦夫「♪神田の東工か♪東工の神田かー実学の達人 中尾哲二郎」/「アート情報」/戸田慎一「ジャズの周辺④ジャズ出版の全体像(前期)」
2012年1月『本の街』第34巻2号〇酒部一太郎「勝海舟追慕・首都圏散策18」/秋山岩夫「フォト・ージャーナリスト 林忠彦ー銀座・酒場『ルパン』を概説する」⑦/戸田慎一「ジャズの周辺⑤ジャズ出版の全体像(中期)」
2015年10月『本の街』第37巻11号〇酒部一太郎「樋口一葉②」
2016年1月『本の街』第38巻2号〇藤田瑞穂「ぼくの庭86 絵は究極のミニマリズム-人間の外付けハードディスクがすべてをまかなうといったところか。なにを今更という思いがする。古来日本には、最小限主義が伝統的にある。茶の湯、能や禅、短歌や俳句、方寸の庵での黙考、等等。」/酒部一太郎「樋口一葉④」
青空文庫ー夏目漱石「ケーベル先生」
木この葉はの間から高い窓が見えて、その窓の隅すみからケーベル先生の頭が見えた。傍わきから濃い藍色あいいろの煙が立った。先生は煙草たばこを呑のんでいるなと余は安倍あべ君に云った。
この前ここを通ったのはいつだか忘れてしまったが、今日見るとわずかの間まにもうだいぶ様子が違っている。甲武線の崖上がけうえは角並かどなみ新らしい立派な家に建て易かえられていずれも現代的日本の産み出した富の威力と切り放す事のできない門構もんがまえばかりである。その中に先生の住居すまいだけが過去の記念かたみのごとくたった一軒古ぼけたなりで残っている。先生はこの燻くすぶり返った家の書斎に這入はいったなり滅多めったに外へ出た事がない。その書斎はとりもなおさず先生の頭が見えた木の葉の間の高い所であった。
余と安倍君とは先生に導びかれて、敷物も何も足に触れない素裸すはだかのままの高い階子段はしごだんを薄暗がりにがたがた云わせながら上のぼって、階上の右手にある書斎に入った。そうして先生の今まで腰をおろして窓から頭だけを出していた一番光に近い椅子に余は坐すわった。そこで外面そとから射さす夕暮に近い明りを受けて始めて先生の顔を熟視した。先生の顔は昔とさまで違っていなかった。先生は自分で六十三だと云われた。余が先生の美学の講義を聴きに出たのは、余が大学院に這入った年で、たしか先生が日本へ来て始めての講義だと思っているが、先生はその時からすでにこう云う顔であった。先生に日本へ来てもう二十年になりますかと聞いたら、そうはならない、たしか十八年目だと答えられた。先生の髪も髯ひげも英語で云うとオーバーンとか形容すべき、ごく薄い麻あさのような色をしている上に、普通の西洋人の通り非常に細くって柔かいから、少しの白髪しらがが生えてもまるで目立たないのだろう。それにしても血色が元の通りである。十八年を日本で住み古した人とは思えない。(以下略)
01/10: 沖縄人民党中央機関紙『人民』
1931年、瀬長亀次郎は神奈川で井之口政雄宅に下宿をしていた。井之口夫人は日本赤色救援神奈川地区の活動家で瀬長は大分お世話になった。飯場生活の瀬長は「全協日本土建神奈川支部」を朝鮮人の金一声らと結成、京浜地区の責任者になった。そして横須賀町久里浜の平作川改修工事に従事していた朝鮮人労働者350人と労働条件改善、全員に仕事をよこせの要求をかかげてストライキに突入、瀬長も、金一声も検挙され一ヶ月投獄された。

瀬長亀次郎は戦後も沖縄人民党行事としてこの碑(人民解放戦士真栄田一郎君に捧ぐ)の前に集い団結を誓った。瀬長亀次郎「弾圧は抵抗を呼ぶ 抵抗は友を呼ぶ」→1991年8月『瀬長亀次郎回想録』新日本出版社
1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社
ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ
写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。
悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫
○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。
郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長
善意の記録として・・・・沖縄県学生会
○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。
第一部
拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人
第二部
土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道
島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光
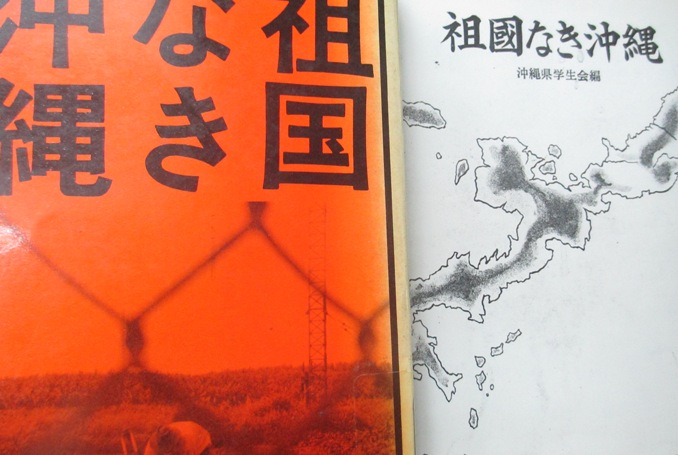
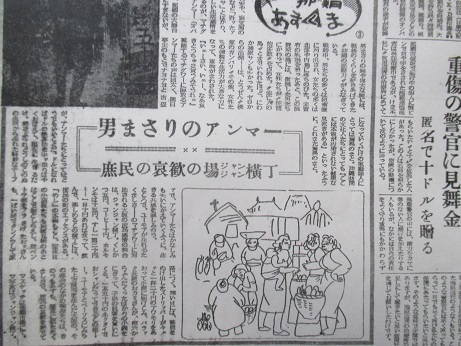
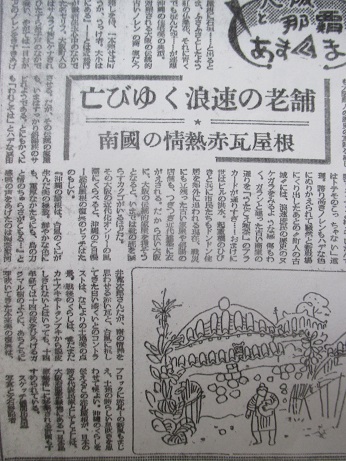
1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」
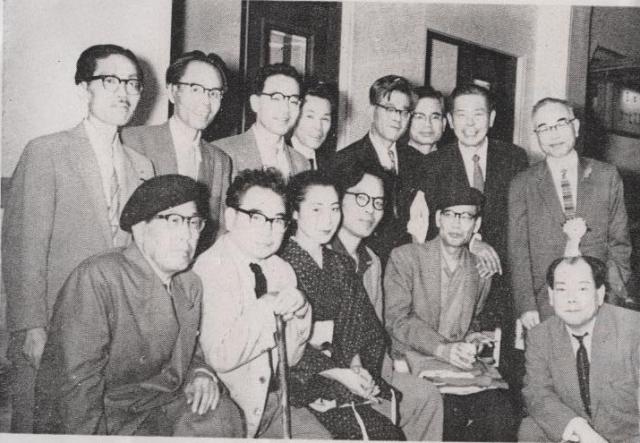
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子
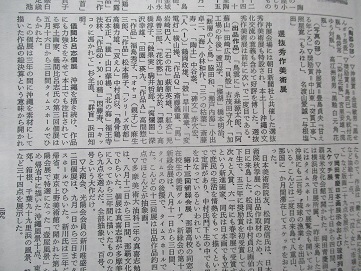

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』
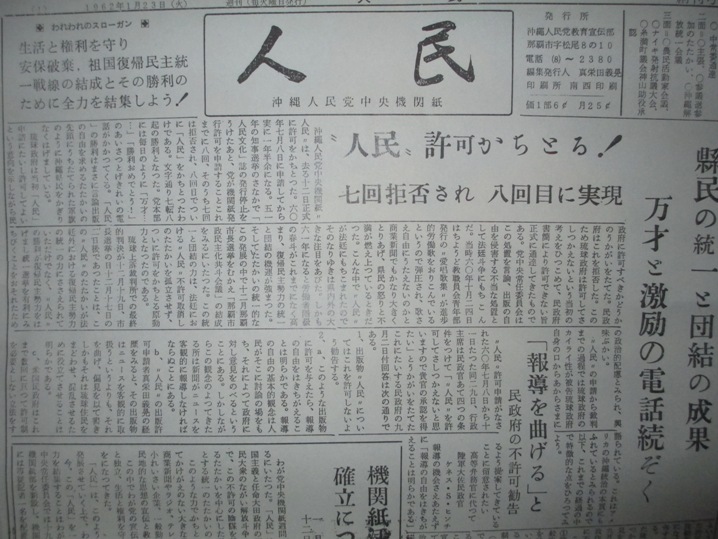

1963年
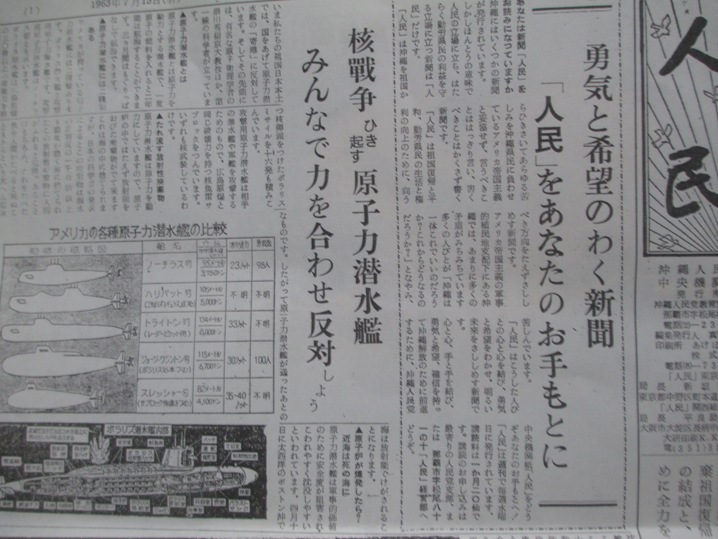
7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」
1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」
1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社
○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫
○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫
○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの
○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二
○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光
○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会
1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」
1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」
2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」
7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)
7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」
9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」
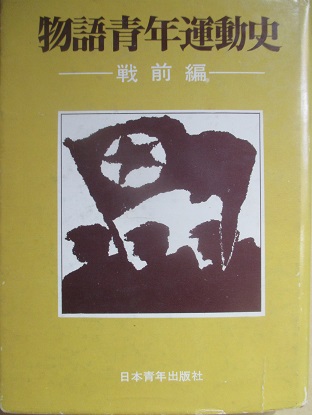

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社
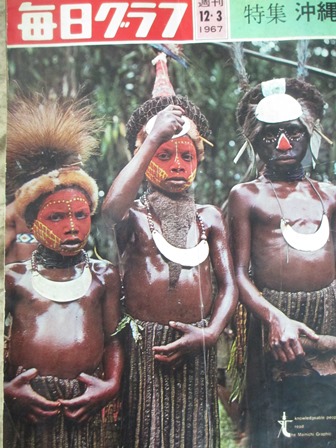
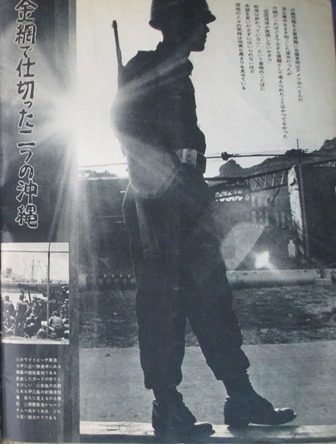
12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」
1968年
6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」
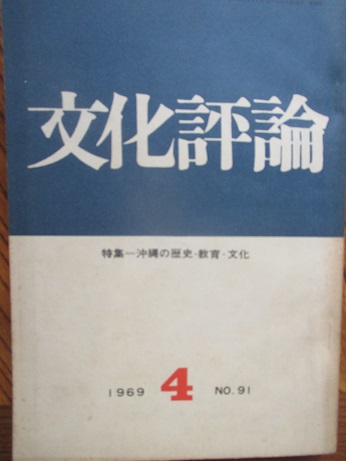
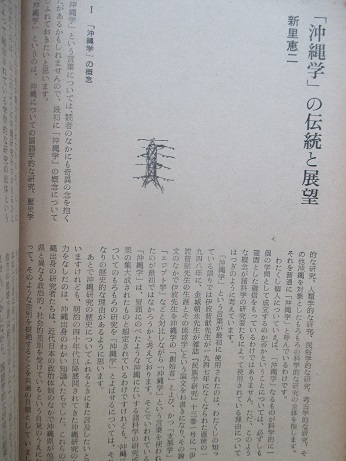
1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」
1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)
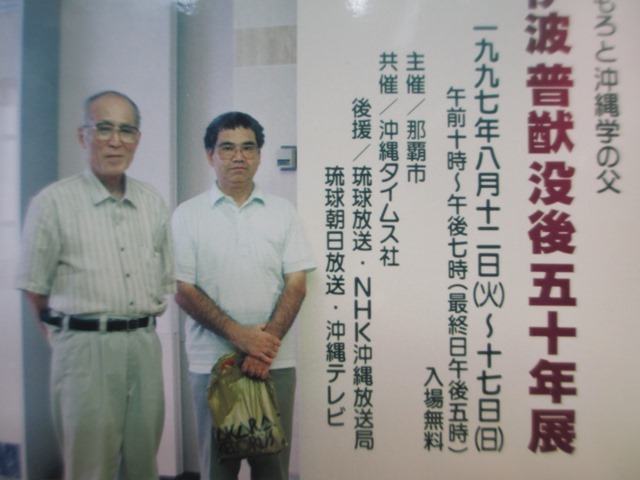
伊波廣定氏と新城栄徳
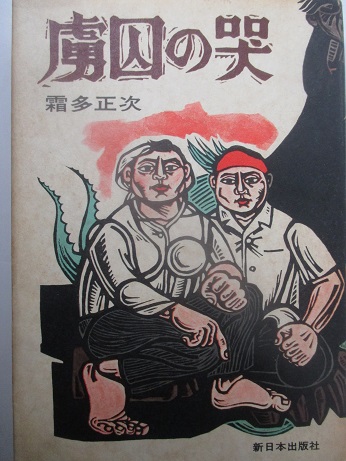
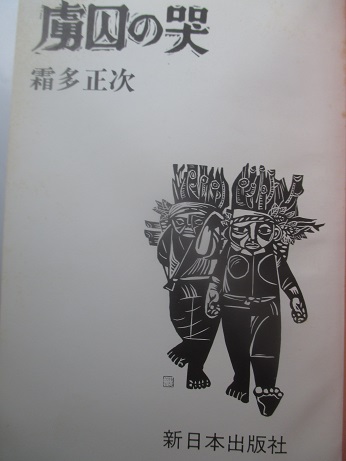
1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」
5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)
8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」
①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)
9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』
□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために
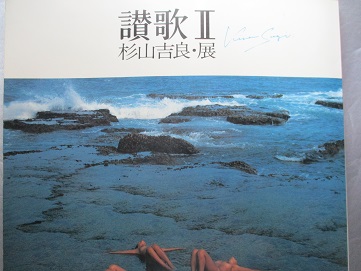
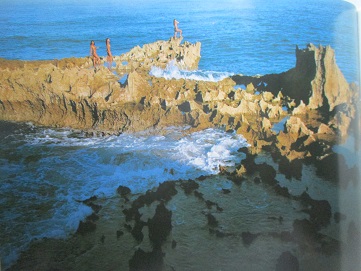
1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』
1971年
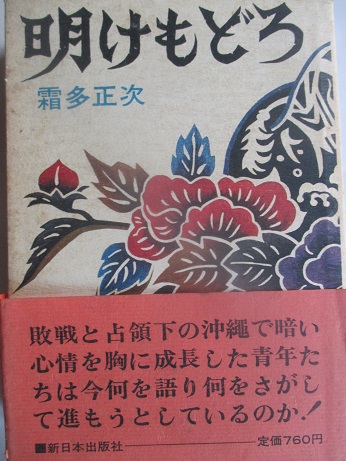
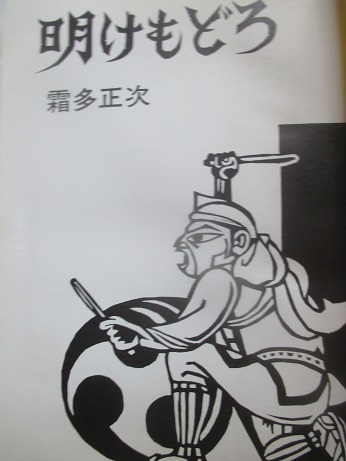
1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」
1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」
1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」
1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」
1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」
2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」
2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」
4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」
5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」
5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④
5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」
6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」
6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」
7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」
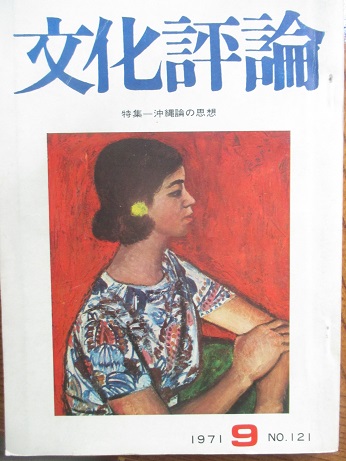
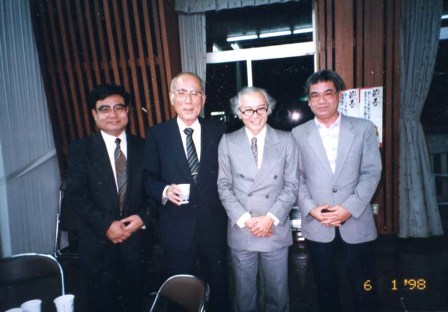
1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
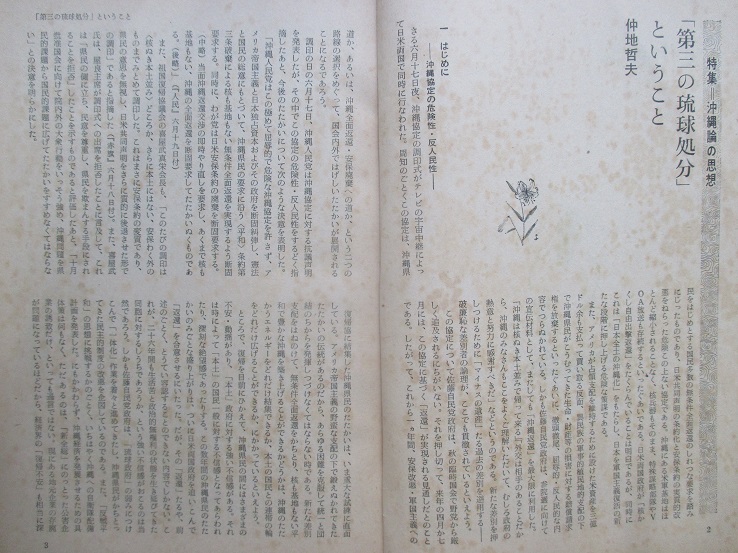
10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」
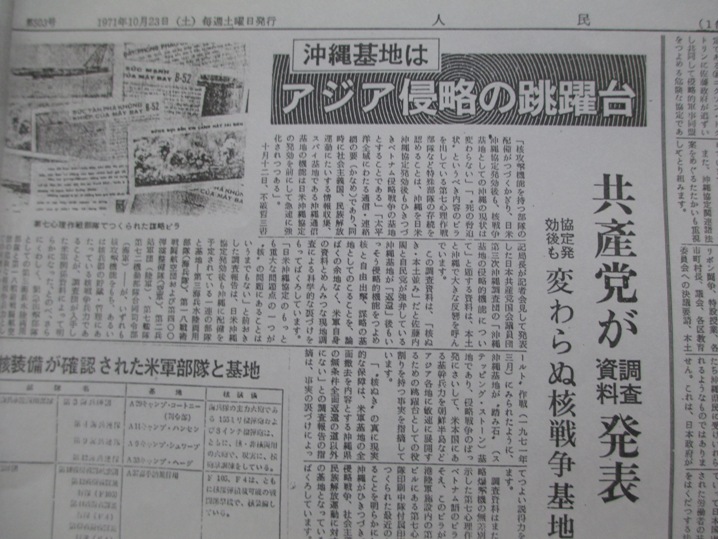
10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」


写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益
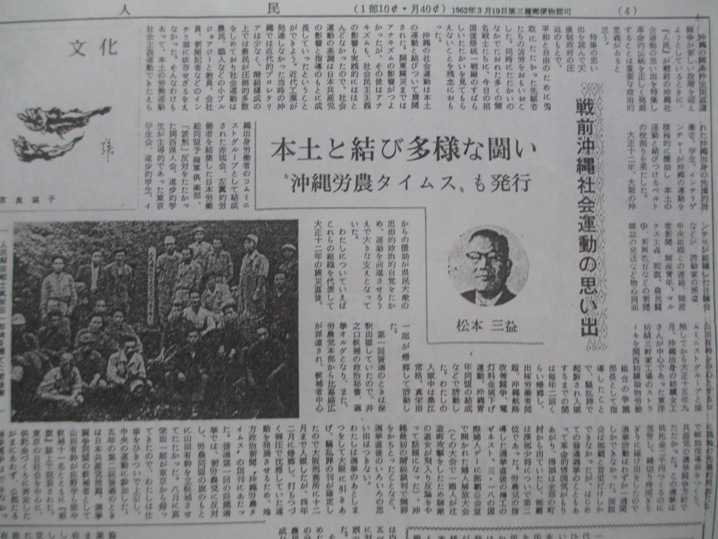
12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」
12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」
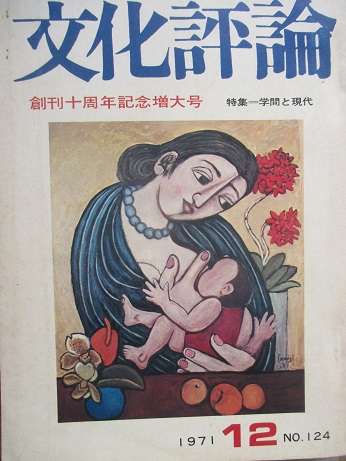
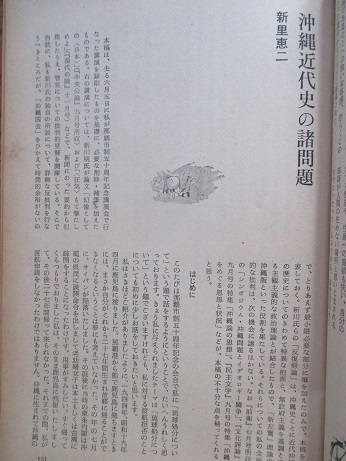
1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」
1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>
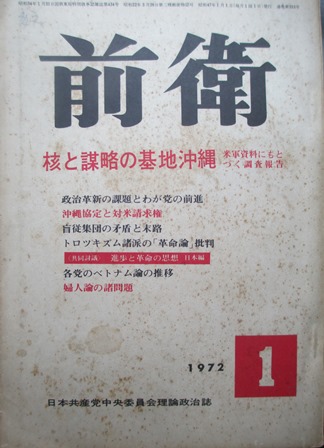

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫
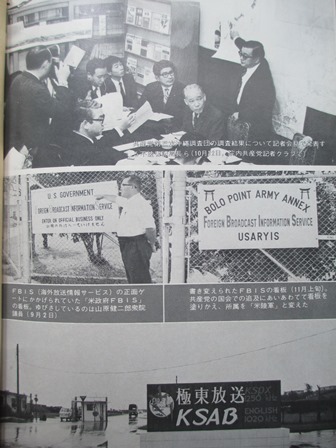
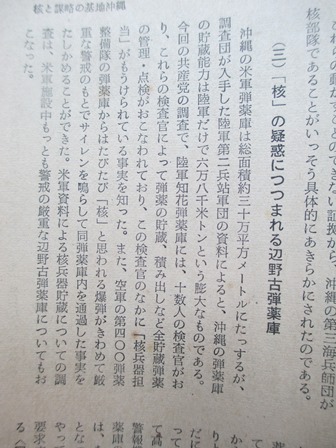
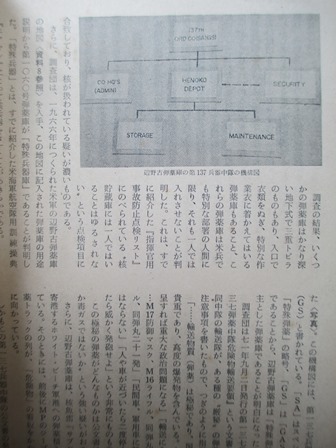
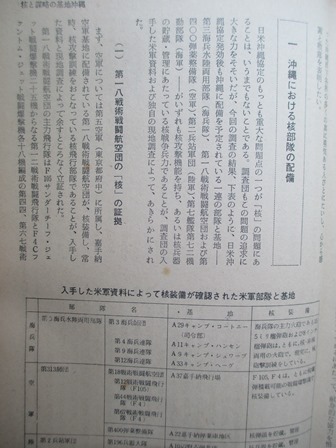


1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」
1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」
2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」
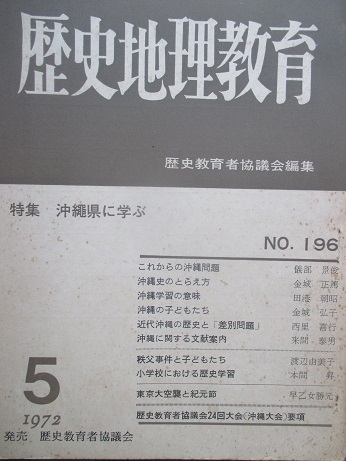
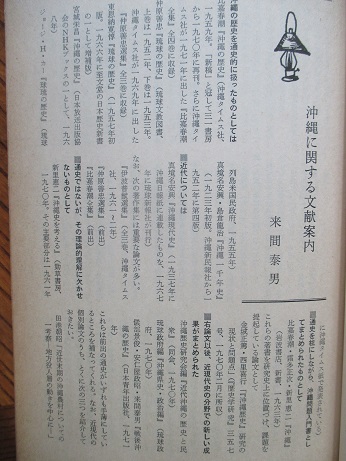
1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」
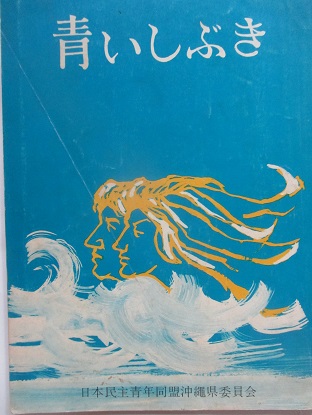
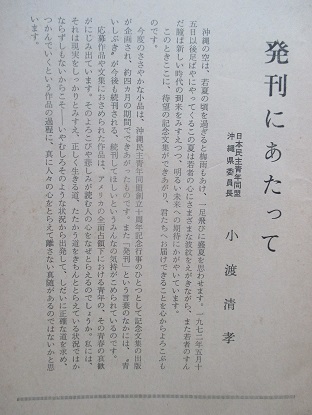
1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

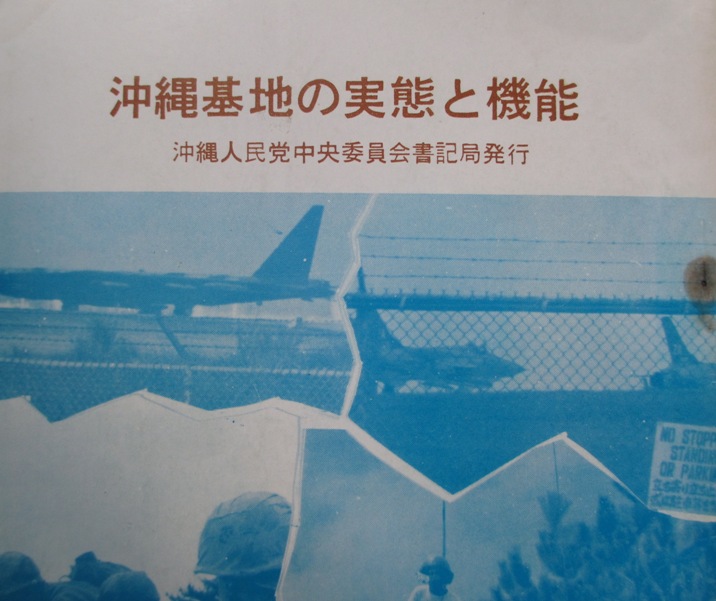
写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』
1973年
1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」
4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」
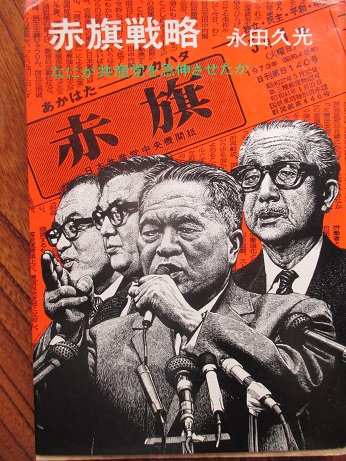
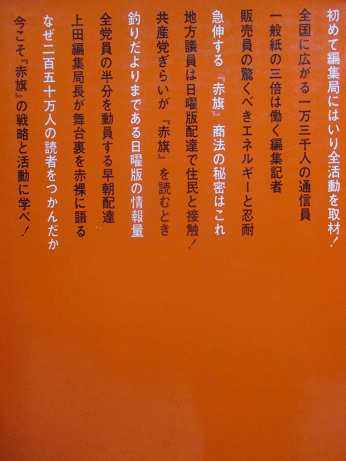
1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社
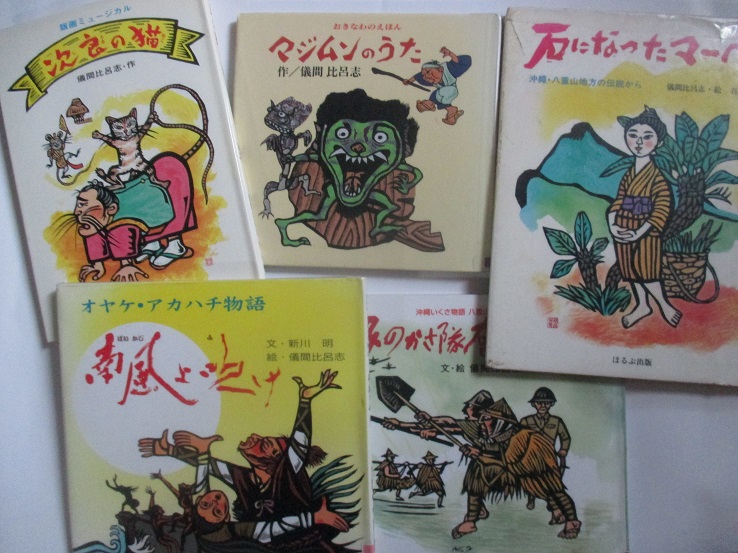
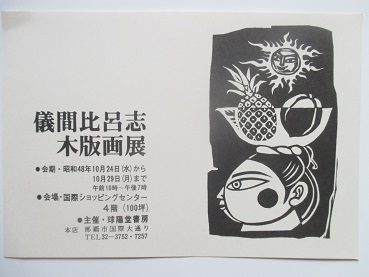
右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房
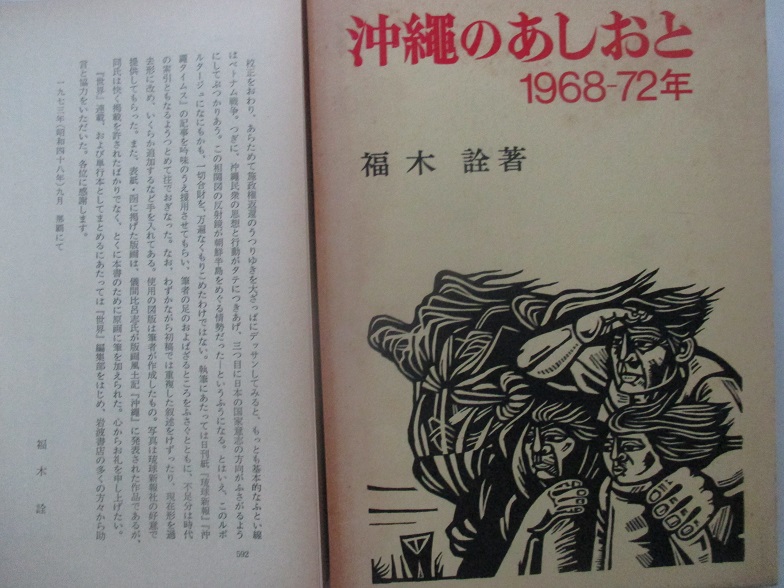
1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。
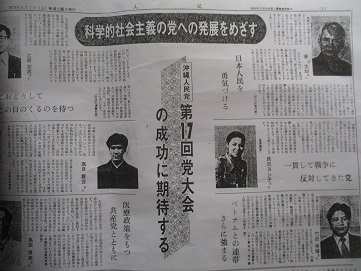
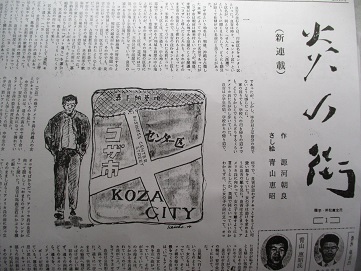
『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭
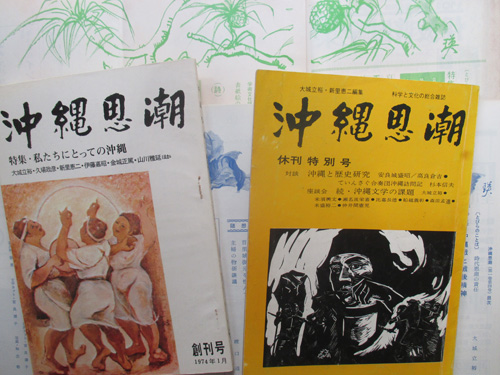
1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」
☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。
1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」
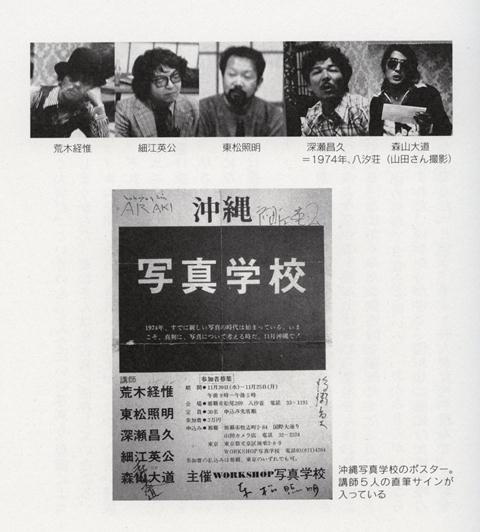
1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」
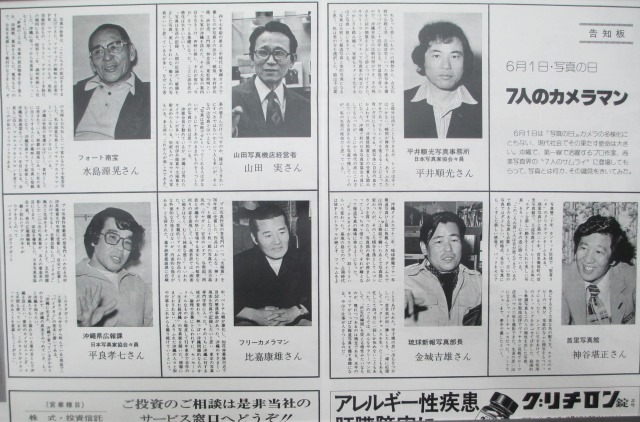
1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」
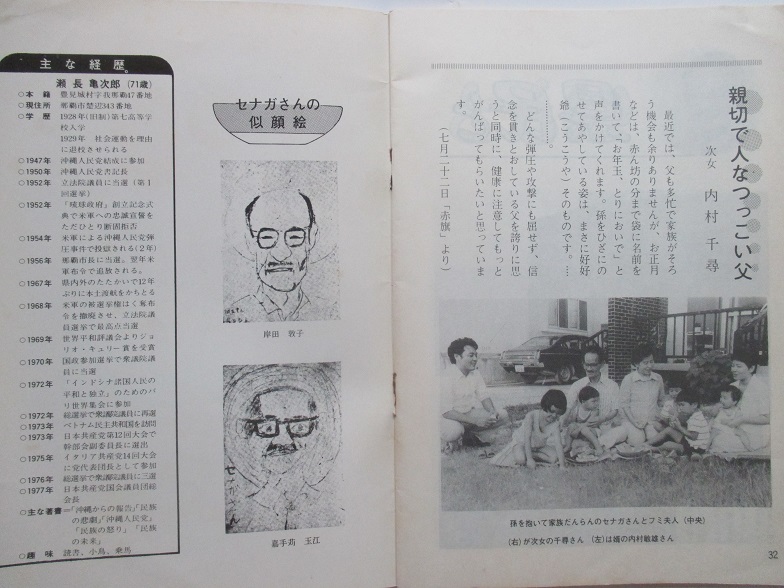
1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会


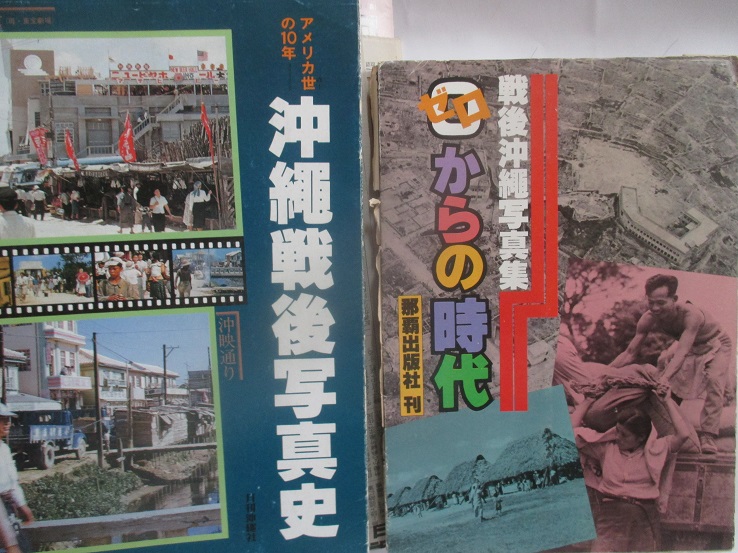
1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社
☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)
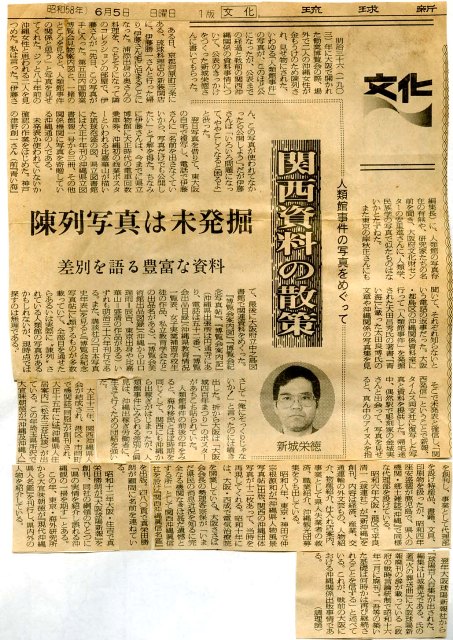
□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」
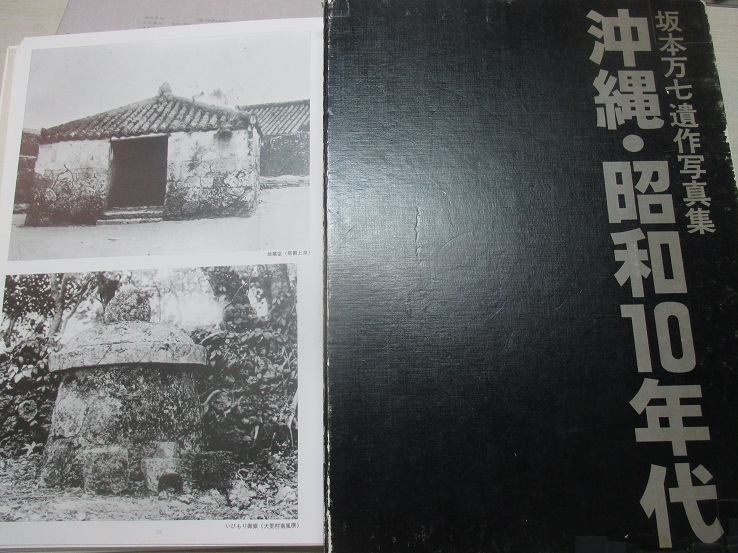
1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書
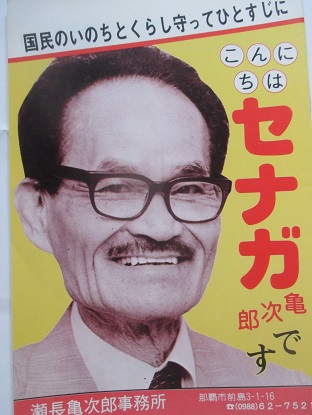
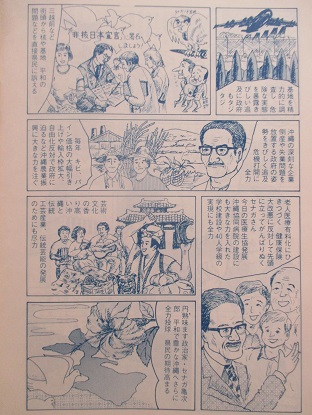
1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所
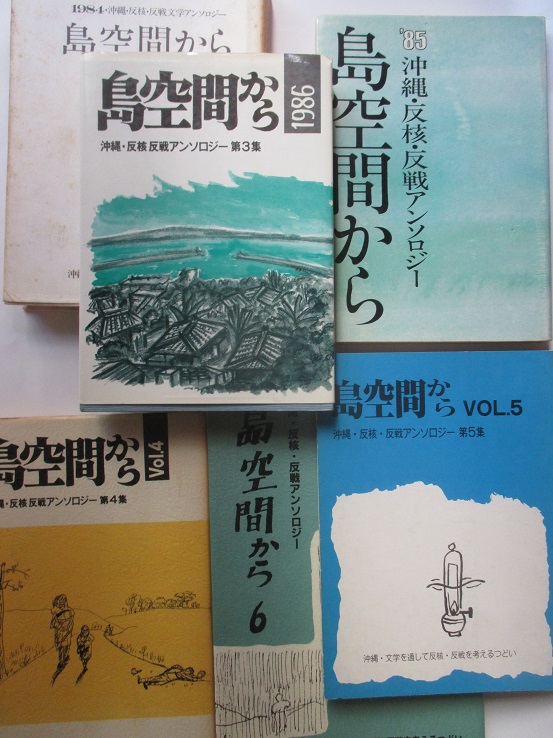
1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)
〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。
いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。
文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。
米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。
1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』
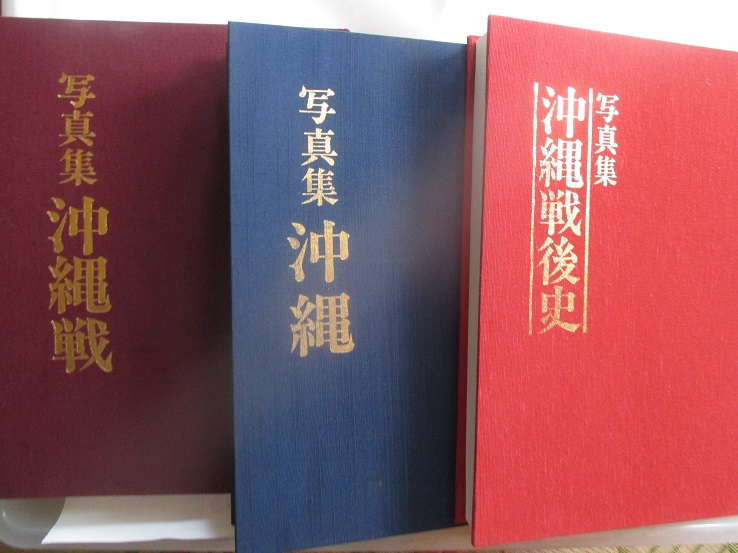
那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實
1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」
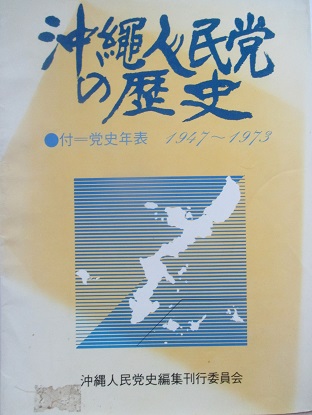
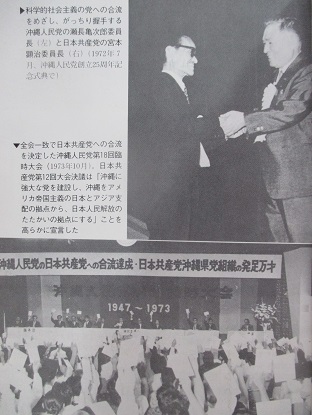
1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会
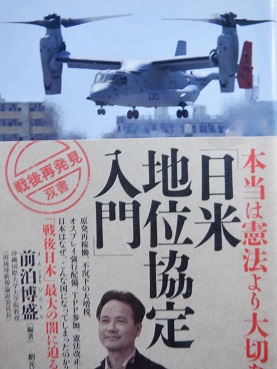
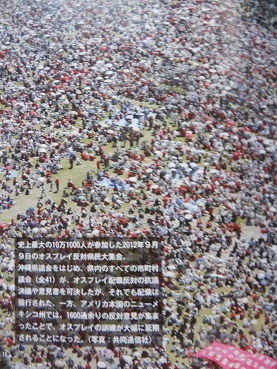
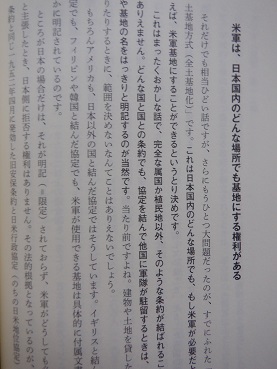
2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社
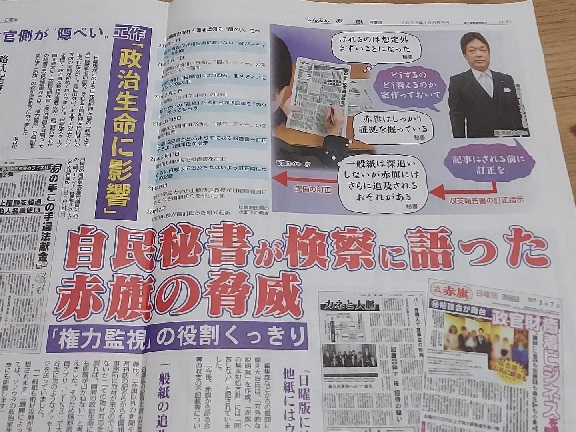

瀬長亀次郎は戦後も沖縄人民党行事としてこの碑(人民解放戦士真栄田一郎君に捧ぐ)の前に集い団結を誓った。瀬長亀次郎「弾圧は抵抗を呼ぶ 抵抗は友を呼ぶ」→1991年8月『瀬長亀次郎回想録』新日本出版社
1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社
ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ
写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。
悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫
○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。
郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長
善意の記録として・・・・沖縄県学生会
○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。
第一部
拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人
第二部
土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道
島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光
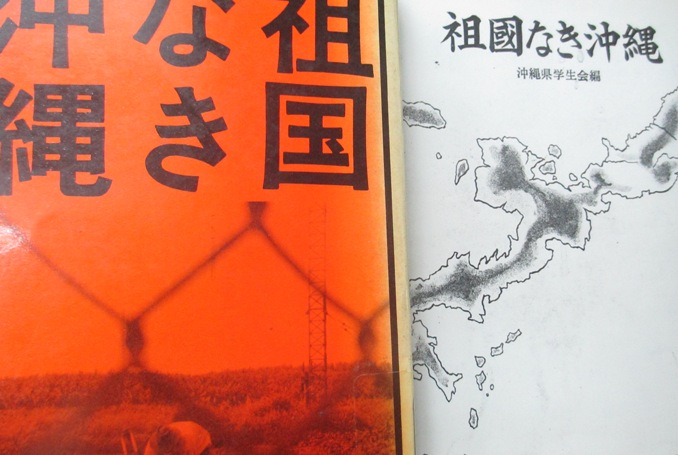
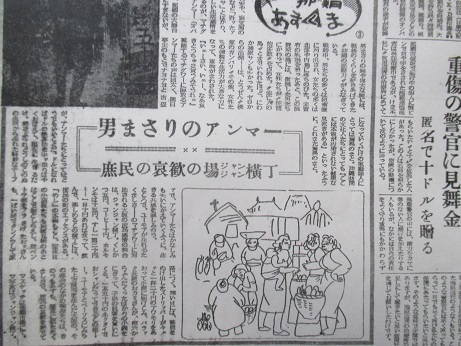
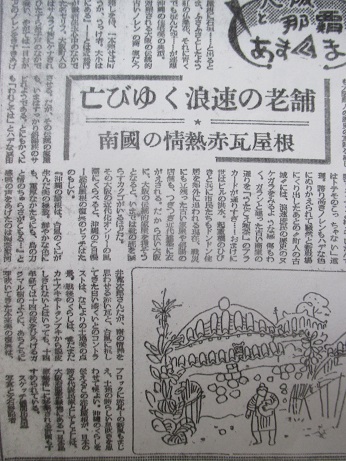
1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」
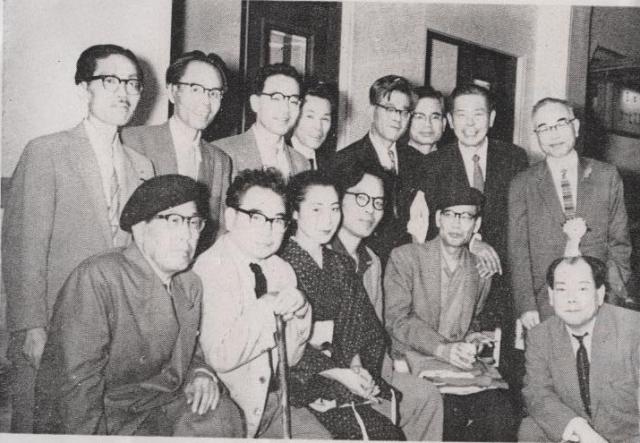
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子
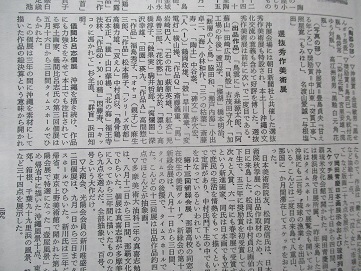

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』
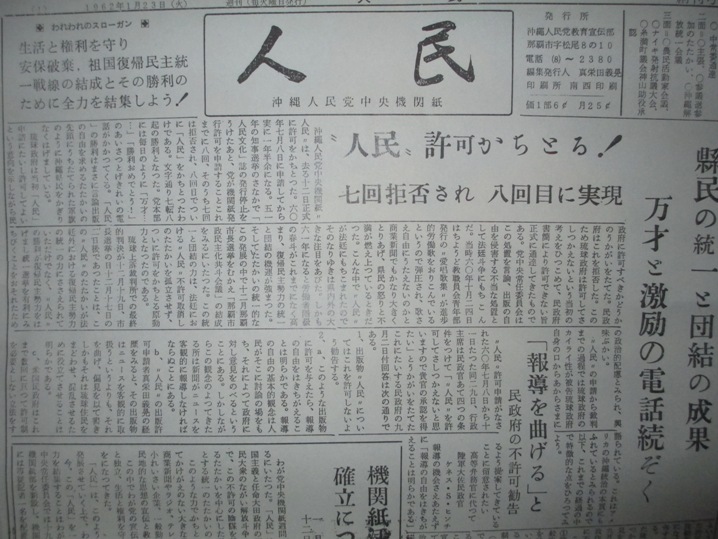

1963年
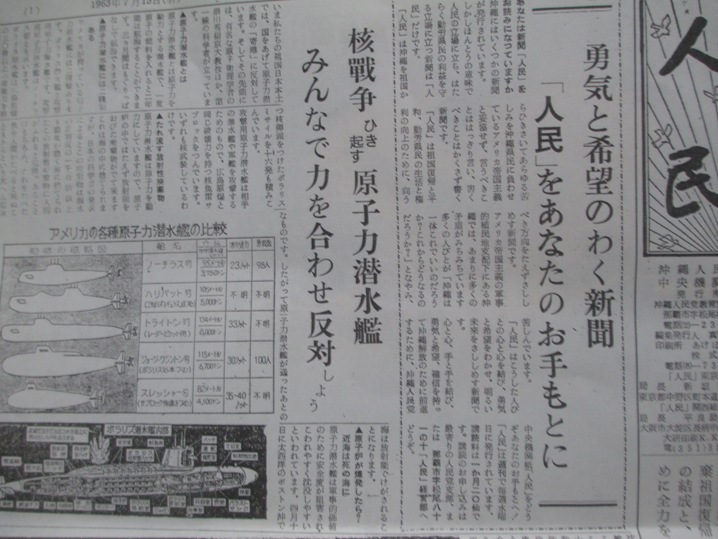
7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」
1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」
1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社
○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫
○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫
○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの
○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二
○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光
○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会
1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」
1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」
2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」
7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)
7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」
9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」
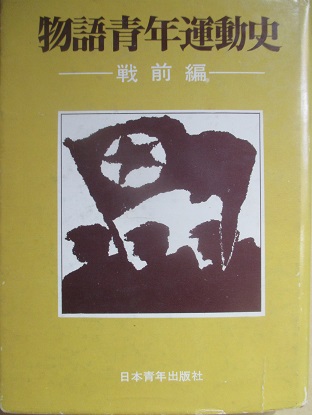

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社
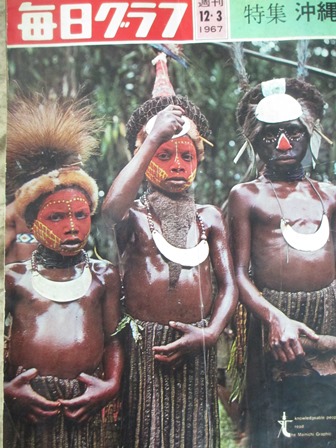
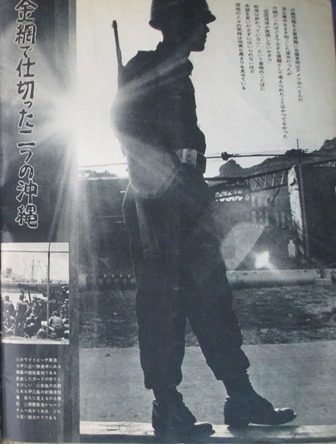
12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」
1968年
6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」
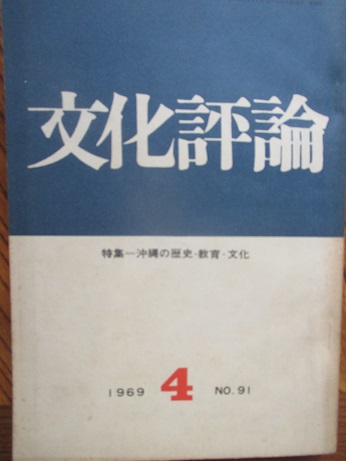
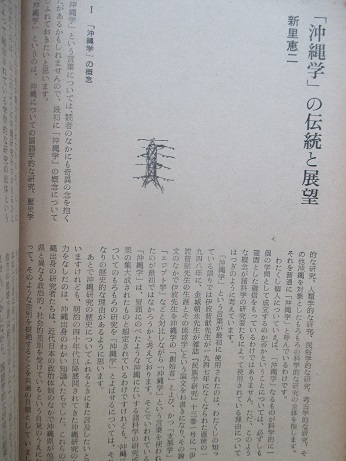
1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」
1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)
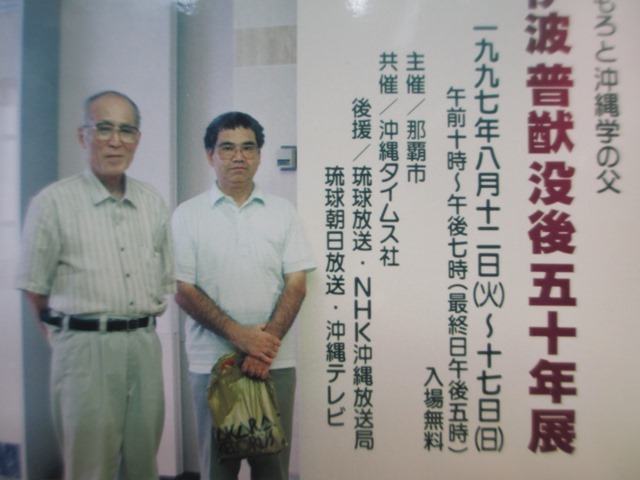
伊波廣定氏と新城栄徳
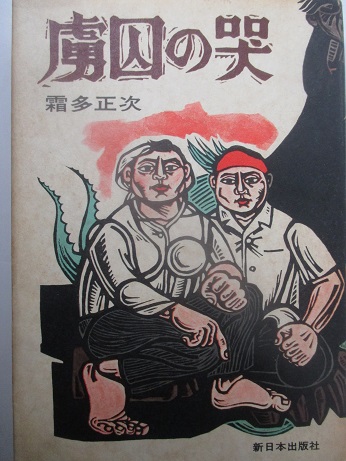
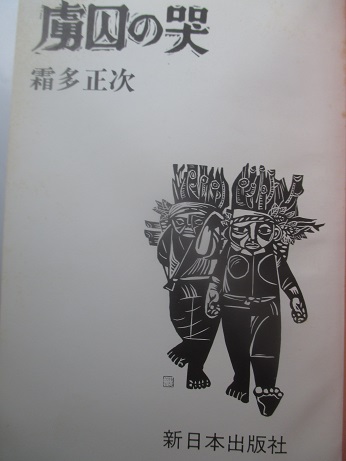
1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」
5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)
8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」
①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)
9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』
□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために
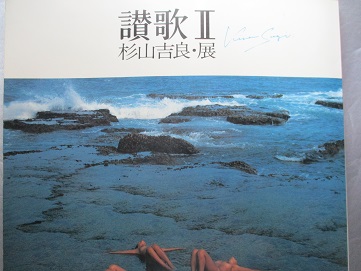
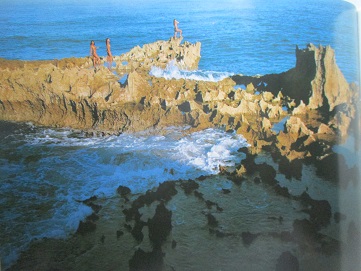
1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』
1971年
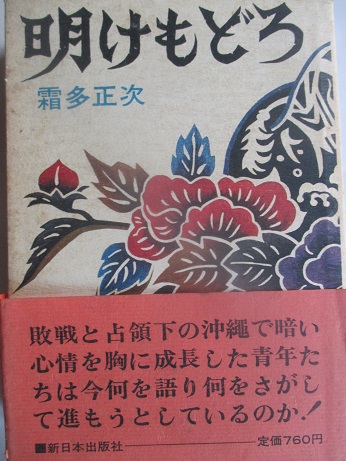
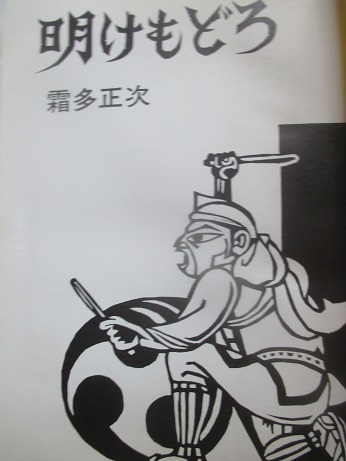
1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」
1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」
1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」
1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」
1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」
2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」
2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」
4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」
5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」
5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④
5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」
6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」
6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」
7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」
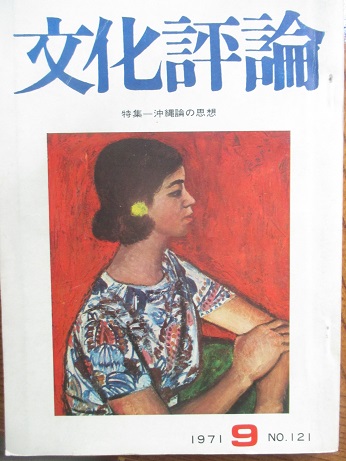
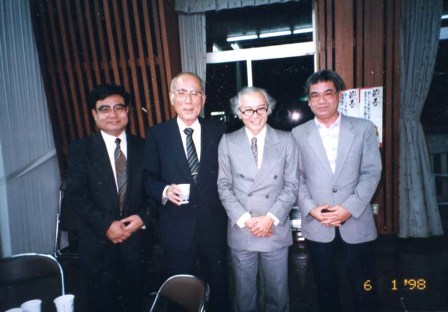
1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
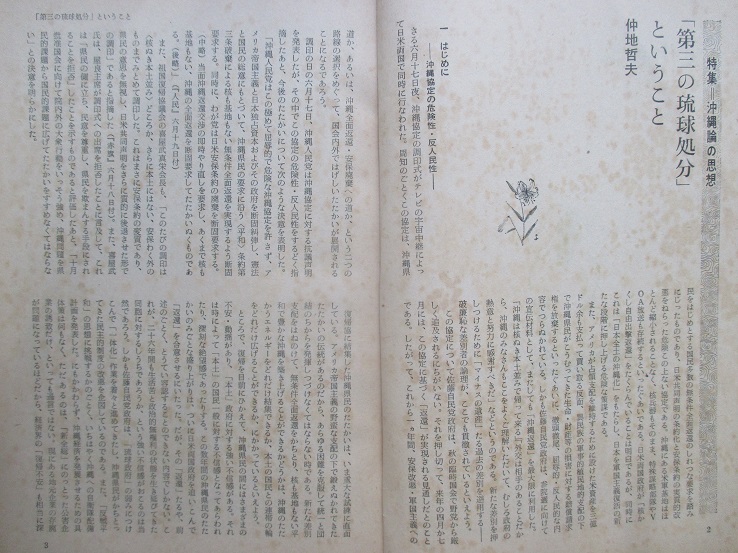
10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」
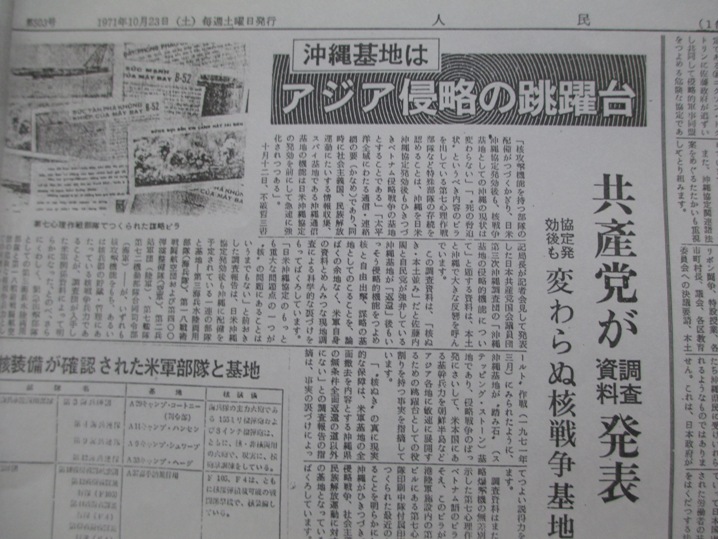
10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」


写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益
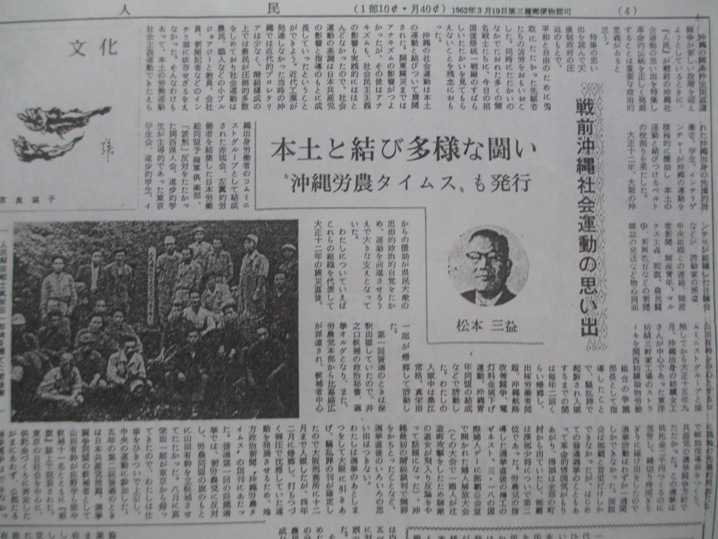
12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」
12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」
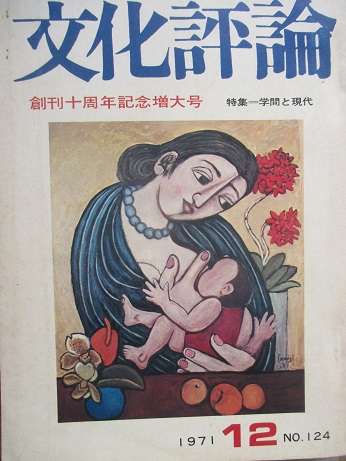
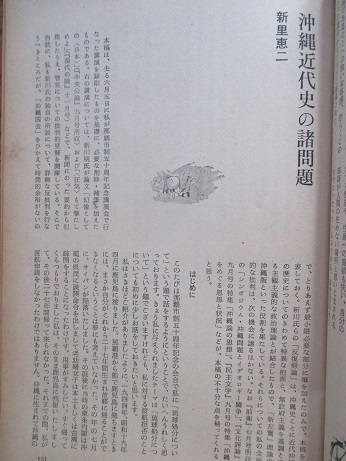
1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」
1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>
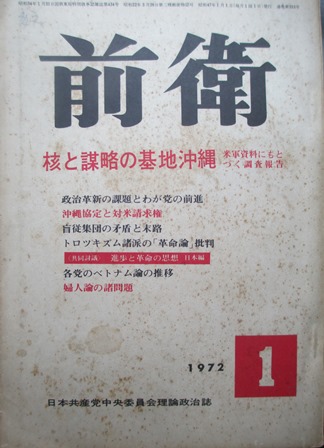

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫
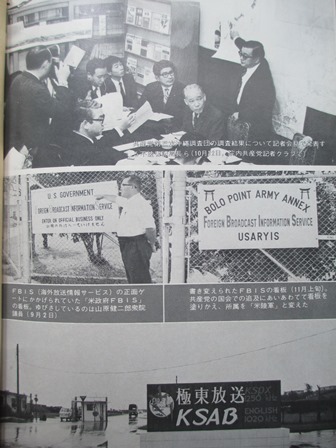
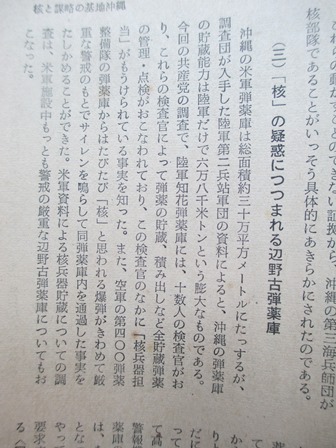
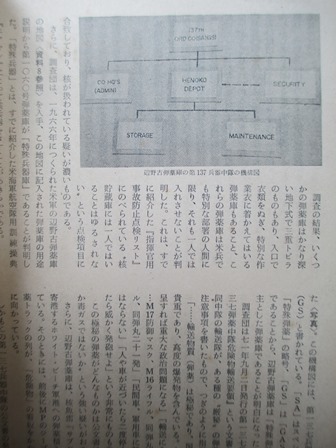
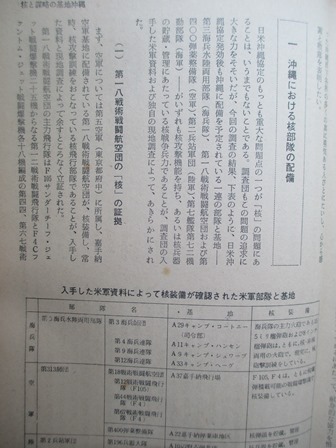


1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」
1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」
2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」
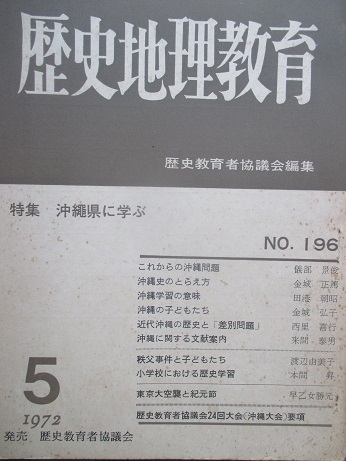
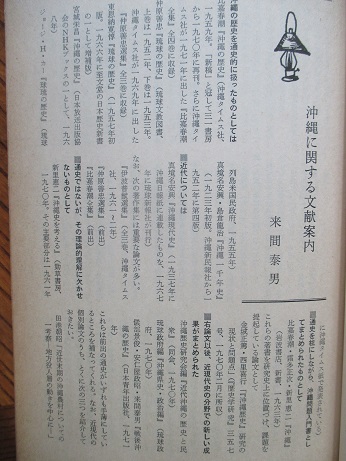
1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」
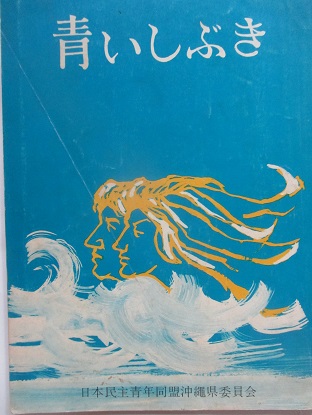
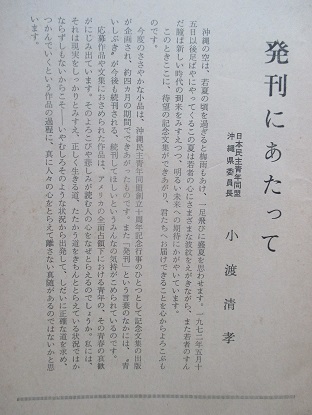
1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

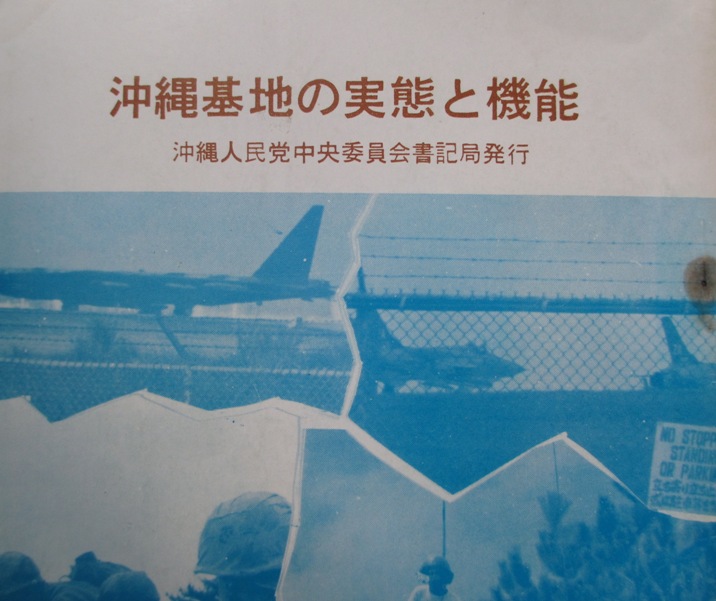
写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』
1973年
1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」
4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」
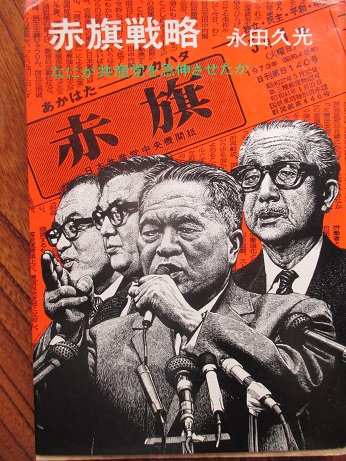
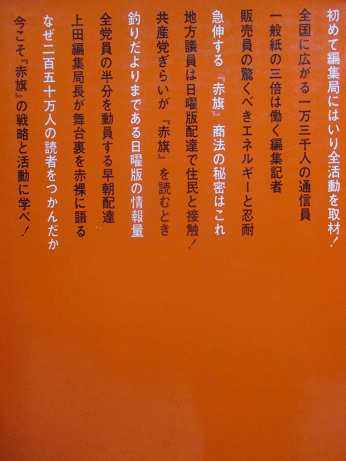
1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社
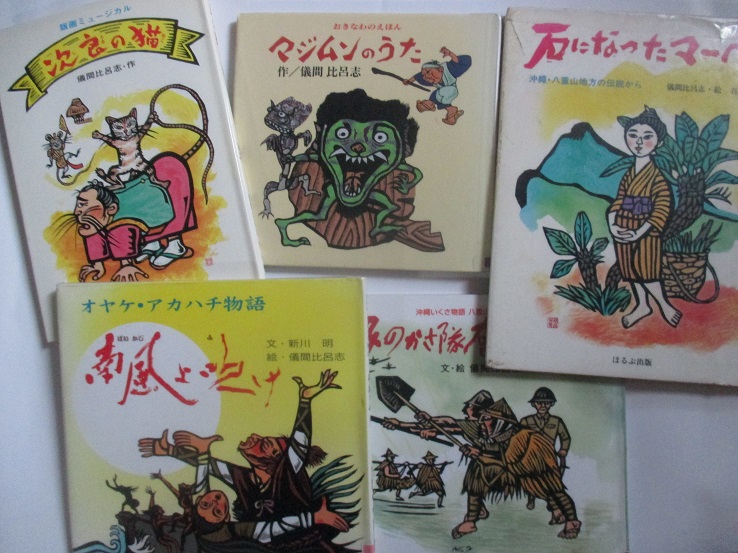
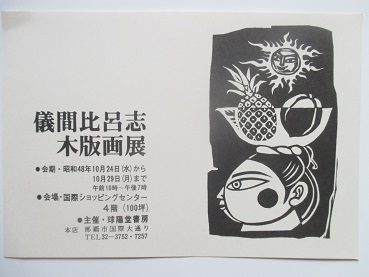
右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房
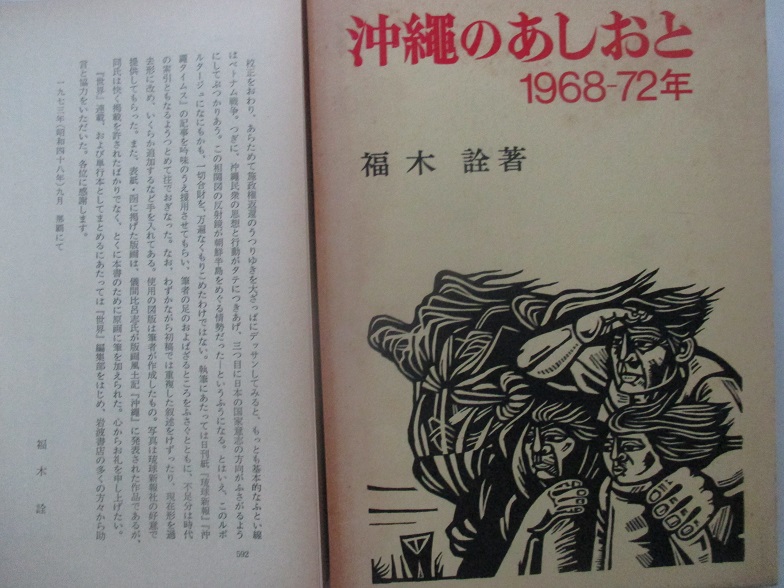
1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。
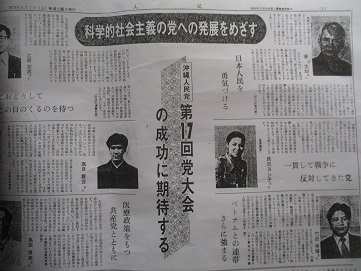
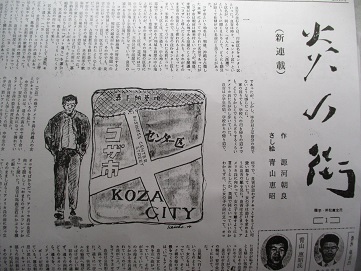
『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭
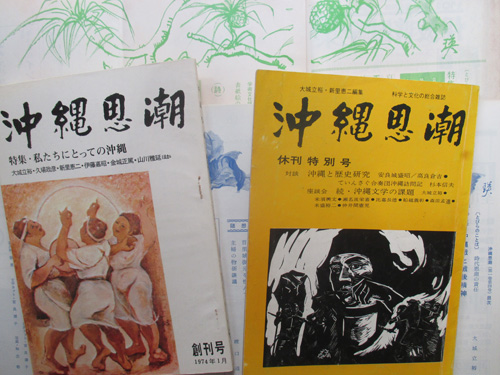
1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」
☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。
1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」
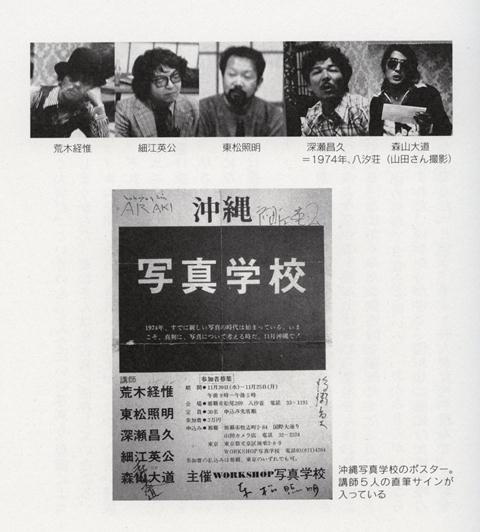
1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」
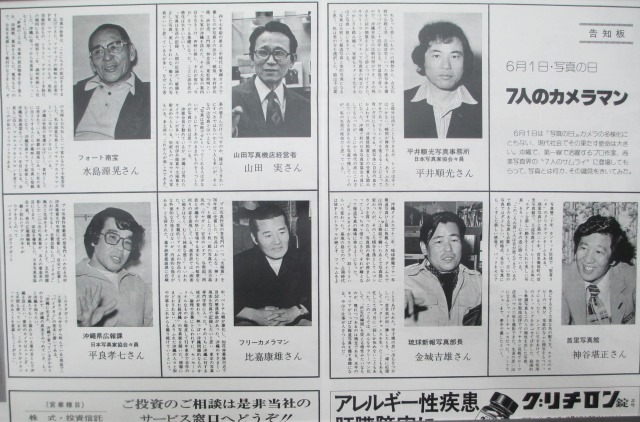
1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」
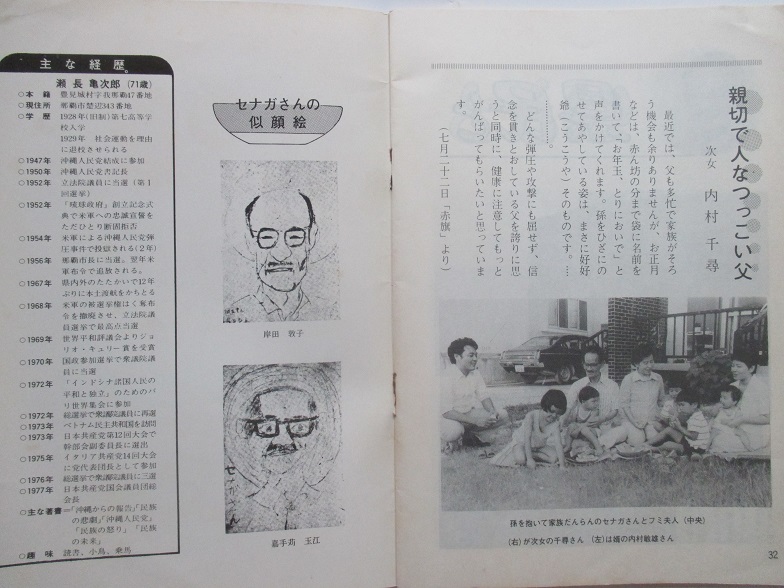
1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会


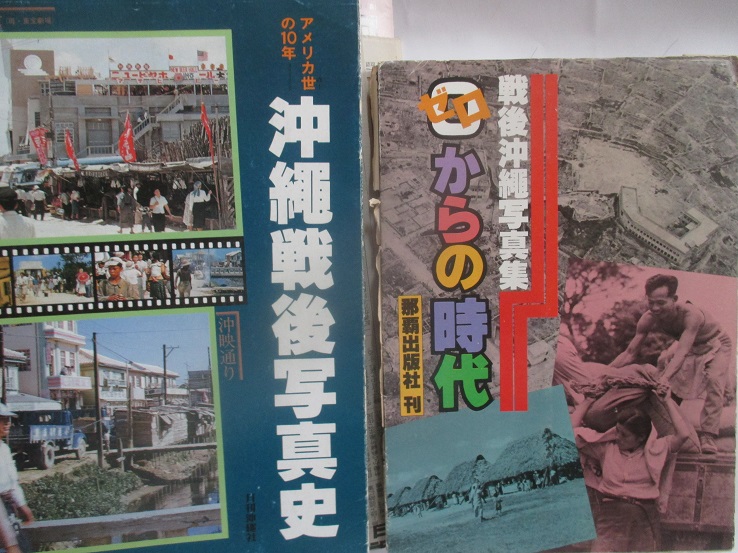
1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社
☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)
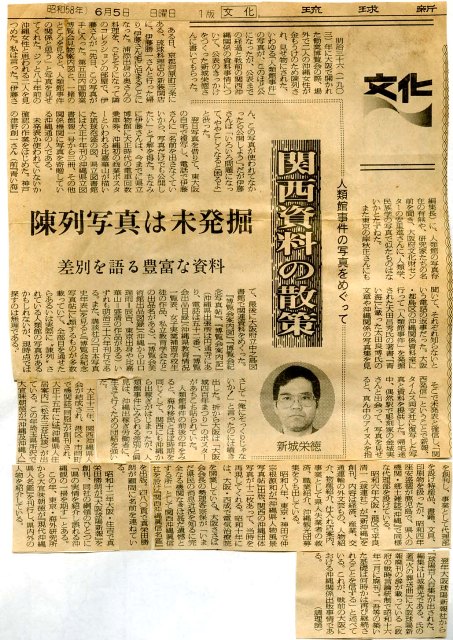
□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」
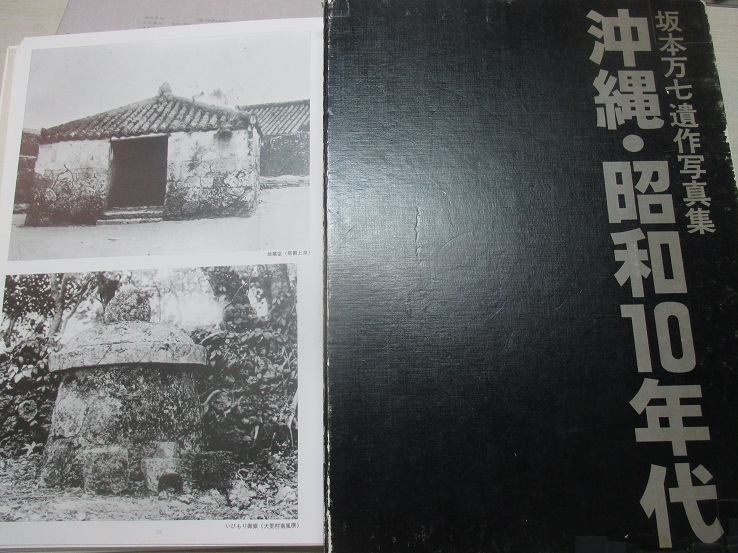
1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書
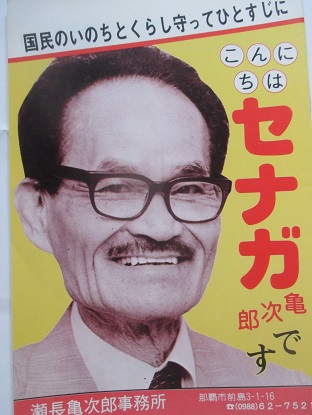
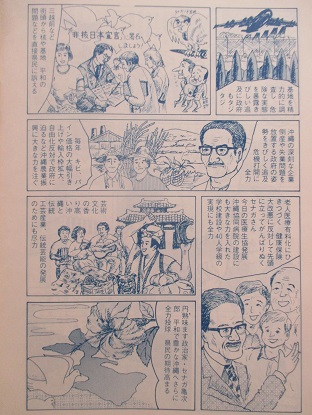
1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所
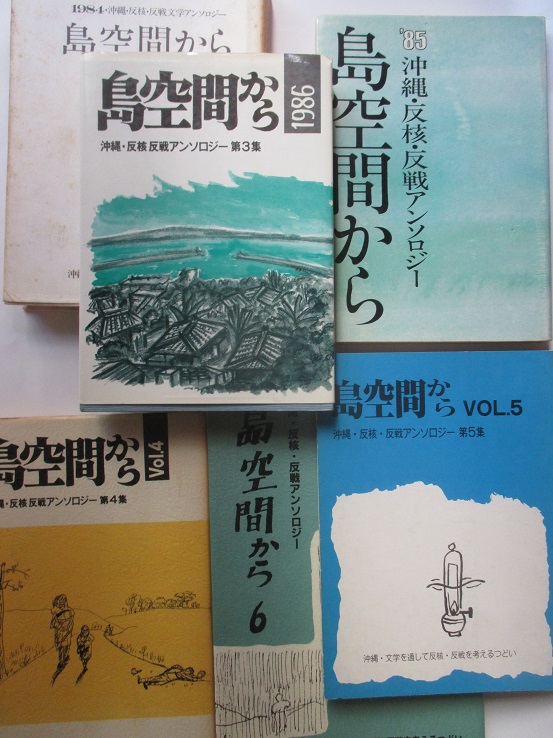
1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)
〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。
いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。
文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。
米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。
1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』
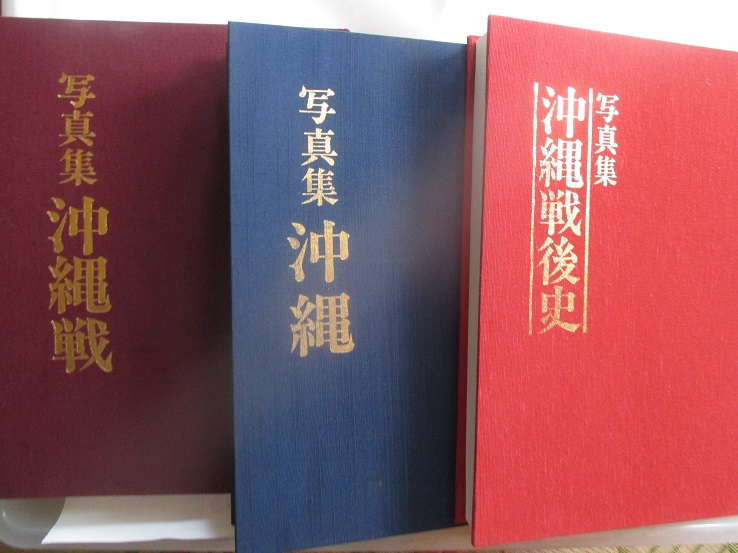
那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實
1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」
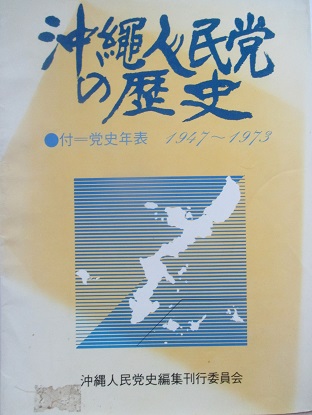
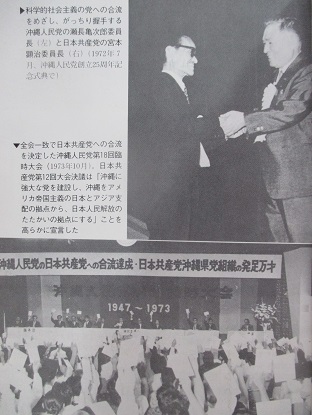
1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会
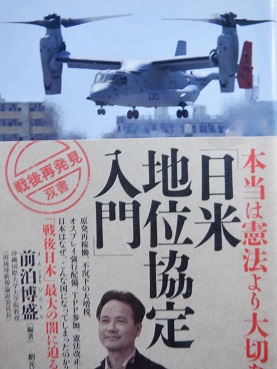
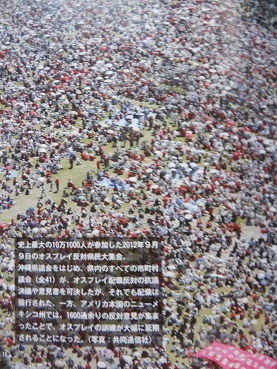
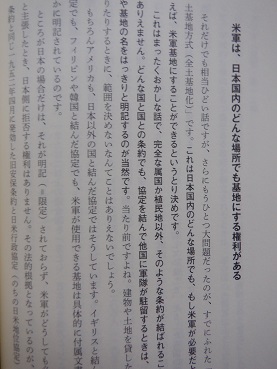
2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社
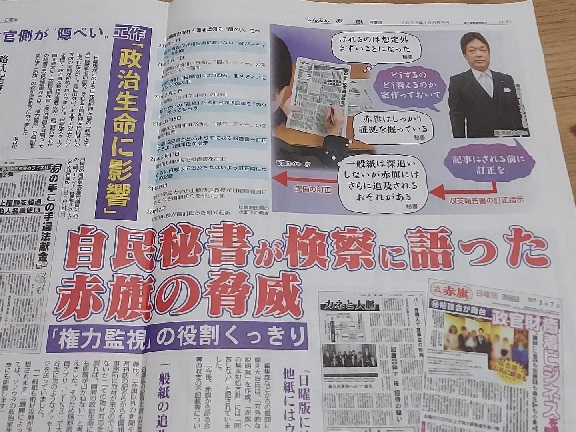
02/01: 新城栄徳「琉球文化史散歩」③
第三回訪沖
12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。
井上昇三(日本旅行協会)/1940年3月ー『月刊民藝』□観光地としての沖縄ー今回、日本民藝協会が主体となって沖縄見学団が組織された際、水沢氏と小生とは観光方面の仕事に協力する目的で参加したのであった。そして幾多の収穫を得て帰ることが出来た。見学の一端は雑誌「旅」に発表する義務があったのだが、それを果たすに際して非常なる困難に逢着したのである。沖縄を琉球と云はぬ様、沖縄県を物珍しく取り扱はぬ様、特異の風俗・言語を他府県と比較したりその差を強調したりしない様等の注意を払ふ必要を感じたのである。他府県の者として沖縄を旅しての印象を正直に記したり、まだ沖縄を知らぬ人々に出来るだけ沖縄に興味を抱かせる様に紹介しようとしたら、恐らく其の筆者は沖縄県民の多大の激怒を買ふに至るのであらうといふ不安があつたのである。
かかる不徹底なる態度で書かなければならなかつた事は私としては誠に不愉快であり、執筆を終わりても其の後味の悪さは日が経過しても薄くならなかつた。所が本誌から原稿を求められて、ここに「旅」には発表し得なかつた部分と、鮮明な態度をとつている本誌に発表するの機会を与へられた事は深く感謝する次第である。
沖縄は気象学、動物学、植物学、言語学、民俗学殊に最近は工藝等の領域に於いては相当の研究がなされ且つ学界には発表せられている様ではあるが、観光学の分野に於いては他の諸学に比して数段遅れている事は否めない。何故かくもこの沖縄県のみ観光的に残されていたのかといふと、他に種々の理由もあらうけれども第一に本州の諸島と余りにも離れていたといふ簡単な理由に過ぎないと思ふ。同じ島でも佐渡の如くに近いと観光的に発展し過ぎてしまふ位にまでなつてしまふのである。この地理的条件は不幸でもあつたらうが他面に発展を伴ふ堕落から免れる幸福もあつたわけである。
次に兎角観光地といふ所では他から来た観光客の好んで見たがる箇所は地元では見せたくない場所が多いといふ問題がある。之は何処でも起こる問題で日本全体としても考慮しなければならないのである。何も沖縄県だけが考へなければならない問題ではないし、何処の府県でもお互い様である。之はもつと気楽に考へて宜しい問題だと思ふ。唯、好意的に観察して貰ふ様に充分なる説明をして納得して行く事は望ましい事である。之は案内記の書き方に依つて相当の効果は挙げる事が可能だらうと思はれる。
以上先ず云ひ難い点を敢て云つておいて本題に入る事としよう。
今回の沖縄の旅ほど、旅は有益であると知つた経験は従来無かつた。百閒も一見に如かざるの真理も充分に知る事が出来た。沖縄県の観光資源の豊富に恵まれていたのには驚嘆した。一月といふ時季に行つた為に特に感じたのかと思ふが、冬季の温暖な事は強味だと思ふ。霜雪を知らぬ土地に育つ植物の見事さ、沖縄全体が温室の如きではないか。寒中に露地で赤々と花の咲いている國が他にあらうか。海の水は空を溶かした様に綺麗だし、海岸の風景は到る処絵の様に美しい。島全体を風致地区として保存したい位だ。口腹の満足せしむる沖縄料理の美味に泡盛の清烈は此の土地で味つてこそ意義がある。加之、目と耳を楽しませるものには民謡と踊りと芝居がある。其の各々に有機的な機関があつて地方色が強くしみ込んで居り、且つ、にじみ出して居る。之等は一つ一つ切り離すべきではない。だから、どうしても沖縄に来られよ、と呼びかけなければいけない。呼びかける以上は相当の自信を以て臨むべきであらう。
観光地沖縄として出来るなれば次の3項目を実行し得たら立派な観光地として自慢出来ると思ふ。現在の社会、経済事情として早急の実現は困難であらうとは思ふが、なるべく其の実現に努力して完成の日の近からむ事を希望する次第である。何でもかんでも作れるなど無理な事を云ふのではない。出来る時にやれる様に常に心掛けておく事が必要なのである。
交通機関の完備 現在の県営鉄道は観光客には利用されていない様である。船は那覇名護間も毎日は通っていない様であるから、どうしても一番頼りにするのは乗合自動車といふ事にならう。そのバスが常に満員であつた事は、時節柄減車の已むなき為でもあつたらうが、もつと運転回数を多くする必要を示すものであらう。バスの能率増進は道路次第であるから、島内の道路網の拡充は他の意味から云つても重要な事業と云へよう。坂の比較的少ない路線は木炭車でも配してみては如何であらうか。一方には遊歩道も欲しいものである。首里と那覇の間は自動車で早々に過ぎ去るには残念な位眺望の良い所がある。殊に首里から那覇へ下りて来る道が良い。私はわざわざ一度人力車で下つてみた。尤も之はバスに乗れなかつたからでもあつたのだけれども、想像以上によい景色に感嘆の声を発した程であつた。道路は全部ペーヴメントとはならなくても今日国頭方面でも自由にバスを通じてる程度のものがあるのだから、其の完成には比較的困難を感じないですむのではないかとも思はれる。そして自由にバスが走り廻れれば申し分ない。
宿泊設備 旅館は現在に於いては余り優秀とは云い難い様に思はれる。旅館の発達しない理由の一に辻の存在が考へられるかも知れない。が、然し、それとは別に切離しても設備の整つた旅館がもう少し欲しい。何も外国人向きのホテルを建てよと叫ぶわけでは決してない。短期滞在の客はいいとして長期滞在の客に対する設備が不完全ではないだらうか。下宿をするといふ事は事実上不可能らしい。この方面の要望は従来なかつたものか、将来の客一に後考を煩したい問題の一である。僅か20数名の団体客が2軒の旅館に下宿しなければならないといふ事は遺憾であつた。せめて30名は一軒に泊まれなくては不便である。
序でに旅館の食事に就いて一言しておく。旅館に泊まる人といへば原則としてその土地の人ではないのであるから、其の土地の料理を出して貰ひたいものである。この事は沖縄だけの問題ではなく、全国的に共通の大問題なのである。某先生が「旅とは米の飯と鮪の刺身と灘の酒の全国的統一である」と云はれるのを聞いた事がある。が現在では白米が7分搗きに代つただけで他は同様である。尤も沖縄では灘の酒より泡盛が幅を利かしているのは僅かな地方差である。旅館では土地で採れるものを土地風に料理して出せ、といふ要望はこの10数年来幾度か叫ばれて来ながら少しも実行されていない。沖縄でも此の例に洩れなかった。沖縄料理を出してくれと特別に注文しても「豚の角煮」が一度出た位のものであつた。もう我々はうんざりしてしまつて、なるべく旅館では朝飯以外に食はない様に努力せざるをえなかつた。郷に入っては郷に従へといふ事もあるのだから、他の土地に来た者には一度は黙つて土地の料理を食はせる。それではいかんといふ客には所謂旅館の料理ー之を標準料理と云つた友人がいたが一寸面白いと思つたーを出せばよい。少なくとも郷土料理か標準料理か何れを希望するか位は聞いて貰ひたい。況や特に注文しても出さないのは言語道断である。古くなつた鮪の刺身を出して特にもてなしたつもりで居られたのではこつちは大迷惑である。聊か脱線したが、沖縄の如く郷土色の豊かで而も美味な料理が残つている所では一層注意して頂きたいと敢えて述べる次第である。
観光地の施設 崇元寺の電柱や旧首里城の龍樋の柵の如き悪例は出来るだけ速やかに改善して頂きたい。将来は棒杭一本、案内板一枚を立てるのにも注意して頂けば結構である。同じ表示板を立てるにしても、風致を破壊する事も出来れば風致を増す事も出来るのである。ぶちこはしは容易だが、其の回復は困難である。例へば万座毛の鳥居の如きである。故に最初の施設が肝要である。ペンキ塗りの棒杭を立てるよりは豊富に産する石材を用いて工夫すれば却つて効果をあげる事さへ出来はしないだらうか。然し徒に風致保存を唱へて住民の生活を犠牲にしてまでも実行せよなどなどわけのわからない事は云はない。ただ何れにしても建てるものであつたら良きものを建てる事にするといふ心掛けは常に失つて頂き度くないのである。
最後に念を押して申上げておきたい事は観光施設の行き過ぎにならぬ様に戒しむ可き事である。観光地として流行した場所で堕落しなかつた土地は先ず無いといつてよい位である。大阪商船の案内書ではないが「観光処女地」沖縄を汚したくないのは県民・観光客共に望む所でなくてはなるまい。尚一言したい事は、沖縄を観光的に発展せしめて一体どうするのか、といふ質問が出るかも知れないので、敢へて述べるならば、之は県の発展、県民の幸福にまで導かれる事だと云ひたいのである。県として最も恵まれたる観光資源を活用して観光客を吸収し、他府県人に金を落させて、而して県として裕福になれば之が県民の幸福にならないものであらうか。妄言多謝(15、2、9)
1940年
1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

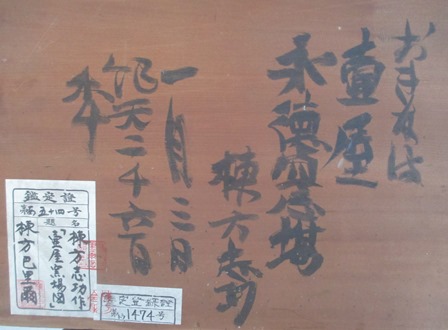
棟方志功「壺屋窯場の図」サエラ(携帯080-1533-3859)所蔵
1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。
1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。
1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。
1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。
1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。
1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。
1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。
1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。
1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。
1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。
第四回訪沖
7月24日ー11月開催予定の皇紀二千六百年奉祝事業の「琉球工藝文化大展覧会」準備のため田中俊雄、坂本万七を伴ない、4回目の訪沖に出発。 沖縄では、言語問題論争がなお続いていた。
8月2日ー沖縄県庁で知事渕上房太郎氏と会見し、標準語絶対反対論者と決めつけられた理由の説明を求める。この日「敢えて学務部の責任を問ふ」を琉球新報に載せる。 展覧会への出品依頼に、尚家をはじめ各方面から古作優品が出さ、陶器百点の外、絵画、染織も加わる。
写真撮影は、主として、「琉球風物写真展」(銀座三越)用の風物撮影を行う。 この間、坂本と撮影した海岸の写真が、海洋警備上の秘密を撮したとされ、警察に連行され、坂本は一夜留置された。
8月22日ー浮島丸にて那覇を発つ。
8月24日ー神戸着
1941年7月『茶わん』蘭郁二郎「琉球のぞ記」寶雲舎
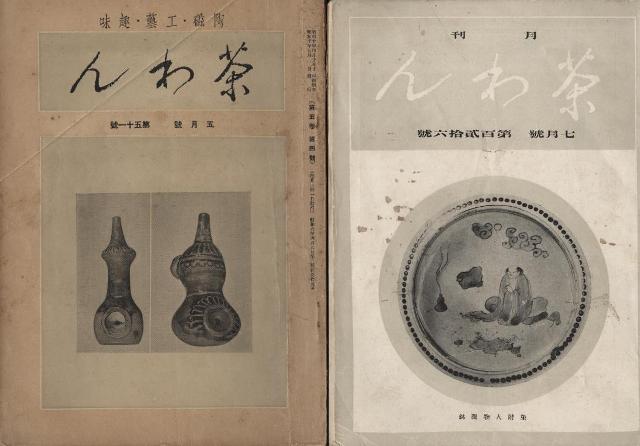
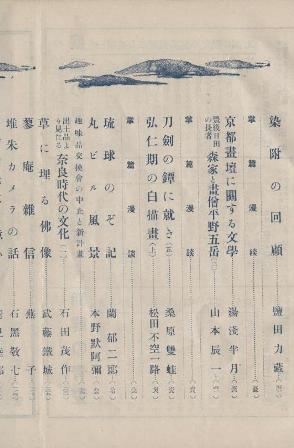

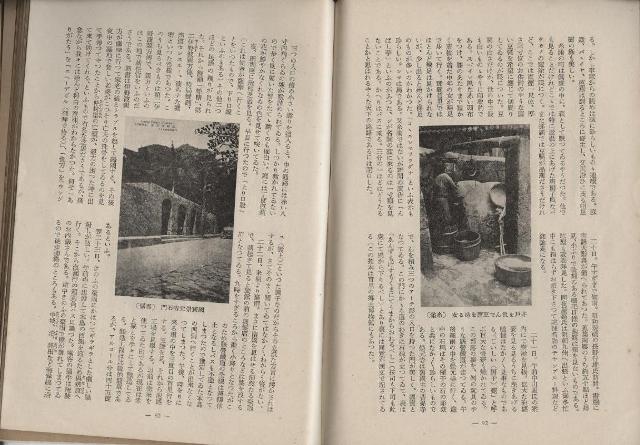
「茶わん」は陶芸愛好家向けの専門誌で、創刊は昭和六年三月。編集発行人は秦秀雄となっているが、実務は小野賢一郎がとりしきっていた。秦に代わって昭和七年五月号から編集発行人として遠藤敏夫の名がクレジットされる。編集部は芝区三田功運町六番地、聖坂を登り切った辺りにあった。(会津信吾「蘭郁二郎の生涯」)
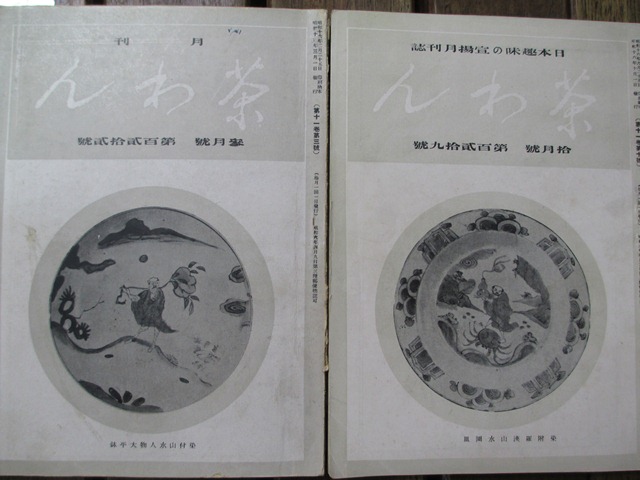
1941年8月『文学建設』蘭郁二郎「琉球ある記」
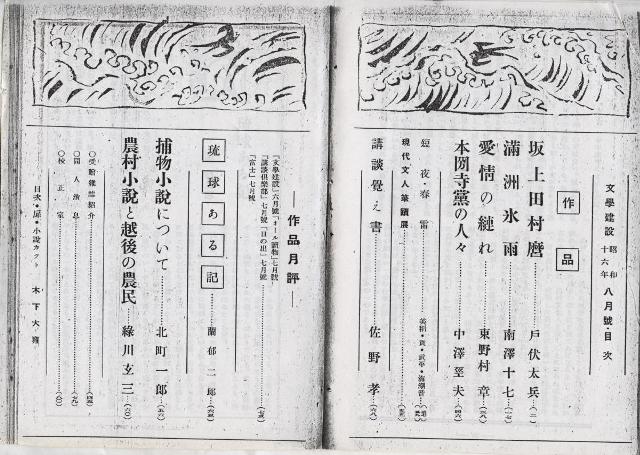
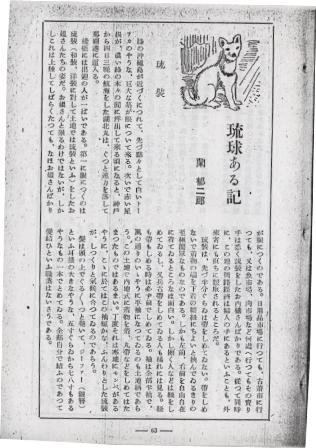
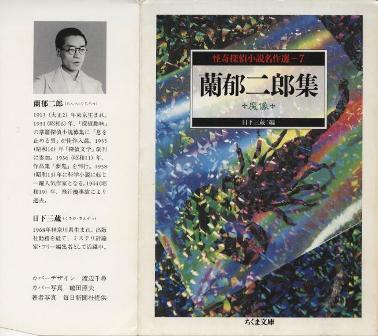
蘭郁二郎 らん-いくじろう 1913-1944 昭和時代前期の小説家。
大正2年9月2日生まれ。「探偵文学」同人となりミステリーをかくが,科学冒険小説に転じ,SF小説の先駆者のひとりとなった。海軍報道班員として台湾にわたり,昭和19年1月5日飛行機事故で死去。32歳。東京出身。東京高工卒。本名は遠藤敏夫。著作に「地図にない島」「地底大陸」など。→コトバンク

1942年9月『朝日新聞』「カメラ腕比べー尚謙・護得久朝章」
12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。
井上昇三(日本旅行協会)/1940年3月ー『月刊民藝』□観光地としての沖縄ー今回、日本民藝協会が主体となって沖縄見学団が組織された際、水沢氏と小生とは観光方面の仕事に協力する目的で参加したのであった。そして幾多の収穫を得て帰ることが出来た。見学の一端は雑誌「旅」に発表する義務があったのだが、それを果たすに際して非常なる困難に逢着したのである。沖縄を琉球と云はぬ様、沖縄県を物珍しく取り扱はぬ様、特異の風俗・言語を他府県と比較したりその差を強調したりしない様等の注意を払ふ必要を感じたのである。他府県の者として沖縄を旅しての印象を正直に記したり、まだ沖縄を知らぬ人々に出来るだけ沖縄に興味を抱かせる様に紹介しようとしたら、恐らく其の筆者は沖縄県民の多大の激怒を買ふに至るのであらうといふ不安があつたのである。
かかる不徹底なる態度で書かなければならなかつた事は私としては誠に不愉快であり、執筆を終わりても其の後味の悪さは日が経過しても薄くならなかつた。所が本誌から原稿を求められて、ここに「旅」には発表し得なかつた部分と、鮮明な態度をとつている本誌に発表するの機会を与へられた事は深く感謝する次第である。
沖縄は気象学、動物学、植物学、言語学、民俗学殊に最近は工藝等の領域に於いては相当の研究がなされ且つ学界には発表せられている様ではあるが、観光学の分野に於いては他の諸学に比して数段遅れている事は否めない。何故かくもこの沖縄県のみ観光的に残されていたのかといふと、他に種々の理由もあらうけれども第一に本州の諸島と余りにも離れていたといふ簡単な理由に過ぎないと思ふ。同じ島でも佐渡の如くに近いと観光的に発展し過ぎてしまふ位にまでなつてしまふのである。この地理的条件は不幸でもあつたらうが他面に発展を伴ふ堕落から免れる幸福もあつたわけである。
次に兎角観光地といふ所では他から来た観光客の好んで見たがる箇所は地元では見せたくない場所が多いといふ問題がある。之は何処でも起こる問題で日本全体としても考慮しなければならないのである。何も沖縄県だけが考へなければならない問題ではないし、何処の府県でもお互い様である。之はもつと気楽に考へて宜しい問題だと思ふ。唯、好意的に観察して貰ふ様に充分なる説明をして納得して行く事は望ましい事である。之は案内記の書き方に依つて相当の効果は挙げる事が可能だらうと思はれる。
以上先ず云ひ難い点を敢て云つておいて本題に入る事としよう。
今回の沖縄の旅ほど、旅は有益であると知つた経験は従来無かつた。百閒も一見に如かざるの真理も充分に知る事が出来た。沖縄県の観光資源の豊富に恵まれていたのには驚嘆した。一月といふ時季に行つた為に特に感じたのかと思ふが、冬季の温暖な事は強味だと思ふ。霜雪を知らぬ土地に育つ植物の見事さ、沖縄全体が温室の如きではないか。寒中に露地で赤々と花の咲いている國が他にあらうか。海の水は空を溶かした様に綺麗だし、海岸の風景は到る処絵の様に美しい。島全体を風致地区として保存したい位だ。口腹の満足せしむる沖縄料理の美味に泡盛の清烈は此の土地で味つてこそ意義がある。加之、目と耳を楽しませるものには民謡と踊りと芝居がある。其の各々に有機的な機関があつて地方色が強くしみ込んで居り、且つ、にじみ出して居る。之等は一つ一つ切り離すべきではない。だから、どうしても沖縄に来られよ、と呼びかけなければいけない。呼びかける以上は相当の自信を以て臨むべきであらう。
観光地沖縄として出来るなれば次の3項目を実行し得たら立派な観光地として自慢出来ると思ふ。現在の社会、経済事情として早急の実現は困難であらうとは思ふが、なるべく其の実現に努力して完成の日の近からむ事を希望する次第である。何でもかんでも作れるなど無理な事を云ふのではない。出来る時にやれる様に常に心掛けておく事が必要なのである。
交通機関の完備 現在の県営鉄道は観光客には利用されていない様である。船は那覇名護間も毎日は通っていない様であるから、どうしても一番頼りにするのは乗合自動車といふ事にならう。そのバスが常に満員であつた事は、時節柄減車の已むなき為でもあつたらうが、もつと運転回数を多くする必要を示すものであらう。バスの能率増進は道路次第であるから、島内の道路網の拡充は他の意味から云つても重要な事業と云へよう。坂の比較的少ない路線は木炭車でも配してみては如何であらうか。一方には遊歩道も欲しいものである。首里と那覇の間は自動車で早々に過ぎ去るには残念な位眺望の良い所がある。殊に首里から那覇へ下りて来る道が良い。私はわざわざ一度人力車で下つてみた。尤も之はバスに乗れなかつたからでもあつたのだけれども、想像以上によい景色に感嘆の声を発した程であつた。道路は全部ペーヴメントとはならなくても今日国頭方面でも自由にバスを通じてる程度のものがあるのだから、其の完成には比較的困難を感じないですむのではないかとも思はれる。そして自由にバスが走り廻れれば申し分ない。
宿泊設備 旅館は現在に於いては余り優秀とは云い難い様に思はれる。旅館の発達しない理由の一に辻の存在が考へられるかも知れない。が、然し、それとは別に切離しても設備の整つた旅館がもう少し欲しい。何も外国人向きのホテルを建てよと叫ぶわけでは決してない。短期滞在の客はいいとして長期滞在の客に対する設備が不完全ではないだらうか。下宿をするといふ事は事実上不可能らしい。この方面の要望は従来なかつたものか、将来の客一に後考を煩したい問題の一である。僅か20数名の団体客が2軒の旅館に下宿しなければならないといふ事は遺憾であつた。せめて30名は一軒に泊まれなくては不便である。
序でに旅館の食事に就いて一言しておく。旅館に泊まる人といへば原則としてその土地の人ではないのであるから、其の土地の料理を出して貰ひたいものである。この事は沖縄だけの問題ではなく、全国的に共通の大問題なのである。某先生が「旅とは米の飯と鮪の刺身と灘の酒の全国的統一である」と云はれるのを聞いた事がある。が現在では白米が7分搗きに代つただけで他は同様である。尤も沖縄では灘の酒より泡盛が幅を利かしているのは僅かな地方差である。旅館では土地で採れるものを土地風に料理して出せ、といふ要望はこの10数年来幾度か叫ばれて来ながら少しも実行されていない。沖縄でも此の例に洩れなかった。沖縄料理を出してくれと特別に注文しても「豚の角煮」が一度出た位のものであつた。もう我々はうんざりしてしまつて、なるべく旅館では朝飯以外に食はない様に努力せざるをえなかつた。郷に入っては郷に従へといふ事もあるのだから、他の土地に来た者には一度は黙つて土地の料理を食はせる。それではいかんといふ客には所謂旅館の料理ー之を標準料理と云つた友人がいたが一寸面白いと思つたーを出せばよい。少なくとも郷土料理か標準料理か何れを希望するか位は聞いて貰ひたい。況や特に注文しても出さないのは言語道断である。古くなつた鮪の刺身を出して特にもてなしたつもりで居られたのではこつちは大迷惑である。聊か脱線したが、沖縄の如く郷土色の豊かで而も美味な料理が残つている所では一層注意して頂きたいと敢えて述べる次第である。
観光地の施設 崇元寺の電柱や旧首里城の龍樋の柵の如き悪例は出来るだけ速やかに改善して頂きたい。将来は棒杭一本、案内板一枚を立てるのにも注意して頂けば結構である。同じ表示板を立てるにしても、風致を破壊する事も出来れば風致を増す事も出来るのである。ぶちこはしは容易だが、其の回復は困難である。例へば万座毛の鳥居の如きである。故に最初の施設が肝要である。ペンキ塗りの棒杭を立てるよりは豊富に産する石材を用いて工夫すれば却つて効果をあげる事さへ出来はしないだらうか。然し徒に風致保存を唱へて住民の生活を犠牲にしてまでも実行せよなどなどわけのわからない事は云はない。ただ何れにしても建てるものであつたら良きものを建てる事にするといふ心掛けは常に失つて頂き度くないのである。
最後に念を押して申上げておきたい事は観光施設の行き過ぎにならぬ様に戒しむ可き事である。観光地として流行した場所で堕落しなかつた土地は先ず無いといつてよい位である。大阪商船の案内書ではないが「観光処女地」沖縄を汚したくないのは県民・観光客共に望む所でなくてはなるまい。尚一言したい事は、沖縄を観光的に発展せしめて一体どうするのか、といふ質問が出るかも知れないので、敢へて述べるならば、之は県の発展、県民の幸福にまで導かれる事だと云ひたいのである。県として最も恵まれたる観光資源を活用して観光客を吸収し、他府県人に金を落させて、而して県として裕福になれば之が県民の幸福にならないものであらうか。妄言多謝(15、2、9)
1940年
1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

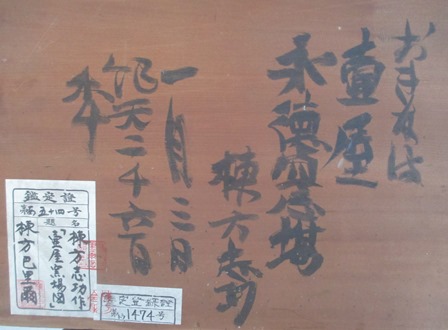
棟方志功「壺屋窯場の図」サエラ(携帯080-1533-3859)所蔵
1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。
1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。
1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。
1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。
1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。
1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。
1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。
1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。
1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。
1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。
第四回訪沖
7月24日ー11月開催予定の皇紀二千六百年奉祝事業の「琉球工藝文化大展覧会」準備のため田中俊雄、坂本万七を伴ない、4回目の訪沖に出発。 沖縄では、言語問題論争がなお続いていた。
8月2日ー沖縄県庁で知事渕上房太郎氏と会見し、標準語絶対反対論者と決めつけられた理由の説明を求める。この日「敢えて学務部の責任を問ふ」を琉球新報に載せる。 展覧会への出品依頼に、尚家をはじめ各方面から古作優品が出さ、陶器百点の外、絵画、染織も加わる。
写真撮影は、主として、「琉球風物写真展」(銀座三越)用の風物撮影を行う。 この間、坂本と撮影した海岸の写真が、海洋警備上の秘密を撮したとされ、警察に連行され、坂本は一夜留置された。
8月22日ー浮島丸にて那覇を発つ。
8月24日ー神戸着
1941年7月『茶わん』蘭郁二郎「琉球のぞ記」寶雲舎
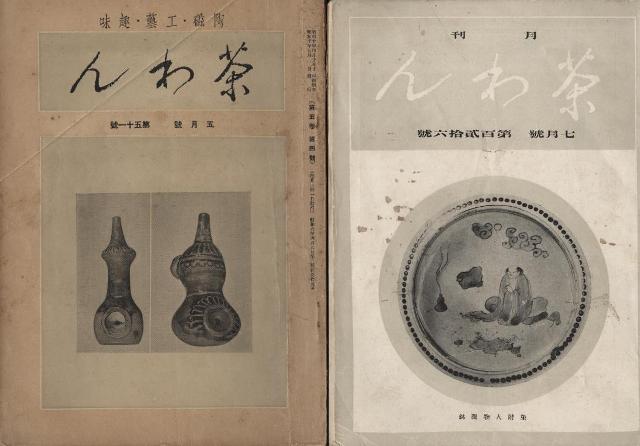
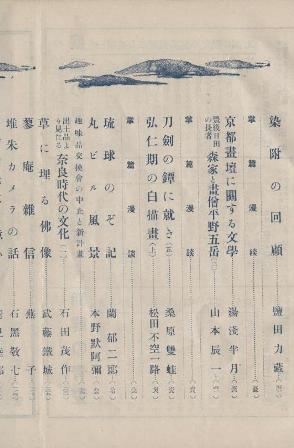

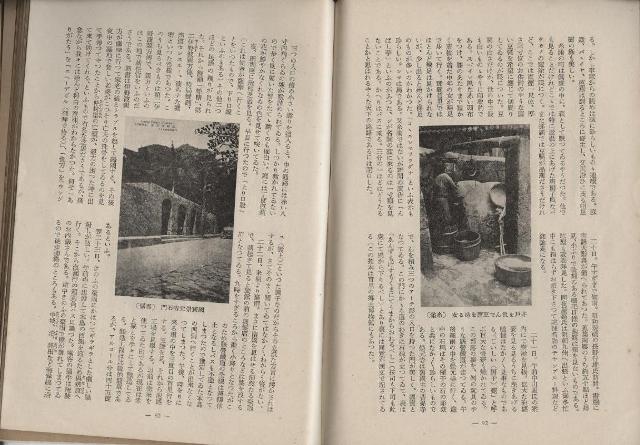
「茶わん」は陶芸愛好家向けの専門誌で、創刊は昭和六年三月。編集発行人は秦秀雄となっているが、実務は小野賢一郎がとりしきっていた。秦に代わって昭和七年五月号から編集発行人として遠藤敏夫の名がクレジットされる。編集部は芝区三田功運町六番地、聖坂を登り切った辺りにあった。(会津信吾「蘭郁二郎の生涯」)
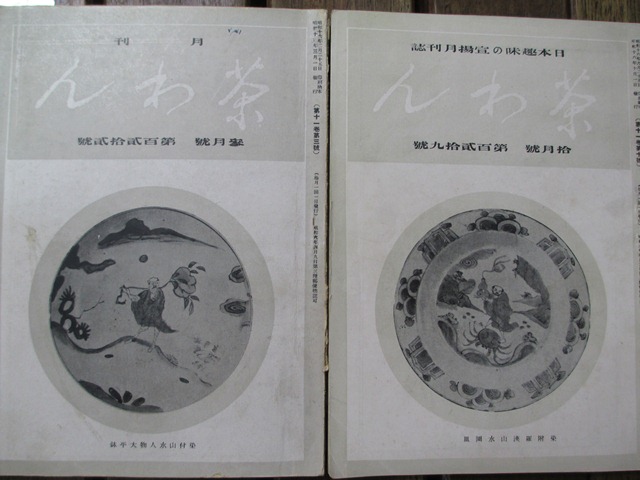
1941年8月『文学建設』蘭郁二郎「琉球ある記」
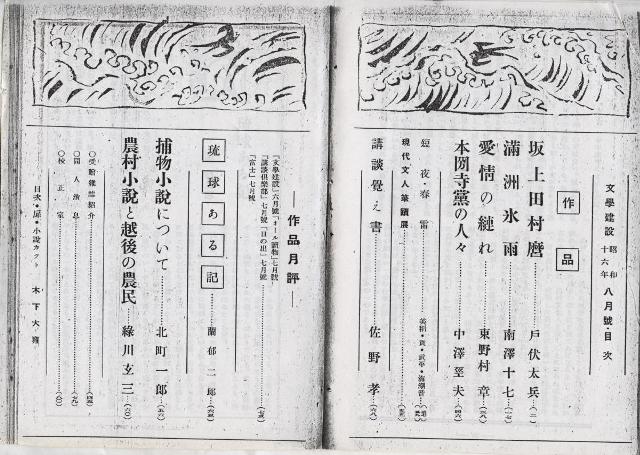
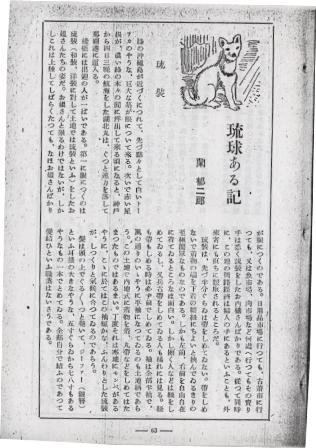
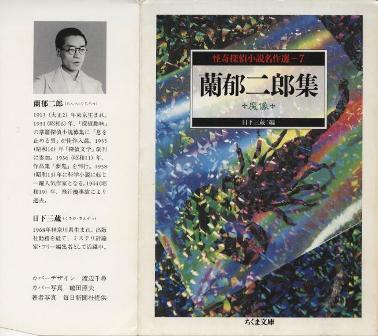
蘭郁二郎 らん-いくじろう 1913-1944 昭和時代前期の小説家。
大正2年9月2日生まれ。「探偵文学」同人となりミステリーをかくが,科学冒険小説に転じ,SF小説の先駆者のひとりとなった。海軍報道班員として台湾にわたり,昭和19年1月5日飛行機事故で死去。32歳。東京出身。東京高工卒。本名は遠藤敏夫。著作に「地図にない島」「地底大陸」など。→コトバンク

1942年9月『朝日新聞』「カメラ腕比べー尚謙・護得久朝章」
1925年 秋ー????宮城昇、仲泊良夫(白金三光町の明治学院文科の寄宿舎)と伊波文雄(小石川の伊波普猷宅に寄宿)に連れられて中野の山里永吉下宿を訪ねる。仲泊の同級生に仲村渠、渡辺修三、平川泰三、矢島などがいた。またダダイストの辻潤、詩人サトウハチロー、後藤寿夫(林房雄)らと交遊していた。
沖縄/ 1933年7月 『詩誌 闘魚』第貮輯 カット・装・ジュン
仲泊良夫「抽象の魔術ー(略)言語は残酷な死刑執行人である。私は自分の書きたいと思う事を書いていない。脳髄を全部露出することは醜悪なる猿である。創造を現実的に考えることは私には不可能である。凡ての現実は凡ての箴言に過ぎない。私は箴言を信じないように精神を信じない。抽象を精神的に考える人間は浪漫的な猫に過ぎない。抽象は異常なる砂漠の花に等しい。抽象は夢想ではない。私は私の創造に就ては極端に孤独なタングステン電球である。人間の馬鹿げた文學活動それはインク瓶をさげた犬の活動にすぎない。どうして諸兄は対象に向かって本能的批判をするのか。詩人のスタイルは本能の鎖をたちきった時に開くバラである。・・・」
闘魚消息ー 山之口貘氏・通信は東京市本所区東両国4ノ56吉川政雄気付/與儀二郎氏・6月10日出覇/仲泊良夫氏・島尻郡与那原2080/比嘉時君洞氏・6月初め久米島より出覇/泉國夕照氏・5月下旬退院/山里永吉氏・『戯曲集』新星堂書房より近く刊行さる、目下印刷中/國吉眞善氏・第参輯より闘魚同人加盟/イケイ雅氏・病気療養中。
沖縄/1933年9月 『詩誌 闘魚』第参輯 カット・装・ジュン
仲泊良夫「世界の創造ー或ひは観念への革命ー乾燥した時間に於て生誕する救世主/循環する世界それは革命する世界である/透明な詩人の純粋の夢/海底の少女と海底の美少年の戦争」
馬天居士『おらが唄』石敢當社(豊見城高良)ー著者馬天居士氏は、ゴミゴミした都会に住んでいる人ではない。そして世に謂う文藝人ではない。氏はあくまでも土に生きる人であり、野に遊ぶ人である。この”おらが唄〝の一巻を愛誦してみたまえ。俳句あり、川柳あり、短歌あり、そして軍歌あり、更に琵琶歌がある。だがそれらの作品はわれわれに何を考えさせるか。われわれは文藝意識に縛られている自分らのいぢけた存在をふりかえってにるにちがいない。それだけにおらが唄の一巻は、野性的な香りを放ち、自由な奔放さに流れ、また一面には辛辣すぎる皮肉さがある。社会のあらゆる階級的の上に端座したる馬天居士氏の八方睨みの静けさを愛する。
闘魚消息ー 與儀二郎氏・7月御祖母死去謹んで哀悼を表す/ 外山陽彦氏・島尻郡久米島仲里村役場気付/新屋敷幸繁・8月10日帰省。8月28日上鹿/南青海氏・与那原216/宮里靜湖氏・島尻郡久米島仲里校/川野逸歩氏・島尻郡具志川村役場/伊波南哲氏・東京市淀橋区淀橋643/志良堂埋木氏・朝日新聞社主催の文芸懇談会を風月樓にて7月22日開催す/イケイ雅氏・休暇中は中頭郡与那城村字饒邊3へ滞在/山里永吉氏・『山里永吉集』出づ大衆小説「心中した琉球王」文芸春秋社オール読物号8月号へ所載。
沖縄/ 1933年11月 『詩誌 闘魚』第四輯 カット・装・ジュン
闘魚消息ー與儀二郎氏・名護町字名護801山入端方へ転居/宮良高夫氏・現在沖縄日報社内/花城具志氏・闘魚社内気付/外山陽彦氏・土木工事多忙の為休稿/有馬潤氏・菓子店「ひなた屋」開業/原神青醉・歌誌「みちしほ」編輯せる氏は同誌一周年紀念号発刊に際し原神青醉歌集を近刊/山里永吉氏・「永吉集」好評。9月上旬 幸楽亭に於いて刊行祝賀会。出席者50名盛況
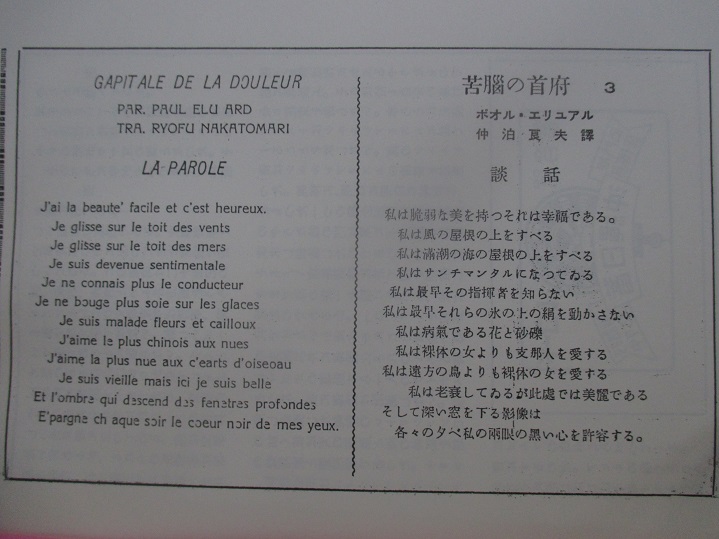
1936年5月『沖縄教育』第237号 仲泊良夫 訳「苦悩の首府」

写真1935年頃辻ー後列右からー山里永吉、仲泊良夫 前列中央が松田枕流(賀哲の弟)
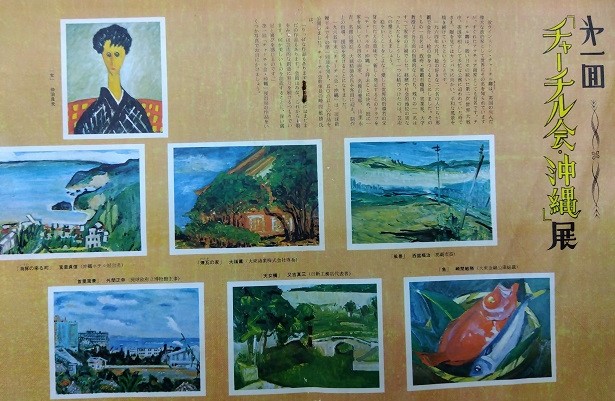
沖縄/ 1933年7月 『詩誌 闘魚』第貮輯 カット・装・ジュン
仲泊良夫「抽象の魔術ー(略)言語は残酷な死刑執行人である。私は自分の書きたいと思う事を書いていない。脳髄を全部露出することは醜悪なる猿である。創造を現実的に考えることは私には不可能である。凡ての現実は凡ての箴言に過ぎない。私は箴言を信じないように精神を信じない。抽象を精神的に考える人間は浪漫的な猫に過ぎない。抽象は異常なる砂漠の花に等しい。抽象は夢想ではない。私は私の創造に就ては極端に孤独なタングステン電球である。人間の馬鹿げた文學活動それはインク瓶をさげた犬の活動にすぎない。どうして諸兄は対象に向かって本能的批判をするのか。詩人のスタイルは本能の鎖をたちきった時に開くバラである。・・・」
闘魚消息ー 山之口貘氏・通信は東京市本所区東両国4ノ56吉川政雄気付/與儀二郎氏・6月10日出覇/仲泊良夫氏・島尻郡与那原2080/比嘉時君洞氏・6月初め久米島より出覇/泉國夕照氏・5月下旬退院/山里永吉氏・『戯曲集』新星堂書房より近く刊行さる、目下印刷中/國吉眞善氏・第参輯より闘魚同人加盟/イケイ雅氏・病気療養中。
沖縄/1933年9月 『詩誌 闘魚』第参輯 カット・装・ジュン
仲泊良夫「世界の創造ー或ひは観念への革命ー乾燥した時間に於て生誕する救世主/循環する世界それは革命する世界である/透明な詩人の純粋の夢/海底の少女と海底の美少年の戦争」
馬天居士『おらが唄』石敢當社(豊見城高良)ー著者馬天居士氏は、ゴミゴミした都会に住んでいる人ではない。そして世に謂う文藝人ではない。氏はあくまでも土に生きる人であり、野に遊ぶ人である。この”おらが唄〝の一巻を愛誦してみたまえ。俳句あり、川柳あり、短歌あり、そして軍歌あり、更に琵琶歌がある。だがそれらの作品はわれわれに何を考えさせるか。われわれは文藝意識に縛られている自分らのいぢけた存在をふりかえってにるにちがいない。それだけにおらが唄の一巻は、野性的な香りを放ち、自由な奔放さに流れ、また一面には辛辣すぎる皮肉さがある。社会のあらゆる階級的の上に端座したる馬天居士氏の八方睨みの静けさを愛する。
闘魚消息ー 與儀二郎氏・7月御祖母死去謹んで哀悼を表す/ 外山陽彦氏・島尻郡久米島仲里村役場気付/新屋敷幸繁・8月10日帰省。8月28日上鹿/南青海氏・与那原216/宮里靜湖氏・島尻郡久米島仲里校/川野逸歩氏・島尻郡具志川村役場/伊波南哲氏・東京市淀橋区淀橋643/志良堂埋木氏・朝日新聞社主催の文芸懇談会を風月樓にて7月22日開催す/イケイ雅氏・休暇中は中頭郡与那城村字饒邊3へ滞在/山里永吉氏・『山里永吉集』出づ大衆小説「心中した琉球王」文芸春秋社オール読物号8月号へ所載。
沖縄/ 1933年11月 『詩誌 闘魚』第四輯 カット・装・ジュン
闘魚消息ー與儀二郎氏・名護町字名護801山入端方へ転居/宮良高夫氏・現在沖縄日報社内/花城具志氏・闘魚社内気付/外山陽彦氏・土木工事多忙の為休稿/有馬潤氏・菓子店「ひなた屋」開業/原神青醉・歌誌「みちしほ」編輯せる氏は同誌一周年紀念号発刊に際し原神青醉歌集を近刊/山里永吉氏・「永吉集」好評。9月上旬 幸楽亭に於いて刊行祝賀会。出席者50名盛況
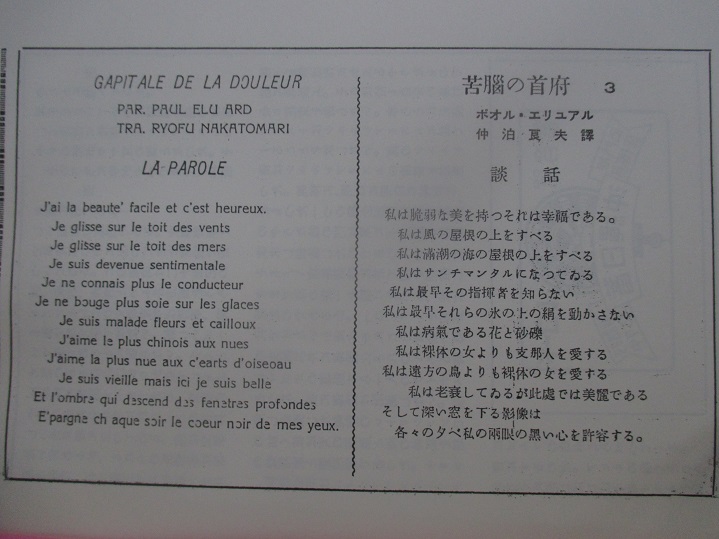
1936年5月『沖縄教育』第237号 仲泊良夫 訳「苦悩の首府」

写真1935年頃辻ー後列右からー山里永吉、仲泊良夫 前列中央が松田枕流(賀哲の弟)
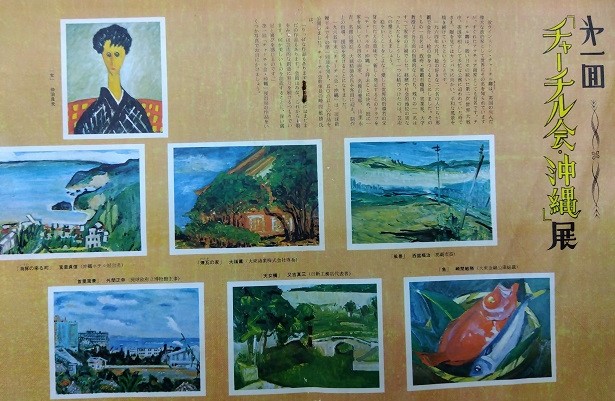
04/08: 新城栄徳「琉球文化史散歩」②
1929(昭和4)年
『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」
□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」
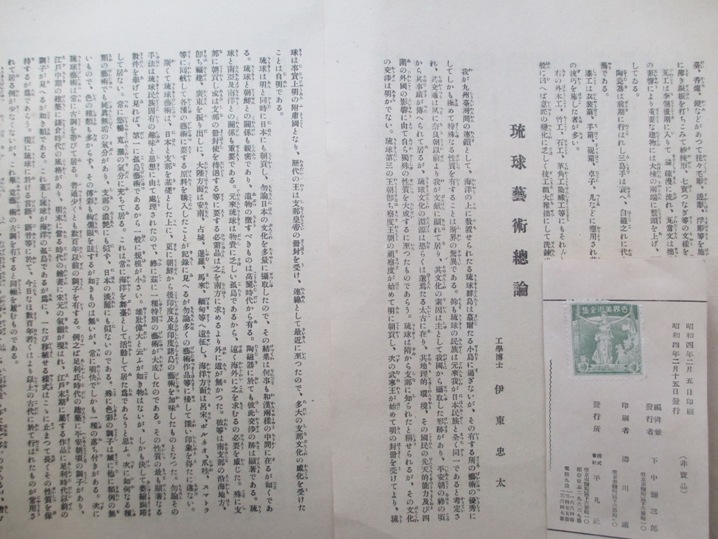
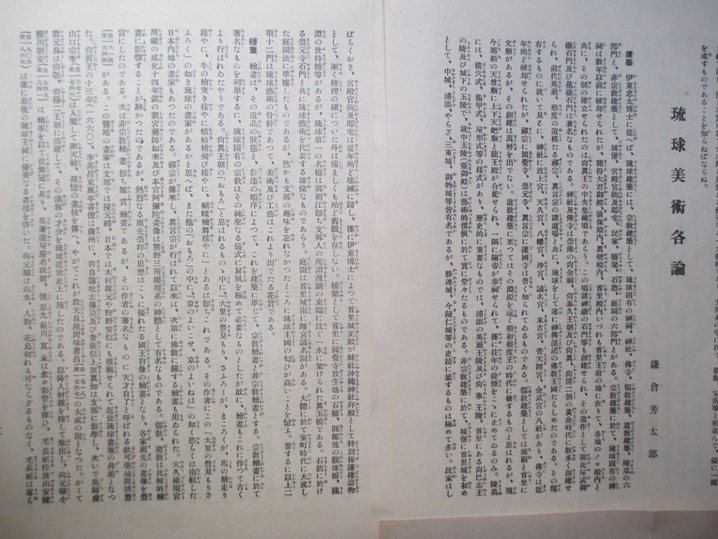
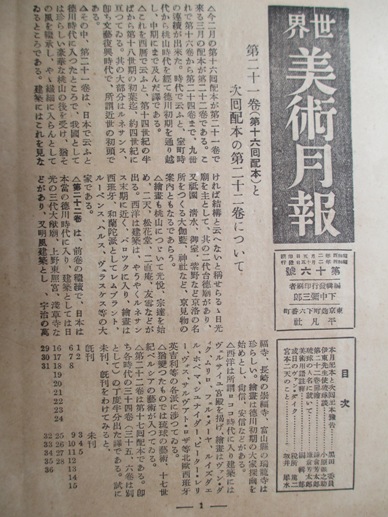
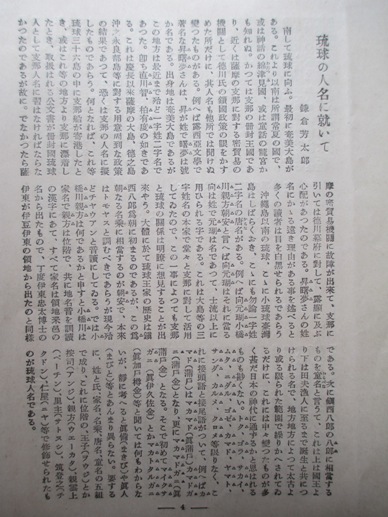
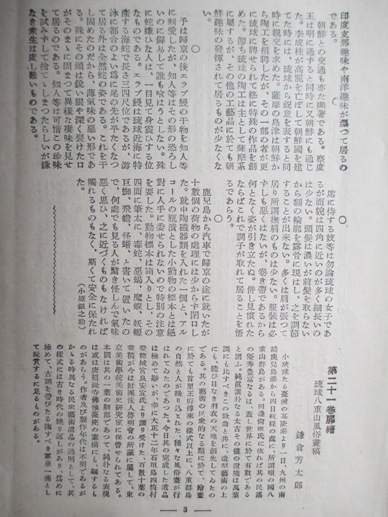
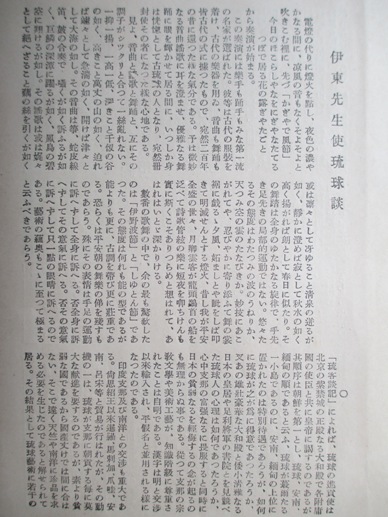
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)
1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社
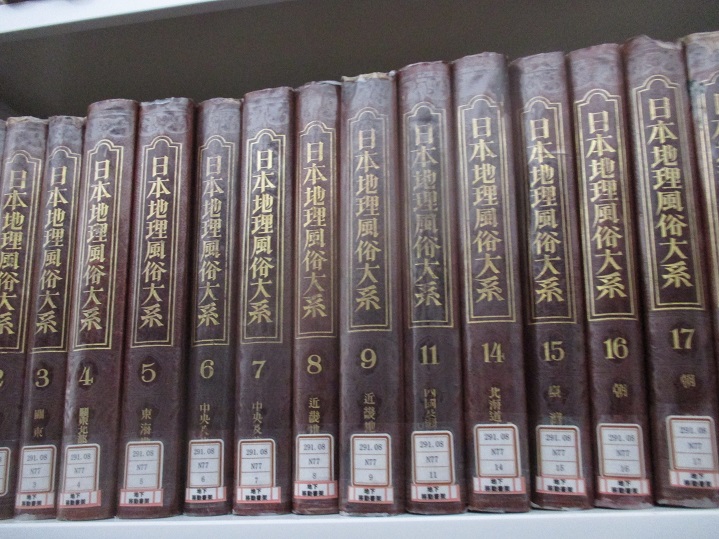
沖縄大学図書館所蔵

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社



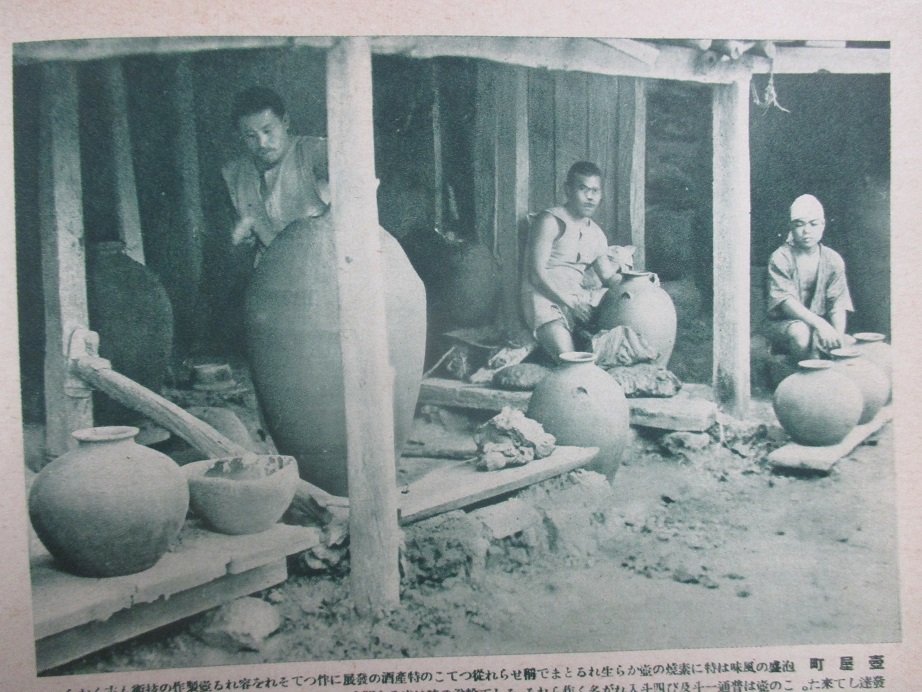


目次
琉球列島ー概説
地形ー列島と海溝/三列の地質構成/珊瑚礁の発達/古生層と珊瑚礁/宮古諸島と八重山諸島
気候と生物ー気温/降水量と風速/季節風/ハブとマングース/亜熱帯性植物
沿革ー開闢伝説/内地との交通/支那との交渉/明治以後
生産ー概説
甘蔗糖/水産物/甘蔗/穀物/林産物/牧場/その他の生産物
薩南諸島ー大隅諸島/土噶喇諸島/大島諸島/島の産物/大島の気温
沖縄諸島ー沖縄島/国頭山岳地域/中頭、島尻丘陵地域/那覇首里の都会地域/人口の減少/属島/大東諸島/先島諸島/八重山群島/尖閣諸島
琉球婦人の黥ー伝説に現れた起原/古文書中の入墨/記事の有無/他島との比較/その宗教的意義
墓ー風葬の俗/古代と風葬/墓の発達/その中間物/板が門/近代式墳墓/その起原
グラヴィアー守礼門/首里附近の聚落状態/奥武山公園/首里附近の民家/野生の蘇鉄/沖縄県庁/沖縄測候所/測候所附近より那覇を望む/天水甕/ハブの毒素採集/ハブ捕り/ハブ/芭蕉の花の咲く頃/辨岳の御願所/識名園の泉水/首里城の正殿/亀甲形の墳墓/尚家の門/波上神社と石筍崖/真玉橋の風光/護国寺の仁王門/聖廟/護国寺境内/末吉神社/辨財天堂と観蓮橋/ベッテルハイム記念碑/識名園/琉球の刳舟/爬龍船競漕図/琉球の甘蔗畑/盆の甘蔗市/農家の製糖小屋/パナマ帽の制作
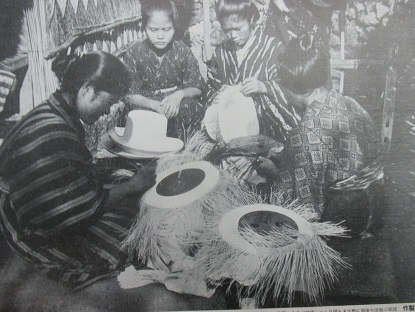
蘇鉄林/パパイヤの樹/辻町の遊女/機を巻く首里の婦人/屋久の杉森/杉の巨木/大島の闘牛/シャリンパイ/大島名瀬港/大島紬工場/奄美大島の蘇鉄林/奄美大島の百合園/那覇港の入口/那覇港第一桟橋/先原崎の灯台/波上神社の石段/首里市内の民屋/那覇市全景/琉球美人
屋上の唐獅子/壺屋町/壺作り/泥藍の紺屋/藍の香高い琉球絣/泡盛製造所/諸味貯蔵場/豚肉販売所/甘蔗売の集り/独特の武術唐手/郷土スポーツ唐手/ズリ馬行列/歓会門/円覚寺本殿/龍潭池附近/円覚寺境内放生池橋/琉球の民家/那覇市附近の露店/那覇旧市街/崇元寺の門/那覇一の商店街/那覇辻遊廓/真玉橋の石橋/沖縄測候所/円覚寺の山門/熱帯植物榕樹/漁村糸満の浜/名物朱塗りの漆器/芭蕉の実り/萬歳舞踊/舞踊/婦人の黥/綱曳遊戯/湧田の旗頭/壮麗な旗頭/浜の賑ひ/野国総官の墓/久志村の山中にあった墓/久高島の墓/破風式の墓/亀の子式の墓/墓と死者の交会/墳墓のストリート/墓のにぎはい/玉陵/墓の平面図/壺屋産の霊置甕/英祖陵
守礼門がカラーで載っている。この本を1987年に安良城盛昭(大阪府立大学教授)氏が沖縄県立博物館に寄贈された。氏のものは父盛英が東京で教師をしていたとき購入したもので氏も愛読し親しんできたものであった。□1929年2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」
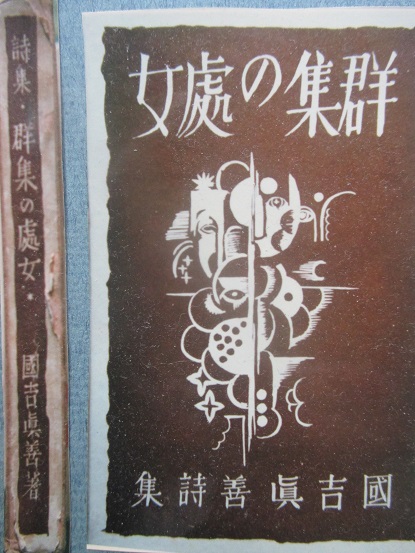
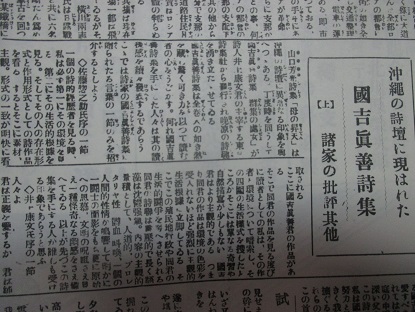
1930年5月 国吉真善『群衆の処女』
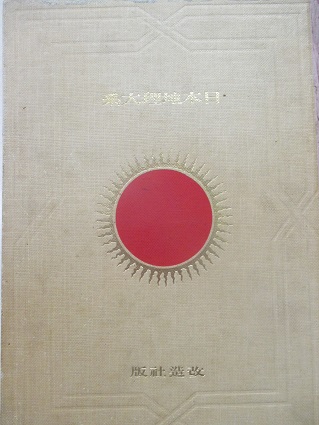
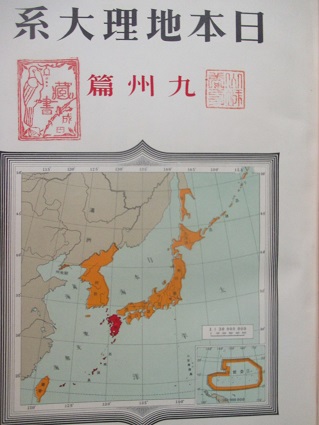
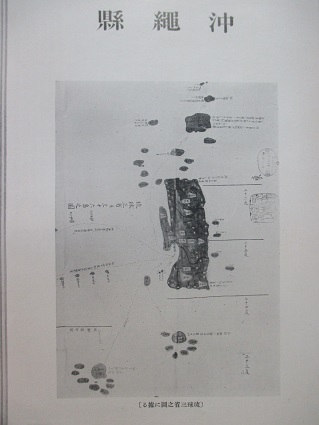
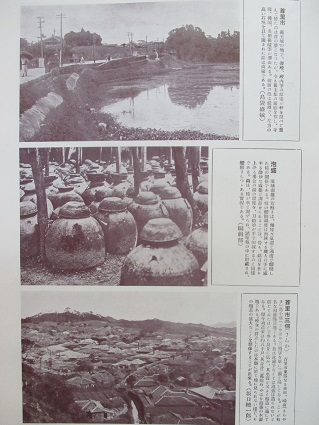
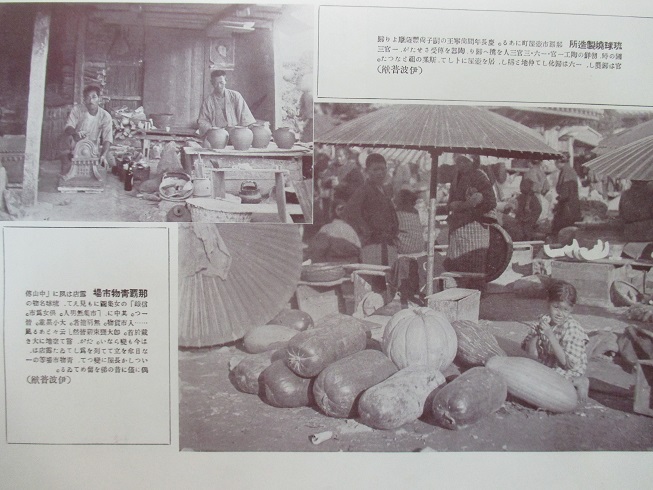
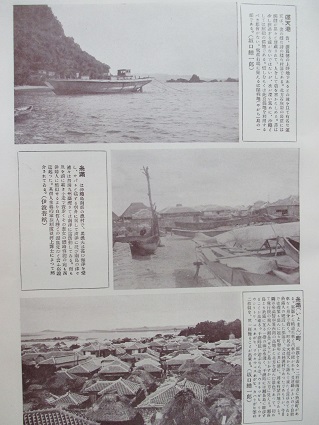
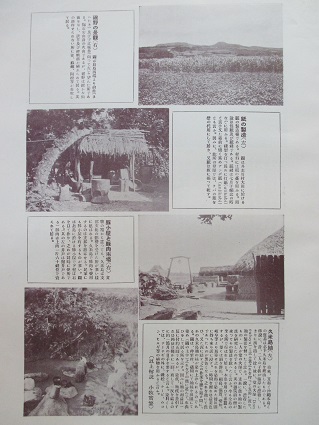
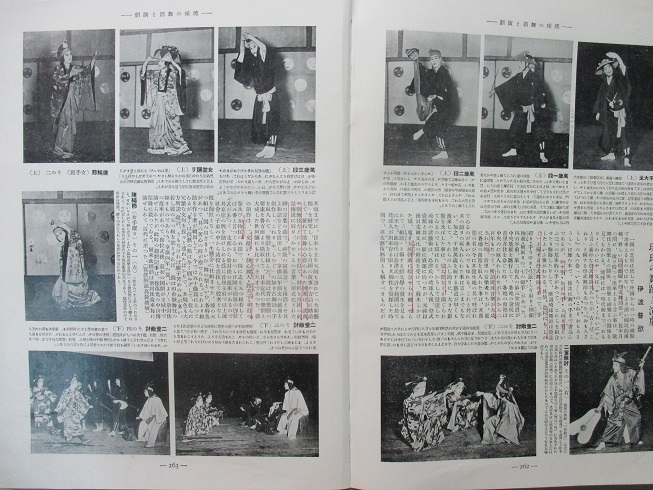
1930年8月 改造社『日本地理大系・九州篇 沖縄県』
目次
沖縄県扉「古地図」
沖縄県概説
ダブルトーン版ー筆架山より見たる那覇港 那覇市街/隆起珊瑚礁と波上神社/琉球焼製造所 那覇青物市場/おてんだの水取舟 崇元寺/金石文と真玉橋/守礼門 歓会門 首里城正殿/首里市 泡盛 首里三個/識名園 首里市/運天港 糸満 糸満町/パパヤ売 金武大川/七島藺の刈取 砂糖の製造 八重山鰹節製造所/久米島(新村 支那式の家屋 久米島の男女 久米島具志川村 仲村渠)/久米島(裾野の景観 紙の製造 豚小屋と豚肉市場 久米島紬)/琉球の墳墓/那覇市郊外の墓 国主より功臣に賜りたる御拝領の墓/田舎の墓 首里郊外貴族の墓/ヤツチのがま 石垣島より竹富島を望む屋我地ヲフルギの純林 甘蔗の栽培 ガジュマル/琉球の舞踊と演劇ー波平大主 萬歳一段 同二段 同三段 女笠踊 諸純節 二童敵討 同二 同三 同四/琉球の年中行事ー八重山の民族舞踊 祭式舞踊 那覇市の綱引行列
綜合解説
1930年8月5日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(1)凡そ神秘的な共産の久高島 島民総出で原始的な出迎 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月6日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(2)凡そ神秘的な共産の久高島 島の由来記と名所旧蹟 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月7日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(3)凡そ神秘的な共産の久高島 原始共産制の名残を観る 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月8日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(4)どこ探しても無い久高島の奇習 珍しい風葬と婦人の貞操試験 『グショウ』見物の巻」
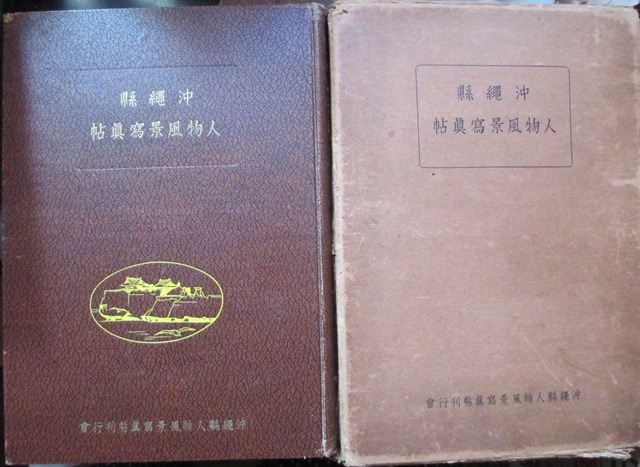

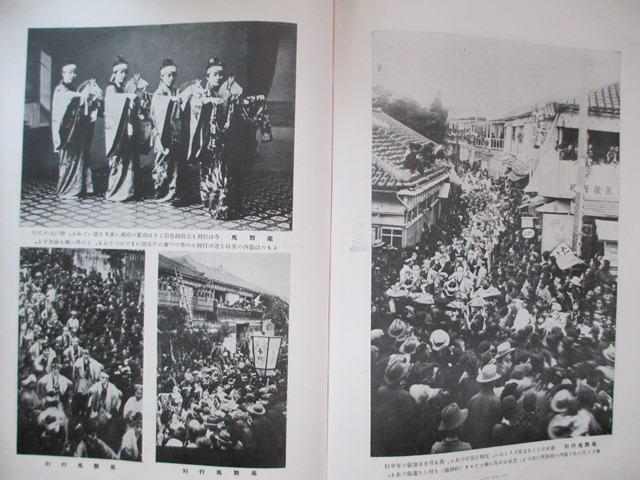
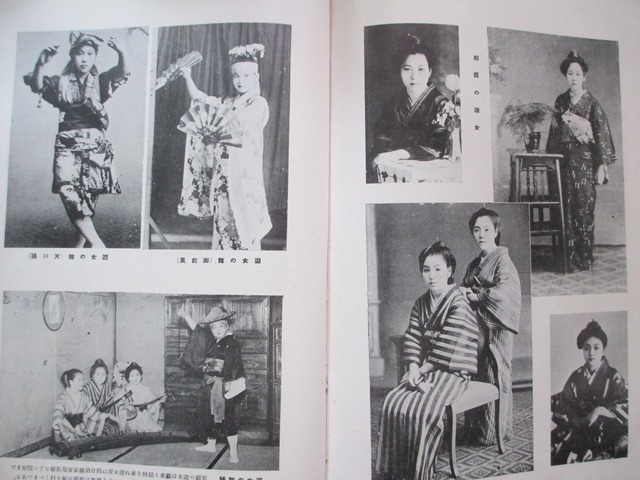
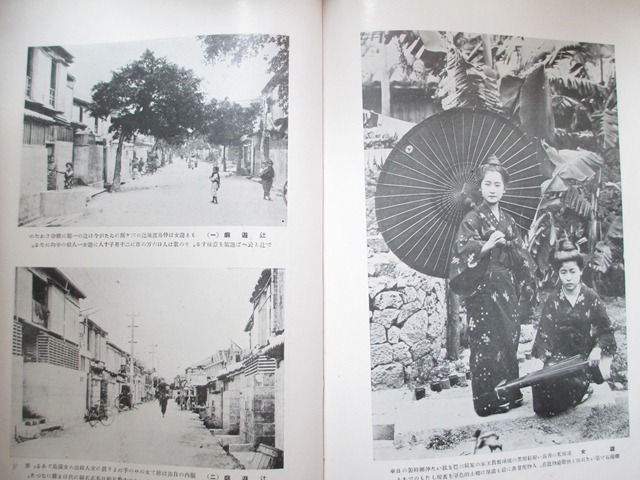
1933年7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』
1934年4月17日『琉球新報』広告□那覇市東町 明視堂写真部ー佐和九郎『正則写真術』『密着と引伸』『現像の実際』『露出の秘訣』『整色写真の研究』『整色写真術』/三宅克巳『写真随筆 籠の中より』『写真のうつし方』『私の写真』『趣味の写真術』/高桑勝雄『フイルム写真術』『写真術五十講』『写真問答』/宇高久敬『写真の新技法』/霜田静志『写真の構図』/南實『原板の手入』/加藤直三郎『中級写真術』/石田喜一郎『プロモイル印画法』/小池晩人『山岳写真の研究』/金丸重嶺『新興写真の作り方』、金丸重嶺・鈴木八郎『商業写真術』/勝田康雄『人物写真のうつし方』/中島謙吉『芸術写真の知識』/吉川速男『写真術の第一歩』『小形カメラの第一歩』『図解写真術初歩』『私のライカ』『十六ミリの第一歩』/鈴木八郎『写真の失敗と其原因』『写真処方集』『整色写真のうつし方』『引伸の実際』/中戸川秀一『写真百科辞典』/寺岡徳二『印画修整の実際』/斎藤こう兒『撮影第一課』『引伸写真の作り方』『芸術写真の作り方』/額田敏『山岳写真のうつし方』/眞継不二夫『芸術写真作画の実際』『アマチュア写真の修整』/山崎悦三郎『修整の実際』/高山正隆『芸術写真入門』『ベストコダック写真術』/石動弘『小形活動フイルム現像法』
1934年5月5日『大阪朝日新聞 九州朝日』「外人の眼に映じた”ハブの國„ クルート女史の興味を晙る視察談」
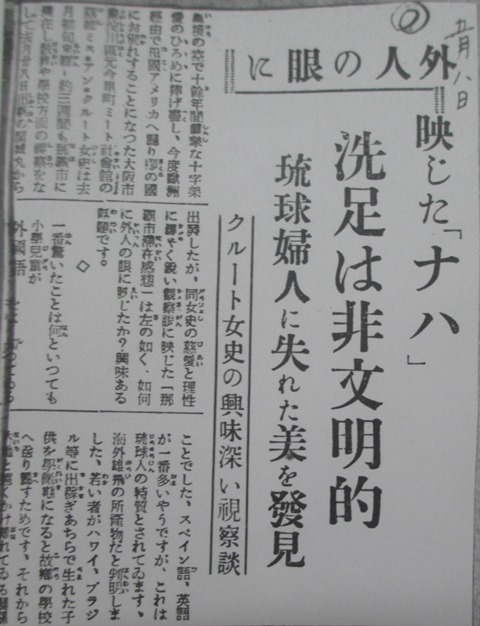

1934年5月8日『琉球新報』?
4月、欧州経由でアメリカに帰途、来沖したミス・アン・クルート(大阪東淀川区ミード社会館)が新聞記者に「那覇の児童がスペイン語、英語を知っているのに驚いた、これは海外雄飛の諸産物で若い者がハワイ・ブラジルらに出稼ぎ、そこで生まれた子を故郷沖縄の学校に送り帰すためです」と答える。
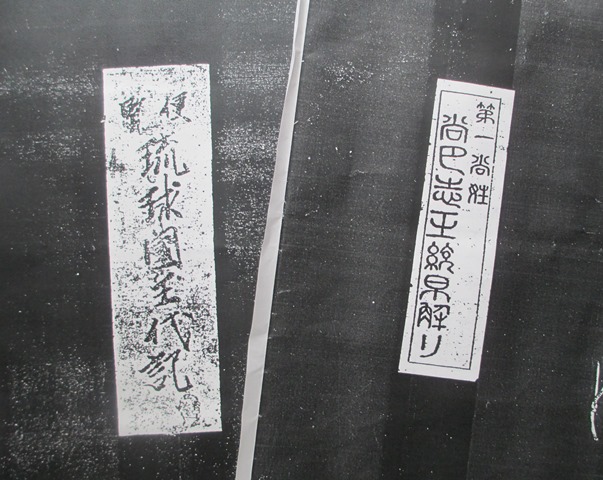
1934年11月 神村朝儀『便覧 琉球國王代記』神村朝忠/1937年3月 神村朝儀『第一尚姓 尚巴志王統早分解り』神村朝忠薬店
○雑誌『おきなわ』復刻版解説に酒井直子さんが「回想ー父 神村朝堅」を書かれていて、「向氏神村家家系図」も添えられていた。13世 朝睦の子供たちが省略されていたので詳しく記入してもらった。その結果、上記の著者・朝儀は叔父で、発行人の朝忠は朝堅氏の父と判明した。
『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」
□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」
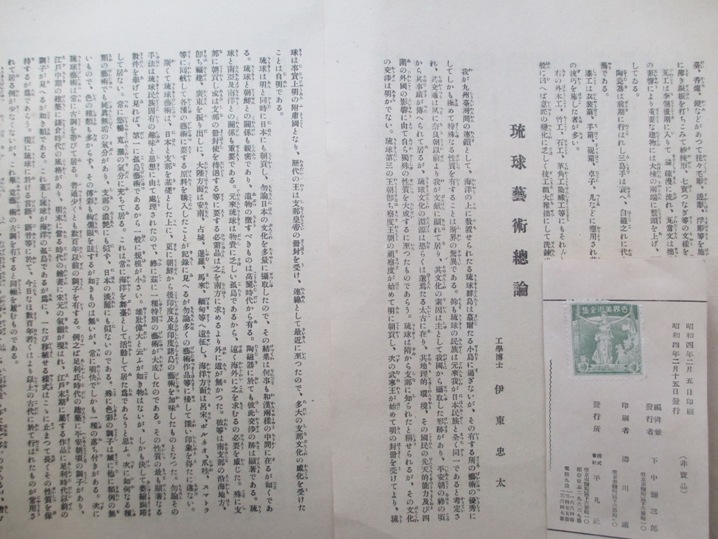
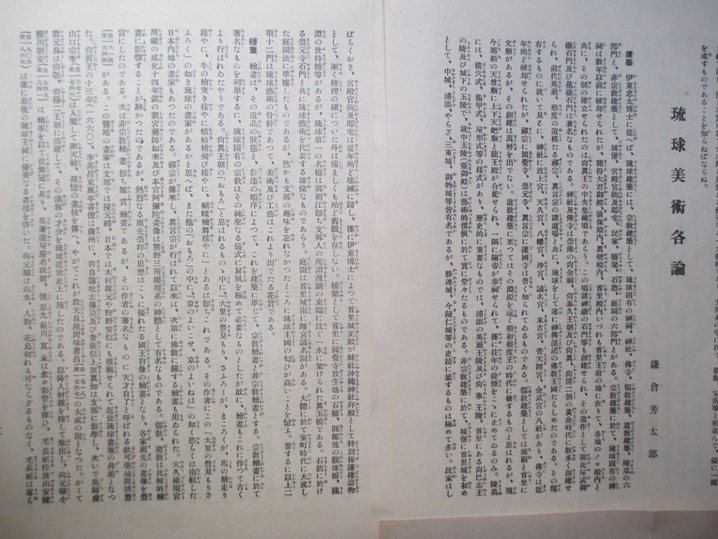
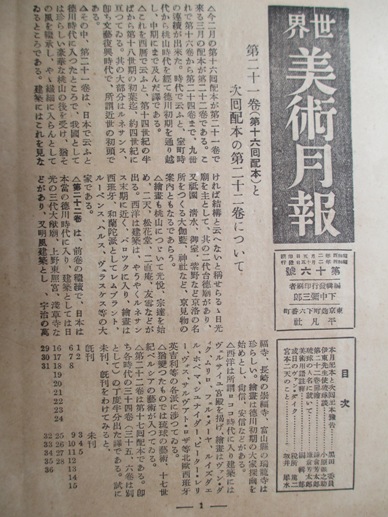
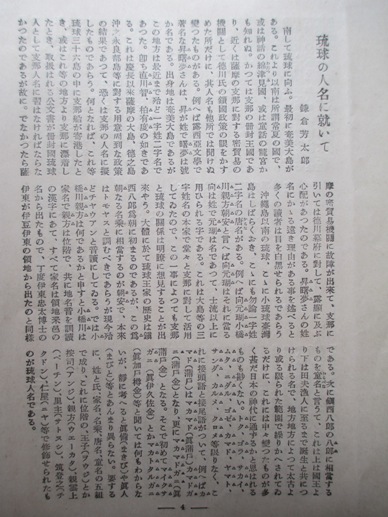
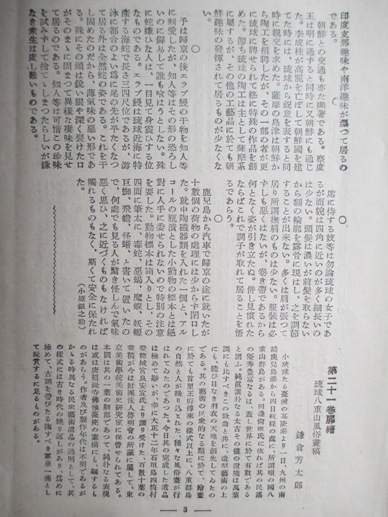
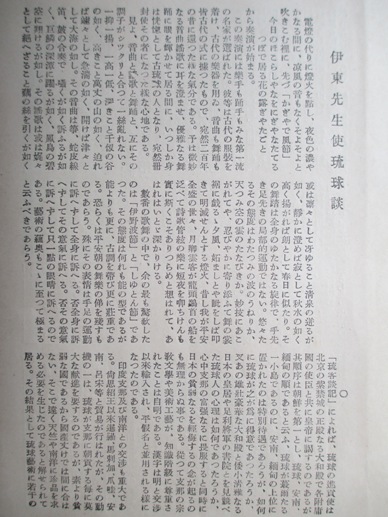
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)
1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社
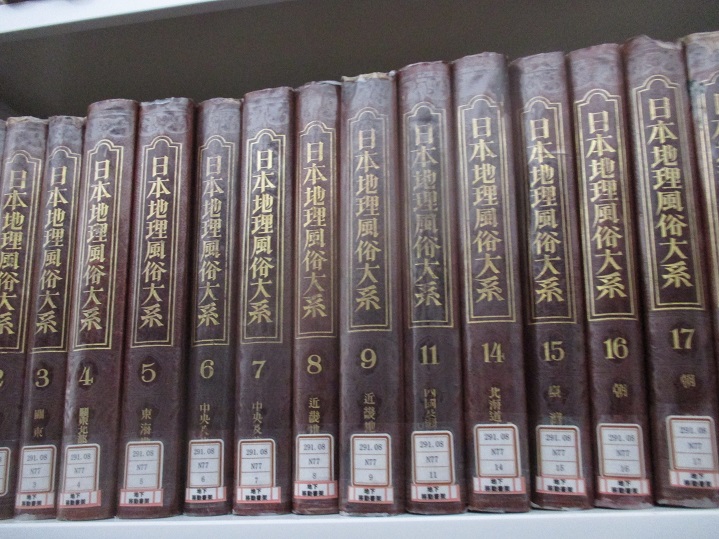
沖縄大学図書館所蔵

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社



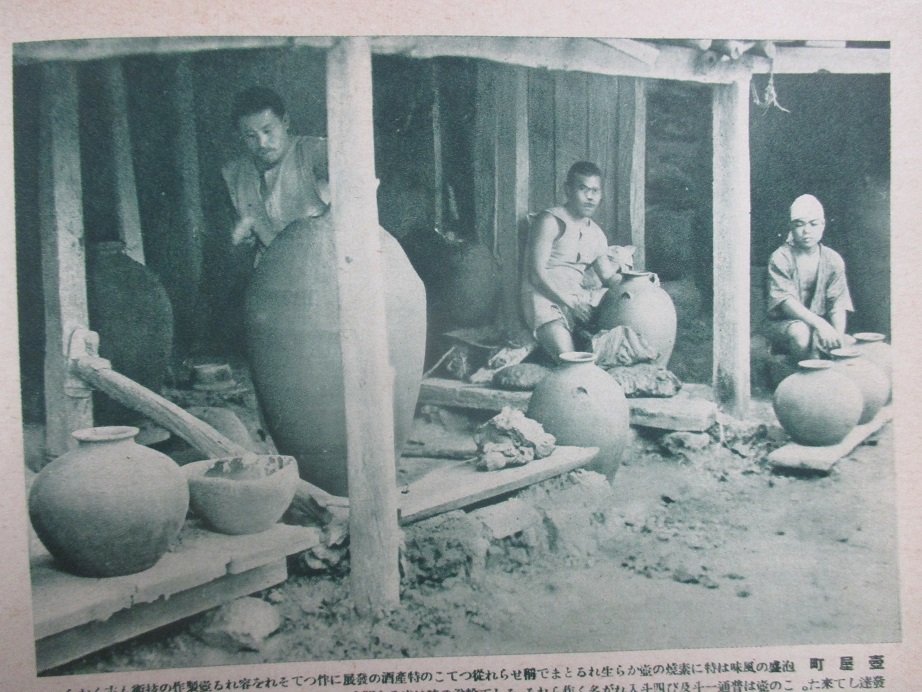


目次
琉球列島ー概説
地形ー列島と海溝/三列の地質構成/珊瑚礁の発達/古生層と珊瑚礁/宮古諸島と八重山諸島
気候と生物ー気温/降水量と風速/季節風/ハブとマングース/亜熱帯性植物
沿革ー開闢伝説/内地との交通/支那との交渉/明治以後
生産ー概説
甘蔗糖/水産物/甘蔗/穀物/林産物/牧場/その他の生産物
薩南諸島ー大隅諸島/土噶喇諸島/大島諸島/島の産物/大島の気温
沖縄諸島ー沖縄島/国頭山岳地域/中頭、島尻丘陵地域/那覇首里の都会地域/人口の減少/属島/大東諸島/先島諸島/八重山群島/尖閣諸島
琉球婦人の黥ー伝説に現れた起原/古文書中の入墨/記事の有無/他島との比較/その宗教的意義
墓ー風葬の俗/古代と風葬/墓の発達/その中間物/板が門/近代式墳墓/その起原
グラヴィアー守礼門/首里附近の聚落状態/奥武山公園/首里附近の民家/野生の蘇鉄/沖縄県庁/沖縄測候所/測候所附近より那覇を望む/天水甕/ハブの毒素採集/ハブ捕り/ハブ/芭蕉の花の咲く頃/辨岳の御願所/識名園の泉水/首里城の正殿/亀甲形の墳墓/尚家の門/波上神社と石筍崖/真玉橋の風光/護国寺の仁王門/聖廟/護国寺境内/末吉神社/辨財天堂と観蓮橋/ベッテルハイム記念碑/識名園/琉球の刳舟/爬龍船競漕図/琉球の甘蔗畑/盆の甘蔗市/農家の製糖小屋/パナマ帽の制作
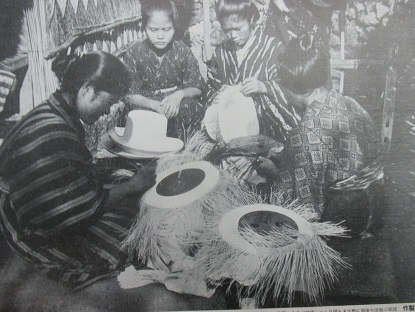
蘇鉄林/パパイヤの樹/辻町の遊女/機を巻く首里の婦人/屋久の杉森/杉の巨木/大島の闘牛/シャリンパイ/大島名瀬港/大島紬工場/奄美大島の蘇鉄林/奄美大島の百合園/那覇港の入口/那覇港第一桟橋/先原崎の灯台/波上神社の石段/首里市内の民屋/那覇市全景/琉球美人
屋上の唐獅子/壺屋町/壺作り/泥藍の紺屋/藍の香高い琉球絣/泡盛製造所/諸味貯蔵場/豚肉販売所/甘蔗売の集り/独特の武術唐手/郷土スポーツ唐手/ズリ馬行列/歓会門/円覚寺本殿/龍潭池附近/円覚寺境内放生池橋/琉球の民家/那覇市附近の露店/那覇旧市街/崇元寺の門/那覇一の商店街/那覇辻遊廓/真玉橋の石橋/沖縄測候所/円覚寺の山門/熱帯植物榕樹/漁村糸満の浜/名物朱塗りの漆器/芭蕉の実り/萬歳舞踊/舞踊/婦人の黥/綱曳遊戯/湧田の旗頭/壮麗な旗頭/浜の賑ひ/野国総官の墓/久志村の山中にあった墓/久高島の墓/破風式の墓/亀の子式の墓/墓と死者の交会/墳墓のストリート/墓のにぎはい/玉陵/墓の平面図/壺屋産の霊置甕/英祖陵
守礼門がカラーで載っている。この本を1987年に安良城盛昭(大阪府立大学教授)氏が沖縄県立博物館に寄贈された。氏のものは父盛英が東京で教師をしていたとき購入したもので氏も愛読し親しんできたものであった。□1929年2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」
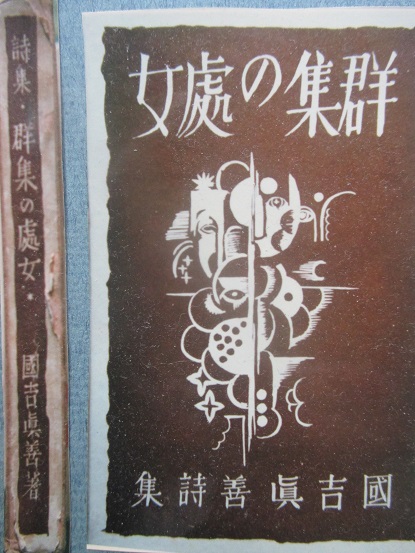
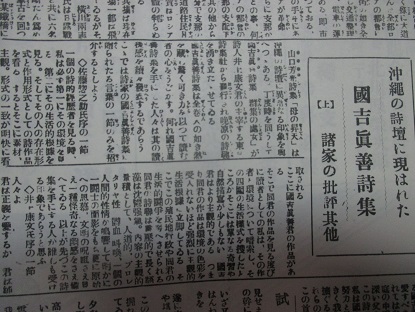
1930年5月 国吉真善『群衆の処女』
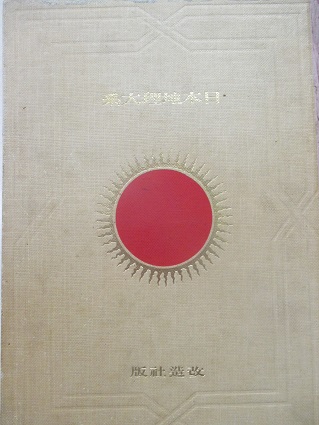
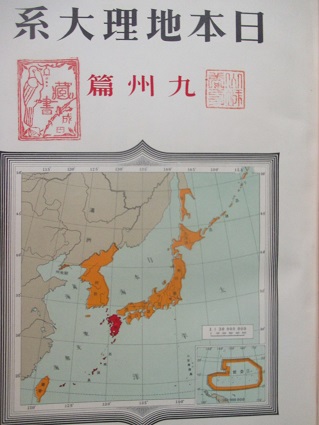
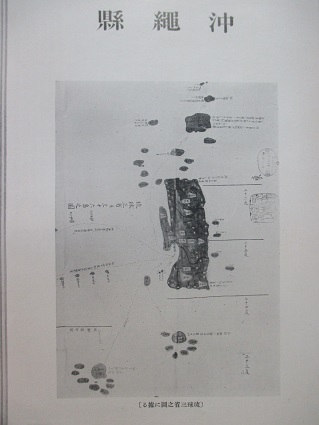
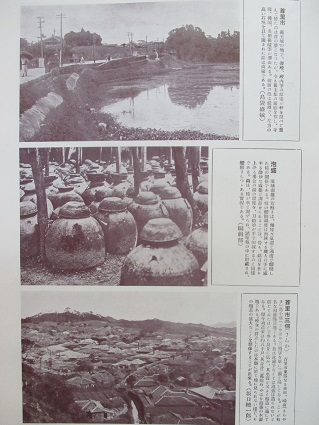
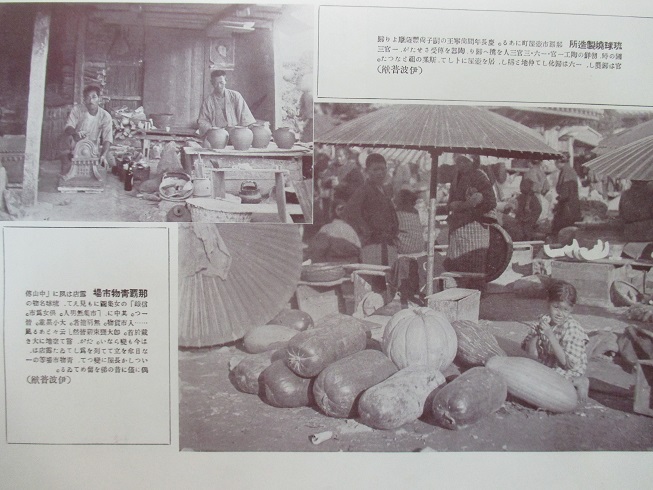
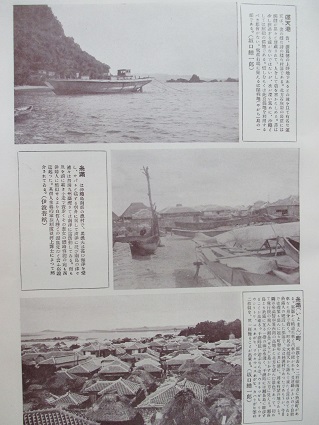
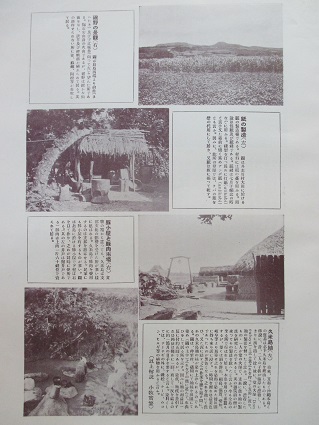
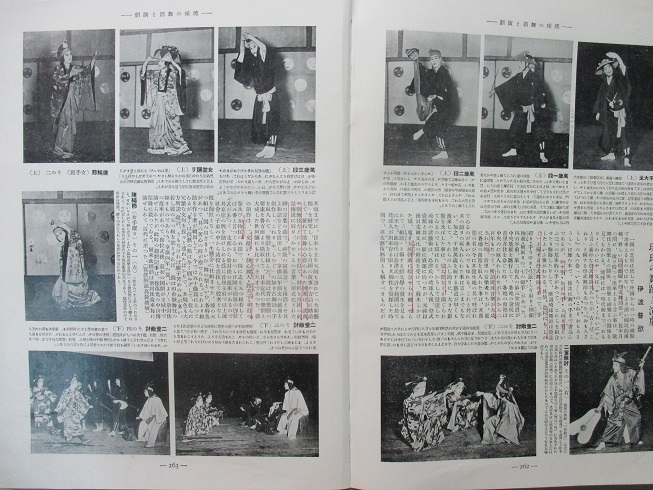
1930年8月 改造社『日本地理大系・九州篇 沖縄県』
目次
沖縄県扉「古地図」
沖縄県概説
ダブルトーン版ー筆架山より見たる那覇港 那覇市街/隆起珊瑚礁と波上神社/琉球焼製造所 那覇青物市場/おてんだの水取舟 崇元寺/金石文と真玉橋/守礼門 歓会門 首里城正殿/首里市 泡盛 首里三個/識名園 首里市/運天港 糸満 糸満町/パパヤ売 金武大川/七島藺の刈取 砂糖の製造 八重山鰹節製造所/久米島(新村 支那式の家屋 久米島の男女 久米島具志川村 仲村渠)/久米島(裾野の景観 紙の製造 豚小屋と豚肉市場 久米島紬)/琉球の墳墓/那覇市郊外の墓 国主より功臣に賜りたる御拝領の墓/田舎の墓 首里郊外貴族の墓/ヤツチのがま 石垣島より竹富島を望む屋我地ヲフルギの純林 甘蔗の栽培 ガジュマル/琉球の舞踊と演劇ー波平大主 萬歳一段 同二段 同三段 女笠踊 諸純節 二童敵討 同二 同三 同四/琉球の年中行事ー八重山の民族舞踊 祭式舞踊 那覇市の綱引行列
綜合解説
1930年8月5日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(1)凡そ神秘的な共産の久高島 島民総出で原始的な出迎 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月6日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(2)凡そ神秘的な共産の久高島 島の由来記と名所旧蹟 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月7日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(3)凡そ神秘的な共産の久高島 原始共産制の名残を観る 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月8日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(4)どこ探しても無い久高島の奇習 珍しい風葬と婦人の貞操試験 『グショウ』見物の巻」
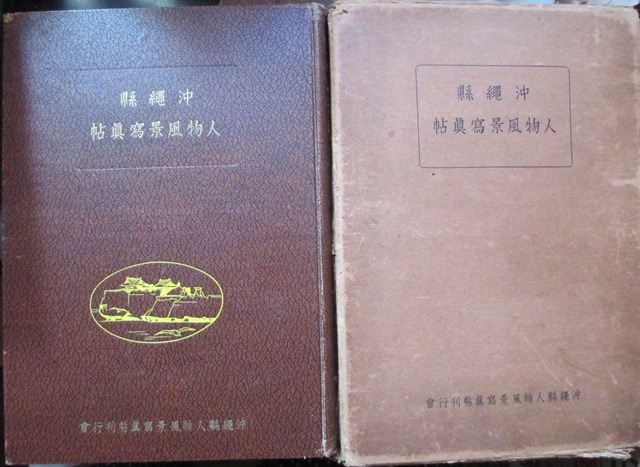

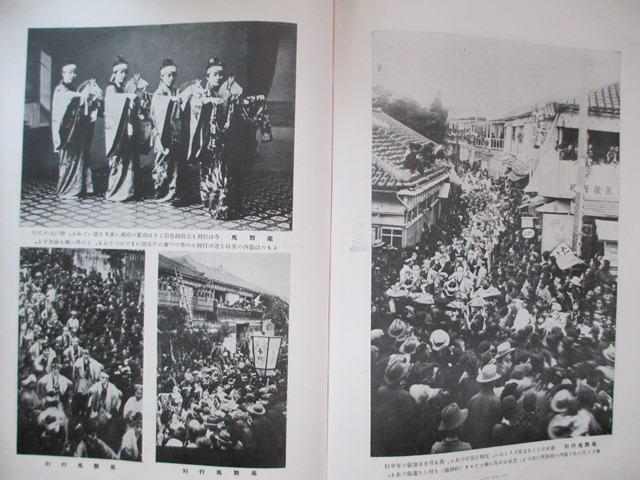
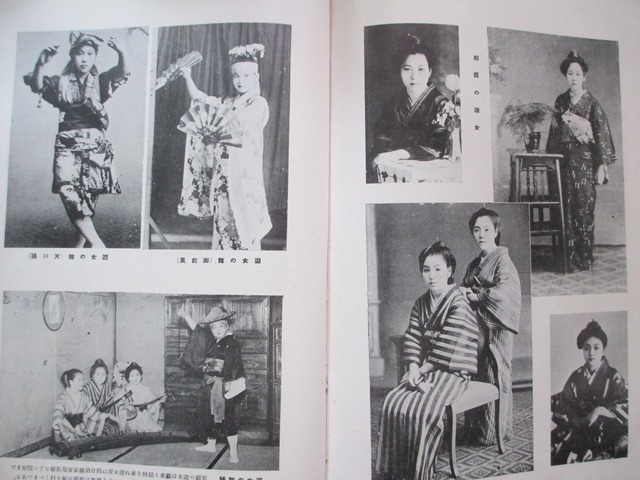
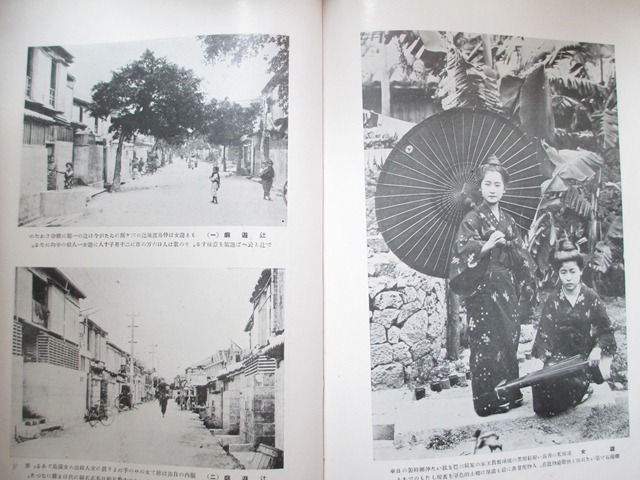
1933年7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』
1934年4月17日『琉球新報』広告□那覇市東町 明視堂写真部ー佐和九郎『正則写真術』『密着と引伸』『現像の実際』『露出の秘訣』『整色写真の研究』『整色写真術』/三宅克巳『写真随筆 籠の中より』『写真のうつし方』『私の写真』『趣味の写真術』/高桑勝雄『フイルム写真術』『写真術五十講』『写真問答』/宇高久敬『写真の新技法』/霜田静志『写真の構図』/南實『原板の手入』/加藤直三郎『中級写真術』/石田喜一郎『プロモイル印画法』/小池晩人『山岳写真の研究』/金丸重嶺『新興写真の作り方』、金丸重嶺・鈴木八郎『商業写真術』/勝田康雄『人物写真のうつし方』/中島謙吉『芸術写真の知識』/吉川速男『写真術の第一歩』『小形カメラの第一歩』『図解写真術初歩』『私のライカ』『十六ミリの第一歩』/鈴木八郎『写真の失敗と其原因』『写真処方集』『整色写真のうつし方』『引伸の実際』/中戸川秀一『写真百科辞典』/寺岡徳二『印画修整の実際』/斎藤こう兒『撮影第一課』『引伸写真の作り方』『芸術写真の作り方』/額田敏『山岳写真のうつし方』/眞継不二夫『芸術写真作画の実際』『アマチュア写真の修整』/山崎悦三郎『修整の実際』/高山正隆『芸術写真入門』『ベストコダック写真術』/石動弘『小形活動フイルム現像法』
1934年5月5日『大阪朝日新聞 九州朝日』「外人の眼に映じた”ハブの國„ クルート女史の興味を晙る視察談」
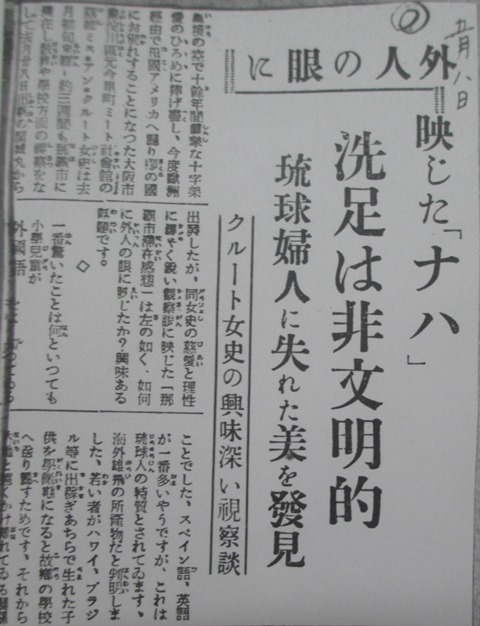

1934年5月8日『琉球新報』?
4月、欧州経由でアメリカに帰途、来沖したミス・アン・クルート(大阪東淀川区ミード社会館)が新聞記者に「那覇の児童がスペイン語、英語を知っているのに驚いた、これは海外雄飛の諸産物で若い者がハワイ・ブラジルらに出稼ぎ、そこで生まれた子を故郷沖縄の学校に送り帰すためです」と答える。
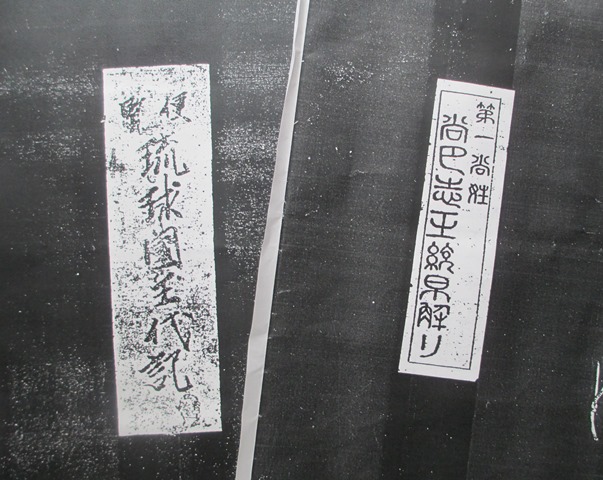
1934年11月 神村朝儀『便覧 琉球國王代記』神村朝忠/1937年3月 神村朝儀『第一尚姓 尚巴志王統早分解り』神村朝忠薬店
○雑誌『おきなわ』復刻版解説に酒井直子さんが「回想ー父 神村朝堅」を書かれていて、「向氏神村家家系図」も添えられていた。13世 朝睦の子供たちが省略されていたので詳しく記入してもらった。その結果、上記の著者・朝儀は叔父で、発行人の朝忠は朝堅氏の父と判明した。
01/28: 辻/1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

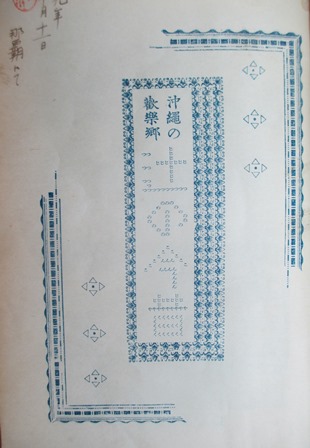


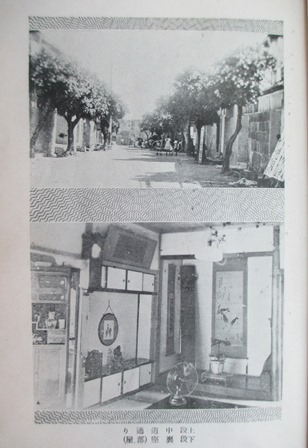
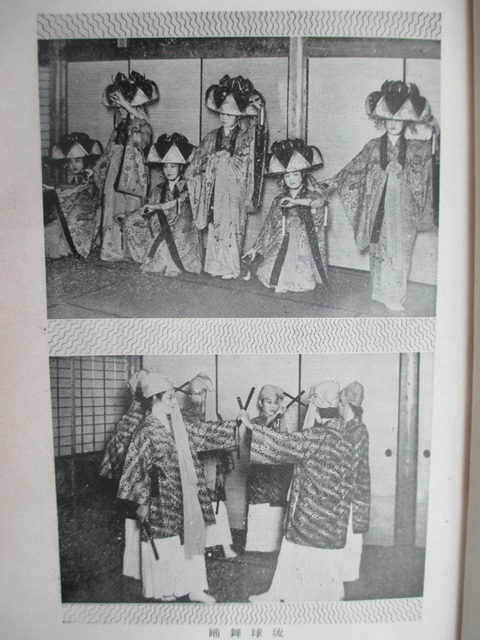
○一向宗の法難と廓
王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。
また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。
明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。
備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。
02/01: 辻の旧二十日正月/はちか・そーがち(新城栄徳撮影)
2012-本日はヤマトの「建国記念日」らしい。那覇では辻の旧二十日正月/はちか・そーがち、があるので写真家の山田勉氏と同行して見に行った。14時に辻新思会のメンバーが、海蔵院(花の代)、志良堂御嶽、祝女井戸、石被、いんだかりの火神/ひぬかん、軸/じく、辻むら開祖之墓を巡拝した。そして、じゅり馬行列が舞い踊った。会場には上江洲安明氏、真喜志康徳氏、壺屋焼物博物館の学芸員、建築家の普久原朝充氏、芸能研究家の与那覇晶子さん、オキナワグラフ記者ら大勢の写真家が来ていた。

写真左からー平良米夫氏、与那覇晶子さん、新城栄徳、山本彩香さん、下地隆司氏 □→「志情(しなさき)の海へ」
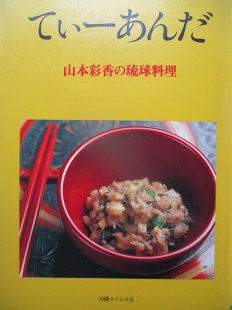
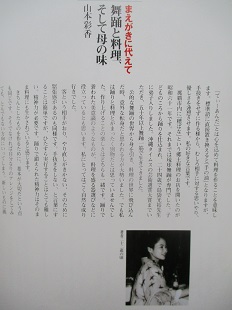
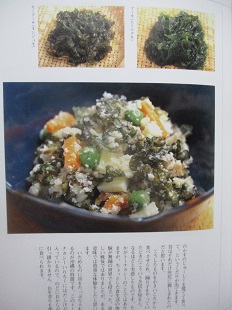
1998年11月 山本彩香『てぃーあんだ 山本彩香の琉球料理』沖縄タイムス社
与那覇晶子さんから『「組踊の系譜ー朝薫の五番から沖縄芝居、そして<人類館>へ」』(研究代表・与那覇晶子)が送られてきた。
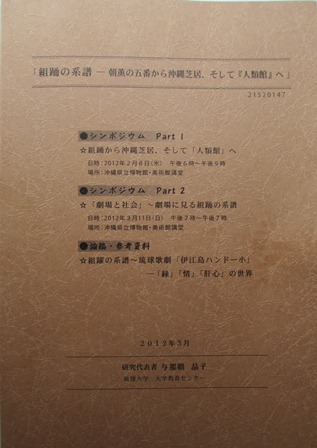
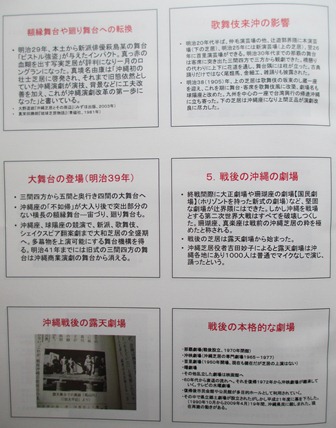
資料/過去の辻の旧二十日正月/はちか・そーがち(新城栄徳撮影)


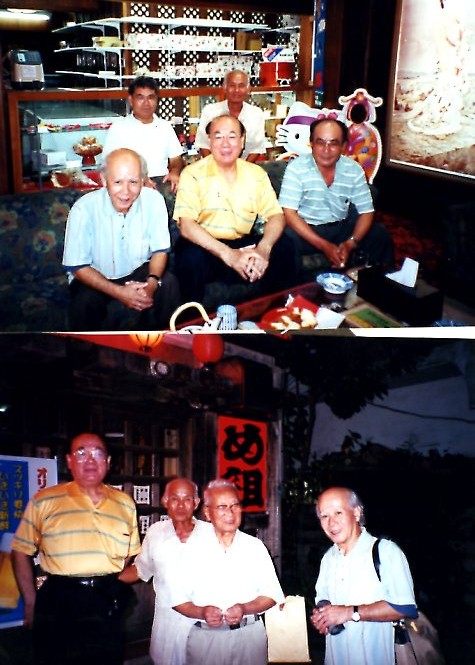

写真左からー平良米夫氏、与那覇晶子さん、新城栄徳、山本彩香さん、下地隆司氏 □→「志情(しなさき)の海へ」
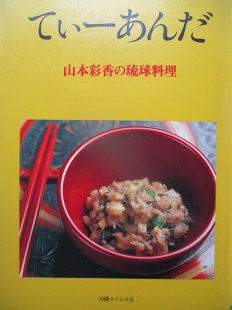
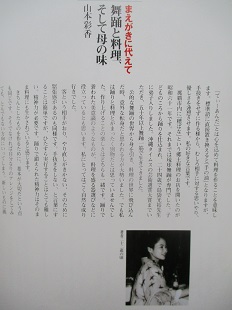
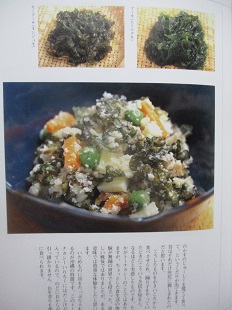
1998年11月 山本彩香『てぃーあんだ 山本彩香の琉球料理』沖縄タイムス社
与那覇晶子さんから『「組踊の系譜ー朝薫の五番から沖縄芝居、そして<人類館>へ」』(研究代表・与那覇晶子)が送られてきた。
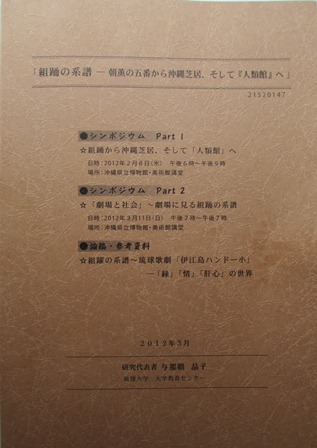
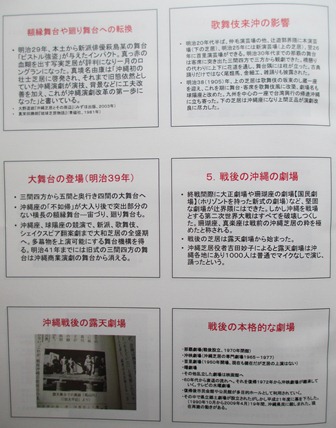
資料/過去の辻の旧二十日正月/はちか・そーがち(新城栄徳撮影)


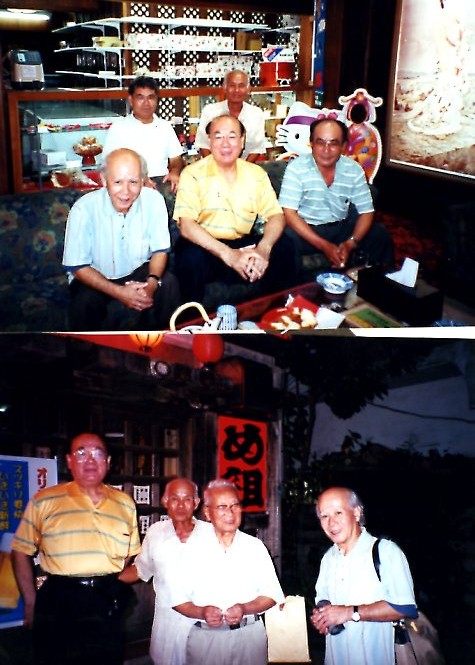
06/24: 人物カタログ/伊原宇三郎

1954年3月『別冊週刊朝日』伊原宇三郎「琉球の踊子(名護愛子)」
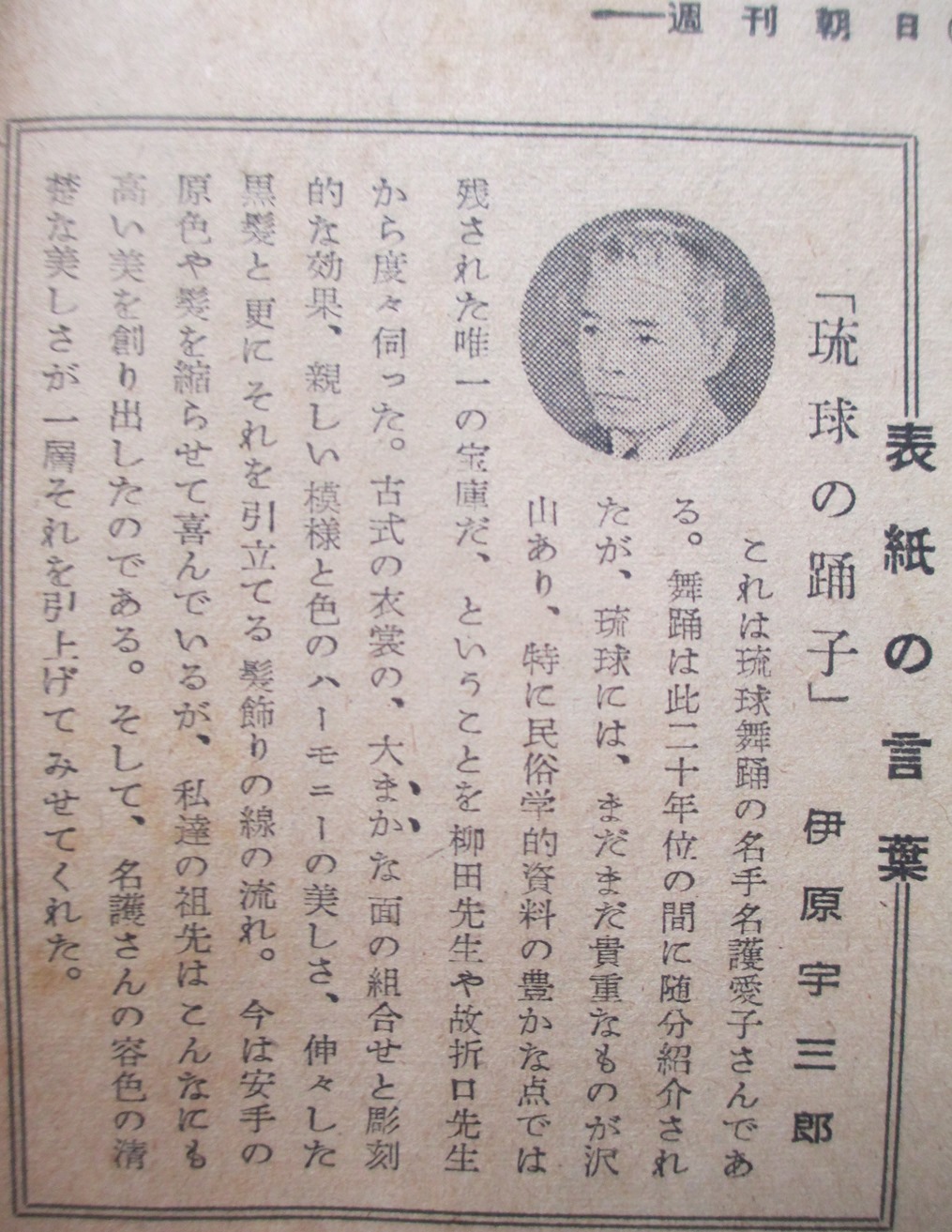
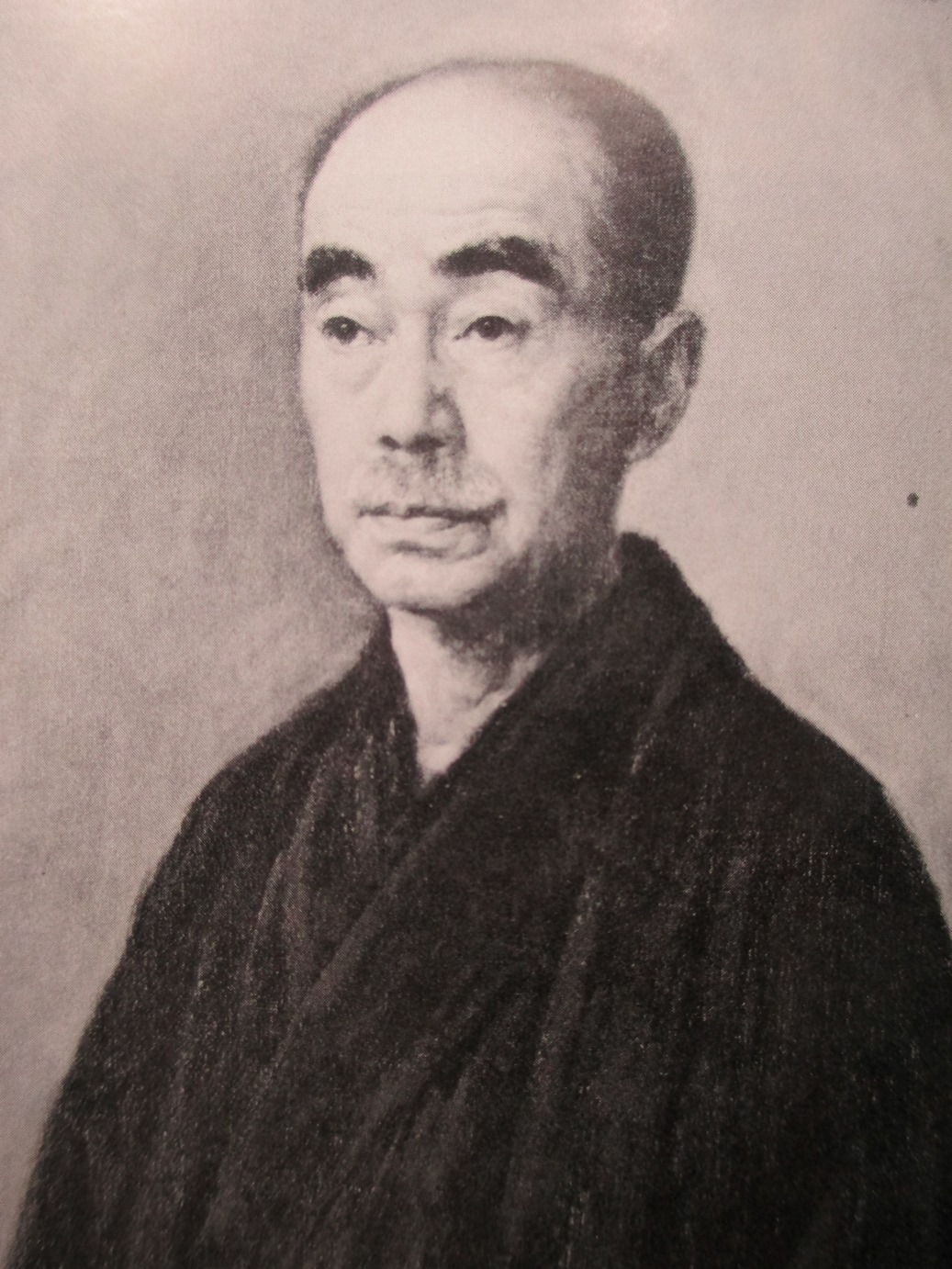
伊原宇三郎「柳田国男」(現在は飯田美術博物館蔵)
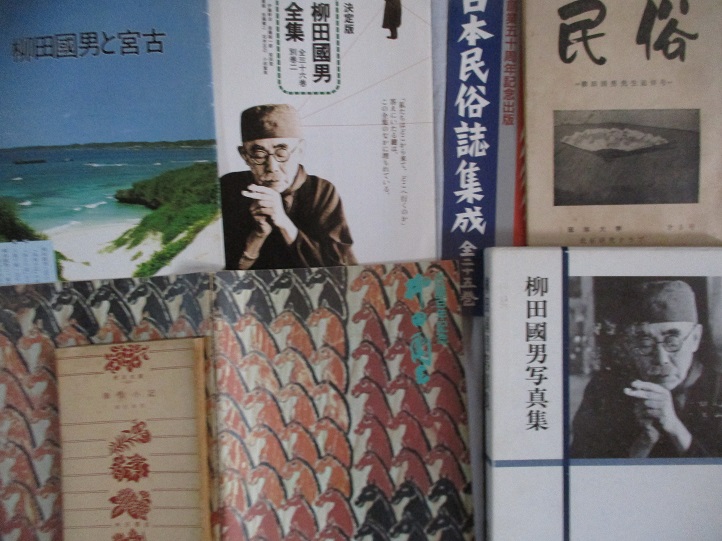
柳田国男 資料

伊原宇三郎「折口信夫」

伊原宇三郎ー洋画家。徳島市生。東美校卒。藤島武二に師事。卒業後渡仏し、帰国して帝展で特選を受賞する等活躍。帝国美術学校(現武蔵野美大)教授、母校助教授をつとめるかたわら戦時中は従軍画家として中国、東南アジアへ赴く。戦後日本美術家連盟創立と同時に委員長となり、美術家の社会的環境の整備に尽力した。フランス政府芸術文化勲章受章。日展参与・審査員。昭和51年(1976)歿、81才。 →コトバンク
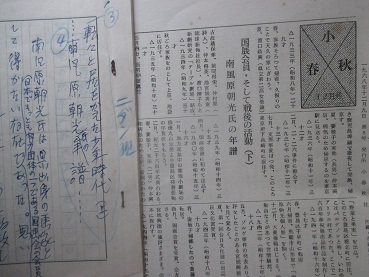
『南風原朝光遺作画集』の年譜は夫人敏子さんのメモの外に、阿波根朝松、有銘興昭、國吉景祉、名渡山愛順、大城光也、金城精栄氏らの記憶によって叙述補正された。これを出来るだけ当時の資料によ基づいて裏付けしたい。
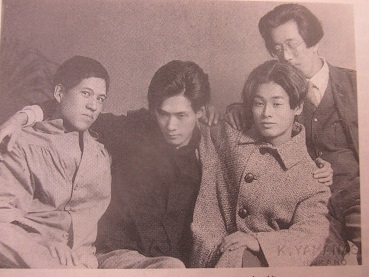
2004年9月 『新生美術』13号「日本美術学校時代ー前列右端 南風原朝光」
1923年(大正12年)9月1日11時58分関東大震災発生
1925年秋 ????宮城昇、仲泊良夫(白金三光町の明治学院文科の寄宿舎)や伊波文雄(小石川の伊波普猷宅に寄宿)に連れられて中野の山里永吉下宿を訪ねる。仲泊の同級生に仲村渠、渡辺修三、平川泰三、矢島などがいた。またダダイストの辻潤、詩人サトウハチロー、後藤寿夫(林房雄)らと交遊していた。
1926年 南風原朝光、日本美術学校へ入学
1929年 南風原朝光、日本美術学校卒業
1930年3月 南風原朝光、仲本敏子と結婚、上京。
1930年5月 神田神保町「五人展」同人は南風原朝光、星野一夫、大橋信一、伊倉普、加治屋隆二
1932年8月『フオトタイムス』????宮城昇「低気圧ースタヂオを建ててしまった。未だ半年にしかならないのに、この猛烈な風に会い、写場の壁紙の北側は台無しになった。北風のすごい事は知っていたが、しかしスタヂオのスラントも北向きが良いとは皮肉だった。(略)少なくとも、写真に対する人心の覚醒をする為には、我々の低気圧を必要とする土地、那覇である。」/圓谷英二(後に特撮の神様といわれゴジラやウルトラマンをつくった)「ホリゾント法に拠るセツテングの研究(1)」
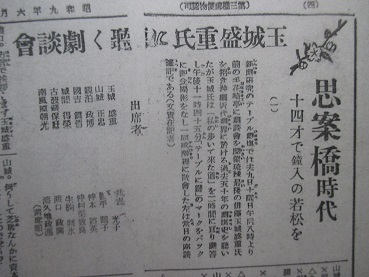
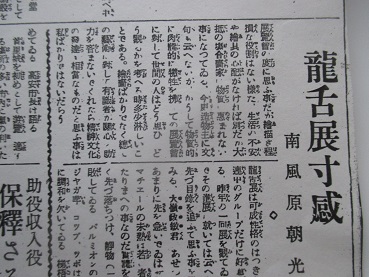
1934年6月11日『琉球新報』/1934年9月7日『琉球新報』
1934年 南風原朝光、家族を残して上京。池袋に居住。

1934年 東京神田の東京堂「沖縄美術協会」展ー後列左から渡嘉敷唯信(?)・新川唯盛・仲嶺康輝・西村菊雄 前列左から 兼城賢章・南風原朝光・大城皓也・山元恵一
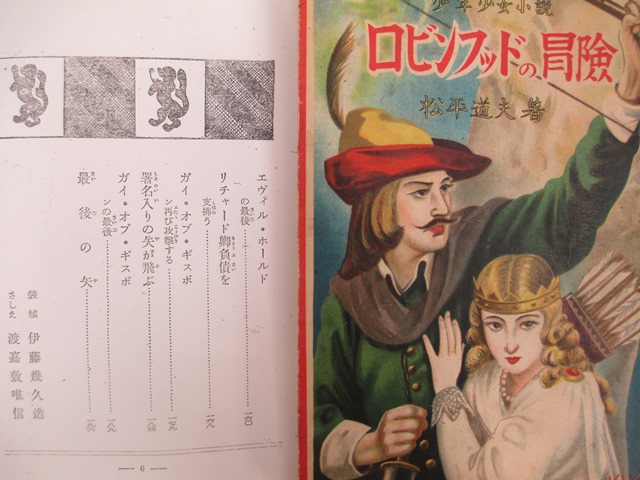

1985年3月 米城律・伊藝滋『石川正通追想集』□渡嘉敷唯信(石川澄子は姉)
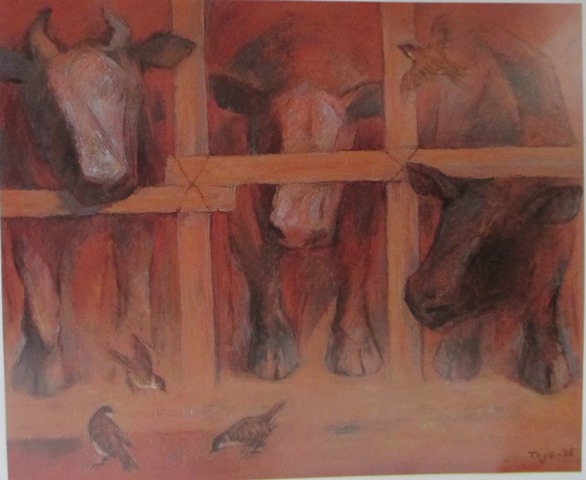
渡嘉敷唯信「牛と雀」1986年
1985年3月 米城律・伊藝滋『石川正通追想集』□渡ケ敷唯信(石川澄子は姉)
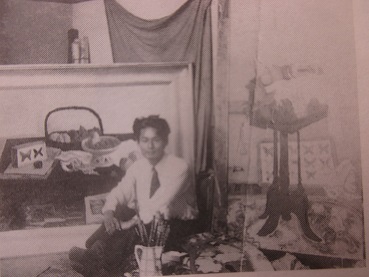
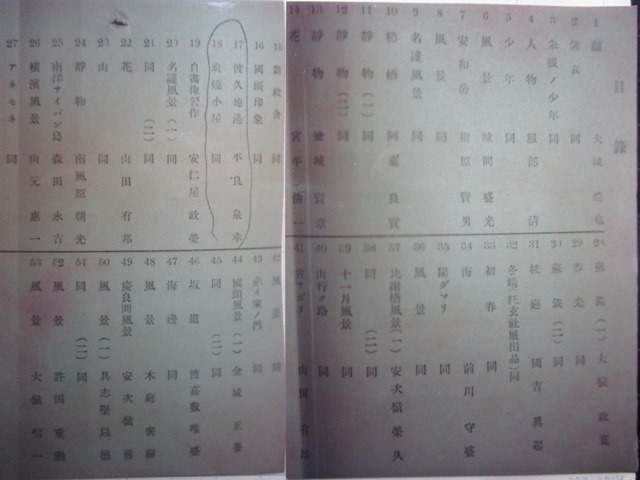
「1935年 長崎町の友人のアトリエ 南風原朝光」/ 1936年4月 第二回沖縄県洋画協会展
宮平清一「花」「新校舎」「国頭印象」/南風原朝光「静物」/山元恵一「横浜風景」「アネモネ」
1938年 山元恵一、東京美術学校卒業。宮森俊三の紹介で東宝映画(トーキーシステムの開発を行う写真化学研究所(Photo Chemical Laboratory、通称 PCLは、1937年関連会社JOと合併)にて円谷栄二の下でしばらくアルバイト。同年12月、東京市役所勤務の大浜信恭(大浜信泉弟で作家志望)の紹介で東京市厚生局勤務。これ以降、東京では殆ど絵を描く時間がなかった。
1938年4月ー世界のフジタ、二科会の重鎮・藤田嗣治が加治屋隆二、竹谷富士雄、南風原朝光を伴って浮島丸で来沖。那覇港には比嘉景常、名渡山愛順、大城皓也らが出迎えた。加治屋は東京の小学校での比嘉景常の教え子。南風原と琉球新報記者の國吉眞哲とは同じ泊出身、親友であった。琉球新報は藤田の講演会、座談会を企画し、藤田作品鑑賞会を後援するなど抱え込んだ。
藤田嗣治の来沖の経緯は、国吉真哲さんが「絵かき仲間の加治屋隆二さん、竹谷不二雄さんと南風原朝光君3人で沖縄へ行こうという話になり、その旅費のことなど打ちあわせている所へ、藤田画伯が来て『おもしろそうな話をしているなあ、ボクも行こう』ということになって沖縄を訪れた」と『南風原朝光遺作画集』の中で述べている。
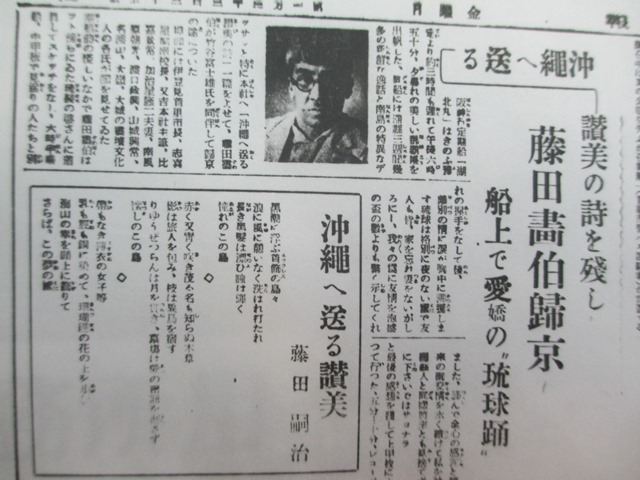
1938年5月20日『琉球新報』「藤田帰京」
□藤田嗣治「沖縄へ送る讃美」
黒潮に浮ぶ首飾の島々/浪に風に憩いなく洗はれ打たれ/長き黒髪は漂ひ瞳は輝く/憧れのこの島
◇
赤く又青く咲き茂る名も知らぬ木草/影は旅人を包み、枝は異鳥を宿す/りゅうぜつらんは月を貫き、墓場は愛の密語を漏さず/懐しのこの島
◇
帯もなき薄衣の女子等/乳も脛も銅に染めて、珊瑚礁の花の上を歩む/海山の幸を頭上に飾りて/さらば、この夢の國
1940年秋 このころ南風原朝光、豊島区椎名町に居住。ここはパルテノンと称し、いわゆるアトリエ村であった。
1941年春 南風原朝光、豊島区千早町に居住。
1943年(昭和18年)
4月 第18回展(東京府美術館、22日~5月2日。大阪市立美術館、5月)
同人制を廃止して会員会友制を復活する。搬入 絵画1362点、版画230点、工芸420点、
写真192点。入選 絵画167点(118名)、版画42点(32名)、工芸73点(58名)、
写真35点(28名)。陳列 絵画237点、版画54点、工芸108点、写真43点。
授賞、会員・会友推薦
国画奨学賞:宗像逸郎、合田好道、南風原朝光(絵)加藤安(版)
山田テツ(工)故・光村利払(写)。
褒状:川村滋,福留章太(絵)森一正・富岡伸吉・古山英司・林二郎・吉本寿(工)。
F夫人賞:宗像逸郎(絵。)
会員推薦:澤野岩太郎(絵)増田三男(工)畦地梅太郎・下澤木鉢郎・前田政雄(版)。
会友推薦:松木満史・中村茂好・渋川駿二・上田清一・宇治山哲平・久本弘一・山田千秋
・橋本三郎・合田好道・鈴木正二・宗像逸郎・松田正平・福井敬一・南風原朝光
・尼川尚達・内堀勉・東克己(絵)。
笹島喜平・関野準一郎・山口源(版)山田テツ・森一正・古山英司(工)。→「国画会展覧会略史」
04/02: 1940年の東京沖縄県人会②ーその周辺
戦前・戦後、常に東京沖縄県人会の指導者であった神山政良氏が1966年3月に『年表ー沖縄問題と在京県人の動き』を琉球新報社東京総局から発行している。その年表によると東京で沖縄県人会という名称は、1921年1月23日に明正塾にあった沖縄県青年会を改称した沖縄県人会が最初のものである。戦前の東京沖縄県人会①には在京の県人会幹部名を列記したが今回は個人別に紹介する。出典は1940年の東京沖縄県人会名簿。
安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町
伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町
上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂
大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町
大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)
大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町
漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)
金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町
喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町
國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国
東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)
呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」
崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町
尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町
城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町
高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦
田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田
知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川
津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町
照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷
渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町
當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)
仲原善忠(成城高等学校教授)ー世田谷区祖師谷、仲原善徳ー世田谷区祖師谷、仲宗根玄愷(昭和生命保健相互会社常務取締役)ー中野区桜山、仲宗根玄康(東京市厚生局)ー滝野川区滝野川町、仲里文英(世田谷区多聞小学校)、仲村常樽(台東小学校)ー淀橋区東大久保町、仲村専義(建築設計業)ー下谷区入谷町、仲本盛行(東京市財務局主税課)ー京橋区新佃島東町、仲本朝愛ー本郷区田町・喜久村方、仲本吉一郎ー渋谷区神山町、仲本宗厚ー渋谷区幡ヶ谷本町、仲本川原ー大森区久ヶ原、仲本徳英ー本郷区駒込千駄木町、仲田多聞ー荏原区羽田町麹谷、仲田新雄ー渋谷区笹塚町、仲尾次清正(東京憲兵隊本部)ー麹町区竹平町、仲井間宗一(文部参与官)ー麹町区平川町、仲井間宗祐(税務懇話会)ー滝野川区上中里町、仲吉良光(東京日々新聞記者)ー横浜市鶴見区鶴見町、仲村渠直和(市ヶ谷刑務所勤務)、仲野廉松ー世田谷区太子堂町
仲兼久長太郎(東京地方専売局蔵前分工場)ー江戸川区小岩町、仲地唯一(東京市電気局)ー渋谷区代々木初台、仲松弥男(荒川区第五峡田小学校)、長嶺善進(糧秣廠)ー下谷区上根岸、長嶺晃(城東区第一亀戸小学校)、長嶺朝昭(東京地方専売局)、長嶺朝英(川越税務署)ー川越市宮下町、長嶺将繁(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、名護朝徳ー荏原区荏原町、名城政教(日本起重機製作所)ー蒲田区糀谷、名城嗣亨(京橋月島第三小学校)ー京橋区月島東河岸町通、長嶺亀助(陸軍少将、軍需会社顧問)ー神奈川県茅ヶ崎、長濱三郎(大森区馬込第一小学校)ー大森区馬込町東、名嘉山徳温(東京市財務局会計課)ー板橋区上板橋、長濱眞詳(石神井西小学校)ー中野区新井町、永島可昌(下谷区竹町小学校)、名嘉繁雄(南武鉄道株式会社技術課)ー品川区北品川町、永井長雄(東京市総務局)ー中野区桜山町
安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町
伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町
上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂
大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町
大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)
大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町
漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)
金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町
喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町
國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国
東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)
呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」
崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町
尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町
城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町
高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦
田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田
知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川
津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町
照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷
渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町
當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)
仲原善忠(成城高等学校教授)ー世田谷区祖師谷、仲原善徳ー世田谷区祖師谷、仲宗根玄愷(昭和生命保健相互会社常務取締役)ー中野区桜山、仲宗根玄康(東京市厚生局)ー滝野川区滝野川町、仲里文英(世田谷区多聞小学校)、仲村常樽(台東小学校)ー淀橋区東大久保町、仲村専義(建築設計業)ー下谷区入谷町、仲本盛行(東京市財務局主税課)ー京橋区新佃島東町、仲本朝愛ー本郷区田町・喜久村方、仲本吉一郎ー渋谷区神山町、仲本宗厚ー渋谷区幡ヶ谷本町、仲本川原ー大森区久ヶ原、仲本徳英ー本郷区駒込千駄木町、仲田多聞ー荏原区羽田町麹谷、仲田新雄ー渋谷区笹塚町、仲尾次清正(東京憲兵隊本部)ー麹町区竹平町、仲井間宗一(文部参与官)ー麹町区平川町、仲井間宗祐(税務懇話会)ー滝野川区上中里町、仲吉良光(東京日々新聞記者)ー横浜市鶴見区鶴見町、仲村渠直和(市ヶ谷刑務所勤務)、仲野廉松ー世田谷区太子堂町
仲兼久長太郎(東京地方専売局蔵前分工場)ー江戸川区小岩町、仲地唯一(東京市電気局)ー渋谷区代々木初台、仲松弥男(荒川区第五峡田小学校)、長嶺善進(糧秣廠)ー下谷区上根岸、長嶺晃(城東区第一亀戸小学校)、長嶺朝昭(東京地方専売局)、長嶺朝英(川越税務署)ー川越市宮下町、長嶺将繁(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、名護朝徳ー荏原区荏原町、名城政教(日本起重機製作所)ー蒲田区糀谷、名城嗣亨(京橋月島第三小学校)ー京橋区月島東河岸町通、長嶺亀助(陸軍少将、軍需会社顧問)ー神奈川県茅ヶ崎、長濱三郎(大森区馬込第一小学校)ー大森区馬込町東、名嘉山徳温(東京市財務局会計課)ー板橋区上板橋、長濱眞詳(石神井西小学校)ー中野区新井町、永島可昌(下谷区竹町小学校)、名嘉繁雄(南武鉄道株式会社技術課)ー品川区北品川町、永井長雄(東京市総務局)ー中野区桜山町
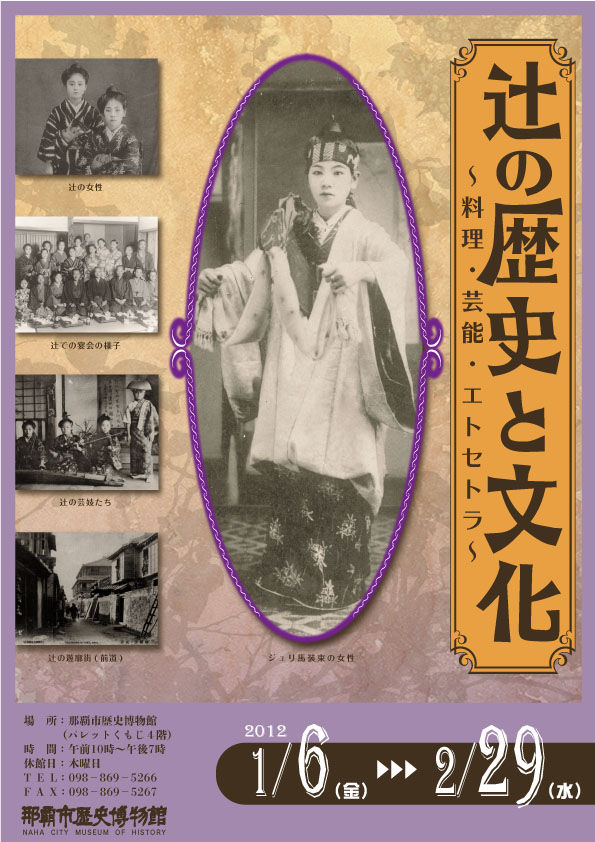
辻遊廓
戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。→2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』
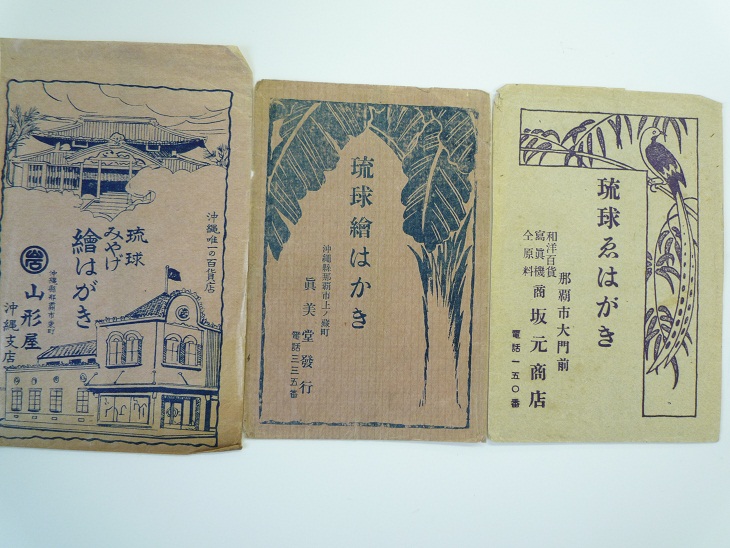
琉球絵はがき
1938年9月15日『大阪球陽新報』
□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。
家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。
県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。
辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である
2006年3月ー『史料編集室紀要』第31号 新里彩「琉球文学における『千鳥』の諸相」
□はじめにー琉球文学において、千鳥はどのように表れているのだろうか。千鳥の歌を集めてみると、琉歌うたわれる千鳥、おもろや古謡にうたわれる千鳥、組踊や舞踊の詞章にうたわれる千鳥などがあることがわかった。そして、そのうたわれ方は、和歌の伝統的な文学イメージでうたわれる他に、琉球文学特有のうたわれ方があることが浮かび上がる。
2007年3月ー『史料編集室紀要』第32号 新里彩「浅地・紺地の琉歌について」
□正直で真面目な泊染屋の職人と辻で名高い遊女マカテとの恋物語『染屋の恋唄』は、古典落語及び浪曲の『紺屋高尾』を題材にしたものであり、物語の展開、登場人物の性格などほぼ同じである。作者は髙江洲紅矢という人物であるが、制作年代は不詳である。
□関東大震災で焼け出された浪曲家・篠田実(日畜専属)の「紺屋高尾」が大当たりした。♬遊女は客に惚れたといい 客は来もせでまたくるという 嘘と嘘との色廓でー♬があちこちのレコードから聞こえた。→内山惣十郎『浪曲家の生活』雄山閣1974年


新城喜一氏と新里彩さん

2015年9月9日ー左から翁長良明氏、新里彩さん

2015年9月9日沖縄県立博物館・美術館屋外展示場「民家」で、新里彩さん
□はじめにー琉球文学において、千鳥はどのように表れているのだろうか。千鳥の歌を集めてみると、琉歌うたわれる千鳥、おもろや古謡にうたわれる千鳥、組踊や舞踊の詞章にうたわれる千鳥などがあることがわかった。そして、そのうたわれ方は、和歌の伝統的な文学イメージでうたわれる他に、琉球文学特有のうたわれ方があることが浮かび上がる。
2007年3月ー『史料編集室紀要』第32号 新里彩「浅地・紺地の琉歌について」
□正直で真面目な泊染屋の職人と辻で名高い遊女マカテとの恋物語『染屋の恋唄』は、古典落語及び浪曲の『紺屋高尾』を題材にしたものであり、物語の展開、登場人物の性格などほぼ同じである。作者は髙江洲紅矢という人物であるが、制作年代は不詳である。
□関東大震災で焼け出された浪曲家・篠田実(日畜専属)の「紺屋高尾」が大当たりした。♬遊女は客に惚れたといい 客は来もせでまたくるという 嘘と嘘との色廓でー♬があちこちのレコードから聞こえた。→内山惣十郎『浪曲家の生活』雄山閣1974年


新城喜一氏と新里彩さん

2015年9月9日ー左から翁長良明氏、新里彩さん

2015年9月9日沖縄県立博物館・美術館屋外展示場「民家」で、新里彩さん
04/19: 琉球芸能史散歩③
2003年10月11日『沖縄タイムス』新城栄徳「うちなー書の森 人の網⑧當間清弘」
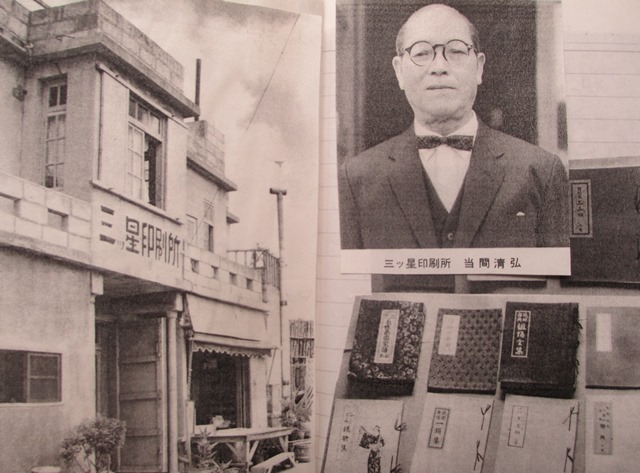
郷土史へ導いてくれた當間清弘氏
母方の伯父や伯母の連れ合いが奄美大島の出身だから、小学生のころから奄美大島は琉球の一部だと理解していた。父・三郎の出会いはちょっと違っていた。1947年、父が那覇の栄町「栄亭」のコック長のとき、用心棒代を店に要求にきた大島ヤクザに立腹し包丁で一人の鼻先を削いでしまった。父はグループの報復を恐れ糸満の親戚の所に身を隠した。翌年に生まれた私の名前の「栄」は、栄町からも来ている。
名瀬市は1972年前後3回、訪ねたが図書館はいつも休館日。だから島尾敏雄とついに出会うこともなかった。しかし、私にとってそれに匹敵する出会いが山下欣一氏だった。氏の『奄美のシャーマニズム』はもう古典的存在である。私も義母がユタをしていたので、それにまつわる話には関心がある。氏が私に資料を贈る義理は無いが気を使ってくださる。
喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。印刷者の神山邦彦は久米蔡氏で元警察官、戦後『辻情史』をまとめ発行し1977年83歳で亡くなった。
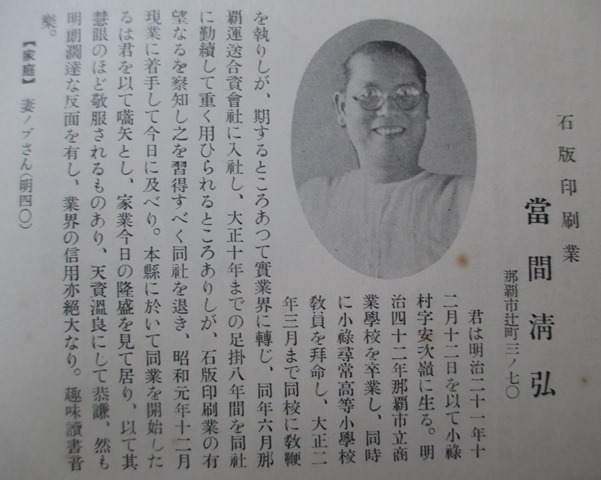
當間清弘
小学4年のころ、首里の琉潭池側の琉球政府立博物館へ「首里那覇港図」をよく見にいった。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

「昭和初期の那覇絵地図」(昭和石版印刷所 辻町3ノ70)
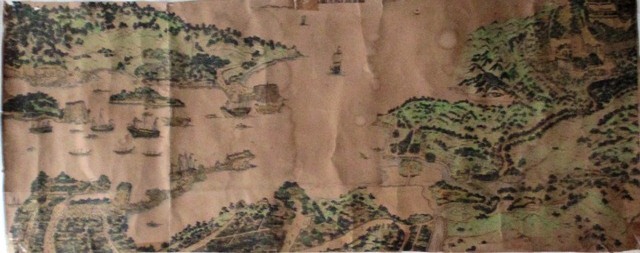
「首里那覇鳥瞰図」氏作成

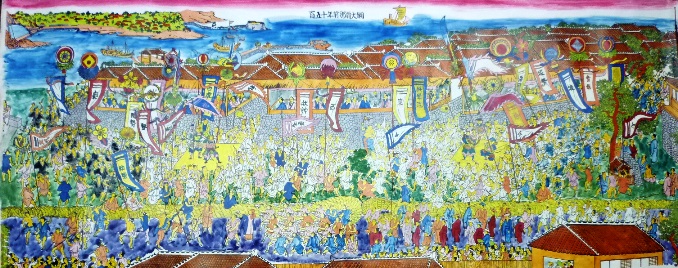
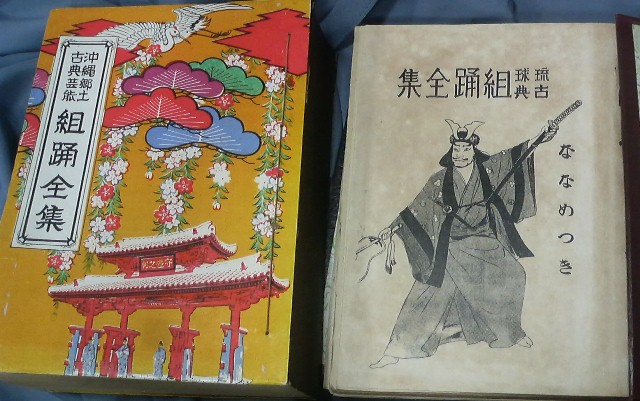
□8月 『琉球古典組踊全集』當間清弘(三ツ星印刷所)→左の本・1965年9月『沖縄郷土古典芸能 組踊全集』
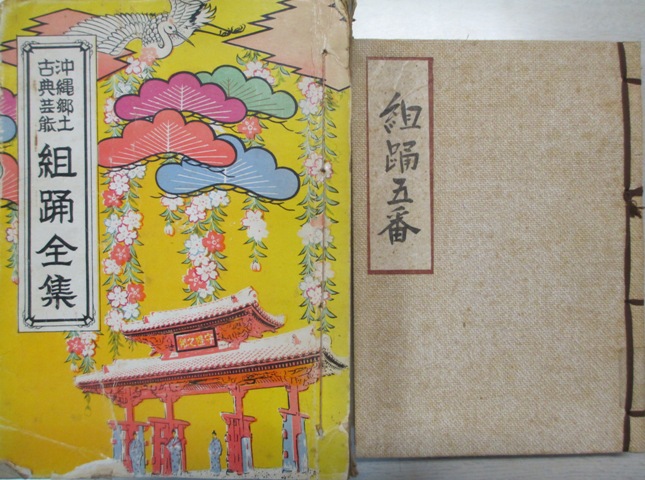
沖縄県立博物館の裏手に「みどり印刷」がある。開業したのは石川逢正氏で、氏はミルクイシチャーと呼ばれる一門の家に生まれた。1955年に開業した当初は首里バスの切符、伝票、名刺などを印刷していた。石川氏は戦前、嘉味田朝春の向春印刷所から始まって戦後は新聞などを印刷していた中丸印刷所を経て独立。今は、息子の石川和男氏が業務をこなす。「みどり印刷」←iここをクリック
2014-9-5 沖縄県立博物館・美術館にて「くしの日 美ら姿 結い遊び(主催:玉木流 琉装からじ結い研究所)」がありました。




モデル・仲里なぎささん
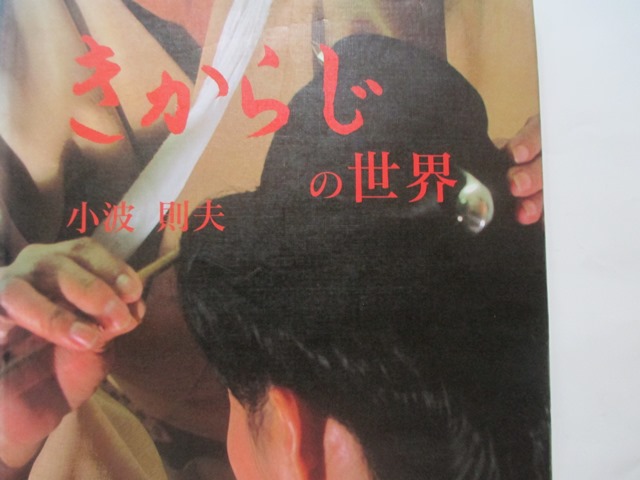
1995年10月 小波則夫/宜保榮治郎『きからじの世界』小波則夫
○グラビア/第一章ー実技編1、小波式琉髪の結い方 2、歌劇にみる髪型 /第二章ー髪型・資料編1、琉球風俗絵図 2、諸外国にみる髪型 3、琉髪と簪の歴史概説 /第三章ー対談1、小波則夫の足跡2、小波則夫の芸談 小波則夫・年譜
○写真ー金武良章、志田房子、佐藤太圭子、親泊興照、真境名由康、宮城能造、島袋光裕、宜保榮治郎、ウミングヮ役の小波則夫、久高将吉、比嘉清子、与座つる、浜元澄子・朝保、比嘉正義、玉城盛重、前田幸三郎、翁長小次郎、小山明子

2013年12月21日 沖縄県立博物館文化講座「『きからじ』と『ジーファー』」

写真左から写真家の山田實さん、牧野浩隆氏、沖縄髪結いの小波則夫氏
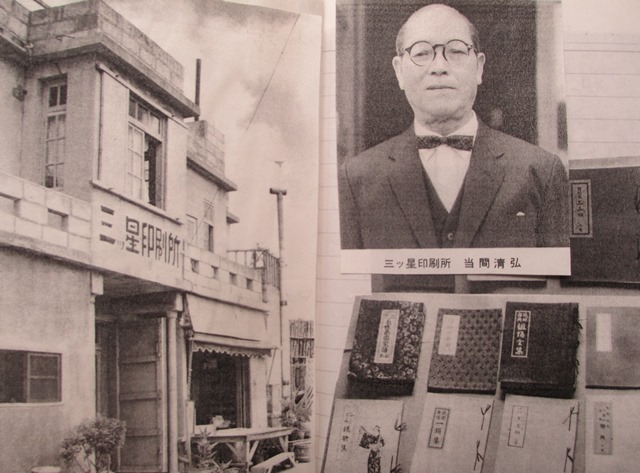
郷土史へ導いてくれた當間清弘氏
母方の伯父や伯母の連れ合いが奄美大島の出身だから、小学生のころから奄美大島は琉球の一部だと理解していた。父・三郎の出会いはちょっと違っていた。1947年、父が那覇の栄町「栄亭」のコック長のとき、用心棒代を店に要求にきた大島ヤクザに立腹し包丁で一人の鼻先を削いでしまった。父はグループの報復を恐れ糸満の親戚の所に身を隠した。翌年に生まれた私の名前の「栄」は、栄町からも来ている。
名瀬市は1972年前後3回、訪ねたが図書館はいつも休館日。だから島尾敏雄とついに出会うこともなかった。しかし、私にとってそれに匹敵する出会いが山下欣一氏だった。氏の『奄美のシャーマニズム』はもう古典的存在である。私も義母がユタをしていたので、それにまつわる話には関心がある。氏が私に資料を贈る義理は無いが気を使ってくださる。
喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。印刷者の神山邦彦は久米蔡氏で元警察官、戦後『辻情史』をまとめ発行し1977年83歳で亡くなった。
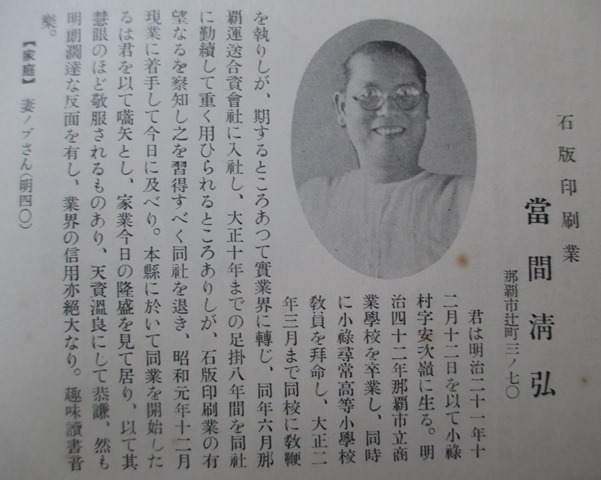
當間清弘
小学4年のころ、首里の琉潭池側の琉球政府立博物館へ「首里那覇港図」をよく見にいった。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

「昭和初期の那覇絵地図」(昭和石版印刷所 辻町3ノ70)
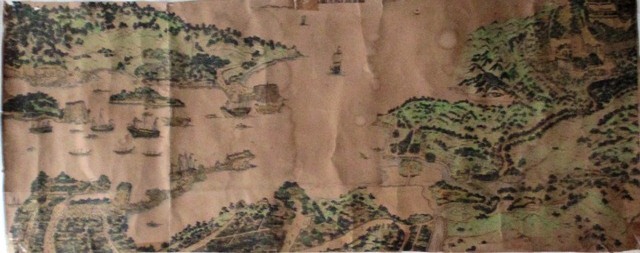
「首里那覇鳥瞰図」氏作成

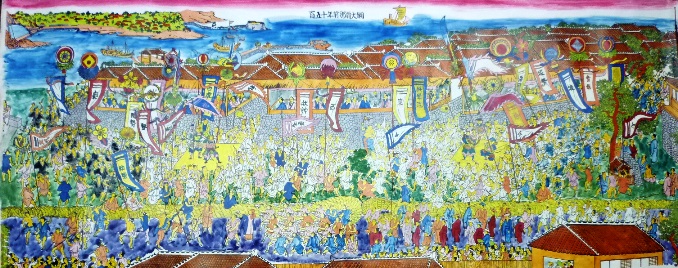
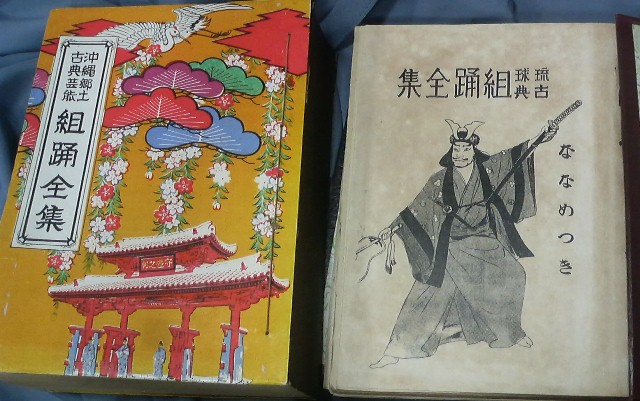
□8月 『琉球古典組踊全集』當間清弘(三ツ星印刷所)→左の本・1965年9月『沖縄郷土古典芸能 組踊全集』
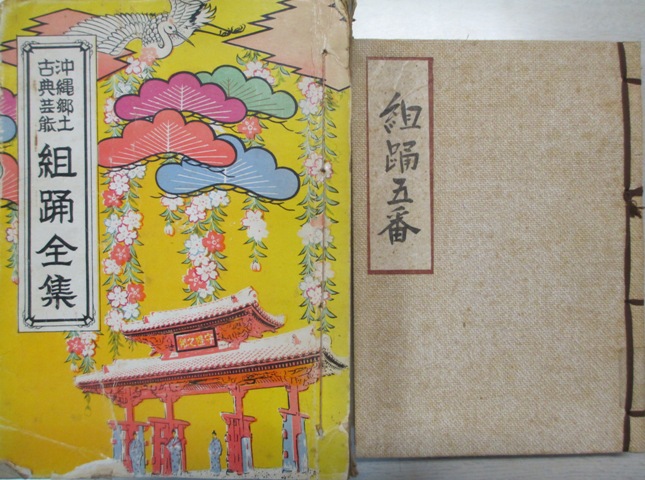
沖縄県立博物館の裏手に「みどり印刷」がある。開業したのは石川逢正氏で、氏はミルクイシチャーと呼ばれる一門の家に生まれた。1955年に開業した当初は首里バスの切符、伝票、名刺などを印刷していた。石川氏は戦前、嘉味田朝春の向春印刷所から始まって戦後は新聞などを印刷していた中丸印刷所を経て独立。今は、息子の石川和男氏が業務をこなす。「みどり印刷」←iここをクリック
2014-9-5 沖縄県立博物館・美術館にて「くしの日 美ら姿 結い遊び(主催:玉木流 琉装からじ結い研究所)」がありました。




モデル・仲里なぎささん
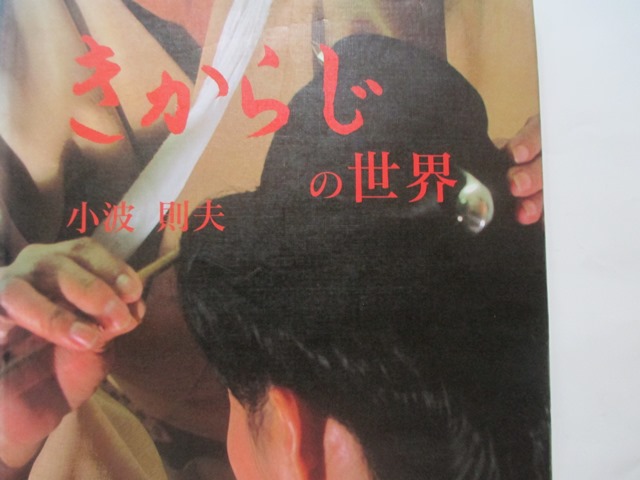
1995年10月 小波則夫/宜保榮治郎『きからじの世界』小波則夫
○グラビア/第一章ー実技編1、小波式琉髪の結い方 2、歌劇にみる髪型 /第二章ー髪型・資料編1、琉球風俗絵図 2、諸外国にみる髪型 3、琉髪と簪の歴史概説 /第三章ー対談1、小波則夫の足跡2、小波則夫の芸談 小波則夫・年譜
○写真ー金武良章、志田房子、佐藤太圭子、親泊興照、真境名由康、宮城能造、島袋光裕、宜保榮治郎、ウミングヮ役の小波則夫、久高将吉、比嘉清子、与座つる、浜元澄子・朝保、比嘉正義、玉城盛重、前田幸三郎、翁長小次郎、小山明子

2013年12月21日 沖縄県立博物館文化講座「『きからじ』と『ジーファー』」

写真左から写真家の山田實さん、牧野浩隆氏、沖縄髪結いの小波則夫氏
06/03: 南方同胞援護会/沖縄協会
□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

右端が吉田嗣延
1968年11月
『沖縄問題基本資料集』南方同胞援護会
編集スタッフ本会編集委員/責任者=吉田嗣延 委員=城間得栄、宮良長欣、河野忍、久保田芳郎、比嘉正詔 沖縄資料センター編集委員/新崎盛暉、屋宜宣仁、我部政男、比屋根照夫
1972年7月
『追補版 沖縄問題基本資料集』南方同胞援護会
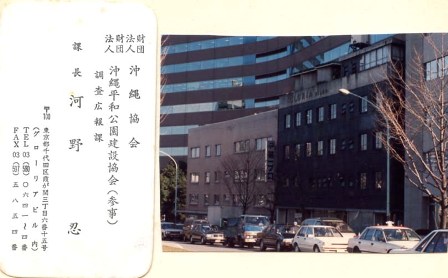
財団法人・沖縄協会(東京都千代田区霞が関3-6-15グローリアビル内)
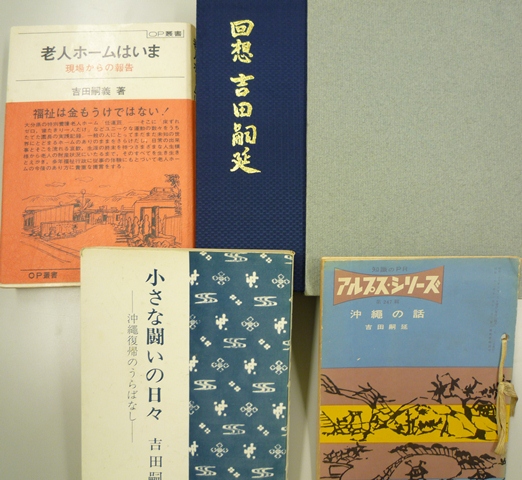
吉田嗣延『小さな闘いの日々ー沖縄復帰のうらばなしー』文教商事/吉田嗣義『老人ホームはいまー現場からの報告』ミネルヴァ書房
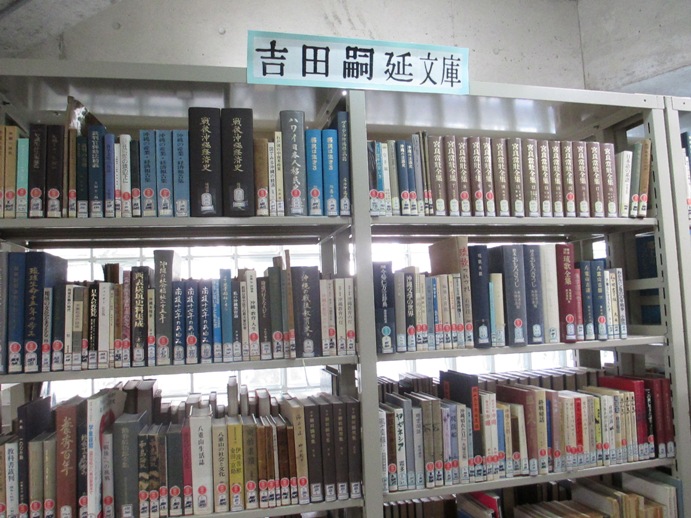
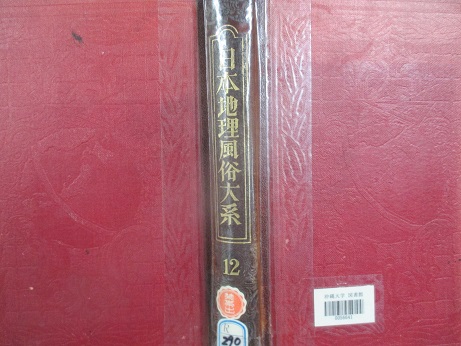
沖縄大学の吉田嗣延文庫/1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社
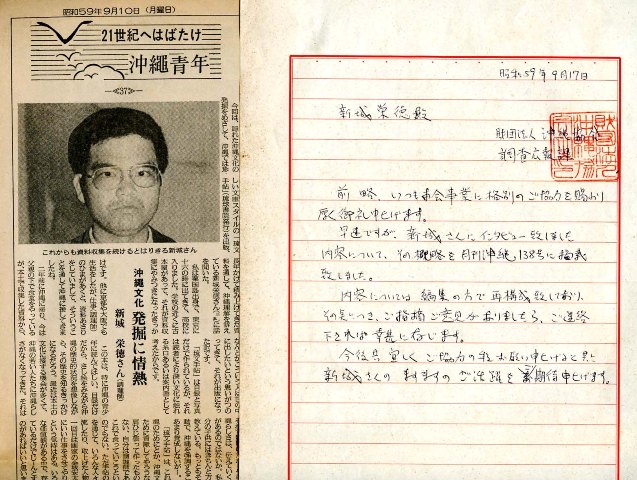
山田實さんは二中樹緑会の会員であった。その樹緑会の古い写真には大嶺政寛・政敏兄弟も写っている。最近、大嶺隆氏が沖縄本や雑誌に沖縄にこだわって発言しているのが目につく。私は画家・大嶺政寛さんには色々と可愛がってもらっていた。政寛さんの弟が画家・政敏、その子が隆氏である。1984年ー国会図書館に寄って帰り沖縄協会に行き、吉田嗣延氏に挨拶すると河野忍さんを紹介された。河野さんは部下の隆氏に私を紹介した。隆氏は私の話を聞き機関紙『沖縄』で紹介してくれた。
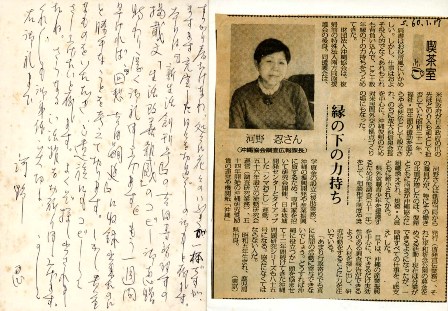
河野忍さんハガキ→新城栄徳宛/河野さんが紹介されている沖縄の新聞1985年1月17日

グローリアビル入口で右・河野忍さん、新城栄徳
〇谷町4丁目界隈を散歩する。道路のあちこちでフイリヤブラン(斑入りヤブラン)が花を咲かせている。紫色の小さいもので穂状に咲いている。このヤブランの仲間を末吉麦門冬が号にしているので、あちこちで麦門冬に見つめられているようだ。大村益次郎(適塾に学ぶ)殉職難碑があった。大阪歴史博物館売店をのぞき、庁舎としては全国でも最も古い(設計・平林金吾、岡本馨/1926年竣工)大阪府庁舎を見る。玄関両脇にソテツがあった。次に大阪府警庁舎(設計・黒川紀章、2007年竣工、建設費617億円)を見る。70年代、青年運動に参加していたので、よくここ大阪府警の売店で警察資料を買った。その一つに霞が関警備研究会『警察用語辞典』(令文社1977年)が今でもある。
『警察用語辞典』は沖縄関係の団体について詳細に記している。索引で「お」を見ると、「沖共闘」「沖青委」「沖青同」「沖縄・小笠原返還同盟」「沖縄青年委員会」「沖縄青年同盟」で、何か懐かしい名前が並んでいる。沖青同は沖縄青年同盟の略で、昭和46年10月沖青委(海邦派)を発展的に解消し、結成した。昭和46年10月18日、活動家3名が衆議院本会議場に傍聴人として入った上、爆竹を鳴らしたり、「沖縄返還協定粉砕」のビラをまくという事案を起こした、などと記されている。今思うには「密約」復帰の事実がありながら、爆竹を鳴らしたぐらいで前科が付くのは如何なものか。前科にすべきは日米両政府ではなかろうか。「密約」は今も続いている。
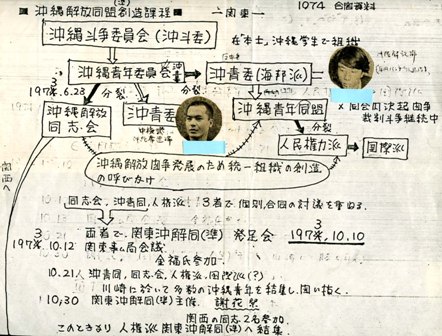
下記の一泊学習会で配布された資料
1974年ー奈良で日本各地の沖縄出身の団体が集まり一泊学習会をした。私(新城栄徳)は彫刻家の金城実氏と徳田球一の弟・正次氏と同じ部屋であった。真夜中まで寝ながら正次氏と語り明かした。そのとき正次氏から徳田球一写真集を企画しているとの話が出た。

右端が吉田嗣延
1968年11月
『沖縄問題基本資料集』南方同胞援護会
編集スタッフ本会編集委員/責任者=吉田嗣延 委員=城間得栄、宮良長欣、河野忍、久保田芳郎、比嘉正詔 沖縄資料センター編集委員/新崎盛暉、屋宜宣仁、我部政男、比屋根照夫
1972年7月
『追補版 沖縄問題基本資料集』南方同胞援護会
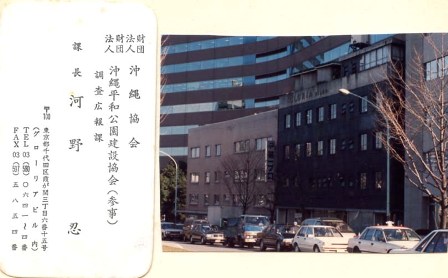
財団法人・沖縄協会(東京都千代田区霞が関3-6-15グローリアビル内)
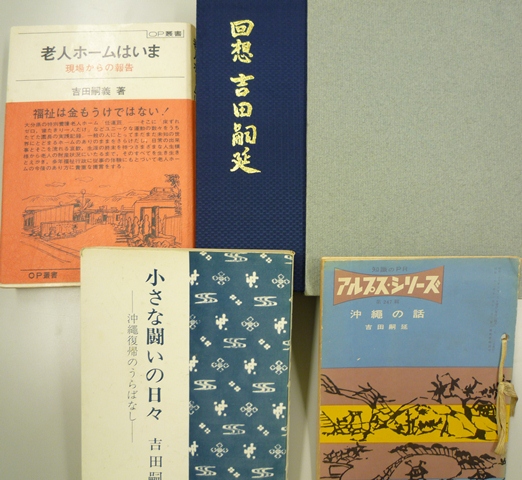
吉田嗣延『小さな闘いの日々ー沖縄復帰のうらばなしー』文教商事/吉田嗣義『老人ホームはいまー現場からの報告』ミネルヴァ書房
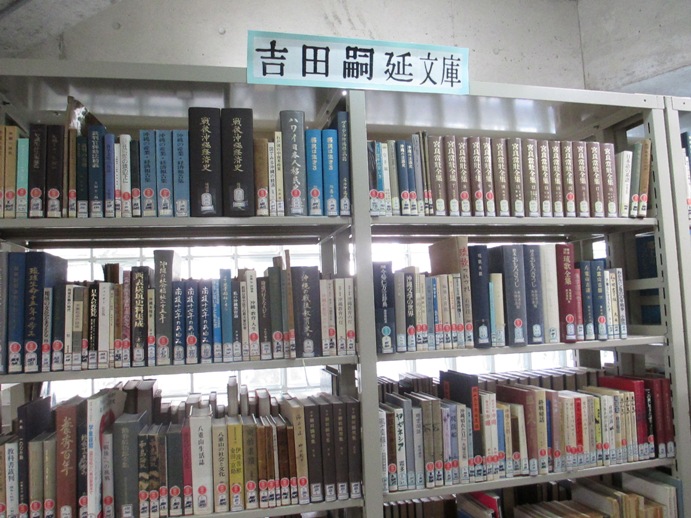
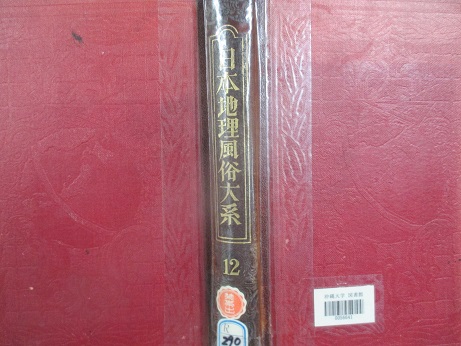
沖縄大学の吉田嗣延文庫/1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社
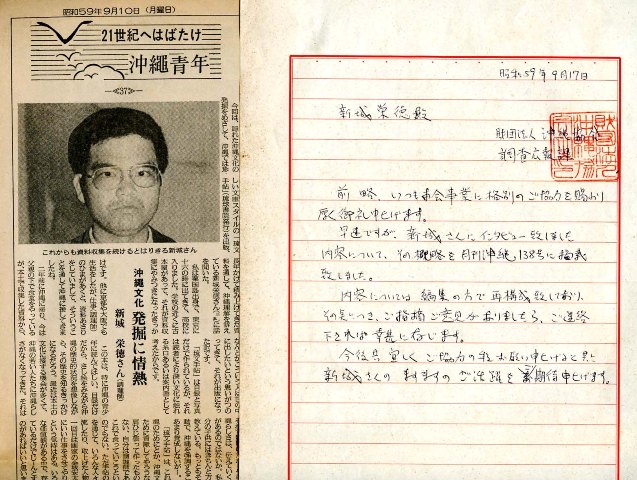
山田實さんは二中樹緑会の会員であった。その樹緑会の古い写真には大嶺政寛・政敏兄弟も写っている。最近、大嶺隆氏が沖縄本や雑誌に沖縄にこだわって発言しているのが目につく。私は画家・大嶺政寛さんには色々と可愛がってもらっていた。政寛さんの弟が画家・政敏、その子が隆氏である。1984年ー国会図書館に寄って帰り沖縄協会に行き、吉田嗣延氏に挨拶すると河野忍さんを紹介された。河野さんは部下の隆氏に私を紹介した。隆氏は私の話を聞き機関紙『沖縄』で紹介してくれた。
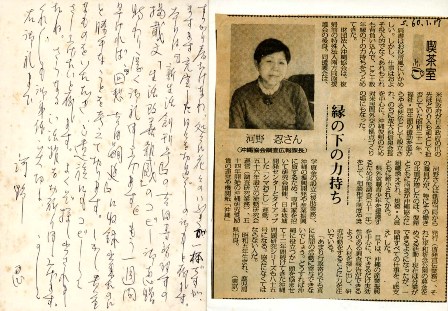
河野忍さんハガキ→新城栄徳宛/河野さんが紹介されている沖縄の新聞1985年1月17日

グローリアビル入口で右・河野忍さん、新城栄徳
〇谷町4丁目界隈を散歩する。道路のあちこちでフイリヤブラン(斑入りヤブラン)が花を咲かせている。紫色の小さいもので穂状に咲いている。このヤブランの仲間を末吉麦門冬が号にしているので、あちこちで麦門冬に見つめられているようだ。大村益次郎(適塾に学ぶ)殉職難碑があった。大阪歴史博物館売店をのぞき、庁舎としては全国でも最も古い(設計・平林金吾、岡本馨/1926年竣工)大阪府庁舎を見る。玄関両脇にソテツがあった。次に大阪府警庁舎(設計・黒川紀章、2007年竣工、建設費617億円)を見る。70年代、青年運動に参加していたので、よくここ大阪府警の売店で警察資料を買った。その一つに霞が関警備研究会『警察用語辞典』(令文社1977年)が今でもある。
『警察用語辞典』は沖縄関係の団体について詳細に記している。索引で「お」を見ると、「沖共闘」「沖青委」「沖青同」「沖縄・小笠原返還同盟」「沖縄青年委員会」「沖縄青年同盟」で、何か懐かしい名前が並んでいる。沖青同は沖縄青年同盟の略で、昭和46年10月沖青委(海邦派)を発展的に解消し、結成した。昭和46年10月18日、活動家3名が衆議院本会議場に傍聴人として入った上、爆竹を鳴らしたり、「沖縄返還協定粉砕」のビラをまくという事案を起こした、などと記されている。今思うには「密約」復帰の事実がありながら、爆竹を鳴らしたぐらいで前科が付くのは如何なものか。前科にすべきは日米両政府ではなかろうか。「密約」は今も続いている。
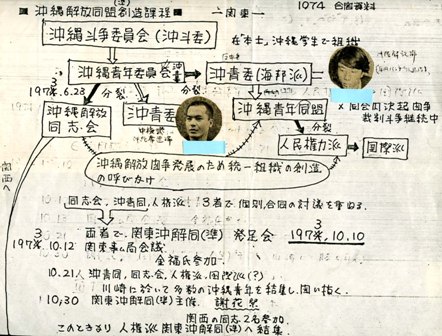
下記の一泊学習会で配布された資料
1974年ー奈良で日本各地の沖縄出身の団体が集まり一泊学習会をした。私(新城栄徳)は彫刻家の金城実氏と徳田球一の弟・正次氏と同じ部屋であった。真夜中まで寝ながら正次氏と語り明かした。そのとき正次氏から徳田球一写真集を企画しているとの話が出た。
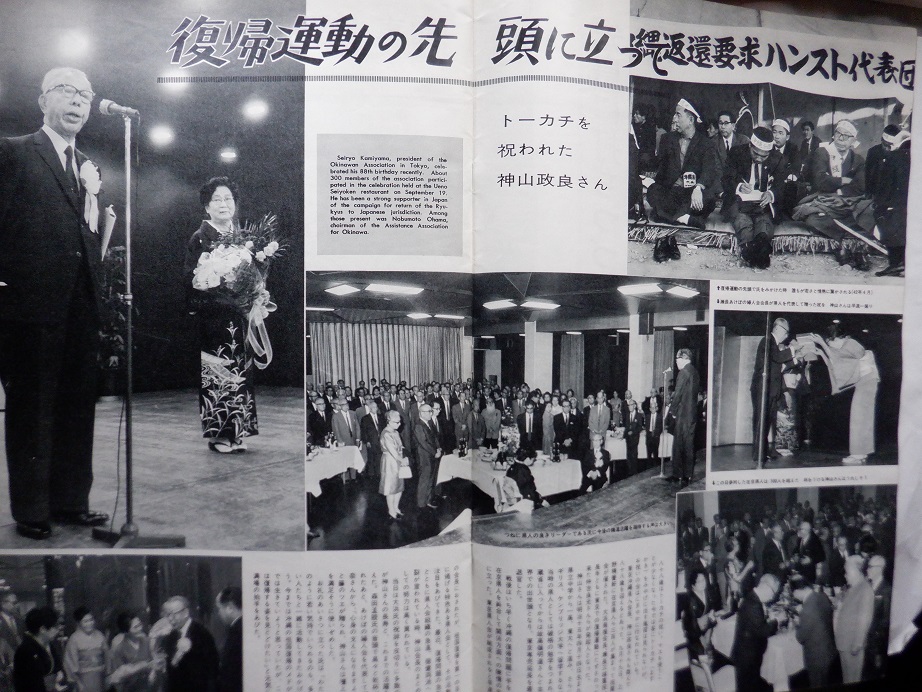
1969年12月『オキナワグラフ』
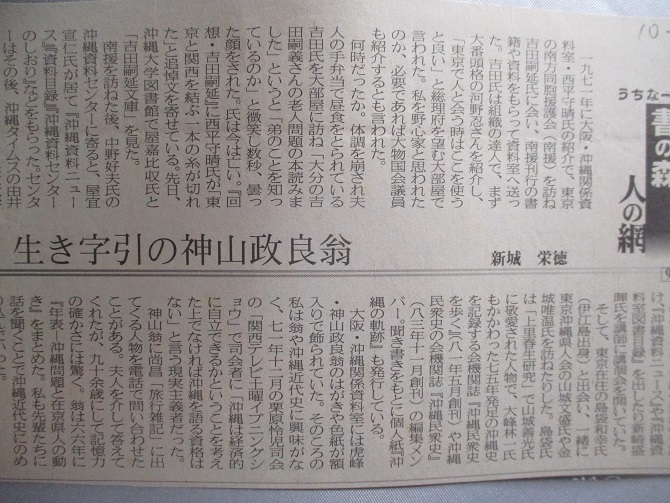
2003年10月25日『沖縄タイムス』新城栄徳「うちなー書の森 人の網⑨ー生き字引の神山政良翁」
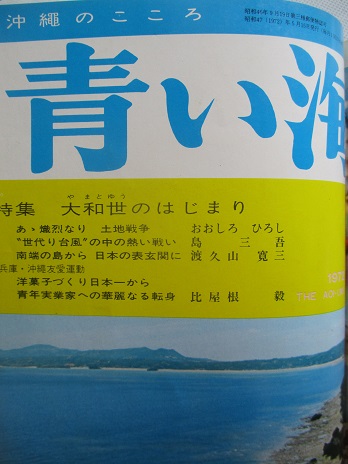
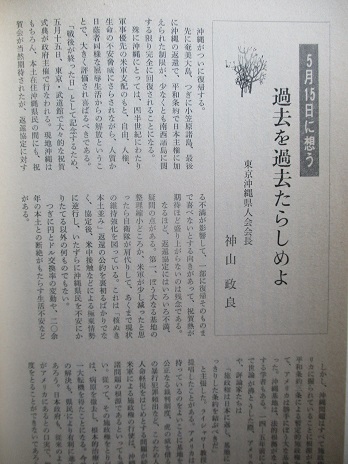
1972年5月『青い海』13号 神山政良(東京沖縄県人会会長)「5月15日に想う 過去を過去たらしめよ」
1940年の東京沖縄県人会『会員名簿』の東京沖縄県人会の沿革によればその歩みはつぎのようになる。京浜沖縄県学生会の会報で補足する□b
1886年ー在京沖縄出身の青年間に勇進社を組織す
1888年ー沖縄学生会と改称
1890年ー沖縄青年会と改称す
1899年ー照屋宏により学生の寄宿舎設立計画さる
1899年ー沖縄青年会仮事務所を麹町区富士見町2ノ7、尚侯爵邸家構内に置く
1909年ー創立20周年記念会を上野精養軒に開き朝野の名士を招待す。来会者3百余名空前の盛事なり 当時会長は護得久朝惟
1910年ー仮事務所廃止
1910年ー護得久朝惟会長提案による沖縄青年会会友会発会式を風月において挙行す
1910年ー護得久朝惟会長辞任、後任会長に漢那憲和
1911年ー寄宿舎設置補助交付の件が沖縄県会を通過、翌年より2ヵ年に亘り金壹萬円也下付せらる。当時日比重明知事、高嶺朝教県会議長、岸本賀昌学務課長
1912年ー沖縄青年会会友会を社団法人とし沖縄育英会と改称す
1913年ー寄宿舎落成式挙行。沖縄県明正塾と命名す 東恩納寛惇舎監に推薦さる
その後1923年に東恩納寛惇、舎監を辞任、神山政良が常任管理委員に推挙さる
1928年、神山政良、舎監を辞任、比嘉良篤、後任に推挙さる
東京沖縄県人会と改称す、役員を理事制度に改め漢那憲和理事長に推薦さる
□1925年5月ー京浜沖縄県学生会結成
1927年ー役員を会長制に改め、新城朝功が会長に当選し神山政良、奥島憲仁が副会長に当選す 神山副会長辞任
1928年
11月11日ー京浜沖縄県秋季総会、会長に尚謙(慶応大学)、副会長に赤嶺康成(高等師範)
□1929年
5月ー京浜沖縄県学生会秋季総会を新宿白十字堂に開く。伊波普猷「方言に現れたる土俗」講演。役員改選で会長に小嶺幸雄(早稲田大学)、副会長に福地唯義(慶応大学)。
6月2日ー京浜沖縄県学生会春期総会を新宿白十字堂ホールに開く、佐藤惣之助の「琉球旅行」の話
1929年ー役員改選さる 会長に渡口精鴻、副会長に比嘉春潮、翁長良保
□1930年
7月ー小川町の多賀羅で在ハワイ同胞母国観光団歓迎会、主賓の金城珍栄以下10余名、県人出席者30余名。
11月9日ー京浜沖縄県学生会秋季総会を神田駿河台下白井喫茶部2階で開く、渡口精鴻、比嘉春潮の談話、女子部の会長に豊川とみ
□1931年
3月19日ー漢那憲和代議士、移民会館建設の準備成功し帰国
4月29日ー大蔵省参事の神山政良、名古屋専売局長に栄転さる。
5月17日ー神楽坂福寿倶楽部で東京沖縄県人会春季総会、役員改選 会長に渡口精鴻留任、副会長に奥島憲仁、恩河朝健
1932年ー明正塾廃止
1936年ー5月、本会沿革及び名簿を謄写す
1936年ー役員改選さる 会長に神山政良、副会長に大濱信泉、八幡一郎
1937年ー東京沖縄県人会(芝区虎ノ門会館 久高特許事務所内)『会員名簿』作成頒布
1938年ー役員改選さる 会長に神山政良、副会長に大濱信泉、八幡一郎
1940年ー東京沖縄県人会『会員名簿』
大宜味朝徳は海外研究所を設立し『我が統治南洋群島案内』『最近のペルー事情』『最近の布哇事情』などを発刊した。1933年1月に南島社(東京市本郷区蓬莱町5)から郷友版『南島』紙を発行する。3号(1933年3月)に「東京琉球泡盛商一覧」が載っているのを始め平敷本舗主人の平敷安用の「「東京に於ける琉球泡盛の今昔」、東京での泡盛委託販売30年の入江藤五郎の「泡盛の黄金時代」、「泡盛界に躍進する三島本舗主・川村禎二君」が載っている。また泡盛商広告に崎山商店(崎山喜昌),うるま本店(金城時男)、琉球古代焼・花瓶置物・琉球漆器・琉球玩具も扱う仲本商店(仲本宗厚)がある。
『南島』4号に「知念松一君、沖縄写真帖計画」が出ている。知念松一は8号の個人消息で「大阪市港区八雲町4で関西沖縄新聞創刊」とある。また空手講習会、南島談話会、泡盛組合、東京沖縄県人会の集会も紹介されている。1934年2月『南島』10号の集会欄に「名古屋県人会(比嘉康進)が神山政良顧問で万歳三唱、舞踊、空手あり」と報じられ、8月の『南島』13号には稲垣国三郎氏の義挙として「大阪稲垣愛日小学校長は6ヵ年間沖縄師範主事として勤務したことがあるが久松五勇士の快挙につき種々尽力、公にし且つ映画化して南島男子の意気を顕揚せしめた。この義挙に対し在阪県人有志の我喜屋宗信、山城興善、下地玄信、平尾喜代松、真栄田勝朗、幸地長堅らが大いに協力した」が載っている。ほかに『南島』の個人消息欄には上原美津子(中央電話局教師)、伊波普猷長男國男君目出度本年度二中に入学、また久志芙沙子の随筆がある。
1936年10月27日午後5時から、神田区小川町の多賀羅亭で東京沖縄県人会臨時総会が開かれた。定刻までに90人が集まった。先ず神山政良会長が開会を宣した後、会則改正の必要を説明。そして新会則案を提出し、副会長の八幡一郎がこれを朗読し審議に入った。神山政良が会長に再選。あと会食。その後に漢那憲和、渡口精鴻の旧会長、幹部の労を謝し、大城兼義がパンフ「沖縄県回生の要訣」を手に憂郷の熱弁を振う。午後10時、大城兼義の音頭とりで「東京沖縄県人会万歳」を三唱して和気藹々のうちに散会した。
1937年
東京沖縄県人会会則
第1条 東京沖縄県人会は東京府下在住の沖縄県人を以って組織す但し府外在住者又は沖縄県に縁故を有する他府県人にして入会を希望する者は之を会員となすことを得
第2条 本会は会員相互の懇親を図り且つ沖縄県人の向上発展に貢献するを以って目的となす
第3条 本会は下の事業を行う
1、会報の発行
2、会員の慶弔
3、県出身優良学生並びに篤行者の奨励表彰
4、県人会館の建設
5、其の他第2条の目的達成上必要と認むる事項
東京沖縄県人会役員
会長ー神山政良 副会長ー大濱信泉、八幡一郎
幹事ー安次富松蔵、伊元富爾、伊豆見元永、井上寛令、我謝秀裕、久高将吉、高嶺明達、高良憲福、仲吉良光、仲原善忠、比嘉良篤、比嘉春潮、船越義英、真玉橋朝起、宮城清、饒平名智太郎
顧問ー伊江朝助、伊波普猷、伊禮肇、大城兼義、漢那憲和、渡口精鴻、東恩納寛惇、尚亘、長嶺亀助、仲宗根玄愷、銘苅正太郎、花城永渡、山本實彦
評議員ー石原三覧、石嶺傳亮、石川正通、池城安信、大城兼真、大城朝申、大宜味朝徳、奥島憲仁、奥間徳一、翁長良保、親泊朝輝、恩河朝健、嘉手苅信世、金城時男、国吉良實、久志助起、国吉真俊、崎原當升、志村宗徳、島袋全達、平敷安川、津波古充計、仲里朝章、仲兼久長太郎、新田宗盛、比屋根安定、宮城幸安、宮城新昌、山川朝賢、山内朝常、山川政功、森田孟睦、読谷山朝宣
東京葛飾区在住の島袋和幸氏の調査によれば、1886年、アメリカ船ゲーリック号でサンフランシスコに到着しミシガン大学準備のため友人らと下宿していた粕谷義三が、友人たちと協同で週刊邦文新聞『第十九世紀』を発行した。後に粕谷は大学を終えて帰国、板垣退助の日本自由新聞社の主筆をつとめた。第5回総選挙で衆院議員に当選、立憲政友会に所属し埼玉支部長もつとめた。粕谷は埼玉県入間市藤沢の出身、その市民会館前に銅像がある。その粕谷義三の知遇を得たのが沖縄美里出身の大宜味朝徳で、粕谷の協力の下で1922年12月に週刊『埼玉公論』紙を創刊する。大宜味が1926年に『沖縄及沖縄人』を発行したのは前回記した。
1921年10月ー沖縄協会創立
沖縄協会創立趣意書
本県は地理上の関係よりして古来本土との交通稀疎にして制度習俗亦従って異なるものあり明治維新後他府県同様法治の制を布かれしも猶各種の関係に於いて特殊の点在するものありしも今や県勢の振興発展は制度に於いて特例なく各般の施設亦他に比し敢えて遜色ありと言ふに非らざるも只だ本県事情の正当なる紹介を得ざる為め較もすれば他の誤解を招き惹いて損失を蒙ることすくなしとせざるものあり更に遺憾とする所は本県関係の重要懸案にして中央と連繋を要するもの益々繋きを加ふべきに而も之に処する何等機関用意の設けなきこと之れなり為めに凡ての企図策応によるべきなく且つ機を逸するの憾みあり之を以って吾が沖縄を広く江湖に紹介し且つ中央との連繋を採る機関の必要は久しく唱導されしも機の熟せざるものありしが機運の際会は之が創立を県内外在住の識者諸賢に提唱するの急に迫るものあり冀くは各位の賛同を得て本県将来の振興発展に資せんことをー大正十年十月。
役員
総裁・床次竹二郎 会長・和田潤 副会長・我如古楽一郎 理事・金城清松、黒木一二、崎浜秀主、銘苅正太郎、伊江朝助、大濱用要、山城五郎、宮城栄喜、伊仲浩、大城亀作、新垣牛一、盛島明長
1922年8月24日、沖縄県庁会議室で沖縄協会第4回理事会ー和田会長挨拶。東京市に沖縄協会支部設置並びに平和紀念東京博覧会の沖縄売店(出品者ー丸山漆器店、米次漆器店、漆器組合、太原漆器店、黒田理平庵、渡久地商店、新西商店、津嘉山商店、西田商店、渡慶次商店、食品会社、古賀商店、酒造組合、水産組合、上運天令儀、時志商店)の状況報告□会議参加者・和田会長、我如古副会長、理事は崎浜秀主、黒木一二、金城清松、山城五郎、宮城栄喜、桑原一郎、新垣牛一
沖縄協会在京会員
安慶名徳潤ー淀橋町柏木、新崎康ジョー小石川区下富坂、安谷屋繁ー小石川区茗荷谷、千原成梧ー青山原宿、東恩納寛惇ー小石川区水道橋、国吉良名ー麻布区、銘苅正太郎ー麻布区六本木、仲宗根玄愷カイー小石川区関口台、仲村政人ー牛込区原町、高山徹ー下渉、上運天令儀ー神田区今川小路
11/01: 1893年9月15日『琉球新報』創刊
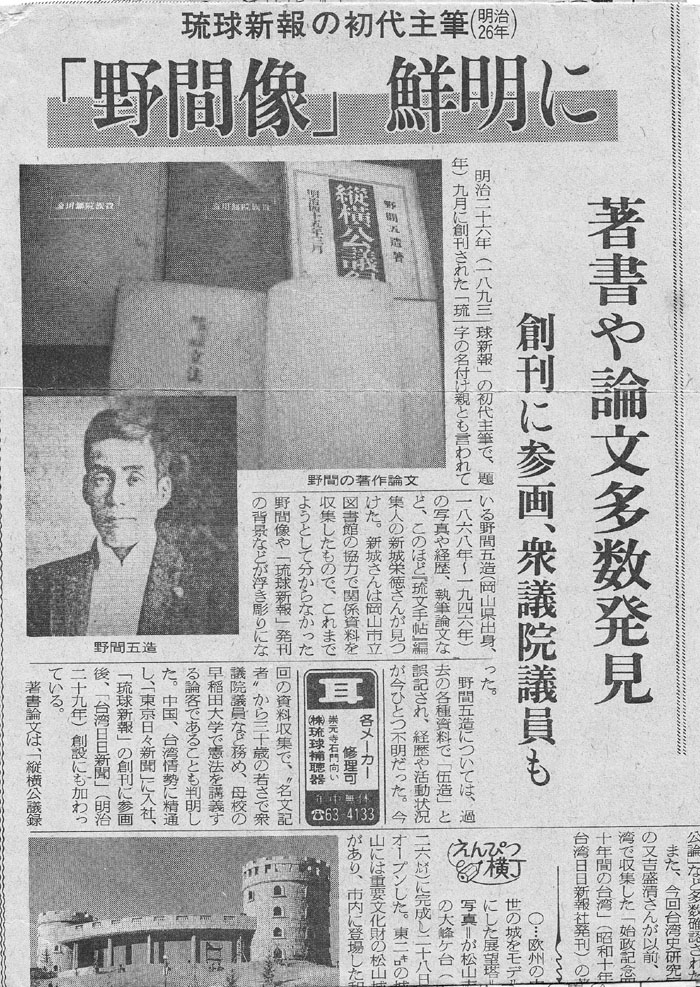
1989年11月30日『琉球新報』松島弘明「琉球新報初代主筆・野間五造の著書や論文発見」
私は1989年11月に、琉球新報初代主筆の野間五造の経歴を発掘したことがある。大阪府立中之島図書館で、たまたま講談社創立者の野間清治のカードを繰っていたら、琉球新報の野間五造を思い出しカードで調べた。著書が次々出てきた。『縦横公儀録』(1912年)、『日支合邦論』(1913年)、『立法一元論ー貴族院無用論』(1926年)などがあった。岡山県出身ということも分かった。岡山市立中央図書館に岡本月村(画家)と共に問い合わせると野間の写真、新聞記事、人名簿などのコピーを送ってくれた。
『中国新聞』によると、「桜痴時代の新聞記者として健筆をふるった五造は、若い血潮にまかせてシナ、琉球、タイワン、満州ととびまわり巨万の富を築いた実業家でもあった」とある。五造は1898年、30歳のとき、若さと金にものをいわせ木堂派の憲政党公認で衆議院に出て当選した。1900年から01年にかけて欧米、インド、北津、ロシアなどを視察して帰国。次いで02年の衆議院にも再選された。政界を引退し満州にわたり水運公司をおこし財をなして07年に帰国。銀座や明石海岸に大邸宅を構え政界を放浪し日夜、遊里で大尽遊びを続けていた。
1911年1月発行の雑誌『グラヒック』に美人論と題し「今日のように新橋全盛の世と移りかわっている。その新橋でも江戸っ子芸者から名古屋の金城美人の全盛を迎え、今は北越種を加味し来り。此のぶんで進めば台湾の生蕃や琉球のアンガが飛び出す時代もくるであろうと思われる」と書いている。五造の女性の好みは知らないが、最近のテレビなどに毎日のように沖縄のアンガが出ていることを
教えてあげたいものだ。
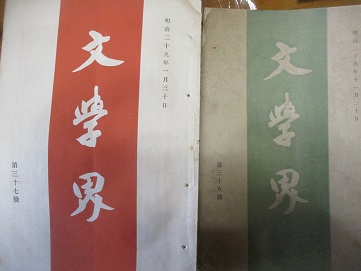

『文學界』(ぶんがくかい)は、1893年(明治26年)1月から1898年(明治31年)1月まで58冊発行された、明治期のロマン主義の月刊文芸雑誌。ほかに、臨時増刊の『うらわか草』(1896年5月)が1冊ある。北村透谷、島崎藤村、平田禿木、樋口一葉、上田敏、田山花袋らが書いた。/創刊時の同人は、星野天知(当時31歳)・戸川秋骨(22歳)・島崎藤村(21歳)・平田禿木(20歳)らで、間もなく馬場孤蝶(24歳)・上田敏(19歳)が加わり、北村透谷(25歳)・樋口一葉(21歳)・戸川残花(38歳)、遅れて、田山花袋・松岡国男・大野洒竹らも書いた。経営・編集には星野天地が当たり、弟の星野夕影が手伝った。→ウィキ
1893年、寺内某が来沖し、料理屋「東家」の協力を得て沖縄芝居の俳優らを雇い関西興行をなす(7月・大阪角座、8月・京都祇園座、9月・名古屋千歳座)。俳優のひとり真栄平房春は病没し大阪上町の了性寺に葬られた。9月15日に『琉球新報』が創刊された。発起人代表が尚順で、護得久朝惟、高嶺朝教、豊見城盛和、芝原佐一(京都出身、京都名産会社経営)、野間五造(岡山県出身、後に衆議院議員)は主筆、宮井悦之輔(元京都養蚕会社支配人、後に大阪の興信社に勤める)、大田朝敷、伊奈訓(新潟出身、県庁役人)、諸見里朝鴻の以上のメンバーで発足した。
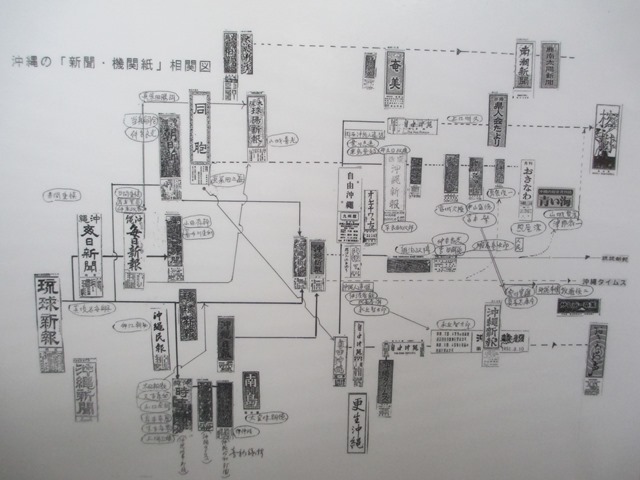
1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。
コルシカ島生まれのナポレオンは、新聞一紙は5千の兵に匹敵するとし新聞統制を計り活用した。駅逓頭・前島密が指導した『郵便報知新聞』が創刊された1872年、川崎正蔵は大蔵省の命で琉球物産調査に赴き「経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島に認められて日本政府郵便蒸気船会社の副頭取に就任し、琉球との郵便航路を開設。73年には海軍大佐柳楢悦らが測量で来琉した。川崎は後に川崎造船所を興し神戸又新日報社、神戸新聞社にかかわる。郵便報知は後に報知新聞となり読売新聞と合併する。
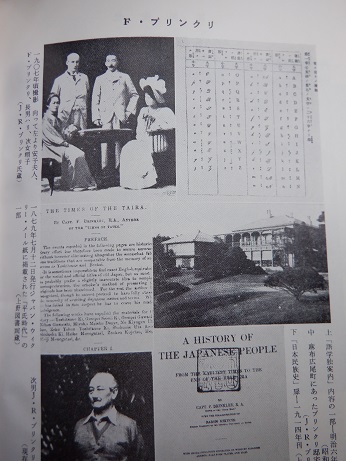
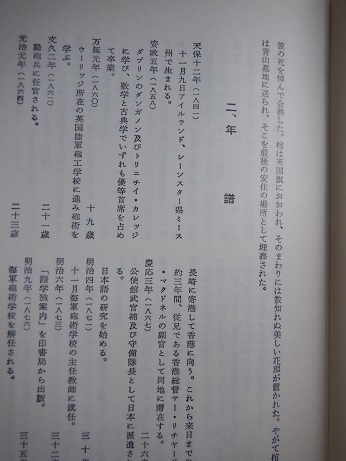
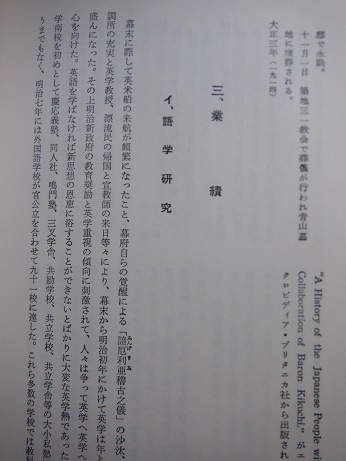
1972年3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書13』「石川啄木 田岡嶺雲 F・ブリンクリ 鹽井両江 木村正辞」
◇フランシス・ブリンクリー(Francis Brinkley、1841年11月9日 - 1912年10月22日)は、イギリスのジャーナリスト、海軍軍人。1841年、アイルランドのミーズ県の名門貴族の家に生まれた。1867年に香港を経由して日本駐屯イギリス砲兵中尉として横浜に来日すると、勝海舟らに見いだされて海軍省のお雇い軍人となった。日本の海軍砲術学校の教師に就任、1871年には『語学独案内』(Guide to English self-taught、1875)という本を著述、好評を博した。ブリンクリーはのちに工部大学校の数学教師となっている。その後、ジャーナリストに転じ、1881年にはジャパンウィークリーメール紙(1870年創刊)を買収、経営者兼主筆となって、以降、親日的な態度により日本の立場を擁護しつつ、海外に紹介している。また、寄書家に広く紙面を解放していた。→ウイキ
1875年9月、日本国郵便蒸気汽船会社解散にともない明治政府は大有丸を琉球藩に下付。11月、郵便汽船三菱会社が琉球航路を開始した。1876年8月27日の『朝野新聞』に「沖縄は他県からの商人50人、陸軍省派遣の職工138人、女性1人」と報じられた。同年、琉球正史『球陽』の書き継ぎが終わっている。
1879年3月、松田道之琉球処分官が、後藤敬臣ら内務官僚42人、警部巡査160人余(中に天王寺公園に銅像がある後の大阪市長・池上四郎も居た)、熊本鎮台分遣隊400人をともない来琉し琉球藩を解体、沖縄県を設置した。この時、内務省で琉球処分事務を担当したのが西村捨三であった。5月には沖縄県令として鍋島直彬が長崎出身官僚32人をともない着任した。前後して、琉球藩王・尚泰は東海丸で那覇港を出帆。6月4日には神戸で2泊。6月6日に新潟丸で東京に向けて神戸港を出帆。
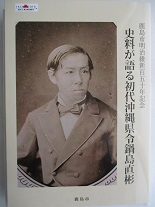

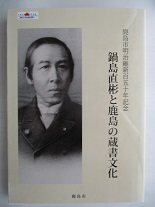

2018年12月 鹿島市民生涯学習・文化振興財団『史料が語る初代沖縄県令鍋島直彬』鹿島市/2018年11月 鹿島市民生涯学習・文化振興財団『鍋島直彬と鹿島の蔵書文化』鹿島市
1880年6月に、郵便汽船三菱会社の貫効丸が琉球、鹿児島・大島、神戸間を運航をはじめた。翌1881年3月に東京上野で開催の第二回内国勧業博覧会に沖縄からも織物、陶器、漆器が出品された。1881年5月18日に上杉茂憲が沖縄県令として赴任してきた。7月の大阪『朝日新聞』に「沖縄県泡盛酒」の広告が載った。翌1882年の『朝日新聞』には、「琉球カスリ-西平筑登之」の広告も載った。
1882年11月16日、第1回沖縄県費留学生の大田朝敷、謝花昇、岸本賀昌、高嶺朝教、今帰仁朝蕃が那覇港から平安丸で上京、29日には神戸に寄っている。1883年4月に岩村通俊が沖縄県令として赴任した。12月には西村捨三が沖縄県令となる。1884年2月6日、大阪中之島の自由亭で尚典新婚帰郷の饗応に岩村通俊、西村捨三、建野郷三らが参加した。3月12日に大阪西区立売堀に鹿児島沖縄産糖売捌所が設立された。5月12日には大阪北区富島町で大阪商船会社が開業。8月、尚泰侯爵、西村捨三と同行し大有丸で那覇港に着く。
1885年2月、尚泰侯爵、西村捨三と同行し金毘羅宮参詣。西村は中井弘滋賀県令と計り尚泰に近江八景遊覧にさそう。8月には元彦根藩士で西村と同士であった横内扶が沖縄県七等属として赴任する。9月、郵便汽船三菱会社、共同運輸会社と合併し日本郵船会社となる。1886年3月、山県有朋内務大臣、益田孝、西村捨三らと同行し来沖。4月には大迫貞清が沖縄県令として赴任。11月、在京沖縄県学生会・勇進社が結成された。

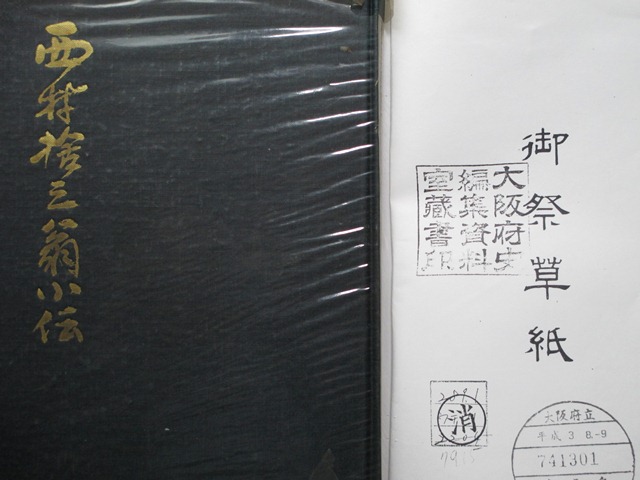
西村捨三
生年: 天保14.7.29 (1843.8.24)
没年: 明治41.1.14 (1908)
明治期の官僚。父は彦根藩(滋賀県)作事奉行西村又治郎,母は貞。幼君井伊愛麿(直憲)に仕え,藩校弘道館に学んだのち同館国学方教授長野義言(主膳)の推薦を得て藩命により江戸に留学,塩谷宕陰に学んだ。この留学中の放蕩に対し,父が幼名の得三郎を捨三に改めると訓戒したのが名の由来。のち一代限騎馬徒士,藩校教授となる。その間京都周旋方として情報収集に当たり,大政奉還後は朝旨遵奉という藩の方針の下で東山道征討に参加した。明治5(1872)年旧藩主直憲に従い欧米を視察,10年内務省に出仕し,警保局長,土木局長などを歴任した。22年大阪府知事に転じ淀川改修,上水道整備に尽力し,次いで農商務次官のとき平安神宮創建に参画。大阪築港にも貢献した。 (コトバンク・長井純市)
1887年2月、森有礼文部大臣が来沖した。6月、尚家資本の広運社が設立され球陽丸を那覇-神戸間に運航させる。11月に伊藤博文総理大臣、大山巌陸軍大臣が軍艦で画家の山本芳翠、漢詩人の森槐南を同行して来沖した。1888年4月に大阪西区立売堀南通5丁目に琉球物産会社「丸一大阪支店」を設置する。9月18日に丸岡莞爾が沖縄県知事として赴任。10月には塙忠雄(塙保己一曾孫)が沖縄県属として赴任した。
塙保己一については『群書類従』『続群書類従』の編纂者として余りにも著名で「塙保己一史料館・温故学会ホームページー公益社団法人 温故学会〒150-0011 東京都渋谷区東2-9-1」を見てもらうことにして沖縄に関りがある保己一の曾孫・塙忠雄についてふれる。1996年8月26日『琉球新報』に「明治の世相、風俗克明に」と紹介され、斎藤政雄温故学会長が温故学会誌に注釈つきで発表したコメントしている。祖父・塙忠宝は、江戸幕府老中安藤信正の命で、前田夏蔭と共に寛永以前の幕府による外国人待遇の式典について調査するも、孝明帝を廃位せしめるために「廃帝の典故」について調査しているとの誤った巷説が伝えられ、勤皇浪士達(伊藤博文と山尾庸三)を刺激。12月21日、幕臣中坊陽之助邸(駿河台)で開かれた和歌の会から帰宅したところ、自宅兼和学講談所の前で知人の加藤甲次郎と共に襲撃され、翌日死去した。→ウィキ。伊藤博文のテロリストの側面が伺える。
父塙忠韶 (はなわ-ただつぐ)1832-1918 幕末-明治時代の国学者。天保(てんぽう)3年生まれ。塙保己一(ほきいち)の孫。塙忠宝(ただとみ)の子。文久2年父が暗殺されたため家をつぎ,幕府の勘定格,和学講談所付となる。維新後は修史局御用掛などをつとめた。大正7年9月11日死去。87歳。江戸出身。初名は保忠。通称は敬太郎,太郎。またチェンバレンが自己の蔵書整理をあたらせたこともある。那覇市歴史博物館の横内家古文書には塙忠雄書簡がある。
写真ー『群書類従』『続群書類従』
写真ー那覇市歴史博物館の横内家古文書
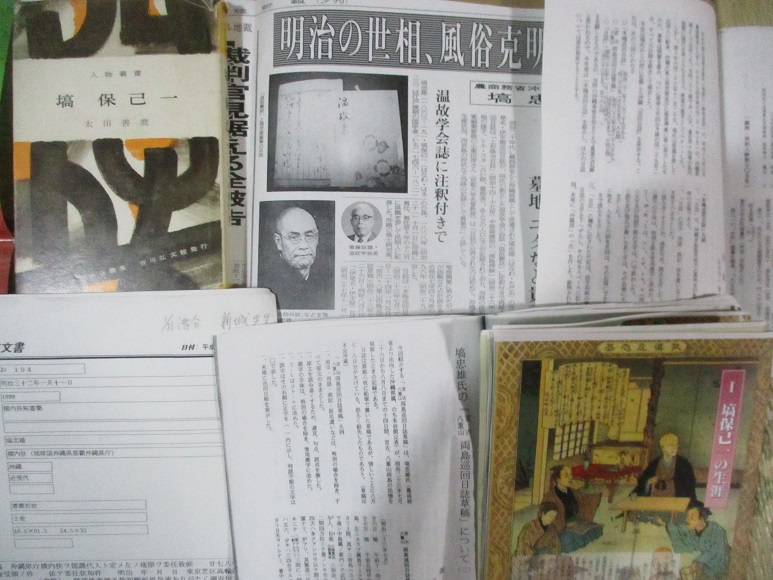
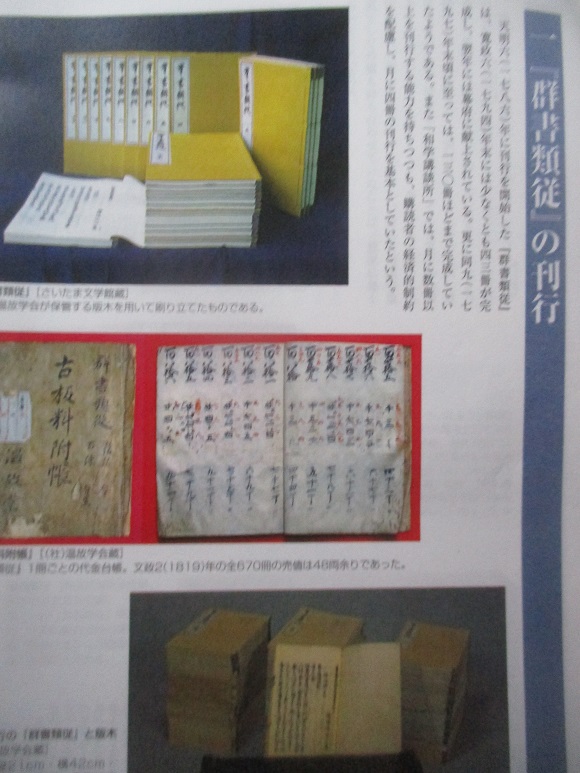
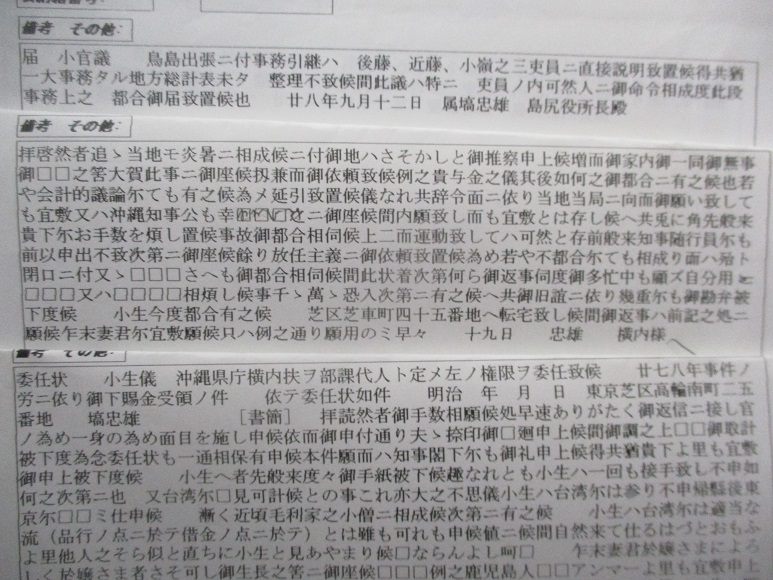
『琉球新報』の創刊は一八九三(明治二十六)年九月十五日だが、実はそれ以前にも新聞発行の動きがあったことが分かっている。一八九〇(明治二十三)年十二月十三日の『官報』に「沖縄新聞、隔日、琉球国泉崎村九番地、沖縄新聞社」と記されているが、この新聞は計画だけで終わった(新城栄徳「琉球新報」九三年四月二十日)。
■明治23年7月6日『九州日日新聞』「沖縄県に一新聞起るー行なきより近来時勢の進歩に連れて其必要を感する者日に増加し先頃来頻りに計画奔走中の者ありし由なるが今度同県庶務課属華族戸田敬義氏等の発起にて準備○○は整頓したるに依り愈々近日より一新聞を発行す○の○合なるが主筆には戸田氏自ら當る筈なりといふ」→國吉まこも氏提供
1890年9月、東京で『沖縄青年雑誌』が創刊される。編集員は富川盛睦、仲吉朝助、謝花昇、諸見里朝鴻であった。1893年、寺内某が来沖し、料理屋「東家」の協力を得て沖縄芝居の俳優らを雇い関西興行をなす(7月・大阪角座、8月・京都祇園座、9月・名古屋千歳座)。俳優のひとり真栄平房春は病没し大阪上町の了性寺に葬られた。9月15日に『琉球新報』が創刊された。発起人代表が尚順で、護得久朝惟、高嶺朝教、豊見城盛和、芝原佐一(京都出身、京都名産会社経営)、野間五造(岡山県出身、後に衆議院議員)は主筆、宮井悦之輔(元京都養蚕会社支配人、後に大阪の興信社に勤める)、大田朝敷、伊奈訓(新潟出身、県庁役人)、諸見里朝鴻の以上のメンバーで発足した。
琉球新報創刊を報じたヤマトの新聞を見ることにする。9月15日の『東京朝日新聞』に「琉球新報の発刊-琉球新報は日刊として沖縄県那覇より本日十五日初号を発刊することとなり主任は同地名族護得久朝惟、高嶺朝教両氏(共に久しく慶応義塾に留学せし人)又東京にても岸本賀昌、今西恒太郎の両氏は同社の成立に尽力せりと」。同日に『時事新報』『郵便報知新聞』『毎日新聞』も同じように報じた。
同年9月22日、『大阪朝日新聞』は「琉球新報-廃藩置県の日浅く他県に比して一層の啓発を要するの地宜なる哉此新報の発刊を見るや新報は隔日刊にして初号には琉球年代記を附録せり」。京都『日出新聞』は「琉球新報-混沌たる暗黒の幕を破りて五百余万の王民に対し閃山一道光燈来の光景を与へんと期する琉球新報は本月十五日を以って第一号を発刊せり紙幅体裁固より内地の発達したる諸新聞紙に比すべくもあらざれど邦人をして琉球に於ける政治社会経済上の事実を知らしめ沖縄県民をして旧慣陋習を破り文明の空気に触れしむるの機関として裨益する処少なからざるべし発行所は那覇西村百二十三番地にして隔日刊行する由」と報じた。
同年9月23日、『読売新聞』は「琉球新報-かねて噂ありたる琉球新報は去十五日第一号を発兌せり吾人は之より琉球が社会上の問題として並びに経済上の問題として天下に紹介さるるを喜ぶ」と報じる。 同年9月26日、『朝野新聞』は「琉球に新報起れリ-昔は絶海の孤島、今は沖縄県の奔蒼裡に、喜ぶべし開明の一機関なる新聞は起これり。今や計画準備全く整頓して、琉球新報と題名し、去る十五日を以って第一号を発兌したりという。発起人は尚順氏の代表者、島按司護得久朝惟、商人芝原佐一、按司高嶺某、同親方豊見城某、宮井悦之助、野間五造の人々にて、発行兼印刷人は伊奈訓氏、編集人は太田朝敷氏、校正は諸見里朝鴻氏なり。印刷機械は従来沖縄県庁に備え付けありしものを七万圓にて払い下げ、維持費には同県庁の公布式を引き受けし年額二千圓余を充つるはずなりとぞ。因に記す、新聞の発行は当分隔日なる由」。27日の『国民新聞』は「琉球新報は去る十五日那覇西村琉球新報に由て発刊せられたり曾て慶応義塾に遊学しつつありたる琉球人の筆になる云ふ」と報じられた。
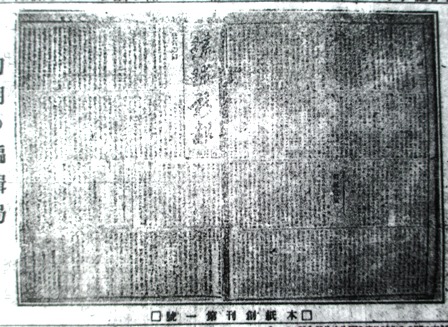

1917年9月24日『琉球新報』「本紙創刊第一號」
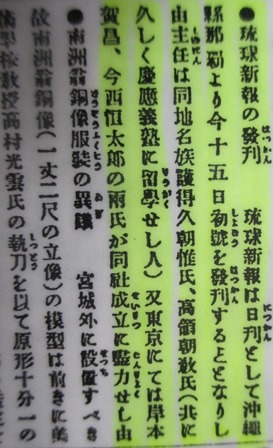
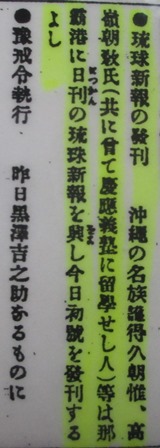
1893年9月15日『毎日新聞』 『郵便報知新聞』
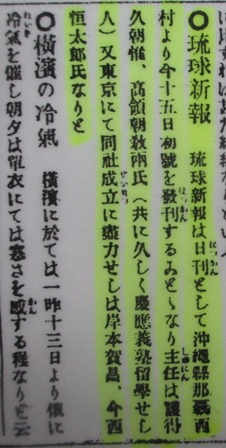
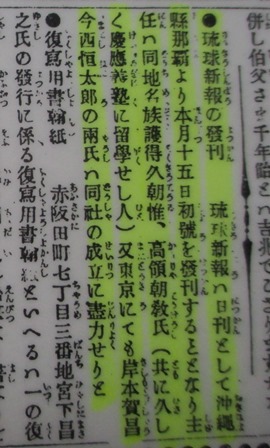
1893年9月15日『時事新報』 『東京朝日新聞』
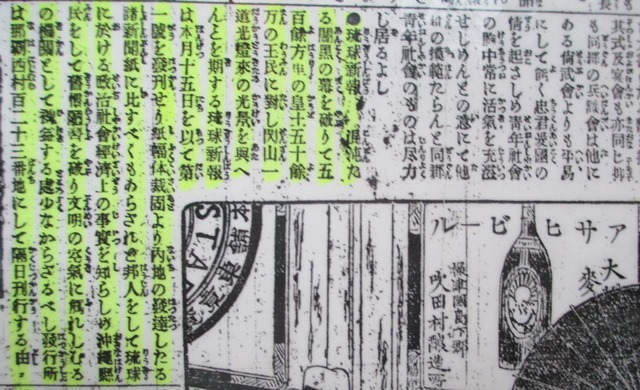
1893年9月22日『日出新聞』
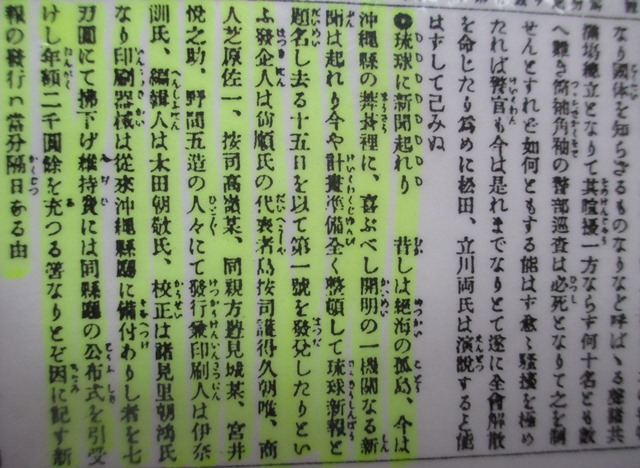
1893年9月26日『朝野新聞』