06/22: 鎌倉芳太郎①
鎌倉芳太郎年譜

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男
1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業
1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。
1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。
○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。
①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)
な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)
1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。
②平田松堂 ひらた-しょうどう
1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。
明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)
③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)
東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)
④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)
美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)
1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立
赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。
①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ
1853-1904 明治時代の実業家。
嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)
②赤星鐵馬
1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。
1901年(明治34年) 東京中学卒。
渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。
1910年(明治43年) 帰国。
1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。
1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。
1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)
③平山成信 ひらやま-なりのぶ
1854-1929 明治-大正時代の官僚。
嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)
1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。
鎌倉芳太郎、首里の座間味家に
□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄
1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。
9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。
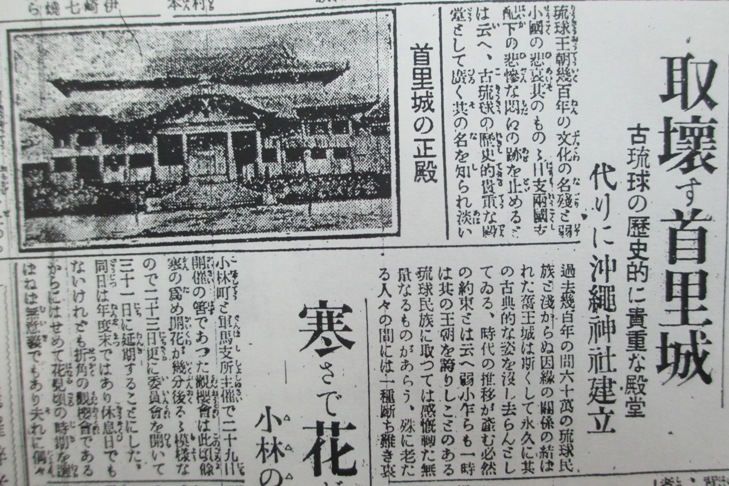
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
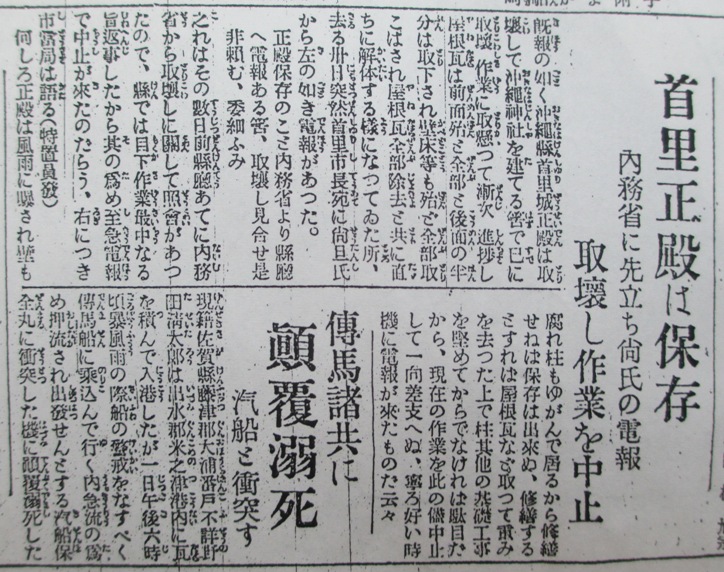
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。
1924-4
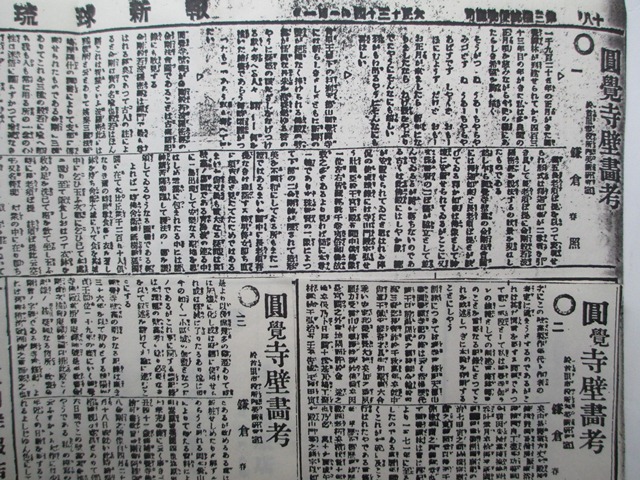
1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。
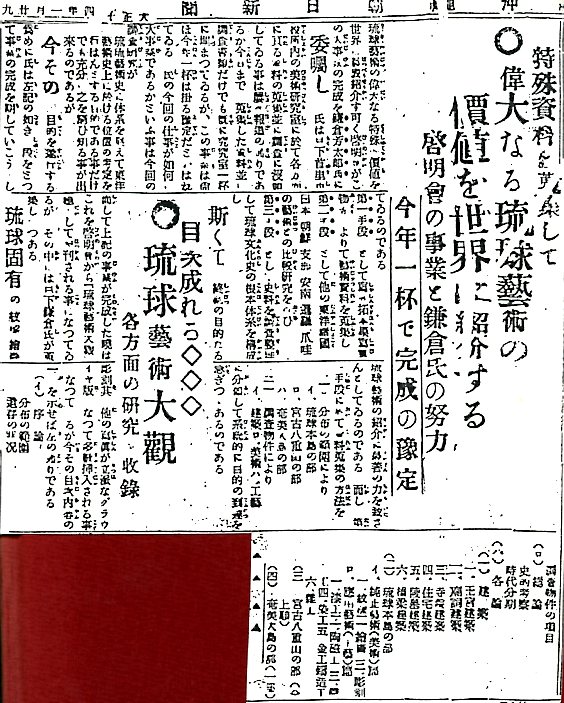
1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」
1925(大正14)年
9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)
12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて
12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」
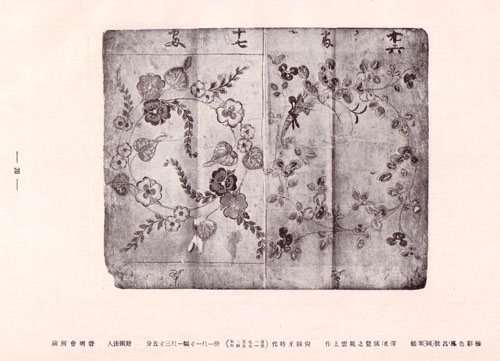
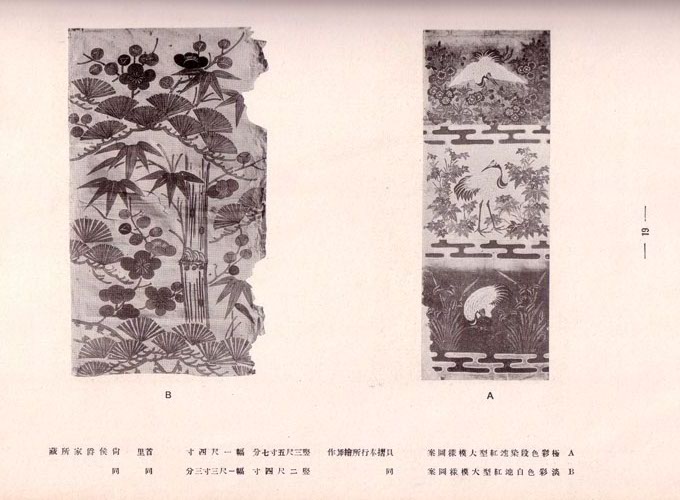
1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」
1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。
9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。
12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」
1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。
1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」
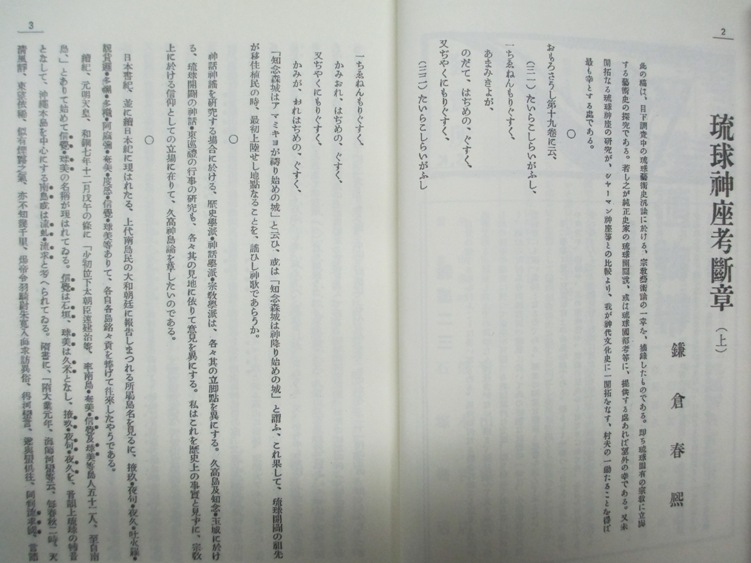
1927年
9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。
1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」


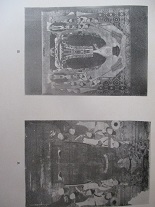

1928-12 『東洋工藝集粋』
『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」
1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」
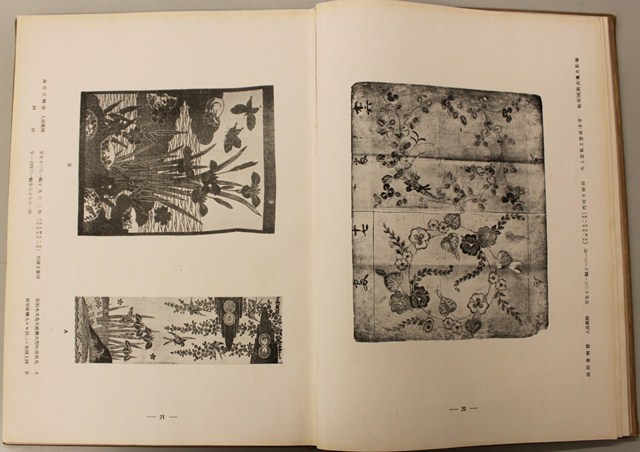
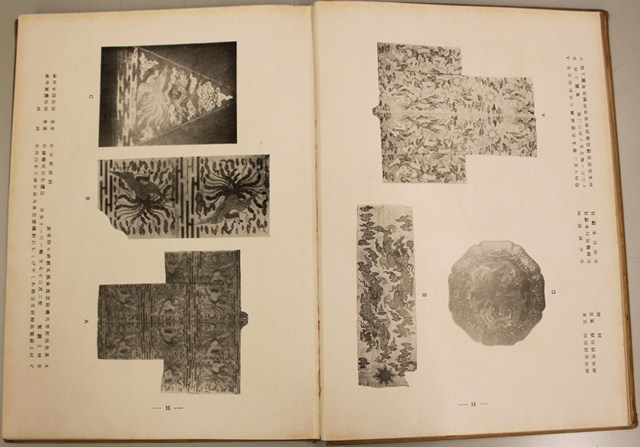
1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」
1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部
1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』
1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)
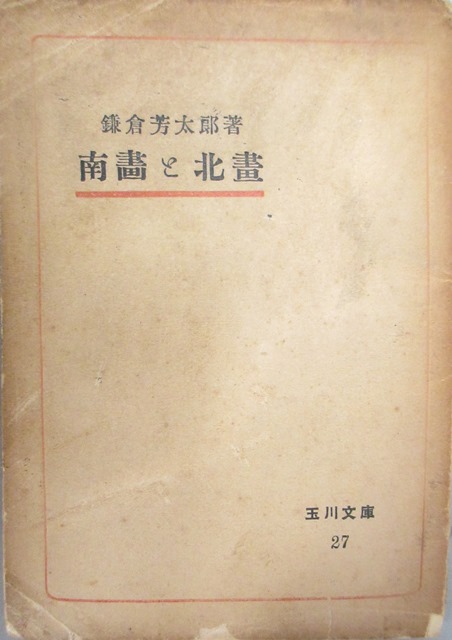
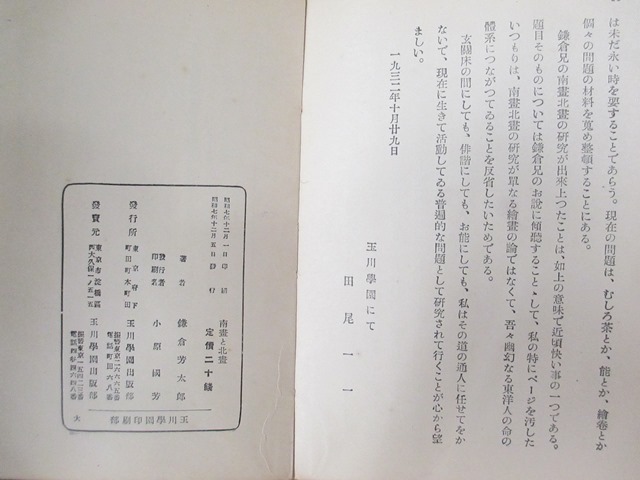
(粟国恭子所蔵)
1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫
1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。
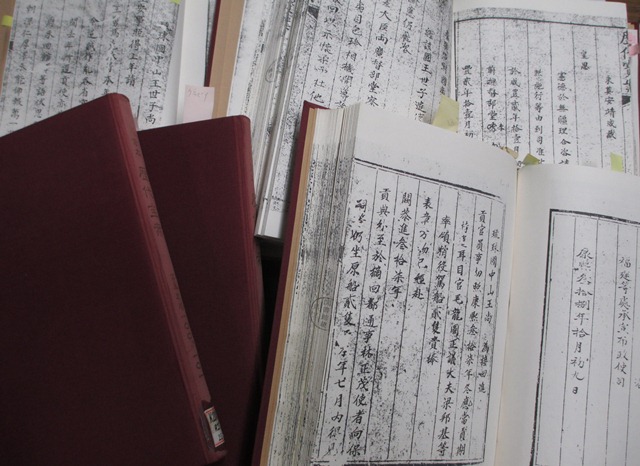
れきだいほうあん【歴代宝案】
琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)
1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」
1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』
1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」
1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖
1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。
1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)
1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。
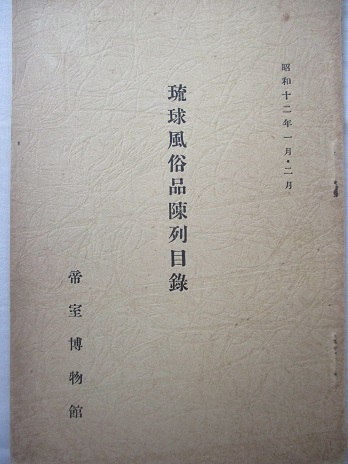
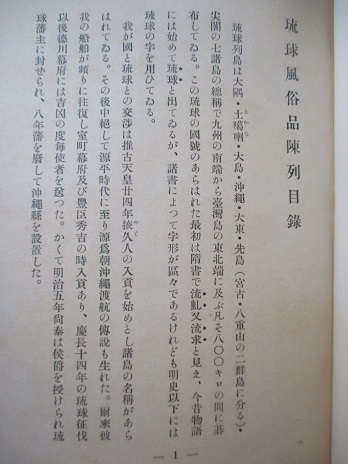
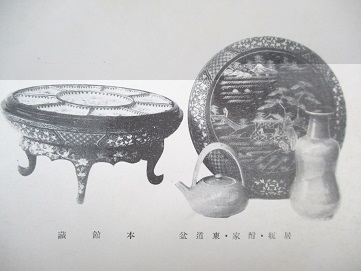


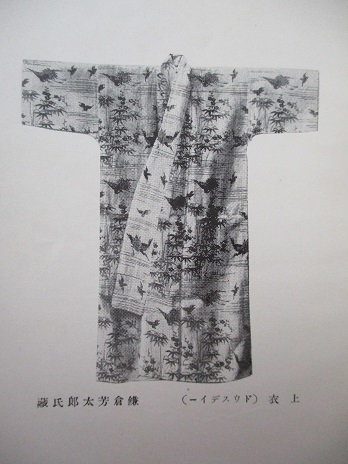

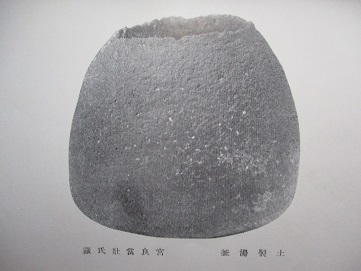
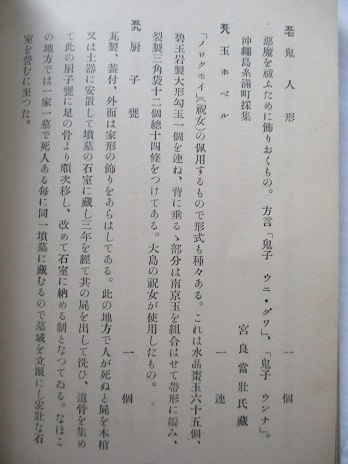
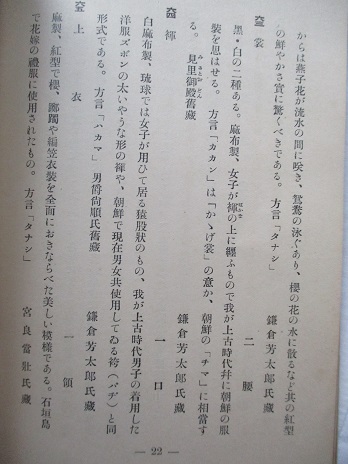
1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』
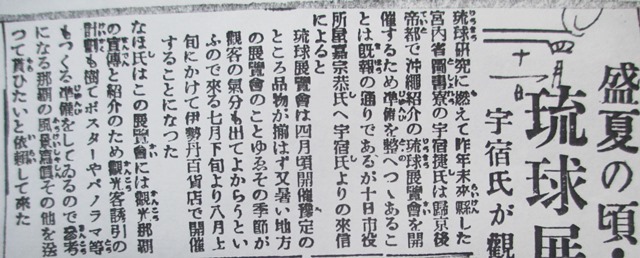
1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』
○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男
1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業
1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。
1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。
○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。
①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)
な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)
1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。
②平田松堂 ひらた-しょうどう
1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。
明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)
③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)
東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)
④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)
美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)
1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立
赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。
①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ
1853-1904 明治時代の実業家。
嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)
②赤星鐵馬
1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。
1901年(明治34年) 東京中学卒。
渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。
1910年(明治43年) 帰国。
1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。
1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。
1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)
③平山成信 ひらやま-なりのぶ
1854-1929 明治-大正時代の官僚。
嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)
1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。
鎌倉芳太郎、首里の座間味家に
□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄
1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。
9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。
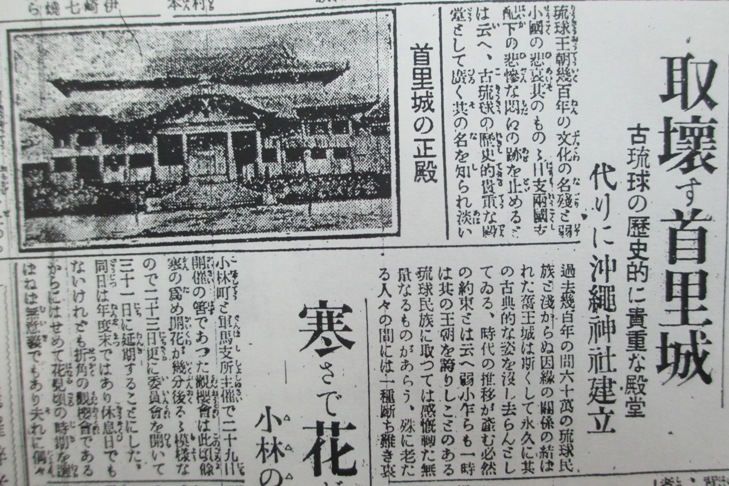
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
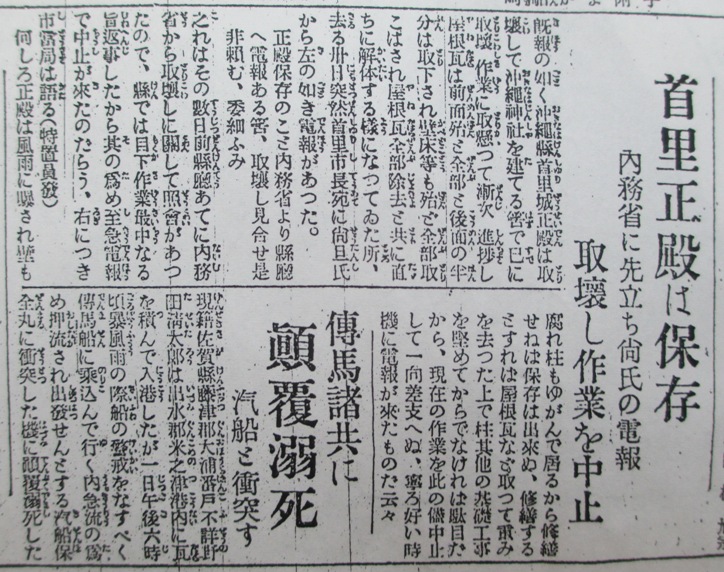
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。
1924-4
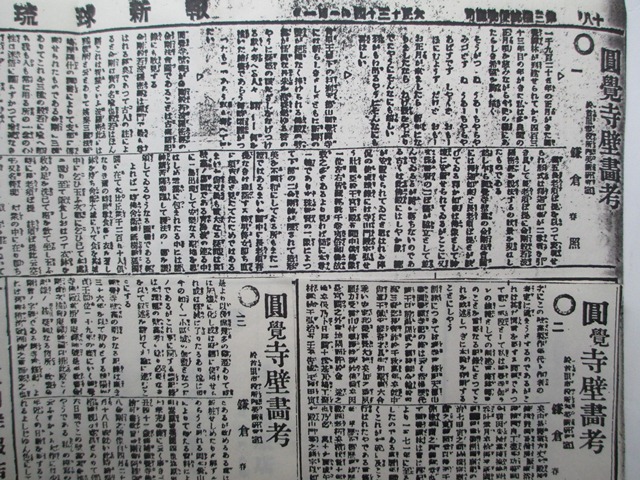
1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。
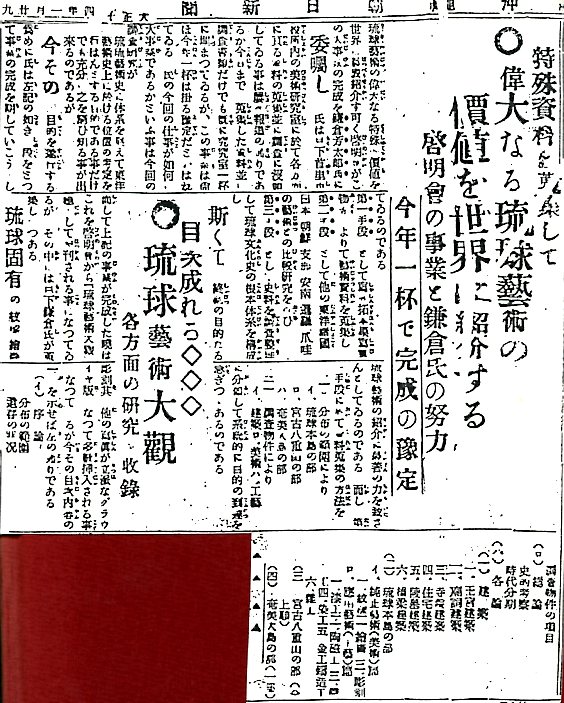
1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」
1925(大正14)年
9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)
12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて
12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」
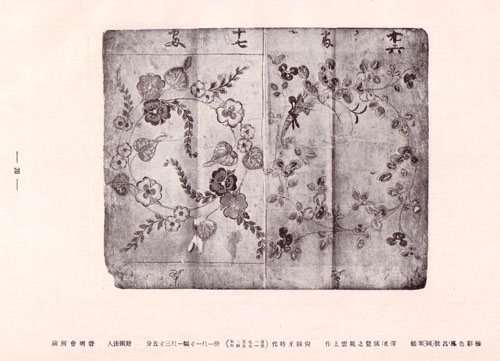
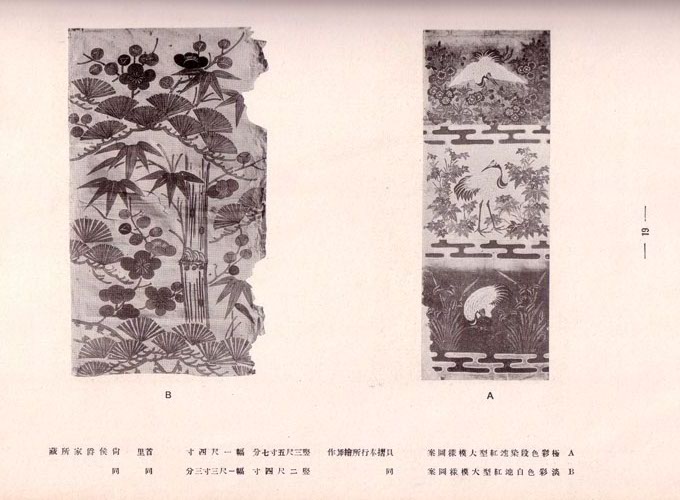
1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」
1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。
9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。
12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」
1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。
1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」
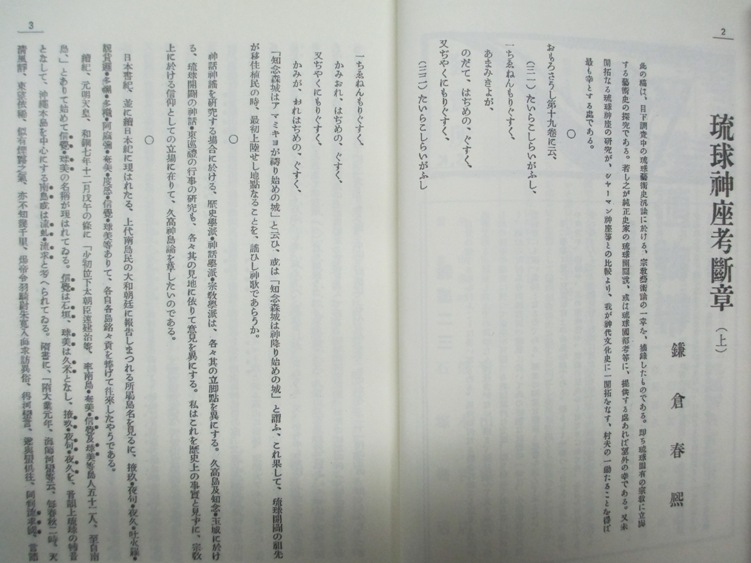
1927年
9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。
1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」


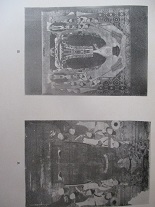

1928-12 『東洋工藝集粋』
『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」
1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」
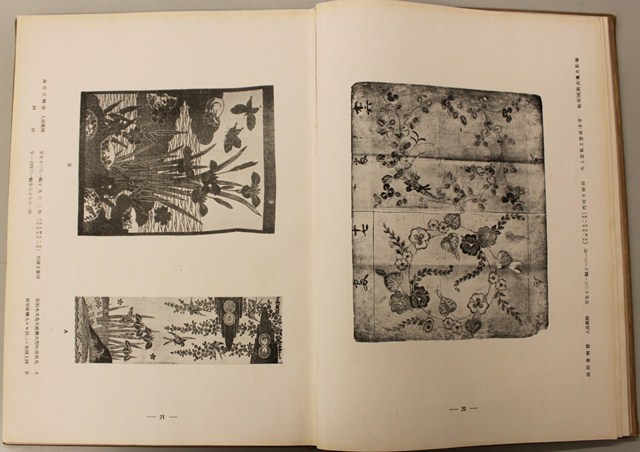
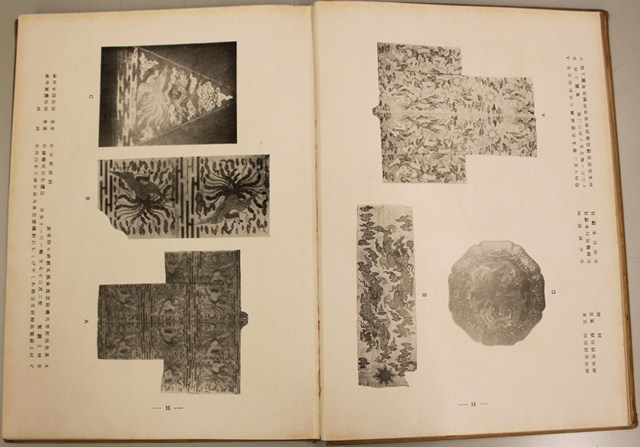
1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」
1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部
1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』
1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)
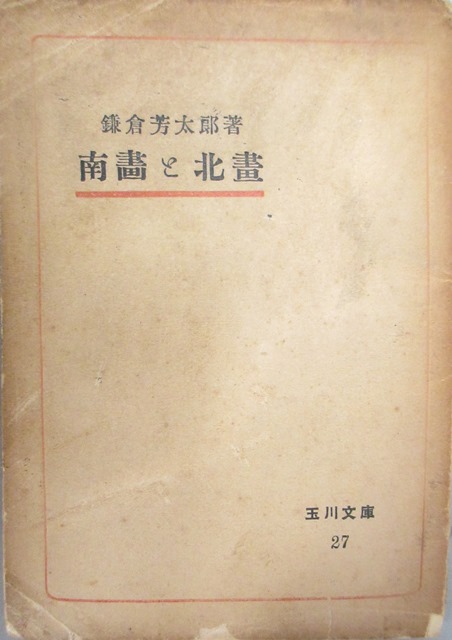
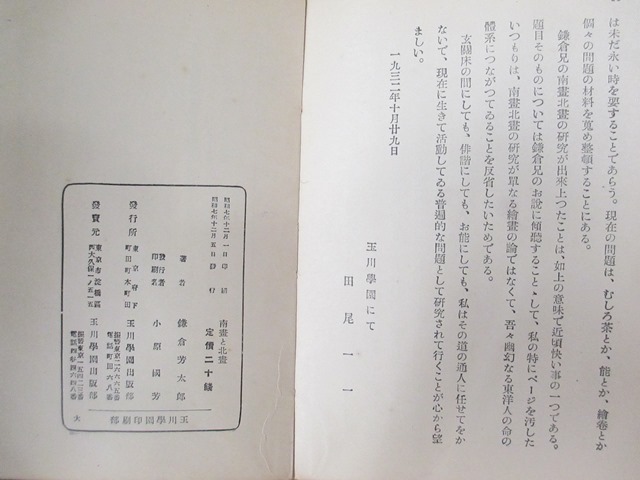
(粟国恭子所蔵)
1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫
1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。
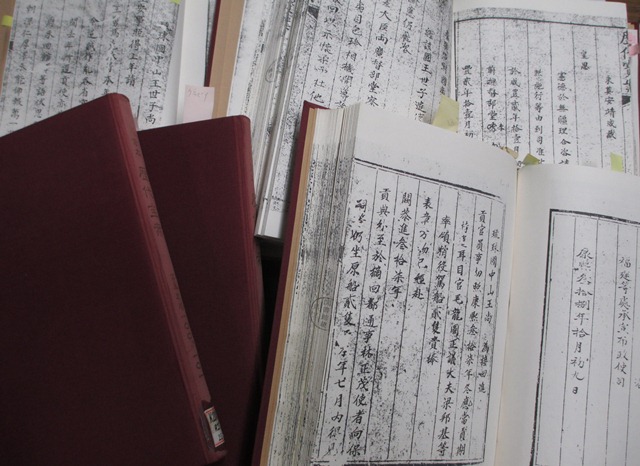
れきだいほうあん【歴代宝案】
琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)
1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」
1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』
1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」
1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖
1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。
1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)
1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。
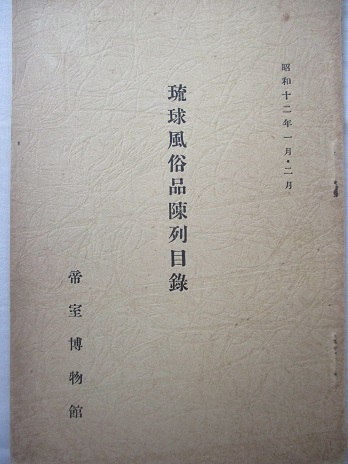
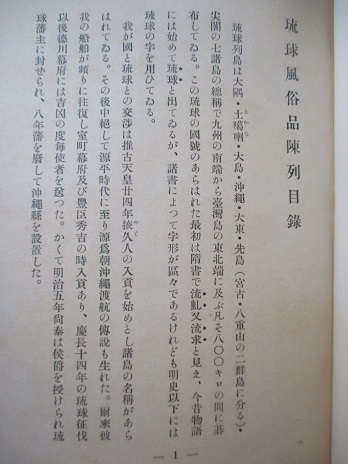
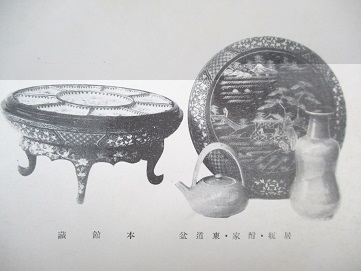


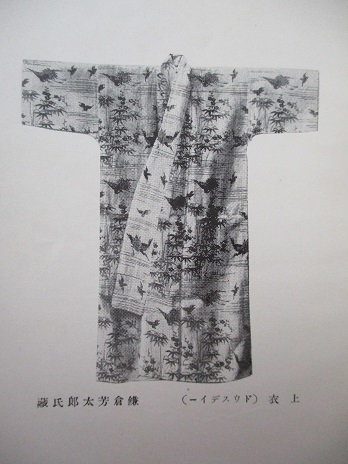

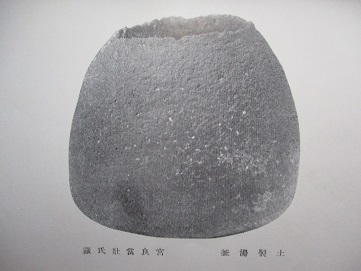
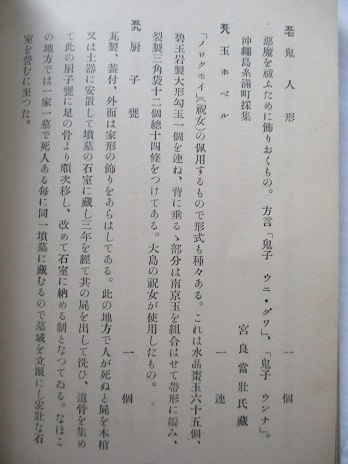
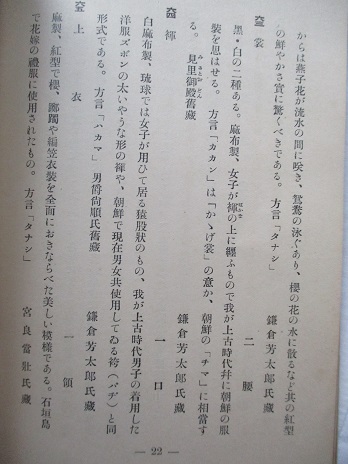
1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』
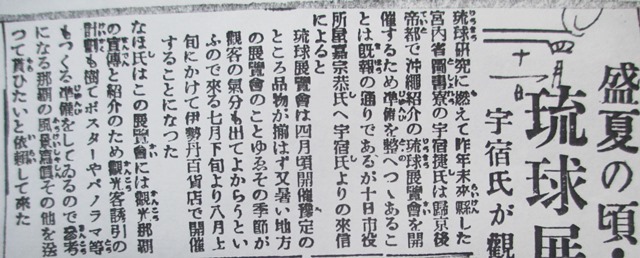
1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』
○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」
09/05: 鎌倉芳太郎②
1954年11月14日『沖縄タイムス』「琉球藝術論を脱稿ー胡屋琉大学長と同大名義出版を約すー世に出るか、鎌倉芳太郎教授の著書(本文・千二百頁、図版五百頁)」
1955-8 日本橋高島屋「沖縄展」鎌倉芳太郎、型紙出品
8月ー東京日本橋高島屋で読売新聞主催「沖縄展」
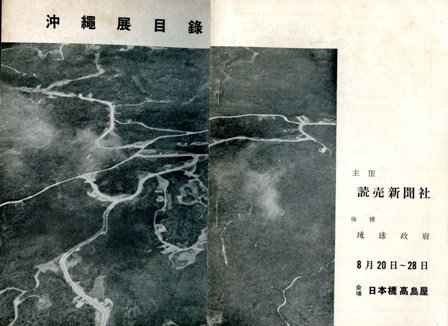
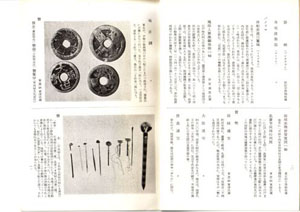
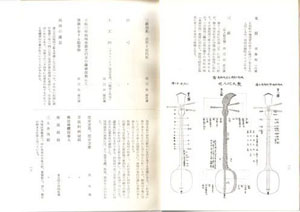
1957-12-1 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「私と沖縄」□交友関係では末吉麦門冬(末吉安久氏の実兄)と意気投合。いろいろ啓発し、されたもの
1958-7-16 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「沖縄の美しいもの」(1)6-15川崎市沖縄文化同好会第8回沖縄文化講座で講演したもの。~7-26(10)
1960-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型型紙の研究』京都書院
1961年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「円覚寺大雄殿壁画」(鎌倉芳太郎模写)、「大島祝女服装図」(鎌倉芳太郎模写)寄贈。鎌倉芳太郎から「ときさうし」「古代祝女衣裳カカン」「古代芭蕉地カカン」、鎌倉秀雄から「進貢船図」購入
1963-9月 鎌倉芳太郎『琉球の織物』京都書院
1964年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「三平等兼題文言集」「呈禀文集」「寺社由来記」「琉球事件 上」「球陽外巻(遺老説伝)」「萬集」「覚世真経」「廃藩後旧例相変り候事件」「浦添御殿本 『王代記』」「大上感応篇大意の序」を寄贈。鎌倉秀雄から「琉球詩集」「琉球官生詩集」「琉球詩録」「毛世輝詩集」「東子祥先生詩集」「平敷屋朝敏文集」「中山王府相卿伝職年譜」「御書院並南風原御殿御床飾」「御座飾帳」「御書院御物帳」「琉球俗語 巻之一」購入
1966ー10 東京ひめゆり同窓会『戦後二十周年記念誌』(表紙・鎌倉芳太郎)□鎌倉芳太郎「回想記ー廃藩置県時代以前の琉球王国時代の美術研究に従事した。その関係で沖縄タイムス主筆 麦門冬末吉安恭氏と親交を続けた。またその縁戚の南村氏とも顔を合わせる機会が多く、したがって当時の沖縄における共産社会主義の猛者連中の思想運動にもふれた・・・」
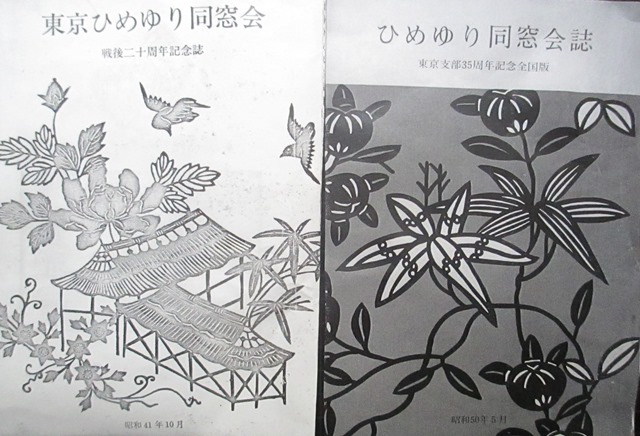
1966年10月/1975年10月
1968年2月 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』京都書院
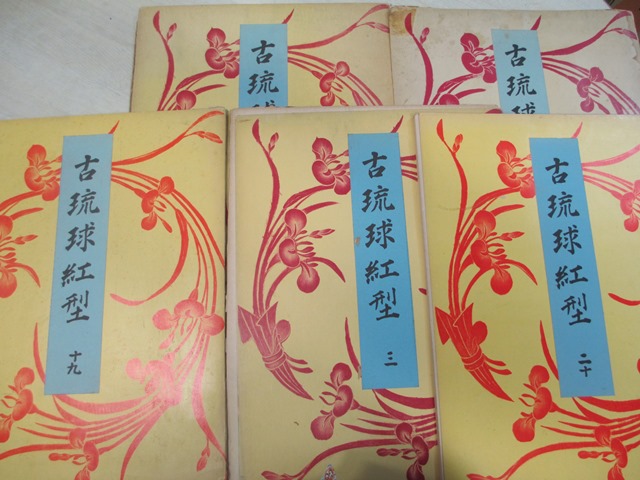
1968-4 日本橋東急百貨店「沖縄展」図録 鎌倉芳太郎「琉球造形美術について」→名古屋の徳川美術館でも中日新聞社共催で開催された。
4月ー東急百貨店日本橋店7階で「沖縄展ー琉球の自然と文化」
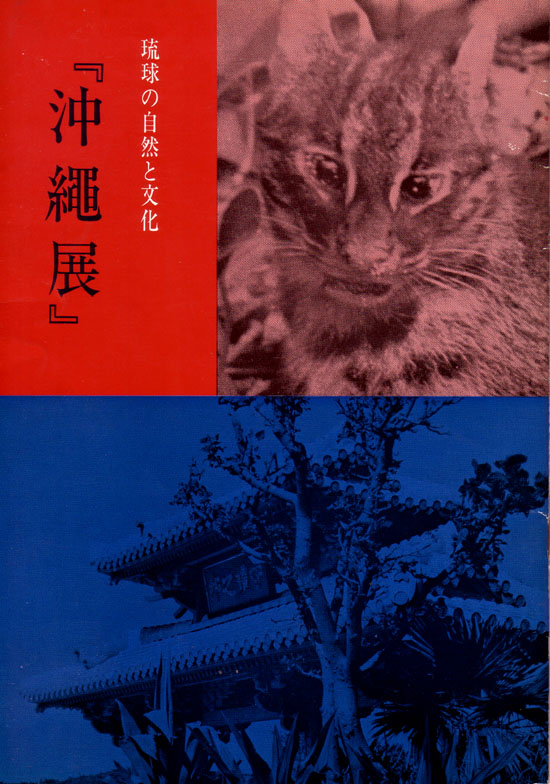
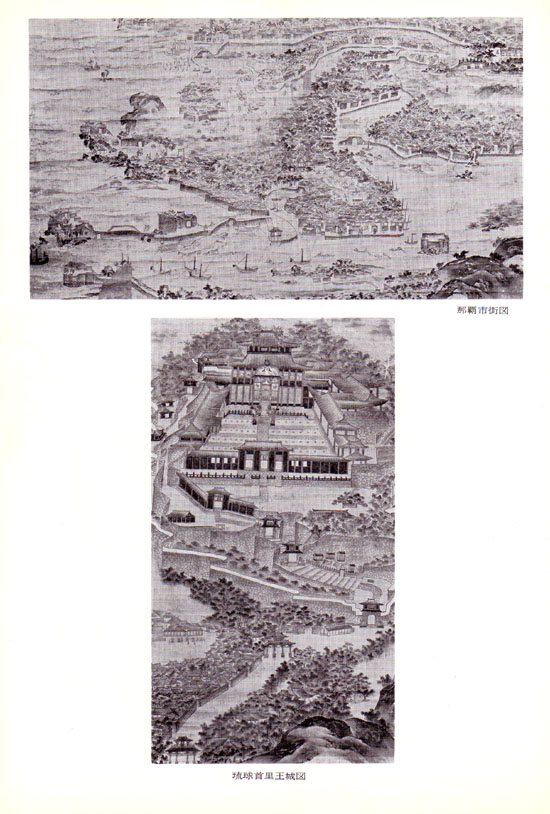
1971-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』上下 京都書院
1971 鎌倉芳太郎『古琉球型紙』京都書院
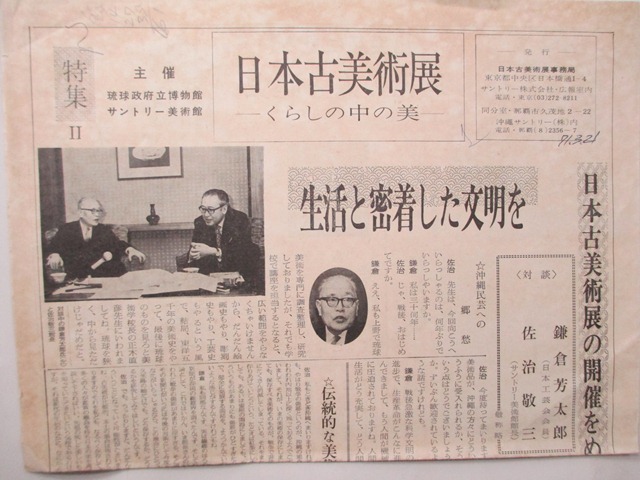
1955-8 日本橋高島屋「沖縄展」鎌倉芳太郎、型紙出品
8月ー東京日本橋高島屋で読売新聞主催「沖縄展」
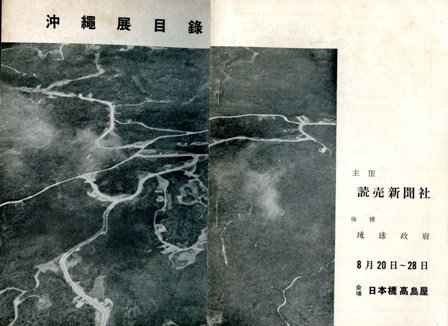
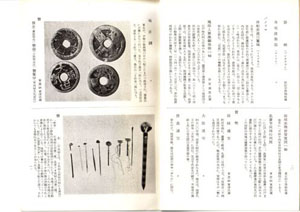
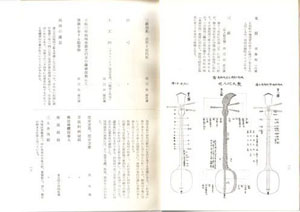
1957-12-1 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「私と沖縄」□交友関係では末吉麦門冬(末吉安久氏の実兄)と意気投合。いろいろ啓発し、されたもの
1958-7-16 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「沖縄の美しいもの」(1)6-15川崎市沖縄文化同好会第8回沖縄文化講座で講演したもの。~7-26(10)
1960-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型型紙の研究』京都書院
1961年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「円覚寺大雄殿壁画」(鎌倉芳太郎模写)、「大島祝女服装図」(鎌倉芳太郎模写)寄贈。鎌倉芳太郎から「ときさうし」「古代祝女衣裳カカン」「古代芭蕉地カカン」、鎌倉秀雄から「進貢船図」購入
1963-9月 鎌倉芳太郎『琉球の織物』京都書院
1964年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「三平等兼題文言集」「呈禀文集」「寺社由来記」「琉球事件 上」「球陽外巻(遺老説伝)」「萬集」「覚世真経」「廃藩後旧例相変り候事件」「浦添御殿本 『王代記』」「大上感応篇大意の序」を寄贈。鎌倉秀雄から「琉球詩集」「琉球官生詩集」「琉球詩録」「毛世輝詩集」「東子祥先生詩集」「平敷屋朝敏文集」「中山王府相卿伝職年譜」「御書院並南風原御殿御床飾」「御座飾帳」「御書院御物帳」「琉球俗語 巻之一」購入
1966ー10 東京ひめゆり同窓会『戦後二十周年記念誌』(表紙・鎌倉芳太郎)□鎌倉芳太郎「回想記ー廃藩置県時代以前の琉球王国時代の美術研究に従事した。その関係で沖縄タイムス主筆 麦門冬末吉安恭氏と親交を続けた。またその縁戚の南村氏とも顔を合わせる機会が多く、したがって当時の沖縄における共産社会主義の猛者連中の思想運動にもふれた・・・」
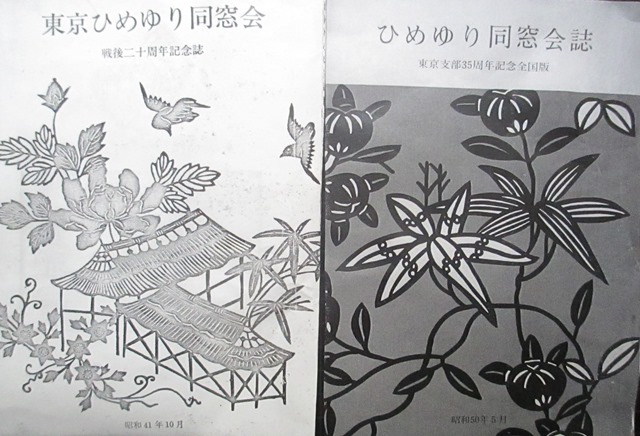
1966年10月/1975年10月
1968年2月 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』京都書院
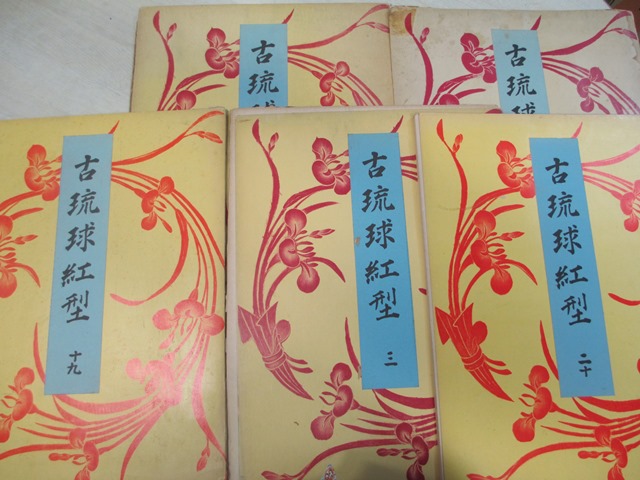
1968-4 日本橋東急百貨店「沖縄展」図録 鎌倉芳太郎「琉球造形美術について」→名古屋の徳川美術館でも中日新聞社共催で開催された。
4月ー東急百貨店日本橋店7階で「沖縄展ー琉球の自然と文化」
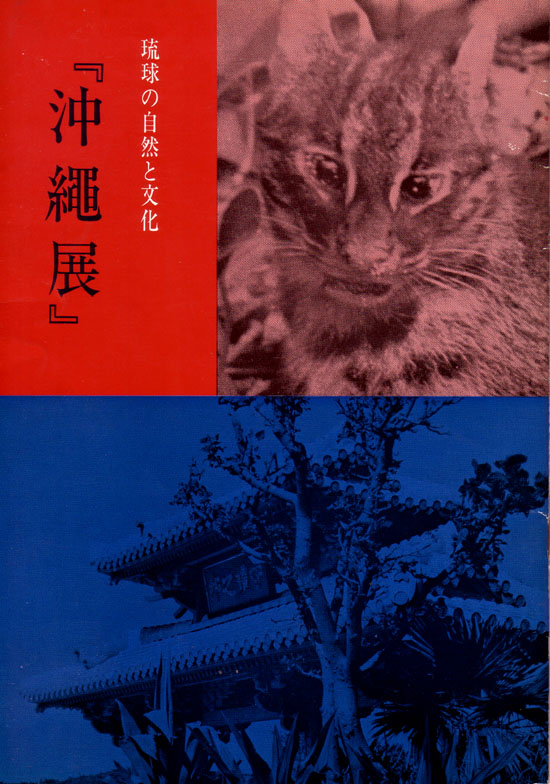
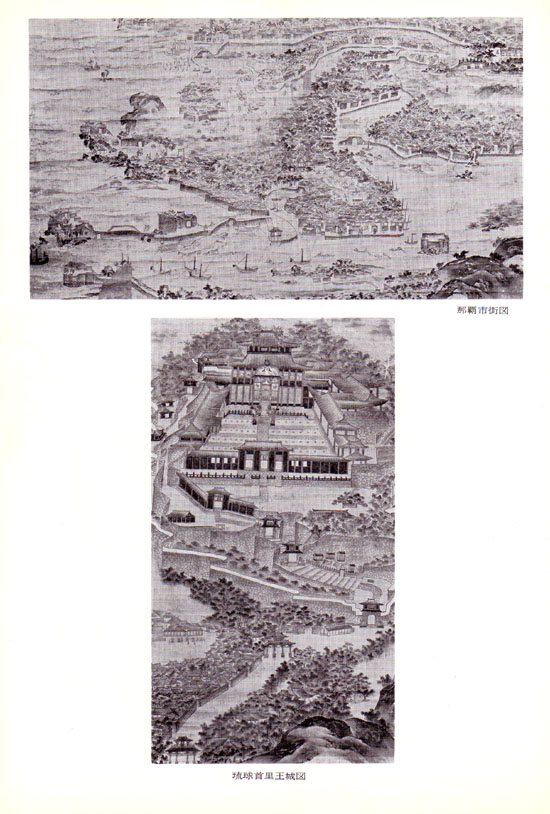
1971-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』上下 京都書院
1971 鎌倉芳太郎『古琉球型紙』京都書院
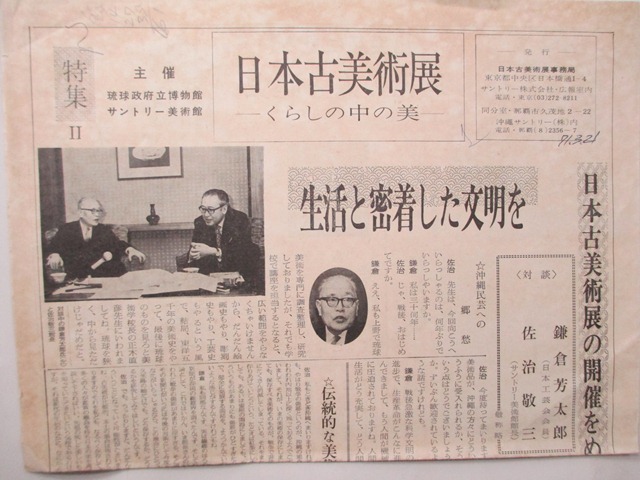
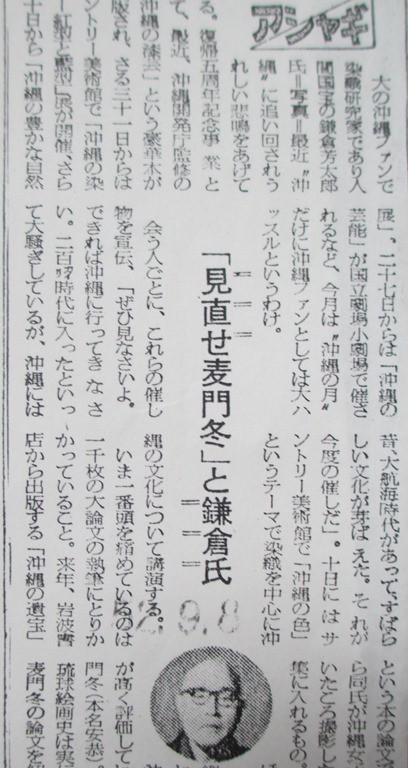
1977年9月8日『琉球新報』「アシャギー『見直せ麦門冬』と鎌倉氏」
1977年 『国語科通信№36』角川書店□鎌倉芳太郎(重要無形文化財<紅型研究>・玉川大学名誉教授)「首里言葉と那覇言葉ー(略)大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、世の中の傾向がデモクラシーの社会運動にゆさぶられている時代であったので、またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育って行った。・・・」
1978-4 『人間国宝シリーズ14 鎌倉芳太郎』講談社
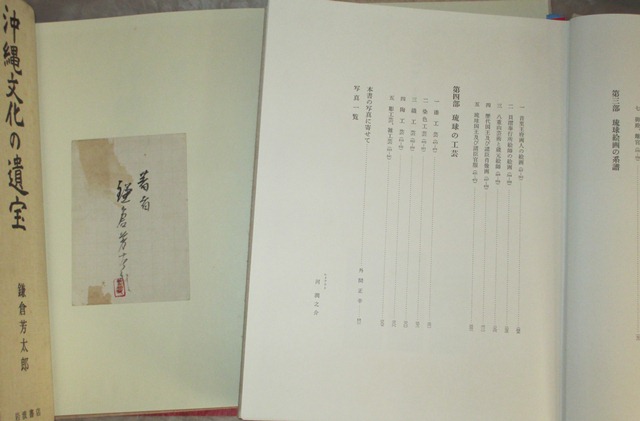
1982-10 鎌倉芳太郎『沖縄文化の遺宝』岩波書店
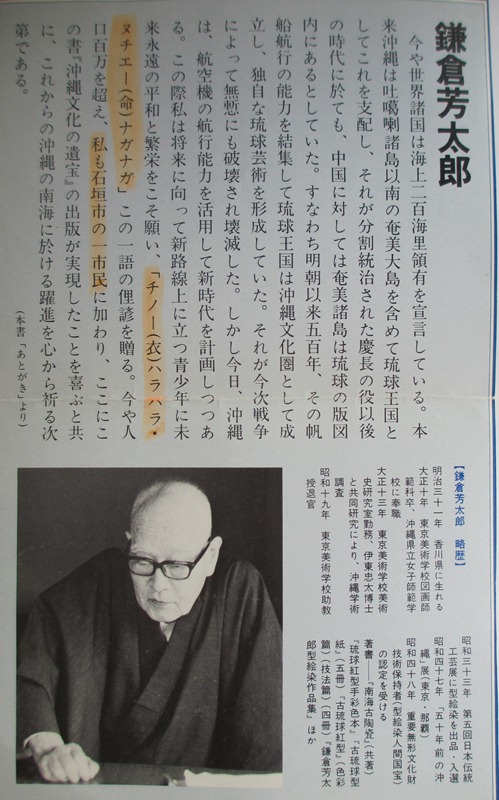
1998年 『沖縄県立博物館紀要』第24号□外間正幸、萩尾俊章「沖縄県立博物館草創期における文化財収集とその背景」
○1、首里博物館の時代 2、日本本土における文化財収集活動ー(1)1958年の文化財収集ー仲原善忠先生と我部政達氏 (2)1959年における文化財収集活動ー森政三氏、神山政良氏、東恩納寛惇先生 (3)1959年~61年の文化財収集ー鎌倉芳太郎先生
2003-9 浦添市美術館「今甦る80年前の沖縄~鎌倉芳太郎の撮った遺宝・風物~」沖縄テレビ・琉球新報社
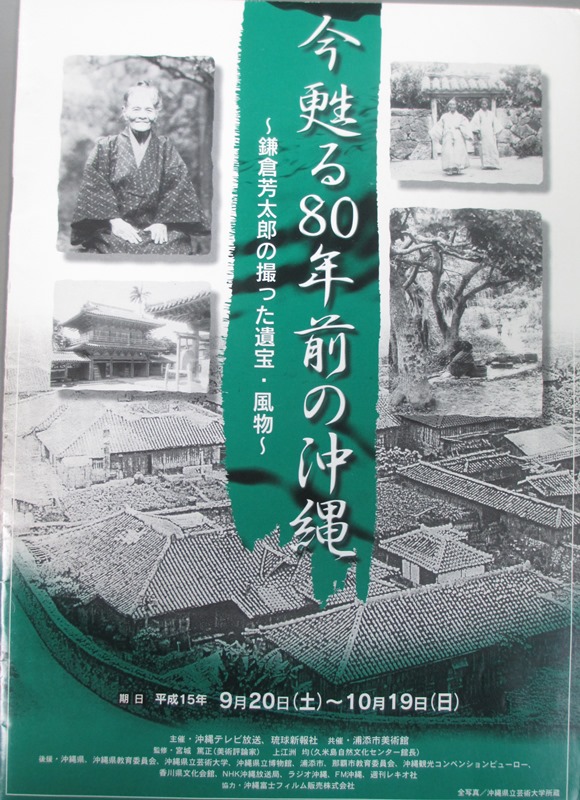
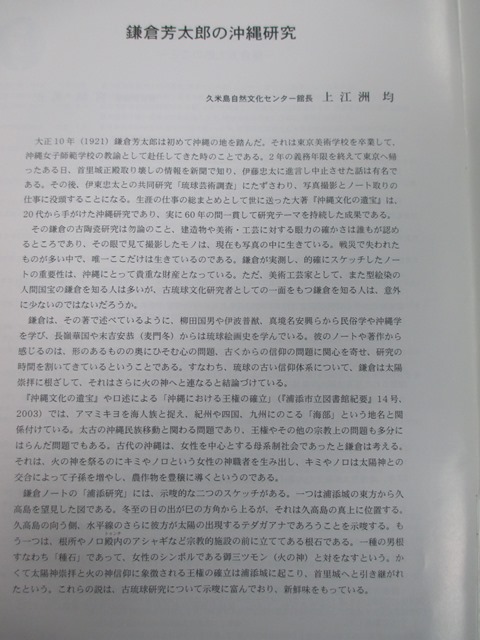
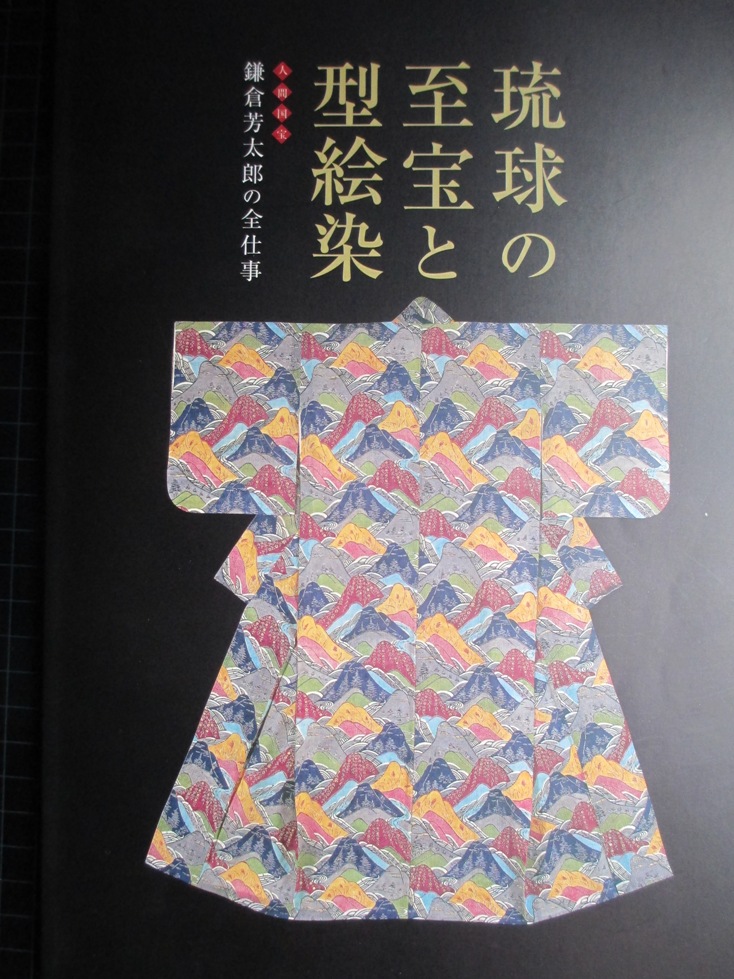
2003-11

2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号/2008年3月『沖縄芸術の科学』第20号
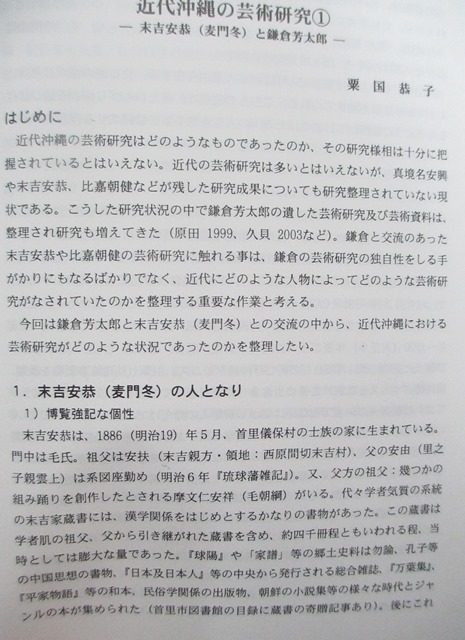
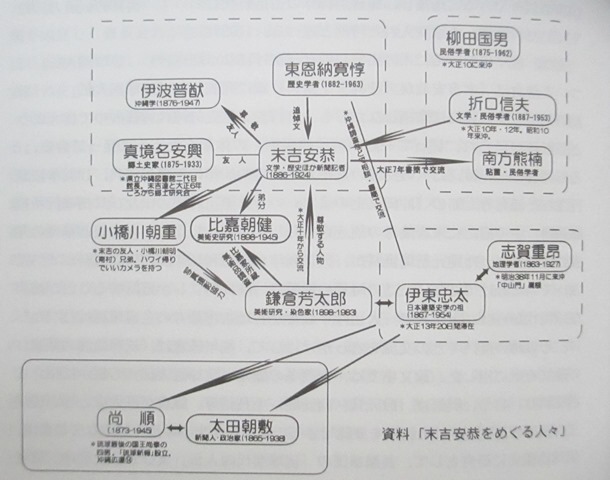
2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号□粟国恭子「近代沖縄の芸術研究①-末吉安恭(麦門冬)と鎌倉芳太郎」
09/01: 水上泰生
『琉文手帖』(1999年5月)「沖縄近代文化年表」の1914年(大正3)の2月5日のところに、画家・水上泰生 平壌丸で来沖とある。
水上泰生 みなかみ-たいせい
1877-1951 大正-昭和時代の日本画家。
明治10年10月24日生まれ。寺崎広業(こうぎょう)に師事。大正3年「琉球の花」,4年「樺太の夏」が文展三等賞をうける。5年上京。昭和2年帝展委員。写実的な花鳥画を得意とした。昭和26年2月21日死去。73歳。福岡県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は泰生(やすお)。⇒コトバンク

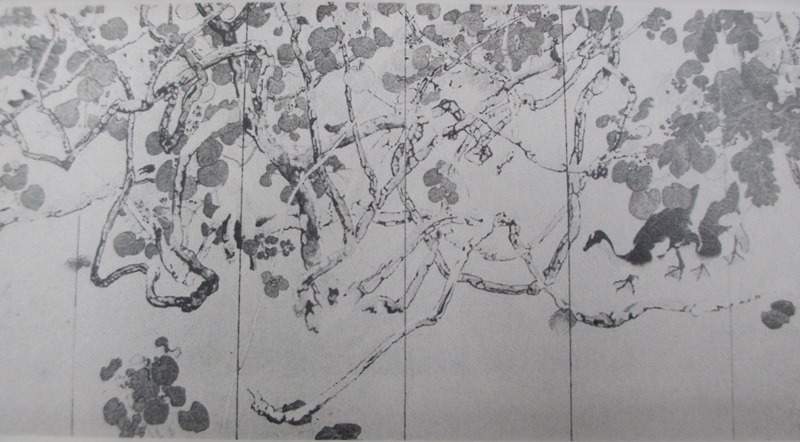
大正3年・第八回文展 水上泰生「琉球の花」(六曲一双)
○1999年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』題1号 原田あゆみ「鎌倉芳太郎略年譜」(参考文献に『琉文手帖』「沖縄近代文化年表」もある)
□1914年 鎌倉芳太郎、第8回文展にて水上泰生の『琉球の花』(3等賞)を見る。1918年 鎌倉芳太郎、水上泰生を麻布本村町の邸宅に訪ねる。早速その日から宿泊し、製作の手伝いをすることになる。狩野派の彩色原理は水上泰生から学ぶ。
水上泰生 みなかみ-たいせい
1877-1951 大正-昭和時代の日本画家。
明治10年10月24日生まれ。寺崎広業(こうぎょう)に師事。大正3年「琉球の花」,4年「樺太の夏」が文展三等賞をうける。5年上京。昭和2年帝展委員。写実的な花鳥画を得意とした。昭和26年2月21日死去。73歳。福岡県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は泰生(やすお)。⇒コトバンク

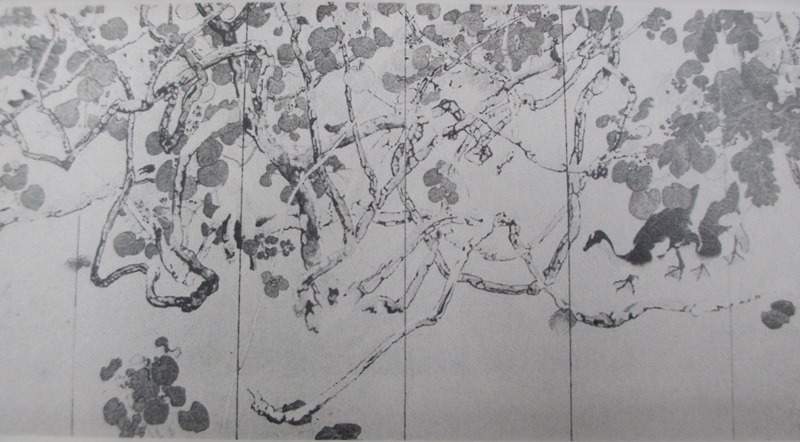
大正3年・第八回文展 水上泰生「琉球の花」(六曲一双)
○1999年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』題1号 原田あゆみ「鎌倉芳太郎略年譜」(参考文献に『琉文手帖』「沖縄近代文化年表」もある)
□1914年 鎌倉芳太郎、第8回文展にて水上泰生の『琉球の花』(3等賞)を見る。1918年 鎌倉芳太郎、水上泰生を麻布本村町の邸宅に訪ねる。早速その日から宿泊し、製作の手伝いをすることになる。狩野派の彩色原理は水上泰生から学ぶ。
08/21: 2013年7月ー宮﨑義敬『繚乱の人』展望社
お盆前、BOOKS じのんで渡久山朝章『周遊快々 片雲有情』を買う。
2012年3月18日『沖縄タイムス』30面「高江判決を問う(下)比屋根照夫さん『規制の網 戦前を想起』/31面「32軍壕問題で学習会ー鉄血勤皇隊師範隊として壕掘りをさせられた渡久山朝章さん(83)読谷村などが従軍慰安婦について証言した。」
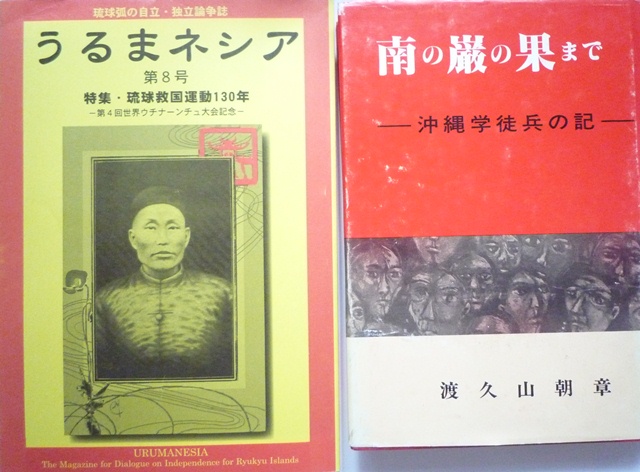
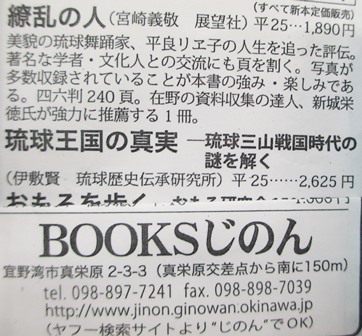
2013年9月14日『琉球新報』(ジュンク堂那覇店は新聞に書評が出ると、書評本のところに並べるはずだが在庫が無いので並べてない。)
タイミングよく本ブログで平良リヱ子さんをアップしたばかりでこの評伝の登場である。神様の引き合わせというべきか、ちなみに著者は神主さんでもある。先ず評伝の基礎資料というべき写真が豊富である。これだけでも本書の価値は十分だが何より著者と平良りヱ子さんとの交流が昭和28年12月以来だから驚く。評伝を書くのに平良さん本人以外にこれ以上の適任者は居ないであろう。欠点をいうと、写真のキャプションの誤植が少々あるのと、リヱ子評伝だから当然ではあるがトラブル問題の殆どが平良さん側の肩を持っていることだろうか。ジュンク堂那覇店をのぞくとこの本が無いのでここで紹介する(2013年9月7日現在ー1冊。じのん□TEL:(098)897-7241 )には在庫がある。この本で岡本太郎、本田安次、鎌倉芳太郎など東京での学者・文化人とリヱ子さんとの交流が活写される。
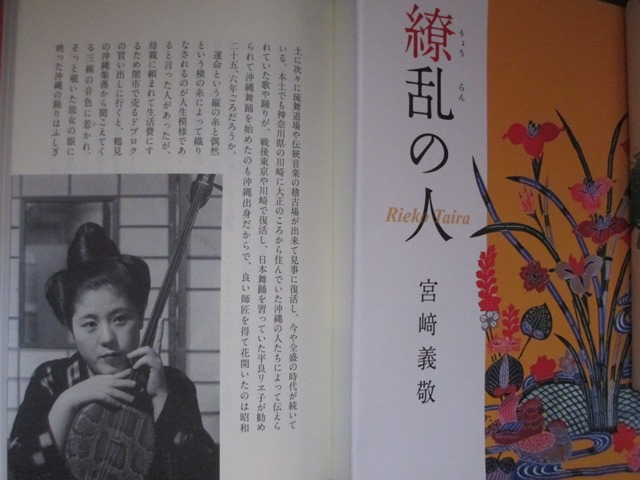
2013年7月ー宮﨑義敬『繚乱の人』展望社(東京都文京区小石川3-1-7 エコービル202 ☎03-3814-1997)
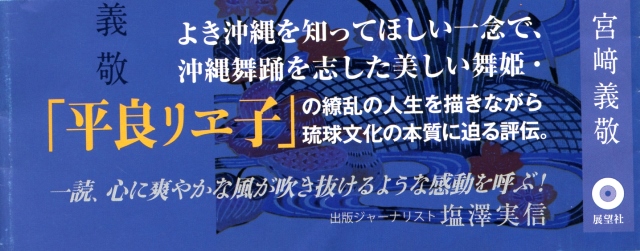

同書よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ
□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」
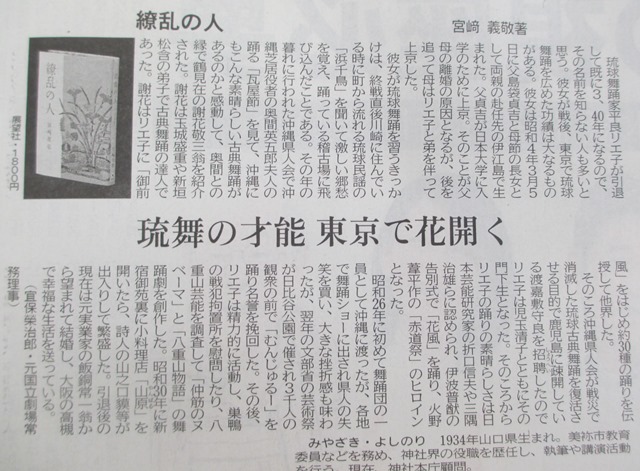
2013年9月22日『琉球新報』宜保榮治郎(元国立劇場常務理事)「綾乱の人ー琉舞の才能 東京で花開く」

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ
□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」
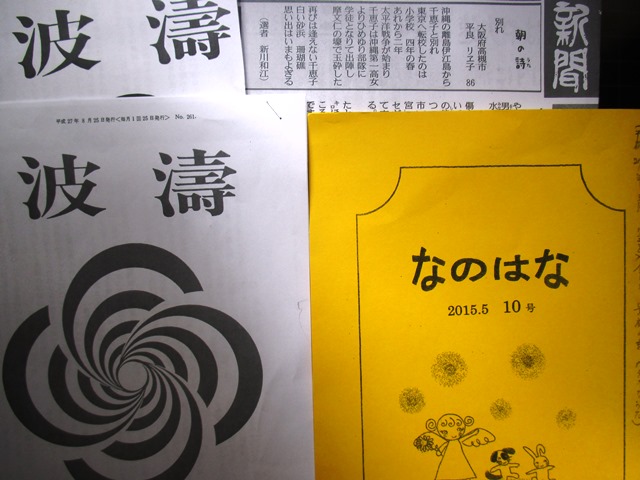
2015年5月『なのはな』10号 平良リヱ子「病い」
2015年6月19日『産経新聞』平良リヱ子「別れ」
2015年7月『波濤』№260 平良リヱ子「グランドを駆け回る児ら窓越しに眺めておれば心しずまる」「わが詩の掲載されたる朝刊に目を疑いてくりかへし見つ」
2015年8月『波濤』№261 平良リヱ子「リハビリに通う日課も楽しかり加齢の友らと癒しのサロン」「老いの身に孤独のしみいる雨の夜はうからの電話に心癒さる」
2012年3月18日『沖縄タイムス』30面「高江判決を問う(下)比屋根照夫さん『規制の網 戦前を想起』/31面「32軍壕問題で学習会ー鉄血勤皇隊師範隊として壕掘りをさせられた渡久山朝章さん(83)読谷村などが従軍慰安婦について証言した。」
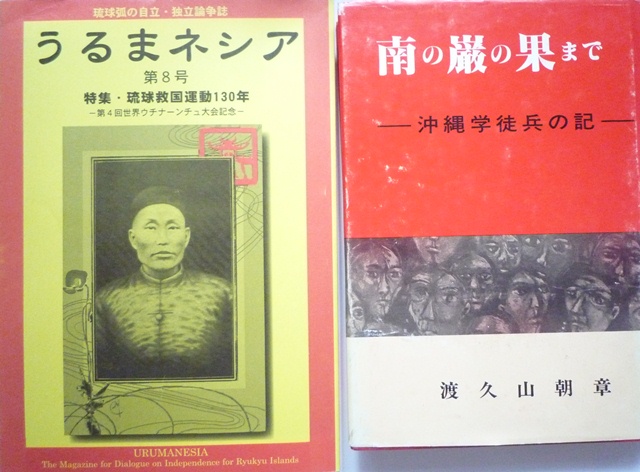
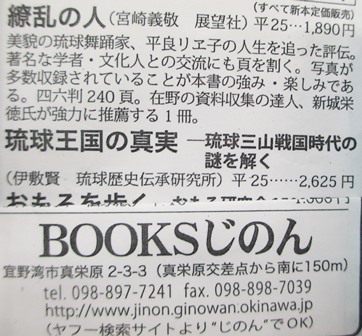
2013年9月14日『琉球新報』(ジュンク堂那覇店は新聞に書評が出ると、書評本のところに並べるはずだが在庫が無いので並べてない。)
タイミングよく本ブログで平良リヱ子さんをアップしたばかりでこの評伝の登場である。神様の引き合わせというべきか、ちなみに著者は神主さんでもある。先ず評伝の基礎資料というべき写真が豊富である。これだけでも本書の価値は十分だが何より著者と平良りヱ子さんとの交流が昭和28年12月以来だから驚く。評伝を書くのに平良さん本人以外にこれ以上の適任者は居ないであろう。欠点をいうと、写真のキャプションの誤植が少々あるのと、リヱ子評伝だから当然ではあるがトラブル問題の殆どが平良さん側の肩を持っていることだろうか。ジュンク堂那覇店をのぞくとこの本が無いのでここで紹介する(2013年9月7日現在ー1冊。じのん□TEL:(098)897-7241 )には在庫がある。この本で岡本太郎、本田安次、鎌倉芳太郎など東京での学者・文化人とリヱ子さんとの交流が活写される。
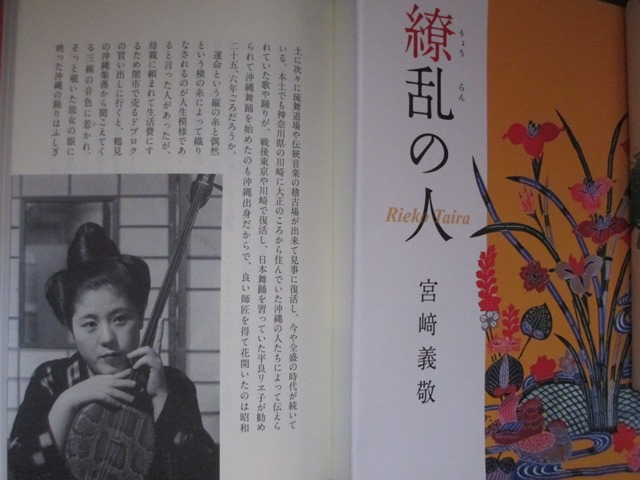
2013年7月ー宮﨑義敬『繚乱の人』展望社(東京都文京区小石川3-1-7 エコービル202 ☎03-3814-1997)
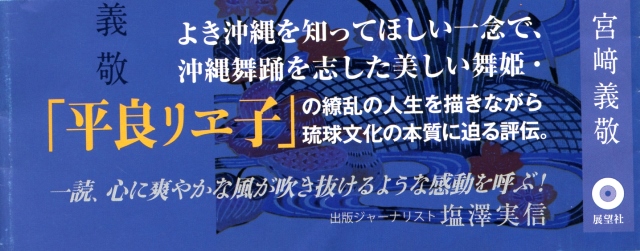

同書よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ
□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」
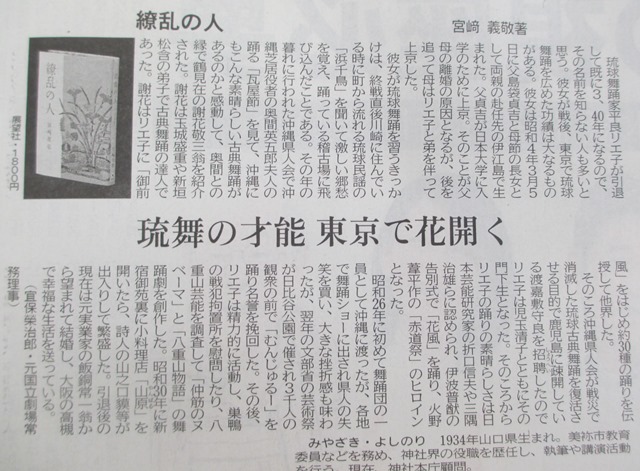
2013年9月22日『琉球新報』宜保榮治郎(元国立劇場常務理事)「綾乱の人ー琉舞の才能 東京で花開く」

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ
□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」
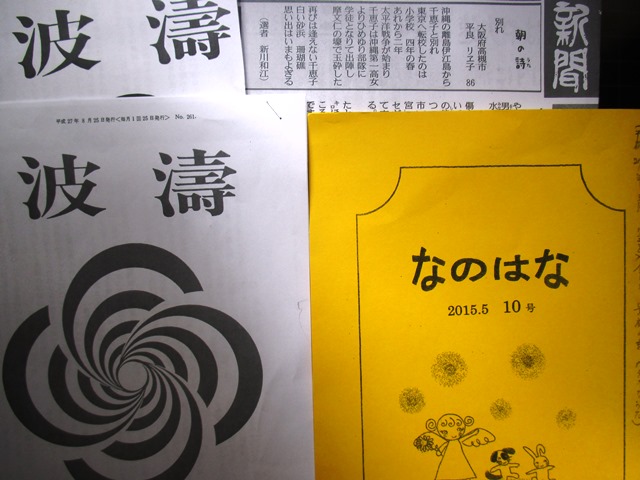
2015年5月『なのはな』10号 平良リヱ子「病い」
2015年6月19日『産経新聞』平良リヱ子「別れ」
2015年7月『波濤』№260 平良リヱ子「グランドを駆け回る児ら窓越しに眺めておれば心しずまる」「わが詩の掲載されたる朝刊に目を疑いてくりかへし見つ」
2015年8月『波濤』№261 平良リヱ子「リハビリに通う日課も楽しかり加齢の友らと癒しのサロン」「老いの身に孤独のしみいる雨の夜はうからの電話に心癒さる」
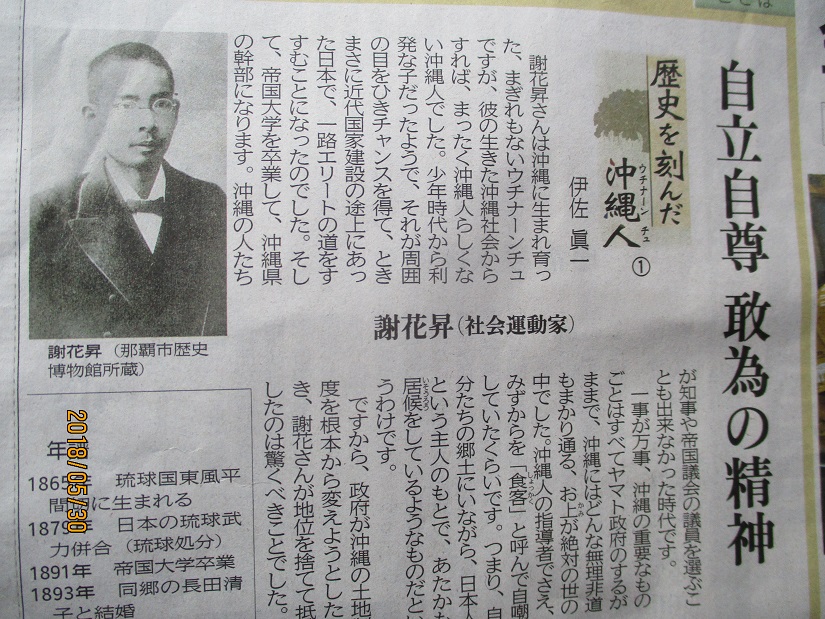
2018年4月8日『沖縄タイムス』伊佐眞一「歴史を刻んだ沖縄人①謝花昇 自立自尊 敢為の精神」
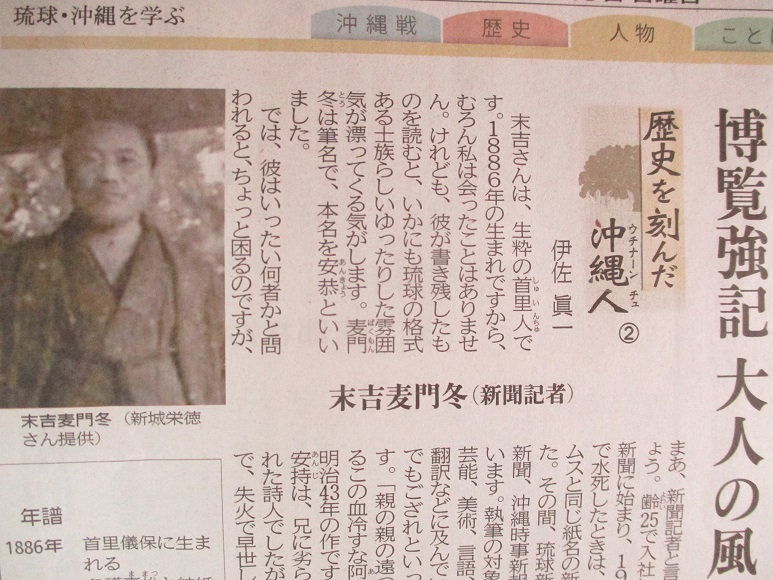
2018年5月13日『沖縄タイムス』伊佐眞一「末吉麦門冬(新聞記者)博覧強記 大人の風格」
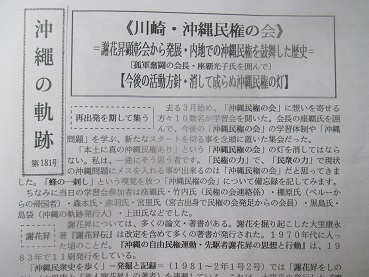
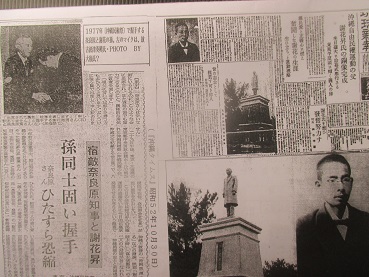
2018年3月3日 『沖縄の軌跡』「《川崎・沖縄民権の会》=謝花昇顕彰会から発展・内地での沖縄民権を鼓舞した歴史=」181号 編集発行人・島袋和幸(葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)
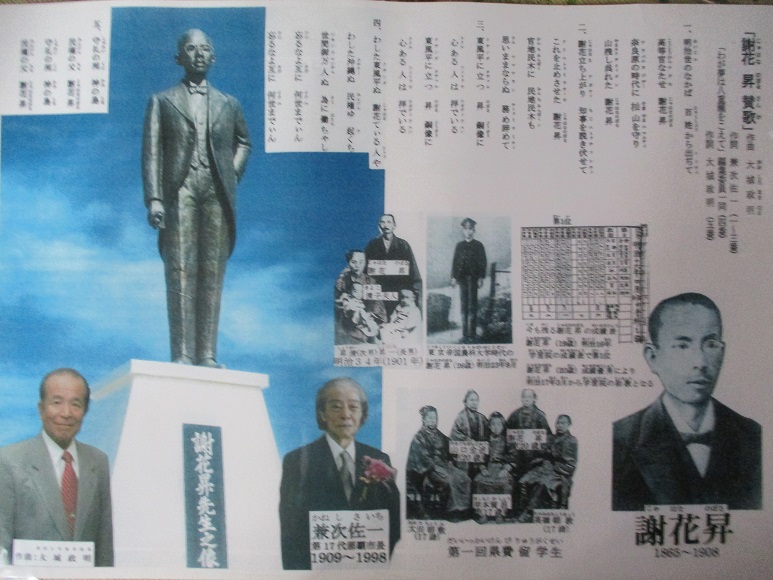

「謝花昇 賛歌」作詞・兼次佐一/作曲・大城政明/大城政明氏、伊佐眞一氏
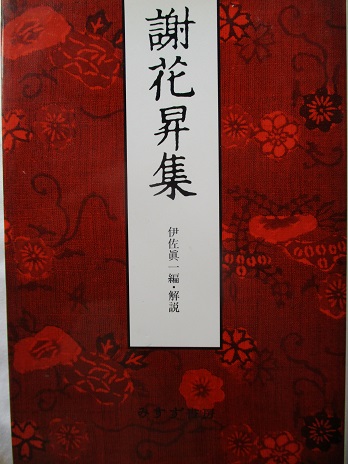
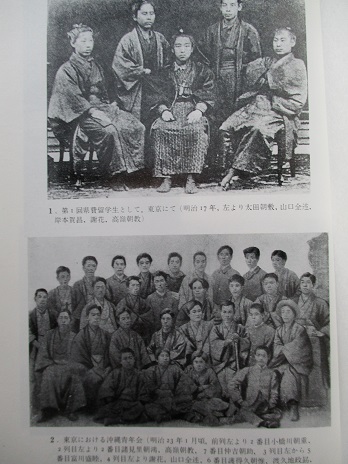
1998年6月 伊佐眞一『謝花昇集』みすず書房
1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号
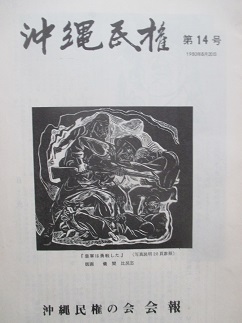
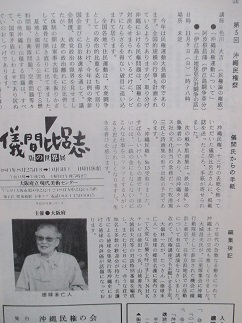
1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)□古波津英興「方言使用スパイ処分文書」
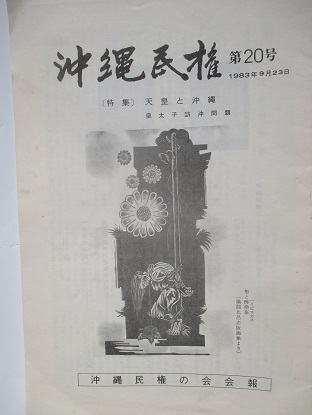
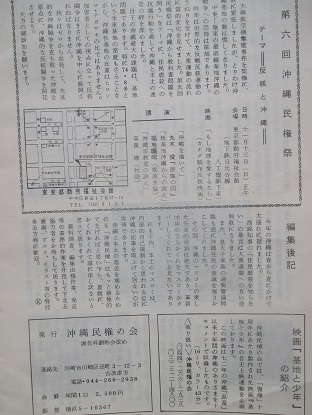
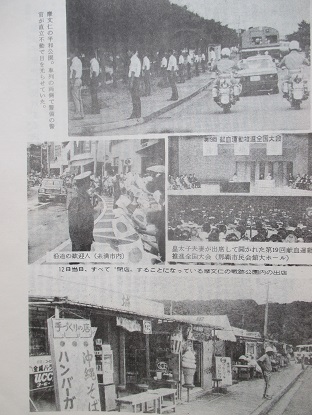

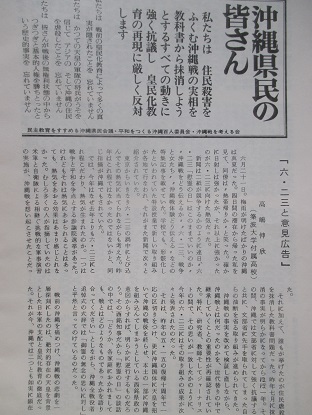
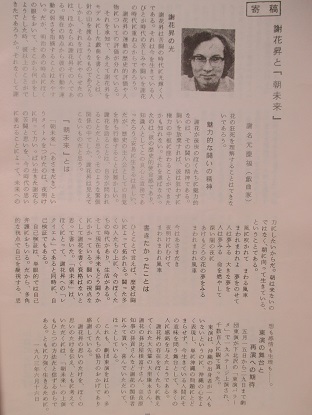
1983年9月23日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「菊と仏桑華」第20号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)


2018年3月14日 みどり印刷前でー石川和男氏(左)、島袋和幸氏/南風原文化センター前で島袋和幸氏
「みどり印刷」←iここをクリック


「鎌倉芳太郎顕彰碑」甥御さんの鎌倉佳光氏案内/「アートギャラリーかまくら 南米珈琲」鎌倉芳太郎生家(島袋和幸提供)
2014年5月 図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』

沖縄県立博物館・美術館ミュージアムショップ「ゆいむい」電話:098-941-0749 メール:yuimui@bunkanomori.jp
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』 販売価格(税込): 1,620 円

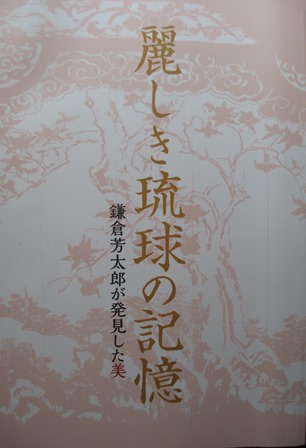
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁く」
図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」

高草茂氏と新城栄徳
2015年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所『沖縄芸術の科学』第27号 高草茂「琉球芸術ーその体系的構造抄論」
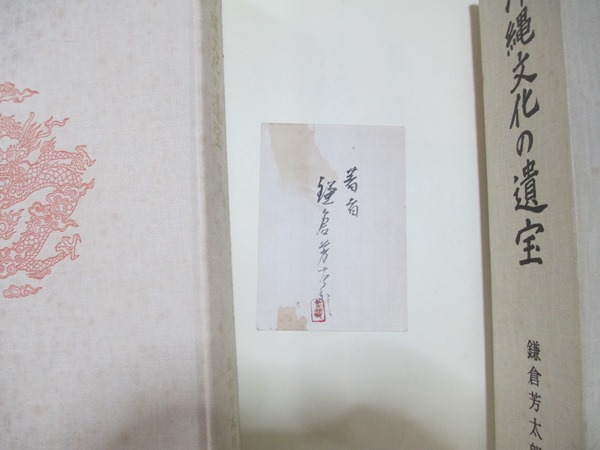
「麗しき琉球の記憶-鎌倉芳太郎が発見した“美”-」関連催事
【日時】5月31日(土)14:00~ 15:30 (開場13:30)
特別講演会/クロストーク
鎌倉芳太郎氏の大著『沖縄文化の遺宝』の編集者である高草茂氏による編集当時のエピソードなどを交えた講演と、「鎌倉ノート」の編集・刊行に携わる波照間永吉氏とのクロストークから、鎌倉氏の沖縄文化に寄せた情熱や思いなどを聞く機会とします。
【講師】高草茂 氏(元岩波書店 顧問)
波照間永吉 氏(沖縄県立芸術大学附属研究所 教授)

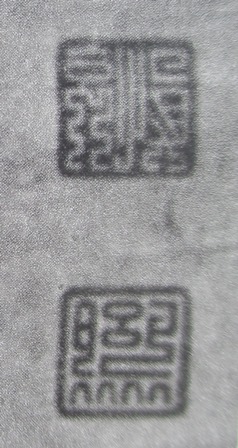
「首里那覇泊全景図」慎思九筆だが印章は慎克熈
沖縄文化工芸研究所□図録の内容を紹介します。
ご遺族や鎌倉自身と交流のあった方、鎌倉資料整理(沖縄県立芸術大学所蔵)に直接に関わった方々が文章を寄せています。記録資料としては将来価値のある図録だと思います。
*波照間永吉「芳太郎収集の沖縄文化関係資料」
*高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」
*佐々木利和「鎌倉芳太郎氏<琉球芸術調査写真>の指定」
*西村貞雄「鎌倉芳太郎がみた琉球の造形文化」
*柳悦州「鎌倉芳太郎が寄贈した紅型資料」
*波照間永吉「古琉球の精神を尋ねてー鎌倉芳太郎の琉球民俗調査ー」
*粟国恭子「鎌倉芳太郎が残した琉球芸術の写真」
*謝花佐和子「鎌倉芳太郎と<沖縄>を取り巻くもの」
*鎌倉秀雄「父の沖縄への思い」
*宮城篤正「回想「50年前の沖縄・写真でみる失われた遺宝」展
*新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁くー」
*三木健「<鎌倉資料>が世に出たころ」
○図版
○年譜
○主要文献等一覧
○写真図版解説
1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」
1893年、京都で平安神宮の地鎮祭が行われ西村捨三が記念祭協賛会を代表し会員への挨拶の中で尚泰侯爵の金毘羅宮参詣時の和歌「海山の広き景色を占め置いて神の心や楽しかるらん」を紹介し、平安神宮建設に尚家から五百圓の寄附があったことも報告された。ちなみに、この時の平安神宮建築技師が伊東忠太。
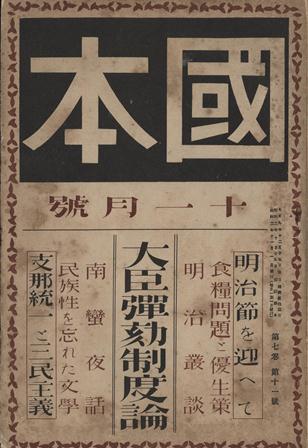
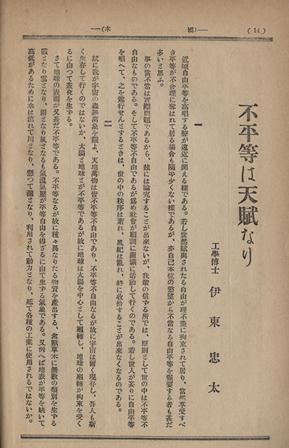
1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」
□翻って考ふれば、宇宙の諸現象は皆不平等、不自由なるが為に生ずるので、一現象毎に一歩づつ平等と自由とに近づくのである。斯くて幾億劫の後には絶対の平等自由が実現されて宇宙は亡びるのである。社会の現象も亦た不平等、不自由の力に由て起こるので、一現象毎に一歩づつ平等自由に近づくのである。斯くて幾万年の後には絶対の平等自由が実現されて社会は滅亡するのである。個人の一生も亦不平等不自由の為に支配せられて活動して居るのである。吾人の一挙一動毎に一歩づつ平等自由に近づくのを以て原則とする。斯くて百年の後絶対の平等自由が得られた時は即ち吾人の死んだ時である。
人は生まれた瞬間より一歩づつ死に向かって進むので、同時に又自由平等に向かって進むのである。絶対の平等自由を強要するのは即ち死を強要する所以である。要するに吾人は各自の職貴を竭して社会文化の向上に貢献すれば善いので社会の安寧秩序を保つべき条件の下に吾人の平等自由が適当に制限さるべきことを認容しなければならぬ。制限なき平等自由は假令之が與えられても吾人は之を受けることを欲せぬものである。何となれば之を與ふる者は悪魔であり、之を受くる者は之が為に身を亡ぼすからである。
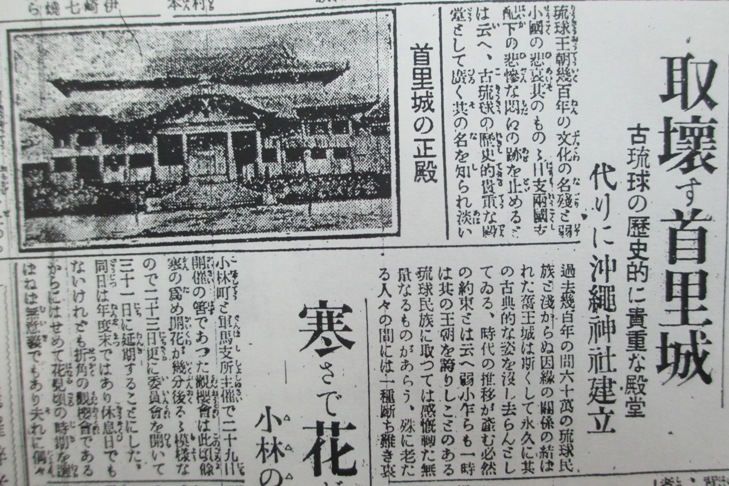
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
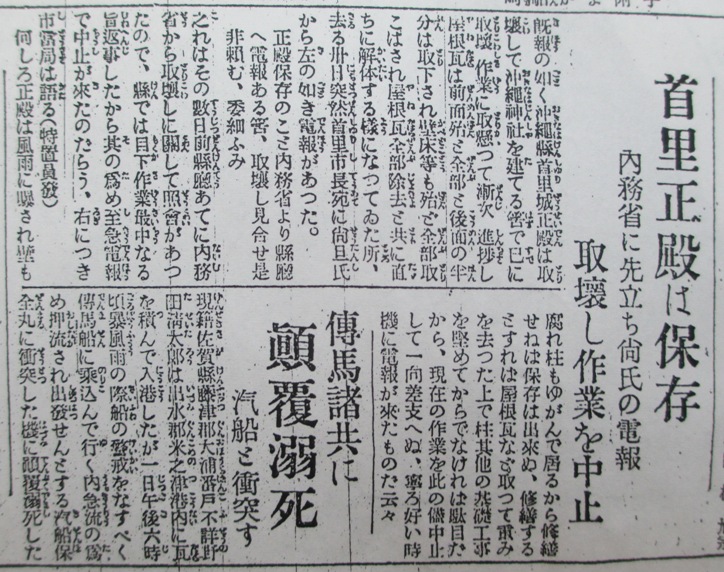
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
1924年
3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。
①『科学知識』「琉球紀行」□余は沖縄到着の第五日目の晩に脚の関節に鈍痛を覚えたので、テッキリやられたと直覚して寝に就いたが、夜半過ぎから疼痛が全身の関節に瀰漫し来り、朝になって見ると起きかえることは愚、寝返りも出来ぬ程の痛さである。(略)兼ねて東京を出発する時、琉球に悪疫の流行して居ることを聞知して居たので、入澤達吉博士に注意事項を問うた処が、博士は若しも沖縄で病気に罹ったら金城医学士の診療を受けるがよいと教えて呉れた。そこで早速同学士の来診を求めた所が、学士は直ちに来て呉れた。一診してこれは軽いデング熱である、2,3日で快癒すると事もなげに断言して呉れたので大いに安心した。(略)金城学士の話によれば、那覇市では殆ど毎戸に患者があって、一家一人も残らず感染した例も珍しくない。那覇6万の人口中、少なくともその三分の二は感染したものと思われるが死者は今の所43人である。夫は何れも嬰児で脳膜炎を併発したのであると云う。余が全治した頃は那覇の方は下火になり、追々田舎の方へ蔓延する模様であった。土地ではこれを「三日熱」と唱えて居る。夫は熱が大抵三日位で去るからである。
8月20日午後3時 大阪商船の安平丸で鹿児島へ。8月22日ー『沖縄タイムス』伊東忠太「琉球を去るに臨みて」。8月25日に東京着□→1925年1月~8月『科学知識』に琉球紀行を連載□1928年5月ー伊東忠太『木片集』萬里閣書房(写真・首里城守礼門)
1925年
1月ー鎌倉芳太郎、沖縄の新聞に啓明会から発行予定の「琉球芸術大観」発表。□(イ)序論ー分布の範囲、遺存の概況、調査物件の項目 (ロ)総論ー史的考察、時代分期
(ハ)各論①建築ー1王宮建築、2廟祠建築、3寺院建築、4住宅建築、5陵墓建築、6橋梁建築 ②琉球本島の部ーイ純止芸術(美術)篇ー1紋様、2絵画、3彫刻 ロ応用芸術(工芸)篇ー1漆工、2陶磁、3織工、4染工、5金工鋳造、6雑工 ③宮古八重山の部 ④奄美大島の部


1925年2月 坂口総一郎『沖縄写真帖』第一輯 画・伊東忠太
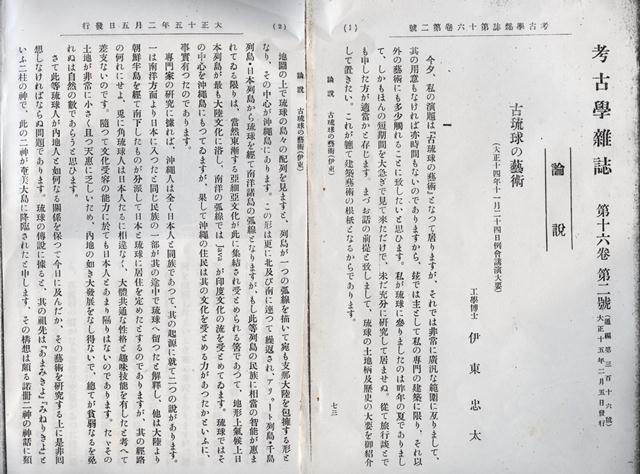
1926年2月『考古学雑誌』第16巻第2号 伊東忠太「古琉球の芸術」
1929(昭和4)年
『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」
□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」
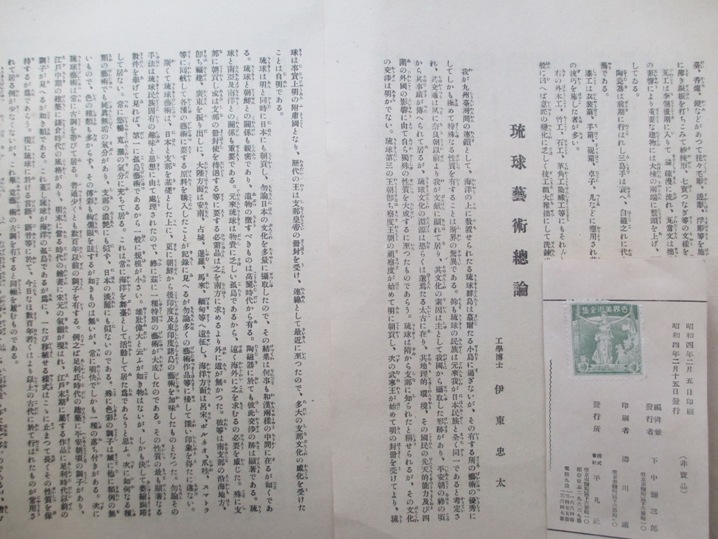
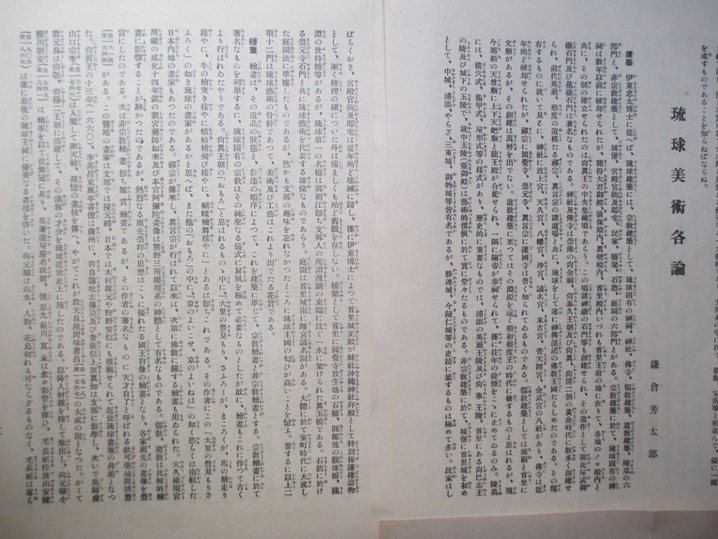
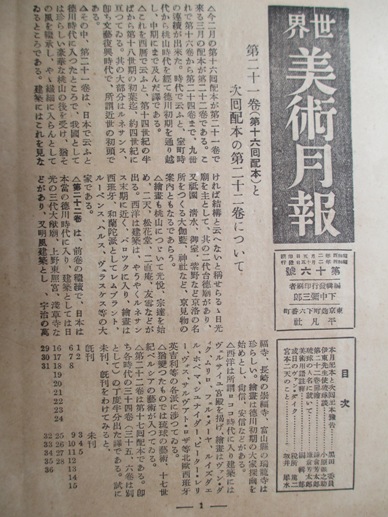
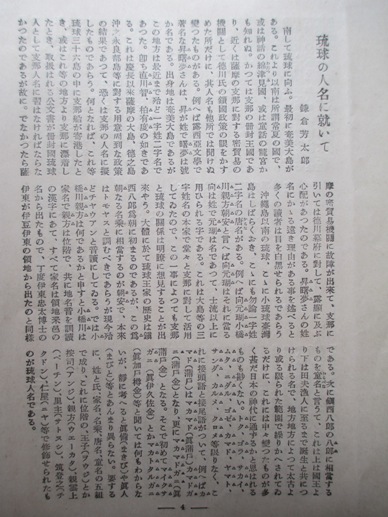
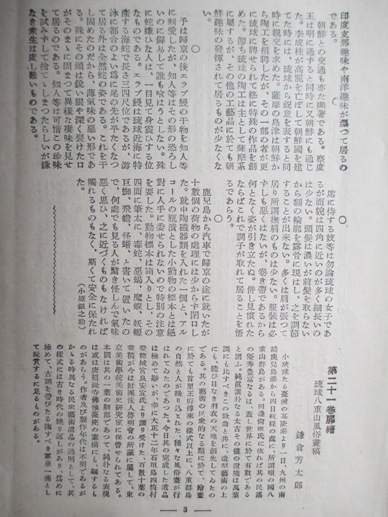
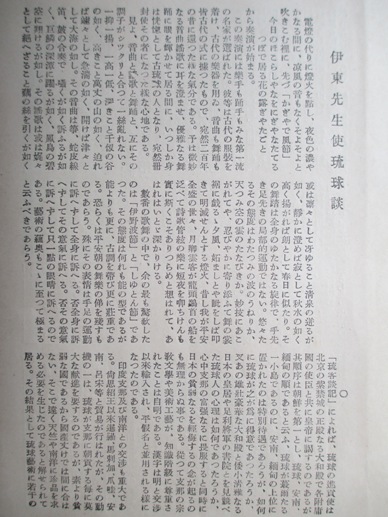
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)
1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社
1929年
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」

3月ー新光社『日本地理風俗体系』第12巻(カラーの守礼門)□伊波普猷「守礼門ー首里府の第一坊門を中山門と言ひ、王城の正門に近い第二坊門を守礼門と言ふ。前者は三山統一時代の創立で、『中山』の扁額を掲げたが、一時代前に毀たれ、後者はそれより一世紀後の創立で、待賢門と称して『首里』の扁額を掲げたが、万暦八年尚永即位の時、明帝の詔勅中より『守礼之邦』の四字を取って『首里』に代えた。以後守礼は首里の代りに用ひられる」
10月ー鎌倉芳太郎・田邊孝次『東洋美術史』玉川学園出版部
10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年
1917年(大正6)
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
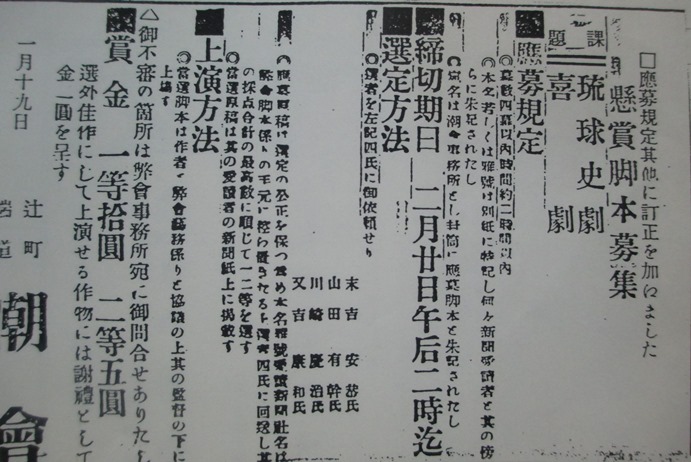
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
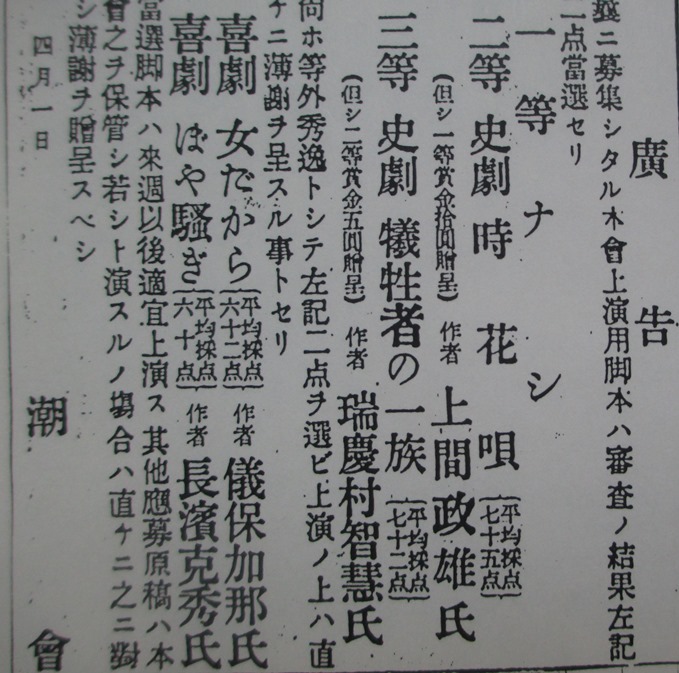
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
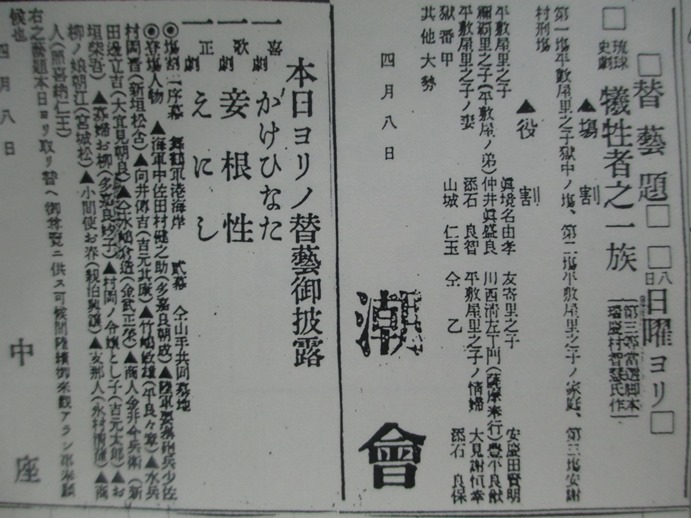
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
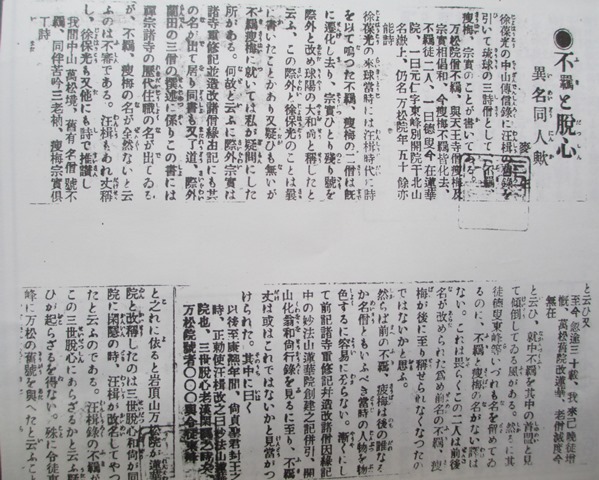
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
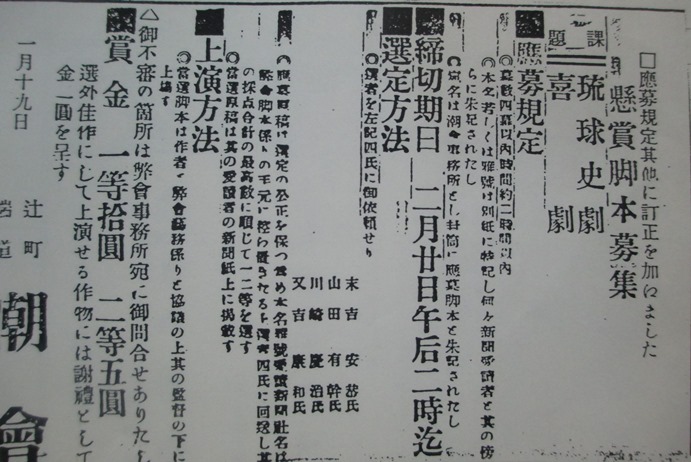
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
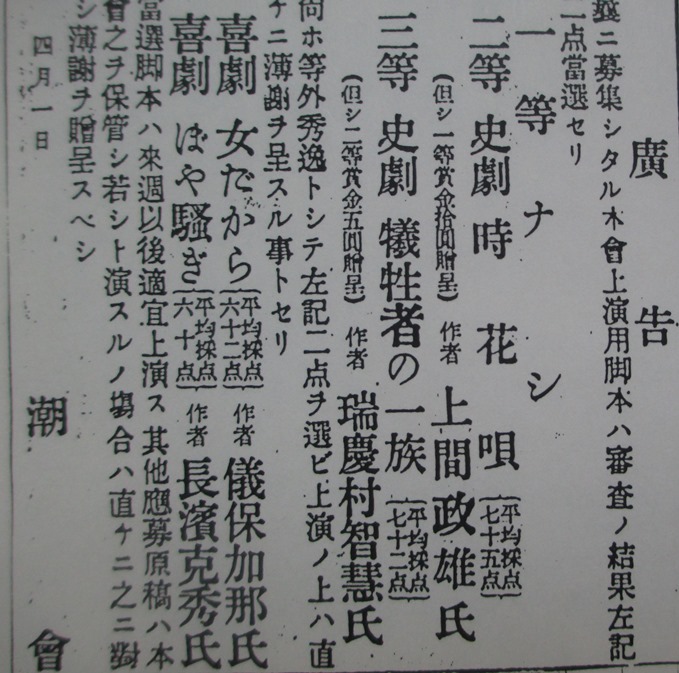
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
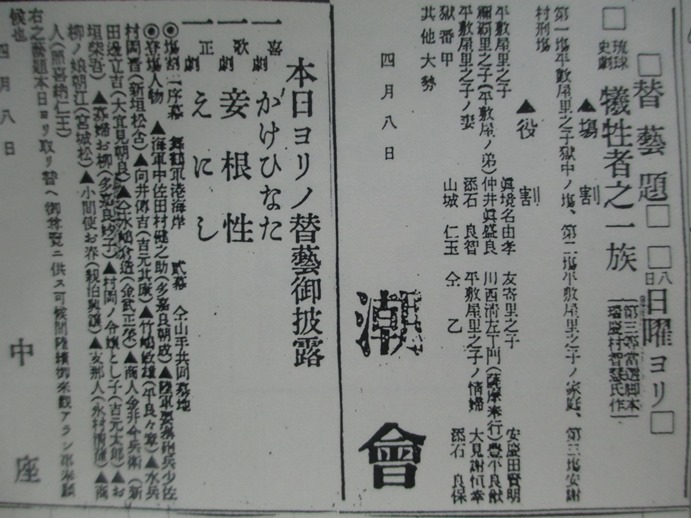
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
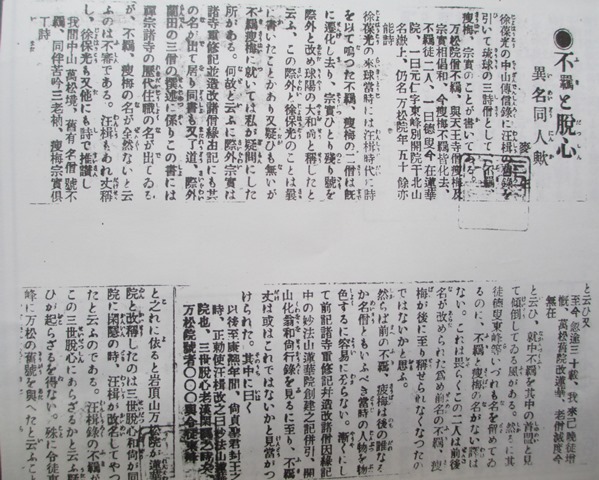
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
10/29: 年譜・末吉麦門冬/1922(大正11)年②
1922(大正11)年
3月30日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<12>ーおもろ双紙の焼失」
3月31日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<14>ー首里城の回禄」
4月1日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<15>ー火災と文献」
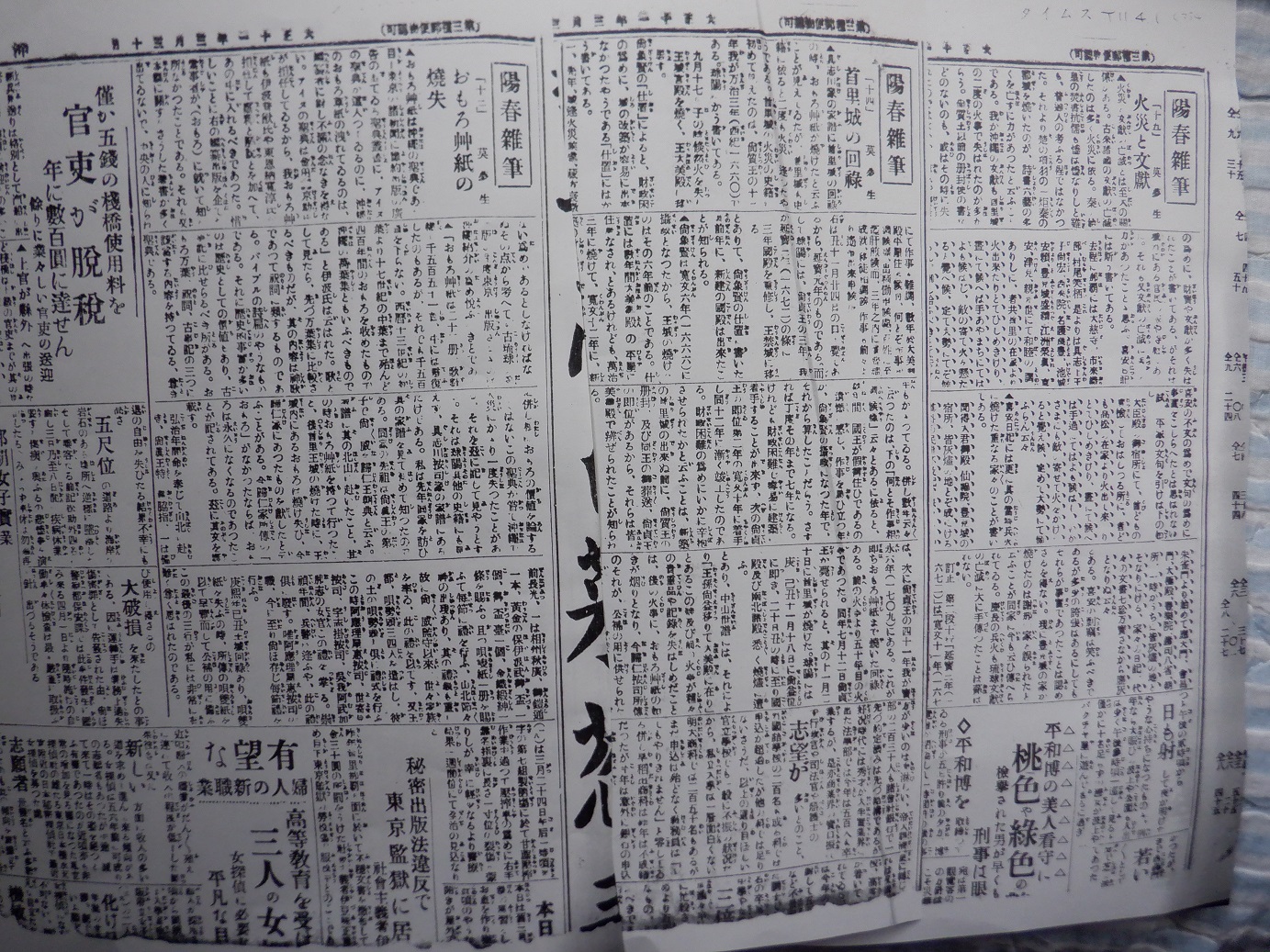
4月2日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<16>ー喜安日記と為朝伝説」
4月4日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<17>ー喜安日記と為朝伝説」
4月5日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<18>ー喜安日記と為朝伝説」
4月7日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<20>ー鎧武者」(『中山世譜』)
4月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<21>ー鎧武者」
4月9日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<22>ー鎧武者」
4月11日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<23>ー倭寇と鎧」
4月12日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<24>ー倭寇の兵力」
4月13日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<25>ー倭寇の戦法」
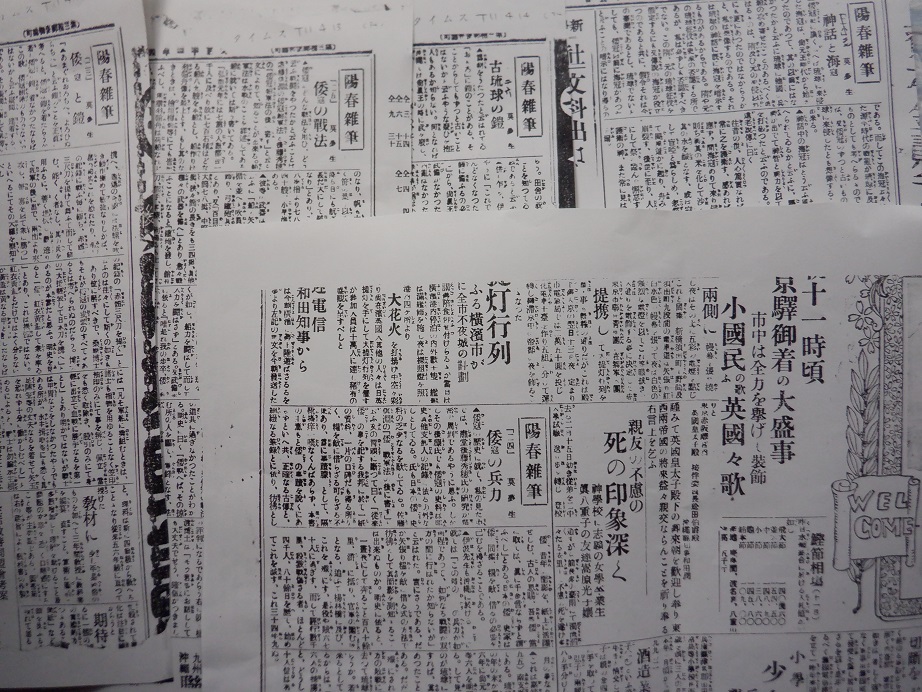
4月14日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<26>ー古琉球の鎧」
4月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<27>ー神話と海寇」
4月17日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<28>ー神遊は神舞」
4月18日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<29>ー詫遊は神舞」(『琉球神道記』)
4月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<30>ー詫遊は神舞」
4月21日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<32>ー詫遊は神舞」
4月22日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<33>ー詫遊は神舞」
4月23日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<34>ー琉球の戦舞」/「中央に紹介さるる沖縄の武術ー東京博物館に於いて開かれる文部省主催の運動体育展覧会へ本県より沖縄尚武会長 富名腰義珍氏が準備整え県を介し発送。書も本県一流の青年書家 謝花雲石氏に依頼・・・・」
4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」
4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」
4月28日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<38>ー仕合」/「本県農業の大恩人 甘藷金城を紹介ー龜島有功翁の苦心」
4月29日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<39>ー古琉球の政治」
5月6日 『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長 百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」
1922年6月 佐藤惣之助(詩人)来沖
1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生「葉隠餘滴ー昔の道路取締」
8月 『日本及日本人』842号 麦生「支那古代の埋葬法」
8月22日 鎌倉芳太郎、麦門冬の紹介状を持って首里儀保の華國・長嶺宗恭を訪ねる。
1922年9月15日『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー慎思九(中)」
〇新城栄徳ー私は1991年12月『真境名安興全集刊行だより№、1』の「笑古漫筆の魅力」で、笑古漫筆には「久米村例寄帳」から抜き書きが多く貴重であると書いた。麦門冬も本随筆で久米村例寄帳から引用している。道路での子どもの遊び、泊阿嘉物語の放歌者は駄目というのがある。
9月 平良盛吉『沖縄民謡集』(上巻)刊
9月 許田普敦『通俗琉球史』(序文・末吉安恭)
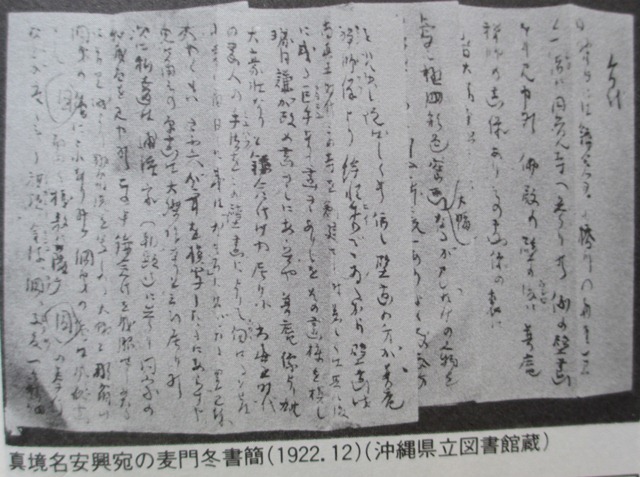
10月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(37)ー琉儒と道教」
10月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(39)ー琉儒と道教」
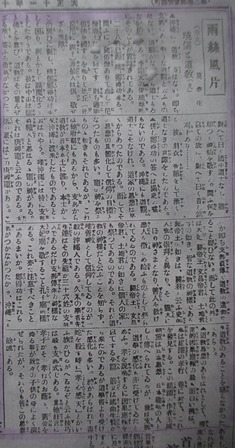

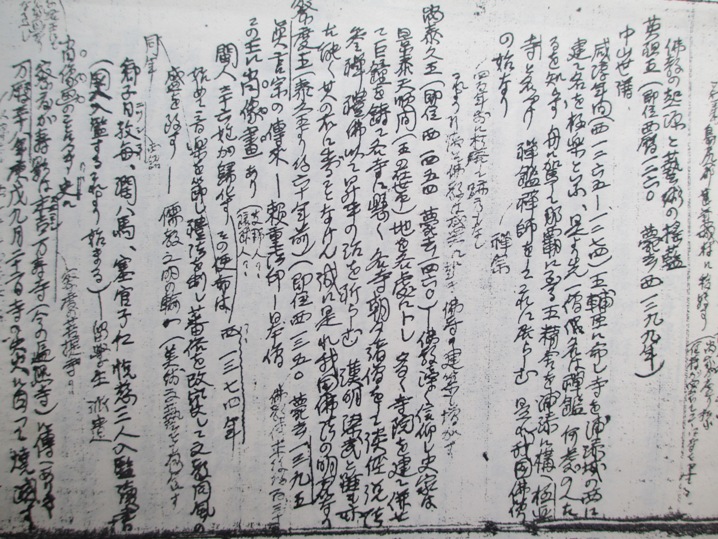
1922年 『沖縄タイムス』末吉莫夢「琉球画人伝」(表題は本朝画人傳を念頭に鎌倉芳太郎が付けたもの)を鎌倉が筆記したもの。
11月 富名腰義珍『琉球拳法唐手』(序文・末吉安恭)
3月30日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<12>ーおもろ双紙の焼失」
3月31日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<14>ー首里城の回禄」
4月1日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<15>ー火災と文献」
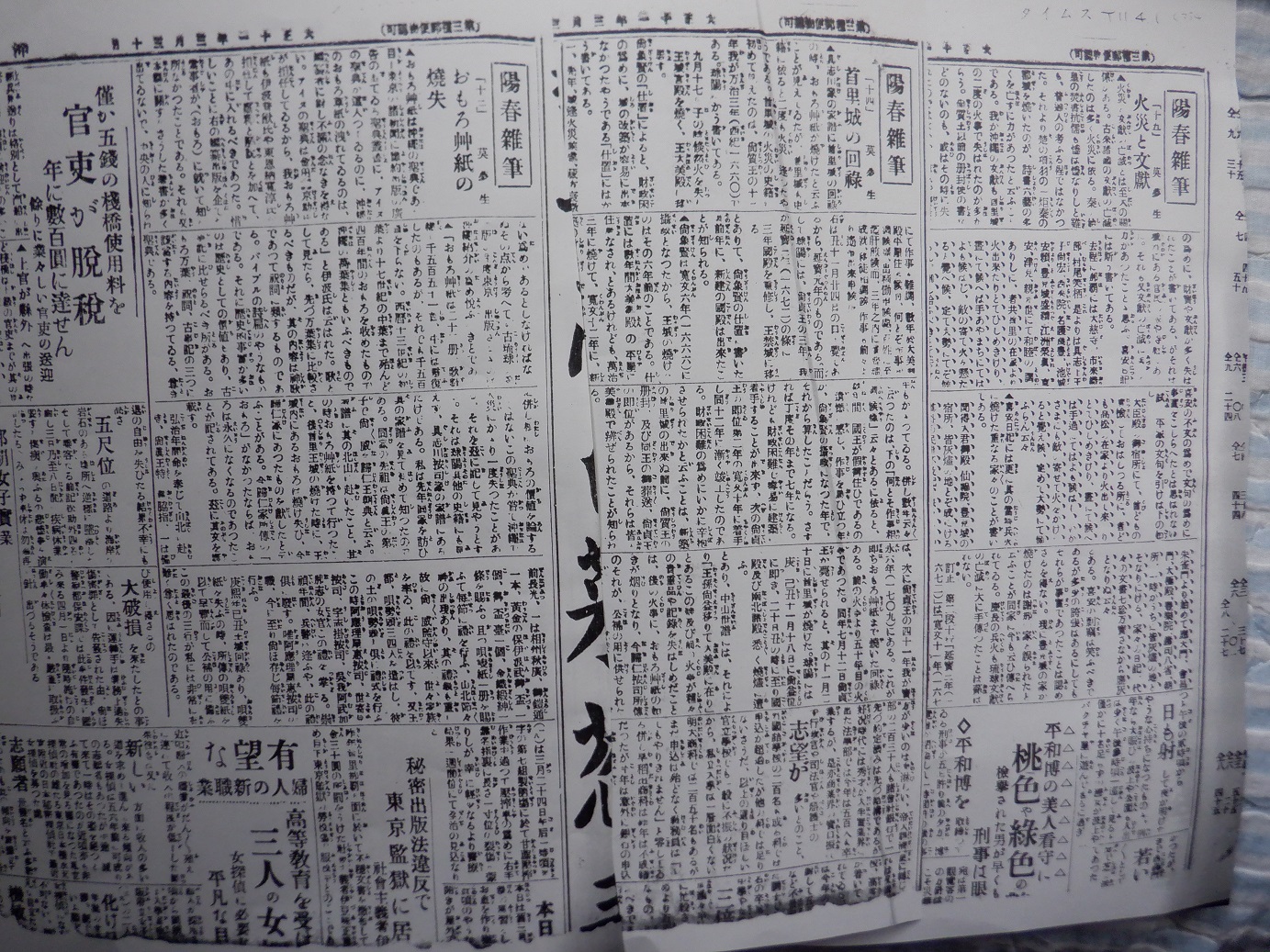
4月2日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<16>ー喜安日記と為朝伝説」
4月4日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<17>ー喜安日記と為朝伝説」
4月5日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<18>ー喜安日記と為朝伝説」
4月7日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<20>ー鎧武者」(『中山世譜』)
4月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<21>ー鎧武者」
4月9日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<22>ー鎧武者」
4月11日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<23>ー倭寇と鎧」
4月12日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<24>ー倭寇の兵力」
4月13日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<25>ー倭寇の戦法」
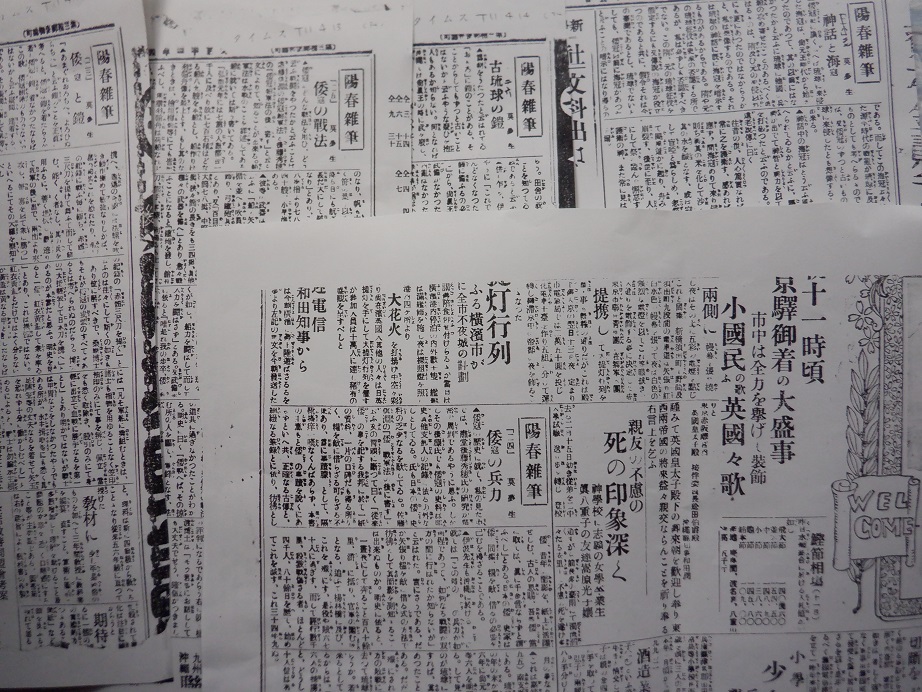
4月14日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<26>ー古琉球の鎧」
4月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<27>ー神話と海寇」
4月17日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<28>ー神遊は神舞」
4月18日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<29>ー詫遊は神舞」(『琉球神道記』)
4月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<30>ー詫遊は神舞」
4月21日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<32>ー詫遊は神舞」
4月22日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<33>ー詫遊は神舞」
4月23日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<34>ー琉球の戦舞」/「中央に紹介さるる沖縄の武術ー東京博物館に於いて開かれる文部省主催の運動体育展覧会へ本県より沖縄尚武会長 富名腰義珍氏が準備整え県を介し発送。書も本県一流の青年書家 謝花雲石氏に依頼・・・・」
4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」
4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」
4月28日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<38>ー仕合」/「本県農業の大恩人 甘藷金城を紹介ー龜島有功翁の苦心」
4月29日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<39>ー古琉球の政治」
5月6日 『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長 百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」
1922年6月 佐藤惣之助(詩人)来沖
1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生「葉隠餘滴ー昔の道路取締」
8月 『日本及日本人』842号 麦生「支那古代の埋葬法」
8月22日 鎌倉芳太郎、麦門冬の紹介状を持って首里儀保の華國・長嶺宗恭を訪ねる。
1922年9月15日『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー慎思九(中)」
〇新城栄徳ー私は1991年12月『真境名安興全集刊行だより№、1』の「笑古漫筆の魅力」で、笑古漫筆には「久米村例寄帳」から抜き書きが多く貴重であると書いた。麦門冬も本随筆で久米村例寄帳から引用している。道路での子どもの遊び、泊阿嘉物語の放歌者は駄目というのがある。
9月 平良盛吉『沖縄民謡集』(上巻)刊
9月 許田普敦『通俗琉球史』(序文・末吉安恭)
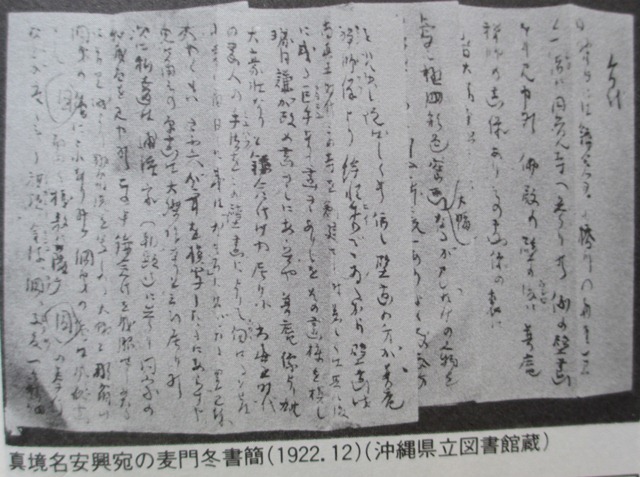
10月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(37)ー琉儒と道教」
10月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(39)ー琉儒と道教」
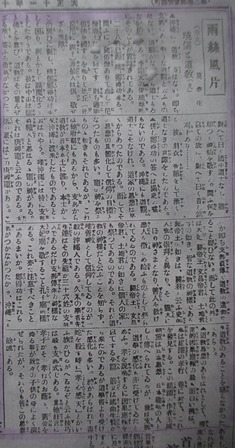

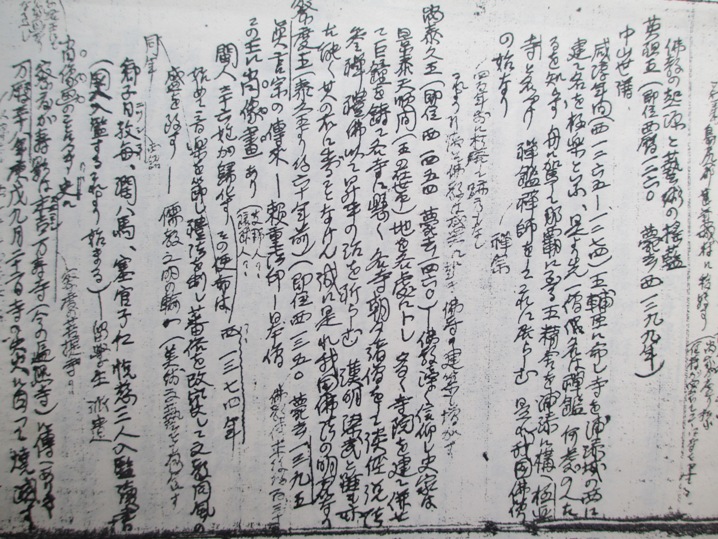
1922年 『沖縄タイムス』末吉莫夢「琉球画人伝」(表題は本朝画人傳を念頭に鎌倉芳太郎が付けたもの)を鎌倉が筆記したもの。
11月 富名腰義珍『琉球拳法唐手』(序文・末吉安恭)
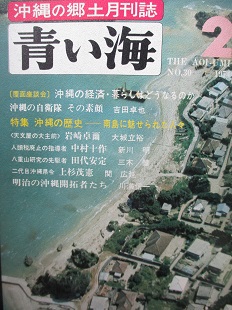

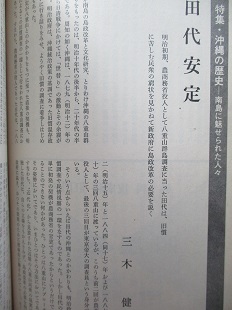
1974年2月号 雑誌『青い海』30号 大城立裕「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」
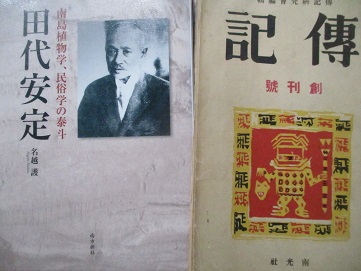
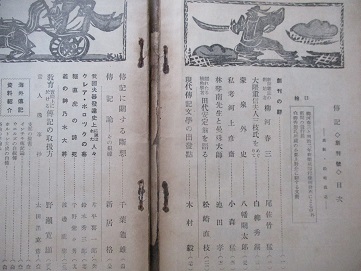


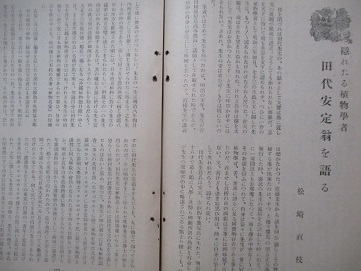
2017年3月 名越護『南島植物学、民俗学の泰斗 田代安定』南方新社/1934年年10月 南光社『傳記』創刊

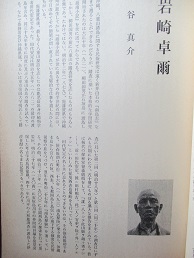

1974年1月『伝統と現代』谷真介「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」
1974年1月『伝統と現代』「日本フォークロアの先駆者」
田代安定(三木健)/笹森儀助(植松明石)/岩崎卓爾(谷真介)/鳥居龍蔵(小野隆祥)/佐々木喜善(菊池照雄)/柳田国男(牧田茂)/折口信夫(村井紀)/早川孝太郎(野口武徳)/筑土鈴寛(藤井貞和)/中山太郎(阿部正路)/南方熊楠(飯倉照平)/渋沢敬三(宮本馨太郎)/金田一京助(浅井亨)/知里真志保(藤本英夫)/伊波普猷(新里金福)/喜捨場永珣(牧野清)/石田英一郎(松谷敏雄)/菅江真澄(石上玄一郎)/近藤富蔵(浅沼良次)
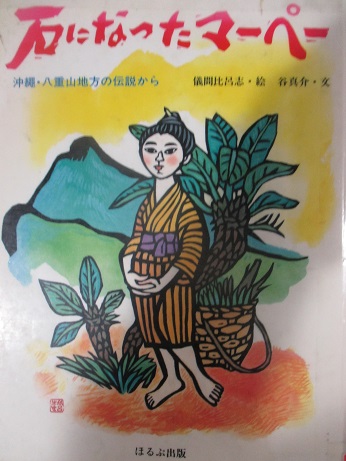
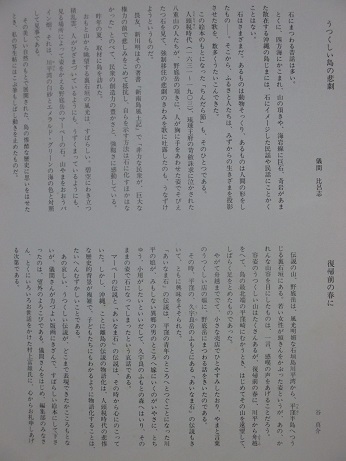
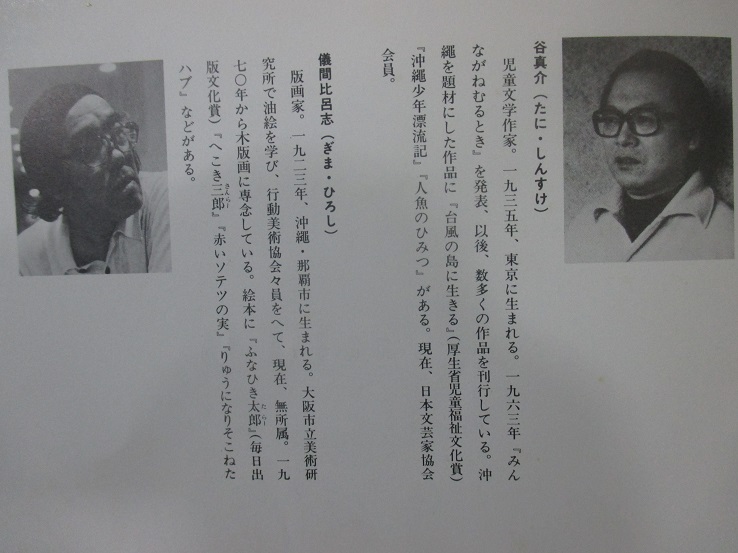
1985年5月 儀間比呂志・絵 谷真介・文『石になったマーペー 沖縄・八重山地方の伝説から』ほるぷ出版
1974年6月 『岩崎卓爾一巻全集』伝統と現代社
ひるぎの一葉/八重山研究/やえまカブヤー/石垣島気候篇/新撰八重山月令/気候雑纂/作品(俳句・短歌・詩)・その他。
註(語彙註)・・・西平守晴・沖縄関係資料室/岩崎卓爾と気候・・・畠山久尚・元気象庁長官/岩崎卓爾と八重山・・・谷川健一・民俗学者/岩崎卓爾翁のことども・・・瀬名波長宣・元石垣島測候所長/父・岩崎卓爾・・・菊池南海子・岩崎卓爾次女/年譜・書誌・・・谷真介①/後記
①谷真介 たに-しんすけ
1935- 昭和後期-平成時代の児童文学作家。
昭和10年9月7日生まれ。子どもの遊びから生まれた冒険世界を多彩な手法でえがき,作品に「みんながねむるとき」「ひみつの動物園」など。「沖縄少年漂流記」,「台風の島に生きる」(昭和51年児童福祉文化奨励賞)など,ノンフィクションも手がける。東京出身。中央大中退。本名は赤坂早苗。→コトバンク
岩崎卓爾年譜(抄録)ー谷真介
1882年ー8月、上杉茂憲、沖縄県令として八重山(石垣島)を巡回。この年、鹿児島の植物学者・田代安定が農商務省官吏として最初の八重山踏査を行う。
1891年ー10月、岩崎卓爾、第二高等中学校を退学し、北海道庁札幌一等測候所に気象研究生として入所。
1893年ー11月、岩崎卓爾、根室一等測候所に配属。この年、青森の笹森儀助が沖縄本島・先島諸島の民情踏査に赴く。
1894年ー5月、笹森儀助『南島探険』刊。8月、日清戦争始まる。
1897年ー6月、岩崎卓爾、富士山頂の測候を命じられる。10月、岩崎卓爾、中央気象台附属石垣島測候所勤務を拝命。12月、石垣島測候所長心得となる。
1899年ー4月、大島測候所長心得として奄美大島名瀬へ赴く。6月、妻・貴志子が仙台より来る。9月、石垣島測候所長として石垣島に帰任。
1900年ー5月、古賀辰四郎は、黒岩恒、宮島幹之助に協力を仰いで尖閣列島を調査。(尖閣列島の命名は黒岩恒)
1902年ーこの年の末、266年にわたって八重山島民を搾取しつづけていた人頭税廃止となる。
1904年ー2月、日露開戦。7月、鳥居龍造、川平仲間嶽貝塚を発掘調査。
1906年ー2月、菊池幽芳、川平大和墓発掘調査。春、岩崎卓爾、蝶の標本として「アカタテハ」「ヤマトシジミ」を岐阜の名和昆虫研究所へ送る。この年、岩崎卓爾、台北より来島した田代安定と会う。
1910年ーこの年。石垣島に白蟻の被害拡がる。イギリスのノルス来島。
1911年ー1月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻に関する通信」、6月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻群飛」。6月、強度の地震あり。岩崎卓爾、名蔵川良峡で「イワサキコノハチョウ」発見。
1912年ー4月、岩崎卓爾『八重山童謡集』刊。5月、岩崎卓爾、粟、稲、麦など害する夜盗虫(アハノヨトウムシ)の駆除法を名和昆虫研究所に問い合わせる。
1913年ー2月、貴志子夫人 7人の子を連れて仙台へ帰る。岩崎卓爾、「イワサキゼミ」「イワサキヒメハルゼミ」の新種発見。
1914年ー3月、岩崎卓爾、八重山通俗図書館を創設。5月、御木本幸吉が石垣島富崎で真珠養殖事業を始める、卓爾に協力を仰ぐ。
1916年ー8月、武藤長平七高教授が来島。
1920年ー9月ごろ岩崎卓爾、台風観測中に右眼を失明す。この年、岩崎卓爾『ひるぎの一葉』刊。
1921年ー岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに柳田国男を石垣港桟橋に迎える。
1922年ー4月17日、岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに上京、柳田国男を訪ねる。4月21日、一ツ橋如水館で開かれた「南島談話会」、出席者、岩崎卓爾、喜舎場永珣、上田万年、白鳥庫吉、三浦新七、新村出、幣原坦、本山桂川、移川子之蔵、中山太郎、折口信夫、金田一京助、東恩納寛惇、松本信広、松本芳夫その他。8月1日、暴風警報が出ているなかを田辺尚雄が民謡研究のため来島。
1923年ー2月、鎌倉芳太郎、桃林寺権現堂の芸術調査で来島。7月、岩崎卓爾、『やえまカブヤー』を八重山通俗図書館から刊行。8月、折口信夫が民俗採集のため来島。
1924年ー9月、岩崎卓爾、文芸同人結社セブン社を主宰、同人誌『せぶん』を創刊。本山桂川、民俗採集で来島、卓爾のすすめに応じて与那国島踏査に赴く→1925年『南島情趣』『与那国島図誌』『与那国島誌』刊行。
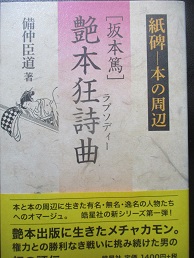
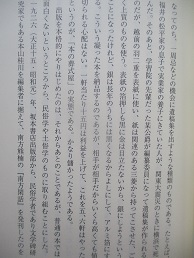
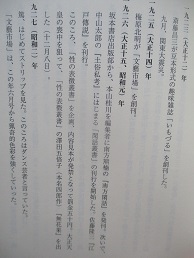
2016年6月 備仲臣道『紙碑ー本の周辺 坂本篤 艶本狂詩曲』皓星社〇1926(大正15・昭和元)年、坂本書店出版部から、民俗学者であり文学碑研究家でもある本山桂川を編集者に据えて、南方熊楠の『南方閑話』を発刊したのを手はじめに、中山太郎の『土俗私考』にはじまる「閑話叢書」を刊行
〇2017年3月 『平成27年度 市立市川歴史博物館館報』三村宜敬(市川歴史博物館学芸員)「本山桂川の足跡を探る」
1926年ー1月、八重山に始めてラジオ受信器設置。
1928年ー4月13日、東京代々木の日本青年館、18日が朝日新聞講堂で初めて八重山芸能(第三回郷土舞踊大会)が公演。
□1974年3月 大城立裕『風の御主前 小説・岩崎卓爾伝』日本放送出版協会
□岩崎卓爾 いわさき-たくじ
1869-1937 明治-昭和時代前期の気象技術者,民俗学者。
明治2年10月17日生まれ。32年沖縄石垣島初代測候所長となる。気象観測のかたわら,八重山の民俗,歴史,生物などを研究。退職後も石垣島にとどまり,「天文屋の御主前(うしゆまい)」としたしまれた。昭和12年5月18日死去。69歳。陸前仙台出身。第二高等学校中退。著作に「ひるぎの一葉」「八重山研究」など。→コトバンク
昨年暮れ、沖縄県立博物館・美術館指定管理者の「文化の杜共同企業体」から今年5月に開催される企画展「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した“美”」の図録に末吉麦門冬と鎌倉芳太郎についての原稿依頼があった。奇しくも今年11月25日は末吉麦門冬の没後90年で、展覧会場の沖縄県立博物館・美術館に隣接する公園北端はかつて末吉家の墓があった場所である。加えて、文化の杜には麦門冬曾孫の萌子さんも居る。私は2007年の沖縄県立美術館開館記念展図録『沖縄文化の軌跡』「麦門冬の果たした役割」の中で「琉球美術史に先鞭をつけたのは麦門冬・末吉安恭で、その手解きを受けた一人が美術史家・比嘉朝健である。安恭は1913年、『沖縄毎日新聞』に朝鮮小説「龍宮の宴」や支那小説「寒徹骨」などを立て続けに連載した。そして15年、『琉球新報』に『吾々の祖先が文字に暗い上に筆不精(略)流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の国ではある』と朝鮮の古書『龍飛御天歌』『稗官雑記』などを引用し、『朝鮮史に見えたる古琉球』を連載した。
画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬
安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。
麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
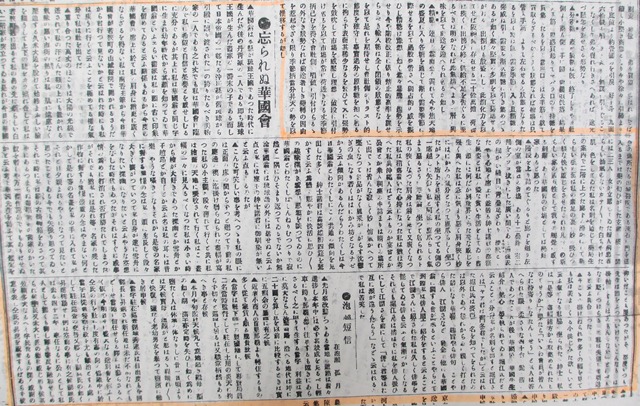
華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・
麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

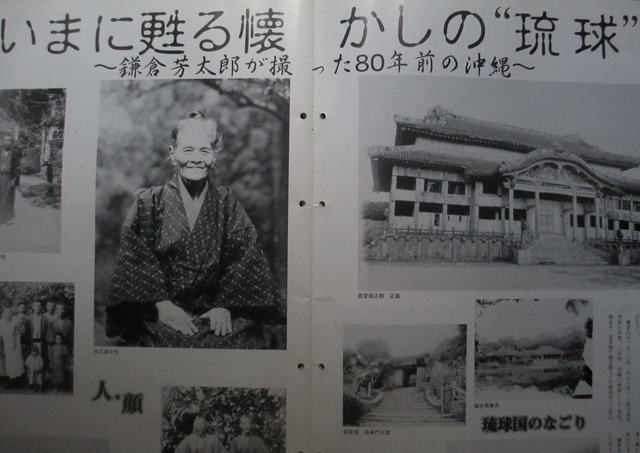
画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬
安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。
麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
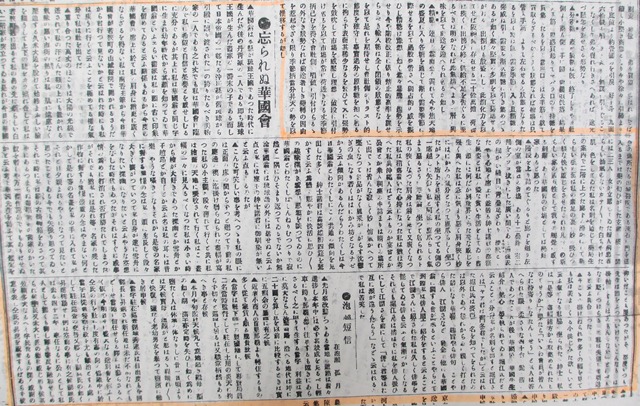
華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・
麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

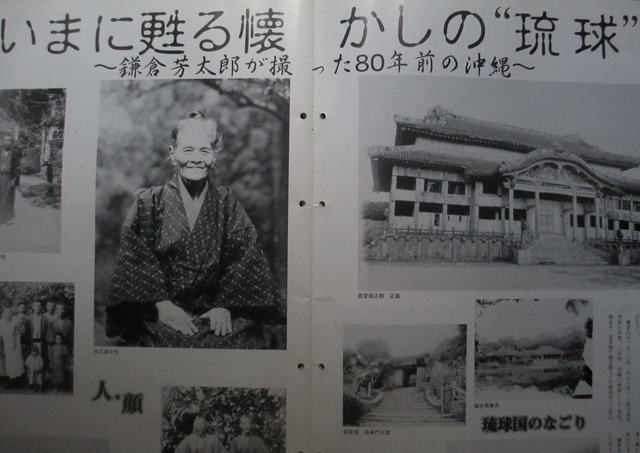
10/20: 10月25日は「空手の日」
1951年2月 雑誌『おきなわ』遠山寛賢(1888年~1966年)「琉洋両楽の発展史」
遠山寛賢(1888年~1966年)は、旧姓を親泊といい、1888年(明治21年)、沖縄県首里市に生まれた。幼少の頃から、板良敷某、糸洲安恒、東恩納寛量らに師事した。それぞれ、どの時期に師事したかは不明であるが、糸洲に師事したのは、遠山が沖縄県師範学校へ入学(1906年)してからであると考えられる。当時の師範学校の唐手師範は糸洲安恒、師範代は屋部憲通が務めていた。在校中の1908年(明治41年)から3年間、遠山は糸洲、屋部の助手を務めた。1911年(明治44年)、師範学校を卒業した。遠山は、徳田安文、真喜屋某らとともに、俗に「糸洲安恒の三羽烏」と呼ばれた。遠山は、ほかに大城某から棒術、釵術を、初代首里区長を務めた知花朝章(知花朝信の本家叔父)から「知花公相君」の型を教わった。1924年(大正13年)には台湾へ渡り、台北の陳仏済、台中の林献堂から中国拳法を学んだ。(→ウィキペディア)
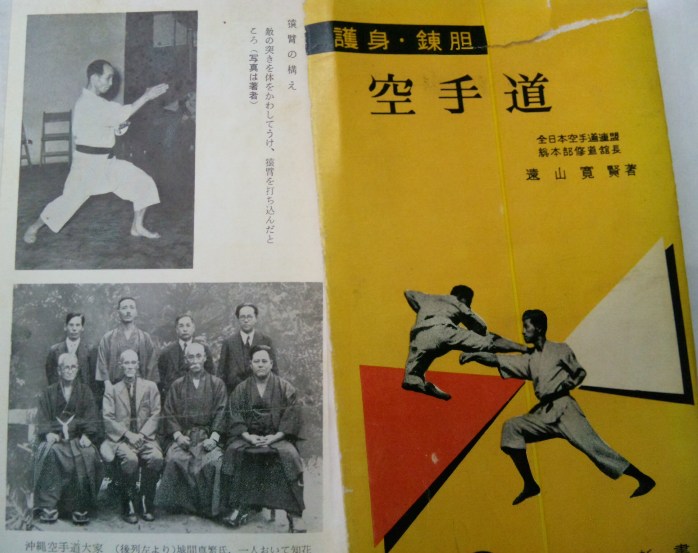
1956年4月 遠山寛賢『空手道』鶴書房
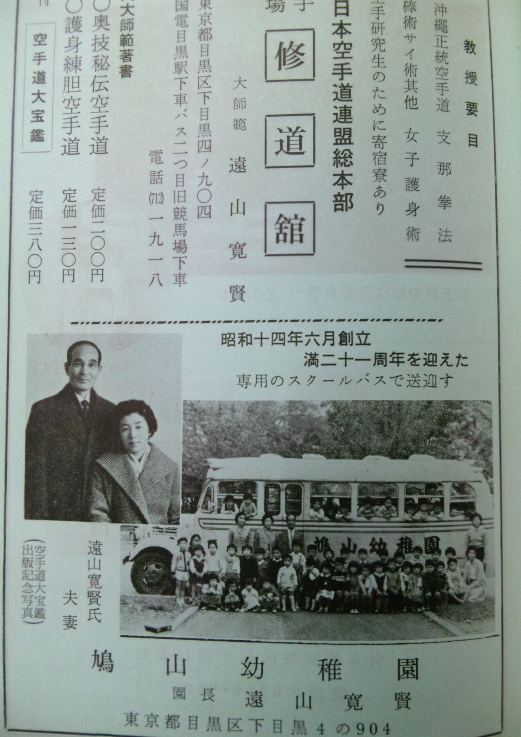
1962年6月 沖縄興信所『琉球紳士録』

1960年1月『オキナワグラフ』


沖縄空手の首里手系の流派、小林流をつくった知花朝信氏(1885~1969年)の没後50周年を記念した「小林流開祖拳聖知花朝信顕彰碑」の除幕式が29日、那覇市首里山川町公民館であった。沖縄小林流空手道協会の宮城驍(たけし)会長をはじめ、門弟代表の上原耕作錬士六段ら国内外約80人が新たな空手の聖地誕生を祝った。
知花朝信は1918年ごろ道場を開設。33年に小林流を命名したとされ、戦後一時期、山川公民館を道場としていたという。宮城会長は「山川公民館は小林流の発祥地。知花先生が指導した門弟らが国内外で活躍している。その功績をたたえたい」と喜んだ。式では知花氏の門下生らが「松村のパッサイ」「クーサンクー大」など伝統の型を演武。山川町自治会の島袋正則会長は「山川町に新たな名所ができた」と歓迎した。→沖縄タイムス2018-7-30
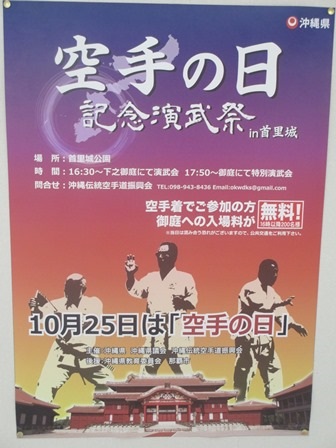
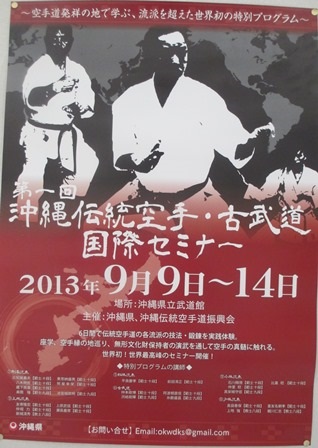
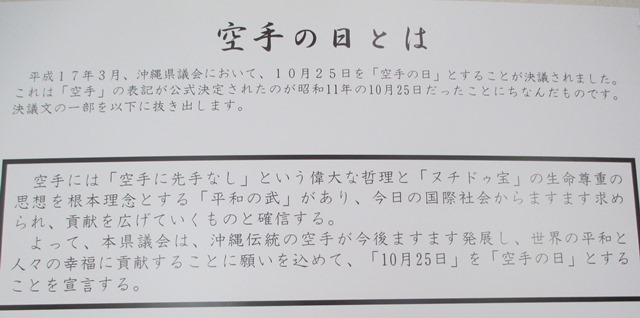
洲安恒の墓。正面右手に「糸洲安恒先生顕彰碑」が建つ

糸洲安恒の墓。正面右手に「糸洲安恒先生顕彰碑」が建つ

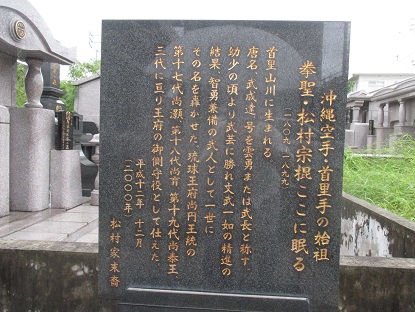
松村宗棍も眠る武氏墓

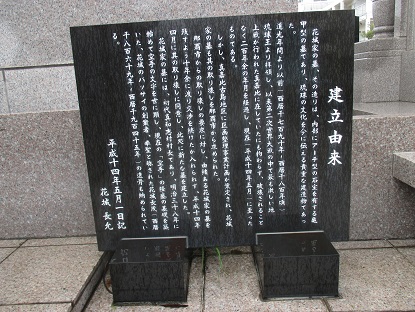
花城家(花城長茂)の墓、その造りは、内部にアーチ型の石室を有する亀甲型の墓であり、琉球の文化を今に伝える貴重な建造物あった。道元年間より以前(西暦千七百九十年・西暦千八百年頃)琉球王より拝領し、以来第二次世界大戦の中で最も激しい地上戦が行われた真嘉比に存していたにも拘わらず、破壊されることなく二百年余の年月を経過し現在(平成十四年五月)に至ったものである。しかし、真嘉比古島地区に区画整理事業計画が策定され、花城家の墓も其の取り壊しを那覇市から求められた。
那覇市からの取り壊しの要求に対し、由緒ある花城家の墓を残すよう十年余に渡り交渉を続けたが入れられず、平成十四年四月に其の取り壊しに同意し、此処に新たな墓を建立した。花城家の墓には、初代真和志村村長であり、明治三十八年に初めて空手の文字を世に顕し、現在の「空手」の隆盛の基礎を築いた、花城のバッサイの創案者、拳聖と称された花城長茂(西暦千八百六十九年ー西暦千九百四十五年)の遺骨も納められている。 平成十四年五月一日記 花城長允
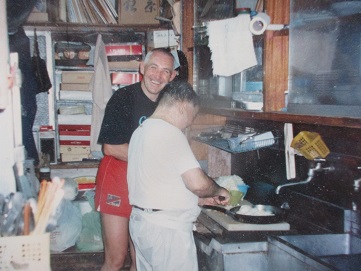

フランスの空手人と新城三郎
遠山寛賢(1888年~1966年)は、旧姓を親泊といい、1888年(明治21年)、沖縄県首里市に生まれた。幼少の頃から、板良敷某、糸洲安恒、東恩納寛量らに師事した。それぞれ、どの時期に師事したかは不明であるが、糸洲に師事したのは、遠山が沖縄県師範学校へ入学(1906年)してからであると考えられる。当時の師範学校の唐手師範は糸洲安恒、師範代は屋部憲通が務めていた。在校中の1908年(明治41年)から3年間、遠山は糸洲、屋部の助手を務めた。1911年(明治44年)、師範学校を卒業した。遠山は、徳田安文、真喜屋某らとともに、俗に「糸洲安恒の三羽烏」と呼ばれた。遠山は、ほかに大城某から棒術、釵術を、初代首里区長を務めた知花朝章(知花朝信の本家叔父)から「知花公相君」の型を教わった。1924年(大正13年)には台湾へ渡り、台北の陳仏済、台中の林献堂から中国拳法を学んだ。(→ウィキペディア)
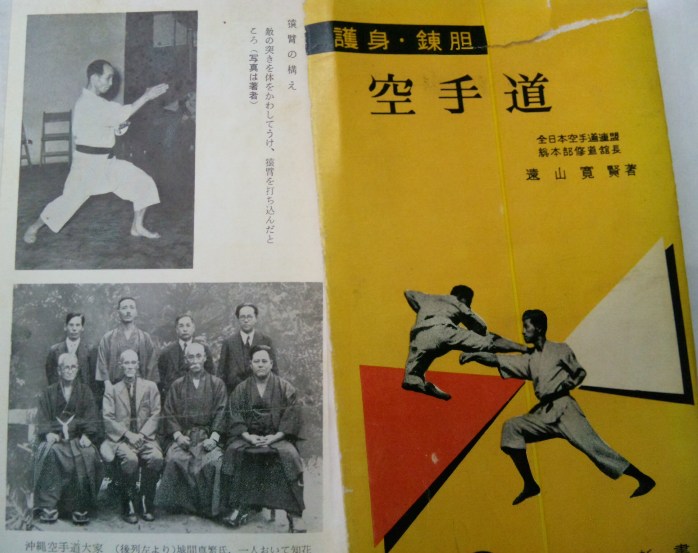
1956年4月 遠山寛賢『空手道』鶴書房
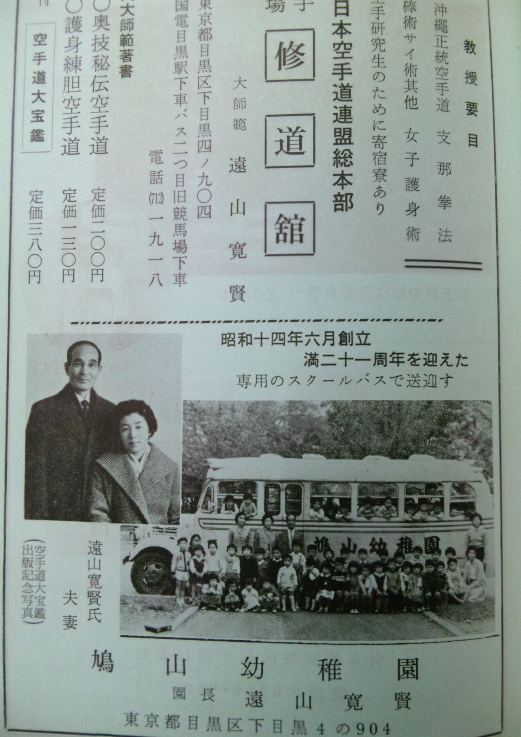
1962年6月 沖縄興信所『琉球紳士録』

1960年1月『オキナワグラフ』


沖縄空手の首里手系の流派、小林流をつくった知花朝信氏(1885~1969年)の没後50周年を記念した「小林流開祖拳聖知花朝信顕彰碑」の除幕式が29日、那覇市首里山川町公民館であった。沖縄小林流空手道協会の宮城驍(たけし)会長をはじめ、門弟代表の上原耕作錬士六段ら国内外約80人が新たな空手の聖地誕生を祝った。
知花朝信は1918年ごろ道場を開設。33年に小林流を命名したとされ、戦後一時期、山川公民館を道場としていたという。宮城会長は「山川公民館は小林流の発祥地。知花先生が指導した門弟らが国内外で活躍している。その功績をたたえたい」と喜んだ。式では知花氏の門下生らが「松村のパッサイ」「クーサンクー大」など伝統の型を演武。山川町自治会の島袋正則会長は「山川町に新たな名所ができた」と歓迎した。→沖縄タイムス2018-7-30
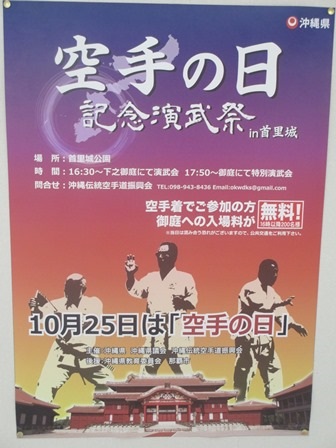
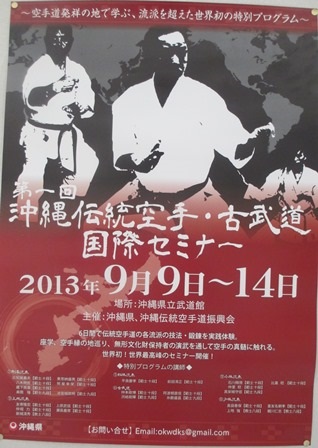
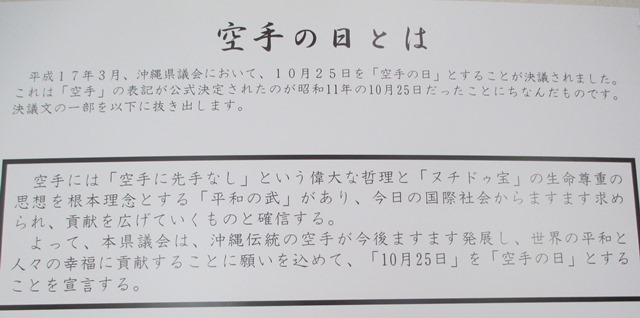
洲安恒の墓。正面右手に「糸洲安恒先生顕彰碑」が建つ

糸洲安恒の墓。正面右手に「糸洲安恒先生顕彰碑」が建つ

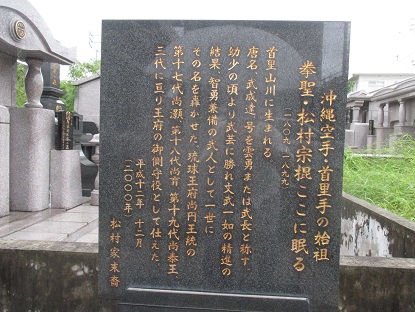
松村宗棍も眠る武氏墓

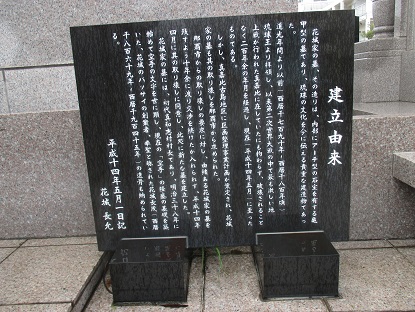
花城家(花城長茂)の墓、その造りは、内部にアーチ型の石室を有する亀甲型の墓であり、琉球の文化を今に伝える貴重な建造物あった。道元年間より以前(西暦千七百九十年・西暦千八百年頃)琉球王より拝領し、以来第二次世界大戦の中で最も激しい地上戦が行われた真嘉比に存していたにも拘わらず、破壊されることなく二百年余の年月を経過し現在(平成十四年五月)に至ったものである。しかし、真嘉比古島地区に区画整理事業計画が策定され、花城家の墓も其の取り壊しを那覇市から求められた。
那覇市からの取り壊しの要求に対し、由緒ある花城家の墓を残すよう十年余に渡り交渉を続けたが入れられず、平成十四年四月に其の取り壊しに同意し、此処に新たな墓を建立した。花城家の墓には、初代真和志村村長であり、明治三十八年に初めて空手の文字を世に顕し、現在の「空手」の隆盛の基礎を築いた、花城のバッサイの創案者、拳聖と称された花城長茂(西暦千八百六十九年ー西暦千九百四十五年)の遺骨も納められている。 平成十四年五月一日記 花城長允
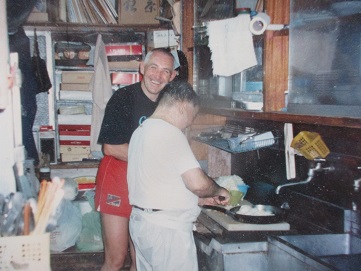

フランスの空手人と新城三郎
02/26: 観光文化/「描かれたジュリ」②
1913年6月5日、岡田雪窓 那覇港から鹿児島へ


1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」
1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」
1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」
1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」
1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」
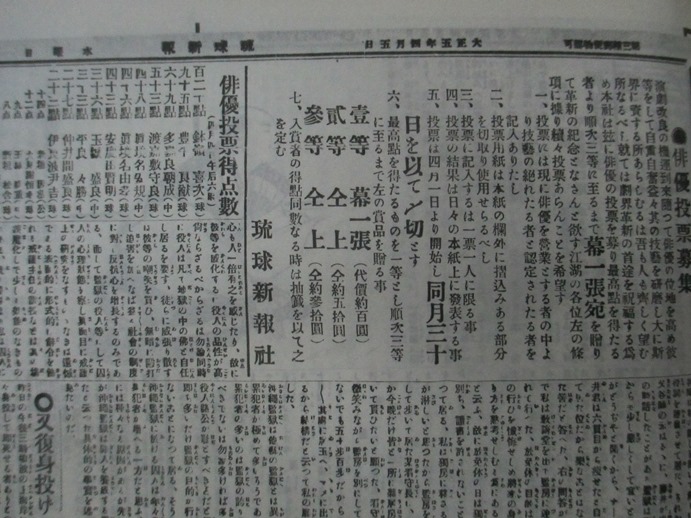
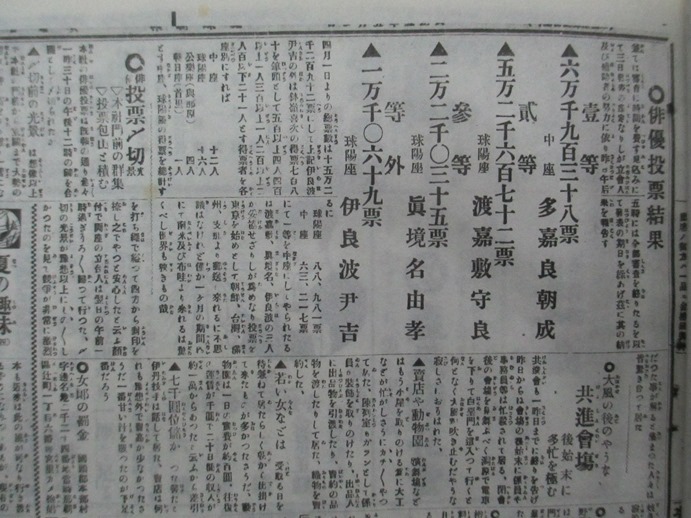
1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」
1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会
1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」
1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店
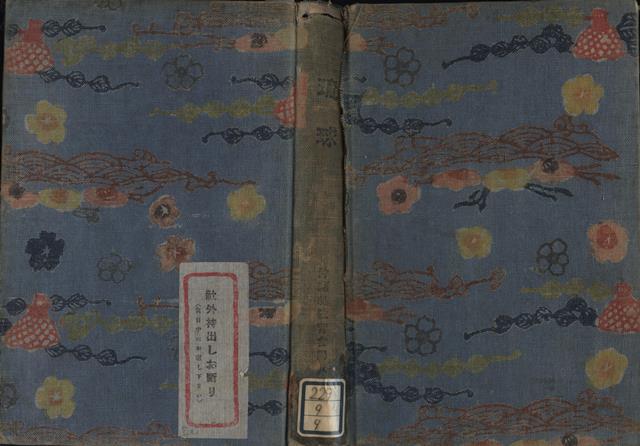
□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。
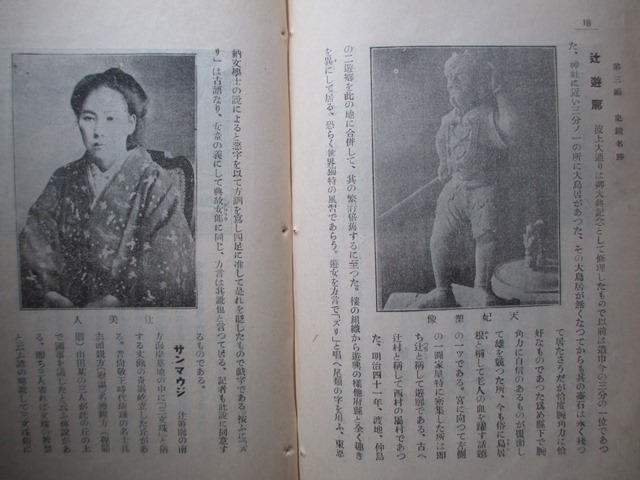
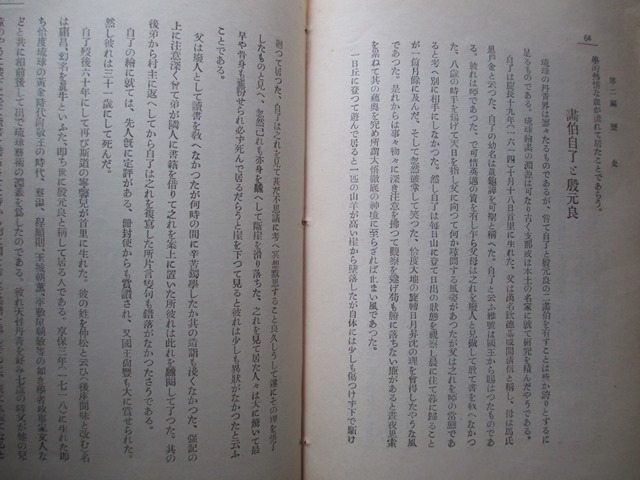
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」


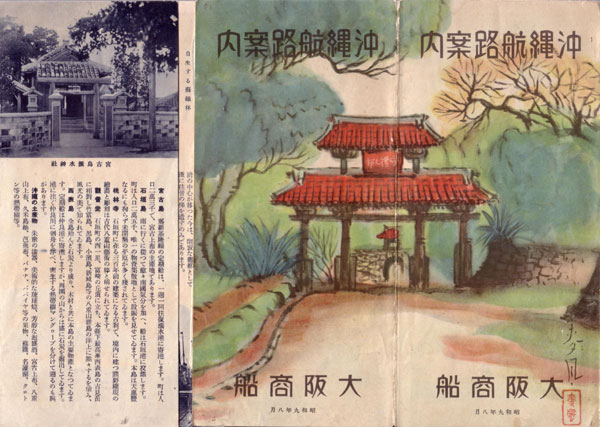
1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)
有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)
1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店
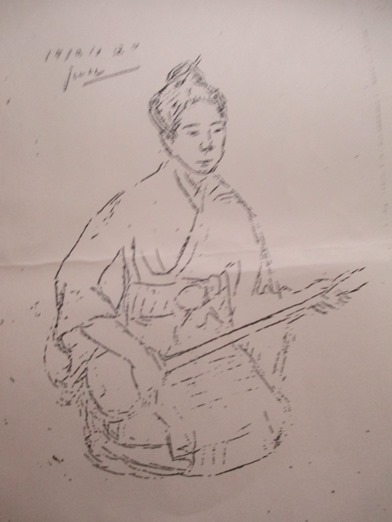
○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」
○ひなた、他九篇
ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。
○佛さま、他十篇
佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。
○母と子、他八篇
○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)




1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

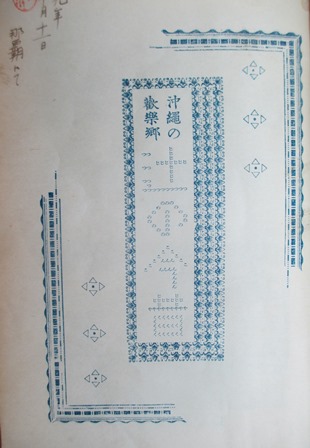


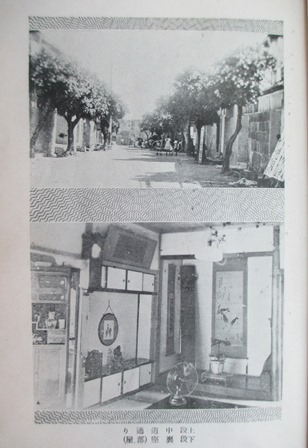
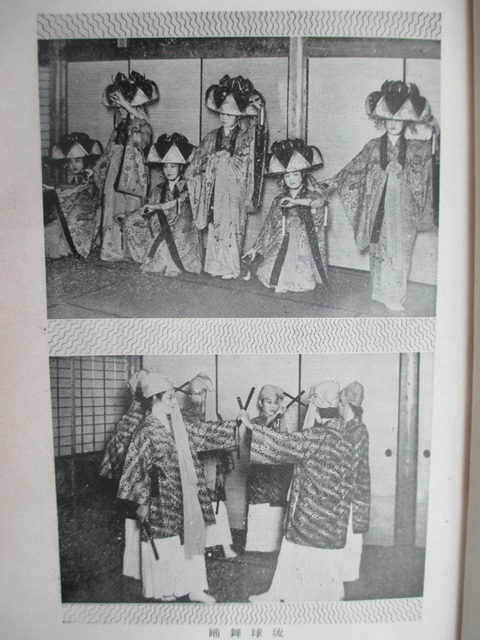
○一向宗の法難と廓
王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。
また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。
明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。
備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。
1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。
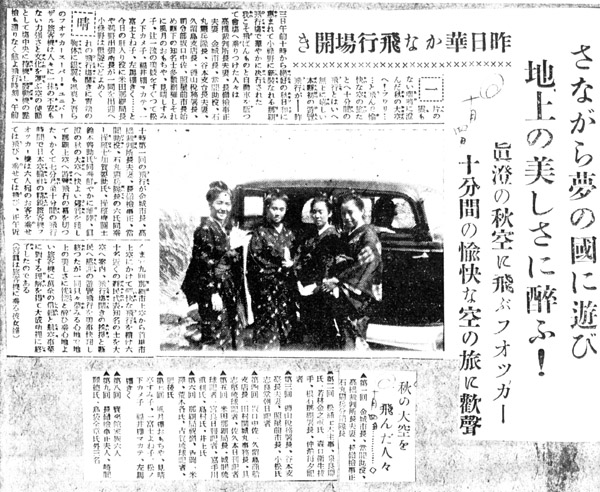
1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行
1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」
1938年9月15日『大阪球陽新報』
□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。
家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。
県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。
辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。


1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」
1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」
1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」
1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」
1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」
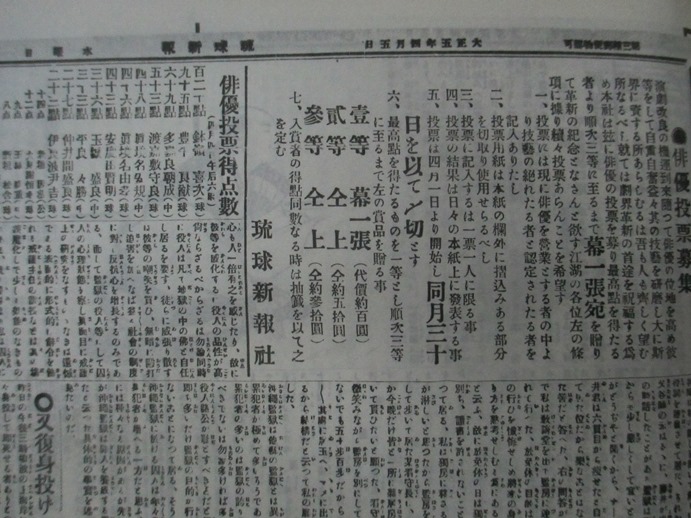
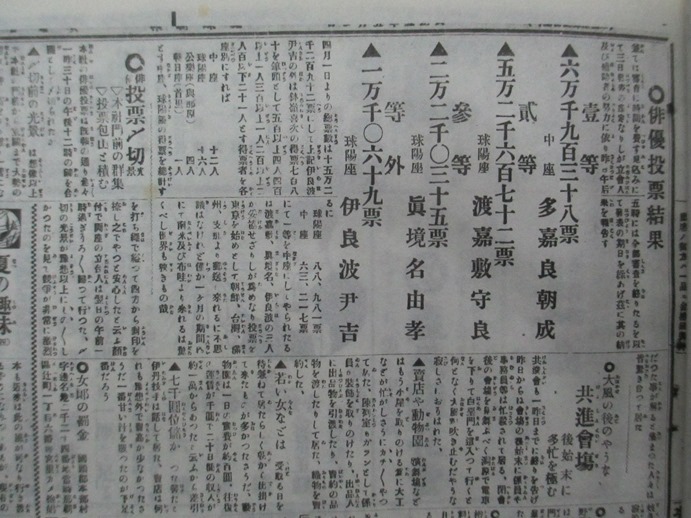
1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」
1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会
1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」
1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店
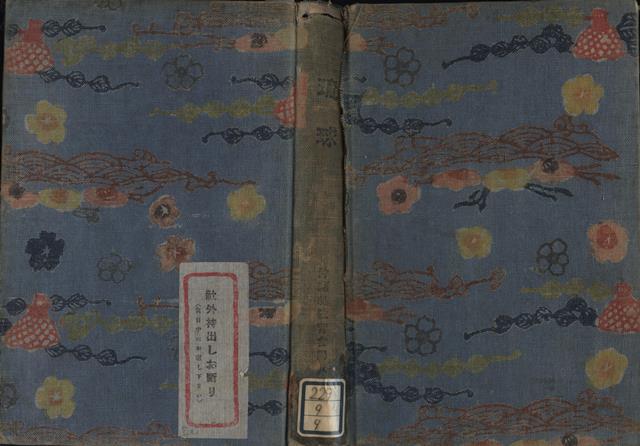
□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。
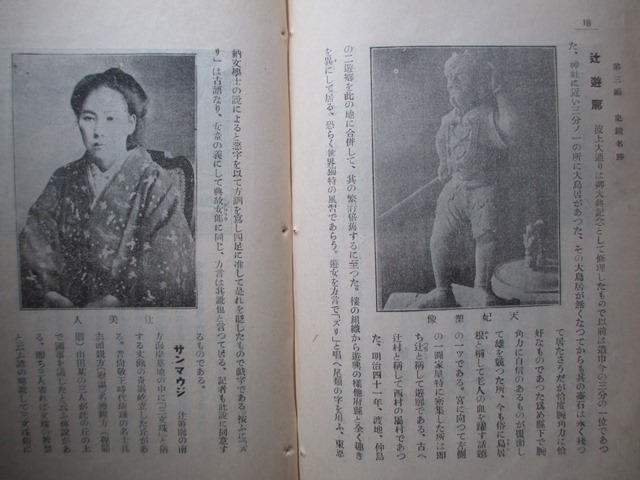
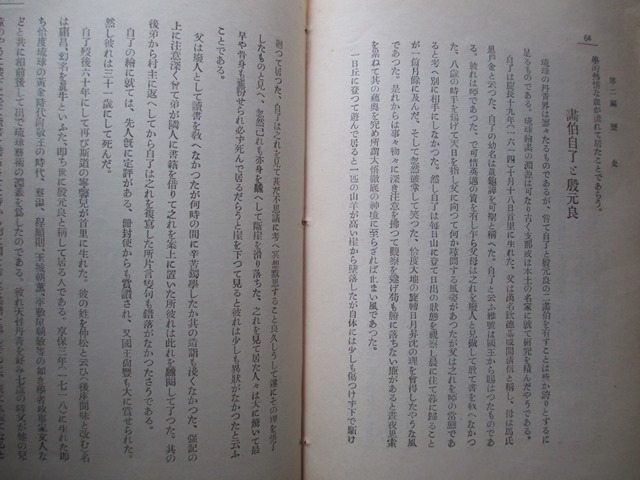
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」


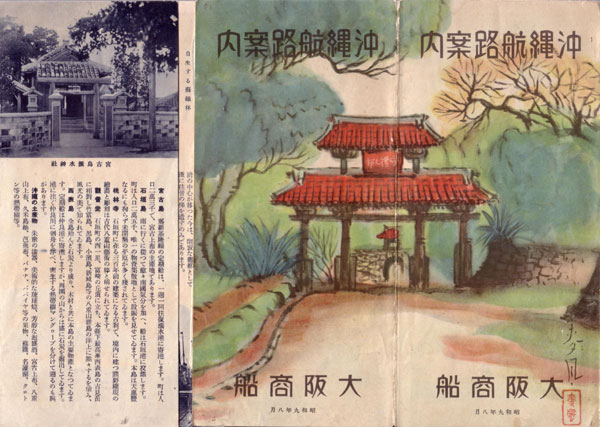
1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)
有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)
1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店
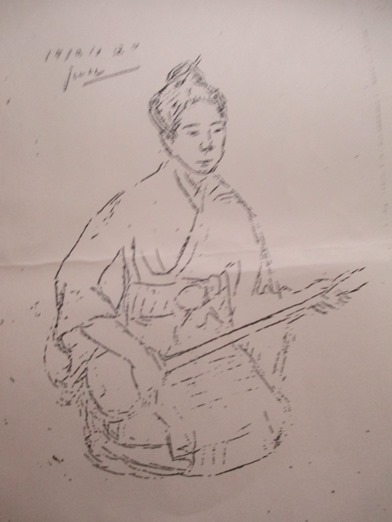
○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」
○ひなた、他九篇
ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。
○佛さま、他十篇
佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。
○母と子、他八篇
○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)




1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

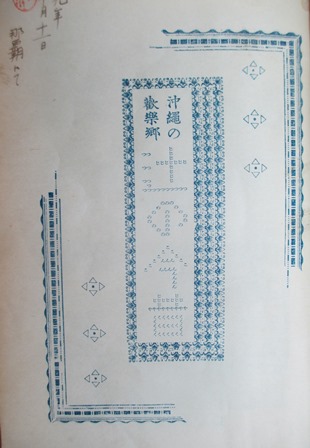


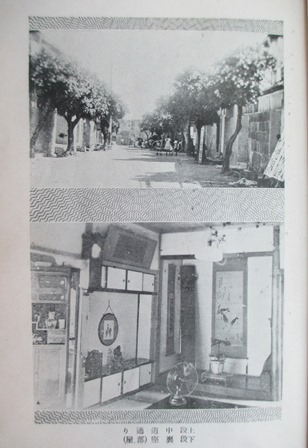
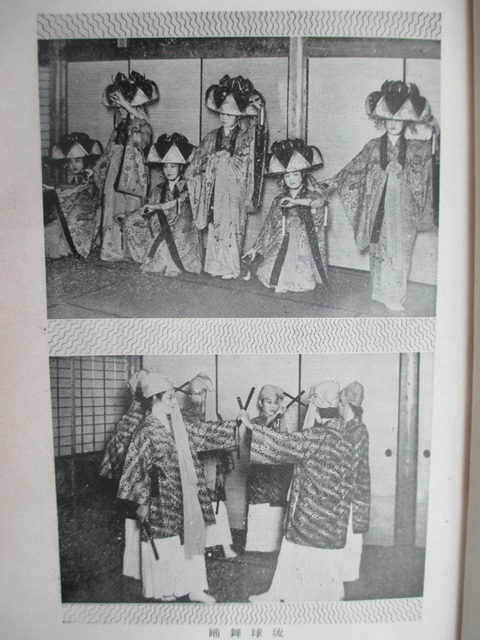
○一向宗の法難と廓
王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。
また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。
明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。
備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。
1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。
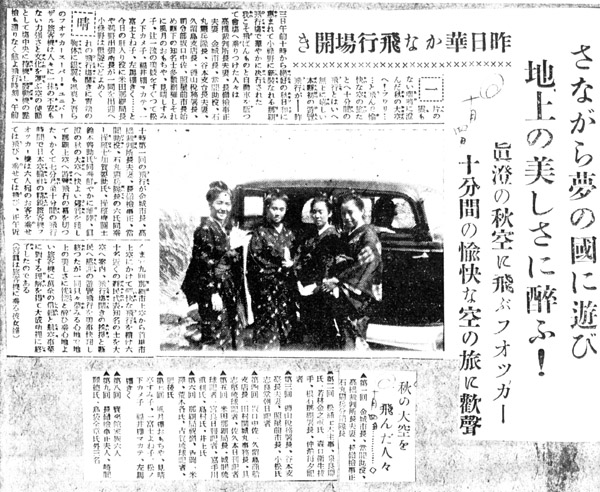
1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行
1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」
1938年9月15日『大阪球陽新報』
□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。
家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。
県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。
辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。
11/08: 年譜・末吉麦門冬/1924(大正13)年 ①
2月 関西沖縄県人会結成
2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行
2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

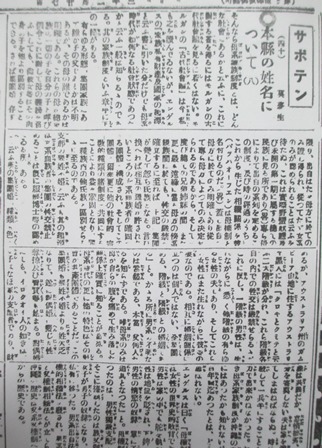
2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)
2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」
3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊
3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。
1924-3
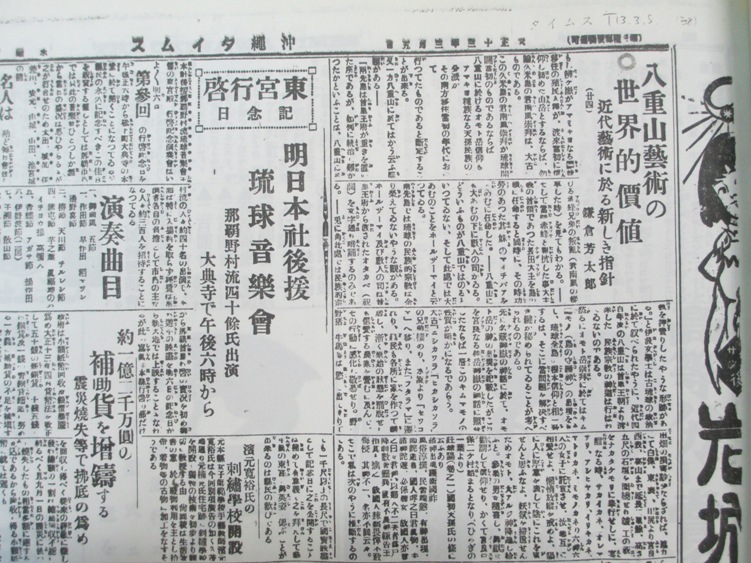
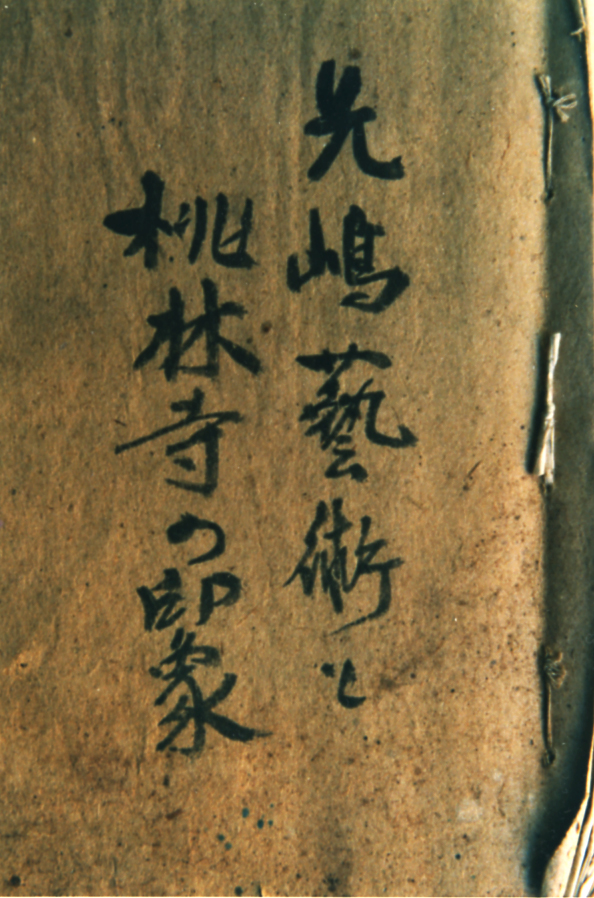 原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの
原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの
4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)
5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。
5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」
6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演
7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店
7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地
7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」
7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港
7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」
7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状
7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。
7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会
8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)
8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京
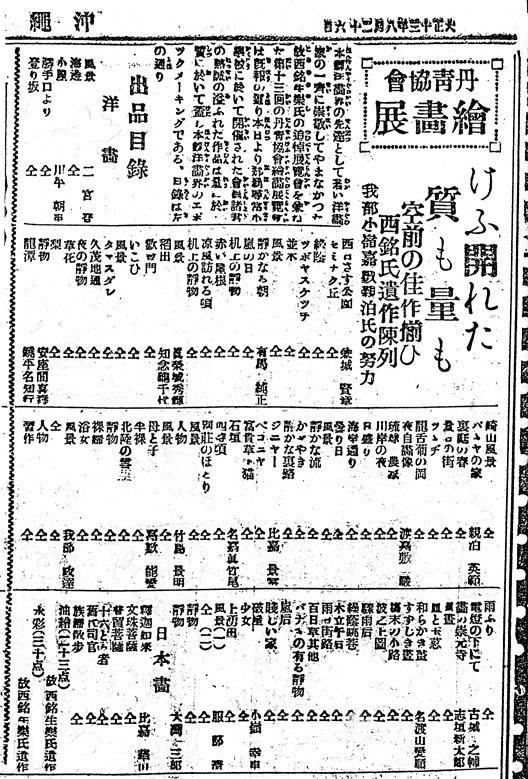
1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会
1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)
2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。
1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。
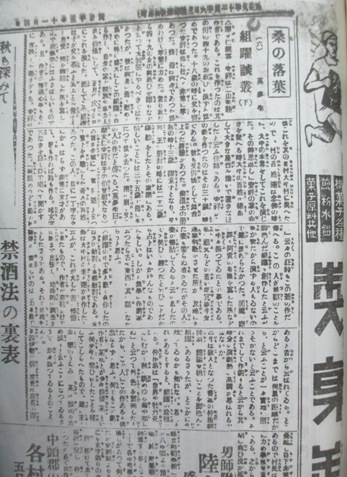
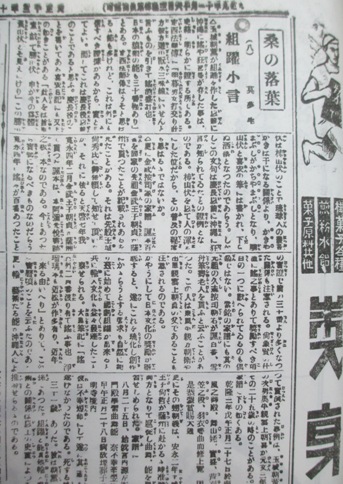
莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。
〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。
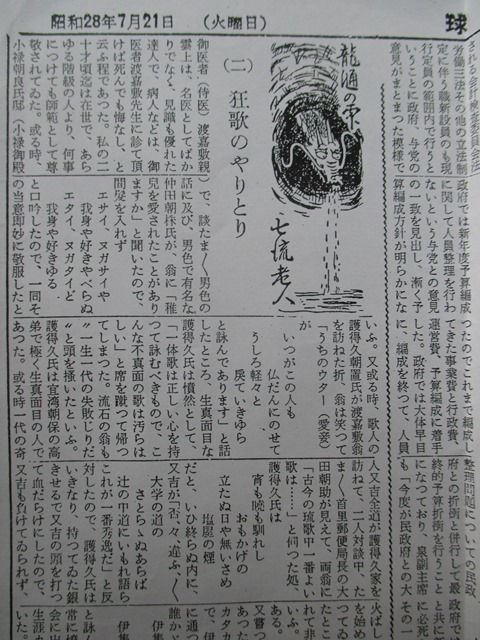
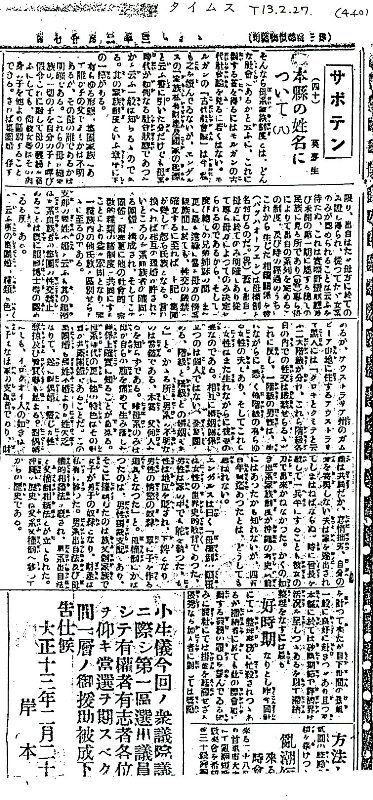
1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」
□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)
2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
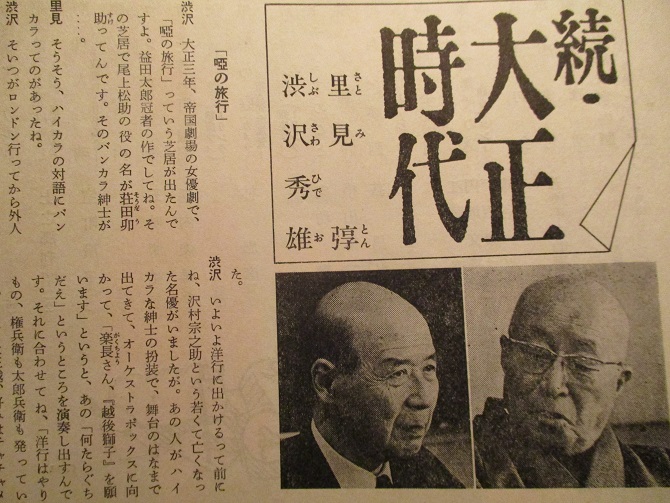
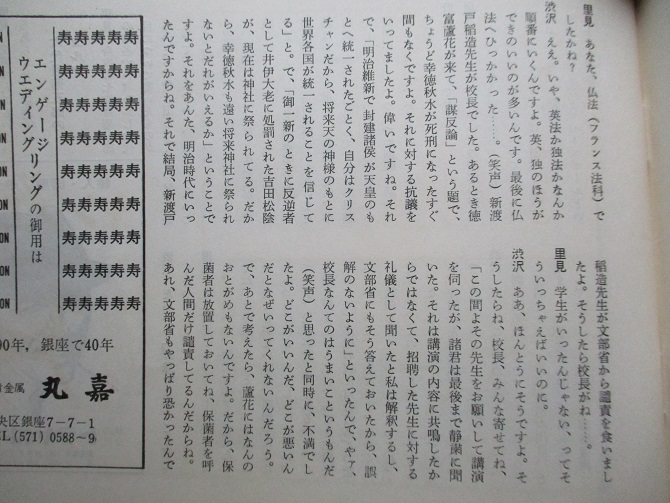
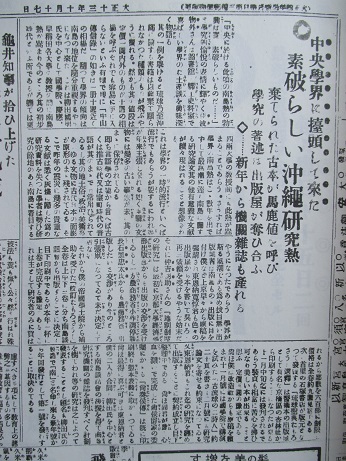
12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」
2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行
2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

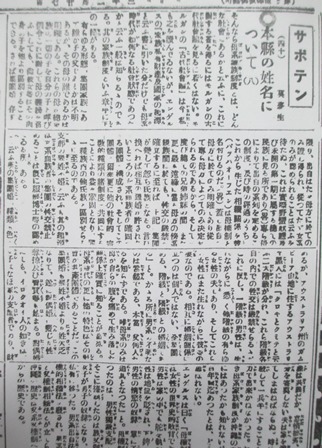
2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)
2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」
3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊
3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。
1924-3
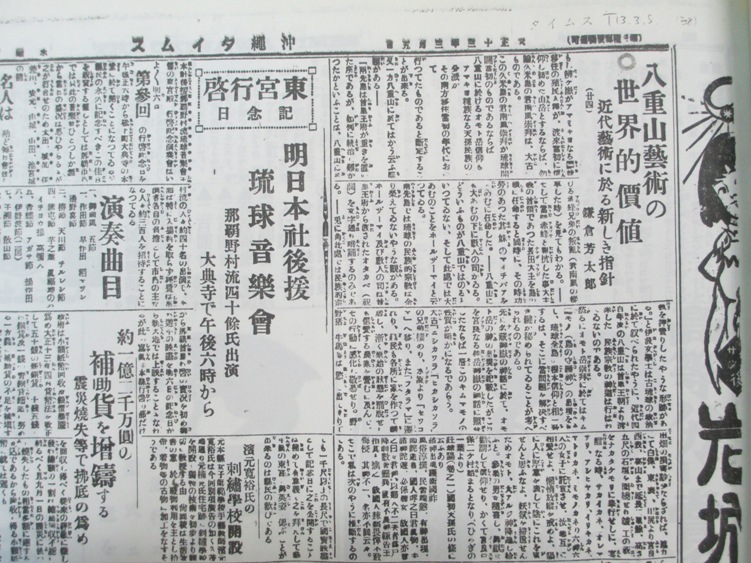
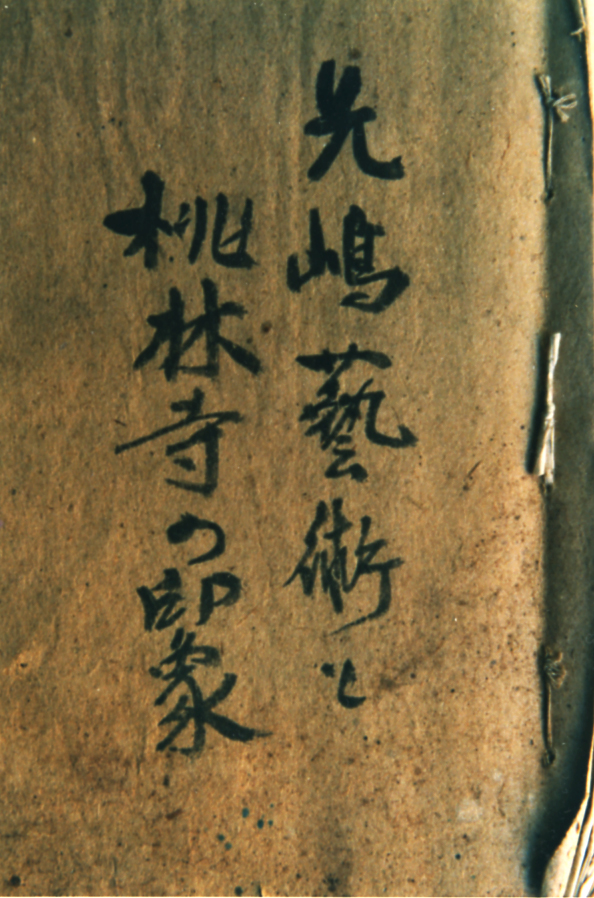 原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの
原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)
5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。
5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」
6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演
7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店
7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地
7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」
7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港
7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」
7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状
7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。
7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会
8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)
8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京
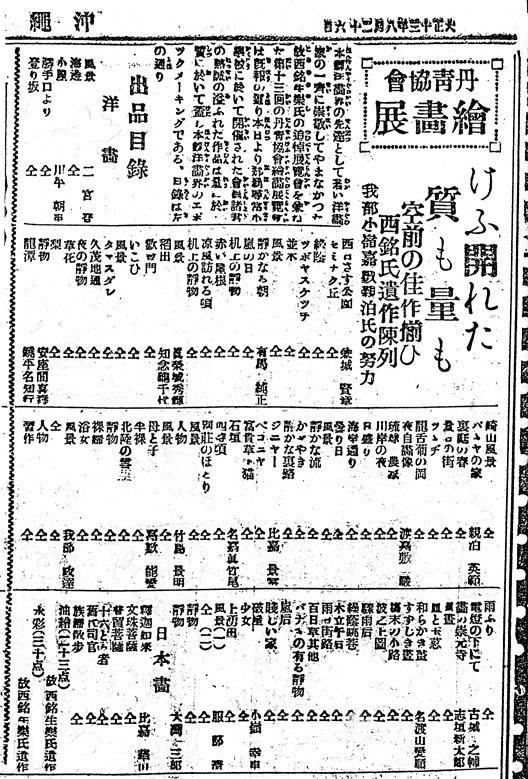
1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会
1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)
2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。
1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。
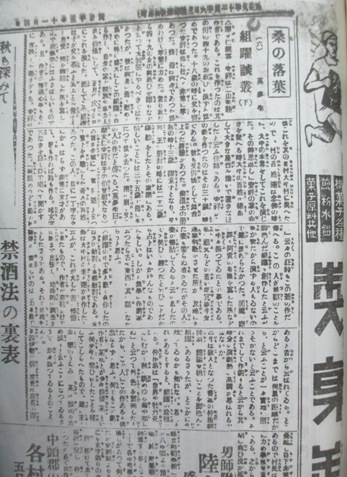
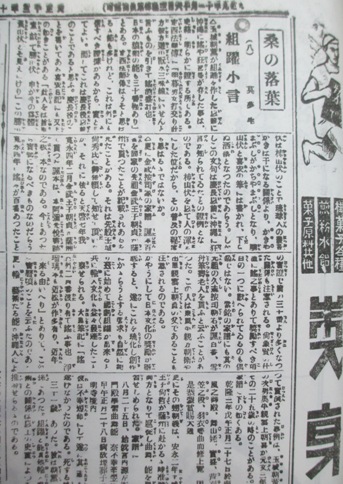
莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。
〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。
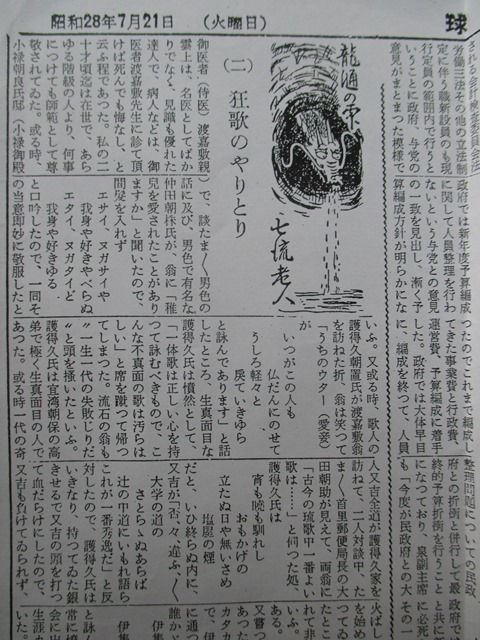
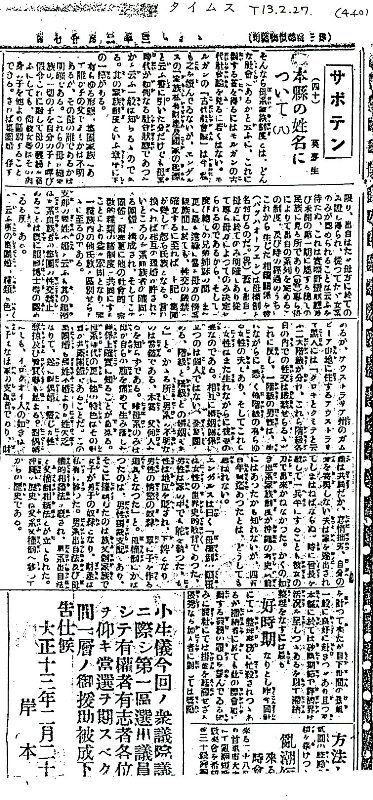
1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」
□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)
2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
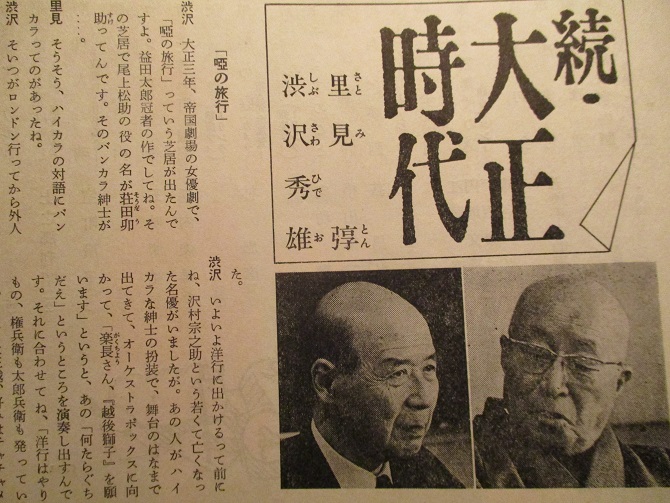
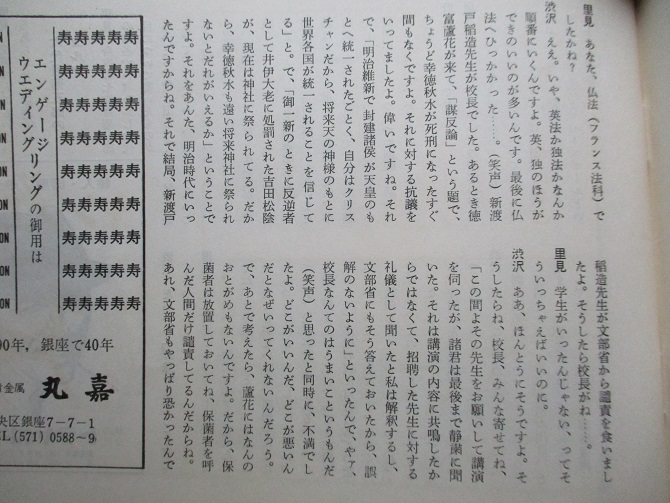
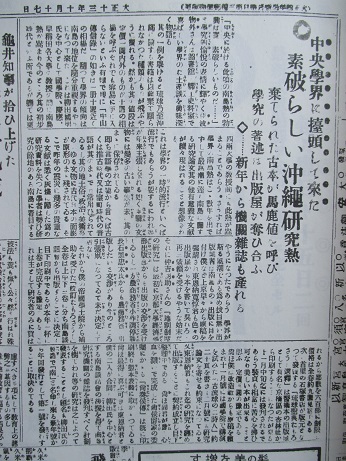
12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」
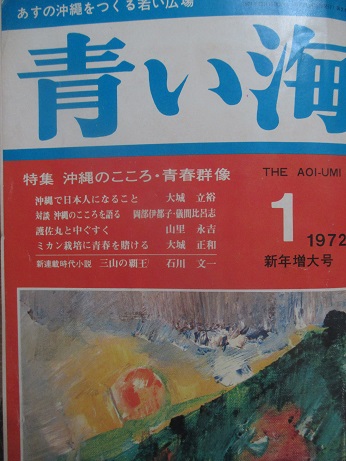

1972年1月 沖縄の雑誌『青い海』9号 山里永吉「沖縄の史跡 護佐丸と中ぐすく」
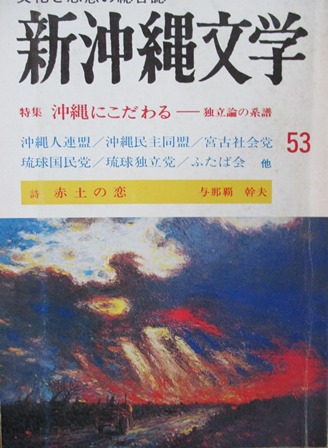

1982年(昭和57) 9月 「山里永吉瞥見」『新沖縄文学』第53号 沖縄タイムス社
【内容】 石鼓 教科書問題の本質 (特集)沖縄にこだわる -独立論の系譜 独立論の位相 川満信一著. 沖縄人連盟 新崎盛暉著.沖縄民主同盟 仲宗根勇著. 宮古社会党 平良好児著. 不発の独立論 大田静男著. 琉球国民党 島袋邦著. 琉球独立党 平良良昭著. ふたば会 太田良博著. 琉球巴邦・永世中立国構想の挫折 仲程昌徳著. 山里永吉暼見 岡本恵徳著.コラム 帰属問題めぐり街の声を聴く/ /反映させよ住民の希望 沖縄自立・独立論関係図書目録 潮流 私学問題と官尊民卑(教育) 「一坪反戦地主会」の発足(住民運動) 多様化する反戦運動(社会) 検定に対する検定を(文化) 沖縄史そぞろある記(10) 嘉手納宗徳著. 動物の鳴き声 儀間進著. 日本人の沖縄人像 親泊寛信著. 琉球の地頭性(3) 宮城栄昌著. 海外ジャーナル 話題ふたつ(アメリカ) 宮城悦二郎著. 新聞とのつきあい(フランス) 大下祥枝著. 香港の漁村にて(東南アジア) 比嘉政夫著. 書評 「地図の風景」 「蝶の島」 「聞書西表炭坑」 「ある二世の轍」 「石扇回想録」 「ふるさとばんざい」 「沖縄の悲哭」 「瞳詩篇」「芝憲子詩集」 「沖縄-戦争と平和」 「沖縄の戦記」 「対馬丸」 「句集琉球切手」 「わが沖縄ノート」 「琉球文学小見」 「琉球の言語と文化」 「沖縄行政機構変遷史料」 「生贄は今」 「沖縄資料センター目録」 第8回「新沖縄文学賞」予選発表 詩 赤土の恋 与那覇幹夫著※与那覇幹男1939年11月26日~2020年1月20日。『赤土の恋』で1983年、第七回山之口貘賞。与那嶺さんは新報でよく出会ったが、2019年に初めての長い電話をくれた。お別れのつもりだっただろう。晶子夫人から僕のことを聞いていたからであろうか。亡くなられたのを知ったのは森口豁さんのFacebook2020-9であった。
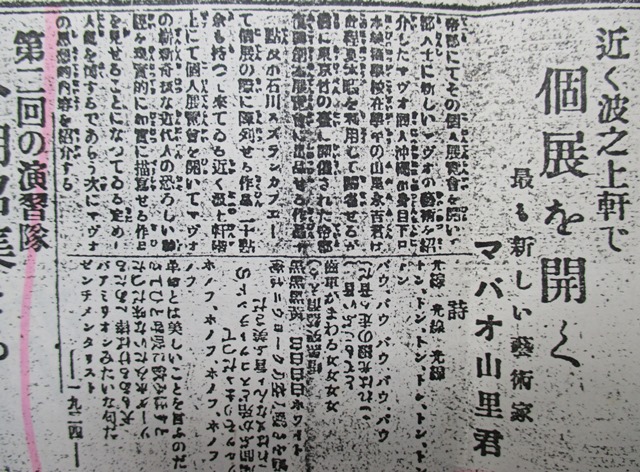
1924年7月18日『沖縄タイムス』
山里永吉が1924年、那覇の波之上軒で開いた個展には「村山知義によって踊られたるワルツ」「インペコーフェンの踊り」もあった。山里永吉自伝□東京では『マヴォ』の雑誌が発売禁止になり、同人は全員、警察の身元調査を受けていて、警視庁からの連絡で私の家にも那覇署員がやってきた。息子の身元調査に親父はびっくりしたらしい。幸い私はその時東京に帰っており行きちがいであった。そんなことがあって親父は東京にいた山田真山先生へ手紙を出し息子を預かってくれと依頼した。真山先生は那覇で展覧会を開いたとき、私の家に泊まっていたので父とは旧知の間柄だった。早速、使いがきて、私は荻窪の先生の家へ引き取られ、お預けの身になった。一年そこら御世話になったが、父が死んで、東京にいてもつまらないので、沖縄へ引き揚げた。昭和2年4月のことである。
1926年9月 『沖縄教育』156号 山里永吉「小説ゆめ」
1933年5月 『沖縄教育』201号 山里永吉「明治神宮壁画『琉球藩設置』」
大火で辻にあった貸家は全部まる焼け、保険金は一文もかけていない。それで父は農工銀行を辞めて生前、漆器店(丸山漆器店ー那覇市上ノ蔵町・電話441番)を始めており、兄貴は勧業銀行の那覇支店に勤めて高給をとっているので辞めようとしない。「お前店番をしろ」というわけで東京から帰った私に申しつけたが、私はそういう仕事は向かない。店のことはいい加減にして、脚本や評論などを新聞に発表したりしていた。

丸山漆器
それからしばらくして伊良波尹吉、真境名由康、島袋光裕の俳優3人が、顔をそろえてやってきて「芝居の脚本を書いてくれ」と懇請された。沖縄芝居はそのころ衰退気味で、新聞を読むほどの人なら芝居を見にいかない。「これじゃ、どうにもならん、ひとつ協力してくれ」と持ちかけてきたものである。最初に書いたのが「一向宗法難記」だった。2作目が「首里城明け渡し」で大当たりに当たった。
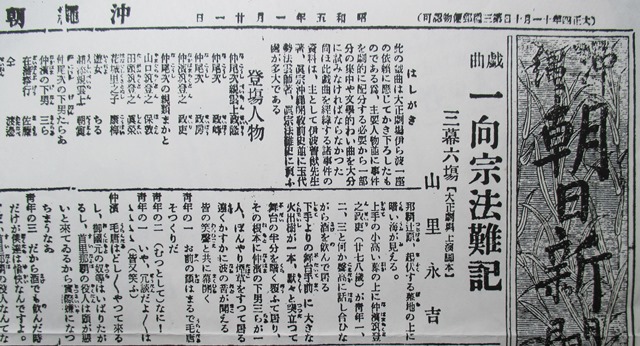
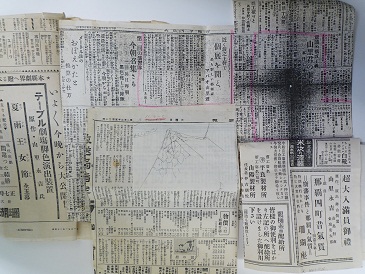
.jpg)
1960年3月30日ー崇元寺調査、黒板、杢、中央の顔が隠れているのが山里永吉
□1960年3月28日ー琉球文化財保護のため文部省文保委会「第一次琉球文化財調査団」の黒板昌夫調査官、杢正夫技官が来沖。
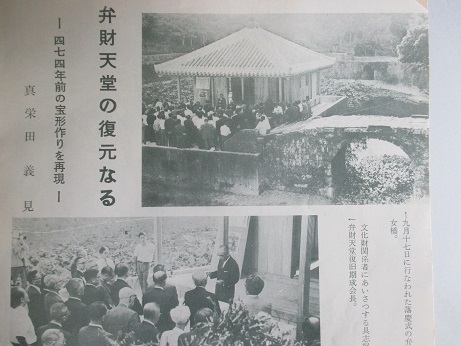
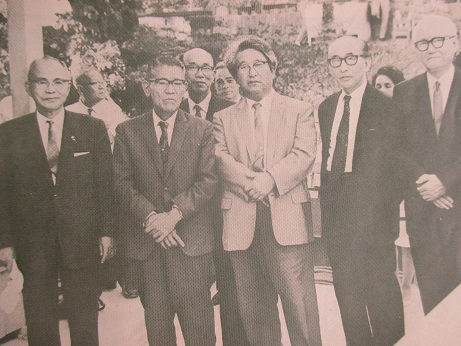
写真左から具志堅宗精復旧期成会長、真栄田義見、川平朝申、不詳、山里永吉
1968年11月『今日の琉球』真栄田義見「弁財天堂の復元なるー474年前の宝形作りを再現」
1971年1月6日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー中央集権とも関連 半世紀の内乱にこりる」<上>
1971年1月7日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー撤廃は歴史家の定説 『反戦平和』の思想思い起こせ」<下>
□1972年9月ー『佛教藝術』88<沖縄の文化と美術特集> 毎日新聞社
沖縄の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新屋敷幸繁
沖縄文化史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉 春潮
沖縄の宗教・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・源 武雄
おもろ十首・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外間 守善
沖縄の梵鐘と金石文・・・・・・・・・・・・・外間 正幸
琉球漆器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡田 譲
沖縄の陶芸史・・・・・・・・・・・・・・・・・・山里 永吉
琉球紅型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鎌倉芳太郎
沖縄の舞踊と楽器・・・・・・・・・・・・・・・仲井真元楷
琉球の建築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田辺 泰
沖縄文化財建造物等の復旧事業・・・杢 正夫
口絵解説・殷元良筆「鶉図」・・・・・・・・真保 亨
沖縄の重要文化財

1960年6月6日 伊野波節石くびれ 左より池宮喜輝、国吉真哲(山里永吉文化財保護委員長・撮影)
.jpg)
石くびりと山里永吉

1989年5月8日『琉球新報』川平朝申「山里永吉氏の逝去を悼む」
1989年5月8日『沖縄タイムス』船越義彰「追悼ー那覇人に徹した山里氏」
04/08: 新城栄徳「琉球文化史散歩」②
1929(昭和4)年
『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」
□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」
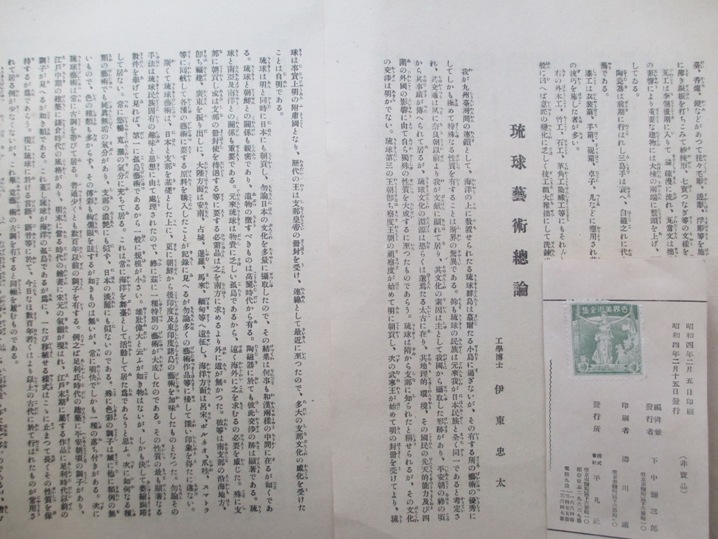
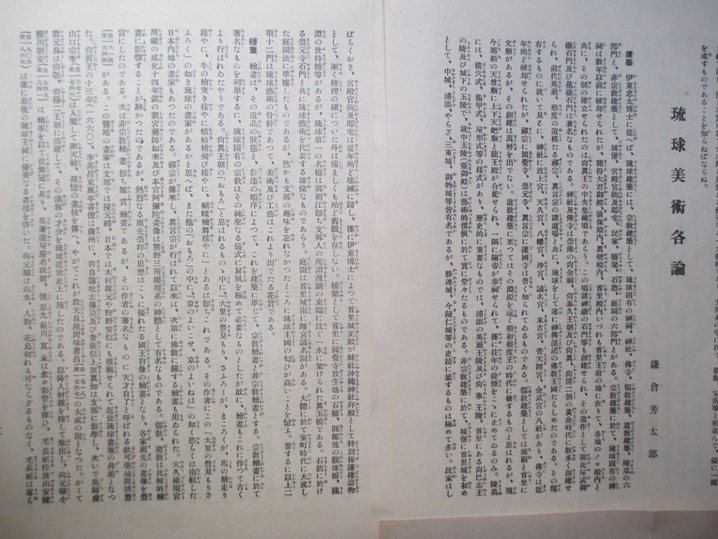
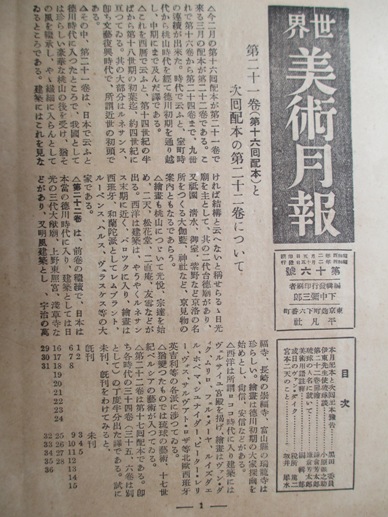
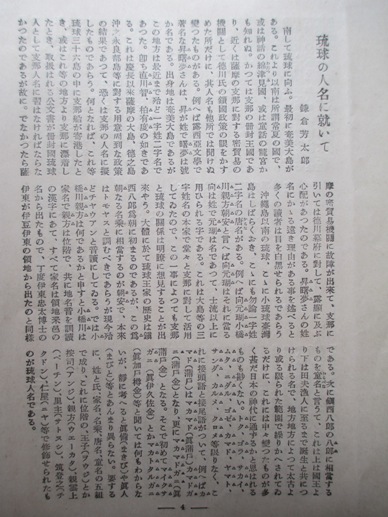
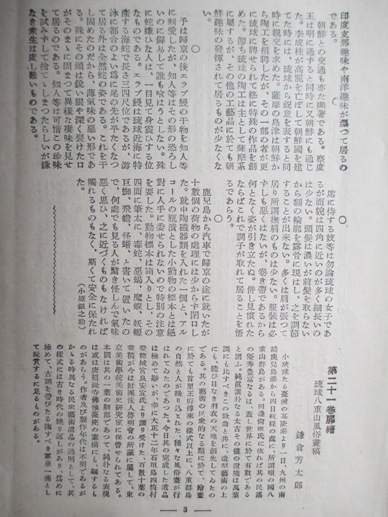
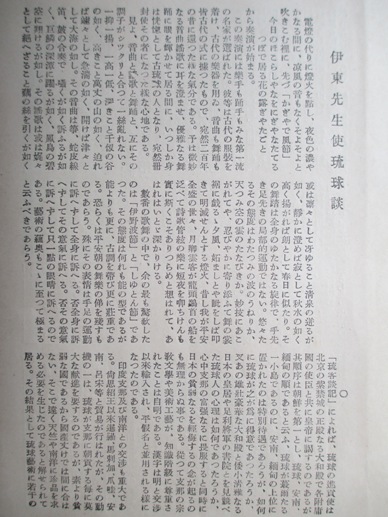
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)
1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社
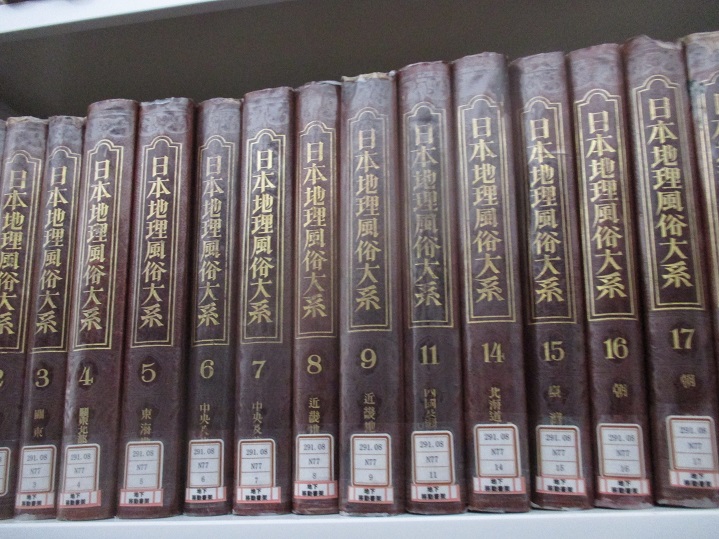
沖縄大学図書館所蔵

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社



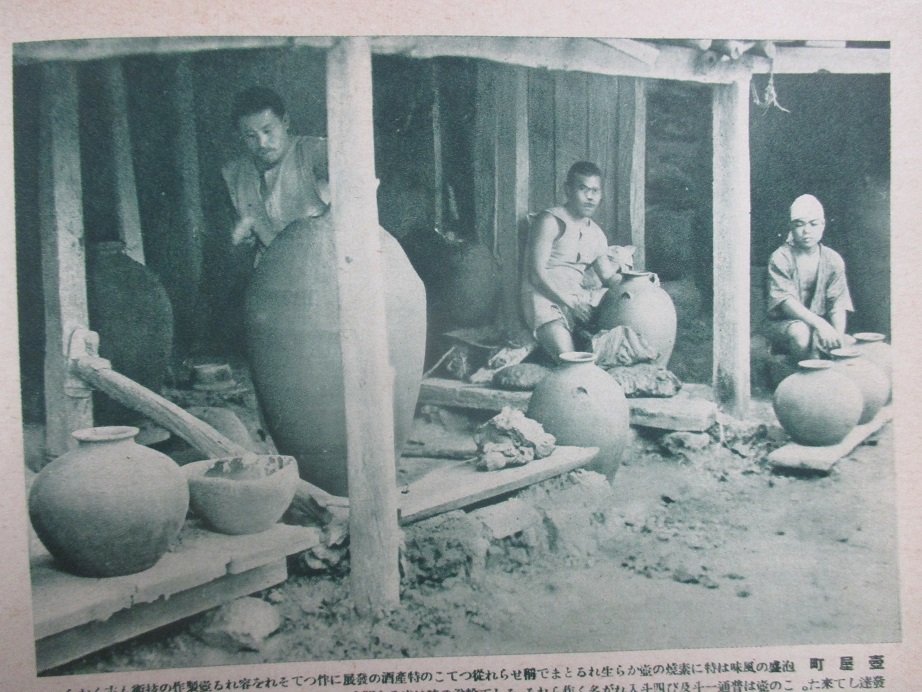


目次
琉球列島ー概説
地形ー列島と海溝/三列の地質構成/珊瑚礁の発達/古生層と珊瑚礁/宮古諸島と八重山諸島
気候と生物ー気温/降水量と風速/季節風/ハブとマングース/亜熱帯性植物
沿革ー開闢伝説/内地との交通/支那との交渉/明治以後
生産ー概説
甘蔗糖/水産物/甘蔗/穀物/林産物/牧場/その他の生産物
薩南諸島ー大隅諸島/土噶喇諸島/大島諸島/島の産物/大島の気温
沖縄諸島ー沖縄島/国頭山岳地域/中頭、島尻丘陵地域/那覇首里の都会地域/人口の減少/属島/大東諸島/先島諸島/八重山群島/尖閣諸島
琉球婦人の黥ー伝説に現れた起原/古文書中の入墨/記事の有無/他島との比較/その宗教的意義
墓ー風葬の俗/古代と風葬/墓の発達/その中間物/板が門/近代式墳墓/その起原
グラヴィアー守礼門/首里附近の聚落状態/奥武山公園/首里附近の民家/野生の蘇鉄/沖縄県庁/沖縄測候所/測候所附近より那覇を望む/天水甕/ハブの毒素採集/ハブ捕り/ハブ/芭蕉の花の咲く頃/辨岳の御願所/識名園の泉水/首里城の正殿/亀甲形の墳墓/尚家の門/波上神社と石筍崖/真玉橋の風光/護国寺の仁王門/聖廟/護国寺境内/末吉神社/辨財天堂と観蓮橋/ベッテルハイム記念碑/識名園/琉球の刳舟/爬龍船競漕図/琉球の甘蔗畑/盆の甘蔗市/農家の製糖小屋/パナマ帽の制作
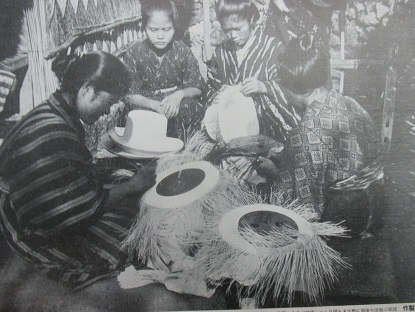
蘇鉄林/パパイヤの樹/辻町の遊女/機を巻く首里の婦人/屋久の杉森/杉の巨木/大島の闘牛/シャリンパイ/大島名瀬港/大島紬工場/奄美大島の蘇鉄林/奄美大島の百合園/那覇港の入口/那覇港第一桟橋/先原崎の灯台/波上神社の石段/首里市内の民屋/那覇市全景/琉球美人
屋上の唐獅子/壺屋町/壺作り/泥藍の紺屋/藍の香高い琉球絣/泡盛製造所/諸味貯蔵場/豚肉販売所/甘蔗売の集り/独特の武術唐手/郷土スポーツ唐手/ズリ馬行列/歓会門/円覚寺本殿/龍潭池附近/円覚寺境内放生池橋/琉球の民家/那覇市附近の露店/那覇旧市街/崇元寺の門/那覇一の商店街/那覇辻遊廓/真玉橋の石橋/沖縄測候所/円覚寺の山門/熱帯植物榕樹/漁村糸満の浜/名物朱塗りの漆器/芭蕉の実り/萬歳舞踊/舞踊/婦人の黥/綱曳遊戯/湧田の旗頭/壮麗な旗頭/浜の賑ひ/野国総官の墓/久志村の山中にあった墓/久高島の墓/破風式の墓/亀の子式の墓/墓と死者の交会/墳墓のストリート/墓のにぎはい/玉陵/墓の平面図/壺屋産の霊置甕/英祖陵
守礼門がカラーで載っている。この本を1987年に安良城盛昭(大阪府立大学教授)氏が沖縄県立博物館に寄贈された。氏のものは父盛英が東京で教師をしていたとき購入したもので氏も愛読し親しんできたものであった。□1929年2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」
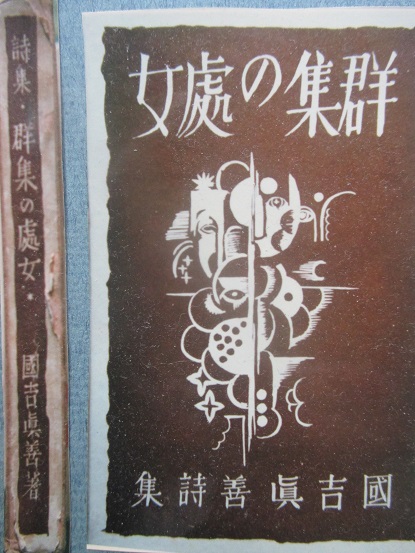
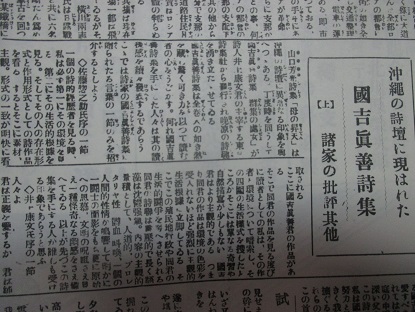
1930年5月 国吉真善『群衆の処女』
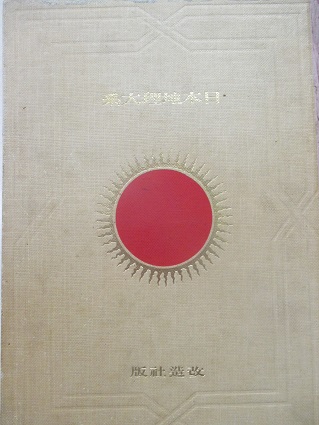
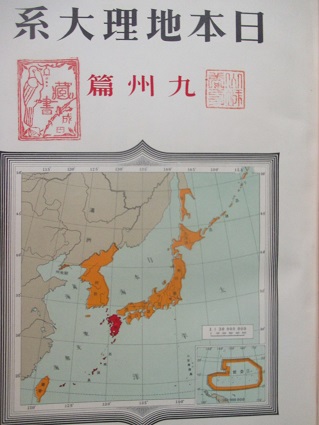
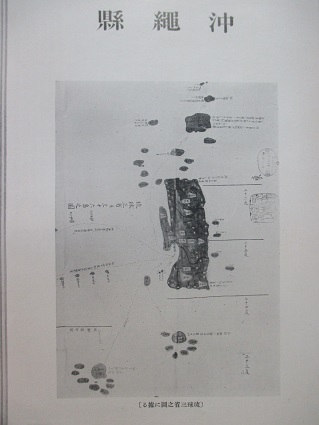
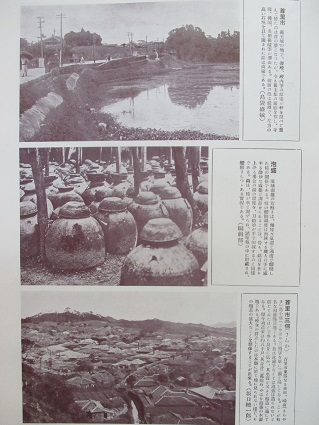
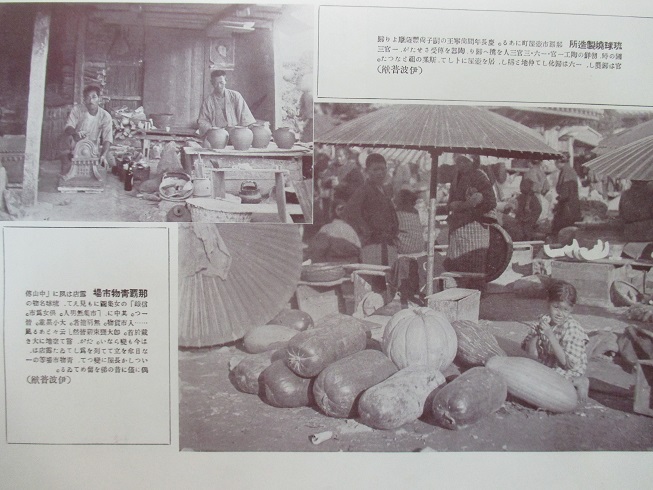
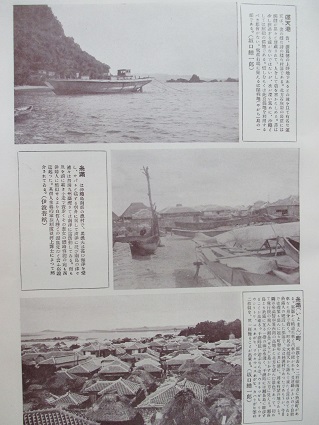
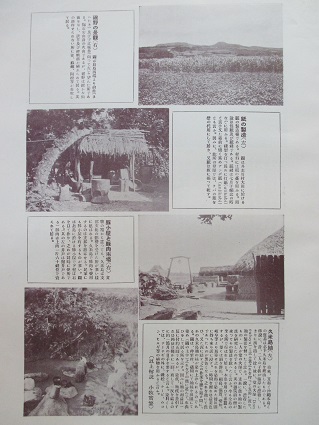
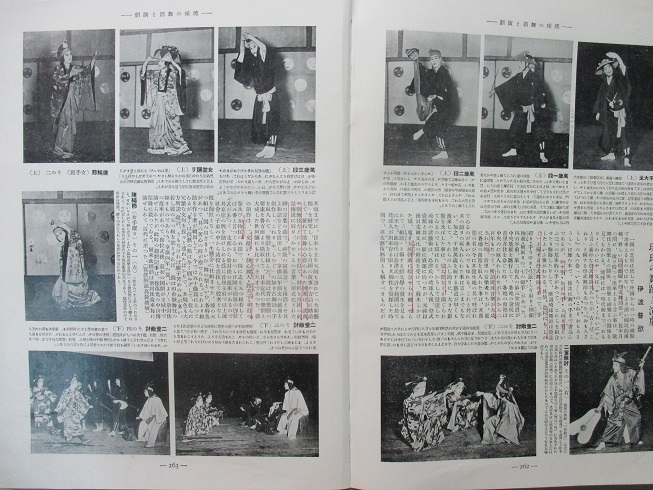
1930年8月 改造社『日本地理大系・九州篇 沖縄県』
目次
沖縄県扉「古地図」
沖縄県概説
ダブルトーン版ー筆架山より見たる那覇港 那覇市街/隆起珊瑚礁と波上神社/琉球焼製造所 那覇青物市場/おてんだの水取舟 崇元寺/金石文と真玉橋/守礼門 歓会門 首里城正殿/首里市 泡盛 首里三個/識名園 首里市/運天港 糸満 糸満町/パパヤ売 金武大川/七島藺の刈取 砂糖の製造 八重山鰹節製造所/久米島(新村 支那式の家屋 久米島の男女 久米島具志川村 仲村渠)/久米島(裾野の景観 紙の製造 豚小屋と豚肉市場 久米島紬)/琉球の墳墓/那覇市郊外の墓 国主より功臣に賜りたる御拝領の墓/田舎の墓 首里郊外貴族の墓/ヤツチのがま 石垣島より竹富島を望む屋我地ヲフルギの純林 甘蔗の栽培 ガジュマル/琉球の舞踊と演劇ー波平大主 萬歳一段 同二段 同三段 女笠踊 諸純節 二童敵討 同二 同三 同四/琉球の年中行事ー八重山の民族舞踊 祭式舞踊 那覇市の綱引行列
綜合解説
1930年8月5日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(1)凡そ神秘的な共産の久高島 島民総出で原始的な出迎 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月6日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(2)凡そ神秘的な共産の久高島 島の由来記と名所旧蹟 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月7日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(3)凡そ神秘的な共産の久高島 原始共産制の名残を観る 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月8日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(4)どこ探しても無い久高島の奇習 珍しい風葬と婦人の貞操試験 『グショウ』見物の巻」
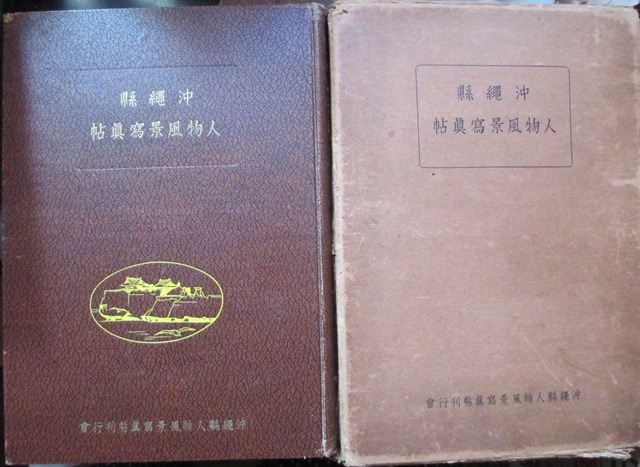

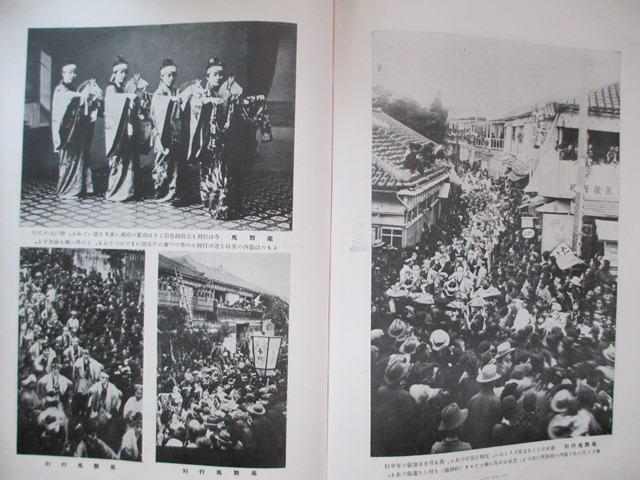
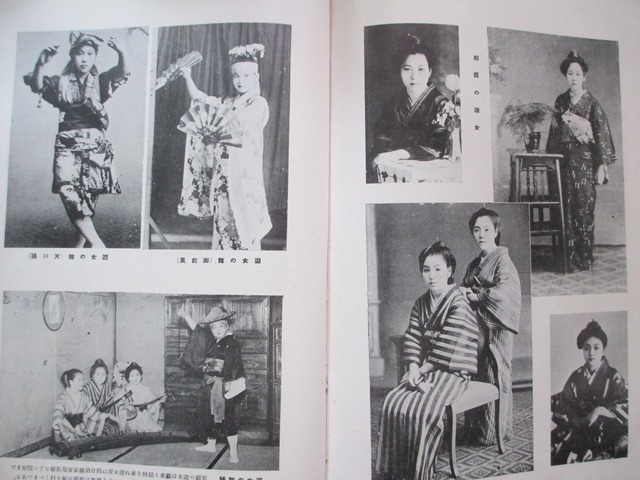
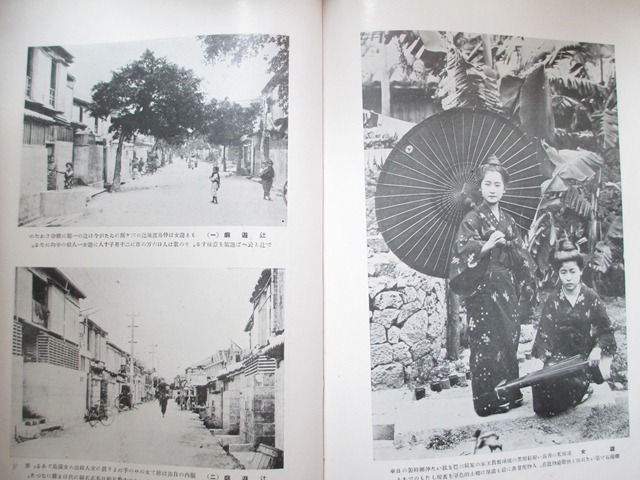
1933年7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』
1934年4月17日『琉球新報』広告□那覇市東町 明視堂写真部ー佐和九郎『正則写真術』『密着と引伸』『現像の実際』『露出の秘訣』『整色写真の研究』『整色写真術』/三宅克巳『写真随筆 籠の中より』『写真のうつし方』『私の写真』『趣味の写真術』/高桑勝雄『フイルム写真術』『写真術五十講』『写真問答』/宇高久敬『写真の新技法』/霜田静志『写真の構図』/南實『原板の手入』/加藤直三郎『中級写真術』/石田喜一郎『プロモイル印画法』/小池晩人『山岳写真の研究』/金丸重嶺『新興写真の作り方』、金丸重嶺・鈴木八郎『商業写真術』/勝田康雄『人物写真のうつし方』/中島謙吉『芸術写真の知識』/吉川速男『写真術の第一歩』『小形カメラの第一歩』『図解写真術初歩』『私のライカ』『十六ミリの第一歩』/鈴木八郎『写真の失敗と其原因』『写真処方集』『整色写真のうつし方』『引伸の実際』/中戸川秀一『写真百科辞典』/寺岡徳二『印画修整の実際』/斎藤こう兒『撮影第一課』『引伸写真の作り方』『芸術写真の作り方』/額田敏『山岳写真のうつし方』/眞継不二夫『芸術写真作画の実際』『アマチュア写真の修整』/山崎悦三郎『修整の実際』/高山正隆『芸術写真入門』『ベストコダック写真術』/石動弘『小形活動フイルム現像法』
1934年5月5日『大阪朝日新聞 九州朝日』「外人の眼に映じた”ハブの國„ クルート女史の興味を晙る視察談」
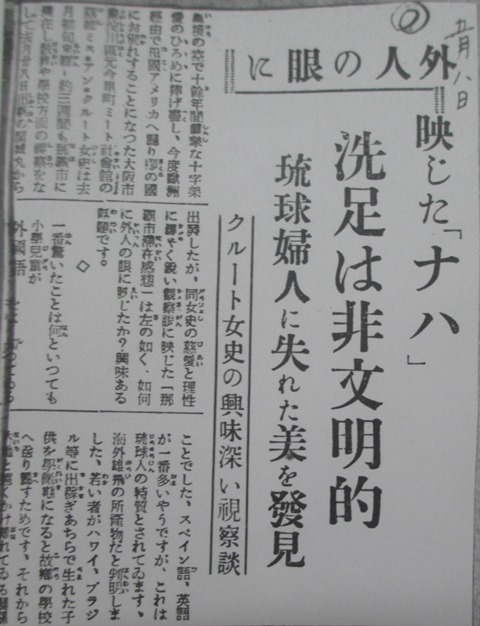

1934年5月8日『琉球新報』?
4月、欧州経由でアメリカに帰途、来沖したミス・アン・クルート(大阪東淀川区ミード社会館)が新聞記者に「那覇の児童がスペイン語、英語を知っているのに驚いた、これは海外雄飛の諸産物で若い者がハワイ・ブラジルらに出稼ぎ、そこで生まれた子を故郷沖縄の学校に送り帰すためです」と答える。
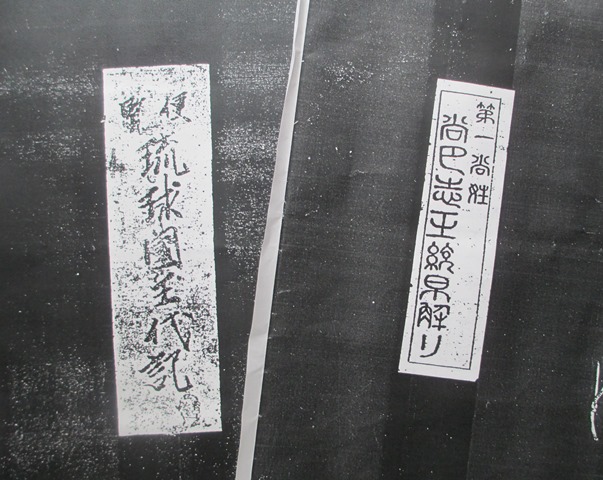
1934年11月 神村朝儀『便覧 琉球國王代記』神村朝忠/1937年3月 神村朝儀『第一尚姓 尚巴志王統早分解り』神村朝忠薬店
○雑誌『おきなわ』復刻版解説に酒井直子さんが「回想ー父 神村朝堅」を書かれていて、「向氏神村家家系図」も添えられていた。13世 朝睦の子供たちが省略されていたので詳しく記入してもらった。その結果、上記の著者・朝儀は叔父で、発行人の朝忠は朝堅氏の父と判明した。
『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」
□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」
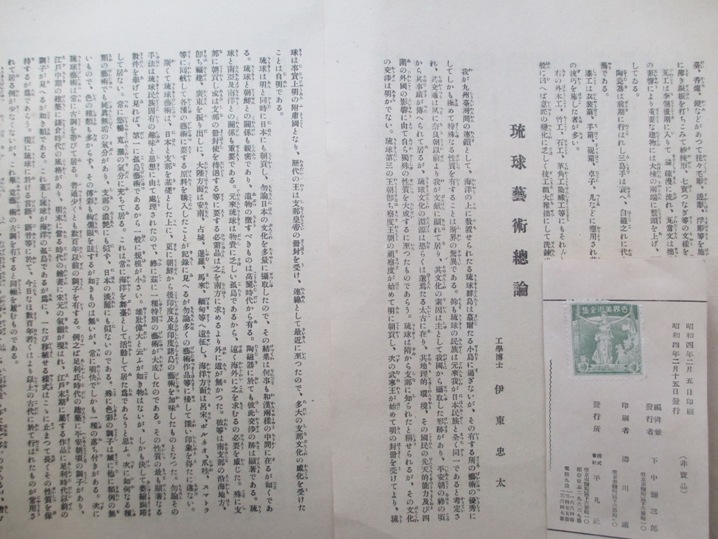
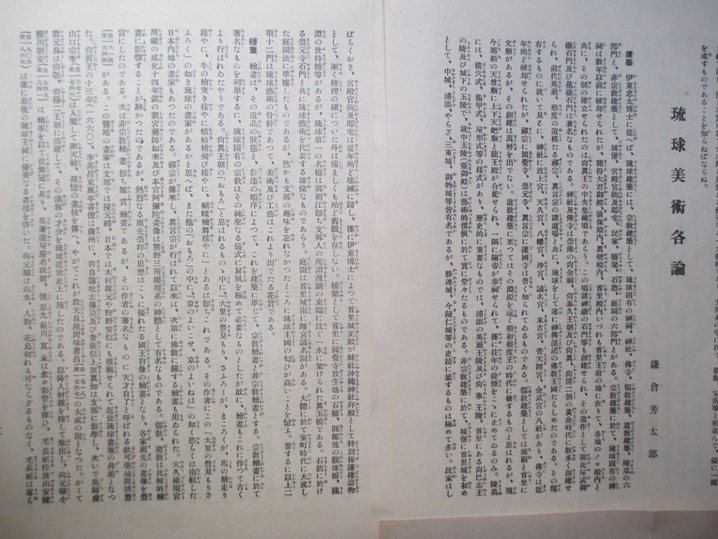
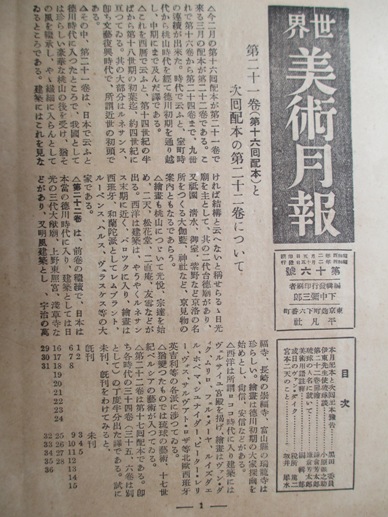
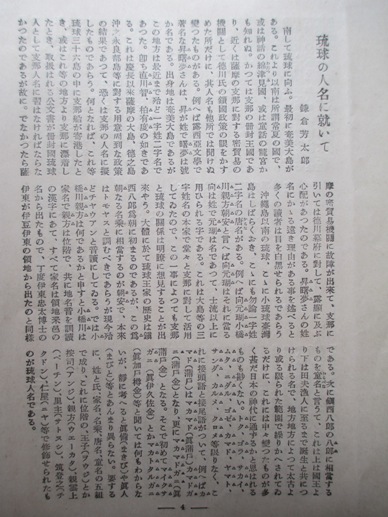
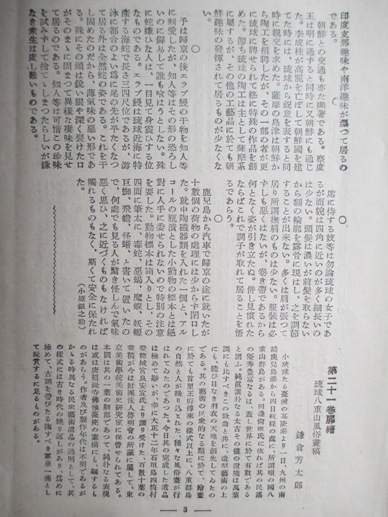
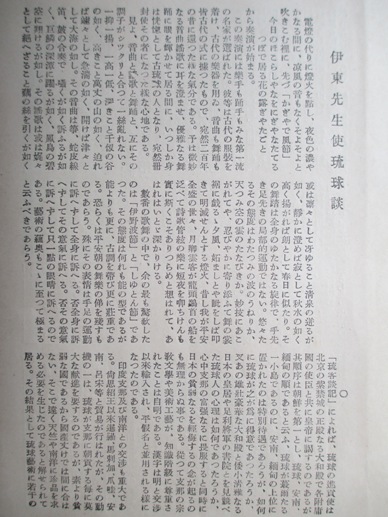
2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)
1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社
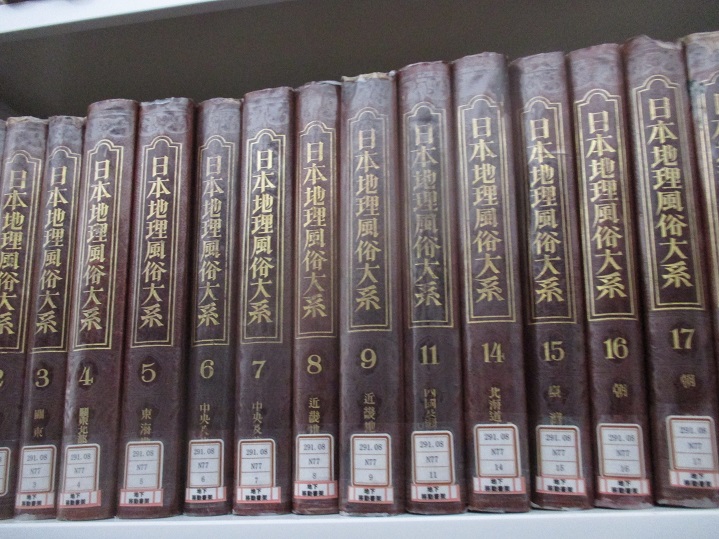
沖縄大学図書館所蔵

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社



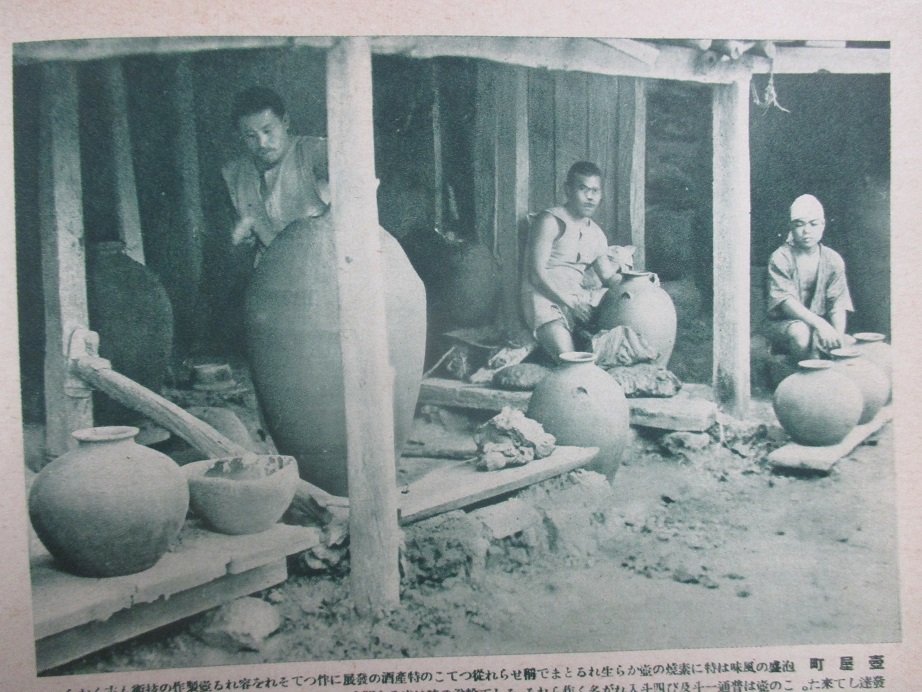


目次
琉球列島ー概説
地形ー列島と海溝/三列の地質構成/珊瑚礁の発達/古生層と珊瑚礁/宮古諸島と八重山諸島
気候と生物ー気温/降水量と風速/季節風/ハブとマングース/亜熱帯性植物
沿革ー開闢伝説/内地との交通/支那との交渉/明治以後
生産ー概説
甘蔗糖/水産物/甘蔗/穀物/林産物/牧場/その他の生産物
薩南諸島ー大隅諸島/土噶喇諸島/大島諸島/島の産物/大島の気温
沖縄諸島ー沖縄島/国頭山岳地域/中頭、島尻丘陵地域/那覇首里の都会地域/人口の減少/属島/大東諸島/先島諸島/八重山群島/尖閣諸島
琉球婦人の黥ー伝説に現れた起原/古文書中の入墨/記事の有無/他島との比較/その宗教的意義
墓ー風葬の俗/古代と風葬/墓の発達/その中間物/板が門/近代式墳墓/その起原
グラヴィアー守礼門/首里附近の聚落状態/奥武山公園/首里附近の民家/野生の蘇鉄/沖縄県庁/沖縄測候所/測候所附近より那覇を望む/天水甕/ハブの毒素採集/ハブ捕り/ハブ/芭蕉の花の咲く頃/辨岳の御願所/識名園の泉水/首里城の正殿/亀甲形の墳墓/尚家の門/波上神社と石筍崖/真玉橋の風光/護国寺の仁王門/聖廟/護国寺境内/末吉神社/辨財天堂と観蓮橋/ベッテルハイム記念碑/識名園/琉球の刳舟/爬龍船競漕図/琉球の甘蔗畑/盆の甘蔗市/農家の製糖小屋/パナマ帽の制作
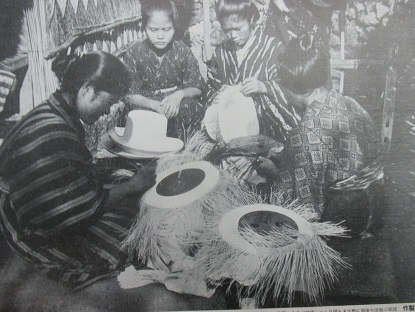
蘇鉄林/パパイヤの樹/辻町の遊女/機を巻く首里の婦人/屋久の杉森/杉の巨木/大島の闘牛/シャリンパイ/大島名瀬港/大島紬工場/奄美大島の蘇鉄林/奄美大島の百合園/那覇港の入口/那覇港第一桟橋/先原崎の灯台/波上神社の石段/首里市内の民屋/那覇市全景/琉球美人
屋上の唐獅子/壺屋町/壺作り/泥藍の紺屋/藍の香高い琉球絣/泡盛製造所/諸味貯蔵場/豚肉販売所/甘蔗売の集り/独特の武術唐手/郷土スポーツ唐手/ズリ馬行列/歓会門/円覚寺本殿/龍潭池附近/円覚寺境内放生池橋/琉球の民家/那覇市附近の露店/那覇旧市街/崇元寺の門/那覇一の商店街/那覇辻遊廓/真玉橋の石橋/沖縄測候所/円覚寺の山門/熱帯植物榕樹/漁村糸満の浜/名物朱塗りの漆器/芭蕉の実り/萬歳舞踊/舞踊/婦人の黥/綱曳遊戯/湧田の旗頭/壮麗な旗頭/浜の賑ひ/野国総官の墓/久志村の山中にあった墓/久高島の墓/破風式の墓/亀の子式の墓/墓と死者の交会/墳墓のストリート/墓のにぎはい/玉陵/墓の平面図/壺屋産の霊置甕/英祖陵
守礼門がカラーで載っている。この本を1987年に安良城盛昭(大阪府立大学教授)氏が沖縄県立博物館に寄贈された。氏のものは父盛英が東京で教師をしていたとき購入したもので氏も愛読し親しんできたものであった。□1929年2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」
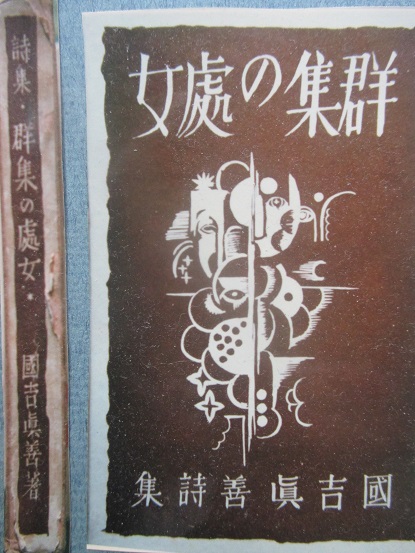
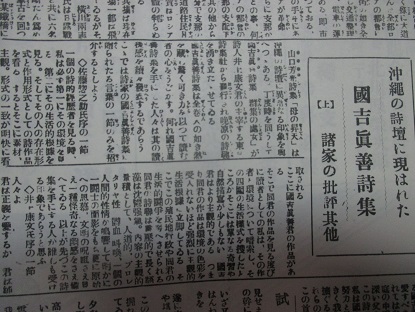
1930年5月 国吉真善『群衆の処女』
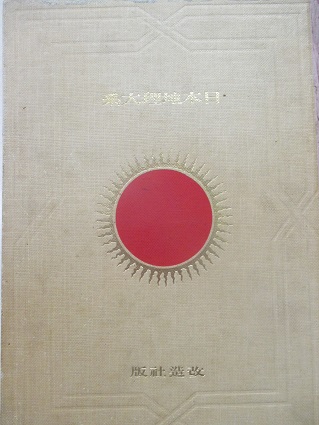
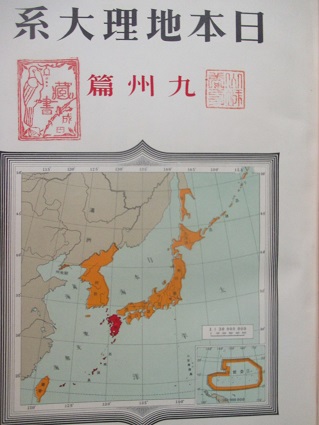
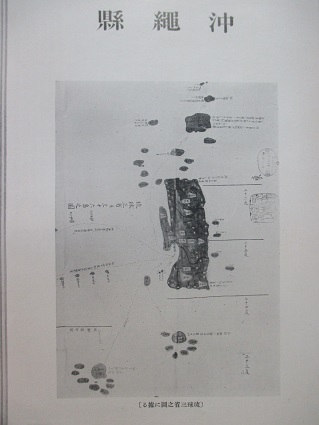
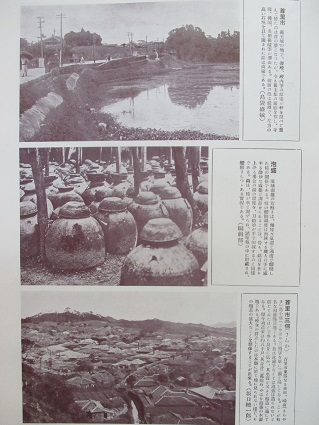
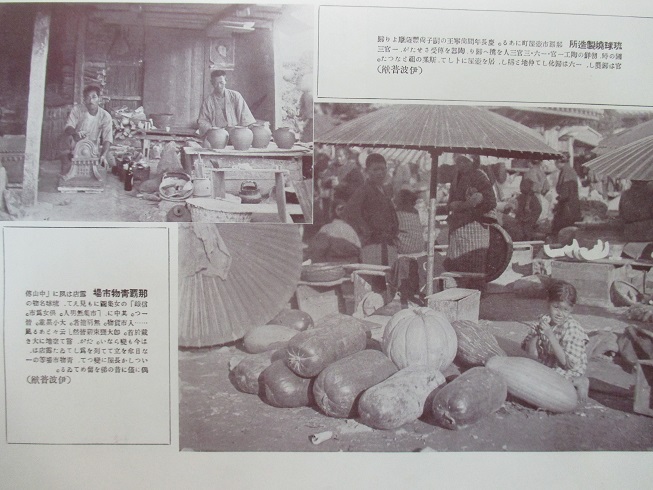
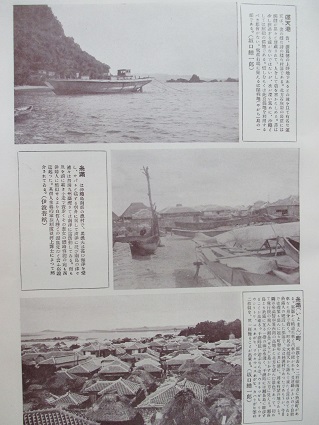
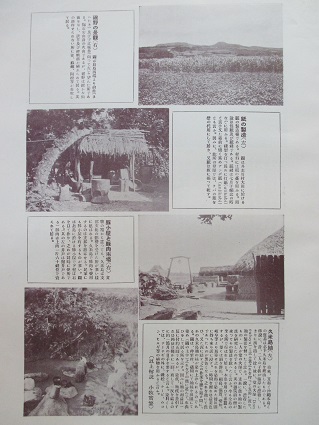
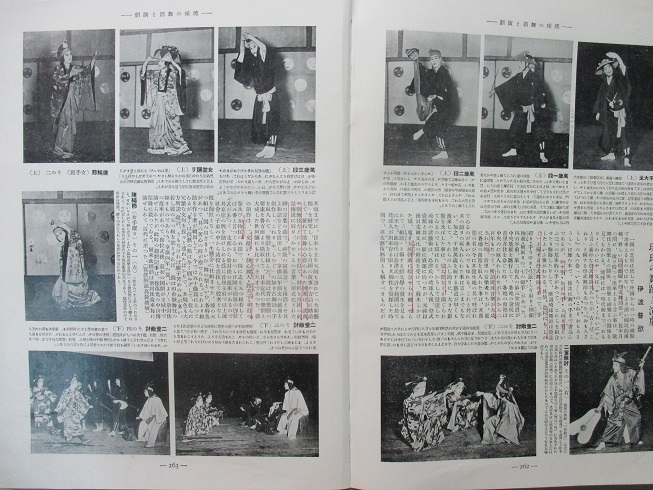
1930年8月 改造社『日本地理大系・九州篇 沖縄県』
目次
沖縄県扉「古地図」
沖縄県概説
ダブルトーン版ー筆架山より見たる那覇港 那覇市街/隆起珊瑚礁と波上神社/琉球焼製造所 那覇青物市場/おてんだの水取舟 崇元寺/金石文と真玉橋/守礼門 歓会門 首里城正殿/首里市 泡盛 首里三個/識名園 首里市/運天港 糸満 糸満町/パパヤ売 金武大川/七島藺の刈取 砂糖の製造 八重山鰹節製造所/久米島(新村 支那式の家屋 久米島の男女 久米島具志川村 仲村渠)/久米島(裾野の景観 紙の製造 豚小屋と豚肉市場 久米島紬)/琉球の墳墓/那覇市郊外の墓 国主より功臣に賜りたる御拝領の墓/田舎の墓 首里郊外貴族の墓/ヤツチのがま 石垣島より竹富島を望む屋我地ヲフルギの純林 甘蔗の栽培 ガジュマル/琉球の舞踊と演劇ー波平大主 萬歳一段 同二段 同三段 女笠踊 諸純節 二童敵討 同二 同三 同四/琉球の年中行事ー八重山の民族舞踊 祭式舞踊 那覇市の綱引行列
綜合解説
1930年8月5日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(1)凡そ神秘的な共産の久高島 島民総出で原始的な出迎 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月6日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(2)凡そ神秘的な共産の久高島 島の由来記と名所旧蹟 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月7日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(3)凡そ神秘的な共産の久高島 原始共産制の名残を観る 苦熱を忘れるローマンス」
1930年8月8日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(4)どこ探しても無い久高島の奇習 珍しい風葬と婦人の貞操試験 『グショウ』見物の巻」
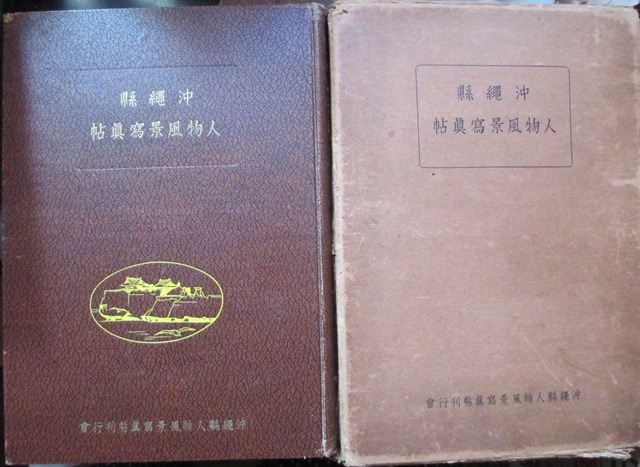

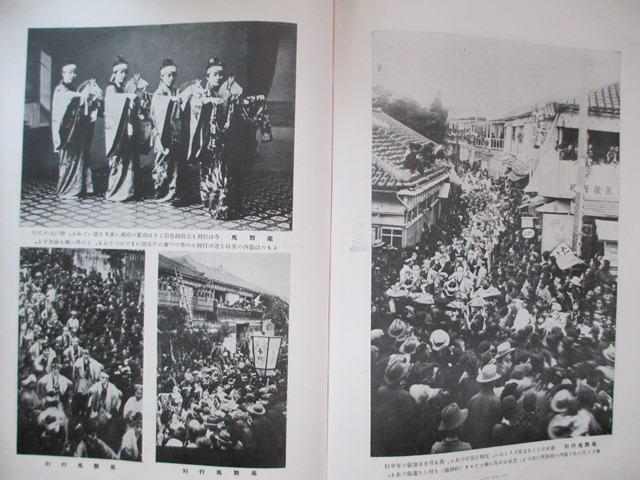
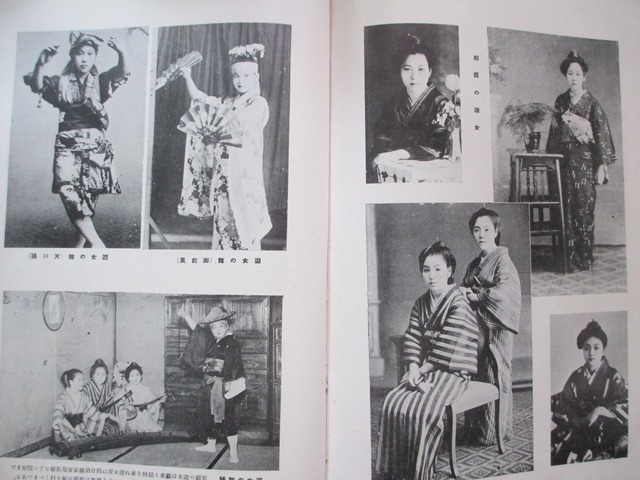
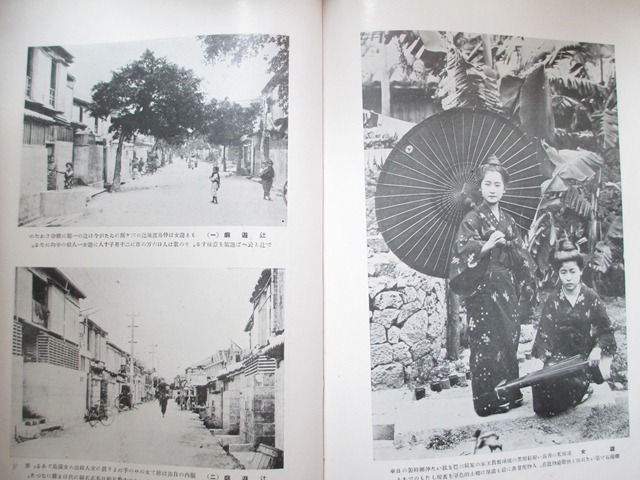
1933年7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』
1934年4月17日『琉球新報』広告□那覇市東町 明視堂写真部ー佐和九郎『正則写真術』『密着と引伸』『現像の実際』『露出の秘訣』『整色写真の研究』『整色写真術』/三宅克巳『写真随筆 籠の中より』『写真のうつし方』『私の写真』『趣味の写真術』/高桑勝雄『フイルム写真術』『写真術五十講』『写真問答』/宇高久敬『写真の新技法』/霜田静志『写真の構図』/南實『原板の手入』/加藤直三郎『中級写真術』/石田喜一郎『プロモイル印画法』/小池晩人『山岳写真の研究』/金丸重嶺『新興写真の作り方』、金丸重嶺・鈴木八郎『商業写真術』/勝田康雄『人物写真のうつし方』/中島謙吉『芸術写真の知識』/吉川速男『写真術の第一歩』『小形カメラの第一歩』『図解写真術初歩』『私のライカ』『十六ミリの第一歩』/鈴木八郎『写真の失敗と其原因』『写真処方集』『整色写真のうつし方』『引伸の実際』/中戸川秀一『写真百科辞典』/寺岡徳二『印画修整の実際』/斎藤こう兒『撮影第一課』『引伸写真の作り方』『芸術写真の作り方』/額田敏『山岳写真のうつし方』/眞継不二夫『芸術写真作画の実際』『アマチュア写真の修整』/山崎悦三郎『修整の実際』/高山正隆『芸術写真入門』『ベストコダック写真術』/石動弘『小形活動フイルム現像法』
1934年5月5日『大阪朝日新聞 九州朝日』「外人の眼に映じた”ハブの國„ クルート女史の興味を晙る視察談」
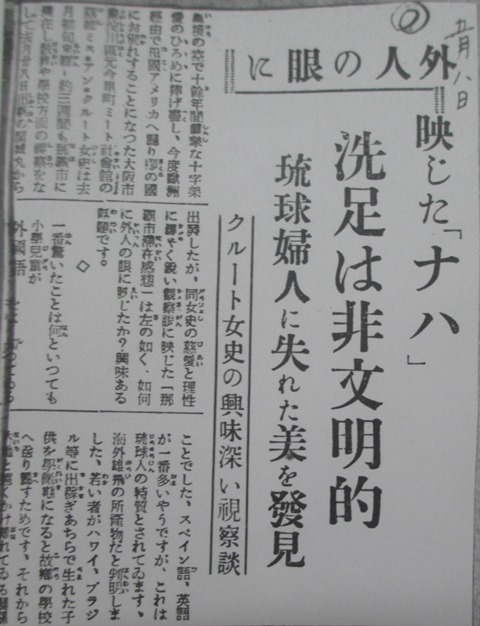

1934年5月8日『琉球新報』?
4月、欧州経由でアメリカに帰途、来沖したミス・アン・クルート(大阪東淀川区ミード社会館)が新聞記者に「那覇の児童がスペイン語、英語を知っているのに驚いた、これは海外雄飛の諸産物で若い者がハワイ・ブラジルらに出稼ぎ、そこで生まれた子を故郷沖縄の学校に送り帰すためです」と答える。
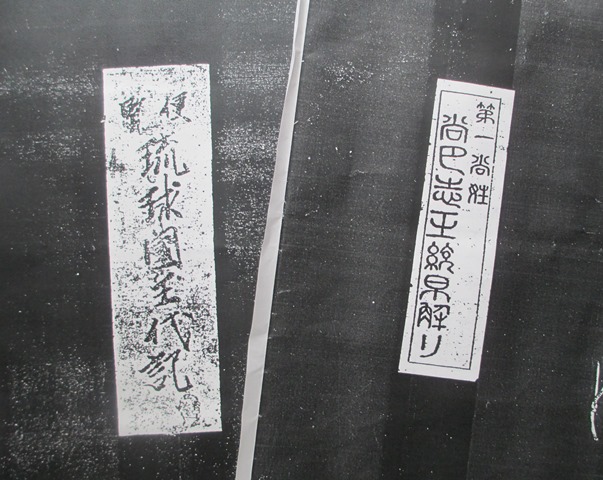
1934年11月 神村朝儀『便覧 琉球國王代記』神村朝忠/1937年3月 神村朝儀『第一尚姓 尚巴志王統早分解り』神村朝忠薬店
○雑誌『おきなわ』復刻版解説に酒井直子さんが「回想ー父 神村朝堅」を書かれていて、「向氏神村家家系図」も添えられていた。13世 朝睦の子供たちが省略されていたので詳しく記入してもらった。その結果、上記の著者・朝儀は叔父で、発行人の朝忠は朝堅氏の父と判明した。
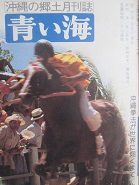
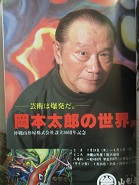

1980年6月 雑誌『青い海』94号 「広告ー岡本太郎の世界ー芸術は爆発だ。-」
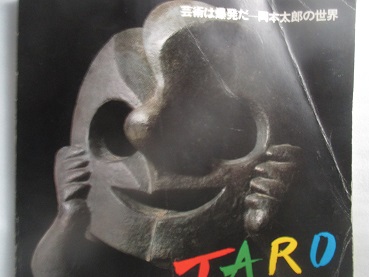

1980年7月 沖縄山形屋設立30周年記念『芸術は爆発だー岡本太郎の世界』

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ
『新沖縄文学』と岡本太郎
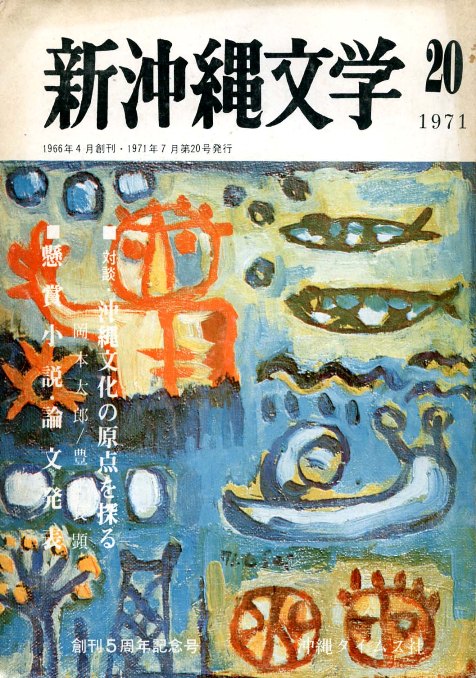
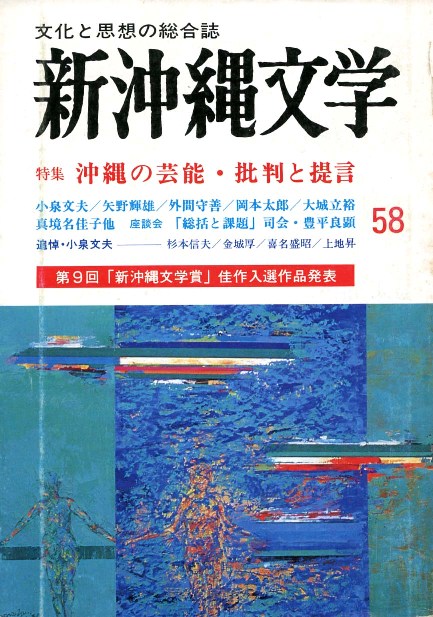
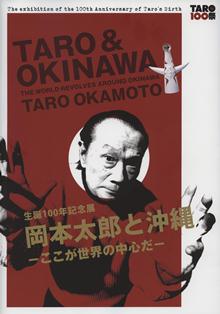
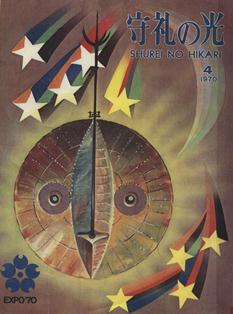
超タイフー「タロウ」オキナワに上陸か


山田實撮影1963-浜田庄司と豊平良顕/1966-岡本太郎
2008年4月ー川崎市市民ミュージアム「オキナワ/カワサキー二つの地をつなぐ人と文化」展
□ごあいさつ・川崎市には戦前から多くの沖縄出身者が在住し、川崎市の産業発展の一翼を担われてきました。大正13(1924)年の発足から84年という長い歴史を有し、戦後すぐから沖縄芸能の保存にも大きく貢献してきました。
川崎市出身の陶芸家・濱田庄司や詩人・佐藤惣之助などは、沖縄の文化と深い関わりを持ったことが知られています。濱田庄司は、自身の作風を確立する上で、沖縄の壺屋の焼物だけでなく、沖縄の風土・生活様式から大きな影響を受けました。佐藤惣之助も沖縄に魅せられた一人で、「おもろさうし」などに刺激され、詩集を出版しています。戦後には、岡本太郎が占領下の沖縄を訪れ、その文化と伝統に触れて強い衝撃を受けています。このように、川崎と沖縄のつながりはきわめて深いものがあり、市民ミュージアムにも壺屋焼の陶器や琉球政府から贈られた石敢当などの沖縄関連資料が収蔵されています。
そこで本展では、沖縄と川崎、この二つの地のつながりをテーマに、沖縄の伝統的な芸術文化を伝える資料と、それらに影響を受けて創造された美術工芸品などを紹介します。琉球文化の美と魅力に触れていただき、人々の手で長年にわたり築きあげられてきた沖縄と川崎の絆を感じ取っていただけば幸いです。 川崎市市民ミュージアム
□川崎市出身の芸術家と沖縄・佐藤惣之助と沖縄/濱田庄司と沖縄/岡田青慶と沖縄/岡信孝と沖縄/岡本太郎と沖縄
□川崎の工場と沖縄県出身労働者
1966年1月10日ー『琉球新報』「川崎市でビル火災ー沖縄出身者4人が焼死」
1968年1月5日ー『毎日グラフ』「本土の中の沖縄(南風サークル/大城真栄/普久原朝喜/金城良明)」「万国博へ全力投球(岡本太郎「抵抗あるものを」)」
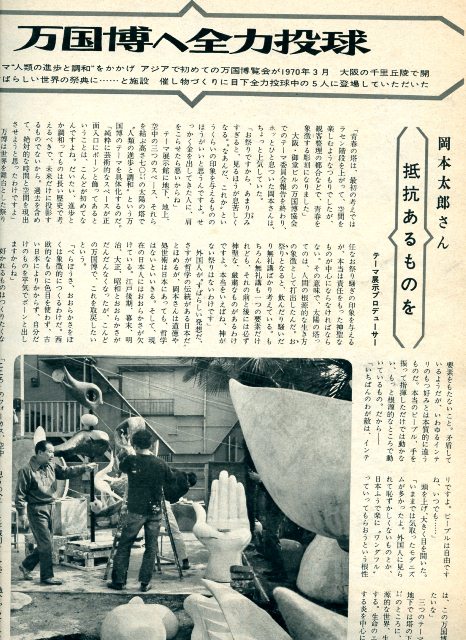
1969年12月30日ー『沖縄タイムス』真栄田義見「古江亮仁(川崎民家園長)氏と語る」
1983年2月10日ー『琉球新報』「川崎の沖縄県人 70年の歩みー2年がかりで完成」、11日ー『沖縄タイムス』「県人の苦難の歴史綴る『七十年の歩み』出版」
1983年8月1日ー『沖縄タイムス』「川崎沖縄青少年京浜会館」「川崎沖縄県人会」
1984年2月11日ー『琉球新報』福地嚝昭「女工哀史(関東大震災)ー富士瓦斯紡績川崎工場の名簿について」
1984年
10月19・20日ー川崎市立労働会館で川崎市制60周年記念「全国地名シンポジウム」開かれる。□谷川健一/仲松弥秀対談「沖縄地名の特色」、山下欣一「奄美のシャーマニズム」、宮田登「ミロク信仰と黒潮」
10月26日ー『琉球新報』「黒潮の流れに沿って 南島と本土の交流史探る」、『沖縄タイムス』「黒潮の流れに沿って沖縄・奄美と川崎結ぶ」「話題ー古江亮仁さんー1957年には県人の古波津英興氏とはかって沖縄文化同好会を作る。月一回、東恩納寛惇(歴史)、比嘉春潮(同)、仲原善忠(同)、芹沢圭介(紅型)、濱田庄司(陶芸)、柳悦孝(織物)等々多彩な沖縄研究者を講師に文化の灯をともした。土地問題で沖縄の大衆運動が燃えていた。」
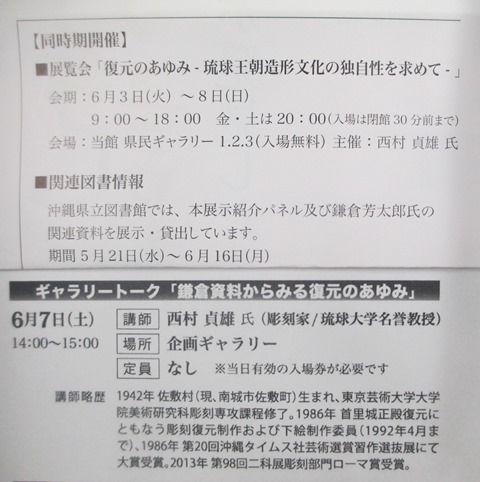

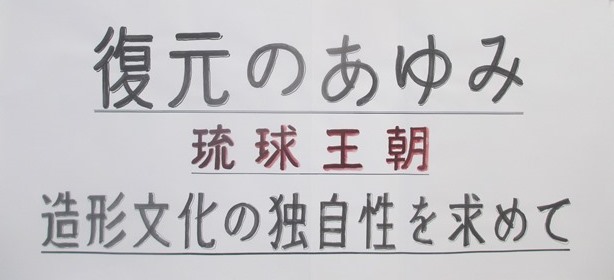





石川和男氏、松島弘明氏
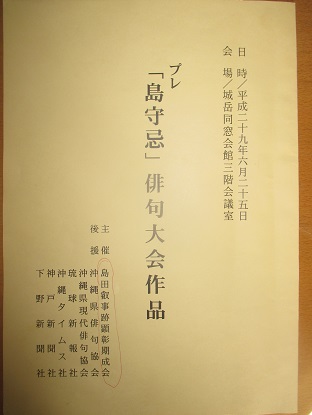
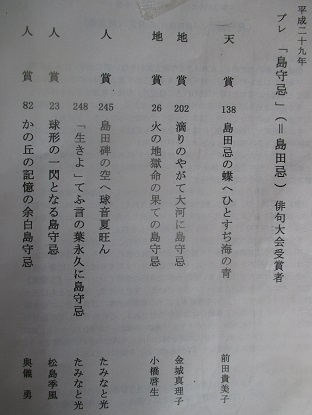
2017年6月 島田叡氏事跡顕彰期成会(嘉数昇明会長)『プレ「島守忌」俳句大会作品』印刷・みどり印刷(石川和男)
同時期開催/6月3日~8日 西村貞雄主催「復元のあゆみー琉球王朝造形文化の独自性を求めてー」


2014年6月7日



早速に那覇市内には「翁長追い落とし」の安倍政権(核押しつけ)追従の謀略ビラが沖縄電力の電信柱に堂々と貼られていたが、翁長那覇市長の沖縄県知事選出馬という想定外に慌てて作ったのか故意か知らないが龍の爪は5本としている。これで翁長市長が沖縄県知事候補辞退という事態になれば儲けものだ。いや、却って辞退ということになったらビラに書かれていることが事実と認めたことになるではないか。安倍政権や黒人大統領のアメリカも余り度がすぎた「核押し付け」をすると、本体の「嘉手納基地」や他の米軍基地、自衛隊基地にもウチナーンチュの「怒り」に油を注ぎ基地存続に重大な結果になりかねない。こういうかつての同志のウラガネを暴露するヒマがあれば、膨大なウラガネ①「思いやり予算」②「政党助成金」が「秘密保護法」が出来ると安倍政権は勝手に税を増やし、使い道も秘密だから自党の選挙資金や反対派懐柔にも使える。。つまり「官房機密費」などを含めて国民からの税を勝手気ままに使える(何に使うかも秘密)ということになる。</b
02/05: 大城精徳と『琉球の文化』③
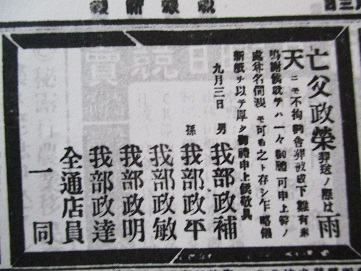
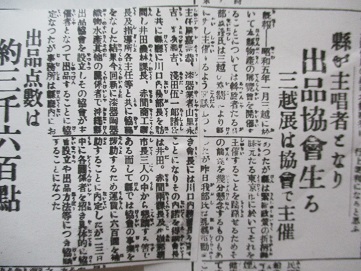
1908年9月ー愼氏我部家7代目・我部政榮葬儀/1929年9月1日『沖縄朝日新聞』「昭和5年1月、三越において本県物産の展覧会を開催することについては斡旋者たる我部政達氏・・・」(この頃、三越に1919年入店の瀬長良直が居る。1934年、銀座支店長。1937年、大阪支店長)
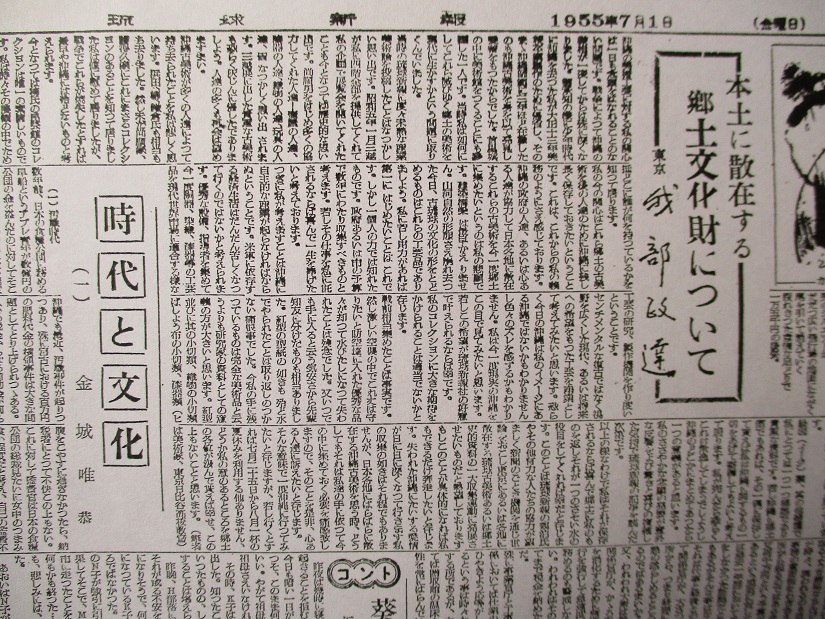
1955年7月1日『琉球新報』我部政達「本土に散在する郷土文化財について」
1973年3月ー『琉球の文化』第三号<特集・琉球の伝統玩具/琉球の塗物>□琉球文化社〒902那覇市安里425丸清ビル2階/コザ支社(城間喜宏)/関西支局(沖縄関係資料室・新城栄徳)/神奈川出張所(平良秀夫)
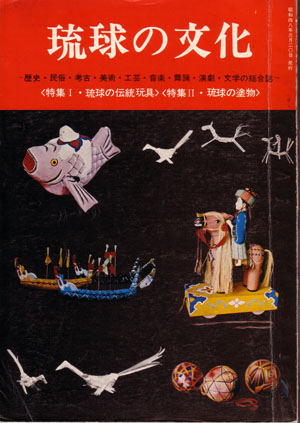
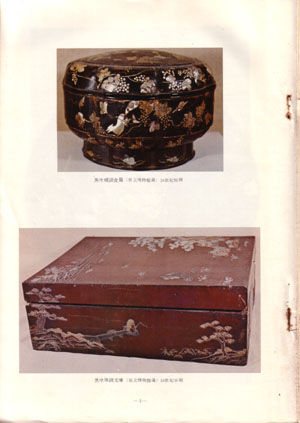
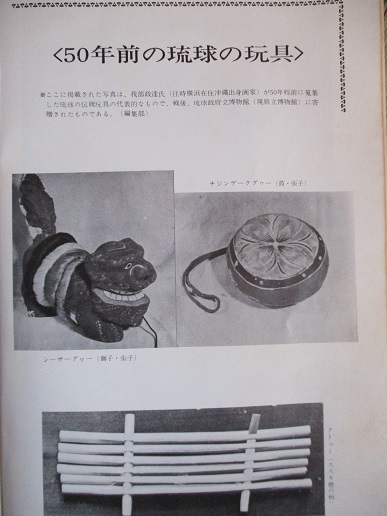
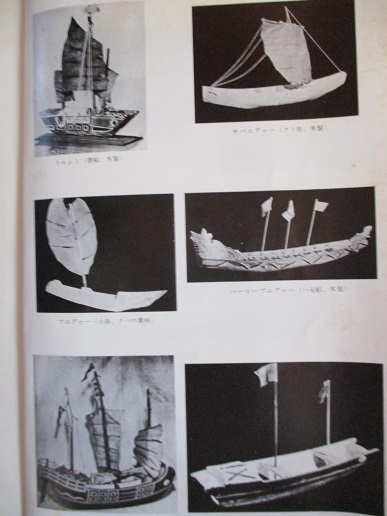
<50年前の琉球の玩具>我部政達が1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」に出品したもの。
特集Ⅱ・琉球の漆器
琉球漆器考(再録)ー石沢兵吾
文献にみる琉球漆器の古さー山里永吉
漆に魅せられてー前田孝允
琉球独得の漆芸「堆錦」についてー編集部
沖縄漆工芸の現状と将来を考えるー伊差川新
沖縄の漆器素材と漆料の問題ー多和田眞淳
琉球の漆工芸・郷土玩具に関する文献ー新城安善
現代沖縄の工芸家ー漆芸家・前田孝允さん
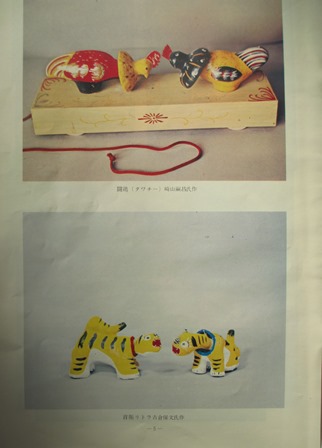
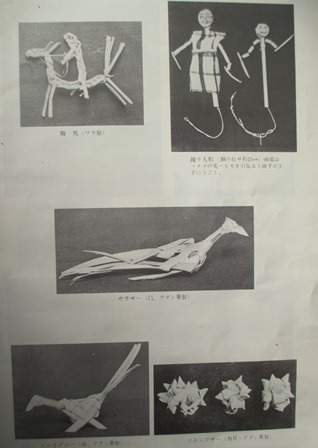
左のカラー図は、崎山嗣昌「闘鶏」/古倉保文「首振りトラ」、
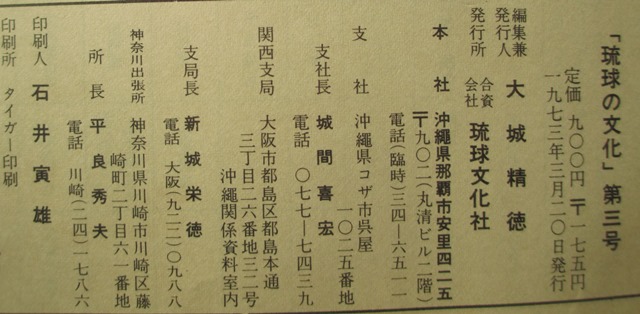
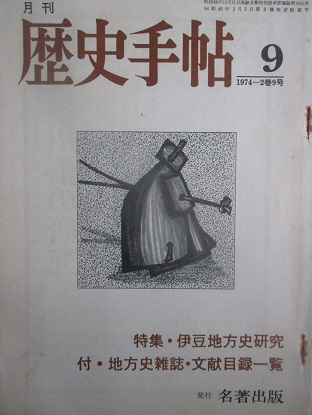
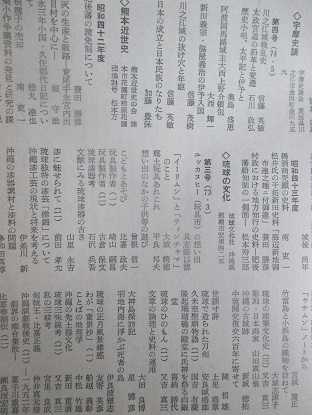
1974年9月 『月刊 歴史手帖』名著出版「地方史雑誌・文献目録ー◇琉球の文化 第三号」
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」
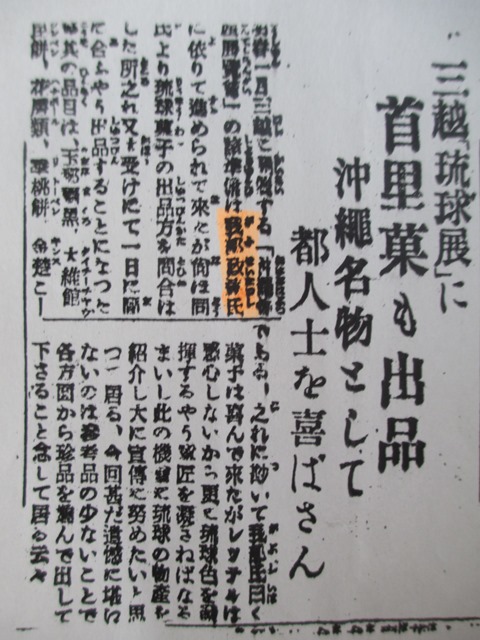
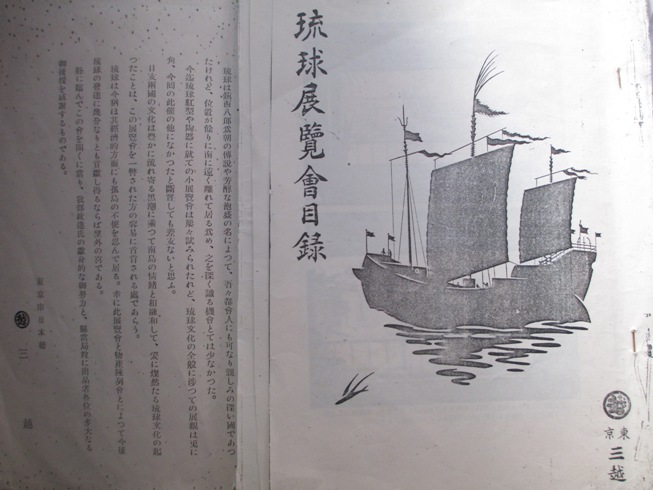

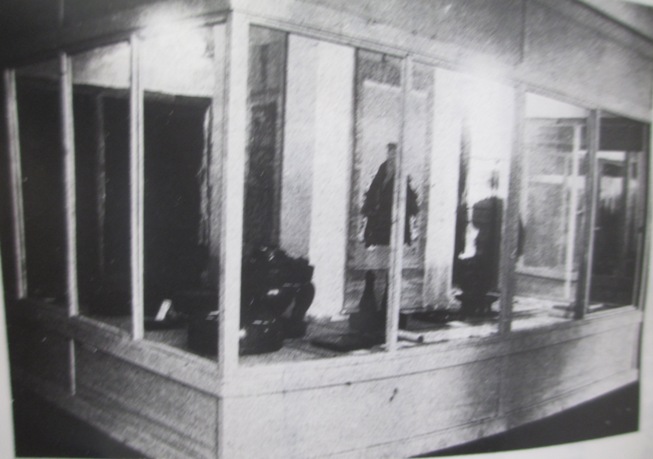
沖縄県立図書館出品の「程順則肖像」が見える
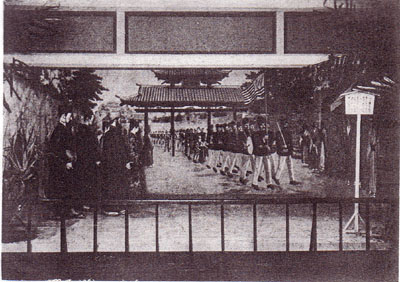
1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」、写真・ペルリ提督の首里城訪問のジオラマ

「二十日正月踊」のジオラマ
1月ー『琉球展覧会出品目録』□永見徳太郎ー琉球女日本男遊楽の図、琉球船競漕の図、琉球人行列/島田佳矢ー琉球木彫聯、琉球木彫額、琉球竹花生、琉球細麻衣(笠、片袖、秋夏模様)、新月型酒入、龍模様花瓶/銘苅正太郎ー東道盆
山村耕花ー麻紅格子衣裳、麻茶地縦格子衣裳、麻紺地蝶梅模様衣裳、麻紺地花笠模様衣裳、麻紺地茄子模様衣裳、麻薄藍地松梅紅葉模様衣裳、木綿薄藍地牡丹鳳凰模様衣裳、木綿白地ドジン、麻風呂敷(三ツ巴に一紋付柳にのし模様)、鼈甲 (廃藩以前婦人使用のもの)、蛇皮線(爪付)、琉球胡弓(弓付)/啓明会ー琉球風俗絵、唐船渡来図、古代紅型裂地(300余年前のもの)、焼物製作に関する証書、紅型型紙図案(15枚)、紅型型紙(11枚)、絣図案(16枚)、絣図案(19枚)、手拭図案(2枚)、墨すり紅型図案(5枚)、風呂敷図案集(2枚)、紅型衣裳(3枚)、古代面 能面(4面)・・・比嘉華山は唐船入港ノ図、尚順は「神猫の絵」、富名腰義珍は唐手軸物、唐手本、唐手写真貼、巻藁(板付)、木刀、十手、唐手術写真、六尺棒などを出品している。①杉浦非水は琉球壺(芳月窯・唐草彫)、琉球壺(南蛮模様彫)を出品。
①杉浦非水 すぎうら-ひすい 1876-1965 明治-昭和時代の図案家。
明治9年5月15日生まれ。グラフィックデザインの開拓者のひとり。地下鉄(昭和2年の開通時)や三越のポスター,たばこのパッケージなどを手がける。図案家の団体「七人社」を設立。昭和10年多摩帝国美術学校(現多摩美大)校長。30年芸術院恩賜賞。光風会会員。昭和40年8月18日死去。89歳。愛媛県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は朝武(つとむ)。(→コトバンク)/日本のデザイン史に燦然と輝くモダンポスターの傑作『三越呉服店 春の新柄陳列会』です。描いたのは、三越の図案部員として次々と傑作ポスターを世に送り出し、「三越の非水か、非水の三越か」と言われるほどの名声を得た近代グラフィックデザインの父・杉浦非水。日本で最初に商業美術という分野を切り拓き、多摩美術学校の初代校長兼図案科主任教授として日本にデザインを根付かせる為に生涯尽力した人物です。(→美の巨人たち)
ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」
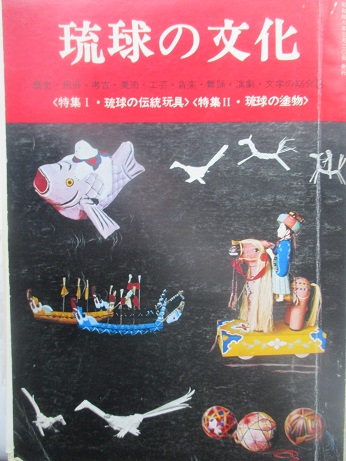
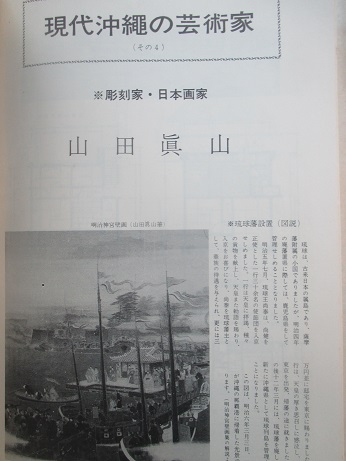
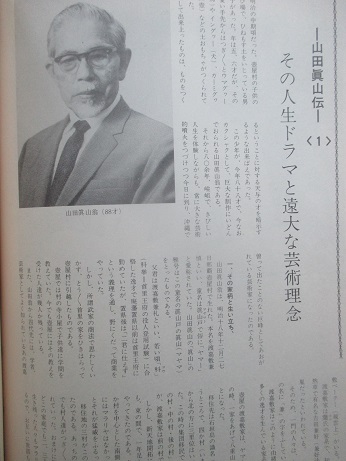

山田真山・住所変遷
山田泰雲君は元篆刻てんこく師の弟子であったが、芦野楠山先生の世話で師の許しを得て私の門下となった。大分出来て来て、これからという処で病歿しました。→青空文庫/高村光雲「幕末維新懐古談・その後の弟子の事」
1916年 東京府下日暮里谷中本1017
□石野瑛『南島の自然と人』表紙・山田真山画「オメントー」
1918年 東京市下谷区三崎南町60
1929年 東京市外井萩町上荻窪963
□2001年3月『新生美術』山田博「具志堅(聖児)先生の思い出」
□真山家族ー妻・博子(小堀鞆音の娘)、長男・真、次男・博、長女・栄子、3男・光三
小堀鞆音 こぼり-ともと
1864-1931 明治-昭和時代前期の日本画家。
文久4年2月19日生まれ。川崎千虎(ちとら)にまなび,歴史画を得意とした。明治31年日本美術院の創立に参加。41年東京美術学校(現東京芸大)教授。大正8年帝国美術院会員。門下に安田靫彦(ゆきひこ),川崎小虎(しょうこ)ら。昭和6年10月1日死去。68歳。下野(しもつけ)(栃木県)出身。旧姓は須藤。本名は桂三郎(けいざぶろう)。作品に「宇治橋合戦」「武士」など。(→コトバンク)
1937年 名古屋市中区米野町居屋敷52
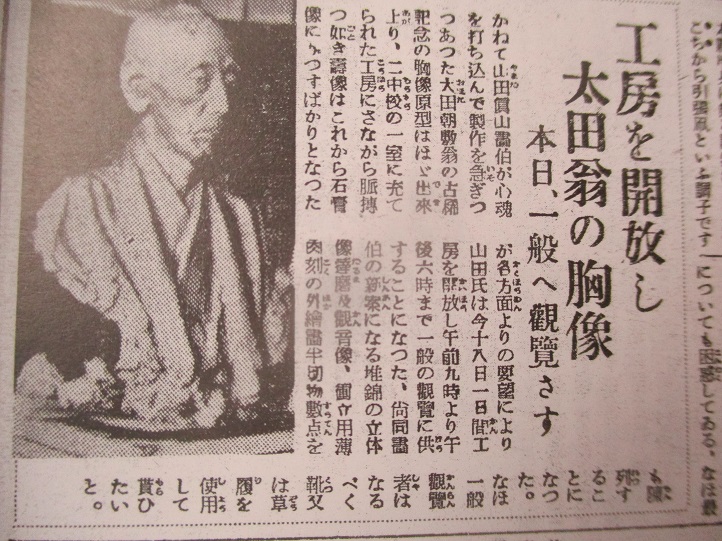
1937年7月18日『琉球新報』「工房を開放し太田翁の胸像 本日、一般へ観覧さす」

山田真山、太田朝敷像制作
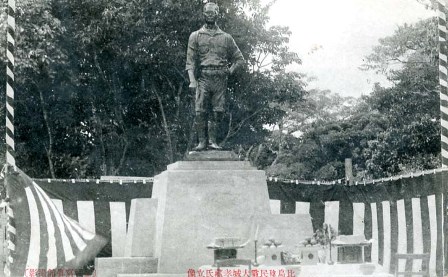
比島移民翁・大城孝蔵立像
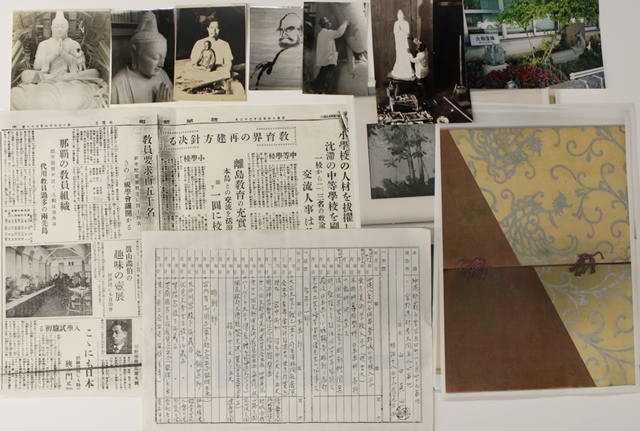
先月、芸大の小林純子准教授研究室に遊びに行くと山田真山資料がまとまってあった。沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館には真山の下絵、スケッチ、平和祈念像の構想図が、1986年に遺族から寄贈された。今回、その整理が終わったので報告を書いているのだと小林さんは言う。小林純子「山田真山による下絵資料について」に真山の略歴がある。私も以前、那覇市が真山の日本画、彫刻作品を購入するにあたって参考資料を提供したことがある。
07/21: 森政三(1895年4月17日~1981年1月6日)
新城栄徳 2020-4-15 私の敬愛する編集者に上間常道氏が居た。氏は大阪生まれの今帰仁2世。東京大学文学部卒。『現代の理論』編集部、その発売元の河出書房新社に無試験で入社。『ドストエーフスキー全集』『トルストイ全集』などを編集する。復帰を機に沖縄に移住。出版社などを経て沖縄タイムスに入る。沖縄タイムス発刊35周年記念で『沖縄大百科事典』(上中下の3巻別刊1巻、約17000項目を収録)の編集を担当、同社より83年5月刊行。06年より出版舎Mugenを主宰。私は河出書房の話は聞いたかもしれないが記憶にない。
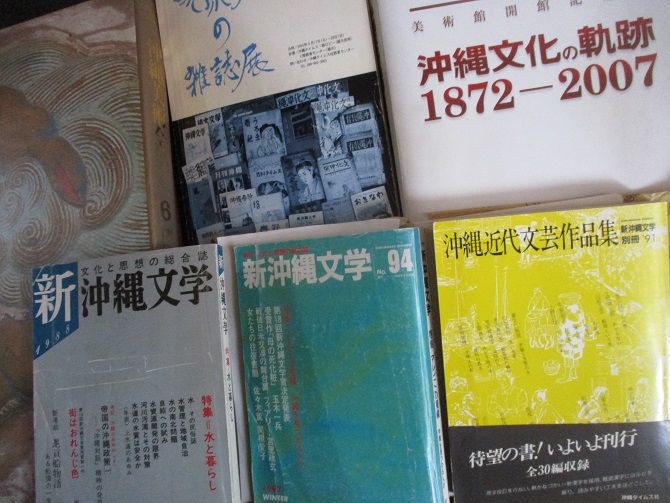
新城栄徳と上間常道氏の共同作業『沖縄美術全集』「年表」/『沖縄近代文芸作品集』/『琉球弧の雑誌展』
森政三ー北海道札幌市に生まれる。東京の中学を終え、蔵前高専工業図案科入学。療養のため中退。1925年、東京美術学校建築学科卒業。歌舞伎座、都美術館、明治生命ビルの設計者・岡田信一郎①早稲田大学教授に師事して和洋建築の実技を習得。和風建築に興味をもち1929年「国宝保存法」の制定にともない文部省技官となる。国宝、重要文化財の調査、記録、修復を担当。1936年に国宝首里城正殿の解体修理工事を担当、1937年、初めて来沖し仲座久雄らと工事に従事。以後、毎年来沖して国宝、重要美術品の指定申請を提出、約20件が指定される。1945年から18年間ー日光東照宮修復の技師長になったほか、二荒山神社、神王寺や長崎の大浦天主堂、出羽三山の建造物などの修復を手掛けた。1955年、戦災沖縄文化財の実情調査と復興計画案を立てる。1956年、園比屋武御嶽石門設計監督、翌年竣工。1957年、守礼門復元工事の設計工事の設計監督委嘱、翌年竣工。泰子夫人との間に1男1女。
①岡田信一郎 おかだ-しんいちろう
1883-1932 明治-昭和時代前期の建築家。
明治16年11月20日生まれ。大正元年大阪市中之島中央公会堂の設計競技で1等当選。ニコライ堂修復のほか,歌舞伎座,東京府美術館,明治生命ビルなど,おおくの洋式建築を設計した。東京美術学校(現東京芸大)教授。昭和7年4月4日死去。50歳。東京出身。東京帝大卒。→コトバンク
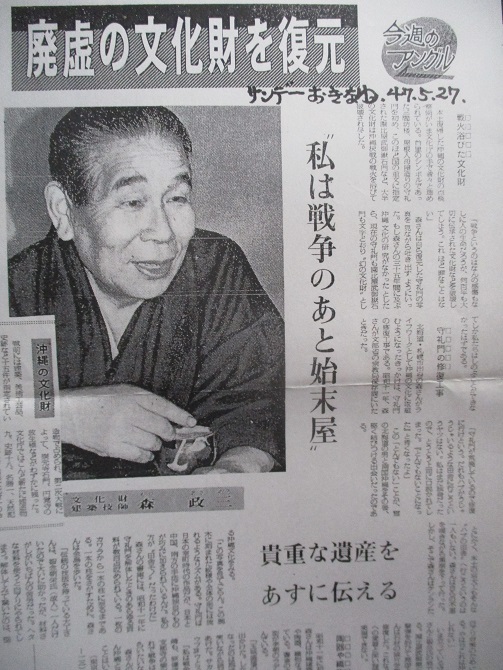
2004年2月 沖縄県立博物館・美術館[企画展] 図録『戦前・戦後の文化財保護 ~仲座久雄の活動をとおして~ |』

写真右から国吉真哲、亀川正東、森政三、名渡山愛順、仲座久雄

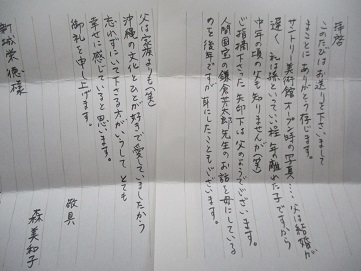
宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ
□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

日光東照宮でー中央に森政三、その右へ仲座久雄、一人置いて又吉眞三
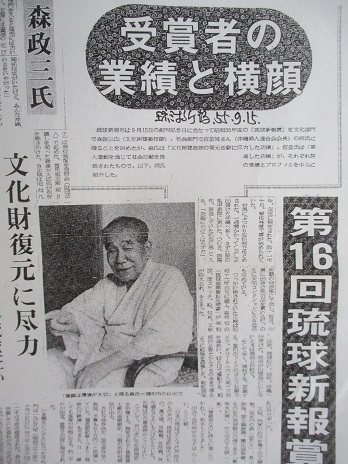
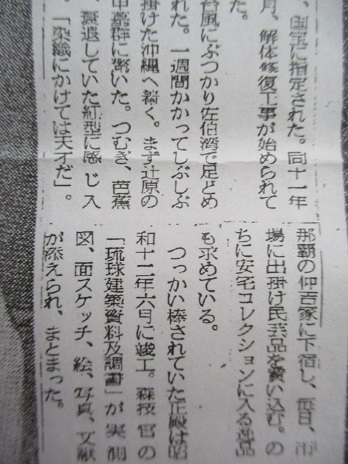
1980年9月15日『琉球新報』


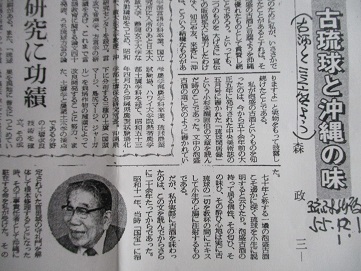
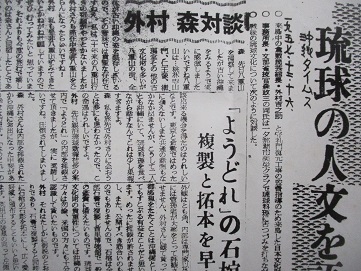


2010年7月28日那覇市歴史博物館「沖縄のシンボル 守礼門」展〇ギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。会場には湖城氏の幼馴染の渡口万年筆の渡口彦邦氏や、南都社長の大城宗憲氏も居られコメントも出た。
講演終了後、大城氏はかつて松尾書店を経営して居られたのと『沖縄春秋』の話をするとパレット地下の日本料理店・彦に誘われた。何を注文するかと聞かれたので、大城さんと同じものでいいですよ、大城さんは年配だしそう食べないだろうと思ったら2段重ねの膳で出てきた。松尾書店から1965年4月に真境名安興『沖縄1千年史』を新城安善作成の索引をつけて発行している。同年11月には雑誌『沖縄春秋』も創刊。
創刊号には「特別座談会・転機を迎えた沖縄問題」が組まれ小渕恵三、宇野宗祐、中村晄兆、翁長助裕が参加、司会が比嘉幹郎であった。『沖縄春秋』第2号にはカメラマンの岡村昭彦氏が来社した記事がある。日本料理屋には湖城英知氏と夫人も居られた。2000円札は沖縄観光のシンボルでもある。これを活かさない手はない。大城宗憲氏も沖縄観光を産業化にして居られる。
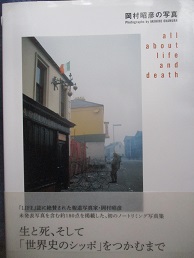
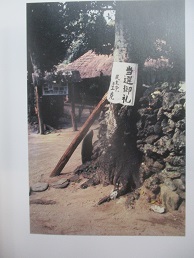
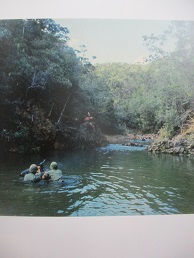
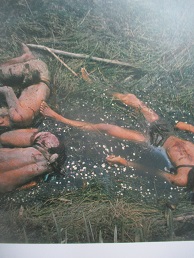
2014年7月 東京都写真美術館(金子隆一、藤村里美 他)『岡村昭彦の写真 生きること死ぬことのすべて』美術出版社
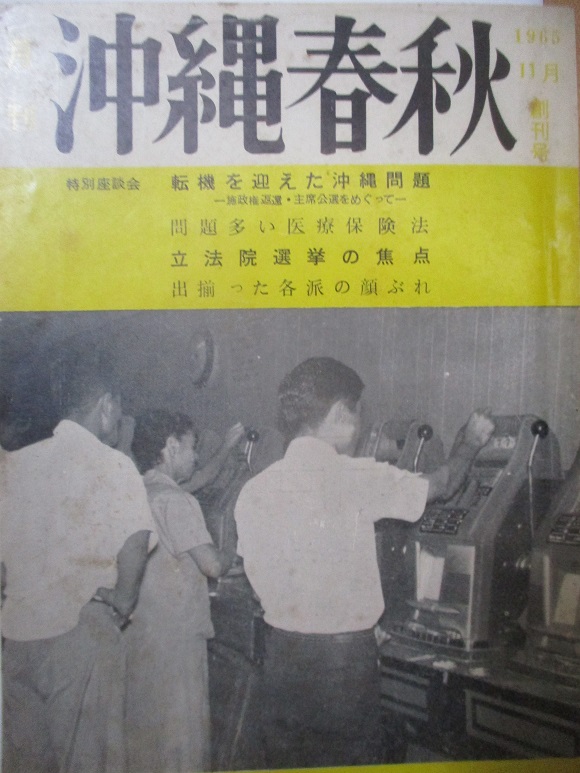
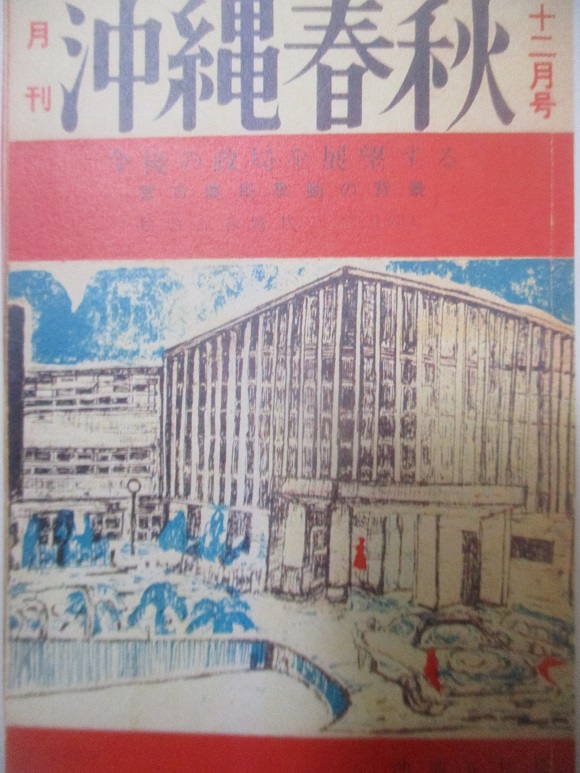
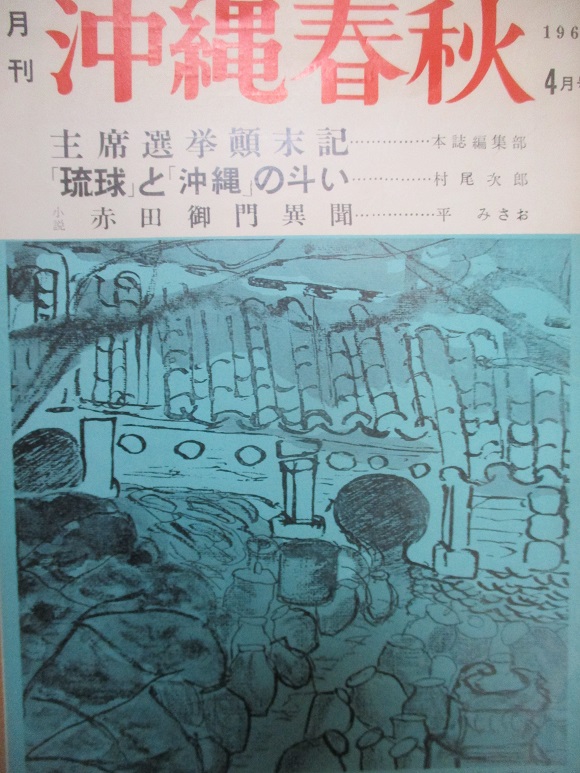
1965年11月『沖縄春秋』第1号 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲
1965年12月『沖縄春秋』第2号「戦争報道写真家の岡村昭彦氏 本社を訪問」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲5丁目
1966年4月『沖縄春秋』第2巻第2号 徳田安周「小説・写真記者物語<2>(宝くじ50万円当たって)悪いけれども亡き親友の弟、山川岩美君に行ってもらうことにした。彼は沖縄から上京したばかりであったが、この話を聞くとフントーナーサイ(ほんとですか)とはじめは信用しなかった。(略)」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲
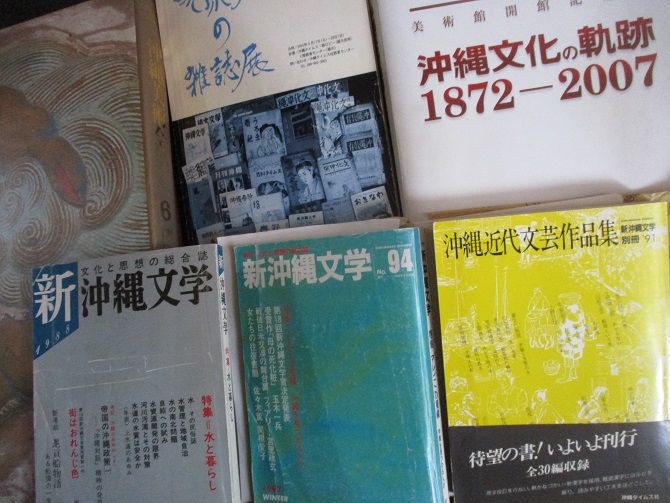
新城栄徳と上間常道氏の共同作業『沖縄美術全集』「年表」/『沖縄近代文芸作品集』/『琉球弧の雑誌展』
森政三ー北海道札幌市に生まれる。東京の中学を終え、蔵前高専工業図案科入学。療養のため中退。1925年、東京美術学校建築学科卒業。歌舞伎座、都美術館、明治生命ビルの設計者・岡田信一郎①早稲田大学教授に師事して和洋建築の実技を習得。和風建築に興味をもち1929年「国宝保存法」の制定にともない文部省技官となる。国宝、重要文化財の調査、記録、修復を担当。1936年に国宝首里城正殿の解体修理工事を担当、1937年、初めて来沖し仲座久雄らと工事に従事。以後、毎年来沖して国宝、重要美術品の指定申請を提出、約20件が指定される。1945年から18年間ー日光東照宮修復の技師長になったほか、二荒山神社、神王寺や長崎の大浦天主堂、出羽三山の建造物などの修復を手掛けた。1955年、戦災沖縄文化財の実情調査と復興計画案を立てる。1956年、園比屋武御嶽石門設計監督、翌年竣工。1957年、守礼門復元工事の設計工事の設計監督委嘱、翌年竣工。泰子夫人との間に1男1女。
①岡田信一郎 おかだ-しんいちろう
1883-1932 明治-昭和時代前期の建築家。
明治16年11月20日生まれ。大正元年大阪市中之島中央公会堂の設計競技で1等当選。ニコライ堂修復のほか,歌舞伎座,東京府美術館,明治生命ビルなど,おおくの洋式建築を設計した。東京美術学校(現東京芸大)教授。昭和7年4月4日死去。50歳。東京出身。東京帝大卒。→コトバンク
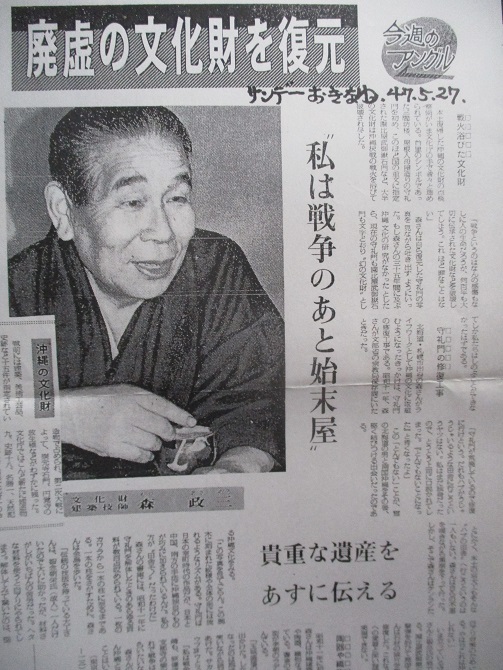
2004年2月 沖縄県立博物館・美術館[企画展] 図録『戦前・戦後の文化財保護 ~仲座久雄の活動をとおして~ |』

写真右から国吉真哲、亀川正東、森政三、名渡山愛順、仲座久雄

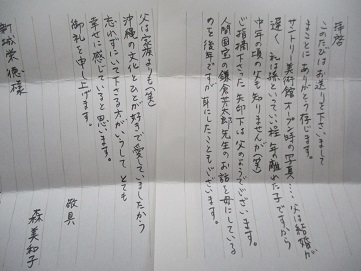
宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ
□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

日光東照宮でー中央に森政三、その右へ仲座久雄、一人置いて又吉眞三
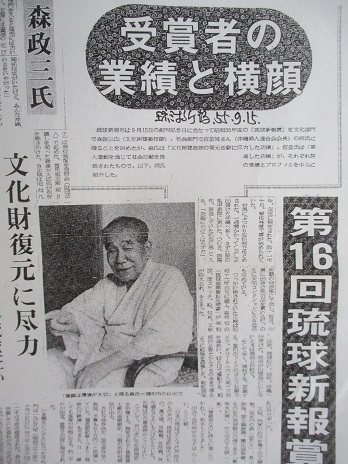
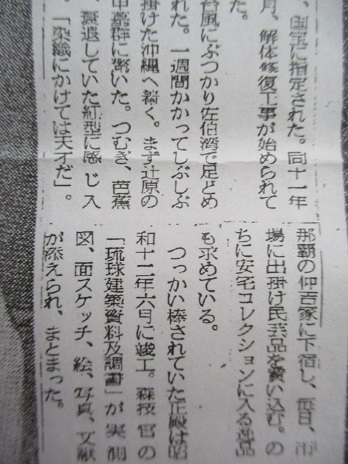
1980年9月15日『琉球新報』


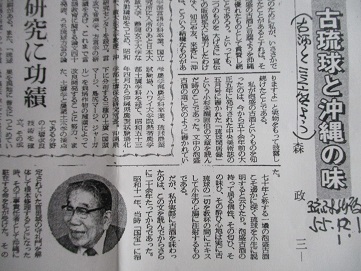
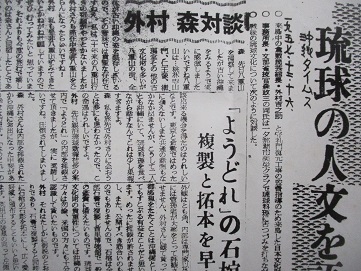


2010年7月28日那覇市歴史博物館「沖縄のシンボル 守礼門」展〇ギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。会場には湖城氏の幼馴染の渡口万年筆の渡口彦邦氏や、南都社長の大城宗憲氏も居られコメントも出た。
講演終了後、大城氏はかつて松尾書店を経営して居られたのと『沖縄春秋』の話をするとパレット地下の日本料理店・彦に誘われた。何を注文するかと聞かれたので、大城さんと同じものでいいですよ、大城さんは年配だしそう食べないだろうと思ったら2段重ねの膳で出てきた。松尾書店から1965年4月に真境名安興『沖縄1千年史』を新城安善作成の索引をつけて発行している。同年11月には雑誌『沖縄春秋』も創刊。
創刊号には「特別座談会・転機を迎えた沖縄問題」が組まれ小渕恵三、宇野宗祐、中村晄兆、翁長助裕が参加、司会が比嘉幹郎であった。『沖縄春秋』第2号にはカメラマンの岡村昭彦氏が来社した記事がある。日本料理屋には湖城英知氏と夫人も居られた。2000円札は沖縄観光のシンボルでもある。これを活かさない手はない。大城宗憲氏も沖縄観光を産業化にして居られる。
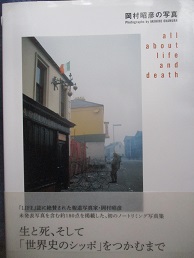
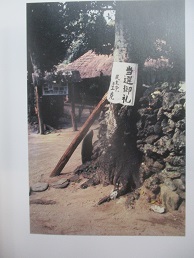
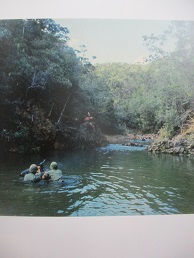
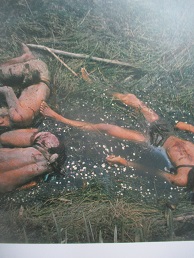
2014年7月 東京都写真美術館(金子隆一、藤村里美 他)『岡村昭彦の写真 生きること死ぬことのすべて』美術出版社
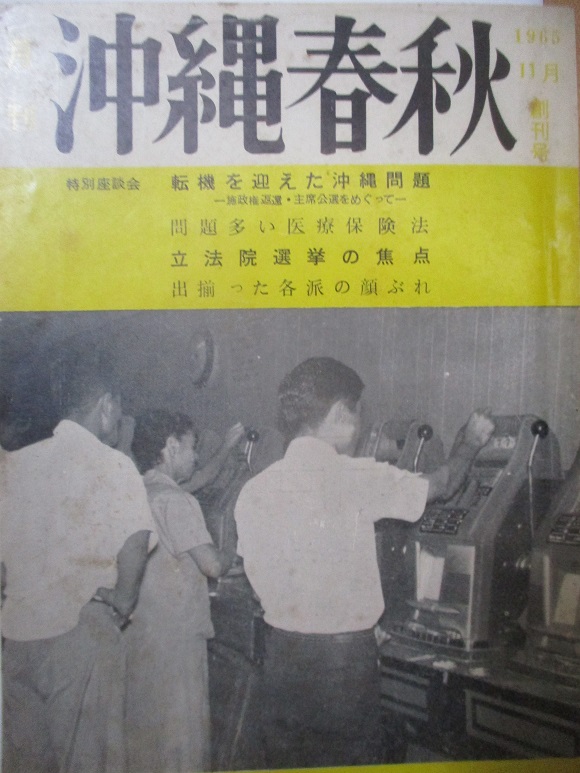
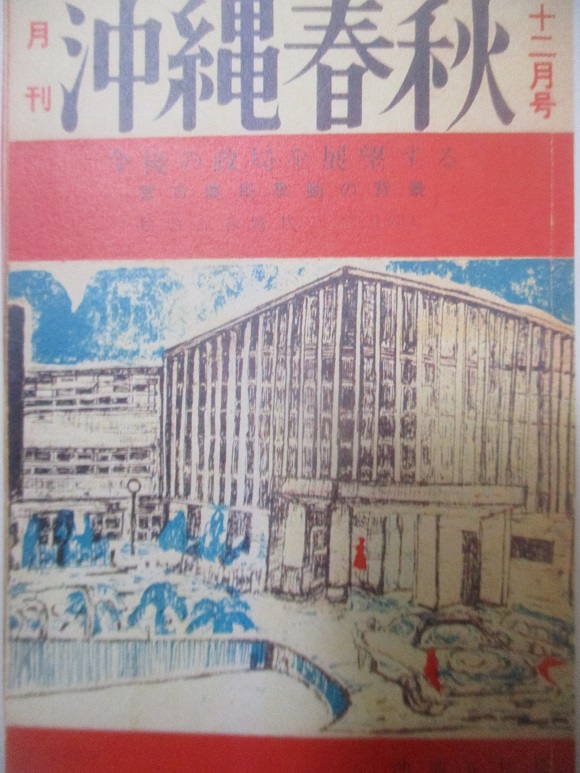
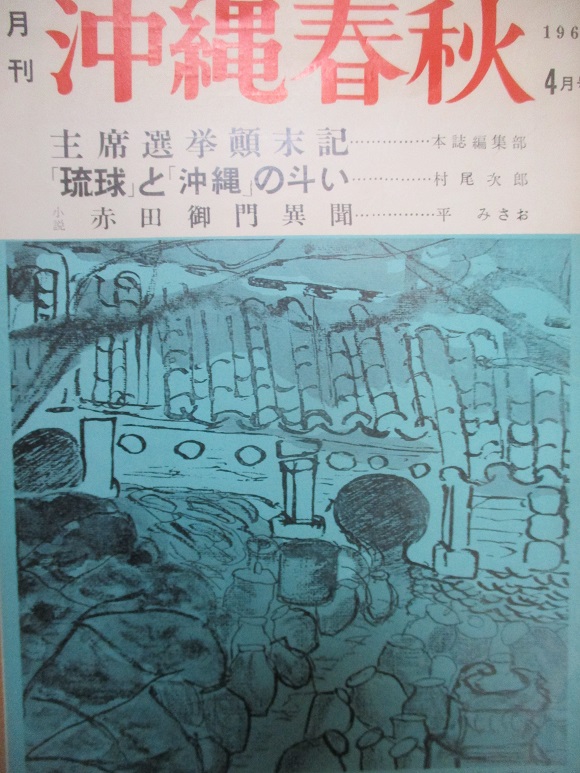
1965年11月『沖縄春秋』第1号 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲
1965年12月『沖縄春秋』第2号「戦争報道写真家の岡村昭彦氏 本社を訪問」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲5丁目
1966年4月『沖縄春秋』第2巻第2号 徳田安周「小説・写真記者物語<2>(宝くじ50万円当たって)悪いけれども亡き親友の弟、山川岩美君に行ってもらうことにした。彼は沖縄から上京したばかりであったが、この話を聞くとフントーナーサイ(ほんとですか)とはじめは信用しなかった。(略)」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲
1962 三重県立博物館「沖縄文化展」沖縄展後援組織委員会 鎌倉芳太郎、東恩納寛惇・・
4月ー三重県立博物館で「沖縄文化展」(沖縄民謡観賞会、空手演武)
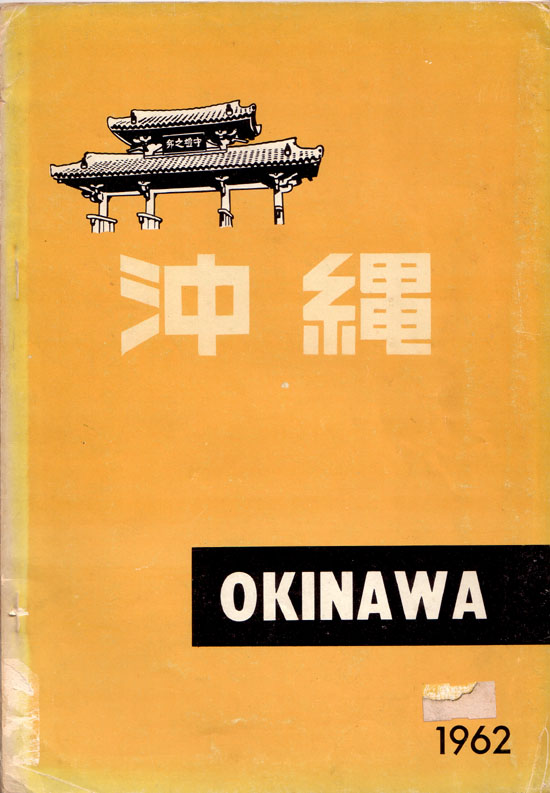
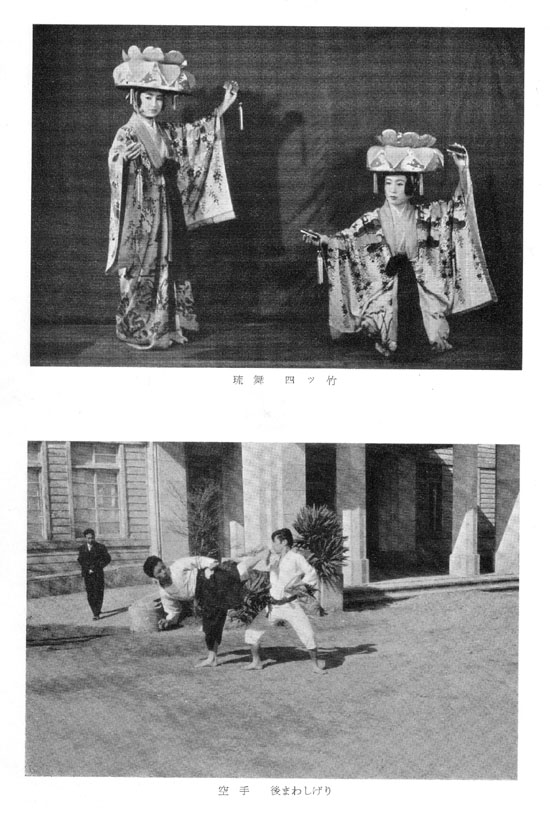
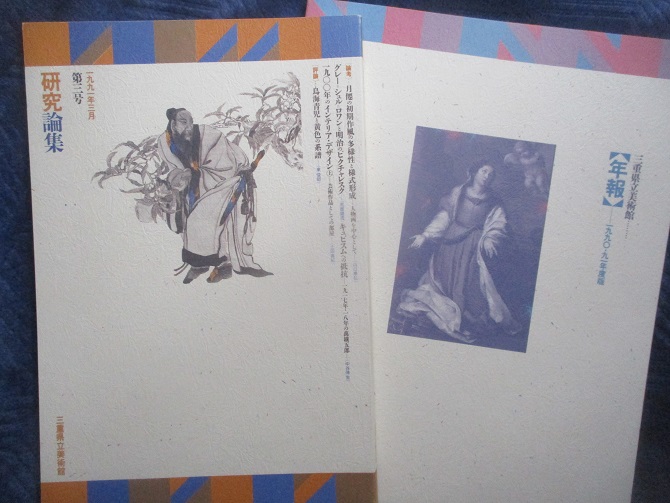
1994年9月 三重県立美術館『年報』/1991年3月 三重県立美術館『研究論集』第3号
4月ー三重県立博物館で「沖縄文化展」(沖縄民謡観賞会、空手演武)
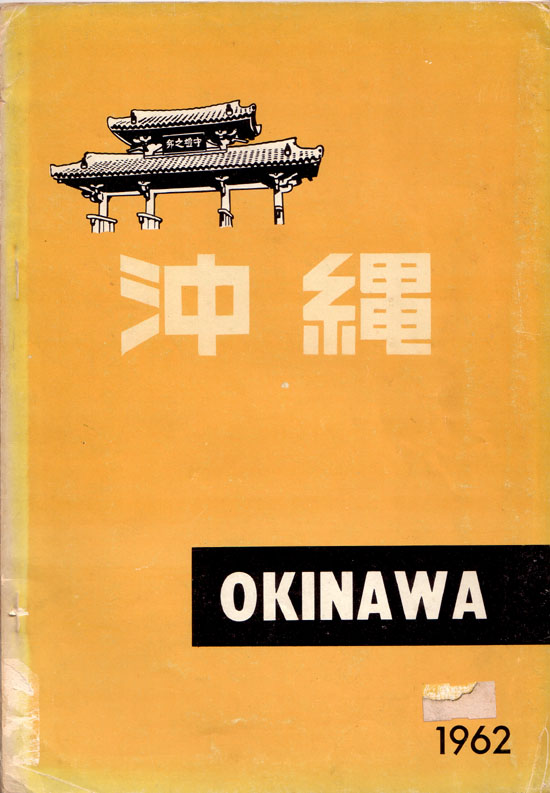
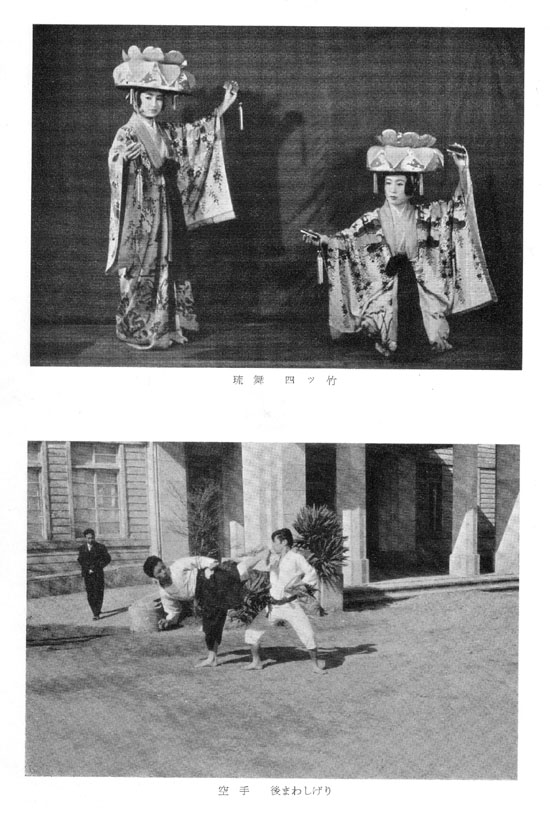
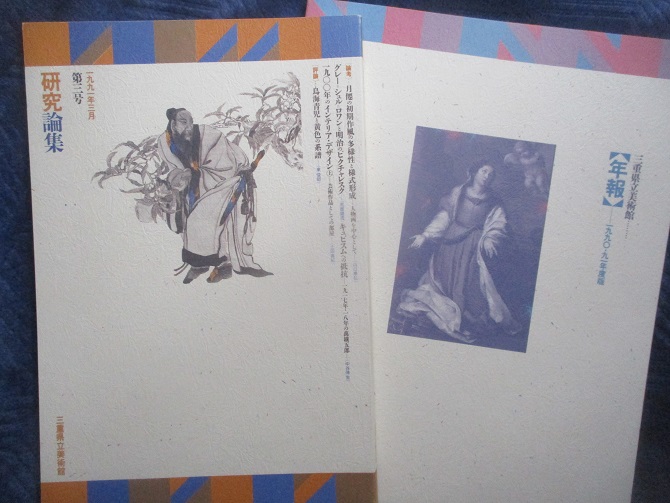
1994年9月 三重県立美術館『年報』/1991年3月 三重県立美術館『研究論集』第3号
08/21: 奈良ーシルクロードの終点
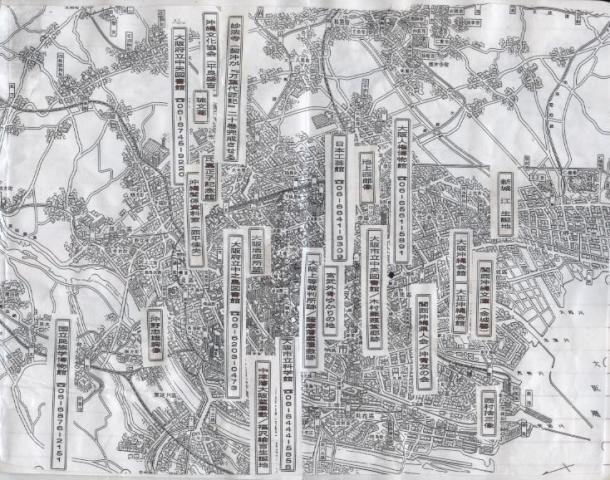
大阪沖縄絵図
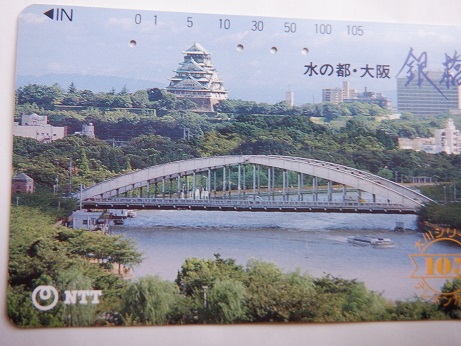
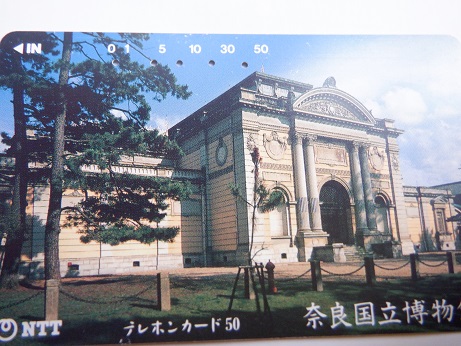
テレホンカード
私の17歳は東京一の繁華街、新宿歌舞伎町の大衆居酒屋「勇駒」で働いた事もある。その頃は若くてパワーもあった。20年ほど前、浅草寺初詣に行ったとき参拝者の列に入ったら全く身動きが取れなく離脱したこともある。とにかく過密都市でのオリンピック開催は気が知れない。いずれにせよ静かな場所に憧れて京都に住み着いたのが1969年であったが、盆地だから夏は暑く、冬は底冷えに寒い。復帰前、沖縄関係資料室主宰の西平守晴さん一家と同行、生駒聖天に初詣したのが生駒との出会いである。その後、私の家族は生駒に直通する近鉄奈良線の布施駅近くに住むことになる。


2022年7月 あけみ、こうた/ユンタンの孫
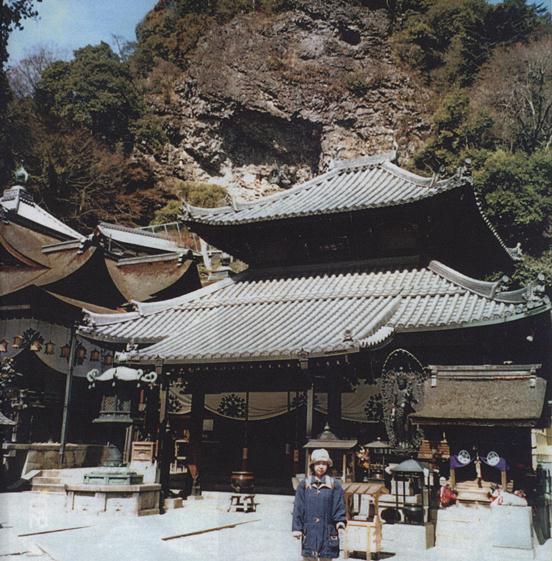
宝山寺と新城あけみ
宝山寺(ほうざんじ)は、奈良県生駒市門前町にある真言律宗大本山の寺院。生駒聖天(いこましょうてん)とも呼ばれる。山号は生駒山(いこまさん)。1678年に湛海律師によって開かれた。本尊は不動明王。鎮守神として歓喜天(聖天)を天堂(聖天堂)に祀っている。仏塔古寺十八尊第十五番。(→ウィキ)
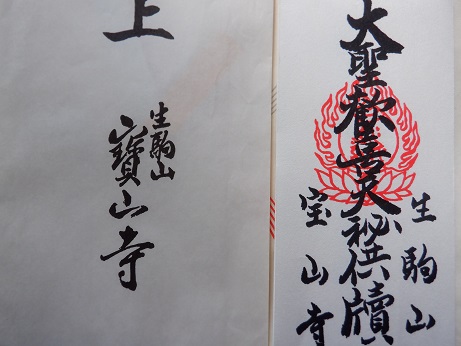
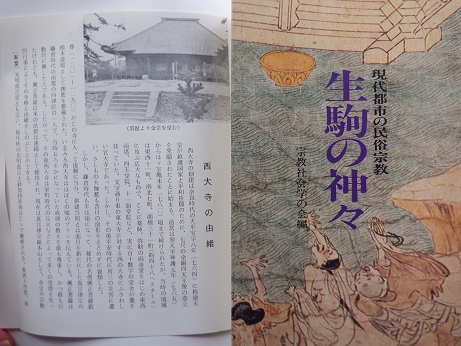
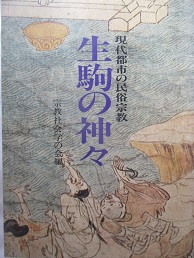
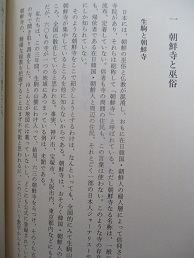

1985年10月 宗教社会学の会編『生駒の神々ー現代都市の民俗宗教』創元社〇朝鮮寺ー在日韓国・朝鮮人の巫俗と信仰ー
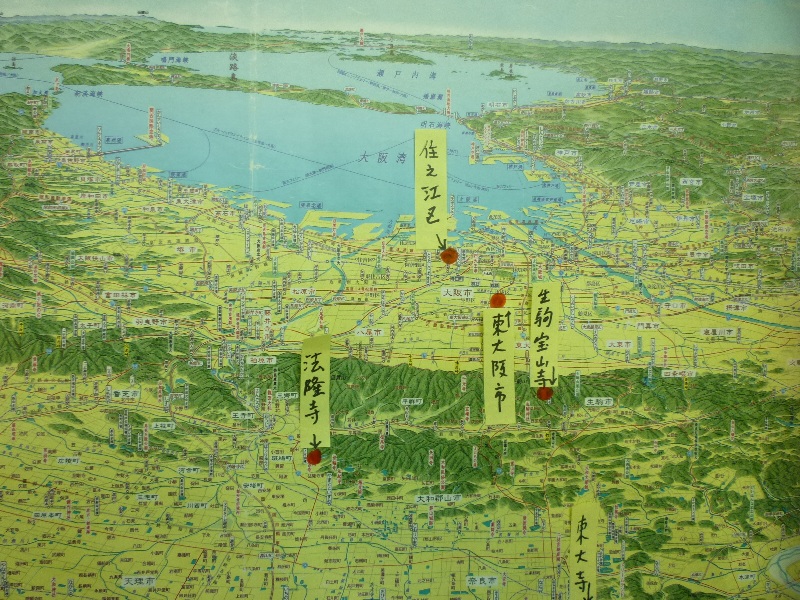
2006「トンビの目のパノラマ地図」
写真ー『沖縄美術全集』4絵画・書 山口宗季「花鳥図」大和文華館所蔵

○我が家は近鉄奈良線の布施駅近く(上の赤丸・東大阪市)にある。奈良公園や、唐招提寺・薬師寺、大和文華館(山口宗季の花鳥図、座間味庸昌の人物画が所蔵されている)、近鉄資料室や大阪ミナミ(道頓堀)に出るのに便利である。奈良はシルクロードの終点と言われているが、1977年発行の辛島昇①編『インド入門』に「日本人のシルクロード好きは、毎秋奈良でひらかれる正倉院展にどっと人があつまる事情と軌を一にしたものである」とし「むかし大東亜共栄圏という日本を扇の要においたひろい意味での文化圏を捏造した国粋主義に通じる」とする。奈良は東大寺の大仏や興福寺の五重塔、阿修羅像でも知られ世界遺産でもある。
①辛島昇 からしま-のぼる
1933- 昭和後期-平成時代の南アジア史学者,インド史学者。
昭和8年4月24日生まれ。専門は南アジア史。昭和50年東大教授。のち大正大教授。平成15年「History and Society in South India:The Cholas to Vijiayanagar(南インドの歴史と社会─チョーラ朝からビジャヤナガル王国へ)」で学士院賞。19年文化功労者。東京出身。東大卒。著作に「インド入門」など。→コトバンク

東大寺大仏殿ー2017年1月/ 『毎日新聞』2019-11-1 那覇市の首里城で起きた火災を受け、奈良県内の文化財でも31日、防火設備の緊急点検などが行われた。 奈良市の東大寺大仏殿では同市中央消防署員ら7人が緊急査察を行い、建物や周辺に設置された消火器や放水銃、自動火災報知機などの防火設備約30カ所を点検した。特に問題はなかったという。

奈良近鉄駅ビル3・4階に歴史・観光の展示館「なら奈良館」(旧・奈良歴史教室)
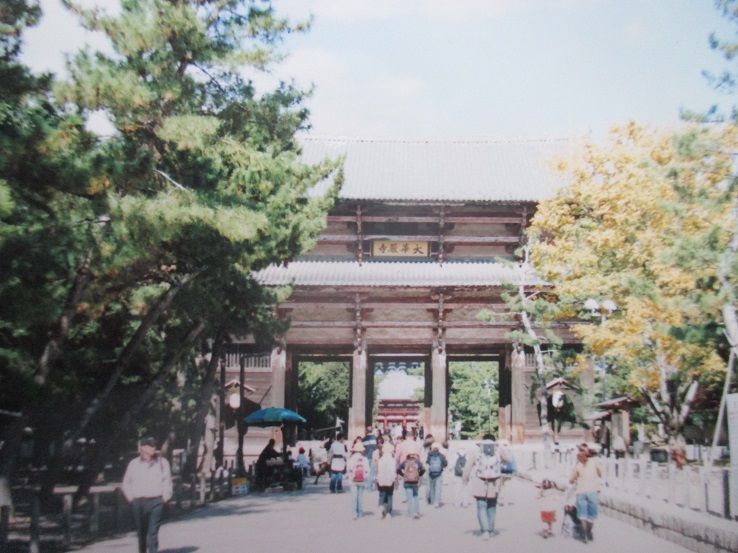
源平争乱によって焼失した東大寺を、重源はその資金を広く寄付にあおいで各地をまわる勧進上人となって、宋人陳和卿の協力を得て再建にあたりました。そのとき採用されたのが、大仏様の建築様式で、大陸的な雄大さ、豪放な力強さを特色するもので、この東大寺南大門が代表的遺構です。

国宝・銅造盧舎那仏坐像/重文・如意輪観音坐像

大仏殿にある広目天像 多聞天像
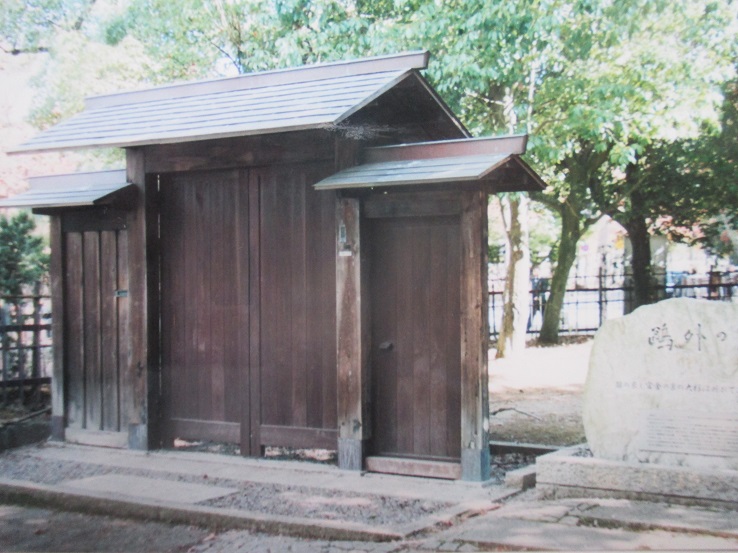
小説家して有名な森鴎外は、大正6年に帝室博物館の総長に任命され、東京・京都・奈良の帝室博物館を統括する要職でした。大正7年から10年まで、秋になると鴎外は正倉院宝庫の開封に立ち合うため奈良を訪れており、滞在中の宿舎はこの場所にありました。
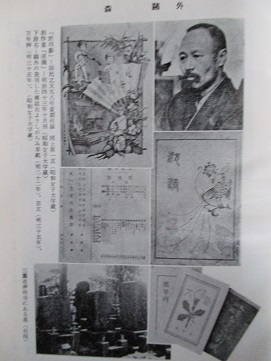
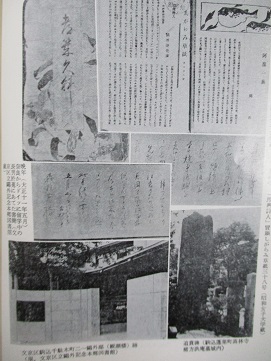
1972月3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書』「森鴎外」第二十巻
2006年5月13日ー午後は、近鉄丹波橋で降りて、御香宮神社に行く。名水「御香水」が境内にある。この神社には京都市天然記念物のソテツがあり、その実は「延命厄除そてつ守」になっている。鳥せい本店側では名水「白菊水」、月桂冠大倉記念館では名水「さかみづ」を飲んだ。同時に昼間からきき酒で顔が赤くなった。
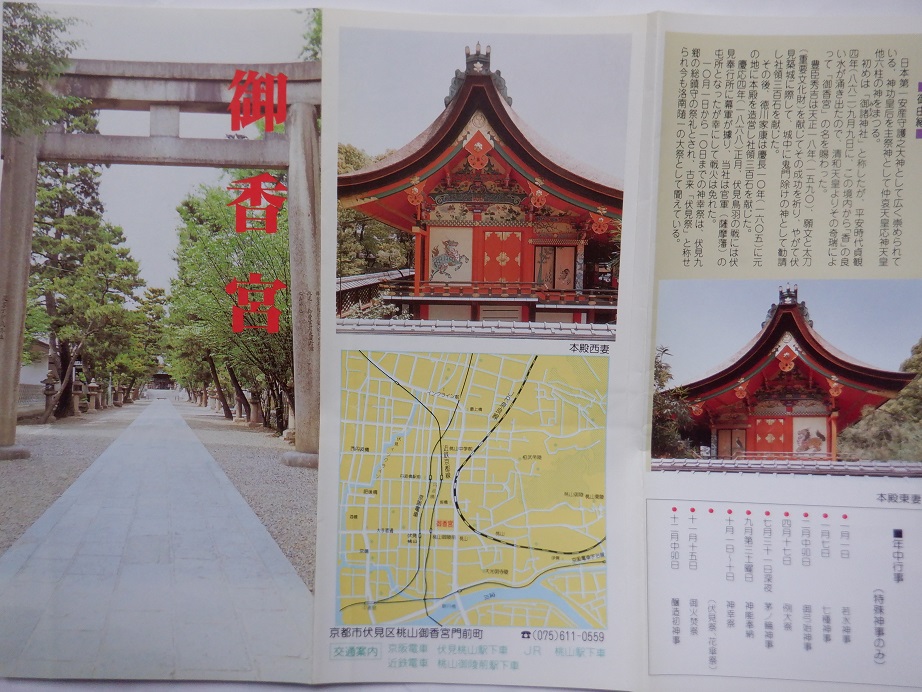

御香宮神社
近鉄奈良駅西口を出て地下道を通って近鉄高天ビルに出て歩道を西の方に歩くと直ぐ通称「山の寺」という看板が見える。奧まったところに「葵」の紋を打った山門が建っているところが浄土宗降魔山「念仏寺」である。門をくぐると降魔山と記された燈篭がある。その傍らに蘇鉄。1614年(慶長19年)11月15日徳川家康が大阪冬の陣の折、木津の戦いで真田幸村の軍勢に敗れ、奈良へ逃げ延び、この地の小字山の寺に至って、桶屋の棺桶の中に隠れ、九死に一生を得た。その後に、家康が豊臣方を破って、天下が治まった、1622年(元和8年)徳川家康の末弟で当時伏見城代を務めていた松平隠岐守定勝が、ここ油坂・漢国町を買い受け、袋中上人を開山として諸堂を建立したのが、山の寺「念仏寺」の始めである。

浄土宗降魔山「念仏寺」
〇御香宮神社は徳川家と深い関わりがある。徳川家康が豊臣秀吉のあとをうけ伏見城で天下の政事をとったおり、尾張、紀伊、水戸の御三家の藩祖と、秀忠の娘千姫はこの伏見で誕生している。御香宮を産土神として特別な崇敬を払っている。御香宮の神門は1622年に水戸中納言頼房(水戸光圀の父)が伏見城大手門を寄進したものと言われている。
□御香宮神社は江戸末期の慶応4年(1868)正月に勃発した「伏見・鳥羽の戦」では、吉井孝助率ら官軍(薩摩藩など)の屯所となった。片や幕府軍は大手筋通りを隔てた南側200mほど離れた伏見奉行所に陣(伝習隊、会津藩、桑名藩、新撰組などが)を構えた。大砲・鉄砲などの弾が激しく飛び交ったが、御香宮は幸いにして戦火には免れている。官軍の屯所となった境内には「明治維新伏見の戦跡」の石碑がある。
寺田屋事件(てらだやじけん)は、江戸時代末期の文久2年4月23日(1862年5月21日)に、伏見の旅館・寺田屋に滞在していた尊皇攘夷の過激派志士が弾圧された事件。薩摩藩の事実上の指導者で藩主茂久の父島津久光はこのとき公武合体を推進する立場で、自らの入京を機に勝手に挙兵討幕を企てる薩摩藩士有馬新七らを快く思わず、志士らの暴発を防止しようと、藩士に命じて従わぬものを上意討ちさせた。同郷の藩士同士が斬り合う凄惨な乱闘となり、7名が死亡して2名が致命傷を負い、後に切腹したものを含めて9人の殉難者を出した。事件後、久光は多くの志士を京都から追放し、勅使大原重徳を擁して江戸に向い、一橋慶喜を将軍後見職、松平慶永を政事総裁職とする幕政改革を行った。→ウィキ
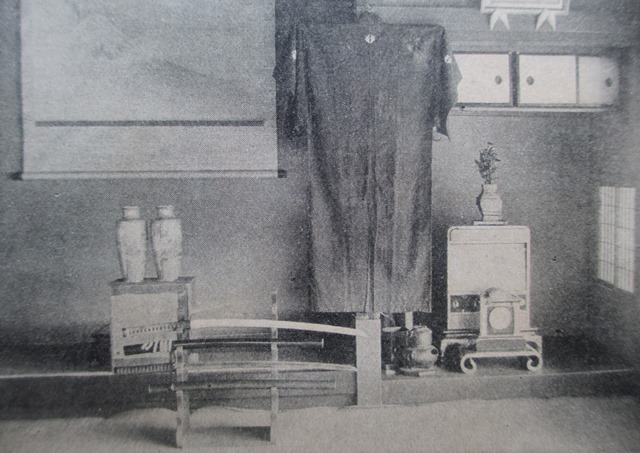
上図単衣は木綿にして奈良原男爵が寺田屋騒動の時着用せられしもの、右肩の白みたる処は血のにじみ付きしものにて五六寸の刀痕あるものなり。/刀ー上段は寺田屋事件の時に用いたもの、下は兄喜左衛門が生麦事件に用いたもの
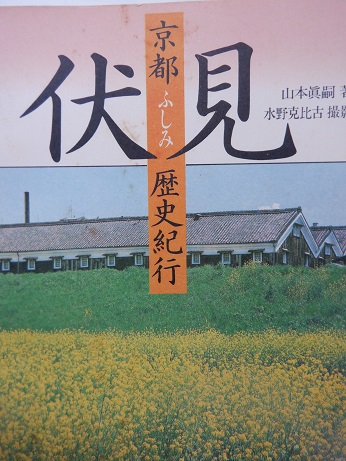
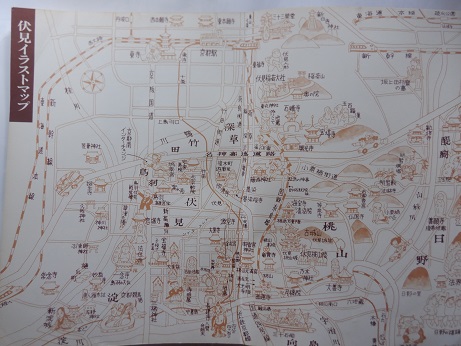
1983年9月 山本眞嗣著・水野克比古撮影『京都伏見歴史紀行』山川出版社
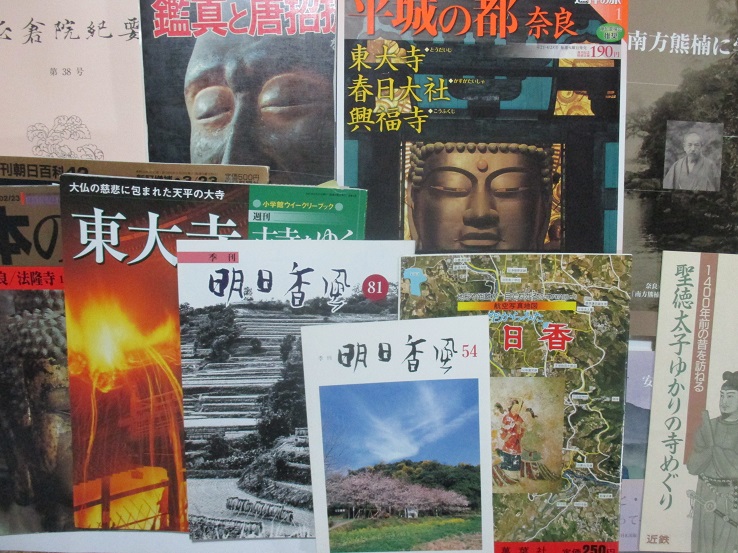
奈良・飛鳥の本
平良盛吉□→1991年1月『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)平良盛吉「村の先生」/平良盛吉(1890年8月28日~1977年6月28日)1912年、沖縄ではじめての総合文化誌『新沖縄』を創刊。琉球音楽研究家。『関西沖縄開発史』の著がある。□→2009年5月『うるまネシア』第10号/新城栄徳「失われた時を求めてー近鉄奈良線永和駅近くに平良盛吉氏が住んでおられた。息子が1歳のとき遊びに行ったら誕生祝をいただいた。袋は今もある」
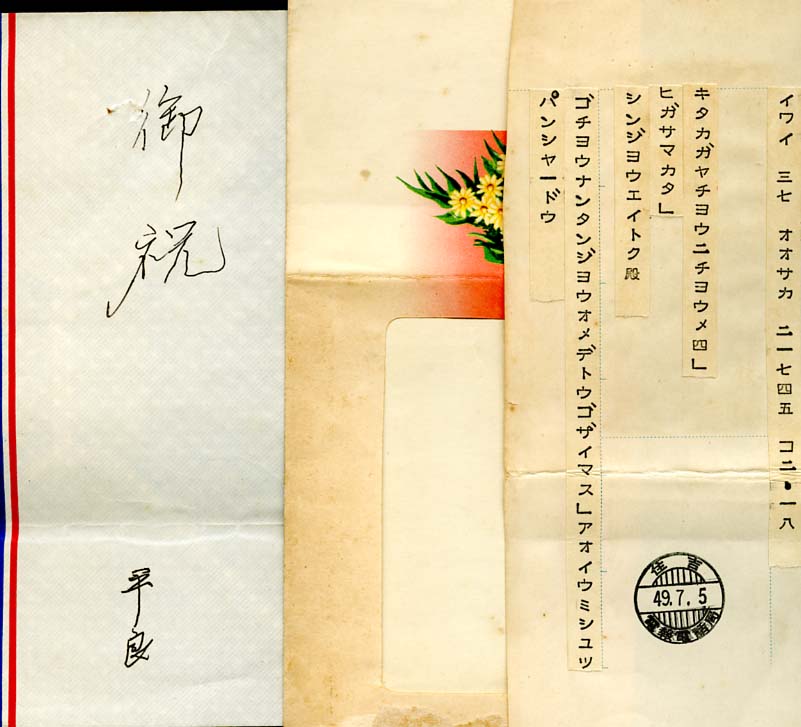
右の電報は青い海出版社から「息子誕生」の祝電である。

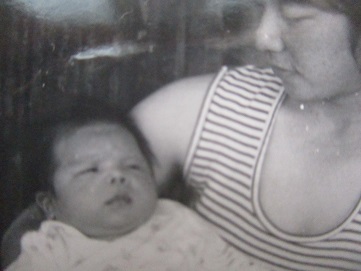
2020-8 こうたろう/1974-7 こうたろうのパパ

伏見桃山城、息子と娘
大阪、奈良の双方から望める金剛生駒国定公園内の大阪生駒霊園に阿氏西平家の墓、近くには大阪沖縄県人会の共同墓地「かりゆしの郷」もある。

元祖阿姓南風原按磁司守忠七世西平親雲上守安四男守秀ー守朋ー守保ー守孝ー守紀ー守諄ー


02/20: 東京/1930(昭和5)年①
1928年11月 エグ・オグニヨフ著/饒平名智太郎・訳『ソウェート学生の日記』世界社
1928年11月『中央公論』饒平名智太郎「出版会のリーダー四人男 講談社の野間氏、改造社の山本氏、新潮社の佐藤氏、平凡社の下中氏其の人と事業の短評。 野間氏は僕の中学時代の国語の先生だ。其頃の野間氏は快活な放胆な、教育者といふよりは一個の遊子ローマンテイストだった。国語の時間に、よく八犬伝を聞かせてくれたものだ。氏の放蕩は、学生の間にも知れ亘っていたから余程遊んだものらしい。それの快打策として当時の中学校長だった大久保氏に世話して貰ったのが、今の野間夫人だ。(以下略)」
1929年7月 饒平名智太郎『プロレタリア芸術教程 第一輯』世界社
1929年11月 饒平名智太郎『プロレタリア芸術教程 第二輯』世界社
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」
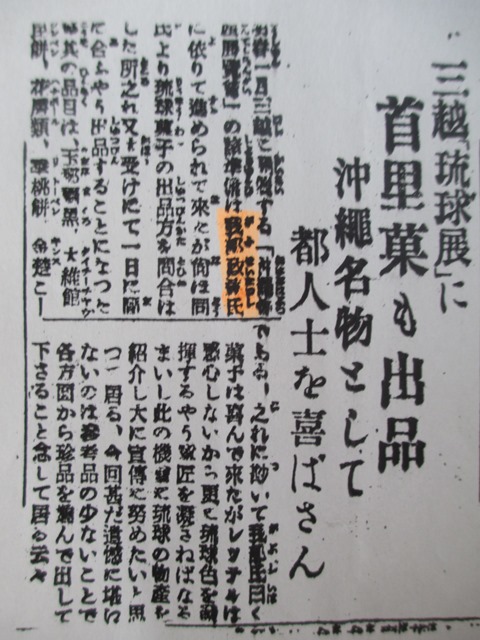
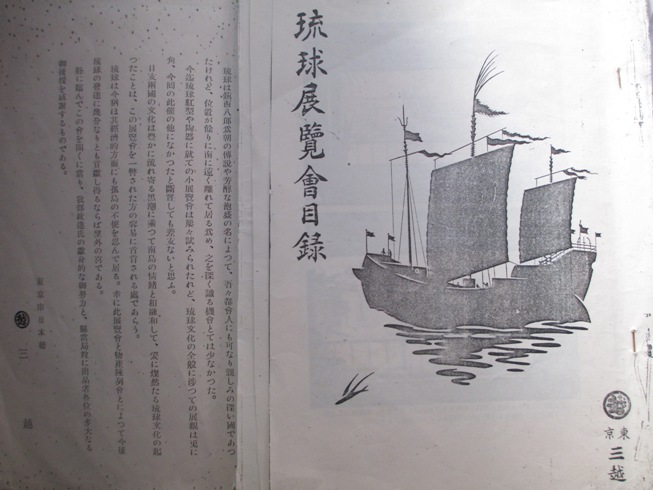

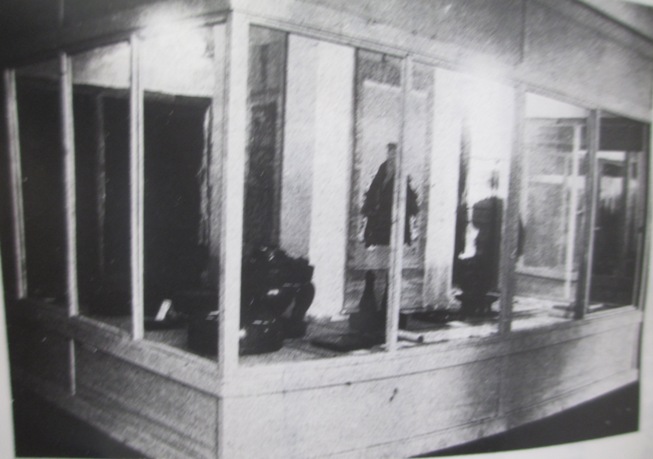
沖縄県立図書館出品の「程順則肖像」が見える
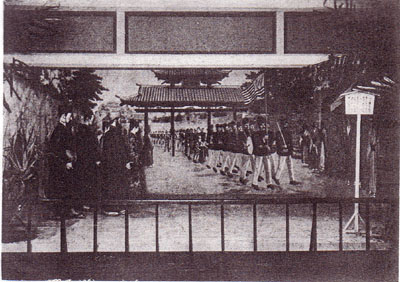
1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」、写真・ペルリ提督の首里城訪問のジオラマ

「二十日正月踊」のジオラマ
1月ー『琉球展覧会出品目録』□永見徳太郎ー琉球女日本男遊楽の図、琉球船競漕の図、琉球人行列/島田佳矢ー琉球木彫聯、琉球木彫額、琉球竹花生、琉球細麻衣(笠、片袖、秋夏模様)、新月型酒入、龍模様花瓶/銘苅正太郎ー東道盆
山村耕花ー麻紅格子衣裳、麻茶地縦格子衣裳、麻紺地蝶梅模様衣裳、麻紺地花笠模様衣裳、麻紺地茄子模様衣裳、麻薄藍地松梅紅葉模様衣裳、木綿薄藍地牡丹鳳凰模様衣裳、木綿白地ドジン、麻風呂敷(三ツ巴に一紋付柳にのし模様)、鼈甲 (廃藩以前婦人使用のもの)、蛇皮線(爪付)、琉球胡弓(弓付)/啓明会ー琉球風俗絵、唐船渡来図、古代紅型裂地(300余年前のもの)、焼物製作に関する証書、紅型型紙図案(15枚)、紅型型紙(11枚)、絣図案(16枚)、絣図案(19枚)、手拭図案(2枚)、墨すり紅型図案(5枚)、風呂敷図案集(2枚)、紅型衣裳(3枚)、古代面 能面(4面)・・・比嘉華山は唐船入港ノ図、尚順は「神猫の絵」、富名腰義珍は唐手軸物、唐手本、唐手写真貼、巻藁(板付)、木刀、十手、唐手術写真、六尺棒などを出品している。①杉浦非水は琉球壺(芳月窯・唐草彫)、琉球壺(南蛮模様彫)を出品。
①杉浦非水 すぎうら-ひすい 1876-1965 明治-昭和時代の図案家。
明治9年5月15日生まれ。グラフィックデザインの開拓者のひとり。地下鉄(昭和2年の開通時)や三越のポスター,たばこのパッケージなどを手がける。図案家の団体「七人社」を設立。昭和10年多摩帝国美術学校(現多摩美大)校長。30年芸術院恩賜賞。光風会会員。昭和40年8月18日死去。89歳。愛媛県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は朝武(つとむ)。(→コトバンク)/日本のデザイン史に燦然と輝くモダンポスターの傑作『三越呉服店 春の新柄陳列会』です。描いたのは、三越の図案部員として次々と傑作ポスターを世に送り出し、「三越の非水か、非水の三越か」と言われるほどの名声を得た近代グラフィックデザインの父・杉浦非水。日本で最初に商業美術という分野を切り拓き、多摩美術学校の初代校長兼図案科主任教授として日本にデザインを根付かせる為に生涯尽力した人物です。(→美の巨人たち)
ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」
1928年11月『中央公論』饒平名智太郎「出版会のリーダー四人男 講談社の野間氏、改造社の山本氏、新潮社の佐藤氏、平凡社の下中氏其の人と事業の短評。 野間氏は僕の中学時代の国語の先生だ。其頃の野間氏は快活な放胆な、教育者といふよりは一個の遊子ローマンテイストだった。国語の時間に、よく八犬伝を聞かせてくれたものだ。氏の放蕩は、学生の間にも知れ亘っていたから余程遊んだものらしい。それの快打策として当時の中学校長だった大久保氏に世話して貰ったのが、今の野間夫人だ。(以下略)」
1929年7月 饒平名智太郎『プロレタリア芸術教程 第一輯』世界社
1929年11月 饒平名智太郎『プロレタリア芸術教程 第二輯』世界社
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」
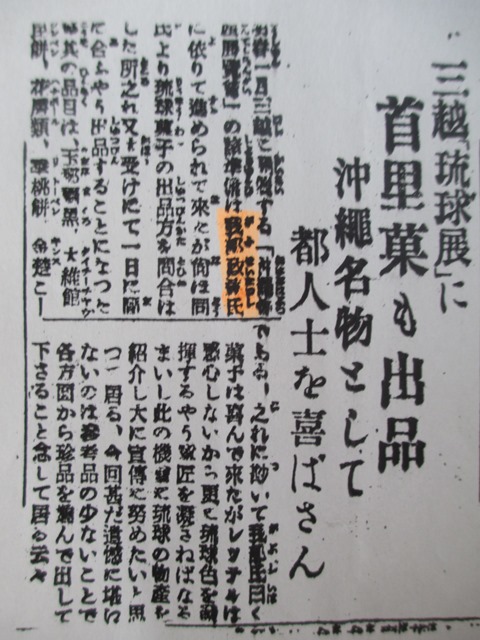
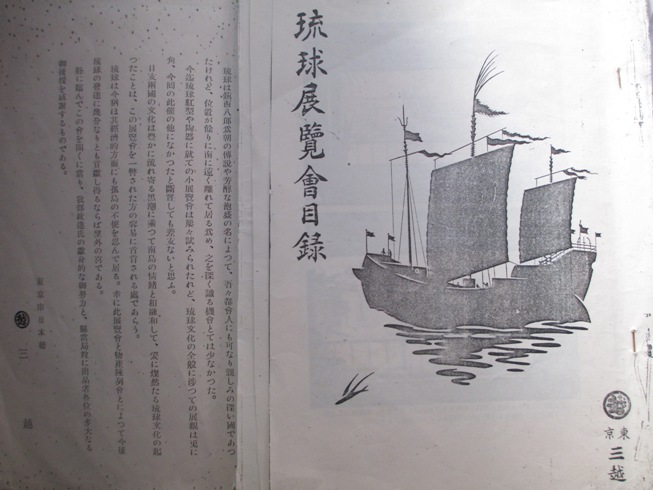

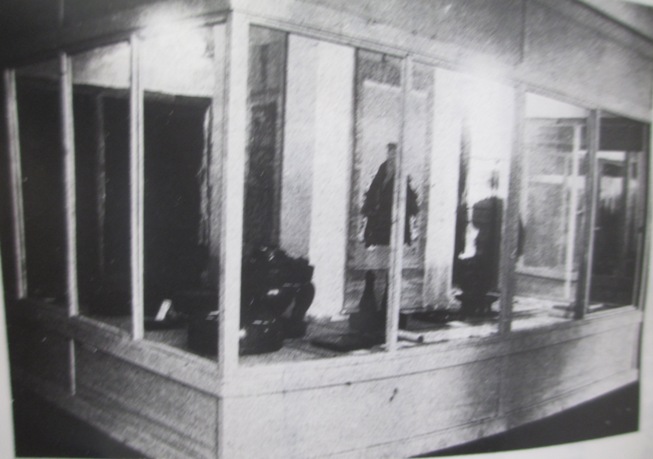
沖縄県立図書館出品の「程順則肖像」が見える
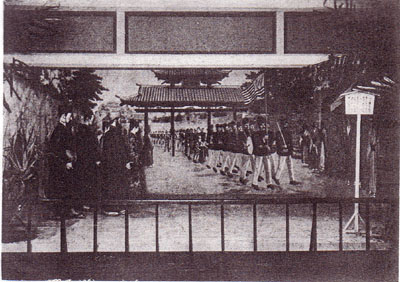
1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」、写真・ペルリ提督の首里城訪問のジオラマ

「二十日正月踊」のジオラマ
1月ー『琉球展覧会出品目録』□永見徳太郎ー琉球女日本男遊楽の図、琉球船競漕の図、琉球人行列/島田佳矢ー琉球木彫聯、琉球木彫額、琉球竹花生、琉球細麻衣(笠、片袖、秋夏模様)、新月型酒入、龍模様花瓶/銘苅正太郎ー東道盆
山村耕花ー麻紅格子衣裳、麻茶地縦格子衣裳、麻紺地蝶梅模様衣裳、麻紺地花笠模様衣裳、麻紺地茄子模様衣裳、麻薄藍地松梅紅葉模様衣裳、木綿薄藍地牡丹鳳凰模様衣裳、木綿白地ドジン、麻風呂敷(三ツ巴に一紋付柳にのし模様)、鼈甲 (廃藩以前婦人使用のもの)、蛇皮線(爪付)、琉球胡弓(弓付)/啓明会ー琉球風俗絵、唐船渡来図、古代紅型裂地(300余年前のもの)、焼物製作に関する証書、紅型型紙図案(15枚)、紅型型紙(11枚)、絣図案(16枚)、絣図案(19枚)、手拭図案(2枚)、墨すり紅型図案(5枚)、風呂敷図案集(2枚)、紅型衣裳(3枚)、古代面 能面(4面)・・・比嘉華山は唐船入港ノ図、尚順は「神猫の絵」、富名腰義珍は唐手軸物、唐手本、唐手写真貼、巻藁(板付)、木刀、十手、唐手術写真、六尺棒などを出品している。①杉浦非水は琉球壺(芳月窯・唐草彫)、琉球壺(南蛮模様彫)を出品。
①杉浦非水 すぎうら-ひすい 1876-1965 明治-昭和時代の図案家。
明治9年5月15日生まれ。グラフィックデザインの開拓者のひとり。地下鉄(昭和2年の開通時)や三越のポスター,たばこのパッケージなどを手がける。図案家の団体「七人社」を設立。昭和10年多摩帝国美術学校(現多摩美大)校長。30年芸術院恩賜賞。光風会会員。昭和40年8月18日死去。89歳。愛媛県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は朝武(つとむ)。(→コトバンク)/日本のデザイン史に燦然と輝くモダンポスターの傑作『三越呉服店 春の新柄陳列会』です。描いたのは、三越の図案部員として次々と傑作ポスターを世に送り出し、「三越の非水か、非水の三越か」と言われるほどの名声を得た近代グラフィックデザインの父・杉浦非水。日本で最初に商業美術という分野を切り拓き、多摩美術学校の初代校長兼図案科主任教授として日本にデザインを根付かせる為に生涯尽力した人物です。(→美の巨人たち)
ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

池宮城友子さん、その作品「島の子守歌ー辺野古2008」

高田陽子さん、その作品「よじれ/distortion」「NO SING」

當銘弓佳さん、その作品「再生」「imitation」

「沖縄~現代日本画作家展2013~」を観賞する佐藤文彦氏
□さとう ふみひこ(美術家/大学講師)1966年東京生まれ。1973年両親とともに沖縄へ移住、現在に至る。沖縄県立芸術大学絵画専攻卒業(1990年)。東京藝術大学大学院後期博士課程油画専攻修了。大学院時代は「琉球の絵画様式」の研究に打ち込み、『「御後絵」再生の現代的意義』にて博士学位取得(1995年)。鎌倉芳太郎著「沖縄文化の遺宝」と出会い、1945年の沖縄戦で消失した歴代の琉球国王の肖像画「御後絵」10点をモノクロ写真をもとに再現し注目された。琉球・沖縄の文化継承や琉球語の消滅、歴史認識が危惧される今日にあって、再現された琉球国王の「御後絵」に対面する事は多くの発見があるだろう。今展では歴代の国王肖像画と佐藤氏の研究の原点とも言える作品を展示する。

6月14日沖縄県立博物館・美術館 講堂「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した美」シンポジウム
■「麗しき琉球の記憶-鎌倉芳太郎が発見した“美”-」関連催事 シンポジウム 美術館
第1部 「“琉球芸術”への今日的視座」
パネリスト:
渡久地 健氏(琉球大学 准教授) 平良 啓氏(株式会社国建 取締役) 粟国 恭子氏(沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員) 岡本 亜紀氏(浦添市美術館 学芸員)
第2部 パネルディスカッション『「鎌倉資料」が現在の沖縄に物語ること』

写真右から平良啓氏(国建 取締役)、粟国恭子さん(沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員)、渡久地健氏(琉球大学法文学部)、岡本亜紀さん(浦添美術館)

写真左から平良啓氏(国建 取締役)、岡本亜紀さん(浦添美術館)、粟国恭子さん(沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員)、倉成多郎氏(壺屋焼物博物館)
同時期開催/6月3日~8日 西村貞雄主催「復元のあゆみー琉球王朝造形文化の独自性を求めてー」

2014年6月15日『沖縄タイムス』那覇】那覇市が若狭の波之上臨港道路沿いの若狭緑地に建設を進めている高さ15メートルの「龍柱」2本の設置工事について、久高将光副市長は「ゲート的なデザインのシンボルモニュメントを設置することで、観光都市としての那覇市の魅力の向上につながる」と述べ、12月末までに完成する予定を示した。9日にあった市議会6月定例会の代表質問で、前田千尋氏(共産)に答弁した。 (略)久高副市長は「若狭の海岸部から国際通りを経て首里に至るルートを都市のシンボル軸のゲートに位置づけ、歴史文化の展開軸として環境整備を図る」と述べた。
■「麗しき琉球の記憶-鎌倉芳太郎が発見した“美”-」関連催事 シンポジウム 美術館
第1部 「“琉球芸術”への今日的視座」
パネリスト:
渡久地 健氏(琉球大学 准教授) 平良 啓氏(株式会社国建 取締役) 粟国 恭子氏(沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員) 岡本 亜紀氏(浦添市美術館 学芸員)
第2部 パネルディスカッション『「鎌倉資料」が現在の沖縄に物語ること』

写真右から平良啓氏(国建 取締役)、粟国恭子さん(沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員)、渡久地健氏(琉球大学法文学部)、岡本亜紀さん(浦添美術館)

写真左から平良啓氏(国建 取締役)、岡本亜紀さん(浦添美術館)、粟国恭子さん(沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員)、倉成多郎氏(壺屋焼物博物館)
同時期開催/6月3日~8日 西村貞雄主催「復元のあゆみー琉球王朝造形文化の独自性を求めてー」

2014年6月15日『沖縄タイムス』那覇】那覇市が若狭の波之上臨港道路沿いの若狭緑地に建設を進めている高さ15メートルの「龍柱」2本の設置工事について、久高将光副市長は「ゲート的なデザインのシンボルモニュメントを設置することで、観光都市としての那覇市の魅力の向上につながる」と述べ、12月末までに完成する予定を示した。9日にあった市議会6月定例会の代表質問で、前田千尋氏(共産)に答弁した。 (略)久高副市長は「若狭の海岸部から国際通りを経て首里に至るルートを都市のシンボル軸のゲートに位置づけ、歴史文化の展開軸として環境整備を図る」と述べた。
1881年5月卒業 速成科
田頭景明(那覇)、知志喜榮(那覇)、富永實政(那覇)、永田長恭(那覇)、花城康故(那覇)
1881年7月卒業 速成科
仲里常徳(那覇)
1881年10月卒業 速成科
仲尾次政雅(那覇)
1881年11月卒業 速成科
照屋興仁(那覇)、山口恵知(那覇)
1882年2月卒業 速成科
饒平名知新(那覇)
1882年4月卒業 速成科
糸数昌功(那覇)、島袋全榮(那覇)、下地寛清(宮古)、砂川昌治(宮古)
1882年6月卒業 速成科
安里昌一(島尻)、太田朝敷(首里)、岸本賀昌(那覇)、謝花昇(島尻)、謝花寛煌(那覇)、高江洲春錦(那覇)、富永實文(那覇)、眞榮田岩助(那覇)
1882年7月卒業 速成科
城間恒洪(那覇)
1882年7月卒業 初等師範学科
嘉手川重慶(那覇)、漢那憲昭(那覇)、比嘉平長(那覇)、松本維榮(那覇)
1882年12月卒業 初等師範学科
伊舎堂孫全(八重山)、大見謝恒有(那覇)、喜舎場英正(八重山)、名嘉眞春教(宮古)、譜久村昌匤(宮古)、松田賀烈(那覇)、安元實明(那覇)
1883年10月卒業 初等師範学科
上江洲由恭(八重山)、嘉数詠詩(那覇)、高良睦喜(那覇)、知念蒲戸(中頭)、平安山長保(那覇)、普久原宗丕(那覇)、眞榮田岩助(那覇)
1883年11月卒業 初等師範学科
大野要一(鹿児島)
1884年11月卒業 初等師範学科
大嶺快安(那覇)、神里多一郎(島尻)、喜屋武英守(中頭)、玉城克全(那覇)
1923年3月卒業 本科第一部
安里永慶(中頭)、安里源秀(中頭・台湾)、新垣信用(八重山・東京深川区毛利校)、新垣壮永(中頭)、上江洲智亭(島尻)、内間仁徳(島尻)、榮野川浩(中頭・旧名)盛貴)、島袋松五郎(中頭)、知念俊吉(中頭・台中州豊原郡神岡校)、吉川眞順(島尻・旧姓 渡嘉敷・東京市本郷区元町校)、仲里朝亭(八重山・台南州新豊郡関廟公学校)、羽地恵信(宮古)、平良恵路(宮古・東京市本所区江東学校)、宮島肇(中頭 ・旧姓 宮城)、宮良寛好(八重山・台湾基隆暖々公学校)、山里昌英(島尻・東京市下谷国民学校)、与那原昌茂(宮古・東京市本所外手校)□1959年5月『オキナワグラフ』「師範学校同期生 大正12年卒ー新垣隆蒸(55・東京工芸社長)、葉山靖(55・旧姓 羽地 江戸川区大杉東小学校長)、喜友名正規(56・江戸川区上一色小学校長)、内間仁徳(56・品川区上神明小学校長)、平良恵路(渋谷区松濤中学校長)、山里昌英(千葉県遠山中学校教頭) 」
1925年3月卒業 本科第一部
石垣英完(八重山・死亡)、糸数昌一(那覇・沖縄県学務課)、伊波嘉三(中頭・国頭楚州校長)、上原健明(島尻)、上里総恭(島尻)、大城亀助(国頭)、兼島方源(宮古)、下地恒忠(宮古・台中州)、島袋貞吉(国頭・東京市中野区野方東国民校)、瀬良垣松重(中頭)、知念清一(中頭)、渡嘉敷眞徳(中頭・死亡)、名幸正期(中頭)、名嘉原安利(中頭)、野原幸輝(島尻)、南風原英寛(八重山・死亡)、比嘉幸全(中頭・東京市中野本郷校)、比嘉永賀(中頭・死亡)、前川守皎(島尻)、宮城清宜(国頭)、宮良寛雄(八重山・朝鮮全州地方法院司法官試補)、本村恵康(宮古・台湾)、屋良朝苗(中頭・台湾台南第二中学校)、屋比久孟林(国頭)、与儀三郎(島尻)
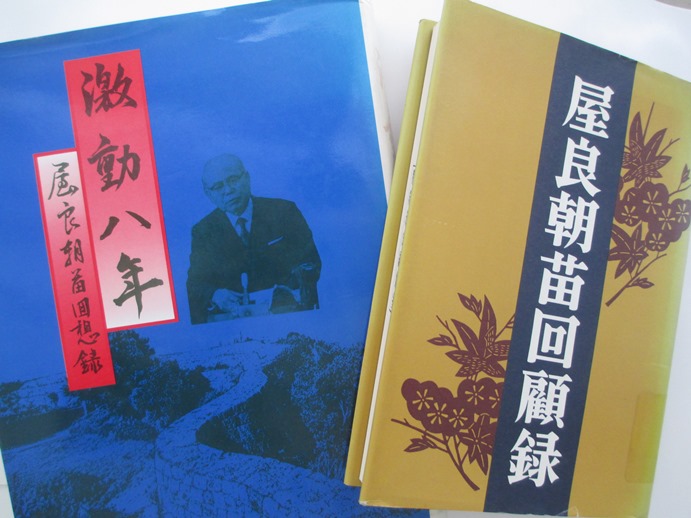
1942年3月卒業 本科第一部
瑞慶村智啓(島尻・八重山与那国校)、砂川恵勝(宮古・与那原校)、西平守晴(八重山・恩納校)
西平守晴□このようにしてようやく卒業、新任教師として国頭郡恩納国民学校へと赴任することになるのです。その間いわゆる徴兵検査を受け甲種合格、しかも海軍への入隊がきまったのが5月末でした。愈々来るものがきたと思うと1年後の4月には軍人として出征しなければならないと思うと、1日1日が惜しまれ身の引き締まる思いで毎日教壇に立ったものでした。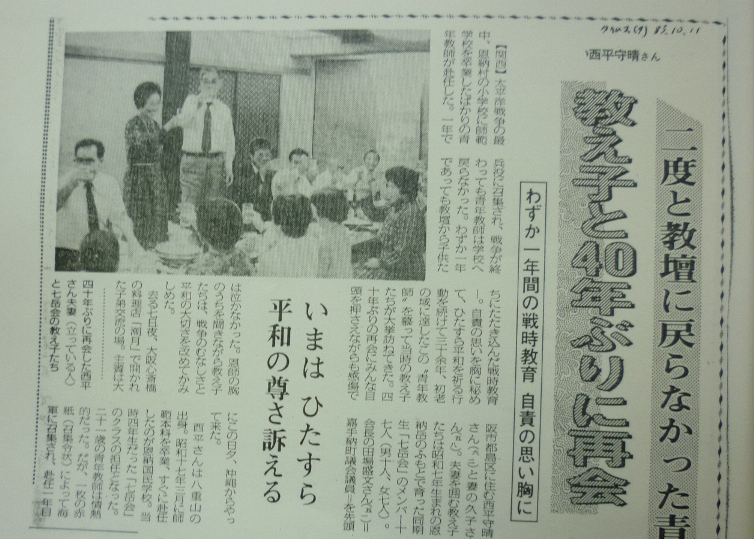
1983年10月11日『沖縄タイムス』「二度と教壇に戻らなかった青年教師ー教え子と40年ぶりに再会」
沖縄県師範学校同窓会資料
田頭景明(那覇)、知志喜榮(那覇)、富永實政(那覇)、永田長恭(那覇)、花城康故(那覇)
1881年7月卒業 速成科
仲里常徳(那覇)
1881年10月卒業 速成科
仲尾次政雅(那覇)
1881年11月卒業 速成科
照屋興仁(那覇)、山口恵知(那覇)
1882年2月卒業 速成科
饒平名知新(那覇)
1882年4月卒業 速成科
糸数昌功(那覇)、島袋全榮(那覇)、下地寛清(宮古)、砂川昌治(宮古)
1882年6月卒業 速成科
安里昌一(島尻)、太田朝敷(首里)、岸本賀昌(那覇)、謝花昇(島尻)、謝花寛煌(那覇)、高江洲春錦(那覇)、富永實文(那覇)、眞榮田岩助(那覇)
1882年7月卒業 速成科
城間恒洪(那覇)
1882年7月卒業 初等師範学科
嘉手川重慶(那覇)、漢那憲昭(那覇)、比嘉平長(那覇)、松本維榮(那覇)
1882年12月卒業 初等師範学科
伊舎堂孫全(八重山)、大見謝恒有(那覇)、喜舎場英正(八重山)、名嘉眞春教(宮古)、譜久村昌匤(宮古)、松田賀烈(那覇)、安元實明(那覇)
1883年10月卒業 初等師範学科
上江洲由恭(八重山)、嘉数詠詩(那覇)、高良睦喜(那覇)、知念蒲戸(中頭)、平安山長保(那覇)、普久原宗丕(那覇)、眞榮田岩助(那覇)
1883年11月卒業 初等師範学科
大野要一(鹿児島)
1884年11月卒業 初等師範学科
大嶺快安(那覇)、神里多一郎(島尻)、喜屋武英守(中頭)、玉城克全(那覇)
1923年3月卒業 本科第一部
安里永慶(中頭)、安里源秀(中頭・台湾)、新垣信用(八重山・東京深川区毛利校)、新垣壮永(中頭)、上江洲智亭(島尻)、内間仁徳(島尻)、榮野川浩(中頭・旧名)盛貴)、島袋松五郎(中頭)、知念俊吉(中頭・台中州豊原郡神岡校)、吉川眞順(島尻・旧姓 渡嘉敷・東京市本郷区元町校)、仲里朝亭(八重山・台南州新豊郡関廟公学校)、羽地恵信(宮古)、平良恵路(宮古・東京市本所区江東学校)、宮島肇(中頭 ・旧姓 宮城)、宮良寛好(八重山・台湾基隆暖々公学校)、山里昌英(島尻・東京市下谷国民学校)、与那原昌茂(宮古・東京市本所外手校)□1959年5月『オキナワグラフ』「師範学校同期生 大正12年卒ー新垣隆蒸(55・東京工芸社長)、葉山靖(55・旧姓 羽地 江戸川区大杉東小学校長)、喜友名正規(56・江戸川区上一色小学校長)、内間仁徳(56・品川区上神明小学校長)、平良恵路(渋谷区松濤中学校長)、山里昌英(千葉県遠山中学校教頭) 」
1925年3月卒業 本科第一部
石垣英完(八重山・死亡)、糸数昌一(那覇・沖縄県学務課)、伊波嘉三(中頭・国頭楚州校長)、上原健明(島尻)、上里総恭(島尻)、大城亀助(国頭)、兼島方源(宮古)、下地恒忠(宮古・台中州)、島袋貞吉(国頭・東京市中野区野方東国民校)、瀬良垣松重(中頭)、知念清一(中頭)、渡嘉敷眞徳(中頭・死亡)、名幸正期(中頭)、名嘉原安利(中頭)、野原幸輝(島尻)、南風原英寛(八重山・死亡)、比嘉幸全(中頭・東京市中野本郷校)、比嘉永賀(中頭・死亡)、前川守皎(島尻)、宮城清宜(国頭)、宮良寛雄(八重山・朝鮮全州地方法院司法官試補)、本村恵康(宮古・台湾)、屋良朝苗(中頭・台湾台南第二中学校)、屋比久孟林(国頭)、与儀三郎(島尻)
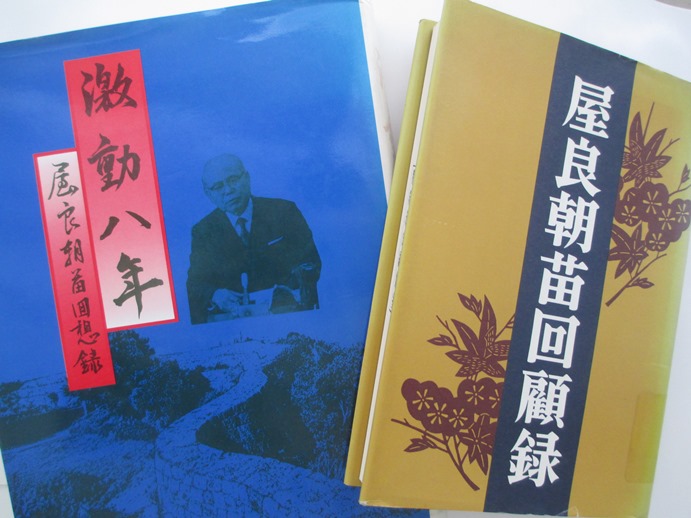
1942年3月卒業 本科第一部
瑞慶村智啓(島尻・八重山与那国校)、砂川恵勝(宮古・与那原校)、西平守晴(八重山・恩納校)
西平守晴□このようにしてようやく卒業、新任教師として国頭郡恩納国民学校へと赴任することになるのです。その間いわゆる徴兵検査を受け甲種合格、しかも海軍への入隊がきまったのが5月末でした。愈々来るものがきたと思うと1年後の4月には軍人として出征しなければならないと思うと、1日1日が惜しまれ身の引き締まる思いで毎日教壇に立ったものでした。
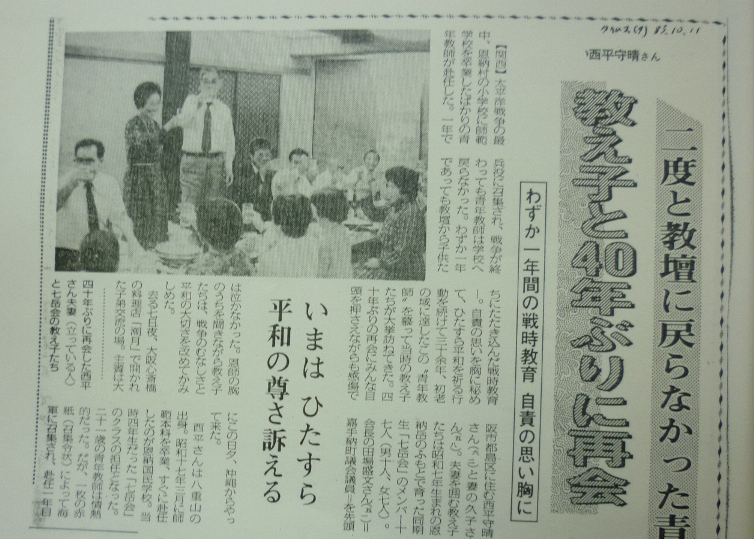
1983年10月11日『沖縄タイムス』「二度と教壇に戻らなかった青年教師ー教え子と40年ぶりに再会」
沖縄県師範学校同窓会資料
05/29: 麦門冬と比嘉朝健
比嘉朝健(1899年11月22日~1945年)
1899年向氏亀山、比嘉カナの間に比嘉次良(次郎)妻はカマド。朝健は父次良、母は辻の女。
1900年7月『琉球新報』「広告ー1、唐茶類 1、銅鑼かね 其他種々ー小生儀此迄諸品買入の為福州へ渡航滞在候處這般帰県右品々廉価に差上げ申候間続々御購求被成下度偏に奉希候也 茶商 比嘉次郎 那覇警察署後通西詰」
1911年1月26日 『琉球新報』「亀山朝恆儀転地療養ノ為メ実父所国頭郡金武村字漢那ニ於テ静養中薬石効ナク去ル二十日死去致シ候此段生前巳知諸君ニ謹告ス 亀山朝奉/朝矩/朝摸/比嘉次郎/朝盛」
沖縄県立第一中学校中退
「女学校の三年生のころ、私はある裕福な家の息子(比嘉朝健)と縁談が進み、卒業までにウブクイ(結納)もとりすましていた。これは松山小学校の教師時代と思うが、解消した。当の婚約者も組合教会に来ていて、私とは話も交わしたりしたが、どうもピンとこない。とっかかりもひっかかりもない感じなのだ。もうこのころ私は、恋愛をへない結婚なんてあるものかとはっきり思っていたので、自分の気持ちが動かないのに困惑した。(略)私は意を決して、二人はどうも合わないと思うので、結婚はやめた方がいいのではと、自分で婚約者に申し出た。ところが相手は母親とは生さぬ仲だったので、自分の方からはどうしても言い出せないから、君の方から直接言い戻してくれという。」金城芳子『なはをんな一代記』(沖縄タイムス社1977年9月)
1920年 沖縄タイムス記者
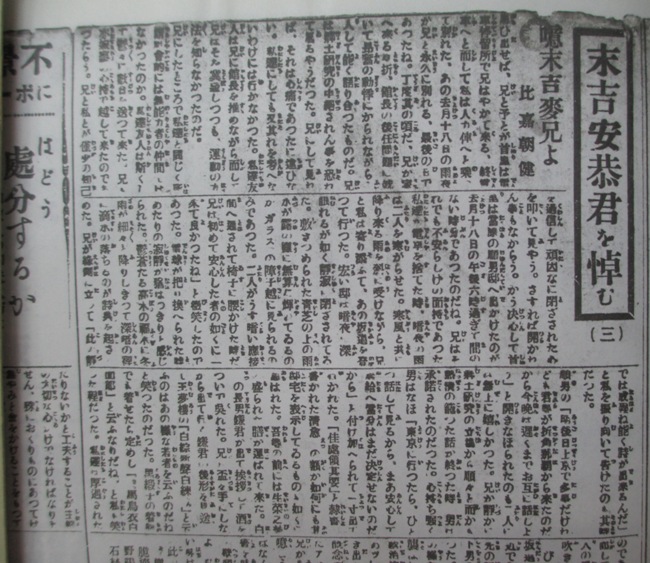
1924年12月16日『沖縄タイムス』比嘉朝健「末吉安恭君を悼む」
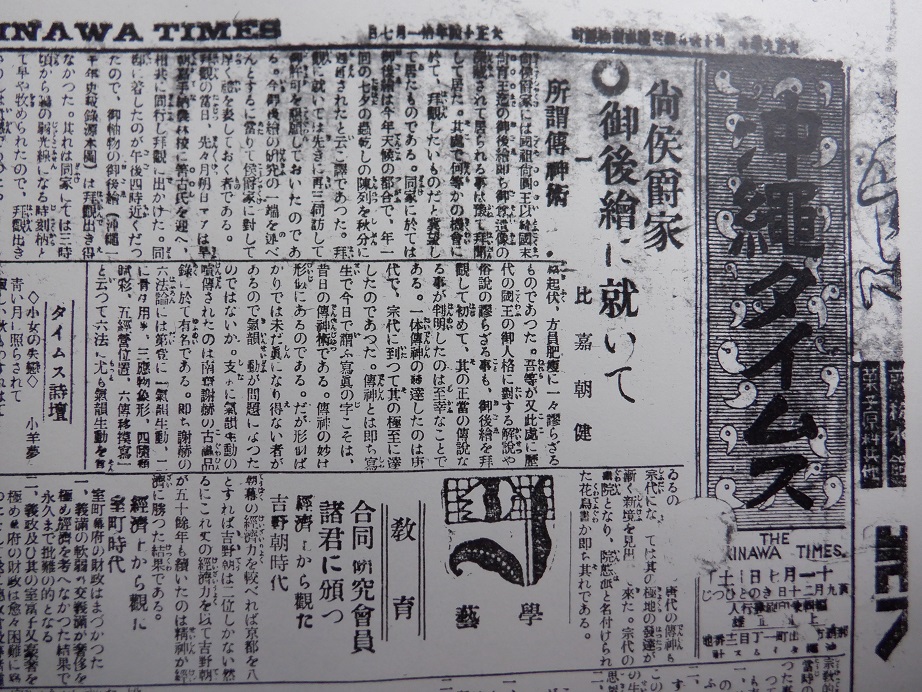
1926年3月、那覇市役所庶務課
1927年6月20日、帝国大学文学部史料編纂掛雇(~1932年1月)
□同僚に森銑三.史料編纂官ー中山久四郎(東洋諸国史料調査)
1937年3月『沖縄教育』第247号/仲吉朝宏「雲海空青録ー博物館たより」
□3月5日帰省中の比嘉朝健氏来訪、之で第2回目である。氏は多年東京に生活せられ、芸術方面の蘊蓄の深い人『陶器講座』第2巻に「琉球の陶器」を紹介せられ、嘗ては自己所有の殷元良の「墨山山水図」を帝室博物館に寄贈せられた特志の人である。今帝室博物館年報の殷元良の記事を録すると
隼者、殷元良は琉球の代表的画人であって、清朝、乾隆帝時代に活躍し、その画風は宗元画風の影響に成り、墨 画彩絵ともに能くした。本図の如きは琉球画の山水図として逸品といふべく、その趣致また日本画と一脈相通ずるも のあるは、日支間に位置する琉球の芸術として感興深きものである。
殷元良の面目躍如たりである。又氏は今迄多数の人が疑問にしていた首里城正殿前の龍柱についても、その作者が謝敷宗相なること、石材が瀬長島海岸から採掘したものなることを、已に大正10年頃に発表せられたとのこと。日支琉の古代芸術の逸品などについて語らるる豊富な話題には只目をみはるのみである。『沖縄などには逸品はありませんよ』と捨台詞のやうな言葉を残して、佐敷方面へ殷元良の先生であった山口呉師虔の子孫を訪問すべく出かけられました。
1899年向氏亀山、比嘉カナの間に比嘉次良(次郎)妻はカマド。朝健は父次良、母は辻の女。
1900年7月『琉球新報』「広告ー1、唐茶類 1、銅鑼かね 其他種々ー小生儀此迄諸品買入の為福州へ渡航滞在候處這般帰県右品々廉価に差上げ申候間続々御購求被成下度偏に奉希候也 茶商 比嘉次郎 那覇警察署後通西詰」
1911年1月26日 『琉球新報』「亀山朝恆儀転地療養ノ為メ実父所国頭郡金武村字漢那ニ於テ静養中薬石効ナク去ル二十日死去致シ候此段生前巳知諸君ニ謹告ス 亀山朝奉/朝矩/朝摸/比嘉次郎/朝盛」
沖縄県立第一中学校中退
「女学校の三年生のころ、私はある裕福な家の息子(比嘉朝健)と縁談が進み、卒業までにウブクイ(結納)もとりすましていた。これは松山小学校の教師時代と思うが、解消した。当の婚約者も組合教会に来ていて、私とは話も交わしたりしたが、どうもピンとこない。とっかかりもひっかかりもない感じなのだ。もうこのころ私は、恋愛をへない結婚なんてあるものかとはっきり思っていたので、自分の気持ちが動かないのに困惑した。(略)私は意を決して、二人はどうも合わないと思うので、結婚はやめた方がいいのではと、自分で婚約者に申し出た。ところが相手は母親とは生さぬ仲だったので、自分の方からはどうしても言い出せないから、君の方から直接言い戻してくれという。」金城芳子『なはをんな一代記』(沖縄タイムス社1977年9月)
1920年 沖縄タイムス記者
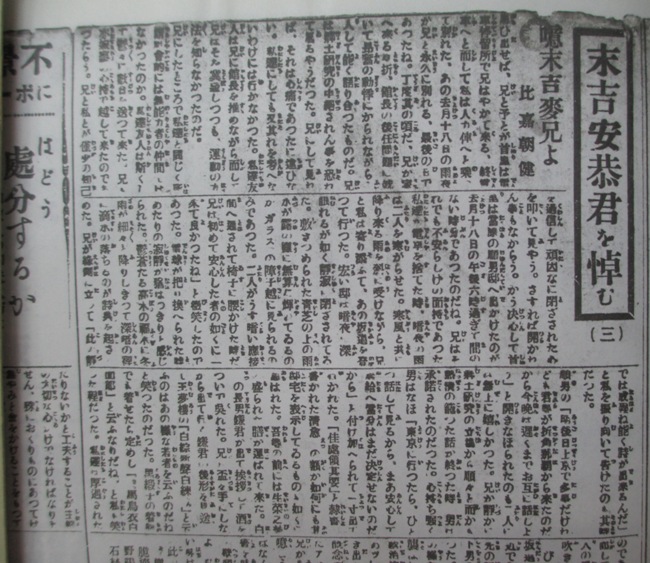
1924年12月16日『沖縄タイムス』比嘉朝健「末吉安恭君を悼む」
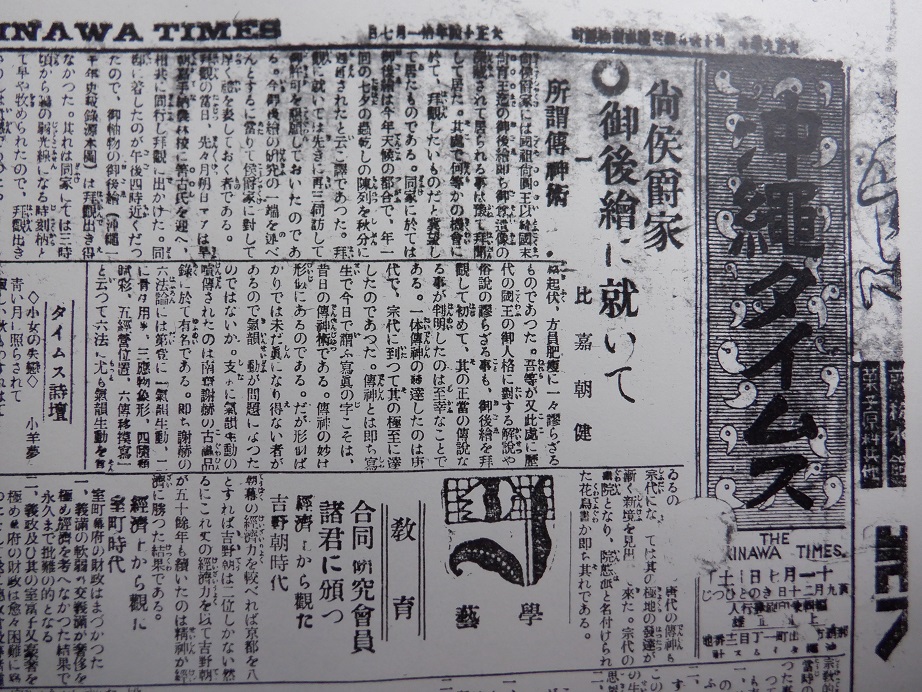
1926年3月、那覇市役所庶務課
1927年6月20日、帝国大学文学部史料編纂掛雇(~1932年1月)
□同僚に森銑三.史料編纂官ー中山久四郎(東洋諸国史料調査)
1937年3月『沖縄教育』第247号/仲吉朝宏「雲海空青録ー博物館たより」
□3月5日帰省中の比嘉朝健氏来訪、之で第2回目である。氏は多年東京に生活せられ、芸術方面の蘊蓄の深い人『陶器講座』第2巻に「琉球の陶器」を紹介せられ、嘗ては自己所有の殷元良の「墨山山水図」を帝室博物館に寄贈せられた特志の人である。今帝室博物館年報の殷元良の記事を録すると
隼者、殷元良は琉球の代表的画人であって、清朝、乾隆帝時代に活躍し、その画風は宗元画風の影響に成り、墨 画彩絵ともに能くした。本図の如きは琉球画の山水図として逸品といふべく、その趣致また日本画と一脈相通ずるも のあるは、日支間に位置する琉球の芸術として感興深きものである。
殷元良の面目躍如たりである。又氏は今迄多数の人が疑問にしていた首里城正殿前の龍柱についても、その作者が謝敷宗相なること、石材が瀬長島海岸から採掘したものなることを、已に大正10年頃に発表せられたとのこと。日支琉の古代芸術の逸品などについて語らるる豊富な話題には只目をみはるのみである。『沖縄などには逸品はありませんよ』と捨台詞のやうな言葉を残して、佐敷方面へ殷元良の先生であった山口呉師虔の子孫を訪問すべく出かけられました。
12/02: 莫夢忌/島袋全発
1920年代、琉球史随筆で大衆を喜ばせた新聞人、末吉麦門冬が24年11月に水死した。その追悼文で島袋全発は「友人麦門冬」と題し「私共の中学時代 客気に駆られ一種の啓蒙運動をなしつつあった頃 麦門冬は蛍の門を出でず静かに読書に耽って居た。あの頃の沖縄は随分新旧思想の衝突が激しかったが物外さんを初め私共の応援家も頗る多かった。氏も恐らく隠れたる同情者の1人であったに違いない。其後私が高等学校に入ってから氏と交わる様になったが一見旧知の如くやはり啓蒙運動家の群の1人たるを失わなかった。私共は苦闘して勝った。啓蒙運動とは何ぞと問われたら少し困る。文化運動と云ってもいい。それを近いうちに麦門冬氏が書くと云っていたそうだが遂に今や亡し。該博なる智識そのものよりも旺盛」なる智識欲が尊い。そして旺盛なる智識欲よりも二十年諭らざる氏の友情は更に尊い。私は稀にしか氏とは会わなかった。喧嘩もした。然し淡々たること水の如くして心底に流動する脉々たる友情はいつでも触知」されていたのである。去年の今頃は私の宅で忘年会をした。そして萬葉集今年の山上憶良の貧窮問答「鼻ひしひしに」や「しかとあらぬひげかきあげし」やに笑い した後 矢張り啓蒙運動の話に夢中になった。今年の春は大根の花咲くアカチラを逍遥し唐詩選の句などを口吟、波之上の茶亭に一夜の清遊を試み歓興湧くが如くであった。せめて晩年の往来をしたので良かったと思う。麦門冬氏の如き詩人は多い。氏の如き郷土史家は少ない。氏の如き友情に至っては今の世極めて稀。今や忽焉として亡し。噫」。
全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。
1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。
1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。
濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。
島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。
また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。
1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。
1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。
全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。
1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。
1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。
濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。
島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。
また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。
1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。
1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。
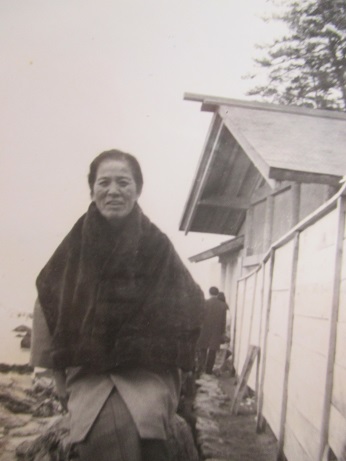
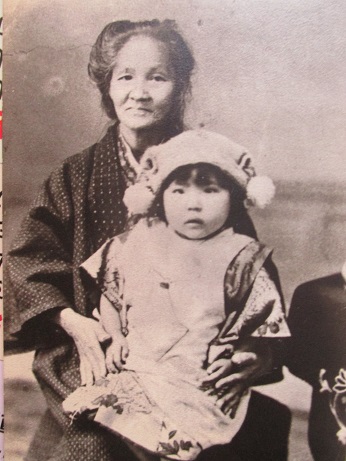
麦門冬妹ウト/貞とパーパー


佐渡山安治御夫妻、二宮忠男・貞御夫妻、末吉麦門冬長女・石垣初枝さん/二宮貞さん
2016年8月18日3時 伊佐眞一氏と首里の万松院通夜室に同行/伊佐氏と共同で作った『琉文手帖』麦門冬特集と、『日本古書通信』「バジル・ホール来琉200周年」をお土産にするという。
2016年8月19日12時 いなんせ斎苑で荼毘

「貞心妙寿信女」 遺族、参列者
2016年8月19日15時 万松院で納骨式

“一握の土”(握り地蔵プロジェクト)二宮貞さん(92)参加

二宮貞の姪であり、麦門冬の孫にあたる石垣市在の、石垣米子詠む
今は亡き 面影しのびつ 捧げなむ
伯母安らかにと 祈る朝夕
今年は二宮貞の姉であり、且つ末吉麦門冬の長女、石垣初枝の25回忌に当たり、その夫である石垣長夫の27回忌を併せて、法要を執り行うとして、麦門冬弟の末吉安久長男で、陶芸家の末吉安允に、法要のお返しとして、お地蔵さんを注文した。そのお地蔵さんを見て米子詠む
おつむなで お顔なでては ほっこりと
合掌地蔵に 心なごめり

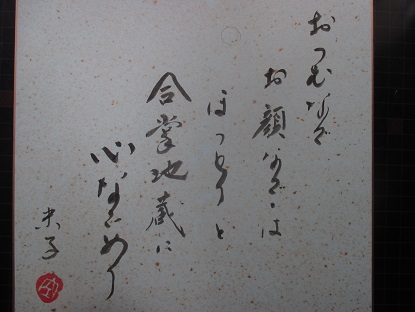
末吉安允作「合掌じぞう」/石垣米子・詠 城谷初治・書


2017年8月16日11時 万松院で「二宮貞1周忌」
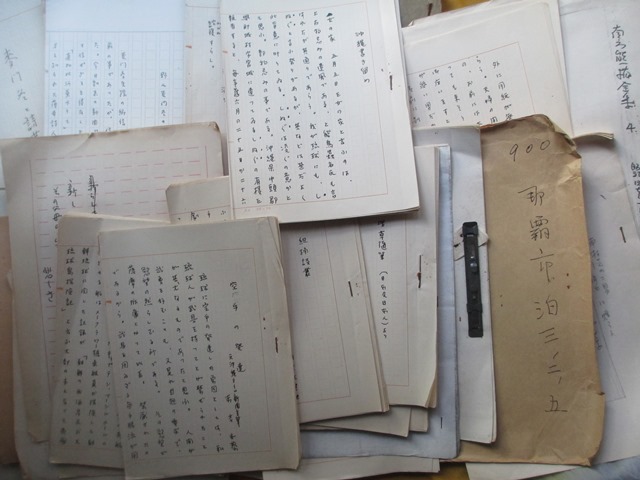
2014年12月5日 首里の末吉安允宅で、安久作成「麦門冬著作・資料」を見る
『琉文手帖』麦門冬特集に富島壮英氏が、麦門冬特集を祝すで「東恩納寛惇の著作・論文などのカード目録を作成していた頃、東恩納文庫の戦前の新聞切抜き帳や各種の目録類に麦門冬の著作・創作などを散見して、彼への関心をもちだしてから10年余になろうか。その頃、元気な宮里栄輝先生から戦前の図書館のこと、研究者のことなどを拝聴している時も麦門冬の話がしばしば出た。このように形成された、おぼろげな麦門冬像は、東恩納寛惇の『野人麦門冬の印象』と相俟って、ますます増長される一方、未知の不思議な人物像の魅力へとつかれていった。7,8年前、麦門冬の末弟の故末吉安久氏が著作集を出すというので、数度東恩納文庫に足を運ばれ、若干の著作のコピーもさし上げたが、ついに日の目を見ずに今日に至っている。おそらく、麦門冬が著作の発表の場とした明治・大正期の雑誌や晩年の30代の新聞が殆どないために、収集に困難をきたしたものと思われる。(後略)」
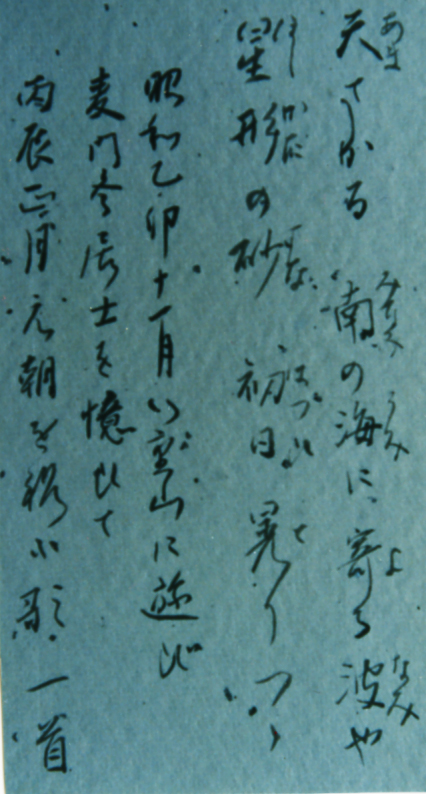
鎌倉芳太郎が1975年11月、八重山に遊び麦門冬の娘・初枝さんと感激の再会。翌年の元旦に詠んだものを書いて石垣市の初枝さんに贈ったもの。
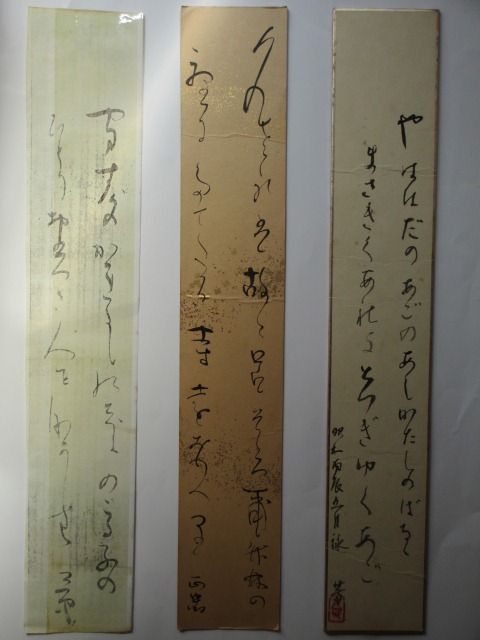
左から折口信夫(複製)短冊ー麦門冬の娘・初枝さんに贈ったもの。/山城正忠/鎌倉芳太郎短冊ー麦門冬のことを聞いた新城栄徳に鎌倉氏が贈ったもの。娘の嫁ぐ日に詠んだ歌だが、その娘の名が恭子さんであるのは偶然なのか。
03/25: 1928年2月 南島研究会『南島研究』創刊号
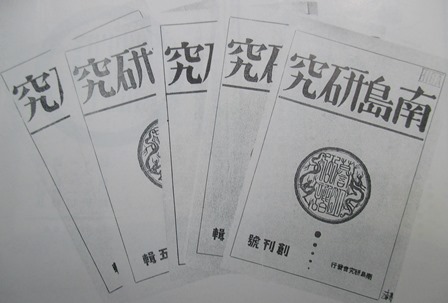
写真ー『南島研究』
南島研究発刊について
世界の文明が、地中海からして大西洋に移り、それから今や漸く太平洋に転ぜんとしつつあるといふ、所謂過渡期に於いて、この太平洋に裾を洗われて居る我が日本の先覚者が、太平洋問題を提げて学界に馳駆せようとせらるることは、近来の痛快事である。これ地中海①に七十倍し、大西洋に二倍するといふ、范々たる大海原のうちには、あらゆる気候とあらゆる人種、あらゆる文化が宝蔵されて居るからである。而して九州の南端から奄美大島を貫いて、東北よりして西南に延び、数十顆の連珠のやうな大島小嶼が、宮古島を経て八重山島の与那国島に至って尽き、この面積が百三十九万里を算しているのが、即ち我が沖縄群島である。この外にも、今から三百余年前に、政治的に切り離されて、鹿児島県に隷属して居る奄美大島諸島も、亦天然の配置としては、往古より琉球王の治下に属し、その人情風俗言語習慣などより考察しても、純然たる琉球人であることは、誰しも首肯せられるだろうと思われる。これらの群島は、東は一帯に太平洋に面して、北は鹿児島県に隣接し、南は一衣帯水の台湾と相呼応し、西は海を隔てて南支那の福建省と相対峙し、而して西南の方は遥かに南洋群島を顧望して居るのであるから、面積の割合にその拡がりは、なかなか大きいように観ぜられるのである。これらの主島が、今日の所謂沖縄島で、我邦本土では、既に一千余年前に於いて、阿児奈波島として知られ、国史とも多くの交渉を保って居るようである。のみならず記録にあらわれた時代からしても、既に五六百年から支那本国や安南、暹羅、馬刺加、朝鮮なども交通し、また爪哇や、比律賓などの南洋諸国とも貿易をやっていたのであるが、之れらは今から三百余年前の所謂薩摩と附庸関係を生じた慶長の役を末期として断絶してしまったのである。
斯やうに沖縄は、往古からして我が本土とは勿論密接な関係があり、また支那本国や南洋諸島などとも関係を有していたために、之れらの影響をうけたのであらうか、一種独特の文化を生んだ一島国であったのである。が交通が不便で顧みられなかったために、今古千年の夢は封ぜられ、恰も武陵桃源のやうな仙境にあったので、外界から能くその真相を知られる機会がなかったのである。それが、幸か、不幸か、その地理的環境のために、能く外国の文化を我が本土に伝へる中継場となると同時に、また我が本土の古文明を忠実に保存する倉庫のやうな、作用をなしていたのである。併しかやうな、神秘的な島国も、廃藩置県後の文明の風潮には、抵抗することが出来なかったやうで、所謂新文明の醗酵すると共に、古琉球の文化は危機に瀕した時代もあったのである。即ち一知半解の徒輩が琉球研究を以て復古思想の再燃と誤解し、古文書の棄却や、名所旧跡の破壊が到る所で企てられ、将に薩州治下に於ける、奄美大島の覆轍を踏まふとしたのであった。
此時に当ってー即ち明治二十五六年頃ー県の中学校に教鞭を執られて居った田島利三郎氏や新田義尊氏や黒岩恒氏などが、琉球の過去現在に趣味を持たれて、その歴史や、歌謡言語及び自然科学などの研究をはじめ出して、漸くこれが価値づけられて、彼等の自覚を促がしこれと前後してわが分科大学講師のチャンバレン氏等も亦渡琉せられて研究をされたのである。是から引きつづいて幣原坦博士や、鳥居龍蔵博士・金沢庄三郎博士なども来県されて、各部門の研究を発表され、暗黒なる琉球が漸く光明へ出されるやうになったのである。而してこれより先土着の沖縄人にも、亦故喜舎場朝賢翁や山内盛憙翁などのやうな郷土研究家もあったけれども、之れが最も高潮されたのは明治の末期からで、即ち畏友伊波普猷氏や、東恩納寛惇氏や、故末吉安恭氏等の研究であったやうに思はれる。これから、古琉球の文化が漸く識者の間に認めらるるやうになったが、未だ一般には徹底しないで疑心を以て迎へられたようであった。然るに最近に至り、柳田国男氏や、伊東忠太博士、黒板勝美博士等の来県があり、これら巨擘を中心として在京諸友は勿論県外の人では、畏友鎌倉芳太郎氏などが、その専門の立場からして、熾に中央で琉球の文化を紹介せられ、又南島談話会なども生まれて東都に於ける琉球研究者の機関も出来るやうになり、殊に啓明会などの財団法人もその研究に同情されて資金を投ぜられ、これで一層鼓吹されたやうに思はれる。
而して琉球研究は、その本場を離れて、中央に持ち出された喜ばしい現象であるが一方郷土に於ても亦之れが閑却せられているといふ訳ではない。逐年この種の研究や紹介は、却って熱烈さを加へて進んでゆくやうであるけれども、之れが機関となるべき定時刊行物がなかったのを最も遺憾とする次第であった。然るに、今回微力を揣らず、吾々同人が主となって、此の「南島研究」といふ小冊子を刊行する機運になlったのは、相互にその研究を援助してこれを発表批判すると同時に、広くこの種研究家の声援を得て、その内容を豊富にし、且つ琉球に関する、滅びゆく古今の研究資料を蒐集して附録とし、広く一般学界の参考に供したい為である。この恵まれたる地理的環境からして、日支文明の交叉点ともいはれまた我邦文化の中継所となり、倉庫ともなった南島、即ち奄美大島から八重山の先端与那国島までの島彙が吾々の研究に資すべき舞台面である。が、この未開拓の曠野からして、何か新生命が見出されて、我が学界に光を投じ得るや否やは、未来の問題で、切に識者各位の熱誠なる御同情と、御後援を待つばかりである。 十一月廿日 県立図書館郷土資料室にて 真境名安興
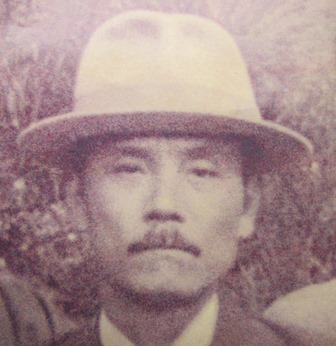
写真ー真境名安興
目次
口絵「泉崎及び金武の火神」
○編集者よりー資料や文献は割拠して居る、系統的に出来た索引のないことはその資料及文献の蒐集に不便な、地方の孤独な研究家をただ空しき努力に終わらせるばかりだ。と云ふことはしばしば吾等が聞く言葉でありました。即ち既に何人かの手によって研究、発表せられた事柄を、これから準備し、これから研究し、かくて仔々倦まざる多年の努力が空しき結果に終ると云ふことになると、本人ばかりの失望でなく、同じ研究者の一員としても見るに忍びないところであります。かくの如き有様でありますから、われらの念頭からは絶えず、何等かの方法で、かかる孤立の研究者たちと連絡をとり、各自の分担的研究を漸次進めて行きたいと云ふ念が去りませんでした。
そこに生まれたのが南島研究でした。なるほど本誌は小冊子ではあり、特に南島研究と銘をうってはありますが、吾等は目を睜つて南島を見たい、そして南島から広い世界を見たいのであります。本誌の主義も、事実の忠実なる採録、文献の尊重と比較研究法の正確を期することに重きを置きたいものだと思って居ます。かくて本誌は読者諸君の本誌であり、又諸君の薀蓄を傾け、互に幇助示導しつつ、吾等の拠るべき、向ふべき道を進んで行きたいのでありまして、吾等は零碎なる報告、交詢の類と雖も克明にこれを雑誌に網羅するに吝ではないのであります。吾等の雑誌は割拠もしなければ、対峙もしない、どこまでも吾等の過去及び現在の記録としたいものであります。
本誌の誇として特筆すべきは、古琉球に関するあらゆる史料の採録で、これのみにても既に一大事業ー吾等としてはーと云ふに恥じないつもりであります。本号から「琉球國中山世鑑」「球陽遺老説傳」「東汀随筆」の三種を採録しました。これは読者諸君の便をはかり、まとまった一冊の本に製本の出来る様に丁附を別にしてあります。
史論・雑録
南島研究の発刊について・・・真境名安興/奈良帝室博物館の雲板について(琉球國王尚泰久の鋳造)・・・真境名安興/火神の象・・・奥野彦六郎/沖縄の士族階級・・・島袋全発/昔の蘇鉄地獄・・・T生/鬼餅伝説(ホーハイに就いて)・宜野湾新城のムーチー/歴史は繰返すー蔡温の林業政策ー/「あこん」に就いて・・・岩崎卓爾/萬葉歌と琉歌・・・エス・エス生
史料
1、琉球國中山世鑑 2、球陽遺老説傳 3、東汀随筆
通信
柳田國男氏より盛敏氏へ/伊波氏より島袋全発氏へ/東恩納氏より真境名笑古氏へ/岩崎氏より真境名氏へ
莫夢忌/1924年12月14日 『沖縄タイムス』仲吉朝助「嗚呼末吉君」
○此の二三十日来、私は俗務に追われて末吉君と面会せなかった。然るに去る9日の夕刻、突然に君の生命に関する不安の噂さを聞いたのでマサカとは思ったが先ず念のためにと君の親友なる小橋川南村君を夜中に訪ふた、南村方で漢那浪笛と小嶺幸欣君とそして主人が鼎座して悲痛の面持ちで打ち沈んでおったが、南村君は私に「只今末吉君を葬送して帰って来たばかりだ」と語ったが、私は自分の耳を疑って、2回も3回も繰り返して聴いて終に君が此の世の人でないことを知った。嗚呼末吉君、君には永久に逢うことが出来ぬのか、私は何とも形容の出来ぬ不安の心持ちでしばらく沈黙して、只だ自分の心臓が波高き鼓動を聞くのであった。吾々4人は沈み勝ちに君の在り世の事ども語りつつ私は夜半の1時過ぎに愴悽たる寒月の冷光に照らされて宅に帰ったが君の面影は眼前にチラついて殆ど夜明まで一睡もせなんだ。ドーしても私は末吉君の死んで居ることを信ずる事は出来ぬ、私の胸裏には今に末吉君は生きて居る、恐らくは苟も学芸の一端でも知って居る我が沖縄人の頭に君は永久に生きて居るであろう。
末吉君、博聞強記で特に琉球文学界の権威であったのは私の申すまでもないことで今更に喋々せぬ、君は天才であって同人間には可なり逸話も多い。私と君とは殆ど十六七年来の知り合いで、君と謹談した機会も相当に多いが、私は君より殆ど二十も年上である関係で君は九骨なる私に対しても常に先輩を以て過ごするので私としては愧ち入って居た、宴席などでも君は私などに対しては無邪気なイタヅラなどもせなかったので、私は君の逸話の材料を持って居ない。ソレ程君が私に対して尊敬の心持ちで交際して呉れた程私は君に対する哀悼を深刻に感ずる次第である。君は文芸上の趣味は頗る多い。この七八年間君は漢詩の研究にも手を染めて来た、私も漢に就いては下手の横好きで漢詩に関して君と数々話し合って居たが先月の中旬頃 図書館で君と面会した、コレは最後の面会であった、其の際 私は君に向かって「万葉」の講議を聞かして貰いたいと頼んだ処、君は謙譲の態度で二三回遠慮したがトウトウ私の持って居る清朝人の四五種の詩集を貸すとの交換条件で来年1月頃から君は私の為に「万葉」の講議をして呉れることを承諾して居た。嗚呼 私は永久に君の万葉講議を聴くことが出来なくなった。
タイムス社の上間君から末吉君に関する私の感想を書いて欲しいとの申込を受けて筆を執ったが、今に末吉君の面影が眼前にチラついて万感が胸に迫るので、私は筆を此辺で止める。嗚呼末吉君、君には果たして永遠に面会することが出来ないのか。
仲吉朝助(1867年4月6日~1926年9月3日)

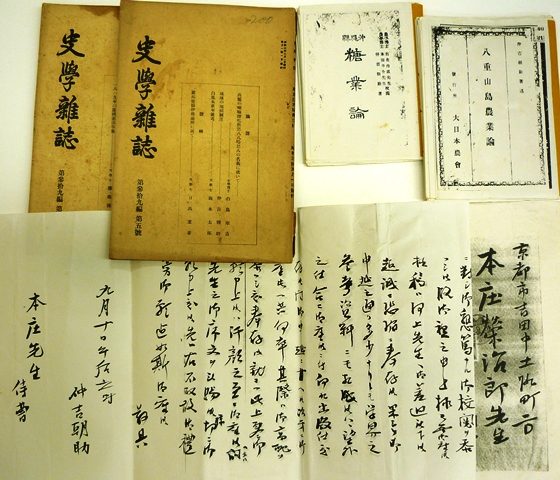
本庄栄治郎 ほんじょう-えいじろう
1888-1973 大正-昭和時代の経済史学者。
明治21年2月28日生まれ。大正12年京都帝大教授。昭和17年大阪商大学長。戦後は上智大,大阪府立大の教授を歴任。近世日本経済史・経済思想史を専攻。日本経済史研究所を設立して後進の育成にもつくした。「本庄栄治郎著作集」がある。40年文化功労者。昭和48年11月18日死去。85歳。京都出身。京都帝大卒。(→コトバンク)
12/04: 龍脈(核の時代)/2015年12月 「若狭龍神」
この「龍柱」は那覇市と中国福州市が、昭和56年(1981年)の友好都市締結から平成23年(2011年)で30周年を迎え、今後の両市の友好・交流を記念して建設されたものであるので、正式には「那覇・福州友好都市交流シンボル像」と云う味も素っ気もない名称だ。だから私は下記のようなことも踏まえて若狭「龍柱」を若狭「龍神」とした。
2014/首里城写真
最近、首里城にちなむ映像写真が話題となっている。4月21日の新報、タイムスの「焼失前の首里城カラー映像」や、5月4日の新報、タイムスの東京在住の写真収集家の「明治の沖縄29枚」である。来る5月20日~6月22日、沖縄県立博物館・美術館で「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した美」が始まる。首里城関係写真も多い。
首里城北殿の階段
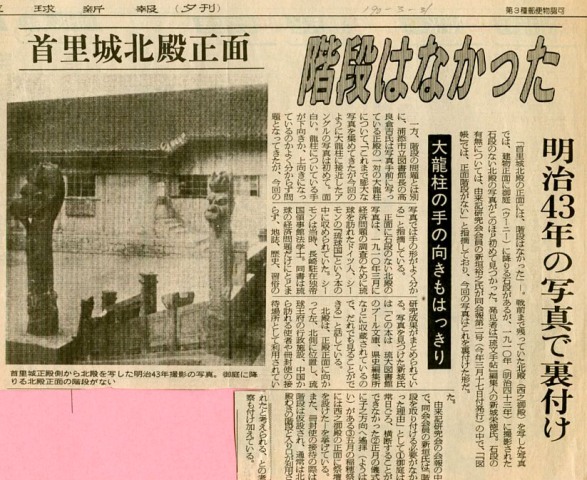
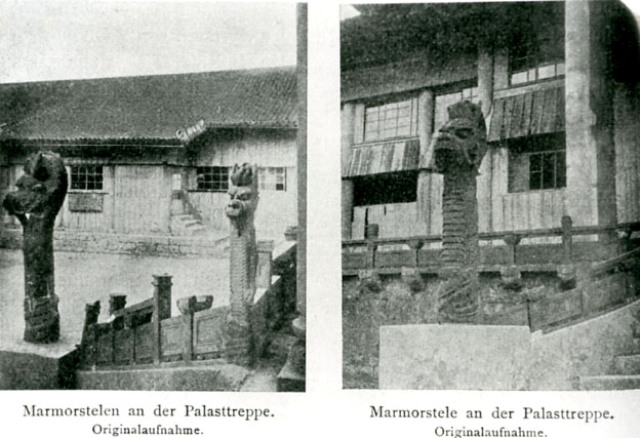
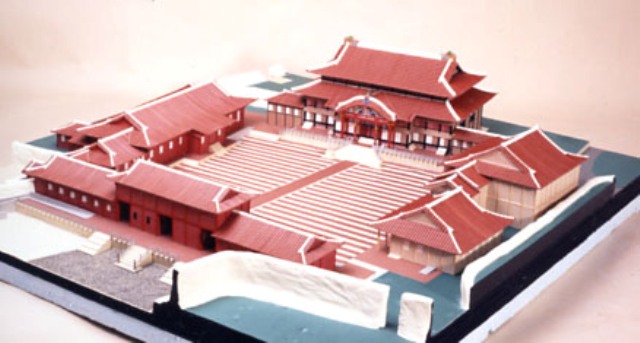

今の所、写真で古いと思われるものは伊藤勝一コレクションの「首里城」である。龍柱が本来の高さで正面向きだ。

今回東京で見つかった明治の沖縄写真は、沖縄写真史の基礎資料とも云うべき『青い目が見た「大琉球」』(1987年8月ニライ社)を見ると1893年3月に来沖したバジル・ホール・チェンバレンの「琉球紀行」で使われた写真にあるから、殆どがチェンバレンが関わっていると思われる。
バジル・ホール・チェンバレン(Basil Hall Chamberlain, 1850年10月18日 - 1935年2月15日)は、イギリスの日本研究家。東京帝国大学文学部名誉教師。アーネスト・サトウやウィリアム・ジョージ・アストン(William George Aston)とともに、19世紀後半~20世紀初頭の最も有名な日本研究家の一人。彼は俳句を英訳した最初の人物の一人であり、日本についての事典"Things Japanese"や『口語日本語ハンドブック』などといった著作、『古事記』などの英訳、アイヌ[1]や琉球[2]の研究で知られる。→ウィキペディア
1997年11月 川平朝申『終戦後の沖縄文化行政史』月刊沖縄社
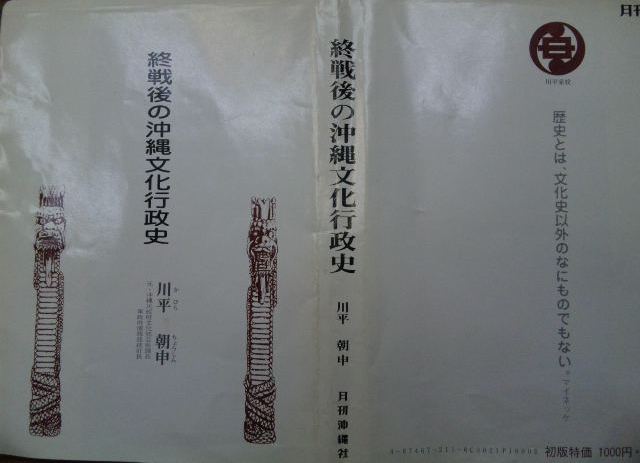
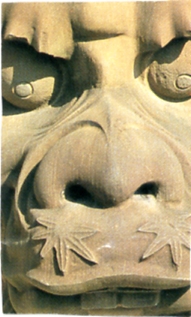
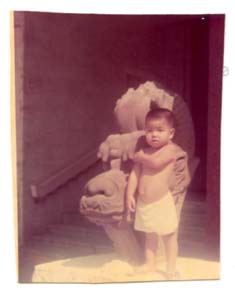
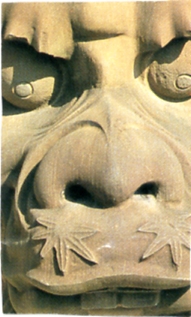
□現在の大龍柱は沖縄神社拝殿の名残を留めて向き合っている。本来は正面向きである。みーぬしんは下方に付いていて、うなーを見下ろすようになっている。真ん中の写真は現在は沖縄県立博物館・美術館にある龍柱で、暑がりの息子が立っている。


2015年12月6日
8日の産経ニュースは「姿を現した2体の龍柱 那覇で設置工事完了 「翁長市政」で推進 中国向け?事業に批判も」と、右派らしく判で押したように報じていた。
若狭
□1979年6月ー邦光史郎・日竎貞夫『丹後若狭路』(カラーブック467)保育社□邦光史郎「若狭・丹後の旅ー敦賀湾の美しさを手放しで礼讃できないのは、この半島に建設された原子力発電所があるからで、福井県は世界でも例を見ない、原子力発電所のメッカで、ずらりと各種タイプの原子炉や、高速増殖炉が並んでいて、不気味である。原子力発電の安全性は保証つきだと政府や電力会社が囃し立て、一基について十億円を超える金が地元に落ちるというので、市町村は原子力発電所の誘致に熱心だが、もし万一事故が起こったら、死の灰に汚染されないとも限らないのである。(略)美しい北陸の海岸は、原子炉の墓標の立ち並ぶ死の海と化しかねない。目先の欲に釣られて、郷土の美を売るようなことはしたくないものである。」


2015年11月22日ー若狭に完成間近の龍柱
那覇市の若狭緑地で市が建設を進めている「龍柱」事業は本体の石材設置作業が22日までに完了し、2体のうちの1体は、覆っていたブルーシートの上半分が外された。前足を掲げた龍の顔面などを見ることができる。1体は海に向かって右側の柱。 現在、周辺整備などの外構工事を進めており、12月25日までに終了する予定。中国福州市との友好都市締結30周年を記念し、計画された。 同事業は当初、一括交付金2億6700万円を使って進めていたが、工事が遅れるなどして活用を断念。市の単独予算を持ち出し工事を再開していた。6月に会計検査院の実施検査を受けたが、「不適切」などの指摘はなかった。→11月23日沖縄タイムス
日本共産党の志位和夫委員長は3日、国会内で記者会見し、
戦後の米軍による土地の強奪、「銃剣とブルドーザー」を用いた無法な基地拡張が沖縄の基地問題の原点であり、「海上の銃剣とブルドーザー」による辺野古新基地を許すのか、この間の一連の選挙で示された新基地建設は許さないという民意を無視することが許されるのかと、知事が問題提起したことの重要性を強調しました。
(略)知事の問題提起に対し、国側代理人が「政治的議論をする場ではない」と言い放ったことについて、志位氏は「沖縄の基地問題について聞く耳を持たない、議論もしないという態度は許し難い。まさにごう慢、強権を象徴するような発言です。いまの安倍政権の姿勢が表れている」と批判。
上記の志位和夫委員長の発言の通りアベ政治はアメリカ黒人大統領オバマ軍の協力も得て下記の通り「まさにごう慢、強権を象徴」粛々と沖縄県民の怒りをかっている。次の選挙で自公は壊滅させねば沖縄の未来は無い。
2014/首里城写真
最近、首里城にちなむ映像写真が話題となっている。4月21日の新報、タイムスの「焼失前の首里城カラー映像」や、5月4日の新報、タイムスの東京在住の写真収集家の「明治の沖縄29枚」である。来る5月20日~6月22日、沖縄県立博物館・美術館で「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した美」が始まる。首里城関係写真も多い。
首里城北殿の階段
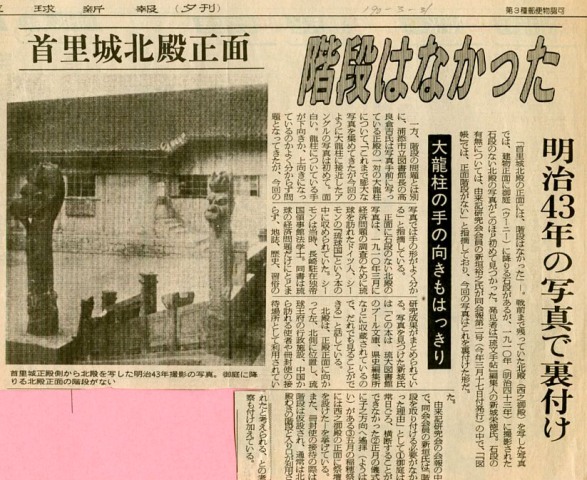
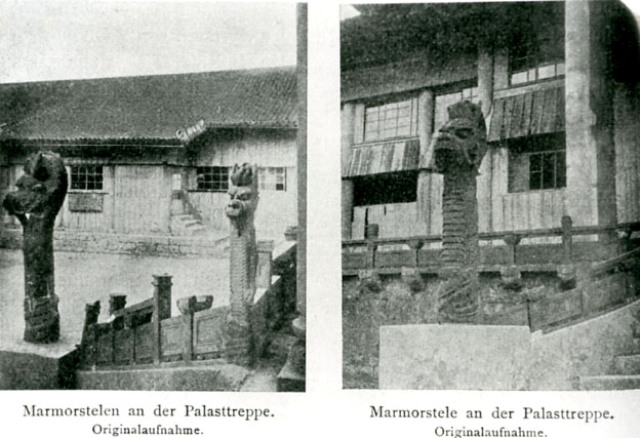
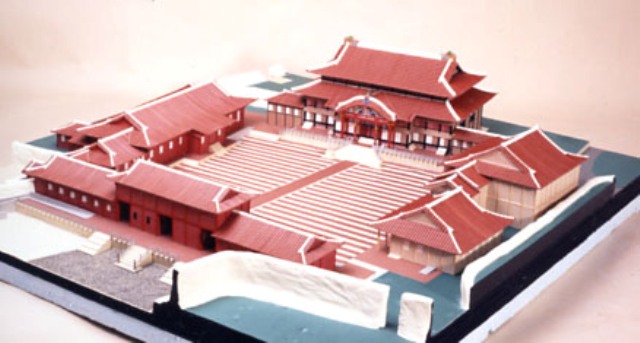

今の所、写真で古いと思われるものは伊藤勝一コレクションの「首里城」である。龍柱が本来の高さで正面向きだ。

今回東京で見つかった明治の沖縄写真は、沖縄写真史の基礎資料とも云うべき『青い目が見た「大琉球」』(1987年8月ニライ社)を見ると1893年3月に来沖したバジル・ホール・チェンバレンの「琉球紀行」で使われた写真にあるから、殆どがチェンバレンが関わっていると思われる。
バジル・ホール・チェンバレン(Basil Hall Chamberlain, 1850年10月18日 - 1935年2月15日)は、イギリスの日本研究家。東京帝国大学文学部名誉教師。アーネスト・サトウやウィリアム・ジョージ・アストン(William George Aston)とともに、19世紀後半~20世紀初頭の最も有名な日本研究家の一人。彼は俳句を英訳した最初の人物の一人であり、日本についての事典"Things Japanese"や『口語日本語ハンドブック』などといった著作、『古事記』などの英訳、アイヌ[1]や琉球[2]の研究で知られる。→ウィキペディア
1997年11月 川平朝申『終戦後の沖縄文化行政史』月刊沖縄社
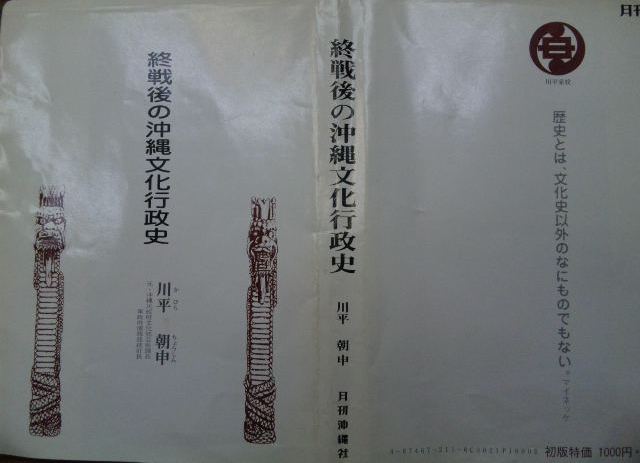
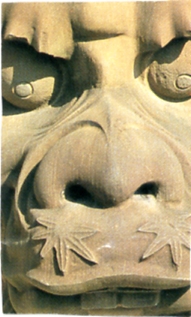
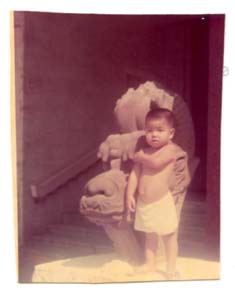
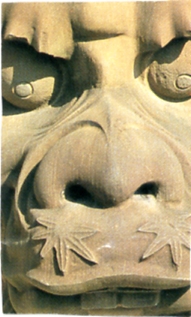
□現在の大龍柱は沖縄神社拝殿の名残を留めて向き合っている。本来は正面向きである。みーぬしんは下方に付いていて、うなーを見下ろすようになっている。真ん中の写真は現在は沖縄県立博物館・美術館にある龍柱で、暑がりの息子が立っている。


2015年12月6日
8日の産経ニュースは「姿を現した2体の龍柱 那覇で設置工事完了 「翁長市政」で推進 中国向け?事業に批判も」と、右派らしく判で押したように報じていた。
若狭
□1979年6月ー邦光史郎・日竎貞夫『丹後若狭路』(カラーブック467)保育社□邦光史郎「若狭・丹後の旅ー敦賀湾の美しさを手放しで礼讃できないのは、この半島に建設された原子力発電所があるからで、福井県は世界でも例を見ない、原子力発電所のメッカで、ずらりと各種タイプの原子炉や、高速増殖炉が並んでいて、不気味である。原子力発電の安全性は保証つきだと政府や電力会社が囃し立て、一基について十億円を超える金が地元に落ちるというので、市町村は原子力発電所の誘致に熱心だが、もし万一事故が起こったら、死の灰に汚染されないとも限らないのである。(略)美しい北陸の海岸は、原子炉の墓標の立ち並ぶ死の海と化しかねない。目先の欲に釣られて、郷土の美を売るようなことはしたくないものである。」


2015年11月22日ー若狭に完成間近の龍柱
那覇市の若狭緑地で市が建設を進めている「龍柱」事業は本体の石材設置作業が22日までに完了し、2体のうちの1体は、覆っていたブルーシートの上半分が外された。前足を掲げた龍の顔面などを見ることができる。1体は海に向かって右側の柱。 現在、周辺整備などの外構工事を進めており、12月25日までに終了する予定。中国福州市との友好都市締結30周年を記念し、計画された。 同事業は当初、一括交付金2億6700万円を使って進めていたが、工事が遅れるなどして活用を断念。市の単独予算を持ち出し工事を再開していた。6月に会計検査院の実施検査を受けたが、「不適切」などの指摘はなかった。→11月23日沖縄タイムス
日本共産党の志位和夫委員長は3日、国会内で記者会見し、
戦後の米軍による土地の強奪、「銃剣とブルドーザー」を用いた無法な基地拡張が沖縄の基地問題の原点であり、「海上の銃剣とブルドーザー」による辺野古新基地を許すのか、この間の一連の選挙で示された新基地建設は許さないという民意を無視することが許されるのかと、知事が問題提起したことの重要性を強調しました。
(略)知事の問題提起に対し、国側代理人が「政治的議論をする場ではない」と言い放ったことについて、志位氏は「沖縄の基地問題について聞く耳を持たない、議論もしないという態度は許し難い。まさにごう慢、強権を象徴するような発言です。いまの安倍政権の姿勢が表れている」と批判。
上記の志位和夫委員長の発言の通りアベ政治はアメリカ黒人大統領オバマ軍の協力も得て下記の通り「まさにごう慢、強権を象徴」粛々と沖縄県民の怒りをかっている。次の選挙で自公は壊滅させねば沖縄の未来は無い。
05/06: 1943年3月 金関丈夫『胡人の匂ひ』東都書籍台北支店
1938年8月から須藤利一は『沖縄教育』に「ベージル・ホール大琉球航海記」を1939年まで連載。1938年12月には台湾愛書会の『愛書』に須藤利一は「琉球の算法書」を発表。
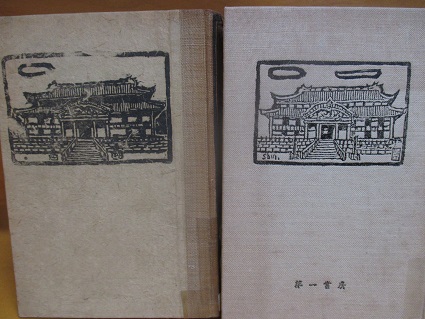
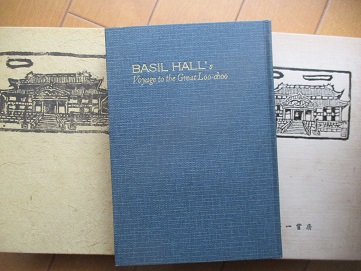
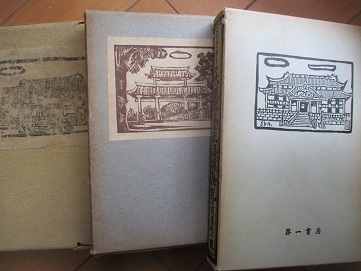
1940年1月、須藤利一は野田書房から『大琉球島探検航海記』を出した。発売所は東京は日本古書通信社代理部、那覇は沖縄書籍となっている。この本は天野文庫と比嘉文庫にあるが口絵に「バジル・ホール肖像」が付いていないが、戦後復刻本には付いている。また川平装幀も微妙に違う。
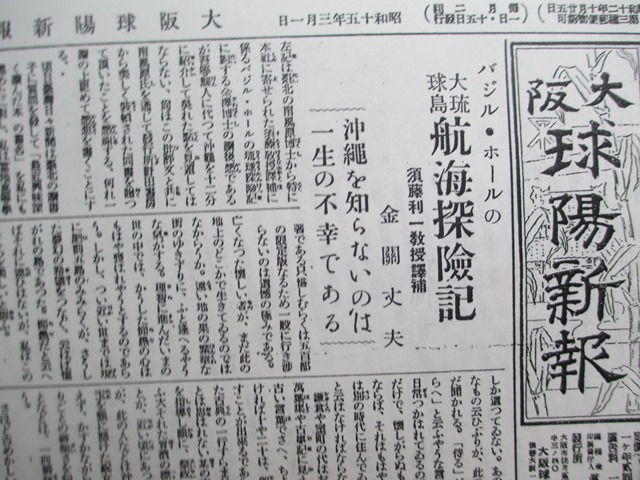
1940年3月1日『大阪球陽新報』金関丈夫
1940年8月、台湾で川平朝申、須藤利一、比嘉盛章、宮良賢貞が編集して『南島』第1輯が野田裕康(台北市兒玉町3ノ9野田書房内)より発行され須藤利一の「アダムスの那覇見聞録」が載っている。1941年、須藤は那覇で発行されている『月刊 文化沖縄』にも「w・ビーチ 琉球記」を連載。1942年3月『南島』第2輯には口絵に「バジル・ホール肖像」、中村忠行が口絵解説(バジル・ホール略傳)をなしている。
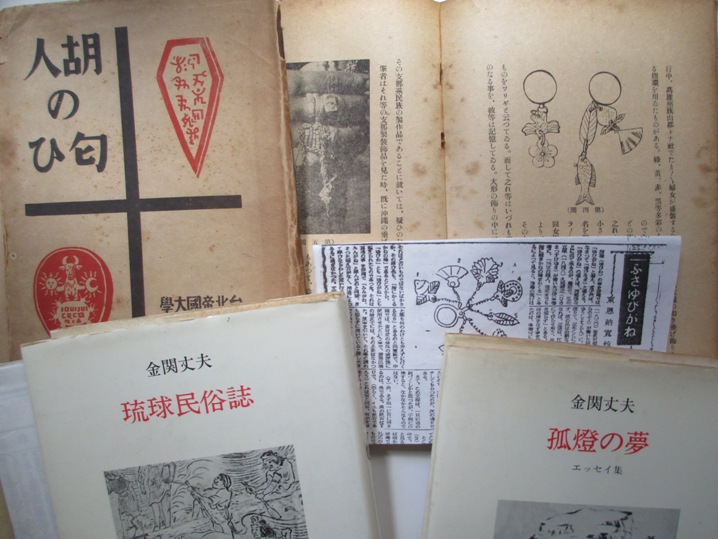
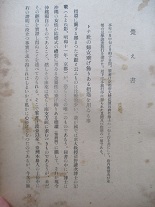
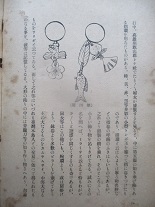
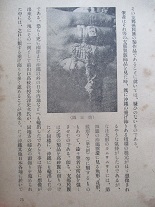
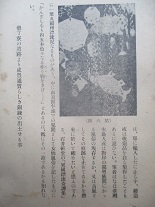
1943年3月 金関丈夫『胡人の匂ひ』東都書籍台北支店
金関丈夫 かなせき-たけお
1897-1983 昭和時代の人類学者,解剖学者。
明治30年2月18日生まれ。九大,鳥取大などの教授をつとめ,のち手塚山(てづかやま)学院大教授となる。弥生(やよい)遺跡出土人骨を研究して日本人渡来説を主張。昭和53年朝日賞受賞。昭和58年2月27日死去。86歳。香川県出身。京都帝大卒。筆名は山中源二郎。著作に「木馬と石牛」「日本民族の起源」など。(コトバンク)
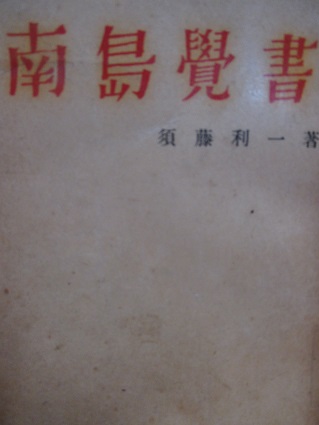
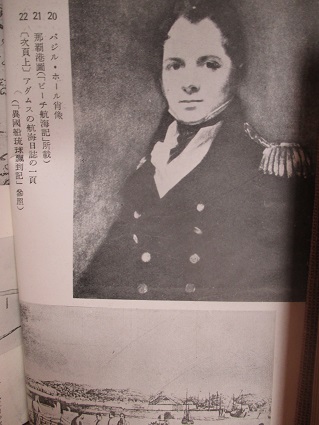
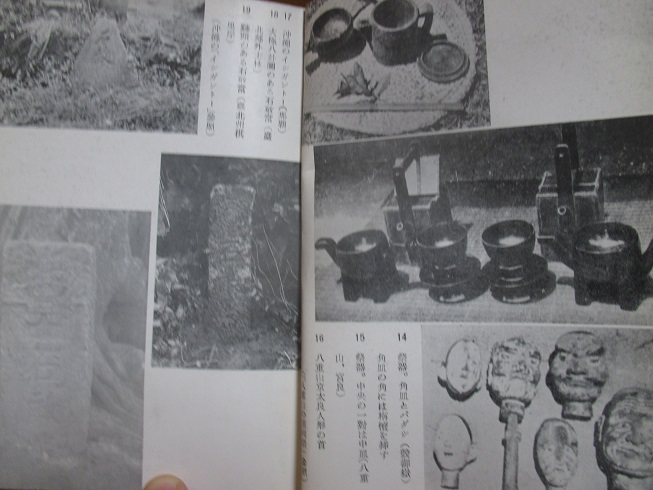
1944年2月 須藤利一『南島覺書』東都書籍
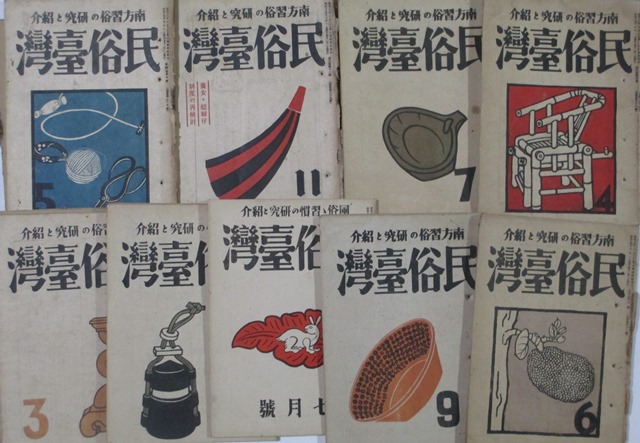
金関丈夫編集『民俗台湾』
□金関丈夫「琉球の旅」ー1928年12月29日、京都駅を発する夜行列車で西下。1930年1月5日、左舷に巨大な島影を見る。これが沖縄本島である。那覇の散策ー沖縄の劇場1・2・3ー黒田理平庵訪問ー沖縄県立図書館ー京都帝国大学教授 武田五一博士ー首里 1月16日ー帰路図書館に立寄って、鎌倉芳太郎氏撮影の琉球古美術写真数十種があるのを知る。これを借用して、先日来預けておいた書籍、人骨等とともに宿に運ぶ。夜は西本町の活動写真館をしばらく覗く。河部・大河内の「弥次喜多」というのをやっていた。9時、宿に帰って写真を見る。
琉球古絵画としては、筆者不明の歴代王像いわゆる「御後絵」や、円覚寺、天久宮、首里観音堂等の仏画の他に、著名な画家の手になるものも多い。欽可聖城間清豊自了(1616~1644)はその最たるもの。冊封使杜三策が顧愷之や王摩詰に比したというのもヨタすぎるが、狩野安信が友とせんといったくらいの値打ちは十分にある。自了と伝えられるものにはほぼ2風ある。一つは玉城盛朝氏所蔵の高士逍遥図や、図書館所蔵の李白観瀑図のように、まず梁楷風のもの、これには落款あるいは印章がある。他は臨海寺渡海観音や、尚順男爵家の陶淵明像のような描線やや繊細のもの、いずれも伝自了である。
自了以後で見るべきものは殷元良(座間味庸昌1718~1767)であろう。遺品、屋慶名氏蔵、松下猛虎図、比嘉氏蔵山水等はいずれも佳品である。ややおくれて呉著温(屋慶名政賀1737~1800)、向元湖(小橋川朝安1748~1841)および毛長禧(佐渡山安健1806~1865)がある。中でも呉著温は山水に巧みで、最も傑出している。自了以下すべて日本画の影響がむしろ大なるものあることは注意すべきである。他に画師査秉徳(上原筑登之親雲上)康煕14年の銘ある久米聖廟の壁画も注意すべきもの。ただしこれは同55年呉師虔というものの修飾を経ている。八重山画家大浜善繁(1761~1815)、喜友名安信(1831~1892)、山里朝次(1848年頃)等の板障画も面白い。彫刻は建築物付属の石刻の他に、仏像、天尊像、古陶人像等あり、手腕は一般に絵画よりも一段優れている。
1939年12月、台湾詩人協会『華麗島』創刊号□川平朝申「幼年思ひ出詩抄」(版画「守礼門」)
1968年、金関丈夫博士古希記念に『日本民族と南方文化』が刊行された。国分直一、須藤利一、三島格らに交じって川平朝申も「さーじ考」を寄稿。那覇市中央図書館の沖縄資料には、川平と台湾で懇意であった金関が台湾から引き揚げのとき「日本には持ち帰れないから」と琉球資料(曼珠沙華艸蔵)を川平に託したのも多い。川平は当時、沖縄同郷会連合会を組織し疎開者救援運動にも関わり、沖縄県立図書館の再建を目指し献本運動も展開していた。
遊学の松岡正剛がブログで「金関丈夫がむちゃくちゃおもしろいということを、どうやって説明したらいいか、困る。ともかく読み耽りたくなる。なかなかの南方熊楠でも、こうはいかない」と金関を紹介している。
3月18日、東京の日本経済評論社から来間泰男『稲作の起源・伝来と”海上の道”』がおくられてきた。本書でも、金関丈夫と宮良當壮の間で展開された起源論争についてふれている。本書の結論はこうである。沖縄では「弥生文化の影響を受けながらも『弥生時代』はなく、農耕が始まっても『農耕中心の社会』にはならなかったのである」。これらをふまえて、沖縄型農耕は「日本型農耕とは異なった、熱帯島嶼的農耕と共通性の強いものとなって展開してきたし、今なお展開しつつある」とする。
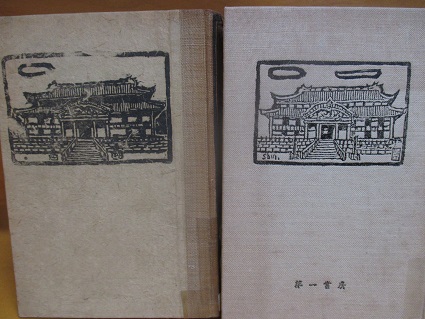
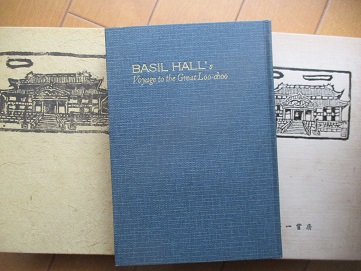
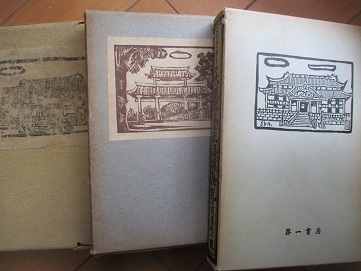
1940年1月、須藤利一は野田書房から『大琉球島探検航海記』を出した。発売所は東京は日本古書通信社代理部、那覇は沖縄書籍となっている。この本は天野文庫と比嘉文庫にあるが口絵に「バジル・ホール肖像」が付いていないが、戦後復刻本には付いている。また川平装幀も微妙に違う。
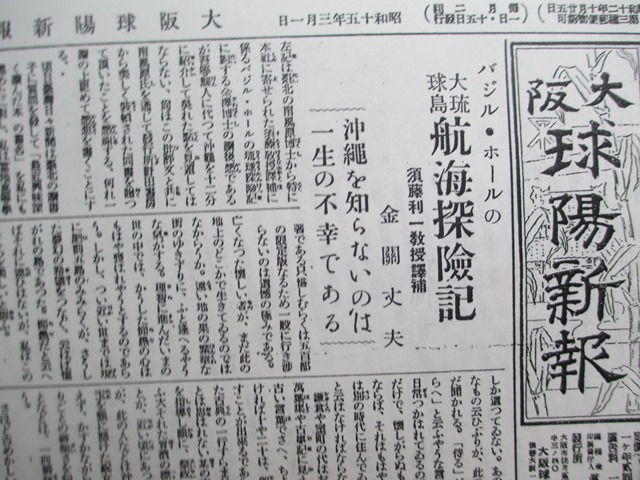
1940年3月1日『大阪球陽新報』金関丈夫
1940年8月、台湾で川平朝申、須藤利一、比嘉盛章、宮良賢貞が編集して『南島』第1輯が野田裕康(台北市兒玉町3ノ9野田書房内)より発行され須藤利一の「アダムスの那覇見聞録」が載っている。1941年、須藤は那覇で発行されている『月刊 文化沖縄』にも「w・ビーチ 琉球記」を連載。1942年3月『南島』第2輯には口絵に「バジル・ホール肖像」、中村忠行が口絵解説(バジル・ホール略傳)をなしている。
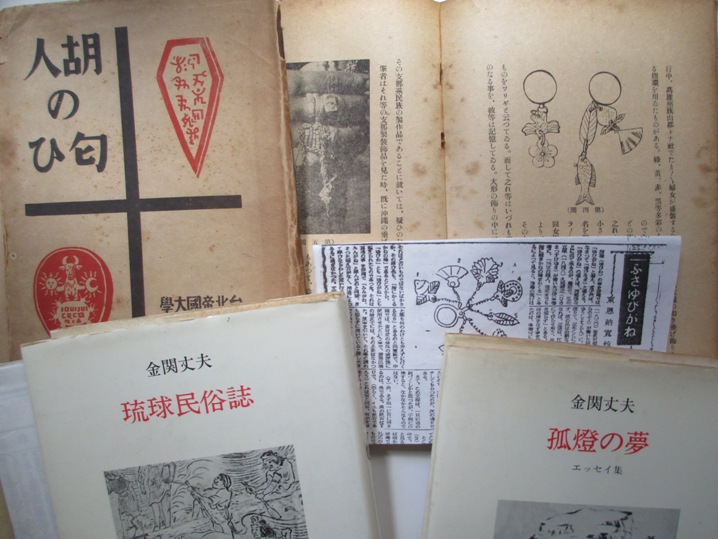
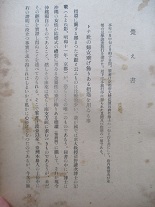
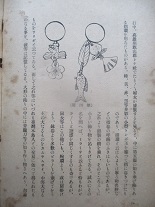
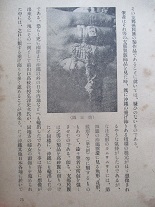
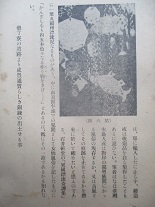
1943年3月 金関丈夫『胡人の匂ひ』東都書籍台北支店
金関丈夫 かなせき-たけお
1897-1983 昭和時代の人類学者,解剖学者。
明治30年2月18日生まれ。九大,鳥取大などの教授をつとめ,のち手塚山(てづかやま)学院大教授となる。弥生(やよい)遺跡出土人骨を研究して日本人渡来説を主張。昭和53年朝日賞受賞。昭和58年2月27日死去。86歳。香川県出身。京都帝大卒。筆名は山中源二郎。著作に「木馬と石牛」「日本民族の起源」など。(コトバンク)
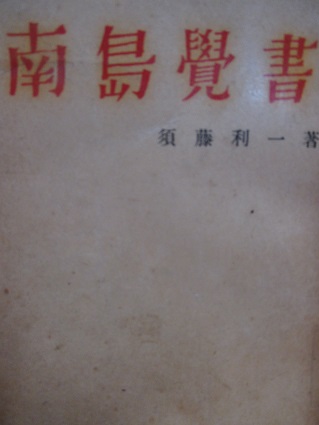
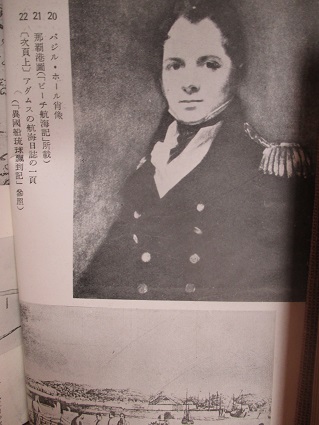
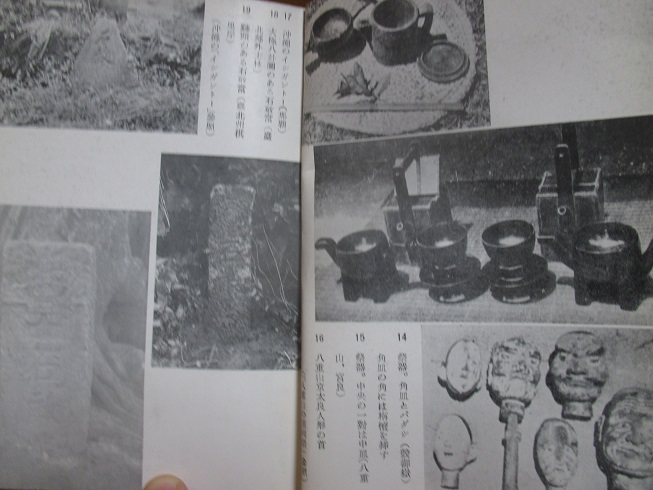
1944年2月 須藤利一『南島覺書』東都書籍
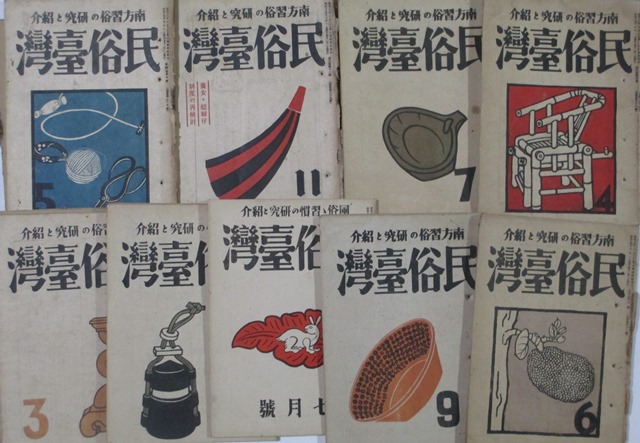
金関丈夫編集『民俗台湾』
□金関丈夫「琉球の旅」ー1928年12月29日、京都駅を発する夜行列車で西下。1930年1月5日、左舷に巨大な島影を見る。これが沖縄本島である。那覇の散策ー沖縄の劇場1・2・3ー黒田理平庵訪問ー沖縄県立図書館ー京都帝国大学教授 武田五一博士ー首里 1月16日ー帰路図書館に立寄って、鎌倉芳太郎氏撮影の琉球古美術写真数十種があるのを知る。これを借用して、先日来預けておいた書籍、人骨等とともに宿に運ぶ。夜は西本町の活動写真館をしばらく覗く。河部・大河内の「弥次喜多」というのをやっていた。9時、宿に帰って写真を見る。
琉球古絵画としては、筆者不明の歴代王像いわゆる「御後絵」や、円覚寺、天久宮、首里観音堂等の仏画の他に、著名な画家の手になるものも多い。欽可聖城間清豊自了(1616~1644)はその最たるもの。冊封使杜三策が顧愷之や王摩詰に比したというのもヨタすぎるが、狩野安信が友とせんといったくらいの値打ちは十分にある。自了と伝えられるものにはほぼ2風ある。一つは玉城盛朝氏所蔵の高士逍遥図や、図書館所蔵の李白観瀑図のように、まず梁楷風のもの、これには落款あるいは印章がある。他は臨海寺渡海観音や、尚順男爵家の陶淵明像のような描線やや繊細のもの、いずれも伝自了である。
自了以後で見るべきものは殷元良(座間味庸昌1718~1767)であろう。遺品、屋慶名氏蔵、松下猛虎図、比嘉氏蔵山水等はいずれも佳品である。ややおくれて呉著温(屋慶名政賀1737~1800)、向元湖(小橋川朝安1748~1841)および毛長禧(佐渡山安健1806~1865)がある。中でも呉著温は山水に巧みで、最も傑出している。自了以下すべて日本画の影響がむしろ大なるものあることは注意すべきである。他に画師査秉徳(上原筑登之親雲上)康煕14年の銘ある久米聖廟の壁画も注意すべきもの。ただしこれは同55年呉師虔というものの修飾を経ている。八重山画家大浜善繁(1761~1815)、喜友名安信(1831~1892)、山里朝次(1848年頃)等の板障画も面白い。彫刻は建築物付属の石刻の他に、仏像、天尊像、古陶人像等あり、手腕は一般に絵画よりも一段優れている。
1939年12月、台湾詩人協会『華麗島』創刊号□川平朝申「幼年思ひ出詩抄」(版画「守礼門」)
1968年、金関丈夫博士古希記念に『日本民族と南方文化』が刊行された。国分直一、須藤利一、三島格らに交じって川平朝申も「さーじ考」を寄稿。那覇市中央図書館の沖縄資料には、川平と台湾で懇意であった金関が台湾から引き揚げのとき「日本には持ち帰れないから」と琉球資料(曼珠沙華艸蔵)を川平に託したのも多い。川平は当時、沖縄同郷会連合会を組織し疎開者救援運動にも関わり、沖縄県立図書館の再建を目指し献本運動も展開していた。
遊学の松岡正剛がブログで「金関丈夫がむちゃくちゃおもしろいということを、どうやって説明したらいいか、困る。ともかく読み耽りたくなる。なかなかの南方熊楠でも、こうはいかない」と金関を紹介している。
3月18日、東京の日本経済評論社から来間泰男『稲作の起源・伝来と”海上の道”』がおくられてきた。本書でも、金関丈夫と宮良當壮の間で展開された起源論争についてふれている。本書の結論はこうである。沖縄では「弥生文化の影響を受けながらも『弥生時代』はなく、農耕が始まっても『農耕中心の社会』にはならなかったのである」。これらをふまえて、沖縄型農耕は「日本型農耕とは異なった、熱帯島嶼的農耕と共通性の強いものとなって展開してきたし、今なお展開しつつある」とする。
05/12: 琉米誌
1899年1月20日ー勝海舟、旧主君徳川慶喜の10男・精(くわし/11歳)を養子婿に迎える
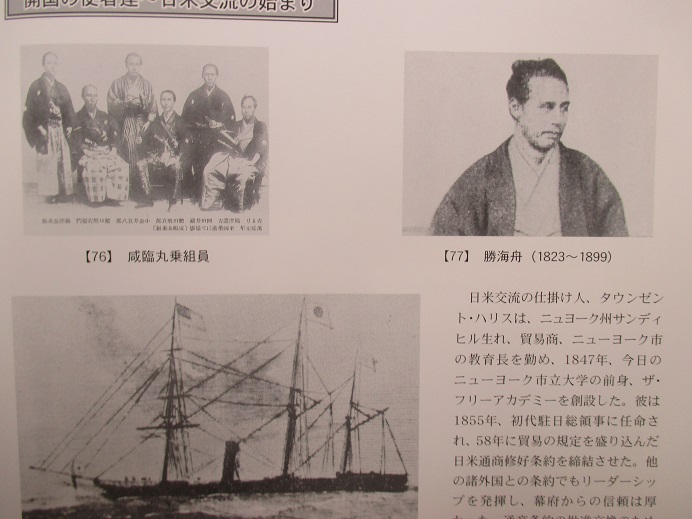
「勝海舟」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
1902年5月19日ー兒玉源太郎台湾総督、井上勝ら福岡丸にて来沖
同年1月に日英同盟条約調印。兒玉源太郎台湾総督(1875年にも来沖)、井上勝ら福岡丸にて来沖。那覇の潟原で那覇首里の小学校の運動会を見る。また首里を遊覧。風月楼で2区の有志及び各役所の高等官60名「歓迎会」。
児玉源太郎 こだまげんたろう
1852(嘉永5)~1906(明治39) 明治時代の陸軍軍人(大将)
徳山藩士児玉半九郎忠碩の長男。戊辰戦争に藩の献功隊士として参加。のち陸軍に入り、佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争に従軍して頭角をあらわした。 1887(M20)陸大校長としてドイツの軍制・戦術の移入紹介につとめ、91ヨーロッパ視察。 92~98陸軍次官兼軍務局長、日清戦争で大本営参謀、功により男爵。96中将に昇進し、長州軍閥の1人として重きをなした。 98台湾総督。1900第4次伊藤内閣・桂内閣で陸相、一時内相と文相を兼任。 04大将に累進して日露戦争に出征し、満州軍総参謀長、戦功により子爵。06参謀総長に就任。南満州鉄道株式会社創立委員長。没後、伯爵。 (はてなキーワード)
日本の近代的交通網を整えた「鉄道の父」
井上 勝 ( いのうえ まさる ) ●天保14年(1843)-明治43年(1910)
勝は天保14年(1843)、藩士井上小豊後勝行の三男として、土原浜坊筋に生まれました。長崎でオランダ士官に兵学を学び、江戸では砲術を修行して、さらに箱館へ行って英国領事館員に英語を学びました。その後航海術習得のため、伊藤博文や井上馨らと英国へ密航してロンドン大学に留学し、鉱山学および鉄道の実業を研究して、明治元年(1868)に帰国しました。明治4年(1871)に鉱山頭兼鉄道頭となり、新橋―横浜間に日本最初の鉄道を開通させて以来、工部大輔・鉄道庁長官等を歴任して、全国各地の近代的交通網を整備しました。明治22年(1889)には、東京―神戸間の東海道線を全通させています。同43年(1910)に鉄道院顧問となり、欧州を視察しましたが、ロンドンで病死しました。享年68歳。
墓は、沢庵和尚を開山として、寛永15年(1625)に3代将軍徳川家光によって創建された品川の東海寺墓地にありますが、ここはJR東海道線と山手線とが分岐するところとなっています。また東京駅頭には、大正3年(1914)に銅像が建てられ、戦時中の金属供出によって台座のみとなっていましたが、没後50周年の昭和34年(1959)に再び銅像が建てられました。(city.hagi.lg.jp)■ちなみに井上勝の娘は松方正義の9男義輔に嫁いでいる。松方の3男幸次郎(元川崎造船社長)は松方コレクションで知られる。
1910年3月9日ー勝精伯爵、農務省水産講習船「雲鷹丸」で来沖。岡雷平やまと新聞記者が同行
1911年6月8日 尚昌、神山政良、イギリス留学の途次サンフランシスコ着、安仁屋政修(沖縄県人会会長)らが出迎える。
1911年11月11日、ブール、シュワルツとともに来沖。→1991年1月 ①伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』
1912年3月27日にポトマック公園で、ヘレン・タフト大統領夫人と珍田日本大使夫人によって桜(ソメイヨシノ種)が植えられた、という。桜の穂木は東京荒川の桜並木だが、台木は兵庫県東野村で育てたものという。詳しくはネット検索で見てほしい。最近、アメリカの首都は何処にあるかと検索したら前記の桜の話が出てきた。アメリカ合衆国の首都はワシントン・コロンビア特別区(Washington,District Of Columbia)で1790年7月16日に設立。

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(ニューヨークで小橋川朝重撮影)
1913年 山田有登、大阪市聖バルナバ病院に勤務。→『沖縄県人録』(1937年)に「山田有登君は那覇市の出身。明治17年1月22日を以て生まれる。沖縄県立中学校を経て金沢医学専門学校に学び、明治42年同校を卒業するや、直ちに石川県立病院に勤務して研鑽を積み同44年6月に愛知県渥美郡田原病院に転じて更に其の蘊奥を極め、大正2年聘せられて大阪市聖バルナバ病院に勤務。同9年転じて久原鉱業経営の鉱山病院に勤務。同11年退職帰県して久米大道りに開業。昭和11年、那覇市に逓信診療所開設されると其の初代所長となり今日に至る。なお君は学生時代野球選手たりしだけに野球に趣味あり」とある。→2011年9月23日、以前から気になっていた天王寺の聖バルナバ病院をのぞく。受付で病院の案内パンフレットをもらう。それによると、同病院は1873年にアメリカ聖公会により派遣された宣教医師Henry Laningが大阪川口居留地に米国伝道会施療院を開設したのに始まる。1923年に川口から天王寺細工谷の現在地に移転しているから、写真家の山田實さんの父・有登は同病院に1913年から1920年まで勤務。その時の場所は川口ということになる。
□川口が貿易港として継続的発展をなしえなかったのは、安治川河口から約6km上流に位置する河川港であるため水深が浅く、大型船舶が入港出来なかったことによる。そのため、外国人貿易商は良港を有する神戸外国人居留地へと移住していった。彼らに代わってキリスト教各派の宣教師が定住して教会堂を建てて布教を行い、その一環として病院、学校を設立し経営を行った。平安女学院、プール学院、大阪女学院、桃山学院、立教学院、大阪信愛女学院といったミッションスクールや聖バルナバ病院等はこの地で創設されたのである。それら施設も高度な社会基盤が整備されるに従い、大阪の上町エリア(天王寺区・阿倍野区など)へ次々と移転して川口は衰退への道をたどることになる。対照的に大型外国船が集まるようになった神戸港は、1890年代には東洋最大の港へと拡大していった。(→ウィキペディア)
1914年5月9日『沖縄毎日新聞』伊波月城「日光浴ー新文明の先駆者たる北米合衆国の平民詩人ワルトホヰットマン②は3、40年これを実行したのである。・・・」
②ウォルター・ホイットマン はアメリカ合衆国の詩人、随筆家、ジャーナリスト、ヒューマニスト。超越主義から写実主義への過渡期を代表する人物の一人で、作品には両方の様相が取り込まれている。アメリカ文学において最も影響力の大きい作家の一人でもあり、しばしば「自由詩の父」と呼ばれる。→ ウィキペディア
1914年6月26日『沖縄毎日新聞』「粗枝大葉ー19世紀の偉大なるアメリカ人ワルト、ホイットマンは大いなる都会とは・・・・」
1915年8月ー前暁鐘社の野里朝淳がマウィ島カフルイ港で写真屋開業
1916年6月9日『琉球新報』平良生(在ロスアンゼルス)「米国通信」
1917年9月、山入端隣次郎、アメリカよりT型フォードを3台導入し沖縄自動車商会を開業、運転手は福井県出身の大宮孝太郎。大宮は沖縄県「運転手免許証」(大正6年10月8日発行)第一号である。12月、布哇沖縄海外協会(當山善真)『会報』□表紙「汎太平洋と布哇」、大城幸之一「沖縄県の疲弊と之が対応策」、比嘉静観「沖縄県救済策」、大田朝敷「沖縄本島巡講行脚」、新城北山「布哇沿岸の琉球民族」/沖縄県海外協会(又吉康和)『南鵬』第1巻第2号□大田朝敷「ハワイと沖縄の関係」
1917年11月23日『琉球新報』「64年前ペリーと琉球を経て浦賀に上陸したハーデー翁が17日来日」
名護朝助
慶応義塾入社名簿に/名護朝助 本籍地 沖縄県首里當蔵35 戸主 士族
明治11年3月生 明治30年5月入社 証人 岸本賀昌
アメリカに渡米、10年余滞在
大正元年10月ー西洋料理「美理軒」(名護朝助経営、コック永田亀寿・元シュワルツ家コック)饒平名病院隣、一味亭跡に開業/11月ー『琉球新報』□食道楽君のピリケンの解釈は違っている。ピリケンとは福の神の意味で寺内総督にピリケンの名を冠したのは惑新聞が七福神の似顔を募った時、総督の三角頭が七福神の一つに及第したことがあるからピリケンのアダ名も蓋し之に出たのであろう。洋食屋の美理軒なるほど語呂はよくないが来る御客様を福の神と見立てたものであるとすれば語呂ぐらいは我慢が出来る。アテ字の美は美味の美、理は料理の理と見れば何れにしても結構じゃないか。
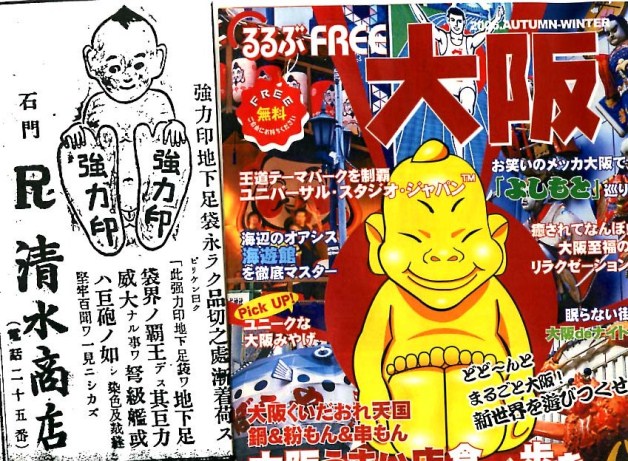
1918(大正7)年3月の『琉球新報』広告/2006年9月『JTBパプリッシング』表紙
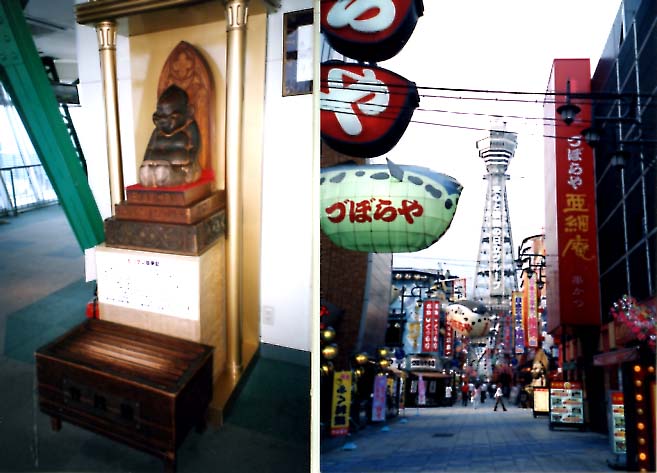
左ー通天閣のビリケンさん/通天閣の見える右下にビリケンさんが見える

□通天閣の展望台で、真っ先に迎えてくれるのが、幸運の神様「ビリケン像」。
合格祈願・縁結びなどあらゆる願いを聞いてくれる、なんでもござれの福の神なんです。通天閣の「ビリケン」は、5階の展望台の立派な台座にちょこんと座っています。
笑っているのか怒っているのか。不思議な表情と、愛敬あるポーズが人気で、いつもお願いする人が絶えません。
ビリケン(BILLIKEN)は、1908年(明治41年)アメリカの女流美術家 フローレンス・プリッツという女性アーティストが、夢で見たユニークな神様をモデルに制作したものと伝えられています。トンガリ頭につりあがった目という、どこかしらユーモラスな姿は、たちまち「幸福のマスコット」「福の神」としてアメリカを始め世界中に大流行しました。
日本でも花柳界などで縁起物として愛されていました。
世界的な流行を受けて、1912年(明治45年)オープンした「新世界」の遊園地「ルナパーク(月の園)」では、さっそく「ビリケン堂」を造りビリケンを安置。これは大当たりし、新世界名物としてその名をとどろかせ、ビリケン饅頭やビリケン人形などのみやげ物まで作られました。また「福の神・ビリケン」を七福神に加え、「八福神めぐり」なども流行したと伝えられています。しかしビリケンは、ルナパークの閉鎖と共に行方不明になってしまいました。
オイルショックが去り、通天閣の灯が復活して新世界に活気がよみがえった1979年〈昭和54年〉、浪速文化の拠点をめざした「通天閣ふれあい広場(現・3階イベントホル)」ができました。その後、1980年(昭和55年3月30日)に新世界に馴染みの深い「ビリケン」の復活も決まりました。しかし、資料になるべき写真が見つからず。思案にくれている時、田村駒株式会社が版権を持っていることが判明。田村駒さんのご好意で、同社の「ビリケン」をもとに木彫で復元したのです。像の彫刻は伊丹市在住の安藤新平さん。(→通天閣)
1919年 宮城与徳、父与正の呼び寄せで渡米→1921年ー屋部憲傳、又吉淳、幸地新政らと「黎明会」結成。
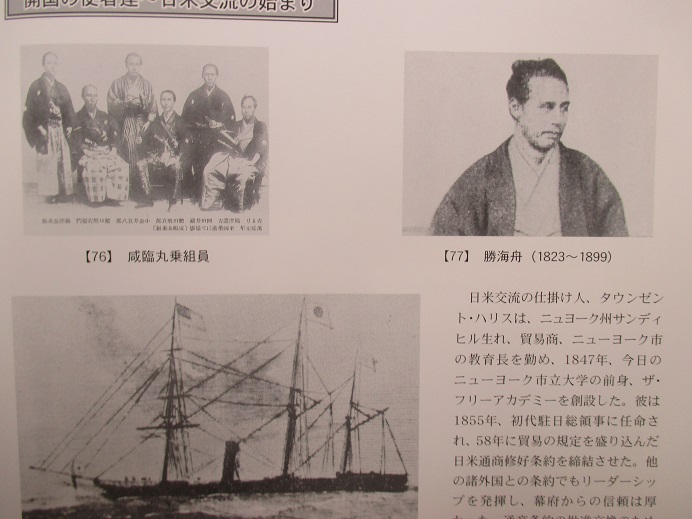
「勝海舟」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
1902年5月19日ー兒玉源太郎台湾総督、井上勝ら福岡丸にて来沖
同年1月に日英同盟条約調印。兒玉源太郎台湾総督(1875年にも来沖)、井上勝ら福岡丸にて来沖。那覇の潟原で那覇首里の小学校の運動会を見る。また首里を遊覧。風月楼で2区の有志及び各役所の高等官60名「歓迎会」。
児玉源太郎 こだまげんたろう
1852(嘉永5)~1906(明治39) 明治時代の陸軍軍人(大将)
徳山藩士児玉半九郎忠碩の長男。戊辰戦争に藩の献功隊士として参加。のち陸軍に入り、佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争に従軍して頭角をあらわした。 1887(M20)陸大校長としてドイツの軍制・戦術の移入紹介につとめ、91ヨーロッパ視察。 92~98陸軍次官兼軍務局長、日清戦争で大本営参謀、功により男爵。96中将に昇進し、長州軍閥の1人として重きをなした。 98台湾総督。1900第4次伊藤内閣・桂内閣で陸相、一時内相と文相を兼任。 04大将に累進して日露戦争に出征し、満州軍総参謀長、戦功により子爵。06参謀総長に就任。南満州鉄道株式会社創立委員長。没後、伯爵。 (はてなキーワード)
日本の近代的交通網を整えた「鉄道の父」
井上 勝 ( いのうえ まさる ) ●天保14年(1843)-明治43年(1910)
勝は天保14年(1843)、藩士井上小豊後勝行の三男として、土原浜坊筋に生まれました。長崎でオランダ士官に兵学を学び、江戸では砲術を修行して、さらに箱館へ行って英国領事館員に英語を学びました。その後航海術習得のため、伊藤博文や井上馨らと英国へ密航してロンドン大学に留学し、鉱山学および鉄道の実業を研究して、明治元年(1868)に帰国しました。明治4年(1871)に鉱山頭兼鉄道頭となり、新橋―横浜間に日本最初の鉄道を開通させて以来、工部大輔・鉄道庁長官等を歴任して、全国各地の近代的交通網を整備しました。明治22年(1889)には、東京―神戸間の東海道線を全通させています。同43年(1910)に鉄道院顧問となり、欧州を視察しましたが、ロンドンで病死しました。享年68歳。
墓は、沢庵和尚を開山として、寛永15年(1625)に3代将軍徳川家光によって創建された品川の東海寺墓地にありますが、ここはJR東海道線と山手線とが分岐するところとなっています。また東京駅頭には、大正3年(1914)に銅像が建てられ、戦時中の金属供出によって台座のみとなっていましたが、没後50周年の昭和34年(1959)に再び銅像が建てられました。(city.hagi.lg.jp)■ちなみに井上勝の娘は松方正義の9男義輔に嫁いでいる。松方の3男幸次郎(元川崎造船社長)は松方コレクションで知られる。
1910年3月9日ー勝精伯爵、農務省水産講習船「雲鷹丸」で来沖。岡雷平やまと新聞記者が同行
1911年6月8日 尚昌、神山政良、イギリス留学の途次サンフランシスコ着、安仁屋政修(沖縄県人会会長)らが出迎える。
1911年11月11日、ブール、シュワルツとともに来沖。→1991年1月 ①伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』
1912年3月27日にポトマック公園で、ヘレン・タフト大統領夫人と珍田日本大使夫人によって桜(ソメイヨシノ種)が植えられた、という。桜の穂木は東京荒川の桜並木だが、台木は兵庫県東野村で育てたものという。詳しくはネット検索で見てほしい。最近、アメリカの首都は何処にあるかと検索したら前記の桜の話が出てきた。アメリカ合衆国の首都はワシントン・コロンビア特別区(Washington,District Of Columbia)で1790年7月16日に設立。

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(ニューヨークで小橋川朝重撮影)
1913年 山田有登、大阪市聖バルナバ病院に勤務。→『沖縄県人録』(1937年)に「山田有登君は那覇市の出身。明治17年1月22日を以て生まれる。沖縄県立中学校を経て金沢医学専門学校に学び、明治42年同校を卒業するや、直ちに石川県立病院に勤務して研鑽を積み同44年6月に愛知県渥美郡田原病院に転じて更に其の蘊奥を極め、大正2年聘せられて大阪市聖バルナバ病院に勤務。同9年転じて久原鉱業経営の鉱山病院に勤務。同11年退職帰県して久米大道りに開業。昭和11年、那覇市に逓信診療所開設されると其の初代所長となり今日に至る。なお君は学生時代野球選手たりしだけに野球に趣味あり」とある。→2011年9月23日、以前から気になっていた天王寺の聖バルナバ病院をのぞく。受付で病院の案内パンフレットをもらう。それによると、同病院は1873年にアメリカ聖公会により派遣された宣教医師Henry Laningが大阪川口居留地に米国伝道会施療院を開設したのに始まる。1923年に川口から天王寺細工谷の現在地に移転しているから、写真家の山田實さんの父・有登は同病院に1913年から1920年まで勤務。その時の場所は川口ということになる。
□川口が貿易港として継続的発展をなしえなかったのは、安治川河口から約6km上流に位置する河川港であるため水深が浅く、大型船舶が入港出来なかったことによる。そのため、外国人貿易商は良港を有する神戸外国人居留地へと移住していった。彼らに代わってキリスト教各派の宣教師が定住して教会堂を建てて布教を行い、その一環として病院、学校を設立し経営を行った。平安女学院、プール学院、大阪女学院、桃山学院、立教学院、大阪信愛女学院といったミッションスクールや聖バルナバ病院等はこの地で創設されたのである。それら施設も高度な社会基盤が整備されるに従い、大阪の上町エリア(天王寺区・阿倍野区など)へ次々と移転して川口は衰退への道をたどることになる。対照的に大型外国船が集まるようになった神戸港は、1890年代には東洋最大の港へと拡大していった。(→ウィキペディア)
1914年5月9日『沖縄毎日新聞』伊波月城「日光浴ー新文明の先駆者たる北米合衆国の平民詩人ワルトホヰットマン②は3、40年これを実行したのである。・・・」
②ウォルター・ホイットマン はアメリカ合衆国の詩人、随筆家、ジャーナリスト、ヒューマニスト。超越主義から写実主義への過渡期を代表する人物の一人で、作品には両方の様相が取り込まれている。アメリカ文学において最も影響力の大きい作家の一人でもあり、しばしば「自由詩の父」と呼ばれる。→ ウィキペディア
1914年6月26日『沖縄毎日新聞』「粗枝大葉ー19世紀の偉大なるアメリカ人ワルト、ホイットマンは大いなる都会とは・・・・」
1915年8月ー前暁鐘社の野里朝淳がマウィ島カフルイ港で写真屋開業
1916年6月9日『琉球新報』平良生(在ロスアンゼルス)「米国通信」
1917年9月、山入端隣次郎、アメリカよりT型フォードを3台導入し沖縄自動車商会を開業、運転手は福井県出身の大宮孝太郎。大宮は沖縄県「運転手免許証」(大正6年10月8日発行)第一号である。12月、布哇沖縄海外協会(當山善真)『会報』□表紙「汎太平洋と布哇」、大城幸之一「沖縄県の疲弊と之が対応策」、比嘉静観「沖縄県救済策」、大田朝敷「沖縄本島巡講行脚」、新城北山「布哇沿岸の琉球民族」/沖縄県海外協会(又吉康和)『南鵬』第1巻第2号□大田朝敷「ハワイと沖縄の関係」
1917年11月23日『琉球新報』「64年前ペリーと琉球を経て浦賀に上陸したハーデー翁が17日来日」
名護朝助
慶応義塾入社名簿に/名護朝助 本籍地 沖縄県首里當蔵35 戸主 士族
明治11年3月生 明治30年5月入社 証人 岸本賀昌
アメリカに渡米、10年余滞在
大正元年10月ー西洋料理「美理軒」(名護朝助経営、コック永田亀寿・元シュワルツ家コック)饒平名病院隣、一味亭跡に開業/11月ー『琉球新報』□食道楽君のピリケンの解釈は違っている。ピリケンとは福の神の意味で寺内総督にピリケンの名を冠したのは惑新聞が七福神の似顔を募った時、総督の三角頭が七福神の一つに及第したことがあるからピリケンのアダ名も蓋し之に出たのであろう。洋食屋の美理軒なるほど語呂はよくないが来る御客様を福の神と見立てたものであるとすれば語呂ぐらいは我慢が出来る。アテ字の美は美味の美、理は料理の理と見れば何れにしても結構じゃないか。
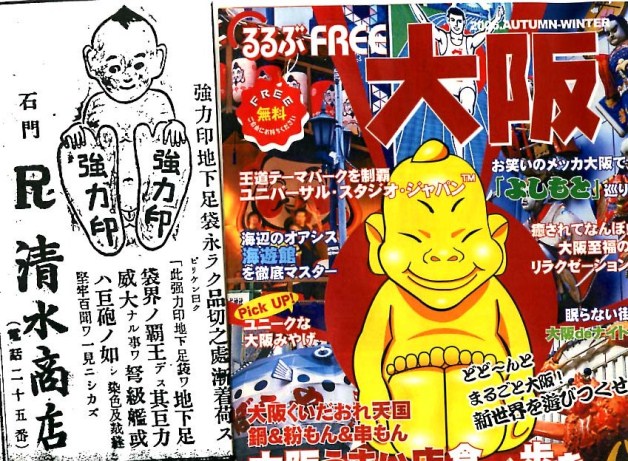
1918(大正7)年3月の『琉球新報』広告/2006年9月『JTBパプリッシング』表紙
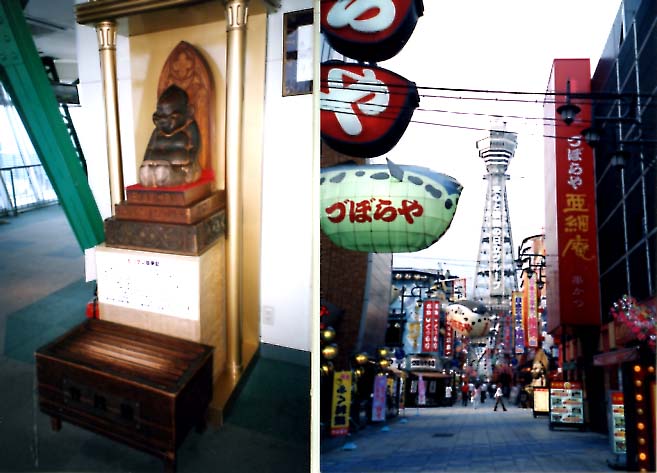
左ー通天閣のビリケンさん/通天閣の見える右下にビリケンさんが見える

□通天閣の展望台で、真っ先に迎えてくれるのが、幸運の神様「ビリケン像」。
合格祈願・縁結びなどあらゆる願いを聞いてくれる、なんでもござれの福の神なんです。通天閣の「ビリケン」は、5階の展望台の立派な台座にちょこんと座っています。
笑っているのか怒っているのか。不思議な表情と、愛敬あるポーズが人気で、いつもお願いする人が絶えません。
ビリケン(BILLIKEN)は、1908年(明治41年)アメリカの女流美術家 フローレンス・プリッツという女性アーティストが、夢で見たユニークな神様をモデルに制作したものと伝えられています。トンガリ頭につりあがった目という、どこかしらユーモラスな姿は、たちまち「幸福のマスコット」「福の神」としてアメリカを始め世界中に大流行しました。
日本でも花柳界などで縁起物として愛されていました。
世界的な流行を受けて、1912年(明治45年)オープンした「新世界」の遊園地「ルナパーク(月の園)」では、さっそく「ビリケン堂」を造りビリケンを安置。これは大当たりし、新世界名物としてその名をとどろかせ、ビリケン饅頭やビリケン人形などのみやげ物まで作られました。また「福の神・ビリケン」を七福神に加え、「八福神めぐり」なども流行したと伝えられています。しかしビリケンは、ルナパークの閉鎖と共に行方不明になってしまいました。
オイルショックが去り、通天閣の灯が復活して新世界に活気がよみがえった1979年〈昭和54年〉、浪速文化の拠点をめざした「通天閣ふれあい広場(現・3階イベントホル)」ができました。その後、1980年(昭和55年3月30日)に新世界に馴染みの深い「ビリケン」の復活も決まりました。しかし、資料になるべき写真が見つからず。思案にくれている時、田村駒株式会社が版権を持っていることが判明。田村駒さんのご好意で、同社の「ビリケン」をもとに木彫で復元したのです。像の彫刻は伊丹市在住の安藤新平さん。(→通天閣)
1919年 宮城与徳、父与正の呼び寄せで渡米→1921年ー屋部憲傳、又吉淳、幸地新政らと「黎明会」結成。
01/10: 沖縄人民党中央機関紙『人民』
1931年、瀬長亀次郎は神奈川で井之口政雄宅に下宿をしていた。井之口夫人は日本赤色救援神奈川地区の活動家で瀬長は大分お世話になった。飯場生活の瀬長は「全協日本土建神奈川支部」を朝鮮人の金一声らと結成、京浜地区の責任者になった。そして横須賀町久里浜の平作川改修工事に従事していた朝鮮人労働者350人と労働条件改善、全員に仕事をよこせの要求をかかげてストライキに突入、瀬長も、金一声も検挙され一ヶ月投獄された。

瀬長亀次郎は戦後も沖縄人民党行事としてこの碑(人民解放戦士真栄田一郎君に捧ぐ)の前に集い団結を誓った。瀬長亀次郎「弾圧は抵抗を呼ぶ 抵抗は友を呼ぶ」→1991年8月『瀬長亀次郎回想録』新日本出版社
1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社
ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ
写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。
悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫
○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。
郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長
善意の記録として・・・・沖縄県学生会
○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。
第一部
拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人
第二部
土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道
島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光
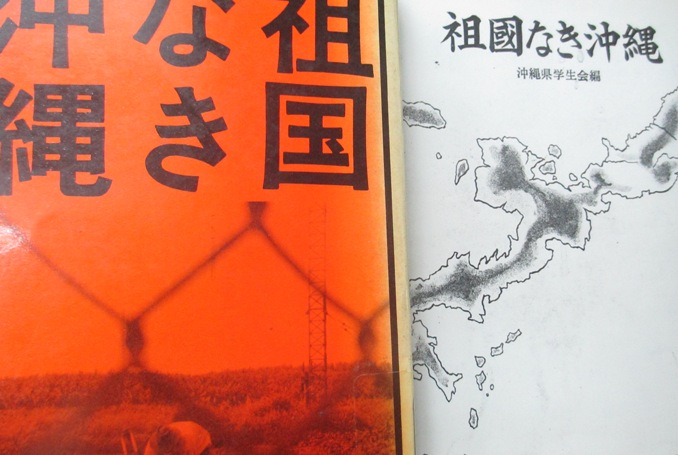
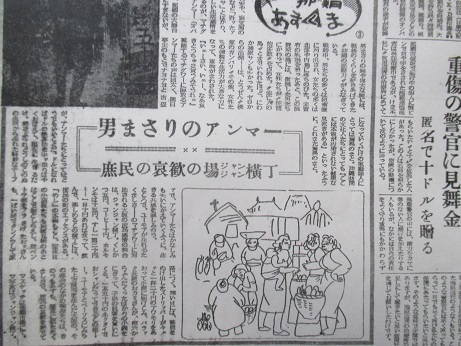
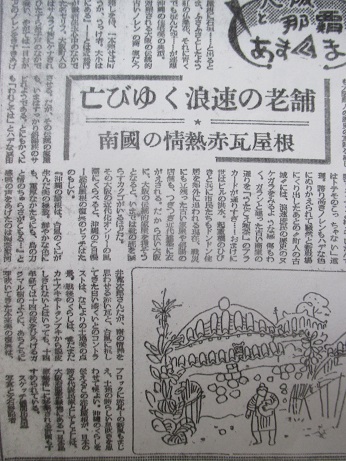
1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」
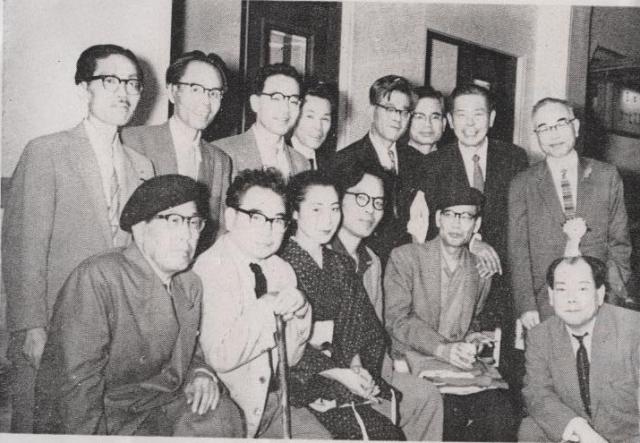
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子
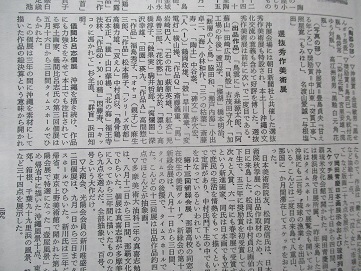

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』
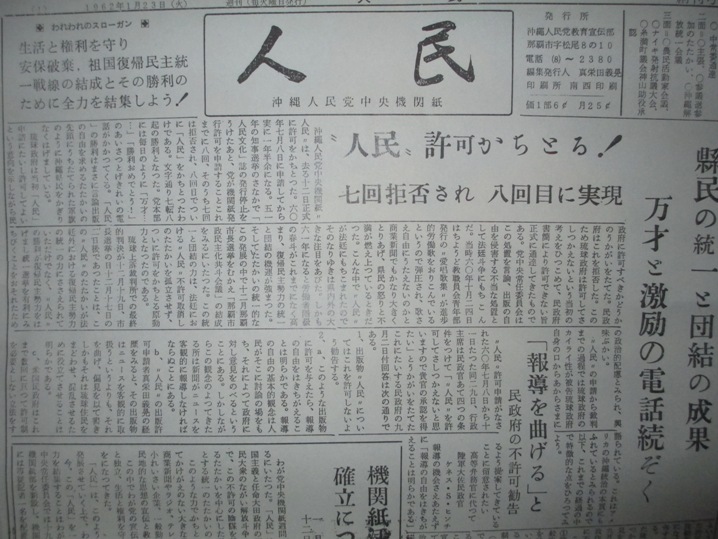

1963年
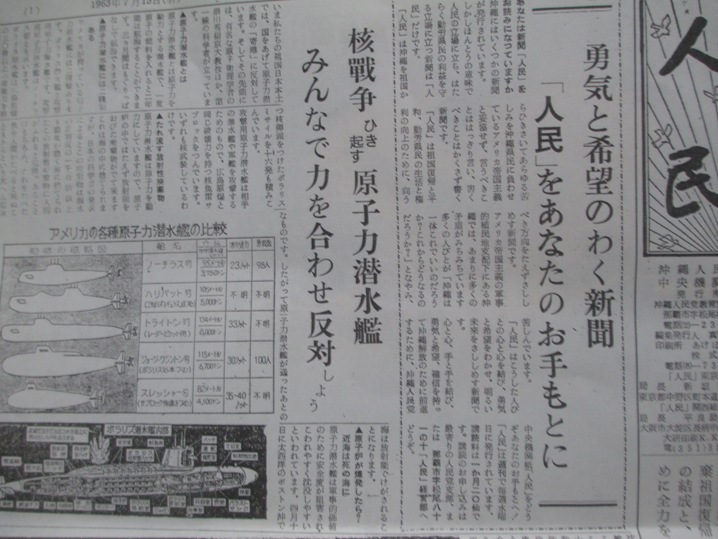
7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」
1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」
1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社
○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫
○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫
○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの
○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二
○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光
○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会
1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」
1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」
2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」
7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)
7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」
9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」
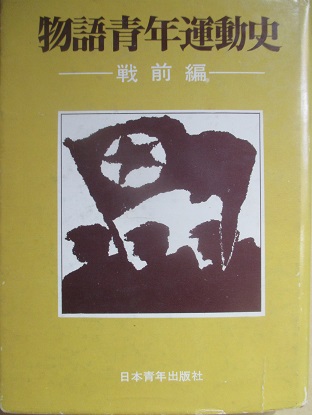

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社
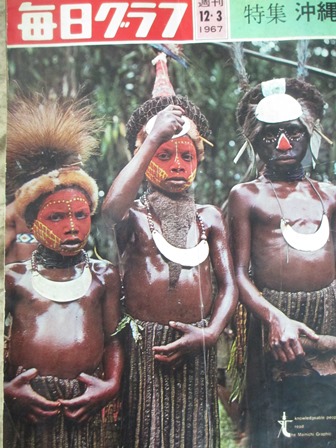
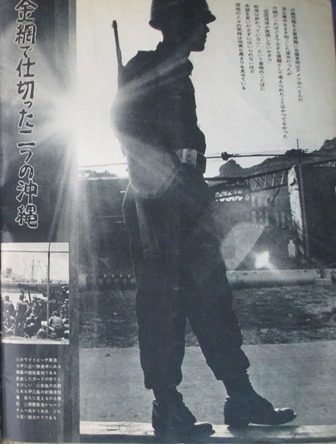
12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」
1968年
6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」
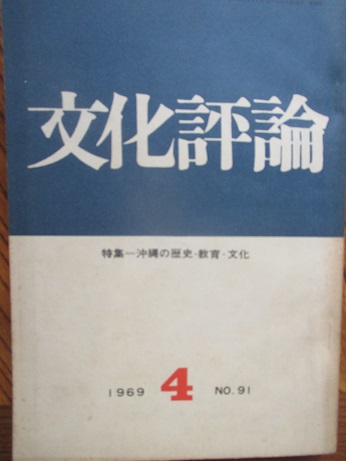
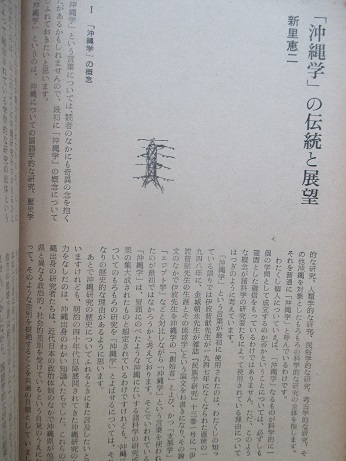
1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」
1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)
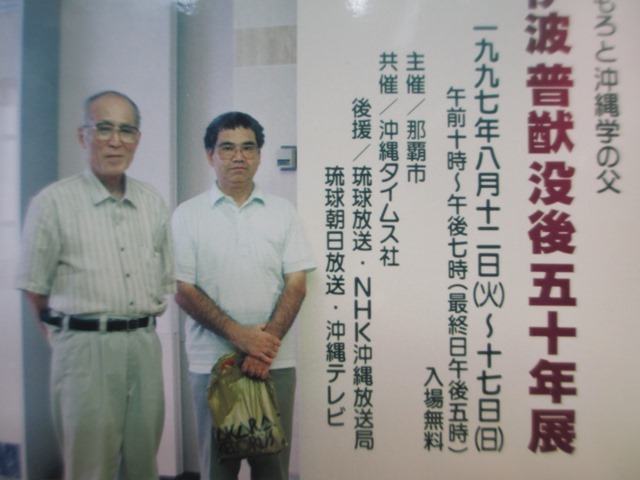
伊波廣定氏と新城栄徳
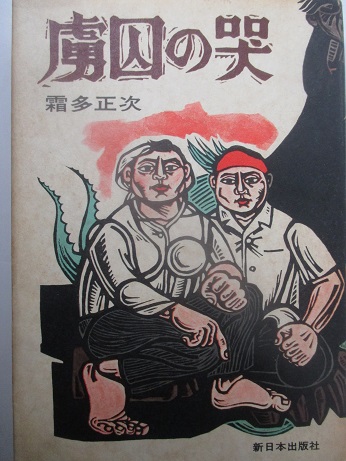
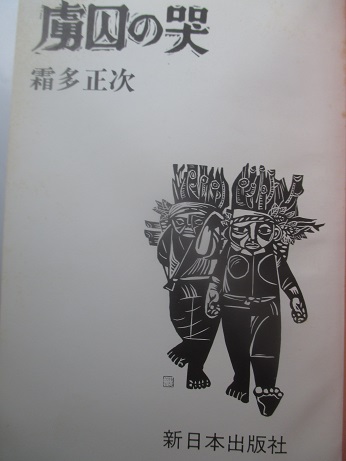
1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」
5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)
8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」
①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)
9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』
□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために
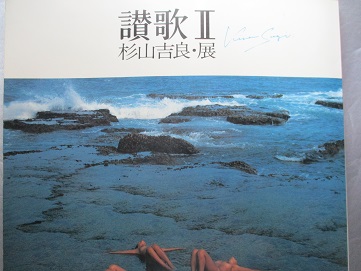
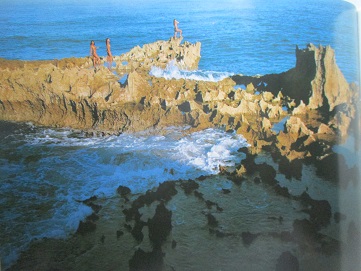
1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』
1971年
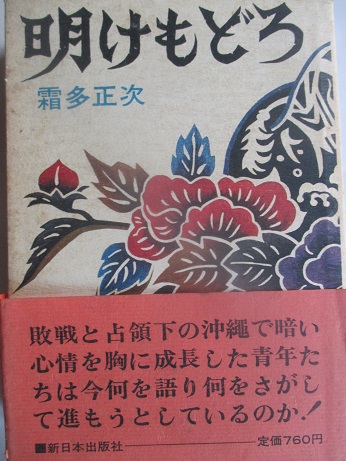
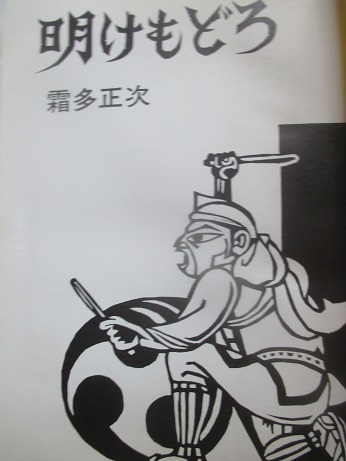
1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」
1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」
1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」
1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」
1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」
2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」
2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」
4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」
5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」
5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④
5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」
6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」
6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」
7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」
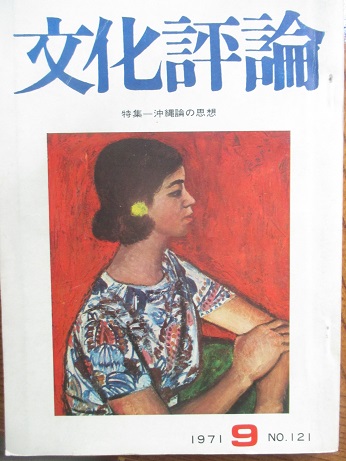
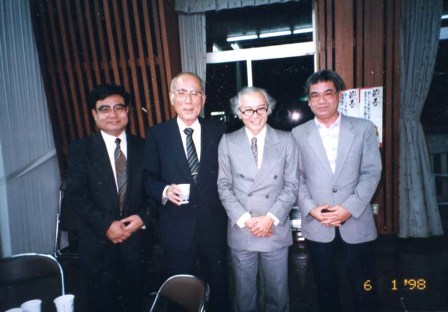
1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
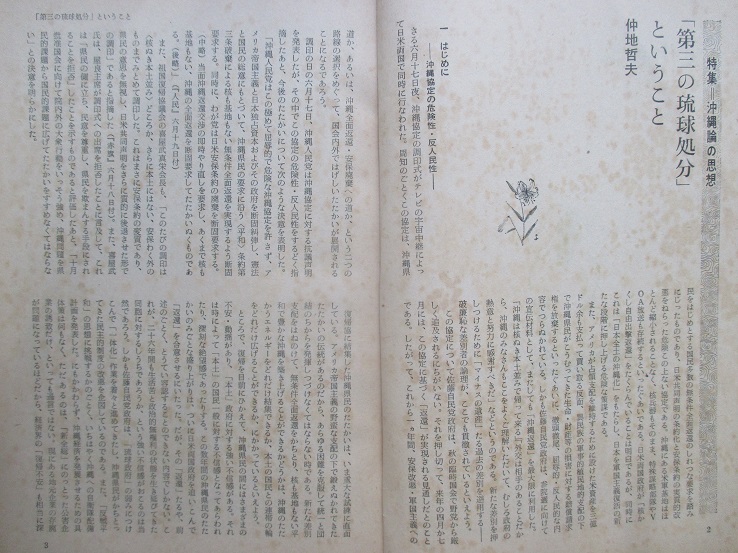
10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」
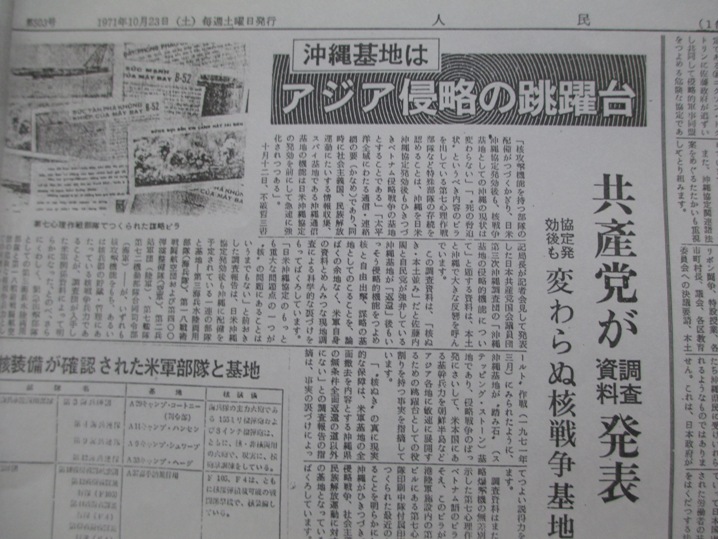
10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」


写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益
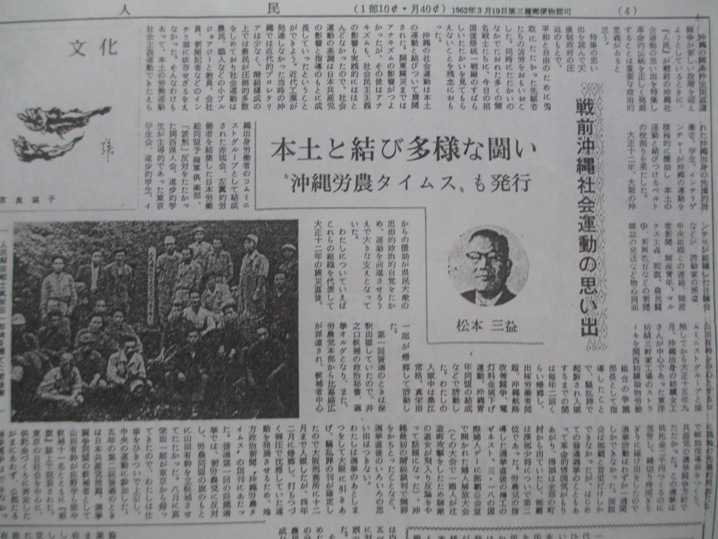
12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」
12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」
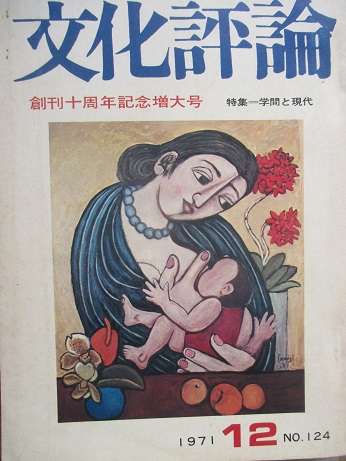
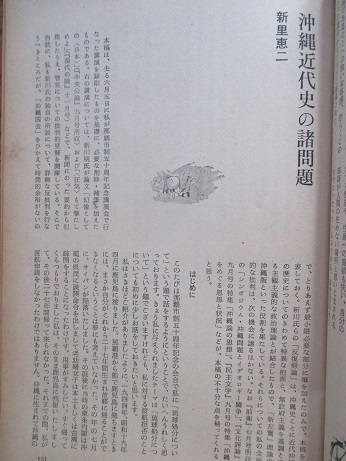
1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」
1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>
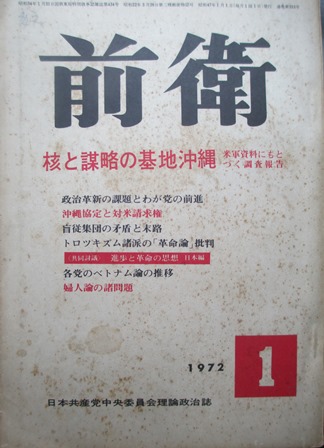

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫
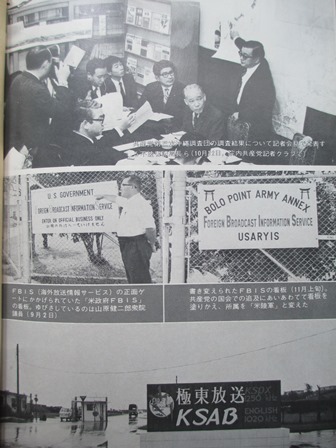
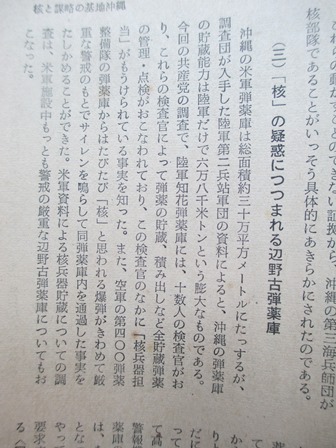
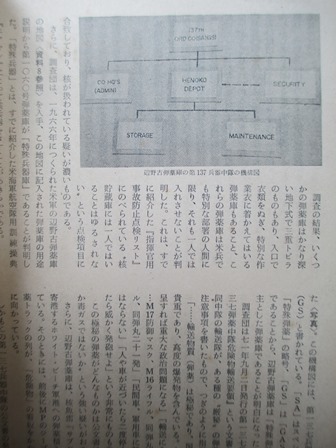
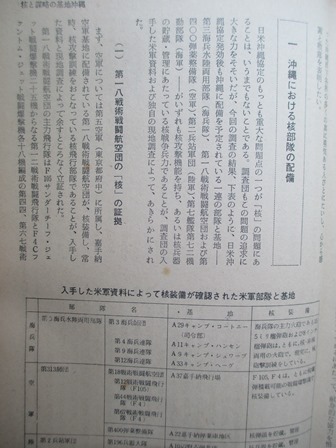


1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」
1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」
2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」
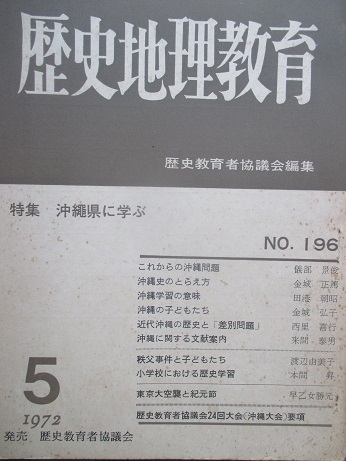
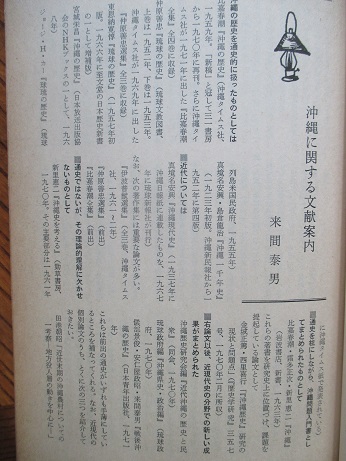
1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」
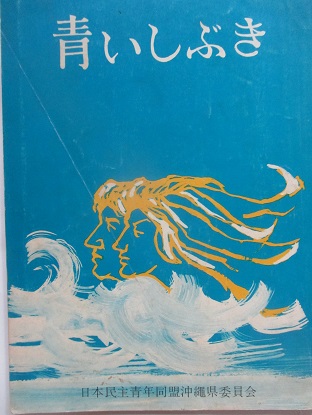
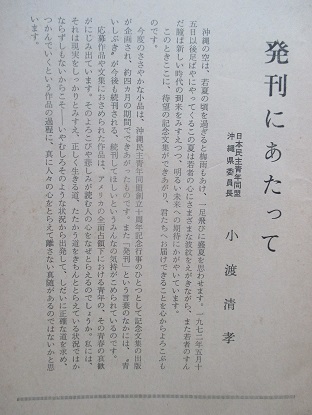
1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

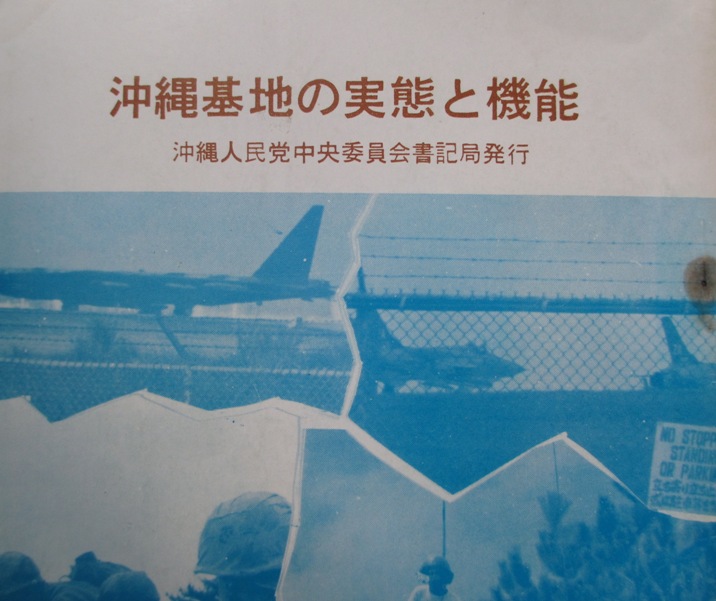
写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』
1973年
1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」
4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」
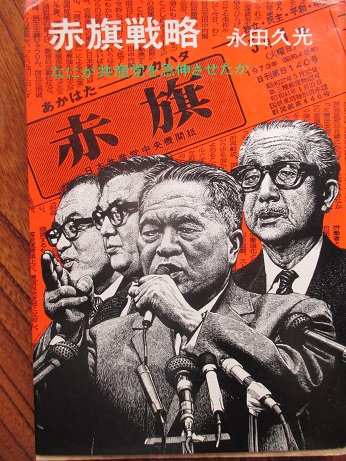
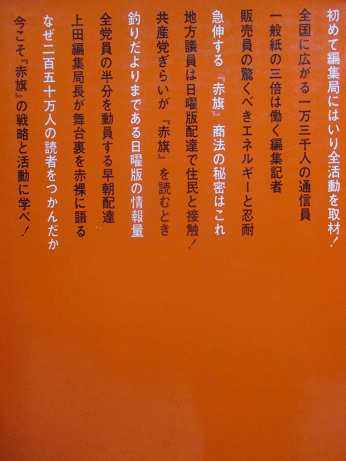
1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社
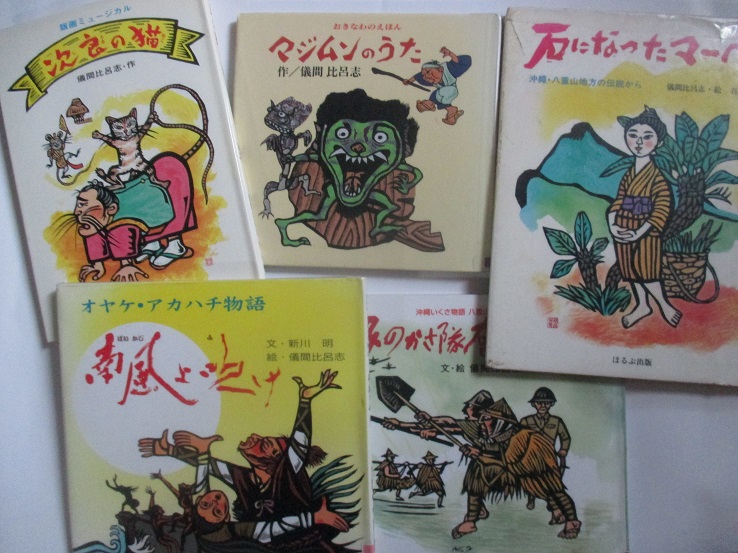
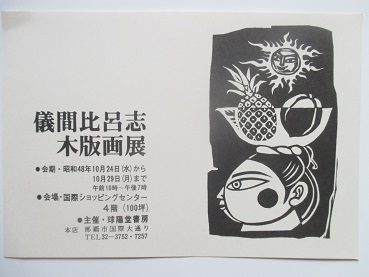
右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房
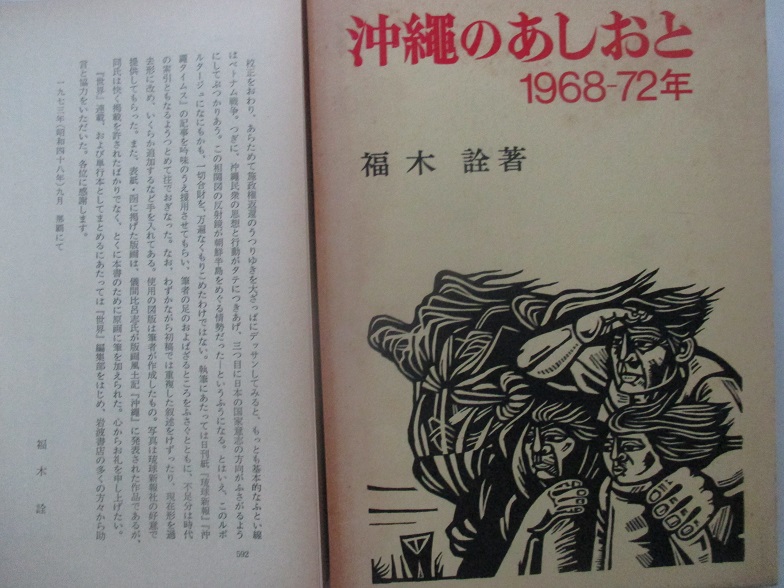
1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。
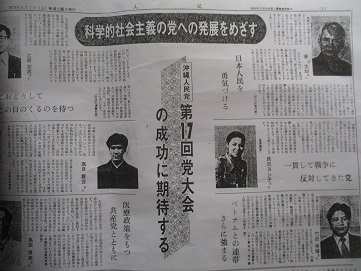
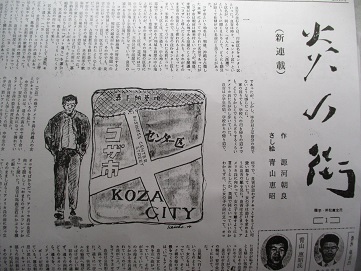
『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭
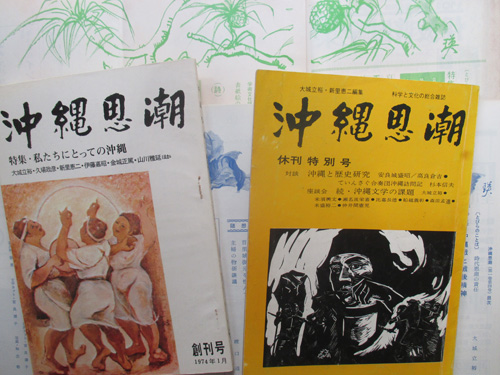
1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」
☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。
1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」
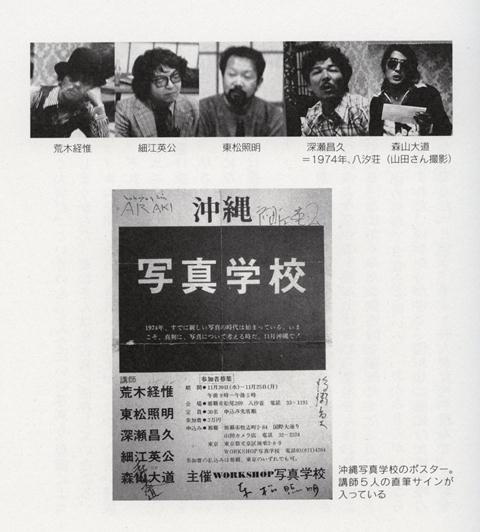
1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」
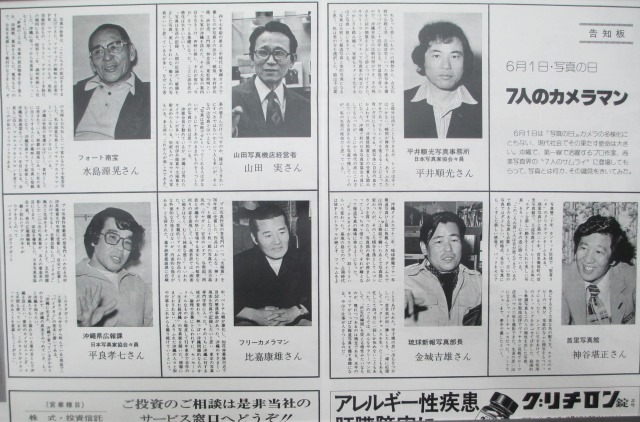
1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」
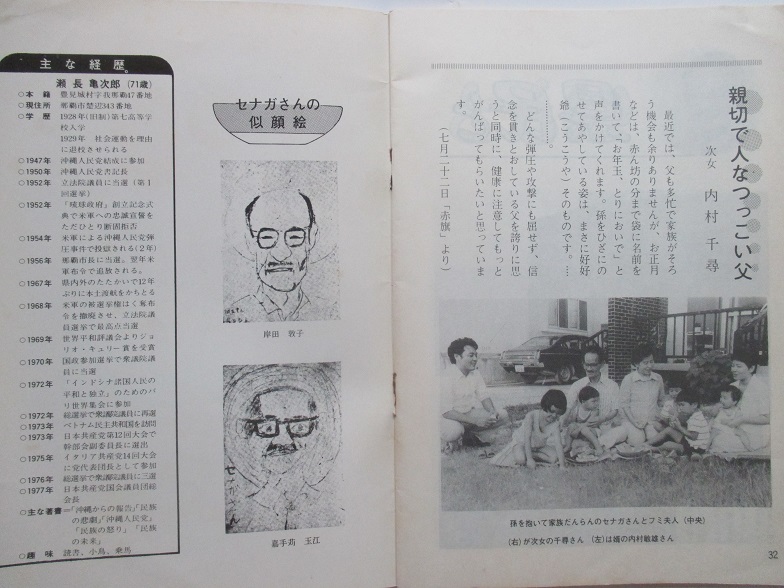
1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会


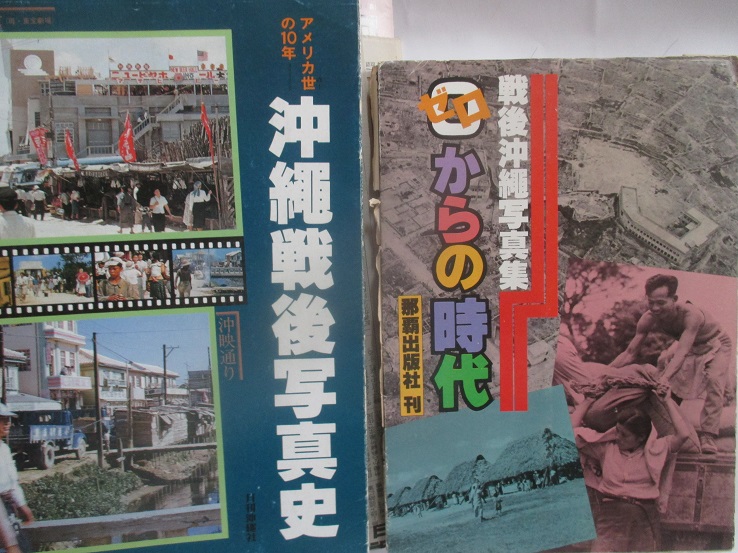
1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社
☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)
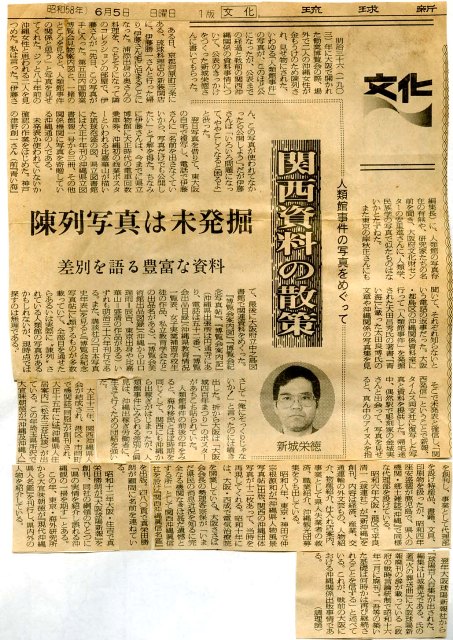
□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」
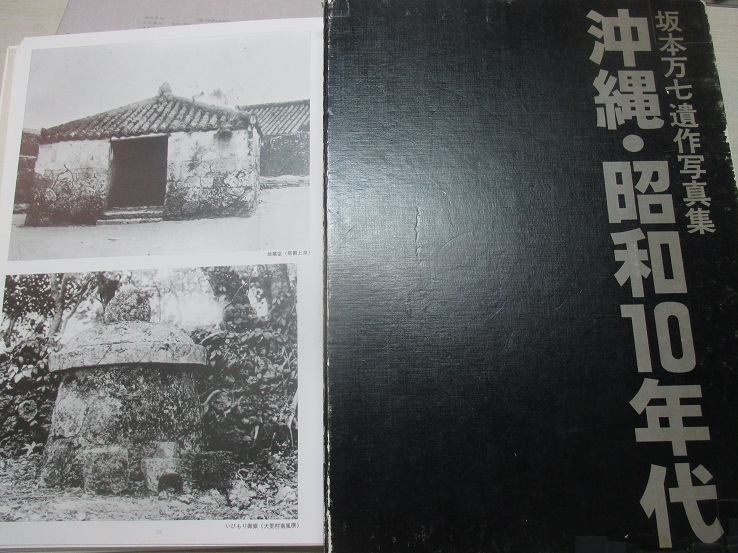
1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書
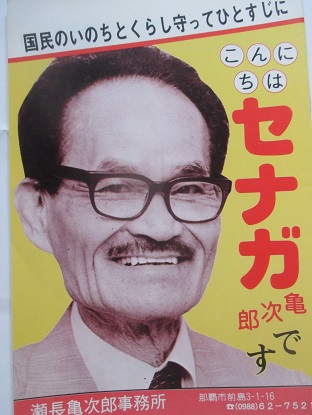
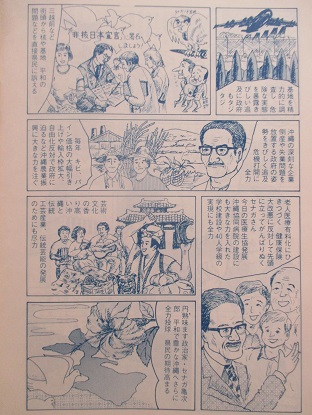
1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所
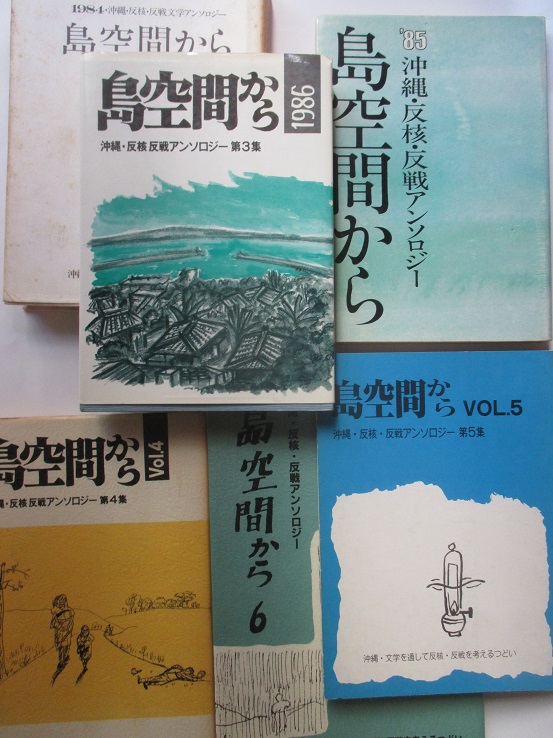
1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)
〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。
いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。
文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。
米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。
1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』
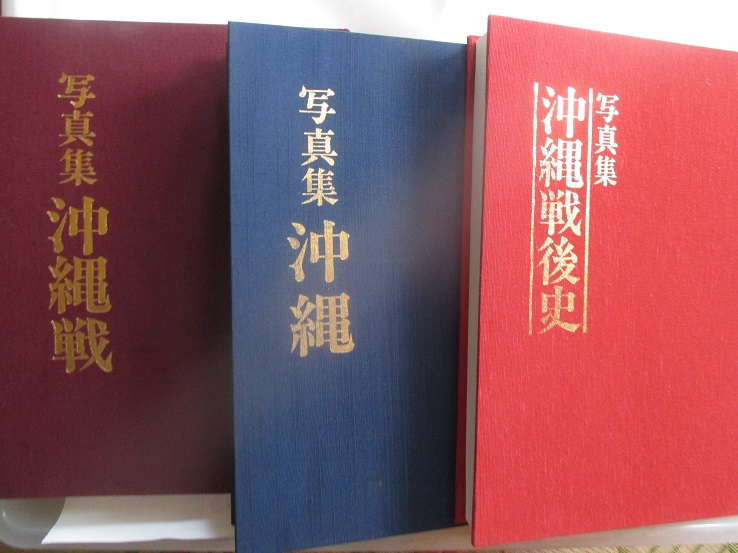
那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實
1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」
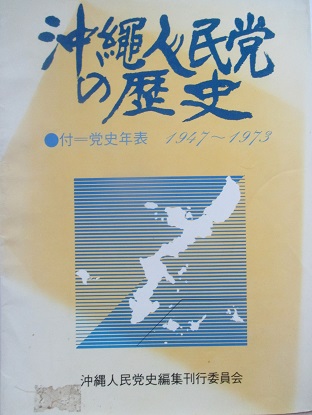
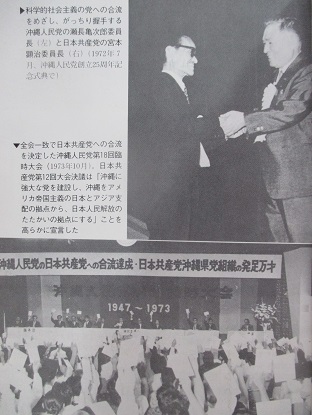
1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会
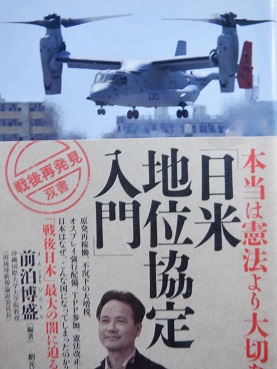
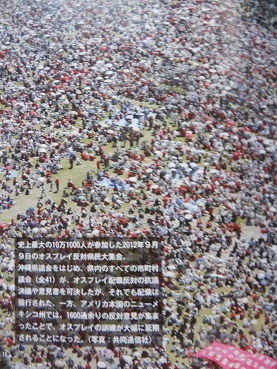
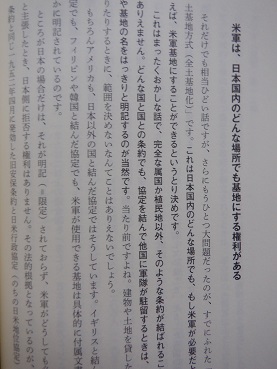
2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社
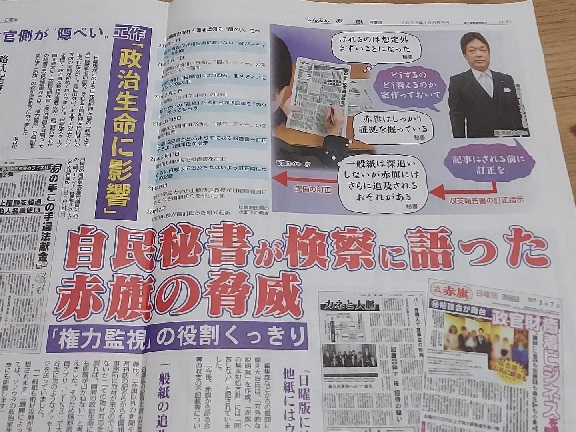

瀬長亀次郎は戦後も沖縄人民党行事としてこの碑(人民解放戦士真栄田一郎君に捧ぐ)の前に集い団結を誓った。瀬長亀次郎「弾圧は抵抗を呼ぶ 抵抗は友を呼ぶ」→1991年8月『瀬長亀次郎回想録』新日本出版社
1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社
ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ
写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。
悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫
○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。
郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長
善意の記録として・・・・沖縄県学生会
○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。
第一部
拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人
第二部
土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道
島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光
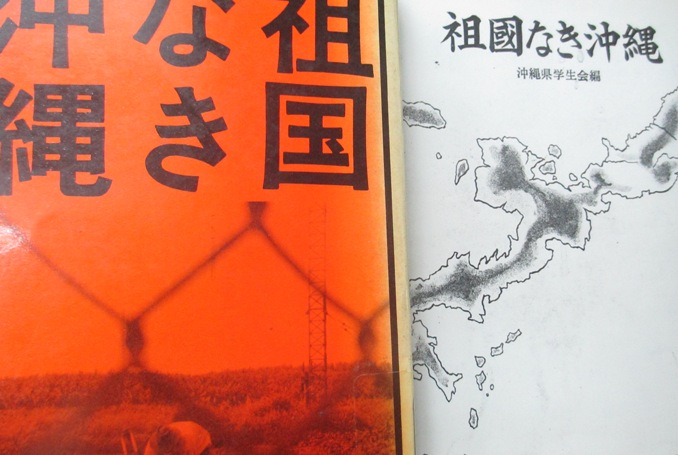
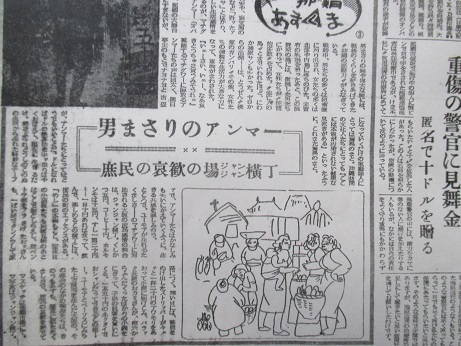
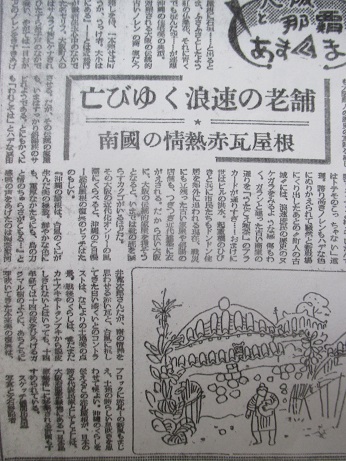
1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」
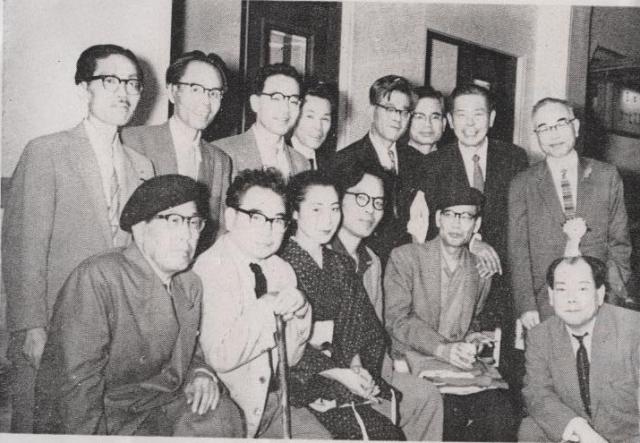
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子
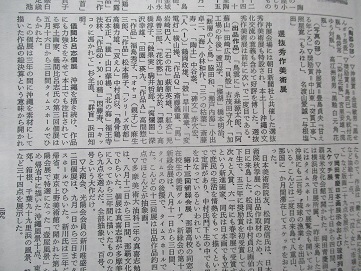

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』
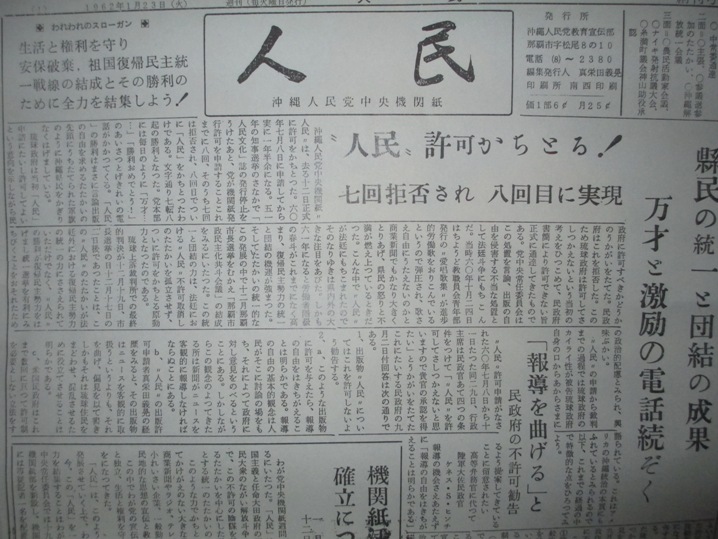

1963年
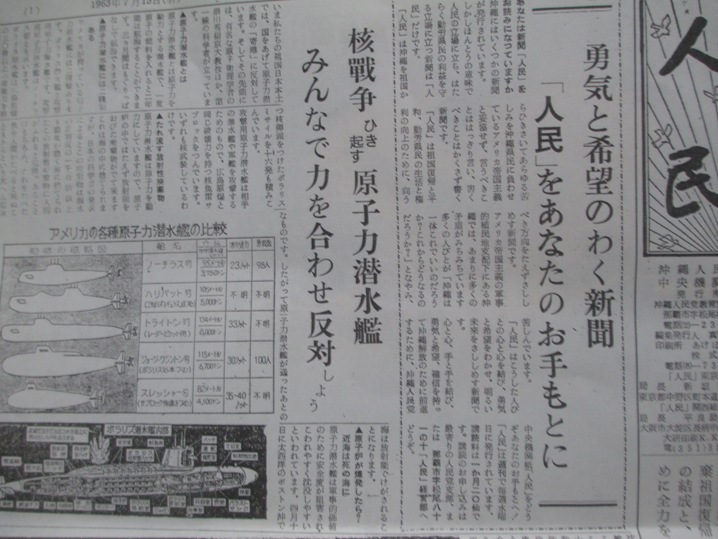
7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」
1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」
1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社
○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫
○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫
○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの
○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二
○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光
○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会
1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」
1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」
2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」
7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)
7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」
9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」
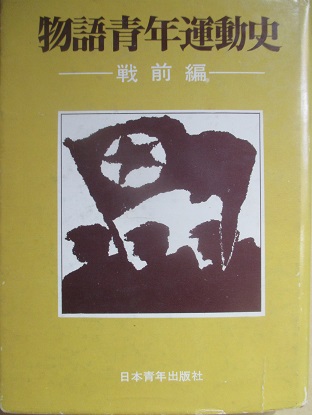

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社
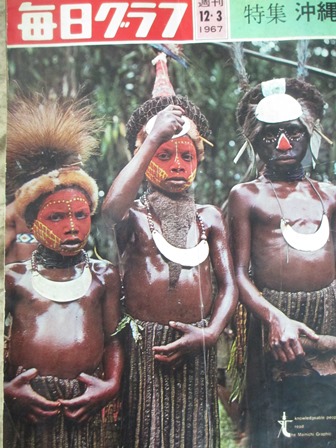
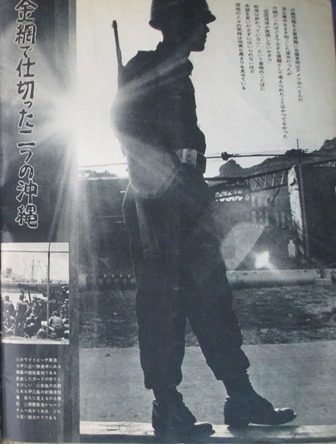
12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」
1968年
6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」
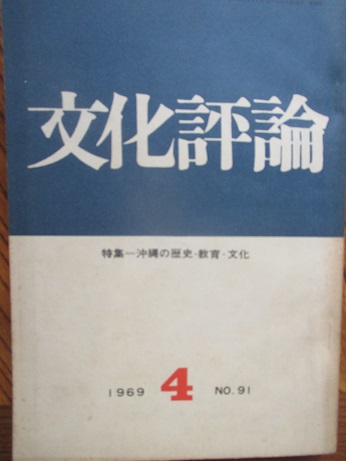
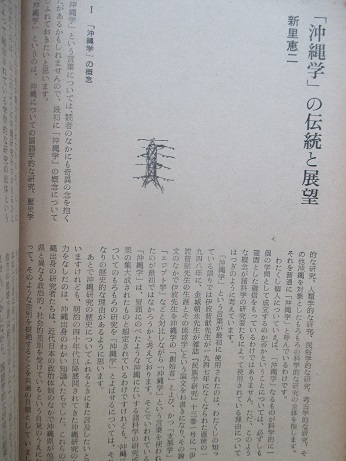
1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」
1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)
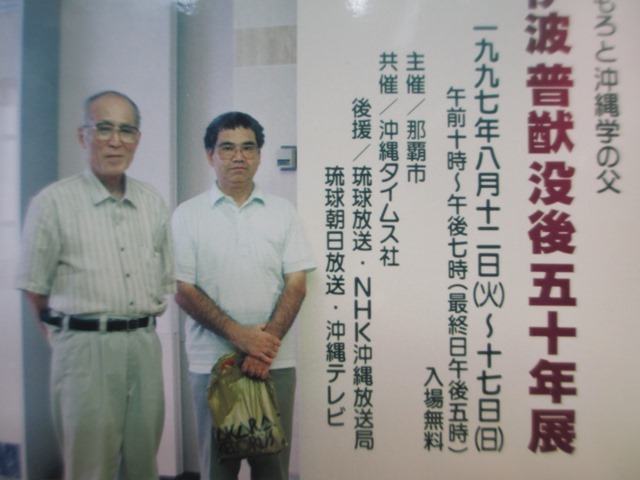
伊波廣定氏と新城栄徳
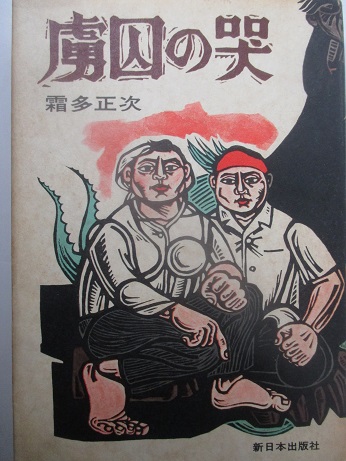
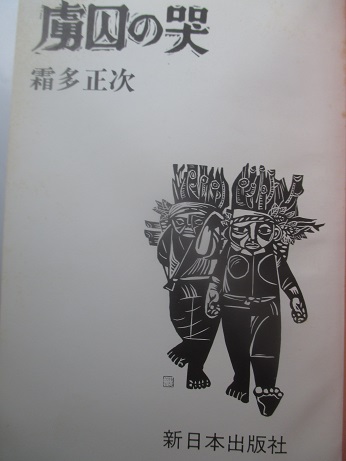
1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」
5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)
8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」
①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)
9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』
□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために
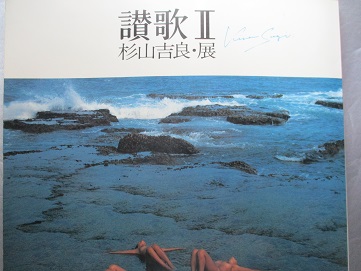
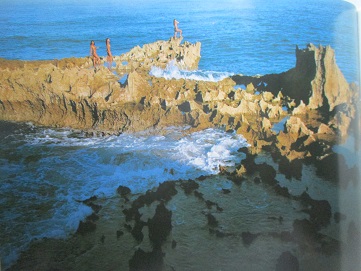
1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』
1971年
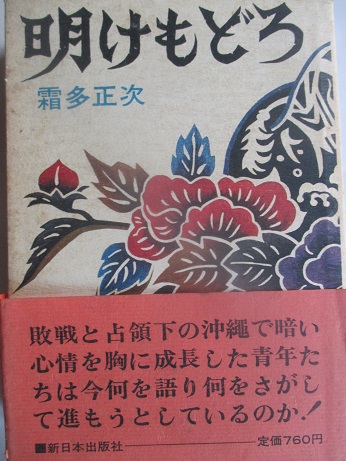
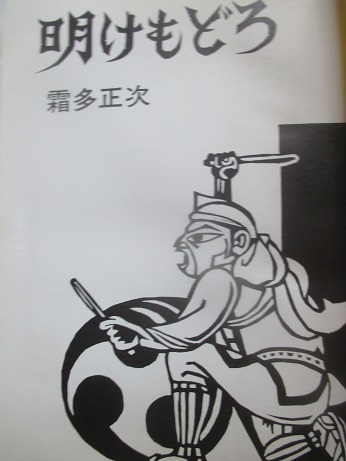
1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」
1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」
1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」
1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」
1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」
2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」
2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」
4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」
5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」
5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④
5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」
6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」
6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」
7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」
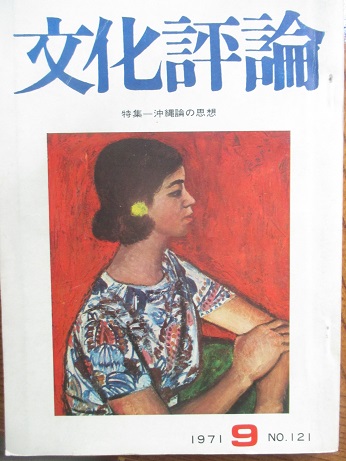
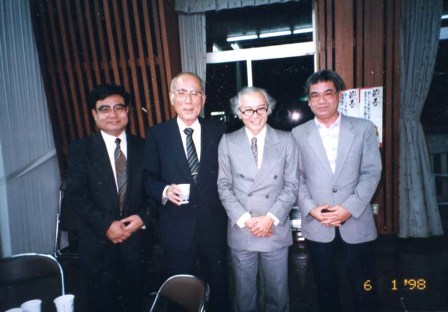
1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
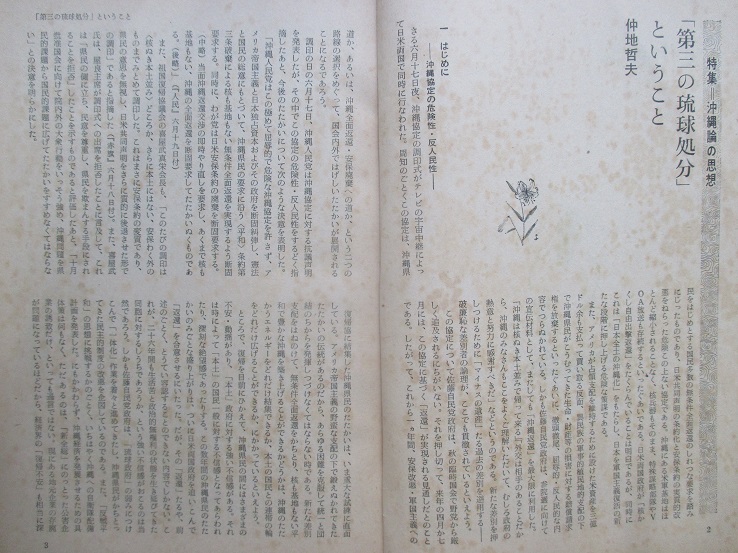
10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」
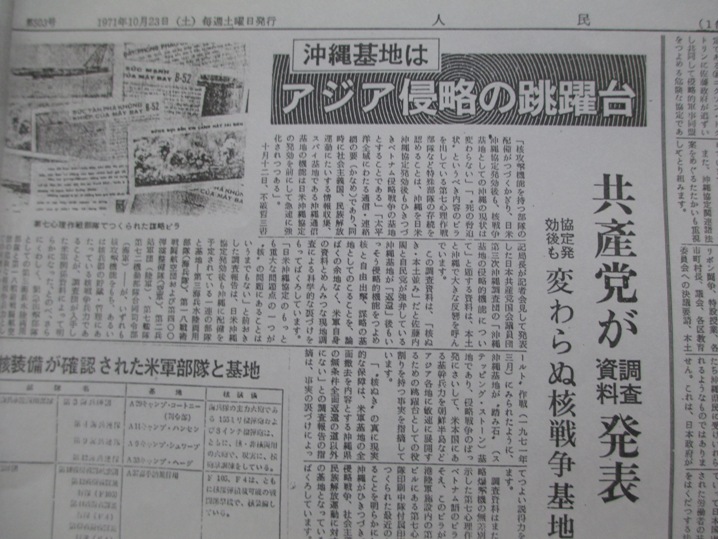
10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」


写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益
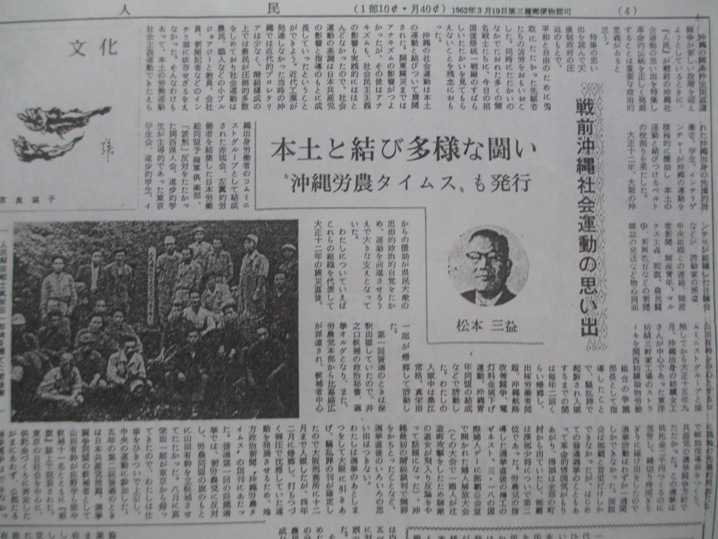
12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」
12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」
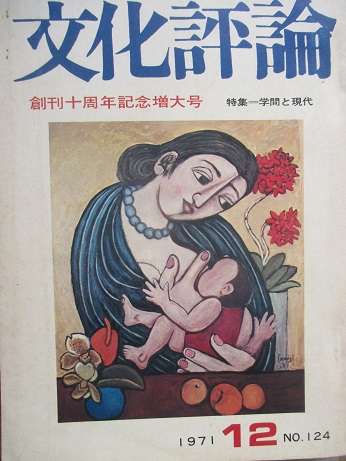
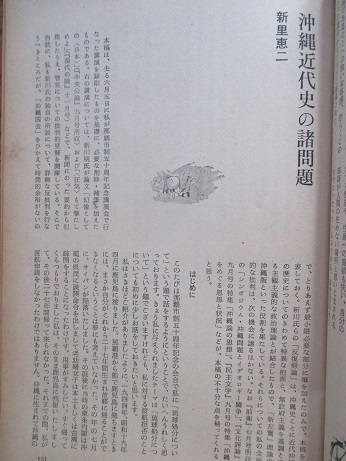
1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」
1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>
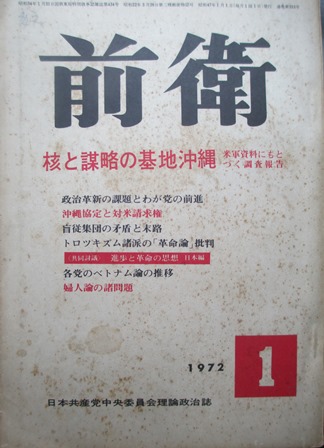

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫
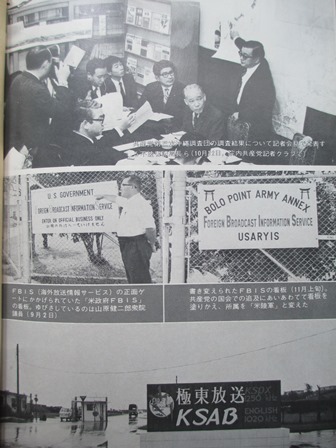
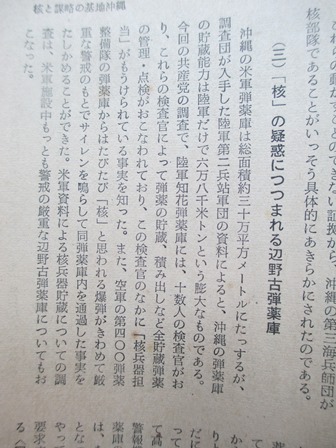
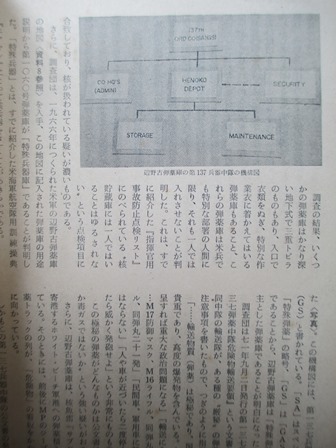
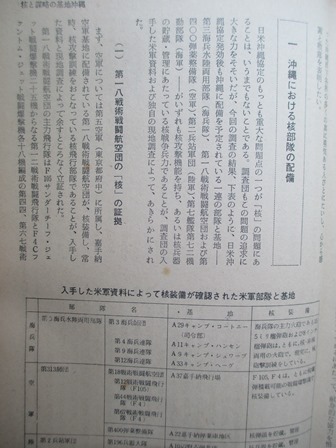


1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」
1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」
2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」
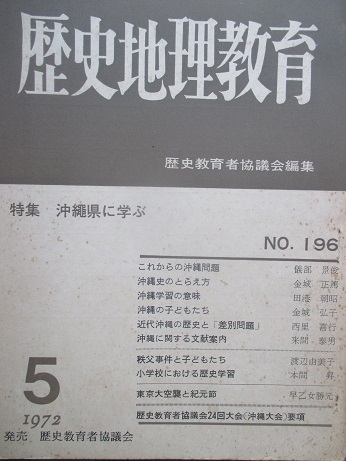
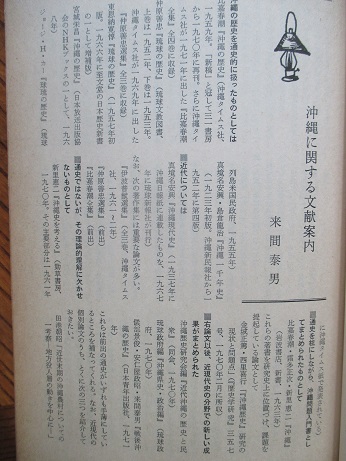
1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」
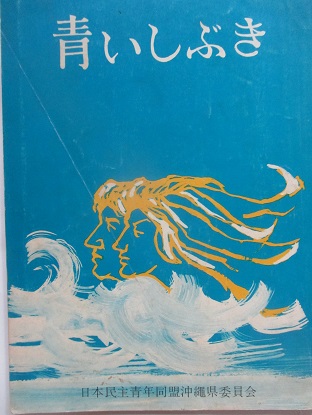
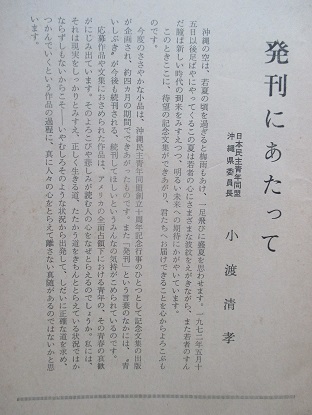
1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

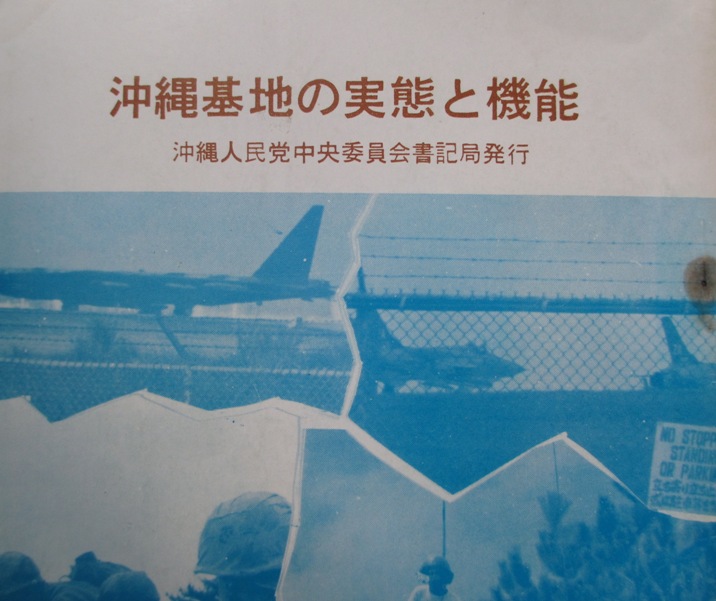
写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』
1973年
1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」
4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」
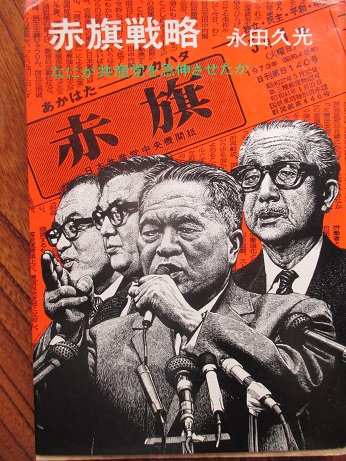
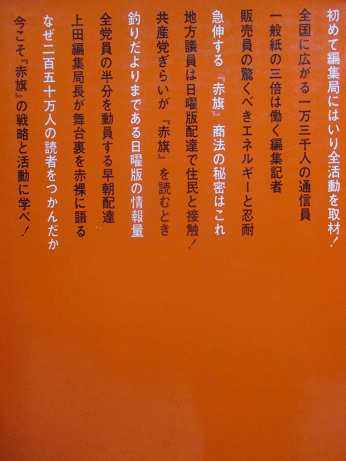
1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社
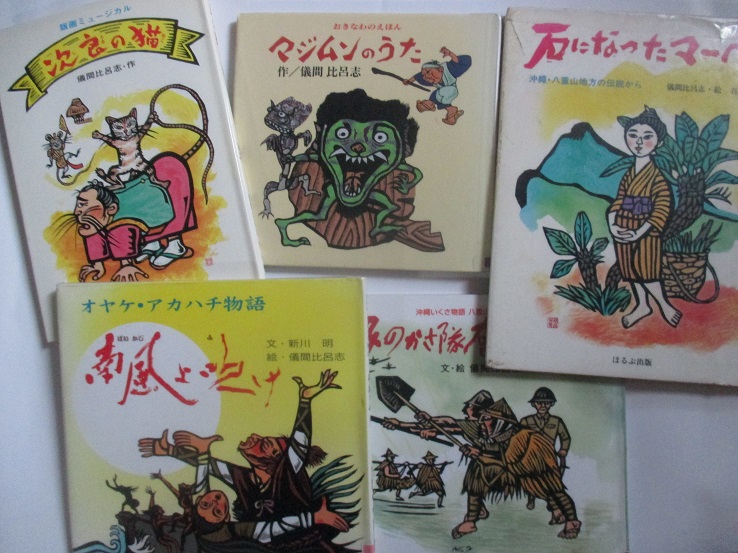
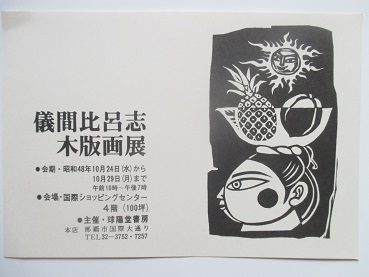
右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房
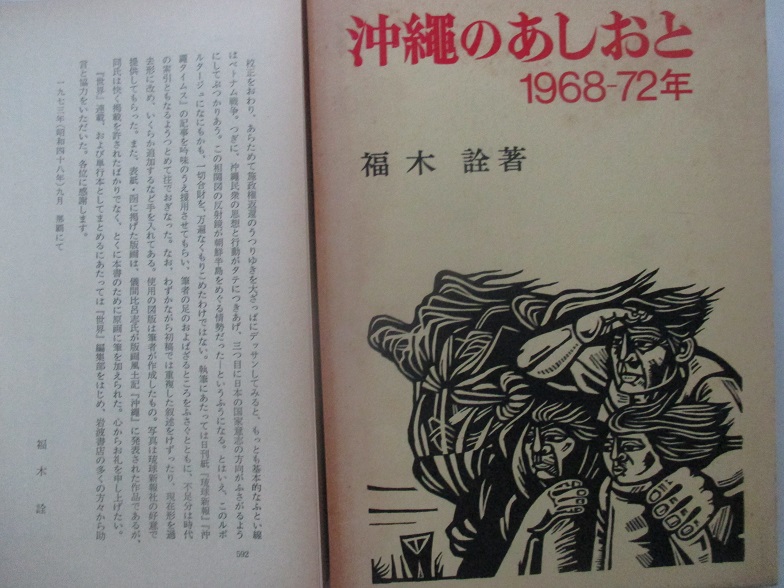
1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。
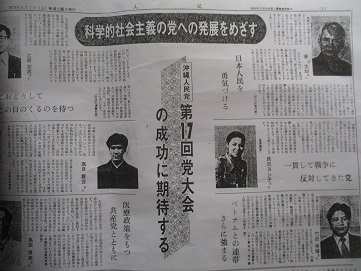
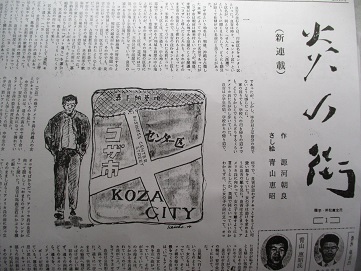
『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭
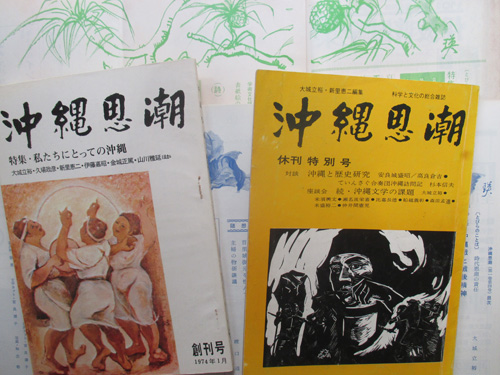
1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」
☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。
1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」
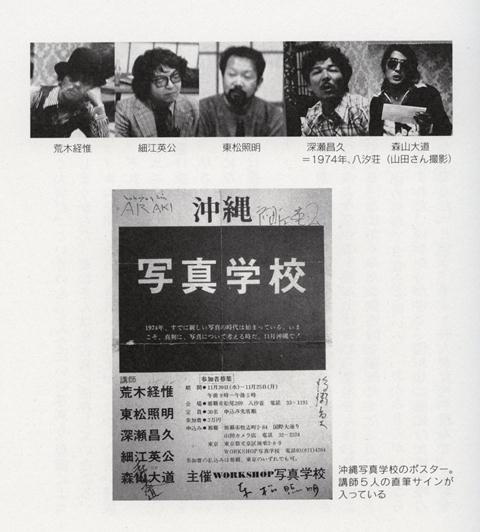
1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」
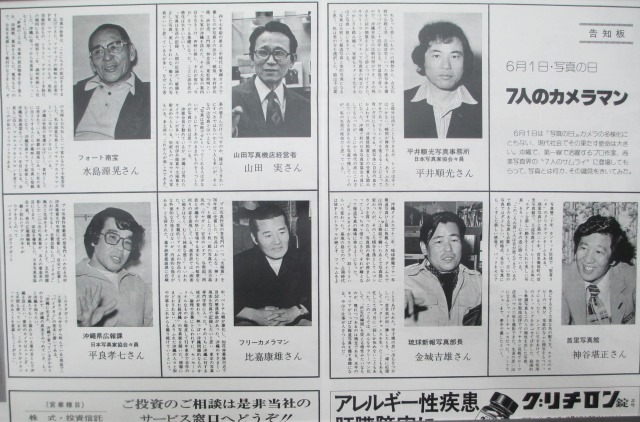
1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」
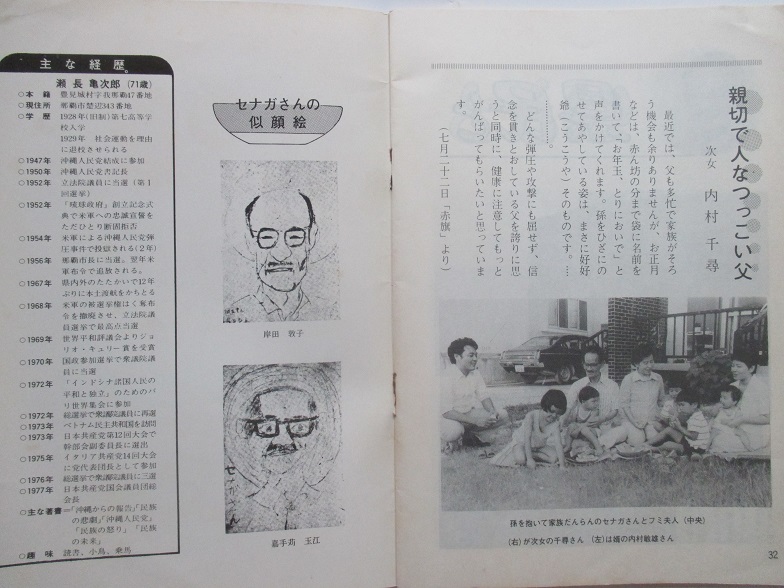
1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会


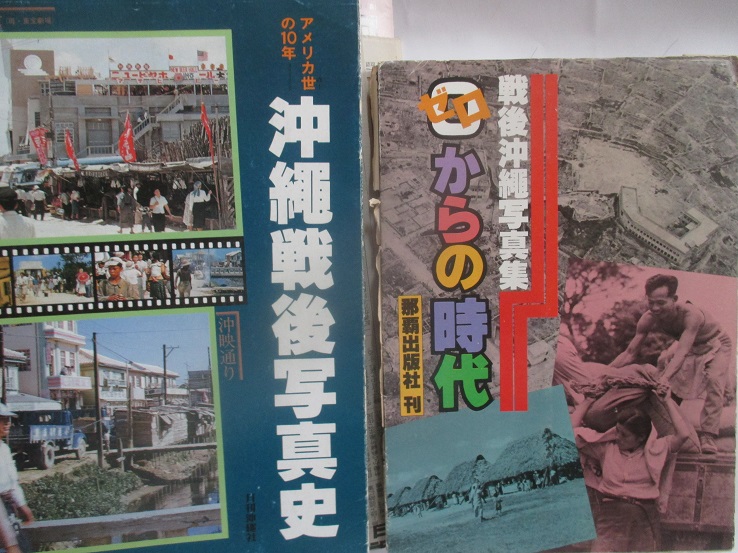
1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社
☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)
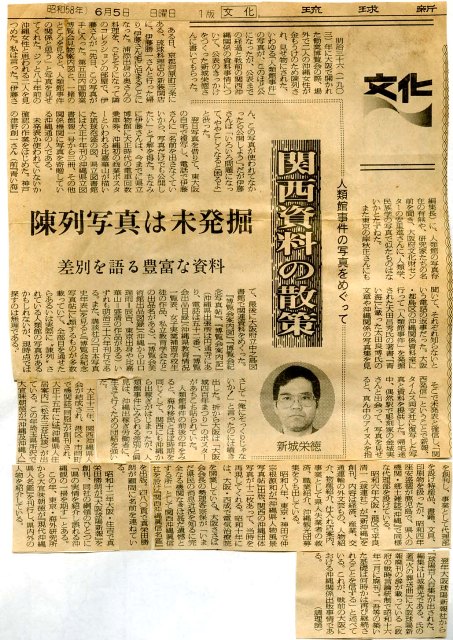
□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」
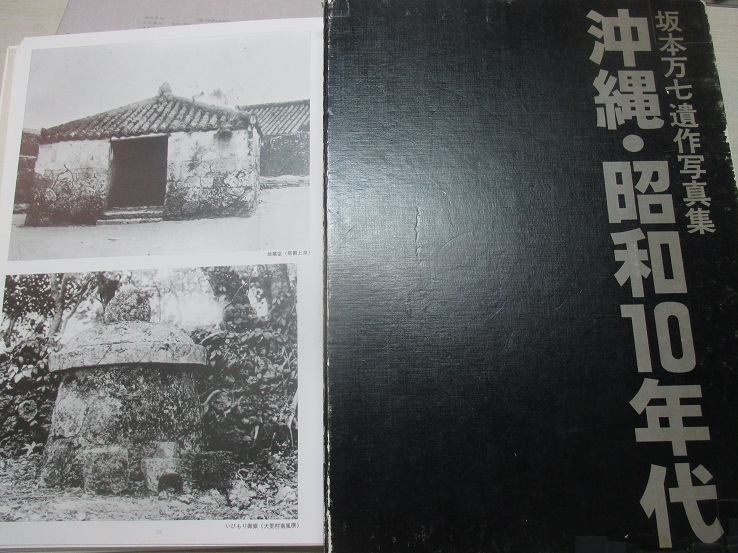
1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書
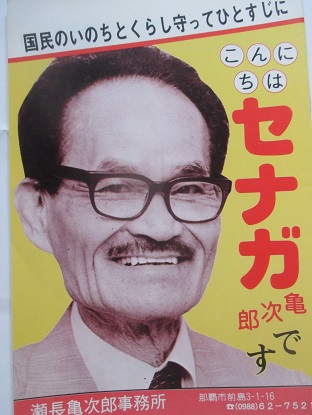
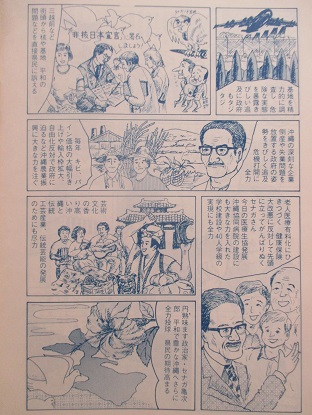
1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所
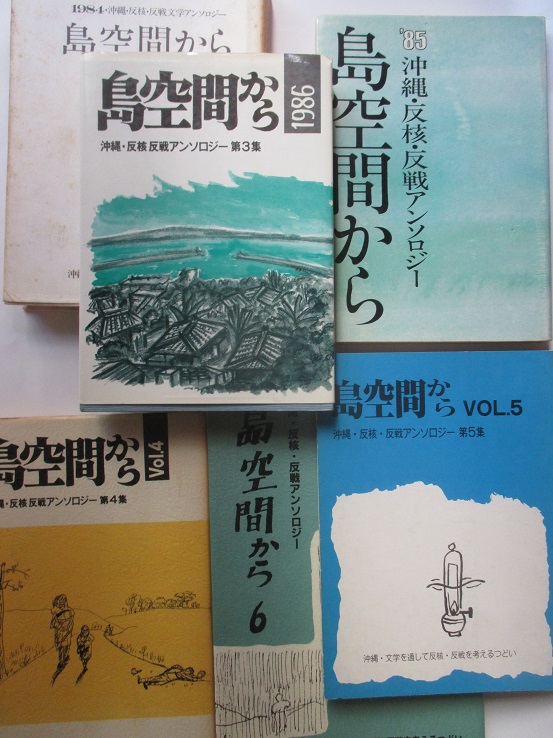
1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)
〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。
いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。
文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。
米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。
1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』
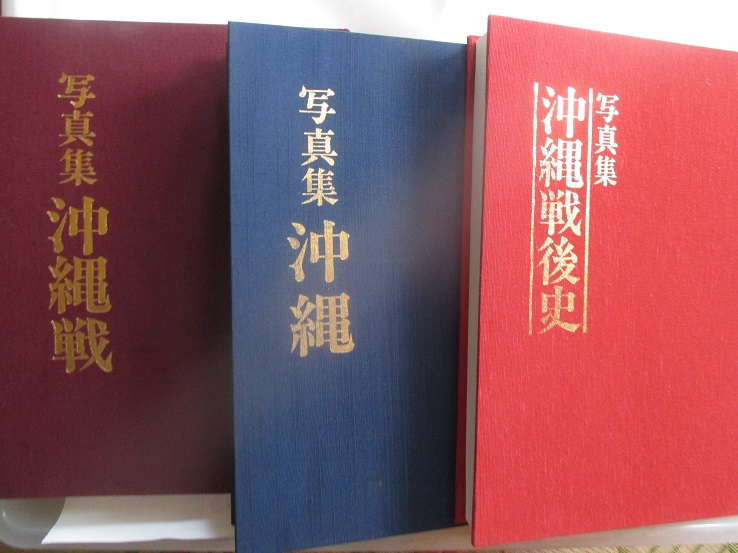
那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實
1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」
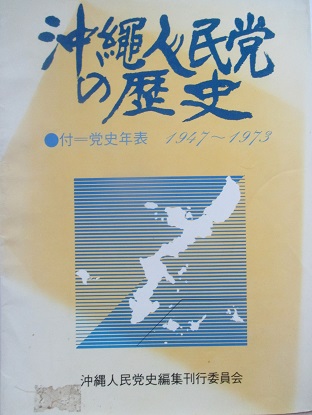
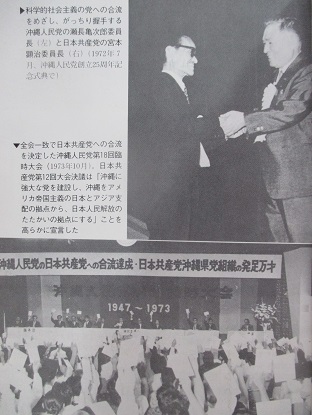
1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会
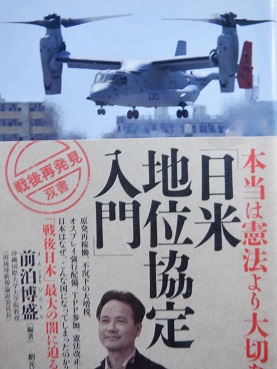
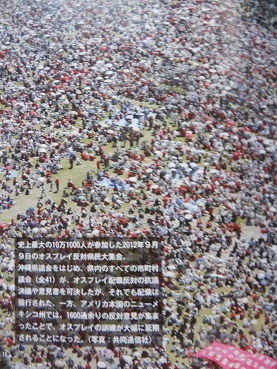
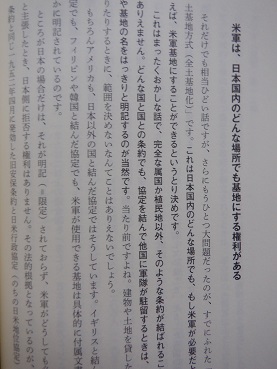
2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社
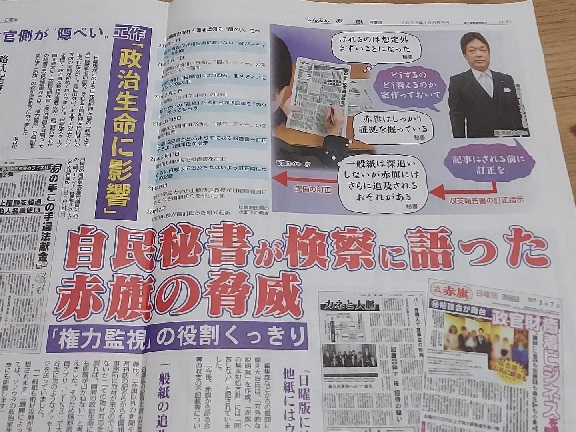
04/19: 琉球芸能史散歩②
真栄里泰山の「はがきエッセイ」№20□ひや!ひや!ひやひやひや!ひやみかちうきり、ひやみかちうきり」の「ひやみかち節」。この歌が出ると心は浮き浮き、誰もが座っておれなくなる。三線の力強いリズムといい歌詞といい、うちなーんちゅの魂のそのもののような歌である。1948年、山内盛彬作曲によるこの歌は、沖縄戦で廃墟となり、米軍統治下におかれ失意のうちにあった沖縄の人々を励ました名歌である。「名に立ちゅる沖縄 宝島でむぬ 心うち合わち うたちみしょり」、「七転び転で、ひやみかち起きて わしたこの沖縄 世界に知らさ」の歌詞は、沖縄の自由民権運動の父・謝花昇の同志で熱血漢の平良新助の作だ。私たちの世代は「腕を組み歌おう 喜びの歌を 僕らみな明るい日本の子、沖縄の子」と歌ったが、それは当時、沖縄教職員会が替え歌にしたものだろう。「ひやみかち節」は沖縄の復帰運動を鼓舞した歌でもあった。
その「ひやみかち節」の歌碑が、山内盛彬翁(1890年~1986年)の生誕120年を記念して、翁夫婦が晩年を過ごし琉球音楽普及の拠点であった沖縄市の社会福祉法人緑樹苑の中庭に建立された。去る3月27日の除幕式では、おもろ主取家の安仁屋眞昭が思い出を語り、首里クェーナ保存会による「あがり世」、山内翁から直伝された「せーぐぁー」こと登川誠仁の歌三線、バンド演奏、踊りなどいろいろなバージョンで「ひやみかち節」が披露された。琉球王朝禮学の復活伝承に生涯をささげた山内翁にふさわしい会であった。
琉球王国の滅亡後、日本の近代教育は皇民化を第一とし、うちなー口はじめ琉球の文化風俗を蔑視し撲滅した。そうしたなかで、沖縄の文化を守るため使命感を持って苦闘した先人達がおられた。おもろと沖縄学の父・伊波普猷はよく知られているが、琉球王朝の御座楽、路次楽、おもろをはじめノロのウムイ、クェーナなどの歌謡を五線譜に採集し、世界に通ずる音楽として広め紹介したのが山内盛彬翁である。翁の祖父盛憙から受け継いだ伝統音楽と西洋音楽の技量を合わせ持ち、秘伝のくえーな「あがり世」などは床下にもぐりこんで採譜したという、沖縄歌謡保存にかけたその烈々たる情熱は、今度の歌碑に刻された翁の「滅びゆく文化 忍で忍ばれめ もち(自費)と命かけて 譜文に遺さ」という歌に込められている。
沖縄音楽というと、大方は宮良長包の数々の名曲を思い浮かべるだろうが、今回の「ひやみかち節」歌碑建立を機に、山内盛彬翁の業績をあらためて見直したいものである。「ひやみかち節」は平和とやさしさ、そして沖縄の誇りを歌った沖縄県民の歌ともいうべき永遠の名歌名曲である。
「花や咲き美さ 音楽や鳴り美さ 聴かさなや世界に 音楽の手並み」(盛彬)(2011年4月10日)
◎YouTube 沖縄民謡「ひやみかち節」登川誠仁、他
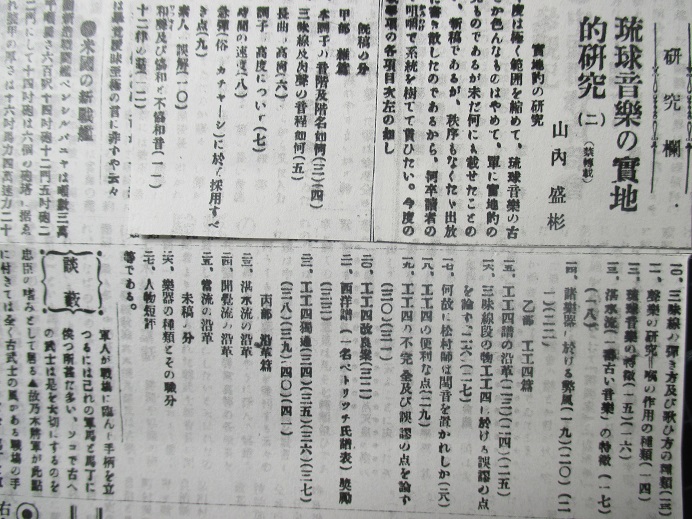
1912年10月1日 『沖縄毎日新聞』山内盛彬「琉球音楽の実地的研究(2)」
1925年5月15日 『沖縄タイムス』山内盛彬「末吉麦門冬氏遺稿『三味線渡来説に就て』」
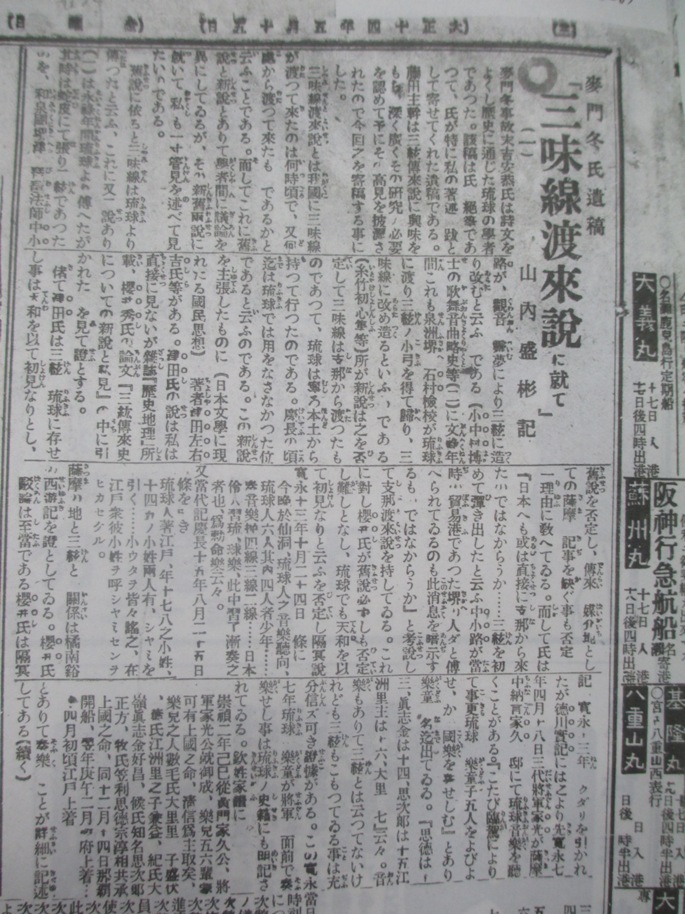
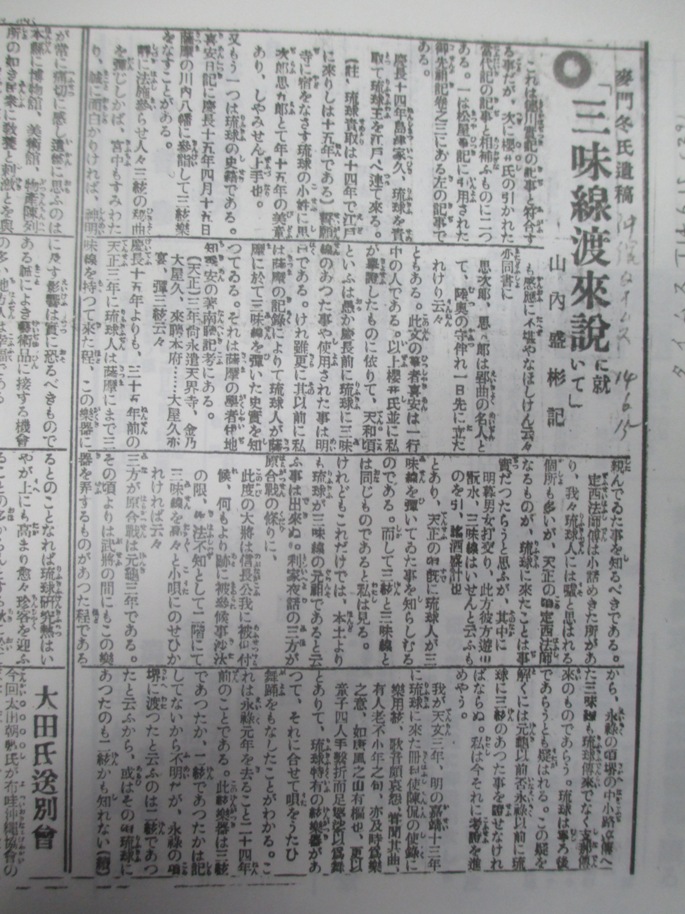
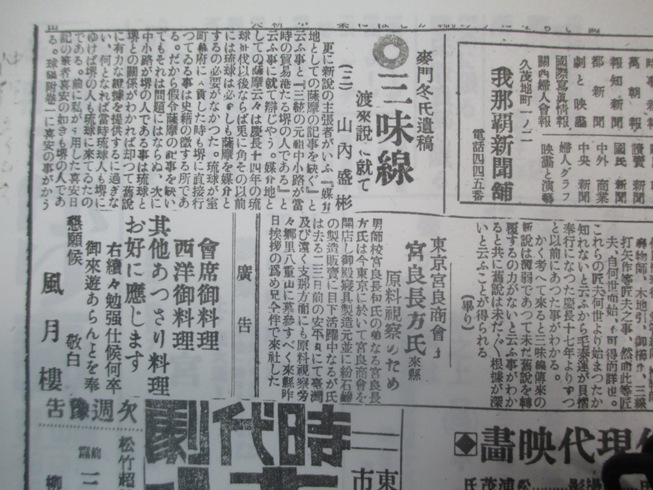
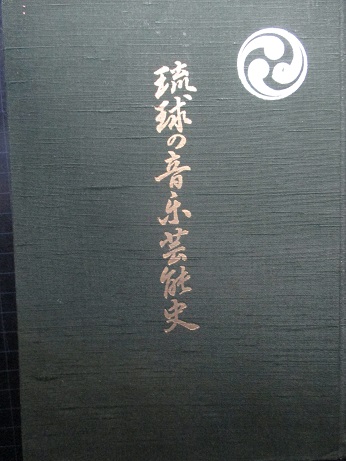
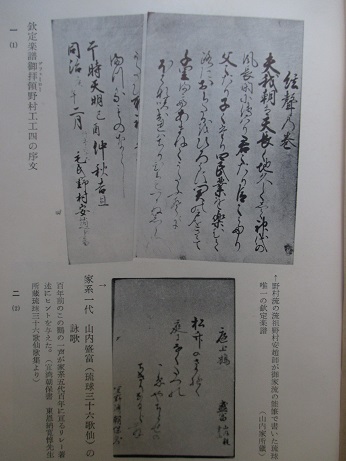
1959年4月 山内盛彬『琉球の音楽芸能史』民族芸能全集刊行会
2月11日「はがきエッセイ」№11
上山中学校3年生の孔子廟参拝で講話をした。学問の神様・孔子様への学業成就祈の願願を兼ねた学校周辺の歴史・文化のユニークなふるさと学習だ。人類の教師として釈迦、孔子、ソクラテス、キリストを紹介し、その4聖人がそれまで弱肉強食で平気でいた人間に初めて人間の愛、人間性を説き教えたこと。仁義礼智信の人間学儒学は中国、韓国、台湾、日本、沖縄、ベトナムで国学となり、ほぼ共通の道徳となっていること。鄭順則など沖縄の儒学は当時の最先端だったことなどを話した。話しながら、ふと今の政治や指導者をこの若者たちはどう感じているのか気になった。基地問題での沖縄に対する民主党政権の傲慢なふるまい、地元名護市長を無視した礼節を欠いた行動、中国の尖閣問題、北方領土のロシアなど、力にまかせた大国主義政治の横行等々。今、本当に必要な道徳教育、経世済民の徳治主義の政治教育はこれら指導者たちにこそ必要ではと思った次第。
その「ひやみかち節」の歌碑が、山内盛彬翁(1890年~1986年)の生誕120年を記念して、翁夫婦が晩年を過ごし琉球音楽普及の拠点であった沖縄市の社会福祉法人緑樹苑の中庭に建立された。去る3月27日の除幕式では、おもろ主取家の安仁屋眞昭が思い出を語り、首里クェーナ保存会による「あがり世」、山内翁から直伝された「せーぐぁー」こと登川誠仁の歌三線、バンド演奏、踊りなどいろいろなバージョンで「ひやみかち節」が披露された。琉球王朝禮学の復活伝承に生涯をささげた山内翁にふさわしい会であった。
琉球王国の滅亡後、日本の近代教育は皇民化を第一とし、うちなー口はじめ琉球の文化風俗を蔑視し撲滅した。そうしたなかで、沖縄の文化を守るため使命感を持って苦闘した先人達がおられた。おもろと沖縄学の父・伊波普猷はよく知られているが、琉球王朝の御座楽、路次楽、おもろをはじめノロのウムイ、クェーナなどの歌謡を五線譜に採集し、世界に通ずる音楽として広め紹介したのが山内盛彬翁である。翁の祖父盛憙から受け継いだ伝統音楽と西洋音楽の技量を合わせ持ち、秘伝のくえーな「あがり世」などは床下にもぐりこんで採譜したという、沖縄歌謡保存にかけたその烈々たる情熱は、今度の歌碑に刻された翁の「滅びゆく文化 忍で忍ばれめ もち(自費)と命かけて 譜文に遺さ」という歌に込められている。
沖縄音楽というと、大方は宮良長包の数々の名曲を思い浮かべるだろうが、今回の「ひやみかち節」歌碑建立を機に、山内盛彬翁の業績をあらためて見直したいものである。「ひやみかち節」は平和とやさしさ、そして沖縄の誇りを歌った沖縄県民の歌ともいうべき永遠の名歌名曲である。
「花や咲き美さ 音楽や鳴り美さ 聴かさなや世界に 音楽の手並み」(盛彬)(2011年4月10日)
◎YouTube 沖縄民謡「ひやみかち節」登川誠仁、他
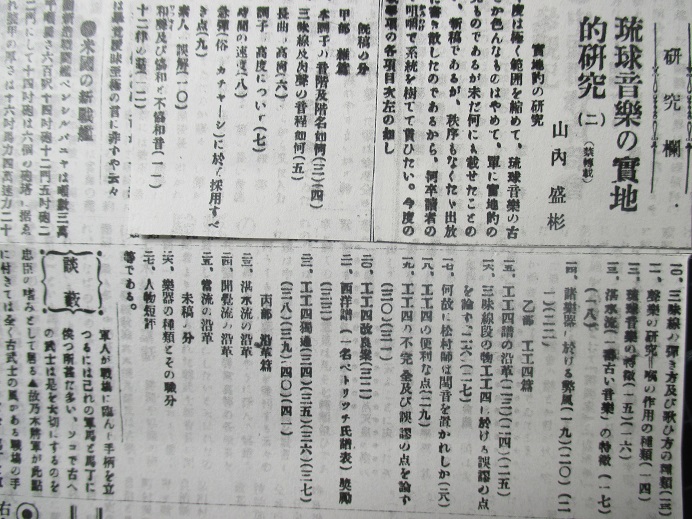
1912年10月1日 『沖縄毎日新聞』山内盛彬「琉球音楽の実地的研究(2)」
1925年5月15日 『沖縄タイムス』山内盛彬「末吉麦門冬氏遺稿『三味線渡来説に就て』」
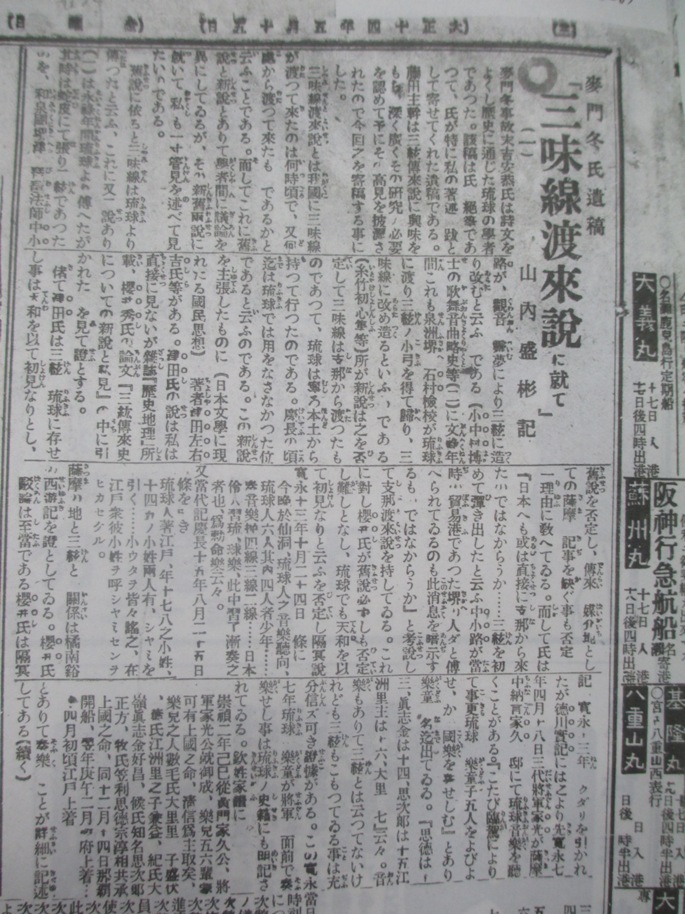
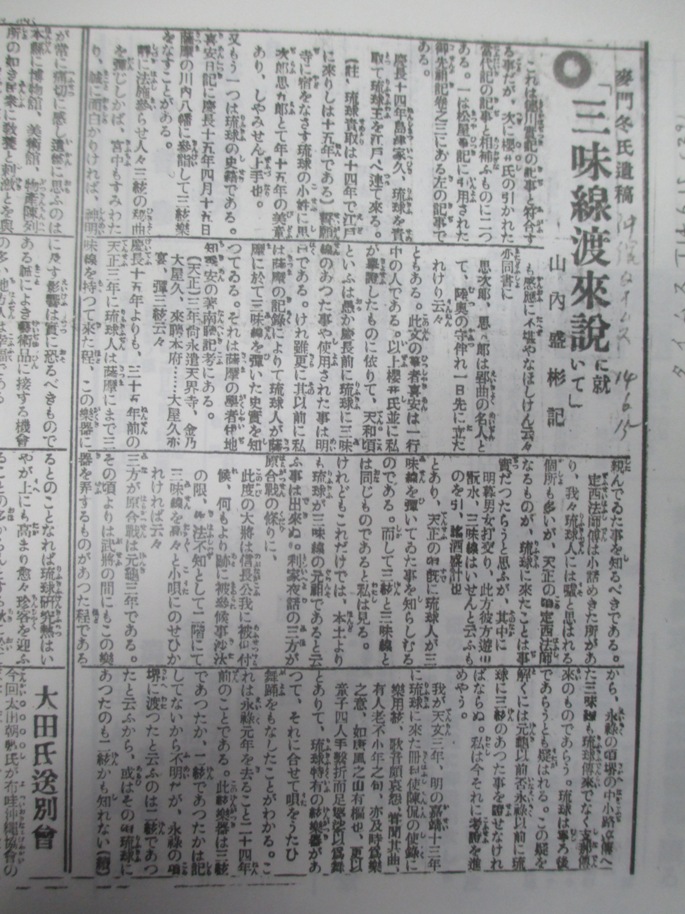
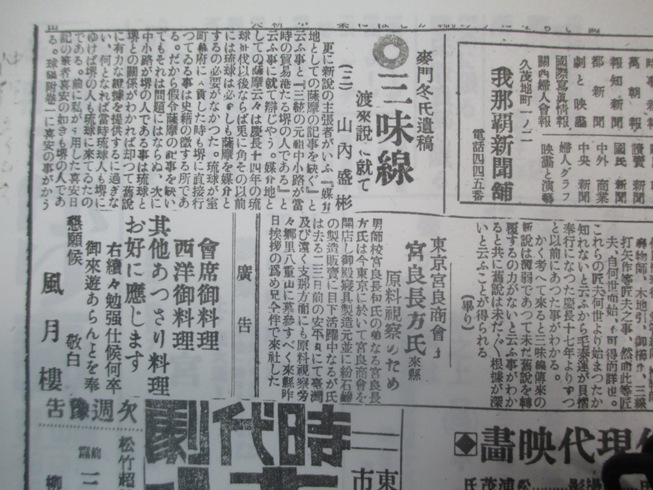
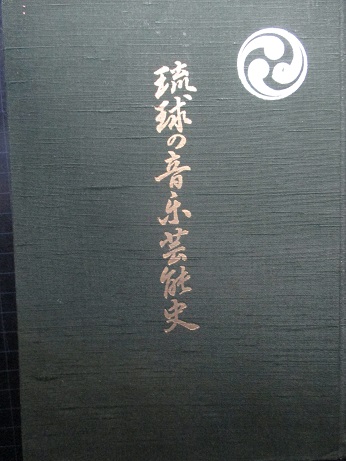
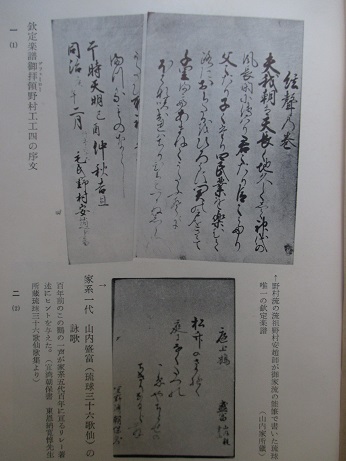
1959年4月 山内盛彬『琉球の音楽芸能史』民族芸能全集刊行会
2月11日「はがきエッセイ」№11
上山中学校3年生の孔子廟参拝で講話をした。学問の神様・孔子様への学業成就祈の願願を兼ねた学校周辺の歴史・文化のユニークなふるさと学習だ。人類の教師として釈迦、孔子、ソクラテス、キリストを紹介し、その4聖人がそれまで弱肉強食で平気でいた人間に初めて人間の愛、人間性を説き教えたこと。仁義礼智信の人間学儒学は中国、韓国、台湾、日本、沖縄、ベトナムで国学となり、ほぼ共通の道徳となっていること。鄭順則など沖縄の儒学は当時の最先端だったことなどを話した。話しながら、ふと今の政治や指導者をこの若者たちはどう感じているのか気になった。基地問題での沖縄に対する民主党政権の傲慢なふるまい、地元名護市長を無視した礼節を欠いた行動、中国の尖閣問題、北方領土のロシアなど、力にまかせた大国主義政治の横行等々。今、本当に必要な道徳教育、経世済民の徳治主義の政治教育はこれら指導者たちにこそ必要ではと思った次第。


かつての京都沖縄青年会同志・中根修氏






右が当真嗣一氏(『沖縄のグスクめぐり』当真嗣一監修、2001年、むぎ社)と西村貞雄氏
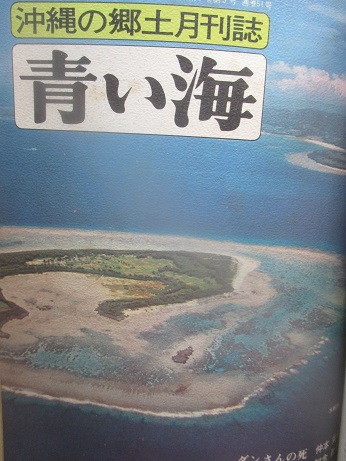
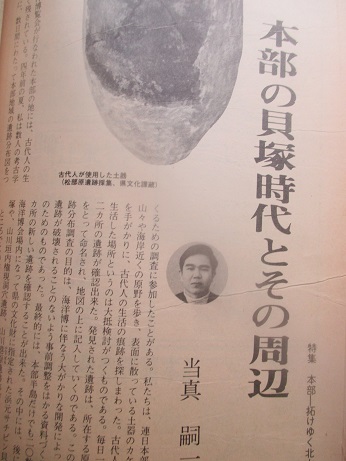
1976年3月 沖縄の雑誌『青い海』51号 当真嗣一「本部の貝塚時代とその周辺」

□2013年7月12日『週刊金曜日』島田健弘「頻発するメディア幹部と安倍首相の会食・会談ー記者の筆がにぶらないわけがない」で示されるようにネットでは「NHKマスゴミ」「ネトウヨ 百田尚樹」「ワタミ ブラック」などが飛び交っている。その中で「嫌中・嫌韓」は「在日人脈と安倍」とも絡んで目立っている。こういったものは匿名なので信頼性に疑問があるが「マンガ」「タレントグラビア」と同様に読み捨てのものと考えてよい。2014年5月『琉球新報』「岐路の憲法ーかすみゆく未来図」に雑誌が「嫌中・嫌韓」特集が目立ってきたという。その中で「タブーに切り込む」が売りの月刊『宝島』が世の雑誌の嫌韓特集に遅れ馳せながら昨年メーン特集で「嫌韓」を組み売り上げを伸ばしているという。ますます新聞雑誌が消える未来図がたち現れてくる。
06/03: 那覇市史編集室(那覇市歴史博物館)
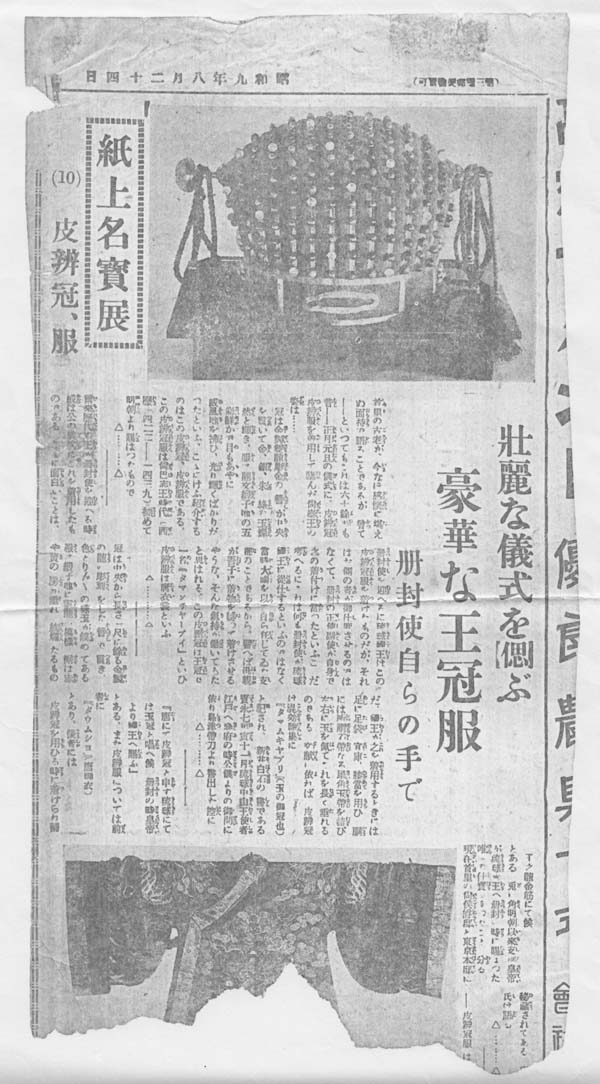
鎌倉芳太郎撮影「王冠」正面
佐野本に、「琉米歴史研究会」の喜捨場静夫インタビューで「(真栄平房敬によると)首里の尚家には那覇市歴史博物館に飾ってあるものより、ずっと立派な王冠があったそうです。(略)」と首里の尚家にあった王冠について述べている。鎌倉芳太郎の『沖縄文化の違宝』にはその首里にあった王冠の後面、横面の写真がある。幸いなことに鎌倉芳太郎は写真撮影メモを残してくれていてそれに王冠の寸法が記されていて王冠高さが18,9cm、ヘリは20、7cm、簪は31,8cmとなっている。上の前面と合わせてほぼイメージが出来ることになる。
那覇市立歴史博物館所蔵は高さが18,4cm、長径21,8cm、簪31,8cm、重さ605グラムとなっている。
□→1938年4月21日ー『大阪毎日新聞』「紙上琉球展覧会①」にも同様な記事がある。
王冠と皮弁服

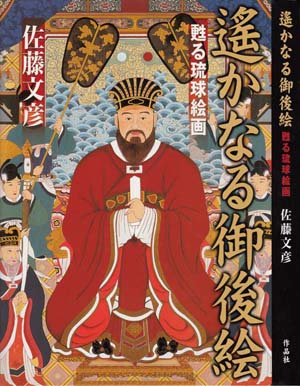
2011年8月21日、那覇市歴史博物館に遊びに行くと、志村絵里奈学芸員が鎌倉芳太郎の『沖縄文化の遺宝』を前に王冠や衣裳の話をしてくれた。先ず、遺宝にある王冠の写真は正面と説明されているがこれは後面だという。正面は上左の新聞に載っているもの。また尚真王御後絵に「方心曲領」は明冊封使の記録には無いが清にはある。皮弁服は尚貞王から石帯をしなくなる。清からは反物でしか領賜されなかったので紋様がある。
2011年5月1・11日『新美術新聞』光田ゆり「新美術時評・震災後の美術」に「美術は非常時に無力ではないか、という言葉は、阪神大震災のときにも発されていた。しかし被災地のがれきのなかに人々が一心に探したのが、家族の写真や記念の品だったことをテレビで知ったとき、人が生きた歴史と記憶を証するものがどれほど大切かを改めて教えてもらえた。(略)個人の記憶は地域の記憶と相互に織り込みあい、時代や歴史をつくる。そこから人は引き剥がせない。人が考え求めたことを証する物品や情報を失うことは、人の存在を損ないかねない欠落をもたらしてしまうことなのだと思える。(略)今こそ大型展覧会中心主義を見直し、美術作品と資料・情報の蓄積の場としての美術館像を提示する時ではないだろうか。地域の文化の記憶を共有し新しい活動につなげていくー」と、人が考え求めたことを証する物品や情報を失うことは、人の存在を損ないかねないと強調している。
人は今、現在起こっていることは余り気にしないものである。無くなって初めて気づくものが多い。そこで記憶が薄れないうちに那覇市史編集室について回想してみる。
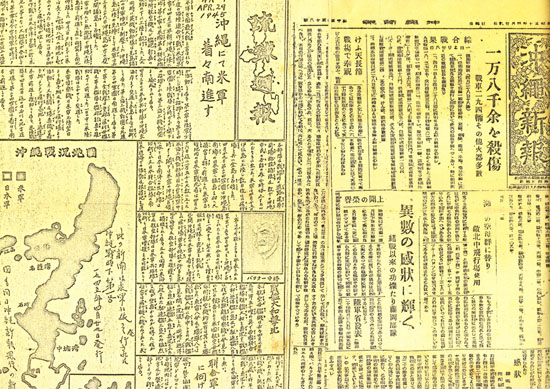
1945年4月ー『沖縄新報』『琉球週報』
1961年5月20日ー那覇・首里市制施行40周年を記念して市史編集を企画。担当は企画部企画室広報係(嘱託1人)
9月29日ー那覇市史編集委員会発足(委員15人)
1966年10月30日ー初の『那覇市史』刊行。『資料編第2巻上(近代新聞集成)』。
1967年7月15日ー那覇市史の編集、課相当の総務部市史編集室で本格的にスタート
1968年4月12日ー那覇市史編集室、家譜のマイクロ撮影を始める
1970年3月ー那覇市史編集室「市立那覇史料館」構想/史料館は、歴史博物館と文書館の両方の性格をかねた綜合資料館とし、設立時期は「那覇市制施行50周年を記念して市史編集室内に設立し、72年の復帰の時点で独立した建物をつくり移転」とある。建設経費として20万ドルを見込んでいた。主要事業に機関誌(市販)の発行をあげている。
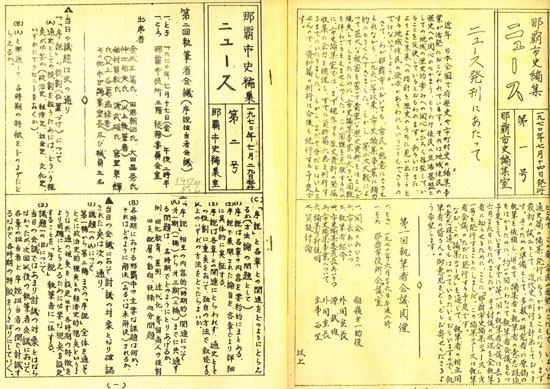
1970年7月ー『那覇市史ニュース』第一号/第二号

1970年ー『那覇市史ニュース』第五号
1971年5月28日ー那覇市制50年記念「歴史民俗資料展」を那覇市民会館、琉球政府立博物館で開催
1974年3月4日ー新城栄徳、那覇市役所内の那覇市史編集室を初めて訪ね大阪で戦前に出された雑誌『新沖縄』を見る

1977年3月

1977年5月ー『那覇の民俗編集ニュース』№17
10/08: 丹青協会初代会長・山口瑞雨
1908年9月4日~14日ー沖縄美術運動の夜明・丹青協会第一回絵画展覧会
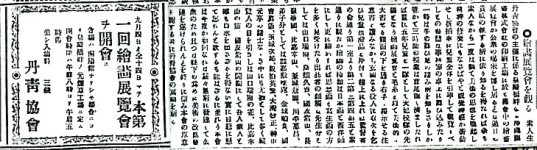
出品者 山口瑞雨(沖縄師範学校教諭心得)、岸畑久吉(沖縄県立中学校教諭心得)、國友朝次郎(首里区立工業徒弟学校助教諭 日本画ー四條派 岡田玉翠に学ぶ)、長嶺華國、比嘉華山、兼城恵園、川平恵昌、渡嘉敷唯選、金城唯貞、大湾政正、神山元享、親泊英繁、玉城次郎、国吉真義(刑務所職員)
瑞雨・山口辰吉はその名が示すごとく1868年(明治元年/戊辰)10月21日に生まれた。辰は、十二支の中で唯一「実在しない生き物」で、これは、或る種のカリスマ性の要因となると云われている。
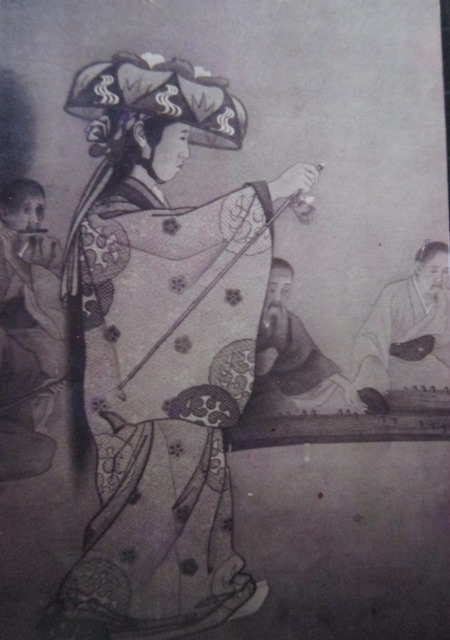

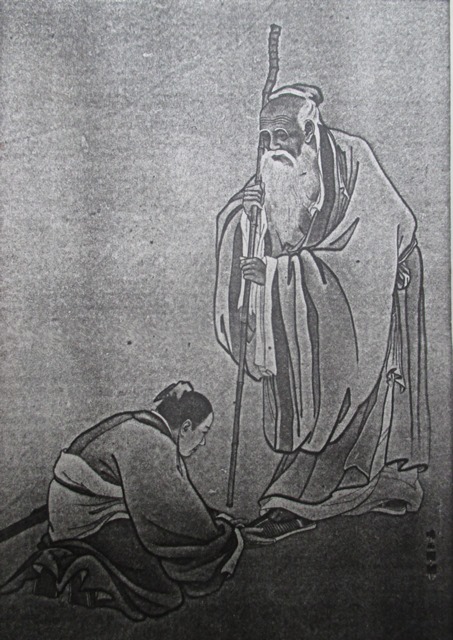
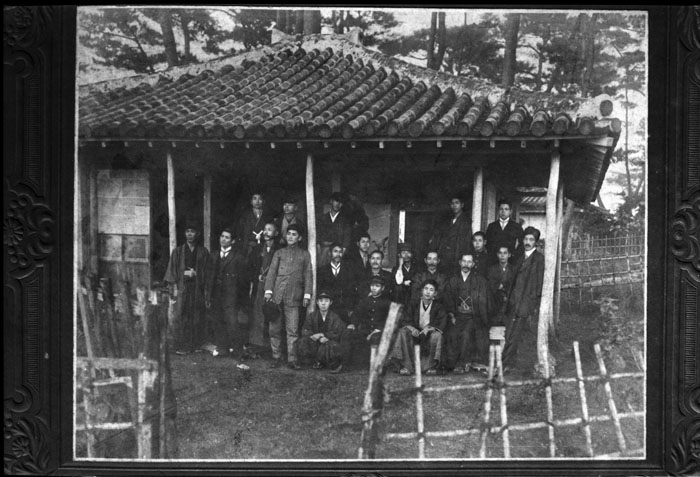
1912年2月ー太平洋画会の吉田博、石川寅治、中川八郎と丹青協会ー真ん中の柱の中列右が瑞雨。瑞雨の上が瑞雨の息子の山口清。左端が比嘉崋山、右へ一人おいて兼城昌興

1908年、沖縄最初の美術団体「丹青協会」が結成されその会長に瑞雨が就いた。11年、2年かがりの「程順則肖像図」の模写が完成。12年の1月、太平洋画会の吉田博、中川八郎、石川寅治が沖縄写生旅行のときの写真には瑞雨や丹青協会メンバーが写っている。
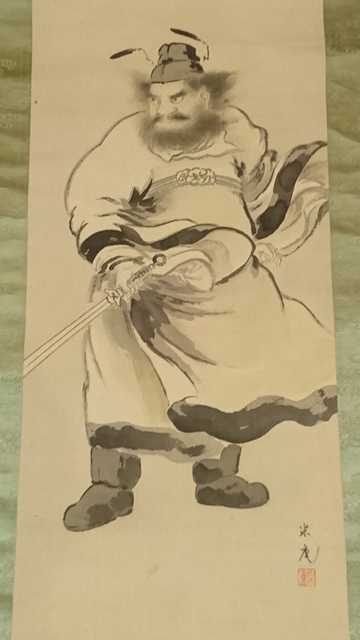
私は山口米庵のひ孫で、善丸と申します。 昨年 12月7日に父 順造が92歳で他界し、山口家のことは今私が記録を残さなければ子孫には皆目わからずじまいになりかねないと、初代、米庵について調べたところ、琉文21に沖縄時代の記録を見ることが出来ました。心より感謝申し上げます。山口家の墓は都営多磨霊園にあります。初代、米庵 瑞雨院米庵智堂居士。 以来代々が埋葬されています。 30年前に母が亡くなった時、墓には地下室が無く、お骨壷を直に埋めていましたが、すべてのお骨壷を掘りあげて一箇所に収納出来るように改修しました。その時、米庵の骨壷はすごく小さいものしか有りませんでした。 なお、家に残っている米庵の掛け軸の写真を添付いたします。

写真左から山口善丸氏、島袋和幸氏
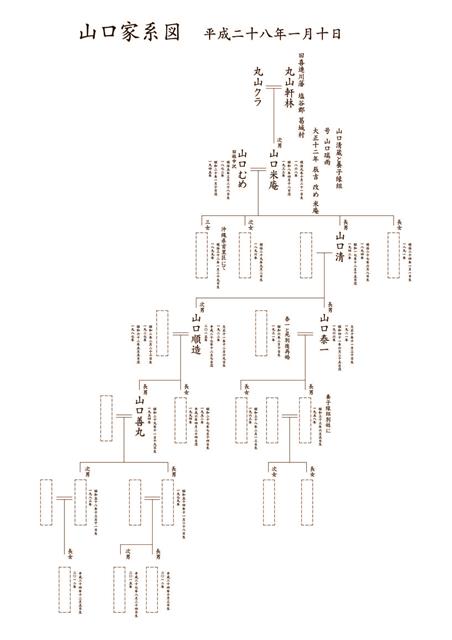

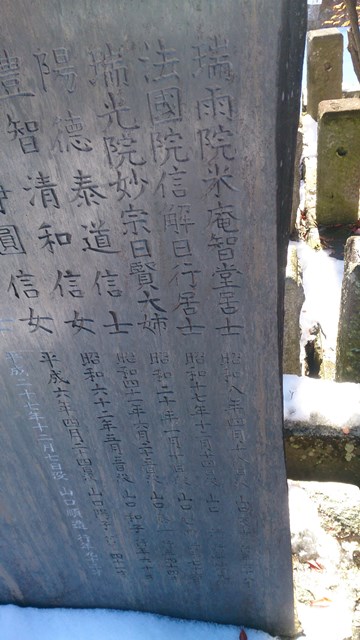
山口瑞雨次女 山口まさ(明治29年9月2日生まれ。大正9年6月21日 浅草にて海上晴①と婚姻)
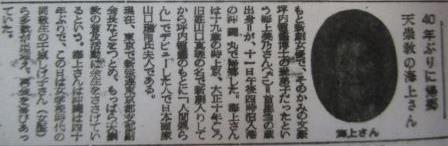
1959年10月12日『琉球新報』□40年ぶりに帰郷 天崇教の海上さんーもと新劇女優で、そのかみの文豪坪内逍遥博士の愛弟子だったという海上美乃さん(62)=首里当蔵出身=が、11日午後4時 泊入港の沖縄丸で帰郷した。海上さんは19歳の時上京、大正10年ごろ旧姓山口真瑳の名で新劇入りしてから坪内逍遥のもとに「人間親鸞」でデビューした人で日本画家山口瑞雨夫人(ママ)である。現在、東京で新宗連東京都支部副会長などをつとめ、もっぱら天崇教の普及活動に余生をささげているという。海上さんは沖縄は40年ぶりで、この日は女学校時代の同級生の千原繁子さん(女医)ら多数が出迎え、再会を喜びあっていた。→1933年5月『沖縄県立第一高等女学校同窓会』に1913年 第10回卒業生に林まさ 旧姓 山口 東京市中野/第12回卒業生に千原繁子 旧姓 渡嘉敷 那覇市上之蔵1ノ18千原医院。
①海上晴
1894年(明治27年)、東京府東京市浅草区(現在の東京都台東区浅草)に生まれる。旧制・早稲田実業学校(現在の早稲田大学系属早稲田実業学校高等部)を中途退学したが、早稲田大学の坪内逍遥に入門し、文学を学ぶ。島村抱月、沢田正二郎ら演劇人と親交を結び、新劇の世界に入る。「創生劇」を主宰、日比谷野外音楽堂で公演を行った。1920年(大正9年)、日活向島撮影所の革新運動に参加し、同撮影所第三部が製作した田中栄三監督の『朝日さす前』に主演する。以降、同部の消滅まで出演をつづけた。関東大震災以降の1925年(大正14年)、兵庫県西宮市の東亜キネマ甲陽撮影所で映画出演する。1928年(昭和3年)6月、加藤精一、佐々木積とともに帝国劇場専属俳優となる。
1936年(昭和11年)、お告げを受け、天崇教を創立する[1]。教祖としての名は「海上晴帆」である。第二次世界大戦後、1948年(昭和23年)に宗教法人登録を行う。1952年(昭和27年)、黒澤明監督の『生きる』で映画界に復帰、以降、東宝作品を中心に出演する。初期の岡本喜八監督作品の常連で、体格がよく貫禄のある役どころが多かった。→林幹 - Wikipedia
1905年4月『琉球教育』第106号「中頭郡女子研究会ー本年1月中頭郡に遊戯唱歌塗板画の講習会開会せし以来女子は遊戯唱歌に男子は塗板画に興味を起こし且つ教授上に大に必要を感じ引続き有志者の集会を企画し男子は首里山口瑞雨氏宅に女子は宜野湾間切普天間に毎月集合して研究怠らず・・・」
1910年4月6日『沖縄毎日新聞』「丹青協会批評会ー去る3日第10回の作品批評会を若狭町クラブに会するも日本画の山口瑞雨を筆頭として董園、比嘉華山、国吉沖山、義村竹斉、洋画の関屋敬治、親泊、渡嘉敷唯選、松島、山城、中村の面々・・・・」
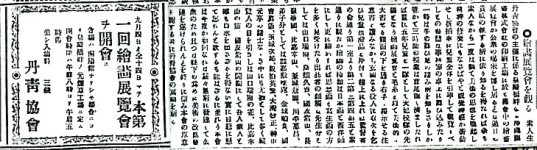
出品者 山口瑞雨(沖縄師範学校教諭心得)、岸畑久吉(沖縄県立中学校教諭心得)、國友朝次郎(首里区立工業徒弟学校助教諭 日本画ー四條派 岡田玉翠に学ぶ)、長嶺華國、比嘉華山、兼城恵園、川平恵昌、渡嘉敷唯選、金城唯貞、大湾政正、神山元享、親泊英繁、玉城次郎、国吉真義(刑務所職員)
瑞雨・山口辰吉はその名が示すごとく1868年(明治元年/戊辰)10月21日に生まれた。辰は、十二支の中で唯一「実在しない生き物」で、これは、或る種のカリスマ性の要因となると云われている。
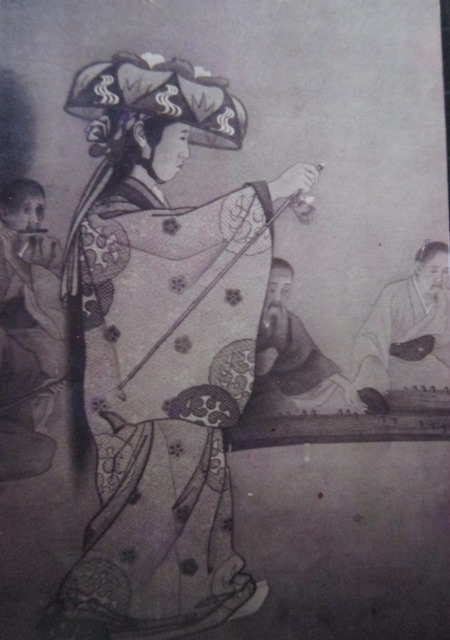

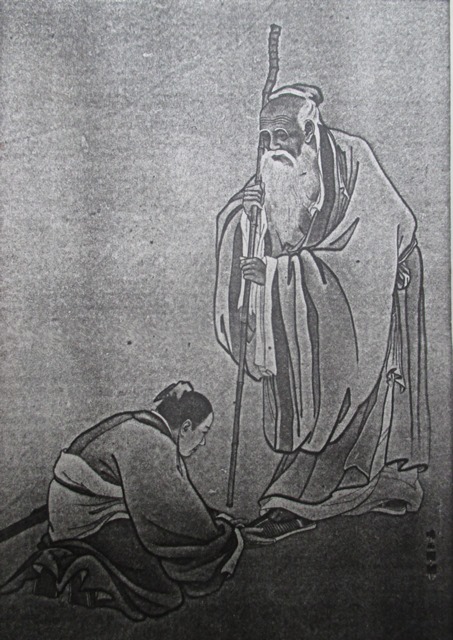
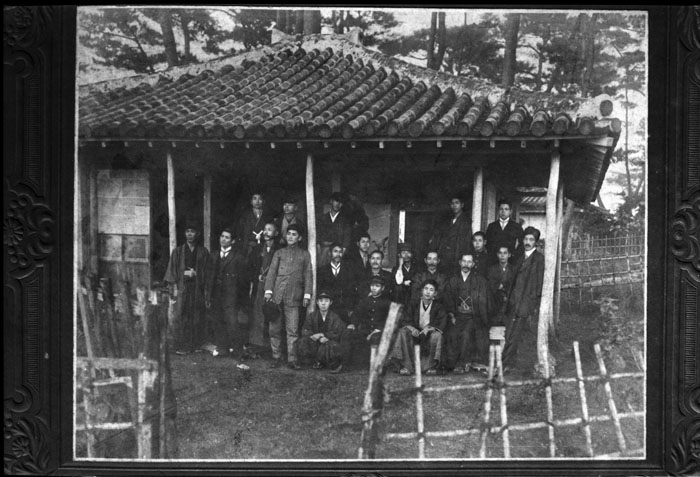
1912年2月ー太平洋画会の吉田博、石川寅治、中川八郎と丹青協会ー真ん中の柱の中列右が瑞雨。瑞雨の上が瑞雨の息子の山口清。左端が比嘉崋山、右へ一人おいて兼城昌興

1908年、沖縄最初の美術団体「丹青協会」が結成されその会長に瑞雨が就いた。11年、2年かがりの「程順則肖像図」の模写が完成。12年の1月、太平洋画会の吉田博、中川八郎、石川寅治が沖縄写生旅行のときの写真には瑞雨や丹青協会メンバーが写っている。
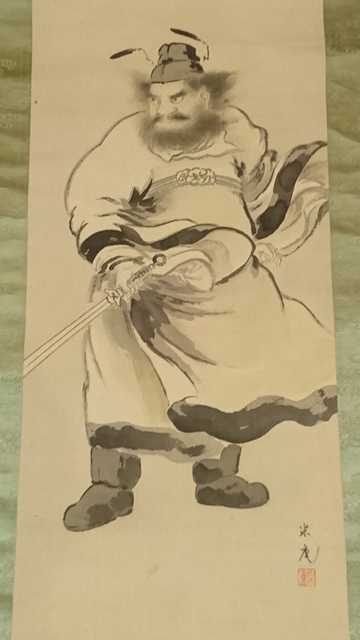
私は山口米庵のひ孫で、善丸と申します。 昨年 12月7日に父 順造が92歳で他界し、山口家のことは今私が記録を残さなければ子孫には皆目わからずじまいになりかねないと、初代、米庵について調べたところ、琉文21に沖縄時代の記録を見ることが出来ました。心より感謝申し上げます。山口家の墓は都営多磨霊園にあります。初代、米庵 瑞雨院米庵智堂居士。 以来代々が埋葬されています。 30年前に母が亡くなった時、墓には地下室が無く、お骨壷を直に埋めていましたが、すべてのお骨壷を掘りあげて一箇所に収納出来るように改修しました。その時、米庵の骨壷はすごく小さいものしか有りませんでした。 なお、家に残っている米庵の掛け軸の写真を添付いたします。

写真左から山口善丸氏、島袋和幸氏
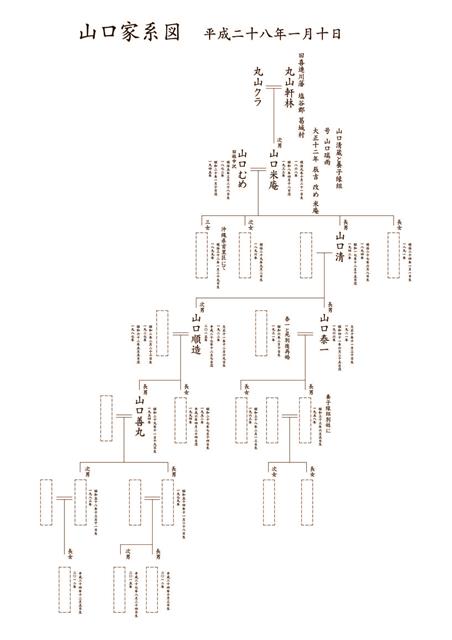

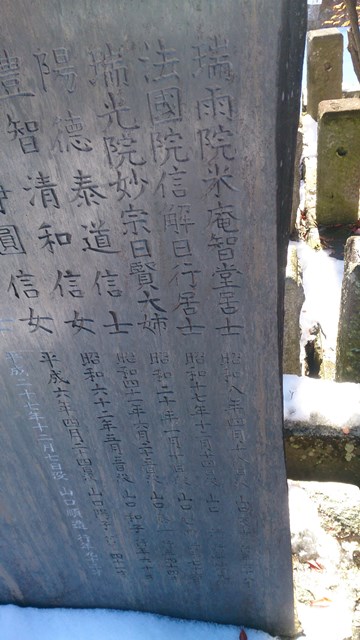
山口瑞雨次女 山口まさ(明治29年9月2日生まれ。大正9年6月21日 浅草にて海上晴①と婚姻)
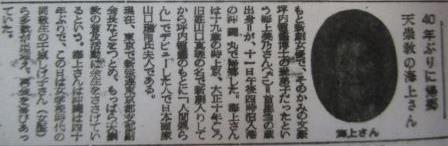
1959年10月12日『琉球新報』□40年ぶりに帰郷 天崇教の海上さんーもと新劇女優で、そのかみの文豪坪内逍遥博士の愛弟子だったという海上美乃さん(62)=首里当蔵出身=が、11日午後4時 泊入港の沖縄丸で帰郷した。海上さんは19歳の時上京、大正10年ごろ旧姓山口真瑳の名で新劇入りしてから坪内逍遥のもとに「人間親鸞」でデビューした人で日本画家山口瑞雨夫人(ママ)である。現在、東京で新宗連東京都支部副会長などをつとめ、もっぱら天崇教の普及活動に余生をささげているという。海上さんは沖縄は40年ぶりで、この日は女学校時代の同級生の千原繁子さん(女医)ら多数が出迎え、再会を喜びあっていた。→1933年5月『沖縄県立第一高等女学校同窓会』に1913年 第10回卒業生に林まさ 旧姓 山口 東京市中野/第12回卒業生に千原繁子 旧姓 渡嘉敷 那覇市上之蔵1ノ18千原医院。
①海上晴
1894年(明治27年)、東京府東京市浅草区(現在の東京都台東区浅草)に生まれる。旧制・早稲田実業学校(現在の早稲田大学系属早稲田実業学校高等部)を中途退学したが、早稲田大学の坪内逍遥に入門し、文学を学ぶ。島村抱月、沢田正二郎ら演劇人と親交を結び、新劇の世界に入る。「創生劇」を主宰、日比谷野外音楽堂で公演を行った。1920年(大正9年)、日活向島撮影所の革新運動に参加し、同撮影所第三部が製作した田中栄三監督の『朝日さす前』に主演する。以降、同部の消滅まで出演をつづけた。関東大震災以降の1925年(大正14年)、兵庫県西宮市の東亜キネマ甲陽撮影所で映画出演する。1928年(昭和3年)6月、加藤精一、佐々木積とともに帝国劇場専属俳優となる。
1936年(昭和11年)、お告げを受け、天崇教を創立する[1]。教祖としての名は「海上晴帆」である。第二次世界大戦後、1948年(昭和23年)に宗教法人登録を行う。1952年(昭和27年)、黒澤明監督の『生きる』で映画界に復帰、以降、東宝作品を中心に出演する。初期の岡本喜八監督作品の常連で、体格がよく貫禄のある役どころが多かった。→林幹 - Wikipedia
1905年4月『琉球教育』第106号「中頭郡女子研究会ー本年1月中頭郡に遊戯唱歌塗板画の講習会開会せし以来女子は遊戯唱歌に男子は塗板画に興味を起こし且つ教授上に大に必要を感じ引続き有志者の集会を企画し男子は首里山口瑞雨氏宅に女子は宜野湾間切普天間に毎月集合して研究怠らず・・・」
1910年4月6日『沖縄毎日新聞』「丹青協会批評会ー去る3日第10回の作品批評会を若狭町クラブに会するも日本画の山口瑞雨を筆頭として董園、比嘉華山、国吉沖山、義村竹斉、洋画の関屋敬治、親泊、渡嘉敷唯選、松島、山城、中村の面々・・・・」

御茶ノ水駅



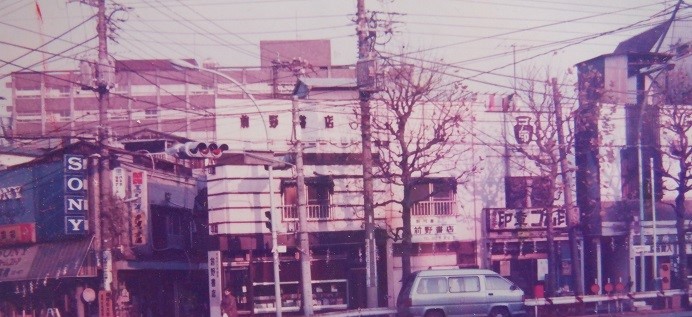
早稲田の古書街
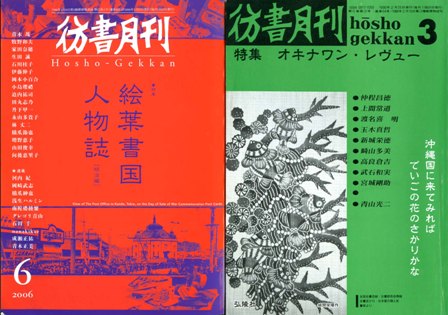
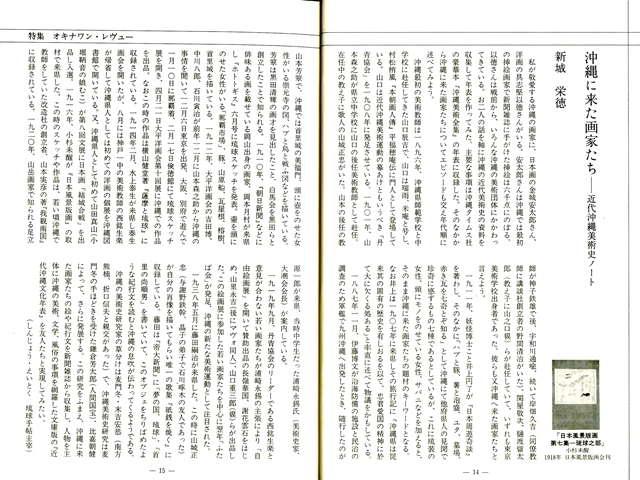
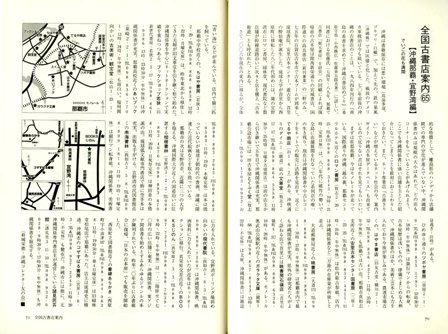
1990年2月『彷書月刊』54号□新城栄徳「沖縄に来た画家たちー(略)沖縄の美術史研究家の草分けは麦門冬・末吉安恭(南方熊楠、折口信夫と親交があった)で、沖縄美術史研究は麦門冬の手ほどきを受けた鎌倉芳太郎(人間国宝)、比嘉朝健によって、さらに発展する。この研究をふまえ、沖縄に来た画家たちの絵や紀行文を新聞雑誌から収集し、人物を主体に沖縄の美術、文学、風俗の事項を網羅した文庫版の『近代沖縄文化年表』を友人たちと実現してみたい。」/この文化年表は下記のように『琉文手帖』4号として1999年5月に発行した。「文人・末吉麦門冬」を補足するものである。/2006年5月『彷書月刊』248号□新城栄徳「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾編」
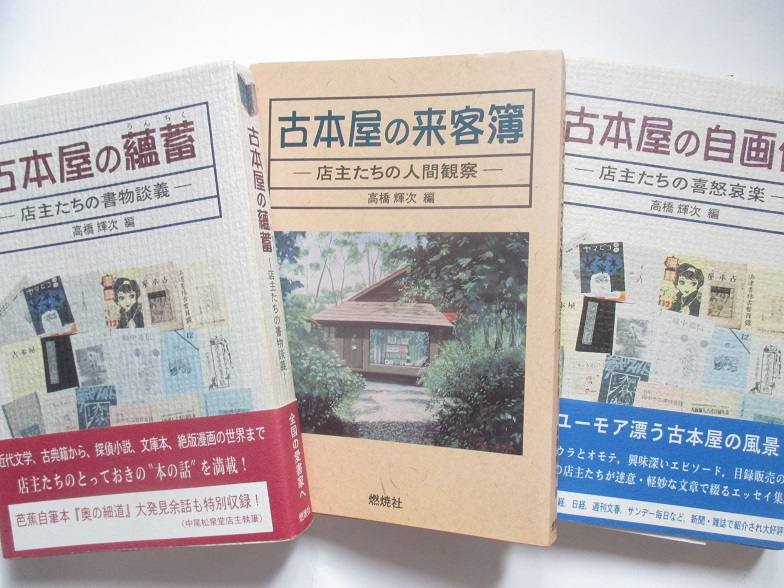
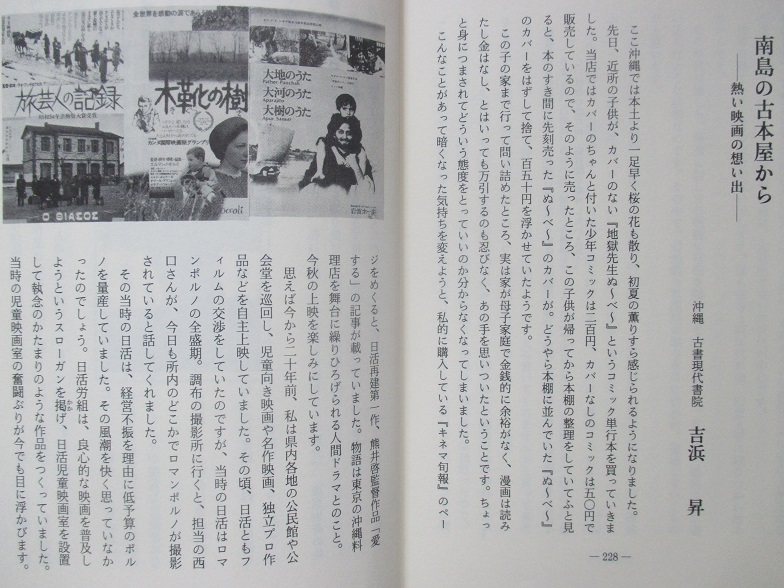
1997年10月 高橋輝次『古本屋の来客簿』燃焼社/吉浜昇「南島の古本屋からー熱い映画の想い出ー」
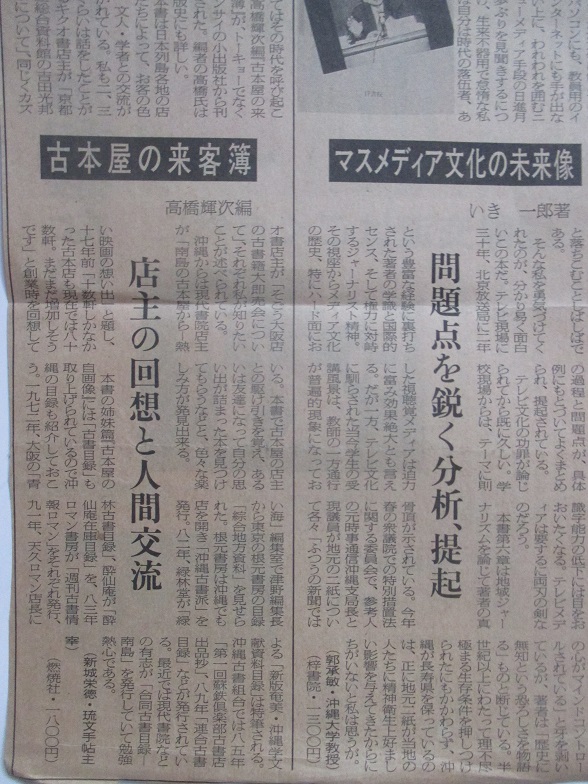
1997年10月26日 『琉球新報』新城栄徳「書評/古本屋の来客簿」/郭承敏「書評/マスメディア文化の未来像」
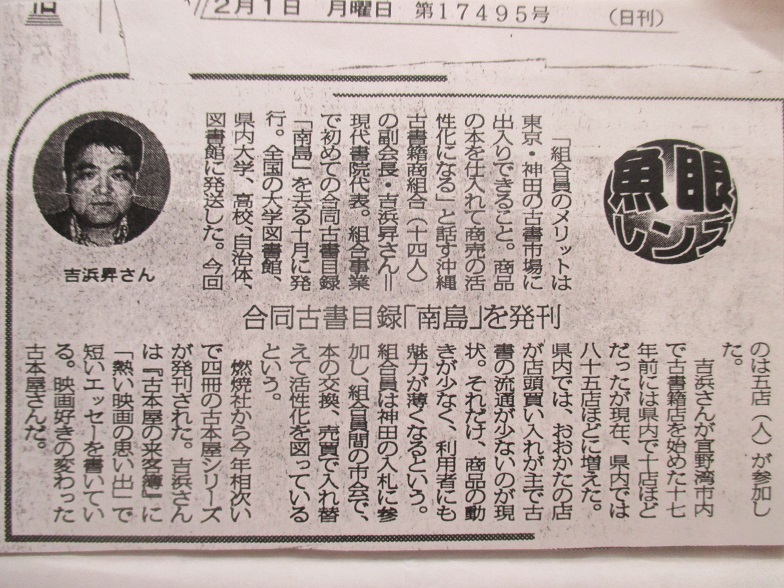
『彷書月刊』(ほうしょげっかん)は、1985年9月に創刊された日本の月刊誌。株式会社彷徨舎から刊行。のち弘隆社より刊行。古書と古書店をテーマにした情報誌で、毎号異なる特集記事、本に関する連載、古書即売会の情報のほか、巻末には数十ページの古書店目録(古書店が売り物を公表するカタログ)が掲載されている。編集長は田村治芳(田村七痴庵)。2010年10月号(300号)をもって休刊した。→ウィキ
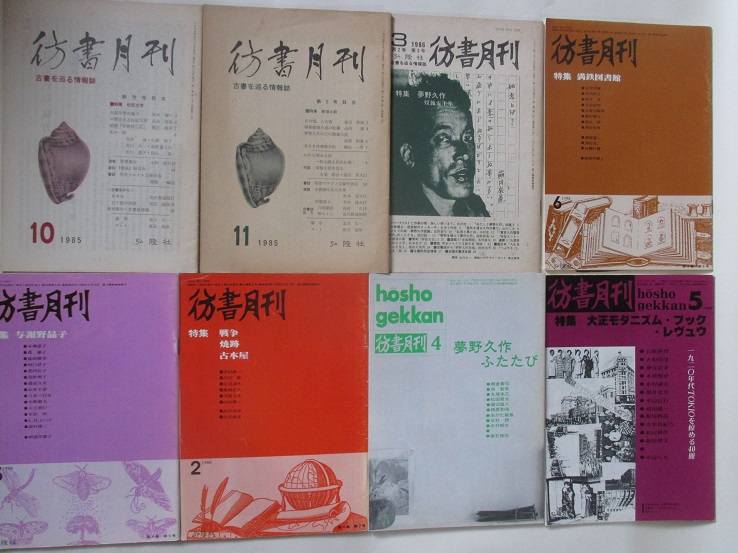
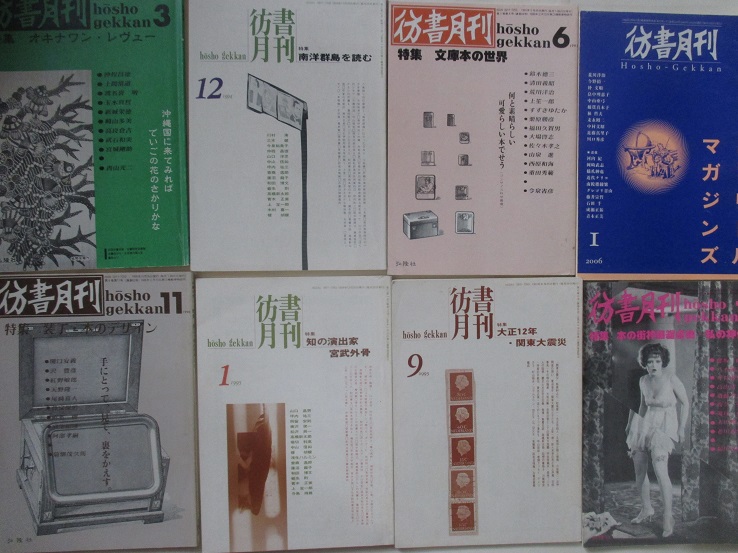
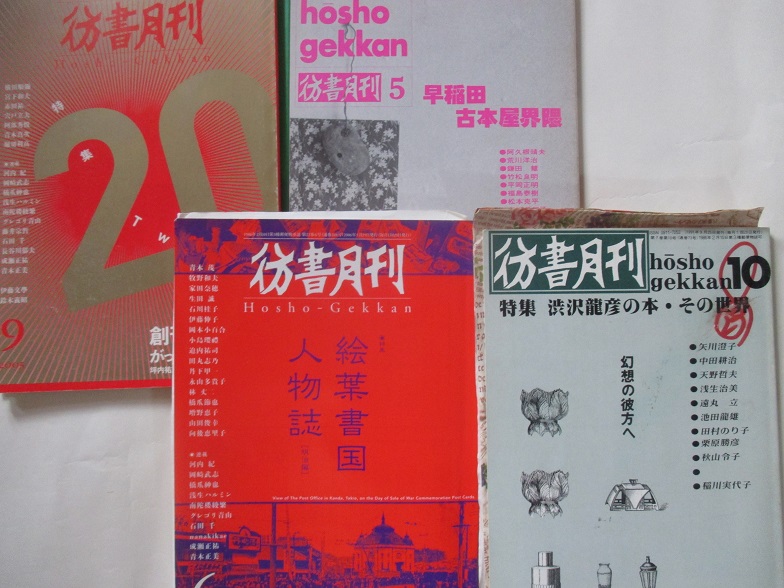
田村治芳、元日に逝く
2011年の元日に、田村治芳が死んだ。享年60。食道がんだった。2日の朝、星谷章くんが電話で知らせてくれた。→源泉館備忘録2011年01月06日
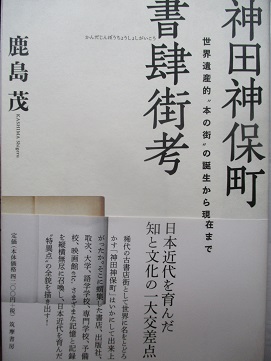
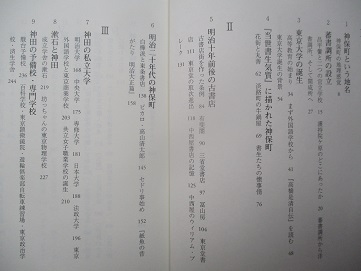
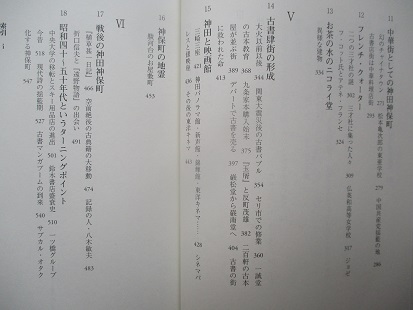
2017年2月 鹿島茂『神田神保町書肆街考-世界遺産的”本の街〟の誕生から現在まで』筑摩書房〇目次ーⅠ・神保町という地名/蕃所調所の設立/東京大学の誕生/『当世書生気質』に描かれた神保町/Ⅱ・明治十年前後の古書店/明治二十年代の神保町/Ⅲ・神田の私立大学/漱石と神田/神田の予備校・専門学校/Ⅳ・神田神保町というトポス/中華街としての神田神保町/フレンチ・クォーター/お茶の水のニコライ堂/Ⅴ・古書肆街の形成/神田と映画館/神保町の地霊/Ⅵ・戦後の神田神保町/昭和四十~五十年代というターニングポイント
◇「学者が去って、オタクがやってきた」私が田村書店洋書部の奥平禎男氏と2001年に月刊誌「東京人」で対談したときの見出しにはたしかにこう書かれていたはずだ。これは果たして、神田神保町の未来を開くことになるのかそれとも閉じることになるのか(略)政府がクール・ジャパンの輸出などと浮かれたことを言っているあいだに、オタクの牙城である神田神保町が崩壊しないとは限らない。杞憂に終わることを祈るのみである。
◇クールジャパンとは、日本の内閣府「クールジャパン戦略のねらい」によると「外国人がクールととらえる日本の魅力」であり、クールジャパンの情報発信・海外展開・インバウンド振興によって世界の成長を取り込み日本の経済成長を実現するブランド戦略「クールジャパン戦略」政策で使われている用語である。 →ウィキペディア
◇青木 正美(あおき まさみ、男性、1933年4月22日 - )は、古書店主、日本近代文学研究者。 東京生まれ。1950年(昭和25年)東京都立上野高等学校定時制課程中退。半年ほど玩具工場に勤務したのち、1953年(昭和28年)東京都葛飾区堀切に古本屋・青木書店 (開業当時の名称は一間堂)を開業する(2008年現在の店主は、青木正一)。 古書店業のかたわら、文筆活動にも精力的に取り組む。神保町の業者中心の「明治古典会」の会員となり、のち会長をつとめた。→ ウィキペディア
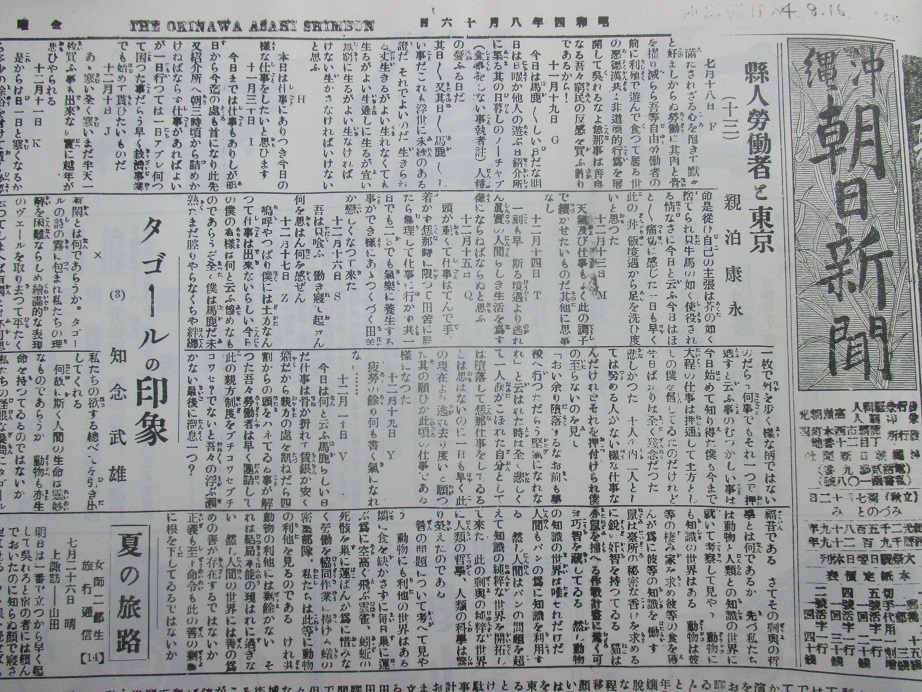
1929年8月16日『沖縄朝日新聞』知念武雄「タゴールの印象」
1936年11月『沖縄教育』243号 源武雄「記紀の神名、思金及麻良に就て」
〇はしがきー此の一篇の論旨から述べてみたい。南島の命名の民俗及び人名の原義を研究する為めに私は各地方各島々の人名、童名を出来るだけ採集した。それを採集しているうちに古事記及日本書紀、萬葉集、風土記を始め我国の古典に出て来る神名や人名の「名の本義」を独自の立場から研究してみることにした。その結果はどうであるか。先づ私を最も驚かしたことは吾々南島人の珍妙な童名は嘗て吾が日本民族が広く愛用したもので決して琉球人独特の珍名ではないことを看破したことである。何れこれに就ては稿を改めて報告したい。次に名の本義を研究していると、之迄発表されている古典研究者国文学者などの説に疑問を持つに至ったのである。そうして、之はどうしても吾々民俗学を研究しているものの仕遂げねばならぬ研究だと思い、ここに民俗学徒の立場から記紀の神名人名を考察することにした。先づその手始めに記紀の天岩戸の所に出て来る思金神及天津麻羅の名の本義を明らかにし世上流布されている古典研究者国文研究者の見解に再吟味を煩わしたいと思う。
(略)
以上記紀の神名、思金神及天津麻羅の名の本義に就て在来の学者の説を批判し検討した結果その誤なるを指摘し、南島民俗の資料を以て之が再吟味をなし、自己の新しき説を提示したのであるが、振り返って何故に之迄の国文研究者が之等神名の本義をつかむことが出来なかったかに就てよく考えてみる必要がある。私は在来の学者が記紀の物語を批判する心構えが不足している結果ではないかと思う。即ち記紀にある民俗をもっとも古いものとして、それ以前の考察を怠っている結果ではないか。記紀が決して古いものでない証拠には神名に沢山の民間語源説がつきまとうて、それで物語を構成している民間語源説話の出来る時代には既にそのものの原義が不明になっていた時代になっていたことを意味している。記紀の物語はそんな時代に生まれたものであって、決して原始的な本然の姿を吾々には伝えていない。故にこれら神名の原義を突き止めるには先づ記紀の物語に脚色を打破し、民間語源説話を全然離れて独自の自由な立場からその真相をつかむようにすべきであろう。
1942年5月『沖縄教育』309号 源武雄〇棺を蓋ふてその人を知るー(略)いつ会っても盛沢山の計画を胸中に描いて居られたことである。その計画を聞くことだけでも愉快であった。部落調査の話をよく聞かされたが、実はあの仕事は大変なものであった。私も二三ぺん実地指導らしいものを受けたがいや実に骨の折れる、そのうえ頭を使う仕事であった。之を一二箇所の部落でなしに全県下に及ぼそうといふ遠大な計画で実は命が一つ二つでは足りないと心配していた。しかし、之が出来上がれば沖縄の癌であるユタ、三世相は徹底的に沈黙させることが出来るのだといふのが、源一郎さんの悲壮な決意であった。ユタ、三世相を根本的に駆逐するには部落調査によって各氏族の系図を正さねばならぬ。といふのがその意図する所であった。部落調査をやっているうちに、沖縄歴史の記録に対しても意見があったらしく新しい沖縄歴史を書いてみたいと洩らしてゐられた。鬱勃たる念が胸中を去来していたのであった。こんな忍耐を要する、しかも金にならぬ仕事は源一郎さんの外にはちょっと手が出ない(以下略)

1958年3月 東恩納寛惇『沖縄今昔』南方同胞援護会「著者近影ー自宅にて郷土史研究家・源武雄君と」(外間正幸君撮影)
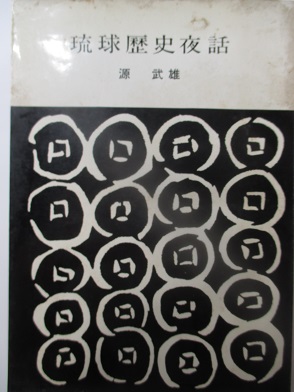
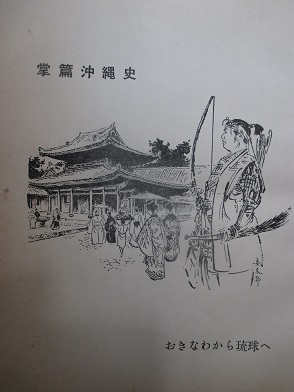
1965年2月 源武雄『琉球歴史夜話』月刊沖縄社□上の挿絵は金城安太郎/末吉安久(麦門冬弟)「表紙画」
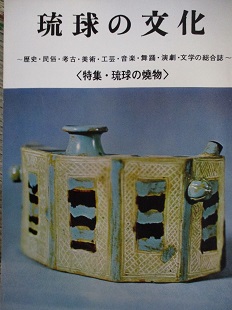
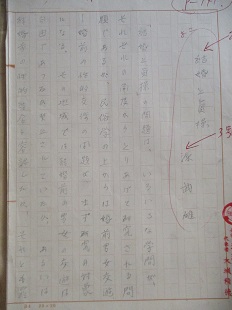

1972年3月 『琉球の文化』創刊号 源武雄「結婚と貞操」
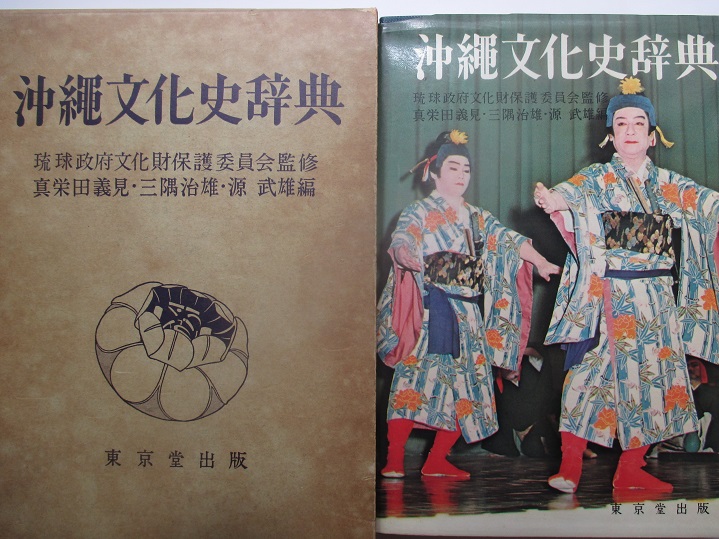
1972年3月 真栄田義見・三隅治雄・源武雄 編『沖縄文化史辞典』東京堂出版
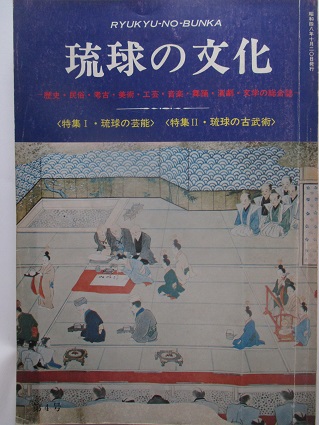

1973年10月 『琉球の文化』第四号 源武雄「朝薫の人及び芸術についての覚書」

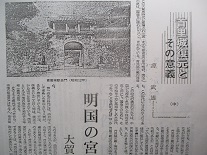

1981年3月3日~5日『琉球新報』源武雄「首里城復元とその意義」
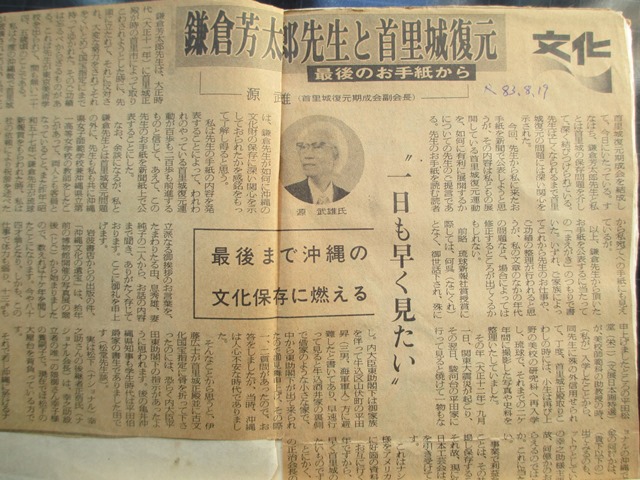
1983-8-19『琉球新報』源武雄「鎌倉芳太郎先生と首里城復元」
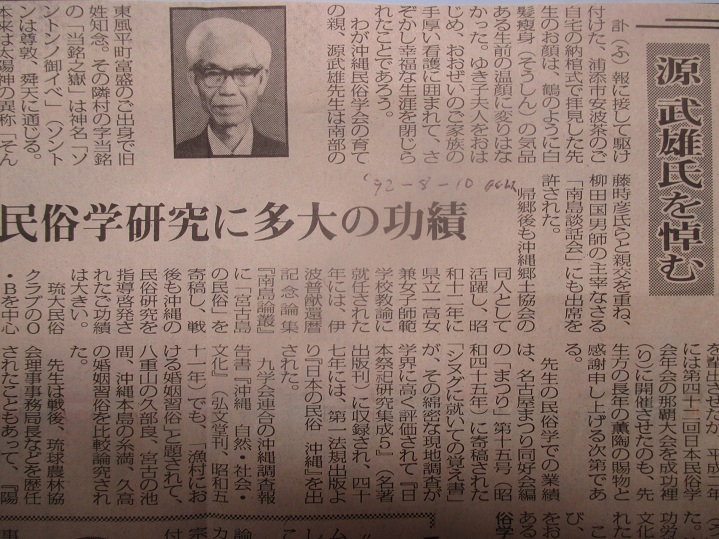
1992年8月10日 『沖縄タイムス』湧上元雄「源武雄氏を悼む」
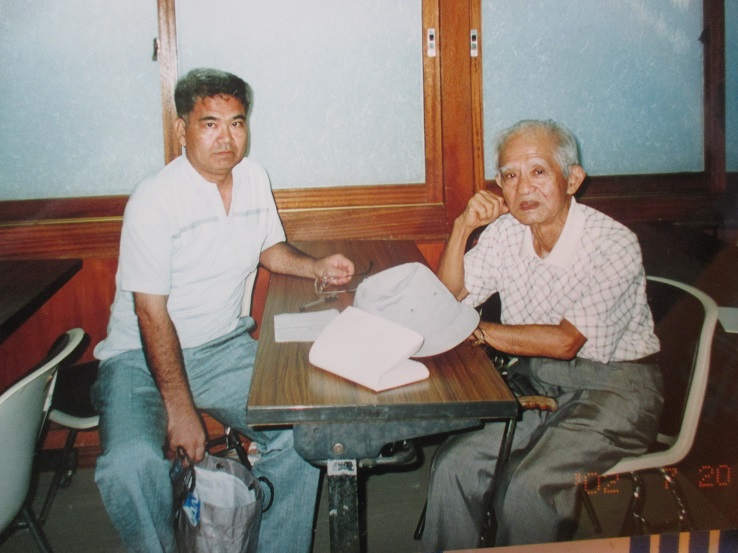
沖縄県立芸術大学でー湧上元雄氏(右)
1932年 東恩納寛惇、年末までに首里侯爵邸に通い2000冊の文献を読破
1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。
1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」
1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。
1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>
1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学
1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く
1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足
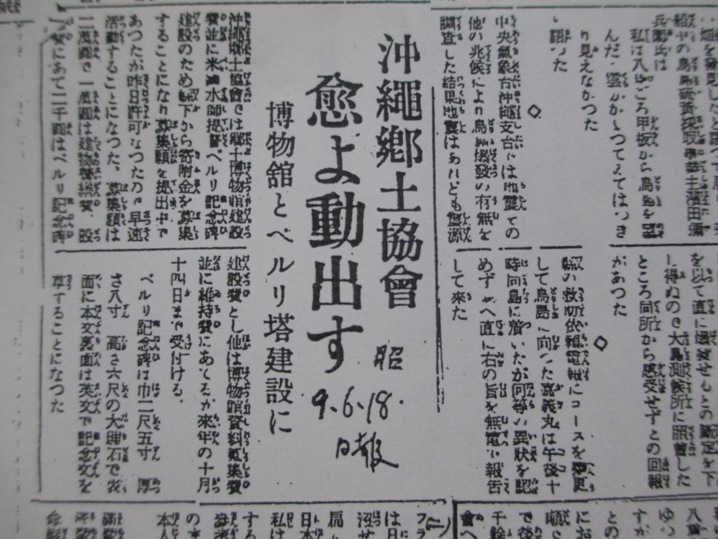
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社
1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式
1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。
□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社
1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)
1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観
1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観
1935年10月 『沖縄教育』第230号
□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部
安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、
1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観
1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」
1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会
1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ
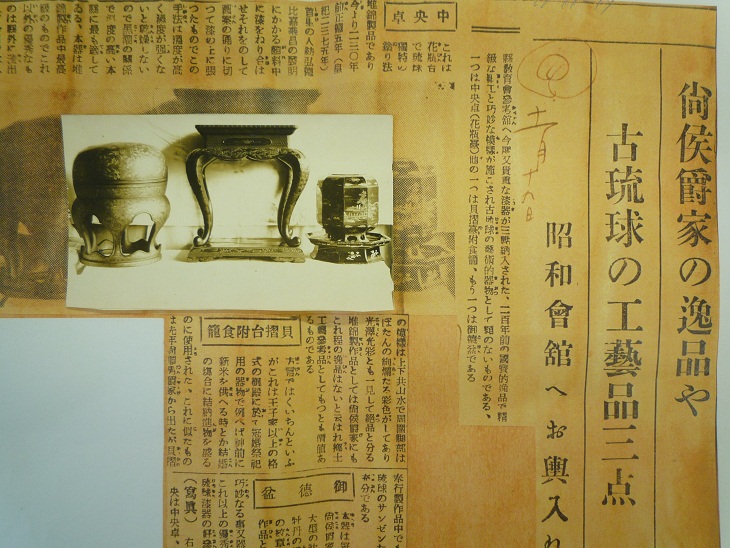
11月19日
1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」
1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観
1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。
1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」
1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。
1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)
1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事
4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)
1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館
1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁
1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。
公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。
又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。
1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」
1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転
1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」
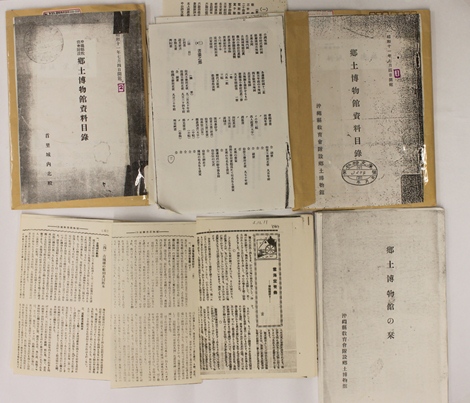
1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」
沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台
□図表之部
喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図
1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房
1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。
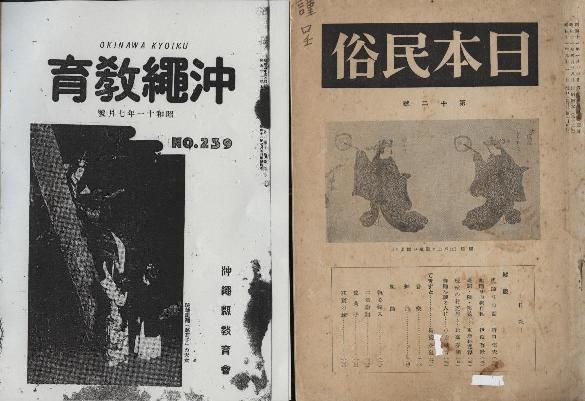
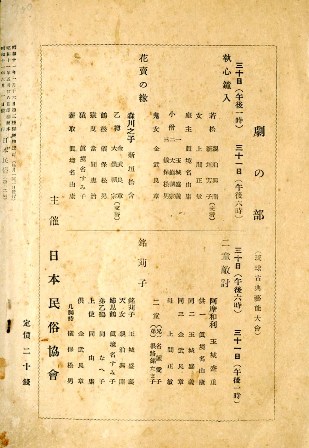
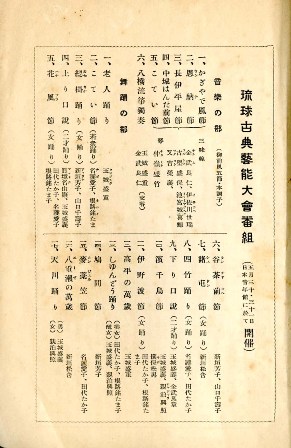
1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔
1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平
1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」
1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆
1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶
1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」
1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通
1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館
1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」
1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。
1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」
□
1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師
1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式
1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」
1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席
1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列
1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」
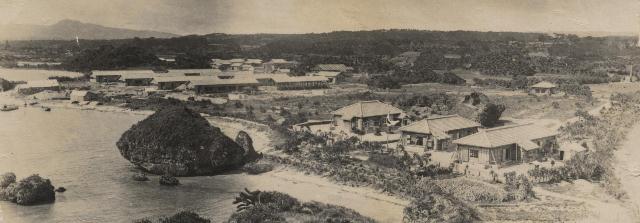
1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」
1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」
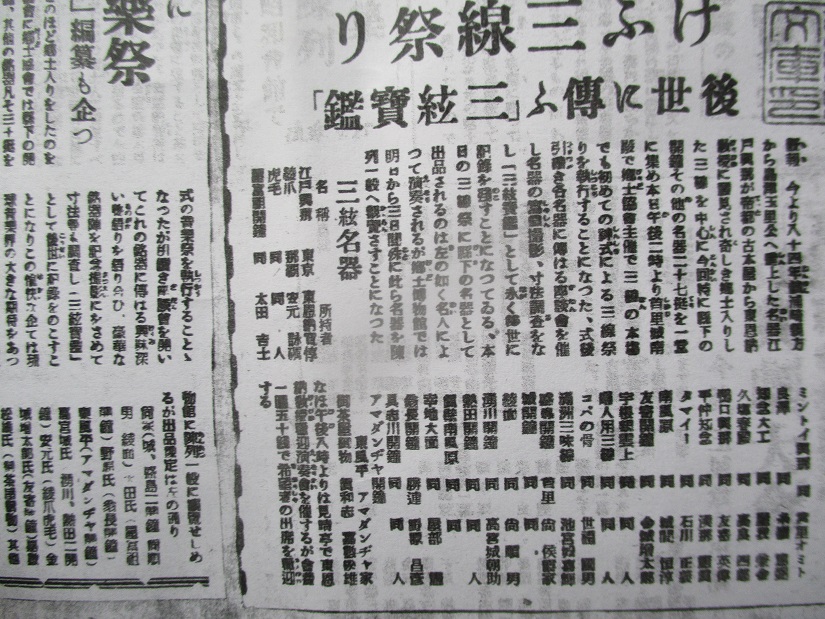
1939年8月5日
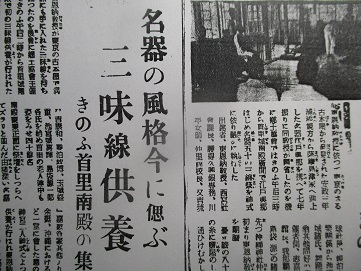
1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」
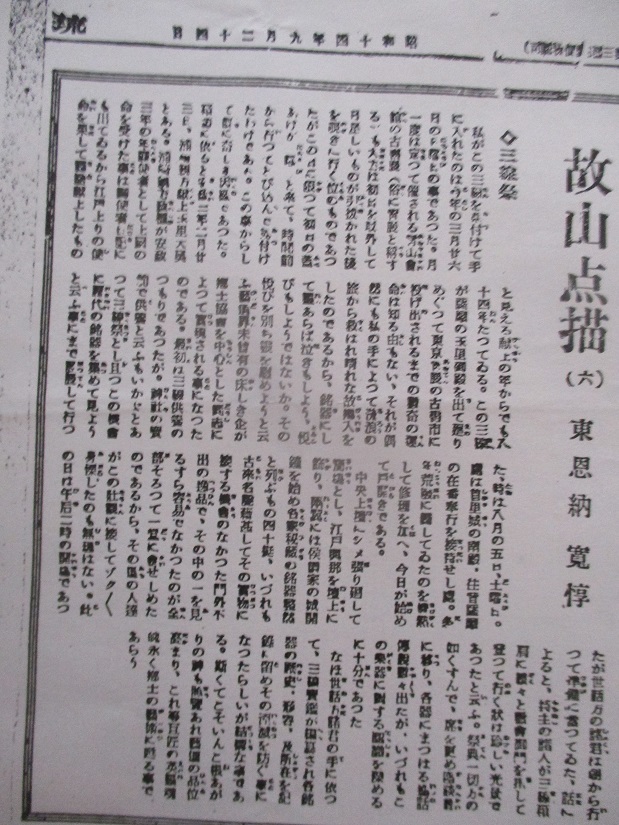
1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」
〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。
1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。
1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」
1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。
1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>
1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学
1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く
1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足
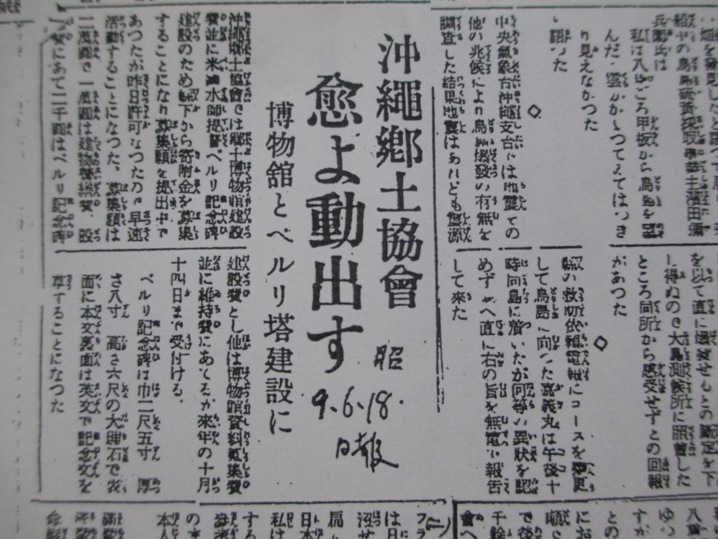
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社
1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式
1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。
□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社
1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)
1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観
1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観
1935年10月 『沖縄教育』第230号
□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部
安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、
1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観
1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」
1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会
1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ
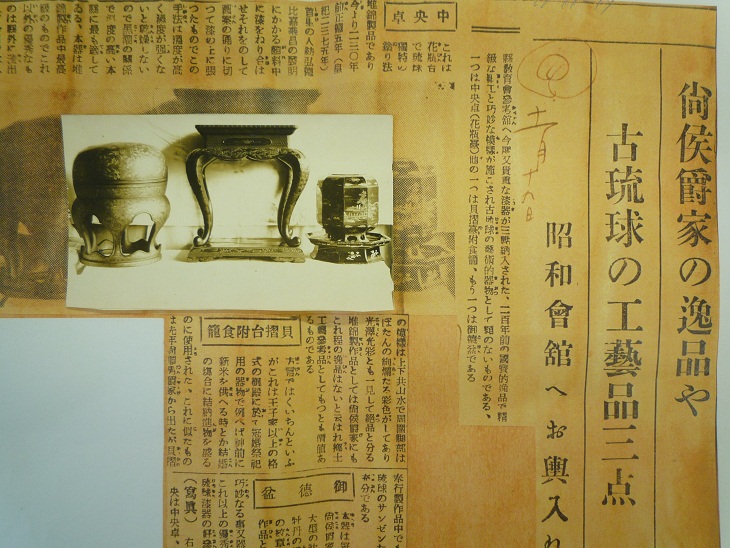
11月19日
1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」
1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観
1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。
1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」
1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。
1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)
1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事
4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)
1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館
1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁
1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。
公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。
又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。
1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」
1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転
1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」
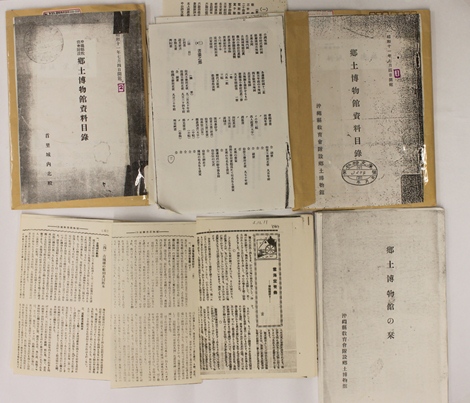
1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」
沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台
□図表之部
喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図
1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房
1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。
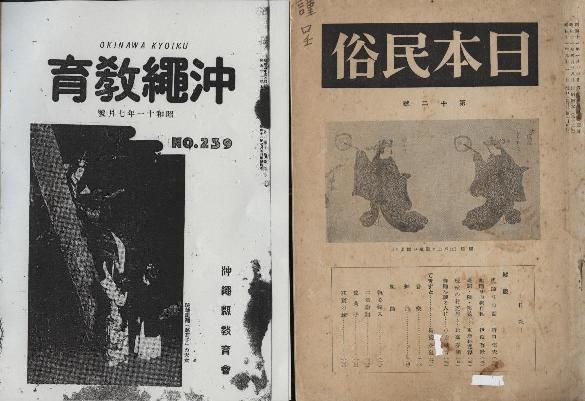
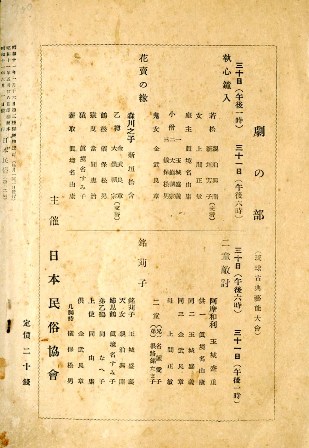
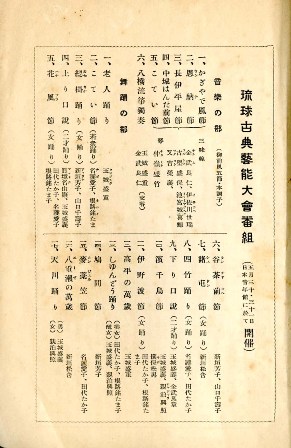
1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔
1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平
1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」
1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆
1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶
1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」
1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通
1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館
1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」
1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。
1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」
□

1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師
1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式
1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」
1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席
1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列
1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」
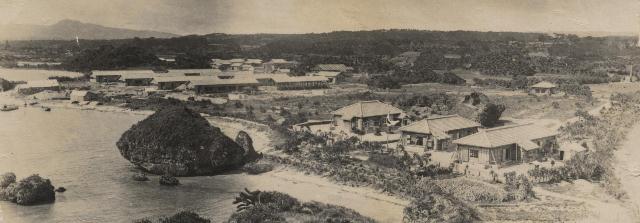
1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」
1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」
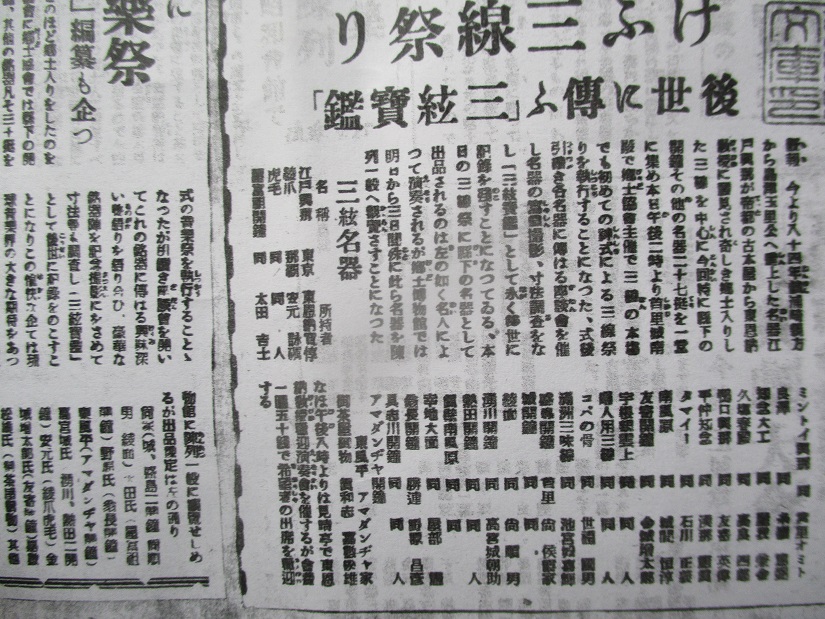
1939年8月5日
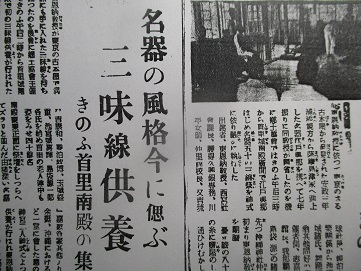
1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」
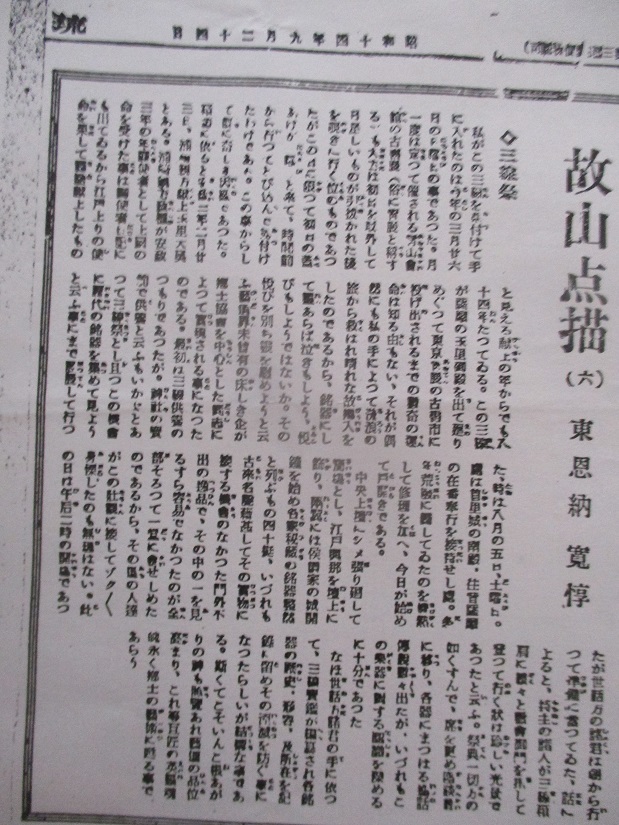
1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」
〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。
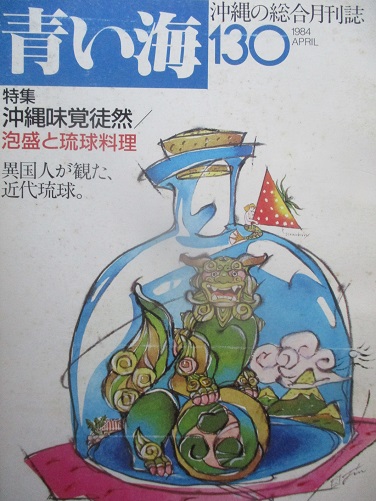
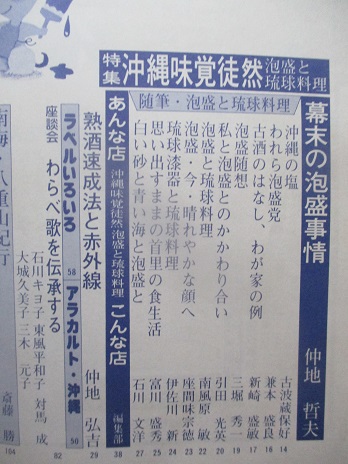
1984年3月 雑誌『青い海』130号「特集・沖縄味覚徒然/」泡盛と琉球料理
1980年9月ー藤井つゆ『シマ ヌ ジュウリ』道の島社1981年
1月ー日本調理師協会『協調』「沖縄に招かれて」(写真)
12月ー日本調理師協会『協調』「沖縄県支部第4回・秋の料理大講習会」(写真)
1982年
1月ー日本調理師協会『協調』「沖縄県支部料理講習会」(写真)
2月ー日本調理師協会『協調』「琉球料理献立」(写真)
沖縄県調理師協会(安里幸一郎会長)『沖調会報』創刊号
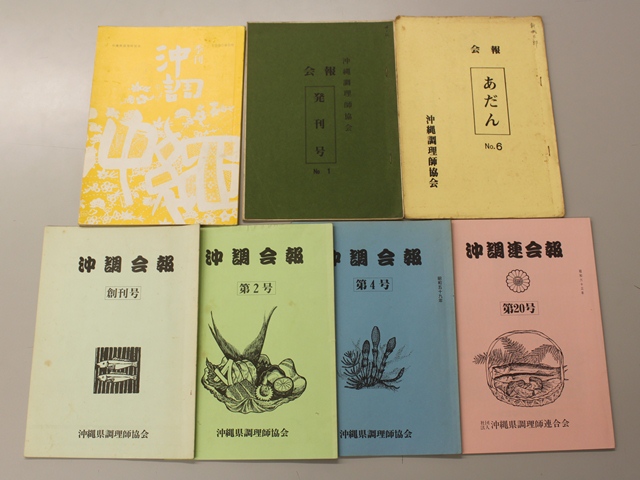
1983年9月 『沖縄ハーバービューホテル 10年のあゆみ』琉球総合開発
1983年 日本調理師協会誌『協調』「写真ー沖縄秋の料理大講習会」
1984年
1月ー沖縄の雑誌『青い海』120号<沖縄そばと生活文化史>
9月ー沖縄ハーバービューホテル調理部『沖縄の素材を生かす西洋料理』新星図書出版
1985年
1月ー沖縄調理師協会『沖調会報』第7号□略歴・中村喜代治、玉寄博昭、山川敏光、福永平四郎
1月ー日中調沖縄県支部『交友誌』
4月ー安里幸一郎『沖縄の海産物料理』新星図書出版
6月ー石川調理師会『石調だより』第2号
7月ー『月刊専門料理』<創刊20周年記念号>柴田書店
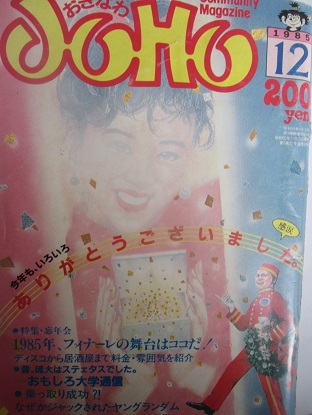

1985年11月『おきなわJOHO』「中ノ橋食堂」

昭和60年度「現代の名工・調理師部門」左から村上信夫氏、土井廣次氏、安里幸一郎氏
1987年3月 日本調理師協会誌『協調』「写真ー昭和62年度 沖縄県調理師連合会新年の集い」/辻元亮裕「沖縄調理師会新春総会」
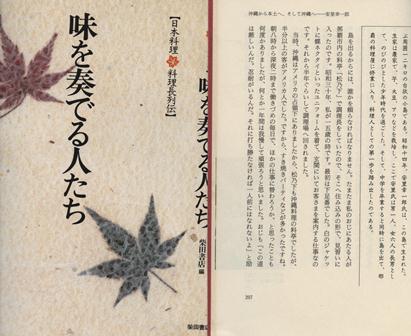
1988年4月ー柴田書店書籍部『味を奏でる人たち』「安里幸一郎(魚安)ー沖縄から本土へ、そして沖縄へ」
1988年4月 喜屋武マサ『沖縄豆腐料理80選』那覇出版社
1988年4月 『聞き書 沖縄の食事』農文協
1988年9月 『塩浜康盛追想集』(ホテル球陽館館主、沖縄ペルー協会初代会長)
1989年6月27日『琉球新報』「コンベンションセンターで第27回全飲連全国沖縄県大会ー21世紀の食文化は沖縄から」
1990年5月 『東急ホテルの歩み』東急ホテルチェーン
1991年8月ー(社)日本全職業調理士協会『料理四季報』<沖縄特集・沖縄 夏の料理>表紙□安里幸一郎「調理一言ー郷土料理は、『土産土法』という料理の原点である。郷土の素材を開発し、料理人として満足のいく献立を作っていくことが、調理師の使命であろう。さらに召し上がる人のことを念頭におき思いやりという心の薬味を添えたいと思って、常に庖丁を握っている。」
1993年1月ー『FUKUOKA STYE ⅤoⅠ.6』「特集・屋台ー食文化と都市の装置」
1993年11月27日『沖縄タイムス』「土曜グラフィックス こんにちは外国のおコメ」
1994年5月18日『琉球新報』「ビジュアル版 コメ戦争ー崩壊寸前の食管制度」
1997年 『サライ』大8号「中華街ーチャイナタウン三都物語」
2000年11月 リゾート時代の波受け「那覇東急ホテル」閉館
2002年3月3日『沖縄タイムス』新城栄徳 書評/中田謹介『笹森儀助「南島探検」百年後を歩く』編集工房風
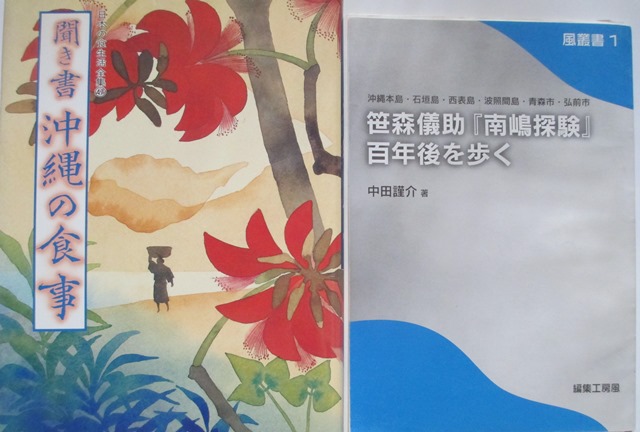
沖縄にかかわりのある東京の編集者といえば、岩波書店を辞めて『酒文化研究』を創刊した田村義也氏などが浮かぶが、本書の著者・中田謹介氏も農文協(社団法人農山漁村文化協会)に36年間勤め『日本農書全集』(第34巻は沖縄編)や、『日本の食生活全集』(第48巻は沖縄の食事は沖縄タイムス出版文化賞を受賞)などの企画・編集に携わった。そして沖縄近世文書探索の先に明治の3大探検家の一人といわれた笹森儀助に出会い、その著『南島探検』が描いた沖縄と中田氏が見た沖縄によって本書が生まれた。
本書はまず笹森のいう女の元服「入墨」(針突)にふれ「いま沖縄で入墨をした女性を見るのは困難である」とし、知人たちのそれぞれのおばあさんの思い出を記し、友人を介して手に入墨をした老人ホームのおばあさんに面談する。次に風土病(マラリア)について「八重山の歴史は、マラリアとの闘いの歴史といっても過言ではない」と戦争マラリアにもふれ、昨今の「癒しのシマ」とか言われ観光ボケした”沖縄土人”が忘れがちなことを思い出させる。
「首里城の語る百年」の項では、前出の編集にかかわった尚弘子、新島正子、仲地哲夫の諸氏に首里城復元についての感想を聞いている。そしてドイツ人の著した『大正時代の沖縄』を引用し「たまたま偶然に居合わせた一人の建築家(伊東忠太)の干渉によってー」、首里城はからくも消滅を免れたとある。が、たまたまではなく、鎌倉芳太郎が沖縄からの新聞を見て伊東に首里城正殿の取り壊しを報告。そして伊東が内務省から取り壊し中止の電報を出し、尚侯爵家で神山政良、東恩納寛惇らと協議を成し沖縄調査に赴いたものである。
本書は編集者が、どのように本を作っていたのか、どう沖縄に向かい合っていたのか分かり資料的にも価値がある。終わりに中田氏の川柳「ヘリポート生むは騒音サンゴの死/普天間の移設皇居が最適地」を紹介する。中田氏を、こころ優しき無頼派と見た。
2004年10月19日『琉球新報』「ビジュアル版 キノコの世界」
2008年10月29日『琉球新報』「ビジュアル版 世界の肥満事情」
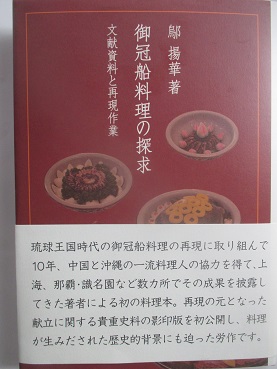
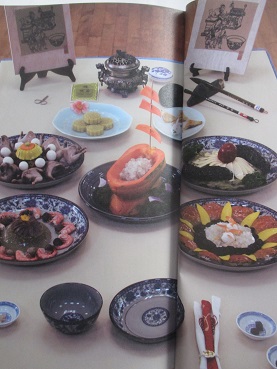
2017年11月 鄔揚華(ウ・ヤンファ)『御冠船料理の探究 文献資料と再現作業』 出版舎Muɡen

左から、新城栄徳、鄔揚華さん、天願恭子さん
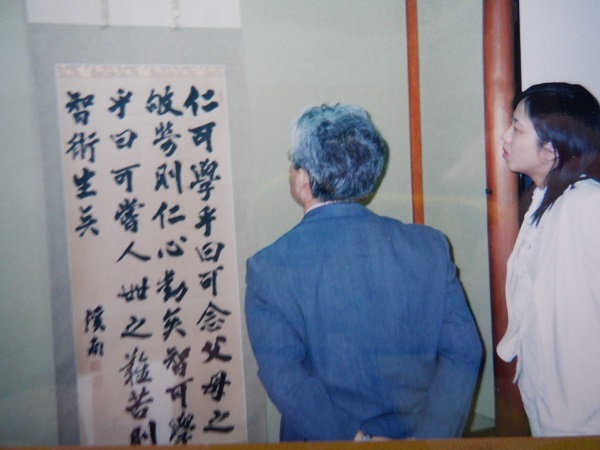
湖城渓南の書を観る鄔揚華さん、屋部夢覚氏
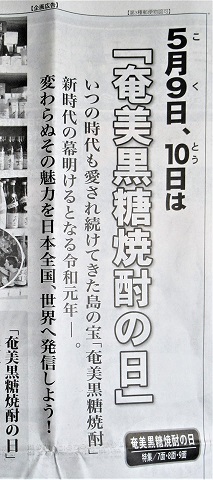

青山恵昭 2019-5-10 〇今日の〝黒糖酒記念日〟は笠利出身の友人からいただいた「里の曙」を、スクトーフをつまみにして嗜むことにしよう!そして、父の生マリジマ・ゆんぬの「島有泉」で仕上げよう。人口11万余の島々に蔵元が18もあるってスゴイ!
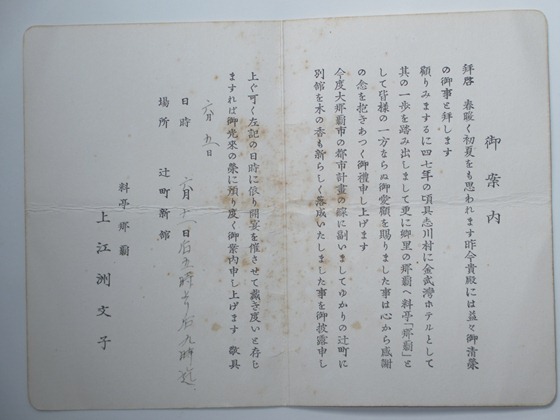
料亭那覇
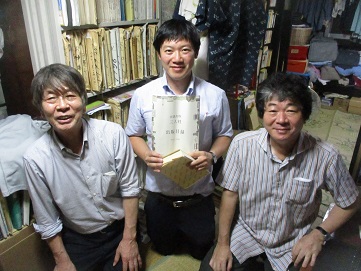
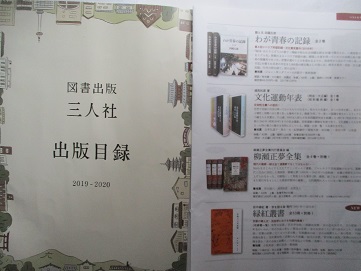
(株)三人社 〒606-8351 京都府京都市左京区岡崎徳成町29-3 岡崎ミントビル■本社代表電話番号/ファクス番号075-761-0368/0369(※変更ございません)
6月22日、福岡の松下博文氏(右/筑紫女学園大学文学部教授)が京都・三人社の越水治氏(左)、山本捷馬氏(中)と来宅された。
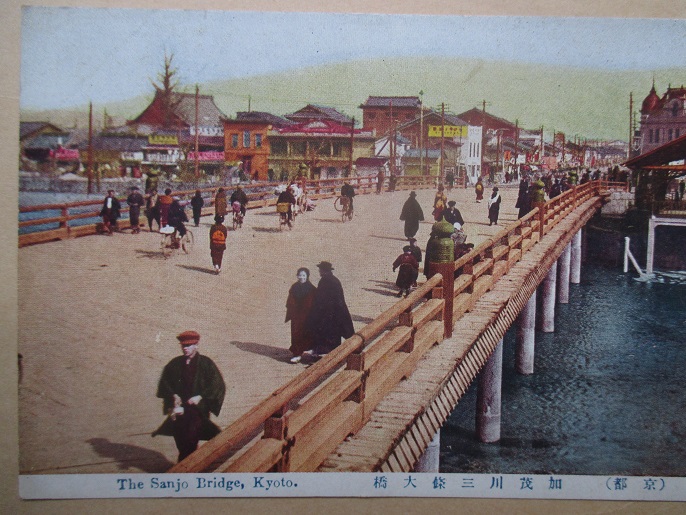
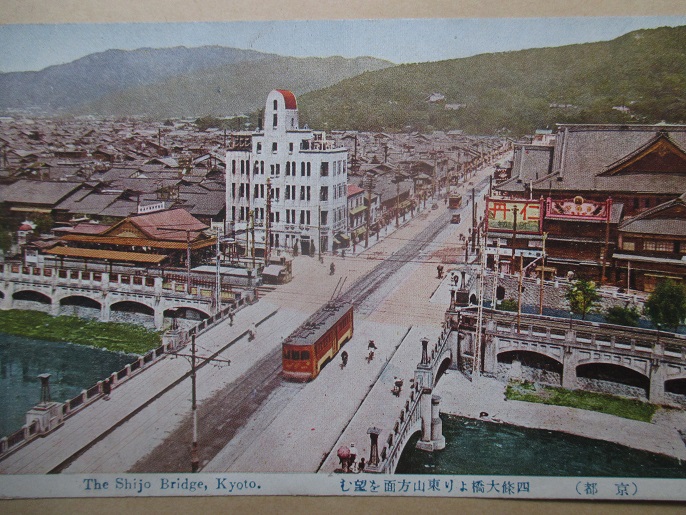
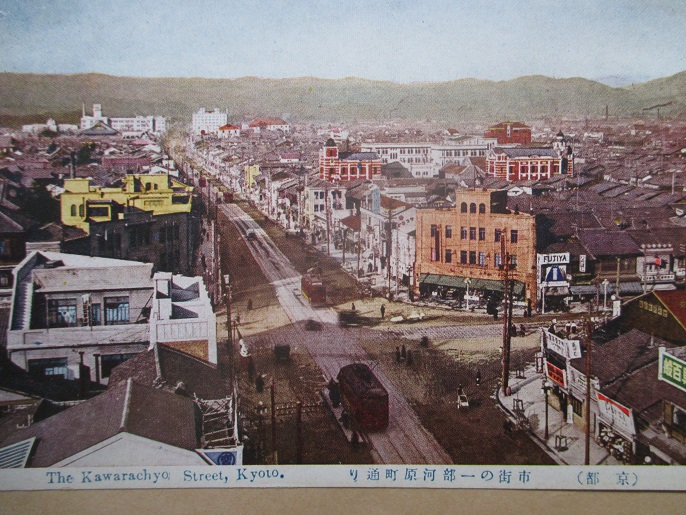
京都絵葉書ー戦前
私は1969年2月、京都駅近鉄名店街の京風料理の店で働いていた。河原町の京都書院①、駸々堂②はよく行った。1972年、京都書院に『琉球の文化』を置いてもらうとき染織と生活社(田中直一代表取締役)を訪ね編集長の富山弘基氏に相談した。京都書院は美術関連の出版社で鎌倉芳太郎の『古琉球紅型』も発行。京都書院河原町店は現代美術の本も豊富で私の好きな場所でもあった。富山編集長の御宅で布コレクションを見せてもらったり、富山編集長依頼の贈物を読谷花織の与那嶺貞さんに持って行ったこともある。
①京都書院(きょうとしょいん)は、かつて美術書を多く出版した京都市の出版社であった。 創業1924年9月、設立1949年。洗練されたカラー印刷を生かした美術書が読者のニーズをつかみ一世を風靡したが、1999年6月に倒産した。負債額22億円。月刊誌「美と工芸」やユニークな豪華本、文庫サイズのアーツコレクションは好評だった。→ウィキ
②大淵渉(1855年‐1907年)によって1881年(明治14年)に京都において書肆駸々堂が創業され、出版も開始する。1883年(明治16年)には大阪の心斎橋に進出、関西出版社としての地歩を固めた。嵩山堂とは出版数を争うよきライバルであり、駸々堂が出版した書籍で木版口絵がついた作品の数も、口絵を描いた画家の数も多様であった。また、旅行案内や時刻表などの方面にも力を注いでいる。→ウィキ
淡交社ー茶道裏千家十四世淡々斎家元の次男、納屋嘉治が同志社大学卒業の翌年、裏千家の機関誌「淡交」を刊行する出版社として設立した。現在は長男、納屋嘉人が経営にあたっている。社名は荘子の「君子之交淡若水」(学徳のある立派な人同士の交わりは、水のように淡々とした、清い関係である。私心のない交わりは壊れることがない)に由来している。 法然院での修行歴のある僧侶で、弘文堂などに勤務していた編集者でもあった臼井史朗(のちに副社長)を引き入れてから、茶道を軸とした伝統文化など様々な分野の書籍、雑誌を刊行。とりわけ京都の観光と文化に関するものが多い。茶道の家元、裏千家と繋がりが深い出版社であり、創立以来裏千家の機関誌である『淡交』を刊行しており、主要株主かつ役員とし千玄室が加わっている。この他、『なごみ』『淡交テキスト』の両誌を刊行している。茶道書以外の分野では、美術工芸、歴史文化、旅ガイド、料理、趣味生活や『京都大事典』、『京都検定公式テキストブック』を始めとする京都関連書籍などの書籍を発行している。日本語以外の言語による書籍も扱っている。 出版以外にも、茶室等の建築、茶道具などの販売も手がけている。京都本社の一階は書籍を販売しているフロアと茶道具関係を販売しているフロアがある。→ウィキ
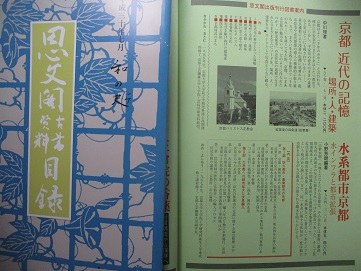
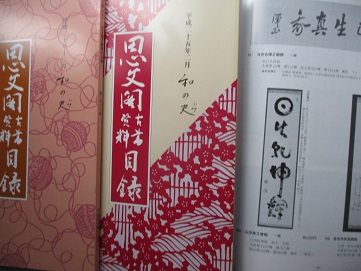
『和の史 思文閣古書資料目録』ー思文閣出版(しぶんかくしゅっぱん)は、京都府京都市東山区古門前通大和大路東入元町355にある出版社。美術商思文閣の出版部で、人文系・美術系の書籍を刊行している。絶版となった古書や花道、歴史、国文、芸術などのオリジナル企画書を刊行している。ベストセラーにならなくても、命の長い本を出版していく方針を取っている。京都市東山区古門前通大和大路東入元町386にぎゃらりぃ思文閣を運営する。 →ウィキ
10/31: 令和元年10月31日 百浦添御殿 焼失
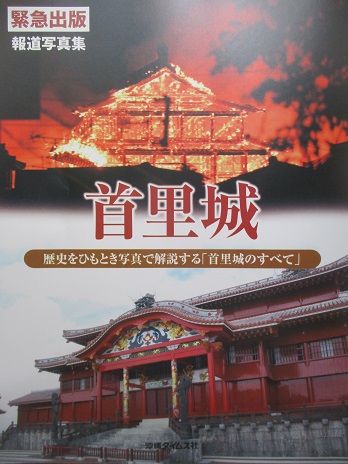

2019年11月15日 『報道写真集 首里城』沖縄タイムス社
2019年10月31日朝一番、ネットのニュースで「首里城公園付近で黒煙が上がっている」首里城の正殿は、いまも延焼中だという。けが人の情報は入っていないという。パリのノートルダム大聖堂の火災以上にショック。木造なので火災には十分に警戒しているはずだが。テレビをつけると、正殿が崩れ落ちる映像、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件のテレビ映像と同様の衝撃であった。かつて又吉真三氏から首里城復元の話を聞き、「大阪城に倣いコンクリートで造ったらどうですか」と言ったら「建築技術継承」の意味合いで木造でなければならない、と言われたが、やんぬるかなである。「建築技術継承」は先の復元過程で建築技術も確認されたであろうから、今後は元々の材質に拘らず火災に強いもので再建すべきだと思う。それより所蔵の文化財は無事だろうか。台風、水害と消費税、アベ主導の「れーわ世」になってからロクな事はないわな。
参考〇沖縄県は1日、沖縄美ら海水族館(本部町)と首里城正殿などの有料区域(那覇市)の管理を始めた。今後は県が指定管理者に指定した沖縄美ら島財団(本部町)が両施設の実質的な管理・運営を担う。指定管理の期間は2019年2月1日から23年1月31日まで。これまで両施設は国が管理してきたが、県へ管理が移行した。今後も両施設の所有権は国が持つため、県は国有財産使用料として年間約7億円(美ら海水族館約5億円、首里城約2億円)を国に支払う。財源は両施設の入場料と売店収入で賄うため、県の財源からの支出はない。現在、入場料の変更なども予定されていない。
県は管理移行に合わせて、安定的な運営維持のために「沖縄県国営沖縄記念公園内施設管理等基金」を設立。財団が毎年県に納める固定納付金(年間約9億円)と歩合納付金から成り、大規模修繕や整備が必要になった場合に支出する。
『沖縄タイムス』11月12日首里城火災で、全焼の正殿など被害に遭った7棟9施設について、損害保険の評価額が100億3500万円に上ることが11日、分かった。県議会(新里米吉議長)の全議員対象の説明会で、首里城を管理運営する沖縄美ら島財団の担当者が明らかにした。財団が年間2940万円を支払っている保険の支払限度額は70億円で「保険会社が現地を調査し、査定する。評価額は100億円だが、支払額が70億円を上回ることはない」と答えた。建物の評価額は、保険料を決めるために建物の価値を算出したもの。9施設の当時の建設費は正殿で33億円、南殿、北殿など3施設で21億円、黄金御殿など5施設で19億円の計73億円だった。
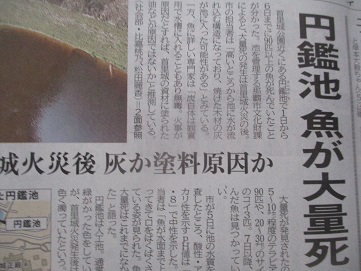
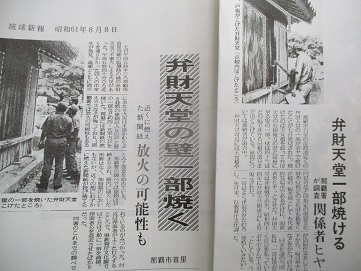
2019年11月16日『沖縄タイムス』「円鑑池 魚が大量死」〇「円覚寺(えんかくじ)」の前の池は「円鑑池(えんかんち)」、池の中央にある赤瓦の堂を「弁財天堂(べざいてんどう)」という。→首里城公園/1986年8月8日『琉球新報』「弁財天堂の壁一部焼く」、8月7日『沖縄タイムス』
1879年 首里城、第六師団熊本分遣隊の兵舎が置かれ、陸軍省所轄地となる。
1904年4月 首里区立工業学校、当蔵の民家から首里城書院に移転
1908年 首里市立女子工芸学校、赤平義村家跡校舎より首里城内に移転
1909年、首里市に壹千五拾四圓五拾五銭にて払下(南風殿、正殿、西殿、鎖の間書院、王子居室、王王妃室、世誇殿、銭蔵、寝廟殿、廣福殿、用物奉行所料理座、門番所、二階殿、厩係詰所、アヤメ居室、奉神門、金蔵,竃家、下役料理座、鐘撞堂、右掖門、淑順門、漏刻門、瑞泉門、久慶門、歓会門、美福門、継世門、衛兵所、洗面洗濯所、銃工室、浴室、伝染病室、敷石、哨兵舎、体操器械、物干)
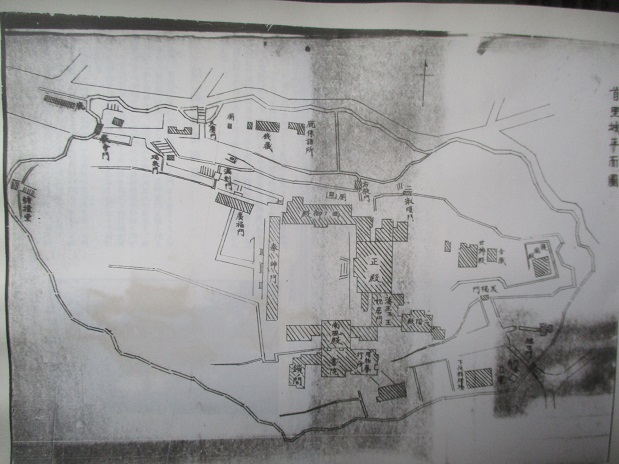
1931年10月 『首里市制十周年記念誌』首里市役所
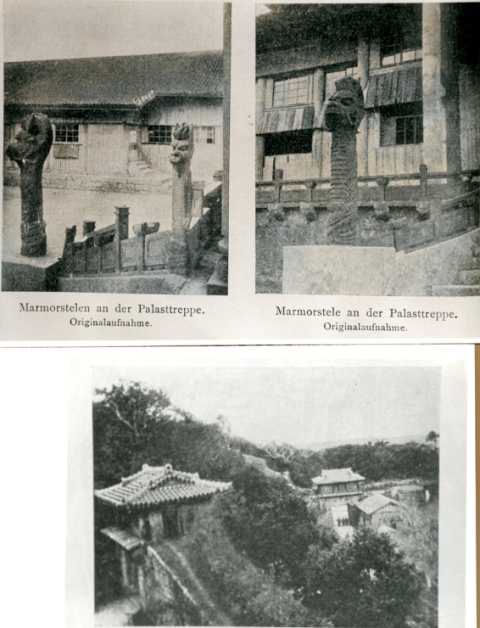
1910年3月7日 ドイツ人エドモンド・シーモン馬山丸で来沖
1910年 首里高等尋常小学校、校舎狭にして一部生徒を首里城西の御殿に仮教室を設けて収容
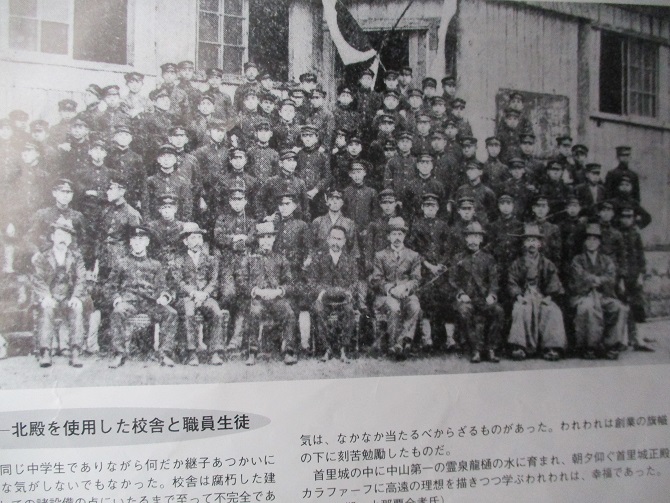
1910年4月 沖縄二中、沖縄中学校の分校として首里城北殿に開校。翌年4月、独立(初代校長・高良隣徳)
2019年1月 国梓としひで『太陽を染める城ー首里城を蘇らせた職人たちの物語』沖縄建設新聞
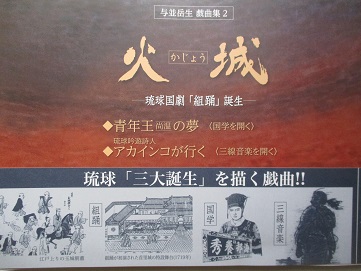
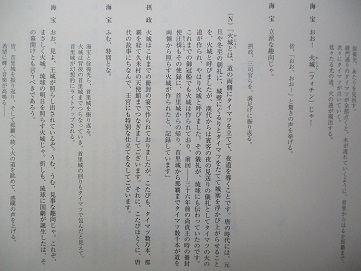
2019年3月 与並岳生 『火城』「●組踊 首里城炎上、大飢饉・・・未曽有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!!●国学 国造りは人造りー琉球人材育成をめざして、「海邦養秀」のスローガンのもと「国学」は誕生した。若き尚温王の教育立国の理念が燃える!●三線音楽 「歌と三線の昔始まりや」-伝説のアカインコ青春行状記! 」新星出版
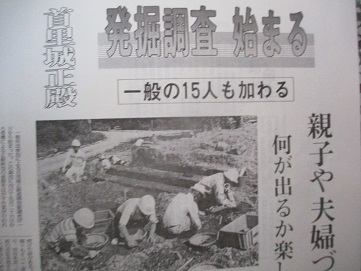

1985年8月1日『沖縄タイムス』「首里城正殿 発掘調査 始まる」/9月7日『琉球新報』「予想以上にひどい首里城の戦災」
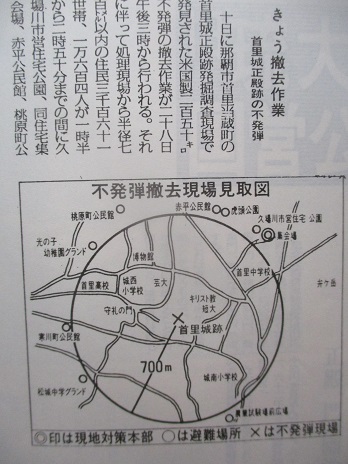
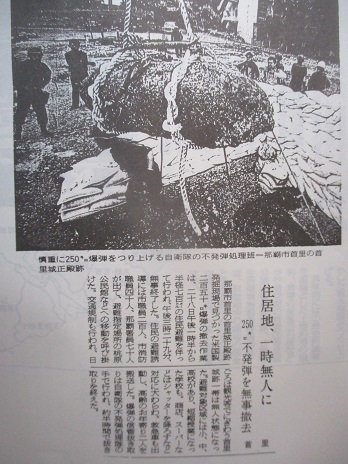
1986年11月28日『沖縄タイムス』/1986年11月29日『沖縄タイムス』「首里城正殿跡発掘現場で見つかったアメリカ製250キロ爆弾撤去」
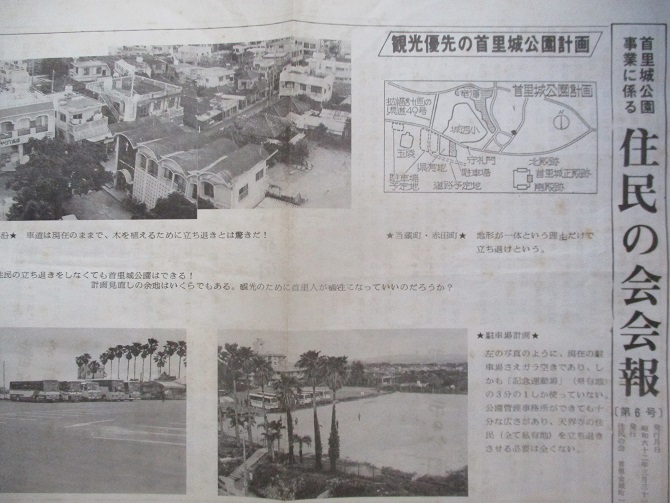
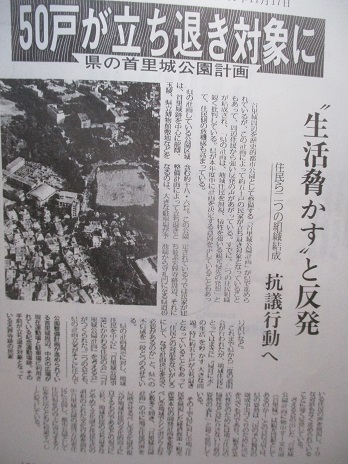
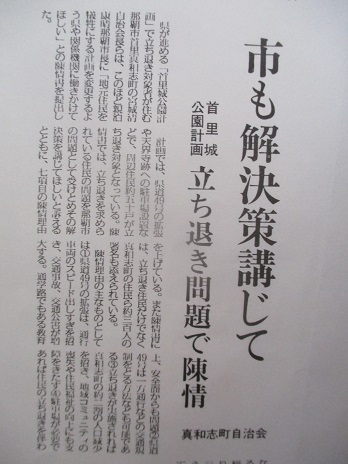
1986年12月4日『琉球新報』/1986年12月22日『沖縄タイムス』
首里城復元に関わっていた又吉眞三氏から、「新城君、君の提供した資料で寸足らずの龍柱が本来の高さに復元出来そうだ」と喜んで居られ、かつ話された、その資料を『首里城復元期成会会報』第7号で紹介してほしいと。同誌に載せたのが比嘉朝健「琉球の石彫刻龍柱」である。
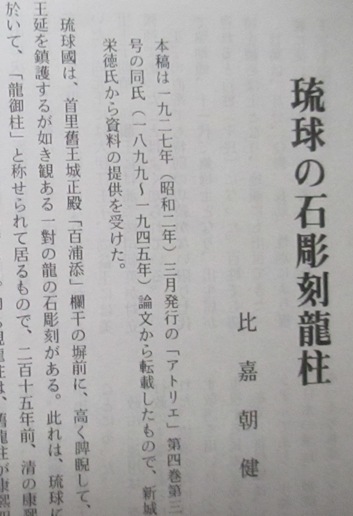
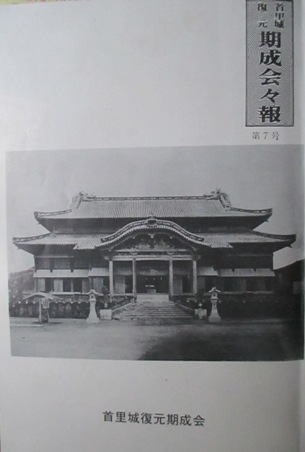
□本稿は1927年(昭和2)3月発行の『アトリエ』第4巻第3号の同氏(1899~1945)論文から転載したもので、新城栄徳氏から資料の提供を受けた。


1974年8月6日『琉球新報』又吉真三「首里城跡の復元をめぐって=文化遺産の活用とあり方=」/1984年11月27日『琉球新報』「首里城・石造欄干の親柱 完ぺきな形で残る」


前列右から宮城篤正氏、又吉真三氏、後列右から首里城復元で「古文書の鬼」と謂われた高良倉吉氏、新城栄徳。/又吉眞三氏を囲んでー右から3人目が又吉眞三氏、左奥から西村貞雄氏、新城栄徳。左手前が首里城の瓦を制作した奥原崇典氏の兄・奥原崇仁氏
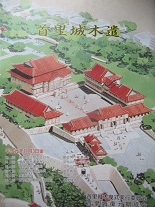
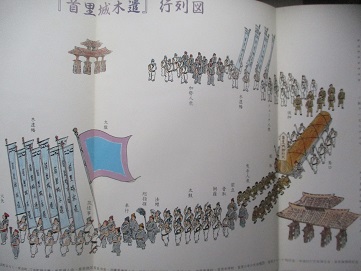

1989年11月3日「首里城木遣」
又吉氏は沖縄県建築士会会長、沖縄県文化財保護審議会会長もつとめ琉球の建築文化史にも詳しい。私は宮内庁三の丸尚蔵館の山本芳翠「琉球中城之東門」の門は又吉氏と検討し「美福門」と断定、1989年11月発行『沖縄美術全集』の年表にその旨を記した。また首里城北殿の階段の問題も相談に乗ってもらい新聞に発表した。
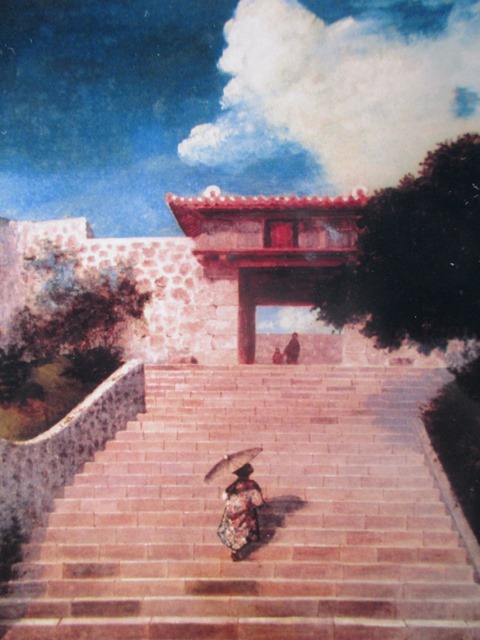

「琉球中城之東門」/北連蔵画「山本芳翠像」

山本芳翠「浦島」
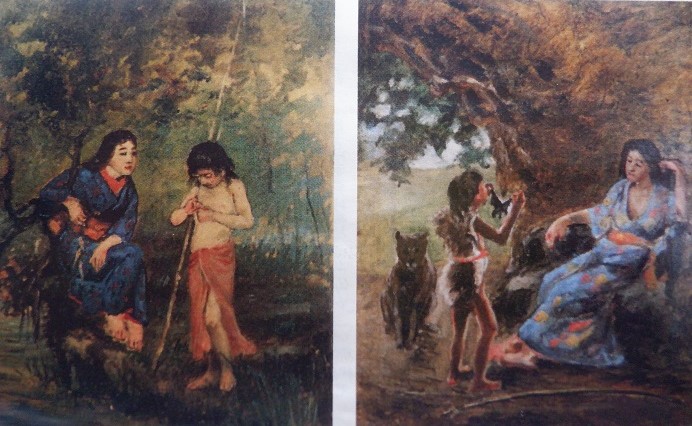
山本芳翠「琉球風景」
首里城北殿の階段 大龍柱は正面を向いている。
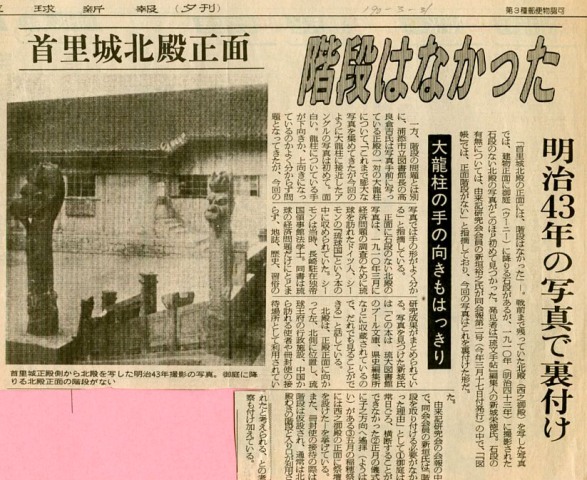
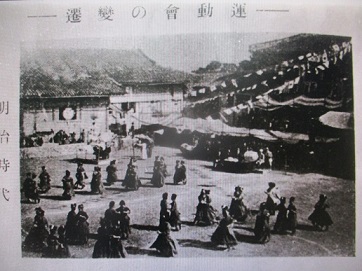
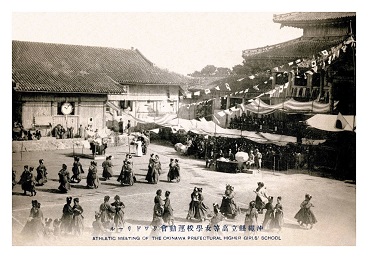
1937年1月『姫百合のかおり』/大塚努(京都市)2019-11-5「1907年ー沖縄県立高等女学校運動会」
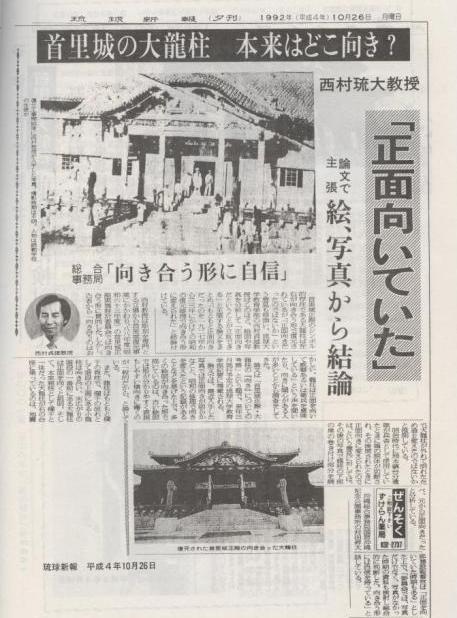

1993年3月27日『琉球新報』「首里城正殿の大龍柱/大龍柱を考える会(宮里朝光会長)『やっぱり正面向き』」

『沖縄タイムス』2019年11月5日〇復元された首里城の龍柱を制作した彫刻家で琉球大学名誉教授の西村貞雄さん(76)=糸満市=は、独自の造形文化が詰め込まれた城の変わり果てた姿に「研究と技術の集積が一瞬にして消えた。でも手掛かりがほとんどなかった戦後の復元と比べ、資料はある。再建に向けもう一度全力投球だ」(略)基本・実施設計の委員で龍柱を含む正殿の復元作業に携わった。わずかに残った戦前の写真や図面を観察し、中国や東南アジアなどを視察した。龍のうろこや背びれの数を数えて柱の高さを確認するなど、地道な作業で戦前の姿を解明していった。
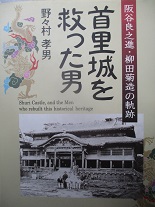
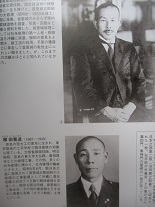
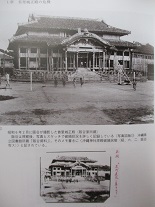
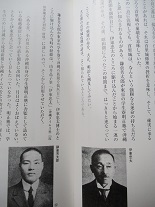
1999年10月 野々村孝男『首里城を救った男ー阪谷良之進・柳田菊造の軌跡』ニライ社
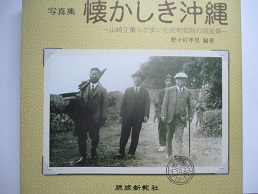
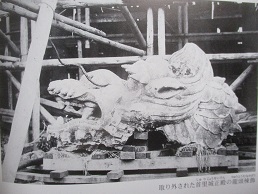
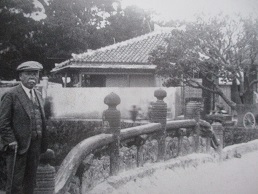
2000年11月 野々村孝男『写真集 懐かしき沖縄~山崎正董らが歩いた昭和初期の原風景から』琉球新報社
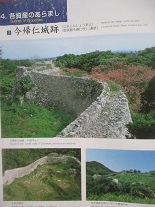
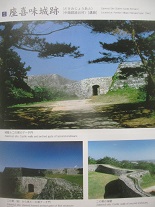
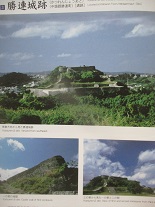
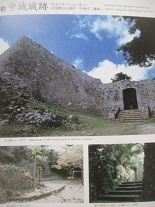
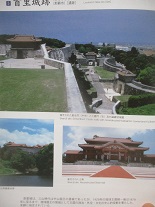
2001年3月「世界遺産 琉球王国のグスク及び関連遺産群」沖縄県教育庁文化課
『琉球新報』2019年9月5日ーしまくとぅばの保存、継承に尽くした沖縄語普及協議会名誉会長の宮里朝光(みやさと・ちょうこう)さんが1日午後2時38分、老衰のため那覇市首里平良町の自宅で死去した。95歳。那覇市首里出身。告別式は5日午後2時から3時、那覇市首里山川町3の1の首里観音堂で。喪主は長男聖(きよし)さん。2000年に沖縄語普及協議会を設立し、06年の「しまくとぅばの日」(9月18日)の制定に尽力した。しまくとぅば指導講師の養成にも取り組み、しまくとぅば保存・継承の機運をつくった。琉球王府の迎賓館ともいわれ、沖縄戦で消失した御茶屋御殿(うちゃやうどぅん)の早期復元を求める御茶屋御殿復元期成会の会長も務めた。沖縄語普及協議会は16年、第38回琉球新報活動賞を受賞した。
11/15: 世相ジャパン⑬/猛火とフェイクに耐えた大龍柱
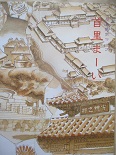
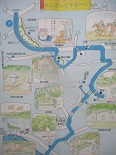

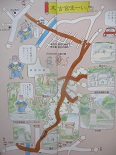
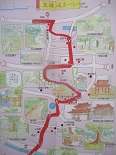
1987年9月 「歴史散歩マップ 首里マーイ」(イラスト・新里堅進)那覇市教育委員会文化課
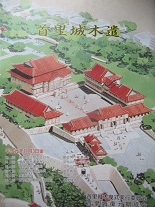
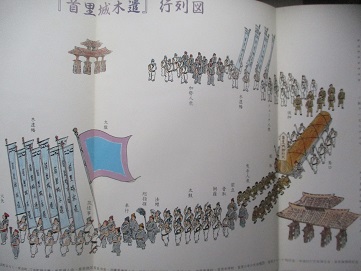

1989年11月3日「首里城木遣」
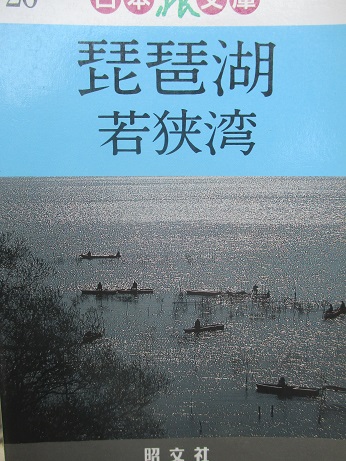
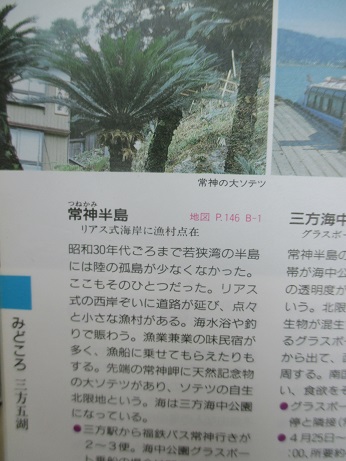
1991年7月 日本旅文庫『琵琶湖・若狭湾』昭文社
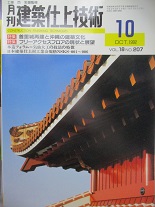
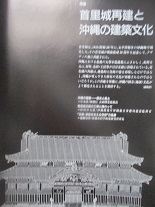


1992年10月 『月刊建築仕上技術』「首里城再建と沖縄の建築文化」工文社


久能山東照宮- 国宝 拝殿・本殿 〈静岡県静岡市〉 /朝鮮ソテツと鼓楼(ころう) →行って見たい神社とお寺

斎藤 陽子(Walnut, California)2019-11-24 10年物のソテツです、こちらは乾燥しているので水やりが欠かせません。


2016年1月8日 若狭の龍柱
安田浩一2018-11-3「沖縄の龍柱は、沖縄のものです」若狭の「龍柱」のデザイン日本列島は龍の形をを担当したのは、沖縄美術界の大家として知られる琉球大学名誉教授の西村貞雄さんだ。「私も『中国の手先』などと直接に面罵されたこともあります。一部で龍柱の意味がまったく理解されていないのが本当に残念です」そう言って、西村さんは悔しそうな表情を見せた。「沖縄の龍柱は、沖縄のものですよ。だいたい、中国各地に存在する龍柱とは形状からして違います」たとえば、中国特有の「龍柱」は、那覇市内の中国式庭園「福州園」に足を運べば目にすることができる。(略)中国式「龍柱」は、龍が柱に巻き付いた形状となっているのに対し、沖縄の「龍柱」は、龍の胴体そのものが柱となっている。そう、デザイン的にはまったくの別物なのだ。

福州園は中国福建省福州市(ふっけんしょう・ふくしゅうし)と那覇市の友好都市締結10周年と、那覇市市制70周年を記念して、1992年に完成しました。園内は中国の雄大な自然と福州の名勝をイメージして造られている。
「私はアジア各国を回って龍柱を見てきましたが、中国の影響を受けつつも、それぞれの国がそれぞれの龍柱を持っている。爪の数にしても同様です。属国の龍柱は5本爪であってはならないというのが通説ですが、私から言わせれば、これも怪しい。モンゴルには3本爪、4本爪、5本爪の三種の龍柱がありましたし、韓国には6本爪の龍柱がありました。私が若狭の龍柱を4本爪にしたのは、単に沖縄の伝統的な龍柱が4本爪だったからにすぎません。歴史どおりに、伝統に基づいてデザインしただけです。そこには中国への忠誠だの、そんな意図が含まれているはずがない。仮に批判を受けいれて5本爪にしたら、それは歴史を無視した、きわめて政治的なデザインとなってしまうではないですか」西村さんによれば、若狭の龍柱には、沖縄の歴史と未来への思いが込められているという。
「一対の龍は向き合っているのではなく、海の方角を向いています。つまり、尾の部分は首里城までつながっているという想定です」西村さんは、これを「龍脈」と呼んでいる。龍のからだは首里城から国際通りの地中をくぐり、海岸線で地中から垂直に飛び出る、といったイメージだ。首里城は沖縄の源流であり、国際通りは戦後復興の象徴である。そして若狭の港は外に開ける海の玄関だ。つまり、この「龍脈」は沖縄の歴史を意味する展開軸、導線なのだ。「龍の頭が海を向いているのは、その先の未来を見ているからなのです。水平線の先にあるニライカナイ(理想郷)ですよ」「龍脈」は過去と未来を結ぶ。中国とも侵略とも関係ない。龍の目玉はニライカナイの海を望む。


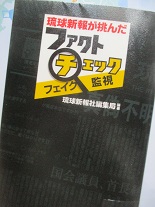
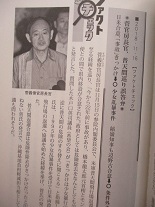
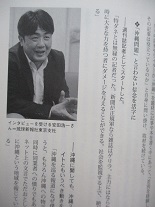
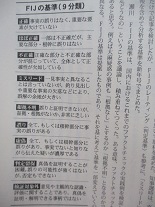
2019年9月 琉球新報編集局『琉球新報が挑んだファクトチェック・フェイク監視』高文研

写真左よりー安田浩一氏、平良肇氏、島袋和幸氏、長嶺福信氏
2017年11月3日13:00 なは市民活動支援センター第三会議室「〔検見川事件を語る会〕学習会」
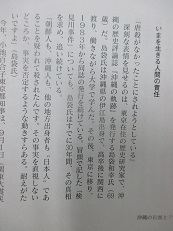

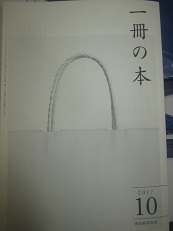
2017年10月 朝日新聞出版『一冊の本』安田浩一「沖縄の右派と〔プロ市民〕7 人々を虐殺に向かわた回路」
安田 浩一(やすだ こういち、1964年(昭和39年)9月28日 - )は日本のジャーナリスト。日本労働組合総評議会(総評)系の機関誌『労働情報』編集委員。静岡県出身。千葉県在住。慶應義塾大学経済学部卒業。伊豆半島の温泉地帯に生まれた。日本経済新聞など様々な新聞社、出版社の記者を経て『週刊宝石』の記者だった1999年(平成11年)前後に、同誌にて創価学会の批判記事を書いていた。『サンデー毎日』時代は名誉毀損で訴えられ、証言台に立った。→ウィキ2014年9月 佐野眞一『あんぽん 孫正義伝』小学館文庫 解説・安田浩一

御菓子御殿 国際通り松尾店ー私が奥原崇典氏(首里城の瓦を手掛けた。1950年-2014年3月12日)を最後に見たのがこの柱の龍を仕上げているときである。
2014年5月20日~6月22日 沖縄県立博物館・美術館「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した美」
同時期開催/6月3日~8日 西村貞雄主催「復元のあゆみー琉球王朝造形文化の独自性を求めてー」


石川和男氏、松島弘明氏

1991年4月19日『レキオ』

末吉安允氏(末吉麦門冬の甥)と西村貞雄氏〇11月5日の沖縄タイムス文化欄に、大城立裕さんが焼けた首里城について「当時の持ち主であった首里市は、取り壊しにかかったが、識者の末吉麦門冬の注進で、建築家の伊東忠太が文部省(当時)に掛け合って温存され、2年後に国宝に指定された」と書いておられるが、結果論としては合っているが、具体的な経緯は別にある。

平良昭隆氏、平良知二氏、新城栄徳、宮城篤正氏

2019年11月12日『沖縄タイムス』宮城篤正「視点 焼けた首里城」

2014年6月5日ー左から伊佐眞一氏、西村貞雄氏、亀島靖氏


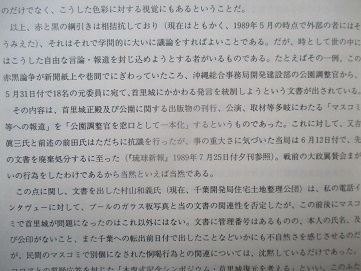
1991年1月 伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子〇編集後記に下の新聞記事の解説

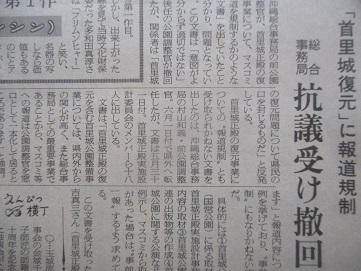
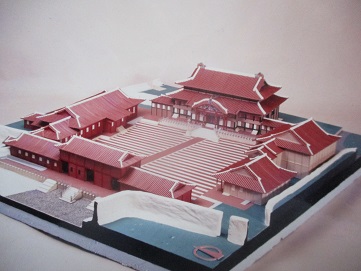
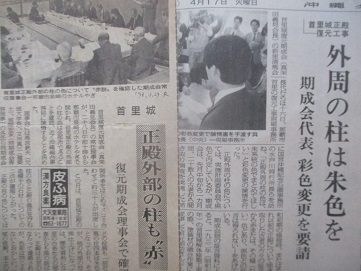


新城栄徳、西村貞雄さん
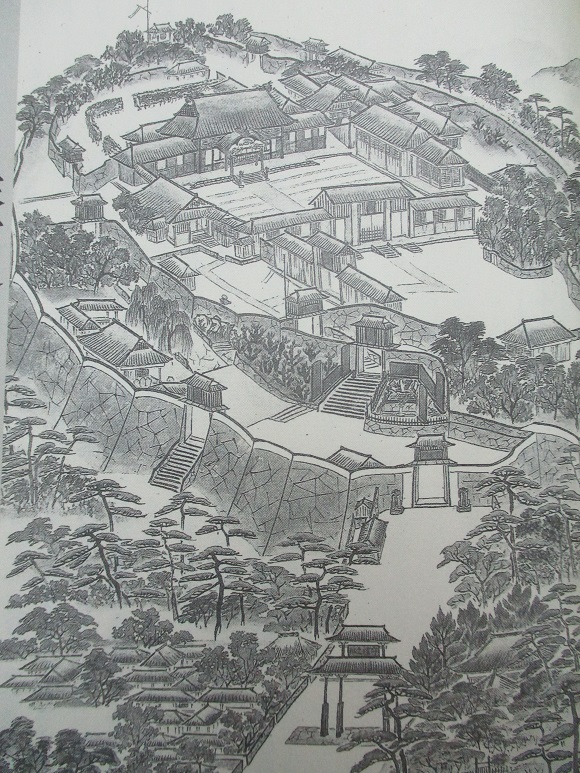
2015年1月『月刊琉球』12・1月合併号 <500円+消費税> Ryukyu企画〒901-2226 宜野湾市嘉数4-17-16 ☎098-943-6945 FAX098-943-6947
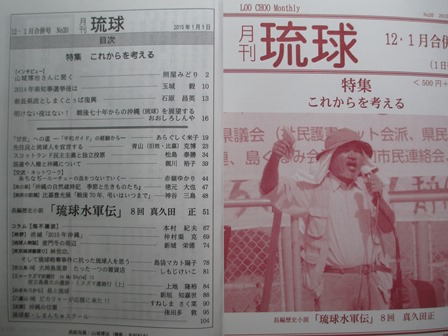
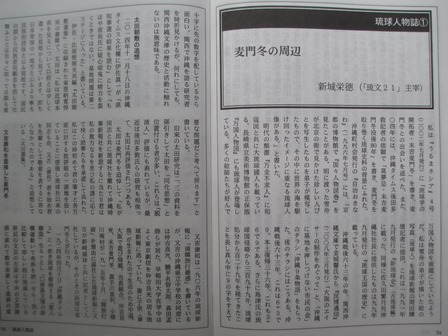
新城栄徳「麦門冬の周辺」
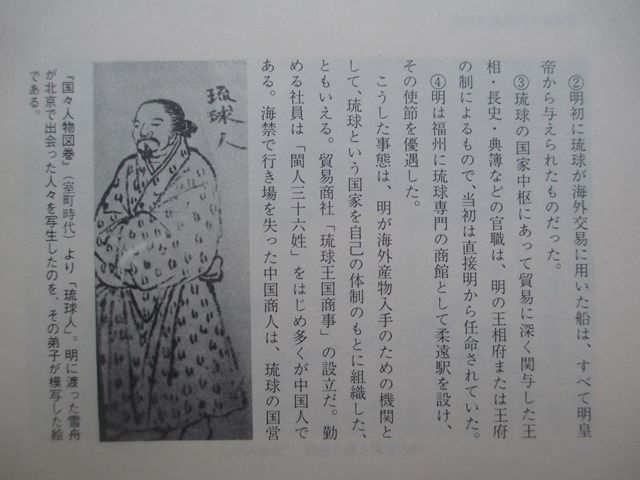
國吉眞哲翁から、そのころ貘と一緒に末吉麦門冬の家に遊びに行った話を伺った。玄関から書斎まで本が積んであって、麦門冬が本を広げている上を鶏が糞を垂れ流しながら走りまわっていたのが印象に残っているとの話であった。思うに貘はそのとき麦門冬の旧号・獏を夢を喰う意味での「獏夢道人」をいくぶん意識に植えつけたのではなかろうか。
又吉康和は一九二三年に『沖縄教育』編集主任になると、麦門冬に「俳句ひかへ帳ー言葉の穿鑿」を書かせている。二五年九月発行『沖縄教育』には、表紙題字を山城正忠に依頼、カット「獅子」を山口重三郎(貘)に依頼し、貘の詩「まひる」「人生と食後」も載せている。編集後記に「山之口貘氏は今般中央の『抒情詩』に日向スケッチ他三篇入選しました之より琉球詩人がどしどし中央の詩壇に出現せんことを念じます。救世者は政治家ではなく、それは詩人と哲人であります」と記して、甥にあたる國吉眞哲と共に上京の旅費を集め貘を東京に送りだしている。
写真上は1925年8月16日、貘2度目の上京前に上左から又吉康和、国吉真哲、国吉真才、一人置いて貘。写真下は貘が戦後帰郷の時。

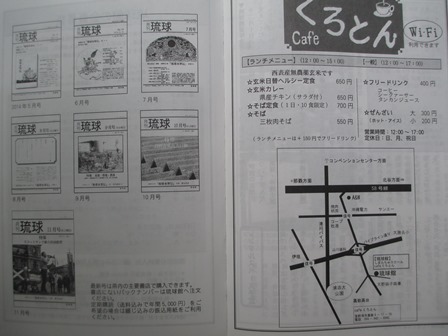
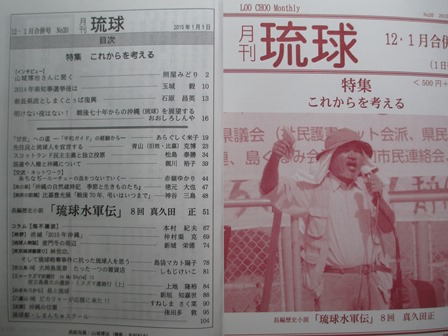
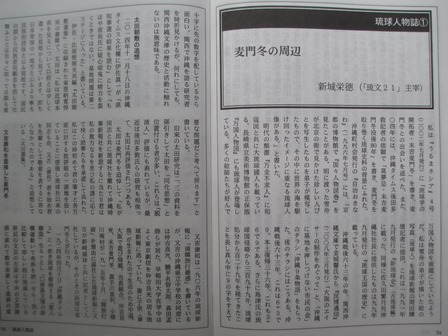
新城栄徳「麦門冬の周辺」
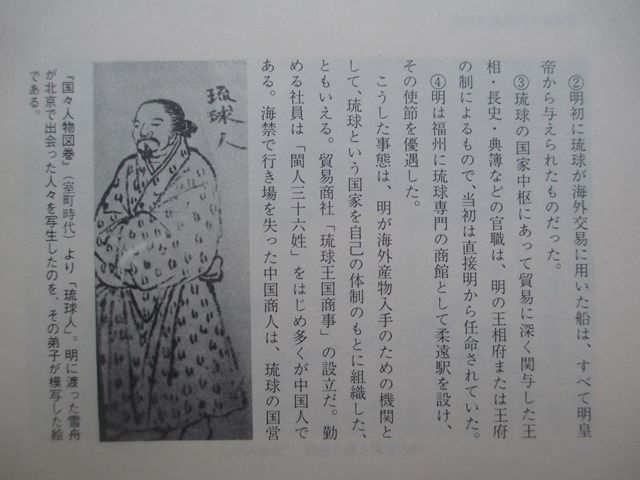
國吉眞哲翁から、そのころ貘と一緒に末吉麦門冬の家に遊びに行った話を伺った。玄関から書斎まで本が積んであって、麦門冬が本を広げている上を鶏が糞を垂れ流しながら走りまわっていたのが印象に残っているとの話であった。思うに貘はそのとき麦門冬の旧号・獏を夢を喰う意味での「獏夢道人」をいくぶん意識に植えつけたのではなかろうか。
又吉康和は一九二三年に『沖縄教育』編集主任になると、麦門冬に「俳句ひかへ帳ー言葉の穿鑿」を書かせている。二五年九月発行『沖縄教育』には、表紙題字を山城正忠に依頼、カット「獅子」を山口重三郎(貘)に依頼し、貘の詩「まひる」「人生と食後」も載せている。編集後記に「山之口貘氏は今般中央の『抒情詩』に日向スケッチ他三篇入選しました之より琉球詩人がどしどし中央の詩壇に出現せんことを念じます。救世者は政治家ではなく、それは詩人と哲人であります」と記して、甥にあたる國吉眞哲と共に上京の旅費を集め貘を東京に送りだしている。
写真上は1925年8月16日、貘2度目の上京前に上左から又吉康和、国吉真哲、国吉真才、一人置いて貘。写真下は貘が戦後帰郷の時。

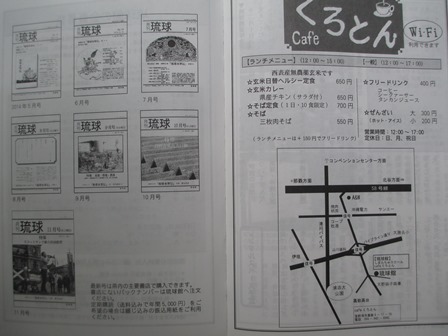


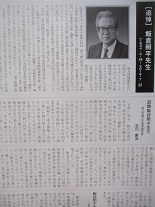
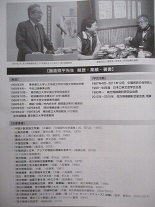
2020年4月1日 南方熊楠顕彰会『熊楠ワークス』№55 「第30回南方熊楠賞決定 北原糸子氏(立命館大学歴史都市防災研究所客員研究員)」/「[追悼]飯倉照平先生」
南方熊楠顕彰館 7月25日 ー南方熊楠顕彰会の前副会長(2011年4月~2015年3月)で、南方熊楠特別賞(第14回時)を受賞された飯倉照平先生が2019年7月24日に逝去されました。飯倉先生は、第1回南方熊楠特別賞受賞者の長谷川興蔵先生とともに、平凡社刊『南方熊楠全集』の刊行に携わられるとともに、『南方熊楠-森羅万象を見つめた少年』などの著書をもって、熊楠翁の業績や人となりを広く世に紹介されました。また、南方熊楠資料研究会の会長として、翁の残した膨大な資料の調査を通して「南方熊楠の基礎的研究」を進められ、『熊楠研究』の編集や『南方熊楠邸蔵書目録』『南方熊楠邸資料目録』の刊行等にもご尽力いただきました。ここに改めて、飯倉照平先生のご功績、並びに南方熊楠顕彰事業へのご尽力に対し敬意と感謝を申し上げますとともに、南方熊楠特別賞ご受賞時の選考報告、コメントとお写真を紹介し、ご冥福をお祈り申し上げます。
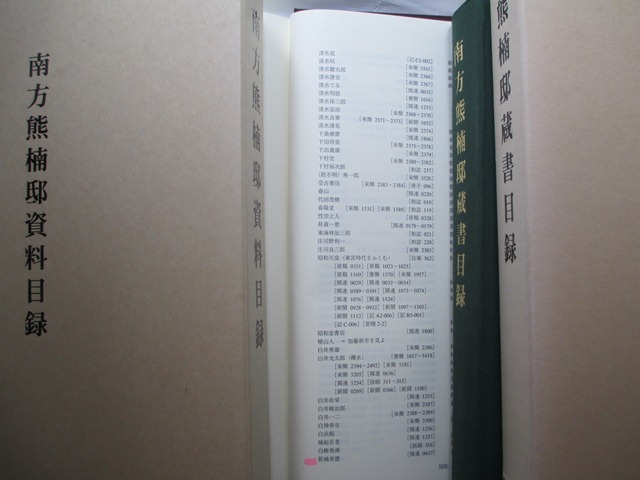
平成17年7月 俳句誌『貝寄風』』(編集発行・中瀬喜陽)新城栄徳「琉球の風②」
4月、南方熊楠顕彰会から『南方熊楠邸資料目録』が贈られてきた。巻末の人名索引に私の名前が有る。驚くと同時に記憶が甦った。1984年の夏、麦門冬・末吉安恭書の軸物「松山うれしく登りつめ海を見たり」を背に担ぎ熊本城を経て、田辺の熊楠邸を訪ねた。折よく文枝さんが居られたので麦門冬の写真を仏壇に供えてくださいと差上げたものであるが、大事に保存され且つ目録にまで記されるとは夢にも考えなかった。飯倉照平先生に電話で伺うと、研究会では熊楠没後の写真なので収録することに悩んだという。と書いた。そして麦門冬の親友・山城正忠を紹介した。正忠は那覇若狭の漆器業の家に生まれた。若狭は漆器業が多い。麦門冬の手ほどきで琉球美術史研究に入った鎌倉芳太郎(人間国宝)は「思うに(福井県)若狭はその地勢、畿内に接して摂津と表裏し(略)、古来日本海における外国貿易の起点となっていたが、十五世紀の初頭以来南蛮船も着船し、この地の代官も書をもって朝鮮国と通交しており、小浜から出て東シナ海に向かい、琉球に新しく出来た那覇港に、貿易物資(漆器)生産のための若狭の居留地が造成された」(『沖縄文化の遺宝』)と推定している。

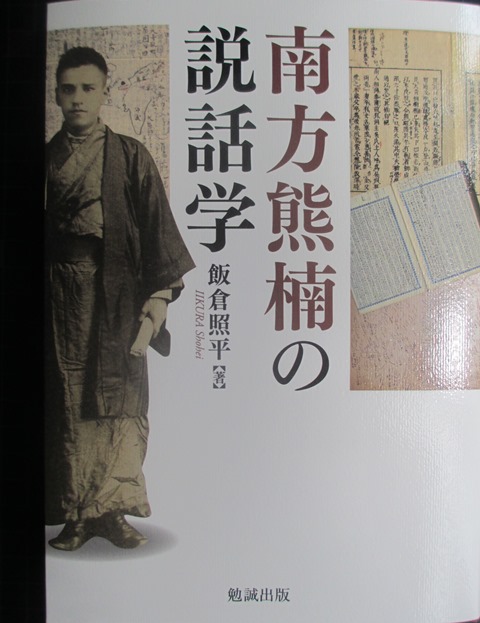
飯倉照平氏(南方熊楠顕彰館)/2013年10月 飯倉照平『南方熊楠の説話学』勉誠出版
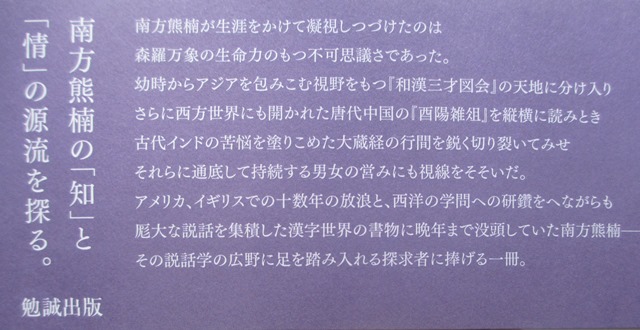
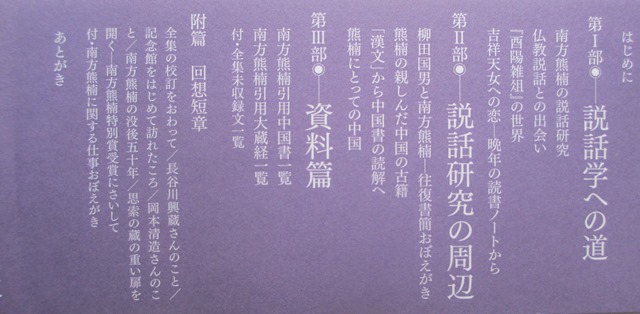
本書『南方熊楠の説話学』にも、「『南方熊楠全集』の校訂をおわって」と題して「平凡社の池田敏雄さんが、そのころまだ代々木駅の近くにあった中国の会の事務所へたずねて来てくれたのは、たしか1969年のはじめごろ{正しくは4月}であったと思う。乾元社版の『南方熊楠全集』に手を加えて出したいが、誤植も少なくないと思われるので目を通してほしいこと、さらに引用されている漢文を読み下し文に直し、全体の表記も読みやすくしたいので手伝ってもらえないか、というのが用件であった。戦争中に『民俗台湾』という雑誌の編集をしていた池田さんから、わたしは中国の昔話や民俗学の本を借りたことがある。また、わたしが以前によその出版社で校正の仕事をしていたことも、依頼されたきっかけの一つになっていたかもしれない。」と「『南方熊楠全集』の校訂に携わるきっかけを書かれておられる。
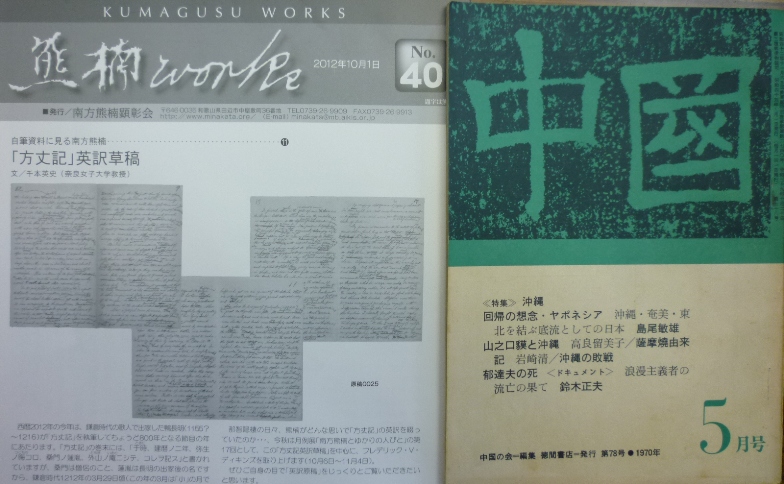
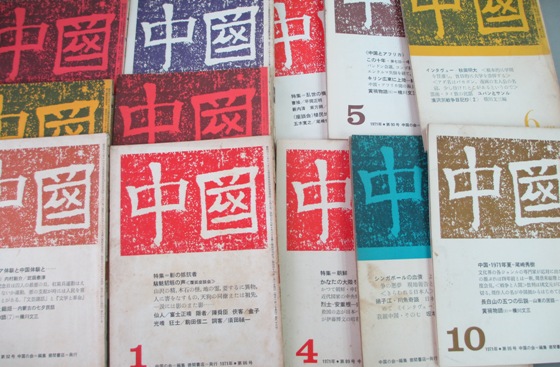
2012年10月『熊楠WORKS』№40に飯倉照平さんが「『漫画』好きの伊東忠太」を記され中に「筆者は、平凡社の『南方熊楠』全集の校訂にたずさわる前に、前後10年近く歴史の復習を旨とする雑誌『中国』の編集を手伝っていた時期がある。」と、かつて私も愛読していた『中国』との関わりについてもふれておられる。同号には考古学者・森浩一氏の第22回南方熊楠賞授賞式も載っていた。
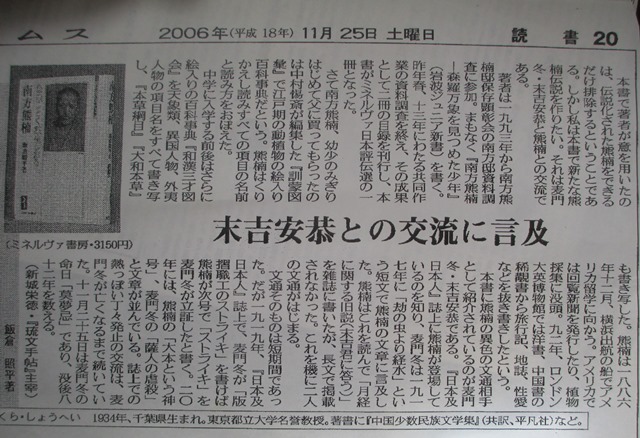
飯倉照平氏は千葉県山武郡大網白里町に住んでおられる。氏の著の書評を2回、沖縄の新聞に書いた。2006年11月25日『沖縄タイムス』新城栄徳(書評)飯倉照平『南方熊楠ー梟のごとく黙座しおる』ミネルヴァ書房ー本書で著者が意を用いたのは、伝説化された熊楠をできるだけ排除するということである。しかし私は本書で新たな熊楠伝説を作りたい。それは麦門冬・末吉安恭と熊楠との交流である。著者は1993年から南方熊楠邸保存顕彰会の南方邸資料調査に参加。まもなく『南方熊楠ー森羅万象を見つめた少年』(岩波ジュニア新書)を書く。昨年春、13年にわたる共同作業を終え、その成果として2冊の目録を刊行し、本書がミネルヴァ日本評伝選の1冊となった。
さて、南方熊楠、幼少のみぎりはじめて父に買ってもらったのは中村惕斎が編集した『訓蒙図彙』で江戸期の動植物の絵入り百科事典だという。熊楠はくりかえし読みすべての項目の名前と読み方をおぼえた。中学に入学する前後はさらに絵入りの百科事典『和漢三才図会』を天象類、異国人物、外夷人物の項目名をすべて書き写し、『本草綱目』『大和本草』も書き写した。熊楠は1886年12月、横浜出航の船でアメリカ留学に向かう。アメリカでは回覧新聞を発行したり、植物採集に没頭。92年、ロンドン大英博物館では洋書、中国書の希覯書から旅行記、地誌、性愛などを抜き書きしたという。
本書に熊楠の異色の文通相手として紹介されているのが麦門冬・末吉安恭である。『日本及日本人』誌上に熊楠が登場しているのを知り、麦門冬は1917年に「劫の虫より経水」という短文で熊楠の文章に言及した。熊楠はこれを読んで「月経に関する旧説(末吉君に答う)」を雑誌に書いたが、長文で掲載されなかった。これを機に2人の文通がはじまる。
文通そのものは短期間であった。だが1919年、『日本及日本人』誌上で、麦門冬が「版摺職工のストライキ」を書けば熊楠が次号で「ストライキ」を麦門冬が立証したと書く。20年には、熊楠の「大本という神号」、麦門冬の「薩人の虐殺」と文章が並んでいる。誌上での熱っぽい丁丁発止の交流は、麦門冬が亡くなるまで続いていた。11月25日は麦門冬の命日「莫夢忌」であり、没後82年を数える。
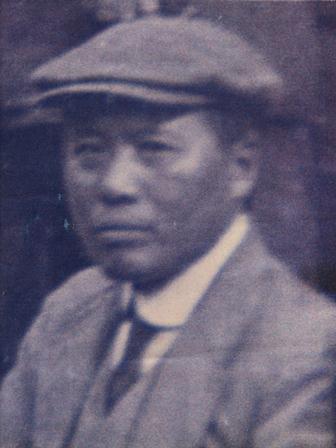
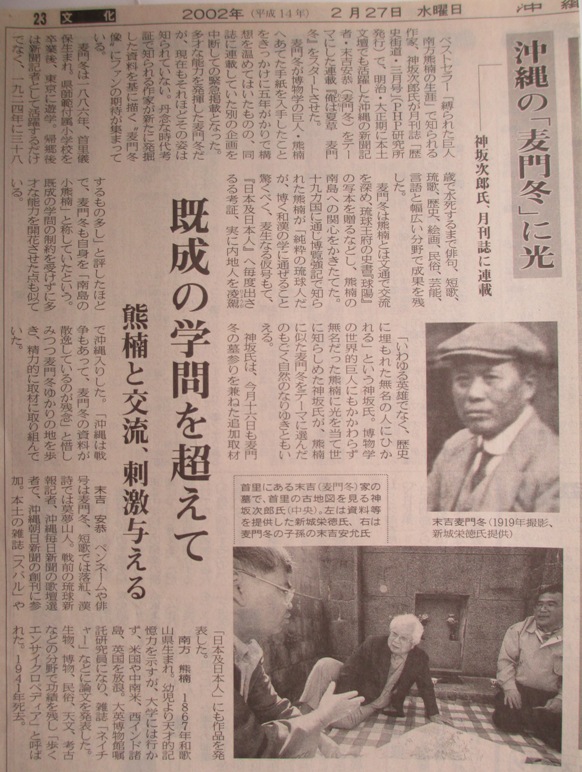
末吉麦門冬/2002年2月27日『沖縄タイムス』
林修 の「ことば検定【テレビ朝日】」よく見ているが、26日は「愚公山を移す(ぐこうやまをうつす)」であった。これは昨日『毛主席語録』1966年北京・外文出版社を読んでいたからすぐ分かった。語録には「いま、中国人民の頭上には、やはり帝国主義と封建主義という二つの大きな山がのしかかっている。(略)この上帝とはほかならぬ全中国の人民大衆である」としている。
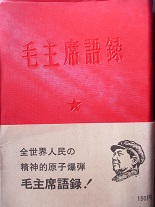



1911(明治44)年1月1日 『沖縄毎日新聞』獏夢道人(末吉安恭)「古手帖(1)」
○古手帖ー冬篭り独り凡に侍つかかつて渋茶に咽を濕し乍暮るる●の早きを惜しみフト垢擦れた古手帖の眼につくままに抽き出して彼処此処拾ひ読みをして見ると僕も随分物数奇であったと見えて能くもこんな色んな物を書き取ったもんだ。此等はいづれ雑書類を繙読してその当時は少なくとも興味を以てしたもんだから今から見ると余りドットしないけれど紙屑買に渡す気でこう原稿紙の四角い物に入れて見ようといふ気になる。右は蜀山人の仮名世説にある大平の逸民の状態はこんなものであった。この超波①は作家として左程●い物ではなかったろうが兎に角、蕪村七部集②にも出ている「五車反古」に載っているのは下の四句だ、早乙女や先づひいやりと庭の先/祇園会や胡瓜花さく所まで/我屋根をはつれてゆかし天川・・・
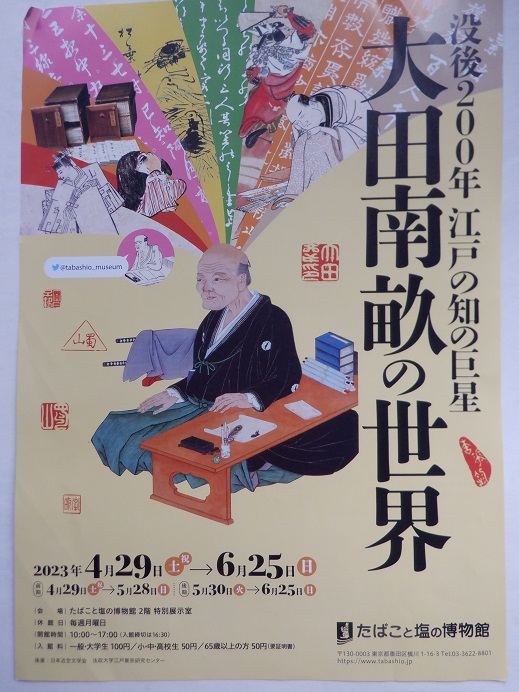
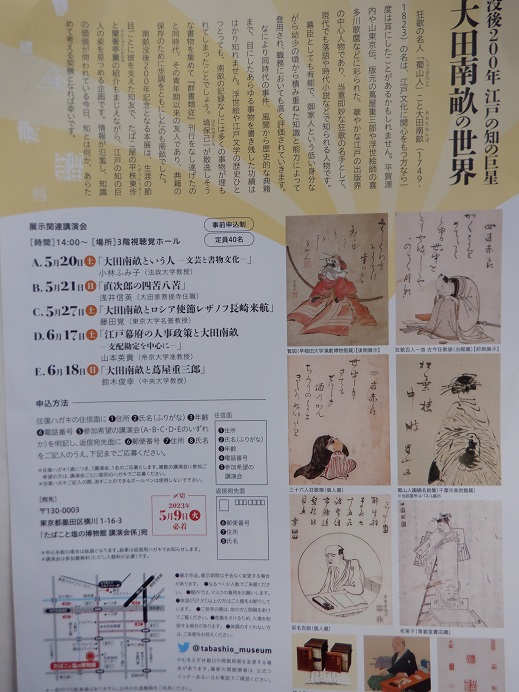
①清水超波 しみず-ちょうは
1702-1740 江戸時代中期の俳人。
元禄(げんろく)15年生まれ。江戸の人。味噌(みそ)商だったが,家業をきらい,桑岡貞佐(ていさ)の門人となる。のち点者となり,独歩庵超波を名のった。元文5年7月27日死去。39歳。通称は長兵衛。初号は長巴。編著に「紙蚕(かみかいこ)」「落葉合(おちばあわせ)」など。→コトバンク
②蕪村七部集ぶそんしちぶしゅう
江戸時代後期の俳諧撰集。菊屋太兵衛らの編。文化5 (1808) 年刊。与謝蕪村関係の代表的俳書『其雪影』『明烏』『一夜四歌仙』『花鳥編』『続一夜四歌仙』『桃李 (ももすもも) 』『続明烏』『五車反古』の8部を収めたもの。
1月7日 『沖縄毎日新聞』安元碧海「沖縄の人物地理」
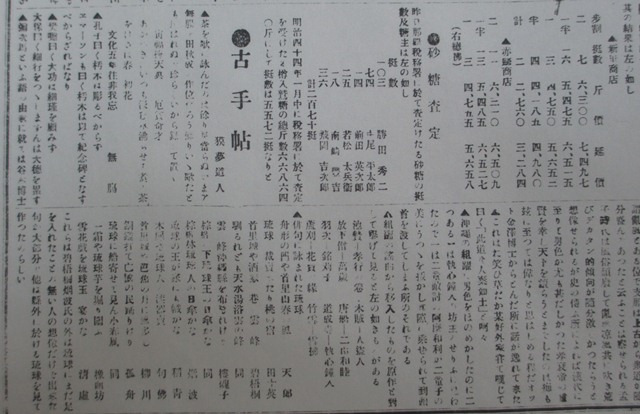
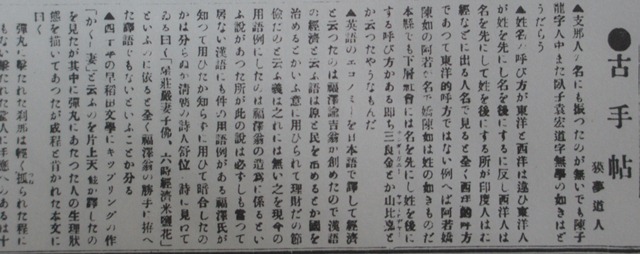
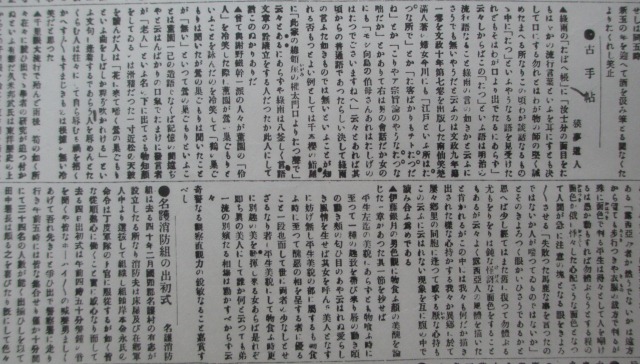
1月10日 『沖縄毎日新聞』獏夢道人(末吉安恭)「古手帖ー緑雨の『おぼへ帳』に・・・」
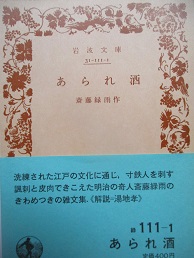

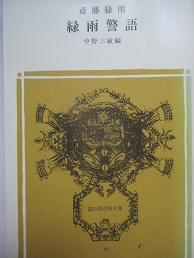
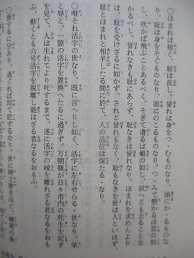
1939年8月 斎藤緑雨『あられ酒』岩波文庫/1991年7月 斎藤緑雨(編・中野三敏)『緑雨警語』冨山房百科文庫
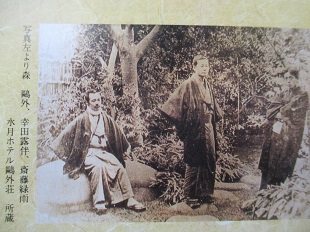

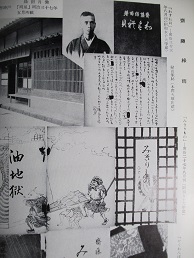
三人冗語ー森鷗外主宰の雑誌《めさまし草》第3~7号(1896年3月~7月)において,鷗外,幸田露伴,斎藤緑雨の3人が行った作品合評。〈頭取(とうどり)〉(鷗外)による作品紹介に続いて,〈ひいき〉〈さし出〉などの変名の人物が批評する形式をとる,最初の匿名座談会形式の文芸時評。当時の批評界の権威として,多くの作品を辛辣に批判したなかで,樋口一葉の《たけくらべ》に対する批評(第4号)は,この小説を絶賛し,彼女の文名を一躍高めたことで有名である。 /1957年12月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書7』「尾崎紅葉 落合直文 齋藤緑雨 原抱一庵 小泉八雲」昭和女子大学光葉会
写真ー1983年4月 『師父 志喜屋孝信』志喜屋孝信先生遺徳顕彰事業期成会 志喜屋孝信(1884年4月19日~1955年1月26日)〇1904年3月、沖縄県立中学校卒業、志喜屋孝信、川平朝令、山川文信、久高将旺、山田有登。4月ー志喜屋孝信、広島高等師範学校(数物化学科)入学。このころ内村鑑三を愛読。玉川学園の創始者小原国芳と親交。1908年3月卒業。4月、岡山県金光中学校に奉職。岡山出身の山室軍平の思想に親近感を抱く。12月、熊本県立鹿本中学校に転任。1911年12月、沖縄県立第二中学校に赴任。1924年3月、校長に就任。1936年3月、二中校長辞し、私立開南中学校を創設、理事長兼校長となる。
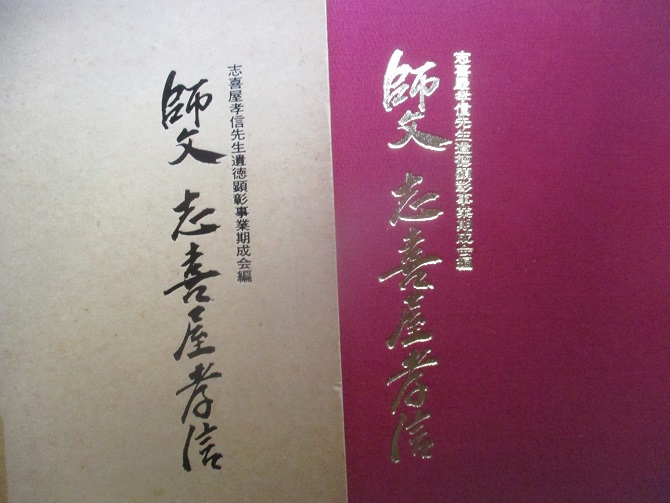
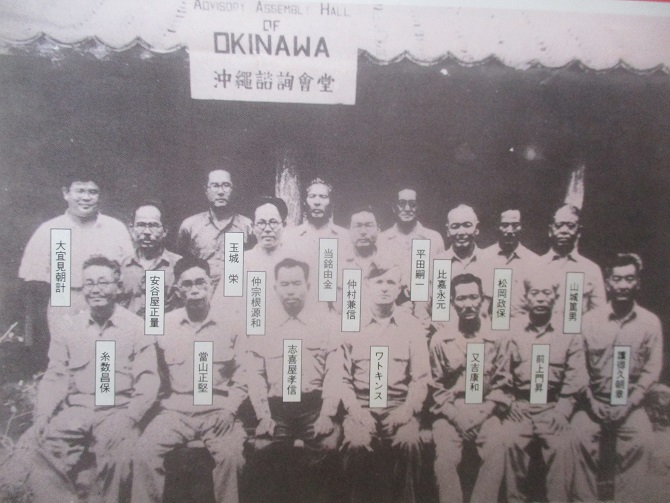
写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。
写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳
写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

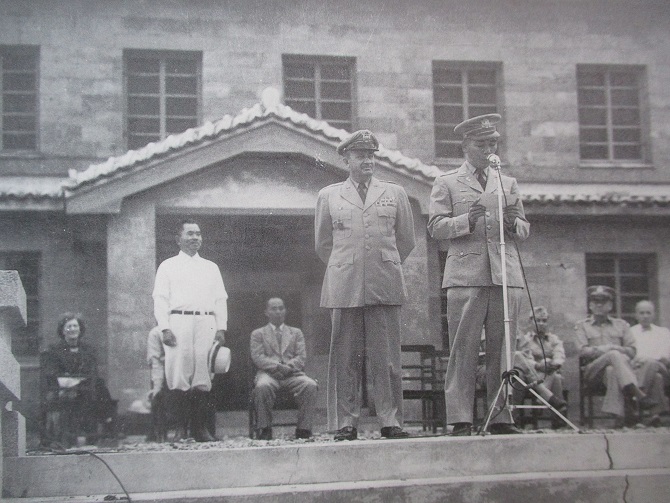
本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。
昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。
1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。
1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。
1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」
1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。
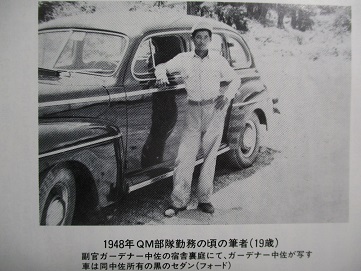
1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号
〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。
1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

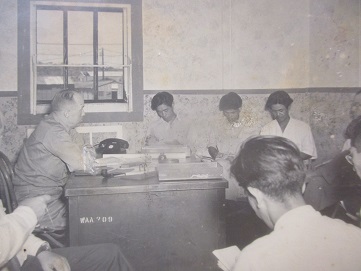
写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

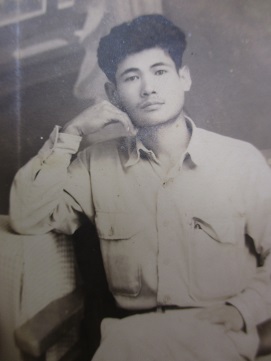
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて


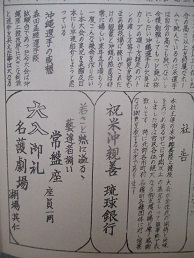
1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号
1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。
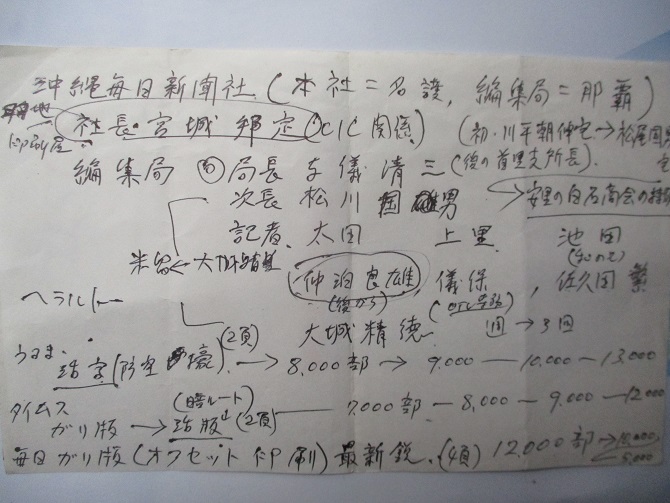
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展
1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。


写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳
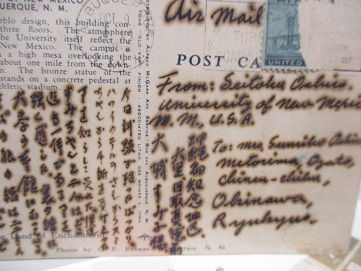
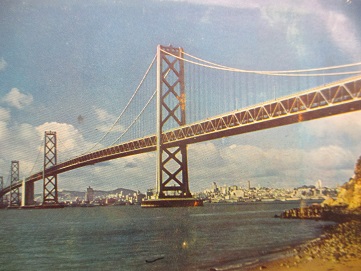
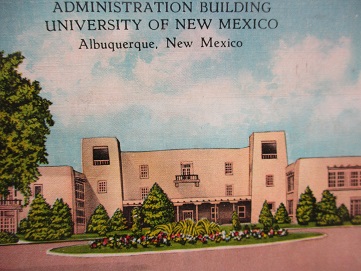

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳


1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山
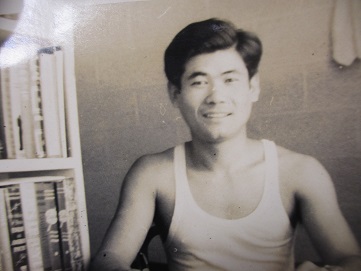

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順
ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」
1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
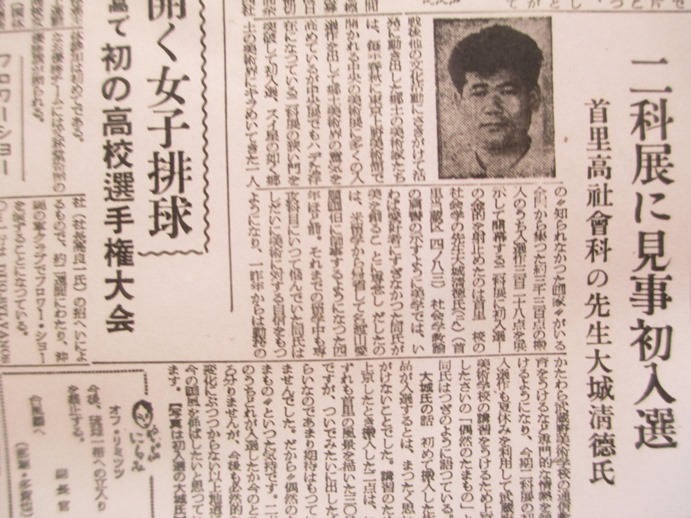
1956年9月1日『琉球新報』

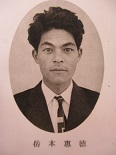
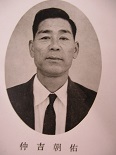
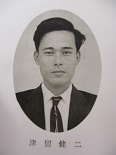
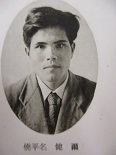
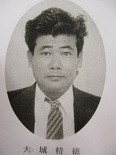
首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク
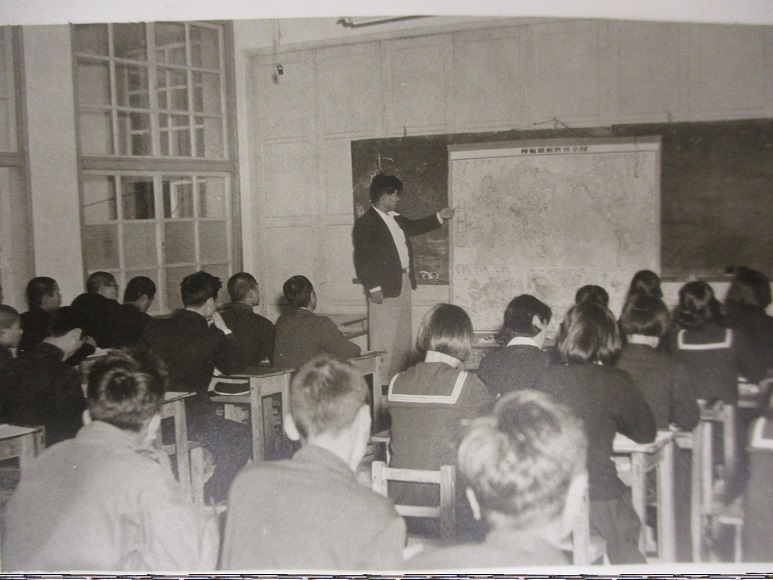
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

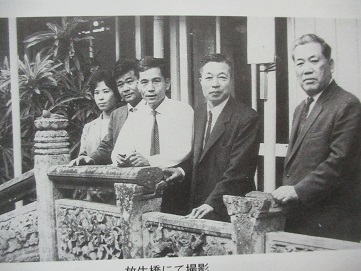
左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』
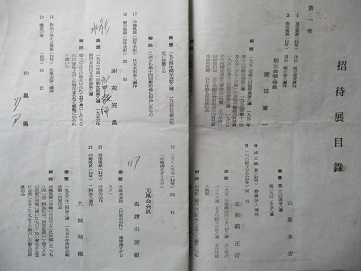
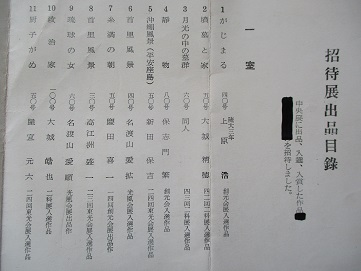
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
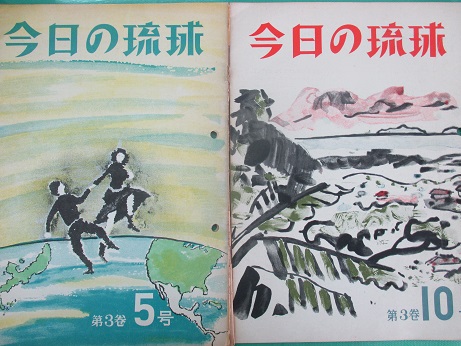
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

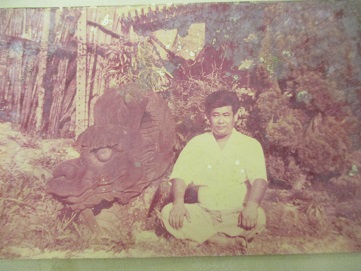


1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて
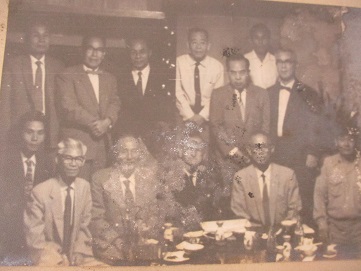

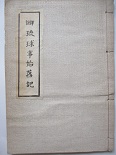




1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。
1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)
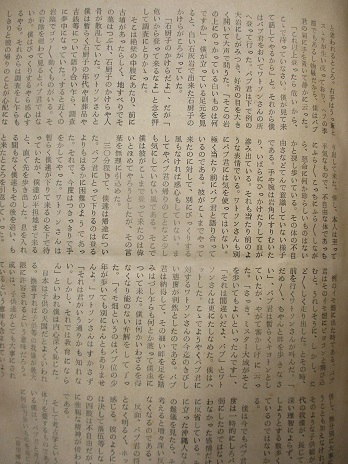
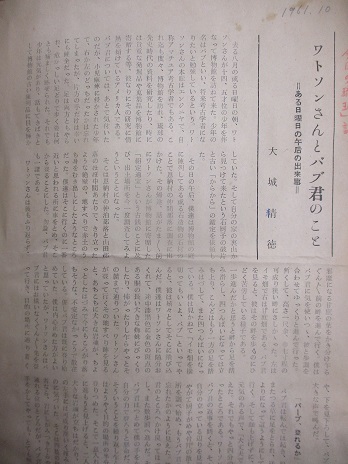
1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」
1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。
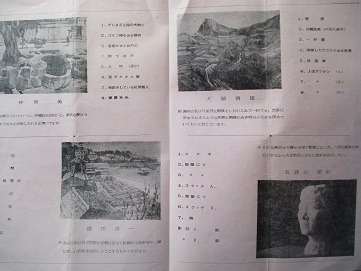
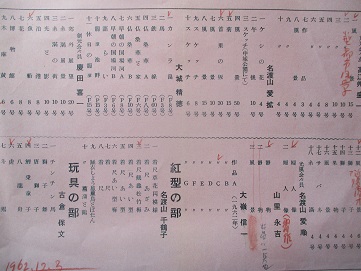
1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館
1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。
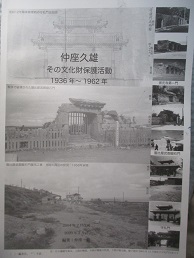
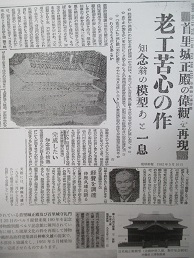
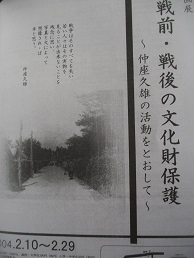
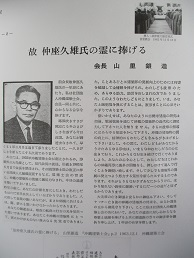
【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』
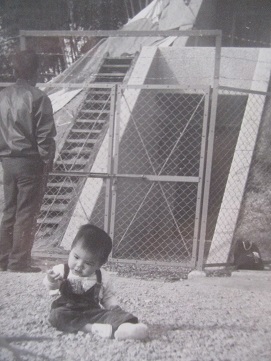
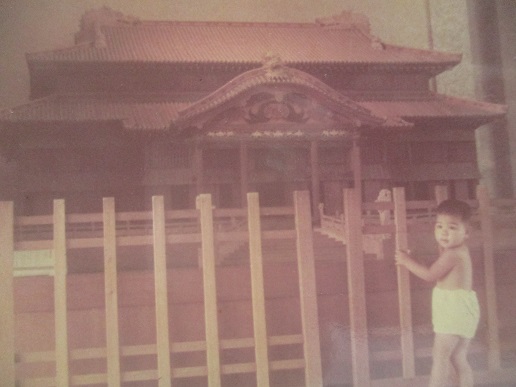
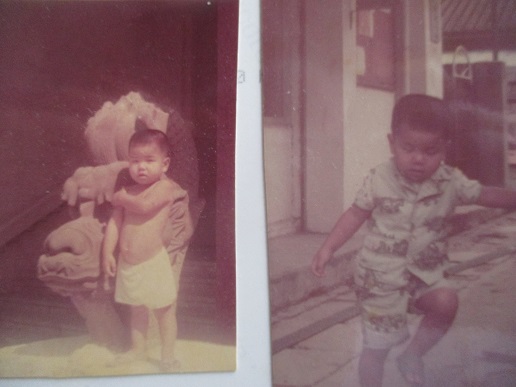
【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

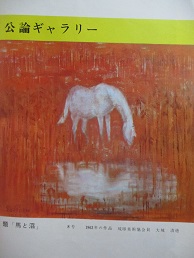
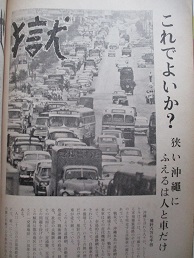
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
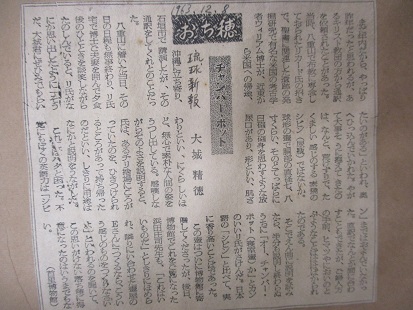
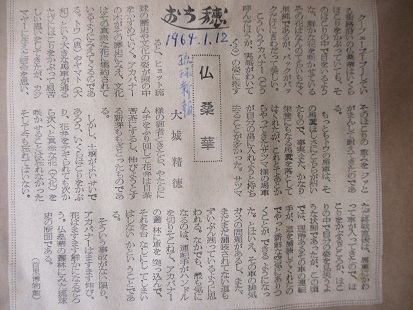
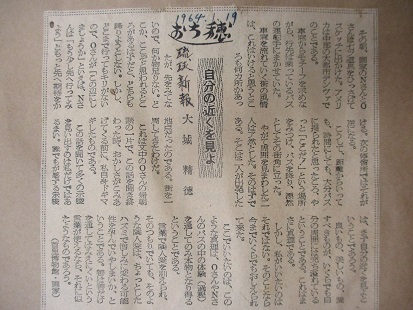
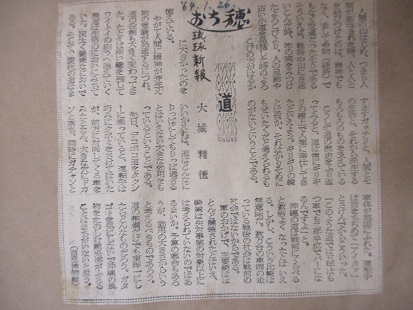
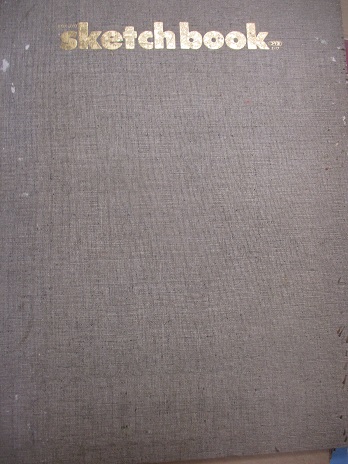

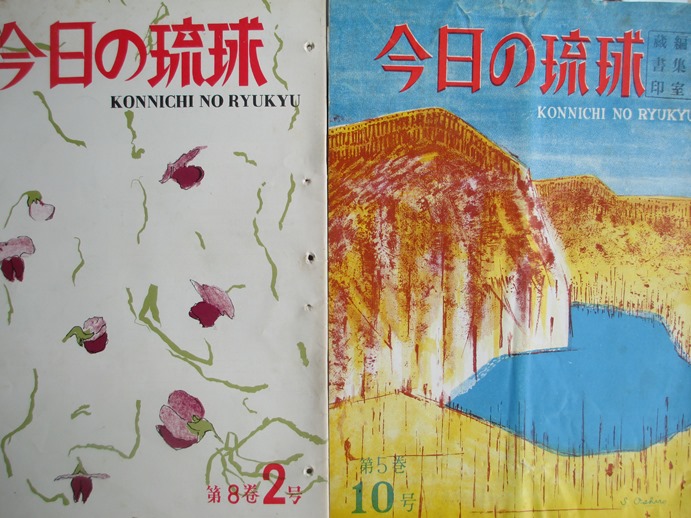
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」
1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。
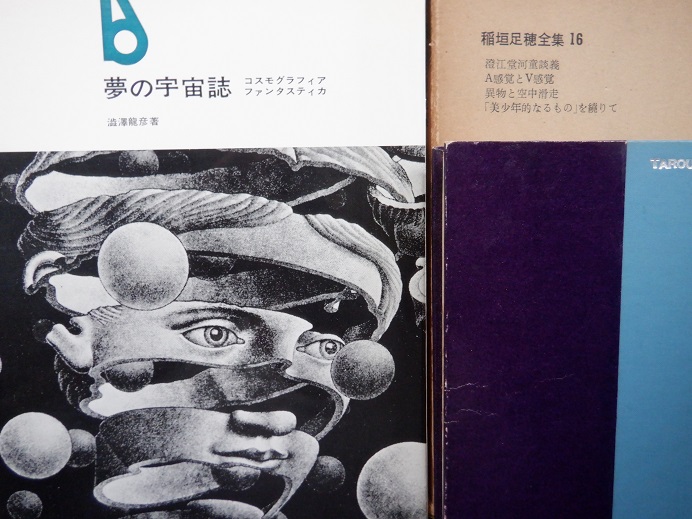
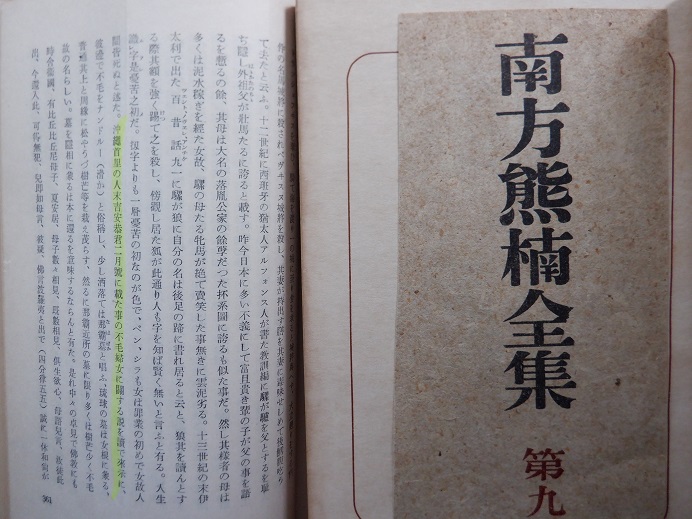
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
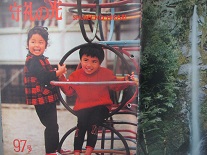
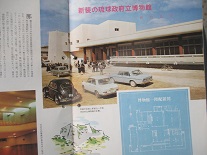
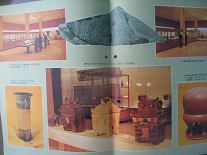

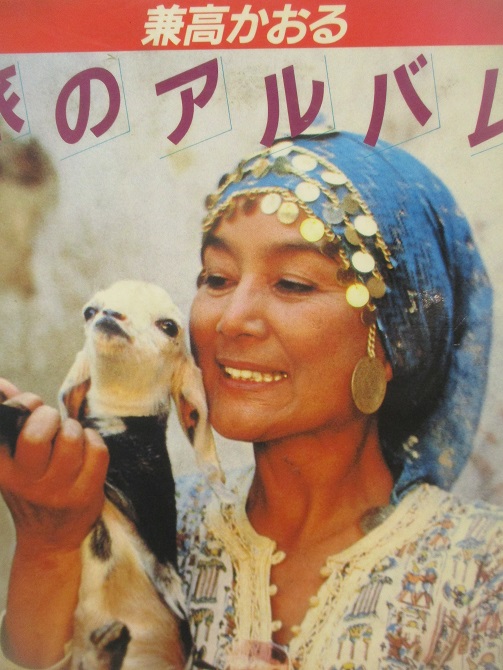
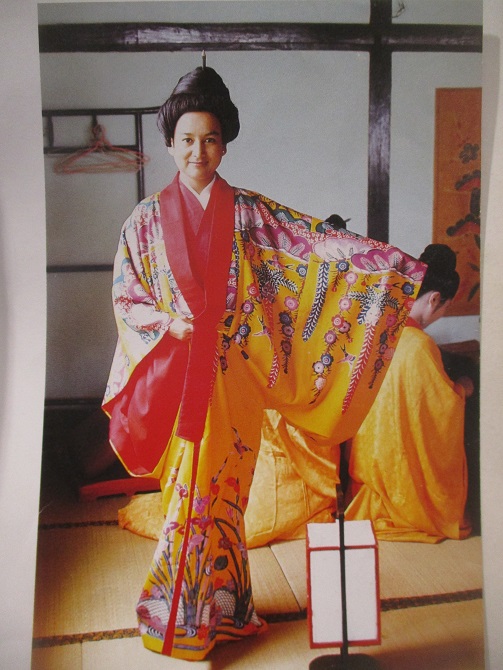
1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社
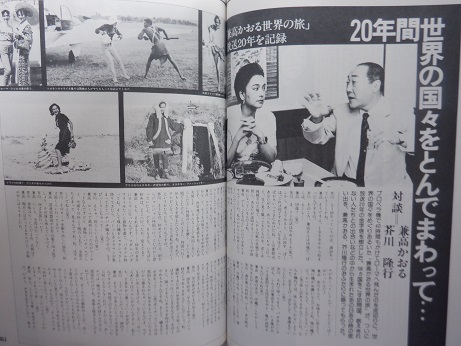
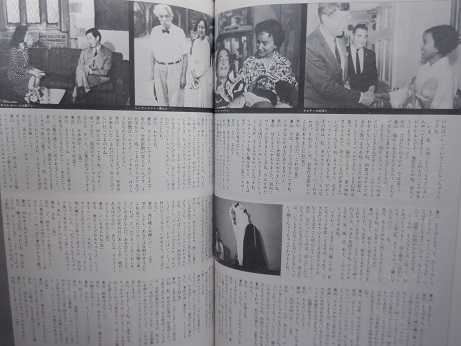
1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号
1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」
1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。


1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会
1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足
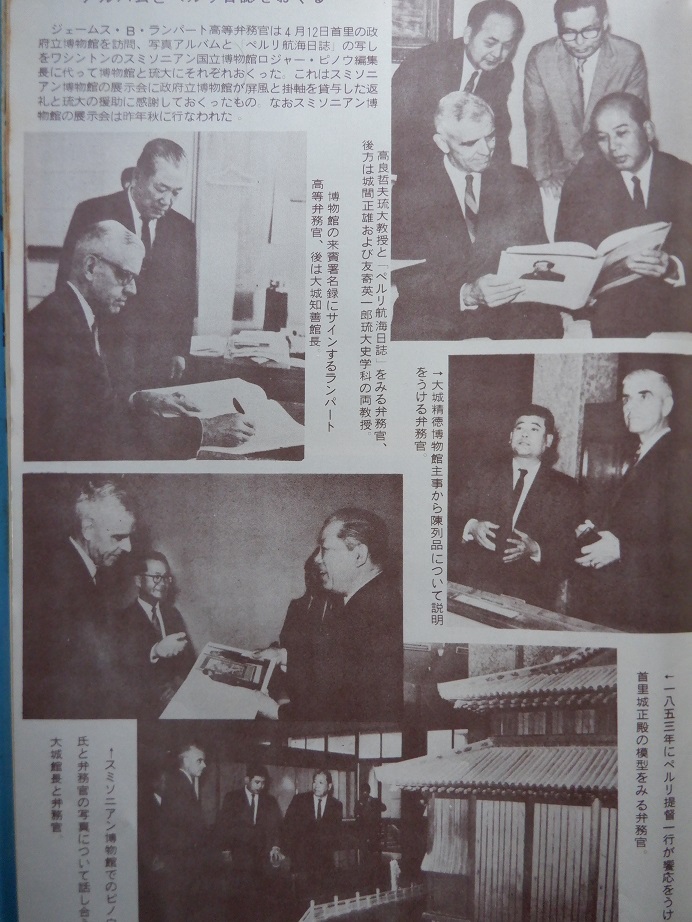
1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社
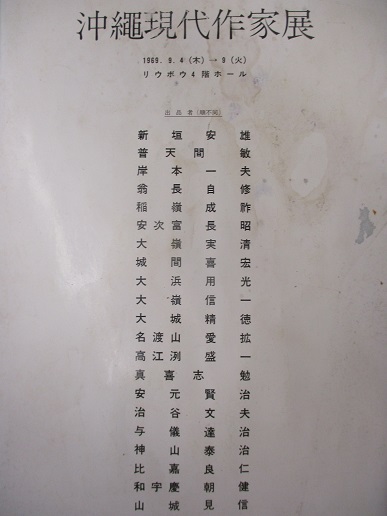
1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」
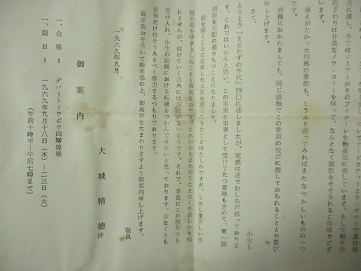
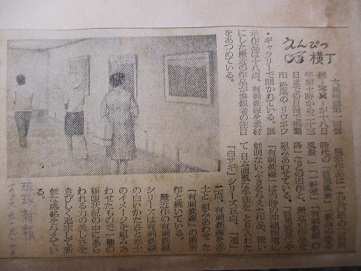
1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」
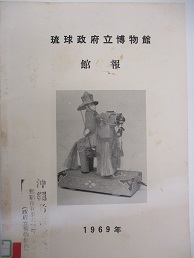
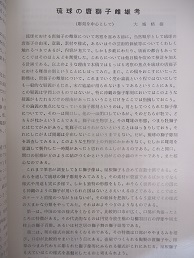
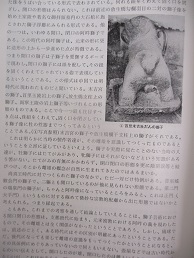
1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」
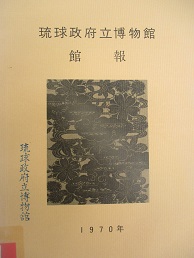
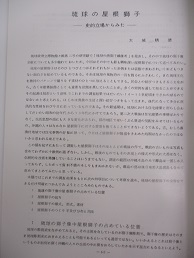
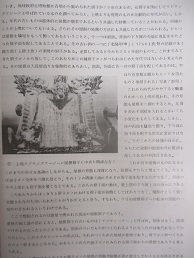
1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社
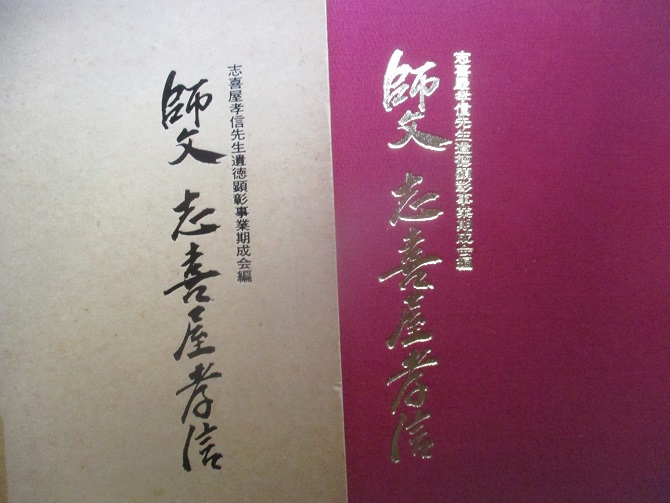
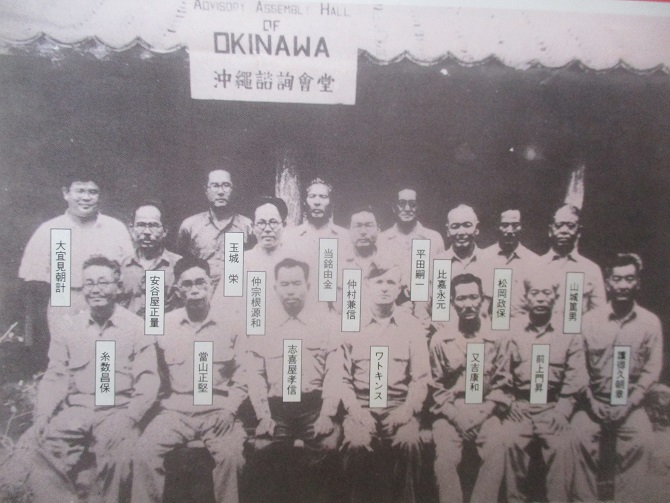
写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。
写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳
写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

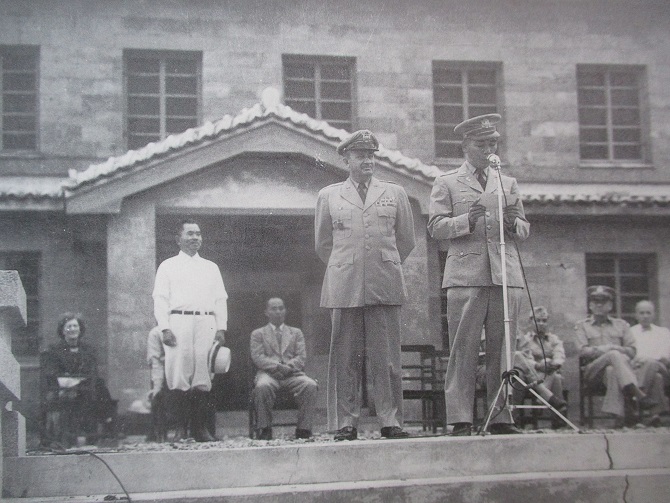
本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。
昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。
1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。
1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。
1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」
1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。
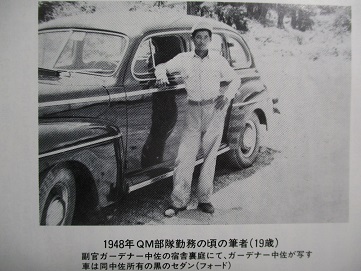
1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号
〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。
1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

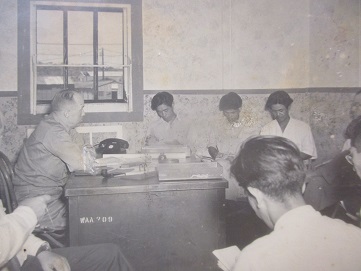
写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

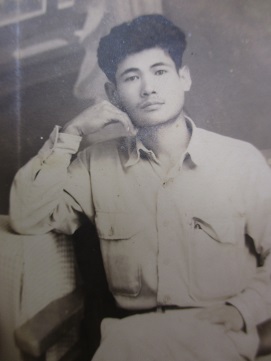
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて


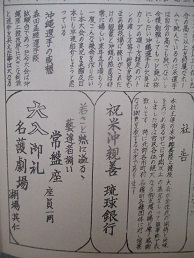
1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号
1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。
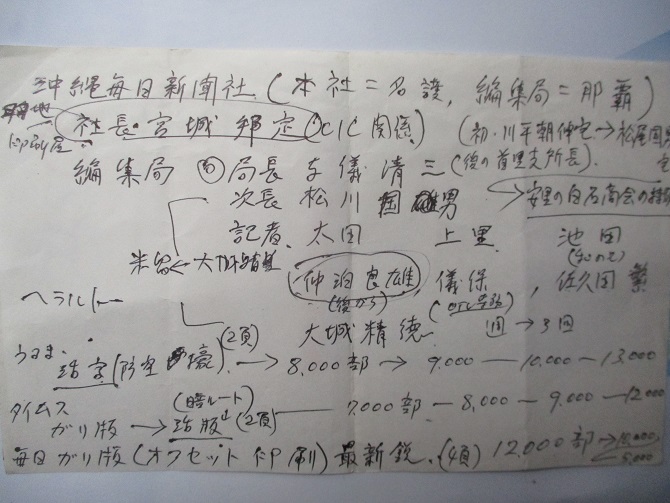
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展
1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。


写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳
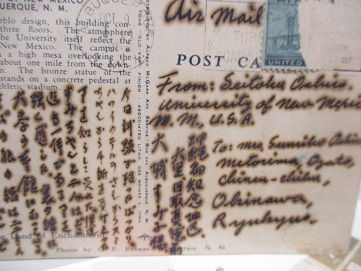
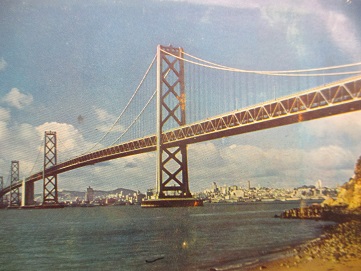
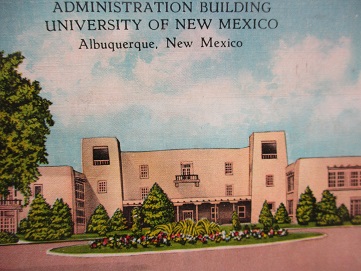

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳


1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山
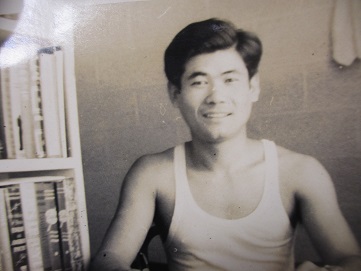

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順
ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」
1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
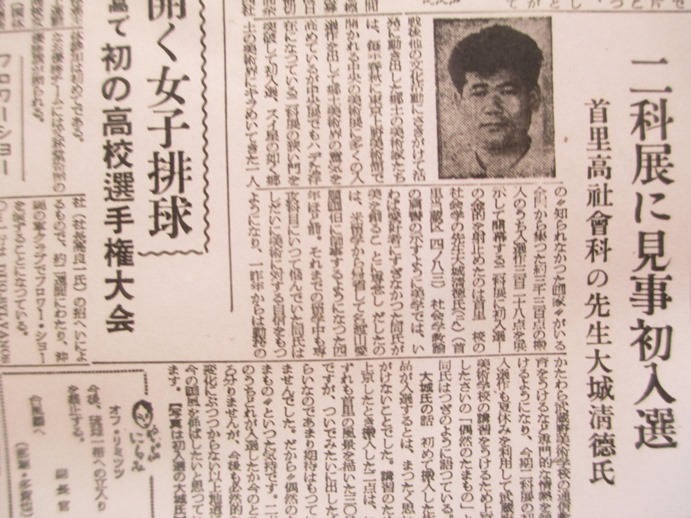
1956年9月1日『琉球新報』

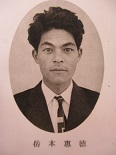
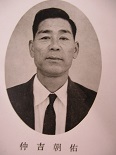
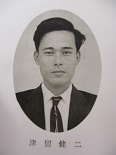
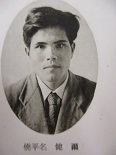
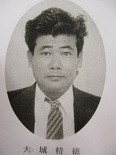
首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク
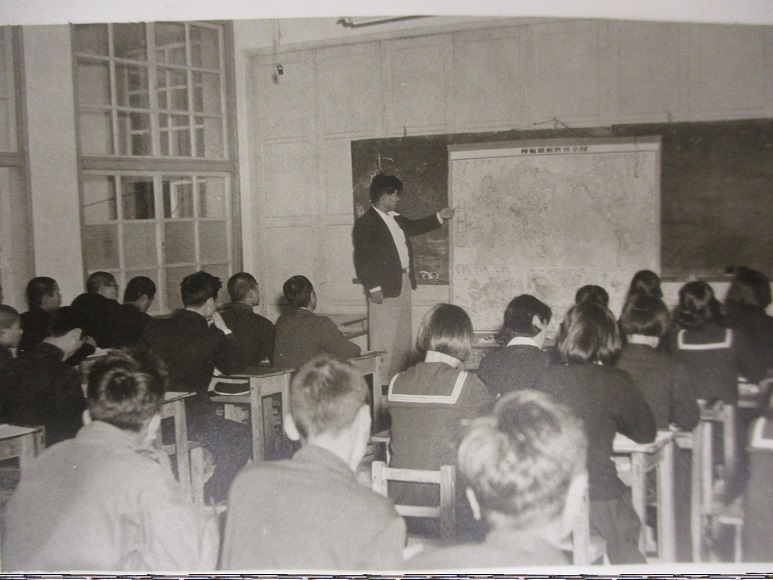
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

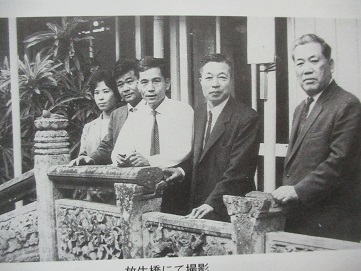
左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』
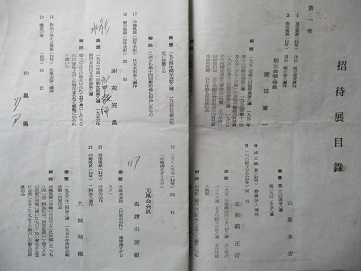
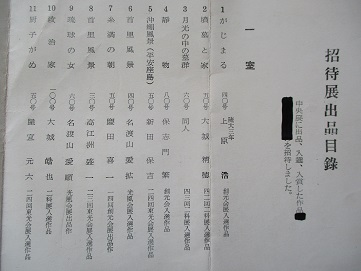
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
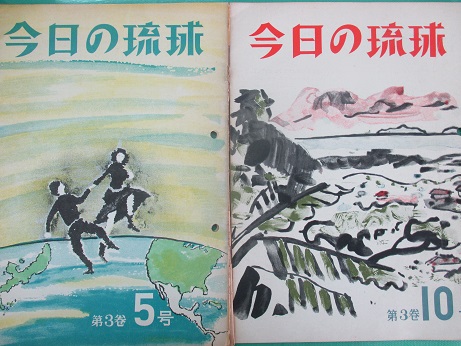
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

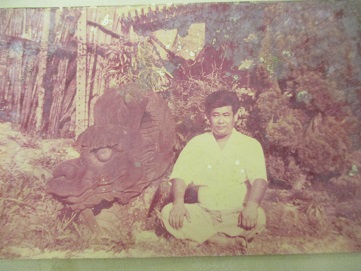


1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて
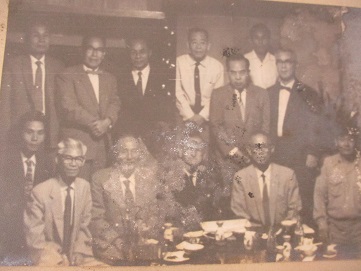

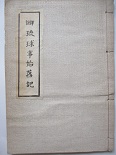




1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。
1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)
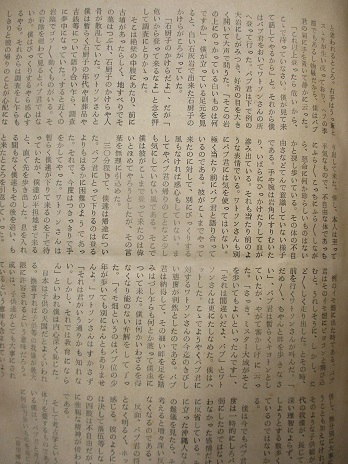
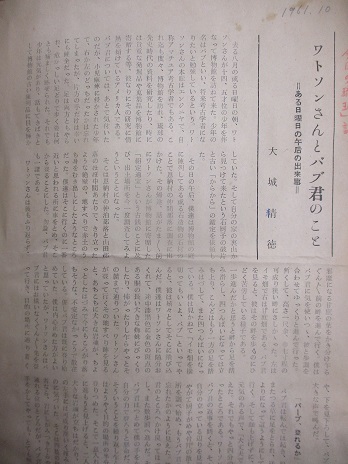
1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」
1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。
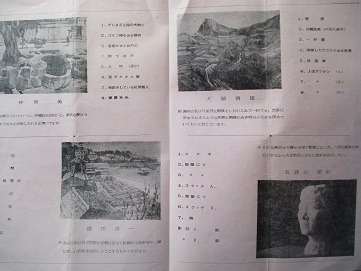
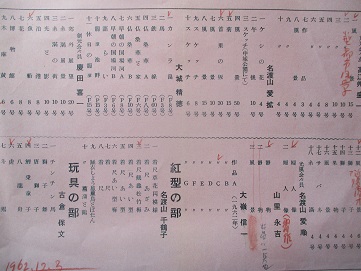
1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館
1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。
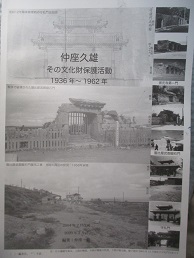
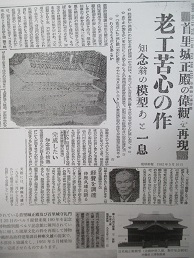
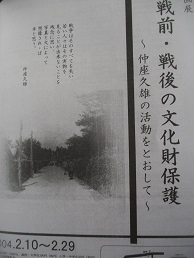
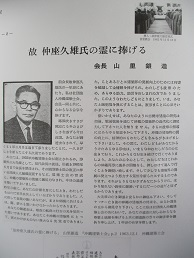
【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』
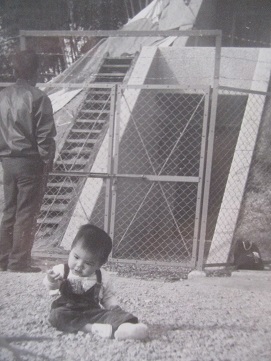
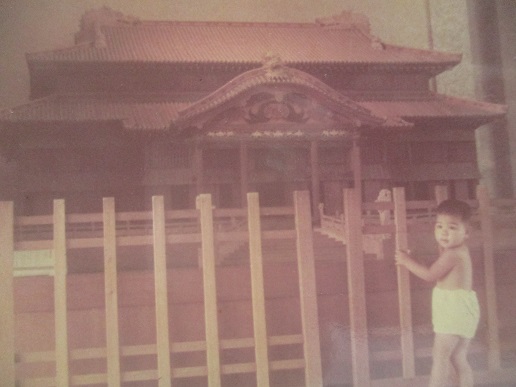
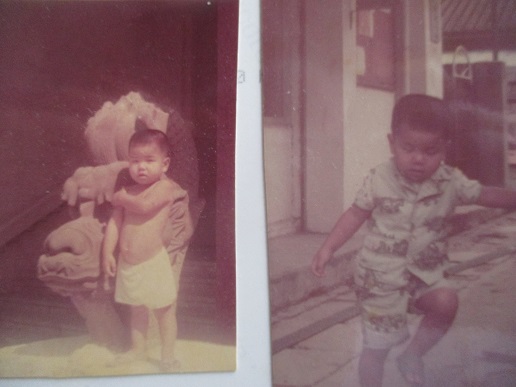
【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

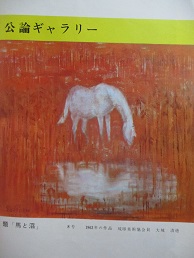
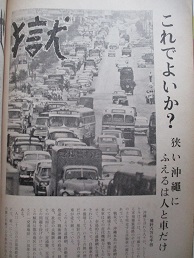
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
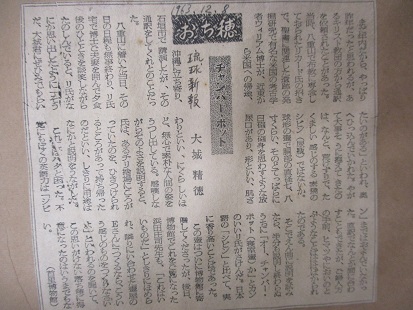
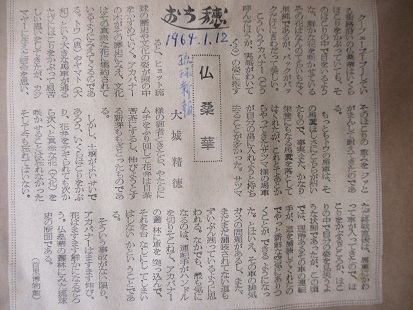
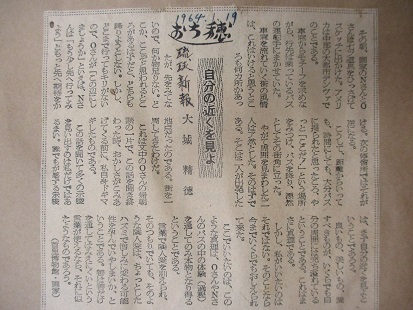
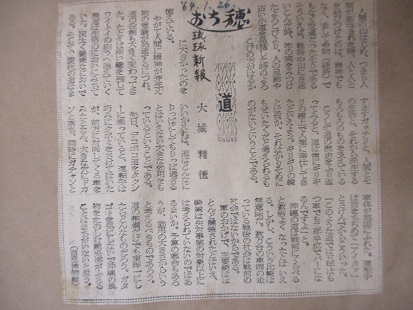
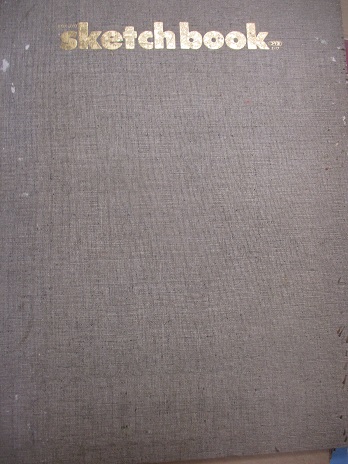

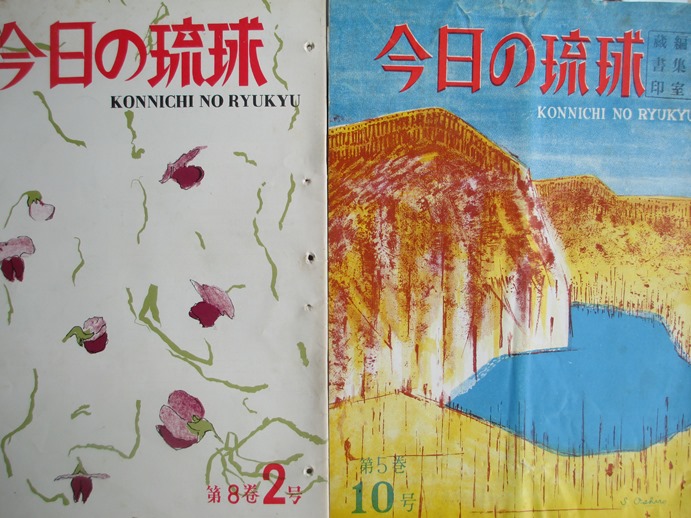
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」
1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。
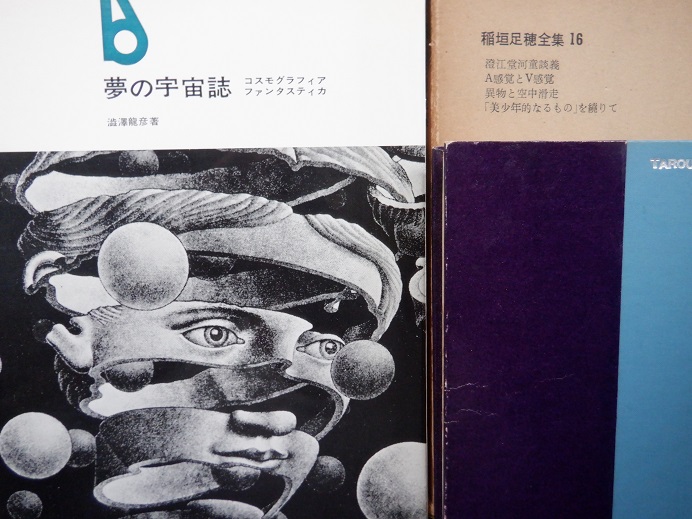
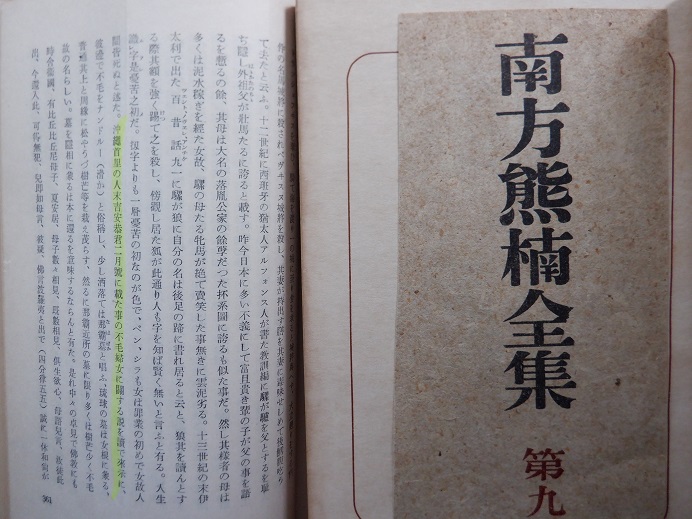
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
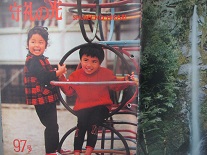
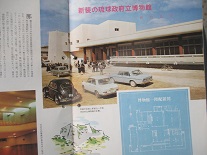
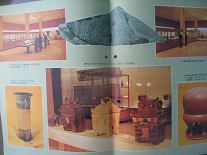

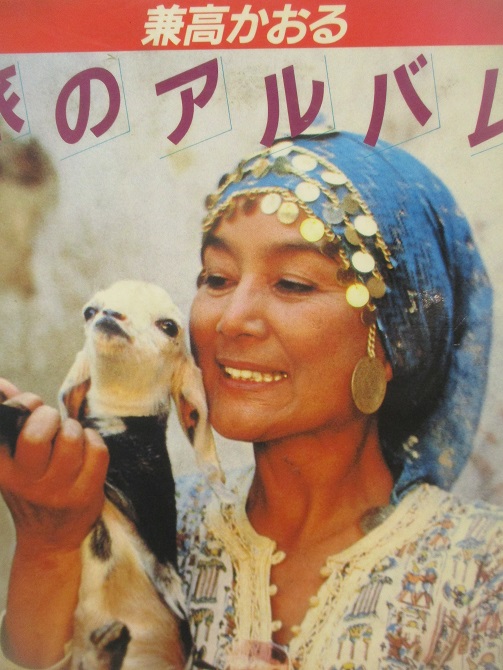
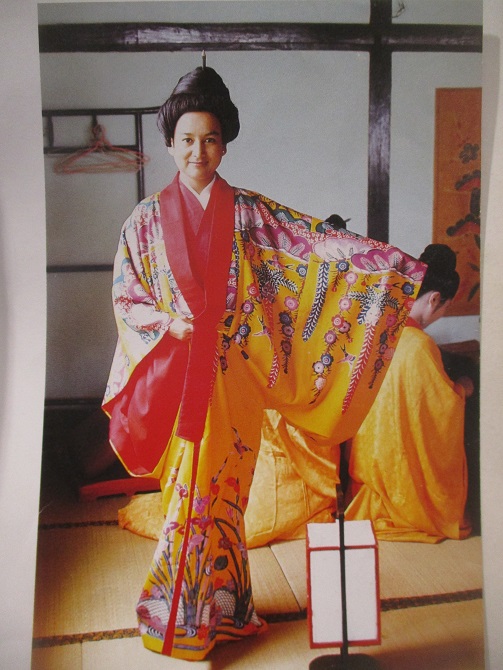
1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社
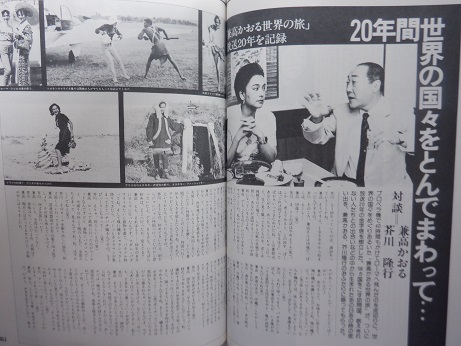
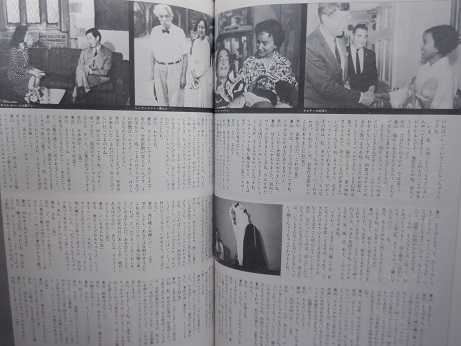
1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号
1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」
1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。


1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会
1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足
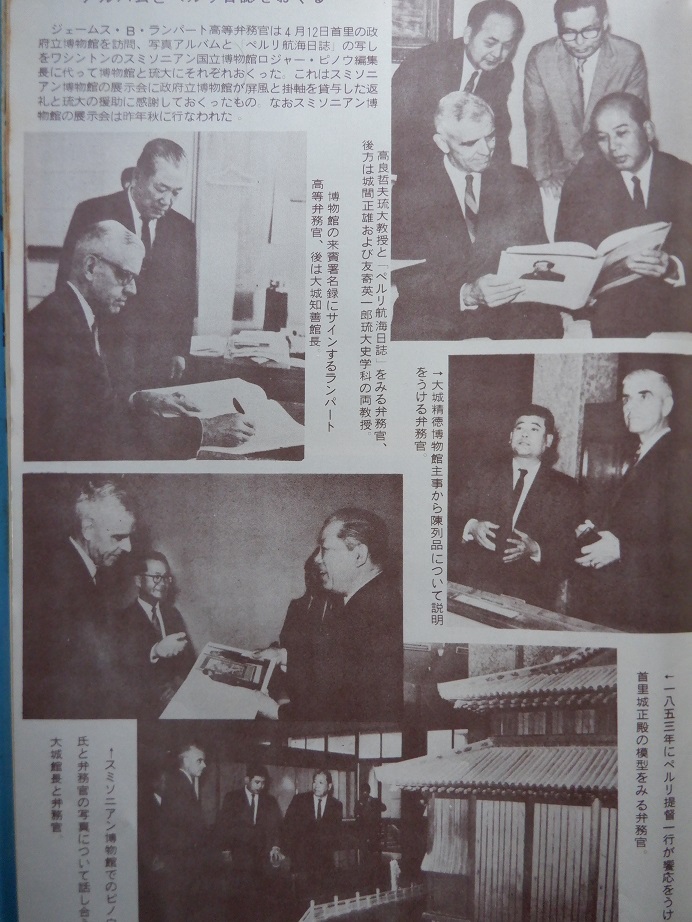
1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社
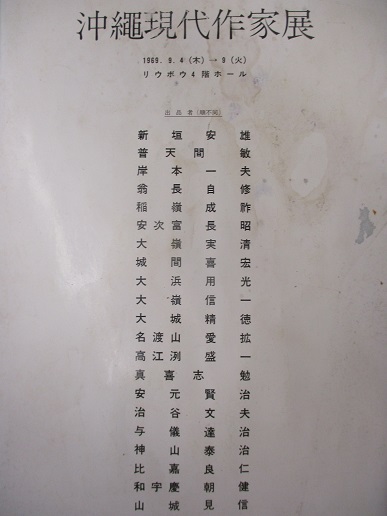
1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」
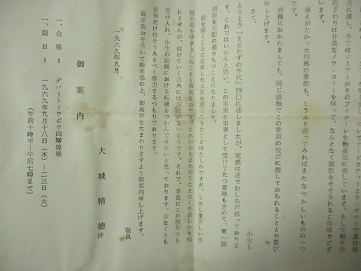
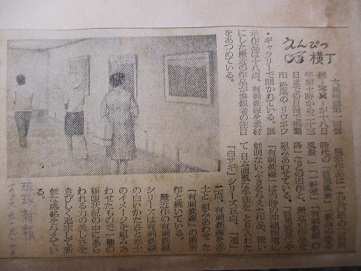
1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」
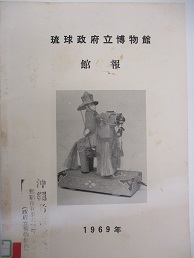
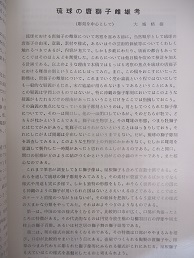
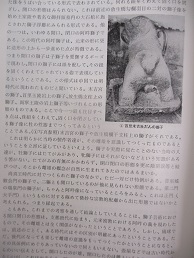
1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」
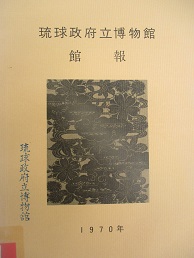
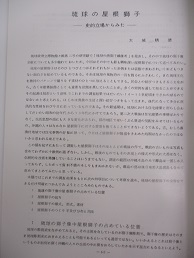
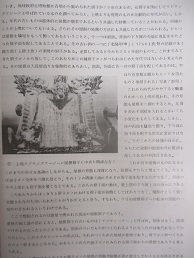
1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社
01/06: 雑誌『おきなわ』(復刻版)不二出版
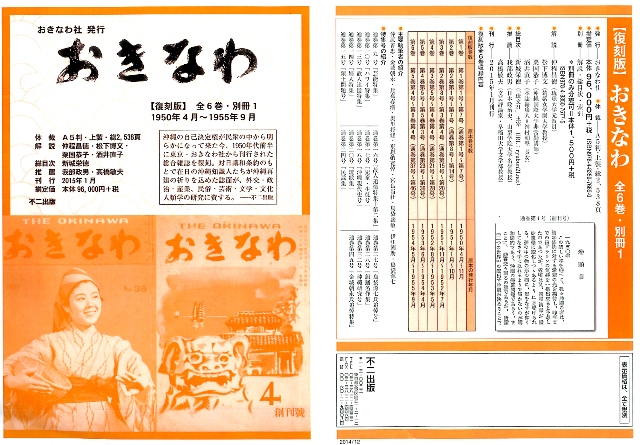
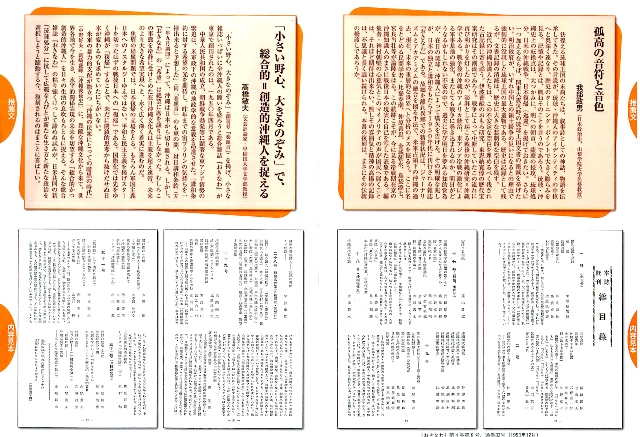
雑誌『おきなわ』第2号に「ハガキ回答ー出郷の日」に宮城聡と共にレッドパージ①直前の松本三益の回答がある「1、大正10年4月頃/1、多分大球丸/1、出稼のため/1、とにかく勉強したい/失業少年」。
雑誌『おきなわ』第3号には松本の親族の真栄田勝朗「琉球芝居の思い出(中座の巻)」が載っている。私は註に「著に『琉球芝居物語』(青磁社、1981)。戦前、大阪で『大阪球陽新報』発行、伊波冬子は妹」と記した。
①レッドパージ(red purge)ー1950年5月3日、マッカーサーは日本共産党の非合法化を示唆し、5月30日には皇居前広場において日本共産党指揮下の大衆と占領軍が衝突(人民広場事件)、6月6日に徳田球一ほか日本共産党中央委員24人、及び機関紙「アカハタ」幹部といわれた人物を公職追放、アカハタを停刊処分にした。同年7月には9人の共産党幹部について団体等規正令に基づく政府の出頭命令を拒否したとして団体等規正令違反容疑で逮捕状が出た(逮捕状が出た9人の共産党幹部は地下潜行し、一部は中国に亡命した)。こうした流れのなかで、7月以降はGHQの勧告及び、9月の日本政府の閣議決定により、報道機関や官公庁や教育機関や大企業などでも共産系の追放(退職)が行われていった(なお、銀行業界では共産系の追放が最小限度に留まった例や、大学では共産系の追放が殆ど行われなかった例もあった)。
当時の日本共産党は1月のコミンフォルム批判(平和革命論を否定)により、徳田を中心とする「所感派」と宮本顕治を中心とする「国際派」に分裂した状態だったこともあり、組織的な抵抗もほとんどみられなかった。この間の6月25日には朝鮮戦争が勃発し、「共産主義の脅威」が公然と語られるようになった。→ウィキペディア