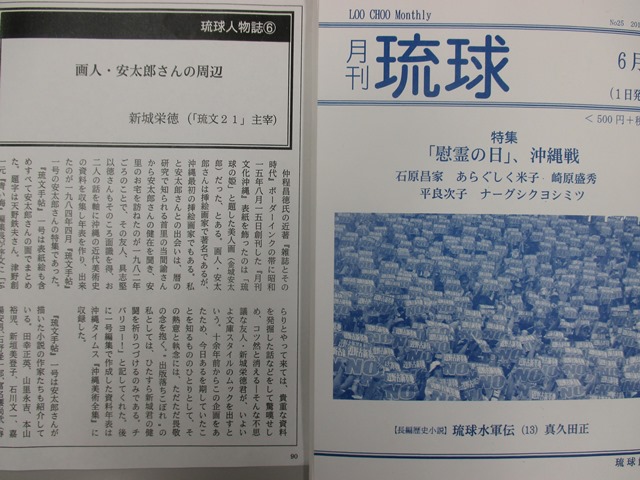
2015年6月『月刊琉球』 <500円+消費税> Ryukyu企画〒901-2226 宜野湾市嘉数4-17-16 ☎098-943-6945 FAX098-943-6947
①1940年8月 『月刊文化沖縄』創刊号
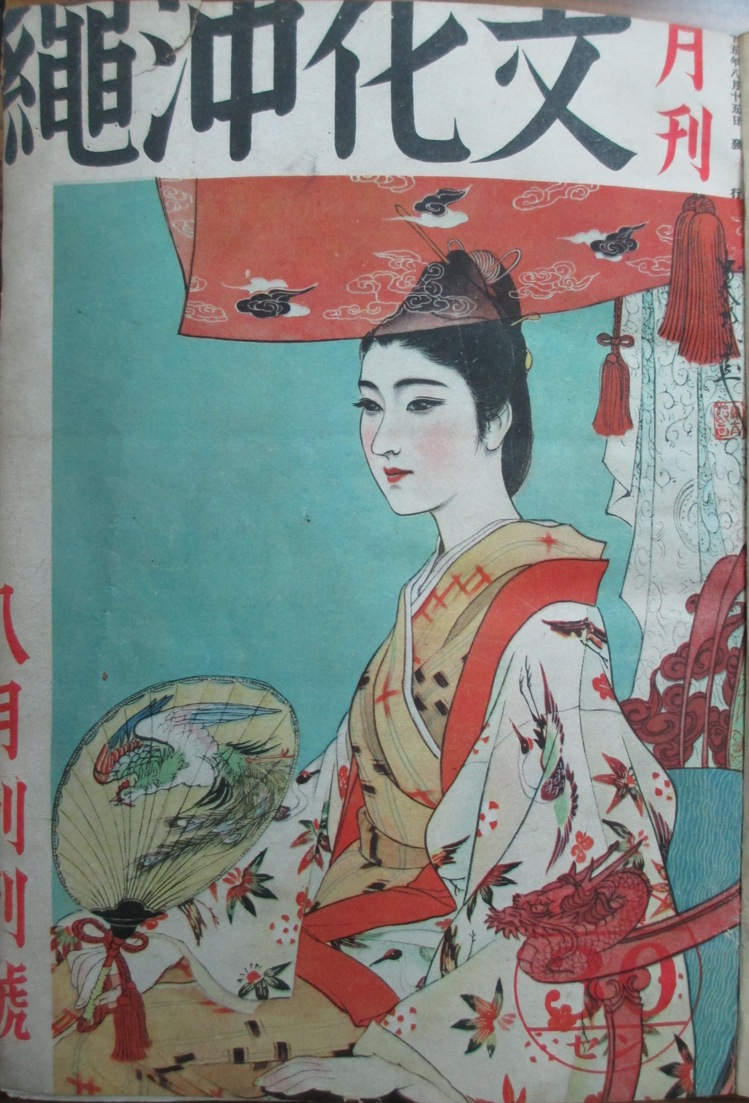
1940年10月号の表紙絵も創刊号と同じ金城安太郎「琉球の姫」
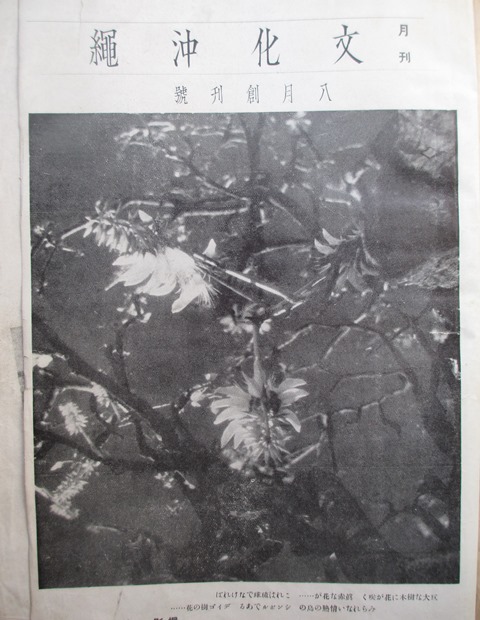
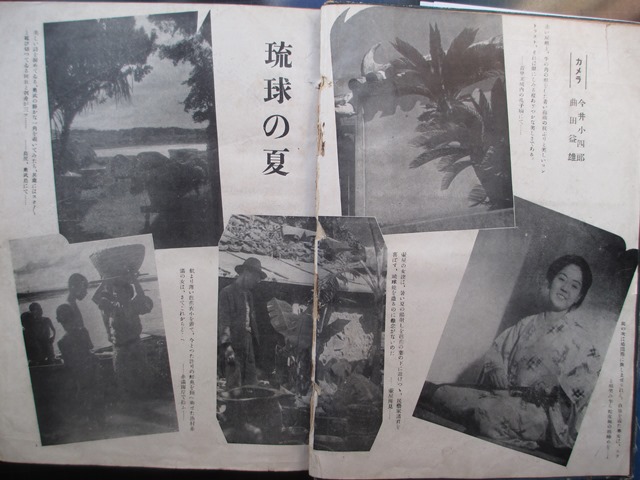


沖縄朝日新聞社前でー左が金城安太郎、本山裕児
=祝 創 刊=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①上山草人をめぐる会(東京市淀橋区東大久保2ノ278) 三村伸太郎・川崎 弘子・山本礼三郎・沼波功雄・前沢末弥・上山草人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 表紙裏
特輯グラビヤ「デイゴ樹の花」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・撮影/今井小四郎・・・・・・・・・・・・(1)
特輯グラビヤ・琉球の夏「蘇鉄ー首里王城内の孔子廟にて」「美女ー蛇皮線の根締」「壷屋所見」「島尻、奥武島にて」「鮮魚を頭へ乗せた糸満の女」「琉球美人」・・・・撮影/今井小四郎、曲田益雄・・・(2)(3)(4)
目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)
郷土の映画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北川鉄夫・全日本映画人連盟書記長 6ー8
琉球研究資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・N・O・N 8
沖縄語彙(絶筆)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・馬天居士 9ー11
初夏の故郷へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊波南哲 11-12
蛙鳴蝉噪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本山裕児 13
東北方言の調査を終りて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮 14-15
日劇の『八重山群島』を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内田岐三雄 15
あの頃の話・琉球の佐倉宗五郎(城間正安)・・・・・・・・・・・・・大城朝貞 16-19
文化沖縄抄/映画鑑賞会生る・ロードショウ・石井みどり・沖縄の姿・土と兵隊・海洋飛躍史・標準語問題 18

1940年5月11日『琉球新報』
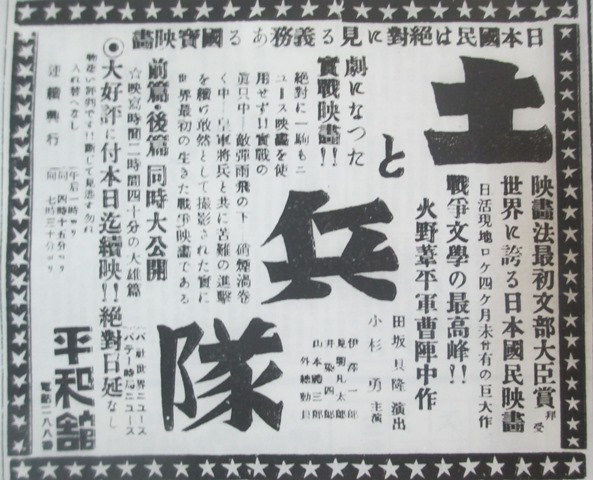
1940年6月20日『琉球新報』
琉球歴史読本・大章 天孫子時代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石川文一 20-21
琉球王国『御法條』より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
読切時代小説・復習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石川文一/挿絵・金城安太郎 22-32
編輯の弁


上山草人 かみやま-そうじん
1884-1954 大正-昭和時代の映画俳優。
明治17年1月30日生まれ。45年近代劇協会設立に参加。新劇俳優として活躍後,大正8年渡米し,ハリウッドで「バグダッドの盗賊」などおおくの映画に出演。昭和4年帰国後,「赤西蠣太(かきた)」「七人の侍」などに脇役で出演。昭和29年7月28日死去。70歳。宮城県出身。東京美術学校(現東京芸大)中退。本名は三田貞(ただし)。→コトバンク
1939 昭和14年4.5. 映画法公布。全日本映画人連盟に統合される。→日本映画監督協会
○6月22日 石川和男ー今、思い出したのですが、父、石川逢正は首里第二高等小学校を卒業して勤めた向春商会印刷部に居た頃、当時(多分昭和8~10年頃)、垣花にお住まいの金城安太郎氏のお宅に、東町から自転車に乗ってイラスト原稿を貰いに行った、と言っていました。だから僕は以前から金城氏の名前だけは知っていました。又、沖縄向学の先代校長名城政治郎氏の父君がよく、教材の印刷の依頼に来ていたとも言っていました。沖縄で最も古い予備校なのだと思います。
●は未確認
●北川 鉄夫(きたがわ てつお、1907年(明治40年) - 1992年)は、日本の映画評論家。本名は西村龍三。北川鉄夫とは、京都宇治の花やしきの北側を宇治川が流れているところから「北川」、山本宣治追悼歌の歌詞「鉄をも砕く」から「鉄」をとった筆名で、山本宣治の同志の田村敬男が命名した。→ウィキペディア
●内田岐三雄
映画評論家。(1901-45)府立第四中学校、第一高等学校、『キネマ旬報』創刊翌年に同人。東京帝国大学法学部卒。大学で飯島正と知り、『キネマ旬報』同人に誘う。1930年からパリに学ぶ。戦時下、疎開中の平塚の妻の実家で被災死。著書 「映画学入門」前衛書房 1928「欧米映画論」書林絢天洞 1935「モダン都市文学 9.モンタアジュ巴里 平凡社,1991.2→はてなキーワード
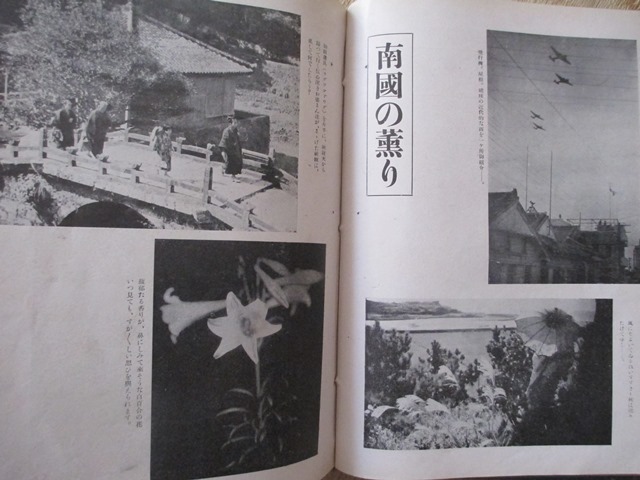
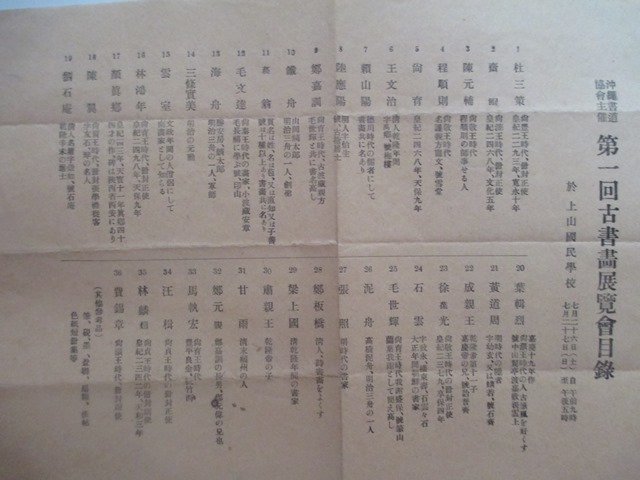
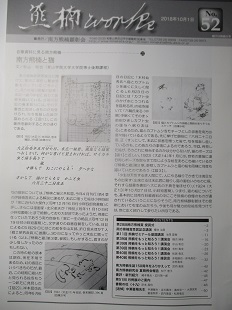


2018年10月4日-『熊楠ワークス』№52に「[追悼]中瀬喜陽先生」が載っている。飯倉照平氏の「先駆的な仕事」の追悼文も載っている。このお二人と神坂次郎氏は、1964年以降、南方熊楠と末吉麦門冬との交流を追及(研究ではない)する過程で出会った。私の熊楠イメージ形成には飯倉氏が1972年『別冊経済評論ー伝記特集・日本のアウトサイダー』に書いた熊楠伝が大半を占める。特に中瀬氏には氏の主宰する俳句雑誌『貝寄風』にエッセイを書かせてもらった。
俳句雑誌『貝寄風』
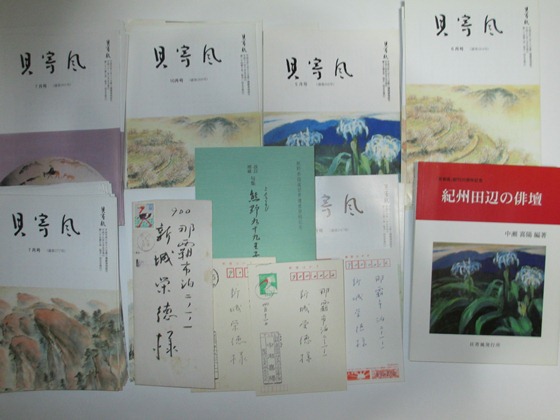
□27年間発行されてきた俳誌「貝寄風(かいよせ)」が、8月号(通巻326号)で終刊となる。主宰の中瀬喜陽さん(78)=和歌山県田辺市神子浜1丁目=は「残念に思うがやむを得なかった。後に残る活動ができた」と振り返っている。貝寄風は、中瀬さんが編集を担当していた俳誌「花蜜柑」の主宰者が亡くなり、中瀬さんが知人の田辺市の串上青蓑さんに声を掛け、1984年7月、串上さんを主宰者として創刊。以来月1回発行し、串上さんが亡くなった後に中瀬さんが主宰を引き継いだ。終刊を惜しむ声もあるが、中瀬さんの体調による理由でやむを得ず決めた。
俳誌には会員の俳句や、中瀬さんによる俳句や短歌の紹介などを掲載している。会員が俳句を作った経緯や思いを掲載しているコーナー「一句の周辺」は、作った俳句を見つめ直すきっかけにしようと設けた。俳句の作り方が分かるという声もあり、人気があるという。会員は創刊当初と同程度の約200人。田辺市や周辺町の住民を中心に、ふるさとについて知ることができるということで県外に住む県出身者らもいる。俳誌のほか、会員で句集「熊野九十九王子」や、創刊20周年を記念した「紀州田辺の俳壇」も発行してきた。また、中瀬さんが研究する南方熊楠を追悼する意味の「熊楠忌」は約10年前、俳人協会に季語として登録された。登録できた背景について中瀬さんは「貝寄風というグループの力があったからこそ」と話している。(→紀伊民報2012年5月19日土曜日)
『貝寄風』 - 新城栄徳「琉球の風」
Category: 99-未分類 Posted by: ryubun
「琉球の風」第1回は2005年4月発行で、作家・神坂次郎氏との出会いを記し「その昔、外様大名の島津家久が徳川家康の許可を得て琉球に出兵し支配下に置いた。そして中国との交易のため『琉球王国』はのこした。島津氏は琉球士族に対して琉球人らしく振舞うよう奨励した。琉球士族は歴史書編纂などで主体性の確立につとめた。清朝から琉球久米村の程順則が持ち帰った『六諭衍義』は島津を介して徳川吉宗に献上された。幕府によって『六諭衍義』は庶民教育の教科書として出版された。それが江戸文学への遠因ともなり滝沢馬琴のベストセラー小説『椿説弓張月』(北斎挿絵)にもつながる。また、清朝の使者歓待のため玉城朝薫がヤマト芸能を参考に『組踊』が生まれるなど新たな琉球文化が展開された」と記した。
平成17年12月 俳句誌『貝寄風』』(編集発行・中瀬喜陽)新城栄徳「琉球の風③末吉安恭と南方熊楠」
7月、立教大学の小峯和明氏と奈良女子大学の千本英史氏から南方熊楠特集『國文学』8月号を恵まれた。小峯氏は「熊楠と沖縄」を執筆され「それにしても、末吉安恭との文通が半年(1918年2月~9月)あまりでとだえてしまったのはなぜであろうか」と疑問を呈しておられる。千本氏は「等身大の熊楠へ」で「熊楠はいたずらに祀り上げるのでなく、その、すぐれた可能性を引き継いでいくことが求められている」としている。
そこで熊楠と末吉安恭の文通の周辺をみてみたい。柳田国男が『郷土研究』を創刊した1913年3月に柳田は伊波普猷に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡を送っている。程なく沖縄県庁では筆耕に『中山世譜』など写本を命じている。6月、黒頭巾・横山健堂が来沖し伊波普猷や安恭らと親しく交わり『大阪毎日新聞』に「薩摩と琉球」を連載。無論、沖縄の新聞にも転載された。
1914年に安恭らは同人雑誌『五人』を創刊、安恭は古手帖(抜書き)をもとに男色をテーマに「芭蕉の恋」を書いた。7月、伊波普猷、真境名安興らは県知事から沖縄史料編纂委員を拝命。1915年の1月に沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁から沖縄県立図書館に移された。主任は安恭の友人で同じ池城毛氏一門の真境名安興である。当然、先の『中山世譜』などは県立沖縄図書館のものとダブルことになる。安恭は安興から『中山世譜』『球陽』などの写本を譲り受けた。安恭は『球陽』などを引用して『琉球新報』に「定西法師と琉球」「琉球飢饉史」、朝鮮史料で「朝鮮史に見えたる古琉球」を書き琉球学の開拓にこれつとめた。
熊楠宛の書簡で安恭は前出の「芭蕉の恋」に関連して「芭蕉翁も男色を好みし由自ら云へりと鳴雪翁の説なりしが、芭蕉がそれを文章に書き著せるもの見当たらず候が、御承知に候はば、御示し下され度候」とある。いかにも見た目には学究的だがその気質は芸術家である。安恭は俳人として麦門冬、歌人として落紅、漢詩人として莫夢山人と号したが俳諧が気質に合っていたようだ。前出の古手帖には「芭蕉」「子規」「俳句に詠まれた琉球」「俳句の肉欲描写」「沖縄の組踊の男色」などが記されている。
安恭は熊楠と文通を通じてお互いに聞きたいことは殆ど聞いたと思う。文通が直接には途絶えても沖縄の事は安恭贈呈の『球陽』で当面間に合う。『日本及日本人』誌上では安恭は亡くなるまで熊楠と投稿仲間であった。1919年1月、折口信夫編集『土俗と伝説』には熊楠の「南方随筆」と並んで安恭の「沖縄書き留め」がある。しかも同年6月、安恭は安興らと「沖縄歴史地理談話会」を設置し活動に入り安恭も自ら企画・講演をなしその内容を新聞記者として、創刊メンバーとして『沖縄時事新報』にも書く忙しさである。
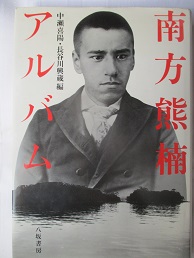
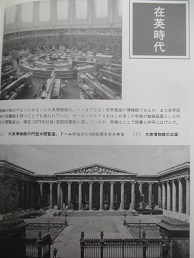
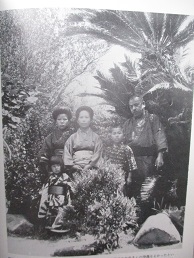
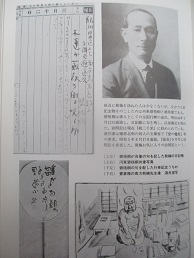
1990年6月 中瀬喜陽・長谷川興蔵編『南方熊楠アルバム』八坂書房
私の手元に中瀬喜陽さん編著『紀州田辺の俳壇』がある。序に「田辺に俳人が訪れたであろう最初を大淀三千風の『行脚文集』に依るのが従来の定説だった」とある。安恭も1917年9月の『日本及日本人』に「大淀三千風の日本行脚文集に『雨雲をなとかは横に寝さすらむ名は正直(ろく)な神風』といふ歌あり、ろくに正直といふ意味ありしか」と『行脚文集』を引用している。同じく中瀬さん共著『南方熊楠アルバム』の1911年3月・熊楠日記には河東碧梧桐俳句「木蓮が蘇鉄の側に咲く所」」と河東写真が並んでいる。碧梧桐は1910年5月に来沖し安恭の俳句は「将来有望」と述べた。
09/29: 世相ジャパン㊾
「くろねこの短語」2020年10月24日 (前略)ところで、年末年始休暇を延長・分散して、初詣などで予想される密を避けようって話が出てきたってね。「1月11日の成人の日まで休みを採るのも一案」てなことを新型コロナ感染症対策分科会が提言しているんだが、そりゃあ正社員はいいでしょうよ。でも、日給の非正規はどうなるんだ。休めば給料貰えないんだから、それこそ年越しテント村の再現ってことになりますよ。年末年始休暇の延長・分散なんてことが語られるほどコロナの先行きってのは誰にも見えていないないわけで、こんなんでオリンピックなんかやれるのかねえ。あっ、そうか・・・このところオリンピック中止とか2032年に先延ばしとかいろいろ噂が飛んでるけど、既にオリンピック中止が織り込み済みの政策ってわけか。妄想だけど。
「くろねこの短語」2020年10月19日 おかしな話だ。何がって、所信表明演説もしないで、国会を無視したままだってのに、特高顔の自称苦労人・カス総理が外遊したことだ。そうした視点をまったくスルーしたまま、「首相、初の外遊スタート」なんてヨイショ報道する新聞・TVもどうなってるんだろうねえ。
コロナ禍の真っ最中にあって、総理大臣が代わり、その直後に「学問の自由」を揺るがしかねない日本学術会議問題が勃発したってのに、国会が閉じたままってのがどれだけ異常なことか。そのくせ、携帯電話料金値下げだの、マイナンバーカードと免許証の一体化だの、地方銀行や中小企業の再編だの、個別な政策は国会での議論もなしに勝手に動き出している。(略)
「くろねこの短語」2020年10月18日 (前略)、いまのタイミングで処理水の海外放出なんてことが俎上に上がること自体おかしな話なのだ。本来なら、国会で議論すべきことなのに、特高顔の自称苦労人・カス総理は国会を開くこともなく、今週は総理就任後初の外遊へお出ましときたもんだ。
でもって、そんなカス総理に阿るように、大阪府知事のイソジン吉村君が「大阪湾で1発目を放出することが必要で、国からの要請があれば、協力すべきだと思う」だとさ。大阪湾に汚染処理水を垂れ流そうってんだが、こいつもまたカス総理と一緒で何でも自分一人の判断でできると勘違いしてるんだね。ひょっとして、イソジン混ぜて流すつもりだったりして・・・妄想ですよ。そう言えば、イソジン吉村君のオヤビンであるお子ちゃま・橋↓も「関西にも米軍の基地負担を」なんてことを口にして顰蹙を買ったことがある。子の親にしてこの子あり、ってなものか。
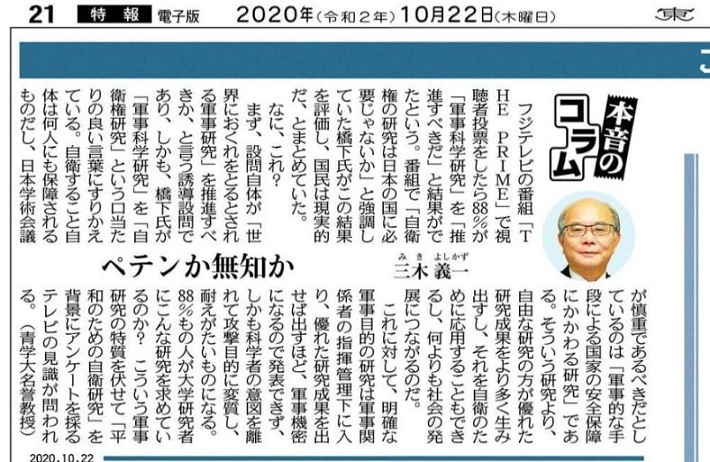
菅 義偉2012-01-28- 民主党は野党時代に政府の文書管理の不備を責め、情報公開を声高に叫んでいました。しかし政権交代後、政治主導の象徴とした政務三役会議など、政策決定過程の多くは非公開で議事録も作成されず、「密室政治」となっています。議事録作成という基本的な義務も果たさず、「誤った政治主導」をふりかざして恣意的に国家を運営する民主党には、政権を担う資格がないのは明らかです。
黒手人 2020年10月16日ーはいさい、やっちー!ちゅーぬ タイムスんかい、高良とぅ与那原恵が 講演・対談 すんでぃぬ 広告が ぬとーん。タイムス「首里城取材班」がやるはじ。14日ぬ タイムス記事や、まったくぬ 高良ぬ「露払い」! ちゅーぬ タイムス文化面かい ぬとーる 知念勇さん意見のー 正当やんやー。なまから うむしるく ないぐとぅ、んーちょーてぃ くぃみそーりよー。
「くろねこの短語」2020年10月14日 (前略)どうやら、警察官僚による官邸支配ってのが、カス政権の本質ってことのようだ。運転免許とマイナンバーカードの一体化なんてのも、警察官僚がバックについているからこそで、昨日のTBS『Nスタ』なんか臆面もなくそうした報道をしてましたからね。
日本学術会議問題は「学問の自由」に手を突っ込んだわけだけど、カス総理が必死こいている携帯電話の料金値下げってのは行きつくところは「表現の自由」への弾圧につながりかねないんだよね。なんとなれば、携帯電話料金ってのは電波の許認可に関わってくる問題で、許認可権を利用すれば放送局への規制も容易にできちゃうんだから。日本学術会議問題は警察国家への手始めで、メディアや一般大衆労働者諸君がどんな反応をするか試してるんじゃないのかねえ。
ところで、あっせん利得疑惑の布袋頭・甘利君が、「日本学術会議は中国の『千人計画』に協力している」ってデマを流したブログをこっそりと書き換えてたってね。睡眠障害とやらで国会から逃亡したように、なんとも姑息な野郎だこと。
2020-10-12 森美琴ちゃん誕生
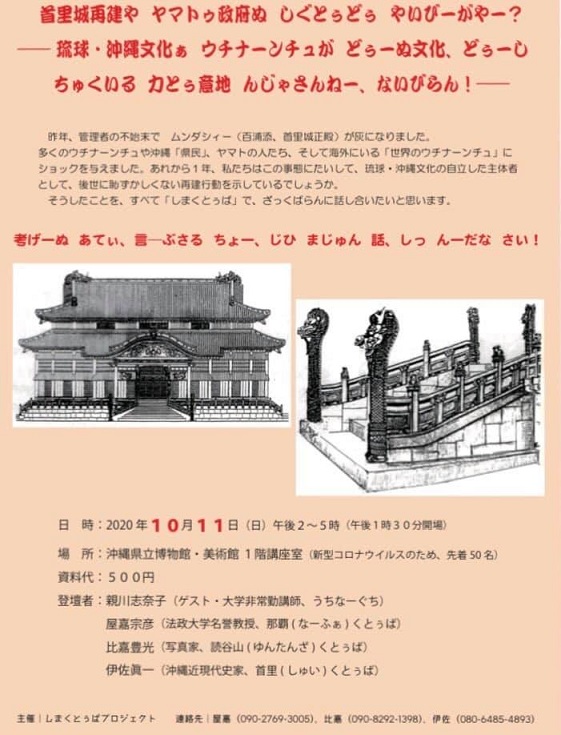
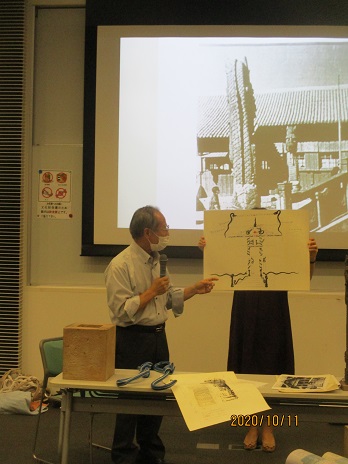




2020-10-11 沖縄県立博物館・美術館講堂 しまくとぅばプロジェクト「しまくとぅば鼎談」親川志奈子、屋嘉宗彦、比嘉豊光、伊佐眞一
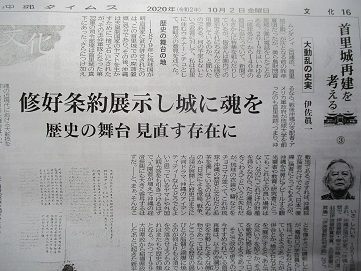

2020-10-2 『沖縄タイムス』伊佐眞一「首里城再建を考える③大動乱の史実」/2020-10-7 『沖縄タイムス』後田多敦「首里城再建を考える⑤沖縄神社」
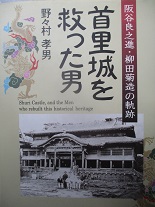
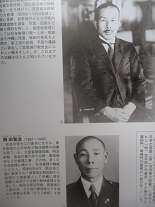
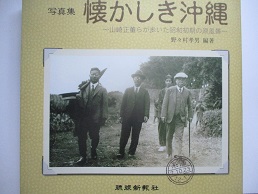
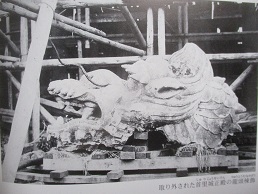
1999年10月 野々村孝男『首里城を救った男ー阪谷良之進・柳田菊造の軌跡』ニライ社/2000年11月 野々村孝男『写真集 懐かしき沖縄~山崎正董らが歩いた昭和初期の原風景から』琉球新報社
1999年3月 (財)南西地域活性化センター(会長・仲井真弘多)『Ⅱ.沖縄県における文化諸施設との現況と課題 調査報告書』
1、第1回 『沖縄と日本、これからの関係は?』出席者:仲井真弘多(沖縄電力)、牧野浩隆(琉銀)、平良朝敬(平盛リゾート)、高良倉吉(琉大)
〇高良倉吉:沖縄が独立した場合のメリット、デメリットについて自分なりに考えてみると、デメリットが多い気がする。したがって、独立ということを担保し、とりあえず留保しておいて、デメリットの方が高まってきたときにはその担保をはずして、いつでも使える状態にしておけばいいと思う。
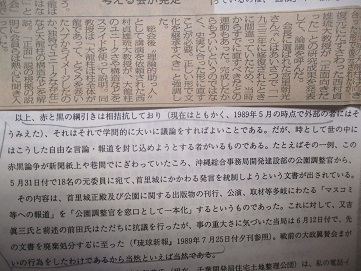
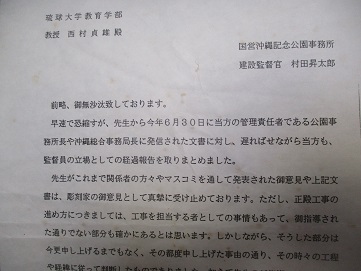
1993年1月22日『琉球新報』「大龍柱を考える会(会長・宮里朝光)発足」/1991年1月 伊佐眞一『アール・ブール人と時代』編集後記/西村氏の抗議にたいする当局の返答

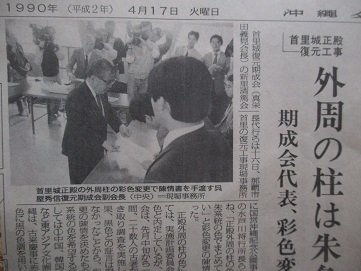






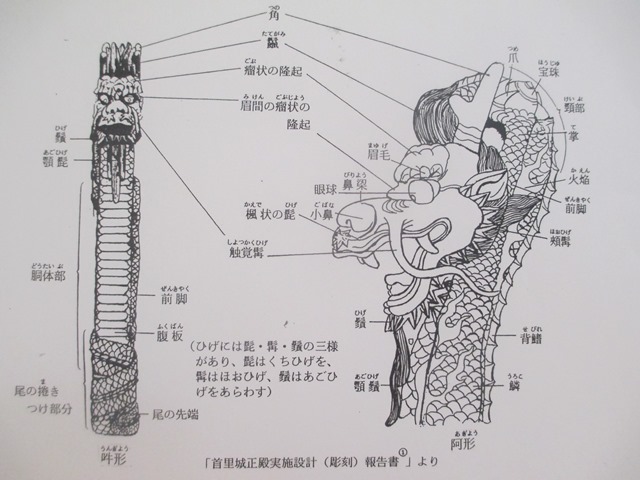

2020-9-11沖縄県立博物館・美術館
特別展「岩石」-石ころから見える地球のダイナミズム―2020年2020年09月08日(火) ~ 2020年11月15日2020

1910年3月 シーモン
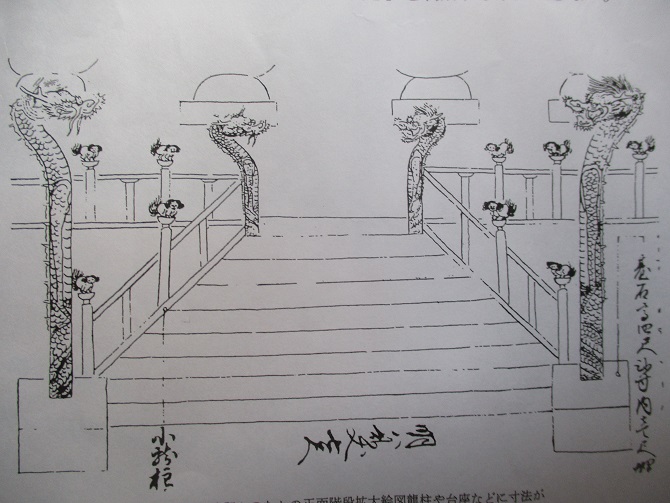
「寸法記」向き合ったら宝珠を持った手がみえるが、これは手を降ろしていて見えない。



2020-9-17 龍柱を考える会
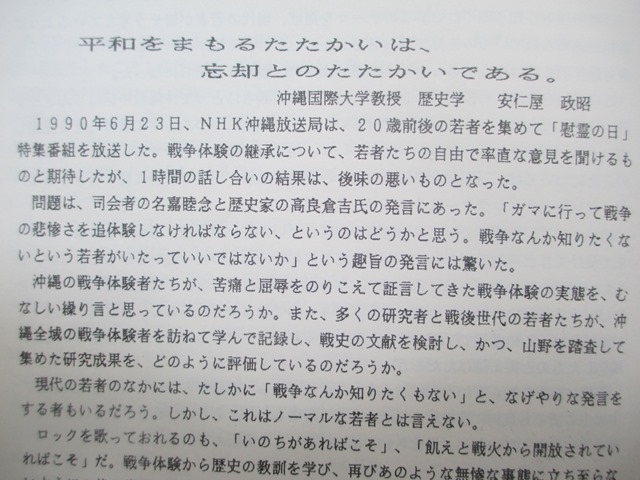
1990年8月 戦争体験記録研究会『次代へ』安仁屋政昭「平和をまもるたたかいは、忘却とのたたかいである。」
「くろねこの短語」2020年10月19日 おかしな話だ。何がって、所信表明演説もしないで、国会を無視したままだってのに、特高顔の自称苦労人・カス総理が外遊したことだ。そうした視点をまったくスルーしたまま、「首相、初の外遊スタート」なんてヨイショ報道する新聞・TVもどうなってるんだろうねえ。
コロナ禍の真っ最中にあって、総理大臣が代わり、その直後に「学問の自由」を揺るがしかねない日本学術会議問題が勃発したってのに、国会が閉じたままってのがどれだけ異常なことか。そのくせ、携帯電話料金値下げだの、マイナンバーカードと免許証の一体化だの、地方銀行や中小企業の再編だの、個別な政策は国会での議論もなしに勝手に動き出している。(略)
「くろねこの短語」2020年10月18日 (前略)、いまのタイミングで処理水の海外放出なんてことが俎上に上がること自体おかしな話なのだ。本来なら、国会で議論すべきことなのに、特高顔の自称苦労人・カス総理は国会を開くこともなく、今週は総理就任後初の外遊へお出ましときたもんだ。
でもって、そんなカス総理に阿るように、大阪府知事のイソジン吉村君が「大阪湾で1発目を放出することが必要で、国からの要請があれば、協力すべきだと思う」だとさ。大阪湾に汚染処理水を垂れ流そうってんだが、こいつもまたカス総理と一緒で何でも自分一人の判断でできると勘違いしてるんだね。ひょっとして、イソジン混ぜて流すつもりだったりして・・・妄想ですよ。そう言えば、イソジン吉村君のオヤビンであるお子ちゃま・橋↓も「関西にも米軍の基地負担を」なんてことを口にして顰蹙を買ったことがある。子の親にしてこの子あり、ってなものか。
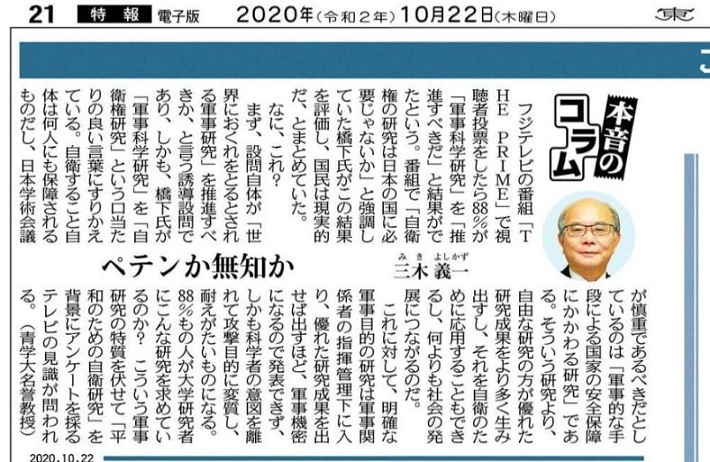
菅 義偉2012-01-28- 民主党は野党時代に政府の文書管理の不備を責め、情報公開を声高に叫んでいました。しかし政権交代後、政治主導の象徴とした政務三役会議など、政策決定過程の多くは非公開で議事録も作成されず、「密室政治」となっています。議事録作成という基本的な義務も果たさず、「誤った政治主導」をふりかざして恣意的に国家を運営する民主党には、政権を担う資格がないのは明らかです。
黒手人 2020年10月16日ーはいさい、やっちー!ちゅーぬ タイムスんかい、高良とぅ与那原恵が 講演・対談 すんでぃぬ 広告が ぬとーん。タイムス「首里城取材班」がやるはじ。14日ぬ タイムス記事や、まったくぬ 高良ぬ「露払い」! ちゅーぬ タイムス文化面かい ぬとーる 知念勇さん意見のー 正当やんやー。なまから うむしるく ないぐとぅ、んーちょーてぃ くぃみそーりよー。
「くろねこの短語」2020年10月14日 (前略)どうやら、警察官僚による官邸支配ってのが、カス政権の本質ってことのようだ。運転免許とマイナンバーカードの一体化なんてのも、警察官僚がバックについているからこそで、昨日のTBS『Nスタ』なんか臆面もなくそうした報道をしてましたからね。
日本学術会議問題は「学問の自由」に手を突っ込んだわけだけど、カス総理が必死こいている携帯電話の料金値下げってのは行きつくところは「表現の自由」への弾圧につながりかねないんだよね。なんとなれば、携帯電話料金ってのは電波の許認可に関わってくる問題で、許認可権を利用すれば放送局への規制も容易にできちゃうんだから。日本学術会議問題は警察国家への手始めで、メディアや一般大衆労働者諸君がどんな反応をするか試してるんじゃないのかねえ。
ところで、あっせん利得疑惑の布袋頭・甘利君が、「日本学術会議は中国の『千人計画』に協力している」ってデマを流したブログをこっそりと書き換えてたってね。睡眠障害とやらで国会から逃亡したように、なんとも姑息な野郎だこと。
2020-10-12 森美琴ちゃん誕生
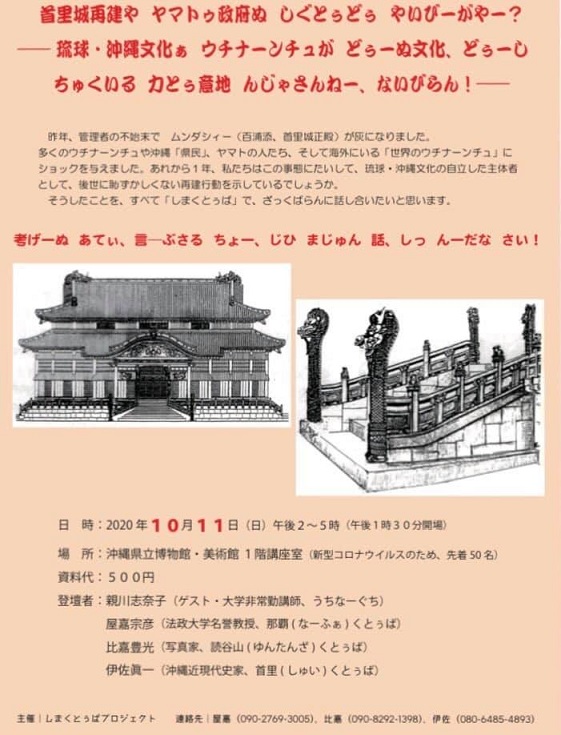
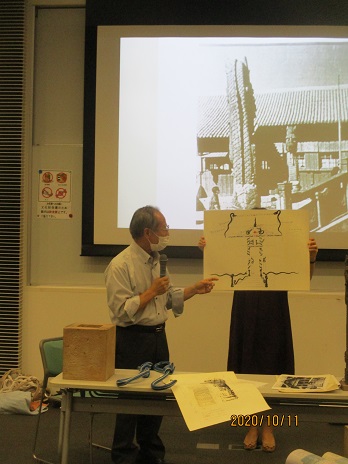




2020-10-11 沖縄県立博物館・美術館講堂 しまくとぅばプロジェクト「しまくとぅば鼎談」親川志奈子、屋嘉宗彦、比嘉豊光、伊佐眞一
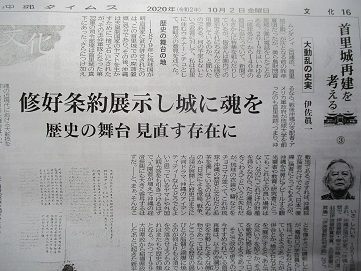

2020-10-2 『沖縄タイムス』伊佐眞一「首里城再建を考える③大動乱の史実」/2020-10-7 『沖縄タイムス』後田多敦「首里城再建を考える⑤沖縄神社」
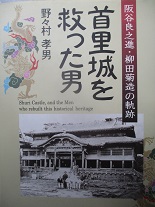
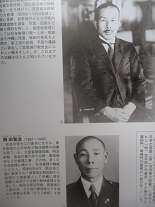
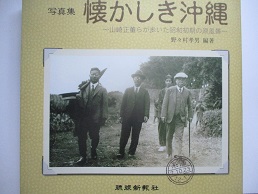
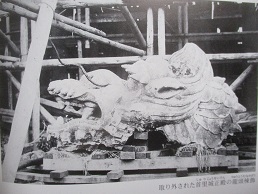
1999年10月 野々村孝男『首里城を救った男ー阪谷良之進・柳田菊造の軌跡』ニライ社/2000年11月 野々村孝男『写真集 懐かしき沖縄~山崎正董らが歩いた昭和初期の原風景から』琉球新報社
1999年3月 (財)南西地域活性化センター(会長・仲井真弘多)『Ⅱ.沖縄県における文化諸施設との現況と課題 調査報告書』
1、第1回 『沖縄と日本、これからの関係は?』出席者:仲井真弘多(沖縄電力)、牧野浩隆(琉銀)、平良朝敬(平盛リゾート)、高良倉吉(琉大)
〇高良倉吉:沖縄が独立した場合のメリット、デメリットについて自分なりに考えてみると、デメリットが多い気がする。したがって、独立ということを担保し、とりあえず留保しておいて、デメリットの方が高まってきたときにはその担保をはずして、いつでも使える状態にしておけばいいと思う。
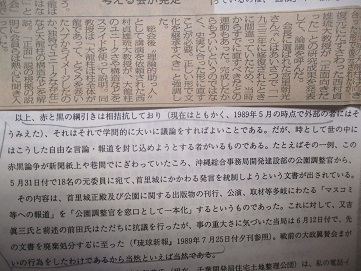
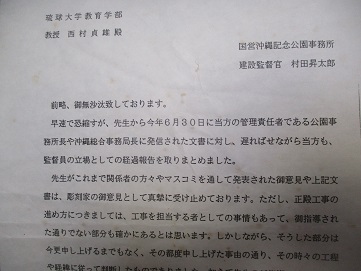
1993年1月22日『琉球新報』「大龍柱を考える会(会長・宮里朝光)発足」/1991年1月 伊佐眞一『アール・ブール人と時代』編集後記/西村氏の抗議にたいする当局の返答

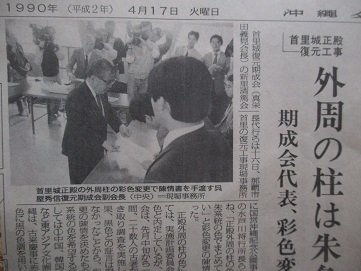






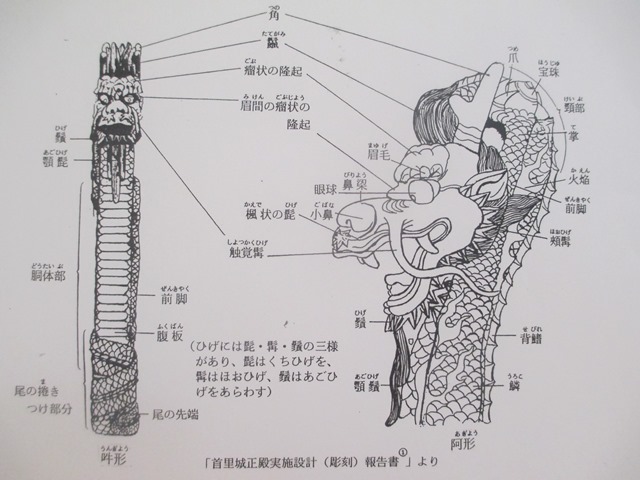

2020-9-11沖縄県立博物館・美術館
特別展「岩石」-石ころから見える地球のダイナミズム―2020年2020年09月08日(火) ~ 2020年11月15日2020

1910年3月 シーモン
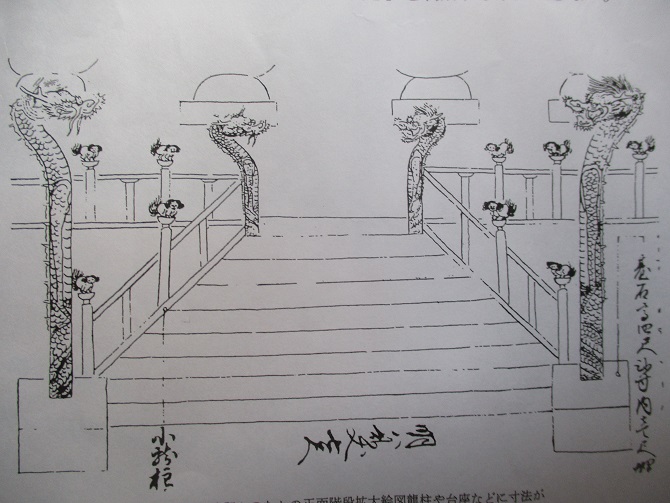
「寸法記」向き合ったら宝珠を持った手がみえるが、これは手を降ろしていて見えない。



2020-9-17 龍柱を考える会
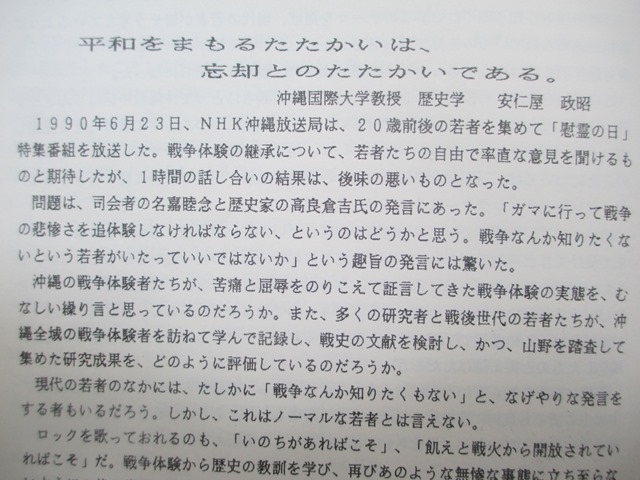
1990年8月 戦争体験記録研究会『次代へ』安仁屋政昭「平和をまもるたたかいは、忘却とのたたかいである。」
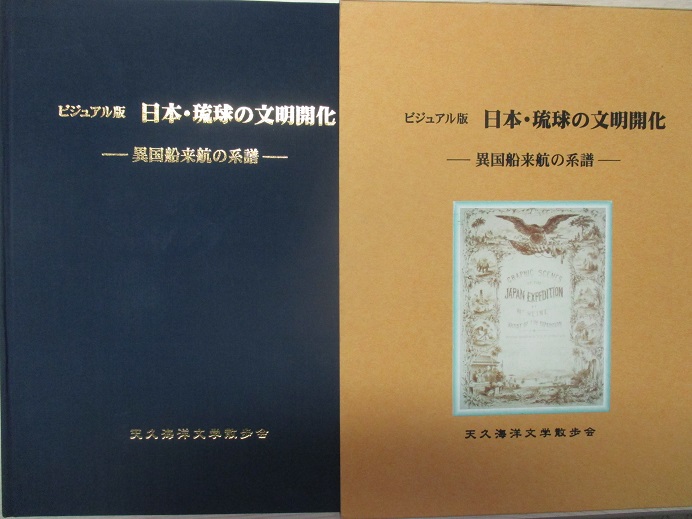 研究会と交流。
研究会と交流。2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
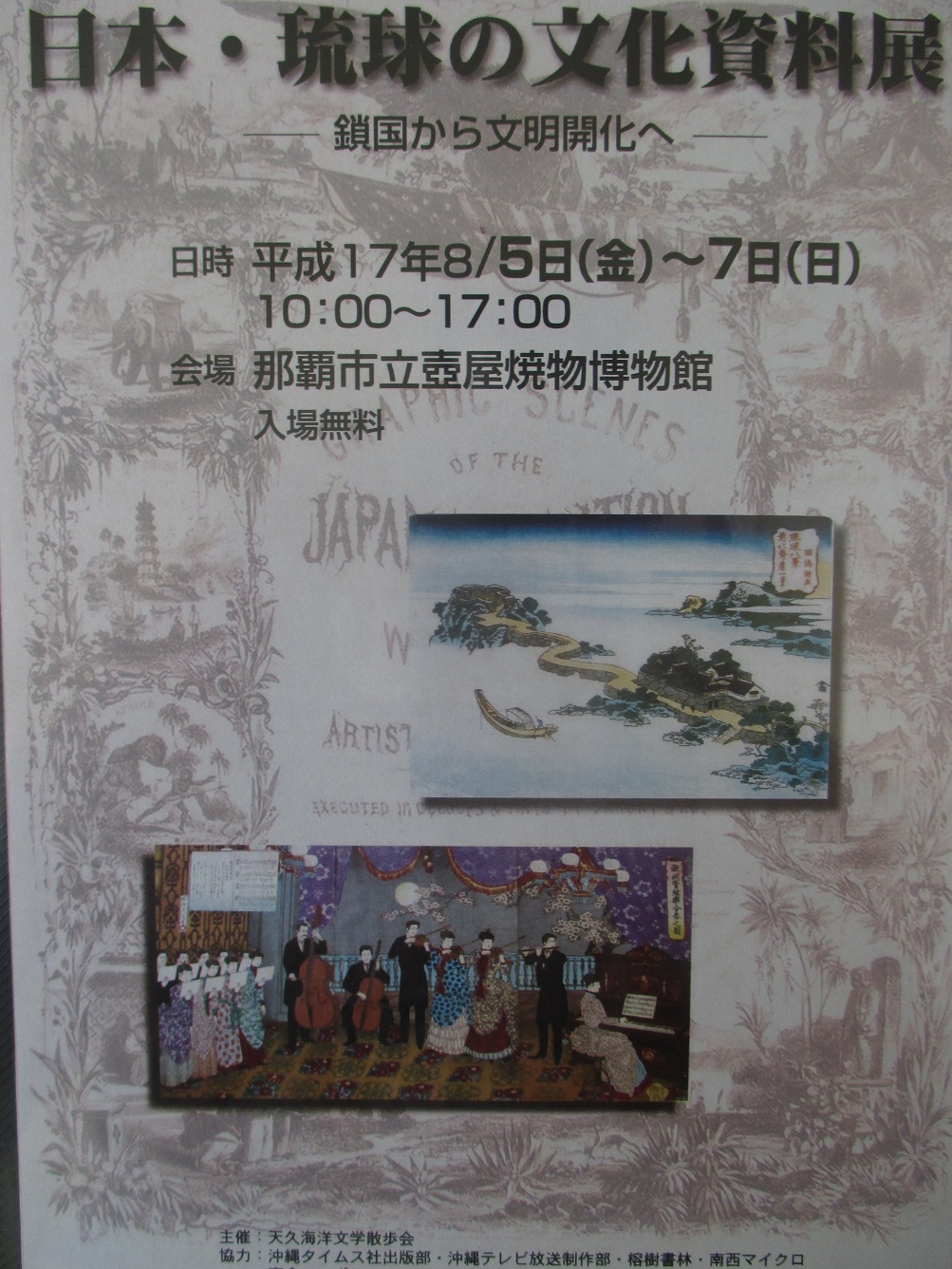
2005年8月 那覇市立壺屋焼物博物館 「日本・琉球の文化資料展ー鎖国から文明開化へー」主催/天久海洋文学散歩会(新城良一)

左が喜納勝代さん


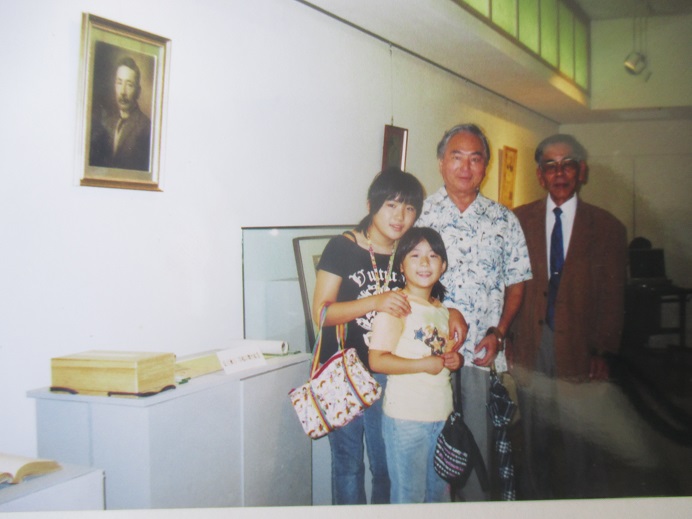
渡口万年筆の渡口彦邦氏と新城良一氏(右)

2012年5月ミズリー州ブルックフィールド(ローズヒル墓地) ベッテルハイム墓碑で新城良一氏
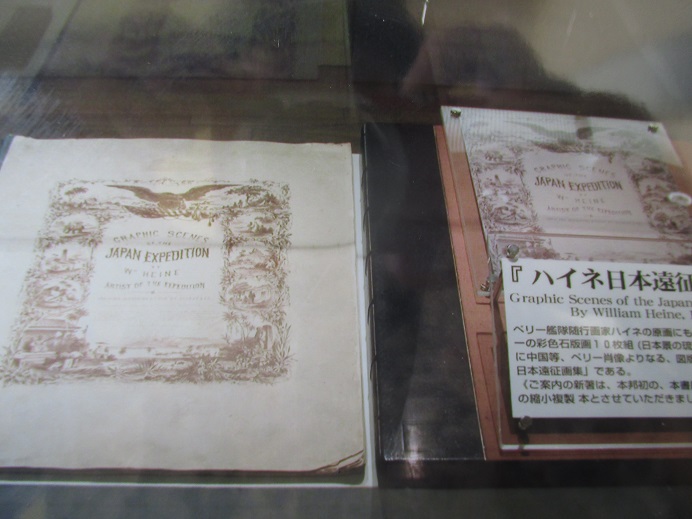
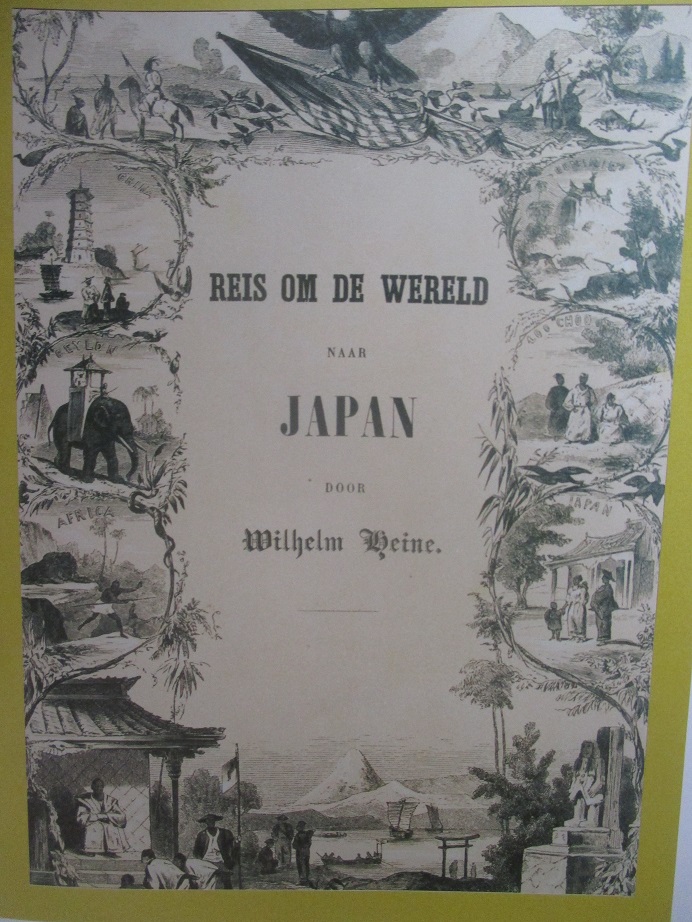


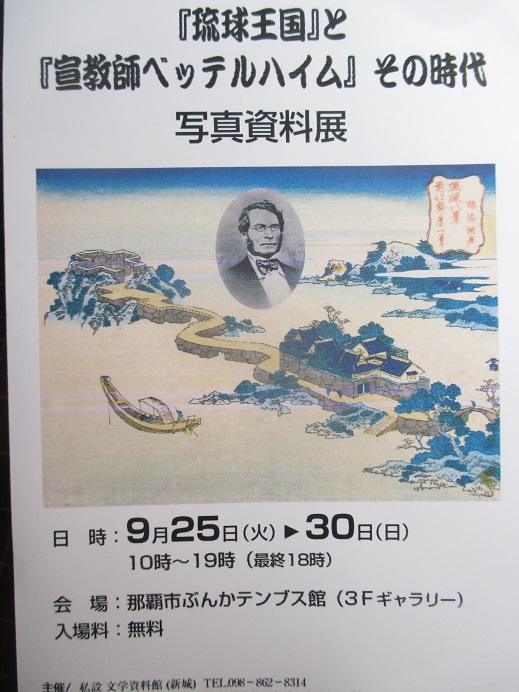
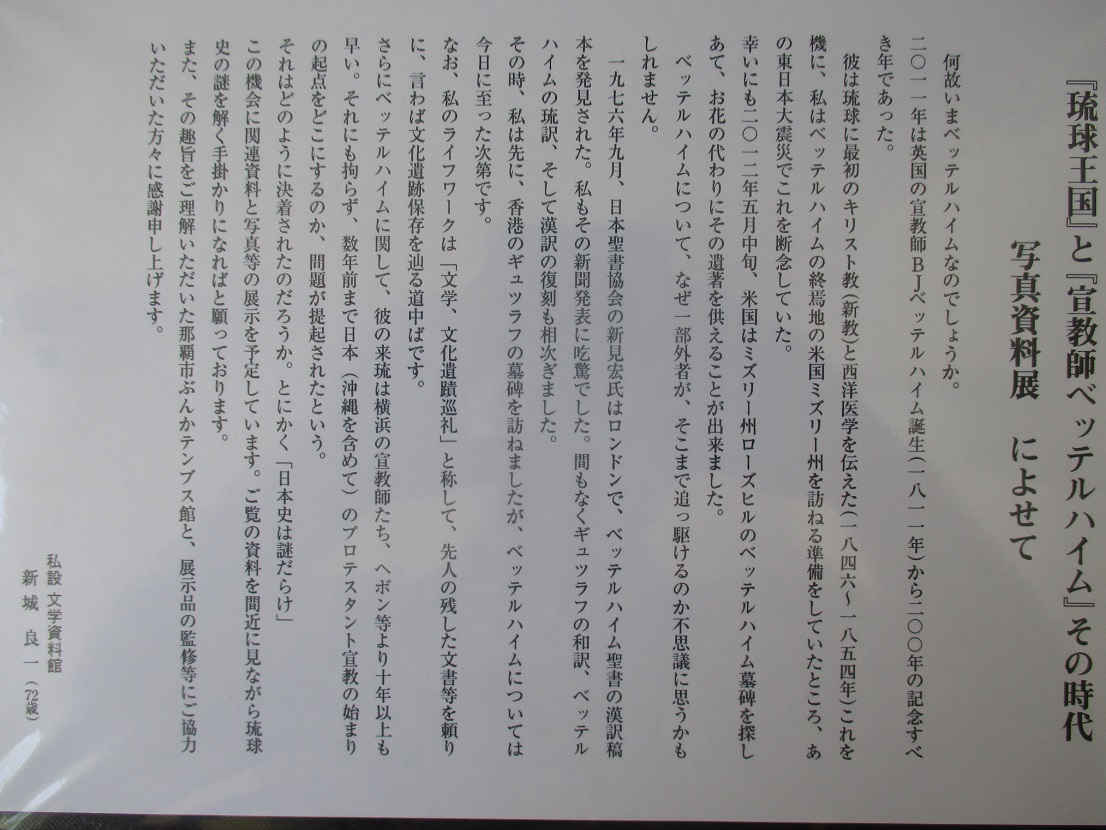
2012年9月 那覇市ぶんかテンブス館3Fギャラリー「写真資料展・『琉球王国』と『宣教師ベッテルハイム』その時代」主催/新城良一「私設・文学資料館」
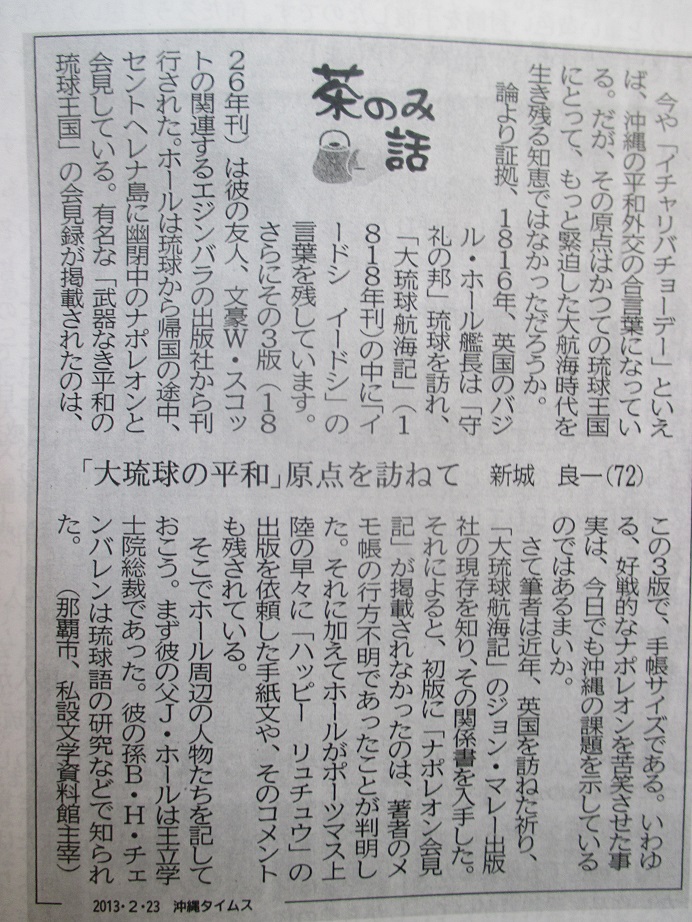
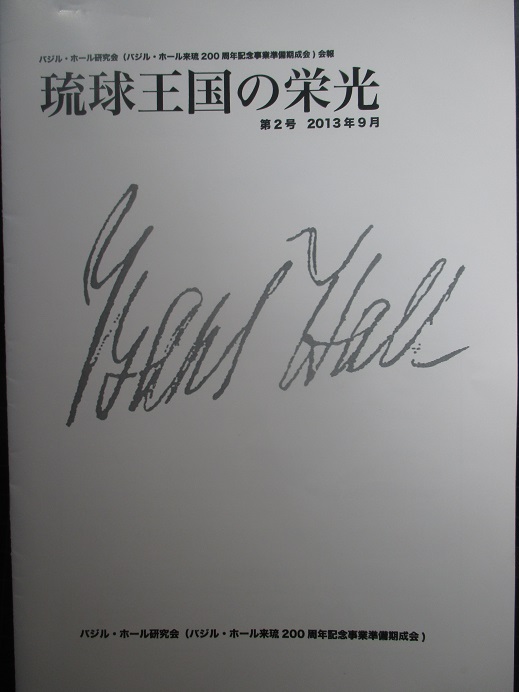
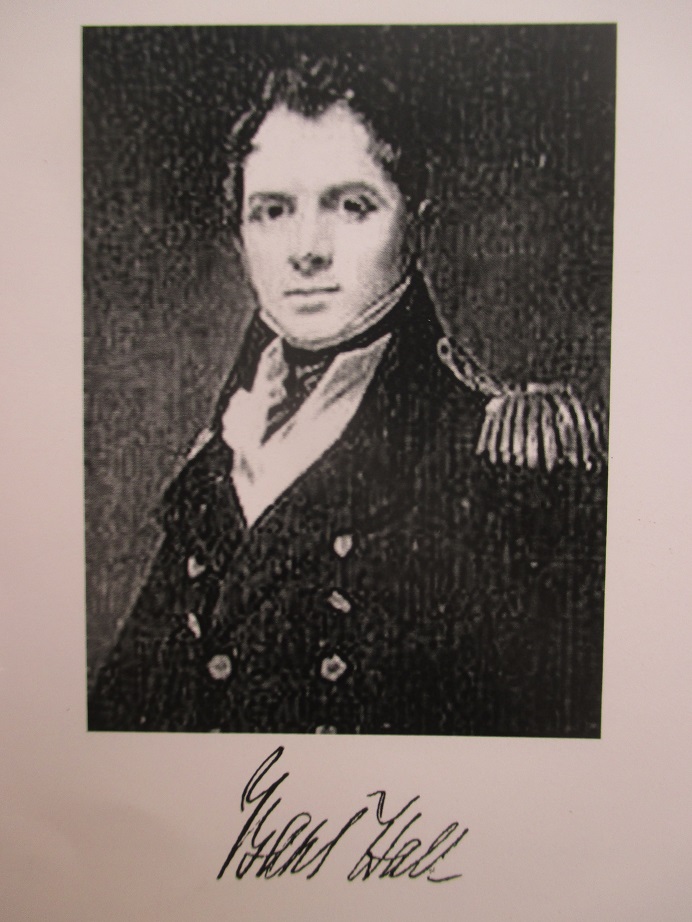
2013年9月 バジル・ホール研究会『琉球王国の栄光』第2号□写真/バジルホールとその自筆署名(新城良一所蔵)
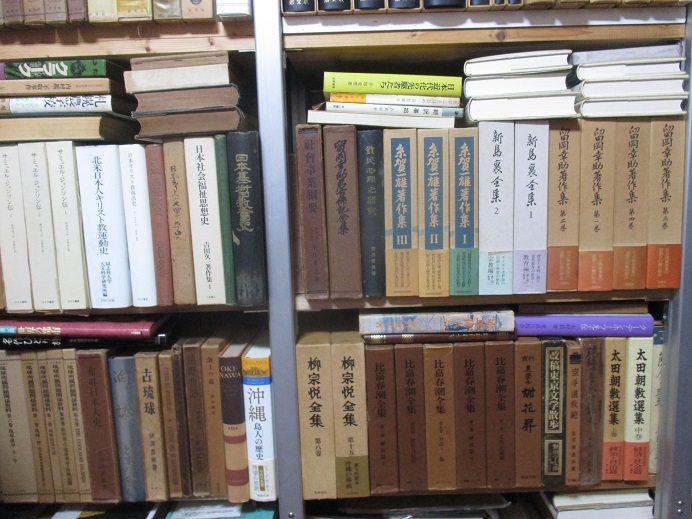
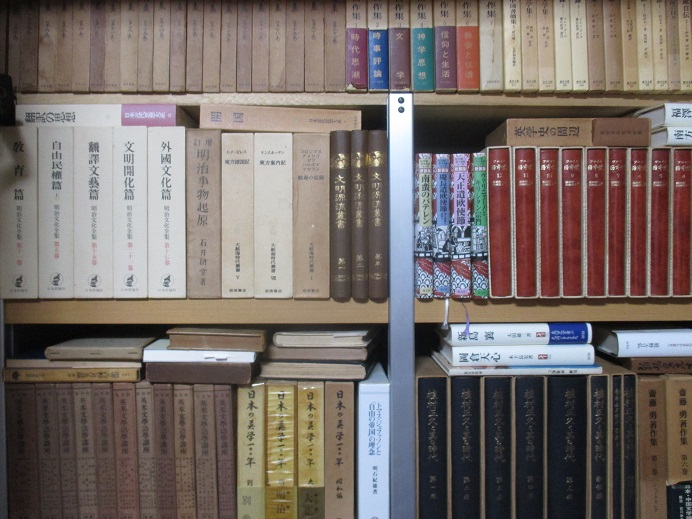
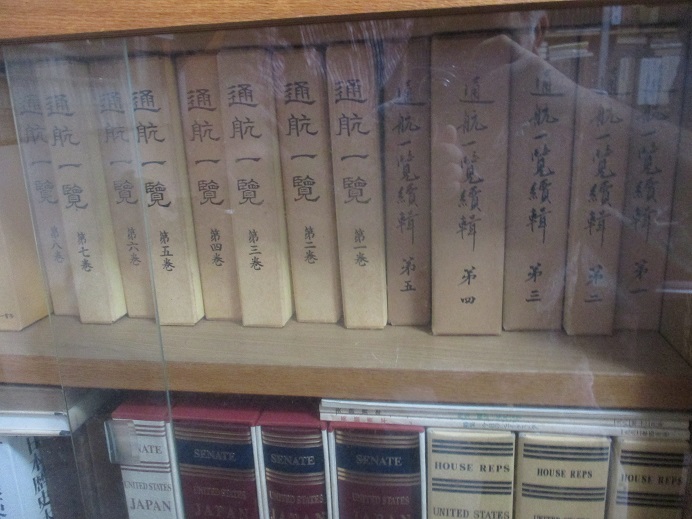
通航一覧つうこういちらんー江戸時代の外交関係史料集。本文 350巻,付録 23巻,凡例総目2巻。幕府の命を受けて,大学頭林あきら (復斎) が史料を収集整理して嘉永3 (1850) 年に完成したもの。琉球,朝鮮,中国をはじめ,東南アジア,欧米諸国の国号の起源,統治者の世系,日本との交通などを,いくつかの項目に分けて書いてある。コトバンク
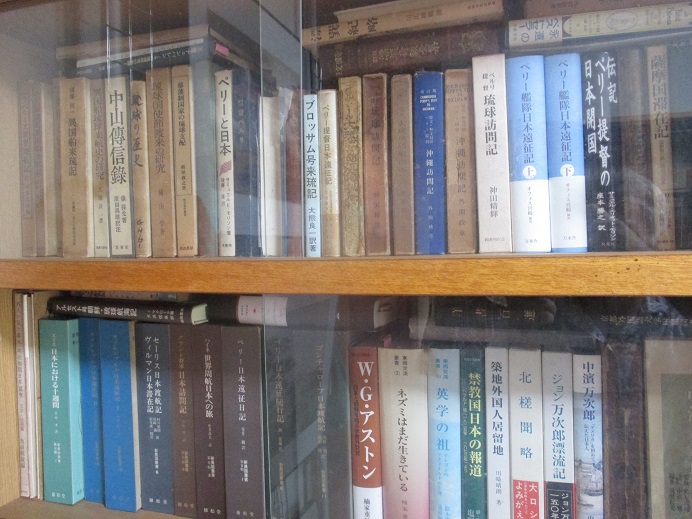
1938年8月から須藤利一は『沖縄教育』に「ベージル・ホール大琉球航海記」を1939年まで連載。(抜き刷りを新城良一氏所蔵)1940年1月、須藤利一は野田書房から『大琉球島探検航海記』を出した。発売所は東京は日本古書通信社代理部、那覇は沖縄書籍となっている。
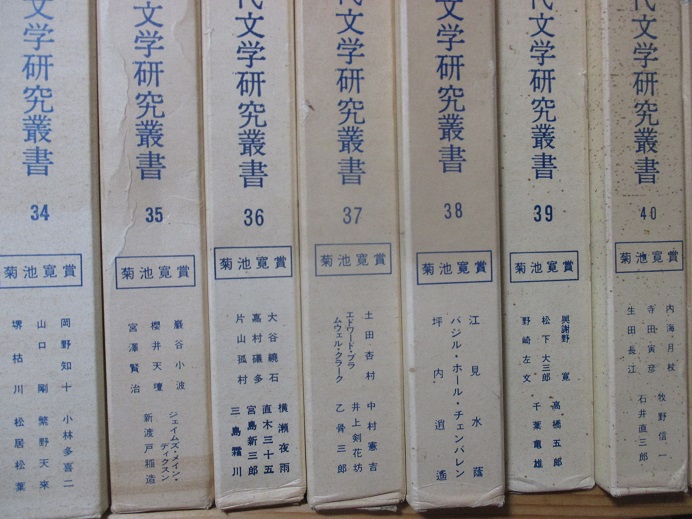
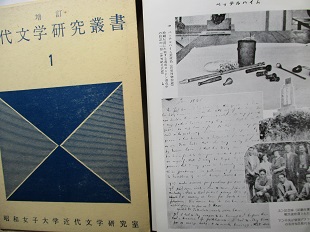

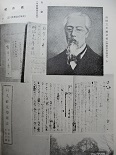
1969年3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書1』「B・J・ベッテルハイム」「八田知紀」「中村正直」
昭和女子大学「近代文化研究所」の中心事業であった『近代文学研究叢書』の刊行は、創立者人見円吉の企画・立案によるもので、大学が誇る図書館(近代文庫)の充実した蔵書を生かして調査研究が開始。38巻は「江見水蔭 B・H・チェンバレン 坪内逍遙」である
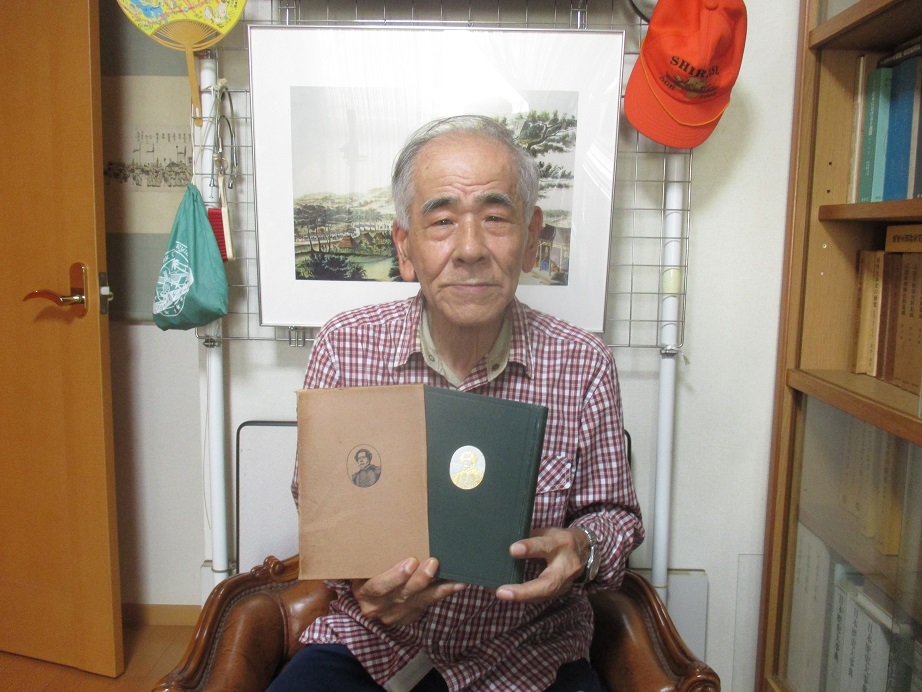
新城良一氏が手にしているのは神田 精輝 訳『ペルリ提督琉球訪問記 』の初版本
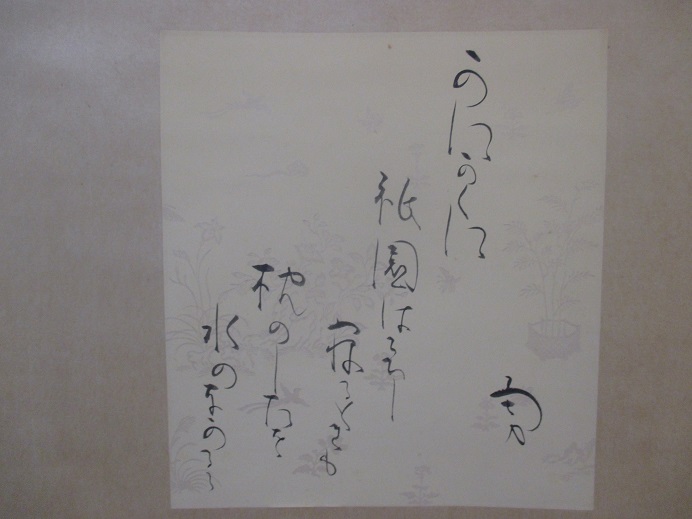
吉井勇の作「かにかくに 祇園はこひし寝(ぬ)るときも 枕のしたを水のながるる」
13:30 開場
14:00 {トーク}(15分×4人)「それぞれの立場から見た山田實」
15::05~15:15 休憩
15:15 {パネルディスカッション}(100分)・質疑応答
パネリスト:大城立裕氏(作家)、金城棟永氏(写真家)、仲里効氏(映像批評家)、仲嶺絵里奈氏(写真史研究所研究員)
コーディネーター:大城仁美(展覧会担当学芸員)
17:00 終了

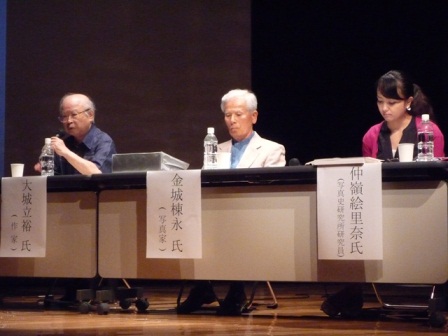
写真左から大城立裕氏、金城棟永氏、仲嶺絵里奈さん
□2012年10月10日『琉球新報』仲嶺絵里奈「美術月報ー今年94歳にして現役の写真家として活動を続ける、山田實の大規模な写真展『山田實展ー人と時の往来』(沖縄県立博物館・美術館企画ギャラリー1・2、9月」11日~11月4日)が開催されている。-」
□2012年10月11日『沖縄タイムス』「展覧会でシンポー山田實作品 本質探るー『原点にシベリア抑留体験』」
14:00 {トーク}(15分×4人)「それぞれの立場から見た山田實」
15::05~15:15 休憩
15:15 {パネルディスカッション}(100分)・質疑応答
パネリスト:大城立裕氏(作家)、金城棟永氏(写真家)、仲里効氏(映像批評家)、仲嶺絵里奈氏(写真史研究所研究員)
コーディネーター:大城仁美(展覧会担当学芸員)
17:00 終了

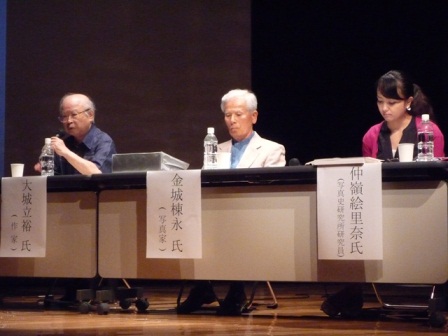
写真左から大城立裕氏、金城棟永氏、仲嶺絵里奈さん
□2012年10月10日『琉球新報』仲嶺絵里奈「美術月報ー今年94歳にして現役の写真家として活動を続ける、山田實の大規模な写真展『山田實展ー人と時の往来』(沖縄県立博物館・美術館企画ギャラリー1・2、9月」11日~11月4日)が開催されている。-」
□2012年10月11日『沖縄タイムス』「展覧会でシンポー山田實作品 本質探るー『原点にシベリア抑留体験』」
09/19: 宜湾朝保(1823年3月5日~1876年8月6日)
宜湾朝保
近世末期琉球の政治家,歌人。唐名は向有恒。明治政府が樹立し,廃藩置県が行われると,維新慶賀副使として上京,琉球藩王を受けて,琉球王国の日本への編入の道を開く。琉球の名門の家に生まれ,父親は幼時に死去したものの,やはり三司官(本土の家老などに相当する首里王府の要職)だった。本人も尚泰15(1862)年から死の前年まで三司官を務める。歌を,香川景樹の高弟で薩摩藩士八田知紀に師事し,『沖縄集』(尚泰23年刊),『沖縄集二編』(同29年刊)を編集刊行するなど大いに歌道を興す。家集に『松風集』がある。
(池宮正治)→コトバンク
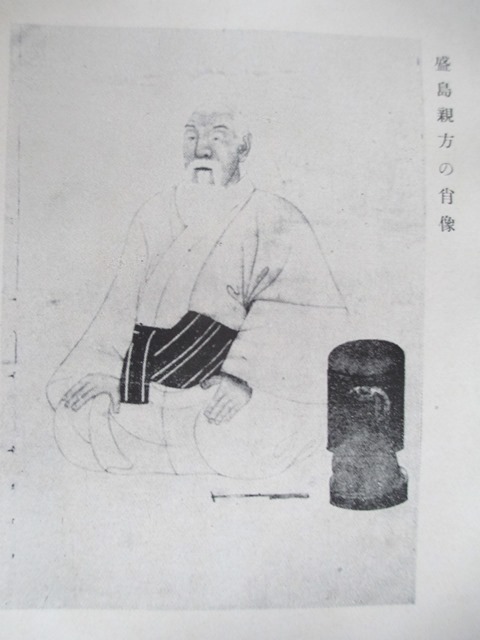
宜湾朝保の父ー向延楷・盛島親方朝昆
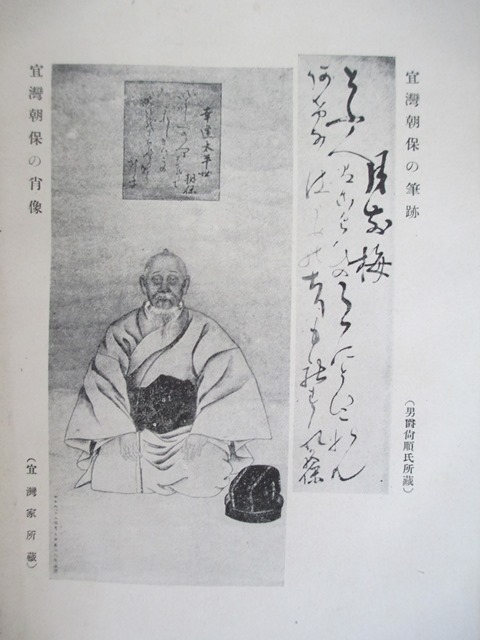
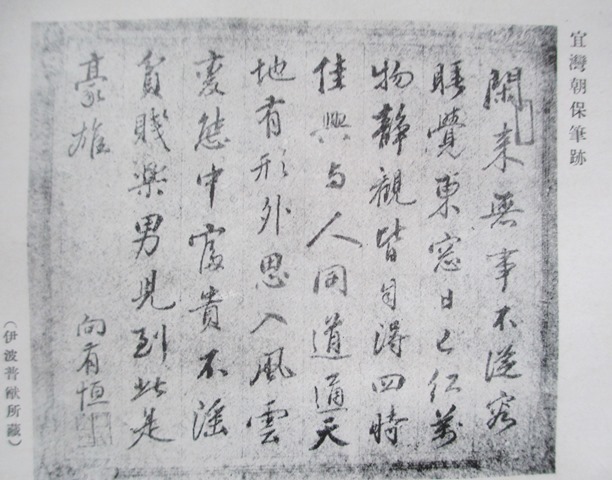
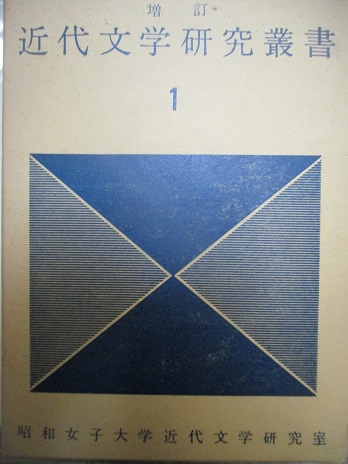
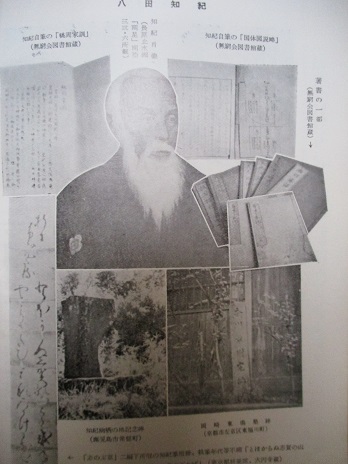
1969年3月 昭和女子大学近代文学研究室『増訂 近代文学叢書』「八田知紀」第一巻 昭和女子大学
近世末期琉球の政治家,歌人。唐名は向有恒。明治政府が樹立し,廃藩置県が行われると,維新慶賀副使として上京,琉球藩王を受けて,琉球王国の日本への編入の道を開く。琉球の名門の家に生まれ,父親は幼時に死去したものの,やはり三司官(本土の家老などに相当する首里王府の要職)だった。本人も尚泰15(1862)年から死の前年まで三司官を務める。歌を,香川景樹の高弟で薩摩藩士八田知紀に師事し,『沖縄集』(尚泰23年刊),『沖縄集二編』(同29年刊)を編集刊行するなど大いに歌道を興す。家集に『松風集』がある。
(池宮正治)→コトバンク
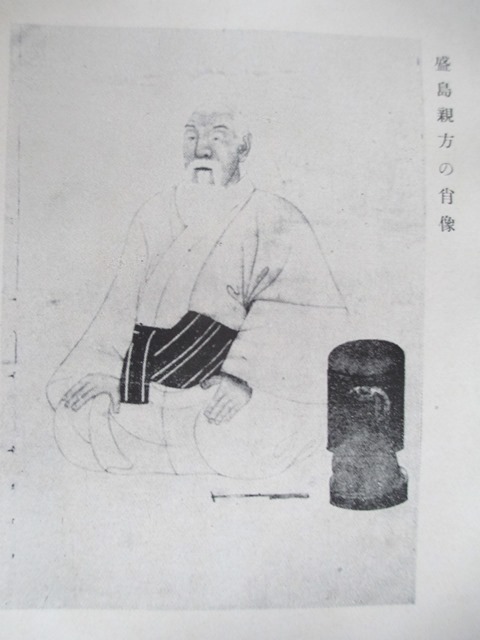
宜湾朝保の父ー向延楷・盛島親方朝昆
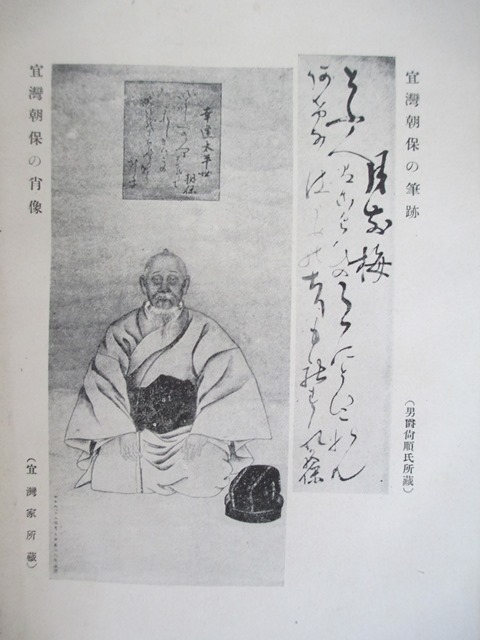
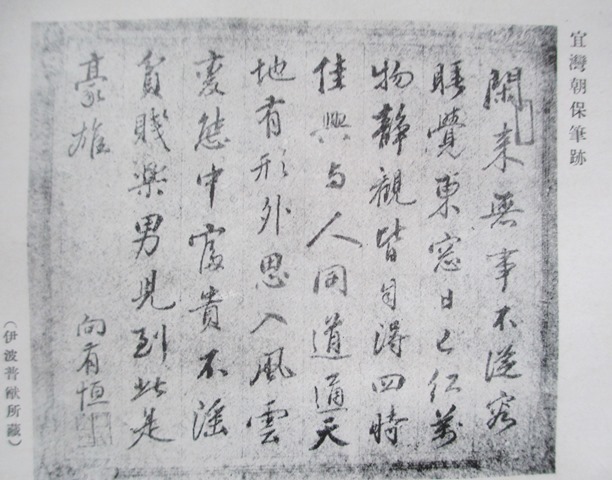
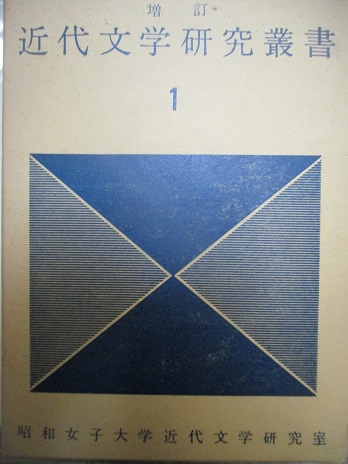
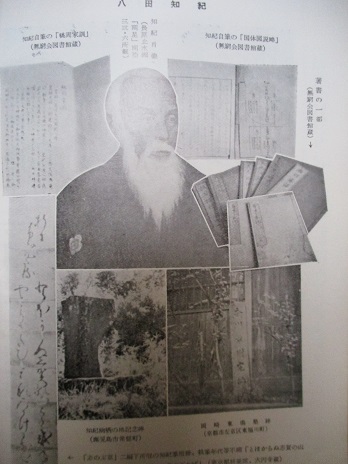
1969年3月 昭和女子大学近代文学研究室『増訂 近代文学叢書』「八田知紀」第一巻 昭和女子大学
昨年暮れ、沖縄県立博物館・美術館指定管理者の「文化の杜共同企業体」から今年5月に開催される企画展「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した“美”」の図録に末吉麦門冬と鎌倉芳太郎についての原稿依頼があった。奇しくも今年11月25日は末吉麦門冬の没後90年で、展覧会場の沖縄県立博物館・美術館に隣接する公園北端はかつて末吉家の墓があった場所である。加えて、文化の杜には麦門冬曾孫の萌子さんも居る。私は2007年の沖縄県立美術館開館記念展図録『沖縄文化の軌跡』「麦門冬の果たした役割」の中で「琉球美術史に先鞭をつけたのは麦門冬・末吉安恭で、その手解きを受けた一人が美術史家・比嘉朝健である。安恭は1913年、『沖縄毎日新聞』に朝鮮小説「龍宮の宴」や支那小説「寒徹骨」などを立て続けに連載した。そして15年、『琉球新報』に『吾々の祖先が文字に暗い上に筆不精(略)流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の国ではある』と朝鮮の古書『龍飛御天歌』『稗官雑記』などを引用し、『朝鮮史に見えたる古琉球』を連載した。
画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬
安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。
麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
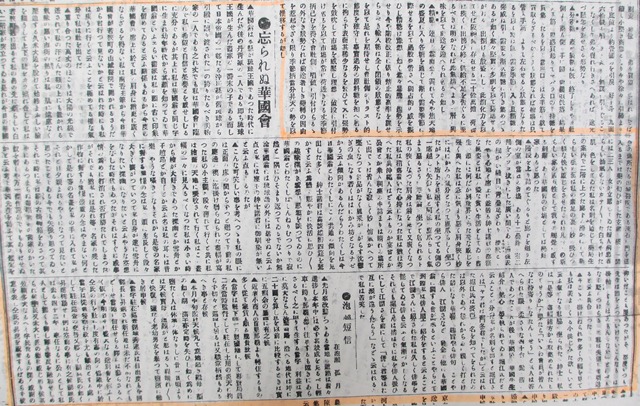
華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・
麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

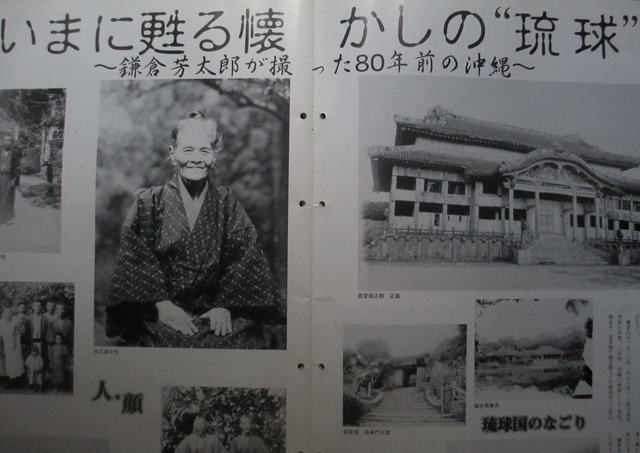
画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬
安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。
麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
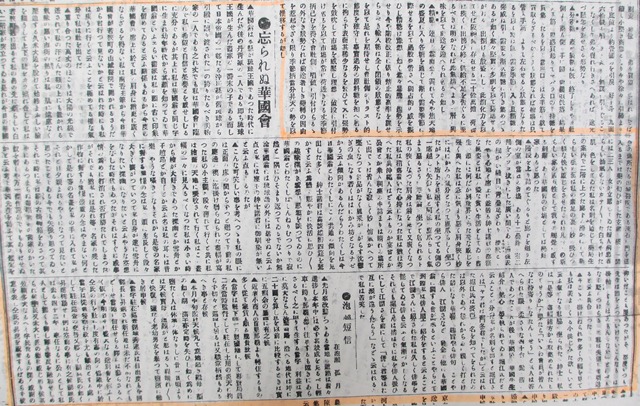
華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・
麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

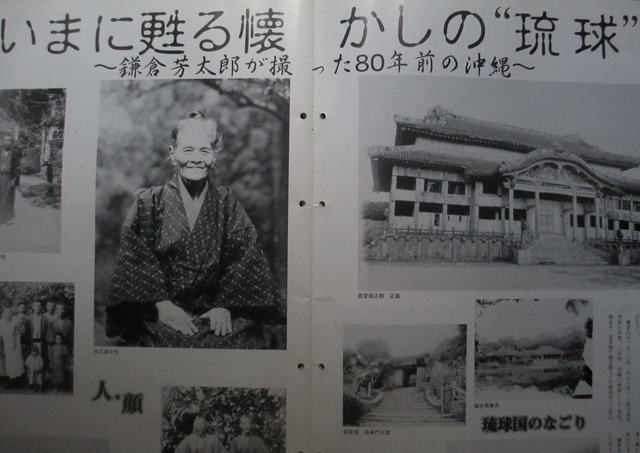
02/19: 神村朝堅 雑誌『おきなわ』創刊への道
1945年8月、国吉真哲・宮里栄輝・源武雄が早く帰還できるよう「県人会」結成を相談。宮里栄輝、熊本沖縄県人会長になる。/女子挺身隊救済で尼崎沖縄県人会結成。
9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。
11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎
11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会
11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行
12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)
1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦
1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。
2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」
3月、『関西沖縄新報』創刊
4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳
4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇
8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久
1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正
1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称
1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮
1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。
1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」
1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。
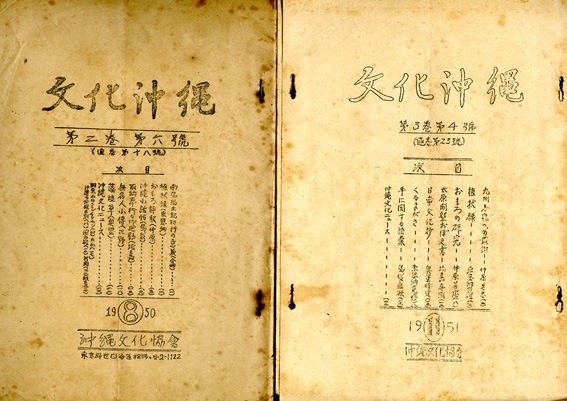
この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝
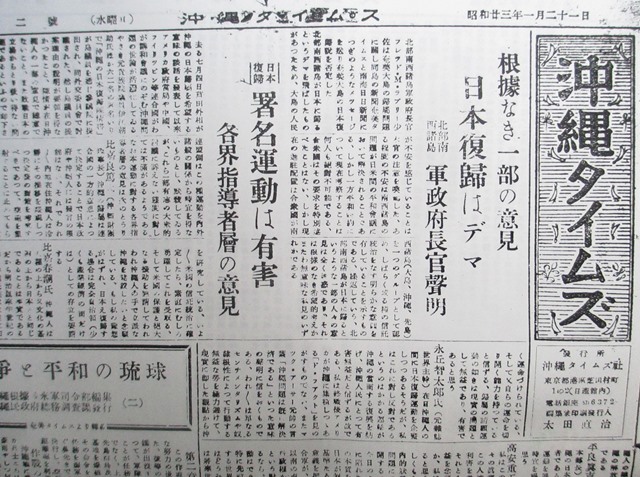
1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号
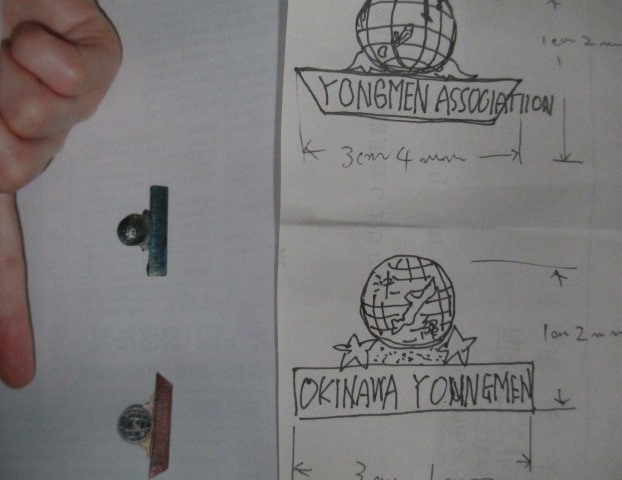
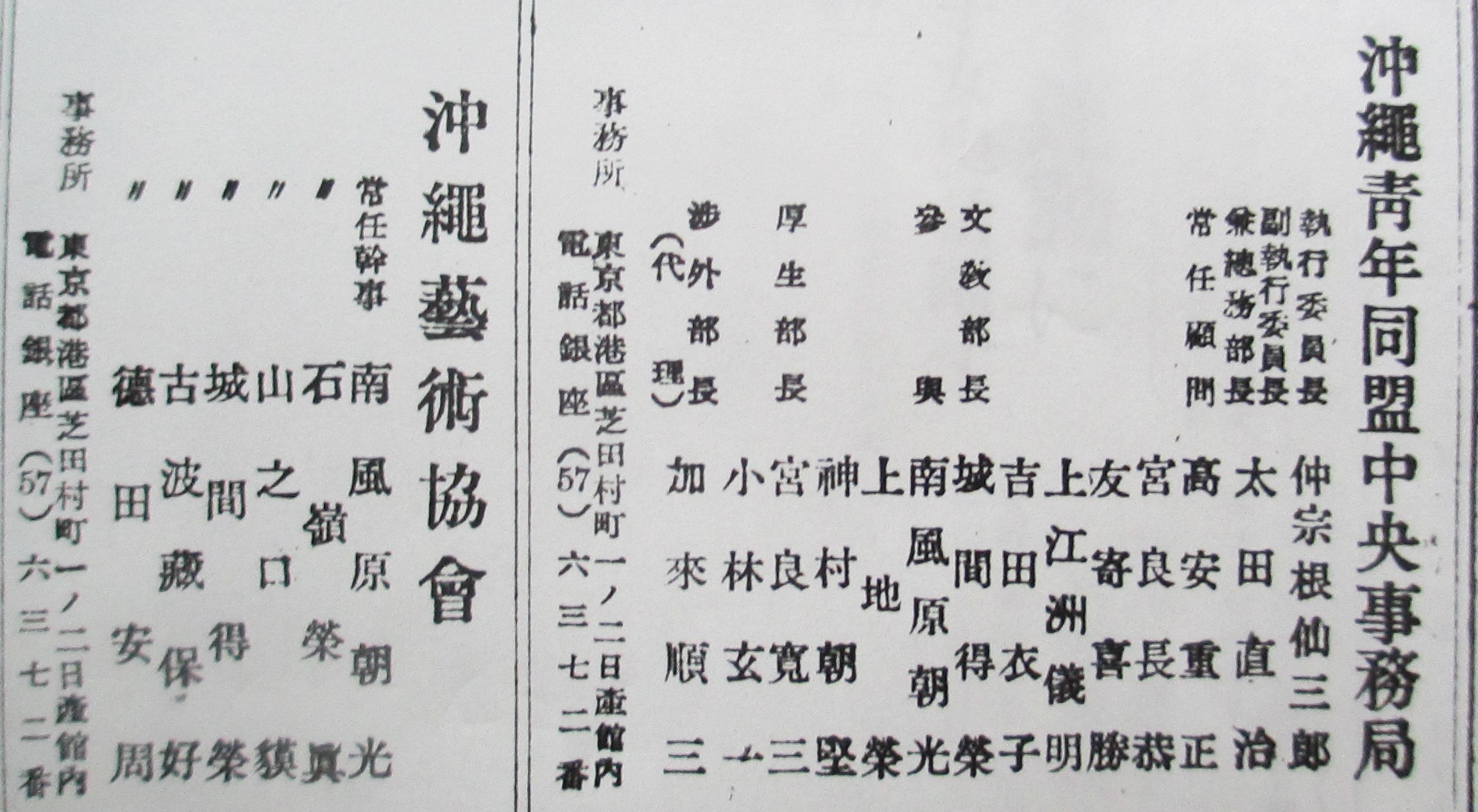
1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号
1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。
②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。
1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。
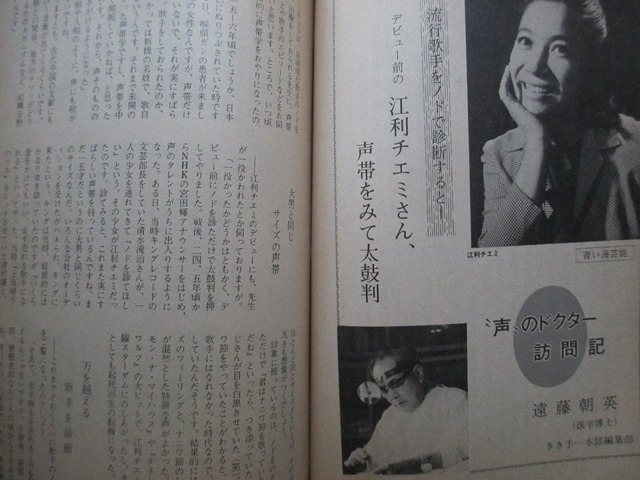
『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士
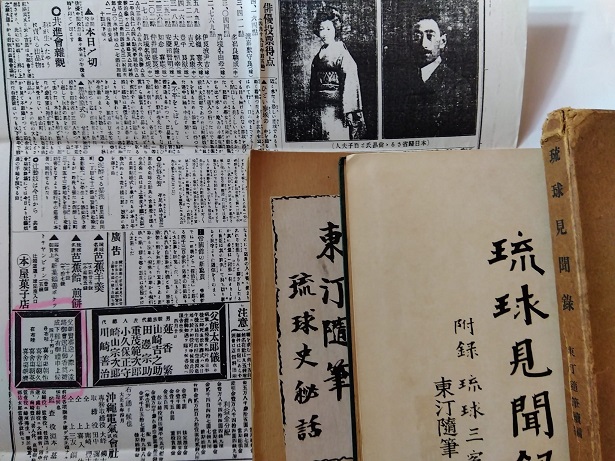
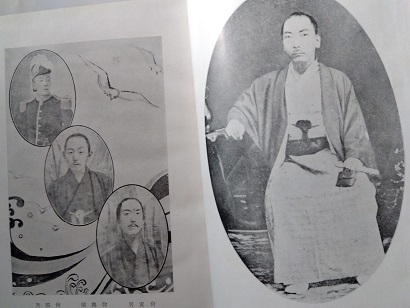
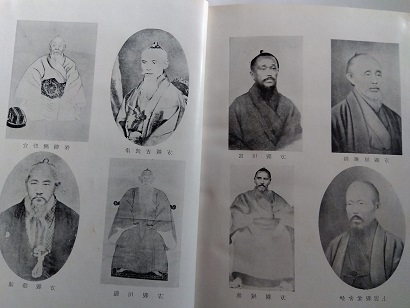
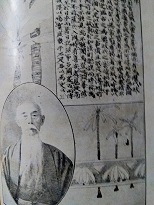
『琉球見聞録』東汀遺著刊行会、1952年11月。
喜舎場 朝賢(きしゃば ちょうけん、1840年〈天保11年〉 - 1916年〈大正5年〉4月14日)は、琉球王国末期の官僚。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、『琉球見聞録』を著した。童名は次郎。唐名は向(しょう)延翼。号は東汀。
晩年の1914年(大正3年)、琉球処分時の記録を『琉球見聞録』として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波普猷が「序に代えて 琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文を、巻末には発行者の親泊朝擢が「喜舎場朝賢翁小伝」をそれぞれ寄せている。波平恒男は、『琉球見聞録』の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で、差し障りがあったのではないかと推測している。→ウイキ
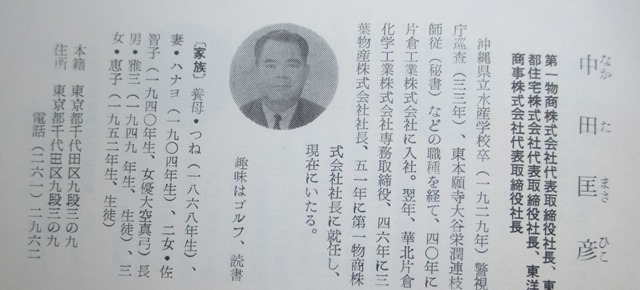
1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』
大空真弓 おおぞら-まゆみ
1940- 昭和後期-平成時代の女優。
昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。
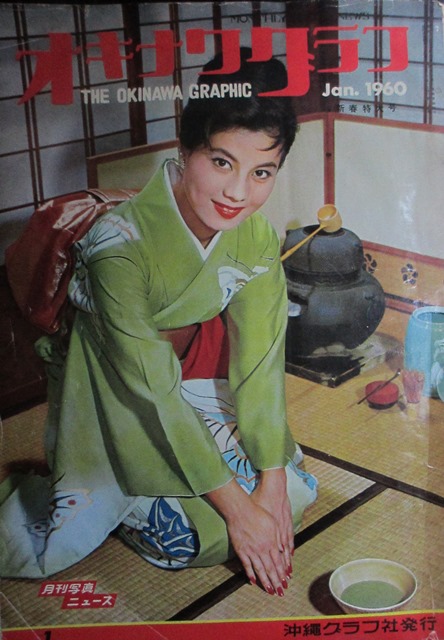
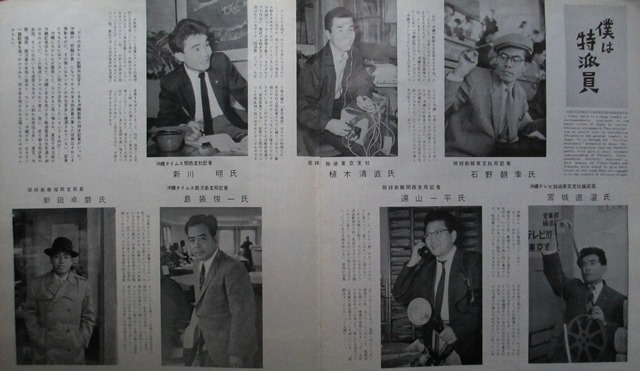
『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。
1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社
1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅
1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社
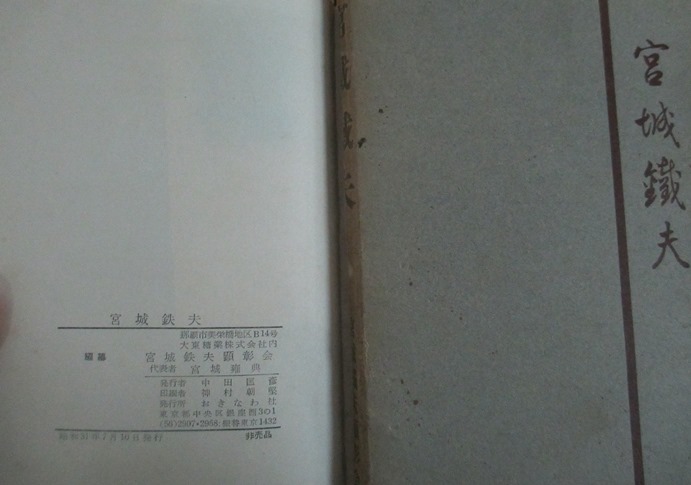 (BOOKSじのん在庫)
(BOOKSじのん在庫)
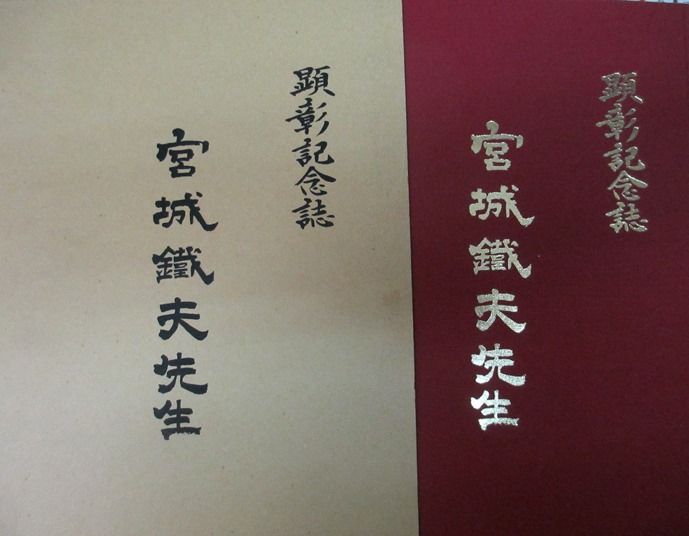
平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)
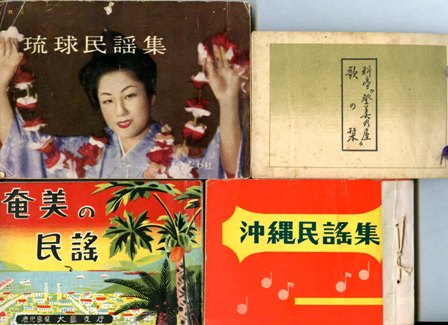
1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)
1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅
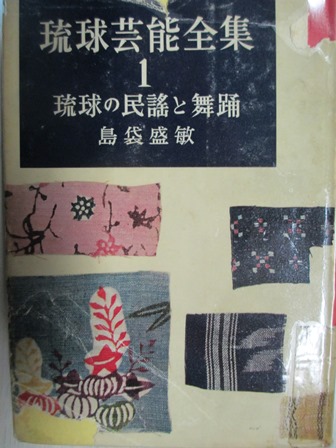
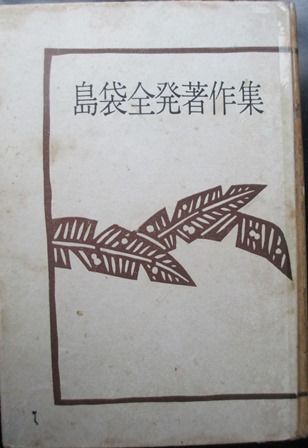
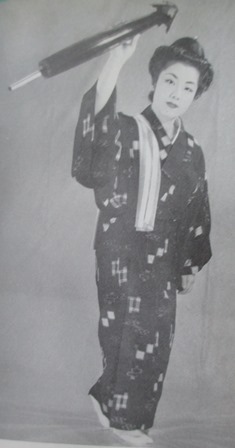
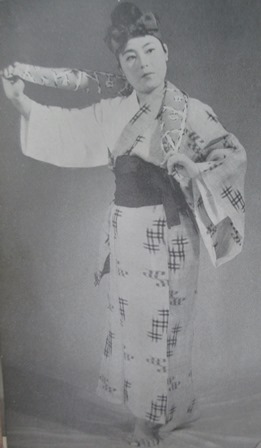
1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社
1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社
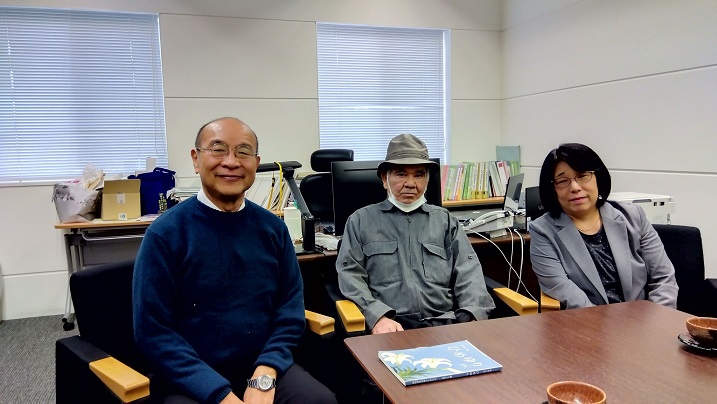
2025-2-5 沖縄県立博物館・美術館館長室:里井洋一館長、新城栄徳、大里知子法政大学沖縄文化研究所 准教授・専任所員
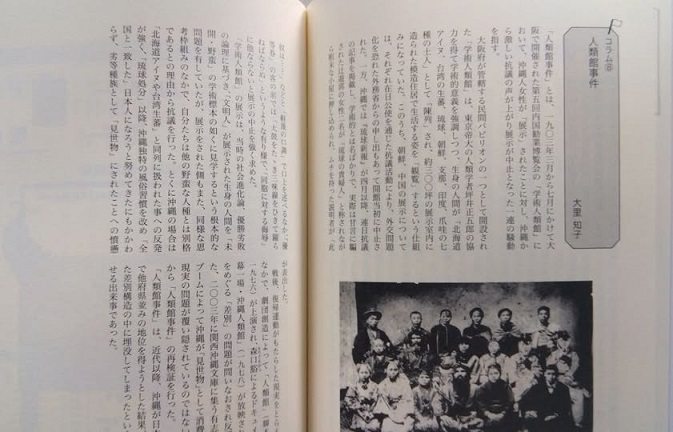
2021-11 『沖縄近現代史』ボーダーインク 大里知子「人類館事件」
1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社
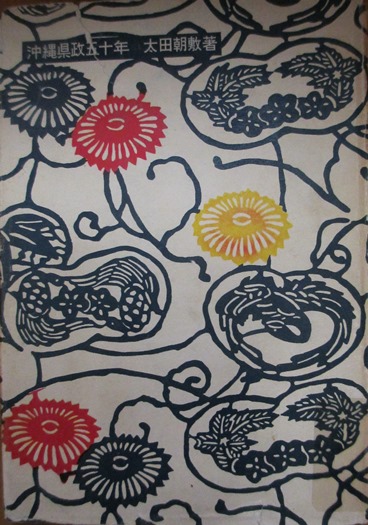
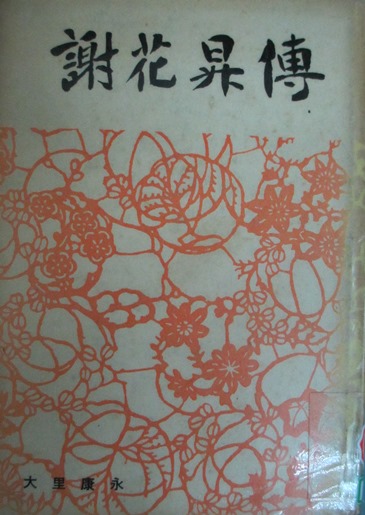
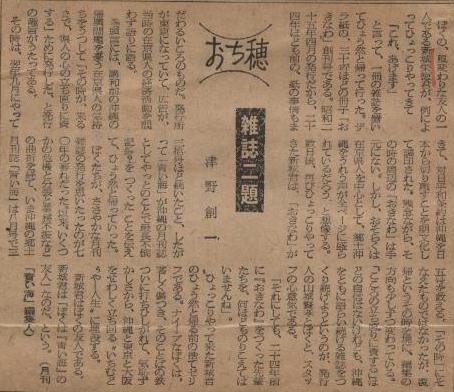
1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」
○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。
巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。
数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。
「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。
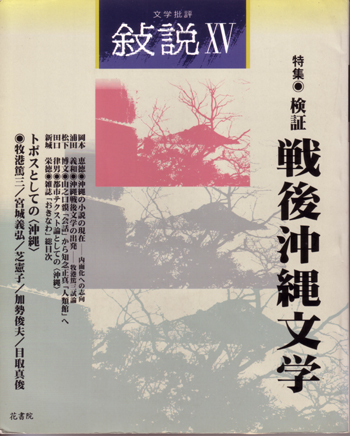

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」
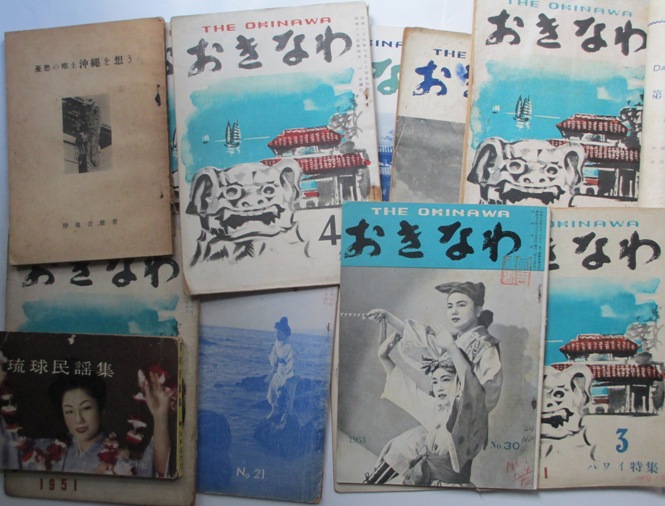
雑誌『おきなわ』
9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。
11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎
11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会
11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行
12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)
1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦
1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。
2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」
3月、『関西沖縄新報』創刊
4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳
4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇
8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久
1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正
1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称
1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮
1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。
1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」
1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。
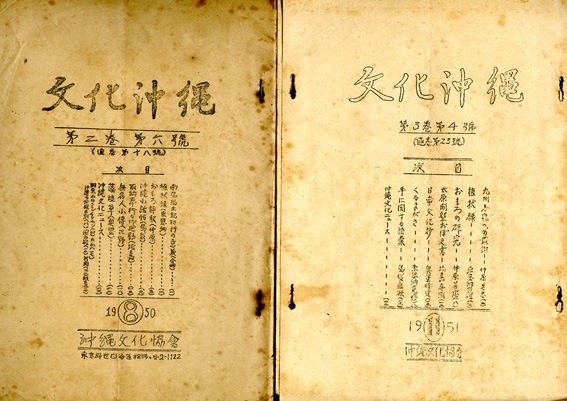
この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝
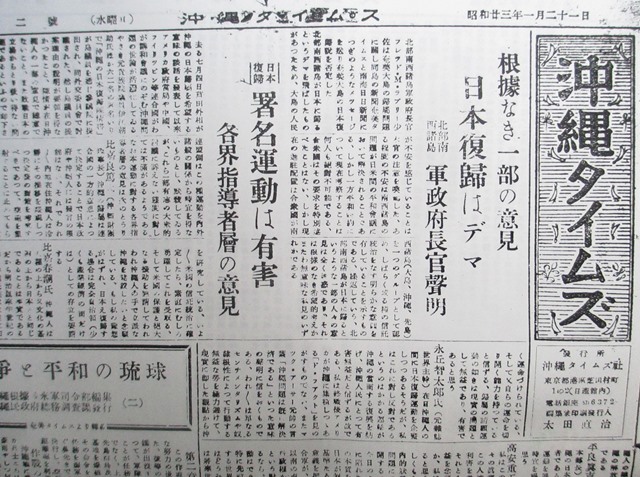
1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号
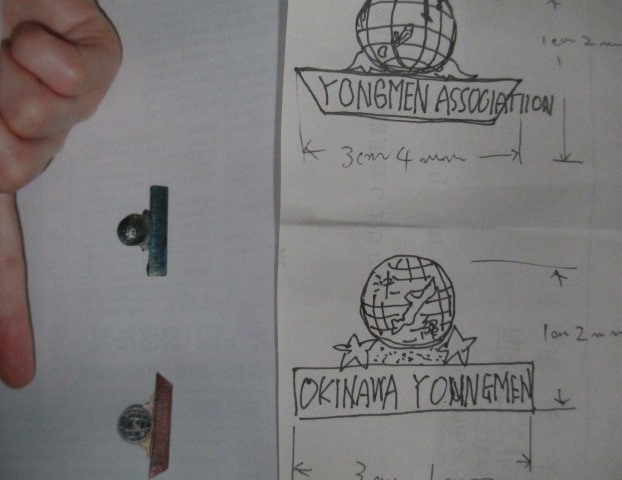
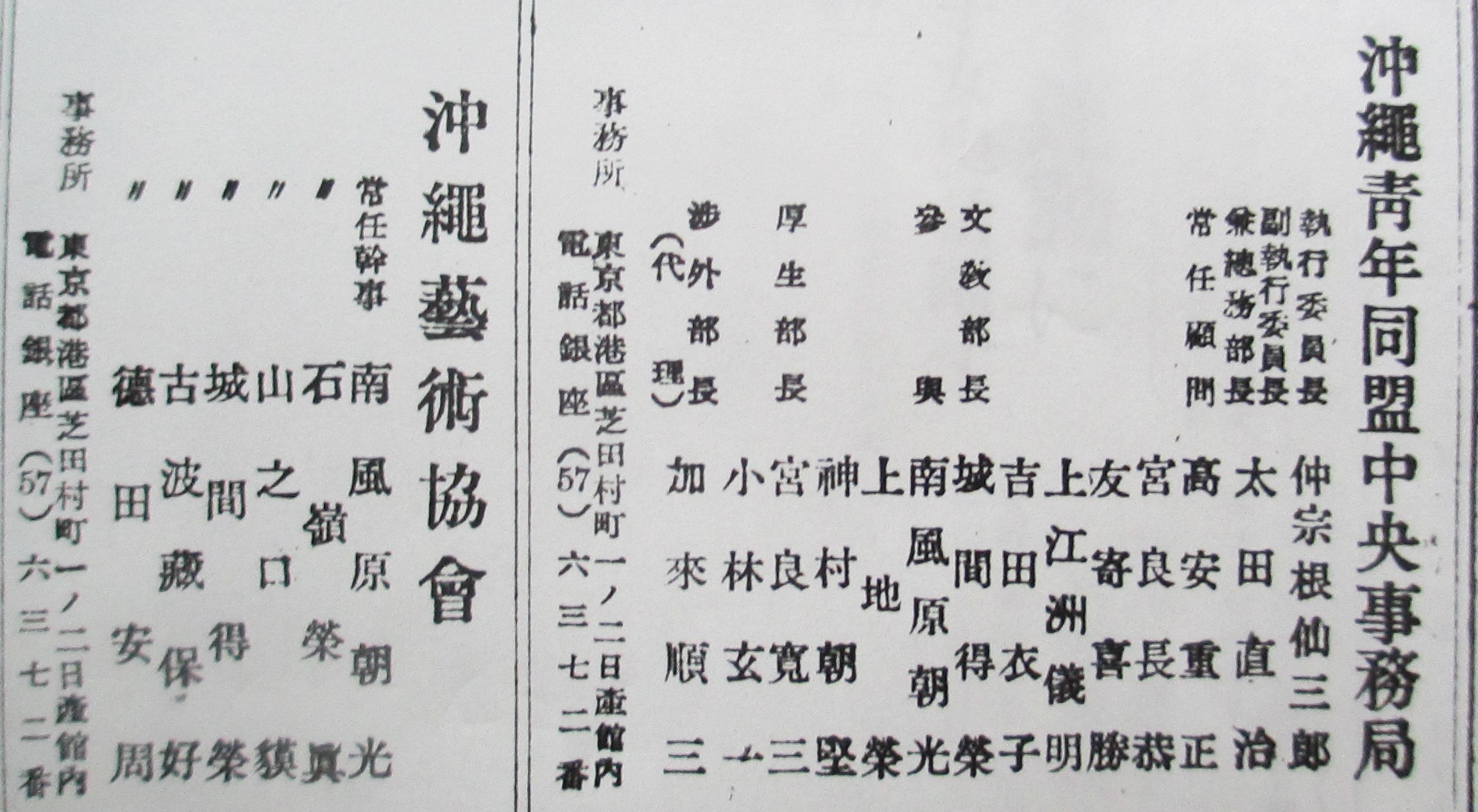
1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号
1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。
②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。
1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。
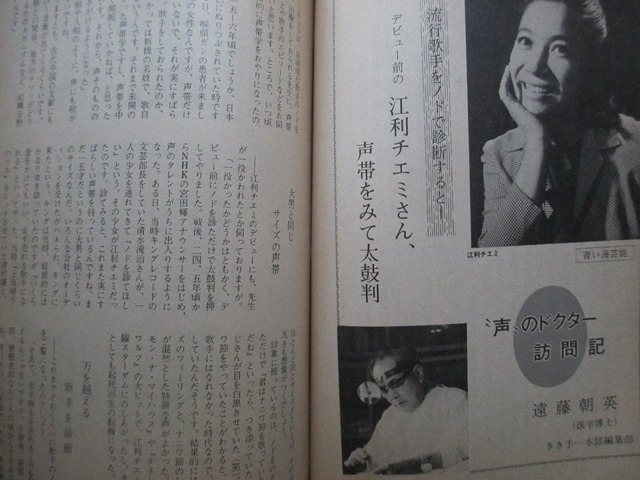
『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士
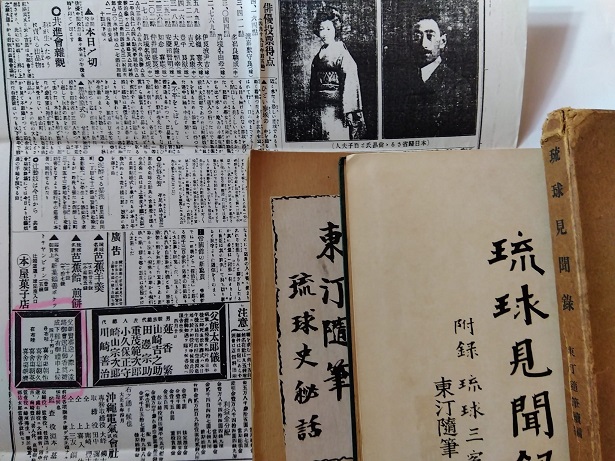
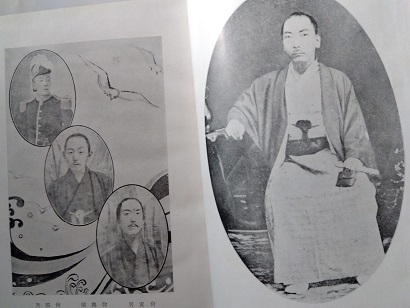
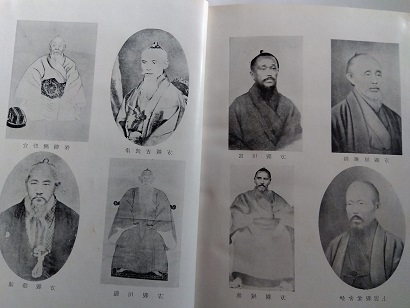
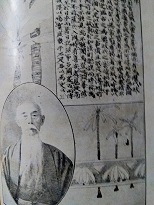
『琉球見聞録』東汀遺著刊行会、1952年11月。
喜舎場 朝賢(きしゃば ちょうけん、1840年〈天保11年〉 - 1916年〈大正5年〉4月14日)は、琉球王国末期の官僚。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、『琉球見聞録』を著した。童名は次郎。唐名は向(しょう)延翼。号は東汀。
晩年の1914年(大正3年)、琉球処分時の記録を『琉球見聞録』として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波普猷が「序に代えて 琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文を、巻末には発行者の親泊朝擢が「喜舎場朝賢翁小伝」をそれぞれ寄せている。波平恒男は、『琉球見聞録』の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で、差し障りがあったのではないかと推測している。→ウイキ
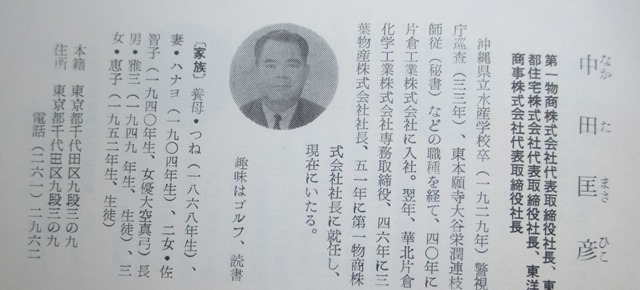
1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』
大空真弓 おおぞら-まゆみ
1940- 昭和後期-平成時代の女優。
昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。
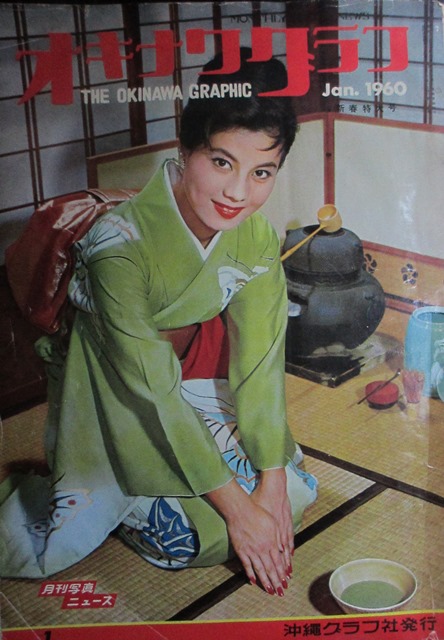
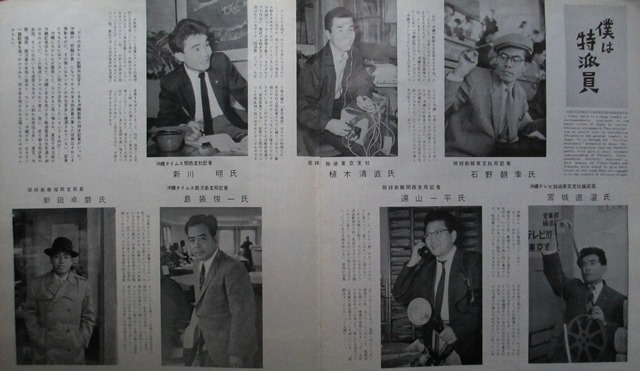
『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。
1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社
1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅
1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社
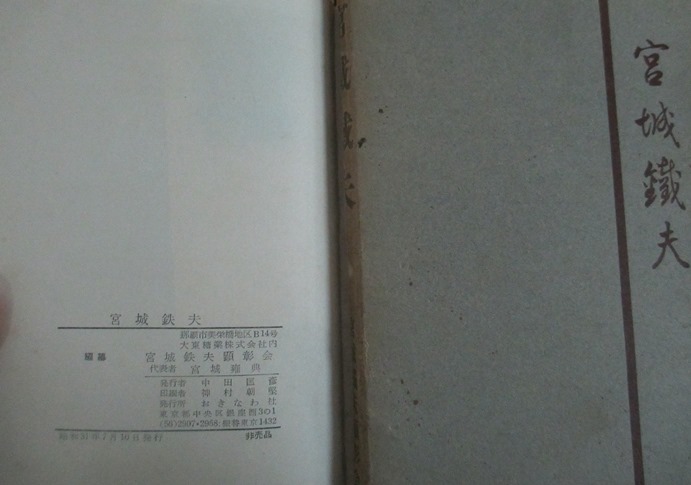 (BOOKSじのん在庫)
(BOOKSじのん在庫)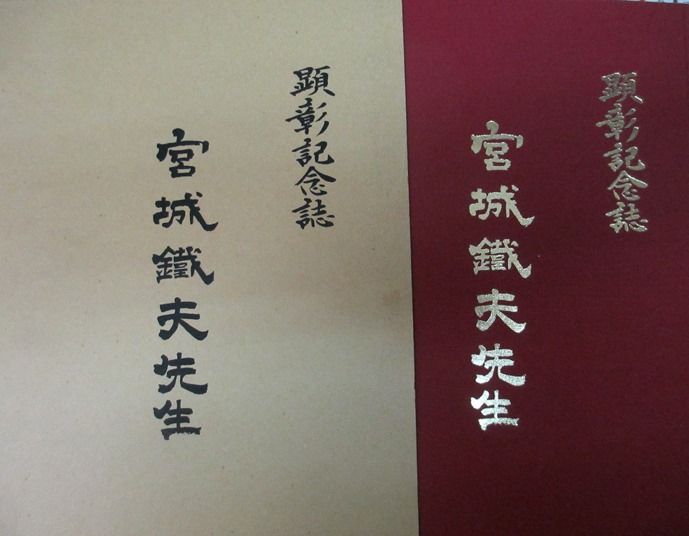
平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)
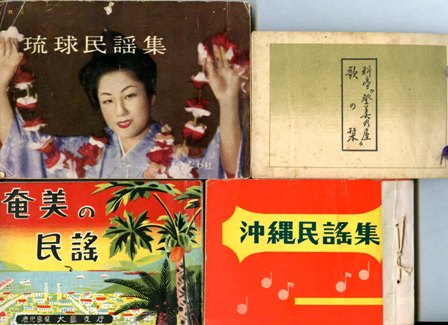
1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)
1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅
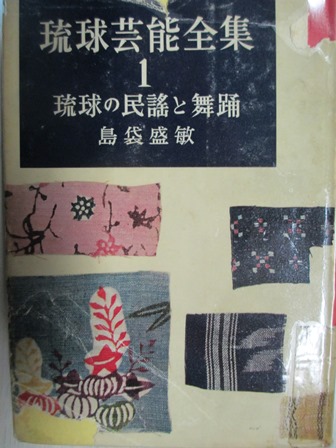
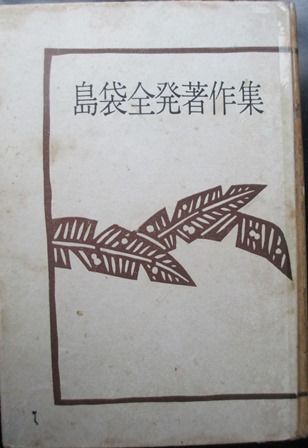
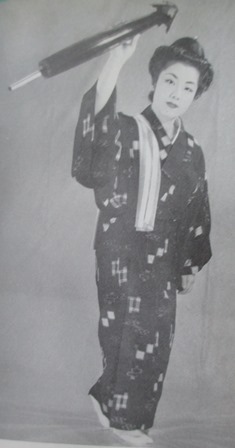
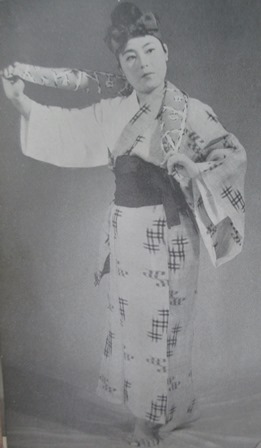
1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社
1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社
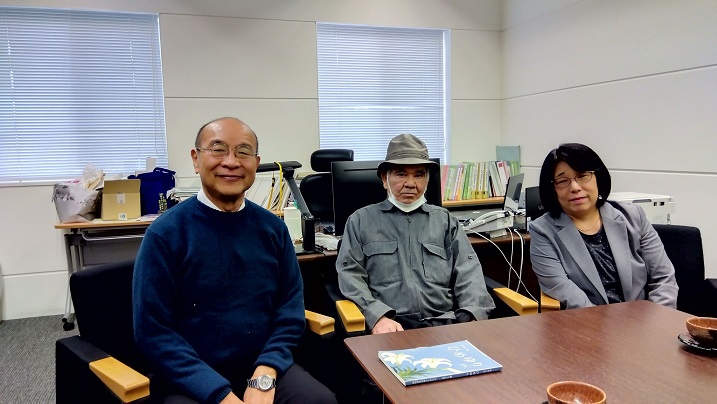
2025-2-5 沖縄県立博物館・美術館館長室:里井洋一館長、新城栄徳、大里知子法政大学沖縄文化研究所 准教授・専任所員
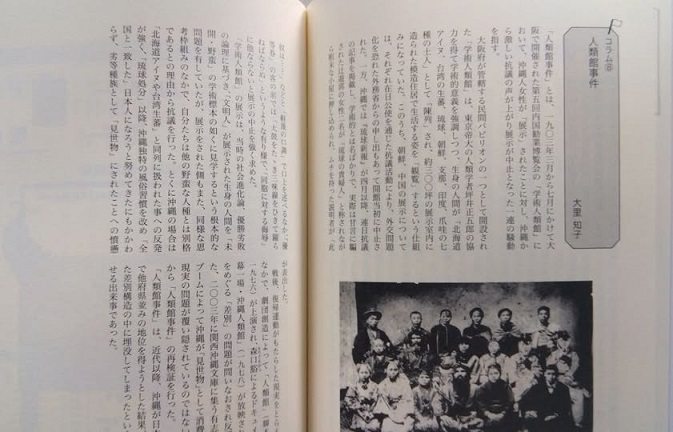
2021-11 『沖縄近現代史』ボーダーインク 大里知子「人類館事件」
1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社
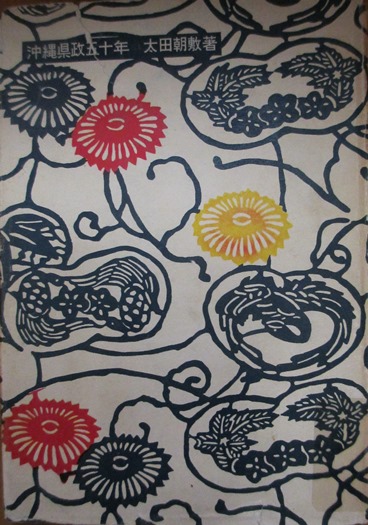
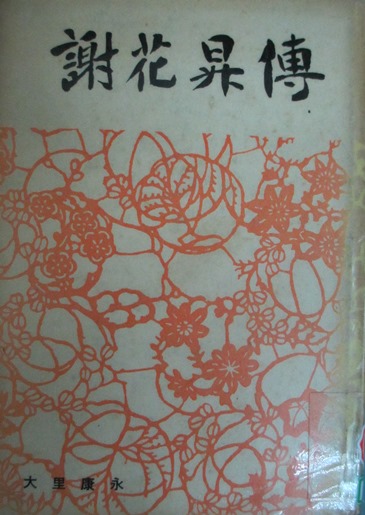
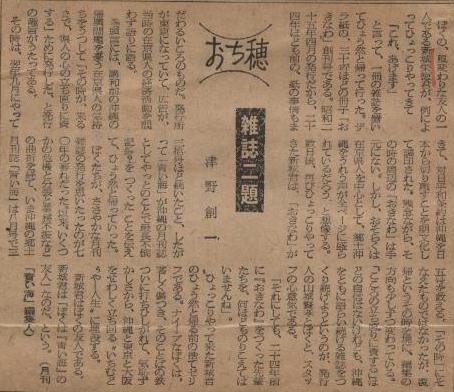
1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」
○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。
巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。
数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。
「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。
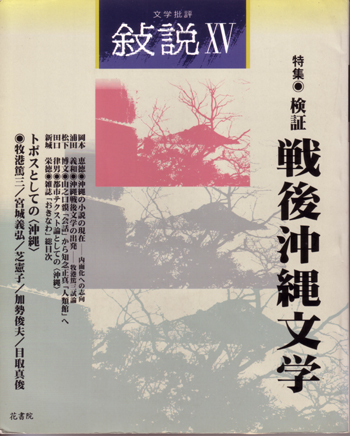

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」
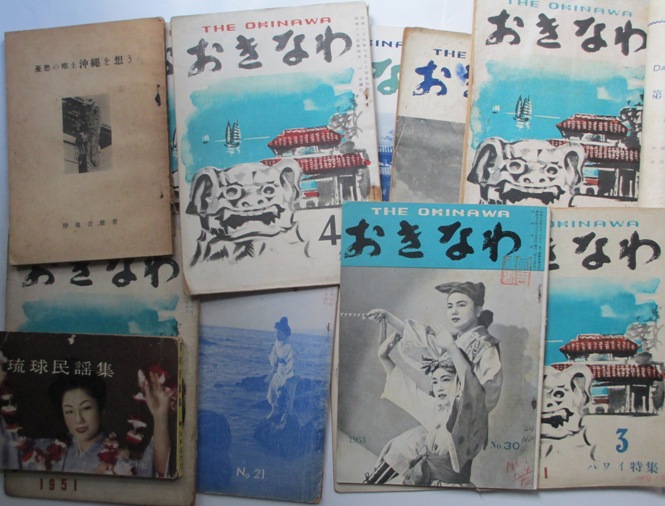
雑誌『おきなわ』
03/08: ウチナー美の森「描かれたジュリ」③
1966年12月ー神山邦彦『辻情史』神山青巧舎
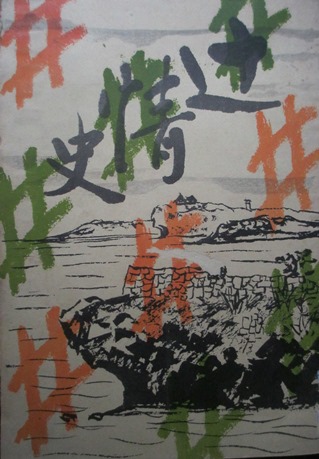

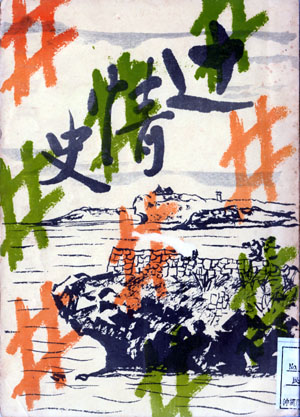
神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書
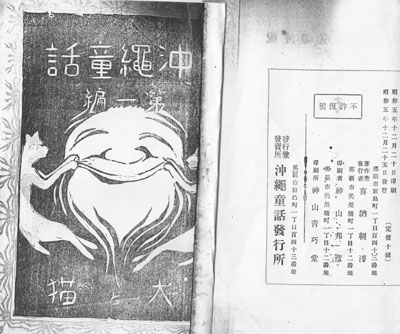
1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂
1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」
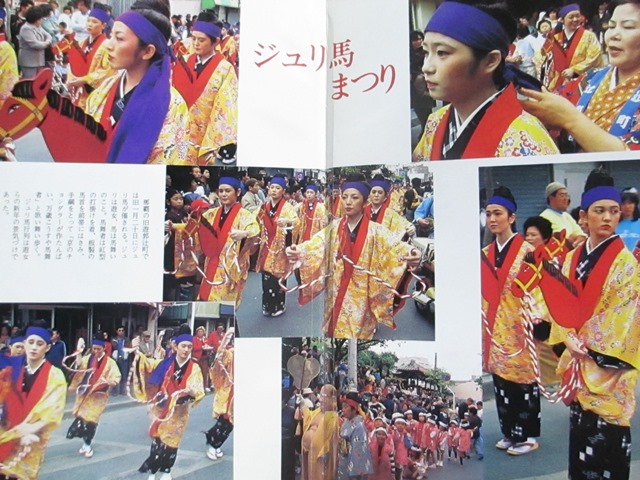
□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会
□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」


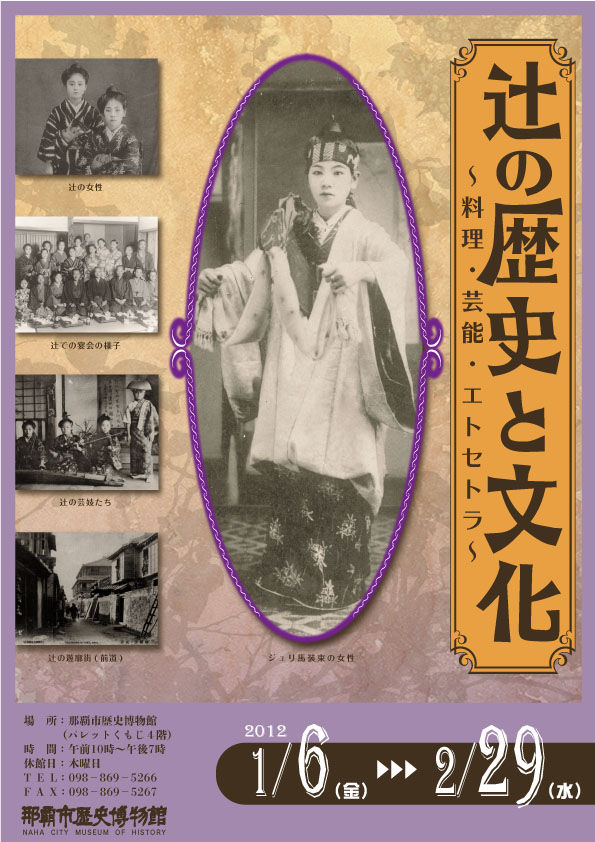
2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」
2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』
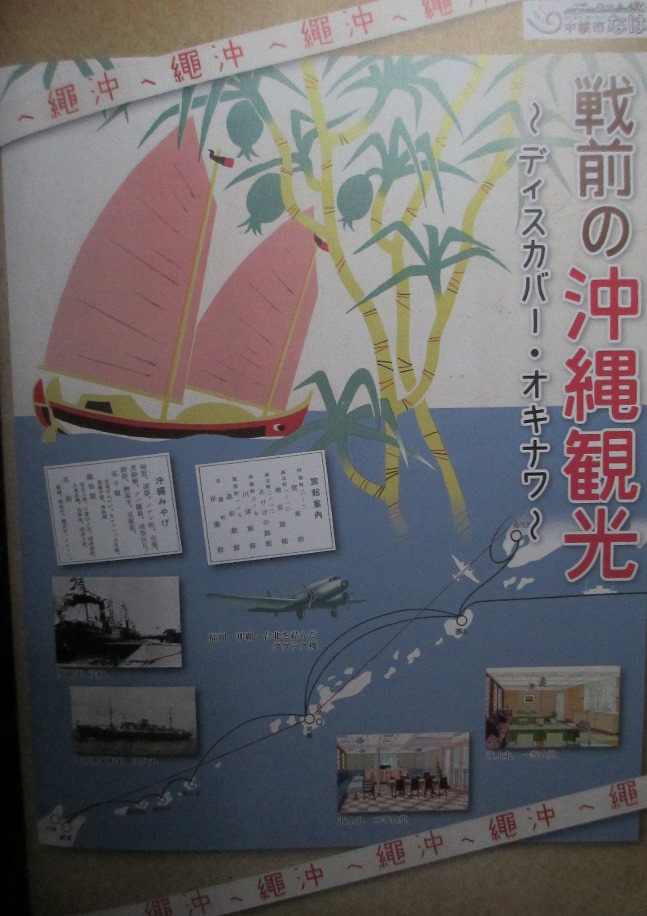
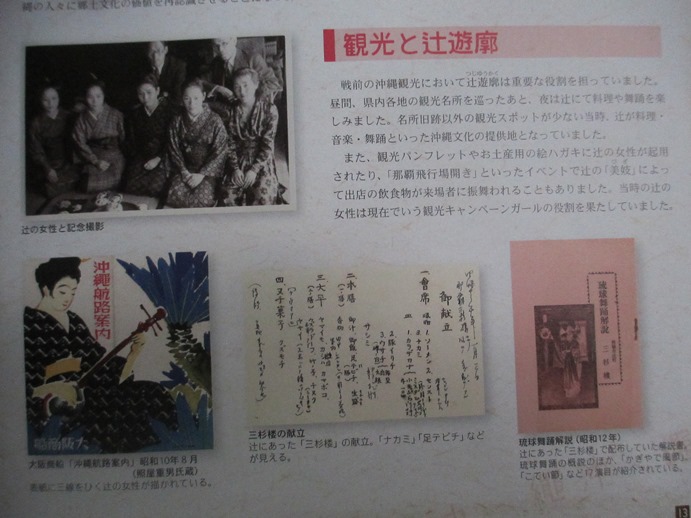
辻遊廓
戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。
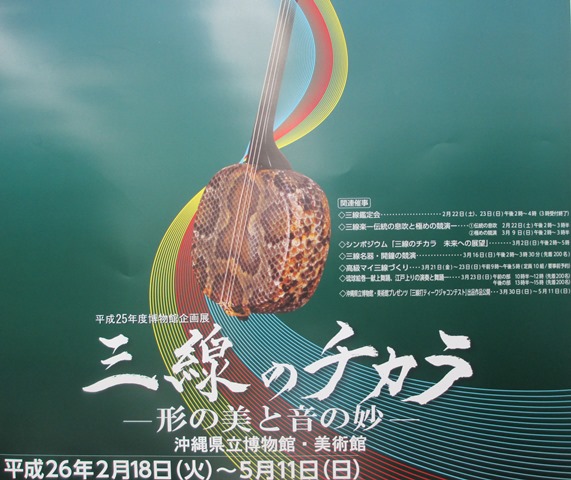
2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」
□三線をひくジュリの絵も展示されている。
沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相
場所:沖縄県立博物館・美術館
日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30




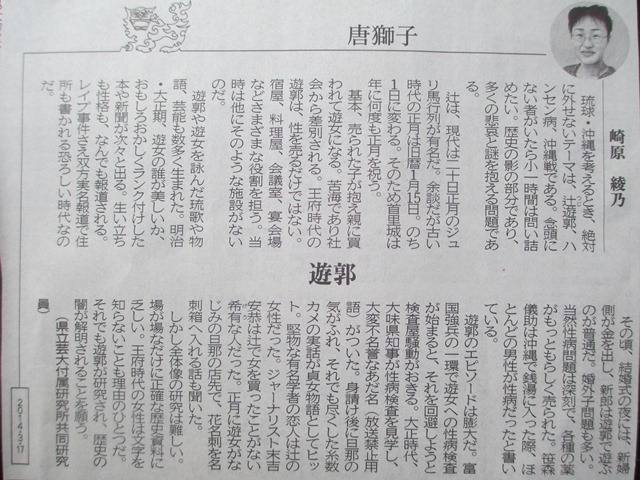
2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」
1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。
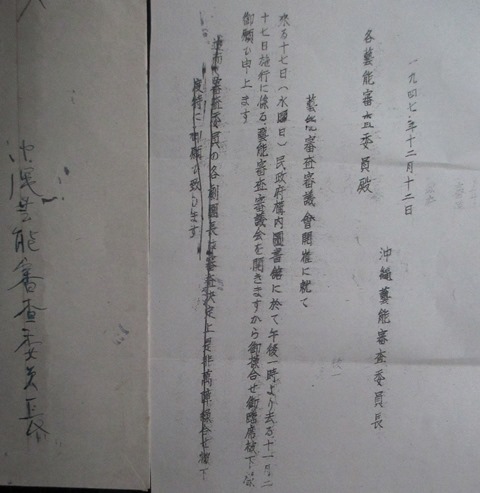
1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣
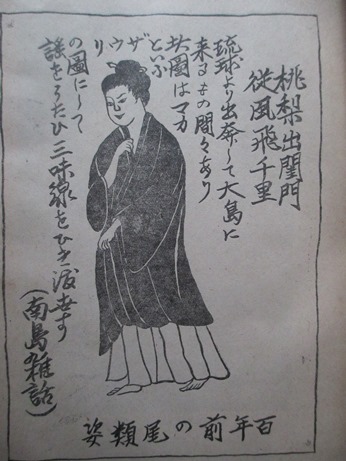
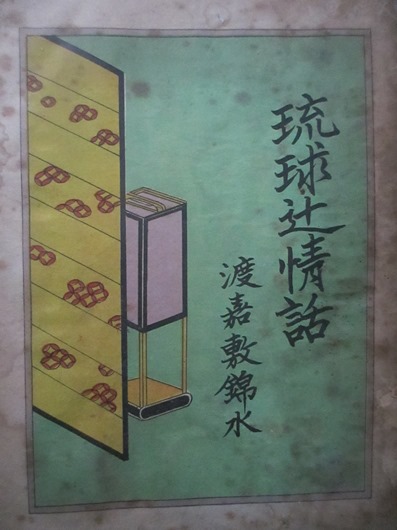
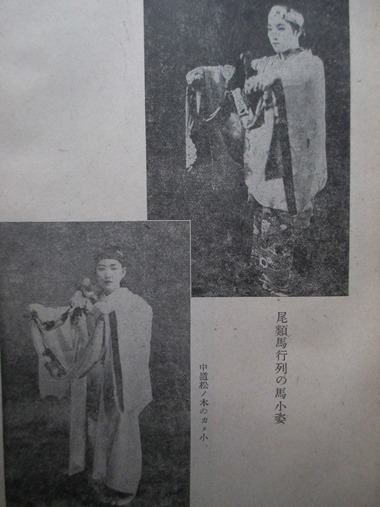
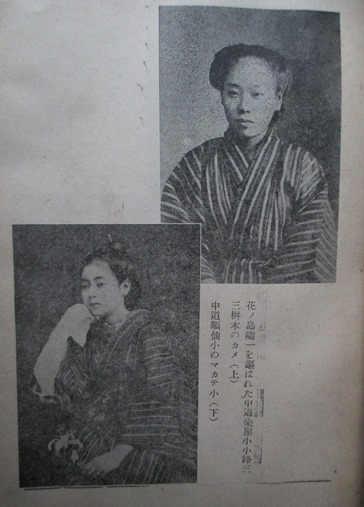
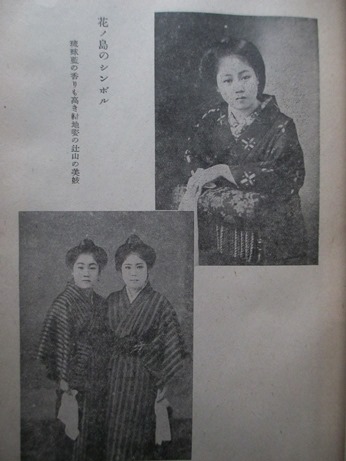
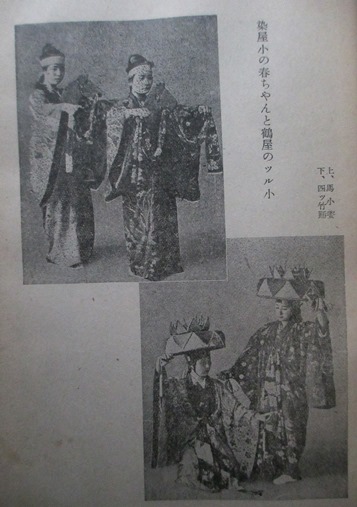




1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)
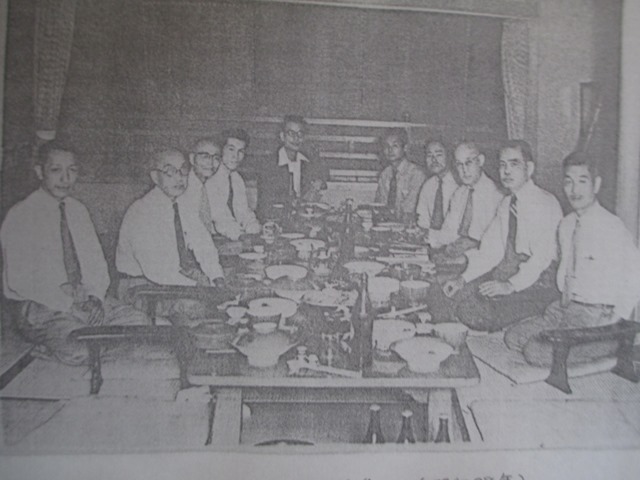
第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠
1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店
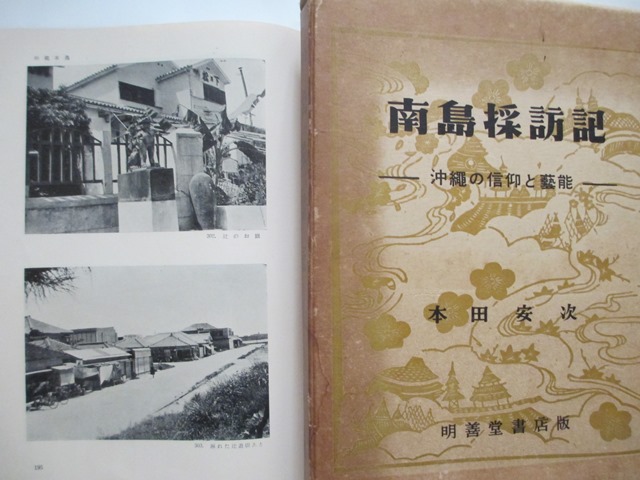
上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと
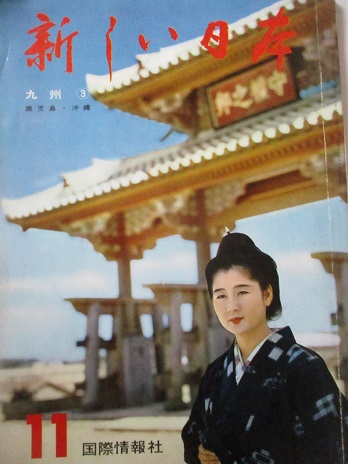
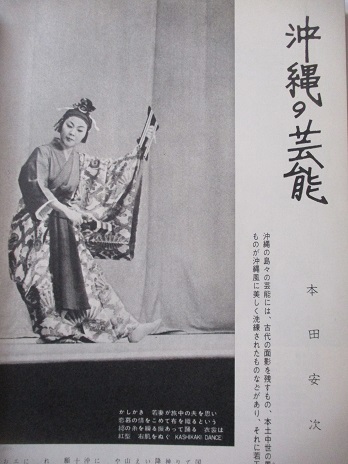
1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」
本田安次 ほんだ-やすじ
1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。
明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク
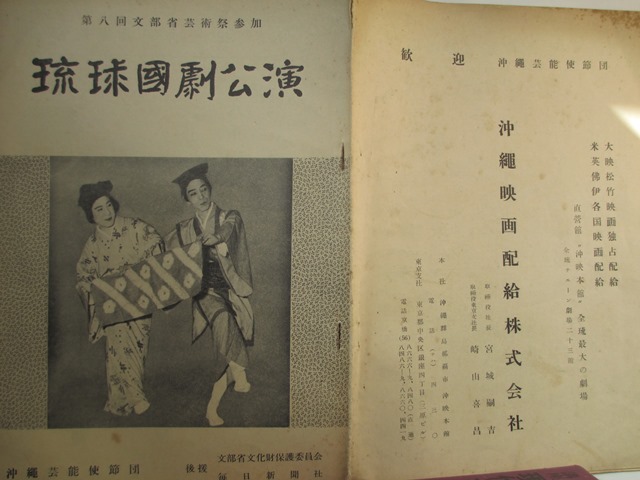
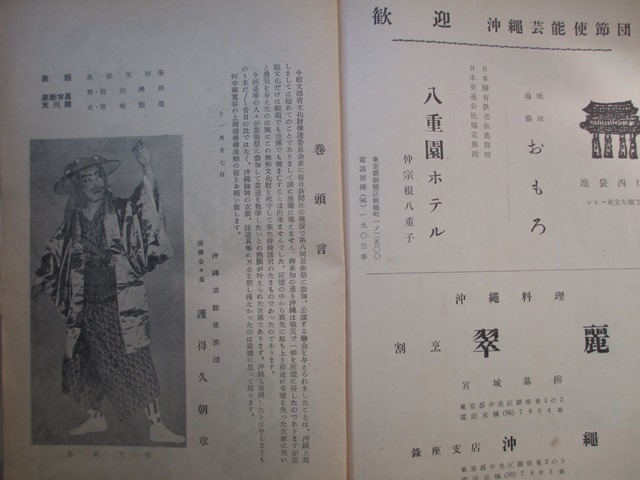
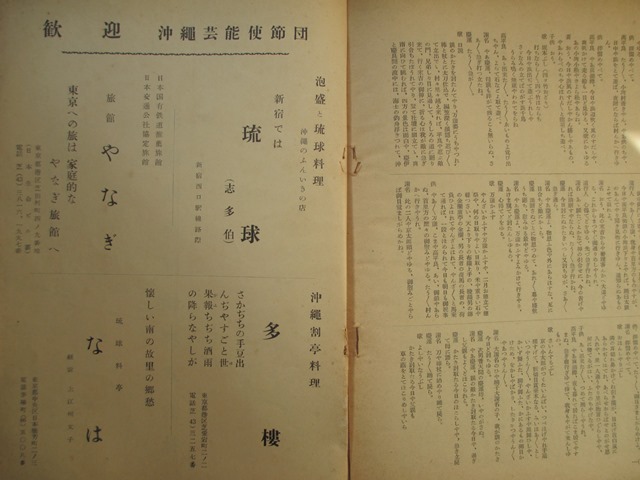
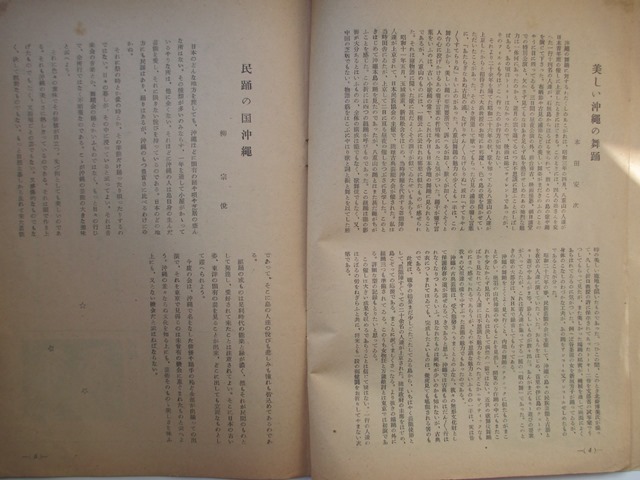
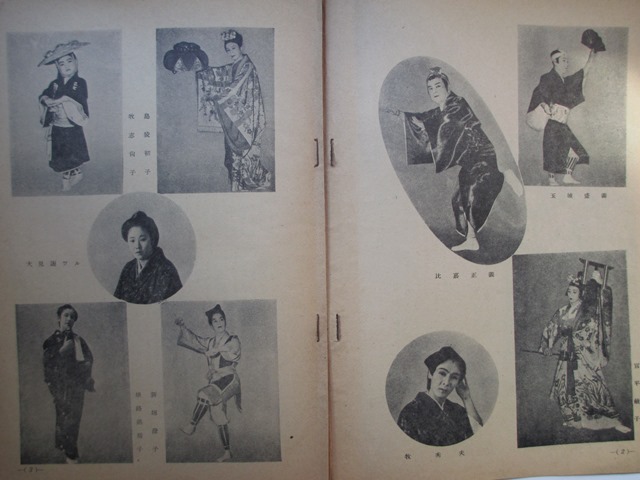
(翁長良明コレクション)
1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」
11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」
11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載
12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載
12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)
12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」
1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」
1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」
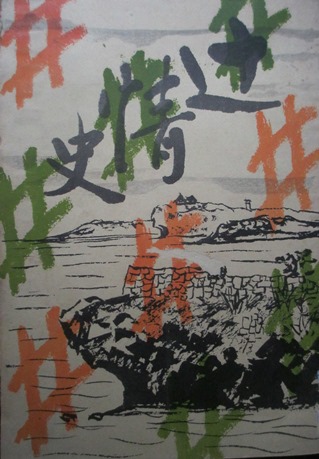

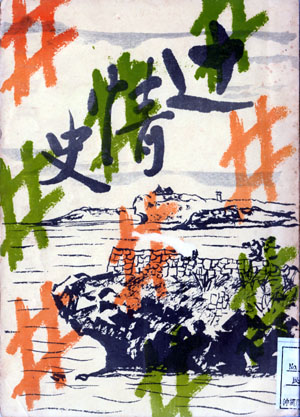
神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書
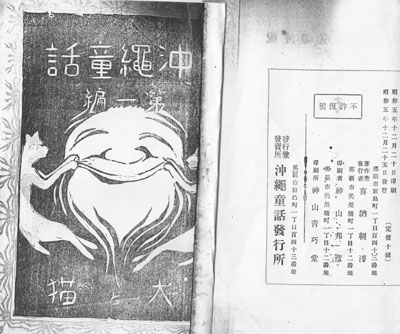
1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂
1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」
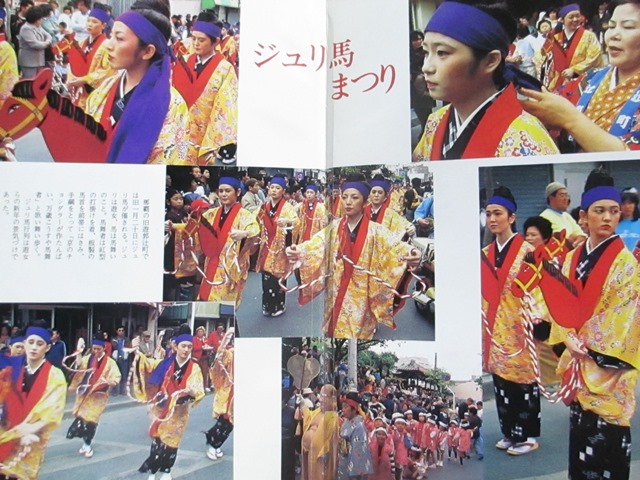
□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会
□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」


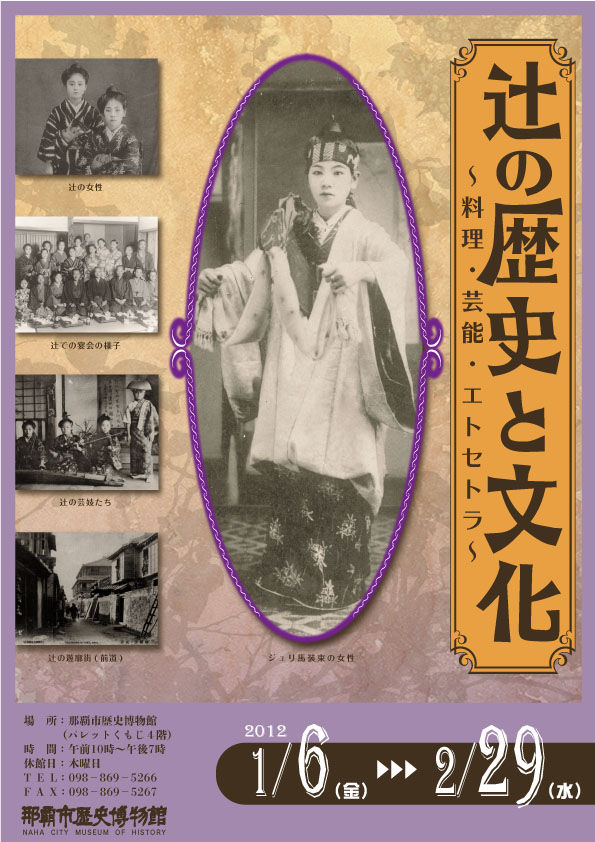
2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」
2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』
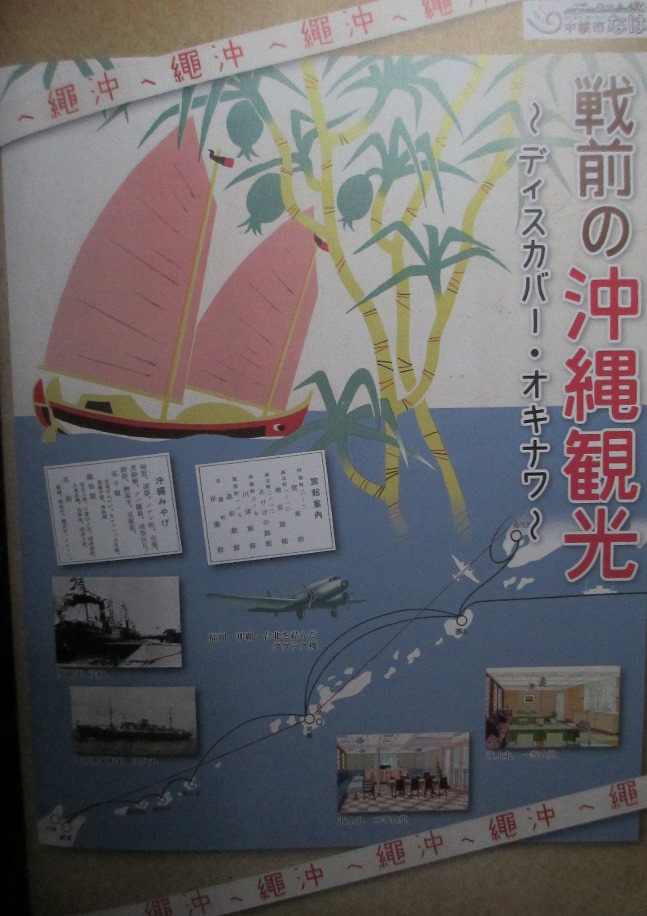
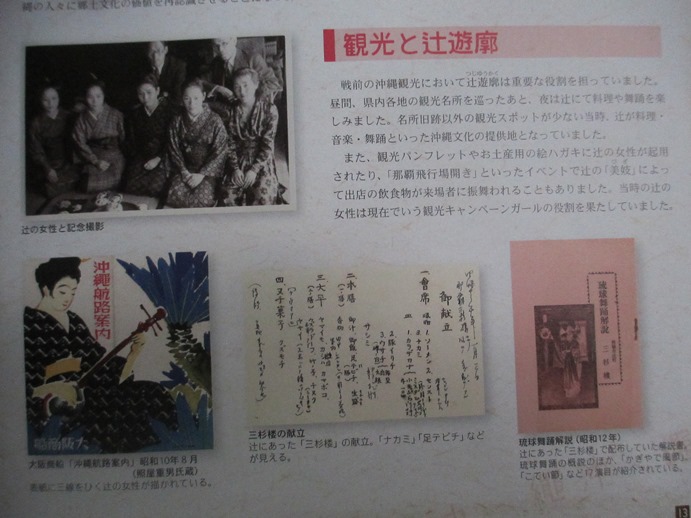
辻遊廓
戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。
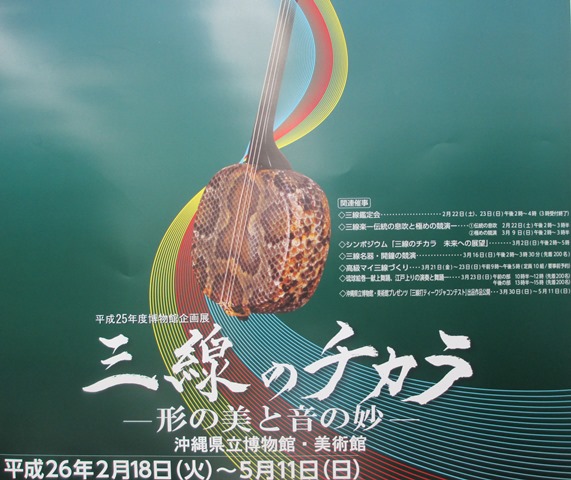
2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」
□三線をひくジュリの絵も展示されている。
沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相
場所:沖縄県立博物館・美術館
日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30




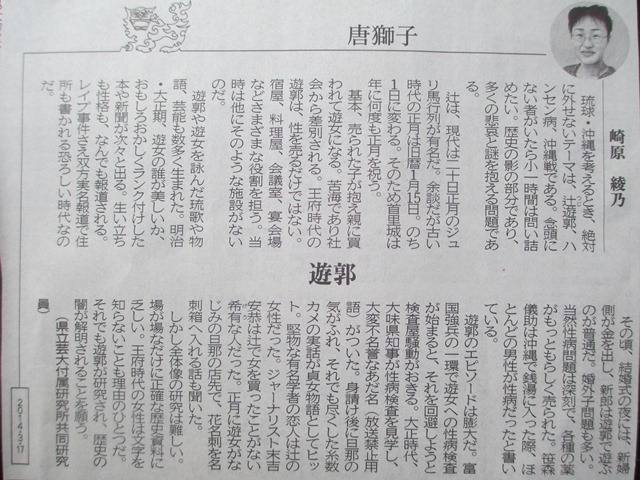
2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」
1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。
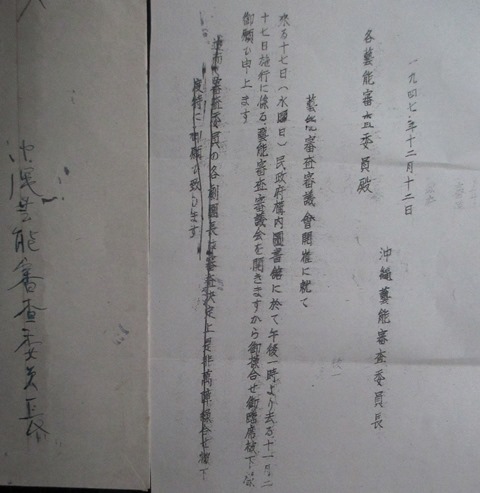
1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣
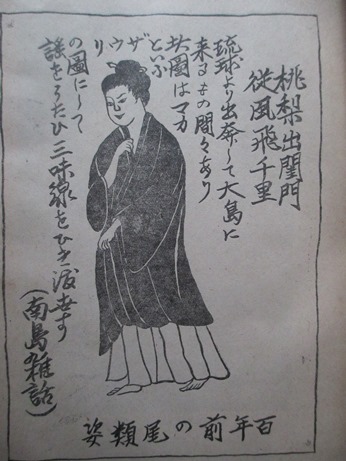
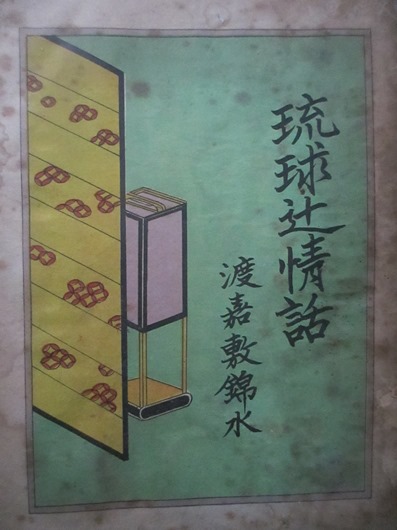
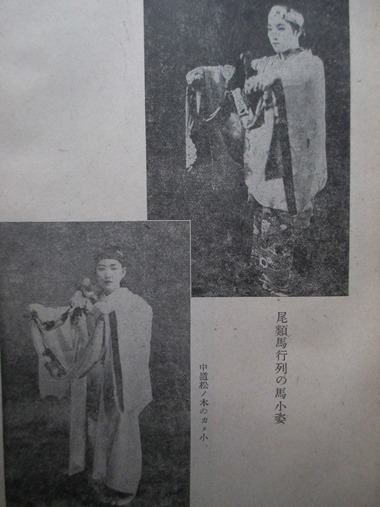
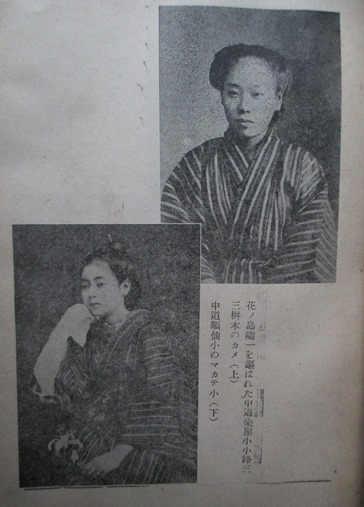
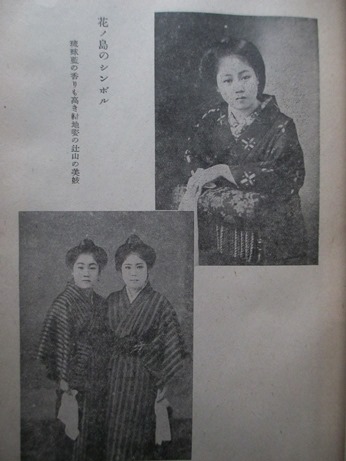
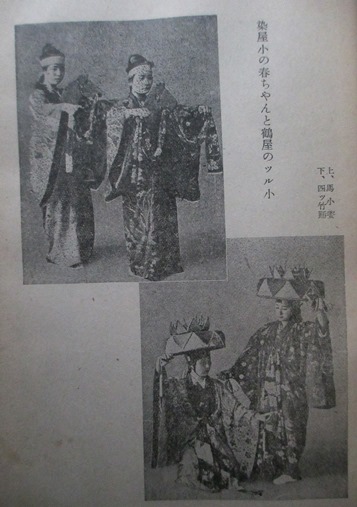




1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)
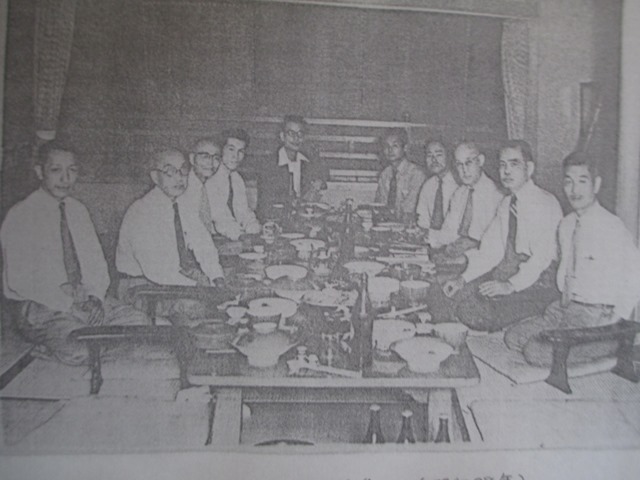
第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠
1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店
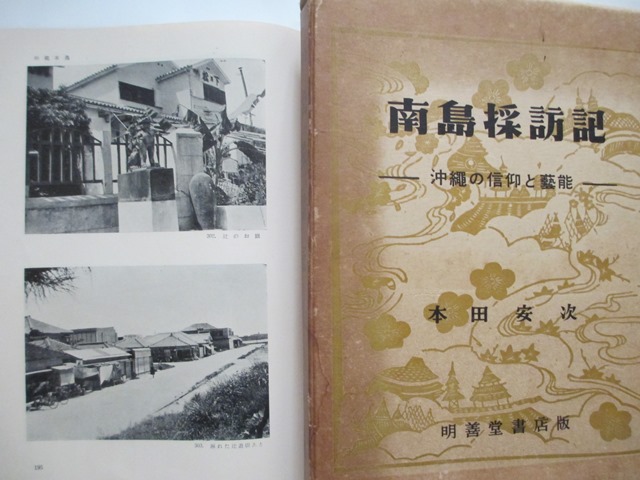
上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと
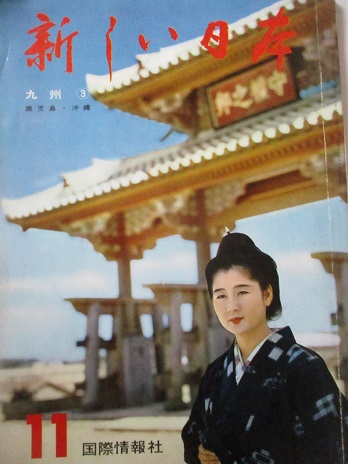
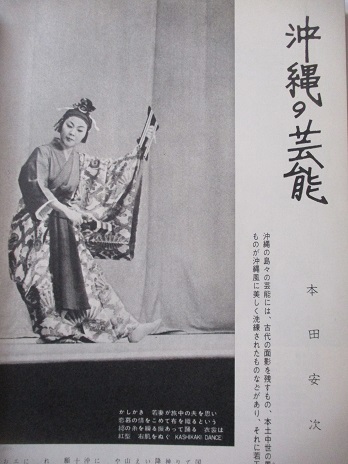
1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」
本田安次 ほんだ-やすじ
1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。
明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク
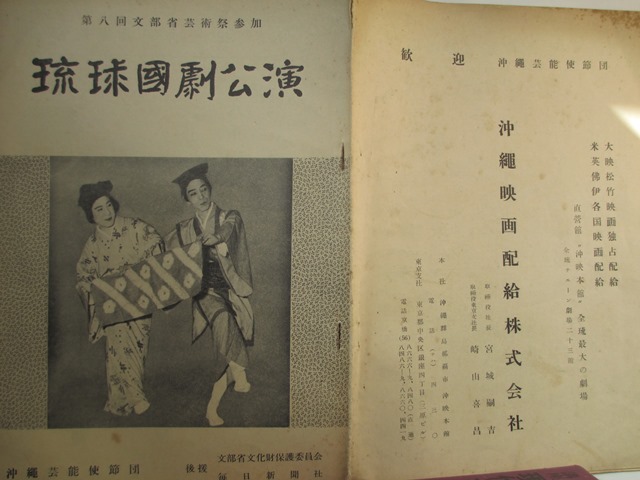
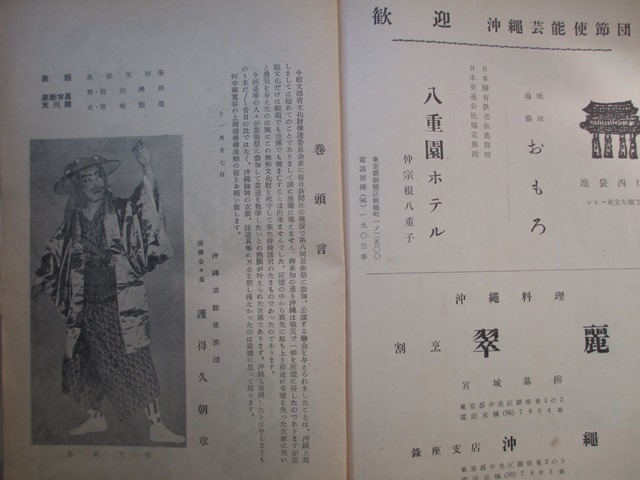
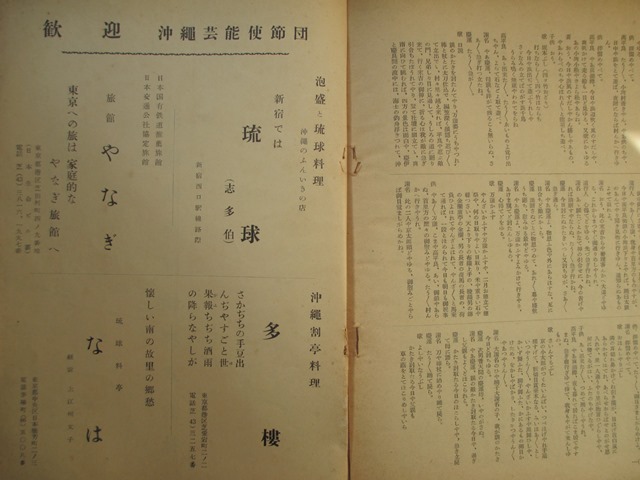
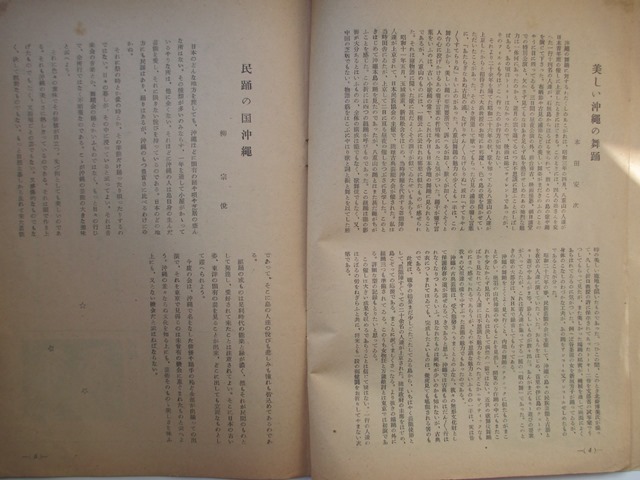
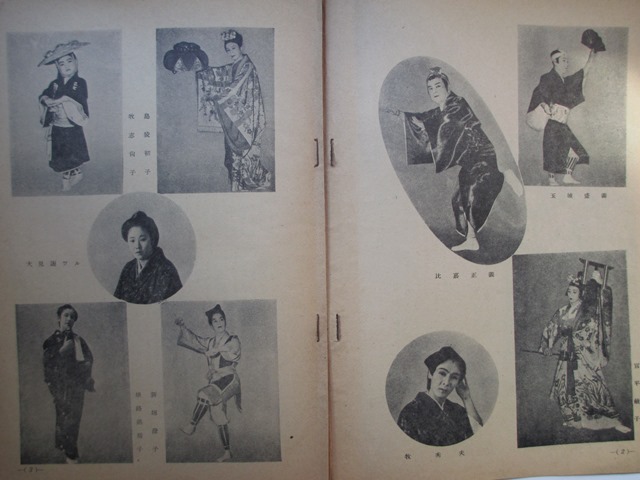
(翁長良明コレクション)
1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」
11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」
11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載
12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載
12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)
12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」
1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」
1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」
06/24: 翁長助静(歌人・原神青醉/翁長沖縄県知事の父)の沖縄戦
慰霊の日で翁長沖縄県知事が「平和宣言」
(略)それは、私たち沖縄県民が、その目や耳、肌に戦のもたらす悲惨さを鮮明に記憶しているからであり、戦争の犠牲になられた方々の安らかであることを心から願い、恒久平和を切望しているからです。戦後、私たちは、この思いを忘れることなく、復興と発展の道を力強く歩んでまいりました。しかしながら、国土面積の0・6%にすぎない本県に、日米安全保障体制を担う米軍専用施設の73・8%が集中し、依然として過重な基地負担が県民生活や本県の振興開発に様々な影響を与え続けています。米軍再編に基づく普天間飛行場の辺野古への移設をはじめ、嘉手納飛行場より南の米軍基地の整理縮小がなされても、専用施設面積の全国に占める割合はわずか0・7%しか縮小されず、返還時期も含め、基地負担の軽減とはほど遠いものであります。
沖縄の米軍基地問題は、我が国の安全保障の問題であり、国民全体で負担すべき重要な課題であります。特に、普天間飛行場の辺野古移設については、昨年の選挙で反対の民意が示されており、辺野古に新基地を建設することは困難であります。そもそも、私たち県民の思いとは全く別に、強制接収された世界一危険といわれる普天間飛行場の固定化は許されず、「その危険性除去のため辺野古に移設する」「嫌なら沖縄が代替案を出しなさい」との考えは、到底県民には許容できるものではありません。国民の自由、平等、人権、民主主義が等しく保障されずして、平和の礎を築くことはできないのであります。政府においては、固定観念に縛られず、普天間基地を辺野古へ移設する作業の中止を決断され、沖縄の基地負担を軽減する政策を再度見直されることを強く求めます。翁長沖縄県知事の宣言に会場からひときわ大きな拍手が沸き起こったが、安倍首相が登壇すると空気が一変。「帰れ」「戦争屋は出て行け」とブーイング。
知事の父・翁長助静が沖縄戦にふれている文章がある。
1944年4月 南風原青年学校長としての転勤命令が来た。若手教員抜てきの美名の下、大山朝常氏、長嶺秋夫氏ら多数も青年学校長に回された。着任当時はまだ週3回、教練だけでなく学科も教えていた。しかし戦局の悪化につれて毎日授業に広げられ、次第に陣地構築、壕堀りの作業が日課に。まさに”壕堀り隊長〝だ。同校では約1年の在任。8月、今や戦場必至の情勢と見た私は妻子4人を台湾に疎開させ、単身で学校長を続けた。翌年4月になると生徒も登校できない状態となり自然解散の状態。3月、田端一村先生が訪ねてこられ「沖縄翼賛会に来て加勢してくれ給え」。師範学校で編成した鉄血勤皇隊千早隊の十数人を部下とする情報宣伝部長が私の役目。翼賛会での私は国民服に戦闘帽、日本刀のいでたち。(略)途中、当時那覇署長をしておられた具志堅宗精氏、山川泰邦署僚などが、兼城の墓の中で署員の指揮をとっており、いまのひめゆりの塔近くでは金城増太郎三和村長が墓地に避難している。こうした人たちに「ここは戦場になるから早く避難して方がいい」と指示したが、行政も警察ももはや指揮系統はめちゃくちゃの状態。そんな所に妹の夫、国吉真政君と出会ったところ「負け戦にになっているのに親を放ったらかして何をしている」という。早速付近をうろうろしている父を見つけ、その日はヤギ小屋で一泊。翌日夕方摩文仁に移動しながら喜屋武岬近くで簡単な壕をつくって小休止。このとき突然米軍の砲撃を受け、目前で父助信が戦死した。同じ壕にいた十数人の避難民のなかで、父だけに破片が命中したのだから悲運としか言いようがない。日本の勝利を信じ命をかけて行動した私にも敗戦思想が強まってきた。敗残兵が住民を壕から追い出し、食糧を奪い取る光景も何度も見てきている。→沖縄タイムス社『私の戦後史 第5集』「翁長助静」
翁長助静(1907年8月25日、真和志村真嘉比生まれ~1983年2月6日)
1925年、沖縄県立第一中学校卒業。一中在学中、高江洲朝和(石野径一郎)、平良良松(那覇市長)らとガリ版の同人誌『はるがん』を発行。1926年、沖縄県師範学校本科二部卒業。第一豊見城、安里、本部、瀬底、の各尋常高等小学校訓導、南風原青年学校長を経て、戦後は大道小学校長、真和志村長、真和志市長、移民金庫専務理事、倉庫公社専務理事、立法院議員などを歴任。のち沖縄都市建設株式会社取締役社長となる。妻・和子(1914年生)、長男・助裕(1936年生)、二男・健二(1947年生)、三男・雄志(1950年生)。
歌人・原神青醉
1930年6月6日『沖縄朝日新聞』原神青醉「『新しさ』の否定ー旧概念で腐食した/生活から/生れ出た型!/そンにほんとうの/新しさがあらうか×トップを切る!/尖端を行く!要するに/旧生活からのつながりはないか ×明日への新しさは/先づ地球の引力から/すばらしい跳躍をしなければ/ならない/先づ旧生活を根本から/破壊しつくさねばならない×やがてそこから/生れて来る/何らかの型!/それこそほんとうの/新しさである 5・31 」
1931年1月26日『琉球新報』原神青醉「みちしほ短歌会」
1931年4月12日『琉球新報』原神青醉「さびしい反逆」
1933年9月『沖縄教育』
原神青醉「文苑ー車中行抄」
夜汽車
ふかぶかといねしづもれる大牟田のまちを/つらぬき汽車はゆくなり/をとこ二人何やら動きゐたりけりいねしづもれる街並みの一つ家に/ふなごやの駅にて乗りし男のめ つめたそうにもわれ見てありき/くらやみの果てのひかげのよびさます 旅愁にひたりて汽車窓にあり/汽車窓ごし見しは一つの燈なりけりくらやみの果てにともりてありき/呼びなれし久留米ときけば親しかりしまどをひらきて夜の街をみる/午前四時うすむらさきの空のもと久留米の街はただありけるも/漸くに暁けになりたるうれしさに座りなほりて煙草を吸ひける/朝あけのみどりうつるガラス戸に煙草のけむりふきかけて居り/博多駅近くの踏切番の四人まで姙婦にてありしは忘れ得られず/ささやかなみづき駅かもみづみづしき早稲のみのりのゆたかなるあたり/刑事ならむ 肩つつきざま職間ふなり/教員といへば笑ひて去りぬ
1933年5月14日『琉球新報』原神青醉「みちしほ短歌会」
1936年2月 『琉球新報』翁長助静「話方教育の一部分ー島尻郡第一区域童話会印象記」連載

沖縄県立博物館・美術館横にある翁長助静、真栄城守行/真和志村立安里尋常高等小学校(現在の安謝小学校)跡の碑

立法院


真喜志好一氏らと「立法院棟保存」を自民党の翁長雄志県議会議員に要望する。

沖縄県公文書館入口に保存されている立法院棟柱
仲村顕さんの調べによると、1932年の「婦人公論」に「滅びゆく琉球女の手記」を書いた作家の久志芙沙子(1903―86年)の父は久志助保(?―1915年)、祖父は久志助法(1835―1900年)でいずれも漢詩人。助法は「顧国柱(ここくちゅう)詩稿」などを書き、漢詩人の森槐南(もりかいなん)とも交流があった。また、琉球王国の評定所で中国や日本への文書を作成する「筆者主取」を廃藩置県(1879年)まで務めた最後の人。那覇市歴史博物館収蔵の尚家関係資料に助法直筆文書が残る。氏集によると、顧氏は大宗顧保安比嘉筑登之親雲上助輝。その四世が久志親方助豊支流二子顧天祐久志里之子助眞が翁長家の祖となっている。他に普天間、名嘉山、津波古などがある。
(略)それは、私たち沖縄県民が、その目や耳、肌に戦のもたらす悲惨さを鮮明に記憶しているからであり、戦争の犠牲になられた方々の安らかであることを心から願い、恒久平和を切望しているからです。戦後、私たちは、この思いを忘れることなく、復興と発展の道を力強く歩んでまいりました。しかしながら、国土面積の0・6%にすぎない本県に、日米安全保障体制を担う米軍専用施設の73・8%が集中し、依然として過重な基地負担が県民生活や本県の振興開発に様々な影響を与え続けています。米軍再編に基づく普天間飛行場の辺野古への移設をはじめ、嘉手納飛行場より南の米軍基地の整理縮小がなされても、専用施設面積の全国に占める割合はわずか0・7%しか縮小されず、返還時期も含め、基地負担の軽減とはほど遠いものであります。
沖縄の米軍基地問題は、我が国の安全保障の問題であり、国民全体で負担すべき重要な課題であります。特に、普天間飛行場の辺野古移設については、昨年の選挙で反対の民意が示されており、辺野古に新基地を建設することは困難であります。そもそも、私たち県民の思いとは全く別に、強制接収された世界一危険といわれる普天間飛行場の固定化は許されず、「その危険性除去のため辺野古に移設する」「嫌なら沖縄が代替案を出しなさい」との考えは、到底県民には許容できるものではありません。国民の自由、平等、人権、民主主義が等しく保障されずして、平和の礎を築くことはできないのであります。政府においては、固定観念に縛られず、普天間基地を辺野古へ移設する作業の中止を決断され、沖縄の基地負担を軽減する政策を再度見直されることを強く求めます。翁長沖縄県知事の宣言に会場からひときわ大きな拍手が沸き起こったが、安倍首相が登壇すると空気が一変。「帰れ」「戦争屋は出て行け」とブーイング。
知事の父・翁長助静が沖縄戦にふれている文章がある。
1944年4月 南風原青年学校長としての転勤命令が来た。若手教員抜てきの美名の下、大山朝常氏、長嶺秋夫氏ら多数も青年学校長に回された。着任当時はまだ週3回、教練だけでなく学科も教えていた。しかし戦局の悪化につれて毎日授業に広げられ、次第に陣地構築、壕堀りの作業が日課に。まさに”壕堀り隊長〝だ。同校では約1年の在任。8月、今や戦場必至の情勢と見た私は妻子4人を台湾に疎開させ、単身で学校長を続けた。翌年4月になると生徒も登校できない状態となり自然解散の状態。3月、田端一村先生が訪ねてこられ「沖縄翼賛会に来て加勢してくれ給え」。師範学校で編成した鉄血勤皇隊千早隊の十数人を部下とする情報宣伝部長が私の役目。翼賛会での私は国民服に戦闘帽、日本刀のいでたち。(略)途中、当時那覇署長をしておられた具志堅宗精氏、山川泰邦署僚などが、兼城の墓の中で署員の指揮をとっており、いまのひめゆりの塔近くでは金城増太郎三和村長が墓地に避難している。こうした人たちに「ここは戦場になるから早く避難して方がいい」と指示したが、行政も警察ももはや指揮系統はめちゃくちゃの状態。そんな所に妹の夫、国吉真政君と出会ったところ「負け戦にになっているのに親を放ったらかして何をしている」という。早速付近をうろうろしている父を見つけ、その日はヤギ小屋で一泊。翌日夕方摩文仁に移動しながら喜屋武岬近くで簡単な壕をつくって小休止。このとき突然米軍の砲撃を受け、目前で父助信が戦死した。同じ壕にいた十数人の避難民のなかで、父だけに破片が命中したのだから悲運としか言いようがない。日本の勝利を信じ命をかけて行動した私にも敗戦思想が強まってきた。敗残兵が住民を壕から追い出し、食糧を奪い取る光景も何度も見てきている。→沖縄タイムス社『私の戦後史 第5集』「翁長助静」
翁長助静(1907年8月25日、真和志村真嘉比生まれ~1983年2月6日)
1925年、沖縄県立第一中学校卒業。一中在学中、高江洲朝和(石野径一郎)、平良良松(那覇市長)らとガリ版の同人誌『はるがん』を発行。1926年、沖縄県師範学校本科二部卒業。第一豊見城、安里、本部、瀬底、の各尋常高等小学校訓導、南風原青年学校長を経て、戦後は大道小学校長、真和志村長、真和志市長、移民金庫専務理事、倉庫公社専務理事、立法院議員などを歴任。のち沖縄都市建設株式会社取締役社長となる。妻・和子(1914年生)、長男・助裕(1936年生)、二男・健二(1947年生)、三男・雄志(1950年生)。
歌人・原神青醉
1930年6月6日『沖縄朝日新聞』原神青醉「『新しさ』の否定ー旧概念で腐食した/生活から/生れ出た型!/そンにほんとうの/新しさがあらうか×トップを切る!/尖端を行く!要するに/旧生活からのつながりはないか ×明日への新しさは/先づ地球の引力から/すばらしい跳躍をしなければ/ならない/先づ旧生活を根本から/破壊しつくさねばならない×やがてそこから/生れて来る/何らかの型!/それこそほんとうの/新しさである 5・31 」
1931年1月26日『琉球新報』原神青醉「みちしほ短歌会」
1931年4月12日『琉球新報』原神青醉「さびしい反逆」
1933年9月『沖縄教育』
原神青醉「文苑ー車中行抄」
夜汽車
ふかぶかといねしづもれる大牟田のまちを/つらぬき汽車はゆくなり/をとこ二人何やら動きゐたりけりいねしづもれる街並みの一つ家に/ふなごやの駅にて乗りし男のめ つめたそうにもわれ見てありき/くらやみの果てのひかげのよびさます 旅愁にひたりて汽車窓にあり/汽車窓ごし見しは一つの燈なりけりくらやみの果てにともりてありき/呼びなれし久留米ときけば親しかりしまどをひらきて夜の街をみる/午前四時うすむらさきの空のもと久留米の街はただありけるも/漸くに暁けになりたるうれしさに座りなほりて煙草を吸ひける/朝あけのみどりうつるガラス戸に煙草のけむりふきかけて居り/博多駅近くの踏切番の四人まで姙婦にてありしは忘れ得られず/ささやかなみづき駅かもみづみづしき早稲のみのりのゆたかなるあたり/刑事ならむ 肩つつきざま職間ふなり/教員といへば笑ひて去りぬ
1933年5月14日『琉球新報』原神青醉「みちしほ短歌会」
1936年2月 『琉球新報』翁長助静「話方教育の一部分ー島尻郡第一区域童話会印象記」連載

沖縄県立博物館・美術館横にある翁長助静、真栄城守行/真和志村立安里尋常高等小学校(現在の安謝小学校)跡の碑

立法院


真喜志好一氏らと「立法院棟保存」を自民党の翁長雄志県議会議員に要望する。

沖縄県公文書館入口に保存されている立法院棟柱
仲村顕さんの調べによると、1932年の「婦人公論」に「滅びゆく琉球女の手記」を書いた作家の久志芙沙子(1903―86年)の父は久志助保(?―1915年)、祖父は久志助法(1835―1900年)でいずれも漢詩人。助法は「顧国柱(ここくちゅう)詩稿」などを書き、漢詩人の森槐南(もりかいなん)とも交流があった。また、琉球王国の評定所で中国や日本への文書を作成する「筆者主取」を廃藩置県(1879年)まで務めた最後の人。那覇市歴史博物館収蔵の尚家関係資料に助法直筆文書が残る。氏集によると、顧氏は大宗顧保安比嘉筑登之親雲上助輝。その四世が久志親方助豊支流二子顧天祐久志里之子助眞が翁長家の祖となっている。他に普天間、名嘉山、津波古などがある。
05/29: 世相ジャパン①/1960年
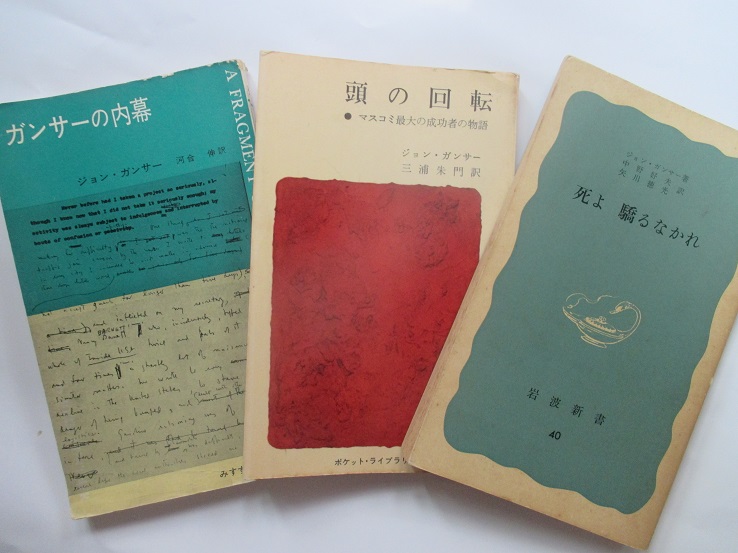
1961年7月 ジョン・ガンサー 三浦朱門 訳『頭の回転=マスコミ最大の成功者の物語=』新潮社
1964年12月7日、カーチス・エマーソン・ルメイ(Curtis Emerson LeMay,)勲一等旭日大綬章を入間基地で浦茂航空幕僚長から授与された。理由は日本の航空自衛隊育成に協力があったためである。12月4日の第1次佐藤内閣の閣議で決定された。叙勲は、浦茂幕僚長がルメイを航空自衛隊創立10周年式典に招待したことを発端とした防衛庁の調査、審査に基づく国際慣例による佐藤内閣の決定であることが明かされている。推薦は防衛庁長官小泉純也と外務大臣椎名悦三郎の連名で行われる。→ウィキ
1965年4月 『思想の科学』№37<特集・日本の黒幕>思想の科学社
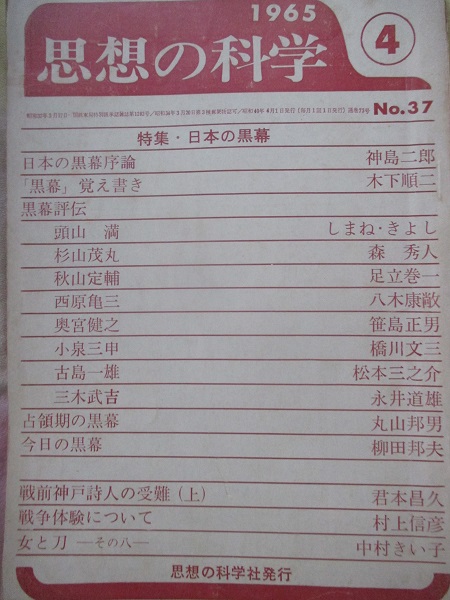
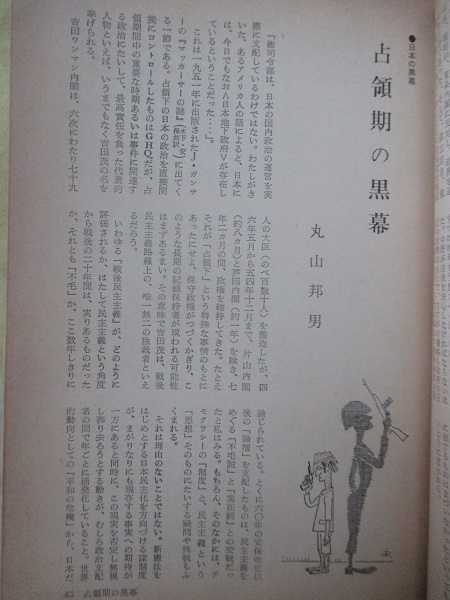
丸山邦男〇占領期の黒幕ー「総指令部は、日本の国内政治の運営を実際に支配しているわけではない。わたしがきいた、あるアメリカ人の話によると、日本には、今日でもなお<日本地下政府>が存在しているということだった・・・・」。これは1951年に出版されたJ・ガンサーの『マッカーサーの謎』(木下・安保共訳)に出てくる一節である。占領下の日本の政治を直接間接にコントロールしたものはGHQだが、占領期間中の重要な時期あるいは事件に関連する政治にたいして、最高責任を負った代表的人物といえば、いうまでもなく吉田茂の名を挙げられる。
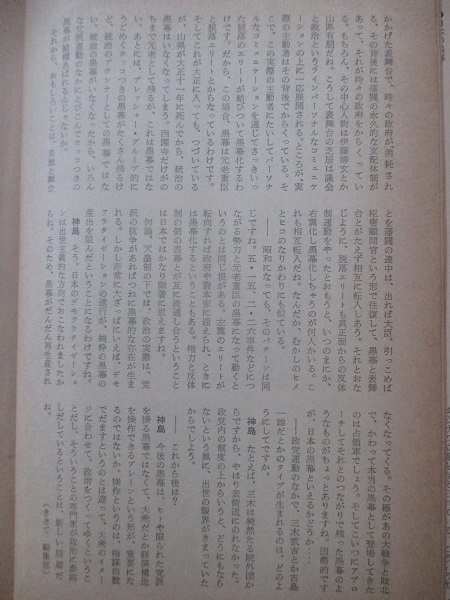
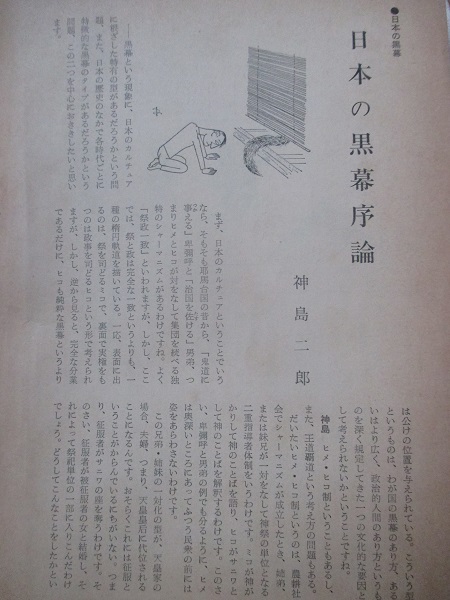
神島二郎〇日本の黒幕序論ー(前略)今後の黒幕は、ヒトや限られた党派を操る黒幕ではなくて、大衆だとか経済構造を操作できるブレーンという形が」、重要になるのではないか。操作というのは、権謀術数でだますというのとは違って、大衆のイメージに合わせて、政治をつくってゆくということだし、そういうことの専門家が政治に参画しだしているということは、新しい問題だね。
1965年8月 大野達三『アメリカから来たスパイたち』新日本出版社□図ー「連合軍総司令部機構」「G2・CIC関係図」「」
1965年6月11日 読谷村喜名小学校5年生の棚原隆子さんが自宅前で米軍演習トレーラーが空から落下し圧死した。
1965年12月 『守礼の光』「実現間近い家庭用原子力発電」
1966年5月25日、アメリカの作家ジョン・トーランド、とし子夫人と来沖□5月30日『沖縄タイムス』「作家トーランド氏の講演・生きた歴史を強調」
1966年5月ー『オキナワグラフ』「ハワイだよりー髙江洲敏子さん」
1966年10月 『守礼の光』坂本万七「写真・伊藤若冲」
1967年3月 『守礼の光』せそこ・ちずえ「琉球昔話 空を飛ぼうとした男(安里周当)」、比屋根忠彦「久高島のイザイホー」
1967年6月 カール・ヨネダ『在米日本人労働者の歴史』新日本出版社□塩田庄兵衛・中林賢二郎「序ーアメリカ合衆国は、もともといわば移民によってきずきあげられた国であるが、ヨーロッパの先進資本主義国から渡航して新しい国の主人公となった白人と、アジアを中心とする『後進地域』から渡航した移民との間には、人種差別という形をとった差別待遇がはっきりみられた。そのなかで日本人は、中国人、朝鮮人などとともに、低賃金労働者として下積みの扱いをうけた黄色人種であった。わが同胞は、アメリカ西部とハワイの農園・鉱山・鉄道・森林・漁場にその労働力をそそぎこみ、今日のアメリカ独占資本主義の富の少なからぬ部分をつくり出した。今日のアメリカの富について考えるばあい、中国人・朝鮮人などとともに、日本人が流した血と汗と涙を無視することはできないのである。・・・・」
1967年12月 『守礼の光』「5年後に110階建て 世界貿易センター出現」
1968年2月 『守礼の光』「現代にも呼びかけるエイブラハム・リンカーンのことば」「アジア地区米陸軍特殊活動隊 粟国・渡名喜両島で奉仕活動」「原子力科学者が語る未来の原子力『食品工場』」
1968年4月 『守礼の光』ジョン・A・バーンズ(ハワイ知事)「琉球の文化的姉妹島ハワイ」
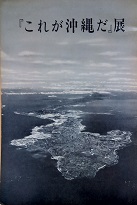
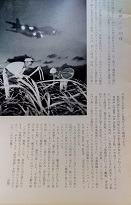

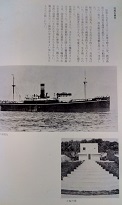
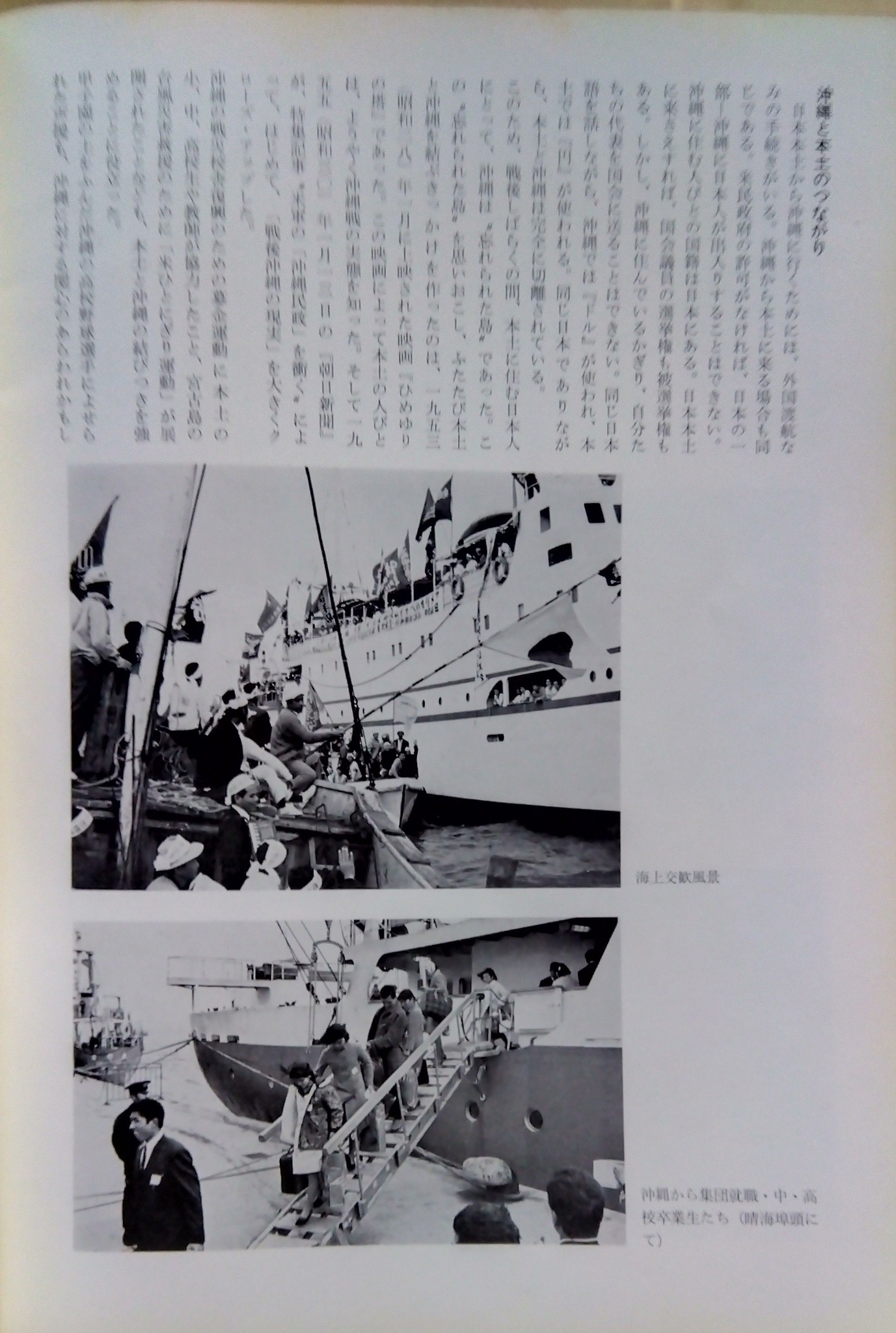
1968年(昭和43)4月 朝日新聞社/沖縄タイムス社『これが沖縄だ』展
執筆者:新崎盛暉・新里恵二・高橋磌一・外間守善 会場:東京三越本店/名古屋名鉄百貨店/大阪アベノ近鉄百貨店/福岡岩田屋/熊本鶴屋
1968年
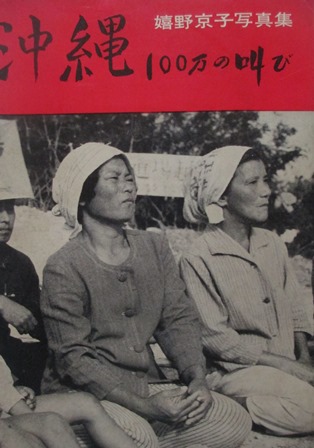
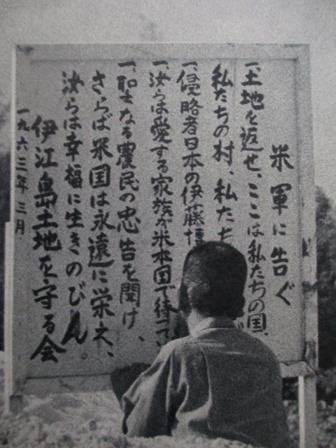
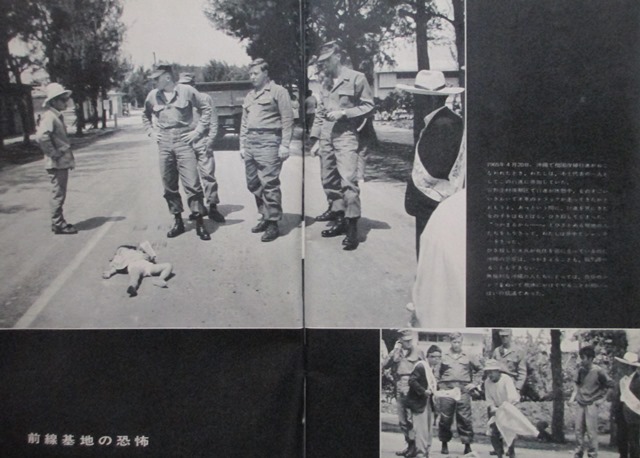
沖縄100万の叫び―嬉野京子写真集 (1968年) →菅原恭正ブログ2016-4-27:【第1660回】
1969年 アメリカ国防省がコンピュータネットワークの実験(UCLA、ユタ大学などを「ARPANET」)で連結に成功
1969年5月 『守礼の光』宮国信栄」「放射能はどこまで人体に安全か」
1969年7月 朝日新聞西部本社企画部『原爆展』(主催・広島市・長崎市・朝日新聞社)
1969年8月 『守礼の光』「四か国で開発中の原子力商船」
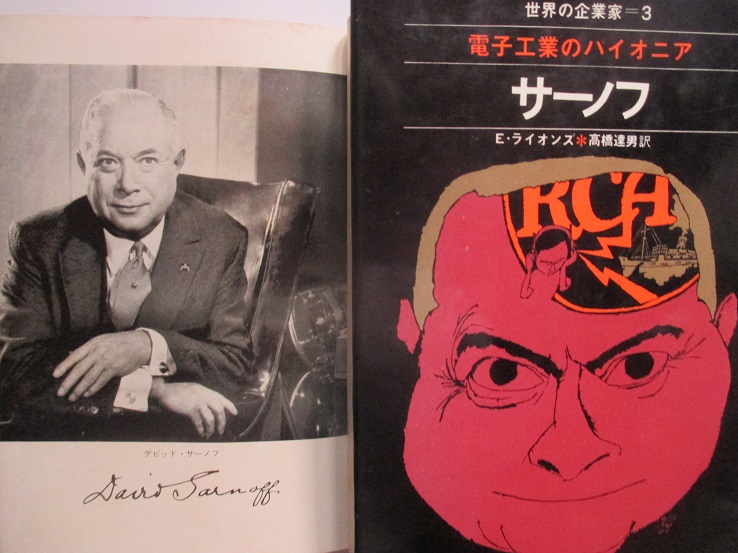
1969年8月 E・ライオンズ/高橋達男 訳『世界の企業家=3 電子工業のパイオニア サーノフ』河出書房新社→デビッド サーノフ1891.2.271971.12.12 米国の無線技術者,実業家。元・RCA社長。ロシア生まれ。1900年にアメリカに移住し、’06年RCAの前進であるマルコニー社に入り、’12年電信技士、’18年検査主任、主任技師となる。同年RCAを設立し、’21年総支配人を経て、’25年副社長、’30年社長となる。アメリカテレビの先駆者として知られ、第二次大戦中は、通信隊顧問として活躍した事もある。→コトバンク
1969年9月 『守礼の光』「フィリピンの発展に役だつ原子力」「コンピューター しくみと働き」
1969年10月 『守礼の光』「宇宙にかける人類の冒険」「期待される放射線」「巨人ジェット機(ボーイング747)の登場」
1972年9月に沖縄キリスト教協議会(比嘉盛仁)から『沖縄キリスト教史料』が発行されている。中に植村正久先生来島記念(1923年)やベッテルハイム記念碑除幕式(1926年)の写真がある。前記には新垣信一、大城カメ、比嘉盛仁、比嘉盛久、久場政用、眞栄田義見ら、後記には島袋源一郎、岸本賀昌、知花朝章、志喜屋孝信、佐久原好伝、アール・ブールらが写っている。
1972年11月 『断悪ー原爆被爆者救援のための実体験の記録』沖縄県原爆被爆者協議会
1973年4月7日 『沖縄タイムス』「海洋博を点検する<21>肥大する三次産業 大阪万博倒産の教訓生かせ 陸は観光スラム 海は石油汚染」
1973年5月15日 『日本経済新聞』「第二部 沖縄特集ー珊瑚礁に夢結ぶ海洋博’75」
1974年1月『基地情報』第4号 基地対策全国連絡会議「国民主権を侵害するもの」/2月『基地情報』第5号「沖縄基地調査特集」
1974年1月 レイチェル・カーソン/青樹簗一 訳『沈黙の春ー生と死の妙薬ー』新潮文庫→レイチェル・カーソン日本協会ー組織運営をめぐり、発足から20年が経過するなかで、組織のリフレッシュをはかる必要性が指摘されることが増えてきた。総会、理事会で「日本協会の今後の在り方」をめぐり意見交換を深めた結果、2008年3月15日、特定非営利活動法人格を返上するための「解散総会」を持つと共に、当面、関東フォーラム、関西フォーラムを拠点にした「ゆるやかなネットワーク組織」としてレイチェル・カーソン日本協会が再発足した。
1975年4月4日 ビル・ゲイツ氏とポール・アレン氏らによってMicrosoft(現在の本社所在地ーワシントン州 レドモンド)が設立された。
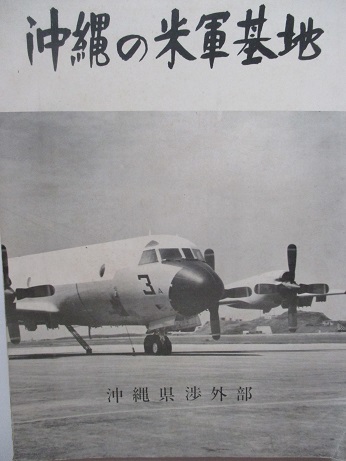
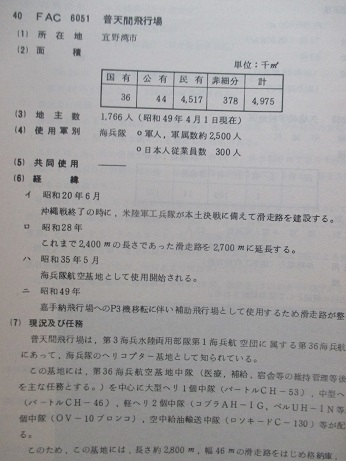
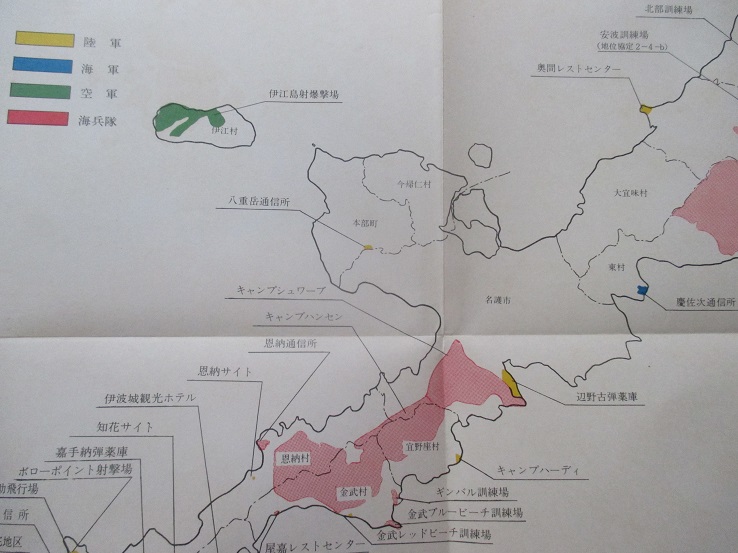
1975年2月 『沖縄の米軍基地』沖縄県渉外部基地渉外課
1975年5月23日 『毎日グラフ』「緊急増刊 勝利した解放戦線」
1975年6月14日 『沖縄タイムス』「原子力と人間<1>核ジャックの恐怖 プルトニウム放射能半減期2万4千年」
1975年8月15日 『週刊読売』「臨時増刊 日本人の戦歴ーソ連側撮影 シベリアの日本兵捕虜」
1975年9月15日 『朝日ジャーナル』「あなたは核兵器を知っているかー1945年7月16日午前5時30分、人類初の原爆、プルトニウム爆弾が実験された実験の暗号名は「トリニティ」(三位一体) アラモゴルドの砂漠の中に記念碑が立っている/米ニューメキシコ州アルバカーキー市に、国立アトミック博物館がある。」
1976年、スティーブ・ウォズニアックがApple Iを製作。これを見たスティーブ・ジョブズは、新しいビジネスになると考え、1977年スティーブ・ウォズニアックと共にApple社(現在の本社所在地ーカリフォルニア州クパチーノ)を設立した。その後発売したApple IIは表計算ソフトVisiCalcと共に大ヒットとなり、これまで一部のマニアのおもちゃでしかなかった「パソコン」が仕事にも使える道具だということが分かり、パソコン市場が出来上がった。→はてなキーワード ????2012年7月『徹底解析!!アップルvsグーグル』洋泉社
1976年4月17日『週刊ピーナツ』「追跡 巣鴨プリズンからのCIAヒモつき出所全リスト 岸信介、児玉誉士夫、笹川良一、他」
1976年5月15日、沖縄ハワイ協会(仲村亀助会長)主催「アメリカ建国200年祭」が那覇市内パシフィックホテルで開催、ノールズ在沖米国総領事夫妻、平良那覇市長らが招かれる。与世盛智郎が挨拶。→与世盛智郎『沖縄仏教読本』(久米島本願寺1976年5月)「戦後、沖縄の世替わりに際し、進駐軍が、アメリカ建国の精神にのっとって宗教政策を重視して、沖縄の寺院に活を入れ、その活動に力をかしていたら民主主義も不消化とならず、従来の守礼の邦の美風を堅持し、一部にある反米思想も起きなかったと思われます」。
1976年6月 『三悪政治とCIA』日本共産党中央委員会出版局→三悪政治(戦犯・金権・売国)ー松川事件、下山事件をめぐるCIAへの疑惑といい、自民党をはじめとする反共政党とCIAの関係といい、今後白日のもとにさらさなければならないことが、あまりにもたくさんあります。
安倍晋三、1977年春に渡米し、カリフォルニア州ヘイワードの英語学校に通うが、日本人だらけで勉強に障害があると判断して通学を止め、その後イタリア系アメリカ人の家に下宿しながらロングビーチの語学学校に通った。秋に南カリフォルニア大学への入学許可が出され、1978年から1979年まで政治学を学んだ。
□横浜・米軍機墜落事故
1977年9月27日午後1時すぎ、厚木基地を飛び立った米軍のファントム偵察機が横浜市緑区(現・青葉区)の住宅地に墜落した。土志田勇さんの娘、和枝さん(当時26)の息子の裕一郎君(3)と康弘君(1)が翌日未明に相次いで死亡。和枝さんも重度のやけどを負い、闘病生活の末、4年4カ月後に亡くなった。勇さんは、和枝さんの遺志を継いで社会福祉法人を設立。「和枝園」と名付けたハーブ園も開くなど「社会への恩返し」を続けている。
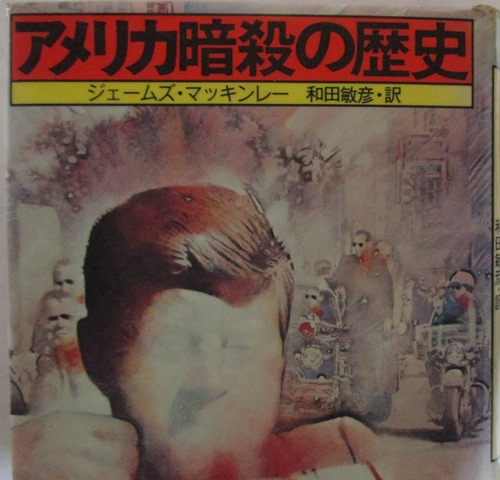
1979年1月 ジェームズ・マッキンレー著/和田敏彦・訳『アメリカ暗殺の歴史』集英社
○アメリカにはじめて移民たちが着いたとき、彼らはここに将来を決する二つのものを持ち込んだ。一つは自分たちが祝福された民であるという神がかり的な夢であり、もう一つは銃である。彼らは艱難に耐えていくためにはこの夢が、またこの夢を新世界に押しつけるには銃が必要だと信じていた。彼らは聖者と銃弾、それに狡猾な取引でこの夢を広めていったから、彼らは間違ってはいなかった。そして彼らが正しかったことは、百六十九年後に独立宣言の署名によって証明された。あの日、市民は家に駆け込むなり、銃を取り、まず祝砲で、ついでアメリカ革命でアメリカの夢を永久的に確認した。・・・・・
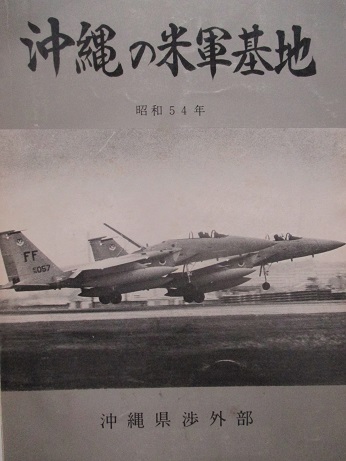
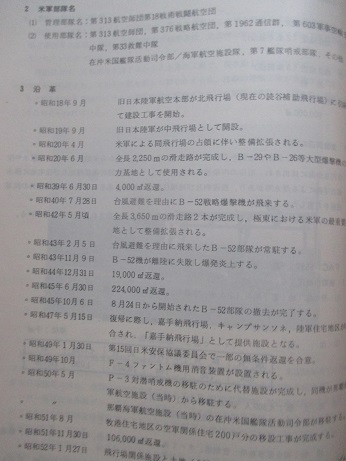
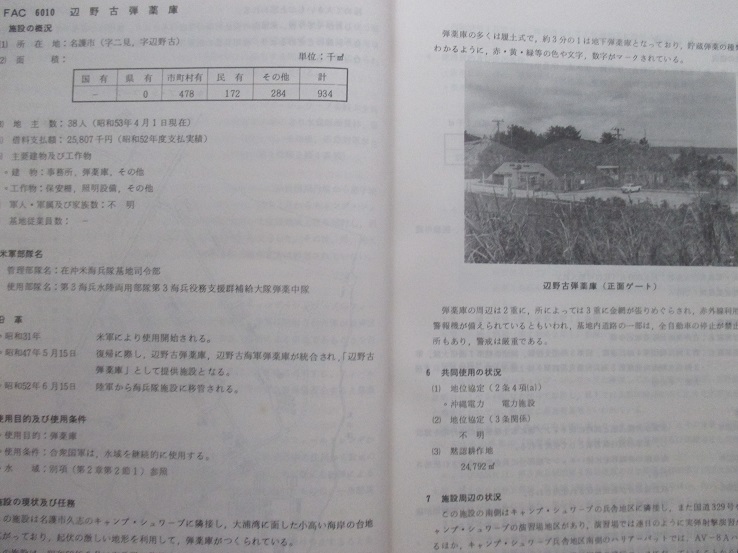
1979年3月 『沖縄の米軍基地』(表紙写真・国吉和夫)沖縄県渉外部基地渉外課
1979年、祖父新一郎に代わって、孫である現店主天牛高志が、 まだほとんど商店がなかった大阪心斎橋西のアメリカ村に、90坪の天牛書店新店舗を開きました。元々は駐車場であった建物を改装し、むき出しの鉄骨の梁、本棚は赤く塗装し、自動販売機を置いた休憩スペースを設け、古くから敷地にあった稲荷祠はそのまま店内に残すなどといった、従来の古本屋のイメージを一新する店作りに挑戦したアメリカ村店は、新しい感覚が若いお客様にもご好評をいただき連日の盛況となります。 しかし、時代の流れとともにアメリカ村が賑やかなファッションの街へと変貌し、古書を売る
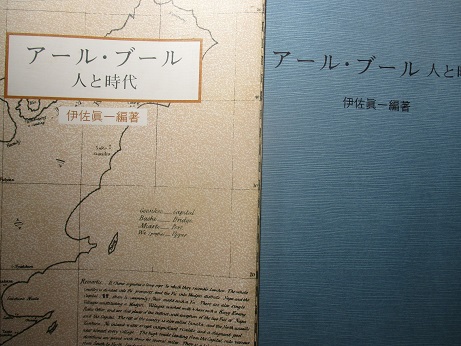
1991年1月 伊佐眞一 編著『アール・ブール : 人と時代』伊佐牧子
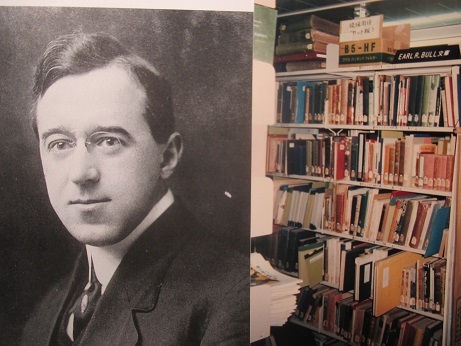
写真・ブール師(the Rev. Earl Rankin Bull,1876~1974)/ブール文庫
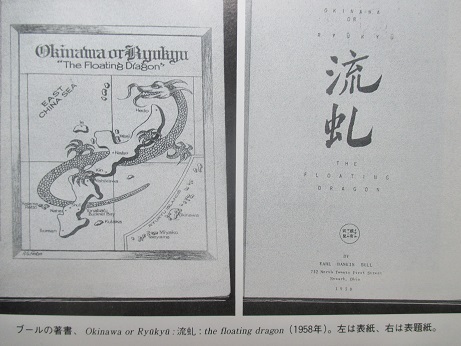
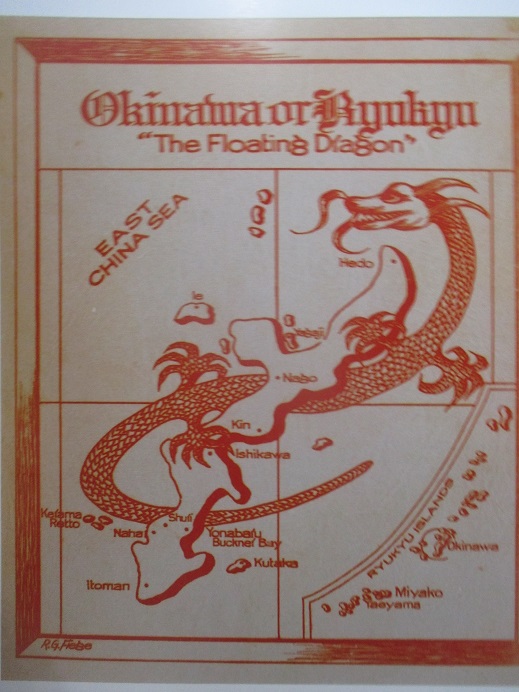
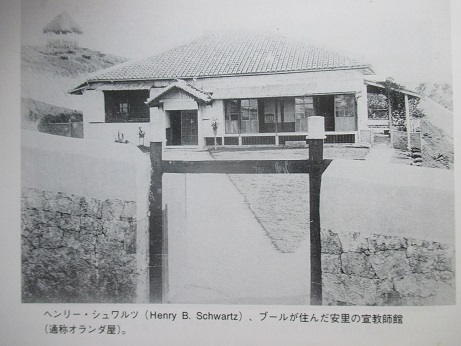
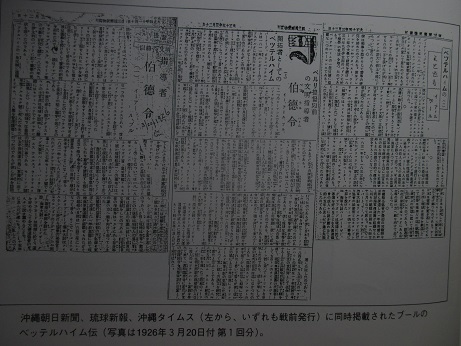

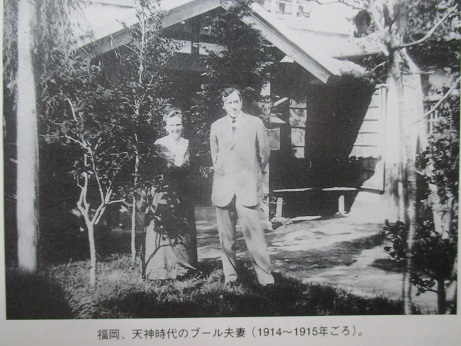
伊佐眞一[アール・ブールと伊波普猷]
伊波普猷は,アール・R・プール宛て1926年1月30日付の手紙で, その末尾を次の言葉で閉じている。 「琉球は昨今非常な窮境に陥って国家の手で救済されなければ ならないやうになってゐますが何だかもう助からないやうな気がします。 この不幸なる民族の為に尚一層御奮闘下さることをお願ひします。」 この書翰は,その年,大正15年5月に, プールが中心になって準備をすすめていた ベッテルハイム渡琉80周年記念事業にちなむ2つのモニュメント, つまり石材記念碑の建立と一対をなす, ブールのベッテルハイム伝への序文を求められたことに対する返信であった。 「一月十一日附の御手紙は,方々まわりまわって, 今朝やっと手許に届きました」というのは,たぶんにブールが, 前年の伊波の上京を知らないで, 沖縄の住所に向けて出したためであろう。 かくて30日の朝になってやっと手紙を読んだ伊波は, その日のうちにペンをとったのであるが,この最後の一節には, 当時の沖縄経済の疲弊状態と, かくなるまでに至った真因についての伊波の認識が 端的にあらわれていると同時に, ブールを媒介にしたキリスト教とのかかわり, さらには沖縄「救済」についての思考のパターンが, くっきりと浮き出ているように思える。 ・・・

2016年2月26日 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ「第33回 東恩納寛惇賞 贈呈式」祝賀会写真右から嵩元政秀氏(第32回東恩納寛惇賞)、新城栄徳、①照屋善彦氏(第24回東恩納寛惇賞)
①照屋善彦[資料収集の鬼:ブール師]
ブール師(the Rev. Earl Rankin Bull,1876~1974)は, 米国のメソジスト監督教会から,1911年, 九州・沖縄地区へ派遣され延べ15年間日本で伝道をした宣教師である。 師は沖縄での本務であるキリスト教の布教のほかに, 中学校での英語を教え, また幕末に来琉した英宣教医ベッテルハイムの記念碑を建立 (大正15年)したりして,大正時代の沖縄で顕著な活動をした。 また師は戦後, 琉球大学附属図書館に「ブール文庫」を寄贈した人としても知られている。 当文庫が設置された1958年頃の琉球大学附属図書館には 蔵書数が著しく少なく, 大学の使命である教育と研究にも支障をきたす状態であった。 特に,洋書の蔵書に至っては寥々たるものであったので, ブール文庫が琉球大学に寄贈された意義は大きい。 筆者や同僚で沖縄の対外関係史を研究していた者にとって, 当文庫はまさに干天に慈雨の如く有り難い贈り物であった。
ブール師は,沖縄への派遣が決定した1911年以後, 終生異常なほどの情熱と執念をもって, 「沖縄」と沖縄における プロテスタント宣教の開拓者ベッテルハイム研究に打ち込んだ。 19世紀中葉,ベッテルハイムが派遣(1846 ~54)された沖縄こそ, 日本キリスト教史における最初のプロテスタント伝道が 開始された場所であったからであろう。 アヘン戦争(1840 ~42) 後のアジアにおける国際情勢の大変化をうけて, カトリック・プロテスタントの中国をはじめ東アジアでの伝道活動が活発になった。 幕末の激動する琉球で, ベッテルハイムが フランスのカトリック宣教師と伝道活動を展開した史的意義は大きい。
師は,ベッテルハイムの研究に着手するや, 精力的に関係資料の大部分を収集し, その研究の成果を英文や邦文で次々と雑誌や新聞紙上で発表した。 特にベッテルハイムの日記・書簡や,彼を派遣した琉球海軍伝道会 (Loo Choo Naval Mission,本部はロンドン在)の報告書等の マイクロフィルム・コピーを師が自費で取り寄せたことは, ベッテルハイム研究史上での最大の功績である。 永い歴史があり公共機関でもない宗教団体から外国人や部外者が, 個人の研究に必要な関係資料を入手することが 如何に至難の技であるかということを, 筆者自身イギリスやフランスで身をもって体験したからである。 恐らくブール師は,欲しい資料に対する鋭い臭覚と 持ち前の粘り強さを発揮して入手したに違いない。 このような彼の精力的な資料収集活動については, 伊佐眞一氏の好著『アール・ブール - 人と時代』 (1991年)で詳しく述べられている。
ベッテルハイム研究は,琉球が置かれた当時の複雑な国際情勢の下で, 基本資料も多彩である。 (1)ベッテルハイムの日記・書簡と琉球海軍伝道会の報告書等, (2)ベッテルハイムが滞在中に接触した欧米人関係の関連資料。 例えばイギリス政府関係(本国・香港政庁・英国東洋艦隊等), 米国のペリー提督の合衆国艦隊,フランスの宣教師や同国艦隊, 欧米の民間船,ロシアのプチャーチン提督の関係資料等である。 さらに, (3)伝道地である琉球の王府(評定所文書等)と薩摩藩や幕府の関連資料, (4)琉球王国の宗主国である清国に関連した資料などがある。 これらの多岐にわたる膨大な資料群の中で, ブール師は(1)と(2)の関係資料の大半を収集している。 その他に琉球海軍伝道会の創立者のクリフォードは, 1816年に沖縄島を訪れたバジル・ホール一行に随行したので, バジル・ホールやマクラウドの航海記も参考にする必要がある。 その他ホールの前後に多数沖縄に来航した英国船関係の資料や, 当時の琉球を中心にした東アジア関係の欧文資料も研究に必要だが, ブール師はこれらの関係資料を戦前・戦後とも精力的に収集している。 年々充実していく本附属図書館で, ブール文庫は依然として貴重な資料の宝庫である.
(琉球大学人文学科教授)

2021-11-24 『琉球新報』伊佐眞一「主体性を問うー首里城復興基金と大龍柱」
記録は記憶を甦生する。トマトの成長過程記録写真495枚を見ると、32年前の撮影時の 庭先やトマトや私自身の様子が鮮明に甦る。生命の戴きの時とお返しの時。トマトの一生を 9点に絞り筆で描いた。祈りのテーマでもある定点PRAYERシリーズから「トマト」を発表。

写真左から、玉城徳正氏、久貝清次氏、岸本徹也氏
2015年12月22日 市民ギャラリー「『戦後70年オキナワ』久貝清次展」

久貝清次氏→ここをクリック「久貝清次ウェブ美術館」
2015年12月24日『琉球新報』「あしゃぎー記録写真の現場を描くー久貝清次さん 東京の百貨店でデザイナーをしていた1970年~71年、丸坊主から髪もひげも伸ばしっぱなしにして1年間、毎日、同じ構図、服装で写真を撮り続けた。周囲の波紋とともに面白がられ、新聞、週刊誌、テレビで時の人になった。・・・・」

1970年9月23日『朝日新聞』「体験的長髪論」

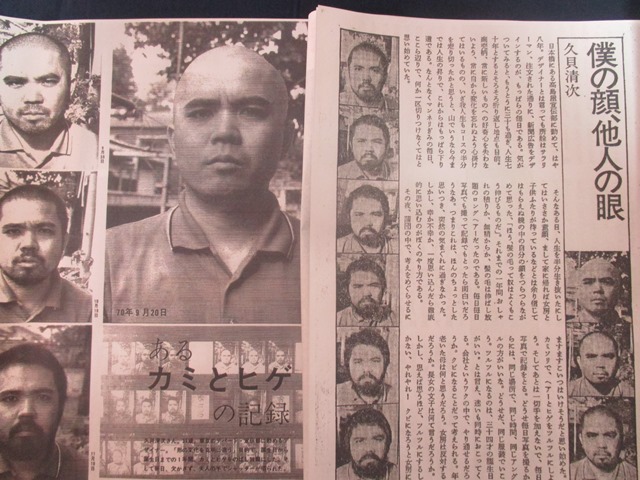
1971年
10月『アサヒグラフ』/12月『話の特集』

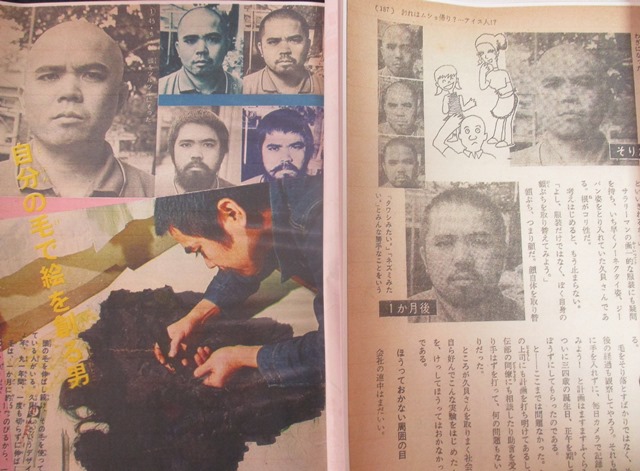
1972年
2月『少年サンデー』/3月『中学三年コース』
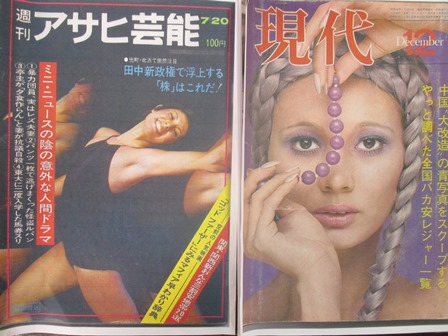
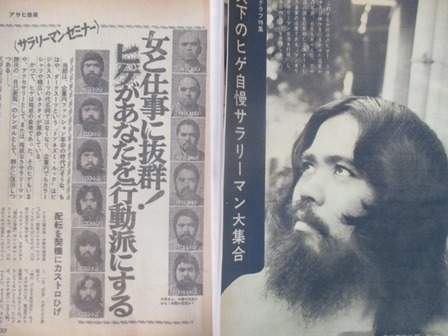
1972年7月『アサヒ芸能』「女と仕事に抜群!ヒゲがあなたを行動派にする」/1970年12月『現代』「ヒゲ自慢サラリーマン大集合」
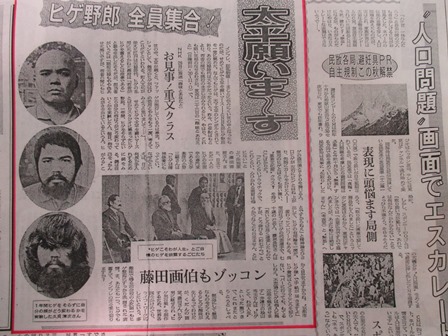
1975年1月23日日『日刊スポーツ』「太平願いまーす」
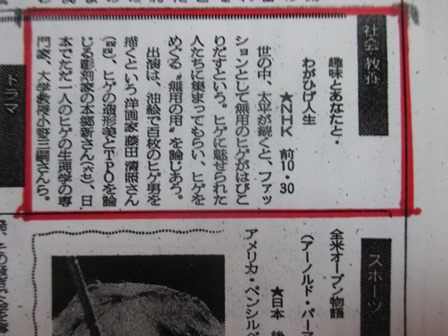
1975年1月26日NHK

写真左から、玉城徳正氏、久貝清次氏、岸本徹也氏
2015年12月22日 市民ギャラリー「『戦後70年オキナワ』久貝清次展」

久貝清次氏→ここをクリック「久貝清次ウェブ美術館」
2015年12月24日『琉球新報』「あしゃぎー記録写真の現場を描くー久貝清次さん 東京の百貨店でデザイナーをしていた1970年~71年、丸坊主から髪もひげも伸ばしっぱなしにして1年間、毎日、同じ構図、服装で写真を撮り続けた。周囲の波紋とともに面白がられ、新聞、週刊誌、テレビで時の人になった。・・・・」

1970年9月23日『朝日新聞』「体験的長髪論」

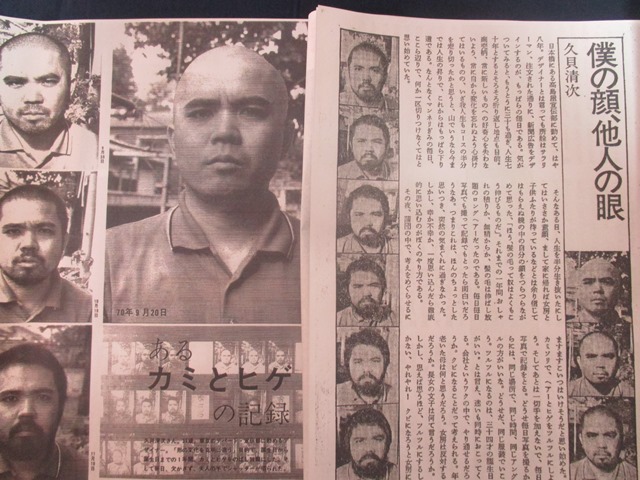
1971年
10月『アサヒグラフ』/12月『話の特集』

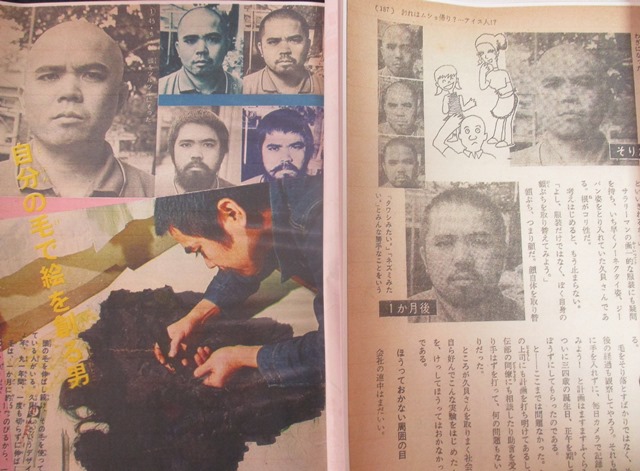
1972年
2月『少年サンデー』/3月『中学三年コース』
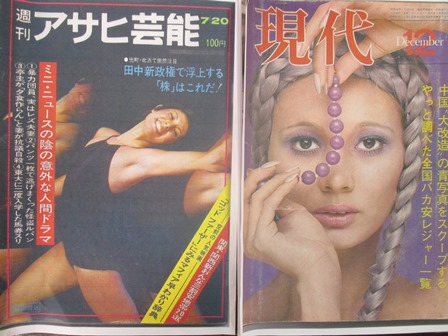
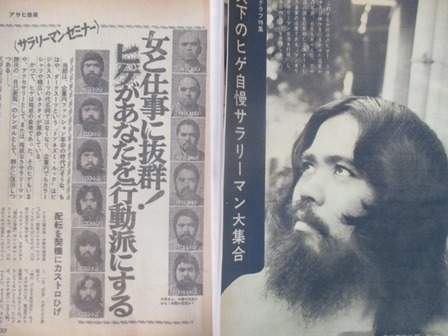
1972年7月『アサヒ芸能』「女と仕事に抜群!ヒゲがあなたを行動派にする」/1970年12月『現代』「ヒゲ自慢サラリーマン大集合」
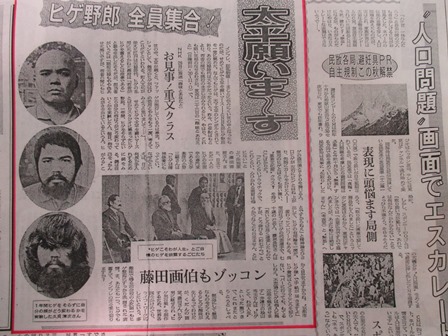
1975年1月23日日『日刊スポーツ』「太平願いまーす」
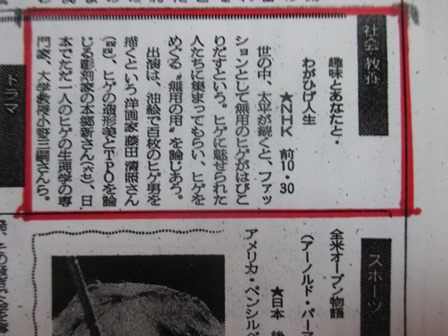
1975年1月26日NHK
01/10: 沖縄人民党中央機関紙『人民』
1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社
ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ
写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。
悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫
○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。
郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長
善意の記録として・・・・沖縄県学生会
○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。
第一部
拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人
第二部
土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道
島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光
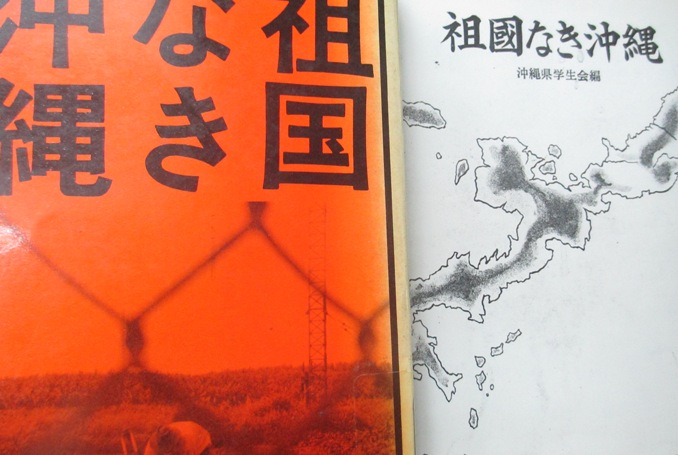
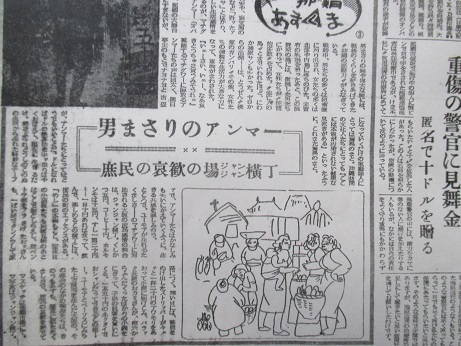
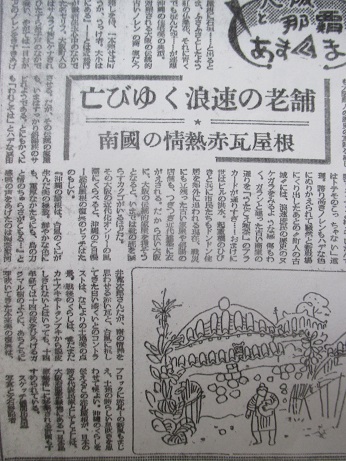
1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」
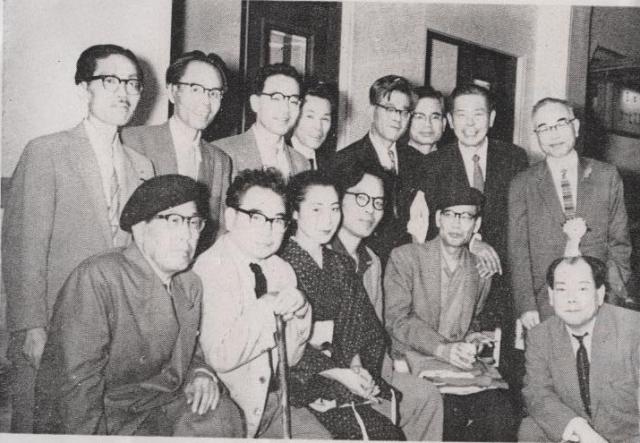
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子
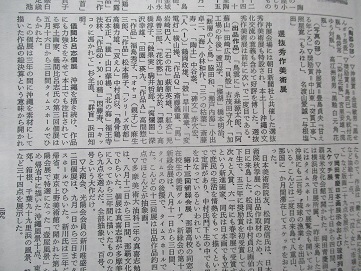

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』
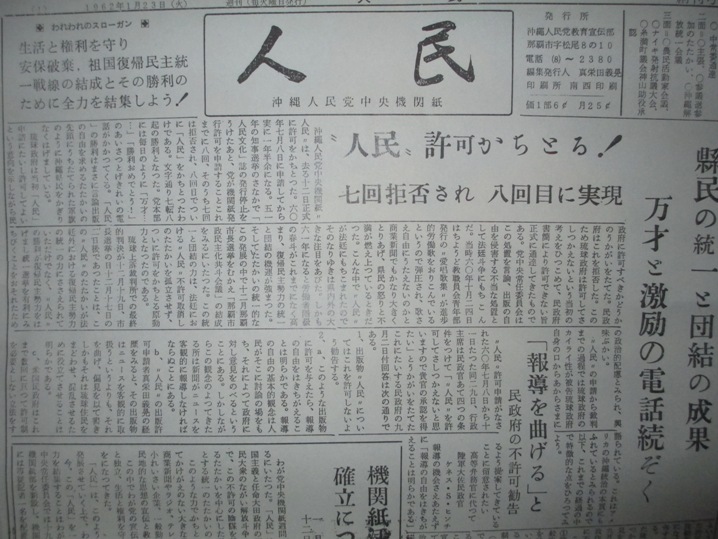

1963年
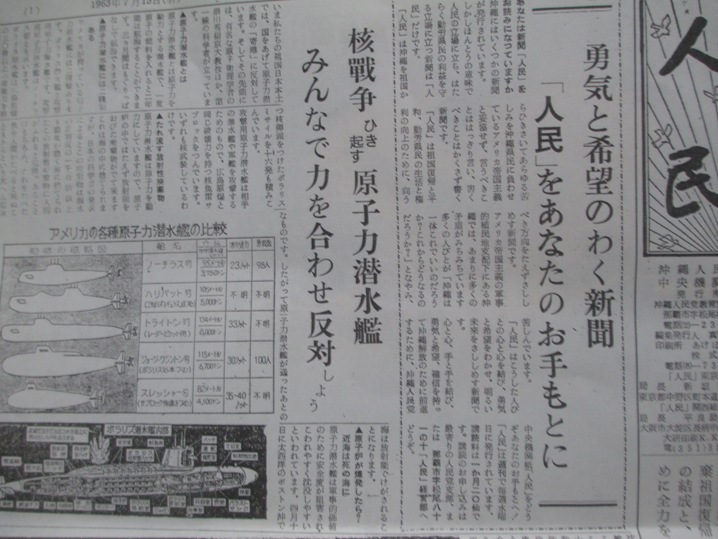
7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」
1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」
1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社
○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫
○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫
○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの
○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二
○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光
○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会
1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」
1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」
2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」
7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)
7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」
9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」
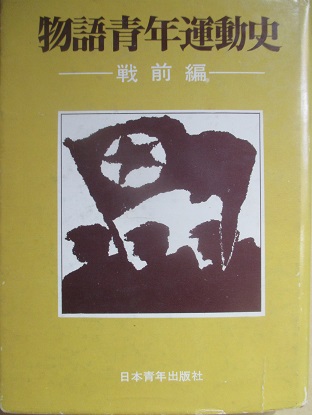

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社
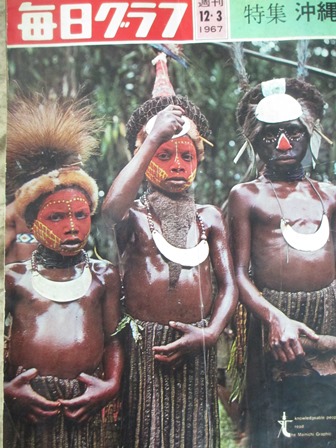
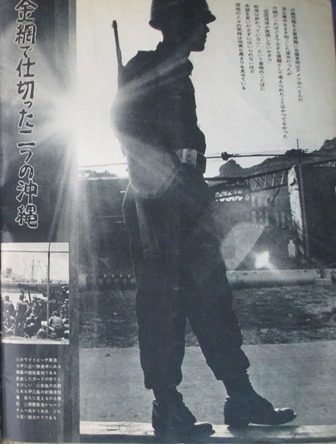
12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」
1968年
6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」
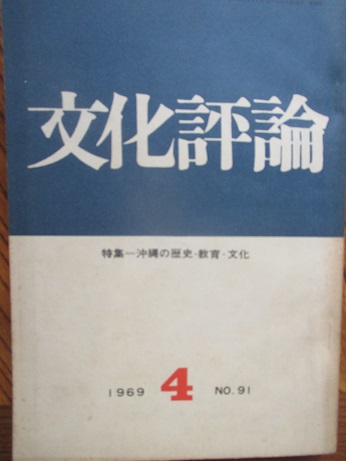
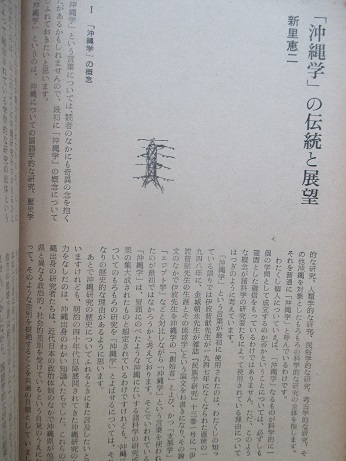
1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」
1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)
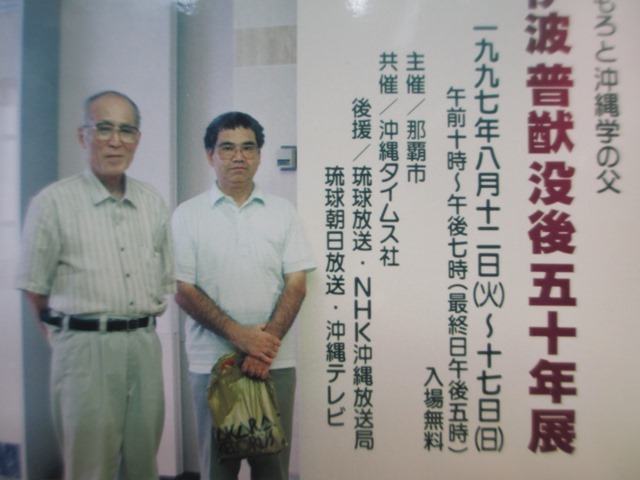
伊波廣定氏と新城栄徳
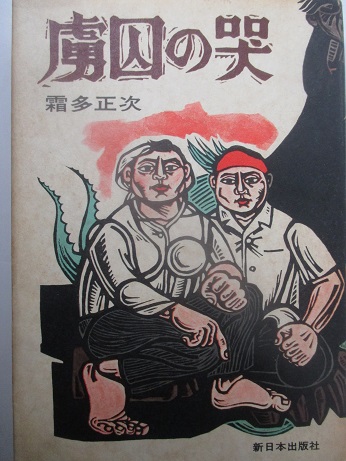
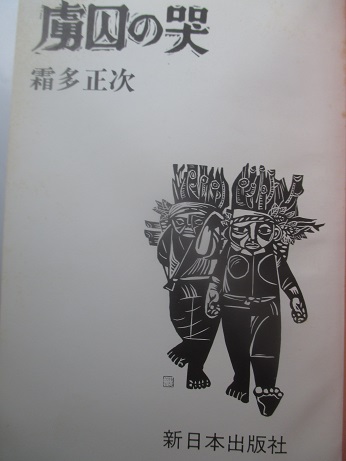
1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」
5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)
8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」
①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)
9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』
□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために
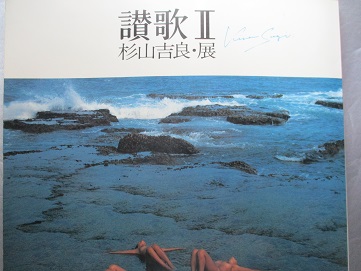
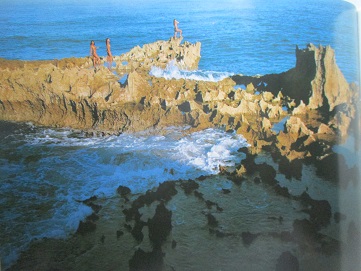
1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』
1971年
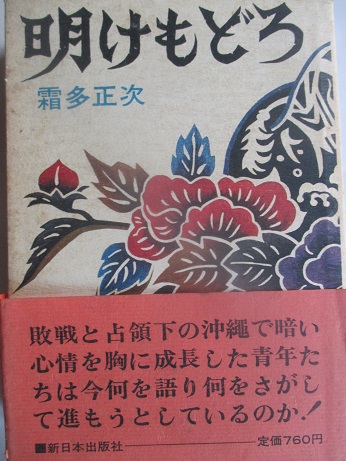
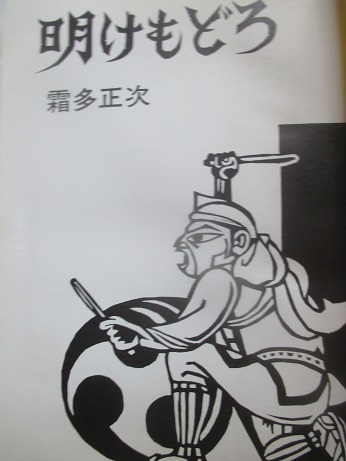
1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」
1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」
1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」
1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」
1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」
2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」
2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」
4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」
5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」
5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④
5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」
6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」
6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」
7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」
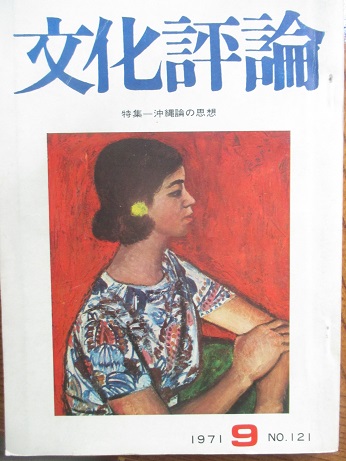
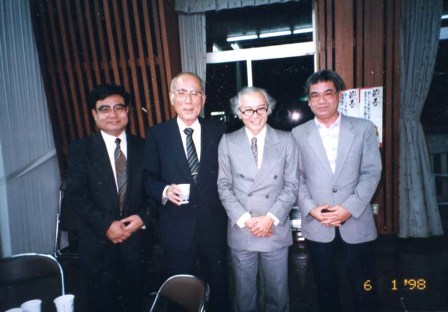
1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
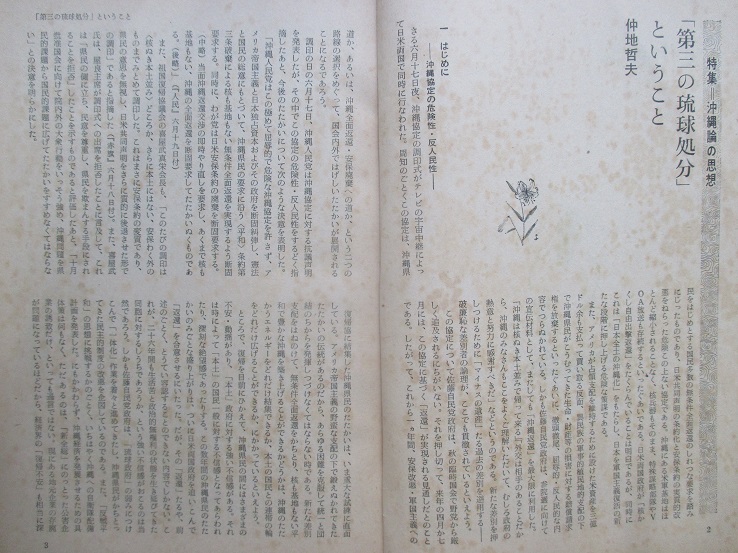
10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」
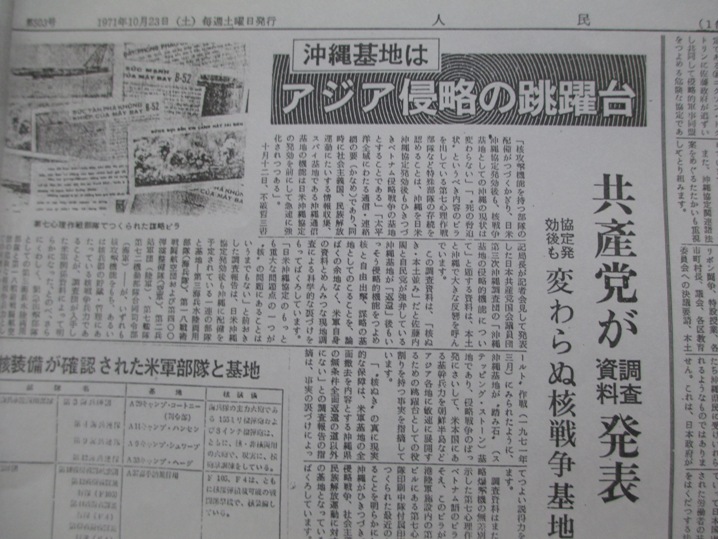
10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」


写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益
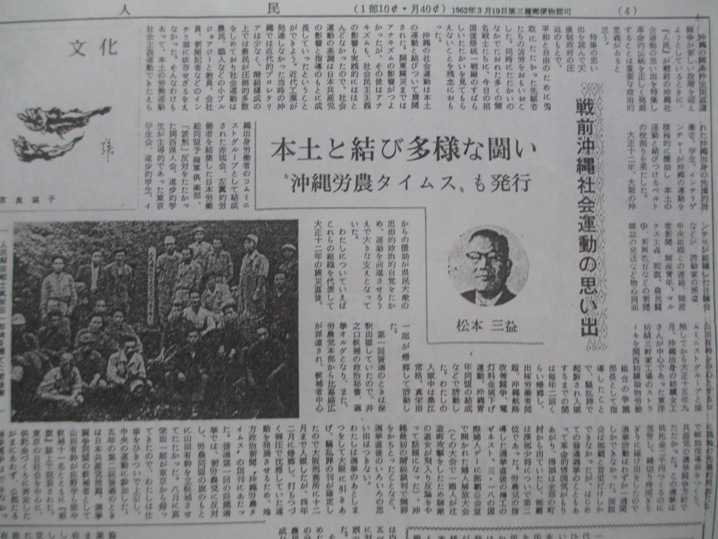
12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」
12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」
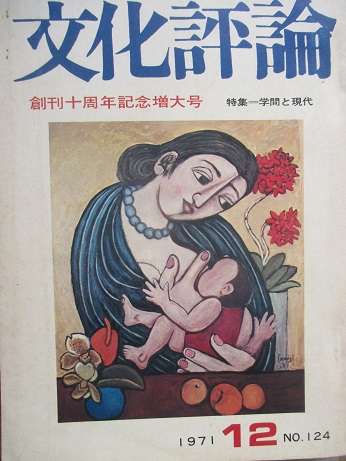
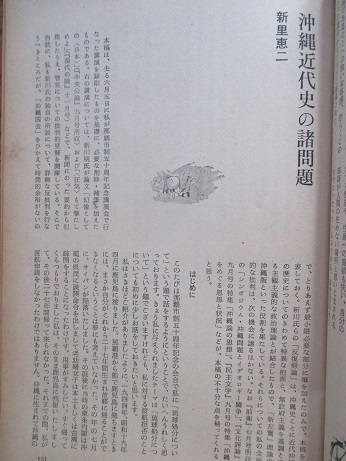
1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」
1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>
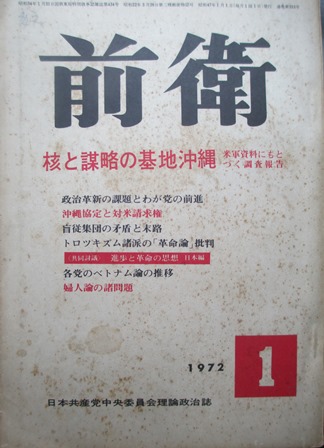

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫
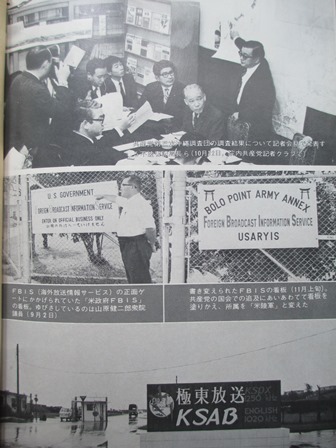
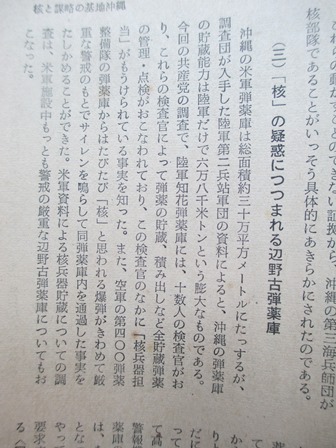
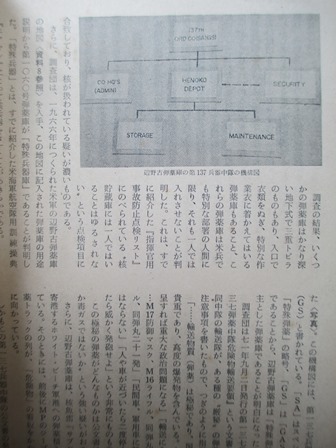
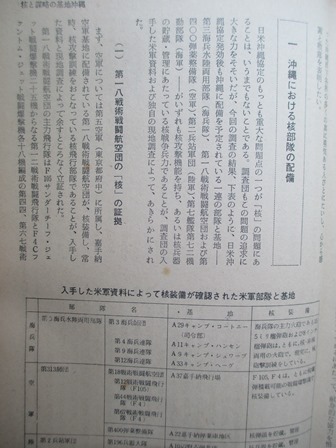


1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」
1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」
2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」
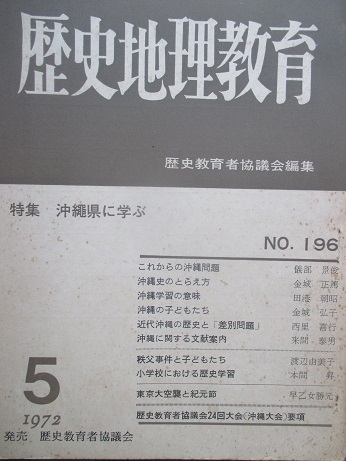
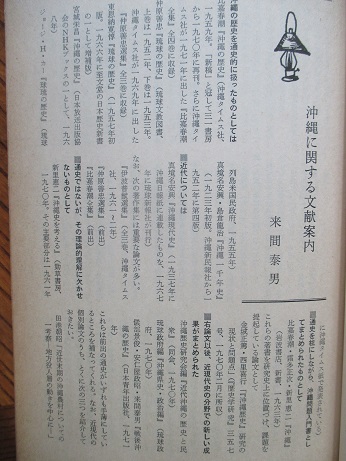
1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」
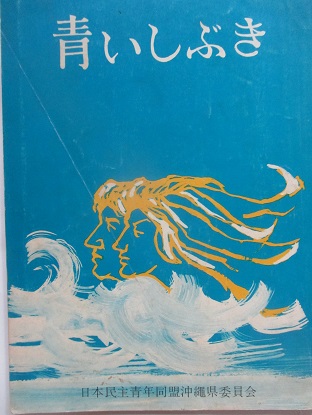
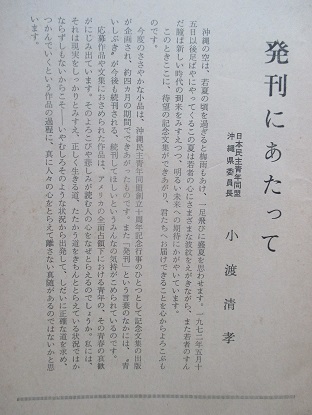
1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

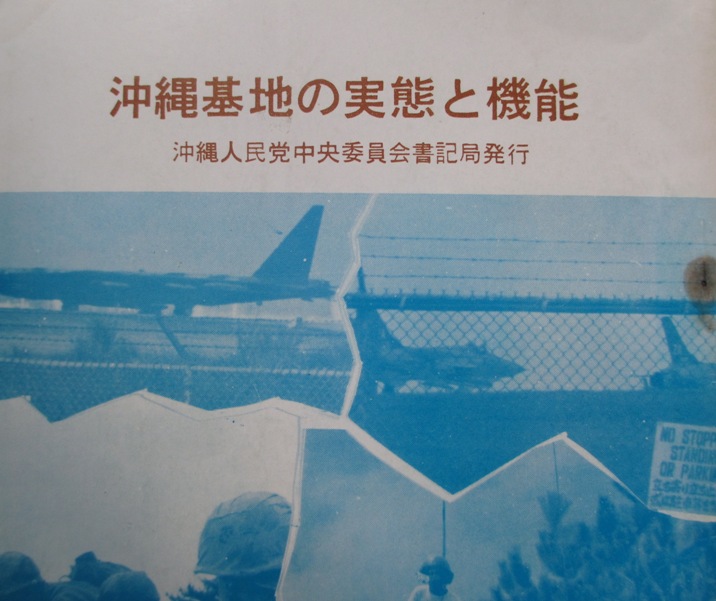
写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』
1973年
1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」
4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」
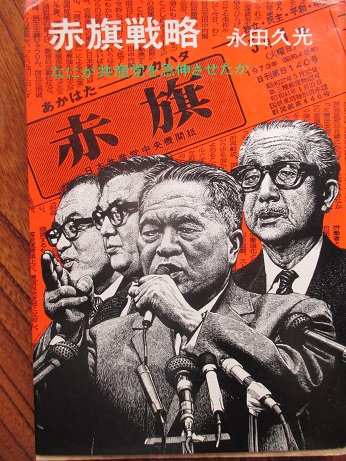
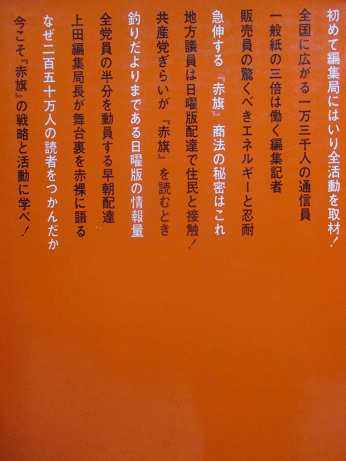
1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社
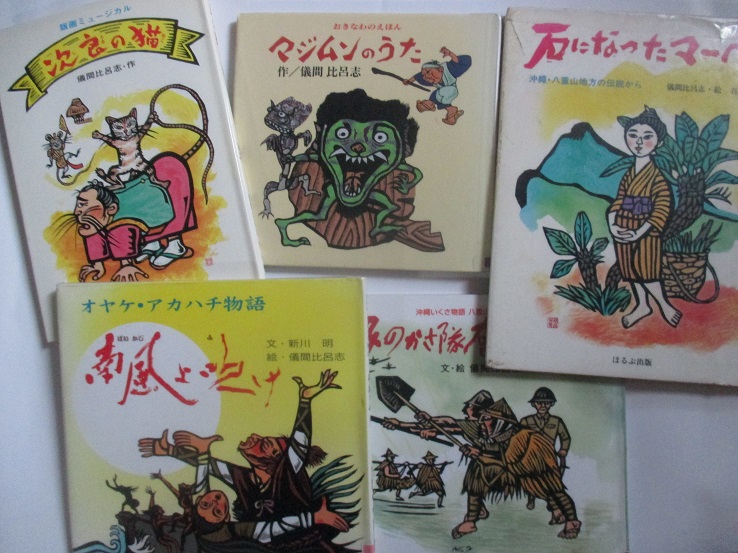
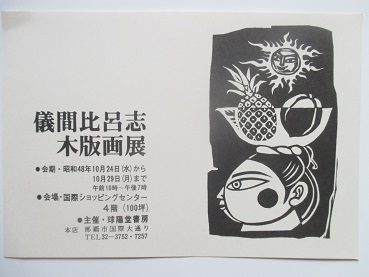
右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房
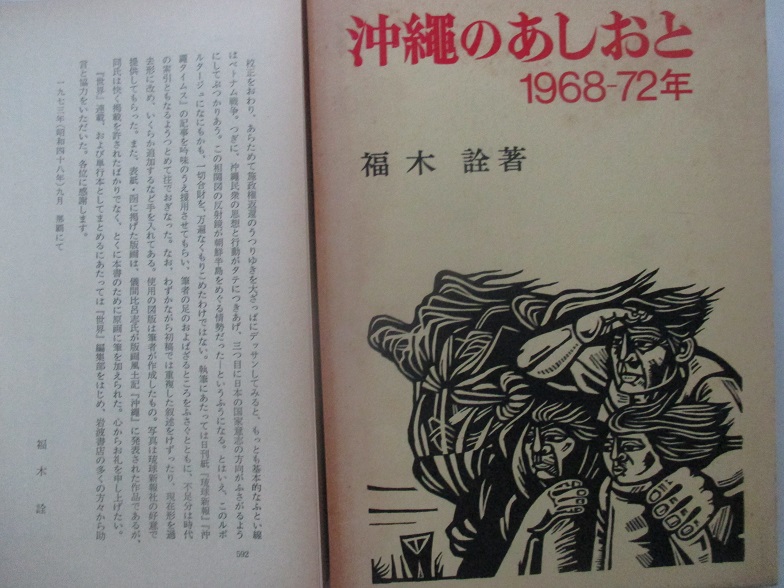
1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。
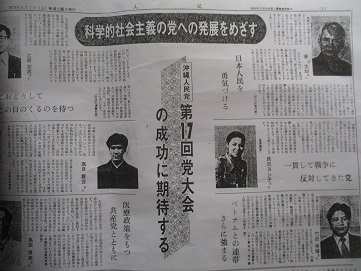
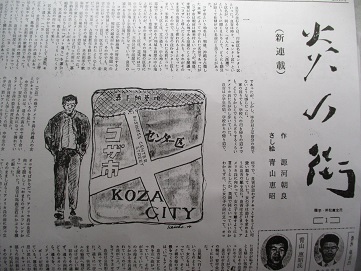
『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭
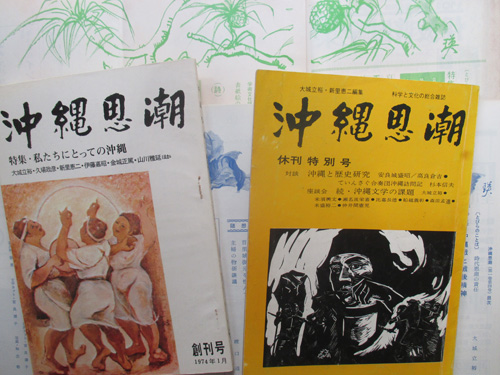
1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」
☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。
1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」
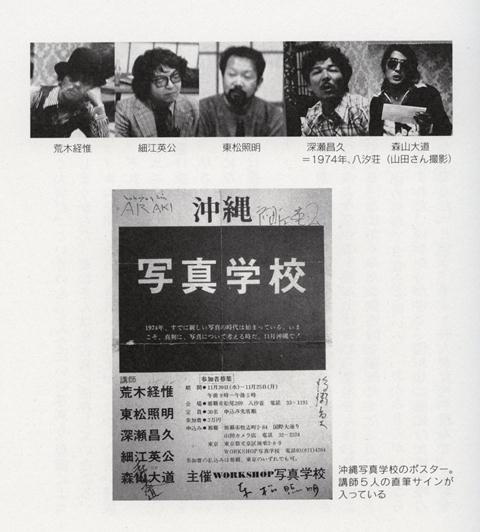
1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」
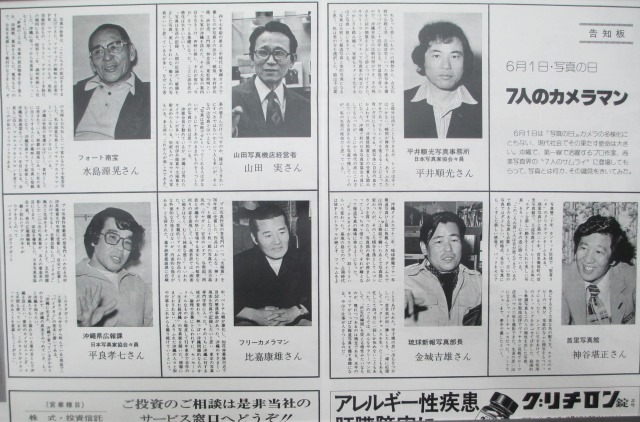
1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」
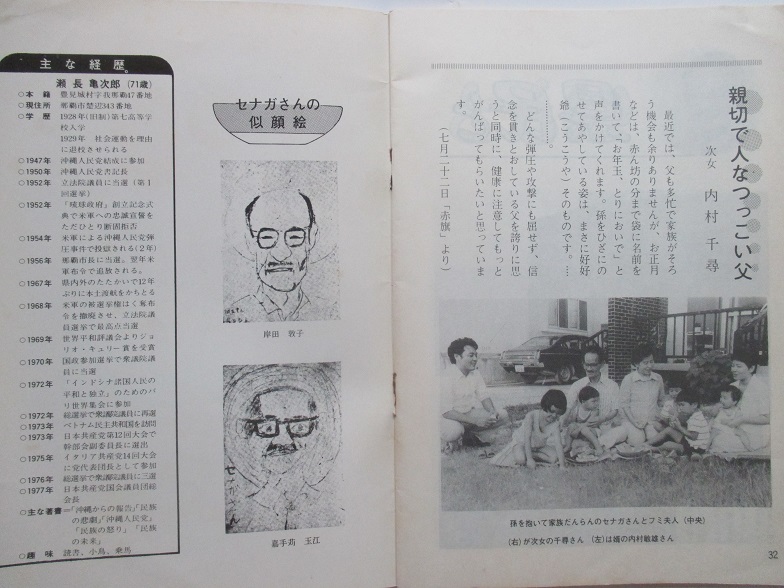
1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会


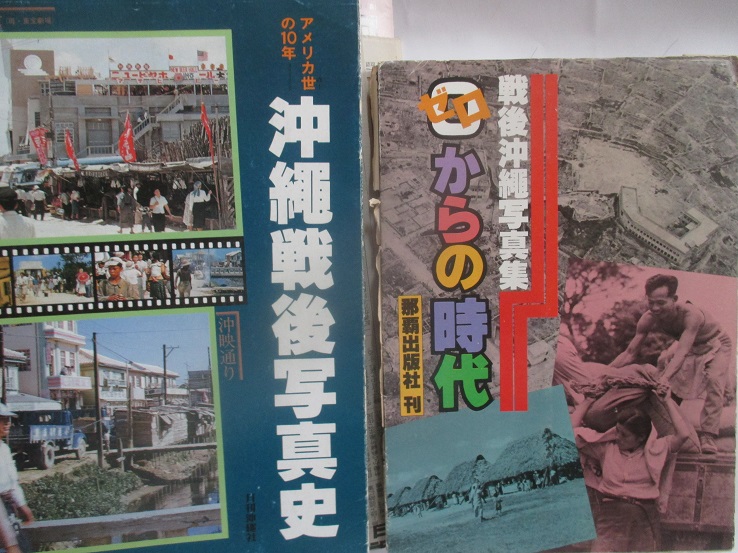
1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社
☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)
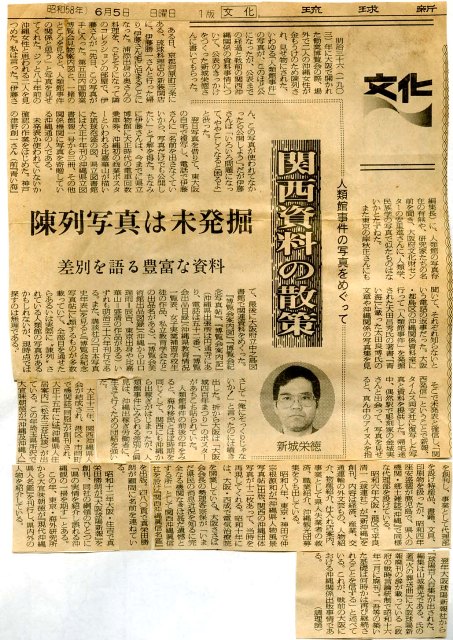
□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」
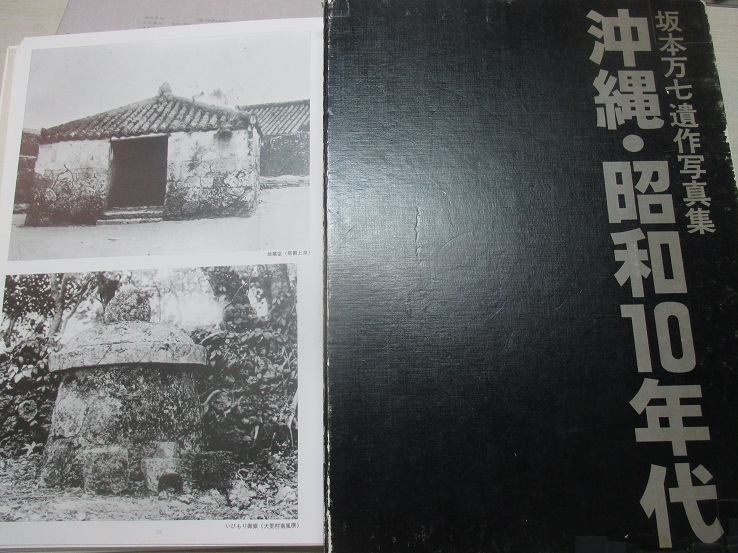
1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書
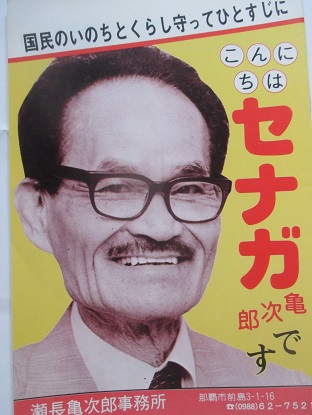
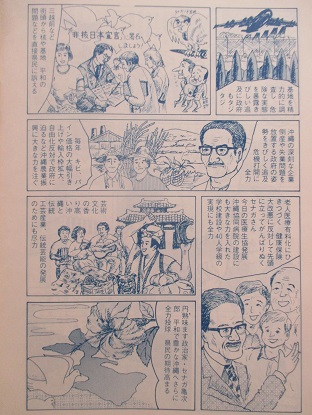
1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所
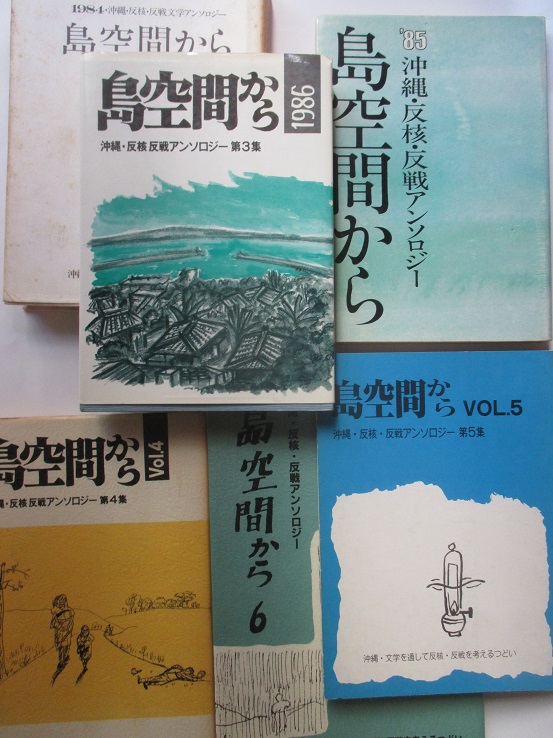
1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)
〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。
いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。
文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。
米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。
1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』
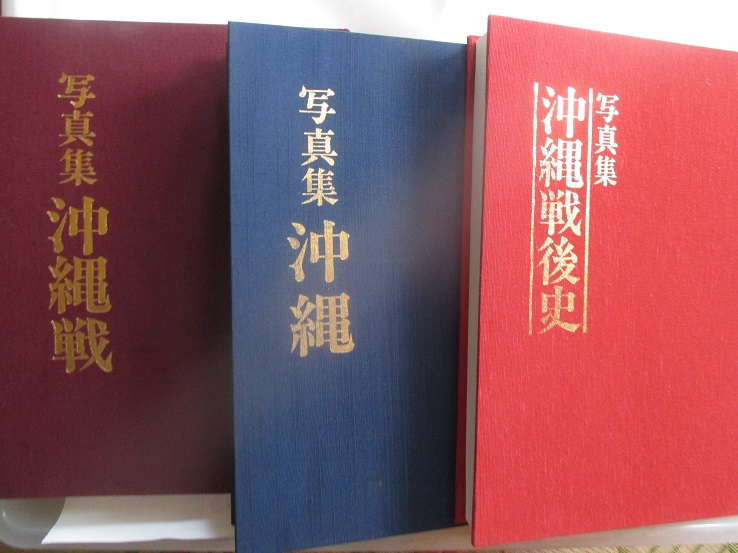
那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實
1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」
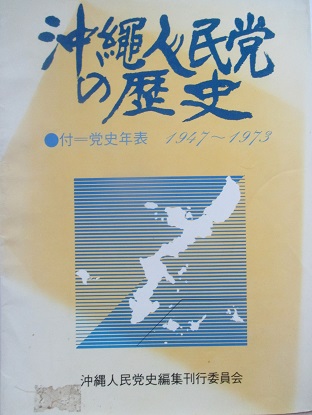
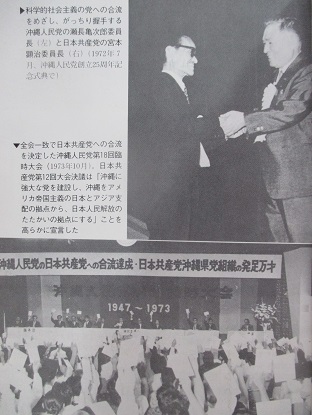
1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会
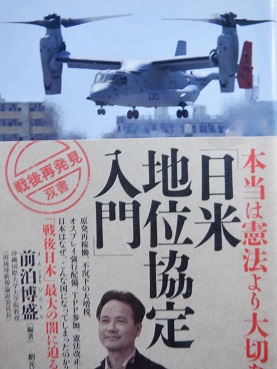
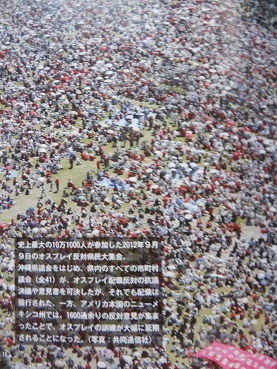
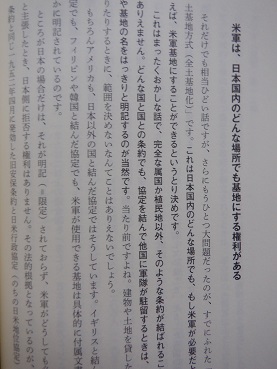
2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社
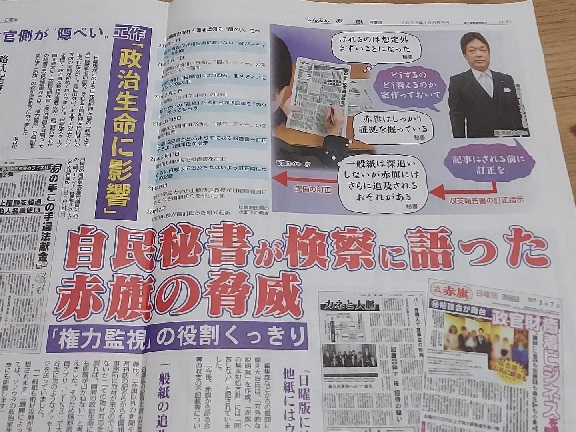
ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ
写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。
悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫
○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。
郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長
善意の記録として・・・・沖縄県学生会
○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。
第一部
拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人
第二部
土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道
島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光
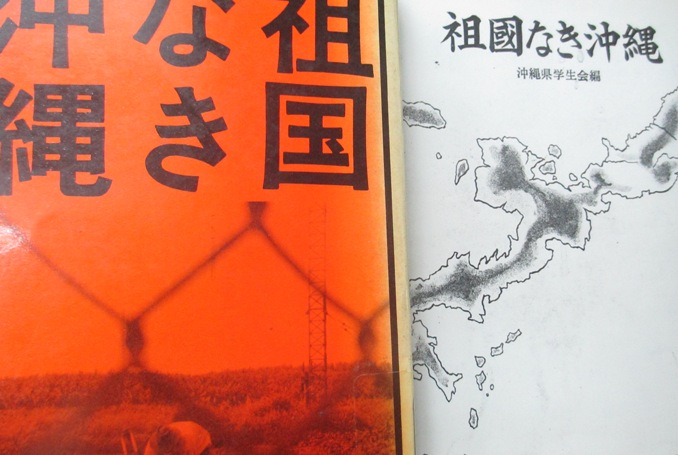
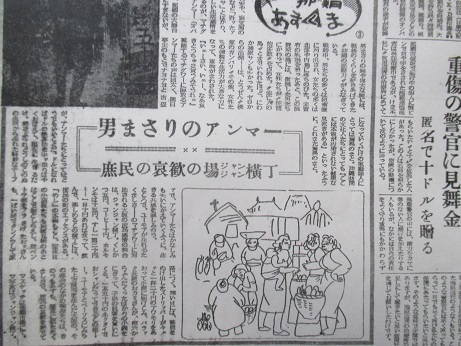
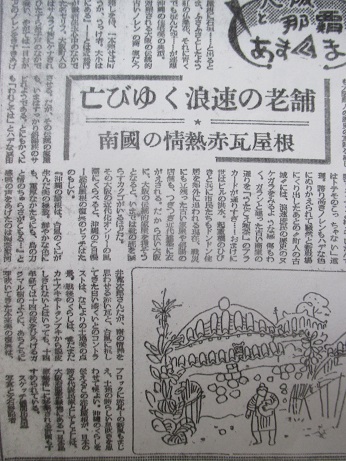
1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」
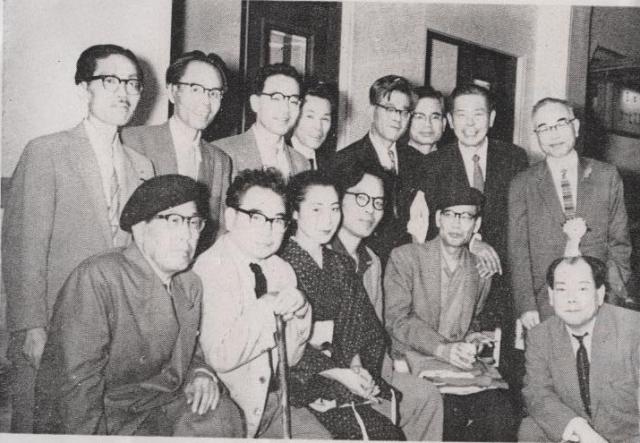
1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子
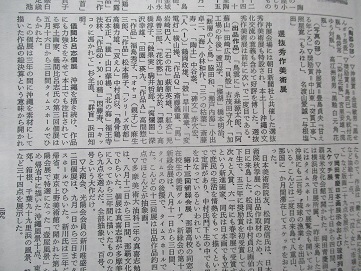

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』
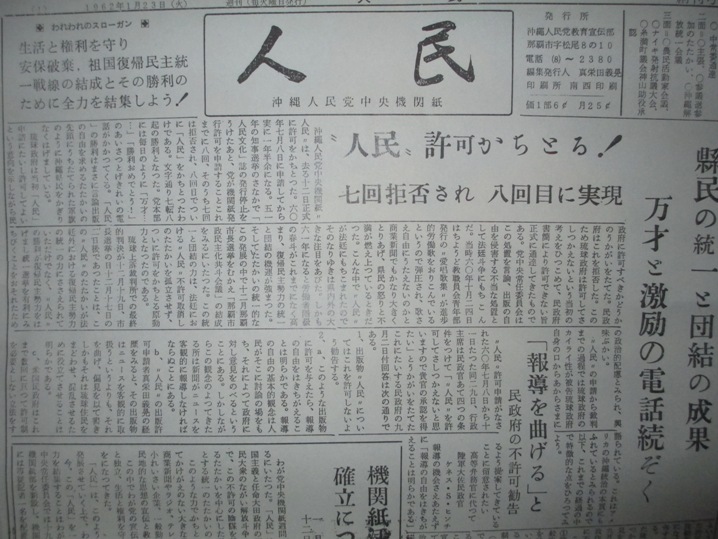

1963年
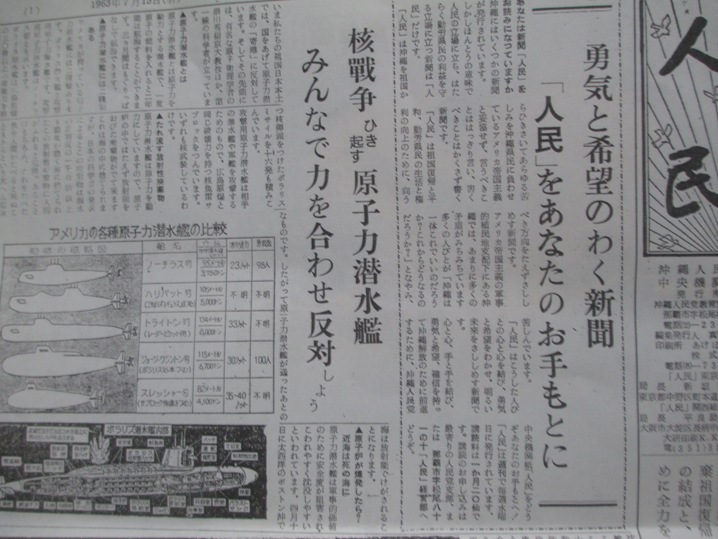
7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」
1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」
1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社
○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫
○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫
○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの
○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二
○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光
○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会
1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」
1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」
2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」
7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)
7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」
9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」
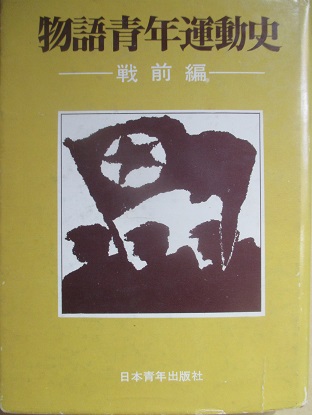

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社
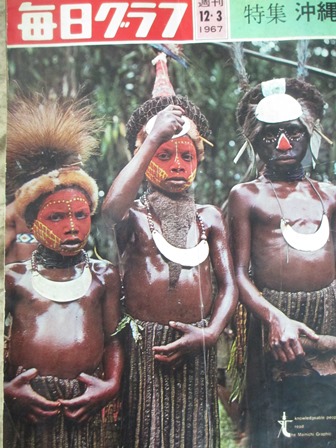
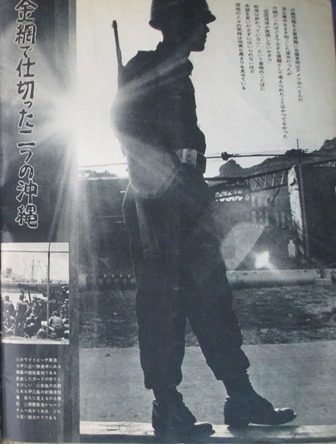
12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」
1968年
6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」
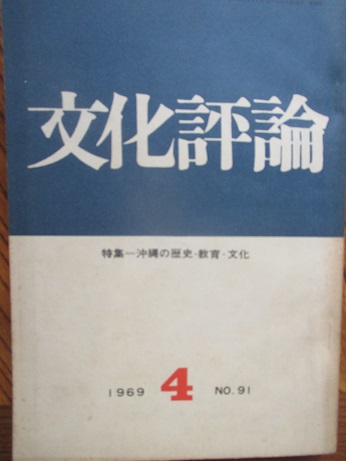
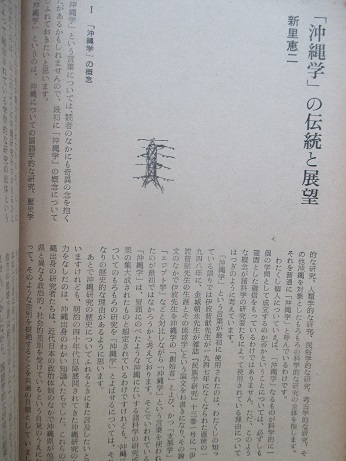
1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」
1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)
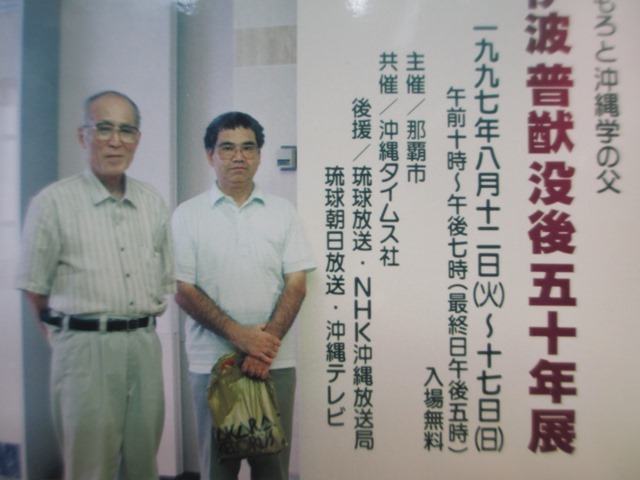
伊波廣定氏と新城栄徳
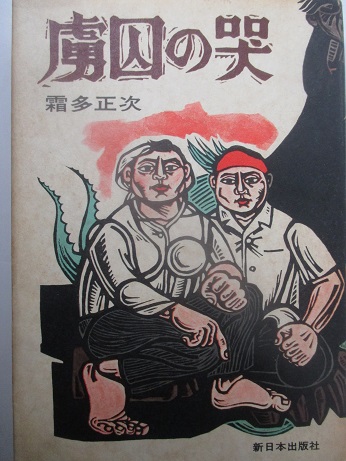
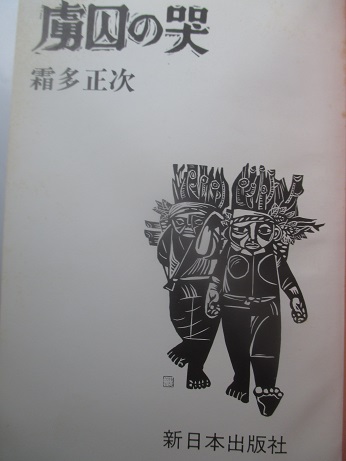
1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」
5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)
8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」
①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)
9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』
□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために
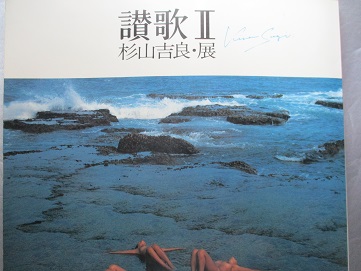
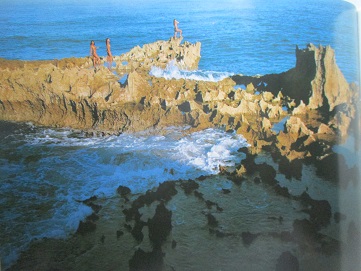
1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』
1971年
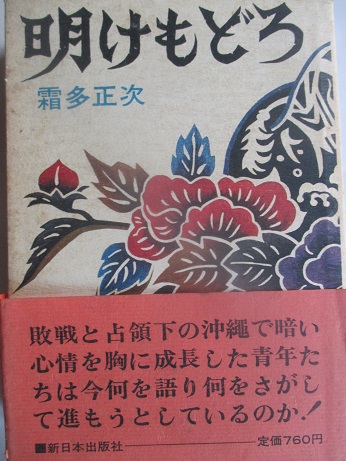
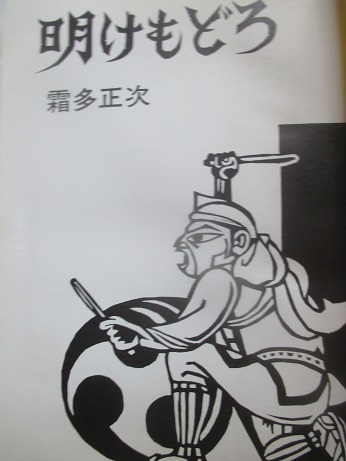
1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)
1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」
1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」
1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」
1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」
1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」
2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」
2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」
4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」
5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」
5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④
5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」
6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」
6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」
7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」
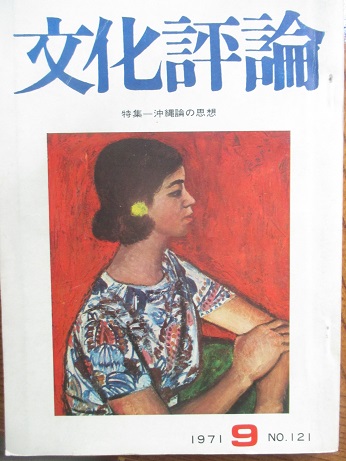
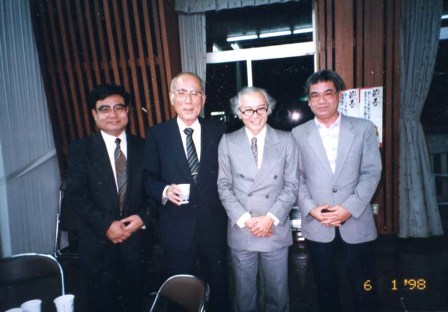
1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
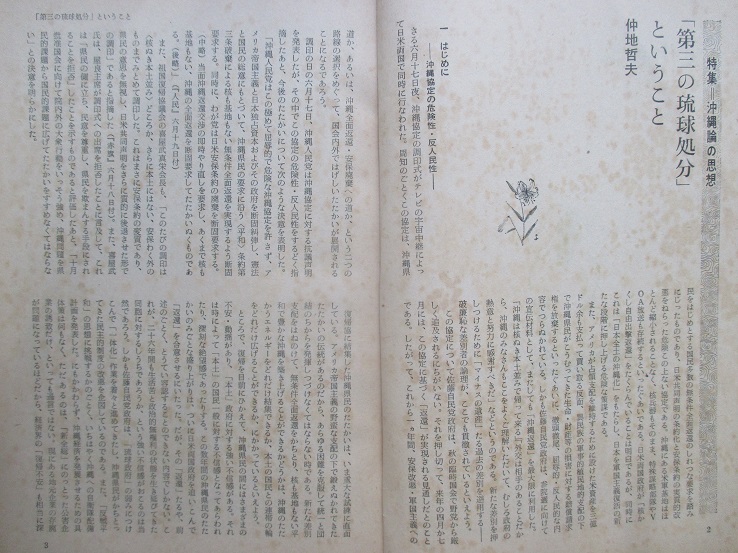
10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」
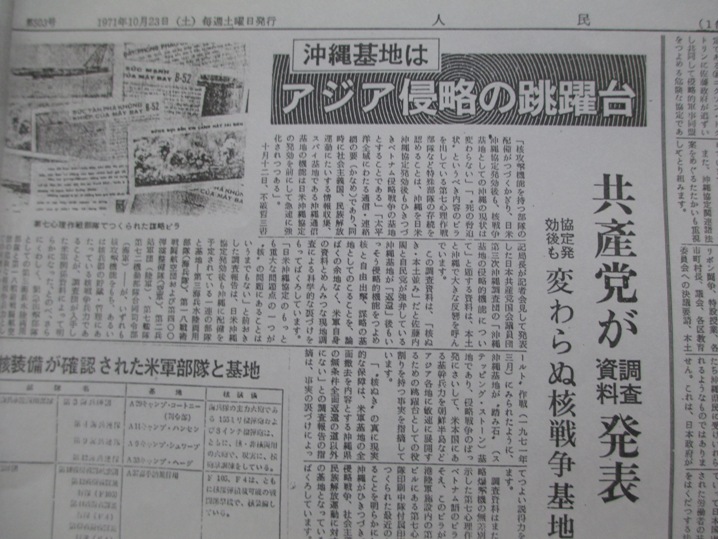
10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」


写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益
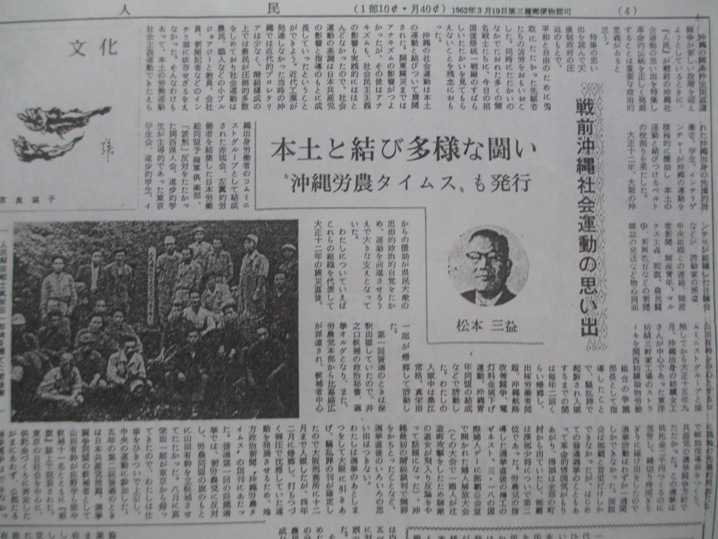
12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」
12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」
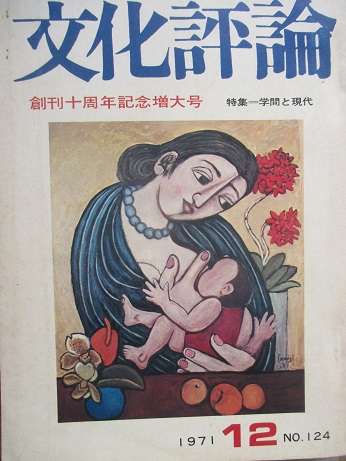
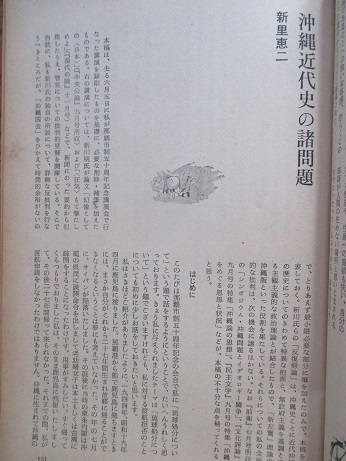
1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」
1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>
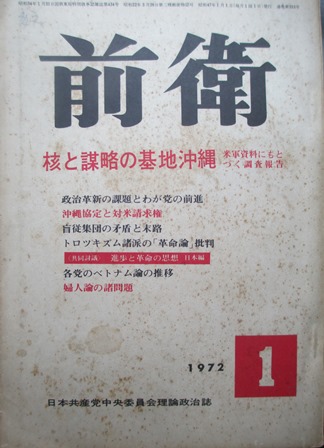

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫
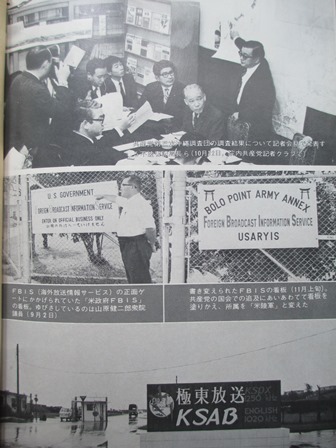
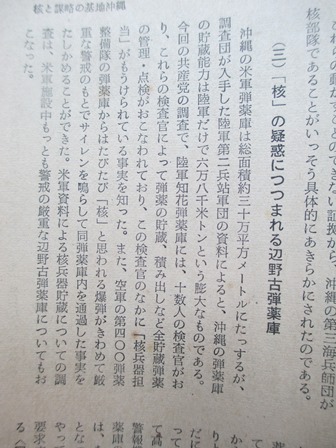
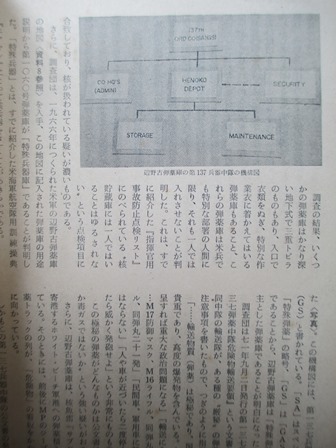
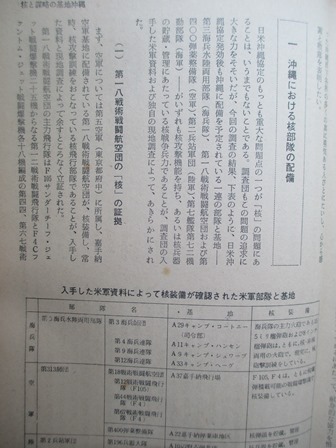


1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」
1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」
2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」
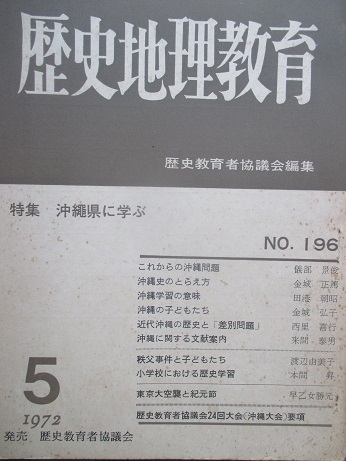
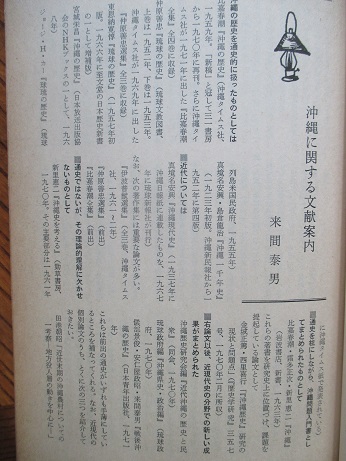
1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」
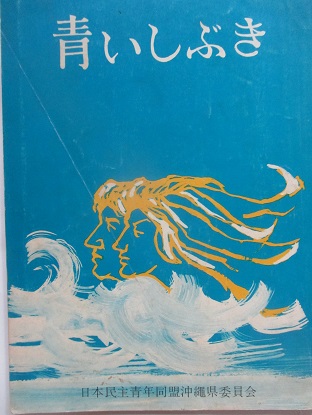
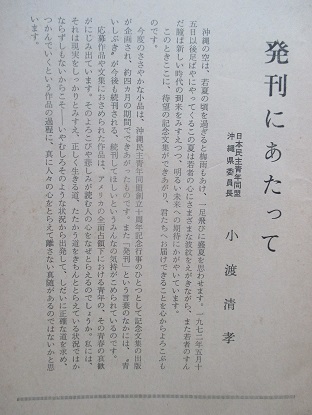
1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

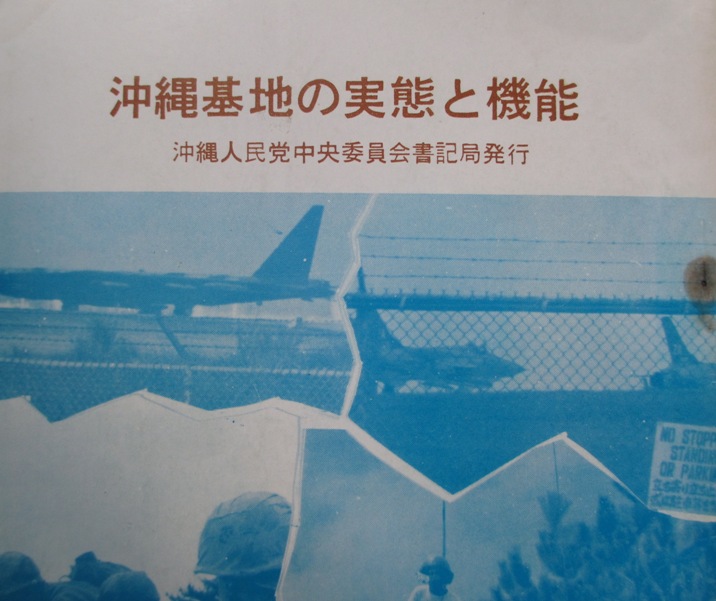
写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』
1973年
1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」
4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」
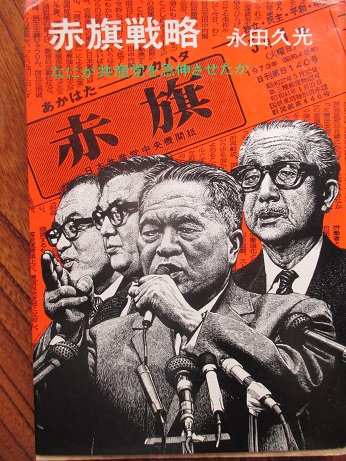
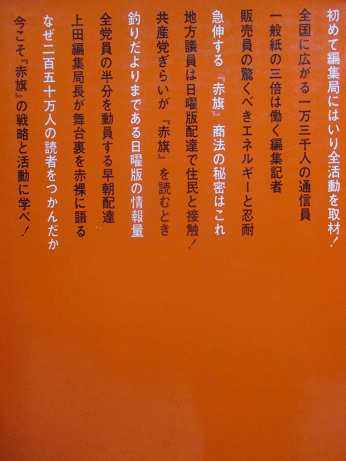
1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社
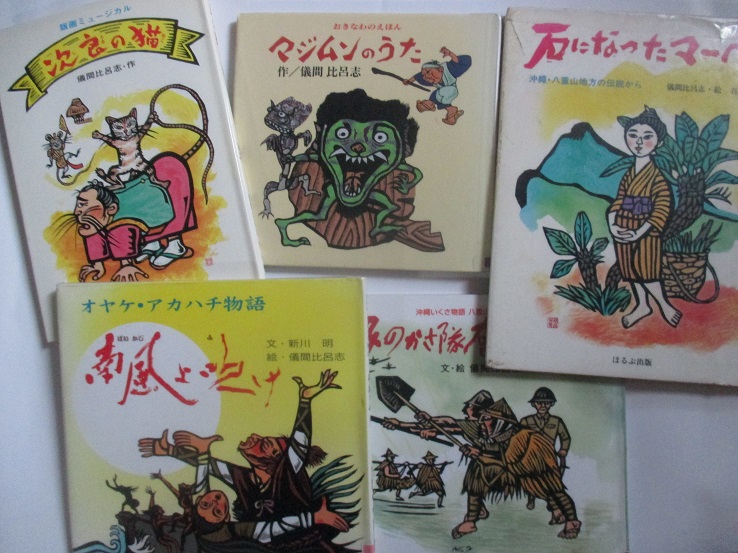
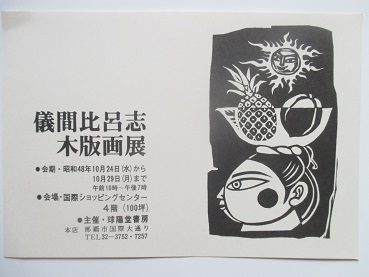
右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房
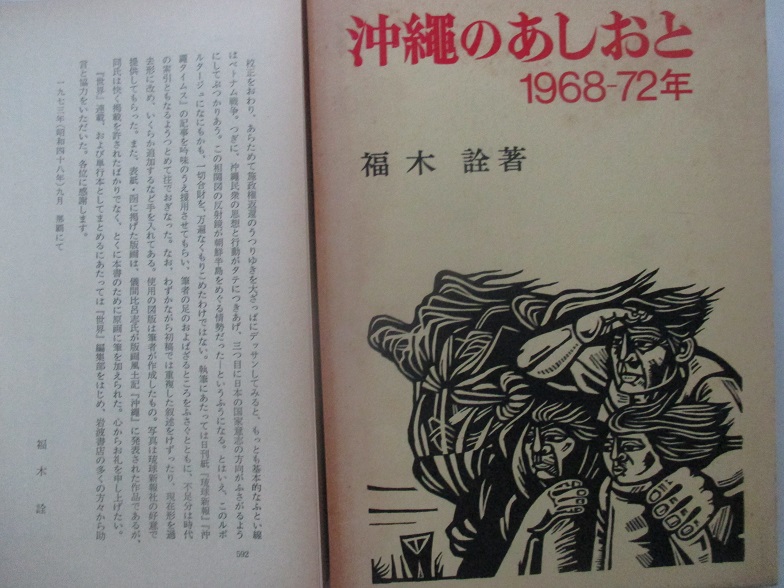
1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。
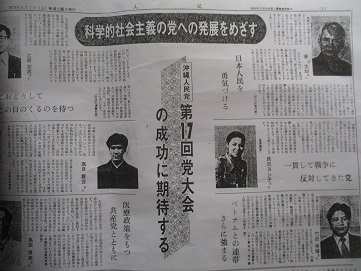
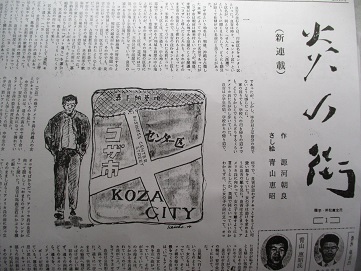
『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭
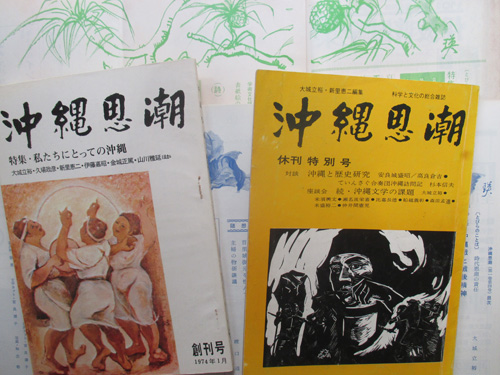
1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」
☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。
1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」
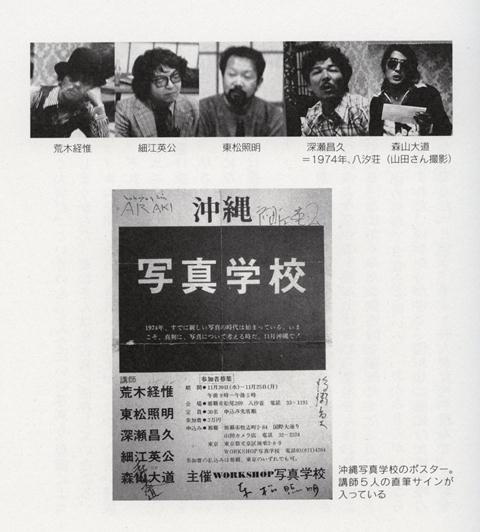
1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」
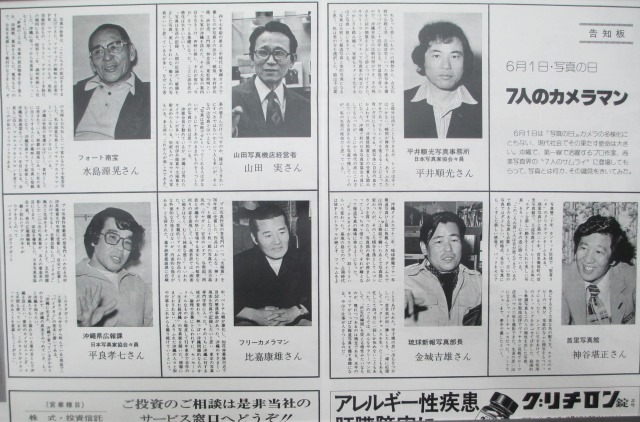
1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」
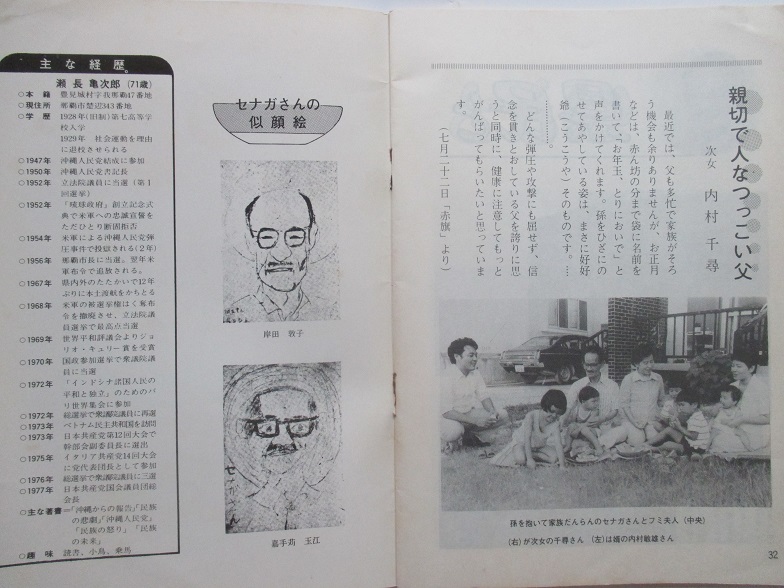
1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会


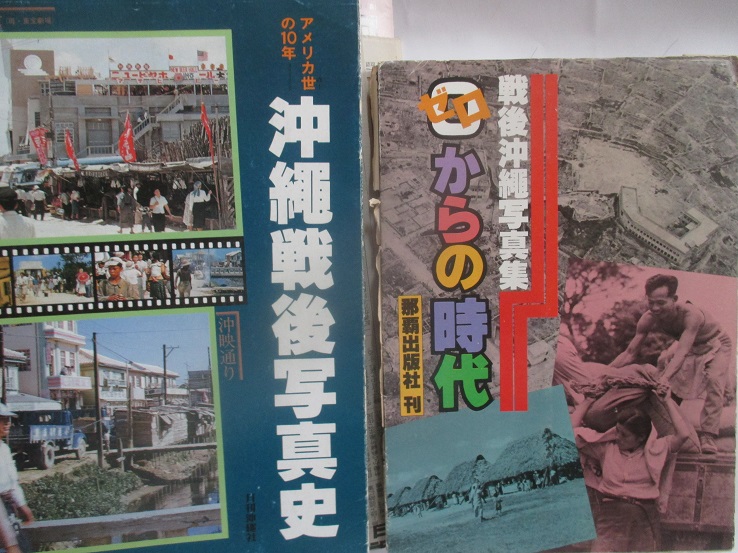
1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社
☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)
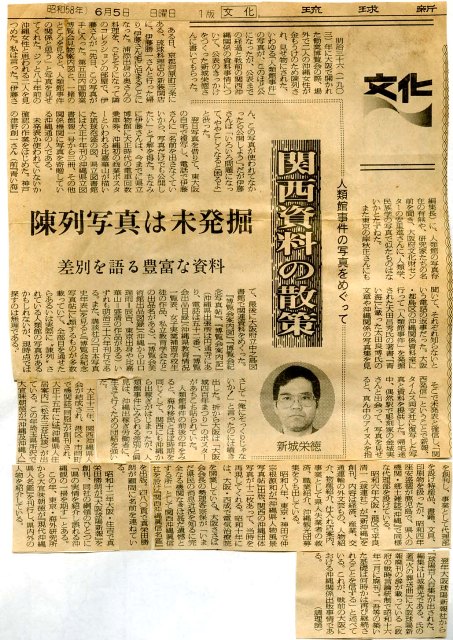
□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」
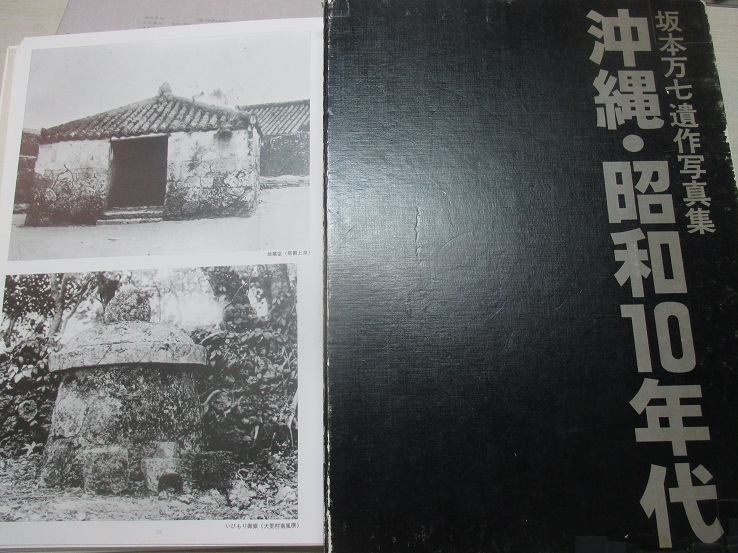
1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書
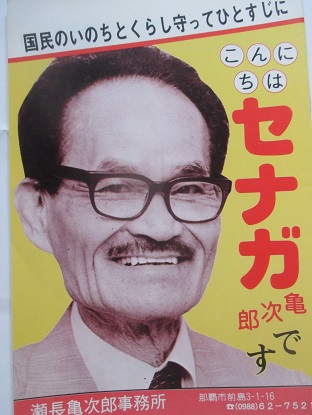
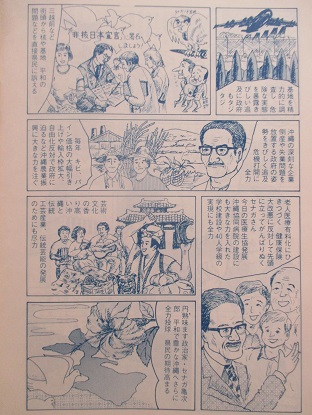
1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所
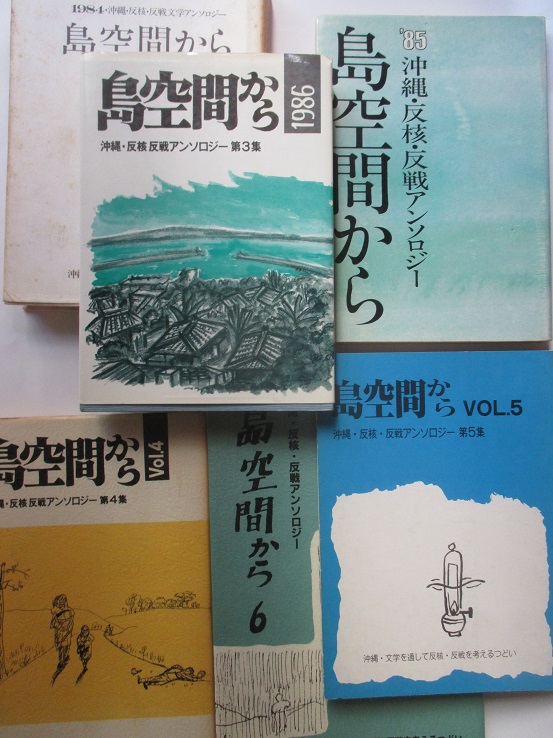
1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)
〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。
いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。
文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。
米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。
1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』
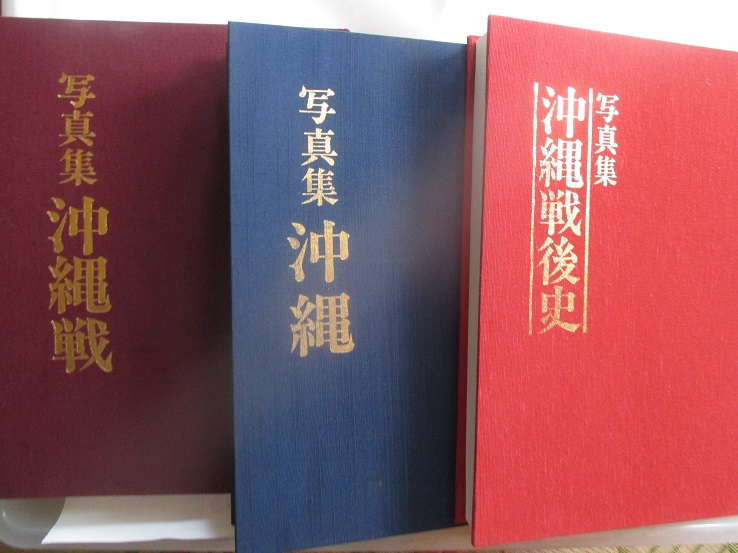
那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實
1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」
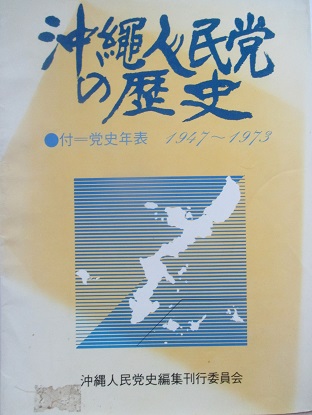
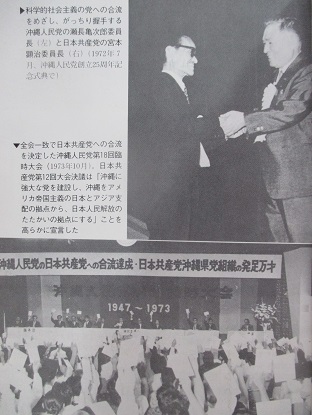
1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会
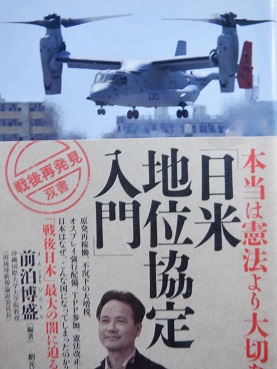
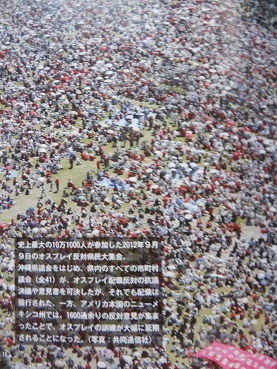
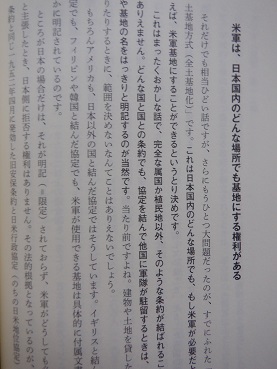
2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社
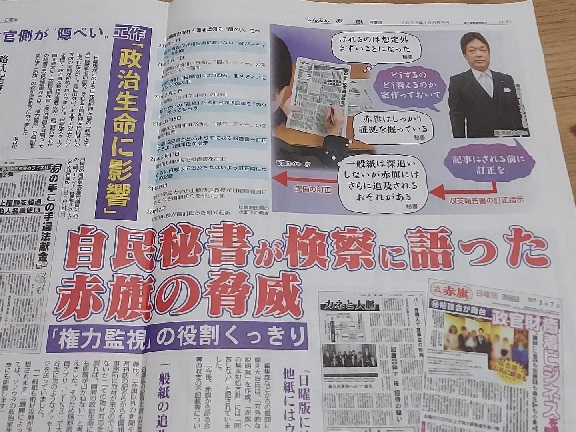
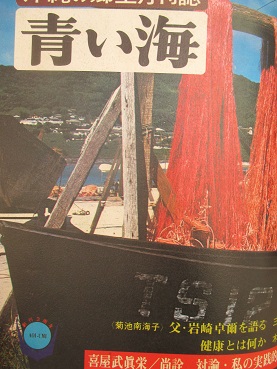
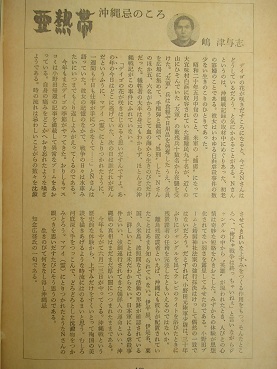
沖縄の雑誌『青い海』1974年6月号 嶋津与志(大城将保)「亜熱帯<沖縄忌>」
1971年『青い海』9月号に星雅彦「沖縄戦からの発想」、間宮則夫(映画監督)「集団自決の思想」が載っている。74年6月号には大城将保が「亜熱帯ー小野田帰還のブームと靖国神社法案の強行採決はけっして偶然の一致ではないだろう。だとすれば残置諜報者の任務を完遂したといえるではないか」と記し沖縄にも離島残置諜報者が配備されていた説く。で、離島残置諜報者の子供たちはー。
大城 将保(おおしろ まさやす、昭和14年(1939年) - )は、沖縄県出身の歴史研究者、作家。ペンネーム「嶋津与志」(しま つよし)で作家活動を行っている。沖縄国際大学講師。「沖縄平和ネットワーク」代表世話人。特定非営利活動法人沖縄県芸術文化振興協会理事長、新沖縄県史編集委員。
沖縄戦での住民の被害調査、平和研究、小説執筆などを行っている。沖縄戦研究では沖縄県史の編集に携わった後、県立博物館長などをつとめた。嶋津与志名では『琉球王国衰亡史』や映画『GAMA 月桃の花』のシナリオ作品などがある。→ウィキ
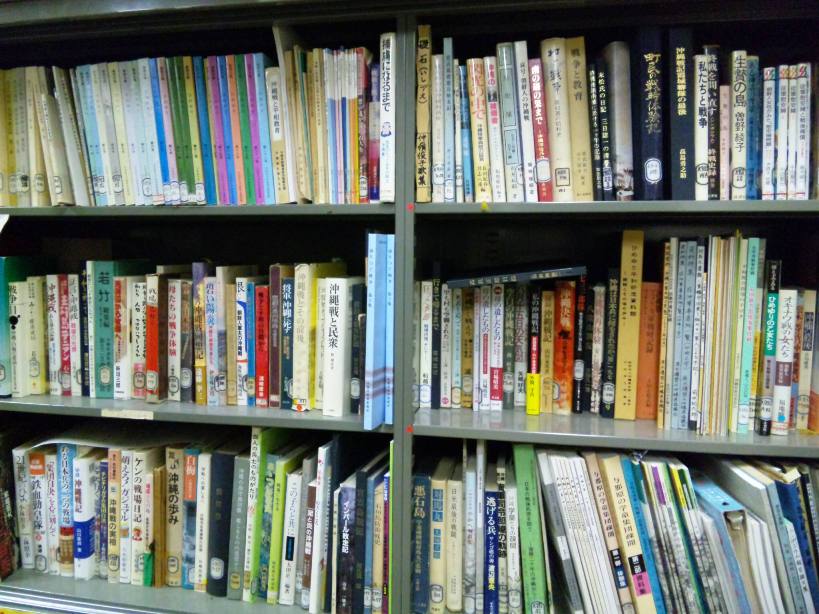
沖縄戦資料
2000年3月 沖縄県教育委員会『沖縄の歴史と文化』ー大城将保・沖縄県立博物館長「4沖縄戦」
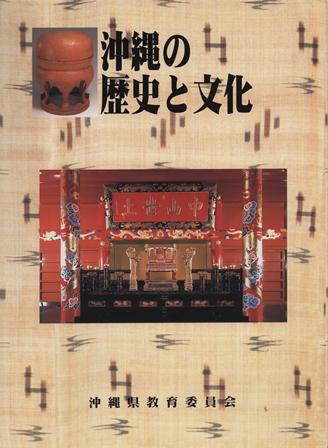
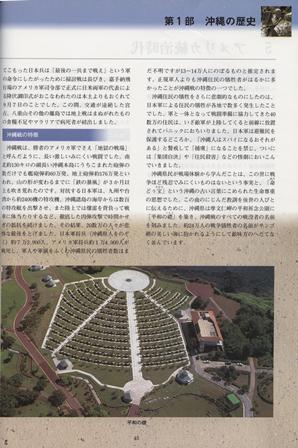
□沖縄戦の特徴
沖縄戦は、勝者のアメリカ軍でさえ「地獄の戦場」と呼んだように、長い激しいみにくい戦闘でした。南北約130キロの細長い沖縄本島にうちこまれた砲弾の数だけでも艦砲弾約60万発、地上砲弾約176万発といわれ、山の形が変わるまでに「鉄の暴風」が3カ月以上も吹き荒れたのです。対抗する日本軍は、九州や台湾から約2400機の特攻機、沖縄諸島の海岸からは数百の特攻艇を出撃させ、また陸上では爆雷」を背負って戦車に体当たりするなど、徹底した肉弾攻撃で時間かせぎの抵抗を続けました。その結果、20数万の人々が悲惨な最後をとげました。日本軍将兵(沖縄県人をのぞく)約7万2,900人、アメリカ軍将兵約1万4,000人が戦死し、軍人や軍属をふくむ沖縄県民の犠牲者数はまだ不明ですが13~14万人にのぼるものと推定されます。正規軍人よりも沖縄住民の犠牲者がはるかに多かったことが沖縄戦の特徴の一つでした。
沖縄住民の犠牲をさらに悲劇的なものにしたのは、日本軍による住民の犠牲が各地で数多く発生したことでした。軍と一体となって戦闘準備に協力したきた40数万の住民は、いざ敵軍が上陸してくると前線に放置されてパニックにおちいりました。日本軍は避難民を保護するどころか、「沖縄人はスパイになるおそれがある」と警戒して「捕虜」になることを禁じ、ついには「集団自決」や「住民殺害」などの惨劇においこんで行きました。
(略)
大城将保の本
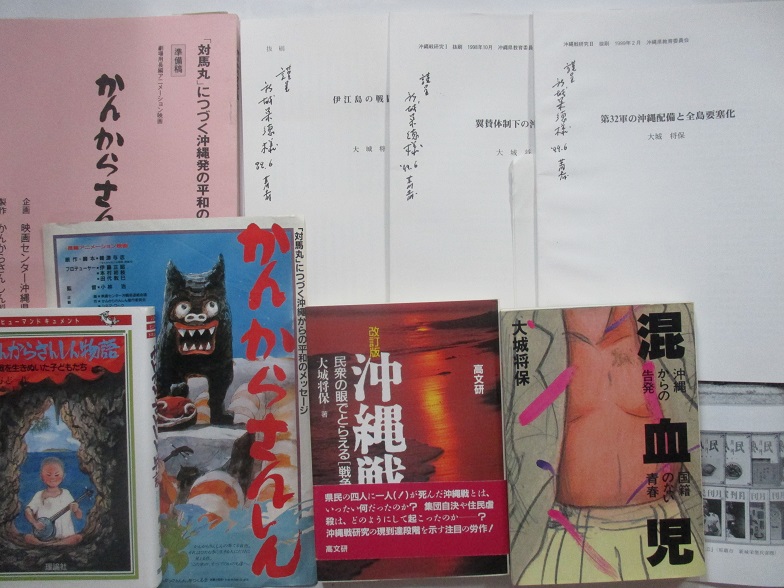

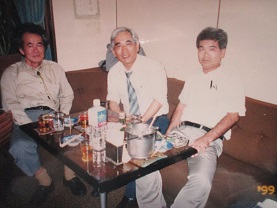
写真ー左が大城将保氏、向かいに儀間比呂志さん、石堂徳一さん/潮平正道さん中央が大城将保氏
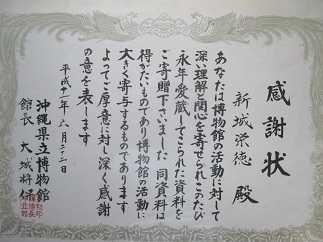
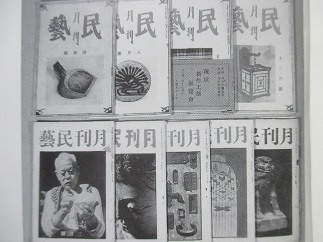
1999年、博物館に『月刊民藝』を寄贈、大城将保・沖縄県立博物館長名で感謝状
03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館




1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」
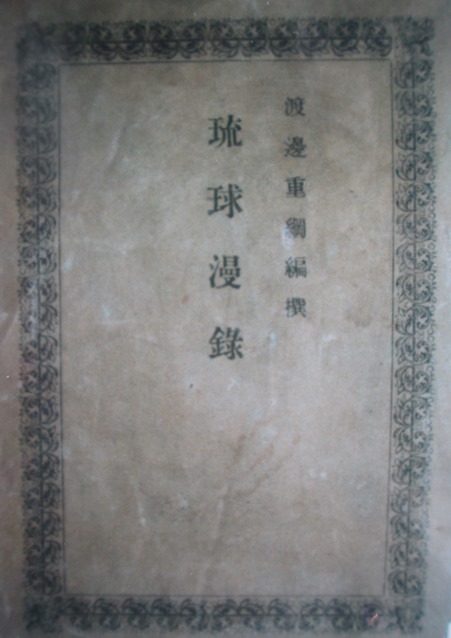

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治
うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。
討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。
1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

兼城昌興


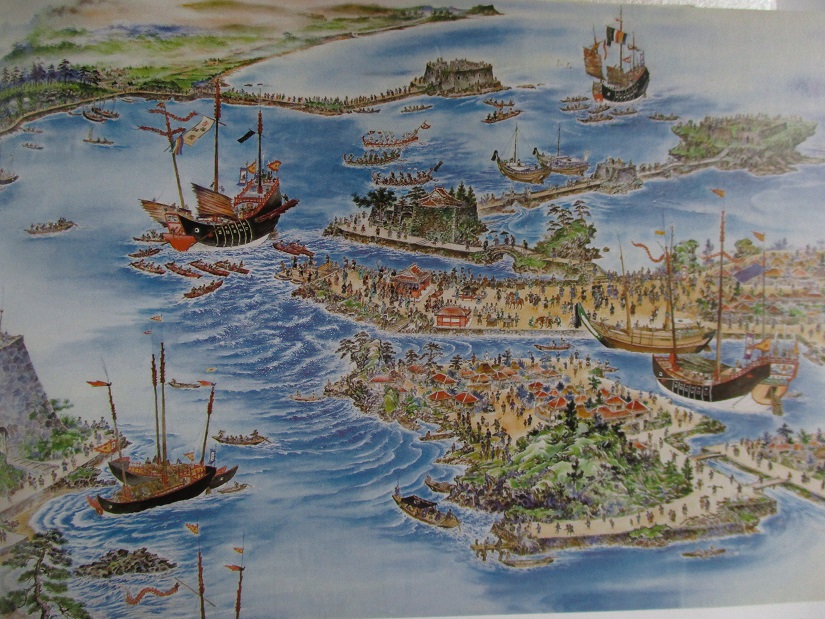
金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」
06/22: 鎌倉芳太郎①
鎌倉芳太郎年譜

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男
1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業
1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。
1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。
○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。
①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)
な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)
1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。
②平田松堂 ひらた-しょうどう
1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。
明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)
③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)
東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)
④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)
美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)
1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立
赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。
①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ
1853-1904 明治時代の実業家。
嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)
②赤星鐵馬
1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。
1901年(明治34年) 東京中学卒。
渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。
1910年(明治43年) 帰国。
1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。
1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。
1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)
③平山成信 ひらやま-なりのぶ
1854-1929 明治-大正時代の官僚。
嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)
1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。
鎌倉芳太郎、首里の座間味家に
□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄
1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。
9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。
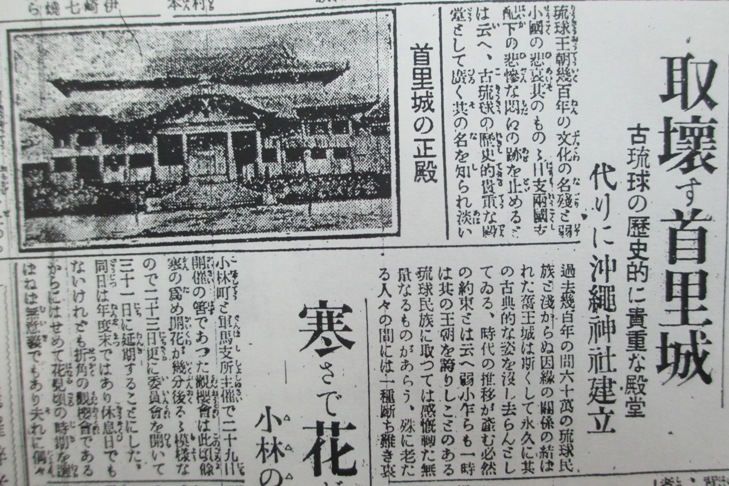
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
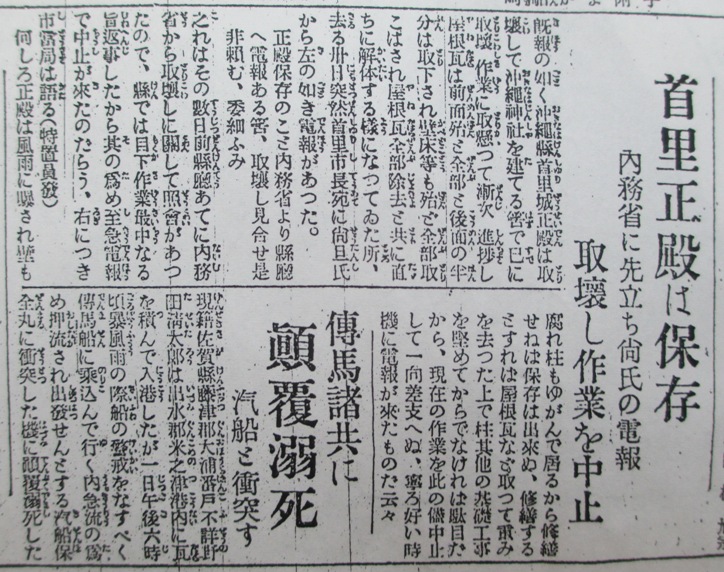
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。
1924-4
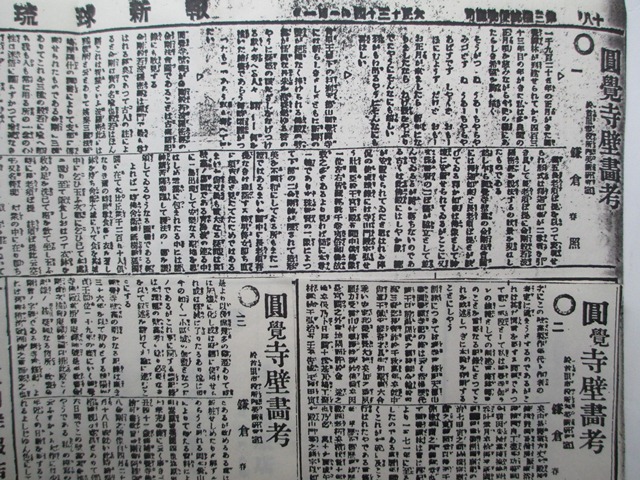
1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。
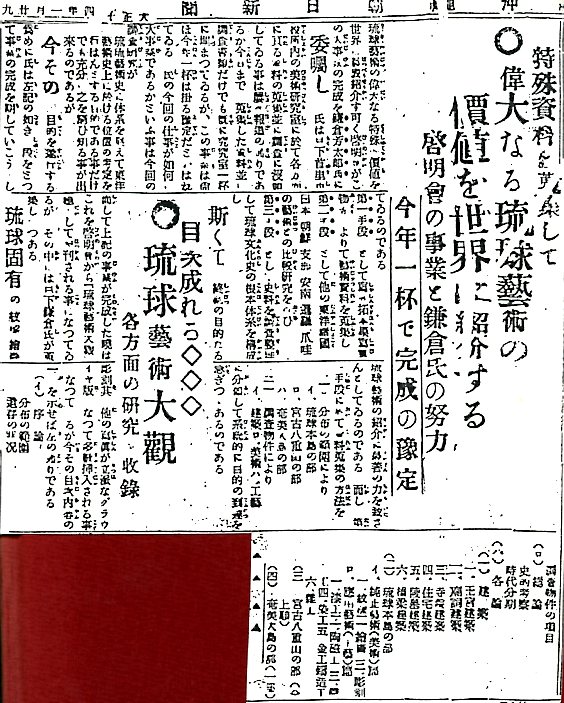
1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」
1925(大正14)年
9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)
12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて
12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」
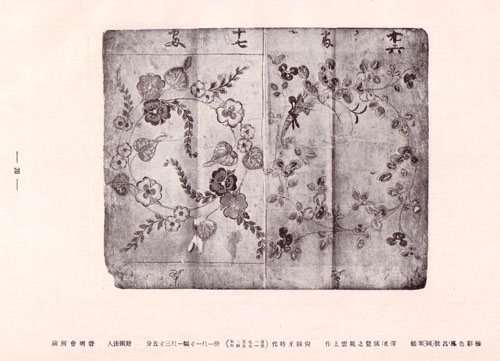
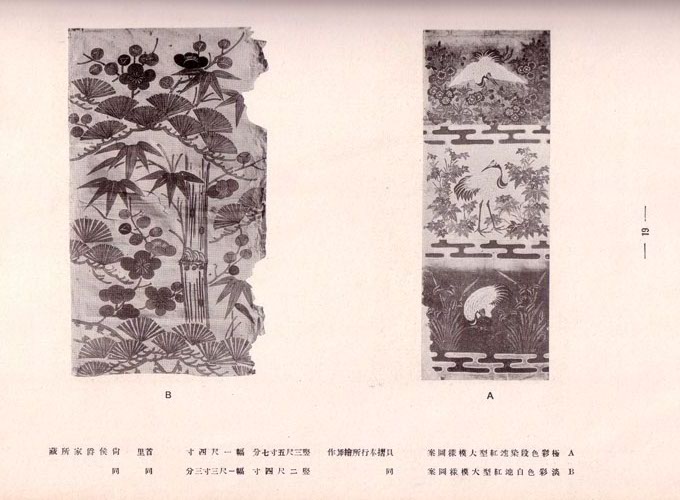
1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」
1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。
9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。
12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」
1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。
1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」
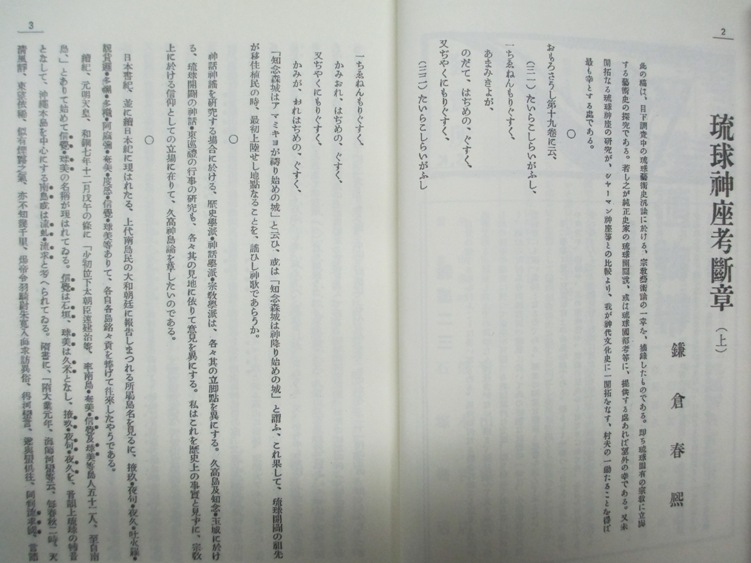
1927年
9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。
1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」


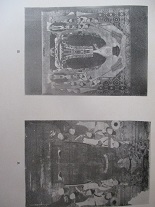

1928-12 『東洋工藝集粋』
『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」
1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」
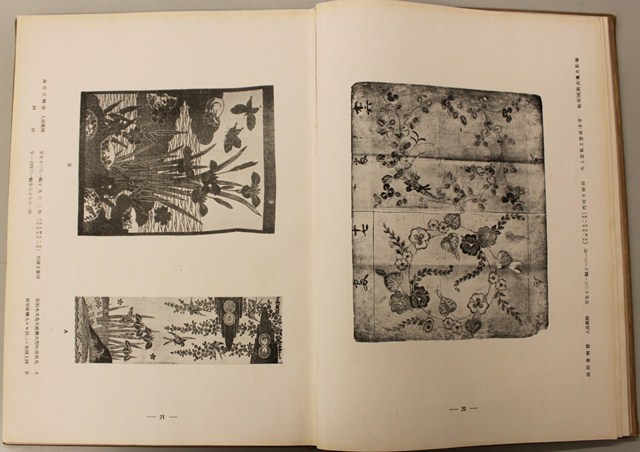
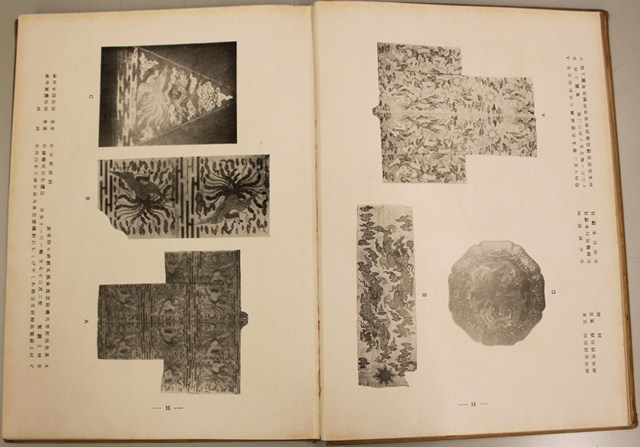
1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」
1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部
1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』
1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)
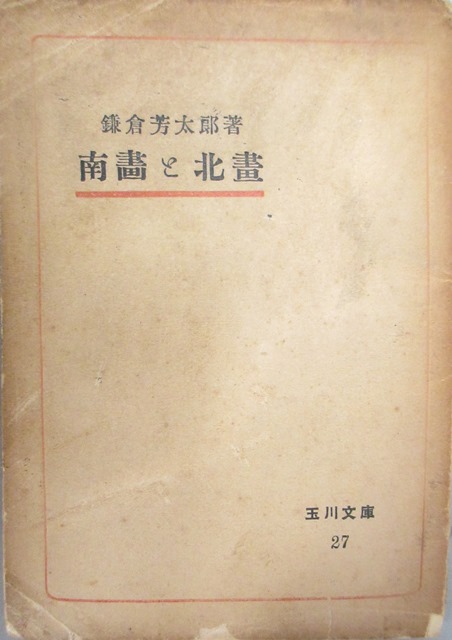
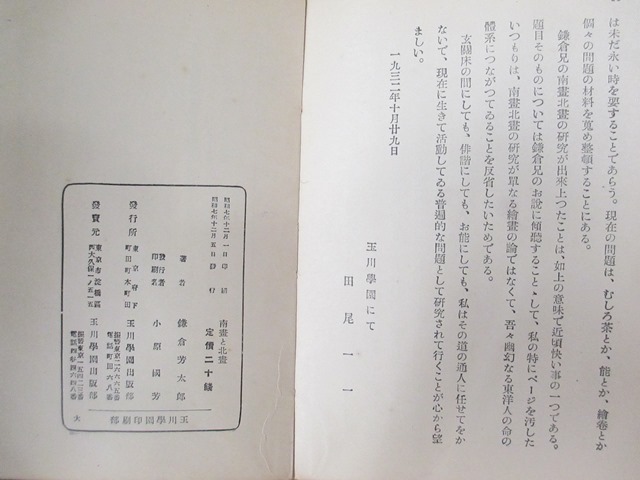
(粟国恭子所蔵)
1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫
1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。
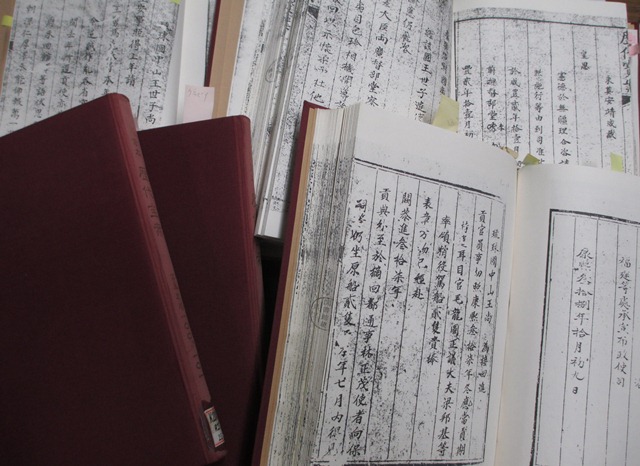
れきだいほうあん【歴代宝案】
琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)
1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」
1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』
1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」
1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖
1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。
1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)
1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。
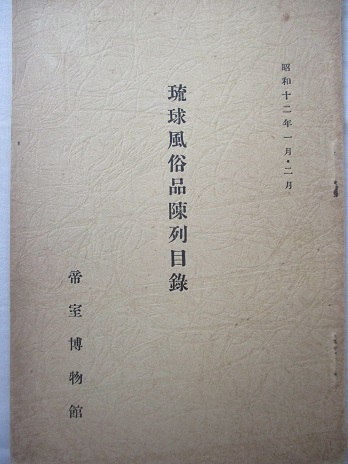
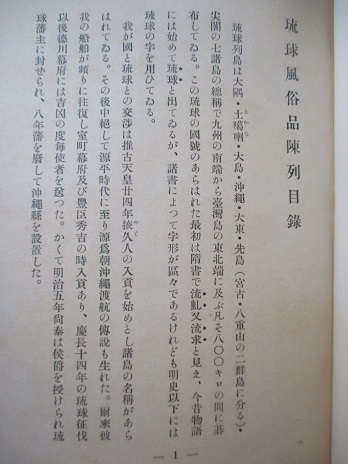
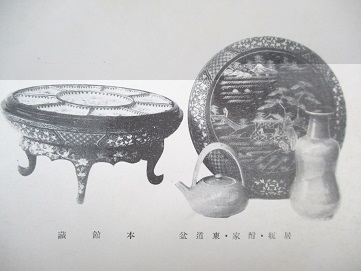


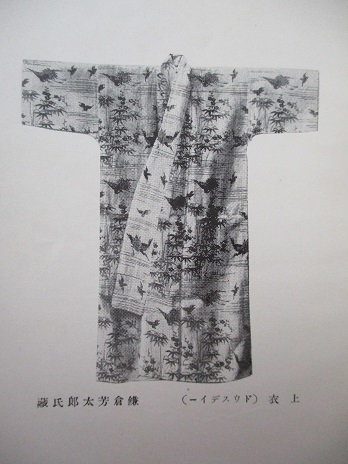

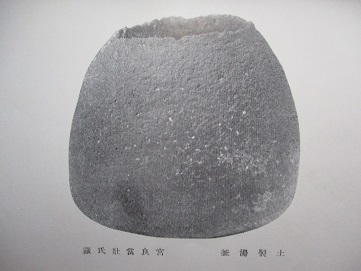
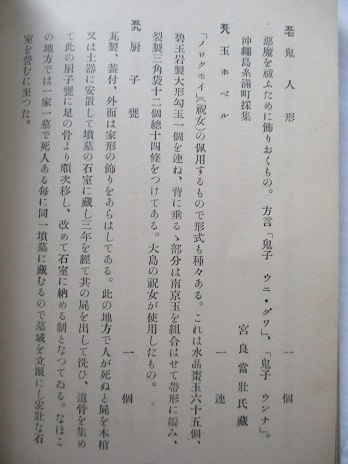
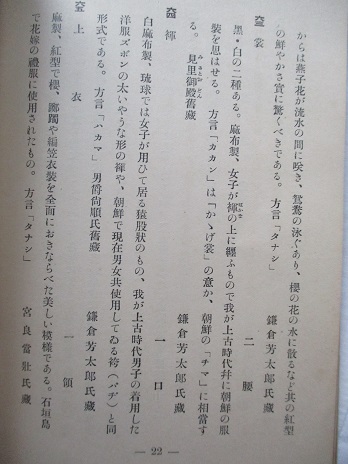
1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』
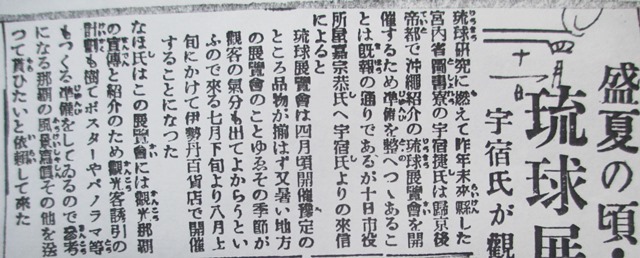
1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』
○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男
1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業
1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。
1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。
○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。
①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)
な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)
1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。
②平田松堂 ひらた-しょうどう
1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。
明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)
③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)
東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)
④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)
美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)
1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立
赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。
①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ
1853-1904 明治時代の実業家。
嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)
②赤星鐵馬
1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。
1901年(明治34年) 東京中学卒。
渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。
1910年(明治43年) 帰国。
1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。
1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。
1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)
③平山成信 ひらやま-なりのぶ
1854-1929 明治-大正時代の官僚。
嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)
1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。
鎌倉芳太郎、首里の座間味家に
□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄
1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。
9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。
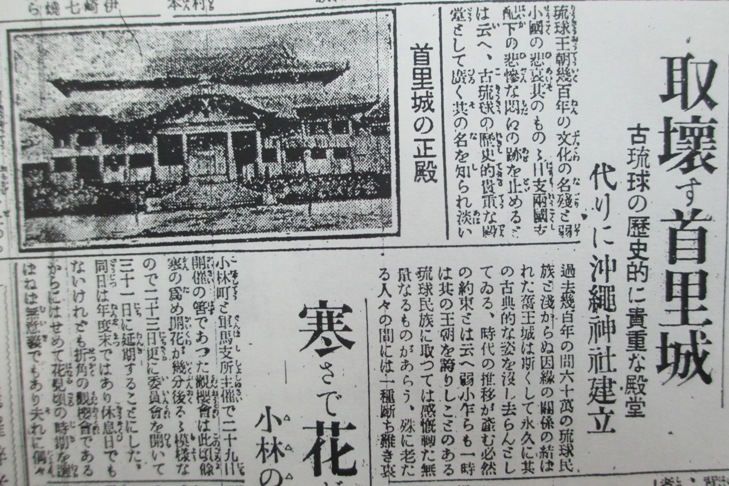
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
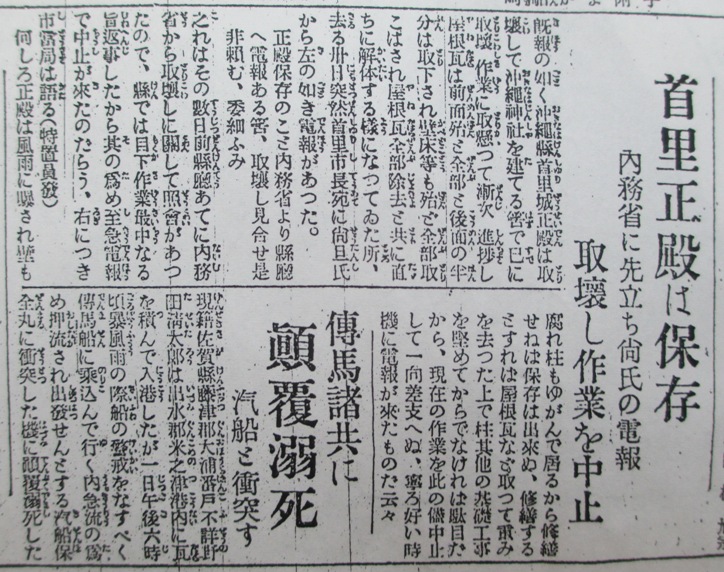
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。
1924-4
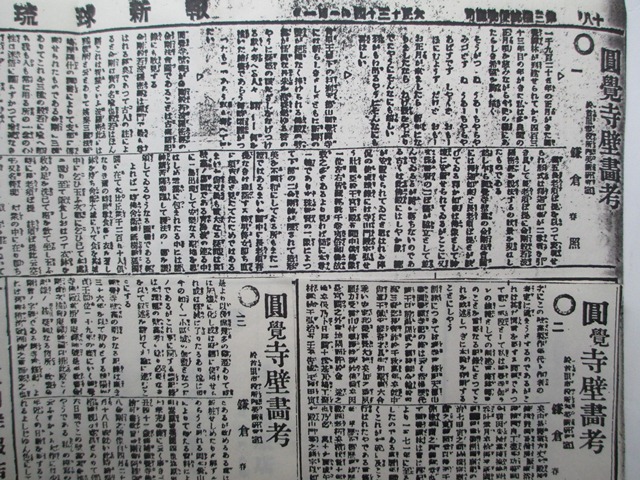
1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。
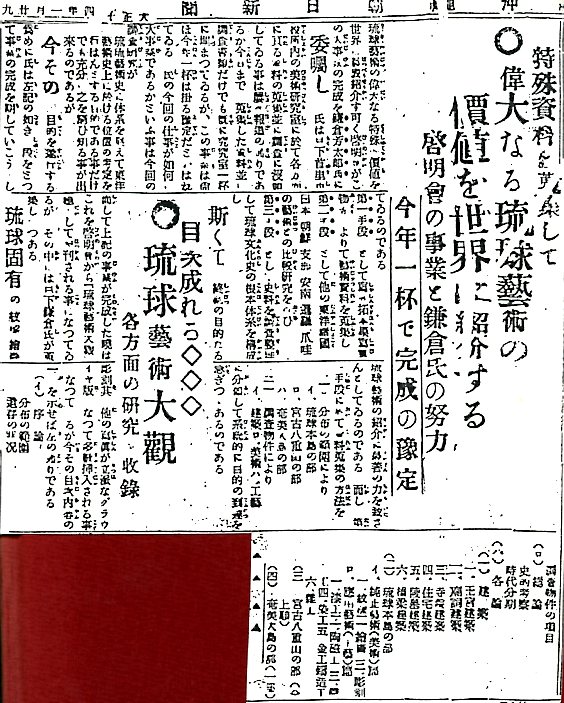
1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」
1925(大正14)年
9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)
12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて
12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」
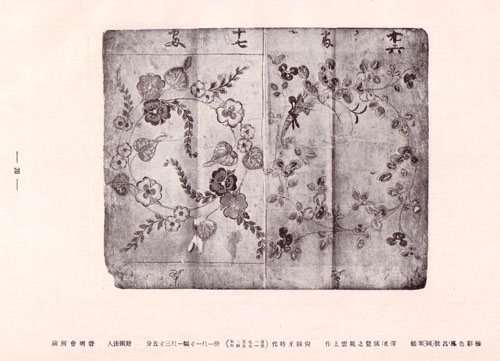
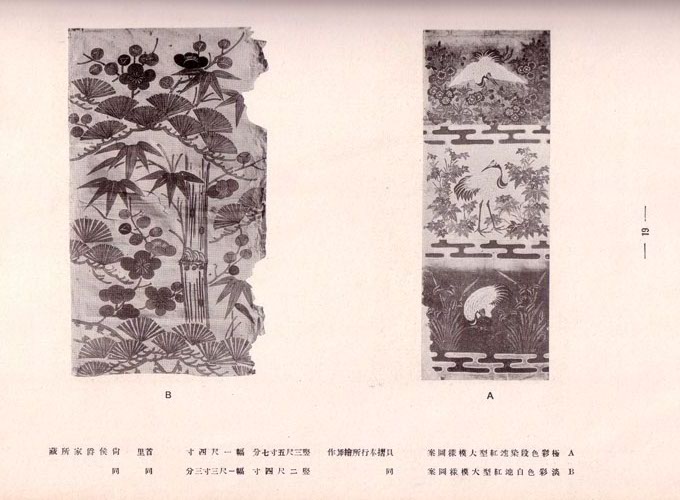
1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」
1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。
9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。
12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」
1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。
1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」
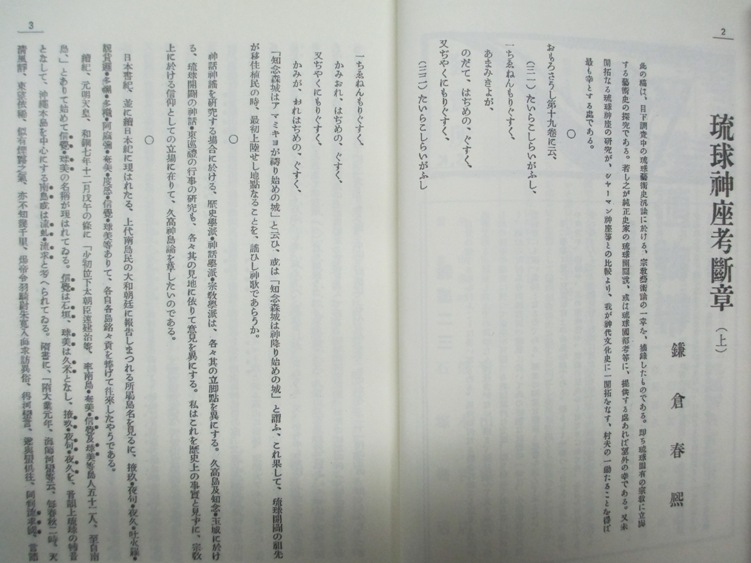
1927年
9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。
1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」


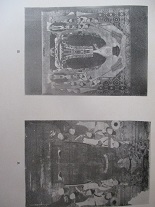

1928-12 『東洋工藝集粋』
『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」
1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」
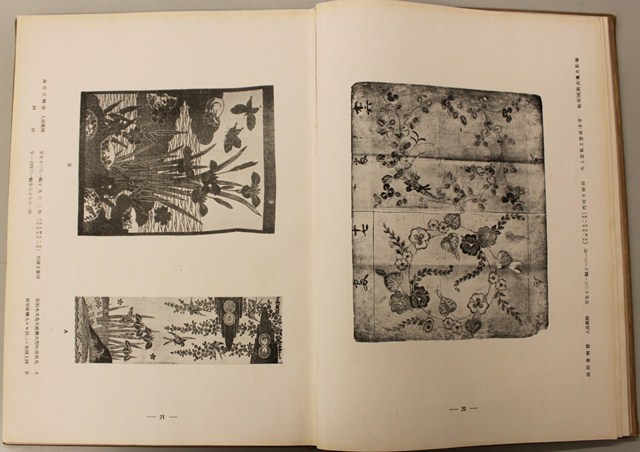
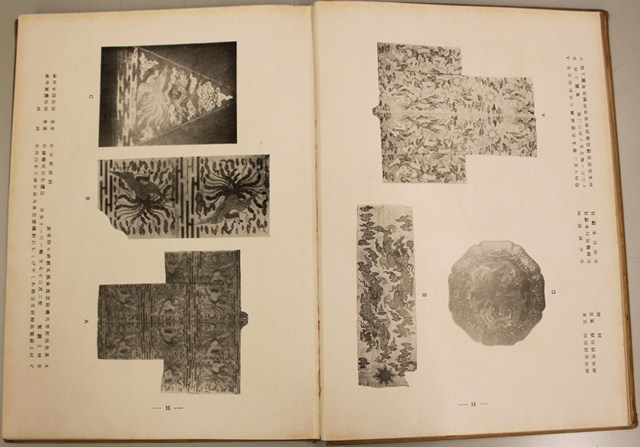
1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」
1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部
1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』
1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)
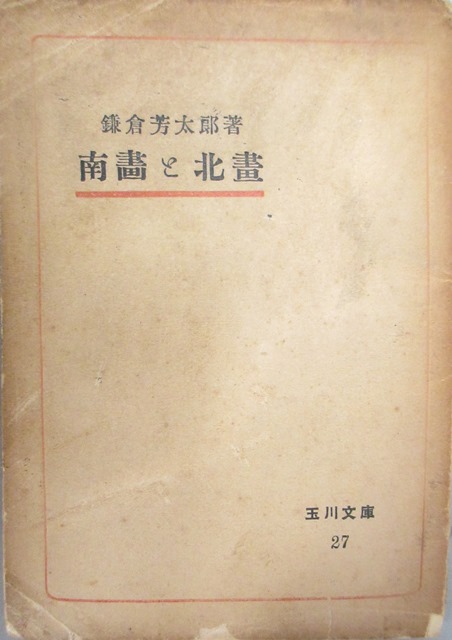
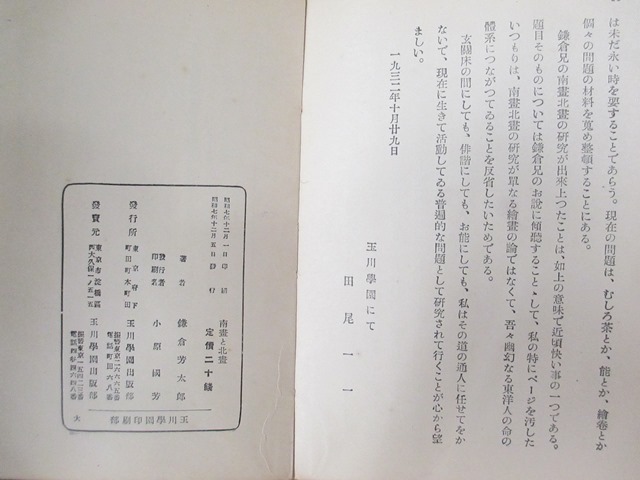
(粟国恭子所蔵)
1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫
1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。
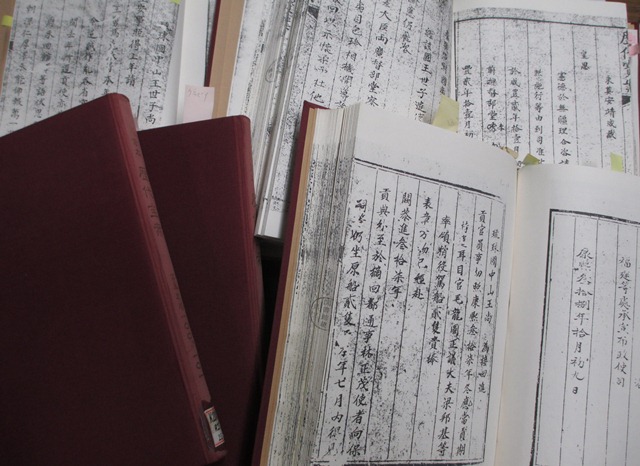
れきだいほうあん【歴代宝案】
琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)
1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」
1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』
1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」
1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖
1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。
1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)
1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。
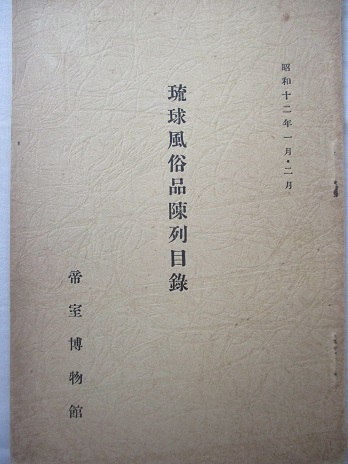
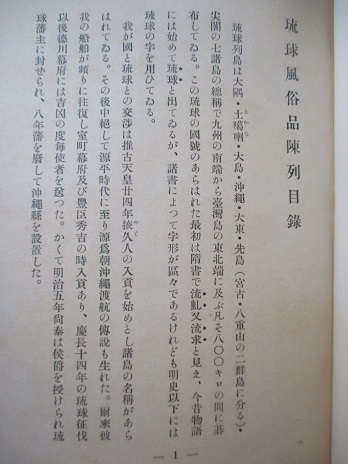
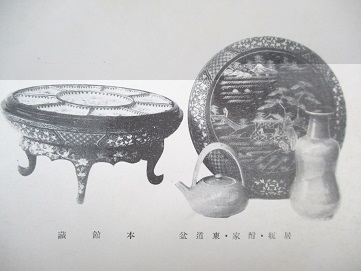


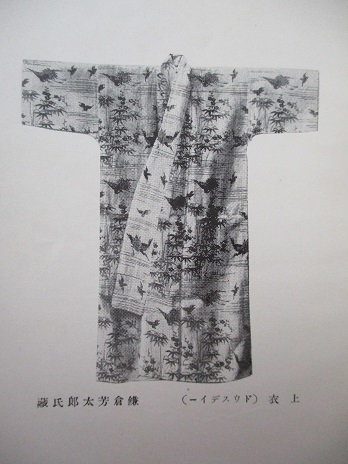

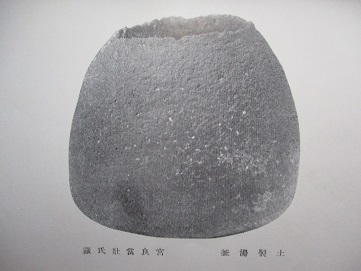
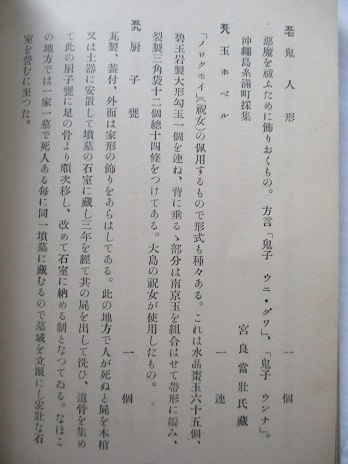
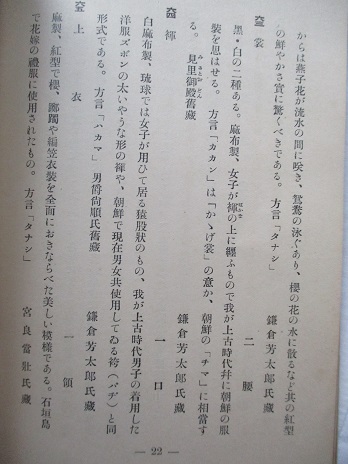
1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』
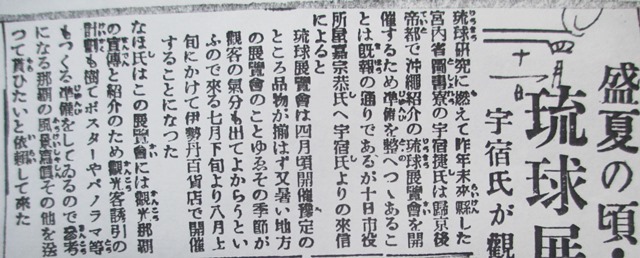
1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』
○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」
09/05: 鎌倉芳太郎②
1954年11月14日『沖縄タイムス』「琉球藝術論を脱稿ー胡屋琉大学長と同大名義出版を約すー世に出るか、鎌倉芳太郎教授の著書(本文・千二百頁、図版五百頁)」
1955-8 日本橋高島屋「沖縄展」鎌倉芳太郎、型紙出品
8月ー東京日本橋高島屋で読売新聞主催「沖縄展」
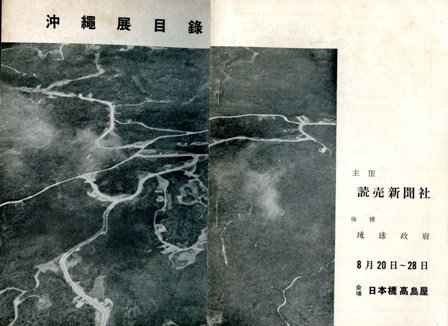
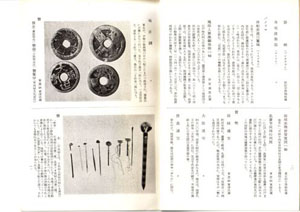
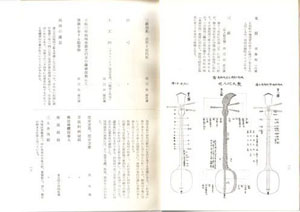
1957-12-1 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「私と沖縄」□交友関係では末吉麦門冬(末吉安久氏の実兄)と意気投合。いろいろ啓発し、されたもの
1958-7-16 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「沖縄の美しいもの」(1)6-15川崎市沖縄文化同好会第8回沖縄文化講座で講演したもの。~7-26(10)
1960-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型型紙の研究』京都書院
1961年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「円覚寺大雄殿壁画」(鎌倉芳太郎模写)、「大島祝女服装図」(鎌倉芳太郎模写)寄贈。鎌倉芳太郎から「ときさうし」「古代祝女衣裳カカン」「古代芭蕉地カカン」、鎌倉秀雄から「進貢船図」購入
1963-9月 鎌倉芳太郎『琉球の織物』京都書院
1964年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「三平等兼題文言集」「呈禀文集」「寺社由来記」「琉球事件 上」「球陽外巻(遺老説伝)」「萬集」「覚世真経」「廃藩後旧例相変り候事件」「浦添御殿本 『王代記』」「大上感応篇大意の序」を寄贈。鎌倉秀雄から「琉球詩集」「琉球官生詩集」「琉球詩録」「毛世輝詩集」「東子祥先生詩集」「平敷屋朝敏文集」「中山王府相卿伝職年譜」「御書院並南風原御殿御床飾」「御座飾帳」「御書院御物帳」「琉球俗語 巻之一」購入
1966ー10 東京ひめゆり同窓会『戦後二十周年記念誌』(表紙・鎌倉芳太郎)□鎌倉芳太郎「回想記ー廃藩置県時代以前の琉球王国時代の美術研究に従事した。その関係で沖縄タイムス主筆 麦門冬末吉安恭氏と親交を続けた。またその縁戚の南村氏とも顔を合わせる機会が多く、したがって当時の沖縄における共産社会主義の猛者連中の思想運動にもふれた・・・」
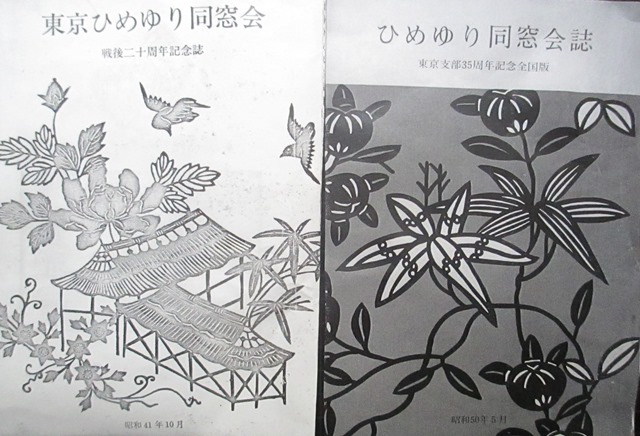
1966年10月/1975年10月
1968年2月 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』京都書院
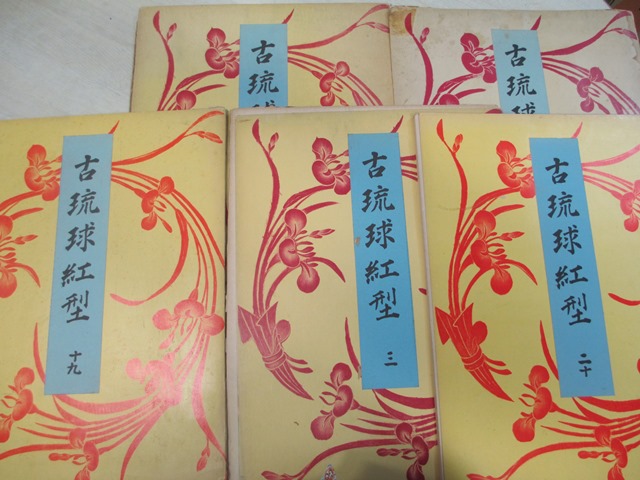
1968-4 日本橋東急百貨店「沖縄展」図録 鎌倉芳太郎「琉球造形美術について」→名古屋の徳川美術館でも中日新聞社共催で開催された。
4月ー東急百貨店日本橋店7階で「沖縄展ー琉球の自然と文化」
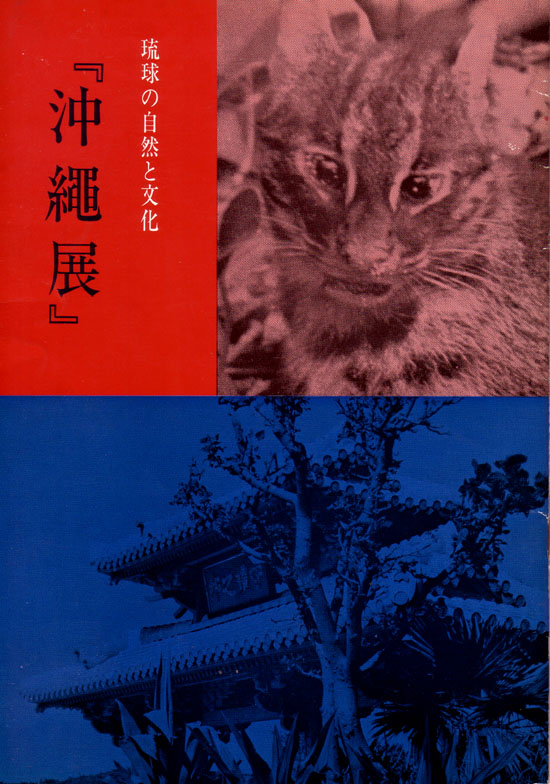
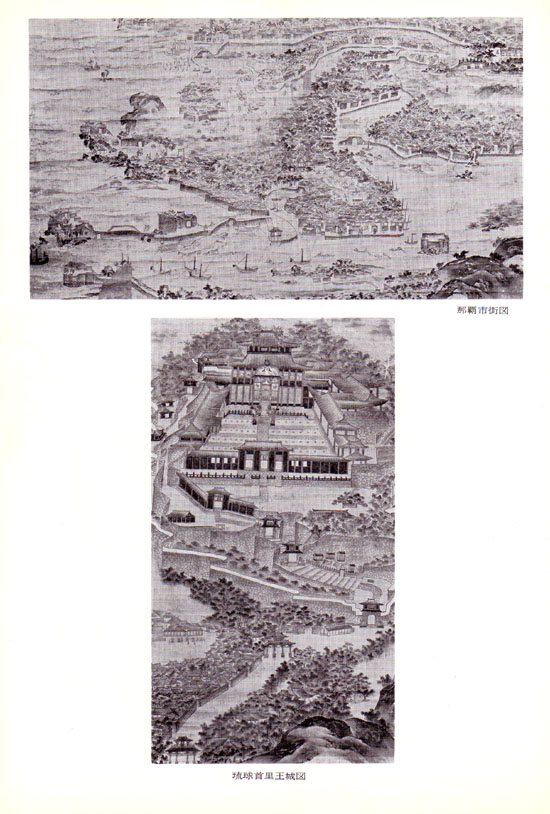
1971-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』上下 京都書院
1971 鎌倉芳太郎『古琉球型紙』京都書院
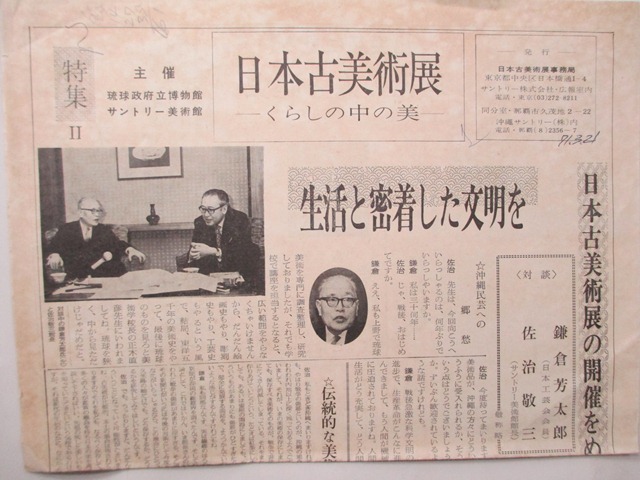
1955-8 日本橋高島屋「沖縄展」鎌倉芳太郎、型紙出品
8月ー東京日本橋高島屋で読売新聞主催「沖縄展」
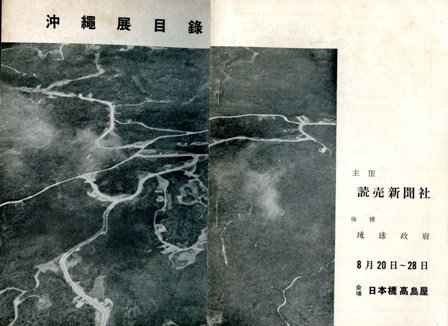
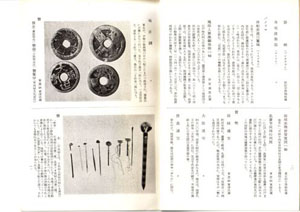
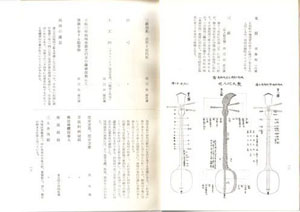
1957-12-1 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「私と沖縄」□交友関係では末吉麦門冬(末吉安久氏の実兄)と意気投合。いろいろ啓発し、されたもの
1958-7-16 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「沖縄の美しいもの」(1)6-15川崎市沖縄文化同好会第8回沖縄文化講座で講演したもの。~7-26(10)
1960-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型型紙の研究』京都書院
1961年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「円覚寺大雄殿壁画」(鎌倉芳太郎模写)、「大島祝女服装図」(鎌倉芳太郎模写)寄贈。鎌倉芳太郎から「ときさうし」「古代祝女衣裳カカン」「古代芭蕉地カカン」、鎌倉秀雄から「進貢船図」購入
1963-9月 鎌倉芳太郎『琉球の織物』京都書院
1964年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「三平等兼題文言集」「呈禀文集」「寺社由来記」「琉球事件 上」「球陽外巻(遺老説伝)」「萬集」「覚世真経」「廃藩後旧例相変り候事件」「浦添御殿本 『王代記』」「大上感応篇大意の序」を寄贈。鎌倉秀雄から「琉球詩集」「琉球官生詩集」「琉球詩録」「毛世輝詩集」「東子祥先生詩集」「平敷屋朝敏文集」「中山王府相卿伝職年譜」「御書院並南風原御殿御床飾」「御座飾帳」「御書院御物帳」「琉球俗語 巻之一」購入
1966ー10 東京ひめゆり同窓会『戦後二十周年記念誌』(表紙・鎌倉芳太郎)□鎌倉芳太郎「回想記ー廃藩置県時代以前の琉球王国時代の美術研究に従事した。その関係で沖縄タイムス主筆 麦門冬末吉安恭氏と親交を続けた。またその縁戚の南村氏とも顔を合わせる機会が多く、したがって当時の沖縄における共産社会主義の猛者連中の思想運動にもふれた・・・」
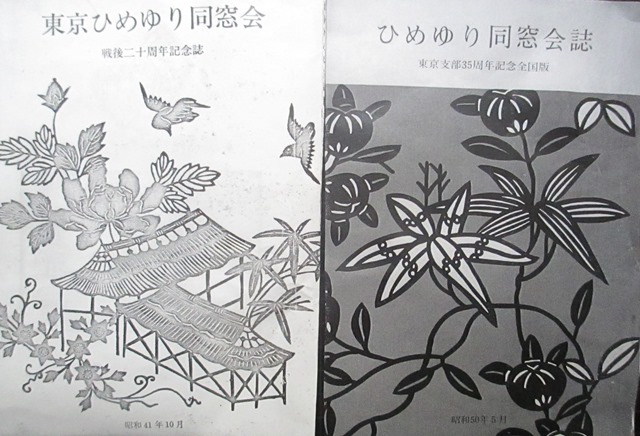
1966年10月/1975年10月
1968年2月 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』京都書院
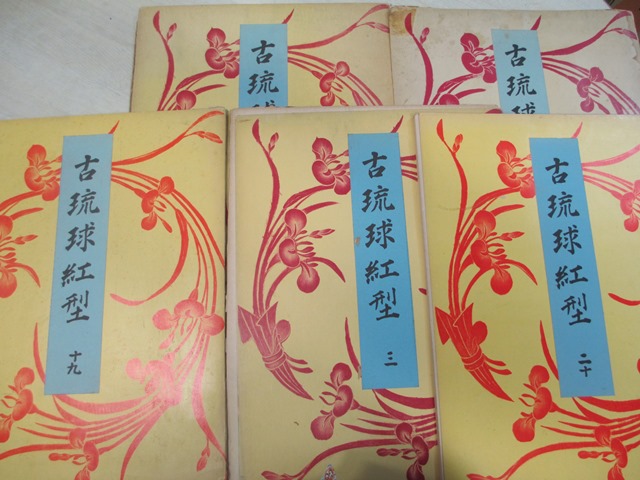
1968-4 日本橋東急百貨店「沖縄展」図録 鎌倉芳太郎「琉球造形美術について」→名古屋の徳川美術館でも中日新聞社共催で開催された。
4月ー東急百貨店日本橋店7階で「沖縄展ー琉球の自然と文化」
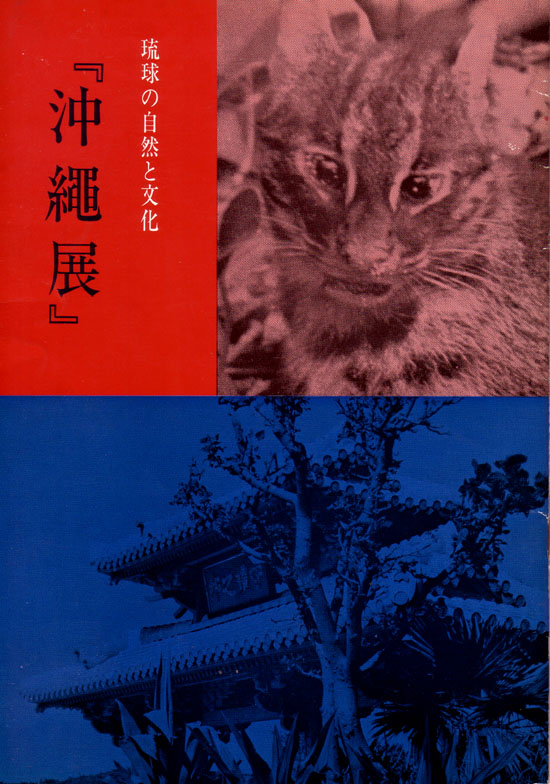
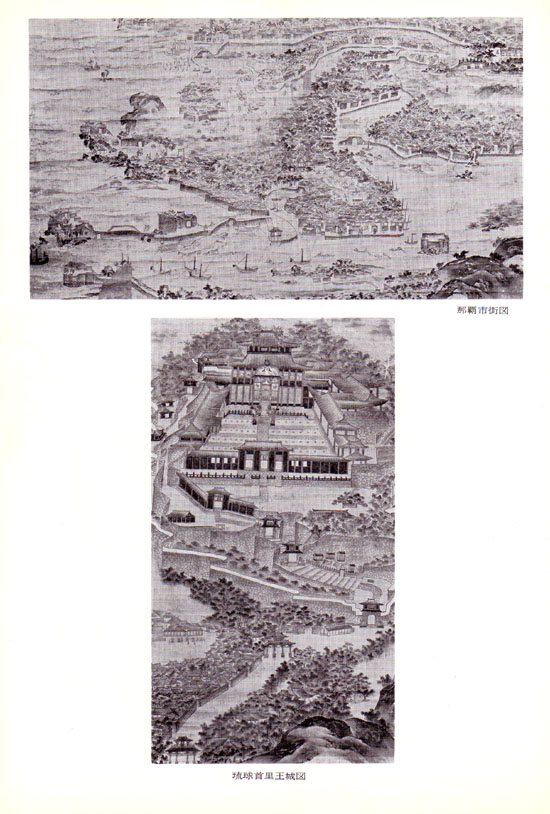
1971-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』上下 京都書院
1971 鎌倉芳太郎『古琉球型紙』京都書院
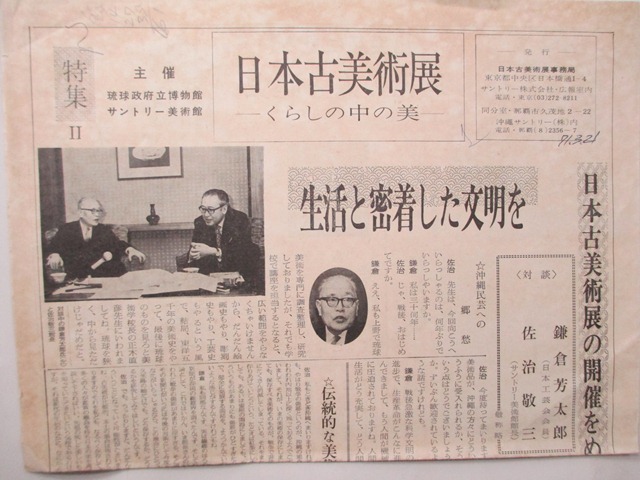
09/16: 那覇市歴史博物館 「沖縄のシンボル 守礼門」展②
守礼門
小峯和明立教大学教授の『今昔物語集の世界』に「ある人は個人の屋敷の門やお寺の三門を想像するでしょうし、ある人はパリの凱旋門や都市の有名な門を連想するかもしれません」と門の話から始まり羅城門(羅生門)で話がはじまっている。ここに出てくる「守礼の門」は扁額が「守礼之邦」となっているところからそう呼ぶのであるが、中には「守礼門」と書いて「しゅれいのもん」と呼ぶのもいる。
大阪「沖縄関係資料室」(西平守晴主宰)には守礼門の扁額の拓本が軸装である。これは1972年に「豊川忠進先生の長寿を祝う会」のため那覇市の又吉真三氏から借用し寄贈されたものである。拓本の先駆者は久場政用。久場には『琉球金石総覧』『琉球列島之文化史料と植物史料』がある。また1926年の『沖縄タイムス』には「久場政用事業広告ー琉球植物園、科学知識普及ノ講話」がある。
新川明氏は『沖縄・統合と反逆』の中で「『守礼門』新札をどう読むか」と題し「扁額の『守禮之邦』という語句は、琉球王国が対外的に礼節を重んずる国であることを内外に宣言した意味を持つ。おのずからその国民は『守礼の民』であるという自己規定が生じる。『守礼門』は、そのような自己規定を媒介する『記号』として共有されてきたのである」とし、続けて「このような伝統は直ちに統治者によって逆手に取られ、支配目的を遂行するために利用されるのが常である。たとえば米軍統治下の沖縄に『守礼の光』と題する雑誌があった」としその側面にも触れている。
守礼門は、首里城が復元されるまでは「沖縄のシンボル」であった。最近は無用の長物の扱いを受け、沖縄教育委員会発行の『概説・沖縄の歴史と文化』の索引にも独立した項目としては無い。首里城に一括りされ冷たい扱いとなっている。1853年6月6日にペリー提督一行が首里城を訪れた。その遠征記には守礼門の版画が掲載されている。扁額の字は「中山府」としか見えないがとにかくもアメリカ史に守礼門が登場した最初のものであろう。
1952年発行の琉球郵便切手に「正殿唐破風」「琉大開学記念」(正殿が描かれている)、53年発行の「ぺルリ来琉百年記念」がある。58年には守礼門復元記念切手が発行された。62年には「国際マラリア防遏事業記念」切手に守礼門が図案化され、65年の「オリンピック東京大会沖縄聖火リレー記念」切手にも守礼門が使われた。復帰のときは守礼門が紅型模様とともに記念切手に使われ、時代の節目には必ず守礼門が使われた。合計6枚もある。スタンプにも数種がある。
丹羽文雄の小説集に『守禮の門』(1948年)がある。ちなみに手元の沖縄の旅行ガイドブックを見ると、1963刊の実業之日本社『沖縄』は口絵カラー写真に「守礼の門」がある。68年の主婦と生活社『カラ―旅・沖縄』はカバーと中扉に守礼門の写真がある。70年の日本旅行研究所『沖縄』には「守礼の門」のカラー写真、72年の山と渓谷社『沖縄と南西の島々』は「夕日の守礼門(しゅれいのもん)」の写真がある。
『おきなわキーワードコラムブック』に小野まさこさんが守礼門を「琉球王国時代には中国使節を迎え、現代においては観光客を迎えている首里王城の一門。観光客も必ず立ち寄る沖縄観光の記念写真の撮影場所となっている。夕日の中の『守礼之門』等、堂々たるシルエットの絵葉書も何枚かある。(略)東急ホテル前のイミテーション守礼門を本物だとカンチガイする人がけっこういるので、ご注意を」と簡潔に説明している。
東恩納寛惇は「首里王府の第一号坊としては中山門があり、王城の門としては、歓会門がある。第二坊が守礼門」と守礼門考に記している。寛惇は続けて「守礼門は尚清王時代の創建で、其頃は待賢門と言うて居たが、中頃になって首里と言う扁額を掲げ、これを首里門と称えて居た」とあるから呼び方も時代によって変遷している。
2010年7月3日から那覇市歴史博物館で「守礼門」展が開かれる。『球陽』の尚巴志7年(1428年)に「国門を創建す。曰く中山」とあるのは中山門で、尚貞13年(1681年)に板葺きが瓦葺に改められた。ちなみに正門の歓会門は尚眞代の建立。守礼門は尚清代の創建とされ、はじめ「待賢門」、のち「首里」の2字の額を掲げていた。尚永代に「守礼之邦」の額を冊封使来流のときにだけ掲げたが、1663年からは常に掲げられるようになった。
小峯和明立教大学教授の『今昔物語集の世界』に「ある人は個人の屋敷の門やお寺の三門を想像するでしょうし、ある人はパリの凱旋門や都市の有名な門を連想するかもしれません」と門の話から始まり羅城門(羅生門)で話がはじまっている。ここに出てくる「守礼の門」は扁額が「守礼之邦」となっているところからそう呼ぶのであるが、中には「守礼門」と書いて「しゅれいのもん」と呼ぶのもいる。
大阪「沖縄関係資料室」(西平守晴主宰)には守礼門の扁額の拓本が軸装である。これは1972年に「豊川忠進先生の長寿を祝う会」のため那覇市の又吉真三氏から借用し寄贈されたものである。拓本の先駆者は久場政用。久場には『琉球金石総覧』『琉球列島之文化史料と植物史料』がある。また1926年の『沖縄タイムス』には「久場政用事業広告ー琉球植物園、科学知識普及ノ講話」がある。
新川明氏は『沖縄・統合と反逆』の中で「『守礼門』新札をどう読むか」と題し「扁額の『守禮之邦』という語句は、琉球王国が対外的に礼節を重んずる国であることを内外に宣言した意味を持つ。おのずからその国民は『守礼の民』であるという自己規定が生じる。『守礼門』は、そのような自己規定を媒介する『記号』として共有されてきたのである」とし、続けて「このような伝統は直ちに統治者によって逆手に取られ、支配目的を遂行するために利用されるのが常である。たとえば米軍統治下の沖縄に『守礼の光』と題する雑誌があった」としその側面にも触れている。
守礼門は、首里城が復元されるまでは「沖縄のシンボル」であった。最近は無用の長物の扱いを受け、沖縄教育委員会発行の『概説・沖縄の歴史と文化』の索引にも独立した項目としては無い。首里城に一括りされ冷たい扱いとなっている。1853年6月6日にペリー提督一行が首里城を訪れた。その遠征記には守礼門の版画が掲載されている。扁額の字は「中山府」としか見えないがとにかくもアメリカ史に守礼門が登場した最初のものであろう。
1952年発行の琉球郵便切手に「正殿唐破風」「琉大開学記念」(正殿が描かれている)、53年発行の「ぺルリ来琉百年記念」がある。58年には守礼門復元記念切手が発行された。62年には「国際マラリア防遏事業記念」切手に守礼門が図案化され、65年の「オリンピック東京大会沖縄聖火リレー記念」切手にも守礼門が使われた。復帰のときは守礼門が紅型模様とともに記念切手に使われ、時代の節目には必ず守礼門が使われた。合計6枚もある。スタンプにも数種がある。
丹羽文雄の小説集に『守禮の門』(1948年)がある。ちなみに手元の沖縄の旅行ガイドブックを見ると、1963刊の実業之日本社『沖縄』は口絵カラー写真に「守礼の門」がある。68年の主婦と生活社『カラ―旅・沖縄』はカバーと中扉に守礼門の写真がある。70年の日本旅行研究所『沖縄』には「守礼の門」のカラー写真、72年の山と渓谷社『沖縄と南西の島々』は「夕日の守礼門(しゅれいのもん)」の写真がある。
『おきなわキーワードコラムブック』に小野まさこさんが守礼門を「琉球王国時代には中国使節を迎え、現代においては観光客を迎えている首里王城の一門。観光客も必ず立ち寄る沖縄観光の記念写真の撮影場所となっている。夕日の中の『守礼之門』等、堂々たるシルエットの絵葉書も何枚かある。(略)東急ホテル前のイミテーション守礼門を本物だとカンチガイする人がけっこういるので、ご注意を」と簡潔に説明している。
東恩納寛惇は「首里王府の第一号坊としては中山門があり、王城の門としては、歓会門がある。第二坊が守礼門」と守礼門考に記している。寛惇は続けて「守礼門は尚清王時代の創建で、其頃は待賢門と言うて居たが、中頃になって首里と言う扁額を掲げ、これを首里門と称えて居た」とあるから呼び方も時代によって変遷している。
2010年7月3日から那覇市歴史博物館で「守礼門」展が開かれる。『球陽』の尚巴志7年(1428年)に「国門を創建す。曰く中山」とあるのは中山門で、尚貞13年(1681年)に板葺きが瓦葺に改められた。ちなみに正門の歓会門は尚眞代の建立。守礼門は尚清代の創建とされ、はじめ「待賢門」、のち「首里」の2字の額を掲げていた。尚永代に「守礼之邦」の額を冊封使来流のときにだけ掲げたが、1663年からは常に掲げられるようになった。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
「華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽とか雪舟とか趙子昂とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代」もあったと安恭は記しているが、この美術家の夢は弟の安久によって実現された。
また大正末期、沖縄県立沖縄図書館長の伊波普猷がスキャンダルの最中、麦門冬の友人たちは後継館長に麦門冬と運動していた。山里永吉の叔父・比嘉朝健は最も熱心で、父の友人で沖縄政財界に隠然たる影響を持つ尚順男爵邸宅に麦門冬を連れていった。かつて麦門冬が閥族と新聞で攻撃した当人である。しかし麦門冬の語る郷土研究の情熱を尚順も理解を示し料理で歓待し長男・尚謙に酌をさせるなど好意を示した。それらは麦門冬の不慮の死で無に帰した。これも弟・安久が戦後、沖縄県立図書館の歴代図書館長に名を連ねている。
麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)
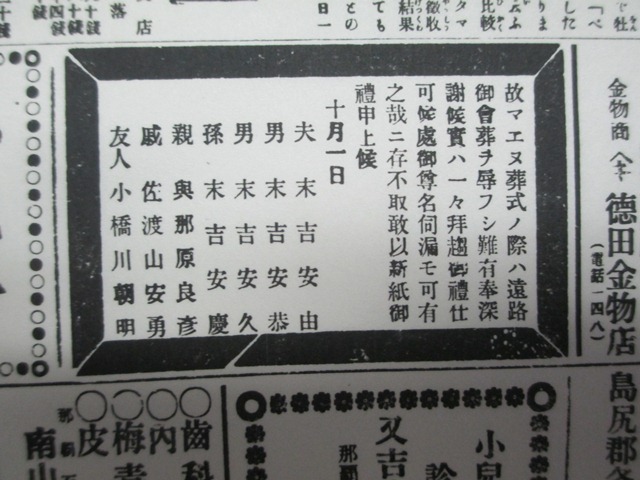
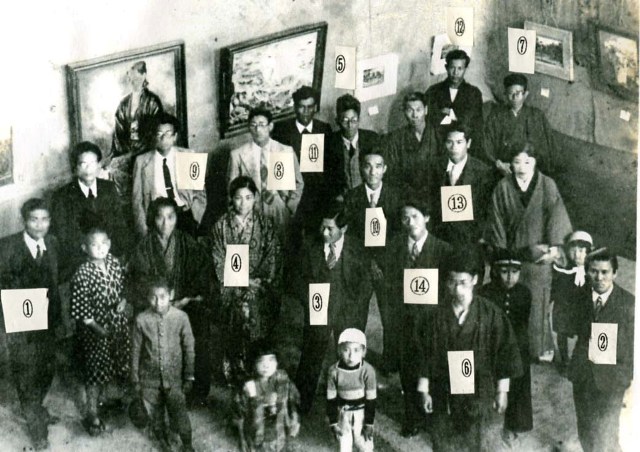
1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

写真左から末吉安久、桃原思石、許田重勲
1944年ー夏 学童疎開の引率で宮崎に
1946年ー秋 首里高校美術科教官に就任するや沖縄民政府文教局にデザイン科の設置を要請し首里に伝わる紅型の復活を図りたい」と嘆願し実現に導いた。

右端が末吉安久
1949年3月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」
1949年4月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」
1949年5月 『月刊タイムス』№4□末吉安久「表紙・カット」
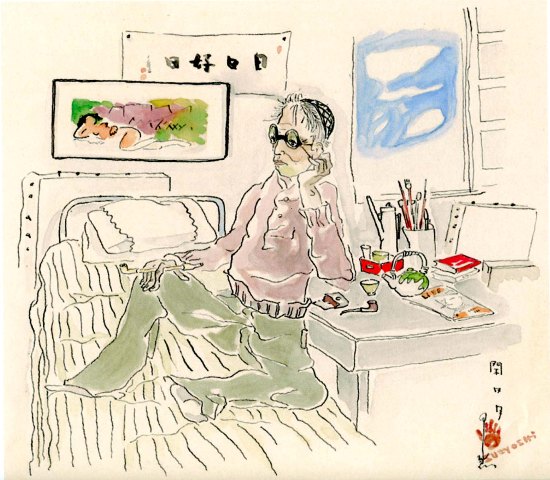
末吉安久「閑日月」

末吉安久「子供達」
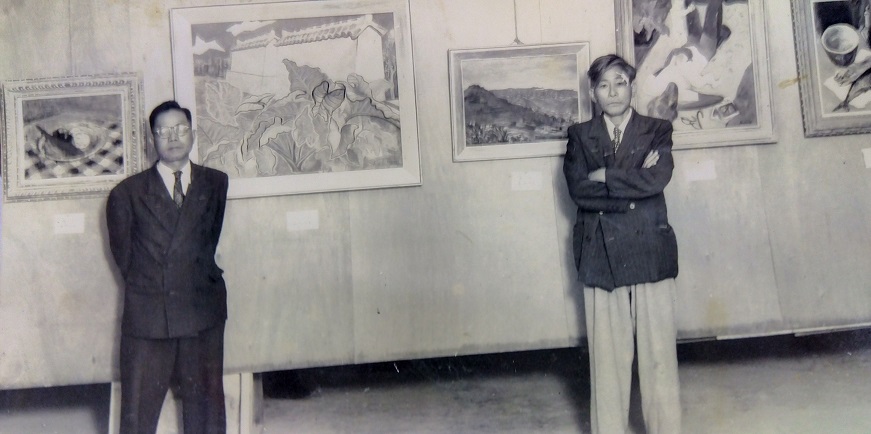
森田永吉、末吉安久
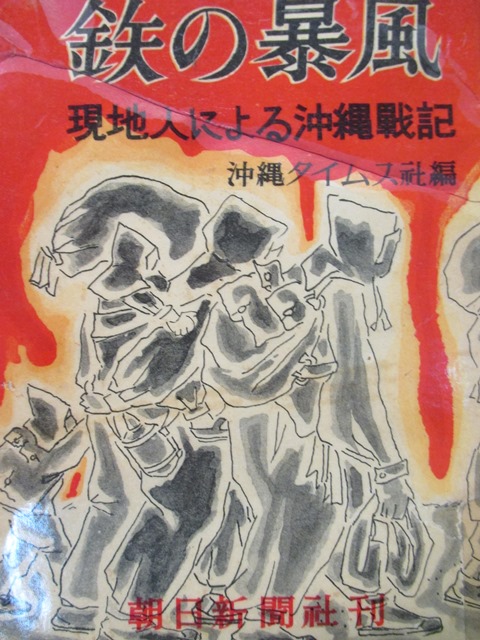
1950年8月 朝日新聞社『鉄の暴風』末吉安久「装幀」/牧港篤三「挿絵」
1950年9月 末吉安久、首里図書館長就任(1957-4)
1951年11月 琉米文化会館「第3回沖縄美術展覧会」末吉安久「子供達」/金城安太郎「楽屋裏」
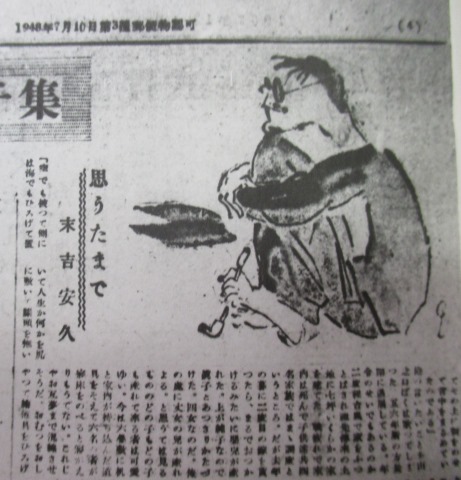
1952年1月1日『沖縄タイムス』末吉安久「思うたまで」

1952年1月1日『琉球新報』末吉安久(Q)「漫画漫詩」

1953年1月1日『沖縄タイムス』「漫画アンデパンダン展」末吉安久「乾かすのか掲げるのか」
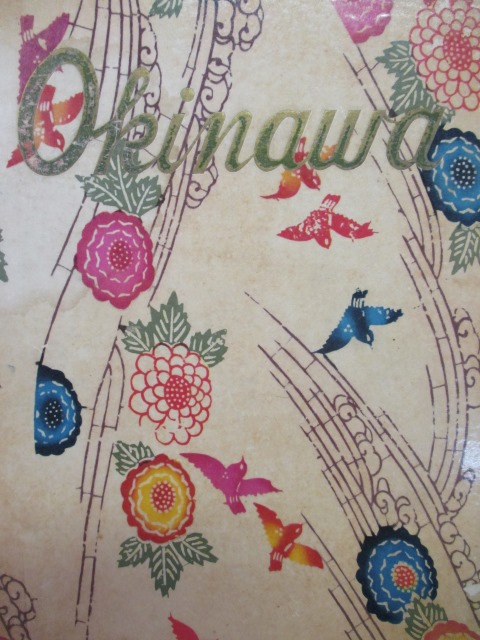
1954年12月に写真集『基地沖縄』が東京新宿市ヶ谷加賀町の大日本印刷で印刷され沖縄タイムス社から発行された。編集は豊平良顕、上間正諭、牧港篤三、金城久重で、装幀が南風原朝光、末吉安久であった。零よりの出発と題して農夫の写真が掲載されていて、説明文に「戦争の破壊は、とにかく地上の人間の営みを根こそぎ奪い去った。戦後の復興はすべて零よりの出発と云ってよい。この老農夫の姿そのままが、零のスタート・ラインに立った終戦直後のオキナワを象徴している」とある。
1955年3月 第7回沖展に末吉安久「花」「サバニ」「静物」「金魚」
1956年3月 第8回沖展に末吉安久「黄色の部屋」「魚」「静物」
1956年8月15日 『沖縄タイムス』末ひさし「居タ居タ鳩ダ」
1956年8月19日 『沖縄タイムス』末ひさし(Q)「静かなデモ」

左から真境名安興、伊波普猷、末吉麦門冬(末吉安久画)
1956年11月 『沖縄タイムス』島袋盛敏「新遺老説傳 沖縄むかしばなし」末吉安久(Q)・絵
1957年3月 第9回沖展に末吉安久「静物」
1958年3月 第10回沖展に末吉安久「黒い月」「漁師たち」
1959年3月 第11回沖展に末吉安久「魚」「月」「大学の丘」「死せる生物」
1960年3月 第12回沖展に末吉安久「石」「根」「花」「珊瑚礁」
1961年3月 第13回沖展に末吉安久「作品」「墓場」
1961年3月 『養秀』養秀同窓会□養秀「表紙装丁カット」「金城紀光氏に聞くー聞き手/末吉安久」
1962年3月 第14回沖展に末吉安久「墓地A」「墓地B」「墓地C」
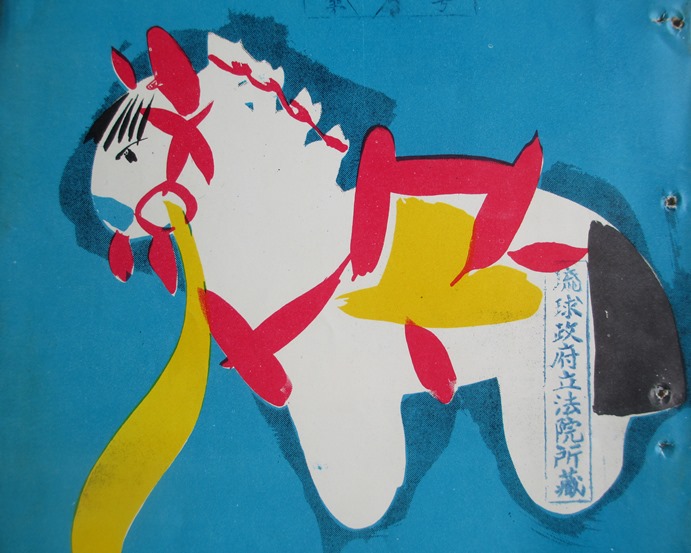
末吉安久/表紙絵 1962年8月『今日の琉球』58号「琉球の玩具」

写真ー末吉安久氏と大城皓也画伯

沖縄県立図書館の左側には「安冨祖流楽祖之碑」がある。安冨祖流絃聲会が1964年1月18日に建立しものだが、設計は末吉安久である。ちなみに、揮毫は島袋光裕、刻字が安里清謙、施行が安里清福である。沖縄県立図書館の館長室には歴代図書館長の一人として末吉安久の写真も飾られている。
1969年2月 『新沖縄文学』第12号 末吉安久「貘さんに る幻想」
1975年1月28日 山之口貘詩碑建立期成会発足(宮里栄輝会長、末吉安久副会長)
1975年7月23日 与儀公園で山之口貘詩碑除幕式
1975年9月7日 那覇文化センターで山之口貘記念会発足
1976年12月 『沖縄風俗絵図』月刊沖縄社□末吉安久「ケンケンパー」「足相撲」「ビー玉」「イットゥガヨー」「ジュークーティ」「クールーミグラセー」「クールーオーラセー」□末吉安久紅型「醜童舞い」「浜千鳥」「馬」「桃売りアングヮー」「カンドーフ売り」
1977年11月29日『沖縄タイムス』「佐渡山安健『名馬・仲田青毛』末吉安久宅に」
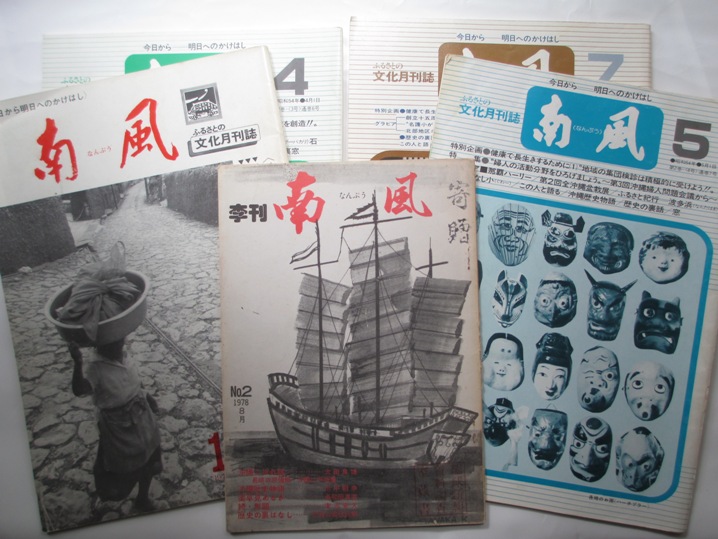
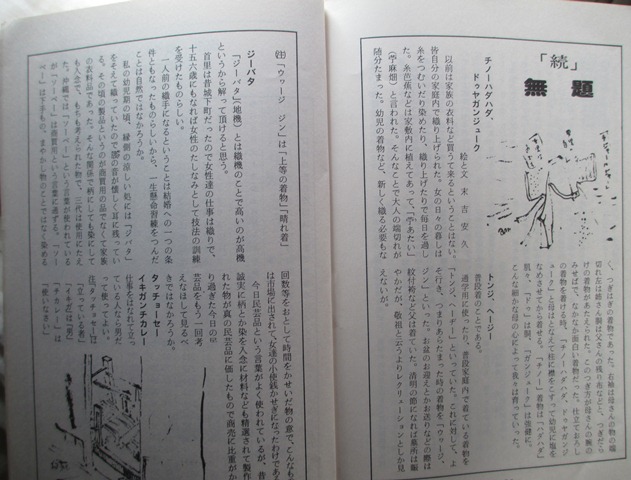
1978年8月 『季刊 南風』№2 末吉安久・絵と文「続・無題」
2015年10月16日『沖縄タイムス』大城冝武「沖縄マンガ史34(末ひさし)末吉安久/大嶺信一」
「華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽とか雪舟とか趙子昂とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代」もあったと安恭は記しているが、この美術家の夢は弟の安久によって実現された。
また大正末期、沖縄県立沖縄図書館長の伊波普猷がスキャンダルの最中、麦門冬の友人たちは後継館長に麦門冬と運動していた。山里永吉の叔父・比嘉朝健は最も熱心で、父の友人で沖縄政財界に隠然たる影響を持つ尚順男爵邸宅に麦門冬を連れていった。かつて麦門冬が閥族と新聞で攻撃した当人である。しかし麦門冬の語る郷土研究の情熱を尚順も理解を示し料理で歓待し長男・尚謙に酌をさせるなど好意を示した。それらは麦門冬の不慮の死で無に帰した。これも弟・安久が戦後、沖縄県立図書館の歴代図書館長に名を連ねている。
麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)
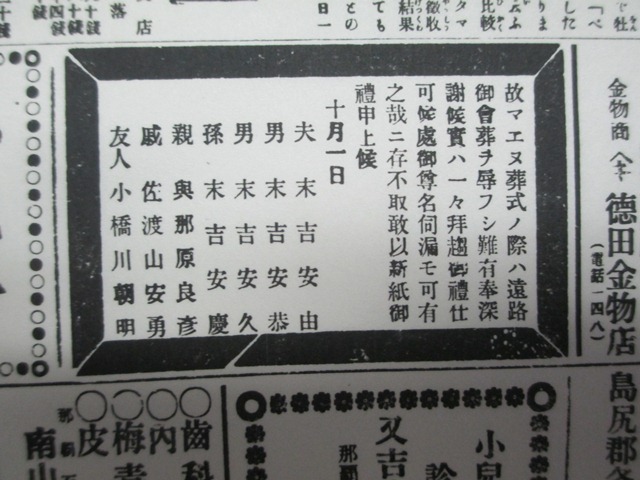
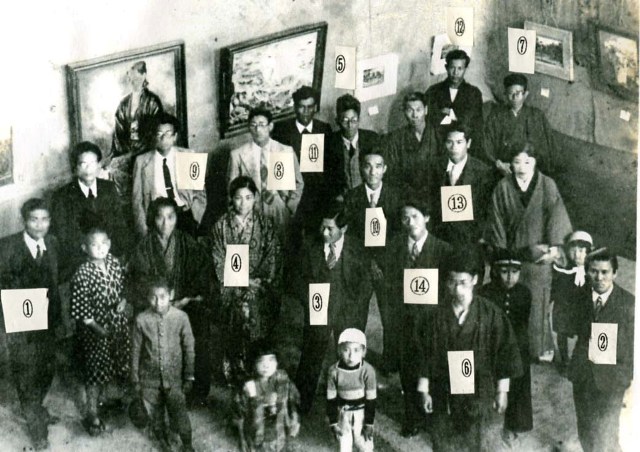
1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

写真左から末吉安久、桃原思石、許田重勲
1944年ー夏 学童疎開の引率で宮崎に
1946年ー秋 首里高校美術科教官に就任するや沖縄民政府文教局にデザイン科の設置を要請し首里に伝わる紅型の復活を図りたい」と嘆願し実現に導いた。

右端が末吉安久
1949年3月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」
1949年4月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」
1949年5月 『月刊タイムス』№4□末吉安久「表紙・カット」
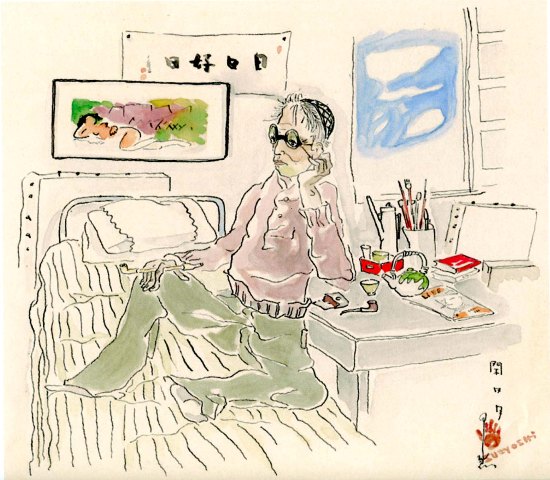
末吉安久「閑日月」

末吉安久「子供達」
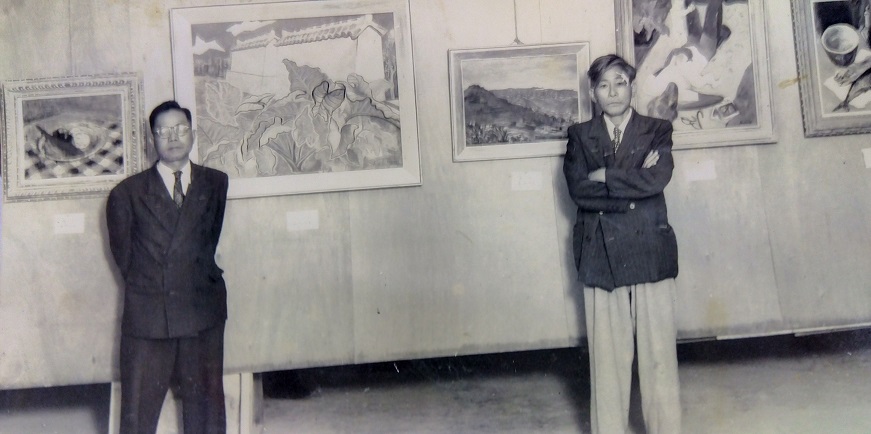
森田永吉、末吉安久
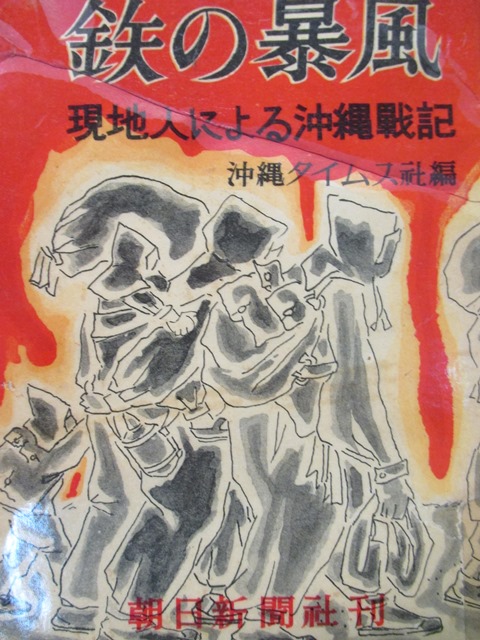
1950年8月 朝日新聞社『鉄の暴風』末吉安久「装幀」/牧港篤三「挿絵」
1950年9月 末吉安久、首里図書館長就任(1957-4)
1951年11月 琉米文化会館「第3回沖縄美術展覧会」末吉安久「子供達」/金城安太郎「楽屋裏」
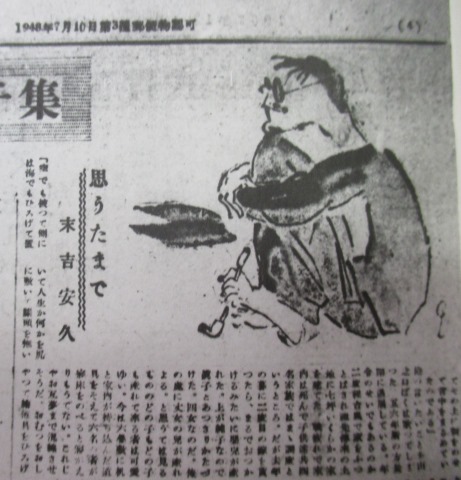
1952年1月1日『沖縄タイムス』末吉安久「思うたまで」

1952年1月1日『琉球新報』末吉安久(Q)「漫画漫詩」

1953年1月1日『沖縄タイムス』「漫画アンデパンダン展」末吉安久「乾かすのか掲げるのか」
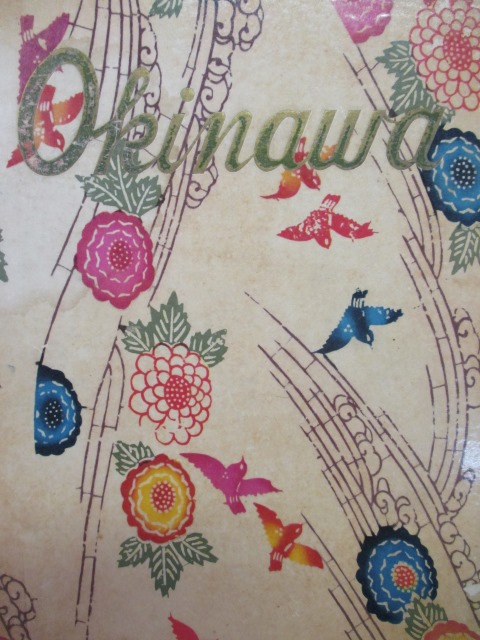
1954年12月に写真集『基地沖縄』が東京新宿市ヶ谷加賀町の大日本印刷で印刷され沖縄タイムス社から発行された。編集は豊平良顕、上間正諭、牧港篤三、金城久重で、装幀が南風原朝光、末吉安久であった。零よりの出発と題して農夫の写真が掲載されていて、説明文に「戦争の破壊は、とにかく地上の人間の営みを根こそぎ奪い去った。戦後の復興はすべて零よりの出発と云ってよい。この老農夫の姿そのままが、零のスタート・ラインに立った終戦直後のオキナワを象徴している」とある。
1955年3月 第7回沖展に末吉安久「花」「サバニ」「静物」「金魚」
1956年3月 第8回沖展に末吉安久「黄色の部屋」「魚」「静物」
1956年8月15日 『沖縄タイムス』末ひさし「居タ居タ鳩ダ」
1956年8月19日 『沖縄タイムス』末ひさし(Q)「静かなデモ」

左から真境名安興、伊波普猷、末吉麦門冬(末吉安久画)
1956年11月 『沖縄タイムス』島袋盛敏「新遺老説傳 沖縄むかしばなし」末吉安久(Q)・絵
1957年3月 第9回沖展に末吉安久「静物」
1958年3月 第10回沖展に末吉安久「黒い月」「漁師たち」
1959年3月 第11回沖展に末吉安久「魚」「月」「大学の丘」「死せる生物」
1960年3月 第12回沖展に末吉安久「石」「根」「花」「珊瑚礁」
1961年3月 第13回沖展に末吉安久「作品」「墓場」
1961年3月 『養秀』養秀同窓会□養秀「表紙装丁カット」「金城紀光氏に聞くー聞き手/末吉安久」
1962年3月 第14回沖展に末吉安久「墓地A」「墓地B」「墓地C」
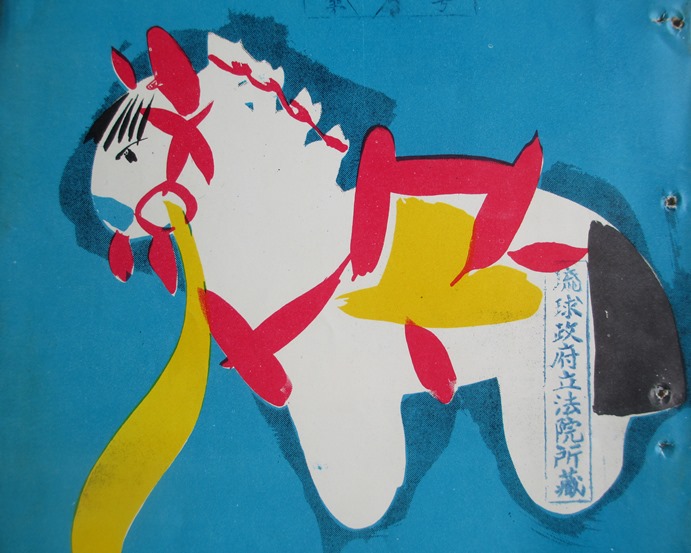
末吉安久/表紙絵 1962年8月『今日の琉球』58号「琉球の玩具」

写真ー末吉安久氏と大城皓也画伯

沖縄県立図書館の左側には「安冨祖流楽祖之碑」がある。安冨祖流絃聲会が1964年1月18日に建立しものだが、設計は末吉安久である。ちなみに、揮毫は島袋光裕、刻字が安里清謙、施行が安里清福である。沖縄県立図書館の館長室には歴代図書館長の一人として末吉安久の写真も飾られている。
1969年2月 『新沖縄文学』第12号 末吉安久「貘さんに る幻想」
1975年1月28日 山之口貘詩碑建立期成会発足(宮里栄輝会長、末吉安久副会長)
1975年7月23日 与儀公園で山之口貘詩碑除幕式
1975年9月7日 那覇文化センターで山之口貘記念会発足
1976年12月 『沖縄風俗絵図』月刊沖縄社□末吉安久「ケンケンパー」「足相撲」「ビー玉」「イットゥガヨー」「ジュークーティ」「クールーミグラセー」「クールーオーラセー」□末吉安久紅型「醜童舞い」「浜千鳥」「馬」「桃売りアングヮー」「カンドーフ売り」
1977年11月29日『沖縄タイムス』「佐渡山安健『名馬・仲田青毛』末吉安久宅に」
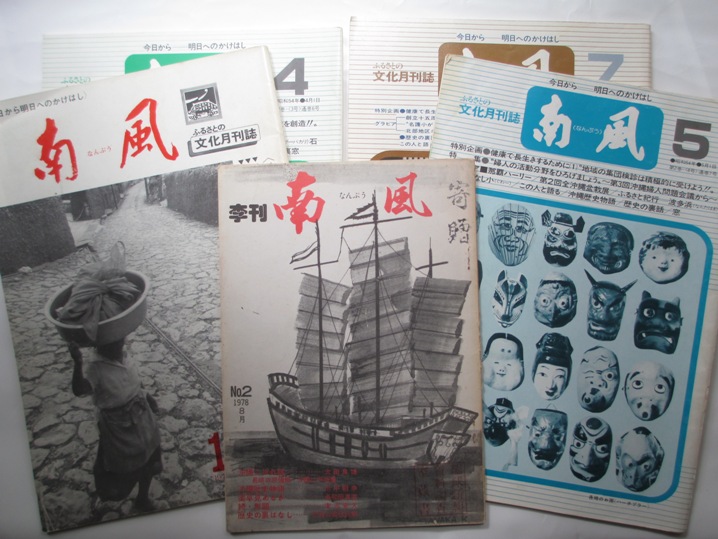
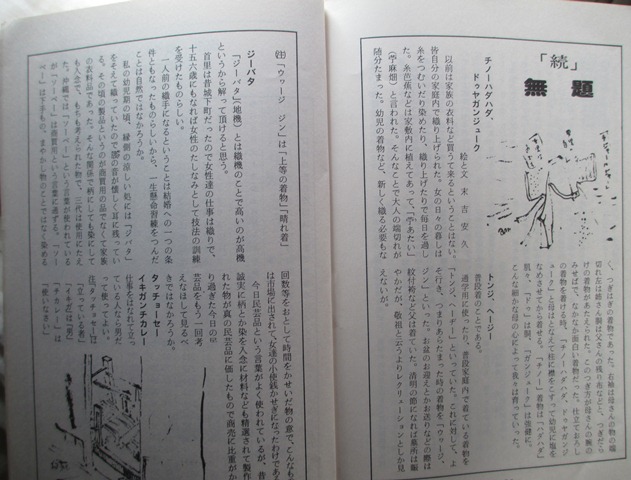
1978年8月 『季刊 南風』№2 末吉安久・絵と文「続・無題」
2015年10月16日『沖縄タイムス』大城冝武「沖縄マンガ史34(末ひさし)末吉安久/大嶺信一」
04/19: 琉球芸能史散歩②
真栄里泰山の「はがきエッセイ」№20□ひや!ひや!ひやひやひや!ひやみかちうきり、ひやみかちうきり」の「ひやみかち節」。この歌が出ると心は浮き浮き、誰もが座っておれなくなる。三線の力強いリズムといい歌詞といい、うちなーんちゅの魂のそのもののような歌である。1948年、山内盛彬作曲によるこの歌は、沖縄戦で廃墟となり、米軍統治下におかれ失意のうちにあった沖縄の人々を励ました名歌である。「名に立ちゅる沖縄 宝島でむぬ 心うち合わち うたちみしょり」、「七転び転で、ひやみかち起きて わしたこの沖縄 世界に知らさ」の歌詞は、沖縄の自由民権運動の父・謝花昇の同志で熱血漢の平良新助の作だ。私たちの世代は「腕を組み歌おう 喜びの歌を 僕らみな明るい日本の子、沖縄の子」と歌ったが、それは当時、沖縄教職員会が替え歌にしたものだろう。「ひやみかち節」は沖縄の復帰運動を鼓舞した歌でもあった。
その「ひやみかち節」の歌碑が、山内盛彬翁(1890年~1986年)の生誕120年を記念して、翁夫婦が晩年を過ごし琉球音楽普及の拠点であった沖縄市の社会福祉法人緑樹苑の中庭に建立された。去る3月27日の除幕式では、おもろ主取家の安仁屋眞昭が思い出を語り、首里クェーナ保存会による「あがり世」、山内翁から直伝された「せーぐぁー」こと登川誠仁の歌三線、バンド演奏、踊りなどいろいろなバージョンで「ひやみかち節」が披露された。琉球王朝禮学の復活伝承に生涯をささげた山内翁にふさわしい会であった。
琉球王国の滅亡後、日本の近代教育は皇民化を第一とし、うちなー口はじめ琉球の文化風俗を蔑視し撲滅した。そうしたなかで、沖縄の文化を守るため使命感を持って苦闘した先人達がおられた。おもろと沖縄学の父・伊波普猷はよく知られているが、琉球王朝の御座楽、路次楽、おもろをはじめノロのウムイ、クェーナなどの歌謡を五線譜に採集し、世界に通ずる音楽として広め紹介したのが山内盛彬翁である。翁の祖父盛憙から受け継いだ伝統音楽と西洋音楽の技量を合わせ持ち、秘伝のくえーな「あがり世」などは床下にもぐりこんで採譜したという、沖縄歌謡保存にかけたその烈々たる情熱は、今度の歌碑に刻された翁の「滅びゆく文化 忍で忍ばれめ もち(自費)と命かけて 譜文に遺さ」という歌に込められている。
沖縄音楽というと、大方は宮良長包の数々の名曲を思い浮かべるだろうが、今回の「ひやみかち節」歌碑建立を機に、山内盛彬翁の業績をあらためて見直したいものである。「ひやみかち節」は平和とやさしさ、そして沖縄の誇りを歌った沖縄県民の歌ともいうべき永遠の名歌名曲である。
「花や咲き美さ 音楽や鳴り美さ 聴かさなや世界に 音楽の手並み」(盛彬)(2011年4月10日)
◎YouTube 沖縄民謡「ひやみかち節」登川誠仁、他
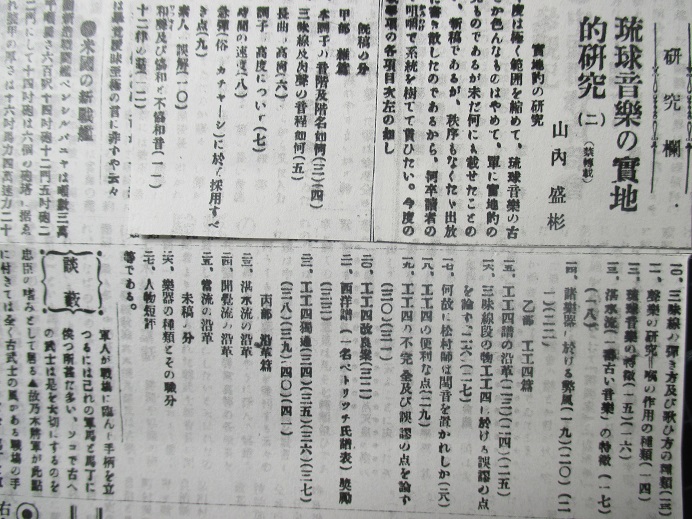
1912年10月1日 『沖縄毎日新聞』山内盛彬「琉球音楽の実地的研究(2)」
1925年5月15日 『沖縄タイムス』山内盛彬「末吉麦門冬氏遺稿『三味線渡来説に就て』」
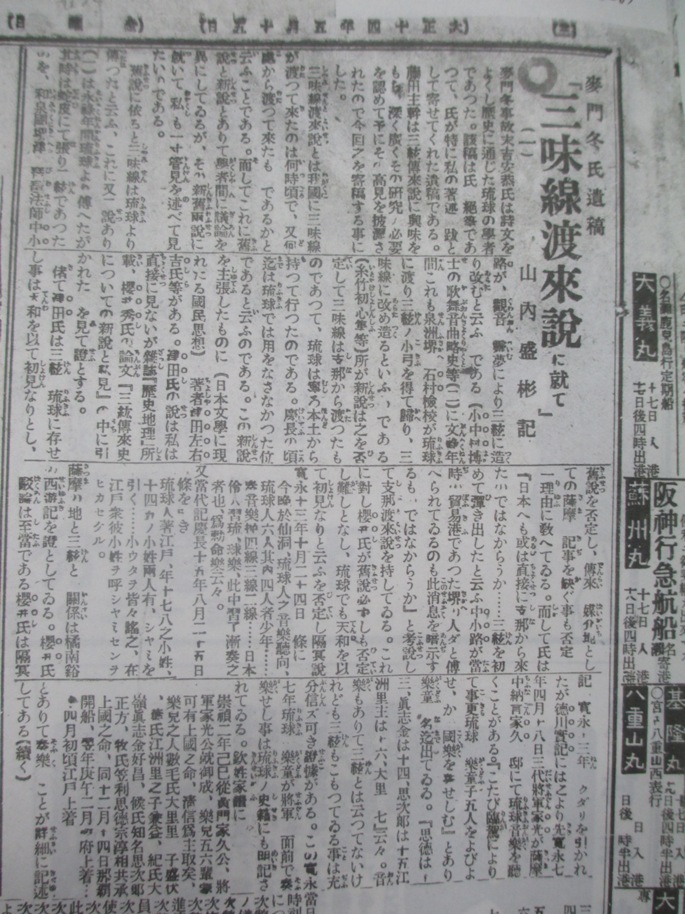
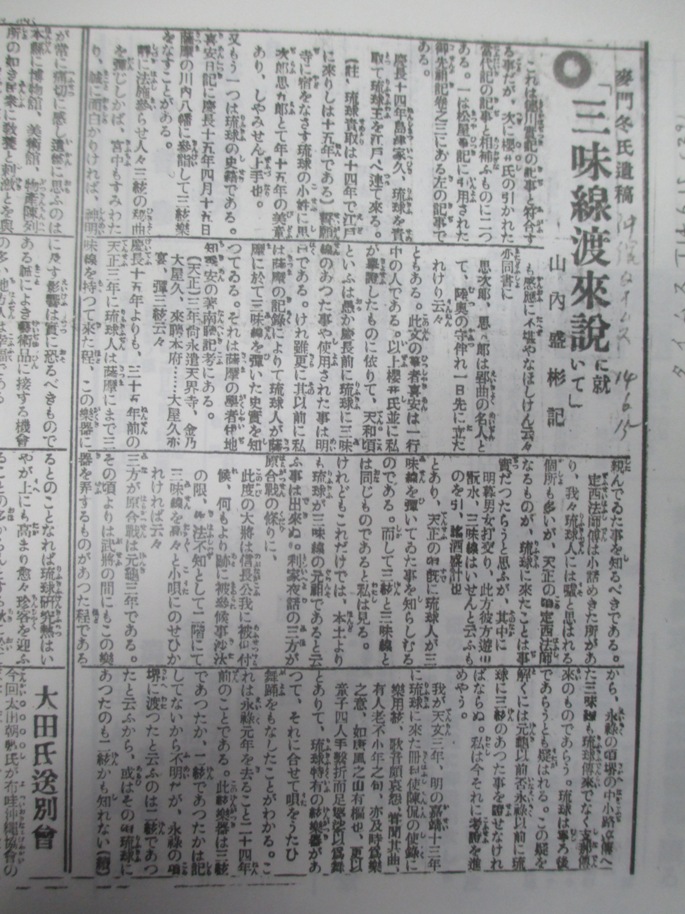
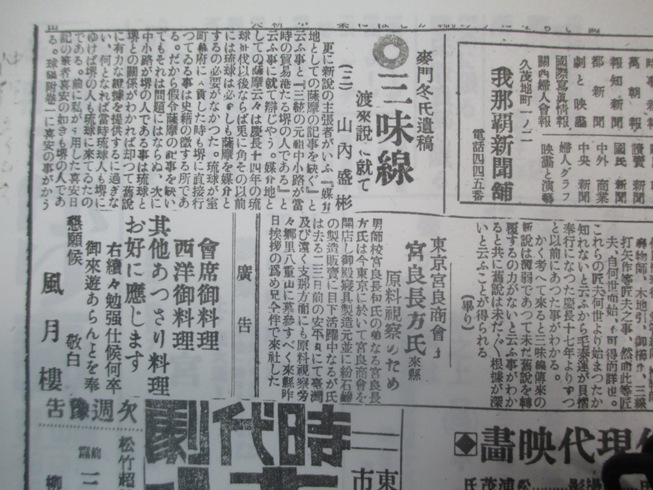
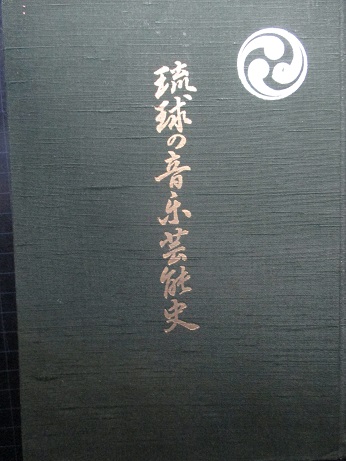
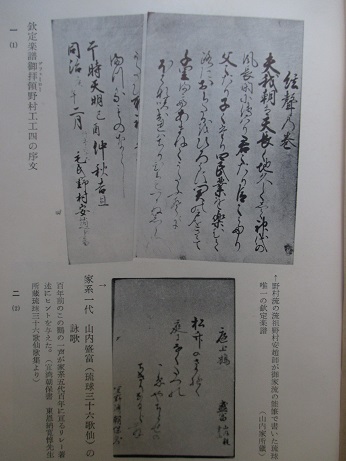
1959年4月 山内盛彬『琉球の音楽芸能史』民族芸能全集刊行会
2月11日「はがきエッセイ」№11
上山中学校3年生の孔子廟参拝で講話をした。学問の神様・孔子様への学業成就祈の願願を兼ねた学校周辺の歴史・文化のユニークなふるさと学習だ。人類の教師として釈迦、孔子、ソクラテス、キリストを紹介し、その4聖人がそれまで弱肉強食で平気でいた人間に初めて人間の愛、人間性を説き教えたこと。仁義礼智信の人間学儒学は中国、韓国、台湾、日本、沖縄、ベトナムで国学となり、ほぼ共通の道徳となっていること。鄭順則など沖縄の儒学は当時の最先端だったことなどを話した。話しながら、ふと今の政治や指導者をこの若者たちはどう感じているのか気になった。基地問題での沖縄に対する民主党政権の傲慢なふるまい、地元名護市長を無視した礼節を欠いた行動、中国の尖閣問題、北方領土のロシアなど、力にまかせた大国主義政治の横行等々。今、本当に必要な道徳教育、経世済民の徳治主義の政治教育はこれら指導者たちにこそ必要ではと思った次第。
その「ひやみかち節」の歌碑が、山内盛彬翁(1890年~1986年)の生誕120年を記念して、翁夫婦が晩年を過ごし琉球音楽普及の拠点であった沖縄市の社会福祉法人緑樹苑の中庭に建立された。去る3月27日の除幕式では、おもろ主取家の安仁屋眞昭が思い出を語り、首里クェーナ保存会による「あがり世」、山内翁から直伝された「せーぐぁー」こと登川誠仁の歌三線、バンド演奏、踊りなどいろいろなバージョンで「ひやみかち節」が披露された。琉球王朝禮学の復活伝承に生涯をささげた山内翁にふさわしい会であった。
琉球王国の滅亡後、日本の近代教育は皇民化を第一とし、うちなー口はじめ琉球の文化風俗を蔑視し撲滅した。そうしたなかで、沖縄の文化を守るため使命感を持って苦闘した先人達がおられた。おもろと沖縄学の父・伊波普猷はよく知られているが、琉球王朝の御座楽、路次楽、おもろをはじめノロのウムイ、クェーナなどの歌謡を五線譜に採集し、世界に通ずる音楽として広め紹介したのが山内盛彬翁である。翁の祖父盛憙から受け継いだ伝統音楽と西洋音楽の技量を合わせ持ち、秘伝のくえーな「あがり世」などは床下にもぐりこんで採譜したという、沖縄歌謡保存にかけたその烈々たる情熱は、今度の歌碑に刻された翁の「滅びゆく文化 忍で忍ばれめ もち(自費)と命かけて 譜文に遺さ」という歌に込められている。
沖縄音楽というと、大方は宮良長包の数々の名曲を思い浮かべるだろうが、今回の「ひやみかち節」歌碑建立を機に、山内盛彬翁の業績をあらためて見直したいものである。「ひやみかち節」は平和とやさしさ、そして沖縄の誇りを歌った沖縄県民の歌ともいうべき永遠の名歌名曲である。
「花や咲き美さ 音楽や鳴り美さ 聴かさなや世界に 音楽の手並み」(盛彬)(2011年4月10日)
◎YouTube 沖縄民謡「ひやみかち節」登川誠仁、他
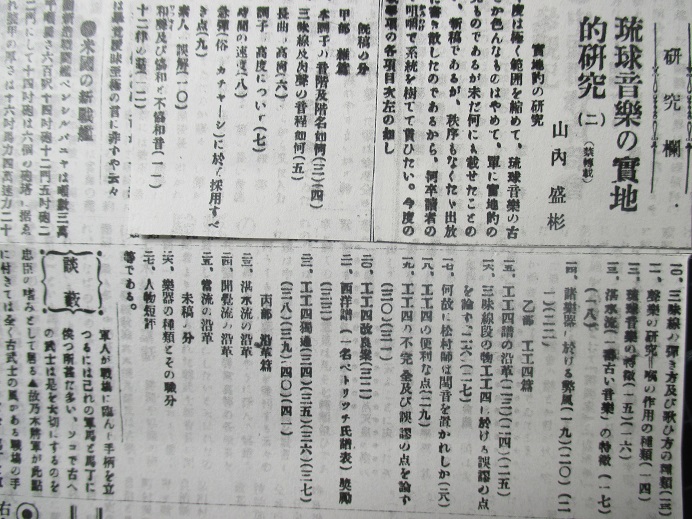
1912年10月1日 『沖縄毎日新聞』山内盛彬「琉球音楽の実地的研究(2)」
1925年5月15日 『沖縄タイムス』山内盛彬「末吉麦門冬氏遺稿『三味線渡来説に就て』」
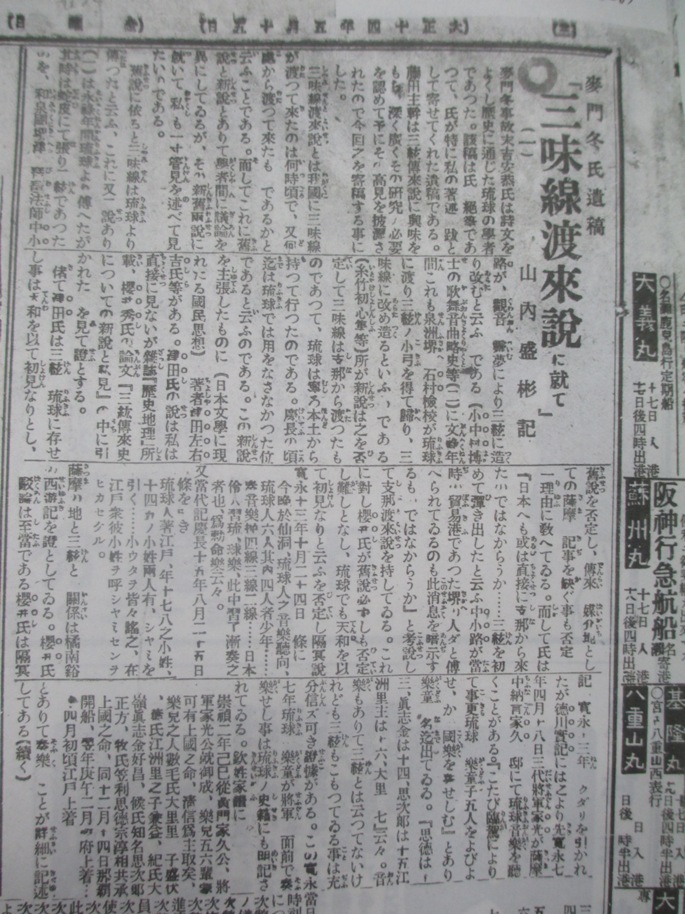
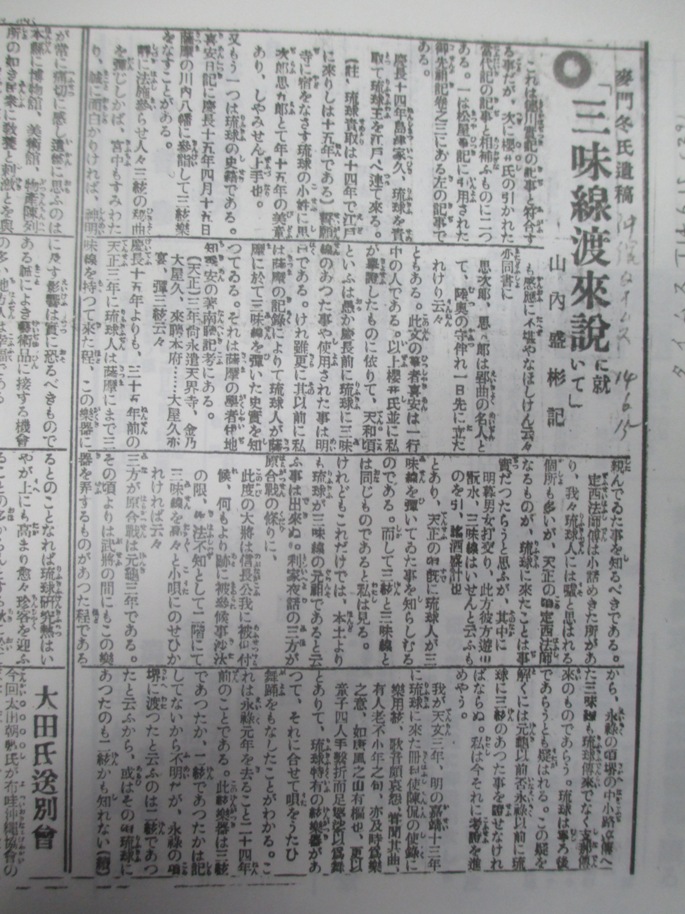
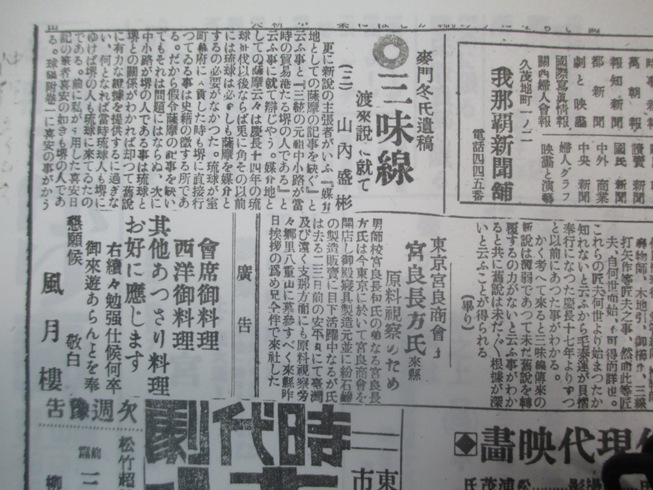
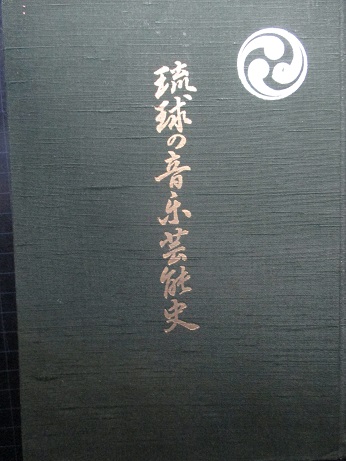
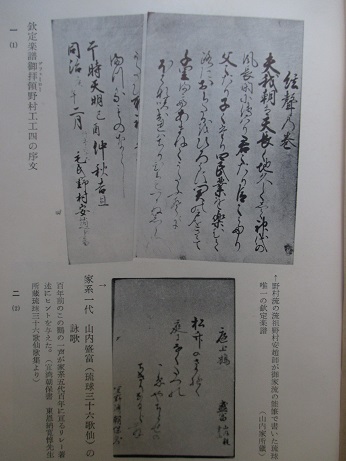
1959年4月 山内盛彬『琉球の音楽芸能史』民族芸能全集刊行会
2月11日「はがきエッセイ」№11
上山中学校3年生の孔子廟参拝で講話をした。学問の神様・孔子様への学業成就祈の願願を兼ねた学校周辺の歴史・文化のユニークなふるさと学習だ。人類の教師として釈迦、孔子、ソクラテス、キリストを紹介し、その4聖人がそれまで弱肉強食で平気でいた人間に初めて人間の愛、人間性を説き教えたこと。仁義礼智信の人間学儒学は中国、韓国、台湾、日本、沖縄、ベトナムで国学となり、ほぼ共通の道徳となっていること。鄭順則など沖縄の儒学は当時の最先端だったことなどを話した。話しながら、ふと今の政治や指導者をこの若者たちはどう感じているのか気になった。基地問題での沖縄に対する民主党政権の傲慢なふるまい、地元名護市長を無視した礼節を欠いた行動、中国の尖閣問題、北方領土のロシアなど、力にまかせた大国主義政治の横行等々。今、本当に必要な道徳教育、経世済民の徳治主義の政治教育はこれら指導者たちにこそ必要ではと思った次第。
05/10: 1905年 山城正忠、新詩社同人
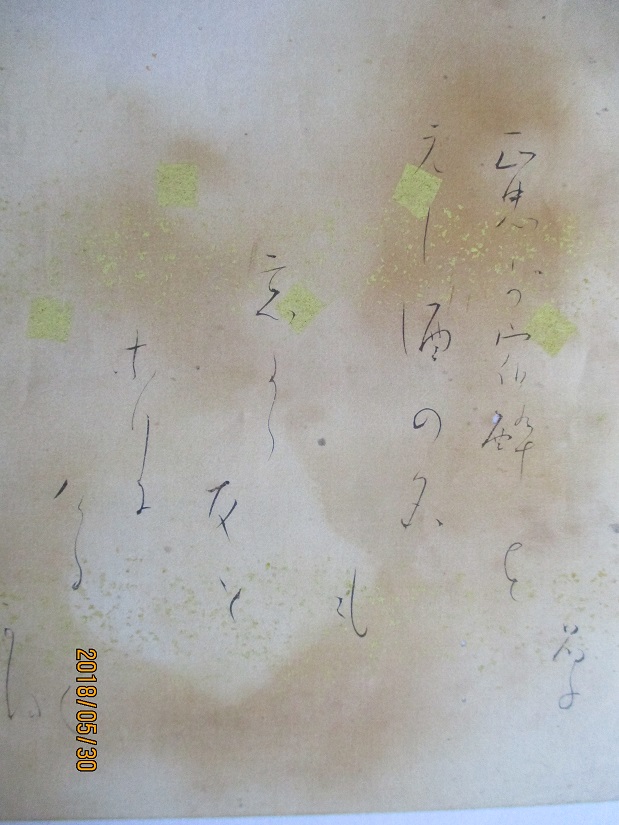
与謝野晶子が山城正忠に贈った色紙
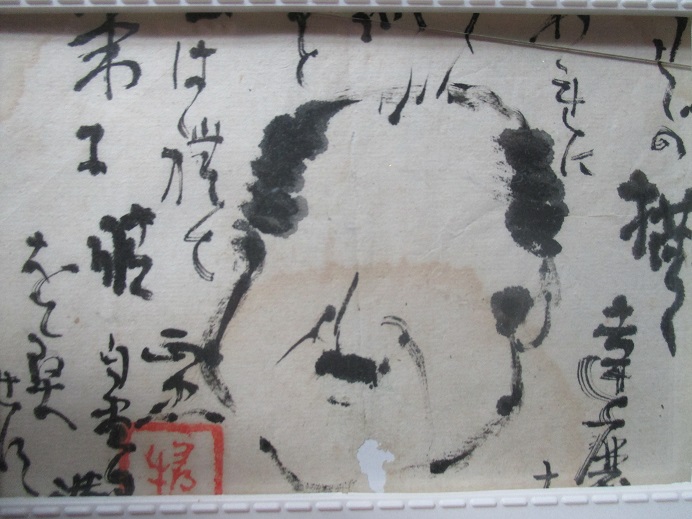
山城正忠自画像
1901年 沖縄県立病院及び医生教習所、産婆養成所を久茂地に移転
1902年 楊長積(永井長積)那覇に歯科医院開業
山城正忠が那覇尋常高等小学校のとき、校長だった山城一は鹿児島県出身で慶応義塾に学び教員に。鶴のように瘠せて背は高かったと教え子はいう。山城一は頑固党の首魁・義村朝明から李鴻章の密使と称し、清国援兵の資金ということで大金を騙し取った男で、山城正忠はこの事件をモデルに「九年母」を書いているが、後に山城は、「私が東京にいる頃、小杉天外先生が経営されていた『無名通信社』の小使をやっている変わりものの老人があった。それを主人公にして、中村星湖氏がかいた『短刀と判取帳』という短篇小説があった。それが誰あろう。山之城先生のなれの果だということを、作者からきいて驚いたことがある。」と『那覇尋常高等小学校四十年記念誌』に書いている。
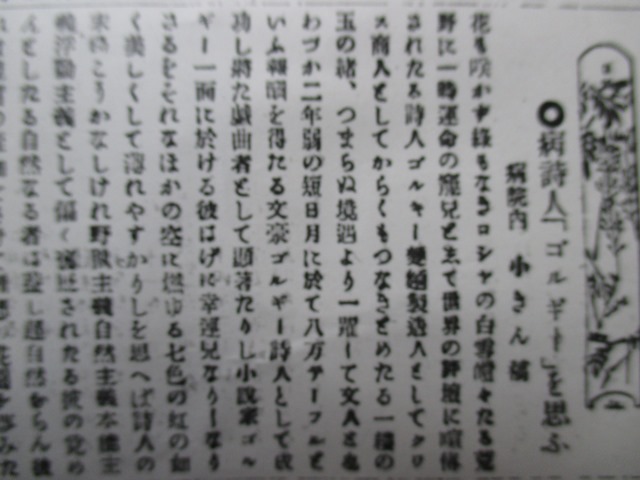
1903年3月11日『琉球新報』小きん(山城正忠)「病詩人『ゴルギー』を思ふ」○花も咲かず緑もなきロシアの白雪曀々たる荒野に一時運命の寵児として世界の評壇に喧伝されたる詩人ゴルギー①
①マクシム・ゴーリキー(Максим Горький, 1868年3月28日(ユリウス暦3月16日) - 1936年6月18日)は、ロシアの作家。本名はアレクセイ・マクシーモヴィチ・ペシコフ(Алексей Максимович Пешков)。ペンネームのゴーリキーとはロシア語で「苦い」の意味。社会主義リアリズムの手法の創始者であり、社会活動家でもあった。→ウィキペディア
1904年 医生教習所の砂辺松勁出征で山城正忠が後任に任命される。
1905年 山城正忠、青山第四聯隊入隊。三念・高江洲康健と広津柳浪を訪問する。
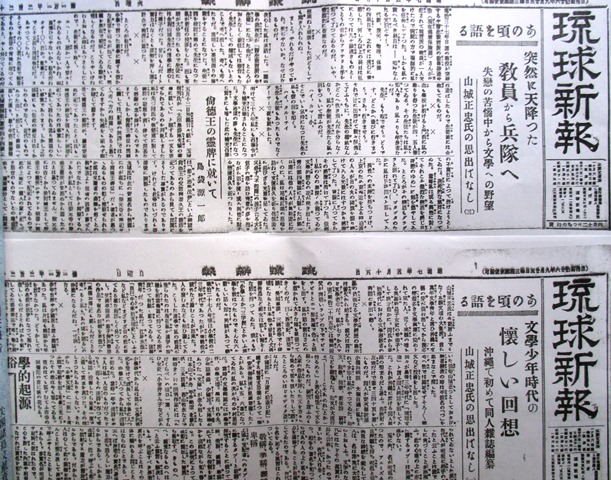
1932年5月15日~ー『琉球新報』「あの頃を語る/山城正忠氏の思出ばなし」
山城正忠氏は今更言ふまでもなく本県文壇の大御所。自ら萬年文学青年と言ひ沖縄に文藝の芽が萌え出してから幾多の変遷多き文学思潮に染め上れて来た人。近く来県の噂ある与謝野晶子女史の愛弟子として歌才豊かに。同氏から明治時代における文学志願者の苦闘の思出を聴く。
(略)石川啄木は痛快な男であった。何時も思索しているやうな瞳でものをみる。彼が私にくれた手紙がある。
復啓、玉稿昨日早朝正に落手仕候。日毎に新聞の続き物に追はれ居候のと、雑誌昴「スバル」のため寸暇を得ず今朝までまだ拝見致しかね居候。今出かけるところ、帰ったらすぐ拝誦可仕候。外出不定なれど夜分は大抵在宅今日は夕刻より屹度居る筈に候へば若しお暇に候はば御散歩がてら御来遊如何。大学の正門(赤門ではなく)の前から西に入り映世神社の向かって左の横手を真直に一町半坂の上の右側がこの宿に候、電話は下谷乙867番。 四十一年十二月二十一日 石川啄木
(以下略)
石川啄木と山城正忠
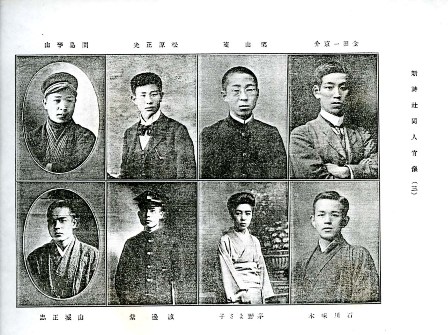
1937年6月『月刊琉球』山城正忠「啄木と私」
○山里君の出題によって、斷れぎれに浮かんで来る記憶を、その場でその儘、まとまりのない覚書にして見たのがこれ。私がはじめて琢木に会ったのは、その頃千駄谷に有った、与謝野先生の家であった。明治何年であったかはっきりしないが、与謝野寛年譜に拠ると、明治38年、皇紀2565、西暦1905年に私は新詩社同人となっているから、少なくともその翌々年位であらう。私と一緒に同人になった連中には、吉井だの北原だの、長田兄弟だの、それから木下杢太郎で盛名を馳せた現在東北大学にいる太田正雄が帝大の金釦で時々顔を見せ、箱根の水難が奇縁となり、天下の名妓萬龍を射止めた恒川石村、今の岡本一平氏夫人かの子さんがまだ大貫姓を名乗っていた。石川は明治三十四年に社中同人となり、私などのはいった頃には、既に鬼才を認められて、可なりその名が喧伝されていた。何でも雨のひどく降りつづく日であった。皆が白地の浴衣着ていたから夏の眞盛りであったとおもふ与謝野先生の家の都合で、近所の生田長江先生の客間を拝借して連中が集まった事がある。とにかく十名内外だったと覚えている。一座の中に、どう見ても気に喰わない男がひとりいた。歳からいふと私より二三下だといふ見当だが、それを寛先生や周囲の人たちが、いやにちやほやしていた。それに関わらず、本人は口数少なく、絶えず天の一角を睨んでいるやうな態度を持していた。青ン張れた顔で、どこか漱石先生の「坊ちゃん」にでてくる「うらなり」といふ感じだったが、それでいて、何かしら、犯しがたい風格と、ただならぬ気魄のあるのを私も見のがさなかった。
その男が突然私に向かって「山城君。君のくにじゃ、今でも人が死んだら喰ふのかい」と、飛んでもない質問をされて、一時カッとなった私は「馬鹿言へ、そんな事があるか」とハネかえしたのを与謝野先生がうまく取りなされた事があった。その場ですぐわかったが、それが誰あらう、わが石川啄木の奴だった。以来私は急速に彼と親しくなり、おれは北だ、貴様は南だ。ひとつ、大ひに提携して、東京の奴等を押へつけてやらう。といふ、盟約まで申込ませる仲になった。ああ、それなのに。といふ慙愧に堪へない私である。しかしそんな事はどうでもよい。今慶大にいる文学博士茅野粛々が、京大に赴く送別歌会の日、「鉢」といふ題で喝采を博したのが、啄木の「怒る時必ず鉢を一つ割り」といふ歌であり、もう一つ、彼が、何かの興行のビラになぞらへ、、寛、晶子、を横綱格に、北原吉井を大関格にしやっと入幕といふ所に、富田碎花、北川英美子、長島豊太郎、山城正忠といふ戯書を認めたのも、その日の会合だったとおもふ。それが現在、新しき村の長島豊太郎が表装して珍蔵しているらしい。
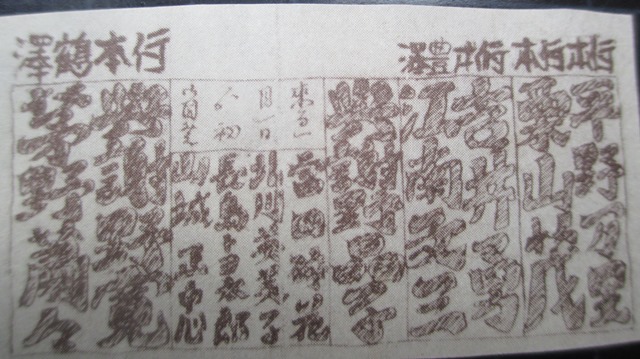
降って明治四十五年頃だと思ふ。当時石川は、本郷の蓋平館別荘にいた。閑なら遊びに来ないかといふ端書に接し、どこかの宴会がへりのささ機嫌で行ったら、別荘とは言へ、実は高等下宿の別棟で、それも特別狭い部屋に屯していた。酔ふていたので、何を話したかよく覚えていないが、その頃彼のかいていた、東京日々かの連載小説、「島影」のモデルが中心となり、それが彼の初恋に及んでいた事は確かである。どういふわけか、厨川白村博士や平野萬里に対して心よからず思っているやうな話だった。それから後の記憶は朦朧としているが、何かの行違いで彼と私の口論となり、結局「貴様とは絶交だ」と私の方で席を蹴って起ち、玄関から出る処を「馬鹿、つまらん事で誤解するか」と、追ひすがってたしなめられた事をかすかに覚えている。かうして私は、天下の石川啄木と別れた。いくばくかもなく、おもひがけない訃報を、私は郷里に於いて受けたのである。大正15年の夏、函館郊外の立待岬にある彼の墓地を訪ふた私は、ただただ、人の世の辞句を忘れた感慨があった。
1912年5月『沖縄教育』第七十三号(編輯兼発行者・親泊朝擢)山城正忠「琉球の二大彫刻家 梅帯華と梅宏昌」○緒言 近時最も喜ぶべき消息に接した、といふは別のことではない。我琉球の畫聖自了が、今度『大日本百科大辞書』といふ、浩瀚なる大著の中に載録されて、弘く世界に紹介されたことである。これより先、昨年の八月琉球教育会の事業として編纂された『偉人傳』中にも先進笑古眞境名安興氏の筆で『畫伯自了と殷元良』の傳記が併録された。そのなかに、首里龍潭池上に架せられた、世持矼の右欄畫は、口碑傳説に拠ると、彼の琉球丹青界の巨臂、自了の作だといはれている、といふことがあった。私は幼少の頃にも一度さういふことを聞いた記憶を持っているしかしそれも歳月と共に、漸次印象が朦朧となっていたが、同氏に依って再び鮮やかな印象の色彩を喚発したのである。而し未だ文献の徴するものがないので、その真偽の程は確証されない相だが、私はどういふものかそれを事実として見たい。そこで、依前は路傍の砂塵にまみれた、無名の作品として一瞥も与へなかった死畫の魚も、急に芸術的価値を論究されるに至った。若し果たしてそれが眞なりとしたら、轍鮒の水を得て再び泳ぎ出したやうな観がある。その後私は数々該橋を通って見たが、そのたんびに絵画の鑑識に乏しい愚眼にもあの彫刻魚の尾鰭が、藻草と小貝の間にからまって、溌剌として動くやうに思はれる。遡って畴昔、冠船渡来に際して池上に龍舟を浮かべ、当時恐ろしく権勢を張っていた冊封使を歓待したといふ、歴史を想像して見ると古式の衣冠帯束の色彩と、あの藻草に鯉魚の彫刻をして、模様画風の石欄画との調和がよほど風韻を帯びている。(華国翁は是を否定していられるらしい)又或人の話に依ると、嘗て岡倉覚三氏も、此両画伯の作品を激賞して『琉球特有の名画』といふ讃辞を吝まなかったといふ。自了は又唐人杜三策や、本邦狩野安信をも驚歎せしめた程の名人である。而しこんなことは人の皆能く知る処、敢えて説く必要もあるまい。
私はこの彫刻の魚を見たり攷へたりする毎に、連続して近代の偉人、琉球彫刻界の二大明星田名宗經翁(梅帯華)並びに其息宗相翁(梅宏昌)の英姿を髣髴として思ひ浮かべずには居られない。故人は実に琉球王国最後の芸術家である。
却説、近来漸く琉球史開拓の機熟し、先輩諸氏の薀蓄せる学識と彩筆を、これら郷土の偉人傳記に傾注されつつあるのは、民族教化、並びに社会教育上、実に慶ぶへき現象である。独りこれのみではない。祖先崇拝の徳を涵養するに就いても、亦多大の効果を奏するであらう。
而し我が田名筑登之親子の事績に至っては、世に之れを伝ふるもの少なく、大分人々の記憶も薄らぎつつあるやうだから、私はその湮滅を恐れ、聯か禿筆を呵して伝記の概略を叙べて、見たいと思ふ。殊に故人はわが字の偉人で、若狭町の誇りである。その関係から言ふても、これは当然私共の義務であるかのやうに考へた。而し私は素より歴史家ではない。加之浅学菲才、此任に当る器ではないが、要はただ、今迄私の手で調査蒐集した零碎な材料を一纏めにして、識者の劉覧を煩し、併せて学者の御教示を須つのである。・・・・
1920年11月 東京歯科医師会、ライオン歯磨本舗と「虫歯デー」実施 柴田米三(東歯)、小那覇全孝(日歯)在学中で参加。
12月4日 沖縄県歯科医師会設立総会(於 天理教会)会長・佐々木義一、副会長・楊長積(永井長積)
1923年3月28日 沖縄県歯科医師会 役員改選で会長・山城正忠、副会長・今井小四郎
1925年1月 『沖縄教育』144号(又吉康和 編) 山城正忠「絵を描くある男との話ー師走のある日、午後のことーそれに死んだ麦門冬のことを思ひ出して、さらでだに、心が晦くなっている矢先ですから、そういへば、末吉さんはほんとにお可哀想なことしましたね。 全くです。つまらんことをして呉れました。これからがほんとうに、彼の生命の、ぐんぐん延びるところでした、だが一面から考へて見ると、彼らしい最後を遂げたとも言へます。『ねがはくは花の下にてわれ死なん』といふ句を、套口のやうに讃仰していましたからね。・・・」
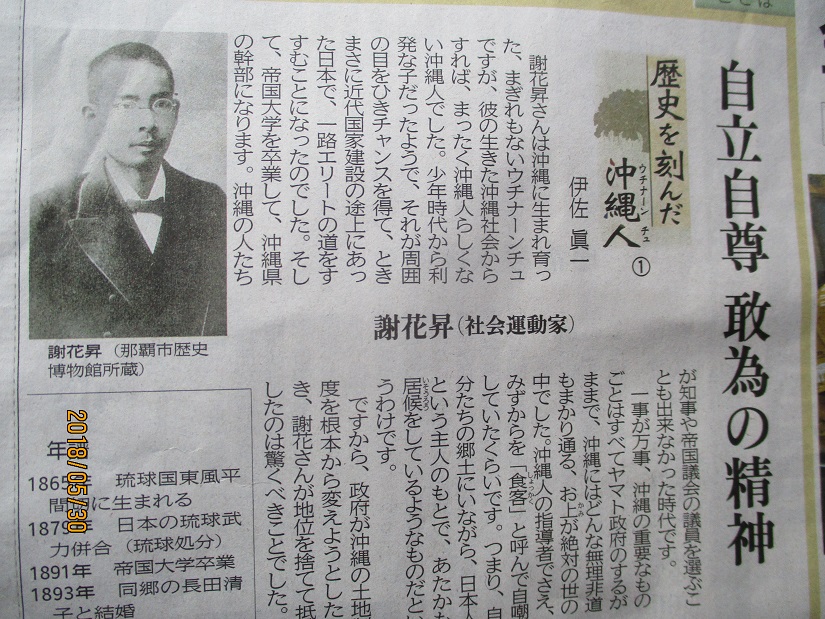
2018年4月8日『沖縄タイムス』伊佐眞一「歴史を刻んだ沖縄人①謝花昇 自立自尊 敢為の精神」
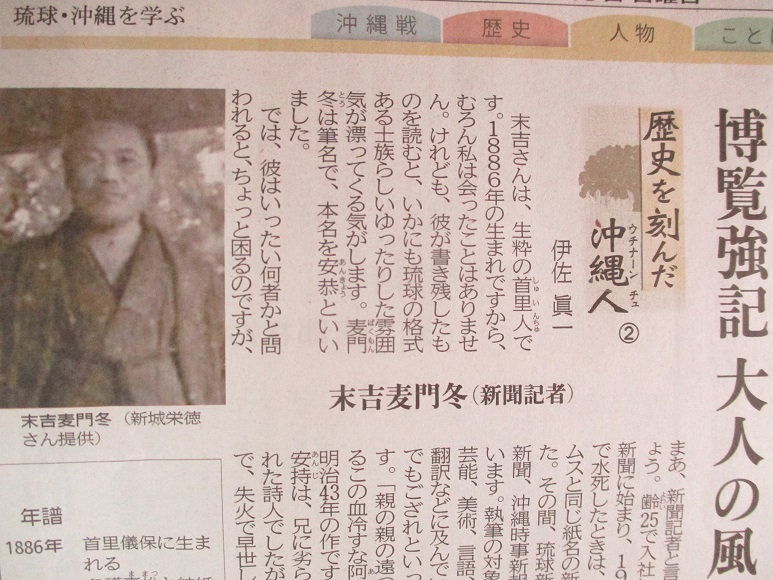
2018年5月13日『沖縄タイムス』伊佐眞一「末吉麦門冬(新聞記者)博覧強記 大人の風格」
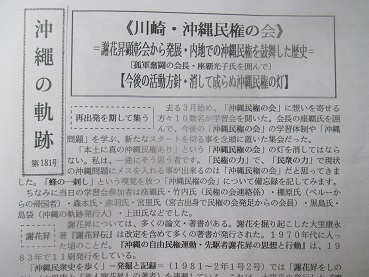
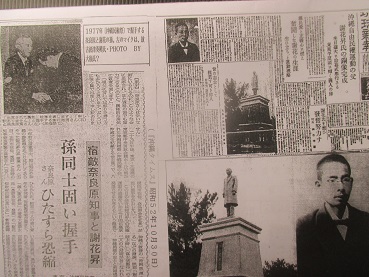
2018年3月3日 『沖縄の軌跡』「《川崎・沖縄民権の会》=謝花昇顕彰会から発展・内地での沖縄民権を鼓舞した歴史=」181号 編集発行人・島袋和幸(葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)
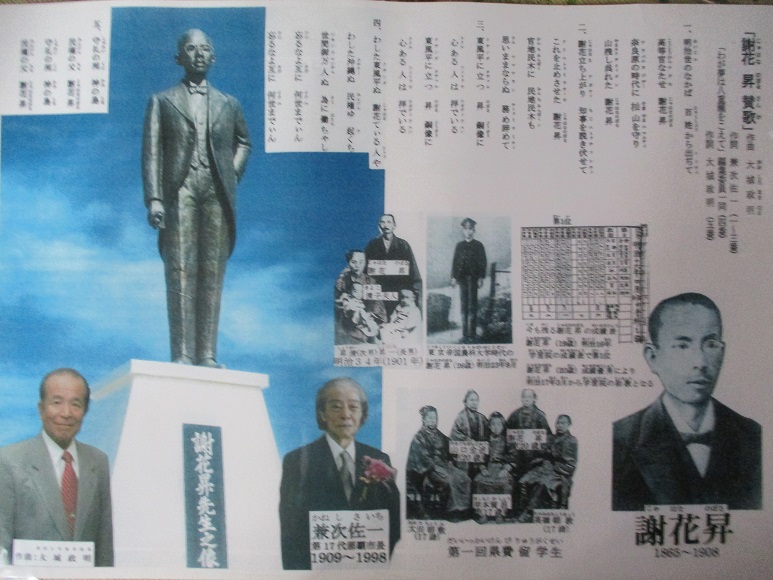

「謝花昇 賛歌」作詞・兼次佐一/作曲・大城政明/大城政明氏、伊佐眞一氏
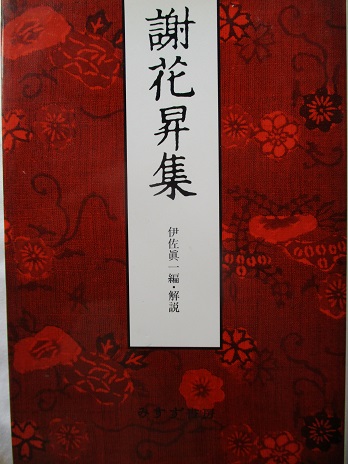
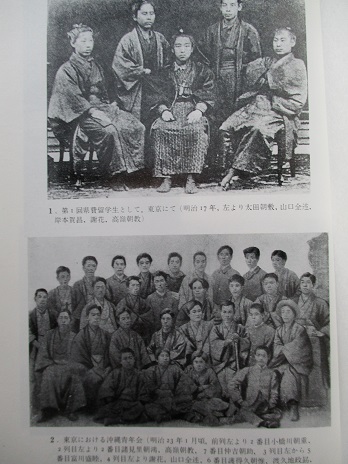
1998年6月 伊佐眞一『謝花昇集』みすず書房
1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号
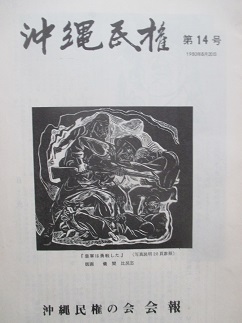
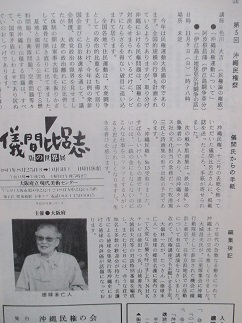
1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)□古波津英興「方言使用スパイ処分文書」
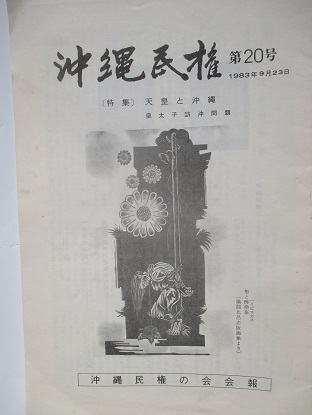
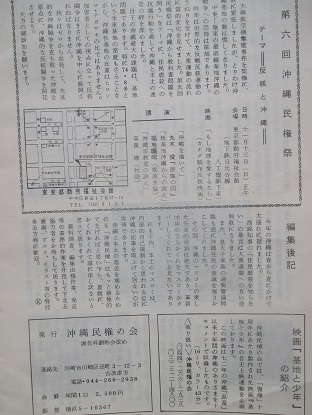
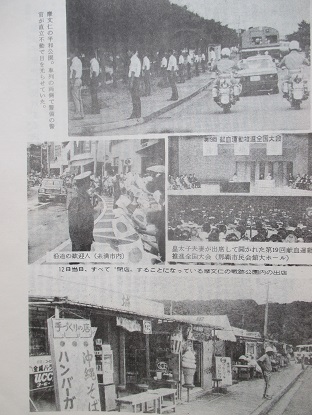

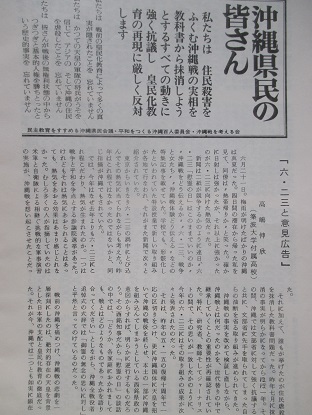
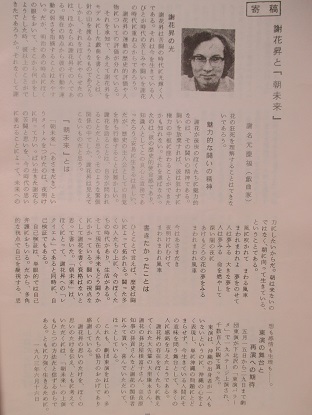
1983年9月23日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「菊と仏桑華」第20号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)


2018年3月14日 みどり印刷前でー石川和男氏(左)、島袋和幸氏/南風原文化センター前で島袋和幸氏
「みどり印刷」←iここをクリック
11/04: 佐久田繁と『月刊沖縄』
佐久田繁(1926年~2005年4月12日)
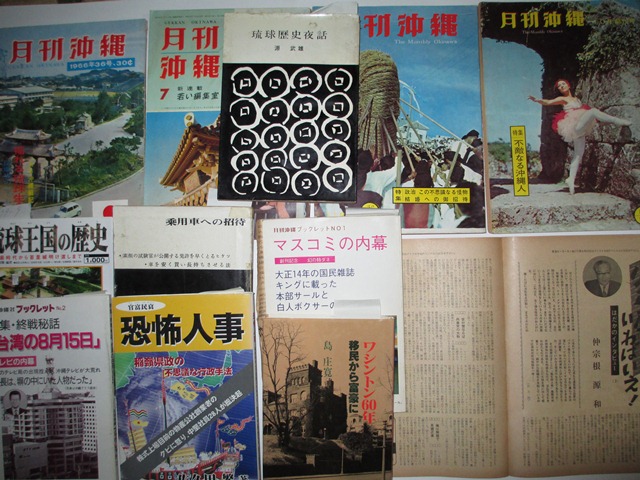
集英社文庫『沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史』の索引に佐久田繁が無い。また宜保俊夫のライバル又吉世喜(スター)は正喜となっている。沖縄に於ける雑誌ジャーナリストの先駆者が索引に無いのは不満である。この戦後史に登場する人物の大概はすでに『月刊沖縄』で取り上げている。1961年11月号に「縄張り”暁に死す”」でスターの西原飛行場事件、1963年3月号では「殺し屋に殺された暴力団」と題し又吉世喜や喜舎場朝信の顔写真を掲載している。その暴力団のアジトは月刊沖縄社の隣り近所に位置する場所である。同年5月号には「嵐を呼ぶ男ー熊谷優」に長嶋茂雄と石原裕次郎にかこまれた熊谷優の写真が掲載されている。
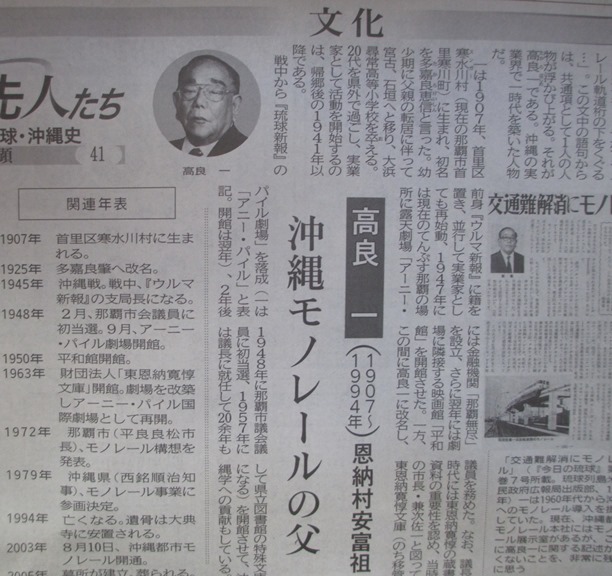
2013年8月9日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー高良一」

高良一□1954年9月 亀川恵信(平良市下里571)『宮古先覚者の面影』池間利秀、義武息廣、佐久田繁「高良一氏半生記」-1924年、大阪実業学校入学。25年中退し早稲田法制学校入学。1927年、徴兵検査で宮古へ帰郷。大阪谷水力伸鋤動社入社。1928年、大阪沖縄県人会運動に参加。1931年、関西沖縄県人会連合会理事。1934年、月刊『礦源社』発行。国粋大衆党此花区第二班遊説部長。1936年、時事写真同盟通信社にニュース記者。波之上丸処女航海の試乗招待で帰沖。本部町政刷新運動に参加。公聲新聞記者。1941年、本部町産興商事組合長。映画演劇「みなと館」経営。本部、那覇、与論間の海運事業「合同運輸会社」設立。那覇で「昭和織物工場」設営。
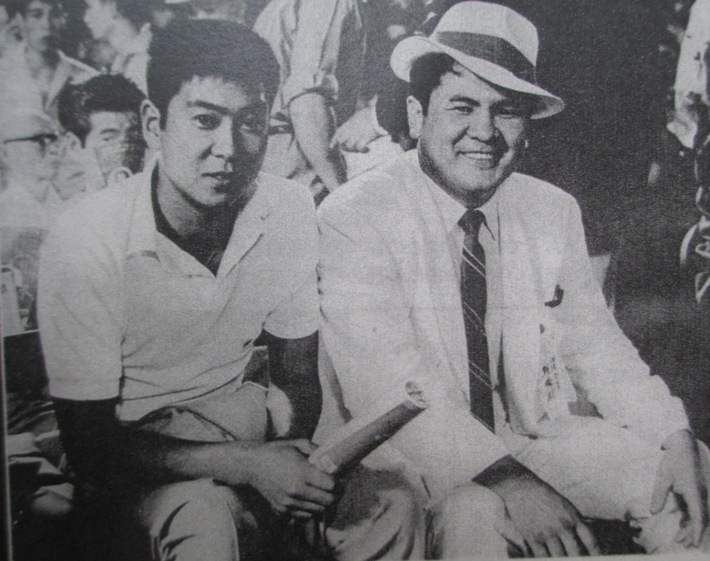
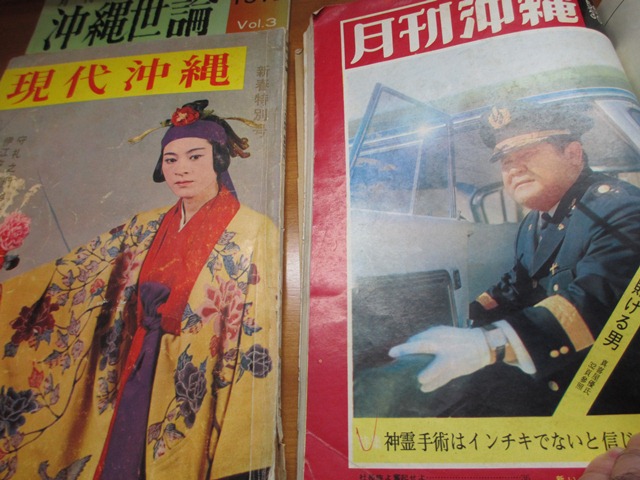
『現代沖縄』表紙ー神村真紀子/『月刊沖縄』表紙は真喜屋優
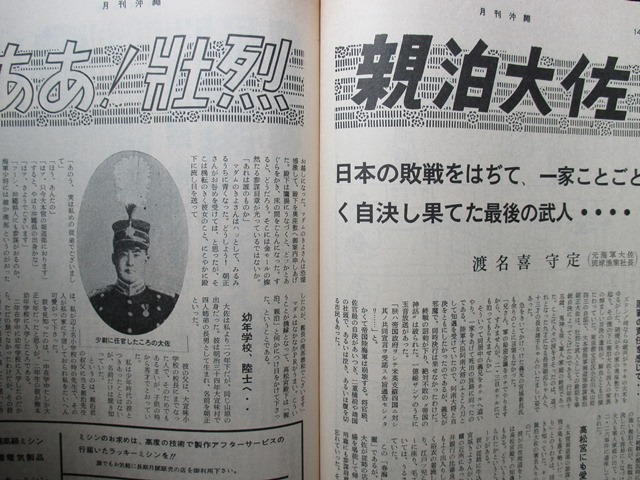
1962年10月『月刊沖縄』渡名喜守定「ああ!壮烈 親泊大佐ー日本の敗戦をはぢて 一家ことごとく自決し果てた最後の武人」
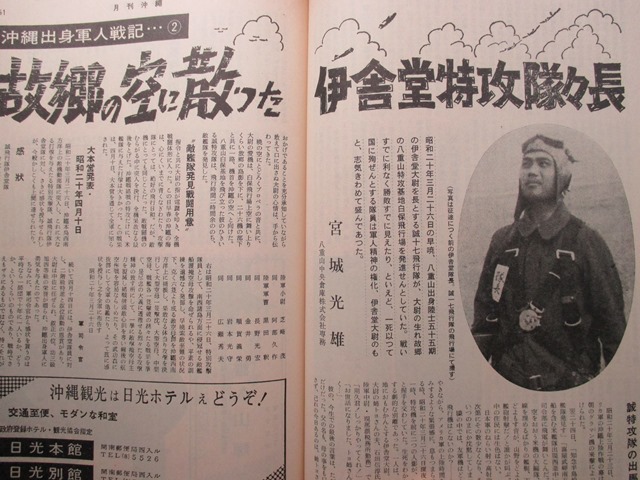
1962年11月『月刊沖縄』「故郷の空に散った伊舎堂特攻隊長」
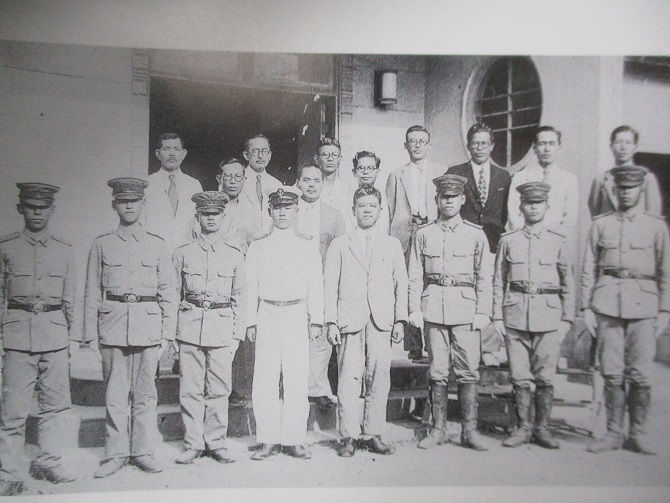
1939年夏季休暇で帰省、二中の職員室前で写真前列右から、山本元、伊舎堂用久、又吉康助、山城篤男校長、安里芳雄、照屋宏明、賀数恵輔、金城清輝
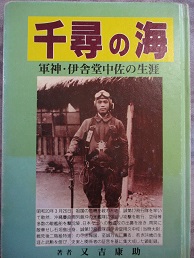
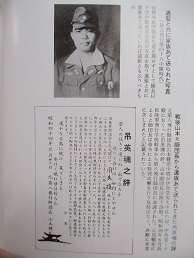

関連ー1989年8月 又吉康助『千尋の海ー軍神・伊舎堂中佐の生涯』

2022-11-26 万座毛
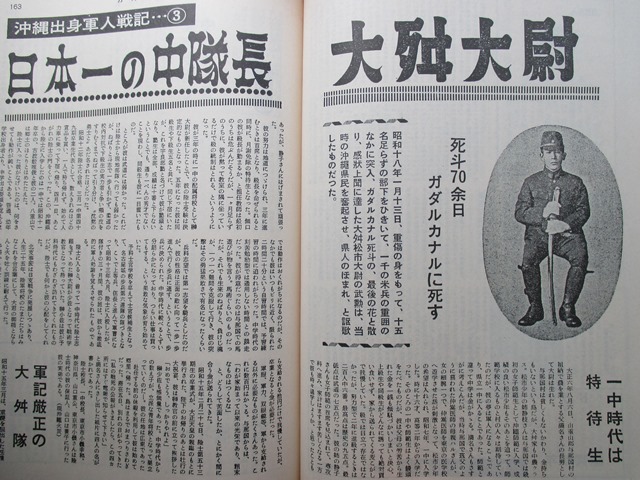
1962年12月『月刊沖縄』「日本一の中隊長 大舛大尉」

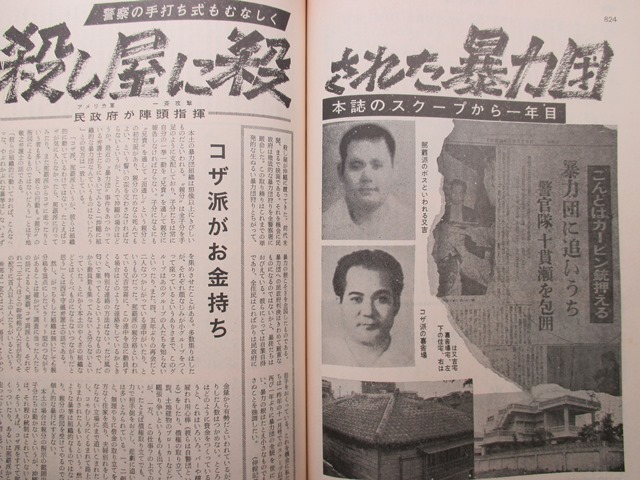
1963年3月『月刊沖縄』「殺し屋に殺された暴力団」
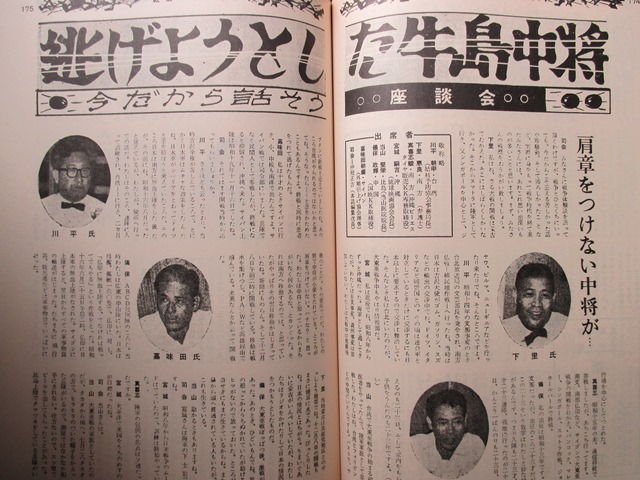
1963年8月『月刊沖縄』「座談会ー今だから話そう/逃げようとした牛島中将」□宮城嗣吉(琉球映画協会会長)ー沖縄戦だが、私はみんなが見る沖縄戦とは見方がちがう。とにかく真相はヤミだ。というのは、沖縄の進駐当時まず慰安所の経営から手をかけた。軍規が乱れていた証拠だねあれは。日本人は我々が小さなとき、武士道とは”死ぬ事と見つけたり″と教え、兵隊では”忠君愛国"などをたたきこみ、組織的に訓練された軍隊だった。ところがどうだ。首里を中心として玉砕すべきだったものが、新垣、安謝から安里へ逃げたうえに陥落寸前に、撃てる銃を破壊したんだったな。陸軍は卑怯だったな。海軍はあんた、7,800名から一割しか生きていない。つかえる銃があるならば、最後まで闘うべきではなかったか、と思うね(略)何はともあれ、牛島中将、長参謀も卑怯だよ。住民が逃げかくれて安全だと思っている壕を占領しようとして、住民を壕から追い出したのだからね。
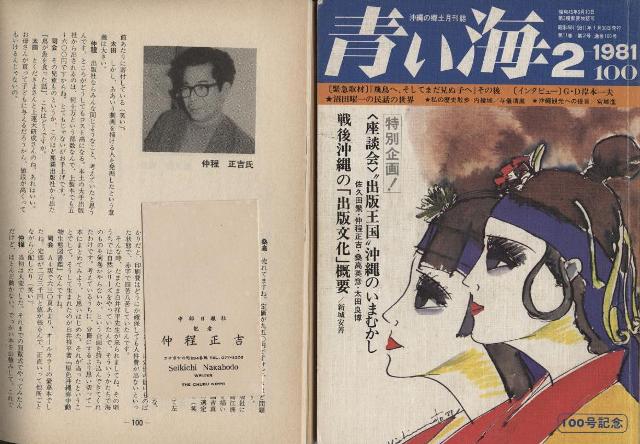
1981年2月『青い海』「出版王国 沖縄のいまむかし」(座談会・佐久田繁、仲程正吉、桑高英彦、太田良博、津野創一)

1963年5月『月刊沖縄』「辻の女軍応召す」
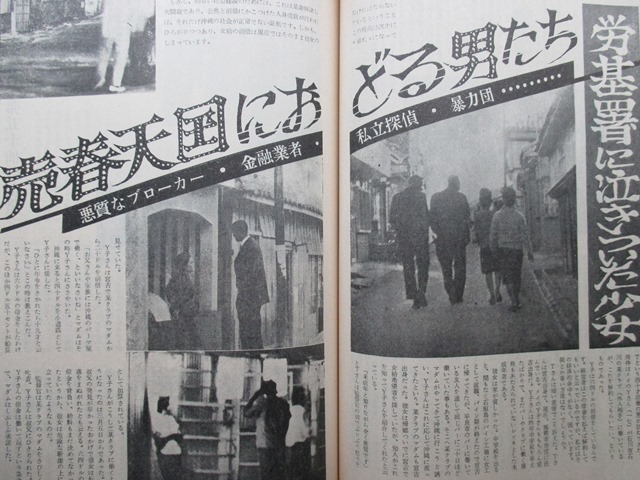
1963年7月『月刊沖縄』「売春天国におどる男たち」
○1961年1月『オキナワグラフ』「コザの迎賓館ープリンスホテル(熊谷優 経営)」
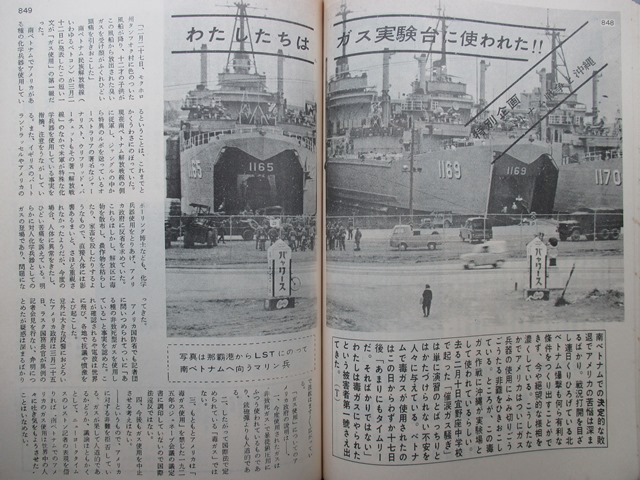
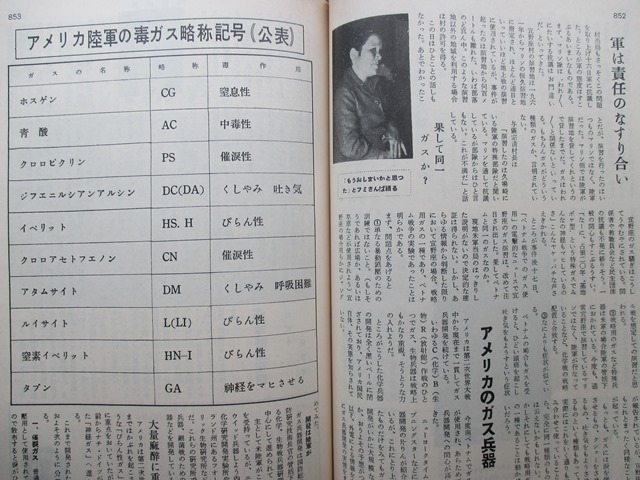
1965年6月『月刊沖縄』「わたしたちはガス実験台に使われた!!」
調理師であった父の数少ない蔵書に、月刊沖縄社が1966年に発行した田島清郷『琉球料理』があった。同年には『乗用車への招待』も発行している。前出の料理本は一般向きでないため1975年に渡口初美の『実用・琉球料理』が発行されている。私が佐久田さんを知ったのは、久茂地の琉球書院で店主の大城精徳さんから紹介されたのが最初の出会いである。このころは青い海出版社や琉球文化社によく出入りしていたから月刊沖縄社はめったに行かなかった。
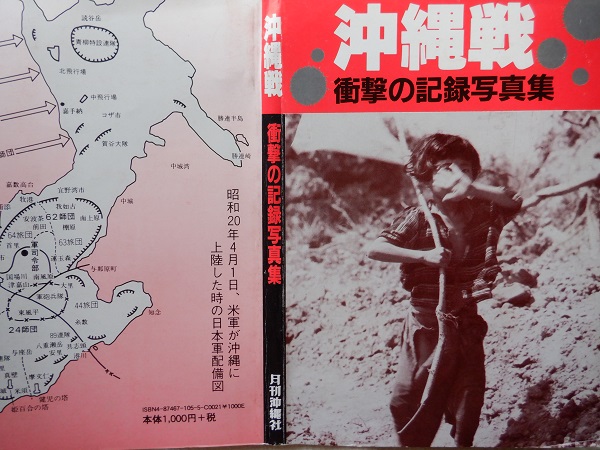
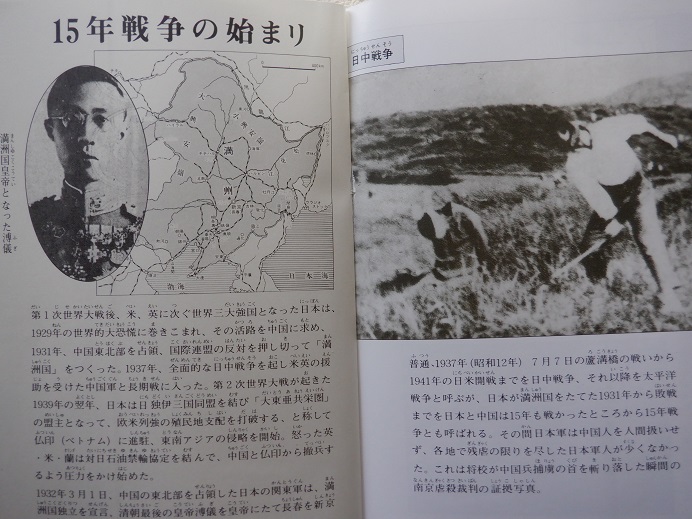
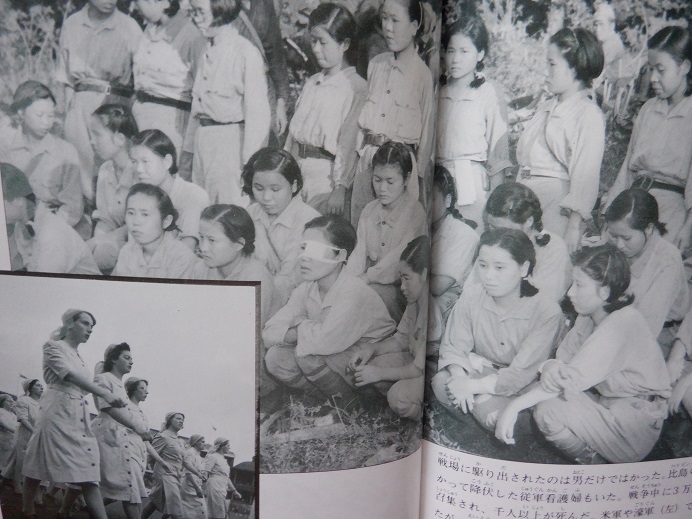
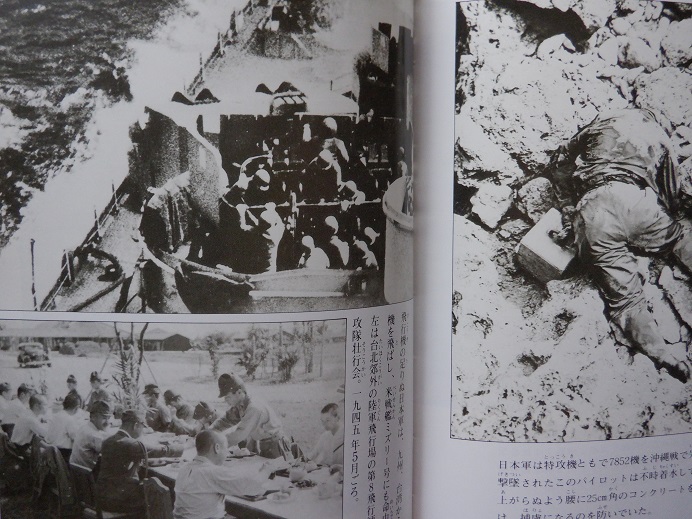
1988年6月 『沖縄戦 衝撃の記録写真集』月刊沖縄社
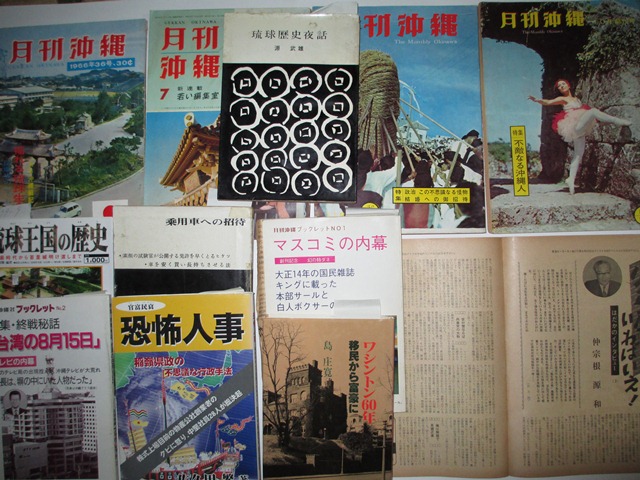
集英社文庫『沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史』の索引に佐久田繁が無い。また宜保俊夫のライバル又吉世喜(スター)は正喜となっている。沖縄に於ける雑誌ジャーナリストの先駆者が索引に無いのは不満である。この戦後史に登場する人物の大概はすでに『月刊沖縄』で取り上げている。1961年11月号に「縄張り”暁に死す”」でスターの西原飛行場事件、1963年3月号では「殺し屋に殺された暴力団」と題し又吉世喜や喜舎場朝信の顔写真を掲載している。その暴力団のアジトは月刊沖縄社の隣り近所に位置する場所である。同年5月号には「嵐を呼ぶ男ー熊谷優」に長嶋茂雄と石原裕次郎にかこまれた熊谷優の写真が掲載されている。
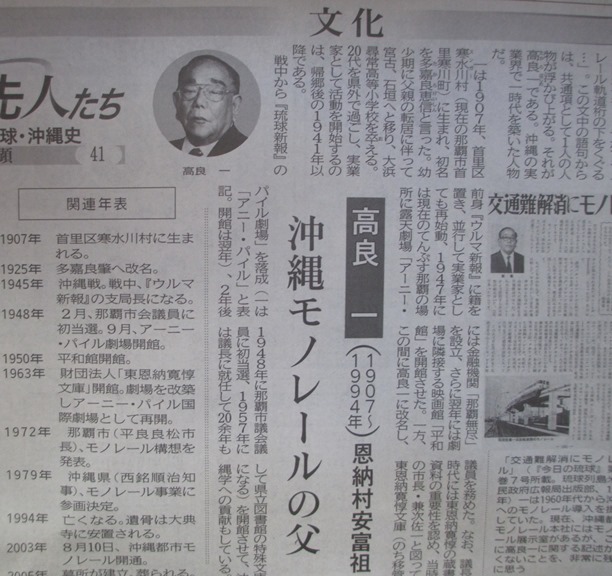
2013年8月9日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー高良一」

高良一□1954年9月 亀川恵信(平良市下里571)『宮古先覚者の面影』池間利秀、義武息廣、佐久田繁「高良一氏半生記」-1924年、大阪実業学校入学。25年中退し早稲田法制学校入学。1927年、徴兵検査で宮古へ帰郷。大阪谷水力伸鋤動社入社。1928年、大阪沖縄県人会運動に参加。1931年、関西沖縄県人会連合会理事。1934年、月刊『礦源社』発行。国粋大衆党此花区第二班遊説部長。1936年、時事写真同盟通信社にニュース記者。波之上丸処女航海の試乗招待で帰沖。本部町政刷新運動に参加。公聲新聞記者。1941年、本部町産興商事組合長。映画演劇「みなと館」経営。本部、那覇、与論間の海運事業「合同運輸会社」設立。那覇で「昭和織物工場」設営。
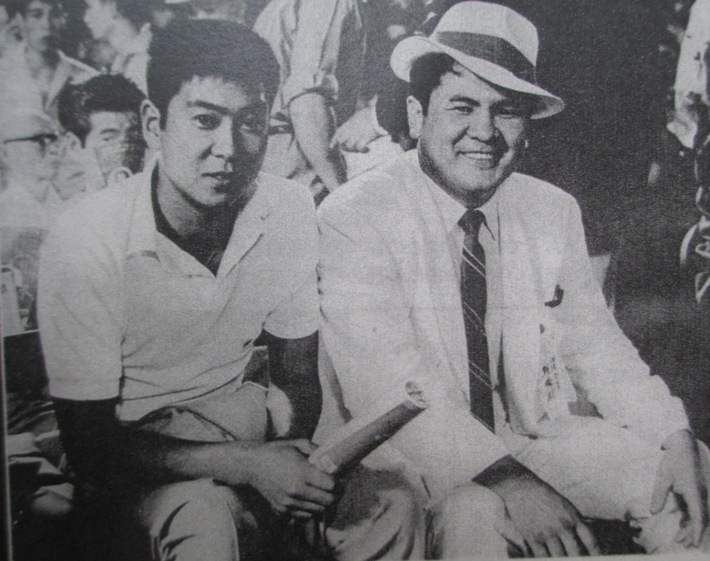
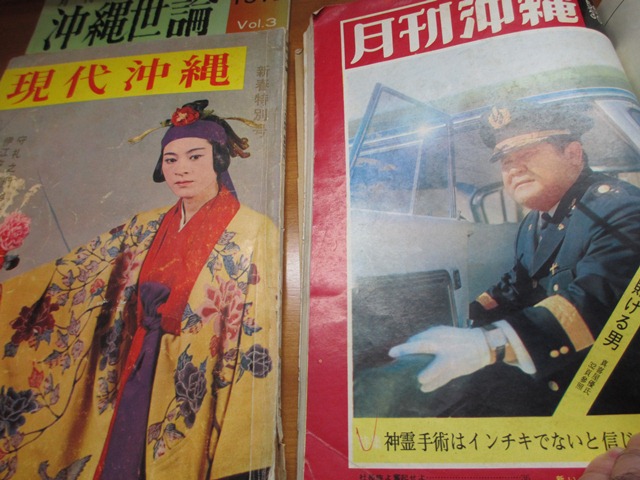
『現代沖縄』表紙ー神村真紀子/『月刊沖縄』表紙は真喜屋優
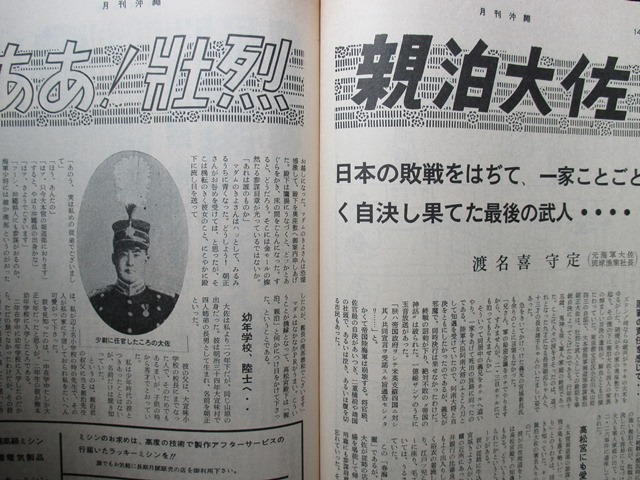
1962年10月『月刊沖縄』渡名喜守定「ああ!壮烈 親泊大佐ー日本の敗戦をはぢて 一家ことごとく自決し果てた最後の武人」
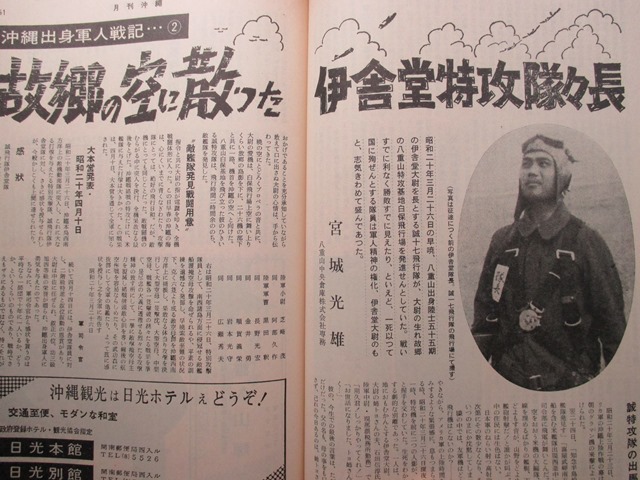
1962年11月『月刊沖縄』「故郷の空に散った伊舎堂特攻隊長」
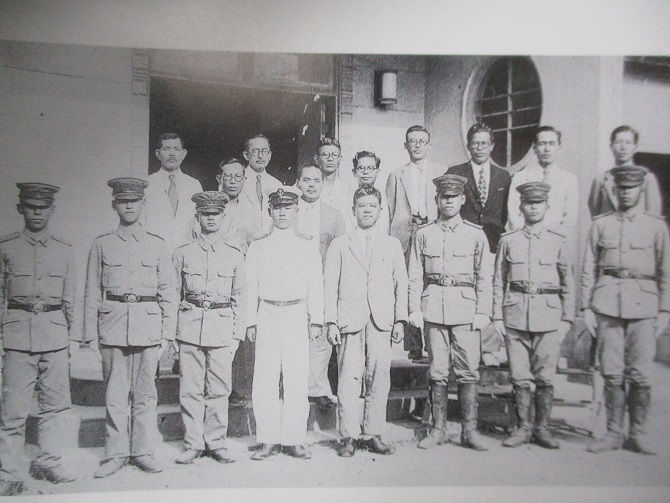
1939年夏季休暇で帰省、二中の職員室前で写真前列右から、山本元、伊舎堂用久、又吉康助、山城篤男校長、安里芳雄、照屋宏明、賀数恵輔、金城清輝
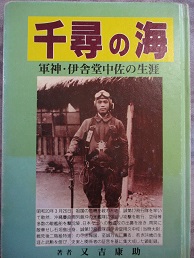
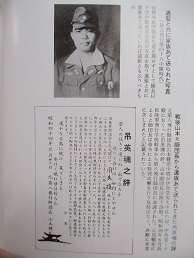

関連ー1989年8月 又吉康助『千尋の海ー軍神・伊舎堂中佐の生涯』

2022-11-26 万座毛
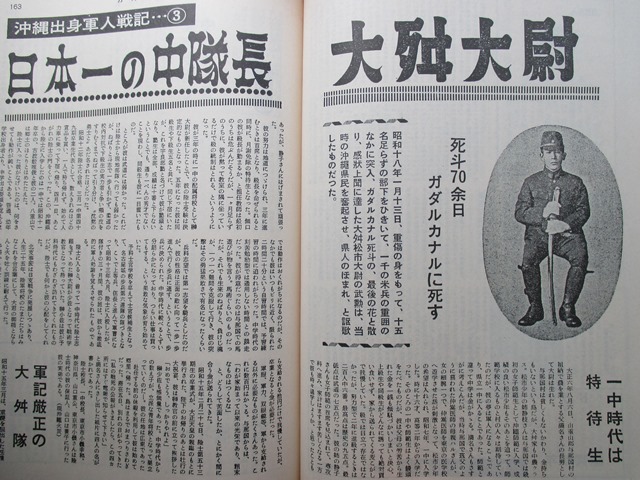
1962年12月『月刊沖縄』「日本一の中隊長 大舛大尉」

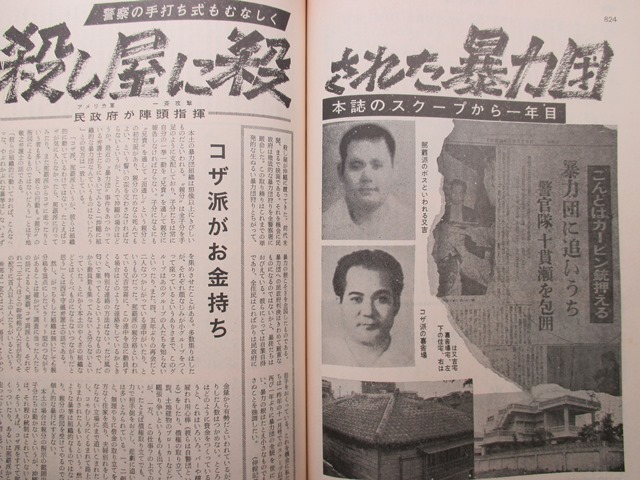
1963年3月『月刊沖縄』「殺し屋に殺された暴力団」
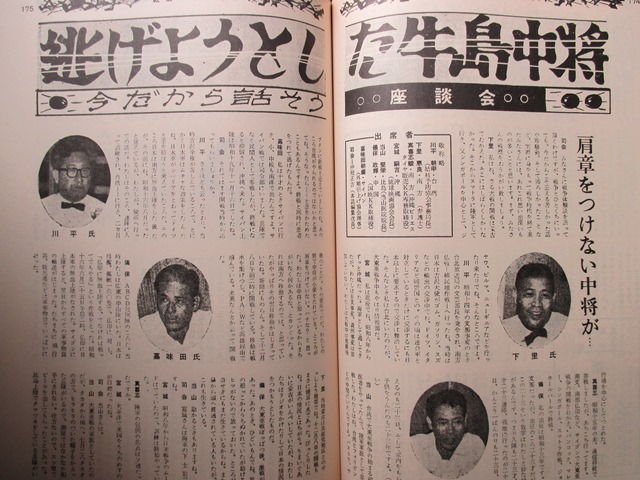
1963年8月『月刊沖縄』「座談会ー今だから話そう/逃げようとした牛島中将」□宮城嗣吉(琉球映画協会会長)ー沖縄戦だが、私はみんなが見る沖縄戦とは見方がちがう。とにかく真相はヤミだ。というのは、沖縄の進駐当時まず慰安所の経営から手をかけた。軍規が乱れていた証拠だねあれは。日本人は我々が小さなとき、武士道とは”死ぬ事と見つけたり″と教え、兵隊では”忠君愛国"などをたたきこみ、組織的に訓練された軍隊だった。ところがどうだ。首里を中心として玉砕すべきだったものが、新垣、安謝から安里へ逃げたうえに陥落寸前に、撃てる銃を破壊したんだったな。陸軍は卑怯だったな。海軍はあんた、7,800名から一割しか生きていない。つかえる銃があるならば、最後まで闘うべきではなかったか、と思うね(略)何はともあれ、牛島中将、長参謀も卑怯だよ。住民が逃げかくれて安全だと思っている壕を占領しようとして、住民を壕から追い出したのだからね。
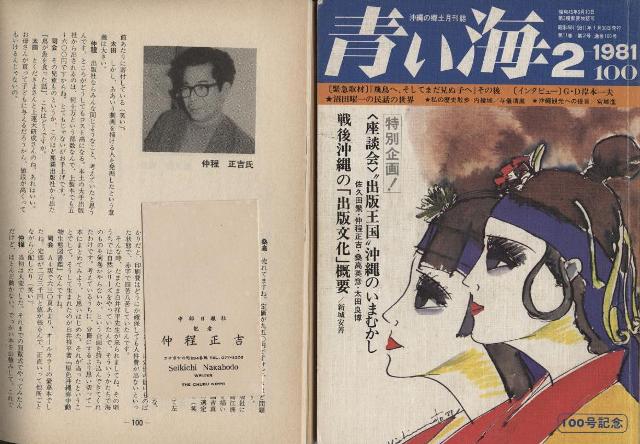
1981年2月『青い海』「出版王国 沖縄のいまむかし」(座談会・佐久田繁、仲程正吉、桑高英彦、太田良博、津野創一)

1963年5月『月刊沖縄』「辻の女軍応召す」
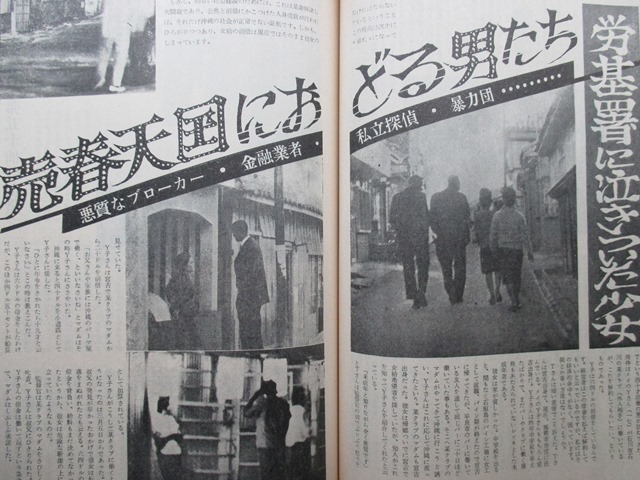
1963年7月『月刊沖縄』「売春天国におどる男たち」
○1961年1月『オキナワグラフ』「コザの迎賓館ープリンスホテル(熊谷優 経営)」
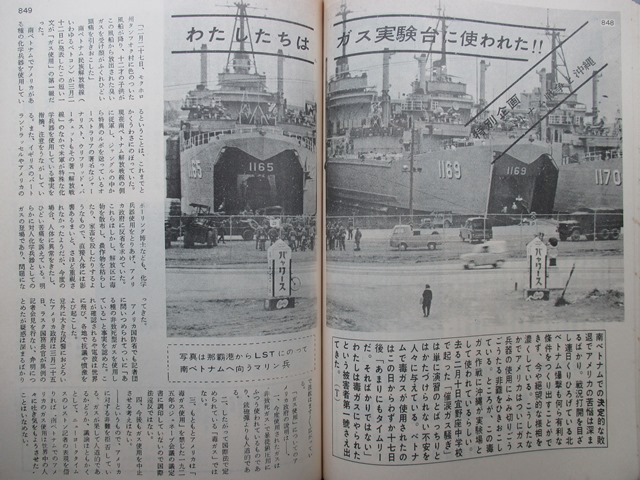
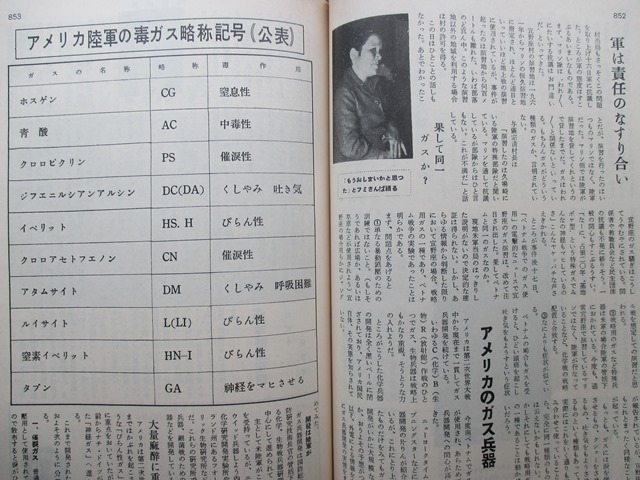
1965年6月『月刊沖縄』「わたしたちはガス実験台に使われた!!」
調理師であった父の数少ない蔵書に、月刊沖縄社が1966年に発行した田島清郷『琉球料理』があった。同年には『乗用車への招待』も発行している。前出の料理本は一般向きでないため1975年に渡口初美の『実用・琉球料理』が発行されている。私が佐久田さんを知ったのは、久茂地の琉球書院で店主の大城精徳さんから紹介されたのが最初の出会いである。このころは青い海出版社や琉球文化社によく出入りしていたから月刊沖縄社はめったに行かなかった。
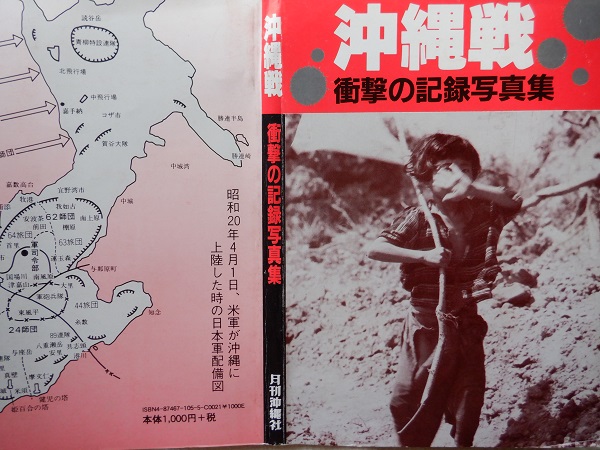
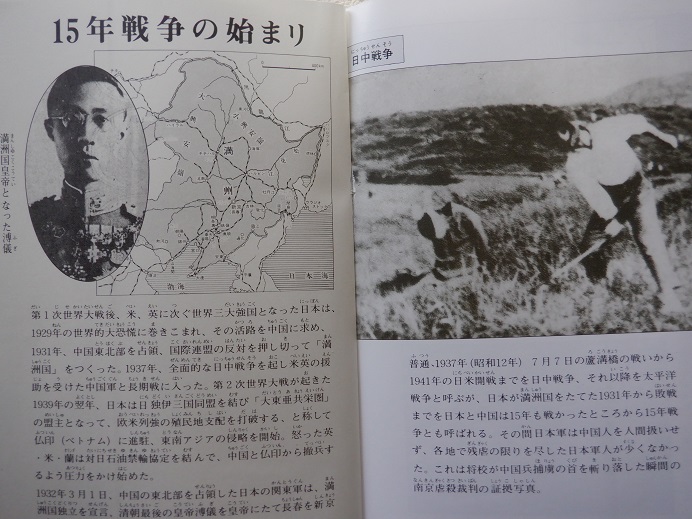
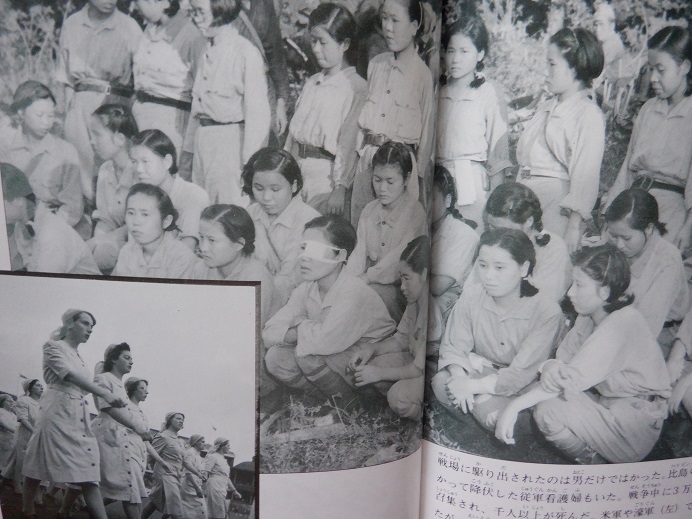
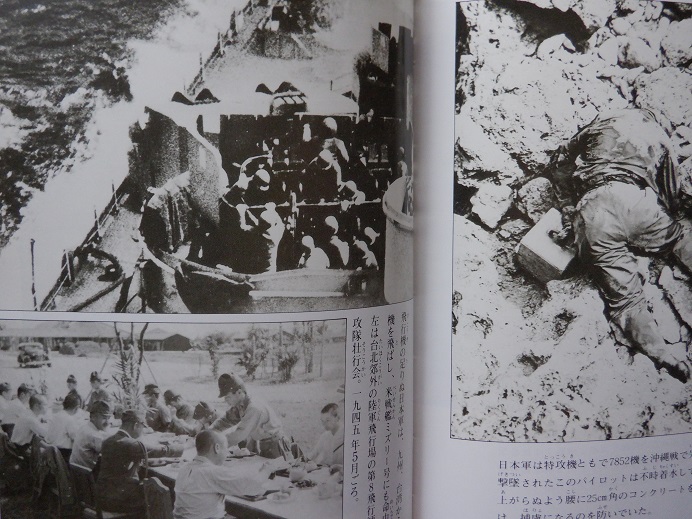
1988年6月 『沖縄戦 衝撃の記録写真集』月刊沖縄社
盆の挨拶回りで親戚のところから帰ると『日本古書通信』(日本古書通信社 〒101-0052 千代田区神田小川町3-8 駿河台ヤギビル5F ☎03-3292-0508 FAX:03-3292-0285)が来ていた。本日は物外忌((沖縄学の父・伊波普猷の命日)である。『日本古書通信』1045号の「バジル・ホール来琉200周年」には伊波普猷のことも記している。
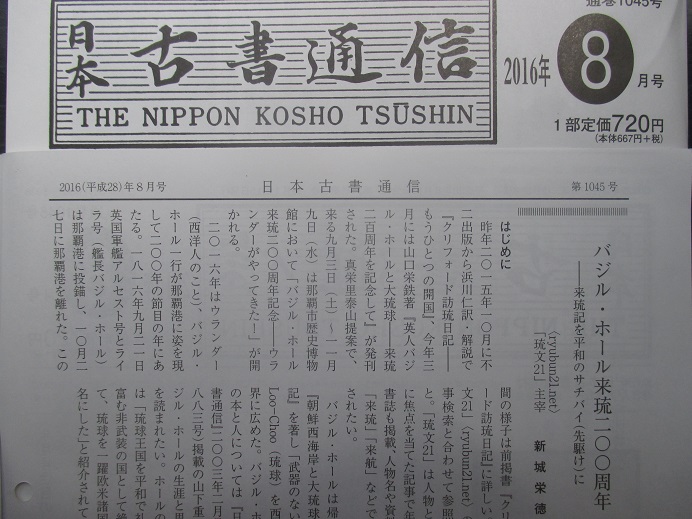
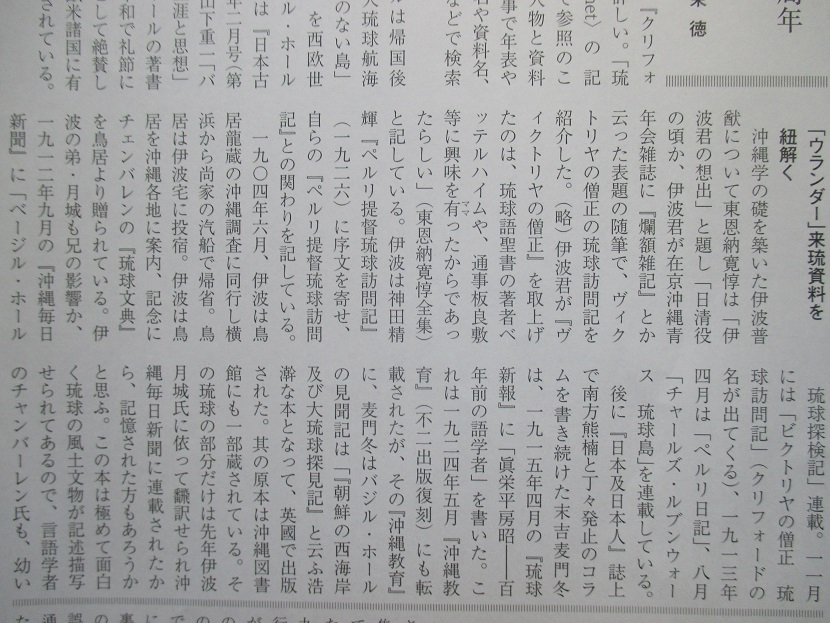
2016年8月 『日本古書通信』1045号 新城栄徳「バジル・ホール来琉200周年」
わが国に航海術や造船術を伝えた英国人ウィリアム・アダムズ(三浦按針)や、平戸のイギリス商館長を勤めた リチャード・コックスも努力した人たちである。アダムズはオランダ船リーフデ号の水先案内人として当時の豊後(大分県)に 漂着した人物である。その後、平戸のイギリス商館長リチャード・コックスの命を受け、シー・アドヴェンチャー号の船長として、 タイへ向かう途中乗組員の不穏な動きを察知して、五島に引き返しているが、その際沖縄から持ち帰った一袋のサツマイモをコックスに 送っている。時に1615年6月2日のことで、コックスはその日の日記に「大御所が大阪の城を取り、フィディア(秀頼)様の軍を 滅ぼした」報せを受けたとも記している。6月19日になって、コックスは、「庭を手に入れて、リケア(琉球)から将来された藷を そこに植え」、1年当たり10匁(英貨5シリング)を支払うと記している。すなわち、平戸に菜園を借り栽培を試みたわけである。 しかし、その後の実績は記されていない。現在平戸の川内浦の鳶の巣に「コックス甘藷畑跡」が残っており、この地域ではサツマイモを 「琉球イモ」または単にイモと呼んでいたといわれるが、そうであるとすると、何らかの実績が見られたのではないかと想像される。→鈴木俊(東京農大国際食料情報学部教授)
1796年 英船プロビデンス号虻田に来航。翌年室蘭に来航
1798年 近藤重蔵、択捉を調査。帰途ルベシベツ山道を開く
1811年 国後でロシア艦ディアナ号艦長ゴローニンが幕府の警備隊に捕らえられる
バジルホールの現在の認知度を画像検索すると「バジルホール(@ashurnasirpal2)」が出て満島ひかりちゃんが出てきた。「満島ひかり」を検索すると、女優の黒柳徹子の自伝的エッセイ『トットひとり』『トットチャンネル』を原作にしたNHKドラマ『トットてれび』で、満島ひかりが黒柳役を務めているが、映画「夏の終り」では若き日の瀬戸内寂聴を艶っぽく演じている。さらに検索すると沖縄県沖縄市出身。ユマニテ所属。弟は俳優の満島真之介、妹はモデルの満島みなみ、となっていて、初めて沖縄出身だとわかった。話が本題から逸れてしまったが、この偶然も必然として見逃してもらいたい。正確にバジル・ホールでウィキペディアを見ると「19世紀のイギリスの海軍将校、旅行家、作家。インド洋、中国、琉球、中南米各地を航海したことで知られる。ベイジル・ホールと記述されることも多い。 ナポレオン1世に『琉球では武器を用いず、貨幣を知らない』と伝えた」とある。また 「Facebook/バジル・ホール研究会」も参考になる。
1816年(文化13)7月25日、イギリス軍艦アルセスト号(艦長マレー・マクスウェル)・ライラ号(艦長バジル・ホール)、那覇に投錨/9月6日、首里王府、マクスウェル館長の国王への謁見要請を謝絶。/7日、両船、那覇を離れる。後にライラ号の乗組員だった退役軍人ハーバード・J・クリフォードが中心となり、琉球海軍伝道会を創設、ベッテルハイムを派遣することになる。→2014年2月 生田澄江『幕末、フランス艦隊の琉球来航ーその時琉球・薩摩・幕府はどう動いたかー』近代文藝社
Basil Hallは1788年12月31日、スコットランド エディンバラで生まれて、1844年9月11日ポーツマス王立ハスラー病院で死去(55歳)。
「経済学の父」ことアダム・スミス、詩人のキーツ、ウォルター・スコット、シャーロック・ホームズの生みの親コナン・ドイル、『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』の作家ロバート・ルイス・スティーヴンソン、ジェームズ・ボズウェル、トマス・カーライル、俳優のショーン・コネリー、ユアン・マクレガー、ジェラルド・バトラーなどはスコットランドの生まれである。
スコットランドは、産業革命以前より、科学・技術の中心地であったため、多くの科学者・技術者を輩出している。その発見・発明は、現代社会にはなくてはならないものが多い。電話を発明したグレアム・ベル、ペニシリンを発見したアレクサンダー・フレミング、蒸気機関を発明したジェームズ・ワット、ファックスを発明したアレクサンダー・ベイン、テレビを発明したジョン・ロジー・ベアード、空気入りタイヤを発明したジョン・ボイド・ダンロップ、道路のアスファルト舗装(マカダム舗装)を発明したジョン・ロウドン・マカダム、消毒による無菌手術を開発したジョゼフ・リスターなどはスコットランドの生まれである。
羊の内臓を羊の胃袋に詰めて茹でたハギスが有名。また、スコッチ・ウイスキーは定義上スコットランド産でなければならない。スコットランドには、100以上もの蒸留所があり、世界的にも愛好家が多い。
コリン・ジョイス(『驚きの英国史』NHK出版新書 2012年pp.79-83)ではイギリス人の生活を皮肉って次の物がすべてスコットランド人によるものだとしている。マーマレード、レインコート、自転車、タイヤ、乾留液(タールマック舗装)、蒸気エンジン、イングランド銀行、糊つき切手、タバコ、電話、ローストビーフ、アメリカ海軍、麻酔薬などである。『聖書』にもスコットランド人が最初に出てくるが、これはジェームズ6世が英訳を進めたからである。→ウィキ
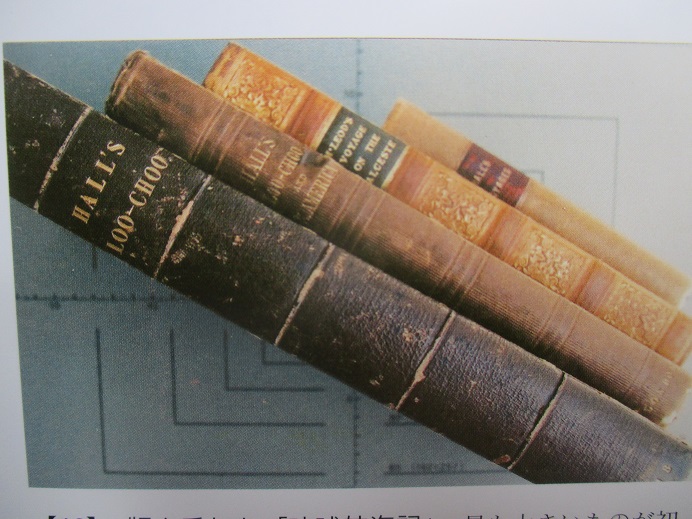
『バジル・ホール琉球航海記』最も大きいのが初版(1818年)
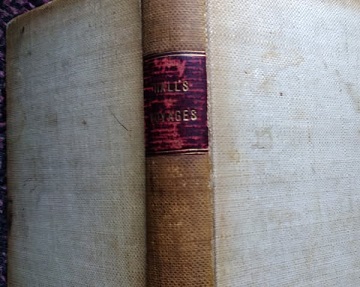
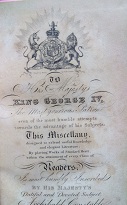
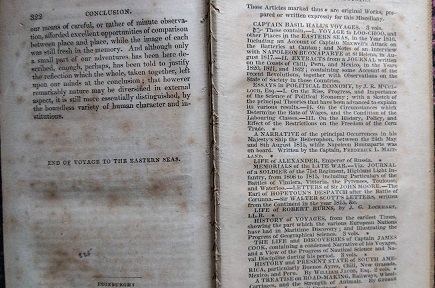
3版(1826年)
2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
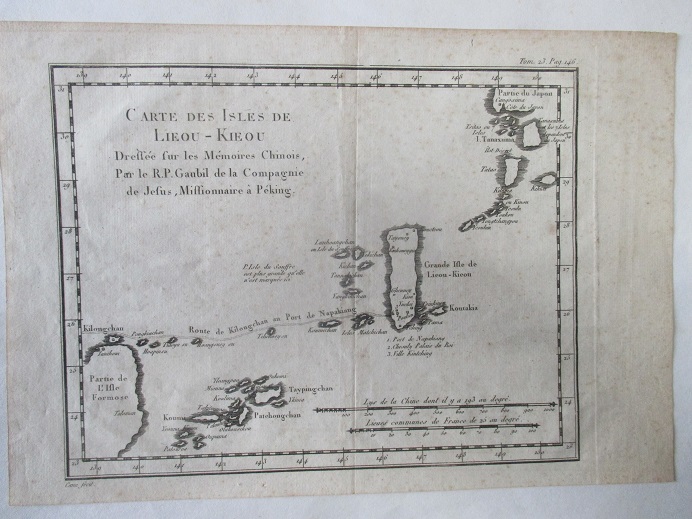
那覇市歴史博物館で「バジル・ホール来琉200周年記念/ウランダーがやってきた!」の図録を見せてもらった。上の地図に書き込みがある地図も掲載されていた。担当の鈴木学芸員がネット「ヨーロピアナ」①で収集したフランス国立図書館蔵のものだ。(2016ー8ー4)
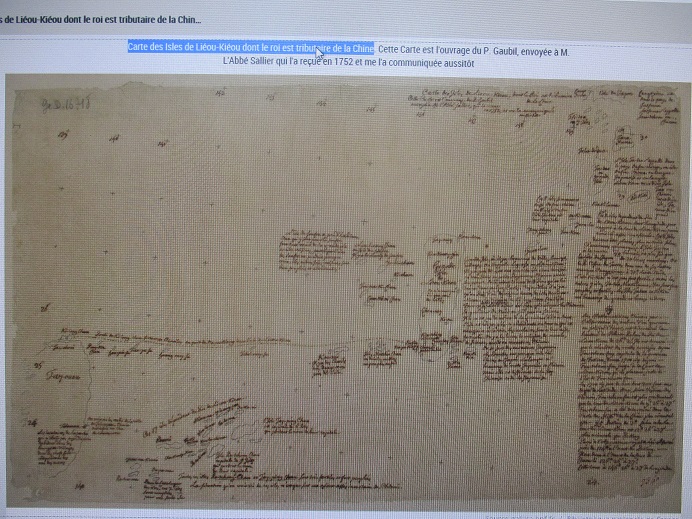
①欧州委員会は、EU加盟国の図書館や博物館が所蔵する書籍、文献、映像、絵画などを検索・閲覧できる「ヨーロピアナ」という電子図書館を開設した。インターネットを通じて、400万件以上のデータに無料でアクセスすることができる。ヨーロピアナは、2008年11月20日に公式オープン。ところが、初日の1時間で1000万件を超えるアクセスがあり、サーバーが停止してしまった。モナリザの絵やベートーベンの楽譜といった有名なアイテムも閲覧することができ、大変な人気となったためだ。オープン早々「一時休館」となったヨーロピアナは、その後、コンピューターの処理能力を上げて、12月24日に再オープンした。ヨーロピアナは、EU加盟国の公用語である23言語で利用可能であり、欧州市民の誰もが身近に利用できるよう配慮されている。もちろん、日本からもアクセスできる。欧州の図書館や博物館が所有する日本関連のアイテムも閲覧することできる。
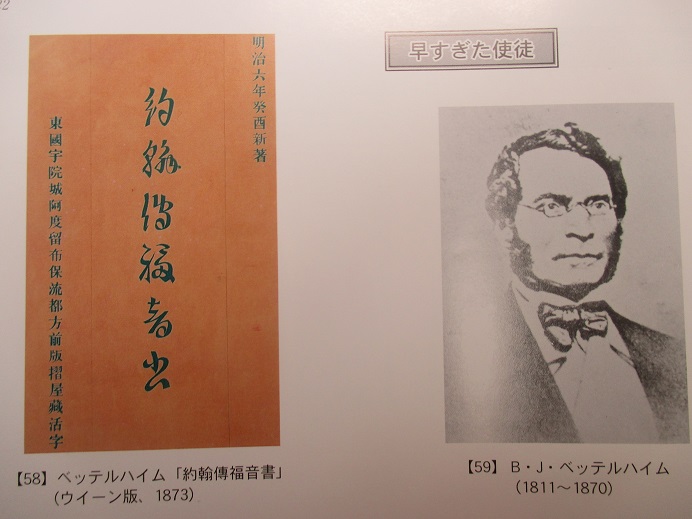
「ベッテルハイム」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
1844年4月28日 フランス人ジャン・バチスト・セーシユ提督率いる5隻の東洋艦隊麾下のフォルニェル・デュプラン大佐の軍艦アルクメーヌ号を琉球へ分遣。宣教師テオドール・オーギュスト・フォルカードと清国人伝道師オーギュスタン・高を那覇に残して5月6日に出帆。→2014年2月 生田澄江『幕末、フランス艦隊の琉球来航ーその時琉球・薩摩・幕府はどう動いたかー』近代文藝社
1853年6月ーペルリ、首里城訪問□→1926年10月ー神田精輝『ペルリ提督琉球訪問記』/1935年3月ー土屋喬雄『ペルリ提督日本遠征記』弘文荘(沖縄県立図書館所蔵本は国吉真哲寄贈)/1947年2月ー大羽綾子『ペルリ提督遠征記』酣燈社/1962年6月ー外間政章『対訳ペリー提督沖縄訪問記』研究社/1985年10月ー金井圓『ペリー日本遠征日記』雄松堂/1994年4月ー大江志乃夫『ペリー艦隊大航海記』立風書房
1856年、チェンバレンは母親エライザ・ジェインの死によって母方の祖母とともにヴェルサイユに移住した。それ以前から英語とフランス語の両方で教育を受けていた。またフランスではドイツ語も学んだ。帰国し、オックスフォード大学への進学を望んだがかなわず、チェンバレンはベアリングス銀行へ就職した。彼はここでの仕事に慣れずノイローゼとなり、その治療のためイギリスから特に目的地なく出航した。1873年5月29日にお雇い外国人として来日したチェンバレンは、翌1874年から1882年まで東京の海軍兵学寮(後の海軍兵学校)で英語を教えた。1882年には古事記を完訳している(以下略)。前出の『チェンバレンの交友』には「日本を広く世界に紹介した人というと、ハーンをあげるものが多い。少し前ならシーボルト。ところが西洋ではシーボルトの次はチェンバレンである。」とし、友人としてサトウ公使、アストン、小泉八雲、門弟の和田万吉、岡倉由三郎(註)らとの交友を紹介している。
岡倉由三郎 生年慶応4年2月22日(1868年) 没年昭和11(1936)年10月31日 英語学者。天心の弟
出生地神奈川・横浜 学歴〔年〕東京帝大文科選科
経歴東大選科でチェンバレンに言語学を学ぶ。東京府立一中教諭、七高教授を経て明治29年嘉納治五郎校長の招きで東京高師教授。新村出らと「言語学雑誌」を発刊、35年から独、英に留学。大正15年に東京高師を退官するまで英語科の主任を務めた。その後、立教大学に奉職。開始当時のNHKラジオの英語講座では巧みな話し方で人気を集め、外国語教育、基礎英語の普及に大きな功績を残した。ヘボン式ローマ字の採用を主張したほか、昭和8年出版された「新英和大辞典」は岡倉辞典といわれ、一般に広く用いられた。→コトバンク
岡倉天心の長男の岡倉一雄は朝日新聞記者で、岡倉覚三の伝記をまとめた。孫(一雄の子)の岡倉古志郎は非同盟運動にも関わった国際政治学者、曾孫(古志郎の子)長男の岡倉徹志は中東研究者、玄孫(徹志の子)長男の岡倉禎志は写真家、玄孫(徹志の子)次男の岡倉宏志は人材開発コンサルタント、西洋史学者の岡倉登志は天心の曾孫にあたる。→ウィキペディア/ラングドン・ウォーナー(一八八一〜一九五五)は、ハーバード大学で考古学を専攻。卒業後、五浦で岡倉天心の薫陶を受け日本美術を研究。
1909年11月、アメリカ人・ウォーナー来沖。

1991年5月30日『琉球新報』松島弘明「文化ノート/ウォーナー資料を追え」
1996年5月17日『沖縄タイムス』「ワーナー資料沖縄の民芸品 米博物館が保存」
ラングドン・ウォーナー(Langdon Warner、1881年8月1日 - 1955年6月9日)は、アメリカの美術史家。ランドン・ウォーナーとも表記される。太平洋戦争中に日本の文化財を空襲の対象から外すよう進言した人物とされるが異論も多い。マサチューセッツ州エセックス生まれ。1903年ハーバード大学卒業。卒業後ボストン美術館で岡倉天心の助手を務め、1907年に同美術館の研修候補生として日本に派遣された。1910年にロンドンで開催される日本古代美術展の準備をしていた岡倉らを手伝い、3冊の詳細な出品カタログ『日本の寺とその宝物』の英訳に協力した。帰国後東洋美術史を講義、ハーバード大学付属フォッグ美術館東洋部長を務めるなど、東洋美術の研究をした。1946年、米軍司令部の古美術管理の顧問として来日。朝河貫一とは親交が深く、数々の書簡を交わしたりウォーナーの著書に朝河が序文を寄せたりした。→ウィキペディア○日本各地にはウォナー記念碑が6か所もある。最初の法隆寺の碑から、最後はJR鎌倉駅前の碑。
1910(明治43)年9月15日、冨山房発行『學生』第一巻第六号 中村清二「琉球とナポレオン」
中村清二(女優の中村メイコは兄の孫にあたる)「チェンバレン氏は英国の使節を廣東に上陸させて待っている間に朝鮮と琉球を見物し、帰国の途次セントヘレナ島を訪れてナポレオンに会見し琉球の物語をしたとある。」と記している。
1912年 バージル・ホール・チェンバレン「ある新しい宗教の発明」(神道の資源を引き継ぎながら新たに作り上げられた天皇崇拝のシステム)→タカシ・フジタニ『天皇のページェントー近代日本の歴史民族誌から』(1994年 日本放送出版協会)/2016年10月『春秋』島薗進「明治天皇崩御と国家神道」
1925年12月 沖縄県海外協会『南鵬』創刊号 真境名安興「ベージル・ホール、渡来に関する琉球側の記録」
1926年6月 武藤長平『西南文運史論』岡書院
○内藤虎次郎「西南文運史論序」/新村出「小序」
○末吉安恭、東風平東助二君の好意で古き『沖縄集』一冊(写本)と新しき『沖縄集』二冊(宜湾朝保輯板本)とを一覧した。
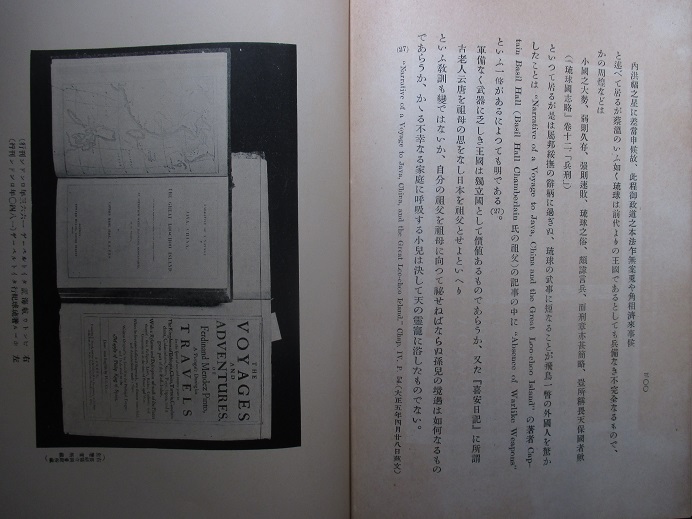
右 ピントウ航海記 1663年ロンドン刊行 ホール著琉球紀行 1840年ロンドン刊行
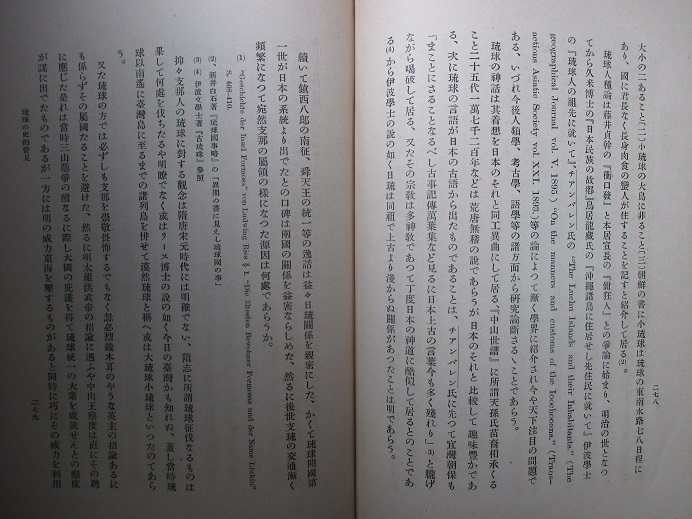
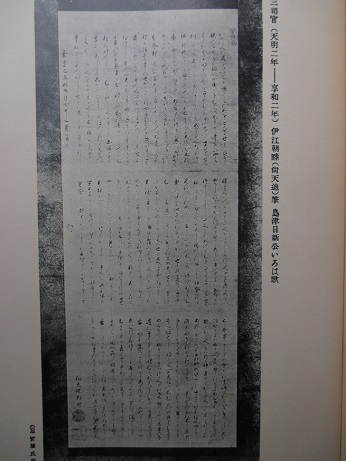
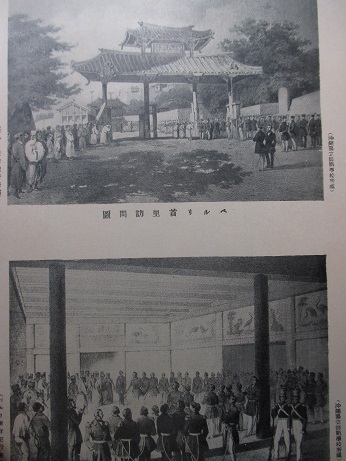
伊江朝睦筆「島津日新公いろは歌」(????宮城氏所蔵)
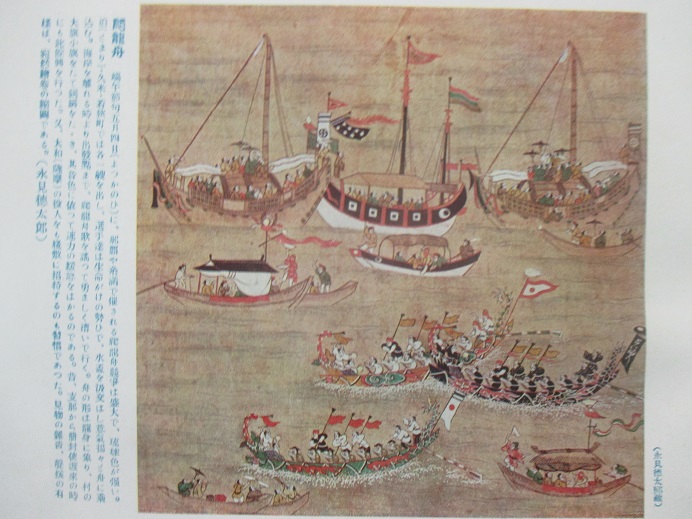
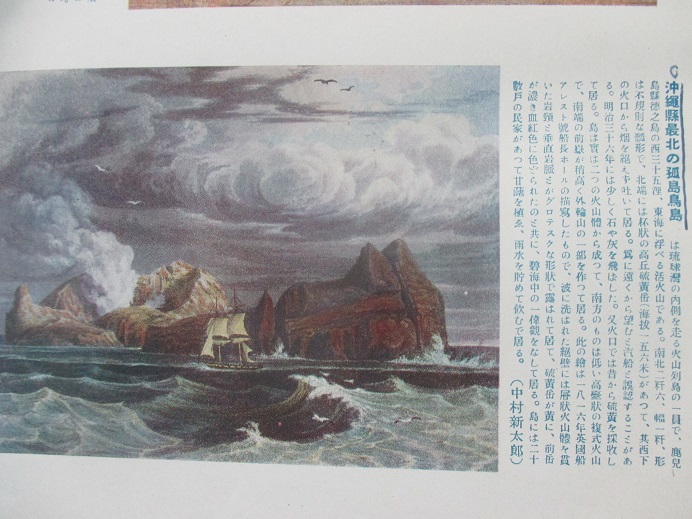
1930年8月『日本地理大系 第九巻 九州篇』改造社
1931年12月『琉球新報』伊波普猷「ナポレオンと琉球」
1932年1月 『改造』伊波普猷「ナポレオンと琉球」
1934年
1月ー沖縄県立図書館の郷土文献以外の参考品(三線、鉢巻、陶器、漆器)は昭和会館の教育参考室に移される
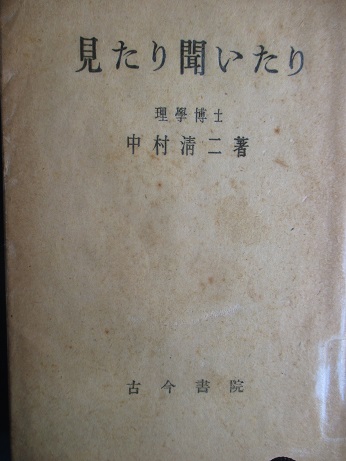
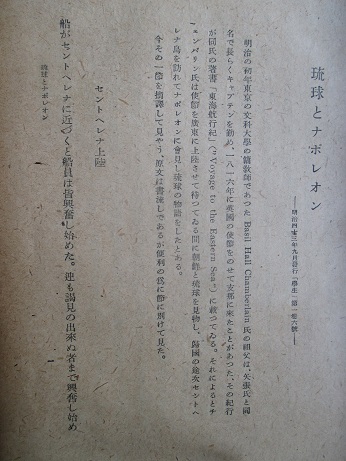
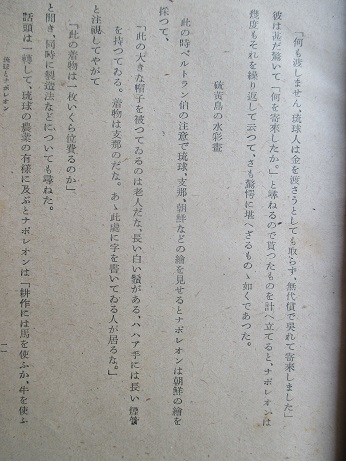
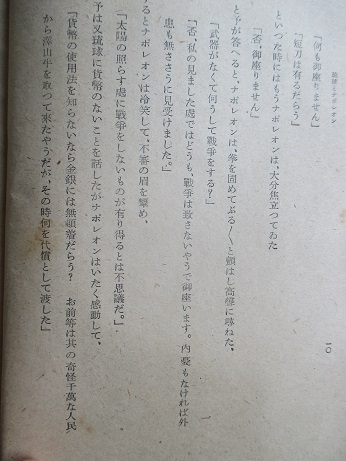
1936年3月(1948年2月 再版) 中村清二『見たり聞いたり』「琉球とナポレオン」(初出1910年9月発行『學生』冨山房)古今書院
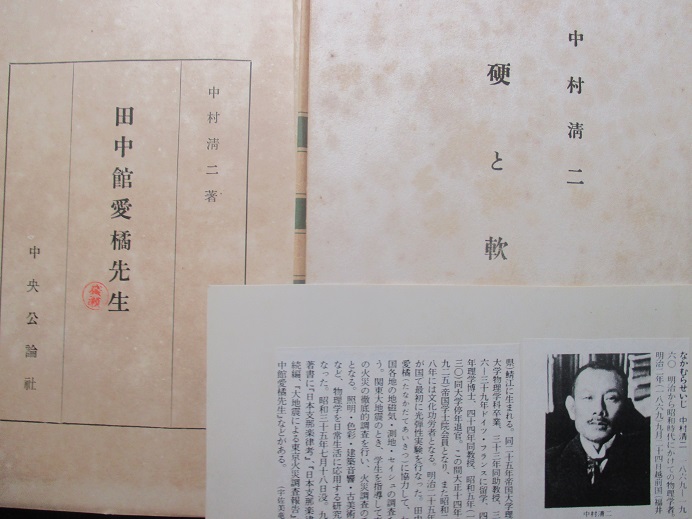
1943年4月 中村清二『田中館愛橘先生』中央公論社/1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房
1937年1月9日、神戸から那覇港に波上丸処女入港/4月、在米沖縄県人会(松田露子)『琉球 THE LOOCHOO』第4号/4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。
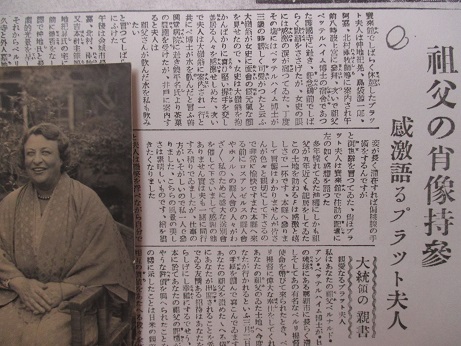
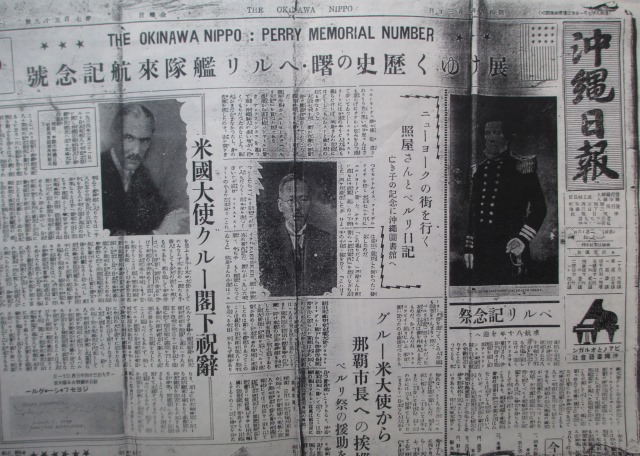

3月30日ー『沖縄日報』「展けゆく歴史の曙・ペルリ艦隊来航記念号」
沖縄日報主催「ペルリ日本来航80年記念祭」講演/神田精輝・島袋源一郎
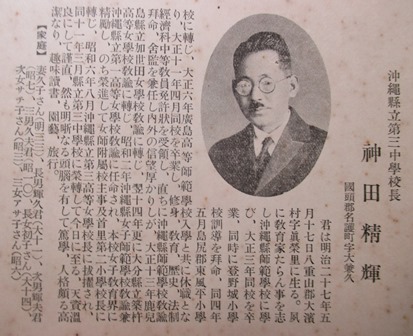
1937年9月 『沖縄県人事録』沖縄朝日新聞社
4月27日ー沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し「沖縄郷土協会」発足、太田朝敷会長
1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足
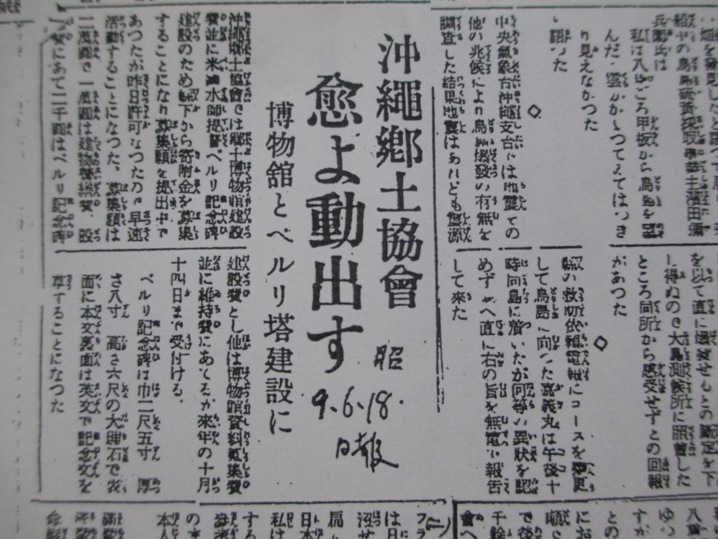
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
関連○2015年3月 『記憶と忘却のアジア』青弓社 泉水英計「黒船来航と集合的忘却ー久里浜・下田・那覇」
1938年8月から須藤利一は『沖縄教育』に「ベージル・ホール大琉球航海記」を1939年まで連載。1938年12月には台湾愛書会の『愛書』に須藤利一は「琉球の算法書」を発表。1940年1月、須藤利一は野田書房から『大琉球島探検航海記』を出した。発売所は東京は日本古書通信社代理部、那覇は沖縄書籍となっている。この本は天野文庫と比嘉文庫にあるが口絵に「バジル・ホール肖像」が付いていないが、戦後復刻本には付いている。また川平装幀も微妙に違う。
1970年4月、『沖縄ポスト』(『沖縄ジャーナル』改題)「沖縄への理解訴えー沖縄関係資料室」/5月11日、NHKラジオ「ここに生きるー沖縄文庫にかける(西平守晴さん)」
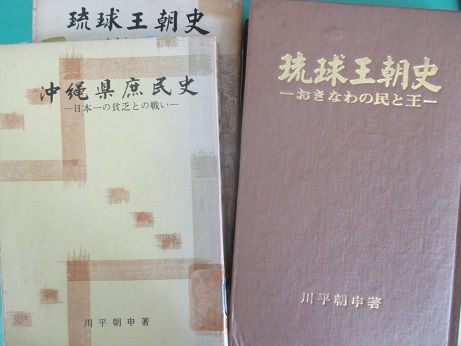
1970年7月 川平朝申『琉球王朝史』月刊沖縄社
1974年5月 川平朝申『琉球王朝史』月刊沖縄社
1974年5月 川平朝申『沖縄県庶民史』月刊沖縄社
1971年4月、『青い海』創刊
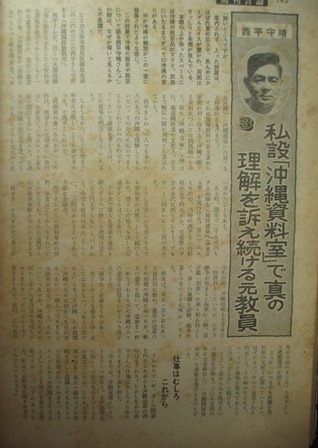
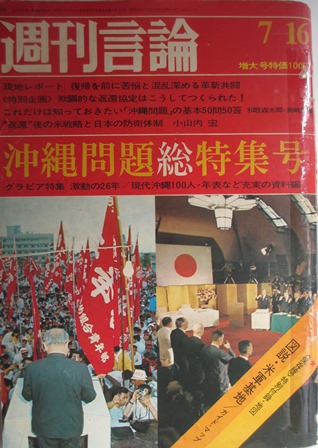
7月16日『週刊言論』「西平守晴ー私設『沖縄資料室』で真の理解を訴え続ける」
この年の前後をみると、1969年4月ー安田寿明『頭脳会社ーシステム産業のパイオニア』ダイヤモンド社、1970年9月ー野口悠紀雄『シンク・タンク』東洋経済が出ている。私も1971年9月発行の『石の声』8号に「関西沖縄青年ミニ・シンクタンク構想」を書いた。

8月11日『読売新聞』(大阪版)「大阪に沖縄ありーサラリーマン部長が沖縄関係資料室」/10月『青い海』第7号□新城栄徳「粟国島」/12月11日、関西テレビ「土曜イブニングショウ」に沖青年友の会出演
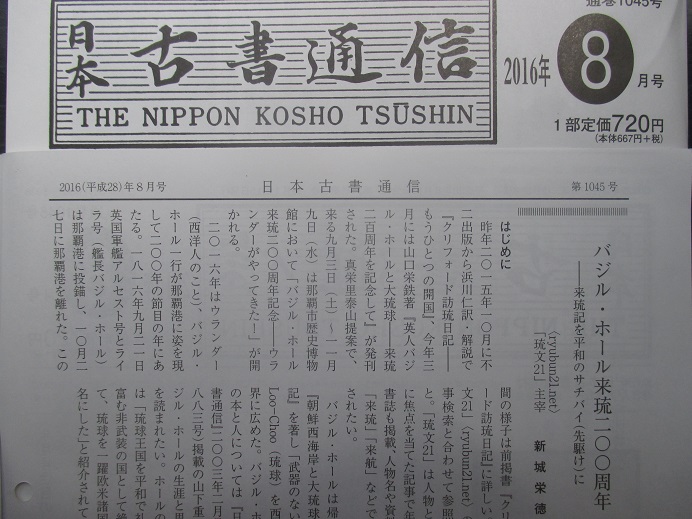
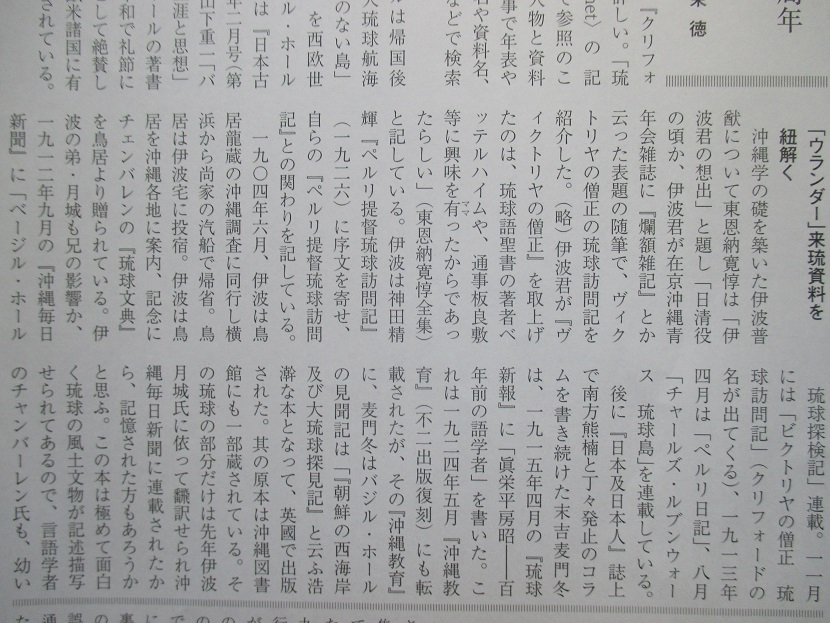
2016年8月 『日本古書通信』1045号 新城栄徳「バジル・ホール来琉200周年」
わが国に航海術や造船術を伝えた英国人ウィリアム・アダムズ(三浦按針)や、平戸のイギリス商館長を勤めた リチャード・コックスも努力した人たちである。アダムズはオランダ船リーフデ号の水先案内人として当時の豊後(大分県)に 漂着した人物である。その後、平戸のイギリス商館長リチャード・コックスの命を受け、シー・アドヴェンチャー号の船長として、 タイへ向かう途中乗組員の不穏な動きを察知して、五島に引き返しているが、その際沖縄から持ち帰った一袋のサツマイモをコックスに 送っている。時に1615年6月2日のことで、コックスはその日の日記に「大御所が大阪の城を取り、フィディア(秀頼)様の軍を 滅ぼした」報せを受けたとも記している。6月19日になって、コックスは、「庭を手に入れて、リケア(琉球)から将来された藷を そこに植え」、1年当たり10匁(英貨5シリング)を支払うと記している。すなわち、平戸に菜園を借り栽培を試みたわけである。 しかし、その後の実績は記されていない。現在平戸の川内浦の鳶の巣に「コックス甘藷畑跡」が残っており、この地域ではサツマイモを 「琉球イモ」または単にイモと呼んでいたといわれるが、そうであるとすると、何らかの実績が見られたのではないかと想像される。→鈴木俊(東京農大国際食料情報学部教授)
1796年 英船プロビデンス号虻田に来航。翌年室蘭に来航
1798年 近藤重蔵、択捉を調査。帰途ルベシベツ山道を開く
1811年 国後でロシア艦ディアナ号艦長ゴローニンが幕府の警備隊に捕らえられる
バジルホールの現在の認知度を画像検索すると「バジルホール(@ashurnasirpal2)」が出て満島ひかりちゃんが出てきた。「満島ひかり」を検索すると、女優の黒柳徹子の自伝的エッセイ『トットひとり』『トットチャンネル』を原作にしたNHKドラマ『トットてれび』で、満島ひかりが黒柳役を務めているが、映画「夏の終り」では若き日の瀬戸内寂聴を艶っぽく演じている。さらに検索すると沖縄県沖縄市出身。ユマニテ所属。弟は俳優の満島真之介、妹はモデルの満島みなみ、となっていて、初めて沖縄出身だとわかった。話が本題から逸れてしまったが、この偶然も必然として見逃してもらいたい。正確にバジル・ホールでウィキペディアを見ると「19世紀のイギリスの海軍将校、旅行家、作家。インド洋、中国、琉球、中南米各地を航海したことで知られる。ベイジル・ホールと記述されることも多い。 ナポレオン1世に『琉球では武器を用いず、貨幣を知らない』と伝えた」とある。また 「Facebook/バジル・ホール研究会」も参考になる。
1816年(文化13)7月25日、イギリス軍艦アルセスト号(艦長マレー・マクスウェル)・ライラ号(艦長バジル・ホール)、那覇に投錨/9月6日、首里王府、マクスウェル館長の国王への謁見要請を謝絶。/7日、両船、那覇を離れる。後にライラ号の乗組員だった退役軍人ハーバード・J・クリフォードが中心となり、琉球海軍伝道会を創設、ベッテルハイムを派遣することになる。→2014年2月 生田澄江『幕末、フランス艦隊の琉球来航ーその時琉球・薩摩・幕府はどう動いたかー』近代文藝社
Basil Hallは1788年12月31日、スコットランド エディンバラで生まれて、1844年9月11日ポーツマス王立ハスラー病院で死去(55歳)。
「経済学の父」ことアダム・スミス、詩人のキーツ、ウォルター・スコット、シャーロック・ホームズの生みの親コナン・ドイル、『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』の作家ロバート・ルイス・スティーヴンソン、ジェームズ・ボズウェル、トマス・カーライル、俳優のショーン・コネリー、ユアン・マクレガー、ジェラルド・バトラーなどはスコットランドの生まれである。
スコットランドは、産業革命以前より、科学・技術の中心地であったため、多くの科学者・技術者を輩出している。その発見・発明は、現代社会にはなくてはならないものが多い。電話を発明したグレアム・ベル、ペニシリンを発見したアレクサンダー・フレミング、蒸気機関を発明したジェームズ・ワット、ファックスを発明したアレクサンダー・ベイン、テレビを発明したジョン・ロジー・ベアード、空気入りタイヤを発明したジョン・ボイド・ダンロップ、道路のアスファルト舗装(マカダム舗装)を発明したジョン・ロウドン・マカダム、消毒による無菌手術を開発したジョゼフ・リスターなどはスコットランドの生まれである。
羊の内臓を羊の胃袋に詰めて茹でたハギスが有名。また、スコッチ・ウイスキーは定義上スコットランド産でなければならない。スコットランドには、100以上もの蒸留所があり、世界的にも愛好家が多い。
コリン・ジョイス(『驚きの英国史』NHK出版新書 2012年pp.79-83)ではイギリス人の生活を皮肉って次の物がすべてスコットランド人によるものだとしている。マーマレード、レインコート、自転車、タイヤ、乾留液(タールマック舗装)、蒸気エンジン、イングランド銀行、糊つき切手、タバコ、電話、ローストビーフ、アメリカ海軍、麻酔薬などである。『聖書』にもスコットランド人が最初に出てくるが、これはジェームズ6世が英訳を進めたからである。→ウィキ
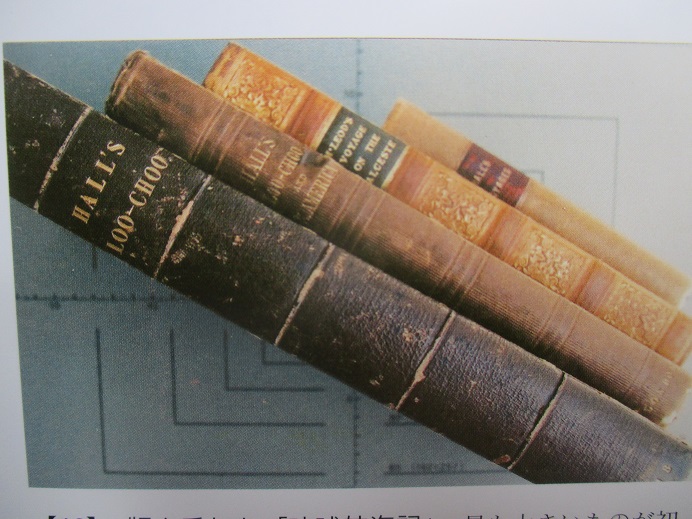
『バジル・ホール琉球航海記』最も大きいのが初版(1818年)
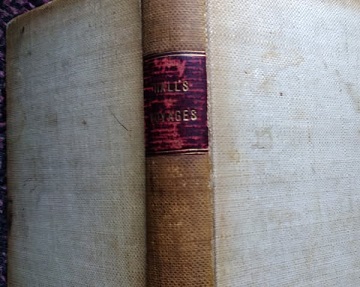
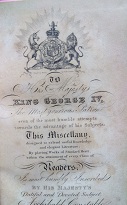
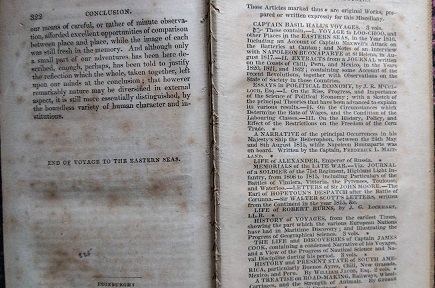
3版(1826年)
2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
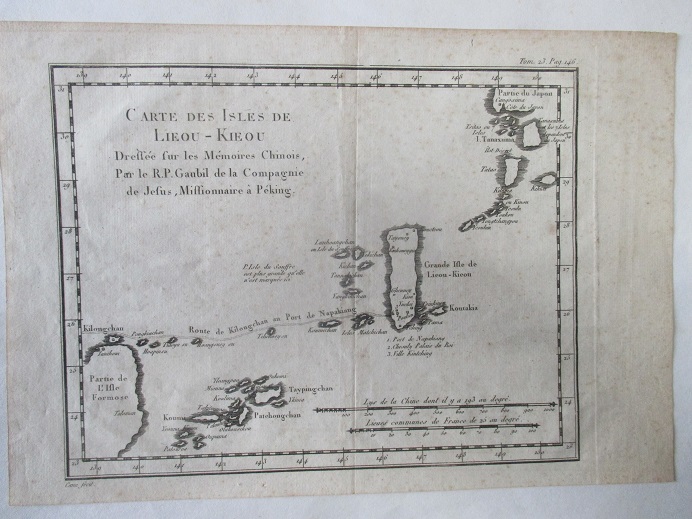
那覇市歴史博物館で「バジル・ホール来琉200周年記念/ウランダーがやってきた!」の図録を見せてもらった。上の地図に書き込みがある地図も掲載されていた。担当の鈴木学芸員がネット「ヨーロピアナ」①で収集したフランス国立図書館蔵のものだ。(2016ー8ー4)
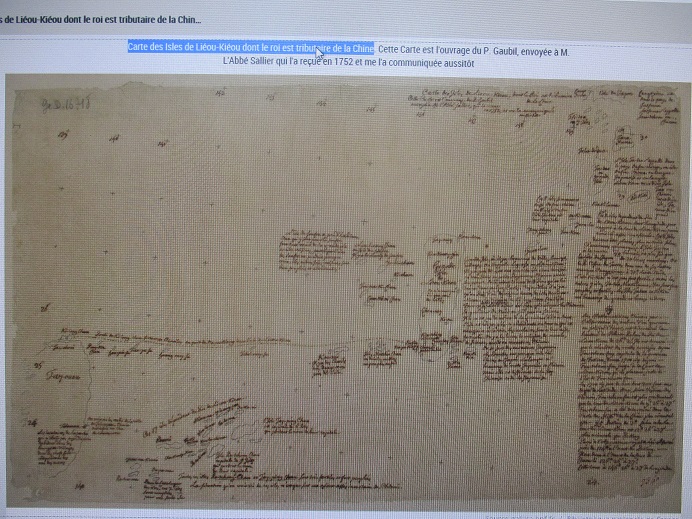
①欧州委員会は、EU加盟国の図書館や博物館が所蔵する書籍、文献、映像、絵画などを検索・閲覧できる「ヨーロピアナ」という電子図書館を開設した。インターネットを通じて、400万件以上のデータに無料でアクセスすることができる。ヨーロピアナは、2008年11月20日に公式オープン。ところが、初日の1時間で1000万件を超えるアクセスがあり、サーバーが停止してしまった。モナリザの絵やベートーベンの楽譜といった有名なアイテムも閲覧することができ、大変な人気となったためだ。オープン早々「一時休館」となったヨーロピアナは、その後、コンピューターの処理能力を上げて、12月24日に再オープンした。ヨーロピアナは、EU加盟国の公用語である23言語で利用可能であり、欧州市民の誰もが身近に利用できるよう配慮されている。もちろん、日本からもアクセスできる。欧州の図書館や博物館が所有する日本関連のアイテムも閲覧することできる。
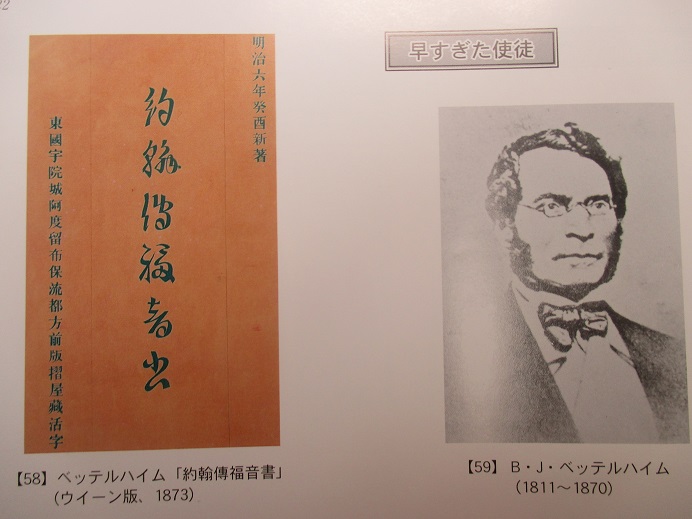
「ベッテルハイム」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
1844年4月28日 フランス人ジャン・バチスト・セーシユ提督率いる5隻の東洋艦隊麾下のフォルニェル・デュプラン大佐の軍艦アルクメーヌ号を琉球へ分遣。宣教師テオドール・オーギュスト・フォルカードと清国人伝道師オーギュスタン・高を那覇に残して5月6日に出帆。→2014年2月 生田澄江『幕末、フランス艦隊の琉球来航ーその時琉球・薩摩・幕府はどう動いたかー』近代文藝社
1853年6月ーペルリ、首里城訪問□→1926年10月ー神田精輝『ペルリ提督琉球訪問記』/1935年3月ー土屋喬雄『ペルリ提督日本遠征記』弘文荘(沖縄県立図書館所蔵本は国吉真哲寄贈)/1947年2月ー大羽綾子『ペルリ提督遠征記』酣燈社/1962年6月ー外間政章『対訳ペリー提督沖縄訪問記』研究社/1985年10月ー金井圓『ペリー日本遠征日記』雄松堂/1994年4月ー大江志乃夫『ペリー艦隊大航海記』立風書房
1856年、チェンバレンは母親エライザ・ジェインの死によって母方の祖母とともにヴェルサイユに移住した。それ以前から英語とフランス語の両方で教育を受けていた。またフランスではドイツ語も学んだ。帰国し、オックスフォード大学への進学を望んだがかなわず、チェンバレンはベアリングス銀行へ就職した。彼はここでの仕事に慣れずノイローゼとなり、その治療のためイギリスから特に目的地なく出航した。1873年5月29日にお雇い外国人として来日したチェンバレンは、翌1874年から1882年まで東京の海軍兵学寮(後の海軍兵学校)で英語を教えた。1882年には古事記を完訳している(以下略)。前出の『チェンバレンの交友』には「日本を広く世界に紹介した人というと、ハーンをあげるものが多い。少し前ならシーボルト。ところが西洋ではシーボルトの次はチェンバレンである。」とし、友人としてサトウ公使、アストン、小泉八雲、門弟の和田万吉、岡倉由三郎(註)らとの交友を紹介している。
岡倉由三郎 生年慶応4年2月22日(1868年) 没年昭和11(1936)年10月31日 英語学者。天心の弟
出生地神奈川・横浜 学歴〔年〕東京帝大文科選科
経歴東大選科でチェンバレンに言語学を学ぶ。東京府立一中教諭、七高教授を経て明治29年嘉納治五郎校長の招きで東京高師教授。新村出らと「言語学雑誌」を発刊、35年から独、英に留学。大正15年に東京高師を退官するまで英語科の主任を務めた。その後、立教大学に奉職。開始当時のNHKラジオの英語講座では巧みな話し方で人気を集め、外国語教育、基礎英語の普及に大きな功績を残した。ヘボン式ローマ字の採用を主張したほか、昭和8年出版された「新英和大辞典」は岡倉辞典といわれ、一般に広く用いられた。→コトバンク
岡倉天心の長男の岡倉一雄は朝日新聞記者で、岡倉覚三の伝記をまとめた。孫(一雄の子)の岡倉古志郎は非同盟運動にも関わった国際政治学者、曾孫(古志郎の子)長男の岡倉徹志は中東研究者、玄孫(徹志の子)長男の岡倉禎志は写真家、玄孫(徹志の子)次男の岡倉宏志は人材開発コンサルタント、西洋史学者の岡倉登志は天心の曾孫にあたる。→ウィキペディア/ラングドン・ウォーナー(一八八一〜一九五五)は、ハーバード大学で考古学を専攻。卒業後、五浦で岡倉天心の薫陶を受け日本美術を研究。
1909年11月、アメリカ人・ウォーナー来沖。

1991年5月30日『琉球新報』松島弘明「文化ノート/ウォーナー資料を追え」
1996年5月17日『沖縄タイムス』「ワーナー資料沖縄の民芸品 米博物館が保存」
ラングドン・ウォーナー(Langdon Warner、1881年8月1日 - 1955年6月9日)は、アメリカの美術史家。ランドン・ウォーナーとも表記される。太平洋戦争中に日本の文化財を空襲の対象から外すよう進言した人物とされるが異論も多い。マサチューセッツ州エセックス生まれ。1903年ハーバード大学卒業。卒業後ボストン美術館で岡倉天心の助手を務め、1907年に同美術館の研修候補生として日本に派遣された。1910年にロンドンで開催される日本古代美術展の準備をしていた岡倉らを手伝い、3冊の詳細な出品カタログ『日本の寺とその宝物』の英訳に協力した。帰国後東洋美術史を講義、ハーバード大学付属フォッグ美術館東洋部長を務めるなど、東洋美術の研究をした。1946年、米軍司令部の古美術管理の顧問として来日。朝河貫一とは親交が深く、数々の書簡を交わしたりウォーナーの著書に朝河が序文を寄せたりした。→ウィキペディア○日本各地にはウォナー記念碑が6か所もある。最初の法隆寺の碑から、最後はJR鎌倉駅前の碑。
1910(明治43)年9月15日、冨山房発行『學生』第一巻第六号 中村清二「琉球とナポレオン」
中村清二(女優の中村メイコは兄の孫にあたる)「チェンバレン氏は英国の使節を廣東に上陸させて待っている間に朝鮮と琉球を見物し、帰国の途次セントヘレナ島を訪れてナポレオンに会見し琉球の物語をしたとある。」と記している。
1912年 バージル・ホール・チェンバレン「ある新しい宗教の発明」(神道の資源を引き継ぎながら新たに作り上げられた天皇崇拝のシステム)→タカシ・フジタニ『天皇のページェントー近代日本の歴史民族誌から』(1994年 日本放送出版協会)/2016年10月『春秋』島薗進「明治天皇崩御と国家神道」
1925年12月 沖縄県海外協会『南鵬』創刊号 真境名安興「ベージル・ホール、渡来に関する琉球側の記録」
1926年6月 武藤長平『西南文運史論』岡書院
○内藤虎次郎「西南文運史論序」/新村出「小序」
○末吉安恭、東風平東助二君の好意で古き『沖縄集』一冊(写本)と新しき『沖縄集』二冊(宜湾朝保輯板本)とを一覧した。
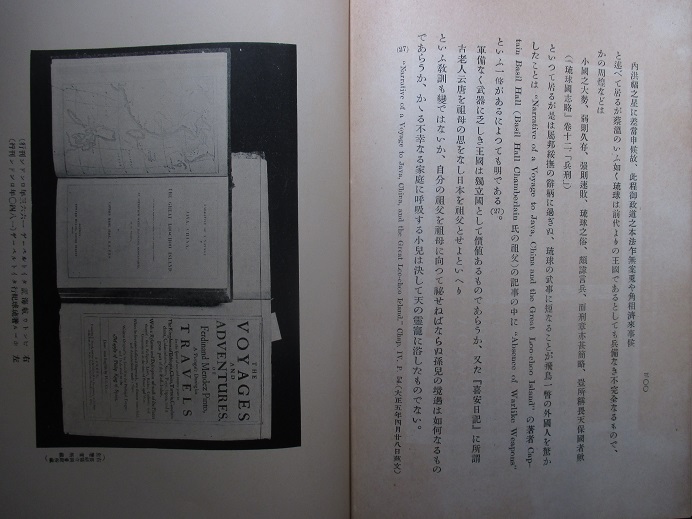
右 ピントウ航海記 1663年ロンドン刊行 ホール著琉球紀行 1840年ロンドン刊行
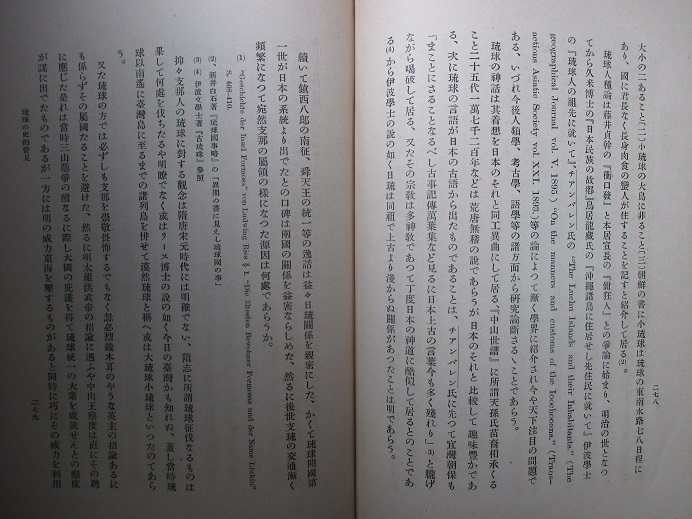
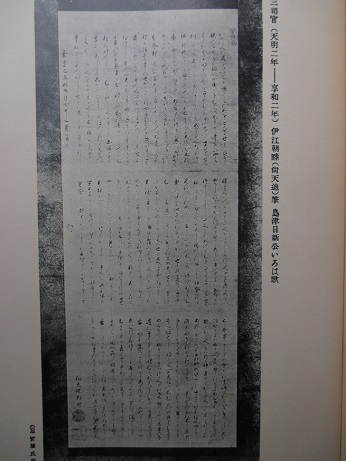
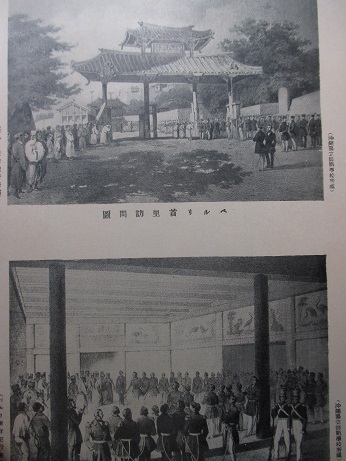
伊江朝睦筆「島津日新公いろは歌」(????宮城氏所蔵)
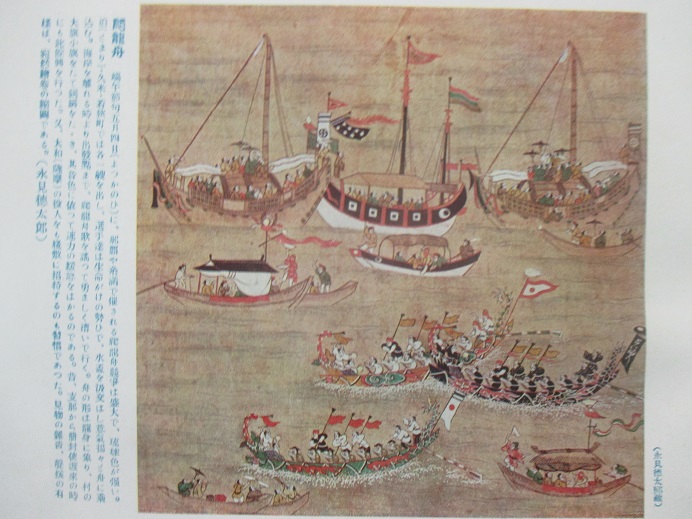
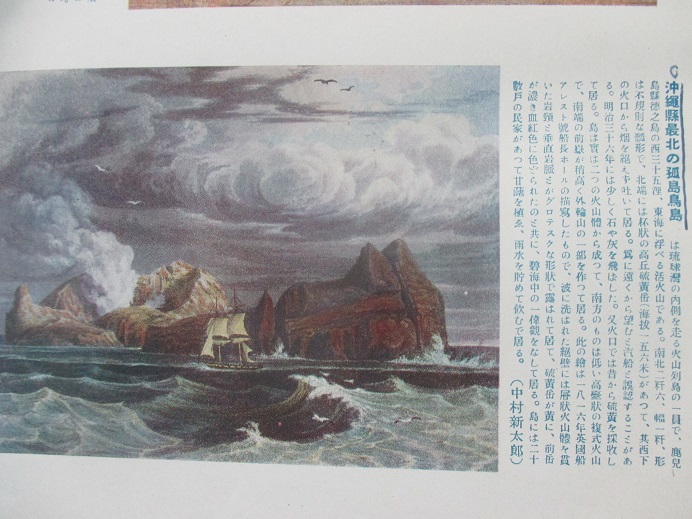
1930年8月『日本地理大系 第九巻 九州篇』改造社
1931年12月『琉球新報』伊波普猷「ナポレオンと琉球」
1932年1月 『改造』伊波普猷「ナポレオンと琉球」
1934年
1月ー沖縄県立図書館の郷土文献以外の参考品(三線、鉢巻、陶器、漆器)は昭和会館の教育参考室に移される
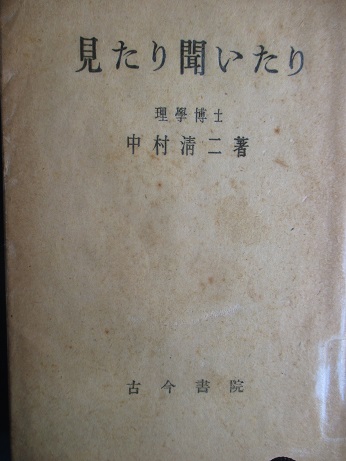
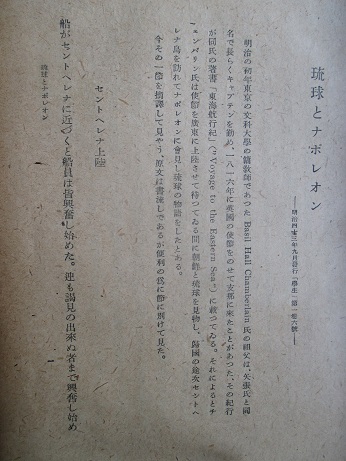
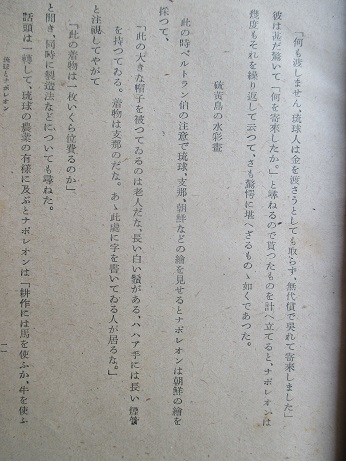
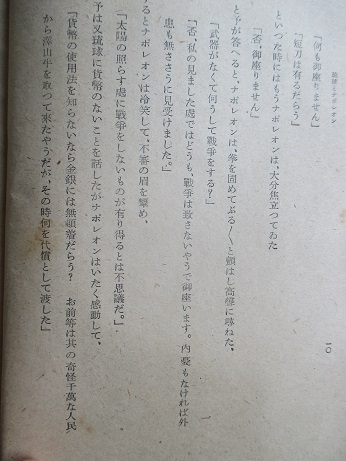
1936年3月(1948年2月 再版) 中村清二『見たり聞いたり』「琉球とナポレオン」(初出1910年9月発行『學生』冨山房)古今書院
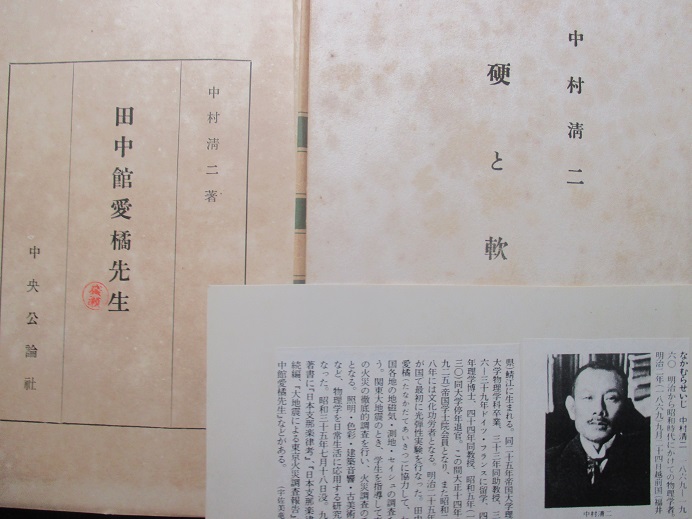
1943年4月 中村清二『田中館愛橘先生』中央公論社/1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房
1937年1月9日、神戸から那覇港に波上丸処女入港/4月、在米沖縄県人会(松田露子)『琉球 THE LOOCHOO』第4号/4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。
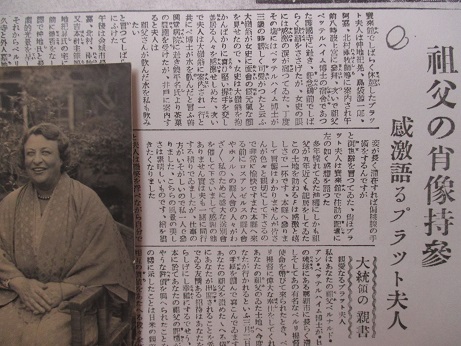
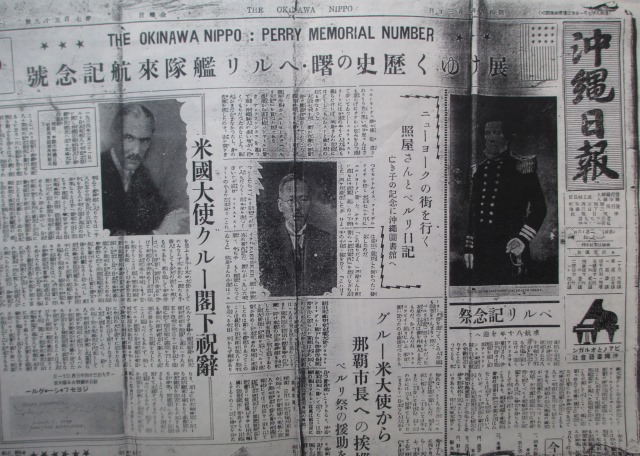

3月30日ー『沖縄日報』「展けゆく歴史の曙・ペルリ艦隊来航記念号」
沖縄日報主催「ペルリ日本来航80年記念祭」講演/神田精輝・島袋源一郎
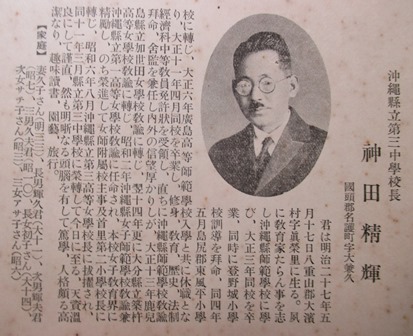
1937年9月 『沖縄県人事録』沖縄朝日新聞社
4月27日ー沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し「沖縄郷土協会」発足、太田朝敷会長
1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足
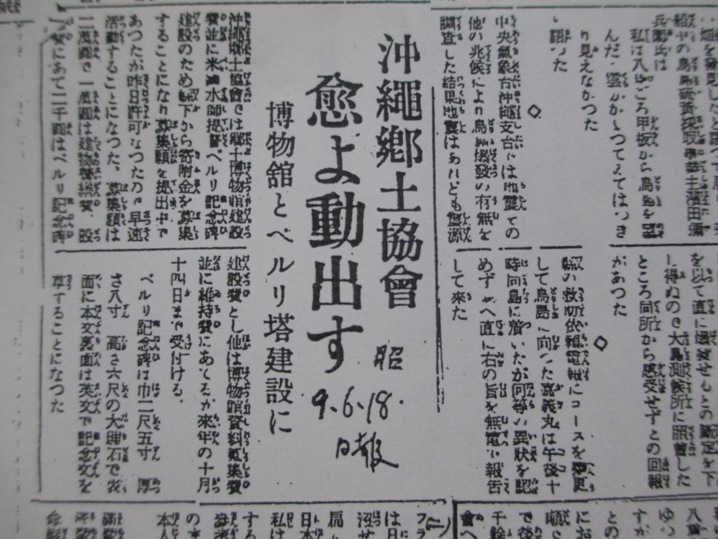
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
関連○2015年3月 『記憶と忘却のアジア』青弓社 泉水英計「黒船来航と集合的忘却ー久里浜・下田・那覇」
1938年8月から須藤利一は『沖縄教育』に「ベージル・ホール大琉球航海記」を1939年まで連載。1938年12月には台湾愛書会の『愛書』に須藤利一は「琉球の算法書」を発表。1940年1月、須藤利一は野田書房から『大琉球島探検航海記』を出した。発売所は東京は日本古書通信社代理部、那覇は沖縄書籍となっている。この本は天野文庫と比嘉文庫にあるが口絵に「バジル・ホール肖像」が付いていないが、戦後復刻本には付いている。また川平装幀も微妙に違う。
1970年4月、『沖縄ポスト』(『沖縄ジャーナル』改題)「沖縄への理解訴えー沖縄関係資料室」/5月11日、NHKラジオ「ここに生きるー沖縄文庫にかける(西平守晴さん)」
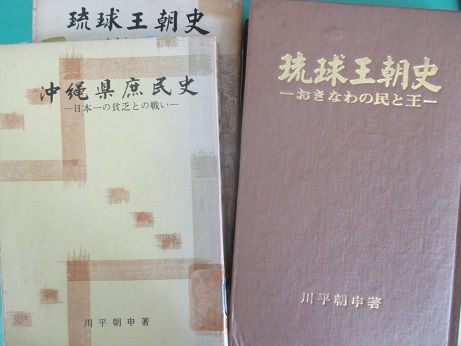
1970年7月 川平朝申『琉球王朝史』月刊沖縄社
1974年5月 川平朝申『琉球王朝史』月刊沖縄社
1974年5月 川平朝申『沖縄県庶民史』月刊沖縄社
1971年4月、『青い海』創刊
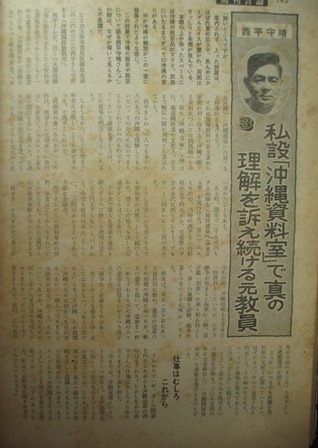
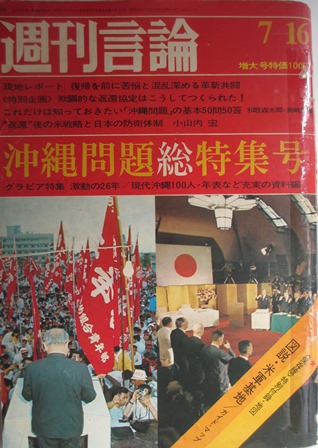
7月16日『週刊言論』「西平守晴ー私設『沖縄資料室』で真の理解を訴え続ける」
この年の前後をみると、1969年4月ー安田寿明『頭脳会社ーシステム産業のパイオニア』ダイヤモンド社、1970年9月ー野口悠紀雄『シンク・タンク』東洋経済が出ている。私も1971年9月発行の『石の声』8号に「関西沖縄青年ミニ・シンクタンク構想」を書いた。

8月11日『読売新聞』(大阪版)「大阪に沖縄ありーサラリーマン部長が沖縄関係資料室」/10月『青い海』第7号□新城栄徳「粟国島」/12月11日、関西テレビ「土曜イブニングショウ」に沖青年友の会出演
01/04: 阿氏門中
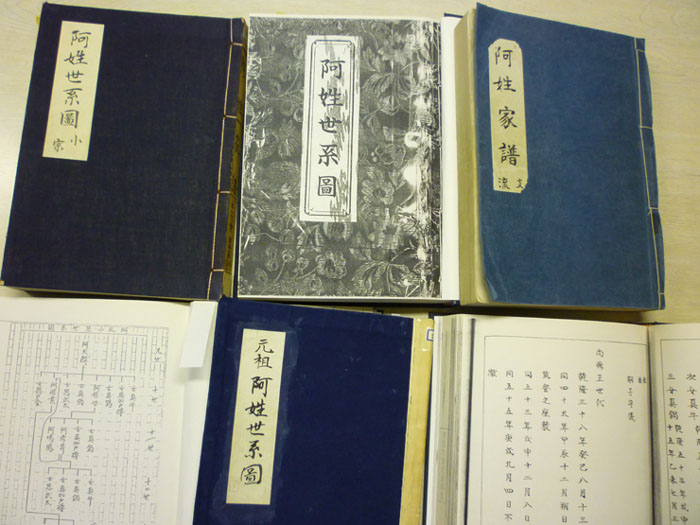
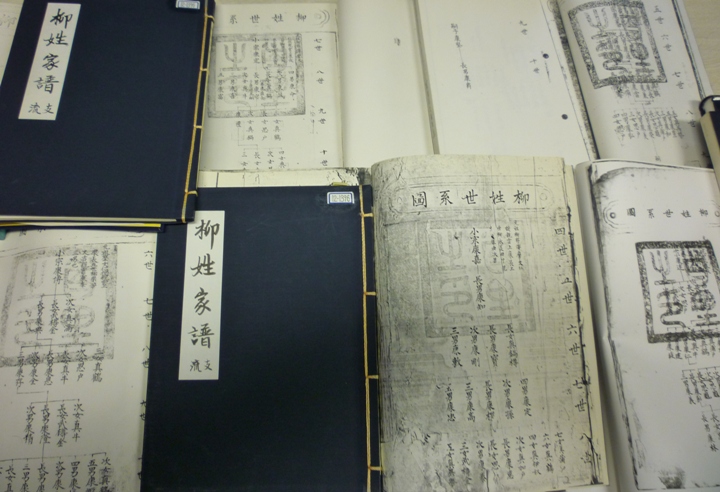
元祖の守忠は、南山王汪応祖の二男で、尚巴志に滅ぼされた他魯毎王の弟。南山城が攻撃されたとき城から脱出して具志頭間切の安里大親に助けられ、のちに大親の嗣子になったことが家譜にある。二世守知(守忠の長男)は首里に上り、偶然に世子尚真の養父を命ぜられる。長女真嘉戸樽は知念間切謝氏知名親雲上成良に嫁した。その女子がのちに尚真王夫人となった華后。三世守庸(守知の二男)。四世守良(守庸の長男)は柳姓元祖・摩文仁掟親雲上康長の父。下の「王位継承」陰謀には南山王統系阿氏一門が関わっているのは間違いない。→「柳姓・真喜志」
大阪・沖縄関係資料室で『阿姓家譜』(阿姓南風原按司守忠 7世西平親雲上守安4男)の原本を見たことがある。元祖の守忠は、南山王汪応祖の二男で、尚巴志に滅ぼされた他魯毎王の弟。南山城が攻撃されたとき城から脱出して具志頭間切の安里大親に助けられ、のちに大親の嗣子になったことが家譜にある。二世守知(守忠の長男)は首里に上り、偶然に世子尚真の養父を命ぜられる。長女真嘉戸樽は知念間切謝氏知名親雲上成良に嫁した。その女子がのちに尚真王夫人となった華后。
三世守庸(守知の二男)。四世守良(守庸の長男)は柳姓元祖・摩文仁掟親雲上康長の父、複製本が那覇市歴史博物館にある。『氏集』を見ると、阿氏には前川、渡名喜、西平、小濱、渡嘉敷、宮平、瀬良垣、伊舎堂、與儀、喜瀬、山元、安和、佐久田、眞謝、江田、金城、照屋の諸家がある。
名古屋の渡久地政司(とぐち まさしー1937(昭和12)年6月2日、大阪市で生れる。豊田市で育つ。73歳、第3の人生のスタート。体と思考を「解す」だけでなく鍛える。)氏のブログに氏の調査で「太田守松 父渡名喜守重、母なべの長男として沖縄県那覇市東町1丁目20番地で明治35年(1902)生まれる。泉崎小学校、沖縄1中卒、神戸高等商業学校卒。滋賀県立彦根商業学校教諭(大正14年4月)。昭和3年短歌会『国民文学』に入社・植松寿樹に師事。以後、短歌運動。昭和22年3月、日本キリスト教団彦根教会で洗礼。1947年(昭和22年10月)、渡名喜姓を先祖が使用していた太田姓に改名。昭和23年、彦根市立西中学校校長。昭和27年、彦根YWCA創立理事長。昭和34年、井伊大老開国百年祭奉賛会事務局次長。昭和38年、原水爆禁止彦根市協議会会長。昭和45年1月、脳溢血で逝去(67)。
○ 太田菊子 父豊見山安健、母オト(1882年生まれ)の長女として 1905年(明治38)沖縄県那覇市で生まれる。沖縄県立第1高等女学校卒業1921年(大正10)、東京山脇高等女学校卒業1924年(大正13)。大正14年12月、渡名喜守松と結婚。平成5年(1993)逝去(88)・1962年(昭和37年2月)。長年同居の母オト逝去(80歳)。」と太田守松と夫人が紹介されている。守松氏も阿氏である。
2012年の12月発行の『週刊新潮』に岸朝子さんが「私は来年で90歳。祖先のルーツを探ってみたくなりました。大宜味尋常小学校校長で教育者だった私の母方の祖父、親泊朝擢は琉球王国第二尚氏3代尚真王の長男・尚維衡(浦添王子朝満)の後裔にあたります。」と情報を提供してほしいと書いている。与並岳生氏は『新 琉球王統史⑦尚寧王』などに、「おそらく、尚維衡の”追放”が、明らかに誤りであったことが、”陰謀”によって生まれた尚清王系尚永王の死去、そして嗣子がなかったことにより、公然と主張され、この機会にその”復権”をはかり、かつ正統に戻そうと至った」と書いている。続けて「つまり、尚元王の妃(尚永王の母)真和志聞得大君加那志(号・梅岳)は、尚維衡の長男、尚弘業(広徳寺浦添親方ともいった)の娘であり、尚弘業の息子尚懿の妻は尚元王の長女・首里大君加那志(尚永王の姉で、真和志聞得大君加那志の子)で、つまりいとこ同士で結婚したわけであり、その子が尚寧です。」と記す。

2023-3 ライブハウスの一角に「あいち沖縄文庫」誕生 800冊、渡久地政司さん、阪井芳貴さんらが寄贈
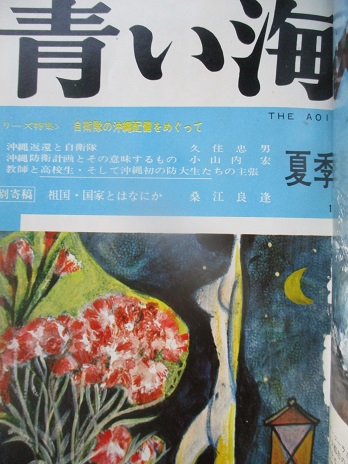
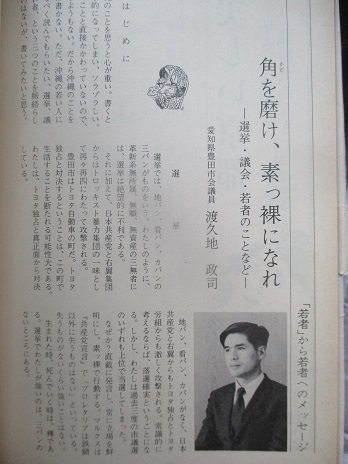
1971年8月 雑誌『青い海』4号 渡久地政司「角を磨け、素っ裸になれー選挙・議会・若者のことなどー」
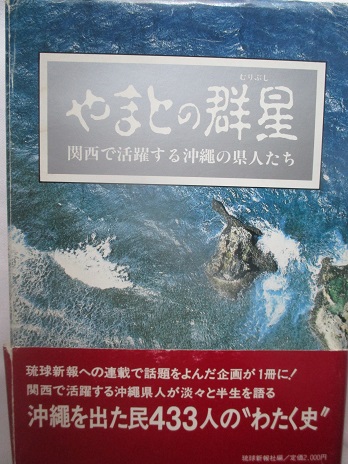
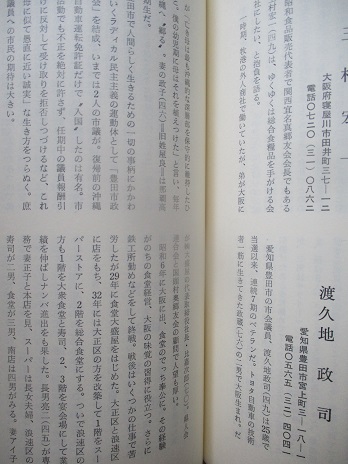
1987年8月 『やまとの群星/関西で活躍する沖縄の県人たち』琉球新報社 「渡久地政司」→本書は元『青い海』編集発行人で作家の津野創一が編集協力した。
愛知の中の沖縄 事柄覚 渡久地政司作成


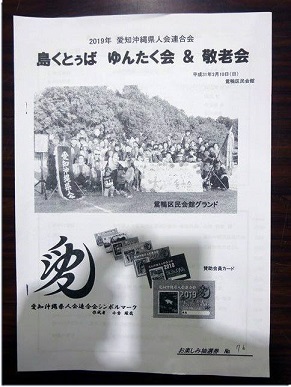

愛知沖縄県人会連合会総会・ゆんたく会・敬老会■ 2019年3月10日 豊田市鴛鴨町・鴛鴨公民館
最長老の屋嘉比信子さん(95)と比嘉俊太郎さん(80)屋嘉比さんは名古屋市今池で沖縄料理「糸満」を30~50年前に経営されていた方です。比嘉さんは、那覇高→名古屋工業大学→愛知工業大学名誉教授→愛知沖縄県人会連合会会長をなさった方です。お二人ともお元気でした。
1986年3月、琉球新報の松島弘明記者から、名古屋、三重のウチナーンチュの取材で大阪に来るという葉書(中城城跡)をもらった。後に琉球新報大阪支社に行き、私も旧知の人たちに会いたく名古屋に同行した。名古屋の県事務所の職員は大阪の県事務所でなじみのある人たちばかりであったので名古屋、三重のウチナーンチュ情報はすぐに得られた。
松島記者は取材過程で、「愛知県沖縄県人会会員名簿」「でいごの会会員名簿」(1974年10月)、「三重県沖縄県人会名簿」(1974年)、「沖縄県名古屋経営者会名簿」(1985年)などを入手した。麦門冬・末吉安恭の甥の佐渡山安正、佐渡山安治さん兄弟、粟国の末吉和一郎さんの取材には同行した。大濱皓氏は病気で会えなかった。
2010年1月31日、沖縄文化の杜で仲村顕さんから愛知の沖縄の話を聞いた。豊橋市に田島利三郎、犬山市には久志富佐子の墓があるという(後日、墓の写真も見た)。
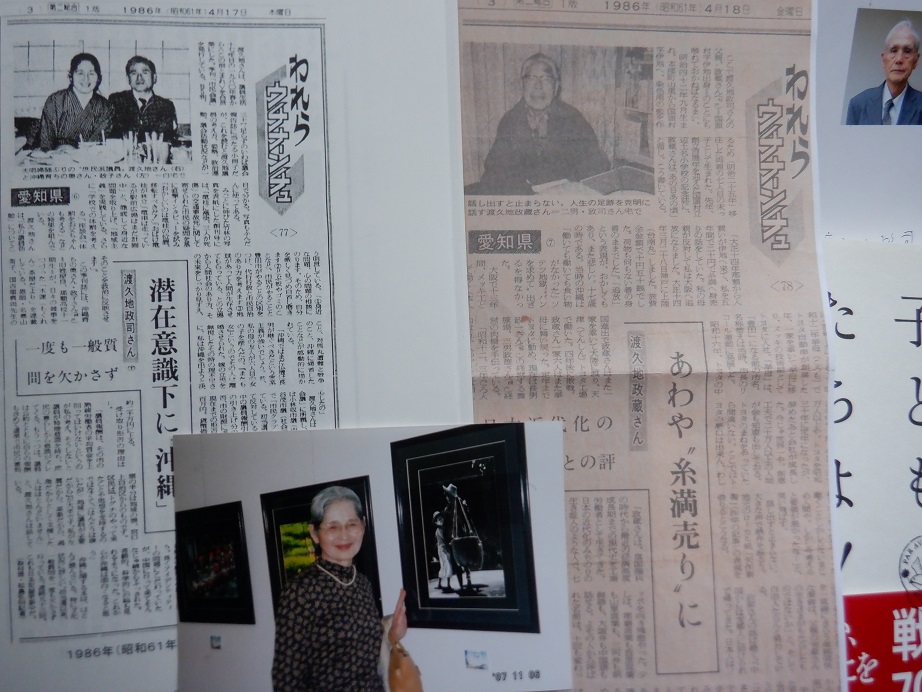
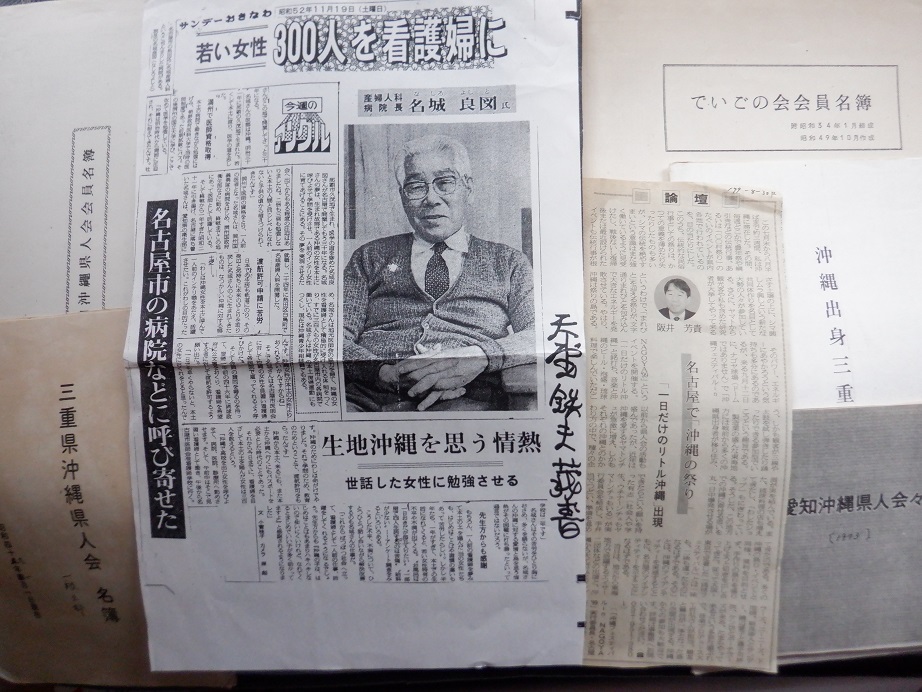
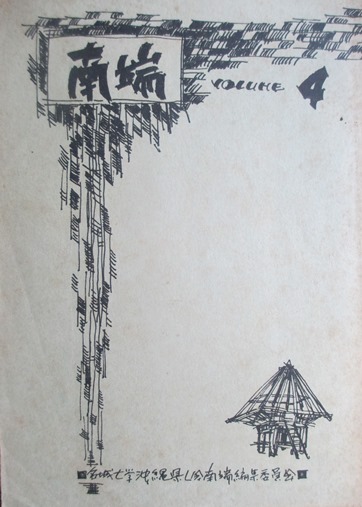
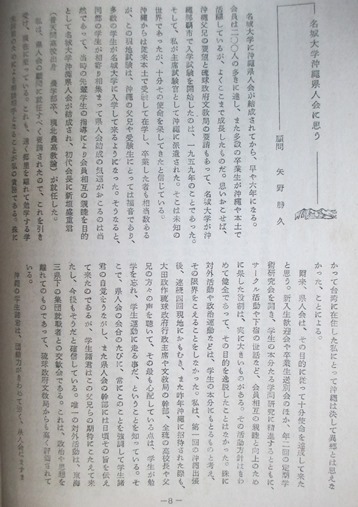
1965年7月 名城大学沖縄県人会『南端』(責任者・糸数哲夫)
糸数哲夫
昭和36年ー那覇高校卒。昭和44年ー名城大学大学院法学研究科修、商学修士、法学修士。昭和44年ー名古屋在加茂会事務所入所。昭和50年ー那覇市にて税理士事務所開業→現在は沖縄県宜野湾市字我如古。
大阪・沖縄関係資料室で『阿姓家譜』(阿姓南風原按司守忠 7世西平親雲上守安4男)の原本を見たことがある。資料室主宰の西平守晴氏が実兄から譲られたものである。複製本が那覇市歴史博物館にある。『氏集』を見ると、阿氏には前川、渡名喜、西平、小濱、渡嘉敷、宮平、瀬良垣、伊舎堂、與儀、喜瀬、山元、安和、佐久田、眞謝、江田、金城、照屋の諸家がある。
名古屋の渡久地政司(とぐち まさしー1937(昭和12)年6月2日、大阪市で生れる。豊田市で育つ。73歳、第3の人生のスタート。体と思考を「解す」だけでなく鍛える。)氏のブログに氏の調査で「○ 太田守松 父渡名喜守重、母なべの長男として沖縄県那覇市東町1丁目20番地で明治35年(1902)生まれる。泉崎小学校、沖縄1中卒、神戸高等商業学校卒。滋賀県立彦根商業学校教諭(大正14年4月)。昭和3年短歌会『国民文学』に入社・植松寿樹に師事。以後、短歌運動。昭和22年3月、日本キリスト教団彦根教会で洗礼。1947年(昭和22年10月)、渡名喜姓を先祖が使用していた太田姓に改名。昭和23年、彦根市立西中学校校長。昭和27年、彦根YWCA創立理事長。昭和34年、井伊大老開国百年祭奉賛会事務局次長。昭和38年、原水爆禁止彦根市協議会会長。昭和45年1月、脳溢血で逝去(67)。
○ 太田菊子 父豊見山安健、母オト(1882年生まれ)の長女として 1905年(明治38)沖縄県那覇市で生まれる。沖縄県立第1高等女学校卒業1921年(大正10)、東京山脇高等女学校卒業1924年(大正13)。大正14年12月、渡名喜守松と結婚。平成5年(1993)逝去(88)・1962年(昭和37年2月)。長年同居の母オト逝去(80歳)。」と太田守松と夫人が紹介されている。守松氏も阿氏である。


2019年3月5日 寒緋桜 満開■沖縄・名護市の農事試験場をルーツにする寒緋桜が満開となりました。場所は宮上公園東側とその後方。3月5日、青空をもピンクにしかねないくらいの勢い、通行中の人々は「まぁ奇麗」の歓声をあげていました。
「渡久地政司ブログ」(略記)2005年7月28日
■ 愛知の中の沖縄 事柄覚 ■
● 名古屋市東区徳川町にある徳川美術館には、琉球王国の文化財が多く収蔵されている。…徳川美術館に20点の琉球楽器、むかし御座楽(うざがく)に使われた楽器が保存
…、寛政8(1796)年に江戸上がりの使者から贈られたという記録が残って…出自がはっきりしているのは、日本中で徳川美術館の楽器だけ…。
大野道雄「徳川美術館の琉球楽器」から抜粋。
● 琉球王国賀慶使・恩謝使(琉球国使江戸上がり)が1610年から1872年までの間、18回おこなわれている。上がり、下がりを入れると約34回、愛知の土地を通過している。
1610(慶長15)年の場合、上がり…8月2日美濃大垣泊、3日尾張清州・成興寺泊、5日岡崎泊、6日吉田(豊橋)泊。下り…9月22日木曽福島泊、24日美濃路落合泊、27日岐阜本誓寺泊…であった。
佐渡山安治(詳細は後記)の調査によれば、寛延(1749)年の江戸上がりの時に殉死した「麻氏渡嘉敷親雲上真厳玄性居士之墓」(古塚達朗「江戸上りの足跡」96-4-2沖縄タイムスでは墓は行方不明とある。しかし、佐渡山安治資料「寛延2年の墓碑」76-3-28沖縄タイムスでは、所在地を発見、と写真入りの記事がある。)と天保3(1832)年に殉死した富山親雲上の墳墓が名古屋市緑区鳴海の瑞泉寺にある。佐渡山安治資料昭和54-12-14沖縄タイムスには、…11月4日、26年ぶりで待望の琉球行列を名古屋に迎える段になって「琉球人通行朝7ツ(午前4時)より本町通京町其外通りに提灯をだし賑合、此日薩摩五ツ過(午前8時)頃御通行、琉球人の行列に先立って、稲葉宿から棺桶が一つ、ひっそりと運ばれて…」。
● 明治26(1893)年9月1日から10日ま で名古屋市で沖縄芝居の興行が行われている。御園座の近くにあった千歳座(広小路南桑名町)。出し物は女花笠踊、上りの口説、下りの口説、女団扇踊、国頭(クンジャン)さばくいなど…、全部ウチナーグチで演じ、客の入りはよくなかったようで、入場料の値引きをしている。明治30(1897)年6月13日、再び名古屋を訪れ、南伏見町の音羽座で公演している。 大野道雄資料から抜粋。
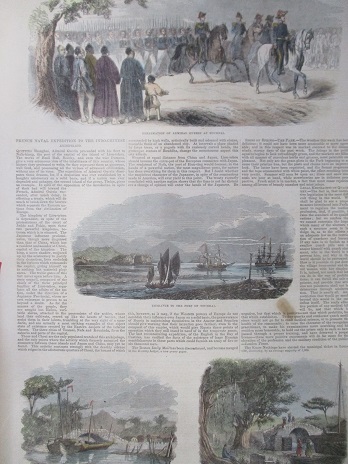
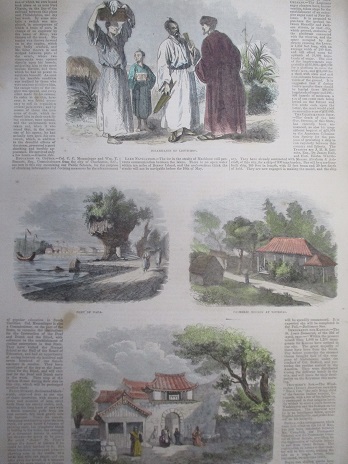
1856年 琉球を紹介した(翁長良明コレクション)『フランク・レスリー ILLUSTRATED NEWSPAPER』
1884年2月6日、大阪中之島の自由亭で尚典新婚帰郷の饗応に岩村通俊、西村捨三、建野郷三らが参加した。3月12日に大阪西区立売堀に鹿児島沖縄産糖売捌所が設立された。5月12日には大阪北区富島町で大阪商船会社が開業。8月、尚泰侯爵、西村捨三と同行し大有丸で那覇港に着く。→1996年6月『大阪春秋』堀田暁生「自由亭ホテルの創業ー大阪最初のホテルー」
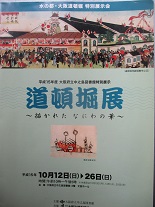
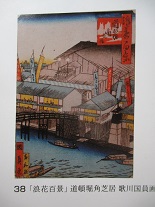
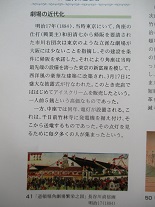
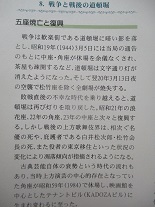
2003年10月 大阪府立中之島図書館「道頓堀展」
1889年11月ー松山傳十郎(1866年10月~1935年2月7日)『琉球浄瑠璃』いろは家→「松山傳十郎」
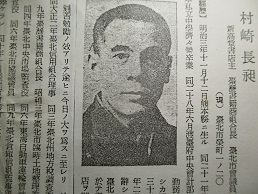

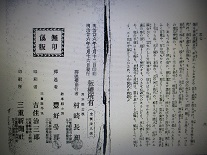
1893年7月 村崎長昶(私立済々中学卒業後沖縄に渡り、沖縄芝居に係る。1894年6月台湾総督府官吏、数年後書店を起こし台湾に永住)・豊好戞郎 『琉球踊狂言』三重新聞社→国会図書館デジタルアーカイブ
□1893年、角座の仕打澤野新七他一名の代理寺内某が来沖し、料理屋「東家」の協力を得て沖縄芝居の俳優らを雇い関西興行をなす(7月・大阪角座、8月・京都祇園座、9月・名古屋千歳座)。俳優のひとり真栄平房春は病没し大阪上町の了性寺に葬られた。1893年7月『歌舞伎新報』「琉球芝居ー沖縄県琉球には昔より音楽師と称えて一種の歌舞を演奏するもの士族の間に伝えられ居たるところ去る明治22年中いづれも俳優の鑑札を受けて我が役者の如きものとなり其の組5組もあるよしにてこのたび其の一組が大阪角の芝居へ乗り込むことに決定し既に去る2日を以って那覇港を解覧し本日ごろは遅くも到着したる手筈なるがー」
「琉球国演劇」の横断幕があるのが角座。下が角座で配られたもの
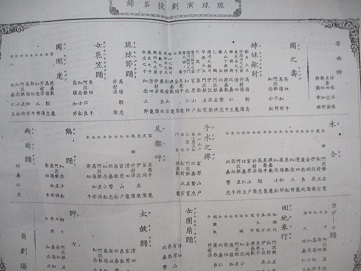
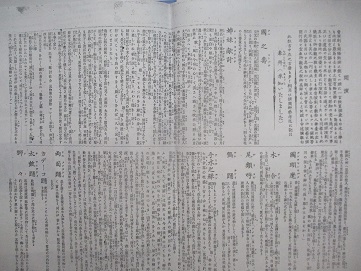
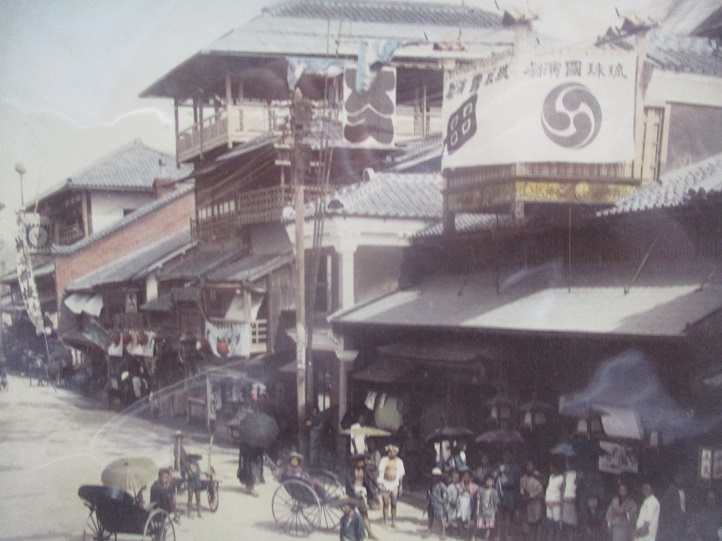
「角座」(翁長良明コレクション)
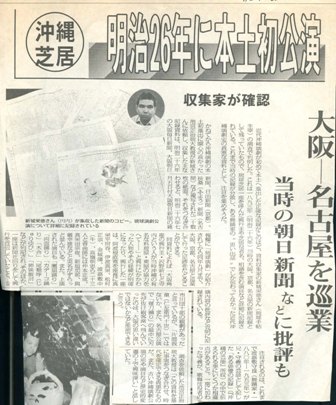

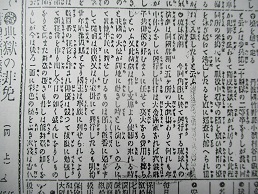
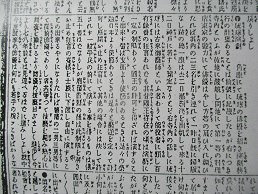
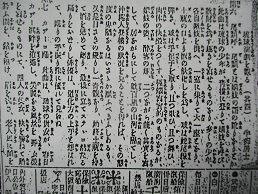
□沖縄芝居ー1893年に大阪・京都・名古屋で公演
◇1991年1月、池宮正治琉大教授と電話で大阪の新聞で沖縄関係を調べているとの話をすると、それなら芸能、特に渡嘉敷守良の芝居も心がけて見てくれと示唆された。それで見当をつけて中之島図書館で大阪朝日新聞、大阪毎日新聞を、京都府総合資料館で日出新聞、名古屋では扶桑新聞をめくると次々と沖縄芝居の記事が出てきた。国会図書館にも行き雑誌も見た。
1897年2月26日 大田朝敷、小川鋠太郎や西常央らとともに沖縄人類学会の発起人となる。
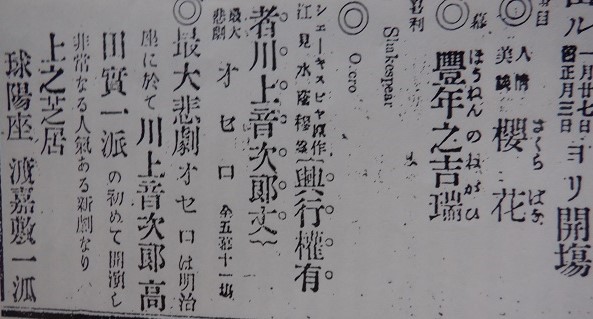
1906年1月 渡嘉敷一派「オセロ」
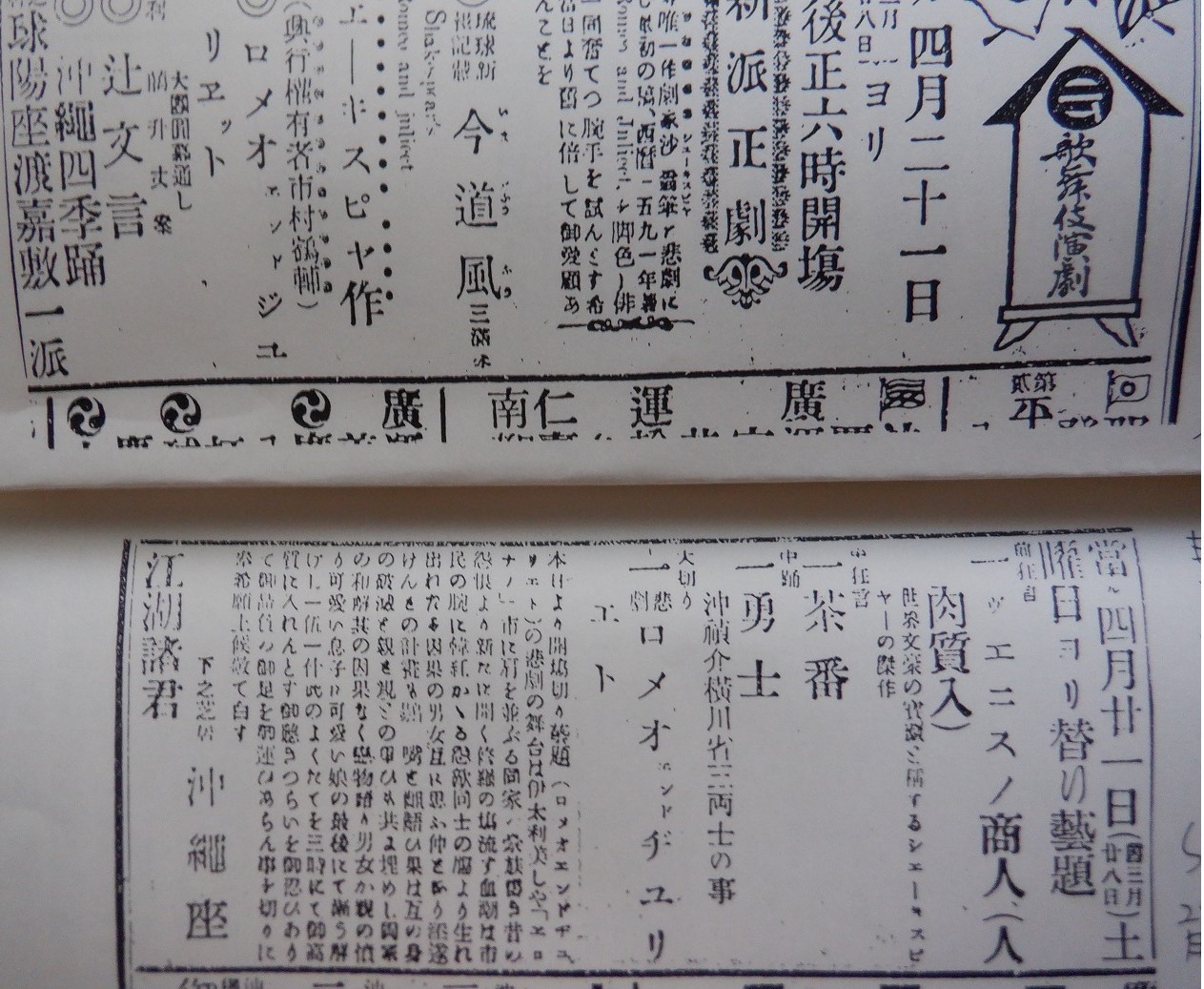
1906年4月渡嘉敷一派「ロメオエンドジュリエット」/沖縄座「ヴエニスノ商人(人肉質入)」「ロメオエンドヂユリエット
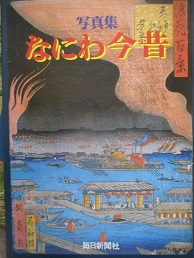

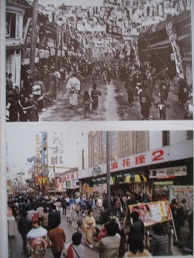
1983年7月『写真集・なにわ今昔』毎日新聞社「道頓堀」(左の写真が角座)
1894年5月 『早稲田文学』第63号 佐々木笑受郎「琉球演劇 手水の縁」
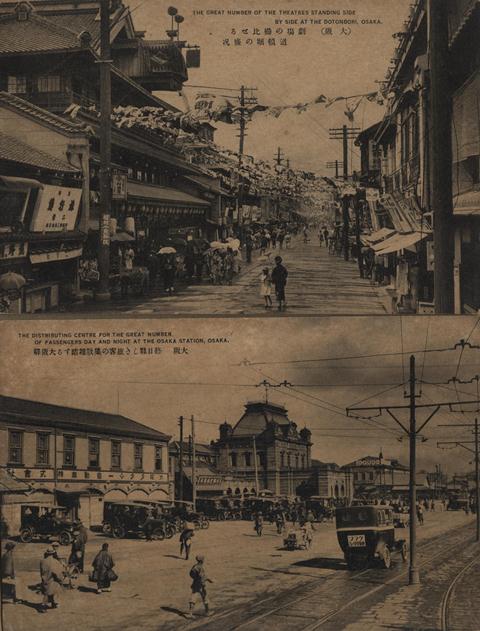
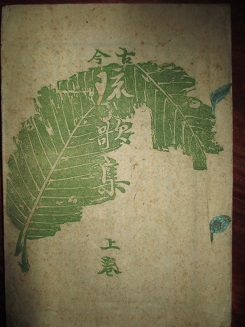
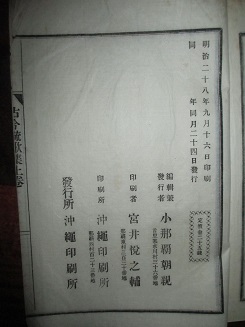
1895年9月 小那覇朝親『古今琉歌集』上卷 沖縄印刷所(宮井悦之輔)
※1907年4月 首里区字山川252小那覇朝親 腸チブスで死去
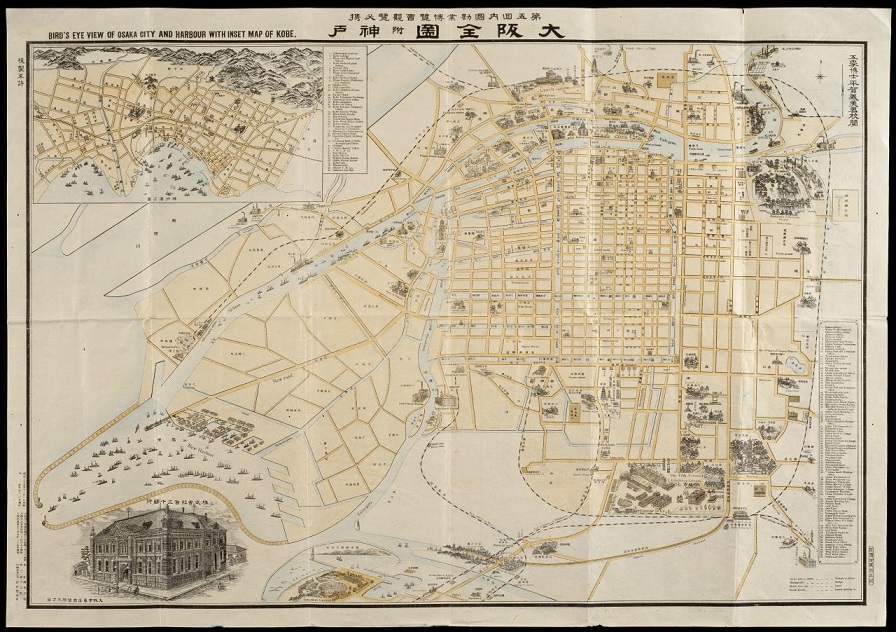
1902年12月『第五回内国勧業博覧会観覧必携 大阪全図 附神戸 博覧会場見取図附』作成者 印刷兼発行所 大阪市東区北久宝寺町 田村豊成堂
1913年4月25日~11月22日『大阪毎日新聞』菊池幽芳「百合子」
1913年10月6日ー大阪道頓堀浪花座で「百合子」劇が開演、百合子役に川上貞奴。来阪中の眞境名安規(桂月)が琉球踊りアヤグを指導。
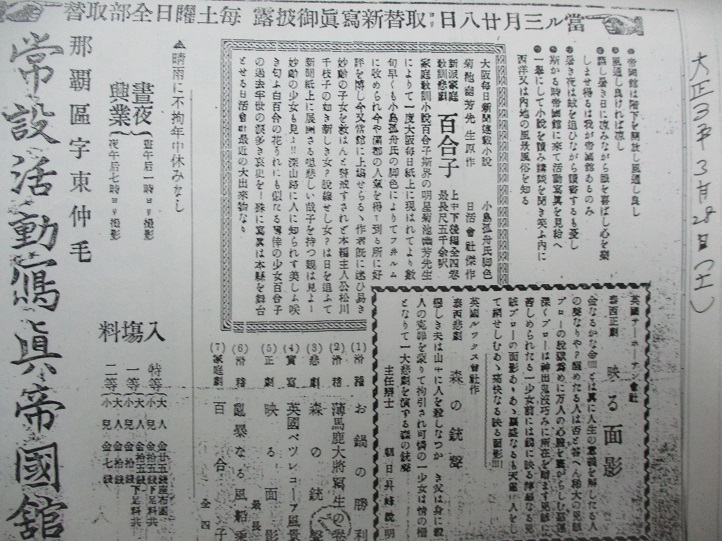
1914年3月

1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊りー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」

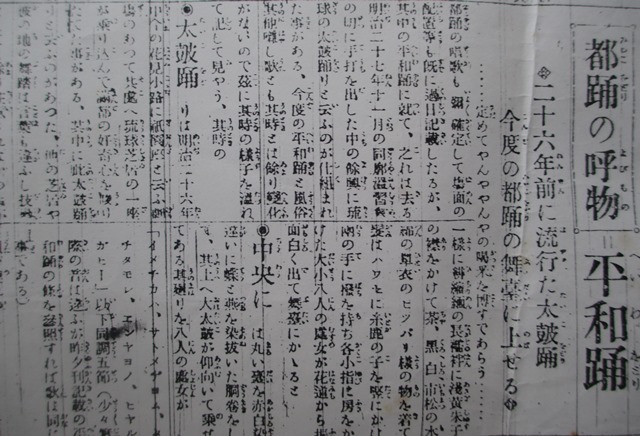

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」
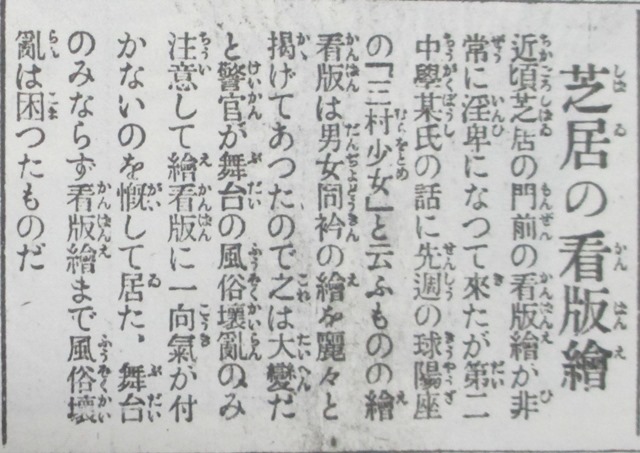
1919年9月14日ー『沖縄時事新報』
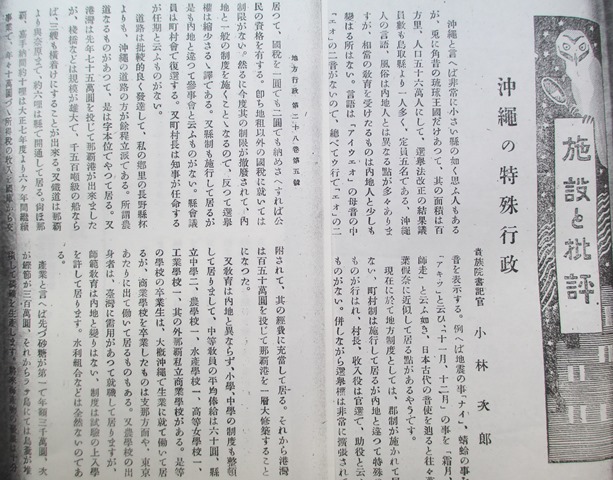
1920年5月 『地方行政』小林次郎「沖縄の特殊行政」
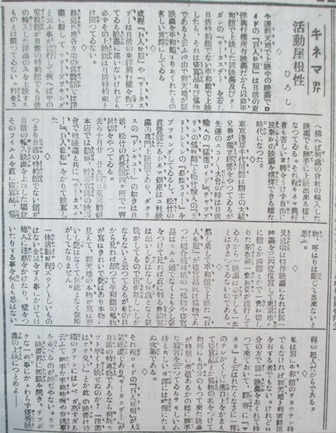
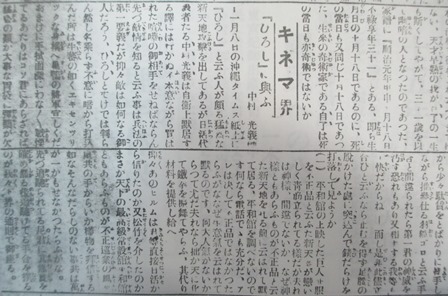
1925年11月『沖縄タイムス』
1932年
●山里永吉の戯曲「那覇四町昔気質」が琉球新報に掲載されたのは昭和7年3月で、山里はその後記で「この戯曲は多分13日から大正劇場で上演されると思うが、考えて見ると大正劇場に拙作『首里城明け渡し』が上演されたのが一昨年の今頃、ちょうど衆議院の選挙が終わった当座だったと覚えている。それから昨年の正月が『宜湾朝保の死』、今度の『那覇四町昔気質』と共に尚泰王三戯曲がここに完成した」と述べている。
1930年11月 那覇の平和館で①「百年後の世界(原名メトロポリス)」/「江戸城総攻メ」上映
①『メトロポリス』(Metropolis)は、フリッツ・ラング監督によって1926年(大正15年)製作、1927年に公開されたモノクロサイレント映画で、ヴァイマル共和政時代に製作されたドイツ映画である。
製作時から100年後のディストピア未来都市を描いたこの映画は、以降多数のSF作品に多大な影響を与え、世界初のSF映画とされる『月世界旅行』が示した「映画におけるサイエンス・フィクション」の可能性を飛躍的に向上させたSF映画黎明期の傑作とされている。SF映画に必要な要素が全てちりばめられており「SF映画の原点にして頂点」と称される。→ウィキペディア
□1985年2月 那覇の国映館で「メトロポリス」上映
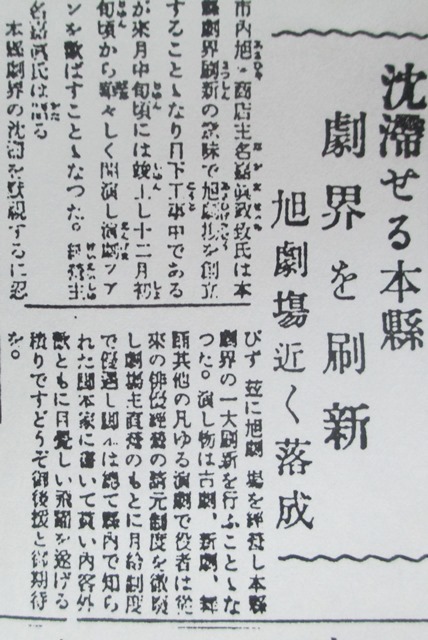
1930年11月『沖縄朝日新聞』




青年劇1935
1935年
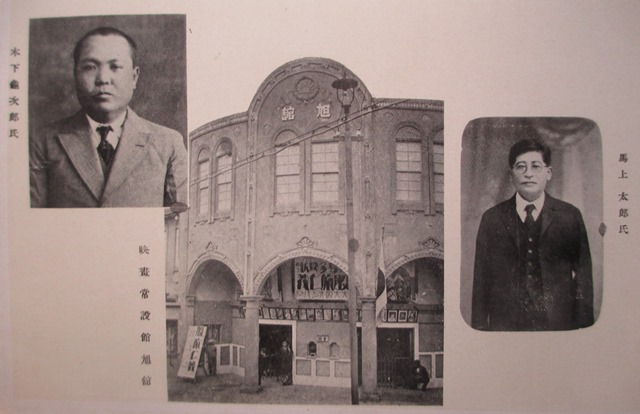
旭館
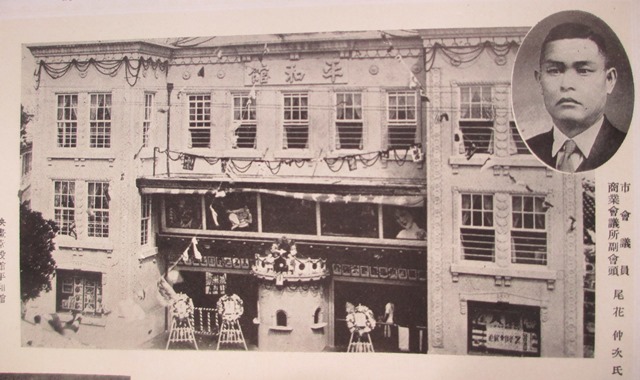
平和館
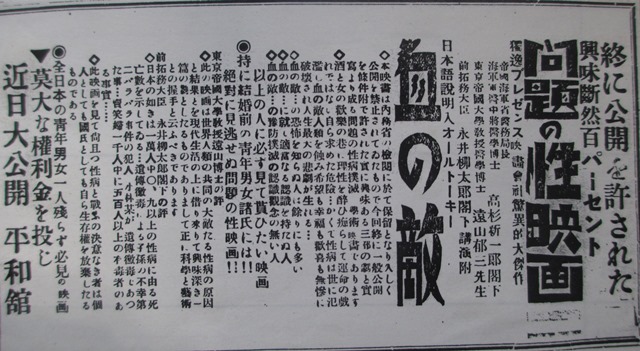
1936年11月
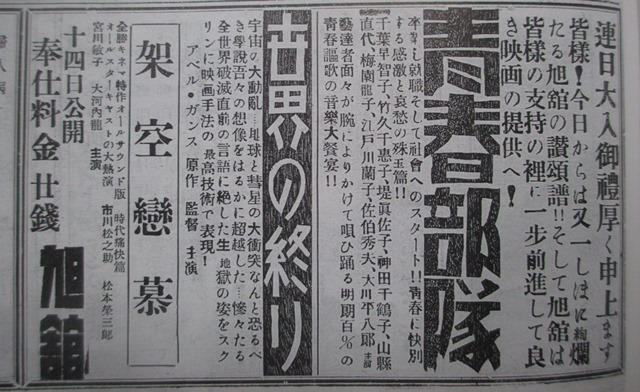
1937年6月 那覇の旭館で「世界の終り」上映
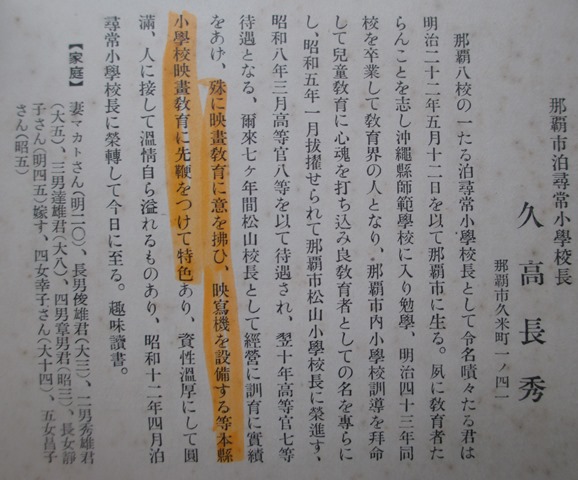
1937年9月 『沖縄県人事録』沖縄朝日新聞社「久高長秀」
1938年2月 那覇の旭館で「巨人コーレム」上映□『巨人ゴーレム』(きょじんゴーレム、Le Golem)は、1936年にチェコで制作されたモンスター・ホラー映画。→ウィキペディア
1938年3月、那覇の旭館で漫画祭、パラマウント映画「ポパイの快投手」「ポパイの動物園荒らし」上映
1938年3月 那覇の平和館で「禁男の家」上映□『禁男の家』( きんだんのいえ、原題: Club de femmes )は、1936年に製作されたフランス映画。1956年に『乙女の館』という作品で再映画化されている。→ウィキペディア

1957年 大阪道頓堀
06/08: 関西沖縄誌

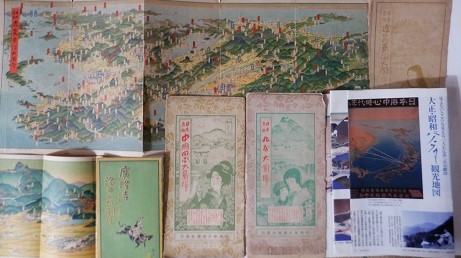
吉田 初三郎(よしだ はつさぶろう、1884年(明治17年)3月4日 - 1955年(昭和30年)8月16日)は、大正から昭和にかけて活躍した鳥瞰図絵師。元の姓は泉。生涯に約1600点とも3000点以上ともいわれる鳥瞰図を制作し、「大正の広重」と呼ばれた。→ウィキ
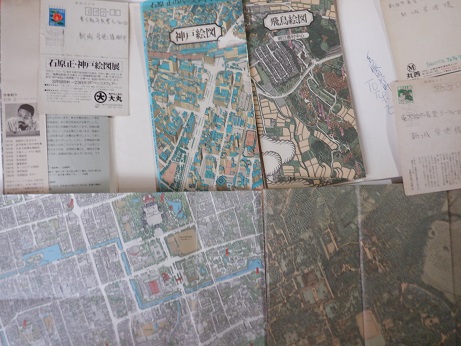
石原 正(いしはら ただし、1937年3月2日 - 2005年3月8日)は、日本の鳥瞰図絵師。北海道函館市出身。北海道函館西高等学校を経て、金沢美術工芸大学を卒業。広告会社に勤務していた時にヘルマン・ボルマンのニューヨーク鳥瞰図に出会い衝撃を受け、1969年に独立。以降、鳥瞰図制作の第一人者として活躍し続けた。→ウィキ

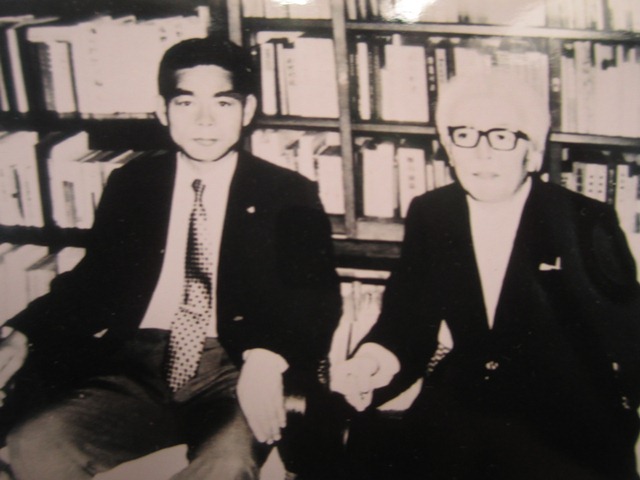
写真左/1999年5月11日沖縄ハーバービューホテルで神坂次郎氏(作家・熊野の生き字引で司馬遼太郎の文学仲間)、新城栄徳。麦門冬・末吉安恭の取材を終えての祝盃。撮影・末吉安允
写真右/1974年4月、司馬遼太郎が沖縄関係資料室に来室、西平守晴と対談司馬遼太郎『街道をゆく6』朝日新聞社
○大阪の都島本通で、篤志でもって「沖縄関係資料室」をひらいていおられる西平守晴氏にもきいてたしかめることができた。西平氏は、「そうです、そんな話があります」といって、南波照間の「南」を、パイと発音した。ついでながら本土語の南風(はえ)は沖縄でも「南」の意味につかう。本土語の古い発音では、こんにちのH音が古くはF音になり、さらに古くはP音になる。つまり花はパナである。八重山諸島の言葉はP音の古発音を残していて、南(ハエ)が南(パイ)になるらしい。西平氏はこのまぼろしの島を、「パイ・ハテルマ」と、いかにもその島にふさわしい発音で言った。
1158年 太宰大弐に任ぜられた平清盛は、太宰府に赴任することはなかったが、宋商船が運んでくる唐物に強い興味を抱き、やがて宋人を太宰府から瀬戸内海へと招いた。
☆神戸の灘の薬師さんの傍らで長年「国語」の研究に専念していた奥里将建翁、最後のまとめとして1964年「沖縄に君臨した平家」を沖縄タイムスに連載(10-8~12-11)した。□10月11日ー『沖縄タイムス』奥里将建「沖縄に君臨した平家」(4)怪傑・平清盛をして天寿を全うさせ、彼が抱いていた南宋貿易の夢を実現させ、中世日本の様相はすっかり一変していたかも知れない。(略)戦後のわが歴史学界において、清盛に対する評価が大分改まって来たのも、彼の経綸と人間的魅力を高く買って来たために外ならない」→「琉文21」雑誌『おきなわ』/1926年4月ー奥里将建『琉球人の見た古事記と萬葉』青山書店
1167年 平清盛、太政大臣となる


写真ー重要文化財本堂 昭和大修営落慶記念 昭和四十四年五月十八日 六波羅蜜寺(新城栄徳所蔵)
六波羅蜜寺は、天暦5年(951)醍醐天皇第二皇子光勝空也上人により開創された西国第17番の札所である。当時京都に流行した悪疫退散のため、上人自ら十一面観音像を刻み、御仏を車に安置して市中を曵き回り、青竹を八葉の蓮片の如く割り茶を立て、中へ小梅干と結昆布を入れ仏前に献じた茶を病者に授け、歓喜踊躍しつつ念仏を唱えてついに病魔を鎮められたという。(現在も皇服茶として伝わり、正月三日間授与している)
現存する空也上人の祈願文によると、応和3年8月(963)諸方の名僧600名を請じ、金字大般若経を浄写、転読し、夜には五大文字を灯じ大萬灯会を行って諸堂の落慶供養を盛大に営んだ。これが当寺の起こりである。上人没後、高弟の中信上人によりその規模増大し、荘厳華麗な天台別院として栄えた。平安後期、平忠盛が当寺内の塔頭に軍勢を止めてより、清盛・重盛に至り、広大な境域内には権勢を誇る平家一門の邸館が栄え、その数5200余りに及んだ。寿永2年(1183)平家没落の時兵火を受け、諸堂は類焼し、独り本堂のみ焼失を免れた。
源平両氏の興亡、北条・足利と続く時代の兵火の中心ともなった当寺はその変遷も甚だしいが、源頼朝、足利義詮による再興修復をはじめ火災に遭うたびに修復され、豊臣秀吉もまた大仏建立の際、本堂を補修し現在の向拝を附設、寺領70石を安堵した。徳川代々将軍も朱印を加えられた。現本堂は貞治2年(1363)の修営であり、明治以降荒廃していたが、昭和44年(1969)開創1,000年を記念して解体修理が行われ、丹の色も鮮やかに絢爛と当時の姿をしのばせている。なお、解体修理の際、創建当時のものと思われる梵字、三鈷、独鈷模様の瓦をはじめ、今昔物語、山槐記等に記載されている泥塔8,000基が出土した。重要文化財の質、量において文字どおり藤原、鎌倉期の宝庫と謂われる所以である。
1260年 英祖王、即位☆麦門冬・末吉安恭は、この時代を「仏教の起源と芸術の揺籃」と称した。
補陀落僧禅鑑、葦軽船で琉球に漂着、英祖王保護のもと極楽寺(のち龍福寺)を創建
1281年 島津長久ら薩摩国の兵を率いて壱岐にて元軍を攻める。
1372年 1月、楊載、来琉
1377年 琉球国王察度、南山王承察度ら明に使者を遣わし馬、方物を貢す。北山王帕尼芝、明に使者、方物を貢す。頼重法印(真言宗)、薩摩坊津から 来琉。
1402年 足利義満、島津伊久に明を侵す鎮西海賊の取締を命ず。
明使が北山第に足利義満を訪ね国書・大統暦、賜物を伝える。
1404年 時中、来琉し武寧に皮弁冠服が頒賜される。
1406年 武寧、寨官の子石達魯ら6人を明に遣わし国子監に学ばせる。
1410年 琉球国官生模都古ら2人、明の国子監に入り学を受ける。
1413年 中山王思紹、太勃奇を明に遣わし馬を貢し、寨官の子ウ同志久・周魯毎らを送り国子監で学ばせる
1415年 琉球国山南王汪応祖の世子他魯らを明朝に遣わす。足利義持、琉球国思紹に「りうきう国よのぬし」で書簡を送る。
1418年 琉球国中山王思紹、長史の懐機らを明に遣わす
1425年 柴山(中官)来琉、勅を齎らし巴志に中山王を嗣がせる。「中山門」扁額を掲げる。
1427年 安国山樹華木之記碑「壮者時有りて舞ひ、老者時有りて歌ふ」
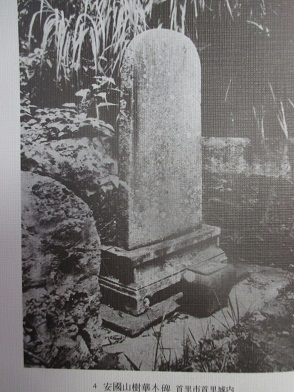
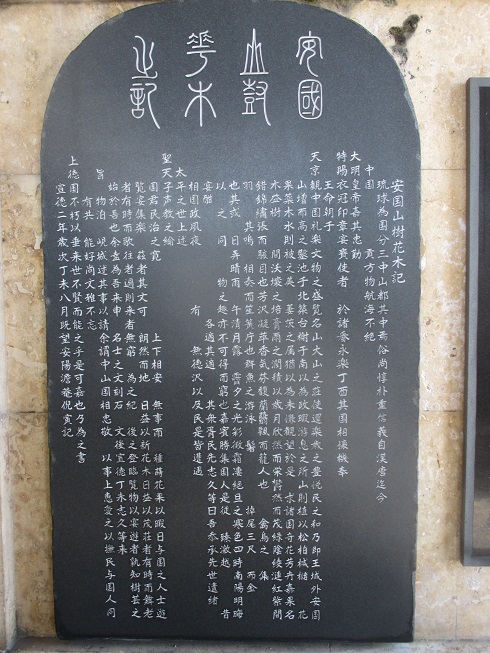
右ー沖縄県公文書館玄関にある安国山樹華木之記□首里王城の威容を増し、合わせて遊息の地とするため、王城の外の安国山に池(龍潭)を掘り、台を築き、松柏・花木を植え、太平の世のシンボルとして永遠の記念とする。
1429年 巴志、三山統一
1430年 巴志、明帝から尚姓を授けられる
1443年 朝鮮通信使の書状官として申叔舟が来日
1453年 朝鮮国、琉球国使者道安の齎らした日本琉球地図表装
1456年 尚泰久王、梵鐘を鋳造し大聖寺、天尊殿、相国寺、普門寺、建善寺、長寿寺、天竜寺、広厳寺、報恩寺、大安寺に寄進
1457年 尚泰久王、梵鐘を鋳造し霊応寺、永福寺、大禅寺、上天妃宮、天妃宮、竜翔寺、潮音寺、万寿寺、魏古(越来)に寄進
1458年 尚泰久王、万国津梁の鐘を正殿にかける。


万国津梁の鐘(沖縄県立博物館・美術館)
尚泰久王、梵鐘を鋳造し永代院に寄進
尚泰久王、梵鐘を鋳造し一品権現御宝殿、東光寺に寄進
1461年 島津立久、尚徳の国王即位を祝い太平書を賜う
1466年 琉球国王尚徳の使者芥隠承琥、足利義政に拝謁、方物を献ず。
□7月28日ー琉球の使者一行が将軍・足利義政に謁見、方物も献上する。
8月1日ー琉球正使・芥隠西堂から蔭涼軒(季瓊)真蘂に大軸(中国から琉球国王に贈られたもの)、南蛮酒を贈る。(義政時代6度目の琉球人 参洛)。
雪舟が描いた琉球人
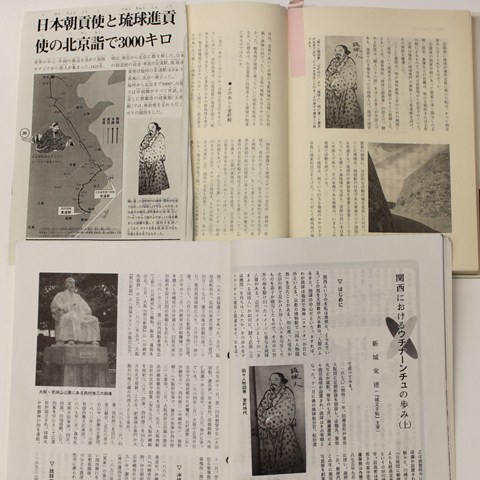
『自治おきなわ』1996年7月号に私(新城栄徳)は「京都の博物館で『国々人物図巻』を見たことがある。明に渡った雪舟が北京の街で見かけた珍しい人びとを写生したものを弟子が模写したもので、その中に世界の海を駆け回ったイメージに重なる琉球人像がある。」と書いた。明代の類書『万金不求人』に和寇図と共に大琉球國人も載っている。長崎県立美術博物館の正保版『万国人物図』にも琉球人が登場している。多くの絵師たちが好んで万国人物図を画題にしていたようだ。私は雪舟の弟子の絵の写真(琉球人)を琉球新報の岡田輝雄記者に提供。これは1991年9月発行の『新琉球史』(古琉球編)に載った。同様に佐久田繁月刊沖縄社長に提供したものは99年9月発行の『琉球王国の歴史』に載った。
1474年 尚円、島津忠昌の家督相続を祝う
1480年 足利幕府、応仁・文明の乱が終わったので琉球に朝貢船を送るよう島津忠昌に催促させる。
1482年 琉球国尚真、奏して陪臣の子蔡賓ら5人を南京国子監において読書させることを乞う。
1492年 ドイツ人地理学者マルティン・ベハイム、地球儀を作成
1492年 尚真王、先王尚円を祀るため円覚寺建設に着手
1497年 万歳嶺記、官松嶺記を建設。円覚寺禅寺記碑
1502年 朝鮮王季揉から贈られた方冊蔵経収集のため円鑑池に小堂を建設(1621年に弁財天像を安置)
1507年 尚真王、書を島津忠昌に送り修好の意志を伝える
1508年 島津忠治、尚真に書を送り、島津氏の印判(琉球渡海朱印状)を持たない商人を点検し船財等を収公を許す
1510年 尚真王、官生蔡進ら5人を南京国子監において読書を乞う。
1527年 尚清王、智仙鶴翁を遣わし明皇帝の日本宛の国書を齎す。足利義晴、書を尚清に送り日明和与の斡旋を謝す。
1530年 月船寿桂、「鶴翁(智仙)字銘并序」で為朝伝、琉球附庸説に言及。
1531年 『おもろさうし』第一巻、成る
1534年 5陳侃(正史)、高澄(副史)那覇着。7尚清冊封の礼。9冊封使、開洋。10陳侃『使琉球録』著わす
1550年 5月4日ー足利義晴、近江穴太(現滋賀県大津市穴太)にて死去。享年40(満39歳没)。
1556年 島津貴久、尚元王が建善寺月泉を遣わしたことに答書し隣交を求める。
1561年 郭汝霖(正史)、李際春(副史)
1568年(永禄11)9月 織田信長、将軍足利義昭を奉じ上洛、当面の仮御所として義昭は本國寺に入り、信長は清水寺を宿所とした。
1569年(永禄12) 仮幕府のおかれた本國寺が襲撃にあったことから、信長は義昭のために二条城(二条御所)を築く。
1569年(永禄12年)、将軍・足利義昭を擁して台頭していた織田信長と二条城の建築現場で初めて対面。既存の仏教界のあり方に信長が辟易していたこともあり、ルイス・フロイスはその信任を獲得して畿内での布教を許可され、グネッキ・ソルディ・オルガンティノなどと共に布教活動を行い多くの信徒を得た。その著作において信長は異教徒ながら終始好意的に描かれている。フロイスの著作には『信長公記』などからうかがえない記述も多く、戦国期研究における重要な資料の一つになっている。その後は九州において活躍していたが、1580年(天正8年)の巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの来日に際しては通訳として視察に同行し、安土城で信長に拝謁している。1583年(天正11年)、時の総長の命令で宣教の第一線を離れ、日本におけるイエズス会の活動の記録を残すことに専念するよう命じられる。以後フロイスはこの事業に精魂を傾け、その傍ら全国をめぐって見聞を広めた。この記録が後に『日本史』とよばれることになる。→ウィキ
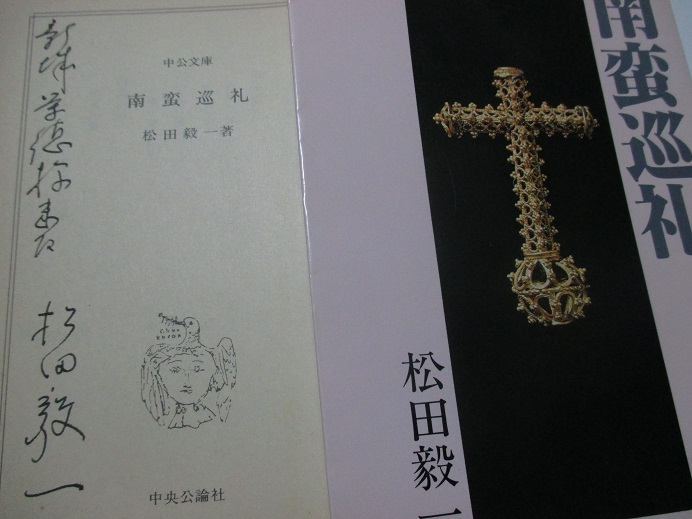
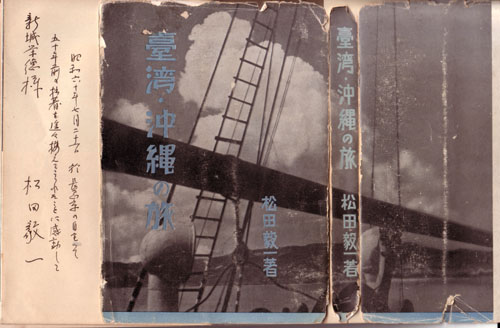
松田 毅一(まつだ きいち、1921年5月1日 - 1997年5月18日)は、日本の歴史学者。香川県高松市出身、大阪市育ち。専門は戦国時代から江戸時代初期の日欧交渉史、特にポルトガル・スペインとの関係史。ヨーロッパ各地(ポルトガル・スペイン・バチカン等)やフィリピン、マカオ等の文書館に保存されている日本関係史料の発見・翻訳・紹介に取り組み、また多数の著書・論文を発表して日本における上記分野の研究の進展に貢献する一方、こうした研究成果の一般市民への啓発・普及、関係諸国との学術・文化交流にも尽力した。→ウィキ
1575年 琉球国の紋船(使僧天界寺南叔、使者金武大屋子)、鹿児島に着く。印判を持たない商船に交易を許したこと、島津使僧広済寺雪芩津興を粗略のことに島津氏に弁明。
1579年 簫崇業(正史)、謝杰(副史)来琉。簫崇業「那覇と首里の二ヶ所で、馬市(mashi)が設けられている。物を売るのはおおむね女-」。
1580年 琉球国尚真、島津義久に九州大半の帰伏を祝い隣交を求める。
1586年(天正14) 豊臣秀吉、聚楽第、方広寺大仏殿造営はじまる。
○国立博物館隣にある豊国神社は、豊臣秀吉死去の翌年の1599年、遺体が遺命により方広寺の近くの阿弥陀ヶ峰山頂に埋葬され、その麓に方広寺の鎮守社として廟所が建立されたのに始まる。後陽成天皇から正一位の神階と豊国大明神(ほうこくだいみょうじん)の神号が贈られ鎮座祭が盛大に行われた。方広寺にあった大仏は、天保年間に現在の愛知県の有志が、旧大仏を縮小した肩より上のみの木造の大仏像と仮殿を造り、寄進した。この大仏は私もよく見にいったが1973年3月28日深夜の火災によって焼失した。

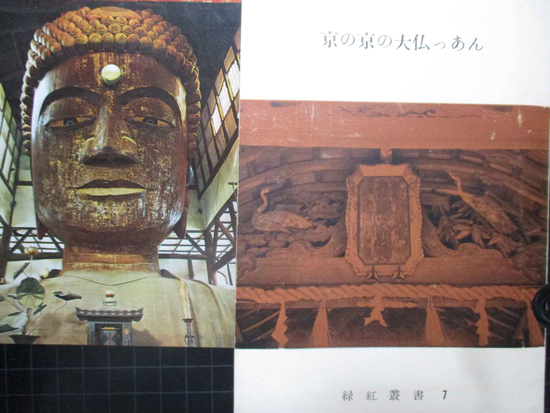
方広寺の大仏
1587年 島津義久、豊臣秀吉に降伏。
1590年 豊臣秀吉、尚寧王に書を送り、全国統一を強調。政化を異域に弘め四海を一家となす志を述べる。
1594年 尚寧王、島津義久に国家衰微のため唐入りの軍役は調達できない旨答える。
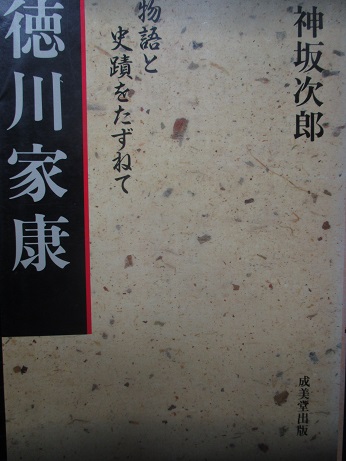
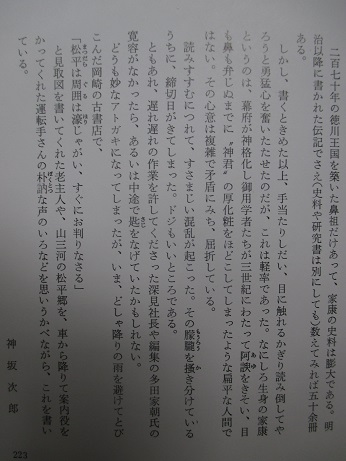
1976年2月 神坂次郎『徳川家康ー物語と史蹟をたずねて』成美堂出版
○二百七十年の徳川王国を築いた鼻祖だけあって、家康の史料は膨大である。明治以降に書かれた伝記でさえ(史料や研究書は別にしても)数えてみれば五十余冊ある。しかし、書くときめた以上、手当たりしだい、目に触れるかぎり読み倒してやろうと勇猛心を奮いたたせたのだが、これは軽率であった。なにしろ生身の家康というのは、幕府が神格化し御用学者たちが三世紀にわたって阿諛(おもねりへつらう意)をきそい、目も鼻も弁じぬまでに”神君〟の厚化粧をほどこしてしまったような扁平な人間ではない。その心意は複雑で矛盾にみち、屈折している。・・・
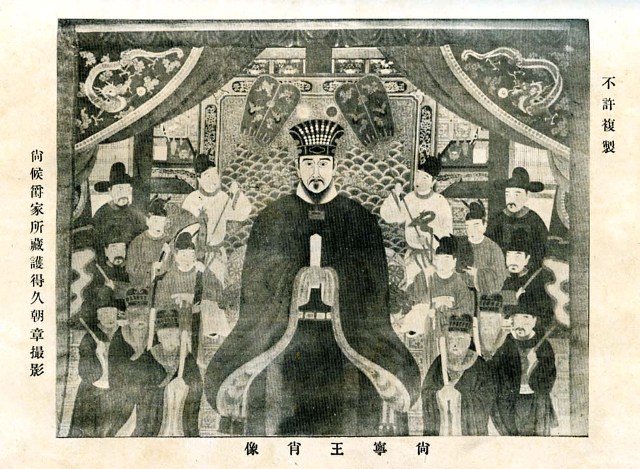
尚寧王
1602年 徳川家康、陸奥国伊達氏領に船で漂着した琉球人を島津忠恒に送還させる。
1604年 野国総官、渡唐、帰国(05年)のとき蕃薯を持ち帰る。
1605年 本多上野介正純、長崎奉行小笠原一庵に平戸漂着の琉球船の荷物没収を命ず。
1606年 山口駿河守直友、薩摩商人の渡海が琉球出兵の妨げにならないよう分別を促す。
1608年 山口駿河守直友、島津家久に、琉球出兵の準備と、再度琉球国王に家康への来聘を促す交渉を命ず。
1609年 3-4島津軍、琉球出兵で山川湊を出帆。
1609年(慶長14)4月 薩摩軍、琉球侵攻/5月 鹿児島に中山王・尚寧を連れ帰る
1610年(慶長15)8月2日 島津家久、中山王・尚寧を連れて駿府に参る/8日 島津家久、中山王・尚寧を連れて登城し徳川家康に拝謁/王弟、具志頭王子尚宏、家康に対面後に病死し興津の清見寺に葬られた。/18日 家久と中山王・尚寧に饗応で猿楽、頼宣、頼房が舞う。その間酒宴
1610年(慶長15)8月25日 島津家久、中山王・尚寧を連れて江戸に参着/28日 尚寧、登城し台徳院(秀忠)に拝謁/9月20日 島津家久、中山王・尚寧を連れて木曽路より帰国
〇大正13年12月 藤田親義『琉球と鹿児島』末吉莫夢「薩摩関係の琉球五異人ー鄭迵謝那利山/薩摩関係の異人として、私は先ず第一に鄭迵謝那親方利山を挙げる。彼は慶長役の時の三司官の一人で、琉球に於いて最も勢力を振い、遂に対薩摩外交を誤り、其身も薩摩に於いて戮された人であるが、琉球の歴史に於いては出色の人物である。」
1611年9月19日 鄭迵・謝名親方利山、斬首
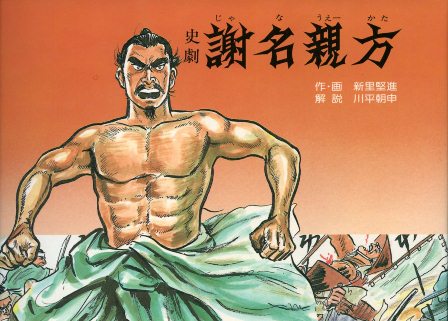
○1983年12月 新里堅進作画(川平朝申解説)『史劇 謝名親方』全教出版
謝名 利山(じゃな りざん、嘉靖28年(1549年/天文18年) - 万暦39年9月19日(1611年10月24日/慶長15年))は、琉球王国の政治家。謝名親方(ウェーカタ)の呼び方で一般に知られる。
唐名は鄭迵(ていどう)。称号は親方。鄭氏湖城家九世。久米村(現・那覇市久米)出身で久米三十六姓の末裔の一人。父・鄭禄の次男として生まれる。1565年、16歳のとき官生に選ばれて明に留学し、翌年、南京の国子監へ入学する。1572年、帰琉。その後は都通事をへて長史となり、進貢使者として数度渡唐する。1580年、総理唐栄司(久米村総役)となる。 1605年、城間親方盛久を讒言して百姓の身分に貶め、自らは三司官となった。薩摩侵略の際には三重城に陣取り那覇港の防衛を行うも尚寧王の降伏によりともに連行される。その後、薩摩藩から起請文に署名するよう求められるが、ただ一人これを拒否し処刑された。(→ウィキペディア)
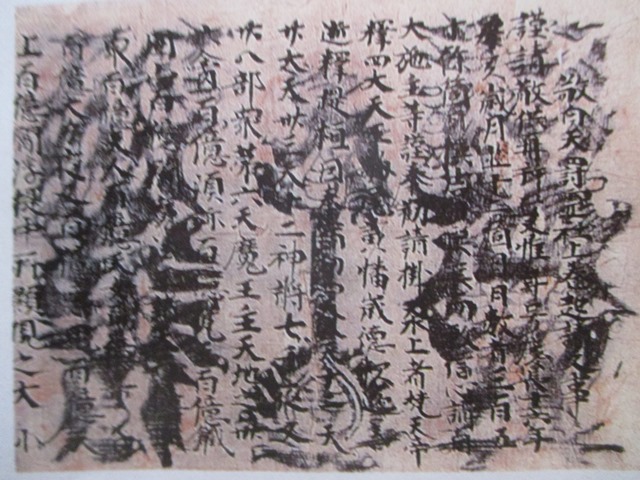
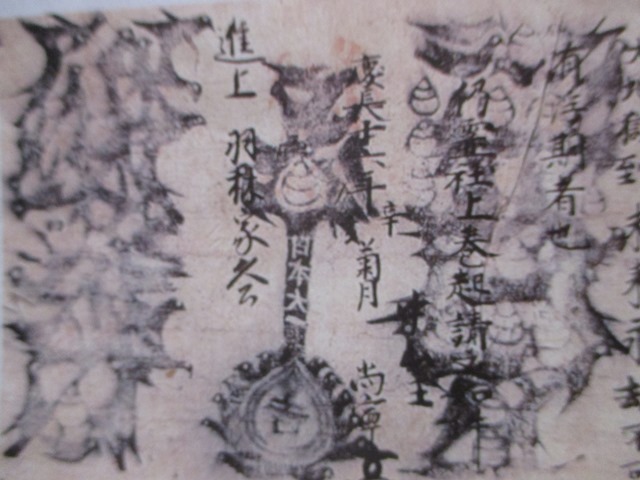
○琉球国中山王尚寧起請文(部分・島津家文書)。起請文は戦国時代、忠誠を誓うもの。豊臣秀吉の拾丸(秀頼)への忠節を尽くさせる血判誓紙も烏点の牛王(うてんのごおう)宝印があるので熊野信仰の流れのひとつであろう。
〇熊野那智大社は、那智山青岸渡寺とともに熊野信仰の中心地として栄華を極め、古来より多くの人々の信仰を集めました。今なお多くの参詣者が訪れ、熊野速玉大社・熊野本宮大社とともに熊野三山の一つ。夫須美神(ふすみのかみ)を御主神としてそれぞれに神様をお祀りしている。伊弉冉尊(いざなみのみこと)とも言われる夫須美神は、万物の生成・育成を司るとされ、農林・水産・漁業の守護神、縁結びの神様また、諸願成就の神としても崇められている。社殿は、仁徳天皇の御世(317年)に現在の位置に創建され、平重盛が造営奉行となってから装いを改め、やがて、織田信長の焼討に遭ったのを豊臣秀吉が再興した。徳川時代に入ってからは、将軍吉宗の尽力で享保の大改修が行われている。→「那智勝浦観光ガイド」参照

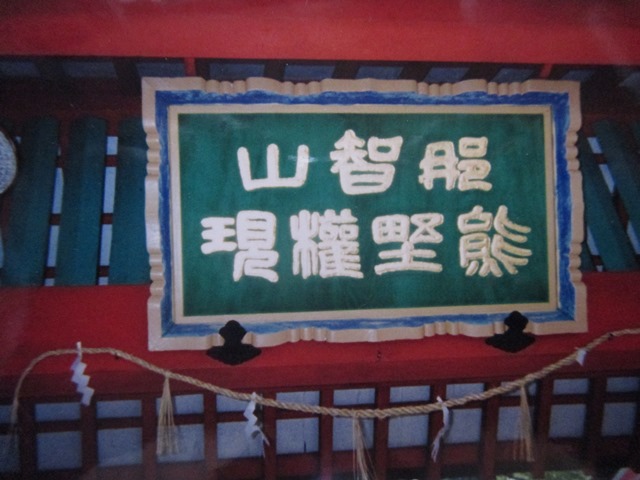


2008年10月15日~12月21日まで 大阪人権博物館で「アジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街」(10月15日~12月21日)と題し展示会があった。見に行って学芸員の仲間恵子さんから『図録』を入手した。中に上田正昭氏が「アジアのなかの大阪ー東アジアと難波津」を執筆されて、完全な「鎖国」の時代はなかった、と説く。仲間さんはアジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街と題して「近現代の大阪についても、生野区のコリアタウンや『リトル沖縄』と称される大正区を訪れることで、人と人との交流が生みだす文化に触れることができる。」と強調している。
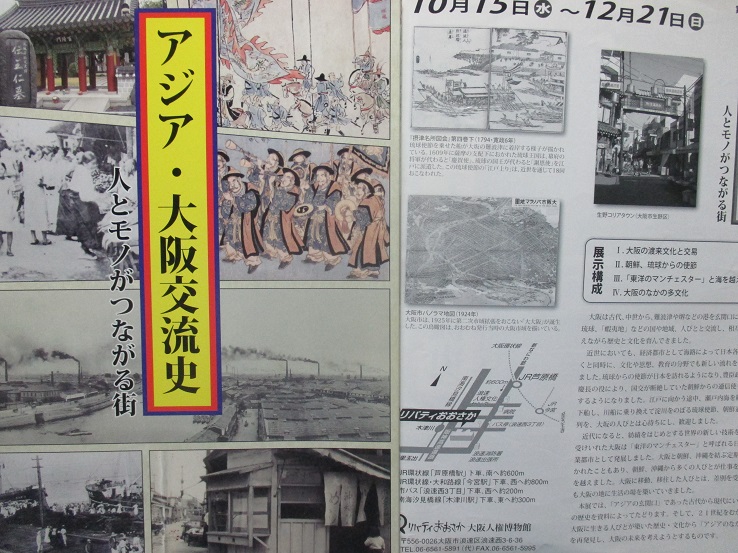
○アジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街・・・・・仲間恵子
○アジアのなかの大阪ー東アジアと難波津・・・・・・・上田正昭
1 大阪の渡来文化
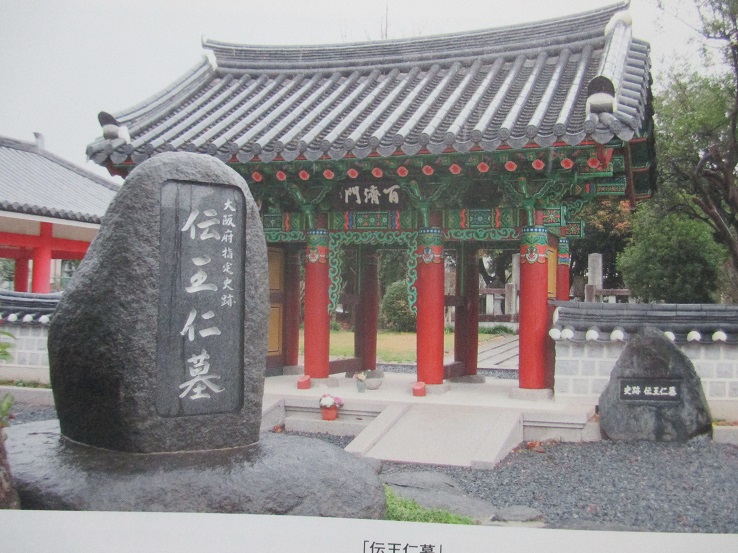
伝王仁墓 - 大阪府枚方市藤阪東町二丁目に王仁の墓が伝えられている。/王仁大明神 - 大阪府大阪市北区大淀中3丁目(旧大淀区大仁町)にある一本松稲荷大明神(八坂神社)は王仁大明神とも呼ばれ、王仁の墓と伝えられていた。また近辺に1960年代まであった旧地名「大仁(だいに)」は、王仁に由来していると伝えられている。→ウィキ
2 朝鮮、琉球からの使節
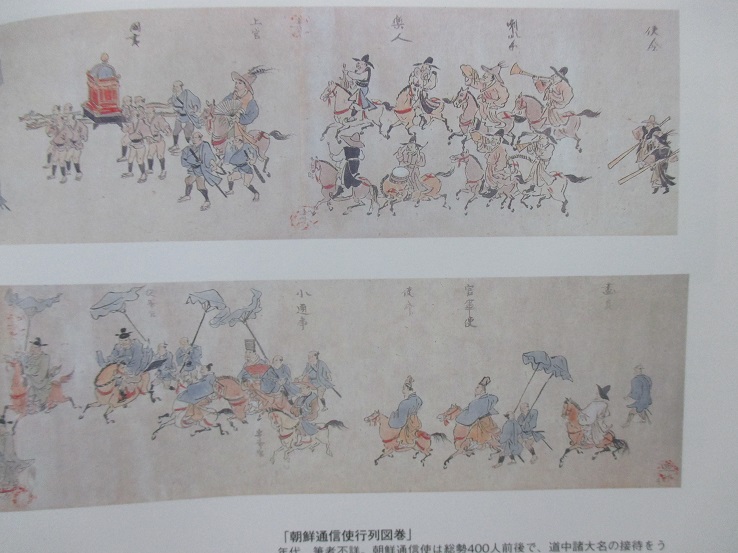
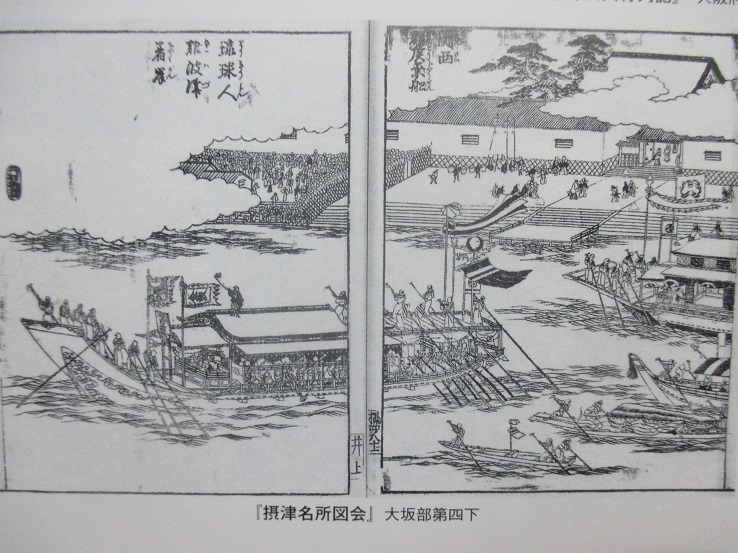
3 「東洋のマンチェスター」と海を越えた人びと
4 大阪のなかの多文化
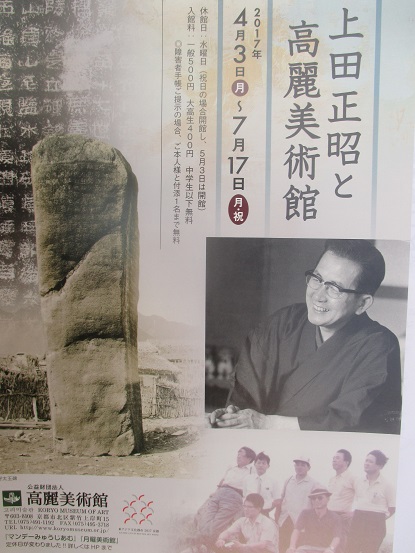
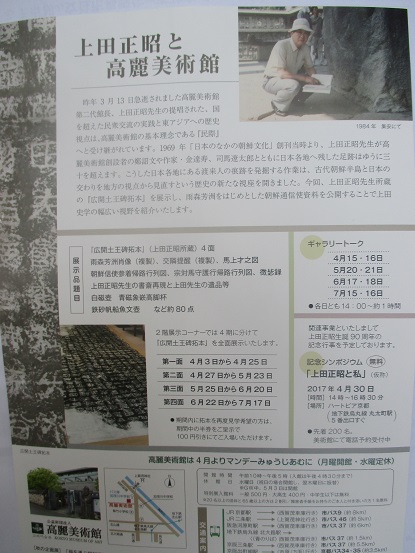
2017年4月3日~7月17日 高麗美術館「上田正昭と高麗美術館」
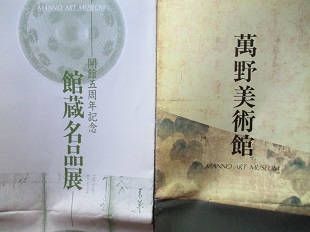
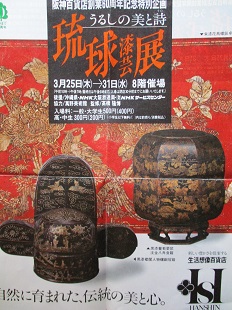


萬野美術館/『2011年度 首里城公園管理センター 萬野裕昭コレクション調査報告書』
2015年7月22日~8月31日 古代出雲歴史博物館「琉球王国ー東アジア交流の盛華」琉球王国のすべてが出雲に集結
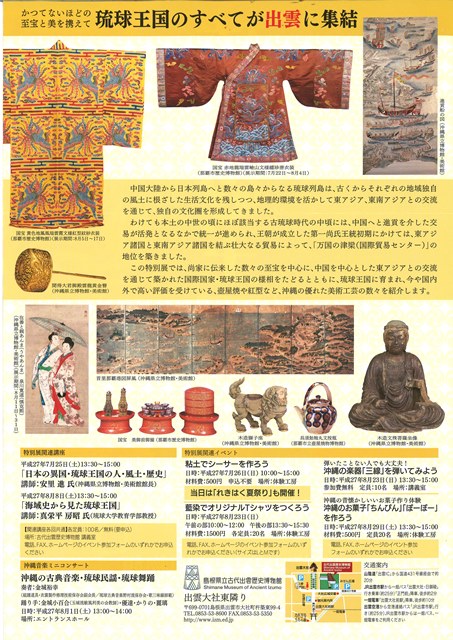
出雲/島根県と沖縄

前列左から前田所長、當間次長、兵庫県人会婦人部ー大城一史の作品を背景に
沖縄県大阪事務所は前田所長、當間次長のとき(1980年)島根県ビルから大阪駅前第3ビルに移転してきた。だから梅田に行くと島根県事務所もよく寄るが、島根(出雲)はまだ行ったことがない。
○森鴎外記念館もりおうがいきねんかん 島根県津和野町町田イ238 電話番号 0856-72-3210
営業時間 9時~16時45分 定休日 12月~3月中旬の月曜(祝日の場合は翌日)
料金 入館600円(森鴎外旧宅の見学料含む) アクセス JR津和野駅→石見交通バス鴎外旧居・長野行きで7分、バス停:鴎外旧居前下車、徒歩3分
森鴎外旧宅に隣接して立つ記念館。軍医であり、文学者でもあった鴎外の生涯を、遺品や直筆の原稿、ハイビジョン映像などで紹介している。鴎外は、幼くして『論語』や『孟子』を学び、天才少年の誉れ高かった。7歳から2年間、養老館で学び、10歳で上京し、その後、鴎外は陸軍軍医となり総監に就任。そのかたわら『舞姫』『山椒大夫』『阿部一族』など多くの小説を著した。鴎外が妻や子どもたちに宛てた書簡や、日記も展示。
○安部榮四郎記念館ー〒690-2102 島根県八束郡八雲村東岩坂1754 ☎FAⅩ(0852)54-1745
安部栄四郎 あべ-えいしろう
1902-1984 昭和時代の和紙製作家。
明治35年1月14日生まれ。出雲国(いずものくに)製紙伝習所で修業し,家業の和紙づくりにはげむ。昭和6年柳宗悦(むねよし)と出あい民芸運動に参加,雁皮紙(がんぴし)の特色をいかした出雲民芸紙を創作。43年人間国宝。昭和59年12月18日死去。82歳。島根県出身。著作に「出雲民芸紙譜」「和紙三昧(ざんまい)」など。(コトバンク)

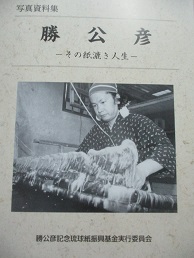



2020年5月 上江州敏夫『写真資料集・勝 公彦ーその紙漉き人生』勝公彦記念琉球紙振興基金実行委員会
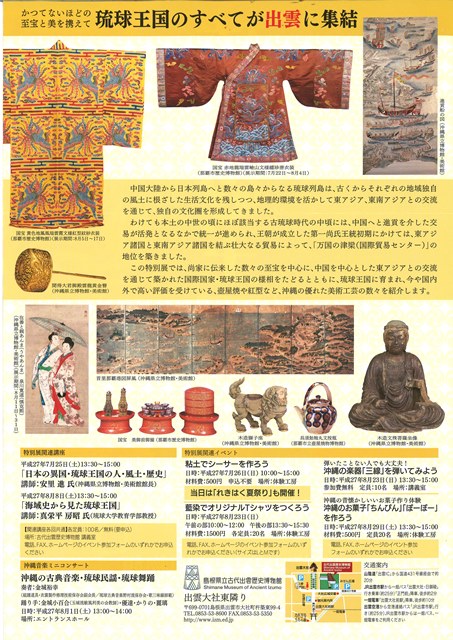
出雲/島根県と沖縄

前列左から前田所長、當間次長、兵庫県人会婦人部ー大城一史の作品を背景に
沖縄県大阪事務所は前田所長、當間次長のとき(1980年)島根県ビルから大阪駅前第3ビルに移転してきた。だから梅田に行くと島根県事務所もよく寄るが、島根(出雲)はまだ行ったことがない。
○森鴎外記念館もりおうがいきねんかん 島根県津和野町町田イ238 電話番号 0856-72-3210
営業時間 9時~16時45分 定休日 12月~3月中旬の月曜(祝日の場合は翌日)
料金 入館600円(森鴎外旧宅の見学料含む) アクセス JR津和野駅→石見交通バス鴎外旧居・長野行きで7分、バス停:鴎外旧居前下車、徒歩3分
森鴎外旧宅に隣接して立つ記念館。軍医であり、文学者でもあった鴎外の生涯を、遺品や直筆の原稿、ハイビジョン映像などで紹介している。鴎外は、幼くして『論語』や『孟子』を学び、天才少年の誉れ高かった。7歳から2年間、養老館で学び、10歳で上京し、その後、鴎外は陸軍軍医となり総監に就任。そのかたわら『舞姫』『山椒大夫』『阿部一族』など多くの小説を著した。鴎外が妻や子どもたちに宛てた書簡や、日記も展示。
○安部榮四郎記念館ー〒690-2102 島根県八束郡八雲村東岩坂1754 ☎FAⅩ(0852)54-1745
安部栄四郎 あべ-えいしろう
1902-1984 昭和時代の和紙製作家。
明治35年1月14日生まれ。出雲国(いずものくに)製紙伝習所で修業し,家業の和紙づくりにはげむ。昭和6年柳宗悦(むねよし)と出あい民芸運動に参加,雁皮紙(がんぴし)の特色をいかした出雲民芸紙を創作。43年人間国宝。昭和59年12月18日死去。82歳。島根県出身。著作に「出雲民芸紙譜」「和紙三昧(ざんまい)」など。(コトバンク)

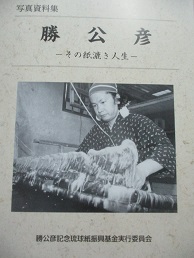



2020年5月 上江州敏夫『写真資料集・勝 公彦ーその紙漉き人生』勝公彦記念琉球紙振興基金実行委員会
08/11: 朝鮮史と末吉麦門冬
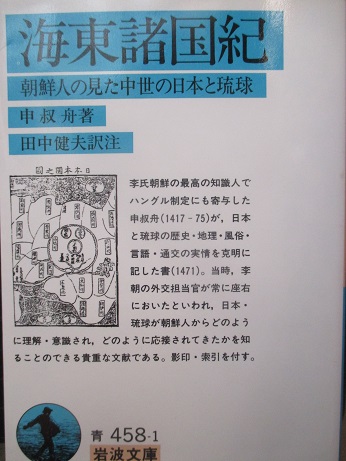
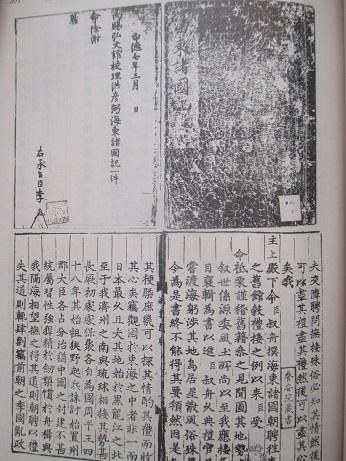
田中健夫訳注 『海東諸国紀 朝鮮人の見た中世の日本と琉球』 岩波文庫、1991年
海東諸国紀』(かいとうしょこくき, 朝鮮語: 해동제국기)は、李氏朝鮮領議政(宰相)申叔舟(しん しゅくしゅう、シン・スクチュ)が日本国と琉球国について記述した漢文書籍の歴史書。1471年(成宗2年)刊行された。 これに1501年(燕山君7年)、琉球語の対訳集である「語音翻訳」が付け加えられ現在の体裁となった。1443年(世宗25年)朝鮮通信使書状官として日本に赴いた後、成宗の命を受けて作成したもので、日本の皇室や国王(武家政権の最高権力者)、地名、国情、交聘往来の沿革、使臣館待遇接待の節目などを記録している。「語音翻訳」は1500年(燕山君6年)に来訪した琉球使節から、宣慰使成希顔が聞き書きし、翌年に兵曹判書李季仝の進言で付け加えられた。→ウィキ
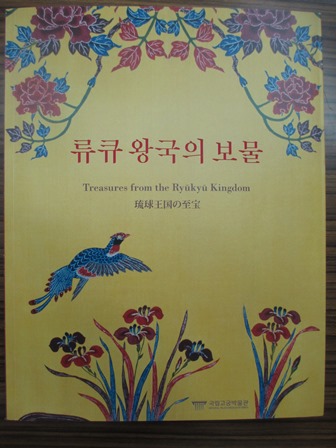
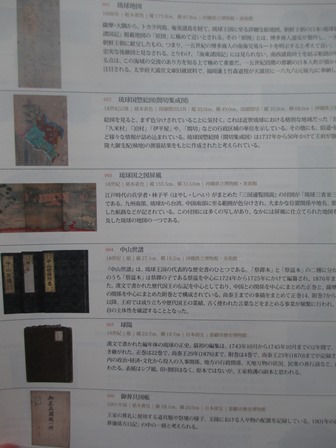
2014年12月9日~韓国・ソウルの国立古宮博物館で「琉球王国の至宝」展
2014年12月9日『沖縄タイムス』琉球王が着用した国宝の「玉冠(たまのおかんむり)」など、琉球国に関する資料約200点を一堂に集めた「琉球王国の至宝」展が9日、韓国・ソウルの国立古宮博物館で開幕する。来年2月8日まで、東アジアの中で独自の歴史と文化を築いた琉球国を、韓国の人々に紹介する。 展示資料は那覇市歴史博物館、県立博物館・美術館、浦添市美術館、美ら島財団(首里城公園)、東京国立博物館などが貸し出している。王族の衣装や当時の風景を描いた絵、高い技術を伝える漆器など第1級の資料が並び、琉球国の文化を伝える。
〇1992年にオープンした国立古宮博物館は、朝鮮時代の宮中で使われていた貴重な物品を文化財として保存、展示しているところです。景福宮、昌徳宮、昌慶宮、宗廟などに分散し埋もれていたこれらの文化財約20,000点あまりを所蔵しています。
1913年5月 『沖縄毎日新聞』襄哉(末吉安恭)譯「朝鮮小説 龍宮の宴」
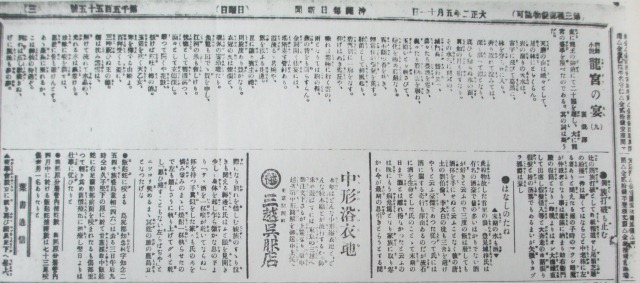
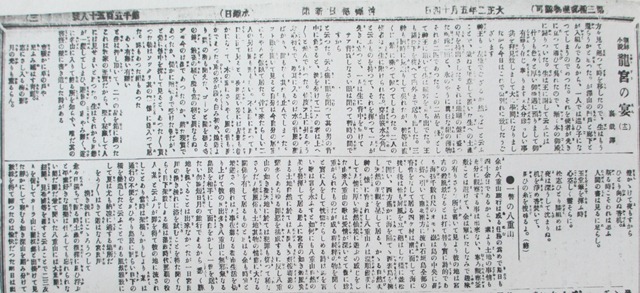
松都に天磨山と云ふ山がある。高く天に沖りてグッと聳へ立った山の姿が厳かなので天磨山の稱も成程と思はせる。この山の中に一つの池がある。周囲は窄いけれど深さが底の知れぬ池で、恰度瓢箪ののやうな形をしてるので瓢淵と云ふ名が利た。
■「金鰲新話」 朝鮮時代初期に政治家であり文学者であった金時習によって書かれた漢文文語体の朝鮮最初の小説です。《萬福寺樗蒲記》《李生窺牆傳》《醉遊浮碧亭記》《龍宮赴宴録》《南炎浮洲志》の5編で構成されています。後世の研究者に依れば元々はそれ以上に書かれていたと推測されていますが、残された資料が少なく定かではありません。また、この作品がその後に書かれた小説に大きな影響を与えたと言われています。ぜひ皆さんもイージー文庫の連載『金鰲新話(クモシナ)』をお楽しみください
王からの招待
松都(高麗時代の都=開城)には天磨山と呼ばれる山がある。その山の高さが天に届く程で、その険しく秀麗である事からその様な名前が付いた。山の中に大きな滝があったが、滝の名を*朴淵(パギョン)と言った。滝つぼの広さはそれ程広くは無かったが、深さは如何程か分からないほどであり、水が落ちてくる滝の高さはとても高かった。この朴淵瀑布(パギョンポクポ)の景色が非常に美しく、地方から松都に来た人々は必ずこの地を訪れて見物して行くの常だった。また、昔からこの滝つぼには神聖な存在が居るとの言い伝えがあり、朝廷では毎年の名節の折に牛を供えて祭祀を執り行っていた。 *朴淵瀑布:高さ37m、幅1.5mの開城にある滝で、金剛山の九龍瀑布、雪岳山の大勝瀑布 と併せて朝鮮三大名瀑に数えられる。
高麗の時代の話である。韓氏の姓を持つ書生が居たが、若い時から書に優れていることで朝廷にも知られ称賛を受けていた。ある日、韓生(ハンセング)は自分の部屋で一日過ごしていると、官吏の正装をした二人の男が天から降りてきて庭にひざまずいた。「朴淵の神龍さまがお呼びで御座います。」韓生は驚きの余り顔色が変わった。「神と人の間は遮られているのに、如何して行き交う事ができるのですか?まして神龍様の居られる水府は水の奥深くにあり、滝の水が激しく落ちるのに如何して行く事ができましょうか?」二人が言った。「門の外に駿馬を準備致しました。どうか遠慮なさらずにお使い下さい。」二人は身体を曲げつつ韓生の袖を引いて門の外に連れ出した。すると外には馬が一頭用意されていたが、金で出来た鞍と玉と絹で作られた手綱で仕立てられており馬には翼が付いてた。その傍には赤い頭巾で額を隠した絹の服を着た10余名の侍従が立っていた。侍従は韓生が馬にまたがるのを助けると、一隊の前に立って先導し、女官と楽隊が後に続いた。また、先の二人も互いに手を取り合って続いた。馬が空中に舞い上がると、その下に見えるのは立ち込めた煙と雲だけであり、他には何も見る事が出来なかった。やがて韓生は龍宮門に到着した。馬から下りると門番たちが蟹、海老、亀の鎧を着て杖を持って立っていたが、その目がとても大きかった。彼らは韓生を見ると皆こぞって頭を下げてお辞儀し用意された席まで案内して休息を勧めた。予め到着を待っていた様であった。彼を案内して来た二人がいち早く中に入って到着を伝えると、すぐに青い服を着た二人の童子が恭しく出迎えて挨拶すると先導を代わった。韓生は先導に従いゆっくりと歩いて宮殿に向った。韓生が門の中に入ると龍王が*切雲冠をかぶり剣を差したまま、手に竹簡を持って階(きざはし)まで降りて迎えた。龍王は韓生を誘い殿閣に上がると座る様に勧めたが、それは水晶宮の中にある白玉の椅子であった。 *切雲冠:雲を衝くほどに高くそびえ立った冠
末吉麥門冬が最初に朝鮮史にふれたのは1915年6月22日『琉球新報』末吉麦門冬「朝鮮史に見えたる古琉球」(1)からである。
1915年6月22日『琉球新報』末吉麦門冬「朝鮮史に見えたる古琉球」(1)
□松下見林の『異称日本伝』の例に倣った訳でもないが、記者は年来琉球史の記実が詳細を欠き、漠として雲を掴むような観あるを、常に憾みとしていた。其の原因は吾々の祖先が文字に暗い上に、筆不精と来てるので、有る事実も材料も使い得ず、官命を帯びて不性無性、筆を執って偶々物したのが、僅かに球陽、中山世譜位のもので其れも憖じいに廻らぬ筆の陳文漢文だから要を得ぬ所が多いのである。其れは先ず正史の方だが沖縄には元来野乗随筆と云った物が無い。正史の缼を補うような材料が得られない。歴史家困らせである。
目下県の事業として真境名笑古氏が満幅の精神を傾けて、材料蒐集に従事して居らるるが、氏も常に語って委しからず、録して汎ねからぬ史籍に憾みを抱き是ではならぬと本邦の史籍は無論支那朝鮮の史料まで眼を通さねばならぬと云って望洋の歎を発している。幸いに氏が不撓の努力と燃犀の史眼は、沙礫の中から珠玉を拾うような苦心で新材料が一つ一つ机の上に転がって来る。其の愉快は又学者ならでは味わえぬことだろう。此の新材料提供の泉の一つが朝鮮の古書である。流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の國ではある。蔚然たる古記録には東洋各國の史料が束になって這いっている。一たび其の堆土の中に熊手を入るれば、敕々雑々として葉山の秋の落葉を掻くが如きものがある。記者も眠気醒ましに熊手代わりの雑筆を揮いて高麗山の落葉を掻いて荒れたる史田の肥料にでもと思い立ちぬ。
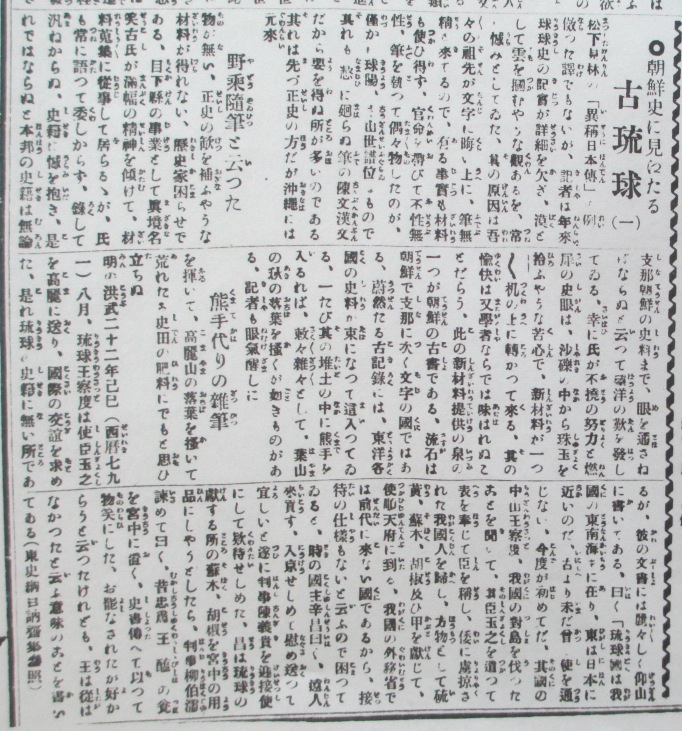
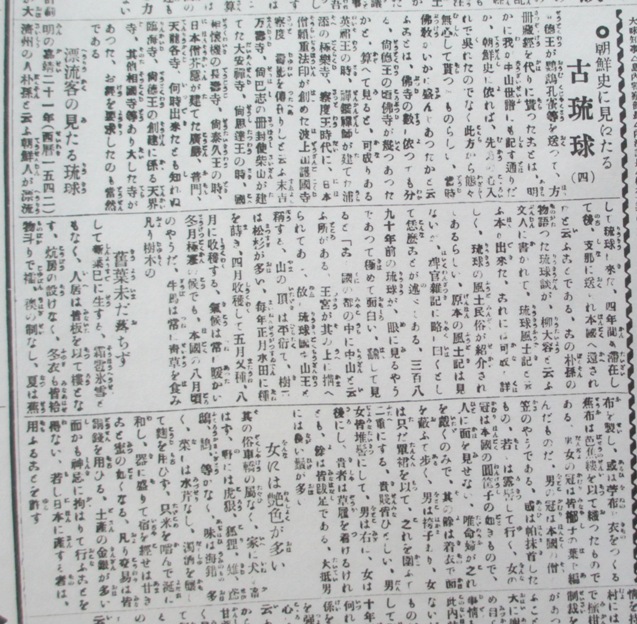
麦門冬が引用した文献資料
○りゅうひぎょてんか【竜飛御天歌】 朝鮮の李朝建国叙事詩。鄭麟趾らの撰。1447年刊,木版本。10巻,125章から成る。初章1聯,終章3聯以外は2聯で,対になったハングル歌,そして漢詩訳が続く。前聯は中国の故事,後聯は朝鮮の事跡で建国の正当性を主張する。世宗(せいそう)前6代祖の事跡を述べるが,太祖(李成桂)に最も詳しい。110章以降は後代の王への訓誡。ハングル(1446年訓民正音として制定)による最初の資料で,注は漢文で書かれて長く,高麗末から李朝初期の中国東北部や日本に関する記事もあり,文学・語学・歴史的にも重要である。
(コトバンク)
○櫟翁稗説・筆苑雑記 李斉賢/徐居正著
高麗・朝鮮王朝の古典の翻訳
韓半島に栄えた高麗・李氏朝鮮の両王朝の2人の高官が書き残したさまざまな人物評や風聞、笑い話、風俗、官僚の姿、制度などの記述に豊富な注と解説を加えた歴史的古典の翻訳。 韓流ブームの中にあって、解説書や入門書の紹介は数多いが、本格的な当時の古文書を翻訳したものは少ないので貴重な書籍である。 とはいえ、全体が短い文でつづられているので、出てくる人物のことやその他の情報を知るにはいささか厳しい。それこそ多数の人物が登場するが、注を読んでもさっぱり分からないことが多い。 しかし、当時の人物が直接書いた感想や評伝なので、歴史的な事実の裏側を知るには貴重な文献とは言えるだろう。 高麗王朝の高官だった李斉賢の「櫟翁稗説」の解説には、当時の高麗王が元の侵略によって、その後の王の名前に「忠」が付いたものが多いことが指摘されている(「忠烈王」「忠宣王」「忠粛王」「忠恵王」など)。
これは解説によれば、「元の圧力によって高麗王は『宗』や『祖』を名乗れなくなったのである」とある。要するに、「『忠』などというのは臣下の徳目であって、王の徳目としてはありえない。最高主権者は『忠』であるべき対象をもたないはずだが、高麗王は元の皇帝に『忠』であることを強制されたのである」。 そのことは世継ぎを「太子」と呼ぶのではなく、「世子」と呼ぶようになったのも元の干渉からきていると訳者は指摘している。 また、李氏朝鮮王朝の高官だった徐居正の「筆苑雑記」では科挙の試験に昔は酒食がふるまわれたことや日本の戦国大名の大内氏の祖先が新羅から来ているのではないかと考察したものや7代王の世祖の時代に「女と見まがう容貌」の男がいて、罪人として法によって処刑することを司法関係の役所では願ったが、王が大目に見て却下したことなど興味深いエピソードが記されている。 (梅山秀幸訳) 中山雅樹
10/31: 令和元年10月31日 百浦添御殿 焼失
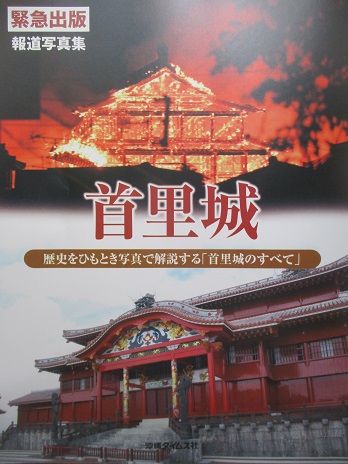

2019年11月15日 『報道写真集 首里城』沖縄タイムス社
2019年10月31日朝一番、ネットのニュースで「首里城公園付近で黒煙が上がっている」首里城の正殿は、いまも延焼中だという。けが人の情報は入っていないという。パリのノートルダム大聖堂の火災以上にショック。木造なので火災には十分に警戒しているはずだが。テレビをつけると、正殿が崩れ落ちる映像、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件のテレビ映像と同様の衝撃であった。かつて又吉真三氏から首里城復元の話を聞き、「大阪城に倣いコンクリートで造ったらどうですか」と言ったら「建築技術継承」の意味合いで木造でなければならない、と言われたが、やんぬるかなである。「建築技術継承」は先の復元過程で建築技術も確認されたであろうから、今後は元々の材質に拘らず火災に強いもので再建すべきだと思う。それより所蔵の文化財は無事だろうか。台風、水害と消費税、アベ主導の「れーわ世」になってからロクな事はないわな。
参考〇沖縄県は1日、沖縄美ら海水族館(本部町)と首里城正殿などの有料区域(那覇市)の管理を始めた。今後は県が指定管理者に指定した沖縄美ら島財団(本部町)が両施設の実質的な管理・運営を担う。指定管理の期間は2019年2月1日から23年1月31日まで。これまで両施設は国が管理してきたが、県へ管理が移行した。今後も両施設の所有権は国が持つため、県は国有財産使用料として年間約7億円(美ら海水族館約5億円、首里城約2億円)を国に支払う。財源は両施設の入場料と売店収入で賄うため、県の財源からの支出はない。現在、入場料の変更なども予定されていない。
県は管理移行に合わせて、安定的な運営維持のために「沖縄県国営沖縄記念公園内施設管理等基金」を設立。財団が毎年県に納める固定納付金(年間約9億円)と歩合納付金から成り、大規模修繕や整備が必要になった場合に支出する。
『沖縄タイムス』11月12日首里城火災で、全焼の正殿など被害に遭った7棟9施設について、損害保険の評価額が100億3500万円に上ることが11日、分かった。県議会(新里米吉議長)の全議員対象の説明会で、首里城を管理運営する沖縄美ら島財団の担当者が明らかにした。財団が年間2940万円を支払っている保険の支払限度額は70億円で「保険会社が現地を調査し、査定する。評価額は100億円だが、支払額が70億円を上回ることはない」と答えた。建物の評価額は、保険料を決めるために建物の価値を算出したもの。9施設の当時の建設費は正殿で33億円、南殿、北殿など3施設で21億円、黄金御殿など5施設で19億円の計73億円だった。
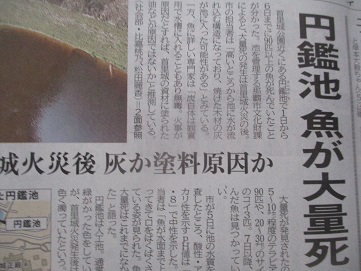
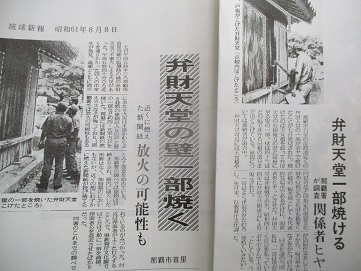
2019年11月16日『沖縄タイムス』「円鑑池 魚が大量死」〇「円覚寺(えんかくじ)」の前の池は「円鑑池(えんかんち)」、池の中央にある赤瓦の堂を「弁財天堂(べざいてんどう)」という。→首里城公園/1986年8月8日『琉球新報』「弁財天堂の壁一部焼く」、8月7日『沖縄タイムス』
1879年 首里城、第六師団熊本分遣隊の兵舎が置かれ、陸軍省所轄地となる。
1904年4月 首里区立工業学校、当蔵の民家から首里城書院に移転
1908年 首里市立女子工芸学校、赤平義村家跡校舎より首里城内に移転
1909年、首里市に壹千五拾四圓五拾五銭にて払下(南風殿、正殿、西殿、鎖の間書院、王子居室、王王妃室、世誇殿、銭蔵、寝廟殿、廣福殿、用物奉行所料理座、門番所、二階殿、厩係詰所、アヤメ居室、奉神門、金蔵,竃家、下役料理座、鐘撞堂、右掖門、淑順門、漏刻門、瑞泉門、久慶門、歓会門、美福門、継世門、衛兵所、洗面洗濯所、銃工室、浴室、伝染病室、敷石、哨兵舎、体操器械、物干)
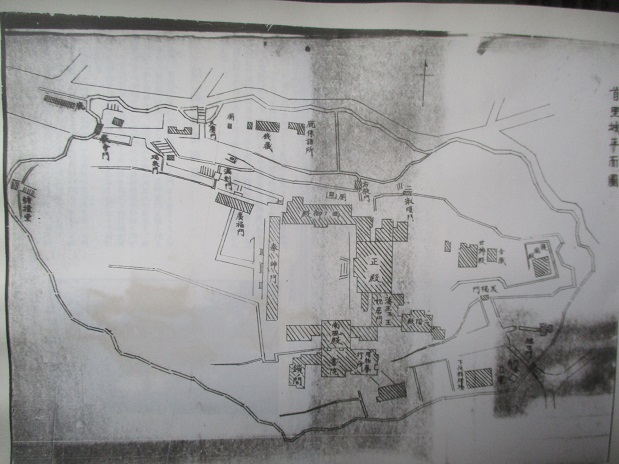
1931年10月 『首里市制十周年記念誌』首里市役所
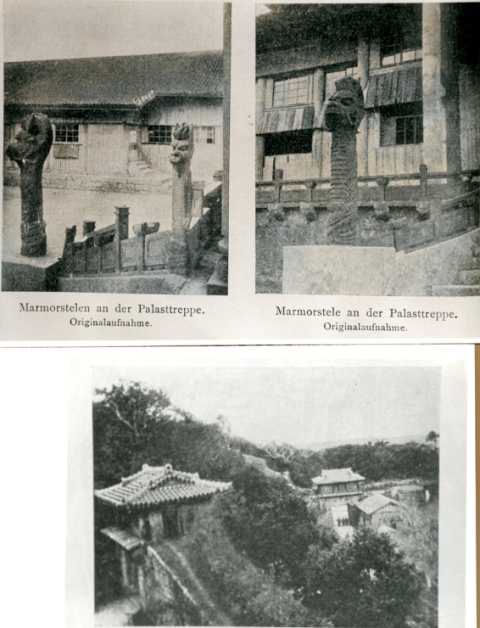
1910年3月7日 ドイツ人エドモンド・シーモン馬山丸で来沖
1910年 首里高等尋常小学校、校舎狭にして一部生徒を首里城西の御殿に仮教室を設けて収容
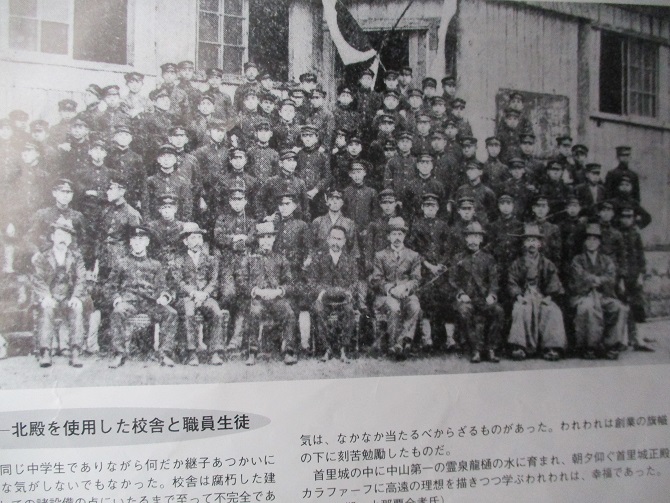
1910年4月 沖縄二中、沖縄中学校の分校として首里城北殿に開校。翌年4月、独立(初代校長・高良隣徳)
2019年1月 国梓としひで『太陽を染める城ー首里城を蘇らせた職人たちの物語』沖縄建設新聞
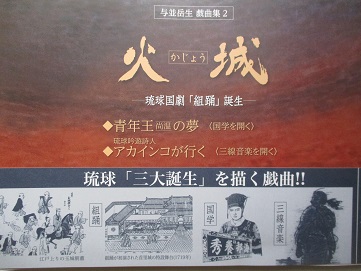
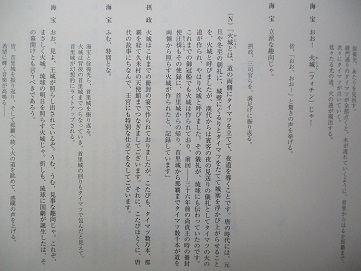
2019年3月 与並岳生 『火城』「●組踊 首里城炎上、大飢饉・・・未曽有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!!●国学 国造りは人造りー琉球人材育成をめざして、「海邦養秀」のスローガンのもと「国学」は誕生した。若き尚温王の教育立国の理念が燃える!●三線音楽 「歌と三線の昔始まりや」-伝説のアカインコ青春行状記! 」新星出版
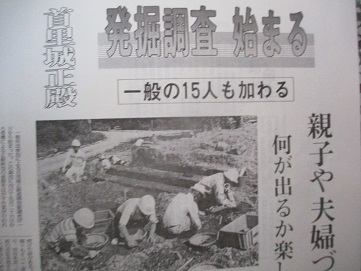

1985年8月1日『沖縄タイムス』「首里城正殿 発掘調査 始まる」/9月7日『琉球新報』「予想以上にひどい首里城の戦災」
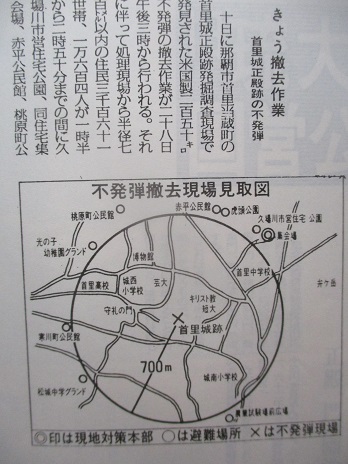
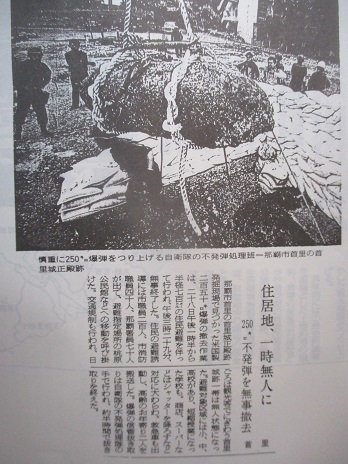
1986年11月28日『沖縄タイムス』/1986年11月29日『沖縄タイムス』「首里城正殿跡発掘現場で見つかったアメリカ製250キロ爆弾撤去」
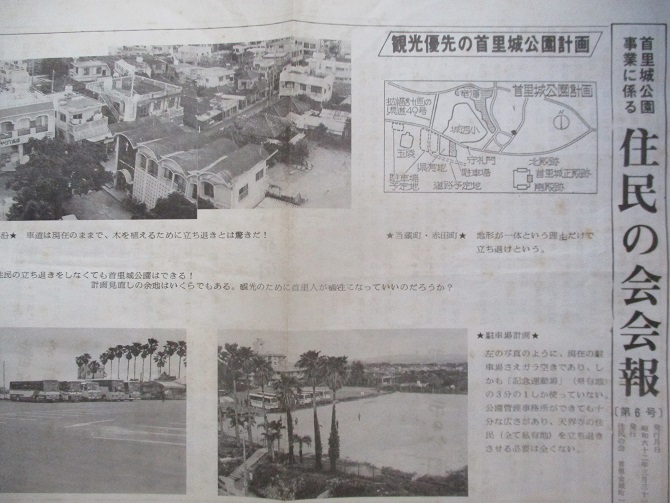
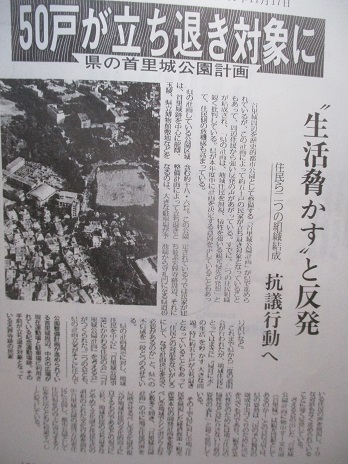
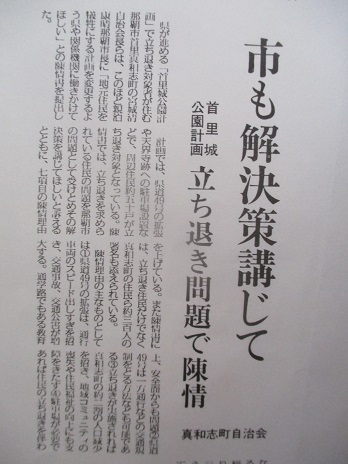
1986年12月4日『琉球新報』/1986年12月22日『沖縄タイムス』
首里城復元に関わっていた又吉眞三氏から、「新城君、君の提供した資料で寸足らずの龍柱が本来の高さに復元出来そうだ」と喜んで居られ、かつ話された、その資料を『首里城復元期成会会報』第7号で紹介してほしいと。同誌に載せたのが比嘉朝健「琉球の石彫刻龍柱」である。
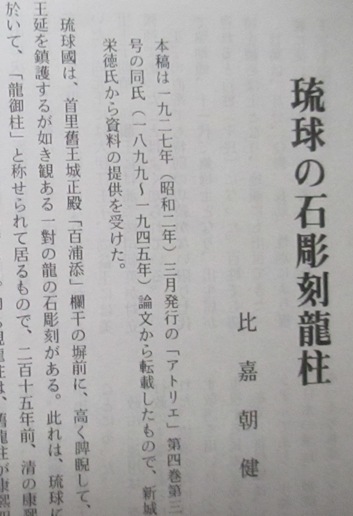
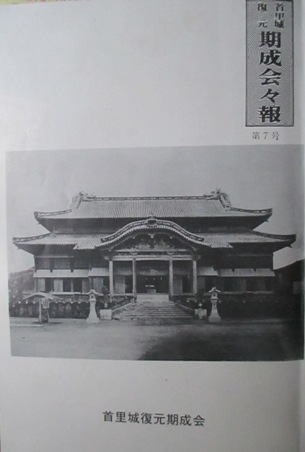
□本稿は1927年(昭和2)3月発行の『アトリエ』第4巻第3号の同氏(1899~1945)論文から転載したもので、新城栄徳氏から資料の提供を受けた。


1974年8月6日『琉球新報』又吉真三「首里城跡の復元をめぐって=文化遺産の活用とあり方=」/1984年11月27日『琉球新報』「首里城・石造欄干の親柱 完ぺきな形で残る」


前列右から宮城篤正氏、又吉真三氏、後列右から首里城復元で「古文書の鬼」と謂われた高良倉吉氏、新城栄徳。/又吉眞三氏を囲んでー右から3人目が又吉眞三氏、左奥から西村貞雄氏、新城栄徳。左手前が首里城の瓦を制作した奥原崇典氏の兄・奥原崇仁氏
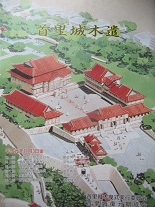
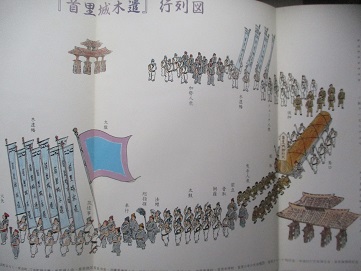

1989年11月3日「首里城木遣」
又吉氏は沖縄県建築士会会長、沖縄県文化財保護審議会会長もつとめ琉球の建築文化史にも詳しい。私は宮内庁三の丸尚蔵館の山本芳翠「琉球中城之東門」の門は又吉氏と検討し「美福門」と断定、1989年11月発行『沖縄美術全集』の年表にその旨を記した。また首里城北殿の階段の問題も相談に乗ってもらい新聞に発表した。
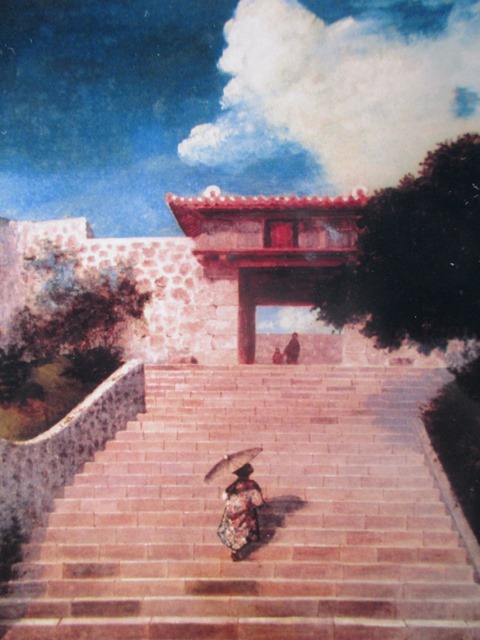

「琉球中城之東門」/北連蔵画「山本芳翠像」

山本芳翠「浦島」
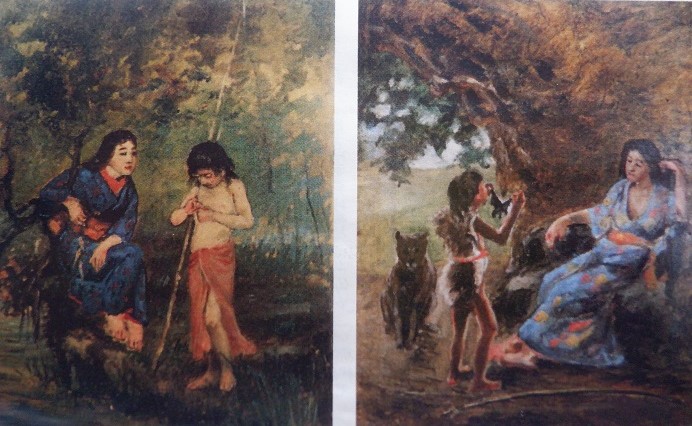
山本芳翠「琉球風景」
首里城北殿の階段 大龍柱は正面を向いている。
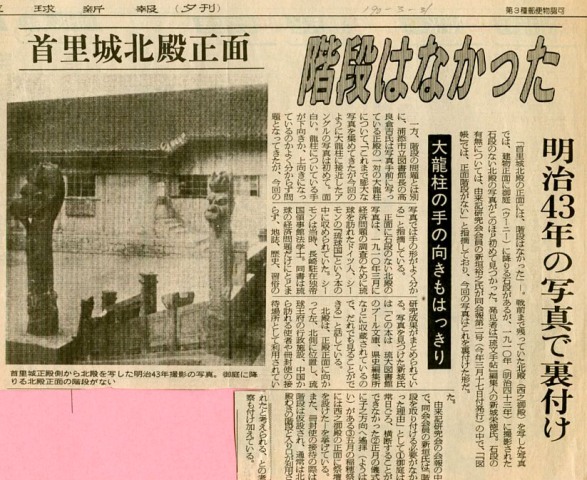
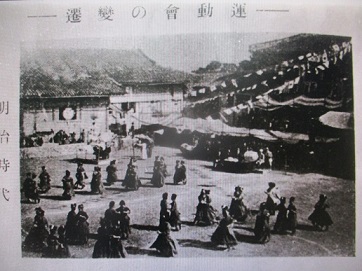
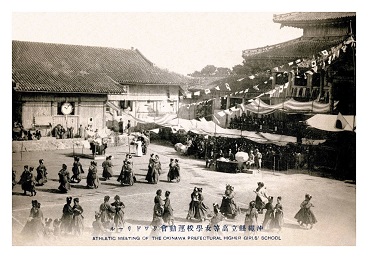
1937年1月『姫百合のかおり』/大塚努(京都市)2019-11-5「1907年ー沖縄県立高等女学校運動会」
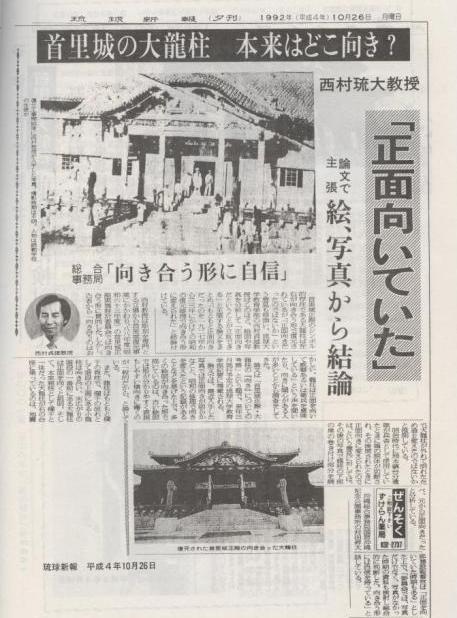

1993年3月27日『琉球新報』「首里城正殿の大龍柱/大龍柱を考える会(宮里朝光会長)『やっぱり正面向き』」

『沖縄タイムス』2019年11月5日〇復元された首里城の龍柱を制作した彫刻家で琉球大学名誉教授の西村貞雄さん(76)=糸満市=は、独自の造形文化が詰め込まれた城の変わり果てた姿に「研究と技術の集積が一瞬にして消えた。でも手掛かりがほとんどなかった戦後の復元と比べ、資料はある。再建に向けもう一度全力投球だ」(略)基本・実施設計の委員で龍柱を含む正殿の復元作業に携わった。わずかに残った戦前の写真や図面を観察し、中国や東南アジアなどを視察した。龍のうろこや背びれの数を数えて柱の高さを確認するなど、地道な作業で戦前の姿を解明していった。
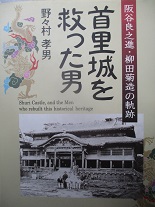
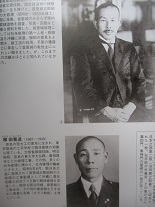
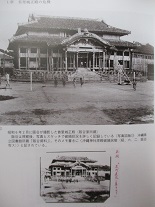
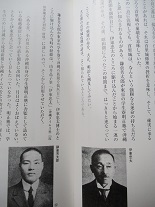
1999年10月 野々村孝男『首里城を救った男ー阪谷良之進・柳田菊造の軌跡』ニライ社
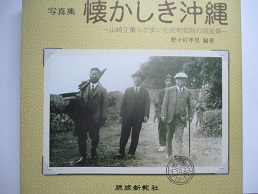
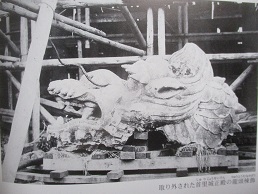
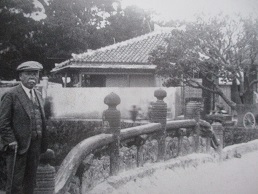
2000年11月 野々村孝男『写真集 懐かしき沖縄~山崎正董らが歩いた昭和初期の原風景から』琉球新報社
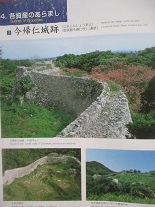
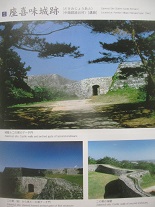
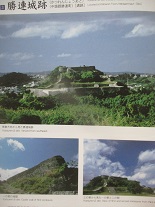
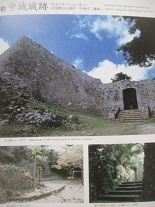
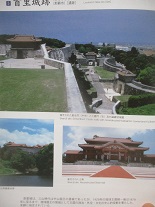
2001年3月「世界遺産 琉球王国のグスク及び関連遺産群」沖縄県教育庁文化課
『琉球新報』2019年9月5日ーしまくとぅばの保存、継承に尽くした沖縄語普及協議会名誉会長の宮里朝光(みやさと・ちょうこう)さんが1日午後2時38分、老衰のため那覇市首里平良町の自宅で死去した。95歳。那覇市首里出身。告別式は5日午後2時から3時、那覇市首里山川町3の1の首里観音堂で。喪主は長男聖(きよし)さん。2000年に沖縄語普及協議会を設立し、06年の「しまくとぅばの日」(9月18日)の制定に尽力した。しまくとぅば指導講師の養成にも取り組み、しまくとぅば保存・継承の機運をつくった。琉球王府の迎賓館ともいわれ、沖縄戦で消失した御茶屋御殿(うちゃやうどぅん)の早期復元を求める御茶屋御殿復元期成会の会長も務めた。沖縄語普及協議会は16年、第38回琉球新報活動賞を受賞した。
11/15: 世相ジャパン⑬/猛火とフェイクに耐えた大龍柱
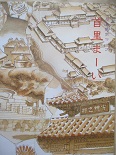
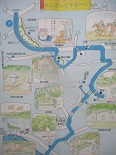

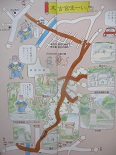
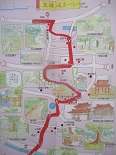
1987年9月 「歴史散歩マップ 首里マーイ」(イラスト・新里堅進)那覇市教育委員会文化課
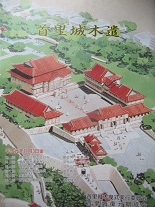
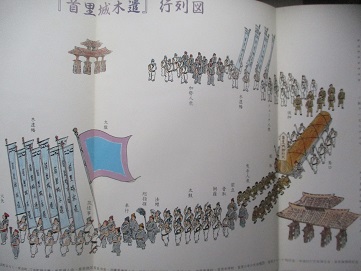

1989年11月3日「首里城木遣」
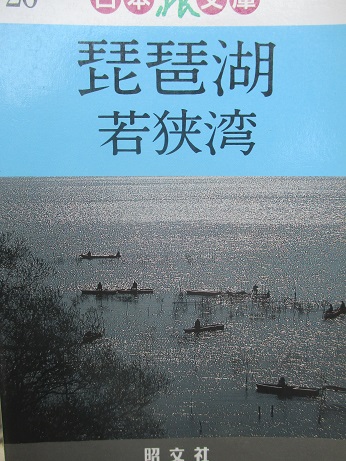
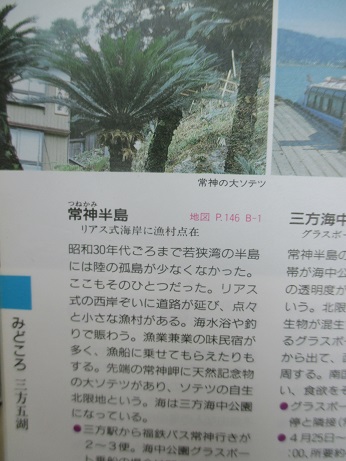
1991年7月 日本旅文庫『琵琶湖・若狭湾』昭文社
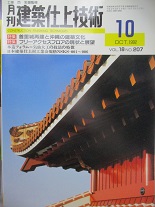
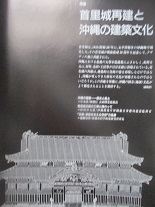


1992年10月 『月刊建築仕上技術』「首里城再建と沖縄の建築文化」工文社


久能山東照宮- 国宝 拝殿・本殿 〈静岡県静岡市〉 /朝鮮ソテツと鼓楼(ころう) →行って見たい神社とお寺

斎藤 陽子(Walnut, California)2019-11-24 10年物のソテツです、こちらは乾燥しているので水やりが欠かせません。


2016年1月8日 若狭の龍柱
安田浩一2018-11-3「沖縄の龍柱は、沖縄のものです」若狭の「龍柱」のデザイン日本列島は龍の形をを担当したのは、沖縄美術界の大家として知られる琉球大学名誉教授の西村貞雄さんだ。「私も『中国の手先』などと直接に面罵されたこともあります。一部で龍柱の意味がまったく理解されていないのが本当に残念です」そう言って、西村さんは悔しそうな表情を見せた。「沖縄の龍柱は、沖縄のものですよ。だいたい、中国各地に存在する龍柱とは形状からして違います」たとえば、中国特有の「龍柱」は、那覇市内の中国式庭園「福州園」に足を運べば目にすることができる。(略)中国式「龍柱」は、龍が柱に巻き付いた形状となっているのに対し、沖縄の「龍柱」は、龍の胴体そのものが柱となっている。そう、デザイン的にはまったくの別物なのだ。

福州園は中国福建省福州市(ふっけんしょう・ふくしゅうし)と那覇市の友好都市締結10周年と、那覇市市制70周年を記念して、1992年に完成しました。園内は中国の雄大な自然と福州の名勝をイメージして造られている。
「私はアジア各国を回って龍柱を見てきましたが、中国の影響を受けつつも、それぞれの国がそれぞれの龍柱を持っている。爪の数にしても同様です。属国の龍柱は5本爪であってはならないというのが通説ですが、私から言わせれば、これも怪しい。モンゴルには3本爪、4本爪、5本爪の三種の龍柱がありましたし、韓国には6本爪の龍柱がありました。私が若狭の龍柱を4本爪にしたのは、単に沖縄の伝統的な龍柱が4本爪だったからにすぎません。歴史どおりに、伝統に基づいてデザインしただけです。そこには中国への忠誠だの、そんな意図が含まれているはずがない。仮に批判を受けいれて5本爪にしたら、それは歴史を無視した、きわめて政治的なデザインとなってしまうではないですか」西村さんによれば、若狭の龍柱には、沖縄の歴史と未来への思いが込められているという。
「一対の龍は向き合っているのではなく、海の方角を向いています。つまり、尾の部分は首里城までつながっているという想定です」西村さんは、これを「龍脈」と呼んでいる。龍のからだは首里城から国際通りの地中をくぐり、海岸線で地中から垂直に飛び出る、といったイメージだ。首里城は沖縄の源流であり、国際通りは戦後復興の象徴である。そして若狭の港は外に開ける海の玄関だ。つまり、この「龍脈」は沖縄の歴史を意味する展開軸、導線なのだ。「龍の頭が海を向いているのは、その先の未来を見ているからなのです。水平線の先にあるニライカナイ(理想郷)ですよ」「龍脈」は過去と未来を結ぶ。中国とも侵略とも関係ない。龍の目玉はニライカナイの海を望む。


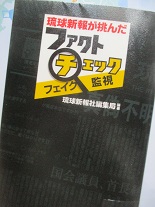
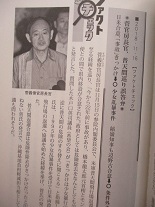
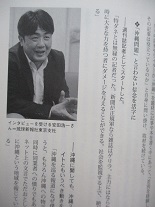
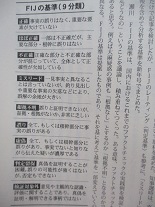
2019年9月 琉球新報編集局『琉球新報が挑んだファクトチェック・フェイク監視』高文研

写真左よりー安田浩一氏、平良肇氏、島袋和幸氏、長嶺福信氏
2017年11月3日13:00 なは市民活動支援センター第三会議室「〔検見川事件を語る会〕学習会」
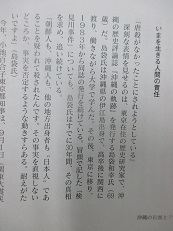

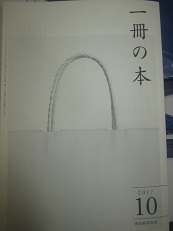
2017年10月 朝日新聞出版『一冊の本』安田浩一「沖縄の右派と〔プロ市民〕7 人々を虐殺に向かわた回路」
安田 浩一(やすだ こういち、1964年(昭和39年)9月28日 - )は日本のジャーナリスト。日本労働組合総評議会(総評)系の機関誌『労働情報』編集委員。静岡県出身。千葉県在住。慶應義塾大学経済学部卒業。伊豆半島の温泉地帯に生まれた。日本経済新聞など様々な新聞社、出版社の記者を経て『週刊宝石』の記者だった1999年(平成11年)前後に、同誌にて創価学会の批判記事を書いていた。『サンデー毎日』時代は名誉毀損で訴えられ、証言台に立った。→ウィキ2014年9月 佐野眞一『あんぽん 孫正義伝』小学館文庫 解説・安田浩一

御菓子御殿 国際通り松尾店ー私が奥原崇典氏(首里城の瓦を手掛けた。1950年-2014年3月12日)を最後に見たのがこの柱の龍を仕上げているときである。
2014年5月20日~6月22日 沖縄県立博物館・美術館「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した美」
同時期開催/6月3日~8日 西村貞雄主催「復元のあゆみー琉球王朝造形文化の独自性を求めてー」


石川和男氏、松島弘明氏

1991年4月19日『レキオ』

末吉安允氏(末吉麦門冬の甥)と西村貞雄氏〇11月5日の沖縄タイムス文化欄に、大城立裕さんが焼けた首里城について「当時の持ち主であった首里市は、取り壊しにかかったが、識者の末吉麦門冬の注進で、建築家の伊東忠太が文部省(当時)に掛け合って温存され、2年後に国宝に指定された」と書いておられるが、結果論としては合っているが、具体的な経緯は別にある。

平良昭隆氏、平良知二氏、新城栄徳、宮城篤正氏

2019年11月12日『沖縄タイムス』宮城篤正「視点 焼けた首里城」

2014年6月5日ー左から伊佐眞一氏、西村貞雄氏、亀島靖氏


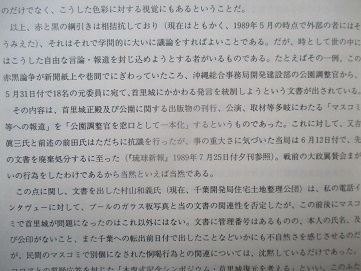
1991年1月 伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子〇編集後記に下の新聞記事の解説

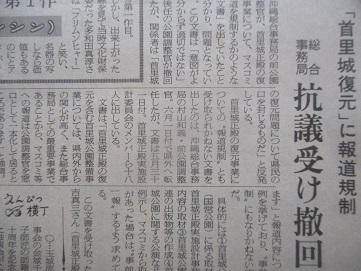
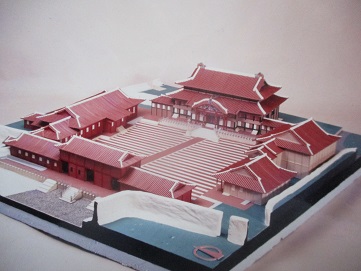
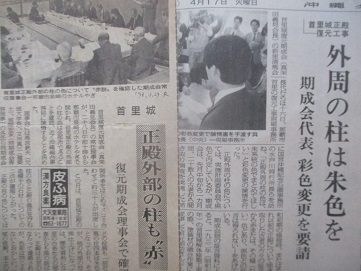


新城栄徳、西村貞雄さん
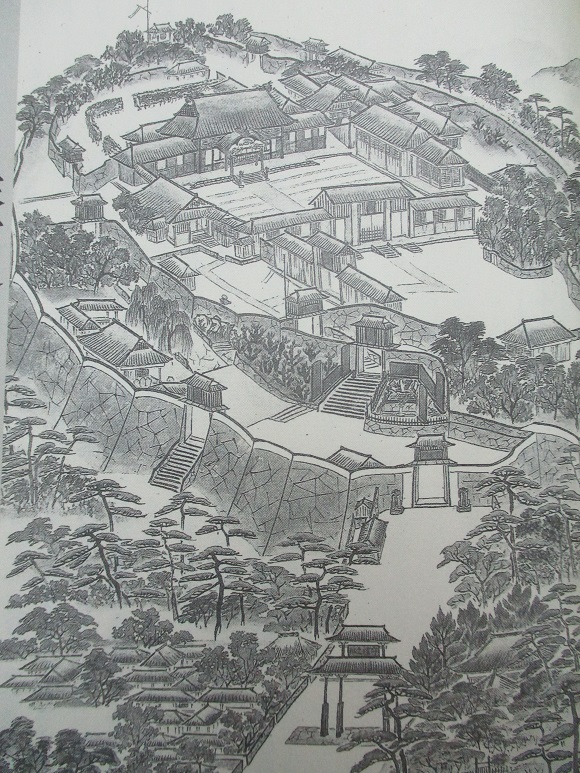
06/22: 世相ジャパン㊲/2020-6④






粟国村観光協会 6月28日 「フェリー粟国」最後の運航日 粟国港を出港する前にセレモニーが執り行われました。最後に”ありがとー”と紙テープで見送りました。
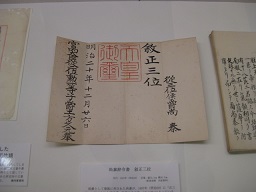
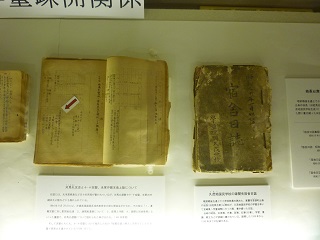

那覇市歴史博物館 6月25日 · 常設展の展示資料紹介
常設展示室では、琉球王国時代から沖縄戦までの資料を展示して、那覇の歴史を紹介しております。トピック展示として、沖縄戦関係の貴重な資料(宿舎日誌など)も紹介しておりますので、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。さて、今回は展示資料の一つ「尚泰辞令書」(尚泰宛 叙正三位位記)を紹介いたします。こちらの資料は天皇から位階を勅授する際に発行した公文書となります。天皇から位階を授けられたのは、琉球王国最後の国王であった尚泰となります。
1879年4月いわゆる「琉球処分」により琉球王国は事実上なくなり、日本の一部として沖縄県が設置されます。最後の国王であった尚泰は同年5月27日に那覇を出港し、上京しました。東京麹町区富士見町の邸宅を与えられ、1885年5月には旧藩主層(尚泰は琉球藩王とされていた)のなかでは大藩並みの扱いとなる侯爵に叙されます(爵位は最も上位が公爵で、以下は侯・伯・子・男爵と続きます)。尚泰は華族の一人として東京で暮らすことになったのでした。今回展示している資料は、侯爵に叙された2年後に正三位に叙された内容となっています。上京後は来客を絶ち、読書に傾注したといわれる尚泰は、どのような思いでこの公文書を受け取っていたのでしょうか。

大濱 聡 6-25
斎藤 陽子 (Walnut, California)6-25 日本時間あと1週間で6月も終わり、コロナ禍で落ち着かない生活を重ねている内に、今年も半年が過ぎてしまいます。3月から始まったロスアンゼルスの、新型コロナウィルスとの闘いの、自宅待機も97日目となりました。南カリフォルニアの日中は27℃ほどと幾らか暑くなりましたが、夜間は12℃と冷え込み、布団が欲しいほどで、昼と夜の気温差が大きいです。
10年前のお正月には常夏のインドネシアで1週間を過ごし、海釣りを楽しもうと沖に船で出ましたら、おびただしいレジ袋やペットボトルが潮の流れに沿って流れている様を見て、釣りをする気になれず早々にホテルに帰って来た記憶があります。日本でもやっとプラスチィク削減目的の、レジ袋使用が見直され、この7月1日からレジ袋を廃止しするようですが、すでにカリフォルニアでは2014年から、スーパーの買い物は自分の「買い物袋」持参が日常化して定着しております。




さて、きょう掲載しますこの写真は過去に数回掲載していますが、再掲載いたします。既にご存知の方も居ると思いますが、今日の投稿をご存じの方は相当な農業通ですが、この実が何かご存知でしょうか。農業に詳しい方でも、ご覧になった人は少ないと思いますが、おそらくカリフォルニアの人でも、この実を知る人は少ないと思います。これは収穫前のピスタチオの実なのです。ピスタチオの実は銀杏やオリーブぐらいの大きさで、果肉はまったく松の葉と同じ匂いがし、この実の中の種子がピスタチオとなります。原産は古代トルコ、ペルシャなどの地中海沿岸で、農耕文明の初期以来、この地に自生していた原種を食用に栽培してきたといいます。一部のアラブ系、アルメニア系、トルコ系などの人達のみに親しまれてきて、その後、植物愛好家が種子をローマに持ち込みヨーロッパに広がり、熟した種子を殻果ごと焙煎し、塩味をつけたものを食用としました。ピスタチオグリーンと呼ばれる緑色が残り、味は他のナッツ類と異なる独特の風味があり、「ナッツの女王」とも呼ばれています。
40年前まではアメリカもピスタチオは中東からの輸入品が主流でしたが、ご存知のように中東は紛争地帯と化して以来、カリフォルニアはオレンジ栽培が主流だった農場を30年前ほどから、ひたすらピスタチオ生産へと転換しピスタチオ農地を拡大し、今ではすっかりカリフォルニア名物のピスタチオとなりました。南カリフォルニアからサンフランシスコに行く途中の、サンウォンキン・バレーという広大な農業地帯では地平線の彼方まで、中東に似た乾燥した気温と太陽の恵みを得て、ピスタチオ畑が広がっています。ピスタチオ畑を訪ねた時は果肉がホンノリと色ずき始めたいました、ピスタチオの実の収穫期は8月から10月まででます。銀杏の様に果肉を取り除いて中の種子を焙煎加工して、ピスタチオは市場に出されますが、その集荷場と加工工場は大きな敷地を有し、その施設に相当な資本力を感じました。
海鳴りの島から6-24 昨日23日は「沖縄戦慰霊の日」で、沖縄は公休日だった。沖縄防衛局も県民からの反発を恐れて工事を止めていたが、一夜が明ければこのような状況だ。沖縄戦の犠牲など日本政府・防衛省にとっては、国土防衛のための献身でしかない。沖縄に新たな犠牲を強いることに、何のためらいもない。
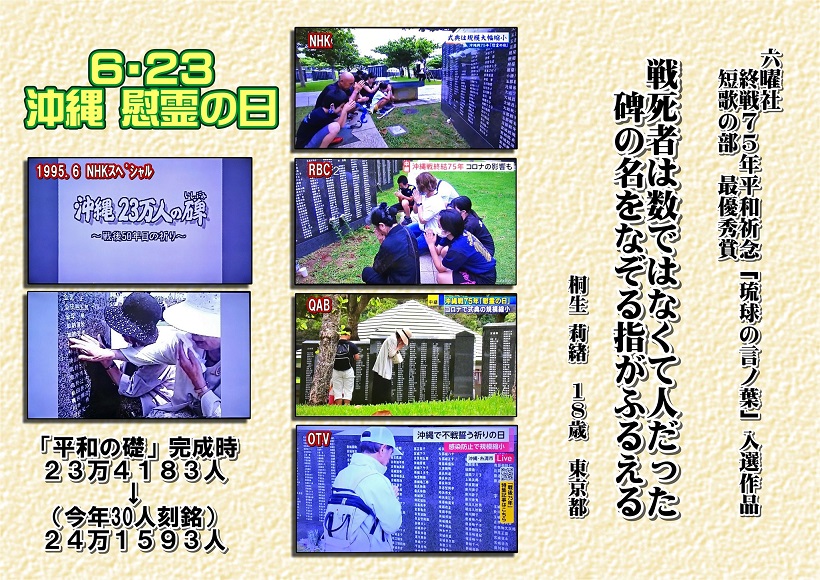
大濱 聡 6-23■今日6.23は沖縄の「慰霊の日」。東京の六曜社(イベント企画・運営、書籍出版)が公募した〈終戦75年平和祈念「琉球の言ノ葉」〉の短歌の部で最優秀賞になった東京の高校生(18歳)の作品がとてもすばらしい。
戦死者は数ではなくて人だった碑の名をなぞる指がふるえる【選評】碑に刻まれた人々の名に死を強く実感した作者。その衝撃が「数ではなくて人だった」と直截に述べられ、読む者の胸をつく。この世に生まれた一人一人が名を持つこと、そして戦争によって生を奪われたことを改めて教える。■今日の「沖縄全戦没者追悼式」で朗読された平和の詩「あなたがあの時」の作者もまた女子高校生(17歳)で、聞く者の心に響く詩だった。若い人たちに戦争の記憶と、「反戦・平和」の思いが継承されていることが嬉しい。■戦後50年の1995年、完成した「平和の礎」をテーマにした「NHKスペシャル 23万人の碑~戦後50年目の祈り~」で制作統括を務めた。完成時に23万4183人だった刻銘者は毎年追加され、今年の30人を含めて24万1593人になった。


青山恵昭 6-23 きょう沖縄反戦平和追悼、摩文仁平和祈念公園にて。
斎藤 陽子(Walnut, California)6-23日本時間 【慰霊の日を迎えて思う】(前略)戦争が終わって3ヶ月目、沖縄 石川の捕虜収容所のテント小屋で、頭にDDTの粉の洗礼を受けた日が、私の沖縄での幼い記憶の最初です。収容所生活の後は玩具も遊び場もないテント生活の、当時6歳の私の様な子どもたちは、戦争の跡の焼け野が原で頭蓋骨など人骨を拾って遊ぶのが、子供たちの当たり前の生活でした。無名の人骨を拾ったら「この穴に投げ入れなさい」と言われたプールのような大きな穴には、沢山の人骨が有ったのを幼い子供だったのにも関わらず、今でも鮮明に覚えています。6歳に野原で拾った骨を投げ入れたプールのような丸い穴は、今では蓋ができ「魂魄コンパクの塔」となって35000人の焼け野が原に散乱していた無名の方がたの遺骨が収められています。摩文仁の丘には多くの慰霊碑がありますが、「魂魄の塔」だけが唯一遺骨の入った慰霊塔でした。
小学校では戦火の中で孤児となり、自分の名前も歳もわからない子どもたちが、西原の孤児院「厚生園」から首里の小学校のクラスに数人通ってきていましたが、あの方たちの将来はどうなったのでしょう。小学校の校舎もない時代、木陰での青空教室が小学校がわりの時代で、教科書も無くノートはわら半紙で針と糸で綴じて作った、ノート持参での一年生でした。沖縄はその後やがて、廃墟の焼け野が原から人びとは立ち上がり、日本政府とは交渉の交流の無い沖縄でしたが、人々は自力で必死で復興への道をひた走り、当時は米軍から戦利品をくすねるのが当たり前の生活で成功を収めた人もいます。かたわら瀬長亀次郎氏が独り「反米、反戦」を叫んでいましたが人々は生活に追われて、瀬長亀次郎の街頭演説を真剣に聞いている人は余りいませんでした。
終戦から米国軍が発行して使用していた軍票B円が、突然、軍票160円が米国1ドルと切り替えられたのも高校時代でした。二日間だけのドルへの切り替えの日には、銀行の屋根の上や銀行入口には、米軍の警備がカービーン銃を持っていた、物々しい光景は今でも忘れることができません。高校の文芸誌は反米思想に偏ってないかの検定を琉球民政府に許可を受けなければならず、反米文章は発刊できない時代でした。また我が首里高校が沖縄で始めて、甲子園で戦った後に甲子園の土を持ち帰ったところ、甲子園という外国からの土は検疫法に違反するとのことで、那覇沖の上陸前の船上で海へ投棄しなければならなかった事件などは、多感な高校生に「甲子園は沖縄にとって外国」という現実を突きつけられて、悔しい思いをしたものです。
18歳の高校生を終わるまでを沖縄で過ごした日々は、まさしく戦後の混沌とした沖縄の歴史を目の当たりにして生きてきました。そして琉球民政府発行の身分証明書をパスポート替わりに持っての、東京での学生生活は60年安保闘争中、デモ隊の中で樺美智子さんが亡くなると言う事件が、私の大学生活の幕開けでした。学生生活と獣医研修等で過ごした7年近くの東京生活では「オキナワ人」と偏見の眼差しで見られる経験を常時し、何故か沖縄人であるがゆえに肩身を狭くして生きていた自分がいました。そして1ドルが360円という留学生には過酷なドル事情のなか、53年まえに、アメリカへと留学して行ったのです。これらのすべての日々をなぜか「慰霊の日」に思い出すのです。私にとっての「慰霊の日」とは、忘却の彼方を思いおこす日でもあります。
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com



平良次子6-30 月下美人が咲いて迎えてくれ、嬉しくて嬉しくていい香りに包まれながら/松田 米雄6-30 庭と玄関先に合わせて13輪の月下美人が咲きました。11時半で5分咲きですが、ほのかな香りが漂っています。
斎藤 陽子 (Walnut, California)6-30日本時間 新型コロナウィルスが発症した後の3月19日以来、100日以上も続く在宅自粛生活に、市民は全ての事に耐えてよく協力しています。新型コロナウィルスを封じ込めに成功しつつあったロスアンゼルスですが、経済的にも限界をきたし、段階的に社会活動を緩和しだした矢先、2週間前から感染率が増加し、段階的に緩和されていたバーなど夜の呑み屋が再び、州知事の厳しい警告に遭い、昨日から再び閉鎖を宣告されました。この感染抑制の効果が無ければ、この後、閉鎖命令の輪はますます他の職場に波及することでしょう。何時まで続くか・・・・憎きコロナです。
【ビートルズ訪日に思う】1966年6月30日ビートルズの日本公演から54年の記念日にあたるといいます。ビートルズが日本に来たのは私がアメリカに留学する半年前の、それこそ私の青春の真っ只中のことでした。敗戦あとも延々と続いた保守的なファションを打破したい若者たちは、銀座のみゆき通りで「みゆき族」なるものを流行らせていた時代です。若者がこれまでを打破したいと思う時代に、容姿もマッシュルームカットにし、これまでにないリズムの音楽を持ち込んだビートルスは、当時の保守的世相の中で悶々としていた、飢餓状態の若者の魂をトリコにしてしまったのです。
明治生まれの父には日本で流行りだしたビートルズの音楽が、過激に聞こえたようで、音楽が流れるたびに腹を立てていましたが、私はビートルズの音楽は好きで、父とジェネレーション・ギャップを感じたものです。当時の私は獣医研修中のしがない身には、ビートルズの武道館コンサートまで行って、高い入場料を払う勇気はありませんでした。この半年あとにアメリカに渡った頃、アメリカの町並みではポール・マッカトニー作の「Hay Jude」が空前の流行りとなり、サンフランシスコの街並みの通りにたむろす、ベトナム戦争反対のヒッピーの群れも、この歌を合唱していましたが、この曲をサンフランシスコの町並みで一日に何度聴いたことか・・・。
そのあとビートルズはインドへ行き伝導師マハラシのもとで、瞑想修行生活を行っていますが、サンフランシスコのヒッピー達にも、瞑想修行のビートルズは多くの影響を与えていました。1967年代後半からジョン・レノンがオノ・ヨーコとベットインなどで平和活動を行う二人が、当時は奇異な活動として私には映って理解しがたいものがありました。先の見えないベトナム戦争のなか、1971年にリリースしたジョン・レノンの作った 平和への願いを込めた「IMAGINE」は、このたび米国の音楽出版協会が、2017年6月 ジョン・レノンとオノ・ヨーコをその共作者として公式に認めたことが明らかになりました。現在 中東などでの混沌とした紛争の続くいま、この「IMAGINE」の歌は人々の心に訴える曲だと思うのは私だけでしょうか。ビートルズは53年前の私の青春の一幕でした。
[海鳴りの島から] 6-30 沖縄県議会の議長選出をめぐって、与党が分裂し、野党による攻勢が強まっている。県議選だけではない。沖縄戦没者追悼式をめぐる対応や万国津梁会議の委託、人選、辺野古新基地問題についての姿勢など、玉城知事のこれまでのあり方に疑問を抱く人は、知事本人が考えている以上に増えているはずだ。基地問題で米国訪問や全国行脚をするのもいいが、玉城知事がそれよりも優先しないといけないのは、沖縄県内をくまなく歩き、各島々で暮らす住民と繋がりをつくることだ。国会議員ではなく県知事なのだから、地方政治家として沖縄内部で根を張っていかなければ、2年後は危うい。

愛知ママの会 解体撤去まで、早くに中止するほど無駄な税金は使わずに済むはず。6-28 東京新聞『五輪会場は今 熱気いずこ』工事中止、野ざらし、解体撤去…。熱気どころか、開催どころか、もはや現実は"どう後始末していくか"のフェーズに着々と移行。で、今日は東京60人。都知事選でまだオリンピック・パラリンピックやる 出来ると言ってる候補者もいるようだ。もう嗤うしかない。〇T・Y 安倍政権と森、ゆり子のオリンピック事業は大失敗誰が責任とる。
6月27日 FB友の通信を見ていたら、「ダークツーリズム」というのが出ていた。検索に「(英語: Dark tourism)とは、災害被災跡地、戦争跡地など、人類の死や悲しみを対象にした観光のこと。ブラックツーリズム(英: Black tourism)または悲しみのツーリズム(英: Grief tourism)とも呼ばれている」とある。最近、松尾の古本屋で買った『写真が語る「負の遺産」』双葉社2014年が手元にある。はじめに、近年、「ダークツーリズム」という観光スタイルが注目されている、と述べている。今、現実のコロナ禍で、目の前がダーク。コロナ禍による世界の死亡者50万人超え、国別の死者は、米国が群を抜いて多く12万5千人超で、次いで南米ブラジルが5万7千人台。西欧諸国では鈍化傾向にあるが、メキシコが2万6千人、インドが1万6千人と増加基調が続いている。中東のイランでも1万人台に上っており、死者が1万人を超えたのは計9カ国。→6-29 KYODO
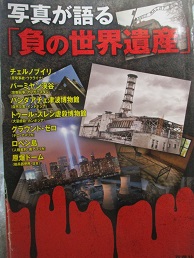
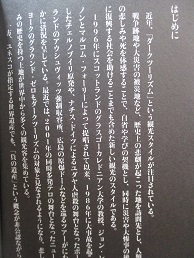
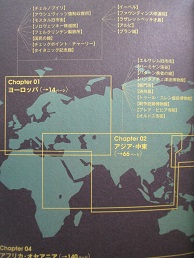
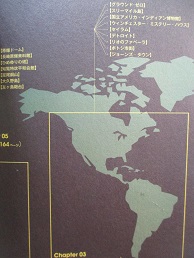
今は目前のコロナ禍さなか!でも日米両政府によるオキナワ破壊(辺野古新基地)が粛々と進んでいる。粛々と言えば那覇の密集地に、新市民会館の工事も進んでいる。コロナ禍の前であれば許容できた「ハコモノ」かも知れないが、次のコロナ禍に備えての設計変更を緊急にしないと「無用の長物」になり兼ねない。



6月4日ー粛々と建設工事が進んでいる「新市民会館」


しんぶん赤旗6-23「『大阪都構想』ーコロナ禍の今なぜ」/6-25「大阪カジノ業者選び延期」/6-27「緊急事態中下で統廃合工事」/「毎日新聞」6-26 大阪市は5月にオンラインや郵送による10万円申請の受け付けを始めた。しかし、二重申請や記載ミスが続き、6月上旬にオンライン申請を中止。「さまざまな苦情対応で人が割かれた」(松井市長)との声も出ているが、内部で詳しい原因が分かっておらず、対象の152万世帯のうち4万7600世帯(25日現在)にしか給付できていない。
大阪府保険医協会 2020/3/5【新型コロナ】大阪市の保健所は僅か一カ所 住民の健康は身近な行政でこそ守られるー現在、新型コロナウイルスが国民の生活に大きな影響を及ぼしています。こうした事態に保健所は大きな役割を担う存在ですが、この20年間で保健所は削減され続けています。そこで保健所を守る大阪市民の会の亀岡照子氏に緊急インタビューを実施しました(取材日:2月26日)―はじめに保健所を守る大阪市民の会の活動について教えて下さい。1994年に地域保健法が制定され、全国の保健所の削減が進みました。不健康都市日本一の大阪市では、市民のいのちと健康を守る砦としての保健所を残して欲しいと1995年11月に「保健所を守る大阪市民の会」が発足し、保健所応援団の活動を始めました。初代会長は、大阪大学医学部衛生学元教授の丸山博先生が務めました。65万枚のビラを配布し、旺盛な宣伝活動を行うとともに、厚労省交渉を5回、大阪市交渉や申し入れを17回繰り返しましたが、残念ながら2000年4月に、大阪市の保健所は1つに統合されてしまいました。
斎藤 陽子 (Walnut, California)6-27 日本時間6月ももうじき終わりますが、新型コロナウィルスでロスアンゼルスに外出禁止令が出て、27日の今日で100日になります。新型コロナウィルスが発症して、在宅自粛100日を迎えようとは想像もしておりませんでした、いささか長すぎる自粛生活で、みな疲れています。24日には何と全米の新規感染者が、たった1日で4万人と最多を記録したとの報道です。カリフォルニアは厳しい外出規制を引いたお陰で、コロナ禍を封じ込める寸前まで行きましたが、余りの厳しい規制で経済面で景気の厳しい状況が出始めて、段階的に外出規制を緩和しだした矢先、この2週間で急に感染者が急激に増え出し、その余りの感染の増え方に、州知事も慌てだしています。
カリフォルニア州は24日、新規感染者が7149人確認され最多を更新し、カリフォルニア州のニューサム知事はここ2週間で100万人以上にウイルス検査を実施し、約5%に陽性判定が出ていると述べています。おもな感染層は20代から40代が占めているとのことで、特にメキシコとの国境沿いに接するカリフォルニアで、感染の蔓延率が激しい様で緊急状態の様です。州知事はしきりに公共の場での、マスク着用を義務付けていますが、他の打つ手は模索中の様です。
プラスチック製削減目的から、日本でもスーパーやコンビニで無料配布されていたプラスチック製ビニール袋が7月1日から、全国一斉に有料化を義務付けられるとの方針の様ですが、カリフォルニアでは2014年から、レジ袋の廃止を実行し、各自がマイ買い物袋(エコバッグ)を持参して買い物をしてました。
ところが・・・・新型コロナウィルスが発症して後、使用を重ねるエコバックが、衛生の面でコロナウィルスの介在源になり得るという感染説が出て、この2週間前ほどから、もとの使い捨てレジ袋使用に戻っています。さてさてカリフォルニアのレジ袋廃止はコロナ禍で、急に方針転換し、今後のレジ袋の行く末がどうなることでしょうか。どなた様も新型コロナウィルスにはくれぐれもお気を付けになって、お過ごしください。
写真ー1983年4月 『師父 志喜屋孝信』志喜屋孝信先生遺徳顕彰事業期成会 志喜屋孝信(1884年4月19日~1955年1月26日)〇1904年3月、沖縄県立中学校卒業、志喜屋孝信、川平朝令、山川文信、久高将旺、山田有登。4月ー志喜屋孝信、広島高等師範学校(数物化学科)入学。このころ内村鑑三を愛読。玉川学園の創始者小原国芳と親交。1908年3月卒業。4月、岡山県金光中学校に奉職。岡山出身の山室軍平の思想に親近感を抱く。12月、熊本県立鹿本中学校に転任。1911年12月、沖縄県立第二中学校に赴任。1924年3月、校長に就任。1936年3月、二中校長辞し、私立開南中学校を創設、理事長兼校長となる。
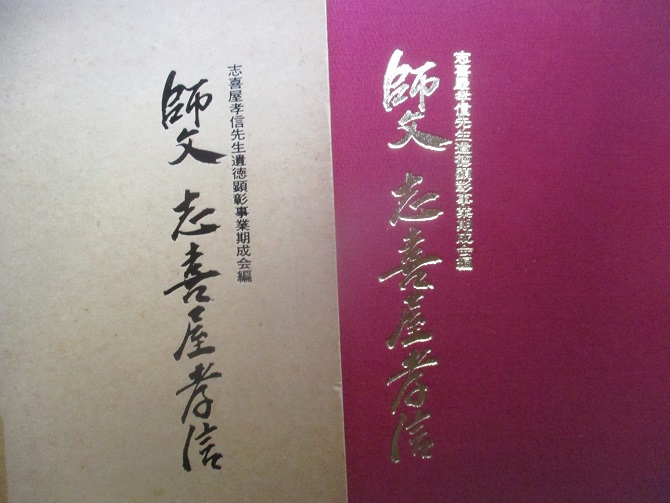
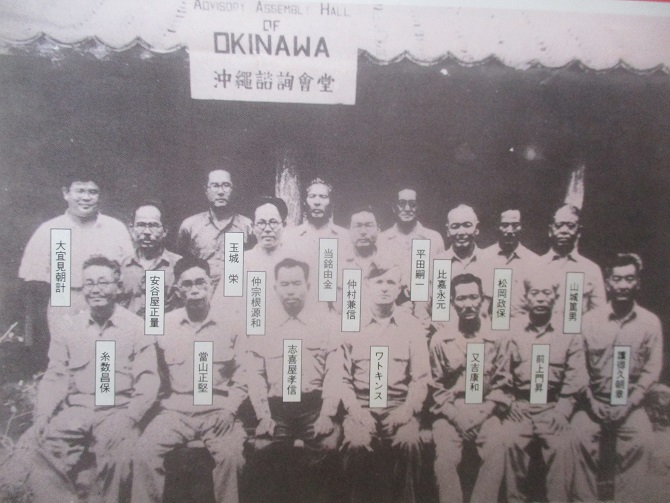
写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。
写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳
写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

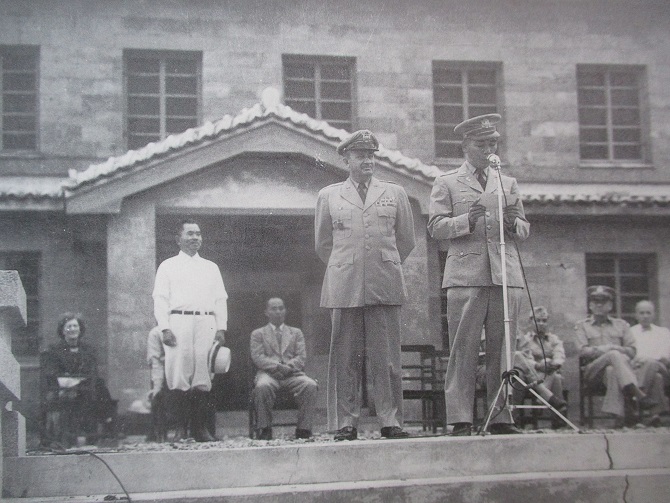
本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。
昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。
1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。
1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。
1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」
1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。
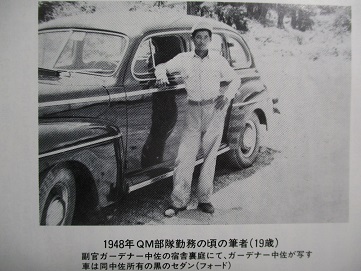
1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号
〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。
1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

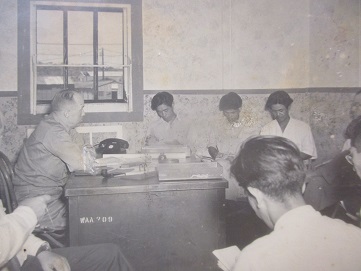
写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

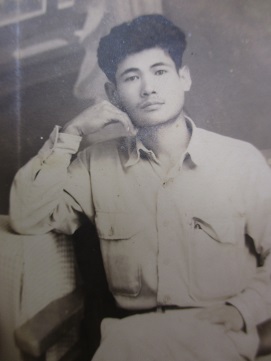
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて


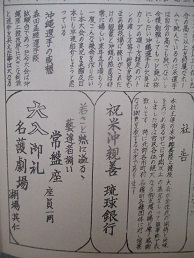
1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号
1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。
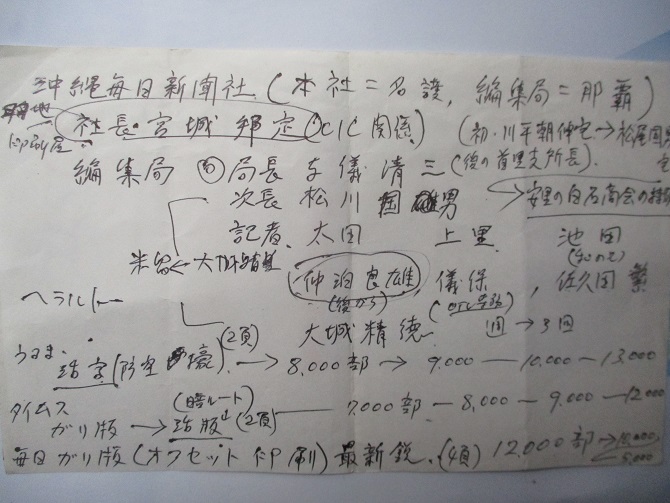
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展
1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。


写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳
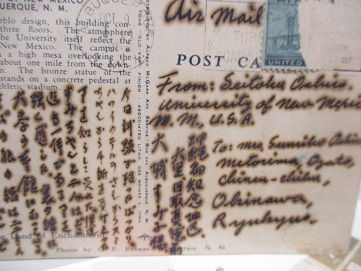
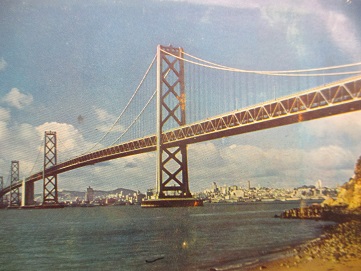
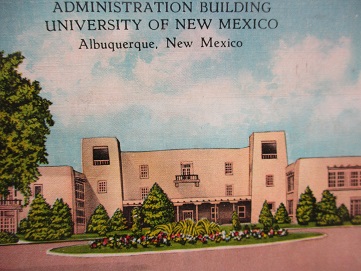

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳


1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山
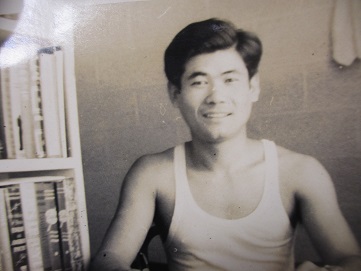

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順
ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」
1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
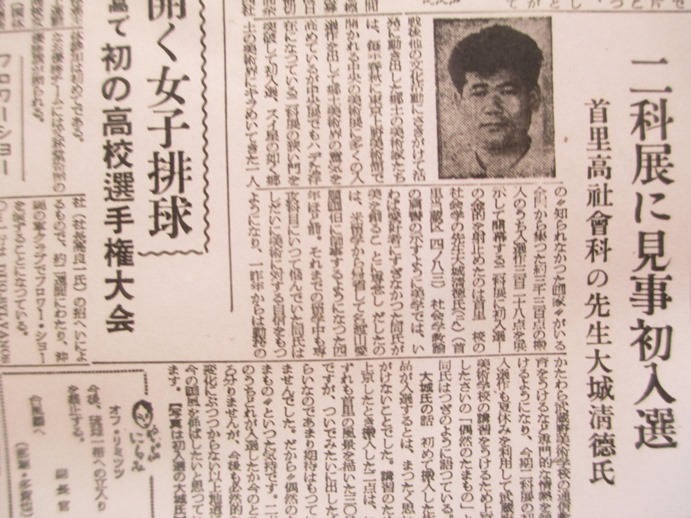
1956年9月1日『琉球新報』

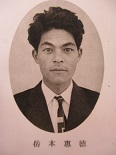
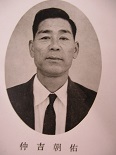
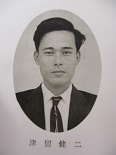
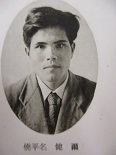
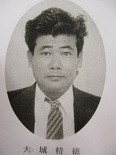
首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク
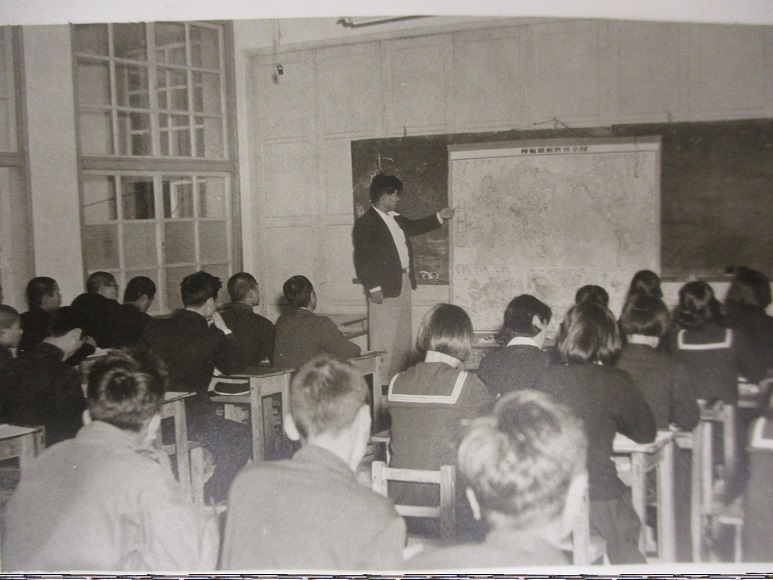
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

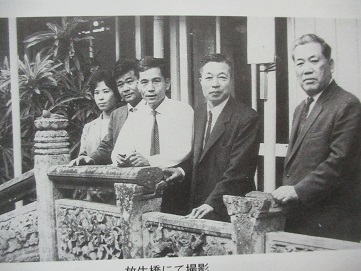
左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』
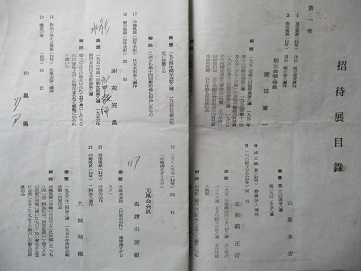
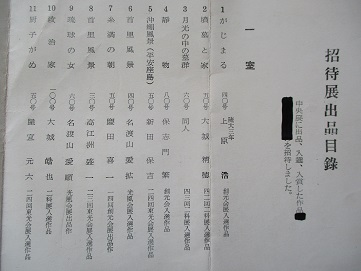
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
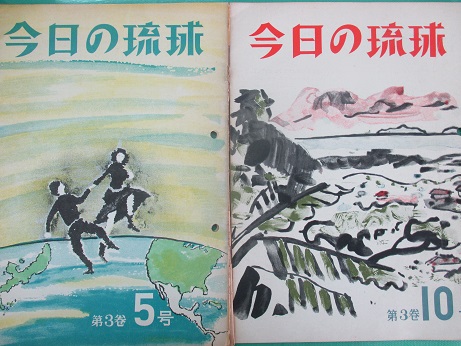
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

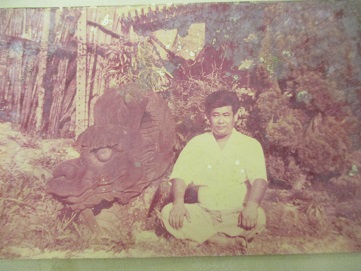


1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて
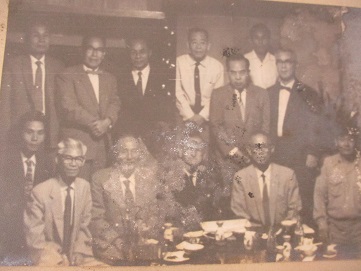

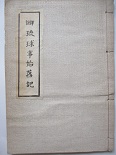




1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。
1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)
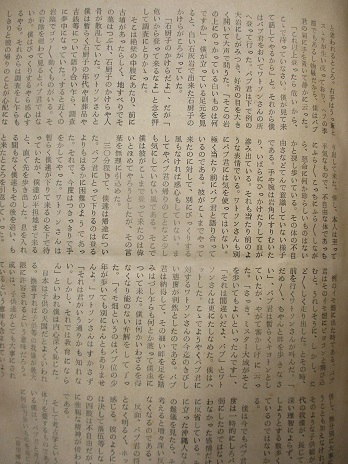
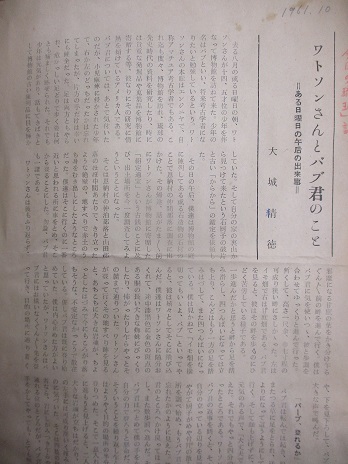
1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」
1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。
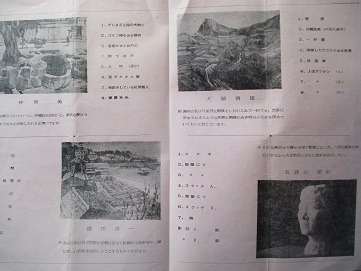
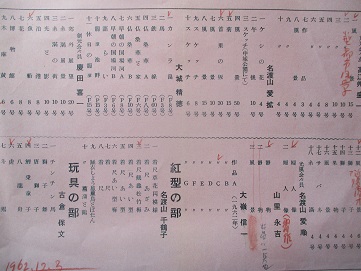
1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館
1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。
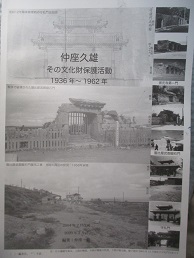
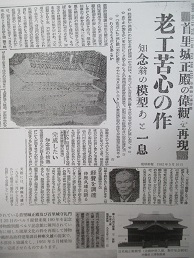
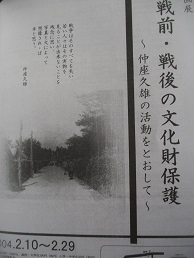
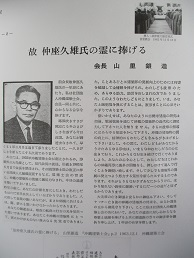
【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』
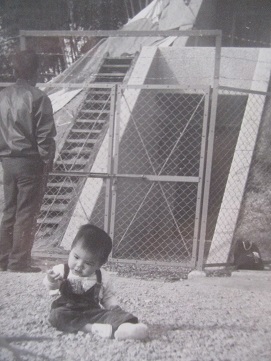
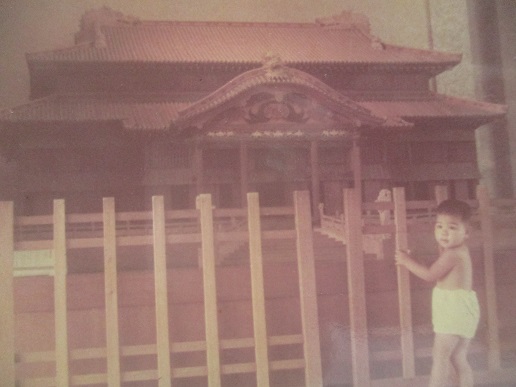
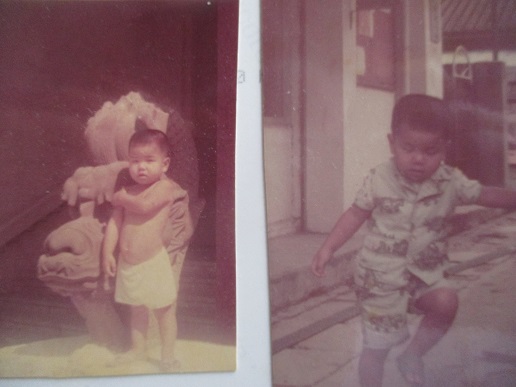
【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

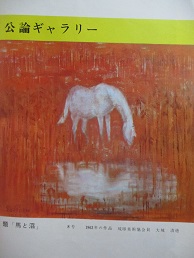
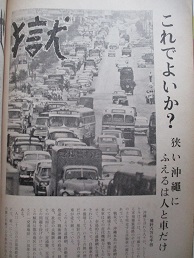
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
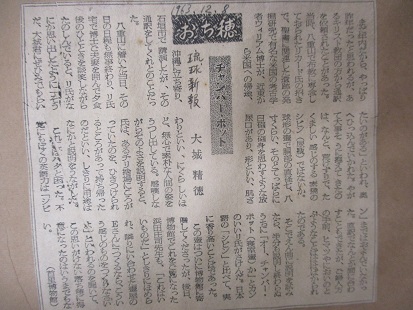
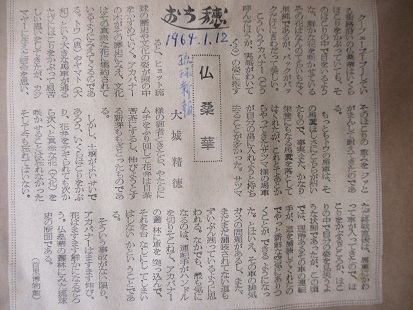
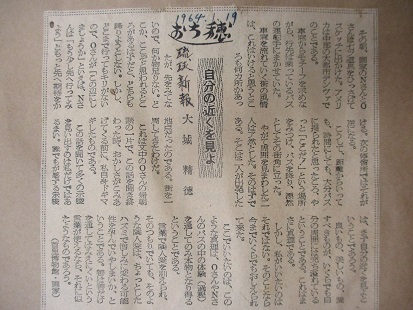
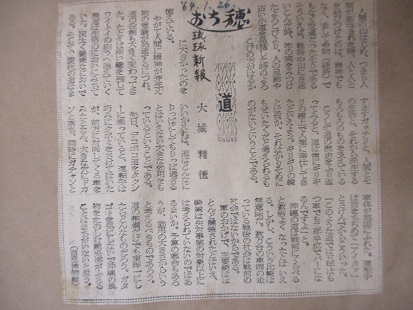
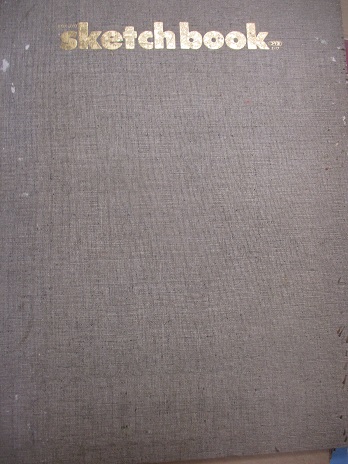

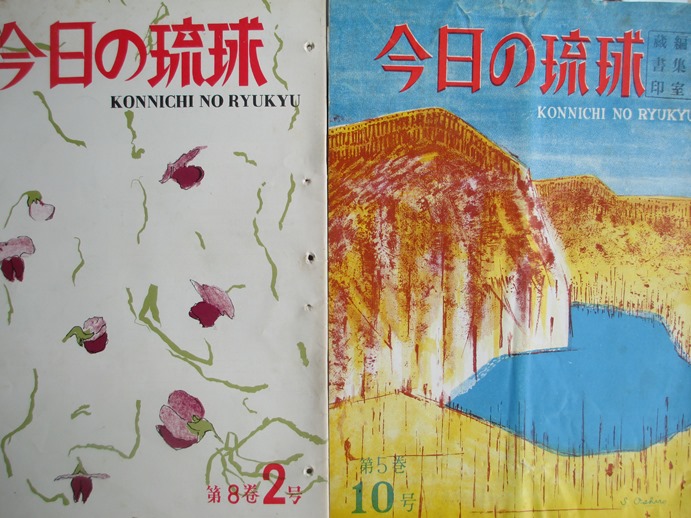
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」
1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。
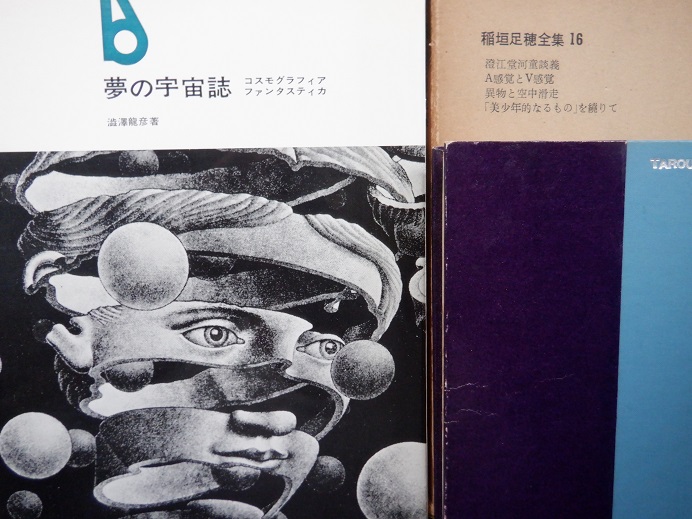
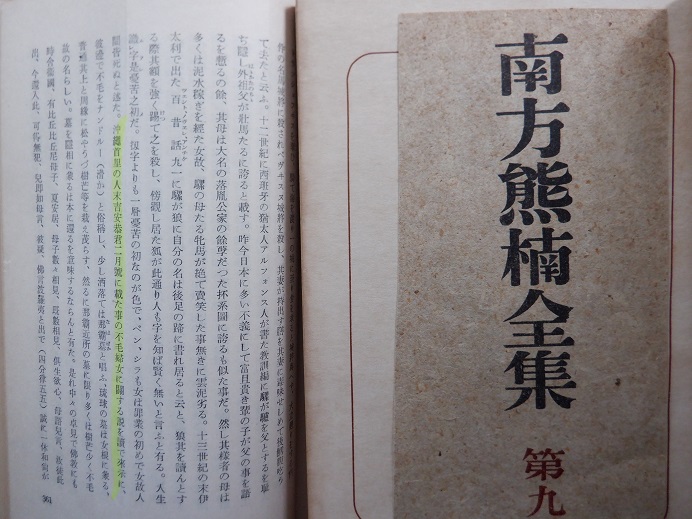
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
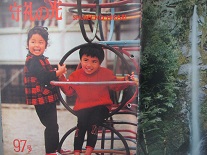
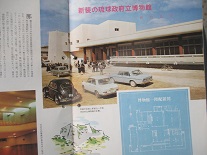
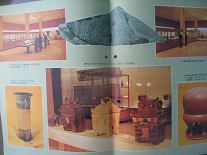

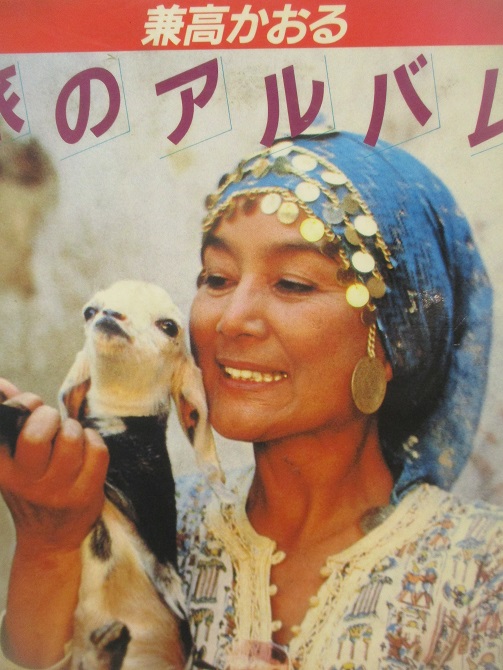
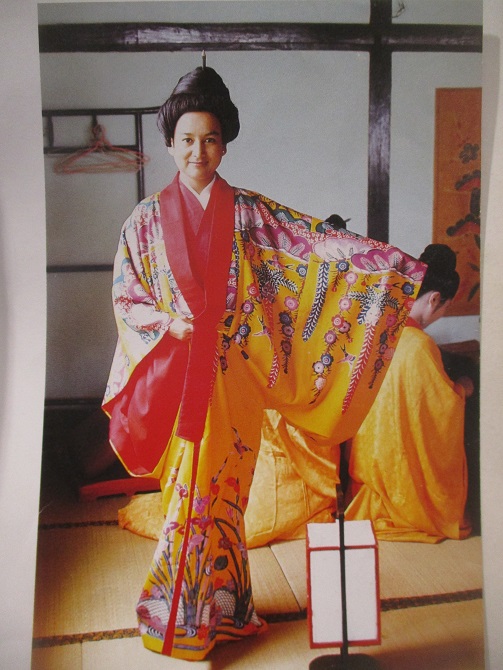
1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社
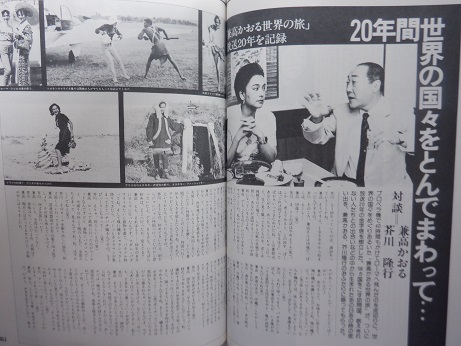
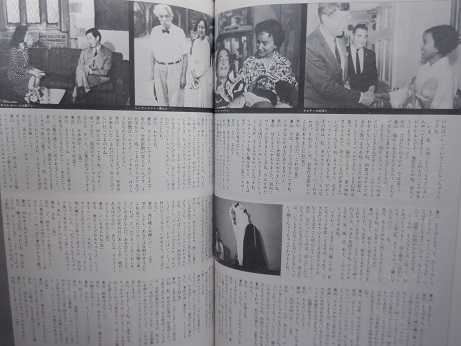
1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号
1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」
1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。


1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会
1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足
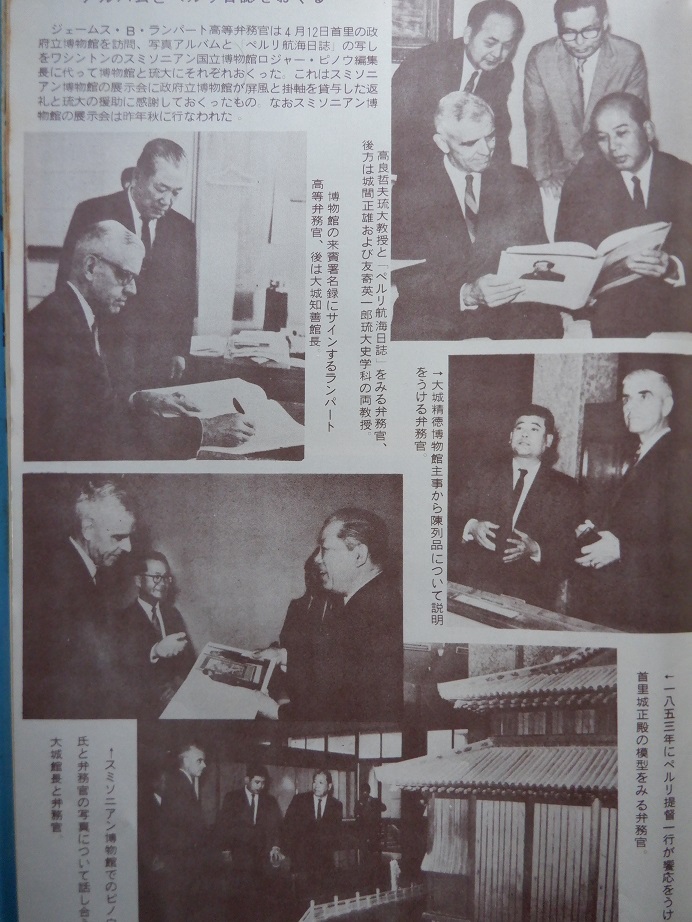
1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社
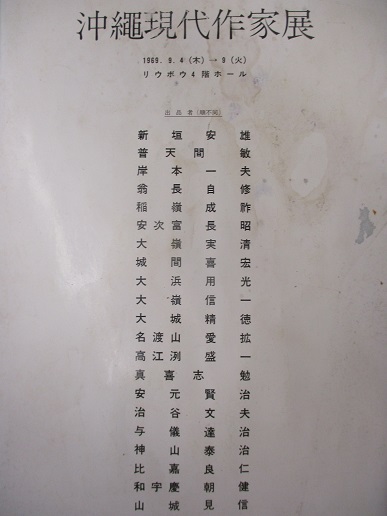
1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」
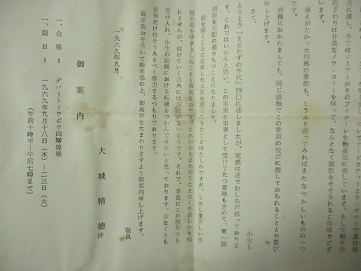
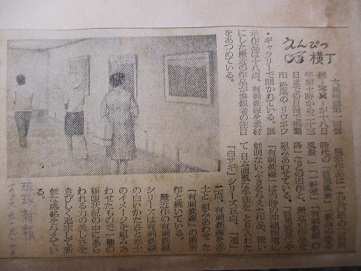
1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」
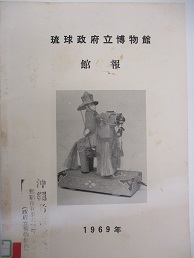
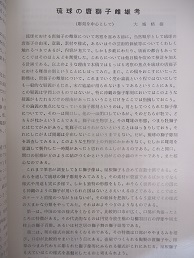
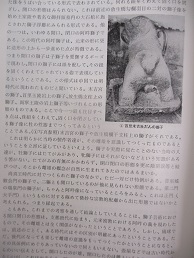
1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」
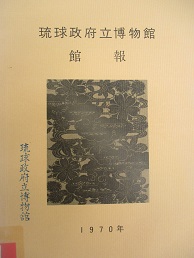
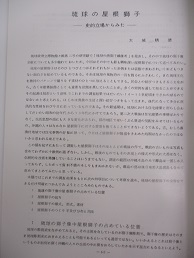
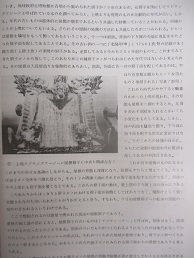
1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社
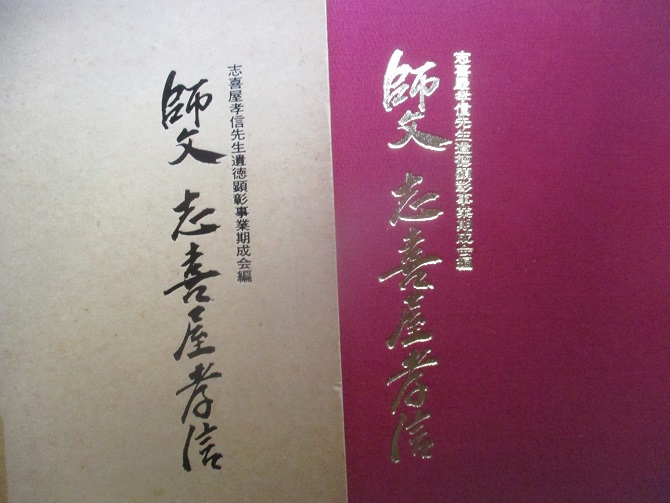
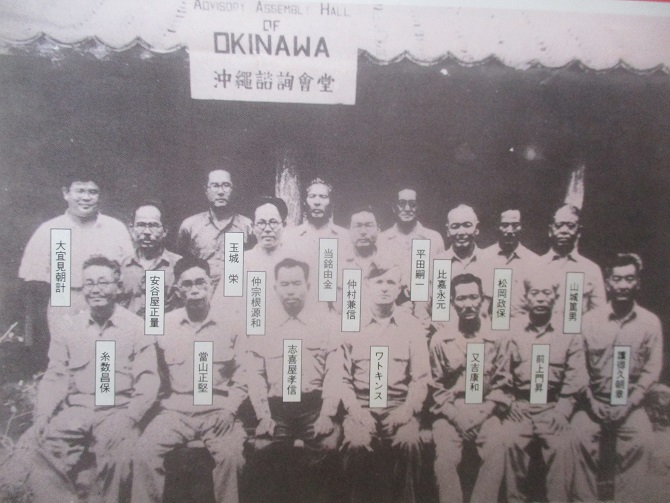
写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。
写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳
写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

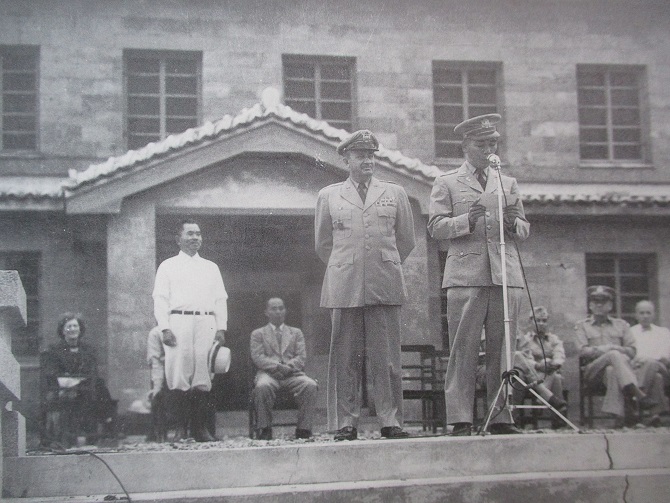
本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。
昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。
1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。
1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。
1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」
1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。
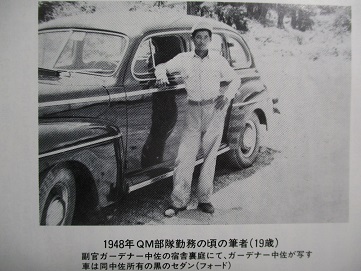
1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号
〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。
1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

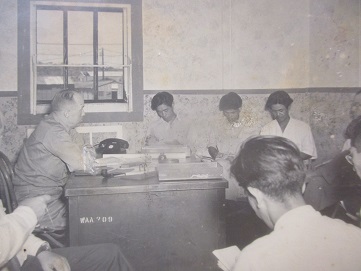
写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

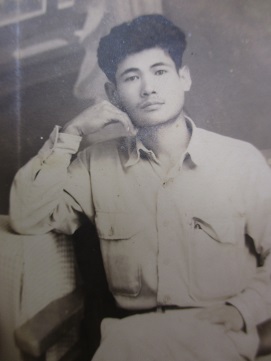
1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて


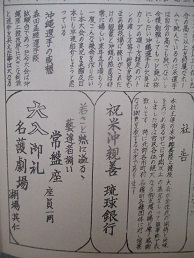
1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号
1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。
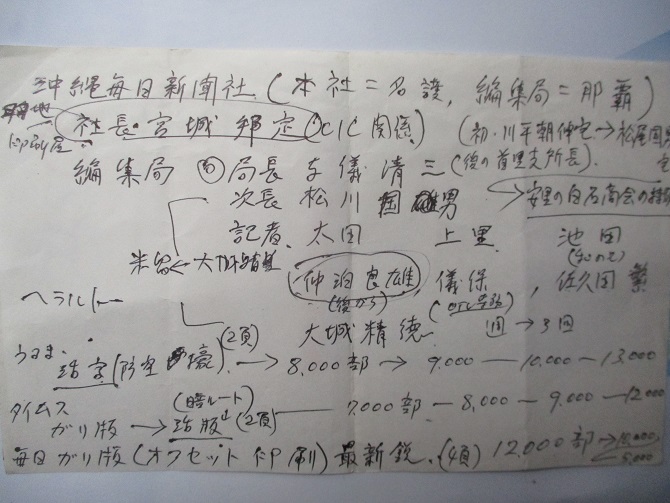
大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ
1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展
1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。


写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳
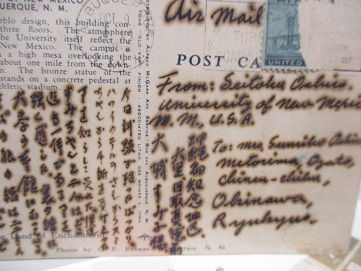
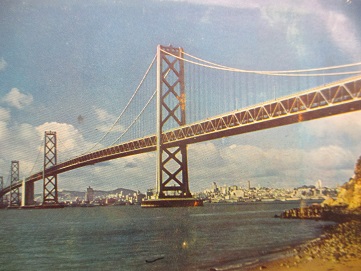
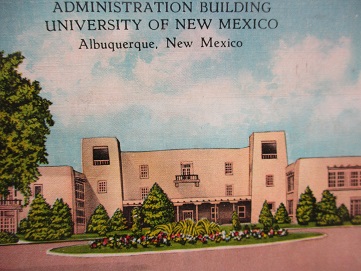

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳


1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山
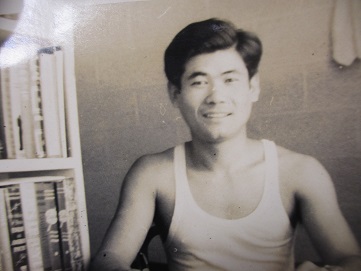

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順
ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」
1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。
1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任
1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。
1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品
1956年 津野創一、首里高等学校卒
1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品
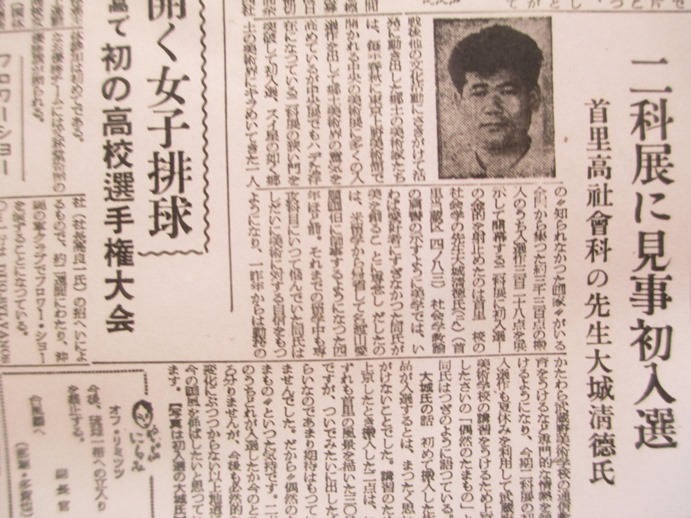
1956年9月1日『琉球新報』

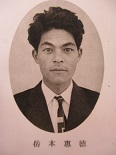
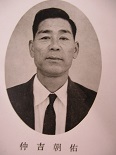
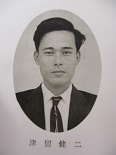
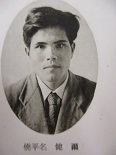
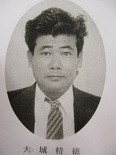
首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク
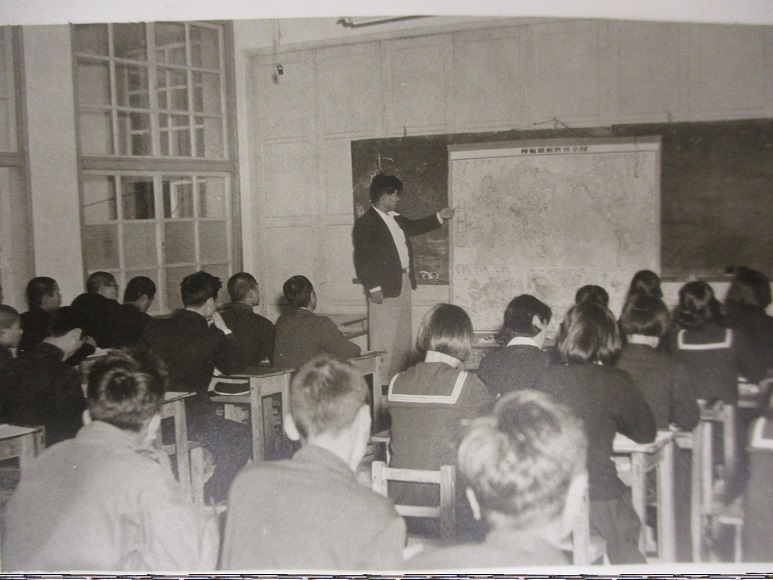
1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任
1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」
1958年 宮城篤正、首里高等学校卒
1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄
1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

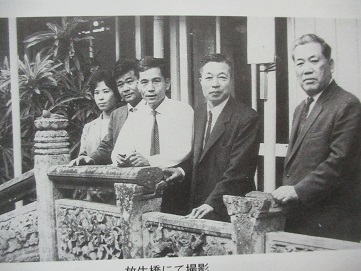
左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』
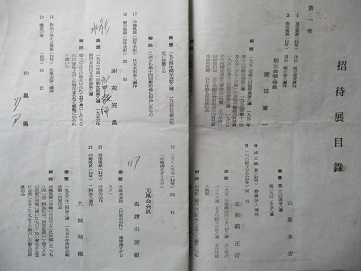
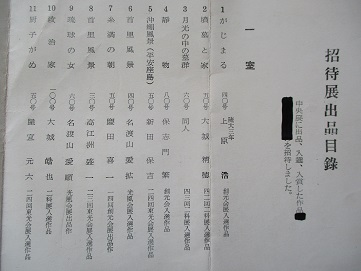
1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール
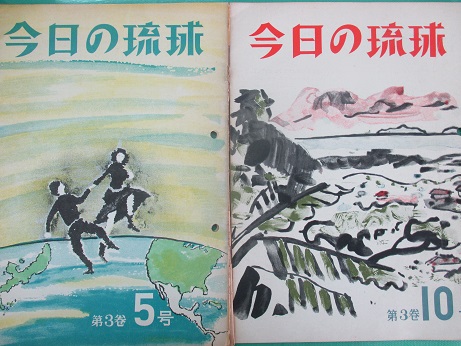
1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

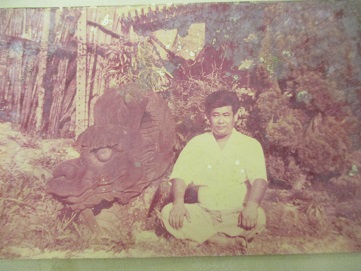


1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて
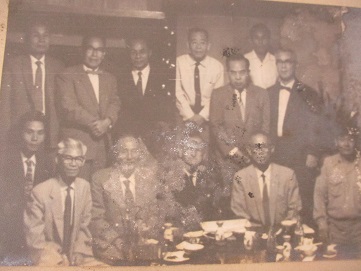

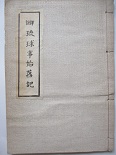




1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。
1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)
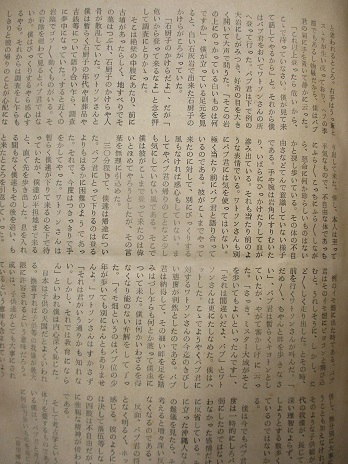
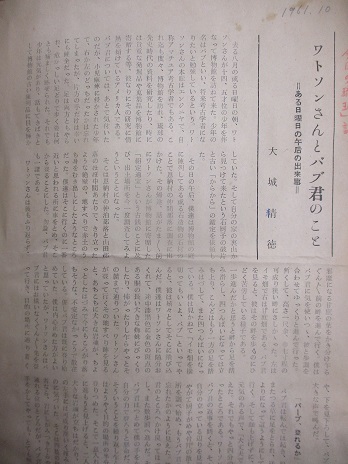
1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」
1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。
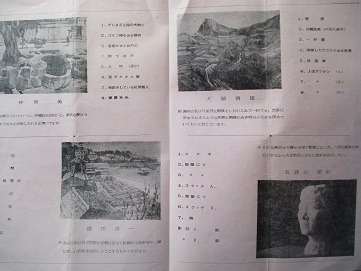
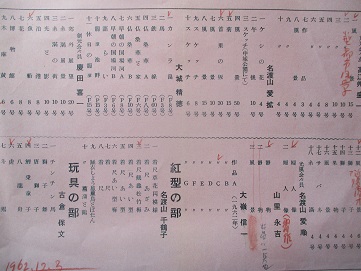
1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館
1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。
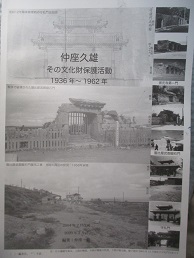
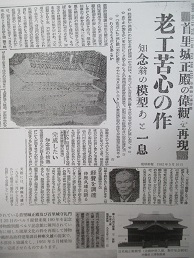
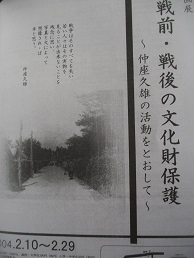
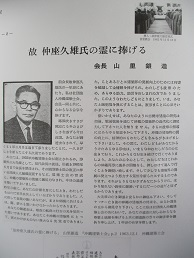
【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』
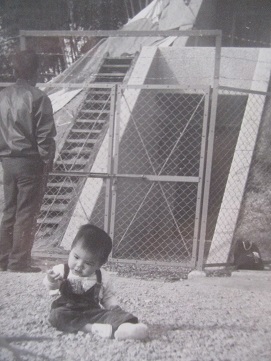
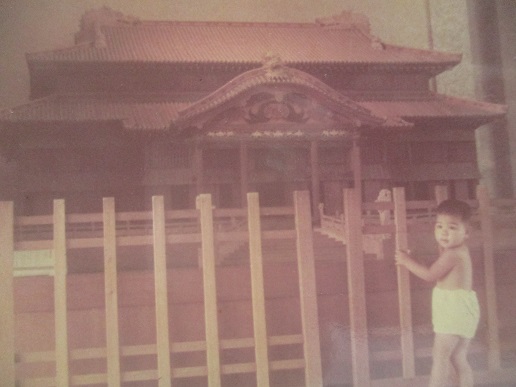
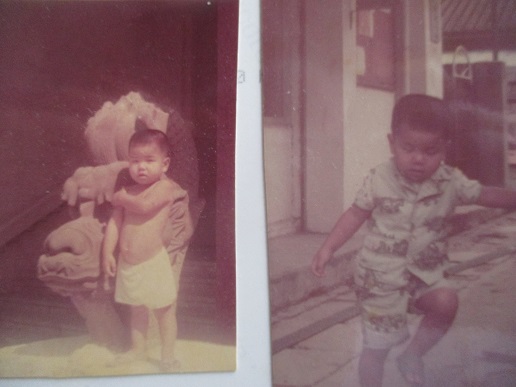
【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

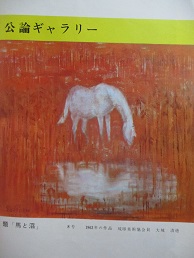
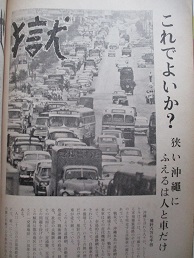
1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」
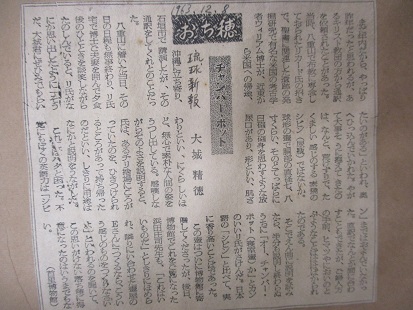
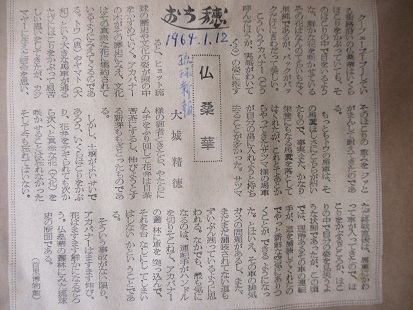
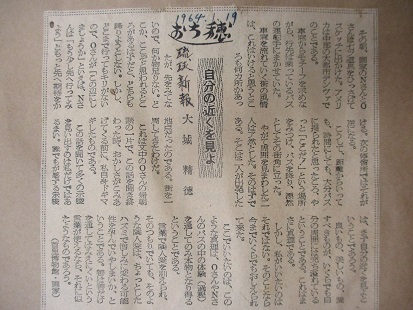
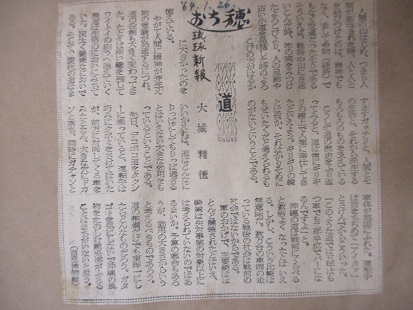
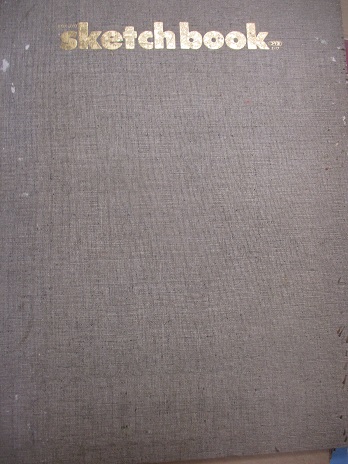

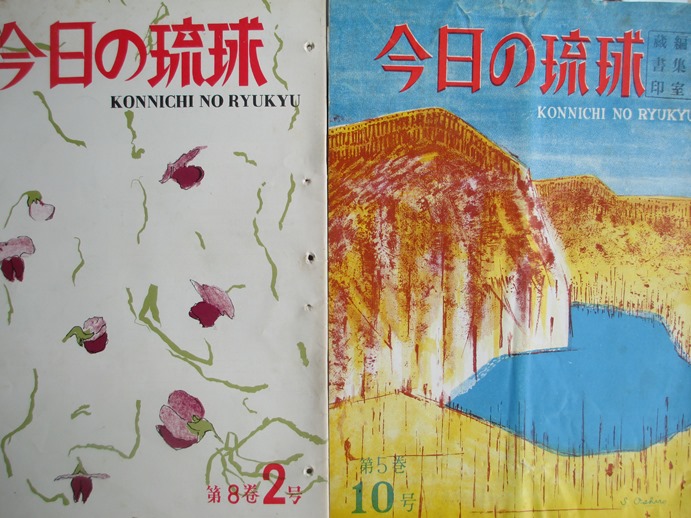
大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」
1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」
1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。
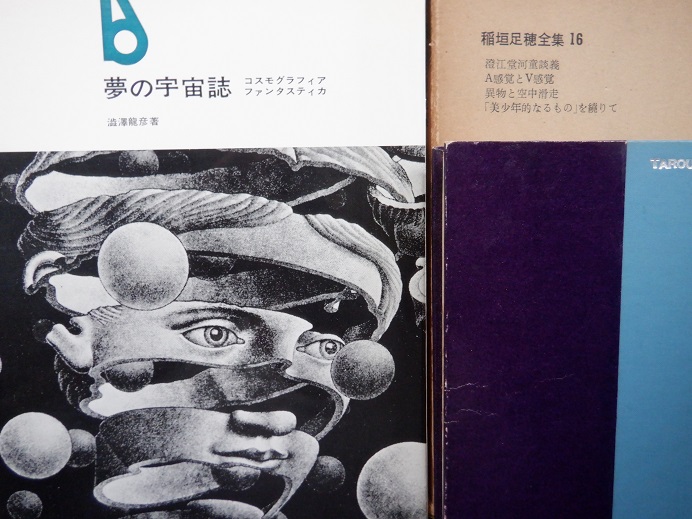
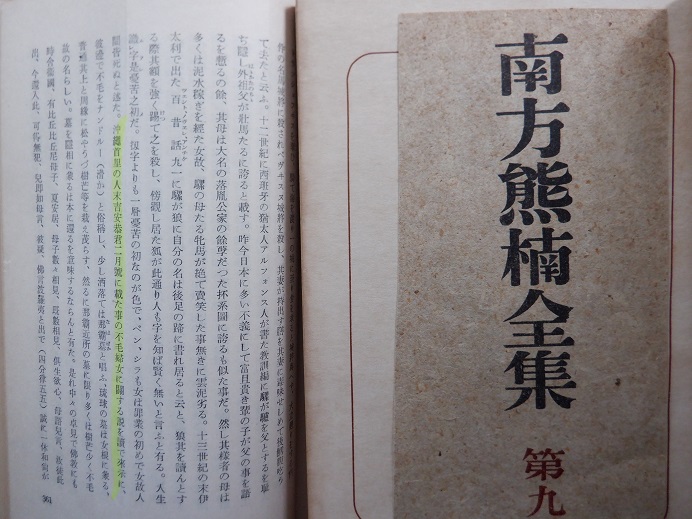
1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士
○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。
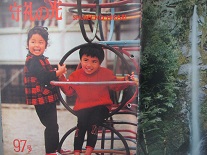
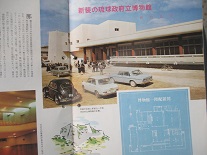
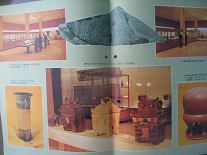

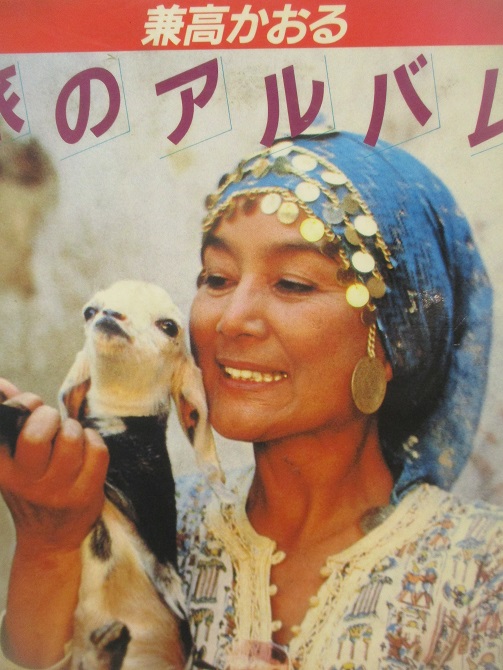
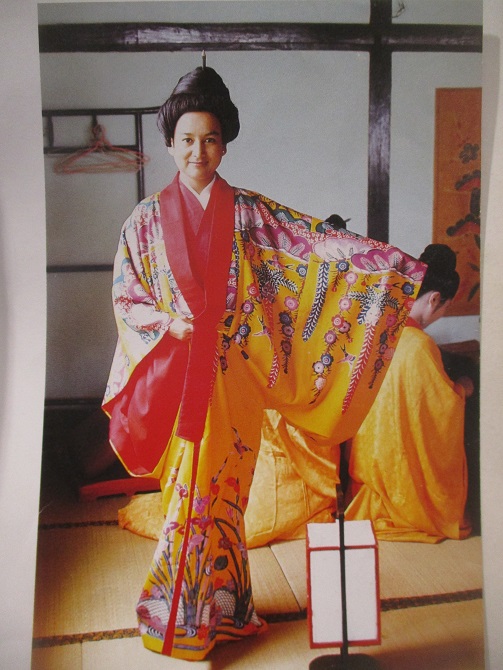
1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社
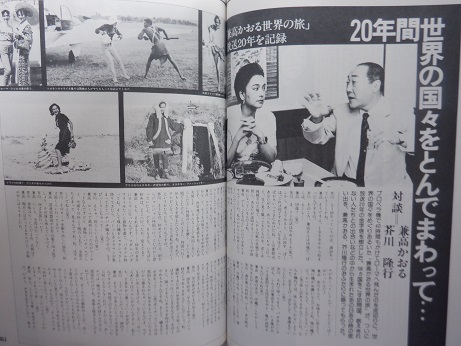
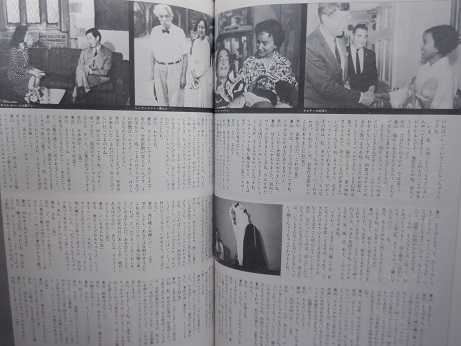
1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号
1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」
1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。


1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会
1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足
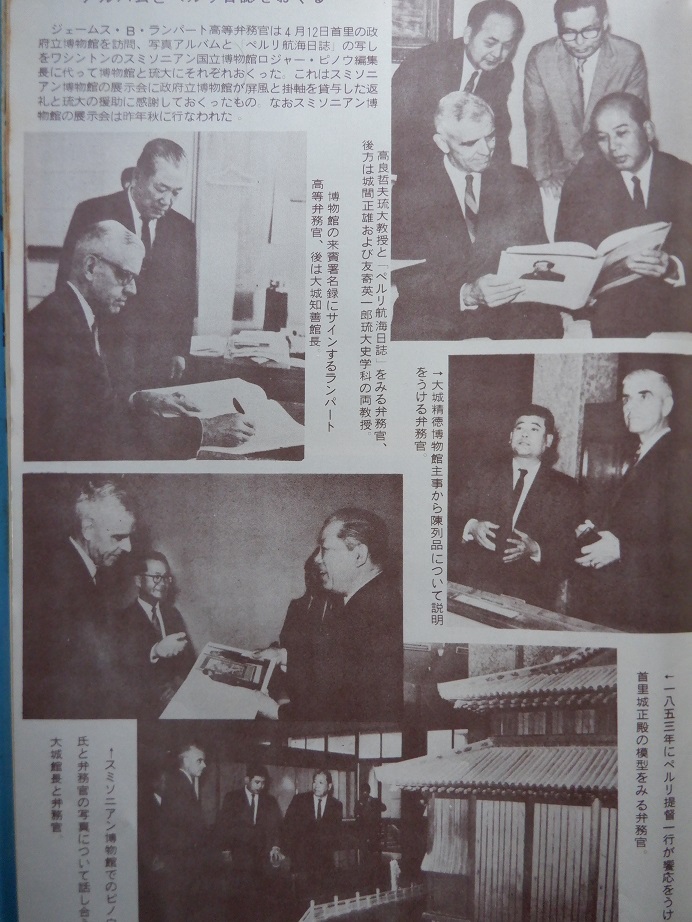
1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社
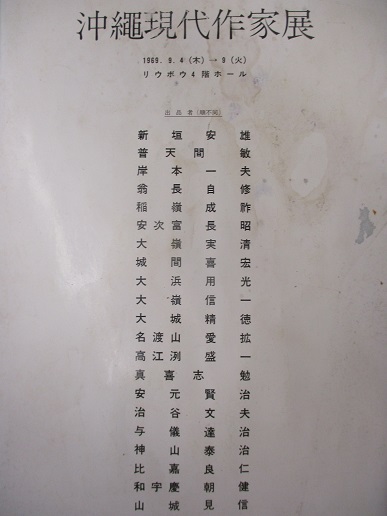
1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」
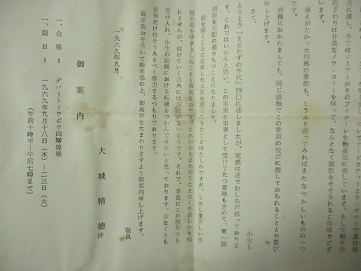
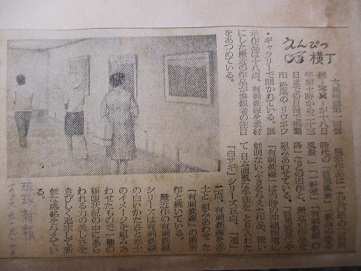
1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」
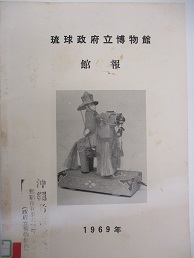
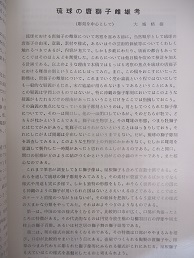
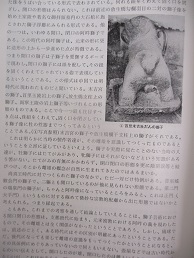
1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」
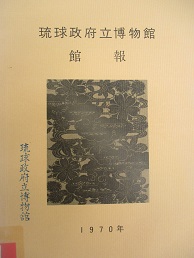
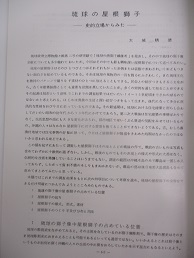
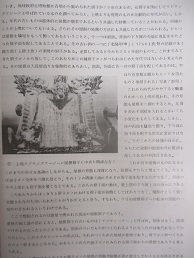
1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社
08/02: 世相ジャパン
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com
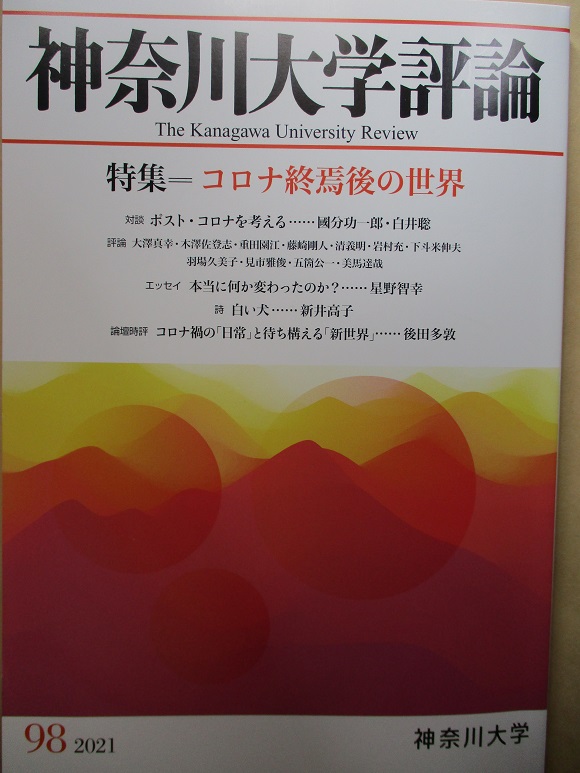
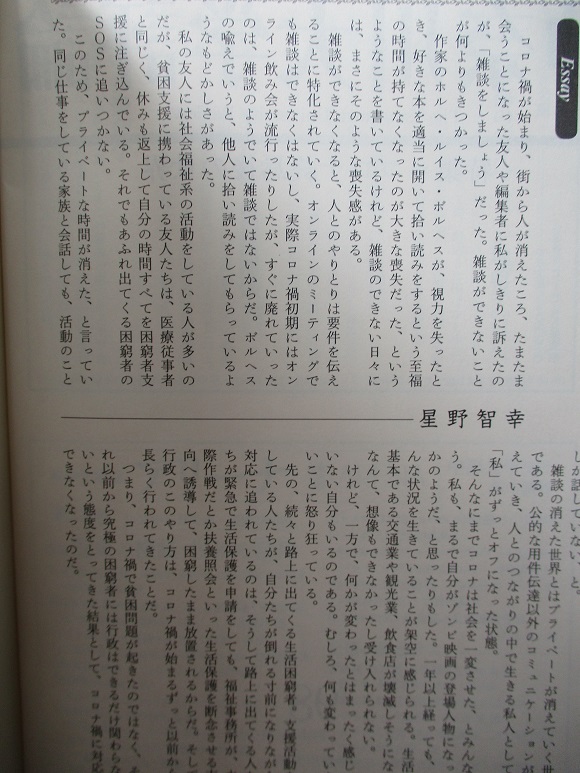
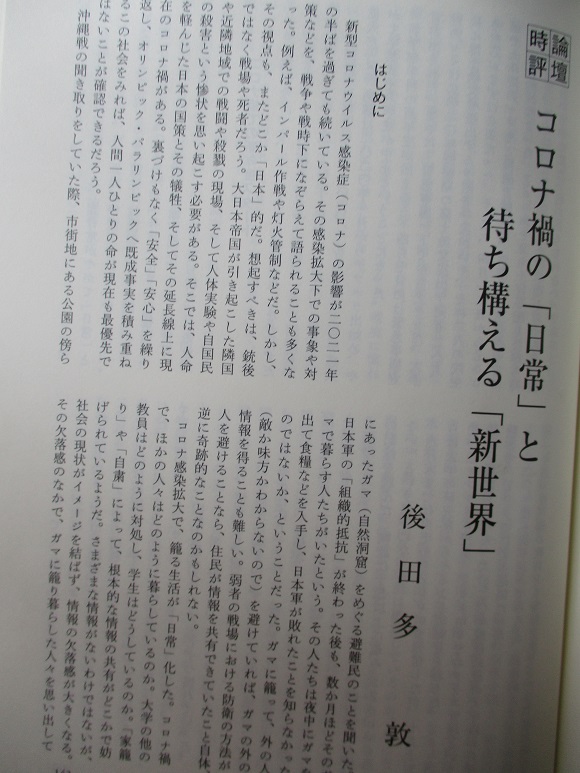
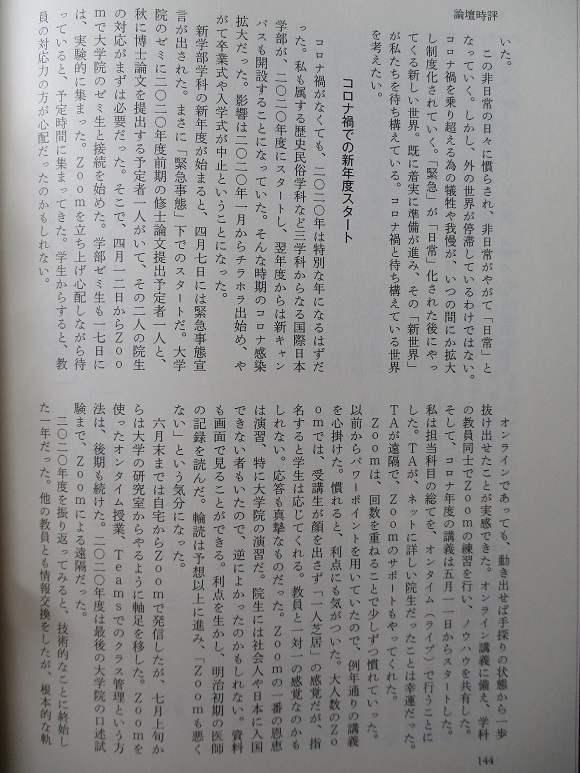
2021年7月『神奈川大学評論』「特集=コロナ終焉後の世界」第98号 星野智幸「本当に何か変わったのか?」、後田多敦(国際日本学部教授)「論壇時評 コロナ禍の『日常』と待ち構える『新世界』」
2021-8-22 横浜市長に共産党神奈川県委員会などが支援する山中竹春候補が当選。



8月16日 18時50分 家の前通り、/泊港方面の夕焼
[沖縄タイムス]8-19 沖縄防衛局は17日、宮古島で陸上自衛隊の訓練施設建設工事をしている工事関係者に、12~16日にかけて、8人の新型コロナウイルス陽性者が確認されたと発表した。
「くろねこの短語」2021年8月18日 相も変わらぬポンコツ首相と腰抜け記者会の馴れ合い会見。聞くだけ言うだけで、中身はスカスカ。ポンコツ首相の言ってることは、まるで空手形連発の選挙公約みたいなもので、なるほど9月12日までの緊急事態宣言延長ってのは衆議院選を意識してのことだったようだ。そんな記者会見にあって、ちょっと気になったのが、分科会の尾身シェンシェイが「個人の行動制限」に言及したことだ。曰く、「飲食店など事業者に制限をかける仕組みはあるが、市民に対してはお願いベースの対策しかできないということがある。法律的に難しい議論はあるが、個人に感染リスクの高い行動を避けてもらうことを可能にするような法的な新たな仕組みの構築や現行の法制度の活用について、まずは検討だけでも早急に行ってもらいたいという意見が分科会であがった」
ちょっと待てよ。分科会が私権制限に関わる法整備について言及するってのは僭越なんじゃないか。都合のいいところだけ専門家の意見を御拝聴ってのがポンコツ首相の常套手段だから、ひょっとしたら裏で手を回してたりして。このところ。加計学園不正献金疑惑の下村君が「緊急事態条項」についてよく口にしてますからね。そもそも、私権制限に関わる法整備ってのはポンコツ首相が勝手にできることではなくて、そのためには国会開く必要があるんだね。何で記者会見でそこのところを突っ込む記者がいないのかねえ。今回ばかりは丁々発止の質問が飛ぶかと思ったけど、いやあ、そんな妄想したオイラがバカだった・・・ってもんです。
「くろねこの短語」2021年8月17日 オオカミ少年もかくやで、顔も頭も貧相なカス総理が緊急事態宣言を9月12日まで延期しますとさ。確か、前回延期した時には「今回の宣言が最後となるよう全力で対策を講じていく」ってのたまっていたのに、その責任はどうなってるんだろうねえ。そう思ってたら、案の定、ぶら下がり会見で記者に突っ込まれて、こんなコメントしやがりました。「ワクチン接種やムニャムニャ・・・新しいムニャムニャ・・・中和抗体の方法ムニャムニャ・・・たとえば薬を世界に先がけて確保し、最小限に国民に影響がない様に全力で目先の事をやるのが私の責務」 なんのこっちゃ。ホント、ポンコツな野郎だこと。
でもって、どうやらパラリンピックは無観客で開催強行するらしい。凄いよねえ。「自分の命は自分で守れ」って言いながら、「さあ、いよいよ次はパラリンピックの開催です」(小池百合子)なんて都知事が宣言しちゃうんだから。さすがに一般大衆労働者諸君も呆れ顔で、共同通信の世論調査によれば、ポンコツ野郎に総理大臣を続けてほしくないという声が65%もあるってさ。この数字が来たる衆議院選挙にどれだけ反映されるか。それによって、この国の有権者の見識のあり様もわかろうというものだ。
「くろねこの短語」2021年8月16日 全国戦没者追悼式のカス総理の式辞は、ペテン師・シンゾー時代のほぼコピペだったてね。政治的理念なんか爪の先程もない政治屋だから、それも当然か。せめて読み飛ばしなんかのボケかまして、カス総理らしさを演出すればいいのに。
そんなことより、なにやら東京都が若者のワクチン接種促進のためのアブリを開発するってね。「接種記録を読み込み、接種済みの人が店舗で割引を受けられたりするアプリ」だそうで、このアブリを含めた「若年層のワクチン接種を促進するためのキャンペーン事業の費用10億円」を補正予算案に計上したってさ。
そのうちワクチンの開発費は2億5千万円。残りの7億5千万円は若年層向けのWEB広告や動画の配信に使われるとか。ワクチン足りないって言ってるのに、これって壮大な無駄遣いなんじゃないの。おそらく裏では電通が一枚噛んでるんだろうね。それにしても、くだらないこと考えつくものだ。フリップ小池も役人も、馬鹿なんじゃない。




8-15 中之橋から安里川/ローソン/セブンイレブン/ユニオン
「くろねこの短語」2021年8月15日 終戦の日とくれば、暑いというのが当たり前だったのに、この涼しさというか肌寒さは何なのかねえ・・・てなことを我が家のドラ猫に囁いてみる大雨の日曜の朝である。そんなラチもないこと考えている間にも、自宅療養を余儀なくされているひとたちの命が危険にされされているんだが、そんな中で「史上最強変異株」とも噂される「ラムダ株」が日本でも確認されたってんだが、なんとその感染者は五輪関係者で、だから確認後2週間も感染を隠していたことが発覚しちゃいました。
なんでも、7月20日にラムダ株感染が確認されていたのに、公表したのは8月6日で、それもメディアから問い合わせがあったからなんだとさ。BS-TBS『報道1930』で、自民党外交部会長のヒゲの三等兵・佐藤君が問い詰められてパラしちゃいました。「五輪と感染拡大は関係ない」って喚き散らすカス総理を慮ってのことなんだろうね。オリンピック直前に五輪関係者がラムダ株に感染なんて、それこそカス総理にとっては悪夢だろうから。
こういうことがあると、他にも隠蔽していることがあるんじゃないかと、猜疑心が強くなるばかり。結果、何を言っても信用されないから、コロナはさらに拡大することになる。こうした負の連鎖を断ち切らない限り、コロナ禍は絶対に終息することはありません。それには、まずカス総理を切ることなんだが、果たして衆議院選はどうなることやら。なんという言い草! →高致死率ラムダ株2週間報告せず「もっと早く問い合わせがあれば答えた」自民党外交部会長が番組で釈明(中日スポーツ)感染症法第十六条 厚生労働大臣は、感染症に関する情報について分析を行い、当該感染症の予防及び治療に必要な情報を適切な方法により積極的に公表しなければならない。この条文に違反するのでは?
昨夜の『報道1930』、世界が警戒するラムダ株の日本初確認は7月23日、国際機関には報告していたが、世の中は8月6日の報道で明らかに。公表しなかった理由を国立感染研に問うと「日本でまだ警戒対象に指定されていなかったから」。23日は開会式、五輪への影響を考え隠していたと思われても仕方がない。最後に、今日の全国戦没者追悼式で、カス総理はどんなギャグかましてくれるんだろう。読み飛ばし、読み間違い・・・いやあ、期待しちゃうなあ。




2021-8-14ユンタンザ墓掃除




2021-8-13 東京の島袋和幸氏から暑中見舞、/自宅から県庁付近まで
「くろねこの短語」2021年8月14日 (前略)おいおい、反省してるのかって問われているのに「自己評価するのは僭越」だってさ。「僭越」とは「自分の身分・地位を越えて、出過ぎた事をすること。そういう態度」を意味する言葉だろう。「自己評価」するのは総理大臣としての「義務」であり「責任」ということをわかっちゃいないんだね。ロックダウンについても、「世界でロックダウンをする、外出禁止に罰金かけても、なかなか守ることができなかったじゃないですか」ってドヤ顔でのたまってくれている。いえいえ、ロックダウンした地域はどこでも一定程度の効果を上げている。ただし、ロックダウンは経済的損失が大きいから短期集中にせざるを得ない。でも、コロナの波に対して、ロックダウンで対応することは、けっして誤りではないんだね。
おそらく、カス総理がロックダウンに否定的なのは、補償とセットということにあるのだろう。10万円の給付金だって、野党がせっついたおかげでようやく実現したことを忘れちゃいけない。とにかく、金は出したくない。だからこそ、なんとかのひとつ覚えで「ワクチン、ワクチン」って言ってるのに違いない。妄想だけど。それにしても、これでパラリンピックをやるつもりなのかねえ。「帰省や旅行は諦めて」って言うんなら「パラリンピックもな」・・・ってなもんです。
「中日スポーツ」8-14 メンタリストDaiGo「昨日の謝罪を撤回致します」 自身の発言を差別的なヘイトスピーチと認め…「否定される苦しみを理解」とあらためて謝罪/DaiGo(ダイゴ、1986年11月22日 - )は、日本のメンタリスト、作家、ニコ生主、YouTuber。企業の研修やコンサルなども行う。静岡県静岡市清水区生まれ、千葉県市川市育ち。身長は174cm。血液型はB型。弟が3人おり[、末弟は東京大学謎解き制作集団AnotherVision元代表の松丸亮吾。→ウィキ
「中国新聞」8-12 国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長の広島訪問の警備費の全額379万円を広島県と広島市が折半することが11日、分かった。IOCや東京五輪・パラリンピック組織委員会側に負担を求めたが受け入れられなかったという。/「中日スポーツ」8-12 沖縄で732人…過去最多の新規感染者「世界でも最悪級…なのに国際通りには観光客うじゃうじゃ」/「中日スポーツ」8-13 東京都の小池百合子知事は13日に記者会見し、13日に開幕する東京パラリンピックについて「これまでの経験を生かし、安全安心な大会にしたい」「競技を見ると本当に感動する。みんな、子どもたちに見せてあげたいと思う」と感染状況を踏まえた上で、児童生徒の現地観戦に意欲を見せた。SNSでは「小池知事」がトレンドワードで急上昇。「いい加減にしろよ! コロナ感染者の爆発を何とかするのが先だ」など厳しい意見が飛び交った。
目取真俊ブログ 8-12 先の見通せない工事のために莫大な予算を浪費する余裕など、今の日本にはないはずだ。感染者が増大し、政権への支持率が下がっても、いざ選挙となれば野党のだらしなさに助けられて勝てる、と菅首相は考えているのだろう。有権者はとことんなめられている。オリンピック報道に埋没していたマスコミも、新型コロナの感染拡大において菅政権の共犯者ではないか。メダル1個当たり、どれだけの市民が犠牲になればいいのか。
「くろねこの短語」2021年8月11日 IOC会長のバッハ野郎が銀ブラしたってんで大騒ぎ。お忍びという体裁も取らず、堂々と銀座を練り歩いたというから、どこまでも空気の読めない野郎だ。そんなバッハ野郎に、ネットでは「五輪に関係無い不要不急な外出」「不要不急の外出をIOCトップがしているのは問題」「政府も注意するべき」と非難囂々なのも当然なんだね。・ネット騒然…バッハ会長が銀座散歩? 選手は観光禁止なのに【動画あり】でもって、そんな批判に対して、ルーピー丸川君が切れ気味にこんなこと喚いてしまいましたとさ。「不要不急かどうかは本人が判断すべきだ」ホント、馬鹿だね。火に油を注ぐとはこういうのを言います。そこまで言われりゃあ、だったらこれまでの「自粛要請」は何だったんだってことになるのは当たり前。これからは「本人の判断」でやらせてもらいます、ってなもんです。女体盛り・西村君は「帰省して親族や同級生で集まることは絶対に避けてもらいたい。今回は自宅でステイホームで過ごしてもらえれば」と改めて「自粛」を呼びかけたそうだが、ルーピー丸川君のひと吠えですべてはおじゃんです。さあ、お盆休みは、「本人の判断」で大いに楽しむことにいたしましょう。
ところで、名古屋出入国在留管理局に収容中に死亡したウィシュマンさんについての最終報告書が公表された。しかしまあ、人一人が亡くなったというのに、誰一人責任も取らず、死因すら特定できないとは。身内による調査の限界が露骨に出た調査報告書に何の意味があるのだろう。入管職員による「いじめ」の結果の死とも言えるんだから、これはもう刑事事件だろう。それなのに、ウィシュマンさんの死に関わった職員の名前も非公表で、いまだに監視カメラの映像も一部は非公開ですからね。こんな最終報告書でお茶を濁されちゃ、遺族はたまったもんではありません。
韓国MBCテレビの番組は10日夜、「不当取引、国情院と日本極右」と題し、櫻井よしこ氏が理事長を務める公益財団法人「国家基本問題研究所(国基研)」が、韓国の情報機関「国家情報院(国情院)」から情報や金銭などの支援を受けていたと報じた。
「くろねこの短語」2021年8月10日 おそらく、もうお手上げ状態だからなのだろう。なんと、新型コロナウイルスを、現在の感染症2類相当から季節性インフルエンザ並みの5類相当へ移行しようと厚労省が検討してるそうだ。2類相当だと「症状がない人も含めた入院勧告や就業制限、濃厚接触者や感染経路の調査」が義務づけられているが、5類相当に格下げすると入院勧告や隔離などの措置は必要なくなる。ようするに、国や自治体の負担は大幅に軽減されるってわけだ。
「中等症は自宅療養」宣言は、こうした流れの先取りとも言えそうだ。いまは指定感染症だから医療費もタダだけど、これが5類相当になったらそうはいかない。医療費が払えないから医者にもかかれないなんてことが起きても不思議じゃないんだね。ま、究極の棄民政策と言っても過言ではありません。そのうち、「コロナはただの風邪」って記事がメディアを賑わすことになりますよ。妄想だけど。
ところで、韓国の情報機関が日本の極右団体を支援していた疑惑が浮上して、その詳細を今日にも韓国MBCテレビが放映するってね。日本の右翼団体関係者としてネトウヨの女王・櫻井よし子君の名前が上がっているとか。ネトウヨの女王・櫻井君とくれば、その親玉はペテン師・シンゾーで、その爺さんの岸信介から受け継いだ韓国利権を握っているんだね。そもそも、ペテン師・シンゾーは統一教会の機関紙の表紙を飾るほどの親韓派で、嫌韓を装っているのはネトウヨ向けのポーズにすぎない。みんな裏では繋がってるってことです。

大濱 聡 2021-8-9
「くろねこの短語」2021年8月9日 大会関係者のコロナ感染が400人を超えてたところでオリンピックがようやく終わった。とは言え、東京2020が抱える問題、たとえば7000億円の予算が4兆円というベラボーに肥大した後始末など山積する問題は残ったままだ。そんな問題のひとつに、オリンピック誘致にまつわる元JOC会長・竹田君の汚職疑惑がある。その汚職疑惑に新たな事実が。なんと、フランス当局の捜査を受けている竹田君の弁護費用の全額をJOCが負担しているんだとさ。フランス当局の捜査が始まってからの3年間で、既に2億円もの弁護費用がかかってるんだとか。捜査終了までJOCは弁護費用を負担するそうだから、弁護費用が最終的にどのくらいの額になるかは見当もつきません。
弁護費用は企業からの協賛金などで賄ているってんだが、JOCがそこまで面倒を見ているってことは、自分たちもグルだからなんじゃないのかねえ。JOCは「竹田前会長はJOCの理事会の承認を受けて、招致委理事長の職に就いた。招致委の活動は、各国オリンピック委員会が責任を持つと五輪憲章に定められている」からって言い訳してるけど、もし竹田君の独断で行われたとすれば、それは背任行為でもあるんだから弁護士費用負担する必要ないはずなんだね。竹田君は身柄拘束の恐れがあるから日本から出ることもできないそうで、金満五輪の象徴みたいな事件の行方やいかに。
「くろねこの短語」2021年8月8日 ちょいと朝寝坊した日曜の朝、ラジオをつけたら、な、なんと、すべての局がマラソン中継。放送の自由はどこ行ったんでしょうねえ。そんなことより、ボランティアなどの弁当を廃棄していた件で、大会組織委員会は4000食という調査結果を発表していたんだが、それがほんの氷山の一角にすぎないことが発覚したってね。弁当廃棄処分をスクープしたTBS『報道特集』がさらに取材を進めた結果、国立競技場以外の会場も併せて13万461食にも上り、その額は1億1600万円だとさ。
これだけの弁当があれば、ホームレスや貧困家庭の子供たちがどれほど助かることか。利権まみれの政治屋や五輪貴族は、そんなことカケラも考えたことないんだろう。そして、いまだに「国を背負って」なんてほざいている一部のアスリートも同じ穴のナントヤラってことだ。オリンピックが終わっても、オリンピックの予算の闇はとことん追及しないとダメだろう。
E・S8-8 21時前に出歩いたことはないが、前島スパーに買い物で帰途、居酒屋の前の歩道に12名が固まって一人はタバコを吸っている。居酒屋は満員。そこでそれを避けて車道を歩いたが、居酒屋も生活が掛かっているのだろう。もう一つは地元紙がオリパラの平良、喜友名の金メダルで大きく紙面を割いてコロナはどこ行ったかと、沖縄県民が軽く考えたのも一因か。
FASH8-8 開会式で用いられたのは、PYRO花火という種類のもので、見たかぎり、スペインかイタリアで生産されたものですね」そう語るのは、ある花火業界関係者だ。世界中から注目される五輪の開会式で打ち上げられた花火が、国産ではなかったというのだ。
「くろねこの短語」2021年8月7日 いやあ、この男のやることなすことすべてがポンコツってことが改めてわかった。何がって、広島平和祈念式典での顔も頭も貧相なカス総理の挨拶読み飛ばし事件だ。それも極めて重要な文言を含む箇所なんだね。読み飛ばしたくだりは以下の通り。「・・・世界の実現に向けて力を尽くします。』と世界に発信しました。わが国は、核兵器の非人道性をどの国よりもよく理解する唯一の戦争被爆国であり、『核兵器のない世界』の実現に向けた努力を着実に積み重ねていくことが重要です。近年の国際的な安全保障環境は厳しく・・・」おかげで、意味不明な挨拶になっちまったとうわけだ。で、カス総理の粗相はこれだけでなく、何と読み間違いもやらかしてたってね。こんな具合です。「広島市」→「ひろまし」「原爆」→「げんぱつ」または「げんばつ」
おそらく、こんな大事な式典だってのに原稿の下読みすらしてなかったのに違いない。エビフリャー河村君が金メダルを噛んで炎上したが、カス総理は原稿読みを噛んでそのポンコツぶりを世界にアピールしちまったというわけだ。読み飛ばしの言い訳が凄いんだよね。「原稿がのりでくっついて剥がれなかった」からだとさ。でも、使用していたのは奉書紙のはずだから糊つけるとこなんかないんじゃないの・・・なんて突っ込みもありまっせ。ただでさえコピペみたいな使いまわしの挨拶文だってのに、これでは原爆で命を落とした10数万人の霊はけっして安らぐことはありません。もう終わりにしよう、ペテン師・シンゾーから続くポンコツ政治の流れは!!
「くろねこの短語」2021年8月5日 どうやら、顔も頭も貧相なカス総理の「自宅放置」宣言は、コロナ対策分科会の尾身シェンシェイへの事前相談もなく決められたってね。昨日の閉会中審査でのやり取りで発覚したんだが、これについて娘が女子アナの厚労大臣・田村君は、「病床のオぺレーションの話なので、政府が決める話」だとさ。意味がわかりません。「中等症のうち重症化のリスクの低い人は自宅療養」のどこが「病床オペレーションの話」なんだ。
さすがにこうしたカス政権の独断専行に自民党内からも反発の声が上がって、党の会合で撤回を求めることを決めたそうだ。選挙も近いし、これ以上ポンコツ政権に付き合ってたら共倒れになっちゃいますからね。それでもカス総理は強気一辺倒で、「撤回しない」「必要な医療を受けられるための措置だ。説明し理解してもらう」とさ。
土建政治の二階君が「菅首相は『続投してほしい』の声が国民の間にも強い」とほざいて、そんな声はどこにもない、難聴なんじゃないのかと冷笑されたようだけど、ひょっとしたら「自宅放置」宣言はカス総理の致命傷になるかもね。最悪50議席減なんて予想もある状況で、こんなポンコツが選挙の顔ではとてもじゃないけど戦えません。オリンピック終わった週明けから、カス降ろしが始まるかも・・・てなことを我が家のドラ猫に囁いてみる危険な暑さの木曜の朝である。
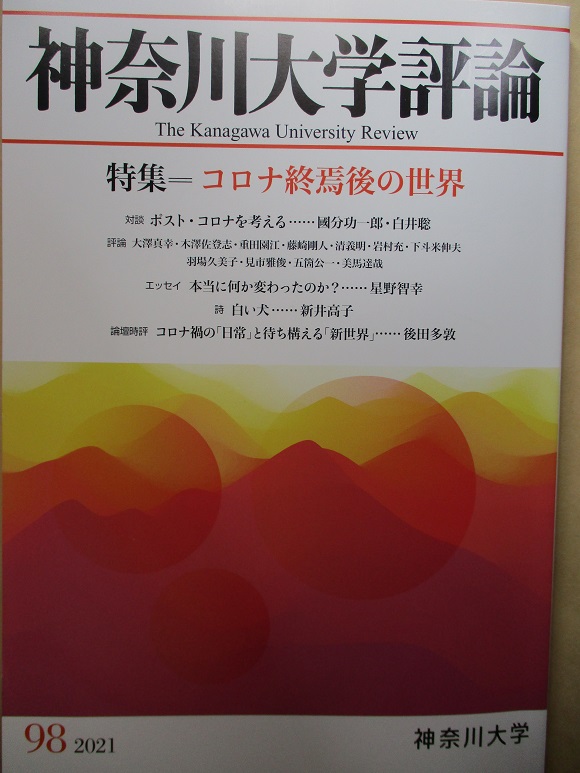
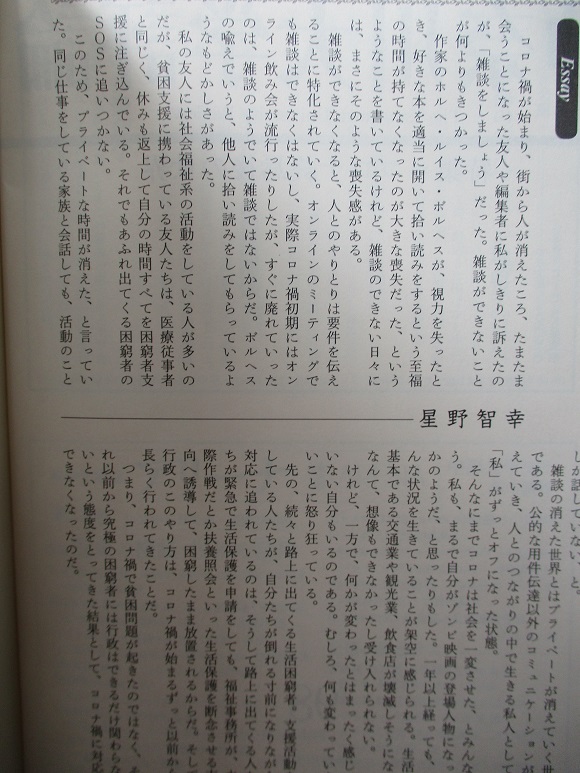
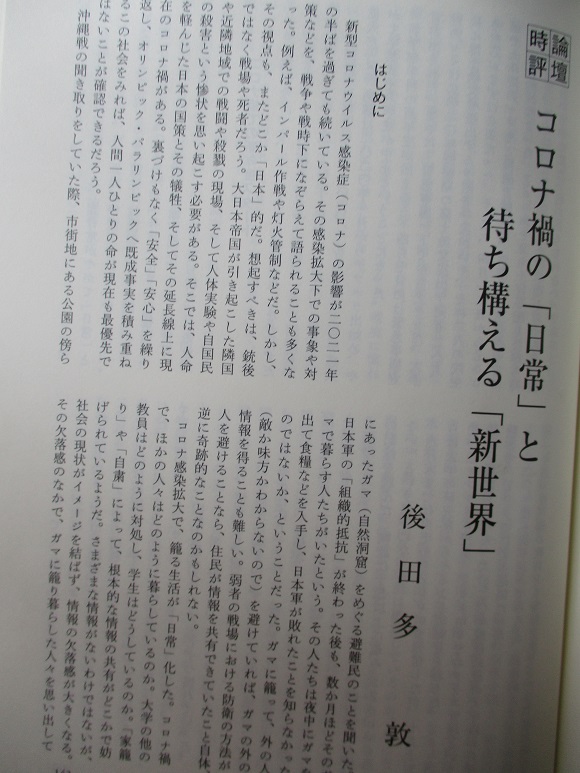
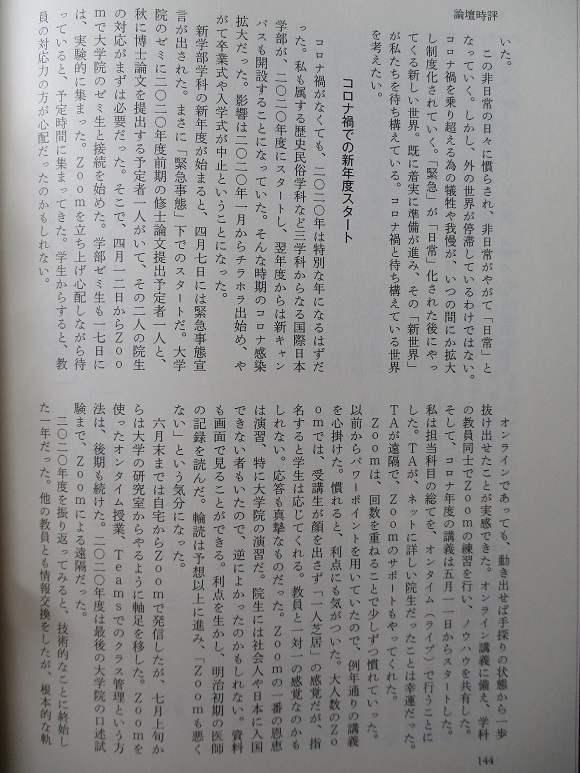
2021年7月『神奈川大学評論』「特集=コロナ終焉後の世界」第98号 星野智幸「本当に何か変わったのか?」、後田多敦(国際日本学部教授)「論壇時評 コロナ禍の『日常』と待ち構える『新世界』」
2021-8-22 横浜市長に共産党神奈川県委員会などが支援する山中竹春候補が当選。



8月16日 18時50分 家の前通り、/泊港方面の夕焼
[沖縄タイムス]8-19 沖縄防衛局は17日、宮古島で陸上自衛隊の訓練施設建設工事をしている工事関係者に、12~16日にかけて、8人の新型コロナウイルス陽性者が確認されたと発表した。
「くろねこの短語」2021年8月18日 相も変わらぬポンコツ首相と腰抜け記者会の馴れ合い会見。聞くだけ言うだけで、中身はスカスカ。ポンコツ首相の言ってることは、まるで空手形連発の選挙公約みたいなもので、なるほど9月12日までの緊急事態宣言延長ってのは衆議院選を意識してのことだったようだ。そんな記者会見にあって、ちょっと気になったのが、分科会の尾身シェンシェイが「個人の行動制限」に言及したことだ。曰く、「飲食店など事業者に制限をかける仕組みはあるが、市民に対してはお願いベースの対策しかできないということがある。法律的に難しい議論はあるが、個人に感染リスクの高い行動を避けてもらうことを可能にするような法的な新たな仕組みの構築や現行の法制度の活用について、まずは検討だけでも早急に行ってもらいたいという意見が分科会であがった」
ちょっと待てよ。分科会が私権制限に関わる法整備について言及するってのは僭越なんじゃないか。都合のいいところだけ専門家の意見を御拝聴ってのがポンコツ首相の常套手段だから、ひょっとしたら裏で手を回してたりして。このところ。加計学園不正献金疑惑の下村君が「緊急事態条項」についてよく口にしてますからね。そもそも、私権制限に関わる法整備ってのはポンコツ首相が勝手にできることではなくて、そのためには国会開く必要があるんだね。何で記者会見でそこのところを突っ込む記者がいないのかねえ。今回ばかりは丁々発止の質問が飛ぶかと思ったけど、いやあ、そんな妄想したオイラがバカだった・・・ってもんです。
「くろねこの短語」2021年8月17日 オオカミ少年もかくやで、顔も頭も貧相なカス総理が緊急事態宣言を9月12日まで延期しますとさ。確か、前回延期した時には「今回の宣言が最後となるよう全力で対策を講じていく」ってのたまっていたのに、その責任はどうなってるんだろうねえ。そう思ってたら、案の定、ぶら下がり会見で記者に突っ込まれて、こんなコメントしやがりました。「ワクチン接種やムニャムニャ・・・新しいムニャムニャ・・・中和抗体の方法ムニャムニャ・・・たとえば薬を世界に先がけて確保し、最小限に国民に影響がない様に全力で目先の事をやるのが私の責務」 なんのこっちゃ。ホント、ポンコツな野郎だこと。
でもって、どうやらパラリンピックは無観客で開催強行するらしい。凄いよねえ。「自分の命は自分で守れ」って言いながら、「さあ、いよいよ次はパラリンピックの開催です」(小池百合子)なんて都知事が宣言しちゃうんだから。さすがに一般大衆労働者諸君も呆れ顔で、共同通信の世論調査によれば、ポンコツ野郎に総理大臣を続けてほしくないという声が65%もあるってさ。この数字が来たる衆議院選挙にどれだけ反映されるか。それによって、この国の有権者の見識のあり様もわかろうというものだ。
「くろねこの短語」2021年8月16日 全国戦没者追悼式のカス総理の式辞は、ペテン師・シンゾー時代のほぼコピペだったてね。政治的理念なんか爪の先程もない政治屋だから、それも当然か。せめて読み飛ばしなんかのボケかまして、カス総理らしさを演出すればいいのに。
そんなことより、なにやら東京都が若者のワクチン接種促進のためのアブリを開発するってね。「接種記録を読み込み、接種済みの人が店舗で割引を受けられたりするアプリ」だそうで、このアブリを含めた「若年層のワクチン接種を促進するためのキャンペーン事業の費用10億円」を補正予算案に計上したってさ。
そのうちワクチンの開発費は2億5千万円。残りの7億5千万円は若年層向けのWEB広告や動画の配信に使われるとか。ワクチン足りないって言ってるのに、これって壮大な無駄遣いなんじゃないの。おそらく裏では電通が一枚噛んでるんだろうね。それにしても、くだらないこと考えつくものだ。フリップ小池も役人も、馬鹿なんじゃない。




8-15 中之橋から安里川/ローソン/セブンイレブン/ユニオン
「くろねこの短語」2021年8月15日 終戦の日とくれば、暑いというのが当たり前だったのに、この涼しさというか肌寒さは何なのかねえ・・・てなことを我が家のドラ猫に囁いてみる大雨の日曜の朝である。そんなラチもないこと考えている間にも、自宅療養を余儀なくされているひとたちの命が危険にされされているんだが、そんな中で「史上最強変異株」とも噂される「ラムダ株」が日本でも確認されたってんだが、なんとその感染者は五輪関係者で、だから確認後2週間も感染を隠していたことが発覚しちゃいました。
なんでも、7月20日にラムダ株感染が確認されていたのに、公表したのは8月6日で、それもメディアから問い合わせがあったからなんだとさ。BS-TBS『報道1930』で、自民党外交部会長のヒゲの三等兵・佐藤君が問い詰められてパラしちゃいました。「五輪と感染拡大は関係ない」って喚き散らすカス総理を慮ってのことなんだろうね。オリンピック直前に五輪関係者がラムダ株に感染なんて、それこそカス総理にとっては悪夢だろうから。
こういうことがあると、他にも隠蔽していることがあるんじゃないかと、猜疑心が強くなるばかり。結果、何を言っても信用されないから、コロナはさらに拡大することになる。こうした負の連鎖を断ち切らない限り、コロナ禍は絶対に終息することはありません。それには、まずカス総理を切ることなんだが、果たして衆議院選はどうなることやら。なんという言い草! →高致死率ラムダ株2週間報告せず「もっと早く問い合わせがあれば答えた」自民党外交部会長が番組で釈明(中日スポーツ)感染症法第十六条 厚生労働大臣は、感染症に関する情報について分析を行い、当該感染症の予防及び治療に必要な情報を適切な方法により積極的に公表しなければならない。この条文に違反するのでは?
昨夜の『報道1930』、世界が警戒するラムダ株の日本初確認は7月23日、国際機関には報告していたが、世の中は8月6日の報道で明らかに。公表しなかった理由を国立感染研に問うと「日本でまだ警戒対象に指定されていなかったから」。23日は開会式、五輪への影響を考え隠していたと思われても仕方がない。最後に、今日の全国戦没者追悼式で、カス総理はどんなギャグかましてくれるんだろう。読み飛ばし、読み間違い・・・いやあ、期待しちゃうなあ。




2021-8-14ユンタンザ墓掃除




2021-8-13 東京の島袋和幸氏から暑中見舞、/自宅から県庁付近まで
「くろねこの短語」2021年8月14日 (前略)おいおい、反省してるのかって問われているのに「自己評価するのは僭越」だってさ。「僭越」とは「自分の身分・地位を越えて、出過ぎた事をすること。そういう態度」を意味する言葉だろう。「自己評価」するのは総理大臣としての「義務」であり「責任」ということをわかっちゃいないんだね。ロックダウンについても、「世界でロックダウンをする、外出禁止に罰金かけても、なかなか守ることができなかったじゃないですか」ってドヤ顔でのたまってくれている。いえいえ、ロックダウンした地域はどこでも一定程度の効果を上げている。ただし、ロックダウンは経済的損失が大きいから短期集中にせざるを得ない。でも、コロナの波に対して、ロックダウンで対応することは、けっして誤りではないんだね。
おそらく、カス総理がロックダウンに否定的なのは、補償とセットということにあるのだろう。10万円の給付金だって、野党がせっついたおかげでようやく実現したことを忘れちゃいけない。とにかく、金は出したくない。だからこそ、なんとかのひとつ覚えで「ワクチン、ワクチン」って言ってるのに違いない。妄想だけど。それにしても、これでパラリンピックをやるつもりなのかねえ。「帰省や旅行は諦めて」って言うんなら「パラリンピックもな」・・・ってなもんです。
「中日スポーツ」8-14 メンタリストDaiGo「昨日の謝罪を撤回致します」 自身の発言を差別的なヘイトスピーチと認め…「否定される苦しみを理解」とあらためて謝罪/DaiGo(ダイゴ、1986年11月22日 - )は、日本のメンタリスト、作家、ニコ生主、YouTuber。企業の研修やコンサルなども行う。静岡県静岡市清水区生まれ、千葉県市川市育ち。身長は174cm。血液型はB型。弟が3人おり[、末弟は東京大学謎解き制作集団AnotherVision元代表の松丸亮吾。→ウィキ
「中国新聞」8-12 国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長の広島訪問の警備費の全額379万円を広島県と広島市が折半することが11日、分かった。IOCや東京五輪・パラリンピック組織委員会側に負担を求めたが受け入れられなかったという。/「中日スポーツ」8-12 沖縄で732人…過去最多の新規感染者「世界でも最悪級…なのに国際通りには観光客うじゃうじゃ」/「中日スポーツ」8-13 東京都の小池百合子知事は13日に記者会見し、13日に開幕する東京パラリンピックについて「これまでの経験を生かし、安全安心な大会にしたい」「競技を見ると本当に感動する。みんな、子どもたちに見せてあげたいと思う」と感染状況を踏まえた上で、児童生徒の現地観戦に意欲を見せた。SNSでは「小池知事」がトレンドワードで急上昇。「いい加減にしろよ! コロナ感染者の爆発を何とかするのが先だ」など厳しい意見が飛び交った。
目取真俊ブログ 8-12 先の見通せない工事のために莫大な予算を浪費する余裕など、今の日本にはないはずだ。感染者が増大し、政権への支持率が下がっても、いざ選挙となれば野党のだらしなさに助けられて勝てる、と菅首相は考えているのだろう。有権者はとことんなめられている。オリンピック報道に埋没していたマスコミも、新型コロナの感染拡大において菅政権の共犯者ではないか。メダル1個当たり、どれだけの市民が犠牲になればいいのか。
「くろねこの短語」2021年8月11日 IOC会長のバッハ野郎が銀ブラしたってんで大騒ぎ。お忍びという体裁も取らず、堂々と銀座を練り歩いたというから、どこまでも空気の読めない野郎だ。そんなバッハ野郎に、ネットでは「五輪に関係無い不要不急な外出」「不要不急の外出をIOCトップがしているのは問題」「政府も注意するべき」と非難囂々なのも当然なんだね。・ネット騒然…バッハ会長が銀座散歩? 選手は観光禁止なのに【動画あり】でもって、そんな批判に対して、ルーピー丸川君が切れ気味にこんなこと喚いてしまいましたとさ。「不要不急かどうかは本人が判断すべきだ」ホント、馬鹿だね。火に油を注ぐとはこういうのを言います。そこまで言われりゃあ、だったらこれまでの「自粛要請」は何だったんだってことになるのは当たり前。これからは「本人の判断」でやらせてもらいます、ってなもんです。女体盛り・西村君は「帰省して親族や同級生で集まることは絶対に避けてもらいたい。今回は自宅でステイホームで過ごしてもらえれば」と改めて「自粛」を呼びかけたそうだが、ルーピー丸川君のひと吠えですべてはおじゃんです。さあ、お盆休みは、「本人の判断」で大いに楽しむことにいたしましょう。
ところで、名古屋出入国在留管理局に収容中に死亡したウィシュマンさんについての最終報告書が公表された。しかしまあ、人一人が亡くなったというのに、誰一人責任も取らず、死因すら特定できないとは。身内による調査の限界が露骨に出た調査報告書に何の意味があるのだろう。入管職員による「いじめ」の結果の死とも言えるんだから、これはもう刑事事件だろう。それなのに、ウィシュマンさんの死に関わった職員の名前も非公表で、いまだに監視カメラの映像も一部は非公開ですからね。こんな最終報告書でお茶を濁されちゃ、遺族はたまったもんではありません。
韓国MBCテレビの番組は10日夜、「不当取引、国情院と日本極右」と題し、櫻井よしこ氏が理事長を務める公益財団法人「国家基本問題研究所(国基研)」が、韓国の情報機関「国家情報院(国情院)」から情報や金銭などの支援を受けていたと報じた。
「くろねこの短語」2021年8月10日 おそらく、もうお手上げ状態だからなのだろう。なんと、新型コロナウイルスを、現在の感染症2類相当から季節性インフルエンザ並みの5類相当へ移行しようと厚労省が検討してるそうだ。2類相当だと「症状がない人も含めた入院勧告や就業制限、濃厚接触者や感染経路の調査」が義務づけられているが、5類相当に格下げすると入院勧告や隔離などの措置は必要なくなる。ようするに、国や自治体の負担は大幅に軽減されるってわけだ。
「中等症は自宅療養」宣言は、こうした流れの先取りとも言えそうだ。いまは指定感染症だから医療費もタダだけど、これが5類相当になったらそうはいかない。医療費が払えないから医者にもかかれないなんてことが起きても不思議じゃないんだね。ま、究極の棄民政策と言っても過言ではありません。そのうち、「コロナはただの風邪」って記事がメディアを賑わすことになりますよ。妄想だけど。
ところで、韓国の情報機関が日本の極右団体を支援していた疑惑が浮上して、その詳細を今日にも韓国MBCテレビが放映するってね。日本の右翼団体関係者としてネトウヨの女王・櫻井よし子君の名前が上がっているとか。ネトウヨの女王・櫻井君とくれば、その親玉はペテン師・シンゾーで、その爺さんの岸信介から受け継いだ韓国利権を握っているんだね。そもそも、ペテン師・シンゾーは統一教会の機関紙の表紙を飾るほどの親韓派で、嫌韓を装っているのはネトウヨ向けのポーズにすぎない。みんな裏では繋がってるってことです。

大濱 聡 2021-8-9
「くろねこの短語」2021年8月9日 大会関係者のコロナ感染が400人を超えてたところでオリンピックがようやく終わった。とは言え、東京2020が抱える問題、たとえば7000億円の予算が4兆円というベラボーに肥大した後始末など山積する問題は残ったままだ。そんな問題のひとつに、オリンピック誘致にまつわる元JOC会長・竹田君の汚職疑惑がある。その汚職疑惑に新たな事実が。なんと、フランス当局の捜査を受けている竹田君の弁護費用の全額をJOCが負担しているんだとさ。フランス当局の捜査が始まってからの3年間で、既に2億円もの弁護費用がかかってるんだとか。捜査終了までJOCは弁護費用を負担するそうだから、弁護費用が最終的にどのくらいの額になるかは見当もつきません。
弁護費用は企業からの協賛金などで賄ているってんだが、JOCがそこまで面倒を見ているってことは、自分たちもグルだからなんじゃないのかねえ。JOCは「竹田前会長はJOCの理事会の承認を受けて、招致委理事長の職に就いた。招致委の活動は、各国オリンピック委員会が責任を持つと五輪憲章に定められている」からって言い訳してるけど、もし竹田君の独断で行われたとすれば、それは背任行為でもあるんだから弁護士費用負担する必要ないはずなんだね。竹田君は身柄拘束の恐れがあるから日本から出ることもできないそうで、金満五輪の象徴みたいな事件の行方やいかに。
「くろねこの短語」2021年8月8日 ちょいと朝寝坊した日曜の朝、ラジオをつけたら、な、なんと、すべての局がマラソン中継。放送の自由はどこ行ったんでしょうねえ。そんなことより、ボランティアなどの弁当を廃棄していた件で、大会組織委員会は4000食という調査結果を発表していたんだが、それがほんの氷山の一角にすぎないことが発覚したってね。弁当廃棄処分をスクープしたTBS『報道特集』がさらに取材を進めた結果、国立競技場以外の会場も併せて13万461食にも上り、その額は1億1600万円だとさ。
これだけの弁当があれば、ホームレスや貧困家庭の子供たちがどれほど助かることか。利権まみれの政治屋や五輪貴族は、そんなことカケラも考えたことないんだろう。そして、いまだに「国を背負って」なんてほざいている一部のアスリートも同じ穴のナントヤラってことだ。オリンピックが終わっても、オリンピックの予算の闇はとことん追及しないとダメだろう。
E・S8-8 21時前に出歩いたことはないが、前島スパーに買い物で帰途、居酒屋の前の歩道に12名が固まって一人はタバコを吸っている。居酒屋は満員。そこでそれを避けて車道を歩いたが、居酒屋も生活が掛かっているのだろう。もう一つは地元紙がオリパラの平良、喜友名の金メダルで大きく紙面を割いてコロナはどこ行ったかと、沖縄県民が軽く考えたのも一因か。
FASH8-8 開会式で用いられたのは、PYRO花火という種類のもので、見たかぎり、スペインかイタリアで生産されたものですね」そう語るのは、ある花火業界関係者だ。世界中から注目される五輪の開会式で打ち上げられた花火が、国産ではなかったというのだ。
「くろねこの短語」2021年8月7日 いやあ、この男のやることなすことすべてがポンコツってことが改めてわかった。何がって、広島平和祈念式典での顔も頭も貧相なカス総理の挨拶読み飛ばし事件だ。それも極めて重要な文言を含む箇所なんだね。読み飛ばしたくだりは以下の通り。「・・・世界の実現に向けて力を尽くします。』と世界に発信しました。わが国は、核兵器の非人道性をどの国よりもよく理解する唯一の戦争被爆国であり、『核兵器のない世界』の実現に向けた努力を着実に積み重ねていくことが重要です。近年の国際的な安全保障環境は厳しく・・・」おかげで、意味不明な挨拶になっちまったとうわけだ。で、カス総理の粗相はこれだけでなく、何と読み間違いもやらかしてたってね。こんな具合です。「広島市」→「ひろまし」「原爆」→「げんぱつ」または「げんばつ」
おそらく、こんな大事な式典だってのに原稿の下読みすらしてなかったのに違いない。エビフリャー河村君が金メダルを噛んで炎上したが、カス総理は原稿読みを噛んでそのポンコツぶりを世界にアピールしちまったというわけだ。読み飛ばしの言い訳が凄いんだよね。「原稿がのりでくっついて剥がれなかった」からだとさ。でも、使用していたのは奉書紙のはずだから糊つけるとこなんかないんじゃないの・・・なんて突っ込みもありまっせ。ただでさえコピペみたいな使いまわしの挨拶文だってのに、これでは原爆で命を落とした10数万人の霊はけっして安らぐことはありません。もう終わりにしよう、ペテン師・シンゾーから続くポンコツ政治の流れは!!
「くろねこの短語」2021年8月5日 どうやら、顔も頭も貧相なカス総理の「自宅放置」宣言は、コロナ対策分科会の尾身シェンシェイへの事前相談もなく決められたってね。昨日の閉会中審査でのやり取りで発覚したんだが、これについて娘が女子アナの厚労大臣・田村君は、「病床のオぺレーションの話なので、政府が決める話」だとさ。意味がわかりません。「中等症のうち重症化のリスクの低い人は自宅療養」のどこが「病床オペレーションの話」なんだ。
さすがにこうしたカス政権の独断専行に自民党内からも反発の声が上がって、党の会合で撤回を求めることを決めたそうだ。選挙も近いし、これ以上ポンコツ政権に付き合ってたら共倒れになっちゃいますからね。それでもカス総理は強気一辺倒で、「撤回しない」「必要な医療を受けられるための措置だ。説明し理解してもらう」とさ。
土建政治の二階君が「菅首相は『続投してほしい』の声が国民の間にも強い」とほざいて、そんな声はどこにもない、難聴なんじゃないのかと冷笑されたようだけど、ひょっとしたら「自宅放置」宣言はカス総理の致命傷になるかもね。最悪50議席減なんて予想もある状況で、こんなポンコツが選挙の顔ではとてもじゃないけど戦えません。オリンピック終わった週明けから、カス降ろしが始まるかも・・・てなことを我が家のドラ猫に囁いてみる危険な暑さの木曜の朝である。
04/12: 麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安正
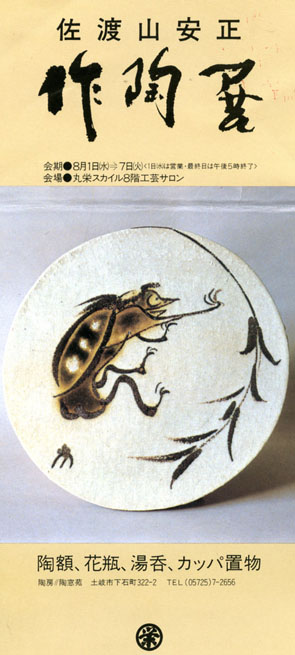
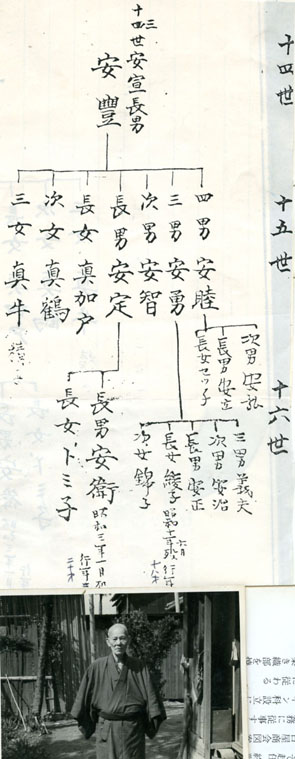
写真右・佐渡山安勇

写真・佐渡山安正
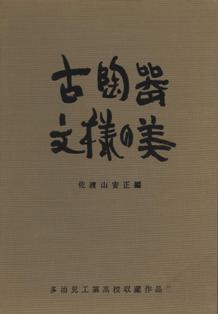
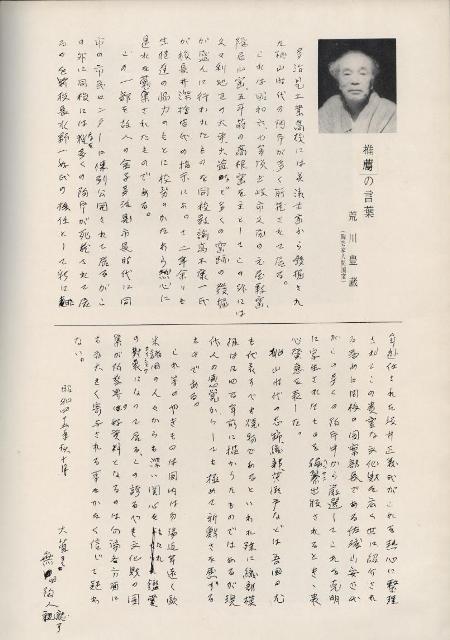
1970年12月ー佐渡山安正『古陶器文様の美』東文堂
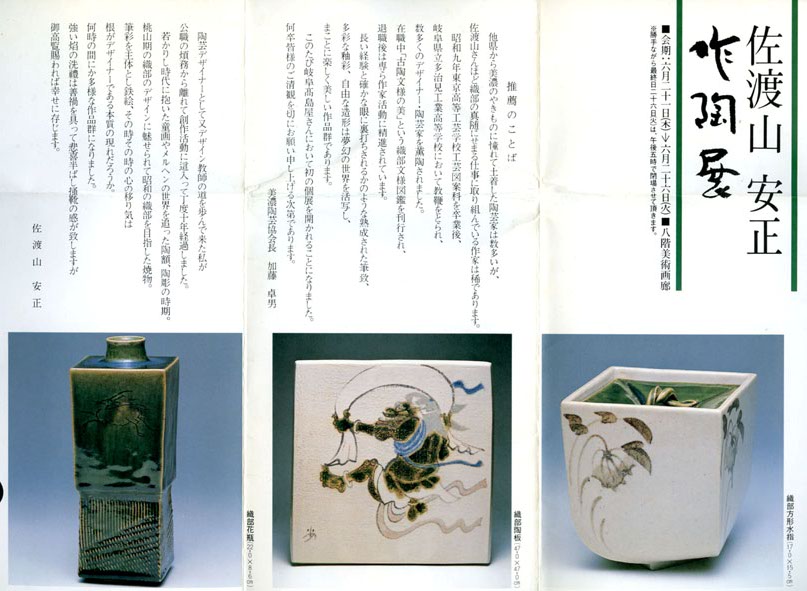
○今日、岐阜県土岐市下石というところに行ってきました。
愛知の沖縄調査の仕事です。で、ついでに、この町を流れる川に架かる橋のたもとに据えられているシーサーを見てきました。しっかり橋と町を守っているようですね。これは、琉球王国時代の絵師佐渡山安健を先祖に持つ、故佐渡山安正の作品です。
町を守りながら、遠く故郷を望んでいるように見えました。写真ではわかりづらいですが、町を囲む山々の紅葉も見頃で、その紅葉をバックに、シーサーもとても見栄えがしました。→2007年12月01日「干瀬のまれびとの座ーまれびとの見る沖縄を語る」
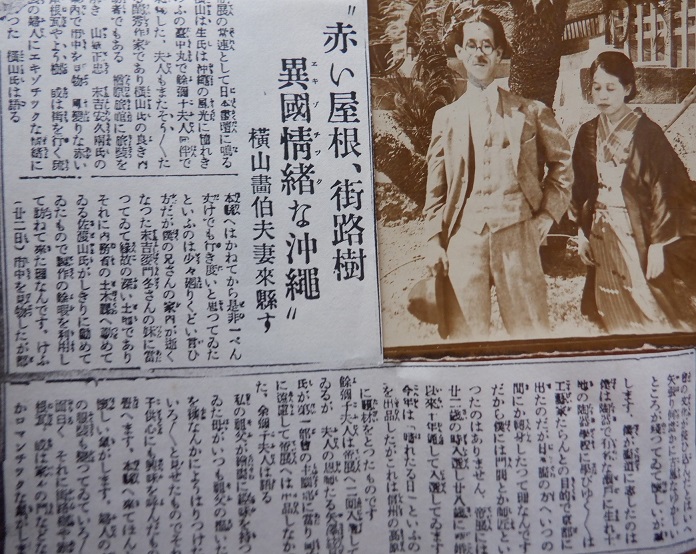
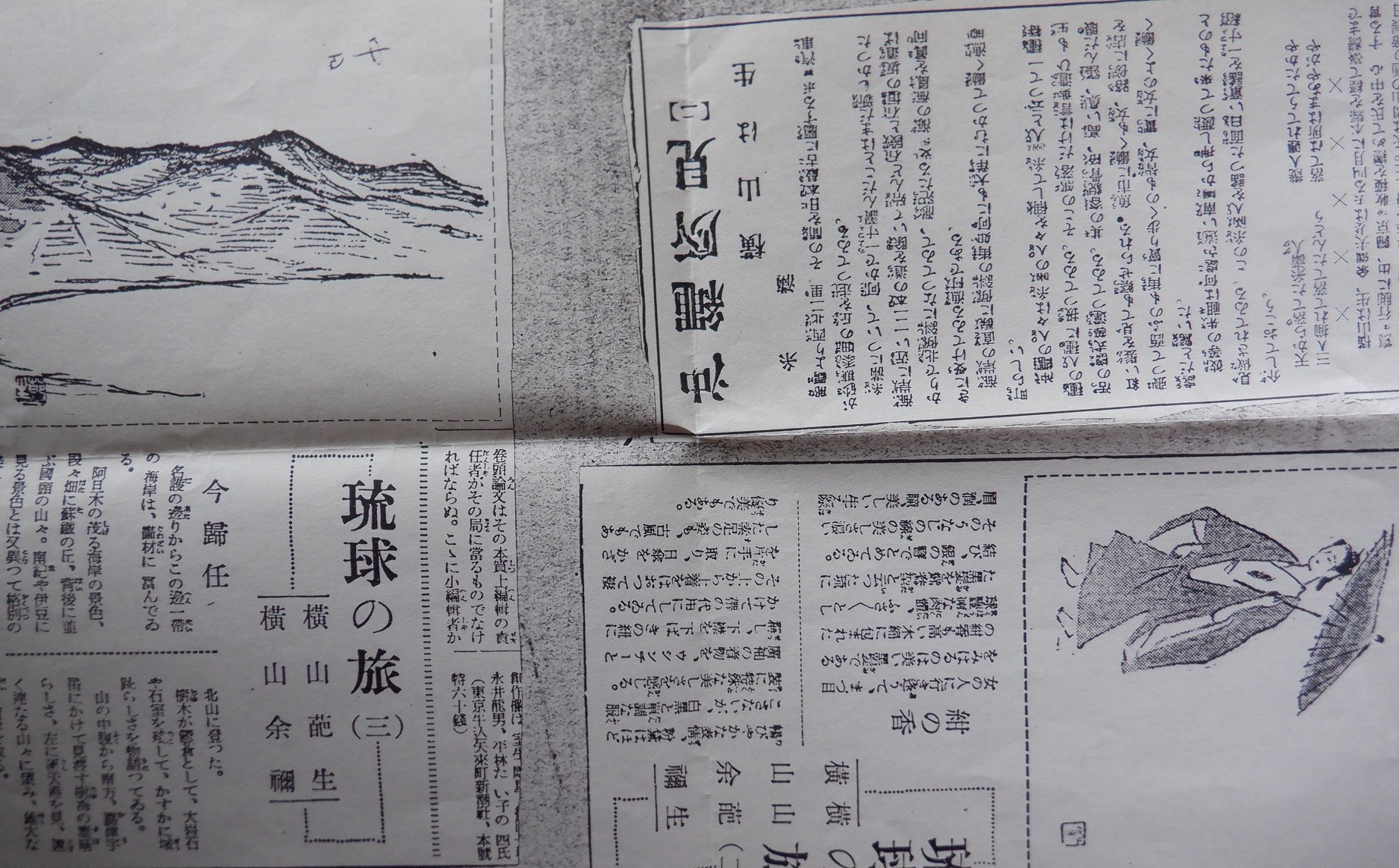
横山葩生、余彌子夫妻来沖
□1936年4月ー台中丸で、帝展画家の横山葩生、余彌子夫妻来沖。「横山画伯夫妻けふ沖縄訪問ー氏の義姉は故末吉麦門冬氏の妹にあたり、古くから憧れていた南島沖縄訪問がやっとこの日実現されたものである。なお氏の来遊に就いて名古屋在住の佐渡山安勇氏より島袋全発図書館長へ世話方を依頼して来ている。」/「」10月ー『塔影』「青樹社第三回展ー名古屋伊藤銀行中支店楼上に開催。同社は横山葩生君を中心とする団体、葩生君の『南国風景』」
横山葩生 (よこやまはせい) 生年 / 没年 : 1899 / 1974
生地 / 没地 : 愛知県瀬戸市 / 愛知県名古屋市 第2回帝展(1920) 中京美術院 青樹社→愛知県美術館

写真ー金城安太郎氏と石垣さん親子(末吉麦門冬娘)
09/23: 世相ジャパン
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com
「くろねこの短語」2021年10月10日 あっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君の顔が出てくるたびに、テレビに向かって物を投げたくなる今日この頃 そんなことより、日大背任事件が、まるで第2の加計学園みていな様相を呈してきた。なんと言っても、日大背任事件相関図にペテン師・シンゾーの名前が出てきますからね。逮捕された理事のひとりはペテン師・シンゾーが「ヤブちゃん」の愛称で親しく付き合っていっただけでなく、「錦秀会グループから安倍元首相の出身派閥である細田派の政治団体『清話政策研究』に、多額の政治献金が寄付されていた」そうだ。錦秀会グループとは西日本最大級の医療グループで、ヤブちゃんはそこの理事長だったんだね。
そんなヤブちゃんがただのゴルフ仲間であるわけがありません。そりゃあ何らかの利権があって、ペテン師・シンゾーと持ちつ持たれつの関係だっただろうことは容易に想像がつく。加計学園の雲隠れ孝太郎との関係を彷彿とさせます。日大事件がどんな展開になるかはわからないけど、おそらく本丸はいろいろ黒い噂のある田中理事長じゃないのかねえ。そこまで捜査の手が伸びないと、ただのトカゲの尻尾切りで終わっちまいますよ。ついでに、ペテン師・シンゾーが金の流れに関与してたら面白いんだけど。
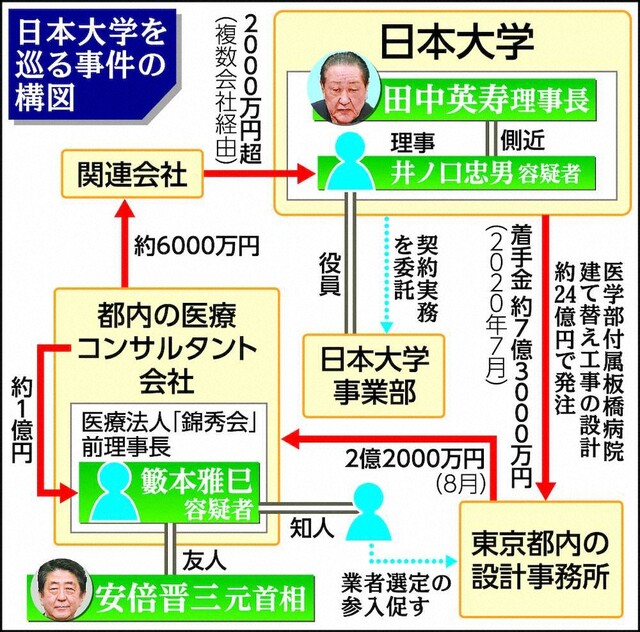
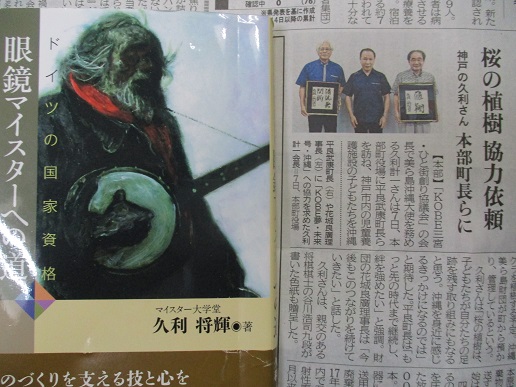

2016年6月 久利将輝『ドイツの国家資格 眼鏡マイスターへの道』マイスター大学堂/2021年10月8日『沖縄タイムス』「桜の植樹 協力依頼 神戸の久利さん本部町長らに」/2019年9月18日『琉球新報』「第55回琉球新報賞 社会・教育功労 久利計一氏 (自然や歴史、文化を体験する事業「KOBE夢・未来号・沖縄」を実施しているKOBE三宮・ひと街創り協議会会長)」
10-11 本日も「波」ウィルス禍、沖縄7人(4)米軍4、大阪49人、東京49人(6)
10-10 本日も「波」ウィルス禍、沖縄14人米軍、大阪105人(2)、東京60人(7)
10-9 本日も「波」ウィルス禍、沖縄15人(5)米軍6、大阪124人、東京82人(9)
10-8 本日も「波」ウィルス禍、沖縄29人(4)米軍2、大阪166人(13)、東京138人(18)
10-7 本日も「波」ウィルス禍、沖縄16人米軍9、大阪165人(5)、東京143人(19)
10-6 本日も「波」ウィルス禍、沖縄30人米軍11、大阪209人(4)、東京149人(5)
10-5 本日も「波」ウィルス禍、沖縄38人(4)米軍9、大阪176人(6)、東京144人(5)
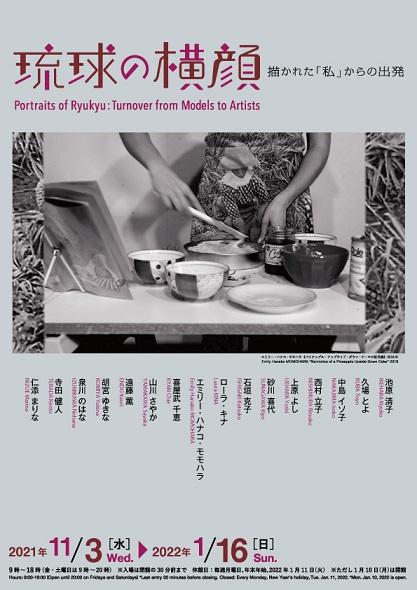
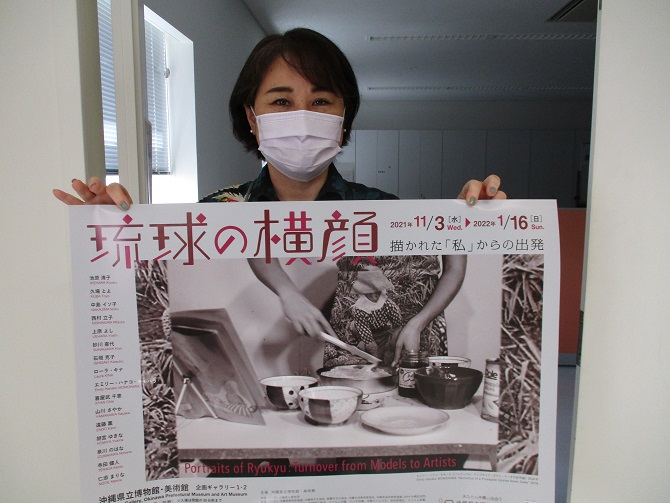
琉球の横顔 ― 描かれた「私」からの出発 沖縄県立博物館・美術館 2021年11月03日(水) ~ 2022年01月16日(日)沖縄に生まれ、あるいは沖縄にゆかりのある16人の作家の作品を紹介します。
アジア諸国と交易をおこなっていた琉球王国時代から、沖縄は独自の文化を形成してきました。しかし、日本の一部となった後の1932年、沖縄出身の久志芙沙子の小説『滅びゆく琉球女の手記(原題は「片隅の悲哀」)』が婦人公論に掲載されると、ハジチなどの習俗に対する表現をめぐり、在京の沖縄県学生会から抗議が起こり、未完のままとなりました。本展は、89年前に久志がすくった「弱者への差別や偏見」という問題を21世紀の今日に受け止め、表現の限界に迫る方法論を実践するアーティストを取り上げます。沖縄系ハワイ移民をルーツに持つアメリカの作家や1977 年に発足した沖縄女流美術家協会の作家、沖縄県立芸術大学などで学んだ作家の作品など、約50点を展示します。沖縄美術の多文化的な側面と可能性を感じていただき、アートの新たな展開を楽しんでいただけることと思います。


那覇市立壺屋焼物博物館 11月2日~12月26日「うちなー赤瓦ものがたり」(観覧料無料)
「くろねこの短語」2021年10月8日 久しぶりの大きな揺れに、一瞬ドキっとしたものの、物が落ちたりはしなかったので安心していたら、なんと朝になったらけっこうな被害が出ていたのにはビックリ。まだ余震がありそうというから、しばらくは要注意かもね。・東京都内で震度5強 各地で水道管破裂、冠水
ビックリと言えば、連合の新会長の発言だ。なんとまあ、「共産の閣外協力はあり得ない。(立民の)連合推薦候補にも共産が両党合意を盾に、共産の政策をねじ込もうという動きがある」って不快感を示したんだとさ。衆 議院選直前に野党共闘を妨害するような発言を、連合の会長がするってのは、明らかな利敵行為だろう。やっぱり、連合なんかもういらない。大企業の御用組合に変貌した連合は、労働者の味方ではありませんからね。
国民民社のタマキンは「国民民主の路線と全く一致している。これまで以上に連携をよく取りたい」ってこの発言を歓迎しているそうで、前川喜平氏が指摘するように、連合がそうであるように国民民主ももはや「自民の補完勢力」にすぎないってことだ。ところで、日大の背任事件で逮捕された理事って、ペテン師・シンゾーと昵懇の間柄なんだってね。日大には私学助成金として90億円の税金が渡っている。背任事件はいわば税金を搾取したようなもので、政治家にもその一部が流れていたりして・・・妄想だけど。その政治家がペテン師・シンゾーだったら、またひとつの疑獄事件の始まりとなるんだが・・・果たして、真相やいかに。
「くろねこの短語」2021年10月7日 ガラクタ内閣の顔ぶれを見ていると、「誰それ?」って聞きたくなるほどイメージ希薄な陣笠揃いと思いがちなんだが、どっこい裏ではけっこうブイブイ言わせてるワルばかりなんだってね。なんでも、「政治とカネ」疑惑大臣が9人もいるそうで、早速、文春砲が炸裂しましたとさ。標的になったのは、ワニ男・平井君の後釜におさまったデジタル大臣のデジ女・牧島かれん君だ。なんとまあ、NTTから2回にわたって高額接待を受けていたってね。「事後的割り勘」で顰蹙買ったワニ男と同じで、ようするにデジタル庁ってのはNTTとつるんだ利権の温床になってるってことだ。
でもって、週刊文春の取材に対して、デジ女・牧島君は、こんな風に開き直ってくれましたとさ。「会食を伴う意見交換を行ったのは事実です。(飲食費を)支払った記憶はございません。政治家として様々な方と意見交換を行うことは重要であり、問題ないと考えています」こんな言い分が通るなら、利害関係のある業者との接待はフリーパスってことになりますよ。デジ女以外にも、巨額年金消失事件に関わった企業との関係が囁かれる厚労大臣、政治資金で高級ブランド爆買いた文科大臣、元公設秘書が凶悪事件を起こしていた国家公安委員長et・・・いやあ、「世に盗人の種は尽きまじ」とはよく言ったものだ。
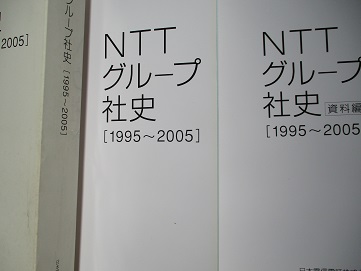
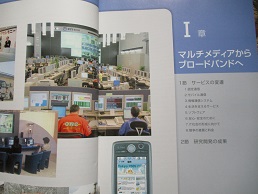
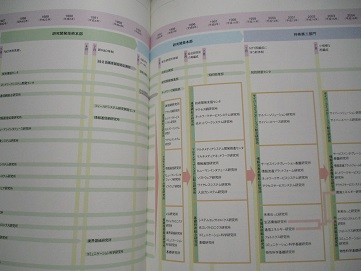
2006年3月 『NTTグループ社史』
「くろねこの短語」2021年10月6日 日本出身の学者がノーベル賞受賞は確かにめでたい。しかし、なぜ真鍋博士がアメリカ国籍を取ったのか。日本ではまともな研究が出来ないという現状をこそ、いま語るべきなんじゃないのか。そんなことより、岸田ガラクタ内閣の支持率だ。発足直後だというのに、なんと共同通信の調査では55.7%、毎日新聞では49%と5割にも届かない低支持率。あのポンコツ内閣だって発足当初は御祝儀もあって70%近くあったんだよね。それがこんな低支持率ってのは、あっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君の幹事長起用ってのがかなり大きく影響しているのは間違いない。それが証拠に、幹事長人事評価しないが54%にも上っている。さらに、森友学園疑獄については「再調査をするべき」が62.8%もありましたとさ。
でもって、河井バカップル買収事件の再調査についても、ひと悶着あったってね。あっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君がNHKの番組で「再調査はしない」と明言したことに反発して、広島県連幹部が昼間の幽霊・岸田君に「まだ今のやり方では広島県民、また国民の皆さんは納得してませんよ」と詰め寄ったそうだ。睡眠障害・甘利君のあっせん利得疑惑を調査する野党合同の追及チームのヒアリングが始まり、岸田ガラクタ内閣は船出早々に座礁の危険性が高まっている。ジョー、フミオなんて馬鹿言ってないで、もっとやるべきことをやりやがれ。




沖縄のシンボル守礼門入口/守礼門、手前右の階段を上ると徐葆光顕彰の碑

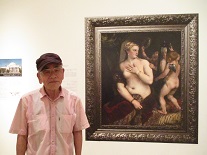


2021-10-3 沖縄県立博物館・美術館 新城良一氏/新城良一氏運転で首里へ、佐藤惣之助詩碑(工事中)




2021-10-3 泊から見た黄金森公園/おもろまちから見た黄金森公園
「くろねこの短語」2021年10月3日 フリップ小池君が特別顧問を務める都民ファーストの会が国政政党設立をするんだとか。でもって、今日にも記者会見ってんだが、なにやら希望の党を想起させますね。民進党を分裂に追い込んで、あわよくば初の女性総理を狙ったものの、「排除します」の一言ですべてが水泡に帰したのはまだ記憶に新しい。「私は都民ファーストの会の動きについて関知していない」ってフリップ小池君は知らぬ存ぜぬを決め込んでいるようだが、どうしてどうして。着々と進む野党共闘を切り崩して、自民党の手助けして恩を売る絶好のチャンスと感じてるんじゃないのか。国民民主のタマキンも連携に色気があるようで、ひょっとすると国民民主を解党して都民ファーストとの新党に合流・・・なんてことがあったりして。
ところで、ワイロ・ドリル・パンツと揶揄される自民党役員人事なんだが、パンツことパンティ高木君には下着泥棒以外に香典疑惑もあったんだね。ひっそり隠れてりゃあいいものを、ノコノコと日の当たる場所に出てくるものだから、それならってんだ過去の悪事が掘り起こされる。 ドリル小渕君にしたって、どのツラ下げてというのが世間の見方で、証拠のハードディスクを破壊した過去はそんなに簡単に消えるものではありません。 ひょっとして、昼間の幽霊・岸田君はそこのところを計算してのワイロ・ドリル・バンツ人事だったりして。あっせん利得疑惑の甘利君なんか、これから週一で記者会見するわけで、針の筵になるんじゃないのかねえ。 過去の悪事が蒸し返されることを予想して、甘利失脚を画策したとしたら・・・ま、それほどの策士なら、もっと早くに総理・総裁になっていたか
「くろねこの短語」2021年10月2日 昼間の幽霊・岸田君が自民党総裁になって、御祝儀相場どころか株価が下落だとさ。そりゃそうだ。あっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君を事もあろうに幹事長に起用するんだもの。睡眠障害男の不景気面を見れば、株価も下がろうというものだ。その甘利君が記者会見に登場。早速、あっせん利得疑惑を突っ込まれて、こんな言い訳しましたとさ。「私は寝耳に水(だった)。事件がどういうものであったのか、わからないところから始まった」「辞任会見で質問が出尽くすまでお答えをいたしました」でも、思い出してみよう。大臣室で業者から現金受け取ったのがバレて、経済再生担当相を辞任する時の記者会見を。この男は、こんなことのたまってたんだよね。「未だ全容の解明には至っておりません。引き続き調査を進め、しかるべきタイミングで公表する機会を持たせていただくことについて御理解を賜れればと思っております」つまり、「質問が出尽くすまでお答え」してないってことだ。野党は調査チームを設置するそうだけど、それを察してか昼間の幽霊・岸田君は予算委員会を開くつもりはないってね。衆議院選を前に睡眠障害・甘利君があっせん利得疑惑で火だるまにされちゃうとまずいからだろう。昼間の幽霊・岸田君にとって、睡眠障害男の存在はアキレス腱となって、いずれ窮地に立たされるんじゃないのかねえ。もう忘れただろうとタカをくくっていたツケが、早くも回ってきたってことか。ざまあありません。
「くろねこの短語」2021年10月1日 (前略)いやあ、それにしても、党役員人事を見るにつけ、誰に忖度したか一目瞭然の面子には、そのあまりの露骨さに反吐が出ます。なかでも、白眉はあっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君の幹事長登用だろう。この男の名前を聞いただけで、昼間の幽霊・岸田君への淡い期待が一気に醒めたとも言われる。そりゃあそうだ。議員会館で金銭やり取りして、秘書にその責任を押し付けたまま説明責任を果たさずに、睡眠障害で病院に逃げ込んだチキン野郎ですからね。
娑婆にいるのが不思議なくらいのまっくろくろすけが幹事長って、つまりは安倍・麻生傀儡政権ですって自分で言ってるようなものなんだね。ちなみに、ブロック大王・河野君の党広報部長ってのは、ていのいい左遷ってことで、見せしめみたいなものか。今日にもあっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君は記者会見するようだが、記者クラブの懲りない面々がどこまでこの男の闇の部分に突っ込めるか・・・ま、期待するだけムダだろうけど、お手並み拝見の台風襲来の朝である。
10-4 本日も「波」ウィルス禍、沖縄9(6)人、大阪96人(1)、東京87人(6)
10-3 本日も「波」ウィルス禍、沖縄29人米軍5、大阪136人、東京161人(7)
10-2 本日も「波」ウィルス禍、沖縄43人(5)米軍15、大阪184人、東京196人(13)
10-1 本日も「波」ウィルス禍、沖縄41人(5)米軍8、大阪241人(1)、東京200人(14)
9-30 本日も「波」ウィルス禍、沖縄64人(5)米軍6、大阪264人(3)、東京213人(12)

大濱聡 9-30
「くろねこの短語」2021年9月30日 「生まれ変わった自民党を国民に示す」(岸田文雄)・・・だったら、モリ・カケ・サクラに河井バカップル買収事件の真相解明に力を尽くせ!!&幹事長に甘利の名前が上がってるようじゃ、ダメだ!ガラクタ4人組による自民党総裁の椅子取りゲームは、昼間の幽霊・岸田君の勝利に終わった。何のことはない、ペテン師・シンゾー、ひょっとこ麻生、そして土建政治・二階による院政の始まりってことだ。
SPA! 9-29 そこでGACKT氏と親密な夫の文信氏が妻である野田聖子を頼り、金融庁に対して圧力をかけたとされる疑惑が浮上。週刊文春(以下、文春)、週刊新潮(以下、新潮)が文信氏の黒い経歴と共に疑惑を報じたのです。そして、この一件で野田氏の夫、文信氏が文春、新潮の2誌を事実無根、名誉毀損として訴えることになったんです」文春を訴えた判決が今年3月24日に出たのだが、その内容はある意味、センセーショナルなものであった。
なんと、裁判で訴えたもの圧力疑惑はなしとされたが、逆に裁判所から「元ヤクザ」と認定されてしまったのである。文春でこうした判決が出たわけなので、新潮は勝ち試合を眺めるだけの状態だったのだが、さらに予想を上回る判決が飛び出したのだ。「新潮の裁判では『原告が指定暴力団・会津小鉄会の昌山組に所属していた元暴力団員であるとの事実の重要な部分は、真実であると認められる』と具体的な組の名前を挙げて、文信氏が組員だったことを認定したのです」
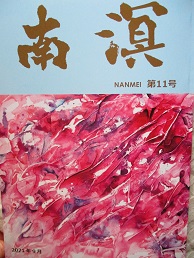


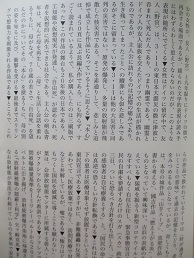
2021年9月 同人誌『南溟』11号 『南溟』同人会-〒904-2166 沖縄市古謝津嘉山町8番9号 TEL&FAX.098-934-2006 平敷武蕉「アンニョン ハセヨ 韓国の空」/真壁朝廣「評論 父の履歴書から考える」/「あとがき」
「くろねこの短語」2021年10月10日 あっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君の顔が出てくるたびに、テレビに向かって物を投げたくなる今日この頃 そんなことより、日大背任事件が、まるで第2の加計学園みていな様相を呈してきた。なんと言っても、日大背任事件相関図にペテン師・シンゾーの名前が出てきますからね。逮捕された理事のひとりはペテン師・シンゾーが「ヤブちゃん」の愛称で親しく付き合っていっただけでなく、「錦秀会グループから安倍元首相の出身派閥である細田派の政治団体『清話政策研究』に、多額の政治献金が寄付されていた」そうだ。錦秀会グループとは西日本最大級の医療グループで、ヤブちゃんはそこの理事長だったんだね。
そんなヤブちゃんがただのゴルフ仲間であるわけがありません。そりゃあ何らかの利権があって、ペテン師・シンゾーと持ちつ持たれつの関係だっただろうことは容易に想像がつく。加計学園の雲隠れ孝太郎との関係を彷彿とさせます。日大事件がどんな展開になるかはわからないけど、おそらく本丸はいろいろ黒い噂のある田中理事長じゃないのかねえ。そこまで捜査の手が伸びないと、ただのトカゲの尻尾切りで終わっちまいますよ。ついでに、ペテン師・シンゾーが金の流れに関与してたら面白いんだけど。
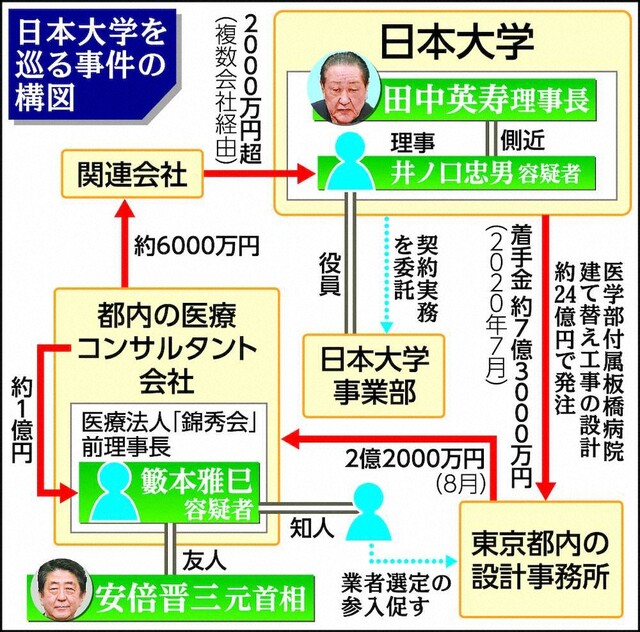
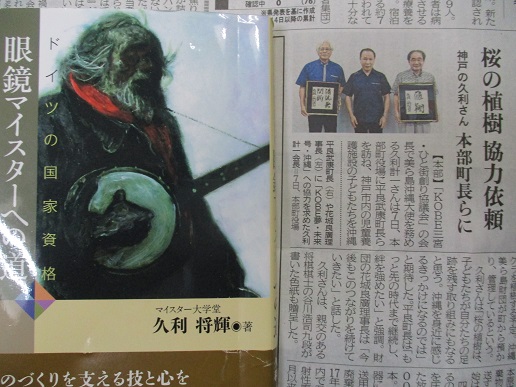

2016年6月 久利将輝『ドイツの国家資格 眼鏡マイスターへの道』マイスター大学堂/2021年10月8日『沖縄タイムス』「桜の植樹 協力依頼 神戸の久利さん本部町長らに」/2019年9月18日『琉球新報』「第55回琉球新報賞 社会・教育功労 久利計一氏 (自然や歴史、文化を体験する事業「KOBE夢・未来号・沖縄」を実施しているKOBE三宮・ひと街創り協議会会長)」
10-11 本日も「波」ウィルス禍、沖縄7人(4)米軍4、大阪49人、東京49人(6)
10-10 本日も「波」ウィルス禍、沖縄14人米軍、大阪105人(2)、東京60人(7)
10-9 本日も「波」ウィルス禍、沖縄15人(5)米軍6、大阪124人、東京82人(9)
10-8 本日も「波」ウィルス禍、沖縄29人(4)米軍2、大阪166人(13)、東京138人(18)
10-7 本日も「波」ウィルス禍、沖縄16人米軍9、大阪165人(5)、東京143人(19)
10-6 本日も「波」ウィルス禍、沖縄30人米軍11、大阪209人(4)、東京149人(5)
10-5 本日も「波」ウィルス禍、沖縄38人(4)米軍9、大阪176人(6)、東京144人(5)
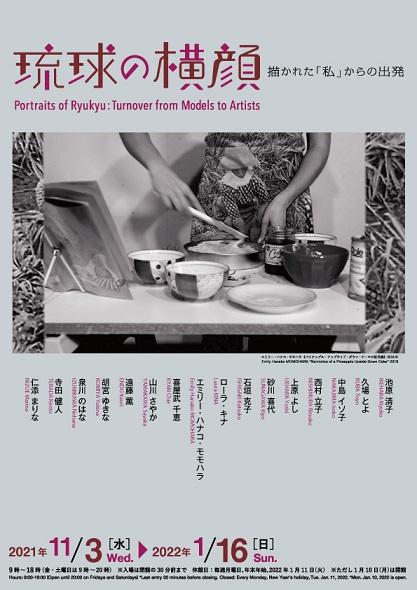
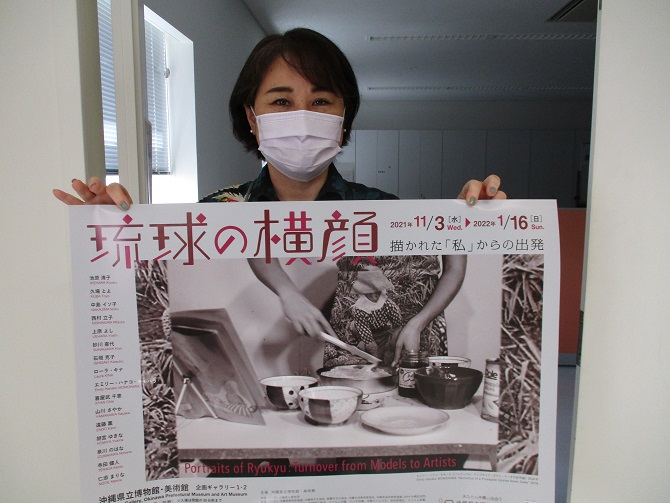
琉球の横顔 ― 描かれた「私」からの出発 沖縄県立博物館・美術館 2021年11月03日(水) ~ 2022年01月16日(日)沖縄に生まれ、あるいは沖縄にゆかりのある16人の作家の作品を紹介します。
アジア諸国と交易をおこなっていた琉球王国時代から、沖縄は独自の文化を形成してきました。しかし、日本の一部となった後の1932年、沖縄出身の久志芙沙子の小説『滅びゆく琉球女の手記(原題は「片隅の悲哀」)』が婦人公論に掲載されると、ハジチなどの習俗に対する表現をめぐり、在京の沖縄県学生会から抗議が起こり、未完のままとなりました。本展は、89年前に久志がすくった「弱者への差別や偏見」という問題を21世紀の今日に受け止め、表現の限界に迫る方法論を実践するアーティストを取り上げます。沖縄系ハワイ移民をルーツに持つアメリカの作家や1977 年に発足した沖縄女流美術家協会の作家、沖縄県立芸術大学などで学んだ作家の作品など、約50点を展示します。沖縄美術の多文化的な側面と可能性を感じていただき、アートの新たな展開を楽しんでいただけることと思います。


那覇市立壺屋焼物博物館 11月2日~12月26日「うちなー赤瓦ものがたり」(観覧料無料)
「くろねこの短語」2021年10月8日 久しぶりの大きな揺れに、一瞬ドキっとしたものの、物が落ちたりはしなかったので安心していたら、なんと朝になったらけっこうな被害が出ていたのにはビックリ。まだ余震がありそうというから、しばらくは要注意かもね。・東京都内で震度5強 各地で水道管破裂、冠水
ビックリと言えば、連合の新会長の発言だ。なんとまあ、「共産の閣外協力はあり得ない。(立民の)連合推薦候補にも共産が両党合意を盾に、共産の政策をねじ込もうという動きがある」って不快感を示したんだとさ。衆 議院選直前に野党共闘を妨害するような発言を、連合の会長がするってのは、明らかな利敵行為だろう。やっぱり、連合なんかもういらない。大企業の御用組合に変貌した連合は、労働者の味方ではありませんからね。
国民民社のタマキンは「国民民主の路線と全く一致している。これまで以上に連携をよく取りたい」ってこの発言を歓迎しているそうで、前川喜平氏が指摘するように、連合がそうであるように国民民主ももはや「自民の補完勢力」にすぎないってことだ。ところで、日大の背任事件で逮捕された理事って、ペテン師・シンゾーと昵懇の間柄なんだってね。日大には私学助成金として90億円の税金が渡っている。背任事件はいわば税金を搾取したようなもので、政治家にもその一部が流れていたりして・・・妄想だけど。その政治家がペテン師・シンゾーだったら、またひとつの疑獄事件の始まりとなるんだが・・・果たして、真相やいかに。
「くろねこの短語」2021年10月7日 ガラクタ内閣の顔ぶれを見ていると、「誰それ?」って聞きたくなるほどイメージ希薄な陣笠揃いと思いがちなんだが、どっこい裏ではけっこうブイブイ言わせてるワルばかりなんだってね。なんでも、「政治とカネ」疑惑大臣が9人もいるそうで、早速、文春砲が炸裂しましたとさ。標的になったのは、ワニ男・平井君の後釜におさまったデジタル大臣のデジ女・牧島かれん君だ。なんとまあ、NTTから2回にわたって高額接待を受けていたってね。「事後的割り勘」で顰蹙買ったワニ男と同じで、ようするにデジタル庁ってのはNTTとつるんだ利権の温床になってるってことだ。
でもって、週刊文春の取材に対して、デジ女・牧島君は、こんな風に開き直ってくれましたとさ。「会食を伴う意見交換を行ったのは事実です。(飲食費を)支払った記憶はございません。政治家として様々な方と意見交換を行うことは重要であり、問題ないと考えています」こんな言い分が通るなら、利害関係のある業者との接待はフリーパスってことになりますよ。デジ女以外にも、巨額年金消失事件に関わった企業との関係が囁かれる厚労大臣、政治資金で高級ブランド爆買いた文科大臣、元公設秘書が凶悪事件を起こしていた国家公安委員長et・・・いやあ、「世に盗人の種は尽きまじ」とはよく言ったものだ。
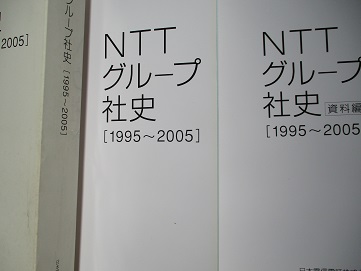
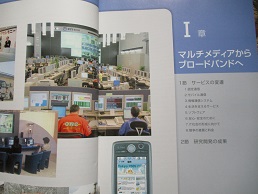
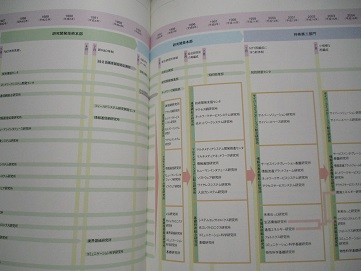
2006年3月 『NTTグループ社史』
「くろねこの短語」2021年10月6日 日本出身の学者がノーベル賞受賞は確かにめでたい。しかし、なぜ真鍋博士がアメリカ国籍を取ったのか。日本ではまともな研究が出来ないという現状をこそ、いま語るべきなんじゃないのか。そんなことより、岸田ガラクタ内閣の支持率だ。発足直後だというのに、なんと共同通信の調査では55.7%、毎日新聞では49%と5割にも届かない低支持率。あのポンコツ内閣だって発足当初は御祝儀もあって70%近くあったんだよね。それがこんな低支持率ってのは、あっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君の幹事長起用ってのがかなり大きく影響しているのは間違いない。それが証拠に、幹事長人事評価しないが54%にも上っている。さらに、森友学園疑獄については「再調査をするべき」が62.8%もありましたとさ。
でもって、河井バカップル買収事件の再調査についても、ひと悶着あったってね。あっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君がNHKの番組で「再調査はしない」と明言したことに反発して、広島県連幹部が昼間の幽霊・岸田君に「まだ今のやり方では広島県民、また国民の皆さんは納得してませんよ」と詰め寄ったそうだ。睡眠障害・甘利君のあっせん利得疑惑を調査する野党合同の追及チームのヒアリングが始まり、岸田ガラクタ内閣は船出早々に座礁の危険性が高まっている。ジョー、フミオなんて馬鹿言ってないで、もっとやるべきことをやりやがれ。




沖縄のシンボル守礼門入口/守礼門、手前右の階段を上ると徐葆光顕彰の碑

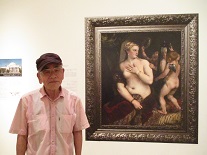


2021-10-3 沖縄県立博物館・美術館 新城良一氏/新城良一氏運転で首里へ、佐藤惣之助詩碑(工事中)




2021-10-3 泊から見た黄金森公園/おもろまちから見た黄金森公園
「くろねこの短語」2021年10月3日 フリップ小池君が特別顧問を務める都民ファーストの会が国政政党設立をするんだとか。でもって、今日にも記者会見ってんだが、なにやら希望の党を想起させますね。民進党を分裂に追い込んで、あわよくば初の女性総理を狙ったものの、「排除します」の一言ですべてが水泡に帰したのはまだ記憶に新しい。「私は都民ファーストの会の動きについて関知していない」ってフリップ小池君は知らぬ存ぜぬを決め込んでいるようだが、どうしてどうして。着々と進む野党共闘を切り崩して、自民党の手助けして恩を売る絶好のチャンスと感じてるんじゃないのか。国民民主のタマキンも連携に色気があるようで、ひょっとすると国民民主を解党して都民ファーストとの新党に合流・・・なんてことがあったりして。
ところで、ワイロ・ドリル・パンツと揶揄される自民党役員人事なんだが、パンツことパンティ高木君には下着泥棒以外に香典疑惑もあったんだね。ひっそり隠れてりゃあいいものを、ノコノコと日の当たる場所に出てくるものだから、それならってんだ過去の悪事が掘り起こされる。 ドリル小渕君にしたって、どのツラ下げてというのが世間の見方で、証拠のハードディスクを破壊した過去はそんなに簡単に消えるものではありません。 ひょっとして、昼間の幽霊・岸田君はそこのところを計算してのワイロ・ドリル・バンツ人事だったりして。あっせん利得疑惑の甘利君なんか、これから週一で記者会見するわけで、針の筵になるんじゃないのかねえ。 過去の悪事が蒸し返されることを予想して、甘利失脚を画策したとしたら・・・ま、それほどの策士なら、もっと早くに総理・総裁になっていたか
「くろねこの短語」2021年10月2日 昼間の幽霊・岸田君が自民党総裁になって、御祝儀相場どころか株価が下落だとさ。そりゃそうだ。あっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君を事もあろうに幹事長に起用するんだもの。睡眠障害男の不景気面を見れば、株価も下がろうというものだ。その甘利君が記者会見に登場。早速、あっせん利得疑惑を突っ込まれて、こんな言い訳しましたとさ。「私は寝耳に水(だった)。事件がどういうものであったのか、わからないところから始まった」「辞任会見で質問が出尽くすまでお答えをいたしました」でも、思い出してみよう。大臣室で業者から現金受け取ったのがバレて、経済再生担当相を辞任する時の記者会見を。この男は、こんなことのたまってたんだよね。「未だ全容の解明には至っておりません。引き続き調査を進め、しかるべきタイミングで公表する機会を持たせていただくことについて御理解を賜れればと思っております」つまり、「質問が出尽くすまでお答え」してないってことだ。野党は調査チームを設置するそうだけど、それを察してか昼間の幽霊・岸田君は予算委員会を開くつもりはないってね。衆議院選を前に睡眠障害・甘利君があっせん利得疑惑で火だるまにされちゃうとまずいからだろう。昼間の幽霊・岸田君にとって、睡眠障害男の存在はアキレス腱となって、いずれ窮地に立たされるんじゃないのかねえ。もう忘れただろうとタカをくくっていたツケが、早くも回ってきたってことか。ざまあありません。
「くろねこの短語」2021年10月1日 (前略)いやあ、それにしても、党役員人事を見るにつけ、誰に忖度したか一目瞭然の面子には、そのあまりの露骨さに反吐が出ます。なかでも、白眉はあっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君の幹事長登用だろう。この男の名前を聞いただけで、昼間の幽霊・岸田君への淡い期待が一気に醒めたとも言われる。そりゃあそうだ。議員会館で金銭やり取りして、秘書にその責任を押し付けたまま説明責任を果たさずに、睡眠障害で病院に逃げ込んだチキン野郎ですからね。
娑婆にいるのが不思議なくらいのまっくろくろすけが幹事長って、つまりは安倍・麻生傀儡政権ですって自分で言ってるようなものなんだね。ちなみに、ブロック大王・河野君の党広報部長ってのは、ていのいい左遷ってことで、見せしめみたいなものか。今日にもあっせん利得疑惑の睡眠障害・甘利君は記者会見するようだが、記者クラブの懲りない面々がどこまでこの男の闇の部分に突っ込めるか・・・ま、期待するだけムダだろうけど、お手並み拝見の台風襲来の朝である。
10-4 本日も「波」ウィルス禍、沖縄9(6)人、大阪96人(1)、東京87人(6)
10-3 本日も「波」ウィルス禍、沖縄29人米軍5、大阪136人、東京161人(7)
10-2 本日も「波」ウィルス禍、沖縄43人(5)米軍15、大阪184人、東京196人(13)
10-1 本日も「波」ウィルス禍、沖縄41人(5)米軍8、大阪241人(1)、東京200人(14)
9-30 本日も「波」ウィルス禍、沖縄64人(5)米軍6、大阪264人(3)、東京213人(12)

大濱聡 9-30
「くろねこの短語」2021年9月30日 「生まれ変わった自民党を国民に示す」(岸田文雄)・・・だったら、モリ・カケ・サクラに河井バカップル買収事件の真相解明に力を尽くせ!!&幹事長に甘利の名前が上がってるようじゃ、ダメだ!ガラクタ4人組による自民党総裁の椅子取りゲームは、昼間の幽霊・岸田君の勝利に終わった。何のことはない、ペテン師・シンゾー、ひょっとこ麻生、そして土建政治・二階による院政の始まりってことだ。
SPA! 9-29 そこでGACKT氏と親密な夫の文信氏が妻である野田聖子を頼り、金融庁に対して圧力をかけたとされる疑惑が浮上。週刊文春(以下、文春)、週刊新潮(以下、新潮)が文信氏の黒い経歴と共に疑惑を報じたのです。そして、この一件で野田氏の夫、文信氏が文春、新潮の2誌を事実無根、名誉毀損として訴えることになったんです」文春を訴えた判決が今年3月24日に出たのだが、その内容はある意味、センセーショナルなものであった。
なんと、裁判で訴えたもの圧力疑惑はなしとされたが、逆に裁判所から「元ヤクザ」と認定されてしまったのである。文春でこうした判決が出たわけなので、新潮は勝ち試合を眺めるだけの状態だったのだが、さらに予想を上回る判決が飛び出したのだ。「新潮の裁判では『原告が指定暴力団・会津小鉄会の昌山組に所属していた元暴力団員であるとの事実の重要な部分は、真実であると認められる』と具体的な組の名前を挙げて、文信氏が組員だったことを認定したのです」
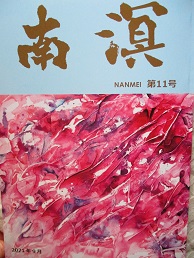


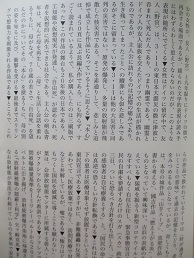
2021年9月 同人誌『南溟』11号 『南溟』同人会-〒904-2166 沖縄市古謝津嘉山町8番9号 TEL&FAX.098-934-2006 平敷武蕉「アンニョン ハセヨ 韓国の空」/真壁朝廣「評論 父の履歴書から考える」/「あとがき」
11/17: 世相ジャパン
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com
11月25日「莫夢忌」
「くろねこの短語」2021年11月25日 衆議院選の茨城6区でヘタレ総理やペテン師・シンゾーの街頭演説に参加した支持者に日当5000円が支給された事件の真相がいまだ解明されてないってのに、同じトラック協会がヘタレ総理のお膝元である広島3区で当選した公明党の鉄オタ・斉藤君の個人演説会に参加した支持者に旅費名目で現金を支給していましたとさ。広島3区はあの河井バカップルによる買収事件の舞台になった選挙区で、なんとも懲りないというか、金金金の選挙が当たり前になっているんだろうね。
週刊文春によれば、参加者への案内状には、手書きで以下のメモが記載されていたそうだ。「各位 当日受付近くで広島北支部のA(注・原文では実名)が旅費をお渡ししますので受付前に対面できる様ご配慮願います。」これって、鉄オタ・斉藤君の事務所が出した案内状なんだよね。そこにトラック協会が手書きのメモを記載しているんだけど、それを見た支持者にすれば鉄オタ・斉藤君の事務所からの旅費支給と思っても不思議じゃない。となると、斉藤事務所側の「広島県トラック協会に個人演説会のご案内を致しました。手書きのメモについては承知しておりません。旅費についても承知しておりません。当方より参加者に対し旅費等の支払いは一切行っておりません」って言い訳は、いかにも苦しい。公明党は遠山デマ彦の違法融資問題もあるし、「平和の党」「福祉の党」の金看板が泣こうというものだ。近いうちに、仏罰があたることだろう。
「くろねこの短語」2021年11月24日 維新のパフォーマンスから始まった文通費問題の火の粉が政党助成金問題に降りかかり、その実体が徐々に明らかになりつつある。そもそも、政党助成金ってのは「余ったら国庫に返すのが原則」なんだね。ところが、維新は「2018~20年の交付金総額約47億円のうち、3割弱をため込み、20年は15億円を超える」ってんで、大ブーメランとなったのは記憶に新しいところ。
では、他の政党はいかがなものかと調べたら、なんと「岸田内閣の閣僚や自民党幹部もタップリと血税を“蓄財”していることが分かった」ってね。先にも触れたように、政党助成金は「余ったら国庫に返すのが原則」だが、なんと「基金」として積み立てれば返納を免れるという裏ワザがありますとさ。こんな具合です。赤旗が岸田内閣と自民党役員の基金のため込み額について調べたところ、岸田首相2638万円、萩生田経産相1259万円、岸防衛相204万円、山際経済再生相99万円と4閣僚が名を連ねる。麻生副総裁1930万円、高木国対委員長1621万円、遠藤選対委員長296万円など党幹部もズラリ。裏ワザのオンパレードである。返納すべき交付金が各議員に流された形だ」
政党助成金ってのは企業献金を無くす代わりにできたはずなのに、いまだに企業献金が続いているのがそもそもの問題なんだね。そこにもてきて、「余ったら国庫に返す」という原則すらも踏みにじって、自分たちの財布に貯金してるってんだから、こういうのを税金ドロボーと言います。政党助成金は政党にとっては濡れ手に粟で、だからこそここを突っ込まれたくないってのが本音なのは間違いない。文通費ほどにメディアが取り上げないのも、そこらあたりを忖度してるからに決まってます。税金を懐に入れて恥じ入る素振りもない自民党や維新の政治屋どもは、MVPの賞金を闘病中の子どもや家族を支援する非営利団体に寄付した大谷翔平の爪の垢でも煎じて飲んでみやがれ。

山城 明 2021-11-24 浜比嘉島比嘉
2021年11月21日15時、ジュンク堂那覇に行く。入って行こうとすると団体が通り過ぎていく。2021年10月 末吉安允著・イラスト湯浅千里『補陀落渡海僧 日秀上人』、著者あとがきに「琉球王国時代に関わった、二人の聖僧(日秀・袋中)の見識を尊重して、琉球を竜宮に例えて物語を作ってみた」とする。首里城正殿を紹介するところでは「末広がりの階段の先端には欄干に繋がるように阿吽の龍の石柱が、御庭を睥睨するが如く屹立」と描写。末吉安允氏と西村貞雄氏

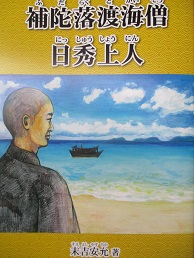


2021年11月20日 ジュンク堂那覇店「知名定寛『琉球沖縄仏教史』榕樹書林 出版記念トークイベント」
〇トーク出演:知名定寛氏、豊見山和幸氏◇「1452年頃の琉球国図には波上熊野権現が記載されている」「熊野信仰も日本・琉球間を往来する海船に搭乗する人々によって伝えられた」
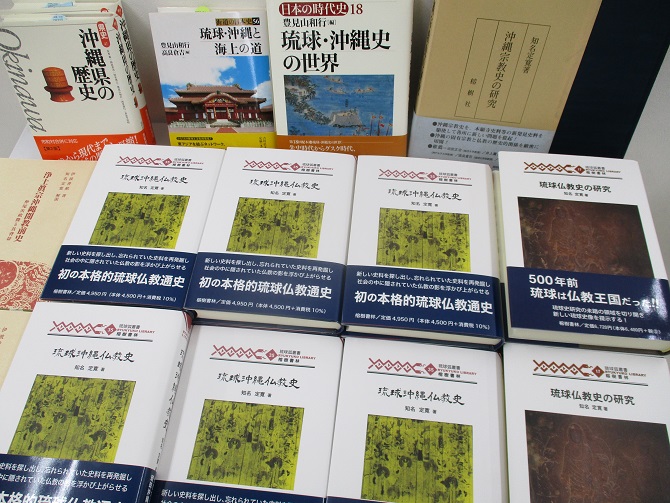



「くろねこの短語」2021年11月20日 (前略)ところで、維新が議員から巻き上げた文通費を寄付するっていうからどこにするのかと思ったら、なんとまあ日本維新の会、つまり党に寄付するんだとさ。これじゃあまるで暴力団の上納金みたいなもんじゃないか。こういうことを恥も外聞もなくやるのが維新なんだね。でもって、その維新の生みの親で、いまも深い関係を保っているお子ちゃま・橋↓君なんだが、「橋下徹をテレビに出すな」がトレンド入りしたってね。維新との濃厚な関係者だってのに、あたかも中立なコメンテーターであるかのように出演をさせるテレビ局の姿勢ってのは、文通費問題にスポットが当たってからというもの特に目に余る。
そんな中、フジテレビ『めざまし8』で、お子ちゃま・橋↓君が一方的に維新の天敵・大石君をなじったってね。大石君は録画出演だったのをいいことに、お子ちゃま・橋↓君の言いたい放題だったったそうで、これって放送法違反なんじゃないのか。こういう欠席裁判まがいのことを平然と仕掛けられるテレビ局って、その存在そのものが犯罪だろう。

大濱 聡 11-15 今、沖縄で――。
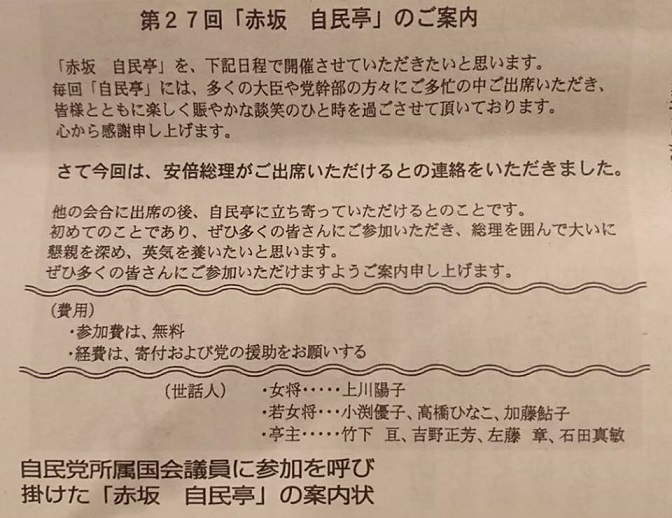
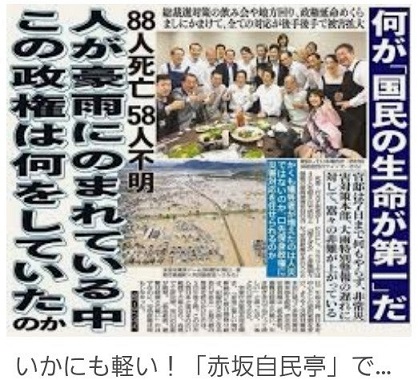
赤坂自民亭事件(あかさかじみんていじけん)とは、平成30年(2018年)7月5日夜に首相の安倍晋三や自民党議員ら約50名が東京・赤坂の議員宿舎で開いた宴会のことである。豪雨警戒の夜であるにも関わらず宴会を開催し、この初動対応の問題が平成30年7月豪雨における被害の拡大につながった。
「くろねこの短語」2021年11月16日 (前略)でもって、大阪のチンピラ市長・松井君も「初当選の議員に支払われる100万円を“特別党費”として徴収した上で、コロナ関連の寄付に充てる考えを示しました」とさ。でもね、これって目的外使用になるんじゃないの。文書交通費ってのはいわば経費で、その原資は税金なんだから、勝手に寄付なんかできるわけがない。ようするに、自分たちで火を付けておいて、その火の粉が飛んできたから慌てて体裁だけ取り繕ってるってことだ。
維新お得意のパフォーマンスも、橋↓の獅子身中の虫・大石君のおかげで返り討ちにあっちゃって、ざまぁ~みろです。こんな維新のパフォーマンスに乗っかって、「民間企業の当たり前が政治の世界に取り入れられるのは大賛成」なんて薄っぺらいコメントしているTBS『Nスタ』のアナウンサーってのもロクなもんじゃありません。
「くろねこの短語」2021年11月12日 (前略)共産党は自ら政党助成金の受け取りを拒否しているんだから、それこそが「身を切る改革」ってもんじゃないのか。今朝もテレビのワイドショーがこの件を取り上げて、あたかも維新の「身を切る改革」の一例であるかのように提灯報道してたけど、だったら維新の議員がやらかした政治資金規正法違反、公職選挙法違反、下半身露出、ひき逃げ、殺傷・殺人未遂未遂etcもちゃんと報道しないといかんだろう。 そもそも、いまだに大阪維新の法律顧問をしているお子ちゃま・橋↓君をコメンテーターに起用していることからしておかしな話なのだ。こんなことしてると、そのうち東京のテレビも大阪みたいに維新と吉本に乗っ取られることになりますよ。
高良 勉 11-13 ハイサイ(拝再)皆さま、お元気でしょうか?本日(13日)12時~13時の間、那覇市県庁前・県民広場で開かれた「宮古島へのミサイル弾頭・弾薬搬入反対の連帯行動」へ参加して、いま帰ってきました。沖縄平和市民連絡会からの緊急な呼びかけだったのですが、約40名~50名が参加して、横断幕やプラカードを掲げてスタンディングをやりました。
私も、急遽指名されて「連帯の挨拶」をさせられました。何よりも、宮古島住民の起ち上がりを支持し連帯すること。奄美群島、沖縄島、宮古島、石垣島、与那国島へ押し寄せ上陸してくる日米軍、日本軍・自衛隊の策謀に反対すること。琉球弧のミサイル・軍事基地化を阻止しよう。沖縄島の起ち上がりが弱いが、共に頑張ろう。という、主旨の挨拶をしました。
明日は、陸上自衛隊が宮古平良港を使って、ミサイル搬入をしようとしています。宮古島住民は、「ミサイルいらない宮古島住民連絡会」を先頭に「抗議声明」を発表し、抗議行動に起ち上がりつつあります。私たちも、その声明に連帯し、できるところから声を上げ、行動しましょう。
11-14 本日もウィルス禍、沖縄1人、大阪18人、東京22人
11-13 本日もウィルス禍、沖縄1人、大阪30人、東京24人
11-12 本日もウィルス禍、沖縄3人(1)、大阪26人、東京22人
11-11 本日もウィルス禍、沖縄3人米1、大阪64(1)人、東京31人(1)
11-10 本日もウィルス禍、沖縄5人、大阪26(1)人、東京25人
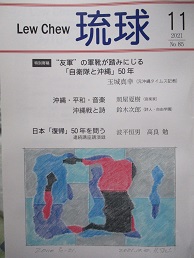
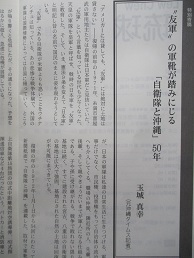


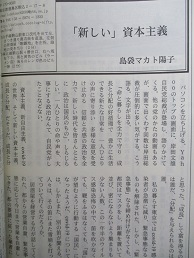
2021年11月『琉球』(隔月刊)№85 琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947 下地ヒロユキ「表紙絵」/玉城真幸「”友軍❞の軍靴が踏みにじる『自衛隊と沖縄50年』」/高良勉「日本『復帰』50年・沖縄解放闘争の継承と克服<2>」/しもじけいこ「宮古IN 宮古市議選終わって……見えてきたこと」/島袋マカト陽子「東京琉球館だより75 『新しい』資本主義」
「くろねこの短語」2021年11月12日 ヘタレ政権は、コロナ禍で困窮する一般大衆労働者諸君を利用して、マイナンバーカードを一気に普及させようって魂胆のようだ。なんでも、マイナンバーカードを新たに取得すれば2万円分のポイントがついてくるんだとか。ところが、その内訳ってのがなんとも手が込んでいて、
マイナンバーカード取得で5000円 健康保険証と紐づけで7500円 預金口座と紐づけで7500円 なんだとさ。共産党の志位君が「給付金をたてに個人情報を差し出せというやり方をとるべきではない」っておかんむりなのもむべなるかなってものです。テレビ朝日の玉川君なんか「「いったいなんなんですか。日本政府がめざしているのは警察国家なんですか」っていきり立ってるってね。
もうここまでくると、なんでもかんでもコロナ禍を口実に、やりたい放題ってことなんだね。加計学園違法献金疑惑の下村君が「「コロナのピンチをチャンスに」と緊急事態条項創設を煽ったのが改めて思い出されてくる。それにしても、たった2万円のポイントでマイナンバーカード普及できると思ってるんだから、一般大衆労働者諸君も舐められたものだ。「マイナンバーカード作ったらお金あげるよ」って言われているようなものなんだね。しかも、その原資ってのは税金ですからね。公明党の山口メンバーは衆議院選で「0歳から高校3年生の年代まで、1人一律10万円を差し上げる」ってまるで自分の金を施すかのように喚いていたものだが、とことん勘違いしちゃってるんだね。そういえば、「税金は国民から吸い上げたもの」って国会答弁したペテン師がいたっけ。なんだ、みんな詐欺師ってことか。
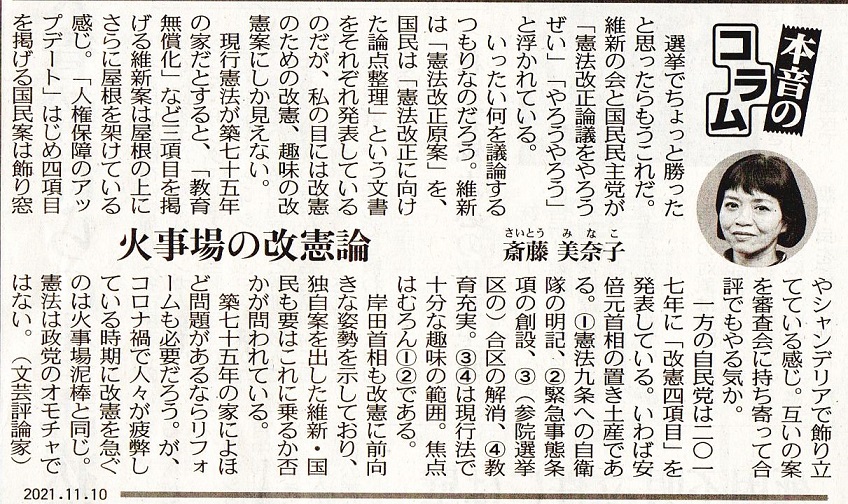
「くろねこの短語」2021年11月8日 国民民主のタマキンの維新へのすり寄りはさすがに目に余る。野党国対委員長会議や野党合同ヒアリングへの不参加を表明したと思ったら、今度は改憲に向けて維新との連携を強化しますとさ。腰の座らない男ってのはわかっていたが、これほどの恥知らずとはねえ。そもそも、維新との連携はついこの前まで否定してたんだよね。さらに、選挙中は改憲なんてのはほとんど争点にもなっていたなかったってのに、選挙の結果か出てたから突然喚きだすってのは定見がないにも程がある。
維新が第3党に躍進して、このままだと党の存続そのものが危ういからなんだろうけど、タマキンの節操のなさってのはなんとも迷惑な話なのだ。こういう信用ならない男があっちについたりこっちについたりすることが、どれだけ野党共闘に悪影響を及ぼしていることか。それにしても、維新のイゾジン吉村ってのも、何様のつもりで改憲を喚き散らすのかねえ。それに乗っかってお調子こいてるタマキンの存在ってのは、まさに百害あって一利なしなんであって、こういうのを国民の敵って言うんでしょうね。
〇東京のフジテレビは、悪名高い在阪メディアの輸入窓口になる気なのかね。https://t.co/L7WFICxGdN—毛ば部とる子 (@kaori_sakai) November 7, 2021/#改憲煽るフジテレビは国民の敵です自民党に「やるなら本気で改憲しろ」とテレビで煽りまくる大阪の吉村知事。現職知事でここまで言うのも異常だが、これを日曜の朝から生でやらせるフジテレビは完全に狂ってる。もはや国民の敵と言っても過言ではない。pic.twitter.com/QJmE2pqi7J
こんな時だからこそ、立憲民主は代表戦でモタモタしてないで、共産党を含めた野党共闘をより進化&深化させるための方針を早いところ打ち出すべきなんだね。その覚悟がないと、来夏の参議院セカは大変なことになりますよ。
「くろねこの短語」2021年11月6日 (前略)もうひとつの「18歳以下に現金10万円」ってのも、なんで給付金に年齢制限なんかつけるかねえ。多くの一般労働者諸君がコロナ禍で疲弊しているんだから、制限なんかつけないで一律給付しなくちゃ意味ないだろう。前回の10万円給付では、ひょっとこ麻生が「貯蓄に回って消費に結びつかない」っていちゃもんつけていたが、それは1回ぽっきりの涙金だからなんだね。アメリカでは3回の現金給付があったけど、3回目でようやく消費に回ったという調査もあるそうだ。
そもそも、18歳以下ってのがよくわからん。公明党の山口メンバーは選挙中から「0歳から高校3年生まで1人一律10万円の現金給付」を喚いていたけど、大学生の困窮が問題になっているってのにそこはどうしてくれるんだ。つまり、事の本質が見えていないってことなんだね。だからこそ、「バラマキ」って言われちゃうわけだ。それにしても、こうした政策の議論が、国会を無視した形で進んでいくってのは、どうなのよ。
『沖縄タイムス』11-16 男性は米軍キャンプ・フォスター所属。ワクチンを2回接種して、症状も出ていなかった。10月30日に米国から成田空港へ到着し、検疫所でPCR検査を受け、陽性が判明。その際、男性は「(米軍)横田基地所属」と申告したという。男性は横田基地には行かず、民間航空機に乗って31日に沖縄へ向かったとみられる。県内の空港に到着後は、知り合いが迎えに来た車で県内の基地に戻った。今月1日に基地内の検査で陽性が分かり、県に連絡があったという。
11月25日「莫夢忌」
「くろねこの短語」2021年11月25日 衆議院選の茨城6区でヘタレ総理やペテン師・シンゾーの街頭演説に参加した支持者に日当5000円が支給された事件の真相がいまだ解明されてないってのに、同じトラック協会がヘタレ総理のお膝元である広島3区で当選した公明党の鉄オタ・斉藤君の個人演説会に参加した支持者に旅費名目で現金を支給していましたとさ。広島3区はあの河井バカップルによる買収事件の舞台になった選挙区で、なんとも懲りないというか、金金金の選挙が当たり前になっているんだろうね。
週刊文春によれば、参加者への案内状には、手書きで以下のメモが記載されていたそうだ。「各位 当日受付近くで広島北支部のA(注・原文では実名)が旅費をお渡ししますので受付前に対面できる様ご配慮願います。」これって、鉄オタ・斉藤君の事務所が出した案内状なんだよね。そこにトラック協会が手書きのメモを記載しているんだけど、それを見た支持者にすれば鉄オタ・斉藤君の事務所からの旅費支給と思っても不思議じゃない。となると、斉藤事務所側の「広島県トラック協会に個人演説会のご案内を致しました。手書きのメモについては承知しておりません。旅費についても承知しておりません。当方より参加者に対し旅費等の支払いは一切行っておりません」って言い訳は、いかにも苦しい。公明党は遠山デマ彦の違法融資問題もあるし、「平和の党」「福祉の党」の金看板が泣こうというものだ。近いうちに、仏罰があたることだろう。
「くろねこの短語」2021年11月24日 維新のパフォーマンスから始まった文通費問題の火の粉が政党助成金問題に降りかかり、その実体が徐々に明らかになりつつある。そもそも、政党助成金ってのは「余ったら国庫に返すのが原則」なんだね。ところが、維新は「2018~20年の交付金総額約47億円のうち、3割弱をため込み、20年は15億円を超える」ってんで、大ブーメランとなったのは記憶に新しいところ。
では、他の政党はいかがなものかと調べたら、なんと「岸田内閣の閣僚や自民党幹部もタップリと血税を“蓄財”していることが分かった」ってね。先にも触れたように、政党助成金は「余ったら国庫に返すのが原則」だが、なんと「基金」として積み立てれば返納を免れるという裏ワザがありますとさ。こんな具合です。赤旗が岸田内閣と自民党役員の基金のため込み額について調べたところ、岸田首相2638万円、萩生田経産相1259万円、岸防衛相204万円、山際経済再生相99万円と4閣僚が名を連ねる。麻生副総裁1930万円、高木国対委員長1621万円、遠藤選対委員長296万円など党幹部もズラリ。裏ワザのオンパレードである。返納すべき交付金が各議員に流された形だ」
政党助成金ってのは企業献金を無くす代わりにできたはずなのに、いまだに企業献金が続いているのがそもそもの問題なんだね。そこにもてきて、「余ったら国庫に返す」という原則すらも踏みにじって、自分たちの財布に貯金してるってんだから、こういうのを税金ドロボーと言います。政党助成金は政党にとっては濡れ手に粟で、だからこそここを突っ込まれたくないってのが本音なのは間違いない。文通費ほどにメディアが取り上げないのも、そこらあたりを忖度してるからに決まってます。税金を懐に入れて恥じ入る素振りもない自民党や維新の政治屋どもは、MVPの賞金を闘病中の子どもや家族を支援する非営利団体に寄付した大谷翔平の爪の垢でも煎じて飲んでみやがれ。

山城 明 2021-11-24 浜比嘉島比嘉
2021年11月21日15時、ジュンク堂那覇に行く。入って行こうとすると団体が通り過ぎていく。2021年10月 末吉安允著・イラスト湯浅千里『補陀落渡海僧 日秀上人』、著者あとがきに「琉球王国時代に関わった、二人の聖僧(日秀・袋中)の見識を尊重して、琉球を竜宮に例えて物語を作ってみた」とする。首里城正殿を紹介するところでは「末広がりの階段の先端には欄干に繋がるように阿吽の龍の石柱が、御庭を睥睨するが如く屹立」と描写。末吉安允氏と西村貞雄氏

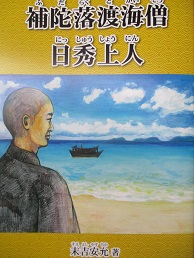


2021年11月20日 ジュンク堂那覇店「知名定寛『琉球沖縄仏教史』榕樹書林 出版記念トークイベント」
〇トーク出演:知名定寛氏、豊見山和幸氏◇「1452年頃の琉球国図には波上熊野権現が記載されている」「熊野信仰も日本・琉球間を往来する海船に搭乗する人々によって伝えられた」
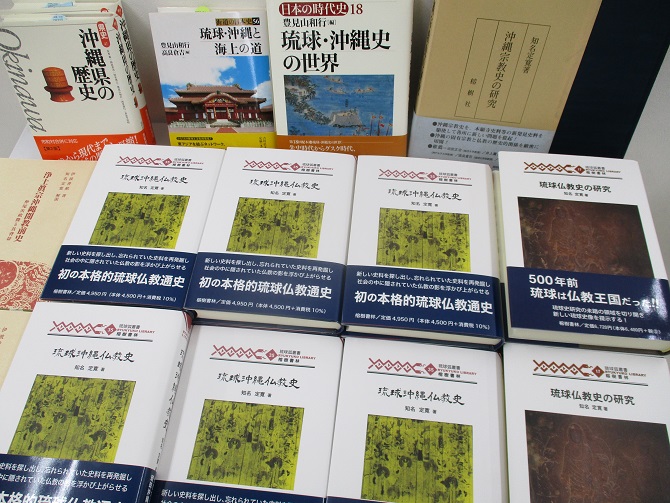



「くろねこの短語」2021年11月20日 (前略)ところで、維新が議員から巻き上げた文通費を寄付するっていうからどこにするのかと思ったら、なんとまあ日本維新の会、つまり党に寄付するんだとさ。これじゃあまるで暴力団の上納金みたいなもんじゃないか。こういうことを恥も外聞もなくやるのが維新なんだね。でもって、その維新の生みの親で、いまも深い関係を保っているお子ちゃま・橋↓君なんだが、「橋下徹をテレビに出すな」がトレンド入りしたってね。維新との濃厚な関係者だってのに、あたかも中立なコメンテーターであるかのように出演をさせるテレビ局の姿勢ってのは、文通費問題にスポットが当たってからというもの特に目に余る。
そんな中、フジテレビ『めざまし8』で、お子ちゃま・橋↓君が一方的に維新の天敵・大石君をなじったってね。大石君は録画出演だったのをいいことに、お子ちゃま・橋↓君の言いたい放題だったったそうで、これって放送法違反なんじゃないのか。こういう欠席裁判まがいのことを平然と仕掛けられるテレビ局って、その存在そのものが犯罪だろう。

大濱 聡 11-15 今、沖縄で――。
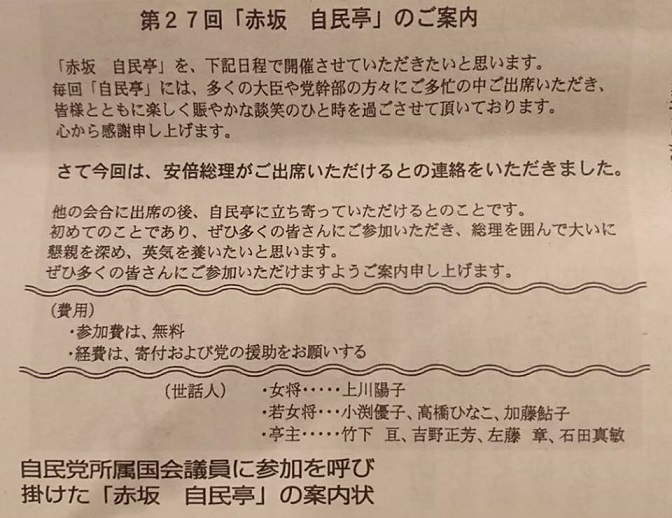
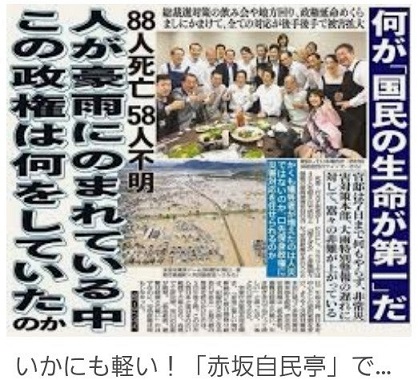
赤坂自民亭事件(あかさかじみんていじけん)とは、平成30年(2018年)7月5日夜に首相の安倍晋三や自民党議員ら約50名が東京・赤坂の議員宿舎で開いた宴会のことである。豪雨警戒の夜であるにも関わらず宴会を開催し、この初動対応の問題が平成30年7月豪雨における被害の拡大につながった。
「くろねこの短語」2021年11月16日 (前略)でもって、大阪のチンピラ市長・松井君も「初当選の議員に支払われる100万円を“特別党費”として徴収した上で、コロナ関連の寄付に充てる考えを示しました」とさ。でもね、これって目的外使用になるんじゃないの。文書交通費ってのはいわば経費で、その原資は税金なんだから、勝手に寄付なんかできるわけがない。ようするに、自分たちで火を付けておいて、その火の粉が飛んできたから慌てて体裁だけ取り繕ってるってことだ。
維新お得意のパフォーマンスも、橋↓の獅子身中の虫・大石君のおかげで返り討ちにあっちゃって、ざまぁ~みろです。こんな維新のパフォーマンスに乗っかって、「民間企業の当たり前が政治の世界に取り入れられるのは大賛成」なんて薄っぺらいコメントしているTBS『Nスタ』のアナウンサーってのもロクなもんじゃありません。
「くろねこの短語」2021年11月12日 (前略)共産党は自ら政党助成金の受け取りを拒否しているんだから、それこそが「身を切る改革」ってもんじゃないのか。今朝もテレビのワイドショーがこの件を取り上げて、あたかも維新の「身を切る改革」の一例であるかのように提灯報道してたけど、だったら維新の議員がやらかした政治資金規正法違反、公職選挙法違反、下半身露出、ひき逃げ、殺傷・殺人未遂未遂etcもちゃんと報道しないといかんだろう。 そもそも、いまだに大阪維新の法律顧問をしているお子ちゃま・橋↓君をコメンテーターに起用していることからしておかしな話なのだ。こんなことしてると、そのうち東京のテレビも大阪みたいに維新と吉本に乗っ取られることになりますよ。
高良 勉 11-13 ハイサイ(拝再)皆さま、お元気でしょうか?本日(13日)12時~13時の間、那覇市県庁前・県民広場で開かれた「宮古島へのミサイル弾頭・弾薬搬入反対の連帯行動」へ参加して、いま帰ってきました。沖縄平和市民連絡会からの緊急な呼びかけだったのですが、約40名~50名が参加して、横断幕やプラカードを掲げてスタンディングをやりました。
私も、急遽指名されて「連帯の挨拶」をさせられました。何よりも、宮古島住民の起ち上がりを支持し連帯すること。奄美群島、沖縄島、宮古島、石垣島、与那国島へ押し寄せ上陸してくる日米軍、日本軍・自衛隊の策謀に反対すること。琉球弧のミサイル・軍事基地化を阻止しよう。沖縄島の起ち上がりが弱いが、共に頑張ろう。という、主旨の挨拶をしました。
明日は、陸上自衛隊が宮古平良港を使って、ミサイル搬入をしようとしています。宮古島住民は、「ミサイルいらない宮古島住民連絡会」を先頭に「抗議声明」を発表し、抗議行動に起ち上がりつつあります。私たちも、その声明に連帯し、できるところから声を上げ、行動しましょう。
11-14 本日もウィルス禍、沖縄1人、大阪18人、東京22人
11-13 本日もウィルス禍、沖縄1人、大阪30人、東京24人
11-12 本日もウィルス禍、沖縄3人(1)、大阪26人、東京22人
11-11 本日もウィルス禍、沖縄3人米1、大阪64(1)人、東京31人(1)
11-10 本日もウィルス禍、沖縄5人、大阪26(1)人、東京25人
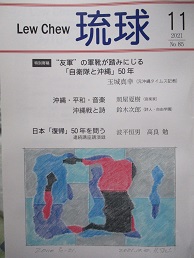
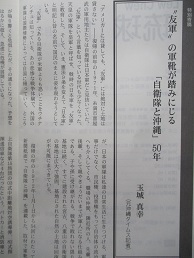


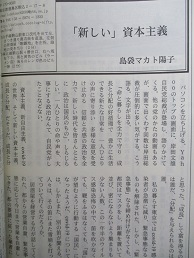
2021年11月『琉球』(隔月刊)№85 琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947 下地ヒロユキ「表紙絵」/玉城真幸「”友軍❞の軍靴が踏みにじる『自衛隊と沖縄50年』」/高良勉「日本『復帰』50年・沖縄解放闘争の継承と克服<2>」/しもじけいこ「宮古IN 宮古市議選終わって……見えてきたこと」/島袋マカト陽子「東京琉球館だより75 『新しい』資本主義」
「くろねこの短語」2021年11月12日 ヘタレ政権は、コロナ禍で困窮する一般大衆労働者諸君を利用して、マイナンバーカードを一気に普及させようって魂胆のようだ。なんでも、マイナンバーカードを新たに取得すれば2万円分のポイントがついてくるんだとか。ところが、その内訳ってのがなんとも手が込んでいて、
マイナンバーカード取得で5000円 健康保険証と紐づけで7500円 預金口座と紐づけで7500円 なんだとさ。共産党の志位君が「給付金をたてに個人情報を差し出せというやり方をとるべきではない」っておかんむりなのもむべなるかなってものです。テレビ朝日の玉川君なんか「「いったいなんなんですか。日本政府がめざしているのは警察国家なんですか」っていきり立ってるってね。
もうここまでくると、なんでもかんでもコロナ禍を口実に、やりたい放題ってことなんだね。加計学園違法献金疑惑の下村君が「「コロナのピンチをチャンスに」と緊急事態条項創設を煽ったのが改めて思い出されてくる。それにしても、たった2万円のポイントでマイナンバーカード普及できると思ってるんだから、一般大衆労働者諸君も舐められたものだ。「マイナンバーカード作ったらお金あげるよ」って言われているようなものなんだね。しかも、その原資ってのは税金ですからね。公明党の山口メンバーは衆議院選で「0歳から高校3年生の年代まで、1人一律10万円を差し上げる」ってまるで自分の金を施すかのように喚いていたものだが、とことん勘違いしちゃってるんだね。そういえば、「税金は国民から吸い上げたもの」って国会答弁したペテン師がいたっけ。なんだ、みんな詐欺師ってことか。
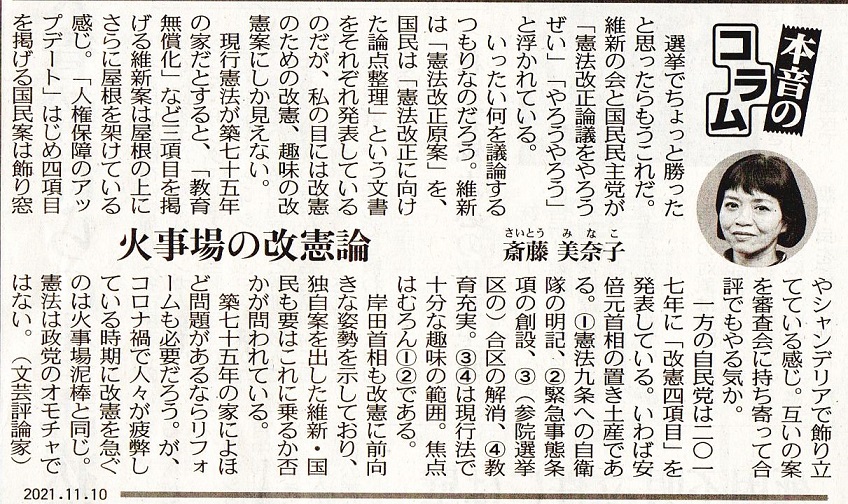
「くろねこの短語」2021年11月8日 国民民主のタマキンの維新へのすり寄りはさすがに目に余る。野党国対委員長会議や野党合同ヒアリングへの不参加を表明したと思ったら、今度は改憲に向けて維新との連携を強化しますとさ。腰の座らない男ってのはわかっていたが、これほどの恥知らずとはねえ。そもそも、維新との連携はついこの前まで否定してたんだよね。さらに、選挙中は改憲なんてのはほとんど争点にもなっていたなかったってのに、選挙の結果か出てたから突然喚きだすってのは定見がないにも程がある。
維新が第3党に躍進して、このままだと党の存続そのものが危ういからなんだろうけど、タマキンの節操のなさってのはなんとも迷惑な話なのだ。こういう信用ならない男があっちについたりこっちについたりすることが、どれだけ野党共闘に悪影響を及ぼしていることか。それにしても、維新のイゾジン吉村ってのも、何様のつもりで改憲を喚き散らすのかねえ。それに乗っかってお調子こいてるタマキンの存在ってのは、まさに百害あって一利なしなんであって、こういうのを国民の敵って言うんでしょうね。
〇東京のフジテレビは、悪名高い在阪メディアの輸入窓口になる気なのかね。https://t.co/L7WFICxGdN—毛ば部とる子 (@kaori_sakai) November 7, 2021/#改憲煽るフジテレビは国民の敵です自民党に「やるなら本気で改憲しろ」とテレビで煽りまくる大阪の吉村知事。現職知事でここまで言うのも異常だが、これを日曜の朝から生でやらせるフジテレビは完全に狂ってる。もはや国民の敵と言っても過言ではない。pic.twitter.com/QJmE2pqi7J
こんな時だからこそ、立憲民主は代表戦でモタモタしてないで、共産党を含めた野党共闘をより進化&深化させるための方針を早いところ打ち出すべきなんだね。その覚悟がないと、来夏の参議院セカは大変なことになりますよ。
「くろねこの短語」2021年11月6日 (前略)もうひとつの「18歳以下に現金10万円」ってのも、なんで給付金に年齢制限なんかつけるかねえ。多くの一般労働者諸君がコロナ禍で疲弊しているんだから、制限なんかつけないで一律給付しなくちゃ意味ないだろう。前回の10万円給付では、ひょっとこ麻生が「貯蓄に回って消費に結びつかない」っていちゃもんつけていたが、それは1回ぽっきりの涙金だからなんだね。アメリカでは3回の現金給付があったけど、3回目でようやく消費に回ったという調査もあるそうだ。
そもそも、18歳以下ってのがよくわからん。公明党の山口メンバーは選挙中から「0歳から高校3年生まで1人一律10万円の現金給付」を喚いていたけど、大学生の困窮が問題になっているってのにそこはどうしてくれるんだ。つまり、事の本質が見えていないってことなんだね。だからこそ、「バラマキ」って言われちゃうわけだ。それにしても、こうした政策の議論が、国会を無視した形で進んでいくってのは、どうなのよ。
『沖縄タイムス』11-16 男性は米軍キャンプ・フォスター所属。ワクチンを2回接種して、症状も出ていなかった。10月30日に米国から成田空港へ到着し、検疫所でPCR検査を受け、陽性が判明。その際、男性は「(米軍)横田基地所属」と申告したという。男性は横田基地には行かず、民間航空機に乗って31日に沖縄へ向かったとみられる。県内の空港に到着後は、知り合いが迎えに来た車で県内の基地に戻った。今月1日に基地内の検査で陽性が分かり、県に連絡があったという。
09/23: 長虹堤①
琉球最古の石橋を持つ長虹堤も、近代になると、泊高橋を経由して首里-那覇間をむすぶ電車の開業(1911年)や、1934(昭和9)年の新県道(現在の国際通り)開通などにより、次第に華やかさを失った裏通りとなり、現在は通りの一部が「十貫瀬(じっかんじ)」の道として残るだけになっている。 →「道の歴史」
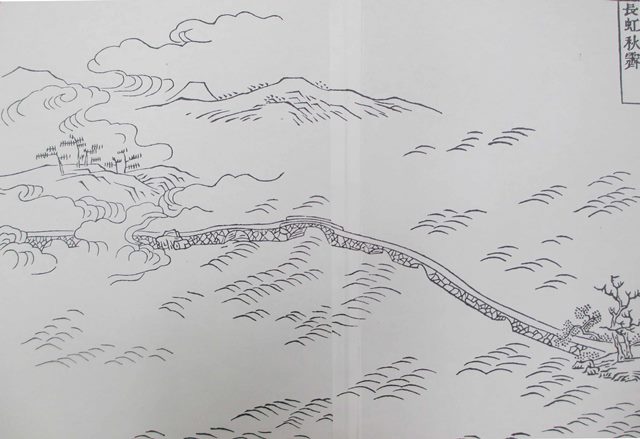
2003年6月 原田禹雄訳注・周煌『琉球國志略』榕樹書林
○ネット上で画像「長虹堤」を見ると、ローゼル川田「琉球風画夢うつつー長虹堤」、琉球ニライ大学の「長虹堤跡を訪ねて」、或いは個人などの画像が豊富である。2010年11月・那覇市歴史博物館発行の『那覇の名橋と知られざる橋』には当然ながら「長虹堤」が載っている。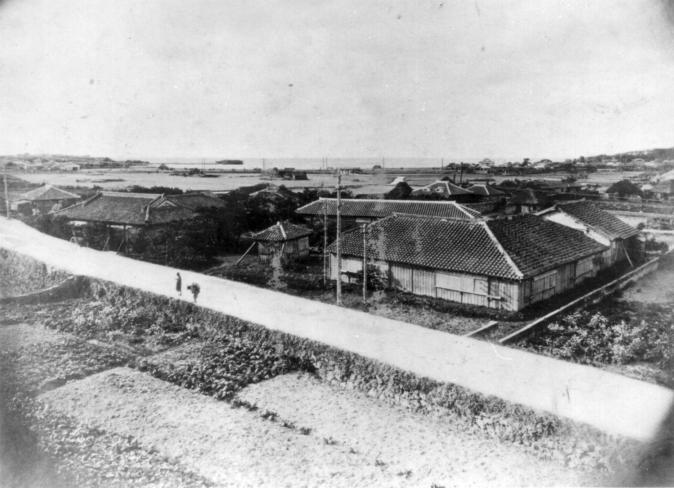
大正期の長虹堤跡(現・十貫瀬通り)
○2013年9月23日ー美栄橋駅周辺の歴史は、琉球王国時代の「長虹堤」の築造に始まる、といってよい。15時からジュンク堂那覇店で、ゆたかはじめ×ローゼル川田「沖縄の鉄道と旅する」トークイベントがあった。冒頭ゆたか氏が周煌『琉球國志略』の那覇風景を見せていたのは偶然か。会場入口でローゼル川田絵ハガキ「長虹堤」を買った。
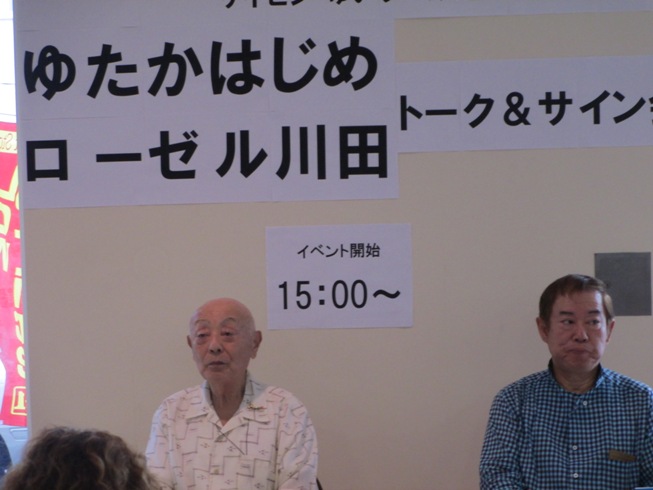
石川和男 みどり印刷2013-9-24□これは仮説ですが。長虹堤も龍潭も懐機①の作とされています。おそらく、現在の龍潭の場所は葦などが茂る湿地帯であったとおもいます。土地がクチャ(不透水)である事から掘り下げて周囲に積み上げハンンタン山などの小山や半島をつくり、現在の中城御殿の左端から城西小前までに長虹堤と同じ手法で堤を東西に築き城西小正門前坂道の前までL字型の堤、同じ手法で世持橋のオーバー フロー・・・建築手法が長虹堤と同じなのです。壊機とその技術スタッフで作られたのが この二つの土木遺構だとおもいます。周辺にはその他にも数箇所の暗渠が今では知る人 も少なくアスファルトの下に眠っています。(機能は果たしています。)
①懐機 【かい・き】
尚巴志王代の琉球王国の国相。中国からの渡来人か。初代尚思紹から5代尚金福に至る第一尚氏歴代の王に仕えた。2代尚巴志代に国相となり,三山統一や中国への進貢貿易に尽力した。尚巴志6(1427)年建立の琉球最古の金石文である「安国山樹華木之記碑」に,北京に派遣されたこと,王城外に池(竜潭)を掘ったことがみえている。また旧港(パレンバン)の宣撫使や中国竜虎山の天師大人(道教教主)に文書や礼物を送っており(『歴代宝案』),その権威の高さがうかがわれる。尚金福王代(1450~53)には那覇と泊を結ぶ長虹堤を創建している。古琉球王国草創期の注目の人物である。 (田名真之)→コトバンク

沖縄県公文書館玄関にある安国山樹華木之記□首里王城の威容を増し、合わせて遊息の地とするため、王城の外の安国山に池(龍潭)を掘り、台を築き、松柏・花木を植え、太平の世のシンボルとして永遠の記念とする。
2005年11月 与並岳生『新 琉球王統史③思紹王、尚巴志王・尚泰久王』「尚金福王と長虹堤建設」新星出版
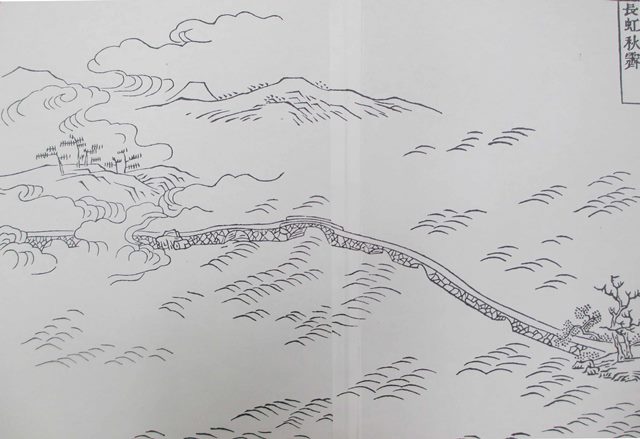
2003年6月 原田禹雄訳注・周煌『琉球國志略』榕樹書林
○ネット上で画像「長虹堤」を見ると、ローゼル川田「琉球風画夢うつつー長虹堤」、琉球ニライ大学の「長虹堤跡を訪ねて」、或いは個人などの画像が豊富である。2010年11月・那覇市歴史博物館発行の『那覇の名橋と知られざる橋』には当然ながら「長虹堤」が載っている。
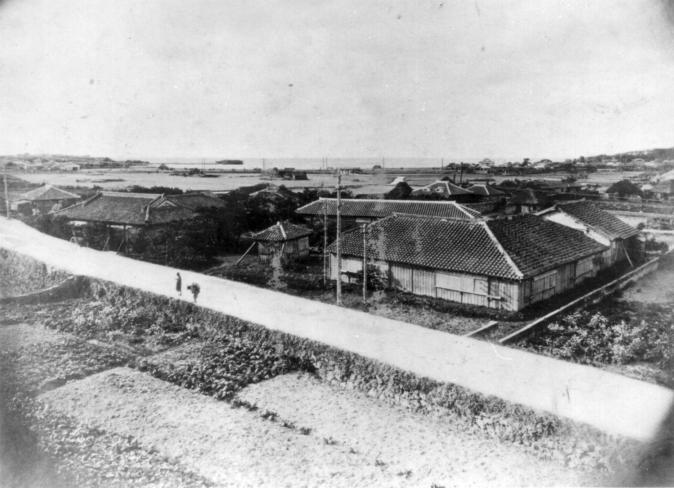
大正期の長虹堤跡(現・十貫瀬通り)
○2013年9月23日ー美栄橋駅周辺の歴史は、琉球王国時代の「長虹堤」の築造に始まる、といってよい。15時からジュンク堂那覇店で、ゆたかはじめ×ローゼル川田「沖縄の鉄道と旅する」トークイベントがあった。冒頭ゆたか氏が周煌『琉球國志略』の那覇風景を見せていたのは偶然か。会場入口でローゼル川田絵ハガキ「長虹堤」を買った。
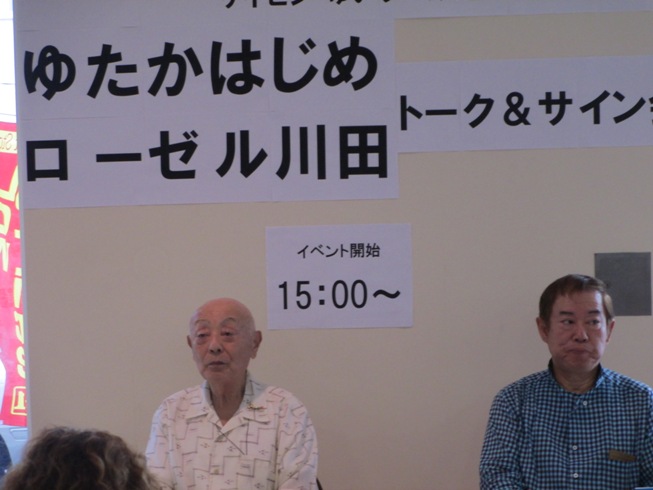
石川和男 みどり印刷2013-9-24□これは仮説ですが。長虹堤も龍潭も懐機①の作とされています。おそらく、現在の龍潭の場所は葦などが茂る湿地帯であったとおもいます。土地がクチャ(不透水)である事から掘り下げて周囲に積み上げハンンタン山などの小山や半島をつくり、現在の中城御殿の左端から城西小前までに長虹堤と同じ手法で堤を東西に築き城西小正門前坂道の前までL字型の堤、同じ手法で世持橋のオーバー フロー・・・建築手法が長虹堤と同じなのです。壊機とその技術スタッフで作られたのが この二つの土木遺構だとおもいます。周辺にはその他にも数箇所の暗渠が今では知る人 も少なくアスファルトの下に眠っています。(機能は果たしています。)
①懐機 【かい・き】
尚巴志王代の琉球王国の国相。中国からの渡来人か。初代尚思紹から5代尚金福に至る第一尚氏歴代の王に仕えた。2代尚巴志代に国相となり,三山統一や中国への進貢貿易に尽力した。尚巴志6(1427)年建立の琉球最古の金石文である「安国山樹華木之記碑」に,北京に派遣されたこと,王城外に池(竜潭)を掘ったことがみえている。また旧港(パレンバン)の宣撫使や中国竜虎山の天師大人(道教教主)に文書や礼物を送っており(『歴代宝案』),その権威の高さがうかがわれる。尚金福王代(1450~53)には那覇と泊を結ぶ長虹堤を創建している。古琉球王国草創期の注目の人物である。 (田名真之)→コトバンク

沖縄県公文書館玄関にある安国山樹華木之記□首里王城の威容を増し、合わせて遊息の地とするため、王城の外の安国山に池(龍潭)を掘り、台を築き、松柏・花木を植え、太平の世のシンボルとして永遠の記念とする。
2005年11月 与並岳生『新 琉球王統史③思紹王、尚巴志王・尚泰久王』「尚金福王と長虹堤建設」新星出版
02/19: 真栄里 泰山[2015年うちなーそーがち年賀状]

辺野古新基地NO
[うちなーそーがち旧暦年賀状]を差し上げます。
来る2月19日は、旧暦の正月元旦 春節です。中国、韓国、台湾、ベトナムなどでは、春節を祝いますが沖縄でも旧暦で正月を祝います。沖縄ではその昔、新暦正月を、新正、大和正月などと呼んで来ましたが戦後の新生活運動の結果、今では新暦正月が定着しています。それでも、沖縄南部の糸満市などでは、今なお旧暦正月がほとんどで、
こんな門松の話題もあります。また、宮古、八重山、本島北部では、旧暦1月16日には、じゅーろくにちー(十六日)、ぐそうのそーがち(あの世の正月) ともいいますがお墓の前で親族がそろってご先祖とともに正月を祝います。宮古・八重山に帰れない方は、那覇の三重城などで、島のお墓に、おとうし{遥拝)をします。那覇や首里ではじゅーろくにちーはやらず、4月から5月にかけて清明祭をやります。
沖縄では、旧暦による行事が多く、沖縄のカレンダーは旧暦がないと役に立ちません。また旧暦本の「琉球暦」が隠れたベストセラーであることは意外と知られていません。お正月が2回もあるというのは子どもたちには嬉しいことですよ。
賀状の「 楽歳之豊 悦民之和 」 は 「安国山樹華木記碑 」の語句の引用です。尚巴志が三山統一を成し遂げ、首里を首都として整備した時の歓びと琉球王国成立の一時期の平和を楽しんだ碑文。琉球・沖縄の歴史上、初出の「平和」の「和」です.島ぐるみ会議、うちなーうまんちゅの会など辺野古新基地建設反対など沖縄基地問題解決のため県民が保革をとわず統一した今の沖縄に重なります。
また、賀状の漢詩は 「聯句」 というもの。その昔は、久米村、首里、八重山で、新年やお祝いのとき内門、床の間、仏壇に掲げて歓びや祝意を表したものです。今の人は忘れてしまっていますが、中国、台湾、韓国ではなお一般的ですが、日本ではお寺や書道に用います。含意をお汲み取りいただければ幸いです。
02/04: 新城栄徳「末吉安恭(麦門冬)没90年」研究発表に寄せて」
新城栄徳「末吉安恭(麦門冬)没90年」研究発表に寄せて」
18日の沖縄タイムス文化欄に、沖縄近代史家の伊佐眞一氏が県知事選の結果を読む、として、もはや翁長雄志氏に疑心暗鬼に精力を裂くときではない。基地問題は第2ステージに入っており、自恃(じじ)のウチナーンチュがひとりでも多くなればなるほど、私たちの郷土は真に自立した道を確実に歩めるはずだ、と書いている。
伊佐・比屋根照夫共編『太田朝敷選集』に、東恩納寛惇宛の書簡で太田は「私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云ふより寧(むし)ろ民族的団体と云ふ見地です。国民の頭から民族差別観念を消して仕舞ふことは吾々に取っては頗(すこぶ)る重要な問題だと考へて居ります」と書いているが、この太田の予言は現在の沖縄にも通底する。
このほか、太田選集には俳句や小説、歴史、民俗など近代沖縄文化の幅広い分野で活躍したジャーナリスト、末吉安恭(麦門冬)を追悼して「私が沖縄時事新報社を新設するに当たり君は私の微力なるを思ひ私の請に応じて快く助筆たるを承諾して呉れた(略)琉球社以来の同志も亦、又吉君を始め君を先輩として敬意を表するに吝(やぶさか)ならなかったのである」と載っている。社会運動家の東恩納寛敷も「沖縄タイムス」の追悼文で「波上軒で麦門冬が酔って興に乗じ幸徳秋水の漢詩を戸板一杯に書いた見事な筆蹟であった」と書いている。
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
鎌倉芳太郎は麦門冬から沖縄美術史の手解きを受けたが、後年「大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、(略)またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育った。」(1977年・『国語科通信№36』)と当時を回想している。
末吉安恭を通して近代沖縄の歩みを振り返ることは、現在の私たちの沖縄社会を考え直す契機になる。 (「琉文21」主宰)
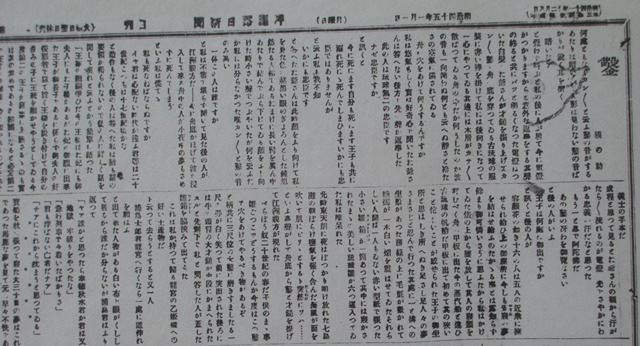
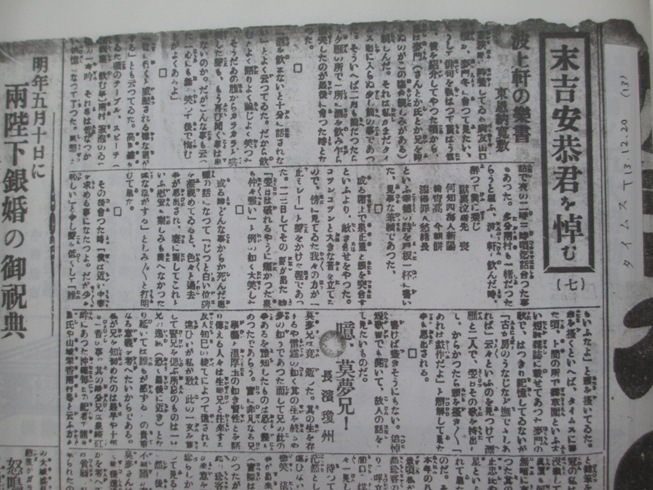
1924年12月20日『沖縄タイムス』東恩納寛敷「末吉安恭君を悼む」
2011年1月ジュンク堂那覇店に行くと大逆事件100年ということで関係書籍が積まれていた。1972年、大阪梅田の古書店で入手したのが『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』であった。幸徳秋水はどういう人物かは知らなかったが写真集といこうことで買った。
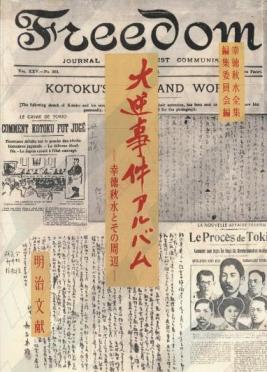
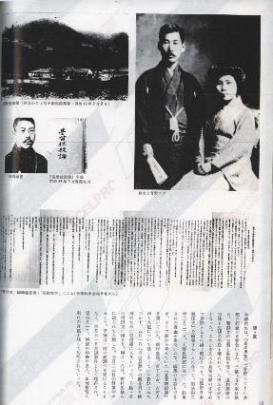
1972年4月ー幸徳秋水全集編集委員会『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』明治文献
1910年6月28日『沖縄毎日新聞』「無政府黨の陰謀」
6月29日『沖縄毎日新聞』「本社発行人(伊舎良平吉)検事の取調べを受ける」
幸徳秋水
生年: 明治4.9.23 (1871.11.5) 没年: 明治44.1.24 (1911)
明治期の社会思想・運動家。高知県中村町の薬種業,酒造業篤明と多治の次男として生まれる。本名は伝次郎で,秋水は師・中江兆民から授かった号である。生後1年たらずで父を失い,維新の社会変動のなか家業も没落し,しかも生来病気がちで満足な教育を受けられなかったことが,秋水をして不平家たらしめ,他面では理想主義に向かわせた。高知県という土地柄もあり,幼くして自由民権思想の影響を受けた。明治21(1888)年より中江兆民のもとに寄寓し,新聞記者となることを目ざし,『自由新聞』『中央新聞』に勤めた。『万朝報』記者時代(1898~1903),社会主義研究会,社会主義協会の会員となり,社会主義者としての宣言を行う。34年5月,日本で最初の社会主義政党である社会民主党の創立者のひとりとして名を連ねた。秋水の著作『社会主義神髄』(1903)は当時の社会主義関係の著書としては最も大きな影響を与えた。36年,日露戦争を前にして戦争反対を唱え,堺利彦と平民社を結成。平和主義,社会主義,民主主義を旗印として週刊『平民新聞』を刊行したが,38年筆禍で5カ月間入獄。出獄後渡米し,権威的社会主義を否定し,クロポトキンなどの影響を受けて無政府共産主義に傾く。39年帰国。43年,説くところの政治的権力と伝統的権威を否定する思想,並びに労働者による直接行動の提唱が,宮下太吉らの明治天皇暗殺計画に結びつけられ,いわゆる大逆事件の首謀者とみなされ,絞首刑に処せられた。<著作>『廿世紀之怪物帝国主義』『基督抹殺論』『幸徳秋水全集』<参考文献>飛鳥井雅道『幸徳秋水』,神崎清『実録幸徳秋水』,大原慧『幸徳秋水の思想と大逆事件』,塩田庄兵衛『幸徳秋水』 (山泉進)□→コトバンク

幸徳秋水の墓ー島袋和幸氏撮影
18日の沖縄タイムス文化欄に、沖縄近代史家の伊佐眞一氏が県知事選の結果を読む、として、もはや翁長雄志氏に疑心暗鬼に精力を裂くときではない。基地問題は第2ステージに入っており、自恃(じじ)のウチナーンチュがひとりでも多くなればなるほど、私たちの郷土は真に自立した道を確実に歩めるはずだ、と書いている。
伊佐・比屋根照夫共編『太田朝敷選集』に、東恩納寛惇宛の書簡で太田は「私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云ふより寧(むし)ろ民族的団体と云ふ見地です。国民の頭から民族差別観念を消して仕舞ふことは吾々に取っては頗(すこぶ)る重要な問題だと考へて居ります」と書いているが、この太田の予言は現在の沖縄にも通底する。
このほか、太田選集には俳句や小説、歴史、民俗など近代沖縄文化の幅広い分野で活躍したジャーナリスト、末吉安恭(麦門冬)を追悼して「私が沖縄時事新報社を新設するに当たり君は私の微力なるを思ひ私の請に応じて快く助筆たるを承諾して呉れた(略)琉球社以来の同志も亦、又吉君を始め君を先輩として敬意を表するに吝(やぶさか)ならなかったのである」と載っている。社会運動家の東恩納寛敷も「沖縄タイムス」の追悼文で「波上軒で麦門冬が酔って興に乗じ幸徳秋水の漢詩を戸板一杯に書いた見事な筆蹟であった」と書いている。
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
鎌倉芳太郎は麦門冬から沖縄美術史の手解きを受けたが、後年「大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、(略)またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育った。」(1977年・『国語科通信№36』)と当時を回想している。
末吉安恭を通して近代沖縄の歩みを振り返ることは、現在の私たちの沖縄社会を考え直す契機になる。 (「琉文21」主宰)
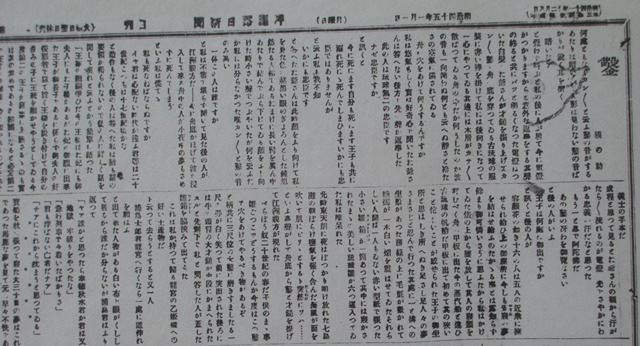
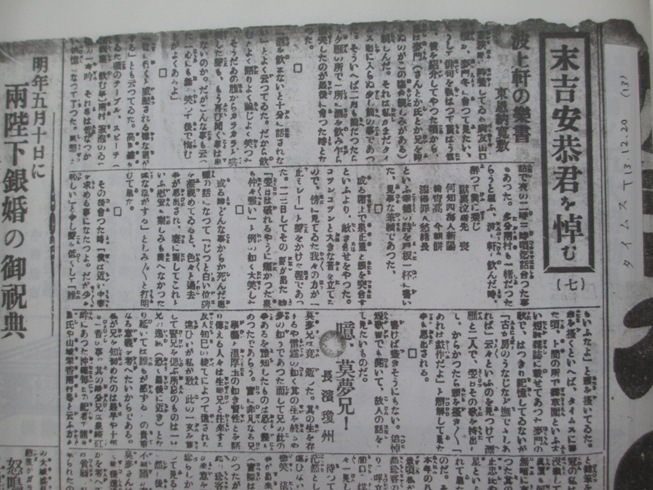
1924年12月20日『沖縄タイムス』東恩納寛敷「末吉安恭君を悼む」
2011年1月ジュンク堂那覇店に行くと大逆事件100年ということで関係書籍が積まれていた。1972年、大阪梅田の古書店で入手したのが『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』であった。幸徳秋水はどういう人物かは知らなかったが写真集といこうことで買った。
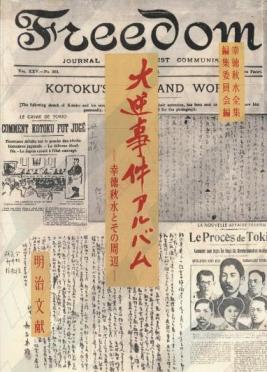
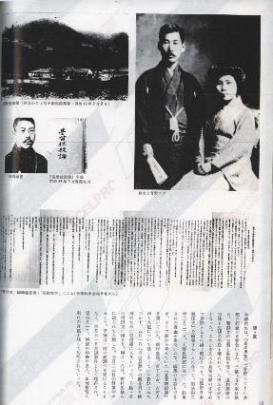
1972年4月ー幸徳秋水全集編集委員会『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』明治文献
1910年6月28日『沖縄毎日新聞』「無政府黨の陰謀」
6月29日『沖縄毎日新聞』「本社発行人(伊舎良平吉)検事の取調べを受ける」
幸徳秋水
生年: 明治4.9.23 (1871.11.5) 没年: 明治44.1.24 (1911)
明治期の社会思想・運動家。高知県中村町の薬種業,酒造業篤明と多治の次男として生まれる。本名は伝次郎で,秋水は師・中江兆民から授かった号である。生後1年たらずで父を失い,維新の社会変動のなか家業も没落し,しかも生来病気がちで満足な教育を受けられなかったことが,秋水をして不平家たらしめ,他面では理想主義に向かわせた。高知県という土地柄もあり,幼くして自由民権思想の影響を受けた。明治21(1888)年より中江兆民のもとに寄寓し,新聞記者となることを目ざし,『自由新聞』『中央新聞』に勤めた。『万朝報』記者時代(1898~1903),社会主義研究会,社会主義協会の会員となり,社会主義者としての宣言を行う。34年5月,日本で最初の社会主義政党である社会民主党の創立者のひとりとして名を連ねた。秋水の著作『社会主義神髄』(1903)は当時の社会主義関係の著書としては最も大きな影響を与えた。36年,日露戦争を前にして戦争反対を唱え,堺利彦と平民社を結成。平和主義,社会主義,民主主義を旗印として週刊『平民新聞』を刊行したが,38年筆禍で5カ月間入獄。出獄後渡米し,権威的社会主義を否定し,クロポトキンなどの影響を受けて無政府共産主義に傾く。39年帰国。43年,説くところの政治的権力と伝統的権威を否定する思想,並びに労働者による直接行動の提唱が,宮下太吉らの明治天皇暗殺計画に結びつけられ,いわゆる大逆事件の首謀者とみなされ,絞首刑に処せられた。<著作>『廿世紀之怪物帝国主義』『基督抹殺論』『幸徳秋水全集』<参考文献>飛鳥井雅道『幸徳秋水』,神崎清『実録幸徳秋水』,大原慧『幸徳秋水の思想と大逆事件』,塩田庄兵衛『幸徳秋水』 (山泉進)□→コトバンク

幸徳秋水の墓ー島袋和幸氏撮影
09/24: 長虹堤②
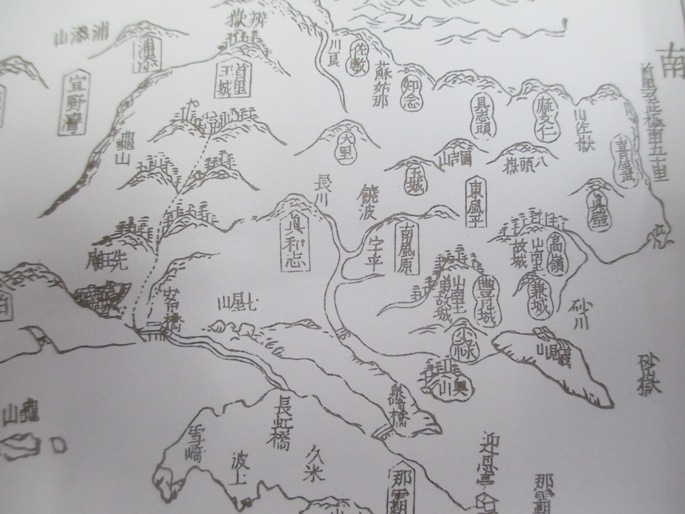
【中山伝信録】中国、清の徐葆光(じよほうこう)の撰。六巻。1721年成立。冊封副使として琉球に派遣された際に見聞した、琉球国の地理・制度・風俗・中国との外交関係などを記す。
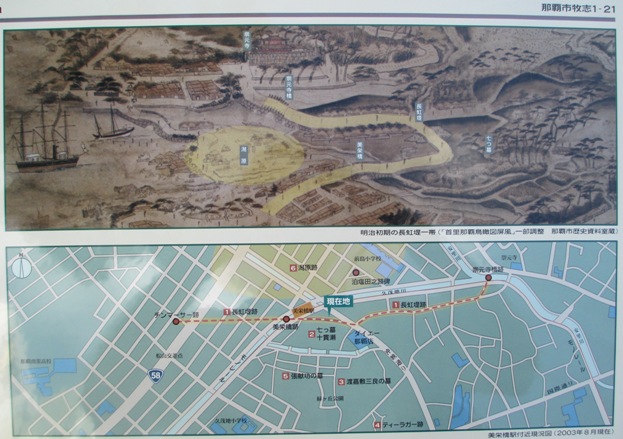
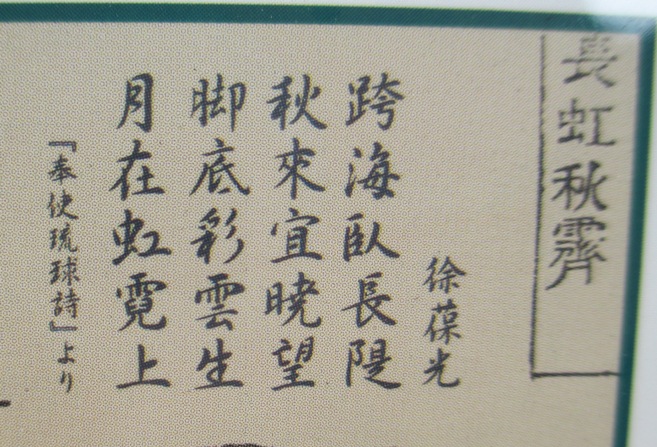
美栄橋駅周辺の史跡・旧跡
美栄橋駅周辺の歴史は、琉球王国時代の「長虹堤」の築造に始まる。
長虹堤は、1451年に築造させた安里橋(現祟元寺橋)からイベガマ(俗に「久茂地のチンマーサー」)に至るまでの約1kmに及ぶ海中道路で、美栄橋はこの道のほぼ中央に架けられた石橋である。長虹堤築造以来、昭和戦前期に至るまで首里・那覇の往来には主にこの道が利用された。また築造により、安里川から流入する土砂が河口に堆積して干潟が形成され、ここで製塩業が営まれた。
近代に入ると、安里橋付近には漆喰屋、瓦葺職人が集まり、美栄橋からチンマーサーにかけては鍛冶屋が軒を並べ、線香屋も数多くあった。
1945年の沖縄戦の後、美栄橋から西側の地域は米軍の物資集積所となり、その後の区画整理により、往時の様子はすっかり変わってしまった。製塩が行われた地域も埋立により宅地化された。ただ美栄橋から祟元寺橋にかけて(牧志2丁目部分)、長虹堤跡の道が残っている。
現在、美栄橋駅周辺には、長虹堤のほか「新修美栄橋碑」、「十貫岩」の話、幽霊伝説の「七つ墓」、天女伝説の「天日井」、沖縄陶芸史上に名を残す「渡嘉敷三良」・「張献功」の墓などの史跡・旧跡が残っている。
The history of the area where the Miebashi monorail station is today began with the construction of the Chokotei causeway in the days of the Kingdom of the Ryukyus.
Chokotei was a kilometer long inter island causeway built in 1451. The Miebashi was a stone bridge in the center of the causeway. When completed, Chokotei became the primary thoroughfare between Shuri and Naha. Construction of the Chokotei gave rise to silt build-up which in turn developed into tidal flats providing beds for a prosperous salt manufacturing industry. In the late feudal period, the area was a concentration of commerce and industry, including plaster craftsmen, blacksmiths and incense manufactures.
After the Battle of Okinawa in 1945, the area just west of Miebashi became a U.S.military depot. Although the look of the area was completely altered later by land redistricting parts of the Chokotei still remain.
Today, the Miebashi Station area has several historical sites besides the Chokotei: the Miebashi Bridge improvement Monument: the legendary Jikkanji rock: Nanatsu-baka the site of a ghost story: Tiraga spring known for the legend of a celestial maiden: and tombs of the famous artisans Tokashiki Sanra and Cho Kenko.
1長虹堤跡
長虹堤は、1451年に築造された那覇と安里を結ぶ1kmの海中道路である。
長虹堤築造以前、那覇は海に浮かぶ「浮島」であったため、首里と那覇の往来には船を利用し、中国からの使者冊封使の来琉の際には、那覇から安里まで船を並べて橋にしたという。1451年国王尚金福は、国相懐機に命じて、首里・那覇を結ぶ道を造らせた。懐機は、この工事は海が深く波が高いので、とても人間の力では出来ない、神の御加護が必要だと、祭壇を設け二夜三昼祈願した。翌日水が引き海底が見えたので、身分を問わず人民を動員し、安里橋(元祟元寺橋)から、①イベガマ(俗に「久茂地のチンマーサー」)に至るまで、石橋七座を設け海中道路を完成させたという。1633年来琉の冊封使杜三策の従客胡靖は、この海中道路を「遠望すれば長虹のごとし」とうたい、それ以降「長虹堤」と称された。
「長虹堤」は1451年以降、明治期まで首里・那覇を結ぶ主要道であった。しかし、1911年首里・那覇間に泊高橋を経由する電車の開業(1933年廃止)や、1934年新県道(現国際通り)の開通により、主要道としての「長虹堤」の地位は低下した。現在、沖縄戦や戦後の都市開発により、「長虹堤」の風情は失われてしまったが、久茂地川沿いの道路に平行に走る道(牧志二丁目部分)が、わずかに「長虹堤」の様子をとどめている。
A kilometer long inter-island causeway called Chokotei linked Naha to Asato. Then, Naha was built across a few islands, and people used small boats to travel from Shuri to Naha. In 1451, King Sho Kinpuku directed Minister Kaiki to construct seven stone bridges from Asato (today's Sogenji Brige area) to Ibegama (known as Kumoji Chinmasa) to establish an inter-island causeway. Kosei, a member of the Chinese investiture delegation which came to the Ryukyus in 1633, noted in his poetry that the road looked like a rainbow (choko) in the distance. Thus, the causeway got its name.
Although Chokotei was the primary access linking Shuri and Naha, traffic volume dropped with the start of train service between Shuri and Naha via Tomari Takahashi in 1911 (discontinued in 1933), and the opening of a new Prefectural road (today's Kokusai Street) in 1934. Much of the Chokotei was lost in the Battle of Okinawa and to later development, but parts of the causeway still remain along the Kumoji River.
「那覇市歴史博物館」

①現在のイベガマ(俗に「久茂地のチンマーサー」)付近

新城喜一「長虹堤」
06/10: 世相ジャパン
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@yahoo.co.jp
「くろねこの短語」6-20 昨日のNHK『日曜討論』で、化粧崩れの高市君が、「新選組の方から『消費税が法人税引き下げに流用されている』かのような発言がこの間から何度かあったが、全くの事実無根だ」「デタラメを公共の電波で言うのはやめていただきたい」「消費税は社会保障にしか使われていません!」とドヤ顔でかまして大炎上。
消費税のうち社会保障に使われているのはわずか27%で、化粧崩れの高市君の発言そのものが「テタラメ」で、「平気で嘘をつく高市早苗」がトレンド入りしましたとさ。というわけで、これからはくろねこも「平気で嘘をつく高市君」と呼ぶことにします。
おそらく、息を吐くように嘘をつく習性ってのは、ペテン師・シンゾー譲りのものなんでしょうね。平気で嘘つく高市君にすれば、してやったりってことだったんだろうけど、世間ってのはそう甘くはいきません。
番組中では、平気で嘘をつく高市君の発言に、バズーカ大石君が手を上げて反論しようとしたら、なんと司会のアナウンサーがこれを無視して別のテーマに移っちゃったんだってね。NHKのこうした番組進行ってのは、不偏不党の放送法に明らかに違反していると思うけどねえ。
そう言えば、今朝のニュースでも、参議院選挙の争点として「国防に対する意識が国民の間出高まっている」なんて解説してたけど、何を根拠にしてそう言い切れるのか。これこそ、印象操作そのものなんじゃないのか。卑怯者、NHK・・・ということで、お後がよろしいようで。
6月19日 沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室 主催『N27』(「時の眼ー沖縄」批評誌)編集室「沖縄戦の教訓を軍事基地のない社会のために!-島田知事賛美の映画と第32軍司令部壕保存公開活動を問う-」



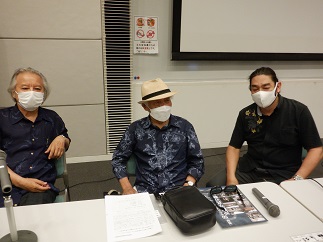
宮城ヨシ子さん、比嘉豊光氏/伊佐眞一氏、新川明氏、友知政樹氏
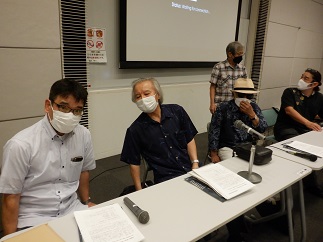

川満彰氏、伊佐眞一氏/ひより、新川明氏、高良勉氏
「くろねこの短語」6-18 福島第一原発事故の国の責任について、最高裁がとんでもない判決を出してくれた。なんと、「実際の津波は想定より規模が大きく、仮に国が東京電力に必要な措置を命じていたとしても事故は避けられなかった可能性が高い」から国に賠償責任はありませんとさ。この論法で行くと「想定外の津波にはどんな対策しても無駄」ってことになるから、「地震の巣と呼ばれる日本列島の上で原発を運転させること自体がもはや犯罪的」(東京新聞社説より)ということになる。そもそも、想定外云々の前に、原発の地震対策について、ペテン師・シンゾーは国会で「全電源喪失はありえない」って答弁してたんだよね。だからさらなる地震対策は必要ないって共産党議員の質問に答えてもいる。
もし、共産党議員の疑問を真摯に受け止めて地震対策を強化していれば、ひょっとしたら津波の被害も防げたかもしれない。「仮に国が東京電力に必要な措置を命じていたとしても事故は避けられなかった可能性が高い」なんて最高裁の言い分はあくまでも仮定であって、だからって「必要な措置」を取らなくていいってことにはならない。最悪の事態を想定して事に当たるのが危機管理であって、「やっても無駄」なんてお役所的発想では国民の命なんか守れませんよ、ったく。
でも、考えようによっては、国の賠償責任は認めなかったものの、東電の責任は確定しているわけだから、これから先万が一にも原発発事故があれば、それは電力会社の責任ってことになる。電力会社にすれば、原発運転のハードルはかなり高くなったということだ。4人の裁判官のうちひとりだけ国の責任を認める反対意見を出していて、「原子力安全・保安院と東電が法令に従って真摯な検討をしていれば事故を回避できた可能性が高い」って言ってるんだが、これこそが国民共通の認識というものだろう。自民党は「原発を最大限に利用」と公約に掲げているけど、事故が起きたら知らん顔なんだから、原発抱えた地域の有権者はよほどの覚悟を持って来たる参議院選に臨んで欲しいものだ。
「くろねこの短語」6-17 自民党が参議院選の公約を発表した。防衛力強化だの改憲だの原発の最大限活用だの、国民の生活なんかどうでもいいってことか。「日本を守る」「未来を創る」がキーワードだそうで、そこに国民の姿はまったく見えてきません。・「反撃能力」獲得し防衛力強化 自民の参院選公約 改憲「早期に実現」原発「最大限活用図る」
「『日本を守る』とは『あなたを守る』ことから始まる」・・・れいわ新選組の公約の方がよっぽど血が通っている。国があって国民があるんじゃなくて、国民があって国がある・・・なんて基本中の基本がどんどん風化するいま、軍事費増額だの反撃能力がどうしただの、勇ましいこと口にする輩が一番信用できないんだね。
そもそも、食料もエネルギーも自給できない国なんだから、どう逆立ちしたって戦争なんか起こせるわけがない。原発に一発ミサイル撃ち込まれたら、それで終わりです。んな現実を知ってか知らずか、なんと国民のタマキンがこんなたわ言抜かしてます。「原子力潜水艦を日本が保有するなど、適度な抑止力を働かせていくことを具体的に検討すべきだ」ペテン師・シンゾーがよく「悪夢の民主党時代」ってのたまってくれるけど、タマキンみたいな存在こそが「悪夢」の原因だったのかもね。
野党面しているけど、本籍は自民党っていう政治屋を排除していかない限り、野党共闘ってのはいつまでたっても絵に描いた餅のままに違いない。今度の参議院選は、そうした輩をあぶり出すという意味でも、重要な選挙だと痛感する今日この頃なのだ。・公明党候補が違法な「無修正」性交動画を公開 比例名簿から削除へ
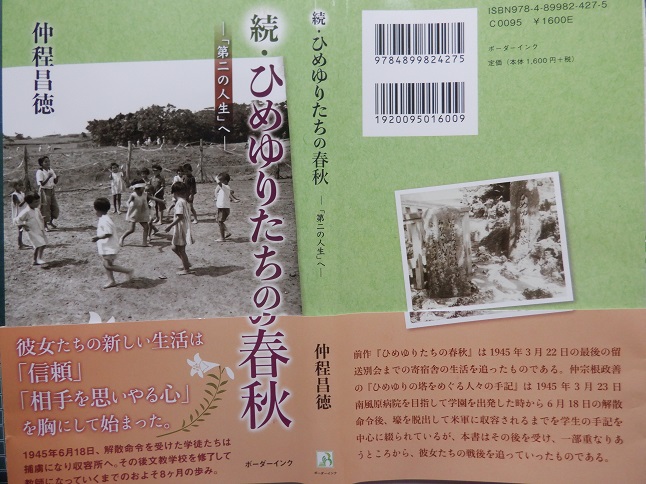
2022年6月 仲程昌徳『続・ひめゆりたちの春秋ー「第二の人生へ」ー』ボーダーインク
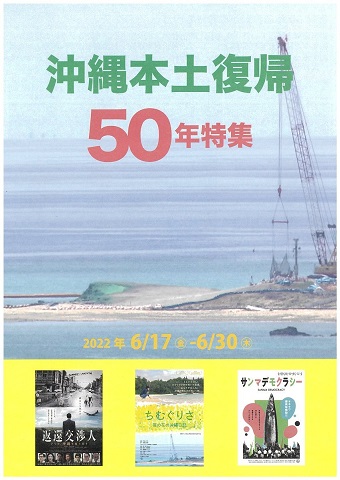
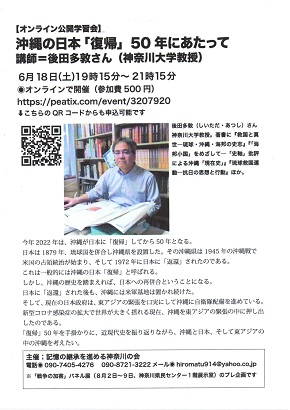
山里 孫存 6-16 東京都写真美術館で「沖縄本土復帰50年特集」として「サンマデモクラシー」が上映されます!

大濱 聡 6-16■知り合いのO.Sさんからハワイの水を守る先住民の闘いのドキュメント(11分35秒)をぜひ見て、と映像が添付されたメールをもらった。■オアフ島に8億リットルの燃料が貯蔵されている米海軍の地下タンクがある。レッドヒルと呼ばれるこの施設では何十年にもわたって燃料漏れを起こしているが、去年11月、水道水から安全基準値の350倍の燃料が検出された。米海軍は事実を隠蔽しようとし、レッドヒルの閉鎖を求める先住民の訴えを拒否している。■作品を見るやいなや、一瞬「これは沖縄ではないか」と思った。嘉手納基地、普天間基地(一部自衛隊基地も)からのPFAS(有機フッ素化合物)汚染で大きな問題になっている沖縄の状況とそっくりなのである。■「オライカワイ(水は命)!」という叫びに、先に復帰50年番組として放送された「命(ぬち)どぅ水」(沖縄テレビ制作)を連想した。
沖縄に20年契約のツタヤ図書館が誕生…村民無視、村議会でも議論なしの異常事態 文=日向咲嗣/ジャーナリスト ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2022/03/「今の村長は、辺野古(の基地建設)に反対しているという点では、いわゆる“オール沖縄”ですが、ふたを開けてみると自民系と同じです。辺野古反対を掲げているのに、地元読谷村の基地にキャンプキンザーからの倉庫を受け入れたり、軍事整施設や武器装備品倉庫を容認したり、ハコモノばかりにお金をかけて福祉には予算をかけません」なるほど、その流れで今回のPFI事業も進められたのだろう。それにしても、一度も村民の意見を聞かないままツタヤ図書館を誘致したことについて、議会はこのまま黙って追認するだけなのだろうか。
◇令和3年4月 読谷村長 石嶺 傳實 (仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業 事業目的 本事業は、本村の知の拠点、文化・情報発信の拠点としての機能が発揮できる施設として、図書館、村史編集室、行政文書保管庫、青少年センター等を複合した(仮称)読谷村総合情報センター、広場・水辺空間及び駐車場(以下、「本施設」という。)の整備と本施設内や同敷地内の余剰地を活用し、民間収益施設の設置を行うことによる賑わいの創出を目的としている。また、図書館運営を民間に委託することにより、従来の図書館運営にない民間の創意工夫を凝らしたサービスの提供を実現する。

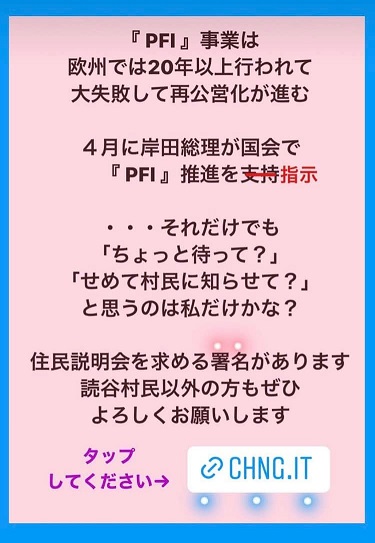
与那覇 沙姫6月15日 21:12
〇2022/03/15kowyoshi TポイントもYahoo!から切られるわ、TSUTAYAも閉店しまくるわで図書館の管理事業に賭けてるのかもしれないが、CCCというだけでもうダメという認識が広まってるんだよなあ 図書館 CCC 沖縄
〇 ここが良い事とされず悪とされてる事がそもそも>豊見城市図書館職員は23人中21人が非正規だったが、近く導入される会計年度任用制度に移行すると人件費が1.4倍に増えることから、この人件費を抑える目的で民間委託
図書館友の会全国連絡会では、『「ツタヤ図書館」の“いま”』改訂2版パンフレットを作成いたしました。
◯衝撃事実発覚 あの樋渡前武雄市長がツタヤ関連企業に天下り! 2015.8.12
◯2016.02.06 ツタヤ図書館、市側の元図書館協議会会長がCCC天下り疑惑…新館長に就任
◯2016.02.15 ツタヤ図書館、市から「天下り入社」疑惑の新館長を直撃!「市長から声かけられた」
◯【TSUTAYA図書館】多賀城市立図書館の館長、「健康上の理由」で辞職へ 2016年10月26日
◯多賀城「ツタヤ」図書館、館長に前多賀城中学校長 2017年4月11日
◯2016.11.17 ツタヤ図書館、強引にCCCへ委託先決めた市教委委員長が新館長就任か…再び天下り人事疑惑


2022年6月22日~7月10日 南城市文化センター「大城精徳展」/なるみ堂にて、左が店主の翁長良明氏、南城市文化センターの大嶋進氏、大嶋久美さん
◇南城市大里出身の名士 大城精徳展 南城市文化センターは、当館初となる展示会を実施します。昨年末、南城市大里稲嶺・目取真出身の故大城精徳氏の絵画がご親族の方から南城市へ寄贈されました。この絵画を中心に出版物及び民具などの作品を展示します。画家としてだけではなく、現在でも学芸員のバイブルとして扱われている雑誌「琉球の文化」(琉球文化社)を創刊するなど、郷土文化研究者として戦後沖縄の文化芸術発展に大きく貢献されました。
期間 : 2022年6月22日(水)~7月10日(日)午前9時~午後5時 ※月曜休館
場所 : 南城市文化センター2階 洋会議室 入場料 : 無料
「くろねこの短語」6-15 ひとつ運用を間違えると「言論の自由」を脅かしかねない「侮辱罪」の厳罰化は、そうした懸念に対する議論を深めることなく成立させたくせに、議員特権のシンホルとも言える「調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)」の使途公開については先送りだとさ。自民党国対委員長のパンティ高木君は「結論を得ることができなかった」ってシラっと言い訳してるようだが、とんでもない。野党が求めた国対委員長会談にさえ応じなかった自民党は、ようするに使途公開したくないってことなんだよね。
領収書もいらず、使い道も好き勝手できる100万円は絶対に手放さないくせに、年金は引き下げるわ、投資という名のギャンブルでなけなしの金は召し上げようってんだから、やらずぶったくりとはこのことか。ここまでコケにされて、それでも参議院選では自民党に投票する何も考えない有権者が多いんでしょうね。どこまでマゾなんだ。
「くろねこの短語」6-13 (前略)それにしても、こんな下衆な世襲政治屋の発言をいちいち取り上げるメディアもどうかしている。そのくせ、「100万円しか」の細田君のセクハラ疑惑、「見ながら自慰」の吉川君の買春スキャンダルは、ほとんど無視したままなんだから、何をかいわんやなのだ。
ペテン師・シンゾーの一連の動きについては、TBS『サンデーモーニング』で、ニュースキャスターの松原耕二君が珍しくまともなコメントをしていた。「気になるのは安倍元首相の動き。アベノミクスを否定されないように必死に立ち回るような言動。これだけ借金を抱える中で大規模緩和を続ける禁じ手が続くわけがない。民主主義というのは、リーダーが変わることでリセットし軌道修正できる。それが本当に機能しているのか」
ヘタレ政権の「骨太の方針」が謳う防衛費増額も1億総投資家も憲法改悪も、これすべてペテン師・シンゾーの政策の丸写しなんだよね。つまり、ペテン師・シンゾーが院政を敷いているようなもので、そんな男の減らず口をいちいち報道するメディアもまた、その片棒を担いでいることほ意味している。国会でわかっているだけでも118回の虚偽答弁してる男ですからね。こんなのがいまだに大きなツラして表舞台に出てくる不思議な国、これが日本だ、僕らの国だ・・・ってなもんです。
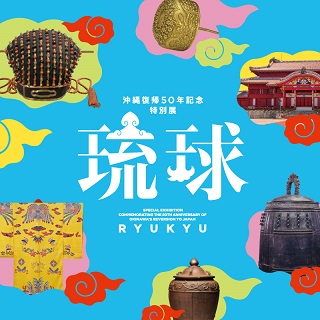

A・E 6ー10 沖縄復帰50年記念特別展「琉球」に。彼女は、どんな琉球展なのか、監視しなきゃ!と。監視に行って大正解????その中身は、明治時代初期の日本政府の"琉球処分"までの、琉球王国時代の華やかできらびやかなものたちの展示と、NHKが作った首里城の3D画像とやら。戦前戦後と復帰からの50年を探したけど、最後のスペースにわずかに戦争で焼かれて破断された石仏像の破片が、狭い場所に展示されているのみ。・・・・・唖然としてしまった。(略)
「復帰50年記念の特別展」と銘打ってますよね。なのになぜ復帰からのこと、戦前、戦中、戦後の展示がないのですか?いびつですよね。…政府だって沖縄に寄り添うと言っているのに、これでは寄り添ってないですね。戦争で"捨て石"にされて4人にひとりが亡くなった沖縄の人々に寄り添ってないでしょ」
「その上に、台湾有事とかって日米が中国の脅威を煽って、琉球弧がミサイル基地を作ってますよね。また沖縄が戦争の犠牲になる可能性もあるのですよ。…それなのに…(私、クドクド)」泣きたいほど本当に酷い展示だった。しかも沢山の人が訪れていた。この特別展の主催は、東京国立博物館、NHK、読売新聞社、文化庁だ????5月3日から6月26日まで開催。"監視"する以外に、ほとんど行く価値がない企画だった。

山城 明 6月1日(水)今日は写真の日だって画像は浜比嘉ビーチ⛱
"家計が値上げを受け入れている”という黒田総裁の発言にTwitterでは「#値上げ受け入れてません」というハッシュタグがトレンド入りするなど批判が殺到。《は?????》《マジで世間知らず》誰が受け入れてんだよ!!! 強制されてるんやろが!!!》《何言ってんだこの人!?️日銀総裁何年やってるんだよ。その間の景気悪化の責任とりなよ》《日銀総裁さん。手取月給20万円で1年間生活してみてから言ってくれない?》値上げラッシュが続くも、給料が上がらない日本の現状を自分の目で見て確かめてほしいものだーー。
6月10日 きっこ@kikko_no_blog「レイプ未遂犯」の田畑毅、「下着泥棒」の高木毅・元復興大臣、「盗撮野郎」の西村康稔・元コロナ担当大臣、「セクハラ常習犯」の細田博之衆院議長、そして「パパ活ハレンチ変質者」の吉川赳、さすがは安倍晋三が「自民党は人材の宝庫」と胸を張るだけのことはある。まるで性犯罪者の楽園だ。


高良勉 6-11 ◆さて今日は、大事なウンチケー(ご案内)とウニゲー(お願い)です。私の一人娘・高嶺美和子が、来る7月24日(日)に国立劇場おきなわで、「第2回 高嶺美和子の会」のリサイタルをやることになりました。
「くろねこの短語」6-20 昨日のNHK『日曜討論』で、化粧崩れの高市君が、「新選組の方から『消費税が法人税引き下げに流用されている』かのような発言がこの間から何度かあったが、全くの事実無根だ」「デタラメを公共の電波で言うのはやめていただきたい」「消費税は社会保障にしか使われていません!」とドヤ顔でかまして大炎上。
消費税のうち社会保障に使われているのはわずか27%で、化粧崩れの高市君の発言そのものが「テタラメ」で、「平気で嘘をつく高市早苗」がトレンド入りしましたとさ。というわけで、これからはくろねこも「平気で嘘をつく高市君」と呼ぶことにします。
おそらく、息を吐くように嘘をつく習性ってのは、ペテン師・シンゾー譲りのものなんでしょうね。平気で嘘つく高市君にすれば、してやったりってことだったんだろうけど、世間ってのはそう甘くはいきません。
番組中では、平気で嘘をつく高市君の発言に、バズーカ大石君が手を上げて反論しようとしたら、なんと司会のアナウンサーがこれを無視して別のテーマに移っちゃったんだってね。NHKのこうした番組進行ってのは、不偏不党の放送法に明らかに違反していると思うけどねえ。
そう言えば、今朝のニュースでも、参議院選挙の争点として「国防に対する意識が国民の間出高まっている」なんて解説してたけど、何を根拠にしてそう言い切れるのか。これこそ、印象操作そのものなんじゃないのか。卑怯者、NHK・・・ということで、お後がよろしいようで。
6月19日 沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室 主催『N27』(「時の眼ー沖縄」批評誌)編集室「沖縄戦の教訓を軍事基地のない社会のために!-島田知事賛美の映画と第32軍司令部壕保存公開活動を問う-」



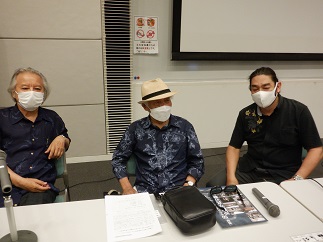
宮城ヨシ子さん、比嘉豊光氏/伊佐眞一氏、新川明氏、友知政樹氏
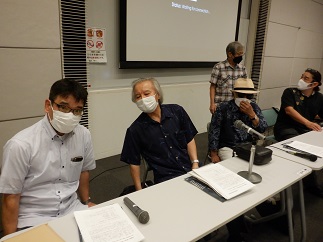

川満彰氏、伊佐眞一氏/ひより、新川明氏、高良勉氏
「くろねこの短語」6-18 福島第一原発事故の国の責任について、最高裁がとんでもない判決を出してくれた。なんと、「実際の津波は想定より規模が大きく、仮に国が東京電力に必要な措置を命じていたとしても事故は避けられなかった可能性が高い」から国に賠償責任はありませんとさ。この論法で行くと「想定外の津波にはどんな対策しても無駄」ってことになるから、「地震の巣と呼ばれる日本列島の上で原発を運転させること自体がもはや犯罪的」(東京新聞社説より)ということになる。そもそも、想定外云々の前に、原発の地震対策について、ペテン師・シンゾーは国会で「全電源喪失はありえない」って答弁してたんだよね。だからさらなる地震対策は必要ないって共産党議員の質問に答えてもいる。
もし、共産党議員の疑問を真摯に受け止めて地震対策を強化していれば、ひょっとしたら津波の被害も防げたかもしれない。「仮に国が東京電力に必要な措置を命じていたとしても事故は避けられなかった可能性が高い」なんて最高裁の言い分はあくまでも仮定であって、だからって「必要な措置」を取らなくていいってことにはならない。最悪の事態を想定して事に当たるのが危機管理であって、「やっても無駄」なんてお役所的発想では国民の命なんか守れませんよ、ったく。
でも、考えようによっては、国の賠償責任は認めなかったものの、東電の責任は確定しているわけだから、これから先万が一にも原発発事故があれば、それは電力会社の責任ってことになる。電力会社にすれば、原発運転のハードルはかなり高くなったということだ。4人の裁判官のうちひとりだけ国の責任を認める反対意見を出していて、「原子力安全・保安院と東電が法令に従って真摯な検討をしていれば事故を回避できた可能性が高い」って言ってるんだが、これこそが国民共通の認識というものだろう。自民党は「原発を最大限に利用」と公約に掲げているけど、事故が起きたら知らん顔なんだから、原発抱えた地域の有権者はよほどの覚悟を持って来たる参議院選に臨んで欲しいものだ。
「くろねこの短語」6-17 自民党が参議院選の公約を発表した。防衛力強化だの改憲だの原発の最大限活用だの、国民の生活なんかどうでもいいってことか。「日本を守る」「未来を創る」がキーワードだそうで、そこに国民の姿はまったく見えてきません。・「反撃能力」獲得し防衛力強化 自民の参院選公約 改憲「早期に実現」原発「最大限活用図る」
「『日本を守る』とは『あなたを守る』ことから始まる」・・・れいわ新選組の公約の方がよっぽど血が通っている。国があって国民があるんじゃなくて、国民があって国がある・・・なんて基本中の基本がどんどん風化するいま、軍事費増額だの反撃能力がどうしただの、勇ましいこと口にする輩が一番信用できないんだね。
そもそも、食料もエネルギーも自給できない国なんだから、どう逆立ちしたって戦争なんか起こせるわけがない。原発に一発ミサイル撃ち込まれたら、それで終わりです。んな現実を知ってか知らずか、なんと国民のタマキンがこんなたわ言抜かしてます。「原子力潜水艦を日本が保有するなど、適度な抑止力を働かせていくことを具体的に検討すべきだ」ペテン師・シンゾーがよく「悪夢の民主党時代」ってのたまってくれるけど、タマキンみたいな存在こそが「悪夢」の原因だったのかもね。
野党面しているけど、本籍は自民党っていう政治屋を排除していかない限り、野党共闘ってのはいつまでたっても絵に描いた餅のままに違いない。今度の参議院選は、そうした輩をあぶり出すという意味でも、重要な選挙だと痛感する今日この頃なのだ。・公明党候補が違法な「無修正」性交動画を公開 比例名簿から削除へ
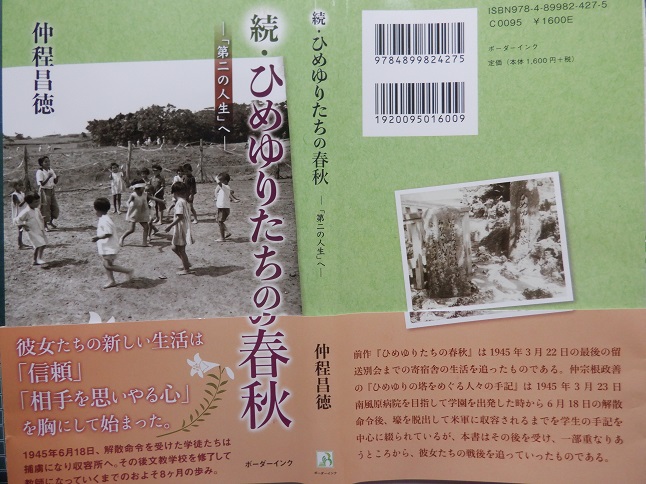
2022年6月 仲程昌徳『続・ひめゆりたちの春秋ー「第二の人生へ」ー』ボーダーインク
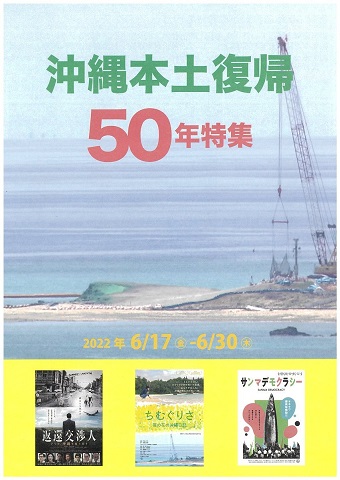
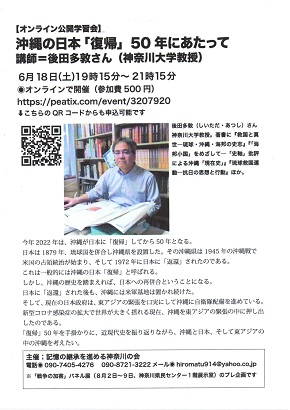
山里 孫存 6-16 東京都写真美術館で「沖縄本土復帰50年特集」として「サンマデモクラシー」が上映されます!

大濱 聡 6-16■知り合いのO.Sさんからハワイの水を守る先住民の闘いのドキュメント(11分35秒)をぜひ見て、と映像が添付されたメールをもらった。■オアフ島に8億リットルの燃料が貯蔵されている米海軍の地下タンクがある。レッドヒルと呼ばれるこの施設では何十年にもわたって燃料漏れを起こしているが、去年11月、水道水から安全基準値の350倍の燃料が検出された。米海軍は事実を隠蔽しようとし、レッドヒルの閉鎖を求める先住民の訴えを拒否している。■作品を見るやいなや、一瞬「これは沖縄ではないか」と思った。嘉手納基地、普天間基地(一部自衛隊基地も)からのPFAS(有機フッ素化合物)汚染で大きな問題になっている沖縄の状況とそっくりなのである。■「オライカワイ(水は命)!」という叫びに、先に復帰50年番組として放送された「命(ぬち)どぅ水」(沖縄テレビ制作)を連想した。
沖縄に20年契約のツタヤ図書館が誕生…村民無視、村議会でも議論なしの異常事態 文=日向咲嗣/ジャーナリスト ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2022/03/「今の村長は、辺野古(の基地建設)に反対しているという点では、いわゆる“オール沖縄”ですが、ふたを開けてみると自民系と同じです。辺野古反対を掲げているのに、地元読谷村の基地にキャンプキンザーからの倉庫を受け入れたり、軍事整施設や武器装備品倉庫を容認したり、ハコモノばかりにお金をかけて福祉には予算をかけません」なるほど、その流れで今回のPFI事業も進められたのだろう。それにしても、一度も村民の意見を聞かないままツタヤ図書館を誘致したことについて、議会はこのまま黙って追認するだけなのだろうか。
◇令和3年4月 読谷村長 石嶺 傳實 (仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業 事業目的 本事業は、本村の知の拠点、文化・情報発信の拠点としての機能が発揮できる施設として、図書館、村史編集室、行政文書保管庫、青少年センター等を複合した(仮称)読谷村総合情報センター、広場・水辺空間及び駐車場(以下、「本施設」という。)の整備と本施設内や同敷地内の余剰地を活用し、民間収益施設の設置を行うことによる賑わいの創出を目的としている。また、図書館運営を民間に委託することにより、従来の図書館運営にない民間の創意工夫を凝らしたサービスの提供を実現する。

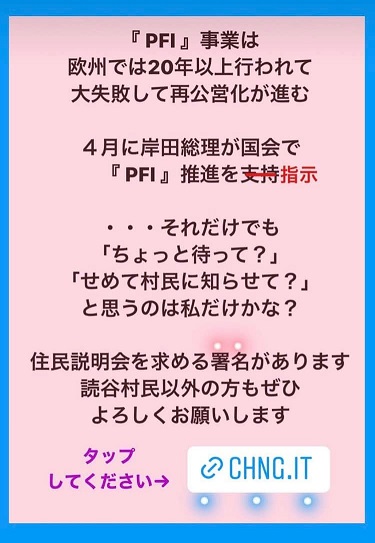
与那覇 沙姫6月15日 21:12
〇2022/03/15kowyoshi TポイントもYahoo!から切られるわ、TSUTAYAも閉店しまくるわで図書館の管理事業に賭けてるのかもしれないが、CCCというだけでもうダメという認識が広まってるんだよなあ 図書館 CCC 沖縄
〇 ここが良い事とされず悪とされてる事がそもそも>豊見城市図書館職員は23人中21人が非正規だったが、近く導入される会計年度任用制度に移行すると人件費が1.4倍に増えることから、この人件費を抑える目的で民間委託
図書館友の会全国連絡会では、『「ツタヤ図書館」の“いま”』改訂2版パンフレットを作成いたしました。
◯衝撃事実発覚 あの樋渡前武雄市長がツタヤ関連企業に天下り! 2015.8.12
◯2016.02.06 ツタヤ図書館、市側の元図書館協議会会長がCCC天下り疑惑…新館長に就任
◯2016.02.15 ツタヤ図書館、市から「天下り入社」疑惑の新館長を直撃!「市長から声かけられた」
◯【TSUTAYA図書館】多賀城市立図書館の館長、「健康上の理由」で辞職へ 2016年10月26日
◯多賀城「ツタヤ」図書館、館長に前多賀城中学校長 2017年4月11日
◯2016.11.17 ツタヤ図書館、強引にCCCへ委託先決めた市教委委員長が新館長就任か…再び天下り人事疑惑


2022年6月22日~7月10日 南城市文化センター「大城精徳展」/なるみ堂にて、左が店主の翁長良明氏、南城市文化センターの大嶋進氏、大嶋久美さん
◇南城市大里出身の名士 大城精徳展 南城市文化センターは、当館初となる展示会を実施します。昨年末、南城市大里稲嶺・目取真出身の故大城精徳氏の絵画がご親族の方から南城市へ寄贈されました。この絵画を中心に出版物及び民具などの作品を展示します。画家としてだけではなく、現在でも学芸員のバイブルとして扱われている雑誌「琉球の文化」(琉球文化社)を創刊するなど、郷土文化研究者として戦後沖縄の文化芸術発展に大きく貢献されました。
期間 : 2022年6月22日(水)~7月10日(日)午前9時~午後5時 ※月曜休館
場所 : 南城市文化センター2階 洋会議室 入場料 : 無料
「くろねこの短語」6-15 ひとつ運用を間違えると「言論の自由」を脅かしかねない「侮辱罪」の厳罰化は、そうした懸念に対する議論を深めることなく成立させたくせに、議員特権のシンホルとも言える「調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)」の使途公開については先送りだとさ。自民党国対委員長のパンティ高木君は「結論を得ることができなかった」ってシラっと言い訳してるようだが、とんでもない。野党が求めた国対委員長会談にさえ応じなかった自民党は、ようするに使途公開したくないってことなんだよね。
領収書もいらず、使い道も好き勝手できる100万円は絶対に手放さないくせに、年金は引き下げるわ、投資という名のギャンブルでなけなしの金は召し上げようってんだから、やらずぶったくりとはこのことか。ここまでコケにされて、それでも参議院選では自民党に投票する何も考えない有権者が多いんでしょうね。どこまでマゾなんだ。
「くろねこの短語」6-13 (前略)それにしても、こんな下衆な世襲政治屋の発言をいちいち取り上げるメディアもどうかしている。そのくせ、「100万円しか」の細田君のセクハラ疑惑、「見ながら自慰」の吉川君の買春スキャンダルは、ほとんど無視したままなんだから、何をかいわんやなのだ。
ペテン師・シンゾーの一連の動きについては、TBS『サンデーモーニング』で、ニュースキャスターの松原耕二君が珍しくまともなコメントをしていた。「気になるのは安倍元首相の動き。アベノミクスを否定されないように必死に立ち回るような言動。これだけ借金を抱える中で大規模緩和を続ける禁じ手が続くわけがない。民主主義というのは、リーダーが変わることでリセットし軌道修正できる。それが本当に機能しているのか」
ヘタレ政権の「骨太の方針」が謳う防衛費増額も1億総投資家も憲法改悪も、これすべてペテン師・シンゾーの政策の丸写しなんだよね。つまり、ペテン師・シンゾーが院政を敷いているようなもので、そんな男の減らず口をいちいち報道するメディアもまた、その片棒を担いでいることほ意味している。国会でわかっているだけでも118回の虚偽答弁してる男ですからね。こんなのがいまだに大きなツラして表舞台に出てくる不思議な国、これが日本だ、僕らの国だ・・・ってなもんです。
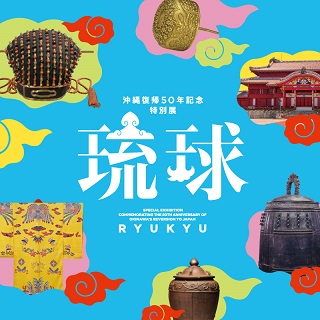

A・E 6ー10 沖縄復帰50年記念特別展「琉球」に。彼女は、どんな琉球展なのか、監視しなきゃ!と。監視に行って大正解????その中身は、明治時代初期の日本政府の"琉球処分"までの、琉球王国時代の華やかできらびやかなものたちの展示と、NHKが作った首里城の3D画像とやら。戦前戦後と復帰からの50年を探したけど、最後のスペースにわずかに戦争で焼かれて破断された石仏像の破片が、狭い場所に展示されているのみ。・・・・・唖然としてしまった。(略)
「復帰50年記念の特別展」と銘打ってますよね。なのになぜ復帰からのこと、戦前、戦中、戦後の展示がないのですか?いびつですよね。…政府だって沖縄に寄り添うと言っているのに、これでは寄り添ってないですね。戦争で"捨て石"にされて4人にひとりが亡くなった沖縄の人々に寄り添ってないでしょ」
「その上に、台湾有事とかって日米が中国の脅威を煽って、琉球弧がミサイル基地を作ってますよね。また沖縄が戦争の犠牲になる可能性もあるのですよ。…それなのに…(私、クドクド)」泣きたいほど本当に酷い展示だった。しかも沢山の人が訪れていた。この特別展の主催は、東京国立博物館、NHK、読売新聞社、文化庁だ????5月3日から6月26日まで開催。"監視"する以外に、ほとんど行く価値がない企画だった。

山城 明 6月1日(水)今日は写真の日だって画像は浜比嘉ビーチ⛱
"家計が値上げを受け入れている”という黒田総裁の発言にTwitterでは「#値上げ受け入れてません」というハッシュタグがトレンド入りするなど批判が殺到。《は?????》《マジで世間知らず》誰が受け入れてんだよ!!! 強制されてるんやろが!!!》《何言ってんだこの人!?️日銀総裁何年やってるんだよ。その間の景気悪化の責任とりなよ》《日銀総裁さん。手取月給20万円で1年間生活してみてから言ってくれない?》値上げラッシュが続くも、給料が上がらない日本の現状を自分の目で見て確かめてほしいものだーー。
6月10日 きっこ@kikko_no_blog「レイプ未遂犯」の田畑毅、「下着泥棒」の高木毅・元復興大臣、「盗撮野郎」の西村康稔・元コロナ担当大臣、「セクハラ常習犯」の細田博之衆院議長、そして「パパ活ハレンチ変質者」の吉川赳、さすがは安倍晋三が「自民党は人材の宝庫」と胸を張るだけのことはある。まるで性犯罪者の楽園だ。


高良勉 6-11 ◆さて今日は、大事なウンチケー(ご案内)とウニゲー(お願い)です。私の一人娘・高嶺美和子が、来る7月24日(日)に国立劇場おきなわで、「第2回 高嶺美和子の会」のリサイタルをやることになりました。
09/21: 世相ジャパン
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@yahoo.co.jp

渡久地 政司 2023年10月25日 · ■コスモス満開■豊田市宮上町一丁目水田 コスモス畑の後方は宮口神社と宮口こども園 撮影:渡久地
神無月は日本における旧暦10月の異称。今日では新暦10月の異称としても用いられる場合も多い。「神無」を「神が不在」と解釈するのは語源俗解である。→ウイキ
沖縄県大阪事務所は前田所長、當間次長のとき(1980年)島根県ビルから大阪駅前第3ビルに移転してきた。だから梅田に行くと島根県事務所もよく寄るが、島根(出雲)はまだ行ったことがない。熊野は熊野本宮大社だけが残っている。1937年7月の『月刊琉球』に沖縄県総務部長の清水谷徹が「王仁三郎を捕ふ」というのを書き「元来、島根県は松江市は有力な大本教の地盤で、その大本教松江分院なるものが、また素晴らしく豪奢なものであった。面白いことには、その隣りが皮肉にも島根県警察部長官舎で、当時私が住んでいた訳である。」と述べている。私は最近、千田稔『華族総覧』講談社を愛読しているが、島根県・亀井家を見ると「王政復古以後、議定、神祇局副知事となり、同局判事に大国隆正を登用した。まさに津和野藩主主従が宗教行政を握ったかであり、廃仏毀釈で神道国教化政策を推進した。(略)亀井家では西周が亀井玆明の養育を担い、森林太郎も同世代として玆明と交流した。日清戦争が勃発すると、亀井玆明は祖先玆矩が琉球守として外征の大志を抱いたことに触発され、従軍写真家として中国に赴く。のちに『明治廿七八年戦役写真貼』を皇室に献本した」とある。


出雲観光ガイド:縁結びの神・福の神として名高い「出雲大社(正式な読みはいづもおおやしろ)」は、日本最古の歴史書といわれる『古事記』にその創建の由縁が記されているほどの古社で、明治時代初期まで杵築大社(きづきたいしゃ)と呼ばれていました。/ハワイ出雲大社はアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市に鎮座する神社/出雲大社沖縄分社 所在地: 〒902-0061 沖縄県那覇市古島1丁目16−13

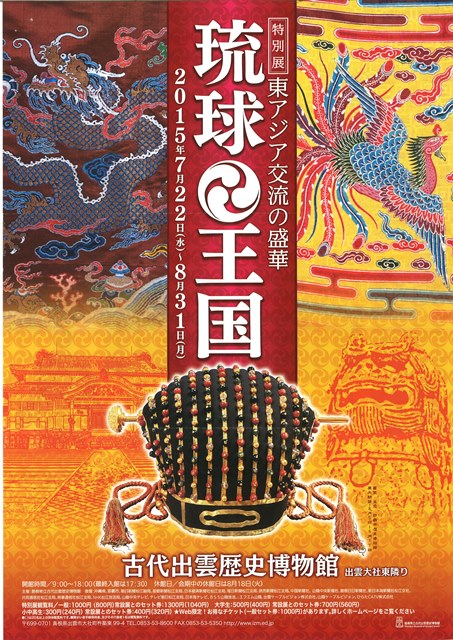
島根大学・郷原すず:須佐神社周辺では、2002 年から「スサノオウォーキング」という
ウォーキングのイベントが同実行委員会により開催されており、2004 年にはコースに須佐
神社周辺も含む「出雲風土記スサノオのみち」が、「美しい日本の歩きたくなる道 500
選」に選ばれている。/2015年7月22日~8月31日 古代出雲歴史博物館「琉球王国ー東アジア交流の盛華」琉球王国のすべてが出雲に集結





10月1日 中之橋/那覇空港/ブックオフ/おもろまち駅/孫こうた



9月29日 我が家の節目


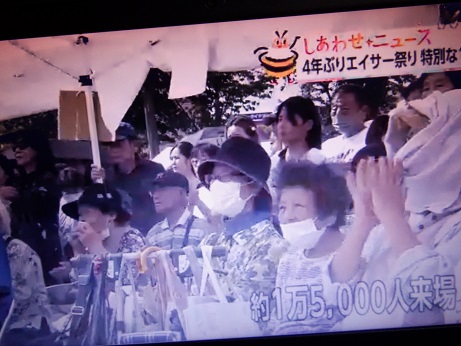
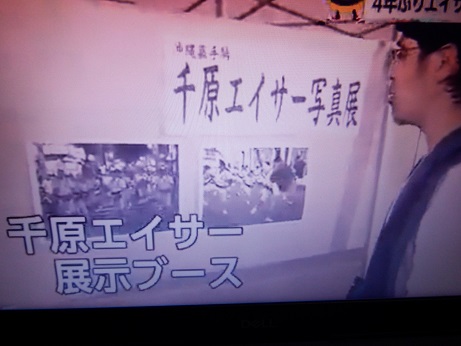
→動画「大阪エイサー祭り 2023」「NHK大阪」
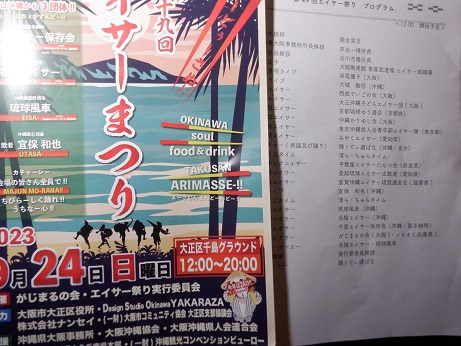
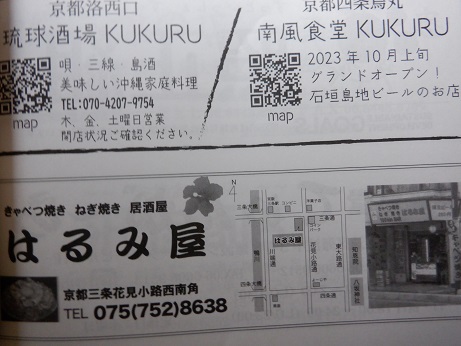
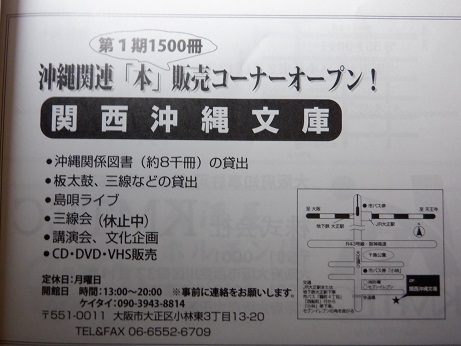
「第49回エイサー祭り」プログラム

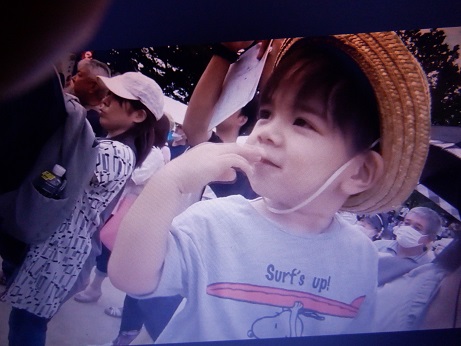
9月24日 がじまるエイサー広報部(大阪) ハイサイでーびる。めっちゃ久しぶりの投稿やいびんどぉさい。がじまるエイサー祭りが4年ぶりに帰って来ましたよぉ~。沖縄から千原エイサーがやって来ます。今年は熱中症対策で例年より2週間うしろにずらしました。お間違えのないように。ゆたさるぐとぅ、うにげぇさびら。/孫こうた参加

いいねうるま市 山城 明 · 9月24日 · おはよう御座います 今日も暑いです
豊里友行 今週の日曜日9月24日は、大阪の「第49回エイサー祭り」に千原エイサーの写真を撮りに行ってきます。めったに県外に出ることがない出不精な私ですが、がじまるの会・エイサー祭り実行委員会より昨年出版した写真録『千原エイサー』(2022年刊、沖縄書房)を見て写真展を開催依頼をいただく。ついでにエイサーとは別の別区画で「おきなわ」豊里友行写真展の大阪展も開催することになりました。ぜひ。エイサーを楽しみつつ、私の写真展も観に来ていただけると嬉しいです。
9月22日 沖縄タイムス 沖縄県浦添市の沖縄県浦添市の松本市長が新しく市内にできたホテルをPRするためSNSに投稿した動画の中で女性従業員をプールに誘う場面などがありました。タイトルは「市長が美女とホテルへ」
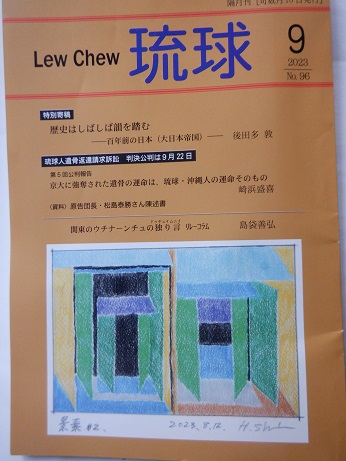
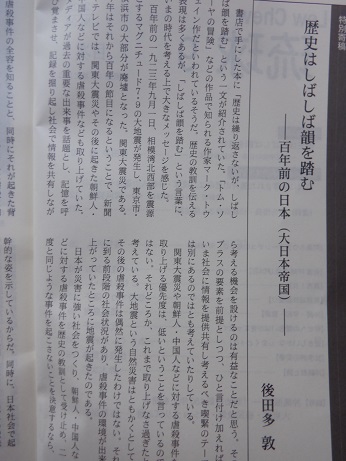
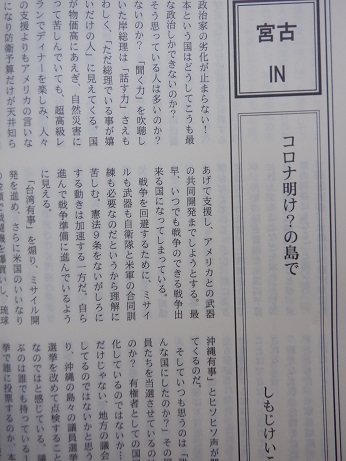
2023年9月『琉球』№68琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947◇後多田敦「歴史はしばしば韻を踏むー百年前の日本(大日本帝国)ー」/しもじけいこ「宮古IN コロナ明け?の島で」



島袋マカト陽子「東京琉球館便り」/伊良波賢弥「焚字炉の葉書②天妃の門」/鈴木次郎「沖縄戦と詩・寒川哲人(名嘉座元司)」


仲松 健雄 「敬老の日」の18日,東京沖縄県人会 川平朝清最高顧問(第7代会長)のカジマヤー祝いをホテルニューオータニ東京「鶴の間」で開催✨「鶴の間」は500名を超える参加者の祝福と熱気に包まれました❗️幕開け 「かぎやで風」東京琉球舞踊協会師匠の皆様/川平ファミリー、仲松 健雄さん




9月17日 明日が敬老の日ということでユンタンの娘と孫の合作「お婆ちゃん」「爺ちゃん」の絵を持ってきたが、どう見てもお婆ちゃんが娘の年齢に見える。沖縄県立博物館・美術館で遊んでコープ、ジュンク堂(地下1階に駿河屋 那覇沖映通り店)

山城 明 ·9月15日 · うるま市南風原漁港から あちさんや〜海面がキラキラ輝いてますよ



9月15日 平和通り傍の通り/沖縄県立博物館・美術館で左から宇佐美賢さん、山本正昭さん、翁長良明さん/那覇市市民文化財課で外間政明さん、課長兼博物館長の上原清実さん
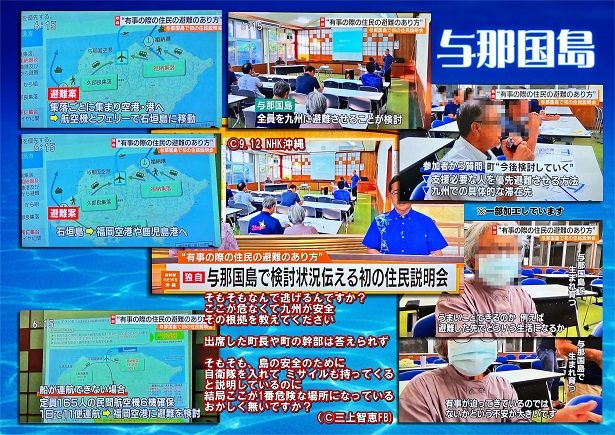
大濱 聡 9月14日 ■Media literacyーー9.12にNHK沖縄が〈独自〉ネタとして報じた「〃有事の際の避難のあり方〃与那国島で検討状況伝える初の住民説明会」――最後は「有事が迫ってきているのではないかという不安が大きいです」でまとめていた。通常は賛否両論の意見を伝えるが、意図的なのか、深く考えずに一人だけにしたのか。■しかし、現場を取材していた三上智恵さん(映画監督)のFBで生々しい実情を知ることができた。以下、一部引用。→三上智恵 2023年9月13日 いよいよ万が一の時の全島避難の住民説明会が与那国島で開かれた
くろねこの短語 2023年9月 8日 (金) 性加害者ジャニーの名前が冠のままでどこが「解体的手直し」だ!!&TV局はジャニーと深い関わりのあった制作局長やプロデューサーを事情聴取して、検証番組を作るべき!!
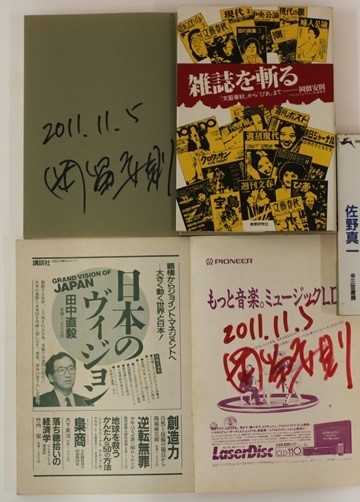
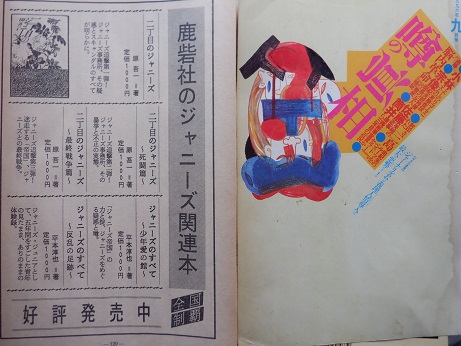
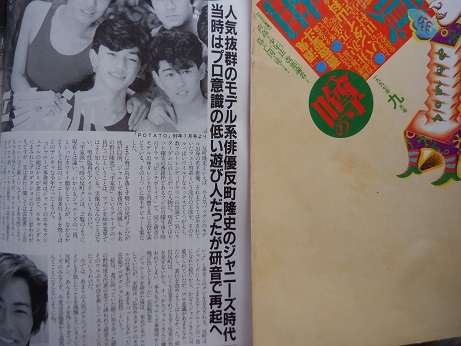
関連:岡留安則/1996年9月 『噂の眞相』/1997年9月 『噂の眞相』

いいねうるま市 山城 明 · 9月6日 · 涼しい風が吹いて気持ち良いですよ!

大濱 聡 ■本日(9.6)「悠仁さま17歳の誕生日」というニュースを伝えていた。ところで、拙著でいちばん古いのは17歳時(1965年・高校2年)の地元紙への投書である。前年に大ヒットしたのが西郷輝彦の「十七才のこの胸に」。よく口ずさんだ。沖縄出身の南沙織のデビュー曲は「17才(1971年)である。■その他、映画などでも「17才(歳)」を冠したものが多いのはなぜだろう。
新城栄徳◇私の17歳は東京一の繁華街、新宿歌舞伎町の大衆割烹「勇駒」で働いていた。その頃は若くてパワーもあった。20年ほど前、浅草寺初詣に行ったとき参拝者の列に入ったら全く身動きが取れなく離脱した。とにかく過密都市でのオリンピック開催は気が知れない。いずれにせよ静かな場所に憧れて京都に住み着いたのが1969年であったが、盆地だから夏は暑く、冬は底冷えに寒い。



9月5日 那覇市民ギャラリー「―表現する布染―平井真人YUGAFU2023」展
東洋経済オンライン ·9月5日 2025年4月に予定されている大阪・関西万博の開催に暗雲が立ち込めています。海外参加国のパビリオンの建設工事が大幅に遅れており、ゼネコン関係者も「手を出さないほうがいい」と冷ややかに見ています。

渡久地 政司 2023年10月25日 · ■コスモス満開■豊田市宮上町一丁目水田 コスモス畑の後方は宮口神社と宮口こども園 撮影:渡久地
神無月は日本における旧暦10月の異称。今日では新暦10月の異称としても用いられる場合も多い。「神無」を「神が不在」と解釈するのは語源俗解である。→ウイキ
沖縄県大阪事務所は前田所長、當間次長のとき(1980年)島根県ビルから大阪駅前第3ビルに移転してきた。だから梅田に行くと島根県事務所もよく寄るが、島根(出雲)はまだ行ったことがない。熊野は熊野本宮大社だけが残っている。1937年7月の『月刊琉球』に沖縄県総務部長の清水谷徹が「王仁三郎を捕ふ」というのを書き「元来、島根県は松江市は有力な大本教の地盤で、その大本教松江分院なるものが、また素晴らしく豪奢なものであった。面白いことには、その隣りが皮肉にも島根県警察部長官舎で、当時私が住んでいた訳である。」と述べている。私は最近、千田稔『華族総覧』講談社を愛読しているが、島根県・亀井家を見ると「王政復古以後、議定、神祇局副知事となり、同局判事に大国隆正を登用した。まさに津和野藩主主従が宗教行政を握ったかであり、廃仏毀釈で神道国教化政策を推進した。(略)亀井家では西周が亀井玆明の養育を担い、森林太郎も同世代として玆明と交流した。日清戦争が勃発すると、亀井玆明は祖先玆矩が琉球守として外征の大志を抱いたことに触発され、従軍写真家として中国に赴く。のちに『明治廿七八年戦役写真貼』を皇室に献本した」とある。


出雲観光ガイド:縁結びの神・福の神として名高い「出雲大社(正式な読みはいづもおおやしろ)」は、日本最古の歴史書といわれる『古事記』にその創建の由縁が記されているほどの古社で、明治時代初期まで杵築大社(きづきたいしゃ)と呼ばれていました。/ハワイ出雲大社はアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市に鎮座する神社/出雲大社沖縄分社 所在地: 〒902-0061 沖縄県那覇市古島1丁目16−13

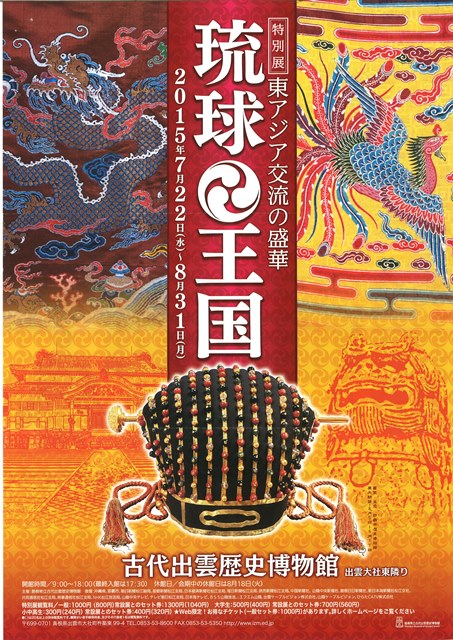
島根大学・郷原すず:須佐神社周辺では、2002 年から「スサノオウォーキング」という
ウォーキングのイベントが同実行委員会により開催されており、2004 年にはコースに須佐
神社周辺も含む「出雲風土記スサノオのみち」が、「美しい日本の歩きたくなる道 500
選」に選ばれている。/2015年7月22日~8月31日 古代出雲歴史博物館「琉球王国ー東アジア交流の盛華」琉球王国のすべてが出雲に集結





10月1日 中之橋/那覇空港/ブックオフ/おもろまち駅/孫こうた



9月29日 我が家の節目


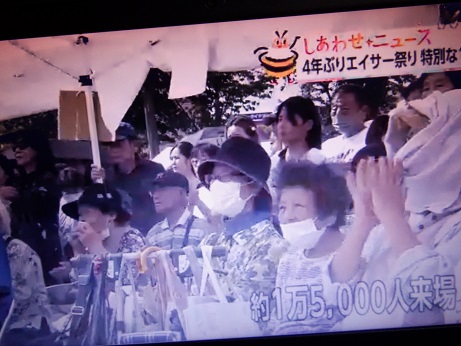
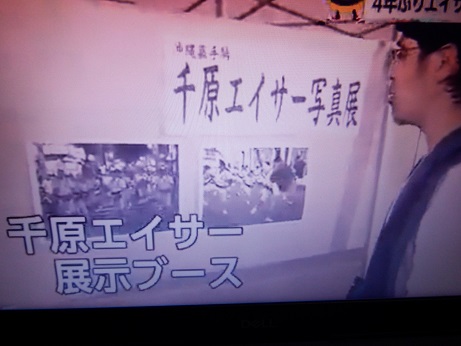
→動画「大阪エイサー祭り 2023」「NHK大阪」
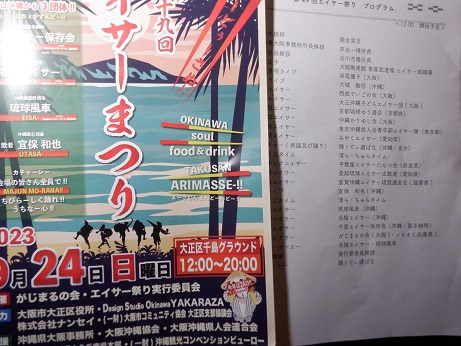
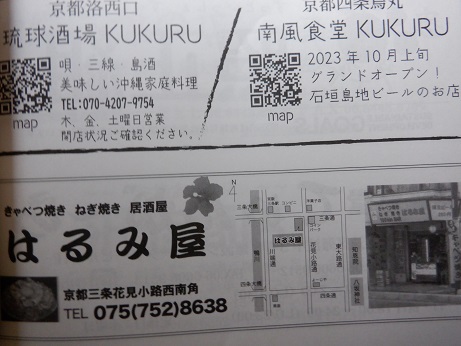
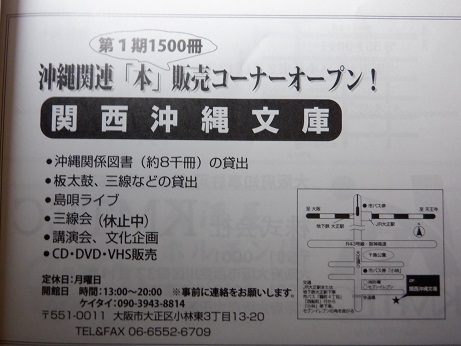
「第49回エイサー祭り」プログラム

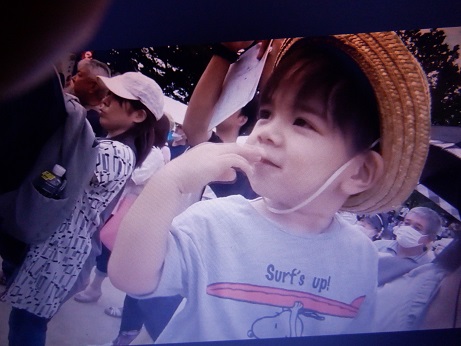
9月24日 がじまるエイサー広報部(大阪) ハイサイでーびる。めっちゃ久しぶりの投稿やいびんどぉさい。がじまるエイサー祭りが4年ぶりに帰って来ましたよぉ~。沖縄から千原エイサーがやって来ます。今年は熱中症対策で例年より2週間うしろにずらしました。お間違えのないように。ゆたさるぐとぅ、うにげぇさびら。/孫こうた参加

いいねうるま市 山城 明 · 9月24日 · おはよう御座います 今日も暑いです
豊里友行 今週の日曜日9月24日は、大阪の「第49回エイサー祭り」に千原エイサーの写真を撮りに行ってきます。めったに県外に出ることがない出不精な私ですが、がじまるの会・エイサー祭り実行委員会より昨年出版した写真録『千原エイサー』(2022年刊、沖縄書房)を見て写真展を開催依頼をいただく。ついでにエイサーとは別の別区画で「おきなわ」豊里友行写真展の大阪展も開催することになりました。ぜひ。エイサーを楽しみつつ、私の写真展も観に来ていただけると嬉しいです。
9月22日 沖縄タイムス 沖縄県浦添市の沖縄県浦添市の松本市長が新しく市内にできたホテルをPRするためSNSに投稿した動画の中で女性従業員をプールに誘う場面などがありました。タイトルは「市長が美女とホテルへ」
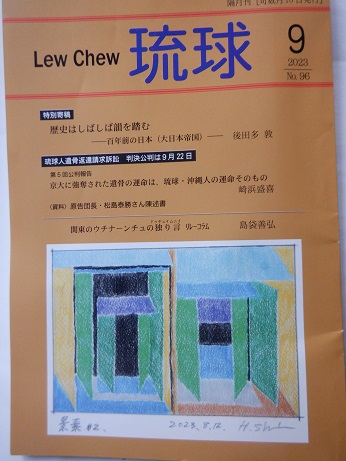
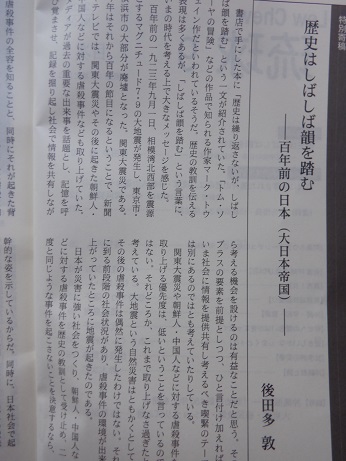
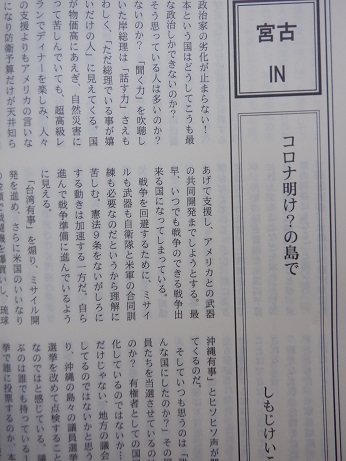
2023年9月『琉球』№68琉球館〒903-0801 那覇市首里末吉町1-154-102 ☎098-943-6945/FAX098-943-6947◇後多田敦「歴史はしばしば韻を踏むー百年前の日本(大日本帝国)ー」/しもじけいこ「宮古IN コロナ明け?の島で」



島袋マカト陽子「東京琉球館便り」/伊良波賢弥「焚字炉の葉書②天妃の門」/鈴木次郎「沖縄戦と詩・寒川哲人(名嘉座元司)」


仲松 健雄 「敬老の日」の18日,東京沖縄県人会 川平朝清最高顧問(第7代会長)のカジマヤー祝いをホテルニューオータニ東京「鶴の間」で開催✨「鶴の間」は500名を超える参加者の祝福と熱気に包まれました❗️幕開け 「かぎやで風」東京琉球舞踊協会師匠の皆様/川平ファミリー、仲松 健雄さん




9月17日 明日が敬老の日ということでユンタンの娘と孫の合作「お婆ちゃん」「爺ちゃん」の絵を持ってきたが、どう見てもお婆ちゃんが娘の年齢に見える。沖縄県立博物館・美術館で遊んでコープ、ジュンク堂(地下1階に駿河屋 那覇沖映通り店)

山城 明 ·9月15日 · うるま市南風原漁港から あちさんや〜海面がキラキラ輝いてますよ



9月15日 平和通り傍の通り/沖縄県立博物館・美術館で左から宇佐美賢さん、山本正昭さん、翁長良明さん/那覇市市民文化財課で外間政明さん、課長兼博物館長の上原清実さん
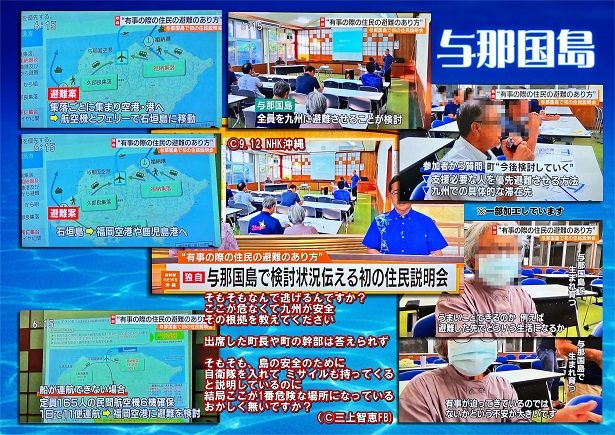
大濱 聡 9月14日 ■Media literacyーー9.12にNHK沖縄が〈独自〉ネタとして報じた「〃有事の際の避難のあり方〃与那国島で検討状況伝える初の住民説明会」――最後は「有事が迫ってきているのではないかという不安が大きいです」でまとめていた。通常は賛否両論の意見を伝えるが、意図的なのか、深く考えずに一人だけにしたのか。■しかし、現場を取材していた三上智恵さん(映画監督)のFBで生々しい実情を知ることができた。以下、一部引用。→三上智恵 2023年9月13日 いよいよ万が一の時の全島避難の住民説明会が与那国島で開かれた
くろねこの短語 2023年9月 8日 (金) 性加害者ジャニーの名前が冠のままでどこが「解体的手直し」だ!!&TV局はジャニーと深い関わりのあった制作局長やプロデューサーを事情聴取して、検証番組を作るべき!!
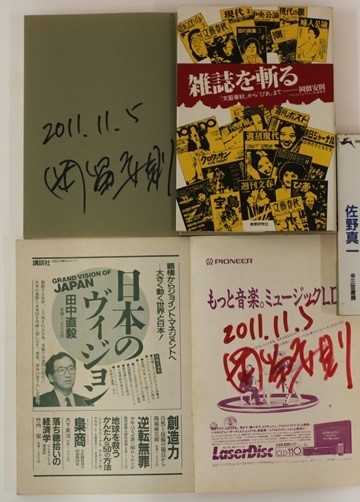
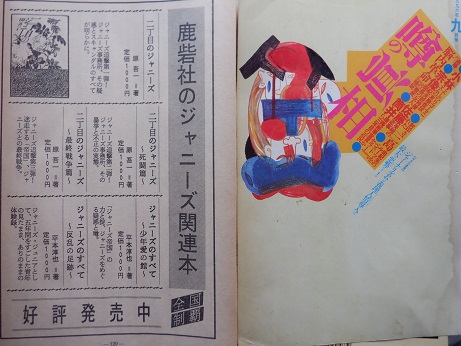
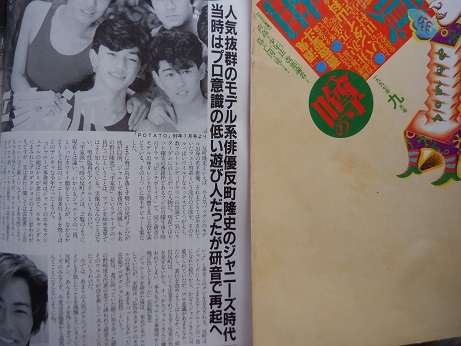
関連:岡留安則/1996年9月 『噂の眞相』/1997年9月 『噂の眞相』

いいねうるま市 山城 明 · 9月6日 · 涼しい風が吹いて気持ち良いですよ!

大濱 聡 ■本日(9.6)「悠仁さま17歳の誕生日」というニュースを伝えていた。ところで、拙著でいちばん古いのは17歳時(1965年・高校2年)の地元紙への投書である。前年に大ヒットしたのが西郷輝彦の「十七才のこの胸に」。よく口ずさんだ。沖縄出身の南沙織のデビュー曲は「17才(1971年)である。■その他、映画などでも「17才(歳)」を冠したものが多いのはなぜだろう。
新城栄徳◇私の17歳は東京一の繁華街、新宿歌舞伎町の大衆割烹「勇駒」で働いていた。その頃は若くてパワーもあった。20年ほど前、浅草寺初詣に行ったとき参拝者の列に入ったら全く身動きが取れなく離脱した。とにかく過密都市でのオリンピック開催は気が知れない。いずれにせよ静かな場所に憧れて京都に住み着いたのが1969年であったが、盆地だから夏は暑く、冬は底冷えに寒い。



9月5日 那覇市民ギャラリー「―表現する布染―平井真人YUGAFU2023」展
東洋経済オンライン ·9月5日 2025年4月に予定されている大阪・関西万博の開催に暗雲が立ち込めています。海外参加国のパビリオンの建設工事が大幅に遅れており、ゼネコン関係者も「手を出さないほうがいい」と冷ややかに見ています。
11/27: 世相ジャパン
☆コメントはメールにお願いします→shinjo8109@yahoo.co.jp
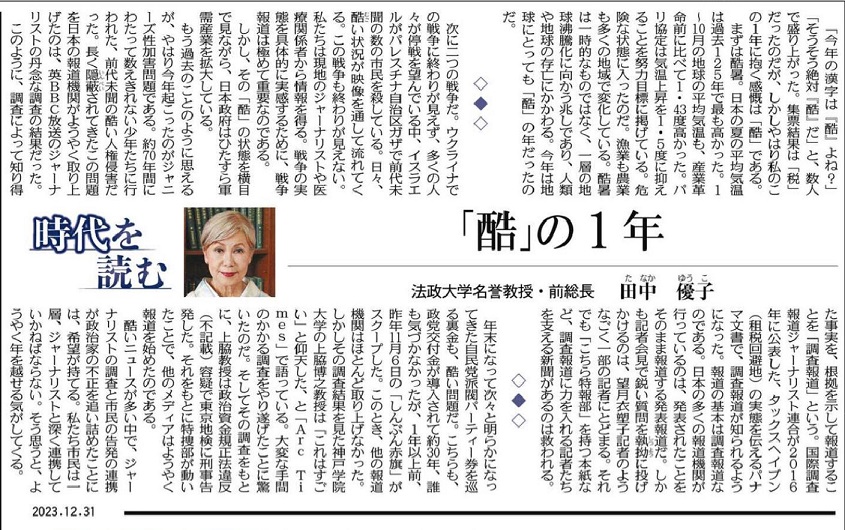
東京新聞「時代を読む」田中優子さん。

大濱 聡 12-29■12.18付『琉球新報』の記事から――東京商工リサーチが行った全国4747企業へのアンケートで、都道府県別の忘・新年会の実施予定にかなりの差があったという。全国平均54.5%、最多は沖縄の78.7%、最少は埼玉の41.1%。
「沖縄は集まってお酒を飲む文化がある」(統計調査会社代表氏のコメント)そうな。
12-28『毎日新聞』米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設を巡り、斉藤鉄夫国土交通相(島根県/公明党)は28日、防衛省による地盤改良工事のための設計変更申請を沖縄県に代わって承認する代執行を実施した。地方自治法に基づき、国が自治体の事務を代執行したのは初めて。県が反発する中で異例の措置となった。
12月16日 『琉球新報』「沖縄県は2023年の梅毒患者報告数が男性98例、女性39例」

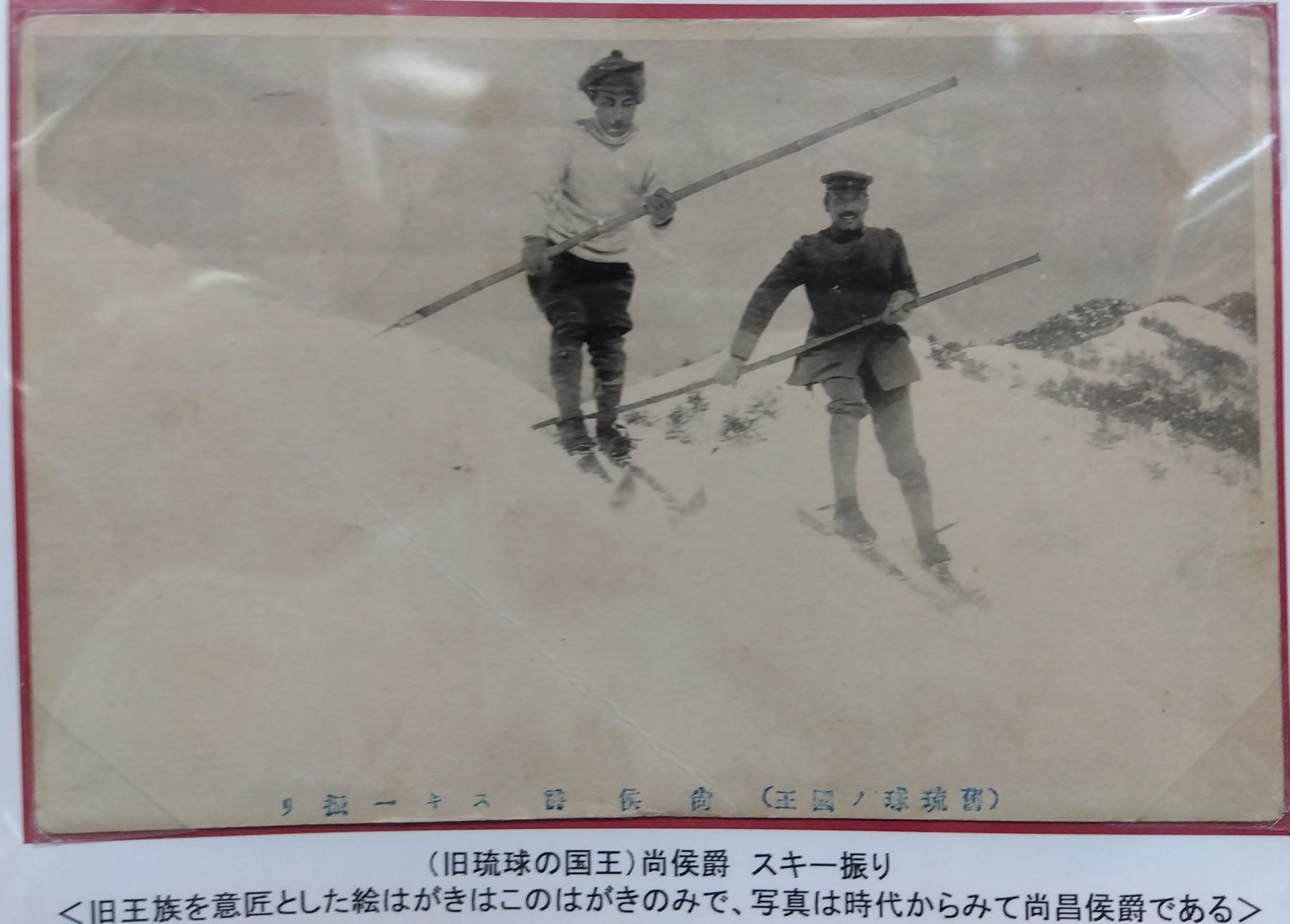
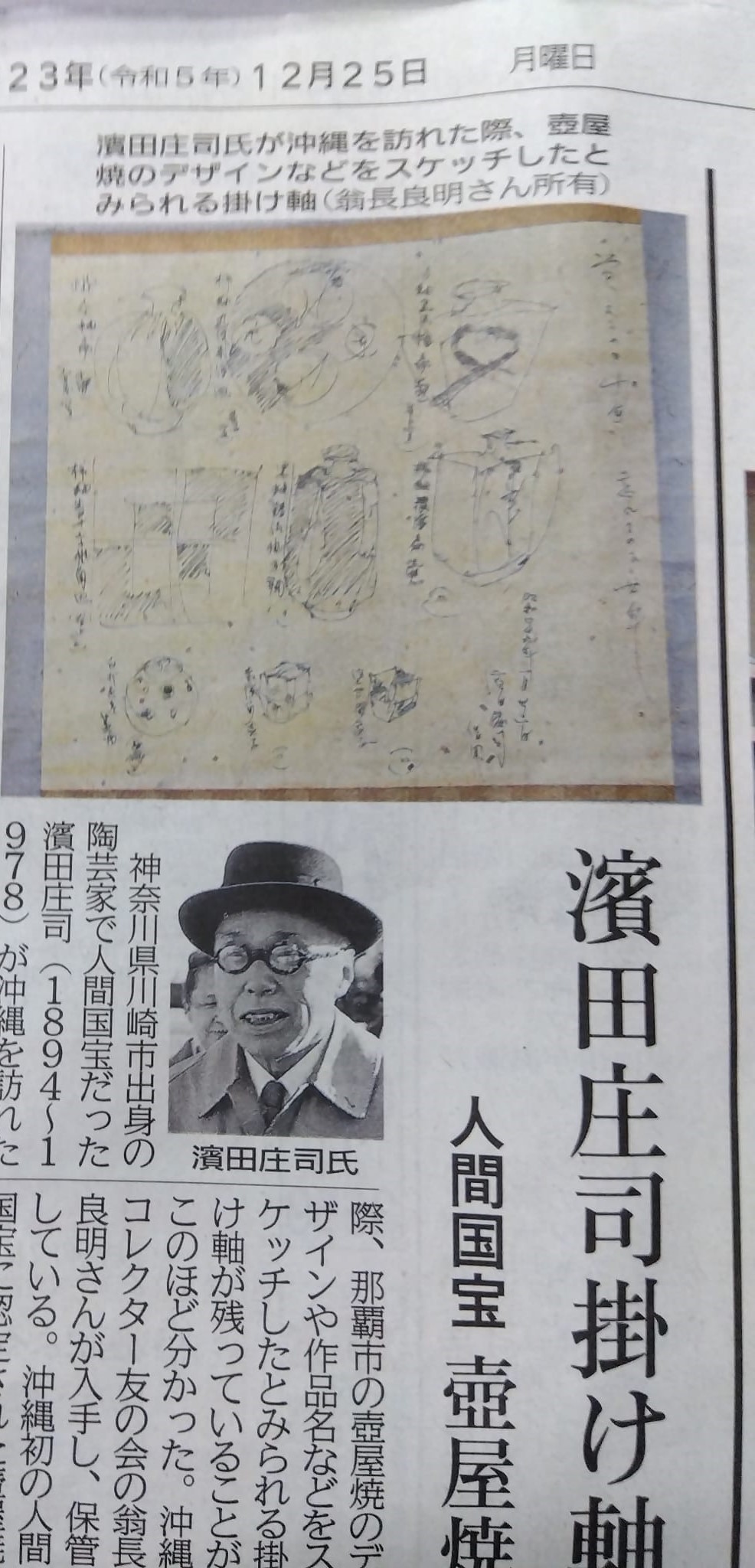

12月25日 なるみ堂に遊びに行く。/左から石澤司さん、翁長良明さん、與那嶺昭さん/石澤さんの「尚昌侯絵葉書」/新報の翁長さん記事/ジュンク堂書店
2023年8月 25日 くろねこの短語 民民のタマキンがひょっとこ麻生のお膝元で、連合の反共会長にお追従するような発言してます。「立憲共産党のような状況になっているのは我々も連合も心配している」だとさ。言ってろ、クズ・・・ってなもんです。そもそも、第3自民党を公言して憚らない無節操な政治屋こそ、消えてなくなるべきなんだね。
他党のことを云云かんぬんdisる暇があったら、、まずは自分の頭の蠅を追いやがれ。それにしても、いまだに「反共」を言い募る連中が白昼堂々と闊歩してるって、いかにこの国の政治が周回遅れに陥っているかわかろうというものだ。
Chizuko Yamada·12月24日 宝島の創業者、蓮見清一氏が80才で亡くなりました。 夫の大学時代、同じ政経学部、革マルのリーダーでした。その後、数年後に、植草甚一の出版社を買い取り、宝島として創業した方です。大宮出身、春日部高校の卒業生。夫が10年前に書いたエッセイが、ネットで上位に上がっています。良かったら、お読み下さい。/蓮見 清一(はすみ せいいち、1942年12月22日 - 2023年12月14日)は、日本の実業家。宝島社創業者。1942年12月14日、関東州(現中華人民共和国)大連市出身。1962年、早稲田大学政治経済学部に入学。1971年、株式会社ジェー・アイ・シー・シーを設立。1974年に、晶文社より権利を取得、月刊誌『宝島』を復刊。1993年、株式会社ジェー・アイ・シー・シーを、株式会社宝島社に名称変更。2010年10月28日テレビ東京放送の『カンブリア宮殿』に出演。2023年12月14日、心不全のため東京都内の自宅で死去。80歳没

『宝島』(たからじま)は、宝島社から発行されていた看板雑誌。休刊時点では「タブーに斬り込む知的探求マガジン」というキャッチコピーの下、アングラ情報を含む情報誌となっていた。休刊時編集長は富樫生。1973年7月10日に晶文社より『WonderLand(ワンダーランド)』として創刊。1970年代のサブカル文化の一翼を担った。10年ごとにコンセプトを変え、アンダーグラウンド→サブカルチャー→アダルト→ビジネス誌→アングラ情報誌と、これまで全く異なるジャンルを横断し、それまでの読者を切り捨ててでもエポックメイキングな誌面を作り出してきた。→ウィキ




12-22 末吉安允さんと那覇市歴史博物館。山田葉子さん、吉田佐和子さん/那覇市民ギャラリー「歩いてみた国・中国」/沖縄銀行前
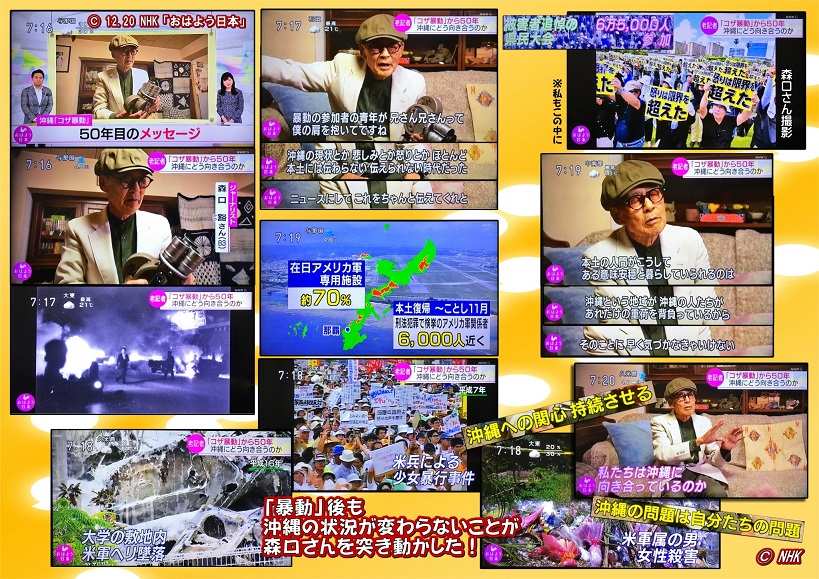
大濱 聡 2020年12月20日 · ■今朝(12.20)のNHK「おはよう日本〈沖縄「コザ暴動」50年目のメッセージ〉」(6分20秒)。当時、日本テレビの記者として沖縄に勤務していた森口 豁さん、「コザ暴動」取材後も変わらない沖縄の状況に突き動かされ、4年後に東京に転勤後も沖縄に通って取材を続け、今日に至っている。沖縄を題材にしたTVドキュメンタリーでは日本で最も数多く制作し、森口さんを凌駕する者はいない。
12-17 FNNプライムオンライン防衛省は17日午後10時40分、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと発表した。政府関係者によると、弾道ミサイルの可能性があるものはすでに落下した。落下地点は日本のEEZ外とみられ、短距離弾道ミサイルの可能性が高いという。




12月15日 夫婦橋/若松橋→「沖縄の風景:若松卸問屋街通り」(1) /前島橋/美栄橋
「朝日新聞」12-11 吉村知事は11日、報道陣の取材に、西村康稔経済産業相が国会で「国が補塡(ほてん)することはない」と答弁したことを念頭に「万博は国の事業で、国が(不足分を)負担しない中、府市が負担するわけがない」と説明。その上で、運営費の対応については、14日に開かれる日本国際博覧会協会(万博協会)の理事会で協議する意向を示した。横山市長も11日、報道陣に「府市で(赤字を)カバーする認識はありません」と述べた。
2023年12月8日 くろねこの短語 官房長官の丸出だめ夫・松野君がパー券裏金疑惑について「お答えを差し控える」と頑なに拒否し続けるのには、口が裂けても言えない後ろめたさがあるに違いない…と妄想してたら、朝日新聞がとどめを刺してくれました。なんとまあ、直近の5年間で1000万円のキックバックを受け取っていましたとさ。そりゃあ、「お答えを差し控える」と突っぱねざるを得ないわけだ。
これが事実なら、官房長官辞任は当然としても、検察の捜査次第では逮捕なんてこともあるかもしれない。そうなったら、ヘタレ内閣はもちろんだが、なによりも安倍派(清和会)にとっては大打撃でしょうね。安倍派解体が視野に入ってきたってことだ。
女体盛り・西村君も、バンティ高木君も、枕を高くして眠れない日が続いていくことでしょう。期せずして、ワクワクする年の瀬になりそうだ。



12-7あっぷるタウン/泊小学校/中之橋




12-7黄金森公園/ヤマダ電機/沖縄県立博物館・美術館



12-6雨 国際通り/平和通り/美栄橋駅


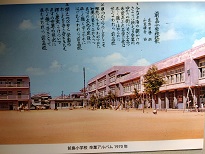
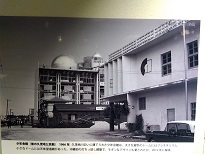
2023年12月1日 なは一と「あの日の久茂地●前島~写真と映像で思い出をふりかえる~」/我が母校・前島校小学校(現・那覇小学校)

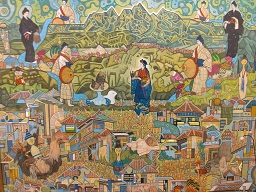


11月28日から12月3日 那覇市民ギャラリー「桑江良健絵画展」/山城みどりさん、桑江純子さん/桑江良健さん、仲本賢沖縄県立芸術大学教授、桑江純子さん
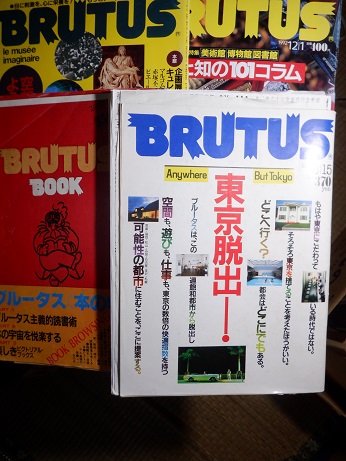
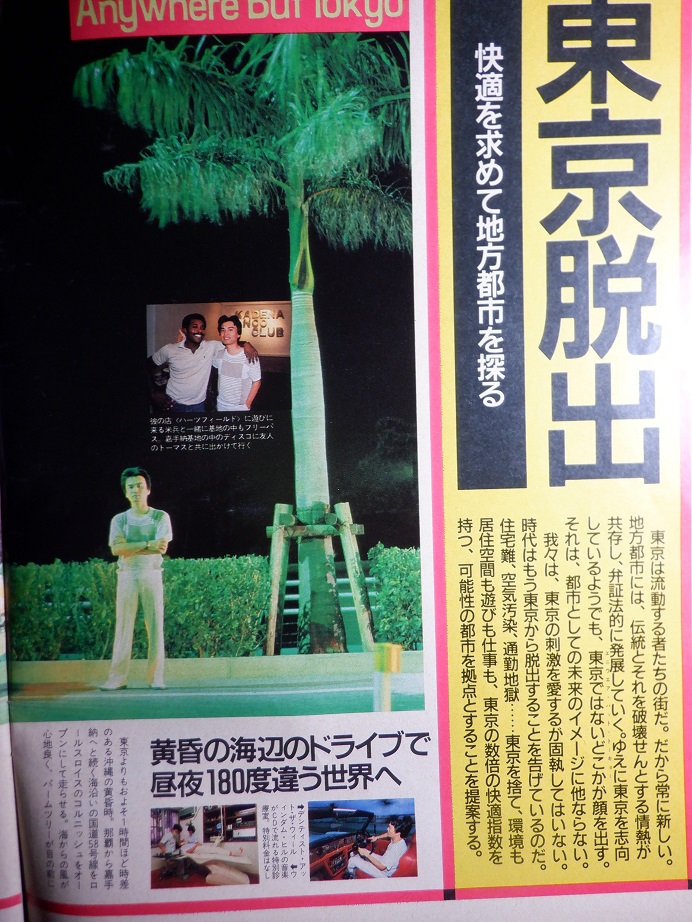
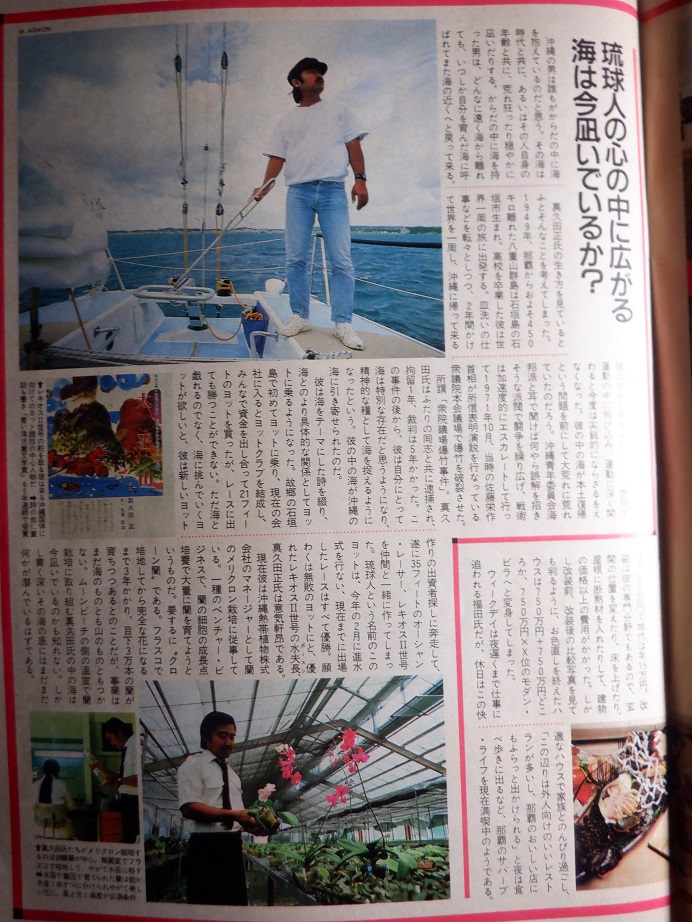
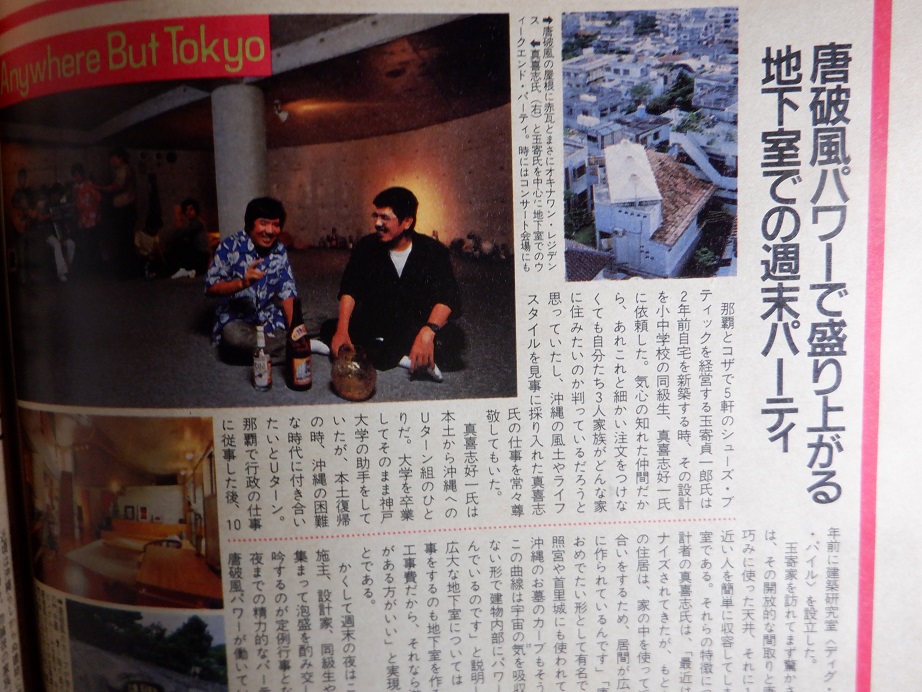
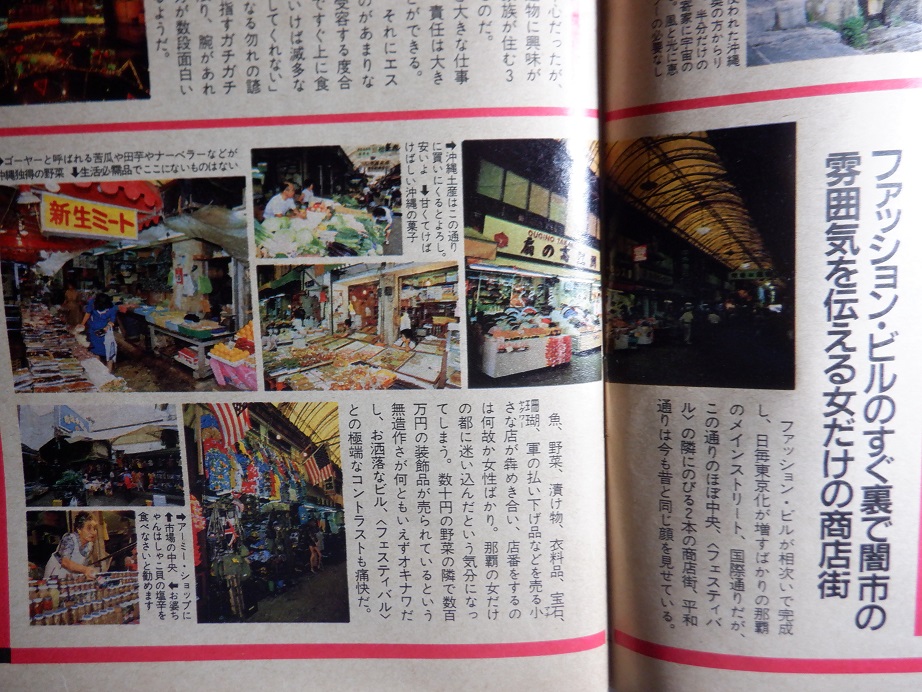
1985年8月那覇 『ブルータス』「東京脱出!ー東京をこよなく愛する我々だが、汚染、住宅難、通勤地獄には我慢ができない。那覇(真久田正・真喜志好一、玉寄貞一郎・公設市場)/福岡/松山/金沢/広島/名古屋/札幌/」
◇1980年 - 「ブルータス」創刊。「男として生きる術を心得た、あらゆる男たちのために」が合言葉であった。
1959年 - 「週刊平凡」創刊。
1964年 - 「平凡パンチ」創刊。若者向けの雑誌として一世を風靡する。
1965年 - 「平凡パンチデラックス」(隔月刊)創刊。
1968年 - 「ポケットパンチOh!」(月刊)創刊。
1970年 - 「an・an」創刊。大型女性誌としてスタート。フランスの「エル ELLE」誌と提携した。集英社の「non-no」とともに人気雑誌となる。
1976年 - 「ポパイ」創刊 "Magazine for City Boys"というサブタイトルでスタート。男性週刊誌のさきがけといわれる。
1977年 - 「クロワッサン」創刊。ニューファミリー生活誌として創刊。
1981年 - 「ダカーポ」創刊。「現代」が3時間でわかる情報誌としてスタートした。
1982年 - 「エル・ジャポン」創刊。「Olive」創刊。"Magazine for Romantic Girls"というサブタイトルを使用した。
1983年 - 会社名を「株式会社マガジンハウス」(〒104-8003東京都中央区銀座3丁目13-10)に変更。ニュージャーナリズム誌「鳩よ!」創刊。
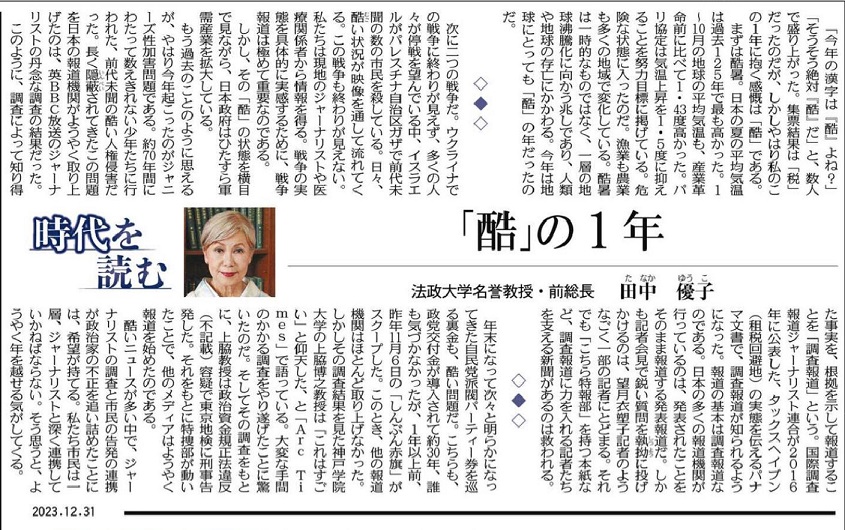
東京新聞「時代を読む」田中優子さん。

大濱 聡 12-29■12.18付『琉球新報』の記事から――東京商工リサーチが行った全国4747企業へのアンケートで、都道府県別の忘・新年会の実施予定にかなりの差があったという。全国平均54.5%、最多は沖縄の78.7%、最少は埼玉の41.1%。
「沖縄は集まってお酒を飲む文化がある」(統計調査会社代表氏のコメント)そうな。
12-28『毎日新聞』米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設を巡り、斉藤鉄夫国土交通相(島根県/公明党)は28日、防衛省による地盤改良工事のための設計変更申請を沖縄県に代わって承認する代執行を実施した。地方自治法に基づき、国が自治体の事務を代執行したのは初めて。県が反発する中で異例の措置となった。
12月16日 『琉球新報』「沖縄県は2023年の梅毒患者報告数が男性98例、女性39例」

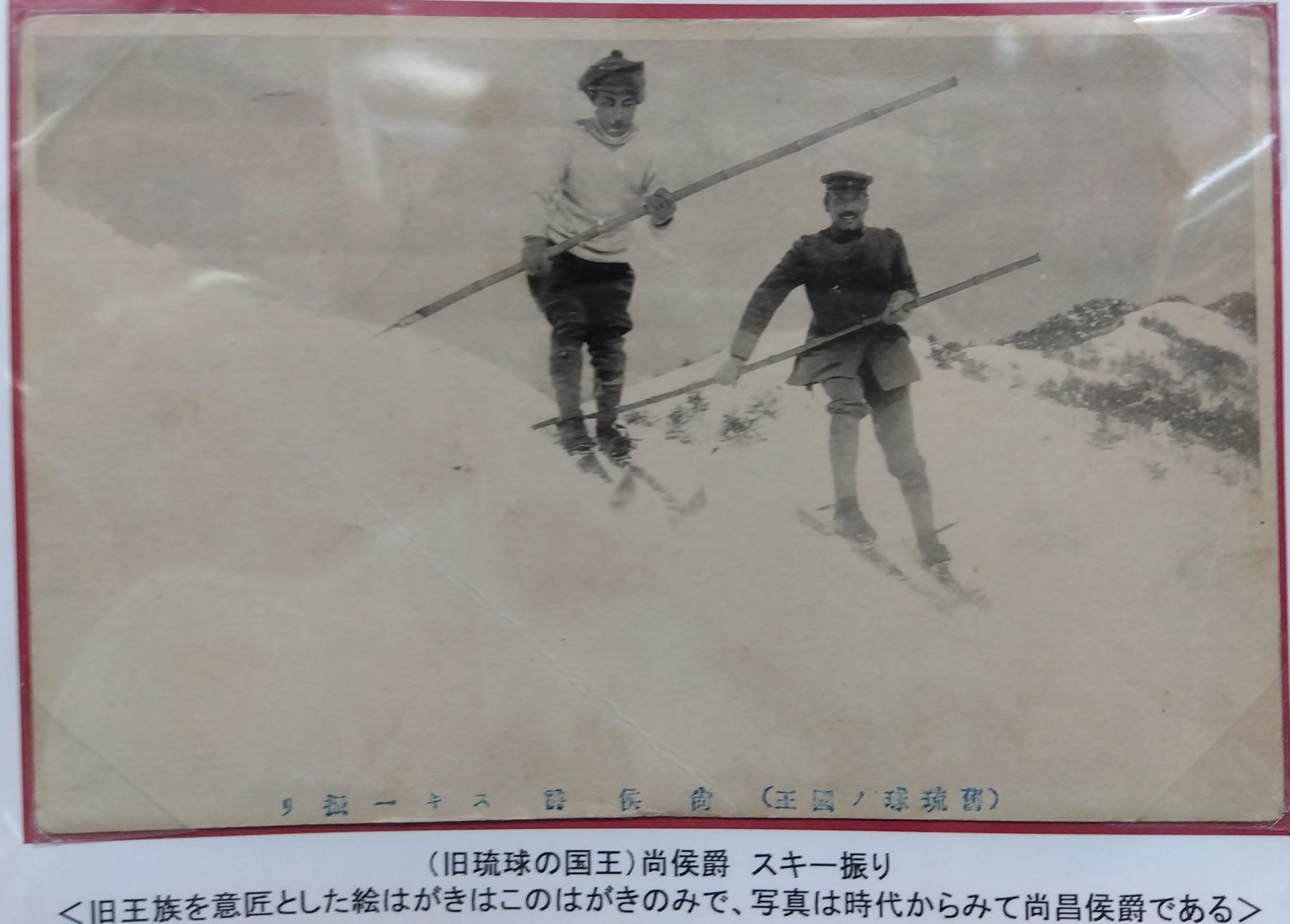
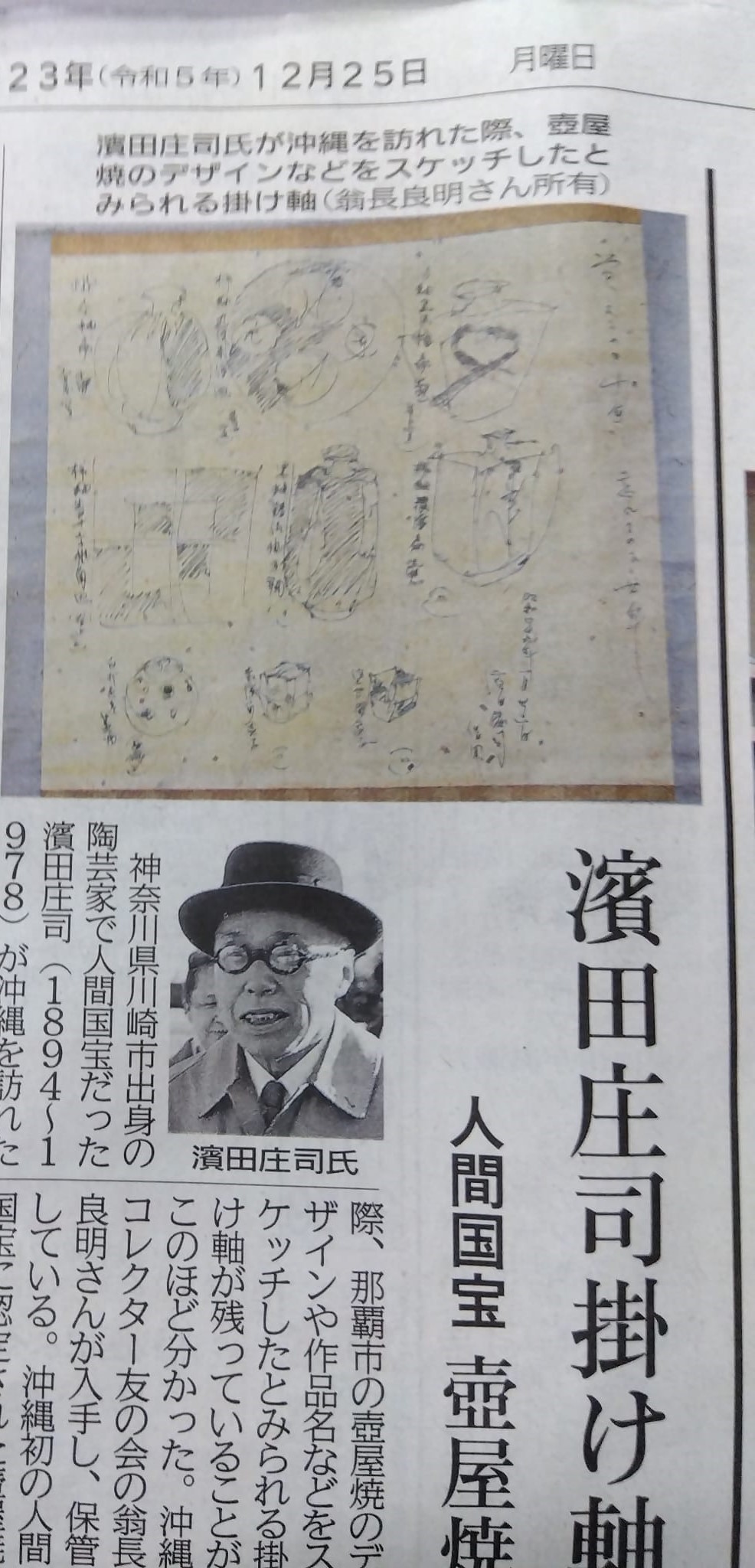

12月25日 なるみ堂に遊びに行く。/左から石澤司さん、翁長良明さん、與那嶺昭さん/石澤さんの「尚昌侯絵葉書」/新報の翁長さん記事/ジュンク堂書店
2023年8月 25日 くろねこの短語 民民のタマキンがひょっとこ麻生のお膝元で、連合の反共会長にお追従するような発言してます。「立憲共産党のような状況になっているのは我々も連合も心配している」だとさ。言ってろ、クズ・・・ってなもんです。そもそも、第3自民党を公言して憚らない無節操な政治屋こそ、消えてなくなるべきなんだね。
他党のことを云云かんぬんdisる暇があったら、、まずは自分の頭の蠅を追いやがれ。それにしても、いまだに「反共」を言い募る連中が白昼堂々と闊歩してるって、いかにこの国の政治が周回遅れに陥っているかわかろうというものだ。
Chizuko Yamada·12月24日 宝島の創業者、蓮見清一氏が80才で亡くなりました。 夫の大学時代、同じ政経学部、革マルのリーダーでした。その後、数年後に、植草甚一の出版社を買い取り、宝島として創業した方です。大宮出身、春日部高校の卒業生。夫が10年前に書いたエッセイが、ネットで上位に上がっています。良かったら、お読み下さい。/蓮見 清一(はすみ せいいち、1942年12月22日 - 2023年12月14日)は、日本の実業家。宝島社創業者。1942年12月14日、関東州(現中華人民共和国)大連市出身。1962年、早稲田大学政治経済学部に入学。1971年、株式会社ジェー・アイ・シー・シーを設立。1974年に、晶文社より権利を取得、月刊誌『宝島』を復刊。1993年、株式会社ジェー・アイ・シー・シーを、株式会社宝島社に名称変更。2010年10月28日テレビ東京放送の『カンブリア宮殿』に出演。2023年12月14日、心不全のため東京都内の自宅で死去。80歳没

『宝島』(たからじま)は、宝島社から発行されていた看板雑誌。休刊時点では「タブーに斬り込む知的探求マガジン」というキャッチコピーの下、アングラ情報を含む情報誌となっていた。休刊時編集長は富樫生。1973年7月10日に晶文社より『WonderLand(ワンダーランド)』として創刊。1970年代のサブカル文化の一翼を担った。10年ごとにコンセプトを変え、アンダーグラウンド→サブカルチャー→アダルト→ビジネス誌→アングラ情報誌と、これまで全く異なるジャンルを横断し、それまでの読者を切り捨ててでもエポックメイキングな誌面を作り出してきた。→ウィキ




12-22 末吉安允さんと那覇市歴史博物館。山田葉子さん、吉田佐和子さん/那覇市民ギャラリー「歩いてみた国・中国」/沖縄銀行前
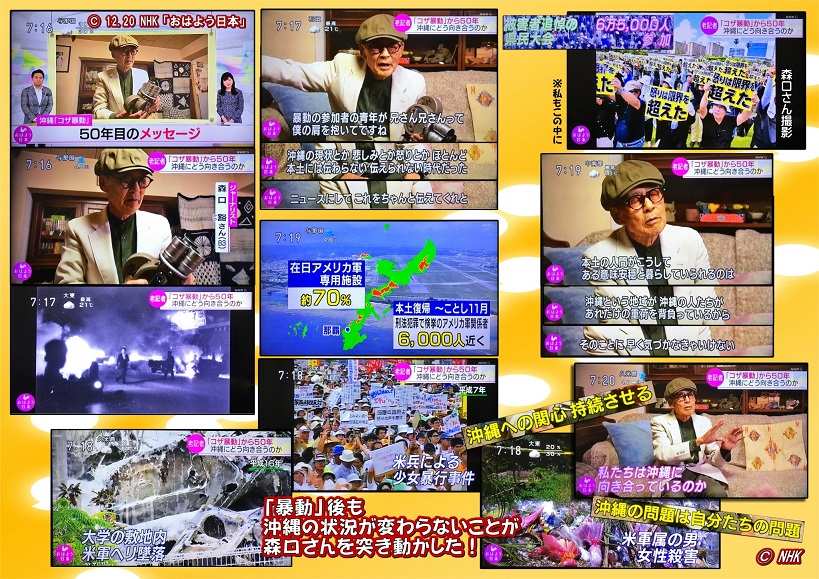
大濱 聡 2020年12月20日 · ■今朝(12.20)のNHK「おはよう日本〈沖縄「コザ暴動」50年目のメッセージ〉」(6分20秒)。当時、日本テレビの記者として沖縄に勤務していた森口 豁さん、「コザ暴動」取材後も変わらない沖縄の状況に突き動かされ、4年後に東京に転勤後も沖縄に通って取材を続け、今日に至っている。沖縄を題材にしたTVドキュメンタリーでは日本で最も数多く制作し、森口さんを凌駕する者はいない。
12-17 FNNプライムオンライン防衛省は17日午後10時40分、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと発表した。政府関係者によると、弾道ミサイルの可能性があるものはすでに落下した。落下地点は日本のEEZ外とみられ、短距離弾道ミサイルの可能性が高いという。




12月15日 夫婦橋/若松橋→「沖縄の風景:若松卸問屋街通り」(1) /前島橋/美栄橋
「朝日新聞」12-11 吉村知事は11日、報道陣の取材に、西村康稔経済産業相が国会で「国が補塡(ほてん)することはない」と答弁したことを念頭に「万博は国の事業で、国が(不足分を)負担しない中、府市が負担するわけがない」と説明。その上で、運営費の対応については、14日に開かれる日本国際博覧会協会(万博協会)の理事会で協議する意向を示した。横山市長も11日、報道陣に「府市で(赤字を)カバーする認識はありません」と述べた。
2023年12月8日 くろねこの短語 官房長官の丸出だめ夫・松野君がパー券裏金疑惑について「お答えを差し控える」と頑なに拒否し続けるのには、口が裂けても言えない後ろめたさがあるに違いない…と妄想してたら、朝日新聞がとどめを刺してくれました。なんとまあ、直近の5年間で1000万円のキックバックを受け取っていましたとさ。そりゃあ、「お答えを差し控える」と突っぱねざるを得ないわけだ。
これが事実なら、官房長官辞任は当然としても、検察の捜査次第では逮捕なんてこともあるかもしれない。そうなったら、ヘタレ内閣はもちろんだが、なによりも安倍派(清和会)にとっては大打撃でしょうね。安倍派解体が視野に入ってきたってことだ。
女体盛り・西村君も、バンティ高木君も、枕を高くして眠れない日が続いていくことでしょう。期せずして、ワクワクする年の瀬になりそうだ。



12-7あっぷるタウン/泊小学校/中之橋




12-7黄金森公園/ヤマダ電機/沖縄県立博物館・美術館



12-6雨 国際通り/平和通り/美栄橋駅


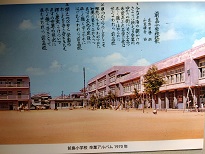
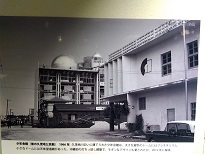
2023年12月1日 なは一と「あの日の久茂地●前島~写真と映像で思い出をふりかえる~」/我が母校・前島校小学校(現・那覇小学校)

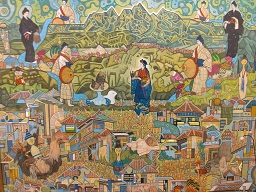


11月28日から12月3日 那覇市民ギャラリー「桑江良健絵画展」/山城みどりさん、桑江純子さん/桑江良健さん、仲本賢沖縄県立芸術大学教授、桑江純子さん
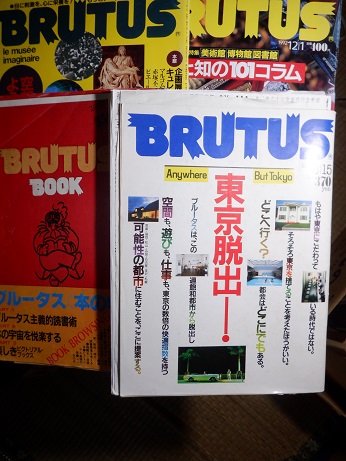
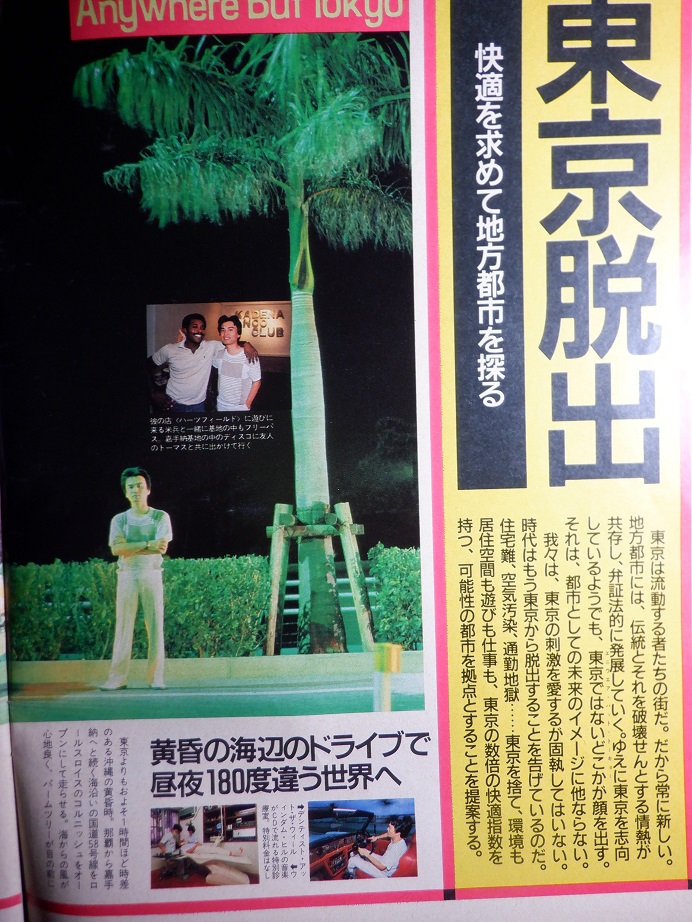
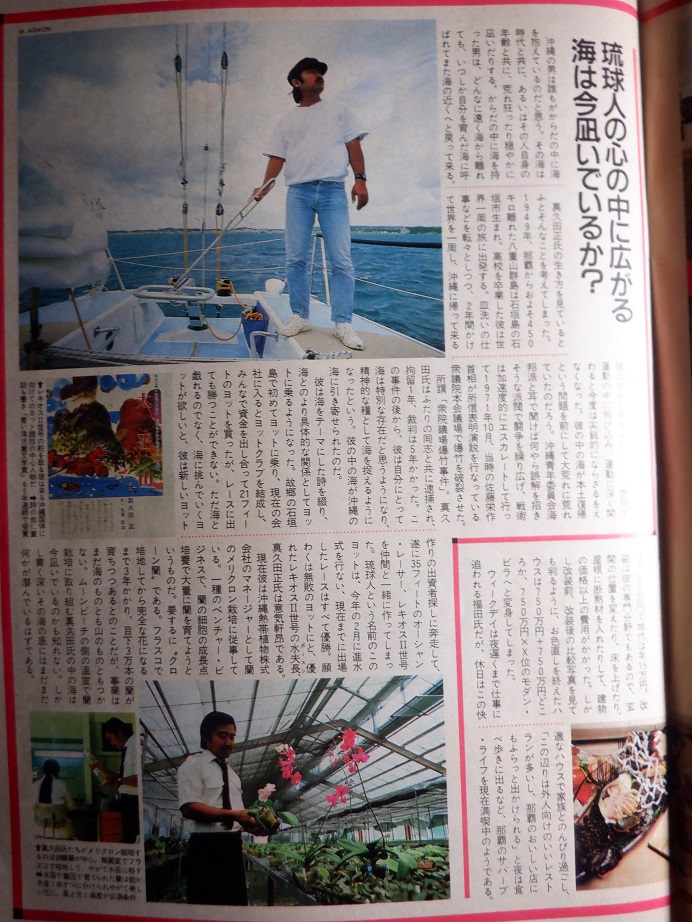
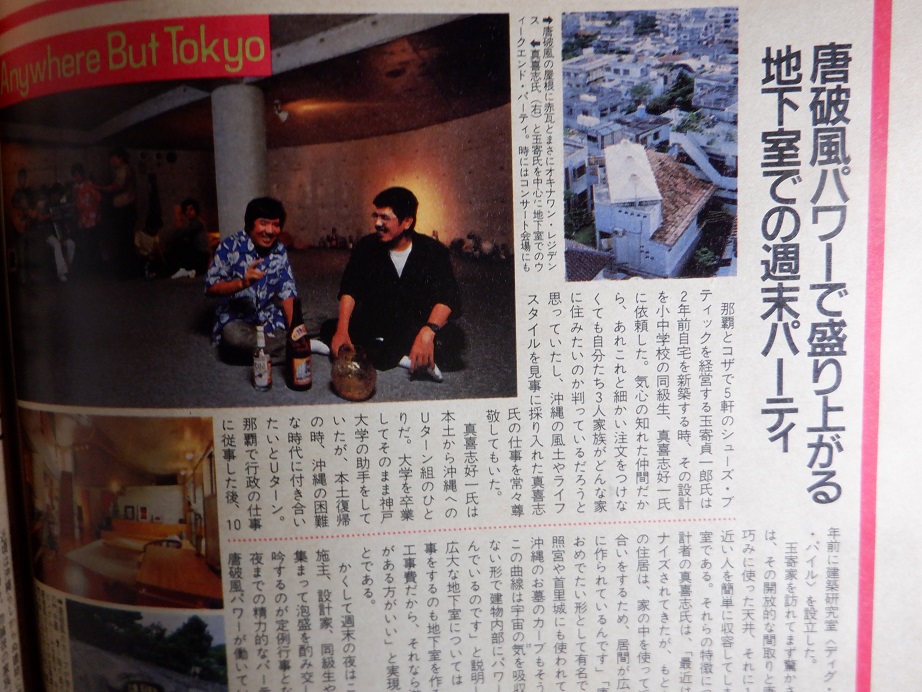
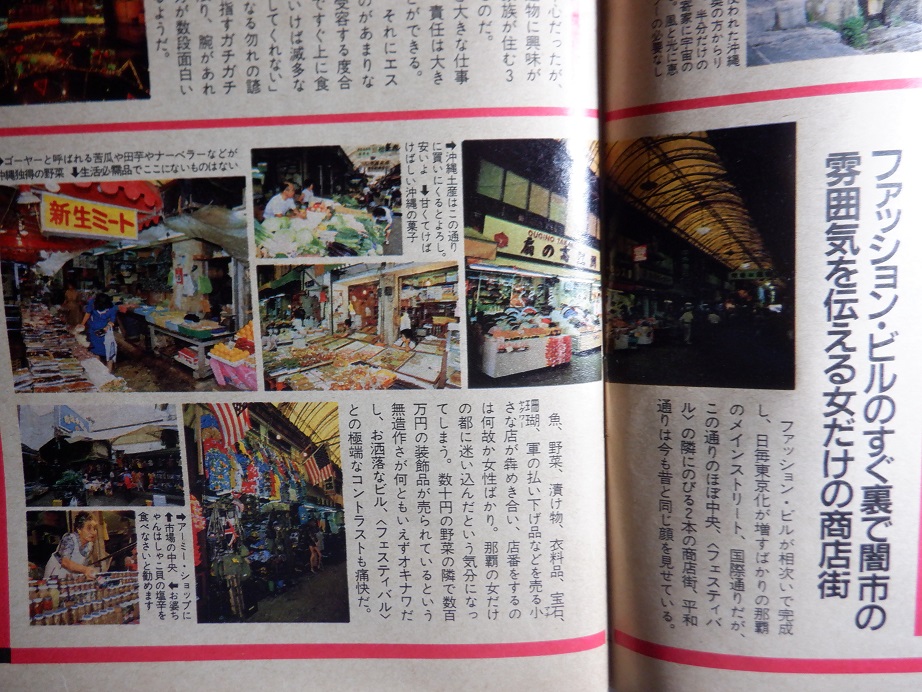
1985年8月那覇 『ブルータス』「東京脱出!ー東京をこよなく愛する我々だが、汚染、住宅難、通勤地獄には我慢ができない。那覇(真久田正・真喜志好一、玉寄貞一郎・公設市場)/福岡/松山/金沢/広島/名古屋/札幌/」
◇1980年 - 「ブルータス」創刊。「男として生きる術を心得た、あらゆる男たちのために」が合言葉であった。
1959年 - 「週刊平凡」創刊。
1964年 - 「平凡パンチ」創刊。若者向けの雑誌として一世を風靡する。
1965年 - 「平凡パンチデラックス」(隔月刊)創刊。
1968年 - 「ポケットパンチOh!」(月刊)創刊。
1970年 - 「an・an」創刊。大型女性誌としてスタート。フランスの「エル ELLE」誌と提携した。集英社の「non-no」とともに人気雑誌となる。
1976年 - 「ポパイ」創刊 "Magazine for City Boys"というサブタイトルでスタート。男性週刊誌のさきがけといわれる。
1977年 - 「クロワッサン」創刊。ニューファミリー生活誌として創刊。
1981年 - 「ダカーポ」創刊。「現代」が3時間でわかる情報誌としてスタートした。
1982年 - 「エル・ジャポン」創刊。「Olive」創刊。"Magazine for Romantic Girls"というサブタイトルを使用した。
1983年 - 会社名を「株式会社マガジンハウス」(〒104-8003東京都中央区銀座3丁目13-10)に変更。ニュージャーナリズム誌「鳩よ!」創刊。
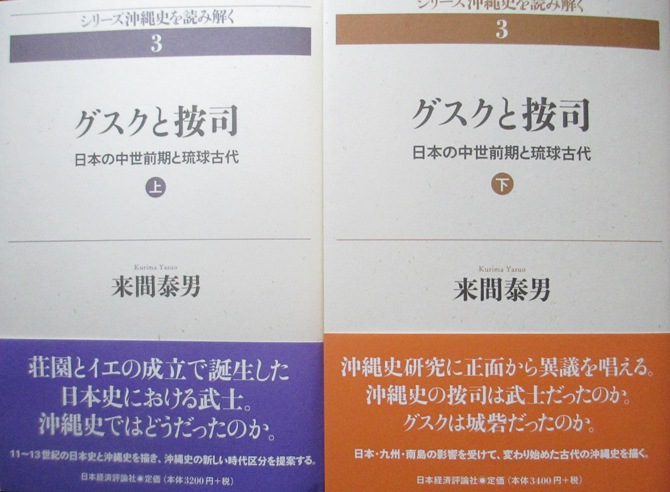
2013年11月 来間泰男『グスクと按司ー日本の中世前期と琉球古代』上下 日本経済評論社(〒101-0051 千代田区神田神保町3-2 電話03-3230-1661/FAX03-3265-2993)
○私は、マルクスの資本主義批判の論理と結果に賛同している。だから大学で四〇年間も「経済原論」(マルクス経済学)の講義を担当してきた。その私は、しかし、「その次に社会主義社会が来る」とは考えない。資本主義に未来はないが、社会主義社会というものは、構想どまりで具体像を描き得ないものである。レーニンも、社会主義をめざした革命を主導したものの、社会主義社会を作る出発点にさえ立てなかった。権力を取ってみてはじめて、社会主義という社会、社会主義経済を基礎ににした社会がどのようなものであるか、初めて考えたような節があるのである。
このことは、社会主義の問題に限らない。帝国主義の植民地支配から脱却して、独立を勝ち取った国々も同じ問題に直面した。独立とは権力を取ることであり、政治を自由に運営するものである。植民地支配から脱却したいというのは、当然の要求である。しかし、経済は自由に運営できるものではない。それはマルクスが論証したように「価値法則」によって一人歩きするものである。アダム・スミスの表現では「見えざる手」によって動くということになる。
□著者は本書で沖縄史の時代区分を提案している。~10世紀ー縄文時代(貝塚時代)、11世紀~14世紀ー琉球古代(沖縄古代)、14世紀~16世紀ー琉球中世(琉球王国時代前期)、17世紀~19世紀ー琉球近世(琉球王国時代後期)、、そして沖縄近代(沖縄県時代)、沖縄現代(米軍占領時代、復活沖縄県時代)へと続くというものである。
○おわりにー(略)私は「沖縄史を読み解い」ていて、いくつかの説に疑問を感じて、それぞれにコメントしてきたが、振り返ってみると、安里進に対する疑問が大きな位置を占めていることに気づく。彼がこの時代について多くを語ってきたからでもある。安里はこれをどのように受け止めるのであろうか。「相対立する学説が、学問的な議論を戦わすことは、学問の進歩にとって必要・不可欠のことである。相互批判を通して自他との{自他のー来間}相違点を明確にするとともに、共通の認識を確認し、これを積み上げて学問の発展に貢献することのあるからだ。その意味で、論争は共同作業だと思う」。これは安里が、金武正紀の批判に答えた時の文章の一節である(『地域と文化』第57号、1990年)。安里が今もこの境地に立っていることを切に願う。
安里への批判は、それを容認し、積極的に受け入れてきた高良倉吉らへの批判に通じる。1980年代以降の沖縄史研究をけん引してきた高良は、沖縄の人びとに勇気と希望を与え、その歴史に自信を持たせたといえる。しかし、それは多くの虚構の上に成り立った「歴史」であった。今回もその一端に触れたが、このシリーズの進行に伴って、さらに明らかになっていくことだろう。(略)
04/07: 世相ジャパン 2024
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@yahoo.co.jp
くろねこの短語5-1(前略)こんな無責任な総括したまま、能登半島はほったらかしで、ヘタレ総理は今日からフランス、パラグアイ、ブラジルへ物見遊山の旅ってんだから、なんともお気楽なものだ。もう帰ってこなけりゃいいのに。
くろねこの短語4-29(前略)今回は低投票率の中でもどうにか立憲と共産の共闘で勝ち抜けたが、解散総選挙となって、同じ低投票率だと統一教会や日本会議、創価学会などの組織票がモノを言うのは間違いない。政権交代がチラつけばチラつくほど、こうした支援団体が総がかりで自公の応援に立ち上がりますからね。
連合の反共会長のように共産アレルギーを野党共闘に待ちこむような愚か者や、第2、第3の自民党を名乗るような維新、国民は切り捨てて、共産、れいわ、社民との野党共闘に立憲は今日から尽力すべきだろう。




4-29 娘、孫たちと沖縄県立博物館・美術館「科学の眼で見る美ら海の生き物展」



4.28 ジュンク堂那覇店 山城智史著『琉球をめぐる十九世紀国際関係史』トークイベント×玉城本生(琉球大学講師)〇川満 昭広さん、玉城本生さん、山城智史さん)
沖縄タイムス4-29 与那国町長、反対意見は「キャンキャンわめいている」 新港建設計画めぐり糸数町長一問一答「発言者は一部に偏っている」
プレジデントオンライン4-27 なぜテレビは万博を「美談」で誤魔化すのか…元テレ東社員が指摘する「大阪万博と東京五輪」の不気味な共通点




4-26雨 首里 数十年振りに県立芸大芸術文化研究所に行く。久万田晋所長が居られ暫しユンタク、近著『沖縄・奄美の島々を彩る歌と踊 民俗芸能の伝統と創造をめぐる旅』ボーダーインクを恵まれた。

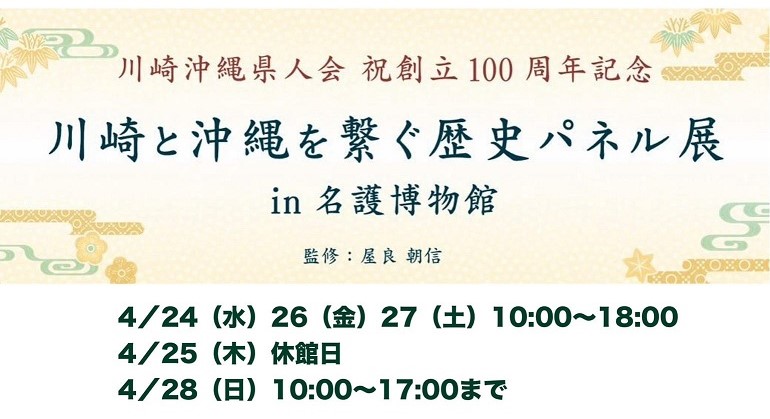

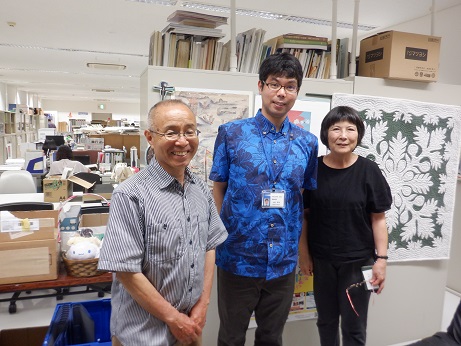
4-23 川崎の屋良朝信さんと沖縄県立博物館・美術館に遊びに行く/屋良朝信さん、大城さゆりさん/屋良朝信さん、大城直也くん、大湾ゆかりさん

いいねうるま市 山城 明 4-22 海中道路駐車場近くのソテツ
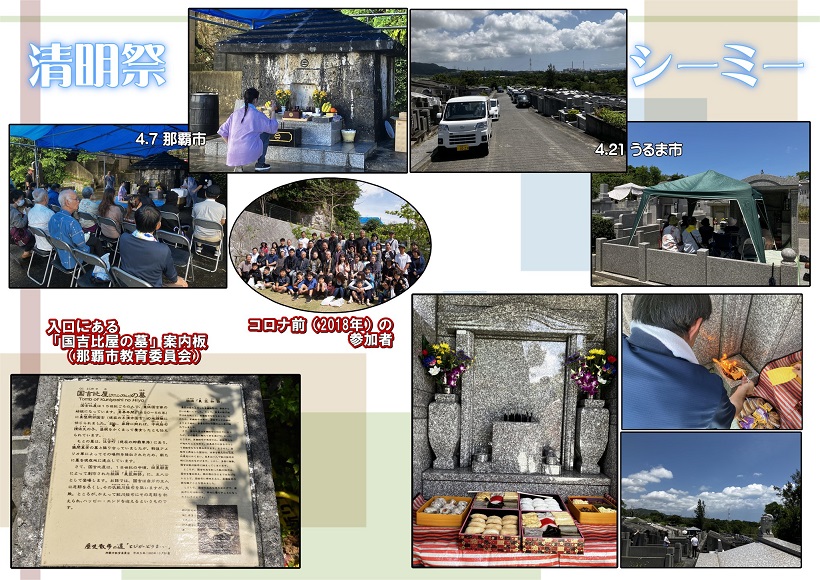
大濱 聡 4-21■4月、沖縄は清明祭(シーミー)のシーズンである。家人の実家は二つのシーミーがある。■第一週は、一世国吉真元(比屋)公(1400年代の人とされる。討死した勝連城主・護佐丸の三男を匿って育てた)に連なる国吉門中の子孫が全島各地から参加して行われる。■大濱家のような八重山、宮古、本島北部地域では、旧暦1月16日に「十六日祭」(後世〈グソー・あの世〉のお正月)として行われる。沖縄の祖先崇拝は根強く、脈々と子孫に受け継がれている。
関連/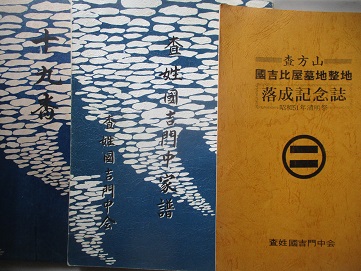
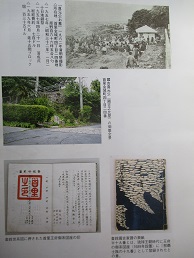
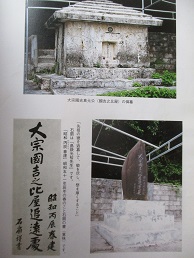
査氏系図(復刻)
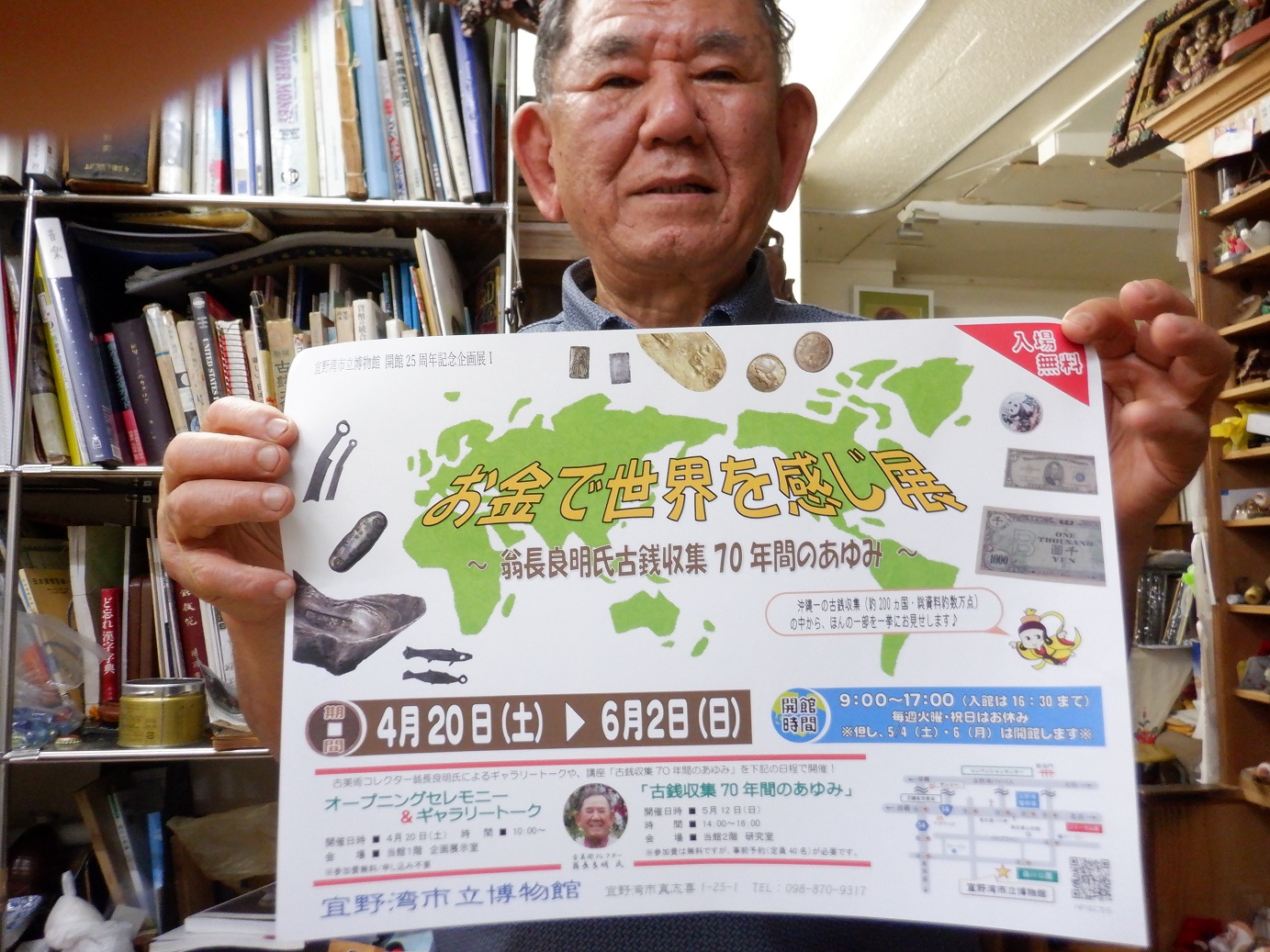
4月20日~6月2日 宜野湾市立博物館「お金で世界を感じ展~翁長良明氏古銭収集70年間のあゆみ」


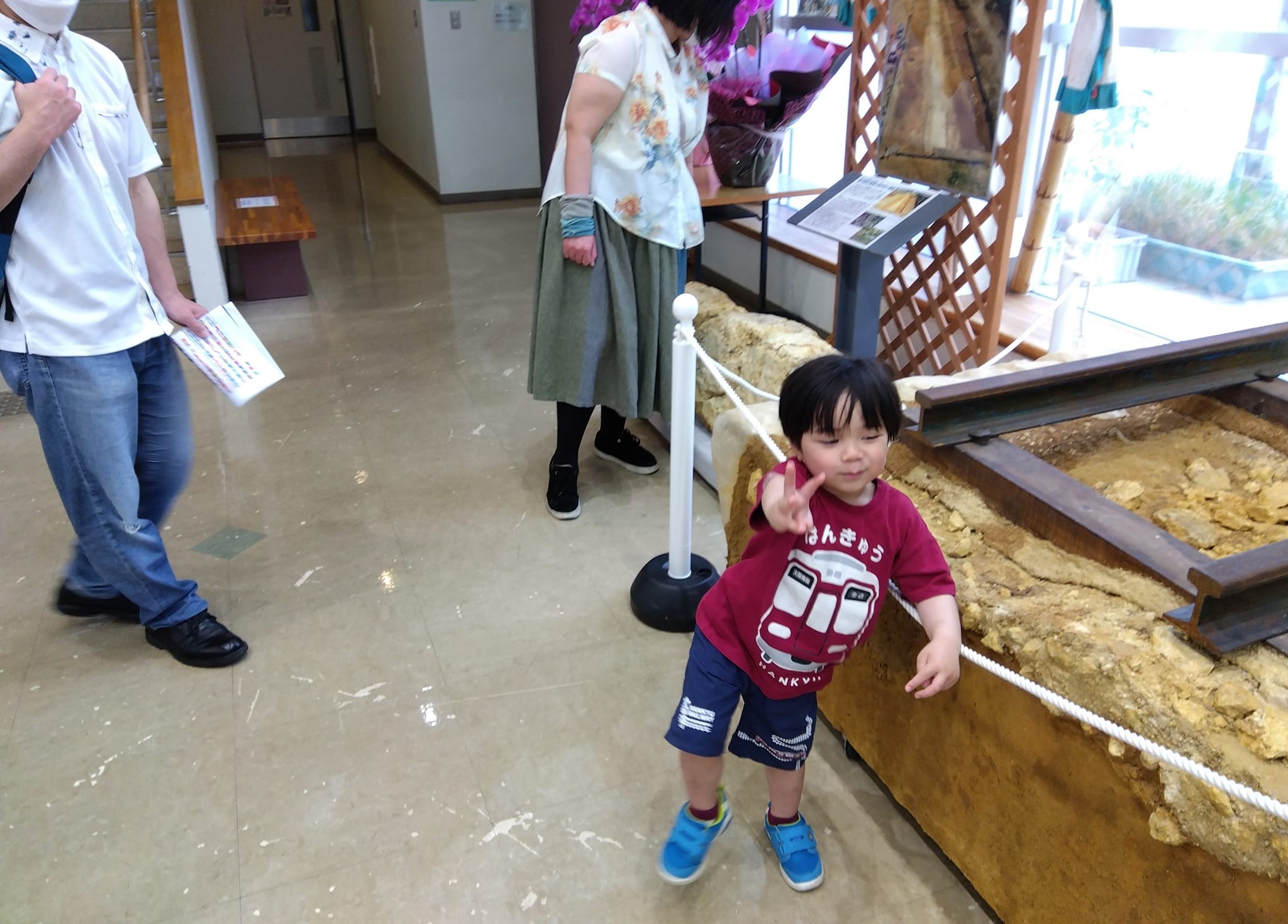

2024年4月20日 宜野湾市立博物館「お金で世界を感じ展〜翁長良明氏古銭収集70年間のあゆみ」テ一プカット/左から平敷兼哉宜野湾市立博物館館長、翁長良明さん、宜野湾市教育委員会・崎間賢氏


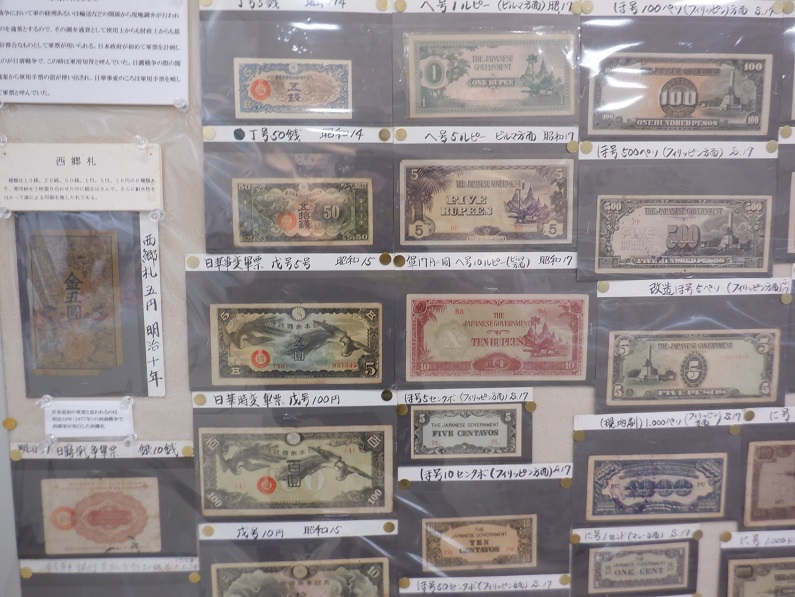




思い出/2004年8月、翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」/真喜志康忠優を囲んで左から新城栄徳、翁長良明さん、真喜志康徳さん



仲松 健雄 東京八重山郷友連合会が主催する『第24回 東京八重山まつり』に参加
東京八重山郷友連合会は、八重山の各地区、各島々の12の郷友会で組織され「八重山はひとつ」の掛け声の下、2000年に発足✨




4-19 こうた、あけみさん


座喜味城は、琉球王国が、日本、中国、東南アジア諸国との交易を通して繁栄した十五世紀初頭、築城の名人と言われた読谷山按司護佐丸によって築かれたと言われています。標高120m余の丘陵地に立地しており、最も高いところからは読谷村のほぼ全域を眺望することが出来ます。(読谷村観光協会)/金武宮『琉球国由来記 巻11 密門諸寺縁起』の〔金峰山観音寺〕の段にある「金峰山補陀落院観音寺縁起」には観音寺の開基について記してあるが、それによれば補陀落山を求めて渡来した日秀上人が、尚清王の御代の嘉靖年間に琉球王国内を行脚し、この地にあった洞窟を霊跡として宮を建て、自身が彫った三尊を権現正体として崇め奉ったとしている。ウィキ


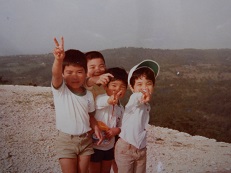
思い出/楚辺の子供と座喜味城址で遊ぶ息子と娘


2024年春 布施の公園 新城こうた
DIME 4-15 Preplyはこのほど、「マナーが悪い都市」に関する調査結果を発表した。本調査は、全国47都道府県に在住する16~55歳の男女2,008人を対象に「自身が住む都市はマナーが悪いと感じるか」「マナーが悪いと感じる行動は何か」など、マナー違反の実態に関するアンケートを実施し、調査結果をランキング形式でまとめたものだ。
マナーが悪い都市ランキングにおいて1位は、2位以下を大きく引き離して大阪が圧倒的な票を集めた。以下、2位が東京、3位が青森、4位が横浜、5位がさいたまと続いた。大阪は日本国内でも特に個性的な文化を持つ地域であり、その豊かな文化や歴史、人々の開放性などが、外から見ると「マナーが悪い」と捉えられることもあるかもしれない。

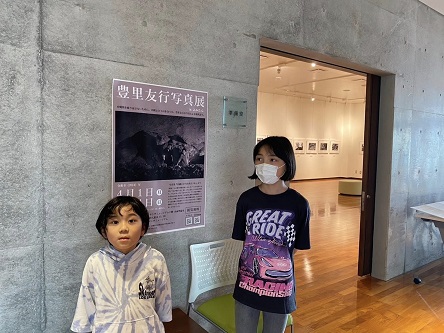
4-14 孫たちユンタンザミュージアム「豊里友行写真展inよみたん」

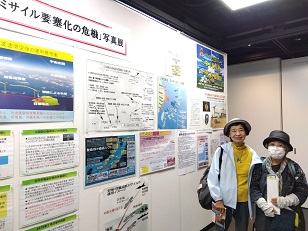

4月14日 新報ギャラリー「南西諸島ミサイル要塞化写真展」/1979年に詩集「海岸線」で山之口貘賞受賞の芝憲子さん、仲宗根さん






仲松 健雄『第19回 関東伊平屋会のつどい』日本教育会館9F 喜山倶楽部で開催/伊平屋会役員紹介/伊平屋村幹部



仲松 健雄『重田辰弥さん とぅしびーを祝う会』(一社)関東沖縄経営者協会7代目会長を務めた重田辰弥さん(現:顧問)が、4月12日に84歳の誕生日を迎えました㊗️数えで85歳のとぅしびー(生年)となります,沖縄の習わしで、とぅしびーには無病息災を願い、長寿を祝う意味があります✨重田辰弥さん「とぅしびー祝い」は、東京ドームホテル4階にある「京料理 熊魚庵 たん熊北店」で開催され、有志23名が参加、美味しい懐石料理をいただきながら、和気藹々と楽しい時間を過ごしました❗️参加者全員からお祝いの言葉とお花を送り 重田さんの益々のご健勝とご活躍をお祈りしました。
くろねこの短語5-1(前略)こんな無責任な総括したまま、能登半島はほったらかしで、ヘタレ総理は今日からフランス、パラグアイ、ブラジルへ物見遊山の旅ってんだから、なんともお気楽なものだ。もう帰ってこなけりゃいいのに。
くろねこの短語4-29(前略)今回は低投票率の中でもどうにか立憲と共産の共闘で勝ち抜けたが、解散総選挙となって、同じ低投票率だと統一教会や日本会議、創価学会などの組織票がモノを言うのは間違いない。政権交代がチラつけばチラつくほど、こうした支援団体が総がかりで自公の応援に立ち上がりますからね。
連合の反共会長のように共産アレルギーを野党共闘に待ちこむような愚か者や、第2、第3の自民党を名乗るような維新、国民は切り捨てて、共産、れいわ、社民との野党共闘に立憲は今日から尽力すべきだろう。




4-29 娘、孫たちと沖縄県立博物館・美術館「科学の眼で見る美ら海の生き物展」



4.28 ジュンク堂那覇店 山城智史著『琉球をめぐる十九世紀国際関係史』トークイベント×玉城本生(琉球大学講師)〇川満 昭広さん、玉城本生さん、山城智史さん)
沖縄タイムス4-29 与那国町長、反対意見は「キャンキャンわめいている」 新港建設計画めぐり糸数町長一問一答「発言者は一部に偏っている」
プレジデントオンライン4-27 なぜテレビは万博を「美談」で誤魔化すのか…元テレ東社員が指摘する「大阪万博と東京五輪」の不気味な共通点




4-26雨 首里 数十年振りに県立芸大芸術文化研究所に行く。久万田晋所長が居られ暫しユンタク、近著『沖縄・奄美の島々を彩る歌と踊 民俗芸能の伝統と創造をめぐる旅』ボーダーインクを恵まれた。

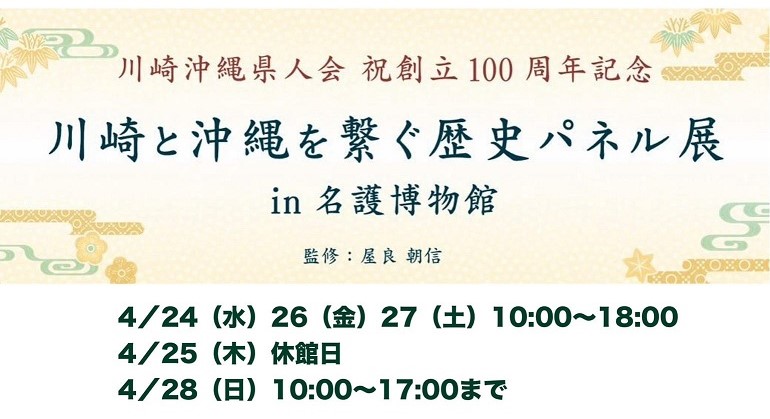

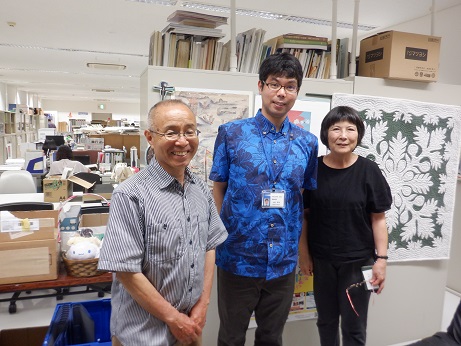
4-23 川崎の屋良朝信さんと沖縄県立博物館・美術館に遊びに行く/屋良朝信さん、大城さゆりさん/屋良朝信さん、大城直也くん、大湾ゆかりさん

いいねうるま市 山城 明 4-22 海中道路駐車場近くのソテツ
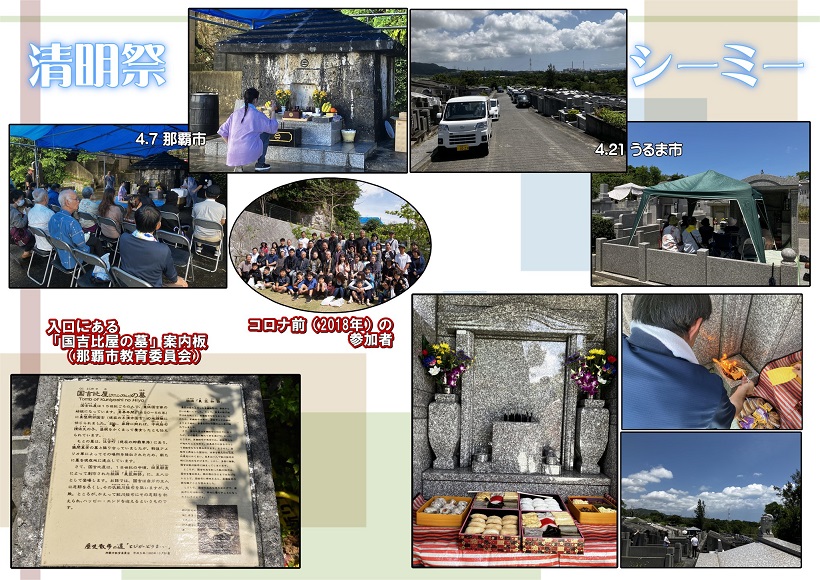
大濱 聡 4-21■4月、沖縄は清明祭(シーミー)のシーズンである。家人の実家は二つのシーミーがある。■第一週は、一世国吉真元(比屋)公(1400年代の人とされる。討死した勝連城主・護佐丸の三男を匿って育てた)に連なる国吉門中の子孫が全島各地から参加して行われる。■大濱家のような八重山、宮古、本島北部地域では、旧暦1月16日に「十六日祭」(後世〈グソー・あの世〉のお正月)として行われる。沖縄の祖先崇拝は根強く、脈々と子孫に受け継がれている。
関連/
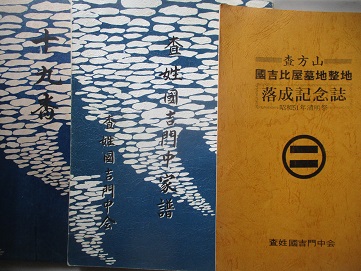
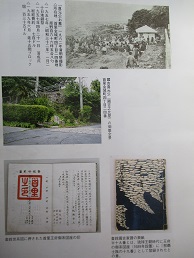
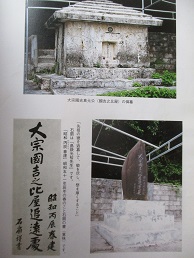
査氏系図(復刻)
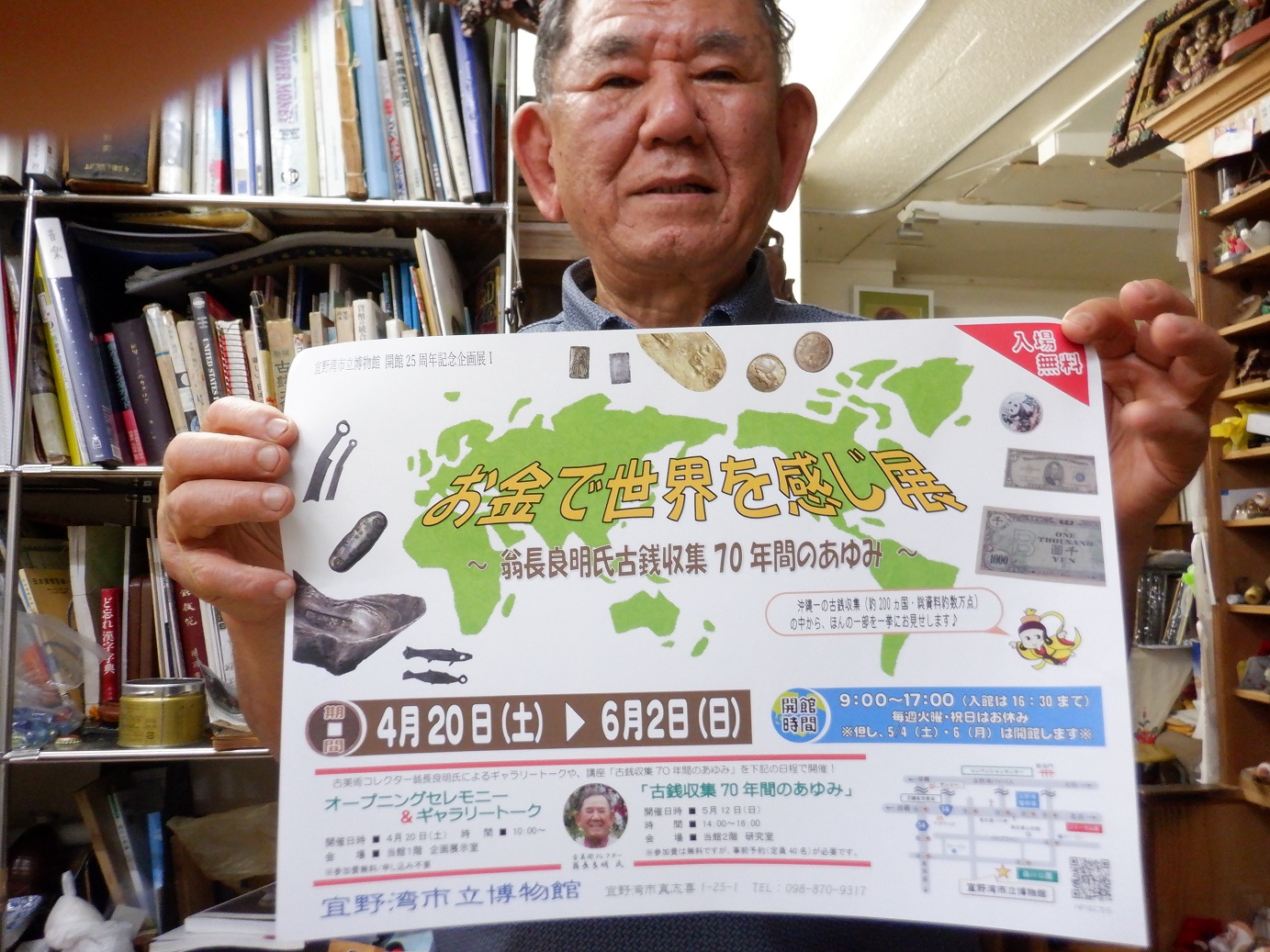
4月20日~6月2日 宜野湾市立博物館「お金で世界を感じ展~翁長良明氏古銭収集70年間のあゆみ」


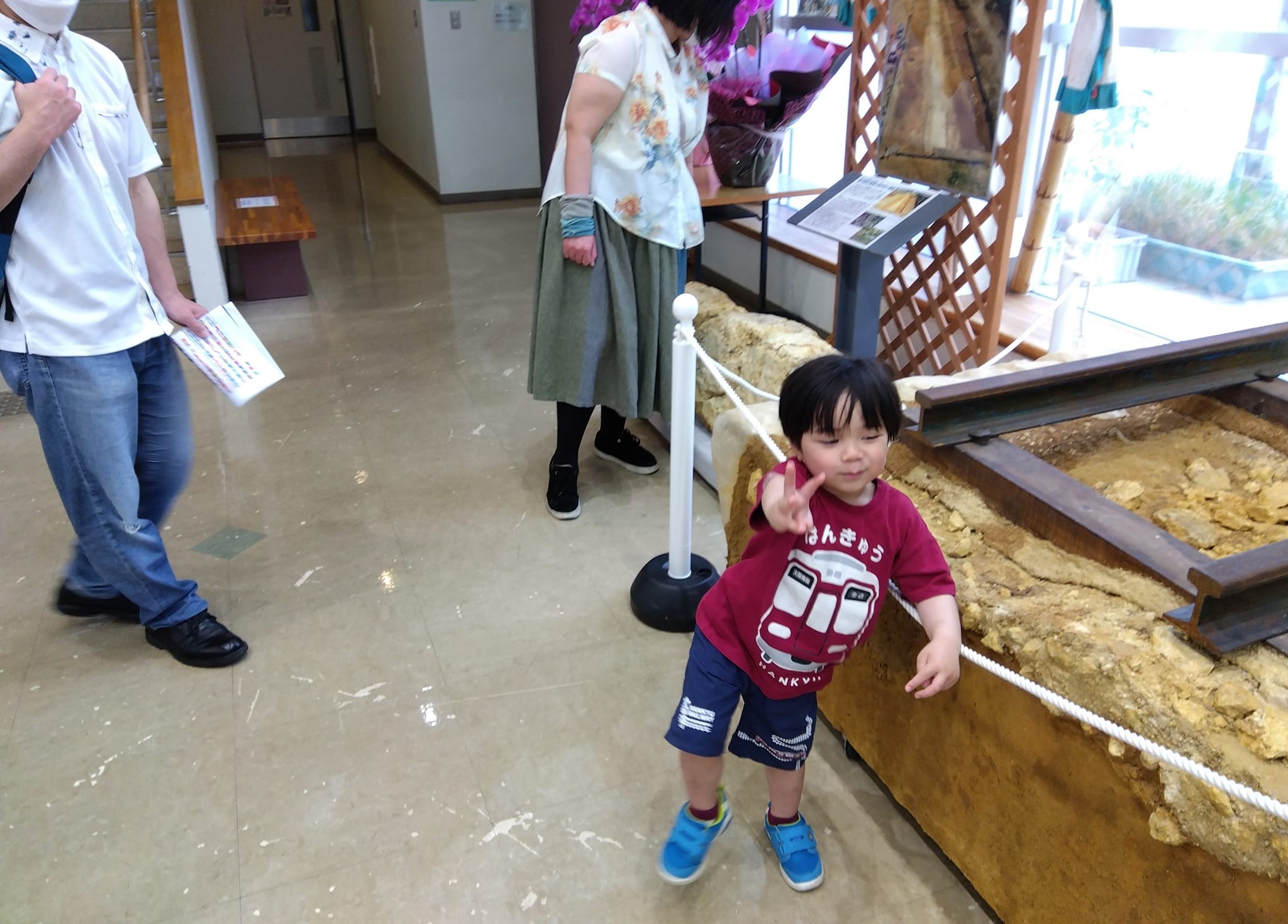

2024年4月20日 宜野湾市立博物館「お金で世界を感じ展〜翁長良明氏古銭収集70年間のあゆみ」テ一プカット/左から平敷兼哉宜野湾市立博物館館長、翁長良明さん、宜野湾市教育委員会・崎間賢氏


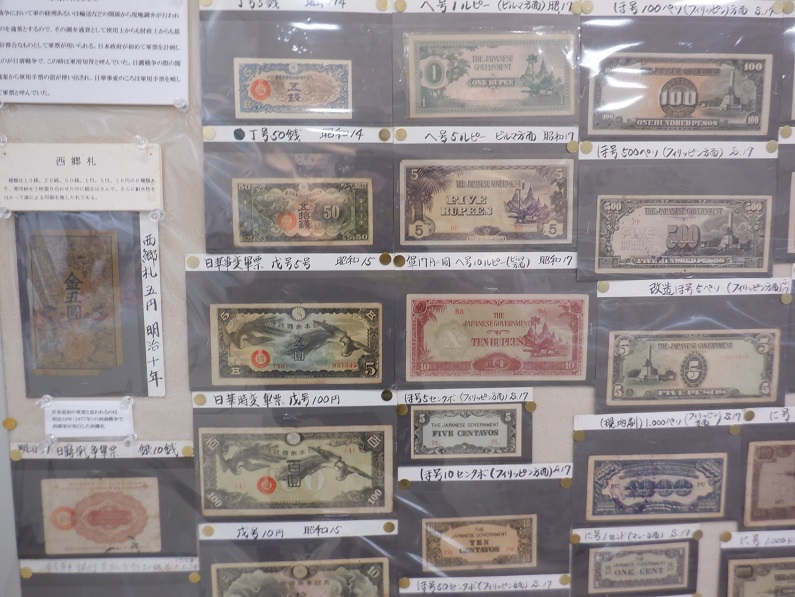




思い出/2004年8月、翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」/真喜志康忠優を囲んで左から新城栄徳、翁長良明さん、真喜志康徳さん



仲松 健雄 東京八重山郷友連合会が主催する『第24回 東京八重山まつり』に参加
東京八重山郷友連合会は、八重山の各地区、各島々の12の郷友会で組織され「八重山はひとつ」の掛け声の下、2000年に発足✨




4-19 こうた、あけみさん


座喜味城は、琉球王国が、日本、中国、東南アジア諸国との交易を通して繁栄した十五世紀初頭、築城の名人と言われた読谷山按司護佐丸によって築かれたと言われています。標高120m余の丘陵地に立地しており、最も高いところからは読谷村のほぼ全域を眺望することが出来ます。(読谷村観光協会)/金武宮『琉球国由来記 巻11 密門諸寺縁起』の〔金峰山観音寺〕の段にある「金峰山補陀落院観音寺縁起」には観音寺の開基について記してあるが、それによれば補陀落山を求めて渡来した日秀上人が、尚清王の御代の嘉靖年間に琉球王国内を行脚し、この地にあった洞窟を霊跡として宮を建て、自身が彫った三尊を権現正体として崇め奉ったとしている。ウィキ


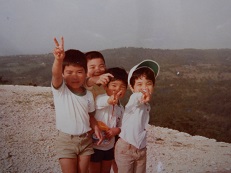
思い出/楚辺の子供と座喜味城址で遊ぶ息子と娘


2024年春 布施の公園 新城こうた
DIME 4-15 Preplyはこのほど、「マナーが悪い都市」に関する調査結果を発表した。本調査は、全国47都道府県に在住する16~55歳の男女2,008人を対象に「自身が住む都市はマナーが悪いと感じるか」「マナーが悪いと感じる行動は何か」など、マナー違反の実態に関するアンケートを実施し、調査結果をランキング形式でまとめたものだ。
マナーが悪い都市ランキングにおいて1位は、2位以下を大きく引き離して大阪が圧倒的な票を集めた。以下、2位が東京、3位が青森、4位が横浜、5位がさいたまと続いた。大阪は日本国内でも特に個性的な文化を持つ地域であり、その豊かな文化や歴史、人々の開放性などが、外から見ると「マナーが悪い」と捉えられることもあるかもしれない。

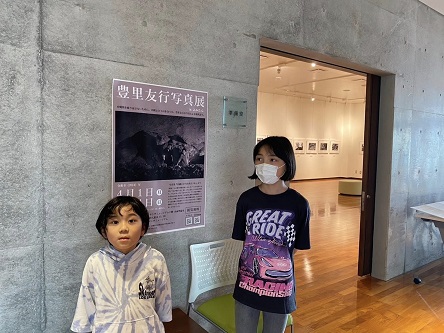
4-14 孫たちユンタンザミュージアム「豊里友行写真展inよみたん」

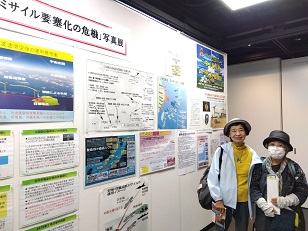

4月14日 新報ギャラリー「南西諸島ミサイル要塞化写真展」/1979年に詩集「海岸線」で山之口貘賞受賞の芝憲子さん、仲宗根さん






仲松 健雄『第19回 関東伊平屋会のつどい』日本教育会館9F 喜山倶楽部で開催/伊平屋会役員紹介/伊平屋村幹部



仲松 健雄『重田辰弥さん とぅしびーを祝う会』(一社)関東沖縄経営者協会7代目会長を務めた重田辰弥さん(現:顧問)が、4月12日に84歳の誕生日を迎えました㊗️数えで85歳のとぅしびー(生年)となります,沖縄の習わしで、とぅしびーには無病息災を願い、長寿を祝う意味があります✨重田辰弥さん「とぅしびー祝い」は、東京ドームホテル4階にある「京料理 熊魚庵 たん熊北店」で開催され、有志23名が参加、美味しい懐石料理をいただきながら、和気藹々と楽しい時間を過ごしました❗️参加者全員からお祝いの言葉とお花を送り 重田さんの益々のご健勝とご活躍をお祈りしました。
10/27: 世相ジャパン 2024
コメントはメールにお願いします→shinjo8109@yahoo.co.jp



11月3日 奥にジュンク堂書店那覇店、手前にミハイル・ゴルバチョフの手形/ジュンク堂前で一箱古本市、ジュンク堂の森本 浩平さん/沖縄県立博物館・美術館で「おきみゅー誕生祭」中村理乃さん,儀保ゆかりさん



11月3日 那覇市民ギャラリー:知念かねみ写真展、増川 陽子さん、知念かねみさん/金城進絵画展、金城進氏/金城明一絵画展、左から松本晴文氏、赤嶺正則氏、金城明一氏、具志喜三氏

11-2 真栄里泰山「琉球王国まつりのパレードに、まみどうま(真美童マ)が出演」
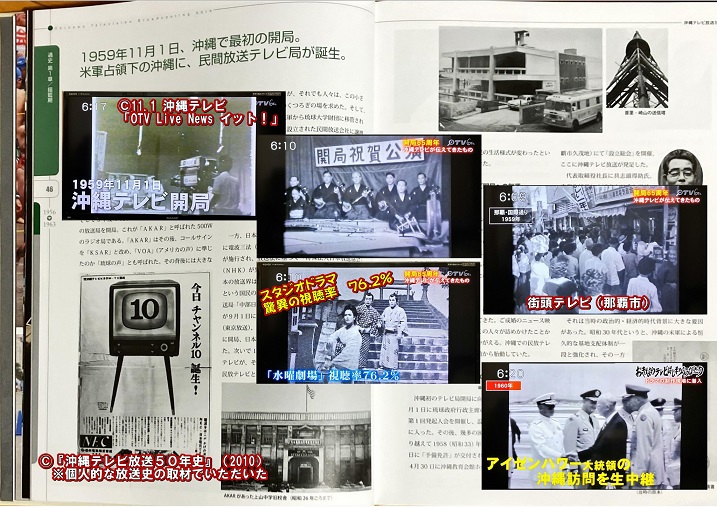
大濱 聡 11-1 ■本日、OTV沖縄テレビ(FNN系列)が開局65周年を迎えた。1959年11月1日、私が小学5年生の時で、沖縄にまだNHKは開局(前身のOHKは1967年開局)してなかったので、沖縄初のテレビ局の誕生であった。我が家にはTVがなかったので、向かいの遊び仲間のN君、K君の家で見せてもらっていた。■OTV開局から5年後、本土~沖縄間のマイクロ回線が開通、本土と同じ番組が同時に見られるようになった。OHKが開局するまで、連続テレビ小説、大河ドラマ、「紅白歌合戦」もOTVで放送(CM入り)されていた。■我が家にTVが入ったのは高校2年の時だったが、高価で買えなかったので電気屋さんの「貸しテレビ」(レンタルという表現はなかった)だった。私がTV(14吋、白黒)を購入したのは上京して1年後の1968年、19歳の時だった。
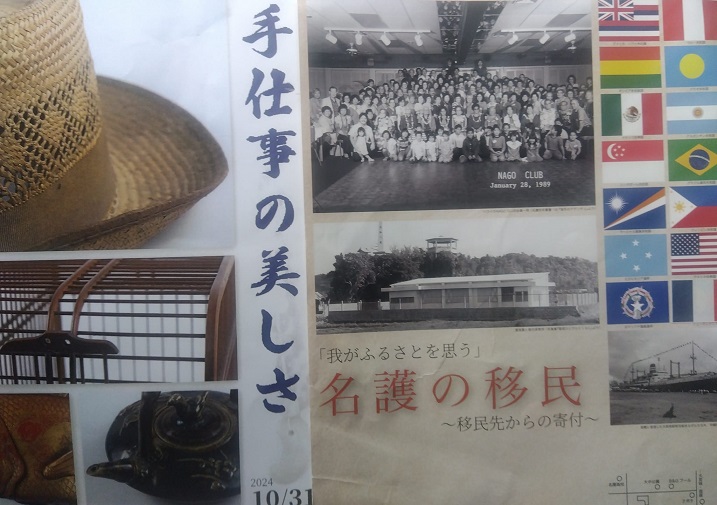







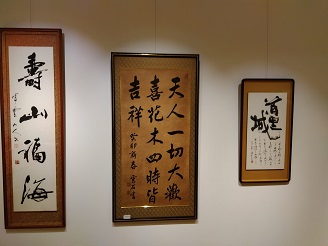





10月31日〜(11月4日、5日は休み)11月 7日 名護博物館ギャラリー「翁長良明コレクション展/手仕事の美しさ」仲里康秀さん、翁長さん、上原さん/名護博物館の田仲康嗣氏、翁長さん、宮城さん/仲里さんが今帰仁に行くというので名護市立図書館まで乗せてもらう。帰りは博物館まで散歩するとスタジオエース、あづま写真館に偶然出会う、フェイスブック友の東さんの親戚。あづま写真館は博物館近くにある。
☆名護のひんぷんガジュマル(ぴんぷんガジマル)名護市大東区 昭和31年(1956)に【県の天然記念物(動物)】に指定された後、平成9年(1997)に【国の天然記念物(植物)】に指定されました。名護市の市街地にあって路上に生育する巨樹で、シンボル的な存在です。樹高19m、推定樹齢は330年です。→名護市役所
異邦人 現行の「健康保険証」について、昨年は「無理に期限に拘るべきではない」という旨の発言をしていた国民民主党の玉木代表だが、いざ自民党に接近し始めるや否や「予定通りやるべき」などと自民党の方針を全面的にアシスト。やはり国民民主党は自民党の補完勢力でしかない。
三上 智恵 10月27日 17:28 · 琉大生が自衛隊の部隊見学?去年に続き山本章子准教授が引率ゼミ生を連れて行った山本章子さんは沖縄県に政策提言をする万国津梁会議のメンバーでも防衛省サイドに近すぎる人という印象を持っています



11月3日 奥にジュンク堂書店那覇店、手前にミハイル・ゴルバチョフの手形/ジュンク堂前で一箱古本市、ジュンク堂の森本 浩平さん/沖縄県立博物館・美術館で「おきみゅー誕生祭」中村理乃さん,儀保ゆかりさん



11月3日 那覇市民ギャラリー:知念かねみ写真展、増川 陽子さん、知念かねみさん/金城進絵画展、金城進氏/金城明一絵画展、左から松本晴文氏、赤嶺正則氏、金城明一氏、具志喜三氏

11-2 真栄里泰山「琉球王国まつりのパレードに、まみどうま(真美童マ)が出演」
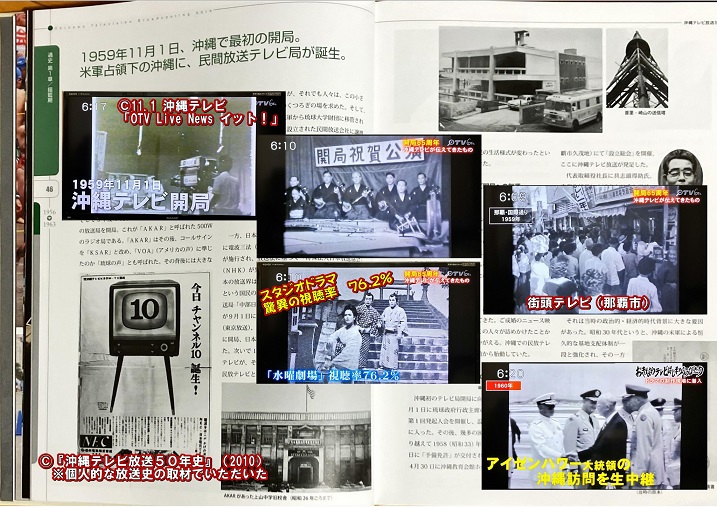
大濱 聡 11-1 ■本日、OTV沖縄テレビ(FNN系列)が開局65周年を迎えた。1959年11月1日、私が小学5年生の時で、沖縄にまだNHKは開局(前身のOHKは1967年開局)してなかったので、沖縄初のテレビ局の誕生であった。我が家にはTVがなかったので、向かいの遊び仲間のN君、K君の家で見せてもらっていた。■OTV開局から5年後、本土~沖縄間のマイクロ回線が開通、本土と同じ番組が同時に見られるようになった。OHKが開局するまで、連続テレビ小説、大河ドラマ、「紅白歌合戦」もOTVで放送(CM入り)されていた。■我が家にTVが入ったのは高校2年の時だったが、高価で買えなかったので電気屋さんの「貸しテレビ」(レンタルという表現はなかった)だった。私がTV(14吋、白黒)を購入したのは上京して1年後の1968年、19歳の時だった。
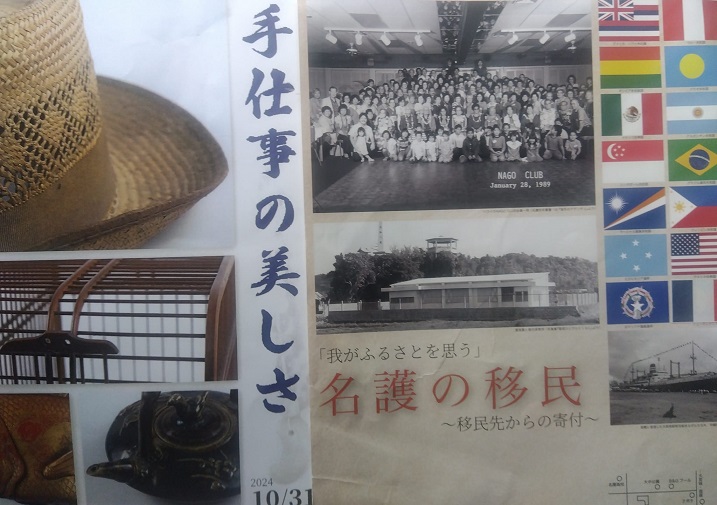







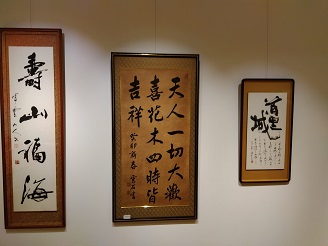





10月31日〜(11月4日、5日は休み)11月 7日 名護博物館ギャラリー「翁長良明コレクション展/手仕事の美しさ」仲里康秀さん、翁長さん、上原さん/名護博物館の田仲康嗣氏、翁長さん、宮城さん/仲里さんが今帰仁に行くというので名護市立図書館まで乗せてもらう。帰りは博物館まで散歩するとスタジオエース、あづま写真館に偶然出会う、フェイスブック友の東さんの親戚。あづま写真館は博物館近くにある。
☆名護のひんぷんガジュマル(ぴんぷんガジマル)名護市大東区 昭和31年(1956)に【県の天然記念物(動物)】に指定された後、平成9年(1997)に【国の天然記念物(植物)】に指定されました。名護市の市街地にあって路上に生育する巨樹で、シンボル的な存在です。樹高19m、推定樹齢は330年です。→名護市役所
異邦人 現行の「健康保険証」について、昨年は「無理に期限に拘るべきではない」という旨の発言をしていた国民民主党の玉木代表だが、いざ自民党に接近し始めるや否や「予定通りやるべき」などと自民党の方針を全面的にアシスト。やはり国民民主党は自民党の補完勢力でしかない。
三上 智恵 10月27日 17:28 · 琉大生が自衛隊の部隊見学?去年に続き山本章子准教授が引率ゼミ生を連れて行った山本章子さんは沖縄県に政策提言をする万国津梁会議のメンバーでも防衛省サイドに近すぎる人という印象を持っています
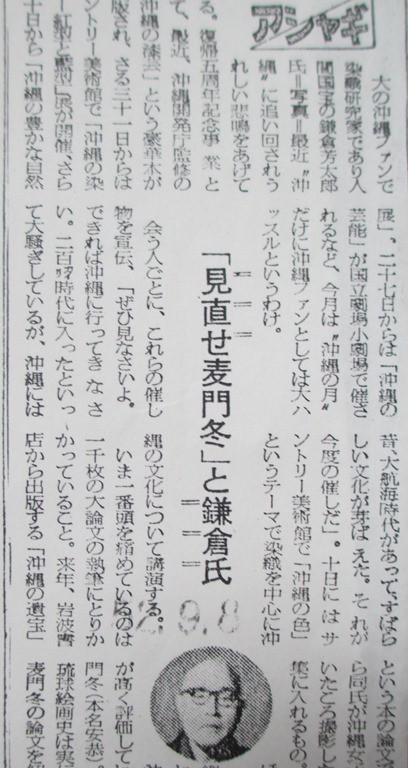
1977年9月8日『琉球新報』「アシャギー『見直せ麦門冬』と鎌倉氏」
1977年 『国語科通信№36』角川書店□鎌倉芳太郎(重要無形文化財<紅型研究>・玉川大学名誉教授)「首里言葉と那覇言葉ー(略)大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、世の中の傾向がデモクラシーの社会運動にゆさぶられている時代であったので、またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育って行った。・・・」
1978-4 『人間国宝シリーズ14 鎌倉芳太郎』講談社
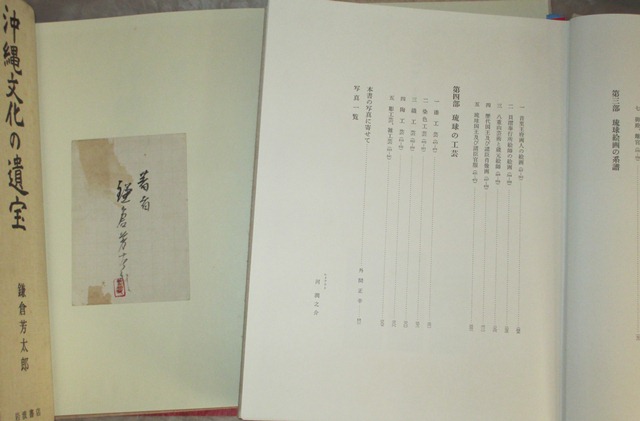
1982-10 鎌倉芳太郎『沖縄文化の遺宝』岩波書店
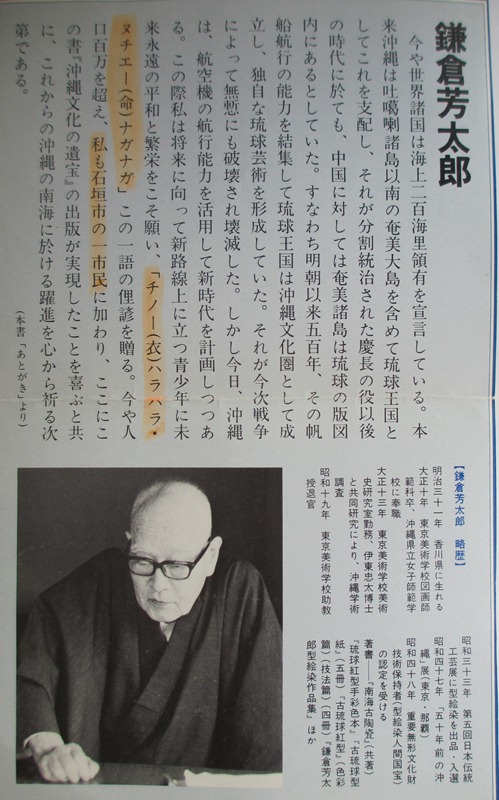
1998年 『沖縄県立博物館紀要』第24号□外間正幸、萩尾俊章「沖縄県立博物館草創期における文化財収集とその背景」
○1、首里博物館の時代 2、日本本土における文化財収集活動ー(1)1958年の文化財収集ー仲原善忠先生と我部政達氏 (2)1959年における文化財収集活動ー森政三氏、神山政良氏、東恩納寛惇先生 (3)1959年~61年の文化財収集ー鎌倉芳太郎先生
2003-9 浦添市美術館「今甦る80年前の沖縄~鎌倉芳太郎の撮った遺宝・風物~」沖縄テレビ・琉球新報社
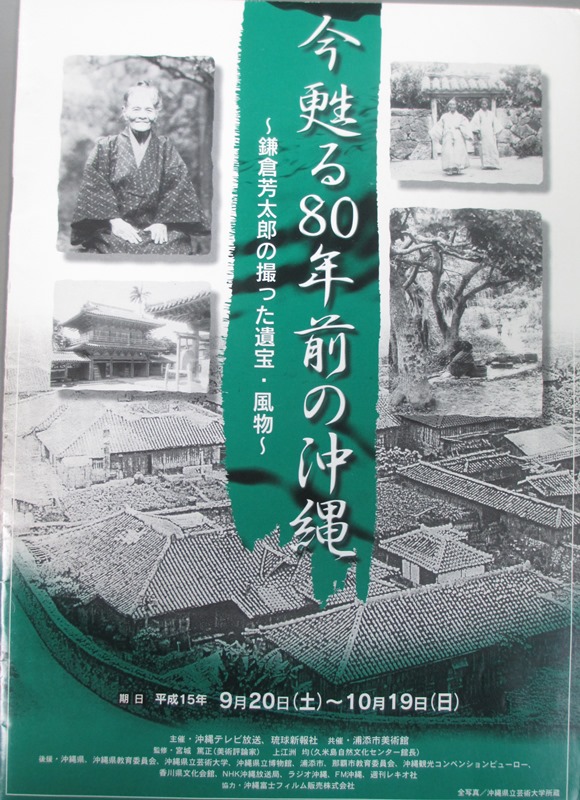
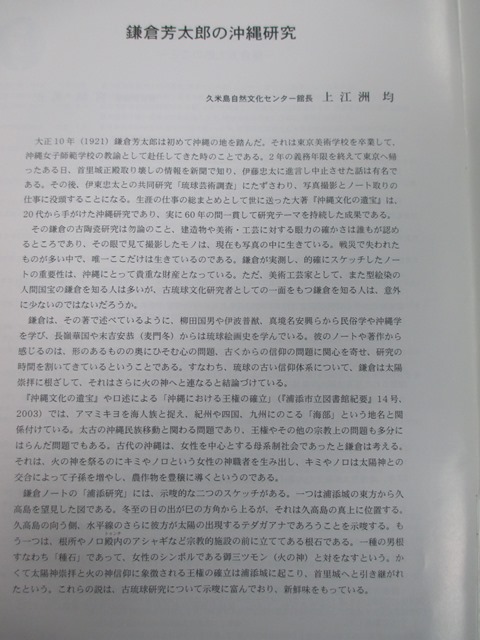
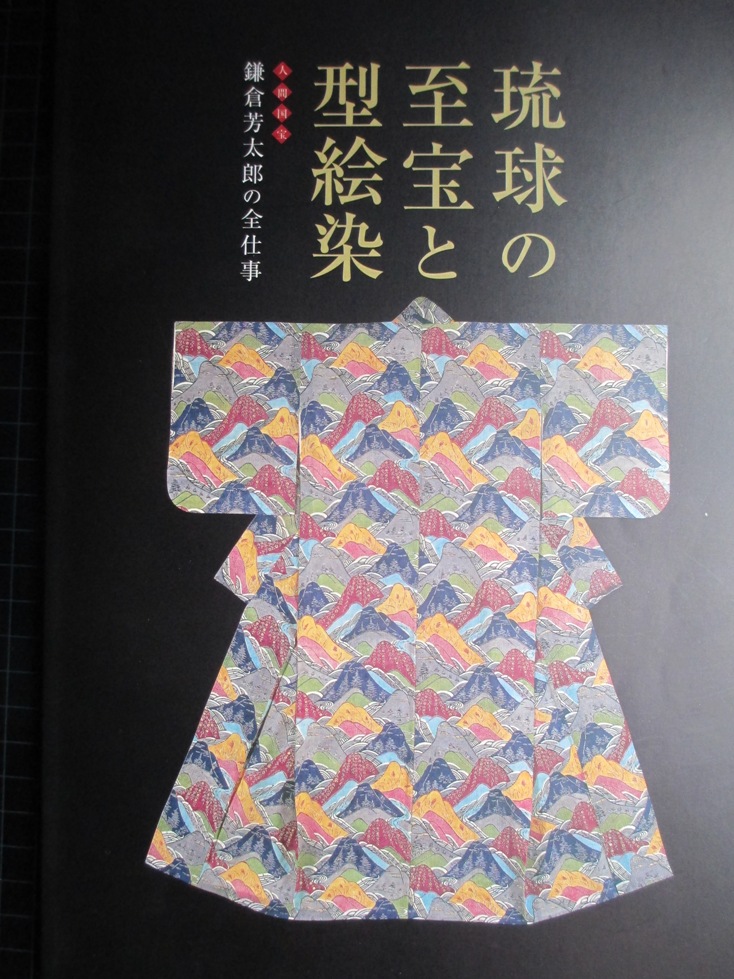
2003-11

2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号/2008年3月『沖縄芸術の科学』第20号
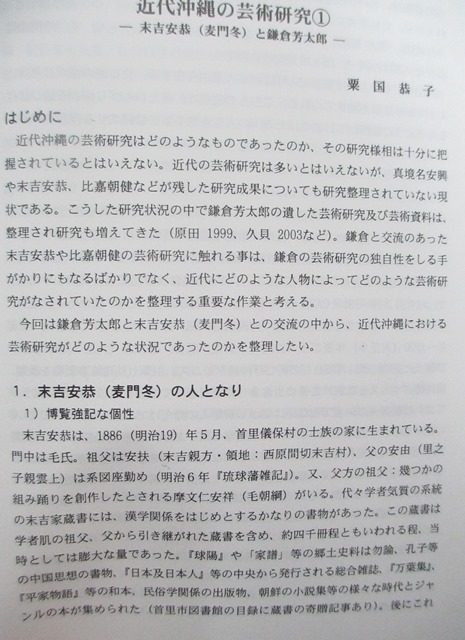
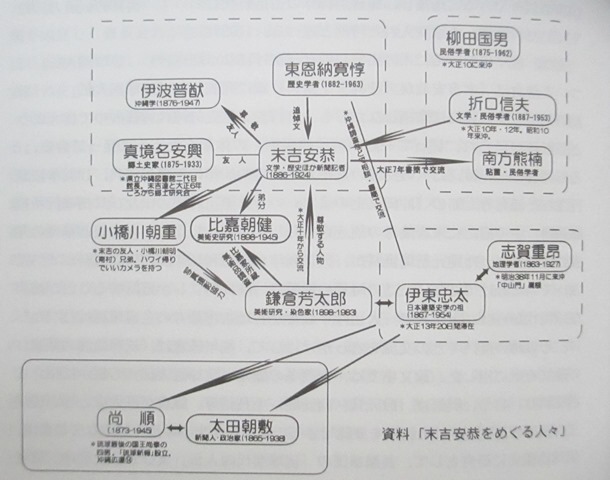
2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号□粟国恭子「近代沖縄の芸術研究①-末吉安恭(麦門冬)と鎌倉芳太郎」