03/03: 日米誌②
1940年1月、在米沖縄県人会『琉球』7号□幸地新政「太平洋の危機と在米同胞ー第一次世界大戦の終わりと共に、来るべき世界制覇の舞台は、周知の如く太平洋に移動したのである。(略)若し、日米間に万一のことがあれば、その直接の発火点は疑いもなく蘭印問題であろう。(略)米国政府は1939年7月26日に日本政府に向かって日米通商航海条約の廃止を通告した。これは日支事変に対する米国の日本への抗議の一形態であり、さらに軍需品禁輸断行の事前工作である。米国にも日米開戦論があると同時に又、日米非戦論即ち日米親善論も決して侮るべからざるものを内包している」


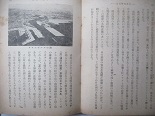
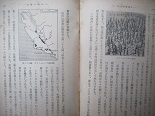
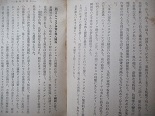
1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。
アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)
1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官
1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。
□731部隊 - Wikipediaja
初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。
原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)
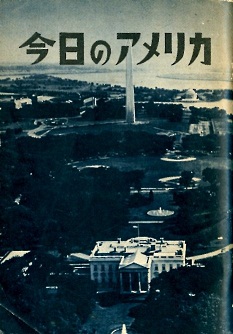

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年
1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ
1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸
1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ
1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。
1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」
1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)
1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」
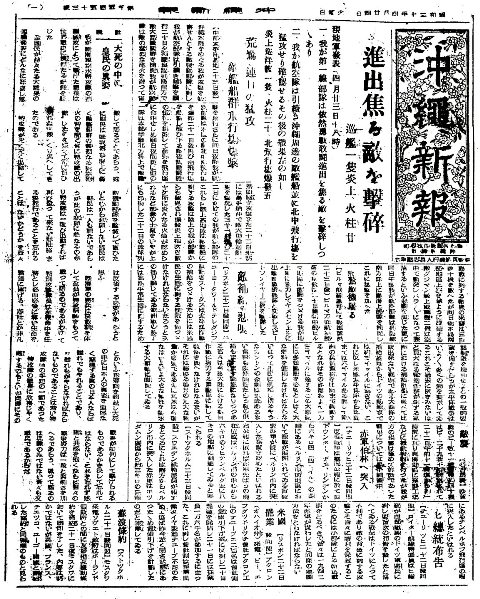
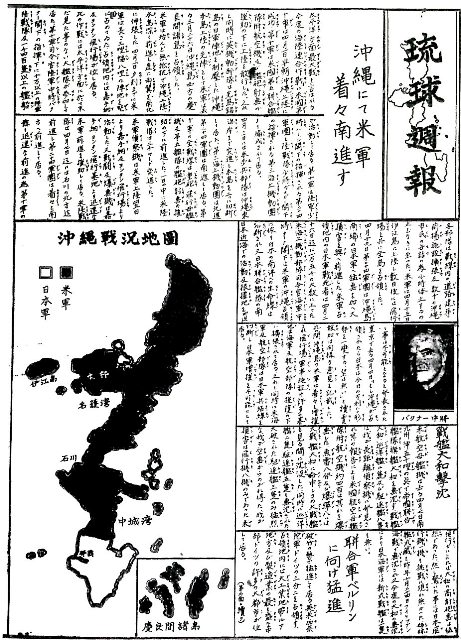
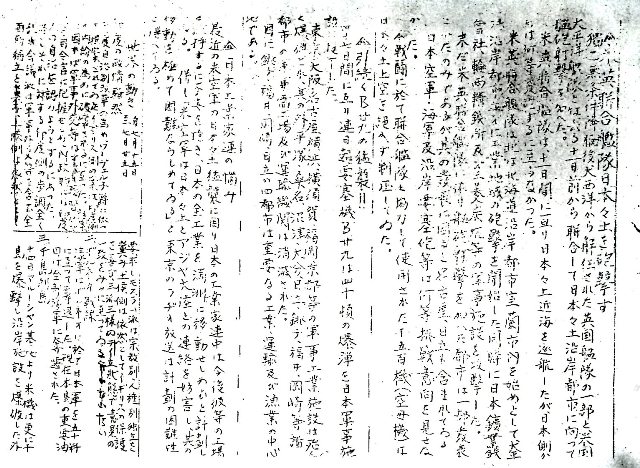
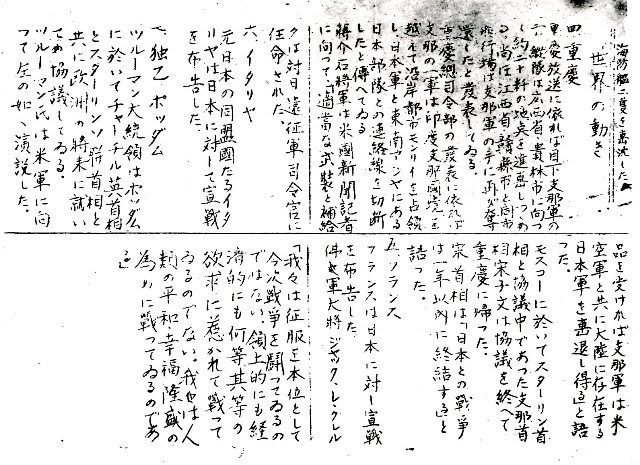
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア
1945年5月7日 石川に城前初等学校開校
1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」
1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動
1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」
1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人
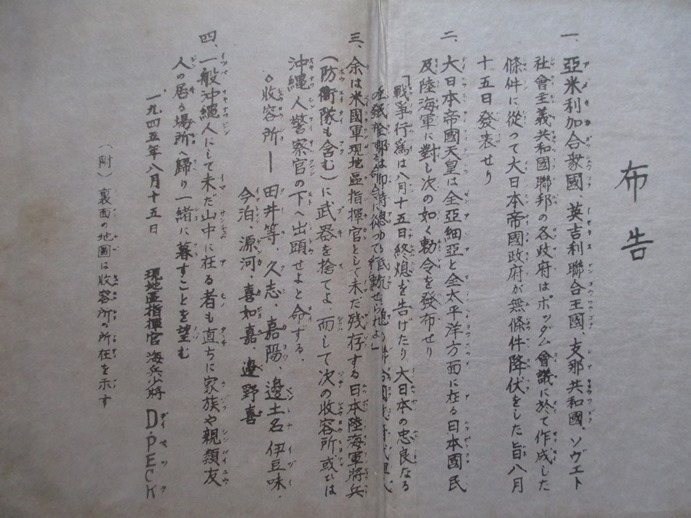
1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」
1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」
1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足
1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」
1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)
1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」
1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」
NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。
ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ
参考資料ー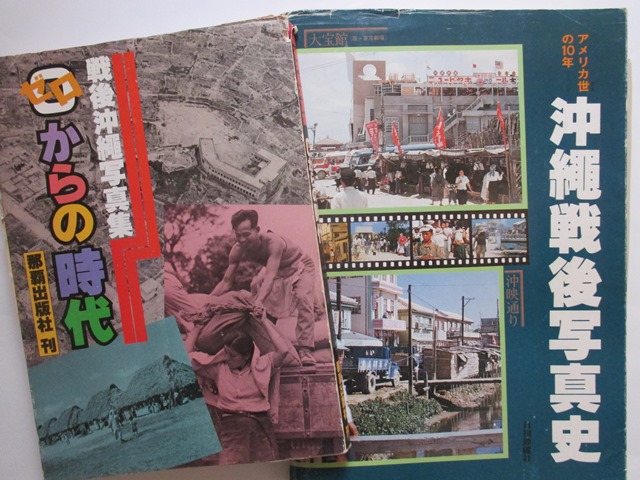
1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社
2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」
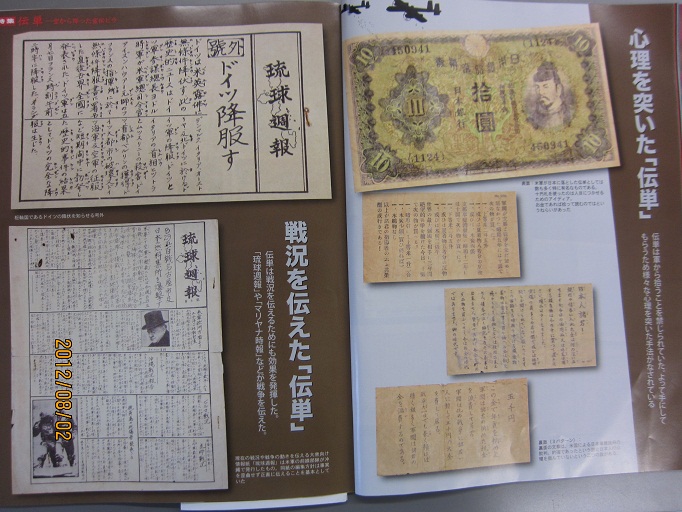
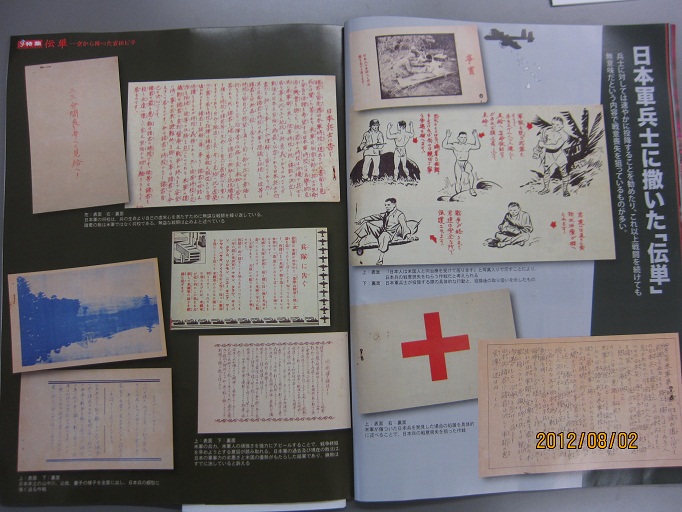
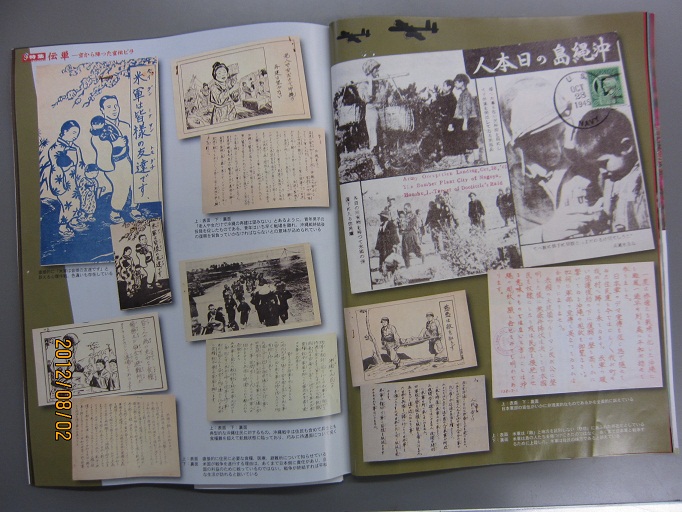
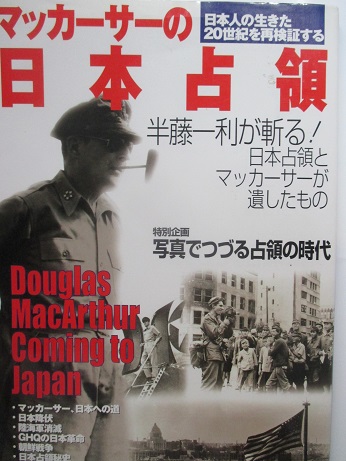
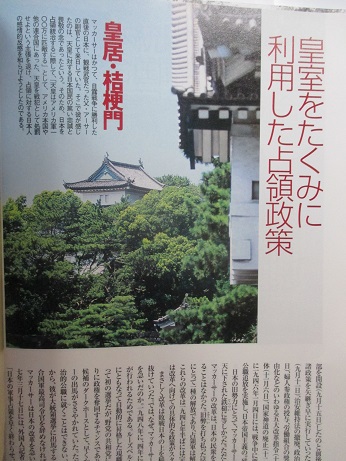
2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社
マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月
。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)
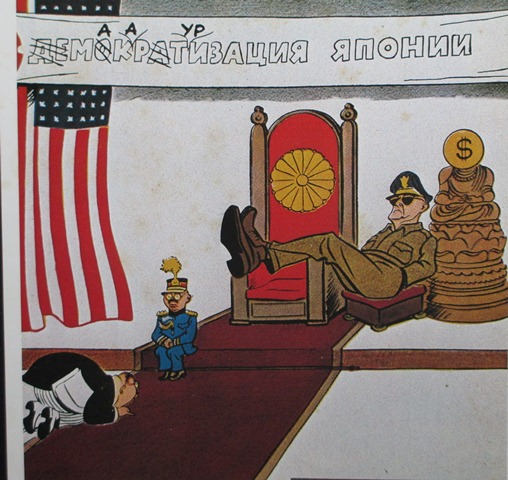
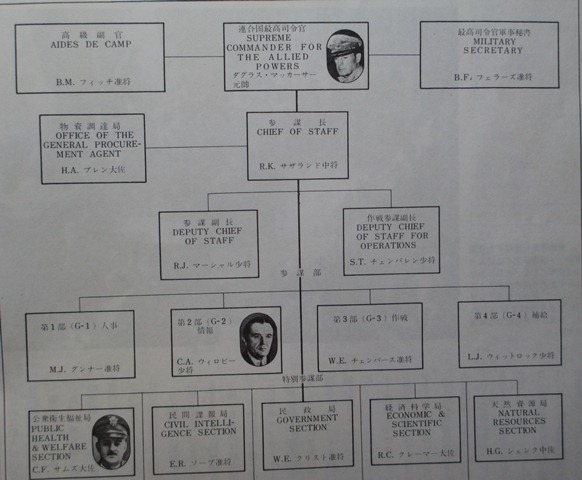
○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。
1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。
1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。
石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。
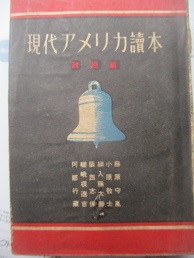
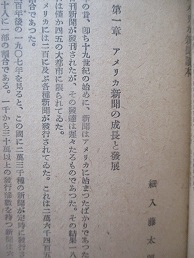

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」
1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ
1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺
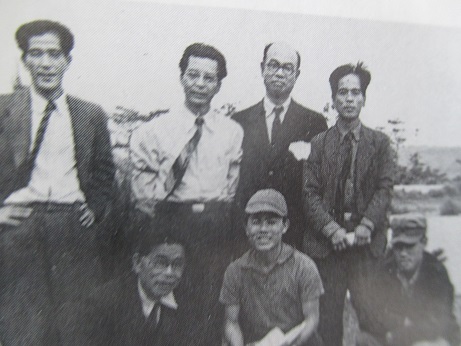
1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝


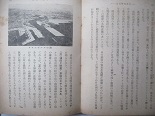
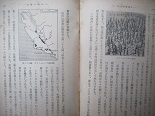
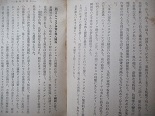
1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。
アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)
1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官
1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。
□731部隊 - Wikipediaja
初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。
原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)
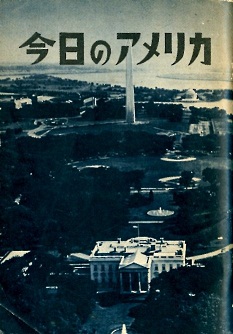

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年
1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ
1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸
1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ
1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。
1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」
1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)
1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」
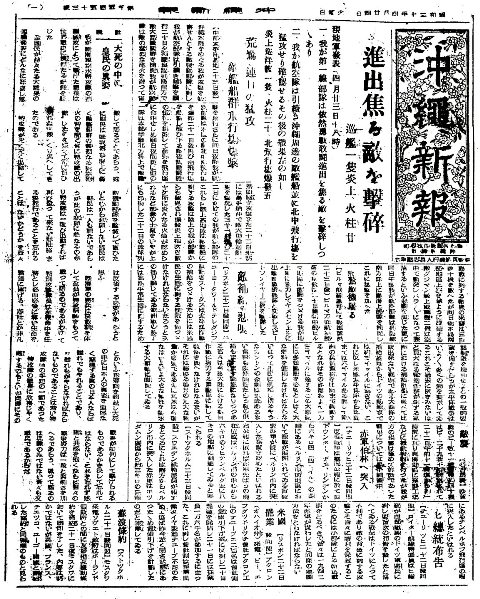
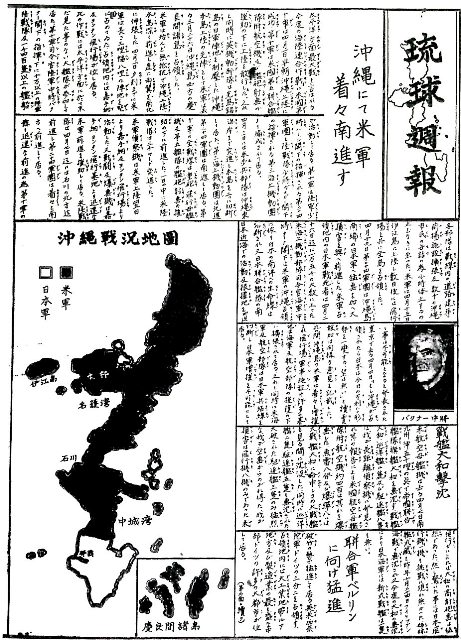
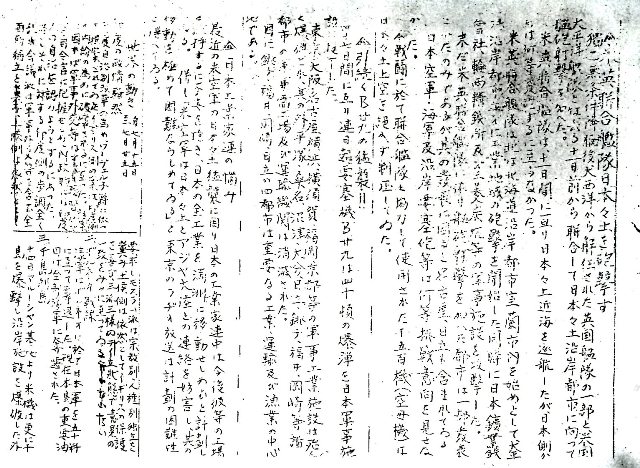
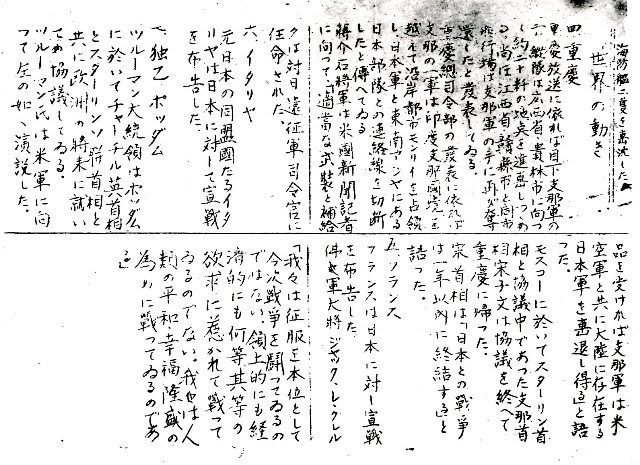
1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号
□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。
□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』
参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店
1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア
1945年5月7日 石川に城前初等学校開校
1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」
1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動
1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」
1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人
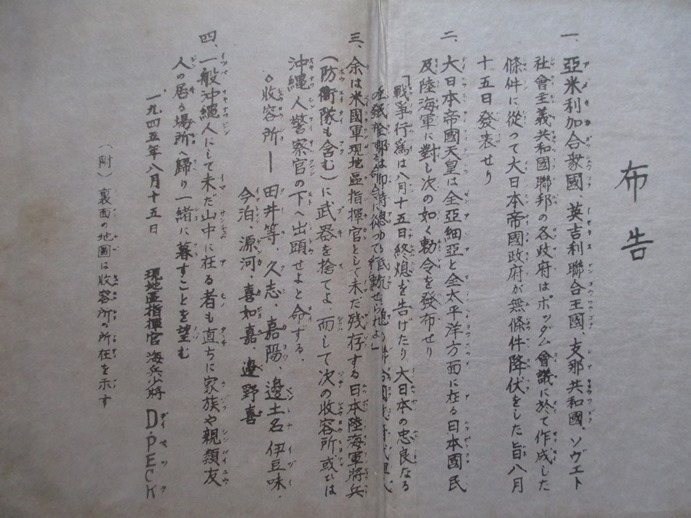
1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」
1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」
1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足
1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」
1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)
1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」
1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」
NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。
ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ
参考資料ー
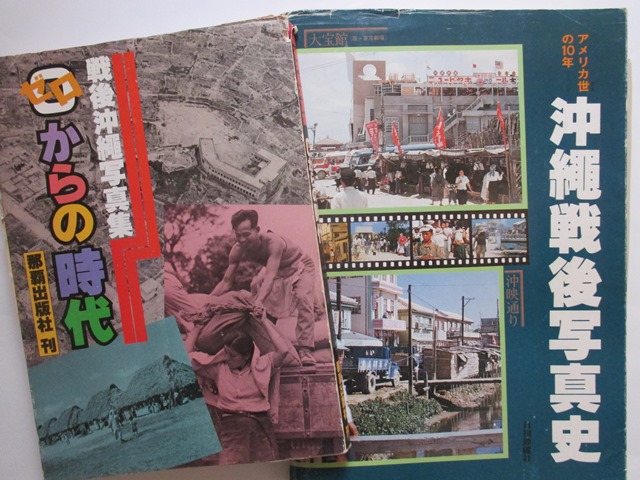
1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社
2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」
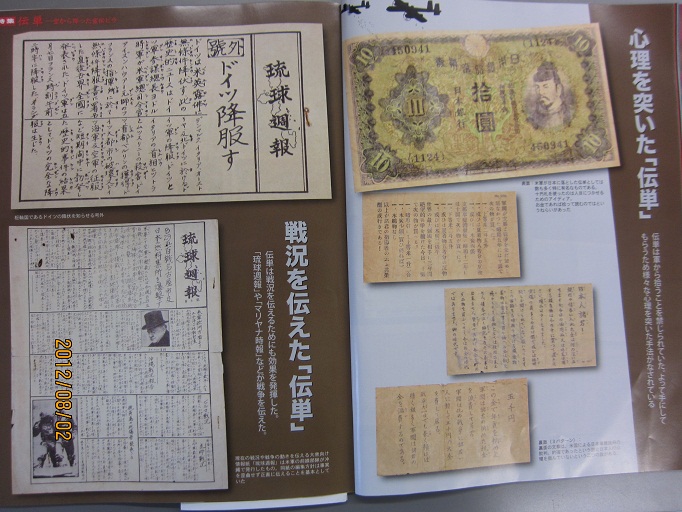
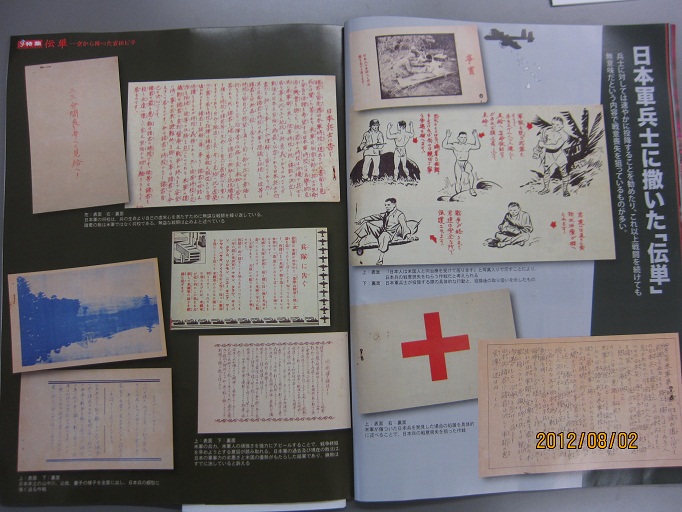
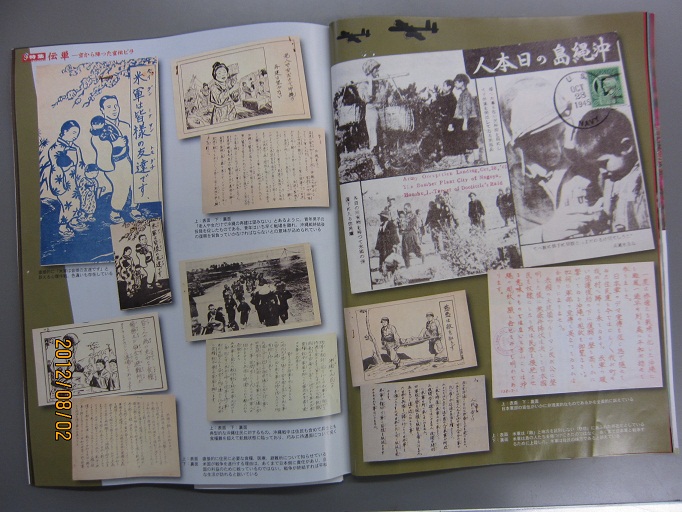
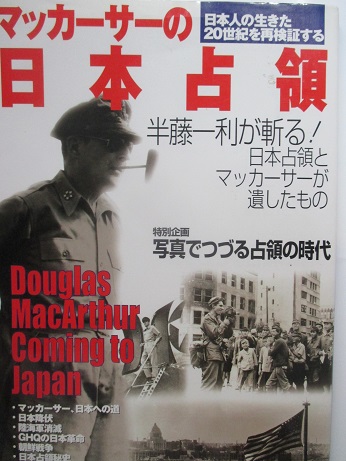
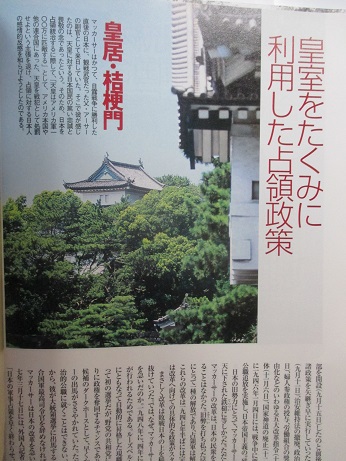
2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社
マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月
。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)
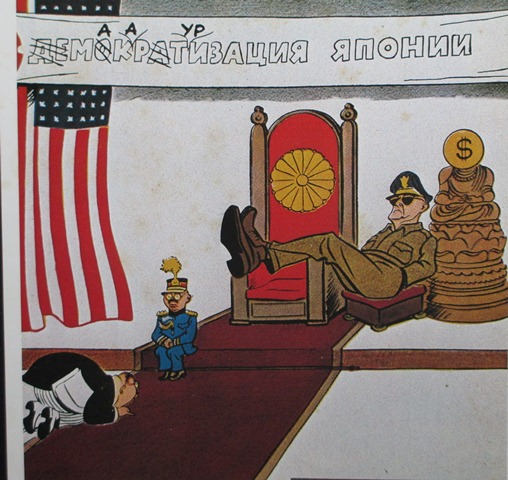
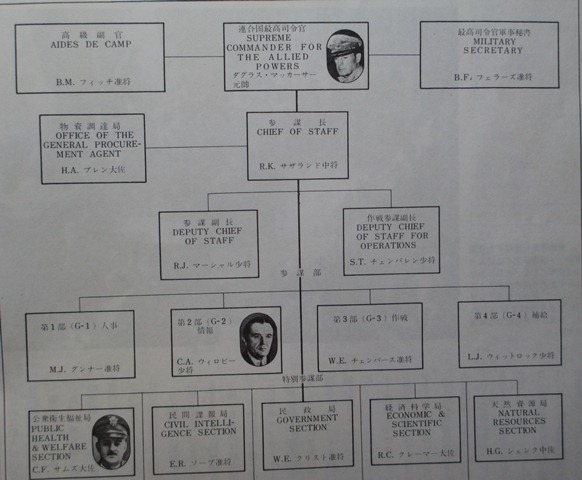
○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。
1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。
1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。
石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。
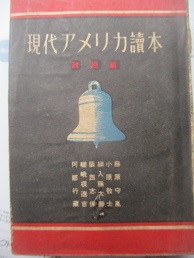
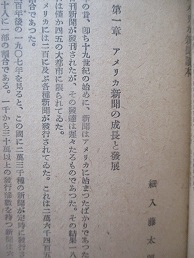

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」
1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ
1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺
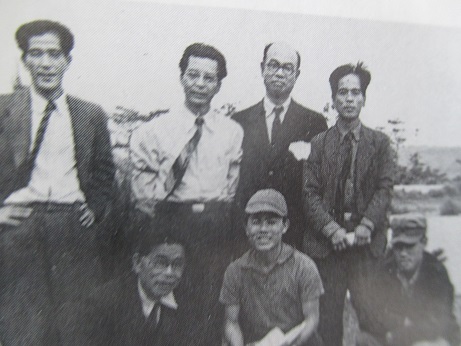
1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝
04/10: 『ペリー提督日本遠征記 』1856年アメリカ政府発刊

『ペリー提督日本遠征記』はペリー提督自身の日記とその部下の日誌や報告書などから編集された記録。同書には、琉球や小笠原諸島、浦賀や横浜、下田や箱館での様々な出来事が記され、多くの石版画や木版画の挿絵が掲載されている。挿絵は、艦隊に従軍した写真家のエリファレット・ブラウン・ジュニアが撮影したダゲレオタイプや、画家のウィリアム・ハイネらが描いた絵をもとに作成されたもの。エリファレットが当時撮影したダゲレオタイプは数枚の現存が確認できるのみで、ほとんどがいまだに発見されていない。石版画や木版画には、ダゲレオタイプをもとに作成された鮮明な画像が描かれている。→JCIIフォトサロン2019年7月
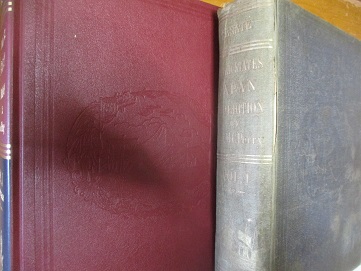
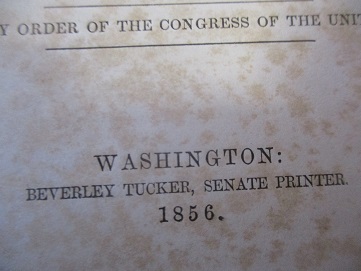
左、復刻版、右、『ペリー提督日本遠征記 』1856年アメリカ政府発刊
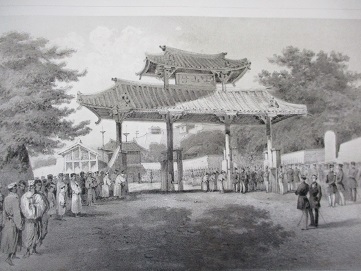
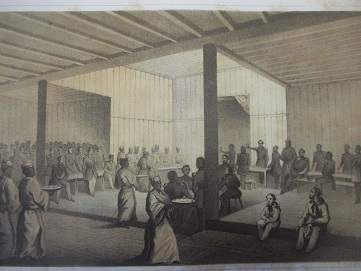


講談社の『日本写真年表』に「1853年(嘉永6)年、5月アメリカのペリー艦隊の従軍写真師Eブラウン.Jr琉球を撮影する」とあり、また那覇のニライ社から刊行された『青い眼が見た「大琉球」』の中にその撮影状況の石版刷りが掲載されている。
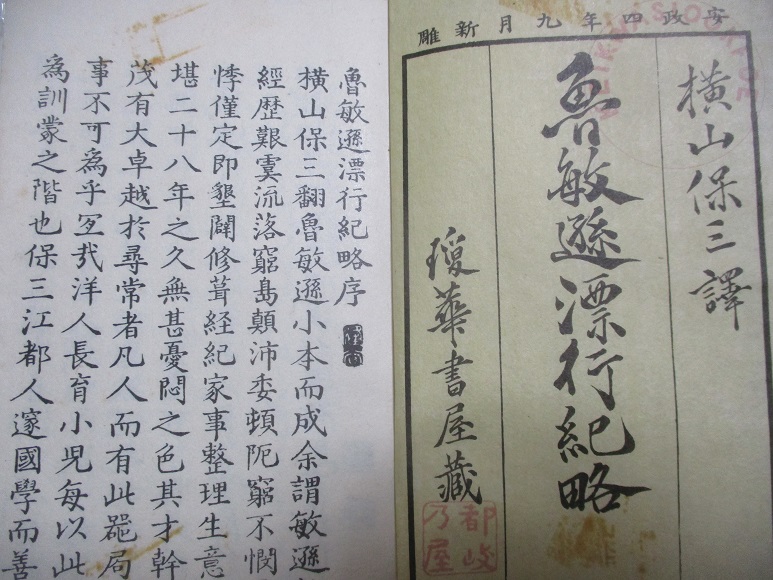
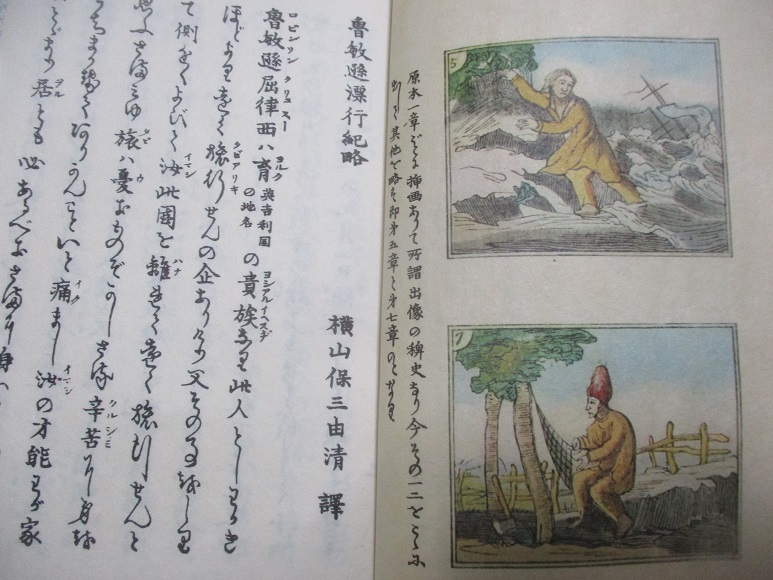
1857年年9月、横山由清訳『魯敏遜漂行紀略』。川上冬崖の色刷木版挿絵

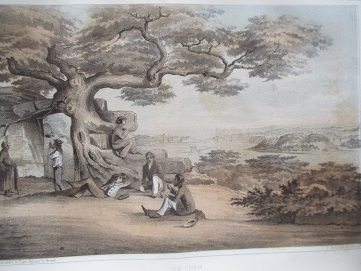
ミシシッピ号(USS Mississippi)は、米国海軍の蒸気外輪フリゲート艦である。名前はミシシッピ川に由来する。マシュー・ペリー代将の個人的な監督の下、フィラデルフィア海軍工廠で起工。1841年12月に就役した。嘉永6年(1853年)のペリーの日本来航の際の四隻の黒船の1隻。 →ウィキ
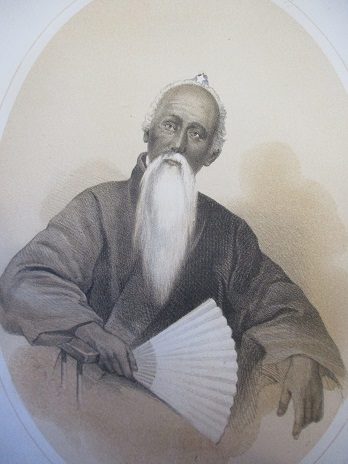
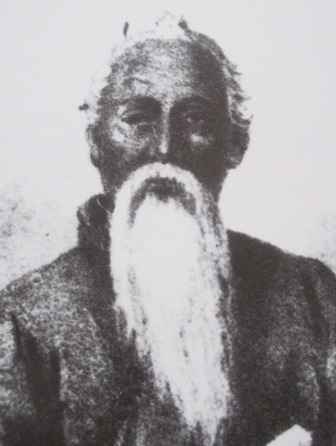
□左の石版画より右の方が末吉安扶に似ていると思われる。
1981年9月 山口栄鉄『異国と琉球』本邦書籍□付録「琉球を語る」ー師弟交信録より(外間政章先生との往復書簡)
外間ー私は先日首里儀保在住の末吉安久氏を訪ねました。氏は元首里高校の美術の先生だった方で、この方の祖父が毛玉麟のようであります。那覇長官を勤めた人は安久氏の祖父安扶だったとのこと。(略)安久氏の長兄安恭は麥門冬と号し新聞記者で有名な作家でしたが、那覇港での事故で溺死された方です。安恭氏は存命中、ブラウン(ペルリ提督一行)の描いたあの威厳のある琉球人の肖像画を見て、これは自分達のタンメーを描いたものといつも話していたそうです。(1901年6月ー末吉安扶没)
末吉麦門冬の甥で「江戸上り」研究家・佐渡山安治氏は本邦書籍発行の『江戸期琉球物資料集覧』第4巻に「琉球使節使者名簿」で1850年(嘉永3)の琉球使節の正使・玉川王子尚愼、副使・野村親方 向元模、儀衛正・魏國香ら99名の一人賛渡使・末吉親雲上を安扶としている。中に後の三司官・与那原良傑も居る。
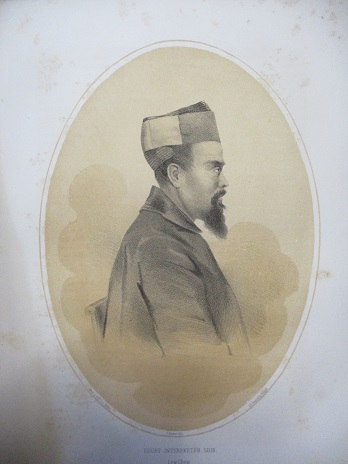
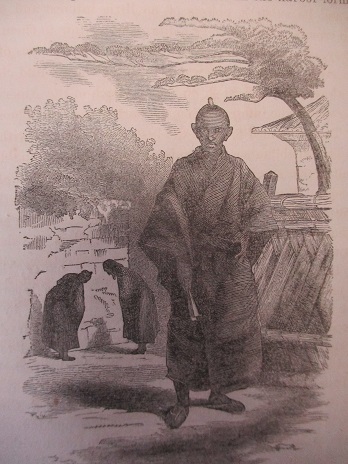
牧志朝忠 生年:尚灝15(1818)没年:尚泰15.7.19(1862.8.14)幕末期の琉球国末期の首里士族。当初は板良敷,次いで大湾,のちに牧志と称した。中国語や英語に堪能で異国通事となる。開化路線を展開した薩摩藩主島津斉彬 から目をかけられ,尚泰10(1857)年には軽輩出ながら表十五人(首里王府の評議機関)の内の日帳主取にまでのぼった。しかし,斉彬の死(1858)を契機に,首里王府内の守旧派は斉彬によって罷免された三司官座喜味盛普の後任人事をめぐる疑獄事件の首謀者として牧志,御物奉行恩河朝恒,三司官小禄良忠を逮捕・投獄した(牧志・恩河事件)。事件は牧志が鹿児島で座喜味を誹謗したことや,その後任選挙において贈賄などによる画策を図ったとの風聞に端を発していた。首里王府の守旧派は,フランス艦船購入の対外政策や斉彬路線に難色を示す座喜味の追放,国王廃立の陰謀を企てたものとの嫌疑をかけたが,明白な証拠をあげることができず,すべて牧志の自白によって審理が展開された。その結果,牧志は久米島へ10年の流刑,小禄は伊江島の照泰寺へ500日の寺入れ,恩河は久米島へ6年の流刑とされた。だが恩河は尚泰13年閏3月13日に獄死。牧志は薩摩藩によって英語教授役とするため保釈されたが,鹿児島への途上,伊平屋島沖合いで投身自殺したとされる。<参考文献>金城正篤「伊江文書牧志・恩河事件の記録について」(『歴代宝案研究』2号) (豊見山和行)

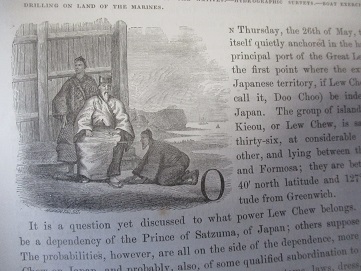


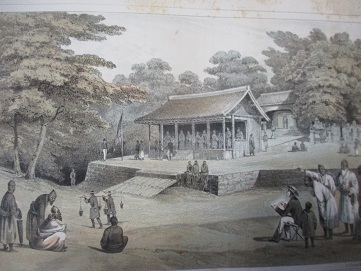
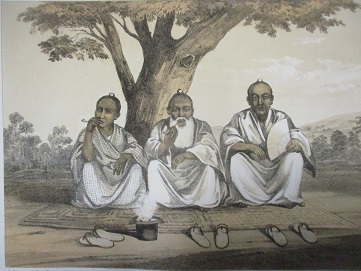
金武番所/
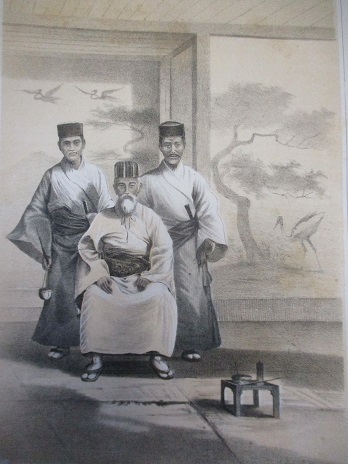

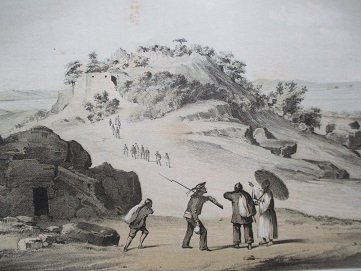

→琉球切手
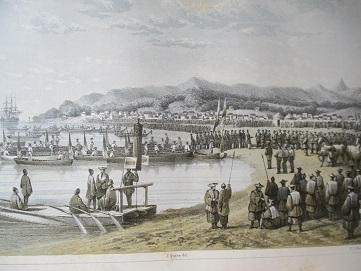
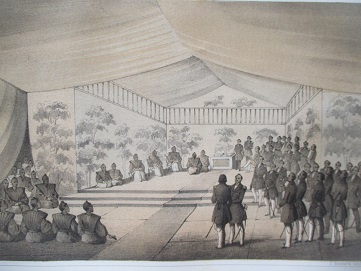

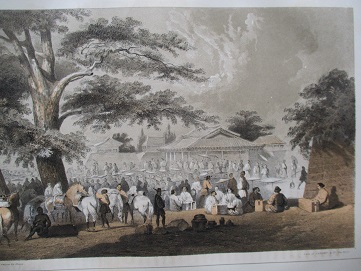
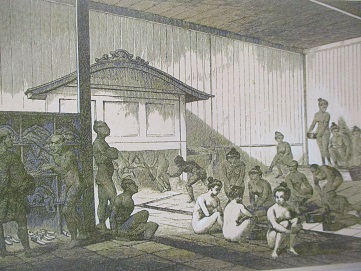

画家ハイネが実景から写生したものを、黄・淡藍・墨の3色刷の砂目石版に複製した「下田の公衆浴場の図」
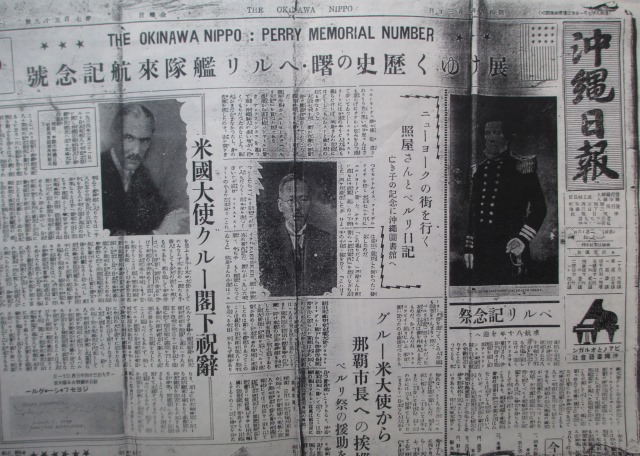

1934年3月30日ー『沖縄日報』「展けゆく歴史の曙・ペルリ艦隊来航記念号」/沖縄日報主催「ペルリ日本来航80年記念祭」講演/神田精輝・島袋源一郎
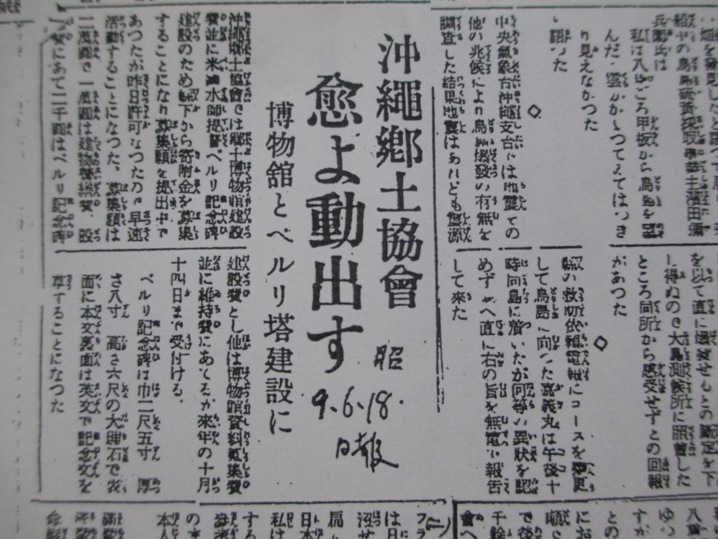
1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。
関連○2015年3月 『記憶と忘却のアジア』青弓社 泉水英計「黒船来航と集合的忘却ー久里浜・下田・那覇」
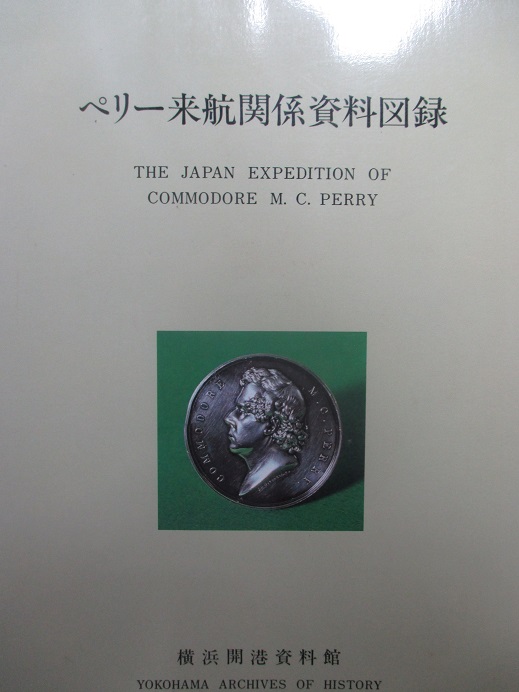
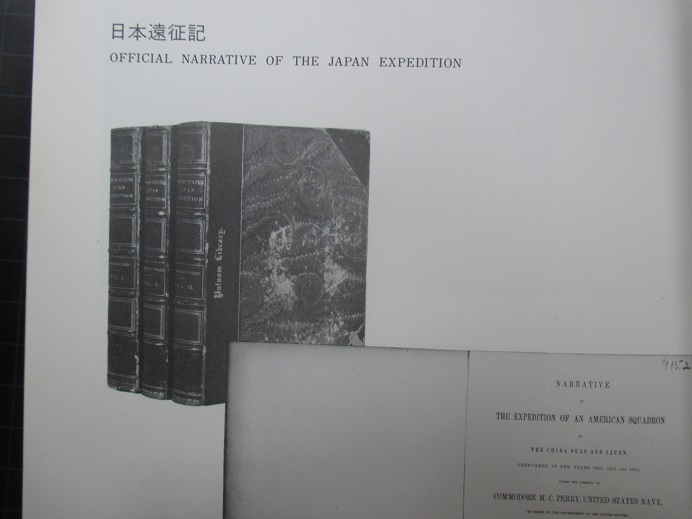
1982年3月 『ペリー来航関係資料図録』横浜開港資料普及協会
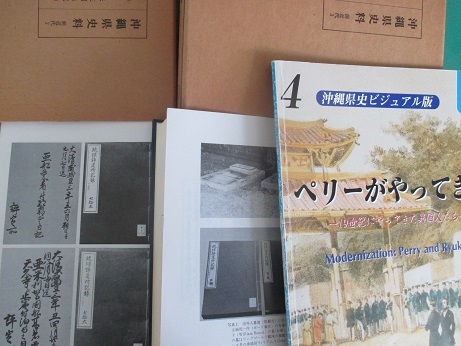
1982年3月『沖縄県史料 前近代2 ペリー来航関係記録1』沖縄県教育委員会

2003年5月30日『琉球新報』「ペリー来琉150周年」
1849年に始まる”ゴールドラッ シュ”に唯一、日本人として足 跡を残したのはジョン万次郎 だといわれる。1841年、14歳の とき漁に出て足摺岬沖で漂流、 鳥島に漂着し、幸運にも米捕鯨 船に救出されその後、捕鯨船長 他の庇護もありアメリカ暮らしと なる。当時は鎖国政策のため、 うかつに本国に戻れなかった時 代だ。望郷の念、止みがたく、帰国 に必要な資金を稼ぎ出すため ゴールドラッシュの噂を耳にし た万次郎はカリフォルニアを目 指した。金鉱で働き二カ月余り で600ドル(当時)の金を得て 1 8 5 2 年 に 首 尾 よく 帰 国 を 果 た す 。
アメ リ カ 移 民 の日 本 女 性 第 1 号ー 同じころの日本、1868年秋、 会津藩が薩摩藩・土佐藩を中心とする明治新政府軍に攻め入られ 鶴ヶ城が陥落した。翌年の春、会津に見切りをつけ、新天地カリフォルニアに渡った藩の一団があっ た。当時、会津藩に使えていたオランダ国籍のヘンリー・シュネル という人物が、農園をつくるため カリフォルニアに土地を購入「Wakamatsu Tea & Silk Farm Colony」と名付け、養蚕やお茶な どの栽培を計画したのだ。藩士と 家族37名が、開拓団に加わった。 長らく知られていなかったが、こ の一団にシュネルとその子どもの 世話係として加わった”おけい”と呼ばれる少女がいた。横浜から米船籍のチャイナ号という船に乗った 一行は、サンフランシスコに到着。 そこからは蒸気船でサクラメント 川を遡り、さらに荷馬車でゴールド ラッシュに沸くコロマ村のゴールド ヒルという原野に落ち着いた。天候 不順(干ばつ)や資金不足から、わずか2年でこの事業は失敗し解体に至る。一説には鉱山作業の影響 で近くの水源が「鉄分と硫黄」に 汚染されていたためともいわれる。
若松コロニーの存在の風化とともに人々の記憶から遠ざかる。コ ロニーも消滅して40年余が過ぎ た1915年(大正4年)の初夏、現地で農園を経営する日本人と邦字新聞「日米新聞」の記者によって, この墓が発見される。最初はなぜこんなところに19歳 の日本人女性の墓があるのか分か らなかったが、近くに住むビーアカ ンプ家を訪ねたところ、そこでおけいの存在と若松コロニーのことを知る。コロニーがなくなった後、おけいはこのビーアカンプ家に引き 取られ働き、同じように引き取られた日本人の桜井松之助らが、おけいのために現地に墓を建てたこ ともわかった。翌年、日系新聞の記 事が掲載され、大きな反響を呼び 世間の知るところとなった。訪れる人もいない墓には、「OKEI」と刻まれていた。「In Memory of OKEI Died 1871, Aged19 years, (A Japanese Girl)おけいの墓 行年一九才」。 2014年 12月、友人とコロマを訪ねた折におけいの墓のある ゴールドヒルに立ち寄った。 コロマから南に8キロほどか。


関連右〇おけいは、会津藩軍事顧問のプロシア人、ヘンリー・スネル家の子守役でした。戊辰戦争後、スネルをリーダーとする会津藩士らとともにカリフォルニアに入植しましたが、開拓に失敗、移民団は離散してしまいました。残されたおけいは、アメリカ人に引き取られましたが、熱病にかかり、19歳の短い生涯を終えました。カリフォルニア州ゴールドヒルと同様の墓が背あぶり山にたてられています。 →会津若松観光ナビ
ゴールドラッシュ時代、数多い絞首刑が行われたので、「ハングタ ウン」とも呼ばれるプラサビルへ の途中の田園地帯だ。移民団入植 から100周年を迎えた1969年には、 当時カリフォルニア州知事だった ロナルド・レーガンが若松コロ ニーの跡地をカリフォルニア州の歴史史跡に指定。同年、ゴールド・ トレイル小学校に隣接する敷地に 「日本移民百周年記念碑」が建立された。カリフォルニア州エルドラ ド郡の小学4年生は読書プログラ ムの一環で、日本からカリフォルニ アに来たおけいの生涯を伝える本 「Okei-san: A Girl’s Journey, Japan to California, 1868-1871」を読むという。 記念碑を訪ねた後、すぐ先のゴー ルドヒルに向かった。入口には倉庫 と思しき大きな木造の家があり、 Okeiに因んだフェスティバル開催 のポスターがあちこちに貼られてい た。30代ぐらいの青年と行きあっ たので”地元の方か?”と聞くと” ここに土地を借りて住んでいるが、 特段おけいとのつながりでここに いるわけではない”とのことだった。 さぁ、だいぶ先に見える丘の上まで30分とみて頂上に向かった。途中、ぬかるみや藪道もあったがのんびり歩き進むうちに丘の上についた。
丘の上にある大木は、元は150年前 に、若松コロニー開拓団が日本から 持参し植えたケヤキの苗木が育っ たものだという。西に向かって遥か 先にサンフランシスコ湾、太平洋を 挟んでその向こうが会津だ。サン フランシスコ湾まで200-300キロか。 晴れていれば海を望めるだろう。 おけいはビーアカンプ家に世話に なっていた時にもこの丘の上まで 足を運んだ。ひとしきり登り道を歩 いて汗をかいた。四方を見渡して 150年前も今もこのあたりの風景は あまり変っていないのかも知れな いと思った。 補遺;2019-6-19日本から最初 にアメリカ本土に入植した移民団 がカリフォルニア州北部ゴールド ヒルにアメリカ本土初の日本人入 植地「若松コロニー」を形成してから8日で150年を迎えた。同日、跡地では記念式典が行われ、日米にいる移民団の末裔や関係者らが 出席。会津松平家の末裔も日本から訪れた。→『鍍金の世界』2019年11月号 屋良朝信「旅の記憶」
10/17: 1926年10月ー伊波普猷『孤島苦の琉球史』春陽堂
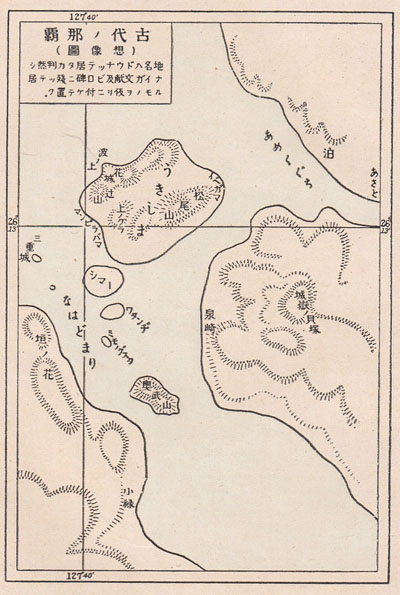
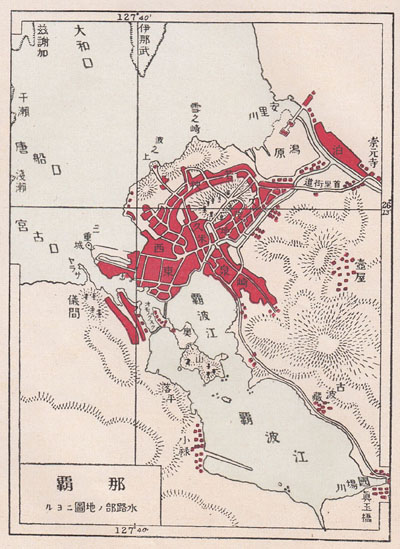
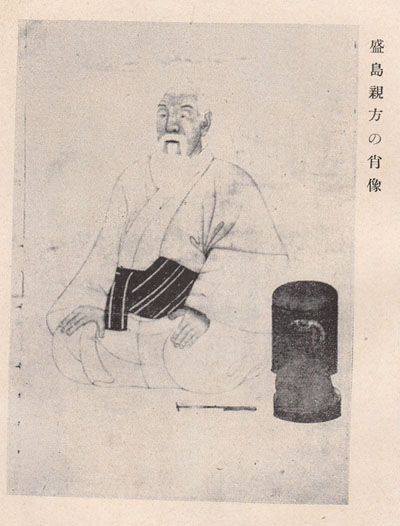
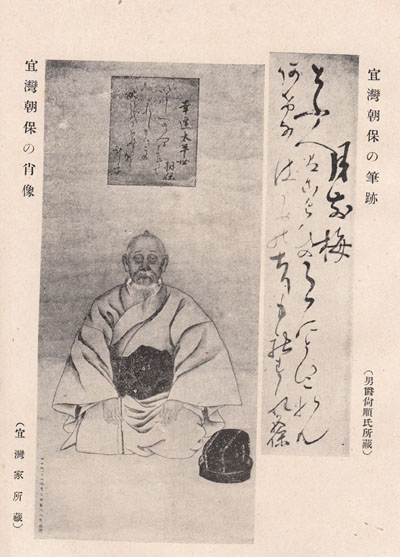
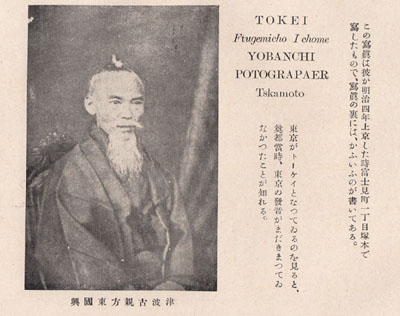
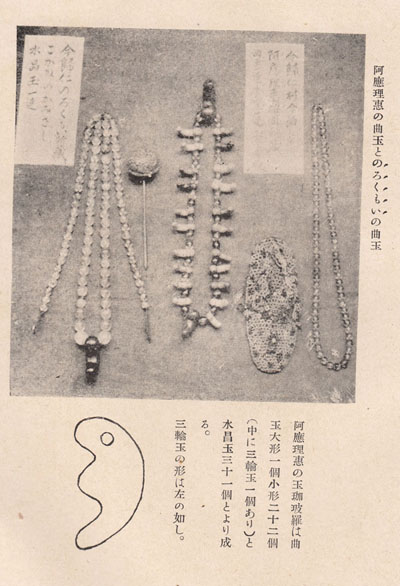
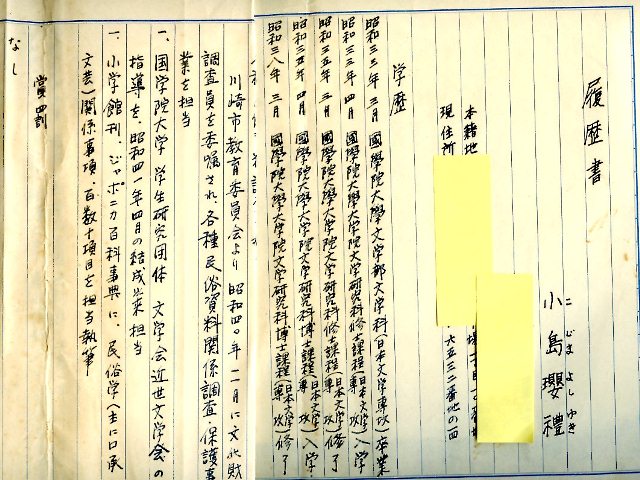
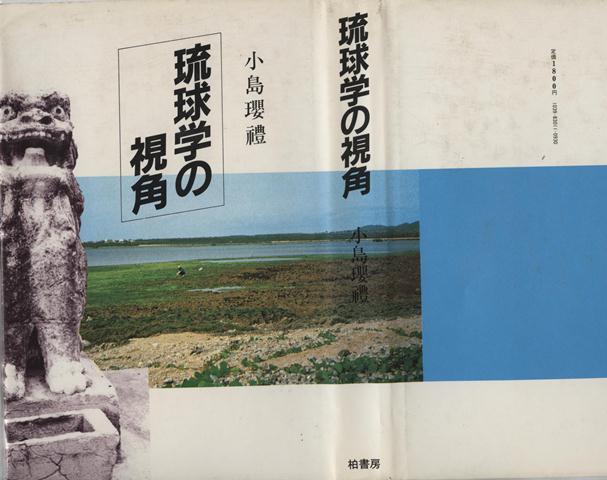
1983年4月ー小島瓔禮『琉球学の視角』柏書房
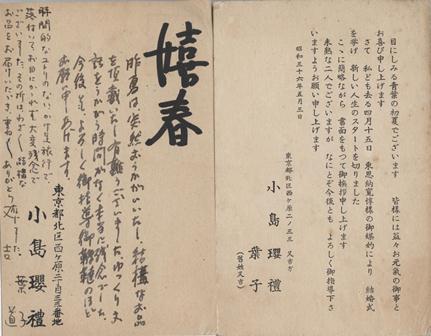
小島瓔禮琉大教授に柳田賞/著作「太陽と稲の神殿」が評価 2000年8月29日『琉球新報』
優れた民俗学研究者に贈られる第39回柳田賞(成城大学・柳田賞委員会主催)が25日決まった。受賞者は、「太陽と稲の神殿」(白水社)を著した小島瓔禮(よしゆき)・琉球大学教授と、「日本人と宗教」(岩波書店)などを著した故宮田登・筑波大学名誉教授の二氏。賞金は各30万円。小島教授は「高校時代に柳田國男の『田社考』を読んで民俗学を志したので、この賞は大変感慨深い」と喜びを語った。
受賞対象となった小島教授の「太陽と稲の神殿」は、朝廷の稲作儀礼の奥に、狩猟時代の面影を伝える儀式があることを指摘し、それが沖縄の民俗行事に残っていることを紹介している。その行事というのは、動物の骨を縄に挟んで村の入り口などに張る「シマクサラシ」と呼ばれているもので、本島南部のある村では現在でも旧暦2月に牛を殺して各戸に配る行事が残っており、与那国島では田を開いた時に鶏か牛の肉を供えたという伝承が残っている、と例を挙げている。

新城栄徳(左)、小島摩文氏
03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館




1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」
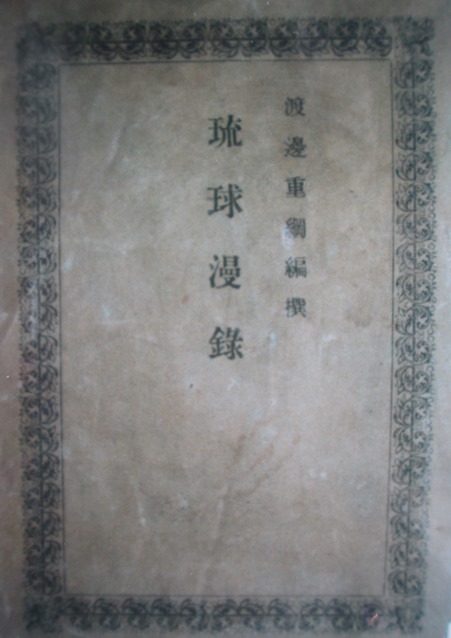

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治
うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。
討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。
1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

兼城昌興


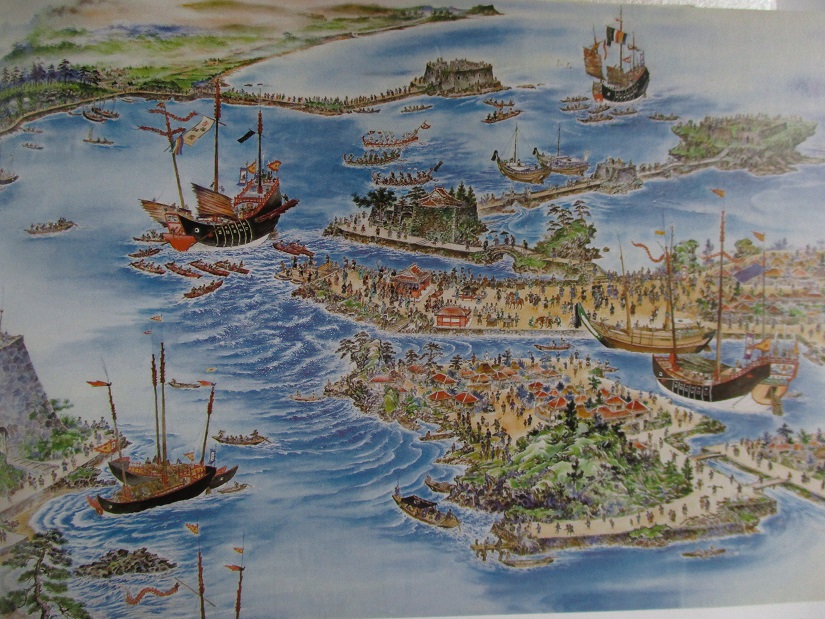
金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」
1892年4月 島袋源一郎、今帰仁尋常小学校入学
1896年4月 島袋源一郎、名護の国頭高等小学校に入学
1904年10月20日 『東京人類学会雑誌』第223号 鳥居龍蔵「沖縄人の皮膚の色に就てー余は本年夏期、沖縄諸島を巡回せしが、其那覇滞在中、首里なる同県師範学校、及び高等女学校に於て、男女学徒の皮膚の色を調査なしたり。(助手は伊波普猷で、師範学校の学徒に島袋源一郎・今帰仁間切20歳、仲原善忠・久米島18歳、比嘉春潮・首里21歳、徳元八一・玉城間切20歳、宮城栄昌・久志22歳、諸見里朝清・首里20歳山城篤男・高嶺間切17歳,
新垣信一などの名前がある。)
□当山正堅「時の図画の先生は日本画に堪能な山口瑞雨先生でありましたが、あの頃から洋画も課さねばならなかったので、先生は予め其の描写法を授けることなしに漫然と首里城を写生して来るようにとの日曜宿題を命ぜられたのであります。すると、島袋源一郎氏は唐破風の棟上に登って屋根の大きさから、両端の龍の胴体、髭の長さを測り更に瓦の数まで一々数えて来てから構想を練って描写に取りかかったと云う熱心さに先生も同級生一同も驚いたと云うことでありました。」
1907年3月 島袋源一郎、沖縄県師範学校卒業。 4月 名護訓導
1926年8月 那覇松山校に於いて西村真次「家族国家としての日本」講演
1927年1月 那覇尋高に於いて嘉納治五郎「柔道の原理と精力善用」講演
1927年4月 『沖縄教育』161号 「教育参考館の建設に就いて」「教育参考館記事」
1927年8月26日~4日間 松山小学校で小原國芳「教育道」講演
1928年3月
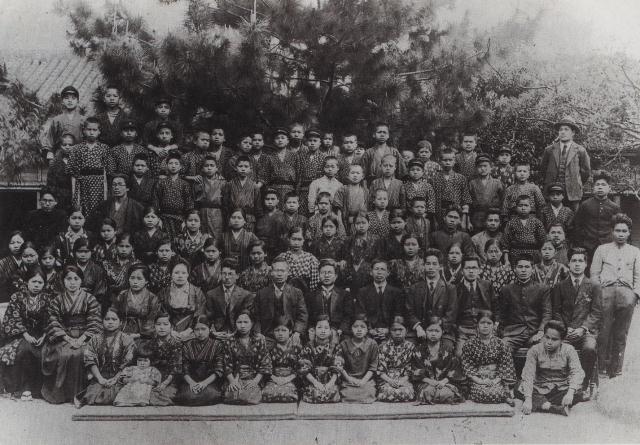
名護東江小学校卒業式ー前列右から5番目が仲原照子(源一郎の妹)、2列目左から7番目が島袋源一郎(当時校長)→1997年4月 仲原照子『想いの中からー随筆・短歌・俳句など』「戦前の郷土博物館ー首里城内の正殿に向かって、右側南殿があり、左側に博物館に使われた北殿がありました。北殿はかつて冊封使の歓待に利用されたところで中国風の造りになっていました。館内の柱は、円柱の大木が使われ左端に昇り龍、右端に降り龍が彫られ、朱色とややくすんだ赤色が塗られていました。館内には尚家の宝物をはじめ、紅型・陶器・漆器・三味線・書画・馬具・龕などが所狭しと展示されていました。」
1928年10月 城青年団同人雑誌『創造青年』創刊号 島袋源一郎「(略)余は只諸君個人個人が各自自己を完成し生まれた価値のある立派な人となり、更に社会的に何か貢献し死後も地球に足跡を印刻し得る偉大な人物になられんことを冀望して擱筆する次第である。」
1929年3月 『南島研究』島袋源一郎『名護城史考』
□(略)沖縄の祖霊崇拝教では之を信じて居るのである。此の宗教は多神教の程度迄発達しているが種々の障碍の為に停頓状態に陥っているのは寔に遺憾である。若し沖縄の宗教が、すべての祈りを吾等の祖神を通じて大宇宙の支配者たる宗教意識に導き得るならば、自然教の境地を脱却して立派な文明教の中に入ることが出来るのである。
1936年7月 『沖縄教育』第239号(表紙・琉球組踊「銘苅子」の天女) 島袋盛敏「琉球芸能感想記」/上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1912年10月8日 『琉球新報』伊波普猷「明治聖代紀念事業(本県に於いて如何なる事業を実行す可きか)・博物館が一番よいー明治時代の紀念事業としては博物館が一番よいと思ひますそして其処には主に教育の参考品を集めついでに沖縄の古物も集めたい壁には明治時代に輩出した名高い政治家軍人実業家教育家文学者宗教家美術家俳優等の肖像を掲げついでに明治時代に輩出した沖縄の名士の肖像迄は掲げるやうにしたい」
1916年2月8日『琉球新報』「大典紀念事業ー首里区では旧城『西ノ殿』に大修理を施し以って公会堂を設置すべく其の経費1千円圓を計上して愈愈5年度より2ヵ年継続を以って起工する事になっている。」

1926年5月2日ーベッテルハイム記念碑(ベッテルハイム師が歴訪した10カ国の石をちりばめた記念碑)除幕式。右端上が島袋源一郎
□ベッテルハイム記念碑除幕式は午後3時より波上護国寺境内に於いて挙行。来賓は亀井知事、佐伯裁判所長、志賀重昴、羽田内務部長、岸本那覇市長、知花朝章、里見学務部長、金城那覇市会議長ら。司会者は伊東平次、聖書朗読は佐久原好伝、祈祷が芹澤浩、除幕が知花朝章、建碑之辞、決算報告がイー・アール・ブル、讃美歌は合唱隊、祝祷が神山本淳。記念写真は久志写真館。
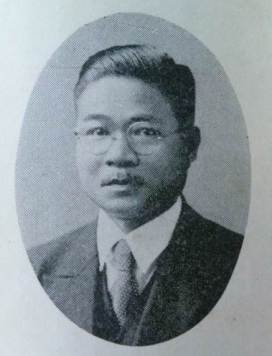
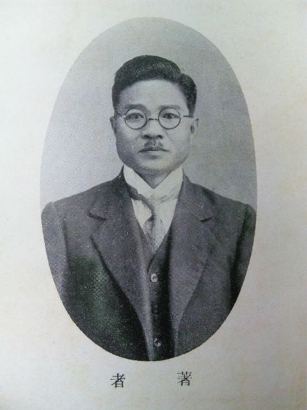
島袋源一郎
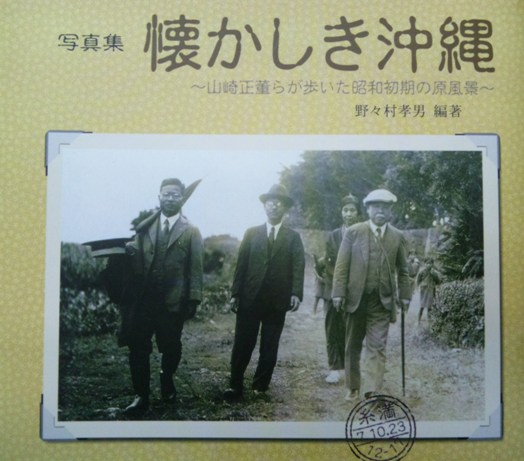
1932年10月23日ー南山城址南側を歩く。写真左から島袋源一郎、宜保、山崎正董、とねく →『写真集 懐かしき沖縄』琉球新報社2000年11月
1937年11月 沖縄師範学校龍潭同窓会『會報』 □仲吉朝睦(県社沖縄神社社司)「惟神の大道」/袋源一郎(沖縄県教育会主事)「同窓の誇と悲」/知念亀千代(東京市月島第一小学校訓導)「手工教育より観たる吾が郷土」
1938年8月28日 午後ー昭和会館で沖縄生活更新協会発会式。式は沖縄県教育会主事島袋源一郎司会のもと進められた。理事長・大城兼義、/理事・當間那覇市助役、勝連首里市助役、上原、眞栄城、新垣各島尻町村会役員、玉井、宮平、伊佐各中頭町村長会役員、仲宗根、山城、池原各国頭町村長会役員、石原宮古町村長会長、大濱八重山町村会長、吉田県社会事業主事、諸見里県社会教育主事、川平女師一高女校長、志喜屋海南中学校長、宮城島尻教育部会長、渡嘉敷中頭教育部会長、比嘉国頭教育部会長、島袋図書館長、金城県農会技師、當眞朝日社長、又吉琉球主筆、親泊日報理事、大城兼義、島袋源一郎、当山正堅、湧上聾人、親泊康永/監事・島袋源一郎、親泊政博/主事・当山正堅/顧問・淵上知事、尚順男、伊江男、平尾貴族院議員、漢那、伊禮、仲井間、崎山、小田各代議士、金城那覇、伊豆見首里両市長、嵩原県会議長、照屋宏、宜保成晴、我如古楽一郎、仲田徳三、盛島明長、長野時之助
1939年3月 沖縄生活更新協会『新生活』(当山正堅)
島袋源一郎□須らく勇往邁進せよー今は我ら大和民族の同胞が八紘一宇の大理想の下に、世界的に飛躍すべき重大な時機に際会している国民の一人一人が最善を尽くして皇国に貢献すべき時である。我等は日本人たるの誇りを持って勇往邁進しなければならぬ。退嬰・卑屈・消極・卑下は禁物である。我等沖縄人は人種学、血清学、言語学、風俗、土俗其他有ゆる角度から考察しても立派な大和民族であり、其の一地方集団であることは各方面の学者が証明している。何を自ら卑下する必要があるか?。然も我等の祖先は激浪と戦って此の南島に渡って来た丈けに実に勇剛であり、驍健であった。四世紀ばかり前欧州人がマラッカ海峡以東に進出して来なかった時代迄日本本土から朝鮮、支那、安南、シャム、呂宋、ボルネオあたり迄の所謂東洋貿易の覇権を掌握していたのは実に我が琉球人であった。西暦1454年以来琉球王は其の港を東亜貿易の一大市場にしょうと努力していたという。
天文の頃葡萄牙人は琉球を「黄金の島大琉球」と称し日本を「銀の島ジャパン」と称していた。目下眞教寺に吊るされている大鐘「中山王殿前に懸くる鐘」の銘に、
琉球國は南海の勝地にして三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車と為し、日域を以て唇歯と為し
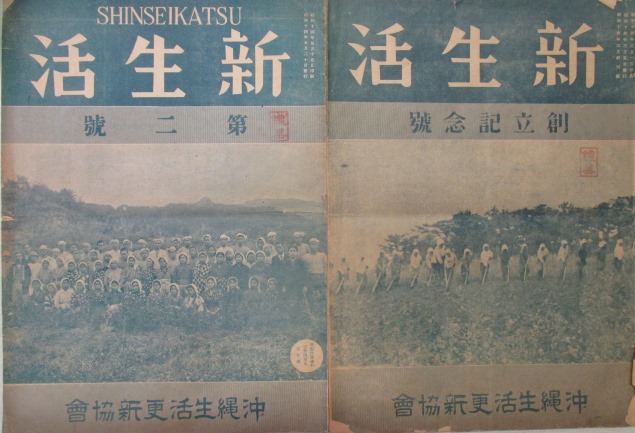
1939年3月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』創刊号
1939年5月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』第2号
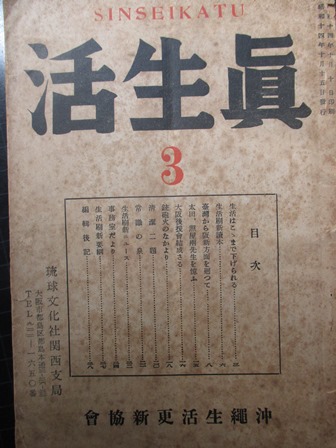
1939年10月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『眞生活』第3号
1939年5月 沖縄生活更新協会『新生活』第2号(当山正堅)
□最近改めたる県内名士の復姓
勝連盛常→山田盛常
嘉数詠俊→日高詠俊
饒平名紀腆→長田紀腆
玻名城長好→山田長好
勢理客宗正→町田宗正
我謝昌饒→重久昌饒
渡嘉敷唯秀→新川唯秀
仲兼久吉盛→宮里吉盛
□式場隆三郎 しきば-りゅうざぶろう
1898-1965 大正-昭和時代の精神医学者。
明治31年7月2日生まれ。静岡脳病院院長などをへて式場病院をひらく。昭和21年ロマンス社社長となり,「ロマンス」「映画スター」などを発行。ゴッホ研究家,放浪の画家山下清の後援者としても知られる。昭和40年11月21日死去。67歳。新潟県出身。新潟医専卒。著作に「ヴァン・ゴッホの生涯と精神病」など。(→コトバンク)
1896年4月 島袋源一郎、名護の国頭高等小学校に入学
1904年10月20日 『東京人類学会雑誌』第223号 鳥居龍蔵「沖縄人の皮膚の色に就てー余は本年夏期、沖縄諸島を巡回せしが、其那覇滞在中、首里なる同県師範学校、及び高等女学校に於て、男女学徒の皮膚の色を調査なしたり。(助手は伊波普猷で、師範学校の学徒に島袋源一郎・今帰仁間切20歳、仲原善忠・久米島18歳、比嘉春潮・首里21歳、徳元八一・玉城間切20歳、宮城栄昌・久志22歳、諸見里朝清・首里20歳山城篤男・高嶺間切17歳,
新垣信一などの名前がある。)
□当山正堅「時の図画の先生は日本画に堪能な山口瑞雨先生でありましたが、あの頃から洋画も課さねばならなかったので、先生は予め其の描写法を授けることなしに漫然と首里城を写生して来るようにとの日曜宿題を命ぜられたのであります。すると、島袋源一郎氏は唐破風の棟上に登って屋根の大きさから、両端の龍の胴体、髭の長さを測り更に瓦の数まで一々数えて来てから構想を練って描写に取りかかったと云う熱心さに先生も同級生一同も驚いたと云うことでありました。」
1907年3月 島袋源一郎、沖縄県師範学校卒業。 4月 名護訓導
1926年8月 那覇松山校に於いて西村真次「家族国家としての日本」講演
1927年1月 那覇尋高に於いて嘉納治五郎「柔道の原理と精力善用」講演
1927年4月 『沖縄教育』161号 「教育参考館の建設に就いて」「教育参考館記事」
1927年8月26日~4日間 松山小学校で小原國芳「教育道」講演
1928年3月
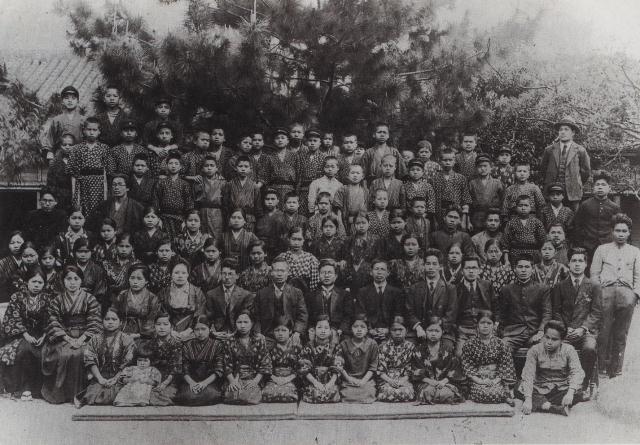
名護東江小学校卒業式ー前列右から5番目が仲原照子(源一郎の妹)、2列目左から7番目が島袋源一郎(当時校長)→1997年4月 仲原照子『想いの中からー随筆・短歌・俳句など』「戦前の郷土博物館ー首里城内の正殿に向かって、右側南殿があり、左側に博物館に使われた北殿がありました。北殿はかつて冊封使の歓待に利用されたところで中国風の造りになっていました。館内の柱は、円柱の大木が使われ左端に昇り龍、右端に降り龍が彫られ、朱色とややくすんだ赤色が塗られていました。館内には尚家の宝物をはじめ、紅型・陶器・漆器・三味線・書画・馬具・龕などが所狭しと展示されていました。」
1928年10月 城青年団同人雑誌『創造青年』創刊号 島袋源一郎「(略)余は只諸君個人個人が各自自己を完成し生まれた価値のある立派な人となり、更に社会的に何か貢献し死後も地球に足跡を印刻し得る偉大な人物になられんことを冀望して擱筆する次第である。」
1929年3月 『南島研究』島袋源一郎『名護城史考』
□(略)沖縄の祖霊崇拝教では之を信じて居るのである。此の宗教は多神教の程度迄発達しているが種々の障碍の為に停頓状態に陥っているのは寔に遺憾である。若し沖縄の宗教が、すべての祈りを吾等の祖神を通じて大宇宙の支配者たる宗教意識に導き得るならば、自然教の境地を脱却して立派な文明教の中に入ることが出来るのである。
1936年7月 『沖縄教育』第239号(表紙・琉球組踊「銘苅子」の天女) 島袋盛敏「琉球芸能感想記」/上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1912年10月8日 『琉球新報』伊波普猷「明治聖代紀念事業(本県に於いて如何なる事業を実行す可きか)・博物館が一番よいー明治時代の紀念事業としては博物館が一番よいと思ひますそして其処には主に教育の参考品を集めついでに沖縄の古物も集めたい壁には明治時代に輩出した名高い政治家軍人実業家教育家文学者宗教家美術家俳優等の肖像を掲げついでに明治時代に輩出した沖縄の名士の肖像迄は掲げるやうにしたい」
1916年2月8日『琉球新報』「大典紀念事業ー首里区では旧城『西ノ殿』に大修理を施し以って公会堂を設置すべく其の経費1千円圓を計上して愈愈5年度より2ヵ年継続を以って起工する事になっている。」

1926年5月2日ーベッテルハイム記念碑(ベッテルハイム師が歴訪した10カ国の石をちりばめた記念碑)除幕式。右端上が島袋源一郎
□ベッテルハイム記念碑除幕式は午後3時より波上護国寺境内に於いて挙行。来賓は亀井知事、佐伯裁判所長、志賀重昴、羽田内務部長、岸本那覇市長、知花朝章、里見学務部長、金城那覇市会議長ら。司会者は伊東平次、聖書朗読は佐久原好伝、祈祷が芹澤浩、除幕が知花朝章、建碑之辞、決算報告がイー・アール・ブル、讃美歌は合唱隊、祝祷が神山本淳。記念写真は久志写真館。
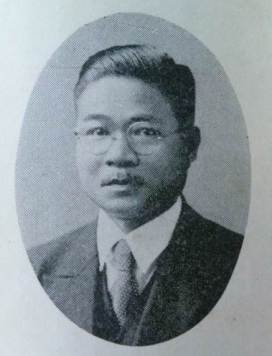
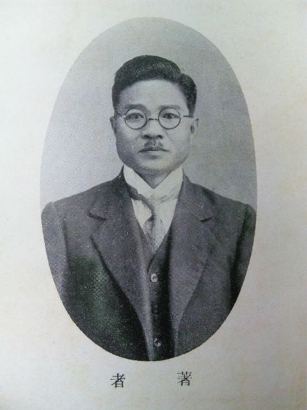
島袋源一郎
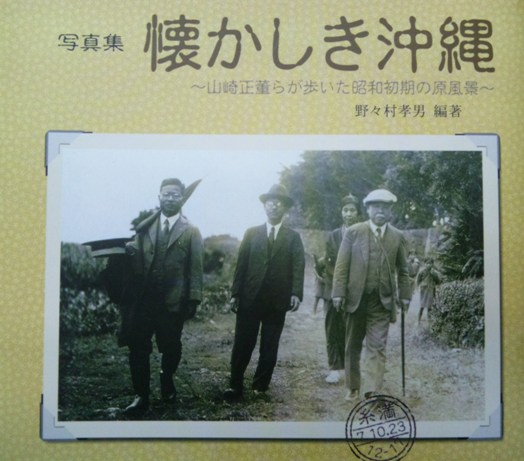
1932年10月23日ー南山城址南側を歩く。写真左から島袋源一郎、宜保、山崎正董、とねく →『写真集 懐かしき沖縄』琉球新報社2000年11月
1937年11月 沖縄師範学校龍潭同窓会『會報』 □仲吉朝睦(県社沖縄神社社司)「惟神の大道」/袋源一郎(沖縄県教育会主事)「同窓の誇と悲」/知念亀千代(東京市月島第一小学校訓導)「手工教育より観たる吾が郷土」
1938年8月28日 午後ー昭和会館で沖縄生活更新協会発会式。式は沖縄県教育会主事島袋源一郎司会のもと進められた。理事長・大城兼義、/理事・當間那覇市助役、勝連首里市助役、上原、眞栄城、新垣各島尻町村会役員、玉井、宮平、伊佐各中頭町村長会役員、仲宗根、山城、池原各国頭町村長会役員、石原宮古町村長会長、大濱八重山町村会長、吉田県社会事業主事、諸見里県社会教育主事、川平女師一高女校長、志喜屋海南中学校長、宮城島尻教育部会長、渡嘉敷中頭教育部会長、比嘉国頭教育部会長、島袋図書館長、金城県農会技師、當眞朝日社長、又吉琉球主筆、親泊日報理事、大城兼義、島袋源一郎、当山正堅、湧上聾人、親泊康永/監事・島袋源一郎、親泊政博/主事・当山正堅/顧問・淵上知事、尚順男、伊江男、平尾貴族院議員、漢那、伊禮、仲井間、崎山、小田各代議士、金城那覇、伊豆見首里両市長、嵩原県会議長、照屋宏、宜保成晴、我如古楽一郎、仲田徳三、盛島明長、長野時之助
1939年3月 沖縄生活更新協会『新生活』(当山正堅)
島袋源一郎□須らく勇往邁進せよー今は我ら大和民族の同胞が八紘一宇の大理想の下に、世界的に飛躍すべき重大な時機に際会している国民の一人一人が最善を尽くして皇国に貢献すべき時である。我等は日本人たるの誇りを持って勇往邁進しなければならぬ。退嬰・卑屈・消極・卑下は禁物である。我等沖縄人は人種学、血清学、言語学、風俗、土俗其他有ゆる角度から考察しても立派な大和民族であり、其の一地方集団であることは各方面の学者が証明している。何を自ら卑下する必要があるか?。然も我等の祖先は激浪と戦って此の南島に渡って来た丈けに実に勇剛であり、驍健であった。四世紀ばかり前欧州人がマラッカ海峡以東に進出して来なかった時代迄日本本土から朝鮮、支那、安南、シャム、呂宋、ボルネオあたり迄の所謂東洋貿易の覇権を掌握していたのは実に我が琉球人であった。西暦1454年以来琉球王は其の港を東亜貿易の一大市場にしょうと努力していたという。
天文の頃葡萄牙人は琉球を「黄金の島大琉球」と称し日本を「銀の島ジャパン」と称していた。目下眞教寺に吊るされている大鐘「中山王殿前に懸くる鐘」の銘に、
琉球國は南海の勝地にして三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車と為し、日域を以て唇歯と為し
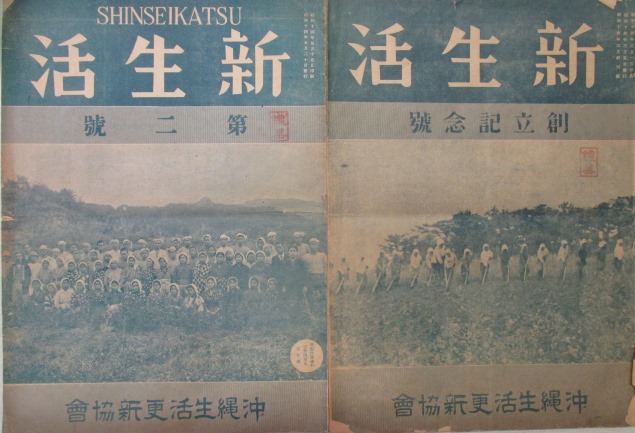
1939年3月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』創刊号
1939年5月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』第2号
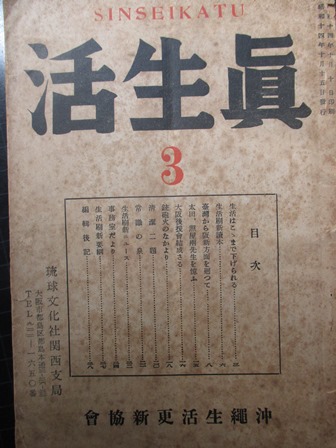
1939年10月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『眞生活』第3号
1939年5月 沖縄生活更新協会『新生活』第2号(当山正堅)
□最近改めたる県内名士の復姓
勝連盛常→山田盛常
嘉数詠俊→日高詠俊
饒平名紀腆→長田紀腆
玻名城長好→山田長好
勢理客宗正→町田宗正
我謝昌饒→重久昌饒
渡嘉敷唯秀→新川唯秀
仲兼久吉盛→宮里吉盛
□式場隆三郎 しきば-りゅうざぶろう
1898-1965 大正-昭和時代の精神医学者。
明治31年7月2日生まれ。静岡脳病院院長などをへて式場病院をひらく。昭和21年ロマンス社社長となり,「ロマンス」「映画スター」などを発行。ゴッホ研究家,放浪の画家山下清の後援者としても知られる。昭和40年11月21日死去。67歳。新潟県出身。新潟医専卒。著作に「ヴァン・ゴッホの生涯と精神病」など。(→コトバンク)
1940年8月 『南島』第1輯 編集兼発行者・野田裕康(台北市兒玉町3ノ9野田書房内)南島発行所目次カット・川平朝申
□編集顧問・浅井恵倫、移川子之蔵、上原景爾、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、喜舎場永珣、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉春潮、萬造寺龍、山中樵
□編集係・川平朝申、須藤利一、比嘉盛章、宮良賢貞
□口絵ー八重山の御嶽と拝殿・西表の節祭とアンガマ踊/進貢船の図/弘化年間来琉の英国船(表紙の地図は中山伝信録より)
□比嘉盛章「西表島の節祭とアンガマ踊」/喜舎場永珣「爬龍船の神事」(黒島)/宮良賢貞「黒島船造りののりと・小濱島のニロー神」/瀬名波長宣「進貢船接貢竝朝鮮船異国船日本他領の船漂着破損等の在番役役公事」/正木任「サマラン號八重山来航事記録」/須藤利一「サマラン號航海記附記」/須藤利一「アダムスの那覇見聞録」/付録ー八重山島由来記・八重山島大阿母由来記・八重山島諸記帳・慶来慶田城由来記・・・解説並びに語句解(比嘉盛章)
1942年3月 『南島』第2輯 編集兼発行者・野田裕康(台北市兒玉町3ノ9)目次カット・川平朝申
□編集顧問・浅井恵倫、伊波普猷、移川子之蔵、上原景爾、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、川平朝令、喜舎場永珣、志喜屋孝信、玉城尚秀、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉春潮、萬造寺龍、柳田国男、山中樵
□編集係・川平朝申、須藤利一、中村忠行、三島格①、宮良賢貞
口絵ーバジル・ホール肖像/日本国古地図(海東諸国記所載)
李朝実録・中世琉球史料・・・・・小葉田淳
久米島おもろに就いて・・・・・・・世禮国男
与那国島の童謡・・・・・・・・・・前新加太郎
孤島武富覚書(八重山)・・・・・・宮良賢貞
岩崎翁のことども・・・・・・・・・・・瀬名波長宜
「沖縄の文化を語る」(座談会)・小葉田、金関、比嘉、須藤、南風原、松村、三島、川平
親雲上の音義に就て・・・・・・・・比嘉盛章
おもろさうし研究(第1回)・・・・・小葉田、金関、松村、木藤、川平、中村、比嘉、須藤、三島
口絵解説(バジル・ホール略傳)中村忠行
新刊紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一
沖縄関係最近文献資料(2)

写真ー1998年10月18日うりずん 左から新城亘氏、①三島格・肥後考古学会会長、新城栄徳、佐藤善五郎氏(那覇市文化協会)
1944年9月 『南島』第3輯 編集者・南島発行所(台北市表町1丁目11番地)発行所・台湾出版文化株式会社目次カット・川平朝申
□編集顧問・浅井恵倫、伊波普猷、移川子之蔵、上原景爾、川平朝令、志喜屋孝信、玉城尚秀、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、喜舎場永珣、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉盛章、柳田国男、比嘉春潮、萬造寺龍、山中樵
□編集・須藤利一、川平朝申、木藤才蔵、中村忠行、松村一雄、三島格、宮良賢貞
□口絵ーロベルト・ゾーン號遭難救助の記念碑・海上から見た同碑のスケッチ・独逸皇帝より贈られた記念品の数々・西郷提督・保力庄の楊友旺・宮古島民遭害の山地・石門の険・墓碑・水野遵氏書簡
□江崎梯三「宮古島のドイツ商船遭難救助記念碑」/石本岩根「独帝謝恩記念品その他」、下地馨「宮古曲玉の研究」、山中樵(台湾総督府図書館長)「宮古島民の台湾遭害」、川平朝健(沖縄新報社員)「宮古の民謡について」、垣花良香「多良間島雑記」
□おもろさうし研究(第2回)・・・・・小葉田、金関、松村、木藤、川平、中村、比嘉、須藤、三島、小山

前列左からー比嘉春潮、川平朝申、柳田国男

□1947年9月7日 アーニパイル國際劇場落成
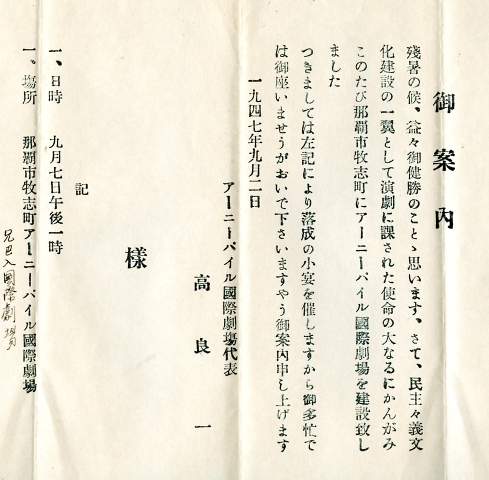
1947年9月5日 『うるま新報』「”國際劇場”那覇に設立ー那覇市牧志町に今回アーニーパイル國際劇場と称する劇場が新設されたが、鉄骨張りの堂々たる建物で収容人員三千五百人とされ9月7日1時より落成式を挙行、沖縄文化連盟主催で西洋音楽、古典舞踊を上演する筈」
1948年2月27日『うるま新報』「映画常設館那覇に出現ーアーニパイル國際劇場は今回映画常設館として娯楽に飢えた那覇っ子を喜ばすことになったが1月21日には文化部主催で盛大な開館式を挙行、当日は軍政府より・・」
□MG会副会長で米軍政府経済部の翻訳官の大城つる女史が、『宗教雑誌を出版したいという人がいるが許可できますか』と訪ねてきた。数日後、本人から出版申請書が出された。終戦直後糸満で壕から這い出した虚脱状態の同胞に希望と笑いをとりもどさせる働きをした与那城勇氏『ゴスペル』(福音)という神の国建設への啓蒙雑誌であり、聖書の解説や迷信の解明など政治色のない編集内容だったので私は喜んで許可した。この月刊誌も『月刊タイムス』と同じ謄写版刷り四六判の30頁、与那城氏が糸満教会に勤務している数年間、根気強く発行した。与那城氏はのち糸満教会を辞し、小禄で歯科医院を開業したが、『ゴスペル』の中jから抜粋した主張や随筆、解説など集めた単行本『琉球エデンの物語』を上梓した。
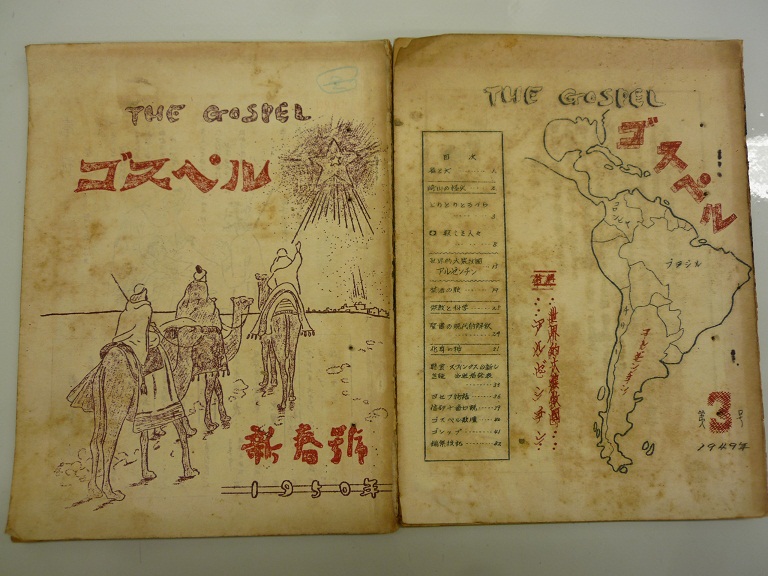 『ゴスペル』
『ゴスペル』
■2012年8月8日、平和通りで我が古里・粟国島に縁故がある玉寄哲永氏と出会い話を聞いた。この与那城勇氏も粟国島と縁故がある。本人が『南歯の歩み』に記した経歴に「14才の時から洋服屋の丁稚、16才で大阪に渡り、回覧雑誌(貸本)の配達をしながら独力で学費を稼いで夜間中学に通っていた私の様な貧しい少年にとってはまさに希望の灯火そのものでありました。私はその頃から『救世軍』という名のキリスト教の一派に加わっていましたが、ゆくゆくは伝道者になろうと心に決めておりました。その計画遂行には独り立ちできる生活力を身につける事が先決だと考えたのですが、たまたま書生として住み込んでいた歯科医院の先生の影響もあって歯科の道を志したのでした。」として猛勉強して朝鮮総督府の歯科医師検定試験に合格した。
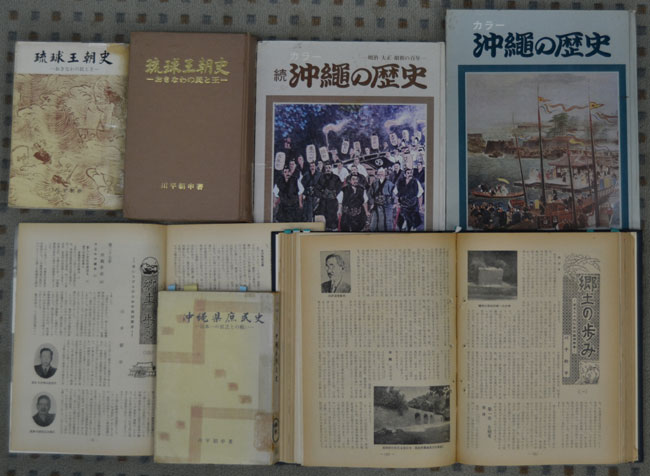
川平朝申の歴史書/下右の1959年7月発行の『今日の琉球』から始まった川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史ー」が私に琉球史へ関心を持たせたもの。②では「人間のおこり」から始まっていた。
2012年9月3日 『沖縄タイムス』斎木喜美子「川平朝申の児童文学①」
□編集顧問・浅井恵倫、移川子之蔵、上原景爾、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、喜舎場永珣、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉春潮、萬造寺龍、山中樵
□編集係・川平朝申、須藤利一、比嘉盛章、宮良賢貞
□口絵ー八重山の御嶽と拝殿・西表の節祭とアンガマ踊/進貢船の図/弘化年間来琉の英国船(表紙の地図は中山伝信録より)
□比嘉盛章「西表島の節祭とアンガマ踊」/喜舎場永珣「爬龍船の神事」(黒島)/宮良賢貞「黒島船造りののりと・小濱島のニロー神」/瀬名波長宣「進貢船接貢竝朝鮮船異国船日本他領の船漂着破損等の在番役役公事」/正木任「サマラン號八重山来航事記録」/須藤利一「サマラン號航海記附記」/須藤利一「アダムスの那覇見聞録」/付録ー八重山島由来記・八重山島大阿母由来記・八重山島諸記帳・慶来慶田城由来記・・・解説並びに語句解(比嘉盛章)
1942年3月 『南島』第2輯 編集兼発行者・野田裕康(台北市兒玉町3ノ9)目次カット・川平朝申
□編集顧問・浅井恵倫、伊波普猷、移川子之蔵、上原景爾、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、川平朝令、喜舎場永珣、志喜屋孝信、玉城尚秀、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉春潮、萬造寺龍、柳田国男、山中樵
□編集係・川平朝申、須藤利一、中村忠行、三島格①、宮良賢貞
口絵ーバジル・ホール肖像/日本国古地図(海東諸国記所載)
李朝実録・中世琉球史料・・・・・小葉田淳
久米島おもろに就いて・・・・・・・世禮国男
与那国島の童謡・・・・・・・・・・前新加太郎
孤島武富覚書(八重山)・・・・・・宮良賢貞
岩崎翁のことども・・・・・・・・・・・瀬名波長宜
「沖縄の文化を語る」(座談会)・小葉田、金関、比嘉、須藤、南風原、松村、三島、川平
親雲上の音義に就て・・・・・・・・比嘉盛章
おもろさうし研究(第1回)・・・・・小葉田、金関、松村、木藤、川平、中村、比嘉、須藤、三島
口絵解説(バジル・ホール略傳)中村忠行
新刊紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一
沖縄関係最近文献資料(2)

写真ー1998年10月18日うりずん 左から新城亘氏、①三島格・肥後考古学会会長、新城栄徳、佐藤善五郎氏(那覇市文化協会)
1944年9月 『南島』第3輯 編集者・南島発行所(台北市表町1丁目11番地)発行所・台湾出版文化株式会社目次カット・川平朝申
□編集顧問・浅井恵倫、伊波普猷、移川子之蔵、上原景爾、川平朝令、志喜屋孝信、玉城尚秀、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、喜舎場永珣、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉盛章、柳田国男、比嘉春潮、萬造寺龍、山中樵
□編集・須藤利一、川平朝申、木藤才蔵、中村忠行、松村一雄、三島格、宮良賢貞
□口絵ーロベルト・ゾーン號遭難救助の記念碑・海上から見た同碑のスケッチ・独逸皇帝より贈られた記念品の数々・西郷提督・保力庄の楊友旺・宮古島民遭害の山地・石門の険・墓碑・水野遵氏書簡
□江崎梯三「宮古島のドイツ商船遭難救助記念碑」/石本岩根「独帝謝恩記念品その他」、下地馨「宮古曲玉の研究」、山中樵(台湾総督府図書館長)「宮古島民の台湾遭害」、川平朝健(沖縄新報社員)「宮古の民謡について」、垣花良香「多良間島雑記」
□おもろさうし研究(第2回)・・・・・小葉田、金関、松村、木藤、川平、中村、比嘉、須藤、三島、小山

前列左からー比嘉春潮、川平朝申、柳田国男

□1947年9月7日 アーニパイル國際劇場落成
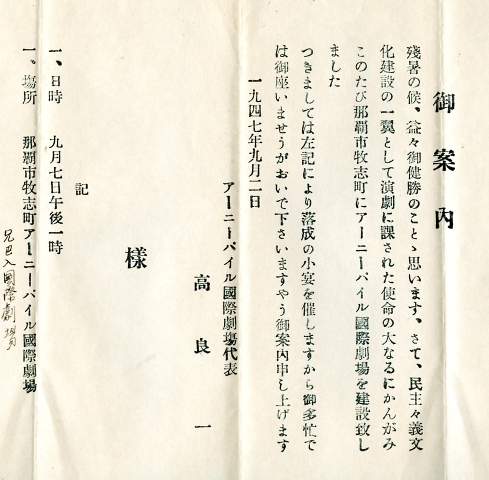
1947年9月5日 『うるま新報』「”國際劇場”那覇に設立ー那覇市牧志町に今回アーニーパイル國際劇場と称する劇場が新設されたが、鉄骨張りの堂々たる建物で収容人員三千五百人とされ9月7日1時より落成式を挙行、沖縄文化連盟主催で西洋音楽、古典舞踊を上演する筈」
1948年2月27日『うるま新報』「映画常設館那覇に出現ーアーニパイル國際劇場は今回映画常設館として娯楽に飢えた那覇っ子を喜ばすことになったが1月21日には文化部主催で盛大な開館式を挙行、当日は軍政府より・・」
□MG会副会長で米軍政府経済部の翻訳官の大城つる女史が、『宗教雑誌を出版したいという人がいるが許可できますか』と訪ねてきた。数日後、本人から出版申請書が出された。終戦直後糸満で壕から這い出した虚脱状態の同胞に希望と笑いをとりもどさせる働きをした与那城勇氏『ゴスペル』(福音)という神の国建設への啓蒙雑誌であり、聖書の解説や迷信の解明など政治色のない編集内容だったので私は喜んで許可した。この月刊誌も『月刊タイムス』と同じ謄写版刷り四六判の30頁、与那城氏が糸満教会に勤務している数年間、根気強く発行した。与那城氏はのち糸満教会を辞し、小禄で歯科医院を開業したが、『ゴスペル』の中jから抜粋した主張や随筆、解説など集めた単行本『琉球エデンの物語』を上梓した。
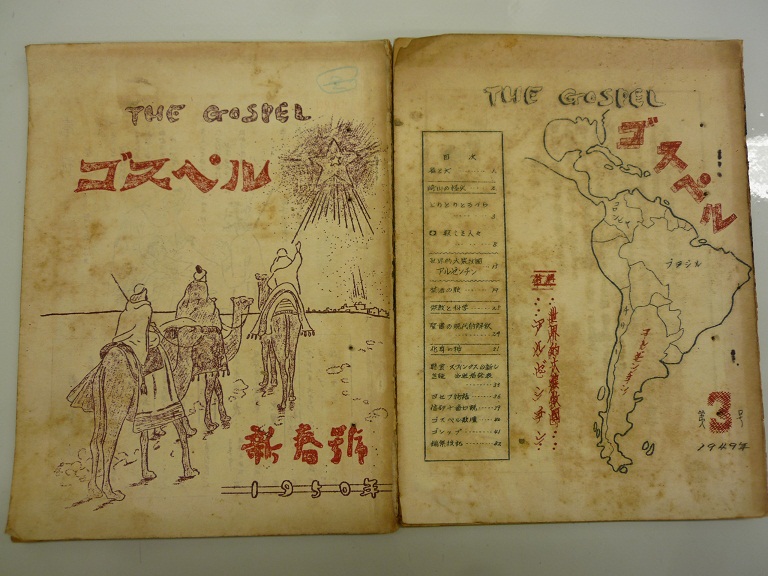 『ゴスペル』
『ゴスペル』■2012年8月8日、平和通りで我が古里・粟国島に縁故がある玉寄哲永氏と出会い話を聞いた。この与那城勇氏も粟国島と縁故がある。本人が『南歯の歩み』に記した経歴に「14才の時から洋服屋の丁稚、16才で大阪に渡り、回覧雑誌(貸本)の配達をしながら独力で学費を稼いで夜間中学に通っていた私の様な貧しい少年にとってはまさに希望の灯火そのものでありました。私はその頃から『救世軍』という名のキリスト教の一派に加わっていましたが、ゆくゆくは伝道者になろうと心に決めておりました。その計画遂行には独り立ちできる生活力を身につける事が先決だと考えたのですが、たまたま書生として住み込んでいた歯科医院の先生の影響もあって歯科の道を志したのでした。」として猛勉強して朝鮮総督府の歯科医師検定試験に合格した。
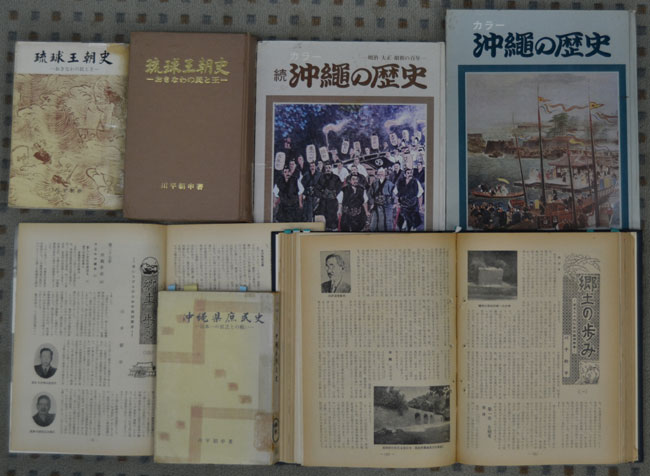
川平朝申の歴史書/下右の1959年7月発行の『今日の琉球』から始まった川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史ー」が私に琉球史へ関心を持たせたもの。②では「人間のおこり」から始まっていた。
2012年9月3日 『沖縄タイムス』斎木喜美子「川平朝申の児童文学①」
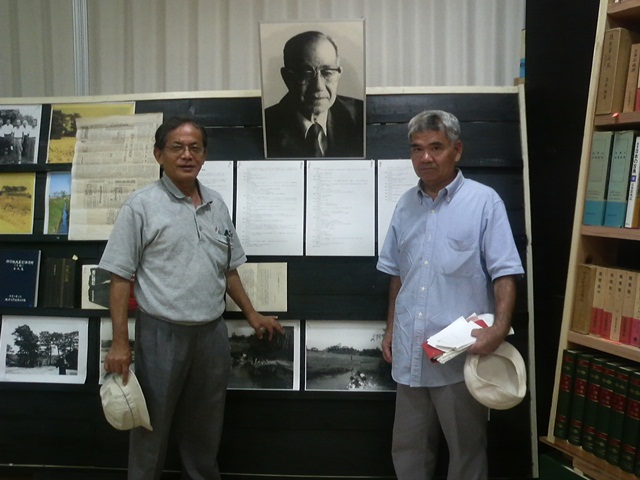
今帰仁村歴史文化センターでー左が館長・仲原弘哲氏と新城栄徳(渚さん撮影)
本日、文化の杜の渚さん運転のクルマで今帰仁と本部を廻った。渚さんは本部生まれで北山高校出身。今帰仁村教育委員会で、今帰仁城発掘や『百按司墓木棺修理報告書』編集にも関わっていて今帰仁に詳しい。今帰仁村歴史文化センターで館長の仲原弘哲氏が出迎えた。仲原氏は渚さんとも旧知の間柄。2012年8月22日寄贈された仲宗根政善の資料・本(100箱余.り)が地下書架に並んでいた。ガラスケースにある『琉球国由来記』(「1946年、山城善光氏帰沖,伊波先生からの手紙と『琉球国由来記』の写本,服部四郎氏から米語辞典が届けられる」と略年譜にある)には仲宗根宛の伊波普猷の署名がある。東江長太郎『通俗琉球北山由来記』(1935年11月)もある。□→1989年3月、東江哲雄、金城善編により那覇出版社から『古琉球 三山由来記集』が刊行された。
全集類は『比嘉春潮全集』(新聞スクラップが貼りこまれている。)『宮良當壮全集』『仲原善忠全集』『琉球史料叢書』などが目についたが、とくに日本図書センターの『GHQ日本占領史』はかなりの巻数である。安良城盛昭『天皇制と地主制』上下もある。
今帰仁関係を始めとして国文学雑誌や、琉球大学関係資料、同僚であった大田昌秀の著書も多数。また伊波普猷との関連で那覇女トリオの新垣美登子、金城芳子、千原繁子の署名入りの贈呈本もある。平山良明の論文原稿①、仲程昌徳『お前のためのバラード』、我部政男、渡邊欣雄、池宮正治、比屋根照夫、野口武徳、川満信一などの本も署名入りが並んでいた。娘婿が編集した『島田寛平画文集 1898-1967」 寛平先生を語る会1994年11月も目についた。
①
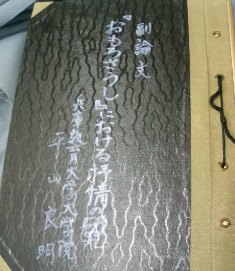 □
□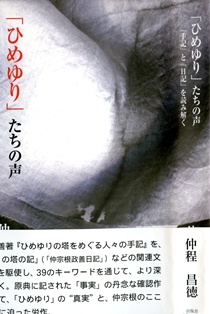 □2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)
□2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)天皇関係、大学紛争を特集した雑誌もある。マクルーハン②の本もあった。マクルーハンは、もともとは文学研究者として出発したが、その後メディア論を論じる(挑発的にして示唆に富んだ)社会科学者として名を成した。60年代後半~80年代前半にかけて爆発的な影響力を誇った。「内容ではなく、むしろそのメディア自身の形式にこそ、人びとに多くをつたえているのだ」と訴えることをつうじて、それまでの活字文化と、ラジオ文化、テレビ文化 相互のあいだにかれが差異線をひいたことは、いまだに重要である。 (ウィキペディア)
②
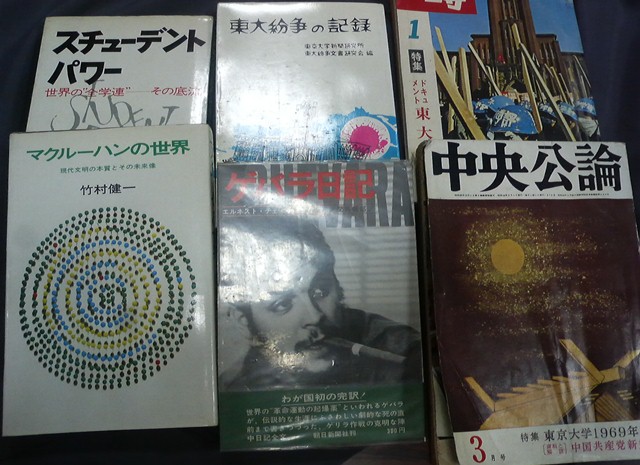
沖縄言語研究センターの「仲宗根政善 略年譜」を見ながら今帰仁村歴史文化センター書架に並んでいる本を思いつくまま記していくことにする。()内・写真・□は新城追加。
1907年(明治40年4月26日)
沖縄県国頭郡今帰仁村字与那嶺にて,父仲宗根蒲二,母カナの長男として生まれる 。生家は農業を営む。母カナは,名護の町を一度見たいというのが夢であったが,終生ついにかなえられなかった。祖父政太郎は,謝花昇(1908年死亡)に私淑していた。謝花は近在まで出張してくる都度,仲宗根家に宿をとった。
□1913年
9月5日 今帰仁村字与那嶺715番地に、父島袋松次郎(教師)、母静子(教師)の長男として霜多正次生まれる。→書架には霜多作品もある。
1914年~1919年(大正3年~8年)
兼次尋常小学校(大正8年4月1日,高等科併置,校名を兼次尋常高等小学校と改名する)に入学。桃原良明校長(4代),安里萬蔵校長(5代),安冨祖松蔵校長(6代),上里堅蒲校長(7代),当山美津(正堅夫人)等から直接教えを受ける。32歳の若さで赴任してきた上里校長に出会ったことによって,生涯を決定される。伊波普猷「血液及び文化の負債」の民族衛生講演で兼次小を訪れる。
1920年(大正9年)
沖縄県立第一中学校に入学。大宜見朝計(書架に1979年発行『大宜見朝計氏を偲ぶ』これに政善は「二人でたどった道」を書いている。川平朝申の文章もある。),島袋喜厚,上地清嗣等, 国頭郡から7名。中城御殿(現博物館)裏にあった駕籠屋新垣小に最初下宿。
母カナ死亡(享年40歳)。14歳になるまで,一晩中目がさえて一睡もできなかったということは一度もなかったが,虫のしらせか母の亡くなった夜だけは,蚊帳の上をぐるぐる飛んでいるホタルが妙に気になって,とうとう一睡もできなかったという経験をする。
泉崎橋の近くで,初めて伊波普猷の姿に接する。4年から5年にかけて,英語を担当していた胡屋朝賞先生の感化を受ける。
1926年(大正15,昭和元年)
福岡高等学校文科乙類に入学。沖縄から最初の入学者であった。級友から珍しがられ,親切にされる。翌27年には,大宜見朝計が入学。
伊波普猷著『孤島苦の琉球史』と『琉球古今記』を買い求め貧り読む。
安田喜代門教授から『万葉集』の講義を聞き,万葉の中に,日常用いている琉球方言がたくさん出て来るのに興味を覚える。また,考古学の玉泉大梁教授から,日本史の中ではじめて琉球史の概要を聞く。ドイツ語担当白川精一教授の感化を受け,ドイツ語に興味を持つ。
1929年(昭和4年)
東京帝国大学文学部国文学科入学。同年入学者に林和比古,永積安明, 吉田精一,犬養孝,岩佐正,西尾光雄等がいた。
本郷妻恋町に最初下宿。2年の時から国語学演習で,橋本進吉教授に厳しく鍛えられる。同ゼミに先輩の服部四郎,有坂秀世氏等がいた。服部氏が,今帰仁村字与那嶺方言のアクセントを調査し整理して,法則を示してくれたことによって, 郷里の方言に一層興味を持つようになる。金田一京助助教授のアイヌ語の講義,佐々木信綱講師の万葉集の講義を受ける。
伊波普猷先生宅に出入りするようになる。
1931(昭和6年)
第二回南島談話会で,はじめて柳田国男,比嘉春潮,仲原善忠, 金城朝永,宮良当壮に会う。
1932(昭和7年)
東京帝国大学文学部国文学科卒業。世は不況のどん底にあって,町にはルンペンがあふれていた。就職口もなく,朝日新聞に広告を出しても家庭教師の口すら年の暮れまで見つけることができないというような状況であった。
たまたま,県視学の幸地新蔵氏から,郷里の第三中学校に来ないかとの手紙があって,伊波普猷先生に相談。「東京でいくら待っても職はないし,2,3年資料でも集めて来てはどうか」と言われ,帰郷する気になる。
★「語頭母音の無声化」(『南島談話』第5号)。
★「今帰仁方言における語頭母音の無声化」(『旅と伝説』)。
1933年(昭和8年)
名護の沖縄県立第三中学校に教授嘱託として赴任。伊波普猷先生から,蚕蛹の方言を調査してほしい旨の手紙を受け,さっそく生徒126名を対象に,国頭郡の各部落の方言を調査し報告する。方言使用禁止の風潮の中で,方言を調べ研究するのを,生徒たちから不思議に思われる。伊礼正次,サイ夫妻の長女敏代と結婚。
1934年(昭和9年)
★「国頭方言の音韻」(『方言』第4巻第10号)。
1936年(昭和11年)
折口信夫先生を嶋袋全幸氏と共に案内。正月を名護で迎える。北山城趾見学の帰り,与那嶺の実家に立ち寄る。
三中から沖縄女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校に転勤を命ぜられる。『姫百合のかおり』(沖縄県女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校,30周年記念号)の編集委員を勤める。
★「加行変格『来る』の国頭方言の活用に就いて」(『南島論叢』)。
1937年(昭和12年)
川平朝令校長から「国民精神文化研究所」に研修に行くことをすすめられ,あまり気のりがしなかったが, 東京へ転ずるきっかけをつかむことができるかも知れないとの希望があって,目黒長者丸にあった同研究所へ入所する。
伊波先生を塔の山の御宅に訪ね,入所報告をすると「紀平正美などが,『神ながらの』道を講じているようだが,あんなのを学問だと思っては大間違いだ。研究所に通うより,うちに来て勉強するがよい」と注意を受けて近くに宿を貸りる。先生に励まされ,研究意欲に燃えて,夏の終わりに帰省。
1909年3月19日ー『沖縄毎日新聞』伊波月城「誓閑寺時代の回顧」(以って入社の辞に代ふ)9年前のことである。家兄が京都に行った後で、迷子同様になった自分は、当時國光社に居られた恩師田島隋々庵氏の京橋南小田原町の僑居に這入り込むことになった所が、元来閑静な所が好きな自分は、間もなく牛込は喜久井なる誓閑寺に、今の甲辰の校長東恩納氏と同居して自炊することになった。お寺に引越したのは8月の上旬である。日はよくは覚えていないが、恰度同郷の友人を誓閑寺の隣なる大龍寺の墓地に葬ってから2日目の夕暮れであった。お寺は浄土宗で、住職の外に、小学校に通う子供と仙台辺の田舎者だと云う婆さんがいた。その婆さんが住職の梵妻なので、住職より10歳も老けて見えた。自分は三畳の室をあてがわれた。室は南向きで風通しはよかったが、戸端から一間先に、墳墓が並んでいたのには、聊か閉口した。併し後では墳墓と親しむようになった。自分が今日墓畔を逍遥するを一種の快楽とするようになったのは詩人イプセンの感化ばかりでもないのである。10日位たつと当間浮鷗氏が其の親戚の外間氏と共に引越して来て仲間になった。それから間もなく諸見里南香氏が上京された。沖縄時論が解散したので、この10年間は郷里には帰れないといって居られた。南香氏は10日ばかりすると日本新聞の記者となられた。誓閑時は俄かに賑わったのである。
8月中は、学校が休みなので、何れものんきに法螺を吹いて暮らしていた。朝は木魚の音と読経の声に目が覚める。総がかりで朝飯の支度をする。朝飯がすむと銘々で散歩に出かける。散歩から帰って来ると昼飯の用意に取りかかる。昼飯がすむと、下町の方に出かけるものもあれば、華胥の國に遊ぶのもいた。共同生活の快楽は一つ釜から飯を食べるということである。併し社会主義というものが、到底地上で行われるべきでないと思ったのはこの時である。一番戦闘力が強かったのは東恩納氏で、一番戦闘力が弱かったのは外間氏であった。外間氏は列強の略奪に遭って泣き出したこともある。浮鷗氏は此頃からの潔癖家である。東恩納氏は有名な無精者で、自分が座っていた2尺平方の掃除も碌にしなかった位である。南香氏は郷里で奮闘した結果、意気消沈してしまって、何らの特色も発揮しなかった。自分は其時からの酔漢で、5名のうちで酒屋の信用が一番重かった方である。
木魚の音と読経の声は聞きなれると心持のよいものである。浮鷗氏が禅味を帯び始めたのもこの頃からであろう。自分が耶蘇に帰依したのも此頃である。誓閑寺時代は自分に取っては忘れることの出来ない時代である。今から考えて見ると誓閑寺の一隅は沖縄の社会の或る一部の縮図であった。9月になって皆下町の方に引越した。思えば昨今のことのようであるが、足かけた年になる。自分は依然たる呉下の旧阿の蒙である。
毎日紙の発刊当時、自分は社友となって、いかがわしい翻訳物を出して世の物笑となって居る所に、去る15日の朝、當間氏から来て呉れとの手紙を受けて、早速いって見ると記者にするつもりであるが如何かとのことであった。自分は一人で決定が出来ないので、帰ってきて家兄と相談した後で承諾と云う意味の手紙を出した。所が文章一つ書けけない自分がどうして記者などになれる。家兄に聞くと君が平常使用している普通語で、君の思想感情を飾りなく、、偽りなくせんじつめて吐き出せ。形容詞も知らなければ知らないでいい。漢字も知らなければ知らなくてもいい。只だ耳障りにならないように書け、10年も書いたらいくらか物になるとのことである。自分は此教訓に遵って書くつもりである。
新聞を起こして見ようということは誓閑寺時代から先輩諸氏が口ぐせのようにいっていたことであるが、10年後の今日この小理想は漸く実現せられて、自分までが編集室の一椅子を占めるようになった。さアこれから自分は、どういう方面に、どう働いたらよかろう?心配でたまらない。(をはり)
◇新宿区喜久井町61 亀鶴山易行院誓閑寺 深川靈嚴寺末
寛永七年靈岸嶋に起立、明暦大火後宗参寺領の内庚申塚に借地移轉。寛文六年七月喜久井町に移る。開山重蓮社本譽上人誓閑和尚、寛永二年五月十五日卒。舊境内借地二千百八十一坪、古跡年貢地済松寺領百三十三坪。境内に直径二尺六寸の大鐘があり、元和二年二月藤原兼長の作で、鐘銘に『荏原郡』と記入してあるので、史家の間に注意されたものである。書上に『境内小川あり、荏原郡と豊島郡との境なり、本堂のある方を荏原と云』とある。(「牛込區史」より)/夏目漱石は自宅すぐ近くの誓閑寺の鉦の音について、随筆「硝子戸の中」でふれている。今は近くに漱石山房記念館、草間彌生美術館。
1900年4月8日「東京・沖縄青年会ー平良保一君卒業記念」

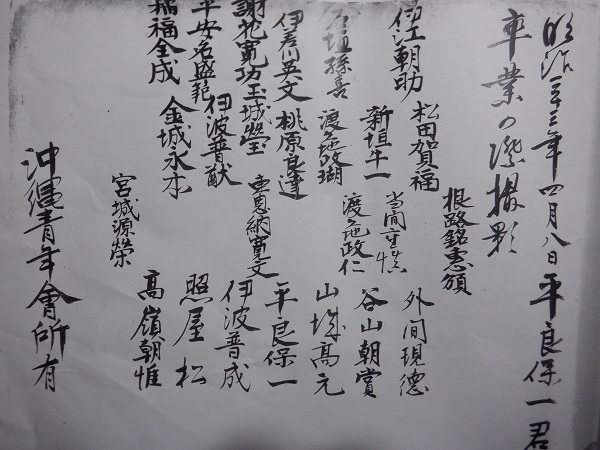
〇伊江朝助、伊波普猷、伊波普成、當間重慎、渡久地政瑚、東恩納寛文ら後に沖縄の新聞界で活躍する面々が居並ぶ。ちなみに外間現徳は前列左端、この写真は沖縄県立図書館の東恩納洋資料にあるもの。この写真の時代背景は伊波普成が1909年3月19日『沖縄毎日新聞』に書いた入社の辞「誓閑寺時代の回顧」でよく分かる。私が最初にこの写真を紹介したのは1994年『沖縄タイムス』粟国恭子「末吉麦門冬」の8月8日。次いで1997年、那覇市文化局資料室の『おもろと沖縄学の父・伊波普猷ー没後50年』に収録した。
8月中は、学校が休みなので、何れものんきに法螺を吹いて暮らしていた。朝は木魚の音と読経の声に目が覚める。総がかりで朝飯の支度をする。朝飯がすむと銘々で散歩に出かける。散歩から帰って来ると昼飯の用意に取りかかる。昼飯がすむと、下町の方に出かけるものもあれば、華胥の國に遊ぶのもいた。共同生活の快楽は一つ釜から飯を食べるということである。併し社会主義というものが、到底地上で行われるべきでないと思ったのはこの時である。一番戦闘力が強かったのは東恩納氏で、一番戦闘力が弱かったのは外間氏であった。外間氏は列強の略奪に遭って泣き出したこともある。浮鷗氏は此頃からの潔癖家である。東恩納氏は有名な無精者で、自分が座っていた2尺平方の掃除も碌にしなかった位である。南香氏は郷里で奮闘した結果、意気消沈してしまって、何らの特色も発揮しなかった。自分は其時からの酔漢で、5名のうちで酒屋の信用が一番重かった方である。
木魚の音と読経の声は聞きなれると心持のよいものである。浮鷗氏が禅味を帯び始めたのもこの頃からであろう。自分が耶蘇に帰依したのも此頃である。誓閑寺時代は自分に取っては忘れることの出来ない時代である。今から考えて見ると誓閑寺の一隅は沖縄の社会の或る一部の縮図であった。9月になって皆下町の方に引越した。思えば昨今のことのようであるが、足かけた年になる。自分は依然たる呉下の旧阿の蒙である。
毎日紙の発刊当時、自分は社友となって、いかがわしい翻訳物を出して世の物笑となって居る所に、去る15日の朝、當間氏から来て呉れとの手紙を受けて、早速いって見ると記者にするつもりであるが如何かとのことであった。自分は一人で決定が出来ないので、帰ってきて家兄と相談した後で承諾と云う意味の手紙を出した。所が文章一つ書けけない自分がどうして記者などになれる。家兄に聞くと君が平常使用している普通語で、君の思想感情を飾りなく、、偽りなくせんじつめて吐き出せ。形容詞も知らなければ知らないでいい。漢字も知らなければ知らなくてもいい。只だ耳障りにならないように書け、10年も書いたらいくらか物になるとのことである。自分は此教訓に遵って書くつもりである。
新聞を起こして見ようということは誓閑寺時代から先輩諸氏が口ぐせのようにいっていたことであるが、10年後の今日この小理想は漸く実現せられて、自分までが編集室の一椅子を占めるようになった。さアこれから自分は、どういう方面に、どう働いたらよかろう?心配でたまらない。(をはり)
◇新宿区喜久井町61 亀鶴山易行院誓閑寺 深川靈嚴寺末
寛永七年靈岸嶋に起立、明暦大火後宗参寺領の内庚申塚に借地移轉。寛文六年七月喜久井町に移る。開山重蓮社本譽上人誓閑和尚、寛永二年五月十五日卒。舊境内借地二千百八十一坪、古跡年貢地済松寺領百三十三坪。境内に直径二尺六寸の大鐘があり、元和二年二月藤原兼長の作で、鐘銘に『荏原郡』と記入してあるので、史家の間に注意されたものである。書上に『境内小川あり、荏原郡と豊島郡との境なり、本堂のある方を荏原と云』とある。(「牛込區史」より)/夏目漱石は自宅すぐ近くの誓閑寺の鉦の音について、随筆「硝子戸の中」でふれている。今は近くに漱石山房記念館、草間彌生美術館。
1900年4月8日「東京・沖縄青年会ー平良保一君卒業記念」

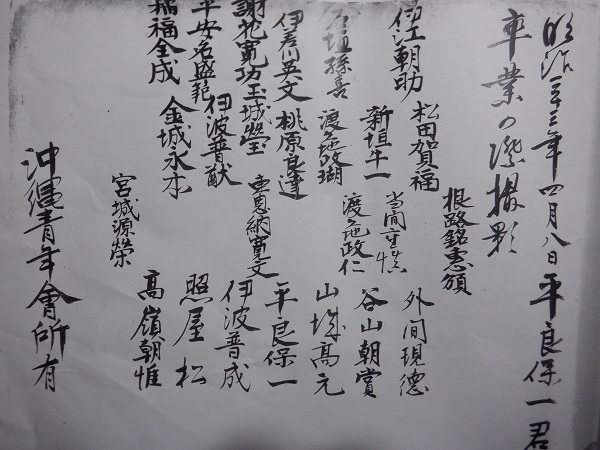
〇伊江朝助、伊波普猷、伊波普成、當間重慎、渡久地政瑚、東恩納寛文ら後に沖縄の新聞界で活躍する面々が居並ぶ。ちなみに外間現徳は前列左端、この写真は沖縄県立図書館の東恩納洋資料にあるもの。この写真の時代背景は伊波普成が1909年3月19日『沖縄毎日新聞』に書いた入社の辞「誓閑寺時代の回顧」でよく分かる。私が最初にこの写真を紹介したのは1994年『沖縄タイムス』粟国恭子「末吉麦門冬」の8月8日。次いで1997年、那覇市文化局資料室の『おもろと沖縄学の父・伊波普猷ー没後50年』に収録した。
1888年・第1回卒業ー高嶺朝申、仲吉朝助(農大乙科卒)、百名朝計(沖縄銀行頭取)/1889年・第2回卒業ー石原榮輔、村山盛福/1891年・第3回卒業ー伊地柴本(首里市役所)、恩河朝祐、金城紀長、仲吉朝紀、若山忠次郎/1893年3月・第4回卒業ー呉屋健哉」、重久雄吉(宮古郡税務署長)、谷川益太郎、與儀喜英(産業銀行) 同年5月・第5回卒業ー大城盛祐(長崎控訴院書記)、大城朝健、仲濱政数(台湾製糖会社那覇事務所)/1894年・第6回卒業ー新垣壽助(小倉電気商会)、赤嶺新竹、奥川鐘太郎(在東京)、島袋松、瀘名波起益、玉那覇重善、知念堅輝(農大実科卒産業銀行重役 大里村長)、照屋孚能、長嶺紀啓、橋本諭吉(在台湾)、安元實得(在米)/1895年・第7回卒業ー伊藤雅二(那覇池田店 那覇市議)、蒲原秀一、本村啓介、久場景述、崎間永行、玉城瑩(早稲田卒)、富盛寛卓(宮古小学校)、比嘉賀学(那覇市助役)、山城瑞喜
1896年・第8回卒業ー伊波普猷(文学士 県立図書館長)、小橋川朝松(八重山)、下地昌道/1897年・第9回卒業ー新垣隆永、伊波善思(県会議員)、伊差川英文、親泊朝輝(愛媛県宇和郡長)、金城紀光(医学士 元順病院 那覇市議)、小禄恵芝、酒井豊雄、松原寛功、祝嶺春棟、高嶺朝扶(早稲田大卒 首里)、武富良秀、照屋徳太郎、友寄善直、名嘉眞武煌、肥後傳熊、真境名安興、山内盛能、屋比久孟昌/1898年・第10回卒業ー浦崎康信、許田普永、久高友輔(首里郵便局長 首里市会議員)、兒玉銓吉、高山徹(元玉那覇 農学士 山本農相別邸)、天願貞靜、渡久地政瑚、田中豊彦、西弘海、根路眼恵頒(普天間)、野原春太郎、饒平名紀腆(名古屋医専卒 那覇波上病院)、東恩納盛亮(台湾高雄州旗山第二公学校)、平野益照(大島庁々書記)、藤田孝男(海軍機関大尉)、古堅宗祐、外間現篤(法学士 朝鮮大邱 弁護士)
1899年・第11回卒業ー新城源次郎、新川善義、新川善長(臺灣花蓮港林田駅内徳森製材所)、石川親忠、伊波普成(牧師 那覇)、喜屋武盛長(在米)、久場守益(那覇 石炭運送業)、熊谷照英、古波蔵信貞、小嶺幸欣(那覇東)、崎山宗秀(東京高等師範卒 文学士 京都大学院)、佐久原好傳(伝道師 メソジスト教会)、玉那覇平益、照屋孚至(久米島登記所)、宮城鐵夫(農学士 台南製糖社宅)、山代質、與古田良成/1900年・第12回卒業ー有川五郎(長崎医専卒)、赤嶺仁太、池ノ上嘉(在台北)、伊波興旺、岩城長蔵、糸数青盛(那覇市役所)、臺数弘榮(県立師範学校教諭)、漢那憲英(那覇甲辰小学校訓導)、國吉眞徳、小嶺幸慶(法学士 勧銀支店)、小波津清榮、崎浜秀主(早稲田高等師範卒 商銀専務取締役)、島袋慶福(真壁小学校長)、富原守昌、仲里貞助(宮崎小林税務署)、仲村渠寛忠、野村安保、東恩納寛惇(文学士 東京府立第一中学校教諭)、肥後武二郎(台南製糖会社西原工場)、比嘉盛珍(福岡県若松炭坑株式会社)、藤田猛(長崎医専卒 長崎開業)、福永兼吉(歩兵大尉 熊本十三聯隊中隊長)、福永福要、眞榮平房貞、山田朝常、與那覇政敷
1901年・第13回卒業ー安次嶺榮華(専修大学卒 那覇市役所)、糸数東榮(在布)、大山岩雄(早稲田大学文科卒 県立農学校教諭)、大山辰二(長崎医専卒 臺灣臺北市西門街開業)、小野榮(商業学校教諭)、大城元次郎(名護村長)、金城加那(那覇技芸学校)、金城盛行、神田橋榮助、金城普照(農大実科卒 島尻郡役所技手)、金城兼吉、城間恒用、城間宏恵(長崎医専卒 支那漢口医院)、桑江良行(早稲田大卒 県立二中教諭)、久場守友(与那原郵便局長)、酒井豊静(開業医)、座喜味盛彰、島袋盛昌、玉城濶(千葉医専卒 糸満開業)、平良仁五郎、玉城安盛、手登根順義、照屋久八(在台湾)、當山順吉(恩納村 役場員)、仲本興賀、仲村政哲(那覇商業銀行)、名嘉山安忠(長崎医専卒 撫臺街開業)、仲本政春(歩兵中尉 那覇市議)、仲村渠榮行(在米)、仲宗根新一郎、前田忠(高商卒 横浜正金銀行シンガポール支店長)、百名朝敏(青山学院卒 尚家家扶心得)、前堂昌俊、松元完榮(県師範学校書記)、宮城寛良(那覇港務所)、宮城嗣謹(八王子小学校教員)、宮里仁榮(大阪医専卒 秋田県山本郡扇淵村)、宮城助友(八重山炭鉱)、勝屋米雄(臺灣総督府通信局)、山城範益(首里市会議員 砂糖委託組合理事)、山城正鳴(臺灣公学校)、與儀正道(在米)
1902年・第14回卒業ー伊仲浩(農大実科卒 那覇)、稲福蒲戸、大橋敬二(巣鴨監獄看守長)、大濱保篤(農大実科卒 鹿児島専売局)、大城幸蔵(ヒリピン大田興行株式会社副社長)、神山政良(法学士 東京市外淀橋専売支局)、金城嘉保(金沢医専卒 那覇医院主)、賀数仁王(開業医 高嶺村與座)、我部政明、嘉手納並藝(後備歩兵少尉 那覇港務所)、喜瀬知彦(宮崎税務署)、國吉眞文(商船学校卒 神戸市日本郵船会社気付デラゴヤ丸)、久高唯忠(医専卒 東京大塚辻町愛仁堂)、小嶺幸輝(名古屋高工卒)、古波鮫唯仁、米須秀松、多嘉良憲(農学士)、玉城實雄(京都医専卒)、高宮城朝三(内閣印刷局)、高嶺朝安(早稲田専門卒)、平良淳榮、渡口精秀(商船学校卒)、渡嘉敷唯續(金沢医専卒 在臺灣)、渡嘉敷通達(県庁)、長嶺亀助(歩兵少佐 陸大卒 参謀本部)、仲本盛松、仲吉朝宏(中城小学校長)、長嶺但吉、仲尾次喜與(在米國桑港)、仲村渠良保、西村助八(農大実科卒 県産業技師物産検査所長)、毛嘉富良、平田直保(県属会計課)、比嘉盛敬、平敷安興(在米)、外間現長(大阪高医卒 大阪府技師)、外間現多(青山学院卒)、丸山芳樹(京大工学士 朝鮮総督府技師)、眞栄平房寛、牧港朝謙(首里市役所)、宮城幸安(商船学校卒 日本郵船会社機関長)、屋富祖徳次郎(金沢医専卒 泊開業)、山川朝棟(沖縄銀行首里支店長)、與儀正榮(農大実科卒 新高製糖会社農課長)
1896年・第8回卒業ー伊波普猷(文学士 県立図書館長)、小橋川朝松(八重山)、下地昌道/1897年・第9回卒業ー新垣隆永、伊波善思(県会議員)、伊差川英文、親泊朝輝(愛媛県宇和郡長)、金城紀光(医学士 元順病院 那覇市議)、小禄恵芝、酒井豊雄、松原寛功、祝嶺春棟、高嶺朝扶(早稲田大卒 首里)、武富良秀、照屋徳太郎、友寄善直、名嘉眞武煌、肥後傳熊、真境名安興、山内盛能、屋比久孟昌/1898年・第10回卒業ー浦崎康信、許田普永、久高友輔(首里郵便局長 首里市会議員)、兒玉銓吉、高山徹(元玉那覇 農学士 山本農相別邸)、天願貞靜、渡久地政瑚、田中豊彦、西弘海、根路眼恵頒(普天間)、野原春太郎、饒平名紀腆(名古屋医専卒 那覇波上病院)、東恩納盛亮(台湾高雄州旗山第二公学校)、平野益照(大島庁々書記)、藤田孝男(海軍機関大尉)、古堅宗祐、外間現篤(法学士 朝鮮大邱 弁護士)
1899年・第11回卒業ー新城源次郎、新川善義、新川善長(臺灣花蓮港林田駅内徳森製材所)、石川親忠、伊波普成(牧師 那覇)、喜屋武盛長(在米)、久場守益(那覇 石炭運送業)、熊谷照英、古波蔵信貞、小嶺幸欣(那覇東)、崎山宗秀(東京高等師範卒 文学士 京都大学院)、佐久原好傳(伝道師 メソジスト教会)、玉那覇平益、照屋孚至(久米島登記所)、宮城鐵夫(農学士 台南製糖社宅)、山代質、與古田良成/1900年・第12回卒業ー有川五郎(長崎医専卒)、赤嶺仁太、池ノ上嘉(在台北)、伊波興旺、岩城長蔵、糸数青盛(那覇市役所)、臺数弘榮(県立師範学校教諭)、漢那憲英(那覇甲辰小学校訓導)、國吉眞徳、小嶺幸慶(法学士 勧銀支店)、小波津清榮、崎浜秀主(早稲田高等師範卒 商銀専務取締役)、島袋慶福(真壁小学校長)、富原守昌、仲里貞助(宮崎小林税務署)、仲村渠寛忠、野村安保、東恩納寛惇(文学士 東京府立第一中学校教諭)、肥後武二郎(台南製糖会社西原工場)、比嘉盛珍(福岡県若松炭坑株式会社)、藤田猛(長崎医専卒 長崎開業)、福永兼吉(歩兵大尉 熊本十三聯隊中隊長)、福永福要、眞榮平房貞、山田朝常、與那覇政敷
1901年・第13回卒業ー安次嶺榮華(専修大学卒 那覇市役所)、糸数東榮(在布)、大山岩雄(早稲田大学文科卒 県立農学校教諭)、大山辰二(長崎医専卒 臺灣臺北市西門街開業)、小野榮(商業学校教諭)、大城元次郎(名護村長)、金城加那(那覇技芸学校)、金城盛行、神田橋榮助、金城普照(農大実科卒 島尻郡役所技手)、金城兼吉、城間恒用、城間宏恵(長崎医専卒 支那漢口医院)、桑江良行(早稲田大卒 県立二中教諭)、久場守友(与那原郵便局長)、酒井豊静(開業医)、座喜味盛彰、島袋盛昌、玉城濶(千葉医専卒 糸満開業)、平良仁五郎、玉城安盛、手登根順義、照屋久八(在台湾)、當山順吉(恩納村 役場員)、仲本興賀、仲村政哲(那覇商業銀行)、名嘉山安忠(長崎医専卒 撫臺街開業)、仲本政春(歩兵中尉 那覇市議)、仲村渠榮行(在米)、仲宗根新一郎、前田忠(高商卒 横浜正金銀行シンガポール支店長)、百名朝敏(青山学院卒 尚家家扶心得)、前堂昌俊、松元完榮(県師範学校書記)、宮城寛良(那覇港務所)、宮城嗣謹(八王子小学校教員)、宮里仁榮(大阪医専卒 秋田県山本郡扇淵村)、宮城助友(八重山炭鉱)、勝屋米雄(臺灣総督府通信局)、山城範益(首里市会議員 砂糖委託組合理事)、山城正鳴(臺灣公学校)、與儀正道(在米)
1902年・第14回卒業ー伊仲浩(農大実科卒 那覇)、稲福蒲戸、大橋敬二(巣鴨監獄看守長)、大濱保篤(農大実科卒 鹿児島専売局)、大城幸蔵(ヒリピン大田興行株式会社副社長)、神山政良(法学士 東京市外淀橋専売支局)、金城嘉保(金沢医専卒 那覇医院主)、賀数仁王(開業医 高嶺村與座)、我部政明、嘉手納並藝(後備歩兵少尉 那覇港務所)、喜瀬知彦(宮崎税務署)、國吉眞文(商船学校卒 神戸市日本郵船会社気付デラゴヤ丸)、久高唯忠(医専卒 東京大塚辻町愛仁堂)、小嶺幸輝(名古屋高工卒)、古波鮫唯仁、米須秀松、多嘉良憲(農学士)、玉城實雄(京都医専卒)、高宮城朝三(内閣印刷局)、高嶺朝安(早稲田専門卒)、平良淳榮、渡口精秀(商船学校卒)、渡嘉敷唯續(金沢医専卒 在臺灣)、渡嘉敷通達(県庁)、長嶺亀助(歩兵少佐 陸大卒 参謀本部)、仲本盛松、仲吉朝宏(中城小学校長)、長嶺但吉、仲尾次喜與(在米國桑港)、仲村渠良保、西村助八(農大実科卒 県産業技師物産検査所長)、毛嘉富良、平田直保(県属会計課)、比嘉盛敬、平敷安興(在米)、外間現長(大阪高医卒 大阪府技師)、外間現多(青山学院卒)、丸山芳樹(京大工学士 朝鮮総督府技師)、眞栄平房寛、牧港朝謙(首里市役所)、宮城幸安(商船学校卒 日本郵船会社機関長)、屋富祖徳次郎(金沢医専卒 泊開業)、山川朝棟(沖縄銀行首里支店長)、與儀正榮(農大実科卒 新高製糖会社農課長)
06/06: 龍脈/沖縄の大本系の教団
私は1999年5月発行の『沖縄近代文化年表』(琉文手帖4号)に「1916(大正5)年9月10日ー暁烏敏来沖」と記した。このときは琉球新報が11日に「暁烏敏先生を訪ふ」が載っている。公文書館が収集した1925(大正14)年3月4日『沖縄朝日新聞』に「暁烏敏 昨日来県、西新町南陽旅館へ」が載っている。
暁烏敏 あけがらす-はや
1877-1954 明治-昭和時代の僧,仏教学者。
明治10年7月12日生まれ。清沢満之(まんし)に師事して浩々洞(こうこうどう)にはいり,明治34年雑誌「精神界」を発刊,精神主義をとなえる。のち生家の石川県真宗大谷派明達寺の住職となり,布教と著述につとめた。昭和26年同派宗務総長。昭和29年8月27日死去。77歳。真宗大(現大谷大)卒。法名は恵祐。著作に「歎異抄講話」など。
【格言など】人が自分を軽蔑して居るというて憤慨するのは自分自らが軽蔑しているのだ。→コトバンク
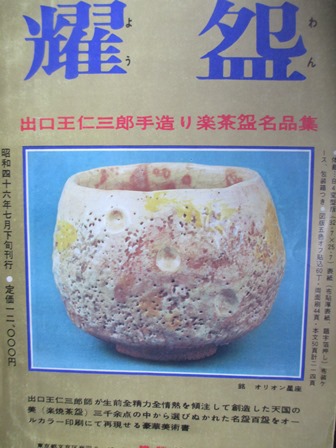
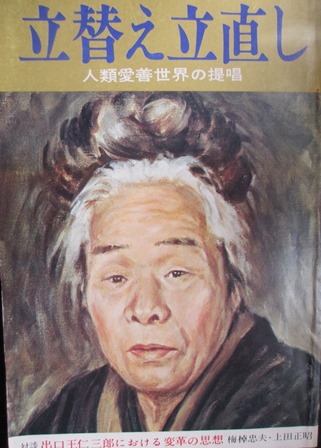
1971年5月 『建替え建直しー人類愛善世界の提唱』出口王仁三郎生誕百年記念会
2003年正月 沖縄県護国神社に行くと鳥居に日本民主同志会/松本明重とあった。懐かしい名前である。平良盛吉翁の『関西沖縄開発史 : 第二郷土をひらく 』1971を援助し日本民主同志会本部名で発行していた。松本氏は世界救世教外事対策委員長、祇園すえひろ会長だが、沖縄に関わり、「京都の塔」「小桜の塔」に碑を建てている。この人とダブって思い出したのが、「元祖スエヒロ」という「しゃぶしゃぶ」の店を経営している大阪日本工芸館長の三宅忠一氏である。この人も沖縄民芸などに力を入れていた。
松本氏は東本願寺紛争にも名が出てくる。相対する西本願寺と云えば弟22世門主・大谷光瑞が思い出される。戦前沖縄の新聞に、光瑞来沖かと云う記事を見たことがあるが、結局来なかったようである。その代わりというか弟の大谷尊由が1918年2月に来沖し相当に歓迎されたようである。光瑞と同じく宗教界の怪物と知られる人物に大本の出口王仁三郎が居る。その大本宣教場の亀岡「天恩郷」は明智光秀の居城跡で、そこに沖縄から奉仕活動に来ていた金城ひろこさんを大城敬人(現名護市会議員)氏に紹介されて遊びによく行った。
虎瀬公園は、モノレール儀保駅から歩いて15分くらいの ところにある公園。 遊具は滑り台や幼児遊具があるので小さい子でも 楽しく遊ぶことが出来る。 園内には、緑が多くとても見ているだけでも気持 ちいい。 公園の隣りには世界救世教の建物がある。

蘇鉄


佐藤惣之助詩碑。1959年五月、惣之助の出身地である川崎市民の厚意によって建立されたものである。当初、首里当之蔵町、旧琉球大学構内(現首里城公園)にあったものを、公園の整備に伴い、当地へ移築したものである。建立に際しては、同じ神奈川県出身の陶芸家浜田庄司の手による陶板が用いられている。碑の文言は「宵夏」。

○せかいきゅうせいきょう 【世界救世教】
岡田茂吉(一八八二~一九五五)が開いた大本教系の新宗教。もと大本教布教師だった岡田が、岡田式神霊指圧療法を始めて大日本観音会を一九三五年に発足させたのが始まり。宇宙の主神を大光明真神とし、岡田の掌から放射する観音力で浄霊が行われ、万病が治るとする。のち大日本健康協会・世界メシヤ教などと変わり現名に。岡田は信者から「お光様」と呼ばれた。所在地・静岡県熱海市桃山町。MOA美術館 創立者の「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」との願いを継承し、1982年にMOA美術館を開館しました。その成り立ちは、昭和32年にまず、熱海市に熱海美術館を開き、昭和57年の創立者生誕百年の年に、現在の美術館を開館、「Mokichi Okada Association」の頭文字を冠するMOA美術館と改め、財団の中心拠点として、美術品の展観をはじめ、いけばな、茶の湯、芸能、児童の創作活動などを通して、幅広い文化活動を展開。

那覇市泊の光明会館(生長の家沖縄県教化部)の蘇鉄
○生長の家は、大本で機関紙の編集主幹をしていた谷口雅春が起こした教団です。生長の家は岡田茂吉の系統と違い、大きな分裂もなく現在に至っています。この教団の特徴は、設立の経緯が同人雑誌だったので現在でも機関紙を定期購読することが信者の勤めとなっていること、またメディア・マスコミには非常に敏感です。マスコミの取材に対してまともに答えを出さない(出せない)新宗教団体が多い中、生長の家だけは毎度ながらもっとも丁寧に回答を出します。生長の家のホームページにも、教義から組織から歴史から沿革その他にいたるまで、丁寧に解説されています。(はてなキーワード)
暁烏敏 あけがらす-はや
1877-1954 明治-昭和時代の僧,仏教学者。
明治10年7月12日生まれ。清沢満之(まんし)に師事して浩々洞(こうこうどう)にはいり,明治34年雑誌「精神界」を発刊,精神主義をとなえる。のち生家の石川県真宗大谷派明達寺の住職となり,布教と著述につとめた。昭和26年同派宗務総長。昭和29年8月27日死去。77歳。真宗大(現大谷大)卒。法名は恵祐。著作に「歎異抄講話」など。
【格言など】人が自分を軽蔑して居るというて憤慨するのは自分自らが軽蔑しているのだ。→コトバンク
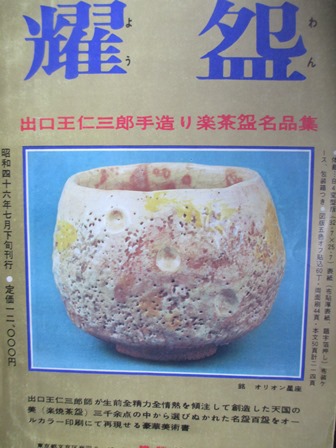
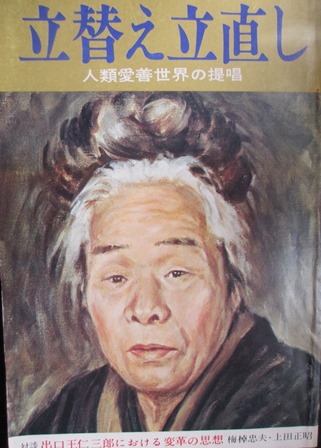
1971年5月 『建替え建直しー人類愛善世界の提唱』出口王仁三郎生誕百年記念会
2003年正月 沖縄県護国神社に行くと鳥居に日本民主同志会/松本明重とあった。懐かしい名前である。平良盛吉翁の『関西沖縄開発史 : 第二郷土をひらく 』1971を援助し日本民主同志会本部名で発行していた。松本氏は世界救世教外事対策委員長、祇園すえひろ会長だが、沖縄に関わり、「京都の塔」「小桜の塔」に碑を建てている。この人とダブって思い出したのが、「元祖スエヒロ」という「しゃぶしゃぶ」の店を経営している大阪日本工芸館長の三宅忠一氏である。この人も沖縄民芸などに力を入れていた。
松本氏は東本願寺紛争にも名が出てくる。相対する西本願寺と云えば弟22世門主・大谷光瑞が思い出される。戦前沖縄の新聞に、光瑞来沖かと云う記事を見たことがあるが、結局来なかったようである。その代わりというか弟の大谷尊由が1918年2月に来沖し相当に歓迎されたようである。光瑞と同じく宗教界の怪物と知られる人物に大本の出口王仁三郎が居る。その大本宣教場の亀岡「天恩郷」は明智光秀の居城跡で、そこに沖縄から奉仕活動に来ていた金城ひろこさんを大城敬人(現名護市会議員)氏に紹介されて遊びによく行った。
虎瀬公園は、モノレール儀保駅から歩いて15分くらいの ところにある公園。 遊具は滑り台や幼児遊具があるので小さい子でも 楽しく遊ぶことが出来る。 園内には、緑が多くとても見ているだけでも気持 ちいい。 公園の隣りには世界救世教の建物がある。

蘇鉄


佐藤惣之助詩碑。1959年五月、惣之助の出身地である川崎市民の厚意によって建立されたものである。当初、首里当之蔵町、旧琉球大学構内(現首里城公園)にあったものを、公園の整備に伴い、当地へ移築したものである。建立に際しては、同じ神奈川県出身の陶芸家浜田庄司の手による陶板が用いられている。碑の文言は「宵夏」。

○せかいきゅうせいきょう 【世界救世教】
岡田茂吉(一八八二~一九五五)が開いた大本教系の新宗教。もと大本教布教師だった岡田が、岡田式神霊指圧療法を始めて大日本観音会を一九三五年に発足させたのが始まり。宇宙の主神を大光明真神とし、岡田の掌から放射する観音力で浄霊が行われ、万病が治るとする。のち大日本健康協会・世界メシヤ教などと変わり現名に。岡田は信者から「お光様」と呼ばれた。所在地・静岡県熱海市桃山町。MOA美術館 創立者の「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」との願いを継承し、1982年にMOA美術館を開館しました。その成り立ちは、昭和32年にまず、熱海市に熱海美術館を開き、昭和57年の創立者生誕百年の年に、現在の美術館を開館、「Mokichi Okada Association」の頭文字を冠するMOA美術館と改め、財団の中心拠点として、美術品の展観をはじめ、いけばな、茶の湯、芸能、児童の創作活動などを通して、幅広い文化活動を展開。

那覇市泊の光明会館(生長の家沖縄県教化部)の蘇鉄
○生長の家は、大本で機関紙の編集主幹をしていた谷口雅春が起こした教団です。生長の家は岡田茂吉の系統と違い、大きな分裂もなく現在に至っています。この教団の特徴は、設立の経緯が同人雑誌だったので現在でも機関紙を定期購読することが信者の勤めとなっていること、またメディア・マスコミには非常に敏感です。マスコミの取材に対してまともに答えを出さない(出せない)新宗教団体が多い中、生長の家だけは毎度ながらもっとも丁寧に回答を出します。生長の家のホームページにも、教義から組織から歴史から沿革その他にいたるまで、丁寧に解説されています。(はてなキーワード)
06/22: 鎌倉芳太郎①
鎌倉芳太郎年譜

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男
1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業
1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。
1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。
○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。
①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)
な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)
1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。
②平田松堂 ひらた-しょうどう
1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。
明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)
③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)
東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)
④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)
美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)
1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立
赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。
①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ
1853-1904 明治時代の実業家。
嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)
②赤星鐵馬
1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。
1901年(明治34年) 東京中学卒。
渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。
1910年(明治43年) 帰国。
1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。
1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。
1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)
③平山成信 ひらやま-なりのぶ
1854-1929 明治-大正時代の官僚。
嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)
1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。
鎌倉芳太郎、首里の座間味家に
□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄
1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。
9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。
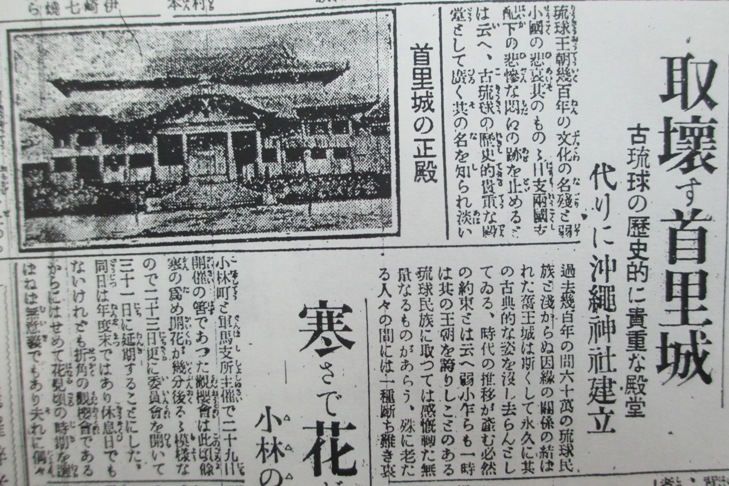
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
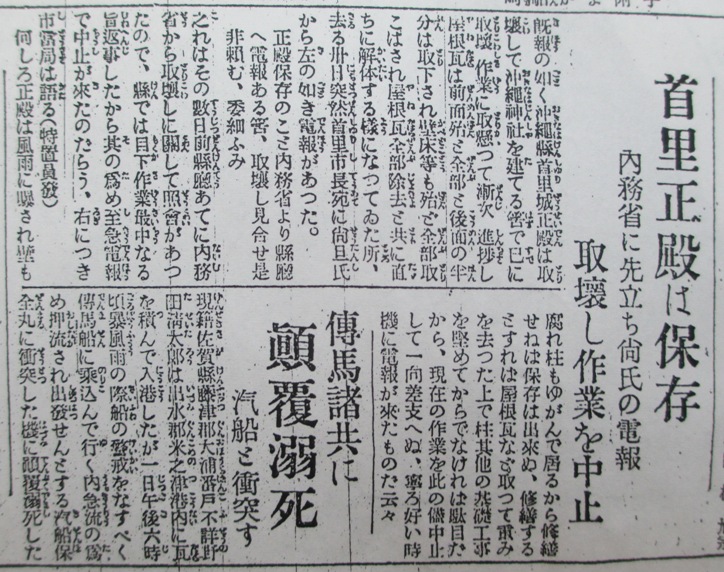
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。
1924-4
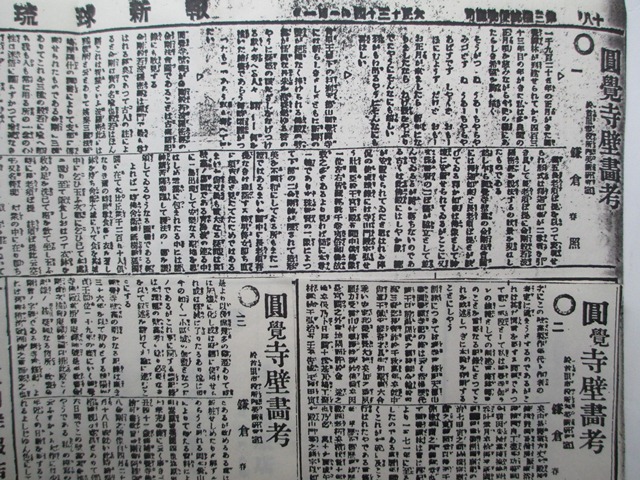
1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。
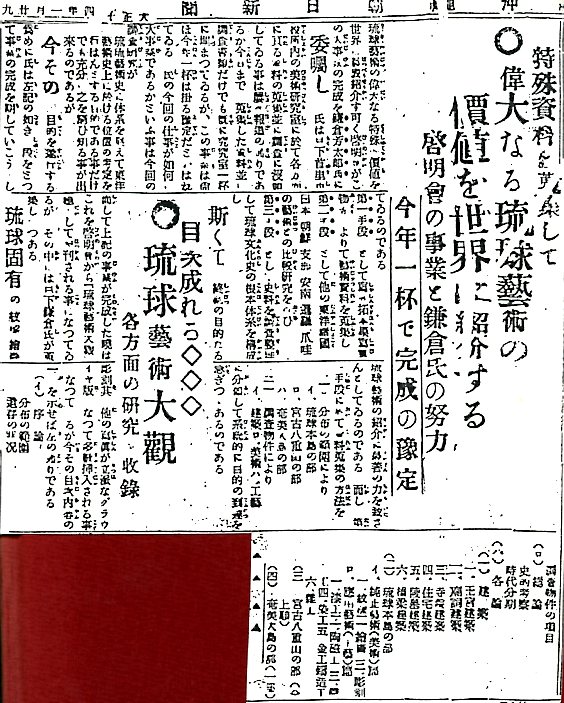
1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」
1925(大正14)年
9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)
12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて
12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」
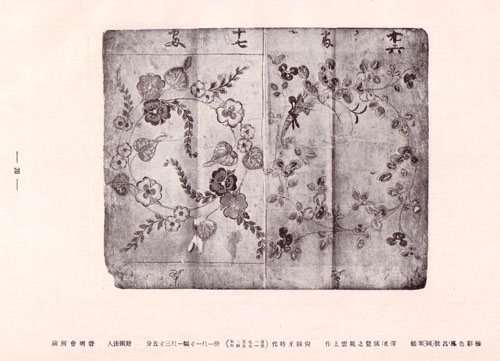
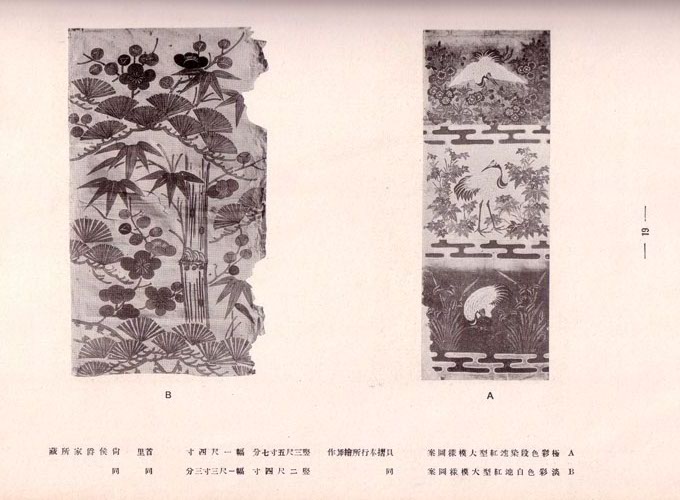
1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」
1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。
9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。
12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」
1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。
1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」
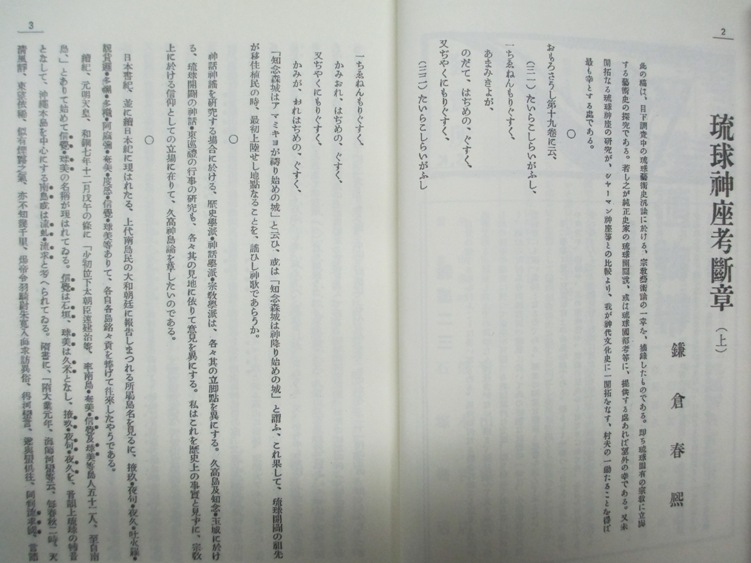
1927年
9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。
1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」


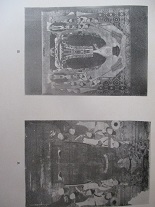

1928-12 『東洋工藝集粋』
『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」
1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」
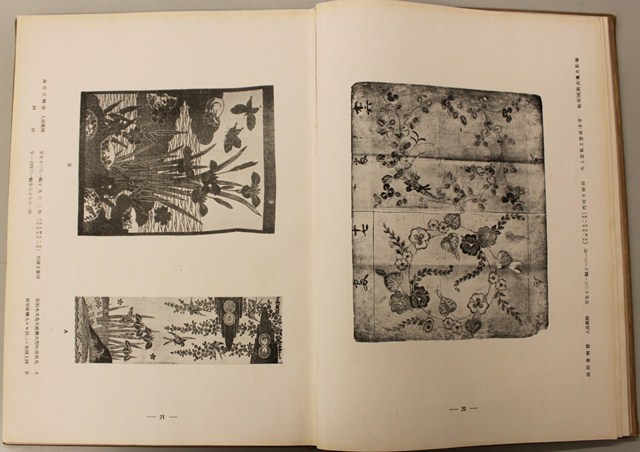
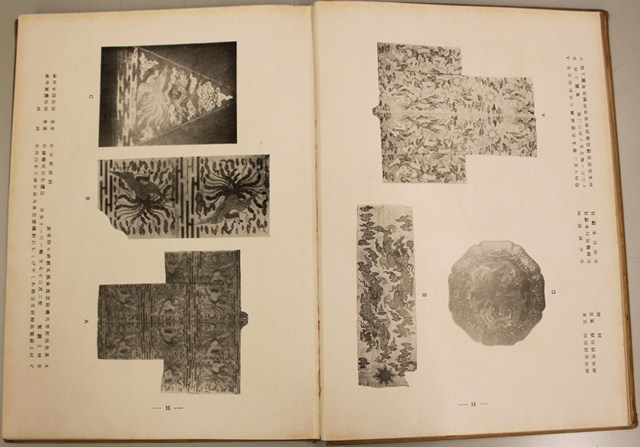
1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」
1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部
1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』
1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)
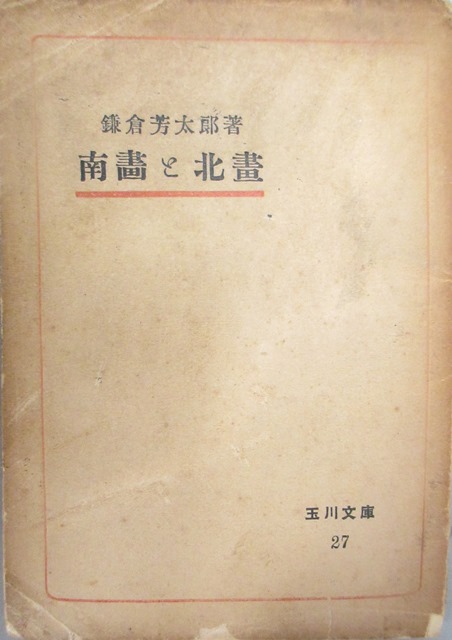
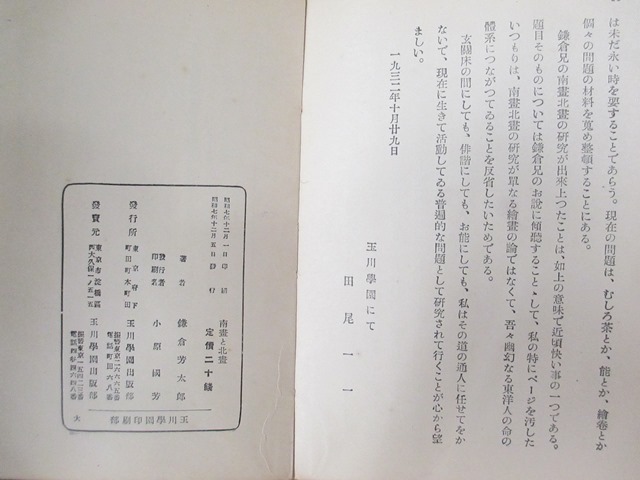
(粟国恭子所蔵)
1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫
1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。
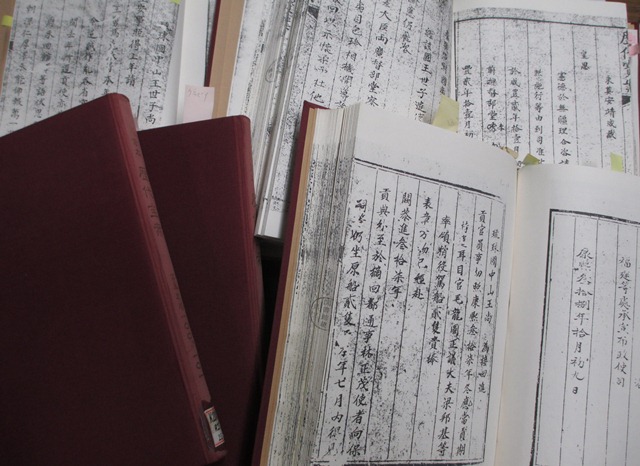
れきだいほうあん【歴代宝案】
琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)
1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」
1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』
1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」
1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖
1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。
1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)
1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。
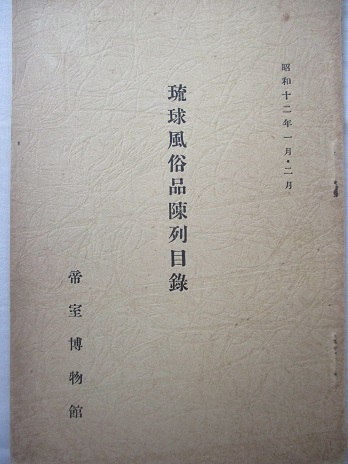
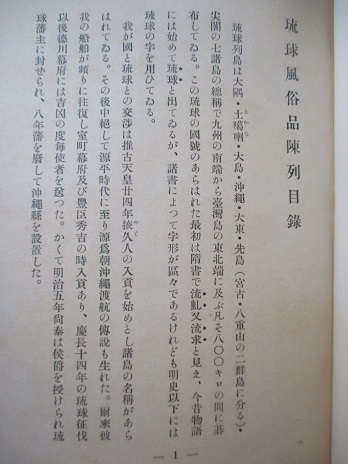
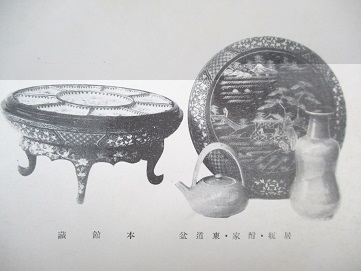


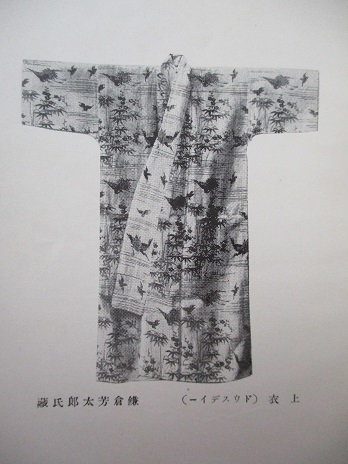

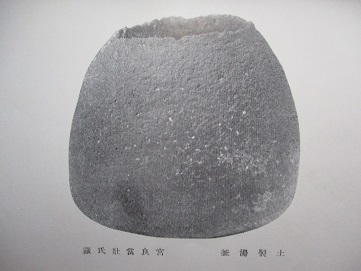
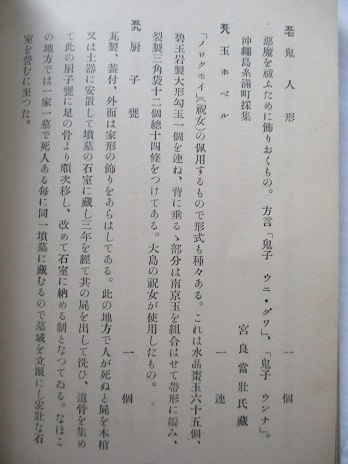
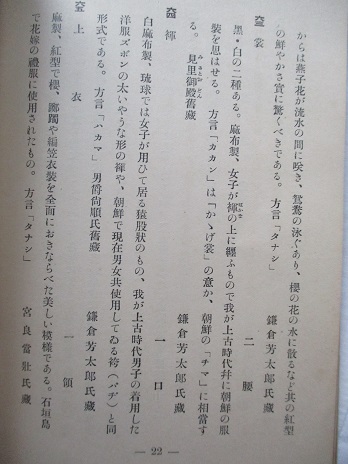
1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』
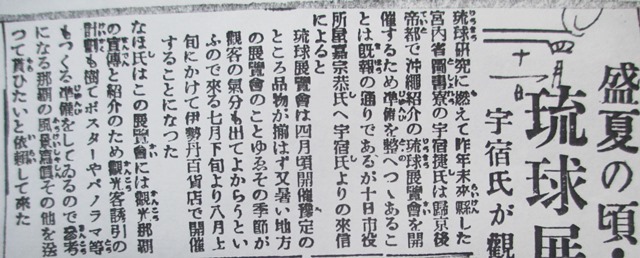
1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』
○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男
1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業
1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。
1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。
○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。
①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)
な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)
1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。
②平田松堂 ひらた-しょうどう
1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。
明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)
③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)
東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)
④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)
美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)
1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立
赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。
①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ
1853-1904 明治時代の実業家。
嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)
②赤星鐵馬
1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。
1901年(明治34年) 東京中学卒。
渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。
1910年(明治43年) 帰国。
1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。
1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。
1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)
③平山成信 ひらやま-なりのぶ
1854-1929 明治-大正時代の官僚。
嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)
1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。
鎌倉芳太郎、首里の座間味家に
□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄
1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。
9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。
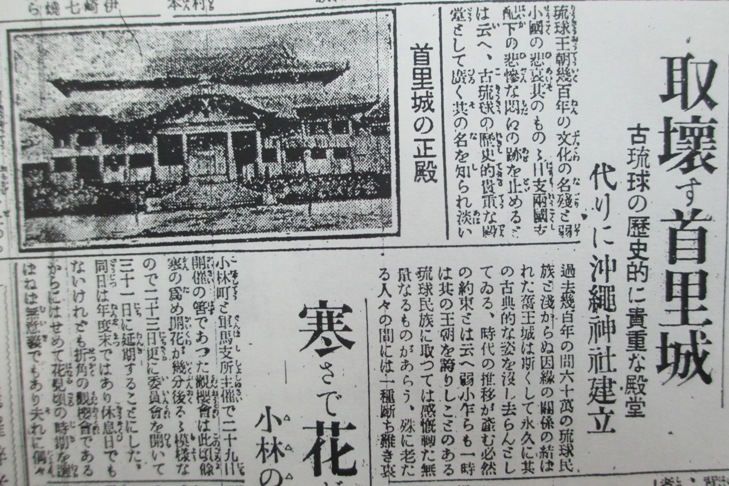
1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」
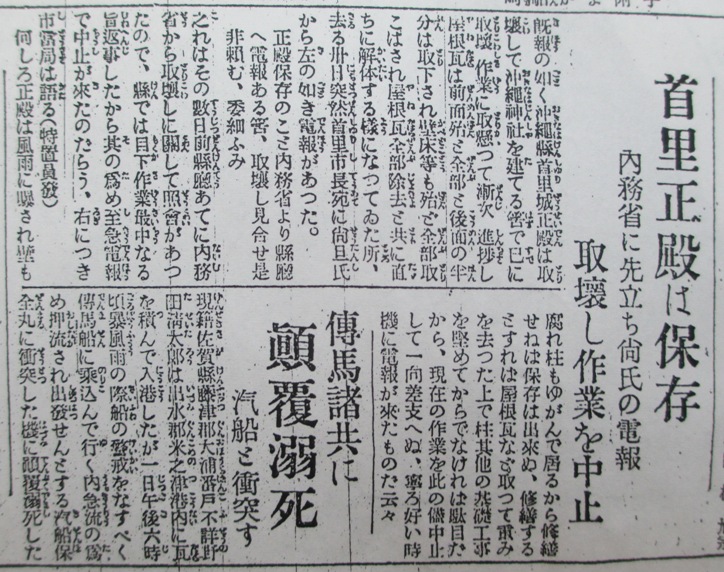
1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」
4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。
1924-4
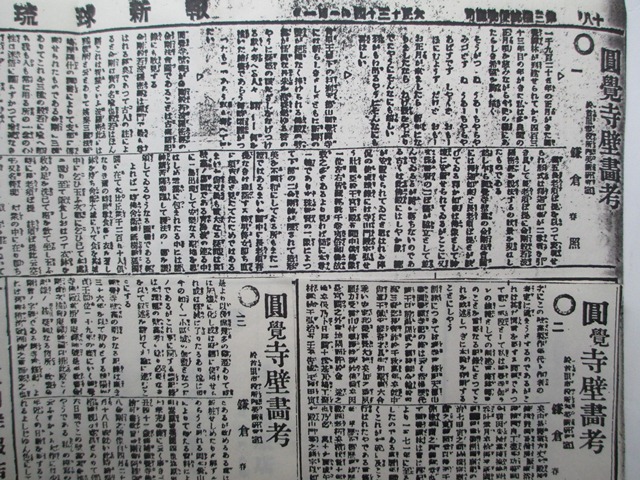
1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。
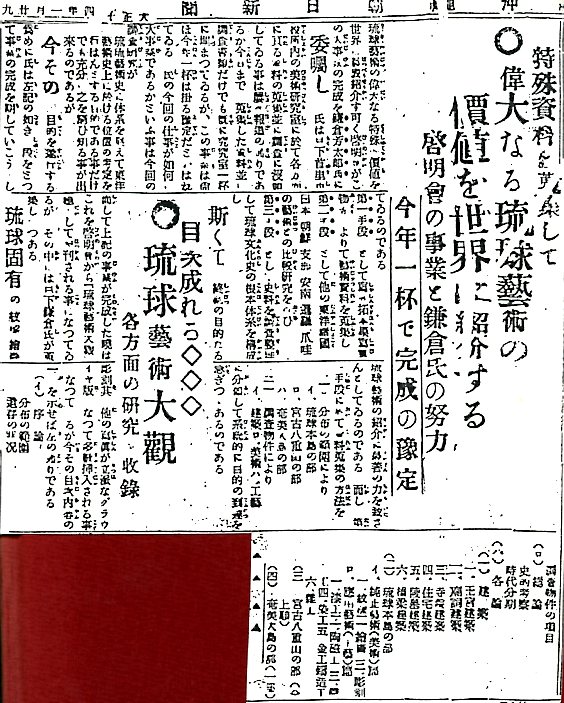
1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」
1925(大正14)年
9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)
12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて
12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」
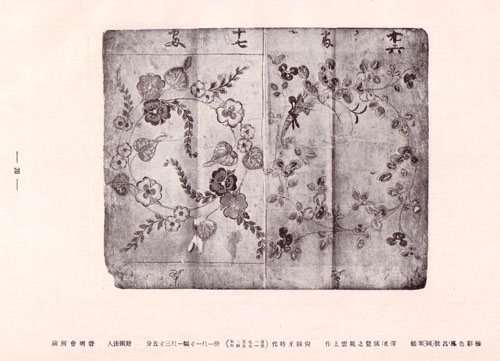
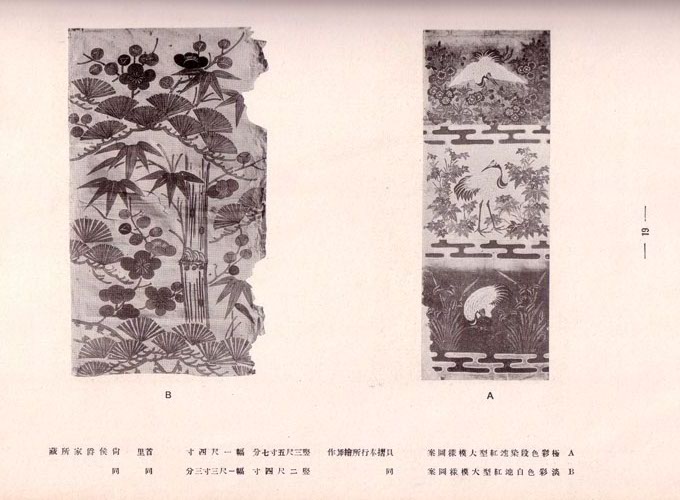
1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」
1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。
9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。
12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」
1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。
1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」
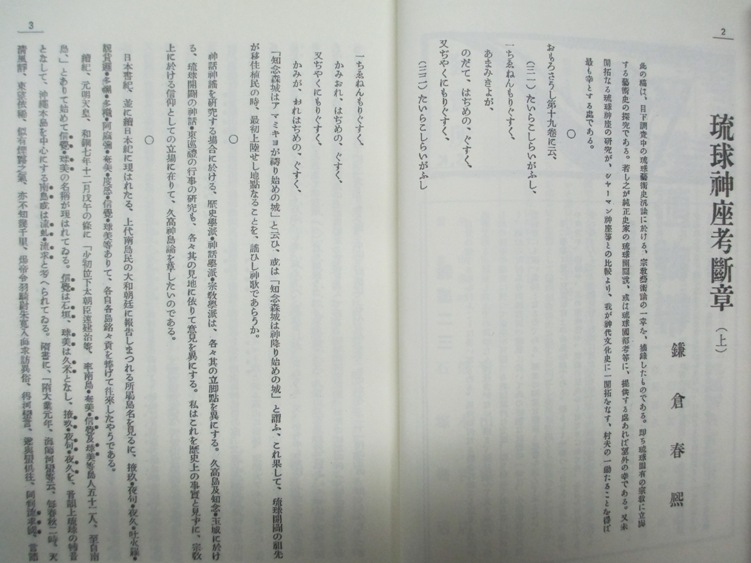
1927年
9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。
1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」


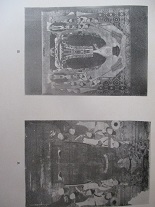

1928-12 『東洋工藝集粋』
『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」
1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」
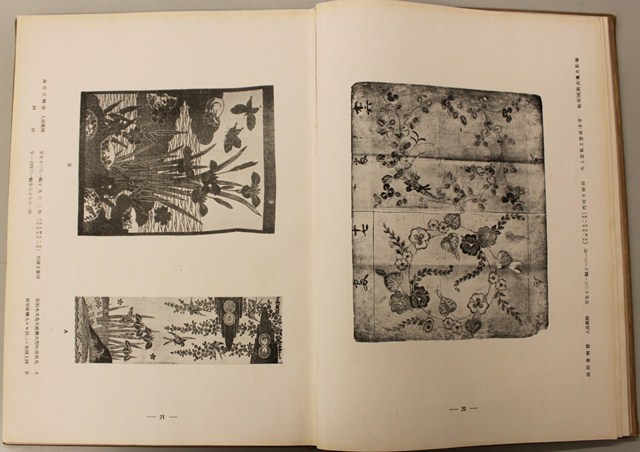
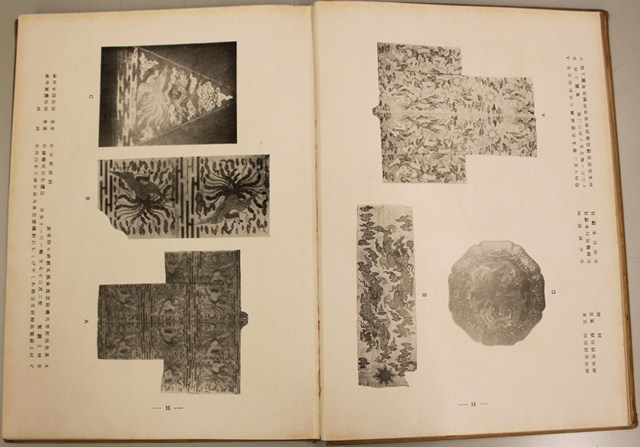
1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」
1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部
1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』
1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)
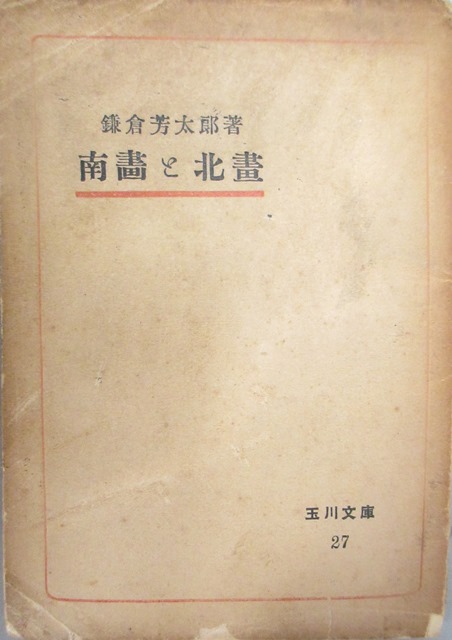
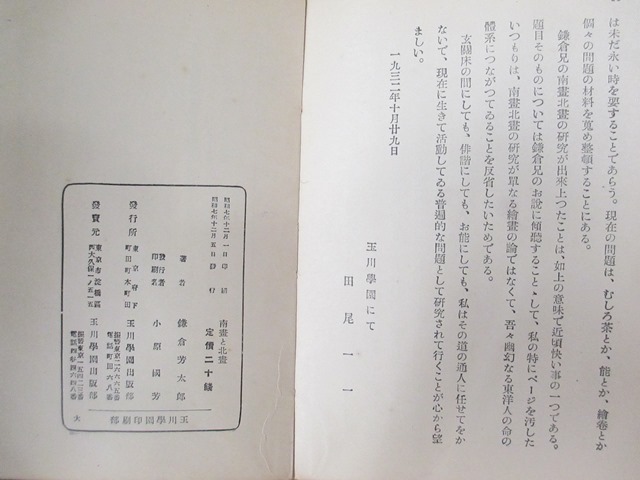
(粟国恭子所蔵)
1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫
1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。
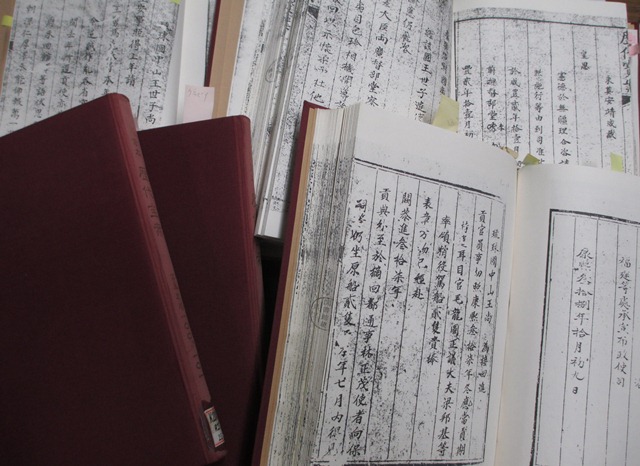
れきだいほうあん【歴代宝案】
琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)
1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」
1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』
1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」
1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖
1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。
1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)
1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。
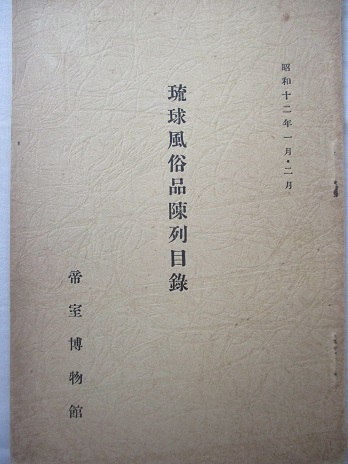
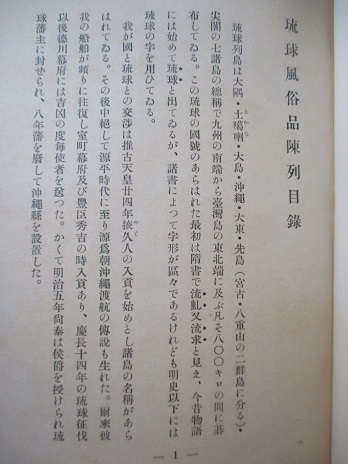
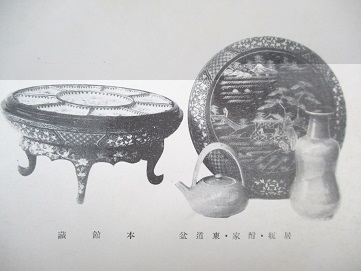


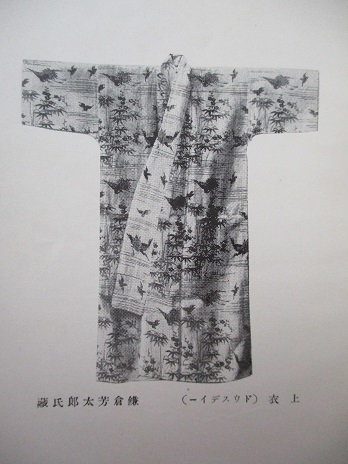

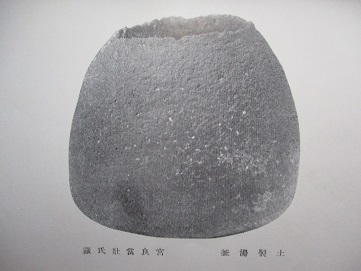
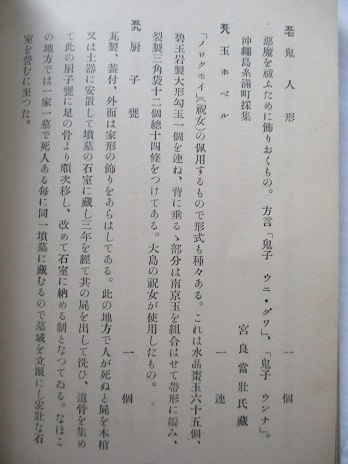
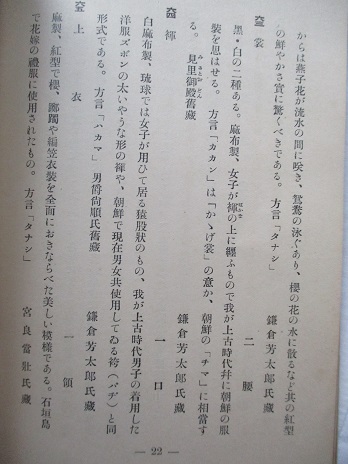
1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』
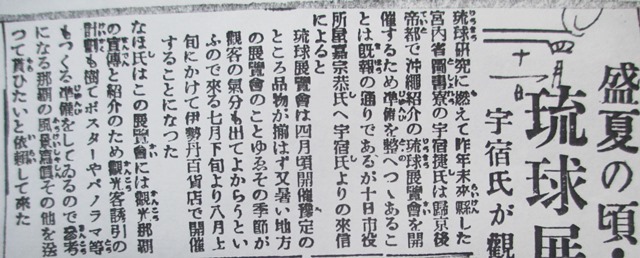
1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』
○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」
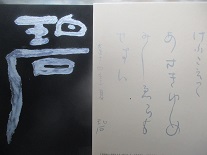
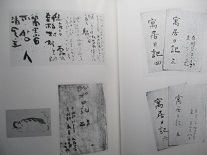
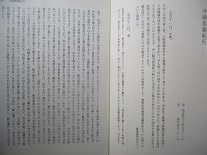
2007年1月 『河東碧梧桐全集』第12巻「沖縄那覇紀行」 文藝書房
〇1910年5月18日に伊波普猷と会話した河東碧梧桐は「沖縄那覇紀行」で伊波の話を紹介している。□5月18日。半晴。臺灣、朝鮮には目下土着人を如何に馴致すべきかの重大な問題が何人の頭をも重圧しつつある。琉球のように多年親日の歴史ある土地に、さような社会問題があろうとは夢想だもせぬところであった。が、人種上に生ずる一種の敵愾心、表面に現れた痕跡は絶無であるにしても、心の奥底に拭うべからざるある印象の存することは争われぬ。伊波文学士ー沖縄人ーの観察はあるいは一方面であるかも知れぬが、這般の消息について多少聞くべきものがある。曰く琉球が親日に勤めたことは、すでに数百年前のことで、時の為政者は大抵そのために種々の施設をしておる。なかんずく向象賢などは時の名宰相であったのであるが、その親日に尽くしたことも一通りではなかった。下って宜湾朝保の如き、八田知紀の門下生となって三十一文字の道にも心を寄せたという位である。が、琉球人の方を主として見ると、島津氏の臨監は、これを支那の恩恵に比すると余り苛酷であった。支那は琉球から租税を徴したことがない。進貢船を派しても、必ずそれ以上の物と交易して呉れる。のみならず、能く諸生の教導をして、留学生なども懇篤な待遇をした。沖縄人が親日の束縛を受けながらも、暗に支那に欸を通じて、衷心その恩を忘れざるものはこれがためである。殊に廃藩置県の際における内地人の処置は、沖縄人の心あるものをして、新たなる敵愾心を起さしめた。蓋し土着の沖縄人を軽蔑することその極に達したからである。
爾来その敵愾心は学問の上に進展して、沖縄人と雖も習字次第内地と拮抗するに足ることを証拠立てた。今日如何に焦燥れても如何に運動しても一種の不文律は沖縄人に政治上及び実業上の権力は与えられぬ。已むなくさる制裁のない学問に向かって力を伸ばす外はないのである。この気風は殊に今日の青年間に隠約の勢力となっておる。今日小中学または師範学校などの教師ー内地人ーは内地で時代後れになった人が多い。新進気鋭の秀才が、かかる南洋の一孤島に来ぬのは自然の数であるけれども、現在の権力掌握者はまた余りに時勢に取り残され方が甚だしい。そこになると、青年の方が遥かに時代の推移を知っておる。如何に圧制的に新刊の書を読むなと禁じても、生徒は暗に、どういうことが書いてあるかも知らずに、と冷笑しておる始末である。殊に我々は沖縄人だという自覚の上に、このまま単に内地人の模倣に終わるべきであろうかという疑問がある。つまらぬ事のようであるけれども、島津氏に対する祖先伝来の一種の嫌悪心も手伝ふて来る。さらばというてもとより沖縄県庁に対して謀反を計るなどという馬鹿なこともないが、それらの暗々裡の不平は、いつか妙な方向に走らせて、青年に社会主義の書物や、露西亜小説の悲痛な物やなど読むものが多くなった。もしこの気風が段々助長して行けば、あるいは人種上の恐るべき争いとならぬとも限らぬ。要するにこの十年前までは単に旧物破壊、日本模倣の単純な社会であったのが、今日は沖縄人としての自覚が芽を萌して、旧物保存、模倣敗斥の端を啓いたのである。
1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」
1910年6月 『ホトトギス』岡本月村「琉球スケッチ」
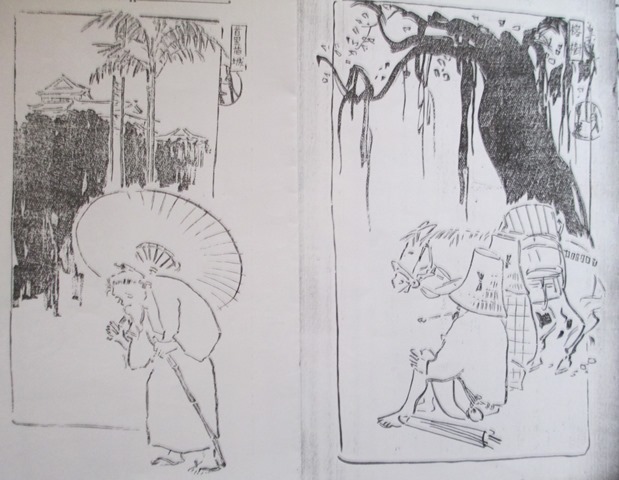

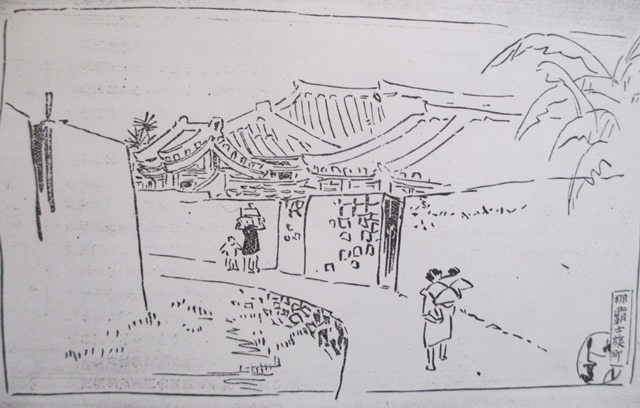
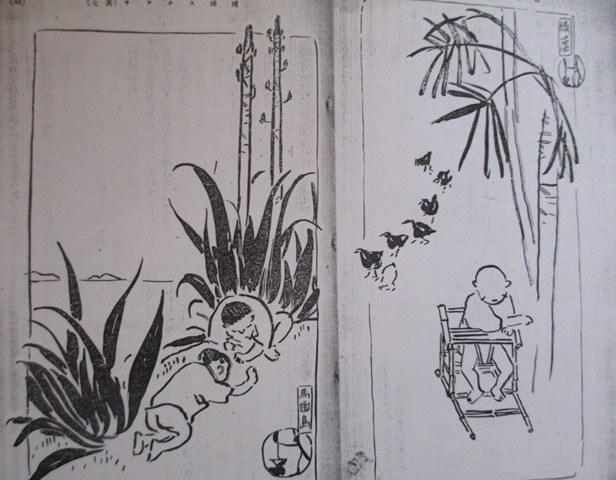
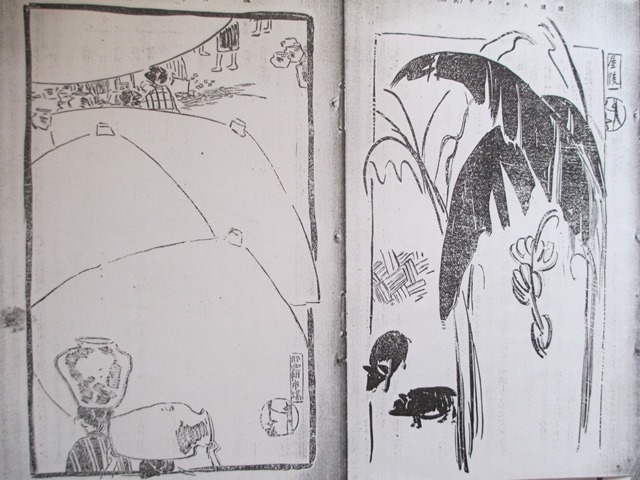
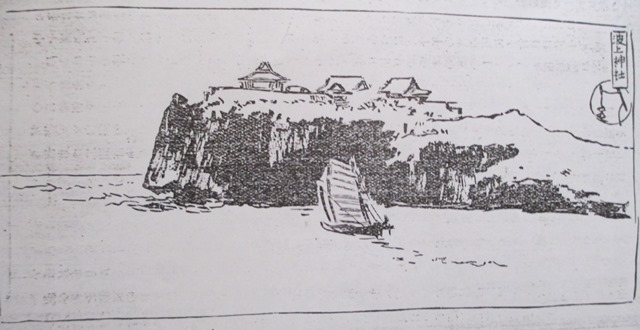
□岡本月村(1876年9月10日~1912年11月11日)
上道郡西大寺(現、岡山市)の人。名は詮。幼くして画技を好み、13歳で徳島県の天蓋芝堂、次いで京都の今尾景年に、また洋画を浅井忠に学んだ。神戸新聞、大阪朝日新聞に俳味ある漫画を載せて異彩を放つ。旅行を好み俳句にも長ず。
麦門冬と河東碧梧桐
1984年12月発行の『琉文手帖』「文人・末吉麦門冬」で1921年以降の『ホトトギス』の俳句も末吉作として収録した。これは別人で熊本の土生麦門冬の作品であるという。土生麦門冬には『麦門冬句集』(1940年9月)があった。1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖したとき、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。
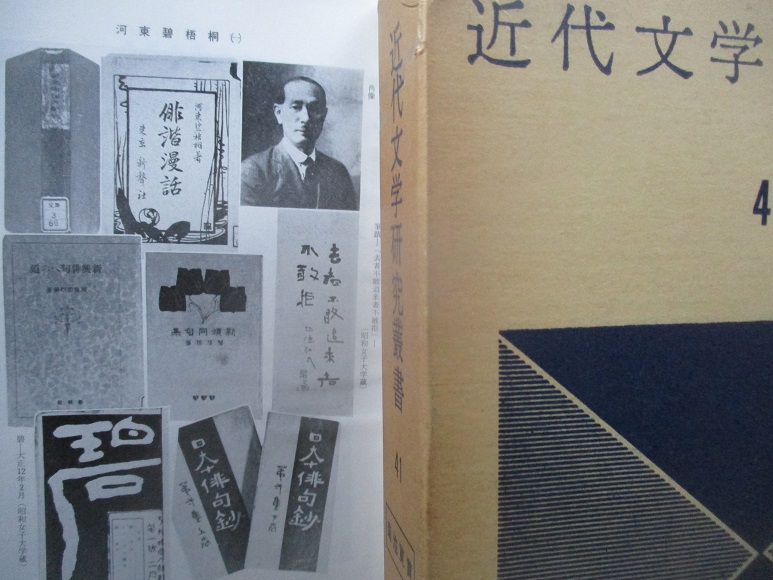
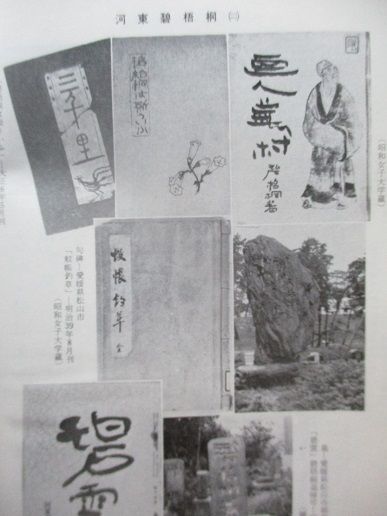
1975年5月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学叢書』41巻「河東碧梧桐」 昭和女子大学近代文化研究所
河東碧梧桐 かわひがし-へきごとう
1873-1937 明治-昭和時代前期の俳人。
明治6年2月26日生まれ。高浜虚子とともに正岡子規にまなび,新聞「日本」の俳句欄の選者をひきつぐ。のち新傾向俳句運動をおこし,中塚一碧楼(いっぺきろう)らと「海紅」を創刊,季題と定型にとらわれない自由律俳句にすすむ。大正12年「碧(へき)」,14年「三昧(さんまい)」を創刊。昭和12年2月1日死去。65歳。愛媛県出身。本名は秉五郎(へいごろう)。作品に「碧梧桐句集」,紀行文に「三千里」など。(コトバンク)
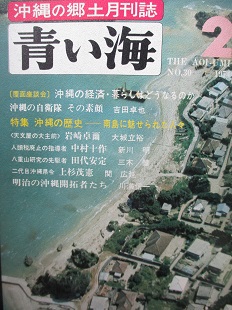

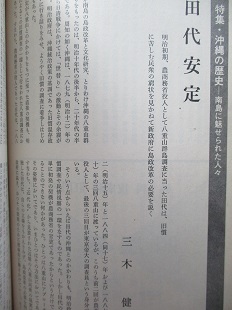
1974年2月号 雑誌『青い海』30号 大城立裕「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」
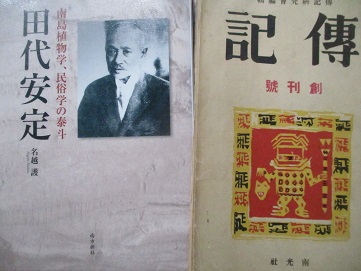
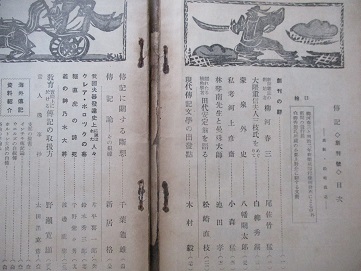


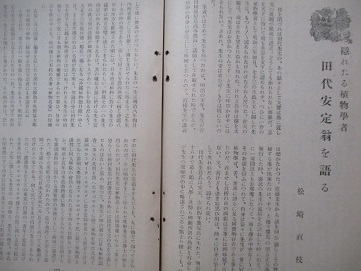
2017年3月 名越護『南島植物学、民俗学の泰斗 田代安定』南方新社/1934年年10月 南光社『傳記』創刊

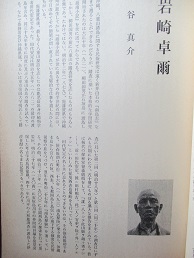

1974年1月『伝統と現代』谷真介「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」
1974年1月『伝統と現代』「日本フォークロアの先駆者」
田代安定(三木健)/笹森儀助(植松明石)/岩崎卓爾(谷真介)/鳥居龍蔵(小野隆祥)/佐々木喜善(菊池照雄)/柳田国男(牧田茂)/折口信夫(村井紀)/早川孝太郎(野口武徳)/筑土鈴寛(藤井貞和)/中山太郎(阿部正路)/南方熊楠(飯倉照平)/渋沢敬三(宮本馨太郎)/金田一京助(浅井亨)/知里真志保(藤本英夫)/伊波普猷(新里金福)/喜捨場永珣(牧野清)/石田英一郎(松谷敏雄)/菅江真澄(石上玄一郎)/近藤富蔵(浅沼良次)
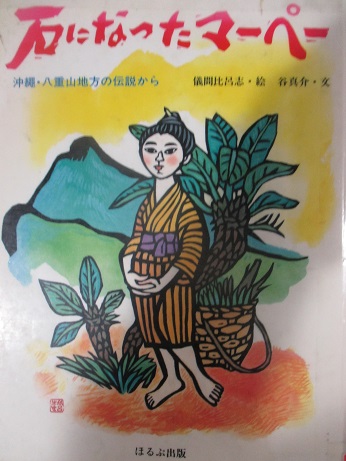
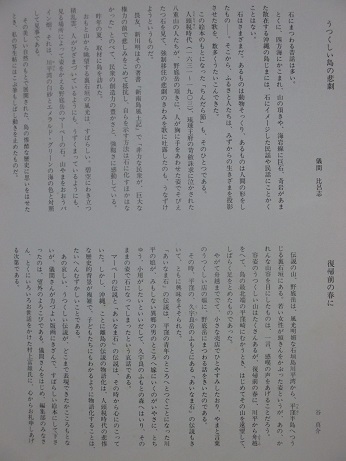
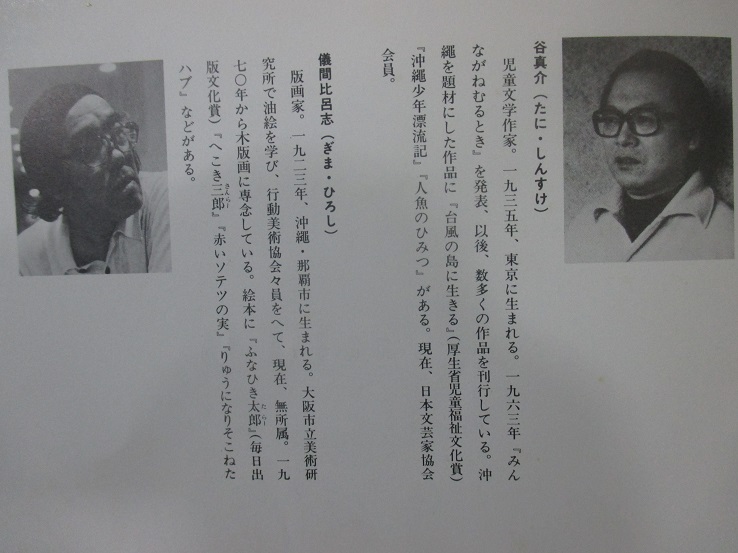
1985年5月 儀間比呂志・絵 谷真介・文『石になったマーペー 沖縄・八重山地方の伝説から』ほるぷ出版
1974年6月 『岩崎卓爾一巻全集』伝統と現代社
ひるぎの一葉/八重山研究/やえまカブヤー/石垣島気候篇/新撰八重山月令/気候雑纂/作品(俳句・短歌・詩)・その他。
註(語彙註)・・・西平守晴・沖縄関係資料室/岩崎卓爾と気候・・・畠山久尚・元気象庁長官/岩崎卓爾と八重山・・・谷川健一・民俗学者/岩崎卓爾翁のことども・・・瀬名波長宣・元石垣島測候所長/父・岩崎卓爾・・・菊池南海子・岩崎卓爾次女/年譜・書誌・・・谷真介①/後記
①谷真介 たに-しんすけ
1935- 昭和後期-平成時代の児童文学作家。
昭和10年9月7日生まれ。子どもの遊びから生まれた冒険世界を多彩な手法でえがき,作品に「みんながねむるとき」「ひみつの動物園」など。「沖縄少年漂流記」,「台風の島に生きる」(昭和51年児童福祉文化奨励賞)など,ノンフィクションも手がける。東京出身。中央大中退。本名は赤坂早苗。→コトバンク
岩崎卓爾年譜(抄録)ー谷真介
1882年ー8月、上杉茂憲、沖縄県令として八重山(石垣島)を巡回。この年、鹿児島の植物学者・田代安定が農商務省官吏として最初の八重山踏査を行う。
1891年ー10月、岩崎卓爾、第二高等中学校を退学し、北海道庁札幌一等測候所に気象研究生として入所。
1893年ー11月、岩崎卓爾、根室一等測候所に配属。この年、青森の笹森儀助が沖縄本島・先島諸島の民情踏査に赴く。
1894年ー5月、笹森儀助『南島探険』刊。8月、日清戦争始まる。
1897年ー6月、岩崎卓爾、富士山頂の測候を命じられる。10月、岩崎卓爾、中央気象台附属石垣島測候所勤務を拝命。12月、石垣島測候所長心得となる。
1899年ー4月、大島測候所長心得として奄美大島名瀬へ赴く。6月、妻・貴志子が仙台より来る。9月、石垣島測候所長として石垣島に帰任。
1900年ー5月、古賀辰四郎は、黒岩恒、宮島幹之助に協力を仰いで尖閣列島を調査。(尖閣列島の命名は黒岩恒)
1902年ーこの年の末、266年にわたって八重山島民を搾取しつづけていた人頭税廃止となる。
1904年ー2月、日露開戦。7月、鳥居龍造、川平仲間嶽貝塚を発掘調査。
1906年ー2月、菊池幽芳、川平大和墓発掘調査。春、岩崎卓爾、蝶の標本として「アカタテハ」「ヤマトシジミ」を岐阜の名和昆虫研究所へ送る。この年、岩崎卓爾、台北より来島した田代安定と会う。
1910年ーこの年。石垣島に白蟻の被害拡がる。イギリスのノルス来島。
1911年ー1月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻に関する通信」、6月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻群飛」。6月、強度の地震あり。岩崎卓爾、名蔵川良峡で「イワサキコノハチョウ」発見。
1912年ー4月、岩崎卓爾『八重山童謡集』刊。5月、岩崎卓爾、粟、稲、麦など害する夜盗虫(アハノヨトウムシ)の駆除法を名和昆虫研究所に問い合わせる。
1913年ー2月、貴志子夫人 7人の子を連れて仙台へ帰る。岩崎卓爾、「イワサキゼミ」「イワサキヒメハルゼミ」の新種発見。
1914年ー3月、岩崎卓爾、八重山通俗図書館を創設。5月、御木本幸吉が石垣島富崎で真珠養殖事業を始める、卓爾に協力を仰ぐ。
1916年ー8月、武藤長平七高教授が来島。
1920年ー9月ごろ岩崎卓爾、台風観測中に右眼を失明す。この年、岩崎卓爾『ひるぎの一葉』刊。
1921年ー岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに柳田国男を石垣港桟橋に迎える。
1922年ー4月17日、岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに上京、柳田国男を訪ねる。4月21日、一ツ橋如水館で開かれた「南島談話会」、出席者、岩崎卓爾、喜舎場永珣、上田万年、白鳥庫吉、三浦新七、新村出、幣原坦、本山桂川、移川子之蔵、中山太郎、折口信夫、金田一京助、東恩納寛惇、松本信広、松本芳夫その他。8月1日、暴風警報が出ているなかを田辺尚雄が民謡研究のため来島。
1923年ー2月、鎌倉芳太郎、桃林寺権現堂の芸術調査で来島。7月、岩崎卓爾、『やえまカブヤー』を八重山通俗図書館から刊行。8月、折口信夫が民俗採集のため来島。
1924年ー9月、岩崎卓爾、文芸同人結社セブン社を主宰、同人誌『せぶん』を創刊。本山桂川、民俗採集で来島、卓爾のすすめに応じて与那国島踏査に赴く→1925年『南島情趣』『与那国島図誌』『与那国島誌』刊行。
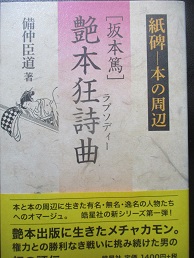
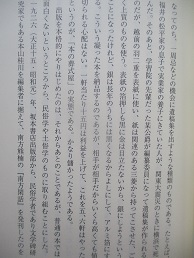
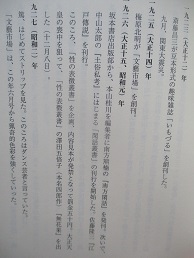
2016年6月 備仲臣道『紙碑ー本の周辺 坂本篤 艶本狂詩曲』皓星社〇1926(大正15・昭和元)年、坂本書店出版部から、民俗学者であり文学碑研究家でもある本山桂川を編集者に据えて、南方熊楠の『南方閑話』を発刊したのを手はじめに、中山太郎の『土俗私考』にはじまる「閑話叢書」を刊行
〇2017年3月 『平成27年度 市立市川歴史博物館館報』三村宜敬(市川歴史博物館学芸員)「本山桂川の足跡を探る」
1926年ー1月、八重山に始めてラジオ受信器設置。
1928年ー4月13日、東京代々木の日本青年館、18日が朝日新聞講堂で初めて八重山芸能(第三回郷土舞踊大会)が公演。
□1974年3月 大城立裕『風の御主前 小説・岩崎卓爾伝』日本放送出版協会
□岩崎卓爾 いわさき-たくじ
1869-1937 明治-昭和時代前期の気象技術者,民俗学者。
明治2年10月17日生まれ。32年沖縄石垣島初代測候所長となる。気象観測のかたわら,八重山の民俗,歴史,生物などを研究。退職後も石垣島にとどまり,「天文屋の御主前(うしゆまい)」としたしまれた。昭和12年5月18日死去。69歳。陸前仙台出身。第二高等学校中退。著作に「ひるぎの一葉」「八重山研究」など。→コトバンク
東京の島袋和幸氏から『日本エスペラント運動史』がおくられてきた。島袋氏は豊川善曄も調べていたから、同書の人名索引には豊川の名前も載っている。
ザメンホフ【Lazaro Ludoviko Zamenhof】
1859‐1917
今日もっとも広く使用されている人工語・国際語エスペラントの創始者。ユダヤ系ポーランド人でワルシャワの眼科医。ペンネームを〈ドクトーロ・エスペラントDro Esperanto〉といい,これより人工語の名前がエスペラントと呼ばれるようになった。ザメンホフは生涯をエスペラントの普及に尽くし,旧約聖書,アンデルセンの童話などをはじめ,多くの文学作品をエスペラントに翻訳した。また,国際的に中立な言語のほかに,すべての宗教に共通である道徳原理の総和ともいうべき中立的な宗教を人類が採用すれば,人間間の関係はよくなるに違いないとする〈ホマラニスモ〉という学説も提唱した。(→コトバンク)
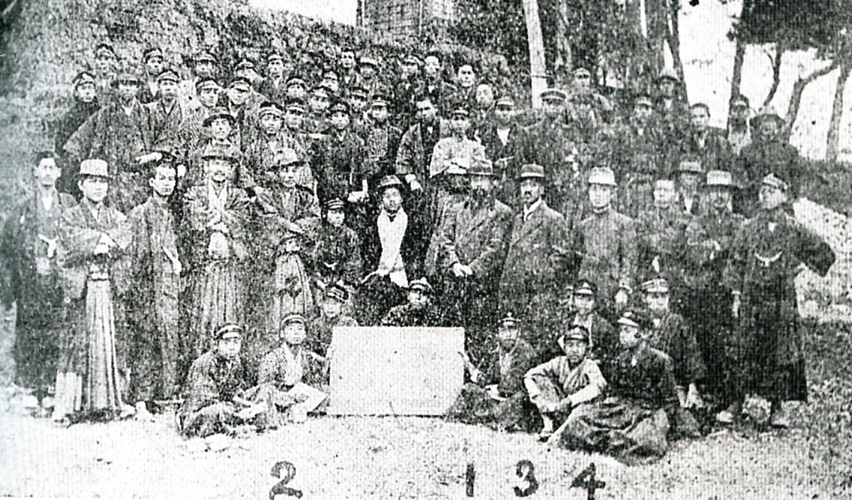
1917年12月ー伊波普猷らが主催したエスペラント研究会の記念写真。中央のヒゲをたくわえているのが伊波、その右が比嘉春潮
1918年1月29日ー日本エスペラント協会は四ツ谷見附の三河屋で理事幹事会を開催し、年々の収入不足に対応するための会費値上げの提案をこの年は見送り、会費(年1円20銭)は前金で納入してもらうことに決めた。また、黒板幹事長の提案で理事を評議員と改称して地方からも選ぶこととし、さらに幹事を改選し、幹事長・黒板、幹事・小坂、浅井を選任した。評議員に、伊波普猷(那覇)、速水真曹(横浜)、千布利雄(神戸)、大石和三郎、高橋邦太郎(広島)、高楠順次郎、田川大吉郎、中村精男、黒板勝美、安孫子貞次郎、斯波貞吉、志村保一の12名が選ばれた。
地方支部は、東京(後藤敬三)、横浜(速水真曹)、横須賀(小林茂吉)、金沢(吉川友吉)、大阪(山口末次郎)、堺(坂上佐兵衛)、広島(高橋邦太郎)、沖縄(比嘉春潮)、台湾(蘇壁輝)が活動し、協会の会員数は8月で286名に回復した。広島の高橋邦太郎は10月に静岡に転居し、静岡支部を設立した。
ザメンホフ【Lazaro Ludoviko Zamenhof】
1859‐1917
今日もっとも広く使用されている人工語・国際語エスペラントの創始者。ユダヤ系ポーランド人でワルシャワの眼科医。ペンネームを〈ドクトーロ・エスペラントDro Esperanto〉といい,これより人工語の名前がエスペラントと呼ばれるようになった。ザメンホフは生涯をエスペラントの普及に尽くし,旧約聖書,アンデルセンの童話などをはじめ,多くの文学作品をエスペラントに翻訳した。また,国際的に中立な言語のほかに,すべての宗教に共通である道徳原理の総和ともいうべき中立的な宗教を人類が採用すれば,人間間の関係はよくなるに違いないとする〈ホマラニスモ〉という学説も提唱した。(→コトバンク)
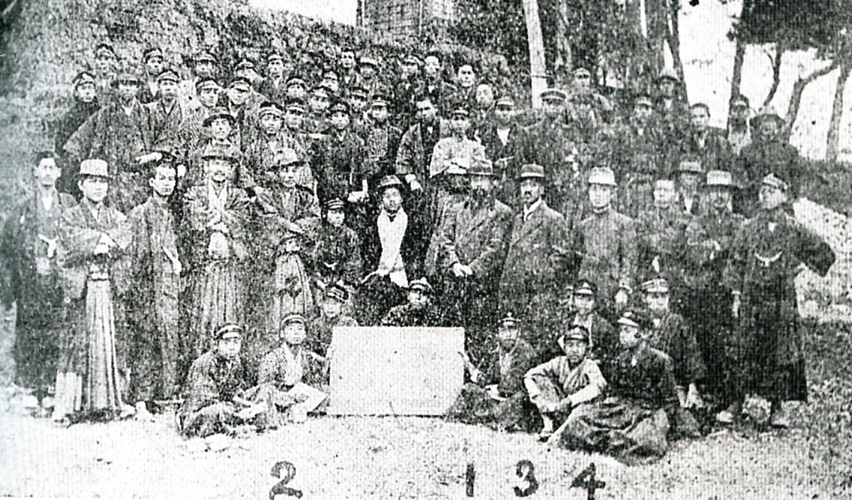
1917年12月ー伊波普猷らが主催したエスペラント研究会の記念写真。中央のヒゲをたくわえているのが伊波、その右が比嘉春潮
1918年1月29日ー日本エスペラント協会は四ツ谷見附の三河屋で理事幹事会を開催し、年々の収入不足に対応するための会費値上げの提案をこの年は見送り、会費(年1円20銭)は前金で納入してもらうことに決めた。また、黒板幹事長の提案で理事を評議員と改称して地方からも選ぶこととし、さらに幹事を改選し、幹事長・黒板、幹事・小坂、浅井を選任した。評議員に、伊波普猷(那覇)、速水真曹(横浜)、千布利雄(神戸)、大石和三郎、高橋邦太郎(広島)、高楠順次郎、田川大吉郎、中村精男、黒板勝美、安孫子貞次郎、斯波貞吉、志村保一の12名が選ばれた。
地方支部は、東京(後藤敬三)、横浜(速水真曹)、横須賀(小林茂吉)、金沢(吉川友吉)、大阪(山口末次郎)、堺(坂上佐兵衛)、広島(高橋邦太郎)、沖縄(比嘉春潮)、台湾(蘇壁輝)が活動し、協会の会員数は8月で286名に回復した。広島の高橋邦太郎は10月に静岡に転居し、静岡支部を設立した。
写真下ー金城真三良(1834年~1916年)首里桃原村に生まれる。武術家、通称・金城大筑
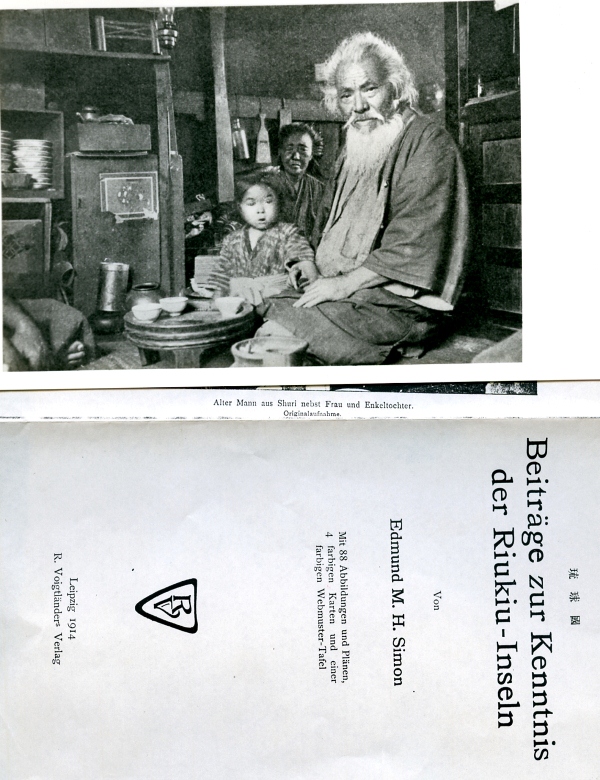
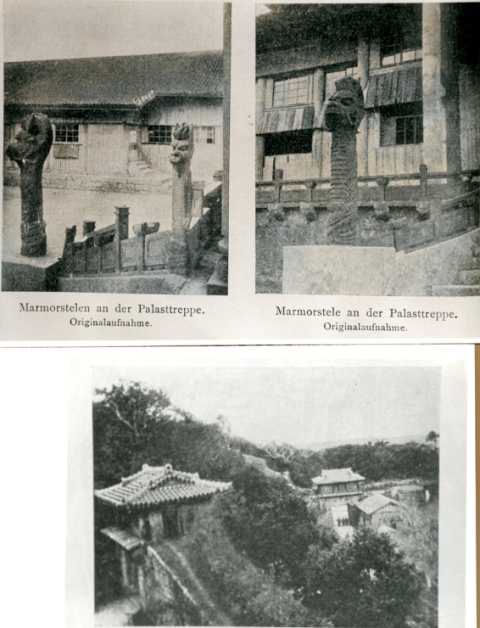
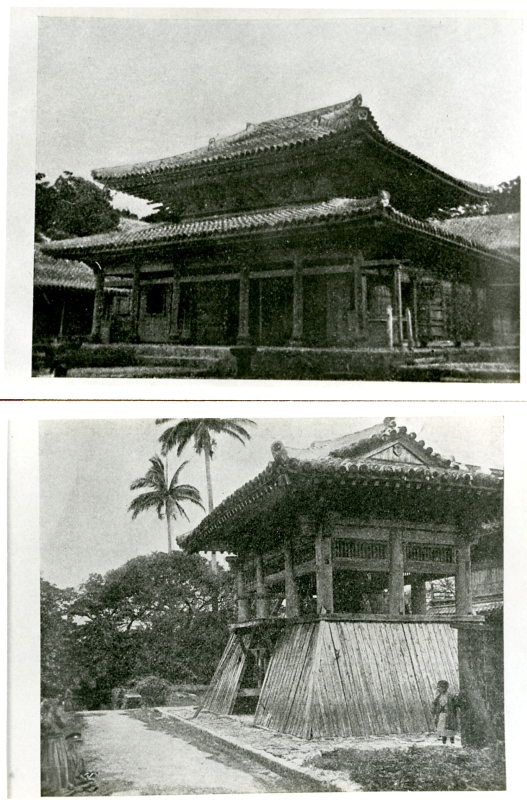
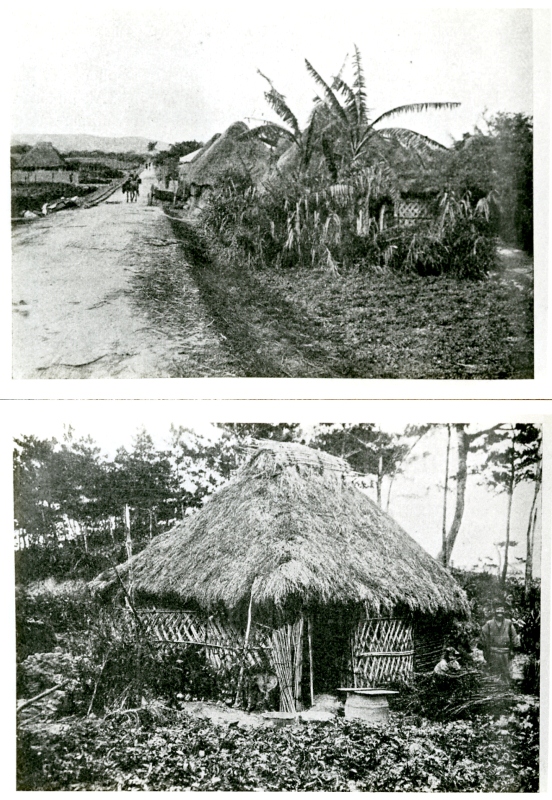
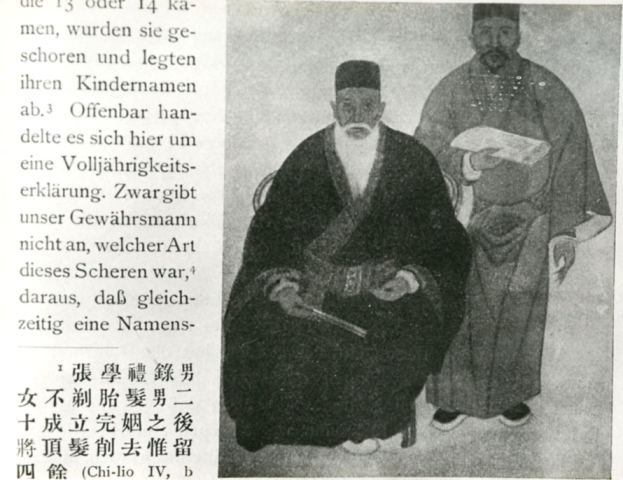
1925年8月」25日 『帝国大学新聞』伊波普猷「独逸に於ける唯一の南島研究者(エドムンド・シーモンの事)」これにはシーモンの伊波宛の手紙が紹介されている。「私が美しい琉球諸島に二度も幸福な数日を過ごしてから長い長い年月になりました。(略)歴史は独逸を消滅させるべく決定をして了ひました。 どうか琉球に関するあなたの新著をご恵与下さい。私はこの愛らしい島には、今だに興味を有っていますから、『名護や山原の』といふ歌は、今なほはっきりと私の耳に響いています。それから私は写真を沢山とったのを嬉しく思ひます。私は時たまそれを取りだして、家のランプの側で見ています・・・」
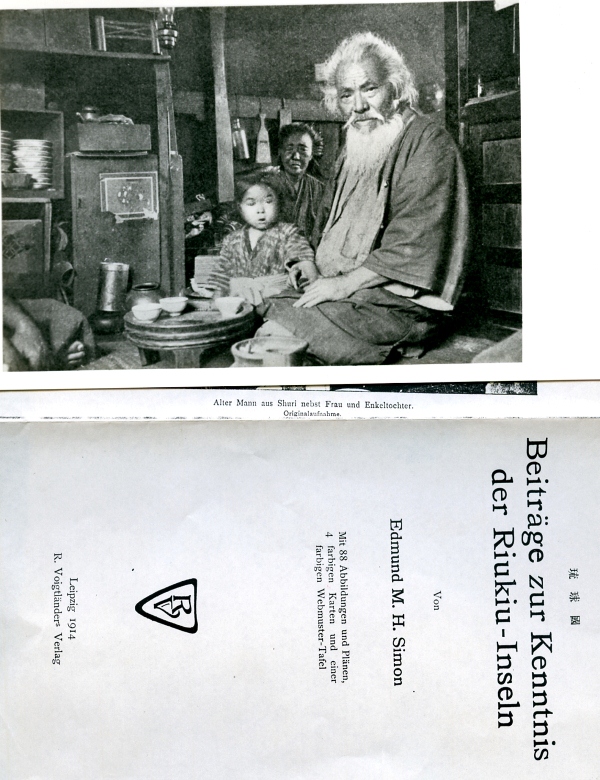
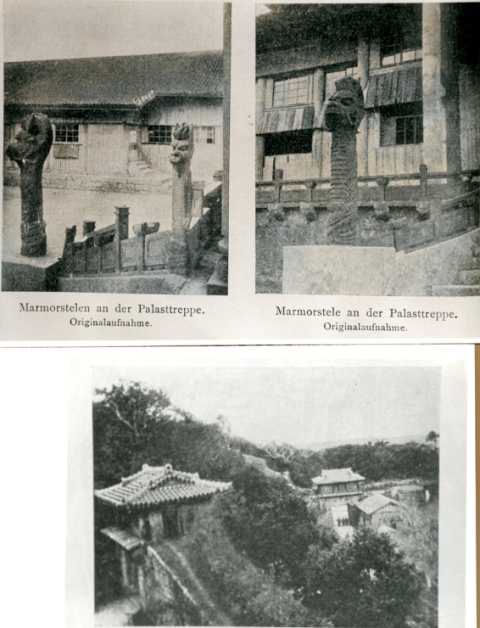
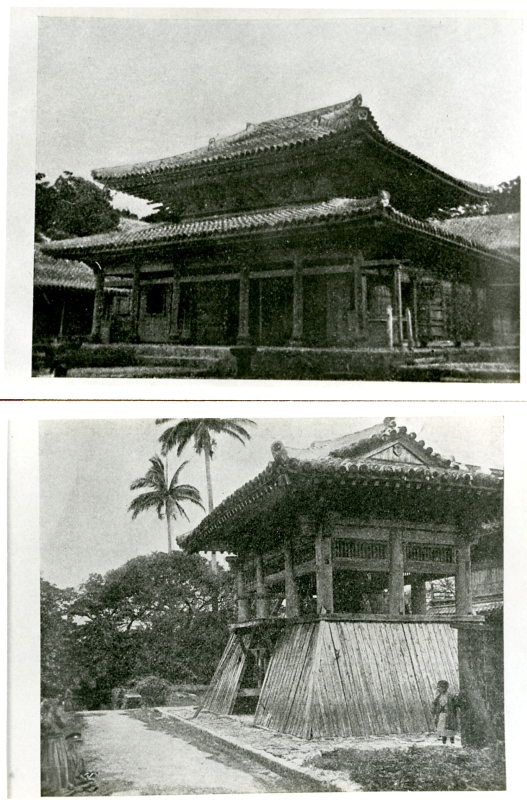
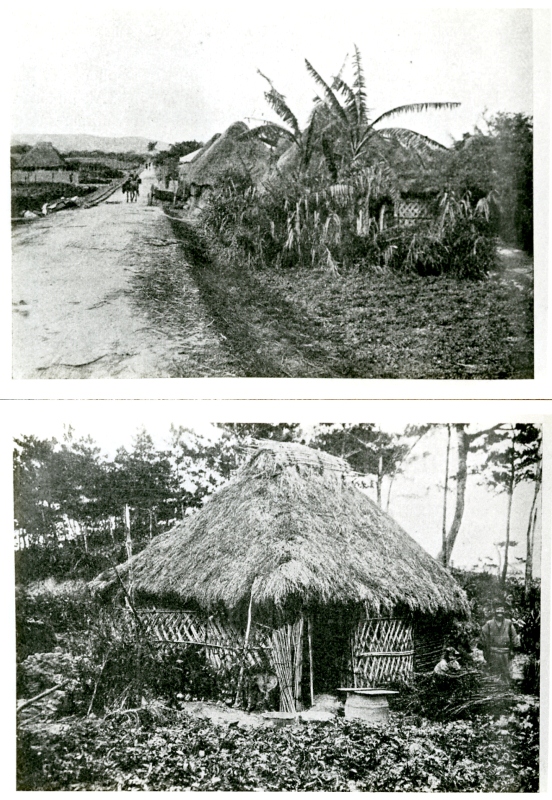
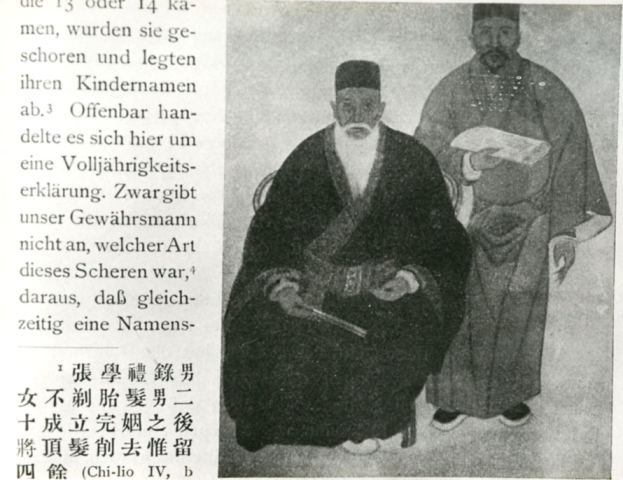
1925年8月」25日 『帝国大学新聞』伊波普猷「独逸に於ける唯一の南島研究者(エドムンド・シーモンの事)」これにはシーモンの伊波宛の手紙が紹介されている。「私が美しい琉球諸島に二度も幸福な数日を過ごしてから長い長い年月になりました。(略)歴史は独逸を消滅させるべく決定をして了ひました。 どうか琉球に関するあなたの新著をご恵与下さい。私はこの愛らしい島には、今だに興味を有っていますから、『名護や山原の』といふ歌は、今なほはっきりと私の耳に響いています。それから私は写真を沢山とったのを嬉しく思ひます。私は時たまそれを取りだして、家のランプの側で見ています・・・」
11/27: 沖縄郷土協会初代会長・太田朝敷
1926年7月8日『沖縄朝日新聞』太田潮東「布哇の其の後」
□ヒロの滞在は悠々保養のつもりであったがヒロ市在留の県人もなを 席の宗教談でも聞きたいという希望があり、ホノムの佛教婦人会からも今一回講演して貰いたいと云う頼みが来たので、これも何かの因縁と思うて快く引き受け、この二席の講演は愈々お名残の講演であるから、多少趣きを加え金儲けと宗教を結びつけて話した。
ハワイに来て居る人々の多くは何れも金儲けを目的として来たに相違ないが、さて佛教に於いてもキリスト教に於いても、その他の宗教に於いても、教壇から金儲けの話しをすることは余りしないようだ。ところが金と云う奴は実に重宝なもので、誰でもこれが嫌いなものは居ない。佛教の或る開教師がしこたま金をためて帰ったそうだが或る人がそれを難したら、その坊さん平然として曰く「佛と云う字は人偏に弗と云う字じゃないか」この坊さんの如きは寧ろ正直の方で、金に執着がないような顔をして居る宗教家中にも、その実内ふくのものが可なり居るようだ。
要するに金を得たいというのは万人が万人共通の欲望だ。吾々の前に開けられている広い広い道は、只この欲望を満足する活動の為に開かれたかのように思わるる位いだ。ところがこの広い道には人の目に見えぬ陥穽もあれば深淵もあり所によっては毒蛇も居れば猛獣も居る。世の中には金儲けの上手と言わるる人が随分多いが、これらの人々は畢竟この危険極まる道の案内をよく知って居るのだ。
陥穽や深淵をよけて通り、毒蛇や猛獣を避け、然も相当に欲望を充たし得るのがマア世渡り上手と言ってよかろう。世渡り上手と云へば一種狡猾なわるがしこい人間のように考えるものが多いようだがこの種の人間はうまく世を渡ろうが、儲け口にありつこうが、それは外面だけのことで内面に於いては常に四苦八苦で少しも満足を得て居ない。
佛教に自利々他の覚行 云うことがあるが、ここに利と云うのは坊さん達に言わすと物質から離脱した精神的の利に局限されて居るが私はそうは見て居ない。詰まり二方に渉った自利々他である。自らも利し他も利する自利共利の道を求むる所に宗教もあり道徳もあるのだ。宗教家はややもすれば消極的にこの危険を避けようとする。殊に佛教徒中には禁欲を根本本義と考えて居るものが多いが、それは佛教の根本義を知らないからだ。
これは私独創の見ではない、佛も一切法は観を根本と為すと説かれてある。欲を殺してしまったら活動はないのだ。既に活動がなければこの世界に生命と称すべきもののある筈はない、即ち世界の死滅だ。然もこの欲を充たす道は自らも利し他も利し自他共に利する所に佛教の眞精神は存するのである。危険を避けて安全に通られる世渡りの自道も此の処に開かれているのである。私の信ずる所の佛教はこれであるから私はこの根本義を宣伝したのだ。
ハワイ各島の中でハワイ島は近来非常に宗教熱が盛んで我が県人を中心とする「真宗深信協会」と称する団体もありその例会の時には三四十哩から出席するのもある。私はかかる状態を見て私が佛教を味わって居たことを多幸と思うた。若し私に佛教の思想がなかったならばハワイ各島の巡講中県人に対するのは兎や角お茶を滑し得たとしても所謂一般講演の場合には聊か困ったらうと思った。
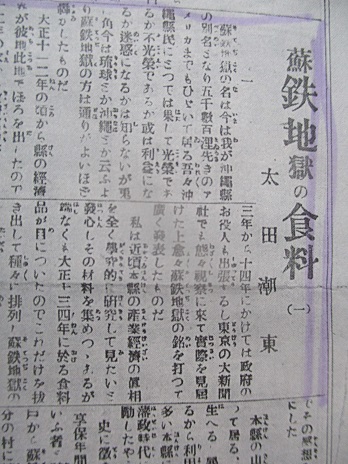
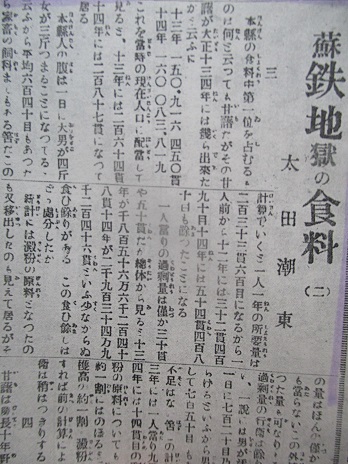
1927年10月13日『沖縄朝日新聞』太田潮東「蘇鉄地獄の食料」
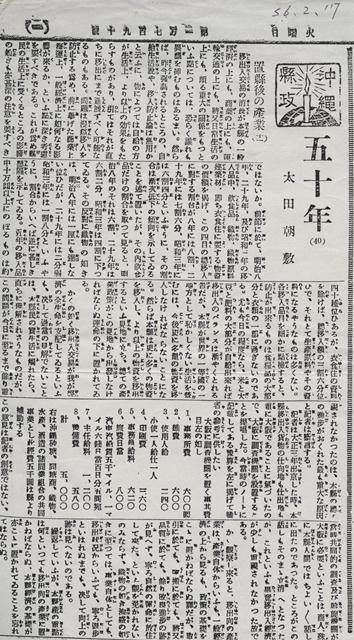
1934年4月27日ー沖縄郷土研究会(1931年1月発足。真境名安興発起)と沖縄県文化協会(1933年8月発足。太田朝敷会長)が合同、沖縄郷土協会が発足し初代会長に太田朝敷が就任。
東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡
□その後はご無沙汰致して居ります。琉球紙の25周年の記念号には広告を通しての社会観を深き興味を以って拝見しましたが今又「離れて観たるその後の沖縄」今朝は只一回しか見ないが物質生活の方面より思想の方面より政治の方面より道徳の方面より種々の形をとって現れた所謂蘇鉄地獄の種々相をえがかれた所一読直ちに「さすがは」と独り叫びました。(略)適者生存の理法は遂にこの士魂を駆逐してしまい物質主義に対しては何らこれを裁制する法則もなく、今日では全く物質的享楽という唯一残された、この思想を最も鮮明に最も適切に見ようとするなら我が沖縄が即ち帝国の縮図です。この縮図の中に一年も生活して居ると夫子自らも矢張り画中の人となり当初の感じは漸次薄らいでくるのです。環境の力の恐ろしさを今更ながら適切に感じます。
□東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡
私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云うより寧ろ民族的団体と云う見地です。(日本)国民の頭から民族的差別観念を消してしまうことは吾々に取っては頗る重要な問題だと考えて居ります。
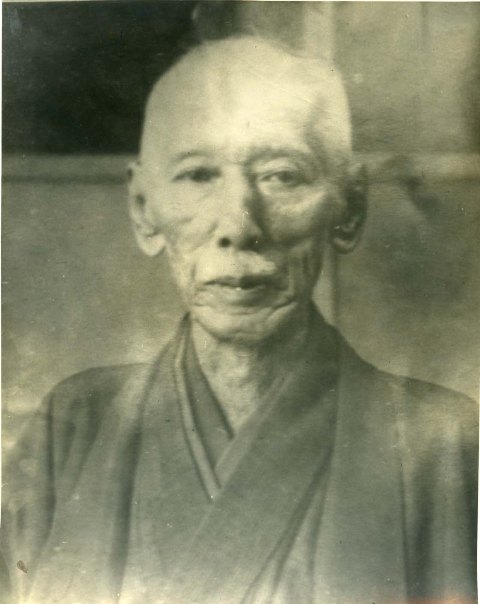
□1991年1月 伊佐真一編『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子
○(略)赤と黒の綱引きは相拮抗しており、それはそれで学問的に大いに議論をすればよいことである。だが、時として世の中にはこうした自由な言論・報道を封じ込めようとする者がいるものである。たとえばその一例、この赤黒論争が新聞紙上や巷間でにぎわっていたころ、沖縄総合事務局開発建設部の村山和義公園調整官から、18名の元委員に宛て、首里城にかかわる発言を統制しようという文書が出されている。その内容は、首里城正殿及び公園に関する出版物の刊行、公演、取材等多岐にわたる「マスコミ等への報道」を「公園調整官を窓口として一本化」するというものであった。これに対して、又吉真三氏と前田氏と前田氏はただちに抗議を行ったが、事の重大さに気づいた当局は6月12日付で、先の文書の廃棄処分するに至った(『琉球新報』1989年7月25日付夕刊)。戦前の大政翼賛会まがいの行為をしたわけであるから当然といえば当然である。(略)
□2009年10月 屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』世織書房
○(略)高良倉吉氏のそのような直接的な政治的役割にかんしてではない。琉球史研究という学問的意匠による非政治的立場を装いながら、きわめて政治的な役割を果たしている、その<政治性>の問題についてである。それは、党派的な主義主張やイデオロギーなどの「政治性」とは位相」を異にした、関係における認識や解釈などの<政治性>の問題である。
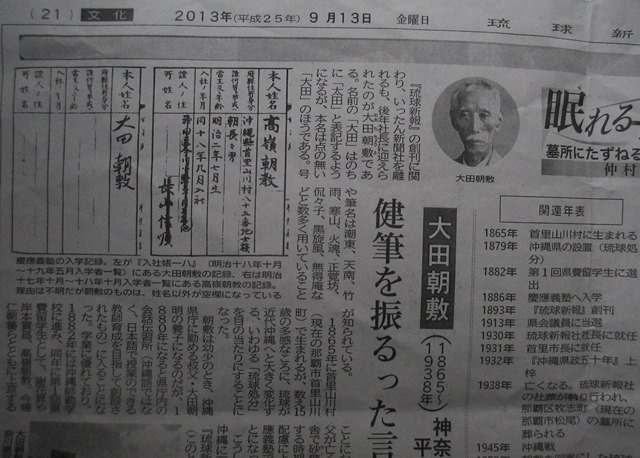
2013年9月13日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー大田朝敷」
□ヒロの滞在は悠々保養のつもりであったがヒロ市在留の県人もなを 席の宗教談でも聞きたいという希望があり、ホノムの佛教婦人会からも今一回講演して貰いたいと云う頼みが来たので、これも何かの因縁と思うて快く引き受け、この二席の講演は愈々お名残の講演であるから、多少趣きを加え金儲けと宗教を結びつけて話した。
ハワイに来て居る人々の多くは何れも金儲けを目的として来たに相違ないが、さて佛教に於いてもキリスト教に於いても、その他の宗教に於いても、教壇から金儲けの話しをすることは余りしないようだ。ところが金と云う奴は実に重宝なもので、誰でもこれが嫌いなものは居ない。佛教の或る開教師がしこたま金をためて帰ったそうだが或る人がそれを難したら、その坊さん平然として曰く「佛と云う字は人偏に弗と云う字じゃないか」この坊さんの如きは寧ろ正直の方で、金に執着がないような顔をして居る宗教家中にも、その実内ふくのものが可なり居るようだ。
要するに金を得たいというのは万人が万人共通の欲望だ。吾々の前に開けられている広い広い道は、只この欲望を満足する活動の為に開かれたかのように思わるる位いだ。ところがこの広い道には人の目に見えぬ陥穽もあれば深淵もあり所によっては毒蛇も居れば猛獣も居る。世の中には金儲けの上手と言わるる人が随分多いが、これらの人々は畢竟この危険極まる道の案内をよく知って居るのだ。
陥穽や深淵をよけて通り、毒蛇や猛獣を避け、然も相当に欲望を充たし得るのがマア世渡り上手と言ってよかろう。世渡り上手と云へば一種狡猾なわるがしこい人間のように考えるものが多いようだがこの種の人間はうまく世を渡ろうが、儲け口にありつこうが、それは外面だけのことで内面に於いては常に四苦八苦で少しも満足を得て居ない。
佛教に自利々他の覚行 云うことがあるが、ここに利と云うのは坊さん達に言わすと物質から離脱した精神的の利に局限されて居るが私はそうは見て居ない。詰まり二方に渉った自利々他である。自らも利し他も利する自利共利の道を求むる所に宗教もあり道徳もあるのだ。宗教家はややもすれば消極的にこの危険を避けようとする。殊に佛教徒中には禁欲を根本本義と考えて居るものが多いが、それは佛教の根本義を知らないからだ。
これは私独創の見ではない、佛も一切法は観を根本と為すと説かれてある。欲を殺してしまったら活動はないのだ。既に活動がなければこの世界に生命と称すべきもののある筈はない、即ち世界の死滅だ。然もこの欲を充たす道は自らも利し他も利し自他共に利する所に佛教の眞精神は存するのである。危険を避けて安全に通られる世渡りの自道も此の処に開かれているのである。私の信ずる所の佛教はこれであるから私はこの根本義を宣伝したのだ。
ハワイ各島の中でハワイ島は近来非常に宗教熱が盛んで我が県人を中心とする「真宗深信協会」と称する団体もありその例会の時には三四十哩から出席するのもある。私はかかる状態を見て私が佛教を味わって居たことを多幸と思うた。若し私に佛教の思想がなかったならばハワイ各島の巡講中県人に対するのは兎や角お茶を滑し得たとしても所謂一般講演の場合には聊か困ったらうと思った。
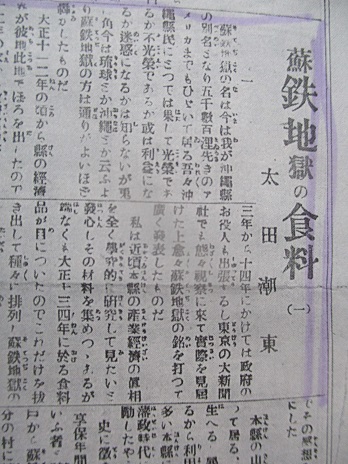
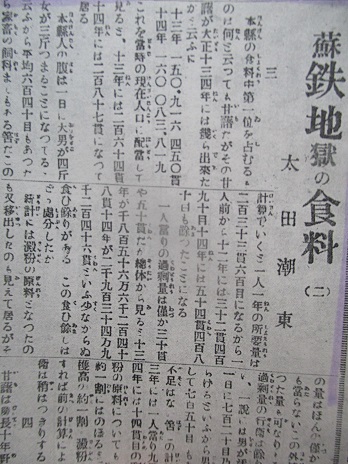
1927年10月13日『沖縄朝日新聞』太田潮東「蘇鉄地獄の食料」
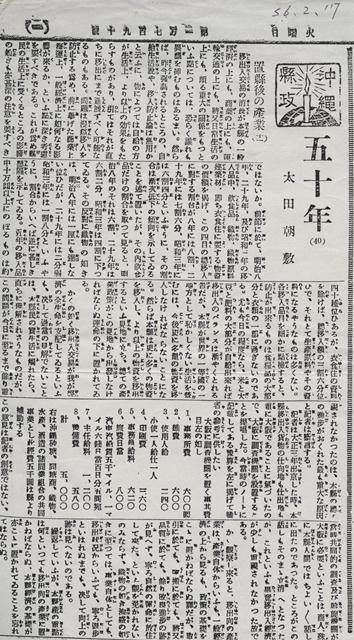
1934年4月27日ー沖縄郷土研究会(1931年1月発足。真境名安興発起)と沖縄県文化協会(1933年8月発足。太田朝敷会長)が合同、沖縄郷土協会が発足し初代会長に太田朝敷が就任。
東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡
□その後はご無沙汰致して居ります。琉球紙の25周年の記念号には広告を通しての社会観を深き興味を以って拝見しましたが今又「離れて観たるその後の沖縄」今朝は只一回しか見ないが物質生活の方面より思想の方面より政治の方面より道徳の方面より種々の形をとって現れた所謂蘇鉄地獄の種々相をえがかれた所一読直ちに「さすがは」と独り叫びました。(略)適者生存の理法は遂にこの士魂を駆逐してしまい物質主義に対しては何らこれを裁制する法則もなく、今日では全く物質的享楽という唯一残された、この思想を最も鮮明に最も適切に見ようとするなら我が沖縄が即ち帝国の縮図です。この縮図の中に一年も生活して居ると夫子自らも矢張り画中の人となり当初の感じは漸次薄らいでくるのです。環境の力の恐ろしさを今更ながら適切に感じます。
□東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡
私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云うより寧ろ民族的団体と云う見地です。(日本)国民の頭から民族的差別観念を消してしまうことは吾々に取っては頗る重要な問題だと考えて居ります。
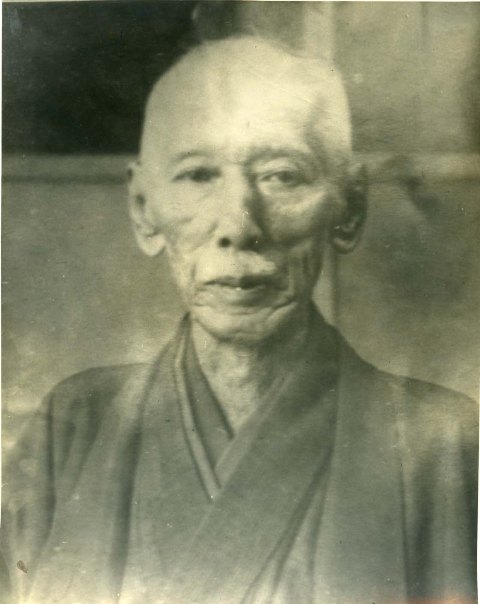
□1991年1月 伊佐真一編『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子
○(略)赤と黒の綱引きは相拮抗しており、それはそれで学問的に大いに議論をすればよいことである。だが、時として世の中にはこうした自由な言論・報道を封じ込めようとする者がいるものである。たとえばその一例、この赤黒論争が新聞紙上や巷間でにぎわっていたころ、沖縄総合事務局開発建設部の村山和義公園調整官から、18名の元委員に宛て、首里城にかかわる発言を統制しようという文書が出されている。その内容は、首里城正殿及び公園に関する出版物の刊行、公演、取材等多岐にわたる「マスコミ等への報道」を「公園調整官を窓口として一本化」するというものであった。これに対して、又吉真三氏と前田氏と前田氏はただちに抗議を行ったが、事の重大さに気づいた当局は6月12日付で、先の文書の廃棄処分するに至った(『琉球新報』1989年7月25日付夕刊)。戦前の大政翼賛会まがいの行為をしたわけであるから当然といえば当然である。(略)
□2009年10月 屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』世織書房
○(略)高良倉吉氏のそのような直接的な政治的役割にかんしてではない。琉球史研究という学問的意匠による非政治的立場を装いながら、きわめて政治的な役割を果たしている、その<政治性>の問題についてである。それは、党派的な主義主張やイデオロギーなどの「政治性」とは位相」を異にした、関係における認識や解釈などの<政治性>の問題である。
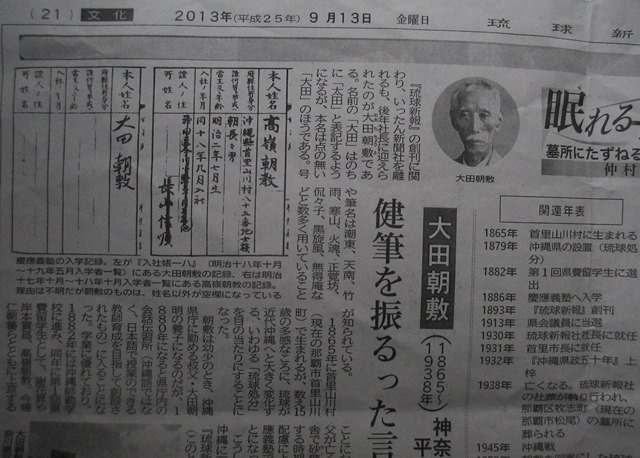
2013年9月13日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー大田朝敷」
目次
編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。
沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦
ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷
沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎
地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇
岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣
女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫
性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎
セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠
耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏
万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建
八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮
琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一
琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎
南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫
阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七
尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)
□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。
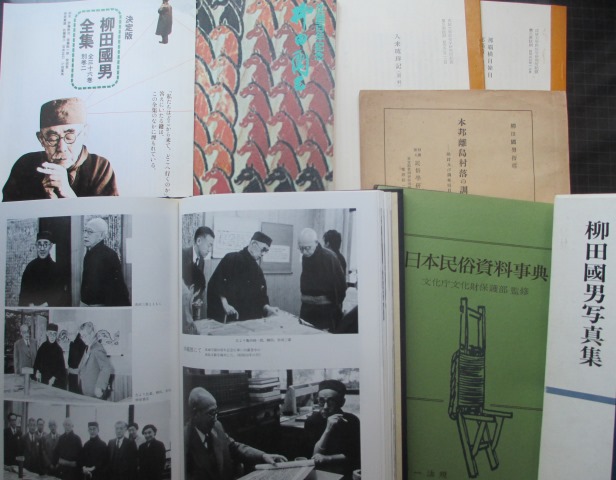
柳田国男 やなぎた-くにお
1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。
明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。
【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク
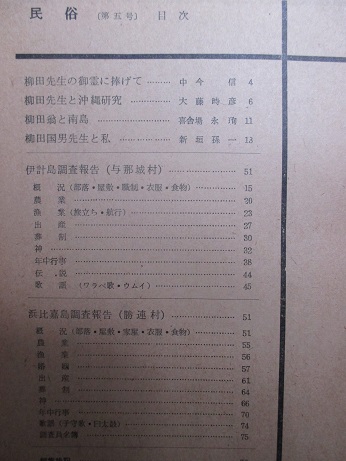
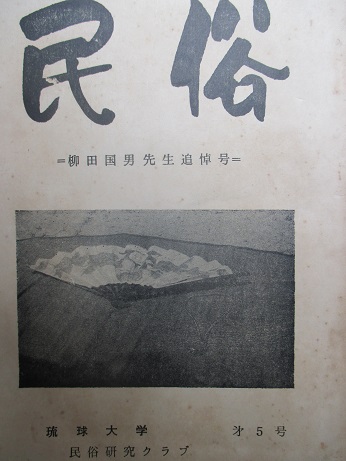
1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号
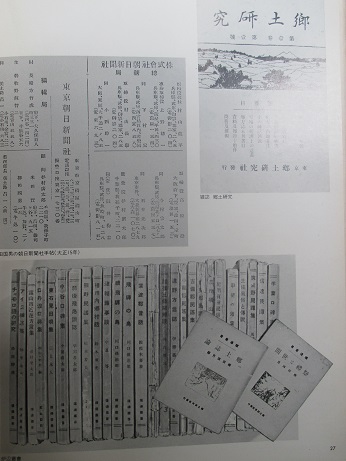
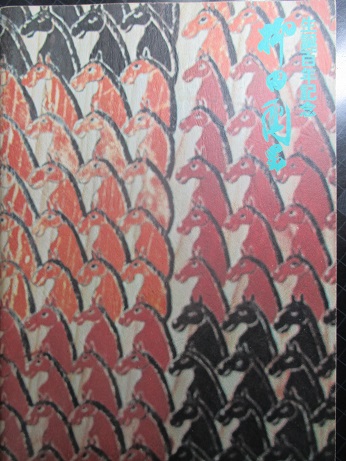
1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展
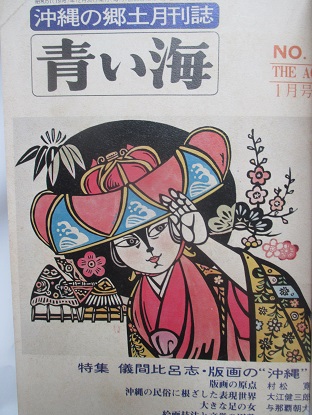
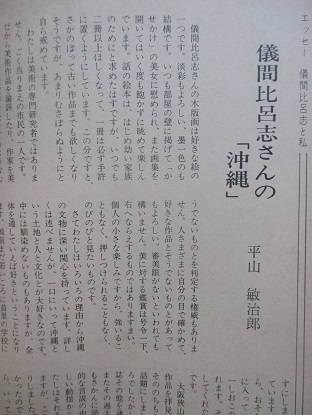
1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」
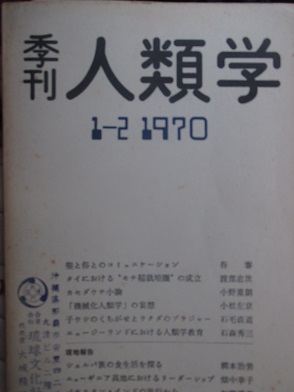
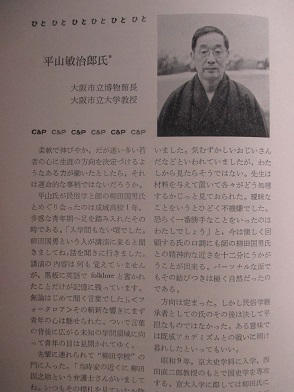
1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」
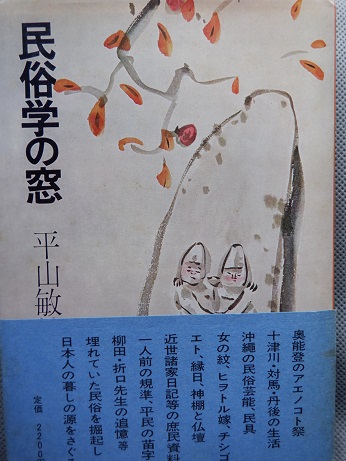
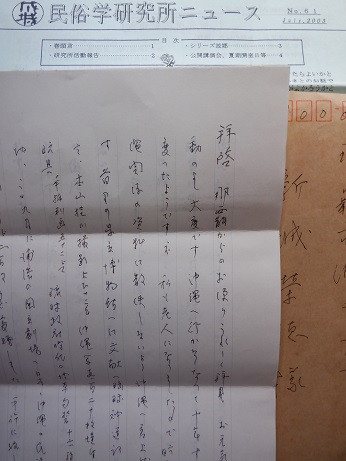
1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡
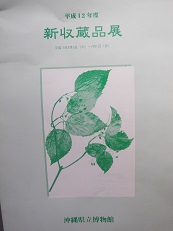

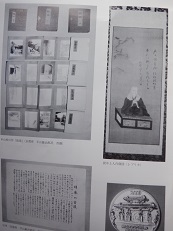
2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈
平山敏治郎
歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)
**略歴
大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。
昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。
**おもな著書
『日本中世家族の研究』(1980)
『民俗学の窓』(1981)
『歳時習俗考』(1984)
『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)
押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)
岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。
浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。
編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。
沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦
ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷
沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎
地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇
岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣
女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫
性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎
セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠
耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏
万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建
八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮
琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一
琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎
南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫
阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七
尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男
○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)
□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。
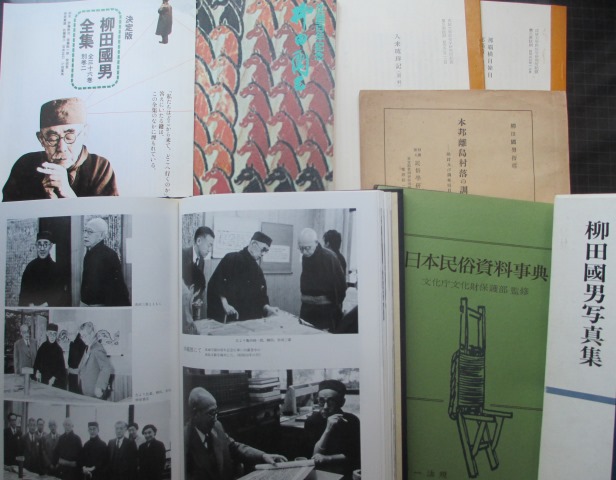
柳田国男 やなぎた-くにお
1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。
明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。
【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク
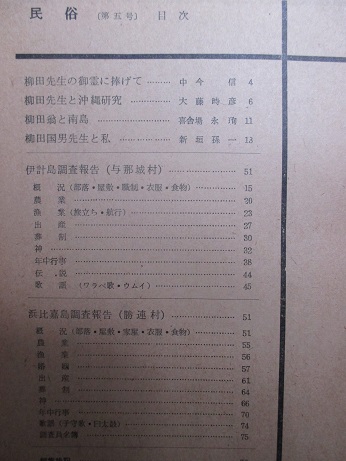
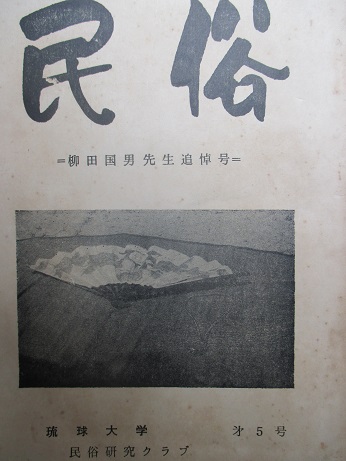
1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号
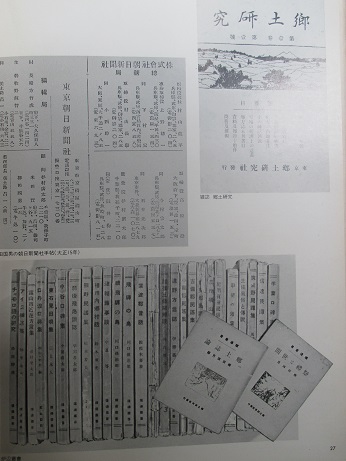
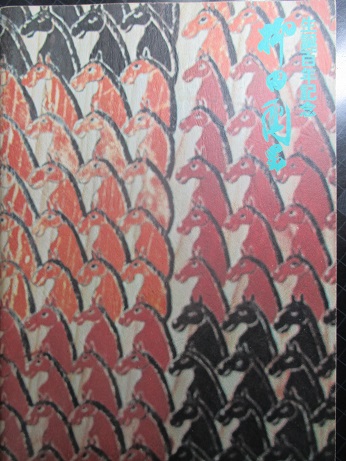
1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展
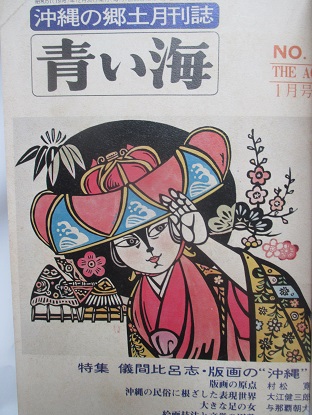
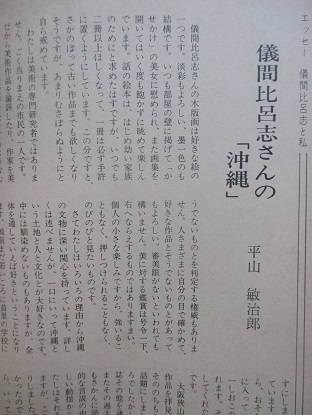
1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」
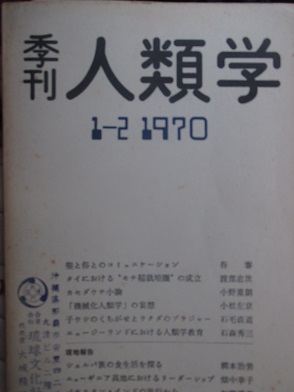
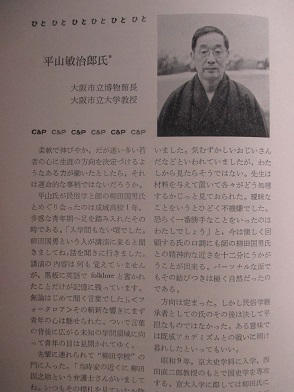
1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」
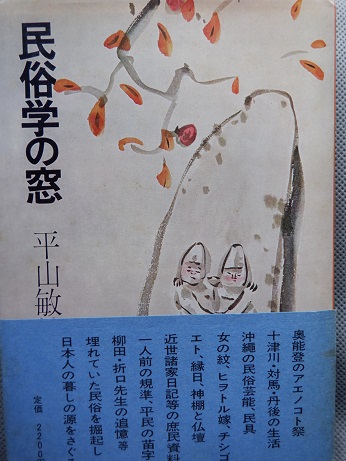
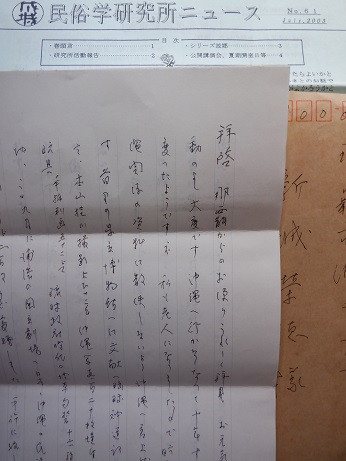
1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡
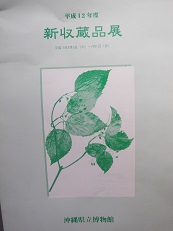

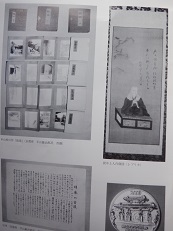
2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈
平山敏治郎
歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)
**略歴
大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。
昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。
**おもな著書
『日本中世家族の研究』(1980)
『民俗学の窓』(1981)
『歳時習俗考』(1984)
『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)
押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)
岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。
浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。
昨年暮れ、沖縄県立博物館・美術館指定管理者の「文化の杜共同企業体」から今年5月に開催される企画展「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した“美”」の図録に末吉麦門冬と鎌倉芳太郎についての原稿依頼があった。奇しくも今年11月25日は末吉麦門冬の没後90年で、展覧会場の沖縄県立博物館・美術館に隣接する公園北端はかつて末吉家の墓があった場所である。加えて、文化の杜には麦門冬曾孫の萌子さんも居る。私は2007年の沖縄県立美術館開館記念展図録『沖縄文化の軌跡』「麦門冬の果たした役割」の中で「琉球美術史に先鞭をつけたのは麦門冬・末吉安恭で、その手解きを受けた一人が美術史家・比嘉朝健である。安恭は1913年、『沖縄毎日新聞』に朝鮮小説「龍宮の宴」や支那小説「寒徹骨」などを立て続けに連載した。そして15年、『琉球新報』に『吾々の祖先が文字に暗い上に筆不精(略)流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の国ではある』と朝鮮の古書『龍飛御天歌』『稗官雑記』などを引用し、『朝鮮史に見えたる古琉球』を連載した。
画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬
安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。
麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
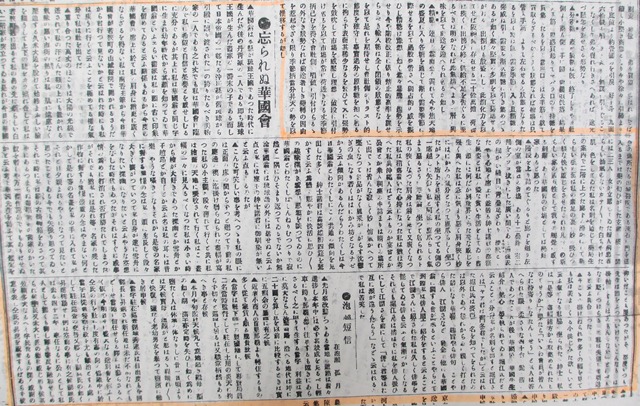
華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・
麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

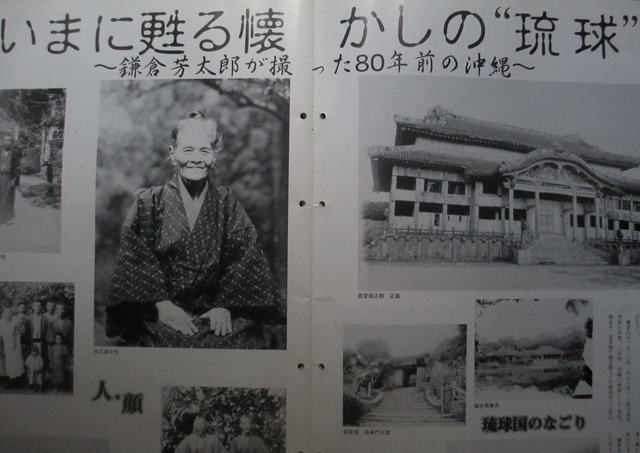
画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬
安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。
麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。
1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」
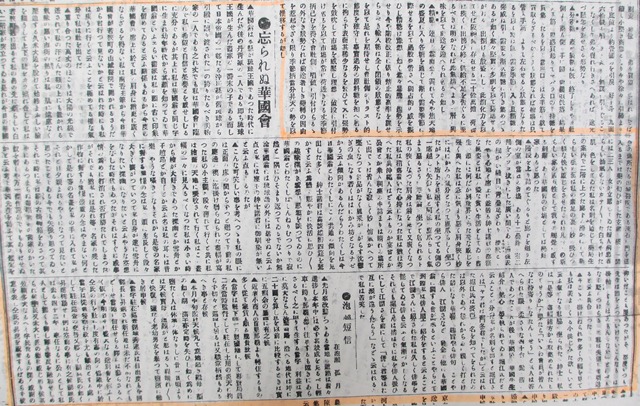
華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・
麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

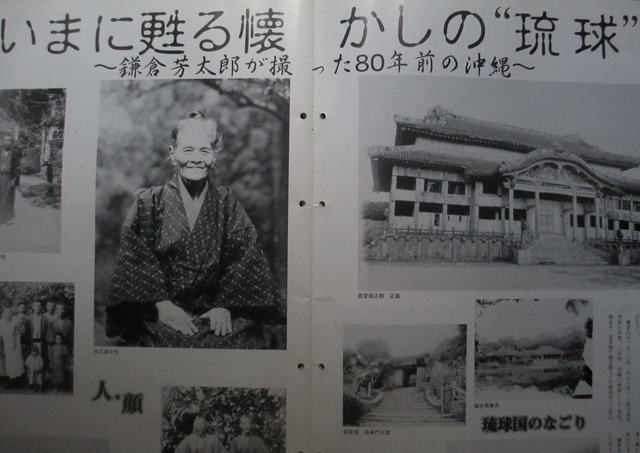
02/19: 神村朝堅 雑誌『おきなわ』創刊への道
1945年8月、国吉真哲・宮里栄輝・源武雄が早く帰還できるよう「県人会」結成を相談。宮里栄輝、熊本沖縄県人会長になる。/女子挺身隊救済で尼崎沖縄県人会結成。
9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。
11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎
11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会
11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行
12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)
1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦
1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。
2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」
3月、『関西沖縄新報』創刊
4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳
4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇
8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久
1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正
1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称
1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮
1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。
1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」
1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。
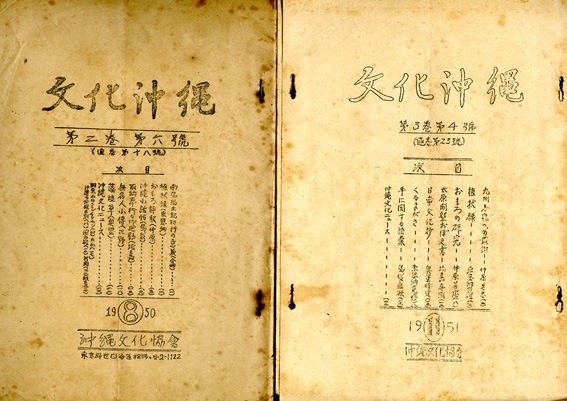
この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝
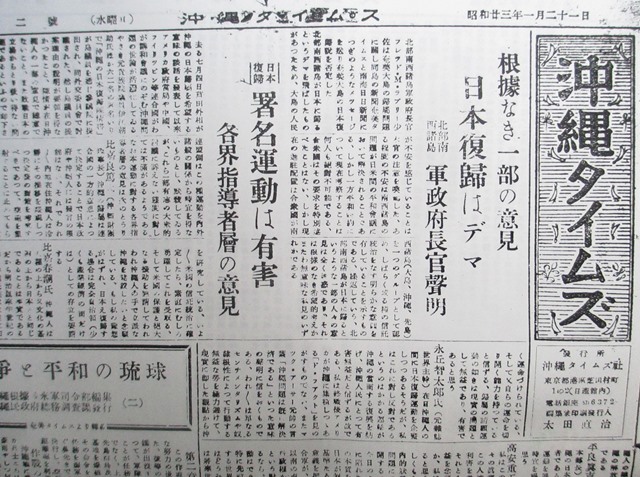
1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号
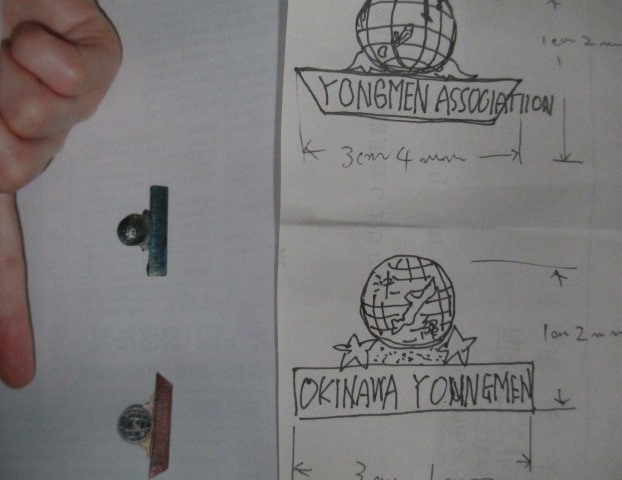
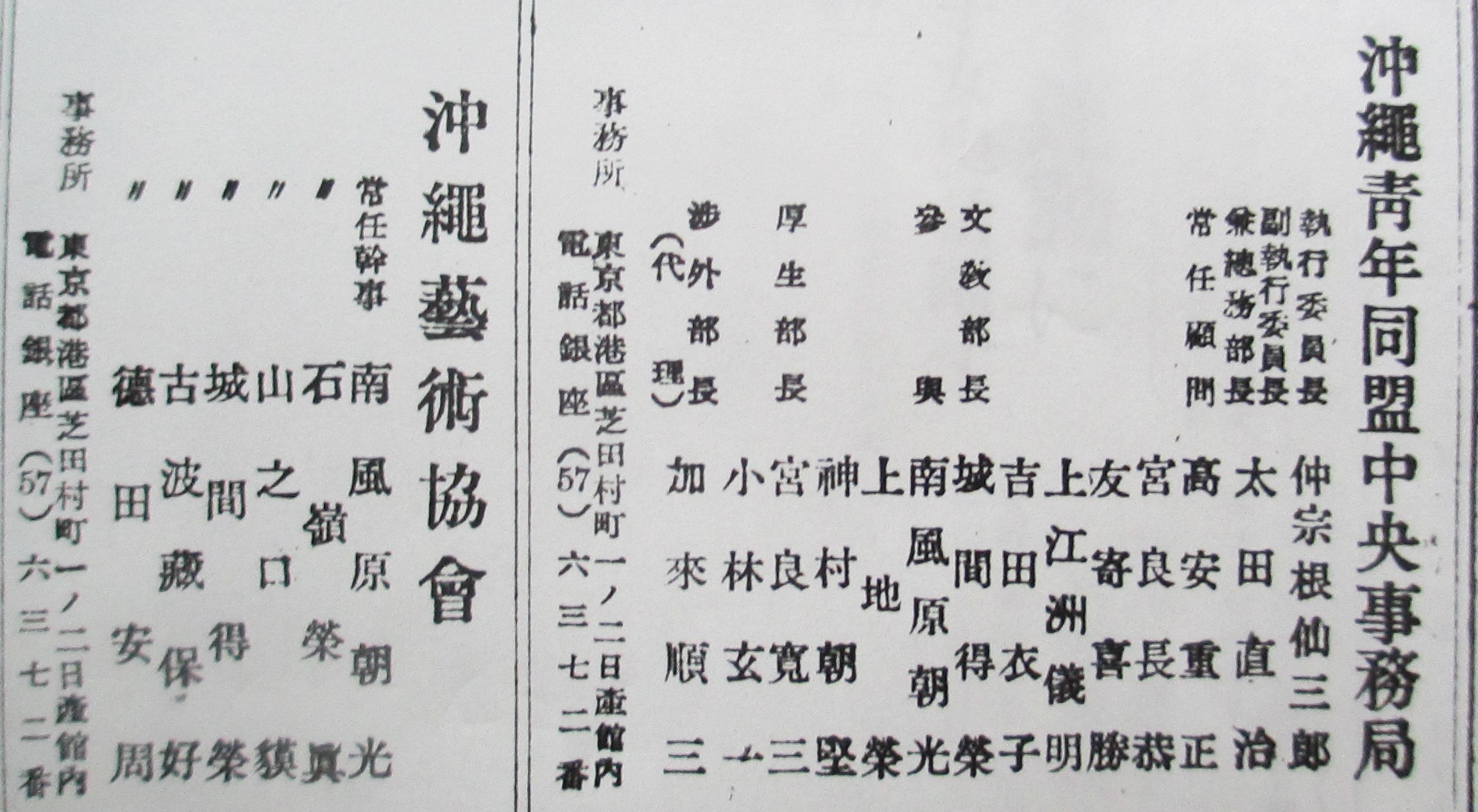
1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号
1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。
②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。
1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。
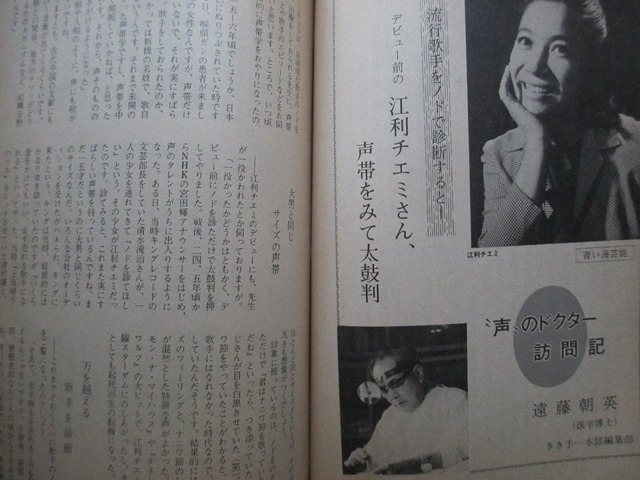
『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士
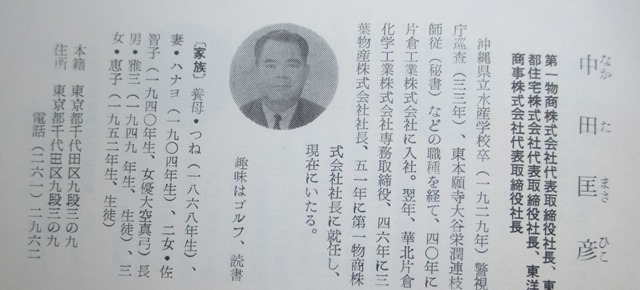
1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』
大空真弓 おおぞら-まゆみ
1940- 昭和後期-平成時代の女優。
昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。
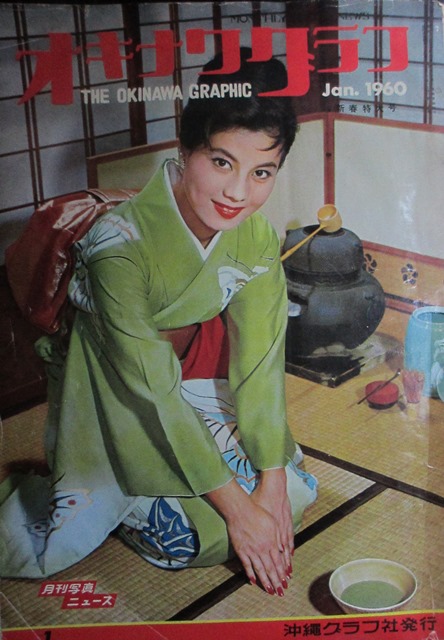
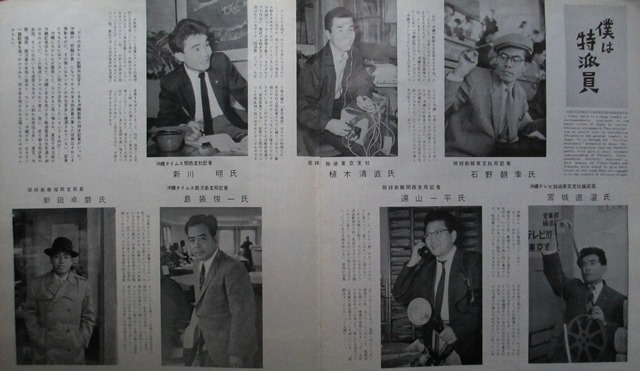
『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。
1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社
1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅
1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社
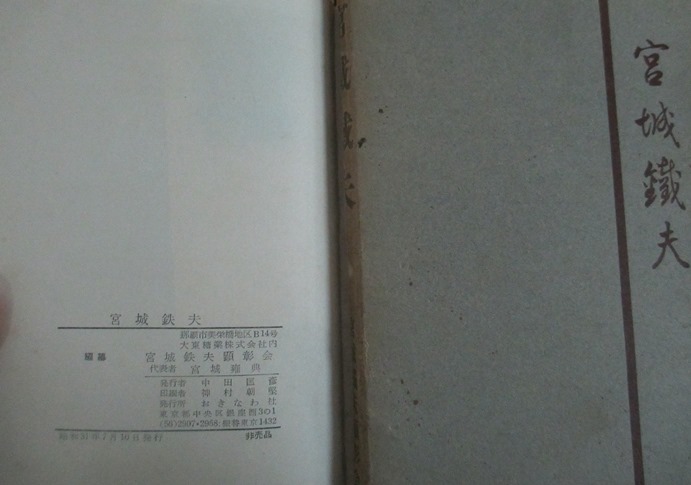 (BOOKSじのん在庫)
(BOOKSじのん在庫)
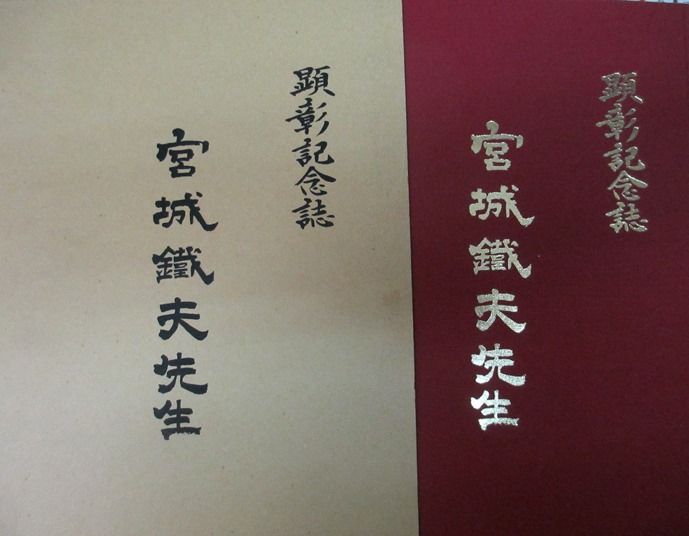
平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)
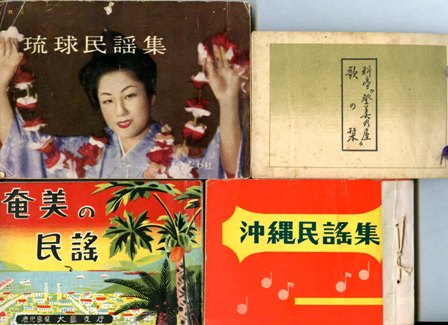
1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)
1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅
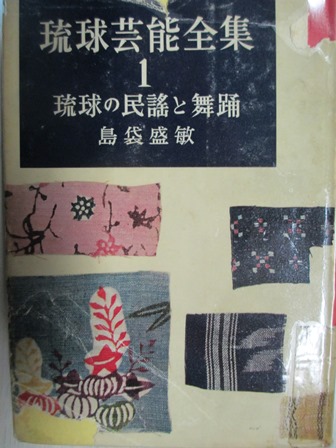
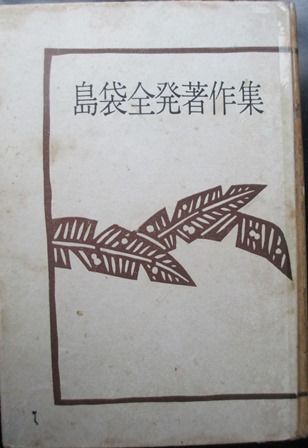
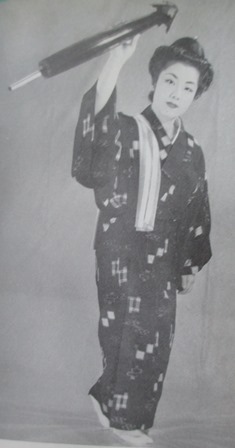
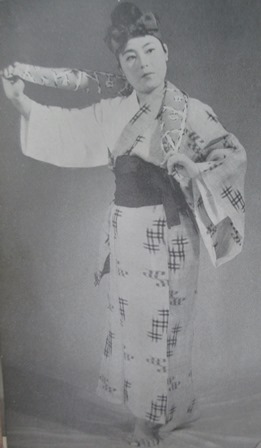
1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社
1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社
1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社
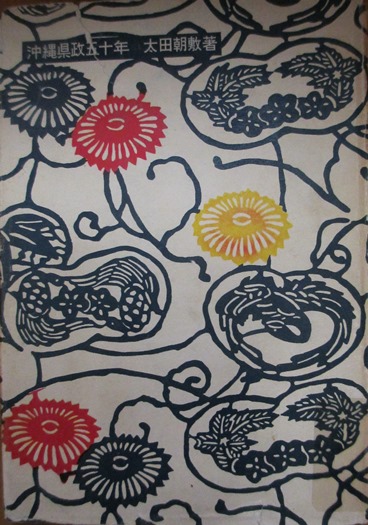
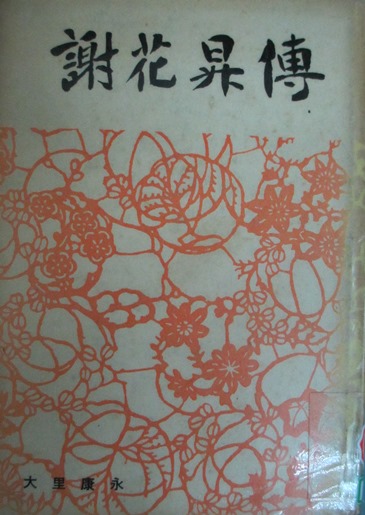
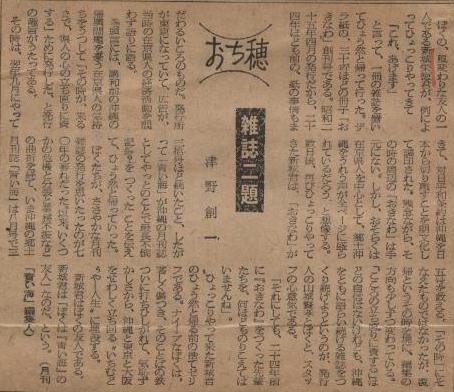
1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」
○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。
巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。
数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。
「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。
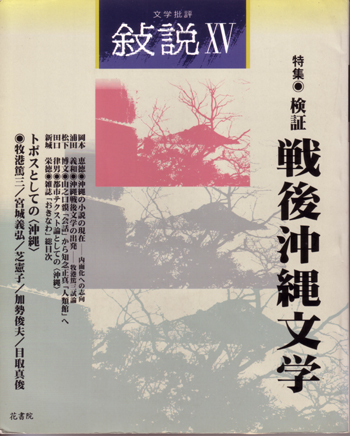

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」
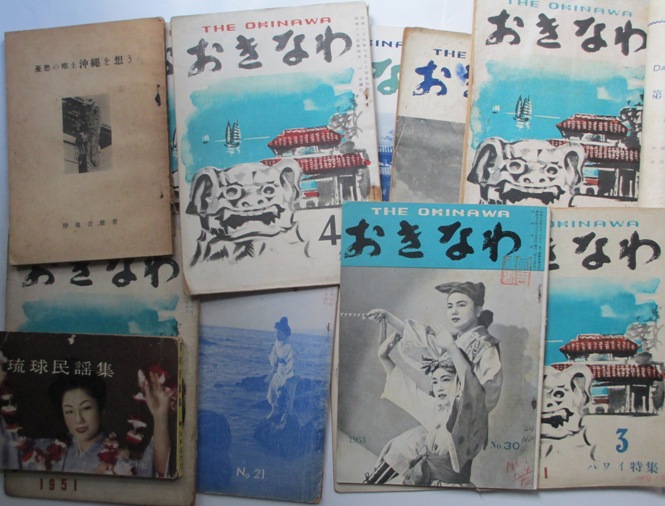
雑誌『おきなわ』
9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。
11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎
11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会
11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行
12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)
1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦
1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。
2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」
3月、『関西沖縄新報』創刊
4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳
4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇
8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久
1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正
1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称
1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮
1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。
1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」
1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。
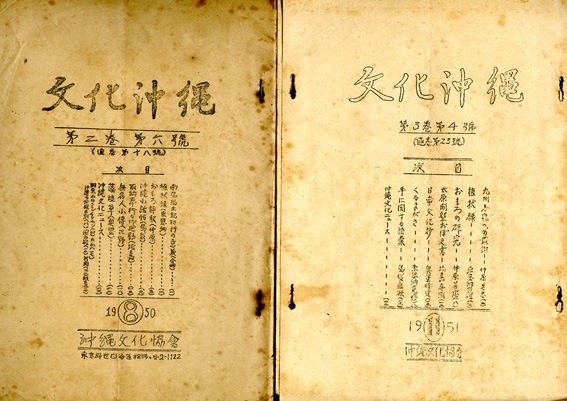
この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝
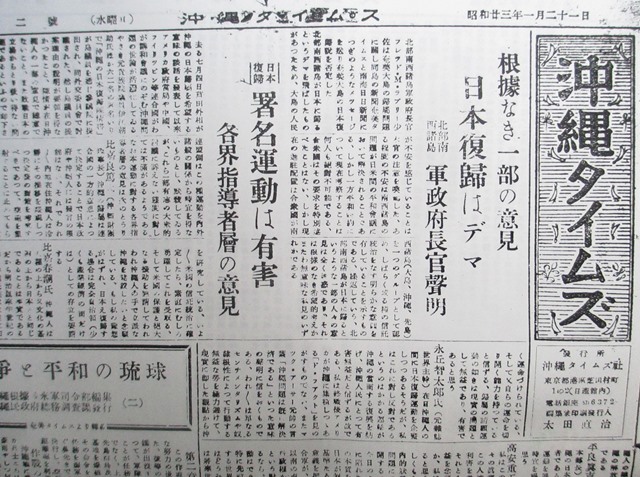
1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号
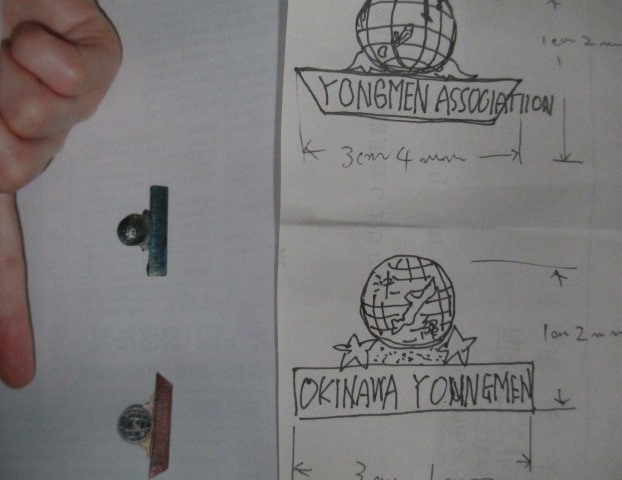
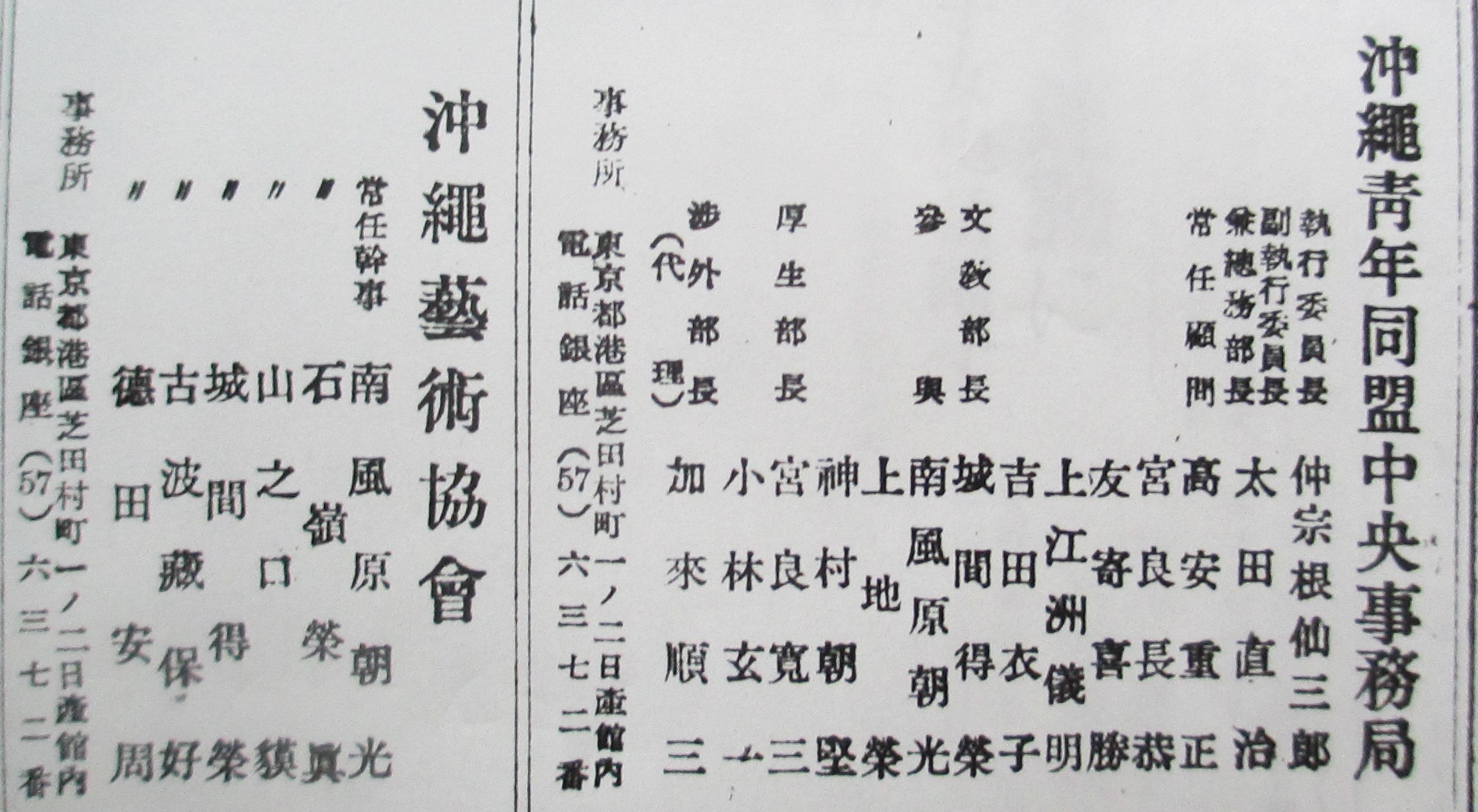
1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号
1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。
②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。
1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。
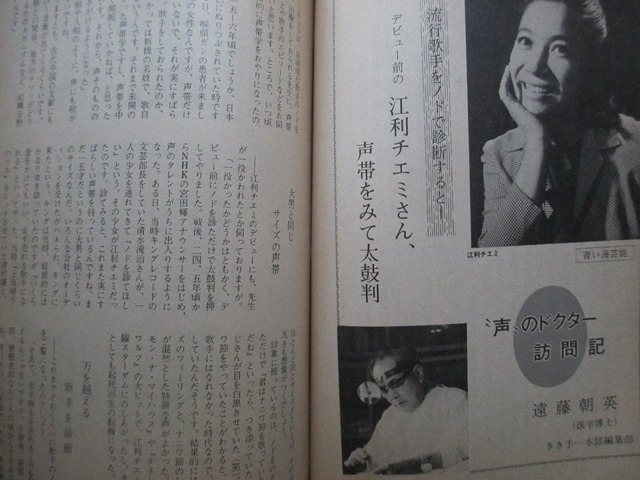
『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士
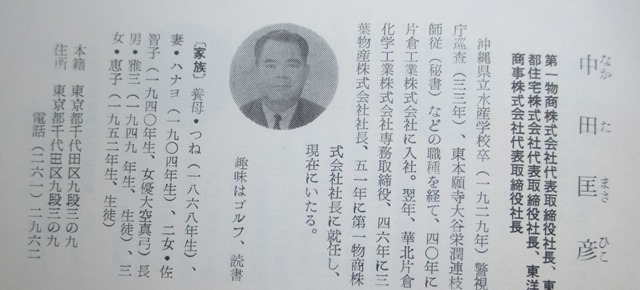
1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』
大空真弓 おおぞら-まゆみ
1940- 昭和後期-平成時代の女優。
昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。
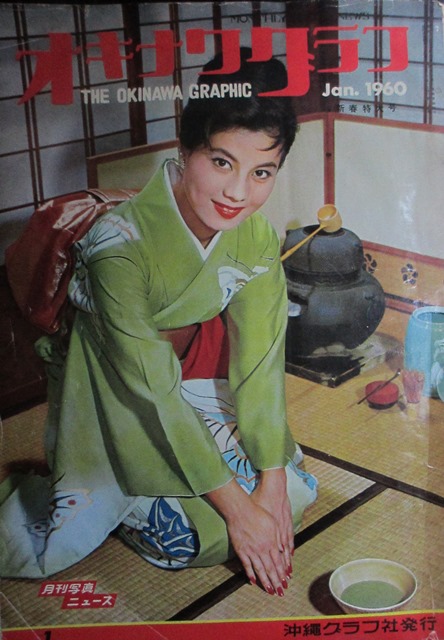
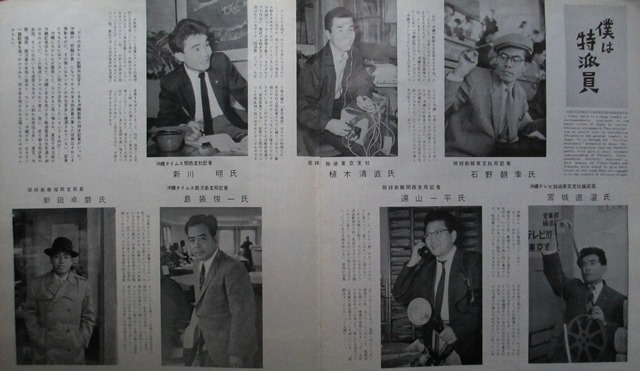
『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。
1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社
1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅
1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社
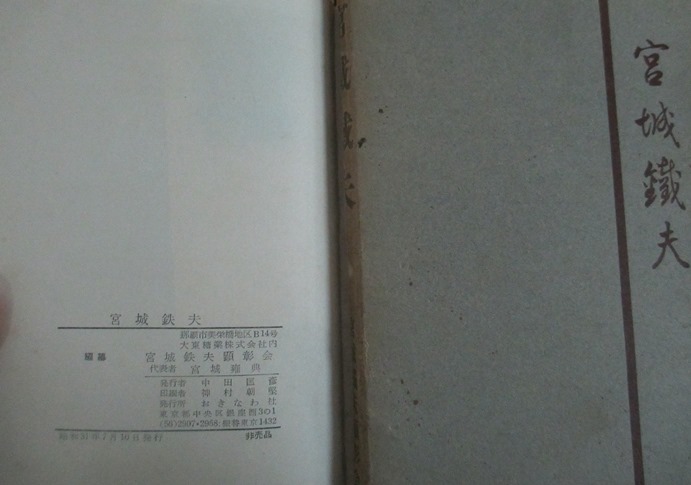 (BOOKSじのん在庫)
(BOOKSじのん在庫)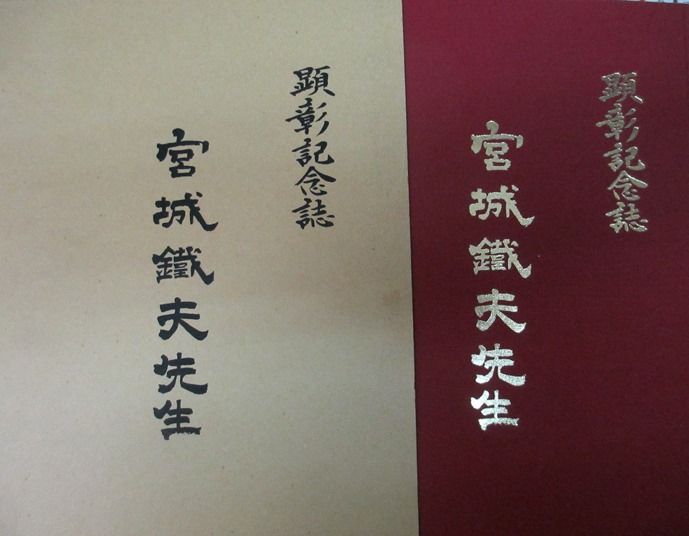
平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)
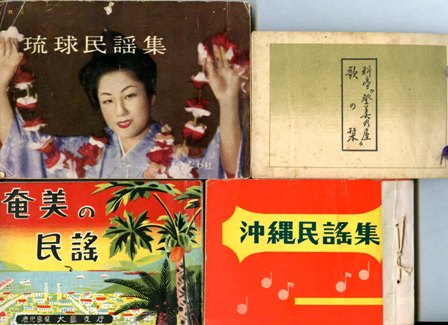
1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)
1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅
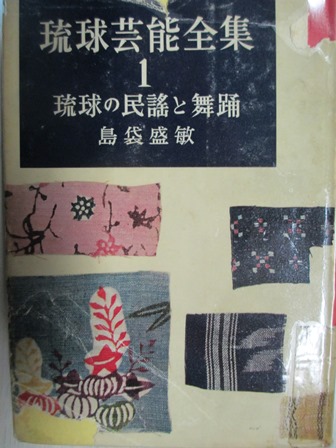
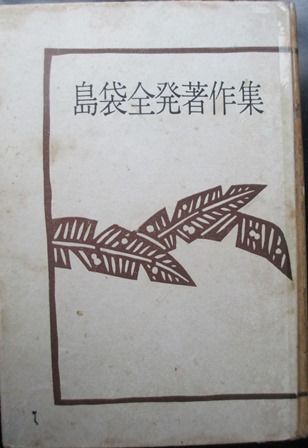
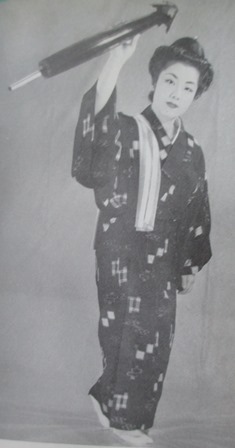
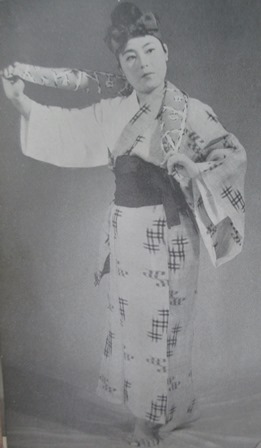
1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社
1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社
1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社
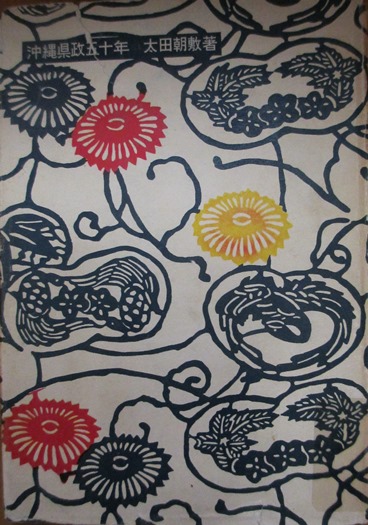
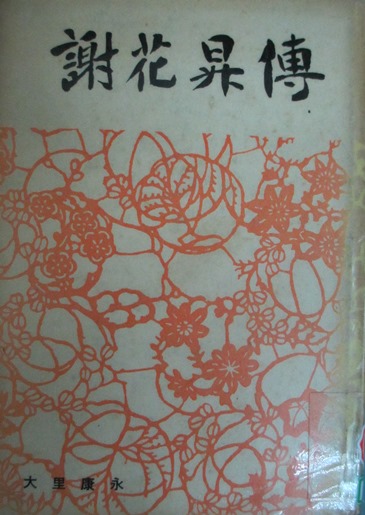
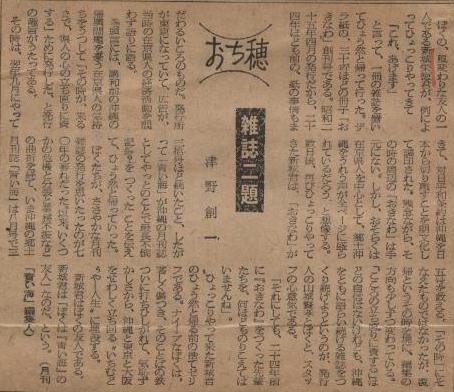
1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」
○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。
巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。
数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。
「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。
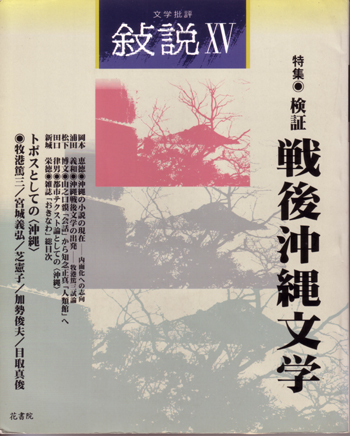

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」
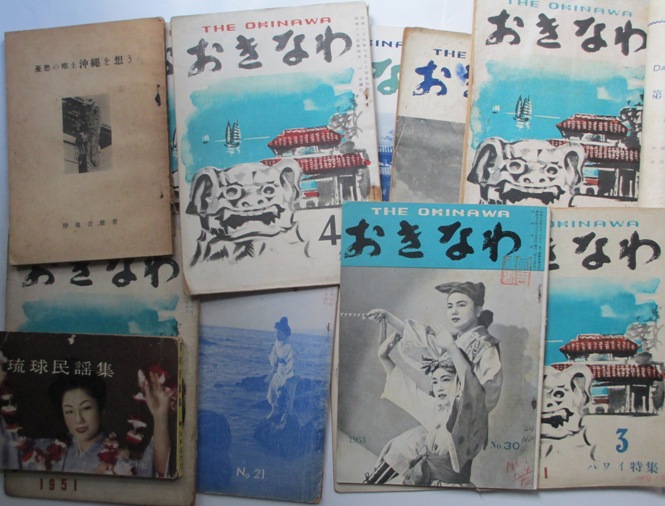
雑誌『おきなわ』
02/26: 観光文化/「描かれたジュリ」②
1913年6月5日、岡田雪窓 那覇港から鹿児島へ


1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」
1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」
1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」
1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」
1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」
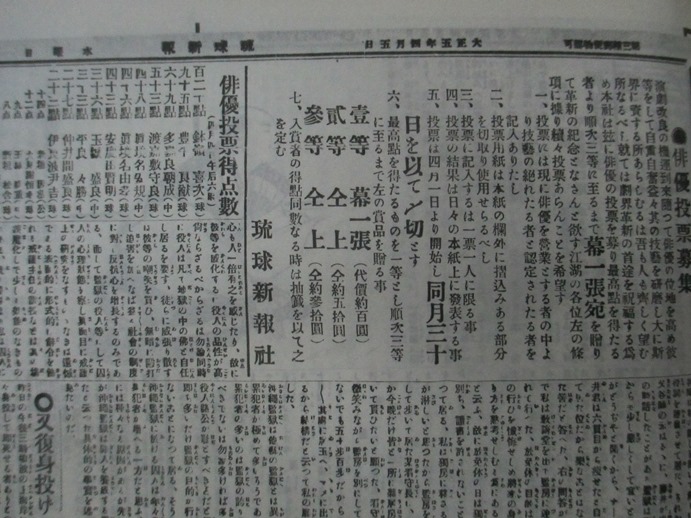
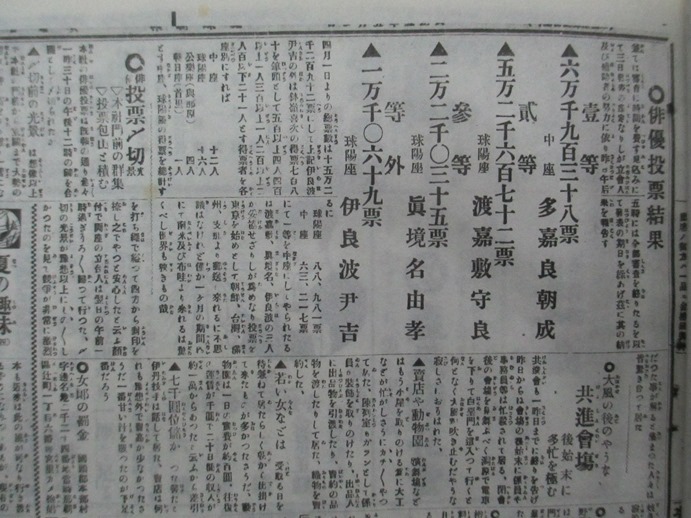
1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」
1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会
1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」
1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店
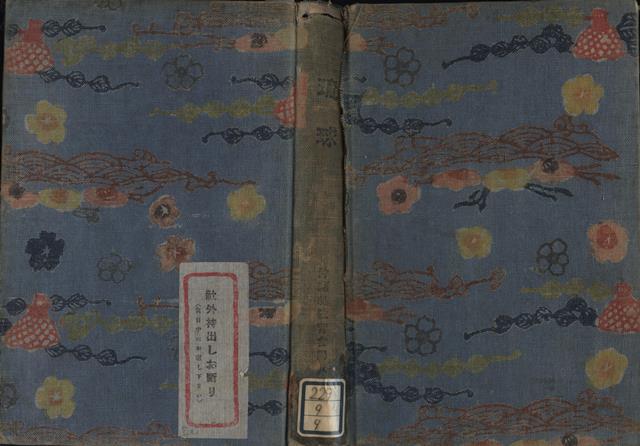
□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。
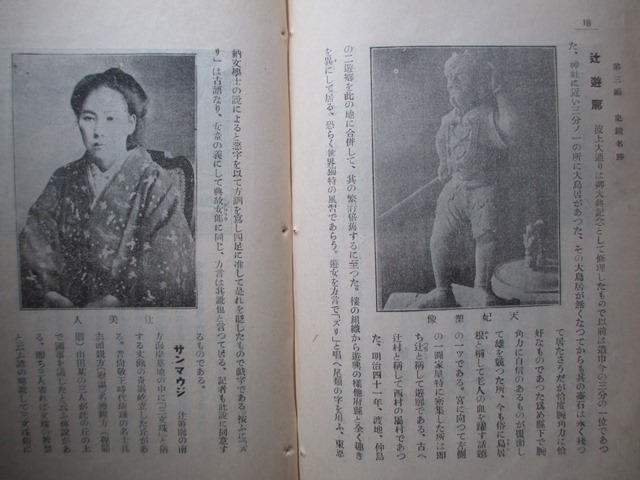
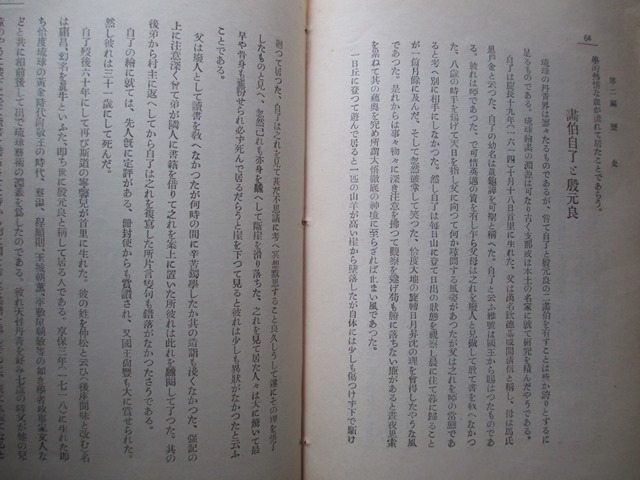
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」


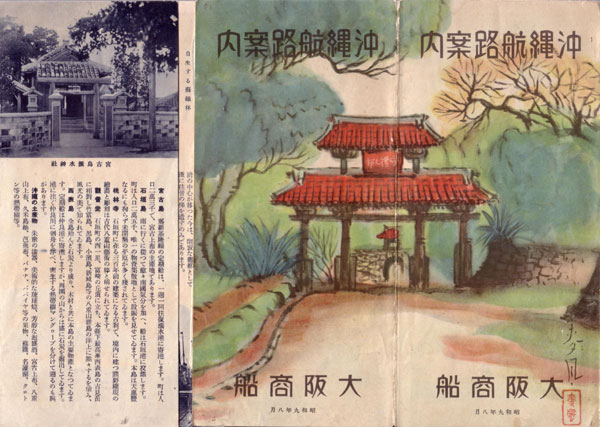
1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)
有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)
1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店
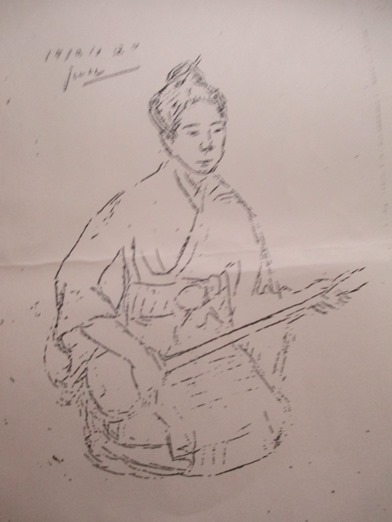
○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」
○ひなた、他九篇
ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。
○佛さま、他十篇
佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。
○母と子、他八篇
○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)




1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

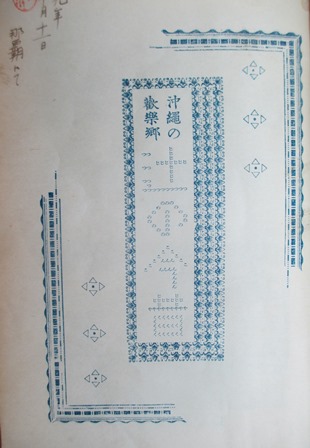


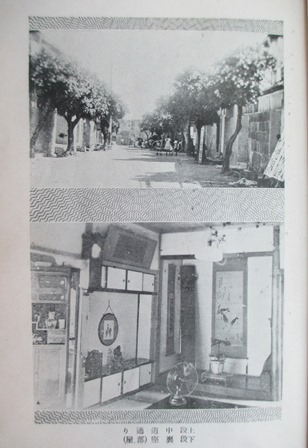
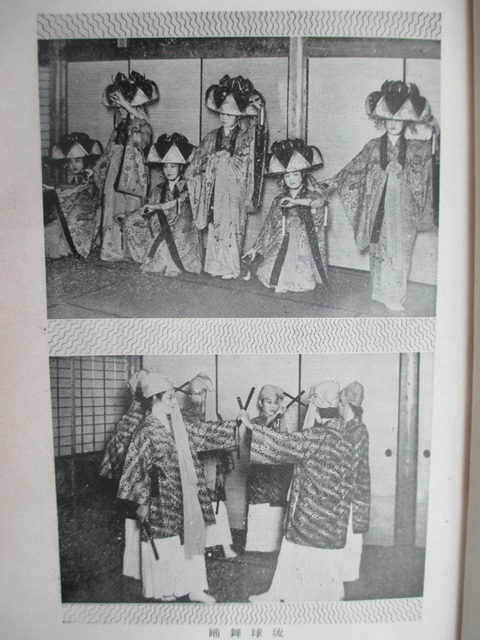
○一向宗の法難と廓
王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。
また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。
明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。
備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。
1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。
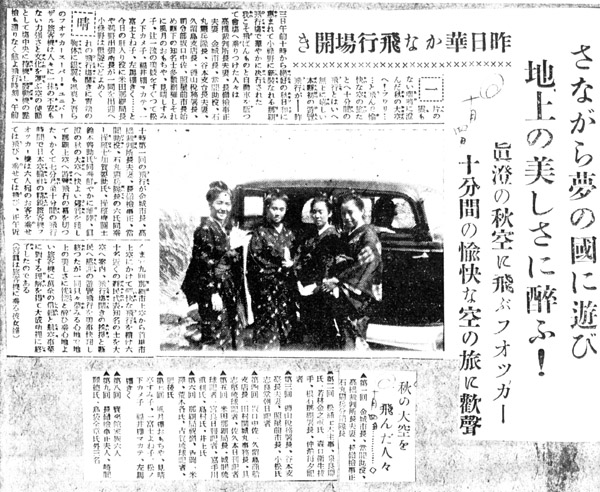
1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行
1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」
1938年9月15日『大阪球陽新報』
□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。
家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。
県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。
辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。


1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り
□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」
1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」
1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」
1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」
1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」
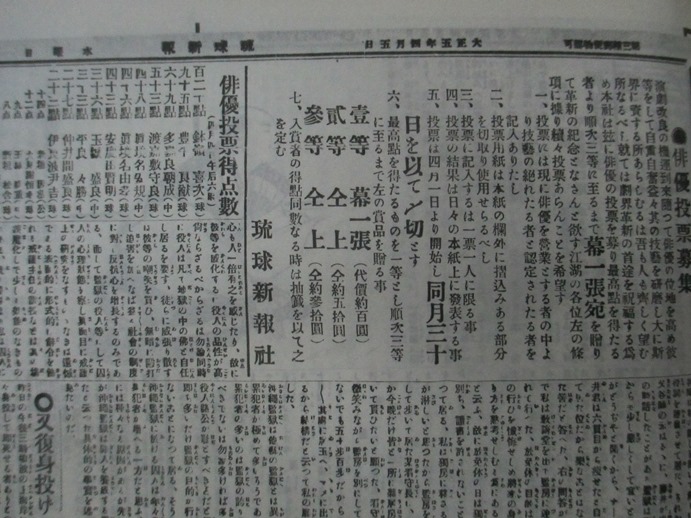
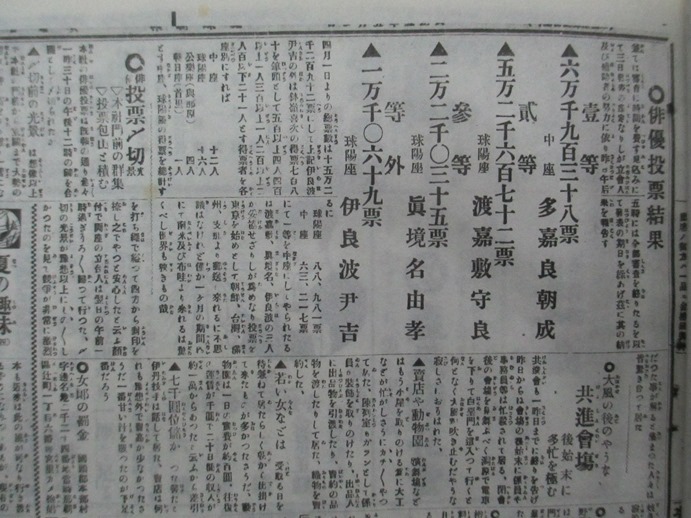
1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」
1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会
1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」
1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店
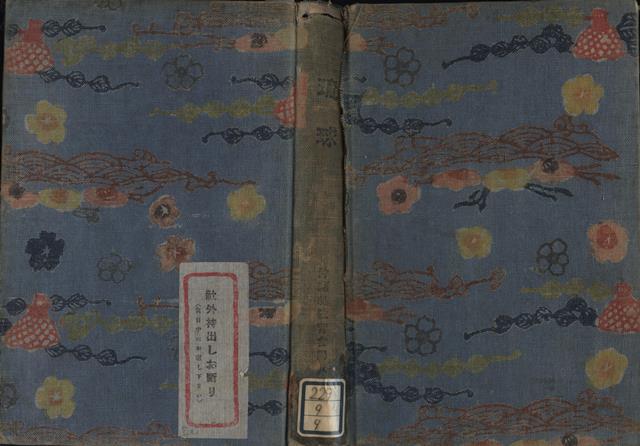
□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。
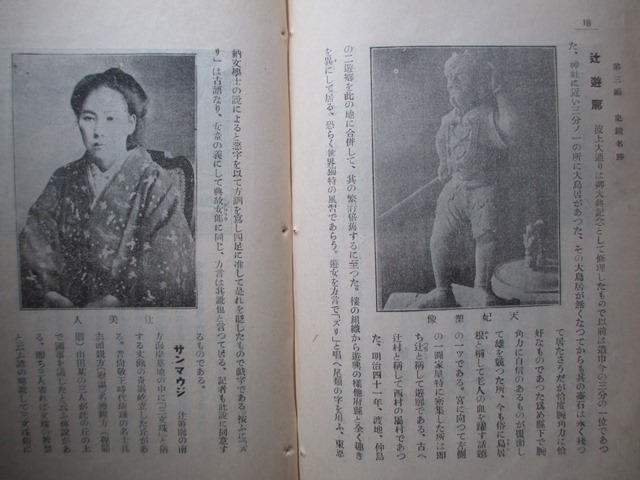
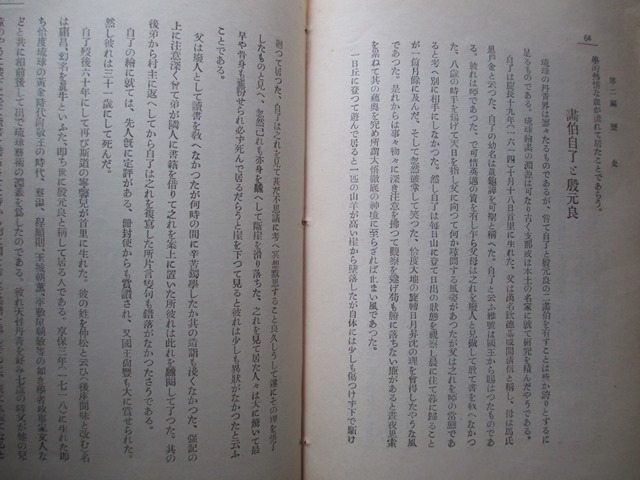
1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」


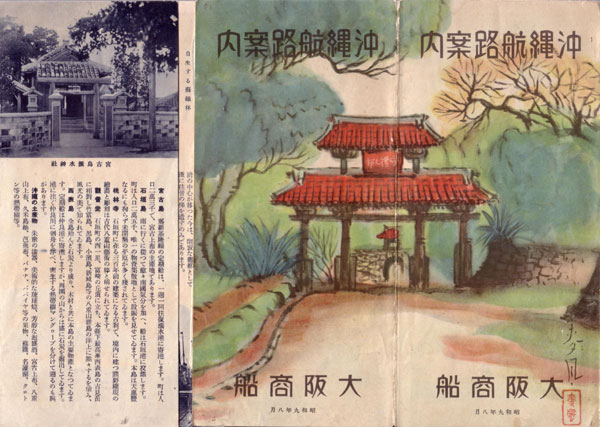
1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)
有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)
1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店
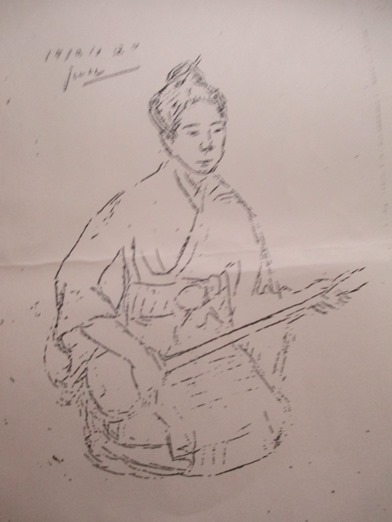
○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」
○ひなた、他九篇
ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。
○佛さま、他十篇
佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。
○母と子、他八篇
○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)




1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

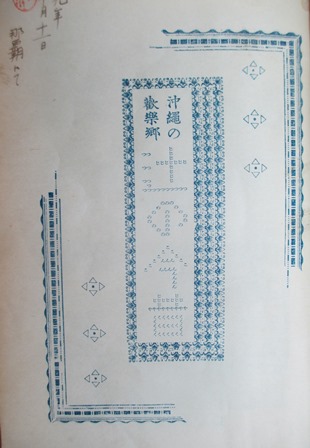


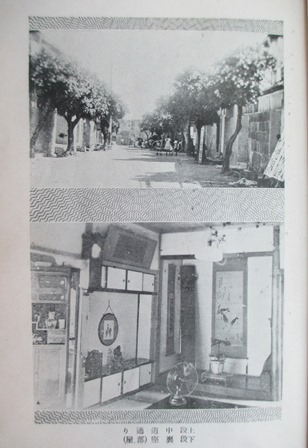
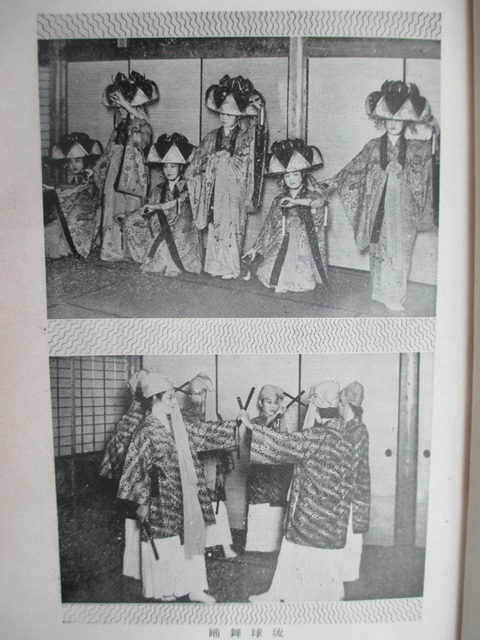
○一向宗の法難と廓
王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。
また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。
明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。
備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。
1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。
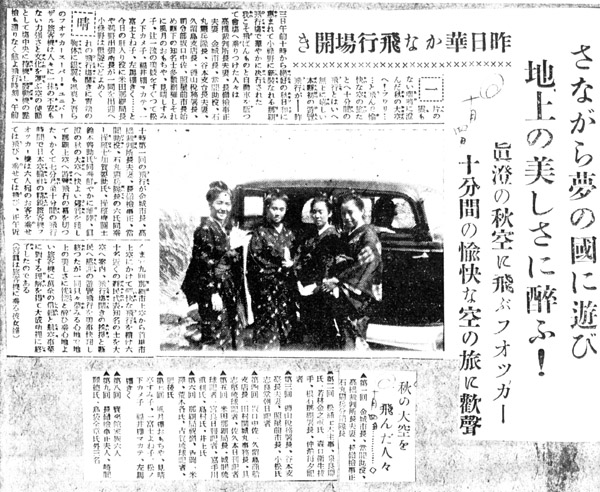
1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行
1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」
1938年9月15日『大阪球陽新報』
□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。
家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。
県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。
辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。
04/15: 沖縄コレクター友の会②
2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん
合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。
ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。
1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。
同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。
2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。
2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。
2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。
沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。
2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。
沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。
那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。
09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」
伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。
1891年
4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)
1900年
9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。
1903年
9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。
1904年
7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。
1905年
8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。
1906年
7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。
1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立
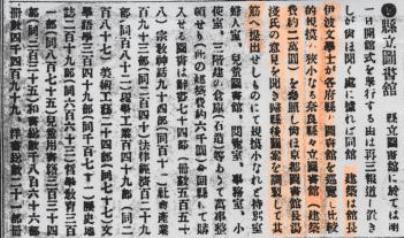
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
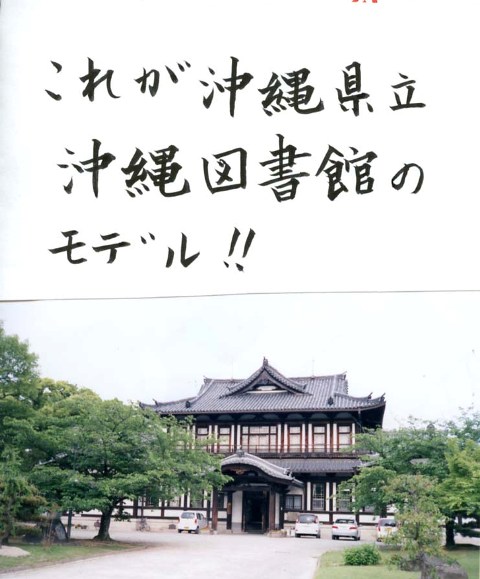
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1911年
4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。
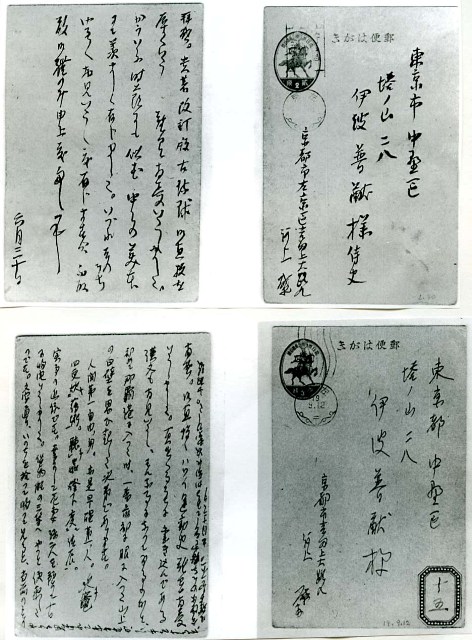
■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)
8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」
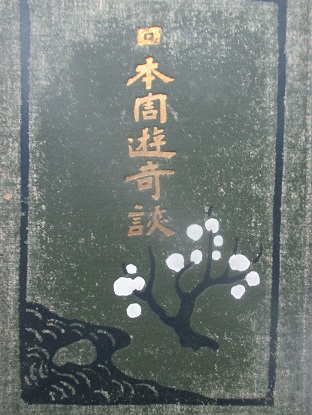
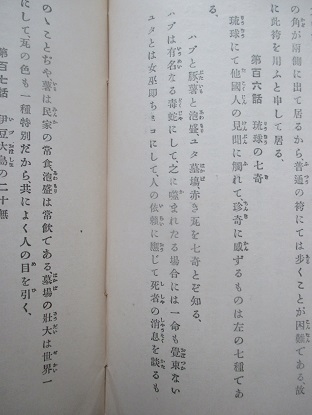
1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館
1912年
4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町
1913年
3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代
1913年
3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。
5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷
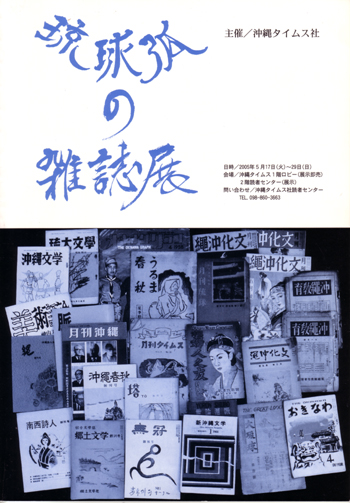
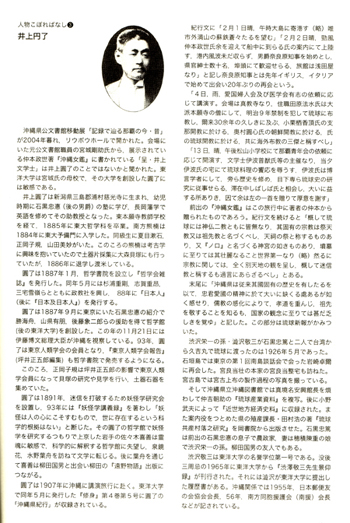
井上円了
『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。
大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。
□井上円了
生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)
没年: 大正8.6.5 (1919)
明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻
(恩田彰) →コトバンク
8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。
9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」
1916年
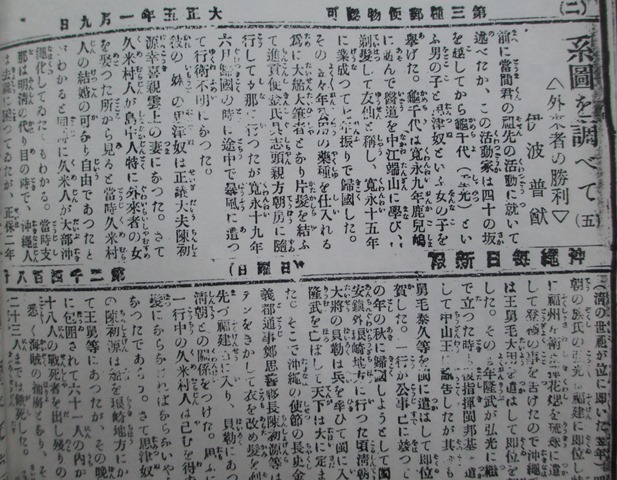
1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)
3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら
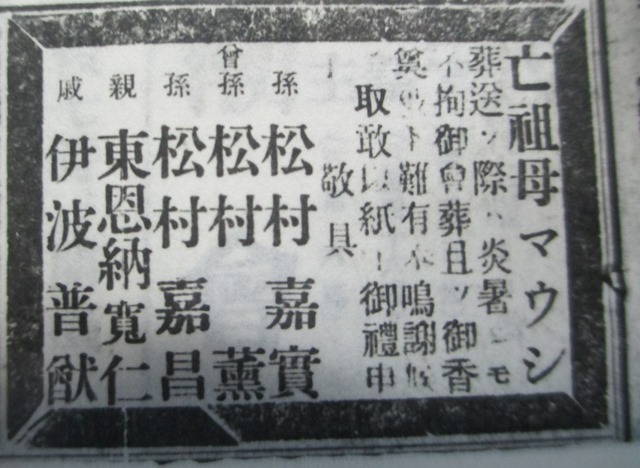
1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」
1918年
3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真
1919年
7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」
1920年
岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」
1921年
5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。
1924年
3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」
3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」
5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」
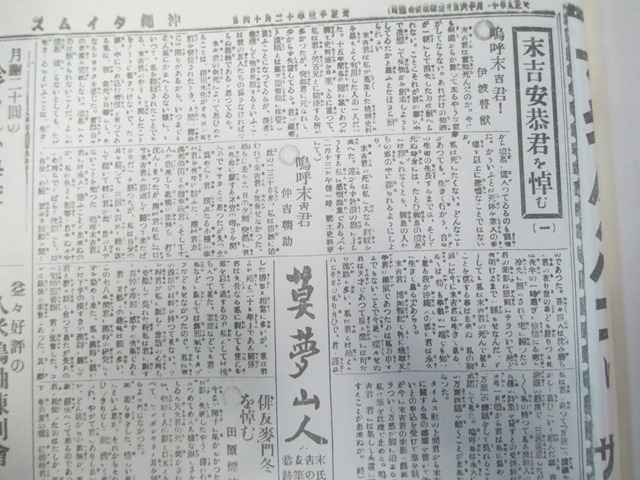
12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」
1925年
2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。
7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」
1926年
1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~
1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)
8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~
9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。
1927年
4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」
1928年
10月ー春洋丸でハワイ着
1929年
2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻
小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候
1931年
6月ー伊波の母(知念)マツル死去
12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居
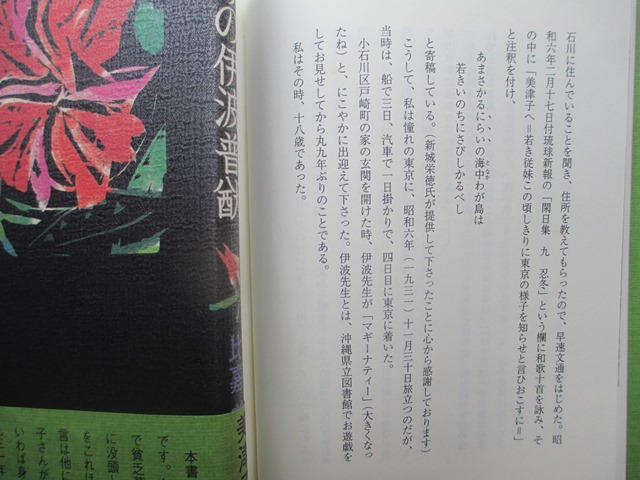
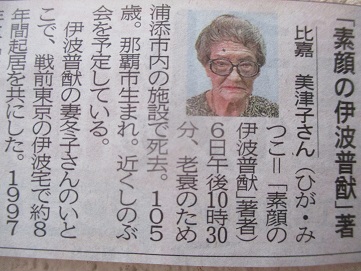
比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん
1932年
1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~
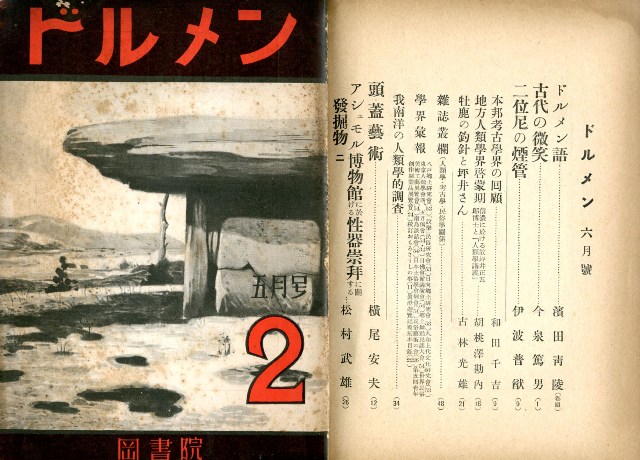
1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」
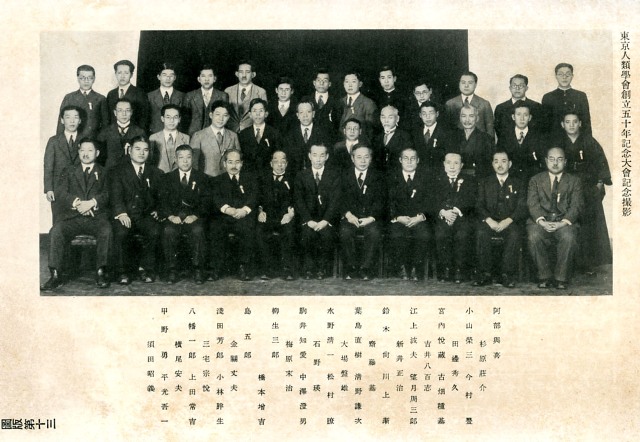
1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会
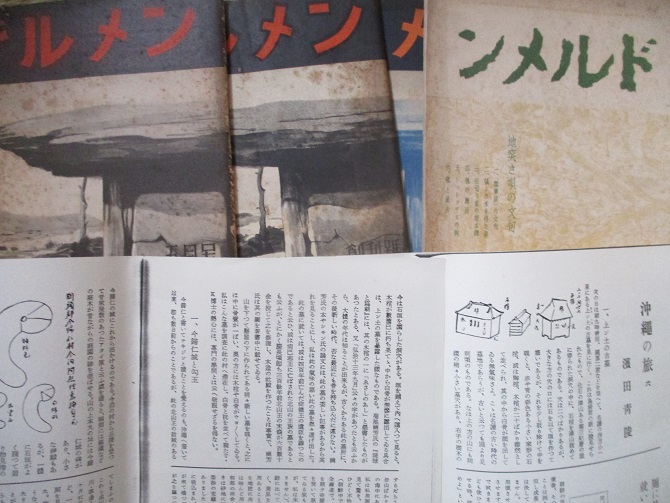
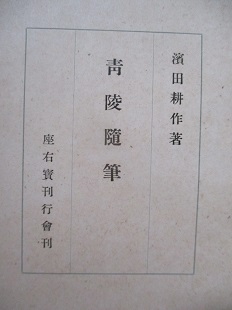
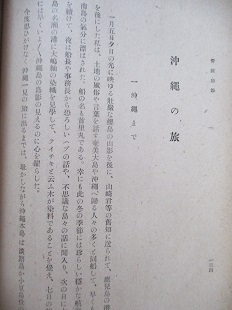
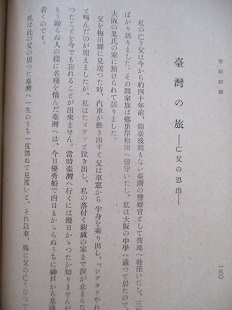
1933年
1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
1934年
7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」
1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号
1937年
1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)
1939年
12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」
1941年
3月ー伊波普猷妻マウシ死去
2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。
1891年
4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)
1900年
9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。
1903年
9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。
1904年
7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。
1905年
8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。
1906年
7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。
1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立
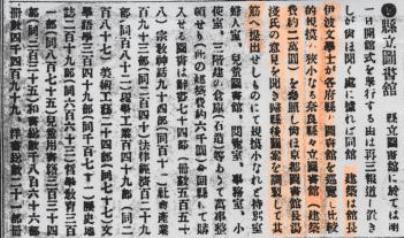
1910年7月31日『沖縄毎日新聞』
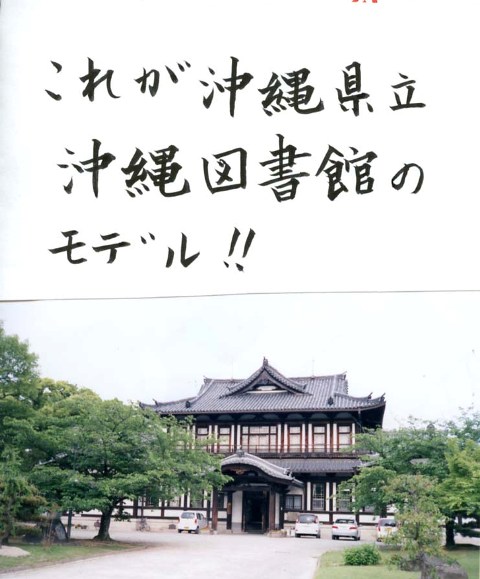
奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。
1911年
4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。
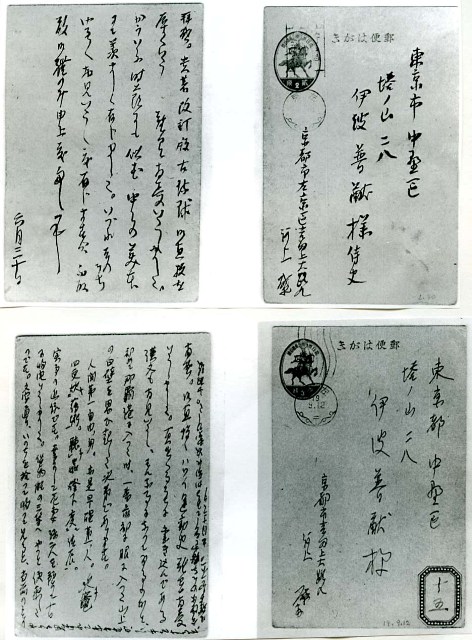
■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)
8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」
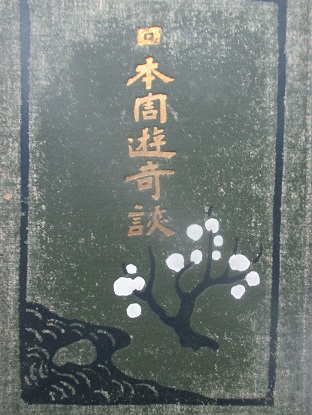
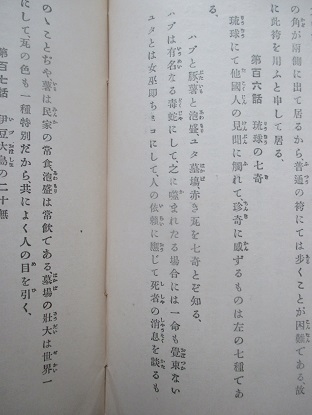
1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館
1912年
4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町
1913年
3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代
1913年
3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。
5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷
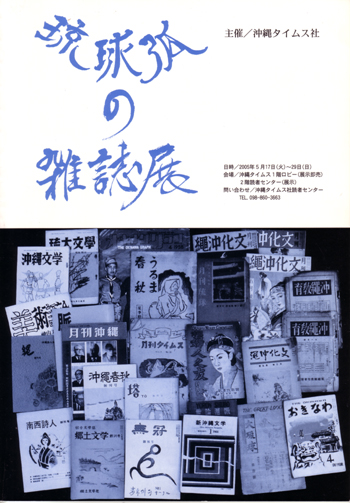
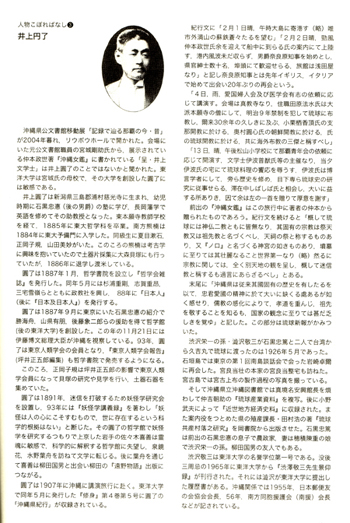
井上円了
『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。
大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。
□井上円了
生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)
没年: 大正8.6.5 (1919)
明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻
(恩田彰) →コトバンク
8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。
9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」
1916年
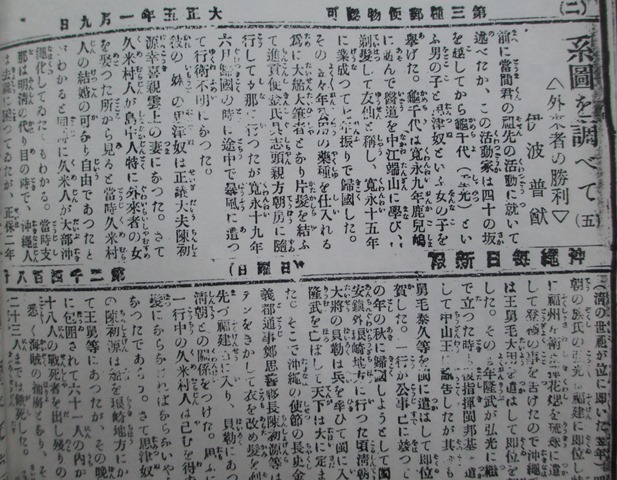
1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)
3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら
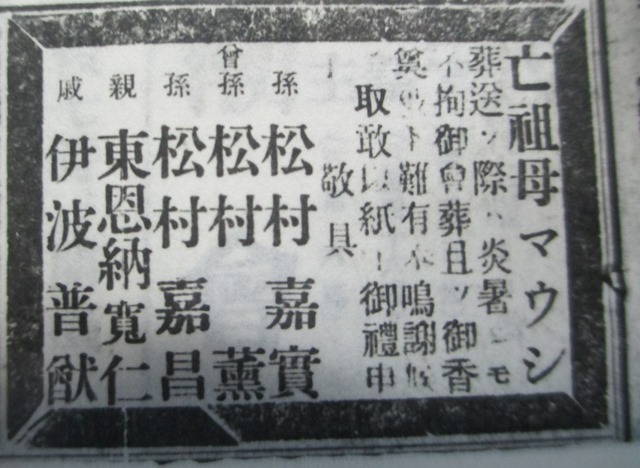
1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」
1918年
3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真
1919年
7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」
1920年
岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」
1921年
5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。
1924年
3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」
3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」
5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」
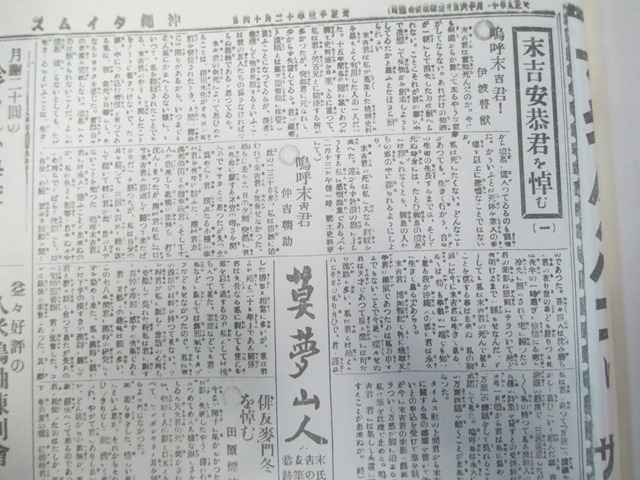
12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」
1925年
2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。
7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」
1926年
1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~
1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)
8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~
9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。
1927年
4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」
1928年
10月ー春洋丸でハワイ着
1929年
2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ
8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演
1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻
小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候
1931年
6月ー伊波の母(知念)マツル死去
12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居
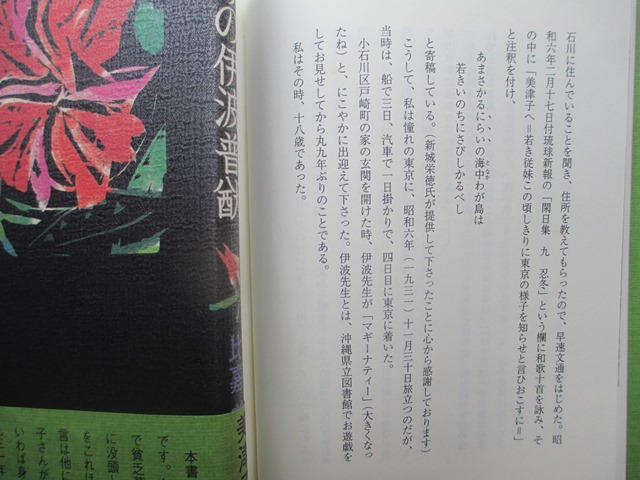
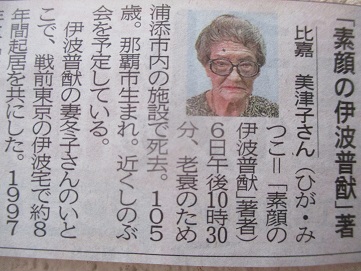
比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん
1932年
1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~
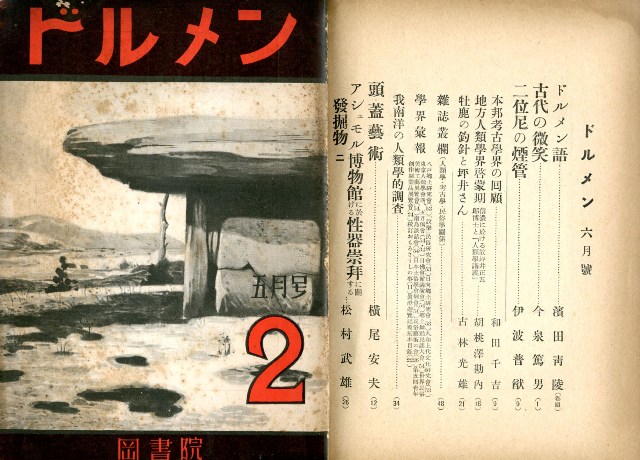
1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」
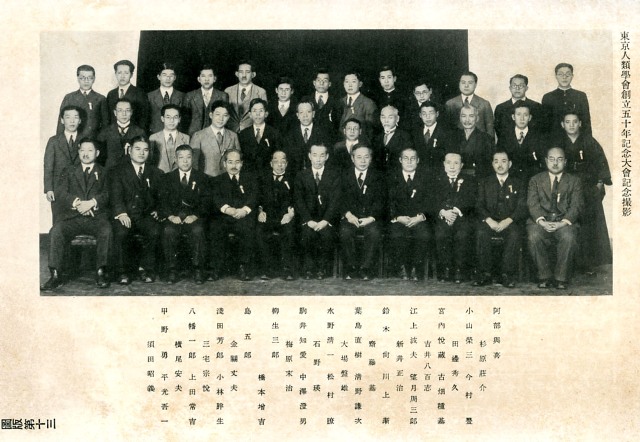
1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会
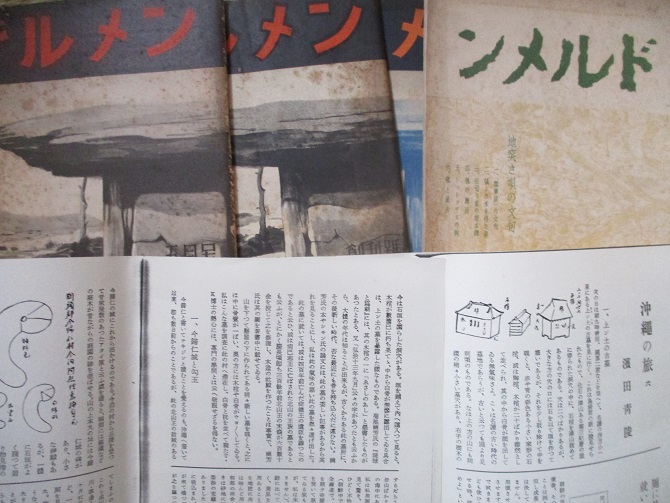
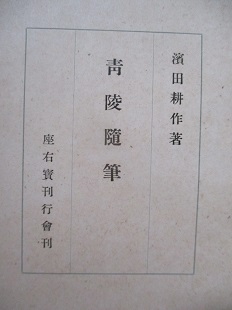
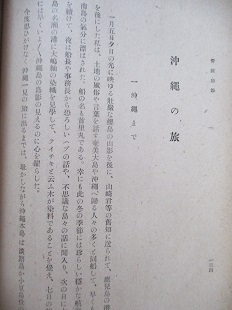
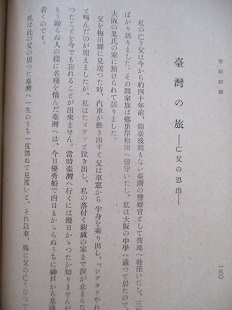
1933年
1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」
1934年
7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」
1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号
1937年
1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)
1939年
12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」
1941年
3月ー伊波普猷妻マウシ死去
2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。
10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年
1917年(大正6)
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
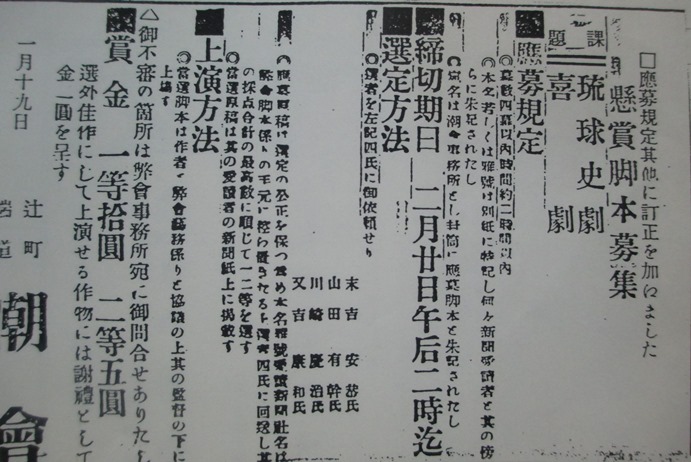
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
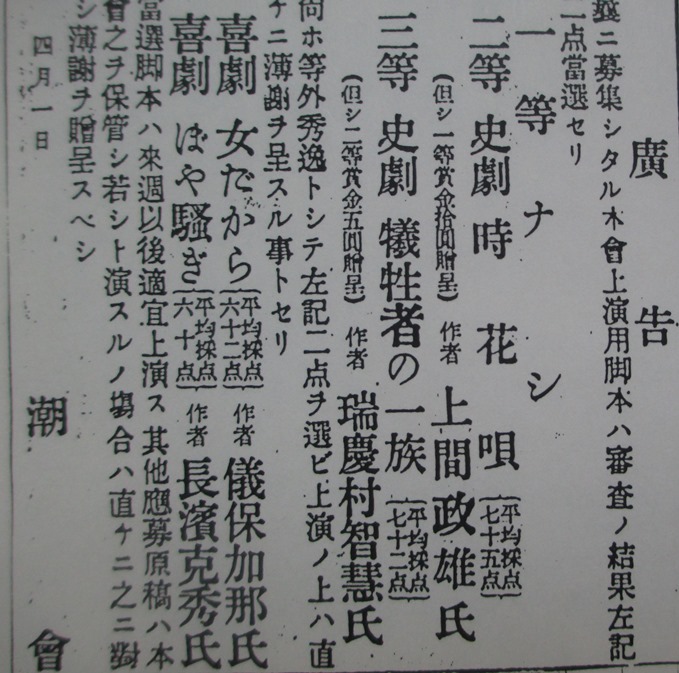
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
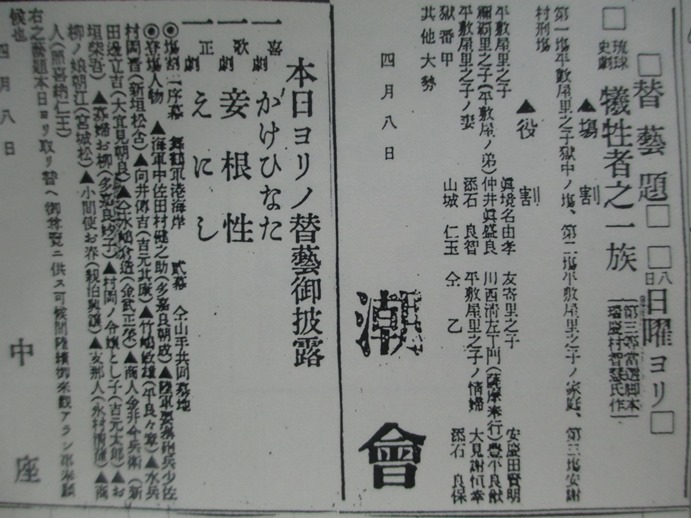
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
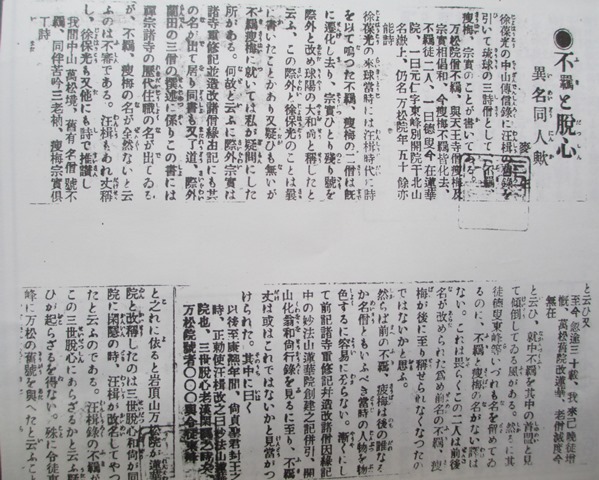
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
1月 『沖縄新公論』創刊
1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」
1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」
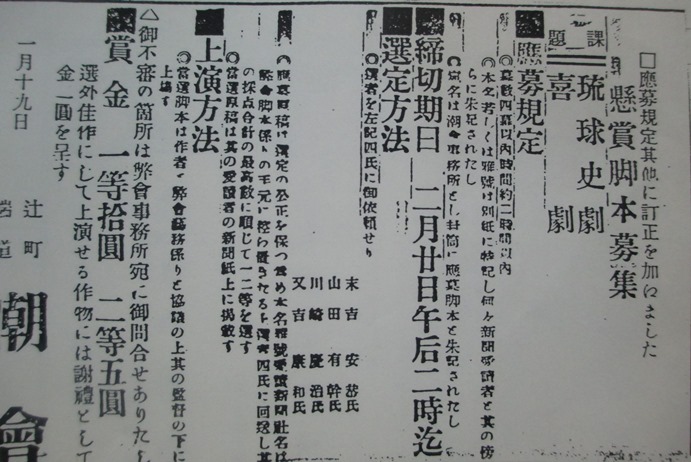
潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)
2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛
3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」
3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」
3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」
3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)
3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」
4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」
4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」
4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」
4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」
4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」
4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」
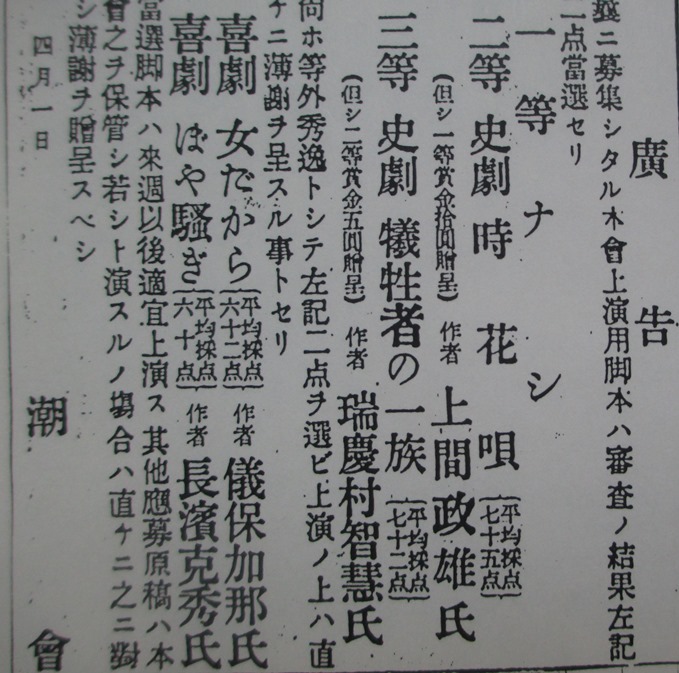
4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」
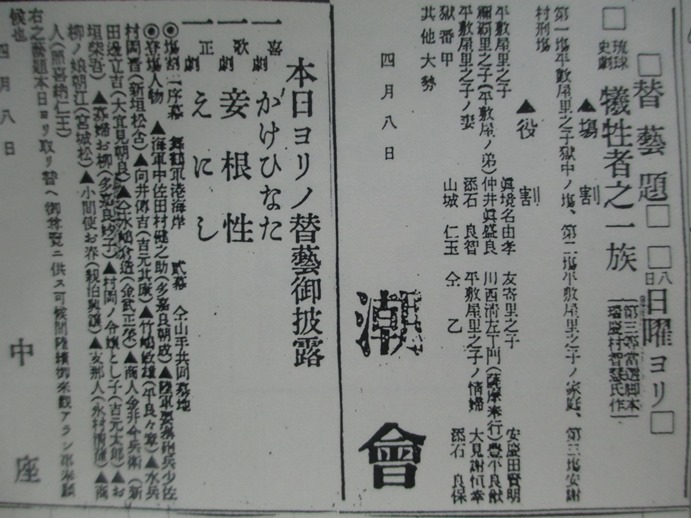
4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載
4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」
5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」
5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」
6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」
6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」
6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」
6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」
6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」
6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」
6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」
1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」
膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。
○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々
8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」
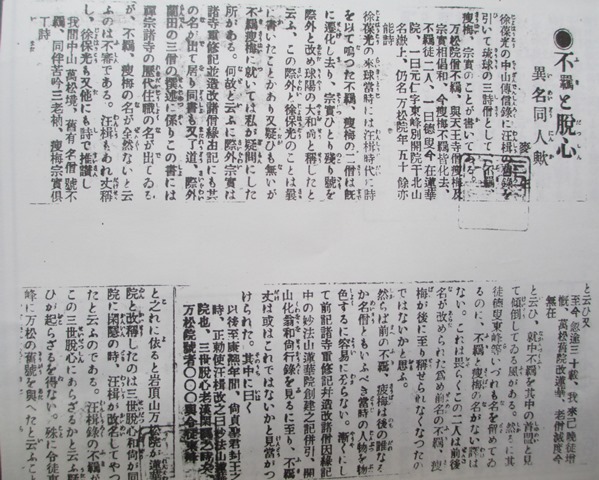
9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」
末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。
9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」
9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」
9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」
9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」
9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」
9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」
9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」
9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」
9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」
9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」
9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。
9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」
10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」
□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信
10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」
10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」
10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話
10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」
10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」
10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」
10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」
10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」
11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」
11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」
12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」
12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」
12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」
12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」
12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」
12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」
12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」
1892年4月 島袋源一郎、今帰仁尋常小学校入学
1896年4月 島袋源一郎、名護の国頭高等小学校に入学
1904年10月20日 『東京人類学会雑誌』第223号 鳥居龍蔵「沖縄人の皮膚の色に就てー余は本年夏期、沖縄諸島を巡回せしが、其那覇滞在中、首里なる同県師範学校、及び高等女学校に於て、男女学徒の皮膚の色を調査なしたり。(助手は伊波普猷で、師範学校の学徒に島袋源一郎・今帰仁間切20歳、仲原善忠・久米島18歳、比嘉春潮・首里21歳、徳元八一・玉城間切20歳、宮城栄昌・久志22歳、諸見里朝清・首里20歳山城篤男・高嶺間切17歳,
新垣信一などの名前がある。)
□当山正堅「時の図画の先生は日本画に堪能な山口瑞雨先生でありましたが、あの頃から洋画も課さねばならなかったので、先生は予め其の描写法を授けることなしに漫然と首里城を写生して来るようにとの日曜宿題を命ぜられたのであります。すると、島袋源一郎氏は唐破風の棟上に登って屋根の大きさから、両端の龍の胴体、髭の長さを測り更に瓦の数まで一々数えて来てから構想を練って描写に取りかかったと云う熱心さに先生も同級生一同も驚いたと云うことでありました。」
1907年3月 島袋源一郎、沖縄県師範学校卒業。 4月 名護訓導
1926年8月 那覇松山校に於いて西村真次「家族国家としての日本」講演
1927年1月 那覇尋高に於いて嘉納治五郎「柔道の原理と精力善用」講演
1927年4月 『沖縄教育』161号 「教育参考館の建設に就いて」「教育参考館記事」
1927年8月26日~4日間 松山小学校で小原國芳「教育道」講演
1928年3月
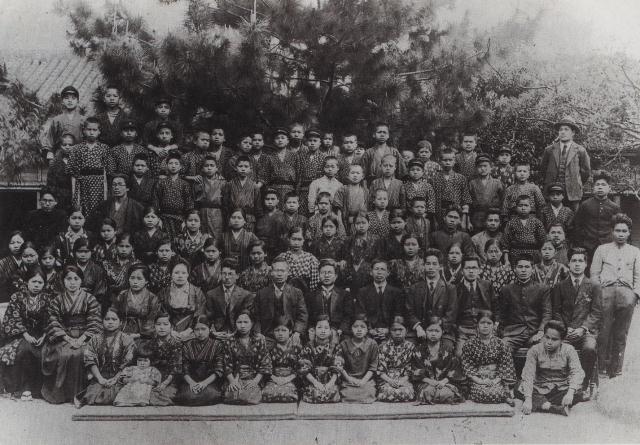
名護東江小学校卒業式ー前列右から5番目が仲原照子(源一郎の妹)、2列目左から7番目が島袋源一郎(当時校長)→1997年4月 仲原照子『想いの中からー随筆・短歌・俳句など』「戦前の郷土博物館ー首里城内の正殿に向かって、右側南殿があり、左側に博物館に使われた北殿がありました。北殿はかつて冊封使の歓待に利用されたところで中国風の造りになっていました。館内の柱は、円柱の大木が使われ左端に昇り龍、右端に降り龍が彫られ、朱色とややくすんだ赤色が塗られていました。館内には尚家の宝物をはじめ、紅型・陶器・漆器・三味線・書画・馬具・龕などが所狭しと展示されていました。」
1928年10月 城青年団同人雑誌『創造青年』創刊号 島袋源一郎「(略)余は只諸君個人個人が各自自己を完成し生まれた価値のある立派な人となり、更に社会的に何か貢献し死後も地球に足跡を印刻し得る偉大な人物になられんことを冀望して擱筆する次第である。」
1929年3月 『南島研究』島袋源一郎『名護城史考』
□(略)沖縄の祖霊崇拝教では之を信じて居るのである。此の宗教は多神教の程度迄発達しているが種々の障碍の為に停頓状態に陥っているのは寔に遺憾である。若し沖縄の宗教が、すべての祈りを吾等の祖神を通じて大宇宙の支配者たる宗教意識に導き得るならば、自然教の境地を脱却して立派な文明教の中に入ることが出来るのである。
1936年7月 『沖縄教育』第239号(表紙・琉球組踊「銘苅子」の天女) 島袋盛敏「琉球芸能感想記」/上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
1896年4月 島袋源一郎、名護の国頭高等小学校に入学
1904年10月20日 『東京人類学会雑誌』第223号 鳥居龍蔵「沖縄人の皮膚の色に就てー余は本年夏期、沖縄諸島を巡回せしが、其那覇滞在中、首里なる同県師範学校、及び高等女学校に於て、男女学徒の皮膚の色を調査なしたり。(助手は伊波普猷で、師範学校の学徒に島袋源一郎・今帰仁間切20歳、仲原善忠・久米島18歳、比嘉春潮・首里21歳、徳元八一・玉城間切20歳、宮城栄昌・久志22歳、諸見里朝清・首里20歳山城篤男・高嶺間切17歳,
新垣信一などの名前がある。)
□当山正堅「時の図画の先生は日本画に堪能な山口瑞雨先生でありましたが、あの頃から洋画も課さねばならなかったので、先生は予め其の描写法を授けることなしに漫然と首里城を写生して来るようにとの日曜宿題を命ぜられたのであります。すると、島袋源一郎氏は唐破風の棟上に登って屋根の大きさから、両端の龍の胴体、髭の長さを測り更に瓦の数まで一々数えて来てから構想を練って描写に取りかかったと云う熱心さに先生も同級生一同も驚いたと云うことでありました。」
1907年3月 島袋源一郎、沖縄県師範学校卒業。 4月 名護訓導
1926年8月 那覇松山校に於いて西村真次「家族国家としての日本」講演
1927年1月 那覇尋高に於いて嘉納治五郎「柔道の原理と精力善用」講演
1927年4月 『沖縄教育』161号 「教育参考館の建設に就いて」「教育参考館記事」
1927年8月26日~4日間 松山小学校で小原國芳「教育道」講演
1928年3月
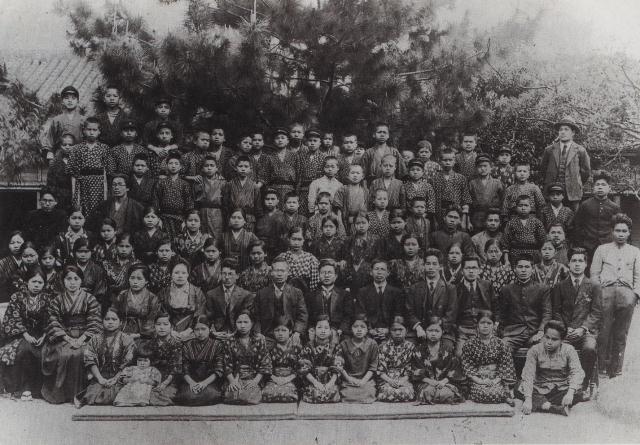
名護東江小学校卒業式ー前列右から5番目が仲原照子(源一郎の妹)、2列目左から7番目が島袋源一郎(当時校長)→1997年4月 仲原照子『想いの中からー随筆・短歌・俳句など』「戦前の郷土博物館ー首里城内の正殿に向かって、右側南殿があり、左側に博物館に使われた北殿がありました。北殿はかつて冊封使の歓待に利用されたところで中国風の造りになっていました。館内の柱は、円柱の大木が使われ左端に昇り龍、右端に降り龍が彫られ、朱色とややくすんだ赤色が塗られていました。館内には尚家の宝物をはじめ、紅型・陶器・漆器・三味線・書画・馬具・龕などが所狭しと展示されていました。」
1928年10月 城青年団同人雑誌『創造青年』創刊号 島袋源一郎「(略)余は只諸君個人個人が各自自己を完成し生まれた価値のある立派な人となり、更に社会的に何か貢献し死後も地球に足跡を印刻し得る偉大な人物になられんことを冀望して擱筆する次第である。」
1929年3月 『南島研究』島袋源一郎『名護城史考』
□(略)沖縄の祖霊崇拝教では之を信じて居るのである。此の宗教は多神教の程度迄発達しているが種々の障碍の為に停頓状態に陥っているのは寔に遺憾である。若し沖縄の宗教が、すべての祈りを吾等の祖神を通じて大宇宙の支配者たる宗教意識に導き得るならば、自然教の境地を脱却して立派な文明教の中に入ることが出来るのである。
1936年7月 『沖縄教育』第239号(表紙・琉球組踊「銘苅子」の天女) 島袋盛敏「琉球芸能感想記」/上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
04/28: 末吉麦門冬旧蔵の『中山世譜』写本
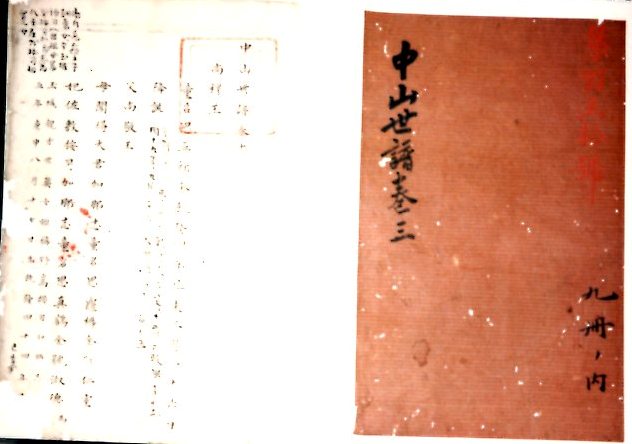
麦門冬の書き込みが見える(岸秋正文庫所蔵)
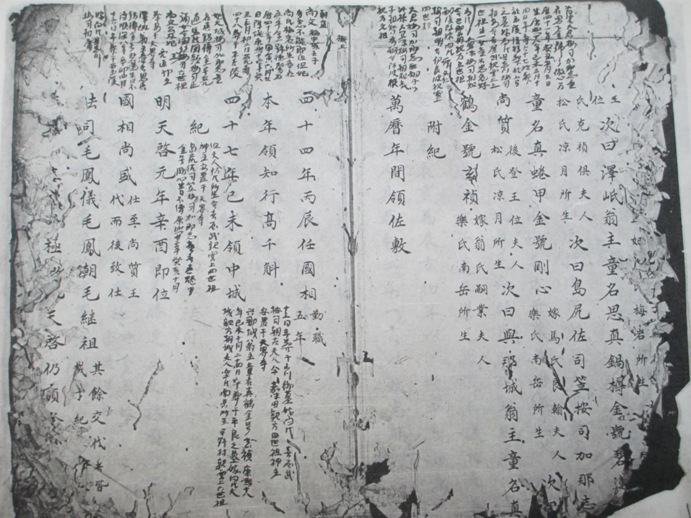
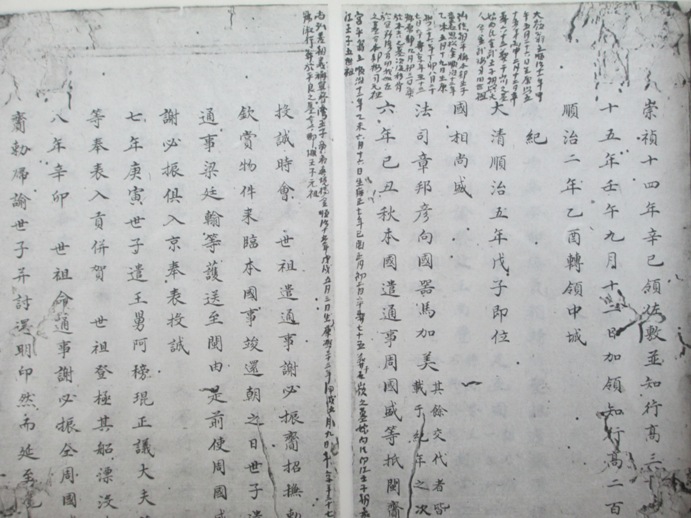
1901年6月ー末吉安扶没
1912年2月ー柳田国男、伊波普猷より『古琉球』3冊寄贈される。
1913年4月ー沖縄県庁でこの程、筆耕に令し『中山世譜』の筆写をなさしめつつある。
1913年7月ー『沖縄教育』(親泊朝擢)桑村生「中山世譜」(1)
1913年8月ー『沖縄教育』(親泊朝擢)桑村生「中山世譜」(2)
1914年7月ー沖縄県知事より、伊波普猷、真境名安興ら沖縄県史編纂委員拝命
1915年1月ー沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁より沖縄県立沖縄図書館に移される(真境名安興主任)
1917年7月15日ー『日本及日本人』709号□末吉麦門冬「十三七つに就いて」「雲助」「劫の虫より経水」(南方熊楠と関連)
1918年2月12日ー東京日本橋区本町三丁目博文館・南方熊楠殿、末吉安恭書簡「拝啓 先生の御執筆の十二支伝説は古今東西に渡りて御渉猟のこととて毎年面白く拝読いたし候(略)琉球にも馬に関する伝説、少なからず候み付、茲に小生の存知の分を記録に出でたるものは原文の侭、然らざるは、簡単に記述いたし候間、御採択なされ候はば幸甚に候。失礼には候へど、御ねがひいたし度きこと沢山これあり候につき御住所御知らせ下さるまじくや(略)」(『球陽』『琉球国旧記』引用)
1917年9月1日ー『日本及日本人』712号□末吉麦門冬「楽屋の泥亀汁」
1918年4月ー『日本及日本人』728号より、三田村鳶魚らによる「東海道中膝栗毛輪講」が連載される。
1818年6月1日ー『日本及日本人』732号□末吉麦門冬「支那のあやつり」「琉球の鬼餅」
1918年7月ー末吉麦門冬、南方熊楠に『球陽』贈る
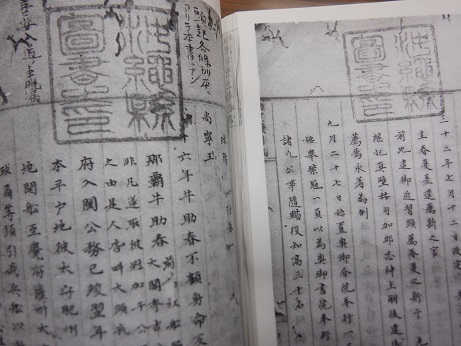
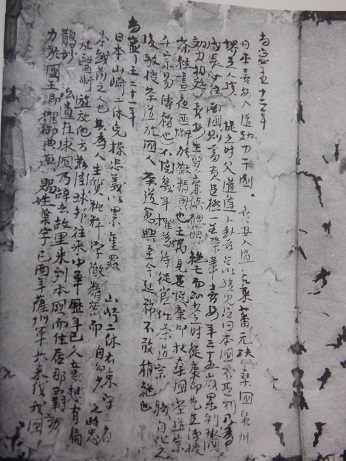
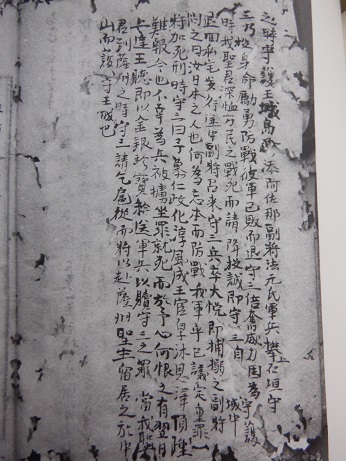
02/06: 伊波普助の孫・伊波普英
2011年4月ー那覇市歴史博物館で、外間政明氏から明治大正時代の医者・伊波普助の曾孫I氏を紹介された。職業は曽祖父の影響か看護師であった。伊波普助の孫・伊波普英氏(沖縄県立第二中学校18期1932年卒業、同期に大山一雄、嘉手納宗徳、黒島寛松)は大阪で琉球居酒屋を経営しておられ私は親しくしてもらったことがある。曾孫I氏はその息子さんであった。
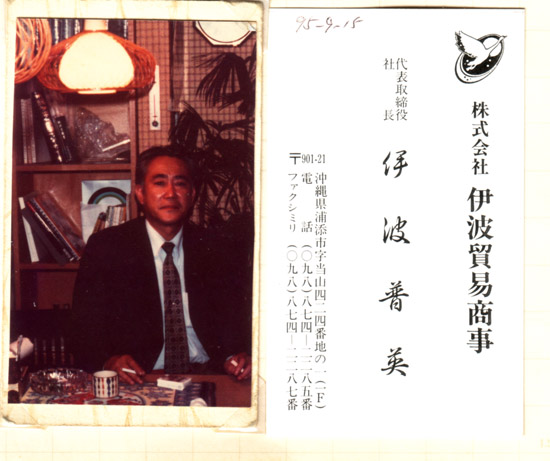
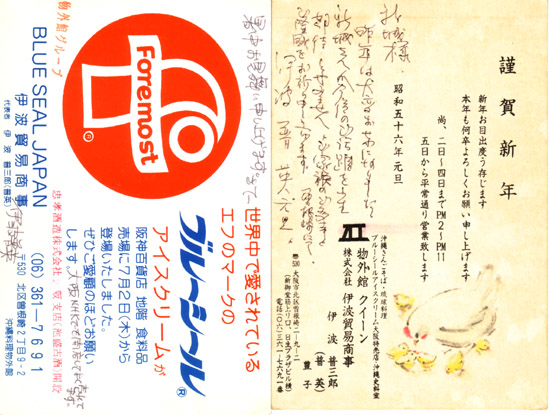
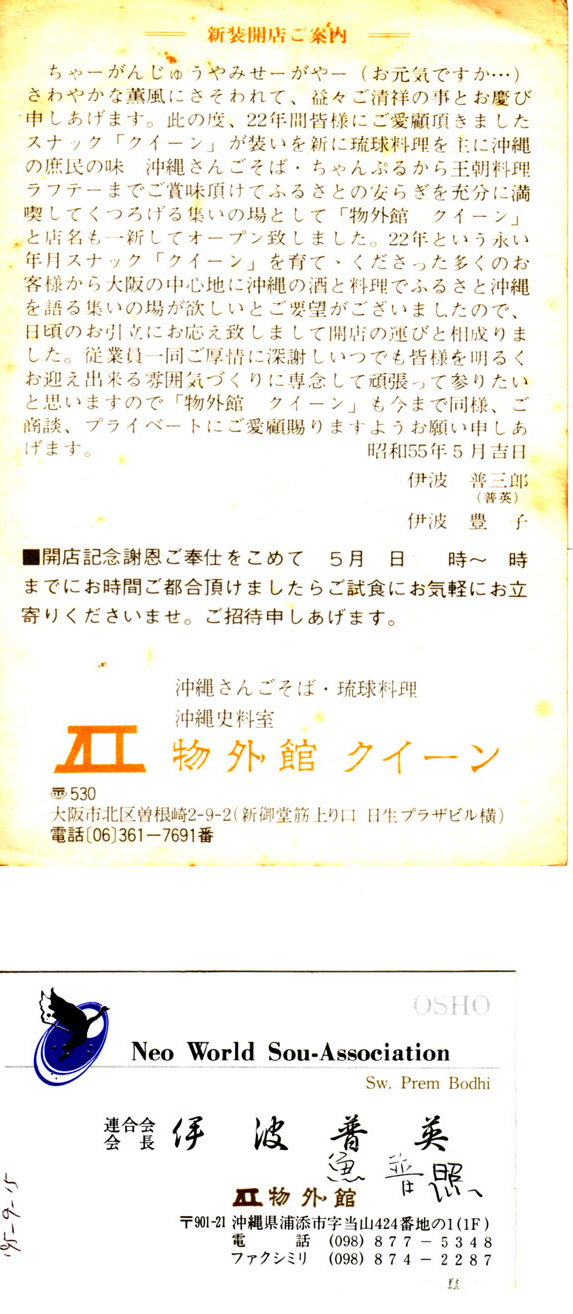
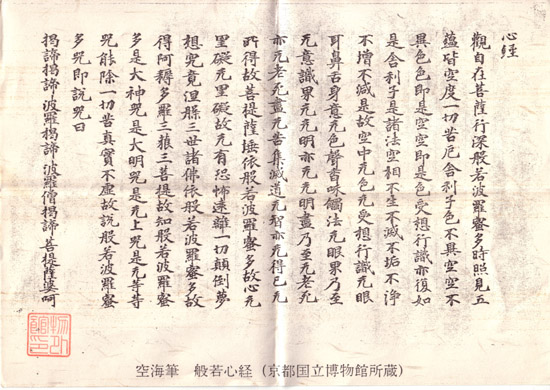
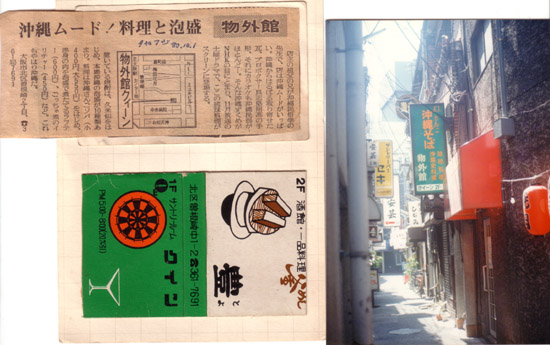
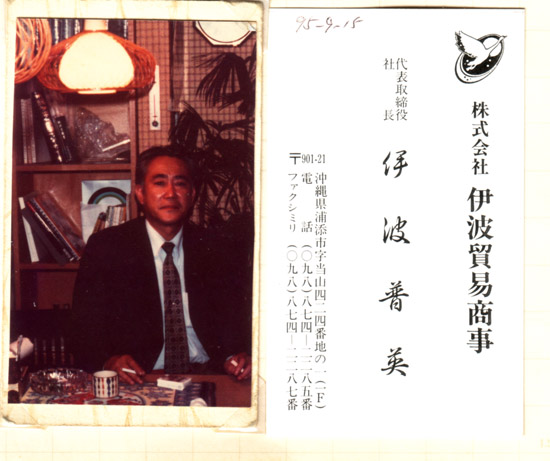
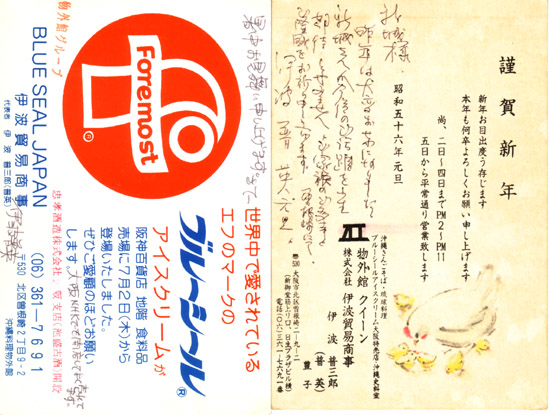
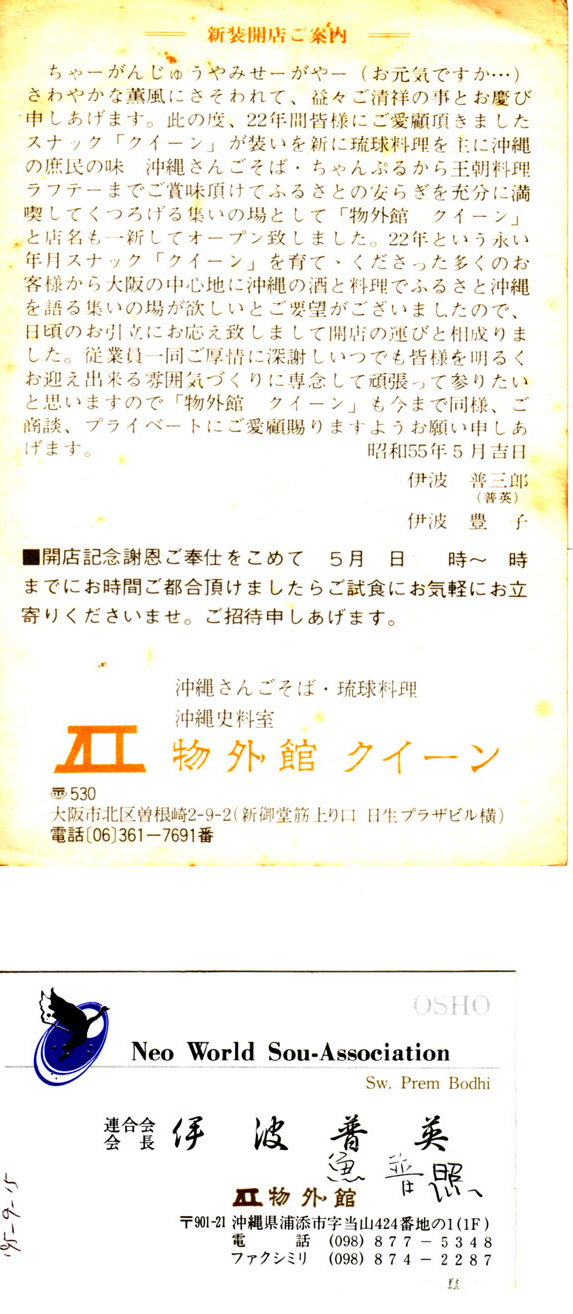
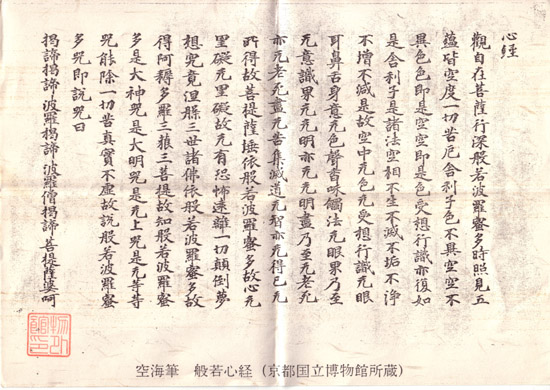
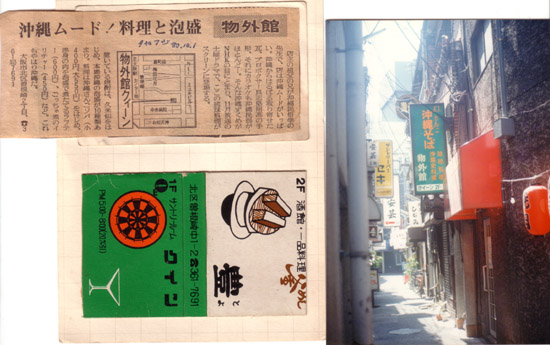
10/29: 年譜・末吉麦門冬/1922(大正11)年②
1922(大正11)年
3月30日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<12>ーおもろ双紙の焼失」
3月31日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<14>ー首里城の回禄」
4月1日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<15>ー火災と文献」
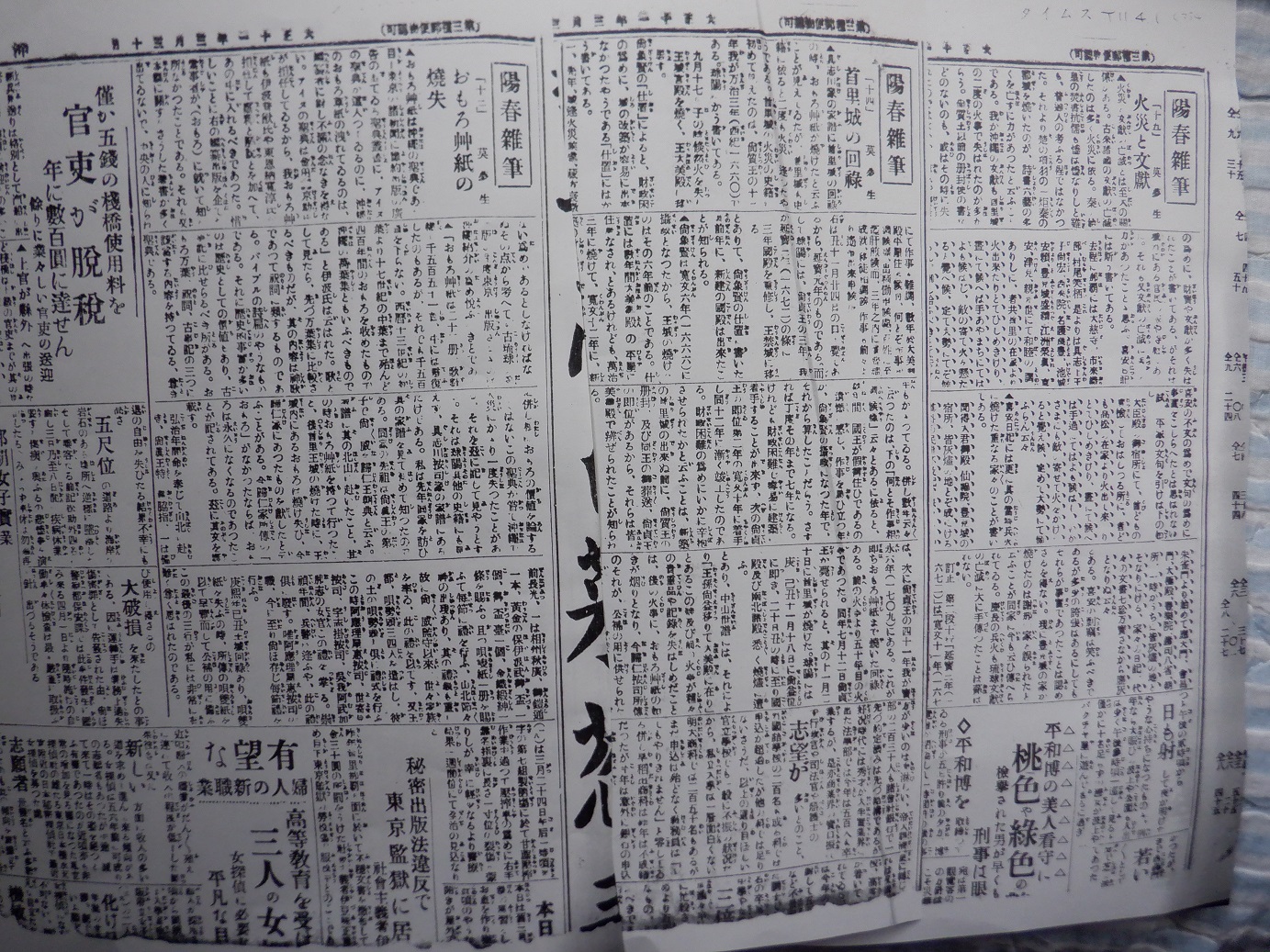
4月2日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<16>ー喜安日記と為朝伝説」
4月4日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<17>ー喜安日記と為朝伝説」
4月5日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<18>ー喜安日記と為朝伝説」
4月7日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<20>ー鎧武者」(『中山世譜』)
4月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<21>ー鎧武者」
4月9日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<22>ー鎧武者」
4月11日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<23>ー倭寇と鎧」
4月12日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<24>ー倭寇の兵力」
4月13日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<25>ー倭寇の戦法」
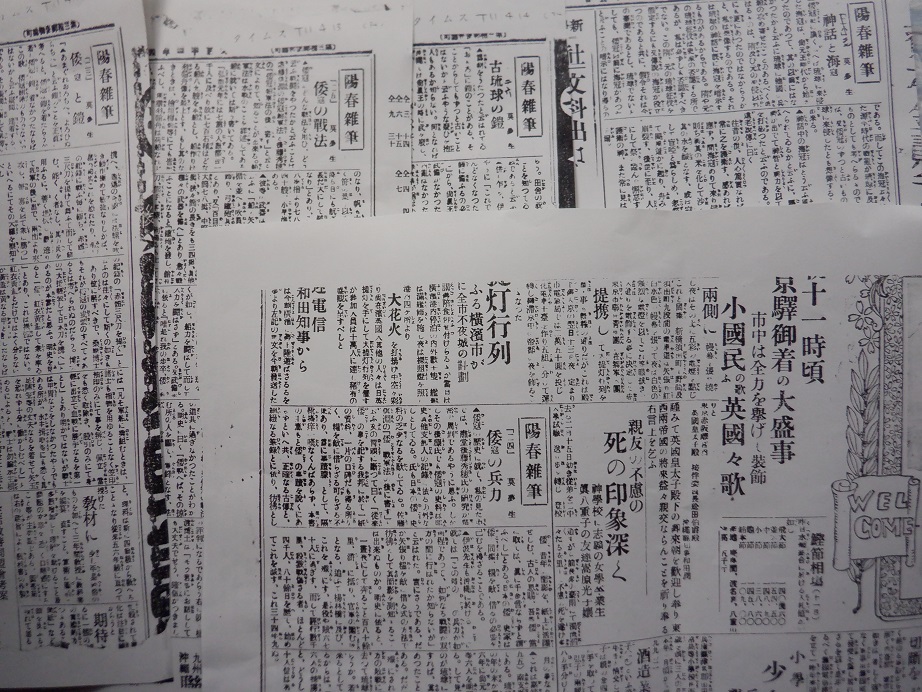
4月14日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<26>ー古琉球の鎧」
4月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<27>ー神話と海寇」
4月17日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<28>ー神遊は神舞」
4月18日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<29>ー詫遊は神舞」(『琉球神道記』)
4月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<30>ー詫遊は神舞」
4月21日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<32>ー詫遊は神舞」
4月22日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<33>ー詫遊は神舞」
4月23日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<34>ー琉球の戦舞」/「中央に紹介さるる沖縄の武術ー東京博物館に於いて開かれる文部省主催の運動体育展覧会へ本県より沖縄尚武会長 富名腰義珍氏が準備整え県を介し発送。書も本県一流の青年書家 謝花雲石氏に依頼・・・・」
4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」
4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」
4月28日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<38>ー仕合」/「本県農業の大恩人 甘藷金城を紹介ー龜島有功翁の苦心」
4月29日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<39>ー古琉球の政治」
5月6日 『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長 百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」
1922年6月 佐藤惣之助(詩人)来沖
1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生「葉隠餘滴ー昔の道路取締」
8月 『日本及日本人』842号 麦生「支那古代の埋葬法」
8月22日 鎌倉芳太郎、麦門冬の紹介状を持って首里儀保の華國・長嶺宗恭を訪ねる。
1922年9月15日『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー慎思九(中)」
〇新城栄徳ー私は1991年12月『真境名安興全集刊行だより№、1』の「笑古漫筆の魅力」で、笑古漫筆には「久米村例寄帳」から抜き書きが多く貴重であると書いた。麦門冬も本随筆で久米村例寄帳から引用している。道路での子どもの遊び、泊阿嘉物語の放歌者は駄目というのがある。
9月 平良盛吉『沖縄民謡集』(上巻)刊
9月 許田普敦『通俗琉球史』(序文・末吉安恭)
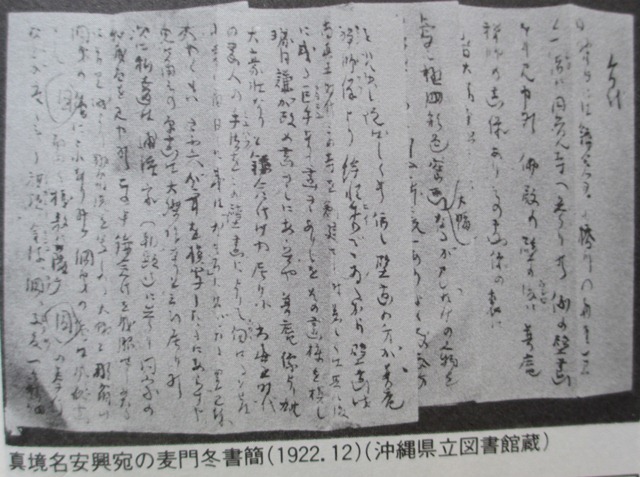
10月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(37)ー琉儒と道教」
10月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(39)ー琉儒と道教」
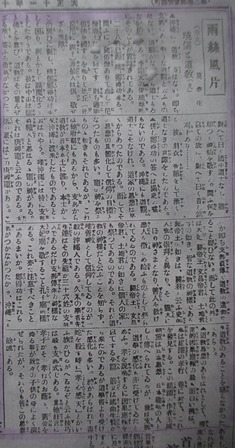

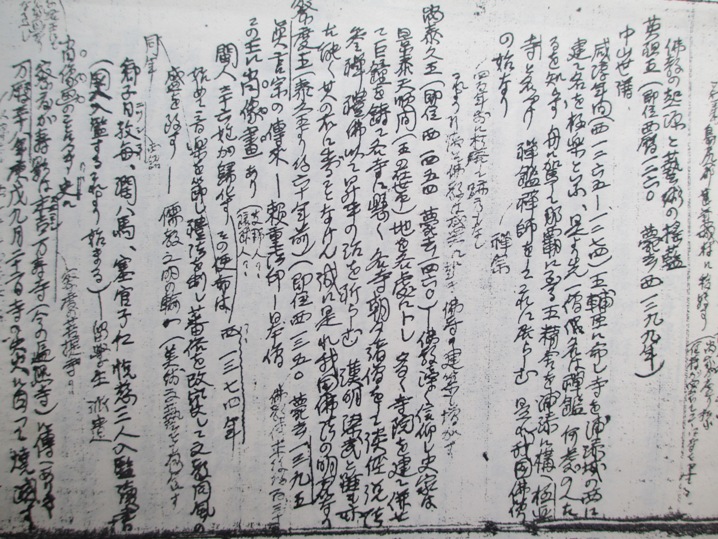
1922年 『沖縄タイムス』末吉莫夢「琉球画人伝」(表題は本朝画人傳を念頭に鎌倉芳太郎が付けたもの)を鎌倉が筆記したもの。
11月 富名腰義珍『琉球拳法唐手』(序文・末吉安恭)
3月30日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<12>ーおもろ双紙の焼失」
3月31日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<14>ー首里城の回禄」
4月1日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<15>ー火災と文献」
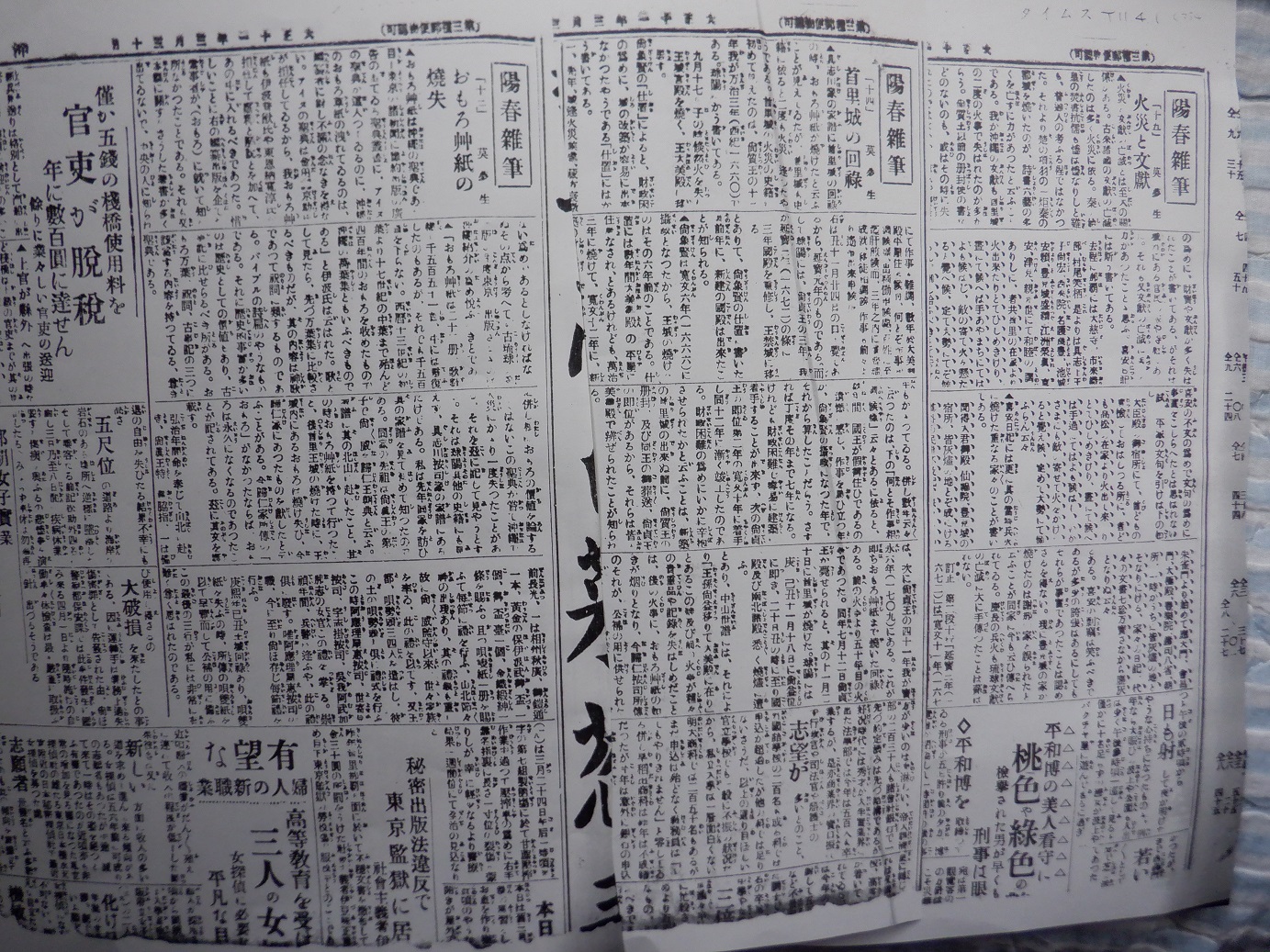
4月2日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<16>ー喜安日記と為朝伝説」
4月4日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<17>ー喜安日記と為朝伝説」
4月5日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<18>ー喜安日記と為朝伝説」
4月7日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<20>ー鎧武者」(『中山世譜』)
4月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<21>ー鎧武者」
4月9日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<22>ー鎧武者」
4月11日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<23>ー倭寇と鎧」
4月12日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<24>ー倭寇の兵力」
4月13日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<25>ー倭寇の戦法」
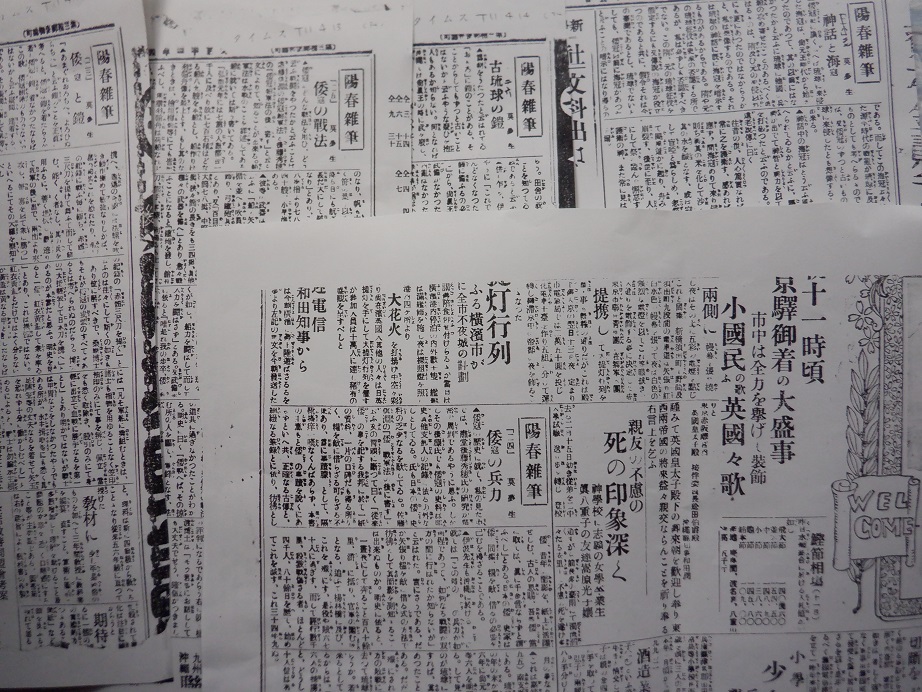
4月14日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<26>ー古琉球の鎧」
4月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<27>ー神話と海寇」
4月17日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<28>ー神遊は神舞」
4月18日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<29>ー詫遊は神舞」(『琉球神道記』)
4月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<30>ー詫遊は神舞」
4月21日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<32>ー詫遊は神舞」
4月22日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<33>ー詫遊は神舞」
4月23日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<34>ー琉球の戦舞」/「中央に紹介さるる沖縄の武術ー東京博物館に於いて開かれる文部省主催の運動体育展覧会へ本県より沖縄尚武会長 富名腰義珍氏が準備整え県を介し発送。書も本県一流の青年書家 謝花雲石氏に依頼・・・・」
4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」
4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」
4月28日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<38>ー仕合」/「本県農業の大恩人 甘藷金城を紹介ー龜島有功翁の苦心」
4月29日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<39>ー古琉球の政治」
5月6日 『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長 百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」
1922年6月 佐藤惣之助(詩人)来沖
1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生「葉隠餘滴ー昔の道路取締」
8月 『日本及日本人』842号 麦生「支那古代の埋葬法」
8月22日 鎌倉芳太郎、麦門冬の紹介状を持って首里儀保の華國・長嶺宗恭を訪ねる。
1922年9月15日『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー慎思九(中)」
〇新城栄徳ー私は1991年12月『真境名安興全集刊行だより№、1』の「笑古漫筆の魅力」で、笑古漫筆には「久米村例寄帳」から抜き書きが多く貴重であると書いた。麦門冬も本随筆で久米村例寄帳から引用している。道路での子どもの遊び、泊阿嘉物語の放歌者は駄目というのがある。
9月 平良盛吉『沖縄民謡集』(上巻)刊
9月 許田普敦『通俗琉球史』(序文・末吉安恭)
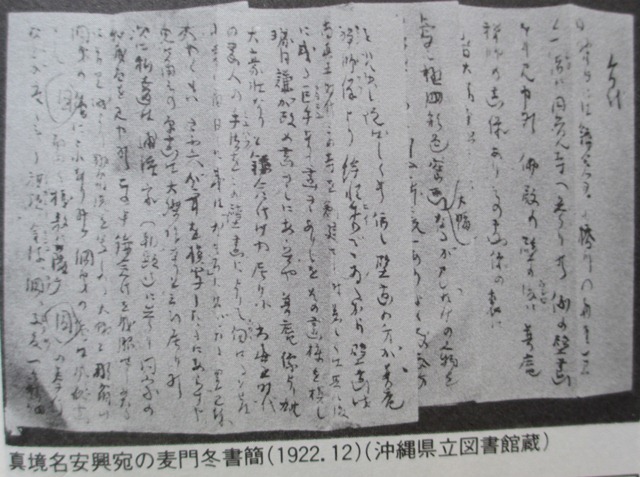
10月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(37)ー琉儒と道教」
10月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(39)ー琉儒と道教」
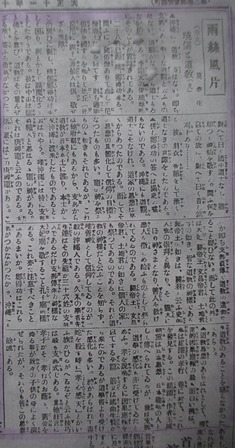

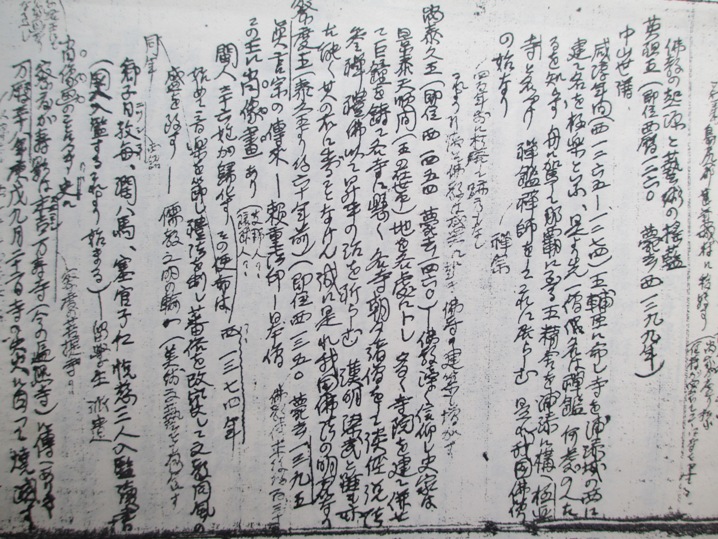
1922年 『沖縄タイムス』末吉莫夢「琉球画人伝」(表題は本朝画人傳を念頭に鎌倉芳太郎が付けたもの)を鎌倉が筆記したもの。
11月 富名腰義珍『琉球拳法唐手』(序文・末吉安恭)
11/08: 年譜・末吉麦門冬/1924(大正13)年 ①
2月 関西沖縄県人会結成
2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行
2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

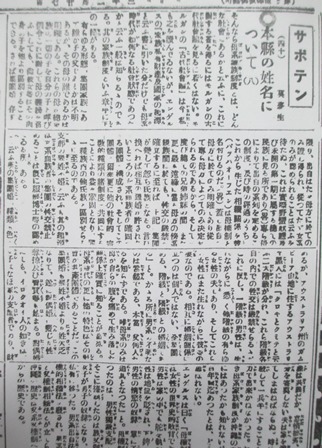
2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)
2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」
3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊
3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。
1924-3
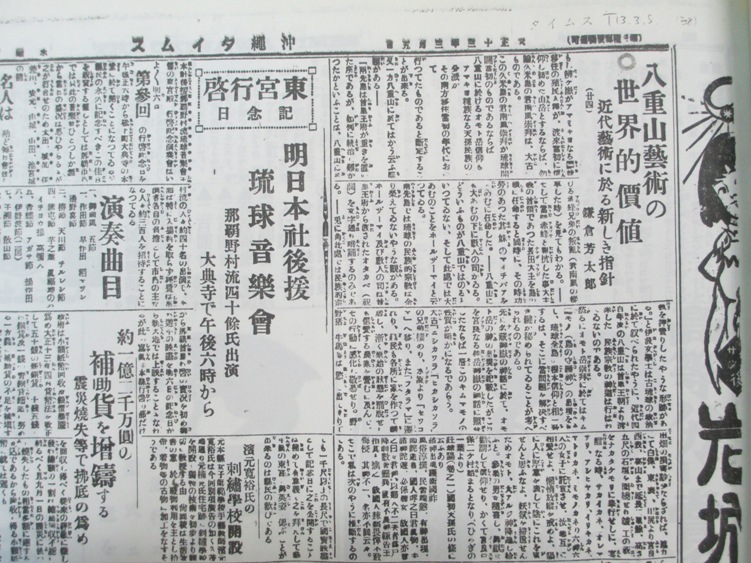
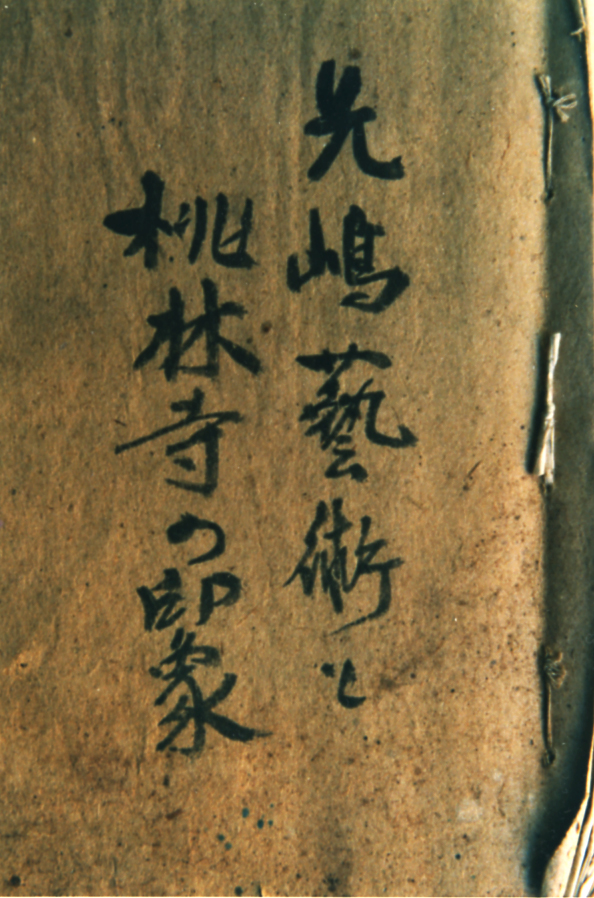 原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの
原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの
4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)
5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。
5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」
6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演
7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店
7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地
7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」
7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港
7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」
7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状
7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。
7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会
8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)
8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京
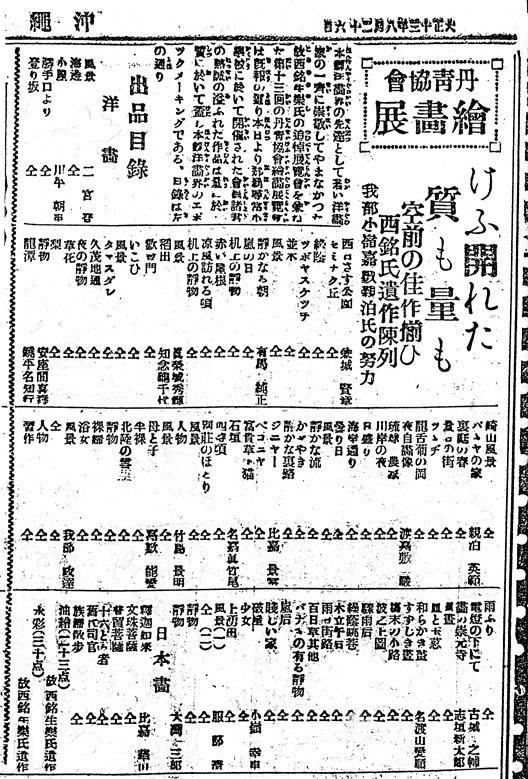
1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会
1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)
2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。
1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。
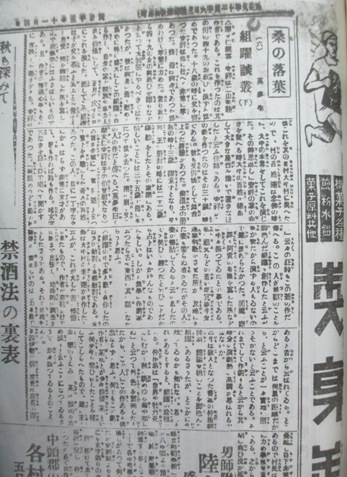
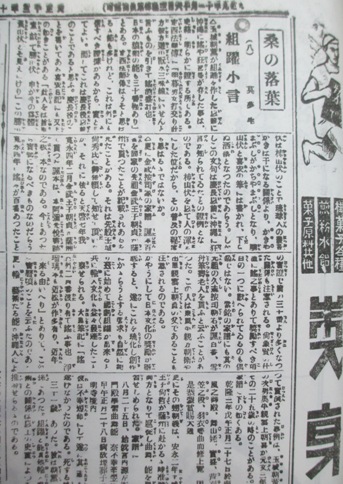
莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。
〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。
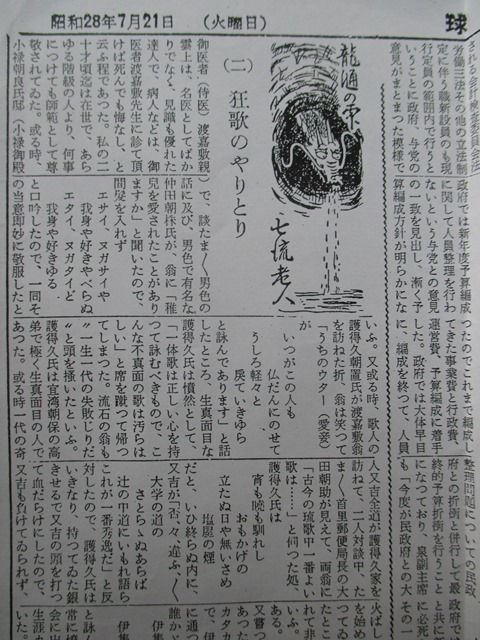
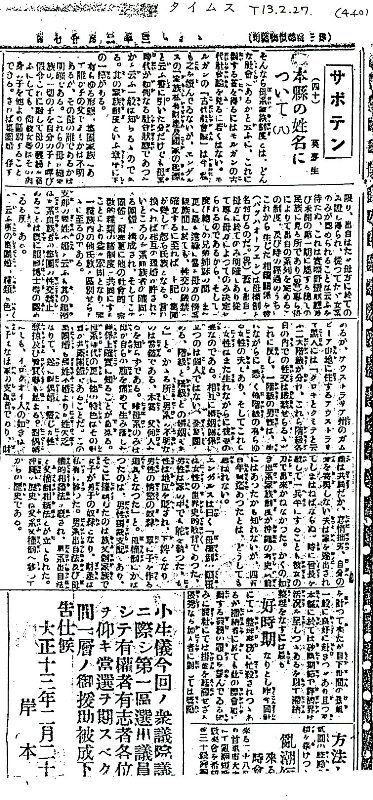
1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」
□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)
2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
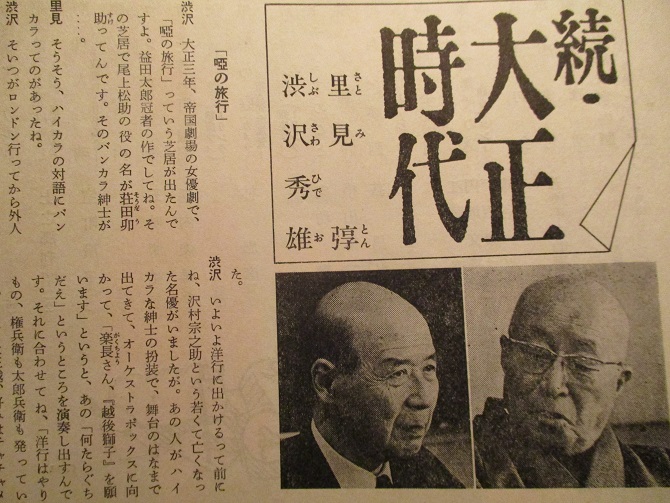
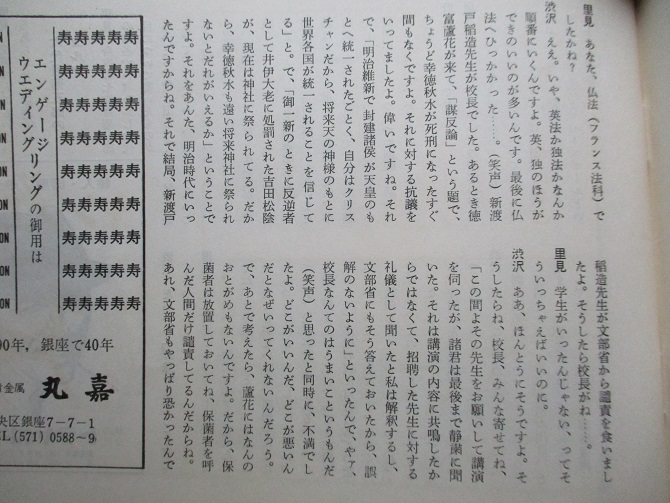
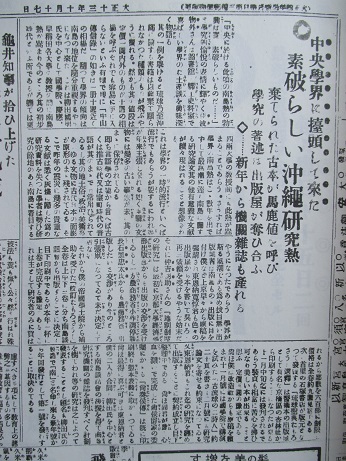
12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」
2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行
2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

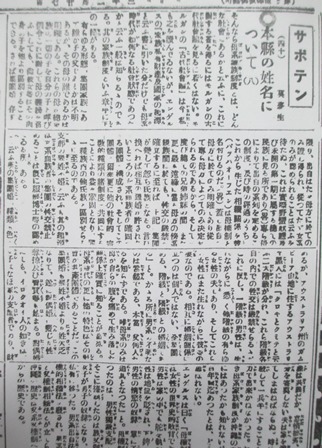
2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)
2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」
3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊
3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。
1924-3
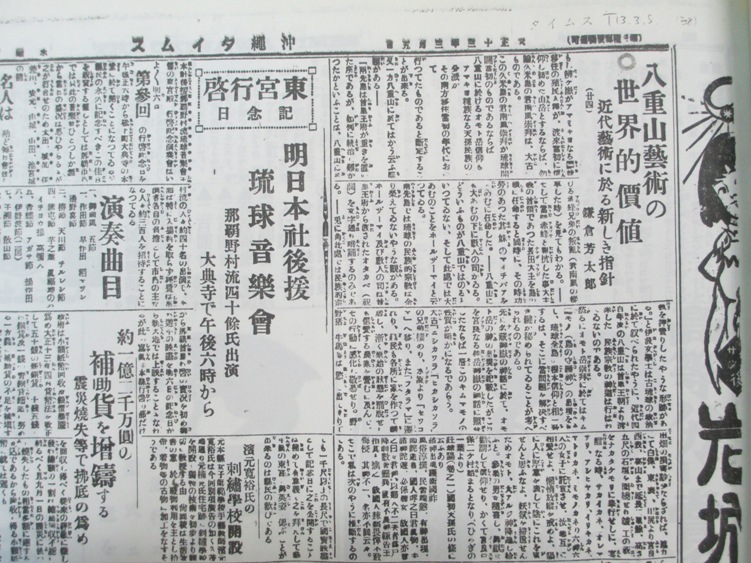
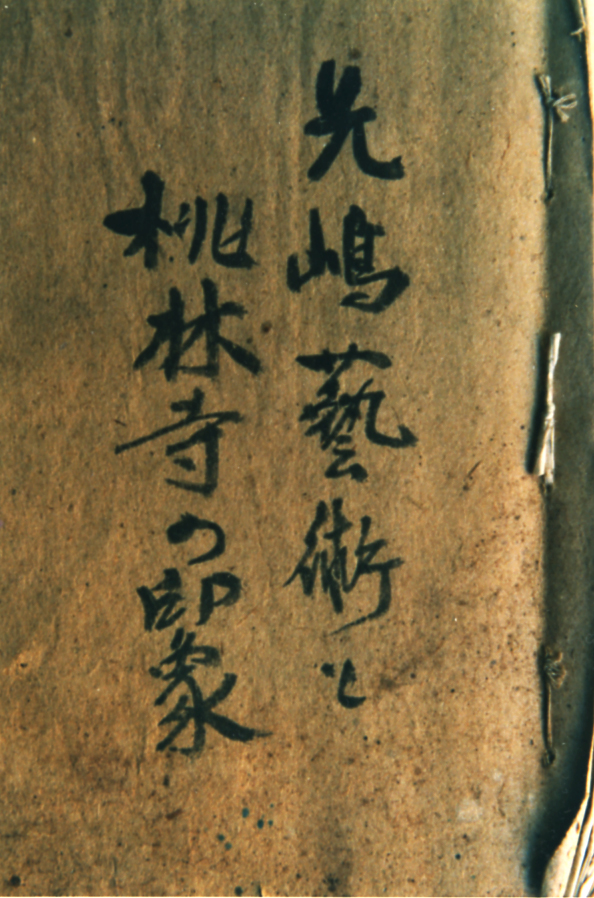 原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの
原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)
5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。
5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」
6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演
7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店
7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地
7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」
7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港
7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」
7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状
7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。
7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会
8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)
8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京
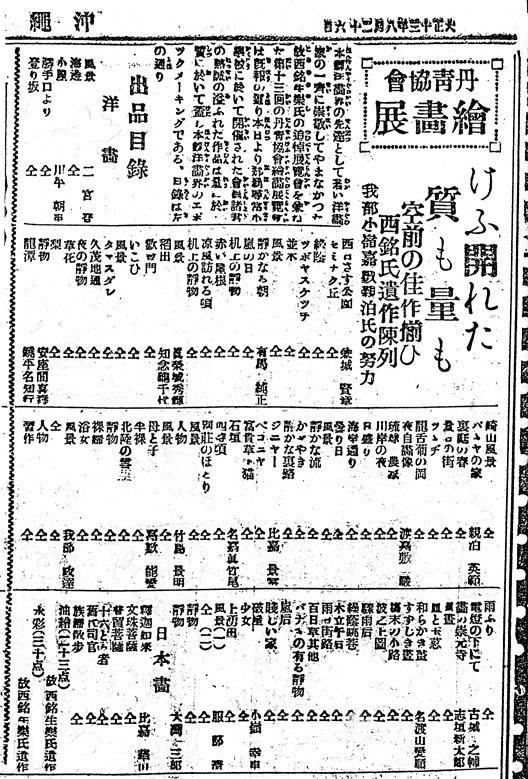
1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会
1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)
2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。
1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。
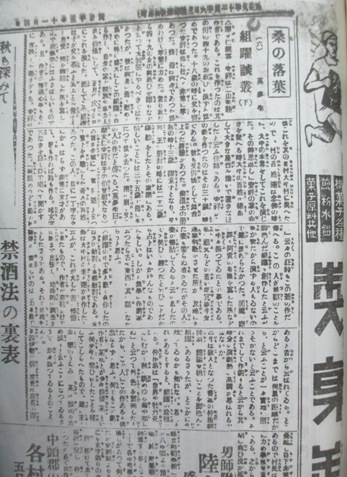
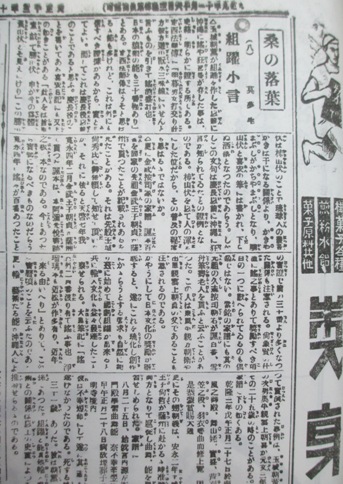
莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。
〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。
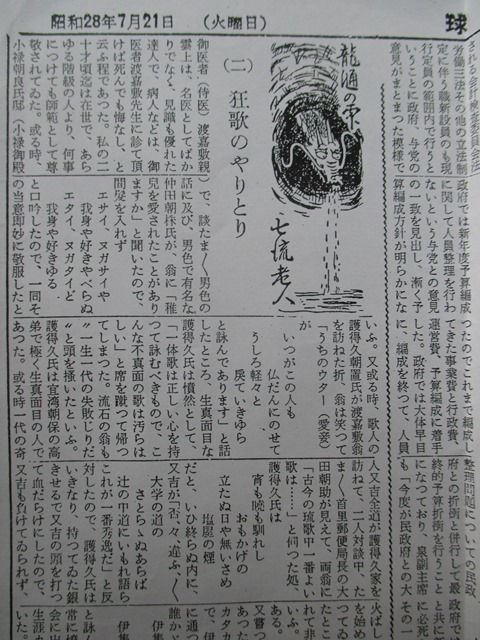
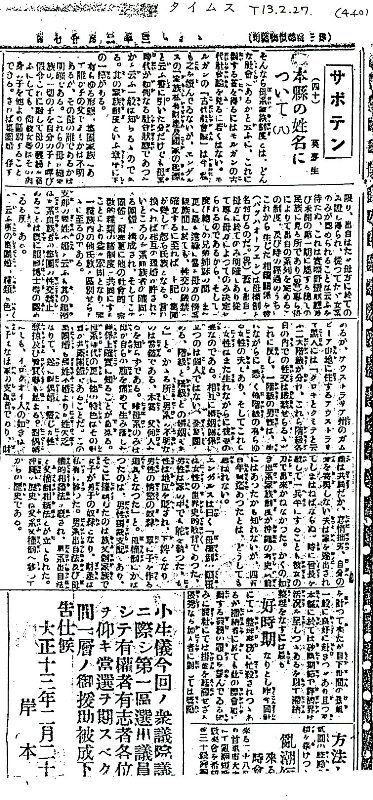
1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」
□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)
2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」
幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。
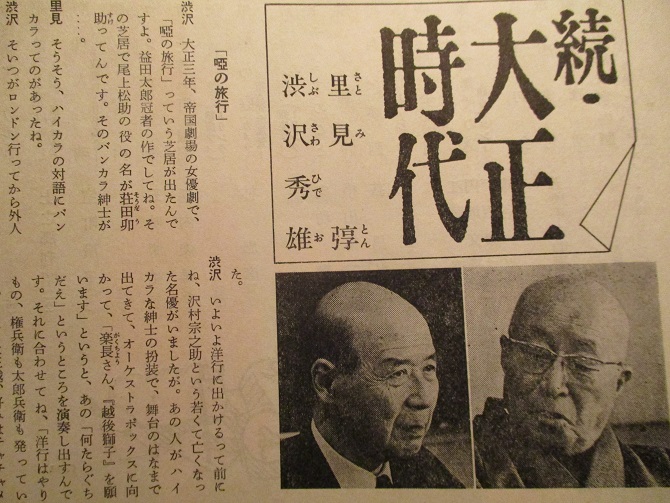
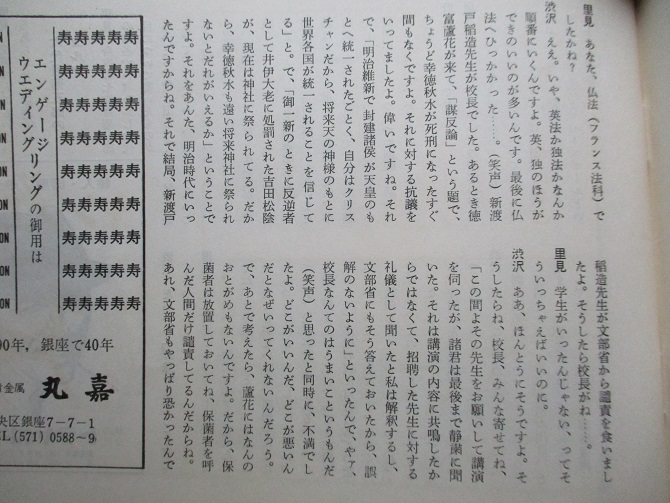
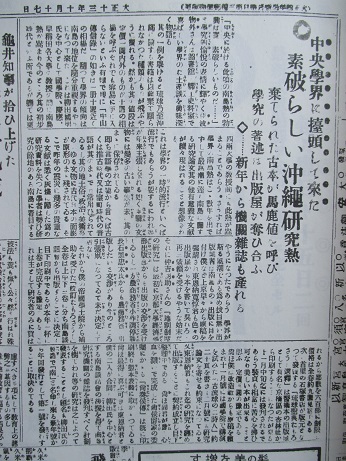
12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」
11/09: 末吉麦門冬没後90年/11月25日は「莫夢忌」①

1925年11月15日『沖縄タイムス』
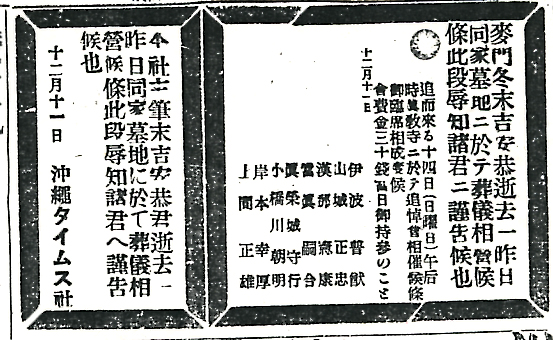
1924年12月11日『沖縄タイムス』「麦門冬末吉安恭逝去一昨日同家墓地ニ於テ葬儀相営候此段辱知諸君ニ謹告候也 追而来る14日(日曜日)午後時眞教寺ニ於テ追悼会相催候條御臨席)相成度候 会費金30銭当日御持参のこと/伊波普猷、山城正忠、漢那憲康、眞栄城守行、小橋川朝明、岸本幸厚、上間正雄」
1924年12月15日『沖縄朝日新聞』「麦門冬・末吉安恭氏の追悼会は既報の如く昨14日午後2時より眞教寺佛堂に於いて執行されたが故人の知己友人等相会する者両市各方面の階級を網羅して百数十名に上り、主催者代表として岸本タイムス社長挨拶を述べ次いで田原法馨師以下役僧の讀経があり故人と近かった仲吉朝助、川平朝令の両氏は交々悲痛なる弔辞を述べ終わって参会者一同順次に焼香を済まし同4時散会した。清く咲き誇れる梅花を■に淋しくも法灯に護られたる『莫夢釈安居』の法名の白木の位牌は故人の在りし日の面影を偲ばせ人々の悲しみを新たならしめた。」
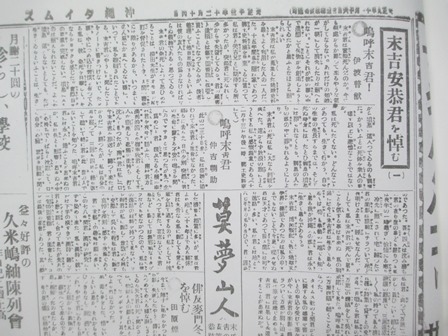
12月14日 『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(1)ー伊波普猷、仲吉朝助、田原煙波」
○伊波普猷ー末吉君は実際死んだのか。今にも何処からか帰って来るやうな気がしてならない。あれだけの知識が一朝にして消失したのは耐へられない。ことにそれが彼の頭の中で温醸して何物かを創造しょうとしていたかと思ふとなほさら耐へられない。末吉君は私が蒐集した琉球史料を最もよく利用した人の一人だった。15年間私の隠れ家であった郷土史料室を見棄てるに当って、私は君と笑古兄に期待する所が多かったが、突然君に死なれて、少からず失望している。君の蔵書と遺稿とは県立図書館に保管して貰ふことになっているが、後者を整理して他日出版するといふことは彼の友人たちの為さなければならぬ義務であると思っている。
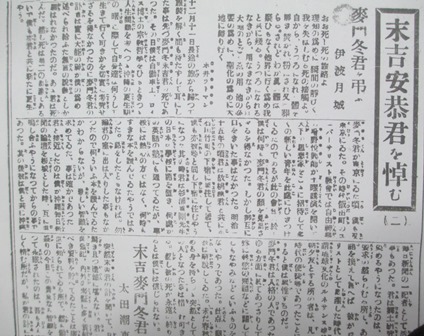
1924年12月15日ー『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む」(2)
□伊波月城「麦門冬君を弔ふ」
おお死ー死の旅路よ
理知の為めに瞬間の静けく
我を愛し失はしむる死の接触よ。
自ら、うつろになれ 體を
解き焚かれ粉にされ又 葬らる。
されどわが眞の體は
疑いもなく他界に行く為我と共に残る。
うつろになれるなきがら。
用なきなきがらは大 のとご いの用 他の必要
の為に、聖化の為に大地に帰り行く
ホイットマン
12月11日長途の旅から帰って旅装を解く間も待たずして耳にした事は先ず麦門冬末吉君の死であった。その日僕は自働車上 ロイス博士の宗教哲学をひもときつつ人生問題を考えつつ沖縄の更生期の曙に際して自分達は如何して生きて行く可きかを切実に考究せざるを得なかったのに麦門冬君の訃音は実に大能の神が僕の為 述べられ給うた無言の説教としか思われなかったのだ。ああ君は死んだ。然し死は第二の出産である。いで僕も亦君と共に新たな更生しよう。
麦門冬君が東京にいた頃、僕も又東京にいた。その時代飯田町のユニバーサリスト教会では自由神学の増野悦興師が土曜講演を開いて天下の思想家をここに招待して多くの新しい青年を此処ににひきつけていたのであるが此の会合に於いて僕は何時も麦門冬君の顔を見出さざるを得なかった。しかしお互いに口をきいた事はなかった。明治35年の頃君は故桃原君と共に小石川竹町の下宿に居住していて、僕も亦彼等と同じ下宿に住むようになった。其の時君は杉浦重剛先生の日本中学校に籍を置き、何処かの英語の塾にも通っていたが、学校には熱心の方ではなく、何時もすきな本を読んでいたようではあった。話をしたこともなければ勿論君の室に出入りした事もなかったので何ういう本を読んでいたかわからないが、新しい智識を求めていた事は確かであった。
君と接近したのは僕が沖縄毎日新聞の論壇を根拠とした時、互いに共鳴し合うようになってからの事であった。其の後彼は僕と共に沖縄毎日新聞の一記者として活動した事もあった。君は郷土研究に指を染めるようになったのは、時代の要求の然らしむ所であって、語を換えて言へば、彼がジアナリストとして出産した時代は、所謂琉球文化のルネサンス時代 其の朝夕友とする所の者は、凡て新時代の使徒等であったことに起因すると僕は思惟するのだ。
麦門冬君は人格の人であった。あらゆる方面に於いてあっさりしている。殊に性欲の問題などに関しては少しも悩みなどというものを知らないようであった。この点に関して彼は解脱していた。未だ春秋に富める身を持ちつつ突然として他界の人となった事は惜しむ可きである。然し彼の死が永遠に終わりであるとは僕には信じられない。
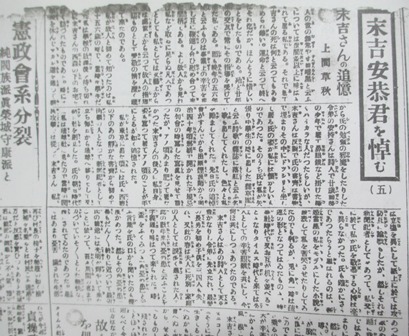
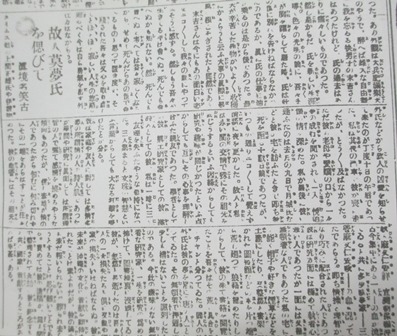
12月18日『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(5)ー上間草秋、眞境名笑古」

12月20日『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(7)ー東恩納寛敷、長浜瓊州」
12月26日『沖縄タイムス』東恩納寛惇「野人麦門冬の印象」
12/02: 莫夢忌/島袋全発
1920年代、琉球史随筆で大衆を喜ばせた新聞人、末吉麦門冬が24年11月に水死した。その追悼文で島袋全発は「友人麦門冬」と題し「私共の中学時代 客気に駆られ一種の啓蒙運動をなしつつあった頃 麦門冬は蛍の門を出でず静かに読書に耽って居た。あの頃の沖縄は随分新旧思想の衝突が激しかったが物外さんを初め私共の応援家も頗る多かった。氏も恐らく隠れたる同情者の1人であったに違いない。其後私が高等学校に入ってから氏と交わる様になったが一見旧知の如くやはり啓蒙運動家の群の1人たるを失わなかった。私共は苦闘して勝った。啓蒙運動とは何ぞと問われたら少し困る。文化運動と云ってもいい。それを近いうちに麦門冬氏が書くと云っていたそうだが遂に今や亡し。該博なる智識そのものよりも旺盛」なる智識欲が尊い。そして旺盛なる智識欲よりも二十年諭らざる氏の友情は更に尊い。私は稀にしか氏とは会わなかった。喧嘩もした。然し淡々たること水の如くして心底に流動する脉々たる友情はいつでも触知」されていたのである。去年の今頃は私の宅で忘年会をした。そして萬葉集今年の山上憶良の貧窮問答「鼻ひしひしに」や「しかとあらぬひげかきあげし」やに笑い した後 矢張り啓蒙運動の話に夢中になった。今年の春は大根の花咲くアカチラを逍遥し唐詩選の句などを口吟、波之上の茶亭に一夜の清遊を試み歓興湧くが如くであった。せめて晩年の往来をしたので良かったと思う。麦門冬氏の如き詩人は多い。氏の如き郷土史家は少ない。氏の如き友情に至っては今の世極めて稀。今や忽焉として亡し。噫」。
全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。
1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。
1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。
濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。
島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。
また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。
1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。
1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。
全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。
1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。
1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。
濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。
島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。
また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。
1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。
1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。
12/23: 莫夢忌/『日本及日本人』誌上での末吉麦門冬と南方熊楠
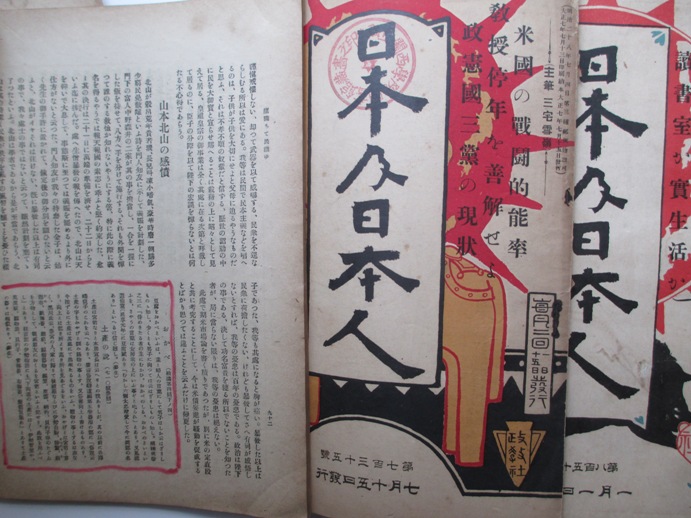
『日本及日本人』赤線内が麦門冬執筆
○この雑誌は、政教社の日本人誌と陸羯南の日本新聞とを継いでいる。これらは元々兄弟のような間柄だったが、1906年、日本新聞社の後任社長伊藤欽亮の運営を不服として、社員12人が政教社に移り、三宅雪嶺が『日本人』誌と『日本新聞』との伝統を継承すると称して、翌年元日から『日本人』誌の名を『日本及日本人』と変え、彼の主宰で発行したのである。創刊号の号数も、『日本人誌』から通巻の第450号だった。雪嶺は1923年(大正12年)秋まで主筆を続けたが、関東大震災後の政友社の再建を巡る対立から、去った。それまでが盛期だった。雪嶺は、西欧を知り、明治政府の盲目的な西欧化を批判する開明的な国粋主義者で、雑誌もその方向に染まっていた。題言と主論説は雪嶺、漢詩の時評の『評林』は日本新聞以来の国分青崖、時事評論の『雲間寸観』は主に古島一雄、俳句欄は内藤鳴雪、和歌欄は三井甲之が担当し、一般募集の俳句欄『日本俳句』は河東碧梧桐が選者で、彼は俳論・随筆も載せた。ほかに、島田三郎、杉浦重剛、福本日南、池辺義象、南方熊楠、三田村鳶魚、徳田秋声、長谷川如是閑、鈴木虎雄、丸山幹治、鈴木券太郎らの在野陣が執筆した。月2回刊、B5より僅か幅広の判だった。たびたび発禁処分を受けた。大正期に入ってからは、三井甲之の論説が増え、中野正剛、五百木良三、植原悦二郎、安岡正篤、土田杏村、布施辰治、寒川鼠骨らが書いて、右翼的色彩も混ざった。1923年(大正12年)の関東大震災に、発行所の政教社は罹災した。雪嶺と女婿の中野正剛とは、社を解散し新拠点から雑誌を継続発行すべきとし、他の同人が反対し、碧梧桐・如是閑が調停したが、雪嶺は去った。以降の『日本及日本人』は、同名の無関係の雑誌とする論もある。1924年年初、政教社が発行し直した『日本及日本人』は、体裁はほぼ以前通りだったが、内容は神秘的国粋論が多くなった。1930年(昭和5年)、五百木良三が政教社社長となって『日本及日本人』を率いた、1935年からは月一回発行になった。(ウィキペディア)
1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」
1912年2月ー柳田国男、伊波普猷より『古琉球』3冊寄贈される。
1913年4月ー沖縄県庁でこの程、筆耕に令し『中山世譜』の筆写をなさしめつつある。
1914年7月ー沖縄県知事より、伊波普猷、真境名安興ら沖縄県史編纂委員拝命
1915年1月ー沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁より沖縄県立沖縄図書館に移される(真境名安興主任)
1917年7月15日ー『日本及日本人』709号□末吉麦門冬「十三七つに就いて」「雲助」「劫の虫より経水」(南方熊楠と関連)
1917年9月1日ー『日本及日本人』712号□末吉麦門冬「楽屋の泥亀汁」
1918年2月12日ー東京日本橋区本町三丁目博文館・南方熊楠殿、末吉安恭書簡「拝啓 先生の御執筆の十二支伝説は古今東西に渡りて御渉猟のこととて毎年面白く拝読いたし候(略)琉球にも馬に関する伝説、少なからず候み付、茲に小生の存知の分を記録に出でたるものは原文の侭、然らざるは、簡単に記述いたし候間、御採択なされ候はば幸甚に候。失礼には候へど、御ねがひいたし度きこと沢山これあり候につき御住所御知らせ下さるまじくや(略)」(『球陽』『琉球国旧記』引用)
1918年8月15日ー『日本及日本人』737号□末吉麦門冬/しなだれ(輪講第二回中)第70号141にしなだれの解出づるも、その語源に就いては更に考ふべきものなきか、松屋筆記に日本霊異記等を引きて詳しく解釈せり、霊異記の■(門+也)は訓註に「シナダリクボ」と見ゆ「シナダリ」はシナダリの通音也。婬汁はしシタダリナガル、物なればシタダリと云ひ、クボ」は玉門のことにいへりとし、又今昔物語の婬もシナダリと訓むべしと云へり、これに依ればしなだれかかると云ふ語も、■れかかる義には相違なけれど、其の出所の元は婬汁のシナダリよりせしとすべきか。/焼餅の値(輪講参照)竹田出雲の小栗判官車街道(元文3年)に、桔梗屋の常陸といふ女郎が千二百両で身請けされたと聞き、二条樋の口の焼餅屋曰く「千二百両の金目を二文賣の焼餅の数に積って見れば、百五十四萬五千六百といふ焼餅が買われるげな」とあり、焼餅の値が二文づつなりしことが知らる。
1918年10月1日ー『日本及日本人』741号□末吉麦門冬/おかべ(輪講第四回下ノ四)豆腐をおかべといふは、素の婦人の言葉にして男子はしか云はざりしものの如し、少なくとも男子に向かっては云はざりしものの如し。醒睡笑巻之三に「侍めきたる者の主にむかひ、おかべのしる、おかべのさいといふを、さやうの言葉は女房衆の上にいふ事ぞと叱られ」とあり。又風流遊仙窟(延び享元年)に豆腐賦あり「むかし六弥田忠澄愛して今に岡部の名あり」といへるは信じ難し。/土産の説(七一〇号参照)土産は宮笥なりと本居宣長は云へりとの説ありしが、其の以前に井澤幡龍子①のこれを云へるあり、廣益俗説辯遺編第五巻期用の部に「俗説云土産の字をみやげと訓み賜物の事とす、又俗書向上と書けるものあり、今按ずるに土産は其処にて出来たるものをいふ、贈物の事とするは非なり、向上とは低き所より高き所を見あぐるをいふ、みやげとは宮笥と書く、黒川氏云、参宮の人、家に帰りて後祓箱ならびに伊勢白粉、陟のり、弱海布、麩海苔、鰹節、鯨髯器物、編笠、笙笛、柄杓、貝柄杓等のたぐいを方物として、親戚朋友におくるを宮笥といふと記せり、此説を用ふべし」とあり、狂言記の伊勢物語にも「下向道の土産には土産には伊勢菅笠や、萬度祓、鯨物差、貝柄杓、青海苔、布海苔、笙笛買集め」とありて土産の品々は相似たり。
①井沢 蟠竜『廣益俗説辨コウエキ ゾクセツベン 』 広益俗説弁, 序目1巻正編20巻後編5巻遺編5巻附編7巻殘編8巻
1919年1月1日ー『日本及日本人』747号□末吉麦門冬「再び琉球三味線に就いて」/「小ぢよくー近松の栬狩劔本地に『親をだしに遺ふは、物どりの奥の手、ヤイ小童今度は是を喰ふかと、杵振上れば』とあり、小童と云はれたのは男の子なり」/「かんから太鼓ー八笑人三編追加上の巻、頭武『イヨイヨヤンヤヤンヤのお声がたよりぢやァ、是はカンカラ太鼓をかりて行かうか』とあり、此編文政7年の作なりと云へば、その以前既にカンカラ太鼓ありと知るべし。安政3年よりも三十三年前なり。」(吉田芳輝氏提供)
1919年4月ー『日本及日本人』□末吉麦門冬「無筆の犬ー無筆の犬といふ話は早く醒睡笑(元和9年)に出づ。曰く『人喰ひ犬のある処へは何とも行かれぬなど語るに、さる事あり、虎といふ字を手の内に書いて見すれば、喰はぬと教ゆる。後犬を見、虎といふ字を書きすまし、手をひろげ見せけるが、何の詮もなく、ほかと喰ふたり。悲く思ひ、或僧に語りければ、推したり、其犬は一圓文盲にあったものよ』云々」
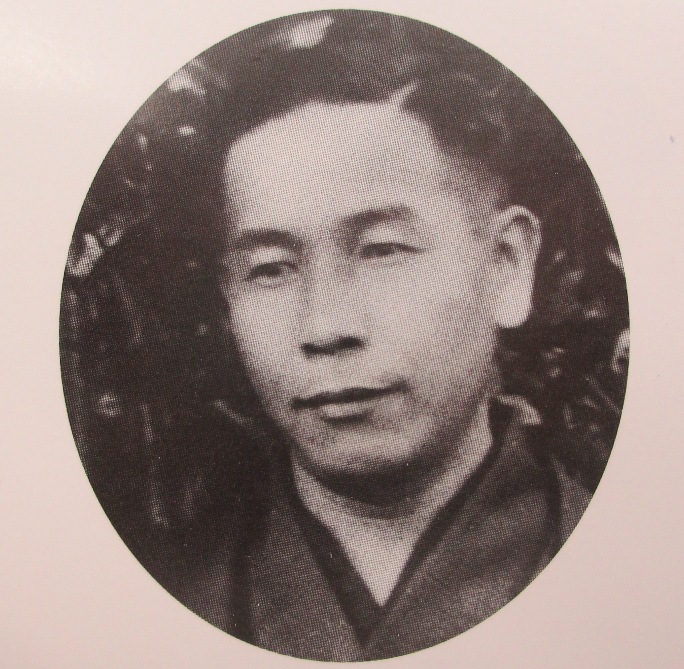
魚住惇吉
○大正13年(1924年)魚住惇吉校長の後を受けて建学当初から教鞭をとられた志喜屋孝信先生が第四代校長に就任した。
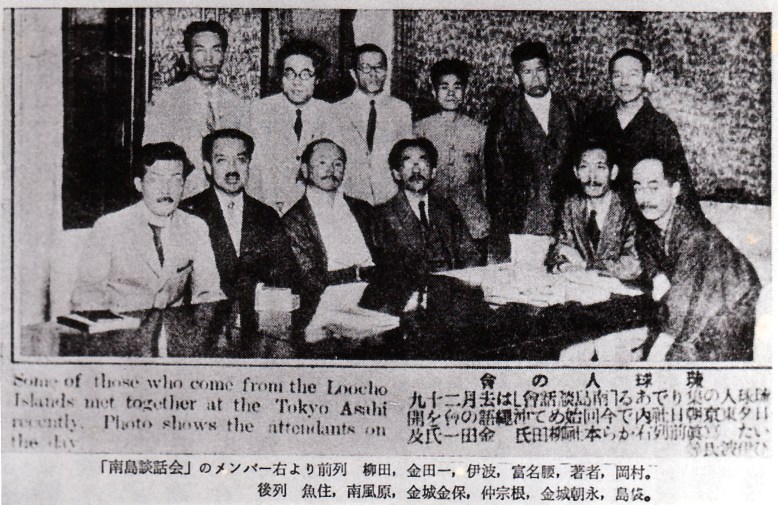
『アサヒグラフ』1927年7月13日号□南島談話会のメンバー/前列右より柳田国男・金田一京助・伊波普猷・富名腰義珍・岡村千秋 後列右より魚住惇吉・南風原驍・金城金保・仲宗根源和・金城朝永・島袋源七

1924年夏 小石川植物園で、向かって右から魚住惇吉、永田千代、
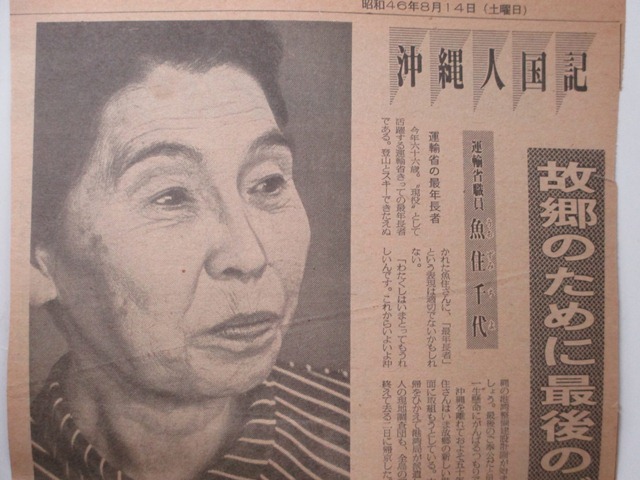
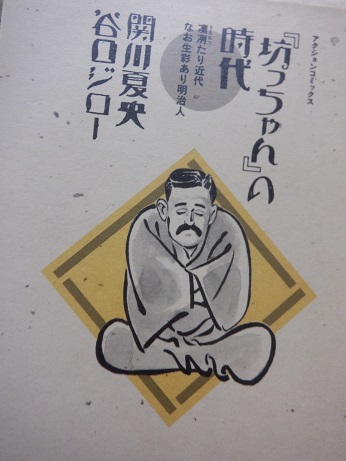
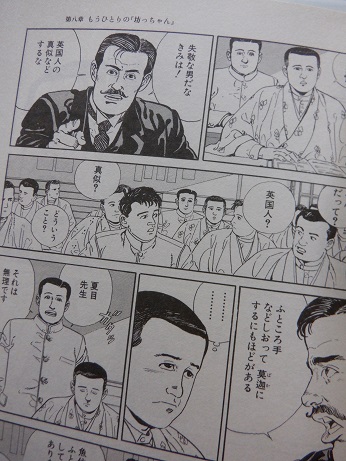
1987年8月 関川夏央・谷口ジロー『「坊っちゃん」の時代』双葉社
1988年8月 日本エッセイスト・クラブ『思いがけない涙』文藝春秋□魚住速人(三菱鉱業セメント副社長)「漱石と隻腕の父ー(略)実をいうと、私の父が、その左手のない学生である。名前は惇吉という。(略)私の父は東大を卒業したあと、中学の英語教師になり、沖縄県立第二中学校の校長を最期に、台湾旅行のとき罹ったマラリアの持病もあって、42歳で早々と引退、自適の生活に入った。ふたたび東大に通い、英文学やラテン語の研究をしていたことを覚えている。(略)私の息子が東大野球部に入り、法政の江川投手を4打数3安打で打ち破ったことがあるのを父が知ったら、さぞかし喜んだことであろう。」
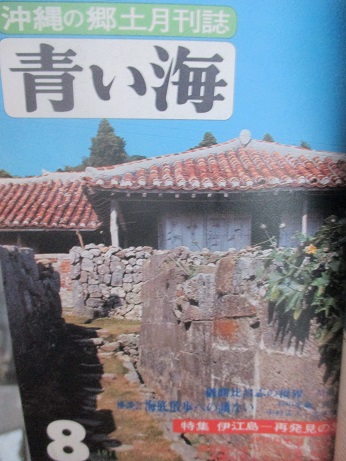
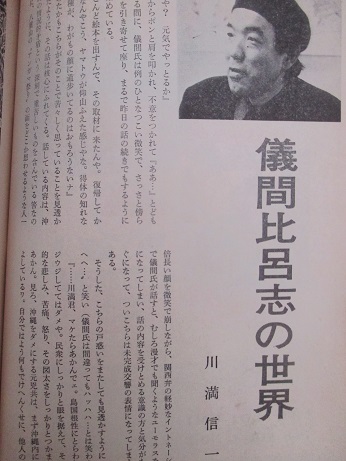
1974年7月 沖縄の雑誌『青い海』35号 川満信一「儀間比呂氏の世界」
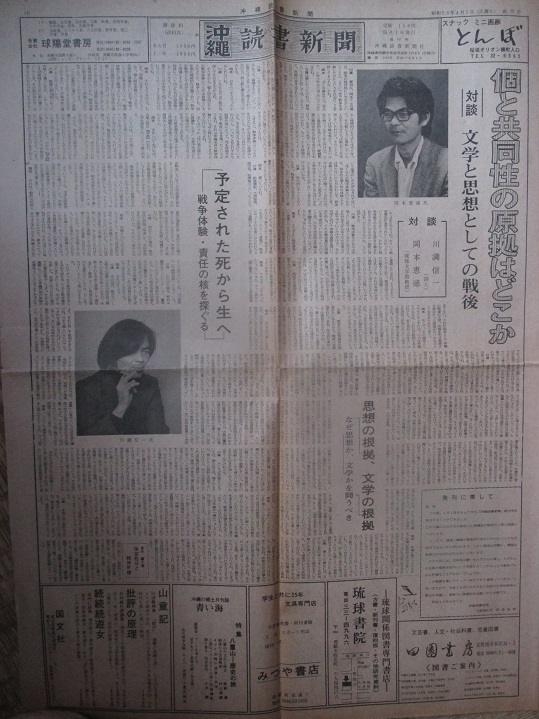
1975年4月『沖縄読書新聞』創刊号 川満信一(詩人)岡本恵徳(琉球大学助教授)「対談・文学と思想としての戦後」


写真左から真久田正氏、中里友豪氏、川満信一氏、新川明氏/左から比嘉康文氏、川満信一氏、新城栄徳
岡本恵徳
岡本恵徳氏は私の顔を見るたび「もっと奄美資料を発掘してくれ」が口癖であった。私は伯父や伯母の連れ合いが奄美出身であったから特に奄美を意識したことがないが、琉球文化には当然に奄美も入っていると思っている。奄美の図書館は島尾敏雄氏に会ってみたいと2回行ったが何時も休館だった。島尾敏雄氏には会えなかったが、その代わりといっていいか分からないが山下欣一氏に出会った。




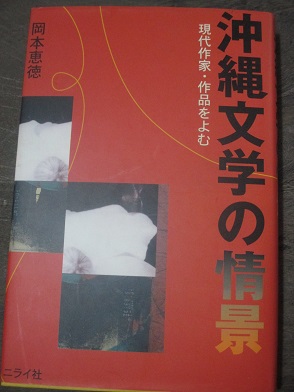
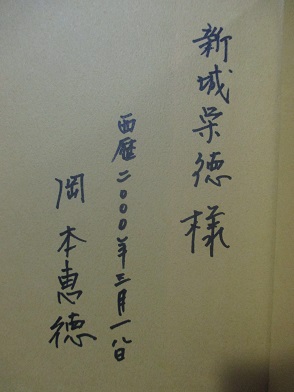
2006年8月6日『琉球新報』岡本恵徳氏が死去 近現代沖縄文学研究で功績 71歳
近現代沖縄文学研究の基礎を築いた琉球大学名誉教授で琉球新報児童文学賞選考委員の岡本恵徳(おかもと・けいとく)氏が5日午後7時25分、肺がんのため、那覇市立病院で死去した。71歳。平良市(現宮古島市)出身。自宅は那覇市首里大名町2ノ76。告別式の日程は未定。喪主は長女亜紀(あき)さん。
「琉大文学」の創刊メンバーの1人で、米軍政に対する抵抗の文学を目指した。「琉球弧の住民運動」「けーし風」など草の根の市民運動にも参加。1982年から琉球大学教授。「現代文学にみる沖縄の自画像」(96年)で伊波普猷賞受賞。琉球新報短編小説賞2次選考委員。
著書に「現代沖縄の文学と思想」(81年)、「沖縄文学の地平」(81年)、「『ヤポネシア論』の輪郭」(90年)、「沖縄文学の情景」(2000年)など。

03/25: 1928年2月 南島研究会『南島研究』創刊号
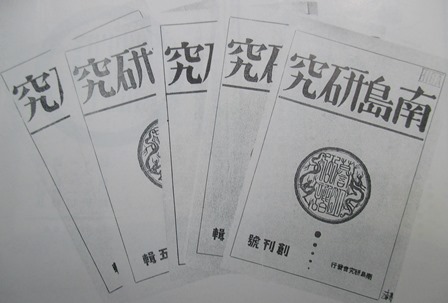
写真ー『南島研究』
南島研究発刊について
世界の文明が、地中海からして大西洋に移り、それから今や漸く太平洋に転ぜんとしつつあるといふ、所謂過渡期に於いて、この太平洋に裾を洗われて居る我が日本の先覚者が、太平洋問題を提げて学界に馳駆せようとせらるることは、近来の痛快事である。これ地中海①に七十倍し、大西洋に二倍するといふ、范々たる大海原のうちには、あらゆる気候とあらゆる人種、あらゆる文化が宝蔵されて居るからである。而して九州の南端から奄美大島を貫いて、東北よりして西南に延び、数十顆の連珠のやうな大島小嶼が、宮古島を経て八重山島の与那国島に至って尽き、この面積が百三十九万里を算しているのが、即ち我が沖縄群島である。この外にも、今から三百余年前に、政治的に切り離されて、鹿児島県に隷属して居る奄美大島諸島も、亦天然の配置としては、往古より琉球王の治下に属し、その人情風俗言語習慣などより考察しても、純然たる琉球人であることは、誰しも首肯せられるだろうと思われる。これらの群島は、東は一帯に太平洋に面して、北は鹿児島県に隣接し、南は一衣帯水の台湾と相呼応し、西は海を隔てて南支那の福建省と相対峙し、而して西南の方は遥かに南洋群島を顧望して居るのであるから、面積の割合にその拡がりは、なかなか大きいように観ぜられるのである。これらの主島が、今日の所謂沖縄島で、我邦本土では、既に一千余年前に於いて、阿児奈波島として知られ、国史とも多くの交渉を保って居るようである。のみならず記録にあらわれた時代からしても、既に五六百年から支那本国や安南、暹羅、馬刺加、朝鮮なども交通し、また爪哇や、比律賓などの南洋諸国とも貿易をやっていたのであるが、之れらは今から三百余年前の所謂薩摩と附庸関係を生じた慶長の役を末期として断絶してしまったのである。
斯やうに沖縄は、往古からして我が本土とは勿論密接な関係があり、また支那本国や南洋諸島などとも関係を有していたために、之れらの影響をうけたのであらうか、一種独特の文化を生んだ一島国であったのである。が交通が不便で顧みられなかったために、今古千年の夢は封ぜられ、恰も武陵桃源のやうな仙境にあったので、外界から能くその真相を知られる機会がなかったのである。それが、幸か、不幸か、その地理的環境のために、能く外国の文化を我が本土に伝へる中継場となると同時に、また我が本土の古文明を忠実に保存する倉庫のやうな、作用をなしていたのである。併しかやうな、神秘的な島国も、廃藩置県後の文明の風潮には、抵抗することが出来なかったやうで、所謂新文明の醗酵すると共に、古琉球の文化は危機に瀕した時代もあったのである。即ち一知半解の徒輩が琉球研究を以て復古思想の再燃と誤解し、古文書の棄却や、名所旧跡の破壊が到る所で企てられ、将に薩州治下に於ける、奄美大島の覆轍を踏まふとしたのであった。
此時に当ってー即ち明治二十五六年頃ー県の中学校に教鞭を執られて居った田島利三郎氏や新田義尊氏や黒岩恒氏などが、琉球の過去現在に趣味を持たれて、その歴史や、歌謡言語及び自然科学などの研究をはじめ出して、漸くこれが価値づけられて、彼等の自覚を促がしこれと前後してわが分科大学講師のチャンバレン氏等も亦渡琉せられて研究をされたのである。是から引きつづいて幣原坦博士や、鳥居龍蔵博士・金沢庄三郎博士なども来県されて、各部門の研究を発表され、暗黒なる琉球が漸く光明へ出されるやうになったのである。而してこれより先土着の沖縄人にも、亦故喜舎場朝賢翁や山内盛憙翁などのやうな郷土研究家もあったけれども、之れが最も高潮されたのは明治の末期からで、即ち畏友伊波普猷氏や、東恩納寛惇氏や、故末吉安恭氏等の研究であったやうに思はれる。これから、古琉球の文化が漸く識者の間に認めらるるやうになったが、未だ一般には徹底しないで疑心を以て迎へられたようであった。然るに最近に至り、柳田国男氏や、伊東忠太博士、黒板勝美博士等の来県があり、これら巨擘を中心として在京諸友は勿論県外の人では、畏友鎌倉芳太郎氏などが、その専門の立場からして、熾に中央で琉球の文化を紹介せられ、又南島談話会なども生まれて東都に於ける琉球研究者の機関も出来るやうになり、殊に啓明会などの財団法人もその研究に同情されて資金を投ぜられ、これで一層鼓吹されたやうに思はれる。
而して琉球研究は、その本場を離れて、中央に持ち出された喜ばしい現象であるが一方郷土に於ても亦之れが閑却せられているといふ訳ではない。逐年この種の研究や紹介は、却って熱烈さを加へて進んでゆくやうであるけれども、之れが機関となるべき定時刊行物がなかったのを最も遺憾とする次第であった。然るに、今回微力を揣らず、吾々同人が主となって、此の「南島研究」といふ小冊子を刊行する機運になlったのは、相互にその研究を援助してこれを発表批判すると同時に、広くこの種研究家の声援を得て、その内容を豊富にし、且つ琉球に関する、滅びゆく古今の研究資料を蒐集して附録とし、広く一般学界の参考に供したい為である。この恵まれたる地理的環境からして、日支文明の交叉点ともいはれまた我邦文化の中継所となり、倉庫ともなった南島、即ち奄美大島から八重山の先端与那国島までの島彙が吾々の研究に資すべき舞台面である。が、この未開拓の曠野からして、何か新生命が見出されて、我が学界に光を投じ得るや否やは、未来の問題で、切に識者各位の熱誠なる御同情と、御後援を待つばかりである。 十一月廿日 県立図書館郷土資料室にて 真境名安興
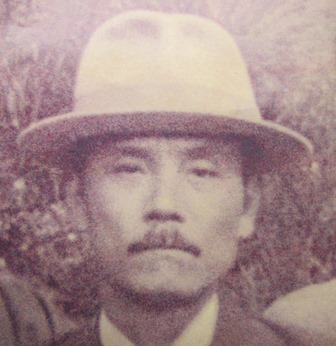
写真ー真境名安興
目次
口絵「泉崎及び金武の火神」
○編集者よりー資料や文献は割拠して居る、系統的に出来た索引のないことはその資料及文献の蒐集に不便な、地方の孤独な研究家をただ空しき努力に終わらせるばかりだ。と云ふことはしばしば吾等が聞く言葉でありました。即ち既に何人かの手によって研究、発表せられた事柄を、これから準備し、これから研究し、かくて仔々倦まざる多年の努力が空しき結果に終ると云ふことになると、本人ばかりの失望でなく、同じ研究者の一員としても見るに忍びないところであります。かくの如き有様でありますから、われらの念頭からは絶えず、何等かの方法で、かかる孤立の研究者たちと連絡をとり、各自の分担的研究を漸次進めて行きたいと云ふ念が去りませんでした。
そこに生まれたのが南島研究でした。なるほど本誌は小冊子ではあり、特に南島研究と銘をうってはありますが、吾等は目を睜つて南島を見たい、そして南島から広い世界を見たいのであります。本誌の主義も、事実の忠実なる採録、文献の尊重と比較研究法の正確を期することに重きを置きたいものだと思って居ます。かくて本誌は読者諸君の本誌であり、又諸君の薀蓄を傾け、互に幇助示導しつつ、吾等の拠るべき、向ふべき道を進んで行きたいのでありまして、吾等は零碎なる報告、交詢の類と雖も克明にこれを雑誌に網羅するに吝ではないのであります。吾等の雑誌は割拠もしなければ、対峙もしない、どこまでも吾等の過去及び現在の記録としたいものであります。
本誌の誇として特筆すべきは、古琉球に関するあらゆる史料の採録で、これのみにても既に一大事業ー吾等としてはーと云ふに恥じないつもりであります。本号から「琉球國中山世鑑」「球陽遺老説傳」「東汀随筆」の三種を採録しました。これは読者諸君の便をはかり、まとまった一冊の本に製本の出来る様に丁附を別にしてあります。
史論・雑録
南島研究の発刊について・・・真境名安興/奈良帝室博物館の雲板について(琉球國王尚泰久の鋳造)・・・真境名安興/火神の象・・・奥野彦六郎/沖縄の士族階級・・・島袋全発/昔の蘇鉄地獄・・・T生/鬼餅伝説(ホーハイに就いて)・宜野湾新城のムーチー/歴史は繰返すー蔡温の林業政策ー/「あこん」に就いて・・・岩崎卓爾/萬葉歌と琉歌・・・エス・エス生
史料
1、琉球國中山世鑑 2、球陽遺老説傳 3、東汀随筆
通信
柳田國男氏より盛敏氏へ/伊波氏より島袋全発氏へ/東恩納氏より真境名笑古氏へ/岩崎氏より真境名氏へ
莫夢忌/1924年12月14日 『沖縄タイムス』仲吉朝助「嗚呼末吉君」
○此の二三十日来、私は俗務に追われて末吉君と面会せなかった。然るに去る9日の夕刻、突然に君の生命に関する不安の噂さを聞いたのでマサカとは思ったが先ず念のためにと君の親友なる小橋川南村君を夜中に訪ふた、南村方で漢那浪笛と小嶺幸欣君とそして主人が鼎座して悲痛の面持ちで打ち沈んでおったが、南村君は私に「只今末吉君を葬送して帰って来たばかりだ」と語ったが、私は自分の耳を疑って、2回も3回も繰り返して聴いて終に君が此の世の人でないことを知った。嗚呼末吉君、君には永久に逢うことが出来ぬのか、私は何とも形容の出来ぬ不安の心持ちでしばらく沈黙して、只だ自分の心臓が波高き鼓動を聞くのであった。吾々4人は沈み勝ちに君の在り世の事ども語りつつ私は夜半の1時過ぎに愴悽たる寒月の冷光に照らされて宅に帰ったが君の面影は眼前にチラついて殆ど夜明まで一睡もせなんだ。ドーしても私は末吉君の死んで居ることを信ずる事は出来ぬ、私の胸裏には今に末吉君は生きて居る、恐らくは苟も学芸の一端でも知って居る我が沖縄人の頭に君は永久に生きて居るであろう。
末吉君、博聞強記で特に琉球文学界の権威であったのは私の申すまでもないことで今更に喋々せぬ、君は天才であって同人間には可なり逸話も多い。私と君とは殆ど十六七年来の知り合いで、君と謹談した機会も相当に多いが、私は君より殆ど二十も年上である関係で君は九骨なる私に対しても常に先輩を以て過ごするので私としては愧ち入って居た、宴席などでも君は私などに対しては無邪気なイタヅラなどもせなかったので、私は君の逸話の材料を持って居ない。ソレ程君が私に対して尊敬の心持ちで交際して呉れた程私は君に対する哀悼を深刻に感ずる次第である。君は文芸上の趣味は頗る多い。この七八年間君は漢詩の研究にも手を染めて来た、私も漢に就いては下手の横好きで漢詩に関して君と数々話し合って居たが先月の中旬頃 図書館で君と面会した、コレは最後の面会であった、其の際 私は君に向かって「万葉」の講議を聞かして貰いたいと頼んだ処、君は謙譲の態度で二三回遠慮したがトウトウ私の持って居る清朝人の四五種の詩集を貸すとの交換条件で来年1月頃から君は私の為に「万葉」の講議をして呉れることを承諾して居た。嗚呼 私は永久に君の万葉講議を聴くことが出来なくなった。
タイムス社の上間君から末吉君に関する私の感想を書いて欲しいとの申込を受けて筆を執ったが、今に末吉君の面影が眼前にチラついて万感が胸に迫るので、私は筆を此辺で止める。嗚呼末吉君、君には果たして永遠に面会することが出来ないのか。
仲吉朝助(1867年4月6日~1926年9月3日)

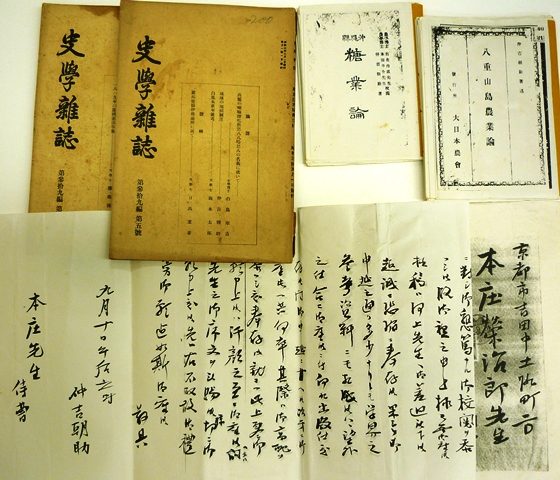
本庄栄治郎 ほんじょう-えいじろう
1888-1973 大正-昭和時代の経済史学者。
明治21年2月28日生まれ。大正12年京都帝大教授。昭和17年大阪商大学長。戦後は上智大,大阪府立大の教授を歴任。近世日本経済史・経済思想史を専攻。日本経済史研究所を設立して後進の育成にもつくした。「本庄栄治郎著作集」がある。40年文化功労者。昭和48年11月18日死去。85歳。京都出身。京都帝大卒。(→コトバンク)
1928年7月 『南島研究』第三輯
口絵「琉球の結婚風俗」
編輯者より・・・西平賀譲
▽研究・雑録△
禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)
▽資料△
1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿
①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没
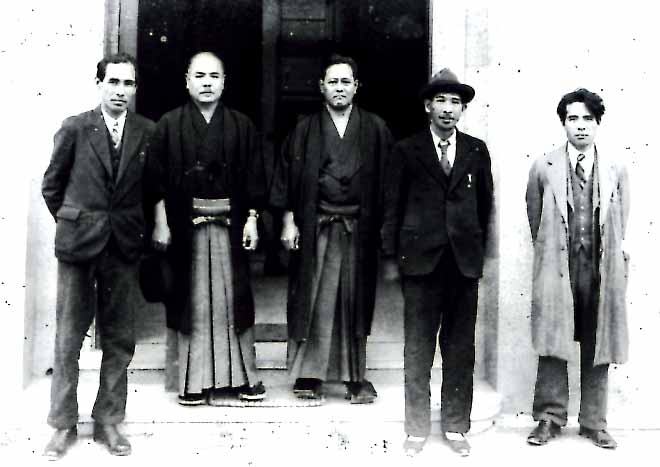
写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)
1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」
1928年11月 『南島研究』第四輯
口絵「進貢船の那覇港解纜」
▽史論・雑録△
北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ
○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。
1929年3月 『南島研究』第5輯
口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」
▽史論・研究△
名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信と寄贈雑誌
○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)
1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社
1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」
1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告
1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」
1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東
口絵「琉球の結婚風俗」
編輯者より・・・西平賀譲
▽研究・雑録△
禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)
▽資料△
1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿
①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没
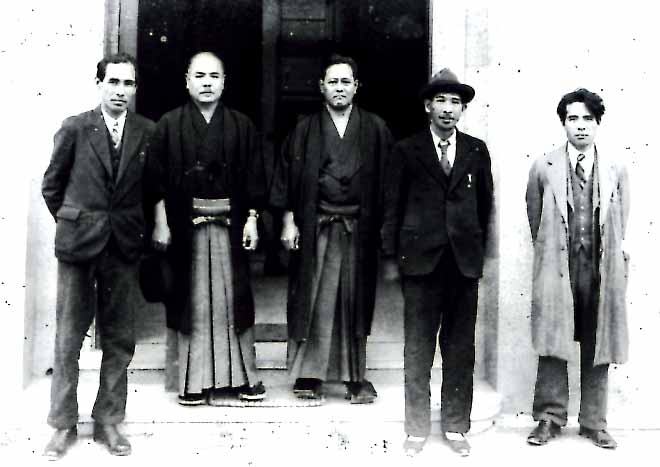
写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)
1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」
1928年11月 『南島研究』第四輯
口絵「進貢船の那覇港解纜」
▽史論・雑録△
北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信
奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ
○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。
1929年3月 『南島研究』第5輯
口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」
▽史論・研究△
名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響
▽資料△
1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆
通信と寄贈雑誌
○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)
1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社
1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」
1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告
1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」
1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東
05/07: 琉米誌/ハワイ②
パンチボウルの丘(国立太平洋記念墓地)ー7万5千年から10万年前の火山活動によって形成された高台のクレーター、パンチボウルは、古代ハワイで「Puowaina(犠牲の丘)」と呼ばれていました。タブーを犯した罪人をいけにえとしてハワイ古代宗教の神に捧げる祭壇が高台に置かれていたのです。国立太平洋記念墓地としてオープンしたのは1949年。第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争で母国のために自らを「犠牲」にした4万6千以上の兵士が眠る丘となりました。。→ハワイナビ/アーニー”アーネスト・テイラー・パイル(Ernest Taylor "Ernie" Pyle, 1900年8月3日 - 1945年4月18日伊江島で戦死)は、アメリカ合衆国のジャーナリストやショージ・オニヅカ(Ellison Shoji Onizuka, 日本名:鬼塚 承次, 1946年6月24日 - 1986年1月28日)は、アメリカ空軍の大佐で、日系人初のアメリカ航空宇宙局宇宙飛行士である。の墓石。
1949年12月 セブンスデーの屋比久孟吉は平信徒でありながら華府本部から特別伝道者の任命を受けて伝道者の資格で沖縄へ赴くことになった。
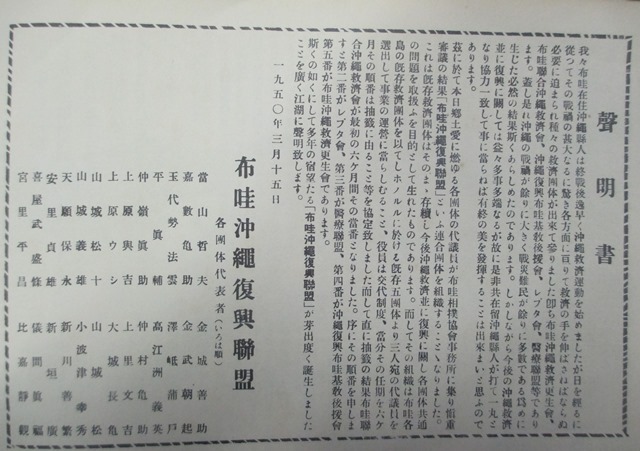
1950年12月 慈光園教団発足ー顧問・小波津幸秀、上原与吉 相談役・伊芸長吉、村岡敏恵、桜田漸、福本元蔵、伊波幸繁、大嶺発市、仲真良樽金、宮城栄吉、大兼久秀一、石川元真、大城太郎、宜野座太郎、伊佐松 名誉教団長・・・与世盛智郎 教団長・山里慈海 理事長・宮里平昌 副・瑞慶覧智珍、仲嶺真助 書記・神谷益栄、上地安宏 会計・真喜志康輝、豊見里友義、監査・宮城麗栄、高良牛、宮城亀盛
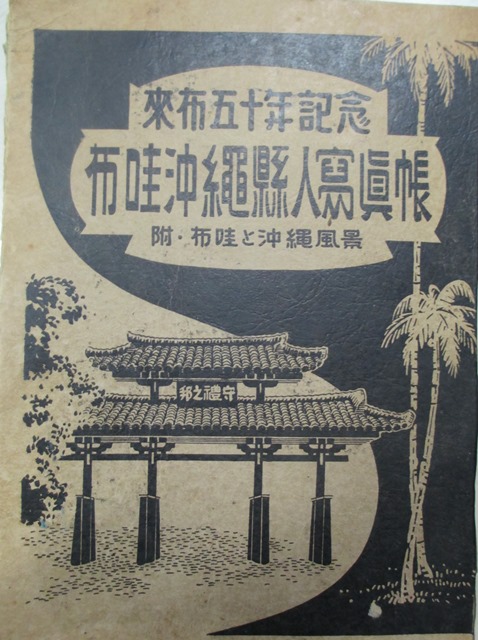
1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』
1951年2月 乙姫劇団が来布公演
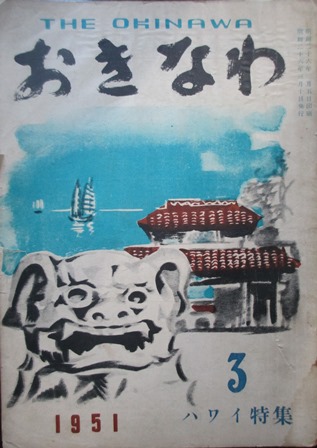
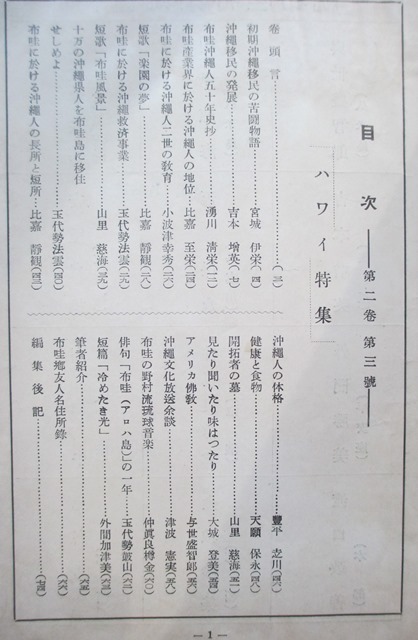
1951年3月 雑誌『おきなわ』<ハワイ特集>
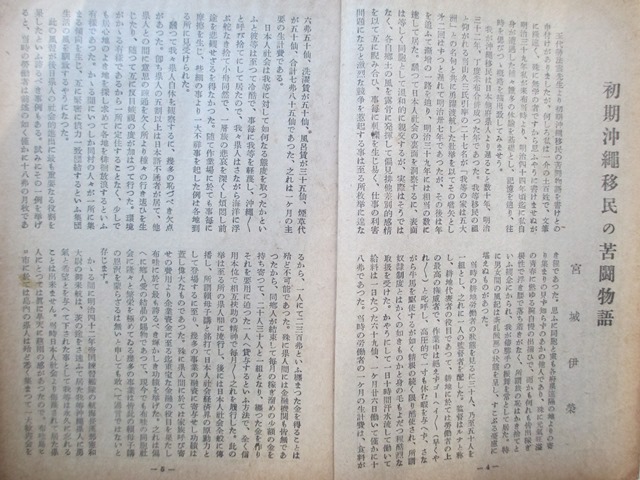
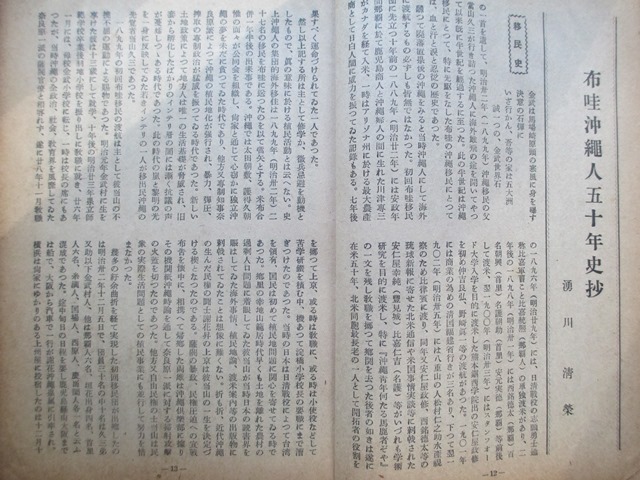
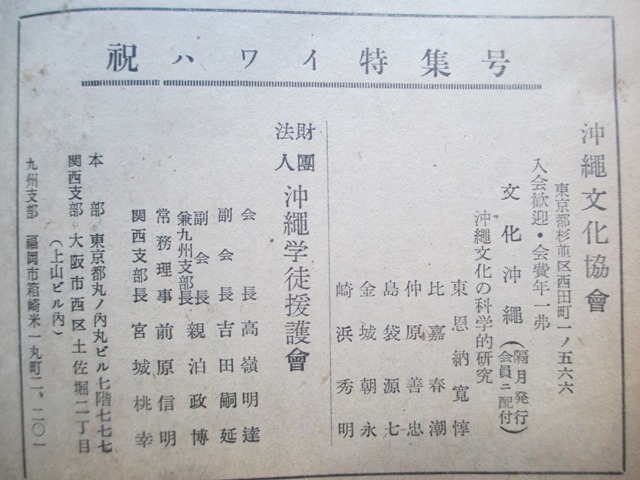
1951年3月 雑誌『おきなわ』湧川清栄「布哇沖縄人五十年史抄」」
1951年3月 雑誌『おきなわ』大城登美「見たり聞いたり味はったり」
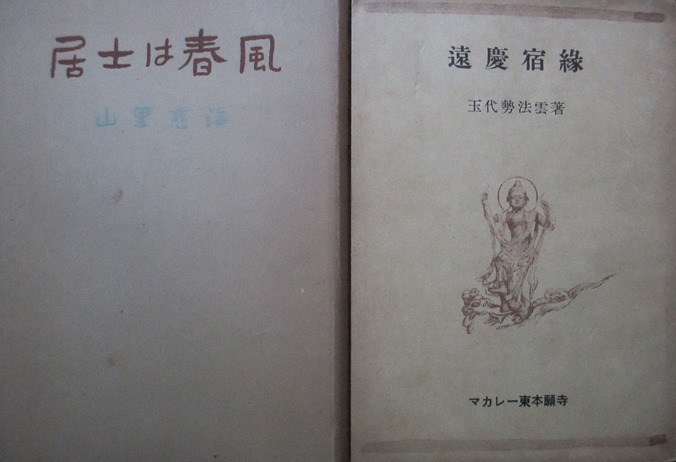
1951年10月 山里慈海『居士は春風』/1953年3月 玉代勢法雲『遠慶宿縁』
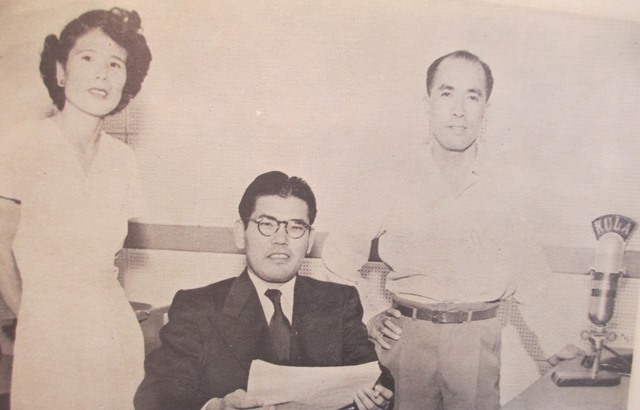
クラ放送局沖縄文化放送部デイゴメロデー/左から大城とみ子、津波實重、山川喜信→1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』
1951年3月 遣米第二回国民指導員来布□志喜屋孝信、大城つる、城間政善、上江洲由道、渡口政義、永山盛三郎、当銘正順、上間亀政、翁長俊郎、大嶺政寛、名渡山愛順、松岡政保、中江実孝、屋田甚助、森敬道、林哲雄、財部つさえ 名渡山愛順「私は終戦後、青年将校の肖像画を五百枚以上も画きました。20数点持参してニューヨークで展覧会を開きますが出来たら帰路にハワイでも開き、又ハワイのカラーも描いて見たいと願っています。」
1951年6月 東京大阪合同琉球芸能団一行8名は渡口政善、金城常盛、上江洲安雄、安谷屋政信の招聘で来布□渡嘉敷守良(我如古安子の叔父)、池宮城喜輝、奥間英五郎、奥間清子、佐久間昌子、渡嘉敷信子、渡嘉敷利秋、島正太郎
1951年6月 南加大学の招聘で琉球音楽を講義しに行く東京沖縄音楽舞踊研究会会長の山内盛彬はツル夫人同伴寄港。
1951年7月 宮里辰彦(第三回沖縄国民指導員)ホノルル郊外ヒッカム飛行場着。此の飛行場は例の日本軍の真珠湾攻撃の際、真っ先に叩かれた所である。
1951年7月 雑誌『おきなわ』<故人追憶特集>
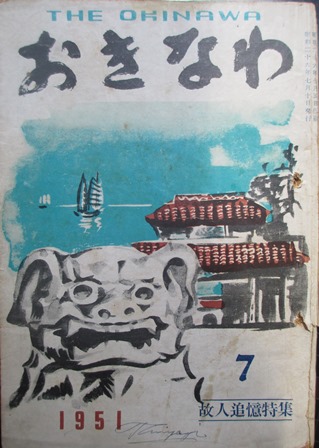
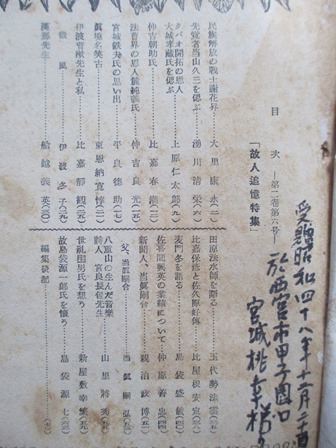
大里康永「民族解放の戦士 謝花昇」/湧川清栄「先覚者 当山久三を偲ぶ」/上原仁太郎「ダバオ開拓の恩人 大城孝蔵氏を偲ぶ」/比嘉春潮「仲吉朝助氏」/仲吉良光「法曹界の恩人 麓純義氏」/平良徳助「宮城鉄夫氏の思い出」/東恩納寛惇「真境名笑古」/比嘉静観「伊波普猷先生と私」/伊波冬子「微風」/船越義英「漢那先生」/玉代勢法雲「田原法水師を語る」/比屋根安定「比嘉保彦と佐久原好傳」/島袋盛敏「麦門冬を語る」/仲原善忠「佐喜間興英の業績について」/親泊政博「新聞人、当眞嗣合」/当眞嗣弘「父、当眞嗣合」/山里将秀「八重山の生んだ音楽詩人 宮良長包先生」/新屋敷幸繁「世礼国男氏を想う」/島袋源七「故 島袋源一郎氏を懐う」/編集後記
1951年8月 ハワイ沖縄連合会発足(理事長・儀間真福)
1953年2月 慈光園で柳宗悦、浜田庄司、バーナード・リーチ講演会「琉球文化を語る」。沖縄紹介映画、幻燈などがあった。
1953年12月 雑誌『おきなわ』№33「ハワイのうつりを語る座談会」
出席者ー平良牛助、玉代勢法雲、比嘉静観、小波津幸秀、金城珍栄、山里慈海、天願保永(おきなわ布晆支局長)
1954年4月 平良リエ子来布/5月 安谷屋政量・琉球工業連合会長「ハワイ第四十九州共進会」に参加で来布。慈光園で「琉球特産品展示会」、6月からハワイ各島で展示する。/12月 金井喜久子来布
1954年4月 雑誌『おきなわ』「ハワイ同胞事業家座談会ー慈光園ホール」
出席者ー仲宗根蒲助(越来)、天願加那(具志川)、上原正義(本部)、伊芸良吉(宜野座)、仲嶺真助(与那原)、山里慈海(久米島)、天願保永(具志川)、平真輔(石川)、長堂嘉吉(真和志)、島袋萬吉、速記ー津嘉山朝吉、瀬長清吉
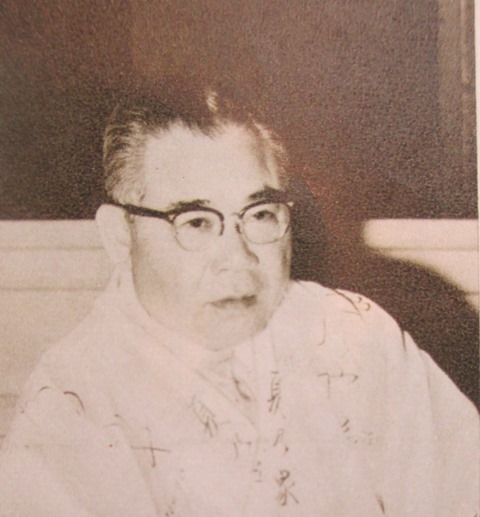
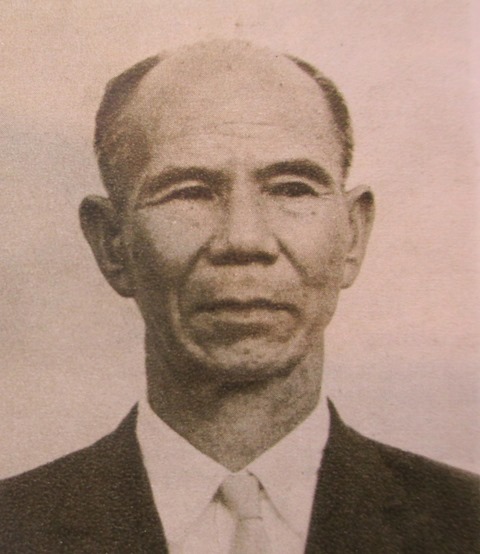
上原正義(エバーグリン・レストラン社長) 天願保永(ハワイ沖縄人連合会)
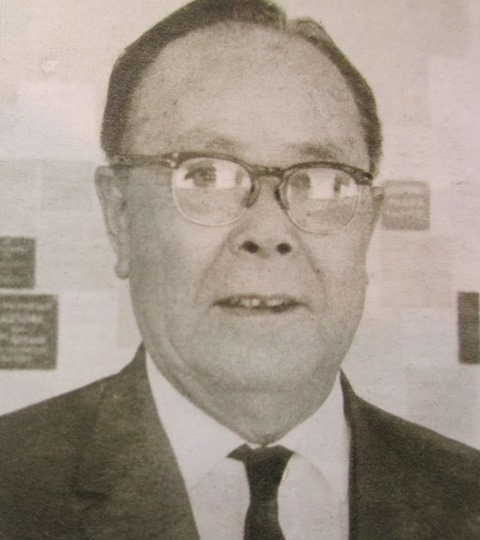
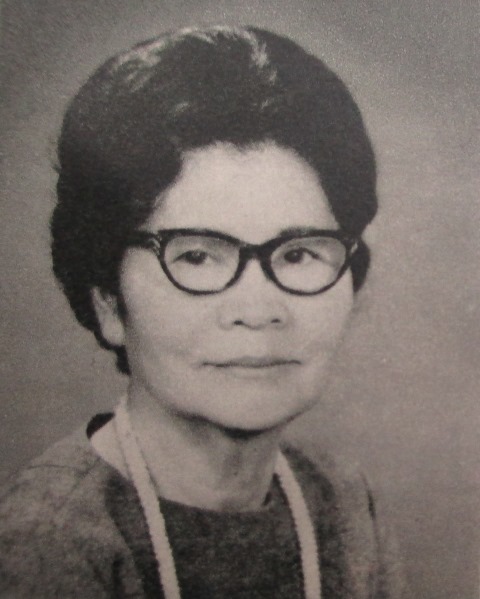
儀間真福(ハワイ沖縄人連合会) 沢岻千恵子(名護市出身)
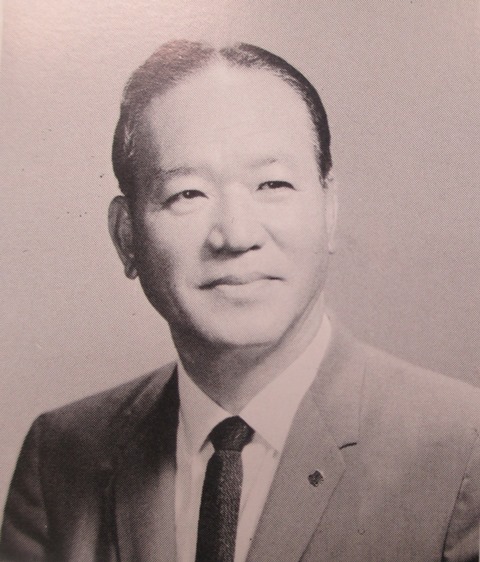

安里貞雄(ハワイ沖縄人連合会) 上江洲智綸
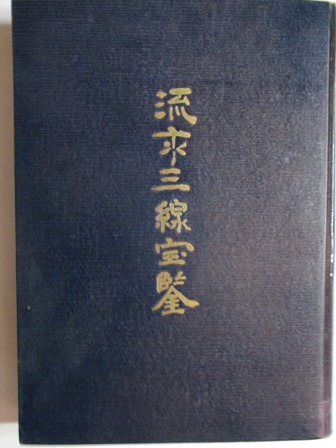

右ー池宮喜輝送別演芸の夕に開演を宣する司会者の仲嶺眞助、ドクトル上原與吉(ホノルル1952年)

布哇ホノルルに於ける三味線祭 焼香する池宮喜輝、左が開教師の山里慈海(1952年2月)
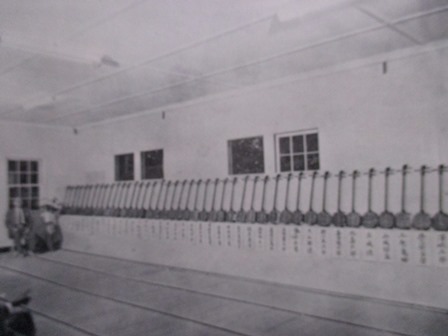
馬哇島ワイルクに於ける三味線展と池宮喜輝(1952年4月)
1954年7月 池宮喜輝『琉球三味線寶鑑』東京沖縄芸能保存会(比嘉良篤)
1955年5月 玉代勢法雲(マッカリー東本願寺住職)逝去/8月 写真業の屋比久孟吉は1953年3月、訪沖し那覇市崇元寺近くにベストソーダ合資会社創立したが、ニューヨーク市に機械購入の途次寄港。/8月 日航機で根路銘房子来布。イオラニ高校で開催の聖公会大会に参加で川平朝申来布。/11月 大浜信泉、国際大学連盟会議出席の後、欧米視察を経てパンナム機で来布、夫人英子は目下アメリカ国務省の招聘でアメリカ滞在中。/12月 高原芳子結婚来布。
1956年4月 ビショップ博物館で初の「琉球古典文化展」。/6月 大伸座長期興行。/8月 MGM社の「八月十五夜の茶屋」の撮影は大成功、同劇に出演して帰国の途にある大映スター根上淳、清川虹子および沢村みち子らの土産話にあったが、芸者(京マチ子)が沖縄舞踊を踊るとき地方になって蛇皮線を弾いた内間ハル子は儀間真福の妹。

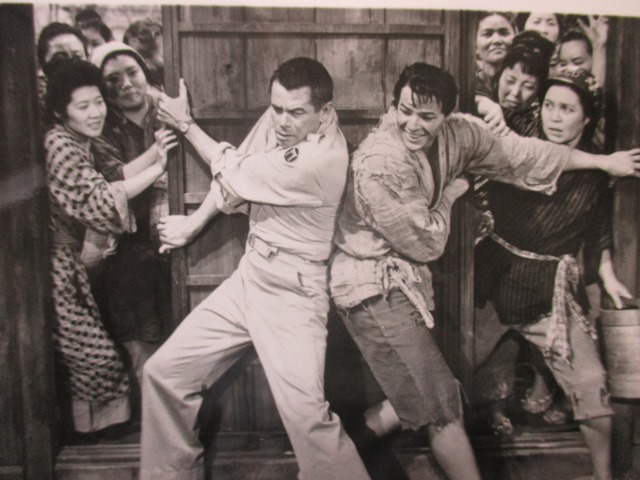

12月 比嘉悦雄はペプシコーラ日本総販売権を獲得し、日本政府の認可で日本飲料株式会社創立。
1958年11月 真境名由康父娘来布
1959年1月 『守礼の光』創刊号(表紙・崎山さん)「写真ー守礼門」、納富浪連子「原子力を平和へ」
1959年6月 ヒロ市の浦崎政致の息子・政一は18ヶ月ぶりで両親見舞いで帰布、1945年8月28日、情報本部附民間人、そしてアメリカ人として最初に東京に入って通訳。琴に東条大将とは死せし約一ヶ月半寝食を共にし世話したので大将から軍服を貰った。
1961年2月 『オキナワグラフ』「沖縄へのアドバイスーホノルル夏の家快談」出席者ー当山哲夫(月刊「市民」社長)、仲嶺真助(2002年7月『仲嶺真助自伝』新報出版)、上原正治(エバーグリン・レストラン社長)、ワーレン比嘉(中央太平洋銀行モイリリ支店長)、安里貞雄(ハワイ沖縄人連合会顧問)、コンラッド赤嶺(元ホノルル日本人青年商工会頭)
1961年3月 『守礼の光』「姉妹都市ー那覇とホノルル」
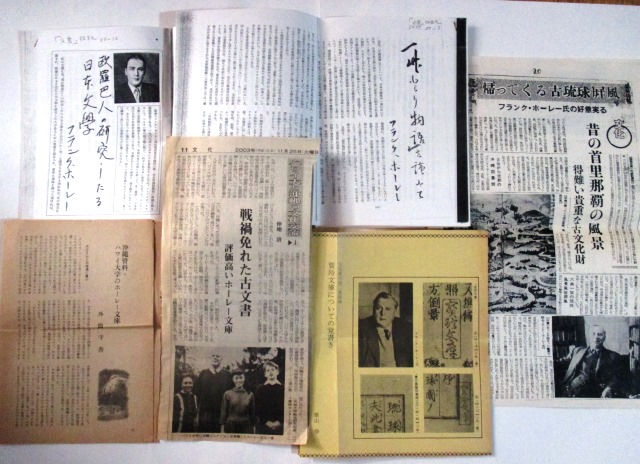
フランク・ホーレー資料
1961年4月 「ホーレー文庫」が布大の手に入り、東西文化センター内に「沖縄文庫」を開設し陳列された。/5月 仲原善忠、比嘉春潮来布
1961年6月 『守礼の光』「東西両文化の新しいかけ橋ーハワイ大学東西文化センター」
1961年8月4日 オバマ・バラク・、ハワイ州ホノルルにある病院(英語版)で生まれる。 実父のバラク・オバマ・シニア(1936年 - 1982年)は、ケニアのニャンゴマ・コゲロ出身(生まれはニャンザ州ラチュオニョ県Kanyadhiang村)のルオ族、母親はカンザス州ウィチタ出身の白人、アン・ダナムである。 父のオバマ・シニアは奨学金を受給していた外国人留学生であった。2人はハワイ大学のロシア語の授業で知り合い、1961年2月2日に周囲の反対を押し切って結婚、 アンは妊娠しており、半年後に、オバマ・ジュニアを出産する。→ウィキペディア
1962年5月 『守礼の光』「立法院議員ハワイを見るーキャラウエイ高等弁務官のあっせんにより、琉球立法院議員の当銘由憲氏、嘉陽宗一氏、真栄城徳松氏、平良幸市氏の一行4人は、このほど6週間にわたり、とこ夏の国ハワイをおとずれました。」
1962年6月 『守礼の光』「ハワイに学ぶ営農の近代化」
1962年6月 宇良啓子がラジオKTRG局より電波に乗せて「沖縄貴族階級の方言で小咄を創作して」放送。
1962年7月 『守礼の光』「ハワイ同胞の警告『あわてて復帰は損』ーハワイ島のヒロ市で、内科と外科の開業医をしているマタヨシ・ゼンコウ博士は、琉球の古い友人や親類の人たちに会うため、このほど23年ぶりに、琉球をおとずれました。」/ヘンリー・ナカソネ(ハワイ大学付属農業試験場)「琉球の園芸の現状と可能性(1)」
1962年10月 『守礼の光』外間政章「1854年に結ばれた琉米条約

1963年 東京ー金城珍栄を囲んで、右から比嘉春潮、比嘉良篤、瀬長良直、當間重剛、金城珍栄、島清、仲原善忠
1963年5月 仲嶺真助、日本人連合協会会長に選出。/10月 琉球国民党総裁の大宜味朝徳は米軍用機で来布。
1963年7月 国際興行の小佐野賢治、ハワイのプリンセス・カイウラニ・ホテル買収□12月、モアナ、サーフライダー2ホテル買収/1974年9月 ワイキキ・シェラトン、マウイ・シェラトン、ロイヤル・ハワイアン3ホテル買収
1949年12月 セブンスデーの屋比久孟吉は平信徒でありながら華府本部から特別伝道者の任命を受けて伝道者の資格で沖縄へ赴くことになった。
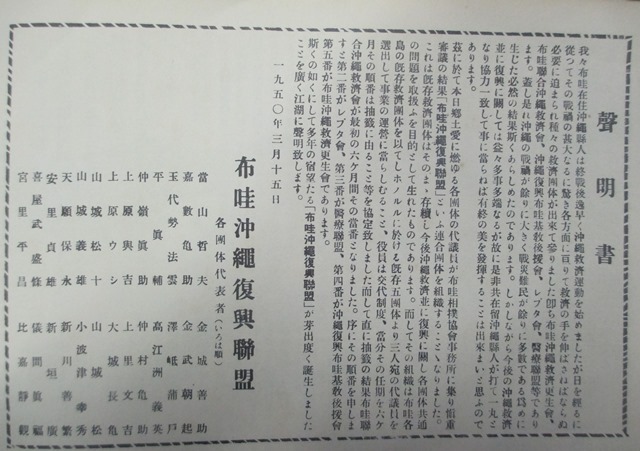
1950年12月 慈光園教団発足ー顧問・小波津幸秀、上原与吉 相談役・伊芸長吉、村岡敏恵、桜田漸、福本元蔵、伊波幸繁、大嶺発市、仲真良樽金、宮城栄吉、大兼久秀一、石川元真、大城太郎、宜野座太郎、伊佐松 名誉教団長・・・与世盛智郎 教団長・山里慈海 理事長・宮里平昌 副・瑞慶覧智珍、仲嶺真助 書記・神谷益栄、上地安宏 会計・真喜志康輝、豊見里友義、監査・宮城麗栄、高良牛、宮城亀盛
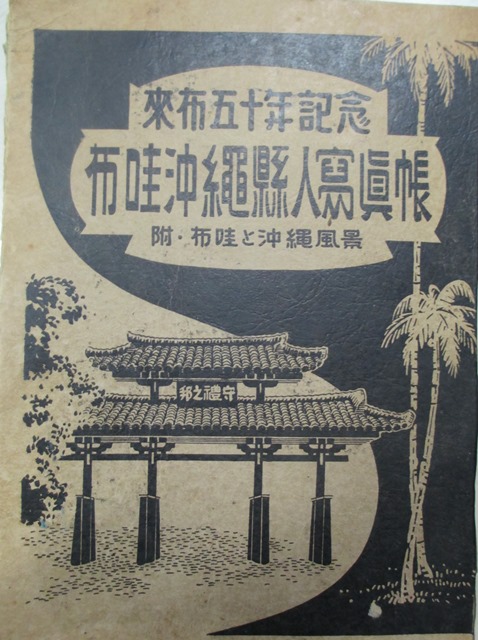
1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』
1951年2月 乙姫劇団が来布公演
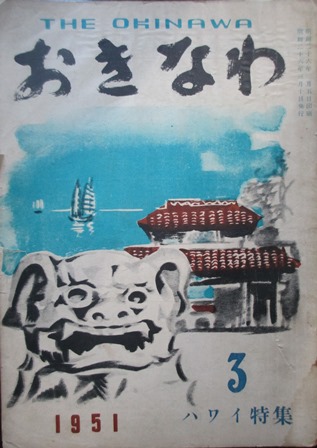
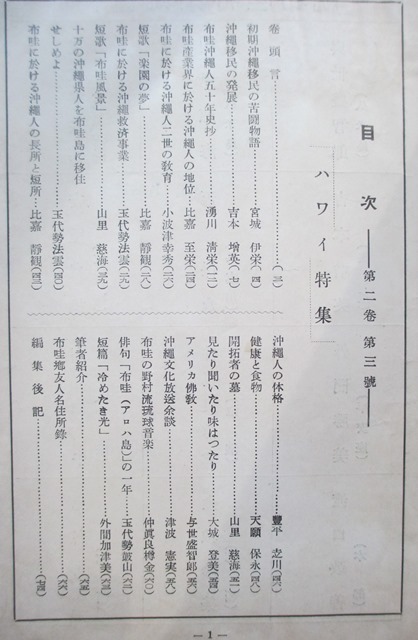
1951年3月 雑誌『おきなわ』<ハワイ特集>
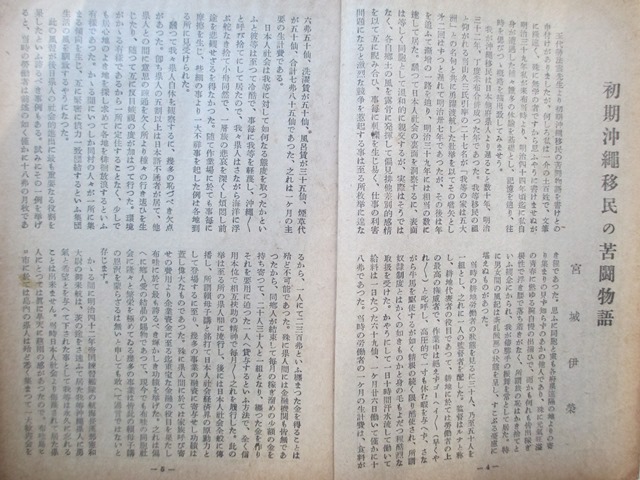
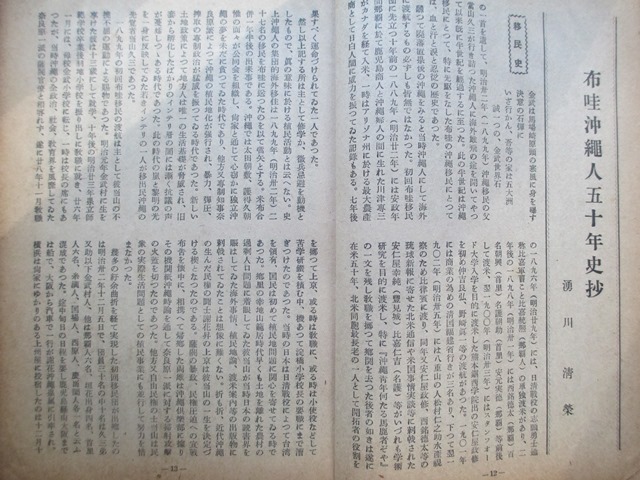
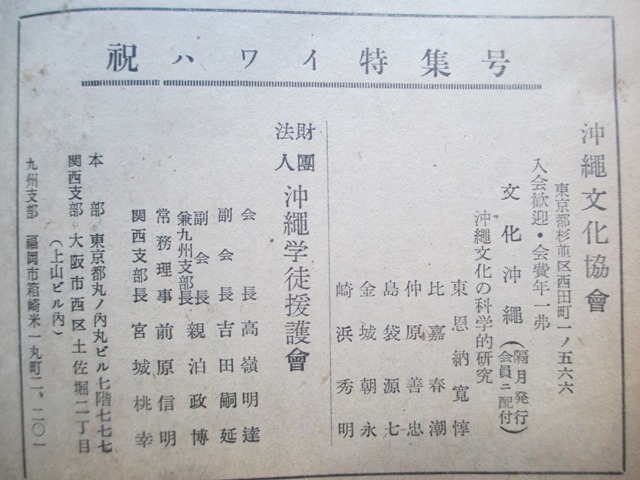
1951年3月 雑誌『おきなわ』湧川清栄「布哇沖縄人五十年史抄」」
1951年3月 雑誌『おきなわ』大城登美「見たり聞いたり味はったり」
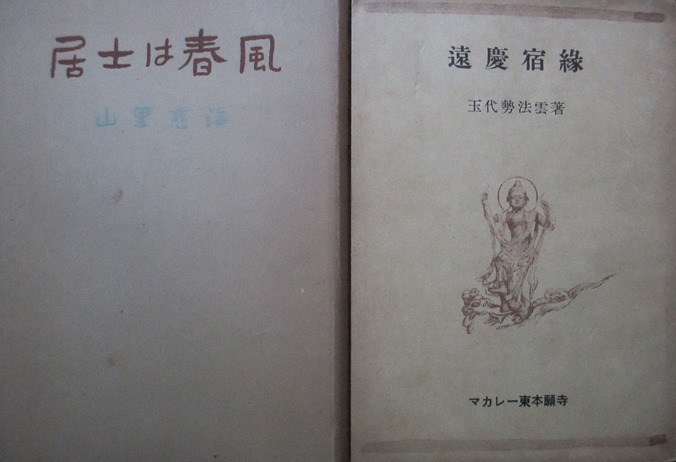
1951年10月 山里慈海『居士は春風』/1953年3月 玉代勢法雲『遠慶宿縁』
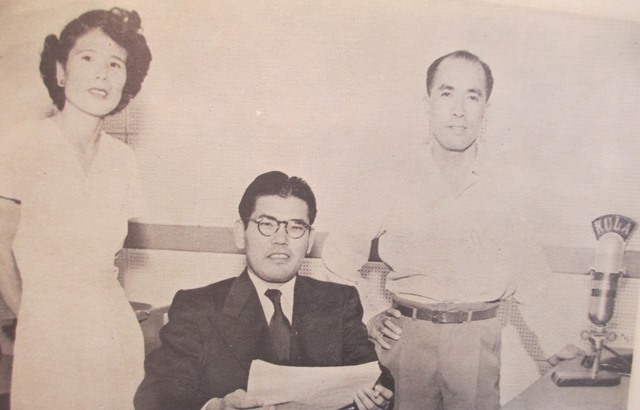
クラ放送局沖縄文化放送部デイゴメロデー/左から大城とみ子、津波實重、山川喜信→1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』
1951年3月 遣米第二回国民指導員来布□志喜屋孝信、大城つる、城間政善、上江洲由道、渡口政義、永山盛三郎、当銘正順、上間亀政、翁長俊郎、大嶺政寛、名渡山愛順、松岡政保、中江実孝、屋田甚助、森敬道、林哲雄、財部つさえ 名渡山愛順「私は終戦後、青年将校の肖像画を五百枚以上も画きました。20数点持参してニューヨークで展覧会を開きますが出来たら帰路にハワイでも開き、又ハワイのカラーも描いて見たいと願っています。」
1951年6月 東京大阪合同琉球芸能団一行8名は渡口政善、金城常盛、上江洲安雄、安谷屋政信の招聘で来布□渡嘉敷守良(我如古安子の叔父)、池宮城喜輝、奥間英五郎、奥間清子、佐久間昌子、渡嘉敷信子、渡嘉敷利秋、島正太郎
1951年6月 南加大学の招聘で琉球音楽を講義しに行く東京沖縄音楽舞踊研究会会長の山内盛彬はツル夫人同伴寄港。
1951年7月 宮里辰彦(第三回沖縄国民指導員)ホノルル郊外ヒッカム飛行場着。此の飛行場は例の日本軍の真珠湾攻撃の際、真っ先に叩かれた所である。
1951年7月 雑誌『おきなわ』<故人追憶特集>
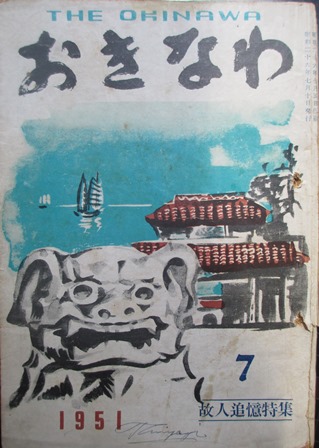
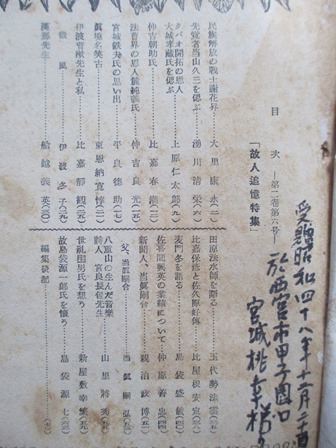
大里康永「民族解放の戦士 謝花昇」/湧川清栄「先覚者 当山久三を偲ぶ」/上原仁太郎「ダバオ開拓の恩人 大城孝蔵氏を偲ぶ」/比嘉春潮「仲吉朝助氏」/仲吉良光「法曹界の恩人 麓純義氏」/平良徳助「宮城鉄夫氏の思い出」/東恩納寛惇「真境名笑古」/比嘉静観「伊波普猷先生と私」/伊波冬子「微風」/船越義英「漢那先生」/玉代勢法雲「田原法水師を語る」/比屋根安定「比嘉保彦と佐久原好傳」/島袋盛敏「麦門冬を語る」/仲原善忠「佐喜間興英の業績について」/親泊政博「新聞人、当眞嗣合」/当眞嗣弘「父、当眞嗣合」/山里将秀「八重山の生んだ音楽詩人 宮良長包先生」/新屋敷幸繁「世礼国男氏を想う」/島袋源七「故 島袋源一郎氏を懐う」/編集後記
1951年8月 ハワイ沖縄連合会発足(理事長・儀間真福)
1953年2月 慈光園で柳宗悦、浜田庄司、バーナード・リーチ講演会「琉球文化を語る」。沖縄紹介映画、幻燈などがあった。
1953年12月 雑誌『おきなわ』№33「ハワイのうつりを語る座談会」
出席者ー平良牛助、玉代勢法雲、比嘉静観、小波津幸秀、金城珍栄、山里慈海、天願保永(おきなわ布晆支局長)
1954年4月 平良リエ子来布/5月 安谷屋政量・琉球工業連合会長「ハワイ第四十九州共進会」に参加で来布。慈光園で「琉球特産品展示会」、6月からハワイ各島で展示する。/12月 金井喜久子来布
1954年4月 雑誌『おきなわ』「ハワイ同胞事業家座談会ー慈光園ホール」
出席者ー仲宗根蒲助(越来)、天願加那(具志川)、上原正義(本部)、伊芸良吉(宜野座)、仲嶺真助(与那原)、山里慈海(久米島)、天願保永(具志川)、平真輔(石川)、長堂嘉吉(真和志)、島袋萬吉、速記ー津嘉山朝吉、瀬長清吉
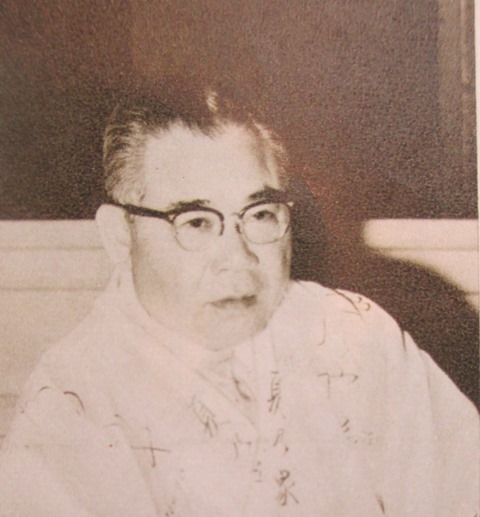
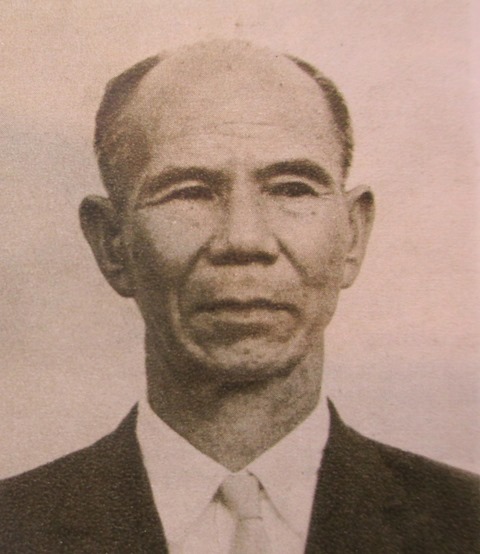
上原正義(エバーグリン・レストラン社長) 天願保永(ハワイ沖縄人連合会)
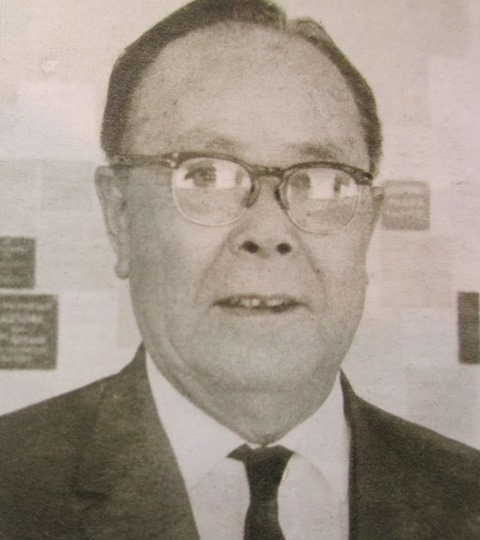
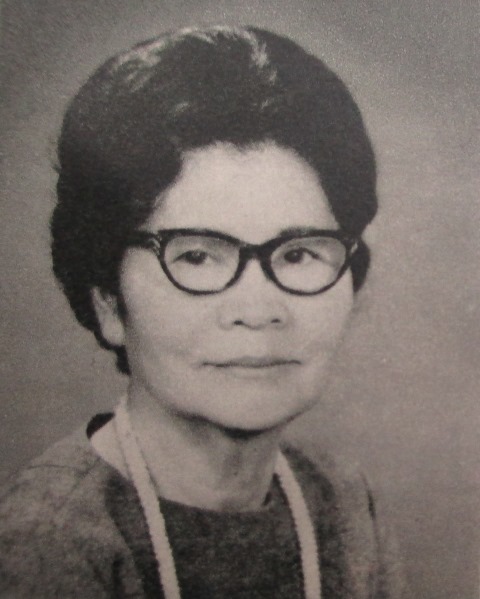
儀間真福(ハワイ沖縄人連合会) 沢岻千恵子(名護市出身)
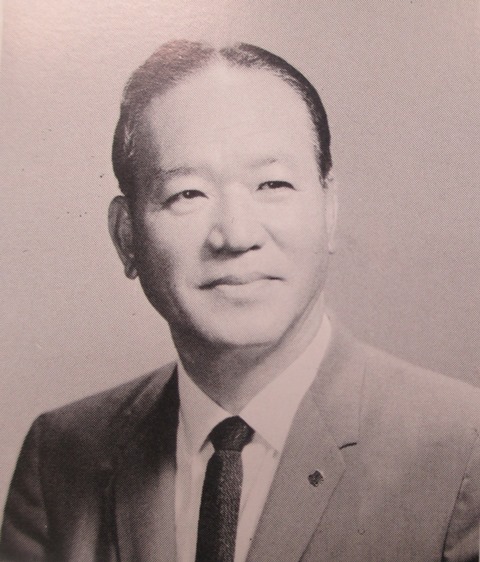

安里貞雄(ハワイ沖縄人連合会) 上江洲智綸
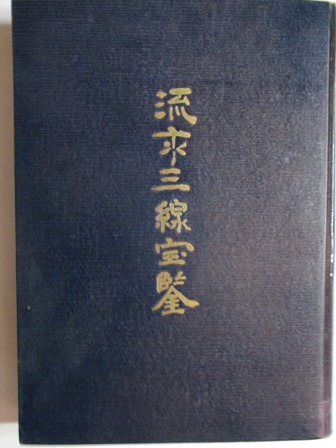

右ー池宮喜輝送別演芸の夕に開演を宣する司会者の仲嶺眞助、ドクトル上原與吉(ホノルル1952年)

布哇ホノルルに於ける三味線祭 焼香する池宮喜輝、左が開教師の山里慈海(1952年2月)
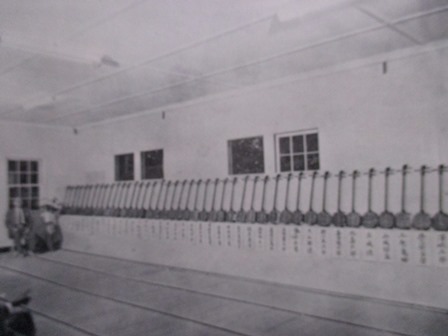
馬哇島ワイルクに於ける三味線展と池宮喜輝(1952年4月)
1954年7月 池宮喜輝『琉球三味線寶鑑』東京沖縄芸能保存会(比嘉良篤)
1955年5月 玉代勢法雲(マッカリー東本願寺住職)逝去/8月 写真業の屋比久孟吉は1953年3月、訪沖し那覇市崇元寺近くにベストソーダ合資会社創立したが、ニューヨーク市に機械購入の途次寄港。/8月 日航機で根路銘房子来布。イオラニ高校で開催の聖公会大会に参加で川平朝申来布。/11月 大浜信泉、国際大学連盟会議出席の後、欧米視察を経てパンナム機で来布、夫人英子は目下アメリカ国務省の招聘でアメリカ滞在中。/12月 高原芳子結婚来布。
1956年4月 ビショップ博物館で初の「琉球古典文化展」。/6月 大伸座長期興行。/8月 MGM社の「八月十五夜の茶屋」の撮影は大成功、同劇に出演して帰国の途にある大映スター根上淳、清川虹子および沢村みち子らの土産話にあったが、芸者(京マチ子)が沖縄舞踊を踊るとき地方になって蛇皮線を弾いた内間ハル子は儀間真福の妹。

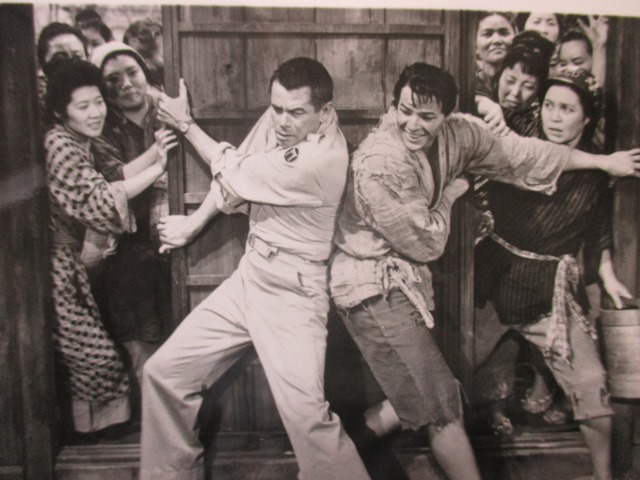

12月 比嘉悦雄はペプシコーラ日本総販売権を獲得し、日本政府の認可で日本飲料株式会社創立。
1958年11月 真境名由康父娘来布
1959年1月 『守礼の光』創刊号(表紙・崎山さん)「写真ー守礼門」、納富浪連子「原子力を平和へ」
1959年6月 ヒロ市の浦崎政致の息子・政一は18ヶ月ぶりで両親見舞いで帰布、1945年8月28日、情報本部附民間人、そしてアメリカ人として最初に東京に入って通訳。琴に東条大将とは死せし約一ヶ月半寝食を共にし世話したので大将から軍服を貰った。
1961年2月 『オキナワグラフ』「沖縄へのアドバイスーホノルル夏の家快談」出席者ー当山哲夫(月刊「市民」社長)、仲嶺真助(2002年7月『仲嶺真助自伝』新報出版)、上原正治(エバーグリン・レストラン社長)、ワーレン比嘉(中央太平洋銀行モイリリ支店長)、安里貞雄(ハワイ沖縄人連合会顧問)、コンラッド赤嶺(元ホノルル日本人青年商工会頭)
1961年3月 『守礼の光』「姉妹都市ー那覇とホノルル」
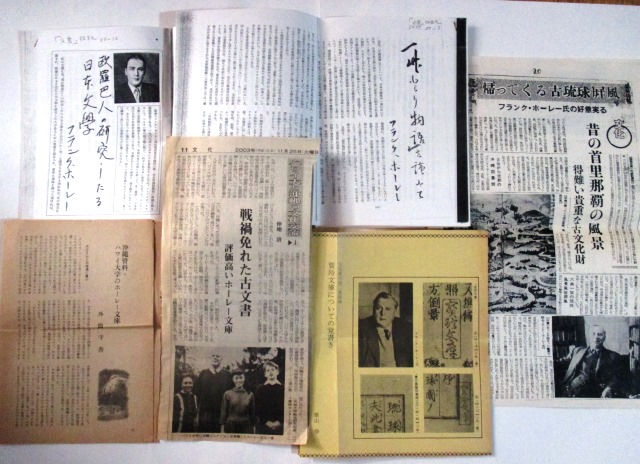
フランク・ホーレー資料
1961年4月 「ホーレー文庫」が布大の手に入り、東西文化センター内に「沖縄文庫」を開設し陳列された。/5月 仲原善忠、比嘉春潮来布
1961年6月 『守礼の光』「東西両文化の新しいかけ橋ーハワイ大学東西文化センター」
1961年8月4日 オバマ・バラク・、ハワイ州ホノルルにある病院(英語版)で生まれる。 実父のバラク・オバマ・シニア(1936年 - 1982年)は、ケニアのニャンゴマ・コゲロ出身(生まれはニャンザ州ラチュオニョ県Kanyadhiang村)のルオ族、母親はカンザス州ウィチタ出身の白人、アン・ダナムである。 父のオバマ・シニアは奨学金を受給していた外国人留学生であった。2人はハワイ大学のロシア語の授業で知り合い、1961年2月2日に周囲の反対を押し切って結婚、 アンは妊娠しており、半年後に、オバマ・ジュニアを出産する。→ウィキペディア
1962年5月 『守礼の光』「立法院議員ハワイを見るーキャラウエイ高等弁務官のあっせんにより、琉球立法院議員の当銘由憲氏、嘉陽宗一氏、真栄城徳松氏、平良幸市氏の一行4人は、このほど6週間にわたり、とこ夏の国ハワイをおとずれました。」
1962年6月 『守礼の光』「ハワイに学ぶ営農の近代化」
1962年6月 宇良啓子がラジオKTRG局より電波に乗せて「沖縄貴族階級の方言で小咄を創作して」放送。
1962年7月 『守礼の光』「ハワイ同胞の警告『あわてて復帰は損』ーハワイ島のヒロ市で、内科と外科の開業医をしているマタヨシ・ゼンコウ博士は、琉球の古い友人や親類の人たちに会うため、このほど23年ぶりに、琉球をおとずれました。」/ヘンリー・ナカソネ(ハワイ大学付属農業試験場)「琉球の園芸の現状と可能性(1)」
1962年10月 『守礼の光』外間政章「1854年に結ばれた琉米条約

1963年 東京ー金城珍栄を囲んで、右から比嘉春潮、比嘉良篤、瀬長良直、當間重剛、金城珍栄、島清、仲原善忠
1963年5月 仲嶺真助、日本人連合協会会長に選出。/10月 琉球国民党総裁の大宜味朝徳は米軍用機で来布。
1963年7月 国際興行の小佐野賢治、ハワイのプリンセス・カイウラニ・ホテル買収□12月、モアナ、サーフライダー2ホテル買収/1974年9月 ワイキキ・シェラトン、マウイ・シェラトン、ロイヤル・ハワイアン3ホテル買収
「ふりむん随筆 未完成公共学(一)」□私は自由の月である。フリームーンである。現在は順天堂大学医科大学教授で英語と文学(国語漢文を含む)の主任教授であるが、学生はわたしのことを「シュセキキョウジュ」と呼んで親しんだりこわがったりしているが「首席教授」の意味だが「酒席狂需」の意味だか、忙しくて辞書を引く暇がないので自分でもよくわからない。どんな辞書を引いたらよいか沖縄隋一の学聖否全日本でも無類の碩学 東恩納寛惇(有名人敬称略、御免)に質してからゆっくり調べることにする。
昔から「金持ち暇無し」と言う通り、事実私は暇がないのである。アルバイトとして桐葉予備校、文京予備校、国際予備校の3校の英語主任も兼務して居り、日本英学院で英文学も講じて居り、丁度目下那覇の大宝館で上映中のグレイアム・グリーンの「落ちた偶像」の原作を英語で講義中である。ささやかながら自分の石川英語学院も手離せない。二つの出版会社の編集顧問も引き受けている関係で原稿依頼も多い。
「ありが英語小や、ゆくしぬうふさぬ、わー英語小けんそーれー」と日夜歌っている身になってごらんなさい。英語ニコヨンはつらいです。ウランダ口アチョールドウは悲しいです。「大和口使て、ウランダ口ならーち、唐書物読むる沖縄二才我身や」と大日本帝国はなやかなりし頃、那覇の一角、中島小掘のほとりでき門の望に明け暮れる母に琉歌を送ってなぐさめた、我が厚顔の青年の日が、昨日や今日のように思い出されて胸がうずく。「日本語も英語も知らぬアンマーはワッター次郎を故郷に待つ」と涙ながらに和琉ちゃんぼの忍び泣きに異郷滞在の不孝の罪を心にわびたのもその頃である。
「ふりむん随筆 未完成公共学(七)」□「大傷繃帯日」も私の予言である。大東亜戦争が天皇の名で宣せられ「大詔奉載日」が制定されるや、私が愛国の至情から国難を予言した)「大傷繃帯日」は物の見事に的中した敗戦直後(終戦という言葉でごまかすな)伊波普猷の家で会ったとき松本三益に「石川先生は徹底的に敗戦論者でしたね」と妙なことを覚えられていて、比嘉春潮も「そうだったか」と私を見直した。「そてつ(蘇鉄)地獄」と沖縄の窮乏をなげき、「ブーサー極楽」と故郷の退廃を憂えていたとき「人口過剰の無人島」と人物缺乏を痛嘆した40年前の私の寸鉄は今日の日本に対する予言となって実現している。「天ぴ大和口」という奇語も私の発明だったかどうか忘れたが、今沖縄ではどんな標準はずれの標準語を使って金をもうけ、恋を語って居るであろうか。
キヤメルを鹿小と呼び、ラッキー・ストライキを旗小と称し、フィリップモリスを黒ん坊と唱えている由、私はふるさと人の語感を頼もしく思い、既に天下をのんでいるその意気に敬意を表して頭を下げる。パチンコと競輪にうつつをぬかして夢中になっている知性の無い今の大和民族にはそんな意気やゆとりのかけらも無い。一度は政治的に亡んだこの国は、今精神的亡国の寸前にある。だからいつまでもまずい煙草をのまされているのだ。煙草から立ち登る煙にすらレジスタンスをしめす気力がないのである。
「竹島は明らかに韓国領土だ。その証拠にはあの島にはパチンコ屋は一軒も無い」と李承晩大統領にすらなめられているていたらくである。日本の大学生はパチンコをしたついでに学校に通う。李承晩ラインの故智にならったわけでもあるまいが、沖縄の周囲に精神的愛郷の比嘉秀平ラインを張りめぐらして人生冒涜の亡国遊戯パチンコの神聖なる沖縄侵入を断固排していると聞く我が同僚沖縄民政府主席比嘉秀平の明智と良しきと勇気に対して在京沖縄人全体ではなく私一人を代表して厚く謝辞を述べて益々その健闘を祈らずには居られない。
「ふりむん随筆 未完成公共学(九)」□(略)当間重剛を語る門外不出の材料も一中、三高、京大、司法官時代と沢山ある。唯彼に一つの欠点がある。それは私に話しかけるとき、パリー語や那覇語を使わないで最初大和口を使うことである。それはよろしくない。今度彼が東京に出て来たら、大いに叱ってやろうと思っている。飲む前に叱るのだ。「石川正通 当間重剛を叱るの図」これは素敵な画題だ。山田真山の麗筆に触れれば雪舟、応挙の塁を摩し、金城安太郎の絹布に上れば、歌麿、写楽を彷彿させ、嘉数能愛のパレットに踊っては関屋敬次の風格と画風を再現し大城皓也のカンバスに現れては曽太郎、龍三郎の域に迫り、渡嘉敷唯夫の画用紙に捕らわれは、近藤日出造、池部均をしのぐ傑作となr山里永吉の画板に乗ればピカソかマチスかマボーあたりを顔色なからしめる旋風を起こすであろう。更にまた瀬名波良持の紅型に染めぬかれれば鳥羽僧正の遺風を伝えて永久に博物館を飾る国宝に指定されるであろう。
波之上神社の鳥居と那覇市役所の馬鹿塔と当間重禄の医者の看板を那覇の三大不用物と指摘したのは崎山嗣朝の余りにも有名な警句で政争の激しかった大正末期の名残を留めて如何にも泊人らしい気概に満ちている。和辻哲郎の「偶像再建」を読むまでもなくヨーロッパの中世思想に抗して興った近代ヨーロッパのアイコノクラズム(偶像破壊)の思想も今日では思想史の数頁をかろうじて占める哲学の足跡に過ぎない。わがふるさとも偶像再建の機運に近づきつつあることと思う。波之上神社の鳥居はカンプーサバチでどうなったか知らないが、前よりも大きな鳥居を建てたらどうだろう。もし神社が残っていたら。それは神の家の門として建ててもやがては那覇の風物詩の一つとなるであろうから。
昔から「金持ち暇無し」と言う通り、事実私は暇がないのである。アルバイトとして桐葉予備校、文京予備校、国際予備校の3校の英語主任も兼務して居り、日本英学院で英文学も講じて居り、丁度目下那覇の大宝館で上映中のグレイアム・グリーンの「落ちた偶像」の原作を英語で講義中である。ささやかながら自分の石川英語学院も手離せない。二つの出版会社の編集顧問も引き受けている関係で原稿依頼も多い。
「ありが英語小や、ゆくしぬうふさぬ、わー英語小けんそーれー」と日夜歌っている身になってごらんなさい。英語ニコヨンはつらいです。ウランダ口アチョールドウは悲しいです。「大和口使て、ウランダ口ならーち、唐書物読むる沖縄二才我身や」と大日本帝国はなやかなりし頃、那覇の一角、中島小掘のほとりでき門の望に明け暮れる母に琉歌を送ってなぐさめた、我が厚顔の青年の日が、昨日や今日のように思い出されて胸がうずく。「日本語も英語も知らぬアンマーはワッター次郎を故郷に待つ」と涙ながらに和琉ちゃんぼの忍び泣きに異郷滞在の不孝の罪を心にわびたのもその頃である。
「ふりむん随筆 未完成公共学(七)」□「大傷繃帯日」も私の予言である。大東亜戦争が天皇の名で宣せられ「大詔奉載日」が制定されるや、私が愛国の至情から国難を予言した)「大傷繃帯日」は物の見事に的中した敗戦直後(終戦という言葉でごまかすな)伊波普猷の家で会ったとき松本三益に「石川先生は徹底的に敗戦論者でしたね」と妙なことを覚えられていて、比嘉春潮も「そうだったか」と私を見直した。「そてつ(蘇鉄)地獄」と沖縄の窮乏をなげき、「ブーサー極楽」と故郷の退廃を憂えていたとき「人口過剰の無人島」と人物缺乏を痛嘆した40年前の私の寸鉄は今日の日本に対する予言となって実現している。「天ぴ大和口」という奇語も私の発明だったかどうか忘れたが、今沖縄ではどんな標準はずれの標準語を使って金をもうけ、恋を語って居るであろうか。
キヤメルを鹿小と呼び、ラッキー・ストライキを旗小と称し、フィリップモリスを黒ん坊と唱えている由、私はふるさと人の語感を頼もしく思い、既に天下をのんでいるその意気に敬意を表して頭を下げる。パチンコと競輪にうつつをぬかして夢中になっている知性の無い今の大和民族にはそんな意気やゆとりのかけらも無い。一度は政治的に亡んだこの国は、今精神的亡国の寸前にある。だからいつまでもまずい煙草をのまされているのだ。煙草から立ち登る煙にすらレジスタンスをしめす気力がないのである。
「竹島は明らかに韓国領土だ。その証拠にはあの島にはパチンコ屋は一軒も無い」と李承晩大統領にすらなめられているていたらくである。日本の大学生はパチンコをしたついでに学校に通う。李承晩ラインの故智にならったわけでもあるまいが、沖縄の周囲に精神的愛郷の比嘉秀平ラインを張りめぐらして人生冒涜の亡国遊戯パチンコの神聖なる沖縄侵入を断固排していると聞く我が同僚沖縄民政府主席比嘉秀平の明智と良しきと勇気に対して在京沖縄人全体ではなく私一人を代表して厚く謝辞を述べて益々その健闘を祈らずには居られない。
「ふりむん随筆 未完成公共学(九)」□(略)当間重剛を語る門外不出の材料も一中、三高、京大、司法官時代と沢山ある。唯彼に一つの欠点がある。それは私に話しかけるとき、パリー語や那覇語を使わないで最初大和口を使うことである。それはよろしくない。今度彼が東京に出て来たら、大いに叱ってやろうと思っている。飲む前に叱るのだ。「石川正通 当間重剛を叱るの図」これは素敵な画題だ。山田真山の麗筆に触れれば雪舟、応挙の塁を摩し、金城安太郎の絹布に上れば、歌麿、写楽を彷彿させ、嘉数能愛のパレットに踊っては関屋敬次の風格と画風を再現し大城皓也のカンバスに現れては曽太郎、龍三郎の域に迫り、渡嘉敷唯夫の画用紙に捕らわれは、近藤日出造、池部均をしのぐ傑作となr山里永吉の画板に乗ればピカソかマチスかマボーあたりを顔色なからしめる旋風を起こすであろう。更にまた瀬名波良持の紅型に染めぬかれれば鳥羽僧正の遺風を伝えて永久に博物館を飾る国宝に指定されるであろう。
波之上神社の鳥居と那覇市役所の馬鹿塔と当間重禄の医者の看板を那覇の三大不用物と指摘したのは崎山嗣朝の余りにも有名な警句で政争の激しかった大正末期の名残を留めて如何にも泊人らしい気概に満ちている。和辻哲郎の「偶像再建」を読むまでもなくヨーロッパの中世思想に抗して興った近代ヨーロッパのアイコノクラズム(偶像破壊)の思想も今日では思想史の数頁をかろうじて占める哲学の足跡に過ぎない。わがふるさとも偶像再建の機運に近づきつつあることと思う。波之上神社の鳥居はカンプーサバチでどうなったか知らないが、前よりも大きな鳥居を建てたらどうだろう。もし神社が残っていたら。それは神の家の門として建ててもやがては那覇の風物詩の一つとなるであろうから。
編輯発行兼印刷人・馬上太郎
月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳
表紙ー崇元寺本堂
巻頭言 ”舟楫を以て萬國の津梁と為し、異産至寶十方に充満せり云々”の雄渾無比なる快文字の銘せられたる梵鐘が、その昔掛着せられたと云ふ首里城内に此の程安置された。古の我が琉球國は、唇歯輔車の仲に在る日本、支那は固より、北は三韓より、南は遠く安南、暹羅、満刺加、爪哇蘇門答刺等の諸域を比隣の如くに往来して、その異産至寶を将来し、その諸種の文化を鍾聚することに力めた。此の雄偉勁抜なる気魄を有したればこそ、洋中の蕞爾(さいじ)たる一小王国たるに拘わらず、清新溌剌たる気分の充満し、闊達にして高雅なる趣致の横溢せる藝術乃至文化を産出することも出来たのであった。
高遠なる大東亜共栄の理想郷建設を豫示するが如き銘文の刻せられたる梵鐘が還元したるを機として、歪曲せられざりし我が民族の本来の面目に立ち帰り、皇国の新進路に向かって活溌溌地の大活動をなさねばならぬ。それに付けても吾人は、郷土史家を糾合して完全なる一大郷土史の編成を期せんことを敢えて提言し度い。従来幾多の郷土史はあれども、或物は忠実なる史料の羅列に過ぎず、或物は簡明なるが如きも粗雑に失するの嫌がある。されば衆智に依って整然たる、学問的な信憑すべき歴史を大成することは今日の急務ではなかろうか。
大舛大尉に就いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤野憲夫・・・・2
大舛大尉を偲ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・糸洲朝松・・・・3
秋夜想出せる詩歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鷺泉・・・・・・・・6
首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11
寒露漫筆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊野波石逕・・・・15
病暦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・18
新発足したる商工経済会に就て・・・・・・・・・・護得久朝章・・・・・20
勤労奉仕(○○造船所にて)・・・・・・・・・・・・・・徳田安俊・・・・・・21
佛領印度支那旅行記(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・與儀喜宣・・・・・23
梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26
無縁墓を訪ねて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐渡山安治①・・28
僕の周囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・徳村静農・・・30
四美具はる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍・・・34
伊豆味・瀬底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉國夕照・・37
編輯後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍
舟楫を萬國の津梁と為す 本来の面目に帰り 大舛大尉に続かん
1942年1月ー月刊『文化沖縄』第3巻第1号 編輯発行兼印刷人・本山豊
月刊文化沖縄社ー那覇市久米町1ノ32 東京支社ー東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局ーパラオ島コロール町 印刷所・向春商会印刷部ー那覇市通堂町2ノ1
巻頭歌「進め一億 火の玉だ!!」
戦捷の感激を生かせ!!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
佐藤惣之助①「決意」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
まこと、戦ふべき時、遂に来る/満を持して、進もう、戦をう/この光輝ある歴史のまへに/この穢れなき皇土のうへに/死すべき命のいかに幸ひなるかな/歓べよ、われら、死し徹して/今ぞ、あらゆる理念を超克し/暴戻なる米英に宣戦しつつ/血と血はたぎり、歯と歯はふるふ/この攻防に於て、究局に進んで/ただ肉を斬らして骨を斬れ/骨を劈いて隋を踏みにじれ/悠然、爆死は桜のちるが如く/笑ってみ國に殉ずることなり/死なんかな、いざ、あくまでも/われらが持場の巨弾にゆらぐまで/必勝の決意に全我の生活を緊め/敢然と進もう、戦をう/つばさは天に、戦艦は海に/見よ、鉄壁の堅陣を有す/われらその奥底の魂に位置し/その凄まじき実相をつかんで/いかなる困苦も来らば来れ/血と血をつなぎ、骨と骨を組み/激しい一億の心臓を堵して/輝く日本の新歴史を作ろう!(宣戦布告の日)
①佐藤惣之助
さとうそうのすけ
[生]1890.12.3. 川崎[没]1942.5.15. 東京
詩人。正規の学業につかず少年の頃から佐藤紅緑の門に入って俳句を学び,18~19歳頃から千家元麿,福士幸次郎らと交友。『白樺』派の影響を受けた詩集『正義の兜』 (1916) ,『狂へる歌』 (17) では人道主義的詩風を示した。→コトバンク
蔵原伸二郎②「大詔を拝し奉りて」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
大詔を拝し奉りて/雀躍勇途にのぼる/一億の草莾/みたみわれら/今ぞ/一天に雲なき/磐空を仰ぎて征かん/ああ 早くも/天涯に敵なく/七つの海に敵なきが如し/見よ わが海鷲潜艦のゆくところ/身命を祖国に捧げ/心を天に奉るもの/歴史の光栄に生きるもの/開戦劈頭たちまち/敵の慴伏を見たり/南海におどれるわれらが血よ/大海原に羽搏くわれらが魂よ/熱河熱山を征くわれらが志よ/神武天皇の向ふところ/烏合百万の敵何するものぞ/敵国よ/更に大軍を擁して来れかし/敵いよいよ多くして/同胞殉国の志いよいよ固く/われらただ/大みことのりを奉じ/最後の一人といへども/闘ひ抜かんのみ
②蔵原伸二郎 くらはら-しんじろう
1899-1965 昭和時代の詩人。
明治32年9月4日生まれ。蔵原惟人の従兄(いとこ)。萩原朔太郎の「青猫」の影響をうけて詩作をはじめ,昭和14年第1詩集「東洋の満月」を出版。16年「四季」同人。昭和40年3月16日死去。65歳。熊本県出身。慶大卒。本名は惟賢(これかた)。詩集に「乾いた道」「岩魚(いわな)」など,詩論集に「東洋の詩魂」。コトバンク
地方文化と生活文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北川鉄夫・・4
戦争手帳「戦争と通信基地」「ボルネオに日本人島」「戦略と天気象」4ー8
「布哇の邦人」「ビール罎」「屠れ!米英 われ等の敵だ!」
本県女教師に望む(上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・米國三郎・・・6
1人1語・戦争と文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田徳太郎・・・9
戦捷 笑唄話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9-10
新体制は遊女より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渡口精鴻・・・10
「この一戦 何がなんでもやり抜くぞ!!」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
島尻郡教育会修養部「教育振興座談会」於 昭和会館・・・・・・・・・・・・・・11
見たか戦果 知ったか底力 進め! 一億火の玉だ!」・・・・・・・・・・・・・・13
連載 琉球記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一・・・14
情報局で壁新聞「空襲に血走るな」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
偉大なる一人の詩人(伊東静雄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新垣淑明・・・16
豆戦艦ABCD陣「比律賓群島」「ミンダナオ島ダヴアオ」「香港」・・・・・・・・・・・16-23
「ウエーキ島」「ペナン島」「グアム島」「ミツドウエイ島」「米の航空機生産高」
ブラジル風景=サン・パウロ=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤清太郎・・・18
敵性撃滅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土岐善麿③・・・19
ルーズヴエルト一チャーチルのことにあらず世界の敵性を一挙に屠れ
ルーズヴエルトよ汝が頼みし戦艦は一瞬にして「顛覆」をせり
チャーチルよ頼みがたなきアメリカを頼みしことを国民に謝せ
世界戦争の煽動者たる「光栄」をアメリカ大統領よ墓に持ちてゆけ
忍び難きを忍びしはただ大東亜の平和のためと思ひ知るべし
③土岐善麿
歌人・国文学者。東京生。哀果と号する。早大卒。中学時代金子薫園の「白菊会」に参加し、大学時代は窪田空穂・若山牧水の影響を受けた。のち石川啄木と知り合い、二人で生活派短歌の基礎を作った功績は大きい。学士院賞受賞。文学博士。芸術院会員。昭和55年(1980)歿、94才。→コトバンク
琉球の古来工芸品(上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・沖縄県工業指導所・・・20
子供の文化を覗く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・亀谷長輝・・・・22
雷火・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・太田水<穏ママ>・・・・・24
天つちの神もおどろけ巌ゆるぐ大き憤りのおほみことのり
しのびきて今ぞ宣らすと仰せ給ふ畏こさに沁みてわれは泣かるる
電撃機雷火を吐くとみる否やとどろきをあげて艦くつがへる
ふきあがる焔のなかに蒼白の照らし出されたる顔おもひ見む
馬来半島クワンタン沖のたたかひに覆へりたるは艦ばかりは
「尽せ総力 護れよ東亜」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
戦時体制下の沖縄/1942年1月ー月刊『文化沖縄』第3巻第1号
和光同塵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本山裕児・・・26
短篇小説「馬」金城安太郎・絵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新垣庸一・・・27
祝 皇軍之大勝 祝 御武運長久 輝やかし大東亜戦勝利の朝謹壽
一億進軍の春 皇紀二千六百二年正月・・・・・月刊 文化沖縄社社員一同
大東亜戦戦果日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳
表紙ー崇元寺本堂
巻頭言 ”舟楫を以て萬國の津梁と為し、異産至寶十方に充満せり云々”の雄渾無比なる快文字の銘せられたる梵鐘が、その昔掛着せられたと云ふ首里城内に此の程安置された。古の我が琉球國は、唇歯輔車の仲に在る日本、支那は固より、北は三韓より、南は遠く安南、暹羅、満刺加、爪哇蘇門答刺等の諸域を比隣の如くに往来して、その異産至寶を将来し、その諸種の文化を鍾聚することに力めた。此の雄偉勁抜なる気魄を有したればこそ、洋中の蕞爾(さいじ)たる一小王国たるに拘わらず、清新溌剌たる気分の充満し、闊達にして高雅なる趣致の横溢せる藝術乃至文化を産出することも出来たのであった。
高遠なる大東亜共栄の理想郷建設を豫示するが如き銘文の刻せられたる梵鐘が還元したるを機として、歪曲せられざりし我が民族の本来の面目に立ち帰り、皇国の新進路に向かって活溌溌地の大活動をなさねばならぬ。それに付けても吾人は、郷土史家を糾合して完全なる一大郷土史の編成を期せんことを敢えて提言し度い。従来幾多の郷土史はあれども、或物は忠実なる史料の羅列に過ぎず、或物は簡明なるが如きも粗雑に失するの嫌がある。されば衆智に依って整然たる、学問的な信憑すべき歴史を大成することは今日の急務ではなかろうか。
大舛大尉に就いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤野憲夫・・・・2
大舛大尉を偲ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・糸洲朝松・・・・3
秋夜想出せる詩歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鷺泉・・・・・・・・6
首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11
寒露漫筆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊野波石逕・・・・15
病暦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉榮眞・・・・・・18
新発足したる商工経済会に就て・・・・・・・・・・護得久朝章・・・・・20
勤労奉仕(○○造船所にて)・・・・・・・・・・・・・・徳田安俊・・・・・・21
佛領印度支那旅行記(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・與儀喜宣・・・・・23
梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26
無縁墓を訪ねて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐渡山安治①・・28
僕の周囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・徳村静農・・・30
四美具はる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍・・・34
伊豆味・瀬底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉國夕照・・37
編輯後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新崎盛珍
舟楫を萬國の津梁と為す 本来の面目に帰り 大舛大尉に続かん
1942年1月ー月刊『文化沖縄』第3巻第1号 編輯発行兼印刷人・本山豊
月刊文化沖縄社ー那覇市久米町1ノ32 東京支社ー東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局ーパラオ島コロール町 印刷所・向春商会印刷部ー那覇市通堂町2ノ1
巻頭歌「進め一億 火の玉だ!!」
戦捷の感激を生かせ!!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
佐藤惣之助①「決意」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
まこと、戦ふべき時、遂に来る/満を持して、進もう、戦をう/この光輝ある歴史のまへに/この穢れなき皇土のうへに/死すべき命のいかに幸ひなるかな/歓べよ、われら、死し徹して/今ぞ、あらゆる理念を超克し/暴戻なる米英に宣戦しつつ/血と血はたぎり、歯と歯はふるふ/この攻防に於て、究局に進んで/ただ肉を斬らして骨を斬れ/骨を劈いて隋を踏みにじれ/悠然、爆死は桜のちるが如く/笑ってみ國に殉ずることなり/死なんかな、いざ、あくまでも/われらが持場の巨弾にゆらぐまで/必勝の決意に全我の生活を緊め/敢然と進もう、戦をう/つばさは天に、戦艦は海に/見よ、鉄壁の堅陣を有す/われらその奥底の魂に位置し/その凄まじき実相をつかんで/いかなる困苦も来らば来れ/血と血をつなぎ、骨と骨を組み/激しい一億の心臓を堵して/輝く日本の新歴史を作ろう!(宣戦布告の日)
①佐藤惣之助
さとうそうのすけ
[生]1890.12.3. 川崎[没]1942.5.15. 東京
詩人。正規の学業につかず少年の頃から佐藤紅緑の門に入って俳句を学び,18~19歳頃から千家元麿,福士幸次郎らと交友。『白樺』派の影響を受けた詩集『正義の兜』 (1916) ,『狂へる歌』 (17) では人道主義的詩風を示した。→コトバンク
蔵原伸二郎②「大詔を拝し奉りて」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
大詔を拝し奉りて/雀躍勇途にのぼる/一億の草莾/みたみわれら/今ぞ/一天に雲なき/磐空を仰ぎて征かん/ああ 早くも/天涯に敵なく/七つの海に敵なきが如し/見よ わが海鷲潜艦のゆくところ/身命を祖国に捧げ/心を天に奉るもの/歴史の光栄に生きるもの/開戦劈頭たちまち/敵の慴伏を見たり/南海におどれるわれらが血よ/大海原に羽搏くわれらが魂よ/熱河熱山を征くわれらが志よ/神武天皇の向ふところ/烏合百万の敵何するものぞ/敵国よ/更に大軍を擁して来れかし/敵いよいよ多くして/同胞殉国の志いよいよ固く/われらただ/大みことのりを奉じ/最後の一人といへども/闘ひ抜かんのみ
②蔵原伸二郎 くらはら-しんじろう
1899-1965 昭和時代の詩人。
明治32年9月4日生まれ。蔵原惟人の従兄(いとこ)。萩原朔太郎の「青猫」の影響をうけて詩作をはじめ,昭和14年第1詩集「東洋の満月」を出版。16年「四季」同人。昭和40年3月16日死去。65歳。熊本県出身。慶大卒。本名は惟賢(これかた)。詩集に「乾いた道」「岩魚(いわな)」など,詩論集に「東洋の詩魂」。コトバンク
地方文化と生活文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北川鉄夫・・4
戦争手帳「戦争と通信基地」「ボルネオに日本人島」「戦略と天気象」4ー8
「布哇の邦人」「ビール罎」「屠れ!米英 われ等の敵だ!」
本県女教師に望む(上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・米國三郎・・・6
1人1語・戦争と文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田徳太郎・・・9
戦捷 笑唄話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9-10
新体制は遊女より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渡口精鴻・・・10
「この一戦 何がなんでもやり抜くぞ!!」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
島尻郡教育会修養部「教育振興座談会」於 昭和会館・・・・・・・・・・・・・・11
見たか戦果 知ったか底力 進め! 一億火の玉だ!」・・・・・・・・・・・・・・13
連載 琉球記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一・・・14
情報局で壁新聞「空襲に血走るな」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
偉大なる一人の詩人(伊東静雄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新垣淑明・・・16
豆戦艦ABCD陣「比律賓群島」「ミンダナオ島ダヴアオ」「香港」・・・・・・・・・・・16-23
「ウエーキ島」「ペナン島」「グアム島」「ミツドウエイ島」「米の航空機生産高」
ブラジル風景=サン・パウロ=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤清太郎・・・18
敵性撃滅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土岐善麿③・・・19
ルーズヴエルト一チャーチルのことにあらず世界の敵性を一挙に屠れ
ルーズヴエルトよ汝が頼みし戦艦は一瞬にして「顛覆」をせり
チャーチルよ頼みがたなきアメリカを頼みしことを国民に謝せ
世界戦争の煽動者たる「光栄」をアメリカ大統領よ墓に持ちてゆけ
忍び難きを忍びしはただ大東亜の平和のためと思ひ知るべし
③土岐善麿
歌人・国文学者。東京生。哀果と号する。早大卒。中学時代金子薫園の「白菊会」に参加し、大学時代は窪田空穂・若山牧水の影響を受けた。のち石川啄木と知り合い、二人で生活派短歌の基礎を作った功績は大きい。学士院賞受賞。文学博士。芸術院会員。昭和55年(1980)歿、94才。→コトバンク
琉球の古来工芸品(上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・沖縄県工業指導所・・・20
子供の文化を覗く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・亀谷長輝・・・・22
雷火・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・太田水<穏ママ>・・・・・24
天つちの神もおどろけ巌ゆるぐ大き憤りのおほみことのり
しのびきて今ぞ宣らすと仰せ給ふ畏こさに沁みてわれは泣かるる
電撃機雷火を吐くとみる否やとどろきをあげて艦くつがへる
ふきあがる焔のなかに蒼白の照らし出されたる顔おもひ見む
馬来半島クワンタン沖のたたかひに覆へりたるは艦ばかりは
「尽せ総力 護れよ東亜」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
戦時体制下の沖縄/1942年1月ー月刊『文化沖縄』第3巻第1号
和光同塵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本山裕児・・・26
短篇小説「馬」金城安太郎・絵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新垣庸一・・・27
祝 皇軍之大勝 祝 御武運長久 輝やかし大東亜戦勝利の朝謹壽
一億進軍の春 皇紀二千六百二年正月・・・・・月刊 文化沖縄社社員一同
大東亜戦戦果日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
07/19: 年譜・末吉麦門冬/1912(明治45)年
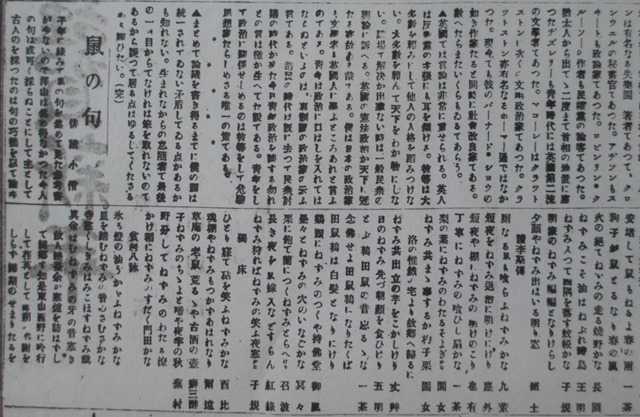
1914年1月1日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「俳諧 鼠の句」
○俳諧 鼠の句ー子年に縁みて鼠の句を集めて見た。参考書が少ないので沢山は集め得なかった今人の句は成可く採らぬことにして主として古人のを採ったのは句の巧拙を以て論せずに古いのが有難いといふ骨董味から出た為めである。それから新年の鼠に嫁が君と云ふ異称があるが、それは俳諧では独立の題になっているので茲にはわざと省いたのである。
1月 親泊朝擢『沖縄県案内』発行/仲吉朝主、印刷/三秀舎「新聞雑誌ー琉球新報、沖縄毎日新聞、沖縄新聞、発展、撫子新聞、福音、沖縄教育、おきなは、演劇週報」
1月 横山健堂『薩摩と琉球』
1月 島津長丸男爵、観光で来沖
1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立
1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社
3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」
卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2
照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6
沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去
6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」
6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」
7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」
7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」
711日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」
7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」
7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」
8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」
8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」
8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」
8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」
8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」
8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」
8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」
9月2日『琉球新報』「我海軍の精華▽悉是れ良智驍勇」「常設活動写真帝国館ー女馬賊」
9月4日『琉球新報』「太平洋に於ける独墺洪海軍力」
9月5日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写着色・ベルサイユ宮殿」
9月6日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・黒金座主(電気応用)、踊り・七月ゑひさあ、歌劇・可憐児(継親念仏)」
9月12日『琉球新報』「球陽座ー琉球史劇・琉球と薩摩」「常設活動写真帝国館ー実写・ピスピユス山噴火」
9月14日『琉球新報』「本社記者 渡口政成退社し沖縄民報社に入社」
9月15日『琉球新報』「『月刊雑誌 五人』ーダヌンチョの死せる街ー嘉手川重利/白き血ー山城正忠/脚本時計ー上間正男/小説題未定ー安次嶺栄裕/芭蕉の恋ー末吉麦門冬/本県婦人観ー美鳩楓渓/希臘思想ー仲吉良光/音楽論ー矢野勇雄/小説帽子ー池宮城寂泡/題未定ー漢那浪笛/サヨリ釣ー潮東庵主人/完成の人孔子ー山田有幹」
9月18日『琉球新報』「粟国事情」「斎藤用之助島尻郡長令弟、中頭郡書記・斎藤熊太郎死去、」
9月26日『琉球新報』素位「泡津海記ーテラの岩屋、日本一の墓、マハナ崎」「球陽座ー琉球史劇・普天間権現之由来記」
10月3日 『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・ノールウェ汽車旅行」「球陽座ー喜利 狂言・伊賀の水月(荒木又右エ門武勇伝)渡嘉敷守禮脚色 」
10月8日 『琉球新報』清村泉水「宮古女性史」①
10月11日 『琉球新報』「三越の新館成る」「常設活動写真帝国館ー実写・伊多利シシリー市街」」「球陽座ー琉球史劇・大濱赤八」
10月15日 『琉球新報』らくこう「琉球歌壇 印度古詩まはばらだ物語を読みて(1)ー我が情我れの衣につつみ行くシャンタヌ王の面白きかな/この河を渡らん人に舟漕かん王者も渡れ乞食人も/絶ち難き情の絆王もなほ黒き瞳の忘れかねつも/天人は樂を奏しぬ花降りぬ若きピスマの願ひの浄きに/仙人の神通力もいかにせむ美人を見て破れけるかも/呪はるることの恐ろしサチヤワチは岸の浮草靡かんとする/十万の矢を空中に射返して流れを下る婿選ひ舟」
10月17日 『琉球新報』「悲惨極まるラサ島移民①」「球陽座ー大喜利・英雄ト美人ーナポレオン(真境名由孝土産)」
10月21日 『琉球新報』らくこう「琉球歌壇 印度古詩まはばらだ物語を読みて(2)ーカミアカの森に入りぬる一千の宮女の群よ夕日春●/五王子は雲を支へて立てるてふサミが木ぬれに刃隠しぬ/あはれなるドラウバテイの艶なるに王妃はめでぬ且つ嫉みつつ/美しき者にともなふ禍を神よ解き去れドラウバテイに/兄嫁の為めにはかりて猛きピーマ敵を取りぬ肉丸にして/アルジユナは怖るる所ろ更にな●一騎手に持つカンデイワの弓/クリシナは高く叫びぬ天神地祇我と共にあり愚かなもの哉/武士の魂さこうカルナ行かず仕ふる家と運を共にせむ」
□『マハーバーラタ』(サンスクリット語: महाभारतम् Mahābhārata)は、古代インドの宗教的、哲学的、神話的叙事詩。ヒンドゥー教の聖典のうちでも重視されるものの1つで、グプタ朝の頃に成立したと見なされている。「マハーバーラタ」は、「バラタ族の物語」という意味であるが、もとは単に「バーラタ」であった。「マハー(偉大な)」がついたのは、神が、4つのヴェーダとバーラタを秤にかけたところ、秤はバーラタの方に傾いたためである。→ウィキペディア
10月31日 『琉球新報』「秦蔵吉、樺山氏主宰の沖縄社に入社」
07/21: 年譜・末吉麦門冬/1914(大正3)年
1月 親泊朝擢『沖縄県案内』発行/仲吉朝主、印刷/三秀舎「新聞雑誌ー琉球新報、沖縄毎日新聞、沖縄新聞、発展、撫子新聞、福音、沖縄教育、おきなは、演劇週報」
1月 横山健堂『薩摩と琉球』
1月 島津長丸男爵、観光で来沖
1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立
1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社
3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」
卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2
照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6
沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去
6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」
6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」
7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」
7月3日『琉球新報』笑古「初夏遊奥山」
7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」
7月7日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選」
7月11日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」
7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」
7月26日『琉球新報』麦門冬「弔薬師楽山君-
7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」
8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」、琉球歌壇ー草秋選 らくこう『球陽座を見て』」
8月3日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選 らくこう『中座の「さんげ劇』を見て』」
8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」
8月16日『琉球新報』「俳紫電」
8月18日『琉球新報』「俳紫電」
8月19日『琉球新報』「俳紫電」
8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」「俳紫電」
8月21日『琉球新報』「俳紫電」
8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」「俳紫電」
8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」「俳紫電」
8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」「俳紫電」
8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」「俳紫電」
8月29日『琉球新報』「俳紫電」
8月30日『琉球新報』「俳紫電」
1月 横山健堂『薩摩と琉球』
1月 島津長丸男爵、観光で来沖
1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立
1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社
3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」
卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2
照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6
沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去
6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」
6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」
7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」
7月3日『琉球新報』笑古「初夏遊奥山」
7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」
7月7日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選」
7月11日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」
7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」
7月26日『琉球新報』麦門冬「弔薬師楽山君-
7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」
8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」、琉球歌壇ー草秋選 らくこう『球陽座を見て』」
8月3日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選 らくこう『中座の「さんげ劇』を見て』」
8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」
8月16日『琉球新報』「俳紫電」
8月18日『琉球新報』「俳紫電」
8月19日『琉球新報』「俳紫電」
8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」「俳紫電」
8月21日『琉球新報』「俳紫電」
8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」「俳紫電」
8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」「俳紫電」
8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」「俳紫電」
8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」「俳紫電」
8月29日『琉球新報』「俳紫電」
8月30日『琉球新報』「俳紫電」
10/03: 新城栄徳「琉球人物誌⑩那覇っ子 石川正通」
石川正通は1897年9月25日ー沖縄県那覇区下泉町にて父正芳・母ツルの二男一女の長男として出生。 1905年、那覇区立甲辰尋常小学校入学。5年生頃よりメソジスト教会牧師H・B・シュワルツ師に英語を学ぶ。この時の小学校の恩師で薫陶を受けたのが佐久本嗣宗。甲辰小学校を初の六年制で卒業。嘉手納時代の沖縄県立第二中学校に入学、通学不便で沖縄県立第一中学校へ入学したのが1911年。当時メソジスト教会牧師のH・B・シュワルツに英語を学んでいた正通は、すでに中学の先生の水準を抜いていた。在学中の1914年に一中代表として英語演説。南方熊楠は、山口沢之助校長と同郷和歌山県の大先輩、奇行に富む世界的大学者。山口校長が折に触れて話した、南方熊楠の逸話は一冊の本にも纏め得るほど、あざやかに正通は覚えている。山口校長の講義は、正通にとっては生理学でなく、熊楠学であった。脱線学の妙味ここにあり、という。
1916年、一中退学し、私立麻布中学校へ転校。傍ら、正則英語学校文学科教室で斎藤秀三郎校長に英語を学ぶ。いつも最前列に陣取り、全身を耳にして講義を聴いていた。ある講義のとき、斉藤先生の誤りを指摘「違います」、再三指摘すると校長室に呼ばれた。斉藤先生「君、あしたからこの学校の先生になれ」の鶴の一声で正則英語学校講師となる。1918年、国民英学会講師、逗子開成中学校講師(ここでの教え子に、平野威馬雄、岡田時彦・女優茉莉子の父、徳山環ー歌手)。
1919年、保善商業学校講師(国語担当)、明治学院専門部講師(現明治学院大学)。1922年、第三版『全訳・シャーロックホームズ』越山堂。文部省中等教員英語科検定試験合格。1923年、8月ー沖縄県立第二中学校講堂で石川正通「英語講座」、伊佐三郎、赤嶺康成ら参加。1924年、東北帝国大学法文学部文学科入学。在学中、土井晩翠の寵愛を受けた。
1922年5月に正通は饒平名智太郎の依頼で鹿子木員信・饒平名智太郎『ガンヂと真理の把握』改造社の英訳も手伝った。
後年、土井晩翠の荒城の月を引いて、正通は漫筆「大阪礼讃 工場の月」の中で、月ヤ昔カラ変ル事無サミ 変テ行ク物ヤ人ヌ心 月には故郷があり、故郷には月がある。十海ヤ距ミテン照ル月ヤ一チ アリン眺ミユラ今日ヌ月ヤ 十海でも渡海でもよい。月で心を清め、心で故郷を浄めよう。「太陽と月と、どちらが必要だ」「勿論、月だ。太陽は明るい昼間に照る。月は暗い夜を照らす」斯ういう二人のウスノロの問答にも捨て難い味がある。通堂港頭で交す「儲キテ来ーヨー」という激励の挨拶に全沖縄の運命は宿り、全沖縄人の希望は繋がる。私は世界語の中にこれほど力強さと哀調とのいみじく融け合った言葉を知らない。故郷への送金額第一位の王座を占める関西五万の沖縄ン人御スーヨー、高らかに歌いましょう。 春工場の鼻の煙/廻る機械に油注して/那覇の港を船出し/ウルマの光今此処に(1939年8月)。
1928年、東北帝国大学法文学部国文科卒業。卒論「近松門左衛門の世話浄瑠璃について」。国民英学会講師に復職、京華高等学校教諭、日本女子高等学院英文学科教授。1929年、雑誌『イギリス文学』に「ヘルンの『沙翁論』」。1933年、『南島』1月1日の消息欄に石川正通氏ー伊波普猷先生と共力で近く日英両文の沖縄案内を発刊する由」。1934年の『南島』8月の漫筆に「友の首途を祝して故郷を語る=武元朝朗・國吉休微両君を叱咤する=(略)最近出た某書店の百科辞典を引いて見たが、おもろ、蔡温、程順則、尚泰侯爵も出て居ない。沢田正二郎、田健次郎等は写真まで出て居る。土田杏村が第二の万葉集と言った『おもろ』も国語国文学校の士すら全般的に知られて居ない」と記す。
1934年4月15日『琉球新報』に山城正忠「旅塵抄」の連載がある。その16回に「東京も琉球」と題し、東京の石川正通の自宅を訪ねたときのことが書かれている。
山城です。と名乗りを上げると、矢庭に襖が放いて、見知り越しの奥さんが顔を見せる。 上がれといふので、遠慮無しにあがった。小ざっぱりとした、八畳の間である。(略)額が二面、襖の上にかかっている。ひとつは、英文で斎藤秀三郎先生の毛筆揮毫だとすぐ判った。勿論、私にそれが読める筈もないが、かねて此家の主人から、その事をきいて居たからである。今ひとつは、巻紙に書いた手紙を表装したもので、おしまひの処に、短歌が一首、書かれて有ったやうに覚えて居る。能くこなされた筆づかひで、酒悦な風格を偲ばせる迫力があった。何人の心憎い業であらうかと、態々立上ってみると「晩翠」といふ署名が鮮やかに、私の網膜に映った。それと同時に、これが、その昔、有名な「天地有情」によって、一代の詩名を謳はれた、土井先生の筆蹟だといふ事を知ったので、一しほ、懐かしく仰がれた。(略)こんな閑寂な処にいて、常住心を落ちつけていたら、きっとそのうちには、自然の脈搏が聴かれるだらう。そしたら、思ふ存分に、自分の貧しい想も練られて行くにちがいない。などと、空想してる所へ「ハイサイ。イチメンソウチャガ」と、例の開けっ放しな聲で、斯う云ひ乍らはいって来たのは、紛れもない、あるじの石川正通君であった。正忠は触れていないが庭には空手家の本部サールーが建てた巻藁もあった。
1944年、戦時中の英語教育政策により京華高等学校退職。東洋大学講師、本海上火災保険に入社(外国課勤務)、同年1月の月刊『文化沖縄』第五巻第一号に石川正通は「産後銃後」と題して母の思い出を書いている。
「(略)母は私達の生まれる前から、春風秋雨、夏冬の分ちなく、渡地中島辻と那覇三村の街々を素足で頭の上には重い石油と更に重い一家族の生命を載せてその石油を行商しながら良人と我々3人の兄弟妹を何不自由なく育てて下さったー自分は多くの不自由を忍びつつ。地球上の如何なる名花、如何なる香料の香よりも私は石油の香が好きだ。私は死ぬ時は石油の香を嗅ぎつつ死に度い。母の背中に負われて嗅いだあの石油、幼年時代の全ての思ひ出を秘めているあの石油の香を。那覇の電燈は伝統的に暗い。私の母が石油を売っていた時代の那覇の夜は今の那覇の夜よりも、断然明るかったに違ひない。私は自分の母ながら、母を那覇を明るくした恩人の一人に数へさせて戴き度い。その母の為にも尊い石油を空費する米英の巨頭一味は憎むべき敵だ。親の仇を討つ日本精神の強烈さに於いて私は敢て曾我兄弟に譲らない。米英の戦争挑発さへ無かったらば石油は人類殺戮の為に悪用されず、人類の福祉向上の為に善用されたであらう」。戦後、正通は親しい友人・横内圓次に母を偲んで詠んだ歌「果てし日も 骨さえ分かぬ命かも 母親返えせ 昭和天皇」を披露している。
1916年、一中退学し、私立麻布中学校へ転校。傍ら、正則英語学校文学科教室で斎藤秀三郎校長に英語を学ぶ。いつも最前列に陣取り、全身を耳にして講義を聴いていた。ある講義のとき、斉藤先生の誤りを指摘「違います」、再三指摘すると校長室に呼ばれた。斉藤先生「君、あしたからこの学校の先生になれ」の鶴の一声で正則英語学校講師となる。1918年、国民英学会講師、逗子開成中学校講師(ここでの教え子に、平野威馬雄、岡田時彦・女優茉莉子の父、徳山環ー歌手)。
1919年、保善商業学校講師(国語担当)、明治学院専門部講師(現明治学院大学)。1922年、第三版『全訳・シャーロックホームズ』越山堂。文部省中等教員英語科検定試験合格。1923年、8月ー沖縄県立第二中学校講堂で石川正通「英語講座」、伊佐三郎、赤嶺康成ら参加。1924年、東北帝国大学法文学部文学科入学。在学中、土井晩翠の寵愛を受けた。
1922年5月に正通は饒平名智太郎の依頼で鹿子木員信・饒平名智太郎『ガンヂと真理の把握』改造社の英訳も手伝った。
後年、土井晩翠の荒城の月を引いて、正通は漫筆「大阪礼讃 工場の月」の中で、月ヤ昔カラ変ル事無サミ 変テ行ク物ヤ人ヌ心 月には故郷があり、故郷には月がある。十海ヤ距ミテン照ル月ヤ一チ アリン眺ミユラ今日ヌ月ヤ 十海でも渡海でもよい。月で心を清め、心で故郷を浄めよう。「太陽と月と、どちらが必要だ」「勿論、月だ。太陽は明るい昼間に照る。月は暗い夜を照らす」斯ういう二人のウスノロの問答にも捨て難い味がある。通堂港頭で交す「儲キテ来ーヨー」という激励の挨拶に全沖縄の運命は宿り、全沖縄人の希望は繋がる。私は世界語の中にこれほど力強さと哀調とのいみじく融け合った言葉を知らない。故郷への送金額第一位の王座を占める関西五万の沖縄ン人御スーヨー、高らかに歌いましょう。 春工場の鼻の煙/廻る機械に油注して/那覇の港を船出し/ウルマの光今此処に(1939年8月)。
1928年、東北帝国大学法文学部国文科卒業。卒論「近松門左衛門の世話浄瑠璃について」。国民英学会講師に復職、京華高等学校教諭、日本女子高等学院英文学科教授。1929年、雑誌『イギリス文学』に「ヘルンの『沙翁論』」。1933年、『南島』1月1日の消息欄に石川正通氏ー伊波普猷先生と共力で近く日英両文の沖縄案内を発刊する由」。1934年の『南島』8月の漫筆に「友の首途を祝して故郷を語る=武元朝朗・國吉休微両君を叱咤する=(略)最近出た某書店の百科辞典を引いて見たが、おもろ、蔡温、程順則、尚泰侯爵も出て居ない。沢田正二郎、田健次郎等は写真まで出て居る。土田杏村が第二の万葉集と言った『おもろ』も国語国文学校の士すら全般的に知られて居ない」と記す。
1934年4月15日『琉球新報』に山城正忠「旅塵抄」の連載がある。その16回に「東京も琉球」と題し、東京の石川正通の自宅を訪ねたときのことが書かれている。
山城です。と名乗りを上げると、矢庭に襖が放いて、見知り越しの奥さんが顔を見せる。 上がれといふので、遠慮無しにあがった。小ざっぱりとした、八畳の間である。(略)額が二面、襖の上にかかっている。ひとつは、英文で斎藤秀三郎先生の毛筆揮毫だとすぐ判った。勿論、私にそれが読める筈もないが、かねて此家の主人から、その事をきいて居たからである。今ひとつは、巻紙に書いた手紙を表装したもので、おしまひの処に、短歌が一首、書かれて有ったやうに覚えて居る。能くこなされた筆づかひで、酒悦な風格を偲ばせる迫力があった。何人の心憎い業であらうかと、態々立上ってみると「晩翠」といふ署名が鮮やかに、私の網膜に映った。それと同時に、これが、その昔、有名な「天地有情」によって、一代の詩名を謳はれた、土井先生の筆蹟だといふ事を知ったので、一しほ、懐かしく仰がれた。(略)こんな閑寂な処にいて、常住心を落ちつけていたら、きっとそのうちには、自然の脈搏が聴かれるだらう。そしたら、思ふ存分に、自分の貧しい想も練られて行くにちがいない。などと、空想してる所へ「ハイサイ。イチメンソウチャガ」と、例の開けっ放しな聲で、斯う云ひ乍らはいって来たのは、紛れもない、あるじの石川正通君であった。正忠は触れていないが庭には空手家の本部サールーが建てた巻藁もあった。
1944年、戦時中の英語教育政策により京華高等学校退職。東洋大学講師、本海上火災保険に入社(外国課勤務)、同年1月の月刊『文化沖縄』第五巻第一号に石川正通は「産後銃後」と題して母の思い出を書いている。
「(略)母は私達の生まれる前から、春風秋雨、夏冬の分ちなく、渡地中島辻と那覇三村の街々を素足で頭の上には重い石油と更に重い一家族の生命を載せてその石油を行商しながら良人と我々3人の兄弟妹を何不自由なく育てて下さったー自分は多くの不自由を忍びつつ。地球上の如何なる名花、如何なる香料の香よりも私は石油の香が好きだ。私は死ぬ時は石油の香を嗅ぎつつ死に度い。母の背中に負われて嗅いだあの石油、幼年時代の全ての思ひ出を秘めているあの石油の香を。那覇の電燈は伝統的に暗い。私の母が石油を売っていた時代の那覇の夜は今の那覇の夜よりも、断然明るかったに違ひない。私は自分の母ながら、母を那覇を明るくした恩人の一人に数へさせて戴き度い。その母の為にも尊い石油を空費する米英の巨頭一味は憎むべき敵だ。親の仇を討つ日本精神の強烈さに於いて私は敢て曾我兄弟に譲らない。米英の戦争挑発さへ無かったらば石油は人類殺戮の為に悪用されず、人類の福祉向上の為に善用されたであらう」。戦後、正通は親しい友人・横内圓次に母を偲んで詠んだ歌「果てし日も 骨さえ分かぬ命かも 母親返えせ 昭和天皇」を披露している。
05/29: 麦門冬と上間朝久
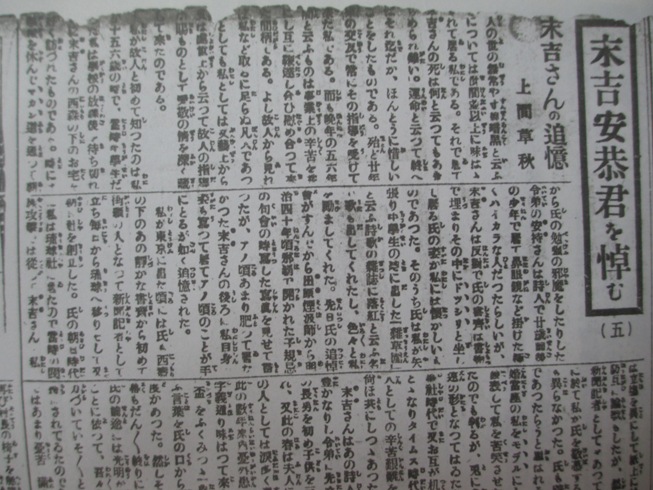
1924年12月18日『沖縄タイムス』上間草秋「末吉安恭君を悼む」
1955年4月19日『琉球新報』上間朝久「琉球舞踊雑観」(1)
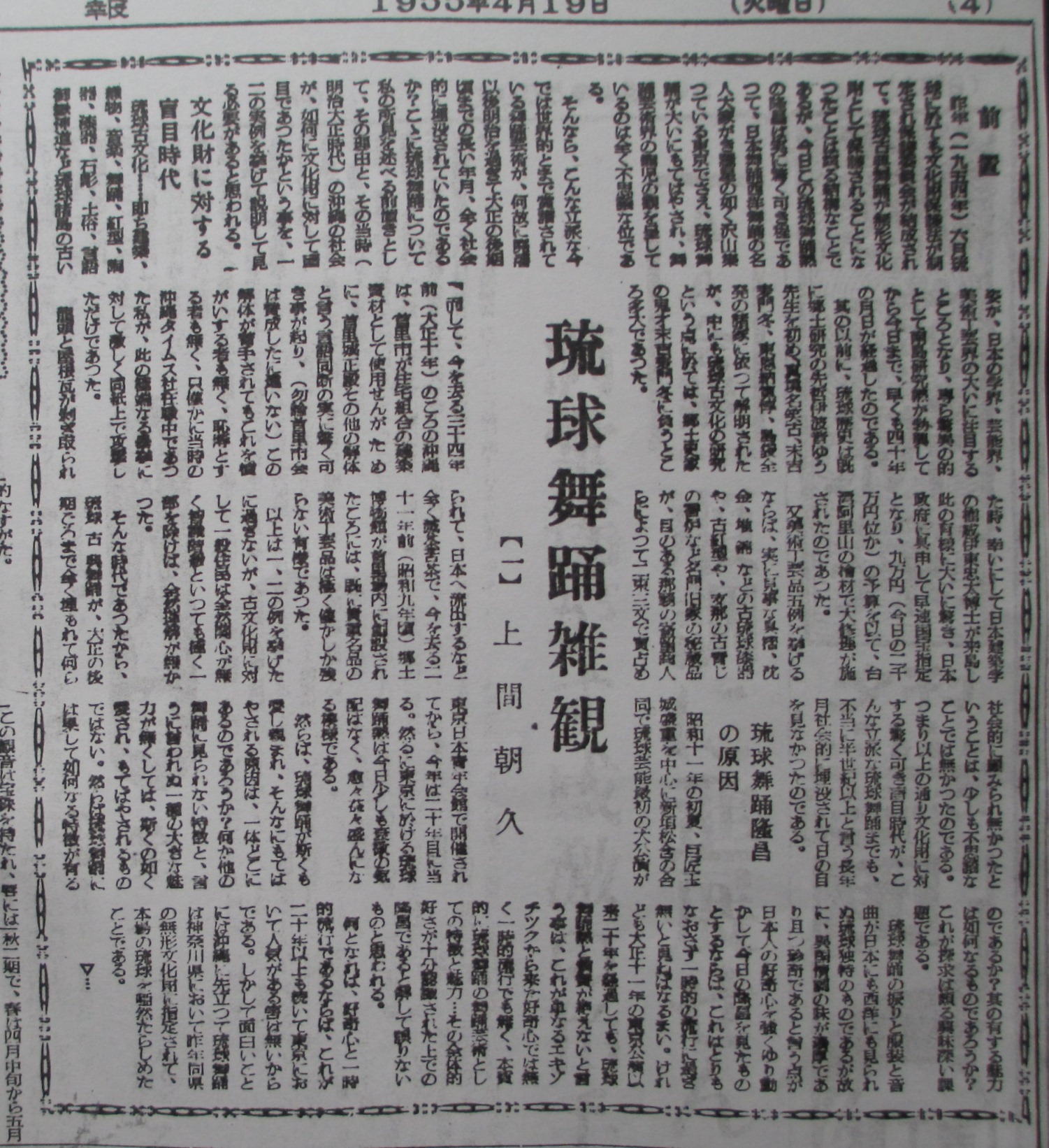
○琉球歴史は既に郷土研究の先哲 伊波普猷先生を初め、真境名笑古、末吉麦門冬、東恩納寛惇、島袋全発の諸家に依って解明されたが、中にも琉球古文化の研究という点に於いては、郷土史家の鬼才 末吉麦門冬に負うところ多大であった。

上間正雄(1890・6・29~1971・4・12)
別名ー草秋、朝久
実父上間正富は松山王子尚順の守役であった。後に那覇上之蔵の亀山朝奉の養子となる。沖縄県立中学校在学中から詩や歌を作り、1910年に同人誌『雑草園』を発行。同年上京。帰郷して樗花、夏鳥、梅泉、正敏のペンネームで新聞雑誌に文芸・美術・芸能の評論や創作を発表する。特に12年に『三田文学』に発表した「ペルリの船」は注目された。14年琉球新報歌壇選者、16年琉球新報記者、19年沖縄時事新報記者、20年沖縄タイムス編集長。→1991年1月 新沖縄文学別冊『沖縄近代文芸作品集』「上間正雄」
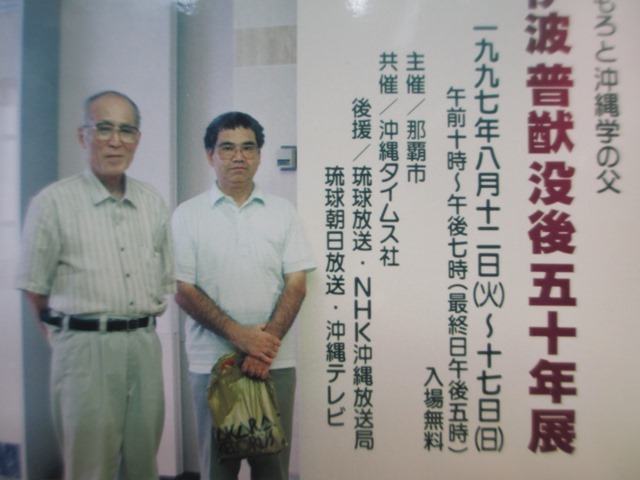
伊波廣定氏と新城栄徳
伊波廣定
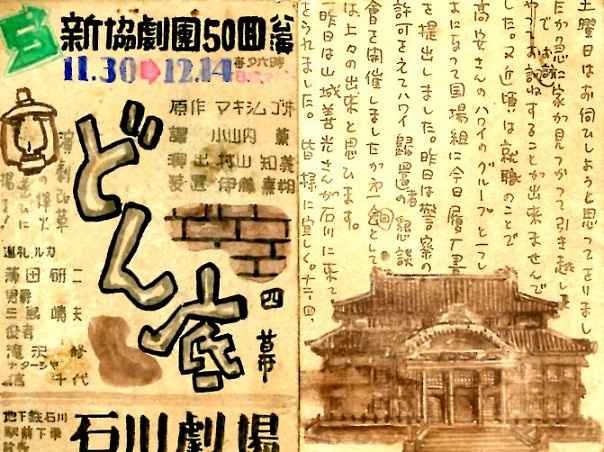
伊波廣定から國吉眞哲宛ハガキ
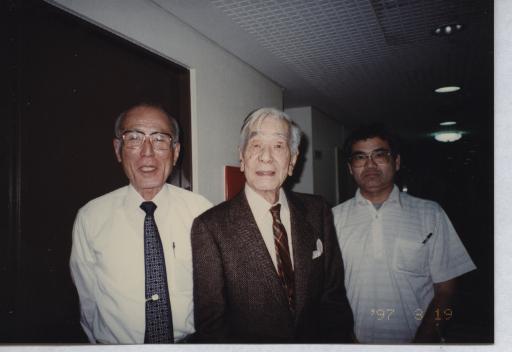
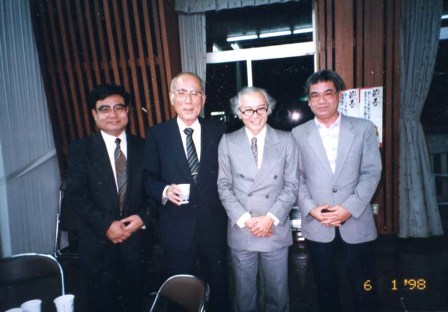
写真ー左から伊波広定氏(元沖縄人民党文化部長)、古波蔵保好氏、新城栄徳/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳
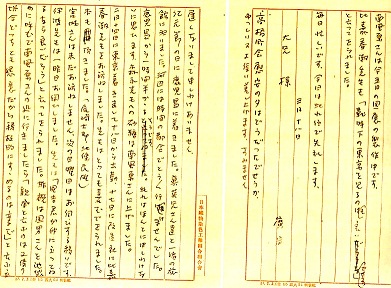
伊波廣定から國吉眞哲宛書簡
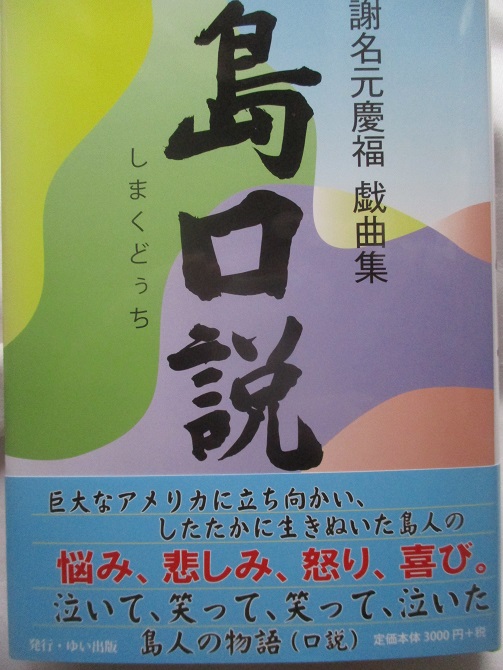
2019/8/13 謝名元 慶福 『謝名元慶福戯曲集 島口説 』ゆい出版
1977年7月 『青い海』64号 謝名元慶福「『レクイエム沖縄』を聴く」
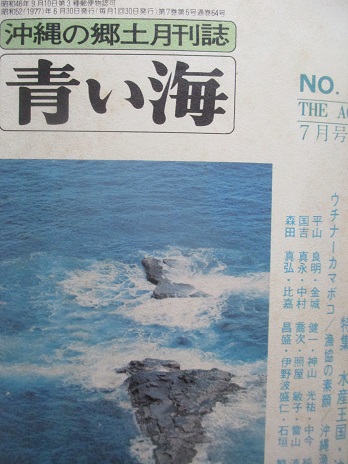

1978年6月 『青い海』74号 謝名元慶福「子ども文化の胎動の中で―沖縄の子どもたちと文化を考えるー」
1978年12月 『青い海』79号 謝名元慶福「沖縄県民の特性と背景 NHK全国県民意識調査から」
1984年1月 『青い海』129号 謝名元慶福「島口説」「『島口説』雑感」、北島角子「島口説とのめぐりあい」
1984年3月 『青い海』130号 謝名元慶福「『朝未来』と『たねだ賞』」
1987年3月 『新沖縄文学』71号 謝名元慶福「チェロ二題」
謝名元慶福ー1942年、沖縄県出身。コザ高校卒業。東京のテレビドラマ研究所に学ぶ。琉球放送、NHK等の放送局勤務と並行し、劇作家として活動を開始。明治から復帰後までの沖縄を舞台に、天皇制や米国といった権力と向き合う民衆の姿を描いた戯曲を数多く発表する。
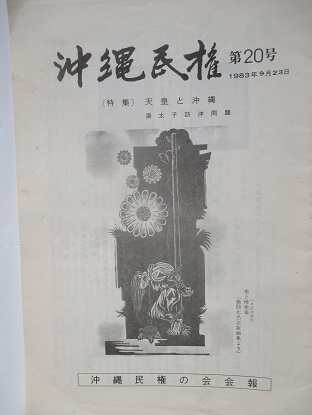
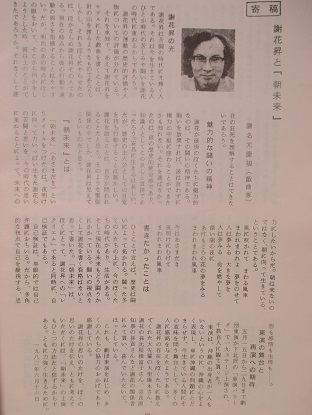
1983年9月23日ー『沖縄民権』第20号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)
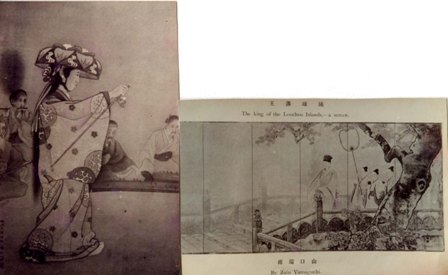
沖縄風俗踊図(1903年)/琉球藩王図(1912年)


1908年5月 菊池幽芳『琉球と為朝』
1911年 那覇尋常高等小学校卒。卒業後香港に渡りイギリス人の会社に就職。5年ほど滞在。
1918年 趣味は琉球古典音楽、古典舞踊、組踊。幼少のころから父・盛輝と祖父・盛矩から影響を受ける。この頃から玉城盛重に琴を師事。さらに三味線を伊佐川世瑞に師事。
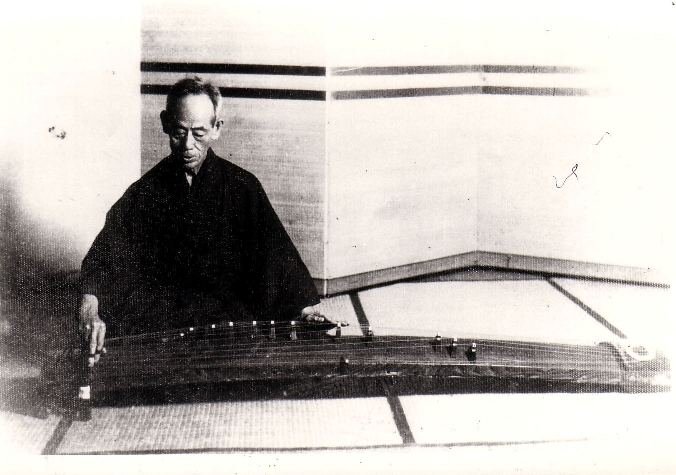
写真ー玉城盛重
□1923年2月24日『沖縄タイムス』田邉尚雄「音楽史上の参考資料ー琉球の琴八橋流 徳川初期のもので今は内地では消滅」
○玉城盛重氏は舞踊の外に八橋流の琴曲も奏せられたが私はここに此の八橋流の琴について一言したいと思ふ、八橋流と云ふのは勿論徳川の初めに京都で八橋検校が開いた箏であって、我が俗箏の開祖である。内地では八橋流は元禄時代に生田流が起こり文化文政時代に江戸で山田流が出たために今では生田や山田に圧倒されて八橋流は全く消えてしまった。然るに琉球には此の八橋流のみが伝わって生田流や山田流はあめり入って居ないのは頗る面白いことであると共に、又内地で滅びたものが琉球に残っていると云ふ点に於いて非常に音楽史上貴重なる材料であると云はなければならぬ。・・・
1922年~1946年 沖縄県鉄道局管理所経理課勤務。

玉城盛重師と仲嶺盛竹(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)
1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁
1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」
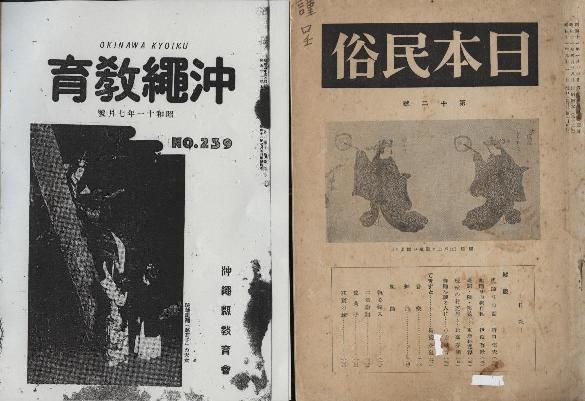
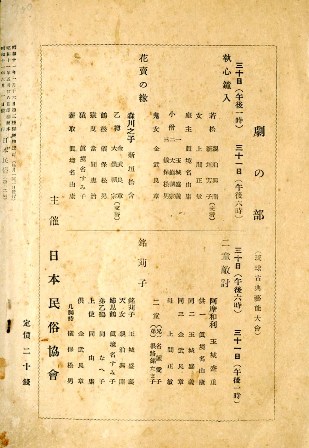
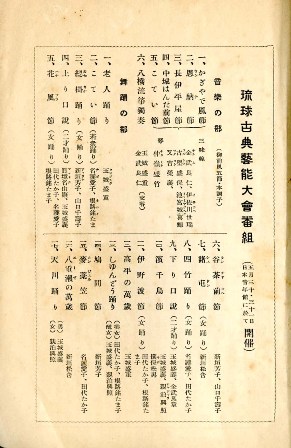
右ー音楽の部に琴・仲嶺盛竹

写真ー前列右から」仲嶺盛竹、玉城盛義、折口春洋、新垣松含、眞境名澄子、玉城盛重、眞境名苗子、伊佐川世瑞、古堅盛保、池宮城喜輝、渡口政興。中央右から眞境名由康、上間正敏、名護愛子、田代タカ、根路銘千鶴子、新垣芳子、二人おいて二代目宜保松男。後列右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照一人おいて山口ちづ子。(雅叙園で)

映画「オヤケアカハチ」制作・東京発声映画製作所/配給・東宝映画/監督・重宗務、豊田四郎/脚本・八田尚之/原作・伊波南哲/撮影・小倉金弥/音楽・大村能章/美術・河野鷹思/録音・奥津武/出演・大日方伝、藤井貢、三井秀男、市川春代、山口勇
写真ー上右から八木明徳、3人目・山城正樹、13人目・山田有登、田代タカ子、玉城盛重、17人目・護得久朝章、19人目・上間朝久、渡口政興、22人目・國場世保、23人目・仲嶺盛竹。中列左端・山田有昴、3人目・奥津。前列左から4人目・藤井貢、監督、8人目・大日方伝、高江洲康享、上間郁子1937年

那覇市歴史資料室収集写真/閑院宮春仁王殿下御前演芸記念写真 /同写真1枚あり/氏名記載あり/前列右より古堅盛保、金城幸吉、玉城盛重、仲嶺盛竹、与世田朝保。後列右より浦崎康華、金城隹子(現在真境名隹子)、渡口政興、国場世保、国場徳八、高嶺てる子。(1941/03/07)
1949年8月『芝居と映画』屋部憲「戦争と藝能」
○終戦当時国頭羽地大川のほとり、川上の山宿で始めて仲嶺盛竹氏の琴を聴いた時、何とはなしに熱ひものが頬を伝はるのを覚えた。別に悲しいのではない。さりとて歓びの感激でもない。勿論生延びた喜びはあるが、それのみの為めじやない。又戦禍に斃れし人々のことを考へた時悲痛の思いはするが、それのみののためでもない。亦死に勝る戦争中の飢餓と労苦を考えた時、血がにじみ出るやうな思ひ出はあるが、然し、その追憶のためでもなひ。今私はこの名状すべからざる感激の詮索に隙を假すことを憚り乍ら、筆を持ちなほしていく。

1954年2月14日 「火野葦平先生招待記念」
前列右から南風原朝光、真境名由康、火野葦平、平良リヱ子、仲嶺盛竹、真境名由祥。中列右から山里永吉、真境名澄子、真境名由苗、宮里春行。後列右から国吉真哲、一人おいて豊平良顕、真境名由乃、真境名佳子、勝連盛重。

1955年 第10回文部省芸術祭公演参加のメンバー(那覇・世界館)前列右から大嶺政寛、玉那覇正吉、國吉眞哲、山本義樹、豊平良顕、南風原朝光、末吉安久、田島清郷。後列右から宮里春行、識名盛人、眞境名由乃、眞境名由苗、牧志尚子、平良雄一、眞境名由康、勝連盛重、宮平敏子、屋嘉宗勝、眞境名佳子、喜納幸子、南風原逸子、仲嶺盛竹、嘉手苅静子、屋嘉澄子、仲嶺盛徳。

仲嶺盛竹(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)□箏は竜になぞらえて作られたと言われ、各部の名称に竜の字が多く使われている。

稽古風景ー仲嶺盛竹師と仲嶺貞夫氏(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)

元氏 仲嶺本家の墓
1993年3月『沖縄芸能史研究会会報』第190号 「第190回研究報告/仲嶺盛竹師を語るー仲嶺貞夫」

写真左が仲嶺貞夫氏(仲嶺盛竹の嗣子)、新城栄徳

写真左が仲嶺貞夫氏(仲嶺盛竹の嗣子)、姪の仲嶺絵里奈さん
12/03: 戦時体制下の沖縄の雑誌/1941年3月 『月刊文化沖縄』
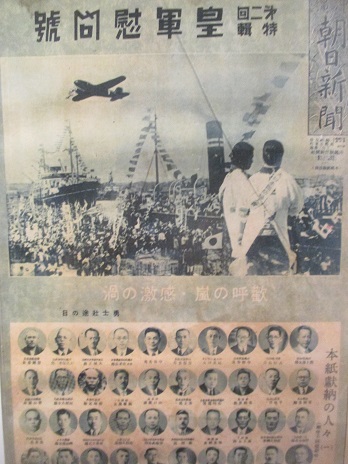

1940年8月25日『沖縄朝日新聞』
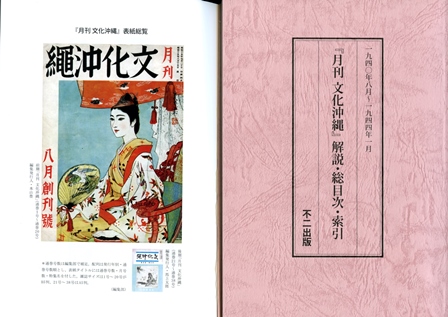
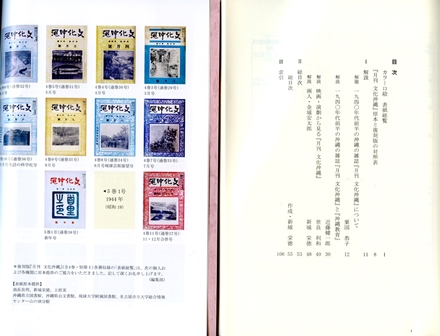
2015年12月 「『月刊文化沖縄』解説・総目次・索引」不二出版
目次 カラ―口絵 表紙総覧
『月刊 文化沖縄』原本と復刻版の対照表
Ⅰ 解題 1940年代前半の沖縄の雑誌『月刊 文化沖縄』について・・・・・・・粟国恭子
解説 1940年代前半の沖縄の雑誌『月刊 文化沖縄』と『沖縄教育』・・近藤健一郎
解説 映画・演劇から見る『月刊 文化沖縄』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・世良利和
解説 画人・安太郎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新城栄徳
Ⅱ 総目次
総目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・作成・新城栄徳
Ⅲ 索引
不二出版株式会社 東京本社 郵便番号 :113-0023. 住所 :東京都文京区向丘1-2-12
電話番号 :03-3812-4433 .FAX :03-3812-4464
私は1996年7月発行の『自治おきなわ』に「関西におけるウチナーンチュの歩み」を書き、その末尾に「最後にー私は大阪で創刊された雑誌『青い海』を全冊、合本し愛蔵していて、その中に載っている事項や人名に解説、注釈を加えてみたいと常に思っていた。『関西沖縄年表』はその過程の副産物でもある。最近またぞろ、自分は安全な所(戦争最高責任者の追及は棚に上げる)に身を置いてウチナーンチュの戰爭責任だの、加害者だのと騒ぎ立てる、クサレヤマトーのインテリ(インチキとハッタリ)文化人が目立ちはじめた。」と書いたが、亡くなられた牧港篤三さんなんかは沖縄戦に新聞人として加担したと自虐的に自分を責めておられた。山里永吉もその意味では戦争協力に加担していたことは否めない。友人の伊佐眞一氏などは伊波普猷や山之口貘の戦争責任も追及している。だが、こういったことはウチナーンチュ自身が追及し反省することで、やまとぅーはやまとぅーで自分の住んでいるところのハエでも追えば良い問題である。しかし現実のニホンはアメリカ属国である。ニホン国民は戦争の出来る核大好きアベ政治(それを支える日米利権官僚)、大阪ではアベ政治の別働隊・日の丸大好き維新を誕生させたので戦争の反省や戦争責任問題が出るような環境にはない。
戦時体制下の沖縄/1941年3月 『月刊文化沖縄』「口絵写真」
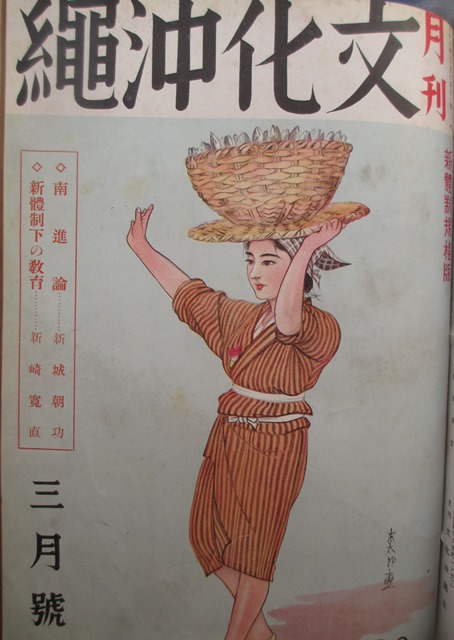
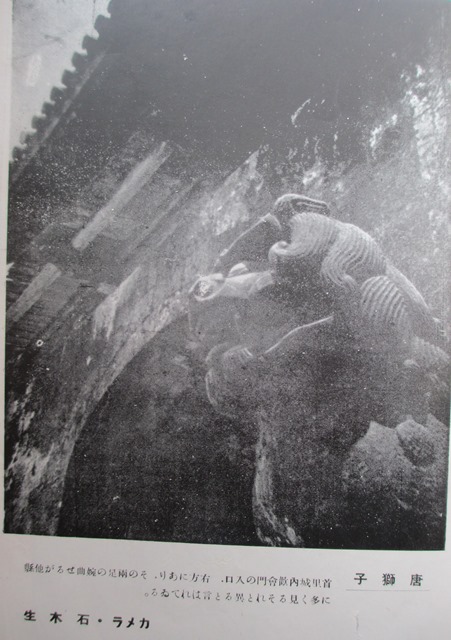
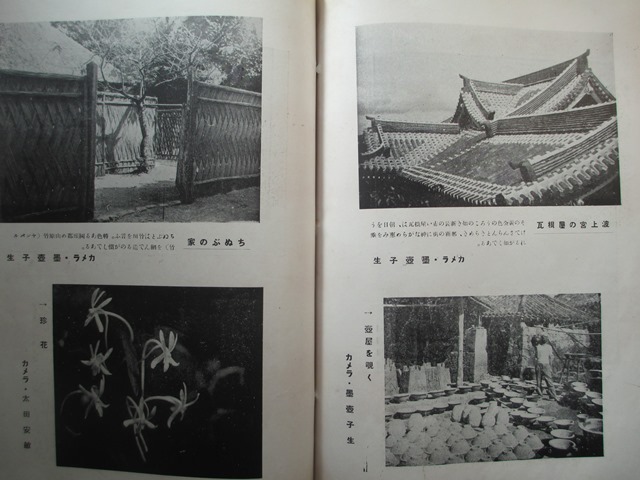
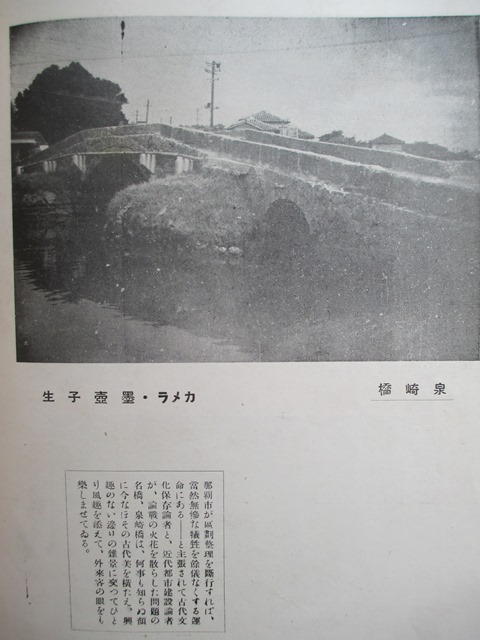
□新たなる闡明ー地方文化の振興急務が叫ばれる。新体制政治下の翼賛運動に重要な役割を帯ぶるからである。わが沖縄の文化を再検討し、強調・是正するに絶好の機会は到来したのである。殊に吾が沖縄は古来特種の文化國であり、他県の追随を許さぬものが多い。是を昴揚してわが地方性を振興、新國民文化の建設発展に、合流せしめねばならぬ。而して此の目的遂行のためには県民各自の職域奉公による協力を必要とする。
県民生活の水準を文化的に高めしめる。之れ特にわが県下に於いて緊急要項たる事は、識者の誰しもが痛感する所であらう。『月刊文化沖縄』微力たりと雖も、此の重大使命を擔って邁進せんを誓ひ、茲に態度を闡明して新たなる声明を送る。単なる文藝運動なりと誤解してはならぬ。県民の文化生活への啓蒙運動をも兼ねるは勿論、併せて新國民たる堅実思想の培養、指導の実を擧げんとするものである。
03/02: 吉田東吾と東恩納寛惇
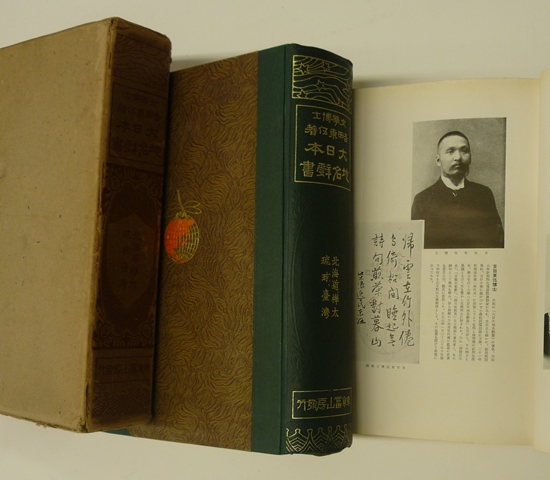
写真ー左、吉田東吾『大日本地名辞書』「北海道、樺太、琉球、臺灣」冨山房/右、『冨山房五十年』
吉田東伍【よしだ・とうご】
生年: 元治1.4.10 (1864.5.15)
没年: 大正7.1.22 (1918)
明治大正期の先駆的な歴史学・歴史地理学者。4月14日誕生説もある。越後(新潟県)蒲原郡の旗野家の3男に生まれ,小学校卒業後,小学校教員になり,大鹿新田(新津市)の吉田家の養子となった。この間北海道に渡り,読書に励んだ成果などを新聞・雑誌に「落後生」などの筆名で投稿,特に『史海』への投書論考は,主筆田口卯吉の注目をひき,学界への登竜門となった。また親戚の市島謙吉に紹介され「徳川政教考」を『読売新聞』に連載し,日清戦争に記者として従軍。また『日韓古史断』を書いて,学界での地位を固めた。その研究は日本歴史の全分野にわたり,歴史地理学の分野で『大日本地名辞書』(全11冊),『日本読史地図』などが先鞭をつけている。社会経済史の分野では『庄園制度之大要』が,近代史の分野では『維新史八講』があり,現代より過去にさかのぼるという歴史的視野の問題を含む通史『倒叙日本史』(全12巻)もある。また『世阿弥十六部集』の発見は学界を刺激した。『海の歴史』『利根川治水論考』や,論文集『日本歴史地理之研究』の問題提起は今日でも注目される。<参考文献>高橋源一郎編『吉田東伍博士追懐録』 (松島榮一)
(→コトバンク)
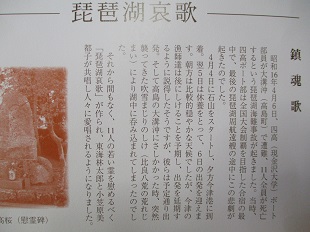
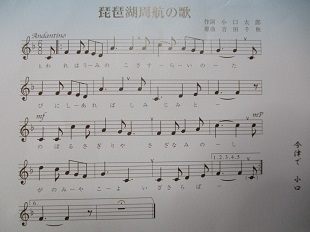
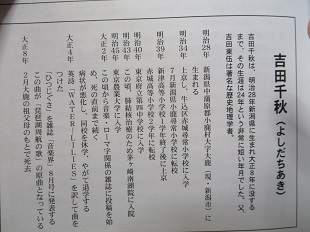
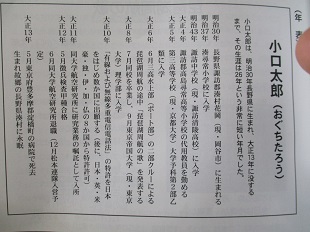
「琵琶湖周航の歌」の基礎知識 小口太郎の出身地、長野県岡谷市の諏訪湖畔の釜口水門河川公園に小口太郎像と歌碑(江崎玲於奈の筆による)がある。昭和63年 太郎生誕90年を記念し岡谷市が建造した。地元では小口太郎顕彰碑等保存会を結成して顕彰に努力されている。/吉田千秋の出身地、新潟市秋葉区(合併前の新津市)では「ちあきの会」を結成して活動している。千秋の父・吉田東伍の記念博物館(阿賀野市保田)でも千秋コーナーを設け資料を展示している。→滋賀県高島市
2016年2月 『月刊琉球』比嘉克博「神々の後裔たちー元祖志向の精神史ー」
2016年2月 『月刊琉球』№32 比嘉克博「神々の後裔たちー元祖志向の精神史ー」(1)
2016年3月 『月刊琉球』№33 比嘉克博「神々の後裔たちー元祖志向の精神史ー」(2)
2016年4月 『月刊琉球』№34 比嘉克博「神々の後裔たちー元祖志向の精神史ー」(3)
大宜味朝徳の『南島』第4号(1933年)に上原美津子(沖縄日日新聞元記者)が清明祭と題して「琉球人は祖先崇拝の民族です」と書いている。琉球学の巨人・東恩納寛惇は祖先崇拝を「現在の殺風景な世態に寛容の情味を注ぎ込み、世界平和の基盤をつくるものとも云える」と書き、系図については「男系を本旨とし、女系には及んでいない。その欠点を補う」ものに内系図(編集本)があると記している。
先日、写真家の山田實氏から山田一門の山田有銘編集『霊前備忘録』(1930年)を借りた。前記の内系図の一種である。平姓家譜から説きおこし、新聞の死亡広告を貼り付けた系図補遺、拝所の読谷残波岬、屋敷や庭園、位牌、墓所などを図示、着色されビジュアルだ。實氏の父有登は医者で、兄の有勝は詩人。洋画家の有邦、社会福祉の有昴、社会運動家の有幹、教育者の有功などが山田一門から出ている。
漢那憲和の家系については那覇市歴史資料室が出している『那覇市史』「家譜資料(4)那覇・泊系」の人名索引で、憲和の父や祖父の経歴、昴氏であることが分かる。憲和の婿兄弟の神山政良の東氏では、昴氏が同門だという伝えもある。先日、中野利子さんと松居州子さん(憲和の孫)が見えられ同門の憲一郎作成「昴姓世系図」と「戸籍謄本」を恵まれた。これで憲和の母親の旧姓が玉那覇と分かる。
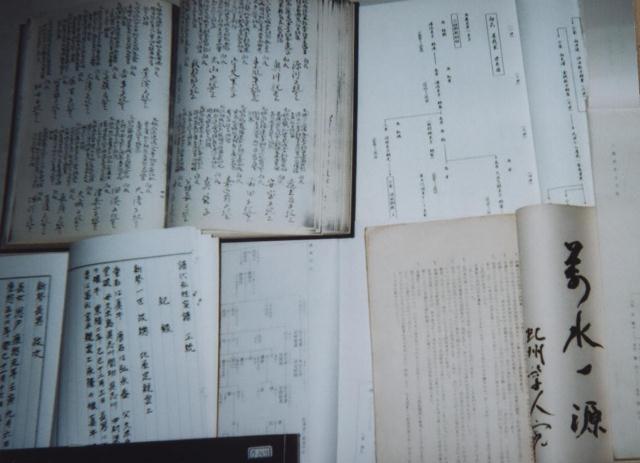
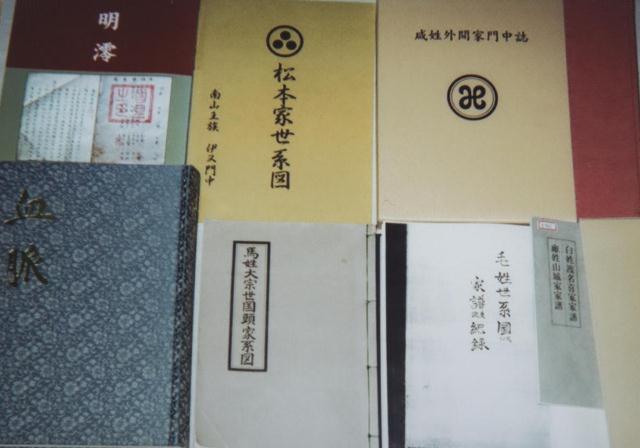
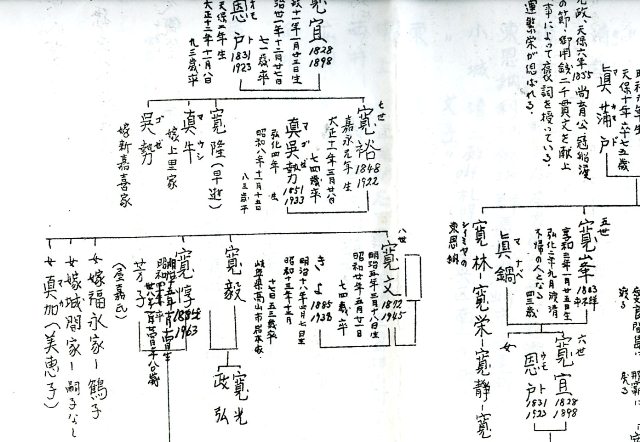
東恩納家系図
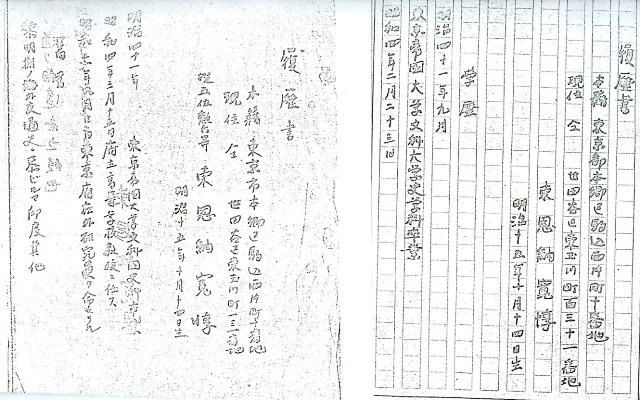
東恩納寛惇自筆履歴書
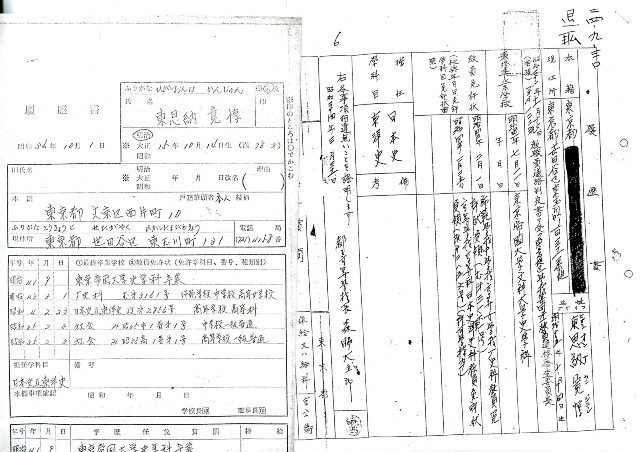
公的機関が作成した東恩納寛惇の経歴書
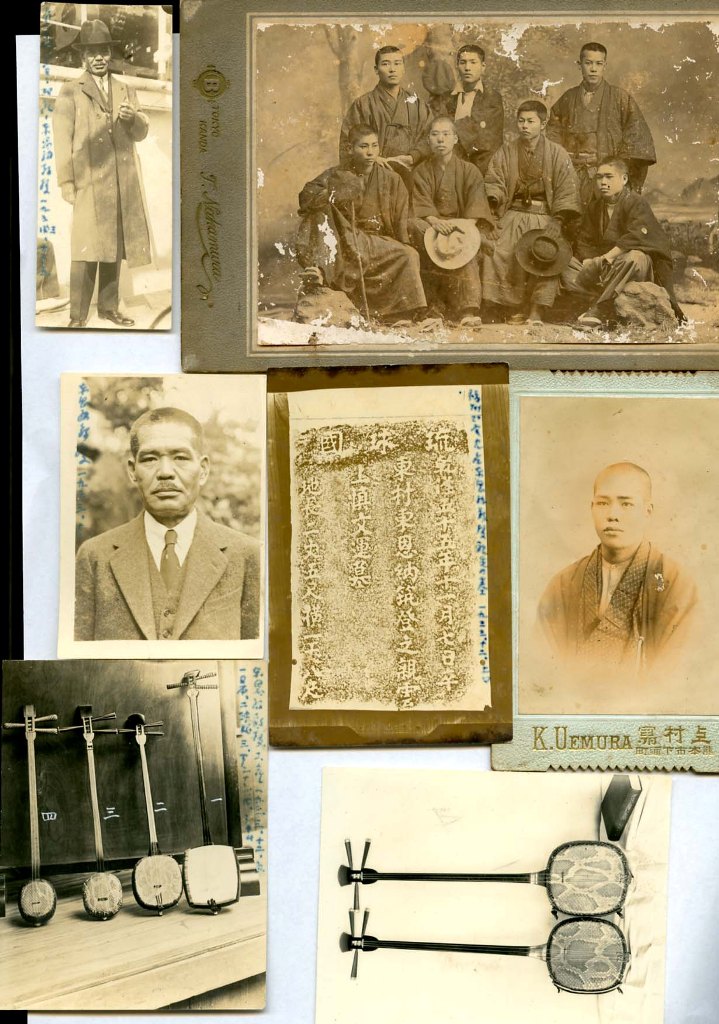
写真上右ー1901年1月4日東京神田小川町・写真館美影堂(中村董)で沖縄中学校の同級生たち前の右から東恩納寛惇、崎浜秀主、国吉真徳、伊波興旺、後列右から赤嶺武太、小嶺幸慶、与那覇政敷。
写真中ー福州において東恩納寛惇が発見した5代目祖先の墓碑。その右ー1901年5月13日熊本市下通町上村嘉久次郎・写真裏に「地上の友なる国吉真徳大兄へー寛惇」
写真下ー1933年12月に東恩納寛惇が安南および福建より持ち帰った三味線、昭和会館に寄贈した。(1)ヤマト、(2)琉球、(3)安南、(4)安南
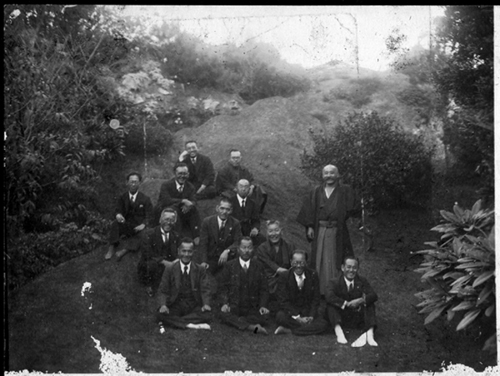
1933年12月ー東恩納寛惇は一中時代の同級生の比嘉盛珍(元内務省土木技師)、島袋慶福(陸軍少尉)、漢那憲英(海外協会)、崎浜秀主(商校長)、糸数青盛(那覇市税務課)、及び旧友の照屋那覇市長、島袋二高女校長、志喜屋二中校長、胡屋一中校長、當間那覇市助役、城間恒淳、千原成悟、山田有登、古波倉博士、新嘉喜倫篤らの諸氏と、久米蔡氏堂に立ち寄り仲良くカメラに収まって後、波の上医院のよ平名さんの案内で那覇でも1,2位を争うという自慢のよ平名家の庭で談話に耽った。
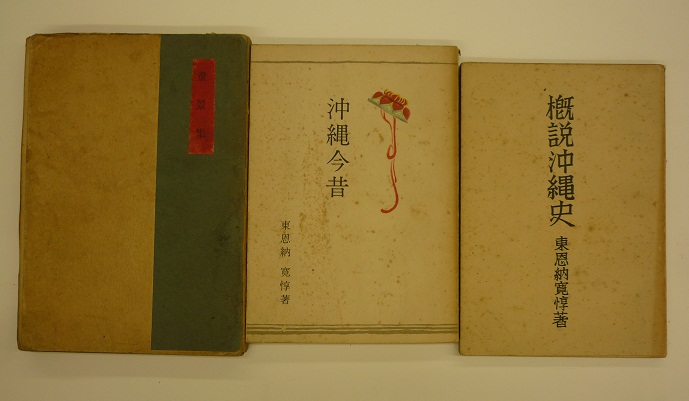

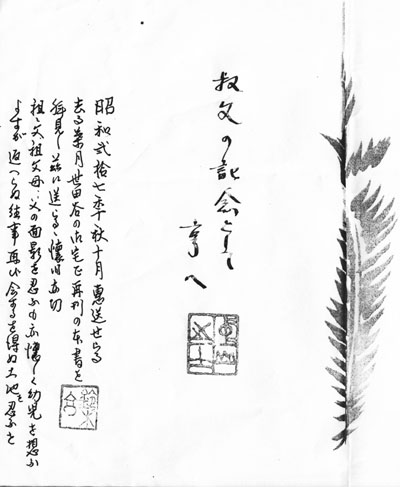
寛惇が『童景集』を瀬長佳奈と甥の鈴木亨に贈ったもの。
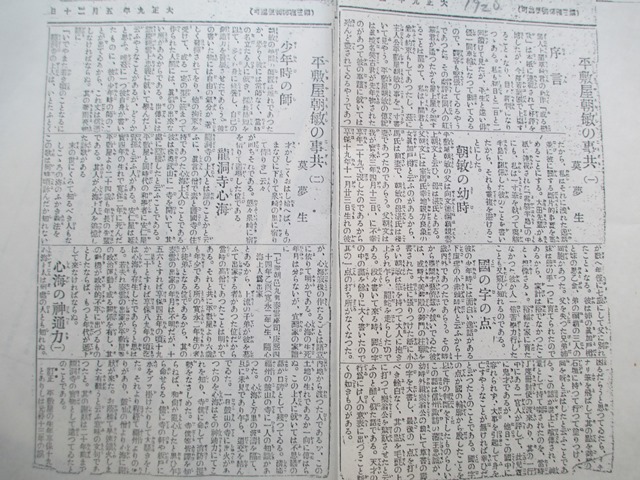
1920年5月ー『沖縄時事新報』莫夢生「平敷屋朝敏の事共」
序言
同人上間草秋君の新作「或る恋歌」は本紙に連載されて好評を博したが、今度若葉団で上場することとなり、目下評判になりつつある。私も初日と二日と二回続けて見たが、平生と違い俳優一同車輪になって働いているので、観客も緊張しているようであった。その劇評は同人の紅華君が遣ったから屋上屋を架することは罷めて、私は上間君と兼々約束もあいてあったし、茲に主人公平敷屋朝敏の事を一寸書いて見よう。平敷屋朝敏の伝記は真境名安興君が先年物されたのがあって彼の事蹟に就いては殆ど尽されているようであったから、私はそれに洩れた逸話並びに彼に関する断片的事実を集めることにする。大田先輩が本紙に連載された「与勝半島」の中にも、私は一寸筆を執って与勝半島に関係した彼のことを書いたから、それも重複を避けることにした。
朝敏の幼時
平敷屋朝敏の父は向文徳禰覇親雲上朝文と云い、母は湛氏とある。父朝文には室馬氏幸地親方良象の女真加戸樽と云うのがあるから、馬氏は前妻で、朝敏の母湛氏は後妻であったのであろう。父朝文は我が宝永三年四月十三日、に不幸享年二十九で没したのであるから享保十九年十一月二十三日生まれの彼が数え年僅かに七歳にして父に別れたこととなる。彼は姉の真加戸樽と妹の思乙金、弟の禰覇の三人の同胞があった。父を失った兄弟姉妹は母の手一つに育てられたのであるから、家計は裕ではなかったことと想像さるる。裕福な家に育たなかった彼が人一倍苦学力行したことも又窺い知られるのである。
國の字の点 少年時の師 龍洞寺心海
心海の神通力(一) 心海の神通力(二) 秘密の古墳
朝敏の頓智 酒と恋愛 此歌の別説 「或る恋歌」
美貌と香臭
平敷屋の美貌は人口に膾炙することであるが又彼には躰に一種の香臭があったとのことである。これ□□小姓時代のことだそうだが、同僚の者が何時も不思議に感ずるのは朝敏が座に就くと何とも云えぬ香ばしい匂いが漂うことであった。いづれもこれを不審なりとし遂に評判になった。或者はそれは彼が匂い物を身につけた為である。衣服の洒落なら兎に角男子として匂い物を身につくるなどとは余りに若気過ぎたざまであると誹り或いは面責してやろうと云う者もあったがそれよりも彼に沐浴を勧めてその性躰を慥むるに若くはないと云うことになり態々風呂を沸かして彼を招き何気なく入浴を勧めた。平敷屋も計略のあるとは夢にも知らず勧めらるるままに湯に入りやがて上がりぬれた躰を
拭く時に一同どやどやと入り来り検査を始めた。所が驚くべし馥郁たる香臭はいつもよりは甚だしく自然に彼の皮膚から醗酵する所のものだあったことが分かった。一同も漸く其の邪推なりしことを悟り實を打開けて遂に大笑いになったとのことである。これを或人は腋香の一種だと云ったがそうかも知れない。美男子美女には往々異性を誘惑する体臭があるとのことだが平敷屋も香水要らずのよい物を持っていたものだ。この話は誇張された虚談なりとしても彼が稀有の美男だったということはこれ等の話があるのでも類推さるるのである。
速筆と強記 他所目忍ぶな
妻女かめ 世の伝ふる所に依ると、下の歌は平敷屋夫婦唱和の歌と云うのである。 夢に夢蔵お側並べたる枕、吹きよおぞますな恋の嵐
上の句を朝敏が詠むと、細君が下句をつけたと云うのである。さてかような歌を詠んだ、平敷屋夫人はどんな才媛であったか、今知る由もないが、其の作ったという下の句の凡手にあらざるを見ても、其の人柄が偲ばるると共に、夫婦仲の円満なりしことも思い遣らるるのである。しからば彼女は如何なる素性の人かと云うに、南山王の系統を引いた阿姓であって、父は阿天壽、知花親方守壽、母は向氏仲田親方朝重の女眞犬金と云い、彼女は名を亀と称し長女であった。元禄13年8月11日の生まれで、夫と同年であるが、月から云うと彼女が長じていた。平敷屋との間に女子一人、男子二人をもうけた。平敷屋が刑死し、其の二人の男の子も流罪に処せられ、家は破滅、憂き困難、其の為に生命を縮めたのか元文4年12月28日即ち夫に別れてから5年の後、享年40歳で彼女も没した。阿姓佐久田家の家譜には 長女亀康煕39年庚辰8月11日生嫁平敷屋、雍正12年甲寅6月26日平敷屋得罪於安謝港八付、島並系記御取揚欠所ニ付貶百姓、乾隆4年巳未12月28日死、享年40號ばい心とある。平敷屋という美男の且つ粋人の妻であるから、彼女も又才貌双絶の佳人であったに違いない。
○私の聴いたこの歌の説は以上の通りだが、故恩河朝裕氏(熱心な琉球の故実研究家であった)の随筆には下のように伝えてある。・・・
○蔡温ー其の性格を儒者一流の弁を以て粉飾するの傾きがある為め門閥を以て一種の誇りとし、自ら文化的、趣味的に於いて優秀なりとした。・・・
○護得久朝常翁の手控本に沖縄の歌人歌学者の姓名並びに生死年代があるがそれに依ると屋良親雲上宣易は順治十五年戊戍の生まれで雍正七年已酉に卒す在世七十二年とあるのである。・・・
文若と朝敏(一) 文若と朝敏(二)
蔡温弾劾落書 千松明蝋燭 東風平親方 屋良親雲上 騎馬の曲者
判官へ助言 朝敏等の判決 罪人の子等 最後の髪結ひ
『琉歌集 琉歌百控乾柔節流 』初頁に「此の歌集ハ友人恩河朝祐君の公務を帯ひて伊平屋島に出張せし折に同島の某家所蔵の古本より寫して特に予に贈りたるものなり 仲吉朝助記(この歌集は友人の恩河朝祐君が公用にて伊平屋島に出張したときに同島の某家の所蔵の古本から写して私に贈ってくれたものである)」とあり、最終頁に「大清乾隆六十年乙卯正月十日 撰寫より書 壬子 旧六月十五日 寫之」とある。またそれに続く朱書から、大正14年3月10日に伊波普猷に贈られたことがわかる。/『琉歌疑問録』解説 明治33(1900) 1冊 16枚。玉山とは恩河朝祐のことである。琉歌や組踊集についての疑問を箇条書きで書き並べたもの。→琉球大学
恩河朝祐(1864~1917年)
1891年、第3回 沖縄中学校卒業
1892年、知事・丸岡莞爾、那覇役所(長・護得久朝常)兼島尻役所勤務~1900年
1914年10月7日『琉球新報』「恩河朝祐 宮古在勤中死去 奥平幸昌 屋部憲通 仲吉朝助」
1914年10月8日『琉球新報』真境名安興「恩河玉山兄を憶ふ」→『真境名安興全集』第四巻
1920年5月ー『沖縄時事新報』莫夢生「平敷屋朝敏の事共」
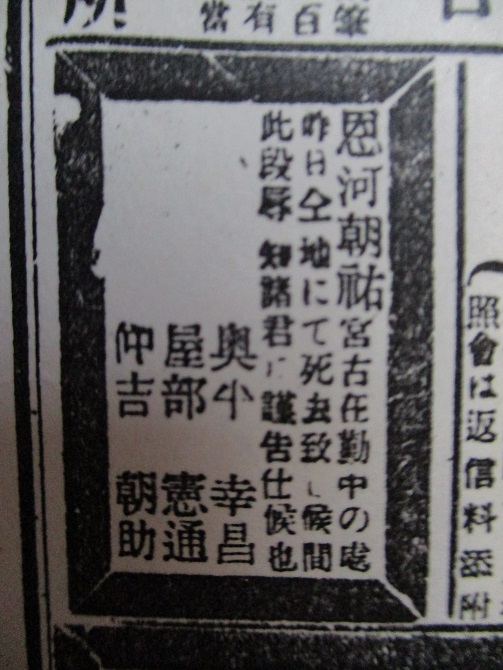
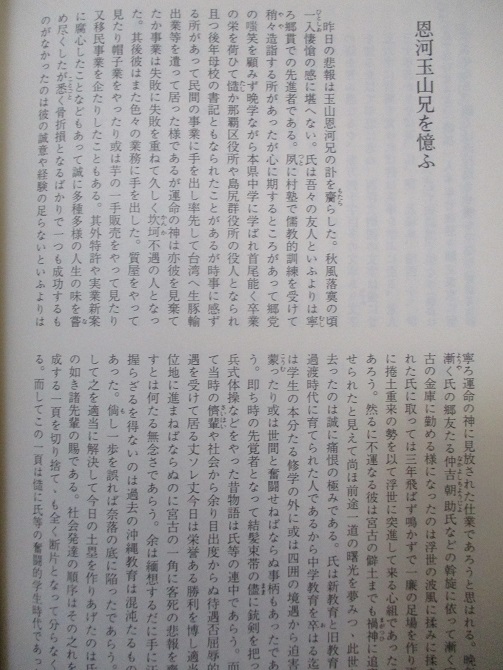
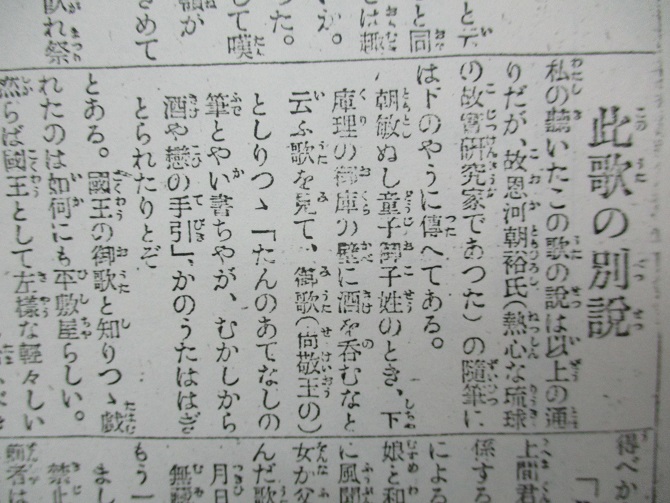
1920年7月20日『沖縄時事新報』に白浪庵(末吉安恭)「龍舟」30が載っています。残念ながらこの1回分しか残っておりませんが、麦門冬の内面が垣間見えるものです。
□汪応祖は腕組みをして独語す。北谷大屋子しばし躊躇して進まず。汪応祖「今俺はたしか刀の柄に手を掛けた。それはあの両人の者を斬ってしまおうと云うのであった。それにしてはこの俺に似合しからぬ料簡ではないか。俺は血腥い戦乱を鎮め、世の中を平和にしたい而して人民の生活を文化的に向上させたい。すべての罪悪をこの社会より根絶させたい。一の理想国をこの南の島の中に実現させたい。こんなことを始終思っている身ではないか。
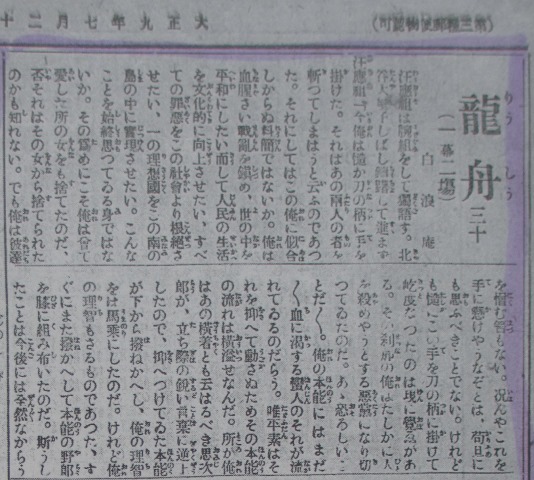
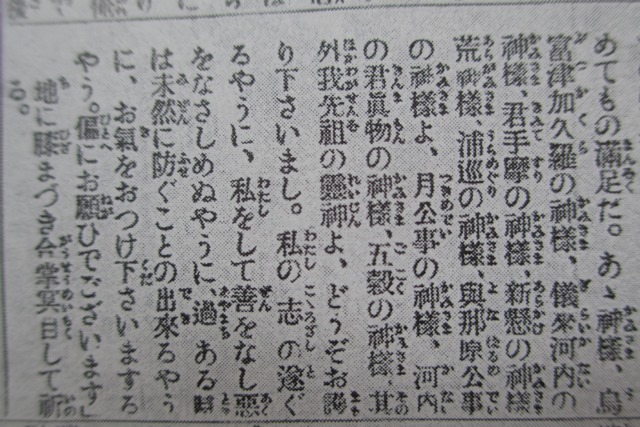
□1915年2月 『琉球新報』末吉麦門冬「琉球饑饉史」
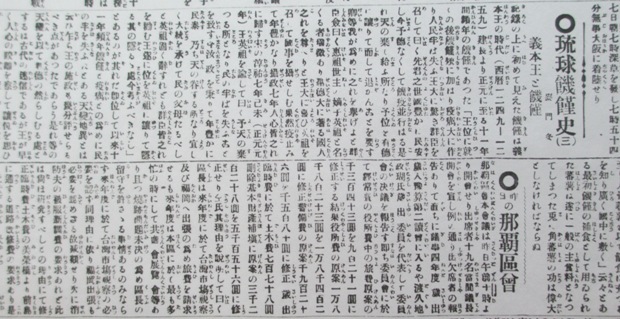
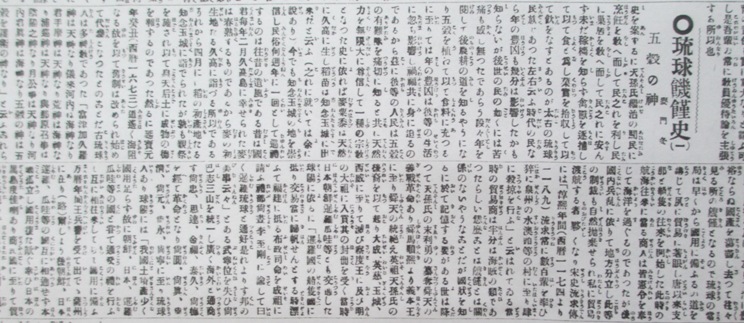
○古琉球人は多神教であった「冨津加久羅神は天神なり儀来河内は海神なり君手摩神は天神なり荒神は海神なり浦巡神は天神なり與那原召亊は陰陽之神なり月公亊は天神なり河内君真神は海神なり五穀の神は五穀を護衛の神なり」と云う。これらの神が婦人二夫に接せざる者に乗り移って遊び給ふと信ぜられて五穀の神などは節々に出現して人民に福を授け給ふと云うのである。・・・
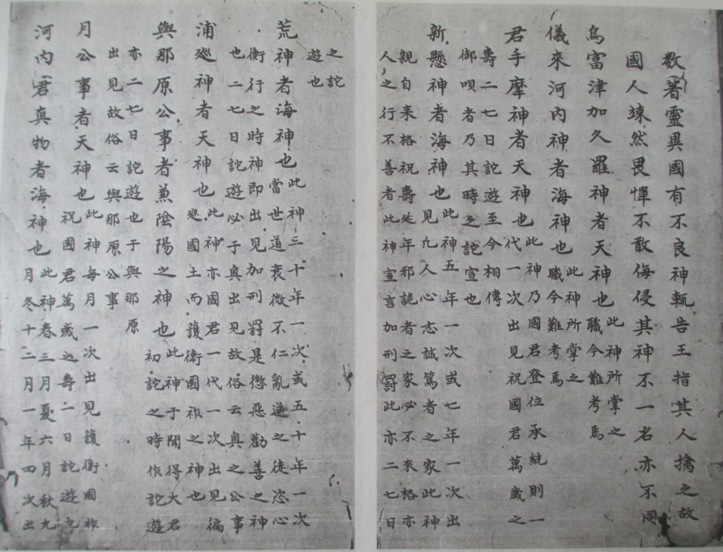
麦門冬は真境名安興から貰った『中山世譜』の神名を引用している。
□この文章の下に「円覚寺の建築」の記事が載っている。□県議事堂建築の為め来県忠の工師氏家重次郎氏は此の程県内の古建築を見て廻ったが首里の円覚寺の建築を見て大変気に入り俄かに研究心を刺激したと見えその視たる儘を語りて曰く円覚寺の創建は四百年前のものに係るようだが建築構造すべてが足利時代の特徴を発揮し兎に角見事なものである。伽藍などに少々缼漏のあるのは火災等の為に原型を失ったのでは無いかと思う。山門の石欄等足利時代の産物たる特色を呈している。寺鐘は佛殿前の小なる者が年代古く八百年前のものらしい同寺建築すべてが今は尚家の私有であるが保存上遺憾なからしむには是非国宝にして維持費を要求せなければならぬが自分の見る所では充分国宝たるの価値を有すると思う早く其の手続きをして国宝に編入されたがよい。今のままに打棄って置くのは実に惜しいものだ云々
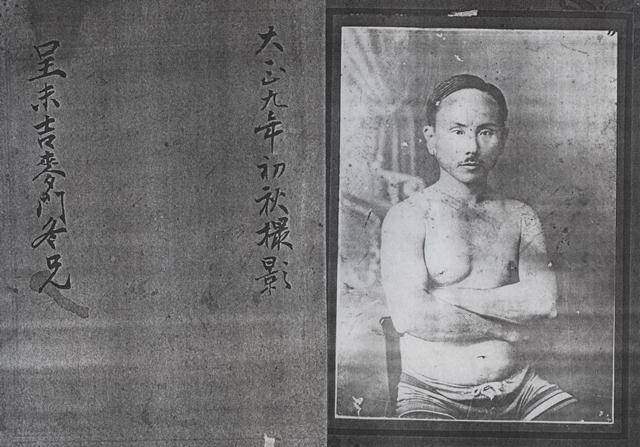
冨名腰(船越)義珍が末吉麦門冬に贈った写真
08/08: 1926年9月 小那覇全孝『琉球年刊歌集』琉球狩社
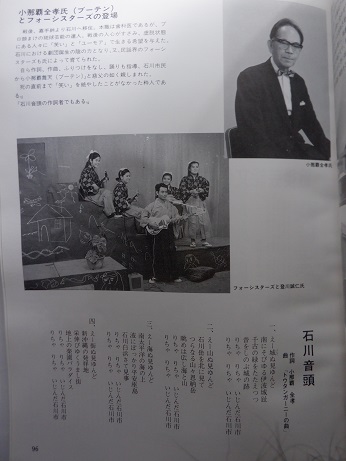
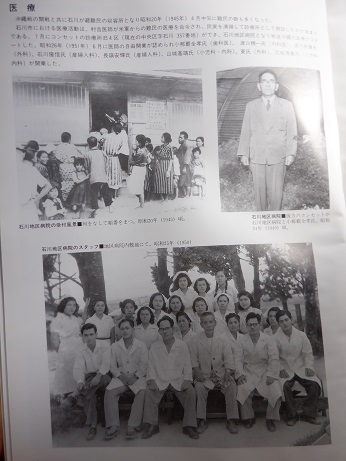
1990年9月 市制45周年記念『『いしかわ』沖縄県石川市
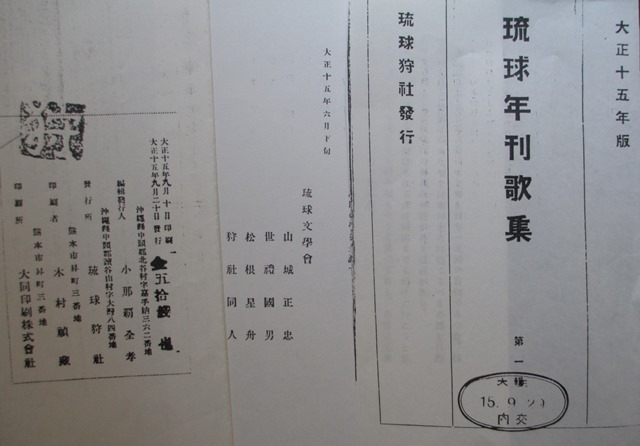
1926年9月 『琉球年刊歌集』琉球狩社
□山城正忠「序に代へて」/琉球文学会ー山城正忠、世禮国男、松根星舟、狩社同人「琉球年刊歌集発刊之辞」
□當間黙牛/北村白楊/島袋九峯/伊豆味山人/伊竹哀灯/宮里潮洋/國吉瓦百/名嘉元浪村/照屋一男/上里堅蒲/比嘉泣汀/池宮城寂泡/新田矢巣雄/間國三郎/川島涙夢/島袋哀子/漢那浪笛/山里端月/又吉光市路/美津島敏雄/江島寂潮/西平銀鳴/山城正斉/大山潮流/池宮城美登子/星野しげる/小栗美津樹/禿野兵太/新島政之助/小林寂鳥/梅茂薫村/水野蓮子/松根星舟
□国吉真哲翁は1924年4月、山城正忠を会長に、上里春生、伊波普哲、山口三路(貘)らで琉球歌人連盟を発足させた。国吉翁はこのころ、貘と一緒に歌人連盟顧問の麦門冬を訪ねた。同年暮れに麦門冬は急死した。連盟の団結は後に『琉球年刊歌集』として結実した。25年9月の『沖縄教育』(又吉康和編集)は山城正忠が表紙題字、カット(獅子)は山口重三郎である。同年11月、真境名安興が沖縄県立沖縄図書館長に就任したころ、国吉翁は又吉康和の後任の『沖縄教育』編集人となる。又吉は沖縄県海外協会に転じた。海外協会の機関誌『南鵬』には国吉翁の詩歌が載っている。琉球新報連載「むかし沖縄」285回に国吉翁撮影の写真がある。真栄田一郎の墓前で池宮城秀意、瀬長亀次郎、城間得栄、上原美津子が写っている。真哲翁は真栄田一郎が死んだ時、姉の冬子から「弟の死顔でも良いから写真に撮って送ってほしい」との依頼を受け、棺を開け写真を撮った。戦後、瀬長はうるま新報の社長、池宮城はうるま新報専務となる。瀬長と池宮城は沖縄人民党結成に参加する。その人民党誕生の瞬間を国吉翁が記録することになる。
□1897年、今帰仁村に生まれました。本名は小那覇全孝といい、彼の本業は歯科医で、県立二中の第一期卒業生にして日本歯科医大学を卒業した秀才です。愛称を「ブーテン」で呼ばれます。第二次世界大戦の戦後復興の時代に、弟子の照屋林助と村々を回って、「命の御祝事さびら」(生きていることを祝いましょう)と呼びかけ、戦禍の傷が癒えない人々に生きる力と勇気を与えました。沖縄の漫談の祖です。三味線に乗せて世相を風刺する抱腹絶倒の漫談は天歳的です。代表作には「石川小唄」「スーヤーヌパァパァ」「盗ドゥ万才」「百歳の花風」があります。1969年に亡くなりました。享年72歳でした。 →(小那覇舞天 おなはぶーてん / ラジカル・ビスケット)
05/12: 琉米誌
1899年1月20日ー勝海舟、旧主君徳川慶喜の10男・精(くわし/11歳)を養子婿に迎える
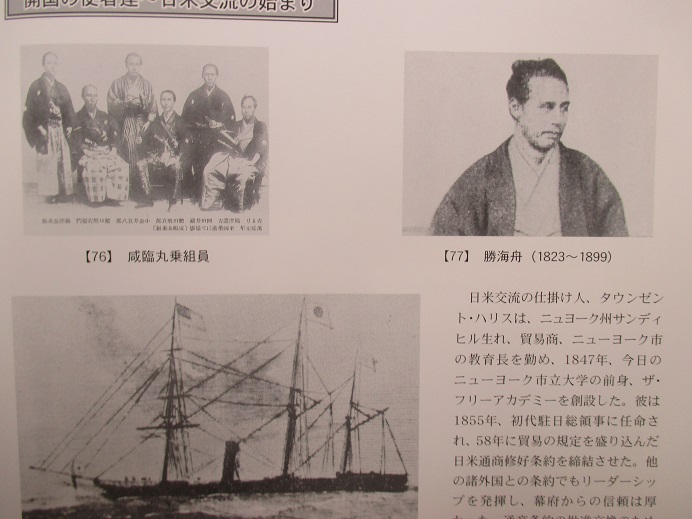
「勝海舟」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
1902年5月19日ー兒玉源太郎台湾総督、井上勝ら福岡丸にて来沖
同年1月に日英同盟条約調印。兒玉源太郎台湾総督(1875年にも来沖)、井上勝ら福岡丸にて来沖。那覇の潟原で那覇首里の小学校の運動会を見る。また首里を遊覧。風月楼で2区の有志及び各役所の高等官60名「歓迎会」。
児玉源太郎 こだまげんたろう
1852(嘉永5)~1906(明治39) 明治時代の陸軍軍人(大将)
徳山藩士児玉半九郎忠碩の長男。戊辰戦争に藩の献功隊士として参加。のち陸軍に入り、佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争に従軍して頭角をあらわした。 1887(M20)陸大校長としてドイツの軍制・戦術の移入紹介につとめ、91ヨーロッパ視察。 92~98陸軍次官兼軍務局長、日清戦争で大本営参謀、功により男爵。96中将に昇進し、長州軍閥の1人として重きをなした。 98台湾総督。1900第4次伊藤内閣・桂内閣で陸相、一時内相と文相を兼任。 04大将に累進して日露戦争に出征し、満州軍総参謀長、戦功により子爵。06参謀総長に就任。南満州鉄道株式会社創立委員長。没後、伯爵。 (はてなキーワード)
日本の近代的交通網を整えた「鉄道の父」
井上 勝 ( いのうえ まさる ) ●天保14年(1843)-明治43年(1910)
勝は天保14年(1843)、藩士井上小豊後勝行の三男として、土原浜坊筋に生まれました。長崎でオランダ士官に兵学を学び、江戸では砲術を修行して、さらに箱館へ行って英国領事館員に英語を学びました。その後航海術習得のため、伊藤博文や井上馨らと英国へ密航してロンドン大学に留学し、鉱山学および鉄道の実業を研究して、明治元年(1868)に帰国しました。明治4年(1871)に鉱山頭兼鉄道頭となり、新橋―横浜間に日本最初の鉄道を開通させて以来、工部大輔・鉄道庁長官等を歴任して、全国各地の近代的交通網を整備しました。明治22年(1889)には、東京―神戸間の東海道線を全通させています。同43年(1910)に鉄道院顧問となり、欧州を視察しましたが、ロンドンで病死しました。享年68歳。
墓は、沢庵和尚を開山として、寛永15年(1625)に3代将軍徳川家光によって創建された品川の東海寺墓地にありますが、ここはJR東海道線と山手線とが分岐するところとなっています。また東京駅頭には、大正3年(1914)に銅像が建てられ、戦時中の金属供出によって台座のみとなっていましたが、没後50周年の昭和34年(1959)に再び銅像が建てられました。(city.hagi.lg.jp)■ちなみに井上勝の娘は松方正義の9男義輔に嫁いでいる。松方の3男幸次郎(元川崎造船社長)は松方コレクションで知られる。
1910年3月9日ー勝精伯爵、農務省水産講習船「雲鷹丸」で来沖。岡雷平やまと新聞記者が同行
1911年6月8日 尚昌、神山政良、イギリス留学の途次サンフランシスコ着、安仁屋政修(沖縄県人会会長)らが出迎える。
1911年11月11日、ブール、シュワルツとともに来沖。→1991年1月 ①伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』
1912年3月27日にポトマック公園で、ヘレン・タフト大統領夫人と珍田日本大使夫人によって桜(ソメイヨシノ種)が植えられた、という。桜の穂木は東京荒川の桜並木だが、台木は兵庫県東野村で育てたものという。詳しくはネット検索で見てほしい。最近、アメリカの首都は何処にあるかと検索したら前記の桜の話が出てきた。アメリカ合衆国の首都はワシントン・コロンビア特別区(Washington,District Of Columbia)で1790年7月16日に設立。

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(ニューヨークで小橋川朝重撮影)
1913年 山田有登、大阪市聖バルナバ病院に勤務。→『沖縄県人録』(1937年)に「山田有登君は那覇市の出身。明治17年1月22日を以て生まれる。沖縄県立中学校を経て金沢医学専門学校に学び、明治42年同校を卒業するや、直ちに石川県立病院に勤務して研鑽を積み同44年6月に愛知県渥美郡田原病院に転じて更に其の蘊奥を極め、大正2年聘せられて大阪市聖バルナバ病院に勤務。同9年転じて久原鉱業経営の鉱山病院に勤務。同11年退職帰県して久米大道りに開業。昭和11年、那覇市に逓信診療所開設されると其の初代所長となり今日に至る。なお君は学生時代野球選手たりしだけに野球に趣味あり」とある。→2011年9月23日、以前から気になっていた天王寺の聖バルナバ病院をのぞく。受付で病院の案内パンフレットをもらう。それによると、同病院は1873年にアメリカ聖公会により派遣された宣教医師Henry Laningが大阪川口居留地に米国伝道会施療院を開設したのに始まる。1923年に川口から天王寺細工谷の現在地に移転しているから、写真家の山田實さんの父・有登は同病院に1913年から1920年まで勤務。その時の場所は川口ということになる。
□川口が貿易港として継続的発展をなしえなかったのは、安治川河口から約6km上流に位置する河川港であるため水深が浅く、大型船舶が入港出来なかったことによる。そのため、外国人貿易商は良港を有する神戸外国人居留地へと移住していった。彼らに代わってキリスト教各派の宣教師が定住して教会堂を建てて布教を行い、その一環として病院、学校を設立し経営を行った。平安女学院、プール学院、大阪女学院、桃山学院、立教学院、大阪信愛女学院といったミッションスクールや聖バルナバ病院等はこの地で創設されたのである。それら施設も高度な社会基盤が整備されるに従い、大阪の上町エリア(天王寺区・阿倍野区など)へ次々と移転して川口は衰退への道をたどることになる。対照的に大型外国船が集まるようになった神戸港は、1890年代には東洋最大の港へと拡大していった。(→ウィキペディア)
1914年5月9日『沖縄毎日新聞』伊波月城「日光浴ー新文明の先駆者たる北米合衆国の平民詩人ワルトホヰットマン②は3、40年これを実行したのである。・・・」
②ウォルター・ホイットマン はアメリカ合衆国の詩人、随筆家、ジャーナリスト、ヒューマニスト。超越主義から写実主義への過渡期を代表する人物の一人で、作品には両方の様相が取り込まれている。アメリカ文学において最も影響力の大きい作家の一人でもあり、しばしば「自由詩の父」と呼ばれる。→ ウィキペディア
1914年6月26日『沖縄毎日新聞』「粗枝大葉ー19世紀の偉大なるアメリカ人ワルト、ホイットマンは大いなる都会とは・・・・」
1915年8月ー前暁鐘社の野里朝淳がマウィ島カフルイ港で写真屋開業
1916年6月9日『琉球新報』平良生(在ロスアンゼルス)「米国通信」
1917年9月、山入端隣次郎、アメリカよりT型フォードを3台導入し沖縄自動車商会を開業、運転手は福井県出身の大宮孝太郎。大宮は沖縄県「運転手免許証」(大正6年10月8日発行)第一号である。12月、布哇沖縄海外協会(當山善真)『会報』□表紙「汎太平洋と布哇」、大城幸之一「沖縄県の疲弊と之が対応策」、比嘉静観「沖縄県救済策」、大田朝敷「沖縄本島巡講行脚」、新城北山「布哇沿岸の琉球民族」/沖縄県海外協会(又吉康和)『南鵬』第1巻第2号□大田朝敷「ハワイと沖縄の関係」
1917年11月23日『琉球新報』「64年前ペリーと琉球を経て浦賀に上陸したハーデー翁が17日来日」
名護朝助
慶応義塾入社名簿に/名護朝助 本籍地 沖縄県首里當蔵35 戸主 士族
明治11年3月生 明治30年5月入社 証人 岸本賀昌
アメリカに渡米、10年余滞在
大正元年10月ー西洋料理「美理軒」(名護朝助経営、コック永田亀寿・元シュワルツ家コック)饒平名病院隣、一味亭跡に開業/11月ー『琉球新報』□食道楽君のピリケンの解釈は違っている。ピリケンとは福の神の意味で寺内総督にピリケンの名を冠したのは惑新聞が七福神の似顔を募った時、総督の三角頭が七福神の一つに及第したことがあるからピリケンのアダ名も蓋し之に出たのであろう。洋食屋の美理軒なるほど語呂はよくないが来る御客様を福の神と見立てたものであるとすれば語呂ぐらいは我慢が出来る。アテ字の美は美味の美、理は料理の理と見れば何れにしても結構じゃないか。
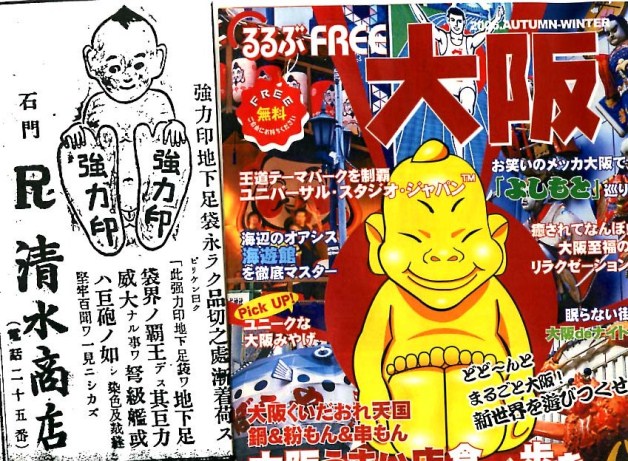
1918(大正7)年3月の『琉球新報』広告/2006年9月『JTBパプリッシング』表紙
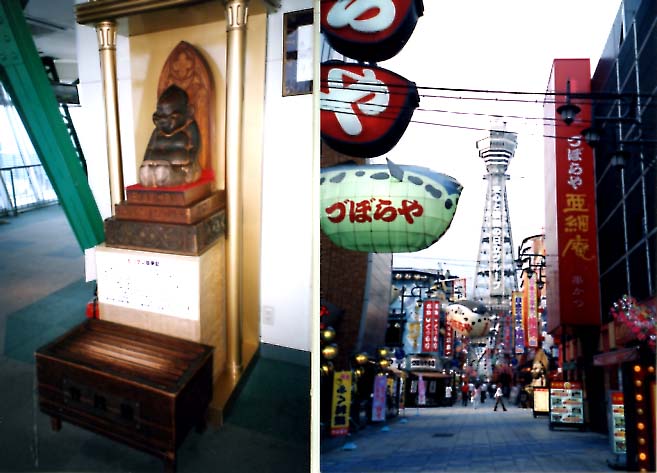
左ー通天閣のビリケンさん/通天閣の見える右下にビリケンさんが見える

□通天閣の展望台で、真っ先に迎えてくれるのが、幸運の神様「ビリケン像」。
合格祈願・縁結びなどあらゆる願いを聞いてくれる、なんでもござれの福の神なんです。通天閣の「ビリケン」は、5階の展望台の立派な台座にちょこんと座っています。
笑っているのか怒っているのか。不思議な表情と、愛敬あるポーズが人気で、いつもお願いする人が絶えません。
ビリケン(BILLIKEN)は、1908年(明治41年)アメリカの女流美術家 フローレンス・プリッツという女性アーティストが、夢で見たユニークな神様をモデルに制作したものと伝えられています。トンガリ頭につりあがった目という、どこかしらユーモラスな姿は、たちまち「幸福のマスコット」「福の神」としてアメリカを始め世界中に大流行しました。
日本でも花柳界などで縁起物として愛されていました。
世界的な流行を受けて、1912年(明治45年)オープンした「新世界」の遊園地「ルナパーク(月の園)」では、さっそく「ビリケン堂」を造りビリケンを安置。これは大当たりし、新世界名物としてその名をとどろかせ、ビリケン饅頭やビリケン人形などのみやげ物まで作られました。また「福の神・ビリケン」を七福神に加え、「八福神めぐり」なども流行したと伝えられています。しかしビリケンは、ルナパークの閉鎖と共に行方不明になってしまいました。
オイルショックが去り、通天閣の灯が復活して新世界に活気がよみがえった1979年〈昭和54年〉、浪速文化の拠点をめざした「通天閣ふれあい広場(現・3階イベントホル)」ができました。その後、1980年(昭和55年3月30日)に新世界に馴染みの深い「ビリケン」の復活も決まりました。しかし、資料になるべき写真が見つからず。思案にくれている時、田村駒株式会社が版権を持っていることが判明。田村駒さんのご好意で、同社の「ビリケン」をもとに木彫で復元したのです。像の彫刻は伊丹市在住の安藤新平さん。(→通天閣)
1919年 宮城与徳、父与正の呼び寄せで渡米→1921年ー屋部憲傳、又吉淳、幸地新政らと「黎明会」結成。
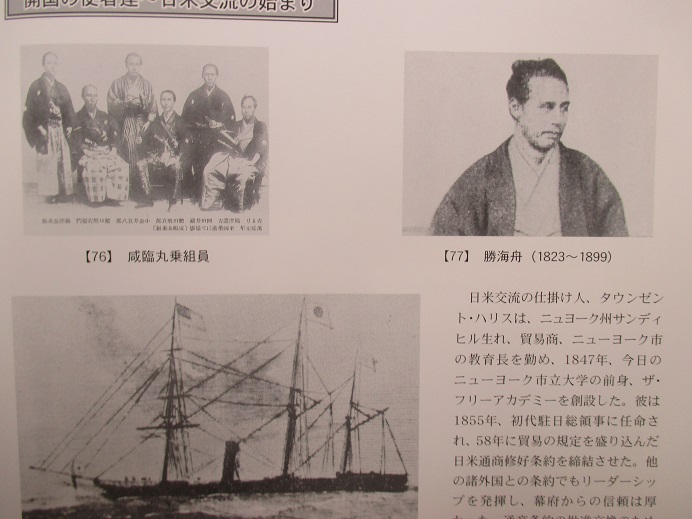
「勝海舟」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会
1902年5月19日ー兒玉源太郎台湾総督、井上勝ら福岡丸にて来沖
同年1月に日英同盟条約調印。兒玉源太郎台湾総督(1875年にも来沖)、井上勝ら福岡丸にて来沖。那覇の潟原で那覇首里の小学校の運動会を見る。また首里を遊覧。風月楼で2区の有志及び各役所の高等官60名「歓迎会」。
児玉源太郎 こだまげんたろう
1852(嘉永5)~1906(明治39) 明治時代の陸軍軍人(大将)
徳山藩士児玉半九郎忠碩の長男。戊辰戦争に藩の献功隊士として参加。のち陸軍に入り、佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争に従軍して頭角をあらわした。 1887(M20)陸大校長としてドイツの軍制・戦術の移入紹介につとめ、91ヨーロッパ視察。 92~98陸軍次官兼軍務局長、日清戦争で大本営参謀、功により男爵。96中将に昇進し、長州軍閥の1人として重きをなした。 98台湾総督。1900第4次伊藤内閣・桂内閣で陸相、一時内相と文相を兼任。 04大将に累進して日露戦争に出征し、満州軍総参謀長、戦功により子爵。06参謀総長に就任。南満州鉄道株式会社創立委員長。没後、伯爵。 (はてなキーワード)
日本の近代的交通網を整えた「鉄道の父」
井上 勝 ( いのうえ まさる ) ●天保14年(1843)-明治43年(1910)
勝は天保14年(1843)、藩士井上小豊後勝行の三男として、土原浜坊筋に生まれました。長崎でオランダ士官に兵学を学び、江戸では砲術を修行して、さらに箱館へ行って英国領事館員に英語を学びました。その後航海術習得のため、伊藤博文や井上馨らと英国へ密航してロンドン大学に留学し、鉱山学および鉄道の実業を研究して、明治元年(1868)に帰国しました。明治4年(1871)に鉱山頭兼鉄道頭となり、新橋―横浜間に日本最初の鉄道を開通させて以来、工部大輔・鉄道庁長官等を歴任して、全国各地の近代的交通網を整備しました。明治22年(1889)には、東京―神戸間の東海道線を全通させています。同43年(1910)に鉄道院顧問となり、欧州を視察しましたが、ロンドンで病死しました。享年68歳。
墓は、沢庵和尚を開山として、寛永15年(1625)に3代将軍徳川家光によって創建された品川の東海寺墓地にありますが、ここはJR東海道線と山手線とが分岐するところとなっています。また東京駅頭には、大正3年(1914)に銅像が建てられ、戦時中の金属供出によって台座のみとなっていましたが、没後50周年の昭和34年(1959)に再び銅像が建てられました。(city.hagi.lg.jp)■ちなみに井上勝の娘は松方正義の9男義輔に嫁いでいる。松方の3男幸次郎(元川崎造船社長)は松方コレクションで知られる。
1910年3月9日ー勝精伯爵、農務省水産講習船「雲鷹丸」で来沖。岡雷平やまと新聞記者が同行
1911年6月8日 尚昌、神山政良、イギリス留学の途次サンフランシスコ着、安仁屋政修(沖縄県人会会長)らが出迎える。
1911年11月11日、ブール、シュワルツとともに来沖。→1991年1月 ①伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』
1912年3月27日にポトマック公園で、ヘレン・タフト大統領夫人と珍田日本大使夫人によって桜(ソメイヨシノ種)が植えられた、という。桜の穂木は東京荒川の桜並木だが、台木は兵庫県東野村で育てたものという。詳しくはネット検索で見てほしい。最近、アメリカの首都は何処にあるかと検索したら前記の桜の話が出てきた。アメリカ合衆国の首都はワシントン・コロンビア特別区(Washington,District Of Columbia)で1790年7月16日に設立。

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(ニューヨークで小橋川朝重撮影)
1913年 山田有登、大阪市聖バルナバ病院に勤務。→『沖縄県人録』(1937年)に「山田有登君は那覇市の出身。明治17年1月22日を以て生まれる。沖縄県立中学校を経て金沢医学専門学校に学び、明治42年同校を卒業するや、直ちに石川県立病院に勤務して研鑽を積み同44年6月に愛知県渥美郡田原病院に転じて更に其の蘊奥を極め、大正2年聘せられて大阪市聖バルナバ病院に勤務。同9年転じて久原鉱業経営の鉱山病院に勤務。同11年退職帰県して久米大道りに開業。昭和11年、那覇市に逓信診療所開設されると其の初代所長となり今日に至る。なお君は学生時代野球選手たりしだけに野球に趣味あり」とある。→2011年9月23日、以前から気になっていた天王寺の聖バルナバ病院をのぞく。受付で病院の案内パンフレットをもらう。それによると、同病院は1873年にアメリカ聖公会により派遣された宣教医師Henry Laningが大阪川口居留地に米国伝道会施療院を開設したのに始まる。1923年に川口から天王寺細工谷の現在地に移転しているから、写真家の山田實さんの父・有登は同病院に1913年から1920年まで勤務。その時の場所は川口ということになる。
□川口が貿易港として継続的発展をなしえなかったのは、安治川河口から約6km上流に位置する河川港であるため水深が浅く、大型船舶が入港出来なかったことによる。そのため、外国人貿易商は良港を有する神戸外国人居留地へと移住していった。彼らに代わってキリスト教各派の宣教師が定住して教会堂を建てて布教を行い、その一環として病院、学校を設立し経営を行った。平安女学院、プール学院、大阪女学院、桃山学院、立教学院、大阪信愛女学院といったミッションスクールや聖バルナバ病院等はこの地で創設されたのである。それら施設も高度な社会基盤が整備されるに従い、大阪の上町エリア(天王寺区・阿倍野区など)へ次々と移転して川口は衰退への道をたどることになる。対照的に大型外国船が集まるようになった神戸港は、1890年代には東洋最大の港へと拡大していった。(→ウィキペディア)
1914年5月9日『沖縄毎日新聞』伊波月城「日光浴ー新文明の先駆者たる北米合衆国の平民詩人ワルトホヰットマン②は3、40年これを実行したのである。・・・」
②ウォルター・ホイットマン はアメリカ合衆国の詩人、随筆家、ジャーナリスト、ヒューマニスト。超越主義から写実主義への過渡期を代表する人物の一人で、作品には両方の様相が取り込まれている。アメリカ文学において最も影響力の大きい作家の一人でもあり、しばしば「自由詩の父」と呼ばれる。→ ウィキペディア
1914年6月26日『沖縄毎日新聞』「粗枝大葉ー19世紀の偉大なるアメリカ人ワルト、ホイットマンは大いなる都会とは・・・・」
1915年8月ー前暁鐘社の野里朝淳がマウィ島カフルイ港で写真屋開業
1916年6月9日『琉球新報』平良生(在ロスアンゼルス)「米国通信」
1917年9月、山入端隣次郎、アメリカよりT型フォードを3台導入し沖縄自動車商会を開業、運転手は福井県出身の大宮孝太郎。大宮は沖縄県「運転手免許証」(大正6年10月8日発行)第一号である。12月、布哇沖縄海外協会(當山善真)『会報』□表紙「汎太平洋と布哇」、大城幸之一「沖縄県の疲弊と之が対応策」、比嘉静観「沖縄県救済策」、大田朝敷「沖縄本島巡講行脚」、新城北山「布哇沿岸の琉球民族」/沖縄県海外協会(又吉康和)『南鵬』第1巻第2号□大田朝敷「ハワイと沖縄の関係」
1917年11月23日『琉球新報』「64年前ペリーと琉球を経て浦賀に上陸したハーデー翁が17日来日」
名護朝助
慶応義塾入社名簿に/名護朝助 本籍地 沖縄県首里當蔵35 戸主 士族
明治11年3月生 明治30年5月入社 証人 岸本賀昌
アメリカに渡米、10年余滞在
大正元年10月ー西洋料理「美理軒」(名護朝助経営、コック永田亀寿・元シュワルツ家コック)饒平名病院隣、一味亭跡に開業/11月ー『琉球新報』□食道楽君のピリケンの解釈は違っている。ピリケンとは福の神の意味で寺内総督にピリケンの名を冠したのは惑新聞が七福神の似顔を募った時、総督の三角頭が七福神の一つに及第したことがあるからピリケンのアダ名も蓋し之に出たのであろう。洋食屋の美理軒なるほど語呂はよくないが来る御客様を福の神と見立てたものであるとすれば語呂ぐらいは我慢が出来る。アテ字の美は美味の美、理は料理の理と見れば何れにしても結構じゃないか。
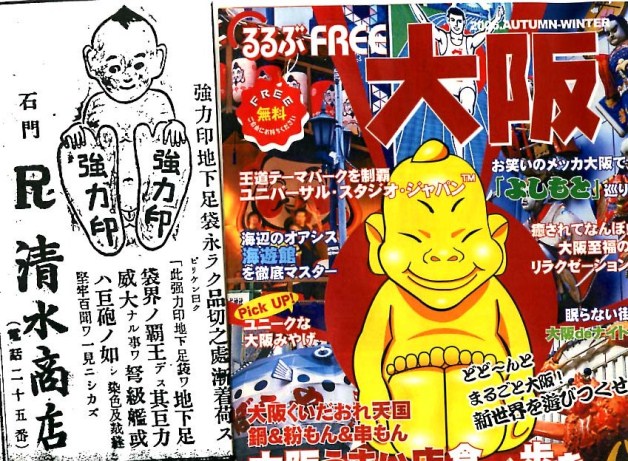
1918(大正7)年3月の『琉球新報』広告/2006年9月『JTBパプリッシング』表紙
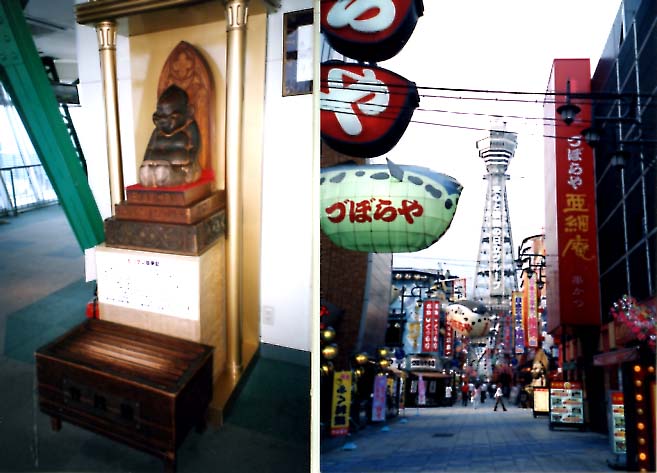
左ー通天閣のビリケンさん/通天閣の見える右下にビリケンさんが見える

□通天閣の展望台で、真っ先に迎えてくれるのが、幸運の神様「ビリケン像」。
合格祈願・縁結びなどあらゆる願いを聞いてくれる、なんでもござれの福の神なんです。通天閣の「ビリケン」は、5階の展望台の立派な台座にちょこんと座っています。
笑っているのか怒っているのか。不思議な表情と、愛敬あるポーズが人気で、いつもお願いする人が絶えません。
ビリケン(BILLIKEN)は、1908年(明治41年)アメリカの女流美術家 フローレンス・プリッツという女性アーティストが、夢で見たユニークな神様をモデルに制作したものと伝えられています。トンガリ頭につりあがった目という、どこかしらユーモラスな姿は、たちまち「幸福のマスコット」「福の神」としてアメリカを始め世界中に大流行しました。
日本でも花柳界などで縁起物として愛されていました。
世界的な流行を受けて、1912年(明治45年)オープンした「新世界」の遊園地「ルナパーク(月の園)」では、さっそく「ビリケン堂」を造りビリケンを安置。これは大当たりし、新世界名物としてその名をとどろかせ、ビリケン饅頭やビリケン人形などのみやげ物まで作られました。また「福の神・ビリケン」を七福神に加え、「八福神めぐり」なども流行したと伝えられています。しかしビリケンは、ルナパークの閉鎖と共に行方不明になってしまいました。
オイルショックが去り、通天閣の灯が復活して新世界に活気がよみがえった1979年〈昭和54年〉、浪速文化の拠点をめざした「通天閣ふれあい広場(現・3階イベントホル)」ができました。その後、1980年(昭和55年3月30日)に新世界に馴染みの深い「ビリケン」の復活も決まりました。しかし、資料になるべき写真が見つからず。思案にくれている時、田村駒株式会社が版権を持っていることが判明。田村駒さんのご好意で、同社の「ビリケン」をもとに木彫で復元したのです。像の彫刻は伊丹市在住の安藤新平さん。(→通天閣)
1919年 宮城与徳、父与正の呼び寄せで渡米→1921年ー屋部憲傳、又吉淳、幸地新政らと「黎明会」結成。